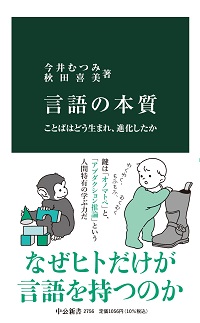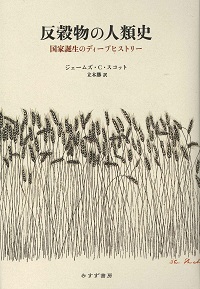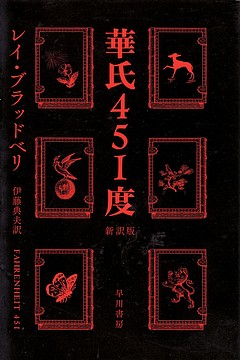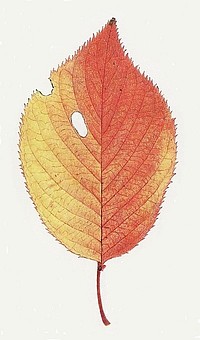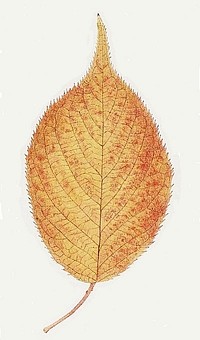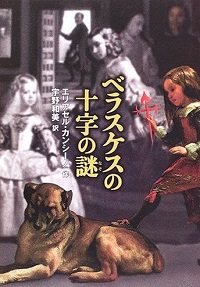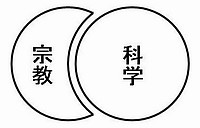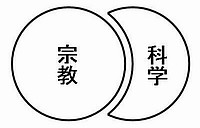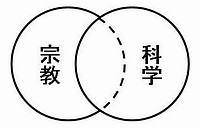No.364 - 言語の本質 [本]
No.344「算数文章題が解けない子どもたち」で、慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏の同名の著作を紹介しました(著者は他に6名)。今回は、その今井氏が名古屋大学准教授の秋田喜美氏(言語心理学者)と執筆した『言語の本質 - ことばはどう生まれ、進化したか』(中公新書 2023。以下、"本書")を是非紹介したいと思います。共同執筆ですが、全体の核の部分は今井氏によるようです。
言うまでもなく、言語は極めて複雑なシステムです。それを、全くのゼロ(=赤ちゃん)から始まってヒトはどのように習得していくのか。本書はそのプロセスの解明を通して、言語の本質に迫ろうとしています。それは明らかに「ヒトとは何か」に通じます。
"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。
しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。
AI研究者との対話
本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。
少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。
上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。
オノマトペ
オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、
感覚イメージを写し取る記号
と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。
もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。
オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。
音象徴
オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。
母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。
さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、
との質問をすると、多くの言語の多くの話者は「左側がマルマ」と答えます。
音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。
マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。
しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。
音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。
言語の習得過程(1)
幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。
そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。
言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。
著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。
このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。
このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。
一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。
対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。
「ノスノス」実験
しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。
「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。
記号接地
もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。
辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。
その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。
身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。
「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。
また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。
こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、
などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。
しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。
そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。
言語の習得過程(2)
子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、
の2つを学んだ子どもが、
事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。
英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。
過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。
推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。
アブダクション推論
論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。
演繹推論
帰納推論
アブダクション推論
もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。
帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。
それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、
という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、
が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。
仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。
「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。
アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、
と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。
という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。
言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。
アブダクションの起源:ヒトと動物の違い
「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、
という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。
言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。
この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。
子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。
そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。
人間は
記号→対象
を学習すると、同時に、
対象→記号
も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、
XだからA
をもとに、
AだからX
という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、
と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。
人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。
ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。
そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、
という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。
乳児は対称性推論をするか
対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。
チンパンジーは対称性推論をするか
チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。
この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。
この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。
つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。
"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。
人類の進化
本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。
人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。
「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。
感想
以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。
「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。
「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。
但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。
原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。
本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。
しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。
さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。
ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。
本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。
これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。
「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。
しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。
岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。
ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。
"言語の本質" とか "言葉とは何か" は、過去100年以上、世界の言語学者、人類学者、心理学者などが追求してきたものです。本書はその "壮大な" テーマを扱った本です。大風呂敷を広げた題名と思えるし、しかも新書版で約280ページというコンパクトさです。大丈夫なのか、見かけ倒しにならないのか、と疑ってしまいます。
しかし実際に読んでみると「言語の本質」というタイトルに恥じない出来映えの本だと思いました。読む立場としても幾多の発見があり、また個々の論旨の納得性も高い。以下に、内容の "さわり" を紹介します。
AI研究者との対話
本書で展開されている著者の問題意識のきっかけが、今井氏による「あとがき」に記されています。その部分を引用すると次の通りです。
| 以降の引用では、段落を増やしたところ、図の番号を修正したところや、漢数字を算用数字にしたところがあります。また下線は原文にはありません) |
|
少々意外なのですが、今井氏の問題意識の発端(の重要な点)は人工知能(AI)研究者との交流だったのですね。本書には、今井氏が自著の『ことばと思考』の冒頭部分を ChatGPT に英訳させた例が載っていて、今井氏は「ほとんど完璧」と書いています。しかし ChatGPT とヒトとの言葉の認識のあり方は全く違っていて、その違いも本書のテーマと結びついています。こういった記述は、今井氏の AI への関心が窺えます。
上の引用のキーワードは「記号接地(symbol grounding)」です。記号接地とは、記号(言語の場合は音の塊・並び)が人間の身体感覚(視覚、聴覚、触覚、心理感覚、・・・・・・ など)と結びつくことを言います。これが言語習得の第一歩だとするのが、本書の第1の主題です。それがオノマトペを例に説明されています。
オノマトペ
オノマトペとは、いわゆる擬音語、擬態語、擬情語(=「ワクワク」「ドキドキ」などの内的感覚・感情を表す語)の総称です。重複形が多いが、そればかりではありません(笑顔を表す擬態語に「ニコニコ」と「ニコッ」がある例)。オノマトペは、
感覚イメージを写し取る記号
と定義できます。ここでのキーワードは、まず「感覚」(視覚、聴覚、触覚、味覚など)です。オノマトペは、形容詞などと同じく "感覚" を表す言葉です。しかし形容詞には感覚("美しい")と、感覚ではないもの("正しい" などの理性的判断)の両方がありますが、感覚ではないオノマトペは考えにくい。"感覚" ではなく "感覚イメージ" と定義してあるのは、擬態語や擬情語を想定しているのでしょう。
もう一つのキーワードは「写し取る」です。表すもの(記号)と、それによって表されるものに類似性があるとき、その記号を「アイコン」と呼びます。アイコンは主として視覚によるもので、たとえばコンピュータ画面のゴミ箱のアイコンや、一般的に使われる笑顔のアイコン( ☺ )は、世界のだれが見てもゴミ箱や笑顔と見えます。
オノマトペもアイコンのように、表すもの(音形)と表されるもの(感覚イメージ)に類似性がある(=模倣性があると感じられる)記号です。このことを本書では "アイコン性" がある、と表現しています。"アイコン" ではなく "アイコン性" としてあるのは、視覚によるアイコンとは違って発音で "写し取る" ため、模倣性に限界があるからです。また、音による模倣は、言語体系がもつ母音・子音のバリエーションや音韻体系に大きく影響されます。アイコン、オノマトペ、オノマトペ以外の言葉の3つを対比させると、次のようになります。
| ☺ | アイコン (日本語話者以外も理解) |
| ニコニコ ニコッ |
アイコン性がある言葉 |
| えがお 笑顔 |
言葉 (日本語話者だけが理解) |
音象徴
オノマトペを考える上で重要なことは、そもそも発音における "音" がアイコン性を帯びていることです。これを「音象徴」と言います。たとえば、清音と濁音の音象徴です。「コロコロ」より「ゴロゴロ」の方が大きくて重いものが転がる様子を表します。「サラサラ」より「ザラザラ」の方が荒くて不快な手触りを示す。「トントン」より「ドンドン」の方が、強い打撃が出すより大きな音を模倣します。g や z や d のような濁音は程度が大きいことを表し、またマイナスのニュアンスが伴いやすい音です。
母音の "あ" と "い" の音象徴もあります。打撃を表「パン」は平手でたたく感じで「ピン」は人差し指で弾くイメージであり、「パン」の方の打撃が大きい。水が飛び散る様子の「パチャパシャ」と「ピチャピチャ」も、「パチャパシャ」の方が飛び散る程度は大きいわけです。"あ" は大きいイメージと結びつき、"い" は小さいイメージと結びつきます。これは、発音のときの口腔の大きさに違いに起因します。
さらに、阻害音(p, t, k, s, d, g, z などの子音が入った音)は、硬く、尖って、角張ったイメージであり、共鳴音(m, n, y, r, w などの子音)は、柔らかく、なめらかで、丸っこい印象と結びつきます。この例として、次の図1を示して、
| 一方が マルマ(maluma)で、一方が タケテ(takete)です。どちらがマルマで、どちらがタケテでしょうか」 |
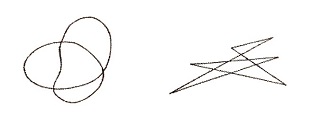
|
図1:マルマとタケテ |
どちらが "マルマ" で、どちらが "タケテ" か |
音象徴は、言語習得以前の赤ちゃんでも認められます。チリで行われた生後4ヶ月の赤ちゃんの実験では、親の膝の上に乗せられた赤ちゃんに、丸、楕円、四角、三角のどれかの図形を、大小をペアにしてスクリーン上に表示します。と同時に、様々な発音(音)を聞かせます。赤ちゃんの視線検知をすると、a を含む音を聞いたときは大きな図形の方を、i を含む音を聞いたときは小さな図形の方を見ることが分かりました。言語経験がほとんどない赤ちゃんですら、母音と図形大きさの関係に気づいているのです。
マルマとタケテの音象徴や、a と i の音象徴は、母語によらない共通性があります。しかし、ほとんどの音象徴は言語により個別です。たとえば、日本語においてカ行とタ行を含むオノマトペ、「カタカタ」「コトコト」「カチカチ」「コツコツ」は、いずれも硬いモノ同士の衝突音を表します。つまり、タ(t)、ト(t)、チ(ch)、ツ(ts)の子音が、音象徴で同じ意味と結びついている。
しかしこれは日本語ならではの音象徴です。たとえば英語では、titter は "忍び笑い"、chitter は "鳥のさえずり" で、t と ch が違う音象徴をもっています。
音がアイコン性をもつのが音象徴です。そしてアイコン性をもつ音の連なり=言葉がオノマトペであり、オノマトペが高度に発達した日本語や韓国語では、オノマトペこそ "身体で感じる感覚イメージを写し取る言葉" なのです。
言語の習得過程(1)
幼児の言語環境はオノマトペにあふれています。0歳児向けの絵本はオノマトペだけだし、0歳児・1歳児に対する親の語りかけもオノマトペが多用されます。そして2歳児以降になると、文や単語を修飾するオノマトペが増える。
そのオノマトペの発端が「音象徴」です。乳幼児は音象徴が認識できるかを著者が実験した結果が本書に書かれています。どうやって調べるのかというと、脳波の「N400 反応」をみます。
言葉を覚えたての1歳過ぎの幼児に知っている単語を聞かせ、同時にモノを見せたとき、単語とモノが合っているときと、単語とモノが違っているときでは脳波の反応が違います。たとえば、「イヌ」という音なのに絵はネコだとすると、音の始まりから400~500ミリ秒たったところで、脳の左右半球の真ん中付近の電位が下がります。これは大人でも単語と提示内容が不整合の場合にみられる反応で、N400反応と呼ばれています(N は Negative、400 は 400ミリ秒の意味)。
著者は、N400反応を利用して、言語習得前の生後11ヶ月の赤ちゃんのN400反応を調べました。次のような図形を用いた「モマ・キピ」実験です。
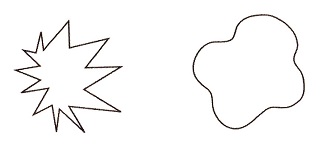
|
図2:モマとキピ |
どちらが「モマ」で、どちらが「キピ」か |
|
このように、ヒトの脳は音と対象の意味付けを生まれつき自然に行っています。これが、言葉の音(=記号)が身体に接地する第一歩になるのではないかというのが著者の意見です。
このことは、音の連なり(単語)にも意味があるという洞察につながります。さらには、対象それぞれに名前があるという "偉大な洞察" につながっていきます。
一般に、言葉の音からその意味を推測することはできません。「サカナ」という音の連なりは "魚" と何の関連性もありません。しかし、オノマトペは違います。「トントン」「ドンドン」(打撃音)や、「チョコチョコ」「ノシノシ」(歩く様子)などは、音が意味とつながっています。仮に「チョカチョカ」「ノスノス」とういう、現実には使われない "オノマトペ" を想定してみても、それが表す歩く様子は「チョコチョコ」「ノシノシ」と同じと感じられる。これは「サカナ」を「サカノ」にすると全く意味がとれなくなるのとは大違いです。
対象それぞれに名前があるというのは "偉大な洞察" だということを、著者はヘレン・ケラーのエピソードを引いて説明しています。
|
「ノスノス」実験
しかし、「対象それぞれに名前がある」という洞察から「語彙爆発」に向かうのは単純なことではありません。単純ではない一つの理由は、音の連なり(=言葉)で対象を説明されたとしても、その言葉が対象の「形」なのか「色」なのか「動作」なのかが曖昧だからです。実はここでも、感覚イメージを写し取るオノマトペが役だちます。著者は、3歳ぐらいの幼児に次の絵(図3)を見てせて動詞(=実際には使われない仮想的な動詞)を教える実験を紹介しています。
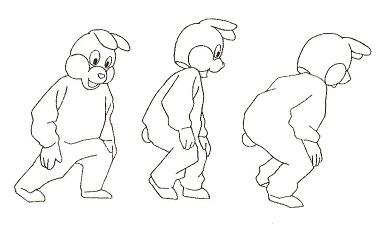
|
図3:ノスノスしている |
ノスノスとはどういう動きを指す擬態語なのか |
|
「ノスノス」は、人物を表すのではなく、動き(たとえば歩く)を表すのでもなく、動き方を表すのだと感覚的に分かるのです。このように、感覚と音が対応すると感じられる(アイコン性がある)オノマトペは言語学習の足場となり、手掛かりになるのです。
記号接地
もちろん、アイコン性のある言葉は言語学習の足場であって、最初の手掛かりに過ぎません。しかし言語という記号体系が意味を持つためには、基本的な一群の言葉の意味はどこかで感覚と接地(ground)していなければなりません。このことを指摘した認知科学者のハルナッドは、大人が中国語を学ぶ例をげて次のように説明しています。
|
辞書の定義だけから言葉の意味を理解しようとするのは、一度も地面に接地することなく「記号から記号への漂流」を続けるメリーゴーラウンドに乗っているようなものです。
その一方で、永遠に回り続けるメリーゴーラウンドを回避するためには、すべての言葉が身体感覚と接地している必要は全くありません。身体感覚とつながる言葉をある程度のボリュームで持っていれば、それらの言葉を組み合わせたり、それらとの対比や、また比喩や連想によって、直接の身体経験がなくても身体に接地したものとして言葉を覚えていくことができるのです。
身体感覚に接地する代表が音象徴であり、オノマトペですが、一般語にも音と意味の繋がりを感じるものがあることに注意すべきです。たとえば「かたい」「やわらかい」はオノマトペではありません。しかし「かたい」の k、t は硬い印象を与える音象徴があり(阻害音)、「やわらかい」は柔らかい印象の音象徴があります(共鳴音)。
「おおきい」「ちいさい」も同様で、大きい印象を与える "o" の長母音と、小さい印象を与える "i" が先頭音にあります。言葉を覚えたての幼児に親が絵本を読んで聞かせるとき、これらの言葉をどういう風に(大袈裟に)発音するかを想像してみたら、それは明確でしょう。
また「たたく(叩く)」「ふく(吹く)」「すう(吸う)」はオノマトペではありませんが、オノマトペの歴史研究によると、これらは「タッタッ」「フー」「スー」という擬音語に、古語における動詞化のための接尾辞「く」をつけたものです。「ひよこ」も、「ヒヨヒヨ」という擬音語に、可愛いものを表す接尾辞「こ」をつけたものです(「ワンコ」「ニャンコ」と同じ原理)。
こういった "隠れたオノマトペ" は非常にたくさんあり、"記号接地" の一助になっていると考えられます。また、このあたりはオノマトペが発達していない英語にも当てはまります。日本語なら「オノマトペ + 動詞」で表現するところを、英語では1語の動詞で表すのが一般的です。たとえば、英語の「話す・言う」ジャンルの言葉に、
| (ペチャクチャ話す) | |
| (ヒソヒソ話す) | |
| (ブツブツ言う) | |
| (キャッと言う) |
などがありますが、これらは cha と チャにみられるように音象徴があります。
しかし、音象徴やオノマトペなどのアイコン性がある言葉があったとしても、基本的に言語は恣意的な記号の体系です。「日本国語大辞典」の見出し語は約50万語ですが、「日本語オノマトペ辞典」は、方言、古語を含んで 4500語です。多めに見積もったとしても、オノマトペは言葉の 1% に過ぎません。言語を習得するためには身体感覚とつながっているオノマトペから離れる必要があります。
そもそも言葉は抽象的で、記号とそれが表すものの関係は全く恣意的です。この恣意的な記号の膨大な体系をどうやって習得していくのか、それが本書の第2の主題です。
言語の習得過程(2)
子どもが言語を習得していく過程を観察すると「過剰一般化」の例がよくあります。具体的には、
| 閉まっているドアをあけて欲しいとき「あけて」と言う | |
| お菓子の袋をあけて欲しいとき「あけて」と言う |
の2つを学んだ子どもが、
| みかんを食べたいときにも「あけて」と言う |
事例がありました。「開ける」は多くの子どもが過剰一般化する有名な動詞です。上の例では子どもが "自分の欲しいモノや場所にアクセスしたいとき「あけて」と言えばよい" と過剰一般化したわけです。それは残念ながら、ミカンでは間違いになる(日本語環境では)。
英語の open も、多くの子どもが過剰一般化します。明かりやテレビをつけるときも "open" という子が多い。しかし中国語ではそれで正解です。中国語の「開」は、日本語の開けると同じ意味に加えて、電気をつけたり、パソコンのスイッチを入れたり、車を運転することにも使うからです(その "開" の意味の一部は漢字を通して日本語に入り、開始、開会、開業、開店、開校、開港、などと使われています。さすがに開車とは言いませんが)。
過剰一般化はあくまで "過剰" なので、子どもの暮らす言語環境では間違いです。しかし子どもは推論しているのです。みかんを剥くことも「あける」だろうと ・・・・・・。みかんの場合は間違いなので、親から「そういうときは、"むいて" と言うのよ」と直されるでしょう。しかしオモチャ箱のフタなら「あける」は正しいので、親は子どもの要望にそのまま応える。そのようにして子どもは言葉を覚えていく。
推論をするから過剰一般化が起きます。キーワードは "推論" であり、学習は丸暗記ではなく推論というステップを経たものなのです。その推論にもいろいろなタイプがありますが、言語習得の鍵となるのは「アブダクション推論」です。
アブダクション推論
論理学における推論は、一般には「演繹推論」と「帰納推論」ですが、アメリカの哲学者・パースはこれに加えて「アブダクション推論」を提唱しました。アブダクション推論は「仮説形成推論」とも言います。この3つの違いを本書での例で説明すると次の通りです(言い方を少々変えました)。
ちなみに、アブダクション(abduction)には「誘拐」「拉致」の意味があり(というより、それが第1義であり)、それとの混同を避けるため、「レトロダクション(retroduction)推論」が使われることも多いようです。
演繹推論
| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |
| この玉は、この袋から取り出したものある(事実)。 | |
| この玉の重さは 10g 以下のはずだ(推論)。 |
帰納推論
| これらの玉はこの袋から取り出したものである(事実)。 | |
| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |
| この袋に入っている玉は全部 10g 以下であろう(一般論の推論)。 |
アブダクション推論
| この袋に入っている玉はすべて10g 以下である(一般論。前提)。 | |
| これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(事実)。 | |
| これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成)。 |
もちろん、常に正しい答えになるのは演繹推論だけです。しかし演繹推論は新しい知識を生みません。新しい知識を創造する(可能性がある)のは帰納推論とアブダクション推論です。
帰納推論は観察した事例での現象や性質が、その事例が属する集合の全体でも見い出されるとする推論です。つまり、部分を観察して全体に一般化する推論です。従って生み出される知識(= 一般化され普遍化された知識)は、部分としては既に観察されているものであり、とりたてて新しいものではありません。
それに対してアブダクション推論は、観察データを説明するための仮説を形成する推論です。この推論では、直接には観察できない何かを仮定し、直接観察したものとは違う種類の何かを推論します。従って、仮説が正しければ従来なかった新しい知識を獲得できます。上の例のアブダクション推論を分析すると、そもそも、
これらの玉はこの袋から取り出したものであろう(仮説形成=A)。
という仮説形成ができる理由は、もし A が正しいとすると、演繹推論(=常に正しい推論)によって、
これらの玉の重さはすべて 10g 以下である(観察された事実=B)
が成り立つからです。つまり A → B を理解した上で、B から A を推論している(B → A)。アブダクション推論が「逆行推論」とも呼ばれるゆえんです。もちろん、A → B は常に正しいのですが、その反対の B → A が常に正しいわけではありません。従って A はあくまで「仮説」であって、仮説には検証が必要です。その検証をパスすると新知識の獲得になる。こういった類の推論がアブダクション推論 = 仮説形成推論です。
仮説形成推論の言語学習における役割について、本書ではヘレン・ケラーのエピソードも引きながら、次のように説明してあります。
|
「すべての対象には名前がある」という洞察は、さらに「名詞は形によって一般化される」「動詞は動作の類似性によって一般化される」という洞察につながっていきます。
アブダクション推論の具体例をもう少し考えてみます。子どものアブダクション推論は "言い間違い" によく現れます。たとえば、
イチゴのしょうゆ(練乳の意味)
と言った子どもがいました。もし大人が練乳を「イチゴの醤油だね」と言ったとしたら、それは意識的な比喩です。しかし子どもは「しょうゆ = 食品にかけておいしくするもの」という推論をした上で、"イチゴのしょうゆ" という "言い間違い" をしたわけです。
足で投げる(蹴るの意味)
という間違いもあります。大人は「投げる」と「蹴る」は全く違う行為だと考えます。しかしよく考えてみると、両方とも「関節を曲げて伸ばすという行為によって何かを遠くへ飛ばす」という構造的類似性があります。子どもはその類似性による推論をして「足で投げる」になった。
言うまでもなく、アブダクション推論(と帰納推論)は常に検証・修正されなければなりせん。特に、アブダクション推論は過剰一般化と隣り合わせです。子どもは、ある時は推論=言い間違いを親から訂正され、またあるときは推論を親にすんなりと受け入れられ、そういう繰り返しで語彙を爆発的に増やしていくのです。
アブダクションの起源:ヒトと動物の違い
「すべての対象には名前がある」という気づきは、言語という記号体系を自分で構築していくための第1歩となる "偉大な" 洞察です。しかしこの洞察の背後には、暗黙に仮定されているもう一つの洞察があります。それは、
名前は形式と対象の双方向性から成り立っている
という洞察です。これはどういうことでしょうか。以下の説明では、モノをカタカナで、その発音をローマ字で記述します。
言葉を覚えたての幼児に、バナナとリンゴとミカンの名前を教えることを想定します。バナナを手にとって「これは banana」と教え、リンゴを手にとって「これは ringo」と教え、ミカンを手にとって「これは mikan」と教えます。何回かやると子どもは果物の名前を覚えます。そのあと、バナナを手にとって「これは ?」と問いかけると、子どもは「banana」と答える。リンゴ、ミカンについても同じです。つまり子どもは、バナナ → banana、リンゴ→ ringo、ミカン → mikan と覚えたわけです(モノ → 発音)。
この段階で、子どもの前にバナナとリンゴとミカンを置きます。そして「ringo はどれ?」と質問すると、こどもは間違いなくリンゴを手にするでしょう。バナナとミカンについても同じです。もし、自分の子どもがそれができない、つまり「ringo はどれ ?」と質問してもバナナを取ったりすると(あるいは、まごついて何もしないと)、親はショックを受けるでしょう。発達障害かと思ってパニックになるかもしれない。
子どもは、モノ → 発音 を習得すると、その裏で自動的に banana → バナナ、ringo→ リンゴ、mikan → ミカン という "逆の推論" をしています。これを「対称性推論」と言います。対象に名前があるということは、このような「形式(=名前)と対象の双方向性」を前提にしているのです。でないと "対象の名前" は意味がなくなる。
そんなこと当たり前だろうと思われるかもしれません。しかしそれは人間だから当たり前なのであって、動物では当たり前ではないのです。本書の著者の今井氏は、子どもが言葉を習得する過程を研究していますが、京都大学霊長類研究所の松沢教授とチンパンジー "アイ" の動画をみて驚愕しました。
|
人間は
記号→対象
を学習すると、同時に、
対象→記号
も学習します。つまり対象性推論を行います。もっと広く言うと、
XだからA
をもとに、
AだからX
という推論をします。たとえば、雨が降ったら道路が濡れる、という一般論をもとに、
家の前の道路が濡れていた → 雨が降ったのだろう
と推論します。しかしこれはアブダクション推論であって、正確に言うと「雨が降ったという仮説形成をした」わけです。事実は、雨が降ったのではなく、向かいの家の人が水を撒いたのかもしれないし、放水車が通ったのかもしれない(そういった可能性はあくまで情況次第です)。
人間は「原因 → 結果」から「結果→原因」という推論をよくやります。もちろんこれは論理的には正しくない推論 = 非論理推論です。過剰一般化だともいえる。このようなアブダクション推論の一つとして、形式と対象の間の対称性推論があります。人間はそれを当然のように行う。しかし、動物は違います。
|
ヒトと祖先が同じであるチンパンジーはどうかというと「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことが結論づけられています。ただし、京都大学霊長類研究所で "アイ" といっしょに飼育されていた "クロエ" という個体だけは対称性推論ができることが確認されています。
そこで疑問が起きます。ヒトの対称性推論はヒトがもともと持っている能力なのか、それともヒトが言語習得の過程で獲得する能力なのかです。今井氏は、前者が正しい、つまり、
言葉を覚える前の乳児が対称性推論ができる
という仮説をたて、それを検証するための実験を行いました。
乳児は対称性推論をするか
対象としたのは生後 8ヶ月の乳児、33人です。この段階の乳児は、音の連なりから単語(=音の固まり)を切り出す学習をしている段階で、知っている単語は極めて少なく、もし対称性推論ができたとしたら、それは言葉の学習の経験から得たものではないことが実証できます。
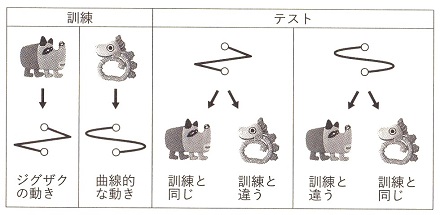
|
図4:乳児の対称性推論の実験 |
|
チンパンジーは対称性推論をするか
チンパンジーは他の動物と同じく、種としては対称性推論をしないことが分かっています。著者の今井氏は、乳児にやったのと同じ実験でこのことを確認しようと考えました。対象は京都大学霊長類研究所の7頭(成体)のチンパンジーです。
|
この実験は「チンパンジーは種としては対称性推論をしない」ことを再確認する結果となりました。ただし、非常に興味深いことに "クロエ" という個体だけは対称性推論をすることが示されました。これは京都大学霊長類研究所の以前の研究と整合的です。
この "クロエ" は「相互排他性推論」もできることが分かっています。相互排他性推論は、ヒトであれば言葉を覚えたての2歳以下の乳児でもできる推論です。つまり "コップ" という言葉は知っているが "ハニーディッパー" は知らない(=言葉もモノも知らない)子どもに対して、コップとハニーディッパーを目の前に置き「ハニーディッパーを取って」と言うと、子どもは躊躇なく、知らないはずのハニーディッパーを取ります。
つまり「未知の名前は自分が知らないものを指す」という推論が、2歳以下の子どもでもできるのです。これが相互排他性推論で、非論理推論と言えます。なぜなら「ピーラーを取って」でもハニーディッパーを取ることになるからです。ただし、「コップとハニーディッパーのどちらかを取ることが正しい」という前提があれば、極めて論理的な推論です。
"クロエ" だけが対称性推論や相互排他性推論といったアブダクション推論(=非論理推論)ができるということは、チンパンジーの中には少数の割合でそれができる個体がいると想像できます。ということは、アブダクション推論の萌芽がヒトとチンパンジーの共通祖先にすでにあり、ヒトの進化の過程でそれが徐々に形成され確立されていったという可能性が出てくるのです。
本書にはない話ですが、NHK BSP の番組、ヒューマニエンス「"イヌ" ヒトの心を照らす存在」(2021年10月21日)で、麻布大学 獣医学部の菊水健史教授が "イヌは相互排他性推論をする" との主旨を語っておられました。
すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。
本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。
すべてのイヌ(ないしはほとんどのイヌ)なのか、一部のイヌなのかは覚えていません。ただこの番組は、家畜化に伴って現れたイヌの性質・性格や、ヒトとの類似性(幼形成熟など)、ヒトとイヌの深い絆の話だったので、「一般的に、訓練されたイヌは相互排他性推論をする」という主旨と考えられます。
本書で述べられているは、「一般に、動物は対称性推論をしない」ということでした。つまり「イヌは対称性推論をしない(できない)」ということになります。A → B を習得して 非A → 非B を推論するのが相互排他性推論ですが、対称性推論は B → A の推論であり、"逆行する推論" です。そこに難しさがあるのかもしれません。
人類の進化
本書で、ヒトと動物の違いの説明があるのは「第7章 ヒトと動物を分かつもの」で、この章は全体のまとめである "終章" の前の最後の章です。その第7章の最後は「人類の進化」という見出しになっています。引用すると次の通りです。
|
人類(ホモ族)発祥の地・アフリカにおいて、チンパンジーは森に残り、霊長類で一般的な植物食、果実食に留まった。一方、東アフリカで乾燥化が進むサバンナの草原地帯に進出したホモ族は、そこでの狩猟採集というライフスタイルに突入し、そこから居住地を全世界に広げていった。それは、不確実な対象、直接の観察や経験が不可能な対象について推測・予測する必要がある生活であった。その結果、ヒトは言語を獲得して進化させ、その要因にアブダクション推論の進化があった、というのが本書の最後の論考ということになります。
「オノマトペ」から始まったはずの考察が、最後に「人類の進化」に行き着くのは驚きですが、そこが本書の魅力です。
感想
以上に紹介したのは本書(新書版で280ページ)の一部というか、"さわり" だけですが、「言語とは何か」を通して「ヒトとは何か」にまでに至る論考には感心しました。その際のキーワードは「記号接地」と「アブダクション推論」です。
「記号接地」に関しては、ヒトと AI の違いは何かが明確に答えられています。特に ChatGPT のような大規模言語モデルによる生成AI が創り出すテキストと人間の言語の違いです。逆にいうと ChatGPT が今後どういう方向を目指すのか、予想できると感じました。
「アブダクション推論」では、ヒトが他の動物と何が違うのか、その答え(の一つ)になっています。まさに「ヒトとは何か」に迫った論考で、特に「非論理的な推論をするからヒトなのだ」という主張です。アブダクション推論をはじめとする非論理的な推論は、言語システムの獲得に必須だし、また仮説形成が科学・技術の発達の原動力であることは言うまでもありません。
但し、その非論理的推論は、検証と修正にささえられています。言語獲得の場合は親との生活の中での(暗黙の)検証と修正の繰り返しだし、科学における仮説は、その正しさを証明する実験や分析が欠かせません。
原因から結果だけではなく、結果から原因を推論するのが人間の本性なのです。しかし検証と修正がない「結果 → 原因」推論は、社会レベルで考えると害悪をもたらします。そういった言説があふれている(メディアの発達がそれを加速している)のが現代社会という見立てもできると思いました。
本書は大変に有益な本ですが、残念なのは構成に難があることです。特に「第3章 オノマトペは言語か」です。ここでは、オノマトペは言語であるとの証明が長々と書かれています。
しかし、オノマトペがシスマティックに発達している日本語を使っている我々日本人にとって、オノマトペが言語なのはあたりまえです。おそらくオノマトペを "言語より一段低いもの" と見なす(ないしは "言語活動における枝葉末節" と見なす)欧米の言語学者への反論なのでしょうが、この章は余計でした。本書の英訳版を出すときに付け加えればよいと思いました。
さらに本書は、著者(今井氏)が過去からの探求の過程を振り返り、いろいろ考えると次々と疑問が沸いてくる、その疑問を解決してきた過程を発見的に書いている部分があります。それが悪いわけではありませんが、必然的に論旨が行き戻りすることがあり、もっとストレートに最新の研究成果に至る道を直線的に記述した方が、全体として分かりやすくなると思いました。ただ、これが本書の魅力と言えば魅力なのでしょう。
ともかく、本書は知的興奮を覚える本であり、久しぶりに読書の楽しみを味わいました。
| 補記:認知科学者がみる ChatGPT |
本書の著者の今井むつみ氏が ChatGPT について書かれた文章を紹介します。子どもが言語を習得する過程に詳しい今井氏ならではの見方が出ています。
これは、岡野原大輔『大規模言語モデルは新たな知能か』(岩波書店 2023)の書評です。岡野原氏は日本の代表的なAI企業であるプリファード・ネットワークス社の共同創業者であり、同社の代表取締役最高研究責任者です。
[この一冊] |
「言語の本質」で展開されている議論に従うと、「ChatGPT は記号接地なしに、記号から記号への漂流を続ける生成 AI」です。それでも、ヒトとまともに会話したり、翻訳したりできます。今井氏も「言語の本質」の中で、"使わなければ損というレベルになっている" と評価していました。
しかし今井氏は、岡野原氏の「大規模言語モデルは新たな知能か」を読んで驚いたのでしょうね(たぶん)。ChatGPT の「注意機構」と「メタ学習」は、乳児が言語を獲得するプロセスと同じではないかと ・・・・・・。発達心理学のプロからすると、そう見えるのでしょう。
岡野原氏も本の中で書いていますが、メタ学習(学習のしかたを学習する)のポイントのなるのは「注意(Attention)機構」です。Google が開発した「トランスフォーマー」という技術は、この「注意機構」実装していました。それを利用して超大規模化モデルを作るとメタ学習まで可能になることを "偶発的に発見した"(岡野原氏)のが OpenAI です。Google や OpenAI の技術者が、当初は全く予想できなかったことが起こっている。
ヒトとは何かを突き詰めるためには、ヒトでないものも知らなければなりません。そのため「言語の本質」ではチンパンジーでの研究が書かれていました。しかし、大規模言語モデルによる生成AI も "ヒトでないもの" であり、しかもヒトと比較するレベルになっています。生成AIの研究がヒトとは何かを探求する一助になりうることを、今井氏の書評は言っているように思えました。
(2023.8.26)
2023-08-26 09:08
nice!(0)
No.232 - 定住生活という革命 [本]
No.226「血糖と糖質制限」で、夏井 睦氏の著書である『炭水化物が人類を滅ぼす』(光文社新書 2013)から引用しましたが、その本の中で西田正規氏(筑波大学名誉教授)の『人類史のなかの定住革命』(講談社学術文庫。2007)に沿った議論が展開してあることを紹介しました。今回はその西田氏の「定住革命」の内容を紹介したいと思います。
定住・土器・農業
まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。
日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。
これはその通りですが、ここで問題は「世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通」としているところです。この認識は橋爪氏のみならず一般的なものでしょう。定住と農業はワンセットであり、それが人類史における革命だった、そこから "分業" や "階級" や "文化" や "都市" や "国家" が生まれた、つまり文明が生まれたというのが、我々が世界史で習う話だと思います。
しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。
遊動生活で進化した人類
"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。
遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。
アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。
従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。
ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。
そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。
◆安全性・快適性の維持
◆経済的側面
◆社会的側面
◆生理的側面
◆観念的側面
普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。
遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。
定住生活の環境要因
「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。
最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。
中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。
魚類資源の利用と定住化
まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。
これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。
上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。
ナッツ類の利用と定住化
植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。
油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。
一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。
これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。
また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。
以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。
定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。
定住が文化を産んだ
「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。
定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。
人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。
磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。
住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。
現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。
いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。
死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。
死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。
定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。
この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。
定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。
「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。
以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。
本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。
遊動生活で進化した人類
これ以降は本書の感想です。
現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。
しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。
脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。
そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。
我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。
ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。
西欧中心史観から離れる
我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。
しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。
"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。
ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、
定住 → 習慣
農業 → 文化
という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。
脳は生産性を追い求める
『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。
狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。
大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。
植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。
その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。
いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。
なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。
西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。
定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。
ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。
しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。
石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。
石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。
石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。
田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。
「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。
「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。
『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。
これを読むと「西アジアでは定住後、すぐに農業が始まった」かのように思ってしまいますが、それは誤解です。最新の研究によると「そもそもの文明の発祥の地であるメソポタミアでも、定住・狩猟採集が長期間続いた」のが正しい。最近、『反穀物の人類史』(ジェームズ・C・スコット著。みすず書房 2019)を読んでいたらそのことが書かれていたので紹介します。著者はイェール大学の政治学部・人類学部教授です。
メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。
ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。
著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。
しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。
しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。
この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。
上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。
著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。
獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。
上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。
我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。
メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。
以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、
となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。
『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。
ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。
それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。
定住・土器・農業
まず No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」で書いた話からはじめます。No.194 は、2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対談を本にした『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016)を紹介したものですが、この本の冒頭で橋爪氏は次のような論を展開していました。
| ◆ | 農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特色である。日本は、定住しても狩猟採集でやっていける環境にあった。世界史的には、農業が始まってから定住が始まるのが普通。 | ||
| ◆ | 定住の結果として生まれたのが土器である。土器は定住していることの結果で、農業の結果ではない。農業は定住するから必ず土器をもっているけども、土器をもっているから農業をしているのではない。 |
橋爪大三郎氏の論を要約
『げんきな日本論』より
『げんきな日本論』より
日本の土器は極めて古いことが知られています。世界史的にみてもトップクラスに古い。この土器は農業とワンセットではありません。土器は定住とワンセットであり「定住+狩猟採集」が縄文時代を通じて極めて長期間続いたのが(そして、それが可能な自然環境にあったのが)日本の特色という主旨です。
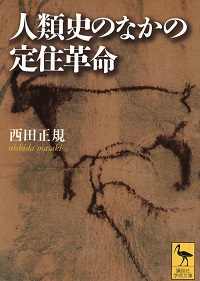
| |||
しかし、そうではないというが西田氏の『人類史のなかの定住革命』で展開されている論です。人類史においては定住生活がまずあり、農業は定住に付帯して発達したものである。定住こそが人類史における(最初の)革命だった、というのが西田氏の論です。この論は人類史についてのみならず、人間とは何かについて深く考えさせられるので、以下にその内容を紹介します。以下の「本書」は『人類史のなかの定住革命』のことです。
遊動生活で進化した人類
"定住生活"(ないしは定住)の反対の言葉は "遊動生活"(遊動)です。本書ではまず、遊動生活がヒトの本来の姿だったことが述べられています。第1章の冒頭の文章です。
|
遊動生活とは、互いに認知している数十人の集団が、集団に固有な一定の地域(遊動域)を、泊まり場(=キャンプ)と次々と変え、狩猟採集で食料を得るというライフスタイルを言います。集団はその中に小集団を作ることがありますが、小集団の離合集散は自由であり、またメンバーが集団を離れて別の集団に移ることも自由です。
アフリカの大地溝地帯にいた初期人類が二足歩行を始めたのが約500万年前だとすると(もっと古いという説もある)、1万年前に定住生活をはじめるまでの500万年の間、ヒトは遊動生活の中で進化してきたわけです。この間、道具の利用、道具を使った狩猟、火の使用、言語の使用、石器の高度化、撚糸と針と布の発明など、さまざまな進化がありましたが、これらのすべては遊動生活の中で培われたものです。
従来、定住生活を支える経済基盤として食料生産(農業)が重視されてきました。その背景には、遊動生活者が遊動するのは定住生活の維持に十分な経済基盤がなかったからという見方が隠されています。しかし本書は、遊動生活者は "定住したくても定住できなかった" というのは思いこみに過ぎないとしています。
|
ここで引用した部分が『人類史のなかの定住革命』の核心の部分です。ここで述べられている視点に立って人類の歴史を眺めてみると、新たに見えてくるものが多数ある。その "見えてくるもの" を、西田氏の縄文時代の研究と世界の人類学者の調査データを駆使して展開したのが本書です。
そもそもなぜ遊動するのか、遊動の理由は何かと問うことが重要です。世界には現在も遊動生活で狩猟採集を行っている人たちがいます。No.221「なぜ痩せられないのか」でとりあげたアフリカ、北タンザニアのハッザ族がそうでした。男たちはキリンやヒヒを狩り、女たちがイモを掘る。これが彼らの「経済基盤」になっています。アフリカではブッシュマン族やピグミー族もそうで、また東南アジアや南アメリカにも遊動生活者がいます。本書ではこれらの遊動生活者の研究データを総合し、「遊動する理由」を次のようにまとめています。
| 遊動することの機能や動機 |
◆安全性・快適性の維持
| ・ | 風雨や洪水、寒冷、酷暑を避けるため | ||
| ・ | ゴミや排泄物の蓄積から逃れるため |
◆経済的側面
| ・ | 食料、水、原材料を得るため | ||
| ・ | 交易をするため | ||
| ・ | 共同狩猟のため |
◆社会的側面
| ・ | キャンプ構成員間の不和の解消 | ||
| ・ | 他の集団との緊張から逃れるため | ||
| ・ | 儀礼、行事を行うため | ||
| ・ | 情報の交換 |
◆生理的側面
| ・ | 肉体的、心理的能力に適度の負荷をかける。 |
◆観念的側面
| ・ | 死、あるいは死体からの逃避。 | ||
| ・ | 災いからの逃避。 |
普通、遊動生活=狩猟採集と言われるように、食料の確保が遊動の理由と考えれています。狩猟であたりの動物が減ったり、キャンプ周辺のイモを掘り尽くしたら他の地域に移動する。それを順々にやると遊動生活になります。もちろん狩猟採集による食料確保は重要ですが、遊動する理由はそれだけではありません。遊動生活者の研究からわかることは、遊動の理由は極めて多岐に渡っていることです。
|
遊動生活の理由を狩猟採集による食料確保のためと考えてしまうと、定住による食料生産(=農業)ができなかったから遊動したのだ、となります。しかし遊動するのは食料確保のためだけではないのです。この視点が本書のまず大切なポイントです。
定住生活の環境要因
「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とする本書の立場からすると、定住を促した何らかの要因あると予想できます。それは氷河期の終了にともなう中緯度地域の環境変化でした。
最終の氷河期は、約7万年前に始まったヴュルム氷河期です。氷河期における中緯度地域は寒帯ないしは亜寒帯であり、草原が広がり、木々もまばらな疎林の状態でした。しかしヴュルム氷河期も1万5000年前あたりから終わりを告げます。途中に "寒の戻り" がありましたが、1万年前になると地球はすっかり温暖化し、中緯度地域は現在のような温帯になりました。この温暖化に伴って中緯度地域には森林が広がってきて、これが人類の食料確保に大きな影響を与えました。定住の考古学的証拠がみつかるのは温暖化に向かう時期です。
|
中緯度地域が森林化することによって狩猟が不調になると、魚類資源や植物性食料への依存度が深まることになります。その内容が以下です。
魚類資源の利用と定住化
まず、野生動物にかわる蛋白源としての魚類が重要になります。以前の旧石器時代でもヤスやモリは使われていましたが、これらは大量のサケが川に遡上するような季節でしか効率的な漁具ではありません。
これに対して新たに出現したのはヤナ(梁)、ウケ(筌)、魚網などの定置漁具、ないしは定置性の強い漁具です。ヤナは、木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から(ないしは下流から)泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具です。ウケは、木や竹で編んだ籠を作り、魚の性質を利用して入り口から入った魚を出られなくして漁をするもので、川や池、湖、浅瀬の海に沈めて使われました。ヤスやモリで魚を突くのは大型の魚にしか向きませんが、定置漁具は小さな魚に対しても有効です。こういった定置漁具の発明が定住化を促進しました。これらの定置漁具の有効性を、本書では次のようにまとめています。
| ◆ | 定置漁具の制作には繊維や木材を加工する高度な技術が必要であり、多くの時間と労力が必要である。 | ||
| ◆ | 魚類資源は、陸上で主な狩猟対象となる動物と比較して単位面積あたりの生産量がはるかに大きく、しかも高緯度地域以外では年間を通じた漁獲が期待できる。 | ||
| ◆ | 陸上動物の狩りや魚類の刺突漁は、獲物を探し、追跡し、接近して倒し、しかもそれを持ち帰らなくてはならない。こに比べて定置漁具は魚類の行動を利用した自動装置であり、必要な労力がはるかに少ない。多くの場合、その活動は単純な作業の反復で構成され、高度な熟練や体力のない女性や子ども、老人であっても行うことができる。 |
上の単位面積あたりの生産量のところですが、その例が本書にあります。現在の日本の湖における漁獲量は、琵琶湖で14.3トン/km2/年、中海(島根県)で37トン/km2/年です。一方、シカの生存量は700kg/km2程度と推定され、資源が枯渇しない程度に捕獲できるのは年間に20%程度とされているので、140kg/km2/年となります。縄文時代に狩られたシカ、イノシシ、サル、クマなどを合わせても数100kg/km2/年です。これと比較すると漁業資源は数10倍の量となります。漁撈は、漁具の制作に多くの労力を投下しても十分見合う漁獲が得られるのです。
ナッツ類の利用と定住化
植物性食料への依存度が深まったとき、広く利用されたのが「ナッツ類」です。ここで言うナッツとは食用になる木の実全般を言います。ナッツには、"油性ナッツ" と "デンプン質ナッツ" があります。
油性ナッツは、ハシバミ(実はヘーゼルナッツ)、ピーナッツ、アーモンド、クルミ、ピスタチオ、マツの実などで、カロリー値が高く、加熱調理をしなくてもそのままで食べられます。これらは氷河期から中緯度地域にあったものです。
一方、デンプン質ナッツは温帯森林の広がりに伴って増加したもので、クリ、各種のドングリ類、ヒシの実(水草である菱の実)、トチの実などです。食べるには加熱調理するか、ないしは粉にする必要があります。ただし油性ナッツより大量に食べられる。
これらナッツ類の特徴は、中緯度地域においては収穫の時期が限られることです(主に秋)。従って1年を通してナッツ類を食料にしようとすると食料保存の必要性がでてきます。特に冬は食料の採集ができないので越冬食料の保存が必須です。また漁撈も、川を遡上する魚に依存すると、それは季節性があるので捕った魚を保存する必要があります。こういった「季節性のある環境での食料保存」が定住を促した要因になりました。
また、温暖期の遺跡からはデンプン質ナッツの大量調理を示す遺物である土器や石皿(臼として使う)、磨石が出土します。これらの携帯できない道具、あるいは携帯に不便な道具も定住化を促進した要因です。なお、石器による時代区分から言うと、この時期は新石器時代の始まり(約1万年前)と一致します。
以上の、定置漁具の使用、食料保存の必要性、土器などの携帯できない道具の使用が、遊動生活から定住生活に向かった理由になりました。
定住イコール農業ではなく、農業は定住の結果として派生したものというのが本書の立場です。その農業が始まった時期は地域によって違います。西アジアが最も早く、中国やヨーロッパが続きました。日本列島では定住・狩猟採集生活の縄文時代が約8000年続き、弥生時代になって農業が始まりました。以上を概観した図が次です。
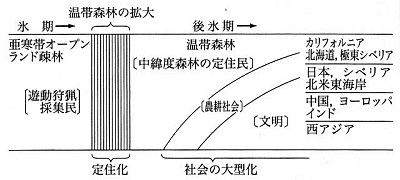
| ||
|
中緯度森林定住民の分布
図にある後氷期とは、氷河期が終わって現在まで続く期間のことである。農耕が普及して社会が大型化する時期は、地域によって差異がある。農耕はまず西アジアで始まり、中国・ヨーロッパ・インドから日本・シベリア・北米東海岸と進んだ。北海道という記述があるが、北海道で非農耕社会が近代まで続いたことを言っている。
「人類史の中の定住革命」より
| ||
定住が文化を産んだ
「定住化の過程は、人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した革命的な出来事」とするのが本書の立場ですが、では具体的にどのような "定住生活に向けた再編成" が必要だったのでしょうか。その再編成では、上に述べた「遊動することの機能や動機」を別の形で実現しなければなりません。本書ではそれが6点にわけて書かれています。
| 環境汚染の防止 |
|
定住するとゴミや排泄物をどうするかが問題になります。またノミ、ダニなどの寄生虫や病原菌の増加も避けられず、定住地を清潔に保つことが必須になります。
|
人間だけではありません。清潔と排泄物のコントロールは、定住する動物ずべてが備えていなければならない行動様式です。巣を作る動物はたくさんいますが、常に巣の中を清潔に掃除し、また巣の外の一定の場所で排泄する行動を本能的にしています。イヌやネコに排泄を躾るのが容易なのも、本来、巣の中で成長する動物だからです。一方、ヒトは「数千万年の進化史を遊動生活者として生きてきた」ので簡単ではないのです。定住によってゴミの処理が変わったことが縄文時代の遺跡に研究から推測できます。
|
| 住居と木材の加工 |
|
磨製石斧は住居を作るためだけでなく、燃料=薪をつくるため木の伐採に使われました。遊動生活では、あたりの枯れ木を拾い集めれば薪になります。しかし定住生活はそれでは成り立たず、定住地周辺の樹木を伐採する必要があります。磨製石斧はそれを効率的に行えるのでした。
| 経済的条件 |
住居と環境維持の他に、定住生活では水、食料、エネルギー源(薪)の調達が必要です。
|
現代のアフリカの狩猟採集民の研究から、彼らの1日の行動範囲はいくら広くてもキャンプから10km以内とされています。定住を始めた人類も、この範囲内ですべての水や食料を調達する必要があったはずです。先にあげた定置漁具による漁撈やナッツ類の利用はそれを可能にするものでした。本書には定住に伴って人間と植物の関係が変化し、植物が定住地周辺で次第に "栽培化" していくことが、縄文時代の遺跡の研究から詳述されているのですが、それは割愛します。
| 社会的緊張の解消 |
いままでの「環境汚染の防止」「住居と木材加工」「経済的条件」は、定住した人間が生きていくための生理的条件からくる要請でした。しかし以降は、人間のメンタルな面、精神活動における「定住の条件」です。このあたりが本書の主張の大きなポイントでしょう。
|
| 死者との共存、災いとの共存 |
|
死者を葬るということは遊動生活でも行われていました。最も古くはネアンデルタール人(約40万年前~2万数千年前)が埋葬をしたことが確認されています。しかし遊動民と定住民では、死者と生者の関係がおのずと違ってきます。
|
死以外にも、病気、怪我、事故など、人間にとっての "災い" は多く、それらは恐れの対象となります。遊動民であれば "災い" が起こった場所には近づかないという生活様式が可能です。しかし定住民の "災い" は定住地で起こるのであり、災いから逃げることができません。従って災いの原因を神や精霊に求め、災いの原因となった邪悪な力を定住地から追放しようとしたり、あるいは神や精霊の怒りを鎮めようとします。これによって定住地が "浄化" される。このような手続きも定住化の帰結として発達するのです。本書の冒頭は次のように始まっています。
| 不快なものには近寄らない、危険であれば逃げていく、この単純きわまる行動原理こそ、高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略である。 |
定住生活は「不快なもの」や「危険なもの」との共存が前提です。「高い移動能力を発達させてきた動物の生きる基本戦略」とは異質な生活に入るのが定住の意味です。
| 心理的負荷の供給 |
この「心理的負荷の供給」という項は「定住革命論」の中でも大変重要なものでしょう。つまり、狩猟採集の遊動民はキャンプを移すたびに見える風景が変化するわけです。新たな地域において食用の植物はどこにあるか、獲物はどこにいるか、薪はあるか、危険な獣はいないかなど、感覚を研ぎ澄まし、探索します。このような条件においては人間の脳の力が最大限に発揮されます。人類は数百万年前から遊動民として生活し、その中で進化し、脳を発達させてきました。しかし定住するとこの条件が一変します。
|
定住者は物理空間を移動するのではなく、心理的空間を拡大し、その中を移動することによって感覚や脳を活性化させ、本来持っている情報処理能力を働かせてきました。それが人類史に異質な展開をもたらしました。それは縄文時代にも顕著です。
|
「生計を維持するための必要性を超えたさまざまな遺物」から一つだけ土版取り上げると、土版とは楕円形、ないしは四角の土製の板で、何らかの呪術的目的のものです。秋田県鹿角市の「大湯 環状列石」から出土した土版は、大湯ストーンサークル館に展示してあります。明らかに人体を表し、かつ数字も表現しています。

| ||
|
大湯 環状列石から出土した土版
大湯ストーンサークル館に展示さている土版の表(左)と裏(右)。1個~6個の穴で人体を表している。裏側の左右3つずつ穴は耳だと考えられている。
(site : jomon-japan.jp)
| ||
以上が「人間の肉体的、心理的、社会的能力や行動様式のすべてを定住生活に向けて再編成した」内容です。本書では以上を次のようにまとめています。
|
本書では「狩猟採集・定住社会」であった縄文時代の詳しい分析が展開されています。また定住以外の話題もあって、たとえば動物を「口型」と「手型」に分類し、人間を「手型動物の頂点」ととらえることによって人類の起源が考察されています。さらに言語の起源、家族の起源、分配の起源に関する考察もあります。このあたりは割愛したいと思います。
遊動生活で進化した人類
これ以降は本書の感想です。
現代は定住社会であり(というより1万年前からそうであり)我々はそれを何の疑いもなく受け入れています。遊動生活というのは、ふつう考えられません。"住所不定" は "犯罪者" とほぼ同一の意味で使われているほどです。世界には現代でも遊動生活を送っている人たちがいて、たとえば国境をまたいで転々としている旅芸人の集団や牧畜民がいたりします。そういう人たちは現代社会としては "困った存在" で、政府は定住させようと躍起になっている。
しかし人間は遊動生活で進化してきたという西田氏の指摘は、あたりまえのことながら改めて言われてみると斬新に感じます。人間の知恵の発揮や工夫、探求などの脳の力は遊動生活で培われた。
脳の働きだけではなく、体の構造や機能もそうです。ちょっと余談になりますが、遊動生活で連想したのが空間把握能力です。No.184「脳の中のGPS」では、脳に備わっている「自己位置把握能力」のことを書きました。また No.50「絶対方位言語と里山」ではオーストラリア原住民の "デット・リコニング能力"(=遠く離れても家の位置が分かる能力)のことを書きました。もちろん、こういった空間把握能力は定住生活でも必要ですが、遊動生活においてより必須のものでしょう。
そういう人間が定住してしまった。定住したから逆に「精神世界での遊動、心理的な遊動」を求めるようになったという指摘や、定住したからこそ権威や宗教(呪術)やルールが発達したというのは、なるほどと思いました。特に、定住生活を水・食料・薪・住居といった物理的・経済的側面だけから考えるのではなく、人の精神活動にまで広げてとらえているのが説得的です。
我々は、あくまで漠然とですが "遊動生活" へのあこがれがあるのだと思います。読書、芸術、映画などの文化装置が提供する「精神世界・心理世界での遊動」だけではもの足らず、物理的でリアルな遊動を求める。西田氏が指摘しているように、遊動・狩猟採集生活では常に神経を研ぎ澄ませているわけです。刺激も多い。我々はそういった意味での "脳の活性化" に憧れる。現代人にとっての「旅行」の意味は(ないしは、旅行が現代の大産業になっている意味は)そこにあるのかと思います。私的な経験を言うと、個人で海外旅行をしたことが何度もありますが、特に初めての国だとすべてが新しい経験になります。緊張感が持続して疲れることは確かですが、逆にいうと刺激が多く、常に神経を研ぎ澄ませる状態が精神のリフレッシュになる、そう思います。もちろん、思い出という貴重な財産も残ります。
ちなみに本書を読んで思い出したのが、動物園のサル山のニホンザル(あるいは自然動物公園のニホンザル)です。野生のニホンザルは遊動生活ですが、サル山のニホンザルは人間が定住生活を強いています。そういう定住生活は「不和の当事者に和解の条件を提示して納得させる拘束力、すなわち、なんらかの権威の体系を育む」と、西田氏は書いています。定住ニホンザルの場合、この「なんらかの権威の体系」とは明らかに "ボスザル" ですね。ボスという存在は定住生活のニホンザル特有のものと言われています。まさに西田理論を補強しているようだと思いました。
西欧中心史観から離れる
我々は歴史の教科書で「農耕=定住=文明」のように学ぶのですが、これはやはり西欧中心史観でしょう。本書を読んでそう思いました。どの民族にとってもそうですが「歴史」は何らかのストーリーでもって自分たちのルーツから現在までを構成したものです。西欧からすると自分たちのルーツをメソポタミア文明に置くのが分かりやすい。つまり、中東における農耕(小麦栽培)の開始 → メソポタミア文明の発生 → エジプト → ギリシャ → ローマ → 西欧全体へと文明が伝播したのが歴史のメイン・ストリームであり、その他としてインドも中国もアラビアもあった、みたいな物語です。
しかし本書にあるように、中東(いわゆる肥沃な三日月地帯)は定住と農耕がきわめて近接して発生した地域で、それは世界的にみると必ずしも一般的ではありません。日本列島では「定住・狩猟採集」が縄文時代の約8000年間続いたわけです。その間に豊かな文化が生まれた。西欧中心史観からすると「定住・狩猟採集」は何となく "遅れている" ように(暗黙に)感じてしまうのですが、決してそんなことはないわけです。
"文化" は英語で culture ですが、これは cultivate(耕す)と同じ語根の言葉だということは良く知られています。これを根拠に「農耕が文化」と、我々は刷り込まれてきたわけです。しかし「耕す」という言葉に「文化」の意味を持たせてしまったのはあくまで西欧なのですね。農耕が文化をもたらしたというのは "西欧の受け売り" なのでしょう。
ここでよく考えてみると、英語には habit(習慣)という言葉がありました。habit はラテン語の「保ち続ける」の意味から派生していますが、同じ語根の inhabit は「住む」という意味です。また habitable は「居住可能な」という意味です(No.204「プロキシマb の発見とスターショット計画」参照)。つまり英語は、
定住 → 習慣
農業 → 文化
という言葉の構造であり、これは大変に暗示的だと思います。習慣(habit)とは「後天的に身につけた、繰り返される行動様式」のことで、人間のライフスタイルでは文化よりもっと根源的・基本的なものです。「農業」以前の根源的なものとして「定住」がある ・・・・・・。そういう示唆のように思いました。
脳は生産性を追い求める
『人類史のなかの定住革命』で書かれている食料獲得の変遷を巨視的に眺めてみると、人類の歴史は「食料獲得の生産性を追求してきた歴史」だと言えるでしょう。つまり「できるだけ少ない労力とコストで、できるだけ多くの食料やカロリーを得ること = 生産性」を人類は追求してきたわけです。
狩猟採集生活において陸上動物を狩るとすると、それは大型動物の方が効率的です。ウサギやネズミを狩るより、シカ、ウマ、ウシ、マンモスを狩る方が生産性が高い。人類は狩猟道具を工夫し、チームワークで大型動物を狩ってきました。崖にウマの群を追い込んで突き落とし、一挙に狩るようなこともあった。
大型動物が絶滅してしまったり気候変動でいなくなると、漁撈に向かう。本書に書いてあるように魚類の方が動物より生息密度が圧倒的に高いわけです。しかも定置漁具を発明・工夫して生産性をあげる。現代まで産業として続いている狩猟採集は漁業だけですが、なぜ続くかのというと、器具さえあれば現代でも成り立つほど生産性が高いからです。
植物性の食料では、定住生活においてデンプン質ナッツの利用が始まります。そのままでは食べられないドングリやクリの実を大量に集め、土器で加熱し、あるいは石皿・臼ですりつぶして利用する。デンプン質ナッツは油性ナッツと比べると大量に食べられるので(本書の指摘)、コスト(採取の労力)・パフォーマンス(得られるカロリー)が高いのですね。
その次に起こったのが小麦(イネ科穀物)の利用=農業です。小麦はナッツとは違って1年性の草本であり、種を蒔けばその年のうちに収穫できます。本書にも書いてありますが、クリやクルミは他家受粉するので品種を固定するのが困難です。しかし小麦(や稲)は自家受粉です。突然変異体を見つければ、それを選別して育種することで品種改良ができる。現在の小麦や稲は実が熟しても飛び散らないという、植物の本来の姿とはかけ離れたものですが、これは人間が収穫しやすいように選別したからそうなるのですね。
いったん高生産性が実現すると、それが前提の生活や社会になり、後には戻れず、より高い生産性を追求し続けるようになります。この "追求" の影の部分として、自然環境の破壊がありました。氷河時代にいた数々の大型動物は人類の狩りで絶滅しました(No.127「捕食者なき世界(2)」参照)。農業が文明の始まりとされているのですが、紀元前数千年の古くから文明が発達した地域は、現在ほとんどが回復不可能な荒野です。その環境破壊は現代も続いています。人間の脳は飽くことなく生産性を追求してきた。そんな感じがします。
なぜ人類は定住化に向かったのか。それは環境の変化による狩猟の不調という要因があるのでしょうが、より高い生産性を求めたからとも考えられると思いました。それは人類の探求心と工夫のたまものであり、その脳の働きは遊動生活で培われた。そいういう見方ができると思います。
| 補記1:石干見(いしひび・いしひみ) |
西田正規氏は『人類史のなかの定住革命』の中で、定住化を促したものとして魚類資源の利用があり、その中でも定置漁具の発達があることを指摘していました。
定置漁具とは「川や池、湖、浅瀬の海などに固定的に設置され、その中に入った魚を捕獲する漁具」です。本文中に書いた定置漁具は以下のものでした。
| ヤナ(梁) 木や竹で簀の子状に編んだ台を川や川の誘導路に設置し、上流から泳いできた魚が簀の子にかかるのを待つ漁具。 | |
| ウケ(筌) 木や竹で編んだ籠を作り、水に沈め、入り口から入った魚を出られなくする漁具。 | |
| 漁網 最も大がかりなのは、海の定置網。魚群の回遊ルートに設置し、魚を網の奥へ奥へと誘導して捕獲する漁具。 |
ヤナ、ウケ、定置網は現代でも使われており、実際に見たことがあるかどうかはともかく、どういうものであるかは理解しているところです。
しかし最近、これらとは全く別種の定置漁具があることを新聞で知りました。日本経済新聞の朝刊最終面(文化欄)に掲載されたので読まれた方も多いと思いますが、「石干見(いしひび・いしひみ)」です。関西学院大学の田和正孝教授が書かれたコラムを以下に紹介したいと思います。
|

|
長崎県諫早市水ノ浦に残る石干見 |
長崎県の有明海沿岸や島原半島では、石干見をスクイと呼ぶ。日本経済新聞より。 |
|
石干見は地方によって呼称が違い、ヒビ、スクイ、スケ、イシアバ、スキ、カキなどと呼ばれています。上の画像はスクイと呼ぶ長崎県諫早市のものです。
石干見は非常にシンプルな仕掛けであり、「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられているそうです。確かに、ヤナ(梁)やウケ(筌)は木材や竹を加工する技術がいるし、魚網も糸を作ってそれを編む技術がいります。しかし石干見は石を積むだけですむ。環境条件が許せば、最も容易な漁法だと考えられます。
|
石干見は東アジア(日本、韓国、台湾)に多くみられます。日本で現在も使われているのは2基のみとありますが、台湾海峡の澎湖諸島(台湾島の西。中華民国)には550基が残り、そのうち100基は今でも使用されているそうです。フィリピンや南太平洋の島、オーストラリアにも残っています。
田和氏のコラムでは、フランスにも調査に行ったとありました。その田和正孝氏編の「石干見」("ものと人間の文化史 135"。法政大学出版局。2007)を見ると、フランスの大西洋岸のビスケー湾に浮かぶ島である "レ島" や "オレロン島"(いずれもフランス本土と橋でつながっている)には石干見が残っていて、実際に使用されているそうです。これらの状況からすると、遠浅の海岸で潮の干満差があるところではかつて世界的に「石干見」があったと推測できます。
「人類最古の漁具・漁法の一つ」と考えられるそうですが、いつ頃から始まったものかの実証はできないでしょう。しかし定置漁具としての石日見が極めて古いというのは、いかにもそういう感じがします。というのも、ヤナやウケと違って石日見は自然を模したものと考えられるからです。つまり、海岸に潮だまりがあるとき、そこに魚が取り残されることがあります。古代の人はそれを見て人工的にその状態を作ったのではないでしょうか。しかも作成には石を積み上げるだけでよい。メインテナンスの労力はかかるが、干潮を待って魚を手づかみすればよいわけです。
「漁船漁業に比べて漁獲効率がはるかに低い」ので現代では廃れたのでしょうが、古代では極めて効率的な食料採集装置だったのではと思いました。
(2019.09.17)
| 補記2:メソポタミアの「定住・狩猟採集」 |
『人類史の中の定住革命』で西田正規氏は「定住後に農業が始まる時期は地域によって違う。西アジアでは比較的早く農業が始まったが、日本では定住・狩猟採集が長期間(8000年程度。いわゆる縄文時代)続いた」という主旨を述べられていました。
|
メソポタミア地方のティグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域の南部にいたシュメール人が世界最初の都市文明や国家の原型を作ったことは世界史で習う通りです。このあたりは、地質学的には沖積層です。つまり川や海の作用で堆積物が重なった地層が陸地化したものです。この南部沖積層にシュメール文化が広がったのですが、都市が出現してくるウルク期(紀元前4000年~3100年。ウルクは都市名)より前のウバイド期(紀元前6500年~3800年。ウバイドは土器の様式名)はどうだったのか。
ポイントは、ペルシャ湾の海岸線がウバイド期には現在よりずっと内陸部にあり、ウバイド期のシュメール遺跡が集中している地域のすぐそばまで海だったことです。これにより、南部沖積層はティグリス・ユーフラテス川が作り出す湿地だった。この時期の南部沖積層を研究したジェニファー・パーネル(Jeniffer Pournelle。サウスカロライナ大学の考古学・人類学者)の成果をもとに、『反穀物の人類史』では次のように解説されています(段落を増やしたところがあります。下線は原文にはありません)。
|
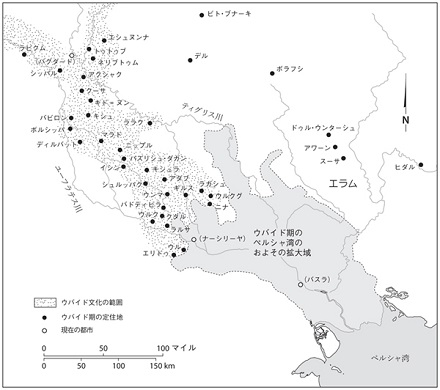
|
メソポタミア沖積層 紀元6500年頃のペルシャ湾拡大域 |
(「反穀物の人類史」より) |
右下の濃い色塗りが現在のペルシャ湾で、その左上の少し薄い色塗りは古代のペルシャ湾拡大域である。点のハッチングの部分がウバイド文化(紀元前6500年~3800年)の範囲を示し、黒丸はウバイド期における定住地である。 |
|
著者は強調しているのですが、狩猟採集より農業(特に畑作による穀物栽培)が優れているというのは思い込みに過ぎません。土地を耕し、種を蒔き、施肥し、畑を維持するのは多大な労力がかかります。灌漑などをすれば、それこそ大変です。狩猟採集で生活できるのであれば、それに越したことない。その証拠に、メソポタミアの初期の農民と同時期の狩猟採集民の骨を比較すると、狩猟採集民の方が栄養が恵まれていたことがわかると言います。
しかし著者は言っています。唯一、作物栽培が簡単にできるのが氾濫原だと ・・・・・・。そこでは年に1回、川が栄養豊富な土の畑を自動的に作ってくれるからで、上の引用はそのことを言っています。我々が世界史で習うのは、古代エジプトにおけるナイル河の氾濫を利用した農業ですが(「エジプトはナイルの賜物」)、基本的にはそれと同じことです。
しかしウバイド期の南部沖積層における作物栽培は一部であり、圧倒的多数は狩猟採集でした。少々長くなりますが、次に引用します。
|
この引用の最初に、ミシシッピ・デルタの「シェニエ」との聞き慣れない言葉がでてきます。Wikipedia で調べてみると、シェニエ(Chenier)とは、波の作用で土砂が海岸とほぼ平行に堆積してできた堤のような土地(日本語で浜堤)で、その背後にできた湿地帯を シェニエ平野(Chenier Plain)と言うようです。
上に引用した文章を読んで、まるで日本の縄文時代の描像のような錯覚を受けました。「季節ごとに移動してくるガゼル」は日本にはいませんが、これを「季節ごとに川を遡上してくる鮭」とすればピッタリです。その鮭も本書に出てきます(次の引用)。
著者によると、南部沖積層の狩猟採集民は汽水域と淡水域の境目あたりに定住しました。汽水域と淡水域の境目は潮汐によって変動するため生態圏が変化し、また雨期には水性資源、乾期には陸生資源が豊富になります。安定的で回復可能な形での狩猟採集が可能でした。さらに、動物性タンパク質を得るための狩猟の説明が続きます。
|
獲物の保存方法として乾燥・塩漬けとありますが、本書の別のところには「家畜という形で生きたまま保存する」こともあったことが記されています(英語で家畜を意味する livestock は直訳すると "生きた在庫" です)。本書にはありませんが、肉の保存については燻製もあります(さらに寒冷地だと冷凍がある)。ちなみに引用の最後に出てくる "キュウリウオ" とは、アユ、シシャモ、シラウオ、ワカサギなどの食用魚を含む分類名です。
上の引用で、湿地に毎年やってくる動物を狩る話が出てきます。これは日本で言うと、まさに川を定期的に遡上する魚を捕獲することに相当します。川に魚を誘導する水路を作り、梁を設置し、そこにかかった魚をとる。これと同じです。
我々は大型哺乳類の狩猟というと、野山をあちこちと探しまわり、移動しながら狩りをするというイメージを思い浮かべがちです。しかし世界をみると「大型哺乳類の大群が定期的に押し寄せてくる場所」があるのですね。人間はそこに定住し、効率的な狩りの仕組みをつくり(梁と同じです)、獲物は「家畜化・塩漬け・乾燥」といった手段で保存すればよい。
メソポタミアの文明発祥の地がかつては湿地帯、というのもそうですが、固定的なイメージを投影して歴史を考察してはいけないのです。
以上のように、メソポタミアの南部沖積層では、狩猟採取民がほぼ農業なしに定住し、中には5000人を越える「町」まであったと言います。まとめると、
| 紀元前6000年代、5000年代のメソポタミアの南部沖積層は、生態系がきわめて多種多様であり、 | |
| そのため食物連鎖上の上位捕食者にとって最適の環境で、 | |
| 上位捕食者の頂点にいる人間にとっては狩猟採集の天国であり、 | |
| 従って狩猟採集民の定住が発達した。 | |
| おまけに、大河の氾濫原という「作物栽培をするのに最適な環境」まであった。これを利用して一部では作物栽培も行われた。 |
となるでしょう。我々が世界史で習うのは、メソポタミアでは乾燥化にともなって大河の周辺に人が集まり、人々は食料確保のために農業を始め、それが灌漑をともなう小麦栽培となり、原始国家の誕生につながったという「物語」です。確かに、現在のシュメール遺跡のあたりは乾燥地帯であり、我々の感覚では砂漠か荒野といってもよい土地です。しかし、そのイメージで紀元前6000年を考えてはダメなのですね。そのころ現在のシュメール遺跡のあたりは湿潤なデルタ地帯であり、多種多様な生物が密集していたわけです。現代のイメージを過去に投影してはならないのです。
『人類史の中の定住革命』で西田先生は「定住が先で農業はその副産物」と言っておられましたが、古代メソポタミアの南部沖積層の住人はまさにそうだったことがわかります。
ただし『反穀物の人類史』では「メソポタミアの南部沖積層が狩猟採集民にとっては天国だったから定住が発達した」というスタンスの説明がされています。『人類史の中の定住革命』にあるように「定住するには様々な克服すべき課題があり、その克服の過程で文化が生まれた」という視点が全くありません。
それは『反穀物の人類史』の副題が "国家誕生のディープヒストリー" であることから分かるように、この本が国家誕生の理由、特に穀物栽培農業との深い関係をメイン主題として追ったものだからでしょう。このメイン主題に関しては興味深い記述がいろいろあるのですが、それは省略したいと思います。
(2020.3.14)
2018-05-19 17:29
nice!(1)
No.191 - パーソナリティを決めるもの [本]
小説『クラバート』に立ち帰るところから始めたいと思います。そもそもこのブログは第1回を『クラバート』から始め(No.1「千と千尋の神隠しとクラバート」)、そこで書いた内容から連想する話や関連する話題を、尻取り遊びのように次々と取り上げていくというスタイルで続けてきました。従って、折に触れて原点である『クラバート』に立ち戻ることにしているのです。
クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、
という問いの答が知りたいからです。
就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。
人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。
では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。
実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。
そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。
行動遺伝学
人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。
遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。
だということを、忘れないようにしなければなりません。
一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、
はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。
行動遺伝学(Behavioral Genetics)という学問があります。この行動遺伝学の手法を使えば、体重についての遺伝の寄与率を求めることができます。行動遺伝学の研究手法は双子の研究です。双子には「一卵性双生児」と「二卵性双生児」があり、一卵性双生児の遺伝子は全く同じです。一方、二卵性双生児は同時に生まれた兄弟であり、両親から半分ずつ遺伝子を受け継ぐので、双子同士の遺伝子は約50%が同じです。双子の家庭内での育児環境は同じだと考えられ、ここがポイントです。
そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、
となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり
とすると、
という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと
となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。
行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。
このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。
この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。
この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。
パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる
では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。
これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。
IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。
さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。
この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。
外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。
『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。
以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。
環境とは何か
『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、
という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。
もちろんハリスも、育児の重要性を否定しているわけはありません。体や脳の発達、言語の習得に育児は大変重要です。また、親から虐待を繰り返された子どもは性格が変わったり、場合によっては脳に回復不可能な損傷を受けることも分かっています。
しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。
まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。
出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。
それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。
両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。
話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。
この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。
なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。
集団社会化説
ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。
これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。
ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。
用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。
「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。
「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。
「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。
ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。
日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。
ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。
これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。
ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。
集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。
一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、
ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。
集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。
ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。
孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。
以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。
『クラバート』の意味
No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。
No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。
さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。
しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、
だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。
しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。
少年・少女の物語
結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。
人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。
世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。
それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。
クラバートは少年の物語ですが、他の少年・少女を主人公にした小説も何回かとりあげました。なぜ子どもや少年・少女の物語に興味があるのか、それは「子どもはどういうプロセスで大人になるのか」に関心があるからです。なぜそこに関心があるかというと、
| ・ | 自分とは何か | ||
| ・ | 自分は、どうして自分になったのか |
という問いの答が知りたいからです。
就職以来の仕事のスキルや、そのベースとなったはずの勉強の蓄積(小学校~大学)は、どういう経緯で獲得したかがはっきりしています。記憶もかなりある。一方、人との関係における振る舞い方やパーソナリティ・性格をどうして獲得してきたか(ないしは醸成してきたか)は、必ずしもはっきりしません。ただ、自分の振る舞い方やパーソナリティの基本的な部分は子どもから10歳代で決まったと感じるし、20歳頃から以降はそう変わっていない気がします。だからこそ「自分はどうして自分になったのか」を知るために、人の少年時代に興味があるのです。
人の個性は遺伝と環境で決まります。「生まれ」と「育ち」、「もって生まれたもの」と「育った環境」で決まる。パーソナリティ(性格・気質)に「遺伝=もって生まれたもの」が影響することは明白で、これは子どもを二人以上育てた人なら完全に同意するでしょう。全く同じように育てたつもりでも、兄弟姉妹で性格が大きく違う。「もって生まれたもの」が違うとしか考えられないわけです。
では「環境」ないしは「育ち」はどう影響するのでしょうか。人のパーソナティ(性格や気質に関係する個性)に影響を与え、自分が自分になったその「環境」とは一体何なのでしょうか。
実はこれについては『子育ての大誤解』(ジュディス・リッチ・ハリス著。早川書房 2000)で展開されていた「集団社会化説」が、私にとっては最も納得できた説明です。この「集団社会化説」を踏まえて、最初に書いた小説『クラバート』を考えてみるのが、この記事の趣旨です。
そこで、まずその前に「遺伝=もって生まれたもの」が人にどの程度影響するのかという科学的知見をまとめておきます。以下の行動遺伝学の話は、安藤寿康『心はどのように遺伝するか』(講談社ブルーバックス 2000)によります。安藤寿康氏は慶応義塾大学教授で、日本の行動遺伝学の第一人者です。
行動遺伝学
人の一生変わらない形質が遺伝で決まるというのは、非常に分かりやすいわけです。血液型、髪の毛の色、虹彩の色はそうだし、特定の病気(血友病とか若年性糖尿病など)は遺伝で決まることがよく知られています(その他、多数ある)。
遺伝とは「親と似る」ということではありません。血液型で言うと、A型の両親から生まれた二人の子どもが二人ともO型というのは十分ありうるわけです。遺伝とは、親から子へと形質を伝達すると同時に、多様性を生み出す仕組みでもある。「蛙の子は蛙」であると同時に「鳶が鷹を生む」こともある、それが遺伝です。
| 遺伝で決まるとは、遺伝子(=もって生まれたもの)で決まるという意味 |
だということを、忘れないようにしなければなりません。
一生変わらない形質が遺伝子で決まるというのは分かりやすいのですが、では、たとえば「体重」はどうでしょうか。普通に考えて、
| 体重は遺伝と環境で決まる |
はずで、この場合の環境とはもちろん生活習慣(食生活)のことです。このうち遺伝の影響はどの程度でしょうか。
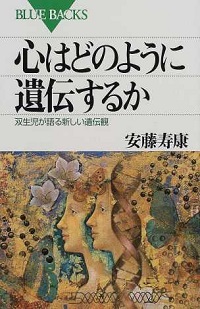
| |||
|
安藤寿康
「心はどのように遺伝するか」 (講談社ブルーバックス 2000) | |||
そこで、一卵性双生児と二卵性双生児、それぞれ数百の体重データを集め、「一卵性双生児の体重の相関係数」と「二卵性双生児の体重の相関係数」を算出します。相関係数は統計学の手法で、二つの量が完全な比例関係(一方が大きければ他方も大きいなど)にある時は "1"、全く無関係なら "0"になります。調べてみると、
| ・ | 一卵性双生児の体重の相関係数:0.80 | ||
| ・ | 二卵性双生児の体重の相関係数:0.43 |
となりました。一卵性双生児の体重は非常に似通っているが、二卵性双生児の体重はそれなりに似ている、という常識的な結果です。ここから遺伝子の影響を算出することができます。つまり、双子の体重が似ているのは、遺伝子が似ている(一卵性双生児は全く同じ)ことと、同じ家庭環境で同時に育ったからと仮定します。つまり
| G:相関係数に対する遺伝子の寄与率 C:相関係数に対する同一環境(家庭)の寄与率 |
とすると、
| 0.80 = C + G 0.43 = C + 0.5*G |
という連立方程式が得られます。0.5という係数は二卵性双生児の遺伝子の類似性が0.5であることによります。この式を解くと
| G = 0.74 C = 0.06 |
となり、遺伝子の寄与率(G)が求まります。行動遺伝学の実際の統計処理はもっと複雑なようですが、本質は上のようなものであることは間違いありません。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』にも、この計算方法が紹介されています。
行動遺伝学では環境を二つに区別し「共有環境」と「非共有環境」という概念を使います。
共有環境
|
このたあたりは定義の問題です。人の形質や性格、行動について、遺伝の影響を除いたものが環境、環境から兄弟で共有される環境を除いたものが非共有環境です。従って非共有環境は「残りすべて」であり、雑多で、訳の分からないものまで含むことになります。
この「遺伝率」「共有環境」「非共有環境」という言葉を使うと、体重については以下のようになります。
| 遺伝率 | 共有環境 | 非共有環境 | |
| 体重 | 0.74 | 0.06 | 0.20 |
この表の解釈は、体重は、その74%が遺伝で説明できるということです。また残りの影響のほとんどは非共有環境(家庭外の環境)だということです。ただし、この数値は統計データであって、多くの人の平均をとってみたらそうなるということに注意すべきです。個々の人に着目すると、過食でメタボリック症候群の人もいれば、ダイエットが趣味で痩せている人もいます。
パーソナリティは遺伝と非共有環境で決まる
では人間の「行動」はどうでしょうか。行動遺伝学で言う行動は、単に「対人関係における振る舞いかた」という意味だけではありません。一般知能(IQ)や論理的推論能力、記憶力などの「認知能力」も含まれます。また「性格・気質」(パーソナリティ)も重要な研究分野で、外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などが含まれます。さらに音楽、数学、美術などの「才能」もあります。
これらの認知能力や性格、才能は、何らかのテストや観察で測定するしかなく、つまり人間の「行動」として外面に現れたものを計測して分析するわけです。それについての遺伝の寄与を研究するのが行動遺伝学です。行動遺伝学の研究で分かってきた重要な点を3点だけあげます。
| 遺伝的影響が年齢とともに増大する |
IQテストで計られる一般知能(IQ)は、決して固定的なものではなく年齢によって変化することが知られていますが、この一般知能についての遺伝の影響は年齢とともに増加する傾向にあります。下の図は一卵性双生児と一卵性双生児の一般知能の相関係数の年齢変化ですが、遺伝的に同一な一卵性双生児は年齢とともに似てくる傾向にあります。
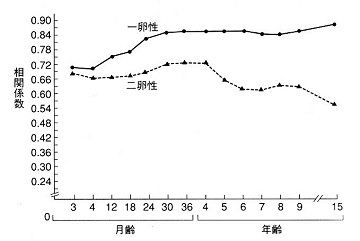
| ||
|
一般知能(IQ)の類似性の発達的変化
(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)
| ||
さらに次の図が示しているのは、一般知能に対する遺伝の影響が年齢とともに増加するとともに、共有環境(家庭環境)の影響が年齢とともに低下することです。それに対し、非共有環境の影響はほぼ一定しています。
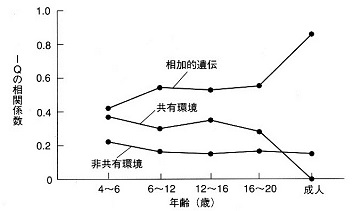
| ||
|
一般知能への遺伝と環境の寄与率の発達的変化
(安藤寿康「心はどのように遺伝するか」より)
| ||
この「遺伝的影響が年齢とともに増大」というのは認知効力に特有の現象のようです。安藤寿康氏の『心はどのように遺伝するか』には次のように説明されています。
|
| 遺伝と非共有環境が性格に影響 |
外向性、神経質傾向、協調性、新規性追求などの性格(パーソナリティ)は、遺伝の影響が50%程度、非共有環境の影響が50%程度です。共有環境の影響は小さいかほとんどない、というのが行動遺伝学の結論です。
| 遺伝的傾向が家庭外環境を選択する |
『心はどのように遺伝するか』には、家庭外環境における子供の「人気者度」「非行傾向」「大学志望傾向」を調査した結果が記載されています。それによると、遺伝的に近いものほど、「人気者度」でも「非行傾向」でも「大学志望傾向」でも、より類似した仲間をもつ傾向が強いことが分かりました。子どもは自分と似た子どもに引かれる、というわけです。
以上のような行動遺伝学の成果を踏まえて書かれたのが、ジュディス・リッチ・ハリスの『子育ての大誤解』です。以降はこの本の内容、特に「非共有環境」とは何かについて紹介します。
環境とは何か
『子育ての大誤解』においてハリスはまず、行動遺伝学の知見にもとづいて「子育て神話」を否定します。子育て神話とは、
| 子ども時代の家庭での親の育て方が、子どもパーソナリティを決め、その影響は大人になっても続く |
という言説ですが、それは "神話" であり、根拠のない思い込みに過ぎないと・・・・・・。
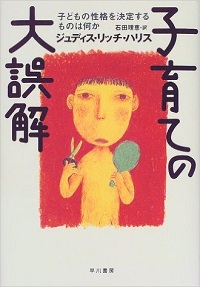
| |||
|
ジュディス・リッチ・ハリス
「子育ての大誤解」 (早川書房 2000) | |||
しかし「普通の」家庭では、育てかたや家庭環境は子どものパーソナリティに影響は与えないか、あったとしても少しなのです。このことをハリスは数々の例をあげて説明してます。そのうちの2~3を紹介します。
まず一卵性双生児の性格です。同じ家庭で育った一卵性双生児も、性格は同じにはなりません。では別々の家庭で育った一卵性双生児の性格はどうでしょうか。世の中には、生まれて直後に養子に出された一卵性双生児があります。双生児の一人を養子に出すという慣習は世界中にあります。別々の家庭で育った一卵性双生児を調査すると、その性格の類似性は、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性とほぼ同じなのです。
出生順は子どもの性格に影響しないというも重要です。ハリスは多くの研究を調査し、出生順は子どもの性格に影響しないか、影響したとしてもわずか、と結論づけています。ではなぜ人々は、出生順が子どもの性格に影響すると思い込むのでしょうか。
それは家庭内での子どもの行動を観察するからです。家庭内で子どもは、第1子は第1子らしく、末子は末子らしく行動するのが普通です。親もそのように教育する。しかし子どもはそれを家庭外には持ち出さない。つまり、子どもの本質的な性格ではないのです。ハリスは次のように書いています。
|
両親の離婚は子どもの性格に影響しないことも書かれています。離婚した両親の子どもは、離婚する前から情緒障害や行動傷害を起こすことがあります。つまり離婚に至るまでの両親の確執の時期からです。しかしこれをもってして、両親の確執や離婚が子どもの性格に影響するとは言えません。
話は逆だというのがハリスの主張です。離婚は「共同生活は無理」と夫婦のどちらか(ないしは双方)が確信するときに起こりますが、それを引き起こすのは夫婦の(ないしはどちらかの)性格特性であることが多い。その性格特性が子どもに遺伝し、両親の確執がトリガーとなって情緒障害を引き起こす。親の離婚と子どもの情緒障害は、遺伝による性格特性の類似がポイントなのです。
この議論から言えることは、家庭環境が子どもに与える影響を議論するときには、親と子ども、兄弟同士で共有されているもの、つまり遺伝子の影響を除外して議論をしないと意味がないということです。
なお性格特性ではありませんが、肥満度の遺伝率は70%程度であり、かつ家庭からの影響は受けないことが書かれています。これは安藤寿康『心はどのように遺伝するか』の体重の遺伝率が 74% であり、残りのほとんどは非共有環境という記述と整合的です。肥満児をさして「親の育て方が悪い」というようなことを言う人がいますが、一般論としては根拠がありません。
集団社会化説
ジュディス・リッチ・ハリスが『子育ての大誤解』に数々の事例をあげているように、家庭環境(子育ての環境。共有環境)はパーソナリティに影響しないか、影響があったとしも少しです。行動遺伝学の知見によると、パーソナリティに影響する環境とは「非共有環境」です。
これは言葉の定義なのですが、遺伝では説明できないものが環境、環境から共有環境(=兄弟に均等に与えられ、兄弟をより類似させる環境。主として家庭環境)を除いたものが非共有環境です。では、パーソナリティに影響する非共有環境とはいったい何なのでしょうか。
ジュディス・リッチ・ハリスはこの問いに対する回答として、以下のような「集団社会化説」を唱えています。
集団社会化説:
|
用語ですが、「集団」とは同年齢、または近い年齢の、二人以上の子どものグループです。子育てをした人なら分かるはずですが、子どもは赤ちゃんの時から自分と年齢が近い、自分に似た子どもに引かれます。子どもは自然と年齢の近い仲間で集団を作る。具体的には、仲のよい友達、近所の遊び仲間、男の子・女の子のグループ、学校のクラスの中のグループ、学校・学校外の各種のサークルでのグループなどです。もちろん、同時に複数の集団に属するのが可能です。
「社会化」とは、集団や社会における「振る舞い方」と「パーソナリティ(性格)」が形作られることを言います。社会化というと一見「振る舞い方」だけを指しているように思えますが、ハリスが言っているのはそうでなくパーソナリティ(性格)も含みます。むしろ、行動遺伝学が対象とする「行動」の全部を指すと言ったほうがいいでしょう。
「同化」とは、自分が属する集団の行動様式に自らを合わせようとすることです。それによって振る舞い方と性格がグループで共有されたものに近づいて行く。
「分化」とは、子どもが集団内で自分なりの役割やポジションを見つけ、集団においてもその子独自の行動様式を身につけていくことです。集団で共有された行動様式の中でも、たとえばリーダーとして振る舞うとか、世話役として振る舞うとかといった「個性」がでてくる。そのことを言っています。
ハリスは「集団対比効果」にも触れています。二つの近接する集団があると、集団の行動様式をより鮮明にするような力学が働く。たとえば男の子グループと女の子グループがあったとき、女の子の行動様式を男の子がやったとすると「女の子みたいだ」と仲間から言われて、その行動は二度とやらなくなる。そういった意味です。
日本ではあまりないのですが、米国には人種問題があります。白人の子どもグループで共有された価値観が「勉強してテストでいい点をとる」ことだとすると、黒人の子どものグループの価値観は全く別の方向に行き(たとえばスポーツ)、勉強していい点をとる黒人の子どもはグループでは異端とされる。そういうことも一つの例になります。
ジュディス・リッチ・ハリスの「集団社会化説」のきっかけになったものの一つは「移住者の子どもが綺麗な英語を話す」という、彼女がハーバード大学の学生の頃の観察だったようです。
|
これは言語習得のケースですが、パーソナリティもそうだという数々の研究報告を、ハリスは掘り起こしていきました。ラリー・アユソという少年のケースが書かれています。
|
ラリーの変身は、ラリーを引き取った白人夫婦の功績ではなく、ラリーの仲間集団が劇的に変わったからだというのがハリスの結論です。ラリーのケースはいかにも(アメリカらしい)極端なケースですが、集団社会化説を象徴する事例として引用しました。
集団社会化説によると、行動遺伝学の知見である「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格が似る」理由は次のように説明できます。つまり「遺伝的傾向の似ている子どもは、より類似した仲間をもつ傾向が強い」という研究成果がありました。子どもは自分と似た性格の仲間たちでグループ・集団を作る傾向にある。その集団の行動様式に同化する中で、性格が似てくるわけです。
一卵性双生児の遺伝子は全く同じですが、パーソナリティの遺伝率は 50% で、残りは非共有環境の影響です。しかし「遺伝的傾向が非共有環境を選択する」としたら「別々の家庭の育った一卵性双生児の性格の類似性も、同じ家庭で育った一卵性双生児の性格の類似性と同じ程度」であることが理解できます。日本のことわざにある、
| ・ | 類は友を呼ぶ | ||
| ・ | 朱に交われば赤くなる |
ということです。子どもはそうして属した集団の中で、自分なりの、自分に合った役割やポジションを見つけていく。そこで「分化」が起こり、パーソナリティが形成される。それが集団社会化説です。
集団社会化説から導かれる結論の一つは、子どもの居住地域の重要性です。特にアメリカでは、親の年収や社会的地位、人種によって住む地域が決まってくる傾向が強い。もちろん、日本を含むどこの国にでもある傾向です。どこに住むかで、子どもの遊び仲間、幼稚園、小学校が決まり、仲間集団の振る舞いや価値観は居住地域によって違ってきます。
ここで直感的に思い出すのは、中国の故事である「孟母三遷」です。孟子は子どもの頃、墓地の近くに住んでいた。すると葬式の真似ごとをするようになった。まずいと思った孟子の母親は、市場の近くに引っ越した。すると孟子は商売の真似ごとをするようになった。これではいけないと、母親は学校の近くに引っ越した。すると孟子は学生がやっている礼儀作法の所作を真似るようになり、母はやっと安心した。そして孟子は中国を代表する儒家になった・・・・・・という故事です。
孟子の母親が偉かったのは、息子に学問の道を歩ませるために、いわゆる「教育ママ」にはならなかったことです。あくまで息子の生活環境を変えた。行動遺伝学の言葉でいうと、孟子の母親は、子どもの成長にとって非共有環境が大切だと理解していたわけです。ジュディス・リッチ・ハリスの集団社会化説は、実は2000年以上前の昔から理解されていたということだと思います。
以上の集団社会化説を踏まえて、小説『クラバート』を振り返ってみたいと思います。
『クラバート』の意味
No.1「千と千尋の神隠しとクラバート(1)」であらすじを紹介したプロイスラー作の小説『クラバート』ですが、舞台はドイツ東部のラウジッツ地方の水車場(製粉所)でした。この水車場は厳しい親方(魔法使いでもある)が支配していて、粉挽き職人はクラバートを含めて12人です。クラバートはこの水車場の職人としての3年間で、自立した大人になっていきます。
No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で書いたように、クラバートの自立に影響を与えたのは粉挽き職人としての労働だと考えられます。人間社会では、労働が人間性を形作る基礎となっているからです。
さらに No.79「クラバート再考:大人の条件」で書いたように、人間にとっては「自己選択できない環境で最善を尽くせる能力」が重要だということも『クラバート』は暗示しています。そのためには、自分自身が「変化する能力」が必要だし、また「努力を持続できる」ことも重要です。それに関係して、No.169「10代の脳」では最新の脳科学の成果から、10代の少年少女は冒険心や適応し変化する能力があることを紹介しました。
しかし、上に紹介した集団社会化説に従って考えると『クラバート』は、
| 水車場の職人という仲間集団における "同化" と "分化"で、クラバートが自己のパーソナリティを確立していく物語 |
だとも言えるでしょう。水車場に来るまでのクラバートは、物乞いで生活している孤児であり、引き取られたドイツ人牧師の家を飛び出した浮浪児です(クラバートはスラブ系民族)。物語に親や家庭生活の影は全くありません。
しかし彼は水車場に来て成長し、物語の最後では水車場を根本から変えてしまうような "強い" 行動に出ます。そこまでの過程にあるのは、11人の職人仲間たちとの共同生活であり、いろいろな性格の職人たちとの人間関係です。その中でクラバートは自己を確立していった。そういう物語として読めると思いました。
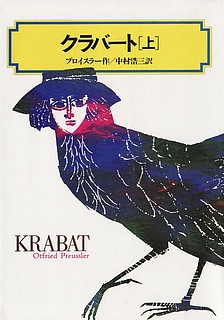
|
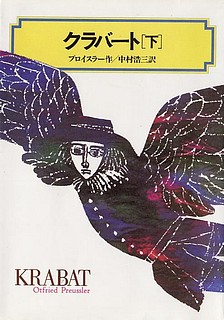
|
少年・少女の物語
結局のところ、人間が一番興味をもつのは人間であり、その中でも一番の関心は「自分」だと思います。自分は、どうして自分になったのか、ということを是非知りたい。
| 日本とは何かを知りたいのも、その一環です。自分の思考パターンが日本文化、その中でも特に日本語に強く影響されていることは確かです。ではその文化の特質は何か。それを知るためには「日本でないもの」を知る必要があります。特に、現代日本が強く影響されている欧米文化を知りたいわけです。 |
人の性格形成に子ども時代から中学・高校あたりまでが重要なことは言うまでもないでしょう。最近の脳科学からしても、その時期に脳は急速に成熟します(No.169「10代の脳」)。才能面でも、たとえば画家の才能は、環境さえあれば10代で開花することは明らかです(No.190「画家が10代で描いた絵」)。ヴァイオリニストなどもそうです(No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」)。
世界中で少年・少女の物語が書かれてきました。このブログでも『クラバート』のほかに、『少公女』『ベラスケスの十字の謎』『赤毛のアン』について書きました。映画では『千と千尋の神隠し』です。これらのいずれの物語も親の影は薄く(千尋以外は、孤児か、孤児相当)、主人公はそれまでとは全く異質な環境に放り込まれて、そこで仲間とともに成長していくことが共通しています。
それ以外にも、少年・少女を主人公にした数々の名作があります。我々が大人になっても少年・少女の物語に惹かれるとしたら、それは「自分とは何か」を知りたいからであり、その答えの重要なポイントが少年・少女の時期にあると直観してるからだと思います。
No.132 - 華氏451度(3)新訳版 [本]
レイ・ブラッドベリ(1920-2012。米国)の小説『華氏451度』(Fahrenheit 451。1953)について、以前に2回にわたって感想を書きました。
の二つです。
日付から推測できるかもしれませんが、作者のレイ・ブラッドベリは、記事を書いた直後(2012.6.5)に92歳で亡くなられました。その時も何か書こうと思ったのですが、適当なテーマが見つけられませんでした。
そうこうするうち、2014年に小説の新訳が出版されました。『華氏451度〔新訳版〕』(伊藤典夫・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房。2014.6.25)です。今回はこの新訳の感想を、ブラッドベリの追悼の意味も込めて書きたいと思います。『華氏451度』のあらすじや、そこで語られていることについては、No.51、No.52 を参照ください。
マルクス・アウレリウス
No.51「華氏451度(1)焚書」に書いたのですが、旧訳の違和感は、Marcus Aurelius という人名を、英語読みそのままに「マーカス・オーレリアス」としてあることです。ここは日本人になじみのあるラテン語読みで「マルクス・アウレリウス」(第16代ローマ皇帝。121-180)とすべきです。マルクス・アウレリウスは世界文学史上に残る『自省録』を書いた人物です。こだわるようですが、「本」をテーマにした小説『華氏451度』で、こういうところをおろそかにする態度はよくない。
新訳ではちゃんとマルクス・アウレリウスとなっていて安心しました。訳者の伊藤氏は当たり前だと言うでしょうが・・・・・・。
人名が出たついでの余談ですが、新訳では主人公・モンターグの上司(隊長)の Beatty を、英語の発音に近い「ベイティー」と表記しています(旧訳ではビーティ)。
ハリウッド俳優に、ウォーレン・ベイティ(Warren Beatty)がいます。彼と、姉のシャーリー・マクレーンの本名は、
Henry Warren Beaty
Shirley MacLean Beaty
です。日本でも昔はウォーレン・ビューティと表記されていましたが、本人の要望で発音に近いベイティとなったようです。本名から t を一つ増やして芸名にしているのは、できるだけ「ビーティ」などと呼ばれることを避けるためだそうです(これはWikipediaの情報)。日本語もそうですが、英語の固有名詞の発音はスペルからは判読しにくいものがあります。しかし固有名詞の翻訳は原則として「原音主義」をとるべきであり、これも伊藤氏の(ささやかな)修正です。
ファイアーマン
主人公のモンターグの職業はファイアーマン(fireman)ですが、言うまでもなく英語で消防士のことです(最近は女性消防士も含めて firefighter と呼ぶのが米国のトレンドのようです)。旧訳では「焚書官」となっていましたが、新訳では「消火」にひっかけた「昇火士」という造語をあてています。これを含めて「火」に関する一連の訳語は、
としてあります。fireは名詞の「火」であり、動詞としては「火をつける」意味です。そのことからすると、現代英語の fireman は「火を消す人」という通常の意味の下に「火をつける人」の意味を内在していると考えられます。事実、蒸気ボイラーなどの火を焚く「缶焚き」の意味でも使われる。新訳は漢字を活用して日本語訳としてのダブル・ミーニングを狙った工夫でしょう。
文芸作品からの引用
ここからが、いわば本題です。新訳の大きな特徴は『華氏451度』に含まれる文芸作品からの引用を、引用だと分かるように翻訳し、かつ巻末に注釈をつけたことです。
英米の小説で、文章の中に文芸作品からの語句を引用することはよくあるわけです。特に、聖書とシェイクスピアを知らないと翻訳はできない、とさえ言われるぐらいです。引用はとりたてて珍しくはありません。
しかし『華氏451度』は、ほかでもない「本」をテーマにした小説です。「本」をテーマにした小説で「本」からの引用がどういう風に使われているのか、それは作者が小説に込めた思いやテーマに直結する可能性があります。「引用を引用と分かるように翻訳する」ことは、とりわけ『華氏451度』では重要だと考えられる。その意味で、伊藤氏の新訳は意義が深いと思いました。
引用で思い出すのが『赤毛のアン』です。No.77「赤毛のアン(1)文学」、No.78「赤毛のアン(2)魅力」で書いたように、あの本には英米文学と聖書からの引用が溢れています。そして実は『赤毛のアン』と『華氏451度』に共通の引用があるのです。まずそのことから始めます。
『赤毛のアン』を振り返る
『赤毛のアン』(1908)には英米の文学作品と聖書からの引用が多数あるのですが、中でも最も有名なのは物語の一番最後のものでしょう。『赤毛のアン』の最終章である第38章「道の曲がり角」の最後の場面は、グリーン・ゲイブルズの窓辺にたたずむアンの記述です。
物語の最後の最後でアンがつぶやく言葉が、文芸作品からの引用です。翻訳者の松本さんの解説を引用します。
ブラウニング(1812-1889)はイギリスのヴィクトリア朝(1837-1901)の詩人です。その詩の一節をつぶやいて物語が終わるところなど、いかにも詩の朗読が得意なアンらしいと言えるでしょう。ちなみに『赤毛のアン』の本の扉に書かれた題辞(モットー)もブラウニングの詩の引用です。作者のモンゴメリ(1874-1942)は明らかにそう計画して書いているわけで、ブラウニングが好きだったようです。参考までに、上田敏の『海潮音』の訳詩と原文は以下です。
実は、この詩の最後の1行が『華氏451度』にも出てきます。本に目覚めた主人公のモンターグは、隠れた本の愛好家であるフェーバー教授と知り合いになり、これから進むべき道についてのアドバイスを受けます。そのあたりの教授の発言の一節ですが、伊藤氏の訳文とブラッドベリの原文は以下です。アンダーラインは原文にはありません。
この最後の一文は、ブラウニングの「All's right with the world !」を踏まえ、それを否定形にしたものですね。『華氏451度』は、ブラウニングの詩や『赤毛のアン』の世界とは全くの対極にある "ディストピア"(アンチ・ユートピア)を描いた小説です。だからこの引用が意味を持つ。新訳ではそれが明瞭になる形で翻訳されています。しかも、松本さんのような原文のストレートな訳( "この世はすべてよし" )ではなく、上田敏の訳( "すべて世は事も無し" )をそのまま持ってきている。この方がよく知られているということだと思います。
聖書
英米文学の「伝統」に従って、聖書からの引用もいろいろ出てくるですが、その例として『華氏451度』のエンディングの部分の新訳を掲げます。
最初の3つの引用は、旧約聖書の「伝道の書」(コヘレトの言葉)の第3章 第1節、第3節、第7節からです。また最後の長めの引用は、新約聖書の「ヨハネの黙示録」の第22章 第2節からです。第22章は、最後の審判のあとの「新しい天と新しい地(=新天新地)」を描く部分であり、黙示録の最終章にあたります。訳者の伊藤氏はここで、文語訳("大正訳")の日本語聖書の文章をもってきています。引用であることを明確にするためでしょう。
『華氏451度』の原書(Del Ray Book版)をみると、旧約聖書・伝道の書の部分には「引用のしるし」はついていません。従って、聖書を知らない人にとって引用だとは分からない。一方、新約聖書・黙示録の部分はイタリック体になっていて、引用だということが明確にされています。『華氏451度』の旧訳では、この黙示録の部分も平文と同じようなスタイルで訳されていたので、我々日本の読者には聖書の引用だとは分かりづらいものでした。
しかし「引用のしるし」があるかないかにかかわらず、クリスチャンで聖書に親しんだ人なら、ないしは英米人なら常識として聖書からの引用だとパッと分かるのでしょう。さらに、最後の最後の引用が新約聖書・黙示録の「新天新地」ということで、作者が『華氏451度』のエンディングに込めた意味が一目瞭然なのだと思います。
そもそも作家が書物からの引用で小説を終えるのは、熟考した結果のはずです。それは小説のテーマや作家の思想にとって重要であり、「重い」ものであることが容易に想像できます。さきほど例示した『赤毛のアン』の最後の引用である、
について訳者の松本さんは「神への信頼と未来への希望に満ちて『赤毛のアン』は幕を閉じる」と書いていました。それに習うとすると『華氏451度』の最後の引用である、
については、「神への信頼と、本が禁止された "ディストピア" が崩壊して新しい世界がくることの希望とともに『華氏451度』は幕を閉じる」と言えるでしょう。新訳ではそれがクリアに分かるのでした。
さらに想像を広げると、ここで「ヨハネの黙示録」を持ち出すのには意図があるのかもしれません。黙示録は紀元1世紀末のローマ帝国によるユダヤ人に対する圧制とキリスト教徒弾圧の時代に書かれた文書と言われています。そこでは「弾圧者への憎悪」と「キリスト教徒への励まし」がないまぜになっているように見える。それはとりもなおさず『華氏451度』の世界における「本を愛読・伝承する人たち」と、その人たちを「弾圧する体制」との関係に思えます。ブラッドベリがそういう構図を意識して最後に黙示録の文章を持ってきたのはありうることだと思いました。
ガリバー旅行記
英国文学からの引用の一つの例として、スウィフトの『ガリバー旅行記』をあげてみます。主人公のモンターグは、密かに本を所持していることを妻のミルドレッドに告白し、いっしょに読もうと誘います。
モンターグがとりあげた本は、スウィフトの『ガリバー旅行記』です。『ガリバー旅行記』の第1篇「リリパット国渡航記」は、リリパットの海岸に打ち上げられて気絶したガリヴァーが、小人の軍隊によって縛られるという出だしです。インド洋の島国・リリパットは、海峡を挟んだ隣の島国のブレフスキュと長年に渡って交戦状態にあります。その戦争の原因は「ゆで卵の殻の正しい剥き方は、大きな端から剥くか、小さな端(尖った方)から剥くかについての意見の違い」に由来します。
風刺文学である『ガリバー旅行記』がここで何を風刺しているのかというと、リリパット国 = 英国、ブレフスキュ国 = フランス、卵 = キリスト教、卵の大きな端 = カトリック、卵の小さな端 = 英国国教会・プロテスタント、というのが一般的な解釈です。作者のジョナサン・スウィフト自身が聖職者だったというのが、この風刺の重要なポイントです。
ブラッドベリは『華氏451度』で、なぜここを引用したのでしょうか。モンターグがまず読む本として、世界文学史上の最も有名な作品の一つから、その比較的よく知られた部分を引用したということでしょうか。
そうかもしれませんが、さらに理由があるように思えます。それは『ガリバー旅行記』の「卵」のくだりを読むと分かります。以下は岩波文庫からの引用です。原文に段落はありません。
2つ目のアンダーラインのところ、つまり「本の禁止」がポイントですね。だからブラッドベリはこの部分を引用した。『ガリバー旅行記』に親しんだ人なら「本の禁止」を思い出すかも知れません。また作者は読者に「わかりますか」という、ささやかな挑戦をしたのかも知れません。
さらに連想することがあります。『ガリバー旅行記』における「卵の割り方に起因する対立」とは「新教と旧教の対立」を揶揄したものと解釈されています。「卵を割るときには小さな端から割るべし。大きな端から割る者は厳罰」という勅令を出した「皇帝」とは、カトリックに対抗して英国国教会を設立したヘンリー8世のことだと考えられているのです。
そこで思い出すのは、英国史における「新教と旧教の対立」を背景にした別の引用が『華氏451度』にあることです。No.51「華氏451度(1)焚書」でも紹介したくだりですが、新訳によってもう一度引用します。「隣人が本を所持している」という密告をうけて「昇火士」たちが老女の家を急襲する場面です。
16世紀の英国において、メアリー1世(ヘンリー8世の娘で、カトリック教徒)はプロテスタントを弾圧し、延べ300人以上を処刑しました。このプロテスタントの中に、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimar)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という、オックスフォードで同時に処刑された2人の主教がいました。老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉です。『華氏451度』の中では、隊長のベイティーもそう解説しています(No.51「華氏451度(1)焚書」参照)。
『ガリバー旅行記』を含めたこのあたりの引用は、英国史、ないしは英文学に関するブラッドベリの強いこだわりが感じられるところです。
ベイティーの挑発
『華氏451度』のストーリーにおいて「昇火士」の隊長のベイティーは、部下のモンターグが密かに本を隠し持ち、読んでいることに気づいています。任務から帰還し、署の隊員仲間でカードゲームをする場面がありますが、そこでベイティーは、本からの引用を「満載」した言葉をモンターグに投げつけ、モンターグを挑発します。『華氏451度』において文芸作品からの引用が最も多く出てくるのはこの場面なのですが、その一部を掲げてみます。①~⑤の数字は原文にはありません。
伊藤氏の注釈によると①~⑤の出典は以下のとおりです。
多数の文芸作品を引用したベイティーの「挑発」は、文庫本で3ページ以上に渡って長々と続きます。
新訳は、引用が引用だとわかるように《》つきで翻訳されています。ブラッドベリの原文でも引用符(')がつけられている。ここで非常に明瞭になることは、本を焼き払う責任者であるベイティーが、実は本の世界に精通していることです。これはどういうことかというと、No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、
のどちらかだと思います。常識的には後者でしょうが、前者のような解釈も捨てがたいと思います。とにかく、次々と出てくる英国文学からの引用を引用だと明確にわかるようにした新訳は、作家の意図をより明確にしているようです。
イギリス文学
「英国文学」と書きましたが、ブラッドベリの引用は聖書を除いてはほとんどがイギリスの文芸作品であり(自国の)アメリカ文学は(少なくとも新訳で伊藤氏が指摘している限りでは)ありません。引用を一覧すると以下の通りです。()内の数字は作家の生年です。
(英国)
(フランス)
(スペイン)
No.51「華氏451度(1)焚書」にも書いたように『華氏451度』には禁止されている本の作者名として、ホイットマン、ソロー、フォークナーなどのアメリカ人作家の名前も出てくるのですが、作品の一部を引用している作家は、そのほとんどが英国人です。
『赤毛のアン』がそうであったように、聖書とシェイクスピアからの引用は一般的ですが、それ以外の引用は作家の個性によります。『赤毛のアン』にはイギリス文学からの引用が多いのですが、アメリカ人作家からのも多々ある(作者のモンゴメリはカナダ人)。そういった意味で『華氏451度』引用はブラッドベリの嗜好を表していると考えられます。また、特に16世紀から19世紀の作品が取り上げられていることからすると、書物の世界における「古典」の重要性、ないしは人類の「知的財産」としの本の重要性を言いたかったのかもしれません。
『華氏451度』の意味 : 反知性主義の世界
翻訳に関する話題はこれぐらいにして、以下は『華氏451度』の感想です。新訳が出たのを機会に改めて『華氏451度』を読み直したのですが、この本の現代的な意義を強く感じました。
No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、『華氏451度』を「本が禁止された世界」だと考えるのは表面的です。『華氏451度』は「本を読むような人が迫害される世界」を描いたものです。もちろん、ここで言う「本」とは知的財産としての本であって、(ブラッドベリの考える)消費財としての本(たとえばダイジェスト本とか漫画)ではありません。
では「本を読むような人」とはどういう人かと言うと、本によって「知識の獲得」や「教養の深化」を目指す人でしょう。また自分のできない体験を疑似的に経験したり、さまざまな人に「会える」のも読書の大きな効用です。しかし「困ったことに」、本の中の言説には応々にして相反することが書いてあります。それは小説の中で、隊長のベイティーが何度か強調していることで、「ベイティーの挑発」として上に引用した箇所にもありました。引用はしませんでしたが、彼は「知識人」を「相反する思想や理論で人を不幸にしたがる連中」と呼んでいます。
しかし考えてみると「相反する」のは当然なのです。一般的に言って、社会における重要な問題、人生の重要な問題には複数の回答案があり、しかもそれらが相反していることが多いわけです。答えは一つではありません。重要になればなるほどそうです。それはビジネスにおける重要課題でも同様です。我々は自ら考え、その中から最良と思うものを選んで決断し、行動に移す。これはある意味では悩ましく、苦しいことです。
そのため、多様なモノの見方や異質な考え方触れることを放棄したり、多様な考えを勘案しつつ「考える」ことをやめてしまって「指導者」の言うがままに行動するとか、同質のグループで凝り固まって「社会的孤立」に向かう人たちが出てくる。
しかしそれでは社会状況や自身をとりまく環境の変化についていけないし、結局のところ人間社会に不幸をもたらす要因になるのだと思います。変化についていくためには、自らが変わらないといけないし、変わるきっかけは「知ること」しかありません。
『華氏451度』が描くのは「考えない」人たちが大量に生み出された世界です。ここで重要なのは、それが上からの押しつけではなく、大衆自らがそういう世界を選びとったということでしょう。小説ではそう説明してあります(No.52「華氏451度(2)核心」参照)。『華氏451度』は究極の「反知性主義の世界」を、その「作られ方」を含めて描いたと言えるでしょう。ここに『華氏451度』の今日的な意味があると思います。
ちょっと思い出すのが、前々回の No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介した、内田樹氏の文章です。内田さんは『街場の共同体論』で次のように警告しているのでした。
内田さんの論は、引用の最後にあるように、反知性主義が階層下位を生みだし、階層下位を固定するように働いているということであり、階層二極化との関連性を述べています。『華氏451度』はそれが究極まで行った "ディストピア" を描いたとも言えるでしょう。
小説の中における隊長のベイティーは本の焼却の責任者である一方で(善か悪かは別にして)極めて知的な人間であり、本の世界に精通しています。モンターグの妻のミルドレッドは「壁テレビ」に浸りきり、上からの指示どおりに動く人間として描かれています。『華氏451度』の世界においては彼女のような人がほとんどです。その間に立ったモンターグは「知の世界に目覚めた普通の人」です。こういう人物配置によって、戯画のような「究極の世界」が描き出されています。
ブラッドベリが1950年代の初頭に行った「問題提起」は、明らかにテレビに代表されるメディアの発達に対する危機感からきています。まるで21世紀の現代を予見したかのような「壁テレビ」がその象徴です。しかしそういう「メディアの問題」にとどまらず、『華氏451度』は人間の本質、ないしは「弱さ」の深いところを突いています。その問題提起は、60年以上たった現代でも全く色褪せていないと感じました。
| ・ | No.51 - 華氏451度(1)焚書〔2012.3.24〕 | ||
| ・ | No.52 - 華氏451度(2)核心〔2012.4.06〕 |
の二つです。
日付から推測できるかもしれませんが、作者のレイ・ブラッドベリは、記事を書いた直後(2012.6.5)に92歳で亡くなられました。その時も何か書こうと思ったのですが、適当なテーマが見つけられませんでした。
そうこうするうち、2014年に小説の新訳が出版されました。『華氏451度〔新訳版〕』(伊藤典夫・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房。2014.6.25)です。今回はこの新訳の感想を、ブラッドベリの追悼の意味も込めて書きたいと思います。『華氏451度』のあらすじや、そこで語られていることについては、No.51、No.52 を参照ください。
| 以下、従来の『華氏451度』(宇野利泰・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房)を「旧訳」と呼ぶことにします。 |
マルクス・アウレリウス
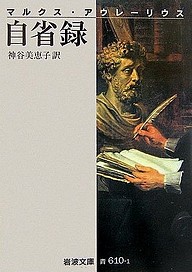
| |||
|
マルクス・アウレーリウス 「自省録」(岩波文庫) | |||
新訳ではちゃんとマルクス・アウレリウスとなっていて安心しました。訳者の伊藤氏は当たり前だと言うでしょうが・・・・・・。
人名が出たついでの余談ですが、新訳では主人公・モンターグの上司(隊長)の Beatty を、英語の発音に近い「ベイティー」と表記しています(旧訳ではビーティ)。
ハリウッド俳優に、ウォーレン・ベイティ(Warren Beatty)がいます。彼と、姉のシャーリー・マクレーンの本名は、
Henry Warren Beaty
Shirley MacLean Beaty
です。日本でも昔はウォーレン・ビューティと表記されていましたが、本人の要望で発音に近いベイティとなったようです。本名から t を一つ増やして芸名にしているのは、できるだけ「ビーティ」などと呼ばれることを避けるためだそうです(これはWikipediaの情報)。日本語もそうですが、英語の固有名詞の発音はスペルからは判読しにくいものがあります。しかし固有名詞の翻訳は原則として「原音主義」をとるべきであり、これも伊藤氏の(ささやかな)修正です。
ファイアーマン
主人公のモンターグの職業はファイアーマン(fireman)ですが、言うまでもなく英語で消防士のことです(最近は女性消防士も含めて firefighter と呼ぶのが米国のトレンドのようです)。旧訳では「焚書官」となっていましたが、新訳では「消火」にひっかけた「昇火士」という造語をあてています。これを含めて「火」に関する一連の訳語は、
| 原書 | 訳語 | 意味 | ||||
| fireman | 昇火士 | 消防士 | ||||
| firehouse | 昇火署 | 消防署 | ||||
| (fire) engine | 昇火車 | 消防車 |
としてあります。fireは名詞の「火」であり、動詞としては「火をつける」意味です。そのことからすると、現代英語の fireman は「火を消す人」という通常の意味の下に「火をつける人」の意味を内在していると考えられます。事実、蒸気ボイラーなどの火を焚く「缶焚き」の意味でも使われる。新訳は漢字を活用して日本語訳としてのダブル・ミーニングを狙った工夫でしょう。
文芸作品からの引用
ここからが、いわば本題です。新訳の大きな特徴は『華氏451度』に含まれる文芸作品からの引用を、引用だと分かるように翻訳し、かつ巻末に注釈をつけたことです。
英米の小説で、文章の中に文芸作品からの語句を引用することはよくあるわけです。特に、聖書とシェイクスピアを知らないと翻訳はできない、とさえ言われるぐらいです。引用はとりたてて珍しくはありません。
しかし『華氏451度』は、ほかでもない「本」をテーマにした小説です。「本」をテーマにした小説で「本」からの引用がどういう風に使われているのか、それは作者が小説に込めた思いやテーマに直結する可能性があります。「引用を引用と分かるように翻訳する」ことは、とりわけ『華氏451度』では重要だと考えられる。その意味で、伊藤氏の新訳は意義が深いと思いました。
引用で思い出すのが『赤毛のアン』です。No.77「赤毛のアン(1)文学」、No.78「赤毛のアン(2)魅力」で書いたように、あの本には英米文学と聖書からの引用が溢れています。そして実は『赤毛のアン』と『華氏451度』に共通の引用があるのです。まずそのことから始めます。
『赤毛のアン』を振り返る
『赤毛のアン』(1908)には英米の文学作品と聖書からの引用が多数あるのですが、中でも最も有名なのは物語の一番最後のものでしょう。『赤毛のアン』の最終章である第38章「道の曲がり角」の最後の場面は、グリーン・ゲイブルズの窓辺にたたずむアンの記述です。
|
物語の最後の最後でアンがつぶやく言葉が、文芸作品からの引用です。翻訳者の松本さんの解説を引用します。
|
ブラウニング(1812-1889)はイギリスのヴィクトリア朝(1837-1901)の詩人です。その詩の一節をつぶやいて物語が終わるところなど、いかにも詩の朗読が得意なアンらしいと言えるでしょう。ちなみに『赤毛のアン』の本の扉に書かれた題辞(モットー)もブラウニングの詩の引用です。作者のモンゴメリ(1874-1942)は明らかにそう計画して書いているわけで、ブラウニングが好きだったようです。参考までに、上田敏の『海潮音』の訳詩と原文は以下です。
|
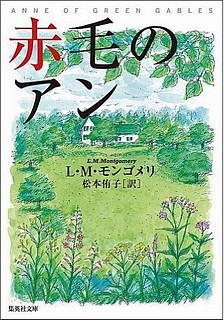
| |||
実は、この詩の最後の1行が『華氏451度』にも出てきます。本に目覚めた主人公のモンターグは、隠れた本の愛好家であるフェーバー教授と知り合いになり、これから進むべき道についてのアドバイスを受けます。そのあたりの教授の発言の一節ですが、伊藤氏の訳文とブラッドベリの原文は以下です。アンダーラインは原文にはありません。
|
この最後の一文は、ブラウニングの「All's right with the world !」を踏まえ、それを否定形にしたものですね。『華氏451度』は、ブラウニングの詩や『赤毛のアン』の世界とは全くの対極にある "ディストピア"(アンチ・ユートピア)を描いた小説です。だからこの引用が意味を持つ。新訳ではそれが明瞭になる形で翻訳されています。しかも、松本さんのような原文のストレートな訳( "この世はすべてよし" )ではなく、上田敏の訳( "すべて世は事も無し" )をそのまま持ってきている。この方がよく知られているということだと思います。
聖書
英米文学の「伝統」に従って、聖書からの引用もいろいろ出てくるですが、その例として『華氏451度』のエンディングの部分の新訳を掲げます。
|
最初の3つの引用は、旧約聖書の「伝道の書」(コヘレトの言葉)の第3章 第1節、第3節、第7節からです。また最後の長めの引用は、新約聖書の「ヨハネの黙示録」の第22章 第2節からです。第22章は、最後の審判のあとの「新しい天と新しい地(=新天新地)」を描く部分であり、黙示録の最終章にあたります。訳者の伊藤氏はここで、文語訳("大正訳")の日本語聖書の文章をもってきています。引用であることを明確にするためでしょう。
『華氏451度』の原書(Del Ray Book版)をみると、旧約聖書・伝道の書の部分には「引用のしるし」はついていません。従って、聖書を知らない人にとって引用だとは分からない。一方、新約聖書・黙示録の部分はイタリック体になっていて、引用だということが明確にされています。『華氏451度』の旧訳では、この黙示録の部分も平文と同じようなスタイルで訳されていたので、我々日本の読者には聖書の引用だとは分かりづらいものでした。
しかし「引用のしるし」があるかないかにかかわらず、クリスチャンで聖書に親しんだ人なら、ないしは英米人なら常識として聖書からの引用だとパッと分かるのでしょう。さらに、最後の最後の引用が新約聖書・黙示録の「新天新地」ということで、作者が『華氏451度』のエンディングに込めた意味が一目瞭然なのだと思います。
そもそも作家が書物からの引用で小説を終えるのは、熟考した結果のはずです。それは小説のテーマや作家の思想にとって重要であり、「重い」ものであることが容易に想像できます。さきほど例示した『赤毛のアン』の最後の引用である、
|
について訳者の松本さんは「神への信頼と未来への希望に満ちて『赤毛のアン』は幕を閉じる」と書いていました。それに習うとすると『華氏451度』の最後の引用である、
|
については、「神への信頼と、本が禁止された "ディストピア" が崩壊して新しい世界がくることの希望とともに『華氏451度』は幕を閉じる」と言えるでしょう。新訳ではそれがクリアに分かるのでした。
さらに想像を広げると、ここで「ヨハネの黙示録」を持ち出すのには意図があるのかもしれません。黙示録は紀元1世紀末のローマ帝国によるユダヤ人に対する圧制とキリスト教徒弾圧の時代に書かれた文書と言われています。そこでは「弾圧者への憎悪」と「キリスト教徒への励まし」がないまぜになっているように見える。それはとりもなおさず『華氏451度』の世界における「本を愛読・伝承する人たち」と、その人たちを「弾圧する体制」との関係に思えます。ブラッドベリがそういう構図を意識して最後に黙示録の文章を持ってきたのはありうることだと思いました。
ガリバー旅行記
英国文学からの引用の一つの例として、スウィフトの『ガリバー旅行記』をあげてみます。主人公のモンターグは、密かに本を所持していることを妻のミルドレッドに告白し、いっしょに読もうと誘います。
|
モンターグがとりあげた本は、スウィフトの『ガリバー旅行記』です。『ガリバー旅行記』の第1篇「リリパット国渡航記」は、リリパットの海岸に打ち上げられて気絶したガリヴァーが、小人の軍隊によって縛られるという出だしです。インド洋の島国・リリパットは、海峡を挟んだ隣の島国のブレフスキュと長年に渡って交戦状態にあります。その戦争の原因は「ゆで卵の殻の正しい剥き方は、大きな端から剥くか、小さな端(尖った方)から剥くかについての意見の違い」に由来します。
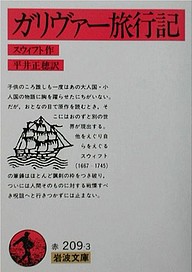
| |||
ブラッドベリは『華氏451度』で、なぜここを引用したのでしょうか。モンターグがまず読む本として、世界文学史上の最も有名な作品の一つから、その比較的よく知られた部分を引用したということでしょうか。
そうかもしれませんが、さらに理由があるように思えます。それは『ガリバー旅行記』の「卵」のくだりを読むと分かります。以下は岩波文庫からの引用です。原文に段落はありません。
|
2つ目のアンダーラインのところ、つまり「本の禁止」がポイントですね。だからブラッドベリはこの部分を引用した。『ガリバー旅行記』に親しんだ人なら「本の禁止」を思い出すかも知れません。また作者は読者に「わかりますか」という、ささやかな挑戦をしたのかも知れません。
さらに連想することがあります。『ガリバー旅行記』における「卵の割り方に起因する対立」とは「新教と旧教の対立」を揶揄したものと解釈されています。「卵を割るときには小さな端から割るべし。大きな端から割る者は厳罰」という勅令を出した「皇帝」とは、カトリックに対抗して英国国教会を設立したヘンリー8世のことだと考えられているのです。
そこで思い出すのは、英国史における「新教と旧教の対立」を背景にした別の引用が『華氏451度』にあることです。No.51「華氏451度(1)焚書」でも紹介したくだりですが、新訳によってもう一度引用します。「隣人が本を所持している」という密告をうけて「昇火士」たちが老女の家を急襲する場面です。
|
16世紀の英国において、メアリー1世(ヘンリー8世の娘で、カトリック教徒)はプロテスタントを弾圧し、延べ300人以上を処刑しました。このプロテスタントの中に、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimar)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という、オックスフォードで同時に処刑された2人の主教がいました。老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉です。『華氏451度』の中では、隊長のベイティーもそう解説しています(No.51「華氏451度(1)焚書」参照)。
『ガリバー旅行記』を含めたこのあたりの引用は、英国史、ないしは英文学に関するブラッドベリの強いこだわりが感じられるところです。
ベイティーの挑発
『華氏451度』のストーリーにおいて「昇火士」の隊長のベイティーは、部下のモンターグが密かに本を隠し持ち、読んでいることに気づいています。任務から帰還し、署の隊員仲間でカードゲームをする場面がありますが、そこでベイティーは、本からの引用を「満載」した言葉をモンターグに投げつけ、モンターグを挑発します。『華氏451度』において文芸作品からの引用が最も多く出てくるのはこの場面なのですが、その一部を掲げてみます。①~⑤の数字は原文にはありません。
|
伊藤氏の注釈によると①~⑤の出典は以下のとおりです。
| ① | 旧約聖書『イザヤ書』53章 6節 の「われわれはみな羊のように迷って、おのおの自分の道に向かって行った。」を踏まえたもの。 | ||
| ② | シェイクスピア『尺には尺を』第5幕 第1場。修道女見習いのイザベラのせりふ。 | ||
| ③ | サー・フィリップ・シドニー(1558-86)の『アーケイディア』(1593)より。シドニーは詩人で廷臣、軍人。エリザベス朝の英国において最も傑出した人物のひとりといわれる。 | ||
| ④ | サー・フィリップ・シドニー『詩の弁護』(1583頃)より。 | ||
| ⑤ | 英国の詩人、アレクサンダー・ポープ(1688-1744)の『批評論』(1711)より |
多数の文芸作品を引用したベイティーの「挑発」は、文庫本で3ページ以上に渡って長々と続きます。
新訳は、引用が引用だとわかるように《》つきで翻訳されています。ブラッドベリの原文でも引用符(')がつけられている。ここで非常に明瞭になることは、本を焼き払う責任者であるベイティーが、実は本の世界に精通していることです。これはどういうことかというと、No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、
| ・ | 『華氏451度』の世界においては、大衆は本から遮断されているが、指導者層は実は本の世界に精通している(それが許されている)。 | ||
| ・ | ベイティーは若いころは(隠れた)読書家であったが、「転向」して本を焼き払う側に回った。 |
のどちらかだと思います。常識的には後者でしょうが、前者のような解釈も捨てがたいと思います。とにかく、次々と出てくる英国文学からの引用を引用だと明確にわかるようにした新訳は、作家の意図をより明確にしているようです。
イギリス文学
「英国文学」と書きましたが、ブラッドベリの引用は聖書を除いてはほとんどがイギリスの文芸作品であり(自国の)アメリカ文学は(少なくとも新訳で伊藤氏が指摘している限りでは)ありません。引用を一覧すると以下の通りです。()内の数字は作家の生年です。
(英国)
| ◆ | ジョン・フォックス(1516) 作品中での老女の言葉「男らしく・・・・・・」の出典となった本を書いた人物。No.51「華氏451度(1)焚書」参照。 | ||
| ◆ | フィリップ・シドニー(1558) | ||
| ◆ | フランシス・ベーコン(1561) | ||
| ◆ | ウィリアム・シェイクスピア(1564) 引用作品は『尺には尺を』『ヴェニスの商人』『テンペスト』『ジュリアス・シーザー』 | ||
| ◆ | ジョン・ダン(1572) 詩人、作家。形而上詩の先駆者。 | ||
| ◆ | ベン・ジョンソン(1572) 劇作家、詩人。シェイクスピアの追悼詩が有名。 | ||
| ◆ | トマス・デッカー(1572頃) 劇作家。 | ||
| ◆ | ロバート・バートン(1577) 神学者、作家。 | ||
| ◆ | ジョナサン・スウィフト(1667) | ||
| ◆ | アレクサンダー・ポープ(1688) 詩人 | ||
| ◆ | サミュエル・ジョンソン(1709) 英語辞典の編纂で著名な文学者。 | ||
| ◆ | ジェイムズ・ボズウェル(1740) 法律家、作家。師匠のサミュエル・ジョンソンの伝記を書いた。 | ||
| ◆ | ロバート・ブラウニング(1812) 詩人 | ||
| ◆ | マシュー・アーノルド(1822) 詩人、文芸評論家。『ドーバー海岸』という詩の一節をモンターグが朗読する場面がある。No.51「華氏451度(1)焚書」参照。 | ||
| ◆ | アレクサンダー・スミス(1829) スコットランドのレース製造業者、詩人、エッセイスト |
(フランス)
| ◆ | ポール・ヴァレリー(1871) |
(スペイン)
| ◆ | ファン・ラモン・ヒメネス(1881) 詩人。ノーベル文学賞受賞。『華氏451度』の題辞はヒメネスから採られている。 |
No.51「華氏451度(1)焚書」にも書いたように『華氏451度』には禁止されている本の作者名として、ホイットマン、ソロー、フォークナーなどのアメリカ人作家の名前も出てくるのですが、作品の一部を引用している作家は、そのほとんどが英国人です。
『赤毛のアン』がそうであったように、聖書とシェイクスピアからの引用は一般的ですが、それ以外の引用は作家の個性によります。『赤毛のアン』にはイギリス文学からの引用が多いのですが、アメリカ人作家からのも多々ある(作者のモンゴメリはカナダ人)。そういった意味で『華氏451度』引用はブラッドベリの嗜好を表していると考えられます。また、特に16世紀から19世紀の作品が取り上げられていることからすると、書物の世界における「古典」の重要性、ないしは人類の「知的財産」としの本の重要性を言いたかったのかもしれません。
『華氏451度』の意味 : 反知性主義の世界
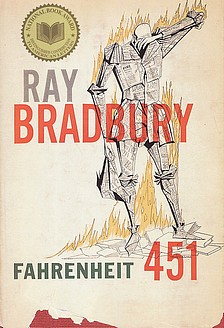
| |||
|
Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Del Ray Book, 1996) 1953年に最初に出版されたハードカヴァーの表紙を採用している
| |||
No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、『華氏451度』を「本が禁止された世界」だと考えるのは表面的です。『華氏451度』は「本を読むような人が迫害される世界」を描いたものです。もちろん、ここで言う「本」とは知的財産としての本であって、(ブラッドベリの考える)消費財としての本(たとえばダイジェスト本とか漫画)ではありません。
では「本を読むような人」とはどういう人かと言うと、本によって「知識の獲得」や「教養の深化」を目指す人でしょう。また自分のできない体験を疑似的に経験したり、さまざまな人に「会える」のも読書の大きな効用です。しかし「困ったことに」、本の中の言説には応々にして相反することが書いてあります。それは小説の中で、隊長のベイティーが何度か強調していることで、「ベイティーの挑発」として上に引用した箇所にもありました。引用はしませんでしたが、彼は「知識人」を「相反する思想や理論で人を不幸にしたがる連中」と呼んでいます。
しかし考えてみると「相反する」のは当然なのです。一般的に言って、社会における重要な問題、人生の重要な問題には複数の回答案があり、しかもそれらが相反していることが多いわけです。答えは一つではありません。重要になればなるほどそうです。それはビジネスにおける重要課題でも同様です。我々は自ら考え、その中から最良と思うものを選んで決断し、行動に移す。これはある意味では悩ましく、苦しいことです。
そのため、多様なモノの見方や異質な考え方触れることを放棄したり、多様な考えを勘案しつつ「考える」ことをやめてしまって「指導者」の言うがままに行動するとか、同質のグループで凝り固まって「社会的孤立」に向かう人たちが出てくる。
しかしそれでは社会状況や自身をとりまく環境の変化についていけないし、結局のところ人間社会に不幸をもたらす要因になるのだと思います。変化についていくためには、自らが変わらないといけないし、変わるきっかけは「知ること」しかありません。
『華氏451度』が描くのは「考えない」人たちが大量に生み出された世界です。ここで重要なのは、それが上からの押しつけではなく、大衆自らがそういう世界を選びとったということでしょう。小説ではそう説明してあります(No.52「華氏451度(2)核心」参照)。『華氏451度』は究極の「反知性主義の世界」を、その「作られ方」を含めて描いたと言えるでしょう。ここに『華氏451度』の今日的な意味があると思います。
ちょっと思い出すのが、前々回の No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介した、内田樹氏の文章です。内田さんは『街場の共同体論』で次のように警告しているのでした。
|
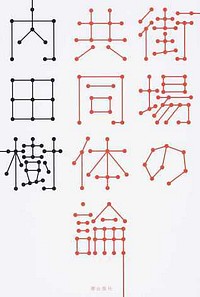 |
小説の中における隊長のベイティーは本の焼却の責任者である一方で(善か悪かは別にして)極めて知的な人間であり、本の世界に精通しています。モンターグの妻のミルドレッドは「壁テレビ」に浸りきり、上からの指示どおりに動く人間として描かれています。『華氏451度』の世界においては彼女のような人がほとんどです。その間に立ったモンターグは「知の世界に目覚めた普通の人」です。こういう人物配置によって、戯画のような「究極の世界」が描き出されています。
ブラッドベリが1950年代の初頭に行った「問題提起」は、明らかにテレビに代表されるメディアの発達に対する危機感からきています。まるで21世紀の現代を予見したかのような「壁テレビ」がその象徴です。しかしそういう「メディアの問題」にとどまらず、『華氏451度』は人間の本質、ないしは「弱さ」の深いところを突いています。その問題提起は、60年以上たった現代でも全く色褪せていないと感じました。
No.79 - クラバート再考:大人の条件 [本]
前々回と前回に書いた『赤毛のアン』は何回目かの「少年少女を主人公とする物語」でした。特に意識しているわけではないのですが、第1回が『クラバート』だったので自然とそういう流れになったのかも知れません。
取り上げた「少年少女を主人公とする物語」は、4つの小説と1つのアニメーション映画です。作品名、発表年、物語の舞台となった国、主人公の名前をまとめると次の通りです。
一見してわかるように、5つの物語は発表年に100年以上の隔たりがあり、物語の舞台となった国は全部違います。しかしその内容には共通点があるように思えます。今回はこの「5つの物語」の共通点を考えてみようというのが主旨です。
5つの物語
No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で、『クラバート』という小説は、一言で言うと少年が「大人になる物語」だと書きました。これは他の4つの物語でも共通しています。大人になるという言い方がそぐわないなら「主人公の少年(少女)が、自立した人間として生きていくためのさまざま経験をし、成長する物語」だと言ってよいでしょう。この共通点は10代の少年少女を主人公にした物語としては自然なものです。少年少女は大人に向かって成長する過程にあるのが当然だからです。
しかし5つの作品には、単に「大人になる物語」というレベルを越えた共通点があります。それは主人公が置かれた環境に関係しています。つまり5つの物語は全て次のような経過をたどるのです。
この物語の構造が5つの作品に共通しています。主人公は「物語の舞台となる環境」で成長していくのですが、それは主人公の意志とは無関係に外部から決められた、全く新しい環境なのです。
孤児であるクラバートがシュバルツコルムの水車場に身を投じたきっかけは「夢のお告げ」でした。彼は「そこがどういうものか全く知らない」状況で、職人の見習いとして働き出します。
ごく平凡な家庭の女の子だった千尋は、湯婆婆の支配する湯屋で働くようになりますが、そのきっかけは、引っ越しの途中に不意に「異空間への入り口」であるトンネルを通ってしまったからです。
セーラがロンドンの学園の屋根裏部屋に住み込んで小間使いとして働き出したのは、父親の突然の死と破産という、まさに晴天の霹靂がきっかけでした。学園の優秀な生徒だったセーラの立場は180度変化します。この小間使いの期間こそ『小公女』の核です。
イタリア人のニコラスが外国であるスペインの宮廷に連れていかれたのは、小人症の子どもを集めていたスペイン宮廷の使者に父親がニコラスを「売った」からでした。
最後のアンはクラバートと同じように両親を無くした孤児です。彼女がグリーン・ゲーブルズに来たのは、マシューとマリラ兄妹の希望に応じて孤児院がアンを選んだからですが、仲介者のミスによって男の子のはずが女の子のアンが選ばれてしまったわけです。
5つの物語は自分の選んだのではない環境と折り合いをつけ成長するというところがキーになっていると思います。というのも、それが大人の重要な条件だと思うからです。
自己選択はできない
我々は人生の節目節目において、種々の選択をしていると考えています。高校、大学への入学、就職、結婚、住居など、重要な時点で自分の考えて判断して「選ぶ」という行為をしていると考えている。
しかし人間社会においては、人生における極めて重要な環境条件が自分では選べないもの、自己選択できないものです。まず誰でも分かるのは「家族」です。我々は両親を選択できないし、兄弟も選択できません。
結婚相手(配偶者)が選択できるかというと、そう単純には言えない。ほとんどの人は職場や学校、サークル活動やコミュニティ活動で「たまたま」知り合い、一緒になってもいいなと思った人と結婚するのだと思います。結婚を決めるのは本人同士ですが、出会いに至る過程とその後の経緯は偶然の積み重ねであり、本人の意志とは無関係なところで決まる。職場で3人と付き合っていて、そのうちの一人を結婚相手として選択した、というような人もいると思いますが、極く少数でしょう。
結婚相手の「条件」がまずあり、その条件に合致する人が現れるまで次々と交際するというのでは、いつまでたっても結婚できません。話が逆なのです。
仕事も、多くの場合は「選択できない」と言った方がよいと思います。もちろん「仕事を自分で選択した」と言い切れる人があるのは確かです。外科医を目指して一所懸命に勉強し、医学部に合格し、国家試験をうけて外科医になった人もいるでしょう。弁護士や検事、パイロットなどもそうです。警察官や消防士も、それを目指してきた人が多いでしょう。自分でベンチャー企業を起こしたり、脱サラしてラーメン店を始めるようなケースも「仕事を自分で選んだ」と言えると思います。
しかし、大学で就職活動をして会社に就職するという、多くの人がたどるケースを考えると「仕事を自分で選択した」とは言い難い。たとえば大学の理系学部にすすみ、自動車会社への就職を希望して、運良く入社したとしましょう。しかし自動車会社における理系の仕事は極めて多様です。①次世代2次電池の研究、②ボディーの外観デザイン、③クリーンなディーゼル・エンジンの開発、④工場における生産設備の開発と、たった4つだけをとってみても仕事の内容は全く違います。必要とする技術、ノウハウ、経験の蓄積が全く違う。(大手の)電機会社だともっと仕事のバリエーションが多いわけです。Panasonicという会社はテレビを作っていますが、産業用の溶接機も作っています。それぞれに研究もあれば工場現場サイドでのものづくりもある。
自動車会社3社と電機会社2社の入社試験をうけ、たまたまPanasonicに採用され、産業用溶接機の部門に配属された人は、仕事を選択したとは言い難いと思います。「ものづくりに従事することを選択した」とは言えるでしょうが「ものづくり」はあまりに大まかすぎて仕事だとは言えません。家業を継ぐ場合と同じく、会社で働く場合も仕事はあくまで外部から「与えられた」ものなのです。
人は「与えられた」仕事でいかに努力をするか、が普通です。自分の仕事が自分に合っていないと感じ、自らの意志で転職を繰り返す人がいますが、こういう人はいつまでたっても重要な仕事はできないし、収入も増えないでしょう。話が逆転しているからです。
現代社会において人間は生きていく過程で、数々の自由意志による選択をしています。何を食べるかから始まって、どこに住むか、どういうクルマを購入するか、趣味は何か、誰と付き合って誰と付き合わないかなど、自由意志で決まることが多々あります。
しかし家庭や仕事などの「社会を成立させている根幹のところ」においては選択ができないことが多い。先ほど弁護士を目指して勉強し、めでたく弁護士になった人もいるという話を書きましたが、誰でも「弁護士」という仕事を選択できるわけではありません。司法試験の難関を突破するためには徹底的な努力が必要であり、努力する能力を身につけていて、かつ才能にも恵まれた人だけに弁護士への道が開かれるのだと思います。
人間社会の成立と継続にとって非常に重要なことは選択できないようになっています。人間の自由意志による選択などにまかせていては、社会が危なくなるからです。
自己選択できない環境で最善を尽くせる
大人の条件の最も重要なことは「自己選択できない環境で最善を尽くせる」ことだと思います。
仕事で成功した人が、その仕事を自ら選択したというようなことを語ることがあります。商社で重要なポストにある人が、日本は貿易立国であり、エネルギーの確保が重要だから商社に就職し、中東諸国とのエネルギープラントの仕事に従事してきた、というような話です。しかしおそらく実態は、たまたま商社に就職でき、たまたまエネルギー部門に配属され、その環境条件で本人が苦労し努力を重ねてきたから重要なポストにつけたのだと思います。「自己選択した」というのは「後付けで作られた物語」です。
結婚もそうです。この人と結婚した理由、その人を選んだ理由は「ない」ケースが多いのではないでしょうか。「何となく」結婚し、その後本人同士が努力を重ねてきたから「幸せな家庭」が築けたということだと思います。独身を通してきた人が「結婚しないという道を選択した」と語るのも同様です。「たまたまそういう風になった」のが実態なのだと思います。自己選択したという物語は事後的に作られる。そういうケースが多いはずです。
「自己選択したから最善を尽くす」のはあたりまえで、子どもでもそういうマインドの形成ができるでしょう。「自己選択したものでなくても最善を尽くせる」のが大人の条件です。
少年少女を主人公にした5つの物語は、この大人の条件を暗示しているように見えます。特に、クラバート、千尋、セーラは10代前半ですが、仕事・労働に従事します。ニコラスも8歳程度の時からスペイン宮廷で「道化」としての役割を与えられます。労働は社会を成立させている根幹ですが、自分の意志とは無関係に外部から強制された仕事を通じての彼らの成長は示唆的です。
アンは、少なくとも第1作の『赤毛のアン』では仕事をしません。しかしアンが孤児院から与えられたグリーン・ゲイブルズという環境(家庭)は仲介者のミスなのですね。望まれない存在としてグリーン・ゲイブルズに来た(それでもアンはうまくやっていった)という作者・モンゴメリの物語設定は大きな意味があると思います。
線引きの容認
「自己選択できない」ということに関連する大人の条件を付け加えると「どこかに線が引かれることを容認できる」ことがあります。人間と人間の間のどこかに線を引く必要がある。「線引きの容認」が大人の条件です。
現代の日本で、子どもが「線引き」という現実を強く感じるのは入学試験でしょう。たとえば高校入試です。私の住んでいる神奈川県の公立高校の入試は全県1区なので、論理的には県内のどの高校を受験してもよいのですが、実際は内申書や学力によって受験できる高校がほとんどピンポイントで決まります。あなたはA高、あなたはB高というように線が引かれる。「線引き」は、スポーツの部活動で正選手に選ばれるか補欠かということでも言えます。
線を引く厳密な基準はないので曖昧性が残るのですが、どこかに線を引かないといけない。もちろん理不尽な基準には文句を言っていいわけです。寄付をたくさんすると高校に入れる、とか・・・・・・。しかし多くの場合は「線を引くしかないから、線を引いている」のですね。
昔、公立高校への全入制度をとっている都道府県がありました。義務教育でないにもかかわらず、住む地域によってどの高校へ入るかが決まっているわけです。これは結局、子どもが「線引き」という現実に直面する時期を大学入試とか就職に遅らせているだけです。それだけ子どもの成長機会を奪っているのだと思います。
5つの物語に戻ると『クラバート』がこの「線引き」を直接的に扱っています。毎年、職人の一人が犠牲になり、反面、次期親方の候補に選ばれる者もいる(クラバート自身ですが)。大人の社会を寓話的に表しているのだと思います。
変化する能力
「自己選択できない環境で最善を尽くせる」という条件からロジカルに導き出せることは、変化する能力が重要だということです。環境の変化や新しい環境に対応して生き延び、他人やコミュニティとの良好な関係を保ち、自分自身としてもより満足を得られるためには、自分を変えていくことが重要です。また、外界の条件に対応した能力を磨くことが必須です。
外界の変化に対応して自らを変えられる能力をもつこと。これは大人の重要な条件です。
No.56「強い者は生き残れない」で進化生物学者・吉村仁氏の著書から「強い生物が生き残るのではない。環境の変化に即応できる生物が生き残るのだ」という主旨の見識を紹介しましたが、それと極めてよく似ています。
もちろん、人の性格とか信念・信条、自分が自分であることの源泉だと信じていることは変わりません。変わったとしても急には変わらない。5つの物語では、セーラ、ニコラス、アンは自尊心というか、プライドを持っている少年少女に描かれています。セーラは虐待(と言えるような仕打ち)をうけても「気品」を失わないし、ニコラスとアンは自分の「身体的特徴」をからかわれると相手が大人であっても猛然と反論します。クラバートや千尋も含めて「自分は自分だ」という意識がある。人の性格・信念・信条などは人の個性を作り出すものであり、非常に大切なものです。
しかしその一方で、それにこだわりすぎて「変わらないもの」が肥大化し過ぎると外界と環境の変化についていけなくなります。
努力を継続できる能力
「自己選択できない環境で最善を尽くせる」という条件から導けるもう一つの大人の条件は「努力する能力」「努力を継続できる能力」です。自分が選んだのではない、よく知らない新しい環境とうまく折り合っていくためには、本人の努力が是非とも必要です。
子どもが学校で身につけるべき最重要ポイントは、この「努力を継続できる能力」でしょうね。それは勉強でも部活でも同じです。「こんな勉強は役に立たない」と思って努力を放棄してしまう子どもがいるとしたら、それは間違っています。
たとえば数学(算数)を例にとると、整数や分数の四則演算が社会で「役に立つ」ことは誰でも分かります。しかし中学も進んでくると何の役に立つのか、一見分からないテーマになる。因数分解とか二次関数とか・・・・・・。本当は論理的思考を養うのに非常に有用だと思うのですが、それは直接的な効能を言えないし、子どもには理解しにくい。
しかし数学(算数)で学ぶ内容、もっと広くは勉強の内容(コンテンツ)もさることながら、勉強をするということ自体(プロセス)が重要です。コンテンツは役立たないこともありうる。しかし努力するプロセスとその経験は必ず役立ちます。大の苦手だった幾何を克服したアンのように・・・・・・。
小さいときから努力することの価値や大切さを教えられなかった子どもは可哀想です。大人の条件を欠いて社会に出ることになるのだから。
「努力することを継続できる能力」とペアになっているのは「自分の欲望を自分で制限できる能力」でしょう。欲望を全面に出して生きていくのでは、努力する時間も余裕もなくなります。努力を継続することは、ある意味で自分を変えることです。
努力するといった場合、目標として何らかの明確なゴールを設定する場合が多いでしょう。たとえば「A大学に合格する」といったような・・・・・・。しかし「ゴールのない目標」「ゴールに到達しえない目標」に向かって努力できる能力もまた重要です。なぜかというと社会と人生における重要な目標はゴールが設定できないからです。到達可能な具体的な目標は、多くの人が同じ目標を持つことになります。A大学に合格するという目標は、同じ年齢の数千人・数万人が同じものを持っている。しかしゴールのない目標は他人と共有できません。それこそが人間の独自性の発揮です。
5つの物語
少年少女を主人公にした5つの物語から類推できる「大人の条件」を何点か書きましたが、その内容は極めてシンプルで、あたりまえのことです。しかし我々大人は日々の生活や仕事の複雑さに追われ、シンプルなことを忘れがちです。少年少女の成長の物語が「大人の条件」を浮かび上がらせる・・・・・・。大人が少年・少女を主人公にした物語を読む(再読する)意義はそこにあると思います。
取り上げた「少年少女を主人公とする物語」は、4つの小説と1つのアニメーション映画です。作品名、発表年、物語の舞台となった国、主人公の名前をまとめると次の通りです。
| ◆ | クラバート(No.1, No.2) | 1971 | ドイツ | クラバート | |
| ◆ | 千と千尋の神隠し(No.2) | 2001 | 日本 | 千尋 | |
| ◆ | 小公女(No.40) | 1888 | イギリス | セーラ | |
| ◆ | ベラスケスの十字の謎(No.45) | 1999 | スペイン | ニコラス | |
| ◆ | 赤毛のアン(No.77, No.78) | 1908 | カナダ | アン |
一見してわかるように、5つの物語は発表年に100年以上の隔たりがあり、物語の舞台となった国は全部違います。しかしその内容には共通点があるように思えます。今回はこの「5つの物語」の共通点を考えてみようというのが主旨です。
5つの物語
No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」で、『クラバート』という小説は、一言で言うと少年が「大人になる物語」だと書きました。これは他の4つの物語でも共通しています。大人になるという言い方がそぐわないなら「主人公の少年(少女)が、自立した人間として生きていくためのさまざま経験をし、成長する物語」だと言ってよいでしょう。この共通点は10代の少年少女を主人公にした物語としては自然なものです。少年少女は大人に向かって成長する過程にあるのが当然だからです。
しかし5つの作品には、単に「大人になる物語」というレベルを越えた共通点があります。それは主人公が置かれた環境に関係しています。つまり5つの物語は全て次のような経過をたどるのです。
| ◆ |
主人公の置かれた環境は「物語の開始時の環境」から、それとは全く異質な「物語の舞台となる環境」へと大きく転換する。 | |
| ◆ |
この「転換」は主人公が選んだものではなく、主人公の意見をもとに決められたものでもない。「転換」に際しては主人公のいかなる意志も意向も反映されない。 | |
| ◆ | 主人公は、自分の選んだのではない環境と何とか折り合いをつけ、自分を磨き、または自分の意志を貫き、成長し、自立していく。 |
この物語の構造が5つの作品に共通しています。主人公は「物語の舞台となる環境」で成長していくのですが、それは主人公の意志とは無関係に外部から決められた、全く新しい環境なのです。
孤児であるクラバートがシュバルツコルムの水車場に身を投じたきっかけは「夢のお告げ」でした。彼は「そこがどういうものか全く知らない」状況で、職人の見習いとして働き出します。
ごく平凡な家庭の女の子だった千尋は、湯婆婆の支配する湯屋で働くようになりますが、そのきっかけは、引っ越しの途中に不意に「異空間への入り口」であるトンネルを通ってしまったからです。
セーラがロンドンの学園の屋根裏部屋に住み込んで小間使いとして働き出したのは、父親の突然の死と破産という、まさに晴天の霹靂がきっかけでした。学園の優秀な生徒だったセーラの立場は180度変化します。この小間使いの期間こそ『小公女』の核です。
イタリア人のニコラスが外国であるスペインの宮廷に連れていかれたのは、小人症の子どもを集めていたスペイン宮廷の使者に父親がニコラスを「売った」からでした。
最後のアンはクラバートと同じように両親を無くした孤児です。彼女がグリーン・ゲーブルズに来たのは、マシューとマリラ兄妹の希望に応じて孤児院がアンを選んだからですが、仲介者のミスによって男の子のはずが女の子のアンが選ばれてしまったわけです。
| 主人公 | 物語の開始時の環境 | 物語の舞台となる環境(主人公の年齢) | 転換のきっかけ |
| クラバート | 浮浪児。物乞いで生活している。 | シュバルツコルムの水車場。魔法使いの親方が支配。(14歳 ~) | 「水車場に来い」という夢のお告げにさそわれる。 |
| 千尋 | 両親と3人暮らしの、ごく平凡な家庭の女の子。 |
湯屋。魔法使いでもある湯婆婆が支配。 (10歳) |
引っ越しの途中でトンネルから「異空間」に迷い込む。 |
| セーラ | インドのダイヤモンド鉱山主の娘。ロンドンの学園で勉学に励む。 |
学園の小間使い。屋根裏部屋に住む。 (11歳 ~) |
父親の破産と死。 |
| ニコラス | ジェノバ近郊に住むイタリア人の息子。 |
スペイン王、フェリペ4世の宮廷。 (7歳か8歳 ~) |
小人症の子供を集めていた宮廷の使者が父親と取引き。 |
| アン | 孤児院 | グリーン・ゲイブルズのマシューとマリラ兄妹の家庭。(11歳 ~) | 仲介者の誤った話をもとに孤児院がアンを選択。 |
5つの物語は自分の選んだのではない環境と折り合いをつけ成長するというところがキーになっていると思います。というのも、それが大人の重要な条件だと思うからです。
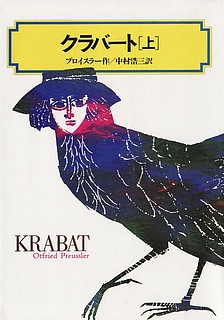
|
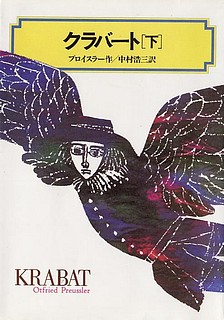
|
自己選択はできない
我々は人生の節目節目において、種々の選択をしていると考えています。高校、大学への入学、就職、結婚、住居など、重要な時点で自分の考えて判断して「選ぶ」という行為をしていると考えている。
しかし人間社会においては、人生における極めて重要な環境条件が自分では選べないもの、自己選択できないものです。まず誰でも分かるのは「家族」です。我々は両親を選択できないし、兄弟も選択できません。
結婚相手(配偶者)が選択できるかというと、そう単純には言えない。ほとんどの人は職場や学校、サークル活動やコミュニティ活動で「たまたま」知り合い、一緒になってもいいなと思った人と結婚するのだと思います。結婚を決めるのは本人同士ですが、出会いに至る過程とその後の経緯は偶然の積み重ねであり、本人の意志とは無関係なところで決まる。職場で3人と付き合っていて、そのうちの一人を結婚相手として選択した、というような人もいると思いますが、極く少数でしょう。
結婚相手の「条件」がまずあり、その条件に合致する人が現れるまで次々と交際するというのでは、いつまでたっても結婚できません。話が逆なのです。
仕事も、多くの場合は「選択できない」と言った方がよいと思います。もちろん「仕事を自分で選択した」と言い切れる人があるのは確かです。外科医を目指して一所懸命に勉強し、医学部に合格し、国家試験をうけて外科医になった人もいるでしょう。弁護士や検事、パイロットなどもそうです。警察官や消防士も、それを目指してきた人が多いでしょう。自分でベンチャー企業を起こしたり、脱サラしてラーメン店を始めるようなケースも「仕事を自分で選んだ」と言えると思います。
しかし、大学で就職活動をして会社に就職するという、多くの人がたどるケースを考えると「仕事を自分で選択した」とは言い難い。たとえば大学の理系学部にすすみ、自動車会社への就職を希望して、運良く入社したとしましょう。しかし自動車会社における理系の仕事は極めて多様です。①次世代2次電池の研究、②ボディーの外観デザイン、③クリーンなディーゼル・エンジンの開発、④工場における生産設備の開発と、たった4つだけをとってみても仕事の内容は全く違います。必要とする技術、ノウハウ、経験の蓄積が全く違う。(大手の)電機会社だともっと仕事のバリエーションが多いわけです。Panasonicという会社はテレビを作っていますが、産業用の溶接機も作っています。それぞれに研究もあれば工場現場サイドでのものづくりもある。
自動車会社3社と電機会社2社の入社試験をうけ、たまたまPanasonicに採用され、産業用溶接機の部門に配属された人は、仕事を選択したとは言い難いと思います。「ものづくりに従事することを選択した」とは言えるでしょうが「ものづくり」はあまりに大まかすぎて仕事だとは言えません。家業を継ぐ場合と同じく、会社で働く場合も仕事はあくまで外部から「与えられた」ものなのです。
人は「与えられた」仕事でいかに努力をするか、が普通です。自分の仕事が自分に合っていないと感じ、自らの意志で転職を繰り返す人がいますが、こういう人はいつまでたっても重要な仕事はできないし、収入も増えないでしょう。話が逆転しているからです。
現代社会において人間は生きていく過程で、数々の自由意志による選択をしています。何を食べるかから始まって、どこに住むか、どういうクルマを購入するか、趣味は何か、誰と付き合って誰と付き合わないかなど、自由意志で決まることが多々あります。
しかし家庭や仕事などの「社会を成立させている根幹のところ」においては選択ができないことが多い。先ほど弁護士を目指して勉強し、めでたく弁護士になった人もいるという話を書きましたが、誰でも「弁護士」という仕事を選択できるわけではありません。司法試験の難関を突破するためには徹底的な努力が必要であり、努力する能力を身につけていて、かつ才能にも恵まれた人だけに弁護士への道が開かれるのだと思います。
人間社会の成立と継続にとって非常に重要なことは選択できないようになっています。人間の自由意志による選択などにまかせていては、社会が危なくなるからです。
自己選択できない環境で最善を尽くせる
大人の条件の最も重要なことは「自己選択できない環境で最善を尽くせる」ことだと思います。
仕事で成功した人が、その仕事を自ら選択したというようなことを語ることがあります。商社で重要なポストにある人が、日本は貿易立国であり、エネルギーの確保が重要だから商社に就職し、中東諸国とのエネルギープラントの仕事に従事してきた、というような話です。しかしおそらく実態は、たまたま商社に就職でき、たまたまエネルギー部門に配属され、その環境条件で本人が苦労し努力を重ねてきたから重要なポストにつけたのだと思います。「自己選択した」というのは「後付けで作られた物語」です。
結婚もそうです。この人と結婚した理由、その人を選んだ理由は「ない」ケースが多いのではないでしょうか。「何となく」結婚し、その後本人同士が努力を重ねてきたから「幸せな家庭」が築けたということだと思います。独身を通してきた人が「結婚しないという道を選択した」と語るのも同様です。「たまたまそういう風になった」のが実態なのだと思います。自己選択したという物語は事後的に作られる。そういうケースが多いはずです。
「自己選択したから最善を尽くす」のはあたりまえで、子どもでもそういうマインドの形成ができるでしょう。「自己選択したものでなくても最善を尽くせる」のが大人の条件です。
少年少女を主人公にした5つの物語は、この大人の条件を暗示しているように見えます。特に、クラバート、千尋、セーラは10代前半ですが、仕事・労働に従事します。ニコラスも8歳程度の時からスペイン宮廷で「道化」としての役割を与えられます。労働は社会を成立させている根幹ですが、自分の意志とは無関係に外部から強制された仕事を通じての彼らの成長は示唆的です。
アンは、少なくとも第1作の『赤毛のアン』では仕事をしません。しかしアンが孤児院から与えられたグリーン・ゲイブルズという環境(家庭)は仲介者のミスなのですね。望まれない存在としてグリーン・ゲイブルズに来た(それでもアンはうまくやっていった)という作者・モンゴメリの物語設定は大きな意味があると思います。

|
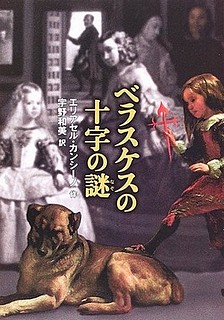
|
線引きの容認
「自己選択できない」ということに関連する大人の条件を付け加えると「どこかに線が引かれることを容認できる」ことがあります。人間と人間の間のどこかに線を引く必要がある。「線引きの容認」が大人の条件です。
現代の日本で、子どもが「線引き」という現実を強く感じるのは入学試験でしょう。たとえば高校入試です。私の住んでいる神奈川県の公立高校の入試は全県1区なので、論理的には県内のどの高校を受験してもよいのですが、実際は内申書や学力によって受験できる高校がほとんどピンポイントで決まります。あなたはA高、あなたはB高というように線が引かれる。「線引き」は、スポーツの部活動で正選手に選ばれるか補欠かということでも言えます。
線を引く厳密な基準はないので曖昧性が残るのですが、どこかに線を引かないといけない。もちろん理不尽な基準には文句を言っていいわけです。寄付をたくさんすると高校に入れる、とか・・・・・・。しかし多くの場合は「線を引くしかないから、線を引いている」のですね。
昔、公立高校への全入制度をとっている都道府県がありました。義務教育でないにもかかわらず、住む地域によってどの高校へ入るかが決まっているわけです。これは結局、子どもが「線引き」という現実に直面する時期を大学入試とか就職に遅らせているだけです。それだけ子どもの成長機会を奪っているのだと思います。
5つの物語に戻ると『クラバート』がこの「線引き」を直接的に扱っています。毎年、職人の一人が犠牲になり、反面、次期親方の候補に選ばれる者もいる(クラバート自身ですが)。大人の社会を寓話的に表しているのだと思います。
変化する能力
「自己選択できない環境で最善を尽くせる」という条件からロジカルに導き出せることは、変化する能力が重要だということです。環境の変化や新しい環境に対応して生き延び、他人やコミュニティとの良好な関係を保ち、自分自身としてもより満足を得られるためには、自分を変えていくことが重要です。また、外界の条件に対応した能力を磨くことが必須です。
外界の変化に対応して自らを変えられる能力をもつこと。これは大人の重要な条件です。
No.56「強い者は生き残れない」で進化生物学者・吉村仁氏の著書から「強い生物が生き残るのではない。環境の変化に即応できる生物が生き残るのだ」という主旨の見識を紹介しましたが、それと極めてよく似ています。
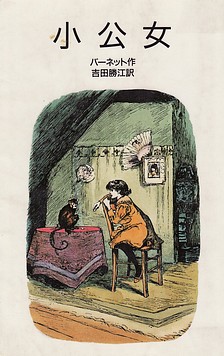
|
しかしその一方で、それにこだわりすぎて「変わらないもの」が肥大化し過ぎると外界と環境の変化についていけなくなります。
努力を継続できる能力
「自己選択できない環境で最善を尽くせる」という条件から導けるもう一つの大人の条件は「努力する能力」「努力を継続できる能力」です。自分が選んだのではない、よく知らない新しい環境とうまく折り合っていくためには、本人の努力が是非とも必要です。
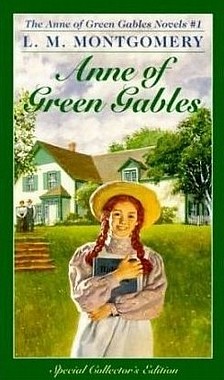
|
たとえば数学(算数)を例にとると、整数や分数の四則演算が社会で「役に立つ」ことは誰でも分かります。しかし中学も進んでくると何の役に立つのか、一見分からないテーマになる。因数分解とか二次関数とか・・・・・・。本当は論理的思考を養うのに非常に有用だと思うのですが、それは直接的な効能を言えないし、子どもには理解しにくい。
しかし数学(算数)で学ぶ内容、もっと広くは勉強の内容(コンテンツ)もさることながら、勉強をするということ自体(プロセス)が重要です。コンテンツは役立たないこともありうる。しかし努力するプロセスとその経験は必ず役立ちます。大の苦手だった幾何を克服したアンのように・・・・・・。
小さいときから努力することの価値や大切さを教えられなかった子どもは可哀想です。大人の条件を欠いて社会に出ることになるのだから。
「努力することを継続できる能力」とペアになっているのは「自分の欲望を自分で制限できる能力」でしょう。欲望を全面に出して生きていくのでは、努力する時間も余裕もなくなります。努力を継続することは、ある意味で自分を変えることです。
努力するといった場合、目標として何らかの明確なゴールを設定する場合が多いでしょう。たとえば「A大学に合格する」といったような・・・・・・。しかし「ゴールのない目標」「ゴールに到達しえない目標」に向かって努力できる能力もまた重要です。なぜかというと社会と人生における重要な目標はゴールが設定できないからです。到達可能な具体的な目標は、多くの人が同じ目標を持つことになります。A大学に合格するという目標は、同じ年齢の数千人・数万人が同じものを持っている。しかしゴールのない目標は他人と共有できません。それこそが人間の独自性の発揮です。
5つの物語
少年少女を主人公にした5つの物語から類推できる「大人の条件」を何点か書きましたが、その内容は極めてシンプルで、あたりまえのことです。しかし我々大人は日々の生活や仕事の複雑さに追われ、シンプルなことを忘れがちです。少年少女の成長の物語が「大人の条件」を浮かび上がらせる・・・・・・。大人が少年・少女を主人公にした物語を読む(再読する)意義はそこにあると思います。
No.78 - 赤毛のアン(2)魅力 [本]
文学から文学を作るという手法
前回に続いて『赤毛のアン』(『アン』と略)の話です。松本 侑子さんは『アン』に引用されている英米文学(以下、テクストと記述)を調べて重要な指摘をしています。それは、モンゴメリが単にテクストから文言だけを抜き出して引用したのではなく、テクストに書かれている物語とその内容を十分に踏まえた上で、引用を盛り込んだ『アン』の文章を書いている、という指摘です。
典型的な例は、前回の No.77「赤毛のアン(1)」で紹介したアメリカの詩人・ロングフェローの『乙女』という詩です。モンゴメリはこの詩の内容を踏まえた上で『アン』の第31章を書いた。それは明らかです。そして、そのことのひそかな(誰も気づかないであろう)しるしとして『乙女』の一節を章の題名にもってきた。
別の例をあげると、第2章でマシュー・カスバートは孤児院からやってくるアンを駅に迎えに行きます。その第2章の冒頭はこうです。
|
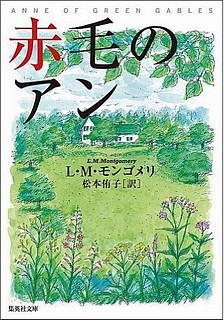
| |||
|
L.M.モンゴメリ作。松本侑子訳 「赤毛のアン」(集英社文庫。2000) | |||
この引用は、美しい初夏の情景を際立たせるためと思えます。しかし単にそれだけではない。出典はアメリカの詩人・批評家のローウェルという人が書いた『サー・ローンファルの夢想』(1848)という詩の一節です。この詩は、アーサー王の円卓の騎士の一人であるサー・ローンファルが聖杯の探索に出かけた時を詠った詩です。つまりモンゴメリは「円卓の騎士が聖杯を探索する旅」に「マシューが孤児院からくるアンを迎えに行く8マイルの旅」を重ね合わせて第2章を書いている。未婚のマシューにとって子どもを家に迎えるというのは全く初めての体験であり、ブライトリバー駅までの道のりは「未知との遭遇」のための「旅」なのです。
もう一つだけ例をあげると、第21章「風変わりな香料」においてカスバート家は新任の牧師夫妻(アラン夫妻)を招いて「お茶会」を開きます。マリラはたくさんの料理を用意し、アンもケーキを作ります。
|
この章は「お茶会」を開く経緯やその準備、会が終わったあとの記述に費やされていて、アンの作ったケーキが出るまでの「お茶会」そのものの様子は「すべては、結婚式の鐘のように愉しく過ぎ」しかありません。ここで「結婚式の鐘」を持ち出すのは少々違和感があるのですが、これは英国の詩人・バイロンの詩の引用なのです。
バイロンの『チャイルド・ハロルドの巡礼』第3巻の中に、ある舞踏会を詠った以下の一節があります。この中からの引用です。
|
これは1815年6月15日に、当時のフランス軍の支配下にあったブリュッセルで開催された舞踏会の様子です。そして「婚礼の鐘」の直後のセンテンスにある「弔いの鐘のような低い響き」とは、ワーテルローの戦いの火蓋が切って落とされた、その砲火の響きです。ヨーロッパ史で有名なワーテルローの戦いは、フランス軍(ナポレオン軍)が、イギリス・オランダ・プロイセン軍に大敗する結果となりました。
そして『アン』においても、すべては愉しく過ぎたお茶会は、最後に出されたアンが作ったケーキによって失敗に終わるのです。
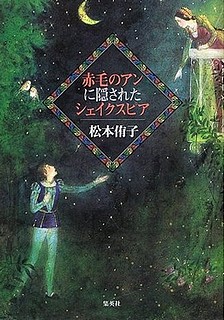
| |||
|
松本侑子「赤毛のアンに 隠されたシェイクスピア」 (集英社。2001) | |||
文学から文学を作るのは「最もオーソドックスな文学の作り方」であり、その手法はいろいろあります。引用はその一つです。そもそもモンゴメリが多数引用しているシェイクスピアのほとんどの戯曲には、先人が書いたタネ本や詩、歴史書があるわけですね。それをもとにシェイクスピアは数々の名作を書いた。
過去から蓄積された文学の層がベースにあり、その上に作家の独自性で個性を光らせる。文学作品の本来のありかただと思います。
『アン』の魅力(1)文学から文学を作る
以上を踏まえて『アン』という小説の魅力を整理してみたいと思います。まず「文学から文学を作る」というモンゴメリのやり方が『アン』という小説の潜在的な、隠れた魅力になっているのだと思います。
アンは「ある本で読んだけれど」と前置きして、本からの引用を言ったりします。読者はその本が何か分からないけれど、アンは知っている。また引用符や段落分けで「引用だとわかるようになっている箇所」があります。作者は元の小説や詩を知っているけれど、読者は知らない。
アンやモンゴメリは知っているけれど、私は知らない。これは読者にとっての「謎」として残ることになります。
さらに『アン』の文章には、引用とは分からないが、ちょっと異質だな、引っかかるな、と思える箇所が随所にあるのです。前回の No.77「赤毛のアン(1)」で紹介した「かたつむりとは似ても似つかぬ軽快な足どりで」のたぐいです。読者はもちろんこれがシェイクスピアのパロディだとは分からない。しかしここでなぜ「かたつむり」が出てくるのか、かすかな「謎」です。
もちろん読者はそんなことをいちいち気にかけることなく読み進みます。しかし次々と現れる「かすかな謎」は、読者に潜在意識として残ると思います。『アン』には謎めいたところがあるという無意識の思いが残る。これが『アン』という物語を魅力的にし、読者を「引き込む」要素になっているのだと思います。
登場人物の心理や物語の進行などのすべてが理路整然と解明できるより、ところどころに「謎」や「不思議さ」や「不可解さ」がある。そういった小説のほうが魅力的なのです。それは実社会や自然界に人間が説明できないことが多々あるのと相似型です。

| ||
| (カナダ:Prince Edward Island のホームページより) | ||
『アン』の魅力(2)美しい自然と四季の描写
『アン』の潜在的な魅力となっている文学作品からの引用を離れて、ここからは『アン』の直接的な魅力についてです。
『アン』の大きな魅力は、プリンス・エドワード島の美しい自然と四季の描写でしょう。前回の No.77「赤毛のアン(1)」で紹介したように、シェイクスピアの「お気に召すまま」が引用されている第24章「ステイシー先生と教え子たちの演芸会」の冒頭は、島の秋の情景描写で始まりました。そのちょうど1年前の秋は、第16章「お茶会、悲劇に終わる」の冒頭にあります。
|
日本人は四季の変化を愛でる国民だということが言われていて、それはその通りだと思いますが、根本のところにあるのは日本が四季の変化に富む自然風土の中にあることです。風土が人間の意識を作る。そしてプリンス・エドワード島も四季の変化の土地なのです。
上の引用でモンゴメリは秋の紅葉(カエデ、山桜)の美しさを描写しています。日本では一般に桜は「花」が注目されます。『アン』でも桜の花の描写はいろいろあって、たとえばアンがはじめてグリーン・ゲイブルズに来て一夜を過ごし、翌朝まず目にするのは窓辺の満開の桜です(第4章「グリーン・ゲイブルズの朝」)。しかし、上の引用の中でモンゴメリが描いた山桜の葉の紅葉(濃い赤と青銅色の綾をなす美しい色合い)は普通、日本人があまり注目しない点でしょう。そう言えばカエデも紅葉だけでなく、春にカエデの樹々が真っ赤な芽をふくという描写があります(第20章の冒頭)。このあたりがモンゴメリの細やかなところです。
|
|
|||||
|
これは写真ではなく作者が描いた絵である。プリンス・エドワード島の山桜が日本の桜のどれに近いかは分からないが、モンゴメリの描写した「濃い赤と青銅色の綾をなす美しい色合い」はこのような感じだと想像できる。
| ||||||
『アン』の魅力(3)アンの個性
『アン』の最大の魅力はアンの個性です。つまり、アンという少女そのものの魅力です。それは読者の誰しもが感じることでしょう。
まずアンは大変なおしゃべりで、マリラがあきれるぐらいの饒舌家です。自分の思いをしゃべらせたら止まらなくなる。
彼女は本が好きで、特に泣かせるストーリーや詩が大好きです。本からの知識という意味では博識で、暗記している詩もあります。詩の暗誦も得意です。暗誦が得意だからでしょうか、時に文語調でしゃべったりします。大げさな言い方や芝居がかった言葉使いが得意で「私の人生は終わったわ」「我が生涯最大の悲劇的失望」「私の生涯は悲しみの黒雲でおおわれるでしょう」などの言い方をします。「私の人生の(生涯の)・・・」というのはアンの口癖に近い。
本が好きなアンはロマンチストで、空想にふけるのが大好きです。自分で物語を作るのも好きで、特に悲劇のヒロインを演じたり、自分をその主人公になぞらえたりします。妖精も大好きです。
その一方で懐疑主義者の面もあり、常識にとらわれないリアリストでもある。「見た目より心」という常識的な教えに対しても「そんなこと信じられない」という思いをもっています。前回の No.77「赤毛のアン(1)」で紹介した「薔薇はどういう名前であっても甘く香る」というジュリエットのせりふについても「そんなことはない」と言っていますね。
アンはかなり興奮しやすいたちです。すぐ頭に血がのぼる。教室で赤毛をからかったギルバートに歩み寄り、彼の頭で石板を叩き割るなどはその典型でしょう。
また彼女なりのプライドも持っています。赤毛をからかわれた事件もそうですが、クラスメートに挑発されて屋根を歩き、すべり落ちて骨折してしまうのも彼女のプライドに端を発しています。
骨折事件にみられるようにアンには失敗が多い。彼女は非常にそそっかしい面があります。『アン』という物語はアンの失敗談続きです。彼女は基本的に活動的でエネルギッシュですが、それに思考が追いつかないときに失敗になる。
料理は好きではない、と自ら言っています。パッチワークも好きではない。決められた手順の繰り返しを好まないようです。
しかし彼女はひたむきで向上心が高く、努力家です。何かに打ち込む時は徹底的にやる。特に勉強です。幾何が大の苦手ですが、なんとか克服してしまう。クィーン学院ではトップの成績で大学の奨学金を手にします。
アンは率直に感情を表すタイプで、変な気取りがありません。喜んでも悲しんでも、すぐに涙を流します。しかし、あとくされがない爽やかな性格です。だけど、ちょっと風変わりなところもある。
前回の No.77「赤毛のアン(1)」で紹介した第31章「小川と河の出会うところ」を境目に、おしゃべりや、そそっかしいところは陰をひそめますが、アンの基本的な性格は変わりません。
まとめると、アンには「女の子はこうあるべきという古い価値観から逸脱している」ところがあります。さらに「自分は自分だという意志の強さ」がある。こういったアンという少女像そのものが、この本の最大の魅力でしょう。

| ||
| (カナダ:Prince Edward Island のホームページより) | ||
アンとセーラの共通点
「自分は自分だという意志の強さ」について思い出すことがあります。No.40「小公女」で紹介したバーネット作『小公女』の主人公、セーラとアンの共通点です。
一見、セーラとアンの共通点は全く無いように思えます。セーラは何不自由なく育った資産家のお嬢様であり、王女のような気品とたたずまいの少女です。孤児でおしゃべりでそそっかしいアンとは全く違う。
しかし2つの点でセーラとアンは似ています。一つは2人とも空想が大好きだということです。そしてもう一つが「自分は自分だという意志の強さ」です。No.40「小公女」で紹介したように、物語の最後の方でセーラは辛かった小間使いの頃を振り返り、つぎのように言います。
I tried not to be anything else.
「私は、ほかのものにはならないようにしていたんです」というような意味ですが、実はこれと同じ主旨の発言をアンがしているのです。
第33章「ホテルでの演芸会」で、アンは島のホテルで開催されたチャリティー演芸会で詩を朗読します。観客は島の名士やホテルの滞在客のアメリカ人(ということは富裕層)です。朗読は大成功に終わるのですが、終わったあとにアンのクラスメートは語ります。ダイヤモンドをつけた服に着飾ったお金持ちたちがうらやましいと・・・・・・。これに対してアンは「でも私は、自分以外の誰にもなりたくないわ。たとえダイヤモンドには、一生、慰められることはなくても」と答えます。
アンの言った「自分以外の誰にもなりたくないわ」のところは、原文では
I don't want to be anyone but myself.
です。これはセーラの発言にそっくりです。ひょっとしたらモンゴメリは『小公女』を踏まえているのかもしれません。『小公女』(1888)は『アン』の20年前に出版されています。ありうるかもと思います。
というのも、余談になりますが、明らかにオルコットの『若草物語』(1868)を踏まえたアンの発言があるからです。髪を染めそこなったアンがマリラに髪を短く切られる場面で
「本に出てくる女の子は、熱病や気高い目的のために髪を切るというのに、私もそんな理由で髪を失うなら、半分も気にならないけど、変てこな色に染めたから切るなんて、何の慰めにもならないわ。」 |
と言っています。この「本に出てくる女の子」とは『若草物語』の4人姉妹の次女のジョーのことですね(松本さんも指摘しています)。ジョーは父が南北戦争の戦場で病に倒れたとき、母が看病に現地に行く旅費の足しにと髪を切って売ります。
それはともかく『小公女』の作者・バーネットもモンゴメリも、人間の価値に対する似たような考えを持っているように見えます。「自分は自分だ」と言い切れることが最大の価値だという人間観。作者のそういう考えがにじみ出ているとことも『アン』の魅力なのだと思います。

| ||
| (カナダ:Prince Edward Island のホームページより) | ||
「連続テレビ小説」とアン
モンゴメリが描き出したアンという少女が大変に魅力的なため、アンは小説の主人公という範囲を遙かに越えて「物語の主人公の一つの原型」というポジションになっている、というのが私の考えです。
NHKの朝の「連続テレビ小説」というシリーズがあります。いわゆる「朝ドラ」ないしは「連ドラ」です。この中に、戦前・戦後を舞台にし、以下のような女性の主人公を描いたドラマが何回かありました。
| ・ | そそっかしく、失敗が多い。誤解されたりもする。 | |
| ・ | しかし明るくて、ひたむきである。 | |
| ・ | 感情の起伏が大きいが、落ち込んでも回復がはやい。 | |
| ・ | 全体的には、人から好かれるさわやかな性格である。 | |
| ・ | 家族や郷土に対する愛情が強い。それを失わない。 | |
| ・ | 努力する時には徹底的に努力する。 | |
| ・ | 前向きに生きて、人生の幸福をつかみとる。 |
そういった女性です。これって、まさにアンなのですね。NHKの「朝ドラ」を書くまでになった脚本家は、小さいころから大の本好きで通っていたはずです。特に女性の脚本家は少女時代にまず間違いなく『アン』を読んでいるでしょう。意識するしないにかかわらず、脚本家にとってアンが「原型」となって主人公の性格が造られる。そういうケースは多いのではないでしょうか。
アンは、夏目漱石の「坊っちゃん」(1906)のように、日本人にとっての「物語の主人公の原型」になっているのだと思います。そういう小説はそんなにはない。モンゴメリの造形した「アン」の影響は大きいと思います。
電子書籍の威力
もう一度、初めに戻ります。そもそも、前回から続くこの文章の発端は No.61「電子書籍と本の進化」で注釈が重要な本の例として『赤毛のアン』を取り上げたことでした。そして、松本侑子・訳『赤毛のアン』を取り出してみて改めて思うのは電子書籍の威力です。
松本さんの引用調査は、書籍の電子化がなければ絶対に出来なかったことは確かです。もちろん電子化されている書籍は一部なので、松本さんも欧米の図書館を丹念にまわり、足でかせいで調査をしている。
しかし、たとえばシェイクスピアの全作品の全文をCD-ROM化したものがなければ判明しなかった引用もいろいろある。モンゴメリも「まさか分からないだろう」と思って引用した部分もあるのではと思います。それが判明する。加えてインターネットの発達です。有名作家の著作権が切れた書物は、自宅で居ながらにして閲覧できるようになった。これも大きい。
300個の注釈がついた『赤毛のアン』の日本語訳は、電子書籍のもたらすインパクトのごく一部の、たった一つの例に過ぎません。電子書籍(とインターネット)が人類の文化史の大きな転換点になるだろう、ということを改めて予感しました。
No.77 - 赤毛のアン(1)文学 [本]
赤毛のアン
No.61「電子書籍と本の進化」で、注釈が重要な本の例として『赤毛のアン』(ルーシー・モード・モンゴメリ著。1908)を取り上げました。この本が英米文学や聖書からの引用に満ちているからです。
また No.76「タイトルの誤訳」でも『赤毛のアン』のオリジナルの題名が「グリーン・ゲイブルズのアン」であることに加えて、文学からの引用について書きました。この本は「大人のための本でもある」という主旨です。
今回はこの小説の魅力を書いてみたいと思います。とっかかりは、この本に盛り込まれた英米文学からの引用です。前にも書きましたが、英米文学や聖書からの引用を全く意識しなくても『赤毛のアン』を読むには支障がないし、十分に魅力的で面白い小説です。しかし実は過去の文学からの引用が『赤毛のアン』の隠された魅力のもとになっていると思うのです。
以降、原則として題名を『アン』と略記します。
松本侑子・訳『赤毛のアン』
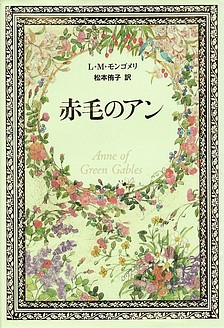
| |||
|
L.M.モンゴメリ作。松本侑子訳 「赤毛のアン」(集英社。1993) | |||
松本さんはこの本を文庫化するときに訳文を見直し、新たに判明した引用を含めて注釈を充実させました。松本侑子・訳『赤毛のアン』(2000年。集英社文庫)には、約300の注釈がつけられています。
さらに松本さんは、引用された英米文学とモンゴメリの引用意図を解説した『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』(2001年。集英社)を出版しました。題には「シェイクスピア」とありますが、シェイクスピアを含む英米文学からの引用(聖書を除く)を解説したものです。
ちなみに、松本さんの本の「訳者あとがき」に次のような話が書かれています。
|
ルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』(1865)は、言葉遊びとパロディに満ち溢れていて、この本を注釈なしで読んでも面白さは半減してしまいます。さすがですね、文豪、マーク・トウェインは。『アン』に文学からの引用とパロディが数々あることにすぐに気付いたのでしょう。
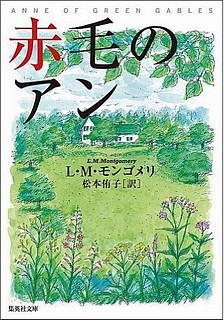
|
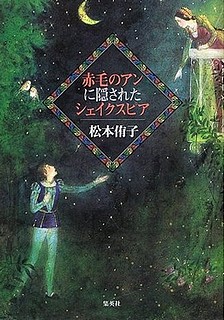
|
|
L.M.モンゴメリ作。松本侑子訳 「赤毛のアン」(集英社文庫。2000) |
松本侑子「赤毛のアンに隠され たシェイクスピア」(集英社。2001) |
以降は松本さんの3つの本の内容に従って、まず『アン』に含まれる引用の例を紹介したいと思います。引用の数は多数です。その中から数個をピックアップします。
英米文学からの引用の例(1)
小説の最初の方で、アンは孤児院からグリーン・ゲイブルズのカスバート家にやってきますが、実はカスバート家は「男の子を」という要望を出していたのに、手違いでアンが来てしまったのです。アンは孤児院に返されることになり、マリラ・カスバートはアンを馬車に乗せて出発します。その道すがら、アンが自分の生い立ちをマリラに語りる場面です。アンは死んだ両親のことも話します。
(以下、引用中のアンダーラインは原文にはありません。)
|
アンは「薔薇はたとえどんな名前で呼ばれても甘く香る」という文言を「本で読んだ」と言っています。ではその本とは何でしょうか。もちろん小説の中には書かれていません。
これはシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』なのです。キャピュレット家のジュリエットは、恋におちたロミオが、敵同士として憎みあってきたモンタギュー家だと知って嘆き悲しみます。そしてキャピュレット家のバルコニーでロミオへの想いを語ります。それを実はロミオが聞いているという、ドラマの最初の方のヤマ場というか劇的な場面です。ジュリエットのせりふは「おお、ロミオ、ロミオ。どうしてあなたはロミオ?」で始まるのですが(この部分は非常に有名)、アンが引用した文言はその後に出てきます。
|
引用の部分を原文で対比してみると、
| シェイクスピア |
That which we call a rose by any other name would smell as sweet
| モンゴメリ |
I read in a book once that a rose by any other name would smell a sweet
です。アンはドラマチックな悲劇が大好きで、ロマンチックなシーンも大好きです。『ロミオとジュリエット』という悲劇の中のジュリエットのこの告白は、いかにもアンが好みそうです。
この引用部分はアメリカのマクミラン社の「引用句辞典」にも載っている有名な句のようです(従ってアンが読んだ本がこの句を引用した本だという可能性はある)。文学好きな人の中にはアンが言っている本が『ロミオとジュリエット』だと分かる人もいるでしょう。だがそういう人ばかりではなく、特に少年少女ではそうでしょう。『アン』を読む多くの人はアンの言っている本とは何か、そのかすかな疑問を残しつつ読み進むと思います。
この部分は、出典は分からないまでも引用だと分かるように書いてあります。また『アン』の中には「引用符でくくってある表現」や「段落を分け、字下げをしてある表現」があり、引用したことを明確にしている部分が多々あるのです。
英米文学からの引用の例(2)
では次のような表現はどうでしょうか。
第23章「アン、名誉をかけた事件で憂き目にあう」で、アンは屋根から落ちて足首を骨折してしまいます。そして7週間のあいだ、自宅で療養します。10月、アンはようやく学校に戻れるようになります。第24章「ステイシー先生と教え子たちの演芸会」の冒頭は、親友のダイアナと通学できるようになったアンの様子から始まります。
|
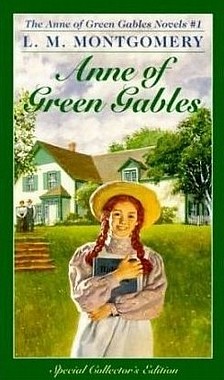
| |||
|
(Puffin Books 1994)
| |||
しかし引用した文章には、よく読むと引っかかるところがあります。それは学校に向かうアンとダイアナの様子を「かたつむりとは似ても似つかぬ軽快な足どりで」と形容していることです。これはちょっと変です。
普通、こういう時の描写に動物を持ち出すなら、たとえば「野ウサギのような軽快な足どりで」というようにするはずです。しかしモンゴメリはわざわざ軽快とは正反対の「かたつむり」を持ち出し、それと「似ても似つかぬ」とすることでアンとダイアナがいそいそと学校に向かう姿を表現している。
これはシェイクスピアの『お気に召すまま』にある表現のパロディなのです。『お気に召すまま』の中で、弟に追放された前公爵(老公爵)の家臣であるジェークイズのせりふにでてきます。ジェークイズは世間を冷ややかに見る皮肉屋で厭世家です。
|
引用の部分を原文で対比してみると
| シェイクスピア |
creeping like snail unwillingly to school
| モンゴメリ |
tripping, unlike snails, swiftly and willingly to school
です。モンゴメリはアンとダイアナが朝日の中を学校へ通う描写を考えたときに、直感的にシェイクスピアの「輝く朝日を顔に受け」が頭に浮かんだのです。そして、シェイクスピアの「creeping like snail unwillingly」を拝借して「tripping unlike snails willingly」とシャレた。引用句辞典に載っているわけでもなく、さして有名でもない語句やシーンが頭に浮かぶ・・・・・・。モンゴメリはシェイクスピアをそうとう読み込んでいる証拠だと考えられます。
この部分は、引用だとかパロディだとか分かるようには書いてありません。そしてこの箇所だけでなく『アン』の中には、引用だとは分からないが、よく読めばこれは引用なのではと思える箇所が実に多いのです。

| ||
| (カナダ:Prince Edward Island のホームページより) | ||
英米文学からの引用の例(3)
シェイクスピアから離れて、アメリカ文学からの引用です。
『アン』の第31章は「小川と河の出会うところ(Where the Brook and River Meets)」と題されています。アンは既にクィーン学院を受験することが決まっていて、夏休みが過ぎ、新学期になってからは受験勉強に邁進し、冬から春へと季節が過ぎていきます。そこまでを書いた章です。
不思議なのは「小川と河の出会うところ」というタイトルです。『アン』の目次をざっと眺めてみれば一目瞭然なのですが(下表)、普通『アン』の全38章のタイトルはその章の内容を具体的に表す名前がついています。題名を見ただけで章の内容が推測できるものがほとんどだし、推測できないまでも中身を読めば題名の意味が一発で分かります(第28章「不運な百合の乙女」、第36章「栄光と夢」、第38章「道の曲がり角」など)。
ところが第31章だけは違います。この章には小川も河も出てきません。もちろん「出会うところ」も出てこない。この章を読んでも、なぜ「小川と河の出会うところ」なのか分からないのです。ということは、小川(brook)や河(river)は何かの象徴だと考えられます。第31章に含まれる何かの・・・・・・。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本さんの注釈によると、第31章の題名はアメリカの詩人、ロングフェローの『乙女』という詩からとられています。
|
松本さんは自身のホームぺージでこの詩の全文を公開しています(モンゴメリ・デジタル・ライブラリ)。それによると、引用の所とその直後の原文は、
Where the brook and river meet,
Womanhood an childhood fleet !
です。
これで第31章の題名の意味が明らかになりました。小川(brook)とは「子ども」の、河(river)とは「女」の象徴なのです。原文は womanhood / childhood なので、松本さんの訳のように「女(子ども)らしさ」でもよいし、「女(子ども)であることのゆえん、特性」と考えてもよいでしょう。
第31章はアンが「子ども」と「女」の境にいること、ないしはアンが「子ども」から「女」に変わっていくことを示しています。第31章で印象的なのはアンの背丈が急速に伸びたという記述です。アンの身長はマリラを追い越してしまいます。そして松本さんは第30章と第31章の次の記述に注目しています。
|
|
松本さんは、ロングフェローの『乙女』の詩と、第30章の「この夏は、少女として過ごす最後の夏かもしれないもの。」というアンの発言、そして第31章の「アンが変わったのは体だけではなかった。歴然とした変化が、ほかにもあった。」という記述の三つを総合して「アンは第31章で初潮を迎えたことが暗示されているのでは」と推測しています。第31章でアンは14歳です。そしてアンには少なくとも3つの歴然とした変化があったと読めます。一つは身長が急速に伸びたことです。二つ目は口数が少なくなったことで、モンゴメリが書いた「歴然とした変化」はここまでです。それでは3つ目は・・・・・・。
これは極めて妥当な推測のように思えます。モンゴメリは第31章のタイトルだけを特別なやりかたでつけています。大多数の読者は知らないロングフェローの詩を引用し、それも第31章を象徴的に表す部分を引用している。そして小川(brook)と河(river)に意味を込めた。こうまでして題をつけるからには、この章に隠された意味があると考えるのが自然です。その隠された意味が松本さんの推測どおりだったとしても意外ではない。
『アン』は、一人の少女の11歳から16歳までの物語です。モンゴメリは、特別なやりかたでタイトルをつけた第31章で、11歳から16歳までの少女に起こる最も特別なことを書いた。いや、最も特別なことを書かなかった。ただ、章の題名だけでひそかに暗示した・・・・・・。ありうることだと思います。

| ||
| (カナダ:Prince Edward Island のホームページより) | ||
以上に紹介したシェイクスピアの2つの戯曲とロングフェローの詩からの引用の例は、『アン』における引用の極く一部です。松本さんの『赤毛のアンにかくされたシェイクスピア』には、シェイクスピアの8作品、それに加えて英米の作家の30作品以上からの引用が紹介されています。アーサー王伝説を踏まえた第28章「不運な百合の乙女」に至っては、章全体が英国の詩人・テニスンの『ランスロットとエレーン』のストーリー展開にそって進み、詩からの引用も多数あることが明らかにされています。
モンゴメリが引用した作家は、文学史上に名を残した人もいます。シェイクスピアをはじめ、テニスン、ディケンズ、ルイス・キャロル、ワーズワース、バイロン、ロングフェローなどです。しかしそれはむしろ少数で、多くはモンゴメリと同時代に近い作家であり、現代では英米でさえ読む人が(ほとんど)いない作家です。
このような作家の作品を引用するモンゴメリの書き方は、上に紹介したシェイクスピアからの引用でも分かるように、
| ◆ | 引用だと分かるようにかいてある箇所 | |
| ◆ | 引用だとはすぐには分からないが、よく読めば引用ではないかと思える部分 |
の二つに分かれます。そして引用だとはすぐには分からない方が圧倒的に多い。松本さんも「引用ではないかと思われるところ」をリストアップし、丹念に文献をあたり、また本国・カナダの研究者の「発見」も総合して『アン』の注釈を書いたわけです。
だとすると、松本さんの本には指摘されていない引用がまだあると推測するのが自然です。さきほど書いたようにモンゴメリは「現代ではほとんど知られていない作家の作品」から多数を引用しているので「疑わしい」わけです。
たとえば次のような箇所はどうでしょうか。第15章の冒頭です。
|
引用はどこにもないようです。少なくとも松本さんの本には書いていない。しかしちょっと引っかかるのですね。「まだ生まれていない人は、今日という日を逸してしまうから気の毒」という言い方で、今日の日の素晴らしさを表現するアンの発言が・・・・・・。こういうモノの言い方は、11歳の子どもにはちょっとそぐわない感じがします。
確かに、アンは「大袈裟な言い方」が大好きで、たとえば「我が生涯最大の悲劇的失望(the most tragical disapointment of my life)」などと言っています。子どもの発言としてはそぐわない感じですが、英語でしゃべると単に大袈裟なだけなのでしょう。
しかし上に引用した所は大袈裟という以上に「技巧的な言い方」です。何だか演劇での俳優のせりふ、言い回しのような感じがする。これは何かの引用か、引用ではないにしても何かの文学作品を踏まえているのではないでしょうか。全くの推測ですが・・・・・・。違うかもしれません。しかし何となく「引っかかる」。
松本さんやカナダの研究者の指摘を越えて、こういった箇所がまだまだあるのが『アン』という小説です。そもそもモンゴメリが引用だと明示している箇所で出典が不明なところさえあるのです。松本さんの本には「引用出典不明」と書いてあります。
隠された引用や過去の文学作品を踏まえた表現・・・・・・。それが読者からすると何となく「引っかかる」。それらはかすかな「謎」として読む人の脳裏に残り、それがまたこの小説の魅力ともなっていると思うのです。
(次回に続く)
No.70 - 自己と非自己の科学(2) [本]
前回の、No.69「自己と非自己の科学(1)」に引き続き、故・多田富雄氏の2つの著作が描く免疫システムの紹介です。ここからは、私自身が多田氏の本を読んで強く印象に残った点、ないしは考えた点です。
免疫システムの特徴
多田氏の2冊の著作が描く免疫システムを概観すると、それは幾つかの際だった特徴をもっていることに気づきます。免疫システムの特徴をキーワードで表すと以下のようになると思います。
免疫は、刻々変わる「自己」と「非自己」に対応してシステムのありようを変え、再組織化していきます。この「自己組織化」は、変化する環境に対応して「困難な」目標を達成するべく運命づけられたシステムの必然なのでしょう。
前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」の中の「免疫のプロセス」で、多田氏の本からそのまま引用してB細胞とT細胞が絡む免疫の過程を紹介しました。このプロセスは、かなり複雑でまわりくどく、また冗長だと感じられます。もっとシンプルにできないのか。
免疫学の歴史上有名な「クローン選択説」があります。オーストラリアのウイルス学者・バーネットが1957年代に出した免疫のしくみを説明する学説で、現代免疫学の根幹をなす重要な学説です。それをB細胞を念頭において模試的に描いたのが次の図です。
図で左端のA・B・C・D・EはB細胞です。B細胞はそれぞれ抗原と特異的に反応する抗体を持っていて、それは細胞ごとに違う。ある抗原が図の「B細胞・C」の抗体と反応すると「B細胞・C」は分裂をはじめ、同じ遺伝的性質の子孫(=クローン)を増やしていく。それは「B細胞・C」のもつ抗体の大量生産につながり、抗原は駆除される。しかし一部のB細胞は組織内に長く残り、それが記憶細胞となって二次免疫反応を起こす・・・・・・。
バーネットが「クローン選択説」を出したときにはT細胞もB細胞も分かっていませんでした。しかし免疫の仕組みの基本的なところを見事に言い当てている。もうこの図で十分だという気がします。
しかし実際の免疫の仕組みはこのようにシンプルではありません。もっと複雑で冗長です。それは「免疫のプロセス」で引用したように、
というプロセスをたどります(キラーT細胞は省略)。「B細胞の抗体が抗原と反応しただけでB細胞が分裂を開始し抗体が大量生産される、ということはない」のです。なぜこんなにまわりくどくて冗長なのか。
おそらく上図のようなシンプルな仕組みは「あぶない」のだと思います。もし、自己のタンパク質と反応する抗体を持つB細胞があるとすると、その抗体が大量生産され、自己の破壊につながる。免疫の仕組みの冗長さは、それなりの理由があると考えられます。
抗原を特異的に認識したり無力化するのは、T細胞抗原受容体(TCR)と免疫グロブリン(Ig)でした。そして、無限のバリエーションがある抗原を「特異的」に認識する仕組みは、まず遺伝子のランダムな組み替えで予期しえない TCR や Ig が作られ(利根川博士の発見)、そこから自己と反応するものが排除されるというプロセスでした。
免疫システムの根幹のところには、この「ランダム性」があります。非常に無駄が多い仕組みに見えますが、不測の事態(抗原の進入)の備えるにはこれしかないのでしょう。
B細胞が作り出す抗体(免疫グロブリン。Ig)は、抗原を直接に認識します。しかし抗体の大量生産のトリガーを引くのはヘルパーT細胞であり、ヘルパーT細胞が認識するのは、MHCに提示された抗原の断片(9個のアミノ酸からなるペプチド)でした。
ここで誰しも思うのは「わずか9個のアミノ酸で抗原が確実に認識できるのだろうか」という疑問です。タンパク質はふつう数百のアミノ酸から成り、数千のアミノ酸で構成されるタンパク質も稀ではありません。9個で大丈夫なのか。
実際、多田氏の本には次の意味の記述があります(免疫の意味論)。
抗原のタンパク質断片でもMHCの溝に「提示」可能なものは少なく、かつそれが人間のタンパク質と異なっているとは限らない・・・・・・。免疫システムは、ある種の「偶然性」の上に成り立っていることになります。多田氏が書いているように、この免疫システムの「欠陥」をついてくる「非自己」もある。
しかし多くの場合はこれで免疫が成り立っています。つまり、抗原もMHCもT細胞も「数が圧倒的に多い」ということなのでしょう。個々の確率は少なくても、母数が多いと安定的に作動するということがあります。
前回、No.69「自己と非自己の科学(1)」の「免疫のプロセス」に出てきたインターロイキン6(IL-6)というサイトカインがあります。これはヘルパーT細胞が作りだし、B細胞がプラズマ細胞に分化するように誘導する重要なサイトカインでした。しかしIL-6には別の作用もあるのです。多田氏の本によると、たとえば
◆キラーT細胞の分化を促す
◆マクロファージの働きを高める
などです。このあたりは免疫細胞に関係した作用であって、抗原を排除するのに役立つのだなと納得がいきます。ところが、IL-6は免疫とは直接関係のない作用もあるのです。つまり
◆神経細胞の成長を促す
◆骨を破壊する破骨細胞を作り出す
◆造血幹細胞や血小板を増やす
などです。同じ分子(タンパク質)が、こういった多種の作用を兼ねていいのかと思うのですが、それだけではありません。IL-6を作るのはヘルパーT細胞だけでなく、
◆マクロファージ
◆B細胞
◆皮膚の上皮細胞
◆血管の内皮細胞
でも作られる、とあるのですね。
B細胞をプラズマ細胞に分化させるという、免疫システムにとっては決定的に重要なサイトカインが、多数の別の「意味」に使われ、しかも各種の細胞がそのサイトカインを出す・・・・・・。IL-6というサイトカインはきわめて「多義性」があることになります。そしてこの多義性は IL-6 だけではないのです。
こんなことで免疫が成立するのかと心配になりますが、一応成立している。こういった「多義性」を含みつつ複雑な目的を実現するところに、自己組織化がポイントである免疫システムの特徴があるように感じます。
免疫システムは「危うさ」をもったシステムです。たとえば「胎児を母親の免疫システムから守る仕組み」です。前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」で、多田氏の本に従って、
という意味のことを書きました。一見これで良いようなのですが、これは非常に「あぶない」仕掛けです。つまり人間には「MHCの発現を抑制する」遺伝子があり、胎盤だけでその遺伝子が働いているというようなことだと想像します。そうだとしたら、もし、がん細胞がその遺伝子を「利用」したらどうなるのか。免疫システムはがん細胞を攻撃できなくなります。事実、多田氏の本には「がん細胞は細胞のMHCを少なくしT細胞の監視からのがれる」という意味のことをが書かれているのです。
そもそもキラーT細胞は自己の細胞を殺す役割の免疫細胞です。もちろん殺すのは「細胞表面のクラス1・MHCに非自己(抗原)の断片を提示している自己の細胞」で、内部になんらかの異変が起きていると想定できる細胞です。ウイルスは自己に潜む非自己、ないしは自己に偽装した非自己なので、ウイルスの駆除までを目的とする免疫システムでは自己の細胞を殺す必要があるのは理解できます。
しかし免疫の仕組みには「偶然性」や「ランダム性」が内在しています。もし間違って本当の自己を提示している細胞を殺してしまったらどうなるのか。そういった反応性をもつキラーT細胞が「自己に反応する免疫細胞を抑制する仕組み(免疫的寛容)」を乗り越えて大増殖したらどうなるのか。免疫システムが自己を攻撃する事態が想像されます。
さらに想像すると、人間のDNAにある遺伝子は全部が活用されていわけでも何でもなく「眠っている」遺伝子がたくさんあることは生命科学の教えることです。その眠っている遺伝子が何かの拍子に発現し、通常では作られないタンパク質が細胞内で生産されるとどうなるのか。人間の免疫系はその細胞(自己)を攻撃することになります。
いろいろと心配の種が尽きない「危うさ」を内包しているのが免疫システムです。そして自己免疫病と総称される病気はまさにこの「危うさ」が現実のものとなった病気だと感じられます。
現代における難病のほとんどは「自己免疫病」です。たとえばバセドー病は甲状腺に反応する抗体ができる免疫反応で起こります。若年性糖尿病はインシュリンを生産する膵臓のβ細胞を自己の免疫系が破壊してしまうことで起こります。人間のほとんどの臓器・部位に対して、そこを攻撃してしまう自己免疫病があると言います。また体内の関節が炎症を起こし萎縮していくリウマチ性関節炎も自己免疫病です。付け加えますと、いわゆるアレルギーは抗原に対する免疫システムの過剰反応が原因です。それによって人間にとっては不要な、時には命にかかわりかねない炎症が起こる。
自己免疫病で最も破壊的なのはSLE(全身性エリテマトーデス)という難病で、これは自己のDNAに対する抗体ができてしまう病気なのです。DNAはすべての細胞にあるわけですから、免疫システムが「すべての自己」を攻撃する。攻撃されて破壊された細胞からはDNAが飛び出し(=抗原!!)、それがまた抗体の生産を促して、悪循環が際限なく続くことになります。
「自己免疫病」を典型とする免疫システムの「危うさ」は、非自己を排除するという極めて困難な目的の達成のために必然的に組み込まれてしまったものだと思いました。花粉症はその「ささやかな」例なのでしょう。
ここで言う「多様性」は、人間が個体ごとに違うという意味での多様性です。
免疫が発動するプロセスは、まず人それぞれに違うMHCが細胞表面にあり、そのMHCに抗原の断片が提示され、その「MHC・抗原断片の複合体」をT細胞が認識する、という過程でした。そこからロジカルに導かれる結論は、
ということです。特定の抗原を認識しやすい人とそうでない人がいる。インフルエンザが流行して学校が閉鎖になっても、まったく病気にならない子もいる。逆にワクチンを接種してもそれが利かずにインフルエンザにすぐかかってしまう子もいる。スギ花粉を吸い込むとアレルギー症状を起こす人もいれば、起こさない人もいる。抗原(病原体)に対する反応は人によって非常に違うわけです。
世界史をみると15世紀のヨーロッパではペストが大流行しました。人口の3分の1が死亡したと言います。3分の1が死亡するという事態は大パニックを起こしたでしょう。しかしペストが大流行しているさなかでケロッとしている人も多いわけです。当時は「細菌による伝染病」という概念は全くありません。死んだ患者と接触した人も多かったはずです。それでも3分の2は死ななかった。もし人口の9割が死んだとしたらヨーロッパ文明は崩壊したと思います。
現代のAIDSは根本的な治療方法がない恐ろしい感染症であり、いったんウイルスに感染すると発症を押さえる抗ウイルス薬を投与し続けるしかありません。しかしAIDSに対してさえ治療なしで元気な人がいます(日経サイエンス・2012年10月号『エイズを発症しない人々』)。免疫がどう作用するかは人によってものすごく違うわけです。
これは決して「抗体に対して強く反応するのがいい」のではありません。強く反応すると、自己に対しても強く反応する可能性が高く、アレルギーになったり自己免疫疾患を発病したりする。あくまで免疫の作用の「多様性」が大切なのです。そしてこの多様性こそ人間の集団が今まで生き延びてきた理由だと強く感じます。特定の病原菌に対して、全員が死ぬか全員がケロッしているかという集団は、早々に死滅してしまうでしょう。
免疫システムと社会
以上の、免疫システムの特徴としてまとめた
◆冗長性
◆多義性
◆ランダム性
◆偶然性
◆多様性
というポイントは「自己組織化」していくシステムの特徴であり、それは社会における複雑な組織体のありようとそっくりだと感じました。複雑な組織体とは、大企業、大都市、国家などです。それらは環境の変化に対しては自らを変え、再組織化をしていかないと生き延びられません。自己組織化するシステムは、同時に「危うさを内包するシステム」です。しかしそれ以外に組織体を永続させる原理はない。そう感じさせられました。
多田氏の2冊の本は2001年、ないしはそれ以前の本です。最近の10年で免疫学はさらに発展しました。その一つとして、人間と共生している細菌が免疫と関係していることが分かってきました。以下にそれを紹介します。
マイクロバイオーム:細菌叢
『エイズを発症しない人々』の記事が掲載されていた日経サイエンス・2012年10月号に『マイクロバイオーム』の特集記事が載っていました。マイクロバイオームとは、人間の皮膚や消化系に住み付いている細菌群の総体を言い、日本語では細菌叢(そう)です。これらの細菌の中には人間に役だっているものがあることは昔から知られていましたが、最近になって人間の免疫もこれらの共生細菌と関係していることが分かってきたのです。
東京大学・服部教授の文章に従って、その事情を紹介しますと以下のようです。まず服部教授は細菌の数の多さ語っています。
人体に住み付いている細菌は「常在菌」と言い、一時的に体内に進入して感染症を引き起こす「病原菌」とは区別されます。常在菌は病原性を示しません。
胎児の発育する子宮は無菌状態ですが、赤ちゃんが産道を通る時、最初の常在菌が皮膚に付着します。それ以降、生活環境の中にいる各種の細菌が体内に入ります。つまり常在菌は人間の誕生とともに体に生息をはじめ、一生をともにします。
そしてこの常在菌の中には「人間の免疫システムの一部として機能している」ものがあることが分かってきたのです。
J ・アッカーマンという米国のサイエンス・ライターが、バクテロイデス・フラジリス(フラジリス菌)について解説しています。その内容を要約すると以下のようです。この中の「制御性T細胞」は多田富雄氏の本に出てこないのですが、免疫反応を押さえる役割を持ったT細胞で、1995年に大阪大学の坂口志文教授が発見しました。近年研究が進んでいます。
あたりまえですが、人間の腸は異物に満ちています。そこは免疫システムの戦いにとっての「最前線」です。その最前線で、腸内細菌の出すサイトカイン相当の分子(PSA)が、結果として腸炎などの炎症をくい止め、免疫システムの過剰反応を抑制する役割を果たしているわけです。
記事によると、人間の常在菌の分布状況は人それぞれで違います。一卵性双生児であっても、生まれてからの生活によって常在菌は違う。免疫系は一人一人違っていて多様性があると前に書きましたが、人間と常在菌の共生を考えると人間だけを前提とするよりもっと多様性があるのです。
それと同時にフラジリス菌の例は、抗生物質の投与で(結果として)常在菌を殺してしまったり、必要以上に「清潔な環境」で生活をすることが「よくない結果」をもたらす可能性を示唆しています。我々人類は、何か間違ったことをやって来たのかもしれないのです。
人間は自己の細胞と細菌(常在菌)の共生系です。細菌の数は、自己の細胞の数の10倍以上です。そしてこの共生は単にギブ・アンド・テイクというレベルを越えています。フラジリス菌の例で言うと、フラジリス菌のPSA分子を作る遺伝子が、人間のゲノム(遺伝子の総体)を補っていると考えたほうがよい。
もちろんこれらの常在菌は免疫だけに役だっているのではありません。たとえば食物の消化です。
服部教授は、「ヒトは、ヒトゲノムとヒト常在菌叢ゲノムから成り立つ超有機体である」というノーベル賞学者(ジョシュア・レーダーバーグ。米国)の言葉を紹介していますが、まさにその通りです。前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」で、多田富雄氏の本に従って
と書きました。免疫とは「自己とは何か」を生物的に規定しているものです。そしてヒトは自分の細胞の数の10倍もある細菌と共存している。つまり生物学的には
なのです。その「拡大された自己」の本格的な研究はこれからです。そこから得られた新たな知見は、人間の生き方に新たな示唆をもたらしてくれるだろうと思います。
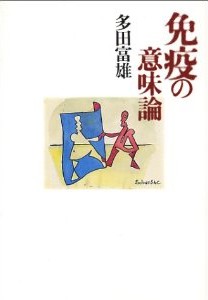
|
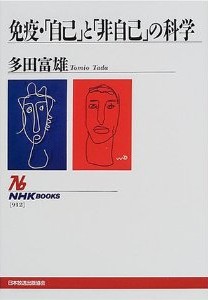
|
|
|
多田富雄 『免疫の意味論』 |
多田富雄 『免疫・自己と非自己の科学』 |
免疫システムの特徴
多田氏の2冊の著作が描く免疫システムを概観すると、それは幾つかの際だった特徴をもっていることに気づきます。免疫システムの特徴をキーワードで表すと以下のようになると思います。
| 自己組織化 |
免疫は、刻々変わる「自己」と「非自己」に対応してシステムのありようを変え、再組織化していきます。この「自己組織化」は、変化する環境に対応して「困難な」目標を達成するべく運命づけられたシステムの必然なのでしょう。
| 冗長性 |
前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」の中の「免疫のプロセス」で、多田氏の本からそのまま引用してB細胞とT細胞が絡む免疫の過程を紹介しました。このプロセスは、かなり複雑でまわりくどく、また冗長だと感じられます。もっとシンプルにできないのか。
免疫学の歴史上有名な「クローン選択説」があります。オーストラリアのウイルス学者・バーネットが1957年代に出した免疫のしくみを説明する学説で、現代免疫学の根幹をなす重要な学説です。それをB細胞を念頭において模試的に描いたのが次の図です。
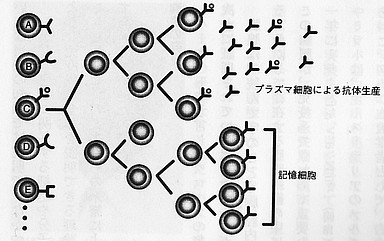
|
|
クローン選択説 (『免疫・自己と非自己の科学』より) |
図で左端のA・B・C・D・EはB細胞です。B細胞はそれぞれ抗原と特異的に反応する抗体を持っていて、それは細胞ごとに違う。ある抗原が図の「B細胞・C」の抗体と反応すると「B細胞・C」は分裂をはじめ、同じ遺伝的性質の子孫(=クローン)を増やしていく。それは「B細胞・C」のもつ抗体の大量生産につながり、抗原は駆除される。しかし一部のB細胞は組織内に長く残り、それが記憶細胞となって二次免疫反応を起こす・・・・・・。
バーネットが「クローン選択説」を出したときにはT細胞もB細胞も分かっていませんでした。しかし免疫の仕組みの基本的なところを見事に言い当てている。もうこの図で十分だという気がします。
しかし実際の免疫の仕組みはこのようにシンプルではありません。もっと複雑で冗長です。それは「免疫のプロセス」で引用したように、
| ① | B細胞による抗原の認識 | |
| ② | B細胞(APC)による抗原の取り込み | |
| ③ | ペプチドに分解した抗原をMHCに提示 | |
| ④ | T細胞による「抗原ペプチド・MHC複合体」の認識 | |
| ⑤ | T細胞の指令によるB細胞の増殖 | |
| ⑥ | T細胞の指令によるB細胞のプラズマ細胞への分化 | |
| ⑦ | プラズマ細胞による抗体の大量生成 |
というプロセスをたどります(キラーT細胞は省略)。「B細胞の抗体が抗原と反応しただけでB細胞が分裂を開始し抗体が大量生産される、ということはない」のです。なぜこんなにまわりくどくて冗長なのか。
おそらく上図のようなシンプルな仕組みは「あぶない」のだと思います。もし、自己のタンパク質と反応する抗体を持つB細胞があるとすると、その抗体が大量生産され、自己の破壊につながる。免疫の仕組みの冗長さは、それなりの理由があると考えられます。
| ランダム性 |
抗原を特異的に認識したり無力化するのは、T細胞抗原受容体(TCR)と免疫グロブリン(Ig)でした。そして、無限のバリエーションがある抗原を「特異的」に認識する仕組みは、まず遺伝子のランダムな組み替えで予期しえない TCR や Ig が作られ(利根川博士の発見)、そこから自己と反応するものが排除されるというプロセスでした。
免疫システムの根幹のところには、この「ランダム性」があります。非常に無駄が多い仕組みに見えますが、不測の事態(抗原の進入)の備えるにはこれしかないのでしょう。
| 偶然性 |
B細胞が作り出す抗体(免疫グロブリン。Ig)は、抗原を直接に認識します。しかし抗体の大量生産のトリガーを引くのはヘルパーT細胞であり、ヘルパーT細胞が認識するのは、MHCに提示された抗原の断片(9個のアミノ酸からなるペプチド)でした。
ここで誰しも思うのは「わずか9個のアミノ酸で抗原が確実に認識できるのだろうか」という疑問です。タンパク質はふつう数百のアミノ酸から成り、数千のアミノ酸で構成されるタンパク質も稀ではありません。9個で大丈夫なのか。
実際、多田氏の本には次の意味の記述があります(免疫の意味論)。
| ◆ |
自然界に存在するタンパク質を人工的に9個のアミノ酸からなるペプチドに分解しても、MHCの溝にうまく入り込むようなペプチドは著しく少ない。 | |
| ◆ |
立体構造も機能もお互いに全く無縁なタンパク質の間でも、しばしば共通のアミノ酸配列が見い出される。そういう部分が切り出されると、異なったタンパク質であるにもかかわらず同じ情報として認識されてしまう。 | |
| ◆ | どんなに人間にとって異物であっても、ペプチドまで分解されると人間の成分と区別できなくなる場合がある。マラリヤや住血吸虫に対して免疫が起こりにくい理由の一つがこれである。 |
抗原のタンパク質断片でもMHCの溝に「提示」可能なものは少なく、かつそれが人間のタンパク質と異なっているとは限らない・・・・・・。免疫システムは、ある種の「偶然性」の上に成り立っていることになります。多田氏が書いているように、この免疫システムの「欠陥」をついてくる「非自己」もある。
しかし多くの場合はこれで免疫が成り立っています。つまり、抗原もMHCもT細胞も「数が圧倒的に多い」ということなのでしょう。個々の確率は少なくても、母数が多いと安定的に作動するということがあります。
| 多義性 |
前回、No.69「自己と非自己の科学(1)」の「免疫のプロセス」に出てきたインターロイキン6(IL-6)というサイトカインがあります。これはヘルパーT細胞が作りだし、B細胞がプラズマ細胞に分化するように誘導する重要なサイトカインでした。しかしIL-6には別の作用もあるのです。多田氏の本によると、たとえば
◆キラーT細胞の分化を促す
◆マクロファージの働きを高める
などです。このあたりは免疫細胞に関係した作用であって、抗原を排除するのに役立つのだなと納得がいきます。ところが、IL-6は免疫とは直接関係のない作用もあるのです。つまり
◆神経細胞の成長を促す
◆骨を破壊する破骨細胞を作り出す
◆造血幹細胞や血小板を増やす
などです。同じ分子(タンパク質)が、こういった多種の作用を兼ねていいのかと思うのですが、それだけではありません。IL-6を作るのはヘルパーT細胞だけでなく、
◆マクロファージ
◆B細胞
◆皮膚の上皮細胞
◆血管の内皮細胞
でも作られる、とあるのですね。
B細胞をプラズマ細胞に分化させるという、免疫システムにとっては決定的に重要なサイトカインが、多数の別の「意味」に使われ、しかも各種の細胞がそのサイトカインを出す・・・・・・。IL-6というサイトカインはきわめて「多義性」があることになります。そしてこの多義性は IL-6 だけではないのです。
こんなことで免疫が成立するのかと心配になりますが、一応成立している。こういった「多義性」を含みつつ複雑な目的を実現するところに、自己組織化がポイントである免疫システムの特徴があるように感じます。
| 危うさを内包するシステム |
免疫システムは「危うさ」をもったシステムです。たとえば「胎児を母親の免疫システムから守る仕組み」です。前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」で、多田氏の本に従って、
| 胎児は母親にとって異物だが、母親の免疫システムに攻撃されないのは胎児が母親と繋がっている胎盤の細胞表面からMHCが消える仕組みがあるからだ |
という意味のことを書きました。一見これで良いようなのですが、これは非常に「あぶない」仕掛けです。つまり人間には「MHCの発現を抑制する」遺伝子があり、胎盤だけでその遺伝子が働いているというようなことだと想像します。そうだとしたら、もし、がん細胞がその遺伝子を「利用」したらどうなるのか。免疫システムはがん細胞を攻撃できなくなります。事実、多田氏の本には「がん細胞は細胞のMHCを少なくしT細胞の監視からのがれる」という意味のことをが書かれているのです。
そもそもキラーT細胞は自己の細胞を殺す役割の免疫細胞です。もちろん殺すのは「細胞表面のクラス1・MHCに非自己(抗原)の断片を提示している自己の細胞」で、内部になんらかの異変が起きていると想定できる細胞です。ウイルスは自己に潜む非自己、ないしは自己に偽装した非自己なので、ウイルスの駆除までを目的とする免疫システムでは自己の細胞を殺す必要があるのは理解できます。
しかし免疫の仕組みには「偶然性」や「ランダム性」が内在しています。もし間違って本当の自己を提示している細胞を殺してしまったらどうなるのか。そういった反応性をもつキラーT細胞が「自己に反応する免疫細胞を抑制する仕組み(免疫的寛容)」を乗り越えて大増殖したらどうなるのか。免疫システムが自己を攻撃する事態が想像されます。
さらに想像すると、人間のDNAにある遺伝子は全部が活用されていわけでも何でもなく「眠っている」遺伝子がたくさんあることは生命科学の教えることです。その眠っている遺伝子が何かの拍子に発現し、通常では作られないタンパク質が細胞内で生産されるとどうなるのか。人間の免疫系はその細胞(自己)を攻撃することになります。
いろいろと心配の種が尽きない「危うさ」を内包しているのが免疫システムです。そして自己免疫病と総称される病気はまさにこの「危うさ」が現実のものとなった病気だと感じられます。
現代における難病のほとんどは「自己免疫病」です。たとえばバセドー病は甲状腺に反応する抗体ができる免疫反応で起こります。若年性糖尿病はインシュリンを生産する膵臓のβ細胞を自己の免疫系が破壊してしまうことで起こります。人間のほとんどの臓器・部位に対して、そこを攻撃してしまう自己免疫病があると言います。また体内の関節が炎症を起こし萎縮していくリウマチ性関節炎も自己免疫病です。付け加えますと、いわゆるアレルギーは抗原に対する免疫システムの過剰反応が原因です。それによって人間にとっては不要な、時には命にかかわりかねない炎症が起こる。
自己免疫病で最も破壊的なのはSLE(全身性エリテマトーデス)という難病で、これは自己のDNAに対する抗体ができてしまう病気なのです。DNAはすべての細胞にあるわけですから、免疫システムが「すべての自己」を攻撃する。攻撃されて破壊された細胞からはDNAが飛び出し(=抗原!!)、それがまた抗体の生産を促して、悪循環が際限なく続くことになります。
「自己免疫病」を典型とする免疫システムの「危うさ」は、非自己を排除するという極めて困難な目的の達成のために必然的に組み込まれてしまったものだと思いました。花粉症はその「ささやかな」例なのでしょう。
| 多様性 |
ここで言う「多様性」は、人間が個体ごとに違うという意味での多様性です。
免疫が発動するプロセスは、まず人それぞれに違うMHCが細胞表面にあり、そのMHCに抗原の断片が提示され、その「MHC・抗原断片の複合体」をT細胞が認識する、という過程でした。そこからロジカルに導かれる結論は、
| 免疫作用は人それぞれに違っている |
ということです。特定の抗原を認識しやすい人とそうでない人がいる。インフルエンザが流行して学校が閉鎖になっても、まったく病気にならない子もいる。逆にワクチンを接種してもそれが利かずにインフルエンザにすぐかかってしまう子もいる。スギ花粉を吸い込むとアレルギー症状を起こす人もいれば、起こさない人もいる。抗原(病原体)に対する反応は人によって非常に違うわけです。
世界史をみると15世紀のヨーロッパではペストが大流行しました。人口の3分の1が死亡したと言います。3分の1が死亡するという事態は大パニックを起こしたでしょう。しかしペストが大流行しているさなかでケロッとしている人も多いわけです。当時は「細菌による伝染病」という概念は全くありません。死んだ患者と接触した人も多かったはずです。それでも3分の2は死ななかった。もし人口の9割が死んだとしたらヨーロッパ文明は崩壊したと思います。
現代のAIDSは根本的な治療方法がない恐ろしい感染症であり、いったんウイルスに感染すると発症を押さえる抗ウイルス薬を投与し続けるしかありません。しかしAIDSに対してさえ治療なしで元気な人がいます(日経サイエンス・2012年10月号『エイズを発症しない人々』)。免疫がどう作用するかは人によってものすごく違うわけです。
これは決して「抗体に対して強く反応するのがいい」のではありません。強く反応すると、自己に対しても強く反応する可能性が高く、アレルギーになったり自己免疫疾患を発病したりする。あくまで免疫の作用の「多様性」が大切なのです。そしてこの多様性こそ人間の集団が今まで生き延びてきた理由だと強く感じます。特定の病原菌に対して、全員が死ぬか全員がケロッしているかという集団は、早々に死滅してしまうでしょう。
免疫システムと社会
以上の、免疫システムの特徴としてまとめた
◆冗長性
◆多義性
◆ランダム性
◆偶然性
◆多様性
というポイントは「自己組織化」していくシステムの特徴であり、それは社会における複雑な組織体のありようとそっくりだと感じました。複雑な組織体とは、大企業、大都市、国家などです。それらは環境の変化に対しては自らを変え、再組織化をしていかないと生き延びられません。自己組織化するシステムは、同時に「危うさを内包するシステム」です。しかしそれ以外に組織体を永続させる原理はない。そう感じさせられました。
多田氏の2冊の本は2001年、ないしはそれ以前の本です。最近の10年で免疫学はさらに発展しました。その一つとして、人間と共生している細菌が免疫と関係していることが分かってきました。以下にそれを紹介します。
マイクロバイオーム:細菌叢
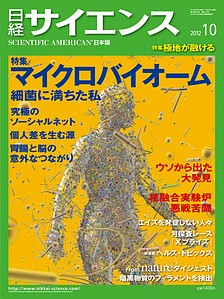
| |||
東京大学・服部教授の文章に従って、その事情を紹介しますと以下のようです。まず服部教授は細菌の数の多さ語っています。
|
人体に住み付いている細菌は「常在菌」と言い、一時的に体内に進入して感染症を引き起こす「病原菌」とは区別されます。常在菌は病原性を示しません。
胎児の発育する子宮は無菌状態ですが、赤ちゃんが産道を通る時、最初の常在菌が皮膚に付着します。それ以降、生活環境の中にいる各種の細菌が体内に入ります。つまり常在菌は人間の誕生とともに体に生息をはじめ、一生をともにします。
常在菌のすみかは、口腔、鼻腔、胃、小腸・大腸、皮膚、膣など全身に及ぶ。人体にはおおよそ 1015 個(1000兆個)の常在菌が生息し、この数はヒトの細胞数(約60兆個)の10倍以上になる。常在菌の種類は1000種前後と見積もられている。 |
そしてこの常在菌の中には「人間の免疫システムの一部として機能している」ものがあることが分かってきたのです。
2010年には、自己免疫疾患を抑制する制御性T細胞の誘導に関係するバクテロイデス・フラジリスが、2011年には同様にこの制御性細胞を誘導するクロストリジウム属が発見された。 |
J ・アッカーマンという米国のサイエンス・ライターが、バクテロイデス・フラジリス(フラジリス菌)について解説しています。その内容を要約すると以下のようです。この中の「制御性T細胞」は多田富雄氏の本に出てこないのですが、免疫反応を押さえる役割を持ったT細胞で、1995年に大阪大学の坂口志文教授が発見しました。近年研究が進んでいます。
| ◆ | 腸内にすむフラジリス菌は表面にポリサッカライドA(PSA)という多糖類の分子をもっている。 | |
| ◆ | 樹状細胞はPSAを取り込み、未分化のT細胞に提示する。 | |
| ◆ | 未分化のT細胞はPSAに刺激されて制御性T細胞になる。制御性T細胞は炎症を起こす免疫細胞の活動を抑制して炎症を押さえる。 | |
| ◆ | PSAを持たないフラジリス菌は免疫細胞から攻撃されて生き延びることはできないが、PSAをもっていると免疫系からは攻撃されない。 |
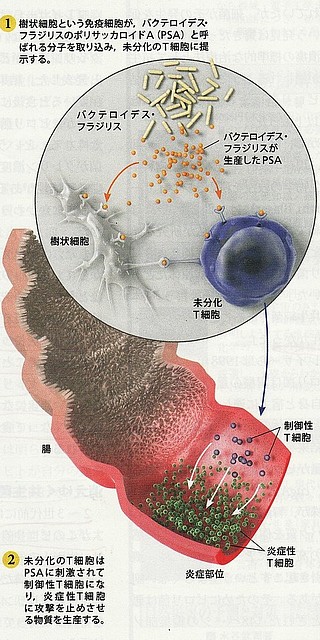
|
|
腸内細菌(フラジリス菌)が作り出す物質(PSA)がトリガーとなって 炎症反応が抑制される様子(「日経サイエンス」2012年10月号より引用) |
あたりまえですが、人間の腸は異物に満ちています。そこは免疫システムの戦いにとっての「最前線」です。その最前線で、腸内細菌の出すサイトカイン相当の分子(PSA)が、結果として腸炎などの炎症をくい止め、免疫システムの過剰反応を抑制する役割を果たしているわけです。
記事によると、人間の常在菌の分布状況は人それぞれで違います。一卵性双生児であっても、生まれてからの生活によって常在菌は違う。免疫系は一人一人違っていて多様性があると前に書きましたが、人間と常在菌の共生を考えると人間だけを前提とするよりもっと多様性があるのです。
それと同時にフラジリス菌の例は、抗生物質の投与で(結果として)常在菌を殺してしまったり、必要以上に「清潔な環境」で生活をすることが「よくない結果」をもたらす可能性を示唆しています。我々人類は、何か間違ったことをやって来たのかもしれないのです。
人間は自己の細胞と細菌(常在菌)の共生系です。細菌の数は、自己の細胞の数の10倍以上です。そしてこの共生は単にギブ・アンド・テイクというレベルを越えています。フラジリス菌の例で言うと、フラジリス菌のPSA分子を作る遺伝子が、人間のゲノム(遺伝子の総体)を補っていると考えたほうがよい。
|
もちろんこれらの常在菌は免疫だけに役だっているのではありません。たとえば食物の消化です。
有益な微生物の代表例は、バクテロイデス・テタイオタオミクロンだ。炭水化物を分解する能力が非常に優れていて、多くの植物性食品に含まれる大きな多糖類を、ブドウ糖などの小さくて単純で消化のしやすい糖類に分解できる。 |
服部教授は、「ヒトは、ヒトゲノムとヒト常在菌叢ゲノムから成り立つ超有機体である」というノーベル賞学者(ジョシュア・レーダーバーグ。米国)の言葉を紹介していますが、まさにその通りです。前回の No.69「自己と非自己の科学(1)」で、多田富雄氏の本に従って
| 免疫は自己と非自己(異物としての抗原)を認識し、非自己を排除することによって自己の統一性を保ち、生命を維持するしくみ |
と書きました。免疫とは「自己とは何か」を生物的に規定しているものです。そしてヒトは自分の細胞の数の10倍もある細菌と共存している。つまり生物学的には
| ヒトに常在している細菌は、自己の重要な一部 |
なのです。その「拡大された自己」の本格的な研究はこれからです。そこから得られた新たな知見は、人間の生き方に新たな示唆をもたらしてくれるだろうと思います。
No.69 - 自己と非自己の科学(1) [本]
理系学問からの思考
No.56「強い者は生き残れない」で、進化生物学者・吉村仁氏の同名の本(新潮選書 2009)の内容から、どういう生物が生き残ってきたかについての学問的知見を紹介しました。ここで以下のように書きました。
| ふつう人間や社会を研究するのは文学、哲学、心理学、社会学、政治学、経済学などの、いわゆる文化系学問だと見なされています。それは正しいのですが、理科系の学問、特に生命科学の分野、物理学、数学などから得られた知見が、人間の生き方や社会のありかたに示唆を与えることがいろいろあると思うのです。 |
いわゆる「理系学問」の一つの大きな目標は、宇宙や生物を含む広い意味での「自然」の原理や成り立ちを探究することです。従ってそこで得られた知見はあくまで自然に関するものですが、しかしそれが人間社会のありかたに対する示唆となる場合があるはずだ・・・・・・。そういう問題意識が『強い者は生き残れない』という本を紹介した理由でした。
全く同じ考えで、別の本の内容を紹介したいと思います。今回も生命化学の一分野ですが、免疫学に関するものです。
多田富雄氏の2つの著作
免疫学について私が過去に読んだ本のなかで印象的だったのは、免疫学者である故・多田富雄氏の、
| ◆ |
免疫の意味論(青土社 1993) | |
| ◆ |
免疫・「自己」と「非自己」の科学(NHKブックス 2001) |
という2つの著作です。
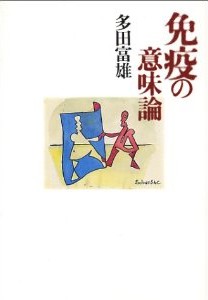
|
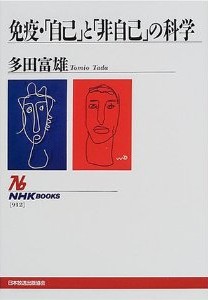
|
|
|
多田富雄 『免疫の意味論』 |
多田富雄 『免疫・自己と非自己の科学』 |
以下、この本の内容をもとに人間の免疫のメカニズムを概観し、そこでの知見が示唆するものを探ってみたいと思います。免疫学は日進月歩で、現在も新しい発見が続いています。その意味では「一時代前の」2冊なのですが、根幹のところは変わらないので、そこに焦点を当てます。
獲得免疫
まず人間の免疫には「自然免疫」と「獲得免疫(適応免疫)」の2系統があります。
自然免疫は一つ一つの異物(抗原)を区別しない免疫システムです。抗原とは、免疫の働きによって排除の対象となる異物を言います。
例えばインフルエンザ・ウイルスが細胞に進入し、DNAを複製して増殖を始めると、細胞はインターフェロンというウイルス抑制物質を出します。この物質は人間の体内にある各種の免疫細胞(マクロファージ、白血球、ナチュラル・キラー細胞など)を活性化させ、それらの免疫細胞はウイルスに感染した細胞を破壊したり飲み込んだりします。この段階でインフルエンザが治癒するケースもあるわけです。しかしそれを越えると「獲得免疫」の出番になる。
獲得免疫とは、ある特定の抗原に対して、それと特異的に反応するタンパク質(抗体)が体内に増え、その抗体が抗原を無力化することで体を防御する仕組みです。「特異的」というところがポイントです。
獲得免疫は自然免疫と違って「免疫の記憶」が成立します。つまり、ある抗原に対する免疫反応が起こると、次に全く同じ抗原が体内に進入した時には、極めて速やかに免疫反応が起こり、抗原を排除します。この結果、病気にならなかったり、なったとしても軽い症状で済む。麻疹(はしか)に一度かかると2度とかからないとか、ある特定タイプのインフルエンザのワクチンを接種しておくとそのインフルエンザにかからない、といった例です。ワクチンは獲得免疫を人為的に作り出す手段です。世界史においてワクチンの先駆けとなったのはもちろんジェンナーで、牛痘のワクチンを接種すると天然痘が予防できることを発見したわけですね。有名な話です。
人間の免疫システムは極めて複雑です。以降は、多田氏の著作のほとんどを占めている獲得免疫のメカニズム、その中で最も重要なT細胞とB細胞の連携プレーで実現される免疫の仕組みに絞り、概要をまとめます。自然免疫の仕組みが解明されたのは1990年代後半以降の比較的最近ですが、獲得免疫は20世紀を通じて免疫研究の中心課題でした。その成果が多田氏の本に結実しています。
免疫システムの主役・リンパ球
免疫システムは極めて多種の細胞の複雑な協調作用で実現されますが、これらの細胞はすべて骨髄の中に存在する「造血幹細胞」が分化して出来たものです。その過程が下図です。
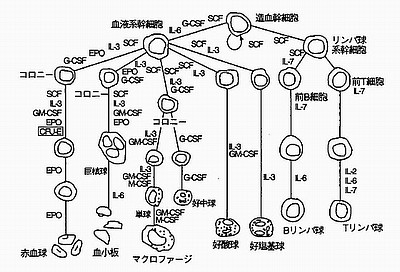
|
|
免疫・造血系細胞の発生 (『免疫・自己と非自己の科学』より) |
免疫の主役はリンパ球(T細胞やB細胞。図ではTリンパ球・Bリンパ球)やマクロファージですが、図の中には、赤血球、血小板、好中球、好塩基球、好酸球といった血液細胞も含まれています。免疫細胞と血液細胞は、元はというと同じ細胞なのです。
| リンパ球の数 |
人間のリンパ球の総数は約2兆個であり、重量にして約1kgもあります。そのうちの70%がT細胞で、残りがB細胞その他です。リンパ球は約100億個が毎日死滅し、新たに作られます。100億個といっても全体のわずか0.5%に過ぎません。しかし1日に100億個ということは1秒間ではリンパ球の100万個が入れ替わる計算になるのです。免疫を知るには、まずこの想像し難いような「量の多さ」を念頭に置いておくべきでしょう。
| サイトカイン |
図の線のところに書き込まれている英字略字は「サイトカイン」を示します。サイトカインとは、細胞が作りだし、細胞間の情報伝達や細胞の活性化・不活性化などの指令に使われるタンパク質の総称です。似た働きをするものにホルモンがありますが、ホルモンは遠隔の細胞まで効果が及ぶのに対し、サイトカインの情報伝達が及ぶのは近接した周辺の細胞という違いがあります。
造血幹細胞が免疫細胞と血液細胞に分化していく過程では、その場でどういうサイトカインが働くかによって細胞が複雑に分化し、免疫システム全体ができあがっていく仕組みになっています。
自己と非自己
多田氏の本で何回か強調されていることですが、
| 免疫は自己と非自己(異物としての抗原)を認識し、非自己を排除することによって自己の統一性を保ち、生命を維持するしくみ |
です。非自己とは「免疫系を刺激し、免疫反応を起こす物質や生物すべて」であり、一般的には細菌やウイルス、タンパク質や多糖類(デンプン、セルロース、グリコーゲンなどの高分子の類)です。化学物質も人間のタンパク質と結びつくことによって抗原となる場合があります。
免疫システムは極めて困難なことを実現しようとするものです。その「困難さ」は以下の3点に集約されるでしょう。
| 自己とは何か |
まず「非自己を排除し、自己を守る」といっても、その「自己」は決して固定的なものではなく、変化していきます。
たとえば幼児期には作らず、成熟して初めて人間の体内で作られるホルモンがあります。これを「非自己」として排除してしまっては人体が成り立ちません。母乳には母乳にしか含まれないタンパク質があります。あたりまえですが母親の免疫システムは(もちろん新生児も)これを「非自己」として排除することはありません。変化に対応できる何らかの「自己」認識の仕組みがあるのです。
| 非自己は無限 |
第2の「困難なこと」は「非自己」の種類は無限に考えられることです。何が来るか分からない。何が来るか分からないけれど、誤って「非自己」を「自己」と認識してしまい、それがたまたま悪性のウイルスだったりすると致命的になる。
不思議なのは、無限にあるはずの非自己=抗原に対し、抗原ごとに特異的に反応する抗体ができ、それが抗原を無力化するという「獲得免疫」のメカニズムです。どうしてこんなことが可能なのか。免疫システムの根幹のところです。
| ウイルスの存在 |
第3の「困難なこと」はウイルスの存在です。ウイルスはもちろん非自己として排除すべきものですが、ウイルスは人間の細胞内に進入し、もともとある細胞のDNAを利用してウイルスのDNAを複製し、そこから新たなウイルスを増殖させて細胞外に飛び出します。人間の細胞の内部、DNAの一部にウイルスのDNAが組み込まれている状態は自己なのか非自己なのか。「自己の中に非自己が潜んでいる状態」と言わざるを得ないでしょう。人間の免疫システムは、これを検知し排除する必要があります。
「自己」は変化し「非自己」のバリエーションは無限です。ウイルスというやっかいな「非自己」もある。免疫は「極めて困難なこと」に立ち向かっていることは確かでしょう。多田氏の著作に「困難なこと」いう表現はありませんが、明らかにそう見えます。「自己と非自己を認識し、非自己を排除する」ための免疫システムは、その仕組みが大変複雑なものであることが直感できます。
自己の標識:MHC
その守るべき「自己」を、免疫システムはどうやって判断しているのでしょうか。その判断の根拠となるのが、MHCと呼ばれる「標識」です。
| MHC |
生物は細胞の表面に「主要組織適合遺伝子複合体。Major Histocompatibility Complex。MHC」と呼ばれるタンパク質を持っています。ヒトの場合、HLAと呼ばれます。これが個人ごとに(もちろん生物種ごとに)全部違い、これが「自己」の標識となっているのです。
ヒトのMHCの形は第6染色体に並んでいる6種の遺伝子で決まります(この遺伝子群もMHCと呼ばれる)。従ってヒトは親から合計12個の遺伝子を受け継ぎ、そのうちの6個でMHCの型(タンパク質分子の形)が決まる。しかも6種の遺伝子それぞれはアミノ酸の入れ替えで「多型」になっています。つまり個人ごとの遺伝子変異が多数あるのです。
これらのことから、一人のMHCの型が他人の型と全く一致することはほとんどありません。ヒトは約60兆個の細胞がありますが、このすべての細胞の表面に数万~数10万のMHCがあります。これらが自己の標識となっていて、免疫システムはこのMHCをたよりに「自己」を見分け「非自己」を排除するのです。まず厳格な自己認識システムがあり、それを利用して自己と認識できないものを非自己と認識する。ここが仕組みの根幹です。
臓器移植が難しい理由は、人間に備わったこの自己認識システムです。生体肝移植にしろ、心臓移植にしろ、強力な免疫抑制剤を使わないと移植は成功しない。免疫抑制剤を使ったとしても、他人の皮膚の移植などは今だに成功しません。人間の免疫の仕組みが極めて鋭敏に他人の細胞を見分け、それを排除しにかかるからです。他人の細胞ではあるものの、同じ人間としての遺伝子をもつ細胞です。同じ機能・役割を果たす細胞であり(MHCさえなければ)全く同じ細胞と言っていい。それが排除されるのです。
|
ノーベル賞を受賞した京都大学・山中教授のiPS細胞が画期的な理由の一つは、まさにこのMHCによる自己認識の仕組みだ、との言い方ができるでしょう。神経や臓器の細胞の損傷・劣化・機能不全・死滅に起因する病気はたくさんあります。自分の皮膚の細胞からiPS細胞を作り、そこから損傷・死滅した細胞に分化・増殖させることが出来たら・・・・・・。遺伝的に全く同じ細胞、つまりMHCまで同じ細胞なので、自己の免疫系が排除することはありません。医療に革新が起こるに違いない・・・・・・。誰しもそう考えるのですね。「移植」と「再生」。この差は限りなく大きい。その差を作り出しているのがMHCなのです。 MHCによる自己と非自己の認識の仕組みで思うのは「ここまでやる必要があるのか」という感じです。何となく「やりすぎ」の感がある。生物の種ごとにMHCの形が決まっていて「人間同士の臓器移植はできるが、種を越えた移植はできない」ぐらいで十分な感じもします。 MHCによる自己認識方式だと、胎児は母親にとって完全な異物になります。胎児は両親のMHC遺伝子を受け継いでいて、母親と胎児のMHCの型は違うからです。胎児は非自己の最たるものであり、母親の免疫系の攻撃対象になって当然なのです。 しかしそれではまずい。多田氏の本によると母親と胎児をつないでいる胎盤の細胞表面からはMHCが消え、免疫系が認識できない分子が現れるというような仕組みがあるらしい。それで胎児は母親の免疫システムの攻撃をまぬがれているようです(他にも仕組みがある)。そうでもしないと種は維持できません。免疫システムは「やりすぎ」と感じるぐらい極めて鋭敏かつ非寛容であり、その結果として胎児の保護のためには特殊な仕掛けが用意されているのです。 しかし多田氏の本の全体を読むと、この「やりすぎ」には重要な意味があることがよく分かります。それは人間という種の維持にとって必須です。後で振り返ります。 |
| MHC・ペプチド複合体による自己認識 |
免疫システムにおける「自己」「非自己」の認識は、単にMHCの相違を見分けるだけでなく、もっと複雑です。
下図にMHC分子の立体構造の模式図を掲げました。左が「横から見た図」、右が「上から見た図」です。「横から見た図」においては下の方が細胞膜に接している部分、上が細胞膜から離れている方向です。
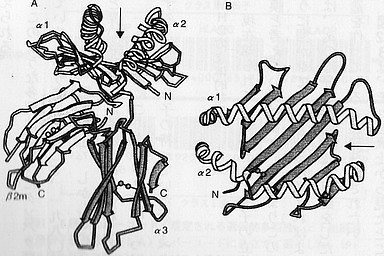
|
|
MHC(クラス1)分子の立体構造 (『免疫・自己と非自己の科学』より) |
よく見ると2つの螺旋構造が目につきます。かつ、2つの螺旋は「向かい合って」いて、その間には「溝」があるような構造になっている(図の矢印のところ)。タンパク質化学では螺旋状のポリペプチド(アミノ酸の連鎖分子)を「アルファ・へリックス」と呼ぶそうですが、アルファ・へリックスは構成するアミノ酸の並びが少し変化しても螺旋の「巻き方」がガラッと変わることが知られています。ということは、MHCがヒトによって違うことを考えると、溝の形もヒトによって違うことになります。
実はこの「溝」には必ず「自己」ないしは「非自己」に由来するタンパク質の断片(=ペプチド)がはさまっているのです。「はさまっている」ペプチドは、必ず9個のアミノ酸から成ります。この「MHC・ペプチド複合体」をもとに免疫システムは「自己」と「非自己」を識別するのです。ペプチドが「溝」にはさまっている状態を「提示されている」と言います。
MHCには実は2種類あります。クラス1・MHCとクラス2・MHCの2種類で、少し形が違いますが、似たような構造をしています。
クラス1・MHCはすべての細胞の表面にあり、提示されているペプチドはその細胞内部で作られたタンパク質の断片です。
クラス2・MHCは、主にAPC(Antigen Presenting Cell。抗原提示細胞。後述)と総称される細胞の表面にあり、提示されているペプチドは、APCが細胞外部からタンパク質を取り込み、断片にしたものです。
もし人間の体内に「非自己」が一切ないとすると、クラス1・MHCもクラス2・MHCも、提示しているのは自己由来のペプチドです。しかしウイルスが細胞内に進入して細胞のDNAを利用してウイルスのタンパク質を合成し始めると、その細胞のクラス1・MHCに提示されるペプチドにはウイルス・タンパク質由来のペプチドが含まれることになります。また何らかの「非自己」が人間の体内に進入すると、APCがもつクラス2・MHCに提示されるのはその非自己由来のペプチドが含まれることになります。
この「MHC・ペプチド複合体」が自己と非自己の判別基準になっているのです。
T細胞
「MHC・ペプチド複合体」によって自己と非自己を判別し、非自己を体内から排除する・・・・・・。この判別を行っているのがT細胞です。T細胞は2兆個あるリンパ球の70%を占める免疫システムの主役です。
「免疫システムの主役・リンパ球」のところで書いたように、すべての血液・免疫細胞は骨髄で作られる造血幹細胞が分化してできたものです。造血幹細胞が「胸腺」に取り込まれると、そこで分裂・増殖を繰り返して、大量のT細胞に分化します。T細胞のTとは胸腺(Thymus)のTです。
人間の胸腺は、心臓の周りの脂肪組織の中にある小さな臓器で、10代で最大の大きさになり、約35グラムです。その後次第に萎縮し、40代では10グラム以下になります。胸腺の萎縮は老化と深い関係があります。
T細胞はTCR(T Cell Antigen Receptor。T細胞抗原受容体)というタンパク質の構造体を細胞表面に持ちます(下図の左)。このTCRが「非自己」を提示しているMHCを認識するのです。つまり、T細胞が抗原と反応したということになります。
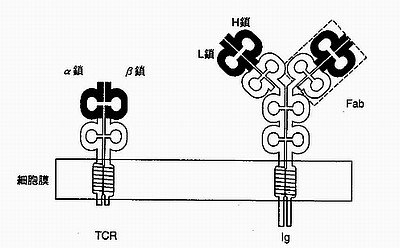
|
|
TCR(左)と抗体(Ig。右)の模式図 長方形は細胞膜で、下が細胞内。 α・β鎖(TCR)、H鎖・L鎖(Ig)が可変部であり、 遺伝子組換えで形成される。TCRとIgは良く似ている。 (『免疫・自己と非自己の科学』より) |
TCRは、胸腺で造血幹細胞がT細胞に分化するときに遺伝子再構成(=遺伝子の断片がランダム組み合わされて、多様なタンパク質の構成を作り出す仕組み)が起こり、無限とも思えるバリエーションが作り出されます。図のα鎖・β鎖のところです。どんな抗原と反応するTCRができるかは予想できません。従って自己由来のペプチドを提示しているMHCと反応してしまうTCRもできてしまうわけです。
しかし胸腺の中で、自己のMHCと強く反応するT細胞は死滅してしまいます。またMHCと全く反応しないものも死滅する。前者は自己を攻撃する危険なT細胞、後者は免疫システムとしては役にたたないT細胞というわけです。「生き残る」のは、分化したT細胞の5%以下と言います。要するにランダムに作ったものから「あぶない」ものと「役にたたない」ものを排除する。この仕組みが獲得免疫を成立させる根幹のところにあるわけです。
生き残ったT細胞はさらに分化します。そのうち、
◆ヘルパーT細胞
◆キラーT細胞
が代表的ものであり、胸腺から出ていって免疫細胞としての役割を担うことになります。
| ヘルパーT細胞 |
ヘルパーT細胞は免疫システムにおける司令塔です。ヘルパーT細胞は表面のTCRを用い、APCが提示している「クラス2・MHCと抗原由来のペプチドとの複合体」を認識すると、増殖を始めます。そしてサイトカインを合成し放出します。このサイトカインはキラーT細胞やB細胞を活性化し、抗原に対する「総攻撃」が始まることになります。
AIDSウイルスはこのヘルパーT細胞を特異的に狙うウイルスです。AIDSウイルスに感染するとヘルパーT細胞が次第に減少し、免疫システムは破綻に向かいます。そして通常なら全く問題ないような病原菌が体内で繁殖し、人間を死に追いやるのです。
| キラーT細胞 |
キラーT細胞はヘルパーT細胞からのサイトカインを受け取ると活性化され、大増殖を始めます。そして抗原の断片を提示しているクラス1・MHCをキラーT細胞の表面のTCRで認識すると、その細胞を殺します。キラーT細胞はヘルパーT細胞と違い、直接に抗原を提示している細胞を殺すT細胞です。
インフルエンザの場合、キラーT細胞が働き出すのは感染から4~5日です(同じタイプのインフルエンザに感染した経験がない場合)。
B細胞と抗体
B細胞は抗体(免疫グロブリン。Igと略称される。上図の右)を合成する能力をもった細胞です。B細胞はIgというタンパク質を細胞の表面に持っています。Igは特定の抗原と特異的かつ直接的に結合し、その抗原を無力化します。IgはB細胞から遊離して体内の循環系の中にあっても、抗原との結合能力を発揮します。
B細胞はヘルパーT細胞からのサイトカインを受け取ると活性化し、分裂しはじめます。さらにB細胞はヘルパーT細胞からの別のサイトカインによってプラズマ細胞に分化します。プラズマ細胞は大量の抗体を生産・分泌する能力があり、この抗体の効果で病気は終息に向かうことになります。
プラズマ細胞による抗体が生産されるのは、インフルエンザの場合、感染から7~8日(同じタイプのインフルエンザに感染していない場合)。
しかしながら増殖したB細胞のすべてがプラズマ細胞に分化するわけではありません。一部は「記憶B細胞」として長く体内に残ります。しかも記憶B細胞においては、Igがより抗体との反応性が高いタイプにに変化します。これが「獲得免疫」であり、次に同じ抗原が体内に進入したときにはこのB細胞の抗体が働くことになります。また増殖したT細胞も体内に残り、これも獲得免疫に寄与します。
| 免疫グロブリン(Ig)の多様性 |
免疫グロブリン(Ig)は特定の抗原に対して特異的に働きます。したがってB細胞ごとにIgの形は違っていて「無限の」多様性があるわけです。この免疫グロブリンはV領域(H鎖・L鎖の部分。=可変部)と、それ以外のC領域(=定常部)にわかれています(上図の右)。
V領域は対応する抗原ごとに違い、極めてバリエーションに富む部分です。この多様性はT細胞のTCRの多様性と同じようにランダムな「遺伝子組み替え」で実現されます。計算上、10の12乗(1兆)のバリエーションが可能と言います。これを発見したのが、1987年にノーベル賞(生理学・医学賞)を単独受賞した利根川進博士です。
| ちなみに第二次大戦後のノーべル生理学・医学賞をみると、単独受賞は67回のうち11回しかありません。また理系の3賞(物理学、化学、生理学・医学)の日本人受賞者・16人(2012年現在)のうち、単独受賞したのは湯川秀樹博士と利根川博士の2人だけです。利根川博士の業績が突出していたということでしょう。 |
一方、C領域は免疫グロブリンの種類(=クラス)を決めます。詳細は割愛しますが、IgMよりもIgG、IgE、IgAが抗原との反応性が高いタイプです。
Igがランダムに作られるということは、TCRと全く同じ理屈で、自己のタンパク質と反応するIgもできてしまうわけです。B細胞は骨髄の中で造血幹細胞から分化してできますが、分化の課程で自己と反応するB細胞は死滅します。しかし胸腺のような特別な「教育機関」があるわけではないので、自己反応性のB細胞も生き残りやすいようです。従って組織の末梢において、自己と反応するB細胞が死滅したり抗原と無反応になるような仕組みがあるのですが、これは省略します。
| APC:抗原提示細胞 |
B細胞で重要なことは、B細胞は抗原提示細胞でもある、ということです。抗原提示細胞(Antigen Presenting Cell。APC)とは
| ① | 抗原を細胞に取り込む。 | |
| ② | 抗原をタンパク質の断片(ペプチド)に分解する。 | |
| ③ | ペプチドを細胞表面のクラス2・MHCの「溝」に提示する。 |
という作用をもった細胞です。人間の体内では、マクロファージ、B細胞、樹状細胞(以上、組織内)、白血球、単球(血液中)などがAPCです。
免疫のプロセス
以上を踏まえて、免疫のプロセスがどう働くのか、そして免疫の記憶がどのように成立するのかを多田氏の文章から引用してみたいと思います。今までの紹介は以下の文章を理解するための「予備知識」とも言えます。B細胞が抗原提示細胞(APC)の役割もする場合の説明です。
|
ちなみに、免疫グロブリンC遺伝子とは、免疫グロブリンの定常部(=C領域)を決定する遺伝子、V遺伝子とはV領域(H鎖・L鎖の部分。可変部)を決める遺伝子です。
免疫的寛容
以上の説明は免疫の仕組みのごく一部であり、実際はもっと複雑で多種の免疫細胞がからみます。さらに抗原が入ってくると必ず上記のような免疫反応が起きるかというと、そうでもないのです。抗原に免疫システムが反応を示さないこともある。これを免疫的「寛容」と言います。
ある特定の抗原に何回もさらされると、その抗原に対して寛容になる場合があります。また経口的に入った抗原に対しては寛容になる。
たとえば卵を食べたとき、卵白のタンパク質であるアルブミンは腸で完全にアミノ酸に分解されるわけではなく、一部は血液中に入ります。その血液中に入る量は、もし注射をしたとしたら間違いなくアナフィラキシー・ショック(全身に起こる急性の免疫過剰反応。命にかかわることがある)を起こす量です。しかしアルブミンという非自己であっても経口的に摂取されると、免疫は寛容になる。
さらに「自己と反応してしまう免疫細胞の存在」があります。B細胞では自己と反応する抗体を持つものが骨髄から抜けだして体内に送られることがあると、先ほど書きました。T細胞でさえ胸腺でのチェックをすり抜けて体内に送られる「自己反応性のT細胞」がある。しかしこれらがすぐに問題を起こすわけではありません。免疫反応を起こすには上に書いた以外にも条件があり、自己反応性のB細胞・T細胞であっても「自己に対しては寛容になる」しかけがあるのです。
(続く)
| 補記1 |
「免疫細胞が自己を攻撃しない」ことの出発点は「自己を攻撃する免疫細胞は胸腺で除かれる」ことでした。多田氏の本が書かれた時代には、その詳しい仕組みは不明でしたが、最近、その一端が解明されはじめたようです。それを報じた新聞記事を引用します。
|
この記事を書いた記者の新井氏は医学関係にかなり詳しいようで、専門用語がポンポン飛び出す記事になっています。しかしその内容は、東大の高柳教授の発見の「意味」を的確に解説した良い記事だと思います。この記事を読んで非常に意外だったのは、下線をつけたところです。つまり、
| Fezf2 が作るたんぱく質は、遺伝子の働きを制御する「転写因子」のひとつで、胸腺細胞で様々な遺伝子のスイッチを入れ、体の各所にあるたんぱく質を合成する |
のところです。普通、学校では次のように習います。
| ◆ | 人間の体は約60兆の細胞でできている。 | ||
| ◆ | すべての細胞には同じ遺伝子(DNA)がある。 | ||
| ◆ | 体の部位によってどの遺伝子が発現するかが決まる。この発現を制御する仕組みがある。 | ||
| ◆ | この仕組みで、筋肉や心臓や皮膚などの多様な臓器や体が出来上がり、維持される。 |
しかし記事によると、胸腺だけは違うのですね。胸腺では、体にあるすべてのたんぱく質が次々と作られる仕組みがあるようなのです。
「攻撃を担う多種多様なT細胞がランダムに作られる」と記事にあるように、非自己を攻撃できるT細胞の能力の源泉は「ランダム」というところにあります。この仕組みを解明したのが、ノーベル医学・生理学賞を単独受賞した利根川進博士であることは本文中に書きました。
ランダムに作られたT細胞の中には、当然、自己を攻撃するものがある。これを排除する仕組みで唯一ありうるのは、T細胞が「標的」を攻撃するかどうかで判断するしかない。その「標的」とは「自己に存在するたんぱく質のすべて」でしかありえない・・・・・・。「どの方向に弾が飛ぶかは決まっているが、飛ぶ方向は全く不明な銃」を作ったとしたら、それは危なくて出荷できません。弾が前に飛ぶことを確認する唯一の手段は、実際に撃ってみることである・・・・・・。よくよく考えてみると、極めてロジカルです。
その論理的には予想できることが、実際の生体の中でどう行われているのか、その仕組みを解明する糸口が見えて来たわけです。高柳教授の発見の意義は記事に書かれている通りです。今後の研究に期待したいと思います。
(2015.11.20)
| 補記2 |
自己を攻撃する危険なT細胞を取り除く胸腺の機構は、完全ではありません。除去に失敗して胸腺の外へ出る危険なT細胞があります。しかしそれを除く別のしくみがあります。その一端が解明されたという報道がありました。それを引用したいと思います。
|
ちなみに記事での「関節炎リウマチ」は、普通は「関節リウマチ」と言うと思います。関節炎には様々な原因があり、その一つが関節リウマチです。
「自己を攻撃する危険なT細胞が胸腺で取り除かれる」というのは、1990年代半ばに判明したことだと記憶しますが、それから20年以上が経過しています。免疫のしくみの解明は今後も続くのでしょう。
(2019.4.12)
No.63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」 [本]
No.19「ベラスケスの怖い絵」でとりあげた名画「ラス・メニーナス」ですが、この絵は数々の芸術家や文学者のインスピレーションを駆り立ててきました。以前にとりあげた例では、
があります。ピカソの『ラス・メニーナスの模写連作』についても No.45 で触れました。今回はその続きで、童話とオペラをとりあげます。
オスカー・ワイルド : 『王女の誕生日』
No.19「ベラスケスの怖い絵」で書いたように、中野京子さんは著書の『怖い絵』で「ラス・メニーナス」に登場する小人症の2人に注目し、そういう異形の人たちを集めて「慰み者」「道化」「使用人」として使った17世紀のスペイン宮廷について書いていました。
この「ラス・メニーナス」に触発され、スペイン宮廷に異形の者たちが集められたという歴史的事実に着目して書かれた童話があります。19世紀後半のイギリスの作家・オスカー・ワイルド(1854-1900)の『王女の誕生日』です。
オスカー・ワイルドは童話集を2つ出版しています。第1童話集は『幸福な王子、その他 - The Happy Prince and Other Tales』(1888)で、5篇が収められています。もちろんこの中の『幸福な王子』が非常に有名です。第2童話集は『ざくろの家 - The House of Pomegranates』(1891)と題されていて、4篇の童話集です。表紙カバーを掲げた新潮文庫版の『幸福な王子』は、以上の9篇全部を収めた「オスカー・ワイルド童話全集」 になっています。
になっています。
『王女の誕生日』は『ざくろの家』の中の1篇で、次のような話です。
その日は12才になったスペインの王女の誕生日でした。この日だけは王女の好きな友達を呼べるので、宮廷のテラスや庭は朝から貴族の子供たちで活気にあふれています。
王は宮殿の窓からその様子を眺めていますが、浮かぬ表情です。それは王女の母親であるフランス人の王妃のことが今も忘れられないからです。王妃は王女を生んでから半年で亡くなりました。庭で遊んでいる王女の「フランス風微笑」は母親そっくりで、それを見るにつけても亡き王妃が思い出されます。王は宮殿内に引きこもってしまいました。
宮廷の庭には「闘技場」があり、そこで誕生日の余興が始まりました。まず闘牛士の格好をした貴族の子弟が、柳細工に獣皮をはった「牛」と対決しました。フランス人の軽業師は綱渡りの芸を披露します。イタリア人のあやつり人形もありました。アフリカからきた奇術師は、砂から白い花を咲かせ、それを鳥に変えます。ジプシーの楽器演奏と歌もありました。
しかし何と言っても、朝の余興で最も盛り上がったのは「こびとの踊り」でした。グロテスクな風貌の「こびと」が、大きな頭をふり、曲がった足でよたよたと闘技場に入ってきたとき、子供たちは大歓声をあげます。
実はこの「こびと」が人々の前に現れたのはこれが初めてでした。昨日、2人の貴族が森で狩りをしているときに発見し、王女への贈り物として宮殿に連れてこられたのです。「こびと」の父親は貧しい炭焼きで、こんな醜い子供を厄介払いできて大喜びでした。
「こびと」は踊っているあいだに王女に心を奪われます。王女も踊りがたいそうおもしろかったので、髪に差していた白い薔薇の花を「こびと」に投げました。すると「こびと」はそれを真に受けてしまい、醜い唇に花を押しつけながら、王女の前で片膝をついたのでした。
余興は終わり、王女たちは食事に宮殿内に入りました。王女は「こびとの踊り」があまりにおもしろかったので、シエスタ(午睡)の後にもう一度踊りを披露させるよう、侍従に言います。
「こびと」も王女のことが忘れられず、遊び仲間になりたいと願いました。彼は王女の知らないことをいっぱい知っています。たくさんの花を知っているし、小鳥のあらゆる鳴き声を知っています。森で生活するすべも知っています。それらを王女に教えてあげたいと思いました。
「こびと」は宮殿に入って王女に会おうとします。やっとのことで、開いたままになっている小さな扉をみつけ、宮殿の中に入りました。宮殿には豪華な部屋いろいろあります。装飾や調度品も見たこともないものばかりです。そして、とある部屋までやってきたときに「こびと」は誰かが自分の方を見ているのに気づきました。よく見るとそれは、これまで見たことがないような「化け物」です。それは「だらりと垂れた大きな顔と、たてがみみたいな黒い髪をした、せむしで、がに股」の姿でした。「こびと」は結局それが、鏡に写った自分の姿だと悟ったのです。
森の中で育った「こびと」は鏡を見た経験はなく、自分の真の姿を今まで知らなかったのです。「こびと」はうめきながら、床に倒れてしまいます。
そこに王女と子供たちが入ってきました。そして床に横たわる「こびと」を見つけます。王女は「こびとを起こしてもう一度踊らせるように」と侍従に言います。侍従が確認しますが「こびと」はこと切れていました。
童話『王女の誕生日』は、ここで終わります。
要約してしまうと短い話のように見えますが、文庫版で24ページの長さの童話です。上の要約では割愛しましたが、王の結婚の経緯や治世、闘技場での各種の余興の様子、「こびと」と草花や鳥の関わりなどが書き込まれています。
童話では「こびと」の内面が詳しく語られています。父親に捨てられ、王侯貴族の子弟にあざけり笑われ、最後には心臓発作で死んでしまう「こびと」は犠牲者でしょう。しかしこの童話では12歳の王女もまた犠牲者だという感じを強く受ける。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分自身の心が蝕ばまれていく。宮廷に生まれたという環境からはそのように育つしかなく、12歳になっても「心」が発達しない。フランス人の母親は王女が物心ついたときにはいません。王女の微笑が母親に似ているという冒頭の王の回想と、最後のシーンで王女が「美しい軽蔑でゆがめた唇」で言う「捨てぜりふ」。この2つの対比が利いています。
この童話は『ラス・メニーナス』に触発されて書かれたのでしょうか?
オスカー・ワイルドの全作品を訳した英文学者の西村孝次氏は、そうだと言っています。「オスカー・ワイルド全集」の『王女の誕生日』の注釈で、西村氏は『ラス・メニーナス』の解説も交えて次のように書いています(太字は原文にはありません)。
引用の最後に出てくるヴィヴィアンとは、オスカー・ワイルドの次男で、父親の伝記を書きました。おそらくその伝記からの引用だと思います。『ラス・メニーナス』に描かれたマルガリータ王女を見て「意地の悪い冷たい表情」と衝撃を受けるオスカー・ワイルドの感性も、相当のものだと思います。
この童話は『ラス・メニーナス』から受けた「衝撃」が発端になっていることは確かなようです。もっと推測すると、マルガリータ王女とマリア・バルボラからインスピレーションを得て書かれた・・・・・・。そう考えれば納得できます。
そして『ラス・メニーナス』と『王女の誕生日』にはもう一つの共通点があります。それは「鏡」です。『ラス・メニーナス』の後景中央には鏡があり、そこには王と王妃が「ぼんやりと」描かれています。『王女の誕生日』の鏡は「こびと」自身の姿を露わにしたのでした。鏡は「真実を映す」という意味でしょう。それは、オスカー・ワイルドが『ラス・メニーナス』から得たもう一つのインスピレーションだと思います。
ツェムリンスキー : 歌劇『こびと』
オスカー・ワイルドの童話『王女の誕生日』は、別の芸術作品を生み出しました。アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーの歌劇『こびと』です。このオペラは『王女の誕生日』が原案になっています。
ツェムリンスキー(1871-1942)はウィーンで活躍した作曲家・指揮者で、ウィーンのフォルクス・オーパーの初代首席指揮者をつとめました。ツェムリンスキーの名前は一度、No.9「コルンゴルト:ヴァイオリン協奏曲」で書いたことがあります。ツェムリンスキーはコルンゴルトの音楽の先生ですが、コルンゴルトと同じようにユダヤ系であったため、ナチスの台頭によってアメリカへ亡命したのです。コルンゴルトはハリウッドの映画音楽で活躍しましたが、ツェムリンスキーはニューヨークで不遇な晩年を送ったようです。
作曲家としてのツェムリンスキーはオペラ、交響曲、室内楽曲、歌曲など各種の作品を残しました。中でも「弦楽四重奏曲 第2番」は素晴らしく、ベートーベン以降の弦楽四重奏の傑作を一つだけあげよと言われたなら、私ならこの曲をあげます。
ツェムリンスキーのオペラで有名なのは『フィレンツェの悲劇』と『こびと』で、この2つともがオスカー・ワイルドの原作に基づいています。同時代のイギリスの文学者に何か共感するものがあったのかもしれません。ちなみにリヒャルト・シュトラウスも、オスカー・ワイルドの『サロメ』をオペラ化しています。
『こびと』は『王女の誕生日』を原案とする1幕もののオペラです。『王女の誕生日』と共通しているのは、
という4点です。オペラの主な登場人物は、
・こびと
・王女:クララ
・執事:ドン・エストバン
・侍女:ギータ
の4人です。骨格は童話と同じなのですが、オペラが童話と違っている点もいろいろある。「こびと」はトルコ皇帝からの贈り物で(オペラらしく)歌の名手ということになっています。王女の年齢も18歳ということにしてある。また童話にはない侍女・ギータが重要な役割を与えられています。ギータは笑い者にされている「こびと」に共感し、王女の「無垢な残酷さ」に心を痛め、「こびと」に真の姿を伝えようかどうかと悩み、「こびと」の最後をみとります。そもそもオペラはドラマの一種なので、王女と「こびと」の対話や「すれ違い」も濃密に表現されています。
ちなみにこのオペラは、誕生日を祝う舞踏会場を抜け出してきた王女の次の言葉で終わります。
歌劇『こびと』についての蘊蓄です。写真を掲げたDVDはロサンジェルス・オペラの公演ですが、指揮をしたジェームズ・コンロン(米国の指揮者。ツェムリンスキーに造詣が深い)は、DVDのライナーノートで次のようなエピソードを紹介しています。
背が低く、醜男で、かつウィーンにおける「異邦人」・・・・・・。ツェムリンスキーは「こびと」に自分自身を託したようです。それは、オスカー・ワイルドというアイルランド出身の詩人・小説家を介して、ベラスケスが描いた『ラス・メニーナス』に登場する「こびと」、マリア・バルボラに(結果として)自分を投影することとなった。そして・・・・・・。
ツェムリンスキーはスペイン王女にアルマ・マーラーを投影したという見方があります。なかなか面白い説ですが、はたして本当なのでしょうか。自分をふってグスタフ・マーラーに走ったとは言え、アルマはかつての恋人です。かつての恋人を『こびと』のスペイン王女のように描けるものなのでしょうか。真の芸術家は、他人に対する「あからさまな あてつけ」で作品を作ったりはしないものだと思うのです。
全くの推測ですが、ツェムリンスキーがスペイン王女を誰かに見立てたとしたのなら、それは「ウィーンそのもの」ではと思います。スペインとオーストリアの2つのハプスブルク家には複雑な婚姻関係があります。『ラス・メニーナス』の中心にいるマルガリータ王女は、15歳でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れしているのです。「こびと」は歌の名手だけれど、王女にとっては玩具にすぎません。ツェムリンスキーも音楽家としては成功したけれど、結果として『こびと』の初演から16年後にウィーンから追い出されてしまいます。
ともかく、『ラス・メニーナス』 → 『王女の誕生日』 → 『こびと』という一連の作品は、芸術における「連鎖反応」の好例だと思います。
| ◆絵画: |
サージェント『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』 | |
| ◆小説: |
カンシーノ『ベラスケスの十字の謎』 |
があります。ピカソの『ラス・メニーナスの模写連作』についても No.45 で触れました。今回はその続きで、童話とオペラをとりあげます。

|
| ベラスケス『ラス・メニーナス』(プラド美術館) |
オスカー・ワイルド : 『王女の誕生日』
(The Birthday of the Infanta)
No.19「ベラスケスの怖い絵」で書いたように、中野京子さんは著書の『怖い絵』で「ラス・メニーナス」に登場する小人症の2人に注目し、そういう異形の人たちを集めて「慰み者」「道化」「使用人」として使った17世紀のスペイン宮廷について書いていました。
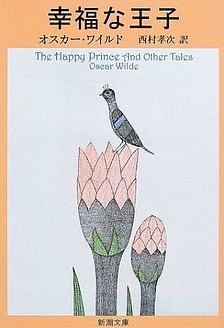
| |||
オスカー・ワイルドは童話集を2つ出版しています。第1童話集は『幸福な王子、その他 - The Happy Prince and Other Tales』(1888)で、5篇が収められています。もちろんこの中の『幸福な王子』が非常に有名です。第2童話集は『ざくろの家 - The House of Pomegranates』(1891)と題されていて、4篇の童話集です。表紙カバーを掲げた新潮文庫版の『幸福な王子』は、以上の9篇全部を収めた「オスカー・ワイルド童話全集」
『王女の誕生日』は『ざくろの家』の中の1篇で、次のような話です。
(以下に『王女の誕生日』のストーリーと
結末が明らかにされています)
結末が明らかにされています)
その日は12才になったスペインの王女の誕生日でした。この日だけは王女の好きな友達を呼べるので、宮廷のテラスや庭は朝から貴族の子供たちで活気にあふれています。
王は宮殿の窓からその様子を眺めていますが、浮かぬ表情です。それは王女の母親であるフランス人の王妃のことが今も忘れられないからです。王妃は王女を生んでから半年で亡くなりました。庭で遊んでいる王女の「フランス風微笑」は母親そっくりで、それを見るにつけても亡き王妃が思い出されます。王は宮殿内に引きこもってしまいました。
宮廷の庭には「闘技場」があり、そこで誕生日の余興が始まりました。まず闘牛士の格好をした貴族の子弟が、柳細工に獣皮をはった「牛」と対決しました。フランス人の軽業師は綱渡りの芸を披露します。イタリア人のあやつり人形もありました。アフリカからきた奇術師は、砂から白い花を咲かせ、それを鳥に変えます。ジプシーの楽器演奏と歌もありました。
しかし何と言っても、朝の余興で最も盛り上がったのは「こびとの踊り」でした。グロテスクな風貌の「こびと」が、大きな頭をふり、曲がった足でよたよたと闘技場に入ってきたとき、子供たちは大歓声をあげます。
実はこの「こびと」が人々の前に現れたのはこれが初めてでした。昨日、2人の貴族が森で狩りをしているときに発見し、王女への贈り物として宮殿に連れてこられたのです。「こびと」の父親は貧しい炭焼きで、こんな醜い子供を厄介払いできて大喜びでした。
「こびと」は踊っているあいだに王女に心を奪われます。王女も踊りがたいそうおもしろかったので、髪に差していた白い薔薇の花を「こびと」に投げました。すると「こびと」はそれを真に受けてしまい、醜い唇に花を押しつけながら、王女の前で片膝をついたのでした。
余興は終わり、王女たちは食事に宮殿内に入りました。王女は「こびとの踊り」があまりにおもしろかったので、シエスタ(午睡)の後にもう一度踊りを披露させるよう、侍従に言います。
「こびと」も王女のことが忘れられず、遊び仲間になりたいと願いました。彼は王女の知らないことをいっぱい知っています。たくさんの花を知っているし、小鳥のあらゆる鳴き声を知っています。森で生活するすべも知っています。それらを王女に教えてあげたいと思いました。
「こびと」は宮殿に入って王女に会おうとします。やっとのことで、開いたままになっている小さな扉をみつけ、宮殿の中に入りました。宮殿には豪華な部屋いろいろあります。装飾や調度品も見たこともないものばかりです。そして、とある部屋までやってきたときに「こびと」は誰かが自分の方を見ているのに気づきました。よく見るとそれは、これまで見たことがないような「化け物」です。それは「だらりと垂れた大きな顔と、たてがみみたいな黒い髪をした、せむしで、がに股」の姿でした。「こびと」は結局それが、鏡に写った自分の姿だと悟ったのです。
|
森の中で育った「こびと」は鏡を見た経験はなく、自分の真の姿を今まで知らなかったのです。「こびと」はうめきながら、床に倒れてしまいます。
そこに王女と子供たちが入ってきました。そして床に横たわる「こびと」を見つけます。王女は「こびとを起こしてもう一度踊らせるように」と侍従に言います。侍従が確認しますが「こびと」はこと切れていました。
|
童話『王女の誕生日』は、ここで終わります。
要約してしまうと短い話のように見えますが、文庫版で24ページの長さの童話です。上の要約では割愛しましたが、王の結婚の経緯や治世、闘技場での各種の余興の様子、「こびと」と草花や鳥の関わりなどが書き込まれています。
童話では「こびと」の内面が詳しく語られています。父親に捨てられ、王侯貴族の子弟にあざけり笑われ、最後には心臓発作で死んでしまう「こびと」は犠牲者でしょう。しかしこの童話では12歳の王女もまた犠牲者だという感じを強く受ける。立場の弱い人間を見下して軽蔑する人間は、そのことで自分自身の心が蝕ばまれていく。宮廷に生まれたという環境からはそのように育つしかなく、12歳になっても「心」が発達しない。フランス人の母親は王女が物心ついたときにはいません。王女の微笑が母親に似ているという冒頭の王の回想と、最後のシーンで王女が「美しい軽蔑でゆがめた唇」で言う「捨てぜりふ」。この2つの対比が利いています。
この童話は『ラス・メニーナス』に触発されて書かれたのでしょうか?
オスカー・ワイルドの全作品を訳した英文学者の西村孝次氏は、そうだと言っています。「オスカー・ワイルド全集」の『王女の誕生日』の注釈で、西村氏は『ラス・メニーナス』の解説も交えて次のように書いています(太字は原文にはありません)。
|
引用の最後に出てくるヴィヴィアンとは、オスカー・ワイルドの次男で、父親の伝記を書きました。おそらくその伝記からの引用だと思います。『ラス・メニーナス』に描かれたマルガリータ王女を見て「意地の悪い冷たい表情」と衝撃を受けるオスカー・ワイルドの感性も、相当のものだと思います。
この童話は『ラス・メニーナス』から受けた「衝撃」が発端になっていることは確かなようです。もっと推測すると、マルガリータ王女とマリア・バルボラからインスピレーションを得て書かれた・・・・・・。そう考えれば納得できます。
そして『ラス・メニーナス』と『王女の誕生日』にはもう一つの共通点があります。それは「鏡」です。『ラス・メニーナス』の後景中央には鏡があり、そこには王と王妃が「ぼんやりと」描かれています。『王女の誕生日』の鏡は「こびと」自身の姿を露わにしたのでした。鏡は「真実を映す」という意味でしょう。それは、オスカー・ワイルドが『ラス・メニーナス』から得たもう一つのインスピレーションだと思います。
ツェムリンスキー : 歌劇『こびと』
オスカー・ワイルドの童話『王女の誕生日』は、別の芸術作品を生み出しました。アレクサンダー・フォン・ツェムリンスキーの歌劇『こびと』です。このオペラは『王女の誕生日』が原案になっています。
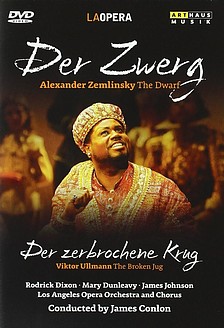
| |||
|
こびと:Rodrick Dixon 王女:Mary Dunleavy ジェームズ・コンロン指揮 ロサンジェルス・オペラ管弦楽団 | |||
作曲家としてのツェムリンスキーはオペラ、交響曲、室内楽曲、歌曲など各種の作品を残しました。中でも「弦楽四重奏曲 第2番」は素晴らしく、ベートーベン以降の弦楽四重奏の傑作を一つだけあげよと言われたなら、私ならこの曲をあげます。
ツェムリンスキーのオペラで有名なのは『フィレンツェの悲劇』と『こびと』で、この2つともがオスカー・ワイルドの原作に基づいています。同時代のイギリスの文学者に何か共感するものがあったのかもしれません。ちなみにリヒャルト・シュトラウスも、オスカー・ワイルドの『サロメ』をオペラ化しています。
『こびと』は『王女の誕生日』を原案とする1幕もののオペラです。『王女の誕生日』と共通しているのは、
| ◆ | スペイン王女の誕生日に「こびと」が贈り物として献呈される。 | |
| ◆ | 「こびと」は王女に惹かれるが、王女は「こびと」を単なる遊び道具としか思っていない。 | |
| ◆ | 「こびと」は鏡で真の自分の真の姿を発見し、そのあと死ぬ。 | |
| ◆ | 王女は何事もなかったかのように舞台を去る。 |
という4点です。オペラの主な登場人物は、
・こびと
・王女:クララ
・執事:ドン・エストバン
・侍女:ギータ
の4人です。骨格は童話と同じなのですが、オペラが童話と違っている点もいろいろある。「こびと」はトルコ皇帝からの贈り物で(オペラらしく)歌の名手ということになっています。王女の年齢も18歳ということにしてある。また童話にはない侍女・ギータが重要な役割を与えられています。ギータは笑い者にされている「こびと」に共感し、王女の「無垢な残酷さ」に心を痛め、「こびと」に真の姿を伝えようかどうかと悩み、「こびと」の最後をみとります。そもそもオペラはドラマの一種なので、王女と「こびと」の対話や「すれ違い」も濃密に表現されています。
ちなみにこのオペラは、誕生日を祝う舞踏会場を抜け出してきた王女の次の言葉で終わります。
| 「プレゼントはもう壊れちゃったわ。18歳になった誕生日にもらったおかしな玩具。そうね、もう少し踊ってくるわ」 |
歌劇『こびと』についての蘊蓄です。写真を掲げたDVDはロサンジェルス・オペラの公演ですが、指揮をしたジェームズ・コンロン(米国の指揮者。ツェムリンスキーに造詣が深い)は、DVDのライナーノートで次のようなエピソードを紹介しています。
| ◆ | ツェムリンスキーはウィーンの音楽学生だったアルマ・シンドラーと恋仲になった(1900)。ちなみにライナーノートにはありませんが、アルマ・シンドラーはそれ以前にグスタフ・クリムトと深い仲だったことがあります。 | |
| ◆ | アルマはツェムリンスキーのカリスマ性に惹かれたが、醜男だったと述懐している。ツェムリンスキーの身長はアルマの肩までしかなく、一緒に歩くのは奇妙だったとも言っている。 | |
| ◆ | アルマはツェムリンスキーをふって、グスタフ・マーラーと結婚した(1901)。 | |
| ◆ | ツェムリンスキーは後に「醜男の悲劇の物語を書いてくれ」と友人に語っている(1909)。彼はそれにこだわり続け、後年の『こびと』に結実した(1922)。 |
背が低く、醜男で、かつウィーンにおける「異邦人」・・・・・・。ツェムリンスキーは「こびと」に自分自身を託したようです。それは、オスカー・ワイルドというアイルランド出身の詩人・小説家を介して、ベラスケスが描いた『ラス・メニーナス』に登場する「こびと」、マリア・バルボラに(結果として)自分を投影することとなった。そして・・・・・・。
ツェムリンスキーはスペイン王女にアルマ・マーラーを投影したという見方があります。なかなか面白い説ですが、はたして本当なのでしょうか。自分をふってグスタフ・マーラーに走ったとは言え、アルマはかつての恋人です。かつての恋人を『こびと』のスペイン王女のように描けるものなのでしょうか。真の芸術家は、他人に対する「あからさまな あてつけ」で作品を作ったりはしないものだと思うのです。
全くの推測ですが、ツェムリンスキーがスペイン王女を誰かに見立てたとしたのなら、それは「ウィーンそのもの」ではと思います。スペインとオーストリアの2つのハプスブルク家には複雑な婚姻関係があります。『ラス・メニーナス』の中心にいるマルガリータ王女は、15歳でオーストリア・ハプスブルク家のレオポルト1世と結婚し、ウィーンに輿入れしているのです。「こびと」は歌の名手だけれど、王女にとっては玩具にすぎません。ツェムリンスキーも音楽家としては成功したけれど、結果として『こびと』の初演から16年後にウィーンから追い出されてしまいます。
ともかく、『ラス・メニーナス』 → 『王女の誕生日』 → 『こびと』という一連の作品は、芸術における「連鎖反応」の好例だと思います。
No.56 - 強い者は生き残れない [本]
理系学問からの思考
No.50「絶対方位言語と里山」において、森林生態学者の四手井 綱英 氏が「里山」という言葉を広め、それが人間と自然の関わり方についてのメッセージの発信になり、社会的な運動を引き起こしたことを書きました。
ふつう人間や社会を研究するのは文学、哲学、心理学、社会学、政治学、経済学などの、いわゆる文化系学問だと見なされています。それは正しいのですが、理科系の学問、特に生命科学の分野、物理学、数学などから得られた知見が人間の生き方や社会のありかたに示唆を与えることがいろいろあると思うのです。
森林は人間と非常に関係が深いので、森林生態学における発見や認識(たとえば里山)が人間の生き方や社会のありかたに影響を与えることはすぐに理解できます。しかし「人間の生き方や社会のありかたへの影響」は何も森林生態学に限ったことではなく、生命に関する学問全般で言えることだし、もっと広く自然科学全般でもありうる思います。
そういった例の一つとして『強い者は生き残れない』という進化論の本を紹介したいと思います。
『強い者は生き残れない』
 この本は吉村仁(よしむら じん)氏が書いた、生物の進化を扱った本です。吉村さんは静岡大学教授であり、またニューヨーク州立大学併任教授、千葉大学客員教授も勤めています。専門は数理生態学で、主に進化論の研究をしていると本の背表紙にありました。『素数ゼミの謎』(文藝春秋)という一般向けの本もあります。
この本は吉村仁(よしむら じん)氏が書いた、生物の進化を扱った本です。吉村さんは静岡大学教授であり、またニューヨーク州立大学併任教授、千葉大学客員教授も勤めています。専門は数理生態学で、主に進化論の研究をしていると本の背表紙にありました。『素数ゼミの謎』(文藝春秋)という一般向けの本もあります。『強い者は生き残れない』の内容は進化のメカニズムから人間社会の考察まで、多岐に渡っています。すべての概要を紹介できませんが、コアと思われる部分を以下に紹介します。
ダーウィンの「自然選択理論」
まず出発点はダーウィンです。本の冒頭にはダーウィンの「自然選択理論」が簡潔に要約されています。
生物の進化について解明したイギリスの生物学者チャールズ・ロバート・ダーウィン(1809-1882)の「自然選択理論」の骨子は、以下の3点である。 |
ダーウィンのそれまでになかった新規性は「個体変異」に注目し、それと自然選択(natural selection)が重なって生物が進化するという基本理論を確立したことです。これは現代でも進化論の基礎となっています。
しかし自然選択と言う場合の「自然」とは、実は「生物からみた環境」なのです。環境選択というのが正しい。
自然選択とは、本来の意味からすると「環境選択(environment selection)」と呼ぶべきであろう。つまり、選択する主体は「環境」であり、選択される対象は「生物の各個体」なのである。だから、当たり前のことであるが、環境が変われば自然選択もかわる。この点は非常に重要で、ダーウィンが生きた19世紀には、自然選択は変化しないというような考えが広く信じられていたが、自然選択はいつもダイナミックに変化しているのだ。 |
重要なことは「環境は変わる = 自然選択は変わる」ということです。森林に住んでいるウサギと草原のウサギでは、食べるエサも危険な捕食者も異なります。太古の昔から森林(ないしは草原)だった環境、森林から草原へと移行した環境、その逆の環境、森林と草原が交互に繰り返された環境では、何が生物の生存にとって有利かが異なってくるのです。
| なお本書に断ってありますが、進化(evolution)という言葉に、かつてのような「進歩」という意味合いはありません。21世紀の進化論研究者が使う用語としての「進化」は「変化」と同じ意味です。 |
環境変化が進化を促す
「環境により選択されて」起きる生物の進化は、どのように進むのでしょうか。吉村さんは今までの学説や自身の数理シミュレーションの成果も引用しながら、あくまで「仮説」と断ってですが、以下のようなモデルを提示しています。
| シーン0 環境安定期 |
|
環境が安定している長期の期間を言います。この時期、自然選択は微弱で、表現型の変化はほとんどありません。「表現型」とは「生物の個体が実際に備えている性質・形質・行動」を言います。生物の種数の変化もあまり起きません。 しかしこの時期に生物の内部では遺伝子の多様化が進みます。それは「中立突然変異」によります。これは1968年に木村資生(もとお。1924-1994)が発見した原理で、
|
| シーン1 環境激変期 |
| 環境が激変すると自然選択のありようも急激に変化し、生物は大絶滅を起こします。この結果生物全体の遺伝子の多様性も激減します。 |
| シーン2 適応放散期 |
| 環境の激変が終わった直後の時期です。大絶滅を生き延びたわずかな種は、他に生物があまりいないので今度は大増殖します。分布域を広げ、個体数が増え、広がった場所に適応していきます。この過程で種の分化が起こります。 |
| シーン3 最適化期 |
| 環境が安定する最初の時期です。シーン2で適応放散した生物は、それぞれの環境に精密に適応していきます。種間の競争も激しく、種数はどんどん絞られますが、適応のレベルはますます高くなります。 |
| シーン4 環境安定期 = シーン0に戻る |
| 以上の比較的短いシーン1~3を経過したあとは、非常に長い環境安定期に移ります。これは最初のシーン0と同じです。これらのシーン0から3が繰り返されることによって生物は進化していきます。このモデルは生物の進化が急激かつ断続的に起こるという、化石研究のデータをもとにした「断続平衡説」ともマッチしています。 |
環境の変化が進化(=生物の変化)を引き起こす・・・・・・。吉村さんは「魚は自分の意志で陸に上がらない」と表現しています。その通りで、海の環境で「何不自由なく」暮らしている魚が、陸にあこがれ、苦難を乗り越えて陸にあがったということはないのです。私なりに補足すると、浅海に多様な魚が生息していたが、その海が地殻変動によって広範囲に干上がり干潟になってしまった。多くは海に逃れたが、干潟に取り残された魚もいた。もちろんその大多数は絶滅します。しかし中には干潟でも皮膚呼吸で生存できる種がいた。その種が次第に肺を発達させ、やがては陸での生活に適応していった(両生類への進化)。魚は「しかたがないから」「やむにやまれず」陸に上がったのです。
これは人間の文明の発生を連想させますね。人間の文明の端緒が「農業」にあることは定説です。しかし狩猟採集で十分暮らしていけるのなら、別に農業などという面倒なことをしなくてもよいわけです。野山に食料となる木の実やフルーツや雑穀が豊富にあるのなら、それを食べていればよい。採ってくるだけなのだから楽です。しかし環境が変わり、降雨量が激減し、森林が無くなって草原になると話は変わってきます。木の実やフルーツや雑穀が容易には入手できなくなる。その時、人間は草原のイネ科の植物に目をつけ、種を撒いて育てるということを始めます。環境が十分な食料を与えてくれなくなったので「しかたがないから」自分で作るわけです。
そうこうしているうちに、もっと環境が悪化して降雨量がさらに減り、草原での農業は無理になった。「しかたがないから」人間は大河のそばに集まり、河から水を引いて畑を作る。そうして人間の集団の共同作業が発達し、都市ができて文明と言えるものが生まれる・・・・・・。
人間はやむにやまれず農業を始めたのだと思います(吉村さんもそう書いています)。「農業」と「魚が陸に上がる」話と共通するのは、環境の変化の中でも「環境の悪化」が、生物を次の進化段階に引き上げるということです。「シーン1 環境激変期」もそうです。大多数にとって環境が悪化するから、大多数が絶滅するのです。
強いものが生き残るとは限らない
以上のことを前提とすると「強いものが生き残って進化した」という単純な見方はおかしいわけです。それはちょっと考えてみれば分かります。本書が言っていることを、私なりに説明すると次のようです。
ある草原地帯に2種の草食動物が生息していたとして、それをSTRONG種とWEAK種とします。STRONG種は体が大きく、力も強く、WEAK種と争うと必ず勝って相手を蹴散らします。草を食べる量も多く、子供の数も多い。一方のWEAK種は全く正反対で、小さくて痩せていて、子供の数も少ない。STRONG種の目が届かない陰でひっそりと草を食べている。どちらの数が多いかと言うとSTRONG種です。しかしWEAK種が絶滅するかというと、そうでもない。草原の草の量には環境条件で決まる限界があり、STRONG種といえどもむやみに数を増やせないからです。
この状況のもとで、環境が変わり、たとえば乾燥化が進んで草の量が激減したらどうなるか。これは基礎代謝量が多く、たくさんの食物摂取が必要なSTRONG種に不利に働きます。体が小さく、食物摂取量が少なく、子供も少ないWEAK種が有利になる。STRONG種は激減するでしょう。STRONG種同士が少ない食料を争って自滅するかもしれない。力が強いということが「アダ」になることもあるのです。
どちらの種が生き延びる上で有利かは環境に依存します。現在の環境に適応しすぎると環境変化に対応できないのです。
本書では環境が変化・変動しているときには、その変化に対応できるように生物は進化することが述べられています。その研究の例が鳥のクラッチ・サイズです。
鳥が一回に生む卵の数を「クラッチ・サイズ」と言います。吉村さんはいろいろな鳥で実験を行い、興味深い事実を発見します。たとえばワシカモメの場合、親鳥は6羽の雛鳥を同時に育てることが出来るにもかかわらず、実際のクラッチサイズは2~3個です。ワシカモメは「余力を残して」卵を生むのであり、これは多くの鳥で成り立ちます。著者はこの原因が「環境悪化に対する対応」だと考えていて、現在も研究しているそうです。
環境が変化・変動しているときには、子供の数、すなわち平均適応度を最大化していくと、逆に不利になる。死亡リスクをかぶらないよう、絶滅しないよう、子供の数を少なく抑えている個体こそが、いざ環境が悪化した時に生き残れるのだ。 |
絶滅するかしないか、という実験は非常に難しいので、鳥のクラッチサイズについての「環境悪化適応説」はまだ仮説です。しかし最低限、認めるべきは
◆環境は変化する
◆資源は有限である
の2点をベースにモノを考えると、従来とは違った様相が見えてくることです。そして「環境は変化し資源は有限」という点は全く正しいのです。
環境からの独立:共生と協調
以上の考察からすると「できるだけ環境からの影響を受けにくい生物」が生き残りやすいということになります。「環境からの独立」です。各種の生物が作る「巣」はそのための手段だと考えられます。そして「環境からの独立」を実現する「切り札」として生物が発達させてきたのが「共生・協力」なのです。
吉村さんはいろいろと共生・協力の例をあげています。たとえば地衣類は藻類と菌類の共生体であり、藻類が光合成を、菌類が栄養の分解を水分の補給を受け持っています。
現在のほとんどの生物を構成している真核細胞(核を持つ細胞)は、原核生物(核を持たない細胞)の共生体であるという説が、1970年にマサチューセッツ大学のマーギュリス教授によって唱えられました。この仮説は、細胞内のミトコンドリアや葉緑体に独自の遺伝子が確認されたことから、現在では定説になっています。
生物の個体同士が協力しあう関係も、シロアリや鳥の例などで説明されています。多くの哺乳類や鳥類がペアを作る「一夫一妻制」も、特定の個体が交尾相手を独占することを防ぎ、集団としての共生・協力関係を引き出すベースになっていると言います。「共生・協力する生物が進化する」のです。そして、このことは人間社会でも同様だ、と吉村さんは考えています。
ゲームの理論と人間社会
『強いものは生き残れない』という本の大きな特徴は、生物の進化についての考察だけでなく、そこからのアナロジーとして人間社会のありように関する考察が書かれていることです。その一つが「協調と裏切り」に関するゲームの理論からの考察です。
「囚人のジレンマ」という有名なゲームの理論の問題があります。アメリカでの司法取引を模したゲームです。2人組の強盗が別件の軽犯罪で逮捕され、別々の部屋で強盗事件の尋問をうけます。2人とも黙秘を通すと(=協調すると)、2人とも軽犯罪で懲役1年の刑になります。1人が自白し(=裏切り)1人が黙秘すると、自白した方は司法取引で無罪放免になり、黙秘した方は強盗の罪で懲役10年の刑になります。2人とも自白したときには、自白したということで刑が少し軽減され、2人とも懲役8年の刑になります。さてどういう戦略がベスト(=自分の懲役が少なくなる)か、という問題です。相手の戦略は分かりません。
この問題において、ゲームの理論では「裏切り」が最良の戦略となります。それはなぜか。
裏切り(自白)という戦略を選択すると、相棒が協調(=黙秘する)の場合は、自分は無罪放免になり、相棒が裏切り(=自白)の場合は懲役8年になります。自分が戦略を変更する(自白から黙秘に変える)と、懲役はそれぞれ1年と10年になる。戦略を変更すると相手の戦略がどうであれ、懲役が増えることになります。この状況は相手にとっても全く同じです。
ゲームの理論に「ナッシュ均衡」(ナッシュ解)という概念があります。アメリカ人の数学者・ナッシュが提唱したもので、彼はこの功績で1994年のノーベル経済学賞を受賞しています(経済学賞という点に注意)。ちなみにラッセル・クロウ主演の映画「ビューティフル・マインド」は、ナッシュの半生を描いたものです。以下がナッシュ均衡の説明です。
ゲームの理論では、ゲームはプレーヤーの間で行われるが、各プレーヤーは自由に戦略を選択できる。ナッシュ均衡は、以下のように定義される。 |
「囚人のジレンマ」ゲームにおいては、2人とも裏切る(自白する)のが、ちょうどナッシュ均衡になっています。自己の利益を最大化しようとすると、ナッシュ均衡に落ち着く。2人とも黙秘すればそれぞれ懲役1年だから、これが全体最適であることは明白です。しかし自分の利益を最大化しようとするあまりに、2人とも懲役8年になってしまう。これは「自分にだけよい戦略」が、いかにまずい戦略になるかを物語っている例なのです。
しかし「囚人のジレンマ」ゲームのナッシュ解(裏切る=自白するという選択)は、実社会の話だとしたら間違った解であって、そうはならないはずです。実社会では「裏切り」を抑制し、協調を増大させる数々の規制があります。一人が裏切って無罪放免になったとしても、裏切り者は許さないという仲間の掟によって殺されるかもしれない。そうでなくても「その道」の連中から「裏切り者」という烙印を押され、それを一生背負わないといけないでしょう(「その道」で生きていくのなら)。仲間や同業がいないとしても、自白で無罪放免になったけれど相棒が服役している容疑者は「良心の呵責」に悩み続けないといけない(良心があればの話ですが)。
とにかく、社会やコミュニティーのルールや規則、道徳、倫理、宗教、慣習など、一言で言うと「社会規範」が、人間同士の協調を促すように人間に刷り込んでいる。この刷り込みに忠実であれば、2人とも黙秘し、2人とも懲役1年で済むわけです。
ゲームの理論は「社会規範」を考慮していません。従ってゲームの理論をもとに人間の社会行動を解釈したり、行動の指針を作ったりすることは間違いです。ところが、そういった間違いがなされ、特にそれが経済学に応用された結果、人間社会が不幸な状況になっているというのが、著者・吉村さんの見方です。以下は本書からの引用です。
ゲーム理論では社会規範による制約が考慮されていない。協同行動の促進には、多くの社会規範の成立が重要な鍵を握っている。その社会規範(協同行動のルール)の進化によって、小さな集落が村や町に、そして都市から国へと巨大化できた。 |
人間社会は環境の不確定性に備えるための「協力」からはじまった。それが民主主義のスタートラインのはずだった。ところが、その民主主義との両輪であるはずの自由主義が高度に発達するにつれて、様相が変わってきた。「個人の利益を最大限に追求する」ために、経済活動においてはゲーム理論の「ナッシュ解」が成立してしまっているのである。 |
この引用で「民主主義」という言葉が出てきます。人間社会は「強い者の一人勝ちを防ぐしくみ」を発達させてきました。それが「協調の促進」の基礎となるからです。一つの例は「一夫一妻制」ですが(財力と体力があるのなら何人の妻を持とうが、かまわないはずです)「民主主義」もそうだというのが吉村さんの考えであり、上記の文章はその文脈で書かれています。
「民主主義は強い者の一人勝ちを防ぐしくみ」であるというのは確かにそうです。一人一票という意志決定プロセスでは、たとえば「富裕層(少数)」から「非富裕層(多数)」への所得移転を起こすような法律(累進課税など)は制定されますが、その逆は通りにくい。現代社会では「強い者=富める者」であることが多いわけですが、自由経済をベースとする資本主義社会は、最低限、民主主義とセットでないと国がおかしくなることは目に見えています。
そして本書のむすびは次のようになっています。
「自由」という錦の御旗の下に、ナッシュ解を求めていったら、絶滅しかあり得ないことは、約40億年の地球の生物たちの進化史が教えてくれているのである。今、「長期的な利益」のために、「短期的な利益」の追求を控え、協調行動をとるべき時なのだ。 |
これ以降は、この本を読んだ感想です。
「生物の進化」と「人間の社会行動」
この本の大きな特徴は
| ◆ | 生物進化の研究からの知見。つまり、環境変化への適応力と、共生・協力を発達させたものが生き残り、種の持続と発展が保たれること | |
| ◆ | 変化適応力と共生・協調の重要性は、人間の社会行動や人間社会においても同じであり、それが人間社会の存続の鍵であること。 |
の2点を述べていることです。もちろん生物進化の記述が多いわけですが、人間社会にも随分と踏み込んだ記述になっている。そもそも本の「まえがき」にトヨタ自動車の渡辺捷昭(かつあき)社長(2005-2009:社長)の言葉が引用されています。
【トヨタ自動車 渡辺社長】 |
この言葉は別に渡辺社長の発明ではなく、英米では昔から警句としてあったようです。しかし先人の言葉であるにせよ大切なことは、日本を代表する企業、最強と見られている企業のトップがこのような問題意識を持っていることです。著者の吉村さんとしては大いに共感するものがあり、引用したのだと思います。
そして、こういう記述のスタイルが、ひょっとしたら学者仲間からの顰蹙をかっているのではないでしょうか。「進化生物学者は、進化や生態のことを語れ。安易なアナロジーで社会現象を語るべきでない」という反発です。
しかし生物学・生態学・進化論から得られた知見を「思考のツール」として使い、人間社会についての「仮説」を立てることは全くかまわないと思います。もちろん、人間社会についての「仮説」は、人間社会における「事実」によって検証することが前提です。
「安易なアナロジー」という批判は当然出るでしょうが、私にはむしろ数理生態学をベースとする進化研究から得られた知見と、トヨタの渡辺社長(当時)の言っていることが、少なくとも外面的には全く同じであることの方が印象的でした。著者が書いているシーン0からシーン4の「生物進化モデル」を読んで直感的に思うのも、現代社会における企業の発展プロセスとの類似性です。
| シーン0 環境安定期 |
| 経済が成長している時期であり、企業は本業で順調に業績を伸ばします。この間、企業は「次の柱となる事業」のネタをいろいろと仕込みます。これはネタであって業績にはほとんど寄与しないし、外面的には現れません。 |
| シーン1 環境激変期 |
| 経済環境が激変する時期で、企業の業績が急速に悪化します。多くの企業はここで破綻したり、回復不可能なダメージを受けます。 |
| シーン2 適応放散期 |
| 何とか激変期を持ちこたえた企業は、シーン0で仕込んでおいた新たな事業に打って出て、生き残りをはかります。 |
| シーン3 最適化期 |
| 新たな事業も、業績に寄与できるまでに成長するのはわずかです。そのわずかな事業が、本業に続く第2の柱となって企業は活力を取り戻します。 |
実際の企業活動はもっと複雑ですが、
| ・ |
環境激変期における「変化対応力」 | |
| ・ |
環境安定期における「次の事業への投資」 |
共生と協調の社会
共生・協調が人間社会を存続させる鍵であるという著者の主張も、全くその通りだと思います。共生・協調を促進する数々の社会規範は人類が作り上げてきた貴重な財産です。このことを前提にすると、次のことが言える。
共生・協調を否定するような動きがあります。自分たちの信じる思想・考えを唯一無二の正義だと信じ、他者の考えをいっさい聞かず、協調を否定する。あげくの果ては意見が違う他者を攻撃にかかる。こういった「共生・協調の拒否」を内在する思想、政治主義、宗教は、人間社会から排除していくべきものでしょう。
生命科学における共生に関して言うと、植物と動物は炭酸ガスと酸素の交換を通じて「共生」関係にあることは常識です。人間もこの「植物・動物共生系」の一部として生活しています。従って人間社会においても「植物を絶滅に追いやる思想・主義」や、「結果としてある地域の植物を絶滅させることになったとき、そのことに対して何の反省も後悔も感じないような思想や主義」は、この地球上から排除していかねばならないのです。
『強いものは生き残れない』という本から感じ取れる人間の行動指針は、こういった非常にシンプルなことだと思います。それに加えて「人間社会で各人が最大限の自己の利益を追求すると、神の手が働いて全体が最適になる」というのは全くの空論であることを、改めて確認した本でした。あたりまえだけど・・・・・・。
クラバートと千尋
それと同時に、この本のメッセージを個人のレベルで考えることもできます。「大人」が持つべき重要な能力は「外界の変化に即応して自らを変えられる能力」なのですね。子どもが大人になる過程で学ぶべき大切なことは「変化する仕方」です。No.1, 2「千と千尋の神隠しとクラバート」で書いたクラバート少年を思い出します。彼は水車場の3年間でこの能力を身につけたはずで、それはクラバートの「自立」の重要な部分を占めていると思います。「千と千尋の神隠し」の千尋も全く同じです。クラバートと千尋は、それまでとは全く異質な世界に「いやおうなしに」引き込まれます。生きるためには自分を変えないといけない。クラバートにとっての水車場、千尋にとっての湯屋は「変化する仕方」を身にしみて学んだ場であったと考えられます。
もちろん No.2 で既に書いたようにクラバートは職人仲間や少女との「相互扶助」によって水車場から脱出し、自立を完成させます。また千尋もハクとの「相互扶助」によって湯屋から脱出します。そして相互扶助の別名である「共生と協力」もまた、この本の重要なメッセージなのでした。
No.52 - 華氏451度(2)核心 [本]
(前回から続く)
『華氏451度』が描くアンチ・ユートピア(続き)
クラリスの言葉による『華氏451度』の世界の描写(前回の最後の部分参照)は、この世界になじめない側からの発言でした。このクラリスの「世の中からの距離感」がモンターグの心を揺さぶることになるのです。
一方、ファイアーマンの署長であるビーティは「体制側」の人間です。彼がモンターグに、こういう世界ができた経緯や理由を語るシーンがあります。なぜ本が禁止されているのかも語られます。ここが『華氏451度』の核心と言えるでしょう。
[ビーティ] |
この世界では、簡略化、ダイジェスト化、短縮化が徹底的に進んでいます。
『ハムレット』を知っているという連中の知識にしたところで、例の、《これ一冊で、あらゆる古典を読破したとおなじ、隣人との会話のため、必須の書物》という重宝な書物につめこまれた1ページ・ダイジェスト版から仕入れたものだ。わかるかね? 育児室からカレッジへ、それからさらに、もとの育児室へ --- そこに、過去5世紀にわたるおれたち人類の知識の型がみられるんだ。 |
みなに、もっと、もっと、スポーツをやらせる必要がある。あれこそ、団体精神のあらわれであり、人生の興味の中心である。あれをやっていれば、ものを考えることがなくなる。そうじゃないか。 |
現代の学校教育は、研究家、批評家、知識人、創作家育成はやめた。そのかわり、ランニングやジャンプの選手、競馬の騎手、おなじくノミ屋、修繕屋、飛行士、水泳選手といった連中を育て上げる機関となっている。当然のことだが《知性》という言葉は、ここではぜったい禁句なんだ。だれもがいつも、仲間からの疎外をおそれている。 |
気がみじかくなって、公道で車をすっとばす群衆が無数にふえてくるが、いい傾向だ。どこへ行こうかなど、考えることはない。ただ、どこかへ行きさえすればいい。ひしめきあって、車をとばせばいいんで、どこへ行くと、目的地を決める必要はない。いわば、ガソリン避難民。街全体がモーテルに変わり、遊牧民となった人々が、潮の出入りを追って、大波のような移動をつづける。 |
マーケットがひろくなればなるほど、少数派の存在は例外的なケースとして、考慮の外におかねばならん。(・・・・中略・・・・)いよいよ数がすくなくなった少数派には、自分たちのことを自分たちで処理してもらわなければならぬ。つまらんことを考える著者には、タイプライターをしまいこんでもらう。そして、事実、そういうことになった。 |
これはけっして、政府が命令を下したわけじゃないんだぜ。布告もしなければ、命令もしない。検閲制度があったわけでもない。はじめから、そんな工作はなにひとつしなかった!工業技術の発達、大衆の啓蒙、それに、少数派への強要と、以上の三者を有効につかって、このトリックをやってのけたのだ。 |
万事につけ、《なぜ》ってことを知ろうとすると、だれだって不幸になるにきまっている。 |
国民を政治的な意味で不幸にしたくなければ、すべての問題には、ふたつの面があることを教えてはならん。 |
まちがっても、哲学とか社会学とかいった危険なものをあたえて、事実を総合的に考える術を教えるんじゃない。 |
考える人間なんか存在させてはならん。本を読む人間は、いつ、どのようなことを考え出すかわからんからだ。そんなやつらを、一分間も野放しにしておくのは、危険きわまりないことじゃないか。 |
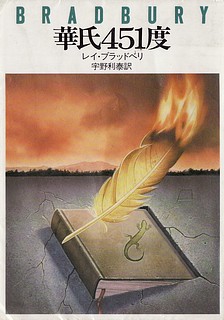
| |||
|
レイ・ブラッドベリ 『華氏451度』 (ハヤカワ文庫NV, 1975) | |||
『華氏451度』の世界でなぜ本が禁止されているのかを、署長のビーティは明確に語っています。なぜ本を禁止するのかと言うと、本を読む行為が蔓延すると社会が危うくなるからなのです。
『華氏451度』における「本」と「本の所有者・読者」の関係は、ちょうど現代日本における「麻薬」と「麻薬所有者・使用者」の関係にそっくりです。麻薬は医療に必要不可欠なものですが、一般の所持・使用は厳しく禁じられています。それは社会をむしばみ、危険に陥れるものだからです。麻薬所持の密告はよくあるし(タレ込みと言うのでしょうか)、発覚すると警察が急襲し、被疑者は逮捕され、起訴・裁判となって処罰され、現物は焼却処分されます。本が麻薬とみなされる世界、それが『華氏451度』の世界です。
なお、署長のビーティですが、彼は老女の最期の言葉が16世紀の英国のヒュー・ラティマーの言葉だと即答しますね(前回の No.51「華氏451度(1)焚書」参照)。彼は本を焼き払う「体制側」の、しかも「指導層」ですが、「体制の指導層」は実は本の世界に精通していることを暗示しています。ないしは、署長のビーティは若い頃には大の読書家だったが、転向して本を抹殺する体制側になったとも考えられます。
いずれにせよ、その体制にとって本を大衆に普及させることがいかに危険か、それがよく理解できる、だから本を禁止する、ということなのでしょう。
『華氏451度』の誤解3:本が禁止されている世界
ブラッドベリの描くアンチ・ユートピアの成り立ちを読むと、この小説は単に「本が禁止されている世界」を描いたものではないことが理解できます。本の禁止は現象面にすぎません。この小説は「本を書いたり読んだりするような少数者が迫害される世界」を描いたものなのです。
『華氏451度』は本が禁止されている世界を描いた小説である、というのは表層的な見方です。本の禁止はその通りなので「誤解」というのは明らかに言い過ぎですが、本質をはずした見方であることは間違いない。
なぜ、本を書いたり読んだりするような少数者が迫害されるのか。まとめると以下のようでしょう。
| ◆ |
大衆社会の進展とともに、刹那的な娯楽がもてはやされ、人々は均質的な欲望を持つようになり、考えることはせず、楽しく平穏無事であることが最大の価値となった。「考えること」は人を不幸にするとみなされている。 | |
| ◆ |
そういう時代、本を読む人は少数者となった。本を読むと、いろんな考えを巡らせ、ものごとの本質に迫ろうとするようになる。そういった少数者は一般社会からみると「うっとうしい存在」であり、多数派の「刹那的価値感をおびやかす存在」である。多数派は本を読むような人を嫌悪するようになり、そしてついには「危険分子」と見なすようになった。 | |
| ◆ | その危険分子を排除し、社会からなくす手段として本の焼却がファイアーマンたちによって行われている。これは決して政府の強権だけで始まったことではない。大衆の合意の上で、むしろ大衆の要望から出来上がった制度である。 |
その「少数者」であり「危険分子」の一人がフェーバー教授です。小説の中でフェーバー教授は、本を読むことの意義として次の3点をあげています。要約すると、
| ◆ | 本にはものごとの本質が示されている。《知》の核心がそこにある。 | |
| ◆ | 本を読むことによって「考える時間」がもてる。内容について、正否を論じあうこともできる。 | |
| ◆ | 「本質」と「考え」の相互作用から、正しい行動にでることができる。 |
の3点です。
言うまでもなく、これらのことがまさに『華氏451度』の世界において「少数者=本を読む者」が排除される理由となっています。そして裏返すと、作者・ブラッドベリの考える「人間にとっての本の意義」でもあるわけです。以上のことをまとめると、
| 『華氏451度』は、究極の「反知性主義」社会を描いた小説である |
と言えるでしょう。
『華氏451度』における作者・ブラッドベリの「思い」
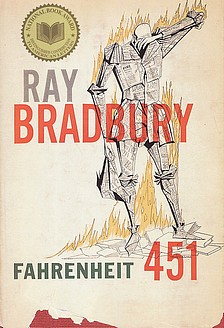
| |||
|
Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Del Ray Book, 1996) このペーパーバックの表紙は、1953年に最初に出版されたハードカヴァーの表紙を採用している
| |||
| メッセージ |
まず非常に分かりやすいのは作者のメッセージです。つまり、
| テレビ(など)の「感覚的で、与えられる情報メディア」ばかりに接し、本を読まなくなると、そのうち人間は考えることをしなくなり、その結果として為政者にいいように操縦される烏合の衆と化してしまうぞ |
という警告です。『華氏451度』はこの警告を、手をかえ品をかえて描き出した小説と考えられます。これは読者にとって非常に分かりやすい。本は人類の知的資産の集合であり、それを大切にすることの重要性は誰しも納得できるはずです。
しかし『華氏451度』をそういう「分かりやすい警告を発した本」と思って安心して読んでいると、途中から「あれ、そんなはずじゃ・・・・・ 」と感じるようになるのです。
| バイアス |
バイアスというのは、作者のものの見方が少々「偏って(かたよって)」いることを言っています。人間誰しも自分なりの「偏り」があるわけで、そうだからといって非難されるわけでは全くありません。「偏り」と書くとマイナスイメージになるので「バイアス」とします。
ブラッドベリの考えには独特のバイアスがあります。たとえば『華氏451度』の世界ではスポーツが奨励され、学校教育でも重視されています。ちょっと極端に言うと「スポーツは、考えない大衆を作りだす手段」と言わんばかりの書き方がされているのです。
また書物のダイジェスト版やラジオにおける名作のダイジェスト放送、雑誌、漫画、などは『華氏451度』の世界で大手を振って流通しています。作者に言わせると、これらは知性には関係ないメディアということなのでしょう(漫画は、1950年代のアメリカ漫画を想像しないといけません)。「美術館には抽象画ばかりが並んでいる」という記述も、作者の「抽象画嫌い」がバックにあるような気がします。
小説の中で、焼却された本として名前があがっている作者もそうです(No.51参照)。古代ギリシャの劇作家からフォークナーまで、個人的経験を言うと、そのうちの2~3の本は読んだことがありますが、ほとんどは読んでいません。仮に名前のあがっている作者の本が今地球上から無くなったとしても、個人的には何の不都合もないのです。もちろん、ここにあがっているのは一部だということは分かるし、すべての本が無くなると考えると恐ろしい。しかし小説を読み進むうちに、ブラッドベリの基準からすると自分は「本に固執する少数派」なのか「本はなくてもよい多数派」なのか、どちらなのかという余計な疑いが出てくるのですね。はじめは「当然、自分は少数派だ、迫害される方だ」と思っているのですが、読み進むうちにそれは本当かという疑念が湧いてくる。果たして本のために「死ぬかもしれないリスク」をとれるのか? 自分は『華氏451度』の世界では、実は、少数者を密告し迫害する方ではないのかと・・・・・・。こう思わせるのは、ブラッドベリの「バイアス」のせいだと思います。
ある本好きの少年がいたとします。小さいころから本が好きで好きでたまらず、小学校の図書室の本は全部読破したような少年です。学校の勉強も大好きで一所懸命やるから、成績はトップクラス。そのかわり性格は内向的で、友達づきあいがうまくできず、女の子からはもてない。運動が苦手で、スポーツは大嫌い。クラスメートからは「ガリ勉」と揶揄されている。家にいても母親から「そんなに本ばかり読んでないで、外で遊んできなさい!」と追い出される。外に出ても友達と遊ぶのではなく、一人で公園に行き、花や虫を見つめ、本で読んだことを夢想する。そして星が出てきた頃、家に帰る。ちょうど、小説に出てくるクラリスのように・・・・・・。
ブラッドベリがこのような少年だったかどうかは知りません。正反対の、外向的でクラスの人気者のような少年だったかもしれない。しかし『華氏451度』を読むと、上に書いたような本好き少年がそのまま大人になって、その思いや、無理解な周囲への「うらみごと」をぶつけたような感じを受けるのですね。何となく屈折しているような、オタクっぽい雰囲気がある(悪いといっているのではありません)。ちょっと「ついていけない感じ」もします。
しかし実は、こういったバイアスがかかった雰囲気がこの小説を大変魅力的にしているのだと思います。「本は大切だ」というようなメッセージを述べただけなら、おもしろくも何ともない。この小説の価値は半減したはずです。
| ペシミズム |
さらにこの小説で感じるのは、全体に何となく漂うペシミズムです。ブラッドベリの「思い」は次のようなものではないでしょうか。
| ◆ | 本が大好きで、本を始終読んでいる(自分のような)人間は、いずれ社会の少数者になり、そして迫害されるだろう。 | |
| ◆ | 科学技術やマスメディアの発達によって、人間は数千年の長きに渡って培ってきた「人間らしさ」や「知的財産」を失っていき、いずれ動物的感覚だけで生きる存在に堕ちていくに違いない。 |
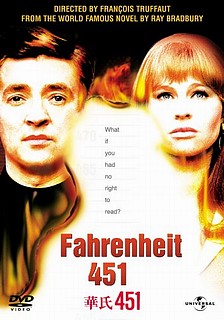
| |||
|
1966年にフランソワ・トリュフォー監督は『華氏451度』を映画化した。
主演:オスカー・ウェルナー、ジュリー・クリスティー | |||
ファイアーマンたちはノズルから「石油」を撒き、火焔放射器で本を焼却します。まるで「毒液」の代名詞のように繰り返される「石油」という言葉に、作者は人類の知の遺産を蝕んでいく文明を象徴させたように思います。
さらに『華氏451度』の世界では、街の上空にジェット機の編隊や爆撃機が飛びかっています。もうすぐ戦争が始まるようなのです(小説の途中で宣戦布告がある)。しかも戦争は短期で、何度も繰り返されているらしいのです。刹那的・感覚的に生きる多数の人々と、その人々とは無関係かのように国のどこか行われている戦争・・・・・・。この殺伐とした世界が文明の行き着く先だと言っているようです。
もちろん、ペシミズムだけというわけではありません。小説の最後には、本の内容を暗記で伝承していこうとする人々が出てきて(仲間はかなりの数です)、次の未来を彼らに託そう、という書き方になっています。しかし全体的に言うと、人間社会は堕ちるところまで堕ちるのだろうという、ほとんど妄想に近いような悲観的見方を感じるのです。
「バイアス」がこの小説を魅力的にしていると書きましたが、このような「ペシミズム」の雰囲気は、さらにこの小説を読者に対する問題提起の本にしていると思います。果たしてブラッドベリの想念は正しいのか、杞憂なのか、妄想だと片付けてよいのか。人間社会はこのアンチ・ユートピアの方向へ向かうのか。それとも全くその逆なのか、というような・・・・・・。
一面の真実を突いた極端な意見・ものの見方は、その前提で考えれば有益なことも多いと思います。
『華氏451度』の今日的意味
『華氏451度』が出版されたのは1953年です。この後、世界の状況は大きく変わりました。冷戦が終了し、ベルリンの壁が崩壊しました(それを促したのは、ブラッドベリが「嫌っている」テレビだと言われています)。1990年代以降はインターネットが爆発的に普及しました。インターネットにおけるホームページ、ブログ、SNS、ツィッター、動画共有サイトなどは、個人が不特定多数に対して情報発信することを可能にしました。個人が「放送局」を持つことも難しいことではありません。2011年に起こったアラブ諸国の民主化(いわゆる、アラブの春)は、インターネットなしには考えられないと思います。だからこそ、現代の独裁政権はインターネットの規制に躍起になっています。
また1953年当時と比較して出版事情も大きく変化しました。数だけからいうと、本の出版件数は飛躍的に増大しています。『華氏451度』の世界とは逆のように見えます。
そしてこの小説に関連して最も大切なことですが、本に関する状況が今、大きく変化しようとしています。それは電子書籍の本格的な普及のきざしです。デジタルデータで購入した本を専用端末やスマートフォン、タブレットPCで読むようなことが、いずれ一般的になるのかもしれません。新刊書がデジタルデータで、ないしはデジタルと紙の両方で提供されるようになると、本を読むという行為はどう変化していくのでしょうか。または変化しないのでしょうか。電子書籍はそれによって得るものも大きいが、失うものもありそうです。
このような現代の状況は『華氏451度』のアンチ・ユートピアから遠ざかったのか、それとも逆に少し近づいているのかを考えるべきでしょう。その判定ポイントは人間がより「考えるようになる」のか「考えなくなる」のか、です。考えることによって、さまざまな意見やモノの見方が生まれ、発展があるのだと思います。「多様化」「多様性」がキーワードです。それは生物も同じです。同質化し、特定環境に適合し過ぎた生物は、わずかの環境変化で絶滅してしまいます。
現代社会を一言でいうと、経済的には市場原理にもとづく資本主義社会ですが、そのバックボーンは民主主義にもとづく意志決定システムです。この民主主義の社会において、国民は一人一票の投票権をもつのですが(現代日本では実質的に一人一票からかけ離れてることが問題なのですが)、実はこのシステムがうまく機能する暗黙の大前提は「一人一人が考える人間」であることなのですね。これが崩れると、どんな異常な世界も現出するはずです。それは歴史が証明しています。もっともその時に異常だと思うのは、少数の迫害されかねない人たちだけだとは思いますが・・・・・・。
『華氏451度』は、メディアが多様化し、電子出版が立ち上がりはじめている現代にこそ、我々に熟考すべき本質的な課題をつきつけていると思います。
(続く)
No.51 - 華氏451度(1)焚書 [本]
No.28「マヤ文明の抹殺」において、16世紀に中央アメリカにやってきたスペイン人たちがマヤの文書をことごとく焼却した経緯を紹介したのですが、そこで、ブラッドベリの名作『華氏451度』を連想させる、と書きました。今回はその連想した本の感想を書きます。米国の作家、レイ・ブラッドベリ(1920 - )の『華氏451度』(宇野利泰・訳。早川書房)です。
華氏451度(Fahrenheit 451 : Ray Bradbury 1953)
まず、この小説のあらすじです。後でも触れますが、1953年に出版された小説ということが大きなポイントです。
未来のある国の話です。どこの国なのか、最初は分からないのですが、途中からアメリカの地名がいろいろ出てきて、舞台が未来のアメリカであることが分かります。
その時代、本の所持と本を読むことが禁止されています。本の所持が見つかると、焚書官と呼ばれる公務員が発見現場に急行し、本を焼きます。小説の題名の華氏451度は摂氏233度に相当し、紙の発火温度を示します。
焚書官と訳されていますが、原文ではファイアーマン(fireman)です。言うまでもなく消防士のことですが、この時代には建物が完全耐火建築になり、消防士(ファイアーマン)は不要になりました。消防士は焚書官(ファイアーマン)となり、かつての消防ホースを石油を放射するノズルに持ち換えて集めた本に噴射し、火焔放射器で焼き尽くすのを任務としています。本の所持については密告が奨励されていて、相互監視社会が実現しています。
小説の主人公のガイ・モンターグはファイアーマンです。年は30歳過ぎで、妻のミルドレッドと2人暮らしです。夫婦に子供はなく、2人の関係は冷えています。
この時代、家の壁がテレビになっていて、数々の娯楽が提供されています。モンターグの家にも「テレビ室」があり、そこは部屋の3面が「テレビ壁」になっています。ミルドレッドはもっぱらテレビに没入する生活を送っていて、もう1面の壁もテレビ壁にしたいと考えています。また人々には「海の貝」と呼ばれる超小型ラジオが提供されています。これは耳の穴に装着できるもので、音楽や娯楽やニュースが流されます。
小説は、主人公のモンターグの任務の光景から始まります。冒頭は次のようです。
モンターグはファイアーマンとしての任務を果たしていくのですが、2人の女性との出会いをきっかけに、彼の中で何かが変わり始めました。
一人は、モンターグの家の隣に引っ越してきた17歳の少女、クラリス・マックルランです。モンターグは家の周辺や公園でたびたびクラリスと顔を合わせます。クラリスは変わった子です。月を眺め、鳥を観察し、芝生のタンポポを見つめ、木の実を拾い、蝶を集め、夜明けに草の葉に露がたまることを知っています。人間観察が得意で、モンターグの職業を知って「あんた幸福なの?」と聞きます。
もう一人はある老女です。その老女が本を所有しいるという密告があり、ファイアーマンたちは老女の家を急襲しました。そして本を集めて家もろとも焼き払おとしたとき、老女は自ら石油に火をつけてその中で自殺してしまいます。モンターグは、その老女にとっては本が命と同じ程度に大切であったことを知りました。
モンターグは本への興味を押さえられなくなります。いったい本には何が書いてあるのか・・・・・・。一生かけて一冊の本を書いた人もいる、と聞いたことがある。本とはそれほどの価値があるものか・・・・・・と。
実は、モンターグは本を持っていました。この1年ほどの間、仕事で本を焼却する時にそっと1冊づつ持って帰り、家に隠していたのです。自殺した老女の本からも1冊持って帰りました。合計20冊程度です。モンターグはそれを堂々と妻の前で取り出し、読み始めようとします。妻のミルドレッドは驚いて、自分たちの生活がだいなしになる、やめるようにと言いますが、モンターグの意志は堅く、逆に妻にも読むように勧めます。
モンターグは今後の行動について、誰かに相談する必要があると考えました。思い当たったのは、以前に公園で話をし、電話番号を交換したフェイバーという名の大学教授です。彼なら本に好意的だと推測したのです。モンターグは本を1冊もって老教授を訪問します。教授はモンターグの立場に立って、なぜ本が大切なのか、これからどう行動すべきかを教えました。
ある日、モンターグが署(fire station)で勤務していると、密告を告げるサインが鳴りました。署長のビーティやモンターグを含む焚書官たちが現場に急行したのですが、その現場はモンターグ本人の家でした。妻のミルドレッドが密告したのです。署長のビーティはモンターグに向かってバカなことをしたものだ、処罰すると言い、本と家を焼き払おうとします。しかしその場でモンターグは、署長を火焔放射器で殺害してしまいます。
全警察から追われる身となったモンターグは、街を逃げ回ります。そして河にたどり着き、河を泳いで郊外に逃げ延びました。そこで野宿をしている5人の老人のグループに出会います。老人たちは、ポータブル受信機でモンターグの逃亡を良く知っていました。そして彼を暖かく迎えます。
実はこの老人たちは元大学教授や元聖職者で、他にもいる仲間と連携し、禁止されている本を暗記し、それを後世に伝えているのでした。仲間全体はかなりの数のようです。各人はどの本を暗記・暗誦するかの担当が決まっています。モンターグはこの人たちと行動をともにすることにしました。
小説はこの後に最後の展開があるのですが、割愛したいと思います。未来へのかすかな希望も示されます。以下に、この小説についてのコメントを何点かあげます。まず『華氏451度』についての2つの誤解からです。
『華氏451度』の誤解1:情報統制が徹底した全体主義社会
小説『華氏451度』に触れた文章で何回か目にしたのは、この小説が民主主義とは対極にある「独裁者による情報統制と検閲が徹底した全体主義社会」を描いたように評したものです。
現代も独裁国家でありますよね。独裁者・政府に都合のよい情報だけが流通し、それに反対したり異論をとなえたりすることは許されず、批判するとすぐに逮捕される、というような国が・・・・・・。そういう国では、反政府・反独裁者の書物は検閲され、没収され、焼却されます。独裁権力が有害で「禁書」と宣告した書物も破棄されます。
ナチス・ドイツの「焚書」を思い出します。ナチスによって「非ドイツ的」と宣告された本、つまり社会主義関係の本やユダヤ人作家の本、ブレヒト、レマルク、ハイネなどが燃やされました。また、ナチスから2000年以上前には、秦の始皇帝の「焚書坑儒」がありました。皇帝を頂点とする中央集権制を徹底させるために、それに反する思想(封建制など)である諸子百家の書物や、秦以外の歴史書が焼却されたわけです。さらにその600年後のローマ帝国では、キリスト教の国教化とともに図書館が閉鎖され「異教の本」が散逸しました(No.27「ローマ人の物語(4)」参照)。
しかし「本を燃やす」ということをもってナチスや秦の焚書をイメージすると『華氏451度』を誤解してしまうのですね。『華氏451度』は独裁者による情報統制と検閲が徹底した全体主義社会を描いた小説ではありません。全く違います。『華氏451度』は「本が禁止された社会」を描いた小説なのです。そこで描写されている「焚書」も、歴史上のナチスや秦の焚書とは意味が違います。「本を禁止する」という意味での「焚書」なのです。特定の思想や主張の本が禁止されているとか、特定の歴史書以外が全部禁止されているとか、そういうことはこの小説には一切出てこないのです。
No.28「マヤ文明の抹殺」においてブラッドベリの名作『華氏451度』を連想させると書いたのも、内容の如何にかかわらず、すべてのマヤ文書が焼却されてしまったからでした。
『華氏451度』の誤解2:活字印刷物を否定した社会
もう一つの(小さな)誤解は、『華氏451度』はすべての活字印刷物を否定した社会だという誤解です。
小説のはじめの方でミルドレッドがモンターグに、テレビ壁で放送されるドラマの台本が送られてきた、と言う場面があります。この台本はあきらかに印刷物です。また小説の中には、業界紙、雑誌、漫画、それを読めばすべての古典が分かるという「超ダイジェスト本」、焚書官が持っている「服務規程」、などの印刷物に言及されています。こういった「実務的印刷物」や「消費材としての印刷物」は、この世界においてもあります。大手を振って流通している本もあるのです。
ブラッドベリも分かっています。すべての活字印刷物を否定したのでは(現代)社会は運営できません。この社会では「消費材としての印刷物」は許容されていて、「知的財産としての書物」が否定されているのです。
『華氏451度』における「本」とは何か
『華氏451度』の世界では「本」が極めて広範囲に禁止されています。ファイアーマンの署には、百万ばかりの禁止書物のリストがある、との記述もあります。では、どういうたぐいの本が禁止されているのでしょうか。ここで、小説に中に現れる「禁止されている本の著者の例(一部は本の題名)」を歴史年代順にリストしてみたのが、右の表です。
一見して分かることは、古代ギリシャ時代からブラッドベリの同時代人(フォークナーは23歳年上)まで、きわめて幅広いことです。また、有名な人物が多数ある反面、あまり世界的には知られていない作家もあります。ピランデルロ、ガセット、オニールなどです(ピランデルロ、オニールはノーベル文学賞作家)。そしてこれら作家の書いた本は、戯曲、歴史、小説、詩、批評、評論、エッセイ、哲学、政治、宗教、社会学、物理学などの書物です。要するに『華氏451度』で具体的にあげられてる本は、人類の知的財産とでも言うべき本(の作者。主として文化系)です。かつ、アメリカ人・ブラッドベリからみた「知的財産」であって、ここには紫式部もドストエフスキーも「アラビアン・ナイト」もないわけです。ブラッドベリが小説の主題としている「本」とは、このようなたぐいの本であることが分かります。
リストには「異色の」人物として、第16代ローマ皇帝、マルクス・アウレリウスの名前がありますが、彼は「哲人皇帝」と言われたほどの人で「自省録」という本を書きました。ローマのカピトリーノ美術館に有名な騎馬像があります(No.25「ローマ人の物語(2)」参照)。塩野七生著「ローマ人の物語 第11巻 終わりの始まり」にはマルクス・アウレリウス帝が活写されています。
なお『華氏451度』の日本語訳では、マルクス・アウレリウス(英語表記:Marcus Aurelius)を、英語読みそのままに「マーカス・オーレリアス」としてありますが、これでは日本の読者にとっては誰のことなのか分かりません。ローマ皇帝という注釈もない。英語読みがよく知られているシーザー(=カエサル)ならともかく、日本で一般的なラテン語読みにすべきでしょう。『華氏451度』にあげられている「本の著者」の中で2回以上名前が出てくる数少ない人物の一人です。
物理学者のアインシュタインも「異色」ですが、一人ぐらいは科学者を入れておきたかったということではと思います。「ブラッドベリ」の名前がありませんが、さすがに気が引けたのかも知れません。
ブラッドベリの言う「本」がどういうたぐいのものか、それを象徴する場面が『華氏451度』の中にあります。隣人が本を所持しているという密告をうけて、ファイアーマンたちが老女の家を急襲する場面です。
あらすじに書いたように、老女は自ら石油に火をつけて自殺するのですが、署に戻る車の中でモンターグは老女の最期の言葉が気になります。「リドリー教授・・・・・・」というのは一体何のことなのか。
それに対して署長のビーティが答えます。
『華氏451度』の読者は、この老女の言葉と署長の解説が、いったいどういうことなのか分からないのではないでしょうか。「オックスフォード」「火刑」「異端」? 私も本を読んだときは分かりませんでした。次のようなことなのです。
16世紀の英国史です。ヘンリー8世は英国史の重要人物であり、数々のエピソード(血なまぐさいものも含めて)には事欠かない国王です。ヘンリー8世の「功績」一つは、カトリック教会から分離した英国国教会の設立です。おりしもヨーロッパ大陸ではプロテスタント運動が盛んで(フランスの状況は、No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」を参照)それは英国にも波及していました。
ところがヘンリー8世の2代あとのメアリー1世(ヘンリー8世の娘)になると「揺り戻し」が起こるのです。彼女は敬虔なカトリック教徒です。そしてプロテスタントの弾圧に乗り出し、延べ300人以上を処刑しました。このためメアリー1世は、ブラッディ・メアリー(Bloody Mary。血まみれのメアリー)という通称がついています。
このとき処刑されたプロテスタントに、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimer)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という聖職者がいたのです。2人はオックスフォードで同時に処刑されました。『華氏451度』で老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉と言われているものです。これはジョン・フォックス(John Foxe)という同時代人が書いた「殉教者列伝」(The Book of Martyrs)に出てきます。
要するに『華氏451度』に出てくる老女は、16世紀の英国史に精通していた、というのが小説としての設定なのです。もちろん、本を家もろとも焼き払われる中で老女が自殺することと、16世紀のプロテスタントの火刑=殉教が重ね合わされています。信念のためには、死をも厭わないというわけです。署長のビーティはわざわざ「異端の罪で」と言っていますね。反体制側からみると「殉教」ですが、体制側からすると「異端」です。ブラッドベリは慎重に言葉を選んでいます。『華氏451度』で作者が主題にしたい本の世界の《知》は、こういうレベル《知》(この場合は英国の歴史)だということの象徴でしょう。
さらに『華氏451度』の中で唯一、文学作品の直接の引用が出てくる箇所があります。モンターグがミルドレッドに、文学とはこういうものと教えるために詩を朗読します。「ドーヴァーの岸辺」という詩です。作者の名は書かれていませんが、これは19世紀イギリスの詩人で文明批評家のマシュー・アーノルド(Matthew Arnold 1822-1888)の作品です(原題は "Dover Beach" )。ブラッドベリの愛好する「本」を表しているではと思います。
『華氏451度』が描くアンチ・ユートピア
『華氏451度』は、アンチ・ユートピア(反ユートピア。ディストピア)を描いてみせた小説です。「本の禁止」をベースとするこの世界は以下のようなものです。
国民の娯楽と情報源は、各家庭にある「テレビ壁」と、皆に配られている超小型ラジオ「海の貝」です。「海の貝」は耳の孔に装着するものです。モンターグの妻のミルドレッドは装着していることが多いので「読唇術がうまくなった」との記述があるくらいです。
この小説か発表されたのは1953年です。アメリカでテレビ放送が始まったのは1940年で、あたりまえですが1953年では小型の白黒のブラウン管テレビしかありません(NHKのTV放送開始がちょうど1953年です)。ラジオ放送が始まってからはだいぶたちますが、現在の高性能小型イヤフォンはもちろんない。1953年の時点において、現在の大型液晶テレビを居間で見て、ステレオイヤフォンを長時間つけているライフスタイルを予見したかのようなこの小説の記述には驚きます。
クラリスという少女は、この世界になじめない人間です。彼女がモンターグに語る言葉から、この世界の実態が見えてきます。何点か引用してみます(太字は原文にはありません)。
まずこの時代は、ジェット・カーと呼ばれる非常に速く走るクルマが一般的になっています。
クラリスは、今はもう学校に行っていません。学校に失望しているのです。
クラリスが語る『華氏451度』の世界を、いくつかのキーワードで表現してみると「機械化」「パターン化」「スピード化」「簡略化」「没個性」「衝動的」という感じでしょう。
華氏451度(Fahrenheit 451 :
まず、この小説のあらすじです。後でも触れますが、1953年に出版された小説ということが大きなポイントです。
(以下に物語のストーリーが明らかにされています)
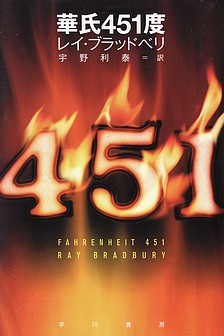
| |||
|
レイ・ブラッドベリ 『華氏451度』 宇野 利泰 訳 (ハヤカワ文庫SF, 2008) | |||
その時代、本の所持と本を読むことが禁止されています。本の所持が見つかると、焚書官と呼ばれる公務員が発見現場に急行し、本を焼きます。小説の題名の華氏451度は摂氏233度に相当し、紙の発火温度を示します。
焚書官と訳されていますが、原文ではファイアーマン(fireman)です。言うまでもなく消防士のことですが、この時代には建物が完全耐火建築になり、消防士(ファイアーマン)は不要になりました。消防士は焚書官(ファイアーマン)となり、かつての消防ホースを石油を放射するノズルに持ち換えて集めた本に噴射し、火焔放射器で焼き尽くすのを任務としています。本の所持については密告が奨励されていて、相互監視社会が実現しています。
小説の主人公のガイ・モンターグはファイアーマンです。年は30歳過ぎで、妻のミルドレッドと2人暮らしです。夫婦に子供はなく、2人の関係は冷えています。
この時代、家の壁がテレビになっていて、数々の娯楽が提供されています。モンターグの家にも「テレビ室」があり、そこは部屋の3面が「テレビ壁」になっています。ミルドレッドはもっぱらテレビに没入する生活を送っていて、もう1面の壁もテレビ壁にしたいと考えています。また人々には「海の貝」と呼ばれる超小型ラジオが提供されています。これは耳の穴に装着できるもので、音楽や娯楽やニュースが流されます。
小説は、主人公のモンターグの任務の光景から始まります。冒頭は次のようです。
火の色は愉しかった。 |
モンターグはファイアーマンとしての任務を果たしていくのですが、2人の女性との出会いをきっかけに、彼の中で何かが変わり始めました。
一人は、モンターグの家の隣に引っ越してきた17歳の少女、クラリス・マックルランです。モンターグは家の周辺や公園でたびたびクラリスと顔を合わせます。クラリスは変わった子です。月を眺め、鳥を観察し、芝生のタンポポを見つめ、木の実を拾い、蝶を集め、夜明けに草の葉に露がたまることを知っています。人間観察が得意で、モンターグの職業を知って「あんた幸福なの?」と聞きます。
もう一人はある老女です。その老女が本を所有しいるという密告があり、ファイアーマンたちは老女の家を急襲しました。そして本を集めて家もろとも焼き払おとしたとき、老女は自ら石油に火をつけてその中で自殺してしまいます。モンターグは、その老女にとっては本が命と同じ程度に大切であったことを知りました。
モンターグは本への興味を押さえられなくなります。いったい本には何が書いてあるのか・・・・・・。一生かけて一冊の本を書いた人もいる、と聞いたことがある。本とはそれほどの価値があるものか・・・・・・と。
実は、モンターグは本を持っていました。この1年ほどの間、仕事で本を焼却する時にそっと1冊づつ持って帰り、家に隠していたのです。自殺した老女の本からも1冊持って帰りました。合計20冊程度です。モンターグはそれを堂々と妻の前で取り出し、読み始めようとします。妻のミルドレッドは驚いて、自分たちの生活がだいなしになる、やめるようにと言いますが、モンターグの意志は堅く、逆に妻にも読むように勧めます。
モンターグは今後の行動について、誰かに相談する必要があると考えました。思い当たったのは、以前に公園で話をし、電話番号を交換したフェイバーという名の大学教授です。彼なら本に好意的だと推測したのです。モンターグは本を1冊もって老教授を訪問します。教授はモンターグの立場に立って、なぜ本が大切なのか、これからどう行動すべきかを教えました。
ある日、モンターグが署(fire station)で勤務していると、密告を告げるサインが鳴りました。署長のビーティやモンターグを含む焚書官たちが現場に急行したのですが、その現場はモンターグ本人の家でした。妻のミルドレッドが密告したのです。署長のビーティはモンターグに向かってバカなことをしたものだ、処罰すると言い、本と家を焼き払おうとします。しかしその場でモンターグは、署長を火焔放射器で殺害してしまいます。
全警察から追われる身となったモンターグは、街を逃げ回ります。そして河にたどり着き、河を泳いで郊外に逃げ延びました。そこで野宿をしている5人の老人のグループに出会います。老人たちは、ポータブル受信機でモンターグの逃亡を良く知っていました。そして彼を暖かく迎えます。
実はこの老人たちは元大学教授や元聖職者で、他にもいる仲間と連携し、禁止されている本を暗記し、それを後世に伝えているのでした。仲間全体はかなりの数のようです。各人はどの本を暗記・暗誦するかの担当が決まっています。モンターグはこの人たちと行動をともにすることにしました。
小説はこの後に最後の展開があるのですが、割愛したいと思います。未来へのかすかな希望も示されます。以下に、この小説についてのコメントを何点かあげます。まず『華氏451度』についての2つの誤解からです。
『華氏451度』の誤解1:
小説『華氏451度』に触れた文章で何回か目にしたのは、この小説が民主主義とは対極にある「独裁者による情報統制と検閲が徹底した全体主義社会」を描いたように評したものです。
現代も独裁国家でありますよね。独裁者・政府に都合のよい情報だけが流通し、それに反対したり異論をとなえたりすることは許されず、批判するとすぐに逮捕される、というような国が・・・・・・。そういう国では、反政府・反独裁者の書物は検閲され、没収され、焼却されます。独裁権力が有害で「禁書」と宣告した書物も破棄されます。
ナチス・ドイツの「焚書」を思い出します。ナチスによって「非ドイツ的」と宣告された本、つまり社会主義関係の本やユダヤ人作家の本、ブレヒト、レマルク、ハイネなどが燃やされました。また、ナチスから2000年以上前には、秦の始皇帝の「焚書坑儒」がありました。皇帝を頂点とする中央集権制を徹底させるために、それに反する思想(封建制など)である諸子百家の書物や、秦以外の歴史書が焼却されたわけです。さらにその600年後のローマ帝国では、キリスト教の国教化とともに図書館が閉鎖され「異教の本」が散逸しました(No.27「ローマ人の物語(4)」参照)。
しかし「本を燃やす」ということをもってナチスや秦の焚書をイメージすると『華氏451度』を誤解してしまうのですね。『華氏451度』は独裁者による情報統制と検閲が徹底した全体主義社会を描いた小説ではありません。全く違います。『華氏451度』は「本が禁止された社会」を描いた小説なのです。そこで描写されている「焚書」も、歴史上のナチスや秦の焚書とは意味が違います。「本を禁止する」という意味での「焚書」なのです。特定の思想や主張の本が禁止されているとか、特定の歴史書以外が全部禁止されているとか、そういうことはこの小説には一切出てこないのです。
No.28「マヤ文明の抹殺」においてブラッドベリの名作『華氏451度』を連想させると書いたのも、内容の如何にかかわらず、すべてのマヤ文書が焼却されてしまったからでした。
『華氏451度』の誤解2:
もう一つの(小さな)誤解は、『華氏451度』はすべての活字印刷物を否定した社会だという誤解です。
小説のはじめの方でミルドレッドがモンターグに、テレビ壁で放送されるドラマの台本が送られてきた、と言う場面があります。この台本はあきらかに印刷物です。また小説の中には、業界紙、雑誌、漫画、それを読めばすべての古典が分かるという「超ダイジェスト本」、焚書官が持っている「服務規程」、などの印刷物に言及されています。こういった「実務的印刷物」や「消費材としての印刷物」は、この世界においてもあります。大手を振って流通している本もあるのです。
ブラッドベリも分かっています。すべての活字印刷物を否定したのでは(現代)社会は運営できません。この社会では「消費材としての印刷物」は許容されていて、「知的財産としての書物」が否定されているのです。
『華氏451度』における
| ||||||||
| ||||||||
一見して分かることは、古代ギリシャ時代からブラッドベリの同時代人(フォークナーは23歳年上)まで、きわめて幅広いことです。また、有名な人物が多数ある反面、あまり世界的には知られていない作家もあります。ピランデルロ、ガセット、オニールなどです(ピランデルロ、オニールはノーベル文学賞作家)。そしてこれら作家の書いた本は、戯曲、歴史、小説、詩、批評、評論、エッセイ、哲学、政治、宗教、社会学、物理学などの書物です。要するに『華氏451度』で具体的にあげられてる本は、人類の知的財産とでも言うべき本(の作者。主として文化系)です。かつ、アメリカ人・ブラッドベリからみた「知的財産」であって、ここには紫式部もドストエフスキーも「アラビアン・ナイト」もないわけです。ブラッドベリが小説の主題としている「本」とは、このようなたぐいの本であることが分かります。
リストには「異色の」人物として、第16代ローマ皇帝、マルクス・アウレリウスの名前がありますが、彼は「哲人皇帝」と言われたほどの人で「自省録」という本を書きました。ローマのカピトリーノ美術館に有名な騎馬像があります(No.25「ローマ人の物語(2)」参照)。塩野七生著「ローマ人の物語 第11巻 終わりの始まり」にはマルクス・アウレリウス帝が活写されています。
なお『華氏451度』の日本語訳では、マルクス・アウレリウス(英語表記:Marcus Aurelius)を、英語読みそのままに「マーカス・オーレリアス」としてありますが、これでは日本の読者にとっては誰のことなのか分かりません。ローマ皇帝という注釈もない。英語読みがよく知られているシーザー(=カエサル)ならともかく、日本で一般的なラテン語読みにすべきでしょう。『華氏451度』にあげられている「本の著者」の中で2回以上名前が出てくる数少ない人物の一人です。
物理学者のアインシュタインも「異色」ですが、一人ぐらいは科学者を入れておきたかったということではと思います。「ブラッドベリ」の名前がありませんが、さすがに気が引けたのかも知れません。
ブラッドベリの言う「本」がどういうたぐいのものか、それを象徴する場面が『華氏451度』の中にあります。隣人が本を所持しているという密告をうけて、ファイアーマンたちが老女の家を急襲する場面です。
かれらは正面のドアをおしやぶって、老女をひとりつかまえた。しかし、その老女たるや、走り出すようすもなければ、逃げだそうとする気持ちもないらしい。ただ、そこにつっ立ったまま、左右にからだをゆするばかりだ。眼はなにを見るまでもなく、前方の壁に、ピタッとむけられているだけ。だれかから、おそろしい一撃を、頭にくらったようなかっこうである。口のなかで、舌をうごかしている。記憶をよびもどそうとする眼つきをみせていたが、やがて、それを思いだしたものか、舌のうごきがことばになった。 |
あらすじに書いたように、老女は自ら石油に火をつけて自殺するのですが、署に戻る車の中でモンターグは老女の最期の言葉が気になります。「リドリー教授・・・・・・」というのは一体何のことなのか。
それに対して署長のビーティが答えます。
「ラティマーという男がいっていることばさ。ニコラス・リドリーという男が、オックスフォードで、生きながら火刑になったそうだ。異端の罪で、1555年の10月16日のことと聞いている」 |
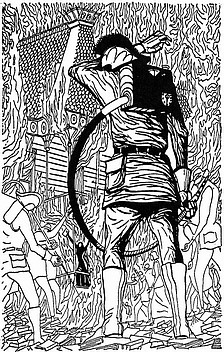
| |||
|
『華氏451度』より (小説の1シーンを表現している) | |||
16世紀の英国史です。ヘンリー8世は英国史の重要人物であり、数々のエピソード(血なまぐさいものも含めて)には事欠かない国王です。ヘンリー8世の「功績」一つは、カトリック教会から分離した英国国教会の設立です。おりしもヨーロッパ大陸ではプロテスタント運動が盛んで(フランスの状況は、No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」を参照)それは英国にも波及していました。
ところがヘンリー8世の2代あとのメアリー1世(ヘンリー8世の娘)になると「揺り戻し」が起こるのです。彼女は敬虔なカトリック教徒です。そしてプロテスタントの弾圧に乗り出し、延べ300人以上を処刑しました。このためメアリー1世は、ブラッディ・メアリー(Bloody Mary。血まみれのメアリー)という通称がついています。
このとき処刑されたプロテスタントに、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimer)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という聖職者がいたのです。2人はオックスフォードで同時に処刑されました。『華氏451度』で老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉と言われているものです。これはジョン・フォックス(John Foxe)という同時代人が書いた「殉教者列伝」(The Book of Martyrs)に出てきます。
要するに『華氏451度』に出てくる老女は、16世紀の英国史に精通していた、というのが小説としての設定なのです。もちろん、本を家もろとも焼き払われる中で老女が自殺することと、16世紀のプロテスタントの火刑=殉教が重ね合わされています。信念のためには、死をも厭わないというわけです。署長のビーティはわざわざ「異端の罪で」と言っていますね。反体制側からみると「殉教」ですが、体制側からすると「異端」です。ブラッドベリは慎重に言葉を選んでいます。『華氏451度』で作者が主題にしたい本の世界の《知》は、こういうレベル《知》(この場合は英国の歴史)だということの象徴でしょう。
さらに『華氏451度』の中で唯一、文学作品の直接の引用が出てくる箇所があります。モンターグがミルドレッドに、文学とはこういうものと教えるために詩を朗読します。「ドーヴァーの岸辺」という詩です。作者の名は書かれていませんが、これは19世紀イギリスの詩人で文明批評家のマシュー・アーノルド(Matthew Arnold 1822-1888)の作品です(原題は "Dover Beach" )。ブラッドベリの愛好する「本」を表しているではと思います。
| 余談ですが、No.10「バーバー:ヴァイオリン協奏曲」で書いたアメリカの作曲家、サミュエル・バーバーは、この詩をもとにバリトン独唱と弦楽4重奏による「 Dover Beach 作品3 」という曲を作っています。 |
『華氏451度』が描く
『華氏451度』は、アンチ・ユートピア(反ユートピア。ディストピア)を描いてみせた小説です。「本の禁止」をベースとするこの世界は以下のようなものです。
国民の娯楽と情報源は、各家庭にある「テレビ壁」と、皆に配られている超小型ラジオ「海の貝」です。「海の貝」は耳の孔に装着するものです。モンターグの妻のミルドレッドは装着していることが多いので「読唇術がうまくなった」との記述があるくらいです。
この小説か発表されたのは1953年です。アメリカでテレビ放送が始まったのは1940年で、あたりまえですが1953年では小型の白黒のブラウン管テレビしかありません(NHKのTV放送開始がちょうど1953年です)。ラジオ放送が始まってからはだいぶたちますが、現在の高性能小型イヤフォンはもちろんない。1953年の時点において、現在の大型液晶テレビを居間で見て、ステレオイヤフォンを長時間つけているライフスタイルを予見したかのようなこの小説の記述には驚きます。
クラリスという少女は、この世界になじめない人間です。彼女がモンターグに語る言葉から、この世界の実態が見えてきます。何点か引用してみます(太字は原文にはありません)。
まずこの時代は、ジェット・カーと呼ばれる非常に速く走るクルマが一般的になっています。
[クラリス] |
クラリスは、今はもう学校に行っていません。学校に失望しているのです。
(学校は)テレビのクラスが1時間、バスケット・ボールか野球かランニングが1時間、歴史か絵画のクラスが1時間、そのほか、スポーツとか、いろいろあるんだけど、あたしたち、質問することがないのよ。ほとんどの生徒がしないわ。教師たちは生徒にむかってしゃべるだけ。あたしたちは4時間以上も、そこにすわっているだけ。なにしろ、教師はフィルムですもの。 |
1日の授業がおわるころには、あたしたち、くたくたになってしまうわ。なにをする気力もなくなっているのよ。ベドに直行するか、遊園地へでも出かけて、みんなをはらはらさせてみるか、でなければ、窓割り遊技場で、窓ガラスをたたき割ったり、自動車破壊場で、車へ大きな鋼鉄ボールをぶつけるか、そんなことでもしなければ、気持ちを落ちつかせることもできないくらいよ。 |
去年一年で、あたしの友だちのうち、6人も射ち殺されたわ。そして、10人は自動車事故で死んでいるの。 |
だれのしゃべっていることも、ぜんぜん変わりがないの。みんな、おなじことばかりだわ。カフェにはいったにしても、そなえつけてある冗談ボックスをつかうと、おなじ冗談がとび出すでしょう。壁面ミュージカルにスイッチを入れれば、色つきの形が上下左右にうごきまわるけど、それ、色がついているというだけで、抽象模様のほか、なにもないんだわ。あんた、美術館に行ったことがあって? あそこも抽象画ばかりならんでいるわね。 |
クラリスが語る『華氏451度』の世界を、いくつかのキーワードで表現してみると「機械化」「パターン化」「スピード化」「簡略化」「没個性」「衝動的」という感じでしょう。
(以下、次回に続く)
No.47 - 最後の授業・最初の授業 [本]
パリ・コミューンと普仏戦争
No.13「バベットの晩餐会(2)」で、この映画の間接的な背景となっているのが、1871年のパリ・コミューンであることを書きました。このパリ・コミューンは普仏戦争におけるフランスの敗戦で引き起こされたものです。この普仏戦争に関連して思い出した小説があるので、今回はその話です。
普仏戦争の結果、講和条約が結ばれ、アルザス・ロレーヌ地区はドイツ(プロイセン)領になります。パリ籠城までして戦ったパリ市民はドイツとの講和に反対して蜂起しましたが(パリ・コミューン)、これは当然(ドイツの支援を受けた)フランス政府軍によって弾圧されたわけです(No.13参照)。支配層が、つい昨日まで敵だった国と裏で手を握り、かつての敵国にいつまでも反対し続ける国民(の一部)を弾圧するというパターンは歴史の常道です。
この普仏戦争の結果、アルザスがドイツ領になったという事実を背景にして書かれた小説があります。アルフォンス・ドーデ(1840-1897)の『最後の授業』(短編集『月曜物語』に収録。1873)です。要約すると以下のような短編です。
『最後の授業 - アルザスの一少年の物語』
ある晴れて暖かな朝、アルザスの少年、フランツは学校に急いでいます。今日はアメル先生がフランス語の分詞法の質問をするので、ずる休みをしようとも思ったのですが、気をとり直したのです。学校へは遅刻してしまいした。
叱られると思ったフランツですが、アメル先生は意外にもやさしいのです。そして普段は着ないような正装をしています。驚いたことに、教室の中には村の人たちもいます。そしてアメル先生が口を開きました。
「みなさん、私が授業をするのはこれが最後です。アルザスとロレーヌの学校では、ドイツ語しか教えてはいけないという命令が、ベルリンからきました・・・・・。新しい先生が明日見えます。今日はフランス語の最後のおけいこです。どうかよく注意してください。」 |
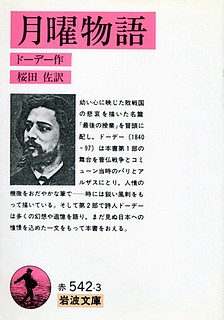
| |||
|
アルフォンス・ドーデ 『月曜物語』 (岩波文庫 1936) | |||
習字の時間になり、アメル先生はお手本を示します。そこには「フランス、アルザス、フランス、アルザス」と書かれていました。習字のあとは歴史の勉強です。
時計が12時を打ったとき、アメル先生は青ざめた顔をして教壇にのぼります。
|
篠沢・フランス文学講義
『最後の授業』は、文庫本でわずか7ページという短いものです。この短編には「フランス語」ないしはそれにまつわるキーワードがたくさん出てきます。そして、明日からフランス語の授業がなくなりドイツ語の授業になるという状況下で、言葉を守ることの重要性と、フランス語を忘れるなということが強調されます。
それもあって読者は「まるで、子供たちが、自分の話したことがない言葉を明日から教えられるような感じ」を無意識に抱いてしまいます。しかしそれは全くの誤解なのです。それが誤解だと指摘したのは、フランス文学者の篠沢秀夫・学習院大学名誉教授です。「篠沢フランス文学講義2」(大修館書店 1980)にそのことが出てきます。少々長いですが引用します。
|
『最後の授業』の真実
講義をそのまま本にしたようなので、読みにくいところもありますが、この篠沢教授の講義がほとんどすべてを言い尽くしています。すこし補足も加えて要約しますと、
| ◆ | アルザスの子供がたちが話していた言葉はドイツ語(のアルザス方言。アルザス語)であり、普仏戦争の結果、アルザスがドイツ(プロイセン)領になったため、学校でのフランス語の授業がなくなった。 | |
| ◆ | アルザス・ロレーヌを取り返せ、という好戦的気分が、普仏戦争後のフランスで盛り上がった。 |
の2点です。
『最後の授業』を読んで「まるで子供たちが、自分の話したことがない言葉を明日から教えられるような感じ」を受けてしまうのは、全くの誤解なのです。むしろ、そういう誤解を生むことは「折り込み済み」で、この小説が書かれたという感じがする。
篠沢教授は、大日本帝国が朝鮮と台湾の学校で日本語を強制したことを書いていますね。『最後の授業』のシチュエーションは、ちょうど第2次世界大戦直後の朝鮮半島・台湾の学校にピッタリと当てはまります。つまり、次のような「想像」が可能なのです。
| 日本はポツダム宣言を受諾し、第2次世界大戦は終了しました。その数日後、朝鮮(あるいは台湾)の小学校で生徒に日本語を教えていた先生が、授業を終わったあと、生徒に言います。「日本語を教えるのは、今日が最後です。先生は日本に帰ることになりました。しかし皆さん、日本語を決して忘れないでください。日本語は世界で一番美しい言葉です。」そして黒板に大きく書きました。「大日本帝国万歳」・・・・・・。 |
この通りのことがあったかどうか、分かりません。おそらくないでしょう。そこまでの日本人教師がいたとは思えない。しかし『最後の授業』を(かつての)日本に当てはめるとこうなります。日常生活は朝鮮語(台湾語)、学校では日本語、日本語の学習が明日からなくなる、という状況です。この状況が篠沢教授の頭をよぎったに違いないと推測します。学者なので、想像だけのことを講義では言いませんが・・・・・・。
もちろん、母語以外の言葉で話すことを強制したのは、19世紀以降をとってみても日本だけではありません。自国の言葉と歴史の教育を禁止されたポーランドの例が有名ですね。「キュリー夫人伝」の最初には、ロシアの視学官に隠れてポーランド語で勉強するマリー(マリア・スクロドフスカ)たちの緊迫した場面が出てきます。その時の様子を伝記作家の文章から引用すると次のとおりです。
学校では、一番年の行かない生徒であり、それでいて、成績はいつでも一番よりさがらない。おそろしいロシアの督学官が来る時、質問をかけられるのは彼女である。鐘が鳴って督学官の入来が知らされると、すべてのポーランド語の本が、先生と生徒たちとの間の暗黙の了解によって、即座に姿を消す。ロシア語だけが許される唯一の言葉であり、マリア・スクロドフスカは非常に正確にロシア語を話す。エカデリナ二世以後皇統をついだすべてのロシア皇帝の名とロシア帝室の全構成員の肩書きを間違えずに暗誦する。しかし、そのあとでは、もはや神経の緊張の限度に達する。督学官が行ってしまうと、マリアはわっと泣き出す。 |
また、No.5「交響詩・モルダウ」で書いたように、かつてのオーストリア・ハンガリー帝国下のチェコではドイツ語が教えられていました。チェコの作曲家スメタナは、子供時代はチェコ語が話せなかったのです。以上のような、朝鮮、台湾、ポーランド、チェコなどの学校での状況がなくなる時が「最後の授業」です。つまり「最後の授業」は19世紀以降、世界各地で行われた可能性があるのです。
牢獄の鍵
篠沢教授は「ドーデはあれは、南フランスの人間で、アルザスのことはよく知らない」と言っています。アルザスの子供たちが普段はドイツ語を話していることをドーデは知らなかった、というような書き方ですが、これはちょっと違うと思います。
よく読むと『最後の授業』には次のような箇所があります。フランス語の分詞法の規則を暗唱できないフランツに対するアメル先生の言葉です(太字は原文にはありません)。
「フランツ、私は君をしかりません。充分罰せられたはずです・・・・・・そんなふうにね。私たちは毎日考えます。なーに、暇は充分ある、明日勉強しようって。そしてそのあげくどうなったかお分かりでしょう・・・・・・ ああ!いつも勉強を明日に延ばすのがアルザスの大きな不幸でした。今あのドイツ人たちにこう言われても仕方ありません。どうしたんだ、君たちはフランス人だと言いはっていた。それなのに自分の言葉を話すことも書くこともできないのか!・・・・・・ この点で、フランツ、君がいちばん悪いというわけではない。私たちはみんな大いに非難されなければならないのです。」 |
アメル先生は、従って作者のドーテは、子供たちがまともにフランス語を話せないことをちゃんと認識しています。それでは、まともに話せる言葉は何かというと、それはドイツ語です。ドイツ語しかない。ドーテは「知らなかった」のではないのです。さらに、言語学者の田中克彦・一橋大学名誉教授によると、ドーデはもっと明確に「アルザス人」のポジションを認識していたようです。以下は、田中克彦著『ことばと国家』からの引用です。
この短篇の副題である「アルザスの一少年の物語」という訳も、ひどく混乱に導くものである。これは、原文どおりに「小さなアルザス人」(un petit Alsacien) あるいは「アルザス人の少年」とすべきである。ドーデはこの少年に、単にアルザスという土地に暮らす少年ではなく、アルザス人という、その特有のたちばをはっきりと明示しているのである。「アルザスの」という地方的な限定だけではあらわせない内容が、この大文字のアルザス人の中には含まれている。 |
そもそもアルザスは、かつては神聖ローマ帝国の一部でした。住民の言葉はドイツ語です。それが30年戦争の終結を決めたヴェストファーレン条約(1648)でフランス領になった。そして学校でフランス語を教えるようになる。それが『最後の授業』の前史です。普仏戦争後、アルザスはドイツ領に戻ります。この時期にアルザスで生まれた有名な人物が、アルベルト・シュヴァイツァー博士ですね。彼はアルザス人です。第一次世界大戦後にアルザスは再びフランス領になる。そして第二次世界大戦でドイツに占領されたあと、戦後にまたフランスになるわけです。現在アルザスはフランスの一部ですが、いまだに住民の多くはドイツ語(の方言のアルザス語)とフランス語のバイリンガルだといいますね。
『最後の授業』の中に次のような箇所があります。
(アメル先生は)、ある民族が奴隷になっても、その国語を保っているかぎりは、その牢獄の鍵を握っているようなものだから、私たちのあいだでフランス語をよく守って、決して忘れてはならないことを話した。 |
「言葉は牢獄の鍵」・・・・・・。言い得て妙、とはこのことです。『最後の授業』に出てくるアルザスの住民たちは、フランス政府のフランス語強制にも関わらずドイツ語を守り通し、アメル先生の言う「牢獄から脱出する鍵」を持ち続けたわけです。アメル先生は、「ああ!いつも勉強を明日に延ばすのがアルザスの大きな不幸でした。」と、アルザス人がフランス語をうまく話せないのはアルザス人が怠惰だからのように言っていますが、そんなことはありません。うまく話せないのは、アルザス人にとってドイツ語こそが「母語」であり「牢獄の鍵」だからです。
篠沢教授の講義にあるように、普仏戦争の敗北後「アルザス・ロレーヌを取り返せという好戦的気分」が出てきます。この小説はその気分盛り上げるために書かれた「愛国宣伝小説」でしょう。
著者のドーデーは、普仏戦争では、国民軍の志願兵として出征して戦争を体験し、さらにパリ籠城でもプロシア軍と戦った愛国者である。 |
その愛国者の書いたプロパガンダが「言葉を守ることの大切さ」という文脈にすり替えられています。そして、ざっと読むとそのすり替えに気づかないようになっている。「言葉を守ることが大切」という言説が、誰が考えても全く正しいために・・・・・・。これは、ある意味では大変に「怖い小説」だと思います。
『最後の授業』は、
| 敗戦で支配者が変わった状況のもと、敗戦国側の教師が学校から去っていく物語 |
です。この次のステップの状況、つまり
| 敗戦で支配者が変わった状況のもと、戦勝国側の教師が学校にやってくる物語 |
があります。『最後の授業』が書かれてから約100年後、アメリカの作家、ジェームズ・クラベル(1924-1994)が書いた『23分間の奇跡』(青島幸男訳。集英社。1983)という短編です。要約すると次のような話です。
(以下には物語のストーリーが明かされています)
『23分間の奇跡』(原題:The Children's Story, 1980)
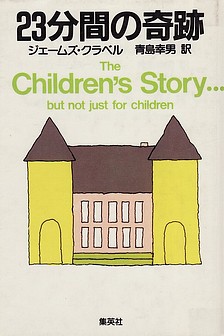
| |||
|
ジェームズ・クラベル 『23分間の奇跡』 (集英社。1983) | |||
9時ちょうどに新しい先生がやってきました。若い女の先生です。「みなさん、おはよう。私が今日からみなさんの新しい先生です」と挨拶しました。子供たちは、言葉になまりが全くないことにびっくりします。海の向こうの別の国から来たはずなのに・・・・・・。
新しい先生は、今までの先生に校長室に行くように言います。今までの先生は泣きながら出ていきます。女の子が泣き顔で、その後を追いかけようとしました。新しい先生はやさしく女の子抱きしめ、床に座って、ゆっくりと歌を歌います。子供たちは思わずその歌声に聞き入ってしまいました。今までの先生は、歌を歌ってくれたことはなかったのです。
子供たちがびっくりしたことに、新しい先生は子供の名前を全部知っているようなのです。先生は、3日かけて座席の位置と名前を全部覚えたことを話します。そして誰が出席しているかが分かるから、出席はとらないと宣言します。朝一番に出席をとるの習慣だったので、これも驚きでした。
朝、最初にすることは何ですか、と、先生はジョニーに聞きます。ジョニーは「国旗に忠誠を誓います」と答えます。しかし先生は「忠誠を誓う、とはどういうこと」と子供たちに問いかけます。子供たちは「誓う」の意味までは何とか分かりますが「忠誠」の意味を答えられる人は誰もいません。先生は、意味の知らないことを言うのはよくないこと、前の先生が意味を教えなかったことはよくないとこと伝え、忠誠の意味を教えます。さらに国旗が人の命より大切というのはおかしいことを説明します。そんなに大切なものなら、私も国旗を少しわけてほしい、という先生は言いました。私も、私も、という声が子供たちからあがり、国旗は小さく切られ、皆に分配されてしまいました。
ジョニーは鬱積していた気持ちを先生にぶつけます。「ぼくのお父さんはどこへいった!」と。ジョニーはお母さんから「もう帰ってこない」と聞いていたのです。先生は、お父さんは間違った考えを持っていたので学校にいっていること、大人も学校にいく必要があること、間違った考えが直れば家に戻れることを言います。ジョニーは何となく納得できません。
先生は言葉巧みに生徒たちを誘導し「キャンディがほしいと神様にお祈りしましょう」と提案します。子供たちは目を閉じて祈りますが、もちろんキャンディは出てきません。そこで先生は「われらの偉大な指導者」に祈ってみましょう、と言います。そして子供たちが目を閉じて祈っている間に、先生は皆にキャンディを配りました。
この様子を密かにジョニーは見ていました。そして「キャンディを配ったのは先生だ!」と大きな声で言ったのです。ところが先生は全く動じず、あっさりとそのことを認めました。そして子供たちに言うのです。何かしてほしいことがあったとき、それを実現するのは神様でも偉大の指導者でもない、実現するのは「誰かほかの人」なんだと・・・・・・。先生は付け加えて「祈る」ことの無意味さを子供たちに言います。
この率直な先生の態度で、ジョニーは先生を好きになろうと決めます。他の子供はすでに、先生の言うことを素直に聞く気になっています。全ては、先生の計画どおりに進行したのでした。
時計を見ると、9時23分でした。
作家の動機
23分間で子供たちの考えが変わり(ないしは完全に順応し)、特に父親を連れ去られたジョニーの考えまで変わってしまう・・・・・・。これは一つの寓話です。
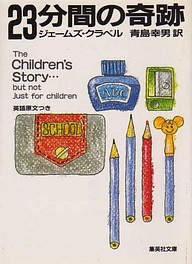
| |||
|
『23分間の奇跡』 (集英社文庫) | |||
どの国の話でもないのですが、実は、作者のクラベルは「作者の後記」の中で、この小説を書いた動機を語っています。
ジェームズ・クラベルはイギリス人です。少年時代は、海軍将校だった父と一緒に、各国のイギリスの軍港を転々としました。そして18歳のときにジャワ島で日本軍の捕虜になり、シンガポールの収容所で第2次世界大戦の終了を迎えます。
戦後に彼はアメリカに渡り、ハリウッドの脚本家、映画監督として活躍しました。スティーヴ・マックィーン主演の映画「大脱走」はクラベルの脚本です。この間、彼はアメリカ国籍をとり、アメリカに帰化しています。そのあとに彼は小説家に転じ、1962年に処女長編を出版し、戦国時代の日本を舞台にした「将軍」(1975)などのベストセラーを出しました。
クラベルが『23分間の奇跡』を書いた動機は、アメリカに渡ってからの彼の経験です。6歳の娘がアメリカの小学校に初めて登校し、帰宅した時のことです。彼女は「お父さん、私、国旗に忠誠を誓うのよ」といって、左の胸に手をあてて、なにやらもぐもぐとしゃべり、手を差しだして「10セントをちょうだい」と言ったのです。学校で「忠誠の誓い」をしっかり暗記するように先生に言われ、ちゃんと出来たらきっとお父さんやお母さんが10セントをくれますよ、と先生が言ったとのことなのです。
クラベルは娘に10セントを払いました。
そして娘に聞いたのです。「忠誠を誓う(pledge allegiance)」ってどういう意味?、と・・・・・・。娘は困った顔になり、その意味を答えられませんでした。先生も、どういう意味かは教えてくれなかったとのことです。
クラベルはアメリカ人のあらゆる知り合いに「忠誠の誓い」のことを聞いてみました。もちろん全員が知っていました。しかし誰一人として、その意味を学校で教えてくれたという人はいなかったのです。
忠誠の誓い:The Pledge of Allegiance
「忠誠の誓い」はアメリカの公立の小中学校や幼稚園で毎朝、星条旗に向かって「唱えられている」文言です。アメリカ人なら誰でも知っているわけです。
The Pledge of Allegiance |
確かにクラベルの娘のように、また小説の中の生徒のように、ちょっと難しい。特に allegiance という単語です。英語を学んでいる日本の高校生は分かるでしょうか。indivisible もアメリカの小学生には難しいのではと思います。
「忠誠の誓い」の under God という文言を問題にする人もいます(今も問題になっている)。大文字で書かれたGodとは、誰が考えてもキリスト教とユダヤ教の共通の「神」のことであり、信教の自由に反するからです。事実、合衆国憲法違反だという裁判所の判断が出たこともあります(撤回されたようですが)。
娘がアメリカの小学校に初めて行ったとき、クラベルはまだイギリス人でした。アメリカ国籍をとる前です。そして海軍将校の息子という経歴から分かるように、クラベルが「典型的なイギリス人としての教育」を受けてきたことは想像に難くありません。そのイギリス人・クラベルからすると、「忠誠の誓い」を意味も分からずに暗唱しようとする娘の姿に強い違和感を感じたのです。その時、「忠誠の誓い」をストーリーの核(の一つ)とする小説の構想が浮かびました。従って、アメリカ人がこの小説を読めば、自国を念頭に置いていることがすぐに分かるしかけになっています。
クラベルが『23分間の奇跡』を書いた「思い」をまとめると、次の2つのどちらかか、あるいは両方でしょう。
| ◆ | 子供の考えや心理は、大人が簡単に誘導できるものだ。そういう子供たちに、意味も分からずに「忠誠」を誓わせていいのか、という疑問。 | |
| ◆ | 意味も分からずに「忠誠」を誓う、というような行為を続けていると、ある日、何らかの事情で全く正反対の考えを吹き込まれても、たやすく誘導されてしまうぞ、という警告。 |
『23分間の奇跡』は小説として考えると、成功作とは言いがたいのですが、寓話の形をとった問題提起という意味はあると思います。
日本における「最初の授業」
ジェームズ・クラベルが書いた「最初の授業の物語」も、ドーデの「最後の授業」と同じように、日本に当てはめて考えることができます。『23分間の奇跡』を訳した青島幸男(1932-2006)は「訳者あとがき」で次のように書いています。
|
青島幸男氏は太平洋戦争の終了時、13歳の「少国民」でした。教育の大転換を目の当たりにした氏の「思い」が、この小説を訳させたのでしょう。
『最後の授業』と『23分間の奇跡』の舞台となっているのは、それまでの価値観を否定するような教育が始まる状況、180度違う価値観の教育に転換する状況です。そのようなことを(結果として)招く世界を作ってはならない。これが、この2つの小説から読者が感じる強いメッセージです。それは、特定の政治的主張に基づく価値観を植え付けてはいけない、ということと表裏一体です。子供たちは、まだ「価値観」を選択できないのだから・・・・・・。
No.45 - ベラスケスの十字の謎 [本]
|
No.19「ベラスケスの怖い絵」でベラスケス(1599-1660)の傑作『ラス・メニーナス』について書きました。また、No.36「ベラスケスへのオマージュ」でもこの絵について触れています。今回は「ラス・メニーナス」に関する児童小説で、スペインの作家、エリアセル・カンシーノの『ベラスケスの十字の謎』(宇野 和美 訳。徳間書店 2006)
『ラス・メニーナス』は謎の多い絵ですが、大きな謎の一つは絵の中の画家本人の胸に描かれた赤い十字で、これはサンチャゴ騎士団の紋章です。サンチャゴ騎士団に入ることは当時のスペインにおいて最大の栄誉であり、ベラスケスは60歳のときに(1659)騎士団への入団をやっと許されました。ところがその3年前に『ラス・メニーナス』は完成していて(1656)、王宮に飾られていたのです。つまり『ラス・メニーナス』の完成時には、ベラスケスはサンチャゴ騎士団員ではありません。従ってその時点で赤い十字は絵になく、後で誰かが十字を描き加えたと考えられているのです。これが『ベラスケスの十字の謎』のテーマとなっています。

|
ベラスケス「ラス・メニーナス」 (プラド美術館) |
小説の主人公は『ラス・メニーナス』に登場するニコラス・ペルトゥサトです。画面の右下で犬に足をかけている少年がそうです。ベラスケスにまつわる歴史的事実も踏まえながら、フィクションを自由に織り交ぜて構成されている『ベラスケスの十字の謎』のあらすじを、以降に紹介します。
(以下には物語のストーリーが明らかにされています)
イタリアからスペインへ
主人公のニコラス・ペルトゥサトは、1643年か1644年にイタリアのミラノの南西の町、アレッサンドリア・デッラ・パッラで生まれました。物語はニコラスが7歳(か8歳)の時に始まり、10年後のニコラスの回想という形で語られます。
ニコラスの母は、彼が生まれたときに死んでしまいました。そして彼は身長が伸びない「小人症」です。父親は、少しでも背が高く見えるようにと、特注の「上げ底」の木靴を作らせ、それを履くことを強制します。ニコラスが自分の年齢があやふやなのは、父親が彼の本当の年齢を他人に知られまいと、しょっちゅう生年をごまかしていたからです。父親はニコラスを憎んでいて、ニコラスもそのことが分かっています。乳母のマリーナだけが彼の味方ですが、その乳母とも別れる日がやってきました。
ある朝、金髪の紳士がペルトゥサト家を訪ねて来ます。デル・カスティーリョという、スペインからきた人です。紳士はニコラスに「これからはニコラシーリョと呼びましょう」と言います。ニコラシーリョとは、ニコラスのスペイン風の愛称です。父親と金髪の紳士あいだでは、既に「話」がついているようで、ニコラスは紳士につれられて家を出ることになります。
|
ニコラスはジェノバの港に着き、そこから船でバルセロナへ向かいます。船室では、ニコラスと似たような背丈だが、れっきとした大人と同室になりました。名前はディエゴ・デ・アセドと言います。たまたま、スペインからの旅行の帰りに乗り合わせたようです。ニコラスはアセドから話を聞いて、自分がスペインに行く本当の理由が分かりました。
|
アセドは、かつてニコラスと同様に親に捨てられて宮廷に連れていかれたのですが、現在は宮廷で重要な地位にあり、財産もあって、人々から敬われているようです。アセドはニコラスに、これから生きていくための数々のアドバイスをします。
| 最初の何年かはつらいものだ。だが、欲しいものは自分で手に入れろ。他人をあてにするな。 | |
| ふざけたあだなをつけられないように。変な名で呼ばれても、絶対に返事をするな。 | |
| 知恵をたくわえ、ほかの者には見えないものを見、聞こえないものを聞き、いつでも自分自身を演じることだ。そうすれば、私のようになれる。 |
などです。そして「スペインに着いて困ったことがあったら、このディエゴ・デ・アセドをたずねてきなさい」と言います。

|
ベラスケス 「ディエゴ・デ・アセド」 (プラド美術館) |
ニコラスはバルセロナから馬車でマドリードに向かいます。そして王宮に入り、フランシスカという王宮の料理人のおばさんにあずけられます。ニコラスはまず調理場で朝から晩まで過ごすことになりました。
マドリードの王宮
ある日、王宮の下っ端役人が、生まれたばかりの子犬を数匹つれて調理場にやってきました。余分な子犬なので、水を張った桶に沈めて殺してしまおうというわけです。そのうちの一匹が、桶の蓋を持ち上げて必死に外に出てきました。ニコラスは思わずその子犬を助け、役人に自分が責任をもって飼うからと必死に訴えて、もらい受けます。マスティフ犬(猟犬や番犬に使われる大型犬)という種類の犬で、ニコラスはその子犬にモーセという名前をつけました。
ニコラスは、王宮に仕える子どもたちの教育係であるアロンソ先生にあずけられて勉強を開始します。スペイン語の読み書きや算術、礼儀作法などです。ある日、アロンソ先生はイタリア語の本をもってきて、これを暗唱してみなさいと命じます。ニコラスは上手にやってのけました。アロンソ先生はこれ以降、古代ギリシャの詩などをニコラスに暗唱させるようになります。国王のもとからは定期的に使者が来て、子どもたちの勉強の進み具合を調べます。ニコラスは好成績であり、特に詩の暗誦は使者を感心させました。
ニコラスが暗誦したイタリア語の本は、実はダンテの『神曲』(の一部)であり、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になります。『ベラスケスの十字の謎』では、以降『神曲』からの引用が要所に出てきて、物語の進行に重要な役割を果たします。
ちなみに、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になるという物語の設定は、ニコラスがイタリア人であり、かつ『神曲』がめずらしくイタリア語で書かれた文学だったからですね。文学はラテン語で書くのが常識だった。それを打破して「方言」で書かれたのが『神曲』だった、と世界史で習いました。
ちなみに、『神曲』の暗誦がニコラスの特技になるという物語の設定は、ニコラスがイタリア人であり、かつ『神曲』がめずらしくイタリア語で書かれた文学だったからですね。文学はラテン語で書くのが常識だった。それを打破して「方言」で書かれたのが『神曲』だった、と世界史で習いました。
ベラスケス
ニコラスは王家に仕える身となります。スペイン語もすらすらと話せるようになり、仕事にも慣れてきて、利発で聡明な子だと評判になります。
そうして何年かが過ぎ、友達もできました。その一人が、ニコラスと同じ小人症の女の子で、本名はバルバラ・アスキン、皆からは愛称でマリバルボラと呼ばれています。ニコラスが来る何年か前にドイツから連れてこられたようです。彼女は王妃が大変にかわいがっている侍女です。
このマリバルボラが、ニコラスをベラスケスに引き合わせることになるのです。ニコラスはある貴族とのトラブルを抱えていました。宮廷内でその貴族に「からまれた」ニコラスが燭台を投げつけ、貴族が怪我をしたという件です。この件の解決の力になってもらおうと、ニコラスはマリバルボラの紹介で王室配室長であるベラスケスを訪問します。王室配室長とは、美術品の収集や室内の装飾、儀式の手配などを受け持つ、宮廷の要職です。
実はニコラスは絵を通してベラスケスを知っていて、ベラスケスに惹かれていました。ニコラスと同じ小人症の人を描いた絵を宮廷で見ていたからです。一つは教育係のアロンソ先生の教室の壁に飾られていた「ドン・セバスティアン・デ・モーラ」の絵で、もう一つはイタリアからスペインに来るときに船で一緒になった「ディエゴ・デ・アセド」の肖像です。
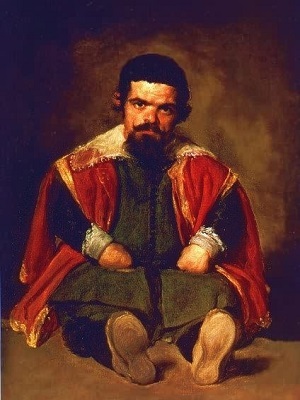
|
ベラスケス 「セバスティアン・デ・モーラ」 (プラド美術館) |
ベラスケスは午前中は王室配室長として働き、午後は宮廷内の工房で絵筆をとるのが普通です。工房に訪ねていくと一人の先客がいました。ニコラスがマリバルボラの紹介で来たと言うと、ベラスケスもニコラスを知っていました。「イタリア語でダンテの神曲を暗唱する子」と評判になっていたからです。ベラスケスはさっそくニコラスに『神曲』の一節を暗唱させます。それを聞いていた先客の男は「この子もあの絵に入れましょう」と言って、工房から去っていきました。ニコラスは貴族とのトラブルの件をベラスケスに話したところ「何を言われても、しらばっくれるように」との指示を受けます。ベラスケスは、先客の男が言い残した言葉が気になっているようです。男の名前はネルバルだと、ニコラスは知りました。
アセドとの再会
そのすぐ後、ニコラスはディエゴ・デ・アセドと再会することになります。アセドがニコラスの部屋を訪ねてきたのです。久しぶりの再会を喜んだ2人ですが、アセドは重要なことを伝えます。国王・フェリペ4世が「ベラスケスに制作中させている絵にニコラスを入れたい」とおっしゃっているとのことなのです。アセドは続けて、ニコラスを入れるように国王に進言したのはネルバルという男であること、ネルバルは素性がはっきりしないが、宮廷に彼が現れてからは誰もが彼の言うなりになっている様子であること、アセドにはネルバルという男がどうしても「引っかかる」こと、などを話します。
しかしアセドはまた「国王のそば仕えに昇格する絶好のチャンスだ、これを逃すな」とも言います。アセドはニコラスの運命が大きく変わろうとしていることを予感し、先輩としてニコラスにいろいろと忠告をすべく訪ねてきたのでした。
フェリペ4世
アセドと再会してから2日後、国王からじきじきのお呼びがかかりました。ニコラスは正装をし、王の間でフェリペ4世に謁見します。国王はニコラスにいくつかの質問をしたあと、ニコラスが貴族とひと悶着起こしたことを尋ねます。ニコラスが口ごもっていると、国王は「本当の事を言え」とピシャリと命じます。国王とニコラスの会話です。
|

|
ベラスケス 「フェリペ4世」 (ロンドン・ナショナルギャラリー) |
国王はニコラスに、ベラスケスに仕えると同時に、制作中の絵のモデルになるよう命じます。そして絵が完成したあとは「よきように、はからってやる」と言います。そして最後に言葉を残しました。
|
10分間の短い謁見でしたが、ニコラスの前途を大きく開いた10分間でした。
ベラスケスの家
ベラスケスは王宮の隣の庭園にある《宝の館》と呼ばれる邸宅に、奥方のフワナ・パチェコと一緒に住んでいます。ニコラスはその館に住み込み、館と王宮の工房を行き来しながら種々の仕事をこなします。朝一番に工房に行って、弟子の画家たちがやってくる前に掃除をし、筆を洗うのも彼の役目です。ニコラスは弟子の一人で、年上のフワン・パレハと仲良くなりました。パレハは元は奴隷だったのですが解放され、今はベラスケスの弟子の画家の一人として師匠を支えています。

|
ベラスケス 「ファン・デ・パレーハ」 (メトロポリタン美術館) |
ニコラスは絵のモデルになります。そしてベラスケスとパレハの会話を聞くうちに、分かってきたことがありました。ベラスケスは制作中の絵について、あれこれと悩み、試行錯誤をし、彼が絵で表現しようとしているものを必死に追求していること。ネルバルが工房や《宝の館》に自由に出入りし、ベラスケスに助言を与えていて、ベラスケスもそれを信用していること。奥方はネルバルを嫌っていることなどです。
ネルバルの家
ある日、ニコラスはベラスケスからネルバルの家に使いに行くように命じられます。急いで伝言を伝えよ、とのことです。
マドリード市内の家にたどり着いたニコラスは、ネルバルに会い、伝言を伝えます。それは「国王と王妃を絵のどこに描けばよいか」という質問です。ネルバルは答えるかわりに壁を指します。するとニコラスはそこに幻影を見るのです。壁が透き通り、工房が見え、絵がはっきりと認識できます。そこにはマルガリータ王女、ベラスケス、マルバルボラ、侍女たち、ニコラス自身、ニコラスの飼い犬のモーセなどが見えます。そしてさらによく見ると、国王夫妻も描かれているのです。
見たままを伝えよ。そう言われてニコラスは王宮に戻ります。
絵の完成
ニコラスは王宮の工房にもどり、ベラスケスに見たままを報告します。実はベラスケスも、ニコラスが見た幻影と同様の夢を見ていました。ところがニコラスの幻影には、ベラスケスの夢にはなかったものがあったのです。絵の中の国王夫妻とその位置です。ベラスケスは驚きますが、深く心を打たれたようです。
翌日からベラスケスは、とり憑かれたように絵の制作に熱中します。ニコラスは《宝の館》に帰るとフワナ奥様に問いつめられました。なぜ、あれほどまでにベラスケスが今の絵に熱中しているのかと・・・・・・。奥方はネルバルに不信をいだいていて、何かあると思っているのです。ニコラスはネルバルの家で見たことを奥方に打ち明けました。当然、奥方はベラスケスに言ったのでしょう、ネルバルと手を切ってほしいと・・・・・・。ニコラスはベラスケスから、もう工房に来なくてよい《宝の館》からも出ていくように、との通告を受けました。
しかしそれから数日後、ニコラスにベラスケスからの使者が来ます。犬のモーセをつれて工房に来るようにとの指示です。ニコラスは迷いますが、再び工房に向かい、愛犬とともに絵のモデルになります。
そして絵は完成しました。
最後の依頼
謁見のときの国王の約束どおり、ニコラスは国王付きの召使いに抜擢され、とんとん拍子に出世します。そうして約3年がたちました。ベラスケスもサンチャゴ騎士団への入団が認められ、また王室配室長の職も続けます。王室配室長として最も重要な仕事は、王家同士の結婚です。ベラスケスは、マリア・テレサ王女とフランス国王・ルイ14世の婚礼(1660)を取り仕切りました。この時の過労がたたり、ベラスケスは病の床についてしまいます。
1660年8月4日の未明、ニコラスはベラスケスからの呼び出しをうけます。《宝の館》に出向いたニコラスは、病床のベラスケスから、あることを依頼されます。王宮に飾られている「あの絵」の中のベラスケスの胸に、赤い十字を描いてほしいという依頼です。ベラスケスはその十字を描くべき工房にある絵筆まで指示し、王室配室長として持っている王宮のマスター・キーをニコラスに渡します。意を決したニコラスはそれを引き受けます。
引き受けたものの、ニコラスは絵を描いたことがありません。そこで、館に居合わせたベラスケスの弟子で懇意のパレハに協力を求めます。その日の夜、ニコラスとパレハは工房に入り、絵筆と、そこにあった赤い十字が描かれた羊皮紙を手にし、王宮の「あの絵」の部屋に忍び込みます。そしてパレハは羊皮紙どおりの十字をベラスケスの胸に描き入れました。
2人が未明に《宝の館》に戻ったとき、もう面会は許されませんでした。容態が悪化したようです。翌朝、王宮の医師の伝言を伝えるためにニコラスが《宝の館》を訪問したとき、館は静まりかえっていました。もう手のほどこしようがないようです。その日の午後2時、ベラスケスは息を引き取りました。
葬儀がすべて終わり、ニコラスが回想記を書き終えたとき、彼はもうすぐ17歳という年齢になっていました。
以上が『ベラスケスの十字の謎』のあらすじです。これ以降は、この本についての補足と感想です。
ミステリー
この小説は「ミステリー仕立て」のフィクションです。最大の謎は、
| 登場人物のネルバルとは、いったい何者か ? | |
| ベラスケスとネルバルの関係は ? なぜベラスケスは赤い十字を描くようにニコラスに指示したのか ? |
という点です。それは物語を読み進むうちに終わりの方で明らかにされます。ミステリーの「なぞ」を書いてしまうのはまずいと思うので「あらすじ」からは割愛しました。しかしよくあるプロットなので、大人の読者なら読み進むうちにすぐに推測できると思います。伏線もいっぱいあります。ありきたり過ぎる感じもするのですが、これは「少年少女向けに書かれた小説」なので、不満を言うのは筋違いでしょう。
「なぞ」と言えば、さらに、
| ベラスケスは絵に何をこめようとしたのか。どういう意図のもとに書かれた絵か。 | |
| 国王がニコラスに向かって言った「最後にきて、すべてを見るもの」とはどういう意味か。 |
も「ミステリー」の重要なポイントです。何回か引用されるダンテの『神曲』の一節も謎と関係しています。このような謎を要所要所に配置しながら、ベラスケスの死まで話を引っ張っていくストーリーは、小説としてよくできていると思います。
目の付けどころの良さ
この小説は「目の付けどころ」によって成功した作品だと言えるでしょう。ポイントは2つで、
| ラス・メニーナスにまつわる物語を書く | |
| ラス・メニーナスに登場するニコラス・ペルトゥサトを主人公にする。 |
の2点です。
①は多くの作家が考えたと思います。しかしこれは難題です。そもそも『ラス・メニーナス』という絵自体が不思議な絵であり、絵の制作目的や解釈については、いろいろの説が言い尽くされています。単純な方法では物語としての構成が難しいし、絵の新しい解釈を示したところでインパクトは弱いでしょう。
②が大きいと思います。ラス・メニーナスに登場する小人症の少年、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にする。そして、ベラスケスの絵に登場する人物を要所に配置し、ラス・メニーナスの謎にまつわる物語を少年の視点で書く・・・・・・。この手法を思いついたとき、作者は「これだ!」と思ったのではないでしょうか。この小説は、その目の付けどころと構成の妙が際だっています。
しかしあえて難点を言うと、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にするなら、もっと少年の成長過程を書き込んでもよかったと思います。父親に捨てられた少年が、フェリペ4世に「その誇りを大切にせよ」と誉められるまでに成長する過程です。そもそも彼は大きなハンディキャップを背負っているのだし、宮廷内の使用人の人間関係は複雑なはずです。悲しみ、苦しみ、怒り、絶望、嫉妬、友情、希望など、幾多の経験をしたでしょう。その中で、いかに人間としての尊厳を保ちつつ、宮廷での地位を高めていったのか、書こうとすればいくらでも書けるような気がします。記述がないわけではありませんが、いかにも少ない。著者であるスペインの作家、エリアセル・カンシーノは、文学のおもしろさを子供たちに知ってもらうために児童小説を書き続けているそうです。その観点からしても、ちょっと惜しいと思いました。
怖い小説
この小説は、ベラスケスの絵の謎にまつわるストーリー展開が大変におもしろいのですが、あとから思い出して強く印象に残るのは、やはり小人症などの「異形」の人たちを集め、道化を演じさせたり、召使いとして働かせるという、当時のスペイン宮廷の「雰囲気」そのものなのです。本書とは直接の関係はありませんが、ベラスケスの後継者にあたる宮廷画家、カレーニョ・デ・ミランダ(1614-1684)が「異形」の子供を描いた作品をあげておきます。
|
|
|||||
|
ベラスケスより15歳年下の宮廷画家、ファン・カレーニョ・デ・ミランダの作品。エウヘニア・マルティネス・バリェーホという名の少女である。絵と英語の説明はプラド美術館の公式ホームページから引用した。Monster(スペイン語で Monstrua)は「奇形」の意味である。プラド美術館の公式カタログによると彼女は 6歳だと言う。同一人物の同じポーズの着衣と裸体を描くという発想は、後年のゴヤの作品を連想させる。 なお、画家のカレーニョ・デ・ミランダは彼が仕えた「カルロス2世」の肖像を描いているが、一見して病的な風貌の国王を描いたその肖像画の詳細な解説が「怖い絵2」にある。 |
||||||
No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、中野京子さんは著書『怖い絵2』で『ラス・メニーナス』について次のように書いています。
|
『ラス・メニーナス』と同じように、カレーニョ・デ・ミランダの2作品も怖い絵です。「同一人物の同じポーズの着衣と裸体を描くという発想は、後年のゴヤの作品を連想させる」などと、のんきなことを絵の説明に書きましたが、ゴヤの作品とのあまりの状況の相違に愕然とするわけです。バッカスの姿をさせられた6歳の少女の裸体画は、現代人を唖然とさせるものがある。
ただし、この「怖い」というのは現代人の感覚からすると怖いという感情にとらわれる、ということであって、それ以上の価値判断は慎むべきだと思います。たとえば「異形の人」を集めたことを理由に、17世紀のスペイン宮廷は「堕落していた」というような・・・・・・。当時の宮廷ではそれがあたりまえであり、むしろ国王の恩恵を異形の人たちに与える「慈善行為」だった可能性さえある。現代人の感覚で過去を断罪するほどバカバカしいことはありません。その意味で、カレーニョの上記の作品を、芸術作品としての価値判断から公式ホームページにちゃんと掲げているプラド美術館の姿勢を支持したいと思います。
話を『ベラスケスの十字の謎』に戻します。
こうした「異形」の人たちの中には、歴史的事実として、宮廷内で高い位になる人もあったようです。ニコラスがそうだし、アセドは王宮の書記官であって、地位も財産もある。マリバルボラ(=マリア・バルボラ)も王妃に寵愛されていて、召使いさえもっていたようです。しかし、一方では「道化」を演じさせられる人もある。小説のはじめの方でアセドは「恥を捨てて道化を演じ、なぐさみ者にされるのだ」と言っていますね。宮廷や貴族に引き取られるのはましな方で、集められた「異形」の人の中には引き取り手が見つからず、置き去りにされる人もあったともあります。いかにもありそうな話です。
その「異形」の人たちをヨーロッパ中から集める役人であるデル・カスティーリョという人物は、物語の最初と最後にしか登場しないのですが、独特の「雰囲気」があります。
イタリアの家からニコラスを連れ出す場面。
|
|
|
ニコラスはベラスケスの葬儀において、デル・カスティーリョと再会します。
|
デル・カスティーリョにとって、ニコラスは愛玩物かモノでしかありません。ニコラスに言わせると、彼は「何も見えていない」のです。『ベラスケスの十字の謎』は、人間をモノや愛玩物とした時代の空気を(結果として)的確に描写することになりました。その意味で、よくよく考えてみると「怖い小説」と思えてきます。
と同時に、ニコラス・ペルトゥサトも、マリア・バルボラ(マリバルボラ)もディエゴ・デ・アセドも、生まれながらにして小人症というハンディキャップを背負いながら、自らの意志と努力で「愛玩物」という位置を乗り越え、宮廷で重要な地位を占めるまでになりました。この小説はまた「人間の可能性」を力強く示そうとした小説でもあると思います。
絵が伝えるもの
この小説のストーリーの背景となっている共通認識があります。それは、小説の作者を含めて、ベラスケスの「道化を描いた絵」(No.19「ベラスケスの怖い絵」参照)を見た者が暗黙に抱いているものです。つまり、
| ベラスケスは宮廷にいる小人症の道化たちに、強い人間的共感をいだいていただろう、という「暗黙の推定」 |
です。事実かどうかは不明です。しかし、この推定がなかったら『ベラスケスの十字の謎』という小説は成立しないと思います。ニコラスが初めてベラスケスに会ったとき、ベラスケスはマリバルボラのことを「バルバリカ」という特別な愛称で呼び「あの子の頼みなら断れない」と言います。またニコラスを大変に信用し、赤い十字を描くという「画家としての遺言」を託すまでになります。これが小説としてのプロットの根幹なのです。「暗黙の推定」があるからこそ、作者はこういうストーリーを作った。
この推定の正否を実証する資料は皆無でしょう。しかし、この小説の作者を含めて我々は、350年以上前に描かれた何枚かの絵だけを見て暗黙に考えているのです。「外見と人間の本質は関係ない。これこそが画家の真意だ」と・・・・・・。絵が持ちうる強いメッセージ性。『ベラスケスの十字の謎』は、その上に成立した小説だと思いました。
|
ピカソの連作が「ベラスケス賛歌」であることは間違いないのですが、17世紀のスペイン宮廷の工房で「ラス・メニーナス」が描かれてから300年後、このような絵が出てくるとはベラスケスもニコラス・ペルトゥサトも想像だに出来なかったでしょう。
No.43 - サントリー白州蒸溜所 [本]
No.31「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」はワインの話ではじめたのですが、そこでウイスキーを引き合いに出して、
というようなことを書きました。これは随分アバウト過ぎる言い方であって、本当はそんな単純なものではないことは分かって書いたわけです。
今回は、ウイスキーそんな単純なものではないことの実証です。もう随分前になりますが、山梨県にあるサントリー白州蒸溜所で、ウイスキー作りの過程を見学したことがあります。ここで「ウイスキーが、いかに複雑なお酒であるか」を納得することになりました。
白州蒸溜所の見学コース
サントリー白州蒸溜所は、中央高速の山梨県・小淵沢インターチェンジの近くで、清里高原や八ヶ岳、蓼科高原にも近いロケーションにあります。南アルプス・甲斐駒ヶ岳へと続く山並みの山麓に蒸溜所はあり、そこはなだらかな傾斜地になっています。ここは一般の人が訪問して、案内ガイドの方に従って、ウイスキー作りのプロセスを見学することができます。
ウイスキー作りは、大きく言うと
①発酵と蒸溜
②貯蔵
③ブレンド
の3つから成り、これが見学コースのポイントでした(もちろんその後に、瓶詰めなどの商品製造工程がある)。この3つの過程に従って、私が見学した時に見聞きしたことをまとめてみます。
まず「発酵」のプロセスは次のように進みます。
次が「蒸溜」です。アルコール発酵させてできたモロミを、ポットスチルというウイスキー独特の銅製の蒸溜釜で蒸溜して、ウイスキーができます。これは後で認識したのですが、2つのポットスチルをワンセットにして使うのですね。1回目が初溜で、2回目が再溜です。モロミのアルコール度は 6~7% ですが、初溜で 22~23% になり、再溜で 65~70% までになります。銅には不快な香りの除去などの作用があるので、ポットスチルを銅で作るのは必須だとのことです。
発酵と蒸溜の 過程を見学して思ったのは、現代の最先端工場だということです。よくスコットランドの小さな蒸溜所を紹介する雑誌記事やテレビの紀行番組にありますよね。職人が麦芽をショベルで蒸溜所の木のフロアいっぱいに並べ、部屋の炉でピートを焚いて乾燥させる。昔ながらの伝統を守って、みたいな・・・・・・。白州蒸溜所の「発酵と蒸溜」プロセスには、そういう牧歌的雰囲気は全くありません。完全な「工場」です。
もちろん部分部分の工程は、長年に渡って積み重ねられてきたノウハウのかたまりであることは容易に想像がつきます。しかしそのノウハウは、近代工場の制御システムの中に組み込まれている感じです。
この「工場」で印象的だったのは、木製の発酵槽が使われていたことでした。近代的な工場の中に木の設備というのが目立ったのです。なぜ木を使うのかは、あとで書きます。
ポットスチルから滴り落ちたばかりの蒸溜酒を「ニューポット」と言うそうです。これは、全くの無色透明なお酒です。少し試飲しましたが「飲めたものではない」という印象でした。舌を刺すような強い刺激があり、ウイスキーだという感じは全くしない。薬品を飲んでいる感じです。本当はニューポットにも、それなりの味と香りがあるのでしょうが、素人がそれを味わうのは無理だと思いました。
ニューポット は北米産オークの樽に詰められ、貯蔵・熟成されます。見学者が次に案内されるのは貯蔵庫です。
もちろんウイスキー好きであれば、熟成についての大体の予備知識を持っています。ウイスキーは10年、20年と貯蔵されるうちに、樽の木の何百という成分が溶けだして、琥珀色の、まろやかで、複雑な味のウイスキーになる。ウイスキーは樽を通して外気と呼吸していて、この呼吸が熟成の命である。呼吸しているから、年に数%の割合で樽の中身が減っていく。この減少分を「天使の分け前」と言う・・・・・・うんぬん。
実際の貯蔵庫は、想像以上に巨大です。高さ10メートルはありそうな棚の各層にビッシリと樽が積まれ、ズラッと並んでいる。見学者たちは貯蔵庫の入り口から樽の一群を眺め、案内孃の説明を聞きます。説明の内容は忘れましたが、上の予備知識のような内容だったと思います。
そして、案内孃がひと通り説明したあと、見学者の誰かが質問するわけです。
「温度や湿度の管理はどうなっているのですか」
これは極めて自然かつ妥当な質問です。私もこの質問をしようと思っていたのですが、別の人に先を越されました。そして、この質問に対する案内孃の答えに、軽い驚きを覚えました。つまり、
「温度や湿度の管理はしません」
というのがその答えなのです。えっ、と思いますよね。近代的な工場を見てきた直後なので、なおさらです。
この答えから、素人でも類推できることがあります。貯蔵庫には、当然のことながら空気の流れが良い所と、空気が淀む所があるはずです。じめじめして湿気の多い場所も当然ある。普通の家でも、それはあたりまえです。天井に近い所の樽と、床に近い所の樽でも、温度・湿度・通風がかなり違うはずです。ウイスキーは外気と呼吸しています。貯蔵されているウイスキーの樽は、貯蔵庫の中のどの位置どの高さに置かれるかによって、熟成の様子が違うだろう・・・・・・と推測できるのです。
しかも貯蔵庫は一つではありません。白州蒸溜所は山麓の傾斜地に作られていますが、各貯蔵庫は傾斜地の下から上へと、間隔をあけて建てられています。ということは、一番下の貯蔵庫と一番上では標高が違います。高原地帯の山麓なので、霧のかかり具合も違うでしょう。つまり、貯蔵庫ごとにも熟成の様子が違ってくることが想像できるのです。
「温度や湿度の管理はしない」ということから、蒸溜所の立地が重要だと類推できます。同じ日本でも、北か南か、夏の気温はどこまで上がるのか、冬の乾燥度合いはどうなのか、朝夕の寒暖差はどうか、梅雨はあるのかないのか、そばに川があるのか海があるのか、そんなものはないのか・・・・・・、などにより、熟成は違ってくる。サントリーの白州(山梨)と山崎(大阪)、ニッカの余市(北海道)と宮城峡(宮城)の各蒸溜所は、明らかに気候条件が違います。そもそも、酒作りに利用する地下水の質からして違うでしょう。とすると、ウイスキー原酒の味・香りは違ってくるはずです。
要するにウイスキーの熟成では、人間は「何もしない」のです。そこにある自然に、完全に任せる。サントリーのCMのキャッチ・コピーで「何も足さない、何も引かない」というのがありました。私はこれを「ウイスキーの成分を、人為的に足したり、引いたりはしない」という意味だとばかり思っていました。もちろんそういう意味もあるのでしょうが、本質的には「ウイスキーの熟成条件に、人為的に手を加えない。条件を足したり、引いたりはしない」という意味だと考えた方が良い。この意味の方が重要です。
「温度や湿度の管理はしない」という案内孃の答えは、我々が現代の食品製造に抱いている暗黙の考えを見事に裏切っています。ウイスキーの貯蔵庫は、醗酵と蒸溜のプロセスで見た最先端工場とは全く対極の姿なのです。そこが驚きでした。
3番目の見学ポイントは「ブレンド」です。さすがにブレンダーの方がいる部屋を見学するわけではないのですが、ブレンドについての展示がある部屋で、案内孃の説明を聞きます。樽の貯蔵庫で「軽い驚き」を覚えているので、人間の感覚だけに依存したブレンドというのは「すごい技術」であることが分かります。
不思議なのは「オールド」や「ローヤル」などの定番ウイスキーの味と香りを、どうやって一定に保つのだろう、ということです。蒸溜したニューポットを樽に詰めた段階で、これは「オールド」用、これは「ローヤル」用と決めて、熟成のやり方コントロールするのではない。あくまで、10年という単位で自然に熟成した結果を判断し、個性が微妙に違う樽のモルト原酒やグレーン原酒をブレンドして、「オールド」の味や「ローヤル」の味を人間が、感覚をたよりに、人為的に作り出しているわけです。それぞれのブランドには固定ファンがいるはずです。味や香りが変わるのをファンは嫌うでしょう。変わると売れ行きにも影響するはずです。ウイスキーというビジネスは、ブレンダーの方の感覚に依存するビジネスである、と理解できました。
まとめると、ウイスキー作りの3段階は、それぞれ主役が全く違います。つまり、
です。この3つの異なる主役の、長期間にわたる共同作業がウイスキー作りであり、そこにウイスキーの妙味があると思いました。念のために付け加えると、発酵と蒸溜の鍵となる部分は、アルコール発酵という微生物の働きであり、工業化と言っても真の主役は酵母菌です。そこは忘れてはならないと思います。
『ウイスキーは日本の酒である』
最近、サントリーのチーフブレンダーの輿水精一氏(こしみず せいいち)が、『ウイスキーは日本の酒である』(新潮新書。2011) という本を出版されました。この本を読むと、白州蒸溜所の見学だけでは分からなかった、ウイスキー作りの重要部分が理解できます。大変におもしろい本だったので、以降、この本に沿って、ウイスキー作りポイントとなる部分を少し紹介します。
という本を出版されました。この本を読むと、白州蒸溜所の見学だけでは分からなかった、ウイスキー作りの重要部分が理解できます。大変におもしろい本だったので、以降、この本に沿って、ウイスキー作りポイントとなる部分を少し紹介します。
輿水さんは、サントリーのブレンド室に所属するブレンダーの6人を束ねる立場にあります。上司は副社長ということですがら、役員クラスでしょうか。チーフブレンダーは、サントリーが販売する全てのウイスキーを設計し、その味と香りと品質に責任を持つ立場です。まさにウイスキーというビジネスの要(かなめ)です。
まず、ウイスキーについての基本事項です。
モルト・ウイスキーは、二条大麦の麦芽(モルト)が原料です。蒸溜はポットスチルによる単式蒸溜(初溜と再溜)で行います。白州蒸溜所で作っているのはこれです。
一方、グレーン・ウイスキーは、トウモロコシや小麦、ライ麦、大麦などの穀物(=グレーン)が原料です。通常はポットスチルを使わない連続式蒸溜で行います。
このあたりからの知識が重要です。ブレンディッド・ウイスキーは、ウイスキーの故郷のスコットランドと日本では意味が少し違います。
スコットランドでは、複数の蒸溜所(会社)のモルト原酒を集め、それをグレーン原酒とブレンドします。蒸溜所は約100ヶ所あるので、これが可能になります。モルト原酒を蒸溜所同士で売り買いする商売習慣も昔からあります。蒸溜所を持たずに、ブレンディッド・ウイスキーを作るのが専門の会社もあります。
日本のブレンディッド・ウイスキーも、モルト原酒と、グレーン原酒をブレンドして作ります。通常は数10種類のモルト原酒をブレンドしますが、このモルト原酒は、ブレンディッド・ウイスキーを作る会社の、複数のタイプのモルト原酒です。日本では、会社をまたがって原酒を売り買いする商習慣はありません。
一つ(シングル)の蒸溜所で作られたモルト原酒だけを混ぜて作るのがシングルモルト・ウイスキーです。一つの蒸溜所の複数の樽のモルト原酒を混ぜるのを、ブレンドと区別してヴァッティングと言います。
なお、一つの樽の原酒だけを瓶詰めしたものは、シングルカスクと言います。
ブランドのボトルに表示されている熟成年数の定義ですが、シングルモルトの場合もブレンディッドの場合も、そのウイスキーに使われているモルト原酒で最も若いもの、の熟成年数を言います。
たとえば、サントリーの「響12年」は、熟成年数 12年以上のモルト原酒をヴァッティングして作られています。使われているモルトは20種類以上にもなります。中には、30年超のモルトも隠し味的に使われている、と本にあります。「12年」というブランドは「12年」だけのモルト原酒を使っているのではありません。
熟成年数は、世界的にみて12年が標準です。その理由について、輿水さんは次のように書いています。
さきほど「ニューポットは飲めたものではない」などと書きましたが、それは素人の発言であって、プロからみるとニューポットの持つ「力強さ」は重要であり、それと熟成とのバランスが、ウイスキーの妙味であるようです。
モルト原酒の多様性
ここまでの知識で分かることは、スコットランドにおけるウイスキー作りと違って、日本のウイスキー作りでは「一つの蒸溜所が保有するモルト原酒の多様さ」が非常に大切で、この多様性こそが日本におけるウイスキー・ビジネスの成立要因であることです。サントリーではこの多様性を以下のように作り出しています。
ポットスチルを加熱して蒸溜するときに、蒸気による間接加熱方式と、直火式の加熱方式の両方を使います。スコットランドでは間接加熱方式です。
発酵槽として、ステンレス槽と木桶槽の両方を使います。現在、世界的にメジャーなのはステンレス槽です。
発酵のプロセスにおいては、酵母の働きが終わる頃から、乳酸菌が働き始めます。木桶槽を使う目的は、木桶に乳酸菌を住み付かせ、酵母と乳酸菌の共同作業を強めることです。
なお酵母は、あえてウイスキー酵母に、ビールに使うエール酵母も混ぜて使います。
世界中のウイスキー全てに共通するのは、オーク材で作った樽で貯蔵することです。どんな木で作った樽でもウイスキーがあのように熟成するのではありません。木の種類が決定的に重要です。
しかしサントリーでは、オーク材(主として北米産)以外に、北海道産のミズナラ材も使います。第二次世界大戦当時に、オーク材が自由に調達できないことから始まったようです。ミズナラは日本のウイスキー固有の樽材です。
また樽の鏡板としては、オーク材だけではなく、杉材、檜材、山桜材も使用します。
樽の形状や大きさも、バーレル(180L)から、シェリー樽(480L)まで数種を使い、これもモルトの多様性を生み出します。
ウイスキーの貯蔵には新樽が使われることもありますが、多くはシェリー酒やバーボン・ウイスキーの貯蔵に一度使った樽を再利用します。前にどんな酒を貯蔵したかで、モルト原酒の味や香りは変わってきます。「響12年」は梅酒樽も使用しているようです。
樽は2度、3度、4度と、樽の木の成分が枯れるまで使われます。何回目の貯蔵かによって、熟成も違ってきます。
ブレンディッド・ウイスキーに使うグレーン原酒の多様性も重要なようです。グレーン原酒を製造するサントリーの知多蒸溜所では、クリーン、ミディアム、ヘビーの3タイプを作っている、とあります。
原酒の多様性を維持するために、数々の工夫がされていることが分かります。そして白州蒸溜所の見学で分かった「ウイスキーの貯蔵では、人間は何もしない」という原則も、それがウイスキー作りの伝統であると同時に、モルト原酒の多様性を維持するためであることが想像できます。樽の周囲の気温・湿度・通風の条件の違い、貯蔵庫の違いで、熟成が微妙に変化する・・・・・・。実は、輿水さんの本を読むと「熟成の状況をテイスティングしてみて、樽の貯蔵位置を変えることがある」という意味のことが書いてあります。いくら多様性といっても、商品価値が薄い樽が出来たのでは、企業としてはまずいのです。この「ささやか」な人為的介入の方法も、熟成は自然の力にまかせるという原則の現れだと思いました。
以上のようなモルト原酒の多様性を考えると、ブレンダーの必須条件は、サントリーなら山崎蒸溜所、白州蒸溜所、近江エージングセラー、に貯蔵されている100タイプ、約80万樽について、隅々まで把握していることです。もちろんチーフブレンダーだけでは無理で、6人のブレンダーで分担し、また貯蔵部門の人たちの協力が必須です。知多蒸溜所のグレーン原酒も知っておく必要があります。
定番商品となると、5年先、10年先の在庫状況を予測しながら、来年に使う樽を決めていく必要があるわけです。そのウイスキー会社が持っている在庫全体の知識がないと、ブレンダーは勤まりません。
我々はブレンダーと聞くと、香水の調香師と同じで、鋭敏で研ぎすまされた味覚と嗅覚を持ち、微妙な味と香りの違いを次々と嗅ぎわけていく、天才肌の人、というイメージがあります。もちろんそれは正しいのですが、輿水さんの本で分かることは、ブレンダーの仕事の根幹は日々の、こつこつとした積み重ねなのですね。80万樽の在庫の状況をつぶさに把握し、次に仕込む樽のキャラクターに対する注文を現場に出し、定番商品の味・香り・品質の維持に腐心し、ウイスキー作りの改善を日々重ねていくという、地道な活動です。そこが理解できたのは、この本の収穫でした。
定番商品
白州蒸溜所見学記の中で「定番ウイスキーの味と香りを、どうやって一定に保つのだろう」という疑問を書きました。それを実現しているのは、ブレンダーの在庫把握力と味・香りに対する感性なのですが、このことについて書いている輿水さんの文章を紹介しておきます。厳密に言うと定番商品の味と香りを一定には保てない、とのことなのです。
なるほど・・・・・・。私には、2008年の『ローヤル』と2009年の『ローヤル』の違いが全くわからない「自信」がありますが、ウイスキー・ファンの中にはそれが分かる人がいるようなのですね。
いや、待てよ・・・・・・。輿水さんが
と書いているのは、実は
という、チーフブレンダーとしてのプライドを反語的に表現しているのかもしれません。この方が当たっている気がする。
ジャパニーズ・ウイスキー
輿水さんの本によると、世界の5大ウイスキーは
◆スコッチ
◆アイリッシュ
◆アメリカン
◆カナディアン
◆ジャパニーズ
であり、ジャパニーズ・ウイスキーは5大ウイスキーの一角を占めているとのことです。これは、認識を新たにしました。
ISC (International Spirits Challenge) という、ウイスキーの有名なコンペティションがあります。2003年にサントリーの『山崎12年』がISCの金賞をとり、ここから日本製のウイスキーの快進撃がはじまりました。2004年には、ISC最高賞トロフィーを(響30年)、2010年にはサントリーが「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」に輝きました。またウイスキー・マガジンが主催する WWA (World Whisky Award) でも、ニッカを含めて、数々のトロフィーを受賞しています。
モルト原酒の多様性で紹介したように、ジャパニーズ・ウイスキーの作り方はスコットランドと比較していろいろと違います。もともとスコッチに学んだものですが、日本で独自の発達を遂げたわけです。樽にしても、ミズナラを使ったり、鏡板に杉を使ったりと、スコッチではありえないようなことをやっています。日本で独自の発達をしたウイスキー作りが、やがて品質の高さで世界に認められ、5大ウイスキーの一角を占めるまでになったわけです。
このストーリーは何かに似ています。つまり、No.38「ガラパゴスの価値」で書いた、日本で独自の発達を遂げた工業製品が、やがて世界に認められ、グローバルなビジネス展開に至る、というストーリーとそっくりなのです。No.38 では、クルマ、オートバイ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、複写機、の例を書きました。ウイスキーはまさに、これらの工業製品と同じ道をたどった(たどりつつある)わけです。
とにかく徹底的に品質にこだわる。新しい試みにチャレンジしつつ、日々の改善を怠らない。長期的視野で人を育成し、技術の蓄積をはかる。貯蔵担当者のような現場のプロを大切にする・・・・・・。輿水さんの本から読み取れる「日本のウイスキー作りの極意」は、まさに日本の「ものづくり」の成功要因そのものなのです。それが理解できたことだけでも『ウイスキーは日本の酒である』という本の価値はあると思いました。
ここからは補足です。「ウイスキーは日本の酒である」の著者である輿水さんは、サントリーの山崎蒸溜所に勤務しています。この「山崎」というのは、知っている方はたくさんいると思いますが、大阪府の京都との府境近くであり、蒸溜所のすぐそばを、名神高速道路、新幹線、JR東海道線、阪急電車が通っています。東海道という日本の交通の大動脈に近接していると同時に、大阪・京都という大都会の目と鼻の先なのです。また蒸溜所のすぐそばにはマンションが建っていて、町並みが迫っています。
なぜサントリーは山崎に蒸溜所を作ったのか。それは近くに3つの川の合流点があり霧が発生しやすいという条件もあるのですが、大きなものはウイスキー作り・酒作りに欠かせない水です。その水は、山崎の後背地に広がる山(天王山)と、そこの森林や竹林が生み出すものなのです。No.37「富士山型の愛国心」で、日本の誇るべきものとして「国土面積に比較して広大な森林が保持されていること」を書きましたが、まさに山崎蒸溜所は、その自然環境の恩恵にあずかっています。
こういった国の交通の大動脈の近傍、大都会と目と鼻の先の蒸溜所というのは、世界でも珍しいのではないでしょうか。サントリーの Web サイトを見ると、山崎蒸溜所の写真として、いかにも「自然の中にある」という印象を与える光景がのっています。しかし山崎蒸溜所を紹介するなら、もっと引いて撮った写真、新幹線と鉄道と高速道路とマンションと町並みと蒸溜所が共存している写真ものせたほうが良い。山崎蒸溜所で作られたシングルモルト・ウイスキーは、ISC の国際舞台で数々の賞をとっています。そのウイスキーは、「新幹線・高速道路・鉄道・市街地」と「森林をバックにした蒸溜所」が共存している、そういう環境で作られたと、世界にアッピールした方が良いと思うのです。都市文明と森林の共存は日本の特質なのだから・・・・・・。
2018年5月16日、サントリーが「響17年」「白州12年」の販売を休止すると発表しました。日本経済新聞から引用します。
記事によると、世界の2016年のウイスキー市場は2007年から6割増えたそうです。また2017年の国内市場は前年比109%であり、過去数十年で一番少なかった2008年から2倍以上に膨らみました。サントリーのウイスキーの販売量もこの期間で2倍以上に伸び、現在の売上げ規模は1500億円程度です。
サントリーのウイスキービジネスは、世界で高い評価を受ける品質の良さ(=現場の技術力)、ハイボールを前面に押し出したマーケティング(=販売戦略)、アメリカの蒸留酒大手のビーム社の買収による世界への販路拡大(=経営戦略)と、企業活動の重要な要素が三拍子揃っているように見えるのですが、そのビジネスの隘路(ボトルネック)は高品質の商品を急速に増産することは出来ないというところにあるのですね。それは白州蒸留所の見学を思い出すとよく理解できるのでした。
ニッカウヰスキーは「余市」「宮城野」の年代物の販売を2015年に停止していますが、創業者の名前を冠した看板商品である「竹鶴」の年代物の販売も終了することを発表しました。
この記事に「原酒の増産に向けた投資も進めている」とありますが、その話は2019年の10月に報道されました。
ニッカウヰスキーが2019年から2021年にかけて設備投資を含む増産体制をとったとしても、原酒不足が完全に解消するのは2030年ということになります。ウィスキーとはそういうビジネスなのだということが改めて理解できました。
| シングルモルト・ウイスキーは個性が際だっている。ブレンド・ウイスキーはバランスがよい。 |
というようなことを書きました。これは随分アバウト過ぎる言い方であって、本当はそんな単純なものではないことは分かって書いたわけです。
今回は、ウイスキーそんな単純なものではないことの実証です。もう随分前になりますが、山梨県にあるサントリー白州蒸溜所で、ウイスキー作りの過程を見学したことがあります。ここで「ウイスキーが、いかに複雑なお酒であるか」を納得することになりました。
白州蒸溜所の見学コース

|
| サントリー白州蒸溜所 [site : SUNTORY] |
サントリー白州蒸溜所は、中央高速の山梨県・小淵沢インターチェンジの近くで、清里高原や八ヶ岳、蓼科高原にも近いロケーションにあります。南アルプス・甲斐駒ヶ岳へと続く山並みの山麓に蒸溜所はあり、そこはなだらかな傾斜地になっています。ここは一般の人が訪問して、案内ガイドの方に従って、ウイスキー作りのプロセスを見学することができます。
ウイスキー作りは、大きく言うと
①発酵と蒸溜
②貯蔵
③ブレンド
の3つから成り、これが見学コースのポイントでした(もちろんその後に、瓶詰めなどの商品製造工程がある)。この3つの過程に従って、私が見学した時に見聞きしたことをまとめてみます。
| 発酵と蒸溜 |
まず「発酵」のプロセスは次のように進みます。
| ◆ | 大麦を発芽させ、乾燥させて発芽を止め、麦芽(モルト)を作る。この時、ピートを焚いて香りをつける。 | |
| ◆ | 麦芽を粉砕し、温水を加え、濾過し、麦汁を作る。 | |
| ◆ | 麦汁に酵母を加えて発酵槽で発酵させ、モロミを作る。 |
次が「蒸溜」です。アルコール発酵させてできたモロミを、ポットスチルというウイスキー独特の銅製の蒸溜釜で蒸溜して、ウイスキーができます。これは後で認識したのですが、2つのポットスチルをワンセットにして使うのですね。1回目が初溜で、2回目が再溜です。モロミのアルコール度は 6~7% ですが、初溜で 22~23% になり、再溜で 65~70% までになります。銅には不快な香りの除去などの作用があるので、ポットスチルを銅で作るのは必須だとのことです。
| ||

| ||
|
白州蒸溜所の 木製発酵槽と ポットスチル
[site : SUNTORY ]
|
もちろん部分部分の工程は、長年に渡って積み重ねられてきたノウハウのかたまりであることは容易に想像がつきます。しかしそのノウハウは、近代工場の制御システムの中に組み込まれている感じです。
この「工場」で印象的だったのは、木製の発酵槽が使われていたことでした。近代的な工場の中に木の設備というのが目立ったのです。なぜ木を使うのかは、あとで書きます。
ポットスチルから滴り落ちたばかりの蒸溜酒を「ニューポット」と言うそうです。これは、全くの無色透明なお酒です。少し試飲しましたが「飲めたものではない」という印象でした。舌を刺すような強い刺激があり、ウイスキーだという感じは全くしない。薬品を飲んでいる感じです。本当はニューポットにも、それなりの味と香りがあるのでしょうが、素人がそれを味わうのは無理だと思いました。
| 貯蔵 |

| |||
|
白州蒸溜所の貯蔵庫 [site : SUNTORY ] | |||
もちろんウイスキー好きであれば、熟成についての大体の予備知識を持っています。ウイスキーは10年、20年と貯蔵されるうちに、樽の木の何百という成分が溶けだして、琥珀色の、まろやかで、複雑な味のウイスキーになる。ウイスキーは樽を通して外気と呼吸していて、この呼吸が熟成の命である。呼吸しているから、年に数%の割合で樽の中身が減っていく。この減少分を「天使の分け前」と言う・・・・・・うんぬん。
実際の貯蔵庫は、想像以上に巨大です。高さ10メートルはありそうな棚の各層にビッシリと樽が積まれ、ズラッと並んでいる。見学者たちは貯蔵庫の入り口から樽の一群を眺め、案内孃の説明を聞きます。説明の内容は忘れましたが、上の予備知識のような内容だったと思います。
そして、案内孃がひと通り説明したあと、見学者の誰かが質問するわけです。
「温度や湿度の管理はどうなっているのですか」
これは極めて自然かつ妥当な質問です。私もこの質問をしようと思っていたのですが、別の人に先を越されました。そして、この質問に対する案内孃の答えに、軽い驚きを覚えました。つまり、
「温度や湿度の管理はしません」
というのがその答えなのです。えっ、と思いますよね。近代的な工場を見てきた直後なので、なおさらです。
この答えから、素人でも類推できることがあります。貯蔵庫には、当然のことながら空気の流れが良い所と、空気が淀む所があるはずです。じめじめして湿気の多い場所も当然ある。普通の家でも、それはあたりまえです。天井に近い所の樽と、床に近い所の樽でも、温度・湿度・通風がかなり違うはずです。ウイスキーは外気と呼吸しています。貯蔵されているウイスキーの樽は、貯蔵庫の中のどの位置どの高さに置かれるかによって、熟成の様子が違うだろう・・・・・・と推測できるのです。
しかも貯蔵庫は一つではありません。白州蒸溜所は山麓の傾斜地に作られていますが、各貯蔵庫は傾斜地の下から上へと、間隔をあけて建てられています。ということは、一番下の貯蔵庫と一番上では標高が違います。高原地帯の山麓なので、霧のかかり具合も違うでしょう。つまり、貯蔵庫ごとにも熟成の様子が違ってくることが想像できるのです。
「温度や湿度の管理はしない」ということから、蒸溜所の立地が重要だと類推できます。同じ日本でも、北か南か、夏の気温はどこまで上がるのか、冬の乾燥度合いはどうなのか、朝夕の寒暖差はどうか、梅雨はあるのかないのか、そばに川があるのか海があるのか、そんなものはないのか・・・・・・、などにより、熟成は違ってくる。サントリーの白州(山梨)と山崎(大阪)、ニッカの余市(北海道)と宮城峡(宮城)の各蒸溜所は、明らかに気候条件が違います。そもそも、酒作りに利用する地下水の質からして違うでしょう。とすると、ウイスキー原酒の味・香りは違ってくるはずです。
要するにウイスキーの熟成では、人間は「何もしない」のです。そこにある自然に、完全に任せる。サントリーのCMのキャッチ・コピーで「何も足さない、何も引かない」というのがありました。私はこれを「ウイスキーの成分を、人為的に足したり、引いたりはしない」という意味だとばかり思っていました。もちろんそういう意味もあるのでしょうが、本質的には「ウイスキーの熟成条件に、人為的に手を加えない。条件を足したり、引いたりはしない」という意味だと考えた方が良い。この意味の方が重要です。
「温度や湿度の管理はしない」という案内孃の答えは、我々が現代の食品製造に抱いている暗黙の考えを見事に裏切っています。ウイスキーの貯蔵庫は、醗酵と蒸溜のプロセスで見た最先端工場とは全く対極の姿なのです。そこが驚きでした。
| ブレンド |
3番目の見学ポイントは「ブレンド」です。さすがにブレンダーの方がいる部屋を見学するわけではないのですが、ブレンドについての展示がある部屋で、案内孃の説明を聞きます。樽の貯蔵庫で「軽い驚き」を覚えているので、人間の感覚だけに依存したブレンドというのは「すごい技術」であることが分かります。
不思議なのは「オールド」や「ローヤル」などの定番ウイスキーの味と香りを、どうやって一定に保つのだろう、ということです。蒸溜したニューポットを樽に詰めた段階で、これは「オールド」用、これは「ローヤル」用と決めて、熟成のやり方コントロールするのではない。あくまで、10年という単位で自然に熟成した結果を判断し、個性が微妙に違う樽のモルト原酒やグレーン原酒をブレンドして、「オールド」の味や「ローヤル」の味を人間が、感覚をたよりに、人為的に作り出しているわけです。それぞれのブランドには固定ファンがいるはずです。味や香りが変わるのをファンは嫌うでしょう。変わると売れ行きにも影響するはずです。ウイスキーというビジネスは、ブレンダーの方の感覚に依存するビジネスである、と理解できました。
| 余談ですが、サントリーがビールの「モルツ」を発売して以降、私はモルツばかりを飲んでいました。しかし今はモルツ「指名買い」することはありません。サントリーが途中でモルツの味を変えたからで、その変更が私にとっては「好ましくない方向への変更」だったからです。サントリーは少なくとも一人の「固定客」を失ったわけです。これはあくまで個人の嗜好の問題です。今の方が良いという人も当然いると思います。 |
まとめると、ウイスキー作りの3段階は、それぞれ主役が全く違います。つまり、
| ① |
発酵と蒸溜 人間の知恵が主役(蓄積したノウハウの工業化) | |
| ② |
貯蔵 自然が主役(人間は全く手を出さない) | |
| ③ |
ブレンド 人間の感覚が主役(嗅覚と味覚) |
です。この3つの異なる主役の、長期間にわたる共同作業がウイスキー作りであり、そこにウイスキーの妙味があると思いました。念のために付け加えると、発酵と蒸溜の鍵となる部分は、アルコール発酵という微生物の働きであり、工業化と言っても真の主役は酵母菌です。そこは忘れてはならないと思います。
『ウイスキーは日本の酒である』
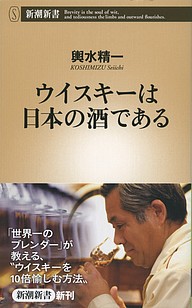
| |||
|
輿水精一 「ウイスキーは 日本の 酒である」
(新潮新書 2011)
| |||
輿水さんは、サントリーのブレンド室に所属するブレンダーの6人を束ねる立場にあります。上司は副社長ということですがら、役員クラスでしょうか。チーフブレンダーは、サントリーが販売する全てのウイスキーを設計し、その味と香りと品質に責任を持つ立場です。まさにウイスキーというビジネスの要(かなめ)です。
まず、ウイスキーについての基本事項です。
| モルト・ウイスキーとグレーン・ウイスキー |
モルト・ウイスキーは、二条大麦の麦芽(モルト)が原料です。蒸溜はポットスチルによる単式蒸溜(初溜と再溜)で行います。白州蒸溜所で作っているのはこれです。
一方、グレーン・ウイスキーは、トウモロコシや小麦、ライ麦、大麦などの穀物(=グレーン)が原料です。通常はポットスチルを使わない連続式蒸溜で行います。
| ブレンディッド・ウイスキー |
このあたりからの知識が重要です。ブレンディッド・ウイスキーは、ウイスキーの故郷のスコットランドと日本では意味が少し違います。
スコットランドでは、複数の蒸溜所(会社)のモルト原酒を集め、それをグレーン原酒とブレンドします。蒸溜所は約100ヶ所あるので、これが可能になります。モルト原酒を蒸溜所同士で売り買いする商売習慣も昔からあります。蒸溜所を持たずに、ブレンディッド・ウイスキーを作るのが専門の会社もあります。
日本のブレンディッド・ウイスキーも、モルト原酒と、グレーン原酒をブレンドして作ります。通常は数10種類のモルト原酒をブレンドしますが、このモルト原酒は、ブレンディッド・ウイスキーを作る会社の、複数のタイプのモルト原酒です。日本では、会社をまたがって原酒を売り買いする商習慣はありません。
| シングルモルト・ウイスキー |
一つ(シングル)の蒸溜所で作られたモルト原酒だけを混ぜて作るのがシングルモルト・ウイスキーです。一つの蒸溜所の複数の樽のモルト原酒を混ぜるのを、ブレンドと区別してヴァッティングと言います。
なお、一つの樽の原酒だけを瓶詰めしたものは、シングルカスクと言います。
| 熟成年数 |
ブランドのボトルに表示されている熟成年数の定義ですが、シングルモルトの場合もブレンディッドの場合も、そのウイスキーに使われているモルト原酒で最も若いもの、の熟成年数を言います。
たとえば、サントリーの「響12年」は、熟成年数 12年以上のモルト原酒をヴァッティングして作られています。使われているモルトは20種類以上にもなります。中には、30年超のモルトも隠し味的に使われている、と本にあります。「12年」というブランドは「12年」だけのモルト原酒を使っているのではありません。
熟成年数は、世界的にみて12年が標準です。その理由について、輿水さんは次のように書いています。
ニューポットが本来もつ力強さと、樽で熟成させた結果、備わっていく香りの華やかさやまろやかな味わい、その両者の微妙なバランスの間に、複雑系であるウイスキーの、酒としての奥深さがある。 |
さきほど「ニューポットは飲めたものではない」などと書きましたが、それは素人の発言であって、プロからみるとニューポットの持つ「力強さ」は重要であり、それと熟成とのバランスが、ウイスキーの妙味であるようです。
モルト原酒の多様性
ここまでの知識で分かることは、スコットランドにおけるウイスキー作りと違って、日本のウイスキー作りでは「一つの蒸溜所が保有するモルト原酒の多様さ」が非常に大切で、この多様性こそが日本におけるウイスキー・ビジネスの成立要因であることです。サントリーではこの多様性を以下のように作り出しています。
| ポットスチルの加熱方式 |
ポットスチルを加熱して蒸溜するときに、蒸気による間接加熱方式と、直火式の加熱方式の両方を使います。スコットランドでは間接加熱方式です。
| 発酵桶と酵母の種類 |
発酵槽として、ステンレス槽と木桶槽の両方を使います。現在、世界的にメジャーなのはステンレス槽です。
発酵のプロセスにおいては、酵母の働きが終わる頃から、乳酸菌が働き始めます。木桶槽を使う目的は、木桶に乳酸菌を住み付かせ、酵母と乳酸菌の共同作業を強めることです。
なお酵母は、あえてウイスキー酵母に、ビールに使うエール酵母も混ぜて使います。
| 樽の木材 |
世界中のウイスキー全てに共通するのは、オーク材で作った樽で貯蔵することです。どんな木で作った樽でもウイスキーがあのように熟成するのではありません。木の種類が決定的に重要です。
しかしサントリーでは、オーク材(主として北米産)以外に、北海道産のミズナラ材も使います。第二次世界大戦当時に、オーク材が自由に調達できないことから始まったようです。ミズナラは日本のウイスキー固有の樽材です。
また樽の鏡板としては、オーク材だけではなく、杉材、檜材、山桜材も使用します。
樽の形状や大きさも、バーレル(180L)から、シェリー樽(480L)まで数種を使い、これもモルトの多様性を生み出します。
| 樽の使用履歴 |
ウイスキーの貯蔵には新樽が使われることもありますが、多くはシェリー酒やバーボン・ウイスキーの貯蔵に一度使った樽を再利用します。前にどんな酒を貯蔵したかで、モルト原酒の味や香りは変わってきます。「響12年」は梅酒樽も使用しているようです。
樽は2度、3度、4度と、樽の木の成分が枯れるまで使われます。何回目の貯蔵かによって、熟成も違ってきます。
| グレーン原酒の多様性 |
ブレンディッド・ウイスキーに使うグレーン原酒の多様性も重要なようです。グレーン原酒を製造するサントリーの知多蒸溜所では、クリーン、ミディアム、ヘビーの3タイプを作っている、とあります。
原酒の多様性を維持するために、数々の工夫がされていることが分かります。そして白州蒸溜所の見学で分かった「ウイスキーの貯蔵では、人間は何もしない」という原則も、それがウイスキー作りの伝統であると同時に、モルト原酒の多様性を維持するためであることが想像できます。樽の周囲の気温・湿度・通風の条件の違い、貯蔵庫の違いで、熟成が微妙に変化する・・・・・・。実は、輿水さんの本を読むと「熟成の状況をテイスティングしてみて、樽の貯蔵位置を変えることがある」という意味のことが書いてあります。いくら多様性といっても、商品価値が薄い樽が出来たのでは、企業としてはまずいのです。この「ささやか」な人為的介入の方法も、熟成は自然の力にまかせるという原則の現れだと思いました。
| 80万樽 |
以上のようなモルト原酒の多様性を考えると、ブレンダーの必須条件は、サントリーなら山崎蒸溜所、白州蒸溜所、近江エージングセラー、に貯蔵されている100タイプ、約80万樽について、隅々まで把握していることです。もちろんチーフブレンダーだけでは無理で、6人のブレンダーで分担し、また貯蔵部門の人たちの協力が必須です。知多蒸溜所のグレーン原酒も知っておく必要があります。
定番商品となると、5年先、10年先の在庫状況を予測しながら、来年に使う樽を決めていく必要があるわけです。そのウイスキー会社が持っている在庫全体の知識がないと、ブレンダーは勤まりません。
我々はブレンダーと聞くと、香水の調香師と同じで、鋭敏で研ぎすまされた味覚と嗅覚を持ち、微妙な味と香りの違いを次々と嗅ぎわけていく、天才肌の人、というイメージがあります。もちろんそれは正しいのですが、輿水さんの本で分かることは、ブレンダーの仕事の根幹は日々の、こつこつとした積み重ねなのですね。80万樽の在庫の状況をつぶさに把握し、次に仕込む樽のキャラクターに対する注文を現場に出し、定番商品の味・香り・品質の維持に腐心し、ウイスキー作りの改善を日々重ねていくという、地道な活動です。そこが理解できたのは、この本の収穫でした。
定番商品
白州蒸溜所見学記の中で「定番ウイスキーの味と香りを、どうやって一定に保つのだろう」という疑問を書きました。それを実現しているのは、ブレンダーの在庫把握力と味・香りに対する感性なのですが、このことについて書いている輿水さんの文章を紹介しておきます。厳密に言うと定番商品の味と香りを一定には保てない、とのことなのです。
とはいえ、毎年、使おうと思う原酒の樽ごとの中身は、やはり微妙に違いがでてきます。定番商品とはいえ、毎年、レシピは変化します。 |
なるほど・・・・・・。私には、2008年の『ローヤル』と2009年の『ローヤル』の違いが全くわからない「自信」がありますが、ウイスキー・ファンの中にはそれが分かる人がいるようなのですね。
いや、待てよ・・・・・・。輿水さんが
| 昨年と今年の違いを感じ取れるようになったら、飲み手としては相当な器量の持ち主といえる |
と書いているのは、実は
| 違いがわかる人は、まずいないと思う。本当に分かる人があったら、手を挙げてみてください |
という、チーフブレンダーとしてのプライドを反語的に表現しているのかもしれません。この方が当たっている気がする。
ジャパニーズ・ウイスキー
輿水さんの本によると、世界の5大ウイスキーは
◆スコッチ
◆アイリッシュ
◆アメリカン
◆カナディアン
◆ジャパニーズ
であり、ジャパニーズ・ウイスキーは5大ウイスキーの一角を占めているとのことです。これは、認識を新たにしました。
ISC (International Spirits Challenge) という、ウイスキーの有名なコンペティションがあります。2003年にサントリーの『山崎12年』がISCの金賞をとり、ここから日本製のウイスキーの快進撃がはじまりました。2004年には、ISC最高賞トロフィーを(響30年)、2010年にはサントリーが「ディスティラー・オブ・ザ・イヤー」に輝きました。またウイスキー・マガジンが主催する WWA (World Whisky Award) でも、ニッカを含めて、数々のトロフィーを受賞しています。
モルト原酒の多様性で紹介したように、ジャパニーズ・ウイスキーの作り方はスコットランドと比較していろいろと違います。もともとスコッチに学んだものですが、日本で独自の発達を遂げたわけです。樽にしても、ミズナラを使ったり、鏡板に杉を使ったりと、スコッチではありえないようなことをやっています。日本で独自の発達をしたウイスキー作りが、やがて品質の高さで世界に認められ、5大ウイスキーの一角を占めるまでになったわけです。
このストーリーは何かに似ています。つまり、No.38「ガラパゴスの価値」で書いた、日本で独自の発達を遂げた工業製品が、やがて世界に認められ、グローバルなビジネス展開に至る、というストーリーとそっくりなのです。No.38 では、クルマ、オートバイ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、複写機、の例を書きました。ウイスキーはまさに、これらの工業製品と同じ道をたどった(たどりつつある)わけです。
とにかく徹底的に品質にこだわる。新しい試みにチャレンジしつつ、日々の改善を怠らない。長期的視野で人を育成し、技術の蓄積をはかる。貯蔵担当者のような現場のプロを大切にする・・・・・・。輿水さんの本から読み取れる「日本のウイスキー作りの極意」は、まさに日本の「ものづくり」の成功要因そのものなのです。それが理解できたことだけでも『ウイスキーは日本の酒である』という本の価値はあると思いました。
ここからは補足です。「ウイスキーは日本の酒である」の著者である輿水さんは、サントリーの山崎蒸溜所に勤務しています。この「山崎」というのは、知っている方はたくさんいると思いますが、大阪府の京都との府境近くであり、蒸溜所のすぐそばを、名神高速道路、新幹線、JR東海道線、阪急電車が通っています。東海道という日本の交通の大動脈に近接していると同時に、大阪・京都という大都会の目と鼻の先なのです。また蒸溜所のすぐそばにはマンションが建っていて、町並みが迫っています。
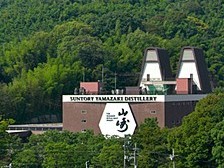
| |||
|
山崎蒸溜所 [site:SUNTORY]
| |||
こういった国の交通の大動脈の近傍、大都会と目と鼻の先の蒸溜所というのは、世界でも珍しいのではないでしょうか。サントリーの Web サイトを見ると、山崎蒸溜所の写真として、いかにも「自然の中にある」という印象を与える光景がのっています。しかし山崎蒸溜所を紹介するなら、もっと引いて撮った写真、新幹線と鉄道と高速道路とマンションと町並みと蒸溜所が共存している写真ものせたほうが良い。山崎蒸溜所で作られたシングルモルト・ウイスキーは、ISC の国際舞台で数々の賞をとっています。そのウイスキーは、「新幹線・高速道路・鉄道・市街地」と「森林をバックにした蒸溜所」が共存している、そういう環境で作られたと、世界にアッピールした方が良いと思うのです。都市文明と森林の共存は日本の特質なのだから・・・・・・。
| 補記1 |
2018年5月16日、サントリーが「響17年」「白州12年」の販売を休止すると発表しました。日本経済新聞から引用します。
|
記事によると、世界の2016年のウイスキー市場は2007年から6割増えたそうです。また2017年の国内市場は前年比109%であり、過去数十年で一番少なかった2008年から2倍以上に膨らみました。サントリーのウイスキーの販売量もこの期間で2倍以上に伸び、現在の売上げ規模は1500億円程度です。
|
サントリーのウイスキービジネスは、世界で高い評価を受ける品質の良さ(=現場の技術力)、ハイボールを前面に押し出したマーケティング(=販売戦略)、アメリカの蒸留酒大手のビーム社の買収による世界への販路拡大(=経営戦略)と、企業活動の重要な要素が三拍子揃っているように見えるのですが、そのビジネスの隘路(ボトルネック)は高品質の商品を急速に増産することは出来ないというところにあるのですね。それは白州蒸留所の見学を思い出すとよく理解できるのでした。
(2018.5.17)
| 補記2 |
ニッカウヰスキーは「余市」「宮城野」の年代物の販売を2015年に停止していますが、創業者の名前を冠した看板商品である「竹鶴」の年代物の販売も終了することを発表しました。
|
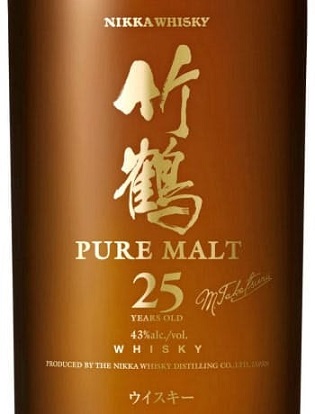
|
NIKKA 竹鶴 25年 |
|
この記事に「原酒の増産に向けた投資も進めている」とありますが、その話は2019年の10月に報道されました。
|
ニッカウヰスキーが2019年から2021年にかけて設備投資を含む増産体制をとったとしても、原酒不足が完全に解消するのは2030年ということになります。ウィスキーとはそういうビジネスなのだということが改めて理解できました。
(2020.1.14)
No.42 - ふしぎなキリスト教(2) [本]
前回より続く
西洋を作ったキリスト教:資本主義の発達
前回に引き続き『ふしぎなキリスト教』(橋爪大三郎・大澤真幸 著。講談社現代新書 2011)の感想です。

| |||
|
橋爪大三郎・大澤真幸 「ふしぎなキリスト教」 (講談社現代新書 2011) | |||
まずその解説をみてみましょう。ポイントはカルヴァン派の救済予定説(予定説)です。つまりカルヴァン派の考え方によると、
| ① | ある人が最後の審判で救済されるかされないかは、あらかじめ神が決めていて、人間の行動がその決定に影響を与えることはできず、 |
| ② | かつ、その神の決定を人間があらかじめ(最後の審判以前に)知ることはできない |
ということなのです。本書で橋爪さんが言っているように、これは一神教の論理のもっとも純粋なヴァージョンであり、一神教を突き詰めて考えるとこうなるわけです。以下、この救済予定説と資本主義の関係を橋爪さんが解説した部分の引用です。
[橋爪] |
この橋爪さんによるヴェーバーの主張の解説は分かります。救済予定説が徹底した時の人間の行動とは、救済予定説から論理的帰結として導かれる人間の行動からはずれた行動になる。なぜならそういう特別な行動をすること自体が神の恩寵だと見なせるから、という論理です。人は勤勉にならざるを得ない。
ここまでは納得なのですが、資本主義の発達の背景の説明としては、問題点が3つあります。
まず第1に、資本主義を成立させるには、その基盤として利子の容認、厳密に言うとキリスト教徒間での利子の容認が必須なことです。本書によると利子の容認はプロテスタントの出現以前から始まっています。本書の立場は、キリスト教における利子の禁止は「困っている同胞を苦しめてはいけない」ということであり、その枠外(たとえば投資のリターンとしての利子)であれば、本来容認してもいい、というものです。プロテスタンティズムが利子を容認したとか、利子の容認を加速させた、ということでもないようなのです。ここは注意すべき点です。
第2は、市場原理にもとづく自由競争がないと資本主義にはならないことです。これは、本書でも少し触れられているように、アダム・スミスの「神の手」論が自由競争を容認するわけですね。これとプロテスタンティズムの関係が、本書の説明としては不明確です。
第3の問題、これが最大の問題なのですが、橋爪さんの解説(する、ヴェーバーの理論)は、カルヴァン派を信仰し予定説を信じた人たちが、
| ・ | 勤勉になる理由は説明されているが |
| ・ | 物財の多さに幸せを感じるようになる理由は説明されていない |
「勤勉だが、清貧」というのでは資本主義になりません。もちろん局所的には「勤勉で清貧」が成立します。子供に財産を残すために勤勉に働き、自分は清貧に生きる、というのは全く問題がない。「勤勉で清貧」はミクロ的には十分可能です。しかしマクロ経済の観点では、経済のバランスがくずれます。全員が「勤勉で清貧」では、資本主義が発達しないのです。資本主義が発達するためには、
・物財の多さに幸せを感じる精神
が必要です。つまり「清貧を否定する論理」が是非とも必要なのです。
極端な例かもしれませんが、アメリカのペンシルヴァニア州に「アーミッシュ」と呼ばれる、プロテスタントの一派の人たちがいます。この人たちは「勤勉だけど、物財の多さに幸せを感じる精神を徹底して否定した生活」を送っています。つまり開拓時代のアメリカそのままの生活をしています。そのことで清貧に生きることを自らに課しているわけです。いくら企業が自動車やスマートフォンを作ってもアーミッシュの人たちには売れません。つまり、この資本主義社会においても局所的ならアーミッシュは成立するのですが、プロテスタント全員がアーミッシュのようなら資本主義は発達しません。
別にアーミッシュまでを引き合いに出す必要はないでしょう。たとえば『バベットの晩餐会』(No.12 - 13 バベットの晩餐会、参照)で描かれたデンマークの寒村の村人たちを思い浮かべればよい。彼らはまじめに働き、清貧な生活を貫き、プロテスタントの信仰に生きています。「料理をおいしいと思うのは悪」という彼らの考えは「物財の多さに幸せを感じるのは悪」と同じことでしょう。それでは資本主義にならない。穿った見方をすれば、パリの高級レストランのシェフであったバベットの料理が村人にもたらした幸福感は、物財の多さに幸せを感じる精神と同じことであり、つまり『バベットの晩餐会』という映画は「プロテスタントの精神」は「資本主義の精神」に転化しうるという寓意なのかもしれません。考えすぎでしょうが・・・・・・。
さらに、資本主義の発達のためには「清貧を否定する論理」だけでなく
・物財の所有量における格差の容認
も同時に必要です。資本主義は「格差と差異」の上に成り立っていて、それが資本主義をドライブしています。現代中国を「中国型資本主義」転換させた政治家は鄧小平ですが、彼は「先富論」を唱えました。「可能な者から先に裕福になれ」という意味です。言い方は美しいけど、要するにこれは「格差を容認する」ということに他なりません。
新約聖書においてイエスは、物財の多さに幸せを感じるという考えでは天国に行けない、という意味の説教を何回もしていますね。「富む者は天国に行けない」と明確に教えています。つまり清貧を推奨している。また、富を持つものは貧者に分け与えよという、格差の容認とは反対の意味のことも言っています。これは資本主義の成立条件とは全く逆です。
「物財の多さに幸せを感じる精神と、物財の所有における格差の容認」が、プロテスタンティズムからどのように導かれるのか、本書にはその説明がありません。ここが、キリスト教が「西洋」を作ったとする、本書の第3部の最大の問題点です。
さらにもっと言うと、予定説を徹底すると「保険」という概念は成立しないのではないでしょうか。「保険」というのは将来起こりうるリスクを想定し、そのリスクをヘッジする手段をあらかじめとっておくということです。「ベニスの商人」のアントニオを思い出します。船を仕立てて異国の産物を輸入するために(仮にですが)全財産を投資すると、航海が成功したときは大金が転がり込むのですが、船が難破したら一文無しになってしまいます。このたぐいのリスクをヘッジするために、ロイズのような保険組合が発達してくるのですね。「保険」は資本主義経済を発達させた根幹のメカニズムの一つだと思います。
この「リスクの想定」というのは、神の計画をあらかじめ人間が推定していることにならないのでしょうか。一神教の論理を最もピュアに徹底させた「予定説」的な考えに反するように思えます。このあたりは、本書の著者に是非聞いてみたいところです。
勤勉に働き、物材の多さに幸せを感じ、市場経済による自由競争を容認し、経済格差を容認し、リスクをとってチャレンジする・・・・・・。この資本主義の精神が、本書が解説しているようにプロテスタントの精神に起因するとしたなら、プロテスタントはトラディショナルなカトリックの秩序と制約を壊したところにこそ意義があるのだと見えます。
西洋近代社会、特に近代資本主義世界を作った中心的な国は、イギリス、オランダ、フランス、ドイツですが、これらの国は、宗教改革後のプロテスタンティズムの国か、王朝と教会の秩序を破壊した「大革命」を経験した国です。つまり、これらの国には明確な共通点があるのです。キリスト教の範疇にとどまりながら、既存の(カトリックによる)社会秩序を破壊した国という共通点です。ここにこそ、近代を作った要因があるように思います。
ちなみにフランス革命(1789- )においては、ルイ16世とマリー・アントワネットの処刑があまりにも有名なため、革命派が攻撃した「旧体制」は王侯・貴族だけだと誤解しそうですが、もちろんそうではありません。革命派が攻撃したもう一つの旧体制は教会と聖職者です。教会の資産が没収され、数々の教会や修道院が閉鎖され、革命に忠誠を宣誓しない聖職者が投獄されたり処刑されたりしました。1794年には、カトリックの一派であるカルメル会の修道女・16人が反革命ということで処刑されました。この件を踏まえて作られたオペラが、プーランクの「カルメル会修道女の対話」です。
余談になりますが、フランス革命による修道院の閉鎖ということで思い出すのがモン・サン・ミシェルですね。フランス革命後、モン・サン・ミシェルは監獄として使われ、聖職者や尼僧、さらには王党派といった反革命派が投獄されました。その後もフランスの正式の監獄として利用され、閉鎖されて修道院としての修復が始まったのは1863年です。約70年の間、監獄として使われたわけです。その間、投獄されたのは約14,000人と言います。フランス革命はバスティーユ監獄の襲撃から始まったと世界史で習うのですが、革命後にバスティーユ監獄が解体された後には、海の上に監獄ができたわけです。私も現地に行った時に初めて、その歴史を知りました。現在でも監獄の「名残り」がいろいろとあります。  アメリカのサンフランシスコ湾にアルカトラズ島がありますが、この島は刑務所として使用されたことで有名です(1861-1963の約100年間)。何となく似ています。アルカトラズは、監獄という意味ではフランスの後を継いだ「アメリカ版 モン・サン・ミシェル」なのでしょう。 |
キリスト教本来の姿に戻ろうという運動が、人々を拘束していた社会の規範を取り除き、それが人々を資本主義的生活に導く・・・・・・。これって、似たような話が近年あったことを思い出します。1960年代の中国の文化大革命です。「走資派」(資本主義をめざす人の意味)を批判し、社会主義の本来の姿に戻るという運動のはずだったのですが、同時に孔子の教えや儒教が徹底的に批判される。これによって2000年間に渡って中国の社会秩序を規定してきたものが一掃されてしまいます。そして文化大革命のあとにやってきたのは「社会主義市場経済」という奇妙な名前の資本主義でした。中国もまた「共産党独裁にとどまりながら、既存の(儒教による)社会秩序を破壊した国」なのです。
キリスト教からの脱却
キリスト教が西洋を作ったというのが『ふしぎなキリスト教』の根本命題であり、それは全くその通りだと思いますが、キリスト教からの脱却が西洋を作った面も強くあります。「脱却」も影響の一つだと言ってしまえばそうなのですが、よく知られているようにキリスト教から離れることで可能になった西洋文化も多い。典型的なのは芸術や文学です。
西洋の音楽も絵画もキリスト教が作ったことは確かですが、しかしそれだけでは我々のなじみの深い音楽も絵画もありえません。その典型がギリシャ・ローマ文化の復興を旗印にしたルネサンスの芸術です。
フィレンツェのウフィツィ美術館に行き、順路に沿って見学していくと、途中にボッティチェリの作品が展示してある大きな部屋に出ます。ここまで来ると、何となくホッとするのですね。その部屋の「目玉作品」である「プリマベーラ(春)」も「ヴィーナスの誕生」も、キリスト教とは無縁の、ギリシャ・ローマ神話に基づく作品だからです。もちろん同じ部屋にはボッティチェリのキリスト教絵画もあります。しかし「ざくろの聖母」(これは傑作です)を見ても、聖母マリアと幼な子イエスという以上に、生身の女性と赤ちゃんという感じが強くするのです。
前回に掲げた「マルタとマリアの家のキリスト」は、画家・フェルメールがキリスト教絵画から出発したことの証明です。しかしその後宗教画をやめオランダ市民の風俗を描くようになった。フェルメールの「至宝」と言われる絵画は全て風俗画(と、風景画 = デルフトの眺望)です。そしてフェルメールの風俗画にちりばめられているのは「手紙」「地図」「地球儀」「望遠鏡」「ガラス窓」といった、当時の西洋近代文明を象徴するアイテムなのです。
べートーべンの楽曲の人気も「宗教から脱却している感じ」ではないでしょうか。べートーべンは宗教曲も書いているし宗教的雰囲気の作品もあるのですが、標題を持つ交響曲、ないしは標題性の強い交響曲である「英雄」「運命」「田園」「七番」「第九」などは、宗教と離れている感じが強い。歌詞がある「第九」も、神の栄光が主役ではない感じです。

| |||
|
ディズニー「ファンタジア」
ベートーベン「田園交響曲」第3楽章(農民達の楽しい集い)のところのアニメーション。神々が葡萄を収穫し、ワインをつくる。 | |||
文学で言うと、シェイクスピアの人気も「キリスト教と無縁な感じ」ではないでしょうか。古代ローマやヴェネチアやヴェローナが舞台の戯曲は宗教とは無縁だし、「真夏の夜の夢」や「テンペスト」では妖精たちが闊歩します。そもそも、神と対立する悪魔や魔女のジャンルだった妖精を「いたずら好きだが悪意はない存在」という本来の姿に引き戻したのはシェイクスピアだと言われていますね。
本書には書いていませんが、キリスト教から離れるという「脱却指向」が西洋を作ったということも、言うまでもないでしょう。もともとキリスト教という中東文化は、西暦4世紀以前の西ヨーロッパの文化的伝統とは無縁のものです。それは、No.24-27「ローマ人の物語」で明白に分かるように、ローマ帝政がヨーロッパ社会に押しつけたものです。押しつけられたものからの脱却指向がエネルギーとなって噴出し、それが新たな文化の伝統を作る・・・・・・。歴史ではよくあることだと思います。
キリスト教と近代文明:キリスト教の相対化
以下では本書の直接の紹介を少し離れて、本書の中心テーマであるキリスト教と近代文明の関係について、感想を中心に記述します。
本書が冒頭に掲げているキリスト教を知る目的は、近代社会のが抱える問題を考えるために近代を相対化したい、そのためには西洋を相対化したい、ということでした。この意味では、キリスト教の相対化も必要なはずです。特に一神教(ユダヤ教、キリスト教、イスラム教)の比較で客観視するのではなく、他の宗教、特に仏教や儒教、ヒンドゥー教、日本の神道などとの比較において、キリスト教を相対化する作業です。
相対化というのは、一段階高い視点から、対立項も含めて客観的・俯瞰的に把握し、その意味を理解し、位置づけを明らかにする、ということだと思います。もう少し踏み込むと、高い視点から宗教を比較し、プラスとマイナス、ポジティヴな面とネガティブな面、光と影を明らかにすることです。以下に何点かあげます。
この世界における人間中心主義
一神教における神と人間の関係、つまり「主人・奴隷原理」は、人間が住む世界では、
・人間 = 主人
・自然 = 奴隷
という関係に容易に転化します。それは、神の摂理を理解できる理性を持っているのは人間だけだ(と仮定される)からです。別の言葉でいうと、地球上では「人間」と「人間以外の自然」の関係において人間中心になるということです。このことは本書においても以下のように解説されています。
[橋爪] |
「クジラに脂身がたくさんあって油が採れるとなれば、クジラを獲ってロウソクをつくってもいい」と書かれているのが印象的ですね。No.20「鯨と人間(1)西欧・アメリカ・白鯨」で書いたように、大西洋・太平洋をまたにかけ、鯨油のために鯨を捕りまくったのはキリスト教徒、特にオランダ、イギリス、アメリカのプロテスタントです。アメリカ東海岸の捕鯨産業がクエーカー教徒によって築かれたことも書きました(それは太平洋捕鯨を通して、結果として日本開国のトリガーを引いた)。また、No.20 で触れたハーマン・メルヴィルの「白鯨」は、聖書に由来する言説や比喩、暗喩に満ちています。「白鯨」は「捕鯨文学」であると同時に「キリスト教文学」と言ってもよいほどだと思います。
ここで橋爪さんは一神教の重要な性格を言っています。一神教は「神はこの世界にはいない、と考える宗教」なのですね。これは、雷鳴が轟くとゼウスのしわざと考える古代ギリシャや、巨樹や滝に神が宿る、ないしは降臨すると考える日本とは大きな違いです。「唯一の超越者」を想定すると、その超越者はこの世界にはいないと考えるしかない。この世界は人間に任されている・・・・・・。これは論理的帰結として当然そうなると思います。
人間の自然に対する自由利用権という考えは、もちろん人間社会における富の増大には大いに役立ったのですが、その一方で、鯨を絶滅危惧種に追い込んだことに象徴されるような大きな問題点を抱え込んでしまったことも明白です。
神に帰依しないものへの非寛容
一神教の大きな特性は「神に帰依しないものへの非寛容」ということだと思います。この非寛容については、No.25「ローマ人の物語(2)宗教の破壊」で詳しく見た通りです。そもそも塩野七生さんの「ローマ人の物語」は寛容と非寛容が大きなテーマとなっていました。
旧約聖書では、エジプトを出たユダヤの民がカナンの地に入り、周辺民族を殲滅して国をつくるわけですが、かなり壮絶な記述が数々ありますね。「7つの民を滅ぼせ」(申命記:7章)はその典型です。
| 「 | あなたが彼らを撃つときは、彼らを必ず滅ぼし尽くさなければならない」(新共同訳聖書。以下同じ) |
| 「 | あなたのなすべきことは、彼らの祭壇を倒し、石柱を砕き、アシェラの像を粉々にし、偶像を火で焼き払うことである」 |
アシェラはユダヤ教からみた、いわゆる「異教」です。2項目の「あなたのなすべきことは・・・・・・」という記述などは、No.25「ローマ人の物語(2)宗教の破壊」で紹介した内容、つまりキリスト教国教化のあとでローマ帝国で起こった事態とそっくりです。
ヨシュア記では、モーゼの後継者であるヨシュアに率いられたユダヤの民がヨルダン川を渡り、カナンの地に入り、そこの部族を次々と殲滅していきます。
| 「 | 彼らは、剣をもってハツォルの全住民を撃ち、滅ぼし尽くして息ある者を一人も残さず、ハツォルを火で焼いた。」(ヨシュア記:11章) |
といった記述が続くのですが、住民を殺し、家屋を破壊し、焼き尽くすのは神への捧げものなのですね。つまり「ホロコースト = 家畜や獣を丸焼きにして神に捧げる儀式」です。住民を奴隷にして売り飛ばしたり財産を奪ったりすると、それは自分たちの利益のために戦ったことになり、神のために戦ったことにはならないのです。
ユダヤの民は他の神を祭る人たちを改宗させようとはしません。世界史をみると「改宗か死かという最後通牒を宗教上の敵対者に迫った事例」は日本を含めて数限りなくあるのですが、ユダヤの民はそうではない。改宗してユダヤの神に帰依する人が増えると困るのでしょう。それだけ選民思想が徹底していたのだと思います。建国の経緯がこれだけ他民族に対して非寛容だと、ユダヤの民が国を滅ぼされてもやむを得ないという気もします。

| ||
|
ニコラ・プッサン(1594-1665)
「アモリびとを打ち破るヨシュア」(1624-5) (ロシア・プーシキン美術館蔵)
旧約聖書におけるモーゼの後継者・ヨシュアが、カナンの地を征服する過程の1場面が描かれている。「ユダヤ民族の栄光の歴史」のひとコマということは理解できるが、アモリびとからすると、外敵に侵略され、皆殺しにされ、土地を奪われるシーンである。ヨーロッパの歴史を知ってはいるが、このホロコーストの場面をフランス人が描き、かつ17世紀絵画の名品とされていることは、絵としての評価は別にして、やはり異様な感じがする。
| ||
ヨシュアに率いられたイスラエルの民がカナンの地に入り、そこの部族を次々と殲滅していくストーリーは、ヨーロッパのキリスト教徒が南北アメリカ、オセアニアで国をつくった経緯とそっくりです。さすがに先住民族絶滅は少ないのですが、しかし、タスマニア人は絶滅させられました。本書でも記述がある、預言者エリヤがバアルの司祭450人を殺害した件(列王記 上:18章)は、No.28「マヤ文明の抹殺」で書いた状況と酷似しています。バアルも、いわゆる「異教」です。
こうしてみると、プロテスタントが始めた各国語訳の聖書は、極めて大きな転換だったと思います。それまではラテン語で書かれた聖書を聖職者が解読し、聖職者が民衆に説教していた。ところがルターから始まった宗教改革では、それではまずいとしてドイツ語訳などの各国語訳聖書を作った。とすると、小さい頃から自国語の聖書を熟読し、慣れ親しむ人たちが出てきます。そういう人たちはどういう考えを抱くのでしょうか。聖書には「愛」が語られています。と同時に「自分たちの神を崇拝しない部族を滅ぼせ」とも言っている。こういった記述は、人々の潜在意識に刻み込まれるのではないでしょうか。
この種の非寛容が歴史書の記述であるなら分かります。どの民族も、多かれ少なかれ他民族に対して「非寛容」だった歴史があるからです。歴史的事実をどう受け止めるか、それは読む人が考えるべきことです。歴史を記述した教科書に対して「特定の歴史観を強制するものだ」とか「いやそうではない」という論争があるぐらいなのだから・・・・・・・。しかし聖書では「宗教の聖典」にこういう記述があるのですね。これは影響が大きいのではないでしょうか。
唯一の正義
キリスト教のバックになっている考え方、つまり、
| 唯一の全知の超越者があり、それが人々のディテールを知っており、人はその超越者が示す規範にのっとって生きるべきだという考え方 |
は、容易に「唯一の正義」という考えに転化すると思います。本当はその「転化」は誤解なのですが・・・・・・。唯一の正義があると思ってしまい、その正義を他人に押しつけようとする考え方。人類の不幸の源泉のほとんどは、この思考様式です。
唯一の正義を振りかざすのがまずいのは、Aさん(A国)の正義とBさん(B国)の正義は違うからで、互いに唯一性を主張すると戦いになるからでです。また唯一の正義を掲げると、その正義の枠組に入らないものがA国の中にもたくさん出てくるので、それらは「反正義」「非正義」「不正義」であり、「悪」として排除することになります。善悪2元論になるのは目に見えています。
世の中には「何かの欠如としてしか定義できないもの、ないしは定義してはいけないもの」がありますね。「平和」という概念がそうです。
「平和」というのは「戦争がない」ということです。それ以上のことを「平和」の定義とするとおかしくなる。たとえば「戦争がなく、民主主義で社会が運営されているのが平和な社会だ」などと考えてしまうと、平和な社会の実現を掲げ、民主主義の実現のために他国に戦争をしかける、という倒錯状態に陥らないとも限らない。
正義も平和に似ています。正義は「不正の欠如」です。何が「不正」であり「悪」であるかは、世界共通的なものもあるが、地域や文化によって相違しているものも多いわけです。従って「不正の欠如状態」が「正義が実現されている状態」と考えるしかない。それ以上の、特定のものの考え方や理念や政治思想を「正義」だとするとおかしくなります。正義の実現を掲げて不正を働くという倒錯に陥るのです。
No.20「鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」で書いた「動物愛護テロ」はその典型でしょう。動物愛護というのは動物虐待をなくすということが目的のはずなのに、虐待がないということをはるかに越えた、何か崇高な唯一の正義としての「愛護」を想定してしまうと、愛護のためにテロを起こすという倒錯状態になります。
「正義」や「平和」などの「誰しも認めざるを得ない崇高な価値や理念」は、その定義のしかた、意味内容によくよく注意しないと、それこそ悲惨な結果を招くと思います。
矛盾と二者択一
科学と宗教が矛盾したとき、現代のキリスト教徒がどう考えるかについての議論が本書にあります。例としてあげられているのは、人間が下等な動物から進化したとする進化論と、人間は神によって(今の形で)創造されたとする創造説の矛盾です。
| ||||||||||||||||||||||||
少数派とは言え、図B派はアメリカではそれなりの数になります。昔ですが「進化論を学校で教えてはいけない」という法律を成立させた州がありましたね。過半数の州議会議員が賛成したということです。実際に進化論を教えた先生が起訴されたこともありました。また最近では「神による創造」を「インテリジェント・デザイン(ID)」と言い換えて、それを進化論と並んで学校で教えよといった運動をしている人たちがいます。近代国家としては信じがたいことなのですが、それだけ図Bのように考える人がいるということでしょう。
『ふしぎなキリスト教』で指摘されていますが、図Aと図Bは似ています。両方とも「矛盾するものの両方を正しいと考えることができない、きわめつきの合理主義」(本書)だからです。表裏一体と言っていいでしょう。
一方、たとえば大多数の日本人は、科学と宗教の矛盾に直面したときには、図Aのように考えるか、ないしは図Cのように考えると思います。図Cというのは「宗教環境下では宗教を信じ、実社会では科学を信じる」わけです。矛盾していると言われるかもしれないけれど、これで何かまずいことがあるとも思えないのです。そもそも日本人のとらえ方としては「宗教と科学が矛盾する」ということ自体が変である。実際のところ、仏教や神道の教えは「科学のスコープ外」のことを言っており、科学と矛盾するものではない。むしろ「諸行無常」にしろ「自然に神が宿る」にしろ、どちらかと言うと科学と整合的である・・・・・・。これが大多数の日本人の暗黙の考えなのではないでしょうか。
図AとB、図Cを、宗教と科学の関係ではなく一般的に社会における「矛盾するもののとらえ方」だとしましょう。そうすると、AやBのように「矛盾をつきつめて考え、二者択一をする」ことは重要ですが、同時にCのように「二者択一をしないこともまた重要」です。実社会における解決すべき課題の多くは、個人的なものでも国レベルのものでも、体系Aで考えると結論はaであり、体系Bで考えると結論はb、というように矛盾することが多いわけです。しかも困ったことに重要な課題になればなるほど矛盾する。こういったときに大切なのは、
| ◆ | 矛盾を矛盾としてそのまま受け入れ、早急な結論を出さない。 |
| ◆ | 矛盾の自分の中で寝かせて、曖昧性を許容しつつ、考えを巡らす。 |
| ◆ | 対立する矛盾点を最大限に解消する、第3の道を模索する。 |
| ◆ | どうしても対立する一方を採用すべき状況になった時には、決断する。 |
| ◆ | しかしその決断は、その時の外部環境や自分の思いに影響されるから、別の機会に同様の決断をするときには、反対の結果になるかもしれないことを認識しておく。 |
という態度です。
広く浸透した宗教のモノの考え方は、宗教を離れて社会における人間の行動パターンに影響を与えます。だからこそ『ふしぎなキリスト教』は、キリスト教が西洋社会作ったという認識から始まっているし、プロテスタントの精神が資本主義にドライブをかけた、と主張しているわけです。宗教的思考が、宗教とは関係ない実社会での思考に影響することは十分に考えておかないといけません。
図AとBは表裏一体ですが、図Cは違います。キリスト教を相対化する行為では、このあたりの認識も大切だと思います。もちろん一般社会においては、図Cは欧米のキリスト教徒においても普通の思考様式だと思います。あたりまえですが・・・・・・。
| 補足ですが、進化論に関しての図B的な動き、つまり進化論を教えるなという法律を作ったり、インテリジェント・デザイン説を標榜したり、というのは、すべてアメリカのプロテスタントの一部(が中心)ですね。カトリック教会やローマ教皇は、別に進化論を否定していないはずだし、多くのプロテスタントもそうです。図Bというのは「アメリカの特殊事情」という面があることは、要注意だと思います。 |
コミュニティーの教え
『ふしぎなキリスト教』を読んで強く思うのは、聖書およびイエスの教えは、ユダヤ人社会という、同質的なコミュニティーの中での教えだということです。それを、パウロが普遍宗教=キリスト教にした。パウロがいなかったらキリスト教はなかったということは、本書で何回か強調されていることです。
そもそもイエスの教えは、イスラエルの神がモーゼを通して与えた律法を皆がもっとよく守るように、というのが原点です。それは新約聖書のはじめの方に出てきます。
| 「 | わたしが来たのは律法や預言者を廃止するためだ、と思ってはならない。廃止するためではなく、完成するためである。はっきりいっておく。すべてのことが実現し、天地が消えうせるまで、律法の文字から一点一画も消え去ることはない。」(ヨハネ:5章) |
イエスは、このような律法と預言者の成就と完成に加えて、ユダヤ人社会の改革、ないしはユダヤ人コミュニティーの新しい原理を説いたわけで、もちろん「世界宗教を作る」などとは思っていない。イエスの言動は、ユダヤ教という宗教を共有する仲間うちの教えであるという面、つまり
| 皆で助け合い寄り添って、外敵と戦い、集団を維持する必要がある、価値観を共有するコミュニティの中の倫理 |
という面を強く感じます。
本書の第2部の「不可解なたとえ話」にあげられている「不正な管理人」(ルカ:16章)の話がそうです。主人の財産の管理人が、主人に無断で他人への貸し金を減額したが、主人はそれに怒るどころか管理人を褒めたという話です。これなどもユダヤ人社会の中での富の再配分、富める人は貧者に施すべきだ、という教えだとすると分からないでもない。一般化した「経済活動」と考えると、不可解極まりなくなります。
「利子の禁止」もそうですね。「借金をするような、困っている同胞から利子をとってはいけない。無利子で貸すべきだ」という倫理なら分かります。事実、ユダヤ教もキリスト教も利子は禁止ですが、ユダヤ教徒がキリスト教徒から利子をとるのは(また、その逆は)禁止ではない。同胞ではないからです。シェイクスピアの「ベニスの商人」という物語(のシャイロックに関係する部分)が成立するゆえんです。
『ふしぎなキリスト教』には出てきませんが、一般に広まっている聖書の有名な教えを考えてみると、たとえば「敵を愛し、迫害するもののために祈りなさい」(マタイ:5章。ルカ:6章)というのがあります。しかし、本当に自国を滅ぼそうとする敵を愛することはできないわけです。ホロコーストを画策している敵を愛すると、民族は絶滅します。そうではなく、ユダヤの民という同胞の中の敵、神の敵ではない「汝の敵」を愛しなさい、という話だとすると、理解できる。寄り添い、団結して生きていかないと存続することさえ怪しい、厳しい状況におかれたコミュニティの倫理だと思います。
「だれかがあなたの右の頬を打つなら、左の頬をも向けなさい」(マタイ:5章。ルカ:6章)も同様です。これを一般論として考えると、右の頬を殴られたのに左の頬を出すというのは、これほどの挑発行為はないわけです。しかしユダヤ人社会において争いをやめよ、汝の敵を愛せということの一環なら、分からないでもない。
「人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい」(マタイ:7章)という教えもあります。この「人にしなさい」の「人」が他国や他民族のことだとしたら、こんな迷惑なことはない。他国では価値観が違うのが一般的だからです。「ありがた迷惑」「余計なお世話」というやつです。「ありがた迷惑」ぐらいならまだしも、人類の歴史上の不幸の大きな要因は「自分(自国)がして欲しいと思うことは、人(他国)もして欲しいだろう、と思ってしまう誤解」です。しかもそれは(ひとりよがりの)善意からきているので始末が悪い。しかし、そういう他国や他民族のことではなく、価値観を共有できる同質的なコミュニティ内部の教えだとしたら、これも理解できないことはない。
もともと同胞の中の教えであったものを、パウロが普遍的な世界宗教にした。当然、普遍性にマッチする部分と、普遍的と言うには無理が生じる部分が出てきます。そこは認識しておく必要があると思います。
日本とは何か
本書を読んで分かることの一つは、キリスト教がユダヤ教と違うのはイエス・キリストの存在だけであり(その存在が大きいわけですが)、また、本書で常に対比して語られているイスラム教とも一神教というスキームでは親戚と言える宗教だということです。
キリスト教とユダヤ教、そしてイスラム教も、中東の近接地域に生まれた、一神教という非常に特別な宗教です。それは言語的には、ヘブライ語(ユダヤ教)、アラム語(キリスト教)、アラビア語(イスラム教)というセム語族の民族から発生したものです。そして世界の多大な地域がこの「中東起源の文化」に、程度の差はあれ「覆われた」わけです。覆われていない地域は僅かです。
さらに、マルクス主義はキリスト教の直系の子孫です。マルクス主義がキリスト教の種々のコンセプト・部品・考え方で構成した「神がいないキリスト教、形を変えたキリスト教」であることは、本書で何回か言及されていることです。キリスト教を経済学へ(無理やり)応用したとも言えるでしょう。
歴史をマクロ視点で見ると、世界の多大な地域が「中東起源の3宗教か、マルクス主義」で覆われたわけです。覆われていないのは、それこそごく僅かです。人口の多い国では、インド、タイ、日本、韓国、台湾ぐらいでしょうか(他にカンボジアなどの仏教国がある)。そのうちの韓国はクリスチャンが多い国です。人口の3割とか4割はキリスト教徒ですね。インドにも一定数のイスラム教徒がいます。人口の10数%程度というけれど、12億人の人口のインドでは絶対数からいうと1億6000万人とかそいういう数字であって、大イスラム教国とも言えます。
『ふしぎなキリスト教』の「はじめに」に、次のような意味のことが書いてあります。
| 近代の根っこにあるキリスト教を「分かっていない」度合いを調べることができたなら、おそらく日本がトップになるだろう。それは日本人が頭が悪いということではなく「日本があまりにもキリスト教とは関係のない文化的伝統の中にあった」からである・・・・・・。 |
この冒頭の言が、本を通読してよく分かりました。全くその通りだと思います。
少々意外なのですが、『ふしぎなキリスト教』を読んで分かる重要なことは「日本とは何か」ということです。「キリスト教ないしはその類似思想と、最も関係がない文化的伝統を持ち、かつ近代化に早くから成功した国」、それが世界における日本のポジションなのですね。このポジションは、現代世界の中である種の困難さを伴うかもしれないが、日本人が今さら取捨選択できない以上、その「希少価値」をどう生かしていくかが重要だと思いました。
(続く)
No.41 - ふしぎなキリスト教(1) [本]
キリスト教への関心
No.24 -27「ローマ人の物語」で、塩野七生・著「ローマ人の物語」の感想を書きましたが、そこでは第14巻の「キリストの勝利」での記述を中心に、ローマ帝国の崩壊を決定づけたキリスト教の国教化と、それに伴うローマ固有の宗教や文化の破壊をテーマにしました。キリスト教は西ローマ帝国の崩壊後もヨーロッパ社会のコアとなっていきます。

| |||
|
橋爪大三郎・大澤真幸 「ふしぎなキリスト教」 (講談社現代新書 2011) | |||
そのキリスト教とは何かを、非常にコンパクトに、かつ全体的に解説した本が2011年に出版されました。『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書 2011)です。 お
この本は二人の社会学者の対論です。一人は橋爪大三郎氏(東京工業大学教授)で、もう一人は大澤真幸(まさち)氏(思想月刊誌 主宰)です。ともに東京大学大学院・社会学研究科出身であり、特に橋爪さんは比較宗教学者であって、この本の主旨からすると適任の人でしょう。対論は大澤さんが「キリスト教のふしぎや疑問点」について橋爪さんに質問したり突っ込んだりし、それに橋爪さんが答えるという形になっています。大澤さんも社会学者なので、橋爪さんの意見に異論をはさむシーンもあり、読みごたえのある内容になっています。
そこで、この本の内容の紹介(一部ですが)と、感想を書いてみたいと思います。
なぜキリスト教を語るのか
『ふしぎなキリスト教』の冒頭に「なぜキリスト教を語るのか」について、この本の主旨が書かれています。それはまず「近代社会」の理解という目的です。つまり
| ◆ | 近代社会とは、西洋的社会がグローバル・スタンダード になっている社会であり | |
| ◆ | その西洋的社会とは、端的に言うとキリスト教型文明社会である |
からです。
現代は「近代社会」のさまざまな問題を乗り越える必要に迫られています。それは環境問題であり、エネルギーの問題であり、異文化の対立や抗争であるわけです。そのためには「近代の相対化」が必要であり、それは「西洋の相対化」ということに他ならない。そのためには、西洋のコアにあるキリスト教の理解が必要です。「相対化」と著者が言っているのは、一つ高い視点から、対立項も含めて客観的・俯瞰的に把握し、その意味を理解し、ポジションを明らかにするということだと思います。
ここで「キリスト教が分からないと、西洋や近代社会が分からない」ということではない、ことに注意すべきだと思います。よく知ったかぶりの人が「やっぱりキリスト教が分かってないと、西洋が理解できないよね」と言いますが、そんなことはありません。西洋を理解するには、そこで発達した資本主義や科学、思想、政治主義などを学べばいいわけです。それで十分、西洋は理解できます。
しかしそうではなく「近代や西洋を相対化し、それが抱える問題を乗り越えるためには、キリスト教の理解が必要だ」と著者は言っているわけで、これは妥当だと思います。近代を相対化し、近代=西洋社会を一つ高いレベルから客観的に俯瞰するためには、西洋社会の背後やルーツにあるキリスト教を理解する必要があるというわけです。本書は「キリスト教入門の本」ではありません。「はじめに」で断ってあるように、近代=西洋社会を理解するための本であり、そのためにキリスト教を理解しようとする本です。「西洋を作った」という視点からキリスト教を見たときに特質は何かを語った本です。そこを間違えると、本書の意味はなくなるでしょう。
キリスト教の「ふしぎ」
キリスト教には、クリスチャンでない日本人からみると、いろいろと「分かりにくい」ところがあります。ちょっとあげてみただけでも、
| ・ | 一神教とは何なのか |
| ・ | キリストという存在(神なのか、人なのか、神の子なのか) |
| ・ | 神と精霊とキリストの三位一体とは。そもそも精霊とは何か。三つが一つとはどういうことか。 |
| ・ | 旧約聖書と新約聖書という、聖典の二重構造。特にユダヤ教の聖典である旧約聖書をキリスト教が温存していること。 |
| ・ | 原罪の考え方。それと関係した「キリストによる贖罪」という思想 |
『ふしぎなキリスト教』には、こういったキリスト教の分かりにくいところが、かなり明快に説明されています。内容はキリスト教全般をカバーしていて多岐に渡るので、すべての感想を語ることはできません。ここでは本書の第1部、第2部、第3部の話題から、近代西洋社会との関係におけるキリスト教という点に絞って感想を書きます。
一神教の論理
第1部は「一神教を理解する」と題されていて、ユダヤ教とキリスト教を中心に、一神教とは何かが解説されています。「近代西洋社会との関係におけるキリスト教」という視点で最も重要だと思ったのは、キリスト教の「一神教」という性格であり、その考え方や、そこから派生する思想が近代西洋社会の形成に多大な影響を与えたということです。
一神教を最も端的に象徴するのは、旧約聖書のはじめの方の「イサクの犠牲」だと思います。イサクの犠牲の話は本書では第1部ではなく「第2部 イエス・キリストとは何か」の中で、原罪と贖罪の説明に出てきますが、引用すると以下のようです。
| イサクの犠牲(創世記:22章) |
[橋爪] |
イサクの犠牲の話で直感的に思うのは、人間を生け贄として神に捧げる、という古代の習俗の記憶ではないかということですね。
それはさておき、ここでみられる神とアブラハムの関係、つまり主の命令で実の息子を殺すという関係は、ちょっと常識を超越している感じがします。人間社会でも「親が、他者と自分の関係において、ある意図をもって、自分の実の子を殺す」ということが、全くないわけではない。もちろん激情にかられて、とか、一家心中とか、子どもの行く末を悲観してとか、保険金目当て、とかは除きます。「他者と自分の関係において」という条件です。
ちょっと飛躍しますが、連想するのは徳川家康が実の息子の信康を切腹させた件ですね。それは、織田信長に武田側との内通を疑われ、信長が要求したからです(家康は、正室の筑山殿も同時に殺害している)。この件はいろいろの説があるようですが、圧倒的な力の差がある主従関係では(当時の信長と家康。正確に言うと信長と家康は主従ではなく同盟者の関係)、こういうことが起こることは「ないわけではない」のです。しかしこの手の話は歴史上に多くはないと思うし、やはり「主の命令で息子を殺す」という関係、しかも「本当に息子を殺せるか、主がアブラハムを試した」という結末は、人間社会の話だとすると常軌を逸していることは確かだと思います。
この「イサクの犠牲」に典型的にみられる、一神教の根本的な考え方が、本書の第1部に説明されています。以下のところです。
[橋爪] |
ここで橋爪さんが God としているのは、日本語で「神」と書くと、なれなれしいニュアンスが紛れ込んでしまうからです。だから一神教の神を「God」としているわけです
この解説が一神教の重要な定義だと思います。つまり神=主人、人間=奴隷という原則、いわば「主人・奴隷原理」が一神教における神と人間の関係なのですね。この一神教の原理は有名な「カインとアベル」の話にもよく現れています。
| カインとアベル(創世記:4章) |
[橋爪] |
橋爪さんによると「人間には神に愛される人と愛されない人がいる。それは受け入れなければならない。」と解釈するようです。
しかし、カインとアベルの話は「主人・奴隷原理」からすると当然ありうる状況です。奴隷ではなく、主人の所有物やモノの関係と考えても同じです。トマトは好きだけどキュウリは嫌いで、サラダのトマトは食べるがキュウリは残すという人がいても(またその逆でも)その理由はないわけです。単に嫌いなだけです。それが非難されるいわれもない。なぜか嫌いなのですかと人間側から神に問うことはできません。そういう問いをすること自体、一神教ではなくなります。原理上、そうなっている。
一神教は、中東地区に生まれた非常に「特別な」宗教形態です。ユダヤ教・キリスト教・イスラム教という、3つの宗教。一神教は基本的にこれしかありません。人類史上、こういうタイプの宗教はまれです。何万、何百万とあったはずの宗教のうちの3つ、しかもほとんど兄弟とも言える宗教しかない。そして、神が一つであるのが一神教ではありません。神が一つであると同時に「主人・奴隷原理」の宗教が一神教なのです。
不可解なたとえ話
「第2部 イエス・キリストとは何か」では、キリスト教の不思議さの根幹であるイエス・キリストについて書かれています。この弟2部で特におもしろかったのは、大澤さんが新約聖書に出てくる「たとえ話」をとりあげて「このたとえ話、不可解でしょう?」と橋爪さんに詰問し、橋爪さんが、それはキリスト教的にはこう解釈する、と答える問答でした。ここで取り上げられている「たとえ話」は、神と人間の関係を端的に表しています。それを3つ取り上げてみたいと思います。
| ブドウ園の労働者(マタイ:20章) |
[大澤] |
普通このたとえ話をどう解釈するかというと、橋爪さんの解説では、
| 幼児洗礼を受けたりして子どもの頃からキリスト教徒である人と、大人になって信徒になった人、晩年に病床で「駆け込み」洗礼を受けた人の、誰が神の国にいくでしょう、というたとえであり、イエス・キリストは、どの人も同じように、神の国に招きたいのだと言っている |
と考えるそうです。
この「ブドウ園方式」で人間社会を運営しようとすると破綻します。言うまでもなくこういった「賃金体系」は公平ではないし、労働者のモチベーションもなくなります。2度とこのブドウ園では働くものか、となるでしょう。経済的にもこのブドウ園の経営は行き詰まりかねない。だから「人は洗礼の時期にかかわらず、神の国に行ける」ということの比喩だ、との解釈ができたと考えられます。
しかし、このたとえ話は大澤さんも言っているように、神と人間の関係を示す比喩のはずです。つまり
・ブドウ園の経営者 = 人間
・労働者 = 人間
と考えるから不可解に見えるわけですね。これはあくまでたとえ話であって、
・ブドウ園の経営者 = 神
・労働者 = 人間
と考えればよい。そうすると「主人・奴隷原理」によって
・ブドウ園の経営者 = 主人
・労働者 = 奴隷
ということになります。主人と奴隷の関係だとすると、この話は不可解なことはない。次のような状況を考えてみます。
|
ブドウを栽培してワインを作っている主人がいます。最良のワインを作るために、今日1日でブドウを摘んでしまいたい。ところが家の奴隷の手が足りない。主人は近所の家に行き、今日1日、一人奴隷を貸してくれないか、奴隷の食事はちゃんと出す、と言って奴隷を借りてきます。 しかし、それでも収穫に間にあわず、その日に2度、3度と別の家を訪ね、奴隷を借ります。そうした結果、ブドウの摘み取りは無事に終了しました。夕食時になって主人は、その家の奴隷や借りてきた奴隷に向かって言います。「今日はよく働いてくれた、夕食は多めに用意した、いっぱい食べて帰ってくれ。」 |
「ブドウ園の労働者」における駄賃を「労働の対価=賃金」だと考えるから不可解になるのです。労働者=奴隷だと考えると、奴隷に賃金を支払う主人はいないわけです。駄賃は、奴隷が生きていくための必要事項(たとえば夕食)だと考えれば、おかしくはない。また、夕食ではなく、奴隷を貸してくれた家に均等に1デナーリずつ払ったとしても、決して不自然ではないと思います。
| 放蕩息子の帰還(ルカ:15章) |
新約聖書の「放蕩息子の帰還」は、非常に有名な話です。本書から引用します。
[大澤] |
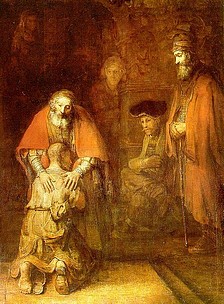
| |||
|
レンブラント 「放蕩息子の帰還」 (エルミタージュ美術館) | |||
橋爪さんによると、この「放蕩息子の帰還」のたとえ話は「神が人間を配慮するやりかたは、人間社会の常識を越えていることを示すためのたとえ話」だそうです。確かに、これを人間社会の話、つまり、
・父親 = 人間
・放蕩息子 = 人間
という枠組みで考えると完全に常識を越えています。しかしこの話は、神と人間の関係を示すためのたとえ話であって、
・父親 = 神
・放蕩息子 = 人間
と考えればよい。そうすると「主人・奴隷原理」によって、
・父親 = 主人
・放蕩息子 = 奴隷
ということになります。この場合、話を分かりやすくするために、
・父親 = 羊飼い
・放蕩息子 = 牧羊犬
として「羊飼いと牧羊犬の関係」に置き換え、次のような「お話」を考えてみればよいと思います。
|
羊飼いが2頭の牧羊犬を使って100頭の羊を放牧していました。牧羊犬の名前は、タローとジローです。ある日、ジローが突如、行方不明になりました。残されたタローは大変です。100頭の羊をタローだけでみなければならないからです。 ジローはどうしていたかというと、野山を徘徊し、果実を食べ小動物を狩って、「労働」もせず、気ままに暮らしていました。しかし、ある年から干ばつがひどくなり、食べ物にも窮するようになります。しかたなく、ジローは元の羊飼いの家に戻ってきました。 羊飼いは、戻ってきたジローをみて「よく戻ってきてくれた、ジロー」と大歓迎しました。「明日から、またタローと一緒に羊を放牧しよう」。 |
この「お話」は、あまりに当たり前すぎます。怒ったタローがジローに噛みつくということもないでしょう。つまり神と人間の関係を示す「たとえ話」だと考えると不可解ではありません。
放蕩息子の帰還は数々の名画の題材になってきました。中でも最も有名なのが、エルミタージュ美術館にあるレンブラントの一枚です。
| マリアとマルタ(ルカ:10章) |
放蕩息子を題材にした絵はレンブラントが有名ですが、次の「たとえ話」に関してはフェルメールが描いています。
[大澤] |
一般的な解釈では、マルタは日常的な生活を象徴し、マリアは宗教的な生活を表し、そしてマルタは日常の瑣末なことにとらわれていた、そこに問題があるとされているようです。これではすんなりとは納得できない。橋爪さんの解釈は次のようです。
[橋爪] |

| |||
|
フェルメール 「マルタとマリアの家のキリスト」 (スコットランド国立美術館) | |||
この話は、やはりイエスの言うように、炊事場で働くよりイエスの言葉を聞く方が重要だということを言っているのでしょう。信仰に生きなさい、ということです。また、ここでも神と人間の関係を「たとえ話」で示していると考えられます。つまり、
・イエス = 神
・姉妹 = 人間
であり、「主人・奴隷原理」にしたがって、これが主人と奴隷の関係だと考えると大いにありうるわけです。主人・奴隷の関係に置き換えて「お話」を作ってみると、たとえばローマ帝国時代に、奴隷が2人いる家で、詩を作るのが趣味の主人がいたとしましょう。ある詩を完成させた主人は(たまたま)夕食を準備中の奴隷に朗読して聞かせます。2人とも聞き入ると夕食の準備はできないので、一人だけが朗読を聞く。その一人は「いいほうをとった」わけです。不可解ではありません。奴隷は主人に文句を言ってはいけないのです。
| ちなみに、フェルメールの絵ではマルタが中央に描かれていて、構図上の主役になっています。これについて「家事にいそしむのが美徳、という当時のオランダの倫理を表している」との説があるようです。フェルメールもまた、聖書のマリアとマルタの話に違和感を持っていたのかもしれません。 |
これらの「不可解なたとえ話」で一貫して主張されているのは、神と人間の関係における一神教の原理だと思います。それを人々に教えるための話だと感じます。
西洋を作ったキリスト教:哲学・思想・科学
第3部の「いかに『西洋』をつくったか」では、キリスト教のモノの考え方や発想が西洋文化のコアとなっていることがテーマで、ここが本書の中核部分です。
要するに、キリスト教の God を信仰するということは、それを客観的にみると世界を統一的に把握する原理が存在するという確信を持つことに他ならないわけです。
聖書の矛盾したテキストを統一的に解釈する作業や、キリストの位置づけを明確にする努力から、三位一体などの教義がうまれ、キリスト教神学が発達します。これが、その後の西洋の哲学の発達につながります。人間の理性への信仰も「神の設計したこの世の構造を理解する人間の理性」への信仰です。フランス革命では「理性神」があがめられましたが、それは神の代替物です。
マルクス主義思想がキリスト教のコピーであることは、本書で何度か強調されています。キリスト教が西洋を作り、その西洋が近代を作ったというのが『ふしぎなキリスト教』の命題ですが、マルクス主義というのはまさに西洋近代社会の申し子だと思います。
科学の発達も世界を統一的に把握する原理があることの確信がベースです。この象徴的存在が、アイザック・ニュートン(1642-1724)ですね。本書には書いていないのですが、ニュートンの「業績」は
①物理学(古典力学)・数学
②錬金術
③聖書研究(聖書の「科学的」解読)
の3つです。
①の物理学では、運動方程式と万有引力の法則という、数学的に記述された極めて少数の原理から、複雑に見える惑星の運動が導出できることを証明したのが有名で、まさに近代科学の原点とも言える業績です。万有引力の法則だけならニュートン以前に何人かの先人が発見しています(フックなど)。ニュートンの偉大なところは「世界を統一的に把握する原理を発見し、定式化した」ことです。
②の錬金術は、今からするとオカルトのようにも思えますが、当時は最先端の化学だったわけですね。ニュートンは65万語に及ぶ錬金術の手稿を残したようです。錬金術は19世紀まで続きます。No.18「ブルーの世界」で書いたマイセンの磁器の(西欧における)発明も、またプルシアン・ブルーという顔料の発見も「錬金術師」と呼ばれた人たちの功績です。錬金術が化学の発達を促したことは明白です。
しかしニュートンはこれらの「科学」と同時に、③の聖書研究にも力を注いでいます。聖書には隠された意味(聖書の暗号、いわゆるバイブル・コード)が潜んでいるはずで、それを解き明かすという研究をニュートンはかなりやっています。残された手稿は130万語に及ぶそうです。こうなるともう完全なオカルトのように見えますが、現代でもバイブル・コードを研究している人はいるようなので、ニュートンの時代にはまじめな「科学」と思われていたのでしょう。
聖書研究、錬金術、物理学という、ニュートンの3つの研究分野は、科学の発達のプロセスを如実に示していると思います。ニュートンの物理学(力学)の業績も、当時としては「神が設計したこの世界の秘密を解き明かした」ということだったと思います。
以上のように、『ふしぎなキリスト教』における「西洋を作ったキリスト教」の解説は明快なのですが、ちょっと問題なのは資本主義の発達とキリスト教の関係の部分です。
(続く)
No.40 - 小公女 [本]
No.18「ブルーの世界」で青色染料である「藍・インディゴ」の話を書きましたが、そのとき、ある小説を連想しました。児童小説である「小公女」です。なぜ「藍」から「小公女」なのかは、後で書きます。
子供のころに「小公子」は読んことがありますが「小公女」の記憶はありません。「小公女」がどんな話かを知ったのは、以前にテレビのアニメ「小公女セーラ」を娘が熱心に見ていたからで、私もつられて見たわけです。非常によくできた話だと感心しました。
「小公女」はイギリス生まれのアメリカの作家、フランシス・ホジソン・バーネット(1849-1924)が1888年に発表した小説です。「小公子」を出版した2年後になります。要約すると次のような話です。
「小公女」(A Little Princess)のあらすじ
舞台は19世紀のイギリスです。冬のロンドンは日中だというのに薄暗く、霧が立ちこめ、ガス灯がともっています。このなかを行く辻馬車に、父と娘が乗っています。ここから物語は始まります。
セーラは7歳の少女で、父親につれられてロンドンのミンチン女子学院に入学しました。ここはミンチン女史が経営する一種の私塾で、4歳から10代前半の女の子たちが、家から離れて学院に寄宿しながら勉強しています。セーラはたちまち人気者になり、この学院の「看板生徒」になりました。
しかしセーラが11歳の誕生日に、悲報がもたらされます。父親が急死し、かつ友人の事業への投資の失敗で一文無しで他界したとのことなのです。母親はセーラが幼少の頃に亡くなっています。身よりも財産もなくなったセーラは、女子学院の屋根裏部屋に住み、学院の「小間使い」として働きはじめます。セーラの、辛い労働の日々が続きます。それでもセーラはくじけず、もともと備わった気品を失いませんでした。
しかし父の友人の事業は、実は復活して大成功し、その友人は何倍にも大きくなった財産を相続するはずのセーラを探していたのでした。その友人がたまたま学院の隣に引っ越してきたことに端を発して、真実が明らかになります。セーラは父の友人に引き取られ、再び幸せな日々に戻ります。
よくできた物語 - 「小公女」第1部
大変によくできた物語で、テレビで「小公女セーラ」を見た時には感心してしまいました。物語は便宜的に、第1部、第2部、第3部の3つに分けられるでしょう。
第1部はセーラの入学にはじまり、幸せな学院生活を送る部分です。セーラは聡明で、人に優しい少女です。話がじょうずで、他の子供たちを引きつけます。髪は黒で、目は緑がかった灰色、背は高いほうで、ほっそりとし、独特の美しさがあります。全体に「王女」のような気品がある少女なのです。
しかもセーラは裕福な家庭に育ちました。ミンチン学院には「特別寄宿生」の中でも特別な生徒として入学します。それは彼女用の
・寝室と居間
・馬車と子馬
・お手伝いさん
が与えられるという、破格の待遇なのです。
物語の第1部を読む(見る)うちに読者(視聴者)は、このまま終わるはずがないと思います。このまま終わってしまえば「あまりにも出来すぎた少女の話」であって、小説とは言えなくなるからです。
そして案の定というか、物語には不吉な影がさすのです。一つはミンチン先生がセーラに敵意を持つことです。ミンチン先生はフランス語が話せないことを人知れず悩んでいました。話せないことを、周りには隠していた。そしてセーラが入学後のフランス語の授業において、彼女はフランス語が話せることが分かるのです。何と彼女の母親はフランス人であり、せーラが幼少の頃に亡くなったのですが、父親はセーラの母を偲んでしょっちゅうセーラにフランス語で話しかけていたのです。授業のあとでフランス語の先生は「この子に教えることはない」とまで言います。これでミンチン先生は内心、セーラに敵意を持つのです。
もう一つの「影」は学院の生徒であるラヴィニアです。ラヴィニアはきれいな子ですが、少々性格に難があって、いじわるなところがある。小さい子供には横柄で、年のいった子供の中ではつんと気取る。そしてセーラが来るまでは自分が学院の総大将だと思っていたのです。そのポジションをセーラに奪われた。それはセーラの優しさや人気によるものなのですが、ラヴィニアはセーラを強くねたむのです。
こういった不吉の兆候から読者は、「幸福なセーラ」がこのままでは終わるはずがない、という予感を持ちます。何かとんでもないことが起こるに違いないと・・・・・・。
よくできた物語 - 「小公女」第2部
読者の「期待」どおり、その「とんでもないこと」が起こって第2部になります。父親が破産して死んでしまうのです。セーラは学院の屋根裏部屋に住み込み、小間使いとして働き始めます。なぜ学校から追い出されなかったのか。それは身よりがなくなったとたんに追い出したのでは学院の評判を落とすと、体面を気にするミンチン先生が考えたからです。「何一つ不自由のない裕福な生徒」から「学院の小間使いという児童労働者」へ・・・・・・。この劇的な変化が「小公女」のストーリーのコアになっています。
小間使いというのは、要するに先生や生徒、学院の料理番などの使用人から言いつけられた仕事を何でもこなす役割です。学院には既に、ベッキーという少女が小間使いとして屋根裏部屋に住み込んでいたのですが、セーラはそこに同居します。
小間使いの労働は厳しいものがあります。たとえば重い石炭箱をさげて教室にはいり、暖炉の灰を掃きだし、石炭をくべる。教室の床の掃除をし、窓ガラスも磨く。生徒の靴も磨く。料理番の手伝いで外へ買い物にも行く。びしょ濡れになりながら、雨の中を遠い所までお使いに行ったりもしました。お使いに行き、目当てのものが見つけられなかったということで、料理番から食事を抜かれたこともある。セーラの服は次第に「つるつるてん」になっていき、町で乞食と間違われてお金を恵んでもらったことさえありました。
セーラに敵意をもっていたミンチン先生、そしてセーラをねたんでいたラヴィニアは、ここぞとばかりにセーラに辛くあたり、無理難題をふっかけ、要するに「いじめる」わけです。ラヴィニアはみすぼらしい格好になったセーラを見て仲間の生徒と一緒に大笑いするし、ミンチン先生もセーラを叱って食事を抜いたりする。現代の日本ならこの女子学院は「いじめ」で新聞沙汰になるだろうし、それ以前に児童相談所に通報されてミンチン先生は逮捕されるでしょう。しかし物語の舞台は現代の日本やイギリスではないのです。
セーラはこの状況にくじけることなく仕事をこなし、人前では涙を見せず、彼女が本来持っていた「気品」を失いません。これがまたミンチン先生やラヴィニアをいらだたせる。もしセーラが泣きじゃくって「もう許してください、ミンチン先生、ラヴィニア様」とでも言うのなら「いじめ」をやめようという気にもなります。しかしセーラは全く正反対なのです。それがおもしろくない。ますますセーラを困らせようとするわけです。
セーラは気品を失わないと同時に、人に対する優しさも失いません。町にお使いに出た時に4ペンス銀貨を拾ったことがありました。おなかを空かしていた彼女はそれでパンを4個買い、おまけとして2個もらうのですが、たまたまいた乞食の少女に5個をあげてしまいます。自分よりよほど「ひもじい」ように見えたからです。
「小公女」という児童文学は、こういったエピソードが続く第2部が大半を占めています。まさにここがハイライトなのですね。この第2部におけるセーラを一言で表せそうな、ぴったりではないかもしれないけれど非常に近い日本語があります。「けなげ」です。
「けなげ」は、非常に特別の状況にしか使わない日本語表現です。それは
姿を表現する言葉です。この「弱小・逆境・忍耐・勤勉の4点セット」のどれが欠けても「けなげ」とは言わない。この4点の程度は強くても弱くてももよいのですが、とにかく4点そろっていることが重要です。おそらく英語に相当する単語はないでしょう。こんなスペシャル・ケースを表わす単語があるぐらいだから、日本人は「けなげ」な姿を見るのが好きだし、愛着を感じる。近年(と言ってもだいぶ前ですが)、最も「けなげ」だった女の子は、言うまでもなく「おしん」ですね。そして「おしん」と同様、アニメ世界名作劇場「小公女セーラ」は大ヒットしました。
しかし「けなげ」なセーラの姿を見るうちに、読者は当然思うのですね。「このままで終わるはずがない」と。このまま終わってしまったら、小説として成立しない。
よくできた物語 - 「小公女」第3部
物語も終わりに近づいて、驚きの事実が判明し第3部になります。セーラが実は大金持ちだったことが、全くの偶然がきっかけとなって分かるのです。
そもそもセーラはインド生まれです。セーラの父親はラルフ・クルーといい、インドに渡って友人のキャリスフォードと一緒にダイヤモンド鉱山の開発をはじめ、それに財産をつぎ込んでいました。当時、インド在住のイギリス人の子供は、長距離旅行ができる年齢になるとロンドンに帰って学校に入るという習慣だったようで、セーラ・クルーもそうしたわけです。
そしてダイヤモンド鉱山の開発は失敗し、ラルフ・クルーは財産を失い、彼自身もマラリアで死んでしまいました。しかし、失敗したと思われた鉱山開発は復活・成功し、友人のキャリスフォードは莫大な財産を築いた。そしてラルフ・クルーが当然得るべき資産を返すため、相続人である娘のセーラを探してロンドンに帰って来ていたのです。
そのキャリスフォード氏が、何と偶然ミンチン女子学院の隣に越して来て住んでいたというのが「小公女」のストーリーであり、お隣の縁でセーラのことが判明するのです。第2部の途中で「インドの紳士」が隣に越してくるのですが、その紳士が亡くなった父の友人だったわけです。
こんなストーリーがありだろうかと思ってしまいますが、ありなのですね。つまり、第1部の「お嬢様」から第2部の「小間使い」へという、あまりに劇的な展開があるため、第3部の「全くの偶然に端を発した、驚愕の事実の判明」にも違和感を感じません。当然そうなるだろう、やっぱり、という感じです。読者にとってこれは想定内の展開なのです。
セーラはキャリスフォード氏に引き取られます。また、何かとセーラに親切にしてくれた小間使いのベッキーもセーラが引き取って、二人で幸せに暮らし始めた、というところで物語は終わります。
共産党宣言
ちょっと唐突ですが「小公女」の物語から、マルクス/エンゲルスの「共産党宣言」(1848)を連想してしまいました。労働者の団結とブルジョアジーの打倒を訴えた共産党宣言は、第1章の冒頭の「今日まであらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。」から始まって、共産主義革命が歴史の必然だと言っています。もちろんそのような歴史認識は変だし、コミュニスト政権の樹立が歴史の必然でもないわけです。しかし一つ言えることは「共産党宣言」のような文書が書かれるに至った根底には、産業革命以降に急速に肥大化した資本主義社会への批判があることです。その批判の大きな要因は、イギリスを含む当時のヨーロッパ社会の「ものすごい貧富の差」です。それは「貧富の差」というレベルを遥かに超えていて、たとえば、小間使いのセーラよりもっとひどい「児童虐待労働」があったわけですね。イギリスの炭鉱などでは・・・・・・。教科書にも出ていました。コミュニズムがヨーロッパにある程度浸透し、一定の勢力を得るに至った理由はそれでしょう。「持てるものと持たざるものの極端な格差」です。内田樹氏の文章でそのあたりの事情を振り返ると以下です。
エンゲルスは父親の経営していたマンチェスターの紡績工場で働いた経験があります。彼が書いた『イギリスにおける労働者階級の状態 - 19世紀のロンドンとマンチェスター』は、彼自身が加担していた "非人間的な労働環境" と "労働者を収奪する仕組み" への嫌悪感に溢れています。鉱山労働の部分のごく一部を引用します(算用数字にして段落を増やしました)。
「小公女」においてセーラは2つの状態をとります。
の2つです。Bの状態は、まともに人間としては扱われず、人としての尊厳さえ破壊されかねない状況です。それでもセーラは「尊厳」を保ったわけですが・・・・・・。とにかくAとBでは「天国と地獄」なのです。
AとBの差はイギリス社会における貴族と平民の差ではありません。小説の題名は Princess ですが、セーラは王族や貴族ではなく「平民」です。「小公女」は「王女と乞食」という身分差の話ではない。AとBの2つの極端な状態変化は、お金を持っているか、お金を持っていないかの違いなのです。そしてAかBかは固定されたものではなく、セーラのように変動しうる。もちろん彼女の場合は極端ですが・・・・・・。
「小公女」は当時のイギリス社会の格差を象徴的に暗示していると考えられます。これはもちろんイギリスだけでなく、ヨーロッパ先進諸国の、そしてもっと広くは日本を含む初期・工業化・資本主義社会の抱える問題だったわけです。資本主義は、野放しにしておくと雪だるま式に格差が拡大していくメカニズムを内包しています。そこは政府が介入して手を打たないと社会の瓦解を招きかねない。20世紀になって各国政府は「社会主義的政策」を導入するわけですが、19世紀はその前の段階です。
「小公女」は「共産党宣言」が書かれるまでに至った19世紀の社会背景を象徴的に表していると思いました。
インドの犠牲
「小公女」はまた、19世紀のイギリスの繁栄がインドの犠牲の上に成り立っていることを、それとなく暗示しています。
セーラが貧乏になるのも、また最後に裕福になるのも、インドにおけるダイヤモンド鉱山開発の成否にかかっている、というのが小説の設定です。現在、世界のダイヤモンド生産国としては南アフリカが有名ですが(産出量で1位はロシア)、ここのダイヤモンド鉱山が発見されたのは19世後半であり、本格的に鉱山が開発されたのは20世紀です。19世紀まではダイヤモンドといえばインドだった。「小公女」にしきりと出てくる「ダイヤモンド鉱山」というキーワードは、インドの富がイギリスに移転したということの象徴だと考えられます。
しかし、ダイヤモンドは貴族や富裕層だけのものです。もっと一般庶民に関係した「インドの富」がいろいろとある。ここで思い出すのが、No.18「ブルーの世界」で書いた、青色染料である「藍」(インディゴ)です。
インディゴ(Indigo)は、その名前のとおり、古代からインドが主要産地でした。インディゴを作る植物は「インド藍」です。青色染料であるインディゴは古代ローマ時代から西欧に輸出され、それは中世を経て近代まで続きました。このインド藍をイギリスの植民地(アメリカ、サウス・カロライナ)で奴隷労働によって生産したのが、イライザ・ルーカス・ピンクニーだったわけです。しかし、イギリスはアメリカという植民地を失います。No.18「ブルーの世界」でも引用した、その後の経緯は次の通りです。
もともとインドの特産品だった「藍・インディゴ」は、イギリスのインド支配を通して、インドの人々に奴隷労働をもたらしたことになります。この文章の冒頭に、No.18「ブルーの世界」の藍・インディゴから「小公女」を連想したと書きましたが、それは「インドつながり」でした。
そしてイギリスの植民地だったアメリカのサウス・カロライナで、藍・インディゴ以上に大々的に奴隷によって栽培され、現在でもアメリカ南部一帯が有力な産地となっている作物があります。綿です。そして綿もインド原産の植物なのです。
綿(木綿・コットン)
No.26「ローマ人の物語(3)」でも引用したヘロドトスの『歴史』に次のような記述があります。
古代ギリシャ人にとって、インドでは木にできる羊毛から衣服が作られるのが非常に珍しいことだったのです。古代ギリシャ・ローマの時代から、綿花と綿織物はインドの特産品でした。それは言葉にも残っています。キャラコという木綿の布があります。細かい織り目の、白い光沢がある布です。このキャラコはインドの綿織物の輸出港であるカリカットが語源になっています。また日本で更紗(さらさ)という布があります。木綿の布に赤や青の文様が染色されているものですが、これはインド更紗がルーツです。古来インドでは、更紗の赤は茜、青はインディゴで染色されました。古代から17世紀まで、綿花・綿織物と言えばインドだった。
しかし18世紀になって、綿花と綿織物の生産環境は激変します。ヨーロッパを中心とするインド産の綿花・綿織物の需要増大に対応して、イギリスは極めて効率のよい綿花生産の方法に乗り出します。アフリカから奴隷をイギリス領アメリカへ運び、そこの大規模プランテーションにおいて奴隷労働で綿花を栽培し、それをイギリスへ輸入するという方法です。
もう一つの激変がイギリスの産業革命です。産業革命は歴史の教科書で習ったとおり、綿工業の機械化から始まりました。紡績機(綿花から糸を紡ぐ機械)と織機(布を織る機械)が発達し、木綿の布が安価に大量に生産できるようになったわけです。このイギリスで機械生産された綿製品は海外に輸出され、もちろんそれはアフリカでは奴隷と交換されたのですが、当然、インドにも大量になだれ込みました。その結果として、インドの綿織物産業は壊滅的な打撃を受けたのです。
独立国であればこういう場合、輸入される綿織物に高い関税をかけて国内産業を保護し、その間に産業の機械化を進めて、徐々に関税を引き下げていく、というような政策をとるわけです。しかし「関税自主権」がないとこんなこともできない。インドの人々は自国の有力産業が失われていくのを、なすすべなく見守るしかなかったわけですね。こういうことが各種の産業で起こると、国はどんどん貧しくなっていきます。19世紀のイギリス、ヴィクトリア女王(在位:1837-1901)の時代の繁栄の裏には、綿工業だけをとってみても「インドの犠牲」があったのは確実です。
ところで、イギリスの綿織物産業と「小公女」の作者は大いに関係があるのです。フランシス・ホジソン・バーネットは1849年にイギリスのマンチェスターで生まれました。マンチェスターは19世紀イギリスの綿織物の製造拠点で、中心地です。フランシスの父親は家具の卸問屋を経営して裕福でしたが、彼女が4歳の時になくなり、母親に託された一家の暮らしは苦しくなりました。そしてフランシスが11歳のときアメリカで南北戦争が勃発し(1861年4月)、一家の暮らしはますます苦しくなります。なぜかと言うと、南北戦争でアメリカから綿花が輸入されなくなり、マンチェスターの綿織物産業が大きな打撃を受けたからです。マンチェスターの町は不況に陥り、それがフランシス一家をも直撃しました。そしてフランシスが16歳のとき、一家は親戚をたよってアメリカのテネシー州に渡ったのです。その一家の家計を助けるために彼女は小説を書きはじめ、雑誌に投稿します。この執筆活動の中から、後の「小公子」「小公女」「秘密の花園」が生まれるのです(以上は、偕成社文庫「小公女」の訳者、谷村まち子氏の解説によります)。
フランシスは、産業革命後のマンチェスターの綿織物産業の発展と不況を体験し、その後のイギリスとアメリカでの苦しい生活を経験したわけです。これが「小公女」のプロットに影響を与えたとも推測できます。
「小公女」のリアリティー
ロンドンを舞台にした「小公女」のストーリーは、裕福なお嬢様(第1部)から小間使いに(第2部)、それから再び元に(第3部)と、ちょっとありえないような展開をします。それでいて妙にリアリティーを感じるのは、当時のイギリスの社会環境である、
・富裕層と底辺労働者の格差
・インドという植民地の存在
を背景にしているからではないでしょうか。
「小公女」という小説は、現代日本を舞台にTVドラマやアニメとしてリメイクしにくい小説だと思います。そんなリメイクをしたら、全くリアリティーがないものになる可能性が高い。それでも近年、志田未来さん主演で現代日本を舞台にリメイクされたようです。そのTVドラマを見ていないので何とも言えませんが、成功したのかどうか。
「小公女」の作者であるイギリス生まれのアメリカ人・バーネットは、当時のイギリスの社会環境への問題意識をもとに小説を書いたのでしょうか。それとも単に読んでハラハラする少女向けの児童小説を書いたのでしょうか。それは分かりません。しかし確実に言えることは、「小公女」のストーリー展開とそこに出てくるエピソードはいかにも極端だけど、作者のバーネットは当時の社会環境を十分に頭に入れた上で、非常にまじめに小説を書いていることです。第2部の「小間使いのセーラ」のところなどは、大げさに言うと「人間の尊厳とは何か」というテーマを扱っているようにも見える。作者の実生活での苦労が反映されているのかもしれません。この作者の「まじめさ」が、多くの人を引きつける要因になっているのでしょう。
小説の終わりの方で(第18章)セーラは辛かった小間使いの時期を思い出して言います。原文で引用すると次のとおりです。
I tried not to be anything else.
「私は、ほかのものにはならないようにしていたんです」というような意味ですが、いかにも英国人(米国人)の作家が書きそうな文章だという気がします。自分を見失わず、これが自分の個性だと思うことは貫き通す。そこにこそ人間の価値がある ・・・・・・。さりげない一言に、小説のテーマの一端が現れていると思います。
No.1, No.2 で取り上げた「クラバート」は、少年が大人になる過程を通して、人間の自立とは何か、社会における労働とは何か、などの普遍的なテーマを扱っていました。作者のプロイスラーはこの児童小説に「普遍性」を盛り込もうと、はじめから意図して書いたと考えられます。それに対して「少公女」のフランシス・バーネットは、そういう意図はなかったと思います。あくまで「少女向け小説」を書いた。しかし作者の意図はどうであれ、この小説はある主のリアリティーと深みを持つことになった。「クラバート」と「少公女」は、「よくできた児童小説は、児童小説の範疇を越えた普遍性をもつ」ことの良い実証例だと思います。
子供のころに「小公子」は読んことがありますが「小公女」の記憶はありません。「小公女」がどんな話かを知ったのは、以前にテレビのアニメ「小公女セーラ」を娘が熱心に見ていたからで、私もつられて見たわけです。非常によくできた話だと感心しました。
「小公女」はイギリス生まれのアメリカの作家、フランシス・ホジソン・バーネット(1849-1924)が1888年に発表した小説です。「小公子」を出版した2年後になります。要約すると次のような話です。
| アニメの「小公女セーラ」は原作より登場人物が拡大されたり、原作にはないエピソードがあったりします。以下は原作をもとに書きますが、アニメ版も、あらすじのレベルでは基本的には同じです。 |
(以下には物語のストーリーが明かされています)
「小公女」(A Little Princess)のあらすじ
舞台は19世紀のイギリスです。冬のロンドンは日中だというのに薄暗く、霧が立ちこめ、ガス灯がともっています。このなかを行く辻馬車に、父と娘が乗っています。ここから物語は始まります。
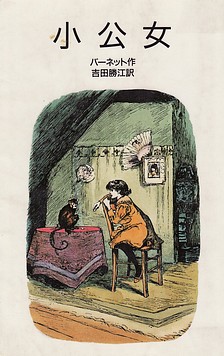
| |||
| 「小公女」(岩波少年文庫) | |||
| Princess という題がついていますが、セーラは王族や貴族ではありません。彼女が王女のような気品をもっていることを言っています。 |
しかしセーラが11歳の誕生日に、悲報がもたらされます。父親が急死し、かつ友人の事業への投資の失敗で一文無しで他界したとのことなのです。母親はセーラが幼少の頃に亡くなっています。身よりも財産もなくなったセーラは、女子学院の屋根裏部屋に住み、学院の「小間使い」として働きはじめます。セーラの、辛い労働の日々が続きます。それでもセーラはくじけず、もともと備わった気品を失いませんでした。
しかし父の友人の事業は、実は復活して大成功し、その友人は何倍にも大きくなった財産を相続するはずのセーラを探していたのでした。その友人がたまたま学院の隣に引っ越してきたことに端を発して、真実が明らかになります。セーラは父の友人に引き取られ、再び幸せな日々に戻ります。
よくできた物語 - 「小公女」第1部
大変によくできた物語で、テレビで「小公女セーラ」を見た時には感心してしまいました。物語は便宜的に、第1部、第2部、第3部の3つに分けられるでしょう。
第1部はセーラの入学にはじまり、幸せな学院生活を送る部分です。セーラは聡明で、人に優しい少女です。話がじょうずで、他の子供たちを引きつけます。髪は黒で、目は緑がかった灰色、背は高いほうで、ほっそりとし、独特の美しさがあります。全体に「王女」のような気品がある少女なのです。
しかもセーラは裕福な家庭に育ちました。ミンチン学院には「特別寄宿生」の中でも特別な生徒として入学します。それは彼女用の
・寝室と居間
・馬車と子馬
・お手伝いさん
が与えられるという、破格の待遇なのです。
物語の第1部を読む(見る)うちに読者(視聴者)は、このまま終わるはずがないと思います。このまま終わってしまえば「あまりにも出来すぎた少女の話」であって、小説とは言えなくなるからです。
そして案の定というか、物語には不吉な影がさすのです。一つはミンチン先生がセーラに敵意を持つことです。ミンチン先生はフランス語が話せないことを人知れず悩んでいました。話せないことを、周りには隠していた。そしてセーラが入学後のフランス語の授業において、彼女はフランス語が話せることが分かるのです。何と彼女の母親はフランス人であり、せーラが幼少の頃に亡くなったのですが、父親はセーラの母を偲んでしょっちゅうセーラにフランス語で話しかけていたのです。授業のあとでフランス語の先生は「この子に教えることはない」とまで言います。これでミンチン先生は内心、セーラに敵意を持つのです。
もう一つの「影」は学院の生徒であるラヴィニアです。ラヴィニアはきれいな子ですが、少々性格に難があって、いじわるなところがある。小さい子供には横柄で、年のいった子供の中ではつんと気取る。そしてセーラが来るまでは自分が学院の総大将だと思っていたのです。そのポジションをセーラに奪われた。それはセーラの優しさや人気によるものなのですが、ラヴィニアはセーラを強くねたむのです。
こういった不吉の兆候から読者は、「幸福なセーラ」がこのままでは終わるはずがない、という予感を持ちます。何かとんでもないことが起こるに違いないと・・・・・・。
よくできた物語 - 「小公女」第2部

| |||
| 小間使いとして働くことになったセーラと、ミンチン先生。この挿画は1891年にアメリカで出版された「小公女」のもの(岩波少年文庫より) | |||
小間使いというのは、要するに先生や生徒、学院の料理番などの使用人から言いつけられた仕事を何でもこなす役割です。学院には既に、ベッキーという少女が小間使いとして屋根裏部屋に住み込んでいたのですが、セーラはそこに同居します。
小間使いの労働は厳しいものがあります。たとえば重い石炭箱をさげて教室にはいり、暖炉の灰を掃きだし、石炭をくべる。教室の床の掃除をし、窓ガラスも磨く。生徒の靴も磨く。料理番の手伝いで外へ買い物にも行く。びしょ濡れになりながら、雨の中を遠い所までお使いに行ったりもしました。お使いに行き、目当てのものが見つけられなかったということで、料理番から食事を抜かれたこともある。セーラの服は次第に「つるつるてん」になっていき、町で乞食と間違われてお金を恵んでもらったことさえありました。
セーラに敵意をもっていたミンチン先生、そしてセーラをねたんでいたラヴィニアは、ここぞとばかりにセーラに辛くあたり、無理難題をふっかけ、要するに「いじめる」わけです。ラヴィニアはみすぼらしい格好になったセーラを見て仲間の生徒と一緒に大笑いするし、ミンチン先生もセーラを叱って食事を抜いたりする。現代の日本ならこの女子学院は「いじめ」で新聞沙汰になるだろうし、それ以前に児童相談所に通報されてミンチン先生は逮捕されるでしょう。しかし物語の舞台は現代の日本やイギリスではないのです。
セーラはこの状況にくじけることなく仕事をこなし、人前では涙を見せず、彼女が本来持っていた「気品」を失いません。これがまたミンチン先生やラヴィニアをいらだたせる。もしセーラが泣きじゃくって「もう許してください、ミンチン先生、ラヴィニア様」とでも言うのなら「いじめ」をやめようという気にもなります。しかしセーラは全く正反対なのです。それがおもしろくない。ますますセーラを困らせようとするわけです。
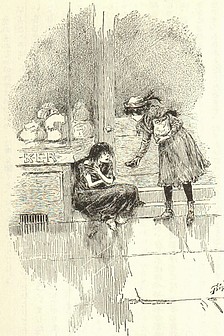
| |||
| 乞食の少女にパンをあげるセーラ(岩波少年文庫より) | |||
「小公女」という児童文学は、こういったエピソードが続く第2部が大半を占めています。まさにここがハイライトなのですね。この第2部におけるセーラを一言で表せそうな、ぴったりではないかもしれないけれど非常に近い日本語があります。「けなげ」です。
「けなげ」は、非常に特別の状況にしか使わない日本語表現です。それは
|
弱小の者が | |||
|
逆境にもかかわらず | |||
|
忍耐強く、くじけないで | |||
|
勤勉に働き、自己の立場を全うしている |
姿を表現する言葉です。この「弱小・逆境・忍耐・勤勉の4点セット」のどれが欠けても「けなげ」とは言わない。この4点の程度は強くても弱くてももよいのですが、とにかく4点そろっていることが重要です。おそらく英語に相当する単語はないでしょう。こんなスペシャル・ケースを表わす単語があるぐらいだから、日本人は「けなげ」な姿を見るのが好きだし、愛着を感じる。近年(と言ってもだいぶ前ですが)、最も「けなげ」だった女の子は、言うまでもなく「おしん」ですね。そして「おしん」と同様、アニメ世界名作劇場「小公女セーラ」は大ヒットしました。
しかし「けなげ」なセーラの姿を見るうちに、読者は当然思うのですね。「このままで終わるはずがない」と。このまま終わってしまったら、小説として成立しない。
よくできた物語 - 「小公女」第3部
物語も終わりに近づいて、驚きの事実が判明し第3部になります。セーラが実は大金持ちだったことが、全くの偶然がきっかけとなって分かるのです。
そもそもセーラはインド生まれです。セーラの父親はラルフ・クルーといい、インドに渡って友人のキャリスフォードと一緒にダイヤモンド鉱山の開発をはじめ、それに財産をつぎ込んでいました。当時、インド在住のイギリス人の子供は、長距離旅行ができる年齢になるとロンドンに帰って学校に入るという習慣だったようで、セーラ・クルーもそうしたわけです。
そしてダイヤモンド鉱山の開発は失敗し、ラルフ・クルーは財産を失い、彼自身もマラリアで死んでしまいました。しかし、失敗したと思われた鉱山開発は復活・成功し、友人のキャリスフォードは莫大な財産を築いた。そしてラルフ・クルーが当然得るべき資産を返すため、相続人である娘のセーラを探してロンドンに帰って来ていたのです。
そのキャリスフォード氏が、何と偶然ミンチン女子学院の隣に越して来て住んでいたというのが「小公女」のストーリーであり、お隣の縁でセーラのことが判明するのです。第2部の途中で「インドの紳士」が隣に越してくるのですが、その紳士が亡くなった父の友人だったわけです。
こんなストーリーがありだろうかと思ってしまいますが、ありなのですね。つまり、第1部の「お嬢様」から第2部の「小間使い」へという、あまりに劇的な展開があるため、第3部の「全くの偶然に端を発した、驚愕の事実の判明」にも違和感を感じません。当然そうなるだろう、やっぱり、という感じです。読者にとってこれは想定内の展開なのです。
セーラはキャリスフォード氏に引き取られます。また、何かとセーラに親切にしてくれた小間使いのベッキーもセーラが引き取って、二人で幸せに暮らし始めた、というところで物語は終わります。
共産党宣言
ちょっと唐突ですが「小公女」の物語から、マルクス/エンゲルスの「共産党宣言」(1848)を連想してしまいました。労働者の団結とブルジョアジーの打倒を訴えた共産党宣言は、第1章の冒頭の「今日まであらゆる社会の歴史は、階級闘争の歴史である。」から始まって、共産主義革命が歴史の必然だと言っています。もちろんそのような歴史認識は変だし、コミュニスト政権の樹立が歴史の必然でもないわけです。しかし一つ言えることは「共産党宣言」のような文書が書かれるに至った根底には、産業革命以降に急速に肥大化した資本主義社会への批判があることです。その批判の大きな要因は、イギリスを含む当時のヨーロッパ社会の「ものすごい貧富の差」です。それは「貧富の差」というレベルを遥かに超えていて、たとえば、小間使いのセーラよりもっとひどい「児童虐待労働」があったわけですね。イギリスの炭鉱などでは・・・・・・。教科書にも出ていました。コミュニズムがヨーロッパにある程度浸透し、一定の勢力を得るに至った理由はそれでしょう。「持てるものと持たざるものの極端な格差」です。内田樹氏の文章でそのあたりの事情を振り返ると以下です。
|
エンゲルスは父親の経営していたマンチェスターの紡績工場で働いた経験があります。彼が書いた『イギリスにおける労働者階級の状態 - 19世紀のロンドンとマンチェスター』は、彼自身が加担していた "非人間的な労働環境" と "労働者を収奪する仕組み" への嫌悪感に溢れています。鉱山労働の部分のごく一部を引用します(算用数字にして段落を増やしました)。
|
「小公女」においてセーラは2つの状態をとります。
| A | 学院の特別寄宿生として、衣食住に何一つ不自由なく、のびのびと勉強し、人間として成長していく少女 | |
| B | 学院の小間使いとして、労働にあけくれ、人にこき使われ、未来への希望も見えず日々を過ごす少女 |
の2つです。Bの状態は、まともに人間としては扱われず、人としての尊厳さえ破壊されかねない状況です。それでもセーラは「尊厳」を保ったわけですが・・・・・・。とにかくAとBでは「天国と地獄」なのです。
AとBの差はイギリス社会における貴族と平民の差ではありません。小説の題名は Princess ですが、セーラは王族や貴族ではなく「平民」です。「小公女」は「王女と乞食」という身分差の話ではない。AとBの2つの極端な状態変化は、お金を持っているか、お金を持っていないかの違いなのです。そしてAかBかは固定されたものではなく、セーラのように変動しうる。もちろん彼女の場合は極端ですが・・・・・・。
「小公女」は当時のイギリス社会の格差を象徴的に暗示していると考えられます。これはもちろんイギリスだけでなく、ヨーロッパ先進諸国の、そしてもっと広くは日本を含む初期・工業化・資本主義社会の抱える問題だったわけです。資本主義は、野放しにしておくと雪だるま式に格差が拡大していくメカニズムを内包しています。そこは政府が介入して手を打たないと社会の瓦解を招きかねない。20世紀になって各国政府は「社会主義的政策」を導入するわけですが、19世紀はその前の段階です。
「小公女」は「共産党宣言」が書かれるまでに至った19世紀の社会背景を象徴的に表していると思いました。
インドの犠牲
「小公女」はまた、19世紀のイギリスの繁栄がインドの犠牲の上に成り立っていることを、それとなく暗示しています。
セーラが貧乏になるのも、また最後に裕福になるのも、インドにおけるダイヤモンド鉱山開発の成否にかかっている、というのが小説の設定です。現在、世界のダイヤモンド生産国としては南アフリカが有名ですが(産出量で1位はロシア)、ここのダイヤモンド鉱山が発見されたのは19世後半であり、本格的に鉱山が開発されたのは20世紀です。19世紀まではダイヤモンドといえばインドだった。「小公女」にしきりと出てくる「ダイヤモンド鉱山」というキーワードは、インドの富がイギリスに移転したということの象徴だと考えられます。
しかし、ダイヤモンドは貴族や富裕層だけのものです。もっと一般庶民に関係した「インドの富」がいろいろとある。ここで思い出すのが、No.18「ブルーの世界」で書いた、青色染料である「藍」(インディゴ)です。

| |||
| インド藍 [Wikipedia] | |||
アメリカの独立によって北米の藍作植民地を失ったイギリスが、ただちにインドに奴隷制藍作プランテーションをつくりあげ、ベンガル地方の人々を新たに奴隷化した・・・・・・・・・ |
もともとインドの特産品だった「藍・インディゴ」は、イギリスのインド支配を通して、インドの人々に奴隷労働をもたらしたことになります。この文章の冒頭に、No.18「ブルーの世界」の藍・インディゴから「小公女」を連想したと書きましたが、それは「インドつながり」でした。
そしてイギリスの植民地だったアメリカのサウス・カロライナで、藍・インディゴ以上に大々的に奴隷によって栽培され、現在でもアメリカ南部一帯が有力な産地となっている作物があります。綿です。そして綿もインド原産の植物なのです。
綿(木綿・コットン)
No.26「ローマ人の物語(3)」でも引用したヘロドトスの『歴史』に次のような記述があります。
インドでは野生の木が羊毛の実を結び、この羊毛は外見も質も羊からとった毛に優る。インド人はこの木の実で作った衣類を用いているのである。 |

| |||

| |||
|
| |||
しかし18世紀になって、綿花と綿織物の生産環境は激変します。ヨーロッパを中心とするインド産の綿花・綿織物の需要増大に対応して、イギリスは極めて効率のよい綿花生産の方法に乗り出します。アフリカから奴隷をイギリス領アメリカへ運び、そこの大規模プランテーションにおいて奴隷労働で綿花を栽培し、それをイギリスへ輸入するという方法です。
もう一つの激変がイギリスの産業革命です。産業革命は歴史の教科書で習ったとおり、綿工業の機械化から始まりました。紡績機(綿花から糸を紡ぐ機械)と織機(布を織る機械)が発達し、木綿の布が安価に大量に生産できるようになったわけです。このイギリスで機械生産された綿製品は海外に輸出され、もちろんそれはアフリカでは奴隷と交換されたのですが、当然、インドにも大量になだれ込みました。その結果として、インドの綿織物産業は壊滅的な打撃を受けたのです。
独立国であればこういう場合、輸入される綿織物に高い関税をかけて国内産業を保護し、その間に産業の機械化を進めて、徐々に関税を引き下げていく、というような政策をとるわけです。しかし「関税自主権」がないとこんなこともできない。インドの人々は自国の有力産業が失われていくのを、なすすべなく見守るしかなかったわけですね。こういうことが各種の産業で起こると、国はどんどん貧しくなっていきます。19世紀のイギリス、ヴィクトリア女王(在位:1837-1901)の時代の繁栄の裏には、綿工業だけをとってみても「インドの犠牲」があったのは確実です。
ところで、イギリスの綿織物産業と「小公女」の作者は大いに関係があるのです。フランシス・ホジソン・バーネットは1849年にイギリスのマンチェスターで生まれました。マンチェスターは19世紀イギリスの綿織物の製造拠点で、中心地です。フランシスの父親は家具の卸問屋を経営して裕福でしたが、彼女が4歳の時になくなり、母親に託された一家の暮らしは苦しくなりました。そしてフランシスが11歳のときアメリカで南北戦争が勃発し(1861年4月)、一家の暮らしはますます苦しくなります。なぜかと言うと、南北戦争でアメリカから綿花が輸入されなくなり、マンチェスターの綿織物産業が大きな打撃を受けたからです。マンチェスターの町は不況に陥り、それがフランシス一家をも直撃しました。そしてフランシスが16歳のとき、一家は親戚をたよってアメリカのテネシー州に渡ったのです。その一家の家計を助けるために彼女は小説を書きはじめ、雑誌に投稿します。この執筆活動の中から、後の「小公子」「小公女」「秘密の花園」が生まれるのです(以上は、偕成社文庫「小公女」の訳者、谷村まち子氏の解説によります)。
フランシスは、産業革命後のマンチェスターの綿織物産業の発展と不況を体験し、その後のイギリスとアメリカでの苦しい生活を経験したわけです。これが「小公女」のプロットに影響を与えたとも推測できます。
「小公女」のリアリティー
ロンドンを舞台にした「小公女」のストーリーは、裕福なお嬢様(第1部)から小間使いに(第2部)、それから再び元に(第3部)と、ちょっとありえないような展開をします。それでいて妙にリアリティーを感じるのは、当時のイギリスの社会環境である、
・富裕層と底辺労働者の格差
・インドという植民地の存在
を背景にしているからではないでしょうか。
「小公女」という小説は、現代日本を舞台にTVドラマやアニメとしてリメイクしにくい小説だと思います。そんなリメイクをしたら、全くリアリティーがないものになる可能性が高い。それでも近年、志田未来さん主演で現代日本を舞台にリメイクされたようです。そのTVドラマを見ていないので何とも言えませんが、成功したのかどうか。
「小公女」の作者であるイギリス生まれのアメリカ人・バーネットは、当時のイギリスの社会環境への問題意識をもとに小説を書いたのでしょうか。それとも単に読んでハラハラする少女向けの児童小説を書いたのでしょうか。それは分かりません。しかし確実に言えることは、「小公女」のストーリー展開とそこに出てくるエピソードはいかにも極端だけど、作者のバーネットは当時の社会環境を十分に頭に入れた上で、非常にまじめに小説を書いていることです。第2部の「小間使いのセーラ」のところなどは、大げさに言うと「人間の尊厳とは何か」というテーマを扱っているようにも見える。作者の実生活での苦労が反映されているのかもしれません。この作者の「まじめさ」が、多くの人を引きつける要因になっているのでしょう。
小説の終わりの方で(第18章)セーラは辛かった小間使いの時期を思い出して言います。原文で引用すると次のとおりです。
I tried not to be anything else.
「私は、ほかのものにはならないようにしていたんです」というような意味ですが、いかにも英国人(米国人)の作家が書きそうな文章だという気がします。自分を見失わず、これが自分の個性だと思うことは貫き通す。そこにこそ人間の価値がある ・・・・・・。さりげない一言に、小説のテーマの一端が現れていると思います。
No.1, No.2 で取り上げた「クラバート」は、少年が大人になる過程を通して、人間の自立とは何か、社会における労働とは何か、などの普遍的なテーマを扱っていました。作者のプロイスラーはこの児童小説に「普遍性」を盛り込もうと、はじめから意図して書いたと考えられます。それに対して「少公女」のフランシス・バーネットは、そういう意図はなかったと思います。あくまで「少女向け小説」を書いた。しかし作者の意図はどうであれ、この小説はある主のリアリティーと深みを持つことになった。「クラバート」と「少公女」は、「よくできた児童小説は、児童小説の範疇を越えた普遍性をもつ」ことの良い実証例だと思います。
No.27 - ローマ人の物語(4)帝政の末路 [本]
(前回より続く)
帝政による「ローマ文化」の破壊
キリスト教の国教化に至る道筋を読んで強く印象に残るのは、キリスト教徒を組織的に迫害したすぐ後の皇帝がキリスト教を公認しているということです。
ディオクレティアヌス帝(285-305)は「ローマ史上初めての本格的かつ組織的なキリスト教弾圧(第13巻:最後の努力)」に乗り出します。303年の「キリスト教弾圧勅令」は、
| ◆ | キリスト教教会の破壊 | |
| ◆ | 信徒の集まり、ミサ、洗礼式などの行事の厳禁 | |
| ◆ | 聖書、十字架などを没収し焼却 | |
| ◆ | 教会財産の没収 | |
| ◆ | キリスト教徒の公職追放 |
という徹底ぶりです。キリスト教を根絶しようという非常に強い意図が感じられます。
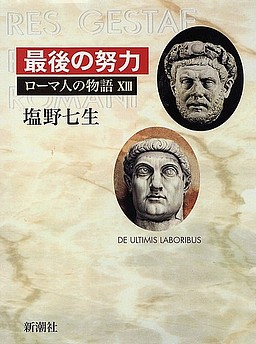 ところがその直後の皇帝・コンスタンティヌス(306-337)は、312年に有名なミラノ勅令を出してキリスト教を公認します。勅令は公認しただけであって国教としたわけではありませんが、その後のコンスタンティヌス帝は国教化に向けた動きとしか思えない行動に出るのです。この時点からテオドシウスス帝(379-395)による392年のキリスト教の国教化は一直線です。
ところがその直後の皇帝・コンスタンティヌス(306-337)は、312年に有名なミラノ勅令を出してキリスト教を公認します。勅令は公認しただけであって国教としたわけではありませんが、その後のコンスタンティヌス帝は国教化に向けた動きとしか思えない行動に出るのです。この時点からテオドシウスス帝(379-395)による392年のキリスト教の国教化は一直線です。ディオクレティアヌス帝によるキリスト教の根絶を目指した大弾圧と、コンスタンティヌス帝によるキリスト教の公認。このわずか8年の間に行われた、大弾圧から公認という政策の大転換に、帝国としての統一的な考えがあったとはとても思えません。
では、コンスタンティヌス帝によるキリスト教公認の理由は何でしょうか。それは塩野さんによると「支配の道具としてキリスト教を使うため」です。皇帝が帝国を支配する根拠を「神」に求めたい。この「神」の位置になりうるのは一神教の神しかない。ユダヤ教はユダヤ民族の宗教にとどまっている。消去法で残された選択肢はキリスト教しかない、というわけです。
現実世界における、つまり俗界における、統治ないしは支配の権利を君主に与えるのが、「人間」ではなく「神」である、とする考え方の有効性に気づいたとは、驚嘆すべきコンスタンティヌスの政治センスの冴えであった |
「支配の道具」としてキリスト教を位置づけた以上、一神教からみた「異教」は排除しなければなりません。ローマ皇帝自身、ローマの政治システム自身がローマ固有宗教の破壊に邁進し出します。それは、帝国自身による組織的かつ強権的なローマ文化の破壊だったわけです。
文明の破壊
キリスト教の国教化による影響はローマ固有の宗教の破壊だけに止まりませんでした。塩野さんは次のように書いています。
首都ローマだけでも28も存在した公共図書館をふくめ、ローマ帝国の中にあった膨大な数の図書館の閉鎖も始まったのだ。ローマ時代の公共図書館の蔵書は、バイリンガル帝国を反映してギリシャ語とラテン語の書物に2分されて公開されていたのだが、これらの書物の内容はほとんどすべて、異教の世界を叙述したものだからであった。図書館の閉鎖につづくのは、蔵書の散逸である。 |
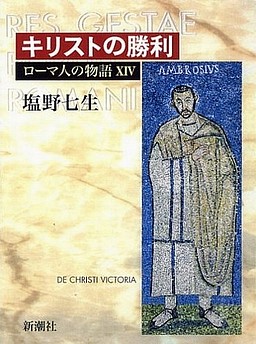 こういう記述を読んで直感的に思うのですが、公共図書館の書物や、それから派生した各種の知的マテリアルに依存して生活していた人たちがいたはずです。哲学、語学、雄弁術、歴史、天文学、幾何学などの学者や教師、文筆で生計をたてている人などです。こういった知識人はこの時期、社会の隅に追いやられたり、攻撃されたり、おおっぴらに活動できなくなったのではないでしょうか。最低限、彼らは図書館が閉鎖され書物が散逸して意気消沈したはずです。「書物の散逸や破棄、知識の軽視」は、国の存続を危うくする行為の代表的なものだと思います。
こういう記述を読んで直感的に思うのですが、公共図書館の書物や、それから派生した各種の知的マテリアルに依存して生活していた人たちがいたはずです。哲学、語学、雄弁術、歴史、天文学、幾何学などの学者や教師、文筆で生計をたてている人などです。こういった知識人はこの時期、社会の隅に追いやられたり、攻撃されたり、おおっぴらに活動できなくなったのではないでしょうか。最低限、彼らは図書館が閉鎖され書物が散逸して意気消沈したはずです。「書物の散逸や破棄、知識の軽視」は、国の存続を危うくする行為の代表的なものだと思います。いや、国の存続を危うくするというより「文明を滅ぼす行為」です。事実、文明の中心地はその後に興ったイスラム世界になっていきます。ギリシャ・ローマの「知」を受け継いだのもイスラム世界です。アラビア語に翻訳され、バグダッドやカイロやイベリア半島のコルドバやトレドに蓄積され研究されたギリシャ・ローマの「知」は、それを西ヨーロッパが発見することでルネサンスへと繋がるわけですね。
塩野さんが書いている「図書館の閉鎖」ですが、この影響を受けて破壊され、蔵書が散逸した世界史上で非常に有名な図書館があります。アレキサンドリアの図書館です。それはプトレマイオス朝のエジプトの時代に作られ、戦乱による建物の破壊と修復を繰り返しつつ維持されてきました。それは数百年かけて蓄積されてきた、ローマ帝国の、というより地中海世界の「知」の結晶であり、文明の粋であったわけです。これを破壊してしまった。
「ローマ人の物語」の最後の数巻を読んで感じるのは、帝政が自らの保身のために、ローマの文化と文明、ローマの強み、ローマがローマたるゆえんを自らの手で破壊していくという、悲惨としか言いようのない姿です。
帝政の末路
帝政が自らの保身のために、ローマを破壊していくという結末を見るにつけ、ローマ的帝政という専制統治システムの機能不全を感じます。
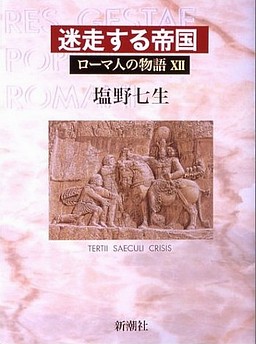 皇帝が国を統治するという「帝政」の機能不全とそれがローマ帝国に与えた悪影響はいろいろあると思いますが、典型的なのは軍人皇帝の乱立です。211年から73年間に、22人の皇帝が登場しては消え、そのうち14人は謀殺だったとあります(第12巻:迷走する帝国)。238年には1年間に5人もの皇帝が(死亡で)退位し、その5人の死亡原因は3人が謀殺、1人が自殺、1人が戦死でした。
皇帝が国を統治するという「帝政」の機能不全とそれがローマ帝国に与えた悪影響はいろいろあると思いますが、典型的なのは軍人皇帝の乱立です。211年から73年間に、22人の皇帝が登場しては消え、そのうち14人は謀殺だったとあります(第12巻:迷走する帝国)。238年には1年間に5人もの皇帝が(死亡で)退位し、その5人の死亡原因は3人が謀殺、1人が自殺、1人が戦死でした。ローマ皇帝は「終身」です。従って皇帝にふさわしくない人物を「意図的に」退位させるには「謀殺」しかないのでしょう。問題はなぜそのような状況に陥るのか、なぜその程度の人物が皇帝の地位につけるのかです。結局のところローマの帝政は一面からみると実質的な軍事独裁制であり、これが人の心をむしばむという「世界史における共通原理」が働いているのだと思います。第7巻「悪名高き皇帝たち」で描かれている「悪名皇帝たち」もそうです。
そのような帝政であっても優れたリーダが出てくることは当然ある。五賢帝の時代、つまりネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウスの5人の皇帝の治世時代 (96-180) は優れたリーダが輩出した時代と言えるでしょう(第9巻:賢帝の世紀)。しかし「五賢帝」という言い方が広まったということは、裏を返すと「愚帝が輩出してローマが傾いた」こと人々が感じ取ったからだと思います。73年間に22人の皇帝が乱立したのは、五賢帝のすぐ後の時代(211-283)です。
そしてローマ帝国の最終段階で起こったことは、帝政が自らの保身のために、また皇帝が自らの権力を正当化するために新たな「支配の道具」を持ち込み、ローマの文化やローマがローマたるゆえんを破壊していくという結末でした。もともとアウグストゥスが完成させたとされる帝政の目的は、簡潔に言うと「広大になった帝国の現状を見据え、意志決定を迅速にして効率的に統治するため」だったはずです。
しかし統治システムを含むあらゆる制度は遅かれ早かれ自己目的化します。自己目的化とは、その制度を作った本来の目的や狙いの実現が二の次、三の次になり、外部環境が変化しているにもかかわらず「制度を守る」ことが第一の目標になることです。なぜ自己目的化するかというと、時間がたつと本来の目的が忘れられるからだし、その制度に依存した既得権益者を生むからです。国のリーダ自身が既得権益者になるという、恐ろしい事態も起こりうる。それ以前に、リーダの周りには既得権益者が群がってくる。
優秀な統治システムとは、その統治システムが自己目的化したときに最も国としての被害が少なく、国家が生き残りやすいシステム、ないしは生き残りやすい方向に自らを修正できるシステムだと思います。そして、自己目的化したときに最悪の制度がローマ的帝政だったというのが率直な感想です。
現代国家における民主制(民主主義)は「あやうい」制度です。民主的に選ばれたリーダが市民を扇動した結果、市民の財産や生命をあやうくするような選択を市民自身が「自由意志で」する、というような事が起こる。現代日本もそれと無縁ではありません。また「民主制の中から独裁制を生む」ようなリスクもあります。完璧と思える民主制の中から、その政体を自ら否定してしまうような国を生んだ20世紀のドイツの例があります。にもかかわらず現代の先進国家の多くが民主制を選んでいる理由は究極的には一つしかないと思います。それは民主制が、制度を守ることが自己目的化したときに最も国民の被害が少なく、衰退の度合いが少なく、国が生き残る可能性が高い統治システムだからです。
混乱の時代
経済が安定的に成長し、外敵の進入少なく、国が安定している時期は、どんな統治システムでも良いのだと思います。安定期のことだけを考えて統治システムの優劣は計れない。統治システムの優劣は、経済の停滞期や下降期、ないしは危機や混迷の時代をどう乗り切れるかにかかっているはずです。「ローマ人の物語」の率直な読後感から言うと危機や混迷を「制度の力」や「システムの力」で乗り切ったのは共和制の時代です。明らかにそう見える。「第2巻:ハンニバル戦記」と「第3巻:勝者の混迷」、および「第4・5巻 ユリウス・カエサル」にはそれが鮮やかに描かれています。
第1巻から5巻までの共和制の時代のローマの政治を形容す言葉を選ぶとすると、一つは「混乱」だと思います。貴族と平民は対立し、その後融和し、再び激しく抗争する。改革を断行するリーダが出現したと思えば、その次のリーダはまったく逆行する政策をとる。そもそも国の指導者層である元老員議員同士が抗争し、内戦状態にもなり、殺し合いにさえなる。独裁的指導者と大衆的指導者がめまぐるしく交代する・・・・・・。仮にオリエントの専制国家の国王から派遣された「大使」がローマに駐在していたとすると「ローマは混乱している。この国の先は長くない」と何度も本国に報告したと思います。常にではないにせよ、そうとしか見えない状況が何度もあったはずです。しかしローマは「長くない」どころか全く逆だった。その「全く逆」を実現したのは、一見「混乱」に見えるもののベースにある「統治システム=ローマ的共和制」であり、宗教を含む広い意味での「文化」なのだと思います。
帝政前期は「パックス・ロマーナ」の時代と言われています。この「パックス・ロマーナ」は共和制の時代に作られた「財産」や「資産」を維持できた時代だと見えます。この財産を、帝政後期に完全に食いつぶしてしまった。
3月15日
「ローマ人の物語」でたびたび引用されているカエサルの言葉があります。
|
この言葉の意味は「意図は正しくても、結果や事実として起きていることが、それに反することが多い。人間は意図を大切にし過ぎるから間違う。」ということでしょう。塩野さんもそう解釈しています。
これは一つの「事例」について言っていますが、これを拡大解釈して、カエサルが構想しオクタヴィアヌスが完成させたとされる「ローマの帝政」について当てはめてみるとどうなるでしょうか。広大なローマ支配地域を統治するためには、共和制ではなく一人の皇帝が効率的に統治するローマ的帝政、という「意図」は正しいと思います。しかしその帝国の400年の結果として起こったことは、自らの基盤を破壊するという自殺行為に等しいものでした。「意図は正しくても、結果や事実として起きていることが、それに反する」わけです。カエサルが構想しオクタヴィアヌスが完成させた帝政は、少なくとも失敗の端緒か遠因を作ってしまった。
優秀な人間は「自分のような人間が将来もリーダになる」ということを(そんなことはあり得ないと分かりながら)暗黙に考えてしまいます。「リーダは、目的と手段をとりちがえるような本末転倒のことはしない」と暗黙に考えてしまいます。自分がそうではないからです。しかし優秀でないリーダは必ず出ます。血筋による継承では「玉石混合」になるのはあたりまえだし、リーダが選ばれるタイプの統治システムにおいても、優秀でないからこそリーダに選ばれる(指名される)という例が多々あります。人間社会とはそういうものです。またある制度が定着すると、その制度に依存した既得権者が必ず出現し、制度本来の目的の遂行を妨害します。必然的にそういう動きになります。
紀元前44年3月15日、カエサルは「共和制維持派」の人たちに暗殺されました。「3月15日は西欧人なら誰でも知っているカエサル暗殺の日」(第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以後)です。この日、カエサルを暗殺した人たちは、伝統的なローマの統治体制の維持しか頭にない、保守的で、蒙昧で、先が読めず、既得権益の維持しか頭にない人たちだったのでしょうか。
むしろ、カエサルを暗殺した人たちの方が直感的にものごとの本質を理解していたのかもしれません。なぜなら最も本質をよく理解できるのは、リーダとしての素質・洞察力・実行力が十分にありながら、自分が「本当はリーダとしては愚鈍な人物かもしれないという恐れ」や「既得権にしがみつくような、リーダとしてはふさわしくない人物かもしれないという恐れ」を無自覚に抱いている人間だからです。
内部環境、外部環境の変化にマッチさせて国を運営していくためには、その阻害要因を取り除く「改革」や「変革」や「修正」が不断に必要になります。これが可能なシステムとその実行能力が国家の、そしてもっと一般化すると組織の必須要件でしょう。これが「ローマ人の物語」の、ローマの興亡に関する部分の読後感です。
神々のその後
「民族伝統の神々の破壊」はローマやコンスタンチノープルという首都だけでなく、ローマ帝国全域で行われました。さらにその後のヨーロッパの歴史をみると、ローマ帝国の領域の周辺へと「民族伝統の神々の破壊活動」が拡大していきます。たとえば12世紀から13世紀にかけては「ヴェンド十字軍」という名目のもとに「異教徒征伐」の戦争が行われ、現在のバルト3国やポーランド付近にもキリスト教が普及していきます。これにともなってその土地の固有宗教は絶滅するか、陰に追いやられて行きました。では固有宗教が全く死に絶えたのかと言うと、そうでもありません。それらは神話、伝承、民話、魔女・魔法使い・妖精の伝説や、各地の伝統行事として残ることとなります。
No.22「クラバートと奴隷 (1) 」に書いたように、ヴェンド十字軍の「ヴェンド」とは、もともとゲルマン民族からみた周辺民族、特にスラヴ人をさす言葉です。No.1, No.2 の「クラバート」において、クラバートは「ヴェンド人」と紹介されていました。このヴェンド人という言い方はドイツ語であって、自民族の言葉ではソルブ人です(No.5「交響詩・モルダウ」)。シュヴァルツコルムのクラバートは、その昔「周辺の非キリスト教民族」として征服され、キリスト教に改宗した(させられた)スラヴ系民族の末裔だという気がします。小説「クラバート」はソルブ人に伝わる「クラバート伝説」がもとになっています。水車場の親方、および彼が駆使する「魔法」や「魔法典」は、ソルブ人が本来持っていた神々や宗教の記憶ではないでしょうか。
現代においても、神々の記憶がキリスト教と共存している例もあります。以前、NHKのTV番組「地球に乾杯」で、スイスのレッチェンタールという村の謝肉祭の様子が放映されました。鬼のような異形の面をかぶった人たちが村中をまわるのですが、日本の秋田県の「なまはげ」とどこが違うのかとさえ思いました。謝肉祭ではあるものの、民族の固有宗教・文化の記憶を強く感じさせるものです。
では「ローマの神々」はどうなったのでしょうか。キリスト教(特にカトリック)には、本来の一神教ではありえない「多神教的性格」があります。
| ◆ | 聖母マリアの崇拝 | |
| ◆ | 数々の聖者や聖人、町の守護聖人の存在 | |
| ◆ | 聖者や聖人に関する「聖遺物」への崇拝 | |
| ◆ | 奇蹟の伝承とその崇拝 | |
| ◆ | ヨーロッパ各地にある聖地への巡礼 |
などです。ローマの神々はキリスト教の枠内で、数百年の時間を経る中で、形を変えて生き残ったとも言えるでしょう。
人間集団のアイデンティティの再構築には時間がかります。と同時に、消し去ろうと思っても容易にはできないコアな部分があって、それが人間社会の持続性と、それに密接に関係している文化の発達をさえているのだと思います。
No.26 - ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ [本]
(前回より続く)
古代地中海世界における宗教
前回、宗教上の像や施設の破壊の経緯を「ローマ人の物語」から引用しました。以降では、古代地中海世界における宗教がどういうものだったかを振り返り、宗教の破壊がどういう意味をもつのかについての想像を巡らせてみたいと思います。
現代の我々日本人は、多くの人が冠婚葬祭やお正月は別として日常は宗教と疎遠な生活をしています。また政治に特定の宗教が影響するということは、政教分離が原則の国家では考えられません。しかし古代では邪馬台国の卑弥呼がそうであったように宗教は日常生活を支配していたし、政治や軍事とまでも結びついていました。No.8「リスト:ノルマの回想」で書いたベッリーニのオペラ「ノルマ」では、ドルイド教の巫女の神託でローマ軍との不戦(ないしは開戦)が決まるわけです。オペラはあくまでフィクションですが、このように神託で政治や軍事が動く例は、古代中国でも邪馬台国でもエジプトでもガリアでもマヤでも、世界各国にいっぱいあったわけです。
では古代地中海世界のギリシャ・ローマではどうだったのかというと、やはり神託で政治が動く例は多々ありました。まず思い出すのはギリシャにおけるデルフォイ(デルポイ)の神託です。デルフォイはパルナッソス山(アテネの西方)の麓にあった都市国家で、アポロン神殿がありました。ここでデルフォイの巫女(ピュティア)が神託を告げます。この神託はギリシャの人々に珍重され、ポリスの政策決定にも影響を与えました。ギリシャの各都市はここに財産庫を構えて神殿に献納しています。
| ちなみにミケランジェロは、カトリックの総本山であるバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井画に古代地中海世界の5人の代表的な巫女を描いていますが、その一人がデルフォイの巫女です。 |
デルフォイの神託の有名な例が、ヘロドトスの「歴史」に書かれている、神託とサラミスの海戦の顛末です。ことの発端はギリシャが大危機に陥ったペルシャ戦争の時、アテナイの滅亡を暗示する神託があったことです。そこでアテナイの使者は出直して再度巫女に乞い、新たな神託を得ます。重要部分だけを抜き書きすると次のようです。
・・・・・・ゼウスはアテナがために木の砦をば、唯一不落の塁となり、汝と汝の子らを救うべく賜るであろうぞ。・・・・・・ |
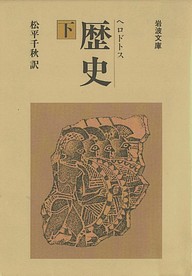 この「木の砦」とは以前は茨の垣根に囲まれていたアクロポリスのことであり、従ってアクロポリスに籠城して戦うべきだと解釈する者もいました。しかしテミストクレスは「木の壁」を船と解釈してアテナイ市民に訴え、三段櫂船を主力としてサラミスの海戦に臨み、ペルシャ軍を破りました。もちろん指導者・テミストクレスにしてみると、神託をうまく利用して自分が正しいと考える戦術を実現しただけかもしれません。しかし印象的なのは、ペルシャ戦争においてギリシャ連合軍が最終勝利を得る転機となった「サラミスの海戦」に至る過程において神託が重要な位置を占めていることです。兵士たちが一致団結する原動力にも神託が役立ったことは想像に難くありません。歴史書に書かれていることがすべて事実とは限りませんが、歴史書に「堂々と」書かれるほど神託は身近なものであり、戦争にも影響を与えたということは、最低限認めざるを得ないと思います。
この「木の砦」とは以前は茨の垣根に囲まれていたアクロポリスのことであり、従ってアクロポリスに籠城して戦うべきだと解釈する者もいました。しかしテミストクレスは「木の壁」を船と解釈してアテナイ市民に訴え、三段櫂船を主力としてサラミスの海戦に臨み、ペルシャ軍を破りました。もちろん指導者・テミストクレスにしてみると、神託をうまく利用して自分が正しいと考える戦術を実現しただけかもしれません。しかし印象的なのは、ペルシャ戦争においてギリシャ連合軍が最終勝利を得る転機となった「サラミスの海戦」に至る過程において神託が重要な位置を占めていることです。兵士たちが一致団結する原動力にも神託が役立ったことは想像に難くありません。歴史書に書かれていることがすべて事実とは限りませんが、歴史書に「堂々と」書かれるほど神託は身近なものであり、戦争にも影響を与えたということは、最低限認めざるを得ないと思います。|
余談ですが、巫女がトランス状態となって予言の神であるアポロンの神託を告げるのは、活断層から出てくる火山性ガスの効果だと言われています。この説は活断層が見つからないため一時否定されましたが、最近の精密な地質調査によって活断層の存在が立証されました。これについては、日経サイエンス 2004年 1月号 に詳しい論文が載っています。 「火山性ガス」と「巫女」と聞いて直感的に思い出すのは下北半島の恐山ですね。恐山は日本のパルナッソス山というところでしょうか。 |
ポエニ戦争と女神
この「デルフォイの神託とサラミスの海戦の顛末」と似たエピソードが共和制時代のローマにあります。ペルシャ戦争の時のギリシャのように、ローマが一大危機に陥った時の話です。これはローマと宗教の関係がどういうものかをうかがわせるものです。No.24「ローマ人の物語(1)」でも引用した、本村凌二・東大教授の「多神教と一神教」から引用します。
前216年、ローマ軍はハンニバル率いるカルダゴ軍に大敗北を喫した。いわゆるカンナエの戦いであるが、その戦死者を上回る戦闘は第一次世界大戦までなかったといわれるほどである。このときローマ人はかかる大敗北の原因として自分たちがあがめるべき神への崇拝を怠ったからではないかと自問する。地中海世界で広く霊験あらたかと信じられていた巫女シビュラの予言にうかがいを立てると、それは小アジアのキュベレ女神であるという。このようにしてキュベレ女神の聖石は大母神としてローマの都に迎えられ、その祭礼の跡は今日でもパラティヌス丘に残されている。この女神の到着後、ローマ軍は反撃し、やがて大勝するのだから、キュベレ女神の加護たるやはかりしれないと喧伝されたにちがいない。 |
このようにして「キュベレ女神」は紀元前3世紀にオリエントからローマに初めて導入されたのですが、同じ本に次のような記述もあります。
キュベレ女神は帝政期の貨幣にも刻印され、公認の祭儀が捧げられている。牡牛と牡羊を殺害する儀礼があり、その血を全身に浴びた者は20年間神聖な人生をおくることができるという。背教者の哲人皇帝ユリアヌス(在位 361-363)にとって、キュベレは「全生命の女主人であり、あらゆる生成の原因者」であった。 |
 オリエントからの外来の神であるキュベレ女神は、少なくとも600年近く、ローマで信仰されたことになります。
オリエントからの外来の神であるキュベレ女神は、少なくとも600年近く、ローマで信仰されたことになります。「ローマ帝国の神々」(小川 英雄 著。中公新書。2003)という本には、ローマおよびローマ帝国内に広まったオリエント由来の神々や宗教が詳しく書かれています。それによると、主だった神だけでもキュベレ神(小アジア)、イシス神(エジプト)、ミトラス(ミトラ)教(ペルシャ由来)、ユダヤ教、キリスト教など、多彩です。キュベレ神をローマに迎えた経緯の詳細も書かれているのですが、ローマはこの神の招請のためにプブリウス・スキピオ・ナシカという名門貴族を団長とする公式使節団を小アジアのペルガモン王国に派遣しているのですね。キュベレ女神の聖石とは隕石だったようです。この聖石は紀元前204年4月4日にローマ到着し、パラティヌス丘に安置されました。
このキュベレ崇拝の輸入の効果はすぐに現れた。翌年のうちにハンニバルはアフリカに押し戻され、紀元前202年のザマの戦いでのローマの勝利によって、第二次ポエニ戦争は終わった。 |
キュベレ女神が第二次ポエニ戦争の勝利をもたらしたという「直接の因果関係」を信じるローマの指導者は、さすがに当時でもいなかったのではと想像します。ローマの指導者たちはローマ市民の気を奮い立たせ、団結を再度強固にし、カルタゴとの戦争の局面を打開するために小アジアの神を利用したのでしょう。しかしこれは非常に重要なことだと思うのです。
キュベレ女神だけではありません。オリエント由来の数々の信仰がローマに広まり、それはローマの指導者層にも及んだようです。ポエニ戦争に勝利したあとの内乱状態において、スッラとマリウスの対決があるのですが、「ローマ帝国の神々」には次のように書かれています。
第三次ポエニ戦役(前149-前146)以後の社会変動と内乱はオリエント系の宗教にとって有利に働いた。まず、シリアの地母神アタルガティス信者エウヌスの下で、シチリアのシリア人奴隷が叛乱を起こした。将軍マリウス(前157-前86)にはシリア人の女予言者マルタがいつも離れることなく従っていた。これに対して、マリウスの敵スラ(前138-前78)はカッパドキアの地母神マー・ベローナを信じていた。スラはまた、イシス女神の祭司たちを連れてきた。 |
ローマの活力
このようなエピソードを読むと、ローマ人の「多神教」、つまり「宗教的寛容」を基礎として外来の神をも受け入れ、それを活力の源泉としていくローマ人の伝統的なメンタリティがローマの発展の根幹にあるのではないかと感じます。そして前回の No.25「ローマ人の物語(2)」で書いたように、4世紀末の時点でこれらのすべての「宗教」は抹殺されてしまいます。これはローマ人のエネルギー源を奪うことになったのではと思うのです。
キュベレ像でも聖石でも、また前回書いたニケ像でもよいのですが、ある神のモニュメント回りに集結したローマの兵士が戦勝を誓ったとします。そしてその行為が最近始まったものではなく百年というレベルの伝統だったとします。そのニケ像なりキュベレ像、聖石が倒されて破棄されたとしたらどうでしょうか。兵士たちに戦意は生まれるのでしょうか。像などは些細なことだと考えるのは、現代人の考え方だと思います。
現代においても「組織がある目標に向かって一致団結し、モチベートされることの強さ」は相当なものです。組織のリーダたるのもは、このモチベートをどうやって実現するのか、それこそが仕事だと言ってもよいでしょう。企業活動を例にとると、もちろんビジネスモデルの優劣や事業戦略の良し悪し、思い切った投資の決断や新事業への進出の判断は重要です。しかし現実はモチベートされ団結した組織さえあれば、戦略や決断はあとからついてくるということがよくある。
現代では「宗教」や「神の像」でモチベートされるわけではなく、企業なら世界最高の製品やサービスを提供するとか、誰もやったことのないことにチャレンジするとか、そういうことです。現代の国家も「戦争の惨禍からの復興」とか「先進国なみの豊かな生活」とかの目標のもとに国民が団結したときは強いし、そういう明白なものを失った時に混迷に至るのは、理解できるはずです。
宗教のありかたが国家の骨格を決めるというのは、近代以前ではあたりまえです。宗教や神のもとに結束して大きな力を発揮することは、有事である戦争に限らずよくあったはずです。ローマは、キリスト教以前の多神教の時代もキリスト教以降も、宗教と国家運営が表裏一体だったことでは一貫していたのではないでしょうか。
ローマの固有信仰
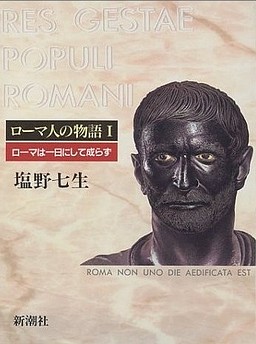 キュベレ女神はオリエントからきた「外来の」神の一つです。しかしもちろん、ローマにはそれ以前から信仰されてた神々がありました。ローマは多神教なので神は数え切れなくあるのですが、まずラテン民族の古来の神であるヤヌス、ラル、ウェスタなどがあります。ローマ建国以来の由緒ある神々は、最高神であるユピテル、ユノ、ミネルヴァの国家の主要三神、マルス、ウェヌス、ディアナなどです。またローマの版図の拡大とともにギリシャの神であるポセイドン、デュオニソス、ヘルメスなども輸入され、信仰されました。ユピテル=ゼウスなど、ローマの神とギリシャの神の同一視(習合)も起こりました。
キュベレ女神はオリエントからきた「外来の」神の一つです。しかしもちろん、ローマにはそれ以前から信仰されてた神々がありました。ローマは多神教なので神は数え切れなくあるのですが、まずラテン民族の古来の神であるヤヌス、ラル、ウェスタなどがあります。ローマ建国以来の由緒ある神々は、最高神であるユピテル、ユノ、ミネルヴァの国家の主要三神、マルス、ウェヌス、ディアナなどです。またローマの版図の拡大とともにギリシャの神であるポセイドン、デュオニソス、ヘルメスなども輸入され、信仰されました。ユピテル=ゼウスなど、ローマの神とギリシャの神の同一視(習合)も起こりました。これれらの神は、国家から家庭まで、戦争から日常生活までの守り神です。もちろん国家レベルの祭祀は、国家公務員である最高神祀官・神祀官・祭司という祭司たちがとりしきります。鳥の飛び方をみて未来を占う鳥占官(アウグル)という公務員もいました。日常生活に関係した神の例として「ローマ人の物語」では、夫婦喧嘩の守護神とされた「ヴィリプラカ女神」が紹介されています。
夫と妻の間に、どこかの国では犬も食わないといわれる口論がはじまる。双方とも理は自分にあると思っているので、それを主張するのに声量もついついエスカレートする。黙ったら負けると思うから、相手に口を開かせないためにもしゃべりつづけることになる。こうなると相手も怒り心頭に発して、つい手がでる、となりそうなところをそうしないで、二人して女神ヴィリプラカを祭る祠に出向くのである。 |
相手の言い分を聞かざるを得ない状況になって、興奮が収まっていき、仲直りにつながるというわけです。
ウェスタの巫女
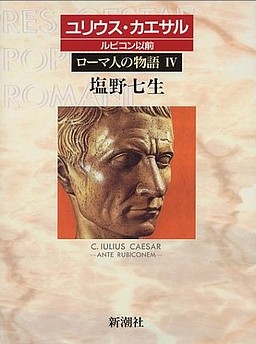 ローマに古くからある固有信仰からの印象的なエピソードを「ローマ人の物語」の中から取りあげます。「ウェスタの巫女」が関係したある「事件」で、これは若きユリウス・カエサルの生涯の分岐点となったものです。
ローマに古くからある固有信仰からの印象的なエピソードを「ローマ人の物語」の中から取りあげます。「ウェスタの巫女」が関係したある「事件」で、これは若きユリウス・カエサルの生涯の分岐点となったものです。話の発端は「独裁者スッラ」の登場です。紀元前1世紀における「民衆派」マリウスと「元老院派」スッラの、血で血を争う内戦の詳細については「ローマ人の物語 第3巻 勝者の混迷」を読むしかないのですが、とにかく紀元前82年にスッラはこの戦いに勝利します。そして「民衆派」の一掃を目指して元老院議員80人を含む4700人の「処罰者名簿」を作成し、処刑と財産没収を始めます。この名簿に18歳の若者の名前があったのです。以下「ローマ人の物語」からの引用です。下線は原文にはありません。
スッラの作成した「処罰者名簿」には、一人の若者の名もあった。マリウスの甥でありキンナの婿であるところから、スッラにすれば若きカエサルも、一掃さるべき「民衆派」の立派な一員だった。 |
塩野さんのこの文章の意図は、引用の最後のところ、スッラが若きユリウス・カエサルを「百人のマリウス」と評したことを書くことですね。つまり「才能は、才能によってのみ認知される」ということだと思います。
しかしそれとは別に、下線の部分に注目すべきことが書かれています。下線の部分の「女祭司(ヴェスターリ)」は、普通ラテン名で「ウェスタの巫女 Vestalis」と呼ばれています(ウェスタの処女、ウェスタの聖女とも言う)。ウェスタの巫女は、かまどの火を司り、家政と結婚の神でもある「ウェスタ神 Vesta」に仕える巫女の一団(6人)です。ウェスタ神はローマの建国以前からラテン民族に伝えられてきた古い神です。巫女となる女性は6~10歳のローマ市民の子女の中から選ばれ、30年の間、実家からは離れて専用の家に住み、勤めを果たします。巫女の最大の責務はパラティヌスのウェスタ神殿の「聖なる火」を絶やさないことです。また各種の聖具を管理し、典礼に参加します。
アルベルト・アンジェラの「古代ローマ人の24時間」(関口英子訳。河出書房新社。2010)は、最新の古代ローマ研究の成果をもとに、紀元115年(皇帝トラヤヌスの時代)のある1日のローマを実況中継風に描いた本です。この中に、パラティヌスの近くで警備隊や従者に囲まれた豪華な飾りの馬車に出会う場面があります。馬車は円形の神殿の前で止まります。
最初に、ベールをかぶった高齢の女性があらわれる。続いて、華奢な女の子が手を借りながら降りてくる。おそらくまだ10歳にもなっていないだろう。ゆったりとした衣服のせいか、動きが少しぎこちない。 |
ウェスタの巫女の最大のポイントは「処女であること」です。従って巫女である間は、彼女たちは純潔を守り通さなければなりません。もしこれに反すると死刑です。この刑の執行方法は独特です。
聖なる火が消えてしまった場合や、巫女が処女を失った場合には、見せしめとしての罰が与えられる。巫女の愛人はフォルムで死ぬまで鞭打たれ、巫女も死刑にされる。ただし、巫女を殺す際には血を一滴も流してはいけないと法律で定められていたため、一塊のパンとランプとともに地下の独房に入れられ、生き埋めにされるのだ。地下の独房はカンプス・スケレラートゥス(呪われた野、の意)というあらかじめ準備された場所にあり、そのまま紛れもない墓となる。 |
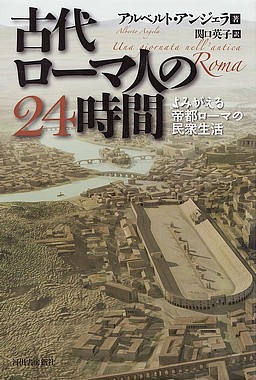 実際にこの刑が行われた例が、西暦1世紀から2世紀にかけてのローマ人であるスエトニウスが書いた「ローマ皇帝伝」(国原吉之助訳。岩波文庫。1986)に出てきます(第8巻 ドミティアヌス帝)。
実際にこの刑が行われた例が、西暦1世紀から2世紀にかけてのローマ人であるスエトニウスが書いた「ローマ皇帝伝」(国原吉之助訳。岩波文庫。1986)に出てきます(第8巻 ドミティアヌス帝)。ウェスタの巫女は祭礼を司るだけではありません。塩野さんやアルベルト・アンジェラが書いてるように、ローマ市民の大変な敬意を払われていたと同時に極めて強い「権威」があったようです。この権威について Wikipedia の「ウェスタの処女(Vestal Virgin)」の項から一部を引用すると、
| ◆ | 競技会や公演会があるときには来賓席が用意された。 |
| ◆ | ローマの女性たちとは異なり、家父長制のもとになく、財産権をもち、意志の表明や投票ができた。 |
| ◆ | 清廉潔白な人間であるとされ、条例のような公文書や重要な決定などでその意見が求められていた。 |
| ◆ | その人格は不可侵なものであった。その身体を傷つけることは死罪を意味し、つねに護衛する人間がついた。 |
| ◆ | 彼女たちは有罪となった囚人や奴隷に面会することで解放してやることができた。 |
| ◆ | 5月15日にはテヴェレ川へアルジェイと呼ばれた宗教的な藁人形を投げ込む役がまかされていた。 |
などです。我々が普通「巫女、女祭司」という言葉から受けるイメージとはかけ離れた「権威」を持っていたわけです。通常の生活から離れてローマのために身を捧げ、処女を貫き通し(=神と結婚し)、厳しい掟を守り、重大な責任を負い、(身代わりの藁人形が) 毎年犠牲になる極めて特別な女性たちの集団。この「特別さ」が権威の源泉ですね。考えてみると、これに類似した話は世界中にありそうです。
|
ここまで書いて直感的に思い出すのは、平安時代から鎌倉時代にあった、賀茂神社と伊勢神宮の「斎王」です。上賀茂神社・下賀茂神社では斎院、伊勢神宮では斎宮とも呼ばれていました。いずれも皇室の未婚女性から選ばれ、1~2年の準備期間の後、特別の場所に住みます。賀茂神社では京都・紫野にあった「斎院御所」、伊勢神宮の場合は「斎宮寮」です。そして巫女としての神事を行うわけです。現代の葵祭(賀茂神社の祭)で一般女性から「斎王代」が選ばれるのは古いしきたりを模しています。 斎王は天皇が皇室から神に差し出す未婚女性ですが、ウェスタの巫女の場合、差し出すのも差し出されるのもローマ市民です。このあたりは国のありようの違いが現れていて興味深いところです。 |

| |||
|
ルーベンス 「マルスとレア・シルウィア」 (リヒテンシュタイン侯爵家蔵) | |||
伝承では、オオカミに育てられた双子のロムルスとレムスがローマを建国しました。このローマ建国神話におけるロムルスとレムスは、軍神・マルスと、ウェスタの巫女であったレア・シルウィアの子です。ウェスタの巫女は「ローマの母」とでも言うべき存在なのです。
話を「ローマ人の物語」に戻します。絶対権力者のスッラは、周囲の助言ぐらいではカエサルを「処罰者名簿」からはずことはなかったが、ウェスタの巫女の要請によってはじめて名簿からはずしたわけです。これはウェスタの巫女がもつ「権威」の大きさを考えると、むしろ当然だったと考えられます。
スッラは温情で処罰者名簿からはずすような「甘さ」がある人間では全くありません。冷徹で鋭利な執政官であり、独裁者だった。しかしスッラは非情な独裁者である以前に「ローマ市民」だった。だから処罰者名簿からカエサルをはずした。
塩野さんがスッラとマリウスの戦いを記述した巻を「勝者の混迷」と名付けているように、当時のローマはまさに内戦状態です。民衆派と元老院派が激しく論争し、互いに殺し合っている。しかしスッラとウェスタの巫女のエピソードからうかがえるのは、処刑する者と処刑される者があったとしても、その根底のところではローマ市民としての強固な「ある種の価値観」を共有していることです。スッラの一見「甘い」と見える行動に、ローマの真の「強さ」を感じます。
ウェスタ神殿に永遠に燃えていた「ローマの運命を左右する象徴的な意味合いをもつ聖なる火」は、スッラがカエサルを処罰者名簿からはずしてから475年後に消されました。古代オリンピックの廃止と同時期です。それは、ほかでもないローマ皇帝の命令によってです。この聖なる火が消えた時点で実質的にローマは滅んだのではないでしょうか。
聖なる火はローマの信仰の極く一部です。そのほかに固有の神々があり、加えてオリエントからの外来の神々があり、数々の神殿があって各種祭祀が執り行われ、日常生活のあらゆるところに(塩野さんが書いているように、夫婦喧嘩の守護神までの)神がいた。前回の No.25「ローマ人の物語(2)」で「ローマ人物語」からいろいろと引用したように、それらはオリエント由来のたった一つの宗教を除いて破壊されたわけです。
ポンペイ展
2010年の3月から6月まで横浜美術館で「ポンペイ展」が開催されたので行ってきました(展示会は日本各地を巡回)。改めて思ったのはポンペイには「神殿、神の像、神を描いたフレスコ画がずいぶんある」ということです。
ポンペイは南北650メートル、東西1200メートル程度の町で、正確な人口は不明ですが、ヴェスビオ山の大噴火の当時は約8000人程度が住んでいたとされます。遺跡の地図をみると西南に公共広場(フォルム)があって、その周りに神殿がかなりあります。ちょっと数えてみただけでも、
| ◆ | アポロ神殿 |
| ◆ | カピトリウム神殿(ローマの3主神であった、ユピテル、ユノ、ミネルヴァを祭る) |
| ◆ | ラル神殿(ラルは家庭の守護神) |
| ◆ | ウェスパシアヌス帝神殿(69-79在位の皇帝) |
| ◆ | ドリス式神殿 |
| ◆ | イシス神殿(イシスはエジプト由来の神) |
という具合です。
 ポンペイ遺跡からは、神殿を飾っていた数々の神の像が出土しています。神殿の名称になっている神以外にも、ウェヌス、ヘルクレス、メルクリウス、ポセイドンなど多様です。右の図はポンペイ展に展示されていたウェヌス(ヴィーナス)像(高さ90センチ)ですが、大変に優美で見事な造形です。前に古代の地中海世界にはルーブルの「ミロのヴィーナス」に匹敵する像がいろいろあったはず、という推測を書きましたが、このウェヌス像を見るとそれはほとんど確信となります。
ポンペイ遺跡からは、神殿を飾っていた数々の神の像が出土しています。神殿の名称になっている神以外にも、ウェヌス、ヘルクレス、メルクリウス、ポセイドンなど多様です。右の図はポンペイ展に展示されていたウェヌス(ヴィーナス)像(高さ90センチ)ですが、大変に優美で見事な造形です。前に古代の地中海世界にはルーブルの「ミロのヴィーナス」に匹敵する像がいろいろあったはず、という推測を書きましたが、このウェヌス像を見るとそれはほとんど確信となります。No.25「ローマ人の物語(2)」に引用しましたが、塩野さんはローマにある「カピトリーノのヴィーナス」について「あまりに美しいために破壊するにしのびず、誰かが意図的に隠しておいたものではないか」という推測をしています。しかしこのポンペイのウェヌス像についてはこういった推測は成り立ち得ない。それは「あたりまえのように」ポンペイの町に飾られていて「たまたま」火山噴火で埋まり「運良く」土の中から掘り出されたものに過ぎないことが明白です。それでいてこのレベルの高さなのです。
 一方、家庭内をみると、展示品には家の中に祭った「小ぶり」の神々の像がありました。右の図は家の守り神であるラル神の小像(高さ19センチ)です。ポンペイの家庭にはララリウムと呼ばれる小さな祠、あるいは祭壇がありました。塩野さんが「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていた」と書いている、その「神棚」です(No.25「ローマ人の物語(2)」の引用を参照)。ラル神はそこに安置されていました。
一方、家庭内をみると、展示品には家の中に祭った「小ぶり」の神々の像がありました。右の図は家の守り神であるラル神の小像(高さ19センチ)です。ポンペイの家庭にはララリウムと呼ばれる小さな祠、あるいは祭壇がありました。塩野さんが「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていた」と書いている、その「神棚」です(No.25「ローマ人の物語(2)」の引用を参照)。ラル神はそこに安置されていました。像だけでなくフレスコ画の壁画もあり、神の姿を描いたものも多数あります。展示ではディオニュソスの絵がありました。ディオニュソス信仰はローマでは禁止されていたはずなのですが「地方都市」ポンペイにまでは及んでいなかったようです。
これらを見るにつけポンペイの人たちは私的場所や公的空間にかかわらず、神々の像や絵に囲まれて生活していたことが分かります。それはローマの他の都市でも同じだったはずです。もし仮にポンペイの町が噴火で埋没せずに4世紀まで残り、キリスト教の国教化に遭遇したらどうでしょうか。これらの神殿、像、壁画、家庭内の祭壇は全部破壊され、かつ宗教行事が全部禁止されたことになります。違反すると死刑です。これはいったいどのような影響を人々に与えたのでしょうか。
あなたが京都人なら
私たちはちょっと想像力を働かせる必要があります。1600年前のローマを想像することは困難なので、現代の日本に置き換えて考えてみます。
いまあなたが仮に京都市内に生まれ育ち、京都で働いているとします。町内会の活動にも熱心で、かつ「京都人」であることに誇りを持っているとします。その誇りを支えている極めて重要なファクターは何かというと、それは京都に現存する神社・仏閣であり、1000年レベルの伝統がある京都の各種行事ではないでしょうか。
もし現在、政府によって仏教・神道が「邪教」とされ、京都においてローマ帝国と同じことが、以下のように政府の強権で実施されたと想像してみます。
主要な神社・寺院・仏閣は破壊し、その他は調度品を破棄して建物を別目的に転用する。従って祇園神社、北野天満宮、貴船神社、上賀茂神社、下鴨神社、平安神宮などの主要神社は破壊。清水寺、知恩寺、南禅寺、東本願寺、東寺、銀閣寺、金閣寺、大徳寺、大覚寺、妙心寺、龍安寺、広隆寺、高台寺、東福寺も破壊。五重の塔も破壊。仏像も破棄。広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像も三十三間堂の千手観音像も焼却処分。
仏教に関係する行事はすべて禁止。檀家組織は解体。大文字山などの五山の送り火や、お盆の種々の行事はすべて禁止。神社にまつわる行事も禁止。従って祇園祭りは廃止。祇園祭りに使用する山鉾もすべて焼却処分。葵祭も時代祭も廃止。各町内の秋祭りも禁止。新年の初詣も禁止。
個人の家にある神棚、仏壇、仏像は撤去。各家庭の台所にある「阿多古祀符 火迺要慎」と書かれた火除けの祀符も、これは愛宕神社の祀符だから破棄。
こういいう事態になっても、あなたはなおかつ「京都人」だと言い続けるでしょうか。もちろん企業に勤めているので生活には困らないでしょう。しかし政府主導の「新しい京都をつくる会」に参加したいとは全く思わないでしょう。
全く同様のことが奈良でも起こったとします。そうするとすべての神社や寺院・仏像の破壊、宗教関連行事の禁止に加えて、例えば正倉院の宝物は全て焼却処分でしょう。正倉院はもともと東大寺の一部だったのですから・・・・・・。もちろん東大寺の大仏は消失します。こうなると京都・奈良以外の人たちにとっても「日本人としての誇り」の一つが完全に失われたことに気づくと思います。そして京都・奈良の人は思うでしょうね。果たしてこれは日本なのか、と。
重要なのは現代の多くの日本人はそんなに宗教に熱心ではないということです。神社は秋祭りや初詣に参加したり、七五三とか厄除け、合格祈願に訪れる程度が一般だと思います。仏教に熱心な人はもちろん多くいますが、仮に統計をとったとすると、日本人が寺院を訪れる理由は仏像鑑賞を含めた広い意味での「観光」が数で圧倒するのではないでしょうか。
にもかかわらず、神社・仏閣とそれに関連した行事・文物がすべてなくなったとすると「日本でなくなる」。宗教を甘くみてはいけないのです。1000年というレベルで長く国民に浸透した宗教は、国民のアイデンティティーの重要部分を占めています。現代日本で言うとそれは「日常生活」「年中行事」「仕事」「観光」「人生の節目」「美術・芸術」「文学」などと、さまざまな関連性をもった「巨大な体系」を作っているのです。
No.21「鯨と人間(2)」に、日本に数え切れないぐらいある「動物供養」の話を書きました。しかし「動物供養」どころか、日本では「モノの供養」も数多くあります。人形供養、針供養を筆頭に、印章、筆、入れ歯、下駄、包丁などの「供養」が限りなくあります。そしてこれらの動物供養やモノ供養の背景には、仏教の殺生を否定する教義や、神社のアニミズム的信仰をルーツとする日本人の「宗教感情」があるわけですね。ほとんど意識はされないと思うけれど・・・・・・。動物供養やモノ供養も広い意味での「宗教体系」の一部です。
この「体系」は、一握りの誰かが決めたものではありません。長い年月をかけ、自然発生的に増殖を繰り返してできあがったネットワークです。
「宗教体系」の破壊
現代の京都・奈良と違って、古代ローマの話です。宗教と人間の日常生活や国家運営との結びつきが現代よりもよほど強いわけです。この世のあらゆる出来事は神々の意思によるものと考えられていた時代であり、占いが神々の意思を知るための大切な行為と考えられていた時代です。その「宗教体系」の破壊は国家が滅びかねないほどの影響を持つのではないでしょうか。
それだけではありません。「新たな宗教体系」として採用された当時のキリスト教は一神教です。一神教の特徴は、もちろん他の宗教との共存を拒否し非寛容であることです。しかしもう一つの特徴、むしろ一神教の最大の特徴は、塩野さんが明確に書いていますが「人間の倫理・道徳や生活スタイルに介入する」ということなのです。
ギリシャ・ローマに代表される多神教と、ユダヤ・キリスト教を典型とする一神教のちがいは、次の一事につきると思う。多神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割を神に求めない。一方、一神教では、それこそが神の専売特許なのである。 |
当時のキリスト教を現代のキリスト教と思ってはいけません。当時のキリスト教はピュアな一神教であり、塩野さんが正確に言い当てているように「人間の行いや倫理道徳を正す役割が神の専売特許」である宗教なのです。「行いや倫理道徳を正す」というのも現代のイメージで考えると大きな間違いです。甘く見てはいけません。非常に強く人間の生き方と社会活動を拘束するものです。
たとえば、もし仮に一神教の聖職者が神の教えとして「自分が食べるものだけを生産しましょう、あとは神に祈りましょう」と説教し、農業に従事する奴隷がその通りにしたら、生産性は低下します。それが社会全体に広まったら、奴隷制度を根幹とする国は衰退するはずです。
「利子をとって金を貸すのは悪いことです。やめましょう」と聖職者が教え、国家がそれを後押し、それが国全体に広まったとしら、国の経済力は確実に衰退します。
「戦うことは悪です」と聖職者が説教し、その教えを実践する「兵役拒否者」が続出したとしたら、軍事力は間違いなく低下します。
以上はあくまで想像ですが、ありうることだと思います。実際のところ、最後の「兵役拒否者」の例は塩野さんの本に出てきます(第14巻:キリストの勝利)。「人間の行いや倫理道徳を正す」ことは国のレベルの経済や軍事にまで影響するはずです。これはちょうど現代のイスラム原理主義をかかげる人たちの行動パターンを考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。
新渡戸稲造と「武士道」
少し脇道にそれますが「一神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割こそが神の専売特許」という塩野さんの文章に関して思い出す話があります。新渡戸稲造(1862-1933)の「武士道」(1899。明治39年。初版)です。新渡戸稲造は、その序文で次のように書いています。
約10年前、著名なベルギーの法学者、故ラヴレー氏の家で歓待を受けて数日を過ごしたことがある。ある日の散策中、私たちの会話が宗教の話題に及んだ。 |
新渡戸稲造が尊敬するこのベルギーの法学者にとって、倫理道徳の教育が宗教のテリトリだということは、何の疑いもなく自明のことなのですね。新渡戸稲造はこの言葉にショックを受けて『武士道』を書くことになるのです。普通の日本人の感覚では、倫理や道徳は「社会に共有され、受け継がれているもの」であって、特定の宗教とは関係ありません。しかしキリスト教では「人間の行いや倫理道徳を正すのが神の役割」であり、つまり、宗教なしに倫理や道徳(教育)はありえないのです。
新渡戸稲造はキリスト教徒です。尊敬する老教授の言葉にショックを受け「キリスト教を広めて日本に道徳教育を根付かせよう」と考えてもよいはずです。そう考えてキリスト教系学校を設立した人もいたわけだから・・・・・・。しかし彼はそうではなかった。新渡戸稲造の偉いところは、特定の宗教とは無関係に日本にも倫理・道徳の体系はあると考え、それを諸外国に説明するために、英文で『武士道』という本にまとめたことです。『武士道』は世界的なベストセラーになり、現代まで読み継がれています。
『武士道』の序文を踏まえて話を古代ローマに戻します。キリスト教の国教化前後のローマ帝国では、倫理・道徳についての二つの異なる考えがあったと推定できます。
| ◆A |
古代ローマ(や日本)の伝統的考え方 倫理・道徳は、長年に渡って社会に蓄積され共有された、人間がとるべき行動や態度の規範である。特定の宗教に依存するものではない。 | |
| ◆B |
一神教(キリスト教)の考え方 倫理・道徳を人々に教えるのは宗教の役割である。それこそが宗教の存在理由である。 |
AとBはかなり違います。AをBに完全に転換するということは、並大抵ではないと思います。それは社会を作り直すことに等しく、簡単にはいかないはずです。そのAからBへの「作り直し」をローマ帝国はキリスト教の国教化でやろうとした。社会に共有された共通の価値観(A)は「国のかたち」を決める最も重要なことのはずですが、それが別のもの=キリスト教の倫理・道徳(B)になる。ローマ市民としてのアイデンティティは極めて不安定になり、国のかたちは崩れ、社会が混乱するでしょう。そういう時に強い外圧があれば、国が滅びかねない。ローマ帝国の末期で起こったことは、どうもそういうことだと感じます。
ローマ帝国と宗教の関係を考えるとき
多神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割を神に求めない。一方、一神教では、それこそが神の専売特許なのである。 |
インフラストラクチャの破壊
もちろん一神教であるキリスト教という新たな宗教のもと、新たな倫理道徳や生活スタイルの体系化を前提とした国を作り、その国を発展させることは可能です。事実、西ヨーロッパは数百年かけてそうなっていきます。しかし、国家のシステム全体を再建するのは、一朝一夕にいくはずはないのです。
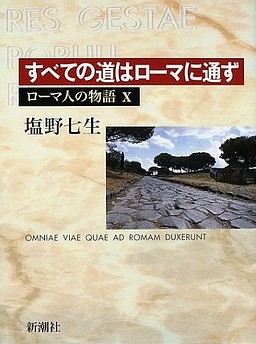 塩野さんの「ローマ人の物語」の大きな特徴は、インフラストラクチャの構築にいかにローマ人が先進的であったかということが詳細に記述されていることです。道路、橋、上下水道、浴場などのハード面はもちろん、法律、教育制度などのソフト・制度面もです。「第10巻:すべての道はローマに通ず」は、1巻がまるまるこのインフラストラクチャの記述に当てられています。
塩野さんの「ローマ人の物語」の大きな特徴は、インフラストラクチャの構築にいかにローマ人が先進的であったかということが詳細に記述されていることです。道路、橋、上下水道、浴場などのハード面はもちろん、法律、教育制度などのソフト・制度面もです。「第10巻:すべての道はローマに通ず」は、1巻がまるまるこのインフラストラクチャの記述に当てられています。こうしたインフラストラクチャのほどんどは「継承」できるわけです。メインテナンスさえすれば継承できます。キリスト教の国教化以降もローマ街道は使われたし、有名な「ローマ法大全」が編纂されたのは、西ローマ帝国が滅亡した後の東ローマ帝国においてでした。しかし、こういったローマ街道に代表されるインフラストラクチャを継承したつもりでも、もっとも本質的なところ、文明を成立させていた最重要のインフラストラクチャ=「人間の心、マインド、アイデンティティ」を、宗教を破壊することによってなくしてしまったのだと思います。その「アイデンティティ」という最重要インフラストラクチャを具体的な目に見える形に可視化し、象徴していたのが、神殿、神々の像、祭壇、聖石、そして言うまでもなくウェスタ神殿に燃え続ける「聖なる火」だった。
No.25「ローマ人の物語(2)」で書いたように、ローマの宗教は「ローマがローマたるゆえん」であり「ローマの最大の強み」だったのではないでしょうか。その1000年間続いた宗教体系をローマは破壊してしまいました。神の像も、宗教行事も、それと密接な関係があったはずの「人の心」もです。新たな宗教体系のもとに国を再建・再構築するのは、一朝一夕にはできないと思うのです。
(以降、続く)
No.25 - ローマ人の物語(2)宗教の破壊 [本]
(前回より続く)
ローマの衰退
本題のローマの衰退についてです。「ローマ人の物語」は「キリスト教の国教化が、ローマの衰退から滅亡への最後の決定的な要因になった」と言っているのだと思います。このようにダイレクトに書かれた箇所はなかったかと思いますが、その有力な「状況証拠」としては第14巻が「キリストの勝利」題されていることです。これは「ローマの敗北」の裏返しです。
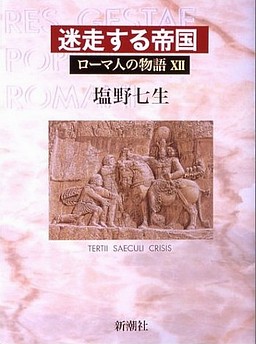 もちろん「キリスト教の国教化」に至った背景には、そうなるぐらいにキリスト教が広まったということがあるわけです。キリスト教徒は最も多い都市で5%と書かれています。5%というと少ないようですが、これ以外に人口の何分の1かの「シンパ」がいるはずだから、それなりの数ではあるわけです。広まった理由としては、経済の混乱や、度重なる外敵の進入、疫病の流行などによるローマ市民の救いを求める心情があるようです。キリスト教徒の拡大の理由については、「第12巻:迷走する帝国」に詳細な分析が書かれています。
もちろん「キリスト教の国教化」に至った背景には、そうなるぐらいにキリスト教が広まったということがあるわけです。キリスト教徒は最も多い都市で5%と書かれています。5%というと少ないようですが、これ以外に人口の何分の1かの「シンパ」がいるはずだから、それなりの数ではあるわけです。広まった理由としては、経済の混乱や、度重なる外敵の進入、疫病の流行などによるローマ市民の救いを求める心情があるようです。キリスト教徒の拡大の理由については、「第12巻:迷走する帝国」に詳細な分析が書かれています。ローマの衰退や滅亡の要因にはキリスト教以外の要因もさまざまなものが考えられます。前回の No.24 「ローマ人の物語 (1) 」にも書いたように、領土が固定化され、奴隷の新規獲得もなくなり、市民権をもつ人が増え、それ以上のローマ化を多くが望まなくなったとき、しかも軍隊が傭兵だらけになったとき、ローマの国家の活力を維持していたダイナミックなメカニズムは働かなくなると思うし、その方が衰退要因としては大きいと感じます。また、No.16「ニーベルングの指環 (指環とは何か) 」で書いたように、3世紀のローマ帝国は猛烈な貨幣価値の下落とインフレが進行するのですが、これも国家経済にとっては致命的事態です。このような経済史からの要因もあるだろうし、No.24「ローマ人の物語 (1) 」の「前提 - 2」で書いたように、環境史からの要因もあるでしょう。さらに「前提 - 3」のように各種要因は原因と結果の連鎖でからまっていて、単独で「取り出す」のは困難なはずです。
しかしキリスト教の国教化がローマ衰退の最後の決定的な要因になった、それがローマの滅亡に向けて「ダメを押した」というのは「ローマ人の物語」全体を読んで納得できました。では、なぜ「キリスト教の国教化」が衰退要因になるのか。その理由について塩野さんの考えは「寛容の喪失」ということに集約されるのではないかと思います。つまりローマは被征服民や異質なものを取り込んで同化し発展してきたが、その根本となっているのは多神教をベースとする「寛容さ」である。これがキリスト教の一神教的性格により決定的に阻害され、この結果「ローマがローマたるゆえん」「ローマの最大の強み」が失われ、崩壊に至った。このようにダイレクトに書かれた箇所もないと思いますが「ローマ人の物語」全15巻を読むと全体としてはそう言っている。「寛容」は「ローマ人の物語」全体をつらぬくキーワードです。
確かにローマの隆盛の要因になった異民族の「同化」は、その根底に「寛容」の精神があるというのは間違いないと思います。しかし「隆盛の要因が寛容である」のは分かるのですが「衰退の要因が寛容の喪失である」というのは、それだけではどうもすっきりしません。もちろん「寛容の喪失」も大きいと思うのですが、私が「ローマ人の物語」を読んでストレートに感じたローマ衰退の理由、つまり「キリスト教の国教化」がなぜ衰退の最後の決定要因になったのかは、非常に単純で以下のようです。
|
キリスト教は一神教であるため、以前からあったローマの宗教に関わるいっさいのもの、皇帝の像、神の像、神殿は破壊され、また一切の宗教行事は取りやめになった。 ローマの多神教をベースとする宗教的情熱、宗教感情は「ローマがローマたるゆえん」「ローマの最大の強み」であった。それが失われてしまい、衰亡を運命づけられた。 |
こう理解する方がシンプルで自然だし、またロジカルです。「ローマ人の物語」読後感とも合っています。以降にこの点について書きます。
宗教の「像」と「施設」の破壊

上の写真は、No.7「ローマのレストランでの驚き」でも紹介したローマのカピトリーノ美術館にある「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」です。実際に行ってみると想像以上に巨大なブロンズ像であることに驚きます。「ローマ人の物語 第13巻:最後の努力」によると、ローマ皇帝の騎馬像は22体存在し、記録によるとカエサルもアウグストゥスもトライアヌスの騎馬像もあった。しかしすべてブロンズであったため、溶解されてしまった。マルクス・アウレリウスの騎馬像が唯一残ったのは、キリスト教を公認したコンスタンティヌスの像と間違われたから、とあります。
ローマ皇帝は死後に神格化され「神」として扱われました(全ての皇帝ではないが)。そして皇帝像は言うに及ばず、ローマ帝国にあったユピテルをはじめとするローマ古来の神々の像は、キリスト教の国教化以降、徹底的に破壊されたようです。
鼻をけずられるなどは、まだ穏やかな排除の方法だった。頭部が打ち落とされ、腕も打ち落とされ、四肢もバラバラになる。これらの作業もめんどうとなれば、崖の上から眼下の岩場に突き落としたり、橋の上から河に突き落としたりして、一挙に処理する方法がとられた。 |
ローマ人はギリシャ彫刻の模作を大量に作りました。これは、ギリシャへ文化への敬愛であり、ローマ人に一貫している寛容の精神によるものだと、塩野さんは言います。これらのギリシャ文化を伝える貴重な模作も破壊されました。
しかし、ハドリアヌス帝の時代という、ローマ時代の模作の質がもっとも高かった時代から200年しか過ぎていない4世紀末、同じローマ人が今度は、かつては大切にし大金を払って購入した傑作の数々を、破壊し河に投げ込むように変わったのだ。寛容とは、辞書には、心が広くおおらかで、他の人の考えも受け容れる、とある。ローマ人が徳の一つとしてさえ考えていた「寛容」(Tolerantia)の精神も、芸術作品の傑作とともに、破壊され捨てられて河に投げ込まれたのである。 |
破壊されたのは、皇帝や神の像だけではありません。当然のことながら神殿も同様です。
ローマ帝国の全域にわたって、その壮麗さで人々の讃嘆を浴びてきた神殿という神殿が、全く姿を消すか、遺ったとしても、崩れ果てた遺跡に変わったのであった。 |
このような破壊活動が「ローマ帝国の全域にわたって」(上記の最後の引用)行われたのです。
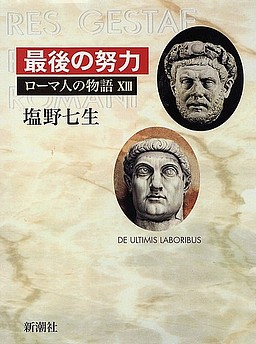
|
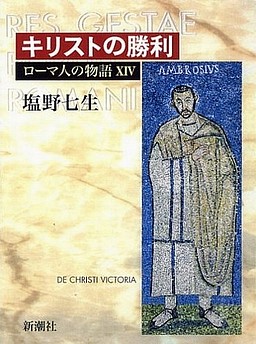
|
ルーブル美術館の「異常」
ルーブル美術館を訪れて「よく考えてみると異常だな」と思うことがあります。ルーブル美術館で最も素晴らしい彫刻は何でしょうか。「ミロのヴィーナス」だというのは衆目の一致するところだと思います。では2番目は ? と言うと、これは答えが分かれるかもしれませんが「サモトラケのニケ像」という意見が多いのではと思います。この2つの彫像は古代ギリシャ・ローマ時代彫像の傑作であると同時に、ルーブル美術館が保有するあらゆる彫像の中でも飛び抜けた「至宝」だと思います。それどころか、ルーブルの全ての美術品から「人類の至宝」を10点だけ厳選してあげよと言われたら、その中に「モナリザ」と並んで「ミロのヴィーナス」と「サモトラケのニケ」を入れるのは、あながち間違ってはいないと思います。いや、10点選ぶなら必ず入る気がする。
それでは、この2つの像はどうやって「発見」されたのかというと、以下のようです。
| ◆ |
ヴィーナス像(愛の女神) エーゲ海のミロス島で、1820年に農地の中からほぼ現在の形発見される。 | |
| ◆ |
ニケ像(勝利の女神) エーゲ海のサモトラケ島(サモトラキ島)で、1863年に断片で発見される。復元されて、現在の形になる。 |

この2つの像とも完全な形ではありません。全部が揃ってはいない。ヴィーナス像は両腕と「手に持っていたかもしれないモノ」がないし、ニケ像に至っては両翼はあるものの、両腕に加えて頭部もありません。つまりエーゲ海の小島から19世紀になってやっとのことで掘り出された、両腕のないヴィーナス像と頭部・両腕のないニケ像が「人類の至宝」となってるのです。この状況はやはり変であり、異常だと考えないといけない。

|

|
| [site : ルーブル美術館] |
ルーブルのミロのビーナス像とサモトラケのニケ像は、確かにすごい芸術品だと思います。しかしギリシャ・ローマ時代にはヴィーナスやニケは人々の敬愛を広く集めた神であり、その彫像も地中海世界にヤマのようにあったはずです。つまり芸術的な観点からルーブルにある像のレベルに達しているヴィーナス像やニケ像は、確率論的に言って、実は昔にはいろいろあったのではないでしょうか。もちろん頭部と両腕が完全に揃っていて、かつ芸術的にも素晴らしい像です。それがほとんど破壊された。
ヴィーナス像は他にも残っているが、ニケ像はほどんどルーブルの像だけだと言います。そう言えば「ニケ」という名前はルーブル美術館へ行って初めてはっきりと認識したような気がします。そういう神がギリシャ・ローマ時代にあったのだと・・・・・・。ニケは英語で言うとナイキです。ドイツのスポーツ・シューズ会社の名前はそこからきているというような知識を世界の人が知ったのは、僅かに残ったニケ像がルーブルにあるからではないでしょうか。またルーブルに僅かに残ったニケ像があるからこそ、そしてそれが船首をかたどった台座の上にあるからこそ、映画「タイタニック」(1997)でケイト・ウィンスレットは船首の甲板の先頭に立ってニケのまねをして見せたのだと思います。彼女が手を横に大きく開くのはニケ像の両翼を模していますね。研究者によると、当然のことながらオリジナルのニケ像にあった両腕は横に大きく開いているわけではありません(神はそんなポーズをしない)。もし仮にルーブルのニケ像に両腕があったとしたら、ケイト・ウィンスレットはあの通りのポーズはしなかったと思います。さらにナイキ社のロゴは翼を図案化したものにならなかったかも知れない。
ニケは紀元前から地中海世界に広まっていたと書きましたが、そのことを想像させるのが南フランスのニースという町です。この町は、もともと紀元前にギリシャ人が建設した町ですが、町の名前の語源がニケなのです。ギリシャを中心に地中海世界に数々あったはずのニケ像は、今となっては頭部と両腕のないルーブルの像を見て「認識」するしかありません。
幸いなことに人間には「想像力」があります。両腕がない、あるいは頭部がない像を見せられると、人間は無意識に完全な姿を想像してしまいます。ニケ像を見るとき、人は暗黙にその人が考えるもっとも美しい姿を思い描いているのでしょう。だからこそ高く評価されるとも言える。しかしこれは「結果論としてそうだ」というだけであって、芸術性を高めるために両腕と頭部を破棄したわけではありません。
ちょっと脇道にそれますが、両腕・頭部がないということに関連して、No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介した中野京子さんの「怖い絵2」に、美術用語である「トルソ」の話が書いてありました。「トルソ」は、頭部や手足のない胴体部のみを造形した彫刻や絵画、またはその概念をさすイタリア語です。これについての、中野さんの解説です。
何といってもトルソという概念は、このルネサンス期に、古代ギリシャ・ローマ彫刻が続々発掘されたことに端を発する。古代遺跡から彫刻を発掘作業する際、強度のある胴体部分は無庇でも、細すぎたり接合部分の弱い四肢や頭部は破損・紛失することが多く、そんな不完全な状態にありながらなおそのプロポーションの素晴らしさが感じられたため、胴体だけでも愛でる価値ありということで、トルソの魅力が発見されたのである。 |
中学校か高校か忘れました。美術室にいくと油絵や胸像が置かれた中にトルソがあったのを覚えています。何だか「不思議な感じ」がすると同時に、何でこんなものがあるのだろうという、ある種の「違和感」感じたものです。その「違和感」の理由が中野さんの解説で分かりました。トルソは、それが美しいと思って人間が作りだしたのではなく、不完全な形に破壊・損傷した断片の中に美を見出そうとしたものだったのです。「違和感」があったとしても当然です。まとめると、トルソという美術概念が成立してしまうほど、古代ギリシャ・ローマ時代の彫刻は、地中から不完全な姿で掘り出される、という形でしか後世に伝えられなかったということだと思います。
古代ギリシャ・ローマ彫刻が「地中から掘り出される形でしか後世に伝えられなかった」理由としては、意図的な破壊か、放置されたか、のどちらかでしょう。放置されると、たとえば地震などで倒壊しても再建はされません。放置とまではいかないまでも、少なくとも「像を守る」ということはなかったはずです。ルーブル美術館のビーナスとニケという個別の像をとってみると、どういう事情で不完全な形で地中に埋まっていたのか、何か特別な事情があったのか、それは分かりません。しかし一般的に言って神々の像が「地中から掘り出される形でしか後世に伝えられなかった」のは、塩野さんが書いているような「意図的な破壊」が大きいはずだし、少なくともそれがトリガーになって派生したさまざまな事象であることは間違いないと思います。
キリスト教を国教としたローマ帝国は、自らの手で、1000年以上の歴史を有する宗教の象徴的な像、しかも芸術的にも素晴らしい数々の像を破壊してしまったというのが実態でしょう。
ここで「1000年以上の歴史を有する宗教を象徴する数々の像がなくなった」ということがどういうことなのか、想像力を発揮する必要があます。日本でも明治時代に廃仏棄釈がありました。しかし幸いなことに国宝級の仏像は多くが残り、全国の寺院の仏像も多くが残っています。もし仏像破壊が徹底的行われ、現代日本に仏像はほとんどなく、もちろん路地端のお地蔵さまもなく、唯一国立博物館にたとえば興福寺の阿修羅王像と法隆寺の救世観音像ぐらいの数点だけが展示されているだけで他に何もないとしたら・・・・・・日本人のアイデンティティの一つが完全に失われているのではないでしょうか。
芸術の破壊
さらに、ローマ帝国にあった神々の像は単なる「宗教上のモニュメント」ではありません。それは明らかに「芸術品」です。しかもこの芸術のレベルは非常に高い。ちょと考えてみると分かるのですがギリシャ・ローマ文化の遺産で、芸術品として、現代の基準からしても最高のものとして通用するのは彫刻です。

|
| カピトリーノのヴィーナス |
それと比較してギリシャ・ローマ文化の絵画、フレスコ画や壷に描かれた絵は「現代の基準からしても最高の芸術品」とは言えない。もちろん歴史資料的価値は大いにあるのですが、ルネサンス以降の近代・現代までの絵画作品と比べてしまうと「見劣り」がします。残念ながら絵画技術が発達していなかったのです。
しかし彫刻は別です。ルーブル美術館の「ミロのヴィーナス」は紀元前の無名の作者によって作られたわけですが、その1500年以上あとに作られたフィレンツェのアカデミア美術館にあるミケランジェロの「ダヴィデ像」と比較して、どちらが芸術作品として素晴らしいかという「愚問」を考えてみると、どちらも同じ様に素晴らしいという答えしかないでしょう。それはちょうど8世紀に作られた奈良の興福寺の国宝・阿修羅王像が、日本の古代から現代までの歴史において、彫像としては最高の「芸術品」の一つであるのとよく似ています。
「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」があるカピトリーノ美術館に「カピトリーノのヴィーナス」という立像があります。ローマ時代の彫刻にしては極めてめずらしく全身が完全な形で残っている立像です。この像について塩野さんは大変に印象的な文章を書いています。完全に残りすぎている、おかしい、と・・・・・・。
私の頭の中には一つの仮説が頭をもたげてくるのだった。それは、四世紀末に生きていた誰かが、石棺の中にでも隠して、地中深く埋めたのではないか、という仮説である。 |
もちろん塩野さんも、実証はむずかしく現時点では「空想」だと断っています。しかし作家の直感というのでしょうか、非常にインパクトのある「空想」です。
4世紀後半のローマで起こったことは「1000年以上の歴史を有する宗教を象徴する数々の像がなくなった」だけではなく「地中海世界における最高の芸術品、現代でも十分に通用するレベルの芸術品が破壊された」のです。これがローマ市民の「心」にどういう影響を与えたのか、よく考えてみる必要があるでしょう。
最高の芸術品を前にしたとき、人はその美しさに感動し、あるいは力強さに打たれ、厳粛な気持ちになり、それに愛着を覚えるようになり、それを生み出した郷土や国を誇りに思うでしょう。こういうレベルの「心の動き」は、現代人でもローマ人でも変わらないと確信します。「現代でも十分に通用するほどの、最高レベルの芸術品が破壊された」時の人々の喪失感は巨大なものだったと思います。
オリンピックの終焉
キリスト教が国教になることで、キリスト教以外の宗教行事は皇帝の命令と元老院決議で禁止になりました。この象徴的な例が古代オリンピック(オリンピア大祭)の廃止です。近代オリンピックと違って古代オリンピックは、もちろん宗教行事です。ギリシャの最高神であるゼウスの神に「競技」を捧げるわけです。日本の相撲の発祥と似ています。
古代オリンピックは紀元前776年にに第1回が開催され、西暦393年の第293回まで、実に1169年の長きに渡って行われてきました。テオドシウス帝がキリスト教を国教としたのは、西暦392年です。そのため西暦393年が最後のオリンピックとなったわけです。
古代オリンピックの最大の特徴、それはギリシャの都市国家が戦争をしているときでも、戦争を中断して開催されたことです。塩野さんが「ちなみに私は、戦争中の国や敗北した国の選手を排斥する近代オリンピックを、古代のオリンピア競技会の継承者とは認めていない。」(第14巻:キリストの勝利)とコメントしているほどです。
ここで最も重要なことは「古代オリンピックは都市国家が生きるか死ぬかの戦争をしている時でさえ、それを中断してでも開催するほどギリシャの人々にとっては重要なものであった。それだけ特別なものだった。それをローマ帝国は強権でもって禁止してしまった」ということだと思います。これは「ギリシャ」というある種の地域共同体を崩壊させる行為でしょう。
宗教儀式の禁止
もちろんオリンピックは廃止された宗教祭儀のごく一部であったわけです。ローマでは国家の運営に組み込まれていた公式の祭儀は全廃されました。ローマの祭司は、最高神祀官・神祀官・祭司・占師というヒエラルキーになっていて、その他に女祭司(巫女)があったわけですが、それらはもちろん廃止です。そもそも「ローマ人の物語」の重要な「主人公」であり、ローマ人の典型であるユリウス・カエサルは37才で最高神祀官に当選し、これが彼のキャリアの重要なステップになったのでした。
さらに、公的祭儀だけでなく、私的な祭儀も禁止されました。再び「ローマ人の物語」から引用します。
「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていたのだが、これも偶像崇拝と見なされ、取り払うよう強制された。違反すれば、待っているのは死罪である。」 |
当初のキリスト教の「偶像崇拝の禁止」がこれらの命令の根拠、というかタテマエとなっています。それがタテマエにすぎないことはその後のキリスト教が偶像崇拝だらけになっていくことが証明しています。さらに、当時の皇帝命令では偶像崇拝を知りながら密告しなかった者にも同額の罰金が科せられたと言います(ギボン「ローマ帝国衰亡史」による)。まさにローマ古来の宗教を根絶するための政策が、次から次へと実行されたわけです。
(以降、続く)
No.24 - ローマ人の物語(1)寛容と非寛容 [本]
No.7「ローマのレストランでの驚き」で、ローマのカピトリーノ美術館の「マルクス・アウレリウス帝の騎馬像」について「唯一、ローマ皇帝の騎馬像で破壊をまぬがれたもの」と書きました。これは、塩野 七生 著「ローマ人の物語」に沿って記述しているわけです。またNo.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」でも、ローマ帝国の銀貨改鋳の歴史を「ローマ人の物語」から引用しました。
その「ローマ人の物語」についての感想を書いてみたいと思います。「ローマ人の物語」は全15巻という大著であり、感想を書き出したらきりがなくなります。ここでは、著者の塩野さんが書いている「ローマの隆盛と滅亡の要因、特に滅亡の要因」に絞って記述したいと思います。なお「ローマ」とは、塩野さんの考えに従って「古代ローマの建国から西ローマ帝国の滅亡までの、ローマという都市を中心(首都)とする国をさすもの」とします。
前提事項-1 歴史を素材とする小説
まず断っておくべき前提事項が3点あります。第1点は「ローマ人の物語」は歴史書というより小説に近いということです。つまりこの本は「過去の歴史研究に基づくローマの歴史、特に政治史・軍事史を素材にし、それを詳細に記述する中で著者の人間観や社会観を述べた小説」と考えた方がよいと思います。従って「ローマ帝国滅亡の原因」というような歴史研究の範疇に属するテーマは本書の第1の主旨ではないわけです。この本はあくまで、随所に記述されている塩野さんの「人間性や社会の本質」に迫ろうとする多様な角度からの洞察にこそ意義があります。その、ほんの数例をあげてみますと、
などです。ほんの一部ですが・・・・・・。
ここで特に取り上げた「洞察」はいずれもローマに対する評言であると同時に、現代ないしは現代日本に向けられたものであるとも言えます。「改革の主導者はしばしば旧勢力の中から生まれる」というのは、まさにその通りです。ペレストロイカを主導したミハイル・ゴルバチョフは、ソ連共産党のエリート中のエリートでした。私の知り合いだったあるアメリカ人は息子にミーシャという名前(本名)をつけましたね。ゴルバチョフの愛称です。それほど彼を尊敬していました。
「言動の明快さが、責任をとることの証明だと人々は感じる」というのは、警告だともとれます。「責任をとる気もないのに、言動だけが明快な人」がいるからです。
「戦争は生きるためにやるのである」というのも「死ぬために戦争をやった(やっている)」人たちへの批判だと思えます。もちろん過去の日本を含めてです。
「人間だれでも金で買えるとは、自分自身も金で買われる可能性を内包する人のみが考えることである」というのは、現代日本のある特定の人たちを痛烈に批判していると聞こえます。「自分は金で買われますよ」と宣言しているに等しい人間を信用する人はいないはずなのですが、現実は不思議なことに信用する人がいるようです。
さらに、こういった社会や人間性についての洞察や考察だけでなく、女性である塩野さんの実感からでしょうか「女とは」「女は」という考察もいろいろあります。
なるほど・・・・・・。参考になります。
前提事項-2 政治史と軍事史
話を本題に戻します。注意すべき前提事項の第2点は、国家の興亡を「ローマ人の物語」が主として扱っている政治史や軍事史だけをもとに語ることはできないということです。世界の歴史を振り返ると、特に古代は気候変動などの自然環境要因も文明の衰退の原因になります。仮に気候の寒冷化により年平均気温が3度程度下がり、小麦の収穫量が半分になったとしたら、国家の経済は破綻状態になるはずです。実際、2世紀の後半から3世紀にかけは寒冷期でした。古代ローマ時代とは比べものにならないほど農業技術が発達した1993年の日本で、夏の平均気温がわずか1~2度下がっただけで米が大凶作に陥り、国をあげての大騒動になったのを思い出します。
また2世紀の後半から3世紀にかけてのローマ帝国ではアントニウスの疫病(165-180)や、キプリアヌスの疫病(251-266)などの伝染病が大流行しました。このうち「アントニウスの疫病」は五賢帝の最後の皇帝、マルクス・アウレリウス帝(=カピトリーノ美術館の騎馬像)の時代です。メソポタミアでアルメニアと戦ったローマ軍はユーフラテス河の沿岸のセレウキアで大勝利をおさめます。青柳正規著「ローマ帝国」(岩波書店 2004)によると、その後の経緯は次のようです。
アントニウスの疫病は天然痘だと言われています。それにしても3割もの人口減少、しかもそれが急激に起こるというのは国家の衰退にもつながりかねない深刻な事態です。「パックス・ロマーナ」においてローマ帝国が防衛・保障してくれる安全は、外敵の進入や内乱からの安全であって、病原菌からの安全ではないのです。あたりまえですが・・・・・・。数百万人規模が死亡したとされるこれら疫病の蔓延は、当然社会不安を引き起こします。病気の原因が神の怒りだとする人々からすると、神の怒りをなだめられない皇帝は皇帝の資格がないわけで、皇帝に対する不信感にもつながるでしょう。皇帝が神格化されていればなおさらです。
さらに経済の観点から言うと、No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で紹介したように、基軸通貨であったデナリウス銀貨の銀の含有率は紀元64年には93%でしたが、265年には5%までに下落しました。またこの間に小麦の価格は80倍にも高騰したのです。こういった貨幣価値の暴落や物価の暴騰・インフレ(ないしはスタグフレーション)は国の経済をマヒさせます。物資の流通は滞り、物々交換が横行し、農業の生産性は低下するはずです。
以上のような環境史や経済史と国の興亡の関係、特に環境史は「ローマ人の物語」のスコープ外であることには注意が必要です。
前提事項-3 巨大組織の崩壊
第3の注意点は、巨大システム・組織の衰退の真の原因は1つであることはまれであり、たいていは複数の要因が複雑にからみあった中で起こるということです。しかも「原因」は別の要因から派生した「結果」でもあり、また「結果」が「原因」を作り出します。その上、一つの衰退の要因を取り除こうとすると同時に国家の「強み」や「アイデンティティー」をなくすことになり「にっちもさっちも行かなくなる」というようなことがあるわけです。ガン細胞だけを手術で切除するようにはいかないのです。
ローマの隆盛:「同化」と「隷属化」
以上のような3点が前提条件ということになりますが、これらに注意しつつ、ローマを隆盛と衰退、特に衰退に導いた重要だと思える要因について読後感を書いてみたいと思います。まず衰退を考える前に、衰退の前提となるローマの発展・隆盛についてです。
ローマの発展・隆盛に関しては、征服した異民族や異文化もローマに迎えて「同化」したということが大きく、その具体的な数々の事例が本書には書かれています。人材を登用し重要なポストにつけたような例はたくさんあり、(記憶が正しければ)元老院議員になった例さえある。少なくとも元老院議員になるまでの道は制度的に開かれていたわけです。二重市民権(二重国籍)まで認められていたようです。こういった「開放性」に関してローマは非常に進んでいて、これが隆盛の大きな原因だということは本書を読んで納得できました。
この「同化」というのも、別の観点からみれば「隷属化」だというのは注意した方がよいと思います。ただし単に「奴隷状態になる」というのとはちょっと違う。貧しくて食うや食わずの生活をしていた「蛮族」があったとします。その「蛮族」がローマと戦争をして征服されたとします。その結果として奴隷に近いような状態でローマに「収奪」されたとしても、ローマの文明と経済力を背景とするシステムの中に組み入れられたとしたら、農業生産力は向上し、結果として生活は以前より安定・向上し「蛮族」としては「うれしい」のではないでしょうか。しかもローマ市民権を得る道や、可能性としては元老院議員になる道まで開けているとしたらです。ローマは征服した属州に次々と「ローマ式都市」を建設しました。道路が舗装され、下水道は完備し、公衆浴場もあり、外敵の進入をさせない強固な防壁の「近代的」都市です。都市間をネットワークで結ぶ道路もある。生活がそれなりに安定した上に近代的な都市に住める期待もあるなら「蛮族」は「喜んでローマに隷属した」という面があるのではと思います。しかも奴隷同士の殺し合いを野外劇場で観戦するという、これ以上は考えられないような「刺激的娯楽」もある。
これはローマの支配層からみると「文明の力」を利用した非常に巧妙な支配システムであると言えます。征服した民が「不満を言わずに奴隷なみに働いて」くれたら、そして「喜んで収奪されて」くれたら、支配する側にとってこんなにうれしいことはない。
ローマの発展と領土拡大のプロセスを読んでいて、ふと、有名なノンフィクション作品「ああ、野麦峠」(山本茂実 著。角川文庫。1977。原著は1968)を思い出しました。明治末期から昭和初期にかけての時代、生糸は日本の非常に重要な輸出品です。そこで資本家は信州の諏訪や岡谷に製糸工場を作るわけです。そして飛騨地方の農家の娘をつのって「工女」として働かせる。野麦峠は飛騨と信州を分ける峠ですね。その製糸工場では夜10時までというような長時間労働がある。体をこわすと即解雇で、何の保証もない。何よりも労働の成果(工女たちが紡いだ絹糸)の量と質が厳しく検査され、それで賃金が決まる。「百円工女」と言われた年間賃金100円のトップクラスの人はごく少数で、多くの工女の賃金は30円~40円程度であり、20円の人もいる。この状況は一面からみると「資本家ないしは工場経営者が、無垢な農家出身の女性労働者を競争させ、長時間労働で搾取している」わけです。「ああ、野麦峠」の副題は「ある製糸工女哀史」となっていますが、そのタイトルそのままです。
しかし著者の山本さんはフェアに書いています。500人以上の元工女にインタビューすると、食事は「うまい」が90%、労働は「普通」が75%、賃金は「高い」が70%なのです。さすがに検査は「泣いた」が90%、病気への対応は「普通」が50%で「冷遇」が40%となっています。しかし総括では「行ってよかった」が90%なのです。その理由は「工女哀史」ではあっても農家の仕事よりは楽だからです。朝5時から夜10時まで女性を働かせるのはひどいと言っても、農家では夜10時、11時まで夜なべをすることがあるわけだし、朝も日の出前から農作業です。工女は年1回の休暇のときに稼いだお金を飛騨の実家に持って帰れます。これが非常に大きい。一家の一年の稼ぎより、一人の工女が持って帰るお金の方が多かったという例さえ出てきます。親に喜んでもらいたい一心で働く。これはつらい労働に耐える極めて大きなモチベーションになります。製糸工場を「工女哀史の舞台となった搾取システムである」と切って捨てるのは簡単ですが、飛騨の農家の娘にとって何が幸せだったのかは別問題だと思います。
「野麦峠」的状況はその後も繰り返されています。以前、はやりました。中国の上海あたりに日本企業が工場を作る。そして四川省などの農村地帯から女性労働者をリクルートする。彼女たちは時間給80円とか、為替レートで換算した日本の水準からすると信じられないような「低賃金」で働くわけです。労働集約商品を作っている日本の企業からするとコストが劇的に下がり、日本に輸入して大きな利益が得られます。一方、農村地帯出身の女性労働者の方からみると、そうして頑張って5年間働いて故郷に帰れば、貯めたお金で両親にささやかな家をプレゼントできるわけです。こんなに「うれしい」ことはない。
現代は「奴隷」とか「属州」とか、そういうものは一切ないわけですが、そんなことに頼らなくてもローマ発展のメカニズムと同じことが「差異」を利用して合法的にできる。むしろそれをやった人が賞賛される。そういう感じがします。但し、ロジカルに考えてみると分かるように、このメカニズムは「差異」がなくなったときに終わりです。ローマ帝国に置き換えてみると、帝国の領土が固定化し、新しい奴隷(低コスト労働力)の獲得がなくなり、多くの人々が生活に満足するようになり、それ以上のローマ化を望まなくなった時に終わりです。それ以上の発展のためには、別のメカニズムが必要になる。
野麦峠と中国工場の話を書きましたが、これはグローバルに場所を変え「差異」を求めて繰り返えされ続けると思います。
「寛容」と「非寛容」
古代ローマの話です。ローマの隆盛の根幹にあるのは「寛容」だと、塩野さんは規定しています。確かにそうで、ローマが征服して属州とした国から人材を登用し重要なポストについたような例はいっぱい出てきます。こういった「敵をも同化する寛容さ」がローマ発展の原動力となったというのは、まさにその通りだと感じました。ギリシャなどの他国の優れた文化を積極的に取り入れたりするのも寛容の精神だと言えるかもしれません。もっとも文化は「高いところから低いところへ流れる」のが自然なので、ローマは高度なギリシャ文化に学んだのだとは思いますが・・・・・・。いずれにせよ、このような「寛容さ」は当時の他国にはなく、だからローマは発展した。これは納得できました。
しかし「ローマ人の物語」全体から受けるもう一つの印象は「ローマは寛容と非寛容の使い分け」で成長したという感じなのです。俗な言い方では「アメとムチ」でしょうか。「寛容」の一方で寛容とは正反対の「非寛容」もまたローマの特質だったと読み取れるのです。
「非寛容」の典型はカルタゴの抹殺です。カルタゴとローマの戦いは第2巻:ハンニバル戦記に詳述されているように幾多の紆余曲折があったわけですが、最終的に第3次ポエニ戦争でローマはカルタゴの市民を殺戮し、あるいは奴隷として売り飛ばし、町に火を放って焼き尽くして「更地」にし、そこに塩を撒いて二度と植物が生えないようにしました。
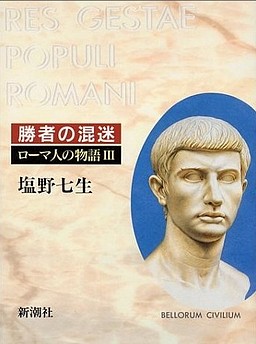 カルタゴをガリアやスペインと同様の「属州」にし、そこから優秀な人材をローマに登用し、それでローマはより発展する、という風にはならなかった。考えてみるとローマは地中海のまわりをぐるっと一つの国にするなら、極めて強大な国ができるというコンセプトのもとに作られた国家です。もちろん、初めからそのように計画されたのではないが、結果としてそういう方向に進んだ。キーとなるのは海上輸送が(陸上に比べて)圧倒的に効率的で、それが経済発展の要だという事実です。そのための必須事項は地中海の制海権の完全掌握です。たとえばナイル河流域の穀倉地帯をローマの直轄領にし、そこから安価な小麦を大量にローマに運び、その食料に依存して国を運営する。しかもローマ市民に小麦を無料配布までする・・・・・・。海上輸送が敵の勢力によって途絶えるリスクがあるのなら、こんな国家運営は絶対にできません。地中海の制海権を握る国家はローマが唯一でなければならない、カルタゴは無いものとしなければならない・・・・・・。政治的に冷静に考えると、ローマのとった行動は理にかなっていると思われます。
カルタゴをガリアやスペインと同様の「属州」にし、そこから優秀な人材をローマに登用し、それでローマはより発展する、という風にはならなかった。考えてみるとローマは地中海のまわりをぐるっと一つの国にするなら、極めて強大な国ができるというコンセプトのもとに作られた国家です。もちろん、初めからそのように計画されたのではないが、結果としてそういう方向に進んだ。キーとなるのは海上輸送が(陸上に比べて)圧倒的に効率的で、それが経済発展の要だという事実です。そのための必須事項は地中海の制海権の完全掌握です。たとえばナイル河流域の穀倉地帯をローマの直轄領にし、そこから安価な小麦を大量にローマに運び、その食料に依存して国を運営する。しかもローマ市民に小麦を無料配布までする・・・・・・。海上輸送が敵の勢力によって途絶えるリスクがあるのなら、こんな国家運営は絶対にできません。地中海の制海権を握る国家はローマが唯一でなければならない、カルタゴは無いものとしなければならない・・・・・・。政治的に冷静に考えると、ローマのとった行動は理にかなっていると思われます。
しかしよく考えてみると、カルタゴというフェニキア人の「通商国家」を壊滅させる意味は大いにあるが、都市を破壊し更地にして塩を撒くということの軍事戦略的意味はないはずです。カルタゴ人を完全に追い出し(抹殺し)、ローマ市民を入植させて、地中海に「にらみ」をきかせる軍事拠点とすることもできるのですから・・・・・・。事実、ローマはその後カルタゴに町を再建し、ローマ人を入植さます。
ではなぜカルタゴを抹殺したのか。考えられるのは「みせしめ」でしょう。地中海全域に住むフェニキア人はカルタゴがたどった運命を聞いて震え上がったのではないでしょうか。都市を破壊し更地にするということは、そこにあった墳墓、墓地も完全に破壊するということです。カルタゴ人の死生観は今となっては分からないのですが、もし古代エジプト人のように死後も魂が永遠に生きるという死生観なら「墓地の破壊」はそれを知った死生観を共有する人々とって最大の恐怖でしょう。また死生観がどうであれ、塩野さんが書いているように、塩を撒いて「神々に呪われた地」になったのだから、ローマに反抗すると死後も魂の安住の地なくなる、と古代の人々が考えるのは自然だと思います。
カルタゴの抹殺が「みせしめ」だと思うのは、ギリシャの都市国家・コリント(コリントス)が、まさにカルタゴと同様の運命をたどって抹殺されたからです。「ローマ人の物語」からそのまま引用すると、
とあります。塩野さんによると、そもそもの発端はコリントを訪問したローマの元老院議員たちがコリント市民から無礼な態度で迎えられたからだそうです。まさに「みせしめ」ですね。「ローマを侮辱するとこうなるぞ」という・・・・・・。もちろん背景としてコリントがギリシャの反ローマ活動の拠点だったというようなことがあり「侮辱」は引き金なのだと想像します。しかしこういう「実績」をいったん作っておくとローマはギリシャ全土に対して圧倒的な優越的地位になりますね。「コリントがどうなったか覚えているだろう」という脅し文句、ないしは最後通牒が可能なのだから・・・・・・。コリントにあったはずのコリント人の墳墓も完全消滅したはずです。
コリントが「抹殺」されたのは紀元前146年で、これはカルタゴの「抹殺」と全く同じ年です。偶然なのでしょうが、地中海におけるローマの覇権を確立するために当時の「先進国」に対して徹底的な破壊行動に出た、と考えるのが妥当でしょう。またスペインにおける反乱軍の拠点となったヌマンツァも、カルタゴやコリントと同じ運命をたどりました。思い起こすと町や村全体が住民もろとも抹殺されるという悲惨な「事件」は、20世紀にもフランス(オラドゥール)やチェコ(リディツェ、レジャーキ)で起こりました。経緯とシチュエーションは全く違うけど、これらの理由も「みせしめ」です。
「みせしめ」以外の「非寛容」の理由は「生かしておいてまずいものは殺す」という論理です。カルタゴはまさに生かしておいてはまずい国家だったわけです。カエサルのガリア戦役でのアレシア攻防戦で、ガリアのリーダーであったヴェルチンジェトリックスは、同胞を救おうとして自ら進んで捕らわれの身になりますが、ローマ側はヴェルチンジェトリックスを処刑します。「生かしておいては危険すぎる、有能な人材」(第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前)だったというわけです。「敵をも同化する」と言ってもそれは国レベルの話で、個人レベルでは有能すぎると殺されるわけです。
次に宗教がらみの「非寛容」をみてみると、ユダヤ王国の中心であったエルサレムはユダヤ戦争で壊滅しました。これもローマにとって危険な一神教を抹殺しようとする意味なら「政治的」に納得できます。ユダヤ教徒迫害はその後も続けられ、五賢帝の一人であるハドリアヌス帝は、ユダヤの最後の決起と言われるバール・コクバの乱(131年)を鎮圧したあと、ユダヤ教とその伝統を根絶させるような迫害政策をとりました。エルサレムへの立ち入りやユダヤ教の礼拝・集会は死刑にする、などです。その結果ユダヤ教徒たちは祖国を完全に失ってしまいました(第9巻:賢帝の世紀)。
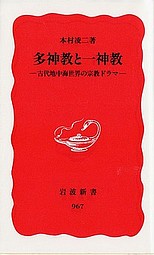 もちろんキリスト教徒も迫害されました。キリスト教徒はローマの国家祭祀や皇帝崇拝を拒否しますね。ローマにとっては危険分子です。「ローマ人の物語」にもその迫害の例がいろいろと出てきます。またどこかの本で読んだ記憶があるのですが、西暦248年のローマ建国一千年祭に参加を拒否したキリスト教徒は全員処刑されたはずです。これはキリスト教徒の迫害というよりも「危険分子の排除」でしょう。ローマの基本的スタンスが理解できます。
もちろんキリスト教徒も迫害されました。キリスト教徒はローマの国家祭祀や皇帝崇拝を拒否しますね。ローマにとっては危険分子です。「ローマ人の物語」にもその迫害の例がいろいろと出てきます。またどこかの本で読んだ記憶があるのですが、西暦248年のローマ建国一千年祭に参加を拒否したキリスト教徒は全員処刑されたはずです。これはキリスト教徒の迫害というよりも「危険分子の排除」でしょう。ローマの基本的スタンスが理解できます。
宗教に関して補足しますと、迫害されたのは他の宗教との共存を拒否する一神教(ユダヤ教、その後にキリスト教)だけではありません。紀元前186年に「ディオニュソス事件」という宗教弾圧が起こりました。これは「ローマ人の物語」には書いてないので、本村凌二・東京大学教授の「多神教と一神教」(岩波新書 2005)から引用します。
ディオニュソス(バッコス)信仰は地中海世界に古くからある信仰ですが、多神教といえども、ローマ社会にとって危険とみなされる信仰は徹底排除されたわけです。
「非寛容」の理由
寛容の意味を考えてみたいと思います。寛容の意味は「寛大で、よく人をゆるし受けいれること。咎めだてしないこと」(広辞苑)です。罪や敵対行動、異質さがあったとしても、咎めず、許し、受け入れるというニュアンスです。これは特定の個人の性質、性格、人格を表現するものとしては(=寛大な人)何ら問題がないと思います。
しかし国家や組織の運営原理としての「寛容」ということを考えてみると、ちょっと違う。こういった国家レベルの運営原理においての「寛容」は「非寛容」と必ずセットのはずです。「寛容の精神で国家や組織を運営する」という宣言は、それだけでは論理的に破綻していて、国家レベルの運営原理にはなりえない。なぜなら「国家や組織が示す寛容」を悪用する人間が必ず出てくるからです。
たとえば「寛容」を利用し、それとは全く逆の専制・専決・排他的体制を作ろうと動く人も出てくるし、「寛容」をうまく利用して富を不当に独占してしまう人が必ず出てきます。「寛容」をいいことに、外面的には国家に服従しながら国家への復讐を狙う人たちも出てくる。人間社会とはそういうものです。「寛容」の精神で国家や組織を運営するが、その運営理念を否定する人や、組織としての統合を危うくするような思想・活動・グループ・集団に対しては徹底的に「非寛容」であるというのが正しい。
「寛容」という、日常的に多くは使わない言葉と国家運営の関係を問題にするのでちょっと分かりにくいのですが、寛容を「自由」という概念に置き換えてみると明瞭になると思います。「自由主義で国家や組織を運営する」とはどういうことでしょうか。
それは「やってはいけない事項、禁止事項が網羅的かつ整合性をもってルール化されていて、それ以外の事項は自由にやってよい」という運営方針です。このルールの中には法律などの明示的なもの以外に、伝統的に決まっている暗黙のルール(しかしながら、それを守らないと集団の中では生活できない実質上の強制、場合によっては明示的ルールよりも強いルール)も含まれます。「禁止事項=非自由」が自由主義の根幹であり、これはちょっと考えてみればあたりまえのことです。現代の自由主義国家の運営はそうなっている。自由主義社会はあくまで「それ以外は自由という社会」なのです。この「それ以外は」というところがミソで、それが人間の創造性をかき立てて国家発展の原動力になる。従ってルールを決め過ぎると発展を阻害することになり、この兼ね合いが難しいわけです。「それ以外は自由」というたった一言を言いたいがために、膨大な時間と試行錯誤のコストを負担してルールと禁止事項を決めているのが自由主義国家です。
しかし、たとえ網羅的に禁止事項が決まっていても、その「抜け穴」を見つけ「アンフェア」な行為で「不当な利益」を得る者が必ず出てきます。そこでルールが改正される。現代は自由主義経済ですが、経済活動おける禁止事項(=非自由)は精緻に決められています。これはたとえば雇用契約における各種のルール(最低賃金、労働時間、年少者の雇用禁止、年間残業時間・・・・・・)だけをみても分かります。象徴的な例を言うと、独占禁止法は自由主義経済を成立させるための最重要ルールなのです。
経済活動におけるルールは先進国を中心にグローバル化=世界共通化が徐々に進んできていますが、一般的に言って禁止事項=非自由の決め方はいろいろなやりかた、流儀があります。従って「自由主義」といっても、組織や国によって違ってきます。「アメリカ合衆国は自由の国だ」という言い方がありますね。それは厳密に言うと「アメリカ合衆国は、アメリカ的自由の国であり、それをはずれる自由は排除される国である」というが正しい理解です。この「排除」されて「非自由」になる部分を指して「アメリカの自由なんて嘘だ」というたぐいのことを言う人がいますが、幼稚だと思います。
「寛容」も「自由」に似ています。「徹底的な非寛容があってこそ、寛容が意味をもつ」のだと思います。ローマの「非寛容」は「敵をも同化して発展する」というローマの隆盛の要因に必然的に付随していたものだと感じました。
その「ローマ人の物語」についての感想を書いてみたいと思います。「ローマ人の物語」は全15巻という大著であり、感想を書き出したらきりがなくなります。ここでは、著者の塩野さんが書いている「ローマの隆盛と滅亡の要因、特に滅亡の要因」に絞って記述したいと思います。なお「ローマ」とは、塩野さんの考えに従って「古代ローマの建国から西ローマ帝国の滅亡までの、ローマという都市を中心(首都)とする国をさすもの」とします。
前提事項-1 歴史を素材とする小説
まず断っておくべき前提事項が3点あります。第1点は「ローマ人の物語」は歴史書というより小説に近いということです。つまりこの本は「過去の歴史研究に基づくローマの歴史、特に政治史・軍事史を素材にし、それを詳細に記述する中で著者の人間観や社会観を述べた小説」と考えた方がよいと思います。従って「ローマ帝国滅亡の原因」というような歴史研究の範疇に属するテーマは本書の第1の主旨ではないわけです。この本はあくまで、随所に記述されている塩野さんの「人間性や社会の本質」に迫ろうとする多様な角度からの洞察にこそ意義があります。その、ほんの数例をあげてみますと、
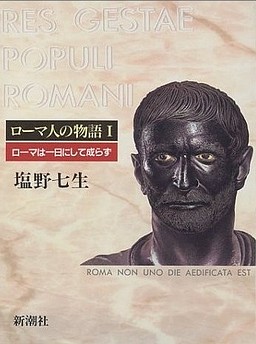
|
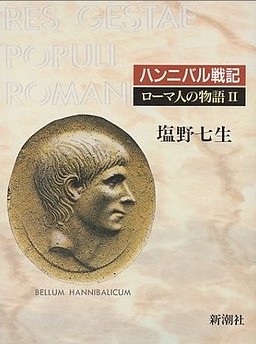
|
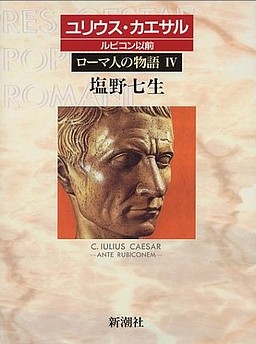
|
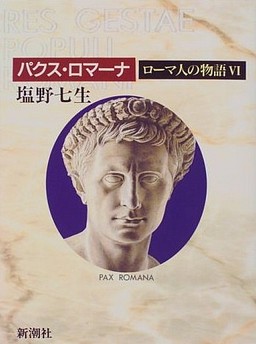
|
| ◆ |
改革の主導者はしばしば新興の勢力よりも、旧勢力の中から生まれるものである。 (第1巻:ローマは一日にして成らず) |
| ◆ |
天才とはその人だけに見える新事実を見ることのできる人ではない。誰もが見ていながら重要性に気づかなかった旧事実に気づく人である。 (第2巻:ハンニバル戦記) |
| ◆ |
言動の明快な人物に人々は魅力を感じる。はっきりするということが責任をとることの証明であるのを感じるからだ。 (第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前) |
| ◆ |
戦争は死ぬためにやるのではなく、生きるためにやるのである。戦争が死ぬためにやるものに変わりはじめると、醒めた理性も居場所を失ってくるから、すべてが狂ってくる。生きるためにやるものだと思っている間は、組織の健全性も維持される。 (第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前) |
| ◆ |
人間だれでも金で買える、とは、自分自身も金で買われる可能性を内包する人のみが考えることである。 (第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前) |
| ◆ |
経済人なら政治を理解しないでも成功できるが、政治家は絶対に経済がわかっていなければならない。 (第6巻:パクス・ロマーナ) |
などです。ほんの一部ですが・・・・・・。
ここで特に取り上げた「洞察」はいずれもローマに対する評言であると同時に、現代ないしは現代日本に向けられたものであるとも言えます。「改革の主導者はしばしば旧勢力の中から生まれる」というのは、まさにその通りです。ペレストロイカを主導したミハイル・ゴルバチョフは、ソ連共産党のエリート中のエリートでした。私の知り合いだったあるアメリカ人は息子にミーシャという名前(本名)をつけましたね。ゴルバチョフの愛称です。それほど彼を尊敬していました。
「言動の明快さが、責任をとることの証明だと人々は感じる」というのは、警告だともとれます。「責任をとる気もないのに、言動だけが明快な人」がいるからです。
「戦争は生きるためにやるのである」というのも「死ぬために戦争をやった(やっている)」人たちへの批判だと思えます。もちろん過去の日本を含めてです。
「人間だれでも金で買えるとは、自分自身も金で買われる可能性を内包する人のみが考えることである」というのは、現代日本のある特定の人たちを痛烈に批判していると聞こえます。「自分は金で買われますよ」と宣言しているに等しい人間を信用する人はいないはずなのですが、現実は不思議なことに信用する人がいるようです。
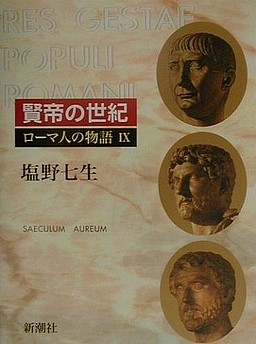
|
| ◆ |
女とはモテたいがために贈り物をする男と、喜んでもらいたい一念で贈り物をする男の違いを敏感に察するものである。 (第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前) |
| ◆ |
女は無視されるのが何よりも傷つくのだ。 (第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前) |
| ◆ |
女とは同性の美貌や富には羨望や嫉妬を感じても、教養や頭の良さには羨望もしなければ嫉妬も感じないものなのだ。 (第9巻:賢帝の世紀) |
なるほど・・・・・・。参考になります。
前提事項-2 政治史と軍事史
話を本題に戻します。注意すべき前提事項の第2点は、国家の興亡を「ローマ人の物語」が主として扱っている政治史や軍事史だけをもとに語ることはできないということです。世界の歴史を振り返ると、特に古代は気候変動などの自然環境要因も文明の衰退の原因になります。仮に気候の寒冷化により年平均気温が3度程度下がり、小麦の収穫量が半分になったとしたら、国家の経済は破綻状態になるはずです。実際、2世紀の後半から3世紀にかけは寒冷期でした。古代ローマ時代とは比べものにならないほど農業技術が発達した1993年の日本で、夏の平均気温がわずか1~2度下がっただけで米が大凶作に陥り、国をあげての大騒動になったのを思い出します。
また2世紀の後半から3世紀にかけてのローマ帝国ではアントニウスの疫病(165-180)や、キプリアヌスの疫病(251-266)などの伝染病が大流行しました。このうち「アントニウスの疫病」は五賢帝の最後の皇帝、マルクス・アウレリウス帝(=カピトリーノ美術館の騎馬像)の時代です。メソポタミアでアルメニアと戦ったローマ軍はユーフラテス河の沿岸のセレウキアで大勝利をおさめます。青柳正規著「ローマ帝国」(岩波書店 2004)によると、その後の経緯は次のようです。
| 『しかし、勝利の美酒に酔いしれていた165年の秋、セレウキアで突然はやりだした疫病は、またたくまに兵士のあいだに蔓延し、ローマ軍はメソポタミアから撤退せざるをえない状況となります。しかも帰還する兵士によって、小アジア、ギシリャ、エジプト、イタリアにこの疫病がひろがったため、帝国各地の人口が3割近くも減少するという深刻な事態となりました。』 |
アントニウスの疫病は天然痘だと言われています。それにしても3割もの人口減少、しかもそれが急激に起こるというのは国家の衰退にもつながりかねない深刻な事態です。「パックス・ロマーナ」においてローマ帝国が防衛・保障してくれる安全は、外敵の進入や内乱からの安全であって、病原菌からの安全ではないのです。あたりまえですが・・・・・・。数百万人規模が死亡したとされるこれら疫病の蔓延は、当然社会不安を引き起こします。病気の原因が神の怒りだとする人々からすると、神の怒りをなだめられない皇帝は皇帝の資格がないわけで、皇帝に対する不信感にもつながるでしょう。皇帝が神格化されていればなおさらです。
さらに経済の観点から言うと、No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で紹介したように、基軸通貨であったデナリウス銀貨の銀の含有率は紀元64年には93%でしたが、265年には5%までに下落しました。またこの間に小麦の価格は80倍にも高騰したのです。こういった貨幣価値の暴落や物価の暴騰・インフレ(ないしはスタグフレーション)は国の経済をマヒさせます。物資の流通は滞り、物々交換が横行し、農業の生産性は低下するはずです。
以上のような環境史や経済史と国の興亡の関係、特に環境史は「ローマ人の物語」のスコープ外であることには注意が必要です。
前提事項-3 巨大組織の崩壊
第3の注意点は、巨大システム・組織の衰退の真の原因は1つであることはまれであり、たいていは複数の要因が複雑にからみあった中で起こるということです。しかも「原因」は別の要因から派生した「結果」でもあり、また「結果」が「原因」を作り出します。その上、一つの衰退の要因を取り除こうとすると同時に国家の「強み」や「アイデンティティー」をなくすことになり「にっちもさっちも行かなくなる」というようなことがあるわけです。ガン細胞だけを手術で切除するようにはいかないのです。
ローマの隆盛:「同化」と「隷属化」
以上のような3点が前提条件ということになりますが、これらに注意しつつ、ローマを隆盛と衰退、特に衰退に導いた重要だと思える要因について読後感を書いてみたいと思います。まず衰退を考える前に、衰退の前提となるローマの発展・隆盛についてです。
ローマの発展・隆盛に関しては、征服した異民族や異文化もローマに迎えて「同化」したということが大きく、その具体的な数々の事例が本書には書かれています。人材を登用し重要なポストにつけたような例はたくさんあり、(記憶が正しければ)元老院議員になった例さえある。少なくとも元老院議員になるまでの道は制度的に開かれていたわけです。二重市民権(二重国籍)まで認められていたようです。こういった「開放性」に関してローマは非常に進んでいて、これが隆盛の大きな原因だということは本書を読んで納得できました。
この「同化」というのも、別の観点からみれば「隷属化」だというのは注意した方がよいと思います。ただし単に「奴隷状態になる」というのとはちょっと違う。貧しくて食うや食わずの生活をしていた「蛮族」があったとします。その「蛮族」がローマと戦争をして征服されたとします。その結果として奴隷に近いような状態でローマに「収奪」されたとしても、ローマの文明と経済力を背景とするシステムの中に組み入れられたとしたら、農業生産力は向上し、結果として生活は以前より安定・向上し「蛮族」としては「うれしい」のではないでしょうか。しかもローマ市民権を得る道や、可能性としては元老院議員になる道まで開けているとしたらです。ローマは征服した属州に次々と「ローマ式都市」を建設しました。道路が舗装され、下水道は完備し、公衆浴場もあり、外敵の進入をさせない強固な防壁の「近代的」都市です。都市間をネットワークで結ぶ道路もある。生活がそれなりに安定した上に近代的な都市に住める期待もあるなら「蛮族」は「喜んでローマに隷属した」という面があるのではと思います。しかも奴隷同士の殺し合いを野外劇場で観戦するという、これ以上は考えられないような「刺激的娯楽」もある。
これはローマの支配層からみると「文明の力」を利用した非常に巧妙な支配システムであると言えます。征服した民が「不満を言わずに奴隷なみに働いて」くれたら、そして「喜んで収奪されて」くれたら、支配する側にとってこんなにうれしいことはない。
ローマの発展と領土拡大のプロセスを読んでいて、ふと、有名なノンフィクション作品「ああ、野麦峠」(山本茂実 著。角川文庫。1977。原著は1968)を思い出しました。明治末期から昭和初期にかけての時代、生糸は日本の非常に重要な輸出品です。そこで資本家は信州の諏訪や岡谷に製糸工場を作るわけです。そして飛騨地方の農家の娘をつのって「工女」として働かせる。野麦峠は飛騨と信州を分ける峠ですね。その製糸工場では夜10時までというような長時間労働がある。体をこわすと即解雇で、何の保証もない。何よりも労働の成果(工女たちが紡いだ絹糸)の量と質が厳しく検査され、それで賃金が決まる。「百円工女」と言われた年間賃金100円のトップクラスの人はごく少数で、多くの工女の賃金は30円~40円程度であり、20円の人もいる。この状況は一面からみると「資本家ないしは工場経営者が、無垢な農家出身の女性労働者を競争させ、長時間労働で搾取している」わけです。「ああ、野麦峠」の副題は「ある製糸工女哀史」となっていますが、そのタイトルそのままです。
しかし著者の山本さんはフェアに書いています。500人以上の元工女にインタビューすると、食事は「うまい」が90%、労働は「普通」が75%、賃金は「高い」が70%なのです。さすがに検査は「泣いた」が90%、病気への対応は「普通」が50%で「冷遇」が40%となっています。しかし総括では「行ってよかった」が90%なのです。その理由は「工女哀史」ではあっても農家の仕事よりは楽だからです。朝5時から夜10時まで女性を働かせるのはひどいと言っても、農家では夜10時、11時まで夜なべをすることがあるわけだし、朝も日の出前から農作業です。工女は年1回の休暇のときに稼いだお金を飛騨の実家に持って帰れます。これが非常に大きい。一家の一年の稼ぎより、一人の工女が持って帰るお金の方が多かったという例さえ出てきます。親に喜んでもらいたい一心で働く。これはつらい労働に耐える極めて大きなモチベーションになります。製糸工場を「工女哀史の舞台となった搾取システムである」と切って捨てるのは簡単ですが、飛騨の農家の娘にとって何が幸せだったのかは別問題だと思います。
「野麦峠」的状況はその後も繰り返されています。以前、はやりました。中国の上海あたりに日本企業が工場を作る。そして四川省などの農村地帯から女性労働者をリクルートする。彼女たちは時間給80円とか、為替レートで換算した日本の水準からすると信じられないような「低賃金」で働くわけです。労働集約商品を作っている日本の企業からするとコストが劇的に下がり、日本に輸入して大きな利益が得られます。一方、農村地帯出身の女性労働者の方からみると、そうして頑張って5年間働いて故郷に帰れば、貯めたお金で両親にささやかな家をプレゼントできるわけです。こんなに「うれしい」ことはない。
現代は「奴隷」とか「属州」とか、そういうものは一切ないわけですが、そんなことに頼らなくてもローマ発展のメカニズムと同じことが「差異」を利用して合法的にできる。むしろそれをやった人が賞賛される。そういう感じがします。但し、ロジカルに考えてみると分かるように、このメカニズムは「差異」がなくなったときに終わりです。ローマ帝国に置き換えてみると、帝国の領土が固定化し、新しい奴隷(低コスト労働力)の獲得がなくなり、多くの人々が生活に満足するようになり、それ以上のローマ化を望まなくなった時に終わりです。それ以上の発展のためには、別のメカニズムが必要になる。
野麦峠と中国工場の話を書きましたが、これはグローバルに場所を変え「差異」を求めて繰り返えされ続けると思います。
「寛容」と「非寛容」
古代ローマの話です。ローマの隆盛の根幹にあるのは「寛容」だと、塩野さんは規定しています。確かにそうで、ローマが征服して属州とした国から人材を登用し重要なポストについたような例はいっぱい出てきます。こういった「敵をも同化する寛容さ」がローマ発展の原動力となったというのは、まさにその通りだと感じました。ギリシャなどの他国の優れた文化を積極的に取り入れたりするのも寛容の精神だと言えるかもしれません。もっとも文化は「高いところから低いところへ流れる」のが自然なので、ローマは高度なギリシャ文化に学んだのだとは思いますが・・・・・・。いずれにせよ、このような「寛容さ」は当時の他国にはなく、だからローマは発展した。これは納得できました。
しかし「ローマ人の物語」全体から受けるもう一つの印象は「ローマは寛容と非寛容の使い分け」で成長したという感じなのです。俗な言い方では「アメとムチ」でしょうか。「寛容」の一方で寛容とは正反対の「非寛容」もまたローマの特質だったと読み取れるのです。
「非寛容」の典型はカルタゴの抹殺です。カルタゴとローマの戦いは第2巻:ハンニバル戦記に詳述されているように幾多の紆余曲折があったわけですが、最終的に第3次ポエニ戦争でローマはカルタゴの市民を殺戮し、あるいは奴隷として売り飛ばし、町に火を放って焼き尽くして「更地」にし、そこに塩を撒いて二度と植物が生えないようにしました。
陥落後のカルタゴは、城壁も神殿も一般の家も、市場の建物も船着場も倉庫も、何もかもが元老院の指令どおりに破壊しつくされた。石塊と土くれだけになった地表は、犂(すき)で平らにならされ、ローマ人が神々に呪われた地にするやり方で、一面に塩が撒かれた。不毛地帯に一変したカルダゴしか見ない人ならば、つい先頃まではこの地に、地中海の富を集めた大都市が存在していたとは思えなかったであろう。 |
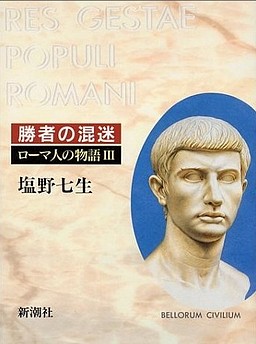 カルタゴをガリアやスペインと同様の「属州」にし、そこから優秀な人材をローマに登用し、それでローマはより発展する、という風にはならなかった。考えてみるとローマは地中海のまわりをぐるっと一つの国にするなら、極めて強大な国ができるというコンセプトのもとに作られた国家です。もちろん、初めからそのように計画されたのではないが、結果としてそういう方向に進んだ。キーとなるのは海上輸送が(陸上に比べて)圧倒的に効率的で、それが経済発展の要だという事実です。そのための必須事項は地中海の制海権の完全掌握です。たとえばナイル河流域の穀倉地帯をローマの直轄領にし、そこから安価な小麦を大量にローマに運び、その食料に依存して国を運営する。しかもローマ市民に小麦を無料配布までする・・・・・・。海上輸送が敵の勢力によって途絶えるリスクがあるのなら、こんな国家運営は絶対にできません。地中海の制海権を握る国家はローマが唯一でなければならない、カルタゴは無いものとしなければならない・・・・・・。政治的に冷静に考えると、ローマのとった行動は理にかなっていると思われます。
カルタゴをガリアやスペインと同様の「属州」にし、そこから優秀な人材をローマに登用し、それでローマはより発展する、という風にはならなかった。考えてみるとローマは地中海のまわりをぐるっと一つの国にするなら、極めて強大な国ができるというコンセプトのもとに作られた国家です。もちろん、初めからそのように計画されたのではないが、結果としてそういう方向に進んだ。キーとなるのは海上輸送が(陸上に比べて)圧倒的に効率的で、それが経済発展の要だという事実です。そのための必須事項は地中海の制海権の完全掌握です。たとえばナイル河流域の穀倉地帯をローマの直轄領にし、そこから安価な小麦を大量にローマに運び、その食料に依存して国を運営する。しかもローマ市民に小麦を無料配布までする・・・・・・。海上輸送が敵の勢力によって途絶えるリスクがあるのなら、こんな国家運営は絶対にできません。地中海の制海権を握る国家はローマが唯一でなければならない、カルタゴは無いものとしなければならない・・・・・・。政治的に冷静に考えると、ローマのとった行動は理にかなっていると思われます。しかしよく考えてみると、カルタゴというフェニキア人の「通商国家」を壊滅させる意味は大いにあるが、都市を破壊し更地にして塩を撒くということの軍事戦略的意味はないはずです。カルタゴ人を完全に追い出し(抹殺し)、ローマ市民を入植させて、地中海に「にらみ」をきかせる軍事拠点とすることもできるのですから・・・・・・。事実、ローマはその後カルタゴに町を再建し、ローマ人を入植さます。
ではなぜカルタゴを抹殺したのか。考えられるのは「みせしめ」でしょう。地中海全域に住むフェニキア人はカルタゴがたどった運命を聞いて震え上がったのではないでしょうか。都市を破壊し更地にするということは、そこにあった墳墓、墓地も完全に破壊するということです。カルタゴ人の死生観は今となっては分からないのですが、もし古代エジプト人のように死後も魂が永遠に生きるという死生観なら「墓地の破壊」はそれを知った死生観を共有する人々とって最大の恐怖でしょう。また死生観がどうであれ、塩野さんが書いているように、塩を撒いて「神々に呪われた地」になったのだから、ローマに反抗すると死後も魂の安住の地なくなる、と古代の人々が考えるのは自然だと思います。
カルタゴの抹殺が「みせしめ」だと思うのは、ギリシャの都市国家・コリント(コリントス)が、まさにカルタゴと同様の運命をたどって抹殺されたからです。「ローマ人の物語」からそのまま引用すると、
ローマ軍によって、コリントは徹底的に破壊され、美術品は没収されてローマに送られ、住民は老若男女を問わず奴隷に売られた。すきとくわで地表をならし、街そのものが消滅してしまった。 |
とあります。塩野さんによると、そもそもの発端はコリントを訪問したローマの元老院議員たちがコリント市民から無礼な態度で迎えられたからだそうです。まさに「みせしめ」ですね。「ローマを侮辱するとこうなるぞ」という・・・・・・。もちろん背景としてコリントがギリシャの反ローマ活動の拠点だったというようなことがあり「侮辱」は引き金なのだと想像します。しかしこういう「実績」をいったん作っておくとローマはギリシャ全土に対して圧倒的な優越的地位になりますね。「コリントがどうなったか覚えているだろう」という脅し文句、ないしは最後通牒が可能なのだから・・・・・・。コリントにあったはずのコリント人の墳墓も完全消滅したはずです。
コリントが「抹殺」されたのは紀元前146年で、これはカルタゴの「抹殺」と全く同じ年です。偶然なのでしょうが、地中海におけるローマの覇権を確立するために当時の「先進国」に対して徹底的な破壊行動に出た、と考えるのが妥当でしょう。またスペインにおける反乱軍の拠点となったヌマンツァも、カルタゴやコリントと同じ運命をたどりました。思い起こすと町や村全体が住民もろとも抹殺されるという悲惨な「事件」は、20世紀にもフランス(オラドゥール)やチェコ(リディツェ、レジャーキ)で起こりました。経緯とシチュエーションは全く違うけど、これらの理由も「みせしめ」です。
「みせしめ」以外の「非寛容」の理由は「生かしておいてまずいものは殺す」という論理です。カルタゴはまさに生かしておいてはまずい国家だったわけです。カエサルのガリア戦役でのアレシア攻防戦で、ガリアのリーダーであったヴェルチンジェトリックスは、同胞を救おうとして自ら進んで捕らわれの身になりますが、ローマ側はヴェルチンジェトリックスを処刑します。「生かしておいては危険すぎる、有能な人材」(第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以前)だったというわけです。「敵をも同化する」と言ってもそれは国レベルの話で、個人レベルでは有能すぎると殺されるわけです。
次に宗教がらみの「非寛容」をみてみると、ユダヤ王国の中心であったエルサレムはユダヤ戦争で壊滅しました。これもローマにとって危険な一神教を抹殺しようとする意味なら「政治的」に納得できます。ユダヤ教徒迫害はその後も続けられ、五賢帝の一人であるハドリアヌス帝は、ユダヤの最後の決起と言われるバール・コクバの乱(131年)を鎮圧したあと、ユダヤ教とその伝統を根絶させるような迫害政策をとりました。エルサレムへの立ち入りやユダヤ教の礼拝・集会は死刑にする、などです。その結果ユダヤ教徒たちは祖国を完全に失ってしまいました(第9巻:賢帝の世紀)。
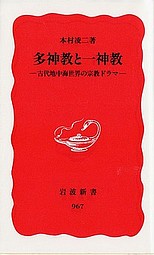 もちろんキリスト教徒も迫害されました。キリスト教徒はローマの国家祭祀や皇帝崇拝を拒否しますね。ローマにとっては危険分子です。「ローマ人の物語」にもその迫害の例がいろいろと出てきます。またどこかの本で読んだ記憶があるのですが、西暦248年のローマ建国一千年祭に参加を拒否したキリスト教徒は全員処刑されたはずです。これはキリスト教徒の迫害というよりも「危険分子の排除」でしょう。ローマの基本的スタンスが理解できます。
もちろんキリスト教徒も迫害されました。キリスト教徒はローマの国家祭祀や皇帝崇拝を拒否しますね。ローマにとっては危険分子です。「ローマ人の物語」にもその迫害の例がいろいろと出てきます。またどこかの本で読んだ記憶があるのですが、西暦248年のローマ建国一千年祭に参加を拒否したキリスト教徒は全員処刑されたはずです。これはキリスト教徒の迫害というよりも「危険分子の排除」でしょう。ローマの基本的スタンスが理解できます。宗教に関して補足しますと、迫害されたのは他の宗教との共存を拒否する一神教(ユダヤ教、その後にキリスト教)だけではありません。紀元前186年に「ディオニュソス事件」という宗教弾圧が起こりました。これは「ローマ人の物語」には書いてないので、本村凌二・東京大学教授の「多神教と一神教」(岩波新書 2005)から引用します。
このころひそかにディオニュソス祭礼の密儀がイタリア半島に浸透している。この祭礼は破廉恥とも見なされる狂騒をともなっており、それはローマの社会の健全さと公共の秩序を脅かすように思われた。元老院はある醜聞をきっかけに、イタリア全土におけるディオニュソス祭礼を禁ずることを決議する。祭司の逮捕、祭礼集会の取締り、神殿の破壊が行われ、信徒たちの大恐慌のなかで、七千人が処刑された、と歴史家リウィウス(前59 - 後17)はいう。 |
ディオニュソス(バッコス)信仰は地中海世界に古くからある信仰ですが、多神教といえども、ローマ社会にとって危険とみなされる信仰は徹底排除されたわけです。
「非寛容」の理由
寛容の意味を考えてみたいと思います。寛容の意味は「寛大で、よく人をゆるし受けいれること。咎めだてしないこと」(広辞苑)です。罪や敵対行動、異質さがあったとしても、咎めず、許し、受け入れるというニュアンスです。これは特定の個人の性質、性格、人格を表現するものとしては(=寛大な人)何ら問題がないと思います。
しかし国家や組織の運営原理としての「寛容」ということを考えてみると、ちょっと違う。こういった国家レベルの運営原理においての「寛容」は「非寛容」と必ずセットのはずです。「寛容の精神で国家や組織を運営する」という宣言は、それだけでは論理的に破綻していて、国家レベルの運営原理にはなりえない。なぜなら「国家や組織が示す寛容」を悪用する人間が必ず出てくるからです。
たとえば「寛容」を利用し、それとは全く逆の専制・専決・排他的体制を作ろうと動く人も出てくるし、「寛容」をうまく利用して富を不当に独占してしまう人が必ず出てきます。「寛容」をいいことに、外面的には国家に服従しながら国家への復讐を狙う人たちも出てくる。人間社会とはそういうものです。「寛容」の精神で国家や組織を運営するが、その運営理念を否定する人や、組織としての統合を危うくするような思想・活動・グループ・集団に対しては徹底的に「非寛容」であるというのが正しい。
「寛容」という、日常的に多くは使わない言葉と国家運営の関係を問題にするのでちょっと分かりにくいのですが、寛容を「自由」という概念に置き換えてみると明瞭になると思います。「自由主義で国家や組織を運営する」とはどういうことでしょうか。
それは「やってはいけない事項、禁止事項が網羅的かつ整合性をもってルール化されていて、それ以外の事項は自由にやってよい」という運営方針です。このルールの中には法律などの明示的なもの以外に、伝統的に決まっている暗黙のルール(しかしながら、それを守らないと集団の中では生活できない実質上の強制、場合によっては明示的ルールよりも強いルール)も含まれます。「禁止事項=非自由」が自由主義の根幹であり、これはちょっと考えてみればあたりまえのことです。現代の自由主義国家の運営はそうなっている。自由主義社会はあくまで「それ以外は自由という社会」なのです。この「それ以外は」というところがミソで、それが人間の創造性をかき立てて国家発展の原動力になる。従ってルールを決め過ぎると発展を阻害することになり、この兼ね合いが難しいわけです。「それ以外は自由」というたった一言を言いたいがために、膨大な時間と試行錯誤のコストを負担してルールと禁止事項を決めているのが自由主義国家です。
しかし、たとえ網羅的に禁止事項が決まっていても、その「抜け穴」を見つけ「アンフェア」な行為で「不当な利益」を得る者が必ず出てきます。そこでルールが改正される。現代は自由主義経済ですが、経済活動おける禁止事項(=非自由)は精緻に決められています。これはたとえば雇用契約における各種のルール(最低賃金、労働時間、年少者の雇用禁止、年間残業時間・・・・・・)だけをみても分かります。象徴的な例を言うと、独占禁止法は自由主義経済を成立させるための最重要ルールなのです。
経済活動におけるルールは先進国を中心にグローバル化=世界共通化が徐々に進んできていますが、一般的に言って禁止事項=非自由の決め方はいろいろなやりかた、流儀があります。従って「自由主義」といっても、組織や国によって違ってきます。「アメリカ合衆国は自由の国だ」という言い方がありますね。それは厳密に言うと「アメリカ合衆国は、アメリカ的自由の国であり、それをはずれる自由は排除される国である」というが正しい理解です。この「排除」されて「非自由」になる部分を指して「アメリカの自由なんて嘘だ」というたぐいのことを言う人がいますが、幼稚だと思います。
「寛容」も「自由」に似ています。「徹底的な非寛容があってこそ、寛容が意味をもつ」のだと思います。ローマの「非寛容」は「敵をも同化して発展する」というローマの隆盛の要因に必然的に付随していたものだと感じました。
(以降、続く)
No.19 - ベラスケスの「怖い絵」 [本]
 No.7「ローマのレストランでの驚き」の冒頭に、ローマで訪れたカピトリーノ美術館の「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」を掲げましたが「その日はローマのいろいろの場所を訪れた」とも書きました。その訪れた場所の一つが、ドーリア・パンフィーリ宮殿です。
No.7「ローマのレストランでの驚き」の冒頭に、ローマで訪れたカピトリーノ美術館の「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」を掲げましたが「その日はローマのいろいろの場所を訪れた」とも書きました。その訪れた場所の一つが、ドーリア・パンフィーリ宮殿です。ドーリア・パンフィーリ宮殿はローマの中心部、ヴェネツィア広場の北に位置し、パンテオンからも近い位置にあります。ここはパンフィーリ家所有の宮殿であり、現在も住居とし使われていて、その一部が美術館として公開されています。ここにはカラヴァッジョの初期の絵画「マグダラのマリア」と「エジプトへの逃避途中の休息」があります。
しかし何といってもこの美術館の「目玉」は、絵画史上における肖像画の傑作、最高傑作と言ってもいい絵画作品です。ベラスケス(1599-1660) が描いた「インノケンティウス十世の肖像」(1650) です。スペイン王室の宮廷画家だったベラスケスがイタリアに招かれ、当時75歳のローマ教皇を描いたものです。
インノケンティウス十世の肖像 [1650]

|
|
ベラスケス:インノケンティウス十世の肖像
(ローマ:ドーリア・パンフィーリ美術館) |
「インノケンティウス十世の肖像」については、中野京子さんがその著書「怖い絵」(2007。朝日出版社)で「完璧」と思える解説を書いています。この絵について触れようとすると、中野さんの文章の引用は避けて通れないでしょう。
|
「フェリペ4世」「マルガリータ王女」などの代表的な肖像モチーフでベラスケスを紹介した上で、その人間観察力は「インノケンティウス十世の肖像」でも遺憾なく発揮されていると、中野さんは言います。「インノケンティウス十世は神に仕える身というより、どっぷり俗世にまみれた野心家であることが暴露されている」と・・・・・・。このあとに続く文章で、この肖像画が的確に描写されています。
|
実際に美術館でこの絵を見ると「衝撃」を受けるのですが、なぜ衝撃なのかが余すことなく書かれています。引用した中野さんの文章だけを読むと信じられないのですが、この絵はまぎれもない「ローマ教皇」を描いたものなのです。私もしばしこの絵の前で立ち止まっていました。美術館においてこの絵は、この絵だけが飾られている小さな部屋にあったと記憶しています。明らかに「特別扱い」です。それだけ美術館としても随一の「傑作」という評価なのでしょう。
伝えられている逸話によると、肖像画を注文した本人であるインノケンティウス十世は、完成品をみて「真を穿(うが)ちすぎている」と漏らしたといいますが、中野さんは「真偽はわからない」と書いています。
|
この絵の強烈な印象は一言で言うと、その「迫真性」、つまり「真に迫っている感じ」です。
迫真性の理由
なぜ私たちはこの絵を見るとき「迫真性」を感じるのか、考えてみると不思議です。私たちはインノケンティウス十世がどういう人間であったのか、どういう性格であったのかを何も知らないのです。もちろん歴史家であればある程度調べられるでしょう。中野さんも調べて書いているのかも知れません。しかしほかでもないローマ教皇が、中野さんが描写した通りの人間であるという「公式記録」なり「公式文書」はありえないはずだし、私的文書でそういうものがあったとしても、極く少ないのではないでしょうか。教皇に対する評言としては「書くのがはばかられる」ことだからです。各種資料から推定はできるかもしれませんが・・・・・・。とにかく我々にとっては、教皇が「ふさわしくない高位へ政治力でのし上がった人間、いっさいの温かみの欠如した人間」かどうかは「分からない」というのが実態です。
にもかかわらず、この絵が真実に迫っている、真実をえぐりだしている、と見る人が感じて衝撃をうけるのは、次の2つの心の働きによると思います。
| A: | この絵を見る人は、描かれた人物が「ふさわしくない高位へ政治力でのし上がった人間」だと、強くほとんど確信的に推測してしまう。 |
| B: | その「ふさわしくない高位へ政治力でのし上がった人間」を、余すところなくキャンバスに暴き出し、定着させたベラスケスの力量に驚く。 |
という、A + B の2つの心の動きです。Aで推測した人物と、実際に目の前にした人物Bの一致に驚く。だから迫真性に衝撃を受ける。
しかし、言うまでもなくAもBも画家が作り出したものです。私たちはベラスケスに誘導され、それに従い、そして驚いているわけです。
人は、ある人物を一瞥して「どういう人物かの推定をする」という心の働きに慣れきっています。人間が社会を構成し生きていくための「本能」のようなものでしょう。人は「人を一瞥して、その人が既知の誰かを特定する」ことと共に、「既知の人でない場合は、どういうタイプの人間かを一瞥で推定する」ことを無意識にやっています。
人は見かけによらぬもの、という諺があります。「一瞥での人物推定」と「本当の人物」が違っていることを言っているのですが、こういう諺があるということは裏を返すと「多くの場合、人は見かけによる」ということだと思います。もっと正確に言うと「実際は分からないけど、人は見かけによると思って行動して、多くの場合間違いはない」ということです。
|
中野京子さんの「怖い絵」3冊のシリーズでは、合計60点の絵が紹介されています。その中でも「インノケンティウス十世の肖像」に関する文章は凝っています。それは、この絵に刺激されて制作された20世紀の画家、フランシス・ベーコンの「ベラスケス《インノケンティウス十世像》による習作」の紹介を通してベラスケスのこの絵を紹介するという、ちょっと複雑な構造になっていることです。ベーコンの絵は、ベラスケスの絵を知っている人にとっては一目で「ベラスケスからインスピレーションを受けた」と分かるようになっている絵で、これはこれでかなり「怖い」絵です。
しかし、なのです。ベーコンの絵の「怖さ」をさんざん解説したあと、最後に中野さんはどんでん返しのように書いています。「真に怖いのはベラスケスの絵の方だ」と。
怖い絵
中野京子さんの「怖い絵」は、続編の「怖い絵2」(2008)「怖い絵3」(2009)と併せて3冊のシリーズになっていて、絵画を見る新しい視点を提供した本として大変話題になりました。
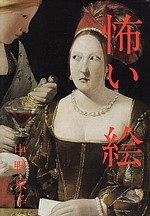
|
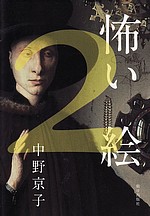
|
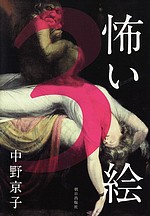
|
| 怖い絵(2007) |
怖い絵2(2008) |
怖い絵3(2009) |

| |||
| (パリ:オルセー美術館) | |||

| |||
|
(ダルムシュタット: ヘッセン州立美術館) | |||
| 余談になりますが、このブリューゲルの絵で連想するのが、ロッシーニのオペラ「泥棒かささぎ」ですね。このオペラのヒロインは銀食器を盗んだ罪(=冤罪)で死刑にされそうになりますが、その銀食器はかささぎが盗んで鐘楼に隠していたことが分かり、ハッピーエンドで終わります。 |
絵画を見る新たな視点を提出して秀逸なのは、インノケンティウス十世の肖像を描いたベラスケスの「最大傑作」である「ラス・メニーナス」のページです。
ラス・メニーナス(宮廷の召使いたち) [1656]
ラス・メニーナスは、スペインのフェリペ4世の宮廷おけるベラスケスのアトリエを描いた絵で、マリガリータ王女を中心に、画家本人を含む9人の人物が登場します。鏡に写った国王夫妻を入れると11人です。歴史調査によって、召使いを含む登場人物の名前はすべて判明しています。

|
|
ベラスケス:ラス・メニーナス
(プラド美術館) |
プラド美術館の「至宝」であるこの絵に関しては、ありとあらゆる評論が書かれてきました。しかし中野さんが「怖い絵」で着目するのは、右下にまどろんでいる犬のそばに描かれた2人の小人症の道化です。犬に足を乗せている少年はニコラス・ペルトゥサトという名前で、画面が途切れているために分かりにくいのですが、彼の背骨は曲がっています。その隣の正面を向いた女性はマリア・バルボラと言い、頭部と身長のアンバランスによって矮(わい)人症の女性だとすぐに分かります。
|
そして、こういう紹介をするときの中野さんの文章の常として「道化」の歴史的背景が明らかにされます。ここが核心です。
|
ラス・メニーナスに描かれたバルボラは贅沢な衣装を着ています。つまり衣食住には恵まれていたようです。それは王侯貴族の「装飾」ないしは「ステイタス・シンボル」、「富の誇示」として「飼われて」いたからなのです。
|
ベラスケスが描いた「矮人」の絵「セバスティアン・デ・モーラ」は、2002年に国立西洋美術館で開催された「プラド美術館展」で展示されました。この絵を中野さんは「ラス・メニーナス」の解説に関連して、以下のように紹介しています。
|
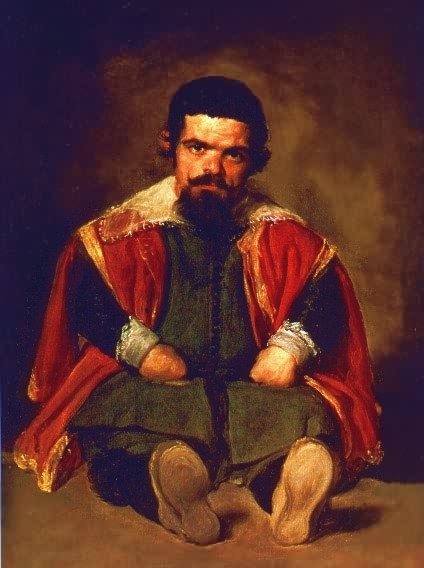
|
|
セバスティアン・デ・モーラ (プラド美術館) |
そして再びラス・メニーナスに戻って、この絵の「怖さ」がまとめられています。ここが結論です。
|
慰み者

|
|
バルタサール・カルロス王子 (ボストン美術館) |
またプラド美術館の以下の3枚の絵も「矮人」の絵です。ディエゴ・ディ・アセドの絵は、いっしょに描かれている本の大きさで、体の大きさが推測できます。ちなみに、フランシスコ・レスカーノはバルタサール・カルロス王子に仕えた人物で、ボストン美術館の絵の人物です(プラド美術館の公式カタログによる)。

|
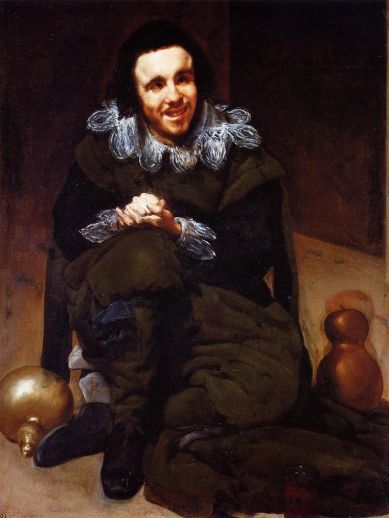
|

|
| ディエゴ・デ・アセド | ファン・カラバーサス | フランシスコ・レスカーノ |
| (これら3枚の絵は、いずれもプラド美術館) | ||
慰み者の存在意義は、私にだって推測できます。最大の存在意義は、中野さんも書いているように「人に優越感を与える」ことですね。主人は自分の奴隷に言うでしょう。「お前は奴隷だ。しかし、あの慰み者よりはまともな人間だ。そうだろう」と・・・・・・。「人に優越感を与える」ための存在を意図的に作り出し、それを支配の道具にする。こういったことは歴史上いっぱいあります。日本史にもあります。
我々がベラスケスの描く「慰み者」を見て直感的に思うのは「画家は慰み者に共感を抱いている」ということです。「慰み者」を描くということは、宮廷に飼われている高価な犬や猫(=愛玩用動物)を描くに等しいという言い方もできると思います。しかし犬を描く理由は、画題としての動物がもつ美しさや愛らしさでしょう。しかし慰み者は「通常とは外見が違う」人間です。そのような人間をわざわざ描く理由は「共感」ではないだろうか・・・・・・。これは中野さんも同意見のようです。
さらに思い出すことがあります。ラス・メニーナス以下、ボストン美術館の絵以外の5点はプラド美術館にあるのですが、この5点の絵は同じ部屋に「かためて」展示してあるのです。ラス・メニーナスを中心にし、左にディエゴ・ディ・アセド、ファン・カラバーサスの2枚、右にフランシスコ・レスカーノ、セバスティアン・デ・モーラの2枚というように・・・・・・。もちろん展示方法はいつでも変更できるので、現在もそうかは分かりません。しかしこういう展示方法を見るにつけ、ラス・メニーナスはマリア・バルボラが画題の中心のように思えてきます。
「ベラスケスがラス・メニーナスで真に描きたかったのはマリア・バルボラ。彼女がこの絵の真の主役」と、中野さんは言いたかったのかもしれません。しかしそこまでは書かなかった。というより、そこまで書くと「推測のしすぎ」になるので、まっとうな「絵の評論」としては書けなかった。だから「バルボラの存在感は王女を圧倒してはいないだろうか」という表現になった。
しかしたとえ「主役」ではないにせよ、きわめて重要な位置であることは間違いないと思います。ラス・メニーナスをもう一度よく見ると、正面をしっかりと見据えているのは明らかに3人です。画家自身、マルガリータ王女、マリア・バルボラの3人で、この3人は「同じ種類の」表情と態度をしているように見えます。身分・地位が全く違うので、その表現形態は違いますが・・・・・・。ラス・メニーナスこの3人が主役なのだと思います。この3人を主役にすることで、宮廷画家であったベラスケスが、自らが生きたあかしを後世に伝えようとしたのがこの絵だ、と直感します。
奴隷
ラス・メニーナスの歴史的背景で忘れてはならないのは、スペインの王宮には数百人の奴隷がいたと明記されていることです。この時代の「奴隷」はどうだったのでしょうか。近代における「奴隷」と聞いて、まず誰もが思い出すのはアメリカ大陸の奴隷の歴史だと思います。ちょうど、No.18 「ブルーの世界」で、18世紀のサウス・カロライナ植民地における藍の栽培と染料製造プランテーションの話を書いたところです。ちょっとアメリカの奴隷制度を振り返ってみたいと思います。
ベラスケスが亡くなったのは17世紀中頃の1660年です。この同じ年にボストンで絞首刑になった女性がメアリー・ダイアーでした( No.6「メアリー・ダイアー」参照)。この頃、北アメリカ大陸東海岸のヴァージニア植民地では、すでにタバコを栽培する大規模農場(プランテーション)が作られていました。当初、ここでの労働は旧大陸からきた白人の「年季奉公人」か、ないしは奴隷化されたネイティブ・アメリカンの人たちでしたが、ちょうど17世紀の後半からアフリカから連れて来られた黒人奴隷に徐々に置き換えられていったのです。
ヴァージニア植民地はアメリカ独立と深い因縁があります。1619年、ここでイギリス領植民地の代表が集まった最初の植民地議会が開催されました。アメリカの議会制の始まりだと言われています。そしてヴァージニアに最初の奴隷船が到着したのがその1619年です。アメリカのイギリス領植民地においては、共和制議会政治と奴隷制は同時に始まったわけです。後の18世紀におけるアメリカ独立のキーパーソンであるジョージ・ワシントンとトマス・ジェファーソンは、いずれもヴァージニア最大級のタバコ・プランテーションのオーナーです。付け加えると、No.18 「ブルーの世界」で書いたように、18世紀に発展したサウス・カロライナ植民地の藍の栽培とインディゴ染料の生産プランテーションも、イライザ・ルーカスとピンクニー家を通してアメリカ独立と深く結びついています。
アメリカの奴隷制にはその前史があります。17世紀の当時、すでにポルトガルやスペイン、さらにはオランダ、イギリス、フランスなどのヨーロッパ各国は競って「奴隷貿易」に精を出していました。だからこそ、イギリスの植民地であったアメリカ東海岸にまで奴隷制が広がってきたのです。奴隷貿易の先鞭をつけたのはポルトガルで、すでに15世紀末、1486年にポルトガル王室は「リスボン奴隷局」を設立しています。奴隷商人たちはアフリカなどに出向き、強制連行や金銭で「人間という商品」を手に入れ、ヨーロッパ・中東・西インド諸島、そして南北アメリカで「販売」していたのです。そして新大陸のプランテーションでは綿花やサトウキビ、タバコ、藍、カカオ、コーヒーが栽培され、それがヨーロッパに輸入されるという「三角貿易」が発達しました。
しかし奴隷制度や奴隷の売買・貿易は何も近代に始まったわけではありません。それは地中海世界では古代エジプト以来、綿々と続いてきたものです。古代ギリシャ・ローマが奴隷制度に基づいていたのはもちろんです。またイタリアの都市国家、ジェノヴァやヴェネツィアの繁栄は、奴隷貿易と切り離しては考えられません。この場合の商品(奴隷)は非キリスト教徒のヨーロッパ人で、得意先はイスラム世界でしたが・・・・・・。そして15世紀から国力が強大になったスペイン帝国においても、当然のことながら「奴隷」はあったわけです。そのごく一部として「慰み者」があり、17世紀に遠い異国のドイツから「買われて」きてスペイン宮廷で「飼われて」いたバルボアが、ベラスケスとマルガリータ王女とともにラス・メニーナスに登場することとなった。
世界の歴史をマクロ的に見ると「生きた人間を何の疑問も持たず、牛馬と同等の労働力や愛玩物とし、売買の対象やそれと同等の扱いとした時代」がほとんどだったわけです。そのことを忘れてはならないと思います。
再び「怖い絵」
「怖い絵」を読んで印象的なのは、中野さんの絵を見る目の確かさやバックにある歴史・文化の膨大な知識はもちろんなのですが、それ以上に文章力です。これだけ達意の文章を書ける人はそうはいないと思います。ここまで書けるのなら「烏を鷺といいくるめる」こともできるかもしれない、我々は著者の文章のうまさによって「本当はたいして怖くない絵を怖いと思いこまされているのかもしれない」という「疑い」さえ抱いてしまいます。もちろん「恐怖」は個人的なもので、人によって感じ方に大きな差異があるのは当然なのですが・・・・・・。
2010年の2月から3月にかけて、NHKで「怖い絵で人間を読む」というシリーズ番組が放映され、中野さん本人が出演して絵の「解説」をされました。彼女はアナウンサーでも女優でもキャスターでもないので「じゃべる」のは文章を書くように「達意」というわけにはいきません。どちらかというと「とつとつ」と、しかし「真剣に人に伝えようという熱意」が、番組を見ている立場にも十分伝わってきました。このTV番組を見て「疑い」はなくなりましたね。あたりまえだけど・・・・・・。
「怖い絵」は、絵を見る3つの視点、つまり、
① 見る人の印象や直感
② 画家の思いや人生(の推測や知識)
③ 歴史ないしは文化背景
の3つのバランスのあり方を提示した名著だと思います。そして何よりも最後に書いたように、その文章が持つ力によって読書の楽しみを満喫させてくれた本でした。
| 補記 |
ラス・メニーナスに関連した絵画・小説・オペラなどの話題や、ベラスケスの作品を以下で取り上げています。
|
No.36 - ベラスケスへのオマージュ No.45 - ベラスケスの十字の謎 No.63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」 No.133 - ベラスケスの鹿と庭園 No.230 - 消えたベラスケス(1) No.231 - 消えたベラスケス(2) No.264 - ベラスケス:アラクネの寓話 No.284 - 絵を見る技術 |
No.3 - 「ドイツ料理万歳!」(川口マーン惠美) [本]
ドイツ料理
No.2「千と千尋の神隠しとクラバート(2)」の最後で、ドイツのザクセン地方を舞台にした小説『クラバート』と料理の関係を書きました。今回はそのドイツと料理の関係についてです。
そもそも「ドイツ料理」は世界から「おいしい料理」だとは認められていないと思います。たとえば、例の「アイスバイン」です。豚の「すね肉」の塊を茹でたものですが、こういう料理がドイツ料理の代表(の一つ)となっていること自体、世界におけるドイツ料理のポジションを暗示しています。ひょっとしたらアイスバインをドイツ料理の代表のように喧伝するのは、ドイツをおとしめるための、周辺の「食通国」の人たちの陰謀ではないだろうか、と思えるほどです。
ベルリンに旅行した時のことです。ある夜、「地球の歩き方」に載っている「ドイツ家庭料理」の店に入ったところ、隣のテーブルに20歳過ぎらしい若いカップルがいて、その女性のほうがアイスバインを注文していました。皿の上に骨付きの豚肉が「ゴロッと」置いてあります。「どうするのだろう」と思って食事をしながらチラチラと見ていましたが、その若い女性はぺろっと食べてしまったのです。注文したのだから食べるのはあたりまえ、と言ってしまえばそれまでですが、真実を目のあたりにして軽いショックを受けました。
もし私が20歳前後の学生で、ドイツの大学に留学していたとして、地元の女子学生に「淡い好意」をもち、首尾良くレストランに誘い出したとします。そこで彼女がアイスバインを注文して平らげたとしたら・・・・・・私の淡い好意はそれ以上には進展しないのではないでしょうか。だって、そうでしょう。もしさらに進んで、彼女が自分の家に招待して手料理を振る舞ってくれることになって「得意料理はアイスバイン」と宣告されたら・・・・・・と想像すると、進展しないのではないかと思うのです。料理を含む「文化」は実に多様で、そのことで他国の人を差別をしたり、差別意識を持ってはいけないということは重々承知しているつもりですが、日本人である立場からすると率直な感じなのです。
アイスバインの真実
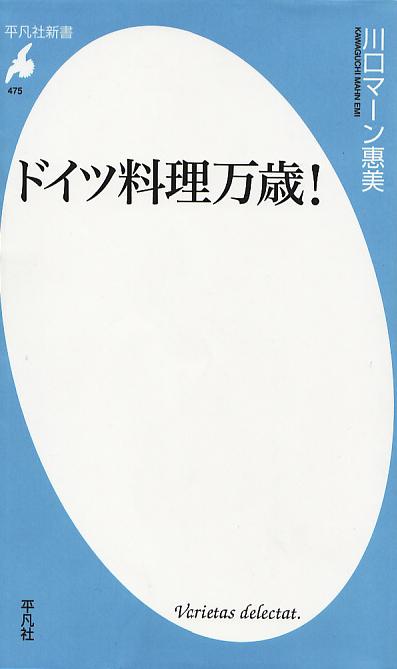 ところが、川口マーン惠美さんの本『ドイツ料理万歳!』(平凡社新書 2009年)
ところが、川口マーン惠美さんの本『ドイツ料理万歳!』(平凡社新書 2009年)なるほど、これで納得できます。「アイスバインをドイツ料理の代表のように喧伝するのはドイツ料理を揶揄するための陰謀」という説も、ちょっぴり現実味を帯びてきたようです。一般に、外国在住歴の長い人が書いた「××料理万歳」というたぐいの本には、おいしくもない料理をおいしいと言い張る「ひいきの引き倒し」のようなものがあるのですが、川口さんのこの本は信用できそうです。
しかしちょっと待てよ。川口さんは「地元」であるシュトゥットガルトを愛するあまり、ベルリンをけなしているだけではないだろうか。
シュトゥットガルトのワイン村
と思って読み進むと「シュトゥットガルトのワイン村」という記述があります。彼女が在住のシュトゥットガルトでは毎年、8月の終わりから9月にかけての12日間、街の中心部でワイン祭りが大々的に行われる。これが「ワイン村」で地元のレストランやワイン酒場、約120店が出店して、地元(シュトゥットガルトのあるバーデン・ヴュルテンベルク州)のワインが供される。この祭りはもう20年以上前からハンブルクの魚市場と交換出店の契約を結んでいるから、シュトゥットガルトにもハンブルクから魚貝類の食材が届いて並べられる・・・・・・というような説明があったあと、すぐに続けて川口さんはこう書くわけです。
蛇足ながら、私のあまり好まないワインは、実は、地元ヴュルテンベルクのワイン。先ほどのワイン村で供されるワインである。・・・・・・やはりワインは、太陽を一杯に浴びた葡萄から作られた華やかなものがいいな、と思う。夜、家中が寝静まったあと、一人でそんなワインを空ける。イタリア、スペイン、フランスといった、濃厚な大地の香りのするワイン(お値段は日本の半値以下!)を飲みながら、本を読んだり、音楽を聞いたり、原稿を書いたりする。「ドイツに住んでいてよかった!」と思う至福のひとときである。 |
最後の表現は「EU域内に住んでいてよかった!」の方が正確だとは思いますが、彼女の意見には120%賛成です。ますます、この本は「信用がおける」感じです。
シュバインスハクセと、ハンブルクの名物料理
アイスバインに話を戻すと「野蛮料理」であるアイスバインのかわりに彼女が紹介しているのが「シュバインスハクセ」です。バイエルン名物で、豚(シュバイン)のすね肉(ハクセ)の塊にニンニク、塩、香料類をなすりつけ、時間をかけてオーブンでグリルする。焼いているあいだ何度も肉汁やビールで表面を湿らしながらカラッと仕上げあるので、香ばしいかおりがする・・・・・・。
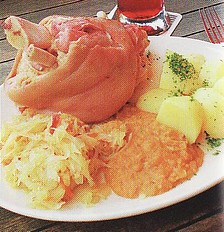
| |||
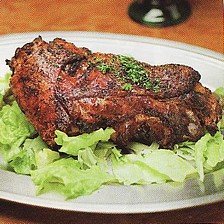
| |||
|
アイスバイン(上)と シュヴァインスハクセ(下) (本書より) | |||
川口さんの本にあるドイツ料理をもう一つ紹介しますと、ハンブルクに彼女が旅行したときに食べた「ハンブルク名物」の「ラプスカウズ」です。ラプスカウズとは「塩漬けの牛肉を茹でたものと玉ねぎのみじん切りの炒めたものを、肉挽き機で挽いてぐちゃぐちゃにし、そこに、さらにマッシュポテトを混ぜて加熱してあるだけ」の料理(本からそのまま引用)です。名物料理を紹介するにしてはちょっとショッキングな記述スタイルです。思い起こすと、日本ではこういったコンセプトの食べ物を、昔から「〇〇まんま」と言うのではないのでしょうか。もちろん日本のは残飯の有効活用という側面があり、そこが違うわけですが・・・・・・。
白アスパラ
日本人からすると「疑問符」がつくような料理ばかりを取り上げたようですが、この本は決してそればかりではありません。著者が自信をもって「おいしい」と勧める料理ももちろん紹介されていて、それはソーセージであり、チーズ、ニジマスなどの川魚料理、農家が期間限定で自宅で行うベーゼン(ワイン酒場)などです。川魚料理に関して補足すると、友人の家に招待されて、その知り合いの男性(オーバーラウジッツ出身。「クラバート」の舞台!)から鯉料理を振る舞われた話もでてきます。ニジマスとは違って、鯉は川口さんの口に合わなかったようですが。
「おいしい」ドイツ料理の中でも、著者が絶賛するのが白アスパラです。
白アスパラについては私も印象的な思い出があります。本に書いてあるように白アスパラの旬は5月頃で、ドイツで食べようとするとその前後に旅行しないといけないわですが、私が旅行できるのはほとんどが夏休み期間で、白アスパラが旬の時にドイツに行った経験はありません。ところが10年ほど前、たまたま5月下旬にまとまった休暇がとれることになり、プラハからプダペストに行き、ウィーンに数日滞在したことがあります。このときウィーンのレストランで出会ったのが白アスパラでした。最初に食べたレストランでは、確かメニューにはなくて「本日のお勧め」をチョークで黒板に書いたものにあったと思います。ドイツ語で「ヴァイス・シュパーゲル」です。ゆがいた白アスパラにオランダ風ソースという、卵の黄身とバターを混ぜたものをつけて食べるのですが、オランダ風以外にも何種類かのメニューがあったと思います。味の形容は言葉では難しいのですが、基本的に「ほのかな味と香り」で、歯触りがサクサクとしていて、野菜がもつ甘さもあり、大変においしかった記憶があります。

| |||
|
エドゥアール・マネ 「アスパラガス」(1880) ヴァルラフ・リヒャルツ美術館 (ドイツ・ケルン) [美術館のホームページより。 本書とは関係ありません] | |||
ところで、本書で川口さんがいみじくも書いているように、ドイツの白アスパラは「日本で言うなら、まさにタケノコ」なのです。その日の堀りたてが一番おいしく、ただしこれは大変に高価で手に入りにくい。旬の季節以外は出回らず、味と香りは「ほのか」で、歯触りが独特・・・・・・。もちろん味と食感は違いますが、タケノコが日本で占めているポジションは、ドイツで言えば白アスパラというわけです。ここで浮かび上がる大きな疑問は、白アスパラのように「繊細かつ微妙」で「歯触りが独特」で「旬の感覚が大切」で「タケノコとコンセプトが瓜二つの食材」が愛でられているというのに、どうしてアイスバインなのか、どうしてシュバインスハクセなのかということです。これは全くもって謎です。ドイツでは「そこにある食材」を最もストレートな形で食する、ということなのでしょうか。
ドイツ料理を歴史的に振り返る
そう思ってこの本を振り返ってみると、著者が好意的に書いている料理は、ビール・ワインなどの酒類やコーヒー、パン、ケーキのたぐいを除くと、
| ◆ | ソーセージ(さすがドイツで、種類は多数) | |
| ◆ | チーズ(これも種類多数) | |
| ◆ | 白アスパラ | |
| ◆ | ニジマスの塩焼きなどの川魚料理 | |
| ◆ | マウルタッシュ(巨大なラヴィオリのような料理) | |
| ◆ | じゃがいも料理(特にサラダ) |
です。このうち、ソーセージ、チーズ、白アスパラは、残念ながら「料理」ではなくて「食材」と言うべきでしょう。つまり「ドイツ料理万歳!」というタイトルの本にしては意外に「料理」が少ないことに気付きます。感嘆符まで付いているこの本のタイトルは、ドイツ料理に対する反語的な「皮肉」ないしは「あてつけ」なのでしょうね。たぶん。
もっとも「食材」であろうとおいしければそれでよいわけで、私の経験でもミュンヘンで食べたお湯の中に浮かんでいる白ソーセージなどは絶品でした。しかし「料理」という視点でみると川口さんも書いているようにやはり「ドイツ料理」というカテゴリーは歴史的に発達しなかった、と考えた方がよいと思われます。
その理由について川口さんは次のような3つの理由を書いています。第1の理由は食材の貧困(寒冷地である、土地が痩せている、海が少ない)、第2の理由はドイツ人はもともと狩猟民族で、農耕の定着は8世紀であったこと、第3の理由は中世以降もドイツはイタリア・フランスの文化的優位に甘んじていたこと(音楽をはじめ、料理も)の3つです。
これらの理由から歴史的に醸成されてきたドイツ人の食事に対する気質は「空腹が満たされるなら、内容にはそれほど拘らない」「目先の変わったものを食べてみようとも思わない」「昨日食べていたものを、今日も、そして、明日も変わらず食べていけるなら、たいていのドイツ人は満足」だそうです。そして川口さんは次のようにまとめるのです。
この質実剛健というか「贅沢は敵だ」の精神がどこに由来するかと考えると、どうもプロテスタントの影響のような気がしてならない。 |
第1から第3の理由は、はたして妥当なのでしょうか。食材の貧困を言うなら「ロシア料理はどうなる」となります。ロシアは「寒冷地で、土地が痩せていて、海が少ない」のではないでしょうか。狩猟民族うんぬんも、農耕が発達して1000年以上たつのだから、食文化の発達には十分すぎる時間が経過したはずです。フランス・イタリアの文化的優位に甘んじていたというけれど、それなら世界に冠たる「ドイツ音楽」の発達(もともとイタリアからの輸入です)はどうなるのでしょうか。
やはり根幹は川口さんが最後に書いている「プロテスタントの影響」であり、それが醸成した気質ではないでしょうか。というのも私には、映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからです。この映画の舞台は19世紀のデンマークの寒村ですが、これをフランスやイタリアやスペインに置き換えることは絶対に不可能です。でも、19世紀のドイツに置き換えるのは極めて容易だと思うのです。
『ドイツ料理万歳!』は「食」と「文化」の相関関係の深淵を覗かせてくれた好著でした。と同時に、川口さんの文章のうまさに感心しました。この本の一番の魅力です。
No.2 - 「千と千尋の神隠し」と「クラバート」(2) [本]
(前回より続く)
労働の場
「クラバート」はどういう物語でしょうか。
これは一言で言うと「大人になる物語」です。1人の少年が水車場という「労働の場」に入り、そこで学び、生きるすべを獲得し、大人になります。水車場は一般の社会における組織やコミュニティの象徴と考えて良いでしょう。その大人になるプロセスのキーワードは「魔法」と「自立」です。
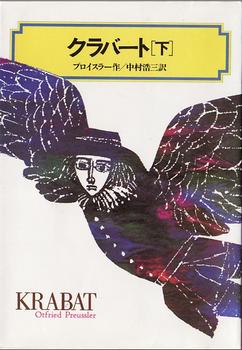
クラバート(下) (偕成社文庫 4060) |
水車場では親方の厳格な支配のもと、あらきじめ決まっている厳格なルール、しきたり、規律があって、クラバートはそれに従うしかありません。クラバートは自分を律し、自分をそこに適合させることにまず全力を傾けます。水車場での「ルール、規則、決まり」は、なぜそうなっているのか不明なものも多いわけです。そもそも労働の目的や意味がはっきりしません。麦を粉にすること自体の価値は理解できますが(それは農業に付帯する必須作業です)、誰のためにその労働をしているのか、大親分とは誰なのか、物語の最後まで必ずしもはっきりしないのです。
こういった労働の場を象徴するのが、親方が職人たちに伝授する「魔法」です。
魔法
魔法はクラバートや職人に強力な力を与えるものです。この力の効果は絶大です。汗を流して作業をするかわりに魔法を使うこともできるのですから。
と同時に、魔法はクラバートを制約します。親方は魔法の力で弟子の逃亡を阻止し、懲罰を与え、恐怖で弟子を支配しているのです。
魔法についての大変に印象的なシーンが物語に出てきます。クラバートと仲間は、泥炭の採掘場に牛を引いて泥炭を取りに行きますが、途中で沼地の上に板を渡さないと通れない箇所に来ます。そこで、魔法に上達している職人の1人が、板を渡すのを魔法で一瞬のうちにやってしまいます。この魔法を見てクラバートは圧倒されます。以下はその部分の引用です。
クラバードは叫んだ。「自分たちの手でしなくてはならないことが、何でも魔法でできるのに、いったいぜんたいどうしてまた働く必要があるのか」。「たしかに、そうだ」とトンダは言った。「しかし、そんな生活にはすぐにうんざりしてしまうということも考えてみたまえ。人は働かなければけっきょくはだめになり、おそかれ早かれ、破滅するしかないのだ。」 |
唐突なようですが、日本国憲法第27条が規定するように、労働は「権利」であると同時に「義務」です。「労働」は「しなくて済むものなら、しなくてよい」わけでは決してありません。「労働」が人間社会を成立させている根幹であり、と同時に、トンダが言うように人間性を担保しているファクターでなのです。
人は社会をつくって生きる動物ですが、その社会は「相互扶助」「助け合い」「ギブ・アンド・テイク」で成り立っています。人は「利己行動」だけでは生きていけません。「利他行動」こそが、人が人たるゆえんであり、人間社会を成立させているものです。そして人間社会で普遍的に行われている利他行動が労働です。労働は何らかの形で利他行動につながっている。報酬のある無しにかかわらず "労働が人間性の原点にある" のです。水車場が単なる異境(魔法の学校)ではない「労働の場」である意味がそこにあります。
自立
クラバートは単に水車場の規則に従っているだけではありません。クラバードは自ら意志をもち、考え、職人たちと友情をはぐくみ、親方の意向とは別に行動し、危険をおかして少女と心を通わします。そのために親方から懲罰もうけます。もちろん最大の「自立」は、最後の場面で自らの命をかけて親方と対決するところです。そのクラバートの「自立」を、水車場からクラバートを助け出すというかたちで完成させたのが少女です。ないしは少女がクラバートを思いやる心です。この、物語のエンディングである「目隠しをされた少女が、12人の職人の中からクラバートを差し示すことによって、クラバードは水車場から出る」という場面が意味するものは何でしょうか。
それは、キリストによる救済、ないしは「少女」ということで、聖母・マリアによる救済を象徴していると感じられます。「愛によって人は救済される」というわけです。そもそも水車場は「キリストと12人の弟子」の陰画になっています(親方と12人の職人)。「クラバート」という物語全体も、キリスト教の祭が要所要所に挟み込まれ、展開していきます。少女の名前がいっさい記述されていないことも、少女=聖なる存在、を暗示しています。
しかしキリスト教を離れて、もっと一般的な人間社会の原理としてこの物語のエンディングを解釈することもできるでしょう。つまりクラバードの「自立」は、少女が水車場からクラバートを助け出すという形で完成する、という点が示唆していることです。
言うまでもなく人間は人間同士のネットワークの中で生きています。そして人間の価値の多くはネットワークの中での関係性にあります。「自立」もそうであって「あの人は自立している人だ」と周りの人間から思われ、信頼され、従って相談を受けたり、自然と他人がその人に従ってくれることが「自立」です。それは本人だけの努力や力量だけでは決して完成しません。自立を成し遂げる要点は、他者からの信頼を得て、他者からの援助を引き出せることです。そのためのポイントは他者に対する思いやりと礼儀正しさでしょう。クラバートがまさにそうです。少女に対する態度などは特にそうです。クラバートが少女に脱出のための援助を依頼したきっかけはユーローから水車場の秘密を聞き出したことでしたが、ユーローもクラバードを信頼したからこそ、教えたのでしょう。
「千と千尋の神隠し」
「魔法に象徴される労働の場に少年(少女)が入り、生きるすべを知り、そこから脱出することによって自立が完成する」のを「クラバート型の物語」と呼ぶとすると「千と千尋の神隠し」(2001年公開)はまさに「クラバート型の物語」です。「千と千尋の神隠し」を、「不思議の国のアリス」や「オズの魔法使い」、「浦島太郎」などの、いわゆる「異境訪問説話」の一種とみなす考えがありますが、決して単なる異境訪問説話ではありません。それは「クラバート型の物語」です。
湯屋の世界から元の世界に帰りたい千尋に、湯婆婆は「変身動物判別テスト」を出します。つまり豚の群れを前に「この中からお前のお父さんとお母さんをみつけな。チャンスは1回だ。ピタリと当てられたら、お前達は自由だよ」と湯婆婆は千尋に問います。この設問に千尋は正解し、もとの世界に戻ります。クラバートの先輩のヤンコーは「変身動物判別テスト」に失敗して死にますが、千尋はヤンコーのかたきをとったわけです。「クラバート」を読んで非常に印象に残るのが、この「変身動物判別テスト」です。それはユーローがクラバートに語る話にしか出てこないのだけど、印象は強い。水車場からの脱出、という物語のクライマックスに直結する事項だからでしょう。これは全くの想像ですが、おそらく宮崎さんもそうで「変身動物判別テスト」を最後にもってくる物語を作ったのではないでしょうか。
クラバートの場合と違って、千尋の正解回答は「ここにはお父さんもお母さんもいない」というものでした。このシーンはもちろん映画の冒頭での「豚になった両親」と一対になっています。この冒頭場面と千尋の回答はどのように考えたらよいのでしょうか。この映画はファンタジーなのでいろいろな解釈が可能だと思いますが、「豚になった両親」というのは、千尋が親の醜い面を見たと思った、その千尋の内面の象徴だと考えられます。当然のことですが、こどもは成長するにつれ大人の「醜い面」「不条理・不合理な面」「いいかげんさ」などが、無意識にせよ目につくようになります。その象徴が「豚になった両親」の姿です。一方「豚の群れの中に両親はいない」という最後の場面での千尋の回答は、「豚になった両親」は本当の両親の姿ではない、という千尋の人間理解を表わすと考えられます。「醜い」と見えた姿は千尋の誤解で、実は両親は社会を生きて来た、また生きていく自然な人間だ、両親は豚でなない、人間なんだ・・・というような・・・。この理解に到達できたのは、もちろん湯屋での千尋のさまざまな経験です。
千尋の物語では「自立」の重要な部分を「親からの自立」が占めていることになります。孤児であるクラバートとはそこが違います。冒頭で「豚になった両親」に驚き、エンディングで「豚の群に両親はいない」と断言する・・・宮崎さんの作った物語の環は完璧です。
「千と千尋の神隠し」がそうであるような「クラバート型の物語」は、今まで繰り返し語られ、言い伝えられてたはずです。最近も「クラバート型」のストーリーをもつハリウッド映画がありました(プラダを着た悪魔)。「千と千尋の神隠し」は物語の型としてはきわめて普遍的なものではないでしょうか。この映画がベルリン国際映画祭の金熊賞(アニメ映画で初)やアカデミー長編アニメ賞をとったのが象徴的だと思います。
再び「クラバート」
もう一度「クラバート」の本に戻ると、この物語にはドイツ東部に住むヴェンド人の生活や当時のキリスト教の風習などの豊富かつ多彩な「風俗描写」があって、それが物語を魅力的にしています。しかし「当然あってしかるべきと思える風俗描写」がありません。それは「食に関する記述」です。食べ物の記述は、復活祭のクッキー、焼き肉、ぶどう酒ぐらいしかないのです。
職人のたちの労働は過酷なので「食べる」ことは何よりの楽しみのはずです。もちろん日々の食事は質素で簡素なものですが、「ハレ」の日にはご馳走を食べることもあります。例えば、復活祭の前日は職人は働く必要がないのですが、その日の記述は次のようになっています。
「この日は昼食と夕食がいっしょだった。栄養も量も特別豊富だったので、水車場の職人たちにはまるで宴会のようだった」 |
ご馳走であるのに、何を食べたかの記述がありません。
「水車すえつけのパーティには焼き肉とぶどう酒がでた」 |
という記述もあります。どういう肉なのでしょうか。豚か牛か鳥なのか、どういう部位なのか。ありきたりのものでも、職人たちにとっては大きな喜びだったはずです。
「食」に関する記述を盛り込むなら、いくらでもやりようがあるはずです。例えばドイツ内陸部の湿地帯では(クラバートの舞台がまさにそうです)鯉の料理が名物のはずです。クリスマスなどのハレの日には鯉料理で祝う風習があるとも聞きます。復活祭の日、職人たちが沼地に鯉を取りに行き、それを料理して宴会をした、鯉の調理法はこれこれこうで・・・、というような記述があってもよいわけです。もちろんこれは全くの想定例ですが・・・。
そういった小さな「不満」があったとしても、この物語はスラブ系ヴェンド人の村を舞台に、郷土色を濃密に書き込みながら、人間が生きる型を普遍的なメッセージとして提出し得たものです。児童文学の傑作と言っていいと思います。
| 補記(2013.2.21) |
2013年2月21日の新聞に、プロイスラー氏の訃報が載っていいました。
|
ご冥福をお祈り申し上げます。
No.1 - 「千と千尋の神隠し」と「クラバート」(1) [本]
「千と千尋の神隠し」を映画館で見たときのことですが、「クラバート」によく似た物語の展開だなと感じました。この「感じ」は映画の最後の場面で決定的になったのを覚えています。あとで映画のパンフレットを読むと「クラバート」への言及があるし、宮崎駿さんのインタビューなどでは、彼はその影響を否定していないようです。
「クラバート」は、チェコに生まれたドイツの児童文学者・プロイスラーが1971年に発表した小説です(日本語訳:中村浩三。偕成社。1985年)。実は、丸谷才一・木村尚三郎・山崎正和の3氏による書評本「固い本やわらかい本」(文藝春秋社。1986年)で「クラバート」が紹介されていたため、購入して読んでいたのです。文芸評論の「大家」である3氏の本に児童小説が紹介されていることに興味をそそられたわけです。「千と千尋の神隠し」はよく知られていますが「クラバート」を実際に読んだ人は少数でしょう。そこで「クラバート」のあらすじを紹介して「千と千尋の神隠し」との関係考えてみたいと思います。
断っておきますが「千と千尋の神隠しは、クラバートに影響されてできた映画だ」と言うつもりはありません。あの映画は宮崎さんの作り出した独創的なキャラクター群が何よりも魅力的だし(湯婆婆、銭婆、ハク、オクサレさま、カオナシ・・・)、影響どうのこうの言うなら、日本や東アジアの神話や民族伝承の影響がとてもたくさんあります。ハクが川の神に設定されていることなど、その典型です。宮崎さんに影響を与えた一つとして「クラバード」を考えればよいと思います。
「クラバート」の背景
物語の舞台はドイツの東よりのザクセン選帝公国で、時代は18世紀初頭に設定されています。当時のザクセンは歴史上有名なアウグスト1世(強健王)の治世下にあり、スエーデンとの戦争(いわゆる北方戦争)を戦っていた時期でもありました。公国の首都はドレスデンですが、その北東のポーランド国境近くがラウジッツ地方で、ここが物語の舞台です。この付近にはヴェンド人と呼ばれる民族が住んでいて、ドイツ語とは別系統であるスラヴ語系のヴェンド語が話されています。物語の主人公のクラバートは14歳のヴェンド人です。
クラバートの両親は天然痘で死亡し、孤児となった彼は土地のドイツ人牧師に引き取られました。しかし、ドイツ語での会話をはじめ、そこでの生活が息苦しくなった彼は、牧師の家を逃げ出して浮浪児の群に飛び込みました。そして音楽などを演奏し、物乞いをして生活しています。物語はクラバート少年の3年間の物語ですが、その3年間をかいつまんで紹介します。
1年目
元日から主顕節(1月6日)のあたりのこと、クラバートは奇妙な夢を見る。11羽のカラスが「シュヴァルツコルムの水車場に来い」と呼びかける夢である。それに引かれてクラバートはシュヴァルツコルムの村のはずれ、コーゼル湿地の水車場(製粉所)に行った。水車場の親方はヴェンド語を話し、黒い衣服を着ていて、左の目に眼帯をつけ、青白い顔をしている。皮装の厚い本が机にあるのが目に付く。クラバートはここで働くことに決める。
水車場の職人は11人で、皆が、ヴェンド語を話した。職人頭はトンダという。トンダはクラバートに目をかけてくれた。「まぬけのユーロー」と呼ばれる職人もいる。リュシュコーという職人は親方と裏で通じているようだ。
水車場では休みなしの厳しい労働が続く。製粉、雪かき、氷割りなど、仕事は山のようにある。親方の命令は絶対で、逆らうことは許されない。水車場には、7台のひき臼があり、うち6台を使用して大麦、小麦、カラス麦、ソバを挽く毎日が続く。ところが、お客がいっこうに顔を見せないのだ。
2月、クラバートが夜に目を覚ますと、6頭立ての馬車が水車場に横付けされていた。赤い鶏の羽を帽子につけた御者が見える。これが「大親分」であることがのちに分かる。職人たちは袋を馬車から水車場に運び込み、粉を詰めた袋を馬車に積み見込んでいる。大親分は新月のたびに訪れるのだ。親方は大親分をたいそう恐れている。
3ヶ月の試用期間が過ぎたとき、親方がクラバートを呼んで「弟子にする」と伝える。そのとき、水車場に秘密の一端が明らかになった。実は水車場は魔法の学校であり「魔法典」に従って、親方は弟子に魔法を教えていたのである。クラバートは他の職人とともに親方の魔法でカラスの姿に変身させられ、止まり木にとまって魔法の呪文を少しずつ習うことになる。この「授業」は毎週金曜の晩に行われる。この時以降、クラバートは正式に「見習い職人」として働き始める。
復活祭(3月)の前夜は、職人は全員戸外で野宿する決まりである。クラバートは職人頭のトンダと共に出かける。ルールに従って、相手の額に炭で五線星形の印をつける。このとき村の方から少年少女の歌声が聞こえてきた。クラバードはその中のソロパートを歌った金髪の少女に気を引かれる。この少女はのちにクラバードと愛を育むようになり、物語の最終場面で決定的な役割を果たす。
親方は習得した魔法を実際に使う場面を弟子のために作ることがあった。親方の指示で2人の職人が農夫と牛に変身し、村の家畜市に「偽の」牛を売りに行ったこともあった(物語ではこの種のエピソードがいろいろある)。
11月が過ぎ年末に近づくと、職人たちは何でもないことで腹を立てたり、いらだったり、喧嘩をしたりするようになる。クラバートにはその理由が分からないが、職人たち全体が不安にかられているようだ。そして大晦日の夜中、一人の呻き声が聞こえてきた。明けて元日、職人頭のトンダが死んでいるのが発見される。どうも不慮の事故ではなさそうだ。職人たちはトンダを埋葬する。
2年目
1月の主顕節の日、ちょうど1年前のクラバートのように、1人の新入りの少年が水車場で働くようになる。その日の晩、クラバートは親方に呼ばれて、見習い期間が過ぎ正式の職人することを告げられる。クラバートは時期が早いのに驚くが、水車場の1年は、普通の3年に相当することを知る。
水車場では、親方に指示された仕事を越えて、人の仕事を助けたり手伝ったりすることは厳禁である。ある職人が新入りの見習いを密かに助け、仕事を軽減してやったことがあった。しかしそれを親方に密告した職人がいた。親方は新入り助けた職人を厳しく罰する。職人たちは密告者のリシュコーとは口をきかなくなる。
復活祭の前夜、クラバートはで再びソロを歌っている少女の姿をみるが、このときも話しかけはしなかった。
2年目の大晦日の夜も、また職人が一人(ミヒャル)が死ぬ。
3年目
何回か水車場からの逃亡を企て、その都度失敗した職人(メルテン)が、とうとう首吊り自殺をはかる。しかし親方の魔法の力で自殺未遂に終わる。親方は言う。「この水車場でだれが死ぬかを決定するのはわしだ」。
3年目の復活祭の前日の夜、クラバートはもう1人の職人と野宿に出かける。例年のように、村から歌声が聞こえてくる。ソロパートを歌う少女の声も聞こえる。クラバートは魔法の力で少女に話しかけ、水汲みの仕事が終わったら他の少女から遅れて待っていてください、と頼む。この依頼は少女に通じ、クラバートは初めて少女に会う。
クラバートは「まぬけのユーロー」から水車場の秘密を聞き出した。ユーローは実は、まぬけを装っていただけだった。彼は「魔法典」をこっそり読んでいて、秘密を知ったのだった。その秘密とは次のようなものである。
この秘密を知ったクラバートは村に出かけて、少女に自分の「救出」を依頼し、少女は了承する。クラバートにはカラスに変身した職人たちの間から少女が自分を見つけるための秘策があった。
結末
大晦日も近くなったころ、親方はクラバートを呼び「自分の後継者にならないか」と申し出る。「今年は誰が死ぬべきか、いっしょに相談して決めてもよい」とさえ言う。クラバートは、申し出を拒否したなら今度の大晦日に死ぬのは自分だということを悟るが、拒否する。親方は1週間考える時間をやると言う。1週間後、親方はふたたびクラバートを呼んで問うが、クラバートは再び拒否する。親方は「コーゼル湿地に墓穴を掘れ。それが最後の仕事だ」と命じる。
大晦日の夜、約束通り少女は水車場にやってきた。そして「わたしの大事な人を渡してください」と親方に要求する。親方は職人たちを黒い部屋に並ばせた。親方は少女に目隠しをし、部屋につれていき「どれがおまえの大事な人か、わしに示すことができたら、そいつを連れていってよい」と言う。
想定(=少女がカラスに変身した職人たちの中からクラバートを当てる)とは全く違ったのでクラバートは愕然とし、これで少女も自分の命も終わりだと強い不安にかられる。目隠しをした少女は3度、職人たちの列の前を歩いた。そして、手をのばしてクラバートを指した。「この人がそうです」。
これで決着がついた。職人は全員解放された。親方は元日を迎えないだろうことは、職人全員が知っていた。クラバートと少女の2人は水車場を出て、コーゼル湿地を抜けてシュヴァルツコルムと向かった。
最後の場面でクラバートは少女と会話を交わす。「どうやってきみは仲間の職人の中から、おれをさがしだしたの?」「あなたが不安になっているのを、感じ取ったのよ」と娘は言った。「わたしのことが心配で不安になっているのを。それであなただとわかったのよ」
以上は、水車場の謎を中心としたストーリーを、ごくかいつまんで紹介しただけです。この物語の魅力は、このようなストーリー以外に数々のエピソードが書き込まれていることにあります。以下のようなものです。
などなどです。ヴェンド人の風俗や土地の描写、キリスト教の年中行事などの記述が豊富にあることも魅力です。
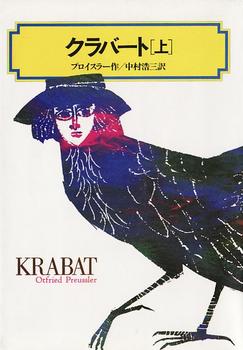
クラバート(上) (偕成社文庫 4059) |
断っておきますが「千と千尋の神隠しは、クラバートに影響されてできた映画だ」と言うつもりはありません。あの映画は宮崎さんの作り出した独創的なキャラクター群が何よりも魅力的だし(湯婆婆、銭婆、ハク、オクサレさま、カオナシ・・・)、影響どうのこうの言うなら、日本や東アジアの神話や民族伝承の影響がとてもたくさんあります。ハクが川の神に設定されていることなど、その典型です。宮崎さんに影響を与えた一つとして「クラバード」を考えればよいと思います。
「クラバート」の背景
物語の舞台はドイツの東よりのザクセン選帝公国で、時代は18世紀初頭に設定されています。当時のザクセンは歴史上有名なアウグスト1世(強健王)の治世下にあり、スエーデンとの戦争(いわゆる北方戦争)を戦っていた時期でもありました。公国の首都はドレスデンですが、その北東のポーランド国境近くがラウジッツ地方で、ここが物語の舞台です。この付近にはヴェンド人と呼ばれる民族が住んでいて、ドイツ語とは別系統であるスラヴ語系のヴェンド語が話されています。物語の主人公のクラバートは14歳のヴェンド人です。
クラバートの両親は天然痘で死亡し、孤児となった彼は土地のドイツ人牧師に引き取られました。しかし、ドイツ語での会話をはじめ、そこでの生活が息苦しくなった彼は、牧師の家を逃げ出して浮浪児の群に飛び込みました。そして音楽などを演奏し、物乞いをして生活しています。物語はクラバート少年の3年間の物語ですが、その3年間をかいつまんで紹介します。
(以下には物語の筋の根幹部分が明かされています)
1年目
元日から主顕節(1月6日)のあたりのこと、クラバートは奇妙な夢を見る。11羽のカラスが「シュヴァルツコルムの水車場に来い」と呼びかける夢である。それに引かれてクラバートはシュヴァルツコルムの村のはずれ、コーゼル湿地の水車場(製粉所)に行った。水車場の親方はヴェンド語を話し、黒い衣服を着ていて、左の目に眼帯をつけ、青白い顔をしている。皮装の厚い本が机にあるのが目に付く。クラバートはここで働くことに決める。
水車場の職人は11人で、皆が、ヴェンド語を話した。職人頭はトンダという。トンダはクラバートに目をかけてくれた。「まぬけのユーロー」と呼ばれる職人もいる。リュシュコーという職人は親方と裏で通じているようだ。
水車場では休みなしの厳しい労働が続く。製粉、雪かき、氷割りなど、仕事は山のようにある。親方の命令は絶対で、逆らうことは許されない。水車場には、7台のひき臼があり、うち6台を使用して大麦、小麦、カラス麦、ソバを挽く毎日が続く。ところが、お客がいっこうに顔を見せないのだ。
2月、クラバートが夜に目を覚ますと、6頭立ての馬車が水車場に横付けされていた。赤い鶏の羽を帽子につけた御者が見える。これが「大親分」であることがのちに分かる。職人たちは袋を馬車から水車場に運び込み、粉を詰めた袋を馬車に積み見込んでいる。大親分は新月のたびに訪れるのだ。親方は大親分をたいそう恐れている。
3ヶ月の試用期間が過ぎたとき、親方がクラバートを呼んで「弟子にする」と伝える。そのとき、水車場に秘密の一端が明らかになった。実は水車場は魔法の学校であり「魔法典」に従って、親方は弟子に魔法を教えていたのである。クラバートは他の職人とともに親方の魔法でカラスの姿に変身させられ、止まり木にとまって魔法の呪文を少しずつ習うことになる。この「授業」は毎週金曜の晩に行われる。この時以降、クラバートは正式に「見習い職人」として働き始める。
復活祭(3月)の前夜は、職人は全員戸外で野宿する決まりである。クラバートは職人頭のトンダと共に出かける。ルールに従って、相手の額に炭で五線星形の印をつける。このとき村の方から少年少女の歌声が聞こえてきた。クラバードはその中のソロパートを歌った金髪の少女に気を引かれる。この少女はのちにクラバードと愛を育むようになり、物語の最終場面で決定的な役割を果たす。
親方は習得した魔法を実際に使う場面を弟子のために作ることがあった。親方の指示で2人の職人が農夫と牛に変身し、村の家畜市に「偽の」牛を売りに行ったこともあった(物語ではこの種のエピソードがいろいろある)。
11月が過ぎ年末に近づくと、職人たちは何でもないことで腹を立てたり、いらだったり、喧嘩をしたりするようになる。クラバートにはその理由が分からないが、職人たち全体が不安にかられているようだ。そして大晦日の夜中、一人の呻き声が聞こえてきた。明けて元日、職人頭のトンダが死んでいるのが発見される。どうも不慮の事故ではなさそうだ。職人たちはトンダを埋葬する。
2年目
1月の主顕節の日、ちょうど1年前のクラバートのように、1人の新入りの少年が水車場で働くようになる。その日の晩、クラバートは親方に呼ばれて、見習い期間が過ぎ正式の職人することを告げられる。クラバートは時期が早いのに驚くが、水車場の1年は、普通の3年に相当することを知る。
水車場では、親方に指示された仕事を越えて、人の仕事を助けたり手伝ったりすることは厳禁である。ある職人が新入りの見習いを密かに助け、仕事を軽減してやったことがあった。しかしそれを親方に密告した職人がいた。親方は新入り助けた職人を厳しく罰する。職人たちは密告者のリシュコーとは口をきかなくなる。
復活祭の前夜、クラバートはで再びソロを歌っている少女の姿をみるが、このときも話しかけはしなかった。
2年目の大晦日の夜も、また職人が一人(ミヒャル)が死ぬ。
3年目
何回か水車場からの逃亡を企て、その都度失敗した職人(メルテン)が、とうとう首吊り自殺をはかる。しかし親方の魔法の力で自殺未遂に終わる。親方は言う。「この水車場でだれが死ぬかを決定するのはわしだ」。
3年目の復活祭の前日の夜、クラバートはもう1人の職人と野宿に出かける。例年のように、村から歌声が聞こえてくる。ソロパートを歌う少女の声も聞こえる。クラバートは魔法の力で少女に話しかけ、水汲みの仕事が終わったら他の少女から遅れて待っていてください、と頼む。この依頼は少女に通じ、クラバートは初めて少女に会う。
クラバートは「まぬけのユーロー」から水車場の秘密を聞き出した。ユーローは実は、まぬけを装っていただけだった。彼は「魔法典」をこっそり読んでいて、秘密を知ったのだった。その秘密とは次のようなものである。
|
親方は大親分と契約を結んでいて、毎年、弟子のひとりを生け贄として差し出さなければならない。さもないと、親方自身が生け贄になる。
水車場から脱出する方法は1つある。もし、職人を好きな少女がいて、大晦日の晩にその少女が職人を自由にしてくれと親方に申し出て、その少女が「魔法典」で規定するテストに合格したら、職人は自由になる。 そのテストとは、少女が職人の中からどれが目的の職人なのか、探しあてるというものである。「魔法典」にかかれているのはそれだけだが、親方はこの文言を自由に解釈してテストを行える。もしテストに合格しなれけば、職人も少女も死ぬ。一方、テストに合格したら、死ななければならないのは親方になる。そして親方が死んだとすると、親方が職人に教えてくれた魔法の力はすべて消え失せてしまう。 以前、ヤンコーという職人がいて、彼はテストを試みた。この時は、カラスに変身した12人の職人から、どれが目的の職人か当てよ、と親方は少女に命じた。これは失敗し、ヤンコーも少女も死んだ。 この秘密を知っている職人は他にもいるが、職人はテストを試みないで毎年1人の職人の死に目をつぶっている。その理由は、毎年死ぬのは12人の中の1人だという理由と、魔法の力を失いたくないからである。 もしこのテストやろうとするなら、その少女が誰かを親方に悟られてはならない。親方が察知すると、魔法の力で少女を死に追いやることでテストそのものを阻止しようとするからである。トンダはそれで少女を失った。 |
この秘密を知ったクラバートは村に出かけて、少女に自分の「救出」を依頼し、少女は了承する。クラバートにはカラスに変身した職人たちの間から少女が自分を見つけるための秘策があった。
結末
大晦日も近くなったころ、親方はクラバートを呼び「自分の後継者にならないか」と申し出る。「今年は誰が死ぬべきか、いっしょに相談して決めてもよい」とさえ言う。クラバートは、申し出を拒否したなら今度の大晦日に死ぬのは自分だということを悟るが、拒否する。親方は1週間考える時間をやると言う。1週間後、親方はふたたびクラバートを呼んで問うが、クラバートは再び拒否する。親方は「コーゼル湿地に墓穴を掘れ。それが最後の仕事だ」と命じる。
大晦日の夜、約束通り少女は水車場にやってきた。そして「わたしの大事な人を渡してください」と親方に要求する。親方は職人たちを黒い部屋に並ばせた。親方は少女に目隠しをし、部屋につれていき「どれがおまえの大事な人か、わしに示すことができたら、そいつを連れていってよい」と言う。
想定(=少女がカラスに変身した職人たちの中からクラバートを当てる)とは全く違ったのでクラバートは愕然とし、これで少女も自分の命も終わりだと強い不安にかられる。目隠しをした少女は3度、職人たちの列の前を歩いた。そして、手をのばしてクラバートを指した。「この人がそうです」。
これで決着がついた。職人は全員解放された。親方は元日を迎えないだろうことは、職人全員が知っていた。クラバートと少女の2人は水車場を出て、コーゼル湿地を抜けてシュヴァルツコルムと向かった。
最後の場面でクラバートは少女と会話を交わす。「どうやってきみは仲間の職人の中から、おれをさがしだしたの?」「あなたが不安になっているのを、感じ取ったのよ」と娘は言った。「わたしのことが心配で不安になっているのを。それであなただとわかったのよ」
以上は、水車場の謎を中心としたストーリーを、ごくかいつまんで紹介しただけです。この物語の魅力は、このようなストーリー以外に数々のエピソードが書き込まれていることにあります。以下のようなものです。
| ◆ |
ザクセンはスウェーデンと戦争中であり、選定候の派遣した徴兵隊が水車場の近くにも来る話。 |
| ◆ |
親方とクラバートがドレスデンの宮殿へ出かけ、アウグスト殿下と面会する逸話。 |
| ◆ |
職人たちが総出で、新しい水車をつくるエピソード |
| ◆ |
親方が友人の魔法使いのイルコーのことをクラバートに語る挿話。イルコーはオスマン・トルコ帝国軍にやとわれ、神聖ローマ帝国側で従軍した親方と戦場で「魔法対決」をし、親方はイルコーを殺してしまう。 |
| ◆ |
農民が親方に「雪を降らせてほしい」と頼みにくるエピソード。雪が降らないと秋撒きの苗が霜でダメになるから。 |
などなどです。ヴェンド人の風俗や土地の描写、キリスト教の年中行事などの記述が豊富にあることも魅力です。