No.309 - 川合玉堂:荒波・早乙女・石楠花 [アート]
東京・広尾の山種美術館で「開館55周年記念特別展 川合玉堂 ── 山﨑種二が愛した日本画の巨匠」と題した展覧会が、2021年2月6日~4月4日の会期で開催されたので、行ってきました。
山種美術館の創立者の山﨑種二(1893-1983)は川合玉堂(1873-1957)と懇意で、この美術館は71点もの玉堂作品を所蔵しています。そういうわけで、広尾に移転(2009年)からも何回かの川合玉堂展が開催されましたが(2013年、2017年など)、今回は所蔵作品の展示でした。
このブログでは、過去に川合玉堂の作品を何点か引用しました。制作年順にあげると次のとおりです。
これらはいずれも補足的なトピックとしての玉堂作品でしたが、今回はメインテーマにします。とは言え、展示されていた作品は多数あり、この場で取り上げるにはセレクトする必要があります。今回は "玉堂作品としてはちょっと異質" という観点から、『荒海』『早乙女』『石楠花』の3作品のことを書きます。
荒海
この絵については、2021年3月2日の朝日新聞に紹介記事がありました。執筆は朝日新聞・文化くらし報道部の西田健作記者です。的確な内容だと思ったので、まずそれを引用します。
この文章を要約すると、以下のようになるでしょう。
玉堂は "何でも描ける画家" だと思うのですが、その中でも典型的な "玉堂スタイル" の絵というと「日本らしい、季節感あふれる自然や風景があり、その中に人物が点景として配置されている絵」です。その自然は山河であることが多く、また田園地帯のこともある。
しかしこの絵に人物はなく、さらに風景は海です。そこが "ちょっと異質" です。もちろんこれは、文部省戦時特別美術展に出品するという制約下で描かれたからです。特別美術展でこの絵を観た人は、おそらく全員が「岩 = 日本」と考えたはずです。
しかし、そうであっても "玉堂らしさ全開の絵" という印象を受けるのは、引用した記事にある通りです。朝日新聞の西田記者は同じ記事で、この絵の「見どころ」として次の3点をあげていました。
全体は黒(墨)と白(胡粉)の水墨画のような感じですが、淡い群青が使ってあります。群青=海、胡粉=波しぶきであり、その全体が各種の線で表現されています。ジグザク状の線で視線を誘導するダイナミックな構図と相まって、白い波しぶきが鑑賞者に迫ってくるような印象を受けます。海の群青が近くになるほど薄まって白一色になっていくのも、その印象を強めている。
この絵で玉堂は "海の波の5態" を描いたように見えます。遠景から近景までを順に書くと次のとおりです。
さきほど「鑑賞者に迫ってくるような」と書きましたが、このような荒海の水の5態を描き分けることで、数秒~十数秒程度の時間の経緯までが画面に凝縮されているかのようです。川合玉堂の透徹した眼、観察眼を感じさせる素晴らしい作品だと思います。
この『荒海』とほぼ同じ時期に、玉堂は全く違った画題と雰囲気をもつ絵を描いています。それが次の絵で、『荒海』と対比して鑑賞すると興味深い作品です。
早乙女
『荒海』が描かれて以降の玉堂の軌跡をたどると次のようです。
1944年(昭和19年。71歳)
1945年(昭和20年。72歳)
『早乙女』は、古里村白丸で描かれた絵です。この絵について、2013年6月30日のNHKの日曜美術館では「自宅が焼失して意気消沈した時期に描かれた」という意味の説明がありました。田植えの時期は地域によるとは思いますが、関東では5月から6月といったところです。まさにその時期の光景と考えてよいでしょう。
山を少し上ったところから水田を見下ろしたような構図です。画面のほどんどを水田が占め、右上には水路が流れていて舟が浮かんでいます。極めて単純化された画面の中で、5人の早乙女が田植えに勤しんでいる。その表情は楽しそうにも見えます。色数の少ない画面の中で、鮮やかな緑の"たらし込み" で描かれたあぜ道が印象的です。
戦時下の厳しい時期です。東京も大空襲で焼け野原になった年です。それでもこの絵の人々は、従来と変わらず田植えをしている。まさに、そこを描きたかったのだと思います。稲作は長期に渡る一連のプロセスで成立します。田起こし → 代掻き → 田植え → 雑草取り → 稲刈り → 脱穀 → 精米 と、半年以上にわたる作業が続きます。その他にも、あぜ道や水路の維持などが必要で、この絵はバックにあるそういった生活サイクルを暗示しています。
川合玉堂は(現)東京藝大の教授になり(1915年。大正4年。42歳)、文化勲章を受け(1940年。昭和15年。67歳)、皇后陛下の絵の指導までした人です。日本の画壇では、いわば "功成り名を遂げた" 日本画の大家です。その人が、72歳で自宅を完全に失ってしまった。さぞかし茫然とし、落胆したでしょう。
しかし疎開先の奥多摩の農民は、変わることなく日々の作業に勤しんでいる。玉堂は奥多摩で毎日、スケッチブックを持って散歩に出かけ、山道を歩き、野山や植物のスケッチを繰り返したと言います。そして帰ってきて画室で絵を描く。
この絵は "玉堂スタイル" からするとちょっと異質です。"玉堂スタイル" の多くの絵は、山河や農村、田園地帯の風景があり、そこで働く人々が点景として描かれています。田植えを描いた絵として静岡県立美術館が所蔵する『田植図』がありますが、この絵のような構図が典型でしょう。人物は風景の一部になっている。
しかし『早乙女』は働く人々がクローズアップされていて、田植えという「人の営み」が中心的な画題です。「人の営み」というと、玉堂が多数描いた『鵜飼』の絵を思い出しますが、それは故郷の岐阜の光景です。それに対し『早乙女』には、日本のどこにでもある「普通の人の普通の営み」が描かれている。
玉堂は『早乙女』の制作以降も、1957年(昭和32年)に83歳で亡くなるまで御岳に住んで描き続け、その創作意欲が衰えることありませんでした。玉堂は『早乙女』に描かれた農民の姿、毎年のサイクルでつつましく生きる人々の姿に、自らの画家としてのあるべき姿を重ね合わせたのだと思います。
石楠花
この絵が実際に経験した情景だとすると、山道を歩いていて、ふと石楠花が目に付く。それを凝視してから眼をそらすと、遠くに残雪をいだいた険しい連峰が見える。そういった光景でしょう。
この絵の特徴は、花卉図と山水図を合体させたような描き方にあります。題名にあるように近景に描かれた石楠花がメインのモチーフなのだろうけれど、中景の崖と木々から遠景の連峰までがちゃんと描き込まれています。このような構図は玉堂作品としては "ちょっと異質" だと思います。
この構図で直感的に思い浮かべるのが歌川広重です。広重の風景画には「近景の事物を大写しにし、そこから遠方を望む」という構図が多々あります。有名な作品で言うと「名所江戸百景」の『深川洲崎十万坪』(近景に鷹、遠景に深川の雪景色と筑波山を配した有名な絵)や、『亀戸梅屋敷』(ゴッホが模写した作品。近景に梅の古木が画面いっぱいにあり、その向こうに梅園が見える)があります。
この "広重好みの構図" をさらに絞り込んで「近景に花、遠景に山」という作品を選ぶと、例えば「名所江戸百景」の『隅田川 水神の森 真崎』です。この絵は近景に八重桜を配し、その向こうに水神の森から隅田川とその対岸の真崎地区を描き、遠景には筑波山という構図です。これによって遠近感が際だちます。八重桜は極端にクローズアップされ、幹、枝、花の全てがカットアウトされている。いかにも広重らしい描き方です。
これと玉堂の『石楠花』は、構図のコンセプトがそっくりです。もちろん玉堂が広重に影響されたかどうかは分かりません。しかし玉堂は過去からの日本の絵の伝統を熟知している画家です。無意識にせよ江戸後期の風景画を踏まえたということがありうるのではないか。我々は19世紀後半のフランス絵画を見て「これは浮世絵の影響だ」とか、よく言います(No.224「残念な北斎とジャポニズム展」)。だとしたら、ほかでもない日本の画家の絵を見て浮世絵の影響を感じるのは当然ではないかと思うのです。
当たり前ですが『石楠花』は広重と違ってリアルです。まるで山道を歩いていて、ふと立ち止まって見たシーンのようです。しかし考えてみると、人間の眼にこの絵のような光景は見えません。実際に現場に立ったとしたら、我々の眼は石楠花と連峰に交互にピントを合わせて見るしかない。このように近景と遠景の差を極端にとり、その両方をリアルに同一平面に描くのは、絵画ならではの表現です。展覧会にある幾多の玉堂の絵の中で、この絵の前に立つとその「絵画ならでは」にハッとさせられる。そう感じました。
山種美術館の創立者の山﨑種二(1893-1983)は川合玉堂(1873-1957)と懇意で、この美術館は71点もの玉堂作品を所蔵しています。そういうわけで、広尾に移転(2009年)からも何回かの川合玉堂展が開催されましたが(2013年、2017年など)、今回は所蔵作品の展示でした。
このブログでは、過去に川合玉堂の作品を何点か引用しました。制作年順にあげると次のとおりです。
『冬嶺孤鹿』(1898。25歳)
『吹雪』(1926。53歳)
『藤』(1929。56歳)
『鵜飼』(1931。58歳。東京藝術大学所蔵)
『吹雪』(1926。53歳)
『藤』(1929。56歳)
『鵜飼』(1931。58歳。東京藝術大学所蔵)
これらはいずれも補足的なトピックとしての玉堂作品でしたが、今回はメインテーマにします。とは言え、展示されていた作品は多数あり、この場で取り上げるにはセレクトする必要があります。今回は "玉堂作品としてはちょっと異質" という観点から、『荒海』『早乙女』『石楠花』の3作品のことを書きます。
荒海

|
川合玉堂(1873-1957) 「荒海」(1944) |
85.8cm × 117.6cm (山種美術館) |
この絵については、2021年3月2日の朝日新聞に紹介記事がありました。執筆は朝日新聞・文化くらし報道部の西田健作記者です。的確な内容だと思ったので、まずそれを引用します。
美の履歴書 686 |
この文章を要約すると、以下のようになるでしょう。
| この絵は1944年(昭和19年)の文部省戦時特別美術展に出品された。この美術展には「戦意の高揚に資する」という出品の条件がついていた。 | |
| この絵も、難局(=荒波)に立ち向かい、微動だにしない日本(=磯の岩場)という象徴性があるのだろう。 | |
| しかし玉堂は画題の制約条件に従いつつも、描きたいものを描いた。それは荒海の波そのものである。 | |
| 玉堂は実際の海を徹底的に観察して描いた。波は日本画の特徴である "線を駆使した表現" で描かれていて、そこには画家の "気合" が注入されているようだ。 |
玉堂は "何でも描ける画家" だと思うのですが、その中でも典型的な "玉堂スタイル" の絵というと「日本らしい、季節感あふれる自然や風景があり、その中に人物が点景として配置されている絵」です。その自然は山河であることが多く、また田園地帯のこともある。
しかしこの絵に人物はなく、さらに風景は海です。そこが "ちょっと異質" です。もちろんこれは、文部省戦時特別美術展に出品するという制約下で描かれたからです。特別美術展でこの絵を観た人は、おそらく全員が「岩 = 日本」と考えたはずです。
しかし、そうであっても "玉堂らしさ全開の絵" という印象を受けるのは、引用した記事にある通りです。朝日新聞の西田記者は同じ記事で、この絵の「見どころ」として次の3点をあげていました。
| 遠くの海ほど群青の色が濃くなっている。 | |
| 胡粉を使った手前のしぶきには薄墨で輪郭線が描かれている。 | |
| 波がぶつかる瞬間と、波が引いて水が流れ落ちる瞬間が同時に描かれているようにも見える。 |
全体は黒(墨)と白(胡粉)の水墨画のような感じですが、淡い群青が使ってあります。群青=海、胡粉=波しぶきであり、その全体が各種の線で表現されています。ジグザク状の線で視線を誘導するダイナミックな構図と相まって、白い波しぶきが鑑賞者に迫ってくるような印象を受けます。海の群青が近くになるほど薄まって白一色になっていくのも、その印象を強めている。
この絵で玉堂は "海の波の5態" を描いたように見えます。遠景から近景までを順に書くと次のとおりです。
| 海の波の一般的なかたちである遠方の波。静かな海だとほとんど波が立たないこともあるが、描かれているのは荒れた海であり、波も大きい。 | |
| その波が陸地の浅瀬に近づくと、波頭が立ち上がる。 | |
| 波が磯の岩場にぶつかり、砕けて飛び散る。その水しぶきは離れて見ると霧のようにも見える。 | |
| 岩場からは、ぶつかった波の "残骸" がしたたり落ちる。 | |
| さらに波頭は岩場を越えてくるが、それが引くときには寄せる波とぶつかって激しい水沫が立ち上がる。それは③の "霧" ではなく、あくまで "水のしぶき" として見える。 |
さきほど「鑑賞者に迫ってくるような」と書きましたが、このような荒海の水の5態を描き分けることで、数秒~十数秒程度の時間の経緯までが画面に凝縮されているかのようです。川合玉堂の透徹した眼、観察眼を感じさせる素晴らしい作品だと思います。
この『荒海』とほぼ同じ時期に、玉堂は全く違った画題と雰囲気をもつ絵を描いています。それが次の絵で、『荒海』と対比して鑑賞すると興味深い作品です。
早乙女

|
川合玉堂 「早乙女」(1945) |
53.6cm × 87.1cm (山種美術館) |
『荒海』が描かれて以降の玉堂の軌跡をたどると次のようです。
1944年(昭和19年。71歳)
| 東京都下西多摩郡三田村御岳(現、青梅市御岳)に疎開。 | |
| 文部省戦時特別美術展に『荒海』を出品。 | |
| 下西多摩郡古里村白丸(現、奥多摩町白丸)に転居。 |
1945年(昭和20年。72歳)
| 東京都牛込区(現、新宿区)若宮町にあった自宅が空襲で焼失。 | |
| 敗戦。 | |
| 御岳に戻る。ここが終の住処となる。 |
『早乙女』は、古里村白丸で描かれた絵です。この絵について、2013年6月30日のNHKの日曜美術館では「自宅が焼失して意気消沈した時期に描かれた」という意味の説明がありました。田植えの時期は地域によるとは思いますが、関東では5月から6月といったところです。まさにその時期の光景と考えてよいでしょう。
山を少し上ったところから水田を見下ろしたような構図です。画面のほどんどを水田が占め、右上には水路が流れていて舟が浮かんでいます。極めて単純化された画面の中で、5人の早乙女が田植えに勤しんでいる。その表情は楽しそうにも見えます。色数の少ない画面の中で、鮮やかな緑の"たらし込み" で描かれたあぜ道が印象的です。
戦時下の厳しい時期です。東京も大空襲で焼け野原になった年です。それでもこの絵の人々は、従来と変わらず田植えをしている。まさに、そこを描きたかったのだと思います。稲作は長期に渡る一連のプロセスで成立します。田起こし → 代掻き → 田植え → 雑草取り → 稲刈り → 脱穀 → 精米 と、半年以上にわたる作業が続きます。その他にも、あぜ道や水路の維持などが必要で、この絵はバックにあるそういった生活サイクルを暗示しています。
川合玉堂は(現)東京藝大の教授になり(1915年。大正4年。42歳)、文化勲章を受け(1940年。昭和15年。67歳)、皇后陛下の絵の指導までした人です。日本の画壇では、いわば "功成り名を遂げた" 日本画の大家です。その人が、72歳で自宅を完全に失ってしまった。さぞかし茫然とし、落胆したでしょう。
しかし疎開先の奥多摩の農民は、変わることなく日々の作業に勤しんでいる。玉堂は奥多摩で毎日、スケッチブックを持って散歩に出かけ、山道を歩き、野山や植物のスケッチを繰り返したと言います。そして帰ってきて画室で絵を描く。
|
しかし『早乙女』は働く人々がクローズアップされていて、田植えという「人の営み」が中心的な画題です。「人の営み」というと、玉堂が多数描いた『鵜飼』の絵を思い出しますが、それは故郷の岐阜の光景です。それに対し『早乙女』には、日本のどこにでもある「普通の人の普通の営み」が描かれている。
玉堂は『早乙女』の制作以降も、1957年(昭和32年)に83歳で亡くなるまで御岳に住んで描き続け、その創作意欲が衰えることありませんでした。玉堂は『早乙女』に描かれた農民の姿、毎年のサイクルでつつましく生きる人々の姿に、自らの画家としてのあるべき姿を重ね合わせたのだと思います。
石楠花

|
川合玉堂 「石楠花」(1930) |
72.0cm × 101.5cm (山種美術館) |
この絵が実際に経験した情景だとすると、山道を歩いていて、ふと石楠花が目に付く。それを凝視してから眼をそらすと、遠くに残雪をいだいた険しい連峰が見える。そういった光景でしょう。
この絵の特徴は、花卉図と山水図を合体させたような描き方にあります。題名にあるように近景に描かれた石楠花がメインのモチーフなのだろうけれど、中景の崖と木々から遠景の連峰までがちゃんと描き込まれています。このような構図は玉堂作品としては "ちょっと異質" だと思います。
この構図で直感的に思い浮かべるのが歌川広重です。広重の風景画には「近景の事物を大写しにし、そこから遠方を望む」という構図が多々あります。有名な作品で言うと「名所江戸百景」の『深川洲崎十万坪』(近景に鷹、遠景に深川の雪景色と筑波山を配した有名な絵)や、『亀戸梅屋敷』(ゴッホが模写した作品。近景に梅の古木が画面いっぱいにあり、その向こうに梅園が見える)があります。
|
これと玉堂の『石楠花』は、構図のコンセプトがそっくりです。もちろん玉堂が広重に影響されたかどうかは分かりません。しかし玉堂は過去からの日本の絵の伝統を熟知している画家です。無意識にせよ江戸後期の風景画を踏まえたということがありうるのではないか。我々は19世紀後半のフランス絵画を見て「これは浮世絵の影響だ」とか、よく言います(No.224「残念な北斎とジャポニズム展」)。だとしたら、ほかでもない日本の画家の絵を見て浮世絵の影響を感じるのは当然ではないかと思うのです。
当たり前ですが『石楠花』は広重と違ってリアルです。まるで山道を歩いていて、ふと立ち止まって見たシーンのようです。しかし考えてみると、人間の眼にこの絵のような光景は見えません。実際に現場に立ったとしたら、我々の眼は石楠花と連峰に交互にピントを合わせて見るしかない。このように近景と遠景の差を極端にとり、その両方をリアルに同一平面に描くのは、絵画ならではの表現です。展覧会にある幾多の玉堂の絵の中で、この絵の前に立つとその「絵画ならでは」にハッとさせられる。そう感じました。
2021-04-17 11:07
nice!(0)
No.308 - 人体の9割は細菌(2)生態系の保全 [科学]
(前回から続く)
|
| 21世紀病 20世紀後半に激増して21世紀には当たり前になってしまった免疫関連疾患、自閉症、肥満などを、著者は「21世紀病」と呼んでいます。これと、ヒトと共生している微生物の関係を明らかにしています。 |
| 生態系の保全 ヒトと微生物が共生する「人体生態系」を正常に維持するためは何をすべきか。またその逆で、人体生態系に対するリスクは何かを明らかにしています。 |
前回は「21世紀病」の部分の紹介でしたが、今回は「生態系の保全」の部分から「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の内容を紹介します。なお本書で「生態系の保全」という言い方をしているわけではありません。
抗生物質のリスク
ペニシリンの発見(1928年)以降、抗生物質は人類に多大な恩恵を与えてきました。実は本書の著者も2005年、22歳のとき、マレーシアでコウモリの調査中に熱帯病に感染し、一時まともな生活が送れないようになりましたが、抗生物質による治療で回復しました。
しかし著者は、抗生物質の意義とメリットを十分に認識しつつも、その使用にはリスクがあることを説明しています。つまり、投与された抗生物質が感染症の原因菌だけでなく、ヒトと共生している微生物も殺してしまい、マイクロバイオータの様相が変わってしまうというリスクです。
その抗生物質が、現代社会においては感染症の治療以外に過剰に使用されているのが現実で、その一つが畜産業です。
|
ここで懸念が出てきます。家畜が抗生物質で太るなら人間も太るのではないかという点と、家畜の肉に残留した抗生物質が人間に悪影響を与えるのではという懸念です。
また家畜の糞は有機農業に使われますが、家畜に投与された抗生物質のおよそ75%は糞となって排出されます。家畜の肉に残留している抗生物質の規制はありますが、農地に撒かれる肥料に含まれる抗生物質の規制はありません。つまり、動物由来の肥料で有機栽培された野菜は安全なのかという疑問も出てくるのです。
さらに家畜だけでなく、ヒトに対しても、本来の感染症治療を越えた抗生物質の投与がされる現実があります。
|
|
抗生物質が殺すのは細菌であって、ウイルスではありません。従ってウイルスが原因の病気に抗生物質は利きませんが、このことを知っている患者は少ない。患者はどうしても薬の処方を医者に求める傾向にあり、医者も細菌による感染症を防ぐために "念のため" 抗生物質を処方するという現実があるのです。
抗生物質の多用が生み出す問題点の一つは耐性菌の出現です。ペニシリンが感染症の治療に使われ始めたのは1940年代前半ですが。数年後には早くもペニシリン耐性菌が見つかり、1950年代にはごく一般的な黄色ブドウ球菌がペニシリン耐性を持つようになりました。
1959年、イギリスでペニシリン耐性の黄色ブドウ球菌を治療するためにメチシリンという新しい抗生物質が使われ始めましたが、早くも3ヶ月後にはペニシリンとメシチリンの両方に耐性をもつ黄色ブドウ球菌の新株が出現しました。これが MRSA(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌)です。以来、MRSAは全世界で毎年数万人から数十万人の命を奪っています。もちろん耐性菌はMRSAのほかにもあります。
さらに問題点は、抗生物質が病気の原因菌だけでなく、広範囲の細菌を殺すということです。もちろんヒトと共生している微生物も影響を受けるわけで、ここが本書の眼目です。
|
抗生物質は大量破壊兵器というか、無差別爆撃をしているようなものです。目標とする病原菌以外の細菌も広範囲に殺してしまう。この悪影響が極端に現れたのが「クロストリジウム・ディフィシル感染症」です。
|
広域抗生物質がマイクロバイオータを攪乱すると、クロストリジウム・ディフィシル感染症だけでなく様々な副作用が出てくると想定できます。
では「21世紀病」と「抗生物質の多用」は関係しているのでしょうか。たとえば肥満です。統計によると抗生物質の使用量の増加と肥満の増加には相関関係があります。しかし相関関係があるからといって因果関係を断定できません。
実は、抗生物質の投与でヒトの体重が増えるという結果は、既に1950年代に出ていました。もちろん倫理的な理由により実験はできませんが「意図せずに行った実験」があるのです。
|
抗生物質が体重を増やすとして、では現在の肥満(BMIが30超)の広がりは抗生物質と関係しているのでしょうか。抗生物質がマイクロバイオータにおける細菌の構成比を変え、それが肥満につながるという「仮説」については数々の研究があります。仮説が正しいとする研究もあるのですが、著者はまだ断定するのは早いと言っています。
抗生物質と自閉症についても議論の最中ですが、全く無関係とは思えないと著者は書いています。エレン・ボルトの息子のアンドリューが自閉症を発症したのは抗生物質での治療中でした(No.307「人体の90%は細菌(1)」の「21世紀病:自閉症」の項)。
また抗生物質がアレルギーのリスクを高めることについては、数々のエビデンスがあります。さらに、1型糖尿病は感染症にかかったあとに発症することが多いことが知られていますが、これは感染症の治療に使われた抗生物質が原因ではないかと疑われています。
著者はマレーシアでのフィールドワークでダニから熱帯病に感染し、抗生物質の投与で治癒しました(前述)。しかし治癒したあとに別の体の不調に悩まされるようになりました。発疹ができたり、胃腸が弱くなったり、感染症にかかりやすくなったりです。このことが、まさに著者が本書を執筆した動機でした。21世紀病との関係で言うと、今まで展開してきた2つの議論、つまり、
| マイクロバイオータの変調が21世紀病の一因になっている | |
| 抗生物質がマイクロバイオータを攪乱する |
を結びつけると「抗生物質の多用が21世紀病の一因になっている」というのは蓋然性が高いと考えられます。現在、さまざまな研究・議論が行われているところです。とにかく、感染症の治療以外の目的での抗生物質の使用(食肉生産のコスト削減が代表的)は無くすべきでしょう。
自然出産と母乳の意味
マイクロバイオータが体内で発達する第1段階は、出産と授乳のプロセスにあります。母親の体内の胎児は無菌状態です。その子が共生する微生物を受け取るのは、まず母親からです。それは第1に出産のときであり、第2に母乳からです。
| 自然出産 |
|
このプロセスをみると、帝王切開で生まれた子どもは母親からの最初の微生物を受け取らないことになります。従来、帝王切開のリスクとして赤ん坊の皮膚に傷がつくことがあるとか、一時的な呼吸障害などの短期的なリスクが指摘されてきました。
|
その他、自閉症、強迫性障害、1型糖尿病、セリアック病などの発症リスクが、経膣出産(自然出産)よりも高まることが指摘されています。肥満でさえ、帝王切開との関連を指摘するデータがあります。
|
本書に「いまでは開腹手術で最も多い手術が帝王切開」とあります。それほど帝王切開が広まっている。もちろん帝王切開は医療上の重要な手段です。一部の女性にとってはこの方法しか子どもを生む手段がありません。しかしWHOは帝王切開の実施率を全出産の10~15%に収めるべきだとしています。「出産の危険から母子を守る」ことと「帝王切開によるリスクを避ける」ことのバランスをとるためには、この程度の数字が妥当なのです。
| 母乳 |
赤ちゃんが母親から受け継ぐ微生物環境の第2番目は、母乳由来のものです。
オリゴ糖と総称される糖類があります。これはブドウ糖などの単糖類が数個~10個程度結合したものです。母乳にはオリゴ糖が含まれていますが、ヒトの消化酵素はオリゴ糖を分解できません。実は、母乳のオリゴ糖は細菌の餌です。1983年に、ジェニー・ブランド=ミラー教授とその夫が行った研究が「母乳に含まれるオリゴ糖の意味」を明らかにしました。
|
しかも、母乳のオリゴ糖の量は赤ちゃんの発達とともに変化します。これは赤ちゃんの腸内細菌の変化に対応しています。
|
上の引用にもあるように、母乳には免疫細胞と抗体など、オリゴ糖以外の多様なものが含まれています。その一つが細菌です。これが最初に分かったのは "母乳バンク" でした。母乳バンクを運用する病院は、母親からの献乳を受け、それを母乳育児が困難な赤ちゃんに与えます。このとき、どんなに消毒をして採乳しても献乳の中に細菌が見つかるのです。
|
オリゴ糖だけでなく、母乳に含まれる細菌も時間の経過とともに変化します。
|
まとめると、赤ちゃんは母乳から細菌を受け取ると同時に、その細菌の餌になるオリゴ糖も摂取します。その両方が赤ちゃんの成長に従って変化していく。となると、粉ミルクだけで育つ赤ちゃんにはリスクがあることが推定できます。現代の粉ミルクには重要な栄養成分がたくさん加えられていますが、免疫細胞や抗体、オリゴ糖、生の細菌までは入っていないのです
|
母親か赤ちゃん、または両方の理由で母乳育児が不可能な場合があります。その場合は粉ミルクが必要ですが、これはあくまで "やむをえない場合の策" と考えるべきでしょう。
食物繊維の重要性
本書には「あなたはあなたの微生物が食べたものでできている」と題した章があります(第6章)。よく言われるのは「あなたはあなたの食べたものでできている」で、 これはバランスの良い食事が大切だという意味です。そして、ヒトは微生物と共生している以上、微生物に必要な "餌やり" も重要なのです。
イタリアの研究者の調査結果が紹介されています。彼らはブルキナファソ(西アフリカの国)のある村の子どもと、フィレンツェの子どもの比較研究をしました。
|
著者は、先進国では食物繊維の摂取が減っているとし、それをイギリスの具体例で説明しています。
| イギリスの成人は、1940年代に1日およそ70グラムの食物繊維を摂取していたが、いまでは20グラムに落ちこんだ。 | |
| 1942年には、食料供給が限られていた戦時中だったにもかかわらず、現在のほぼ2倍の野菜を食べていた。 | |
| 典型的な1日の食事でとる新鮮な緑の野菜は、1940年代に7Oグラムだったが、2000年代には27グラムだ。 | |
| 食物繊維に富む豆類、穀類(パンを含む)、ジャガイモも、1940年代以降は減っている。 |
などです。国によって違うとは思いますが、60年程度の長いレンジでみると、このような傾向は日本も同じではないでしょうか。
|
マイクロバイオータの細菌の種類は食生活によって変化します。アメリカで行われたボランティアによる実験のことが本書に書かれています。この実験では、肉や卵、チーズなど動物性食品を食べるグループと、穀類や豆類、果物、野菜など植物性食品を食べるグループに分けて、腸内微生物がどう変化するかを観察しました。予想どおり、腸内細菌の組成比が変わりました。植物食のグループは植物の細胞壁を分解できるタイプの細菌を急速に増やした一方、動物食のグループは植物好きの細菌を失い、蛋白質を分解し、ビタミンを合成し、炭化した肉に含まれる発癌物質を解毒するタイプの細菌を増やしました。
このように、食生活によってマイクロバイオータは変化します。そして著者は、このことが「異例なものを食べる集団にはとりわけ役に立つ」と書いていて、そこで日本人のことあげています。
|
日本に住むヨーロッパ人で海苔や海藻が苦手な人は多いようです。生まれ育ったヨーロッパで海藻を食べる文化がないからですが、それは単なる好き嫌いだけではなく、海藻を分解する細菌を腸に持っていないからなのでしょう。そして多くの日本人がもつこの細菌の遺伝子は、もともと海藻と共生していた細菌から来たものだった ・・・・・・。こういうところにも、進化の速度が速い細菌と共生している意義が認められます。
余談ですが、著者(英国人のアランナ・コリン)は海苔を食べる日本人を「異質なものを食べる」例として書いていますが、ウェールズの海岸地方では(ヨーロッパでは珍しく)海藻を食べます(Wikipediaの「ウェールズ料理」および「レイヴァーブレッド」の項参照)。アランナ・コリンはイングランド出身なのでしょう。もう少し英国の食文化に詳しければこういう表現にはならなかったと思います。
話を食物繊維に戻します。植物性食品に富む食生活は、痩せ型のマイクロバイオータを育てます。なぜそうなるのか。
No.307「人体の9割は細菌(1)」の「21世紀病:肥満」の項で、アッカーマンシア・ムニシフィラという細菌が腸壁の粘膜層を厚くし、細菌由来のリポ多糖(LPS)が血液中に入り込んで脂肪細胞に炎症を起こすのを防ぐ(=従って肥満を防ぐ)ことを書きました。食物繊維の一種であるオリゴフルクトース(=フルクラオリゴ糖)は、腸内のアッカーマンシアを大増殖させることが分かってきました。
さらに微生物が食物繊維を分解するときに出す短鎖脂肪酸が重要な働きを持っています。
|
また、短鎖脂肪酸一つである酪酸は、腸壁の細胞を結合している蛋白質の鎖を強め、腸壁を強固にします。
|
短鎖脂肪酸が、腸内細菌とヒトの細胞のあいだの情報伝達物質になっているわけです。これはちょうど腸内細菌が出すPSAが制御性T細胞を誘導する話(No.307「人体の9割は細菌(1)」の「21世紀病:免疫関連疾患」の項)とそっくりです。
ヒトが自らの消化酵素で消化できない食物繊維が腸内細菌の餌になり、腸内細菌が食物繊維を消化した「余り」の脂肪酸が重要なメッセージ物質となって炎症などの免疫反応やや脂肪の蓄積がコントロールされる ・・・・・・。ヒトは細菌と共生し、メリットを与え合い、互いに最適化してきたことがよく分かります。
ここまでで、アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」の "さわり" の紹介は終わりです。本書には以上のほかにも、皮膚常在菌や腸疾患、糞便移植(=マイクロバイオータを正常に回復させる)など、興味深い話題があるのですが、省略したいと思います。以降は本書を通読した感想です。
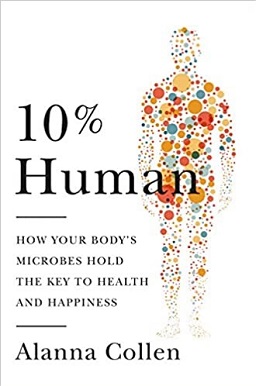
|
本書の原題は「10% Human」で、副題を直訳すると「あなたの体の微生物が、いかに健康と幸福の鍵を握っているか」となる。 |
本書の感想
ヒトと共生している常在菌、特に腸内細菌とそれがヒトにあたえる影響については研究が進み、一般にも知識が広まってきました(NHKでも近年、特集が組まれた)。本書の多くはその "広まりつつある知識" ですが、それを包括的にまとめて記述したところに意義があると思いました。特に、個々の研究テーマについて、その発端から研究の進展を取材してストーリーを追って書いた構成が優れています。また、巻末にあげられている多数の参考文献・論文は、サイエンス・ライターとしての著者の姿勢を明確にしています。
本書のメッセージをシンプルに要約すると、
ヒトは細菌と共生している。それを前提に考えよう
ということだと思います。ヒトは細菌にメリットを与え、細菌はヒトにメリットを与える。その関係が最適化されて進化してきたのが人体であるということです。この前提に立つと、以下の様なことが見えてきます。
| すぐに分かることは、ヒトが細菌に与えるメリットとは食べ物だということです。ということは、バランスの良い食事が重要だと理解できます。特に野菜を食べないのはまずい。なぜなら腸内細菌の餌を絶つことになるからです。もちろん、野菜に限らず餌を与えすぎてもいけない。「何事も適度に」です。 | |
| 細菌がヒトに与えているメリットは実感できませんが、我々が健康に過ごすということの多くが共生している細菌と関係していると想像できます。 | |
| 従って、共生細菌を殺してしまう行為はまずい。抗生物質の使用は感染症の原因菌を殺すという本来の目的に止めないと(それでさえ副作用が考えられる)、何が起こるか分かりません。畜産や養殖のコスト削減のためだけに抗生物質を使うなど論外ということになります。 | |
| 食品添加物は大丈夫でしょうか。許可されている添加物はヒトにとって安全という検証がされているはずですが、ヒトと共生している細菌に影響は無いのか、そこまで配慮されているのかが疑問です。食品添加物を一切とらない生活は不可能だと思いますが、なるべく少なくするのが重要でしょう。 | |
| 抗生物質が腸内の細菌を殺すものなら、体につける各種の抗菌剤入り商品は皮膚の常在菌を殺すことになります。抗菌剤のヒトにとってのメリットはない(=メリットよりデメリットが大きい)でしょう。手を洗うなら石鹸で十分です(本書でも指摘してあります)。 | |
| 共生細菌はヒトが外界から取り入れたものです。ということは、自然出産や母乳による育児が大切なことが理解できるし、清潔過ぎる環境で生活するのは問題です。 |
以上のようなことは、「ヒトは細菌と共生するのが前提」と考えれば、最新科学の知識がなくても理解、ないしは推測ができます。本書の訳者の矢野真千子氏は「訳者あとがき」で次のように書いていました。
|
自然生態系と同じように、人体生態系(ヒト + 共生微生物)を破壊してはならないし、人体生態系が持続可能なようにするのが、すなわち我々が生きていくということである ・・・・・・。そう理解できるでしょう。
本書を読んで、ヒトは微生物と共生しているという時の "共生" の意味を深く理解できたと感じました。普通 "共生" と言うと、上に書いたように「互いにメリットを与え合っている」という風に理解します。それは正しいのですが、それだけではありません。本書に次のような例が出てきます。
| アッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が腸壁を覆う粘膜層の表面に棲んでいる。この細菌はヒトの遺伝子に化学信号を送って粘液の分泌を促し、それによって自分たちの棲み処を確保する。そうすると粘膜層が厚くなり、細菌由来のリポ多糖が血液中に入り込むのが阻止される。この結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれなくなる(=肥満を防ぐなどの効果)。 | |
| 腸壁の上皮細胞は蛋白質の鎖でつながっている。この鎖がゆるむと、本来、血液中に入ってはいけない物質が透過し、免疫系を刺激して炎症を起こし、21世紀病の原因の一つになる。 細菌が食物繊維を分解したあとにできる酪酸(短鎖脂肪酸の一つ)は、腸壁の蛋白質の鎖を作る遺伝子の発現量を決めている。微生物が酪酸を多く出せば出すほど、ヒトの遺伝子は多くの蛋白質の鎖を作り、腸壁は堅固になる。
No.308「人体の9割は細菌(2)」の「食物繊維の重要性」
| |
| バクテロイデス・フラジリスという細菌は、多糖類A(PSA)という物質を産生し、それを微小なカプセルに入れて細胞表面から放出する。このカプセルが大腸で免疫細胞に貪食されると、PSAが制御性T細胞を起動させる。制御性T細胞は他の免疫細胞に、バクテロイデス・フラジリスを攻撃しないようメッセージを送る。 | |
| 細菌が食物繊維を分解したあと、大腸には短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)が大量にたまる。短鎖脂肪酸は免疫細胞の表面にあるG蛋白質共役受容体(GPR43)に結合し、それが細菌を攻撃しないようにというメッセージになる。そのGPR43は脂肪細胞の表面にもあり、そこに短鎖脂肪酸が結合すると脂肪細胞は肥大するのをやめて分裂する(=肥満を防ぐ)。
No.308「人体の9割は細菌(2)」の「食物繊維の重要性」
|
つまりヒトと共生している細菌は、腸の壁を厚くし、腸壁の透過性を減少させ、過剰な免疫反応を防ぎ、脂肪細胞の肥大化を防ぐわけです。これはすなわち、
ヒトはヒトのからだのコントロールの一部を共生微生物にゆだねている
ことを意味します。「ヒトと微生物は共生するように進化してきた」とはそういうことです。改めて共生微生物の重要性を認識させられました。
本書には研究途中の事項もたくさん含まれています。著者も「確かな話はここまでで、ここからは推測である」「断定はできない」「相関関係があるからといって因果関係があるとは限らない」などの表現で、"確実に判明しているのではないこと" を明確にしています。このような記述態度には好感を持ちました。
最後に、本書の大きな特長は文章が優れていることです。おそらく著者と訳者の両方の力量だと思いますが、科学書としては珍しいような出来映えです。科学的知見を一般向けにどう平易に記述し、読者に訴えることができるか。やはり文章力は大切だと感じました。
| 補記:腸内細菌による難病治療 |
2023年1月28日の日本経済新聞に、オーストラリアで腸内細菌による難病治療が承認されたとの記事が掲載されました。腸内細菌が人の健康に影響を与えるという認識は既にあたりまえであり、世界の最先端の研究は「腸内細菌を如何に病気の治療(精神疾患やアレルギー疾患の治療も含む)に使うか」ということだと認識できます。
|
2021-04-03 17:49
nice!(0)






