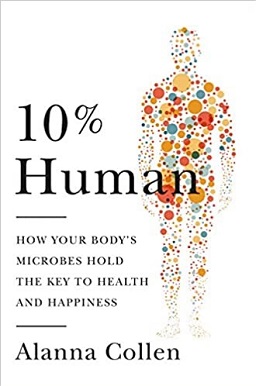前回の No.307「人体の9割は細菌(1)」は、
アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」(訳:矢野真千子。河出書房 2016。河出文庫 2020。原題 "10% Human"。以下「本書」と書きます)の紹介でした。この本は大きく分けて次の2つのことが書かれています。
| ◆ | 21世紀病
20世紀後半に激増して21世紀には当たり前になってしまった免疫関連疾患、自閉症、肥満などを、著者は「21世紀病」と呼んでいます。これと、ヒトと共生している微生物の関係を明らかにしています。
|
| ◆ | 生態系の保全
ヒトと微生物が共生する「人体生態系」を正常に維持するためは何をすべきか。またその逆で、人体生態系に対するリスクは何かを明らかにしています。
|
前回は「21世紀病」の部分の紹介でしたが、今回は「生態系の保全」の部分から「抗生物質」「自然出産と母乳」「食物繊維」の内容を紹介します。なお本書で「生態系の保全」という言い方をしているわけではありません。
抗生物質のリスク
ペニシリンの発見(1928年)以降、抗生物質は人類に多大な恩恵を与えてきました。実は本書の著者も2005年、22歳のとき、マレーシアでコウモリの調査中に熱帯病に感染し、一時まともな生活が送れないようになりましたが、抗生物質による治療で回復しました。
しかし著者は、抗生物質の意義とメリットを十分に認識しつつも、その使用にはリスクがあることを説明しています。つまり、投与された抗生物質が感染症の原因菌だけでなく、ヒトと共生している微生物も殺してしまい、マイクロバイオータの様相が変わってしまうというリスクです。
その抗生物質が、現代社会においては感染症の治療以外に過剰に使用されているのが現実で、その一つが畜産業です。
1940年代後期、アメリカの科学者たちは思いがけず、ニワトリに抗生物質を与えると成長が50%近く促進されることを見出した。当時、アメリカでは都市に人口が流入し、市民は生活費の高さに辟易していた。戦後の「欲しいものリスト」の上位に安価な食肉が挙がった。抗生物質によるニワトリへの成長促進効果はまさに天からの贈り物で、農家はウシやブタ、ヒツジ、7面鳥の飼料に毎日少量の薬を混ぜるだけで食肉家畜がどんどん大きくなるのを見て上機嫌だった。
農家は、薬が成長を促すメカニズムについても、その結果についても知らなかった。食料不足で価格が高騰していたこの時代、薬の費用よりもニワトリが太ることで得られる利益が大幅に上回った。以来、「治療量以下」の抗生物質を投与するのは畜産業での日常業務となった。
ざっと推定すると、アメリカでは抗生物質の70%が家畜用に使われているという。おまけに、抗生物質を使えば感染症を心配せずに狭い場所に多くの家畜をつめこむことが可能だ。アメリカでは、この成長促進剤なしに同じ重量の食肉を出荷しようとすると、4億5200万羽のニワトリと、2300万頭のウシ、1200万頭のブタが毎年余分に必要になる。
アランナ・コリン
『あなたの体は9割が細菌』
(矢野真千子 訳。河出文庫 2020)p.218
|
ここで懸念が出てきます。家畜が抗生物質で太るなら人間も太るのではないかという点と、家畜の肉に残留した抗生物質が人間に悪影響を与えるのではという懸念です。
また家畜の糞は有機農業に使われますが、家畜に投与された抗生物質のおよそ75%は糞となって排出されます。家畜の肉に残留している抗生物質の規制はありますが、農地に撒かれる肥料に含まれる抗生物質の規制はありません。つまり、
動物由来の肥料で有機栽培された野菜は安全なのかという疑問も出てくるのです。
さらに家畜だけでなく、ヒトに対しても、本来の感染症治療を越えた抗生物質の投与がされる現実があります。
抗生物質による治療はぜったいに必要なものではない。アメリカの疾病管理予防センター(CDC)の推定によれば、同国で処方されている抗生物質の半分は不必要または不適切なものだという。その多くは、風邪またはインフルエンザを1日でも早く治したいと切望する患者に、半ば気休めで処方されている。風邪もインフルエンザも細菌ではなくウイルスによる病気であり、抗生物質は効かない。それに、ほとんどの風邪は命を危険にさらすことはなく、数日か数週間で治る。
「同上」p.223
|
アメリカで1998年に行われた調査によると、プライマリケア医が処方した抗生物質の4分の3が、5種類の呼吸器系感染症への治療目的だった。耳感染症、副鼻腔炎、咽頭炎、気管支炎、上気道感染症だ。上気道感染症で医者を訪れた2500万人のうち、30%に抗生物質が処方された。そんなに多くないとあなたは感じたかもしれないが、細菌が原因の上気道感染症はたったの5%しかない。咽頭炎も同様で、同じ年にそう診断された1400万人のうち62%に抗生物質が処方された。細菌性が原因の咽頭炎は10%しかないにもかわらず。全体でみるとその年に処方された抗生物質の55%は不必要なものだった。
「同上」p.224
|
抗生物質が殺すのは細菌であって、ウイルスではありません。従ってウイルスが原因の病気に抗生物質は利きませんが、このことを知っている患者は少ない。患者はどうしても薬の処方を医者に求める傾向にあり、医者も細菌による感染症を防ぐために "念のため" 抗生物質を処方するという現実があるのです。
抗生物質の多用が生み出す問題点の一つは耐性菌の出現です。ペニシリンが感染症の治療に使われ始めたのは1940年代前半ですが。数年後には早くもペニシリン耐性菌が見つかり、1950年代にはごく一般的な黄色ブドウ球菌がペニシリン耐性を持つようになりました。
1959年、イギリスでペニシリン耐性の黄色ブドウ球菌を治療するためにメチシリンという新しい抗生物質が使われ始めましたが、早くも3ヶ月後にはペニシリンとメシチリンの両方に耐性をもつ黄色ブドウ球菌の新株が出現しました。これが MRSA(メシチリン耐性黄色ブドウ球菌)です。以来、MRSAは全世界で毎年数万人から数十万人の命を奪っています。もちろん耐性菌はMRSAのほかにもあります。
さらに問題点は、抗生物質が病気の原因菌だけでなく、広範囲の細菌を殺すということです。もちろんヒトと共生している微生物も影響を受けるわけで、ここが本書の眼目です。
抗生物質は細菌の単一種だけを標的にすることはできない。ほとんどの抗生物質は、広範囲の細菌種を殺す「広域抗生物質」だ。このタイプの薬は問題を引き起こしている細菌の種類を特定することなくあらゆる感染症に使えるため、医者にとっては好都合だ。原因菌を特定するには培養と同定の作業が必要で、それにはお金も時間もかかるうえ、ときには不可能なこともある。
標的を絞った「狭域抗生物質」でさえ、病気の直接原因となっている菌種だけを選んで殺すことはできない。同じグループに属する細菌すべてを標的としてしまう。こうした大量破壊兵器がもたらす結果はアレクサンダー・フレミング(引用注:ペニシリンの発見者)でさえ予測できなかった。
「同上」p.229
|
抗生物質は大量破壊兵器というか、無差別爆撃をしているようなものです。目標とする病原菌以外の細菌も広範囲に殺してしまう。この悪影響が極端に現れたのが「クロストリジウム・ディフィシル感染症」です。
耐性獲得と大量破壊という抗生物質の両方のマイナス面が重なって出現した危険な病気に、クロストリジウム・ディフィシル感染症がある。クロストリジウム・ディフィシルという細菌が引き起こすこの感染症は、1999年にイギリスで500人の死者を出した。その多くは抗生物質の治療を受けた患者だった。2007年には、同じ感染症で4000人近くが死亡した。
できることならこの病気では死にたくない。腸内に棲むクロストリジウム・ディフィシルは毒素を産生し、悪臭をともなう絶え間ない水状の下痢を引き起こす。それにより、脱水症状、重篤な腹痛、急激な体重減少が生じる。クロストリジウム・ディフィシル感染症の患者は、たとえ腎不全を免れたとしても、中毒性の巨大結腸症を生き延びなければならない。巨大結腸症とは読んで字のごとく、腸内で発生した余分なガスが結腸を異常に膨らませてしまう症状だ。虫垂炎と同じく破裂の危険があり、破裂したときの危険性は虫垂炎どころではない。腹腔内に糞便とあらゆる種類の細菌がばらまかれることになるため、生存率は著しく下がる。
クロストリジウム・ディフィシル感染症の発生件数および死亡者数の上昇は、抗生物質耐性菌の進化と歩調を合わせている部分がある。1990年代に、クロストリジウム・ディフィシルは危険な新株に進化し、病院内で広まった。この株は耐性が強いだけでなく、毒性も強かった。そして、もう一方の原因である抗生物質の過剰使用の問題をくっきりと浮かび上がらせた。
クロストリジウム・ディフィシルは一部の人の腸内においては、さほどトラブルを起こさず、かといって役に立つこともせずに無為に過ごしている。だが、ほんのちょっとしたきっかけで牙をむく。そのきっかけをつくるのは抗生物質だ。腸内マイクロバイオータが健康でバランスがとれているあいだは、クロストリジウム・ディフィシルは小さなくぼみに押しこめられて身動きがとれないから、悪さをすることもできない。だが、抗生物質、とりわけ広域抗生物質がマイクロバイオータを攪乱すると、クロストリジウム・ディフィシルが勢力を広げる「余地」ができる。
「同上」p.229
|
広域抗生物質がマイクロバイオータを攪乱すると、クロストリジウム・ディフィシル感染症だけでなく様々な副作用が出てくると想定できます。
では「21世紀病」と「抗生物質の多用」は関係しているのでしょうか。たとえば肥満です。統計によると抗生物質の使用量の増加と肥満の増加には相関関係があります。しかし相関関係があるからといって因果関係を断定できません。
実は、抗生物質の投与でヒトの体重が増えるという結果は、既に1950年代に出ていました。もちろん倫理的な理由により実験はできませんが「意図せずに行った実験」があるのです。
1953年にアメリカ海軍は新兵に抗生物質で治療する試験を開始した。連鎖球菌の感染症を減らすのに、オーレオマイシン(引用注:現在ではヒトに対しては皮膚の化膿性感染症の治療に使われる抗生物質)を予防的に使えるかどうかを調べたのだ。新兵の若者たちは軍の規定により身長と体重を記録されていたため、それがのちに予定外のテーマを研究するときのデータとなった。抗生物質を投与された新兵は、見た目はそっくりのプラセボを投与された新兵より著しく体重を増やした。このときも、抗生物質の投与は栄養価を高める潜在力があるとして好意的に受けとられ、懸念材料とみなされることはなかった。
「同上」p.235
|
抗生物質が体重を増やすとして、では現在の肥満(BMIが30超)の広がりは抗生物質と関係しているのでしょうか。抗生物質がマイクロバイオータにおける細菌の構成比を変え、それが肥満につながるという「仮説」については数々の研究があります。仮説が正しいとする研究もあるのですが、著者はまだ断定するのは早いと言っています。
抗生物質と自閉症についても議論の最中ですが、全く無関係とは思えないと著者は書いています。エレン・ボルトの息子のアンドリューが自閉症を発症したのは抗生物質での治療中でした(
No.307「人体の90%は細菌(1)」の「21世紀病:自閉症」の項)。
また抗生物質がアレルギーのリスクを高めることについては、数々のエビデンスがあります。さらに、1型糖尿病は感染症にかかったあとに発症することが多いことが知られていますが、これは感染症の治療に使われた抗生物質が原因ではないかと疑われています。
著者はマレーシアでのフィールドワークでダニから熱帯病に感染し、抗生物質の投与で治癒しました(前述)。しかし治癒したあとに別の体の不調に悩まされるようになりました。発疹ができたり、胃腸が弱くなったり、感染症にかかりやすくなったりです。このことが、まさに著者が本書を執筆した動機でした。21世紀病との関係で言うと、今まで展開してきた2つの議論、つまり、
| ・ | マイクロバイオータの変調が21世紀病の一因になっている
|
| ・ | 抗生物質がマイクロバイオータを攪乱する
|
を結びつけると「抗生物質の多用が21世紀病の一因になっている」というのは蓋然性が高いと考えられます。現在、さまざまな研究・議論が行われているところです。とにかく、感染症の治療以外の目的での抗生物質の使用(食肉生産のコスト削減が代表的)は無くすべきでしょう。
自然出産と母乳の意味
マイクロバイオータが体内で発達する第1段階は、出産と授乳のプロセスにあります。母親の体内の胎児は無菌状態です。その子が共生する微生物を受け取るのは、まず母親からです。それは第1に出産のときであり、第2に母乳からです。
細胞の数だけで言うなら、赤ん坊はこの世に生まれて最初の数時間で「大半がヒト」の状態から「大半が微生物」の状態に切り替わる。子宮内部の羊水につかっているとき、胎児は外界の微生物からも母親の微生物からも守られている。だが、破水と同時に微生物の入植がはじまる。赤ん坊は産道を通るとき、微生物のシャワーを浴びる。ほぼ無菌状態だった赤ん坊を、膣の微生物が覆っていく。
産道から顔を出すとき、赤ん坊は膣の微生物とはまた別のタイプの微生物を受けとる。そう、誕生直後に母親の糞便を摂取するのはコアラだけではないのだ。子宮収縮ホルモンの作用と降りてくる胎児の圧力を受けて、陣痛中や出産時にほとんどの女性は排便する。赤ん坊は顔を母親のお尻の側に向けて頭から先に出てくる。そして母親がつぎの陣痛に備えて体を休めているあいだ、赤ん坊の頭と口はうってつけの位置に来る。あなたは本能的に顔をしかめるかもしれないが、これは幸先のいいスタートだ。母から子への最初の贈り物、糞便と膣の微生物が無事に届けられることになるのだから。
これは進化的に「適応した」誕生だ。肛門が膣口のすぐそばにあるのも、子宮収縮ホルモンが直腸を刺激して排便を促すのも、別段悪いことではない。自然選択は、それが赤ん坊の役に立つから選んだのだろう。あるいは、少なくとも害にはならないから排除しなかった。微生物とその遺伝子 ── 母のゲノムとうまく調和して働いていた遺伝子 ── を受けとった赤ん坊は、希望に満ちた人生のスタートを切る。
「同上」p.300
|
このプロセスをみると、帝王切開で生まれた子どもは母親からの最初の微生物を受け取らないことになります。従来、帝王切開のリスクとして赤ん坊の皮膚に傷がつくことがあるとか、一時的な呼吸障害などの短期的なリスクが指摘されてきました。
しかし、帝王切開で生まれた子の長期的な影響まで言及されることはめったにない。以前はさして害のない代替手段と思われていた帝王切開だが、母子ともに健康リスクがあることが徐々に明らかになってきた。早くにわかったこととして、帝王切開で生まれた赤ん坊は感染症になりやすいというのがある。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した新生児の80%は帝王切開で生まれている。帝王切開で生まれた子は幼児期にアレルギーを発症しやすい。母親がアレルギーで(おそらく遺伝因子があり)、なおかつ帝王切開で生まれた子は、そうでない子より7倍もアレルギーになりやすい。
「同上」p.308
|
その他、自閉症、強迫性障害、1型糖尿病、セリアック病などの発症リスクが、経膣出産(自然出産)よりも高まることが指摘されています。肥満でさえ、帝王切開との関連を指摘するデータがあります。
すでにお気づきのとおり、これらはどれも21世紀病だ。細かく見れば、それぞれに環境要因や遺伝因子など幅広い要素が関係しているものの、帝王切開が21世紀病のリスクを高めているのは明らかだ。
赤ん坊の腸のマイクロバイオータを採取・分析すると、生後数か月が経過していても、その子が帝王切開で生まれたか経膣出産で生まれたかがわかる。産道をとおって生まれた赤ん坊の体外と体内にできている膣由来微生物のコロニーが、帝王切開で生まれた赤ん坊にはできていないのだ。
母親のお腹の「サンルーフ」から(引用注:帝王切開で)出てきた赤ん坊が最初に出合うのは環境中の微生物だ。手袋をはめた手で引っぱり出され、母親の腹部の皮膚をさっとかすめ、不安そうな両親に少しばかり挨拶し、そそくさと手術室から連れ出され、タオルにくるまれ詳細な検査を受ける。消毒が徹底された手術室で生まれる赤ん坊にとってはじめて出合う微生物は、母親と父親、医療スタッフの皮膚の細菌だ(運が悪ければ連鎖球菌や緑膿菌やクロストリジウム・ディフィシルなど強靭な細菌と出合ってしまう)。帝王切開で生まれた赤ん坊の腸のマイクロバイオータは、皮膚の細菌が基礎となって形成される。
「同上」p.308
|
本書に「いまでは開腹手術で最も多い手術が帝王切開」とあります。それほど帝王切開が広まっている。もちろん帝王切開は医療上の重要な手段です。一部の女性にとってはこの方法しか子どもを生む手段がありません。しかしWHOは帝王切開の実施率を全出産の10~15%に収めるべきだとしています。「出産の危険から母子を守る」ことと「帝王切開によるリスクを避ける」ことのバランスをとるためには、この程度の数字が妥当なのです。
赤ちゃんが母親から受け継ぐ微生物環境の第2番目は、母乳由来のものです。
オリゴ糖と総称される糖類があります。これはブドウ糖などの単糖類が数個~10個程度結合したものです。
母乳にはオリゴ糖が含まれていますが、ヒトの消化酵素はオリゴ糖を分解できません。実は、母乳のオリゴ糖は細菌の餌です。1983年に、ジェニー・ブランド=ミラー教授とその夫が行った研究が「母乳に含まれるオリゴ糖の意味」を明らかにしました。
オリゴ糖は単糖が数個結合した炭水化物の総称で、ヒトの母乳には130種類ほどが含まれている。この種類の多さはヒトに特有な性質であり、たとえばウシの乳には数種類のオリゴ糖しか含まれていない。私たちは大人になってからオリゴ糖を含む食品を食べることはない。それなのに、妊娠期と授乳期に女性の乳房組織でつくられる。機能のないものをわざわざつくるのは、そこに重要な何かがあるからだと2人は思った。
ブランド=ミラーと夫は仮説を確かめようと試験をした。赤ん坊にグルコースを水に溶かして与えたときと、精製したオリゴ糖を水に溶かして与えたときの、呼気に含まれる水素量を測定した。グルコースでは水素量が増えなかった。グルコースは小腸で吸収されてしまい、腸内細菌の餌にならなかったということだ。だが、オリゴ糖を与えたときの呼気には水素が大量にあった。オリゴ糖の分子は小腸をそのまま通過して、消化酵素ではなく腸内細菌に分解されていたということだ。
いまでこそ周知されているが、オリゴ糖は赤ん坊の腸の「苗床」で正しい細菌種を栄えさせる役目を果たしている。母乳で育つ赤ん坊には、ラクトバチルス属とビクテリウム属が優勢なマイクロバイオータが育っている。ヒトはオリゴ糖を消化できないが、ビフィドバクテリウム属の細菌は特殊な酵素を生成して、オリゴ糖を唯一の食料源にする。その廃棄物として出るのが短鎖脂肪酸だ。酪酸、酢酸、プロピオン酸は3大短鎖脂肪酸だが、このとき4番目の短鎖脂肪酸である乳酸塩(単に乳酸と呼ばれることもある)が放出される。これが赤ん坊にとって貴重な物質となる。乳酸塩は大腸の細胞に吸収され、赤ん坊の免疫系の発達に重要な役割を果たす。簡単に言うと、大人に食物繊維が必要なように、赤ん坊には母乳に含まれるオリゴ糖が必要なのだ。
細菌の餌となることだけが母乳に含まれるオリゴ糖の役目ではない。人生最初の数日と数週間、赤ん坊の腸のマイクロバイオータはとても単純で不安定だ。特定の細菌がいきなり増えたかと思うと、忽然と消える。肺炎連鎖球菌のような病原性の細菌が1つ入ってきただけで大混乱を起こし、多くの有益な細菌が破壊されることもある。オリゴ糖は混乱した腸内環境を平常に戻す働きをする。病原性細菌はなんらかの破壊行為をする前に、まず腸壁に付着する。そのためには細菌表面にある特別な結合部を使わなければならない。オリゴ糖はその結合部にぴったりはまって、病原性細菌が足場を築くのを阻止する。母乳に含まれる130種類のオリゴ糖のうち、数十種類は特定の病原体に鍵と鍵穴のように結合することがわかっている。
「同上」p.314
|
しかも、母乳のオリゴ糖の量は赤ちゃんの発達とともに変化します。これは赤ちゃんの腸内細菌の変化に対応しています。
母乳の成分は、赤ん坊の成長段階に応じて変わる。出産直後に出る初乳は免疫細胞と抗体に富んでいて、母乳1リットルあたりに小さじ4杯相当のオリゴ糖をたっぷり含んでいる。
数週間たって赤ん坊のマイクロバイオータが安定してくるころ、母乳の中のオリゴ糖含有量は減ってくる。出産後4か月になると1リットルあたり小さじ3杯未満となり、子どもが1歳の誕生日を迎えるころには小さじ1杯未満となる。
「同上」p.315
|
上の引用にもあるように、
母乳には免疫細胞と抗体など、オリゴ糖以外の多様なものが含まれています。その一つが細菌です。これが最初に分かったのは "母乳バンク" でした。母乳バンクを運用する病院は、母親からの献乳を受け、それを母乳育児が困難な赤ちゃんに与えます。このとき、どんなに消毒をして採乳しても献乳の中に細菌が見つかるのです。
消毒の精度を極限まで上げた採乳技術とDNA解析技術を使って調べたところ、献乳の際に見つかる細菌は、もとから母乳にいた細菌だった。赤ん坊の口や母親の乳首から乗り移って混入したのではなく、乳房組織の中に入りこんでいた。いったいどこから? 乳房組織にいる細菌の多くは皮膚によくいる細菌とは違った。つまり、乳房の皮膚から乳汁に侵入したわけではない。乳房組織にいる細菌は、通常は膣や腸にいる乳酸菌だった。母親の糞便を解析すると、腸と母乳にいる細菌は同じだった。これらの微生物は大腸から乳房へと移動したようだ。
血液を調べて移動ルートがわかった。樹状細胞と呼ばれる免疫細胞の中に入って移動していたのだ。樹状細胞は細菌の密入国を手助けすることで知られている。腸を取り囲む厚い免疫組織の中にある樹状細胞は、長い腕(樹状突起)を伸ばして腸内にどんな細菌がいるかをチェックする。そして通常は、病原体を見つけたらそれを飲みこみ、別の免疫細胞(ナチュラルキラー細胞)の軍団がやってきて退治してくれるのを待つ。ところがなんと、樹状細胞は害のない有益な細菌までつかまえて飲みこみ、血流に乗って乳房に運ぶ。
「同上」p.317
|
オリゴ糖だけでなく、母乳に含まれる細菌も時間の経過とともに変化します。
赤ん坊の成長に合わせて母乳のオリゴ糖含有量が変わるように、母乳に含まれる細菌も変わる。生後1日目に必要な微生物は、1か月後、2か月後、6か月後に必要な微生物とは違う。
出産直後の数日に出る初乳には数百種の微生物が入っている。ラクトバチルス属、連鎖球菌属、エンテロコックス属、ブドウ球菌属の細菌はすべて含まれており、その数は1ミリリットルあたり1000個体にもなる。赤ん坊は1日およそ80万個の細菌を母乳のみで摂取していることになる。
やがて母乳に含まれる微生物は数を減らしながら種類を変えていく。出産から数か月たった母乳には、成人の口内にいるのと同じ微生物が入っている。赤ん坊の離乳に備えてのことだろう。
「同上」p.318
|
まとめると、赤ちゃんは母乳から細菌を受け取ると同時に、その細菌の餌になるオリゴ糖も摂取します。その両方が赤ちゃんの成長に従って変化していく。となると、粉ミルクだけで育つ赤ちゃんにはリスクがあることが推定できます。現代の粉ミルクには重要な栄養成分がたくさん加えられていますが、免疫細胞や抗体、オリゴ糖、
生の細菌までは入っていないのです
まず、粉ミルクで育つ赤ん坊は感染症にかかりやすい。母乳だけの赤ん坊に比べ、粉ミルクだけの赤ん坊は、耳感染症になるリスクが2倍、呼吸器感染症で入院するリスクが4倍、胃腸感染症になるリスクが3倍、そして腸の組織が死ぬ壊死性腸炎になるリスクが2.5倍とそれぞれ高くなる。乳幼児突然死症候群で死亡するリスクも2倍だ。
アメリカでの乳児死亡率(1歳未満で死亡する割合)は、母乳で育つ赤ん坊より粉ミルクで育つ赤ん坊のほうが1.3倍も高い。なお、この数字は、妊娠中の喫煙や貧困、教育など多方面の要素を考慮し、また赤ん坊自身の病気のために母乳育児が困難だったケースを除外している。先進国では乳児死亡率はすでに低くなっているので、1歳になる前に死亡する乳児を人数で見ると、母乳育児で1000人のうち2.1人、粉ミルク育児では2.7人である。もちろんこの程度で親が大騒ぎして心配する必要はないが、アメリカで毎年、400万人の赤ん坊が生まれていることを思えば、そのうち720人は、落とさずにすんだ命を落としているのかもしれない。
「同上」p.322
|
母親か赤ちゃん、または両方の理由で母乳育児が不可能な場合があります。その場合は粉ミルクが必要ですが、これはあくまで "やむをえない場合の策" と考えるべきでしょう。
食物繊維の重要性
本書には「あなたはあなたの微生物が食べたものでできている」と題した章があります(第6章)。よく言われるのは「あなたはあなたの食べたものでできている」で、 これはバランスの良い食事が大切だという意味です。そして、ヒトは微生物と共生している以上、微生物に必要な "餌やり" も重要なのです。
イタリアの研究者の調査結果が紹介されています。彼らはブルキナファソ(西アフリカの国)のある村の子どもと、フィレンツェの子どもの比較研究をしました。
ブルキナファソとイタリアの子どもの食事を改めて比べてみると、摂取量が明らかに違う栄養成分が見つかる。それは食物繊維だ。ブルキナファソの食事に大きな割合を占めている野菜、穀類、豆類はどれも繊維質を多く含んでいる。2歳から6歳までのイタリアの子どもが食事で摂取する食物繊維は2%に満たない。ブルキナファソでは3倍以上の6.5%である。
「同上」p.278
|
著者は、先進国では食物繊維の摂取が減っているとし、それをイギリスの具体例で説明しています。
| ・ | イギリスの成人は、1940年代に1日およそ70グラムの食物繊維を摂取していたが、いまでは20グラムに落ちこんだ。
|
| ・ | 1942年には、食料供給が限られていた戦時中だったにもかかわらず、現在のほぼ2倍の野菜を食べていた。
|
| ・ | 典型的な1日の食事でとる新鮮な緑の野菜は、1940年代に7Oグラムだったが、2000年代には27グラムだ。
|
| ・ | 食物繊維に富む豆類、穀類(パンを含む)、ジャガイモも、1940年代以降は減っている。
|
などです。国によって違うとは思いますが、60年程度の長いレンジでみると、このような傾向は日本も同じではないでしょうか。
ブルキナファソの子どもたちのマイクロバイオームを遺伝子解析すると、プレボテラ属とキシラニバクテル属の細菌が75%という高い割合で見つかる。この両グループの細菌には、植物の細胞壁を形成しているキシランとセルロースを分解する酵素をつくる遺伝子がある。ブルキナファソの子どもはプレボテラとキシラニバクテルを腸に棲まわせているおかげで、食事の大半を占める穀類や豆類、野菜から、より多くの栄養を引き出すことができる。
一方、イタリアの子どもの腸にはプレボテラもキシラニバクテルもいない。植物性の餌が常時なければ生き残れない両グループの細菌は、イタリア人の腸内では適応できないからだ。そのかわり、イタリアの子どもの腸内ではフィルミクテス門の細菌が繁栄している。フィルミクテス門は、いくつかのアメリカの研究で肥満に関連していることがわかった分類群である。痩せた人の腸に多いのはバクテロイデーテス門の細菌だ。フィルミクテスとバクテロイデーテスの比率は、イタリアの子どもでは3対1だったのに対し、ブルキナファソの子どもでは1対1であった。
「同上」p.279
|
マイクロバイオータの細菌の種類は食生活によって変化します。アメリカで行われたボランティアによる実験のことが本書に書かれています。この実験では、肉や卵、チーズなど動物性食品を食べるグループと、穀類や豆類、果物、野菜など植物性食品を食べるグループに分けて、腸内微生物がどう変化するかを観察しました。予想どおり、腸内細菌の組成比が変わりました。植物食のグループは植物の細胞壁を分解できるタイプの細菌を急速に増やした一方、動物食のグループは植物好きの細菌を失い、蛋白質を分解し、ビタミンを合成し、炭化した肉に含まれる発癌物質を解毒するタイプの細菌を増やしました。
このように、食生活によってマイクロバイオータは変化します。そして著者は、このことが「
異例なものを食べる集団にはとりわけ役に立つ」と書いていて、そこで日本人のことあげています。
たとえば、寿司好きの日本人にとって海苔は食生活の大きな部分を占める。日本人の多くは、海藻に含まれる炭水化物を分解するポルフィラナーゼという酵素をつくる遺伝子をもつ細菌(バクテロイデス・プレビウス)を腸内に棲まわせている。この遺伝子は元来、海藻の共生菌であるゾベリア・ガラクタニボランスの遺伝子だ。日本人の腸内にいるバクテロイデス・プレビウスは、過去のいつかの時点でゾベリア・ガラクタニボランスの遺伝子を盗み取ったようだ。
「同上」p.280
|
日本に住むヨーロッパ人で海苔や海藻が苦手な人は多いようです。生まれ育ったヨーロッパで海藻を食べる文化がないからですが、それは単なる好き嫌いだけではなく、海藻を分解する細菌を腸に持っていないからなのでしょう。そして多くの日本人がもつこの細菌の遺伝子は、もともと海藻と共生していた細菌から来たものだった ・・・・・・。こういうところにも、進化の速度が速い細菌と共生している意義が認められます。
余談ですが、著者(英国人のアランナ・コリン)は海苔を食べる日本人を「異質なものを食べる」例として書いていますが、ウェールズの海岸地方では(ヨーロッパでは珍しく)海藻を食べます(Wikipediaの「ウェールズ料理」および「レイヴァーブレッド」の項参照)。アランナ・コリンはイングランド出身なのでしょう。もう少し英国の食文化に詳しければこういう表現にはならなかったと思います。
話を食物繊維に戻します。植物性食品に富む食生活は、痩せ型のマイクロバイオータを育てます。なぜそうなるのか。
No.307「人体の9割は細菌(1)」の「21世紀病:肥満」の項で、アッカーマンシア・ムニシフィラという細菌が腸壁の粘膜層を厚くし、細菌由来のリポ多糖(LPS)が血液中に入り込んで脂肪細胞に炎症を起こすのを防ぐ(=従って肥満を防ぐ)ことを書きました。食物繊維の一種であるオリゴフルクトース(=フルクラオリゴ糖)は、腸内のアッカーマンシアを大増殖させることが分かってきました。
さらに微生物が食物繊維を分解するときに出す短鎖脂肪酸が重要な働きを持っています。
じつのところ、重要なのは微生物そのものではなく微生物が食物繊維を分解するときに出す物質、短鎖脂肪酸(SCFA)だ。第3章でも述べたように(引用注:No.307「人体の9割は細菌(1)」の「21世紀病:自閉症」の項)、代表的な3つの短鎖脂肪酸は酢酸、プロピオン酸、酪酸で、微生物が食物繊維を分解したあと大腸に大量にたまる。この微生物の消化活動による副産物は、さまざまな作用の「鍵穴」にぴたりとはまる「鍵」となる。だが、短鎖脂肪酸の働きが私たちの健康に与える影響は、何十年ものあいだ過小評価されてきた。
そんな鍵穴の1つにG蛋白質共役受容体(GPR43)がある。これは免疫細胞の表面にある受容体で、短鎖脂肪酸の鍵がやってきて解錠されるのを待っている。だが、GPR43は何をするためのものなのか? こういうとき生物学では、この受容体をつくる遺伝子の機能を失わせたノックアウト動物がどうなるのかを観察するのが早道だ。
ある研究チームは、GPR43のノックアウト・マウスを使った実験に取り出した。そして、この受容体をもたないマウスはひどい炎症を起こすこと、大腸炎や関節炎、喘息を発症しやすいことを突き止めた。受容体(鍵穴)は正常で、短鎖脂肪酸(鍵)がない場合はどうだろう。無菌マウスの腸には食物繊維を分解する微生物がいないので、鍵をつくることができない。鍵穴はあるのに解錠されない無菌マウスは、やはり炎症系の病気になりやすかった。
この実験結果は、GPR43が微生物とヒト免疫系のコミュニケーション経路であることを意味している。食物繊維好きの微生物は短鎖脂肪酸という鍵をつくって免疫細胞のドアを開け、自分たちを攻撃しないようにというメッセージを伝える(引用注:その結果、炎症が起きない)。GPR43は免疫細胞だけでなく脂肪細胞にもついている。短鎖脂肪酸の鍵が脂肪細胞のGPR43を解錠すると、脂肪細胞は肥大するのをやめて分裂する。脂肪細胞にとっては細胞分裂するのが健全なエネルギー蓄積法だ。さらに、短鎖脂肪酸の鍵でGPR43を解錠するとレプチンが放出され、満腹中枢が刺激される。食物繊維を食べると満腹感が得られるのはこのためだ。
「同上」p.284
|
また、短鎖脂肪酸一つである酪酸は、腸壁の細胞を結合している蛋白質の鎖を強め、腸壁を強固にします。
不健全な微生物集団は、腸壁の上皮細胞を結合させている鎖をゆるめる方向に働く。ゆるんだ腸壁にはすき間ができ、本来な血液中に入ってはいけない物質を通してしまう。その過程で免疫系が刺激されて起こる炎症が、21世紀病のいくつかの原因になっている。酪酸の働きはそのすき間をふさぐことだ。
腸の細胞を結合させている蛋白質の鎖は、人体のあらゆる作用を担っている蛋白質がそうであるように、遺伝子の指示で作られる。だが、ヒトはそうした遺伝子のコントロール権の一部を微生物の譲渡してしまった。腸壁の蛋白質の鎖をつくる遺伝子の発現量を決めているのは微生物だ。酪酸はそのメッセージを伝える。微生物が酪酸を多く出せば出すほど、ヒトの遺伝子は多くの蛋白質の鎖をつくり、腸壁は堅固になる。腸壁を堅固にするのに必要な条件は2つある。まずは正しい微生物だ(特定の食物繊維を小さな分子に分解するビフィイドバクテリウムや、その小さな分子を酪酸に変換するフィーカリバクテリウム・プラウスニッツィ、ロセッブリア・インテスチナリス、エウバクテリウム・レクタレなど)。そしてもう一つは、そうした微生物の餌となる食物繊維をあなたが多く食べることだ。そうすれば、あとは勝手にやってくれる。
「同上」p.286
|
短鎖脂肪酸が、腸内細菌とヒトの細胞のあいだの情報伝達物質になっているわけです。これはちょうど腸内細菌が出すPSAが制御性T細胞を誘導する話(
No.307「人体の9割は細菌(1)」の「21世紀病:免疫関連疾患」の項)とそっくりです。
ヒトが自らの消化酵素で消化できない食物繊維が腸内細菌の餌になり、腸内細菌が食物繊維を消化した「余り」の脂肪酸が重要なメッセージ物質となって炎症などの免疫反応やや脂肪の蓄積がコントロールされる ・・・・・・。
ヒトは細菌と共生し、メリットを与え合い、互いに最適化してきたことがよく分かります。
ここまでで、アランナ・コリン著「あなたの体は9割が細菌」の "さわり" の紹介は終わりです。本書には以上のほかにも、皮膚常在菌や腸疾患、糞便移植(=マイクロバイオータを正常に回復させる)など、興味深い話題があるのですが、省略したいと思います。以降は本書を通読した感想です。
|
本書の原題は「10% Human」で、副題を直訳すると「あなたの体の微生物が、いかに健康と幸福の鍵を握っているか」となる。
|
本書の感想
ヒトと共生している常在菌、特に腸内細菌とそれがヒトにあたえる影響については研究が進み、一般にも知識が広まってきました(NHKでも近年、特集が組まれた)。本書の多くはその "広まりつつある知識" ですが、それを包括的にまとめて記述したところに意義があると思いました。特に、個々の研究テーマについて、その発端から研究の進展を取材してストーリーを追って書いた構成が優れています。また、巻末にあげられている多数の参考文献・論文は、サイエンス・ライターとしての著者の姿勢を明確にしています。
本書のメッセージをシンプルに要約すると、
ヒトは細菌と共生している。それを前提に考えよう
ということだと思います。
ヒトは細菌にメリットを与え、細菌はヒトにメリットを与える。その関係が最適化されて進化してきたのが人体であるということです。この前提に立つと、以下の様なことが見えてきます。
| ・ | すぐに分かることは、ヒトが細菌に与えるメリットとは食べ物だということです。ということは、バランスの良い食事が重要だと理解できます。特に野菜を食べないのはまずい。なぜなら腸内細菌の餌を絶つことになるからです。もちろん、野菜に限らず餌を与えすぎてもいけない。「何事も適度に」です。
|
| ・ | 細菌がヒトに与えているメリットは実感できませんが、我々が健康に過ごすということの多くが共生している細菌と関係していると想像できます。
|
| ・ | 従って、共生細菌を殺してしまう行為はまずい。抗生物質の使用は感染症の原因菌を殺すという本来の目的に止めないと(それでさえ副作用が考えられる)、何が起こるか分かりません。畜産や養殖のコスト削減のためだけに抗生物質を使うなど論外ということになります。
|
| ・ | 食品添加物は大丈夫でしょうか。許可されている添加物はヒトにとって安全という検証がされているはずですが、ヒトと共生している細菌に影響は無いのか、そこまで配慮されているのかが疑問です。食品添加物を一切とらない生活は不可能だと思いますが、なるべく少なくするのが重要でしょう。
|
| ・ | 抗生物質が腸内の細菌を殺すものなら、体につける各種の抗菌剤入り商品は皮膚の常在菌を殺すことになります。抗菌剤のヒトにとってのメリットはない(=メリットよりデメリットが大きい)でしょう。手を洗うなら石鹸で十分です(本書でも指摘してあります)。
|
| ・ | 共生細菌はヒトが外界から取り入れたものです。ということは、自然出産や母乳による育児が大切なことが理解できるし、清潔過ぎる環境で生活するのは問題です。
|
以上のようなことは、「ヒトは細菌と共生するのが前提」と考えれば、最新科学の知識がなくても理解、ないしは推測ができます。本書の訳者の矢野真千子氏は「訳者あとがき」で次のように書いていました。
自分の体を生態系として眺めれば、森林伐採、外来種の持ちこみ、農薬の使用、肥料のやりすぎを警戒すべき理由はいくらでもみつかる。
矢野真千子「訳者あとがき」
「あなたの体は9割が細菌」p.425
|
自然生態系と同じように、
人体生態系(ヒト + 共生微生物)を破壊してはならないし、人体生態系が持続可能なようにするのが、すなわち我々が生きていくということである ・・・・・・。そう理解できるでしょう。
本書を読んで、ヒトは微生物と共生しているという時の "共生" の意味を深く理解できたと感じました。普通 "共生" と言うと、上に書いたように「互いにメリットを与え合っている」という風に理解します。それは正しいのですが、それだけではありません。本書に次のような例が出てきます。
| ◆ | アッカーマンシア・ムシニフィラという細菌が腸壁を覆う粘膜層の表面に棲んでいる。この細菌はヒトの遺伝子に化学信号を送って粘液の分泌を促し、それによって自分たちの棲み処を確保する。そうすると粘膜層が厚くなり、細菌由来のリポ多糖が血液中に入り込むのが阻止される。この結果、脂肪細胞に過剰な脂肪が詰め込まれなくなる(=肥満を防ぐなどの効果)。
|
| ◆ | 腸壁の上皮細胞は蛋白質の鎖でつながっている。この鎖がゆるむと、本来、血液中に入ってはいけない物質が透過し、免疫系を刺激して炎症を起こし、21世紀病の原因の一つになる。
細菌が食物繊維を分解したあとにできる酪酸(短鎖脂肪酸の一つ)は、腸壁の蛋白質の鎖を作る遺伝子の発現量を決めている。微生物が酪酸を多く出せば出すほど、ヒトの遺伝子は多くの蛋白質の鎖を作り、腸壁は堅固になる。
No.308「人体の9割は細菌(2)」の「食物繊維の重要性」
|
| ◆ | バクテロイデス・フラジリスという細菌は、多糖類A(PSA)という物質を産生し、それを微小なカプセルに入れて細胞表面から放出する。このカプセルが大腸で免疫細胞に貪食されると、PSAが制御性T細胞を起動させる。制御性T細胞は他の免疫細胞に、バクテロイデス・フラジリスを攻撃しないようメッセージを送る。
|
| ◆ | 細菌が食物繊維を分解したあと、大腸には短鎖脂肪酸(酢酸、プロピオン酸、酪酸)が大量にたまる。短鎖脂肪酸は免疫細胞の表面にあるG蛋白質共役受容体(GPR43)に結合し、それが細菌を攻撃しないようにというメッセージになる。そのGPR43は脂肪細胞の表面にもあり、そこに短鎖脂肪酸が結合すると脂肪細胞は肥大するのをやめて分裂する(=肥満を防ぐ)。
No.308「人体の9割は細菌(2)」の「食物繊維の重要性」
|
つまりヒトと共生している細菌は、腸の壁を厚くし、腸壁の透過性を減少させ、過剰な免疫反応を防ぎ、脂肪細胞の肥大化を防ぐわけです。これはすなわち、
ヒトはヒトのからだのコントロールの一部を共生微生物にゆだねている
ことを意味します。「ヒトと微生物は共生するように進化してきた」とはそういうことです。改めて共生微生物の重要性を認識させられました。
本書には研究途中の事項もたくさん含まれています。著者も「確かな話はここまでで、ここからは推測である」「断定はできない」「相関関係があるからといって因果関係があるとは限らない」などの表現で、"確実に判明しているのではないこと" を明確にしています。このような記述態度には好感を持ちました。
最後に、本書の大きな特長は文章が優れていることです。おそらく著者と訳者の両方の力量だと思いますが、科学書としては珍しいような出来映えです。科学的知見を一般向けにどう平易に記述し、読者に訴えることができるか。やはり文章力は大切だと感じました。
2023年1月28日の日本経済新聞に、オーストラリアで腸内細菌による難病治療が承認されたとの記事が掲載されました。腸内細菌が人の健康に影響を与えるという認識は既にあたりまえであり、世界の最先端の研究は「腸内細菌を如何に病気の治療(精神疾患やアレルギー疾患の治療も含む)に使うか」ということだと認識できます。
腸内細菌で難病治療 米豪承認
日本も先進医療開始
人の腸内に100兆個存在しているとされる「腸内細菌」を、難病治療に活用する動きが広がっている。2022年11月に難治性感染症に対して腸内細菌を使った治療がオーストラリアで世界で初めて承認されたほか、米国でも同月末に初承認された。日本でも今月から先進医療が始まった。腸内細菌を巡る開発競争が過熱してきた。
腸内には1000種類、100兆個の細菌がいるとされ、乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌、大腸菌やブドウ球菌といった悪玉菌などが、腸内で「細菌叢(そう)」と呼ばれる集団を形成している。生活リズムや食生活など個々人によって状態は異なり、この細菌の集団に働きかけて病気を治療する手法が腸内細菌治療だ。
先陣を切ったのは豪州のスタートアップのバイオームバンクだ。腸内細菌の一つ「クロストリディオイデス・ディフィシル(C・ディフィシル)」による腸炎の治療法として、腸内細菌を活用する製品を開発。22年11月9日に世界で初めて豪州の規制当局から承認を取得した。
C・ディフィシルはほとんどの抗生物質が使えない難治性の感染症。バイオームバンクは健康な人の体内にある腸内細菌の成分を病気の人に移植することで治療につなげる治療法を製品化した。
同様の治療製品の開発は、米国で盛んだ。スイスのバイオ企業のフェリング・ファーマシューティカルズは、腸内細菌の成分を移植する治療製品「レビオタ」を開発。米食品医薬品局(FDA)は22年11月に米国初の製品として承認した。
腸内細菌の可能性は感染症の治療だけではない。近年の研究では、肥満や精神疾患、アレルギー疾患など様々な病気で腸内の細菌集団に異常が起きていることが判明した。細菌集団への介入が新たな治療法につながるとして、世界で開発競争が過熱。調査会社のマーケッツ&マーケッツは、今後数年で治療や診断、研究技術が進展すると想定。市場規模は29年に13億ドル(約1700億円)と、現在の10倍以上に拡大すると予測する。
海外で実用化が進むなか、日本でも腸内細菌の臨床応用が始まった。順天堂大学は今月4日、大腸の粘膜に炎症や潰瘍ができる「潰瘍性大腸炎」に対して、腸内細菌を移植する治療法が先進医療として承認されたと発表。同大の付属病院や金沢大学付属病院などで医療提供を始めた。
世界ではスタートアップを中心に腸内細菌を活用した治療法開発の治験が700件以上進む。
日本では武田薬品工業が仏バイオ企業のエンテロームなどと組み、腸内細菌領域の開発を進めている。ただ企業の参入はごくわずかで「日本は周回遅れ」(国内証券関係者)との声もある。急成長が見込まれる腸内細菌市場。世界の開発競争に乗り遅れないためにも、規制や評価の体制を準備するなど、国をあげて開発を促す体制を整備する必要がありそうだ。(先端医療エディター 高田倫志)
日本経済新聞(2023年1月28日)
|