No.25 - ローマ人の物語(2)宗教の破壊 [本]
(前回より続く)
ローマの衰退
本題のローマの衰退についてです。「ローマ人の物語」は「キリスト教の国教化が、ローマの衰退から滅亡への最後の決定的な要因になった」と言っているのだと思います。このようにダイレクトに書かれた箇所はなかったかと思いますが、その有力な「状況証拠」としては第14巻が「キリストの勝利」題されていることです。これは「ローマの敗北」の裏返しです。
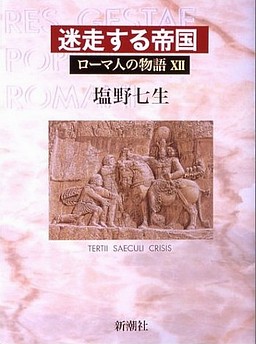 もちろん「キリスト教の国教化」に至った背景には、そうなるぐらいにキリスト教が広まったということがあるわけです。キリスト教徒は最も多い都市で5%と書かれています。5%というと少ないようですが、これ以外に人口の何分の1かの「シンパ」がいるはずだから、それなりの数ではあるわけです。広まった理由としては、経済の混乱や、度重なる外敵の進入、疫病の流行などによるローマ市民の救いを求める心情があるようです。キリスト教徒の拡大の理由については、「第12巻:迷走する帝国」に詳細な分析が書かれています。
もちろん「キリスト教の国教化」に至った背景には、そうなるぐらいにキリスト教が広まったということがあるわけです。キリスト教徒は最も多い都市で5%と書かれています。5%というと少ないようですが、これ以外に人口の何分の1かの「シンパ」がいるはずだから、それなりの数ではあるわけです。広まった理由としては、経済の混乱や、度重なる外敵の進入、疫病の流行などによるローマ市民の救いを求める心情があるようです。キリスト教徒の拡大の理由については、「第12巻:迷走する帝国」に詳細な分析が書かれています。ローマの衰退や滅亡の要因にはキリスト教以外の要因もさまざまなものが考えられます。前回の No.24 「ローマ人の物語 (1) 」にも書いたように、領土が固定化され、奴隷の新規獲得もなくなり、市民権をもつ人が増え、それ以上のローマ化を多くが望まなくなったとき、しかも軍隊が傭兵だらけになったとき、ローマの国家の活力を維持していたダイナミックなメカニズムは働かなくなると思うし、その方が衰退要因としては大きいと感じます。また、No.16「ニーベルングの指環 (指環とは何か) 」で書いたように、3世紀のローマ帝国は猛烈な貨幣価値の下落とインフレが進行するのですが、これも国家経済にとっては致命的事態です。このような経済史からの要因もあるだろうし、No.24「ローマ人の物語 (1) 」の「前提 - 2」で書いたように、環境史からの要因もあるでしょう。さらに「前提 - 3」のように各種要因は原因と結果の連鎖でからまっていて、単独で「取り出す」のは困難なはずです。
しかしキリスト教の国教化がローマ衰退の最後の決定的な要因になった、それがローマの滅亡に向けて「ダメを押した」というのは「ローマ人の物語」全体を読んで納得できました。では、なぜ「キリスト教の国教化」が衰退要因になるのか。その理由について塩野さんの考えは「寛容の喪失」ということに集約されるのではないかと思います。つまりローマは被征服民や異質なものを取り込んで同化し発展してきたが、その根本となっているのは多神教をベースとする「寛容さ」である。これがキリスト教の一神教的性格により決定的に阻害され、この結果「ローマがローマたるゆえん」「ローマの最大の強み」が失われ、崩壊に至った。このようにダイレクトに書かれた箇所もないと思いますが「ローマ人の物語」全15巻を読むと全体としてはそう言っている。「寛容」は「ローマ人の物語」全体をつらぬくキーワードです。
確かにローマの隆盛の要因になった異民族の「同化」は、その根底に「寛容」の精神があるというのは間違いないと思います。しかし「隆盛の要因が寛容である」のは分かるのですが「衰退の要因が寛容の喪失である」というのは、それだけではどうもすっきりしません。もちろん「寛容の喪失」も大きいと思うのですが、私が「ローマ人の物語」を読んでストレートに感じたローマ衰退の理由、つまり「キリスト教の国教化」がなぜ衰退の最後の決定要因になったのかは、非常に単純で以下のようです。
|
キリスト教は一神教であるため、以前からあったローマの宗教に関わるいっさいのもの、皇帝の像、神の像、神殿は破壊され、また一切の宗教行事は取りやめになった。 ローマの多神教をベースとする宗教的情熱、宗教感情は「ローマがローマたるゆえん」「ローマの最大の強み」であった。それが失われてしまい、衰亡を運命づけられた。 |
こう理解する方がシンプルで自然だし、またロジカルです。「ローマ人の物語」読後感とも合っています。以降にこの点について書きます。
宗教の「像」と「施設」の破壊

上の写真は、No.7「ローマのレストランでの驚き」でも紹介したローマのカピトリーノ美術館にある「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」です。実際に行ってみると想像以上に巨大なブロンズ像であることに驚きます。「ローマ人の物語 第13巻:最後の努力」によると、ローマ皇帝の騎馬像は22体存在し、記録によるとカエサルもアウグストゥスもトライアヌスの騎馬像もあった。しかしすべてブロンズであったため、溶解されてしまった。マルクス・アウレリウスの騎馬像が唯一残ったのは、キリスト教を公認したコンスタンティヌスの像と間違われたから、とあります。
ローマ皇帝は死後に神格化され「神」として扱われました(全ての皇帝ではないが)。そして皇帝像は言うに及ばず、ローマ帝国にあったユピテルをはじめとするローマ古来の神々の像は、キリスト教の国教化以降、徹底的に破壊されたようです。
鼻をけずられるなどは、まだ穏やかな排除の方法だった。頭部が打ち落とされ、腕も打ち落とされ、四肢もバラバラになる。これらの作業もめんどうとなれば、崖の上から眼下の岩場に突き落としたり、橋の上から河に突き落としたりして、一挙に処理する方法がとられた。 |
ローマ人はギリシャ彫刻の模作を大量に作りました。これは、ギリシャへ文化への敬愛であり、ローマ人に一貫している寛容の精神によるものだと、塩野さんは言います。これらのギリシャ文化を伝える貴重な模作も破壊されました。
しかし、ハドリアヌス帝の時代という、ローマ時代の模作の質がもっとも高かった時代から200年しか過ぎていない4世紀末、同じローマ人が今度は、かつては大切にし大金を払って購入した傑作の数々を、破壊し河に投げ込むように変わったのだ。寛容とは、辞書には、心が広くおおらかで、他の人の考えも受け容れる、とある。ローマ人が徳の一つとしてさえ考えていた「寛容」(Tolerantia)の精神も、芸術作品の傑作とともに、破壊され捨てられて河に投げ込まれたのである。 |
破壊されたのは、皇帝や神の像だけではありません。当然のことながら神殿も同様です。
ローマ帝国の全域にわたって、その壮麗さで人々の讃嘆を浴びてきた神殿という神殿が、全く姿を消すか、遺ったとしても、崩れ果てた遺跡に変わったのであった。 |
このような破壊活動が「ローマ帝国の全域にわたって」(上記の最後の引用)行われたのです。
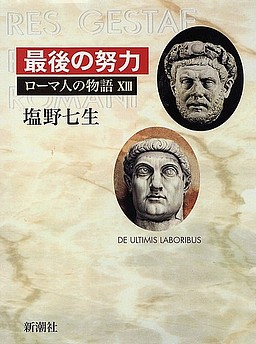
|
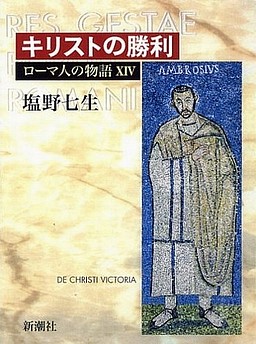
|
ルーブル美術館の「異常」
ルーブル美術館を訪れて「よく考えてみると異常だな」と思うことがあります。ルーブル美術館で最も素晴らしい彫刻は何でしょうか。「ミロのヴィーナス」だというのは衆目の一致するところだと思います。では2番目は ? と言うと、これは答えが分かれるかもしれませんが「サモトラケのニケ像」という意見が多いのではと思います。この2つの彫像は古代ギリシャ・ローマ時代彫像の傑作であると同時に、ルーブル美術館が保有するあらゆる彫像の中でも飛び抜けた「至宝」だと思います。それどころか、ルーブルの全ての美術品から「人類の至宝」を10点だけ厳選してあげよと言われたら、その中に「モナリザ」と並んで「ミロのヴィーナス」と「サモトラケのニケ」を入れるのは、あながち間違ってはいないと思います。いや、10点選ぶなら必ず入る気がする。
それでは、この2つの像はどうやって「発見」されたのかというと、以下のようです。
| ◆ |
ヴィーナス像(愛の女神) エーゲ海のミロス島で、1820年に農地の中からほぼ現在の形発見される。 | |
| ◆ |
ニケ像(勝利の女神) エーゲ海のサモトラケ島(サモトラキ島)で、1863年に断片で発見される。復元されて、現在の形になる。 |

この2つの像とも完全な形ではありません。全部が揃ってはいない。ヴィーナス像は両腕と「手に持っていたかもしれないモノ」がないし、ニケ像に至っては両翼はあるものの、両腕に加えて頭部もありません。つまりエーゲ海の小島から19世紀になってやっとのことで掘り出された、両腕のないヴィーナス像と頭部・両腕のないニケ像が「人類の至宝」となってるのです。この状況はやはり変であり、異常だと考えないといけない。

|

|
| [site : ルーブル美術館] |
ルーブルのミロのビーナス像とサモトラケのニケ像は、確かにすごい芸術品だと思います。しかしギリシャ・ローマ時代にはヴィーナスやニケは人々の敬愛を広く集めた神であり、その彫像も地中海世界にヤマのようにあったはずです。つまり芸術的な観点からルーブルにある像のレベルに達しているヴィーナス像やニケ像は、確率論的に言って、実は昔にはいろいろあったのではないでしょうか。もちろん頭部と両腕が完全に揃っていて、かつ芸術的にも素晴らしい像です。それがほとんど破壊された。
ヴィーナス像は他にも残っているが、ニケ像はほどんどルーブルの像だけだと言います。そう言えば「ニケ」という名前はルーブル美術館へ行って初めてはっきりと認識したような気がします。そういう神がギリシャ・ローマ時代にあったのだと・・・・・・。ニケは英語で言うとナイキです。ドイツのスポーツ・シューズ会社の名前はそこからきているというような知識を世界の人が知ったのは、僅かに残ったニケ像がルーブルにあるからではないでしょうか。またルーブルに僅かに残ったニケ像があるからこそ、そしてそれが船首をかたどった台座の上にあるからこそ、映画「タイタニック」(1997)でケイト・ウィンスレットは船首の甲板の先頭に立ってニケのまねをして見せたのだと思います。彼女が手を横に大きく開くのはニケ像の両翼を模していますね。研究者によると、当然のことながらオリジナルのニケ像にあった両腕は横に大きく開いているわけではありません(神はそんなポーズをしない)。もし仮にルーブルのニケ像に両腕があったとしたら、ケイト・ウィンスレットはあの通りのポーズはしなかったと思います。さらにナイキ社のロゴは翼を図案化したものにならなかったかも知れない。
ニケは紀元前から地中海世界に広まっていたと書きましたが、そのことを想像させるのが南フランスのニースという町です。この町は、もともと紀元前にギリシャ人が建設した町ですが、町の名前の語源がニケなのです。ギリシャを中心に地中海世界に数々あったはずのニケ像は、今となっては頭部と両腕のないルーブルの像を見て「認識」するしかありません。
幸いなことに人間には「想像力」があります。両腕がない、あるいは頭部がない像を見せられると、人間は無意識に完全な姿を想像してしまいます。ニケ像を見るとき、人は暗黙にその人が考えるもっとも美しい姿を思い描いているのでしょう。だからこそ高く評価されるとも言える。しかしこれは「結果論としてそうだ」というだけであって、芸術性を高めるために両腕と頭部を破棄したわけではありません。
ちょっと脇道にそれますが、両腕・頭部がないということに関連して、No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介した中野京子さんの「怖い絵2」に、美術用語である「トルソ」の話が書いてありました。「トルソ」は、頭部や手足のない胴体部のみを造形した彫刻や絵画、またはその概念をさすイタリア語です。これについての、中野さんの解説です。
何といってもトルソという概念は、このルネサンス期に、古代ギリシャ・ローマ彫刻が続々発掘されたことに端を発する。古代遺跡から彫刻を発掘作業する際、強度のある胴体部分は無庇でも、細すぎたり接合部分の弱い四肢や頭部は破損・紛失することが多く、そんな不完全な状態にありながらなおそのプロポーションの素晴らしさが感じられたため、胴体だけでも愛でる価値ありということで、トルソの魅力が発見されたのである。 |
中学校か高校か忘れました。美術室にいくと油絵や胸像が置かれた中にトルソがあったのを覚えています。何だか「不思議な感じ」がすると同時に、何でこんなものがあるのだろうという、ある種の「違和感」感じたものです。その「違和感」の理由が中野さんの解説で分かりました。トルソは、それが美しいと思って人間が作りだしたのではなく、不完全な形に破壊・損傷した断片の中に美を見出そうとしたものだったのです。「違和感」があったとしても当然です。まとめると、トルソという美術概念が成立してしまうほど、古代ギリシャ・ローマ時代の彫刻は、地中から不完全な姿で掘り出される、という形でしか後世に伝えられなかったということだと思います。
古代ギリシャ・ローマ彫刻が「地中から掘り出される形でしか後世に伝えられなかった」理由としては、意図的な破壊か、放置されたか、のどちらかでしょう。放置されると、たとえば地震などで倒壊しても再建はされません。放置とまではいかないまでも、少なくとも「像を守る」ということはなかったはずです。ルーブル美術館のビーナスとニケという個別の像をとってみると、どういう事情で不完全な形で地中に埋まっていたのか、何か特別な事情があったのか、それは分かりません。しかし一般的に言って神々の像が「地中から掘り出される形でしか後世に伝えられなかった」のは、塩野さんが書いているような「意図的な破壊」が大きいはずだし、少なくともそれがトリガーになって派生したさまざまな事象であることは間違いないと思います。
キリスト教を国教としたローマ帝国は、自らの手で、1000年以上の歴史を有する宗教の象徴的な像、しかも芸術的にも素晴らしい数々の像を破壊してしまったというのが実態でしょう。
ここで「1000年以上の歴史を有する宗教を象徴する数々の像がなくなった」ということがどういうことなのか、想像力を発揮する必要があます。日本でも明治時代に廃仏棄釈がありました。しかし幸いなことに国宝級の仏像は多くが残り、全国の寺院の仏像も多くが残っています。もし仏像破壊が徹底的行われ、現代日本に仏像はほとんどなく、もちろん路地端のお地蔵さまもなく、唯一国立博物館にたとえば興福寺の阿修羅王像と法隆寺の救世観音像ぐらいの数点だけが展示されているだけで他に何もないとしたら・・・・・・日本人のアイデンティティの一つが完全に失われているのではないでしょうか。
芸術の破壊
さらに、ローマ帝国にあった神々の像は単なる「宗教上のモニュメント」ではありません。それは明らかに「芸術品」です。しかもこの芸術のレベルは非常に高い。ちょと考えてみると分かるのですがギリシャ・ローマ文化の遺産で、芸術品として、現代の基準からしても最高のものとして通用するのは彫刻です。

|
| カピトリーノのヴィーナス |
それと比較してギリシャ・ローマ文化の絵画、フレスコ画や壷に描かれた絵は「現代の基準からしても最高の芸術品」とは言えない。もちろん歴史資料的価値は大いにあるのですが、ルネサンス以降の近代・現代までの絵画作品と比べてしまうと「見劣り」がします。残念ながら絵画技術が発達していなかったのです。
しかし彫刻は別です。ルーブル美術館の「ミロのヴィーナス」は紀元前の無名の作者によって作られたわけですが、その1500年以上あとに作られたフィレンツェのアカデミア美術館にあるミケランジェロの「ダヴィデ像」と比較して、どちらが芸術作品として素晴らしいかという「愚問」を考えてみると、どちらも同じ様に素晴らしいという答えしかないでしょう。それはちょうど8世紀に作られた奈良の興福寺の国宝・阿修羅王像が、日本の古代から現代までの歴史において、彫像としては最高の「芸術品」の一つであるのとよく似ています。
「皇帝マルクス・アウレリウスの騎馬像」があるカピトリーノ美術館に「カピトリーノのヴィーナス」という立像があります。ローマ時代の彫刻にしては極めてめずらしく全身が完全な形で残っている立像です。この像について塩野さんは大変に印象的な文章を書いています。完全に残りすぎている、おかしい、と・・・・・・。
私の頭の中には一つの仮説が頭をもたげてくるのだった。それは、四世紀末に生きていた誰かが、石棺の中にでも隠して、地中深く埋めたのではないか、という仮説である。 |
もちろん塩野さんも、実証はむずかしく現時点では「空想」だと断っています。しかし作家の直感というのでしょうか、非常にインパクトのある「空想」です。
4世紀後半のローマで起こったことは「1000年以上の歴史を有する宗教を象徴する数々の像がなくなった」だけではなく「地中海世界における最高の芸術品、現代でも十分に通用するレベルの芸術品が破壊された」のです。これがローマ市民の「心」にどういう影響を与えたのか、よく考えてみる必要があるでしょう。
最高の芸術品を前にしたとき、人はその美しさに感動し、あるいは力強さに打たれ、厳粛な気持ちになり、それに愛着を覚えるようになり、それを生み出した郷土や国を誇りに思うでしょう。こういうレベルの「心の動き」は、現代人でもローマ人でも変わらないと確信します。「現代でも十分に通用するほどの、最高レベルの芸術品が破壊された」時の人々の喪失感は巨大なものだったと思います。
オリンピックの終焉
キリスト教が国教になることで、キリスト教以外の宗教行事は皇帝の命令と元老院決議で禁止になりました。この象徴的な例が古代オリンピック(オリンピア大祭)の廃止です。近代オリンピックと違って古代オリンピックは、もちろん宗教行事です。ギリシャの最高神であるゼウスの神に「競技」を捧げるわけです。日本の相撲の発祥と似ています。
古代オリンピックは紀元前776年にに第1回が開催され、西暦393年の第293回まで、実に1169年の長きに渡って行われてきました。テオドシウス帝がキリスト教を国教としたのは、西暦392年です。そのため西暦393年が最後のオリンピックとなったわけです。
古代オリンピックの最大の特徴、それはギリシャの都市国家が戦争をしているときでも、戦争を中断して開催されたことです。塩野さんが「ちなみに私は、戦争中の国や敗北した国の選手を排斥する近代オリンピックを、古代のオリンピア競技会の継承者とは認めていない。」(第14巻:キリストの勝利)とコメントしているほどです。
ここで最も重要なことは「古代オリンピックは都市国家が生きるか死ぬかの戦争をしている時でさえ、それを中断してでも開催するほどギリシャの人々にとっては重要なものであった。それだけ特別なものだった。それをローマ帝国は強権でもって禁止してしまった」ということだと思います。これは「ギリシャ」というある種の地域共同体を崩壊させる行為でしょう。
宗教儀式の禁止
もちろんオリンピックは廃止された宗教祭儀のごく一部であったわけです。ローマでは国家の運営に組み込まれていた公式の祭儀は全廃されました。ローマの祭司は、最高神祀官・神祀官・祭司・占師というヒエラルキーになっていて、その他に女祭司(巫女)があったわけですが、それらはもちろん廃止です。そもそも「ローマ人の物語」の重要な「主人公」であり、ローマ人の典型であるユリウス・カエサルは37才で最高神祀官に当選し、これが彼のキャリアの重要なステップになったのでした。
さらに、公的祭儀だけでなく、私的な祭儀も禁止されました。再び「ローマ人の物語」から引用します。
「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていたのだが、これも偶像崇拝と見なされ、取り払うよう強制された。違反すれば、待っているのは死罪である。」 |
当初のキリスト教の「偶像崇拝の禁止」がこれらの命令の根拠、というかタテマエとなっています。それがタテマエにすぎないことはその後のキリスト教が偶像崇拝だらけになっていくことが証明しています。さらに、当時の皇帝命令では偶像崇拝を知りながら密告しなかった者にも同額の罰金が科せられたと言います(ギボン「ローマ帝国衰亡史」による)。まさにローマ古来の宗教を根絶するための政策が、次から次へと実行されたわけです。
(以降、続く)
2011-04-22 19:31
nice!(0)
トラックバック(1)



