No.344 - 算数文章題が解けない子どもたち [社会]
No.234「教科書が読めない子どもたち」は、国立情報学研究所の新井紀子教授が中心になって実施した「全国読解力調査」(対象は中学・高校生)を紹介したものでした。
この調査の経緯ですが、新井教授は日本数学会の教育委員長として、大学1年生を対象に「大学生数学基本調査」を実施しました。というのも、大学に勤める数学系の教員の多くが、入学してくる学生の学力低下を肌で感じていたからです。この数学基本調査で浮かび上がったのは、そもそも「誤答する学生の多くは問題文の意味を理解できていないのでは」という疑問だったのです。
そこで本格的に子どもたちの読解力を調べたのが「全国読解力調査」でした。その結果は No.234 に概要を紹介した通りです。
ところで最近、小学生の学力の実態を詳細に調べた本が出版されました。慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏(他6名)の「算数文章題が解けない子どもたち ── ことば・思考の力と学力不振」(岩波書店 2022年6月)です(以下「本書」と記述)。新井教授の本とよく似た(文法構造が全く同じの)題名ですが、触発されたのかもしれません。
新井教授は数学者ですが、本書の今井教授は心理学者であり、認知科学(特に言語の発達)や教育心理学が専門です。いわば、読解力を含む「学力」とは何かを研究するプロフェッショナルです。そのテーマは「算数文章題」で、対象は小学3年生・4年生・5年生です。
私は教育関係者ではないし、小学生ないしは就学前の子どもがあるわけでもありません。しかしこの本を大変に興味深く読みました。その理由は、
と感じたからです。著者にそこまでの意図はなかったと思いますが、そういう風にも読める。ということは、要するに "良い本" だということです。そこで是非とも、本書の "さわり" を紹介したいと思います。以下の引用では、原文にはない下線や段落を追加したところがあります。また引用した問題文の漢字には、本書ではルビがふってありますが、省略しました。
問題意識
まず、本書の冒頭に次のように書いてあります。
著者(たち)は広島県教育委員会から「小学生の学力のベースとなる能力を測定し、学力不振の原因を明らかにすることができるアセスメントテストの作成」を依頼されました。県教委からは次のようにあったそうです(この引用の太字と下線は原文通りです)。
その「つまずいている子どもが なぜつまずいているのか」を知る目的で、著者は認知科学と教育心理学の長年の研究成果をもとに、2種類の「たつじんテスト」を開発しました。
の2つです。そして
の成績と「たつじんテスト」の成績の相関関係を統計的に明らかにしました。また、相関関係をみるだけでなく、子どもたちの誤答を詳細に分析し「なぜつまずいているのか」を明らかにしました。この詳細分析が最も重要な点だと言えるでしょう。
本書には「算数文章題テスト」と、2つの「たつじんテスト」の内容、誤答の分析、「算数文章題テスト」と「たつじんテスト」の相関関係、学力を育てる家庭環境とは何かなどが書かれています。それを順に紹介します。
算数文章題テスト
算数文章題テストは、広島県福山市の3つの小学校の3・4・5年生を対象に行われました。調査参加人数は、3年生:167人、4年生:148人、5年生:173人でした。問題は3・4年生用と5年生用に分かれています。
3・4年生用の算数文章題は8問です。いずれも教科書からとられたもので、
です。具体的な問題は次の通りでした。
これらの問題の正答率は次の通りでした。
本書では、このような全体の成績だけでなく、誤答を個別に分析し、誤答を導いた要因(= 子どもの認知のあり方)を推測しています。その例を2つ紹介します。
問題1(列の並び順)
問題1は小学1年の教科書から採られた問題ですが、正答率が衝撃的に低くなりました。3年生の正答率は30%を切り、4年生でも半分程度しか正解できていません
ちなみに、同じ問題を5年生もやりましたが、正答率は72.3% でした。つまり5年生になっても3割の子どもが間違えたわけで、これも衝撃的です。3・4年生の代表的な誤答を調べると次のようになります。まず、
という回答をした子がいます。2桁と1桁の掛け算は正確にできていますが、このタイプの子どもは「文の意味を深く考えず、問題文にある数字を全部使って式を立て、計算をして、何でもよいから答えを出そうという文章題解決に対する考え方を子どもがもっている可能性が高い」(本書)わけです。
そもそも「問題文の状況のイメージを式にできない」子どもがいることも分かりました。問題文のイメージをつかむために、回答用紙に図を描いた子どもはたくさんいます。つまり、14人の列の一人一人を ○ で描いた子どもです。しかしそれをやっても、問題文を正しく絵に出来ない子どもがいる。文章に書かれていることの意味を読み取れないのです。さらに、誤答の中に、
というのがありました。問題文に現れる人数を表す数字は 14 と 7 の2つだけです。従って上のような式になった。この子は「文章に現れる数字(だけ)を使って回答しなければならないという誤ったスキーマ」を持っていると考えられます。
ここで言うスキーマとは認知心理学の用語で「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。言うまでもなく正しい式は、
ですが、式には人数として 1 という、文章には現れない数字が必要であり、それを文章から読み取る必要があるわけです。
また、14 - 7 = 7 (答)7人 という回答をした子どもの中には、正しい図を描いた子もいました。このような誤答は「メタ認知能力」が働いていないと考えられます。
メタ認知能力とは「自分をちょっと離れたところから俯瞰的に眺め、自分の知識の状態や行動を客観的に認知する能力」のことです。批判的思考ができる能力と言ってもよいでしょう。7人が正しい答えかどうか、正しい図を書いているのだから「振り返ってみれば」分かるはずなのです。
問題2(必要ケーキ数)
この問題で多かった誤答の例を2つあげると次のようです。まず、
という答です。この回答は、問題文にある最初の2つの数字だけをみて、しかも問題文を勝手に読み替えています。つまり「ケーキを 4つ入れた箱から 2つを配ると何個残りますか」というような問題に読み替えている。問題文の読み取りが全くできていません。
という答もありました。もちろん問題2の正答は、
ですが、4 × 2 = 8、8 × 3 = 24 という2段階の思考が必要です。このような「マルチステップの認知処理上の負荷を回避する」傾向が誤答を招いた例がよくありした。
本書に「作業記憶と実行機能をうまく働かせられていない」と書いてあります。この問題に正答するためには、4 × 2 = 8 の「8こ」をいったん「作業記憶」にいれ、次には作業記憶の 8 と問題文の 3 だけに着目して(4 と 2 は忘れて)掛け算をする必要があります。心理学で言う「実行機能」の重要な側面は「必要な情報だけに集中し、余計な情報を無視できる認知機能」です。誤答する子どもはこれができないと考えられます。
5年生用の算数文章題は8問です。このうち問題1、4、5、6は3・4年生用の問題と共通です。まとめると次の通りです。
正答率は次の通りでした。
問題12:お菓子の量の問題
誤答の分析から1つだけを紹介します。問題12「お菓子の量の問題」に次のような回答がありました。以下の(図)は、回答用紙の(図)欄に子どもが書いたコメントです。
この回答を書いた子どもは増量の意味が分かっています。30% が 0.3 だということも分かっている。「答は増えるはずだ」という「メタ認知」もちゃんと働いています。しかも、小数での割り算(250 ÷ 0.3)もできて、おおよそですが合っています。何と、本当は掛け算にすべきだということまで分かっている!! そこまで分かっているにも関わらず、正しい立式ができていません。言うまでもなく正しい式は、
ですが、この問題の文章に 1.3 という数字はありません。この子は 30% 増量が 1.3 倍だということが思いつかなかったのです。ないしは2番目の立式のような「マルチステップの思考」ができなかったのです。
この例のように、算数文章題が苦手な子どもは「文章に書かれていない数字を常識で補って推論する」ことがとても苦手です。読解力で大切なのは「文章で使われている言葉の意味をきちんと理解し、常識を含む自分の知識で "行間を補う"」ことなのですが、誤答した多くの子どもはそれができないのです。
算数文章題の誤答分析
以上は3つの誤答の例ですが、3・4・5年生の誤答の全体を分析すると次のようになります。
まず、典型的な誤答では、小数や分数などの数の概念が理解できていないことが顕著でした。小数や分数を理解するためには、整数・分数・小数という演算間の関係性の理解、つまり「数」という "システム" の理解が必要ですが、それが全くできていないのです。つまり「数」の知識が「システム化された数の知識」になっていない。
また時間の計算においては「秒・分・時間・日」の単位変換が苦手なことが顕著でした(3・4・5年生の問題4の正解率参照)。これも「秒・分・時間・日」の概念をバラバラに覚えているだけで「システム化された知識」になっていないのが原因と考えられます。
また、しばしばある誤答の理由は、文章の読みとり(=読解)ができず、従って文章に描かれている状況がイメージできないという点です。その「読解ができない」ことの最大の要因は、推論能力が足りないことです。文章に書かれていないことを、自分のスキーマに従って補って推論する力が足りないのです。
さらに、多くの子供たちが「足し算とかけ算は数を大きくする、引き算と割り算は数を小さくするという誤ったスキーマ」をもっていることが見て取れました。
「誤ったスキーマ」の最たるものが「数はモノを数えるためにある」というスキーマです。数学用語を使うと「すべての数は自然数である」というスキーマです。このスキーマをもっていると、分数・小数の理解が阻害され、その結果として誤答を生み出す。
以上のような要因に加え、作業記憶が必要なマルチステップの問題や、実行機能(ある部分だけを注視して他を無視するなど)が必要な問題では、それによる「認知的負荷」が複合的に加わって、それが誤答を生み出しています。認知的負荷が高いと誤ったスキーマが顔を出す傾向も顕著でした。
ことばのたつじん
「ことばのたつじん」は、算数文章題に答えるための "基礎的な学力" と想定できる「言語力」の測定をするものです。これには、
の3つがあります。
これは "一般的な語彙力" をみるテストで、
の3種があります。「ことばの意味」は30問からなり、そのうちの25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。その例をあげます。
標準問題の例
チャレンジ問題の例
「にていることば」も30問からなり、25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。
標準問題の例
チャレンジ問題の例
「あてはまることば」は、慣用句や慣習的な比喩表現、一つの語から連想される "共起語" の知識をみるものです。29問の「標準問題」(3つの選択肢から1つの正解を選ぶ)と、5問の「チャレンジ問題」(4つの選択肢から2つの正解を選ぶ)から成ります。その例をあげます。
標準問題の例
チャレンジ問題の例
特に成績が悪かった問題の一つは、「ことばのいみ」の中の「期間」を正解とする、次の標準問題でした。
3年生の正答率は「きかん(=正解)」が64%、「きげん」が26%、4年生では「きかん(=正解)」が75%、「きげん」が23% でした。「きかん」と「きげん」と誤答するのは、
といった要因が複合していると推測されます。これらの要因があると正答率が下がるのは「にていることば」でも同様でした。本書に次のような記述があります。
①「語彙の深さと広さ」は一般的な語彙の知識のテストでしたが、②「空間・時間のことば」は、"空間ことば"(前後左右など)と "時間ことば"(2日前、5日後、1週間先など)に絞って、それらを状況に応じて柔軟かつ的確に運用できるかをみるテストです。その例を引用します。
宝物さがし問題(自分と同じ視点)
宝物さがし問題(自分と逆の視点)
この2つの問題の正答率は
でした。全般的に「空間ことば」の問題では、単純な質問では正しく答えられる子どもが多いのですが、上に引用した「宝探し問題」、特に「自分と逆の視点」では正答率が下がります。
「自分と逆の視点」に正解するためには、「視点変更能力」(= 自分以外の視点でものごとを見る力)や、「作業記憶」を使う認知能力、自分の視点を抑制する「実行機能」が必要です。つまり問題解決に必要な情報全体に目配りをしつつ部分を統合する必要があり、それが、部分部分の知識を「生きた知識」として活用できることなのです。
「生きた知識」を持っているかどうかは、他の情報との統合を必要とする "認知の負荷が高い状況" で、個々のことばの知識を本当に使えるのかを評価する必要があることがわかります。
カレンダー問題
上の例では「ちょうど一週間後」を聞いていますが、問題の全体では「あした・ちょうど一週間後・きのう・2日前・5日後・来週の月曜日・ちょうど1週間前・先週の月曜日・5日先・2日後・1週間先・2日先・5日前」の13種の日が、カレンダーでどの日に当たるかを質問しました。
著者は「この問題の正答率の低さに驚いた」と書いています。正答率の低い原因は、時間の関係を表す「前」「後」「先」が "分かりにくい" からです。その理由を著者は次のように書いています。
「先」ということばも曲者です。「さっき言ったでしょう」の「先」は過去ですが、「1週間さき」の「先」は未来です。また、同じ漢字を使う「先週」は過去です。耳からの言葉で覚えた子どもが「さっき」と「さき」を混同するのは分かるし、同じ「先」を使う「先週」を未来だと誤認するのも分かるのです。ちなみに、日本語を母語としない外国人にとって「先」にはとても苦労するそうです。
時間は目に見えない抽象概念であり、もともと子どもには理解しづらいものです。それに加え、日本語では「未来 → 過去」と「過去 → 未来」という2種のモデルが存在し、大人はそれを混在して使っています。子どもが "時間ことば" の理解や使用に苦労するのは当然なのです。
日常的な動作を表す動詞について、システム化された「生きた知識」をもっているかをテストするものです。たとえば、
というような、( )を埋める問題です。このタイプの問題に正答するためには、類似概念を日本語がどのように分割しているかを知っていなければなりません。たとえば身につける動作は、帽子なら「かぶる」、上着なら「きる」、パンツや靴なら「はく」です。かつ、動詞の活用の形(=文法)と統合して答える必要があります。システム化された「生きた知識」があってこそ正答できるのです。
「動作のことば」の回答を分析すると、問題ごとに正解率が大きく違うことがわかります。そして正解率が低いのは「チーズを縦に(裂いて)います」「草を鎌で(刈って)います」などの問題です。これらの動作は、小学生が日常生活で見たり、自分で行ったりすることが少ない動詞です。だから正答率が低い。
逆に、これらの動作の動詞を知っていて的確に使える子どもは、日常会話だけでなく、本などから語彙を学んでいると考えられるのです。
「ことばのたつじん」と学力の関係
「ことばのたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は次のとおりでした。
この相関係数はすべて 0.1% の水準で統計的に有意(その値が偶然によってもたらされる確率が0.1% 以下)でした。
この表を見ると「ことばのたつじん」と学力(この場合は算数文章題)とが、極めて強い相関関係にあることがわかります。特に「空間・時間のことば」です。この傾向は標準学力テスト(国語・算数)との相関係数と同様でした。
かんがえるたつじん
「かず・かたち・かんがえるたつじん」(略称:かんがえるたつじん)は、子どもの思考力のアセスメントです。
の3部から構成されています。
大問1:整数の数直線上の相対位置
0 から 100 までの数直線の上に、与えられた数のだいたいの位置の目印を書き込む問題です。たとえば 18 と提示されたら、それは 20 に近いので、数直線をだいたい 5 分割して、それよりちょっと 0 に近いところに目印をつける、といった感じです。4つの小問(提示数:18, 71, 4, 23)があります。
これは「整数は相対的な大きさを示す」というスキーマを子どもたちが持っているかどうかを見るものです。このスキーマを理解していない子どもは、18 と提示されると定規を取り出して 18mm のところに目印をつけたりします。誤答をする少なからぬ子どもがそうしていました。
大問2:小数・分数の大小関係
どちらが大きいかを問う問題です。12の小問があります。5年生の平均正答率とともに引用します。
小問10、小問11、小問12 は「ケーキの12こ分と13こ分ではどちらがたくさん食べることができますか」のような "文章題" になっています。
特に正答率が悪いのは、小問2, 7, 8 です。小問2 と「同程度に難しいはず」の小問3 の正答率が高いのは(小問2 の正答率より 35% も跳ね上がっている)、小問3では「たまたま分母の数も分子の数も大きい方が大きい」からだと考えられます。
このデータは、少なからぬ子どもが分数や小数の概念的理解ができていないことを示しています。また分数や小数が、いかに直感的にとらえどころがないものかも示しています。
大問3:心的数直線上での小数・分数の相対位置
0 から 1 までの数直線があり、10分割した目盛りがついています。与えられた小数や分数が数直線上のどの位置にあるかの目印をつける問題です。6つの小問があります。
特に成績の悪かったのは、12と25でした。5年生の平均正答率では、12が 46.0%、25が 31.3% でした。
12は日常生活で頻繁に使われます。しかし正答できない子どもは、「ケーキ」のような具体的なモノが与えられずに、「1を基準にしたときにそれに対してどの割合の量なのか」という純粋な「数」としての理解ができていないのです。
25の正答率が異様に低いのは、0 から 1 の数直線に10分割した目盛りが振ってあるからです。つまり正答するためには「2目盛りを1単位としてそれが2つ」という心的操作をしなければならない。これが問題を特に難しくしています。
「1」には、モノを数えるときに「1個ある」という意味と、任意のモノを「1」として、それを分割したり比較のしたりするときの基準の意味があります。「数はモノを数えるもの」という誤ったスキーマを持っていると「基準としての1」が理解できません。この理解なしに分数や小数の意味は理解できないのです。
また大問2・大問3の誤答分析からは、誤答する子どもたちが整数・分数・小数をバラバラに理解していて、それらの関連付けがされていないことがわかります。分数の単元で分数だけ、小数の単元で小数だけという現在の小学校の教え方では「システム化」された知識の習得は難しいのです。
図形の問題です。図形を折る、隠す、回転させるという操作を心の中でできるかどうかです。具体的な問題の例をあげます。
大問4:図形を折ったときのイメージ
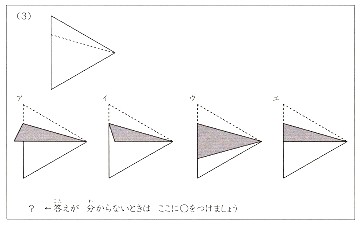
大問5:図形の隠れた部分のイメージ
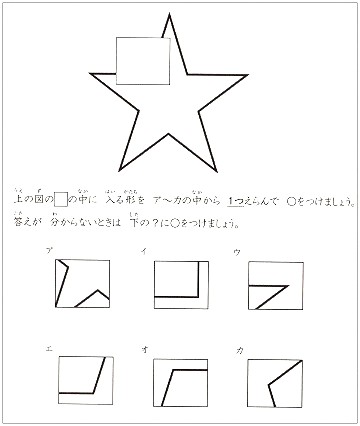
大問6:図形を回転させたときのイメージ
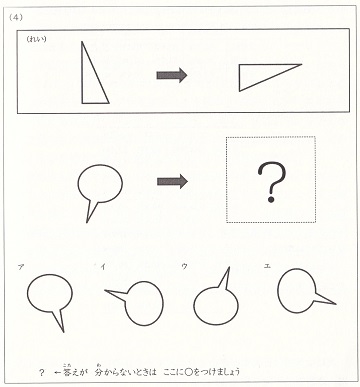
これらの問題に正解するためには「複数のことを同時に処理しなければない」わけです。誤答を分析すると、一つの状況なら楽にできる心的操作が、複数のことを同時に処理しなければらない状況では破綻してしまい、その結果、問題解決に失敗する傾向が見て取れました。
また大問6に顕著ですが、正答する子どもは図形に補助線を引き、補助線が回転後にどうなるかを考えて答を出しています。つまり、図形の回転は認知的負荷が高いのを直感し、負荷を軽減する方略を自分で考えられたので正解できたのです。問題解決のための方略を自分で考えられるのが "できる" 子どもの特徴だと言えます。
「推論」が学力と関係しているという分析は本書のこれまでにもにありましたが、ここでは推論だけを純粋にとりあげます。問題の例を以下にあげます。
大問7:推移的推論
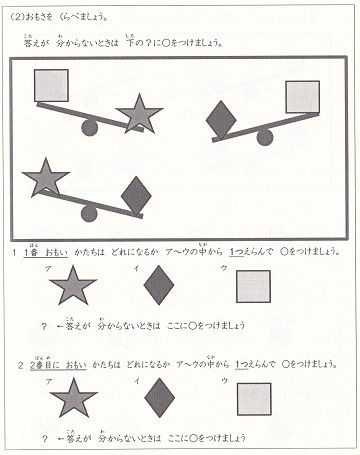
大問8:複数次元の変化を伴う類推
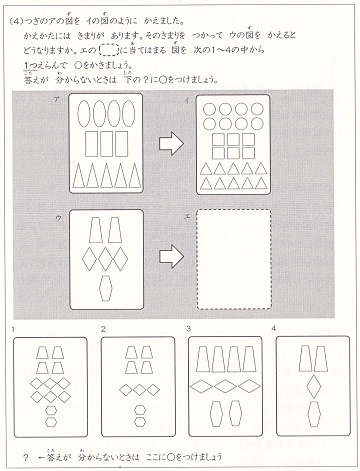
大問9:実行機能を伴う拡張的類推
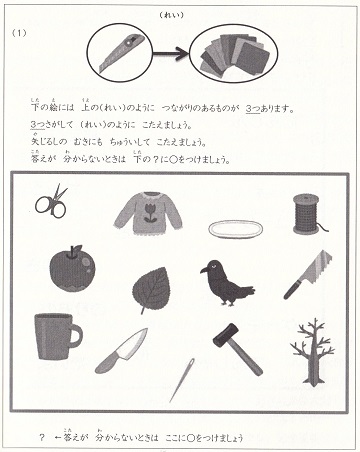
大問9の例に関してですが、この場合の実行機能とは、注意点を取捨選択し、不要な注意点を抑制し、必要に応じて注意点を切り替えられる機能です。またこの例では見本のペアとその向きを常に短期記憶におきつつ、図の中から同じ関係のペアを見いだす必要があります。
絵の中には関係するものが複数あります。たとえば、木は葉っぱや鳥や鋸と関係がある。また糸だと、関係するのはハサミと針です。つまり「見本のペアの関係ではない関係への注意」を抑制する必要がある。これができて正解することができます。
以上の「かんがえるたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は、0.37~0.48 で、高いものでした。最も高かったのが大問8(複数次元の変化を伴う類推)で、その次が 大問2(小数・分数の大小関係)でした。
算数文章題と「たつじん」テストの相関
本書には、次の6つの「たつじんテスト」、
「ことばのたつじん」
「かず・かたち・かんがえるたつじん」
の成績と、算数文章題の成績の相関係数を計算した表が本書にあります。それをみると、3・4年生では6つのテスト中5つが0.5を超え(「動作のことば」だけが0.38)、5年生では5つが 0.39~0.47の範囲になっています(「動作のことば」だけが0.3)。またすべてにおいて、0.1% 水準で有意(=全く偶然にその相関係数になるのは 0.1% 以下の確率)になっています。
ただ、6つの「たつじんテスト」は相互に相関関係があるはずなので、1つのテストが算数文章題と相関をもつと、それにつられて関係のある他のテストも算数文章題と相関します。つまり、どの「たつじんテスト」が算数文章題の成績に "利いて" いるのかは、相関係数だけでは分かりません。
そこで本書には、重回帰分析(説明変数=「たつじんテスト」の成績6種、被説明変数=算数文章題の成績)の結果が載っています。それによると、算数文章題の成績に最も寄与しているのが「空間・時間のことば」でした。これは国語と算数の標準学力テストでも同じでした。
従来からの心理学の研究で、言語能力が学力と深い関わりを持っていることが分かっていて、このことは広く受け入れられています。しかし想定されている「言語能力」とは「語彙のサイズ」(=どれだけ多くの言葉を知っているか)でした。
しかし今回の研究から、「語彙の広さと深さ」よりも「空間・時間のことばの運用」の方が頑健に「学力」を説明することがわかりました。このことは、教育現場で当たり前のようにして使われいている「言語能力」の考え方を見直す必要があることを示しています。
重回帰分析の結果から、「空間・時間のことば」の次には「推論の力」が算数文章題の成績に寄与していることも分かりました。その次が「整数・分数・小数の概念」です。
つまづきの原因
本書では全体の「まとめ」として「第6章:学習のつまずきの原因」と題した章があり、各種のテストでの誤答を分析した結果を総括し、これをもとに教育関係者への提言がされています。この中から「つまずきの原因」の何点かを紹介します。まず、
ことです。これは「たし算・引き算・かけ算・割り算」の関係性が理解できず、それぞれの計算手続きは分かるものの、問題解決に有効に使える知識になってないという意味です。それぞれの単元での学習結果が断片的な知識となっていて「数の世界の、計算というシステム」としての理解になっていない。また、
のもつまずきの原因です。算数文章題の場合、誤ったスキーマの根は一つです。それは「数はモノを数えるためのもの」というスキーマです。このスキーマをもっていると「1」が「全体を表すもの」あるいは「単位を表すもの」という概念が受け入れられません。
「足し算とかけ算は数を増やす計算」と「引き算と割り算は数を減らす計算」という誤ったスキーマもよく見られたものです。これは、まず「増やす計算」と「減らす計算」でそれぞれを教えるからだと考えれます。子どもたちは誤ったスキーマを自分で作り出してしまうのです。
似ているのが「割り算は必ず割り切れる」というスキーマです。これも 12÷4 のような割り切れる数の計算が最初に導入されるからです。誤ったスキーマをもってしまうと、答えが整数にならない割り算を教えられても、なかなか受け入れることができません。本書には「永遠の後出しじゃんけん」という表現を使って次のように書いてあります。
さらに、
のも、つまづきの要因です。「たつじんテスト」で最も強く学力を予測していたのは「空間・時間ことば」でしたが、前・後・左・右はまさに相対的であり、誰を基準にするか、どの点を基準にするかで変わってきます。
また、数直線上に与えられた数の位置を示すには、0~100 あるいは 0~1 というスケールの中で相対的に考える必要がありますが、これができない子どもが多数いました。著者は「驚くほど多かったのはショックだった」と書いています。これは「数」という概念の核である「数の相対性」が理解できていないことを端的に示しています。
「相対的にものごとを見る」ことは「視点を柔軟に変更・変換できる」ことと深い関係があります。そして視点変更の柔軟性は、ことばの多義性の理解につながります。「1」はモノが1個のことであるというスキーマをもった子どもが、「1」は「子ども 140人」でも「水 50リットル」でもよい、「全体」ないしは「単位」を表すものだという認識に進むためには、過去のスキーマの抜本的な修正が必要です。「相対的にものごとを見る能力」=「視点変更の柔軟性」は、誤ったスキーマを修正できる力に関わっています。そして誤ったスキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力なのです。
その他、本書では
などが総括としてまとめられています。
ほんものの学力を生む家庭環境
本書では付録として、テストをうけた児童の保護者に44項目のアンケート調査をし、その結果と子どもの学力(たつじんテストと、国語・算数の標準学力テスト)の相関を示した大変に興味深い表が載っています。44項目の質問は、子どもの基本的生活習慣、家庭学習、しつけの考え方、読書習慣、小学校に入る前のひらがな・数字への関心、小学校に入る前の時間・ひらがな・数字の家庭教育など、多岐にわたります。
これらの中で、最も学力との相関が強かったのは「読書習慣・読み聞かせ」に関する3項目と、「家庭内の本の冊数」に関する2項目でした。その次に相関が強かったのは小学校入学前の「ひらがな・数字への興味・関心」の2項目と「時間・ひらがな・数字の教育」3項目でした。この結果から著者は次のように記しています。
本書の感想
最初に書いたように、本書は、
と思いました。つまり我々大人が社会で生きていく際に必要な思考力の重要な要素を示しているように感じたのです。
たとえばその一つは、「ある目的や機能を遂行する何か」を「システムとしてみる力」です。「システム」として捉えるということは、「何か」が複数のサブシステムからなり、それぞれのサブシステムは固有の目的や機能を持っている。それが有機的かつ相互依存的に結合してシステムとしての目的や機能を果たす。そのサブシステムは、さらに下位の要素からなる、という見方です。これは社会におけるさまざまな組織、自治体、ハードウェア、サービスの仕組み、プロジェクト、学問体系 ・・・・・ などなどを理解し、それらを構築・運用・発展させていく上で必須でしょう。
「相対的に考える」のも重要です。他者からみてどう見えるか、第3者の視点ではどうか、全体を俯瞰するとどうなるのか、対立項が何なのか、全体との対比で部分をみるとどうなるのか、という視点です。
そして、相対的に考える思考力は「スキーマを修正する力」につながります。本書のキーワードの一つである "スキーマ" とは「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。人は必ず何らかのスキーマに基づいて判断します。そして社会において個人が持つ「誤ったスキーマ」の典型は「自らの成功体験からくるスキーマ」です。社会環境が変化すると、そのスキーマには捨てなければならない部分や付け加えなければならないものが出てくる。本書に「スキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力」とありますが、全くその通りです。
さらに「抽象的に考える」ことの重要性です。"良く練られた" 抽象的考えは、より一般性があり、より普遍的で、従ってよりパワーを発揮します。「抽象的でよく分からない、具体的にはどういうことか」というリクエストに答えて具体例を提示することは重要ですが、それは抽象的考えを理解する手だてとして重要なのです。
子どもは小学校から(公式に)抽象の世界に踏み出します。「言葉・語彙」がそうだし「数」がそうです。本書からの引用を再掲しますと、
とありました。抽象性の大きな壁である「9歳の壁」を乗り越えた子どもは、その次の段階へと行けます。これは中学校・高校・大学と「学び」を続ける限り、抽象性の壁を乗り越えることが繰り返されるはずです。だとすると、社会に出てからも繰り返されるはずだし、学校での「学び」はその訓練とも考えられます。
ともかく、10歳前後の小学生の誤答分析から明らかになった「学力」や「思考力」の源泉は、大人の社会に直結していると思いました。
分数は直感的に理解しづらい
最後に一つ、「分数は直感的に理解しづらい」ということの実例を書いておきます。
本書の「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問2:小数・分数の大小関係」のところで、テストの結果データの分析として「多くの子どもたちが、分数や小数の概念的な理解ができていない」と書かれていました。そして「これは、正答できない子どもたちの努力が足りないと片づけてよい問題ではない。分数・小数がいかに直感的に捉えどころがないものかを示すデータなのである」とも書いてありました。
分数で言うと、12や13は「任意の」モノを「1」としたとき、それを「均等に」2分割、あるいは3分割した数です。この「任意の」と「均等に」が非常に抽象的で、捉えどころがないのです。
我々大人は分数を理解していると思っているし、それを使えると思っています。大小関係も分かると自信を持っている。しかし本来「分数は直感的に捉えどころがない」のなら、それは大人にとってもそうであり、ほとんどの場合は正しく使えたとしても、何かの拍子に「捉えどころのなさ」が顔を出すはずです。
そのことを実例で示したような記述が本書にありました。「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問1:整数の数直線上の相対的位置」の説明のところです。どのような問題かを著者が説明した文章です。
えっ! と思いましたが、何度読み直しても、これでは 23 あたりに目印をつけることになります。本書に書いてある採点方法だと、5点満点の 3点(ないしは4点)です。
本書の著者は大学教授の方々、計7名で、原稿は著者の間で何回もレビューし、見直し、確認したはずです。岩波書店に渡った後も、原稿や校正刷りの各段階での何回ものチェックがされたはずです。それでも「100を4分割すると20」になってしまう。どの段階でこうなったかは不明ですが ・・・・・・。
これは単にケアレスミスというより、そもそも「14が分かりにくいから、ないしは15や20100が分かりにくいから」、つまり「分数は抽象的で理解しづらい概念」ということを示していると思います。子どもが算数文章題につまずく理由、その理由の一端を本書が "身をもって" 示しているのでした。
この調査の経緯ですが、新井教授は日本数学会の教育委員長として、大学1年生を対象に「大学生数学基本調査」を実施しました。というのも、大学に勤める数学系の教員の多くが、入学してくる学生の学力低下を肌で感じていたからです。この数学基本調査で浮かび上がったのは、そもそも「誤答する学生の多くは問題文の意味を理解できていないのでは」という疑問だったのです。
そこで本格的に子どもたちの読解力を調べたのが「全国読解力調査」でした。その結果は No.234 に概要を紹介した通りです。
ところで最近、小学生の学力の実態を詳細に調べた本が出版されました。慶応義塾大学 環境情報学部教授の今井むつみ氏(他6名)の「算数文章題が解けない子どもたち ── ことば・思考の力と学力不振」(岩波書店 2022年6月)です(以下「本書」と記述)。新井教授の本とよく似た(文法構造が全く同じの)題名ですが、触発されたのかもしれません。

|
新井教授は数学者ですが、本書の今井教授は心理学者であり、認知科学(特に言語の発達)や教育心理学が専門です。いわば、読解力を含む「学力」とは何かを研究するプロフェッショナルです。そのテーマは「算数文章題」で、対象は小学3年生・4年生・5年生です。
私は教育関係者ではないし、小学生ないしは就学前の子どもがあるわけでもありません。しかしこの本を大変に興味深く読みました。その理由は、
小学生の「算数文章題における学力とは何か」の探求を通して、「人間の思考力とは何か」や「考える力の本質は何か」という問題に迫っている
と感じたからです。著者にそこまでの意図はなかったと思いますが、そういう風にも読める。ということは、要するに "良い本" だということです。そこで是非とも、本書の "さわり" を紹介したいと思います。以下の引用では、原文にはない下線や段落を追加したところがあります。また引用した問題文の漢字には、本書ではルビがふってありますが、省略しました。
問題意識
まず、本書の冒頭に次のように書いてあります。
|
著者(たち)は広島県教育委員会から「小学生の学力のベースとなる能力を測定し、学力不振の原因を明らかにすることができるアセスメントテストの作成」を依頼されました。県教委からは次のようにあったそうです(この引用の太字と下線は原文通りです)。
|
その「つまずいている子どもが なぜつまずいているのか」を知る目的で、著者は認知科学と教育心理学の長年の研究成果をもとに、2種類の「たつじんテスト」を開発しました。
| ことばのたつじん」
→ ことばに関する知識を測る
| |
| かず・かたち・かんがえるたつじん」 | |
| 略称「かんがえるたつじん」)
→ 数と図形に関する知識と推論能力を測る
|
の2つです。そして
| 算数文章題テスト | |
| 主として教科書にある算数文章題) | |
| 国語・算数の標準学力テスト |
の成績と「たつじんテスト」の成績の相関関係を統計的に明らかにしました。また、相関関係をみるだけでなく、子どもたちの誤答を詳細に分析し「なぜつまずいているのか」を明らかにしました。この詳細分析が最も重要な点だと言えるでしょう。
本書には「算数文章題テスト」と、2つの「たつじんテスト」の内容、誤答の分析、「算数文章題テスト」と「たつじんテスト」の相関関係、学力を育てる家庭環境とは何かなどが書かれています。それを順に紹介します。
算数文章題テスト
算数文章題テストは、広島県福山市の3つの小学校の3・4・5年生を対象に行われました。調査参加人数は、3年生:167人、4年生:148人、5年生:173人でした。問題は3・4年生用と5年生用に分かれています。
| 3・4年生:問題とテスト結果 |
3・4年生用の算数文章題は8問です。いずれも教科書からとられたもので、
| :1年生の教科書 | |
| :3年生の教科書 |
です。具体的な問題は次の通りでした。
|
問題1 (順番) | 子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |
|
問題2 (かけ算) | ケーキを4こずつ入れたはこを、1人に2はこずつ3人にくばります。ケーキは、全部で何こいりますか。 |
|
問題3 (時間の引き算1) | けんさんは、午前9時 20 分に家を出て、午前10時40分に遊園地へ着きました。家から遊園地まで、何時間何分かかりましたか。 |
|
問題4 (時間の引き算2) | えりさんは、山道を5時間10分歩きました。山をのぼるのに歩いた時間は、2時間 50 分です。山をくだるのに歩いた時間は、何時間何分ですか。 |
|
問題5 (割り算) | 1まいの画用紙から、カードが8まい作れます。45まいのカードを作るには、画用紙は何まいいりますか。 |
|
問題6 (分数) | りんさんが、ジュースを37L(リットル)のんだので、残りは27L(リットル)になりました。 はじめにジュースは、何 L(リットル)ありましたか。 |
|
問題7 (小数) | リボンが4m ありました。けんたさんが、何m か切り取ったので、リボンは1.7m になりました。けんたさんは、何m 切り取りましたか。 |
|
問題8 (倍率) | なおきさんのテープの長さは、えりさんのテープの長さの4 倍で、48 cm です。えりさんのテープの長さは何cm ですか。 |
これらの問題の正答率は次の通りでした。
| 3年生 | 4年生 | |
| 問題1 順番 | 28.1% | 53.4% |
| 問題2 かけ算 | 57.5% | 72.5% |
| 問題3 時間の引き算1 | 56.0% | 63.4% |
| 問題4 時間の引き算2 | 17.7% | 26.0% |
| 問題5 割り算 | 41.1% | 48.9% |
| 問題6 分数 | 84.4% | 87.0% |
| 問題7 小数 | 48.2% | 63.4% |
| 問題8 倍率 | 45.0% | 62.6% |
本書では、このような全体の成績だけでなく、誤答を個別に分析し、誤答を導いた要因(= 子どもの認知のあり方)を推測しています。その例を2つ紹介します。
問題1(列の並び順)
子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |
問題1は小学1年の教科書から採られた問題ですが、正答率が衝撃的に低くなりました。3年生の正答率は30%を切り、4年生でも半分程度しか正解できていません
ちなみに、同じ問題を5年生もやりましたが、正答率は72.3% でした。つまり5年生になっても3割の子どもが間違えたわけで、これも衝撃的です。3・4年生の代表的な誤答を調べると次のようになります。まず、
(式)14 × 7 = 98 (答)98人 |
という回答をした子がいます。2桁と1桁の掛け算は正確にできていますが、このタイプの子どもは「文の意味を深く考えず、問題文にある数字を全部使って式を立て、計算をして、何でもよいから答えを出そうという文章題解決に対する考え方を子どもがもっている可能性が高い」(本書)わけです。
そもそも「問題文の状況のイメージを式にできない」子どもがいることも分かりました。問題文のイメージをつかむために、回答用紙に図を描いた子どもはたくさんいます。つまり、14人の列の一人一人を ○ で描いた子どもです。しかしそれをやっても、問題文を正しく絵に出来ない子どもがいる。文章に書かれていることの意味を読み取れないのです。さらに、誤答の中に、
(式)14 - 7 = 7 (答)7人 |
というのがありました。問題文に現れる人数を表す数字は 14 と 7 の2つだけです。従って上のような式になった。この子は「文章に現れる数字(だけ)を使って回答しなければならないという誤ったスキーマ」を持っていると考えられます。
ここで言うスキーマとは認知心理学の用語で「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。言うまでもなく正しい式は、
14 - 7 - 1 = 6 |
ですが、式には人数として 1 という、文章には現れない数字が必要であり、それを文章から読み取る必要があるわけです。
また、14 - 7 = 7 (答)7人 という回答をした子どもの中には、正しい図を描いた子もいました。このような誤答は「メタ認知能力」が働いていないと考えられます。
メタ認知能力とは「自分をちょっと離れたところから俯瞰的に眺め、自分の知識の状態や行動を客観的に認知する能力」のことです。批判的思考ができる能力と言ってもよいでしょう。7人が正しい答えかどうか、正しい図を書いているのだから「振り返ってみれば」分かるはずなのです。
問題2(必要ケーキ数)
ケーキを4こずつ入れたはこを、1人に2はこずつ3人にくばります。ケーキは、全部で何こいりますか。 |
この問題で多かった誤答の例を2つあげると次のようです。まず、
(式)4 - 2 = 2 (答)2こ |
という答です。この回答は、問題文にある最初の2つの数字だけをみて、しかも問題文を勝手に読み替えています。つまり「ケーキを 4つ入れた箱から 2つを配ると何個残りますか」というような問題に読み替えている。問題文の読み取りが全くできていません。
(式)4 × 3 = 12 (答)12こ |
という答もありました。もちろん問題2の正答は、
(式)4 × 2 × 3 = 24 (答)24こ |
ですが、4 × 2 = 8、8 × 3 = 24 という2段階の思考が必要です。このような「マルチステップの認知処理上の負荷を回避する」傾向が誤答を招いた例がよくありした。
本書に「作業記憶と実行機能をうまく働かせられていない」と書いてあります。この問題に正答するためには、4 × 2 = 8 の「8こ」をいったん「作業記憶」にいれ、次には作業記憶の 8 と問題文の 3 だけに着目して(4 と 2 は忘れて)掛け算をする必要があります。心理学で言う「実行機能」の重要な側面は「必要な情報だけに集中し、余計な情報を無視できる認知機能」です。誤答する子どもはこれができないと考えられます。
| 5年生:問題とテスト結果 |
5年生用の算数文章題は8問です。このうち問題1、4、5、6は3・4年生用の問題と共通です。まとめると次の通りです。
| :1年生の教科書 | |
| :3年生の教科書 | |
| :5年生の教科書、および作問したもの |
|
問題1 (順番) | 子どもが 14 人、1れつにならんでいます。ことねさんの前に7人います。ことねさんの後ろには、何人いますか。 |
|
問題4 (時間の引き算2) | えりさんは、山道を5時間10分歩きました。山をのぼるのに歩いた時間は、2時間 50 分です。山をくだるのに歩いた時間は、何時間何分ですか。 |
|
問題5 (割り算) | 1まいの画用紙から、カードが8まい作れます。45まいのカードを作るには、画用紙は何まいいりますか。 |
|
問題6 (分数) | りんさんが、ジュースを37 L(リットル)のんだので、残りは27L(リットル)になりました。 はじめにジュースは、何 L(リットル)ありましたか。 |
|
問題9 (距離の計算) | えみさんの家から学校までの距離は 3.6km で、あきらさんの家から学校までの距離より35km 遠いそうです。あきらさんの家から学校までは、何km ですか。 |
|
問題10 | こうたさんの学校の今年の児童数は 476人で、10年前の 200% に当たります。10年前の児童数は何人ですか。 |
|
問題11 | 2時間で108km 走る電車があります。この電車は、3時間で何km 進みますか。 |
|
問題12 (倍率・増量) | 250g入りのお菓子が、30%増量して売られるそうです。お菓子の量は、何gになりますか。 |
正答率は次の通りでした。
| 5年生 | |
| 問題1 順番 | 72.3% |
| 問題4 時間の引き算2 | 53.9% |
| 問題5 割り算 | 59.6% |
| 問題6 分数 | 87.2% |
| 問題9 距離の計算 | 17.7% |
| 問題10 倍率・割り戻し | 55.3% |
| 問題11 速さと距離の計算 | 66.7% |
| 問題12 倍率・増量 | 37.6% |
問題12:お菓子の量の問題
250g入りのお菓子が、30%増量して売られるそうです。お菓子の量は、何gになりますか。 |
誤答の分析から1つだけを紹介します。問題12「お菓子の量の問題」に次のような回答がありました。以下の(図)は、回答用紙の(図)欄に子どもが書いたコメントです。
(式)250 ÷ 0.3 = 800 (答え)800g (図)
ふつうならかけだけど かけにしてしまうと逆に減ってしまうので(0.3だから)÷ にしてふやす
|
この回答を書いた子どもは増量の意味が分かっています。30% が 0.3 だということも分かっている。「答は増えるはずだ」という「メタ認知」もちゃんと働いています。しかも、小数での割り算(250 ÷ 0.3)もできて、おおよそですが合っています。何と、本当は掛け算にすべきだということまで分かっている!! そこまで分かっているにも関わらず、正しい立式ができていません。言うまでもなく正しい式は、
250 × 1.3 = 325 ないしは、 250 × 0.3 = 75 250 + 75 = 325 |
ですが、この問題の文章に 1.3 という数字はありません。この子は 30% 増量が 1.3 倍だということが思いつかなかったのです。ないしは2番目の立式のような「マルチステップの思考」ができなかったのです。
この例のように、算数文章題が苦手な子どもは「文章に書かれていない数字を常識で補って推論する」ことがとても苦手です。読解力で大切なのは「文章で使われている言葉の意味をきちんと理解し、常識を含む自分の知識で "行間を補う"」ことなのですが、誤答した多くの子どもはそれができないのです。
算数文章題の誤答分析
以上は3つの誤答の例ですが、3・4・5年生の誤答の全体を分析すると次のようになります。
まず、典型的な誤答では、小数や分数などの数の概念が理解できていないことが顕著でした。小数や分数を理解するためには、整数・分数・小数という演算間の関係性の理解、つまり「数」という "システム" の理解が必要ですが、それが全くできていないのです。つまり「数」の知識が「システム化された数の知識」になっていない。
また時間の計算においては「秒・分・時間・日」の単位変換が苦手なことが顕著でした(3・4・5年生の問題4の正解率参照)。これも「秒・分・時間・日」の概念をバラバラに覚えているだけで「システム化された知識」になっていないのが原因と考えられます。
また、しばしばある誤答の理由は、文章の読みとり(=読解)ができず、従って文章に描かれている状況がイメージできないという点です。その「読解ができない」ことの最大の要因は、推論能力が足りないことです。文章に書かれていないことを、自分のスキーマに従って補って推論する力が足りないのです。
さらに、多くの子供たちが「足し算とかけ算は数を大きくする、引き算と割り算は数を小さくするという誤ったスキーマ」をもっていることが見て取れました。
「誤ったスキーマ」の最たるものが「数はモノを数えるためにある」というスキーマです。数学用語を使うと「すべての数は自然数である」というスキーマです。このスキーマをもっていると、分数・小数の理解が阻害され、その結果として誤答を生み出す。
以上のような要因に加え、作業記憶が必要なマルチステップの問題や、実行機能(ある部分だけを注視して他を無視するなど)が必要な問題では、それによる「認知的負荷」が複合的に加わって、それが誤答を生み出しています。認知的負荷が高いと誤ったスキーマが顔を出す傾向も顕著でした。
ことばのたつじん
「ことばのたつじん」は、算数文章題に答えるための "基礎的な学力" と想定できる「言語力」の測定をするものです。これには、
| 「語彙の深さと広さ」 | |
| 「空間・時間のことば」 | |
| 「動作のことば」 |
の3つがあります。
| ①「語彙の深さと広さ」 |
これは "一般的な語彙力" をみるテストで、
| ことばのいみ」 | |
| にていることば」 | |
| あてはまることば」 |
の3種があります。「ことばの意味」は30問からなり、そのうちの25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。その例をあげます。
標準問題の例
ねんどなどを 力を 入れて よく まぜること 1. まぶす 2. たたく 3. こねる |
チャレンジ問題の例
おゆが じゅうぶんに あつくなること 1. ほてる 2. ふっとうする 3. わく 4. こみあげる |
「にていることば」も30問からなり、25問は3つの選択肢から1つの正解を選ぶ「標準問題」、5問は4つの選択肢から2つの正解を選ぶ「チャレンジ問題」です。
標準問題の例
ひかくする : もちものを ひかくします。 1. ならべます 2. くらべます 3. しらべます |
チャレンジ問題の例
まず : まず 手を あらいましょう 1. 後で 2. 先に 3. はじめに 4. いちどに |
「あてはまることば」は、慣用句や慣習的な比喩表現、一つの語から連想される "共起語" の知識をみるものです。29問の「標準問題」(3つの選択肢から1つの正解を選ぶ)と、5問の「チャレンジ問題」(4つの選択肢から2つの正解を選ぶ)から成ります。その例をあげます。
標準問題の例
あつい( )を よせています。 1. しんらい 2. 親切 3. しんじつ |
チャレンジ問題の例
( )が 広いです。 1. 顔 2. かかと 3. きもち 4. 心 |
特に成績が悪かった問題の一つは、「ことばのいみ」の中の「期間」を正解とする、次の標準問題でした。
ある日から そのあとの ある日まで 何かが つづくこと 1. きげん 2. きかん 3. しゅるい |
3年生の正答率は「きかん(=正解)」が64%、「きげん」が26%、4年生では「きかん(=正解)」が75%、「きげん」が23% でした。「きかん」と「きげん」と誤答するのは、
| 発音の類似 | |
| 意味の類似 | |
| 漢語である | |
| 抽象名詞である | |
| そもそも時間の概念が抽象概念である |
といった要因が複合していると推測されます。これらの要因があると正答率が下がるのは「にていることば」でも同様でした。本書に次のような記述があります。
|
| ②「空間・時間のことば」 |
①「語彙の深さと広さ」は一般的な語彙の知識のテストでしたが、②「空間・時間のことば」は、"空間ことば"(前後左右など)と "時間ことば"(2日前、5日後、1週間先など)に絞って、それらを状況に応じて柔軟かつ的確に運用できるかをみるテストです。その例を引用します。
宝物さがし問題(自分と同じ視点)
あなたは 友だちと いっしょに 町に 来ました 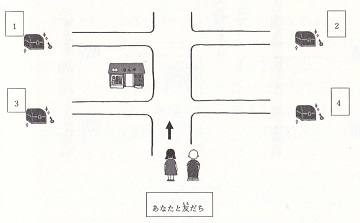 あなたが ほんやの 手前の 道を 右に まがると たからものがあります。 たからものは どこですか。 1ばん 2ばん 3ばん 4ばん |
宝物さがし問題(自分と逆の視点)
あなたは 友だちと いっしょに 町に 来ました 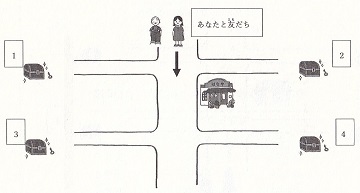 あなたが さいしょの こうさてんで 右に まがると たからものがあります。 たからものは どこですか。 1ばん 2ばん 3ばん 4ばん |
この2つの問題の正答率は
| 同じ視点 | 逆の視点 | |
| 3年生 | 59.1% | 42.7% |
| 4年生 | 72.8% | 55.0% |
でした。全般的に「空間ことば」の問題では、単純な質問では正しく答えられる子どもが多いのですが、上に引用した「宝探し問題」、特に「自分と逆の視点」では正答率が下がります。
「自分と逆の視点」に正解するためには、「視点変更能力」(= 自分以外の視点でものごとを見る力)や、「作業記憶」を使う認知能力、自分の視点を抑制する「実行機能」が必要です。つまり問題解決に必要な情報全体に目配りをしつつ部分を統合する必要があり、それが、部分部分の知識を「生きた知識」として活用できることなのです。
「生きた知識」を持っているかどうかは、他の情報との統合を必要とする "認知の負荷が高い状況" で、個々のことばの知識を本当に使えるのかを評価する必要があることがわかります。
カレンダー問題
りんちゃんの たん生日は 3月14日です。たん生日の ちょうど 一週間後は おわかれ会です。カレンダーの 中から おわかれ会の日を 一つ えらび ○をしましょう。 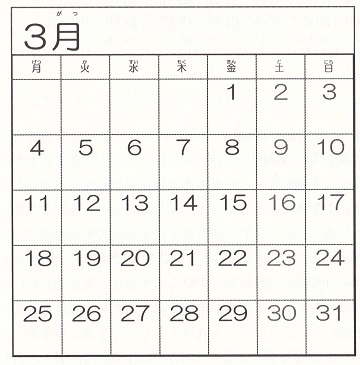 |
上の例では「ちょうど一週間後」を聞いていますが、問題の全体では「あした・ちょうど一週間後・きのう・2日前・5日後・来週の月曜日・ちょうど1週間前・先週の月曜日・5日先・2日後・1週間先・2日先・5日前」の13種の日が、カレンダーでどの日に当たるかを質問しました。
著者は「この問題の正答率の低さに驚いた」と書いています。正答率の低い原因は、時間の関係を表す「前」「後」「先」が "分かりにくい" からです。その理由を著者は次のように書いています。
|
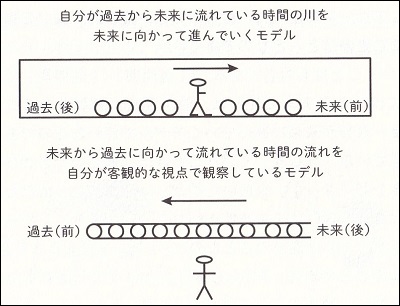
|
2つの時間モデル |
上のモデルでは、過去から未来への時の流れに乗って、自分が未来に向かって進んでいく。下のモデルは、未来から過去に流れる時の流れを、自分が客観的視点から観察している。この2つのモデルで「前」の意味は逆転する。日本語では2つのモデルを混在して使う。 |
「先」ということばも曲者です。「さっき言ったでしょう」の「先」は過去ですが、「1週間さき」の「先」は未来です。また、同じ漢字を使う「先週」は過去です。耳からの言葉で覚えた子どもが「さっき」と「さき」を混同するのは分かるし、同じ「先」を使う「先週」を未来だと誤認するのも分かるのです。ちなみに、日本語を母語としない外国人にとって「先」にはとても苦労するそうです。
時間は目に見えない抽象概念であり、もともと子どもには理解しづらいものです。それに加え、日本語では「未来 → 過去」と「過去 → 未来」という2種のモデルが存在し、大人はそれを混在して使っています。子どもが "時間ことば" の理解や使用に苦労するのは当然なのです。
| ③「動作のことば」 |
日常的な動作を表す動詞について、システム化された「生きた知識」をもっているかをテストするものです。たとえば、
何をしていますか。 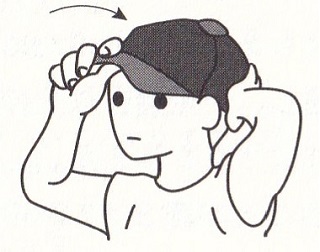 ぼうしを 頭に( )います。 |
というような、( )を埋める問題です。このタイプの問題に正答するためには、類似概念を日本語がどのように分割しているかを知っていなければなりません。たとえば身につける動作は、帽子なら「かぶる」、上着なら「きる」、パンツや靴なら「はく」です。かつ、動詞の活用の形(=文法)と統合して答える必要があります。システム化された「生きた知識」があってこそ正答できるのです。
「動作のことば」の回答を分析すると、問題ごとに正解率が大きく違うことがわかります。そして正解率が低いのは「チーズを縦に(裂いて)います」「草を鎌で(刈って)います」などの問題です。これらの動作は、小学生が日常生活で見たり、自分で行ったりすることが少ない動詞です。だから正答率が低い。
逆に、これらの動作の動詞を知っていて的確に使える子どもは、日常会話だけでなく、本などから語彙を学んでいると考えられるのです。
「ことばのたつじん」と学力の関係
「ことばのたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は次のとおりでした。
| 3年生 | 4年生 | 5年生 | |
| ①語彙の深さと広さ | 0.49 | 0.58 | 0.44 |
| ②空間・時間のことば | 0.58 | 0.67 | 0.47 |
| ③動作のことば | 0.34 | 0.35 | 0.30 |
この相関係数はすべて 0.1% の水準で統計的に有意(その値が偶然によってもたらされる確率が0.1% 以下)でした。
この表を見ると「ことばのたつじん」と学力(この場合は算数文章題)とが、極めて強い相関関係にあることがわかります。特に「空間・時間のことば」です。この傾向は標準学力テスト(国語・算数)との相関係数と同様でした。
|
かんがえるたつじん
「かず・かたち・かんがえるたつじん」(略称:かんがえるたつじん)は、子どもの思考力のアセスメントです。
| 整数・分数・小数の概念 | |
| 図形イメージの心的操作 | |
| 推論の力 |
の3部から構成されています。
| ①整数・分数・小数の概念 |
大問1:整数の数直線上の相対位置
0 から 100 までの数直線の上に、与えられた数のだいたいの位置の目印を書き込む問題です。たとえば 18 と提示されたら、それは 20 に近いので、数直線をだいたい 5 分割して、それよりちょっと 0 に近いところに目印をつける、といった感じです。4つの小問(提示数:18, 71, 4, 23)があります。
これは「整数は相対的な大きさを示す」というスキーマを子どもたちが持っているかどうかを見るものです。このスキーマを理解していない子どもは、18 と提示されると定規を取り出して 18mm のところに目印をつけたりします。誤答をする少なからぬ子どもがそうしていました。
大問2:小数・分数の大小関係
どちらが大きいかを問う問題です。12の小問があります。5年生の平均正答率とともに引用します。
| 小問1 | 13と23 | 94.0% |
| 小問2 | 12と13 | 49.7% |
| 小問3 | 23と12 | 85.9% |
| 小問4 | 0.3 と 0.1 | 96.6% |
| 小問5 | 1 と 0.9 | 98.7% |
| 小問6 | 1.5 と 2 | 99.3% |
| 小問7 | 0.5 と13 | 42.3% |
| 小問8 | 12と 0.7 | 54.4% |
| 小問9 | 0.2 と12 | 82.6% |
| 小問10 | 12と13 | 78.5% |
| 小問11 | 13と23 | 71.8% |
| 小問12 | 13と14 | 69.1% |
小問10、小問11、小問12 は「ケーキの12こ分と13こ分ではどちらがたくさん食べることができますか」のような "文章題" になっています。
特に正答率が悪いのは、小問2, 7, 8 です。小問2 と「同程度に難しいはず」の小問3 の正答率が高いのは(小問2 の正答率より 35% も跳ね上がっている)、小問3では「たまたま分母の数も分子の数も大きい方が大きい」からだと考えられます。
このデータは、少なからぬ子どもが分数や小数の概念的理解ができていないことを示しています。また分数や小数が、いかに直感的にとらえどころがないものかも示しています。
大問3:心的数直線上での小数・分数の相対位置
0 から 1 までの数直線があり、10分割した目盛りがついています。与えられた小数や分数が数直線上のどの位置にあるかの目印をつける問題です。6つの小問があります。
特に成績の悪かったのは、12と25でした。5年生の平均正答率では、12が 46.0%、25が 31.3% でした。
12は日常生活で頻繁に使われます。しかし正答できない子どもは、「ケーキ」のような具体的なモノが与えられずに、「1を基準にしたときにそれに対してどの割合の量なのか」という純粋な「数」としての理解ができていないのです。
25の正答率が異様に低いのは、0 から 1 の数直線に10分割した目盛りが振ってあるからです。つまり正答するためには「2目盛りを1単位としてそれが2つ」という心的操作をしなければならない。これが問題を特に難しくしています。
「1」には、モノを数えるときに「1個ある」という意味と、任意のモノを「1」として、それを分割したり比較のしたりするときの基準の意味があります。「数はモノを数えるもの」という誤ったスキーマを持っていると「基準としての1」が理解できません。この理解なしに分数や小数の意味は理解できないのです。
また大問2・大問3の誤答分析からは、誤答する子どもたちが整数・分数・小数をバラバラに理解していて、それらの関連付けがされていないことがわかります。分数の単元で分数だけ、小数の単元で小数だけという現在の小学校の教え方では「システム化」された知識の習得は難しいのです。
| ②図形イメージの心的操作 |
図形の問題です。図形を折る、隠す、回転させるという操作を心の中でできるかどうかです。具体的な問題の例をあげます。
大問4:図形を折ったときのイメージ
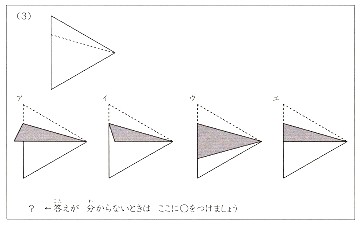
大問5:図形の隠れた部分のイメージ
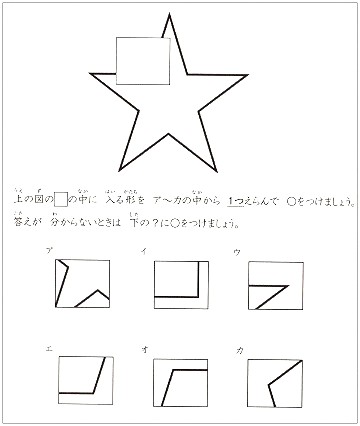
大問6:図形を回転させたときのイメージ
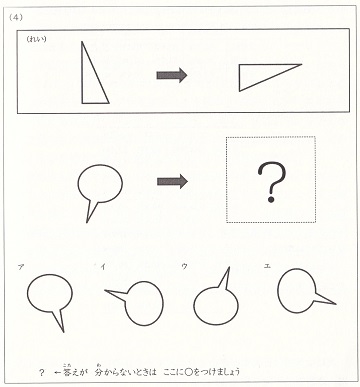
これらの問題に正解するためには「複数のことを同時に処理しなければない」わけです。誤答を分析すると、一つの状況なら楽にできる心的操作が、複数のことを同時に処理しなければらない状況では破綻してしまい、その結果、問題解決に失敗する傾向が見て取れました。
また大問6に顕著ですが、正答する子どもは図形に補助線を引き、補助線が回転後にどうなるかを考えて答を出しています。つまり、図形の回転は認知的負荷が高いのを直感し、負荷を軽減する方略を自分で考えられたので正解できたのです。問題解決のための方略を自分で考えられるのが "できる" 子どもの特徴だと言えます。
| ③推論の力 |
「推論」が学力と関係しているという分析は本書のこれまでにもにありましたが、ここでは推論だけを純粋にとりあげます。問題の例を以下にあげます。
大問7:推移的推論
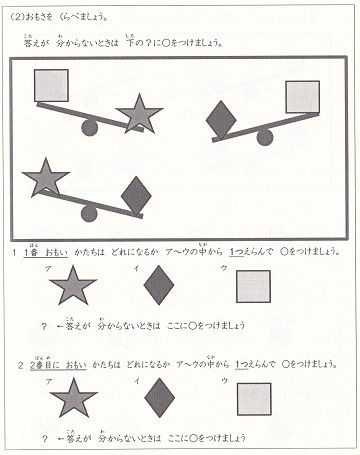
大問8:複数次元の変化を伴う類推
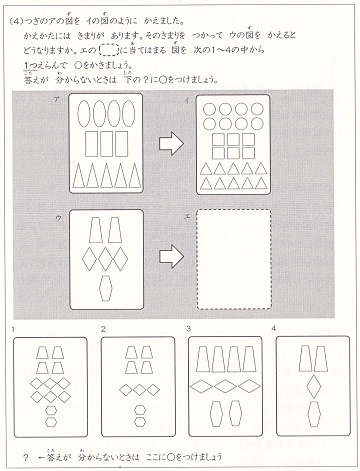
大問9:実行機能を伴う拡張的類推
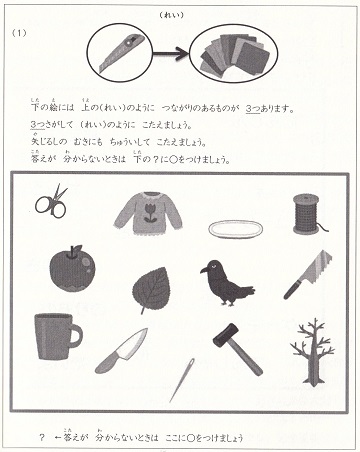
大問9の例に関してですが、この場合の実行機能とは、注意点を取捨選択し、不要な注意点を抑制し、必要に応じて注意点を切り替えられる機能です。またこの例では見本のペアとその向きを常に短期記憶におきつつ、図の中から同じ関係のペアを見いだす必要があります。
絵の中には関係するものが複数あります。たとえば、木は葉っぱや鳥や鋸と関係がある。また糸だと、関係するのはハサミと針です。つまり「見本のペアの関係ではない関係への注意」を抑制する必要がある。これができて正解することができます。
以上の「かんがえるたつじん」と「算数文章題」の得点の相関係数は、0.37~0.48 で、高いものでした。最も高かったのが大問8(複数次元の変化を伴う類推)で、その次が 大問2(小数・分数の大小関係)でした。
算数文章題と「たつじん」テストの相関
本書には、次の6つの「たつじんテスト」、
「ことばのたつじん」
| 語彙の深さと広さ | |
| 空間・時間のことば | |
| 動作のことば |
| 整数・分数・小数の概念 | |
| 図形イメージの心的操作 | |
| 推論の力 |
の成績と、算数文章題の成績の相関係数を計算した表が本書にあります。それをみると、3・4年生では6つのテスト中5つが0.5を超え(「動作のことば」だけが0.38)、5年生では5つが 0.39~0.47の範囲になっています(「動作のことば」だけが0.3)。またすべてにおいて、0.1% 水準で有意(=全く偶然にその相関係数になるのは 0.1% 以下の確率)になっています。
ただ、6つの「たつじんテスト」は相互に相関関係があるはずなので、1つのテストが算数文章題と相関をもつと、それにつられて関係のある他のテストも算数文章題と相関します。つまり、どの「たつじんテスト」が算数文章題の成績に "利いて" いるのかは、相関係数だけでは分かりません。
そこで本書には、重回帰分析(説明変数=「たつじんテスト」の成績6種、被説明変数=算数文章題の成績)の結果が載っています。それによると、算数文章題の成績に最も寄与しているのが「空間・時間のことば」でした。これは国語と算数の標準学力テストでも同じでした。
従来からの心理学の研究で、言語能力が学力と深い関わりを持っていることが分かっていて、このことは広く受け入れられています。しかし想定されている「言語能力」とは「語彙のサイズ」(=どれだけ多くの言葉を知っているか)でした。
しかし今回の研究から、「語彙の広さと深さ」よりも「空間・時間のことばの運用」の方が頑健に「学力」を説明することがわかりました。このことは、教育現場で当たり前のようにして使われいている「言語能力」の考え方を見直す必要があることを示しています。
重回帰分析の結果から、「空間・時間のことば」の次には「推論の力」が算数文章題の成績に寄与していることも分かりました。その次が「整数・分数・小数の概念」です。
つまづきの原因
本書では全体の「まとめ」として「第6章:学習のつまずきの原因」と題した章があり、各種のテストでの誤答を分析した結果を総括し、これをもとに教育関係者への提言がされています。この中から「つまずきの原因」の何点かを紹介します。まず、
知識が断片的でシステムの一部になっていない
ことです。これは「たし算・引き算・かけ算・割り算」の関係性が理解できず、それぞれの計算手続きは分かるものの、問題解決に有効に使える知識になってないという意味です。それぞれの単元での学習結果が断片的な知識となっていて「数の世界の、計算というシステム」としての理解になっていない。また、
誤ったスキーマをもっている
のもつまずきの原因です。算数文章題の場合、誤ったスキーマの根は一つです。それは「数はモノを数えるためのもの」というスキーマです。このスキーマをもっていると「1」が「全体を表すもの」あるいは「単位を表すもの」という概念が受け入れられません。
「足し算とかけ算は数を増やす計算」と「引き算と割り算は数を減らす計算」という誤ったスキーマもよく見られたものです。これは、まず「増やす計算」と「減らす計算」でそれぞれを教えるからだと考えれます。子どもたちは誤ったスキーマを自分で作り出してしまうのです。
似ているのが「割り算は必ず割り切れる」というスキーマです。これも 12÷4 のような割り切れる数の計算が最初に導入されるからです。誤ったスキーマをもってしまうと、答えが整数にならない割り算を教えられても、なかなか受け入れることができません。本書には「永遠の後出しじゃんけん」という表現を使って次のように書いてあります。
|
さらに、
相対的にものごとを見ることができない
のも、つまづきの要因です。「たつじんテスト」で最も強く学力を予測していたのは「空間・時間ことば」でしたが、前・後・左・右はまさに相対的であり、誰を基準にするか、どの点を基準にするかで変わってきます。
また、数直線上に与えられた数の位置を示すには、0~100 あるいは 0~1 というスケールの中で相対的に考える必要がありますが、これができない子どもが多数いました。著者は「驚くほど多かったのはショックだった」と書いています。これは「数」という概念の核である「数の相対性」が理解できていないことを端的に示しています。
「相対的にものごとを見る」ことは「視点を柔軟に変更・変換できる」ことと深い関係があります。そして視点変更の柔軟性は、ことばの多義性の理解につながります。「1」はモノが1個のことであるというスキーマをもった子どもが、「1」は「子ども 140人」でも「水 50リットル」でもよい、「全体」ないしは「単位」を表すものだという認識に進むためには、過去のスキーマの抜本的な修正が必要です。「相対的にものごとを見る能力」=「視点変更の柔軟性」は、誤ったスキーマを修正できる力に関わっています。そして誤ったスキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力なのです。
その他、本書では
| 認知処理能力をコントロールしながら推論する力が弱い、また推論で行間を埋められない | |
| メタ知識が働かず、答えのモニタリングができない | |
| 学習無力感をもっている。何のために算数を学ぶのか分からず、算数の意味を感じ取れていない |
などが総括としてまとめられています。
ほんものの学力を生む家庭環境
本書では付録として、テストをうけた児童の保護者に44項目のアンケート調査をし、その結果と子どもの学力(たつじんテストと、国語・算数の標準学力テスト)の相関を示した大変に興味深い表が載っています。44項目の質問は、子どもの基本的生活習慣、家庭学習、しつけの考え方、読書習慣、小学校に入る前のひらがな・数字への関心、小学校に入る前の時間・ひらがな・数字の家庭教育など、多岐にわたります。
これらの中で、最も学力との相関が強かったのは「読書習慣・読み聞かせ」に関する3項目と、「家庭内の本の冊数」に関する2項目でした。その次に相関が強かったのは小学校入学前の「ひらがな・数字への興味・関心」の2項目と「時間・ひらがな・数字の教育」3項目でした。この結果から著者は次のように記しています。
|
本書の感想
最初に書いたように、本書は、
小学生の「算数文章題における学力とは何か」の探求を通して、「人間の思考力とは何か」や「考える力の本質は何か」という問題に迫っている
と思いました。つまり我々大人が社会で生きていく際に必要な思考力の重要な要素を示しているように感じたのです。
たとえばその一つは、「ある目的や機能を遂行する何か」を「システムとしてみる力」です。「システム」として捉えるということは、「何か」が複数のサブシステムからなり、それぞれのサブシステムは固有の目的や機能を持っている。それが有機的かつ相互依存的に結合してシステムとしての目的や機能を果たす。そのサブシステムは、さらに下位の要素からなる、という見方です。これは社会におけるさまざまな組織、自治体、ハードウェア、サービスの仕組み、プロジェクト、学問体系 ・・・・・ などなどを理解し、それらを構築・運用・発展させていく上で必須でしょう。
「相対的に考える」のも重要です。他者からみてどう見えるか、第3者の視点ではどうか、全体を俯瞰するとどうなるのか、対立項が何なのか、全体との対比で部分をみるとどうなるのか、という視点です。
そして、相対的に考える思考力は「スキーマを修正する力」につながります。本書のキーワードの一つである "スキーマ" とは「人が経験から一般化、抽象化した、無意識に働く思考の枠組み」のことです。人は必ず何らかのスキーマに基づいて判断します。そして社会において個人が持つ「誤ったスキーマ」の典型は「自らの成功体験からくるスキーマ」です。社会環境が変化すると、そのスキーマには捨てなければならない部分や付け加えなければならないものが出てくる。本書に「スキーマを自ら修正できる力は、知識を発展させるための最重要の能力」とありますが、全くその通りです。
さらに「抽象的に考える」ことの重要性です。"良く練られた" 抽象的考えは、より一般性があり、より普遍的で、従ってよりパワーを発揮します。「抽象的でよく分からない、具体的にはどういうことか」というリクエストに答えて具体例を提示することは重要ですが、それは抽象的考えを理解する手だてとして重要なのです。
子どもは小学校から(公式に)抽象の世界に踏み出します。「言葉・語彙」がそうだし「数」がそうです。本書からの引用を再掲しますと、
|
とありました。抽象性の大きな壁である「9歳の壁」を乗り越えた子どもは、その次の段階へと行けます。これは中学校・高校・大学と「学び」を続ける限り、抽象性の壁を乗り越えることが繰り返されるはずです。だとすると、社会に出てからも繰り返されるはずだし、学校での「学び」はその訓練とも考えられます。
ともかく、10歳前後の小学生の誤答分析から明らかになった「学力」や「思考力」の源泉は、大人の社会に直結していると思いました。
分数は直感的に理解しづらい
最後に一つ、「分数は直感的に理解しづらい」ということの実例を書いておきます。
本書の「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問2:小数・分数の大小関係」のところで、テストの結果データの分析として「多くの子どもたちが、分数や小数の概念的な理解ができていない」と書かれていました。そして「これは、正答できない子どもたちの努力が足りないと片づけてよい問題ではない。分数・小数がいかに直感的に捉えどころがないものかを示すデータなのである」とも書いてありました。
分数で言うと、12や13は「任意の」モノを「1」としたとき、それを「均等に」2分割、あるいは3分割した数です。この「任意の」と「均等に」が非常に抽象的で、捉えどころがないのです。
我々大人は分数を理解していると思っているし、それを使えると思っています。大小関係も分かると自信を持っている。しかし本来「分数は直感的に捉えどころがない」のなら、それは大人にとってもそうであり、ほとんどの場合は正しく使えたとしても、何かの拍子に「捉えどころのなさ」が顔を出すはずです。
そのことを実例で示したような記述が本書にありました。「かんがえるたつじん ① 整数・分数・小数の概念」の「大問1:整数の数直線上の相対的位置」の説明のところです。どのような問題かを著者が説明した文章です。
|
えっ! と思いましたが、何度読み直しても、これでは 23 あたりに目印をつけることになります。本書に書いてある採点方法だと、5点満点の 3点(ないしは4点)です。
本書の著者は大学教授の方々、計7名で、原稿は著者の間で何回もレビューし、見直し、確認したはずです。岩波書店に渡った後も、原稿や校正刷りの各段階での何回ものチェックがされたはずです。それでも「100を4分割すると20」になってしまう。どの段階でこうなったかは不明ですが ・・・・・・。
これは単にケアレスミスというより、そもそも「14が分かりにくいから、ないしは15や20100が分かりにくいから」、つまり「分数は抽象的で理解しづらい概念」ということを示していると思います。子どもが算数文章題につまずく理由、その理由の一端を本書が "身をもって" 示しているのでした。
2022-08-31 18:25
nice!(0)
No.268 - 青森は日本一の「短命県」 [社会]
No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」で、都道府県の "幸福度" を数値化する指標の一つである平均寿命を取り上げました。この「都道府県別の平均寿命」は青森県が最下位です。そのことを指して、
と書きました。私は知らなかったのですが、実は「青森は日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、2005年から大がかりなプロジェクトが進んでいます。そのことは最近の新聞で初めて知りました。その認識不足の反省も込めて、今回は進行中のプロジェクトの話を書きます。まず、No.247 で取り上げた「都道府県別の平均寿命」の復習です。
都道府県別の平均寿命
厚生労働省は5年に1回、「生命表」を公表しています。最新は2015年のデータで、ここでは男女別の平均余命が全国および都道府県別に集計されています。ゼロ歳の平均余命が、いわゆる「平均寿命」です。
No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」は、「2018年版 都道府県幸福度ランキング」(日本総合研究所編)の内容を紹介したものでしたが、ここで指標の一つとして使われた平均寿命は、厚生労働省の「道府県別平均寿命データ(2015年)」の男女の平均値でした。つまり男と女の平均寿命を単純平均したもの(小数点以下1桁)です。
今回は、厚生労働省の原データ(小数点以下2桁)から再計算した結果を掲げます。No.247 の表とは微妙に違っていますが、有効数字の違いであり、大筋では同じです。もちろん都道府県の順位は変わりません。表の用語の意味は以下の通りです。
最後に掲げた「平均」は、もちろん「都道府県別平均寿命の平均」です。厚生労働省の原データにおける全国の平均寿命(2015年)は、男:80.77歳、女:87.01歳で、日本人の平均寿命という場合の値がこれです。男女の平均寿命の単純平均は83.89歳になります。
都道府県別の平均寿命を眺めてみると ・・・・・・
表には分かりやすいように「偏差値」を併記しました。大学入試における偏差値の感覚からいうと、
ということになります。「青森は日本一の短命県」とタイトルに書きましたが、その認識は甘いのです。「ダントツの、飛び抜けた短命県」というのが正しい。1位の長野県と47位の青森県の平均寿命の差は約2.4歳なので、大したことないと思えるかもしれません。しかし数値の中身を調べると青森県だけが異常値であることがわかります。
ちなみに、上表は男女の平均値ですが、厚生労働省の原データをみると男女とも青森県が最下位です。男性の1位の滋賀県(81.78歳)と青森県(78.67歳)の寿命の差は3.11歳、女性の1位の長野県(87.67歳)と青森県(85.93)の寿命の差は1.74歳です。
1位の長野県と最下位の青森県が日本におけるリンゴの2大産地なのも気になります。生産量では青森が全国の約60%、長野が約20%で、この2県で日本のリンゴ生産の大半を占めています。英語の有名な諺(ことわざ)に
というのがあります。長野県の平均寿命をみると正しい諺に思えますが、青森県をみると "本当か?" という気になる。もっとも、リンゴに多くの栄養成分が含まれていることは確かな事実ですが ・・・・・・。
岩木健康増進プロジェクト
2019年7月27日の朝日新聞(土曜版)に「岩木健康増進プロジェクト」が紹介されていました。このプロジェクトは弘前大学の特任教授・中路重之氏をリーダとする弘前大学のチームが中心となり、「日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、県や自治体、市民団体とも連携して推進しているプロジェクトです。
健診測定の結果は当日のうちに、生活上の改善点とともに受検者に伝えられ伝えられます。詳細結果は後日、受検者に郵送されます。これは一般的な健康診断と同じで、要するに健康増進を通じて「短命県」を返上しようとする試みです。
ただし「毎年、10日間で、1000人に対し、2000項目のデータをとる」という大規模診断であることが特色で、この規模の調査は世界でも例がないとのことです。実施するのは大変なはずですが、自治体の検診とも連動しており、1日に約300人が検診の対応にあたります。弘前大学の教職員・学生、弘前市の保健職員、企業からの応援、市民の健康リーダーなどです。
短命県である理由
中路教授がこの「岩木健康増進プロジェクト」を立ち上げるまでには数々の苦労があったようです。
「長寿の長野県と比べると、ほとんどの年齢層で青森県の死亡率が大きく上回っている」という主旨が書かれています。この原因は何でしょうか。中路教授は記者のインタビューに次のように答えています。
No.247 に「塩分の取りすぎだと聞いたことがある」と書きましたが、そんな単純な話ではないのですね。「社会の総合力の差」です。それを変えていくには、市民全体の健康意識を増進するしかない。これが「岩木健康増進プロジェクト」の主旨です。
健康ビッグデータの意義
記事には詳しく書いてなかったのですが、15年にわたり1000人の2000項目の健康データが蓄積されているということは、そのビッグデータを解析することで、健康(ないしは疾病)と各種項目の因果関係がデジタル数値で分かることになります。こういったビッグデータの分析が一般に使われる例が「予測」や「予兆の発見」です。つまり疾病の予兆が発見ができ、疾病を回避するための詳細なアドバイスにつながる可能性がある。これは単に岩木地区の弘前市民や青森県民のためだけでもなく、一般的な健康増進に役立つ新たな知見を得ようとするプロジェクトということになります。
このようなプロジェクトの性格上、健康関連の企業が強い関心をもち、プロジェクトに参加しています。
このプロジェクトは、内閣府の「第1回 日本オープンイノベーション大賞(2018年度)」で最高賞(内閣総理大臣賞)を受けました。高齢化社会を迎え、医療費の適正な社会配分を行う為にも健康寿命を伸ばすことが必要です。「岩木健康増進プロジェクト」の "健康ビッグデータ" は、そのための重要データになる可能性が大なのです。弘前大学COIのホームページには、プロジェクトの意義と蓄積しているデータ(の一部)が紹介されています。以下に引用します
「岩木健康増進プロジェクト」は、青森県が「ダントツで最下位の短命県」であるからこそ組織できたものでしょう。他県ではここまでの大プロジェクトを起こすモチベーションを得にくいと思います。しかも青森県がダントツで最下位ということは、もし平均寿命の改善ができたとしたら、その理由と過程が "見える化" しやすいわけです。
中路教授と弘前大学は青森県が日本一の短命県であるということを逆手にとって、世界に類のない「健康ビッグデータ・プロジェクト」を組織化し、地域の健康増進・活性化のみならず、少子高齢化が進む日本全体への貢献をも目指している。その姿勢と努力に感心しました。
健康ビッグデータと倫理規定
上に「岩木健康増進プロジェクト」を推進している弘前大学COIのホームページから図を引用しましたが、このホームページを見て気になることがありました。それは、
という点です。No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」に書いたように、一般的に言って個人に関するビッグデータの解析と分析は、使いようによっては "社会として不都合な状態" を作り出すことになりかねません。つまり、差別を助長したり、プライバシーを侵害したり、人々を階層化したり、一方的な経済的不利益をもたらしたりといった、社会的正義に反する状態です。
たとえば弘前大学COIのホームページによると「岩木健康増進プロジェクト」参加している企業の一つが明治安田生命で、その目的は「未病予測モデルの開発」だとあります。「未病予測モデルの開発」は良いことだと思うし、そのモデルが「疾病の予測」→「疾病の未然防止」→「保険会社の収益向上」→「保険料の引き下げ」→「保険加入者の利益」というような良い循環になれば、社会全体の利益につながります。保険加入者と保険会社の双方が Win-Win になる。
しかしこの「未病予測モデル」が、「疾病の予測」→「疾病のリスクの判明」→「特定個人の保険料のアップ(ないしは保険加入の拒否)」というように保険会社によって使われたとしたら、"皆で助け合う" という保険の本来の主旨を逸脱することになります。もちろん明治安田生命はこういうことをしないでしょうが、No.240 で紹介したキャシー・オニールが力説している通り、数学モデルはこのように使われるリスクが常にあり、その数学モデルへのインプットがビッグデータだということは忘れてはならないと思います。"健康階層社会" や "健康スコア化社会" の到来はまっぴらです。
さらに "コスト" の問題があります。例えば「疾病の予測」が可能になったとして、その為の検査データの取得に高額な費用がかかるとしたら、貧困層はその検査ができないということになりかねません。あるいは健康保険でカバーできるのは「ラフな予測」だが、高額な個人負担をすると「精密な予測」ができるということもありうる。
「疾病の予測」ができたとして、その後の問題もあります。つまり疾病を回避するためにどうするかです。その回避手段が "生活習慣の改善" であれば問題ありません。しかし、ある高額な "治療" をすると疾病が回避できるとなったとき、その "治療" は医療ではないので保険がきかず、個人負担になるはずです。とすると、富裕層しか "治療" が受けられないということも考えられます。
以上はあくまで例ですが、弘前大学としては最低限、健康ビッグデータの利用に関する次のような「原則」を確立する必要かあると思います。つまり、
という原則です。これ以外にも「健康ビッグデータ倫理規定」は、いろいろ必要でしょう。
当然のことならがら弘前大学は、個人データのセキュリティの確保(必須の必須)とともに、倫理規定の検討を十分に行っていると思います。しかし、それがホームページを見る限り分かりません(2019-9-20 現在)。「岩木健康増進プロジェクト」が世界に例を見ない先進的なプロジェクトと言うなら、「健康ビッグデータの倫理規定、データ処理のルール、公的な規制のあり方」についても情報を発信し、世界をリードして欲しいと思いました。
青森県民が塩気の利いた食品(漬け物など)を好むからだという説を聞いたことがありますが、青森県当局としてはその原因を追求し対策をとるべきでしょう。
と書きました。私は知らなかったのですが、実は「青森は日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、2005年から大がかりなプロジェクトが進んでいます。そのことは最近の新聞で初めて知りました。その認識不足の反省も込めて、今回は進行中のプロジェクトの話を書きます。まず、No.247 で取り上げた「都道府県別の平均寿命」の復習です。
都道府県別の平均寿命
厚生労働省は5年に1回、「生命表」を公表しています。最新は2015年のデータで、ここでは男女別の平均余命が全国および都道府県別に集計されています。ゼロ歳の平均余命が、いわゆる「平均寿命」です。
No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」は、「2018年版 都道府県幸福度ランキング」(日本総合研究所編)の内容を紹介したものでしたが、ここで指標の一つとして使われた平均寿命は、厚生労働省の「道府県別平均寿命データ(2015年)」の男女の平均値でした。つまり男と女の平均寿命を単純平均したもの(小数点以下1桁)です。
今回は、厚生労働省の原データ(小数点以下2桁)から再計算した結果を掲げます。No.247 の表とは微妙に違っていますが、有効数字の違いであり、大筋では同じです。もちろん都道府県の順位は変わりません。表の用語の意味は以下の通りです。
| 平均寿命
男性の平均寿命と女性の平均寿命を単純平均したもの。
| |
| 偏差
平均値からのズレ。正か負の値。
| |
| 標準偏差
偏差の2乗を平均したものが分散で、分散の平方根が標準偏差(正の値)
| |
| 標準化変量
偏差を標準偏差で割ったもの(正または負)。つまり標準化変量は、平均がゼロ、標準偏差が1になるようにデータを正規化したもの。
| |
| 偏差値
標準化変量を10倍し、50を足したもの。偏差値は平均が50、標準偏差が10になるようにデータを正規化したもの。大学入試などに使われる学力偏差値と同じ。
|
平均寿命のランキング
| : | 都道府県別生命表(厚生労働省)。調査年は2015年 | |
| : | 男性平均寿命と女性平均寿命の平均 |
| 順位 | 偏差 | 偏差値 | |||
| 1 | 長野 | 84.7125 | 0.8753 | 1.9129 | 69 |
| 2 | 滋賀 | 84.6750 | 0.8378 | 1.8309 | 68 |
| 3 | 福井 | 84.4050 | 0.5678 | 1.2409 | 62 |
| 4 | 京都 | 84.3750 | 0.5378 | 1.1753 | 62 |
| 5 | 熊本 | 84.3550 | 0.5178 | 1.1316 | 61 |
| 6 | 岡山 | 84.3515 | 0.5143 | 1.1239 | 61 |
| 7 | 奈良 | 84.3050 | 0.4678 | 1.0223 | 60 |
| 8 | 神奈川 | 84.2800 | 0.4428 | 0.9677 | 60 |
| 9 | 島根 | 84.2150 | 0.3778 | 0.8256 | 58 |
| 10 | 広島 | 84.2050 | 0.3678 | 0.8038 | 58 |
| 11 | 大分 | 84.1950 | 0.3578 | 0.7819 | 58 |
| 12 | 東京 | 84.1650 | 0.3278 | 0.7164 | 57 |
| 13 | 石川 | 84.1600 | 0.3228 | 0.7054 | 57 |
| 14 | 宮城 | 84.0750 | 0.2378 | 0.5197 | 55 |
| 15 | 山梨 | 84.0350 | 0.1978 | 0.4323 | 54 |
| 16 | 香川 | 84.0300 | 0.1928 | 0.4213 | 54 |
| 17 | 静岡 | 84.0250 | 0.1878 | 0.4104 | 54 |
| 18 | 富山 | 84.0150 | 0.1778 | 0.3886 | 54 |
| 19 | 新潟 | 84.0050 | 0.1678 | 0.3667 | 54 |
| 20 | 兵庫 | 83.9950 | 0.1578 | 0.3449 | 53 |
| 21 | 愛知 | 83.9800 | 0.1428 | 0.3121 | 53 |
| 22 | 千葉 | 83.9350 | 0.0978 | 0.2137 | 52 |
| 23 | 三重 | 83.9250 | 0.0878 | 0.1919 | 52 |
| 24 | 岐阜 | 83.9100 | 0.0728 | 0.1591 | 52 |
| 25 | 福岡 | 83.9000 | 0.0628 | 0.1372 | 51 |
| 26 | 佐賀 | 83.8850 | 0.0478 | 0.1045 | 51 |
| 27 | 沖縄 | 83.8550 | 0.0178 | 0.0389 | 50 |
| 28 | 山形 | 83.7400 | -0.0972 | -0.2124 | 48 |
| 28 | 埼玉 | 83.7400 | -0.0972 | -0.2124 | 48 |
| 30 | 宮崎 | 83.7300 | -0.1072 | -0.2343 | 48 |
| 31 | 群馬 | 83.7250 | -0.1122 | -0.2452 | 48 |
| 32 | 鳥取 | 83.7200 | -0.1172 | -0.2561 | 47 |
| 33 | 山口 | 83.6950 | -0.1422 | -0.3108 | 47 |
| 34 | 長崎 | 83.6750 | -0.1622 | -0.3545 | 46 |
| 35 | 高知 | 83.6350 | -0.2022 | -0.4419 | 46 |
| 36 | 北海道 | 83.5250 | -0.3122 | -0.6823 | 43 |
| 37 | 徳島 | 83.4900 | -0.3472 | -0.7588 | 42 |
| 37 | 愛媛 | 83.4900 | -0.3472 | -0.7588 | 42 |
| 39 | 大阪 | 83.4800 | -0.3572 | -0.7806 | 42 |
| 40 | 鹿児島 | 83.4000 | -0.4372 | -0.9554 | 40 |
| 41 | 茨城 | 83.3050 | -0.5322 | -1.1631 | 38 |
| 42 | 福島 | 83.2600 | -0.5772 | -1.2614 | 37 |
| 43 | 和歌山 | 83.2050 | -0.6322 | -1.3816 | 36 |
| 44 | 栃木 | 83.1700 | -0.6672 | -1.4581 | 35 |
| 45 | 岩手 | 83.1500 | -0.6872 | -1.5018 | 35 |
| 46 | 秋田 | 82.9450 | -0.8922 | -1.9498 | 31 |
| 47 | 青森 | 82.3000 | -1.5372 | -3.3594 | 16 |
| ◆平均 | : | 83.8372(歳) |
| ◆標準偏差 | : | 0.4576(歳) |
最後に掲げた「平均」は、もちろん「都道府県別平均寿命の平均」です。厚生労働省の原データにおける全国の平均寿命(2015年)は、男:80.77歳、女:87.01歳で、日本人の平均寿命という場合の値がこれです。男女の平均寿命の単純平均は83.89歳になります。
都道府県別の平均寿命を眺めてみると ・・・・・・
表には分かりやすいように「偏差値」を併記しました。大学入試における偏差値の感覚からいうと、
| 長野県(69)と滋賀県(68)は素晴らしい成績。3位を6ポイント以上、引き離している。 | |
| 偏差値50以下では、岩手県(35)ぐらいまでが、何とか大学に入れるレベル(ボーダー・フリーの大学は別として)。 | |
| 岩手県より4ポイント低い秋田県(31)は入学不適格。 | |
| 青森県(16)は論外。 |
ということになります。「青森は日本一の短命県」とタイトルに書きましたが、その認識は甘いのです。「ダントツの、飛び抜けた短命県」というのが正しい。1位の長野県と47位の青森県の平均寿命の差は約2.4歳なので、大したことないと思えるかもしれません。しかし数値の中身を調べると青森県だけが異常値であることがわかります。
ちなみに、上表は男女の平均値ですが、厚生労働省の原データをみると男女とも青森県が最下位です。男性の1位の滋賀県(81.78歳)と青森県(78.67歳)の寿命の差は3.11歳、女性の1位の長野県(87.67歳)と青森県(85.93)の寿命の差は1.74歳です。
1位の長野県と最下位の青森県が日本におけるリンゴの2大産地なのも気になります。生産量では青森が全国の約60%、長野が約20%で、この2県で日本のリンゴ生産の大半を占めています。英語の有名な諺(ことわざ)に
An apple a day keeps the doctor away.(1日1個のリンゴは医者を遠ざける)
というのがあります。長野県の平均寿命をみると正しい諺に思えますが、青森県をみると "本当か?" という気になる。もっとも、リンゴに多くの栄養成分が含まれていることは確かな事実ですが ・・・・・・。
岩木健康増進プロジェクト
2019年7月27日の朝日新聞(土曜版)に「岩木健康増進プロジェクト」が紹介されていました。このプロジェクトは弘前大学の特任教授・中路重之氏をリーダとする弘前大学のチームが中心となり、「日本一の短命県」という "汚名" を返上すべく、県や自治体、市民団体とも連携して推進しているプロジェクトです。
|
健診測定の結果は当日のうちに、生活上の改善点とともに受検者に伝えられ伝えられます。詳細結果は後日、受検者に郵送されます。これは一般的な健康診断と同じで、要するに健康増進を通じて「短命県」を返上しようとする試みです。
ただし「毎年、10日間で、1000人に対し、2000項目のデータをとる」という大規模診断であることが特色で、この規模の調査は世界でも例がないとのことです。実施するのは大変なはずですが、自治体の検診とも連動しており、1日に約300人が検診の対応にあたります。弘前大学の教職員・学生、弘前市の保健職員、企業からの応援、市民の健康リーダーなどです。
短命県である理由
中路教授がこの「岩木健康増進プロジェクト」を立ち上げるまでには数々の苦労があったようです。
|
「長寿の長野県と比べると、ほとんどの年齢層で青森県の死亡率が大きく上回っている」という主旨が書かれています。この原因は何でしょうか。中路教授は記者のインタビューに次のように答えています。
|
No.247 に「塩分の取りすぎだと聞いたことがある」と書きましたが、そんな単純な話ではないのですね。「社会の総合力の差」です。それを変えていくには、市民全体の健康意識を増進するしかない。これが「岩木健康増進プロジェクト」の主旨です。
健康ビッグデータの意義
記事には詳しく書いてなかったのですが、15年にわたり1000人の2000項目の健康データが蓄積されているということは、そのビッグデータを解析することで、健康(ないしは疾病)と各種項目の因果関係がデジタル数値で分かることになります。こういったビッグデータの分析が一般に使われる例が「予測」や「予兆の発見」です。つまり疾病の予兆が発見ができ、疾病を回避するための詳細なアドバイスにつながる可能性がある。これは単に岩木地区の弘前市民や青森県民のためだけでもなく、一般的な健康増進に役立つ新たな知見を得ようとするプロジェクトということになります。
このようなプロジェクトの性格上、健康関連の企業が強い関心をもち、プロジェクトに参加しています。
|
このプロジェクトは、内閣府の「第1回 日本オープンイノベーション大賞(2018年度)」で最高賞(内閣総理大臣賞)を受けました。高齢化社会を迎え、医療費の適正な社会配分を行う為にも健康寿命を伸ばすことが必要です。「岩木健康増進プロジェクト」の "健康ビッグデータ" は、そのための重要データになる可能性が大なのです。弘前大学COIのホームページには、プロジェクトの意義と蓄積しているデータ(の一部)が紹介されています。以下に引用します

|
(弘前大学COIのホームページより) |
「岩木健康増進プロジェクト」は、青森県が「ダントツで最下位の短命県」であるからこそ組織できたものでしょう。他県ではここまでの大プロジェクトを起こすモチベーションを得にくいと思います。しかも青森県がダントツで最下位ということは、もし平均寿命の改善ができたとしたら、その理由と過程が "見える化" しやすいわけです。
中路教授と弘前大学は青森県が日本一の短命県であるということを逆手にとって、世界に類のない「健康ビッグデータ・プロジェクト」を組織化し、地域の健康増進・活性化のみならず、少子高齢化が進む日本全体への貢献をも目指している。その姿勢と努力に感心しました。
健康ビッグデータと倫理規定
上に「岩木健康増進プロジェクト」を推進している弘前大学COIのホームページから図を引用しましたが、このホームページを見て気になることがありました。それは、
健康ビッグデータをどのように扱うべきか、その際の倫理規定やルールが書かれていない、特に、健康ビッグデータから得られた知見をもとにして「やっていいこと」と「やってはいけないこと」が書かれていない
という点です。No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」に書いたように、一般的に言って個人に関するビッグデータの解析と分析は、使いようによっては "社会として不都合な状態" を作り出すことになりかねません。つまり、差別を助長したり、プライバシーを侵害したり、人々を階層化したり、一方的な経済的不利益をもたらしたりといった、社会的正義に反する状態です。
たとえば弘前大学COIのホームページによると「岩木健康増進プロジェクト」参加している企業の一つが明治安田生命で、その目的は「未病予測モデルの開発」だとあります。「未病予測モデルの開発」は良いことだと思うし、そのモデルが「疾病の予測」→「疾病の未然防止」→「保険会社の収益向上」→「保険料の引き下げ」→「保険加入者の利益」というような良い循環になれば、社会全体の利益につながります。保険加入者と保険会社の双方が Win-Win になる。
しかしこの「未病予測モデル」が、「疾病の予測」→「疾病のリスクの判明」→「特定個人の保険料のアップ(ないしは保険加入の拒否)」というように保険会社によって使われたとしたら、"皆で助け合う" という保険の本来の主旨を逸脱することになります。もちろん明治安田生命はこういうことをしないでしょうが、No.240 で紹介したキャシー・オニールが力説している通り、数学モデルはこのように使われるリスクが常にあり、その数学モデルへのインプットがビッグデータだということは忘れてはならないと思います。"健康階層社会" や "健康スコア化社会" の到来はまっぴらです。
さらに "コスト" の問題があります。例えば「疾病の予測」が可能になったとして、その為の検査データの取得に高額な費用がかかるとしたら、貧困層はその検査ができないということになりかねません。あるいは健康保険でカバーできるのは「ラフな予測」だが、高額な個人負担をすると「精密な予測」ができるということもありうる。
「疾病の予測」ができたとして、その後の問題もあります。つまり疾病を回避するためにどうするかです。その回避手段が "生活習慣の改善" であれば問題ありません。しかし、ある高額な "治療" をすると疾病が回避できるとなったとき、その "治療" は医療ではないので保険がきかず、個人負担になるはずです。とすると、富裕層しか "治療" が受けられないということも考えられます。
以上はあくまで例ですが、弘前大学としては最低限、健康ビッグデータの利用に関する次のような「原則」を確立する必要かあると思います。つまり、
健康ビッグデータを利用して得られた成果が個人に恩恵をもたらすとき、その恩恵はすべての人が平等に受けられる機会が与えられ、またすべての人が平等な個人負担で受けられる
という原則です。これ以外にも「健康ビッグデータ倫理規定」は、いろいろ必要でしょう。
当然のことならがら弘前大学は、個人データのセキュリティの確保(必須の必須)とともに、倫理規定の検討を十分に行っていると思います。しかし、それがホームページを見る限り分かりません(2019-9-20 現在)。「岩木健康増進プロジェクト」が世界に例を見ない先進的なプロジェクトと言うなら、「健康ビッグデータの倫理規定、データ処理のルール、公的な規制のあり方」についても情報を発信し、世界をリードして欲しいと思いました。
2019-09-20 17:52
nice!(0)
No.265 - AI時代の生き残り術 [社会]
今回は No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きで、「AI時代に我々はどう対応していけばよいのか」というテーマです。まず、今までにAIについて書いた記事を振り返ってみたいと思います。次の15の記事です。
これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。
取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。
AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。
要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。
しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。
No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。
AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。
No.196「東ロボにみるAIの可能性と限界」と No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」は、"ロボットは東大に入れるか。" プロジェクト(略称:東ロボ)を通して分かった、AIの得意と不得意の話でした。東ロボくんは、MARCH・関関同立の特定学部であれば合格ラインに達しました。ただし東大合格は無理で、今後も無理だろうと推測されます。それは、東ロボくんに不得意課目があるからです。
ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。
一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。
No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。
題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。
No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、
ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。
今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。
読解力・論理力・コミュニケーション能力
このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。
新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。
しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。
要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。
新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。
① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。
読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。
② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。
③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。
① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。
私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。
その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。
新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。
次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。
仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。
顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。
新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。
最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。
乱世こそ地道に
このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。
玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、
の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、
となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。
以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。
AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。
| データの見えざる手(1) | |
| データの見えざる手(2) | |
| インフルエンザの流行はGoogleが予測する | |
| ディープマインド | |
| 半沢直樹は機械化できる | |
| 将棋電王戦が暗示するロボット産業の未来 | |
| アルファ碁の着手決定ロジック(1) | |
| アルファ碁の着手決定ロジック(2) | |
| 東ロボにみるAIの可能性と限界 | |
| 囲碁とAI:趙治勲 名誉名人の意見 | |
| AI vs.教科書が読めない子どもたち | |
| 教科書が読めない子どもたち | |
| フランスのAI立国宣言 | |
| 破壊兵器としての数学 | |
| データ階層社会の到来 |
これらの15の記事をテーマごとに分類してみると、次のようになるでしょう。
| ゲーム : No.174, 176, 180, 181, 197 |
取りあげたゲームは囲碁と将棋ですが、この分野におけるAIの進歩は目覚ましいものがあります。2016年に英国・ディープマインド社の "アルファ碁" が世界トップクラスの棋士に勝って大きな話題になりましたが、その後のAIの進歩で名人といえどもAIに勝てなくなりました。囲碁と将棋は "完全情報ゲーム(すべての意思決定の過程が全員にオープンにされているゲーム)" の代表格であり、しかも最も複雑な部類です。この領域ではAIが人間を凌駕したわけです。
AIの特長は進化のスピードが速いことです。特に囲碁や将棋ではAI同士の自己対戦や強化学習で、人間同士の対戦では考えられないほどの対局をこなすことができます。AIの打ち手(指し手)の最適化が猛烈なスピードで進む。No.181「アルファ碁の着手決定ロジック(2)」で、アルファ碁(2015年末の時点の技術)が ① 囲碁の常識をあらかじめ人間がインプットし、かつ ② 人間同士の対局データの機械学習で開発されたことを指して「道は遠い」と書きましたが、その予想はハズレでした。その後2年程度で ① ② が不要なアルファ碁・ゼロ(2017年末)が登場したからです。想像を遙かに越える進化のスピードです。趙治勲 名誉名人が「人間の天才棋士が20年かかるところを、AIは2ヶ月で進歩した」という意味の発言をしていましたが(No.197)まったくその通りです。
要するに、ルールが明快で情報が完全に把握できる領域では AI は人間を凌駕することが明確になったわけです。もちろん実社会ではルールが曖昧であったり、人の感情に左右されたり、あるいは情報が不完全な中での意思決定が必要です。完全情報ゲームのようにはいきません。ゲームのAIは、あくまで非常に "狭い" 世界での話です。
しかしその一方で、ゲームはIT技術の進歩と深く関わってきました。1970年代後半のインベーダー・ゲームは(電卓とともに)マイクロ・プロセッサーの発達を促したし、現在のAIにおける深層学習を効率的に行うGPUという超並列プロセッサーは、ゲームの3D表示で発達してきました。2019年になって、5Gを見据えて Google などが発表した Cloudゲームや、今後広まりそうな VR(ヴァーチャル・リアリティ)を使ったゲームも、IT技術・コンピュータ技術の発達の結果です。ゲームが革新を導くことがよくあります。ゲームを侮ってはいけないのです。
| ビッグデータ + 統計分析 : No.165, 166, 173 |
No.165,166「データの見えざる手」と、No.173「インフルエンザの流行はGoogleが予測する」は、いわゆるビッグデータを収集し、それを統計理論を主体とする数学手法で分析することで、データに含まれる法則や規則性、関係性を見いだし、それを予測や推定や意志決定に役立てるというものでした。これが2010年代にブレイクしたAIの主流の方法論です。文字・画像認識、機械の故障予測、X線・CT画像からの病巣の発見などは、すべてこの方法論によっています。
| AIと倫理 : No.237, 240, 250 |
AI技術は、使い方によっては社会にデメリットをもたらします。つまり格差を助長・固定化したり、不平等をもたらしたり、プライバシーを侵害したり、といった不都合点です。No.237「フランスのAI立国宣言」、No.240「破壊兵器としての数学」、No.250「データ階層社会の到来」は、そういったAI(広くいうと数学、ないしは数学モデル)の危険性と、それを克服するための社会倫理の構築が必要という話でした。
| AIの可能性と限界 : No.196, 233 |
|
ちなみに No.196の「補記」に東ロボくんが全くできなかった英語のリスニング問題(=バースデーケーキの問題)を掲載しました。なぜ受験生ができる問題がAIにとって困難なのか(研究者によると "絶対に無理"とのこと)の一例が良く理解できます。
一般的に「AIが不得意なもの、AIの限界」について語られることが少ないのですが、東ロボはそれを実証的に見極めたという意味で貴重なプロジェクトでした。それは大学入試という限られたものだけれども、大学入試は10代後半の若者の知力が試される普遍的な場です。そこにAIで挑戦したという意義がありました。
| AIによる雇用の変化 : No.175 |
No.175「半沢直樹は機械化できる」は、AIの時代における雇用の変化です。特に、2013年にオックスフォード大学の教授が出した「雇用の未来:我々の仕事はどこまでコンピュータに奪われるか?」では、現存する職種の47%がAIに奪われるという推定があり、それがセンセーショナルに報道されました(AIの専門家による70職種の推測を、数学モデルで700職種に拡大したもの)。
題名の「半沢直樹」は銀行マンで「融資の妥当性を判断する業務」の担当です。この仕事は機械化できるという予測が2013年頃に立てられたのですが、それから6年後の現在では「AIによる融資判断」が花盛りの状態です。予測通りに事態が進行して来ているようです。
| AIの時代に必要なスキル : No.234, 235 |
No.234「教科書が読めない子どもたち」は東ロボのプロジェクトを主導した国立情報学研究所の新井紀子教授が実施したリーディング・スキル・テスト(Reading Skill Test。RST)で判明した驚くべき事実でした。RSTの "ミソ" は、
東ロボ・プロジェクトで分かった読解力についてのAIの得意・不得意が、小中高校生ならどうかが分析できるようにテスト設計がされている
ことです。AIが不得意な分野こそ人間が優位に立てるはずなのに、意外にもその分野では人間も正解率が悪いことが分かった。このままではAI時代についていけない人が多数発生する、というのが新井教授の危機感でした。それを受けて No.235「三角関数を学ぶ理由」は、小中高校の勉強はこれからのAIの時代に増々大切になるということを主張したものでした(三角関数は一例です)。
今回はその No.234「教科書が読めない子どもたち」と、No.235「三角関数を学ぶ理由」の続きです。2019年6月の日本経済新聞に、東ロボと RST のプロジェクトを主導した新井教授のインタビュー、「AI時代の生き残り術」が掲載されました。このインタビューの内容は極めて妥当だと思ったので、その一部をネタに「生き残り術」を考えてみたいと思います。
読解力・論理力・コミュニケーション能力
このインタビューは日本経済新聞の玉利編集委員が行ったものですが、玉利氏の「人工知能(AI)が仕事を奪うことについての不安が広がっている。若い世代ほど将来不安が強いようだ」という問題提起に対し、新井教授は次のように答えています。
|
新井教授の話の最後に出てくる「医師」は、"最もAIに取って換わることがなさそうな職業" であることは確かでしょう。オックスフォード大学の予測でもそうなっていました。しかし、医師の仕事のある部分はAIで置き換えられることもまた確かです。
しばしば経験することですが、病院に行くとまず検査に回され、医者はその検査結果のパソコン画面の数字を見ながら、患者の方には目も向けずに、また質問など無しに、あれこれと "診断" をするということがあります。こういった "診断" は機械化・ロボット化できるわけです。将来は血液1滴だけの分析で(ないしは、ごく少量の生体サンプルの分析で)、その人がどういう病気になっているか、その予兆も含めてすべての診断できるようになるでしょう。こうなれば「パソコン画面を見つめるだけの医師」は不要です。
要は「医師」とか「公務員」というのは、今までの社会の枠組みにおける職種であり、今後予想される激動期においては、その職種が無くならないまでも、職種に求められるスキルがガラッと変わりうるわけです。人が仕事をするということは社会にとってどういう意味と価値があるのか、そこを考えないといけない。
|
新井教授は、求められるのは ① 読解力、② 論理力、③ コミュニケーション能力、の3つだと言っています。この3つの内容を具体的に言うと次のようになるでしょう。
① 読解力は、主として文章で表現された意味内容を正確に把握できる力です。実社会では文章表現を補足するものとして、図や表やグラフが使われることが多々ありますが、これらの読解も含みます。
読解力は、社会におけるすべての仕事、研究、タスク、作業の基本となるものと言えます。また、自分が表現したいことを他者に間違いなく伝わる形で文章や図にする力(=表現力)は、読解力があってこそのものです。表現力はあるが読解力がない、というのはありえないというか、矛盾しています。
② 論理力は「論理的にものごとを考えられる力」です。学校の勉強で言うと、数学は論理だけでできあがっています。その他の理系科目や文系科目の多くも、論理的に考えることが重要なのは言うまでもありません。
③ コミュニケーション能力は、対人関係において相手の意向を読みとり、相手の言わんとしていることを理解し、また自分の主張を相手に伝わるように述べ、さらには相手を説得したり、妥協点を見つける能力でしょう。
① ② ③ が「AI時代における有能さ」の最もべーシックなスキルだというのは、大変納得性が高いわけです。それはおそらく、小学生ころから始まる訓練で培われるはずです。
私の知り合いで小・中・高校生に勉強を教えている塾の講師の方がいます。その人によると、中学受験をするような小学生に最も必要なのは「読解力」と「計算力」と「集中力」だそうです。受験そのものにコミュニケーション能力は不要なので、「計算力=論理力の一部」と考えると新井教授の説に似ています。さらに、集中力が "生産性"(= 正確に速く作業を遂行する)を左右するのはその通りでしょう。
その小学校にも近年、英語やプログラミングを取り入れる動きが進み、また大学や企業はAI人材の育成に力を入れ始めています。こういった社会情勢の中で、しかも先が読めない時代だから学生も親も企業も不安にかられ、すべての能力を備えようと焦る。あれやこれやに手を伸ばし「英語ができて、AIのプログラミングが出来て、コミュニケーション能力も高い」というような理想像を描いてしまう、と新井教授は言っています。しかし本当に必要なスキルは何なのか。プログラミングを例にとってそれが説明されています。
|
新井教授の発言にある「高度プログラミング」を、「実社会で実務に使用するプログラムを作ること」と考えます。そこでまず必要なのは、プログラムが果たすべき機能を正確に漏れなく記述した仕様書です。それは、例外ケースにおいてプログラム(=コード)がどう振る舞うべきかというところまで記述しなればなりません。
次に、その仕様にもとづいて、何らかのプログラミング言語を用いて機能をコンピュータが処理できる形に実装する必要があります。このフェーズおいては C++ や Java や Python などの(例です)プログラミング言語を使うわけですが、言語の修得は勉強すればできます。それよりも、論理的に考えるとか、集中力を発揮してケアレスミスのない(バグがない)コードを書けることが大切です。
仕様書は別の人が書き、その仕様に沿って自分が実装するということもあるでしょう。そこで必要なのは読解力です。さらに論理力も必要です。往々にして仕様書には曖昧なところやヌケ・モレ、記述不足、不整合などの不具合があります。その不具合を見抜く力が必要で、そのためには「不具合がなく首尾一貫している仕様とは何か」を想定できる論理力が必要です。論理的にものごとを考える力があってこそ論理的におかしいという指摘ができるのです。
顧客から受託して、顧客の要望で仕様書を書き、コードを実装することもあるでしょう。この時に必要なのはコミュニケーション能力です。顧客の真の要望や意図を理解しないと始まりません。限られた予算と納期のなかでのプログラム開発では顧客の説得も必要だし、優先度を考えて落とし所を探ることも必要です。まさに対人的なコミュニケーション能力が必要な場です。
新井教授は「AIを使うプログラマーに欠かせないのは数学」という趣旨の発言をしていますが、まさにその通りです。現代のAIは徹頭徹尾、数学でできています。回帰分析、クラスター分析、主成分分析、深層学習、トピック分析など、現代のAIと言われるものの中身は数学です。「数学は嫌いだがAIのプログラミングは好き」というのは矛盾しています。
最近は「AIプラットフォーム」と呼ばれる "AIプログラムのライブラリ" が無料公開されていて、それを使えば比較的簡単にAIプログラムが開発できます。プリファード・ネットワークス社の Chainer や、Google社の Tensorflow などが有名です。しかしこれらのプラットフォームを使っているだけの自称 "プログラマー" は、新井教授が言うように早晩淘汰されるでしょう。
乱世こそ地道に
このインタビューを行った日本経済新聞の玉利編集委員は、全体を "乱世こそ地道に" とまとめています。それを次に引用します。
|
玉利編集委員がインタビューのまとめとして書いていることで重要なポイントは、
| 乱世こそ地道なやり方しか通用しなくなる。 | |
| 乱世では普遍性のある、どこでも通用するものしか生き残れない。 |
の2つです。これはまさにその通りでしょう。この2つを逆の視点から言うと、
| 安定した世の中で作られた枠組みに沿って、専門特化した領域だけしか知らない・知ろうとしない人は、ひとたび乱世になると足元を掬われて行き場を失う(ことになりかねない)。 |
となるでしょう。専門特化した人材が一見、生産性が高いように見えるのは、本人が「基本的なスキルが高い有能な人材であるから」ではなく、「その専門領域で先人たちが過去から蓄積し継承してきた経験や知識があるから」かもしれないのです。その経験や知識がデジタル化されてしまうと、自称 "スペシャリスト" は一気に行き場を失うはずです。
以上の日本経済新聞の記事を読んで改めて思うのは、教育の大切さです。特に小学校・中学校・高校における教育で、それは No.235「三角関数を学ぶ理由」に書いたような勉強と、学校というミニ社会における共同生活です。我々はそこで、読解力・論理力・コミュニケーション能力といった「普遍性のある、どこでも通用するスキル」を育成していると考えられます。勉学の課目はいわゆる文系から理系までいろいろありますが、その勉強によって我々は、たとえば「読解力・論理力のさまざまなパターン」を修得できるのです。
AIによる機械化が進もうとしている時代、小学校から英語やプログラミングを取り入れようとしている時代にこそ「普遍性のある、どこでも通用するスキル」の大切さに眼を向けるべきだと思いました。
2019-08-09 18:16
nice!(0)
No.250 - データ階層社会の到来 [社会]
No.240「破壊兵器としての数学」は、アメリカのキャシー・オニールが書いた『破壊兵器としての数学』(=原題。2016年に米国で出版)の紹介でした。日本語訳の題名は『あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠』(インターシフト 2018.7.10)です。この中でオニールはアメリカにおける、
などをとりあげ、これらの野放図な利用がいかに社会に害悪を及ぼすか(または及ぼしているか)を厳しく警告していました。
このうち、"大学ランキング" は "組織体のランキング" ですが(日本の例として "都道府県幸福度ランキング" を書きました。No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」)、その他は "個人をランキングする"、ないしは "個人を分類する" ものです。そこに数学が使われているため、それが害悪になるときに「破壊兵器としての数学」だとオニールは言っているのでした。
ところで、最近の「週刊 東洋経済」(2018年12月1日号)で「データ階層社会」という特集が組まれ、現代社会において "個人をランキングしたり分類する" 動きがいかに進んでいるかを、多方面の視点から解説していました。時を得たタイムリーな特集企画だったと思ったので、その一部を紹介したいと思います。ここで使われている "データ階層社会" という言葉の定義は後回しにして、まず中国における "信用スコア" の話から紹介します。
信用スコアとは "金銭の支払いや決済に関する個人の信用度をスコア化したもの" で、キャシー・オニールの本の日本語訳では "クレジット・スコア" とか "eスコア" となっていました。ここでは "信用スコア" で統一します。
全国民の信用情報を政府当局が一元的に管理
週刊 東洋経済には、上海在住のジャーナリスト・田中信彦氏の中国レポートが掲載されていました。話は "芝麻信用" から始まります。
ダボス会議には世界の著名経済人や政治家が集まりますが、ダボスはスイスの都市です。欧州の先進国は特に人権意識やプライバシー意識が進んでいますが、そのど真ん中でのジャック・マー氏の発言です。欧米の企業家なら、たとえ内心で思っていたとしても公の場では決して口に出さない発言です。おそらくジャック・マー氏(=中国共産党員。2018.11.26 の人民日報)は、自分の発言が欧米社会からみると異様に映るとは全く考えなかったのでしょう。その "芝麻信用" とは何か、それが次の解説です。
中国は共産党の一党独裁国家であり、以前から個人情報の一元管理のしくみがあります。西欧流の "プライバシー" の概念は未成熟で、個人情報が公的機関や私企業に収集されることに対する抵抗感は薄いのが実状です。むしろ、個人情報の提供に相応のメリットがあるなら積極的に公開してもよいと考える人が多数派である。田中信彦氏はそう書いています。
このような背景のもとで芝麻信用が生まれてきたわけですが、ではどういう風に発展してきたのかが次です。
支払いについての信用力が高い人はデポジットが不要になる。これは信用スコアの真っ当な使い方です。しかし芝麻信用は次第にエスカレートしていきます。
一企業が収集した個人情報にもとづくスコアが人生を左右しかねない、しかもスコアの付け方は非公開、というのは明らかに行き過ぎです。中国政府は規制に乗り出します。
「人間そのものの格付け」になりかねないサービスを政府が規制するのは当然です。しかしこれは「民間会社がやってはいけない」ということであって、中国政府は逆に個人情報を徹底的に収集しようとしています。要するに「政府がやろうとしていることを、民間企業はやるな」というのが、信聯を設立した意味のようです。
この政府の信用情報システムは詳細が不明な部分が多いと、田中氏は書いています。芝麻信用などの民間サービスとの連携も伝えられているが、実態は不明で、情報の連結がどの程度なされているのかは、よくわかりません。しかし今後、政府の信用情報システムがますます強化されるのは間違いないと、田中氏は次のように結んでいます。
この田中信彦氏のレポートにある「全国民的な信用情報ネットワーク」ですが、北京市の具体的な内容が朝日新聞(2018年12月23日)で報告されていました。それを次に紹介します。
北京市民を監視 点数化の新制度
この朝日新聞の記事にある「クルマの通過情報を記録するシステム」ですが、日本では「Nシステム」として既に30年以上の歴史があり、1980年代後半から設置が始まりました。これは "自動車利用犯罪" の捜査のために警察庁(一部は都道府県警)が設置しているもので、高速道路や主要国道、重要施設周辺道路に設置されています。これは北京市とは違ってカメラ画像だけからクルマのナンバープレートを識別する装置で、数々の犯罪捜査に役だった実績をもっています。
しかしこの日本の「Nシステム」も "犯罪が疑われる個人の動向監視" に使われた例が指摘され、問題視されたことがあります。北京市のシステムが自動車利用犯罪の捜査や交通量の詳細把握に役立つことは確かでしょうが、そこは中国なので(特定の)市民の監視に使われることは間違いないでしょう。
週刊 東洋経済の田中信彦氏のレポートと、朝日新聞の新宅記者の記事をまとめると、次のようになるでしょう。
中国は共産党の一党独裁国家です。従って中国共産党の方針に合わない個人の行動は「反社会的行動」になります。天安門事件についてネットに書き込むのは内容の如何にかかわらず「反社会的行動」だし、都市の行政当局(責任者は共産党員)の政策を批判するのも、それが国のためを思った建設的な意見であっても反社会的行動になるでしょう。それはスコアの減少になる。逆に、政府の意向に沿った言動をする個人はスコア・アップになる。芝麻信用で起こったようなスコア競争になる可能性もありそうです。
まるで、ジョージ・オーウェルが『1984年』(1949年刊行)で描いた社会のような感じがします。オーウェルは共産主義やファシズムにみられる「全体主義」への批判を念頭において『1984年』を書いたわけですが、それはオーウェルの念頭にあった旧ソ連よりも中国で具現化されつつあるようです。中国は従来にも増して「監視社会」「プライバシー喪失社会」に向かっていると言えるでしょう。
中国の状況は他国の話か
以上のような中国の状況は、欧米や日本などの民主主義や人権を社会の基盤とする社会とは無縁の "特殊な" 状況なのでしょうか。
そうとも言えます。欧米や日本において「個人信用情報の一元管理システム」を作るなど、絶対に無理でしょう。また基本的人権という概念が確立しています(国によっては怪しい面もありますが)。つまり「人は生まれながらにして、たとえ政府であっても侵せない人権を持っている」という考え方で、たとえば思想、言論、信教の自由です。この面でも中国は異質です。
しかし我々は中国の状況を見て、反面教師として学ばなければならないとも思います。その第1の理由は、日本の政府や官僚、指導層の中にも中国政府のように考える人がいるに違いないからです。たとえば「全国民の生体識別情報(指紋など)を一元管理すれば犯罪捜査やテロ予防などの強力なツールになり、それは国民の福祉の増大につながる」と考える人がいてもおかしくはないと思います。こういった一元管理は確かにプラス面があるので、考える(夢想する)人はいるでしょう。もちろんマイナス面の方が圧倒的に多いのですが ・・・・・・。分野ごとの個人情報の一元管理は、ほかにも "健康状態"(プラス面は医療費の削減) や "資産状況"(プラス面は公平な税負担)など、いろいろ考えられます。
第2の理由は、現代社会は「データがお金と同じような価値を持つ社会」に急速に向かっているからです。データにもいろいろありますが、個人データを収集し、分析し、スコア化することも大きな価値を生む。だとすると、自由主義経済の中ではその動きが民間ベースで加速することが間違いないでしょう。それを、週刊 東洋経済の特集の「データ階層社会」というキーワードで整理してみたいと思います。
データ階層社会
"データ階層社会" とは何かですが、まず "データ" とは社会や個人の状況を表現したり、社会や個人の活動によって発生する情報のすべてです。現代では主に「コンピュータで処理可能なデジタル情報」を言います。
データのうち、個人の状況を表現したり個人の活動や行動によって発生するデータが "個人データ(個人情報)" です。これはその人の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業から始まって、顔写真や遺伝子(DNA)、指紋、健康検査値などの生体情報、個人が社会生活を営むための各種のアカウント情報や識別情報(銀行口座、SNS、決済、マイナンバー、年金番号 ・・・・・・)など、個人を説明するすべての情報が含まれます。さらに個人の行動や生活で刻々と発生する情報も個人データです。現在位置情報、インターネットサイトの閲覧履歴、検索履歴、物品の購買履歴、公共サービスの利用履歴、各種の身体活動データなどです。
"データ階層社会" と言う場合のデータとは個人データを指します。「データがお金と同様の価値を持つ社会」になりつつありますが、個人データもそれ自体が価値を持っており、また個人データ集積して分析することで新たな価値が生まれます。そのときの重要なキーワードが "プロファイリング" です。
プロファイリングとは、もともと犯罪捜査の手法です。つまり、過去の犯罪の情報の蓄積(データベース)を使って、新たに起こった犯罪を分析し、犯人像を描き出すことです。
しかし個人データについて言われるプロファイリングは少々別の意味で使われます。EUが2018年に制定した GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation。データとは個人データのこと)では、プロファイリングを次のように定義しています。
法律英語の直訳なのでわかりにくいですが、自然人とは法人(企業など)の対立概念で、個人データという場合の個人のことです。上の定義をかいつまんで箇条書きにすると、
となるでしょう。この定義における「自動的な処理」ですが、これはコンピュータを使って行われることが多く、特にその中でもAI(人工知能)の技術を使うことが増えてきました。これが一つのポイントです。
プロファイリングの結果として得られた「個人の一定の側面」のことを "プロフィール" と呼ぶことにすると、プロフィールはさまざまな形で表現可能です。言葉や文章で表現してもよいし、たとえば映画の嗜好だと "ジャンル" とか "好きな俳優" で表現が可能でしょう。
プロフィールのうち、一つの数値で個人をランク付けできるように表現されたものが "スコア" です。ないしは、個人に関するものであることを明確にしたい場合は "個人スコア" です。最初に引用した中国の芝麻信用は、個人の支払い・決済に関する信頼度のスコアなので "信用スコア" です。
"データ階層社会" を定義すると、
と言えるでしょう。"スコア化社会" ないしは "格付け社会" という言い方もできる。個人が位置づけられる "階層" は、もちろん個人にとって固定的なものではなく、変化します。ただし、スコアの作り方によっては固定的になる傾向が出てくることにもなるでしょう。たとえば信用スコアだと、いちど支払いの延伸(債務不履行)を起こすと長期間にわたって下位の階層に位置づけられる、ということがスコア化の方法によっては起こり得るわけです。
プロファイリングはすでに大々的に行われていて、その一つが「ターゲティング広告」です。個人データから個人の嗜好や好みといったプロフィールを分析し、その個人にとって最適な広告を打つ。もちろんこれは広告主と個人の双方にとって有益な面があるのは確かです。ただし、そのネガティブな面にも着目すべきです。No.240「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールが指摘していたのは、個人の知識不足につけ込んで "困り果てた人に(合法ではあるが)詐欺まがいの広告を大量に打つ" 行為です。オニールはこれを「略奪的広告」と呼んでいるのでした。
また、ターゲティング広告の手法が選挙に使われる可能性についても、オニールは警鐘を鳴らしていました。たとえば "この人は有機食品を多く買うので環境問題への関心が高いと推定できる" というプロファイリングがあったとすると(これは例です)、候補者がその個人には「環境問題にいかに力を入れているかというアッピールをメールで送る」といったたぐいです。こうなると民主主義の根幹を崩しかねません。
プロファイリングとターゲティング広告が重要なビジネスモデルになっているのが、Facebook を筆頭とする SNS です。もっと一般化すると、SNS は大々的な個人データ収集装置であり、収集した個人データとそのプロファイリングによってビジネス拡大と利益の増大を図るのがビジネスモデルの根幹と言えるでしょう。
SNS が個人データの収集と利潤化という観点からすると Facebook からの個人データ流出事件は、起こるべくして起こったとも言えます。2018年3月に内部告発で判明したのは、Facebook の8700万人の個人データが英国のデータ分析会社、ケンブリッジ・アナリティカに流出し(2014年)、それがアメリカ大統領選挙の選挙運動に使われたことでした。この事件は Facebook の "脇の甘さ" が露呈したわけです。ちなみにケンブリッジ・アナリティカは、米国トランプ大統領の首席戦略官兼上級顧問だったスティーヴン・バノン氏が立ち上げた会社です。
さらに2018年6月にニューヨーク・タイムズは「Facebook がスマホや端末機メーカー約60社に対して、個人データへのアクセスを許していた」ことをスッパ抜きました。報道によると友達関係もたどれるようにしていたとのことです。日本では考えられない話ですが「個人データの収集と利潤化」を目的にしている Facebook としては "自然で、当たり前の" 行為だったのでしょう。
以上のように、個人データの収集とプロファイリングは、SNS やターゲット広告などを通して我々の生活と既に関係を持っているのですが、以下はプロファイリングの結果として得られる "個人スコア" に話を絞ります。
スコア化社会の到来
日本においても個人スコアにもとづくビジネスを展開する企業が現れてきました。2016年9月15日にソフトバンクとみずほ銀行が新会社を設立することを発表しましたが(No.175「半沢直樹は機械化できる」の「補記1」参照)、その会社が J・Score(ジェイスコア)です。
週刊 東洋経済には J・Scoreの大森社長へのインタビューも載っていました。
J・Score のビジネスモデルは「レンディング(lending)」と「リワード(reward)」です。レンディングとは "貸出し(融資)" であり、リワードとは(他企業からの)"特典提供" です。しかし大森社長の発言から明らかなことは、J・Score は出来るだけ多くの個人データを集め、それを利益に転換することを目的としていることです。「スコアアップのための項目が150ほどあり、これは入力すればするほどスコアが上がる」のは、まさに多くの個人データを集めたいからです。また「ヤフーなどとの情報連携に同意すれば基本スコアアップにつながる」のも、そうすることで個人がヤフーで行ったショッピングやオークションや情報閲覧の履歴が入手できるからです。
なぜ多くの個人データを集めるとスコアアップになるかと言うと、一つの理由は、信用スコアの精度が向上するからです。精度が悪いと、AIで算出したスコア範囲の最低ランクに位置づけざるを得ない。企業としてのリスク回避のためにはそうなるわけで、逆に精度が向上するとスコアアップになる(可能性が高い)ことになります。
さらにもう一つの(さらに重要な)理由は、集めた個人データが信用スコアの精度向上という以上に価値を持つからです。まさに「データがお金と同様の価値をもつ」社会に突入しています。たとえばヤフーとしては J・Scoreの個人データ(ないはそれを自動処理してできた信用スコア)を入手できるのは多大な金銭的メリットになるでしょう。
「レンディング」と「リワード」は、「出来るだけ多くの個人データを集めて、それを利益に転換する」というJ・Score のビジネスモデルの「最初の例」に過ぎないと思います。
身体・生活習慣データと "健康スコア"
個人データでも特に気になるのが "身体・生活習慣データ" で、その中でも健康に関係すると考えらるデータです。これは普通、健康診断や人間ドックの検査結果として個人に通知され、我々は生活習慣の改善や治療の判断に使うわけです。これが個人にとどまることなく、企業活動との関係が出てくることが懸念されます。その一つが医療保険や生命保険をビジネスにしている保険会社です。
保険会社にとって、個人の身体データ、特に長期間にわたって経年的に把握可能な身体データは "のどから手が出るほど欲しい情報"(週刊 東洋経済)です。身体データの分析によって保険の加入の判断や保険金額の査定に使えるからです。
もちろん分析によって「従来、保険に加入出来なかった人が加入できるようになる」というメリットが生まるでしょう。たとえば死亡率の高い病気にかかった人は、完治したとしても生命保険に加入できないということがあります。しかし身体データの分析によって再発リスクが薄いと判断できれば加入の道が開ける、こういったことが起こり得ます。しかし全く逆のことも起こり得る。
"究極の身体データ" とも言うべきものが、個人の遺伝子データです。2017年の11月~12月、保険会社4社の約款に遺伝に関する記載があることが判明して問題になりました(日本生命、メットライフ生命保険、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、SBI生命保険)。約款には「健康状態、遺伝、既往症などが社内基準に合わない場合は保険料の支払いを一部削減する場合がある」などどあったわけです。各保険会社は、昔の約款が残っていた、今は遺伝を利用していない、約款から遺伝を削除する、と釈明に追われました。
2013年、女優のアンジェリーナ・ジョリーは両乳房切除手術を受け、それを公表しました。母親を乳癌で失い、自身も遺伝子検査で乳癌になる確率が高いと示されたからです。しかし母親が乳癌になった主たる原因が遺伝子にあったという証明はなく、また彼女に乳癌の予兆とか何らかの身体的不調があったわけでもありません。とにかく彼女はリスクを低減する方向に行動した。そしてその行動は世間から称賛されました。少なくとも好意的に受け取られた。
これを保険会社と医療保険・生命保険の加入申請者に当てはめたらどうなるでしょうか。加入申請者の遺伝子情報から乳癌のリスクが高いと判断されると、その申請を切る(=申請を却下する)ということになります。アンジェリーナ・ジョリーの決断を称賛するのなら、そいういう風潮に次第になっていってもおかしくはない。
週刊 東洋経済によると、世界には保険・雇用分野において遺伝子情報による差別を法律で禁止している国があり、米国、ドイツ、フランス、スイス、カナダ、韓国がそうだとあります。ところが日本にはそういった法律はないのです(2018年現在)。
遺伝子データはさておき、一般的な身体データ・生活習慣データを利用して個人の「健康スコア」を作ることは容易に考えられます。もちろん国レベルでそういうことは無いでしょうが、企業・組織レベルでは考えられる。「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールは、「(アメリカでは)独自の健康スコアを策定し、スコアに応じて健康保険料を変えるところが現れている」と書いていて、さらに次のように警鐘を鳴らしているのでした。
「健康スコア」によって個人が健康問題に向き合えるように後押しするのは悪いことではありません。重要なのは、それが「提案」でとどまるべきことです。それが「命令・強制」になったり何らかの差別(=階層化)になると、それは個人の自由の侵害になるのです。
ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け"
週刊 東洋経済の「データ階層化社会」の特集には、ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け" の話が出ていました。
こうした機械的な格付けが公正だとするのは幻想です。運転手への人種的偏見が紛れ込む恐れもあるし、低格付けという「仕返し」を恐れて理不尽な乗客に耐える運転手もいます。渋滞への不満が運転手に向けられることもありうる。運転手は不満を訴えるすべがなく、格付けの理由も透明性に欠けます。要するに "デジタル格付け" という「見えない上司」が運転手の一挙手一投足をひそかに監視しているのです。
日本を含む民主主義国家にける「スコア化社会(格付け社会)」、もっと大きく言うと「データ階層社会」は、中国のように国家レベルではなく、J・Scoreやウーバー・テクノロジーズのように企業レベルで進行するはずです。そのメンバーになるかどうかは個人の意志決定ですが、現代人が各種の企業活動に "覆われて" 生活している以上、必然的に「データ階層社会」の一員とならざるを得なくなると想定できます。
以上、週刊 東洋経済の「データ階層社会」特集の一部を紹介したわけですが、以降は、データ階層社会の到来に備えた「個人の権利の重要性」についての動向です。
個人データに関する権利の重要性
個人データに関する「個人の権利」という意味で画期的なのは、2018年5月25日から EEA(=欧州経済域。EU加盟28ヶ国+ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で施行された GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation)です。GDPRでは「データ主体の8つの権利」が明確化されました。「データ主体」とは個人データを提供する個人のことです。また、以下の「管理者」とは個人データを収集する企業や各種団体・組織のことです。「データ主体の8つの権利」は以下の8つを言います。
◆情報権
◆アクセス権
◆訂正権
◆削除権
◆制限権
◆データポータビリティの権利
◆異議権
◆自動化された "個人についての判断" に関する権利
この中でも重要なのは、まず「削除権」でしょう。個人データを削除することで、個人データを収集した管理者から「忘れられる」という権利です。
「データポータビリティの権利」は、今後広まると考えられる "情報銀行" を意識しているはずです。個人データを管理し、使い道を決め、修正・追加・削除する権限は、データの主体 = 個人にあるべきです。しかし個人がデータを全面的に管理するのはやりきれません。そこで専門の "情報銀行" に個人データを預け(預金ならぬ "預データ")、許可した事業者に個人データの使用を可能にして、その対価やリワードを得るしくみが必要になってきます。このとき、個人データを収集している事業者(SNS、検索、eコマース、フリマ、・・・・・・)から個人データを集めて "情報銀行" に預けるという行為が必要になります。この行為の権利を個人に保証するのがデータポータビリティです。"情報銀行" の法制度は日本でも整備されたわけですが、GDPRはそれを実効的にする権利をいち早く定めたと言えるでしょう。
また「異議権」は、「ダイレクト・マーケティングの対象にならない権利」もその中に含まれることになります。
さらに最後の「自動化された個人についての判断に関する権利」は、AIを強く意識しているところが重要です。つまり、最近のAI技術はビッグデータを収集し、機械学習でコンピュータを訓練し、それによって予測や判断をするのが主流です。人間はなぜコンピュータがそう判断したのか、必ずしも分からない。AIの危ういところです。GDPRの規制は、AIを含む自動処理はあくまで人間の判断の補助に使え、ということでしょう。
これに関連しますが、最近、日本政府の「人間中心のAI社会原則 検討会議」は「AIの7原則」を打ち出しました(日本経済新聞 2018.11.27 による)。この7原則の6番目は「AIを利用した企業は決定過程の説明責任を負う」というものです。日本経済新聞の記事の見出しは「AI判断 企業に説明責任」というものでした。7原則の中でもこの「説明責任」が重要(ないしは各国のAI原則とくらべても特徴的)ということでしょう。
日本は GDPR のような個人データを扱いのルール整備が遅れていると言われています。そもそも「保険、雇用分野において遺伝子情報による差別をしてはならない」という法律がありません。週刊 東洋経済の特集にあった「データ階層社会」は、必然的にその方向に向かうと考えられます。ルール整備が喫緊の課題だと思いました。
本文の中で、Facebookについて次の主旨のことを書きました。
その個人データを利益に転換する最大のものが、Facebookのターゲティング広告です。それについて、日本経済新聞(2019年3月21日)に記事があったので紹介します。Facebookがターゲティング広告の機能制限をしたという記事の一部です。
この記事では「フェイスブックは2019年3月19日に、求人や住宅売買、信用貸しの3分野のネット広告について、性別、人種、郵便番号などをもとに配信先を絞り込めなくすると発表した」と紹介されていました。ターゲティング広告が差別を助長しているとの批判を受けて機能を制限をしたものです。
しかしこの機能制限には実質的な意味がほとんど無いと推測されます。3分野だけということと、性別、人種、郵便番号(=居住地域)が分からなくても、個人の投稿などからそれらを推定することができるからです。記事にも、次のようにありました。
最近のAI技術の発展で、個人データを分析する能力は飛躍的に高まりました。その分析力を悪用すると、現代社会における人権や倫理の破壊につながることは明白です。個人データの保護規程や倫理規程の整備が急がれるところでしょう。
| ・ | 教師評価システム | ||
| ・ | USニューズの "大学ランキング" | ||
| ・ | 個人の行動履歴にもとづくターゲティング広告 | ||
| ・ | 個人の信用度あらわす "eスコア" | ||
| ・ | 個人の健康度をはかる健康スコア |
などをとりあげ、これらの野放図な利用がいかに社会に害悪を及ぼすか(または及ぼしているか)を厳しく警告していました。
このうち、"大学ランキング" は "組織体のランキング" ですが(日本の例として "都道府県幸福度ランキング" を書きました。No.247「幸福な都道府県の第1位は福井県」)、その他は "個人をランキングする"、ないしは "個人を分類する" ものです。そこに数学が使われているため、それが害悪になるときに「破壊兵器としての数学」だとオニールは言っているのでした。
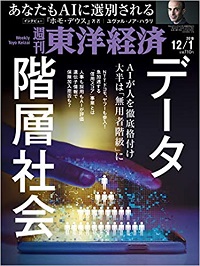
| |||
信用スコアとは "金銭の支払いや決済に関する個人の信用度をスコア化したもの" で、キャシー・オニールの本の日本語訳では "クレジット・スコア" とか "eスコア" となっていました。ここでは "信用スコア" で統一します。
全国民の信用情報を政府当局が一元的に管理
週刊 東洋経済には、上海在住のジャーナリスト・田中信彦氏の中国レポートが掲載されていました。話は "芝麻信用" から始まります。
|
ダボス会議には世界の著名経済人や政治家が集まりますが、ダボスはスイスの都市です。欧州の先進国は特に人権意識やプライバシー意識が進んでいますが、そのど真ん中でのジャック・マー氏の発言です。欧米の企業家なら、たとえ内心で思っていたとしても公の場では決して口に出さない発言です。おそらくジャック・マー氏(=中国共産党員。2018.11.26 の人民日報)は、自分の発言が欧米社会からみると異様に映るとは全く考えなかったのでしょう。その "芝麻信用" とは何か、それが次の解説です。
|
中国は共産党の一党独裁国家であり、以前から個人情報の一元管理のしくみがあります。西欧流の "プライバシー" の概念は未成熟で、個人情報が公的機関や私企業に収集されることに対する抵抗感は薄いのが実状です。むしろ、個人情報の提供に相応のメリットがあるなら積極的に公開してもよいと考える人が多数派である。田中信彦氏はそう書いています。
このような背景のもとで芝麻信用が生まれてきたわけですが、ではどういう風に発展してきたのかが次です。
|
支払いについての信用力が高い人はデポジットが不要になる。これは信用スコアの真っ当な使い方です。しかし芝麻信用は次第にエスカレートしていきます。
|
一企業が収集した個人情報にもとづくスコアが人生を左右しかねない、しかもスコアの付け方は非公開、というのは明らかに行き過ぎです。中国政府は規制に乗り出します。
|
「人間そのものの格付け」になりかねないサービスを政府が規制するのは当然です。しかしこれは「民間会社がやってはいけない」ということであって、中国政府は逆に個人情報を徹底的に収集しようとしています。要するに「政府がやろうとしていることを、民間企業はやるな」というのが、信聯を設立した意味のようです。
|
この政府の信用情報システムは詳細が不明な部分が多いと、田中氏は書いています。芝麻信用などの民間サービスとの連携も伝えられているが、実態は不明で、情報の連結がどの程度なされているのかは、よくわかりません。しかし今後、政府の信用情報システムがますます強化されるのは間違いないと、田中氏は次のように結んでいます。
|
この田中信彦氏のレポートにある「全国民的な信用情報ネットワーク」ですが、北京市の具体的な内容が朝日新聞(2018年12月23日)で報告されていました。それを次に紹介します。
北京市民を監視 点数化の新制度
|
この朝日新聞の記事にある「クルマの通過情報を記録するシステム」ですが、日本では「Nシステム」として既に30年以上の歴史があり、1980年代後半から設置が始まりました。これは "自動車利用犯罪" の捜査のために警察庁(一部は都道府県警)が設置しているもので、高速道路や主要国道、重要施設周辺道路に設置されています。これは北京市とは違ってカメラ画像だけからクルマのナンバープレートを識別する装置で、数々の犯罪捜査に役だった実績をもっています。
しかしこの日本の「Nシステム」も "犯罪が疑われる個人の動向監視" に使われた例が指摘され、問題視されたことがあります。北京市のシステムが自動車利用犯罪の捜査や交通量の詳細把握に役立つことは確かでしょうが、そこは中国なので(特定の)市民の監視に使われることは間違いないでしょう。
週刊 東洋経済の田中信彦氏のレポートと、朝日新聞の新宅記者の記事をまとめると、次のようになるでしょう。
| ◆ | 中国は全国民を対象とする個人信用情報の一元管理に向かっている。 | ||
| ◆ | そこでの信用とは、金銭の支払いについての点数化(スコア化)のみならず、社会での個人の行動(反社会的行動や迷惑行為)も考慮した点数化である。 | ||
| ◆ | 高スコアでは公共サービスや就職などで利益を得るが、低スコアでは個人の行動が制限される(いわゆるブラックリスト。「一歩も歩けなくなる」「外出もままならなくなる」)。 |
中国は共産党の一党独裁国家です。従って中国共産党の方針に合わない個人の行動は「反社会的行動」になります。天安門事件についてネットに書き込むのは内容の如何にかかわらず「反社会的行動」だし、都市の行政当局(責任者は共産党員)の政策を批判するのも、それが国のためを思った建設的な意見であっても反社会的行動になるでしょう。それはスコアの減少になる。逆に、政府の意向に沿った言動をする個人はスコア・アップになる。芝麻信用で起こったようなスコア競争になる可能性もありそうです。
まるで、ジョージ・オーウェルが『1984年』(1949年刊行)で描いた社会のような感じがします。オーウェルは共産主義やファシズムにみられる「全体主義」への批判を念頭において『1984年』を書いたわけですが、それはオーウェルの念頭にあった旧ソ連よりも中国で具現化されつつあるようです。中国は従来にも増して「監視社会」「プライバシー喪失社会」に向かっていると言えるでしょう。
中国の状況は他国の話か
以上のような中国の状況は、欧米や日本などの民主主義や人権を社会の基盤とする社会とは無縁の "特殊な" 状況なのでしょうか。
そうとも言えます。欧米や日本において「個人信用情報の一元管理システム」を作るなど、絶対に無理でしょう。また基本的人権という概念が確立しています(国によっては怪しい面もありますが)。つまり「人は生まれながらにして、たとえ政府であっても侵せない人権を持っている」という考え方で、たとえば思想、言論、信教の自由です。この面でも中国は異質です。
しかし我々は中国の状況を見て、反面教師として学ばなければならないとも思います。その第1の理由は、日本の政府や官僚、指導層の中にも中国政府のように考える人がいるに違いないからです。たとえば「全国民の生体識別情報(指紋など)を一元管理すれば犯罪捜査やテロ予防などの強力なツールになり、それは国民の福祉の増大につながる」と考える人がいてもおかしくはないと思います。こういった一元管理は確かにプラス面があるので、考える(夢想する)人はいるでしょう。もちろんマイナス面の方が圧倒的に多いのですが ・・・・・・。分野ごとの個人情報の一元管理は、ほかにも "健康状態"(プラス面は医療費の削減) や "資産状況"(プラス面は公平な税負担)など、いろいろ考えられます。
第2の理由は、現代社会は「データがお金と同じような価値を持つ社会」に急速に向かっているからです。データにもいろいろありますが、個人データを収集し、分析し、スコア化することも大きな価値を生む。だとすると、自由主義経済の中ではその動きが民間ベースで加速することが間違いないでしょう。それを、週刊 東洋経済の特集の「データ階層社会」というキーワードで整理してみたいと思います。
データ階層社会
"データ階層社会" とは何かですが、まず "データ" とは社会や個人の状況を表現したり、社会や個人の活動によって発生する情報のすべてです。現代では主に「コンピュータで処理可能なデジタル情報」を言います。
データのうち、個人の状況を表現したり個人の活動や行動によって発生するデータが "個人データ(個人情報)" です。これはその人の住所、氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、職業から始まって、顔写真や遺伝子(DNA)、指紋、健康検査値などの生体情報、個人が社会生活を営むための各種のアカウント情報や識別情報(銀行口座、SNS、決済、マイナンバー、年金番号 ・・・・・・)など、個人を説明するすべての情報が含まれます。さらに個人の行動や生活で刻々と発生する情報も個人データです。現在位置情報、インターネットサイトの閲覧履歴、検索履歴、物品の購買履歴、公共サービスの利用履歴、各種の身体活動データなどです。
"データ階層社会" と言う場合のデータとは個人データを指します。「データがお金と同様の価値を持つ社会」になりつつありますが、個人データもそれ自体が価値を持っており、また個人データ集積して分析することで新たな価値が生まれます。そのときの重要なキーワードが "プロファイリング" です。
プロファイリングとは、もともと犯罪捜査の手法です。つまり、過去の犯罪の情報の蓄積(データベース)を使って、新たに起こった犯罪を分析し、犯人像を描き出すことです。
しかし個人データについて言われるプロファイリングは少々別の意味で使われます。EUが2018年に制定した GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation。データとは個人データのこと)では、プロファイリングを次のように定義しています。
(GDPR 第4条 第4項) |
法律英語の直訳なのでわかりにくいですが、自然人とは法人(企業など)の対立概念で、個人データという場合の個人のことです。上の定義をかいつまんで箇条書きにすると、
| ・ | プロファイリングとは個人データの自動的な処理である。 | ||
| ・ | その処理は個人の一定の「側面」を分析したり評価するために行われる。 | ||
| ・ | その側面とは特に、個人の業務実績、経済状況、健康、嗜好、興味、信頼、行動、所在または移動などである。 |
となるでしょう。この定義における「自動的な処理」ですが、これはコンピュータを使って行われることが多く、特にその中でもAI(人工知能)の技術を使うことが増えてきました。これが一つのポイントです。
プロファイリングの結果として得られた「個人の一定の側面」のことを "プロフィール" と呼ぶことにすると、プロフィールはさまざまな形で表現可能です。言葉や文章で表現してもよいし、たとえば映画の嗜好だと "ジャンル" とか "好きな俳優" で表現が可能でしょう。
プロフィールのうち、一つの数値で個人をランク付けできるように表現されたものが "スコア" です。ないしは、個人に関するものであることを明確にしたい場合は "個人スコア" です。最初に引用した中国の芝麻信用は、個人の支払い・決済に関する信頼度のスコアなので "信用スコア" です。
"データ階層社会" を定義すると、
| プロファイリングで得られたスコアによって個人がランク付け(格付け、階層化)され、それが個人の社会的行動に重要な影響を及ぼす社会 |
と言えるでしょう。"スコア化社会" ないしは "格付け社会" という言い方もできる。個人が位置づけられる "階層" は、もちろん個人にとって固定的なものではなく、変化します。ただし、スコアの作り方によっては固定的になる傾向が出てくることにもなるでしょう。たとえば信用スコアだと、いちど支払いの延伸(債務不履行)を起こすと長期間にわたって下位の階層に位置づけられる、ということがスコア化の方法によっては起こり得るわけです。
プロファイリングはすでに大々的に行われていて、その一つが「ターゲティング広告」です。個人データから個人の嗜好や好みといったプロフィールを分析し、その個人にとって最適な広告を打つ。もちろんこれは広告主と個人の双方にとって有益な面があるのは確かです。ただし、そのネガティブな面にも着目すべきです。No.240「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールが指摘していたのは、個人の知識不足につけ込んで "困り果てた人に(合法ではあるが)詐欺まがいの広告を大量に打つ" 行為です。オニールはこれを「略奪的広告」と呼んでいるのでした。
また、ターゲティング広告の手法が選挙に使われる可能性についても、オニールは警鐘を鳴らしていました。たとえば "この人は有機食品を多く買うので環境問題への関心が高いと推定できる" というプロファイリングがあったとすると(これは例です)、候補者がその個人には「環境問題にいかに力を入れているかというアッピールをメールで送る」といったたぐいです。こうなると民主主義の根幹を崩しかねません。
プロファイリングとターゲティング広告が重要なビジネスモデルになっているのが、Facebook を筆頭とする SNS です。もっと一般化すると、SNS は大々的な個人データ収集装置であり、収集した個人データとそのプロファイリングによってビジネス拡大と利益の増大を図るのがビジネスモデルの根幹と言えるでしょう。
SNS が個人データの収集と利潤化という観点からすると Facebook からの個人データ流出事件は、起こるべくして起こったとも言えます。2018年3月に内部告発で判明したのは、Facebook の8700万人の個人データが英国のデータ分析会社、ケンブリッジ・アナリティカに流出し(2014年)、それがアメリカ大統領選挙の選挙運動に使われたことでした。この事件は Facebook の "脇の甘さ" が露呈したわけです。ちなみにケンブリッジ・アナリティカは、米国トランプ大統領の首席戦略官兼上級顧問だったスティーヴン・バノン氏が立ち上げた会社です。
さらに2018年6月にニューヨーク・タイムズは「Facebook がスマホや端末機メーカー約60社に対して、個人データへのアクセスを許していた」ことをスッパ抜きました。報道によると友達関係もたどれるようにしていたとのことです。日本では考えられない話ですが「個人データの収集と利潤化」を目的にしている Facebook としては "自然で、当たり前の" 行為だったのでしょう。
以上のように、個人データの収集とプロファイリングは、SNS やターゲット広告などを通して我々の生活と既に関係を持っているのですが、以下はプロファイリングの結果として得られる "個人スコア" に話を絞ります。
スコア化社会の到来
日本においても個人スコアにもとづくビジネスを展開する企業が現れてきました。2016年9月15日にソフトバンクとみずほ銀行が新会社を設立することを発表しましたが(No.175「半沢直樹は機械化できる」の「補記1」参照)、その会社が J・Score(ジェイスコア)です。
|
週刊 東洋経済には J・Scoreの大森社長へのインタビューも載っていました。
|
J・Score のビジネスモデルは「レンディング(lending)」と「リワード(reward)」です。レンディングとは "貸出し(融資)" であり、リワードとは(他企業からの)"特典提供" です。しかし大森社長の発言から明らかなことは、J・Score は出来るだけ多くの個人データを集め、それを利益に転換することを目的としていることです。「スコアアップのための項目が150ほどあり、これは入力すればするほどスコアが上がる」のは、まさに多くの個人データを集めたいからです。また「ヤフーなどとの情報連携に同意すれば基本スコアアップにつながる」のも、そうすることで個人がヤフーで行ったショッピングやオークションや情報閲覧の履歴が入手できるからです。
なぜ多くの個人データを集めるとスコアアップになるかと言うと、一つの理由は、信用スコアの精度が向上するからです。精度が悪いと、AIで算出したスコア範囲の最低ランクに位置づけざるを得ない。企業としてのリスク回避のためにはそうなるわけで、逆に精度が向上するとスコアアップになる(可能性が高い)ことになります。
さらにもう一つの(さらに重要な)理由は、集めた個人データが信用スコアの精度向上という以上に価値を持つからです。まさに「データがお金と同様の価値をもつ」社会に突入しています。たとえばヤフーとしては J・Scoreの個人データ(ないはそれを自動処理してできた信用スコア)を入手できるのは多大な金銭的メリットになるでしょう。
「レンディング」と「リワード」は、「出来るだけ多くの個人データを集めて、それを利益に転換する」というJ・Score のビジネスモデルの「最初の例」に過ぎないと思います。
身体・生活習慣データと "健康スコア"
個人データでも特に気になるのが "身体・生活習慣データ" で、その中でも健康に関係すると考えらるデータです。これは普通、健康診断や人間ドックの検査結果として個人に通知され、我々は生活習慣の改善や治療の判断に使うわけです。これが個人にとどまることなく、企業活動との関係が出てくることが懸念されます。その一つが医療保険や生命保険をビジネスにしている保険会社です。
保険会社にとって、個人の身体データ、特に長期間にわたって経年的に把握可能な身体データは "のどから手が出るほど欲しい情報"(週刊 東洋経済)です。身体データの分析によって保険の加入の判断や保険金額の査定に使えるからです。
もちろん分析によって「従来、保険に加入出来なかった人が加入できるようになる」というメリットが生まるでしょう。たとえば死亡率の高い病気にかかった人は、完治したとしても生命保険に加入できないということがあります。しかし身体データの分析によって再発リスクが薄いと判断できれば加入の道が開ける、こういったことが起こり得ます。しかし全く逆のことも起こり得る。
|
"究極の身体データ" とも言うべきものが、個人の遺伝子データです。2017年の11月~12月、保険会社4社の約款に遺伝に関する記載があることが判明して問題になりました(日本生命、メットライフ生命保険、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険、SBI生命保険)。約款には「健康状態、遺伝、既往症などが社内基準に合わない場合は保険料の支払いを一部削減する場合がある」などどあったわけです。各保険会社は、昔の約款が残っていた、今は遺伝を利用していない、約款から遺伝を削除する、と釈明に追われました。
2013年、女優のアンジェリーナ・ジョリーは両乳房切除手術を受け、それを公表しました。母親を乳癌で失い、自身も遺伝子検査で乳癌になる確率が高いと示されたからです。しかし母親が乳癌になった主たる原因が遺伝子にあったという証明はなく、また彼女に乳癌の予兆とか何らかの身体的不調があったわけでもありません。とにかく彼女はリスクを低減する方向に行動した。そしてその行動は世間から称賛されました。少なくとも好意的に受け取られた。
これを保険会社と医療保険・生命保険の加入申請者に当てはめたらどうなるでしょうか。加入申請者の遺伝子情報から乳癌のリスクが高いと判断されると、その申請を切る(=申請を却下する)ということになります。アンジェリーナ・ジョリーの決断を称賛するのなら、そいういう風潮に次第になっていってもおかしくはない。
週刊 東洋経済によると、世界には保険・雇用分野において遺伝子情報による差別を法律で禁止している国があり、米国、ドイツ、フランス、スイス、カナダ、韓国がそうだとあります。ところが日本にはそういった法律はないのです(2018年現在)。
遺伝子データはさておき、一般的な身体データ・生活習慣データを利用して個人の「健康スコア」を作ることは容易に考えられます。もちろん国レベルでそういうことは無いでしょうが、企業・組織レベルでは考えられる。「破壊兵器としての数学」でキャシー・オニールは、「(アメリカでは)独自の健康スコアを策定し、スコアに応じて健康保険料を変えるところが現れている」と書いていて、さらに次のように警鐘を鳴らしているのでした。
|
「健康スコア」によって個人が健康問題に向き合えるように後押しするのは悪いことではありません。重要なのは、それが「提案」でとどまるべきことです。それが「命令・強制」になったり何らかの差別(=階層化)になると、それは個人の自由の侵害になるのです。
ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け"
週刊 東洋経済の「データ階層化社会」の特集には、ウーバー・テクノロジーズの "デジタル格付け" の話が出ていました。
|
こうした機械的な格付けが公正だとするのは幻想です。運転手への人種的偏見が紛れ込む恐れもあるし、低格付けという「仕返し」を恐れて理不尽な乗客に耐える運転手もいます。渋滞への不満が運転手に向けられることもありうる。運転手は不満を訴えるすべがなく、格付けの理由も透明性に欠けます。要するに "デジタル格付け" という「見えない上司」が運転手の一挙手一投足をひそかに監視しているのです。
日本を含む民主主義国家にける「スコア化社会(格付け社会)」、もっと大きく言うと「データ階層社会」は、中国のように国家レベルではなく、J・Scoreやウーバー・テクノロジーズのように企業レベルで進行するはずです。そのメンバーになるかどうかは個人の意志決定ですが、現代人が各種の企業活動に "覆われて" 生活している以上、必然的に「データ階層社会」の一員とならざるを得なくなると想定できます。
以上、週刊 東洋経済の「データ階層社会」特集の一部を紹介したわけですが、以降は、データ階層社会の到来に備えた「個人の権利の重要性」についての動向です。
個人データに関する権利の重要性
個人データに関する「個人の権利」という意味で画期的なのは、2018年5月25日から EEA(=欧州経済域。EU加盟28ヶ国+ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)で施行された GDPR(一般データ保護規則。General Data Protection Regulation)です。GDPRでは「データ主体の8つの権利」が明確化されました。「データ主体」とは個人データを提供する個人のことです。また、以下の「管理者」とは個人データを収集する企業や各種団体・組織のことです。「データ主体の8つの権利」は以下の8つを言います。
| データ主体の8つの権利 |
◆情報権
| データ主体は、個人データを収集する管理者から各種の情報の通知を受け取る権利があります。この通知には、管理者の身元と連絡先、予定している個人データの処理内容とその法的根拠、個人データの保管期間、データ主体の各種権利(以下のアクセス権、訂正権、削除権、等々)、プロファイリングを含む自動決定に個人データを使用する場合はその必要性、などが含まれます。 |
◆アクセス権
| 個人データへのアクセスができ、そのコピーを入手できる権利 |
◆訂正権
| 不正確な個人データの訂正を管理者に求める権利 |
◆削除権
| 自分に関する個人データを削除するように管理者に要求できる権利。いわゆる「忘れられる権利」。 |
◆制限権
| 個人データの処理を制限するように管理者に要求できる権利。データ主体が管理者に訂正を求めたり異議を唱えたりしていて、それが解決するまでの期間における処理の禁止など。 |
◆データポータビリティの権利
| 個人データを別の管理者に提供するため、転送可能な形で自分に関する個人データの提供を管理者から受け取る権利。 |
◆異議権
| 管理者が行う個人データの処理に異議を唱える権利。その処理がダイレクトマーケティングであれば、管理者は処理を中止。それ以外なら、管理者はその処理がデータ主体の権利に優先することの根拠を示す必要がある。 |
◆自動化された "個人についての判断" に関する権利
| データ主体が、プロファイリングを含む自動処理のみにもとづいた個人に関する重要な決定の対象にならない権利。重要とは、法的な決定やそれに準じる決定(人事採用、保険加入など)。 |
この中でも重要なのは、まず「削除権」でしょう。個人データを削除することで、個人データを収集した管理者から「忘れられる」という権利です。
「データポータビリティの権利」は、今後広まると考えられる "情報銀行" を意識しているはずです。個人データを管理し、使い道を決め、修正・追加・削除する権限は、データの主体 = 個人にあるべきです。しかし個人がデータを全面的に管理するのはやりきれません。そこで専門の "情報銀行" に個人データを預け(預金ならぬ "預データ")、許可した事業者に個人データの使用を可能にして、その対価やリワードを得るしくみが必要になってきます。このとき、個人データを収集している事業者(SNS、検索、eコマース、フリマ、・・・・・・)から個人データを集めて "情報銀行" に預けるという行為が必要になります。この行為の権利を個人に保証するのがデータポータビリティです。"情報銀行" の法制度は日本でも整備されたわけですが、GDPRはそれを実効的にする権利をいち早く定めたと言えるでしょう。
また「異議権」は、「ダイレクト・マーケティングの対象にならない権利」もその中に含まれることになります。
さらに最後の「自動化された個人についての判断に関する権利」は、AIを強く意識しているところが重要です。つまり、最近のAI技術はビッグデータを収集し、機械学習でコンピュータを訓練し、それによって予測や判断をするのが主流です。人間はなぜコンピュータがそう判断したのか、必ずしも分からない。AIの危ういところです。GDPRの規制は、AIを含む自動処理はあくまで人間の判断の補助に使え、ということでしょう。
これに関連しますが、最近、日本政府の「人間中心のAI社会原則 検討会議」は「AIの7原則」を打ち出しました(日本経済新聞 2018.11.27 による)。この7原則の6番目は「AIを利用した企業は決定過程の説明責任を負う」というものです。日本経済新聞の記事の見出しは「AI判断 企業に説明責任」というものでした。7原則の中でもこの「説明責任」が重要(ないしは各国のAI原則とくらべても特徴的)ということでしょう。
日本は GDPR のような個人データを扱いのルール整備が遅れていると言われています。そもそも「保険、雇用分野において遺伝子情報による差別をしてはならない」という法律がありません。週刊 東洋経済の特集にあった「データ階層社会」は、必然的にその方向に向かうと考えられます。ルール整備が喫緊の課題だと思いました。
| 補記 |
本文の中で、Facebookについて次の主旨のことを書きました。
| ◆ | Facebook は大々的な個人データの収集装置である。 | ||
| ◆ | 収集した個人データとそのプロファイリングで利益を生むのがFacebookのビジネスモデルである。 | ||
| ◆ | 2018年に、Facebookからの大量の個人データ流出が相次いで判明した。 |
その個人データを利益に転換する最大のものが、Facebookのターゲティング広告です。それについて、日本経済新聞(2019年3月21日)に記事があったので紹介します。Facebookがターゲティング広告の機能制限をしたという記事の一部です。
|
この記事では「フェイスブックは2019年3月19日に、求人や住宅売買、信用貸しの3分野のネット広告について、性別、人種、郵便番号などをもとに配信先を絞り込めなくすると発表した」と紹介されていました。ターゲティング広告が差別を助長しているとの批判を受けて機能を制限をしたものです。
しかしこの機能制限には実質的な意味がほとんど無いと推測されます。3分野だけということと、性別、人種、郵便番号(=居住地域)が分からなくても、個人の投稿などからそれらを推定することができるからです。記事にも、次のようにありました。
|
最近のAI技術の発展で、個人データを分析する能力は飛躍的に高まりました。その分析力を悪用すると、現代社会における人権や倫理の破壊につながることは明白です。個人データの保護規程や倫理規程の整備が急がれるところでしょう。
(2019.4.12)
2019-01-18 17:31
nice!(0)
No.247 - 幸福な都道府県の第1位は福井県 [社会]
No.240「破壊兵器としての数学」で、アメリカで一般化している "大学ランキング" の話を書きました。それからの連想で、今回は日本の都道府県のランキングの話を書きます。
No.240で紹介した "大学ランキング" は、キャシー・オニール 著「破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」の紹介でした(日本語版の題名「あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」)。この本の中でキャシー・オニールは、本来多様であるべき大学教育が一つの数字によるランキングで順位付けられることの不合理や弊害を厳しく指摘していました。
ただこれはアメリカの話であり、"不合理・弊害" といっても日本人としては少々実感に乏しいものです。そこで今回は日本のランキングをとりあげ、"一つの数字によるランキング" を書いてみたいと思います。こういったたぐいのランキングがどうやって算出されているのか、それを知っておくのは有用と思うからです。
とりあげるのは「都道府県 幸福度ランキング 2018年版」(寺島実郎 監修。日本総合研究所 編。東洋経済新聞社。2018.6.7発行。以下「本書」と表記)です。都道府県幸福度ランキングは、日本総合研究所が編纂するようになってから、2012年、2014年、2016年と発行されていて、今回が4回目となります。なお以下で日本総合研究所を日本総研と略することがあります。
都道府県 幸福度ランキング
まず「都道府県幸福度」という聞き慣れない言葉の定義は何かです。本書の「まえがき」の最初の文章は、
という問題提起で始まります。その答が「地域の幸福度」なのですが、それは「地域に生きる人々の幸福を考えるための基盤となる要素」と説明されています。具体的には後で説明しますが、その「基盤となる要素」を70の客観指標で、都道府県単位で表現したのが「都道府県幸福度」です。
言うまでもなく、幸福や不幸は人間の主観的なものです。ある地域に住んでいる人は幸福で、別の地域の人は不幸というのは、現在日本で一般的にはありません。2018年の都道府県 幸福度ランキングで総合1位になったのは福井県、47位は高知県ですが、たとえば家族の崩壊と病気が重なって "自分は不幸だ" と思っている高知県在住の方が福井県に移住したら幸福になった、ということはあり得ないわけです。もちろん、戦乱が続く地域とか飢餓が日常化している地域の住民は主観にかかわらず "不幸" だと思いますが、話はそういうことが考えられない現代日本に限定します。
"幸福度" で混同してはいけないのが、国連が調査している「国の幸福度」で、これは主観調査です。つまり「あなたは幸福ですか」という質問に10段階で答えるという調査を150以上の国・地域で大々的にやって、平均値でランキングするという方法です。これはこれで非常にシンプルで、明快です(ちなみに2016年の1位はデンマーク、日本は53位)。
「都道府県幸福度」はそれとは全く違った客観指標によるランキングです。つまり、人が幸福と感じるためには、その基盤として地域の特性や行政サービスのレベル、教育の充実度、インフラの整備度、産業の活性度、健康な生活、地域生活の充足などがあるだろう、その指標を作るということなのです。従って指標の選び方が最大の問題です。
またこれは「都道府県単位の指標」であることに注意が必要です。たとえば、東京都に移住してきて仕事を始めた3人がいるとして、1人は東京23区、1人は奥多摩、1人は小笠原に居を構えたとします。この3人のライフスタイル、価値観、人生観は全く違うことが明白で、従って何を幸福と思うかも全く違うでしょう。そして、奥多摩と23区と小笠原では行政サービスだけをとってみても、そのありようが違うと想定されます。「都道府県幸福度」は「奥多摩・23区・小笠原」を一緒くたにして「東京都」という指標でくくっています。ここに注意すべきです。
2018年版の70の指標
具体的に2018年版の70の指標を見ていくことにします。指標は「基本指標」「一般指標」「追加指標」の3つに大別されます。「一般指標」という言葉は本書では使っていませんが、説明をしやすくするためにここでは使います。以下の指標はすべて公的機関(省庁など)の調査データをもとにしています。
基本指標は2012年版からずっと使われている指標で、かつ都道府県の幸福度の一番の基礎と考えれられているものです。ここに「(3)国政選挙の投票率」を入れたのは納得できます。参政権を行使して地域づくりに責任をもつのは民主主義の基本だからです(ちなみに投票率の1位は山形県で、47位は徳島県)。また「(1)人口増加率」「(2)県民所得」「(5)財政健全度」を基本指標とするのも納得できます。
しかし意外なのは、ここに「(4)カロリーベースの食料自給率」が入っていることです。日本の国レベルの食料自給率は約40%で、これは先進国の中では極めて低く、安全保障上も問題だとされています(アメリカ、フランスなどは優に100%を越えている)。このような状況から「都道府県の食料自給率」も全般的に低くなります。100%を越えているのは、北海道(221%)、秋田県(196%)、山形県(142%)、青森県(124%)、岩手県(110%)、新潟県(104%)の6道県しかなく、逆に10%以下は、埼玉県(10%)、神奈川県(2%)、大阪府(2%)、東京都(1%)の4都府県あります。
なぜ「県レベルの食料自給率」が "都道府県幸福度" の基本指標なのか。本書の説明は次の通りです。
確かに議論することは重要だと思いますが(その前に、国レベルの議論が必要なはずですが)、東京都知事に「食料自給率が1%です。どうしますか」と質問しても話にならないでしょう。食料自給率は農業・漁業が盛んで、かつ人口が少ない県ほど有利になるわけで、農業・漁業が盛んな度合いを "都道府県幸福度" の基本指標に取り入れる意味はないはずです。ひょっとしたらこれは、大都会をかかえる都道府県(東京・大阪とその周辺、愛知など)が基本指標で有利になりすぎないために入れられたのかもしれません。
以下の一般指標も2012年度版からずっと使われているものであり、都道府県幸福度の中心的な指標です。合計50の指標は、5つの分野(大項目)と10の領域(中項目)に分類されています。また指標には「現行指標」と「先行指標」の区別があります。この区別は、
と説明されています(本書)。以下の表で「先行指標」は緑色に塗ってあります。また指標には「大きいほどよいもの」と「小さいほどよいもの」があります。たとえば最初の「(6)生活習慣病受療者数」は「小さいほどよい指標」です。指標ごとに想像はつくので、その区別は省略します。
指標について何点かの補足をします。まず「・・・・・ 数」となっている指標は、それぞれの指標ごとに決められた人口(=母数)で割った "比率" です。たとえば【健康:医療・福祉】の「(6)生活習慣病受療者数」の母数は総人口、「(8)産科・産婦人科医師数」の母数は15~49歳の女性人口、「(9)ホームヘルパー数」の母数は65歳以上人口、といった具合です。
【健康:運動・体力】の「(11)健康寿命」はあまり聞き慣れない言葉ですが、「健康上の問題による日常生活の制限、がない期間」を言います。平均寿命から、入院・寝たきり・要介護などの期間を引いたものです。
【仕事・企業】の「(32)製造業労働生産性」とは、製造業が創出した付加価値(雑駁に言うと利潤+人件費)を製造業の従業員数で割ったものです。
【教育:学校】の「(48)司書教諭発令率」は、公立の小・中・高校のうち、司書教諭を任命している学校の割合です。
【教育:社会】の「(51)社会教育費」は、公民館、図書館、博物館、体育館、文化会館などの費用や、文化財保護の費用などの合計(一人当たり)です。
【教育:社会】の「(53)学童保育設置率」は、学童保育所の数を小学校の数で割ったものです。ほとんどの都道府県でこの数は100%を越えていますが、和歌山、徳島、高知の3県は100%以下です。
【教育:社会】の「(54)余裕教室活用率」は、公立小・中学校の余裕教室のうち、活用されているものの割合です。ほとんどの都道府県は98%以上で、最も低い大分県でも93.1%です。
基本指標と一般指標は、都道府県幸福度ランキング 2012年版からずっと変わらず設定されている指標ですが、追加指標は2014年版以降で付け加えられたものです。次の15項目から成ります。
補足しますと、まず【2014年追加指標】の「(56)信用金庫貸出平均利回り」は、信用金庫の貸出金の残高に対する貸出利息の割合で、低いほど上位にランクされます。つまり、低金利で信用金庫から借りられる都道府県ほど上位になります。ちなみに1位は奈良県の1.21%、47位は高知県の3.71%で、3倍の開きがあります。
【2016年追加指標】の「(64)農業の付加価値創出額」は、紛らわしいのですが、農業の県内総生産を県の総人口で割ったものです。【仕事・企業】の「(32)製造業労働生産性」は、製造業が創出した付加価値(利潤+人件費)を製造業の従業員数で割ったものでしたが、「(64)農業の付加価値創出額」は一人あたりの農業生産高です。従って農業が盛んな都道府県ほどこの指標は高くなります。ちなみに1位は宮崎県の116,519円で、47位は東京都の2,929円で、40倍の開きがあります。
【2018年追加指標】の「(68)子どものチャレンジ率」とは聞き慣れない言葉ですが、文部科学省の「全国学力・学習状況調査」の公立の小・中学校の調査で「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか」という質問に「当てはまる」ないしは「どちらかと言うと当てはまる」と答えた児童・生徒の割合です。ちなみに1位は秋田県の83.4%、47位は徳島県の70.2%です。
本書には「この指標が高ければ、子どもたちのたくましさ、人間力が向上し、先の長い人生のさまざまなステージにおいて、主体的に目標に向かって学習・挑戦できる幸福へとつながる」と説明されています。ただし、公立の小・中学校の学力調査での質問で、長い人生における人間力が計測できるかは疑問だと思います。また、このようなアンケート調査で、83.4%から70.2%までの差にどれほどの意味があるのかも疑問です。
指標の特徴と疑問
全体的にまんべんなく指標が選ばれている感じもしますが、大きな特徴は「国際化」を強く意識していることでしょう。【一般指標】の【文化・国際】の5つの指標や、【2018年追加指標】の「(66)訪日外国人消費単価」がそうです。
疑問点もいくつかあります。まず、農業が盛んな県ほど高くなる指標があることです。【基本指標】の「(4)食料自給率(カロリーベース)」と【2016年追加指標】の「(64)農業の付加価値創出額」です。いずれも最下位は東京都ですが、当然そうなるところでしょう。これは「農業を産業としてもっと振興すべきだ」という日本総研の考え方があるのでしょうが、産業構造は都道府県によって多様で(多様であるべきで)、ちょっと解せない指標です。国レベルの議論なら大変よくわかります。
また、都道府県によってほとんど差が付かない指標、かつ日常生活にとってあまり関係ないと思われる指標がいろいろあるのも疑問です。たとえば【教育:社会】の「(54)余裕教室活用率」は、ほとんどの都道府県は98%以上で、最も低い大分県でも93.1%です。もちろん100%がいいに決まっていますが、93.1%だとまずいとも思えません。不思議な指標です。
同じ【教育:社会】の「(55)悩みやストレスのある者の数」は厚生労働省の「国民生活基礎調査」のデータですが、1位は北海道の44.0%、47位は兵庫県の51.1%です。この差の7.1%は意味のある数字なのかどうか。むしろ現代人としては「悩みやストレスを抱えながら、前向きにかつポジティブに人生を楽しむ」というのが基本だと思います。「(68)子どものチャレンジ率」という指標があるように、日本総研は「チャレンジするのは大事」と考えているようです。チャレンジすれば悩みやストレスも増えるのは当然です。
あとで述べますが、こういった有意な差がない指標でも総合ランキングに利いてくるのです。そこに注意すべきです。
「お金」に関する指標がないのも疑問です。No.240「破壊兵器としての数学」で紹介したアメリカの "大学ランキング" には「お金」に関する項目がありませんでした(授業料など)。同じようにこの都道府県幸福度の指標も都道府県民の「負担」に関する項目が全くありません。つまり、住民税、国民健康保険料、義務教育にかかる費用、子どもの医療費の自己負担額などの、公的な(準公的な)負担額です。一概に負担額が低い都道府県が良いというわけではありませんが、本書の一番の目的は指標値に基づく都道府県のランキングを明確化して「地方の幸福」とは何かを議論することなので、あるべき項目だと思います。
また「安心・安全」に関する指標がないのも不思議です。"幸福な生活" の最も根底にあるのは「安心・安全」のはずで、さまざまな自然災害や事故、火災、犯罪による被害が少なく、市民生活の安寧が守られていることが重要です。2016年追加指標になってやっと「(63)刑法犯認知件数」が出てきますが、この一つでは不足でしょう。一般指標の「分野」か「領域」のレベルに「安心・安全」があってしかるべきだと思います。
多角的な都道府県の分析がポイント
いろいろと疑問はありますが、本書の一番の目的は「各指標ごとのランキングを都道府県ごとに明確化し、地方の幸福とは何かを議論すること」です。本書ではそれが明らかにされていて、都道府県ごとに全国のトップクラスの指標は何か、また課題となる指標は何かが解説されています。また2012年からの変化が大きいもの(上昇や下降など)も指摘されています。こういった分析は、たとえば地方自治に関わる人たち、ないしは地域の団体で活動している人たちへの情報提供として優れていると思います。
また本書ではライフステージごとの幸福度が分析されています。つまり「青少年」「子育て世代」「中堅社会人」「現役のシルバー世代(60歳以上)」などにわけ、それぞれに関わると考えられる幸福度の指標を選定し、各都道府県の傾向や取り組みが分析されています。さらに「健康長寿社会」の到来にともなって、そこでの幸福とは何か、何が必要か、都道府県の傾向はどうかという分析もあります。本書の価値はこういった分析にあります。
ただし、これらの分析で多く使われている指標ごとのランキングは絶対評価ではなく相対評価です。指標値が上がったとしても都道府県の全体の指標値が上がるとランキングは上がりません。指標は「高ければ高いほどよい」ものばかりではないはずです。一定レベルをクリアすれば十分なものもあるはずです。逆に特定の指標が高すぎることが副作用を招くことも考えられます。絶対評価をするのは非常に難しいと思いますが、ランキングはあくまで相対評価だということを念頭において読むべきだと思いました。
総合ランキングの計算方法
ここまでは前置きです。ここからが "問題の" 総合ランキングの算出方法で、この記事の主眼です。本書は 70の指標の都道府県ごとのポイントを計算し、それを総合して「都道府県幸福度ランキング」(これが本の題名)を決めています。このポイントの計算方法は次のように書かれています。
平均値からのずれが「偏差」(正または負)です。「偏差」の2乗を平均したものが「分散」で、分散の平方根が「標準偏差」(正の値)です。上の「標準化変量」とは「偏差」を「標準偏差」で割ったものということになります。これは意味としては、大学入試で一般的な「偏差値」と同じです。「標準化変量」(正または負)を10倍して50を足すと「偏差値」になります。つまり偏差値は平均が50、標準偏差が10としてデータを正規化したものですが、標準化変量は平均が0、標準偏差が1の正規化です。この標準化変量が総合ポイントの計算に使われているわけです。
この計算がどういうものか、2つの例で調べてみます。70の指標には都道府県で指標値の変化があまりない指標と、大きく変化している指標があります。まず変化があまりない指標として、2014年追加指標である「(57)平均寿命」の「標準化変量」と「偏差値」を計算してみたのが次です。この2018年版に記載されている平均寿命は、厚生労働省の2015年時点のデータです。
平均寿命が同じ数字でも順位が違うのは、小数点第2位以下が省略されているからです。この平均寿命の指標は、1位の長野県と47位の青森県では寿命では2.4歳の差ですが、標準化変量では 5.2054ポイントの差になることに注目すべきです。
ちなみに「偏差値」をみると、長野県・滋賀県は69、秋田県は30、青森県は17となります。大学入試の感覚からいうと「長野県・滋賀県は素晴らしい、秋田県は全然ダメ、青森県は論外」ですが、その平均寿命の差は2歳程度なのです。この平均寿命の偏差値で分かるように僅かな差でも状況によってはそれが大きく拡大されるのがこの計算です。
もうひとつ、今度は都道府県の指標値に大きな差があるものを取り上げます。基本指標の一つである「(4)食料自給率(カロリーベース)」(単位は%)です。この標準化変量(と偏差値)の計算をすると以下のようになります。
1位の北海道(221%)と最下位の東京都(1%)の間には大きな開きがありますが、標準化変量の差は 5.8194 ポイントしかありません。平均寿命1位の長野県と47位の青森県の差である 5.2054 ポイントと大して変わらないのです。食料自給率がゼロに近い東京都の偏差値(= 38)は、大学入試の感覚から言うと何とか大学に入れるレベルです。これは青森県の平均寿命の偏差値(= 17)が "論外" だったのとは大きな違いです。そういう風に計算されてしまうということなのです。
そもそも「標準偏差」という概念は、多くの値が平均値の周りに集中し、平均から離れると少なくなるという分布のありよう(=平均への集中度合い)を一つの値で示そうとするものです。食料自給率のように「値が全くバラケてしまっているもの」に対して標準偏差という概念は有効ではなく、つまり標準化変量も意味のある値ではない。そもそも食料自給率の平均である 54.7660% が一体何を意味しているのかが不明です。
とはいえ、総合ポイントを計算するためには無理矢理にでも指標値の正規化をする必要があるので、こういった計算になるということです。
こうした標準化変量を70の指標についてそれぞれ計算し、それらを単純加算すると(小さいほどよい指標は符号を逆転させて加算すると)都道府県の総ポイントが決まります。そのポイントの大小でランキングが決まるというわけです。
総合ランキングの結果
総合ランキングの結果と順位が本書に載っていますが、ここではポイントのグラフを引用します。青い折れ線グラフが総合ポイントで、棒グラフは基本指標、一般指標の各分野、追加指標ごとのポイントを積み上げたものです。
総合1位は福井県で、これで2014年から3回連続の1位です。特に仕事分野と教育分野のポイントが高い。ただし、文化分野は33位です。このグラフを見ると福井県は「平均より下=ゼロより下」の指標がほとんどないことがわかります。かつ「平均より上=ゼロより上」の指標が高いレベルにあることが見て取れます。
2位は東京都で、4回連続の2位です。文化分野のポイントが他の都道府県に比べて圧倒的に高く、基本指標や仕事分野も高い。ただし生活分野は42位です。東京都も福井県と同じで、平均より下の指標があまりありません。このグラフを見ると、次のような傾向が感じ取れます。
私見ですが、この「上位県は多くの指標が上位、下位県は多く指標が下位」という "2極化" で感じるのは、何らかの "隠れた変数" があって、それが多くの指標と因果関係をもっているのではないかということです。その "隠れた変数" は 70 の指標にないかもしれないし、あるかもしれない。ないしは複合的な指標かもしれません。また数値では表し難いものかもしれない。このあたりの分析も欲しいと思いました。
重み付けがないランキング
このランキングで重要な点は、70の指標を正規化して単純加算していて、指標に重みを付けていないことです。これは最初に書いたアメリカの "大学ランキング"(No.240「破壊兵器としての数学」)とは違います。大学ランキングも客観データにもとづくランキングですが、各データに重みをつけて算出しています。もちろんその重みはランキング作成者の考え方に依存しているのですが、ともかく重要度の判断をしている。"大学ランキング"でなぜ重みづけが可能かというと、これは大学の「教育の卓越性」を測定しようとするものだからです。目的が明確なのです。
一方、都道府県幸福度ランキングはそうはいきません。幸福度というのは老若男女、あらゆる市民に関わるランキングです。たとえば、結婚数年の共働きの夫婦がいたとして、これから子育てを考えている場合、「(8)産科・産婦人科医師数」「(38)待機児童率」「(53)学童保育設置率」などが重要だと考えるでしょう。しかしリタイアして趣味や地域活動に励もうとする夫婦は、重要度の考えが全く違うはずです。都道府県幸福度ランキングでは「重み」の設定のしようがないのです。だから70指標(正規化したもの)の単純加算でやるしかない。
つまり70の指標はすべて対等です。「(5)財政健全度」も「(68)子どものチャレンジ率」も「(54)余裕教室活用率」も同じウェイトである(これは例です)。従って総合ランキングでどの都道府県が上位にいくかは、ひとえにどういう指標を選ぶかにかかっているわけです。
このような事情から、少々奇妙なことも起こります。たとえば都道府県の「(5)財政健全度」は、普通に考えて「地域の幸福」の重要な基盤だと思うのですが、たとえば総合ランキング4位の石川県の財政健全度は39位です。総合ランキング5位の富山県の財政健全度は43位です。別にこの2県を悪く言うつもりは全くないのですが、財政健全度が全国で最低レベルでも総合5位というのは、何となく奇妙だなと思うわけです。もちろん相対評価なのですが ・・・・・・。
これは都道府県を "幸福度の基盤で" ランキングしようとする限りやむを得ないのでしょう。逆に言うと「総合ランキング」の順位は、それほど意味のあるものではないのです。本当は、上位、中位、下位ぐらいの3グループのどこに位置するかというぐらいが妥当でしょう。
幸福な都道府県の第1位は福井県
ここで総合ランキングの内容を理解するために、総合ランキング1位の福井県を詳しくみたいと思います。福井県の全70指標のランキングをリストしたのが次の表です。本書には記載されていませんが、ここではランキング1位~47位をほぼ3等分し、視認性を高めるために以下のように色分けしました。
福井県の1位の理由は【仕事・雇用】領域と【教育】分野でトップであることです。また【健康】分野や【生活・個人】領域でも上位グループにある。さらに、2014年以降の追加指標のほとんどで上位グループにあることも大きいでしょう。
全体に赤色の指標(都道府県の上位1/3に入る指標)が多いのは一目瞭然だし、3領域で1位だというのは、総合ランキングでトップになるのも納得できます。
しかしこの総合ランキングはあくまで日本総研が出した「70指標の単純合計」であることに変わりありません。先ほども書いたように、この70指標指標以外にも、幸福度に関係する項目はあります。たとえば、日本総研の指標には「安心・安全」に関する項目がないと上に書きましたが(唯一の例外が「(63)刑法犯認知件数」)、福井県に関して言うと "原子力発電所の集積地" であることが気になります。
現在、日本で稼働中の原子力発電所は12県にあります。「稼働中」とは廃炉が決定したもの、および廃炉の方針が示された "福島第2" を除いたカウントです(もちろん稼働中のなかには、定期点検・地震の影響・政府の要請等で運転停止中の原子力発電所が多々ある)。その12県を北の方から発電所名ともにリストすると、
◆北海道(泊)
◆青森県(東通)
◆宮城県(女川)
◆新潟県(柏崎刈羽)
◆石川県(志賀)
◆福井県(敦賀、美浜、大飯、高浜)
◆茨城県(東海第2)
◆静岡県(浜岡)
◆島根県(島根)
◆愛媛県(伊方)
◆佐賀県(玄海)
◆鹿児島県(川内)
ですが、11道県の原子力発電所は1カ所だけなのに、福井県だけは4カ所もあります。もちろん東日本大震災以降、原発の安全審査は厳しくなったとされていますが、安全といっても「想定内の事態に対して安全」ということであり、東日本大震災のように「想定外」(東電経営陣の主張)の事態が起こると大惨事を招くわけです。
原子力発電所の集積県だということは、各種の補助金や県民の雇用面のメリットが大だと思いますが(= "幸福度" のプラス)、福井県が "4原発集積県" であるということはそれだけ安心面でのデメリットを抱えていることも確かでしょう(= "幸福度" のマイナス。これは隣接する京都府や滋賀県にとっても重大関心事)。もちろん、原子力発電所設置数(ないしは原子炉設置数)などという "指標" は「都道府県幸福度ランキング」には絶対に選ばれないと思いますが ・・・・・・。
「総合ランキング」については、それがどのように作成されたものかを知ることが重要だと思います。似たようなランキングとして最近も、森ビルのシンクタンクである森記念財団都市戦略研究所が「日本の都市力ランキング」を発表しました。これは東京を除く主要72都市のランキングですが、1位は京都市、2位は福岡市、3位は大阪市だそうです(2018年10月3日の日本経済新聞による)。それぞれの都市に "都市力" があることは分かりますが、この全く性格が違う3都市の並びには違和感があります。これも、どういう指標でどうやってランクづけしているのか、それを知らないと何とも言えませんが、要するに「総合ランキング」に無理があるということでしょう。
そういった「総合ランキング」より重要なのは、個々の指標の値と全国にける位置づけでしょう。本書に即して言うと、地域の幸福の基盤となる指標は何か、それは本書があげているもののほかに、各人が考えることも重要でしょう。本書にはそいう議論を進めるトリガーとしての意味があると思いました。
No.240で紹介した "大学ランキング" は、キャシー・オニール 著「破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」の紹介でした(日本語版の題名「あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」)。この本の中でキャシー・オニールは、本来多様であるべき大学教育が一つの数字によるランキングで順位付けられることの不合理や弊害を厳しく指摘していました。
ただこれはアメリカの話であり、"不合理・弊害" といっても日本人としては少々実感に乏しいものです。そこで今回は日本のランキングをとりあげ、"一つの数字によるランキング" を書いてみたいと思います。こういったたぐいのランキングがどうやって算出されているのか、それを知っておくのは有用と思うからです。
とりあげるのは「都道府県 幸福度ランキング 2018年版」(寺島実郎 監修。日本総合研究所 編。東洋経済新聞社。2018.6.7発行。以下「本書」と表記)です。都道府県幸福度ランキングは、日本総合研究所が編纂するようになってから、2012年、2014年、2016年と発行されていて、今回が4回目となります。なお以下で日本総合研究所を日本総研と略することがあります。
都道府県 幸福度ランキング
まず「都道府県幸福度」という聞き慣れない言葉の定義は何かです。本書の「まえがき」の最初の文章は、
| いかなる国、地域に暮らすことが「幸福」と言えるのか |
という問題提起で始まります。その答が「地域の幸福度」なのですが、それは「地域に生きる人々の幸福を考えるための基盤となる要素」と説明されています。具体的には後で説明しますが、その「基盤となる要素」を70の客観指標で、都道府県単位で表現したのが「都道府県幸福度」です。
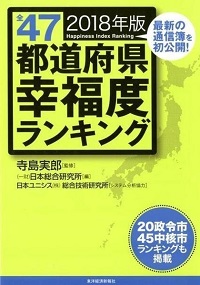
| |||
"幸福度" で混同してはいけないのが、国連が調査している「国の幸福度」で、これは主観調査です。つまり「あなたは幸福ですか」という質問に10段階で答えるという調査を150以上の国・地域で大々的にやって、平均値でランキングするという方法です。これはこれで非常にシンプルで、明快です(ちなみに2016年の1位はデンマーク、日本は53位)。
「都道府県幸福度」はそれとは全く違った客観指標によるランキングです。つまり、人が幸福と感じるためには、その基盤として地域の特性や行政サービスのレベル、教育の充実度、インフラの整備度、産業の活性度、健康な生活、地域生活の充足などがあるだろう、その指標を作るということなのです。従って指標の選び方が最大の問題です。
またこれは「都道府県単位の指標」であることに注意が必要です。たとえば、東京都に移住してきて仕事を始めた3人がいるとして、1人は東京23区、1人は奥多摩、1人は小笠原に居を構えたとします。この3人のライフスタイル、価値観、人生観は全く違うことが明白で、従って何を幸福と思うかも全く違うでしょう。そして、奥多摩と23区と小笠原では行政サービスだけをとってみても、そのありようが違うと想定されます。「都道府県幸福度」は「奥多摩・23区・小笠原」を一緒くたにして「東京都」という指標でくくっています。ここに注意すべきです。
2018年版の70の指標
具体的に2018年版の70の指標を見ていくことにします。指標は「基本指標」「一般指標」「追加指標」の3つに大別されます。「一般指標」という言葉は本書では使っていませんが、説明をしやすくするためにここでは使います。以下の指標はすべて公的機関(省庁など)の調査データをもとにしています。
| 基本指標:5項目 |
| 基本指標 | (1)人口増加率 |
| (2)一人当たり県民所得 | |
| (3)選挙投票率(国政選挙) | |
| (4)食料自給率(カロリーベース) | |
| (5)財政健全度 |
基本指標は2012年版からずっと使われている指標で、かつ都道府県の幸福度の一番の基礎と考えれられているものです。ここに「(3)国政選挙の投票率」を入れたのは納得できます。参政権を行使して地域づくりに責任をもつのは民主主義の基本だからです(ちなみに投票率の1位は山形県で、47位は徳島県)。また「(1)人口増加率」「(2)県民所得」「(5)財政健全度」を基本指標とするのも納得できます。
しかし意外なのは、ここに「(4)カロリーベースの食料自給率」が入っていることです。日本の国レベルの食料自給率は約40%で、これは先進国の中では極めて低く、安全保障上も問題だとされています(アメリカ、フランスなどは優に100%を越えている)。このような状況から「都道府県の食料自給率」も全般的に低くなります。100%を越えているのは、北海道(221%)、秋田県(196%)、山形県(142%)、青森県(124%)、岩手県(110%)、新潟県(104%)の6道県しかなく、逆に10%以下は、埼玉県(10%)、神奈川県(2%)、大阪府(2%)、東京都(1%)の4都府県あります。
なぜ「県レベルの食料自給率」が "都道府県幸福度" の基本指標なのか。本書の説明は次の通りです。
|
確かに議論することは重要だと思いますが(その前に、国レベルの議論が必要なはずですが)、東京都知事に「食料自給率が1%です。どうしますか」と質問しても話にならないでしょう。食料自給率は農業・漁業が盛んで、かつ人口が少ない県ほど有利になるわけで、農業・漁業が盛んな度合いを "都道府県幸福度" の基本指標に取り入れる意味はないはずです。ひょっとしたらこれは、大都会をかかえる都道府県(東京・大阪とその周辺、愛知など)が基本指標で有利になりすぎないために入れられたのかもしれません。
| 一般指標:50項目 |
以下の一般指標も2012年度版からずっと使われているものであり、都道府県幸福度の中心的な指標です。合計50の指標は、5つの分野(大項目)と10の領域(中項目)に分類されています。また指標には「現行指標」と「先行指標」の区別があります。この区別は、
| 現状における経済・社会の安定度を示す指標 | |||
| 将来あるべき姿を見据えた未来への投資状況を示す指標 |
と説明されています(本書)。以下の表で「先行指標」は緑色に塗ってあります。また指標には「大きいほどよいもの」と「小さいほどよいもの」があります。たとえば最初の「(6)生活習慣病受療者数」は「小さいほどよい指標」です。指標ごとに想像はつくので、その区別は省略します。
| 分野 | 領域 | 指標 |
| 健康 | 福祉 |
(6)生活習慣病受療者数 |
| (7)感情傷害(うつ等)受療者数 | ||
| (8)産科・産婦人科医師数 | ||
| (9)ホームヘルパー数 | ||
| (10)高齢者ボランティア活動数 | ||
体力 |
(11)健康寿命 | |
| (12)平均歩数 | ||
| (13)健康診査受診率 | ||
| (14)体育・スポーツ施設数 | ||
| (15)スポーツの活動時間 | ||
| 文化 | 娯楽 |
(16)教養・娯楽支出額(サービス支出) |
| (17)余暇時間 | ||
| (18)常設映画館数 | ||
| (19)書籍購入数 | ||
| (20)文化活動等NPO認証数 | ||
| 国際 | (21)外国人宿泊者数 | |
| (22)姉妹都市提携数 | ||
| (23)語学教室にかける金額 | ||
| (24)海外渡航者率 | ||
| (25)留学生数 | ||
| 仕事 | 雇用 | (26)若者完全失業率 |
| (27)正規雇用者比率 | ||
| (28)高齢者有業率 | ||
| (29)インターンシップ実施率 | ||
| (30)大卒者進路未定者率 | ||
| 企業 | (31)障がい者雇用率 | |
| (32)製造業労働生産性 | ||
| (33)事業所新設率 | ||
| (34)特許出願件数 | ||
| (35)本社機能流出・流入数 | ||
| 生活 | 個人 |
(36)持ち家比率 |
| (37)生活保護受給率 | ||
| (38)待機児童率 | ||
| (39)一人暮らし高齢者率 | ||
| (40)インターネット人口普及率 | ||
| 地域 | (41)汚水処理人口普及率 | |
| (42)道路整備率 | ||
| (43)一般廃棄物リサイクル率 | ||
| (44)エネルギー消費量 | ||
| (45)地縁団体数 | ||
| 教育 | 学校 | (46)学力 |
| (47)不登校児童生徒率 | ||
| (48)司書教諭発令率 | ||
| (49)大学進学率 | ||
| (50)教員一人当たり児童生徒数 | ||
| 社会 | (51)社会教育費 | |
| (52)社会教育学級・講座数 | ||
| (53)学童保育設置率 | ||
| (54)余裕教室活用率 | ||
| (55)悩みやストレスのある者の率 |
指標について何点かの補足をします。まず「・・・・・ 数」となっている指標は、それぞれの指標ごとに決められた人口(=母数)で割った "比率" です。たとえば【健康:医療・福祉】の「(6)生活習慣病受療者数」の母数は総人口、「(8)産科・産婦人科医師数」の母数は15~49歳の女性人口、「(9)ホームヘルパー数」の母数は65歳以上人口、といった具合です。
【健康:運動・体力】の「(11)健康寿命」はあまり聞き慣れない言葉ですが、「健康上の問題による日常生活の制限、がない期間」を言います。平均寿命から、入院・寝たきり・要介護などの期間を引いたものです。
【仕事・企業】の「(32)製造業労働生産性」とは、製造業が創出した付加価値(雑駁に言うと利潤+人件費)を製造業の従業員数で割ったものです。
【教育:学校】の「(48)司書教諭発令率」は、公立の小・中・高校のうち、司書教諭を任命している学校の割合です。
【教育:社会】の「(51)社会教育費」は、公民館、図書館、博物館、体育館、文化会館などの費用や、文化財保護の費用などの合計(一人当たり)です。
【教育:社会】の「(53)学童保育設置率」は、学童保育所の数を小学校の数で割ったものです。ほとんどの都道府県でこの数は100%を越えていますが、和歌山、徳島、高知の3県は100%以下です。
【教育:社会】の「(54)余裕教室活用率」は、公立小・中学校の余裕教室のうち、活用されているものの割合です。ほとんどの都道府県は98%以上で、最も低い大分県でも93.1%です。
| 追加指標:15項目 |
基本指標と一般指標は、都道府県幸福度ランキング 2012年版からずっと変わらず設定されている指標ですが、追加指標は2014年版以降で付け加えられたものです。次の15項目から成ります。
| 追加年 | 指標 |
| 2014年 | (56)信用金庫貸出平均利回り |
| (57)平均寿命 | |
| (58)女性の労働力人口比率 | |
| (59)自殺死亡者数 | |
| (60)子どもの運動能力 | |
| 2016年 | (61)合計特殊出生率 |
| (62)自主防災組織活動カバー率 | |
| (63)刑法犯認知件数 | |
| (64)農業の付加価値創出額 | |
| (65)勤労者世帯可処分所得 | |
| 2018年 | (66)訪日外国人消費単価 |
| (67)市民農園面積 | |
| (68)子どものチャレンジ率 | |
| (69)コンビニエンスストア数 | |
| (70)勤労者ボランティア活動比率 |
補足しますと、まず【2014年追加指標】の「(56)信用金庫貸出平均利回り」は、信用金庫の貸出金の残高に対する貸出利息の割合で、低いほど上位にランクされます。つまり、低金利で信用金庫から借りられる都道府県ほど上位になります。ちなみに1位は奈良県の1.21%、47位は高知県の3.71%で、3倍の開きがあります。
【2016年追加指標】の「(64)農業の付加価値創出額」は、紛らわしいのですが、農業の県内総生産を県の総人口で割ったものです。【仕事・企業】の「(32)製造業労働生産性」は、製造業が創出した付加価値(利潤+人件費)を製造業の従業員数で割ったものでしたが、「(64)農業の付加価値創出額」は一人あたりの農業生産高です。従って農業が盛んな都道府県ほどこの指標は高くなります。ちなみに1位は宮崎県の116,519円で、47位は東京都の2,929円で、40倍の開きがあります。
【2018年追加指標】の「(68)子どものチャレンジ率」とは聞き慣れない言葉ですが、文部科学省の「全国学力・学習状況調査」の公立の小・中学校の調査で「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していますか」という質問に「当てはまる」ないしは「どちらかと言うと当てはまる」と答えた児童・生徒の割合です。ちなみに1位は秋田県の83.4%、47位は徳島県の70.2%です。
本書には「この指標が高ければ、子どもたちのたくましさ、人間力が向上し、先の長い人生のさまざまなステージにおいて、主体的に目標に向かって学習・挑戦できる幸福へとつながる」と説明されています。ただし、公立の小・中学校の学力調査での質問で、長い人生における人間力が計測できるかは疑問だと思います。また、このようなアンケート調査で、83.4%から70.2%までの差にどれほどの意味があるのかも疑問です。
指標の特徴と疑問
全体的にまんべんなく指標が選ばれている感じもしますが、大きな特徴は「国際化」を強く意識していることでしょう。【一般指標】の【文化・国際】の5つの指標や、【2018年追加指標】の「(66)訪日外国人消費単価」がそうです。
疑問点もいくつかあります。まず、農業が盛んな県ほど高くなる指標があることです。【基本指標】の「(4)食料自給率(カロリーベース)」と【2016年追加指標】の「(64)農業の付加価値創出額」です。いずれも最下位は東京都ですが、当然そうなるところでしょう。これは「農業を産業としてもっと振興すべきだ」という日本総研の考え方があるのでしょうが、産業構造は都道府県によって多様で(多様であるべきで)、ちょっと解せない指標です。国レベルの議論なら大変よくわかります。
また、都道府県によってほとんど差が付かない指標、かつ日常生活にとってあまり関係ないと思われる指標がいろいろあるのも疑問です。たとえば【教育:社会】の「(54)余裕教室活用率」は、ほとんどの都道府県は98%以上で、最も低い大分県でも93.1%です。もちろん100%がいいに決まっていますが、93.1%だとまずいとも思えません。不思議な指標です。
同じ【教育:社会】の「(55)悩みやストレスのある者の数」は厚生労働省の「国民生活基礎調査」のデータですが、1位は北海道の44.0%、47位は兵庫県の51.1%です。この差の7.1%は意味のある数字なのかどうか。むしろ現代人としては「悩みやストレスを抱えながら、前向きにかつポジティブに人生を楽しむ」というのが基本だと思います。「(68)子どものチャレンジ率」という指標があるように、日本総研は「チャレンジするのは大事」と考えているようです。チャレンジすれば悩みやストレスも増えるのは当然です。
あとで述べますが、こういった有意な差がない指標でも総合ランキングに利いてくるのです。そこに注意すべきです。
「お金」に関する指標がないのも疑問です。No.240「破壊兵器としての数学」で紹介したアメリカの "大学ランキング" には「お金」に関する項目がありませんでした(授業料など)。同じようにこの都道府県幸福度の指標も都道府県民の「負担」に関する項目が全くありません。つまり、住民税、国民健康保険料、義務教育にかかる費用、子どもの医療費の自己負担額などの、公的な(準公的な)負担額です。一概に負担額が低い都道府県が良いというわけではありませんが、本書の一番の目的は指標値に基づく都道府県のランキングを明確化して「地方の幸福」とは何かを議論することなので、あるべき項目だと思います。
また「安心・安全」に関する指標がないのも不思議です。"幸福な生活" の最も根底にあるのは「安心・安全」のはずで、さまざまな自然災害や事故、火災、犯罪による被害が少なく、市民生活の安寧が守られていることが重要です。2016年追加指標になってやっと「(63)刑法犯認知件数」が出てきますが、この一つでは不足でしょう。一般指標の「分野」か「領域」のレベルに「安心・安全」があってしかるべきだと思います。
多角的な都道府県の分析がポイント
いろいろと疑問はありますが、本書の一番の目的は「各指標ごとのランキングを都道府県ごとに明確化し、地方の幸福とは何かを議論すること」です。本書ではそれが明らかにされていて、都道府県ごとに全国のトップクラスの指標は何か、また課題となる指標は何かが解説されています。また2012年からの変化が大きいもの(上昇や下降など)も指摘されています。こういった分析は、たとえば地方自治に関わる人たち、ないしは地域の団体で活動している人たちへの情報提供として優れていると思います。
また本書ではライフステージごとの幸福度が分析されています。つまり「青少年」「子育て世代」「中堅社会人」「現役のシルバー世代(60歳以上)」などにわけ、それぞれに関わると考えられる幸福度の指標を選定し、各都道府県の傾向や取り組みが分析されています。さらに「健康長寿社会」の到来にともなって、そこでの幸福とは何か、何が必要か、都道府県の傾向はどうかという分析もあります。本書の価値はこういった分析にあります。
ただし、これらの分析で多く使われている指標ごとのランキングは絶対評価ではなく相対評価です。指標値が上がったとしても都道府県の全体の指標値が上がるとランキングは上がりません。指標は「高ければ高いほどよい」ものばかりではないはずです。一定レベルをクリアすれば十分なものもあるはずです。逆に特定の指標が高すぎることが副作用を招くことも考えられます。絶対評価をするのは非常に難しいと思いますが、ランキングはあくまで相対評価だということを念頭において読むべきだと思いました。
総合ランキングの計算方法
ここまでは前置きです。ここからが "問題の" 総合ランキングの算出方法で、この記事の主眼です。本書は 70の指標の都道府県ごとのポイントを計算し、それを総合して「都道府県幸福度ランキング」(これが本の題名)を決めています。このポイントの計算方法は次のように書かれています。
|
平均値からのずれが「偏差」(正または負)です。「偏差」の2乗を平均したものが「分散」で、分散の平方根が「標準偏差」(正の値)です。上の「標準化変量」とは「偏差」を「標準偏差」で割ったものということになります。これは意味としては、大学入試で一般的な「偏差値」と同じです。「標準化変量」(正または負)を10倍して50を足すと「偏差値」になります。つまり偏差値は平均が50、標準偏差が10としてデータを正規化したものですが、標準化変量は平均が0、標準偏差が1の正規化です。この標準化変量が総合ポイントの計算に使われているわけです。
この計算がどういうものか、2つの例で調べてみます。70の指標には都道府県で指標値の変化があまりない指標と、大きく変化している指標があります。まず変化があまりない指標として、2014年追加指標である「(57)平均寿命」の「標準化変量」と「偏差値」を計算してみたのが次です。この2018年版に記載されている平均寿命は、厚生労働省の2015年時点のデータです。
平均寿命のランキング
| : | 2018年版 都道府県幸福度ランキング | |
| : | 都道府県別生命表(厚生労働省)。調査年は2015年 | |
| : | 男性平均寿命と女性平均寿命の平均 |
| 順位 | 偏差 | 偏差値 | |||
| 1 | 長野 | 84.7 | 0.8617 | 1.8690 | 69 |
| 2 | 滋賀 | 84.7 | 0.8617 | 1.8690 | 69 |
| 3 | 福井 | 84.4 | 0.5617 | 1.2183 | 62 |
| 4 | 京都 | 84.4 | 0.5617 | 1.2183 | 62 |
| 5 | 熊本 | 84.4 | 0.5617 | 1.2183 | 62 |
| 6 | 岡山 | 84.4 | 0.5617 | 1.2183 | 62 |
| 7 | 奈良 | 84.3 | 0.4617 | 1.0014 | 60 |
| 8 | 神奈川 | 84.3 | 0.4617 | 1.0014 | 60 |
| 9 | 島根 | 84.2 | 0.3617 | 0.7845 | 58 |
| 10 | 広島 | 84.2 | 0.3617 | 0.7845 | 58 |
| 11 | 大分 | 84.2 | 0.3617 | 0.7845 | 58 |
| 12 | 東京 | 84.2 | 0.3617 | 0.7845 | 58 |
| 13 | 石川 | 84.2 | 0.3617 | 0.7845 | 58 |
| 14 | 宮城 | 84.1 | 0.2617 | 0.5676 | 56 |
| 15 | 山梨 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 16 | 香川 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 17 | 静岡 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 18 | 富山 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 19 | 新潟 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 20 | 兵庫 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 21 | 愛知 | 84.0 | 0.1617 | 0.3507 | 54 |
| 22 | 千葉 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 23 | 三重 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 24 | 岐阜 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 25 | 福岡 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 26 | 佐賀 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 27 | 沖縄 | 83.9 | 0.0617 | 0.1338 | 51 |
| 28 | 山形 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 28 | 埼玉 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 30 | 宮崎 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 31 | 群馬 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 32 | 鳥取 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 33 | 山口 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 34 | 長崎 | 83.7 | -0.1383 | -0.3000 | 47 |
| 35 | 高知 | 83.6 | -0.2383 | -0.5168 | 45 |
| 36 | 北海道 | 83.5 | -0.3383 | -0.7337 | 43 |
| 37 | 徳島 | 83.5 | -0.3383 | -0.7337 | 43 |
| 37 | 愛媛 | 83.5 | -0.3383 | -0.7337 | 43 |
| 39 | 大阪 | 83.5 | -0.3383 | -0.7337 | 43 |
| 40 | 鹿児島 | 83.4 | -0.4383 | -0.9506 | 40 |
| 41 | 茨城 | 83.3 | -0.5383 | -1.1675 | 38 |
| 42 | 福島 | 83.3 | -0.5383 | -1.1675 | 38 |
| 43 | 和歌山 | 83.2 | -0.6383 | -1.3844 | 36 |
| 44 | 栃木 | 83.2 | -0.6383 | -1.3844 | 36 |
| 45 | 岩手 | 83.2 | -0.6383 | -1.3844 | 36 |
| 46 | 秋田 | 82.9 | -0.9383 | -2.0351 | 30 |
| 47 | 青森 | 82.3 | -1.5383 | -3.3364 | 17 |
| ◆平均 | : | 83.8383(歳) |
| ◆標準偏差 | : | 0.4611(歳) |
平均寿命が同じ数字でも順位が違うのは、小数点第2位以下が省略されているからです。この平均寿命の指標は、1位の長野県と47位の青森県では寿命では2.4歳の差ですが、標準化変量では 5.2054ポイントの差になることに注目すべきです。
ちなみに「偏差値」をみると、長野県・滋賀県は69、秋田県は30、青森県は17となります。大学入試の感覚からいうと「長野県・滋賀県は素晴らしい、秋田県は全然ダメ、青森県は論外」ですが、その平均寿命の差は2歳程度なのです。この平均寿命の偏差値で分かるように僅かな差でも状況によってはそれが大きく拡大されるのがこの計算です。
| とは言うものの、青森県の「平均寿命の偏差値は17」は大いに問題でしょう。平均寿命のように、多くの都道府県が83歳台後半から84歳台前半に集中している状況の中で、青森県のように82歳台前半という "外れ値" があるとそうなります。青森県民が塩気の利いた食品(漬け物など)を好むからだという説を聞いたことがありますが、青森県当局としてはその原因を追求し対策をとるべきでしょう。 |
もうひとつ、今度は都道府県の指標値に大きな差があるものを取り上げます。基本指標の一つである「(4)食料自給率(カロリーベース)」(単位は%)です。この標準化変量(と偏差値)の計算をすると以下のようになります。
食料自給率(カロリーベース)のランキング
| : | 2018年版 都道府県幸福度ランキング | |
| : | 都道府県別食糧自給率について(農林水産省)。調査年は2015年 |
| 順位 | 自給率 | 偏差 | 偏差値 | ||
| 1 | 北海道 | 221 | 166.2340 | 3.6415 | 86 |
| 2 | 秋田 | 196 | 141.2340 | 3.0938 | 81 |
| 3 | 山形 | 142 | 87.2340 | 1.9109 | 69 |
| 4 | 青森 | 124 | 69.2340 | 1.5166 | 65 |
| 5 | 岩手 | 110 | 55.2340 | 1.2099 | 62 |
| 6 | 新潟 | 104 | 49.2340 | 1.0785 | 61 |
| 7 | 佐賀 | 92 | 37.2340 | 0.8156 | 58 |
| 8 | 富山 | 83 | 28.2340 | 0.6185 | 56 |
| 9 | 鹿児島 | 82 | 27.2340 | 0.5966 | 56 |
| 10 | 福島 | 77 | 22.2340 | 0.4871 | 55 |
| 11 | 宮城 | 73 | 18.2340 | 0.3994 | 54 |
| 12 | 茨城 | 70 | 15.2340 | 0.3337 | 53 |
| 12 | 栃木 | 70 | 15.2340 | 0.3337 | 53 |
| 14 | 福井 | 68 | 13.2340 | 0.2899 | 53 |
| 15 | 宮崎 | 66 | 11.2340 | 0.2461 | 52 |
| 16 | 島根 | 65 | 10.2340 | 0.2242 | 52 |
| 17 | 鳥取 | 63 | 8.2340 | 0.1804 | 52 |
| 18 | 熊本 | 58 | 3.2340 | 0.0708 | 51 |
| 19 | 長野 | 54 | -0.7660 | -0.0168 | 50 |
| 20 | 石川 | 51 | -3.7660 | -0.0825 | 49 |
| 20 | 滋賀 | 51 | -3.7660 | -0.0825 | 49 |
| 22 | 高知 | 47 | -7.7660 | -0.1701 | 48 |
| 23 | 長崎 | 46 | -8.7660 | -0.1920 | 48 |
| 23 | 大分 | 46 | -8.7660 | -0.1920 | 48 |
| 25 | 三重 | 42 | -12.7660 | -0.2796 | 47 |
| 25 | 徳島 | 42 | -12.7660 | -0.2796 | 47 |
| 27 | 愛媛 | 39 | -15.7660 | -0.3454 | 47 |
| 28 | 岡山 | 36 | -18.7660 | -0.4111 | 46 |
| 29 | 香川 | 34 | -20.7660 | -0.4549 | 45 |
| 30 | 群馬 | 33 | -21.7660 | -0.4768 | 45 |
| 31 | 山口 | 32 | -22.7660 | -0.4987 | 45 |
| 32 | 和歌山 | 29 | -25.7660 | -0.5644 | 44 |
| 33 | 千葉 | 27 | -27.7660 | -0.6082 | 44 |
| 34 | 沖縄 | 26 | -28.7660 | -0.6301 | 44 |
| 35 | 岐阜 | 25 | -29.7660 | -0.6520 | 43 |
| 36 | 広島 | 23 | -31.7660 | -0.6959 | 43 |
| 37 | 福岡 | 20 | -34.7660 | -0.7616 | 42 |
| 38 | 山梨 | 19 | -35.7660 | -0.7835 | 42 |
| 39 | 静岡 | 17 | -37.7660 | -0.8273 | 42 |
| 40 | 兵庫 | 16 | -38.7660 | -0.8492 | 42 |
| 41 | 奈良 | 15 | -39.7660 | -0.8711 | 41 |
| 42 | 京都 | 13 | -41.7660 | -0.9149 | 41 |
| 43 | 愛知 | 12 | -42.7660 | -0.9368 | 41 |
| 44 | 埼玉 | 10 | -44.7660 | -0.9806 | 40 |
| 45 | 神奈川 | 2 | -52.7660 | -1.1559 | 38 |
| 46 | 大阪 | 2 | -52.7660 | -1.1559 | 38 |
| 47 | 東京 | 1 | -53.7660 | -1.1778 | 38 |
| ◆平均 | : | 54.7660(%) |
| ◆標準偏差 | : | 45.6500(%) |
1位の北海道(221%)と最下位の東京都(1%)の間には大きな開きがありますが、標準化変量の差は 5.8194 ポイントしかありません。平均寿命1位の長野県と47位の青森県の差である 5.2054 ポイントと大して変わらないのです。食料自給率がゼロに近い東京都の偏差値(= 38)は、大学入試の感覚から言うと何とか大学に入れるレベルです。これは青森県の平均寿命の偏差値(= 17)が "論外" だったのとは大きな違いです。そういう風に計算されてしまうということなのです。
そもそも「標準偏差」という概念は、多くの値が平均値の周りに集中し、平均から離れると少なくなるという分布のありよう(=平均への集中度合い)を一つの値で示そうとするものです。食料自給率のように「値が全くバラケてしまっているもの」に対して標準偏差という概念は有効ではなく、つまり標準化変量も意味のある値ではない。そもそも食料自給率の平均である 54.7660% が一体何を意味しているのかが不明です。
とはいえ、総合ポイントを計算するためには無理矢理にでも指標値の正規化をする必要があるので、こういった計算になるということです。
こうした標準化変量を70の指標についてそれぞれ計算し、それらを単純加算すると(小さいほどよい指標は符号を逆転させて加算すると)都道府県の総ポイントが決まります。そのポイントの大小でランキングが決まるというわけです。
総合ランキングの結果
総合ランキングの結果と順位が本書に載っていますが、ここではポイントのグラフを引用します。青い折れ線グラフが総合ポイントで、棒グラフは基本指標、一般指標の各分野、追加指標ごとのポイントを積み上げたものです。
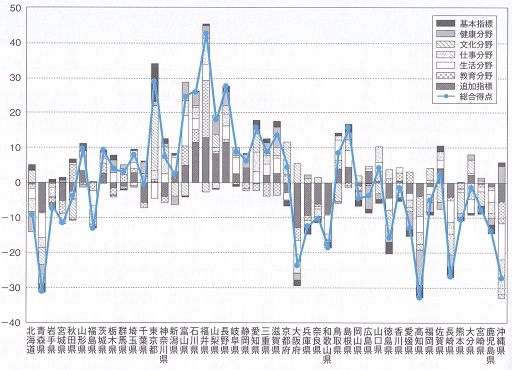
| ||
|
総合ポイント一覧
折れ線上の青点が各都道府県の総合ポイントを示している。1位:福井、2位:東京、3位:長野、4位:石川、5位:富山の順である。逆は、47位:高知、46位:青森、45位:沖縄、44位:長崎、43位:大阪の順。東京と大阪の2大都市が2位と43位に分かれてしまっているが、この総合ポイントの出し方では仕方ないのだろう。都道府県ごとの棒グラフは、基本指標、一般指標の分野ごと、追加指標のポイントを積み重ねたものである。「都道府県 幸福度ランキング 2018年版」(日本総合研究所 編。東洋経済新聞社。2018.6.7)より引用。
| ||
総合1位は福井県で、これで2014年から3回連続の1位です。特に仕事分野と教育分野のポイントが高い。ただし、文化分野は33位です。このグラフを見ると福井県は「平均より下=ゼロより下」の指標がほとんどないことがわかります。かつ「平均より上=ゼロより上」の指標が高いレベルにあることが見て取れます。
2位は東京都で、4回連続の2位です。文化分野のポイントが他の都道府県に比べて圧倒的に高く、基本指標や仕事分野も高い。ただし生活分野は42位です。東京都も福井県と同じで、平均より下の指標があまりありません。このグラフを見ると、次のような傾向が感じ取れます。
| ◆ | 総合ランキングが上位(総ポイントがプラス)の都道府県は、平均より下の指標が少ない(2つ以下が18都道府県)。 | ||
| ◆ | 総合ランキングが下位(総ポイントがマイナス)の都道府県は、平均より上の指標が少ない(2つ以下が19都道府県)。 | ||
| ◆ | 平均より上の指標と下の指標が同数に近い都道府県は中位にランキングされるが、そういった都道府県は比較的少ない(10都道府県)。 |
私見ですが、この「上位県は多くの指標が上位、下位県は多く指標が下位」という "2極化" で感じるのは、何らかの "隠れた変数" があって、それが多くの指標と因果関係をもっているのではないかということです。その "隠れた変数" は 70 の指標にないかもしれないし、あるかもしれない。ないしは複合的な指標かもしれません。また数値では表し難いものかもしれない。このあたりの分析も欲しいと思いました。
重み付けがないランキング
このランキングで重要な点は、70の指標を正規化して単純加算していて、指標に重みを付けていないことです。これは最初に書いたアメリカの "大学ランキング"(No.240「破壊兵器としての数学」)とは違います。大学ランキングも客観データにもとづくランキングですが、各データに重みをつけて算出しています。もちろんその重みはランキング作成者の考え方に依存しているのですが、ともかく重要度の判断をしている。"大学ランキング"でなぜ重みづけが可能かというと、これは大学の「教育の卓越性」を測定しようとするものだからです。目的が明確なのです。
一方、都道府県幸福度ランキングはそうはいきません。幸福度というのは老若男女、あらゆる市民に関わるランキングです。たとえば、結婚数年の共働きの夫婦がいたとして、これから子育てを考えている場合、「(8)産科・産婦人科医師数」「(38)待機児童率」「(53)学童保育設置率」などが重要だと考えるでしょう。しかしリタイアして趣味や地域活動に励もうとする夫婦は、重要度の考えが全く違うはずです。都道府県幸福度ランキングでは「重み」の設定のしようがないのです。だから70指標(正規化したもの)の単純加算でやるしかない。
つまり70の指標はすべて対等です。「(5)財政健全度」も「(68)子どものチャレンジ率」も「(54)余裕教室活用率」も同じウェイトである(これは例です)。従って総合ランキングでどの都道府県が上位にいくかは、ひとえにどういう指標を選ぶかにかかっているわけです。
このような事情から、少々奇妙なことも起こります。たとえば都道府県の「(5)財政健全度」は、普通に考えて「地域の幸福」の重要な基盤だと思うのですが、たとえば総合ランキング4位の石川県の財政健全度は39位です。総合ランキング5位の富山県の財政健全度は43位です。別にこの2県を悪く言うつもりは全くないのですが、財政健全度が全国で最低レベルでも総合5位というのは、何となく奇妙だなと思うわけです。もちろん相対評価なのですが ・・・・・・。
これは都道府県を "幸福度の基盤で" ランキングしようとする限りやむを得ないのでしょう。逆に言うと「総合ランキング」の順位は、それほど意味のあるものではないのです。本当は、上位、中位、下位ぐらいの3グループのどこに位置するかというぐらいが妥当でしょう。
幸福な都道府県の第1位は福井県
ここで総合ランキングの内容を理解するために、総合ランキング1位の福井県を詳しくみたいと思います。福井県の全70指標のランキングをリストしたのが次の表です。本書には記載されていませんが、ここではランキング1位~47位をほぼ3等分し、視認性を高めるために以下のように色分けしました。
| 上位 | 1位~16位 | 赤色 | ||||
| 中位 | 17位~31位 | (色なし) | ||||
| 下位 | 32位~47位 | 青色 |
福井県の70指標のランキング
| 分野など | 指標 | ||
| 基本指標 19位 | (1)人口増加率 | ||
| (2)一人当たり県民所得 | 14位 | ||
| (3)選挙投票率(国政選挙) | 23位 | ||
| (4)食料自給率 | 14位 | ||
| (5)財政健全度 | 22位 | ||
| 健康 8位 |
福祉 5位 |
(6)生活習慣病受療者数 | 13位 |
| (7)感情傷害受療者数 | 14位 | ||
| (8)産科・産婦人科医師数 | 11位 | ||
| (9)ホームヘルパー数 | 45位 | ||
| (10)高齢者ボランティア活動 | 9位 | ||
| 運動・ 体力 15位 |
(11)健康寿命 | 4位 | |
| (12)平均歩数 | 31位 | ||
| (13)健康診査受診率 | 23位 | ||
| (14)体育・スポーツ施設数 | 13位 | ||
| (15)スポーツの活動時間 | 7位 | ||
| 文化 33位 |
余暇・ 娯楽 33位 |
(16)教養・娯楽支出額 | 36位 |
| (17)余暇時間 | 25位 | ||
| (18)常設映画館数 | 4位 | ||
| (19)書籍購入数 | 34位 | ||
| (20)文化活動等NPO認証数 | 45位 | ||
| 国際 32位 |
(21)外国人宿泊者数 | 43位 | |
| (22)姉妹都市提携数 | 38位 | ||
| (23)語学教室にかける金額 | 10位 | ||
| (24)海外渡航者率 | 23位 | ||
| (25)留学生数 | 35位 | ||
| 仕事 1位 |
雇用 1位 |
(26)若者完全失業率 | 4位 |
| (27)正規雇用者比率 | 3位 | ||
| (28)高齢者有業率 | 5位 | ||
| (29)インターンシップ実施率 | 2位 | ||
| (30)大卒者進路未定者率 | 1位 | ||
| 企業 25位 |
(31)障がい者雇用率 | 7位 | |
| (32)製造業労働生産性 | 33位 | ||
| (33)事業所新設率 | 42位 | ||
| (34)特許出願件数 | 11位 | ||
| (35)本社機能流出・流入数 | 39位 | ||
| 生活 5位 |
個人 (家族) 2位 |
(36)持ち家比率 | 4位 |
| (37)生活保護受給率 | 3位 | ||
| (38)待機児童率 | 1位 | ||
| (39)一人暮らし高齢者率 | 3位 | ||
| (40)インターネット普及率 | 26位 | ||
| 地域 29位 |
(41)汚水処理人口普及率 | 9位 | |
| (42)道路整備率 | 5位 | ||
| (43)一般廃棄物リサイクル率 | 35位 | ||
| (44)エネルギー消費量 | 45位 | ||
| (45)地縁団体数 | 9位 | ||
| 教育 1位 |
学校 1位 |
(46)学力 | 1位 |
| (47)不登校児童生徒率 | 5位 | ||
| (48)司書教諭発令率 | 12位 | ||
| (49)大学進学率 | 13位 | ||
| (50)教員一人当たり生徒数 | 21位 | ||
| 社会 1位 |
(51)社会教育費 | 1位 | |
| (52)社会教育学級・講座数 | 1位 | ||
| (53)学童保育設置率 | 23位 | ||
| (54)余裕教室活用率 | 1位 | ||
| (55)悩みやストレスのある者の率 | 7位 | ||
| 追加 指標 | 2014 年 |
(56)信用金庫貸出平均利回り | 7位 |
| (57)平均寿命 | 3位 | ||
| (58)女性の労働力人口比率 | 1位 | ||
| (59)自殺死亡者数 | 25位 | ||
| (60)子どもの運動能力 | 1位 | ||
| 2016 年 |
(61)合計特殊出生率 | 7位 | |
| (62)自主防災活動カバー率 | 14位 | ||
| (63)刑法犯認知件数 | 9位 | ||
| (64)農業の付加価値創出額 | 33位 | ||
| (65)勤労者世帯可処分所得 | 9位 | ||
| 2018 年 |
(66)訪日外国人消費単価 | 12位 | |
| (67)市民農園面積 | 14位 | ||
| (68)子どものチャレンジ率 | 4位 | ||
| (69)コンビニエンスストア数 | 15位 | ||
| (70)勤労者ボランティア活動 | 5位 | ||
福井県の1位の理由は【仕事・雇用】領域と【教育】分野でトップであることです。また【健康】分野や【生活・個人】領域でも上位グループにある。さらに、2014年以降の追加指標のほとんどで上位グループにあることも大きいでしょう。
全体に赤色の指標(都道府県の上位1/3に入る指標)が多いのは一目瞭然だし、3領域で1位だというのは、総合ランキングでトップになるのも納得できます。
しかしこの総合ランキングはあくまで日本総研が出した「70指標の単純合計」であることに変わりありません。先ほども書いたように、この70指標指標以外にも、幸福度に関係する項目はあります。たとえば、日本総研の指標には「安心・安全」に関する項目がないと上に書きましたが(唯一の例外が「(63)刑法犯認知件数」)、福井県に関して言うと "原子力発電所の集積地" であることが気になります。
現在、日本で稼働中の原子力発電所は12県にあります。「稼働中」とは廃炉が決定したもの、および廃炉の方針が示された "福島第2" を除いたカウントです(もちろん稼働中のなかには、定期点検・地震の影響・政府の要請等で運転停止中の原子力発電所が多々ある)。その12県を北の方から発電所名ともにリストすると、
◆北海道(泊)
◆青森県(東通)
◆宮城県(女川)
◆新潟県(柏崎刈羽)
◆石川県(志賀)
◆福井県(敦賀、美浜、大飯、高浜)
◆茨城県(東海第2)
◆静岡県(浜岡)
◆島根県(島根)
◆愛媛県(伊方)
◆佐賀県(玄海)
◆鹿児島県(川内)
ですが、11道県の原子力発電所は1カ所だけなのに、福井県だけは4カ所もあります。もちろん東日本大震災以降、原発の安全審査は厳しくなったとされていますが、安全といっても「想定内の事態に対して安全」ということであり、東日本大震災のように「想定外」(東電経営陣の主張)の事態が起こると大惨事を招くわけです。
原子力発電所の集積県だということは、各種の補助金や県民の雇用面のメリットが大だと思いますが(= "幸福度" のプラス)、福井県が "4原発集積県" であるということはそれだけ安心面でのデメリットを抱えていることも確かでしょう(= "幸福度" のマイナス。これは隣接する京都府や滋賀県にとっても重大関心事)。もちろん、原子力発電所設置数(ないしは原子炉設置数)などという "指標" は「都道府県幸福度ランキング」には絶対に選ばれないと思いますが ・・・・・・。
「総合ランキング」については、それがどのように作成されたものかを知ることが重要だと思います。似たようなランキングとして最近も、森ビルのシンクタンクである森記念財団都市戦略研究所が「日本の都市力ランキング」を発表しました。これは東京を除く主要72都市のランキングですが、1位は京都市、2位は福岡市、3位は大阪市だそうです(2018年10月3日の日本経済新聞による)。それぞれの都市に "都市力" があることは分かりますが、この全く性格が違う3都市の並びには違和感があります。これも、どういう指標でどうやってランクづけしているのか、それを知らないと何とも言えませんが、要するに「総合ランキング」に無理があるということでしょう。
そういった「総合ランキング」より重要なのは、個々の指標の値と全国にける位置づけでしょう。本書に即して言うと、地域の幸福の基盤となる指標は何か、それは本書があげているもののほかに、各人が考えることも重要でしょう。本書にはそいう議論を進めるトリガーとしての意味があると思いました。
2018-12-06 22:46
nice!(0)
No.245 - スーパー雑草とスーパー除草剤 [社会]
今まで3回に渡って、主として米国における "遺伝子組み換え作物"( = GM作物)について書きました。
の3つで、特にGM作物の中でも除草剤に耐性を持つ(= 除草剤耐性型の)トウモロコシや大豆、綿花についてでした。最近ある新書を読んでいたら、その米国のGM作物の状況が出ていました。菅 正治氏の『本当はダメなアメリカ農業』(新潮新書 2018。以下「本書」と記述)です。
著者の菅氏は時事通信社に入社して経済部記者になり、2014年3月から2018年2月までの4年間はシカゴ支局に勤務した方で、現在は農業関係雑誌の編集長とのことです。本書は畜産業を含むアメリカ農業の実態を書いたもので、もと時事通信社の記者だけあって資料にもとづいた詳細なレポートになっています。
そこで今回は、本書の中から「GM作物、特に除草剤耐性型のGM作物」と、GM作物とも関連がある「オーガニック(有機)作物」の話題に絞って紹介したいと思います。No.102、No.218 と重複するところがありますが、No.102、No.218 の補足という意味があります。
なお、本書全体の内容は「アメリカ農業・畜産業は極めて強大だが、数々の問題点や弱みもある」ということを記述したものです。"アメリカ農業がダメだ" とは書いてありません。題名の「本当はダメな」というのは(おそらく新潮社の編集部がつけた)販売促進用の形容詞でしょう。
アメリカ農業の規模
GM作物の議論に入る前に、アメリカの農業の規模を押さえておきます。アメリカ農業の3大作物はトウモロコシ・大豆・小麦で、2017年の作付け規模は以下の通りです。
トウモロコシと大豆の作付け面積は、それぞれが日本の国土面積(3779万 ha)に匹敵するという広さです。本書には書いてありませんが、日本の可住地面積(= 国土から林野と河川・湖沼を引いた面積。いわゆる平地の面積。農地はその一部)は、国土面積の1/3程度です。「アメリカには日本のすべての平地の3倍の大豆畑があり、それと同じ広さのトウモロコシ畑がある」と表現したら、その広大さがイメージできると思います。
数字でわかるように、3大作物の中でもトウモロコシと大豆が中心的な作物です。この2つは生産に適した気候が似ていて、両方を生産する農家も多い。アイオワ州からオハイオ州に広がる "コーンベルト" と呼ばれる地域が生産の中心です。
そのトウモロコシの 35%~40% は飼料に加工され、それと同じ程度の量がバイオ・エタノールになります。10数% は輸出され、10% 程度はコーンスターチやコーンフレークなどの食品になります。
大豆は半分がそのまま輸出されますが、その大半は中国向けです。また4割程度が大豆油や家畜の飼料になります。残りは食用や工業用です。
一方、小麦はトウモロコシ・大豆の半分程度の作付面積であり、減少が続いています。そしてこれら3大作物に続くのが、
で、南部のテキサス州やジョージア州などの "コットン・ベルト" で生産されています。
GM作物(GMO)
遺伝子組み替え技術を使って、今までに無かった新たな性質を付与した作物を "GM作物" と呼んでいます。英語では Genetically Modified Organism であり、略して GMO と呼びます。GM作物でない、というのは Non GMO、ノン GMO です。
GM作物を世界で初めて商品化したのがモンサント社で、1996年に除草剤(グリホサート)をかけても枯れない GM大豆(= 除草剤耐性型の大豆)が最初でした。その後、モンサントのライバルであるアメリカのデュポンやダウ・ケミカル、ドイツのバイエルなどがGM作物に参入し、激しい競争を繰り広げています。米国農務省の調査によると、2017年の主要3作物の作付面積に占めるGM作物は次の通りです。
1996年に最初に開発されてから20年で、トウモロコシ、大豆、綿花のほぼ全てがGM作物に置き換えられたわけです。ちなみに3大作物の一つである小麦については、"GM小麦" が開発されているにもかかわらず、作付面積はゼロです。その理由は「米国人が直接食べる食物だから」です(ただし、GM小麦を認可すべきだという意見が米農業界にあることが、本書で紹介されています)。
米国で商業栽培が承認されたGM作物は、18作物、175品種です。トウモロコシ、大豆、綿花が多いのですが、ジャガイモ、リンゴ、トマト、コメもあります。ただし商用栽培はほとんど行われていないようです。
ちなみに日本でのGM作物の商用栽培は、10作物、153品種が承認されています。内訳は、トウモロコシが68品種、大豆が25品種、綿花が29品種、その他が31品種ですが、日本で実際に栽培されているGM作物はサントリーが開発した青いバラだけです。ただし日本は家畜の飼料向けにアメリカからGMトウモロコシやGM大豆を大量に輸入しており、GM作物の大消費国です。
バーモント州の「遺伝子組み替え表示法」のその後
No.103の「補記」で、アメリカ北東部のバーモント州で、遺伝子組み替え表示法(= 食品にGM作物を含むという表示を義務づける法律)が制定されたことを書きました。その後の経緯が本書に詳しく載っているので紹介します。
バーモント州は人口がわずか62万人で、全米50州のなかで49番目に小さな州です(一番人口が少ないのはワイオミング州)。しかし、この小さな州の「遺伝子組み替え表示法」が全米に与えたインパクトは大きいものでした。法案は2014年5月8日に知事が署名して成立し、施行は2年後の2016年7月1日です。
当然のことながら米国の食品業界は猛反発し、食品製造業協会(GMA。Grocery Manufacturers Association)は法案の撤廃を求める訴訟をバーモント州の連邦地裁に起こしました。しかし連邦地裁は、2015年4月、GMA の訴えを退ける判定を下しました。これにより2016年7月1日に法案が施行される可能性が現実味を帯びてきました。
そこで GMA は「GM食品を表示するかどうかは企業の判断に任せる」とする連邦法案の成立に軸足を移しました。しかしこの連邦法案も、2016年3月に米国上院で否決されてしまいました。この間、従来は表示義務化に反対していたキャンベル・スープやケロッグなどの食品大手が「今後は反対しない」と表明し、またフランスの大手食品会社のダノンがGM食品の取り扱いをやめると宣言しました(2016年4月)。
ここまでで食品業界の "敗北" に見えたのですが、GMA は新たに「表示は義務づけるが、商品に直接表示しなくてもよい」とする連邦法案の成立をめざし、2016年6月に上院共和党から法案として提出されました。つまり表示は「文字」のほかに「記号」や「デジタルリンク」でもいいのです。デジタルリンクとは、たとえば商品にQRコードをつけ、そこから食品メーカーのホームページにアクセスしてGM食品かどうかを調べられるというものです。
当然ながら、全米での表示義務化を求めていた「食品安全センター」などの NPO団体は「これは実質的にGM食品の非表示法案だ」と猛反対しました。しかし多くの議員が賛成に回り、上院・下院で可決され、2016年7月末にオバマ大統領が署名して成立しました。そしてこの法案の成立と同時に、2016年7月1日からバーモント州で施行された表示義務化は無効とされたのです。バーモント州の表示義務化(=商品への直接表示)は、1ヶ月で終わったということになります。
この連邦法案の成立に裏で寄与したのが、オーガニック(有機栽培)農家で作る有機取引協会(OTA。Organic Trade Association)です。OTAは、法案には欠陥があると認めながらも、食品の情報開示の一定の前進だとして賛成に回りました。当然、食品安全センターなどの NPO団体からは "裏切り" との非難を浴びたようです。
ともかく「表示は義務化、ただし表示方法は企業の選択、デジタルリンクでもOK」ということで決着したのが最新の状況です。
この顛末の感想です。菅氏が実際にやってみたところでは、QRコードからたどってGM食品を判別するのは手間であり、「実質的にGM食品の非表示法案」という NPO団体の主張はその通りのようです。
しかし、とにかく「義務化された」というのは大きいと思います。デジタルリンクだと消費者が店舗でいちいちスマホを取り出してGM食品かどうかを調べることは滅多にないでしょう。ただ、従来から表示義務化を推進してきた NPO団体はGM食品かどうかを調査できるし、その一覧をメーカーごとに広く公表することもできます。メーカーの "GM食品率ランキング" みたいなものを作ることも可能です。またスーパーなどの食品販売業者もGM食品かどうかを、たとえば POP で表示できます(そういうコストをかけても有益だという判断があればですが)。食品メーカーとしては、GM食品でありながら何らかの方法で表示しないとコンプライアンス違反になり、ブランドの毀損に繋がります。
さらに、従来から食品メーカーは「GM食品は安全で、ノンGM食品と何ら変わることがない。ことさらGM食品だと表示することは消費者に誤解を与えるし、企業のコストアップになるだけだ」と主張していたわけですが、その主張を撤回したことになります。これは大きいのではないでしょうか。
以上を考えると、有機取引協会(OTA)の「食品に関する情報開示の一定の前進」という評価は妥当だと思いました。
スーパー雑草の蔓延とスーパー除草剤
1996年にモンサント社が除草剤(グリホサート)をかけても枯れない GM大豆 を商品化して以降、グリホサートとグリホサート耐性作物の組み合わせによる農業が急速に広まりました。その状況を本書から引用します。
これだけ広まったグリホサートですが、案の定、グリホサートを散布しても枯れない雑草が出現してきました。いわゆる "スーパー雑草" です。
しかし、雑草が特定の除草剤に対する耐性を獲得するという現象は以前から良く知られていました。それがグリホサートでも起こったに過ぎないのです。
グリホサートに耐性をもつスーパー雑草が出現する科学的なメカニズムは、No.102「遺伝子組み換え作物のインパクト(1)」に書いたとおりです。グリホサートは、植物が成長する基本的な仕組みのところを阻害する物質です。それは除草剤と言うより "除植物剤" であり、たとえば成長力が非常に強い竹もグリホサートで枯れます。しかし生命が生き残る仕組みは巧妙で、そういうグリホサートの効果を回避する突然変異体が現れる。グリホサートが広範囲に使われるほど、そういった変異体の出現確率は高まるわけです。
結局、「グリホサートとグリホサート耐性作物の組み合わせ」は「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導し、それが農家にとって深刻な事態を招いたのです。当然、モンサント社の業績も悪化し、除草剤部門もGM作物部門も売り上げが減少してリストラに追われるという状況になりました。
この事態に対応するためにモンサント社(及び大手の種子・農薬会社)がとった策は「"スーパー雑草" には、より強力な "スーパー除草剤" で対抗する」という方法でした。
モンサント社が目をつけたのは、以前から除草剤として使われていたジカンバという農薬です。モンサント社はジカンバをかけても枯れないGM大豆とGM綿花を開発し、これは2015年1月に米国農務省から認可されました。
しかしジカンバは揮発性が高く、農地に散布した後、空中に漂い、風に乗って周囲に飛散しやすいという特徴があります。つまり「ジカンバ耐性のGM大豆畑」にジカンバを散布すると、隣接した農地が「グリホート耐性のGM大豆畑」であれば、そこに飛散して大豆を枯らしてしまう危険性があるのです。案の定、2016年になると EPA(米国環境保護庁。United States Environment Prortection Agency) には、ジカンバによって作物を枯らされたという農家からの報告が多数寄せられるようになりました。農家間のトラブルも相次ぎ、殺人事件まで起っています。
実はモンサント社は、より揮発性の低い新しいジカンバを開発し、ジカンバ耐性大豆・綿花と同時期に EPA に認可申請をしていました。それがようやく2016年11月に認可されました(GM大豆・GM綿花は2015年1月に農務省によって認可済)。
ジカンバに耐性を持たせた新GM作物と新ジカンバにより、モンサント社の業績はV字回復します。2017年8月期の純利益は、前年同期比59%増になりました。しかし、新ジカンバを市場投入しても被害はなくならなかったのです。
2万5000ドルの罰金というと、日本円で300万円近い大金です。アーカンソー州当局の危機感が伝わってきます。さらに深刻なのは、主な加害者も被害者も同じ大豆農家だということです。
被害はアーカンソー州だけではありません。大豆生産トップのイリノイ州やテネシー州、ミズーリ州など、全米の20以上の州で被害が発生しました。
最も被害が大きかったアーカンソー州では、2017年は7月11日からの120日間、ジカンバの販売と散布を禁止しましたが(上の引用)、2018年はこの禁止期間を4月16日から10月31日に拡大することを決めました。これは大豆の作付け(4~5月)から収穫(9~10月)までの期間であり、事実上のジカンバ使用禁止です。
EPA(米国環境保護庁)も2018年から「特別の訓練を受けた農家にだけジカンバを販売する」や「散布記録の保管」などの規制強化を決めました。しかしアーカンソー州のような使用禁止までには踏み込んでいません。これは、どちらかというとモンサント社の主張に沿った処置です。
モンサント社は、ジカンバの商品ラベルに記載された使用方法を守るなら(バッファー地帯の設定、専用ノズルの使用、正しい噴射圧力、など)農地外には飛散しないということを、実験やアンケートをもとに繰り返し主張しています。かつ、ジカンバとジカンバ耐性GM大豆を使用した農家からは、雑草管理で非常に満足する結果が得られたとの声が上がっています。
このような状況から、2018年のジカンバ耐性GM大豆の作付面積は、全米の大豆作付面積の4割になるだろうと予測されています。
以下は感想です。スーパー雑草とスーパー除草剤の話は、軍拡競争に似ています。他国を攻撃するミサイルを作ったとすると、それを撃ち落とすミサイル防衛システムが作られる。次には、その防衛システムを無力化するような新型ミサイルが開発される ・・・・・・。
ジカンバに耐性をもつ "ウルトラ雑草" が出現するのは時間の問題だと思われます。当然、モンサント社をはじめとする種子・農薬会社は、その出現を予測し、"ウルトラ雑草" に対抗する "ウルトラ除草剤" の研究と、それに耐性をもつ "新・新GM作物" の研究に余念がないのでしょう。だとしても、さらにその次には "スーパー・ウルトラ雑草" が出現するのでしょう。
この状況は、種子・農薬会社のビジネスが永続することを意味しています。ただし、"ウルトラ除草剤" とそれに耐性をもつ "新・新GM作物" が開発できなかったらアウトです。アウトにならないためには研究開発費がますます必要で、これは種子・農薬会社の合併・統合・巨大化を促進するでしょう。また業種を越えて、たとえば巨大穀物メジャー(穀物商社)が種子・農薬会社を買収するようなことが起こるのかもしれません。
こういった状況は、農業の主導権を農民・農業従事者ではなく、この資本主義社会の中の巨大企業が持つということを意味します。農業は製造業と違って世界のどこでも生産できるものではなく、その国の土地と自然に密着したものです。企業の存在目的を一つだけあげるなら「利益」であり、農業に企業の論理を持ち込むことは有益なことも多いと思いますが、行きすぎた利潤の追求は、一番大切なはずの農業従事者と自然環境の利益にはならない。米国のスーパー雑草とスーパー除草剤をめぐる "騒動" は、それが教訓だと思います。
GM作物で農業生産性は上がらない
全米科学アカデミー、全米技術アカデミー、米国医学研究所の3団体は、2016年5月にGM食品・GM作物に関する研究報告をまとめました。これは過去20年間に蓄積された900以上の研究報告を検証し、また80人の専門家から改めて話を聴いて400ページ近い報告書にまとめたものです。この報告書は「GM食品を食べることで人間の健康に悪影響が出るとの証拠は得られなかった」と結論づけました。
もちろん農業界や種子・農薬会社はこの報告を大歓迎しました、しかし GM食品の安全性に懸念を表明してき NGO からは、委員会メンバーは種子・農薬業界から多額の研究資金の提供を受けており、公正中立な報告ではないと批判しました。この報告書がGM食品の安全性論争に終止符を打つまでには至らなかったようです。
しかし注目すべきは、この報告書には健康問題のほかに、もう一つの重要な事実が指摘してあったことです。
この委員会の指摘は重要です。つまり GM作物の導入の必要性として(種子・農薬会社によって)必ず語られるのが、増大する一方の世界に人口に対応するために農業生産性を増大させる必要があるということです。農業の適地はすでに開発し尽くされていて、農地の拡大には限界があるのです。つまり、
という論理です。これが(少なくとも現時点では)正しくないことが結論づけられたわけです。GM作物に関しては、メリットとデメリットのバランスを考え直すべき時でしょう。
オーガニックへなびく消費者と Amazon の戦略
本書には、GM食物とも関係する "オーガニック商品" の状況が書かれています。アメリカ農務省(USDA。United States Department of Agriculture)は "オーガニック" であることの具体的条件を定めていて、その柱は「農薬を使わない」「化学肥料を使わない」「GM作物を使わない」の3点です。条件を満たすと「USDAオーガニック」のマークをつけて販売することができます。つまり「USDAオーガニック」の商品は自動的に「GM作物を使っていない」ことになる(= ノンGMO)わけです。
上の引用で有機取引協会(OTA)が「表示は義務化、ただし表示方法は企業の選択、デジタルリンクでもOK」という連邦法案に「一定の前進である」ことを理由に賛成したことを書きましたが(法案は成立)、オーガニックを推進したいという思いがあったのかもしれません。このオーガニック商品の伸びが顕著なようです。
本書には、2016年において、全野菜・果物の 15% はオーガニックになったとあります。この消費者の動向を見据え、大手食品メーカーもそれに対応した動きをしています。たとえばケロッグですが、"ケロッグ" ブランドのコーンフレークはGM食品ですが(QRコードによるデジタルリンクで表示)、子会社が別ブランドで展開するコーンフレークは「USDAオーガニック」や「ノンGMO」の表示を大々的に行い、オーガニックでかつGM食品でないことをアッピールしています。
このような消費者や食品業界の動向から、皮肉なことに米国産のオーガニック作物が不足し、輸入が急増する事態になっています。
0.6~2.9%の農地を有機栽培に切り替えるのは簡単そうに見えますが、これがそうではないのです。農務省(USDA)からオーガニックの認定を受けるには、最低3年の移行期間が必要です。また、「除草剤 + 除草剤耐性GM作物」の農業を「除草剤なし農業」にするのは農法の大転換になります。簡単には切り替えられません。
世界最大のトウモロコシと大豆の生産国であるアメリカが、ことオーガニック作物に関しては、8割(大豆)や5割(トウモロコシ)を輸入に頼るというのは、確かに異常事態です。
アメリカにおいて、オーガニックやノンGM食品にこだわってきたスーパー・マーケットが、ホールフーズ・マーケット(Whole Foods Market)です。ホールフーズは1978年の創業以来、有機野菜や自然食品、健康食品など、素材にこだわった品ぞろえを展開し、成長してきました。店内には「USオーガニック」のマークが貼られた商品や「ノンGMO」の表示がずらりと並んでいます。
アマゾン・ドット・コムは2017年6月、このホールフーズを137億ドル(日本円で約1兆5000億円)で買収すると発表し、2017年8月に買収を完了しました。アマゾンはさっそくホールフーズのオーガニック食品をネットで販売する攻勢をかけています。すでに一部の都市ではアマゾン・プライムのユーザを対象に、数千アイテムのホールフーズのオーガニック食品から 35ドル以上購入すれば2時間以内に無料配達するというビジネスを始めています。
アマゾンのホールフーズ買収は日本では「アマゾンがリアル店舗に進出」という文脈で報道されたと思うのですが、もう一つのアマゾンの狙いは、消費者の意識変化に対応して「オーガニック商材」を手に入れることでした。ひょっとしたら、これが買収の最大の狙いだったのかもしれません。
ノンGMO、オーガニックの社会的意義
以下は本書に描かれた「GM作物」「オーガニックへの動き」を読んだ感想です。オーガニックと言うと、無農薬、有機肥料、ノンGM作物ですが、これは "安全" で "健康に良い" と見なされることが多いわけです。しかし安全・健康だけでオーガニックを語ることはできない。本文中にあったように、GM作物が健康に良くないという証拠はありません。もちろん導入されてからまだ20年少々なので、長期にわたる摂取で健康に悪影響が出てくるというリスクはあります。しかし現在のところはそのリスクは顕在化していません。
むしろGM作物の問題点は、社会的な問題だと見えます。つまりGM作物はバイオテクノロジーを駆使する一握りの「大手種子・農薬会社」の農業支配を強めることになります。農民たちは企業の意のままに操られることになりかねない。またGM作物は明らかに「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導します。もっと大きく言うと「単一農法(品種や農薬、耕作方法)」に農業を誘導することになり、農業の多様性を奪ってしまう。これがリスクを孕んでいることは、スーパー雑草のところで見たとおりです。これが果たして「持続可能な農業」なのか。
健康問題に関して言うと、除草剤などの農薬の使用もそうです。少なくとも先進国では人体に危険を及ぼす農薬は規制され、また散布方法も規制されています。もちろん隠れたリスクは考えられて、たとえば人体には安全とされていたグリホサートも、近年発ガン性があるのではと疑われています。しかし大局的に言って、正しい農薬を正しい散布方法で使い、かつ正しく出荷すれば安全なのでしょう。
むしろ農薬の問題は「自然環境破壊」という社会的な問題だと思われます。人間には安全であっても、小動物や昆虫、土壌中の微生物にとってはそうではない(可能性がある)。日本の朱鷺が絶滅したのは餌の小動物が農薬の影響でいなくなったのが原因の一つと言われているし、メダカを見ることはほとんど無くなりました。朱鷺やメダカが絶滅しても、人間の暮らしは安泰に見えます。しかし、どこかでそのしっぺ返しがくるのではないか。人々がは潜在的にそう感じているこそ、オーガニック指向なのです。
また、化学肥料が健康に悪いという理由はありません。化学肥料は植物に必須の栄養素を人間が合成したものだからです。一方、農業・畜産の派生物から作った有機肥料は、土壌中の微生物がそれを分解し、植物の栄養素になる無機物(化学肥料の成分)を作ってくれて始めて、その有効性が発揮できます。つまり有機肥料は土壌の改善になります。だから、化学肥料より即効性がなくてコスト高であっても、有機肥料の価値があるわけです。また農業・畜産業におけるリサイクルの促進にもなります。
オーガニック(有機農法)は「農業従事者が主体の、自然によりそった農業」であり「持続可能な農業」です。だから少々高くてもオーガニック食品を選ぶというのがスジです。つまり健康問題よりも、社会的意義が大きいと思います。
工業製品と違って、食品・食料は自然環境と密接に結びついています。食料・食品に低価格や低コスト、利潤だけを求めてはならない。そのことがアメリカのGM作物の実態を通して改めて理解できるのでした。
| No.102 - 遺伝子組み換え作物のインパクト(1) No.103 - 遺伝子組み換え作物のインパクト(2) No.218 - 農薬と遺伝子組み換え作物 |
の3つで、特にGM作物の中でも除草剤に耐性を持つ(= 除草剤耐性型の)トウモロコシや大豆、綿花についてでした。最近ある新書を読んでいたら、その米国のGM作物の状況が出ていました。菅 正治氏の『本当はダメなアメリカ農業』(新潮新書 2018。以下「本書」と記述)です。

| |||
|
菅 正治
「本当はダメなアメリカ農業」 (新潮新書 2018) | |||
そこで今回は、本書の中から「GM作物、特に除草剤耐性型のGM作物」と、GM作物とも関連がある「オーガニック(有機)作物」の話題に絞って紹介したいと思います。No.102、No.218 と重複するところがありますが、No.102、No.218 の補足という意味があります。
なお、本書全体の内容は「アメリカ農業・畜産業は極めて強大だが、数々の問題点や弱みもある」ということを記述したものです。"アメリカ農業がダメだ" とは書いてありません。題名の「本当はダメな」というのは(おそらく新潮社の編集部がつけた)販売促進用の形容詞でしょう。
アメリカ農業の規模
GM作物の議論に入る前に、アメリカの農業の規模を押さえておきます。アメリカ農業の3大作物はトウモロコシ・大豆・小麦で、2017年の作付け規模は以下の通りです。
| 3650万 ha | |||
| 3646万 ha | |||
| 1861万 ha |
トウモロコシと大豆の作付け面積は、それぞれが日本の国土面積(3779万 ha)に匹敵するという広さです。本書には書いてありませんが、日本の可住地面積(= 国土から林野と河川・湖沼を引いた面積。いわゆる平地の面積。農地はその一部)は、国土面積の1/3程度です。「アメリカには日本のすべての平地の3倍の大豆畑があり、それと同じ広さのトウモロコシ畑がある」と表現したら、その広大さがイメージできると思います。
数字でわかるように、3大作物の中でもトウモロコシと大豆が中心的な作物です。この2つは生産に適した気候が似ていて、両方を生産する農家も多い。アイオワ州からオハイオ州に広がる "コーンベルト" と呼ばれる地域が生産の中心です。
そのトウモロコシの 35%~40% は飼料に加工され、それと同じ程度の量がバイオ・エタノールになります。10数% は輸出され、10% 程度はコーンスターチやコーンフレークなどの食品になります。
大豆は半分がそのまま輸出されますが、その大半は中国向けです。また4割程度が大豆油や家畜の飼料になります。残りは食用や工業用です。
一方、小麦はトウモロコシ・大豆の半分程度の作付面積であり、減少が続いています。そしてこれら3大作物に続くのが、
| 510万 ha |
で、南部のテキサス州やジョージア州などの "コットン・ベルト" で生産されています。
GM作物(GMO)
遺伝子組み替え技術を使って、今までに無かった新たな性質を付与した作物を "GM作物" と呼んでいます。英語では Genetically Modified Organism であり、略して GMO と呼びます。GM作物でない、というのは Non GMO、ノン GMO です。
GM作物を世界で初めて商品化したのがモンサント社で、1996年に除草剤(グリホサート)をかけても枯れない GM大豆(= 除草剤耐性型の大豆)が最初でした。その後、モンサントのライバルであるアメリカのデュポンやダウ・ケミカル、ドイツのバイエルなどがGM作物に参入し、激しい競争を繰り広げています。米国農務省の調査によると、2017年の主要3作物の作付面積に占めるGM作物は次の通りです。
作付面積に占めるGM作物の割合
(2017年。米・農務省調査)
(2017年。米・農務省調査)
| トウモロコシ | 大豆 | 綿花 | ||||
| 除草剤耐性型 | 12% | 92% | 94% | 94% | 11% | 96% |
| 害虫抵抗型 | 3% | 0% | 5% | |||
| 除草剤+害虫 | 77% | 0% | 80% | |||
1996年に最初に開発されてから20年で、トウモロコシ、大豆、綿花のほぼ全てがGM作物に置き換えられたわけです。ちなみに3大作物の一つである小麦については、"GM小麦" が開発されているにもかかわらず、作付面積はゼロです。その理由は「米国人が直接食べる食物だから」です(ただし、GM小麦を認可すべきだという意見が米農業界にあることが、本書で紹介されています)。
米国で商業栽培が承認されたGM作物は、18作物、175品種です。トウモロコシ、大豆、綿花が多いのですが、ジャガイモ、リンゴ、トマト、コメもあります。ただし商用栽培はほとんど行われていないようです。
ちなみに日本でのGM作物の商用栽培は、10作物、153品種が承認されています。内訳は、トウモロコシが68品種、大豆が25品種、綿花が29品種、その他が31品種ですが、日本で実際に栽培されているGM作物はサントリーが開発した青いバラだけです。ただし日本は家畜の飼料向けにアメリカからGMトウモロコシやGM大豆を大量に輸入しており、GM作物の大消費国です。
バーモント州の「遺伝子組み替え表示法」のその後
No.103の「補記」で、アメリカ北東部のバーモント州で、遺伝子組み替え表示法(= 食品にGM作物を含むという表示を義務づける法律)が制定されたことを書きました。その後の経緯が本書に詳しく載っているので紹介します。
バーモント州は人口がわずか62万人で、全米50州のなかで49番目に小さな州です(一番人口が少ないのはワイオミング州)。しかし、この小さな州の「遺伝子組み替え表示法」が全米に与えたインパクトは大きいものでした。法案は2014年5月8日に知事が署名して成立し、施行は2年後の2016年7月1日です。
当然のことながら米国の食品業界は猛反発し、食品製造業協会(GMA。Grocery Manufacturers Association)は法案の撤廃を求める訴訟をバーモント州の連邦地裁に起こしました。しかし連邦地裁は、2015年4月、GMA の訴えを退ける判定を下しました。これにより2016年7月1日に法案が施行される可能性が現実味を帯びてきました。
そこで GMA は「GM食品を表示するかどうかは企業の判断に任せる」とする連邦法案の成立に軸足を移しました。しかしこの連邦法案も、2016年3月に米国上院で否決されてしまいました。この間、従来は表示義務化に反対していたキャンベル・スープやケロッグなどの食品大手が「今後は反対しない」と表明し、またフランスの大手食品会社のダノンがGM食品の取り扱いをやめると宣言しました(2016年4月)。
ここまでで食品業界の "敗北" に見えたのですが、GMA は新たに「表示は義務づけるが、商品に直接表示しなくてもよい」とする連邦法案の成立をめざし、2016年6月に上院共和党から法案として提出されました。つまり表示は「文字」のほかに「記号」や「デジタルリンク」でもいいのです。デジタルリンクとは、たとえば商品にQRコードをつけ、そこから食品メーカーのホームページにアクセスしてGM食品かどうかを調べられるというものです。
当然ながら、全米での表示義務化を求めていた「食品安全センター」などの NPO団体は「これは実質的にGM食品の非表示法案だ」と猛反対しました。しかし多くの議員が賛成に回り、上院・下院で可決され、2016年7月末にオバマ大統領が署名して成立しました。そしてこの法案の成立と同時に、2016年7月1日からバーモント州で施行された表示義務化は無効とされたのです。バーモント州の表示義務化(=商品への直接表示)は、1ヶ月で終わったということになります。
この連邦法案の成立に裏で寄与したのが、オーガニック(有機栽培)農家で作る有機取引協会(OTA。Organic Trade Association)です。OTAは、法案には欠陥があると認めながらも、食品の情報開示の一定の前進だとして賛成に回りました。当然、食品安全センターなどの NPO団体からは "裏切り" との非難を浴びたようです。
ともかく「表示は義務化、ただし表示方法は企業の選択、デジタルリンクでもOK」ということで決着したのが最新の状況です。
この顛末の感想です。菅氏が実際にやってみたところでは、QRコードからたどってGM食品を判別するのは手間であり、「実質的にGM食品の非表示法案」という NPO団体の主張はその通りのようです。
しかし、とにかく「義務化された」というのは大きいと思います。デジタルリンクだと消費者が店舗でいちいちスマホを取り出してGM食品かどうかを調べることは滅多にないでしょう。ただ、従来から表示義務化を推進してきた NPO団体はGM食品かどうかを調査できるし、その一覧をメーカーごとに広く公表することもできます。メーカーの "GM食品率ランキング" みたいなものを作ることも可能です。またスーパーなどの食品販売業者もGM食品かどうかを、たとえば POP で表示できます(そういうコストをかけても有益だという判断があればですが)。食品メーカーとしては、GM食品でありながら何らかの方法で表示しないとコンプライアンス違反になり、ブランドの毀損に繋がります。
さらに、従来から食品メーカーは「GM食品は安全で、ノンGM食品と何ら変わることがない。ことさらGM食品だと表示することは消費者に誤解を与えるし、企業のコストアップになるだけだ」と主張していたわけですが、その主張を撤回したことになります。これは大きいのではないでしょうか。
以上を考えると、有機取引協会(OTA)の「食品に関する情報開示の一定の前進」という評価は妥当だと思いました。
スーパー雑草の蔓延とスーパー除草剤
1996年にモンサント社が除草剤(グリホサート)をかけても枯れない GM大豆 を商品化して以降、グリホサートとグリホサート耐性作物の組み合わせによる農業が急速に広まりました。その状況を本書から引用します。
|
これだけ広まったグリホサートですが、案の定、グリホサートを散布しても枯れない雑草が出現してきました。いわゆる "スーパー雑草" です。
|
しかし、雑草が特定の除草剤に対する耐性を獲得するという現象は以前から良く知られていました。それがグリホサートでも起こったに過ぎないのです。
|
グリホサートに耐性をもつスーパー雑草が出現する科学的なメカニズムは、No.102「遺伝子組み換え作物のインパクト(1)」に書いたとおりです。グリホサートは、植物が成長する基本的な仕組みのところを阻害する物質です。それは除草剤と言うより "除植物剤" であり、たとえば成長力が非常に強い竹もグリホサートで枯れます。しかし生命が生き残る仕組みは巧妙で、そういうグリホサートの効果を回避する突然変異体が現れる。グリホサートが広範囲に使われるほど、そういった変異体の出現確率は高まるわけです。
結局、「グリホサートとグリホサート耐性作物の組み合わせ」は「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導し、それが農家にとって深刻な事態を招いたのです。当然、モンサント社の業績も悪化し、除草剤部門もGM作物部門も売り上げが減少してリストラに追われるという状況になりました。
この事態に対応するためにモンサント社(及び大手の種子・農薬会社)がとった策は「"スーパー雑草" には、より強力な "スーパー除草剤" で対抗する」という方法でした。
モンサント社が目をつけたのは、以前から除草剤として使われていたジカンバという農薬です。モンサント社はジカンバをかけても枯れないGM大豆とGM綿花を開発し、これは2015年1月に米国農務省から認可されました。
しかしジカンバは揮発性が高く、農地に散布した後、空中に漂い、風に乗って周囲に飛散しやすいという特徴があります。つまり「ジカンバ耐性のGM大豆畑」にジカンバを散布すると、隣接した農地が「グリホート耐性のGM大豆畑」であれば、そこに飛散して大豆を枯らしてしまう危険性があるのです。案の定、2016年になると EPA(米国環境保護庁。United States Environment Prortection Agency) には、ジカンバによって作物を枯らされたという農家からの報告が多数寄せられるようになりました。農家間のトラブルも相次ぎ、殺人事件まで起っています。
|
実はモンサント社は、より揮発性の低い新しいジカンバを開発し、ジカンバ耐性大豆・綿花と同時期に EPA に認可申請をしていました。それがようやく2016年11月に認可されました(GM大豆・GM綿花は2015年1月に農務省によって認可済)。
|
ジカンバに耐性を持たせた新GM作物と新ジカンバにより、モンサント社の業績はV字回復します。2017年8月期の純利益は、前年同期比59%増になりました。しかし、新ジカンバを市場投入しても被害はなくならなかったのです。
|
2万5000ドルの罰金というと、日本円で300万円近い大金です。アーカンソー州当局の危機感が伝わってきます。さらに深刻なのは、主な加害者も被害者も同じ大豆農家だということです。
|
被害はアーカンソー州だけではありません。大豆生産トップのイリノイ州やテネシー州、ミズーリ州など、全米の20以上の州で被害が発生しました。
最も被害が大きかったアーカンソー州では、2017年は7月11日からの120日間、ジカンバの販売と散布を禁止しましたが(上の引用)、2018年はこの禁止期間を4月16日から10月31日に拡大することを決めました。これは大豆の作付け(4~5月)から収穫(9~10月)までの期間であり、事実上のジカンバ使用禁止です。
EPA(米国環境保護庁)も2018年から「特別の訓練を受けた農家にだけジカンバを販売する」や「散布記録の保管」などの規制強化を決めました。しかしアーカンソー州のような使用禁止までには踏み込んでいません。これは、どちらかというとモンサント社の主張に沿った処置です。
モンサント社は、ジカンバの商品ラベルに記載された使用方法を守るなら(バッファー地帯の設定、専用ノズルの使用、正しい噴射圧力、など)農地外には飛散しないということを、実験やアンケートをもとに繰り返し主張しています。かつ、ジカンバとジカンバ耐性GM大豆を使用した農家からは、雑草管理で非常に満足する結果が得られたとの声が上がっています。
このような状況から、2018年のジカンバ耐性GM大豆の作付面積は、全米の大豆作付面積の4割になるだろうと予測されています。
以下は感想です。スーパー雑草とスーパー除草剤の話は、軍拡競争に似ています。他国を攻撃するミサイルを作ったとすると、それを撃ち落とすミサイル防衛システムが作られる。次には、その防衛システムを無力化するような新型ミサイルが開発される ・・・・・・。
ジカンバに耐性をもつ "ウルトラ雑草" が出現するのは時間の問題だと思われます。当然、モンサント社をはじめとする種子・農薬会社は、その出現を予測し、"ウルトラ雑草" に対抗する "ウルトラ除草剤" の研究と、それに耐性をもつ "新・新GM作物" の研究に余念がないのでしょう。だとしても、さらにその次には "スーパー・ウルトラ雑草" が出現するのでしょう。
この状況は、種子・農薬会社のビジネスが永続することを意味しています。ただし、"ウルトラ除草剤" とそれに耐性をもつ "新・新GM作物" が開発できなかったらアウトです。アウトにならないためには研究開発費がますます必要で、これは種子・農薬会社の合併・統合・巨大化を促進するでしょう。また業種を越えて、たとえば巨大穀物メジャー(穀物商社)が種子・農薬会社を買収するようなことが起こるのかもしれません。
こういった状況は、農業の主導権を農民・農業従事者ではなく、この資本主義社会の中の巨大企業が持つということを意味します。農業は製造業と違って世界のどこでも生産できるものではなく、その国の土地と自然に密着したものです。企業の存在目的を一つだけあげるなら「利益」であり、農業に企業の論理を持ち込むことは有益なことも多いと思いますが、行きすぎた利潤の追求は、一番大切なはずの農業従事者と自然環境の利益にはならない。米国のスーパー雑草とスーパー除草剤をめぐる "騒動" は、それが教訓だと思います。
GM作物で農業生産性は上がらない
全米科学アカデミー、全米技術アカデミー、米国医学研究所の3団体は、2016年5月にGM食品・GM作物に関する研究報告をまとめました。これは過去20年間に蓄積された900以上の研究報告を検証し、また80人の専門家から改めて話を聴いて400ページ近い報告書にまとめたものです。この報告書は「GM食品を食べることで人間の健康に悪影響が出るとの証拠は得られなかった」と結論づけました。
もちろん農業界や種子・農薬会社はこの報告を大歓迎しました、しかし GM食品の安全性に懸念を表明してき NGO からは、委員会メンバーは種子・農薬業界から多額の研究資金の提供を受けており、公正中立な報告ではないと批判しました。この報告書がGM食品の安全性論争に終止符を打つまでには至らなかったようです。
しかし注目すべきは、この報告書には健康問題のほかに、もう一つの重要な事実が指摘してあったことです。
|
この委員会の指摘は重要です。つまり GM作物の導入の必要性として(種子・農薬会社によって)必ず語られるのが、増大する一方の世界に人口に対応するために農業生産性を増大させる必要があるということです。農業の適地はすでに開発し尽くされていて、農地の拡大には限界があるのです。つまり、
| ・ | 除草剤耐性GM作物の導入で、雑草が(低コストで)無くなり、 | ||
| ・ | 害虫耐性GM作物の導入で、害虫による農業被害が減少し、 | ||
| ・ | 乾燥耐性GM作物の導入で、干魃による農業被害が減少し、 | ||
| ・ | その結果、収穫量が増えて農業生産性が増大し、 | ||
| ・ | 世界の食料増産に役立つ |
という論理です。これが(少なくとも現時点では)正しくないことが結論づけられたわけです。GM作物に関しては、メリットとデメリットのバランスを考え直すべき時でしょう。
オーガニックへなびく消費者と Amazon の戦略
本書には、GM食物とも関係する "オーガニック商品" の状況が書かれています。アメリカ農務省(USDA。United States Department of Agriculture)は "オーガニック" であることの具体的条件を定めていて、その柱は「農薬を使わない」「化学肥料を使わない」「GM作物を使わない」の3点です。条件を満たすと「USDAオーガニック」のマークをつけて販売することができます。つまり「USDAオーガニック」の商品は自動的に「GM作物を使っていない」ことになる(= ノンGMO)わけです。
上の引用で有機取引協会(OTA)が「表示は義務化、ただし表示方法は企業の選択、デジタルリンクでもOK」という連邦法案に「一定の前進である」ことを理由に賛成したことを書きましたが(法案は成立)、オーガニックを推進したいという思いがあったのかもしれません。このオーガニック商品の伸びが顕著なようです。
|
本書には、2016年において、全野菜・果物の 15% はオーガニックになったとあります。この消費者の動向を見据え、大手食品メーカーもそれに対応した動きをしています。たとえばケロッグですが、"ケロッグ" ブランドのコーンフレークはGM食品ですが(QRコードによるデジタルリンクで表示)、子会社が別ブランドで展開するコーンフレークは「USDAオーガニック」や「ノンGMO」の表示を大々的に行い、オーガニックでかつGM食品でないことをアッピールしています。
このような消費者や食品業界の動向から、皮肉なことに米国産のオーガニック作物が不足し、輸入が急増する事態になっています。
|
0.6~2.9%の農地を有機栽培に切り替えるのは簡単そうに見えますが、これがそうではないのです。農務省(USDA)からオーガニックの認定を受けるには、最低3年の移行期間が必要です。また、「除草剤 + 除草剤耐性GM作物」の農業を「除草剤なし農業」にするのは農法の大転換になります。簡単には切り替えられません。
世界最大のトウモロコシと大豆の生産国であるアメリカが、ことオーガニック作物に関しては、8割(大豆)や5割(トウモロコシ)を輸入に頼るというのは、確かに異常事態です。
アメリカにおいて、オーガニックやノンGM食品にこだわってきたスーパー・マーケットが、ホールフーズ・マーケット(Whole Foods Market)です。ホールフーズは1978年の創業以来、有機野菜や自然食品、健康食品など、素材にこだわった品ぞろえを展開し、成長してきました。店内には「USオーガニック」のマークが貼られた商品や「ノンGMO」の表示がずらりと並んでいます。
アマゾン・ドット・コムは2017年6月、このホールフーズを137億ドル(日本円で約1兆5000億円)で買収すると発表し、2017年8月に買収を完了しました。アマゾンはさっそくホールフーズのオーガニック食品をネットで販売する攻勢をかけています。すでに一部の都市ではアマゾン・プライムのユーザを対象に、数千アイテムのホールフーズのオーガニック食品から 35ドル以上購入すれば2時間以内に無料配達するというビジネスを始めています。

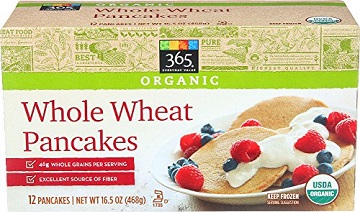
| ||
|
Whole Foods の店舗内の "Organic Zone" の例と、Amazon.com で売られている Whole Foods のプライベート・ブランド商品の例。商品の右下に "USDA Organic" の表示がある。
| ||
アマゾンのホールフーズ買収は日本では「アマゾンがリアル店舗に進出」という文脈で報道されたと思うのですが、もう一つのアマゾンの狙いは、消費者の意識変化に対応して「オーガニック商材」を手に入れることでした。ひょっとしたら、これが買収の最大の狙いだったのかもしれません。

|
日本のスーパーで購入した乾燥イチジク(有機栽培)。米国の Safe Food Corporation 社製で、イチジクはトルコ産。「USDA ORGANIC」と「NON GMO VERIFIED」のマークがついている。 |
ノンGMO、オーガニックの社会的意義
以下は本書に描かれた「GM作物」「オーガニックへの動き」を読んだ感想です。オーガニックと言うと、無農薬、有機肥料、ノンGM作物ですが、これは "安全" で "健康に良い" と見なされることが多いわけです。しかし安全・健康だけでオーガニックを語ることはできない。本文中にあったように、GM作物が健康に良くないという証拠はありません。もちろん導入されてからまだ20年少々なので、長期にわたる摂取で健康に悪影響が出てくるというリスクはあります。しかし現在のところはそのリスクは顕在化していません。
むしろGM作物の問題点は、社会的な問題だと見えます。つまりGM作物はバイオテクノロジーを駆使する一握りの「大手種子・農薬会社」の農業支配を強めることになります。農民たちは企業の意のままに操られることになりかねない。またGM作物は明らかに「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導します。もっと大きく言うと「単一農法(品種や農薬、耕作方法)」に農業を誘導することになり、農業の多様性を奪ってしまう。これがリスクを孕んでいることは、スーパー雑草のところで見たとおりです。これが果たして「持続可能な農業」なのか。
健康問題に関して言うと、除草剤などの農薬の使用もそうです。少なくとも先進国では人体に危険を及ぼす農薬は規制され、また散布方法も規制されています。もちろん隠れたリスクは考えられて、たとえば人体には安全とされていたグリホサートも、近年発ガン性があるのではと疑われています。しかし大局的に言って、正しい農薬を正しい散布方法で使い、かつ正しく出荷すれば安全なのでしょう。
むしろ農薬の問題は「自然環境破壊」という社会的な問題だと思われます。人間には安全であっても、小動物や昆虫、土壌中の微生物にとってはそうではない(可能性がある)。日本の朱鷺が絶滅したのは餌の小動物が農薬の影響でいなくなったのが原因の一つと言われているし、メダカを見ることはほとんど無くなりました。朱鷺やメダカが絶滅しても、人間の暮らしは安泰に見えます。しかし、どこかでそのしっぺ返しがくるのではないか。人々がは潜在的にそう感じているこそ、オーガニック指向なのです。
また、化学肥料が健康に悪いという理由はありません。化学肥料は植物に必須の栄養素を人間が合成したものだからです。一方、農業・畜産の派生物から作った有機肥料は、土壌中の微生物がそれを分解し、植物の栄養素になる無機物(化学肥料の成分)を作ってくれて始めて、その有効性が発揮できます。つまり有機肥料は土壌の改善になります。だから、化学肥料より即効性がなくてコスト高であっても、有機肥料の価値があるわけです。また農業・畜産業におけるリサイクルの促進にもなります。
オーガニック(有機農法)は「農業従事者が主体の、自然によりそった農業」であり「持続可能な農業」です。だから少々高くてもオーガニック食品を選ぶというのがスジです。つまり健康問題よりも、社会的意義が大きいと思います。
工業製品と違って、食品・食料は自然環境と密接に結びついています。食料・食品に低価格や低コスト、利潤だけを求めてはならない。そのことがアメリカのGM作物の実態を通して改めて理解できるのでした。
2018-11-09 20:13
nice!(1)
No.240 - 破壊兵器としての数学 [社会]
No.237「フランスのAI立国宣言」で紹介した新井教授の新聞コラムに出てきましたが、マクロン大統領がパリで主催した「AI についての意見交換会」(2018年3月)に招かれた一人が、アメリカの数学者であるキャシー・オニールでした。彼女は、
という本を書いたことで有名です。Weapons of Mass Destruction(大量破壊兵器。WMDと略される)に Math(Mathematics. 数学)を引っかけた題名です(上の訳は新井教授のコラムのもの)。この本は日本語に訳され、2018年7月に出版されました。
です(以下「本書」)。一言で言うと、ビッグデータを数式で処理した何らかの "結果" が社会に有害な影響を与えることに警鐘を鳴らした本で、まさに現代社会にピッタリだと言えるでしょう。今回はこの本の内容をざっと紹介したいと思います。なお、原題にある Weapons of Math Destruction は、そのまま直訳すると「数学破壊兵器」で、本書でも(題名以外は)そう訳してあります。
本書で扱っているテーマ
本書をこれから買おうと思っている方のために、2つの留意点を書いておきます。
まず注意すべきは、本書は題名とは違ってAIについての本ではないということです。原題が暗示するように "数学"(Math)が社会に与える影響、特に悪影響(ダークサイド。暗黒面)についての本です。もちろん AI も数学の一部なのですが、直接的にAIはほとんど出てきません。日本語の題名に原題には無い "AI" を入れたのは、本が売れやすいようにということだと思います。最近の各種メディアでは「なんでもかんでも AI というタイトルをつける」傾向にありますが、その風潮に乗っかった日本語題名と言えるでしょう。
数学が社会に与える影響と書きましたが、もっと詳しく言うと「数学モデル(数理モデル)が社会に与える影響」です。この数学モデルは人間が考え出したものであり、単純な数式のこともあれば、複雑な(数学的)アルゴリズムのこともあります。AIはその極めて複雑な部類です。この数学モデルにはデータ(ないしはビッグデータ)が入力されます。そして計算の結果として、
などが出力されます。その多くは個人に関するものですが、組織体(大学、高校、企業、自治体、国、・・・・・)について評価のこともあり、また「犯罪発生場所の予測」といった場所・地区に関する数値であったりもします。
最も単純な数学モデルの例は、本書でも出てくる BMI(Body Mass Index。ボディマス指数)でしょう。人の身長と体重を入力とし、"数学モデル" によって「肥満度の評価指標値」を出し、同時に人を「肥満・普通・痩せ」に分類します。この場合の "数学モデル" は、体重(kg)を身長(m)の2乗で割るという単純な数式です。
もちろん数学モデルの利用は近代科学が始まったときからの歴史があります。むしろ数学モデルを使うことで近代科学が生まれたと言えるでしょう。現代でも身近なところでは、気象の予測には膨大な計算を必要とする数学モデル(=物理モデルをもとにした数学モデル)が使われています。もちろん自然科学だけなく社会科学にも使われます。
この数学モデルが社会に悪影響を与えるとき、キャシー・オニールはそれを「数学破壊兵器 = WMD」と呼んでいるわけです。悪影響とは、たとえば差別を助長するとか、貧困を加速するとか、公正ではない競争を促進するとか、平等の原則を阻害するとかであり、その具体的な例は本書に出てきます。
2つめに留意すべきは、本書に取り上げられているのはアメリカでの事例だということです。日本では考えられないような実例がいろいろ出てきます。それらを単純に日本に当てはめることはできない。
しかし我々としてはアメリカでの数学破壊兵器の実態を反面教師とし、そこから学ぶことができます。かつ、本書に出てくるアメリカの巨大IT企業(フェイスブック、グーグル、アマゾンなど)は日本でもビジネス展開をしているわけで、我々も常時利用しています。もちろん、これらのIT企業が数学破壊兵器を使っていると言っているのではなく、その危険性があると指摘しているわけです。こういった知識を得ることも有用でしょう。
キャシー・オニールの経歴
本書の内容を理解するためには、著者のキャシー・オニールの経歴に注目する必要があります。彼女は小さい時から数学マニア("オタク" が適当でしょう)だったようで、14歳のときには「数学キャンプ」に参加したとあります(そんなキャンプがある!)。数学は現実世界から身を隠す「隠れ家」でもあったと、彼女は述懐しています。そしてハーバード大学で数学の博士号(代数的整数論)をとり、コロンビア大学で終身在職権付きの教授になりました。そしてその教授職を辞して、大手ヘッジファンド、D.E.ショーに転職し、クオンツとして働きました。クオンツとは数学的手法で分析や予測を行う、金融工学の専門家(データ・サイエンティスト)です。通常のヘッジファンドのクオンツはトレーダーの下働きですが、D.E.ショーではクオンツが最高位だったとあります。ちなみに D.E.ショー は金融工学(フィンテック)の先駆けとも言えるヘッジファンドで、アマゾンを創立する以前のジェフ・ベゾス氏が働いていたことでも知られています。
まさにキャシー・オニールは学者としてエリートであり、ヘッジファンドに転職というのも華麗な経歴です。ところが転職して1年あまりの2008年秋、世界経済は崩壊に直面しました(= リーマン・ショック)。彼女は次のように書いています。
本書の根幹にあるキャシー・オニールの "思い" とは、愛する数学が社会に災いをもたらすことへの危機感(ないしは "数学をもて遊ぶ人たち" への怒り)と、短期間とはいえ "災いをもたらす側で数学者として働いた" という自責の念、の2つでしょう。本書の第2章では「内幕」と題して2008年の前後の金融業界・ヘッジファンドの内情が生々しく語られています。
彼女はヘッジファンドを離職し、現在は企業が使うアルゴリズムを監査する会社(彼女自身が立ち上げたもの)のトップを努めています。もちろん彼女は数学モデルやアルゴリズム(AIもその一種)を否定しているのではありません。「盲信するな」と警告しているわけです。
そのようなスタンスは本書でも明らかです。本書には「明白な数学破壊兵器の例」もありますが、「数学破壊兵器になりかねないもの」や「有益なツールだが、使い方によっては数学破壊兵器になるもの」、「将来、数学破壊兵器へと発展しかねないリスクがあるもの」の例などが出てきます。幅広い見地から "数学の有害利用" を指摘しアラームをあげることによって、それを正そうとする本と言えるでしょう。
以下に本書にある多数の事例から3つの例だけを紹介します。教育と犯罪に関するものです。
教師評価システム
本書で最初にあげられている数学破壊兵器の例が、教師の評価スコアを算出するツールです。
ワシントンDCの教師だったサラ・ウィソッキーの例が出てきます。彼女はマクファーランド中学で第5学年(日本式に言うと中学1年)の受け持ちでした。彼女は子供たちに対するきめ細かい配慮で保護者からも高く評価されていました。ところが2009~10年の学年度末に、IMPACTによる評価の結果、下位5% に相当するとされ、他の205名とともに解雇されてしまったのです。
この原因は、2009~10年の学年度からIMPACTに新たに組み込まれた「付加価値モデル」で、彼女のこのスコアが著しく低かったのです。「付加価値モデル」は、教師が数学と英語を教える能力を評価しようとするもので、生徒の学力がどれほど向上したかで判定されます。この評価はIMPACTの評価の半分を占めていました。残りの半分は学校の経営陣からの評価や保護者からの評価などです。
サラ・ウィソッキーは自分の評価が不当だと思い、調べ始めました。「付加価値モデル」はワシントンDC学区と契約を結んだプリンストンの「政策数理研究所(Mathematical Policy Research)」が開発したモデルで、生徒の学習進捗度を測定した上で、学力の向上・低下についての教師の貢献度を評価しようとするものです。これは当然のことながら、多数の要因が関わる極めて複雑なものになります。サラ・ウィソッキーは自分の評価が低かった理由の説明を求めましたが、結局、誰からも説明を聞くことができませんでした。IMPACTを運用するワシントンDC学区の役員でさえ説明できないという「完全なブラックボックス」だったのです。
キャシー・オニールはこの「付加価値モデル」について2つ指摘しています。まずこの数学モデルを作ったときのサンプル数が少なすぎることです。わずか25~30名の生徒の学習進捗度調査がもとになっているといいます。学力の向上についての教師の貢献度というような複雑なテーマなら「無作為に抽出した生徒、数千~数百万のサンプル」が必要と書いています。必要数とともに "無作為抽出" がキーポイントです。
さらに、数学モデルで必須の "フィードバック" がないことが問題です。フィードバックの例としてアマゾンの商品のレコメンデーションを考えてみると、レコメンデーションのアルゴリズム(=数学モデル)が良いか悪いかは、レコメンドした商品を顧客がクリックしてくれるかどうかで測定できます。この測定をもとに、レコメンデーションのアルゴリズムがたえず調整されています。
ところが「付加価値モデル」にはフィートバックがありません。数学モデルが良いか悪いか、それを学習して修正する機会がありません。特に、教師を解雇してしまったらそれで終わりです。あとの追跡もできない。キャシー・オニールは次のように書いています。
サラ・ウィソッキーの話には続きがあります。彼女はマクファーランド中学の5年生(日本式に言うと中学1年)を受けもっていますが、入学してくる生徒の大半はバーナード小学校の出身でした。
教師は生徒の学力テストの成績が悪ければ自分の職が危うくなることを知っています。逆に成績が良ければ最高 8000ドルの特別手当が支給される。ましてや、リーマンショック後の労働市場が大打撃を受けていた時期です。小学校の教師が生徒の回答を修正したのではないかと疑われるのです。
サラ・ウィソッキーはこのことを知って、自分が解雇されたことに合点がいきました。しかしワシントンDC学区の責任者は聞く耳をもちません。「回答用紙の消し跡は "示唆的" であって、彼女の受け持ったクラスの数値に誤りがあった可能性はある。しかし決定的証拠ではない。彼女に対する処遇は公正だった」というのが責任者の言い分でした。
このあたりが数学破壊兵器の怖いところです。数学モデルで算出されたということで、人間が聞く耳を持たなくなってしまうのです。一人の人生をひっくり返すような決定をしているにもかかわらず ・・・・・・。
教師を評価する「付加価値モデル」の別の例が出てきます。ニューヨーク州の中学の英語教師、ティム・クリフォードは勤続26年の教師ですが、ある年、ワシントンDC学区と類似の「付加価値モデル」で解雇の標的となりました。100点満点で6点という最悪の成績だったからです。幸い彼は終身雇用を保証されていたので解雇されませんでしたが、スコアの低い年が続けば教師の職に居づらくなります。
「付加価値モデル」はクリフォードに落第点をつけましたが、改善点についてのアドバイスをしたわけではありません。彼は今まで通りの教え方を続けましたが、翌年の彼の評価スコアは何と96点でした。教師の "能力" が1年で90ポイントも変動するというのは、要するにデタラメということにほかなりません。このデタラメが持ち込まれた理由について、キャシー・オニールは統計学的に分析していますが、次のところが最も重要でしょう。
クリフォードのような例は多く、ある分析では同じ科目を何年か連続して教えた教師の4人に1人で、評価スコアが40ポイント以上変動していたといいます。キャシー・オニールは次のように結論づけています。
本書には、今も40の州とワシントンDCで「付加価値モデル」が使用されていると書かれています。
数学モデルには、それを作る側の「見解」が反映されます。どんなデータを収集するのか、何をアンケートで問いかけるのかにも、作り手の価値観や欲求・欲望が反映されます。さらにそこに、先入観や誤解、バイアス(偏見)が入り込む。
教師を評価する「付加価値モデル」に関して言うと、その最大の誤解は人を教えるという教師の能力を数値で評価できるという考えそのものでしょう。
USニューズの "大学ランキング"
2つ目の例は、これも教育に関するもので、時事雑誌「USニューズ」が発表している大学ランキングです。
この最初のランキングは、大学総長などの意見をもとに評価点を決めました。雑誌の読者には好評でしたが、多くの大学経営陣を怒らせ、不公平だという声が殺到しました。
そこでUSニューズは、データをもとにランキングを決めようとしました。しかし大学の「教育の卓越性」を計る指標を作るなど無理です。大学が1人の学生に4年間でどれだけ影響を与えたかは定量化できないし、全米で数千万もいる学生に対する影響など計りようがありません。そのためUSニューズは、測定可能で「教育の卓越性」と関係がありそうなデータ = "代理データ" をもとにランキングを決めようとしました。代理データとは次のようなものです。★は少ないほど良い指標です。
大学の評価点の75%はこのような代理データ(計、14項目)をもとに、それぞれに重みをつけて算出されます。そして残りの25%は大学総長や学部長の外部評価(他大学の評価を問う質問票のスコア)で決まります。外部評価が最大の重みを与えられていますが、こうした評価は広く名が知られた有名校ほど有利になることに注意すべきです。この合計15項目を点数化し、その合計点で大学のランキングをつけるわけです。
ランキングを上げるために "捨て身の" 行動に出る大学も出てきました。ある大学は入学予定者にお金を払って大学進学適性試験(SAT)を再受験させていました(本書には書いていませんが、おそらくSATのスコアが悪かった入学予定者だと思います)。またUSニューズに嘘のデータを送る大学も出てきました(データはUSニューズからの調査票に回答する形で収集されます。回答しなかった大学についてはUSニューズが独自調査をします)。
さらに意図しない有害な状況も生まれてきました。ランキングの元になるデータの一つに合格率があります。これは低いほど(= 競争率が高いほど)良いとされる数値で、この数値を下げるためのまっとうなやり方は、大学の評判を高めて多くの入試受験者を呼び込むことです。しかしもう一つ、やり方があります。合格者数を少なくすればよいのです。
「滑り止め」の受験ということがあります。「滑り止め」にされる大学としては、合格しても入学を辞退する学生がいることが過去の経験からわかっているので、定員より一定数だけ多めに合格を出すのが普通です。これは合格率を上げることになります。そこで大学側としては「滑り止め」で受験したと推定できる学生をアルゴリズムで割り出し、その学生には合格を出さないという対応を始めました。今や「滑り止め」という概念は消えつつあり、そうなったのにはUSニューズのランキングが大きく影響しています。
これは受験生と大学の双方にとって不幸な状況です。受験生にとっては「滑り止め」が意味をなさなくなり、大学にとっては、たとえ「滑り止め」であっても入学してくれたかもしれない優秀な学生を失うことになるからです。
さらに、大学ランキングの大きな過ちは「入学金と授業料」がデータに含まれないことだと、キャシー・オニールは指摘しています。つまり「入学金と授業料は低いほど良い」という評価がされないのです。この理由を彼女は推測しています。つまり大学ランキングを作るときにUSニューズはハーバード大学、スタンフォード大学、プリンストン大学、イエール大学のような、誰しも認めるような一流大学を調べたのだろう。そのような大学では、学生のSATの点数が高く、滞りなく卒業し、卒業生の年収が高いため母校に高額の寄付をしている。一方、これらの大学は入学金と授業料が高いことでも有名だ。もし入学金と授業料が低いほど良いという評価を入れると、これらの一流大学がランキング上位に並ばない可能性も出てくる。これではランキングの信憑性を疑わせることになる ・・・・・・。
大学ランキングの数学モデルは、ハーバード大学、スタンフォード大学、プリンストン大学、イエール大学などが上位に並ぶべく設計されています。つまり、モデルを作った人の 見解 が反映されているのです。
USニューズはランキングを拡張し、医科大学や高校までに広げています。また、このランキングを上げるためのコンサルティング会社、適切な入学募集をするためのコンサルティング会社、入学見込みの高い学生を予測するシステムを販売する会社などがあり、大学ランキングは巨大なエコシステム(生態系)の様相を呈しています。
キャシー・オニールが指摘しているように大学ランキングの最大の問題点は、多様性を否定する単一の物差しということでしょう。それが広まってしまった結果、全ての大学経営陣がそれに囚われてしまい、この物差しに向けて大学経営を最適化するようになった。まさに "破壊兵器" と呼ぶにふさわしいものです。
犯罪予測モデル
アメリカの北部、中西部から大西洋岸にかけて "ラストベルト"(Rust Belt)と呼ばれる地域があります。rust は錆の意味なので、直訳すると "錆地帯" です。この地域はアメリカの製造業や重工業の中心ですが、グローバル化による工場の海外移転、製造業の競争力低下などで経済的不振に陥っています。トランプ大統領(2017年1月に就任)の誕生の原動力の一つが、ラストベルトの白人貧困層だと言われました。本書にはそのラストベルトにある都市の事例が出てきます。
レディングにおける犯罪予測システムの導入は、やむにやまれぬ決断だったと言えるでしょう。しかし今や、このようなシステムの導入が大都市も含め全米に広まってきました。
プレドポル社はカリフォルニア大学ロサンジェルス校(UCLA)のジェフリー・ブランティンガム教授が創立した会社です。プレドポル社の犯罪予測システムには、人種や犯罪歴などの個人データはいっさい含まれていません。システムが照準を合わせるのは「区画」です。過去にどのような犯罪がどの区画でどの時刻に起こったというデータが基礎です。具体的な詳細は明らかにされていせんが、システムには区画の数々の特性データが入力されるのでしょう。ATMやコンビニなどの犯罪が起こりやすいポイントの存在も重要データのはずです。また、犯罪が起きる周期的なパターンにも注目していると言います。
この犯罪予測システムを使ったとしても、犯罪の実行前に警官が人々を逮捕・拘束するようなことはありません。あくまで犯罪の発生確率を区画ごとに予測するものであり、警官にその区画のパトロールを促すものです。そのような区画に警官が長く留まれば住居侵入や車上窃盗を阻止でき、地域住民のためになります。その意味で公平性は保たれていると考えられ、警察活動の効率性の観点から優れたシステムと考えられます。しかしキャシー・オニールはこの犯罪予測システムが「有害」になる危険性を次のように指摘しています。
自己成就予言という言葉があります。たとえ根拠のない予言であっても、人々がその予言を信じて行動することで予言が現実のものとなることを言います。ある銀行が危ないという予言がされると人々が預金をおろす行動に出て、本当にその銀行が倒産するようなことを言います。
迷惑犯罪を組み込んだ犯罪予測システムも自己成就予言に似ています。もちろん予測には数学モデルにもとづく根拠があるのでしょうが、「予測することによって予測が確実になっていく」のは大変よく似ている。考えてみると、前の項に紹介したUSニューズの大学ランキングも自己成就予言の要素があります。ランキング下位の大学は、そのことによって「教育の卓越性」が失われていき(大学経営陣が対策を打たないと)、それがランキングをさらに下げる。
キャシー・オニールは「どのような犯罪に注目するかを選択しているのは警察である」と書いています。もちろん重犯罪を除く、軽犯罪・迷惑犯罪についてです。犯罪予測モデルを数学破壊兵器にしないためには、モデルから軽犯罪を除外することが必要なのです。
個人を分類し、スコアリングする
本書に取り上げられたトピックから、「教師評価モデル」「大学ランキング」「犯罪予測モデル」の3つを紹介しましたが、本書には他にも多数の事例が出てきます。この中でも特に印象的なのは「個人を分類しスコアリングする」技術や数学モデルです。
そのもとになるのは、ビッグデータとして収集される個人の「行動データ」です。これにはネットでの検索履歴、商品の購買履歴、Webサイトの閲覧、SNSなどでの情報発信、モバイル機器の位置情報などです。これらを数学モデルで分析し、個人が分類され、あるいは個人にスコアがつけられる。行動データから性別や年齢はもちろんのこと、年収、性格まで推定できると言います。(やろうと思えば)位置情報から住所や勤務地を容易に推定できます。
ターゲティング広告はそのような行動データに基づいています。その個人が興味を惹きそうな広告を個人ごとに提示する。これは日本でも一般的ですが、これが有害になることがあります。つまり意図的に貧困層の人、困り果てている人、無知な人を狙って大量のターゲティング広告をうち、詐欺まがいの商品やサービスを購入させて "収奪" することができる(略奪型広告と書いてあります)。いわゆる「弱みにつけこむ」というやつです。
個人の信用度をスコアリングする、信用スコア(クレジット・スコア)に関する問題も提起されています。アメリカではFICOと呼ばれるクレジット・スコアが広まっています。これは個人のクレジットカード、住宅ローン、携帯電話料金などの支払い履歴から計算されるスコアです。このスコアは支払い履歴のみから計算され、計算方法が公開されています。また個人が自分のスコアに疑問や不審をもったとき、そのデータの公開を請求できます。さらに企業がスコアをマーケティングに利用することは法律で禁じられています。これらは信用格付け会社が法律で規制されているからです(日本でもクレジット業界の与信審査では同様のスコアがある)。
その一方、法律の規制を受けない個人スコアが広まっていて、本書ではこれを "eスコア" と呼んでいます。それは個人のありとあらゆる行動履歴や郵便番号などから数学モデルで算出されるもので、法の規制を受けません。これが企業活動に使われる。こういった "eスコア" は有害だと、キャシー・オニールは指摘しています。象徴的には、治安の悪いとされる地区からアクセスして中古車を調べていた人物は "eスコア" が低くなり、ローンの金利が高くなるといった例です。
個人の健康度を計ろうとする動きも非常に気になるところです。すでに保険会社では独自の健康スコアを策定し、スコアに応じて健康保険料を変えるところが現れています。キャシー・オニールはこういった動きが一般的に広まることを懸念しています。
血圧、血糖値、中性脂肪値、胴囲、コレステロール値など、健康を計る基礎値には事欠かないので、これらをもとに「健康スコア」が作られる可能性は高いわけです。その、すでに広まっているスコアの一つの例として、BMI(Body Mass Index。ボディマス指数)があります。
BMIは「体重(kg)を身長(m)の2乗で割る」という数式で計算されます。そして日本では 25 以上が「肥満」、18.5以下が「痩せ」とされる。しかしこれは肥満度をおおまかに知るための粗い代理数値です。「平均的な男性」を基準にしているので、たとえば女性は太りすぎと判断されやすくなります。また筋肉は脂肪より重いので、体脂肪率の少ない筋肉隆々のアスリートのBMIは高くなります。
エンゼルスの大谷翔平選手の身長は193cm、体重は92kgですが、シーズンオフには97kg程度のこともあるようです。体重を92kg~97kgとすると、大谷選手のBMIは24.7~26.0となり、「もう少しで肥満 ~ 肥満」ということになります(日本基準)。これはどう考えてもおかしいわけです(もちろん大谷選手のことは本書にはありません)。
「健康スコア」によって人々が健康問題に向き合えるように後押しするのは、決して悪いことではありません。重要なのはそれが「提案」なのか「命令・強制」なのかです。企業や組織が健康スコアによって何らかの強制や差別をするようになると(キャシー・オニールはそれを懸念している)、それは個人の自由の侵害になるのです。
民主主義を脅かす危険性
本書の原題は「破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」です。この「民主主義を脅かすか」の部分が本書の最終章に書かれています。それは、選挙に数学破壊兵器が持ち込まれるリスクです。
2010年のアメリカの中間選挙において、フェイスブックは「投票しました(I voted)」というボタンを設け、投票した人がボタンをクリックすると、友達ネットワークのニュースフィードを通してそれが拡散するようにしました。この結果、投票率が2%上昇したとフェイスブックは分析しています。
また2012年の大統領選挙(オバマ大統領が再選された)では、その3ヶ月前からフェイスブックのユーザ200万人(政治に関わる人)を対象に実験が行われました。ニュースフィードに流すニュースを選ぶアルゴリズムに手を加え、200万人に対しては政治のニュースを意図的に多く流すようにしたのです。後日、アンケートで投票行動を調べた結果、投票率は64%から67%に上昇したと推定しています。
わずか2%~3%の差ですが、これはSNSの巨大な影響力を示しています。投票率が上がることは、社会通念上は良いことです。フェイスブックの行為も善意からかもしれません。しかし投票率によって選挙の当落が左右される(ことがある)のは常識です。特に、投票率が特定の候補者や政党に影響することがある(日本でも雨天で投票率が悪いと特定の政党が有利だという話があります)。フェイスブックは膨大な個人情報を握っているわけで、例えば特定の地域の投票率が上がるように「投票しました(I voted)」を拡散させることは技術的に十分可能でしょう。フェイスブックがそういうことをやっているというのではなく、そういうリスクがあるということです。
Googleのような検索エンジンも、検索結果の上位に何をもってくるかは Googleが決めています。特定の候補、ないしは政党に有利(ないしいは不利)になる情報を上位にもってくることがアルゴリズムの工夫によって可能であり、ここにもリスクがあります。
さらにターゲッティング広告が既に一般化していることを考えると、ネットを選挙運動使うことにも危険性があります。個人の行動履歴から、その個人がどういう政治課題に関心があるかをプロファイリングできます(自然保護、治安強化、女性の地位向上 ・・・・・・)。すると候補者は、その課題解決を前面に押し出したメールを個人に配信することができる。別の関心事項をもつ個人には別の内容のメールを送る ・・・・・・。結局、候補者が当選後にどの公約を前面に押し出すのか、誰にも予想できません。本書はマイクロ・ターゲティングと言っていますが、ネット広告で既に行われているのだから「候補者を売り込む」のが目的の選挙でも可能です。数学モデルはこういったことを可能にし、それは民主主義を歪めていくことになるのです。
もちろん、新聞やテレビも選挙の報道をします。候補者の政見を乗せるし、特定の政党を支持する社説を掲載する新聞もある。しかしそれらはオープンであり、どういう報道がされているかを誰もが眼にでき、検証できます。つまり透明性が確保されている。しかしネット上のマイクロ・ターゲティングは、誰が誰にどういう種類の情報やメッセージを流しているかは全く分かりません。つまり不透明です。
本書の最終章は「第10章 政治 - 民主主義の土台を壊す」と題されています。そういうリスクがあることは十分に認識しておくべきだと思います。
EUのGDPRの意味
以降は、本書を読んで思ったことです。No.237「フランスのAI立国宣言」で書いたように、2018年3月末、マクロン大統領は、
を前面に押し出したAI国家戦略を発表しました。これはまさに本書の主張と軌を一にするものです。フランスがキャシー・オニールを招待したのは当然だったようです(もちろんフランスの戦略は、そのことによって自国を有利にしようとするものです)。
さらに思い出したのは2018年5月25日より施行された「EU 一般データ保護規則 - GDPR(General Data Protection Regulation)」です。これは欧州経済域(EEA。EU加盟28ヶ国+ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)に居住する市民の個人データ、およびEEAを本拠として収集された個人データの管理と移転に関する規則で、個人データをEEA域外に移転することが原則禁止されます。さらに「データ主体に認められる8つの権利」が明文化されています。データ主体とは個人データを提供する(個人データを収集される)一般市民です。
8つの権利でも特に重要なのは「削除権」で、データ主体は自分に関する個人データを削除するよう、データ管理者に要求できます。いわゆる「忘れられる権利」です。
さらにデータ主体は「プロファイリングを含む自動処理によって個人についての決定がなされない権利」を持ちます。プロファイリングとは「個人データを自動処理することによって、個人のある側面、特に仕事の実績、経済状況、健康、嗜好、関心、行動、所在、移動などを分析・予測する」ことです。また「個人についての決定」とは法的な決定、ないしはそれと同等に個人にとって重要な決定です。本書には「教師評価システム」によって解雇された事例がありましたが(1番目に紹介した事例)、もしGDPRがアメリカにあったとしたらこのような解雇は無効になるに違いありません。
GDPRを本書の視点から見ると「数学破壊兵器の野放図な増殖を食い止めるための規制」というのが、その(一つの)意味でしょう。また、個人データを独占しているアメリカの巨大IT企業の活動を制限する意図が透けて見えます。
キャシー・オニールの本「破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」と、フランスの「AI立国宣言」、EUのGDPR(一般データ保護規則)の3つは、一つの水脈でつながっていると思いました。
| 「 | Weapons of Math Destruction - How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy」(2016) | ||
| 「 | 破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」 |
という本を書いたことで有名です。Weapons of Mass Destruction(大量破壊兵器。WMDと略される)に Math(Mathematics. 数学)を引っかけた題名です(上の訳は新井教授のコラムのもの)。この本は日本語に訳され、2018年7月に出版されました。
キャシー・オニール 著(久保尚子訳)
「あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」
(インターシフト 2018.7.10)
「あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」
(インターシフト 2018.7.10)
です(以下「本書」)。一言で言うと、ビッグデータを数式で処理した何らかの "結果" が社会に有害な影響を与えることに警鐘を鳴らした本で、まさに現代社会にピッタリだと言えるでしょう。今回はこの本の内容をざっと紹介したいと思います。なお、原題にある Weapons of Math Destruction は、そのまま直訳すると「数学破壊兵器」で、本書でも(題名以外は)そう訳してあります。
本書で扱っているテーマ
本書をこれから買おうと思っている方のために、2つの留意点を書いておきます。
| AIについての本ではない |
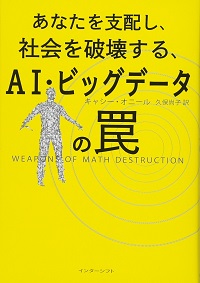
| |||
|
キャシー・オニール
(久保尚子訳) 「あなたを支配し、社会を破壊する、AI・ビッグデータの罠」 (インターシフト) | |||
数学が社会に与える影響と書きましたが、もっと詳しく言うと「数学モデル(数理モデル)が社会に与える影響」です。この数学モデルは人間が考え出したものであり、単純な数式のこともあれば、複雑な(数学的)アルゴリズムのこともあります。AIはその極めて複雑な部類です。この数学モデルにはデータ(ないしはビッグデータ)が入力されます。そして計算の結果として、
| 評価、判断、分類、予測、グループ分け、ランキング(ランク付け、順位付け)、スコアリング(スコア付け、点数付け)、指数、指標 |
などが出力されます。その多くは個人に関するものですが、組織体(大学、高校、企業、自治体、国、・・・・・)について評価のこともあり、また「犯罪発生場所の予測」といった場所・地区に関する数値であったりもします。
最も単純な数学モデルの例は、本書でも出てくる BMI(Body Mass Index。ボディマス指数)でしょう。人の身長と体重を入力とし、"数学モデル" によって「肥満度の評価指標値」を出し、同時に人を「肥満・普通・痩せ」に分類します。この場合の "数学モデル" は、体重(kg)を身長(m)の2乗で割るという単純な数式です。
もちろん数学モデルの利用は近代科学が始まったときからの歴史があります。むしろ数学モデルを使うことで近代科学が生まれたと言えるでしょう。現代でも身近なところでは、気象の予測には膨大な計算を必要とする数学モデル(=物理モデルをもとにした数学モデル)が使われています。もちろん自然科学だけなく社会科学にも使われます。
この数学モデルが社会に悪影響を与えるとき、キャシー・オニールはそれを「数学破壊兵器 = WMD」と呼んでいるわけです。悪影響とは、たとえば差別を助長するとか、貧困を加速するとか、公正ではない競争を促進するとか、平等の原則を阻害するとかであり、その具体的な例は本書に出てきます。
| アメリカの事例 |
2つめに留意すべきは、本書に取り上げられているのはアメリカでの事例だということです。日本では考えられないような実例がいろいろ出てきます。それらを単純に日本に当てはめることはできない。
しかし我々としてはアメリカでの数学破壊兵器の実態を反面教師とし、そこから学ぶことができます。かつ、本書に出てくるアメリカの巨大IT企業(フェイスブック、グーグル、アマゾンなど)は日本でもビジネス展開をしているわけで、我々も常時利用しています。もちろん、これらのIT企業が数学破壊兵器を使っていると言っているのではなく、その危険性があると指摘しているわけです。こういった知識を得ることも有用でしょう。
キャシー・オニールの経歴

| |||
|
キャシー・オニール
Cathy O'Neil (site:www.barnesandnoble.com) | |||
まさにキャシー・オニールは学者としてエリートであり、ヘッジファンドに転職というのも華麗な経歴です。ところが転職して1年あまりの2008年秋、世界経済は崩壊に直面しました(= リーマン・ショック)。彼女は次のように書いています。
|
本書の根幹にあるキャシー・オニールの "思い" とは、愛する数学が社会に災いをもたらすことへの危機感(ないしは "数学をもて遊ぶ人たち" への怒り)と、短期間とはいえ "災いをもたらす側で数学者として働いた" という自責の念、の2つでしょう。本書の第2章では「内幕」と題して2008年の前後の金融業界・ヘッジファンドの内情が生々しく語られています。
彼女はヘッジファンドを離職し、現在は企業が使うアルゴリズムを監査する会社(彼女自身が立ち上げたもの)のトップを努めています。もちろん彼女は数学モデルやアルゴリズム(AIもその一種)を否定しているのではありません。「盲信するな」と警告しているわけです。
そのようなスタンスは本書でも明らかです。本書には「明白な数学破壊兵器の例」もありますが、「数学破壊兵器になりかねないもの」や「有益なツールだが、使い方によっては数学破壊兵器になるもの」、「将来、数学破壊兵器へと発展しかねないリスクがあるもの」の例などが出てきます。幅広い見地から "数学の有害利用" を指摘しアラームをあげることによって、それを正そうとする本と言えるでしょう。
以下に本書にある多数の事例から3つの例だけを紹介します。教育と犯罪に関するものです。
教師評価システム
本書で最初にあげられている数学破壊兵器の例が、教師の評価スコアを算出するツールです。
|
ワシントンDCの教師だったサラ・ウィソッキーの例が出てきます。彼女はマクファーランド中学で第5学年(日本式に言うと中学1年)の受け持ちでした。彼女は子供たちに対するきめ細かい配慮で保護者からも高く評価されていました。ところが2009~10年の学年度末に、IMPACTによる評価の結果、下位5% に相当するとされ、他の205名とともに解雇されてしまったのです。
この原因は、2009~10年の学年度からIMPACTに新たに組み込まれた「付加価値モデル」で、彼女のこのスコアが著しく低かったのです。「付加価値モデル」は、教師が数学と英語を教える能力を評価しようとするもので、生徒の学力がどれほど向上したかで判定されます。この評価はIMPACTの評価の半分を占めていました。残りの半分は学校の経営陣からの評価や保護者からの評価などです。
サラ・ウィソッキーは自分の評価が不当だと思い、調べ始めました。「付加価値モデル」はワシントンDC学区と契約を結んだプリンストンの「政策数理研究所(Mathematical Policy Research)」が開発したモデルで、生徒の学習進捗度を測定した上で、学力の向上・低下についての教師の貢献度を評価しようとするものです。これは当然のことながら、多数の要因が関わる極めて複雑なものになります。サラ・ウィソッキーは自分の評価が低かった理由の説明を求めましたが、結局、誰からも説明を聞くことができませんでした。IMPACTを運用するワシントンDC学区の役員でさえ説明できないという「完全なブラックボックス」だったのです。
キャシー・オニールはこの「付加価値モデル」について2つ指摘しています。まずこの数学モデルを作ったときのサンプル数が少なすぎることです。わずか25~30名の生徒の学習進捗度調査がもとになっているといいます。学力の向上についての教師の貢献度というような複雑なテーマなら「無作為に抽出した生徒、数千~数百万のサンプル」が必要と書いています。必要数とともに "無作為抽出" がキーポイントです。
さらに、数学モデルで必須の "フィードバック" がないことが問題です。フィードバックの例としてアマゾンの商品のレコメンデーションを考えてみると、レコメンデーションのアルゴリズム(=数学モデル)が良いか悪いかは、レコメンドした商品を顧客がクリックしてくれるかどうかで測定できます。この測定をもとに、レコメンデーションのアルゴリズムがたえず調整されています。
ところが「付加価値モデル」にはフィートバックがありません。数学モデルが良いか悪いか、それを学習して修正する機会がありません。特に、教師を解雇してしまったらそれで終わりです。あとの追跡もできない。キャシー・オニールは次のように書いています。
|
サラ・ウィソッキーの話には続きがあります。彼女はマクファーランド中学の5年生(日本式に言うと中学1年)を受けもっていますが、入学してくる生徒の大半はバーナード小学校の出身でした。
|
教師は生徒の学力テストの成績が悪ければ自分の職が危うくなることを知っています。逆に成績が良ければ最高 8000ドルの特別手当が支給される。ましてや、リーマンショック後の労働市場が大打撃を受けていた時期です。小学校の教師が生徒の回答を修正したのではないかと疑われるのです。
サラ・ウィソッキーはこのことを知って、自分が解雇されたことに合点がいきました。しかしワシントンDC学区の責任者は聞く耳をもちません。「回答用紙の消し跡は "示唆的" であって、彼女の受け持ったクラスの数値に誤りがあった可能性はある。しかし決定的証拠ではない。彼女に対する処遇は公正だった」というのが責任者の言い分でした。
このあたりが数学破壊兵器の怖いところです。数学モデルで算出されたということで、人間が聞く耳を持たなくなってしまうのです。一人の人生をひっくり返すような決定をしているにもかかわらず ・・・・・・。
教師を評価する「付加価値モデル」の別の例が出てきます。ニューヨーク州の中学の英語教師、ティム・クリフォードは勤続26年の教師ですが、ある年、ワシントンDC学区と類似の「付加価値モデル」で解雇の標的となりました。100点満点で6点という最悪の成績だったからです。幸い彼は終身雇用を保証されていたので解雇されませんでしたが、スコアの低い年が続けば教師の職に居づらくなります。
「付加価値モデル」はクリフォードに落第点をつけましたが、改善点についてのアドバイスをしたわけではありません。彼は今まで通りの教え方を続けましたが、翌年の彼の評価スコアは何と96点でした。教師の "能力" が1年で90ポイントも変動するというのは、要するにデタラメということにほかなりません。このデタラメが持ち込まれた理由について、キャシー・オニールは統計学的に分析していますが、次のところが最も重要でしょう。
|
クリフォードのような例は多く、ある分析では同じ科目を何年か連続して教えた教師の4人に1人で、評価スコアが40ポイント以上変動していたといいます。キャシー・オニールは次のように結論づけています。
|
本書には、今も40の州とワシントンDCで「付加価値モデル」が使用されていると書かれています。
数学モデルには、それを作る側の「見解」が反映されます。どんなデータを収集するのか、何をアンケートで問いかけるのかにも、作り手の価値観や欲求・欲望が反映されます。さらにそこに、先入観や誤解、バイアス(偏見)が入り込む。
教師を評価する「付加価値モデル」に関して言うと、その最大の誤解は人を教えるという教師の能力を数値で評価できるという考えそのものでしょう。
USニューズの "大学ランキング"
2つ目の例は、これも教育に関するもので、時事雑誌「USニューズ」が発表している大学ランキングです。
|
この最初のランキングは、大学総長などの意見をもとに評価点を決めました。雑誌の読者には好評でしたが、多くの大学経営陣を怒らせ、不公平だという声が殺到しました。
そこでUSニューズは、データをもとにランキングを決めようとしました。しかし大学の「教育の卓越性」を計る指標を作るなど無理です。大学が1人の学生に4年間でどれだけ影響を与えたかは定量化できないし、全米で数千万もいる学生に対する影響など計りようがありません。そのためUSニューズは、測定可能で「教育の卓越性」と関係がありそうなデータ = "代理データ" をもとにランキングを決めようとしました。代理データとは次のようなものです。★は少ないほど良い指標です。
| ◆ | 合格率(入試の受験者数に対する合格者数の割合★) | ||
| ◆ | 学生の大学進学適性試験(SAT)の成績 | ||
| ◆ | 2年生に進学した新入生の割合 | ||
| ◆ | 6年以下で卒業できた学生の割合 | ||
| ◆ | 教員1人当たりの学生数(★) | ||
| ◆ | 1クラス当たりの学生数(★) | ||
| ◆ | 常勤教員の比率 | ||
| ◆ | 教員の給料 | ||
| ◆ | 学生1人あたり大学が使った費用 | ||
| ◆ | 存命の卒業生のうち、大学に寄付をした人の割合 |
大学の評価点の75%はこのような代理データ(計、14項目)をもとに、それぞれに重みをつけて算出されます。そして残りの25%は大学総長や学部長の外部評価(他大学の評価を問う質問票のスコア)で決まります。外部評価が最大の重みを与えられていますが、こうした評価は広く名が知られた有名校ほど有利になることに注意すべきです。この合計15項目を点数化し、その合計点で大学のランキングをつけるわけです。
|
ランキングを上げるために "捨て身の" 行動に出る大学も出てきました。ある大学は入学予定者にお金を払って大学進学適性試験(SAT)を再受験させていました(本書には書いていませんが、おそらくSATのスコアが悪かった入学予定者だと思います)。またUSニューズに嘘のデータを送る大学も出てきました(データはUSニューズからの調査票に回答する形で収集されます。回答しなかった大学についてはUSニューズが独自調査をします)。
さらに意図しない有害な状況も生まれてきました。ランキングの元になるデータの一つに合格率があります。これは低いほど(= 競争率が高いほど)良いとされる数値で、この数値を下げるためのまっとうなやり方は、大学の評判を高めて多くの入試受験者を呼び込むことです。しかしもう一つ、やり方があります。合格者数を少なくすればよいのです。
「滑り止め」の受験ということがあります。「滑り止め」にされる大学としては、合格しても入学を辞退する学生がいることが過去の経験からわかっているので、定員より一定数だけ多めに合格を出すのが普通です。これは合格率を上げることになります。そこで大学側としては「滑り止め」で受験したと推定できる学生をアルゴリズムで割り出し、その学生には合格を出さないという対応を始めました。今や「滑り止め」という概念は消えつつあり、そうなったのにはUSニューズのランキングが大きく影響しています。
これは受験生と大学の双方にとって不幸な状況です。受験生にとっては「滑り止め」が意味をなさなくなり、大学にとっては、たとえ「滑り止め」であっても入学してくれたかもしれない優秀な学生を失うことになるからです。
さらに、大学ランキングの大きな過ちは「入学金と授業料」がデータに含まれないことだと、キャシー・オニールは指摘しています。つまり「入学金と授業料は低いほど良い」という評価がされないのです。この理由を彼女は推測しています。つまり大学ランキングを作るときにUSニューズはハーバード大学、スタンフォード大学、プリンストン大学、イエール大学のような、誰しも認めるような一流大学を調べたのだろう。そのような大学では、学生のSATの点数が高く、滞りなく卒業し、卒業生の年収が高いため母校に高額の寄付をしている。一方、これらの大学は入学金と授業料が高いことでも有名だ。もし入学金と授業料が低いほど良いという評価を入れると、これらの一流大学がランキング上位に並ばない可能性も出てくる。これではランキングの信憑性を疑わせることになる ・・・・・・。
大学ランキングの数学モデルは、ハーバード大学、スタンフォード大学、プリンストン大学、イエール大学などが上位に並ぶべく設計されています。つまり、モデルを作った人の 見解 が反映されているのです。
|
USニューズはランキングを拡張し、医科大学や高校までに広げています。また、このランキングを上げるためのコンサルティング会社、適切な入学募集をするためのコンサルティング会社、入学見込みの高い学生を予測するシステムを販売する会社などがあり、大学ランキングは巨大なエコシステム(生態系)の様相を呈しています。
キャシー・オニールが指摘しているように大学ランキングの最大の問題点は、多様性を否定する単一の物差しということでしょう。それが広まってしまった結果、全ての大学経営陣がそれに囚われてしまい、この物差しに向けて大学経営を最適化するようになった。まさに "破壊兵器" と呼ぶにふさわしいものです。
犯罪予測モデル
アメリカの北部、中西部から大西洋岸にかけて "ラストベルト"(Rust Belt)と呼ばれる地域があります。rust は錆の意味なので、直訳すると "錆地帯" です。この地域はアメリカの製造業や重工業の中心ですが、グローバル化による工場の海外移転、製造業の競争力低下などで経済的不振に陥っています。トランプ大統領(2017年1月に就任)の誕生の原動力の一つが、ラストベルトの白人貧困層だと言われました。本書にはそのラストベルトにある都市の事例が出てきます。
|
レディングにおける犯罪予測システムの導入は、やむにやまれぬ決断だったと言えるでしょう。しかし今や、このようなシステムの導入が大都市も含め全米に広まってきました。
プレドポル社はカリフォルニア大学ロサンジェルス校(UCLA)のジェフリー・ブランティンガム教授が創立した会社です。プレドポル社の犯罪予測システムには、人種や犯罪歴などの個人データはいっさい含まれていません。システムが照準を合わせるのは「区画」です。過去にどのような犯罪がどの区画でどの時刻に起こったというデータが基礎です。具体的な詳細は明らかにされていせんが、システムには区画の数々の特性データが入力されるのでしょう。ATMやコンビニなどの犯罪が起こりやすいポイントの存在も重要データのはずです。また、犯罪が起きる周期的なパターンにも注目していると言います。
この犯罪予測システムを使ったとしても、犯罪の実行前に警官が人々を逮捕・拘束するようなことはありません。あくまで犯罪の発生確率を区画ごとに予測するものであり、警官にその区画のパトロールを促すものです。そのような区画に警官が長く留まれば住居侵入や車上窃盗を阻止でき、地域住民のためになります。その意味で公平性は保たれていると考えられ、警察活動の効率性の観点から優れたシステムと考えられます。しかしキャシー・オニールはこの犯罪予測システムが「有害」になる危険性を次のように指摘しています。
|
自己成就予言という言葉があります。たとえ根拠のない予言であっても、人々がその予言を信じて行動することで予言が現実のものとなることを言います。ある銀行が危ないという予言がされると人々が預金をおろす行動に出て、本当にその銀行が倒産するようなことを言います。
迷惑犯罪を組み込んだ犯罪予測システムも自己成就予言に似ています。もちろん予測には数学モデルにもとづく根拠があるのでしょうが、「予測することによって予測が確実になっていく」のは大変よく似ている。考えてみると、前の項に紹介したUSニューズの大学ランキングも自己成就予言の要素があります。ランキング下位の大学は、そのことによって「教育の卓越性」が失われていき(大学経営陣が対策を打たないと)、それがランキングをさらに下げる。
キャシー・オニールは「どのような犯罪に注目するかを選択しているのは警察である」と書いています。もちろん重犯罪を除く、軽犯罪・迷惑犯罪についてです。犯罪予測モデルを数学破壊兵器にしないためには、モデルから軽犯罪を除外することが必要なのです。
個人を分類し、スコアリングする
本書に取り上げられたトピックから、「教師評価モデル」「大学ランキング」「犯罪予測モデル」の3つを紹介しましたが、本書には他にも多数の事例が出てきます。この中でも特に印象的なのは「個人を分類しスコアリングする」技術や数学モデルです。
そのもとになるのは、ビッグデータとして収集される個人の「行動データ」です。これにはネットでの検索履歴、商品の購買履歴、Webサイトの閲覧、SNSなどでの情報発信、モバイル機器の位置情報などです。これらを数学モデルで分析し、個人が分類され、あるいは個人にスコアがつけられる。行動データから性別や年齢はもちろんのこと、年収、性格まで推定できると言います。(やろうと思えば)位置情報から住所や勤務地を容易に推定できます。
ターゲティング広告はそのような行動データに基づいています。その個人が興味を惹きそうな広告を個人ごとに提示する。これは日本でも一般的ですが、これが有害になることがあります。つまり意図的に貧困層の人、困り果てている人、無知な人を狙って大量のターゲティング広告をうち、詐欺まがいの商品やサービスを購入させて "収奪" することができる(略奪型広告と書いてあります)。いわゆる「弱みにつけこむ」というやつです。
個人の信用度をスコアリングする、信用スコア(クレジット・スコア)に関する問題も提起されています。アメリカではFICOと呼ばれるクレジット・スコアが広まっています。これは個人のクレジットカード、住宅ローン、携帯電話料金などの支払い履歴から計算されるスコアです。このスコアは支払い履歴のみから計算され、計算方法が公開されています。また個人が自分のスコアに疑問や不審をもったとき、そのデータの公開を請求できます。さらに企業がスコアをマーケティングに利用することは法律で禁じられています。これらは信用格付け会社が法律で規制されているからです(日本でもクレジット業界の与信審査では同様のスコアがある)。
その一方、法律の規制を受けない個人スコアが広まっていて、本書ではこれを "eスコア" と呼んでいます。それは個人のありとあらゆる行動履歴や郵便番号などから数学モデルで算出されるもので、法の規制を受けません。これが企業活動に使われる。こういった "eスコア" は有害だと、キャシー・オニールは指摘しています。象徴的には、治安の悪いとされる地区からアクセスして中古車を調べていた人物は "eスコア" が低くなり、ローンの金利が高くなるといった例です。
個人の健康度を計ろうとする動きも非常に気になるところです。すでに保険会社では独自の健康スコアを策定し、スコアに応じて健康保険料を変えるところが現れています。キャシー・オニールはこういった動きが一般的に広まることを懸念しています。
|
血圧、血糖値、中性脂肪値、胴囲、コレステロール値など、健康を計る基礎値には事欠かないので、これらをもとに「健康スコア」が作られる可能性は高いわけです。その、すでに広まっているスコアの一つの例として、BMI(Body Mass Index。ボディマス指数)があります。
|
BMIは「体重(kg)を身長(m)の2乗で割る」という数式で計算されます。そして日本では 25 以上が「肥満」、18.5以下が「痩せ」とされる。しかしこれは肥満度をおおまかに知るための粗い代理数値です。「平均的な男性」を基準にしているので、たとえば女性は太りすぎと判断されやすくなります。また筋肉は脂肪より重いので、体脂肪率の少ない筋肉隆々のアスリートのBMIは高くなります。
エンゼルスの大谷翔平選手の身長は193cm、体重は92kgですが、シーズンオフには97kg程度のこともあるようです。体重を92kg~97kgとすると、大谷選手のBMIは24.7~26.0となり、「もう少しで肥満 ~ 肥満」ということになります(日本基準)。これはどう考えてもおかしいわけです(もちろん大谷選手のことは本書にはありません)。
「健康スコア」によって人々が健康問題に向き合えるように後押しするのは、決して悪いことではありません。重要なのはそれが「提案」なのか「命令・強制」なのかです。企業や組織が健康スコアによって何らかの強制や差別をするようになると(キャシー・オニールはそれを懸念している)、それは個人の自由の侵害になるのです。
民主主義を脅かす危険性
.jpg)
| |||
|
Cathy O'Neil
「Weapons of Math Destruction」 | |||
2010年のアメリカの中間選挙において、フェイスブックは「投票しました(I voted)」というボタンを設け、投票した人がボタンをクリックすると、友達ネットワークのニュースフィードを通してそれが拡散するようにしました。この結果、投票率が2%上昇したとフェイスブックは分析しています。
また2012年の大統領選挙(オバマ大統領が再選された)では、その3ヶ月前からフェイスブックのユーザ200万人(政治に関わる人)を対象に実験が行われました。ニュースフィードに流すニュースを選ぶアルゴリズムに手を加え、200万人に対しては政治のニュースを意図的に多く流すようにしたのです。後日、アンケートで投票行動を調べた結果、投票率は64%から67%に上昇したと推定しています。
わずか2%~3%の差ですが、これはSNSの巨大な影響力を示しています。投票率が上がることは、社会通念上は良いことです。フェイスブックの行為も善意からかもしれません。しかし投票率によって選挙の当落が左右される(ことがある)のは常識です。特に、投票率が特定の候補者や政党に影響することがある(日本でも雨天で投票率が悪いと特定の政党が有利だという話があります)。フェイスブックは膨大な個人情報を握っているわけで、例えば特定の地域の投票率が上がるように「投票しました(I voted)」を拡散させることは技術的に十分可能でしょう。フェイスブックがそういうことをやっているというのではなく、そういうリスクがあるということです。
Googleのような検索エンジンも、検索結果の上位に何をもってくるかは Googleが決めています。特定の候補、ないしは政党に有利(ないしいは不利)になる情報を上位にもってくることがアルゴリズムの工夫によって可能であり、ここにもリスクがあります。
さらにターゲッティング広告が既に一般化していることを考えると、ネットを選挙運動使うことにも危険性があります。個人の行動履歴から、その個人がどういう政治課題に関心があるかをプロファイリングできます(自然保護、治安強化、女性の地位向上 ・・・・・・)。すると候補者は、その課題解決を前面に押し出したメールを個人に配信することができる。別の関心事項をもつ個人には別の内容のメールを送る ・・・・・・。結局、候補者が当選後にどの公約を前面に押し出すのか、誰にも予想できません。本書はマイクロ・ターゲティングと言っていますが、ネット広告で既に行われているのだから「候補者を売り込む」のが目的の選挙でも可能です。数学モデルはこういったことを可能にし、それは民主主義を歪めていくことになるのです。
もちろん、新聞やテレビも選挙の報道をします。候補者の政見を乗せるし、特定の政党を支持する社説を掲載する新聞もある。しかしそれらはオープンであり、どういう報道がされているかを誰もが眼にでき、検証できます。つまり透明性が確保されている。しかしネット上のマイクロ・ターゲティングは、誰が誰にどういう種類の情報やメッセージを流しているかは全く分かりません。つまり不透明です。
本書の最終章は「第10章 政治 - 民主主義の土台を壊す」と題されています。そういうリスクがあることは十分に認識しておくべきだと思います。
EUのGDPRの意味
以降は、本書を読んで思ったことです。No.237「フランスのAI立国宣言」で書いたように、2018年3月末、マクロン大統領は、
| 人権と民主主義に貢献するAI 人間性のためのAI |
を前面に押し出したAI国家戦略を発表しました。これはまさに本書の主張と軌を一にするものです。フランスがキャシー・オニールを招待したのは当然だったようです(もちろんフランスの戦略は、そのことによって自国を有利にしようとするものです)。
さらに思い出したのは2018年5月25日より施行された「EU 一般データ保護規則 - GDPR(General Data Protection Regulation)」です。これは欧州経済域(EEA。EU加盟28ヶ国+ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン)に居住する市民の個人データ、およびEEAを本拠として収集された個人データの管理と移転に関する規則で、個人データをEEA域外に移転することが原則禁止されます。さらに「データ主体に認められる8つの権利」が明文化されています。データ主体とは個人データを提供する(個人データを収集される)一般市民です。
8つの権利でも特に重要なのは「削除権」で、データ主体は自分に関する個人データを削除するよう、データ管理者に要求できます。いわゆる「忘れられる権利」です。
さらにデータ主体は「プロファイリングを含む自動処理によって個人についての決定がなされない権利」を持ちます。プロファイリングとは「個人データを自動処理することによって、個人のある側面、特に仕事の実績、経済状況、健康、嗜好、関心、行動、所在、移動などを分析・予測する」ことです。また「個人についての決定」とは法的な決定、ないしはそれと同等に個人にとって重要な決定です。本書には「教師評価システム」によって解雇された事例がありましたが(1番目に紹介した事例)、もしGDPRがアメリカにあったとしたらこのような解雇は無効になるに違いありません。
GDPRを本書の視点から見ると「数学破壊兵器の野放図な増殖を食い止めるための規制」というのが、その(一つの)意味でしょう。また、個人データを独占しているアメリカの巨大IT企業の活動を制限する意図が透けて見えます。
キャシー・オニールの本「破壊兵器としての数学 - ビッグデータはいかに不平等を助長し民主主義を脅かすか」と、フランスの「AI立国宣言」、EUのGDPR(一般データ保護規則)の3つは、一つの水脈でつながっていると思いました。
2018-08-31 17:46
nice!(0)
No.235 - 三角関数を学ぶ理由 [社会]
No.233-4 で新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」の内容を紹介して感想を書いたのですが、引き続いてこの本の感想を書きます。
本書を読んで一番感じたのは「小学校・中学校・高校での勉強は大切だ」ということです。今さらバカバカしい、あたりまえじゃないかと思われそうですが、改めて「勉強は大切」と思ったのが本書を読んだ率直な感想です。それは、AI技術を駆使した東ロボくんの "勉強方法" や 模試の成績と関係しています。また本書で説明されている「リーディング・スキル・テスト」の結果とも関連します。なぜ勉強は大切と思ったのか、その理由を順序だてて書いてみます。
ここでは「勉強」の範囲を、東ロボくんがセンター模試と東大2次試験の模試に挑戦(2016年)した、国語・英語・数学・世界史・日本史・物理の科目とし、小中学校の場合はそれに相当する教科ということにします。もちろん学校での勉強はこれだけではありません。また各種の学校行事や部活も教育の一貫だし、何よりも集団生活をすることによる "学び" が大切でしょう。
以下、小中高校の「勉強」で我々は何を学ぶのか(学んだのか・学ぶべきか)を、何点かあげてみます。
論理的に考える
タイトルを「三角関数を学ぶ理由」としました。三角関数は現状の高校数学では数Ⅲであり、従って大学入試では理系ということになりますが、もちろん三角関数でなくてもいいし、また数学でなくてもかまいません。ただ、説明のしやすさの観点から数学を取り上げ、その例として三角関数から始めます。
下の図ですが、出発点は直角三角形による「三角比の定義」です。直角三角形なので、角度は 0°より大、90°未満です。その三角比を一般化したのが「三角関数の定義」です。角度の単位はラジアンで、その範囲に限定はありません。
三角関数の定義から「加法定理」を導くことができます。下図には加法定理が成り立つ理由の "図形的理解" を書きました。また加法定理からすぐに「和積の公式(和や差を積にする公式)」が導出できます。もちろんこれらは三角関数の定理や公式のごく一部です。
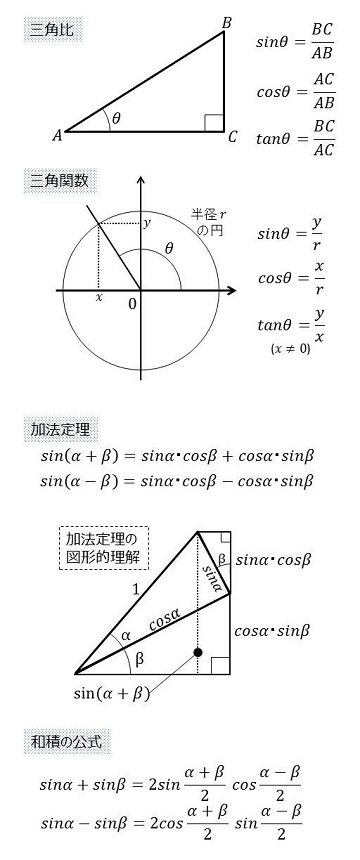 三角関数の微分ですが「sin x の微分が cos x になることを証明しなさい」と言われたらどうするか。下図では「和積の公式」を使って式を変形し、さらに三角関数の定義に立ち帰って sinθ/θ ⇒ 1(θ ⇒ 0)を証明して、sin x の微分が cos x になることの証明に使っています。
三角関数の微分ですが「sin x の微分が cos x になることを証明しなさい」と言われたらどうするか。下図では「和積の公式」を使って式を変形し、さらに三角関数の定義に立ち帰って sinθ/θ ⇒ 1(θ ⇒ 0)を証明して、sin x の微分が cos x になることの証明に使っています。
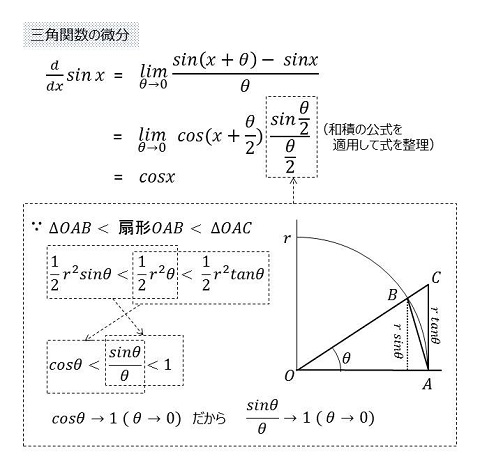 あたりまえですが、最初の定義から定理、公式、微分の証明までが、こうだからこうなるというように論理的にすべてつながっています。そのことを思い出すために、あえてここに書きました。
あたりまえですが、最初の定義から定理、公式、微分の証明までが、こうだからこうなるというように論理的にすべてつながっています。そのことを思い出すために、あえてここに書きました。
我々は社会のさまざまなシーンにおいて「論理的にものごとを考える」必要性が出てきます。人を説得したり自分の意見を主張するにも、"こうだからこうなる" という筋道が通った説明が重要です。ビジネスのシーンでも、分かりやすいプレゼンテーションをするにはスライドに書かれた主張内容の論理的なつながりが必須です。そして「論理的にものごとを考える」ための絶好の訓練になるのが、学校での数学の勉強です。数学は純粋に人間の考え出した論理だけでできているからです。そこが他の学問・勉強と違うところです。
三角関数を見てもわかるように、出発点となる定義(三角比)は大変にシンプルです。それが一般化され(三角関数)、定理が導かれ(加法定理)、そこから別の定理や公式が派生します(和積の公式)。実際に問題を解くときには(微分の証明の例)適用する定理・公式を選択し、ある時にはそもそもの三角関数の定義に立ち返って論理をつなげていくことになります。こういった定義・定理・公式の体系は、幹があり、そこから枝が伸び、その枝に葉がつくという構造になっている。そのような "ひとまとまりの体系" を学ぶことによって、我々は、
というように、段階的かつ論理的に考える訓練を自然にしています。この「原理・原則から始まって枝葉末節まで、階層的に整理された知識体系」は、社会のさまざまなジャンルに出てきます。数学を学ぶということは、そいういう風に頭を働かせる訓練をしていると考えられます。
曖昧に表現された問題を論理的に考える
数学の勉強は「論理的にものごとを考える」絶好の訓練ですが、No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」で紹介した東ロボくんを振り返ってみたいと思います。
東ロボくんは東大2次試験の数学の模試(理系)で、偏差値 77.2 という驚異的な成績をあげました。これは問題文を数式に直訳し "数式処理" の技術で解くという、全く論理だけの処理でこの好成績をとったわけです。世界史や国語、英語などの教科が大量のデータを集めて統計処理で答えるのとは大きな違いです。No.233 で「正確で限定的な語彙からなる問題文であれば、論理的な自然言語処理と数式処理で解ける」としましたが、つまり、純粋な論理だけだとAIやコンピュータが得意なのです。
しかし現実社会や人生で与えられる "問題文" は「正確で限定的な語彙からなる」ものでは決してありません。そこには曖昧性があるし、解くために必要な情報が欠落しているし、また明示されていない "常識" が前提になっています。こういった現実社会の状況は、東ロボくんが最も苦手とするものです。しかし我々人間は、欠落している情報を補い、不足している条件には仮定を置き、あるいは推測を加えて "問題文" を読み解き、論理的に再構成することができる。それこそ人間の価値です。そのとき必要なのは、言葉を操る力に加えて「論理的にものごとを考える」能力です。曖昧性を排除した論理的な "問題文" にしてかつ論理的に答えるためには、それが必須なのです。
論理的思考の訓練のためには、学校における勉強では "論理しかない" 数学が最適でしょう。三角関数はその一つです。また数学における各種のジャンル(方程式、幾何、関数、・・・・・・)は、「論理的に考えることのさまざまな基礎的側面」を表しているのだと思います。
多くの情報を頭に詰め込み、それを自由に引き出せる
数学を離れて他の科目をみると、数学と並んで東ロボくんの得意科目に世界史がありました。No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」で紹介した東大2次試験の世界史の模試は、次のような論述問題でした。
大変に "難しそうな" 問題ですが、東ロボくんはこのような世界史の論述問題で偏差値 61.8 を獲得しました。
この問題の回答文を書くためには、どの時代の設問が出るわからないという前提で、まず世界史のさまざまな知識が頭の中に入っていなければなりません。かつ、それを各種の「引き出し」から取り出せるように整理した形で入れておく必要があります。「引き出し」とは、時代、地域、国、政治、経済、文化などの区分けです。上の問題でいうと
といった条件で知識を引っ張り出し、それを取捨選択して一連のストーリーにまとめ上げなければならない。また「論じなさい」となっているので、歴史上の事実を順に語るだけではなく、たとえばそれが次の時代にどう影響したかなどの「意味」を見つける必要があります。つまり答えるためには明らかに言葉を操る能力と論理的思考が必要です。しかし、その前にまず、
ことが必須なのは明らかです。「頭に中に整理したかたちで」というのは「丸暗記」ではありません。教科書にある歴史記述の内容を理解し、それで得た「知識」を記憶することです。この東大の2次の問題はあくまで大学入試であり、また大学入試の中でも高校3年生にとっては非常に難しい問題でしょう。しかし我々が社会で生きていくことを考えると、
は、さままなシーンで出てきます。今、世界史の話をしましたが、世界史に限らず小中高校の勉強科目には、多かれ少なかれ「暗記」が必要です。子どもたちはさまざまなタイプの「暗記」をすることによって、社会で生きていくための訓練をしていると考えられます。
新井 紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」にあったように、東ロボくんは意味を解しません。意味が理解するのが人間であり、そこにこそ人間の価値があります。しかし現実の人間の活動は、東ロボくんのように「意味を関知しない情報処理」で行っていることが多々あります。センター試験で東ロボくんが "結構当たる(世界史では平均的な受験生以上に当たる)" ように、それで問題ないケースも多い。多忙な現代社会においては、いちいち意味を考えている余裕はありません。もちろん重要な問題、大切な問題、意志決定の必要な問題には、論理的思考とともに "意味" を十分に考えるわけです。だけど「意味を関知しない情報処理」もまた多い。その前提として「知識として暗記する力」が必要です。
学校で履修する科目のうち、特定の科目を「暗記科目」だとして "小馬鹿にする" 子どもがいたとしたら、大変可哀想な子だと思います。
提出された問題の意図を推察できる
東ロボくんが受験した東大2次試験の世界史模試をもう一度考えてみます(上の引用)。ここで「論じなさい」という設問を回答にどう盛り込むかです。考えるべきことは「問題の出題者はどういう意図でこの問題を出したのだろう」ということです。問題出題者が受験生に「論じて欲しい」論点があると考えられます。それはもちろん一つではないし、模範回答があるとしたら複数あるはずです。問題出題者は何を期待しているのか。たとえば上に書いたように、東アジア諸国の貿易が国の政策によって停滞に向かい、それがヨーロッパ諸国との関係において18世紀~19世紀に重要な影響を与えた(=次の時代とのかかわり)というのも、論点の一つでしょう。
センター試験の3択・4択問題のように、答が明白に一つに決まる問題は別です。しかし一般的にテストの問題の中には、問題の意図を推察することが大切なものがあります。こういった「意図の推察」はテストだけでなく、教室での先生の質問に答える場合も同じです。そして「質問の意図を推察する」のは社会においては大変に重要です。
質問や与えられた課題の意図はなにか、それを推察して我々は回答しようとします。たとえば企業において上司から「我が部門のこの10年の売上げと損益を分析した資料を作ってほしい」と言われたとき、それが「大変伸びている」という観点にするのか(対外報告資料など)、伸びが鈍化していて危機感を持つべきだという観点にするのか(部門内資料など)で作り方が全く違ってくるでしょう。同じ数字を使っても内容が違う資料になる。そもそもの課題の意図が何かによります。
出題者(質問者)はどういう回答を欲しいのか、それを推察して答えることを我々は始終やっているし、それは社会人としての重要なスキルです。
言葉の多様な側面を使いこなせる
我々は言葉で思考しています。言葉の多様な側面を使いこなせることが生きていく上で大切です。学校の教科の「国語」は言葉(日本語)の基礎の訓練ですが、その他の科目も(英語以外は)日本語で学習します。国語と数学と歴史の教科書に使われている日本語はずいぶん用語の種類が違うし、言葉の使い方や記述のスタイルが違います。我々はそういった勉強を通して日本語(=自然言語)の多様な側面に触れているのだと考えられます。
一方、数学には数式や図形が頻繁に出てきます。また各種のグラフは数学だけでなくいろいろな教科に出てきます。今後はコンピュータのプログラム言語も出てくるでしょう。こういった、数式、図形、グラフ、プログラムなどは、自然言語を拡張した、いわば "人工の言語" です。自然言語では表しにくい(伝えにくい)事項を簡潔に(かつ厳密に)表現するためのものです。このような人工の言語までを含めて「広い意味での言葉」と考えられるでしょう。
その "言葉" の視点から考えてみると、我々は文字で記される「書き言葉」が「話し言葉」とは違うことを理解しています。文章でしか使わない表現がいっぱいあるからです。それは理解しているものの、我々は暗黙に「会話・発声を正確に記録として残すために文字が出来た」と思っているのではないでしょうか。
しかし文字発祥の歴史はそうではありません。メソポタミアのシュメール人が作った世界最古の文字で書かれた初期の記録は、作物の出来高や徴税記録などの実用文書です。会話・発声では表現できないもの、あるいは表現しにくいものを記そうとしたのが、歴史や神話や物語を記述する以前の文字の発端なのです。
その意味で、現代の学校の学習に出てくる各種の記号、絵文字、グラフ、数式、表、図、図形、プログラムなどは「拡張された言語」といえるでしょう。つまり広い意味での言葉です。我々は学校で「広い意味での言葉」を駆使する能力を学ぶのです。
その具体例をあげると、No.234「教科書が読めない子どもたち」で紹介した「リーディング・スキル・テスト」で「イメージ同定」がありました。文章を読んでその内容を表している図やグラフを答えるものですが、これは東ロボくんが苦手な(というより不可能な)ものでした。「イメージ同定」という基礎的読解力は社会において重要です。それは人にわかりやすく伝えるために的確な図やグラフを作れる能力でもある。図やグラフはさまざまな教科に出てきますが、「イメージ同定」も広い意味での言葉を使いこなすことだと思います。
この「イメージ同定」に限らず、リーディング・スキル・テストは日本語を操る能力のうちの「基礎的読解力」をテストするものでした。その基礎的読解力が子どもたちの「伸びしろ」を決めてしまうと、新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」にありました。ということは「言葉を使いこなす能力が子どもたちの将来を左右する」とも言えるでしょう。
なぜそうすべきか、理由が分からないことに真摯に取り組める
三角関数なんて勉強しても役にたたない、サイン・コサインなんて使い道がない、だから勉強しないという子どもがいたとします。また「入試に出るから仕方なしに勉強している」と思っている子がいたとします。
確かに、高校を卒業して以降は三角関数の使い道は限定的です。大学の理系の学部であれば出てくるし、ものづくり系の企業の設計部門でも必要でしょう。しかしその必要性は、高校生の全体からすると少ないと考えられます。また必要だとしても、高校で習う三角関数の定理・公式などのすべてが必要な訳ではありません。
三角関数はあくまで例ですが、問題は「この勉強は役に立たない、だから学ばない、ないしは適当にやり過ごす」という考え方です。ないしは「自分にとって利益があるか無いかで勉強を判断する態度」です。
この「学ぶべき理由が理解できるものしか学ばない」という考えが、人生において「何かを修得する」ことを阻害し、結局何も修得できないことになるのですね。
大変に逆説的ですが、人生における学習は学んだあと、あるいは学んでからかなりの時間がたってから学ぶべき理由が分かるというタイプが多いのです。その理由は学習に励んで自分を向上させ、その向上した視点で考えないと学ぶべき理由が分からないからです。あるいは学ぶべき理由が分かるようになることが、学ぶことの大きな目標の一つだからです。
人生において学ぶということはそういうことであり、特に人生で "大切な学習" はそうです。三角関数を例にして学ぶことの大切さ(この場合は "論理的にものごとを考える")を言いましたが、それは大人になった立場だからそう言えるのであって、高校生に真に理解してもらうのは大変でしょう。高校生相手に説明することを考えるとそう思います。
まったく別の例を一つあげますと「素読」という教育方法があります。江戸時代以降、戦前までは「漢文の素読」が教育の重要なものでした。素読とは文章(特に名文とされているの)を声をあげて読むことです。文章の意味はひとまず無視し、ただ単純に読みあげる。
東ロボくんは素読はしませんが、これは現在のAI技術で非常に進んでいる分野です。いわゆる「テキスト読み上げ」であり、テキストだけから極めて自然な、人間と見分けがつかない音声を合成できます。
漢文の素読は今はありませんが、最近の学校や塾では素読を取り入れているところがあるようです。夏目漱石の小説や、滝廉太郎の「荒城の月」のような詩を素読させたりしている。小学生だと意味が分からない単語がいろいろ出てくるでしょう。AI技術で完璧にできる素読を小学生にやらせることにどういう効用があるのか。
それは日本語の文章(名文)のリズムを体に染み込ませることだと思います。村上春樹さんは次のよう言っています(No.135「音楽の意外な効用(2)村上春樹」参照)。
リズムとは「言葉の組み合わせ、センテンスの組み合わせ、パラグラフの組み合わせ、均衡と不均衡の組み合わせ、句読点の組み合わせ、トーンの組み合わせ」だと、村上さんは言っています。この発言の主旨は、その大切なリズムを音楽から学んだということですが、それはさておきます。音楽を持ち出す以前に、名文を素読して体に覚え込ませることは、リズムがある読みやすい文章を書くための訓練になるはずです。
別に小説家になるためというのではありません。人生においては「読みやすい文章を書く」ことはその人のスキルとして重要です。村上さんも言っているようにマニュアルブックを書くにも必要だし、そこまでいかなくても文章を書く必要性は社会において多々あります。
小学生を相手に「文章には、前に前にと読み手を送っていく内在的な律動感が重要で、そのために素読をやるのだ」と言ったところで、理解されないでしょう。それは大人になってからしか分からないし、大人になったとしてもそういう意識は全くないかもしれないのです。文章を書くことが身についてしまっている人にとっては ・・・・・・。
なぜそうすべきか、理由が分からないことに真摯に取り組めることは大変重要だと思います。「自分にとって有益だと理解できることを勉強する」のは "あたりまえ" です。「自分にとって有益だと分かっていても勉強しない」のは "怠惰" です。しかし大切なのは「自分にとって有益なことを勉強するのはもちろん、自分にとって有益かどうか分からないことでも勉強する」ことなのです。
社会が要請することに、まじめに取り組める
社会が成り立つためには「社会が要請することに個人がまじめに取り組む」ことが必要です。社会を構成するのは、国から始まって自治体に至る組織、企業、地域のコミュニティー、非営利団体などがありますが、そこには多かれ少なかれ個人に対する要請がある。
もちろん社会が要請しないことに取り組むこともあります。例えば今までに全くなかった仕事を発案し、ベンチャー企業(スタートアップ)やNPO法人を立ち上げるなどがそうです。それは社会の活力を生み、経済を成長させる上でも大変に重要ですが、これも社会の要請にまじめに答えている多数の人たちがバックにいるからこそ成り立つわけです。自分がやりたいことをやるというマインドは大切ですが、全ての人がやりたいことをやったのでは社会が成立しません。
小中高校における勉学は、現代の日本社会が6歳~18歳の子どもたちに要請していることです。なぜ勉強をすべきかはともかく、先生から言われたらまずそれにまじめに取り組む(取り組める)姿勢が大切です。
もちろん社会の要請に従順に従っているだけでは個人の進歩は望めないし、組織も発展しません。しかしまず "従順さ" をもってこなせることが社会の維持と発展には是非とも必要です。
さらに考えてみると小中高校の勉強は、少なくとも日本に生まれた日本国籍の人が "似たような経験をする" ことにこそ意義があるのかもしれません。もちろん学校によって(ないしは、公立か私立かによって)勉強の内容は違う部分があるでしょうが、それらは文科省の学習指導要領に沿っている "似たような勉強" です。また時代によっても勉強内容は変わりますが、何十年と "似たような勉強" をしてきた部分も多いのではないでしょうか。
このことは実は、日本人としてのアイデンティティーを育成するのに役立っていると思います。それは愛国心のあり方などという "高尚な" こと以前の問題です。しょせん現代人は国民国家の枠で生活をしていくのだから、政治信条の違い、地域の違い、年代の違いを超えた、国民としての何かしらの "一体感" が必要です。その一体感は何らかの "認識" や "体験" を共有していることから始まるはずです。小中高校の勉強や学校生活はその "体験" の一つだと思います。
わかりやすい例で言うと、誰もが知っている歌は小学校で習った曲であり、誰もが知っている絵画作品は中学の美術の教科書に出てきた絵、ということがあるのではないか。また多くの人が「京都・奈良へ修学旅行に行った」という共通体験を持っています。これは日本人だけの共通体験なのですね。国語、数学、歴史などの科目も「勉強という共通体験」の意味があると思います。
教育は時代とともに変わることも必要ですが、変わらないこともそれ以上に重要だと思います。50年前と似たような勉強をするということは、祖父母と孫の代が同じ経験をするということです。生活スタイルは50年前とは激変しているにもかわらず、勉強はそう違わない。そこが大変に重要だと思います。そして、こういったことの重要性 = 勉強をすべき理由は、小中高校生の段階では分からなくて当然です。つまり、分からなくても真面目に取り組むべきなのです。
努力を継続できる
もうひとつ、小中高校の勉強で獲得できる(獲得すべき)スキルを言うと、前回(No.234)にも少し書きましたが「努力を継続できる能力」でしょうか。あたりまえですが、テストで良い点を取るためには努力が必要です。やりたいことを我慢し、安易な方向に流れることがないようにし、参考書や問題集に取り組み、それを反復する必要があります。
そういう努力が苦にならないこと、また、努力することの価値や大切さが直感的に理解できることは人生にとって極めて大切でしょう。そういうマインドの醸成に勉強が知らず知らずのうちに役だっている、そう思います。
スターバックスで働くとしたら
唐突ですが「スターバックスで働く」ということと「学校での勉強」の関係を考えてみたいと思います。というのも、今この文章をスターバックスのある店で書いているからです。スターバックスで働きたいと思い、面接に合格し、研修を受け、店舗で働き出すとします。その過程でどういうスキルが必要かを考えてみます。
スターバックスの内情は知らないので(いわゆる "スタバ本" は読んだことがありません)想像で書くと、スターバックスでは接客方法、ドリンクやフードの提供方法、店舗運営などについてのマニュアルがあると想定できます。それはまず重要な心構えから始まって、基本事項から詳細へとブレークダウンされているはずです。接客だけでもシチュエーションはさまざまです。混雑時にどうするか、クレームへの対応、顧客からの要求・要望への対応など、細かいことやスペシャルケースまで、いろいろとあるはずです。どこまで明文化されているかは知りません。明文化されていない各店舗なりのルールがあるのかもしれません。
一つだけ公開されている情報があります。それはスターバックス・ジャパン(正式名:スターバックス コーヒー ジャパン)のホームぺージの「Our Mission and Values」というページです。ここには
という前置きがあって、Our Mission と Our Values が書かれています。その Our Values のところには次のようにあります。
これはスターバックス・ジャパンがどういう「価値」を大切にしているかを宣言した文章です。ちなみに、ここに出てくる「パートナー」は "スタバ用語" というのでしょうか、正社員かアルバイトかにかかわらず「ともに働く仲間」という意味です(協力企業や仕入先の意味ではない)。こういう文章は初めの方に出てくる言葉ほど重要なのが一般的です。特徴的な言葉をピックアップして、かみ砕いて言うと、
などです。ひとつのポイントは初めの方に出てくる "パートナー" でしょうか。また、誰もが(=お客様とパートナーが)自分の居場所と感じられるというところ、いわゆる「第3の場所、サード・プレイス」です。さらに、私たちはこう行動しますという言い方(=行動指針)で大切にしている「価値」を表現しているところもポイントです。
スターバックス・ジャパンが優秀な企業であれば(優秀な企業だと思いますが)、ここで宣言された Our Values がマニュアル(接客・商品提供・店舗運営など)の重要事項と直結しているはずだし、その重要事項にもとづいて細部が展開されているでしょう。スターバックスで働くためのスキルは、まず、そういった一連の情報を知識として短期間に(研修期間中に)修得できるスキルです。そして、店舗においてはマニュアルにそった行動をし、マニュアルに出てこないようなレアな状況に遭遇したときには守るべき心構えに沿って行動し、それでも迷ったら Our Values に立ち返って判断することです。
そういうことができるための基礎的なスキルは、実は、学校における勉強で得られるスキルと非常に似ていると思います。論理的に考えるとか、知識としていつでも引き出せるようにな形で情報を頭に入れるとか、そいういった基礎的なスキルです。Our Values にあるように「現状に満足せず、新しい方法を求める」にしても、まず基礎が必須です。"現状" をきっちりとこなせて初めて "新しい方法" が求められるのだから。
もちろん以上のようなことはスターバックスで働く場合だけでなく、社会のさまざまなシーンに出てくるのは、言うまでもありません。
AIと共存する時代
小中高校での各教科の勉強は、一見、社会で役立たないように見えるものがあるかもしれないけれど、実は我々が社会で一定のポジションをこなしていく上での極めてベーシックなスキルを育成しているのだと思います。そしてここが大切なのですが、小中高校での勉強で得られるものは、東ロボくん(AI)と共存していく必要がある現代人にとって、今まで以上にますます重要になると強く思います。新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」の最大の教訓は、そのことなのでした。
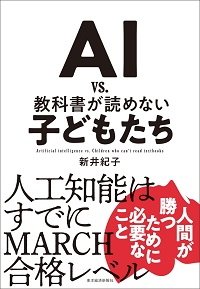
| |||
|
| |||
ここでは「勉強」の範囲を、東ロボくんがセンター模試と東大2次試験の模試に挑戦(2016年)した、国語・英語・数学・世界史・日本史・物理の科目とし、小中学校の場合はそれに相当する教科ということにします。もちろん学校での勉強はこれだけではありません。また各種の学校行事や部活も教育の一貫だし、何よりも集団生活をすることによる "学び" が大切でしょう。
以下、小中高校の「勉強」で我々は何を学ぶのか(学んだのか・学ぶべきか)を、何点かあげてみます。
論理的に考える
タイトルを「三角関数を学ぶ理由」としました。三角関数は現状の高校数学では数Ⅲであり、従って大学入試では理系ということになりますが、もちろん三角関数でなくてもいいし、また数学でなくてもかまいません。ただ、説明のしやすさの観点から数学を取り上げ、その例として三角関数から始めます。
下の図ですが、出発点は直角三角形による「三角比の定義」です。直角三角形なので、角度は 0°より大、90°未満です。その三角比を一般化したのが「三角関数の定義」です。角度の単位はラジアンで、その範囲に限定はありません。
三角関数の定義から「加法定理」を導くことができます。下図には加法定理が成り立つ理由の "図形的理解" を書きました。また加法定理からすぐに「和積の公式(和や差を積にする公式)」が導出できます。もちろんこれらは三角関数の定理や公式のごく一部です。
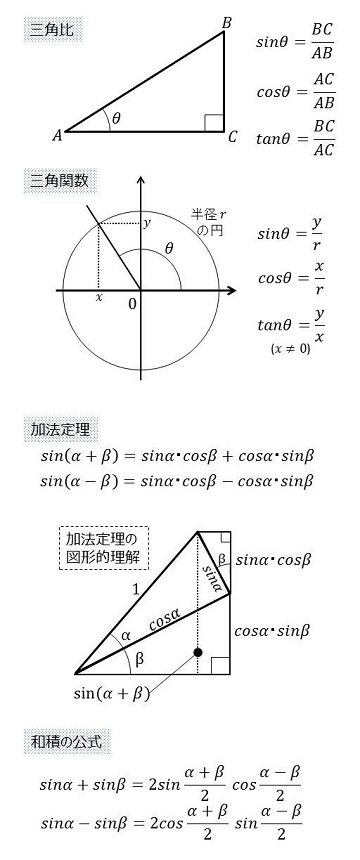
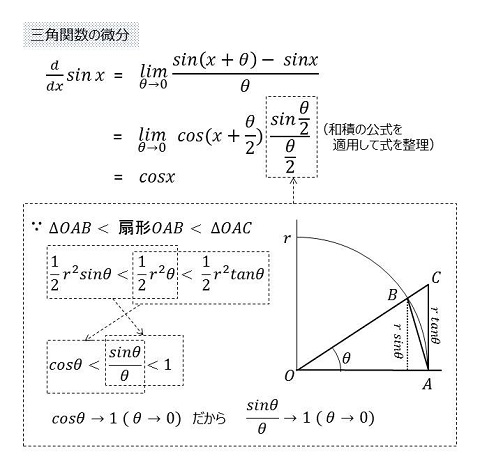
我々は社会のさまざまなシーンにおいて「論理的にものごとを考える」必要性が出てきます。人を説得したり自分の意見を主張するにも、"こうだからこうなる" という筋道が通った説明が重要です。ビジネスのシーンでも、分かりやすいプレゼンテーションをするにはスライドに書かれた主張内容の論理的なつながりが必須です。そして「論理的にものごとを考える」ための絶好の訓練になるのが、学校での数学の勉強です。数学は純粋に人間の考え出した論理だけでできているからです。そこが他の学問・勉強と違うところです。
三角関数を見てもわかるように、出発点となる定義(三角比)は大変にシンプルです。それが一般化され(三角関数)、定理が導かれ(加法定理)、そこから別の定理や公式が派生します(和積の公式)。実際に問題を解くときには(微分の証明の例)適用する定理・公式を選択し、ある時にはそもそもの三角関数の定義に立ち返って論理をつなげていくことになります。こういった定義・定理・公式の体系は、幹があり、そこから枝が伸び、その枝に葉がつくという構造になっている。そのような "ひとまとまりの体系" を学ぶことによって、我々は、
| ◆ | 最も大切なことは何か、根幹は何か | ||
| ◆ | そこから導かれる重要なことは何か | ||
| ◆ | 重要なことから派生して言えることは何か、それが成り立つための前提条件は何か |
というように、段階的かつ論理的に考える訓練を自然にしています。この「原理・原則から始まって枝葉末節まで、階層的に整理された知識体系」は、社会のさまざまなジャンルに出てきます。数学を学ぶということは、そいういう風に頭を働かせる訓練をしていると考えられます。
曖昧に表現された問題を論理的に考える
数学の勉強は「論理的にものごとを考える」絶好の訓練ですが、No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」で紹介した東ロボくんを振り返ってみたいと思います。
東ロボくんは東大2次試験の数学の模試(理系)で、偏差値 77.2 という驚異的な成績をあげました。これは問題文を数式に直訳し "数式処理" の技術で解くという、全く論理だけの処理でこの好成績をとったわけです。世界史や国語、英語などの教科が大量のデータを集めて統計処理で答えるのとは大きな違いです。No.233 で「正確で限定的な語彙からなる問題文であれば、論理的な自然言語処理と数式処理で解ける」としましたが、つまり、純粋な論理だけだとAIやコンピュータが得意なのです。
しかし現実社会や人生で与えられる "問題文" は「正確で限定的な語彙からなる」ものでは決してありません。そこには曖昧性があるし、解くために必要な情報が欠落しているし、また明示されていない "常識" が前提になっています。こういった現実社会の状況は、東ロボくんが最も苦手とするものです。しかし我々人間は、欠落している情報を補い、不足している条件には仮定を置き、あるいは推測を加えて "問題文" を読み解き、論理的に再構成することができる。それこそ人間の価値です。そのとき必要なのは、言葉を操る力に加えて「論理的にものごとを考える」能力です。曖昧性を排除した論理的な "問題文" にしてかつ論理的に答えるためには、それが必須なのです。
論理的思考の訓練のためには、学校における勉強では "論理しかない" 数学が最適でしょう。三角関数はその一つです。また数学における各種のジャンル(方程式、幾何、関数、・・・・・・)は、「論理的に考えることのさまざまな基礎的側面」を表しているのだと思います。
多くの情報を頭に詰め込み、それを自由に引き出せる
数学を離れて他の科目をみると、数学と並んで東ロボくんの得意科目に世界史がありました。No.233「AI vs.教科書が読めない子どもたち」で紹介した東大2次試験の世界史の模試は、次のような論述問題でした。
(東大2次試験:世界史模試) |
大変に "難しそうな" 問題ですが、東ロボくんはこのような世界史の論述問題で偏差値 61.8 を獲得しました。
この問題の回答文を書くためには、どの時代の設問が出るわからないという前提で、まず世界史のさまざまな知識が頭の中に入っていなければなりません。かつ、それを各種の「引き出し」から取り出せるように整理した形で入れておく必要があります。「引き出し」とは、時代、地域、国、政治、経済、文化などの区分けです。上の問題でいうと
| ◆ | 時代(17世紀) | ||
| ◆ | 地域(東アジア、東南アジア) | ||
| ◆ | 国(東アジア、東南アジア、ヨーロッパ諸国) | ||
| ◆ | 経済(海上貿易) | ||
| ◆ | 政治(貿易政策) |
といった条件で知識を引っ張り出し、それを取捨選択して一連のストーリーにまとめ上げなければならない。また「論じなさい」となっているので、歴史上の事実を順に語るだけではなく、たとえばそれが次の時代にどう影響したかなどの「意味」を見つける必要があります。つまり答えるためには明らかに言葉を操る能力と論理的思考が必要です。しかし、その前にまず、
| 歴史上の事項を暗記し、頭に中に整理したかたちで詰め込むことができる。それを各種の引き出しから自在に引き出せる。 |
ことが必須なのは明らかです。「頭に中に整理したかたちで」というのは「丸暗記」ではありません。教科書にある歴史記述の内容を理解し、それで得た「知識」を記憶することです。この東大の2次の問題はあくまで大学入試であり、また大学入試の中でも高校3年生にとっては非常に難しい問題でしょう。しかし我々が社会で生きていくことを考えると、
| それなりに多くの情報を、比較的短期間で頭の中に知識の形で詰め込み、かつ、それを自在に引き出す必要性 |
は、さままなシーンで出てきます。今、世界史の話をしましたが、世界史に限らず小中高校の勉強科目には、多かれ少なかれ「暗記」が必要です。子どもたちはさまざまなタイプの「暗記」をすることによって、社会で生きていくための訓練をしていると考えられます。
新井 紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」にあったように、東ロボくんは意味を解しません。意味が理解するのが人間であり、そこにこそ人間の価値があります。しかし現実の人間の活動は、東ロボくんのように「意味を関知しない情報処理」で行っていることが多々あります。センター試験で東ロボくんが "結構当たる(世界史では平均的な受験生以上に当たる)" ように、それで問題ないケースも多い。多忙な現代社会においては、いちいち意味を考えている余裕はありません。もちろん重要な問題、大切な問題、意志決定の必要な問題には、論理的思考とともに "意味" を十分に考えるわけです。だけど「意味を関知しない情報処理」もまた多い。その前提として「知識として暗記する力」が必要です。
学校で履修する科目のうち、特定の科目を「暗記科目」だとして "小馬鹿にする" 子どもがいたとしたら、大変可哀想な子だと思います。
提出された問題の意図を推察できる
東ロボくんが受験した東大2次試験の世界史模試をもう一度考えてみます(上の引用)。ここで「論じなさい」という設問を回答にどう盛り込むかです。考えるべきことは「問題の出題者はどういう意図でこの問題を出したのだろう」ということです。問題出題者が受験生に「論じて欲しい」論点があると考えられます。それはもちろん一つではないし、模範回答があるとしたら複数あるはずです。問題出題者は何を期待しているのか。たとえば上に書いたように、東アジア諸国の貿易が国の政策によって停滞に向かい、それがヨーロッパ諸国との関係において18世紀~19世紀に重要な影響を与えた(=次の時代とのかかわり)というのも、論点の一つでしょう。
センター試験の3択・4択問題のように、答が明白に一つに決まる問題は別です。しかし一般的にテストの問題の中には、問題の意図を推察することが大切なものがあります。こういった「意図の推察」はテストだけでなく、教室での先生の質問に答える場合も同じです。そして「質問の意図を推察する」のは社会においては大変に重要です。
質問や与えられた課題の意図はなにか、それを推察して我々は回答しようとします。たとえば企業において上司から「我が部門のこの10年の売上げと損益を分析した資料を作ってほしい」と言われたとき、それが「大変伸びている」という観点にするのか(対外報告資料など)、伸びが鈍化していて危機感を持つべきだという観点にするのか(部門内資料など)で作り方が全く違ってくるでしょう。同じ数字を使っても内容が違う資料になる。そもそもの課題の意図が何かによります。
出題者(質問者)はどういう回答を欲しいのか、それを推察して答えることを我々は始終やっているし、それは社会人としての重要なスキルです。
言葉の多様な側面を使いこなせる
我々は言葉で思考しています。言葉の多様な側面を使いこなせることが生きていく上で大切です。学校の教科の「国語」は言葉(日本語)の基礎の訓練ですが、その他の科目も(英語以外は)日本語で学習します。国語と数学と歴史の教科書に使われている日本語はずいぶん用語の種類が違うし、言葉の使い方や記述のスタイルが違います。我々はそういった勉強を通して日本語(=自然言語)の多様な側面に触れているのだと考えられます。
一方、数学には数式や図形が頻繁に出てきます。また各種のグラフは数学だけでなくいろいろな教科に出てきます。今後はコンピュータのプログラム言語も出てくるでしょう。こういった、数式、図形、グラフ、プログラムなどは、自然言語を拡張した、いわば "人工の言語" です。自然言語では表しにくい(伝えにくい)事項を簡潔に(かつ厳密に)表現するためのものです。このような人工の言語までを含めて「広い意味での言葉」と考えられるでしょう。
その "言葉" の視点から考えてみると、我々は文字で記される「書き言葉」が「話し言葉」とは違うことを理解しています。文章でしか使わない表現がいっぱいあるからです。それは理解しているものの、我々は暗黙に「会話・発声を正確に記録として残すために文字が出来た」と思っているのではないでしょうか。
しかし文字発祥の歴史はそうではありません。メソポタミアのシュメール人が作った世界最古の文字で書かれた初期の記録は、作物の出来高や徴税記録などの実用文書です。会話・発声では表現できないもの、あるいは表現しにくいものを記そうとしたのが、歴史や神話や物語を記述する以前の文字の発端なのです。
その意味で、現代の学校の学習に出てくる各種の記号、絵文字、グラフ、数式、表、図、図形、プログラムなどは「拡張された言語」といえるでしょう。つまり広い意味での言葉です。我々は学校で「広い意味での言葉」を駆使する能力を学ぶのです。
その具体例をあげると、No.234「教科書が読めない子どもたち」で紹介した「リーディング・スキル・テスト」で「イメージ同定」がありました。文章を読んでその内容を表している図やグラフを答えるものですが、これは東ロボくんが苦手な(というより不可能な)ものでした。「イメージ同定」という基礎的読解力は社会において重要です。それは人にわかりやすく伝えるために的確な図やグラフを作れる能力でもある。図やグラフはさまざまな教科に出てきますが、「イメージ同定」も広い意味での言葉を使いこなすことだと思います。
この「イメージ同定」に限らず、リーディング・スキル・テストは日本語を操る能力のうちの「基礎的読解力」をテストするものでした。その基礎的読解力が子どもたちの「伸びしろ」を決めてしまうと、新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」にありました。ということは「言葉を使いこなす能力が子どもたちの将来を左右する」とも言えるでしょう。
なぜそうすべきか、理由が分からないことに真摯に取り組める
三角関数なんて勉強しても役にたたない、サイン・コサインなんて使い道がない、だから勉強しないという子どもがいたとします。また「入試に出るから仕方なしに勉強している」と思っている子がいたとします。
確かに、高校を卒業して以降は三角関数の使い道は限定的です。大学の理系の学部であれば出てくるし、ものづくり系の企業の設計部門でも必要でしょう。しかしその必要性は、高校生の全体からすると少ないと考えられます。また必要だとしても、高校で習う三角関数の定理・公式などのすべてが必要な訳ではありません。
三角関数はあくまで例ですが、問題は「この勉強は役に立たない、だから学ばない、ないしは適当にやり過ごす」という考え方です。ないしは「自分にとって利益があるか無いかで勉強を判断する態度」です。
この「学ぶべき理由が理解できるものしか学ばない」という考えが、人生において「何かを修得する」ことを阻害し、結局何も修得できないことになるのですね。
大変に逆説的ですが、人生における学習は学んだあと、あるいは学んでからかなりの時間がたってから学ぶべき理由が分かるというタイプが多いのです。その理由は学習に励んで自分を向上させ、その向上した視点で考えないと学ぶべき理由が分からないからです。あるいは学ぶべき理由が分かるようになることが、学ぶことの大きな目標の一つだからです。
人生において学ぶということはそういうことであり、特に人生で "大切な学習" はそうです。三角関数を例にして学ぶことの大切さ(この場合は "論理的にものごとを考える")を言いましたが、それは大人になった立場だからそう言えるのであって、高校生に真に理解してもらうのは大変でしょう。高校生相手に説明することを考えるとそう思います。
まったく別の例を一つあげますと「素読」という教育方法があります。江戸時代以降、戦前までは「漢文の素読」が教育の重要なものでした。素読とは文章(特に名文とされているの)を声をあげて読むことです。文章の意味はひとまず無視し、ただ単純に読みあげる。
東ロボくんは素読はしませんが、これは現在のAI技術で非常に進んでいる分野です。いわゆる「テキスト読み上げ」であり、テキストだけから極めて自然な、人間と見分けがつかない音声を合成できます。
漢文の素読は今はありませんが、最近の学校や塾では素読を取り入れているところがあるようです。夏目漱石の小説や、滝廉太郎の「荒城の月」のような詩を素読させたりしている。小学生だと意味が分からない単語がいろいろ出てくるでしょう。AI技術で完璧にできる素読を小学生にやらせることにどういう効用があるのか。
それは日本語の文章(名文)のリズムを体に染み込ませることだと思います。村上春樹さんは次のよう言っています(No.135「音楽の意外な効用(2)村上春樹」参照)。
[村上春樹] |
リズムとは「言葉の組み合わせ、センテンスの組み合わせ、パラグラフの組み合わせ、均衡と不均衡の組み合わせ、句読点の組み合わせ、トーンの組み合わせ」だと、村上さんは言っています。この発言の主旨は、その大切なリズムを音楽から学んだということですが、それはさておきます。音楽を持ち出す以前に、名文を素読して体に覚え込ませることは、リズムがある読みやすい文章を書くための訓練になるはずです。
別に小説家になるためというのではありません。人生においては「読みやすい文章を書く」ことはその人のスキルとして重要です。村上さんも言っているようにマニュアルブックを書くにも必要だし、そこまでいかなくても文章を書く必要性は社会において多々あります。
小学生を相手に「文章には、前に前にと読み手を送っていく内在的な律動感が重要で、そのために素読をやるのだ」と言ったところで、理解されないでしょう。それは大人になってからしか分からないし、大人になったとしてもそういう意識は全くないかもしれないのです。文章を書くことが身についてしまっている人にとっては ・・・・・・。
なぜそうすべきか、理由が分からないことに真摯に取り組めることは大変重要だと思います。「自分にとって有益だと理解できることを勉強する」のは "あたりまえ" です。「自分にとって有益だと分かっていても勉強しない」のは "怠惰" です。しかし大切なのは「自分にとって有益なことを勉強するのはもちろん、自分にとって有益かどうか分からないことでも勉強する」ことなのです。
社会が要請することに、まじめに取り組める
社会が成り立つためには「社会が要請することに個人がまじめに取り組む」ことが必要です。社会を構成するのは、国から始まって自治体に至る組織、企業、地域のコミュニティー、非営利団体などがありますが、そこには多かれ少なかれ個人に対する要請がある。
もちろん社会が要請しないことに取り組むこともあります。例えば今までに全くなかった仕事を発案し、ベンチャー企業(スタートアップ)やNPO法人を立ち上げるなどがそうです。それは社会の活力を生み、経済を成長させる上でも大変に重要ですが、これも社会の要請にまじめに答えている多数の人たちがバックにいるからこそ成り立つわけです。自分がやりたいことをやるというマインドは大切ですが、全ての人がやりたいことをやったのでは社会が成立しません。
小中高校における勉学は、現代の日本社会が6歳~18歳の子どもたちに要請していることです。なぜ勉強をすべきかはともかく、先生から言われたらまずそれにまじめに取り組む(取り組める)姿勢が大切です。
もちろん社会の要請に従順に従っているだけでは個人の進歩は望めないし、組織も発展しません。しかしまず "従順さ" をもってこなせることが社会の維持と発展には是非とも必要です。
さらに考えてみると小中高校の勉強は、少なくとも日本に生まれた日本国籍の人が "似たような経験をする" ことにこそ意義があるのかもしれません。もちろん学校によって(ないしは、公立か私立かによって)勉強の内容は違う部分があるでしょうが、それらは文科省の学習指導要領に沿っている "似たような勉強" です。また時代によっても勉強内容は変わりますが、何十年と "似たような勉強" をしてきた部分も多いのではないでしょうか。
このことは実は、日本人としてのアイデンティティーを育成するのに役立っていると思います。それは愛国心のあり方などという "高尚な" こと以前の問題です。しょせん現代人は国民国家の枠で生活をしていくのだから、政治信条の違い、地域の違い、年代の違いを超えた、国民としての何かしらの "一体感" が必要です。その一体感は何らかの "認識" や "体験" を共有していることから始まるはずです。小中高校の勉強や学校生活はその "体験" の一つだと思います。
わかりやすい例で言うと、誰もが知っている歌は小学校で習った曲であり、誰もが知っている絵画作品は中学の美術の教科書に出てきた絵、ということがあるのではないか。また多くの人が「京都・奈良へ修学旅行に行った」という共通体験を持っています。これは日本人だけの共通体験なのですね。国語、数学、歴史などの科目も「勉強という共通体験」の意味があると思います。
教育は時代とともに変わることも必要ですが、変わらないこともそれ以上に重要だと思います。50年前と似たような勉強をするということは、祖父母と孫の代が同じ経験をするということです。生活スタイルは50年前とは激変しているにもかわらず、勉強はそう違わない。そこが大変に重要だと思います。そして、こういったことの重要性 = 勉強をすべき理由は、小中高校生の段階では分からなくて当然です。つまり、分からなくても真面目に取り組むべきなのです。
努力を継続できる
もうひとつ、小中高校の勉強で獲得できる(獲得すべき)スキルを言うと、前回(No.234)にも少し書きましたが「努力を継続できる能力」でしょうか。あたりまえですが、テストで良い点を取るためには努力が必要です。やりたいことを我慢し、安易な方向に流れることがないようにし、参考書や問題集に取り組み、それを反復する必要があります。
そういう努力が苦にならないこと、また、努力することの価値や大切さが直感的に理解できることは人生にとって極めて大切でしょう。そういうマインドの醸成に勉強が知らず知らずのうちに役だっている、そう思います。
スターバックスで働くとしたら
唐突ですが「スターバックスで働く」ということと「学校での勉強」の関係を考えてみたいと思います。というのも、今この文章をスターバックスのある店で書いているからです。スターバックスで働きたいと思い、面接に合格し、研修を受け、店舗で働き出すとします。その過程でどういうスキルが必要かを考えてみます。
スターバックスの内情は知らないので(いわゆる "スタバ本" は読んだことがありません)想像で書くと、スターバックスでは接客方法、ドリンクやフードの提供方法、店舗運営などについてのマニュアルがあると想定できます。それはまず重要な心構えから始まって、基本事項から詳細へとブレークダウンされているはずです。接客だけでもシチュエーションはさまざまです。混雑時にどうするか、クレームへの対応、顧客からの要求・要望への対応など、細かいことやスペシャルケースまで、いろいろとあるはずです。どこまで明文化されているかは知りません。明文化されていない各店舗なりのルールがあるのかもしれません。
一つだけ公開されている情報があります。それはスターバックス・ジャパン(正式名:スターバックス コーヒー ジャパン)のホームぺージの「Our Mission and Values」というページです。ここには
| すべてのお客様へ最高のスターバックス体験(感動体験)を提供できるように行動指針を定め、日々体現しています |
という前置きがあって、Our Mission と Our Values が書かれています。その Our Values のところには次のようにあります。
|
これはスターバックス・ジャパンがどういう「価値」を大切にしているかを宣言した文章です。ちなみに、ここに出てくる「パートナー」は "スタバ用語" というのでしょうか、正社員かアルバイトかにかかわらず「ともに働く仲間」という意味です(協力企業や仕入先の意味ではない)。こういう文章は初めの方に出てくる言葉ほど重要なのが一般的です。特徴的な言葉をピックアップして、かみ砕いて言うと、
| ◆ | 私たちの目的は、お客様へ "スターバックス体験(=感動体験)"を提供することである。 | ||
| ◆ | その中心になるのは、パートナー(ともに働く仲間)とコーヒー(商品、ないしはサービス)、お客様である。 | ||
| ◆ | 誰もが自分の居場所と感じられるような場所を作る。店舗が「自分の居場所」と感じられるような「スターバックス文化」を作る。 |
などです。ひとつのポイントは初めの方に出てくる "パートナー" でしょうか。また、誰もが(=お客様とパートナーが)自分の居場所と感じられるというところ、いわゆる「第3の場所、サード・プレイス」です。さらに、私たちはこう行動しますという言い方(=行動指針)で大切にしている「価値」を表現しているところもポイントです。
スターバックス・ジャパンが優秀な企業であれば(優秀な企業だと思いますが)、ここで宣言された Our Values がマニュアル(接客・商品提供・店舗運営など)の重要事項と直結しているはずだし、その重要事項にもとづいて細部が展開されているでしょう。スターバックスで働くためのスキルは、まず、そういった一連の情報を知識として短期間に(研修期間中に)修得できるスキルです。そして、店舗においてはマニュアルにそった行動をし、マニュアルに出てこないようなレアな状況に遭遇したときには守るべき心構えに沿って行動し、それでも迷ったら Our Values に立ち返って判断することです。
そういうことができるための基礎的なスキルは、実は、学校における勉強で得られるスキルと非常に似ていると思います。論理的に考えるとか、知識としていつでも引き出せるようにな形で情報を頭に入れるとか、そいういった基礎的なスキルです。Our Values にあるように「現状に満足せず、新しい方法を求める」にしても、まず基礎が必須です。"現状" をきっちりとこなせて初めて "新しい方法" が求められるのだから。
もちろん以上のようなことはスターバックスで働く場合だけでなく、社会のさまざまなシーンに出てくるのは、言うまでもありません。
AIと共存する時代
小中高校での各教科の勉強は、一見、社会で役立たないように見えるものがあるかもしれないけれど、実は我々が社会で一定のポジションをこなしていく上での極めてベーシックなスキルを育成しているのだと思います。そしてここが大切なのですが、小中高校での勉強で得られるものは、東ロボくん(AI)と共存していく必要がある現代人にとって、今まで以上にますます重要になると強く思います。新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」の最大の教訓は、そのことなのでした。
2018-06-22 19:31
nice!(0)
No.234 - 教科書が読めない子どもたち [社会]
(前回より続く)
前回に引き続き、新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」(以下「本書」)の紹介と感想です。本書は前半と後半に分かれていて、前半のAIの部分を前回紹介しました。今回は後半の「リーティング・スキル・テスト」の部分です。
リーティング・スキル・テストの衝撃
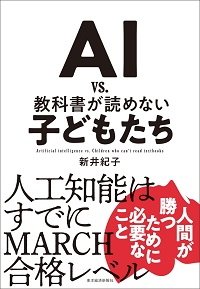
| |||
|
| |||
リーティング・スキル・テスト(RST。Reading Skill Test)は新井教授が主導して行った世界で初めての調査です。RSTとはどんなテストか、本書にその問題が例示してあります。問題は「係り受け」「照応解決」「同義文判定」「推論」「イメージ同定」「具体例同定」の6つのジャンルがあります。それがどういうものか、問題のサンプルを本書から引用します。
| 係り受け |
|
「係り受け」とは、主語と述語の関係、修飾語と被修飾語の関係のように、一つの文の中で単語がどの単語に "係る" か、ある単語がどの単語を "受ける" か、を問うものです。係り受けをAIで判定する研究は進んでいて、80%以上が可能と本書にあります。
| 照応解決 |
|
文章には「これ」「それ」といった指示代名詞、あるいは人称代名詞が出てきます。その代名詞が何を指しているのかを、文をまたがって判断するのが「照応解決」です。日本語の文章でしばしば見られるように、上の文章には指示代名詞がありませんが「(ここには)かつて大量の水があった証拠が見つかっており」と省略されているとし、「ここ」を答える問題と考えると照応解決になります。照応解決は AI の研究が急速に進んでいる分野です。
しかし急速に進んでいるといっても、AIにとって難しい問題であることは変わりません。たとえば、次の2つの文があったとします。
| このハサミは私のペンシルケースに入らない。それが小さ過ぎるからだ。 | |
| このハサミは私のペンシルケースに入らない。それが大き過ぎるからだ。 |
①の「それ」はペンシルケースですが、②の「それ」はハサミです。つまりこの例では「モノの大小」と「入る・入らない」の関係という "知識" をAIに教え込まないと正解できないのです。これはほんの一例であり、このような例が膨大にあることは明白です。
| 同義文判定 |
|
同義文判定はAIではまだまだ難しい問題です。というのも、上の2つの文でも分かるように同義文の問題においては、同じ意味でも異なる意味でも出現する重要な単語がほぼ同じだからです。
そして以下の「推論」「イメージ同定」「具体例同定」は、現在のAI技術では全く歯が立たない問題です。AIは意味を理解せず、また常識をもっていないからです。この3つは「人間がAIに勝てる可能性のある」ジャンルです。
| 推論 |
|
「推論」は文章の構造を理解した上で、生活体験やさまざまな知識を総動員して文の意味を理解する力です。いわば「一を聞いて十を知る」能力であり、現代のAI技術では困難な問題です。「エルブルス山」というのは(ほとんどの)中高生が知らない(であろう)山です。実はエルブルス山は黒海とカスピ海の間にある山で、ロシアの最高峰です。もちろんエベレストより低い。それを知らなくても推論で答えるのがこの問題です。
高校3年ぐらいになると「エルブルス山」が実在の山なのか、それとも架空の山なのかによって答えが違ってくると考えるかもしれません。もし実在の山だと「①正しい」が正解です。しかし架空の山、たとえばファンタジー小説に出てくる山だと問題文だけでは「③判断できない」となる可能性があります。しかしここで「問題を作った側の意図」を推察し、これが1つを選ぶ3択問題だということを考える必要があります。もし「③判断できない」が正解だとすると「引っかけ」問題に近く、基礎的読解力を試す問題ではなくなります。エルブルス山は実在の山だと「推論」でき、「①正しい」が唯一の正解です。
| イメージ同定 |
|
イメージ同定は文章と図やグラフを見比べて、内容が一致しているかどうかを認識する能力です。現在のAI技術では全くできないものです。
| 具体例同定 |
|
具体例同定は、定義を読んでそれと合致する具体例を認識する能力です。定義には国語辞典的な定義と数学的な定義があり、上は数学的な定義の例です。意味を理解しないAIでは全く歯が立たない問題です。
以上の6つのジャンルは、東ロボくんのプロジェクトにおいてAIに読解力をつけるための研究から生まれたものです。また問題に使った文章は、教科書と新聞(科学面や小中学生向けの記事)から採用されました。それが読解できないと人生において明らかに不利になるからです。
問題は各ジャンルで数百問作成され、受検者はパソコンで回答します。問題は各受検者に対してジャンルごとにランダムに表示され、かつ制限時間の間に順に解いていきます。ある受検者は20問解き、ある受検者は5問といった具合です。
問題が妥当かどうかの検証もされました。つまり多数の受検者のデータを集め、ジャンルごとに個々の受検者の「能力値」を6段階で決めます。「能力値が高いほど正解率が高まる」というシンプルな関係になれば、その問題は妥当ということになります。またヤル気がなくていいかげんに答える受検者を判別するしかけ(作問上の工夫や、受検者の回答パターンや回答時間からの推定)もあります。以下に掲げる正答率は、まじめに答えていないと判断された受検者を除いた値です。
テストを受けた人は総計25,000人にのぼりました。その結果は衝撃的です。その問題の例を以下にいくつか上げます。
宗教問題(係り受け)
|
正解はもちろん「②キリスト教」ですが、この問題の正答率は以下のとおりでした。
「宗教問題」の正答率
| 中 学 生 |
中学1年(197名) | 63% |
| 中学2年(223名) | 55% | |
| 中学3年(203名) | 70% | |
| 平均(623名) | 62% | |
| 高 校 生 |
高校1年(428名) | 73% |
| 高校2年(196名) | 73% | |
| 高校3年(121名) | 66% | |
| 平均(745名) | 72% |
この結果の理解について、新井教授は次のように書いています。
|
Alex問題(係り受け)
|
この問題は中学校の英語の教科書の註からとられたものです。もちろん「①Alex」が正しいのですが、その正答率は次の通りでした。
「Alex問題」の正答率
| 中 学 生 |
中学1年(68名) | 23% |
| 中学2年(62名) | 31% | |
| 中学3年(105名) | 51% | |
| 平均(235名) | 38% | |
| 高 校 生 |
高校1年(205名) | 65% |
| 高校2年(150名) | 68% | |
| 高校3年(77名) | 57% | |
| 平均(432名) | 65% |
高校生の3分の1は不正解であり、中学生の正答率は半分を切っています。中学1年生の正答率は23%ですが、この問題は4択なので、あてずっぽうで答えても25%の正答率になります。つまりこの成績は「ランダム並み」「サイコロ並み」ということになります。
なぜこうなるのかが分析されています。つまり受検者の能力値で回答の傾向をみると、能力値の低い子は「④女性」を選ぶ傾向にあります。その理由は「愛称」という言葉の意味が分からず、それを飛ばして読んでいるのだと推測できます。つまり「Alexandra は女性である」は正しい文章だから「女性」と答えてしまう。そういう「読み」の習慣がついてしまっている。
思うのですが、文章をちゃんと読む習慣がついていると、たとえ「愛称」の意味が分からなくても正解できます。「愛称」のところを伏せ字にした問題を作ってみると、
次の文を読みなさい。〇〇にはある同じ言葉が入ります。
|
伏せ字で、かつ選択肢がなくても正解は「Alex」しかありません。たとえ一部の単語の意味が分からなくても、文の構造を理解して大意をつかむというのは、人が社会で生きていくための大変に重要なスキルです。しかしそういった「読み」の習慣がついていないのです。逆にいうと、読解力をつけるための処方箋のヒントがここにあると、新井教授は示唆しています。
この問題は「係り受け」の中でも正答率が低い問題です。「係り受け」全体の正答率は中学生が約70%、高校生が80%です。国語が苦手な東ロボくんは、だいたい高校生程度です。ただし東ロボくんは文の意味を理解しているわけではありません。それでも高校生程度には「当たる」のです。
「少しは背筋に寒気を覚えていただけましたか ?」と、新井教授は書いています。
ポルトガル人問題(同義文判定)
|
答えは当然「異なる」ですが、AIにとっては結構難しい問題です。2つの文に出てくる単語がほぼ同じだからです。では人間の方が優秀かというと残念ながらそうではないのです。ポルトガル人問題の正答率は次の通りです。
「ポルトガル人問題」の正答率
| 中 学 生 |
中学1年(301名) | 56% |
| 中学2年(270名) | 61% | |
| 中学3年(286名) | 55% | |
| 平均(857名) | 57% | |
| 高 校 生 |
高校1年(627名) | 71% |
| 高校2年(360名) | 71% | |
| 高校3年(152名) | 76% | |
| 平均(1,139名) | 71% |
中学生の正答率は 57% しかありません。残りの43%の子どもは「一人で教科書を読んで勉強する」ということが出来ないでしょう。
円の問題(イメージ同定)
|
正解は①(=①だけ)ですが、このようなイメージ同定は、現在のAI技術では全く歯が立たない問題です。しかし人間には簡単なはずです。何も難しいことは聞いていないからです。数学の試験には絶対に出ないような "簡単な問題" です。しかし大変な結果になりました。
「円の問題」の正答率
| 中 学 生 |
中学1年(145名) | 10% |
| 中学2年(199名) | 22% | |
| 中学3年(152名) | 25% | |
| 平均(496名) | 19% | |
| 高 校 生 |
高校1年(181名) | 29% |
| 高校2年(54名) | 30% | |
| 高校3年(42名) | 45% | |
| 平均(277名) | 32% |
この「円の問題」の正答率は他の問題とは傾向が違います。能力値で受検者を6段階に分けたとき、他の問題は能力値が高いほど正答率が上がるのですが、「円の問題」に限っては、能力値の中位(4以下)までは正答率が低いままであり、上位(5と6)になってようやく正答率が上がるのです。本書ではこのタイプの問題を「能力上位層をよく識別する問題」と呼んでいます。
AIが不得意な問題は、人間も不得意
RSTの結果をまとめた最新データが本書に載っています。小学6年から高校2年までのデータですが、その正答率を範囲で示してみたのが下の表です。小学6年が一番低く高校2年が一番高いのが普通ですが、一部に逆転現象もあります(ただし、有意な差ではない)。
| RST問題 | 正答率 |
| 係り受け | 65.1%~81.5% |
| 照応解決 | 58.2%~82.6% |
| 同義文判定 | 62.1%~81.0% |
| 推論 | 57.3%~68.5% |
| イメージ同定 | 30.9%~55.3% |
| 具体例同定(辞書) | 31.0%~46.9% |
| 具体例同定(数学) | 19.6%~45.7% |
この表には注意が必要です。RSTは選択式問題ですが、選択肢の数が問題によって違うからです。たとえば同義文判定は「同じ」「異なる」の2択なので、ランダムに答えても50%の正答率になります。本書にはそれを考慮して「ランダム並みよりましとは言えない受検者のパーセンテージ」示して分析してあるのですが、省略します。本書の分析の結論を要約すると以下になるでしょう。
| ◆ | 表層的な読解力である「係り受け」「照応解決」成績が比較的良い。しかしこの分野ではAIも好成績がとれる。 | ||
| ◆ | AIと差別化しなければならないはずの「同義文判定」「推論」「イメージ同定」「具体例同定」の成績は、中高生も悪い。 |
こういった基礎的読解力は高校卒業までに出来上がります。つまり、RSTでみる限り「AIができないタスクやAIが難しいタスクは、人間にとっても難しい」と予想されるのです。
御三家の教育法は参考にならない
基礎的読解力を測定するRSTの問題は、上に掲げた例題でもわかるように "非常に基礎的な" ものです。こんな問題は中学入試にもまず出ません。従って「基礎的読解力がないよりはある方がいいに決まっているが、そんなに大騒ぎするほどのことでもない」と考える人もいます。しかし、その考えは甘いのです。基礎的読解力と高校の偏差値の相関関係を分析した表が本書に載っています。
|
さらに分析を進めると、高校の基礎的読解力の平均値とその高校の旧帝大進学率に高い相関があることもわかりました。旧帝大とは、東大・京大・東北大・阪大・名大・北大・九大の7つの国立大学です。
|
御三家の中学入試の問題は、新井教授の言う「能力上位層をよく識別する問題」がふんだんに盛り込まれているのでしょう。新井教授は「基礎的読解力が、その子のその後の伸びしろを決める」と書いています。それが人生というレベルでみれば格差を生み、結果として人生を左右するのです。
最近、大学や高校で "アクティブ・ラーニング" の重要性が強調されているそうです。文科省の用語集によると "アクティブ・ラーニング" とは、
| 教員による一方的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習などが含まれるが、教室内でのグループディスカッション、ディベート、グループ・ワークなども有効なアクティブ・ラーニングの方法である。 |
と説明されています。しかし新井教授はこれに疑問を呈しています。教科書を読めない学生・生徒にアクティブ・ラーニングができるはずがない、アクティブ・ラーニングは現場の実態を知らない文部科学省、およびその委託をうけた中央教育審議会の人たちの発案した「絵に描いた餅」だと・・・・・・。
残された課題
新井教授が想定する "暗い未来" は、「仕事はいっぱいあるのに、その仕事をこなせる人間が僅かしかいない」という状況です。本書で繰り返し述べられているように、AIには限界があります。AIでできないことは多い。しかしその「AI ではできない仕事」をできる人間が少なくなっていく。これは労働市場の分断になります。こういった分断は技術革新によってすでに起こっていると思いますが、この傾向をAI技術が強力に加速する。中間層がいなくなると経済原則に従って個人消費が低迷し、"AI不況" に陥ります。
ではどうすればよいのか。どうやったら基礎的読解力はつくのか。新井教授はどのような生活習慣や学習習慣が読解力を育てるのか(逆に損なうのか)、中学の生徒たちに網羅的なアンケート調査をしました。しかし関係ありそうな要因が見つかりません。「読書習慣」「学習時間」「得意科目」「スマホを何時間使うか」「新聞を読むか」「ニュースはどの媒体から知るか」など、どれもが基礎的読解力と相関関係がないのです。小さいころから読書が好きと答えた生徒の読解力が高いわけでもない。
しかし新井教授は "はたと" 思い当たりました。そもそも「宗教問題」や「ポルトガル人問題」に答えられない生徒にアンケート調査をすること自体が無意味だと・・・・・・。
ただ、一つだけ気になる点があります。就学補助をうけている子どもの読解力が低いという、明らかな負の相関があるのです。貧困が読解力にマイナスの影響を与える・・・・・・。これは大きな問題です。
とはいえ、貧困だけが読解力に影響するわけでもないでしょう。何が読解力を決めるのか、それを明らかにするのが今後の課題です。また、たとえ大人になったとしても読解力が向上することを、新井教授は数々の例を引いて説明しています。このあたりの要因と対策が今後の課題です。
「教科書が読めない子どもたち」の感想
以降は新井紀子著「AI vs.教科書が読めない子どもたち」の後半部分、「リーティング・スキル・テスト」の感想です。
新井教授はリーディング・スキル・テスト(RST)を自ら実践するなかで中高校生の読解力不足を指摘したわけですが、これは現場の実態や現場の先生たちの意見と遊離している教育行政のあり方に一石を投じたものと言えるでしょう。本書の「アクティブ・ラーニングは絵に描いた餅」というところでは、いわゆる「ゆとり教育」を思い出しました。
「ゆとり教育」も「アクティブ・ラーニング」も、発想の基本が非常に似ていると思います。つまり「自ら考え、自発的に学ぶことが大切」という考えです。これは一面の真実であることは確かだと思います。間違ってはいない。「発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習」と文科省の資料にありますが、創造性を養う上で大切なことです。
しかし大学生はともかく中高生についていうと「自発的に学ぶ」ためには、それができるだけの基本スキルが身についていることが条件です。そのスキルの重要なポイントが読解力です。教科書、参考書は言うに及ばす、世の中に学ぶための情報、マテリアルが溢れています。読解力さえあれば自発的に学ぶことがいくらでもできる。問題解決学習で議論した結果を自ら検証することもできます。しかし読解力がなければそれが出来ない。まさに「絵に描いた餅」になるのです。
読解力があったとしても、さらに問題があります。「自発的に学ぶための、ゆとりの時間」が与えられたとき、勉強が楽しい一部の子どもは自ら学ぶと思いますが、多くの子どもは "怠ける" のではないでしょうか。怠ける子が悪いというのではなく、人間というのは安易な方向に流れやすいのであって、現実としてそうなっていくと思います。
おそらく日本の教育方針を決めている文科省の官僚や中教審の人たちは、「自発的に学ぶための、ゆとりの時間」が与えられたとしたら、喜々として自分の思うやり方でどんどん勉強するタイプの人たちではないでしょうか。教科書と同じことを繰り返す授業など退屈でしかなく、読めば分かることを授業で聞いても無意味だと思って "内職" に励んだのではないでしょうか。"分かる" からおもしろいし、おもしろいから努力を重ねてテストでよい点数を取ろうとする。
新井教授は「"御三家" と呼ばれるような超有名私立中高一貫校の教育方針は、教育改革をする上で何の参考にもならない」と書いています。「御三家」は、どちらかと言うと "自由放任主義" で知られていますね。かつ学校行事も多いようです。
御三家だけではありません。私の知っている神奈川県の県立高校は県下でもトップクラスの進学校ですが、学校行事が多いことで有名です。縄跳び大会やマラソン大会、合唱コンクールなど、伝統の行事が目白押しで、3年生が仕切る秋の体育祭まで続く。授業を受け、部活をし、そのうえ各種行事の練習までして息つく暇もない。いったいいつ勉強するのかと思うほどですが、それでいて国立難関大学や難関私立大への進学が多いわけです。結局、生徒たちは時間を作り出し、努力を重ねて勉強をし、3年生は体育祭が終わったら一心不乱に猛勉強をする。そういうことが出来る子が集まっているのですね。
日本の教育行政を指導している人たちも、おそらくそういった中高生の時代を過ごしたのではないでしょうか。だから「自発的に勉強できるゆとりの時間を与えると子どもたちは伸びる」と考えるわけです。なぜなら自分がそうだったから。
しかし現実はそういう子ばかりではありません。"ゆとり" を与えられると勉強しない子が少なからずいるだろうし、勉強しようと思っても基礎的読解力がなければ進みません。結局のところ「ゆとり」とか「アクティブ」という考え方は子どもたちを選別し、社会を分断していく方向に働くはずです。本書で公表されている RST の結果は、そのことを明確にしていると思いました。
本書を読んでいて非常に気になったは、RSTで明らかにされた中高生の読解力が「昔からそうだった」のか「近年、低下してきている」のか、ということです。直感的には、こういった極めて基礎的なスキルは「昔からそうだった」のではと思います。
基礎的読解力は何で差がつくのか、また、向上させるのはどうしたらよいのか。本書では「今後の課題」となっているのですが、こういう問題を考えるときにまず考慮すべきは遺伝の影響です。No.191「パーソナリティを決めるもの」で書いたように、行動遺伝学の知見から言うと一般知能(IQ)の遺伝率は10代で 0.6 程度です。つまり一般知能(IQ)の60%程度は「もって生まれたもの」で説明できるわけです。
基礎的読解力が一般知能(IQ)と同様かどうかは分かりません。しかし遺伝の影響があると強く推測できる証拠があります。ディスレクシアという症状の存在です。ディスレクシアは「難読症」「識字障害」とも言われ、本人の知性や聞く・話す能力は全く問題がないのに、読み書きができなかったり、読んで理解するのに大変苦労したりする症状です。俳優のトム・クルーズがディスレクシアだと自ら公表して有名になりました。Wikipedia によると、俳優ではキアヌ・リーブスもディスレクシアだと公表したそうです。また映画つながりで言うと、スティーヴン・スピルバーグ監督もディスレクシアであり、そのため小学校の卒業が2年も遅れ、今でも脚本を読むのに人の2倍の時間がかかるそうです。
ディスレクシアは遺伝性であることが知られています。またディスレクシアといっても重度のものからごく軽いものまでがあるようで、その軽いディスレクシアの子どもが周囲から気付かれることがなく「基礎的読解力がない」と判定されていることが考えられます。新井教授は RST が「読み障害」のある子を発見するツールとなってくれればと言っていますが、そういう子どもを早期に発見し、科学的なケアをすることが望まれると思いました。
もちろん基礎的読解力は遺伝だけで決まるのではなく、それ以外の本人の性格とか環境の影響もあるはずです。本書にも基礎的読解力が大人になっても向上した例が出てきます。では何が基礎的読解力を決めるのか。
それは個人的には「集中力」だと思います。数分でも数10分でも "あること" に集中し、没頭できる。休憩をとりながらであれば数時間でも没頭できる。そういった資質が大切なのではと思います。RSTの問題の一文を読解するのは数秒~10秒前後だと思いますが、集中して "深く" ものごとに当たれる能力が影響するのではと直感的に思います。
もう一つ付け加えると「努力を継続できる力」でしょうか。努力することの価値が直感的にわかる子ども、先生から(ないしは親から)言われれば、まずその実現を目指して素直に努力する子ども、そういった子の基礎的読解力が向上し、伸びていくと感じます。
とにかく新井教授が本書で書いているように、基礎的読解力に差がつく原因や、その改善策は今後の課題です。次の著書ではその処方箋の1つでも2つでも提示したいと、本書にありました。おそらく実証研究に基づく処方箋になるはずです。新井教授の次作に期待したいと思います。
(次回に続く)
2018-06-08 19:37
nice!(0)
No.218 - 農薬と遺伝子組み換え作物 [社会]
No.102-103「遺伝子組み換え作物のインパクト」で、農薬と遺伝子組み換え作物(=GM作物)の関係について書いたのですが、その続編です。前回は、新たな除草剤の使用がそれに耐性をもつ "スーパー雑草" を生み出す経緯でしたが、そのスーパー雑草に対抗する除草剤の話です。
農薬とGM作物を使った農業
まず、No.102-103「遺伝子組み換え作物のインパクト」の復習です。アメリカで始まった「農薬と遺伝子組み換え作物(GM作物)をペアにした農業」は次のような経緯をたどってきました。
この第1段階は、長年にわたって行われている農薬開発のひとコマです。農薬は除草剤だけでなく病害虫の駆除や植物の成長促進など、各種の目的のものが開発されてきました。しかし次の第2段階で話は大きく変わりました。
遺伝子組み換え作物と除草剤の組み合わせは、農業のあり方を変える "革新" です。ゲームのルールを変えるに等しいわけで、農家としては新しいルールに従わないとゲームに参加できなくなります。しかしこの新ルールには弊害もあります。それは2000年代になって顕著になってきました。
除草剤・ジカンバと、ジカンバ耐性作物
No.102「遺伝子組み換え作物のインパクト」で引用した日経サイエンスの記事(2011.8)に「モンサント社は他の除草剤に対する耐性をもったGM作物を売り出す計画」とありました。この "他の除草剤" としてモンサント社が目をつけたのが "ジカンバ" という化学物質です。日経産業新聞の2017年10月4日付に、このジカンバについての記事があったので以下に紹介します。
補足しますと、ジカンバは広葉植物を枯らす化学物質で、トウモロコシや麦類などのイネ科植物は枯れません。従ってそれらの畑では除草剤として使われています。日本の農水省もトウモロコシや麦類についての残留ジカンバの規制値を決めています。しかし大豆、綿、ナタネなどの広葉植物の畑では使えなかった。ところがモンサントが開発したジカンバ耐性種子を植え付けると、大豆畑や綿花畑でもジカンバを除草剤として使えます。グリホサート耐性をもつスーパー雑草も駆除できる。ここがポイントです。
ジカンバによる被害報告が相次ぐ
引用した日経産業新聞の記事は、実はジカンバによる農作物被害をレポートするのが主眼でした。その被害の状況を記事の見出しとともに引用します。
ジカンバとジカンバ耐性作物の広がり
上の引用でもわかるように「農薬と農薬耐性作物による農業」は次の段階に入ってきました。つまりジカンバによる農作物被害が広がるほどに、ジカンバが広く使われ出したわけです。
ジカンバは揮発性が高く、空気中を飛散して意図しない農作物を枯らす危険性があることは以前から分かっていました。いわゆる「ドリフト」による被害です。従ってEPAも各州当局もモンサント社も、ジカンバを耐性大豆や耐性綿花の畑に用いるための規制・指導を行ったようです。つまり畑のまわりに緩衝帯を設けるとか、風速15メートル以上では使用禁止とか、飛行機による空中散布禁止といったたぐいの規制です。推測するに、規制どおりにジカンバを使えば問題はほぼ起こらないのでしょう。モンサント社もそのことを確認する実験をやったと思われます。
しかしこういった規制のとおりにすると農家にとっては労力やコストがかさみます。自家農地の耐性大豆・耐性綿花がジカンバで枯れないと分かっている以上、できるだけ労力が少ない方法で散布したいと農家が思ったとしても不思議ではありません。そもそも「ジカンバとジカンバ耐性作物の組み合わせ」は農業のコスト削減のために開発されたものなのです。ジカンバによる作物被害の責任は、第1義的には「不適切使用をした農家」でしょうが、そこに暗黙に誘導したのはモンサント社と認可した規制当局だと思います。だからこそ、被害を前にしていくつかの州当局は一時的禁止、ないしはその継続を検討している。とにかく、除草剤と耐性作物による農業は、
の段階になってきました。そして確実に予期できることは、その次の第5段階があるということです。つまり、
です。大豆農家・綿花農家が使う除草剤として、グリホサートもジカンバも意味がなくなる日がくるのは確実でしょう。
スーパー雑草の出現は "ビジネスチャンス"
そもそも、除草剤を使うとそれに耐性を持つ植物が(遅かれ早かれ)出現するのは農業関係者の常識です。これは抗生物質の使用と耐性菌の出現の関係と同じです。そういう風に自然はできている。モンサント社もそれを先刻承知のはずで、ジカンバ耐性雑草の出現を予測し、新たな除草剤とそれに耐性をもつ作物の開発に余念がないと想像します。数種の候補を同時並行的に研究しているかもしれない。
この状況は、いわゆる "イタチごっご" です。そしてこの "イタチごっご" はモンサントのようなバイオ化学企業にとってのビジネスチャンスになります。永続的に続くと考えられる "イタチごっご" だからこそ、ビジネスの機会も永続的に続く。もしスーパー雑草が出現しないとモンサント社は困ったことになります。グリホサートだけで雑草管理が永続的に可能なら、グリホサート耐性作物の特許はいずれ切れるので、モンサント社は独占的地位を保てなくなります。農家もモンサント社だけに種子を頼る必要がなくなる。現にグリホサートの特許はすでに切れていて、同一成分をもつ "ジェネリック除草剤" が出回っています。
しかしバイオ化学企業にとって、新たなスーパー雑草が出現しないという心配をする必要はないのです。自然のメカニズムは耐性植物・耐性菌が出現するようにできているのだから・・・・・・。バイオ化学企業は "自作自演" のイタチごっこを演出し、除草剤ビジネスのネタが尽きることが無いように農業を誘導しているというわけです。
もちろんバイオ化学企業にとってのリスクもあります。新たな農薬とそれに耐性がある作物を作り出せなかったら "アウト" だからです(少なくとも除草剤の分野では)。他社に負けると競争に生き残れません。従ってますます研究開発への投資が必要になります。この状況はバイオ化学企業の寡占化・巨大化を促進すると考えられます。巨大研究投資に耐えられる企業が生き残るわけです。
また「除草剤と耐性作物のペアによる農業」が進展していくと、農家は巨大バイオ化学企業への依存度をますます高めることになるでしょう。イタチごっこに巻き込まれた農家は、独占的地位にある企業の手足となって(= 隷属して)農地を耕作するだけの存在になっていくと考えられます。
食料に低コストだけを求める愚
グリホサートやジカンバに耐性をもつ作物は、遺伝子組み換え技術で作り出されたGM作物です。そのGM作物の中には人類にとってメリットが多い(デメリットはほとんどない)と考えられるものがあります。たとえば耐乾燥性のGM作物は干魃被害が深刻な地域の食料生産を増大させ、乳幼児の死亡率を低下させるかもしれない。そういったことが考えられます。
しかし「除草剤と除草剤耐性GM作物をペアにした農業」の主眼は農業コストの削減です。そして食料や食品に低コストだけを求めるのは愚の骨頂です。食品の安全、自然環境や生態系の保全、食料資源の持続可能性など、コスト以外の(コストよりもっと大切な)考慮点がいっぱいあるからです。
アメリカはTPP(環太平洋経済連携協定)から離脱し、今後は日本を始めとする各国とのFTA(自由貿易協定)を目指すそうです。FTAの農業分野でGM作物が交渉項目になるかどうか分かりませんが、日本としては上に引用したようなアメリカ農業の実態を詳細に把握してから交渉に望むべきでしょう。
ジカンバの新聞記事を読んでふと思ったことがあります。日本での農業の一つの例ですが、島根県の奥出雲地方、仁多郡で作られる「仁多米」は「東の魚沼・西の仁多」と言われるほどコシヒカリの有名ブランドです。この地方では無農薬・有機栽培が進んでいます。地元の畜産農家と協力して有機肥料も確保をしている(いわゆる循環型農業)。そのため、この地域には絶滅危惧種(メダカ、タガメなど)や準絶滅危惧種(トノサマガエルなど)が多く生息しています。
このような例は仁多だけではないし、また日本だけでもありません。世界には「アメリカ発の、除草剤と除草剤耐性GM作物をペアにした農業」とは全くの対極にある農業が厳然としてあり、それが高い評価を受けていることを忘れてはいけないと思います。
| GMは Genetically Modified(=遺伝子組み替えされた)の略。 |
農薬とGM作物を使った農業
まず、No.102-103「遺伝子組み換え作物のインパクト」の復習です。アメリカで始まった「農薬と遺伝子組み換え作物(GM作物)をペアにした農業」は次のような経緯をたどってきました。
| 第1段階:除草剤 "グリホサート" の開発 |
| ◆ | 1970年にアメリカの農薬会社・モンサントは除草に使う "グリホサート" という化学物質を開発し、これを「ランウンドアップ」という商品名で売り出した。 | ||
| ◆ | グリホサートは植物の葉に直接散布することによってすべての植物を枯らす効果を発揮する。除草剤というより、強力な "除植物剤" である。 | ||
| ◆ | すべての植物を枯らすため、グリホサートが使えるのは作物の芽が出る前である。作物の芽が出る前に生えてきた雑草に対してグリホサートをあたり一面に散布することで雑草を駆除できる。 | ||
| ◆ | 作物が成長したあとでは「あたり一面に散布」はできない。畑に分け入って人手で雑草を取ったり、他の除草剤を使う必要がある。 |
この第1段階は、長年にわたって行われている農薬開発のひとコマです。農薬は除草剤だけでなく病害虫の駆除や植物の成長促進など、各種の目的のものが開発されてきました。しかし次の第2段階で話は大きく変わりました。
| 第2段階:グリホサート耐性作物の開発 |
| ◆ | 1996年、モンサント社は遺伝子組み換え技術を使ってグリホサート耐性をもつ大豆(= グリホサートを散布しても枯れない大豆)を開発し、「ランウンドアップ・レディ」という商品名で発売した。その後、グリホサート耐性をもつ綿、ナタネ、トウモロコシも発売した。 | ||
| ◆ | グリホサート耐性大豆は農家の雑草管理のあり方を一変させた。農家としてはグリホサート耐性大豆を植え、その芽が出る前でも芽が出た後でもグリホサートを散布すればよい。グリホサート耐性大豆だけが生き残り、雑草を駆除できる。飛行機からグリホサートを散布するような手段も使えるため、雑草管理の手間は圧倒的に少なくなり、コストは削減された。 | ||
| ◆ | その反面、グリホサート耐性大豆(GM作物)とグリホサート(除草剤)の組み合わせは、農業を「単一農薬の広範囲使用」に誘導した。 |
遺伝子組み換え作物と除草剤の組み合わせは、農業のあり方を変える "革新" です。ゲームのルールを変えるに等しいわけで、農家としては新しいルールに従わないとゲームに参加できなくなります。しかしこの新ルールには弊害もあります。それは2000年代になって顕著になってきました。
| 第3段階:スーパー雑草の出現 |
| ◆ | 2000年代に入って米国では "スーパー雑草" が蔓延しはじめた。スーパー雑草とはグリホサート耐性をもつ(=グリホサートを散布しても枯れない)雑草である。 | ||
| ◆ | スーパー雑草には極めて繁殖力の強いものがあり、大豆や綿、トウモロコシの畑にはびこり出した。農家の中には人海戦術で雑草を除去したり、畑を放棄するものも出ている。 | ||
| ◆ | スーパー雑草に対抗するため、モンサント社は他の除草剤に対する耐性をもったGM作物を売り出す計画である(『日経サイエンス』2011.8 の記事) |
除草剤・ジカンバと、ジカンバ耐性作物
No.102「遺伝子組み換え作物のインパクト」で引用した日経サイエンスの記事(2011.8)に「モンサント社は他の除草剤に対する耐性をもったGM作物を売り出す計画」とありました。この "他の除草剤" としてモンサント社が目をつけたのが "ジカンバ" という化学物質です。日経産業新聞の2017年10月4日付に、このジカンバについての記事があったので以下に紹介します。
|
補足しますと、ジカンバは広葉植物を枯らす化学物質で、トウモロコシや麦類などのイネ科植物は枯れません。従ってそれらの畑では除草剤として使われています。日本の農水省もトウモロコシや麦類についての残留ジカンバの規制値を決めています。しかし大豆、綿、ナタネなどの広葉植物の畑では使えなかった。ところがモンサントが開発したジカンバ耐性種子を植え付けると、大豆畑や綿花畑でもジカンバを除草剤として使えます。グリホサート耐性をもつスーパー雑草も駆除できる。ここがポイントです。
ジカンバによる被害報告が相次ぐ
引用した日経産業新聞の記事は、実はジカンバによる農作物被害をレポートするのが主眼でした。その被害の状況を記事の見出しとともに引用します。
|
|
ジカンバとジカンバ耐性作物の広がり
上の引用でもわかるように「農薬と農薬耐性作物による農業」は次の段階に入ってきました。つまりジカンバによる農作物被害が広がるほどに、ジカンバが広く使われ出したわけです。
ジカンバは揮発性が高く、空気中を飛散して意図しない農作物を枯らす危険性があることは以前から分かっていました。いわゆる「ドリフト」による被害です。従ってEPAも各州当局もモンサント社も、ジカンバを耐性大豆や耐性綿花の畑に用いるための規制・指導を行ったようです。つまり畑のまわりに緩衝帯を設けるとか、風速15メートル以上では使用禁止とか、飛行機による空中散布禁止といったたぐいの規制です。推測するに、規制どおりにジカンバを使えば問題はほぼ起こらないのでしょう。モンサント社もそのことを確認する実験をやったと思われます。
しかしこういった規制のとおりにすると農家にとっては労力やコストがかさみます。自家農地の耐性大豆・耐性綿花がジカンバで枯れないと分かっている以上、できるだけ労力が少ない方法で散布したいと農家が思ったとしても不思議ではありません。そもそも「ジカンバとジカンバ耐性作物の組み合わせ」は農業のコスト削減のために開発されたものなのです。ジカンバによる作物被害の責任は、第1義的には「不適切使用をした農家」でしょうが、そこに暗黙に誘導したのはモンサント社と認可した規制当局だと思います。だからこそ、被害を前にしていくつかの州当局は一時的禁止、ないしはその継続を検討している。とにかく、除草剤と耐性作物による農業は、
| 第4段階:ジカンバとジカンバ耐性作物の広範囲使用 |
の段階になってきました。そして確実に予期できることは、その次の第5段階があるということです。つまり、
| 第5段階:ジカンバに耐性を持つスーパー雑草の出現 |
です。大豆農家・綿花農家が使う除草剤として、グリホサートもジカンバも意味がなくなる日がくるのは確実でしょう。
スーパー雑草の出現は "ビジネスチャンス"
そもそも、除草剤を使うとそれに耐性を持つ植物が(遅かれ早かれ)出現するのは農業関係者の常識です。これは抗生物質の使用と耐性菌の出現の関係と同じです。そういう風に自然はできている。モンサント社もそれを先刻承知のはずで、ジカンバ耐性雑草の出現を予測し、新たな除草剤とそれに耐性をもつ作物の開発に余念がないと想像します。数種の候補を同時並行的に研究しているかもしれない。
この状況は、いわゆる "イタチごっご" です。そしてこの "イタチごっご" はモンサントのようなバイオ化学企業にとってのビジネスチャンスになります。永続的に続くと考えられる "イタチごっご" だからこそ、ビジネスの機会も永続的に続く。もしスーパー雑草が出現しないとモンサント社は困ったことになります。グリホサートだけで雑草管理が永続的に可能なら、グリホサート耐性作物の特許はいずれ切れるので、モンサント社は独占的地位を保てなくなります。農家もモンサント社だけに種子を頼る必要がなくなる。現にグリホサートの特許はすでに切れていて、同一成分をもつ "ジェネリック除草剤" が出回っています。
しかしバイオ化学企業にとって、新たなスーパー雑草が出現しないという心配をする必要はないのです。自然のメカニズムは耐性植物・耐性菌が出現するようにできているのだから・・・・・・。バイオ化学企業は "自作自演" のイタチごっこを演出し、除草剤ビジネスのネタが尽きることが無いように農業を誘導しているというわけです。
もちろんバイオ化学企業にとってのリスクもあります。新たな農薬とそれに耐性がある作物を作り出せなかったら "アウト" だからです(少なくとも除草剤の分野では)。他社に負けると競争に生き残れません。従ってますます研究開発への投資が必要になります。この状況はバイオ化学企業の寡占化・巨大化を促進すると考えられます。巨大研究投資に耐えられる企業が生き残るわけです。
また「除草剤と耐性作物のペアによる農業」が進展していくと、農家は巨大バイオ化学企業への依存度をますます高めることになるでしょう。イタチごっこに巻き込まれた農家は、独占的地位にある企業の手足となって(= 隷属して)農地を耕作するだけの存在になっていくと考えられます。
食料に低コストだけを求める愚
グリホサートやジカンバに耐性をもつ作物は、遺伝子組み換え技術で作り出されたGM作物です。そのGM作物の中には人類にとってメリットが多い(デメリットはほとんどない)と考えられるものがあります。たとえば耐乾燥性のGM作物は干魃被害が深刻な地域の食料生産を増大させ、乳幼児の死亡率を低下させるかもしれない。そういったことが考えられます。
しかし「除草剤と除草剤耐性GM作物をペアにした農業」の主眼は農業コストの削減です。そして食料や食品に低コストだけを求めるのは愚の骨頂です。食品の安全、自然環境や生態系の保全、食料資源の持続可能性など、コスト以外の(コストよりもっと大切な)考慮点がいっぱいあるからです。
アメリカはTPP(環太平洋経済連携協定)から離脱し、今後は日本を始めとする各国とのFTA(自由貿易協定)を目指すそうです。FTAの農業分野でGM作物が交渉項目になるかどうか分かりませんが、日本としては上に引用したようなアメリカ農業の実態を詳細に把握してから交渉に望むべきでしょう。
ジカンバの新聞記事を読んでふと思ったことがあります。日本での農業の一つの例ですが、島根県の奥出雲地方、仁多郡で作られる「仁多米」は「東の魚沼・西の仁多」と言われるほどコシヒカリの有名ブランドです。この地方では無農薬・有機栽培が進んでいます。地元の畜産農家と協力して有機肥料も確保をしている(いわゆる循環型農業)。そのため、この地域には絶滅危惧種(メダカ、タガメなど)や準絶滅危惧種(トノサマガエルなど)が多く生息しています。
このような例は仁多だけではないし、また日本だけでもありません。世界には「アメリカ発の、除草剤と除草剤耐性GM作物をペアにした農業」とは全くの対極にある農業が厳然としてあり、それが高い評価を受けていることを忘れてはいけないと思います。


| ||
|
仁多郡の米作り風景(奥出雲観光文化協会のサイト) 下の写真の棚田については、奥出雲観光文化協会のサイトに説明がある。かつて奥出雲町では砂鉄を原料とする「たたら製鉄」が盛んに行われていた。砂鉄は、山を切り崩し土砂を水路に流す「鉄穴流し(かんなながし)」で採取されたが、この棚田は「鉄穴流し」の跡を水田に転用したものである。平成24 年に「奥出雲たたら製鉄及び棚田の文化的景観」として国重要文化的景観に選定された。
(site : www.okuizumogokochi.jp)
| ||
2017-11-11 07:39
nice!(0)
No.138 - フランスの「自由」 [社会]
2015年1月7日、フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」のパリ本社がテロリストに襲撃される事件が起きました。この後の一連の報道に接する中で、以前の記事 No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で書いたフランス革命の話を連想したので、その経緯を書いてみたいと思います。
シャルリー・エブド
2015年1月7日午前11時半ごろ(日本時間、同日19時半頃)フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」のパリの本社に2人のテロリストが乱入して銃を乱射し、編集長、編集関係者、風刺画家、警官の12人が射殺されました。テロリストは「シャルリー・エブド」がイスラム教の預言者・ムハンマドの風刺画を掲載していることに反発したようです。
1月11日、フランス全土で「シャルリー・エブド」への連帯を示すデモ行進が行われ、350万人以上が参加しました。パリでは100万人以上とも言われる規模の行進が行われました。このときの「私はシャルリー」というスローガンは、
の表明です。この「パリ大行進」では、フランス、イギリス、ドイツの大統領・首相と並んでイスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナ自治政府のアッバス議長が先頭に立ったのが印象的でした。
1月14日に発行された「シャルリー・エブド」は再びムハンマドの風刺画を掲載しましたが、今度はこれに抗議するデモが世界各国のイスラム教国で発生しました。
今回のテロに関しては「アラビア半島のアルカイダ」が犯行声明を出しているので、いわゆるイスラム過激派、ないしはそれに感化された犯人によるテロであることは間違いないでしょう。しかし、テロリストはイスラム教徒を標榜してはいるが、イスラム教とは無縁の存在であることは確実です。自分たちはイスラム教徒の「つもり」かもしれないが、テロリストのやった行動は「イスラム教を貶めるもの」に他なりません。また、社会(フランス、ヨーロッパ)の混乱と不安定化を招こうとする意図があったのかもしれない。とにかく大多数のイスラム教徒にとってテロリストの行為は許しがたいものであり、また今後予想されるイスラム教徒への差別や迫害を予想して「迷惑千万」とも映ったでしょう。
ちなみに犯人は、フランスで生まれ、フランスで育ったフランス人でした。このことも今回の事件の大きなポイントです。
ところで私がこの事件で考えさせられたことは、表現の自由とは何かということです。テロを断固排斥することを大前提として、以下、この事件の背後にある「表現の自由」について考えてみたいと思います。
表現の自由
問題の「表現の自由」についてですが、ローマ法王であるフランシスコ教皇は、1月15日に、
と発言しました。もちろん宗教家のサイドから発言ですが、極めて妥当で、まっとうな見解だと思いました。
またイスラムの側からの発言として、朝日新聞がパレスチナ自治政府のアッバス議長に行った単独インタビューがあります。アッバス議長はイスラエルのネタニヤフ首相らとともに「パリ大行進」に参加した理由について「テロに反対することを世界に示すため」と述べ、さらに次のように語っています。
アッバス議長がイスラエルのネタニヤフ首相と並んで「パリ大行進」に参加したことはパレスチナの住民からの批判も強いようですが、それはまた別の問題です。ともかく、上に引用したアッバス議長の発言はフランシスコ法王と並んで極めて妥当で、まっとうな意見だと思いました。
さらにフランスのあるメディアが行ったフランス人の世論調査でも「預言者の風刺画を掲載してもよい」という意見とともに「預言者の風刺画を掲載すべきでない」という意見もありました。テレビで見ただけでウロ覚えなのですが、両者は6対4ぐらいの比率だったと思います。世論調査はやり方によって結果が左右されるので確定的なことは言えませんが、フランスにおいても少なからぬ人々が預言者の風刺画に批判的なのです。
しかし(少なくともフランスにおいては)「預言者の風刺画を掲載してもよい」という意見が多数あるのも確かです。それも、どこかの新興宗教の預言者ではなく、キリスト、ムハンマド、モーゼといった、1000年、2000年という長期に渡って「数億人レベルの多数の人々の信仰の核となっている預言者」ないしは「民族のアイデンティティーとなっている預言者」なのです。この「掲載してもよい」とする代表的な意見が、朝日新聞(2015.1.20)のオピニオン・ページに載っていたので、それを紹介・考察してみたいと思います。
宗教への批判は絶対の権利
2015年1月20日付の朝日新聞のオピニオン・ページに、フランスの作家で哲学者のベルナール = アンリ・レビ氏にインタビューした記事が載っていました。レビ氏の経歴は以下のように紹介されています。
この記事の見出しは「宗教への批判は絶対の権利」です。この「絶対の権利」という言い方は過激ですが、実はレビ氏自身が語っていることなのです。以下、レビ氏の発言内容の紹介ですが(下線は原文にはありません)、まず記事の冒頭からです。
この発言は極めて妥当です。「表現の自由には例外がある」というのは、表現の自由がある国のすべてに共通していることだからです。例外は法律で規定されているものもあります。日本でも「名誉毀損」は犯罪だし「犯罪を呼びかけたり教唆する表現」も犯罪です。フランスでは「人種差別」や「反ユダヤ」の表現も法律が禁じているようですが、それは国の(歴史的)事情によるのでしょう。ドイツでは確か「ナチを礼賛する表現」が法律で禁止されているはずです。
もちろん「表現の自由の例外」が法律で規定されていなくても、表現の自由・言論の自由がある国では新聞やメディアが発達しているので、たとえば日本でも政治家が「人種差別発言」をするとメディアに批判され、陳謝に追い込まれたりして、そのことによって実質的に表現の自由が制限されるという仕掛けになっています(同時に、個人攻撃による表現の自由の圧迫や自粛の強要といった危険性もある)。
表現の自由だけではないですが、「自由がある」ということは「自由の例外がルール・法律によって規定されている、ないしは例外についての暗黙の合意が形成されている」ということです。自由を保障することイコール、その自由の例外を決めることです。ここまでは誰もが納得するでしょう。
問題はこのあとです。レビ氏は上の引用にすぐに続けてこう言っています。
「宗教を批判することは絶対の権利」という言い方には非常に違和感を感じますが、ここまで明白にレビ氏が言うのは、これが個人の考えではないからです。「1905年の法律」とありますが、それ以前のフランスの歴史も関係しているようです。
ベルナール = アンリ・レビ氏は、ラブレー(16世紀)やボルテール(18世紀)といったフランス史を持ち出して「宗教とて他のイデオロギーと同じで、法の前では横並び」と発言しているのですが、ここで私が連想したのが No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で書いたフランス革命の話でした。つまり、現在のフランスの「国のかたち」を作った発端が(少なくとも建前上は)フランス革命(18世紀末)だとすると、フランスは宗教を打倒してできた国だということです。
フランスは宗教を打倒してできた国
No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で、王政とともにフランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)であり、その象徴的な出来事として「カルメル会修道女の処刑」と「監獄になったモン・サン・ミシェル」の2点をあげました。
フランス革命(1979 - )では、カトリックの聖職者が迫害され、投獄、処刑されました。革命政府の「理性神」や共和国憲法・法律に忠誠を誓う宣誓が聖職者に強要され、拒否するものは「反革命」とみなされたのです。1792年9月2日からの数日間、パリの監獄や(監獄として使われていた)修道院を民衆が襲い、収監されていた「反革命派」を殺害した事件(いわゆる"9月虐殺")では、多数の聖職者が犠牲になりました。これは、パリにおいては "サン・バルテルミの虐殺"(1572年8月24日。No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」参照)以来の事件だと言われています。
このカトリックの犠牲の象徴的な事件が、カルメル会修道女16人の処刑です。パリの北東のコンピエーニュにあったカルメル会修道院(カトリックの修道会の一つ)の修道女16人全員が、1794年7月17日、反革命の罪で処刑されました。これはフランシス・プーランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」(1957)の題材になっています。このオペラは、16人の修道女たちが一人一人ギロチンにかけられるシーンで終わります。
もちろんフランス革命においては聖職者だけが「選択的に」迫害されたわけではありません。革命政府の方針に反旗を掲げた民衆、穏健共和派、王党派も「反革命」として徹底的に弾圧されました(ヴェンデ戦争やリヨン大虐殺)。
フランス革命では、教会・修道院が略奪、破壊され、政府による建物・資産の接収と転用が行われました。この象徴がモン・サン・ミシェルです。
モン・サン・ミシェル修道院は革命後に監獄に転用され、聖職者や王党派といった「反革命派」が収監されました。この監獄が閉鎖され、再び修道院としての修復が始まったのが1863年と言いますから、約70年のあいだ監獄だったわけです。その間、投獄されたのは14,000人にのぼると言います。「海のバスティーユ(監獄)」と呼ばれて恐れられたようです。
現在、モン・サン・ミシェル修道院は世界遺産の有名な観光地ですが、現地に行ってみると修道院の歴史が説明されていて、その中には監獄だった過去の説明もあります。囚人が物資を運んだ車輪の設備など、監獄の「名残り」も見学できます。

先ほど「王政とともにフランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)」と書きましたが、これはちょっと不正確です。「フランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)であり、それとともに王政も打倒された」というのがより正確です。このフランス革命の経緯が「シャルリー・エブド」の風刺画の源流にあるようです。明治大学の鹿島茂教授は、2015年1月12日の読売新聞で次のように述べています。
鹿島教授は「1789年の仏革命の最大の敵はカトリック教会」と正確に指摘しています。確かに1792年に王政は廃止されたけれど、それまでは立憲君主的です。1790年当時の革命議会は、法と国王への忠誠を市民に要請しているぐらいです。また、王政廃止後のフランスには王政まがいの「皇帝」が現れました。フランス革命が一貫して「敵」としたのはカトリック教会であり、端的に言うと「宗教」そのものなのです。
1000年というレベルの長期にわたって根づいてきた宗教を打倒して国の基礎ができる・・・・・・。これは世界の歴史でもかなり特別なことではないでしょうか。王政を打倒してできた国はいっぱいあります。イギリスでは国王が処刑され(清教徒革命)、その後の紆余曲折の結果「君臨するも統治せず」の立憲君主制になった。しかし英国国教会はそのまま残っています。カトリックを「打倒」してプロテスタントになった国はヨーロッパにたくさんありますが(ドイツ、英国、オランダなど)、それはキリスト教の中の宗派の争いです。日本の明治維新期の「廃仏毀釈」も仏教の破壊活動であって、その一方で明治政府は神道を擁護・推進しました。
王政が打倒されるとともに宗教そのものが攻撃されたということで唯一思いつくのは、ロシア革命とその後の経緯です。ロマノフ朝が倒れ、国王が処刑されたあとのロシアでは、ロシア正教の教会が破壊され、僧侶が処刑されました。しかしこれは「コミュニズム理論」の実践によるものであって、その実践はわずか70年という短い期間で終わってしまった。世界史の流れからすると「一過性の」出来事に過ぎません。それに対してフランスは、フランス革命という「国のかたち」を作った出来事の継続として200年以上、現在も国が続いているわけです。
フランス革命で、宗教や信仰の特別扱いはなくなりました。信仰上の理由であっても反革命は反革命です。その「革命」の理念として掲げられたのは「自由・平等・友愛」であり、ここから「表現の自由・言論の自由」の考え方が定着するわけですね。それはフランスだけでなく、その後の世界の自由主義国家・民主主義国家に多大な影響を与えた。その「フランス的自由」は、国民同士の悲惨な殺し合いの経験を通してフランス人が勝ち取ったものなのです。そしてその自由の一部として宗教批判がある。
シャルリー・エブドのテロ事件に関するベルナール = アンリ・レビ氏の見解に戻りますと、彼は、
と言っています。この見解は、実はフランス革命を原点とする「フランスという国のかたち」そのものではないか、と思うわけです。国の出発点に宗教批判があるから、現在もそれがないと国の存在基盤が危うくなる(と感じられる)。ましてや「宗教批判はすべきでない」となると、それじゃカトリックの司祭や修道女を処刑したあのフランス革命は何だったのかということになってしまう。国のスタートが間違っていたということになりかねない。
ベルナール = アンリ・レビ氏は「フランスの根元的な価値観を体現する筋金入りの知識人」という印象を受けます。「絶対の権利」という言い方にそれを感じます。再度確認すると「宗教を批判する」とは「堕落した教会や聖職者を批判する」というようなこと(だけ)ではありません。キリスト教会を批判したいのなら、たとえばバチカンの法王や枢機卿の風刺画を載せればよいわけで、それならプロテスタントが500年前に起こした宗教改革と同じです。そうではなくキリストの風刺画を載せるということは、宗教そのものを(宗教の否定も含めて)批判するということです。
今回の「シャルリー・エブド」の襲撃で「表現の自由」が危機に瀕したような報道や論調がありました。しかし、それは違うのではないでしょうか。正しくは「フランス的表現の自由」が危機に陥ったのだと思います。そして日本を含めてフランス以外の国は「フランス的表現の自由」に同意する必要はないのです。
それにもかかわらず、日本を含む世界の一部のメディアは「シャルリー・エブド」の風刺画を(あるものはモザイク付きで)転載しました。その理由として「表現の自由についての議論の素材を提供する」とした日本のメディアがありましたが、違うと思いますね。預言者の風刺画は一般的な表現の自由の議論の素材にはなりません。「シャルリー・エブド」は(いいか悪いかは別にして)フランス固有の伝統にのっとり、フランス的表現の自由を守るという意識のもと、身の危険を承知で掲載したわけです。しかしそれを転載する(たとえば日本の)メディアには、そういった意識も覚悟もないでしょう。それでいて「表現の自由」を建前に、まともなジャーナリズムを装っているから悪質です。もっとも、このような「話題性を狙った扇情的報道」で発行部数を伸ばそうとするメディアが出ることは、言論や表現の自由のある国では避けられないことです。それは民主主義の根幹である「表現の自由」があるという証拠でもある。
社会的弱者を攻撃する「自由」
「表現の自由」は現代の民主主義社会の根幹ですが、そもそも何のためだったのかを考えてみる必要もあるでしょう。歴史を振り返ると明らかなのですが「表現の自由」は民衆の権力への反撃手段として発達し、定着してきたものです。まさにベルナール = アンリ・レビ氏がボルテールやラブレーの例をあげているように、教会、権力、権威、政治などを批判する権利として「表現の自由」があった。あったというよりフランス国民が血みどろの殺し合いの中から獲得したものです。その自由の一部としてフランスでは「宗教を批判する自由」があった。宗教とはもちろんカトリックです。つまり、1000年以上の長い期間にわたってフランスに根付いてきた「自らの宗教」をも批判する自由だった。
しかし、現代はフランス革命の時代や「1905年に法律で国と教会の分離を定めた時代」とは社会環境が全く違っています。今回問題になった「ムハンマドの風刺画」に関して言うと、フランスにおけるイスラム教徒は 7% だと報道されています。その多くは移民、ないしは移民の子であり、フランス社会でも比較的貧しく、若者が職を得るにも苦労すると言います。その移民の多くは、かつてフランスが植民地として支配・搾取した北アフリカのイスラム教国からきた人たちなのですね。移民社会のイスラム教徒にとっては「神とともに生きる」ことが彼らなりの「自由」です。預言者は神の言葉を伝える存在であり、預言者を風刺することは耐えがたいことになります。
ムハンマドの風刺画をメディアに掲載する「表現の自由」は、フランス社会では結果として「社会的弱者を攻撃する自由」になっています。風刺画を掲載する方は、攻撃ではない、それはフランス伝統のエスプリだと言うでしょうが、イスラム教徒からすると自分たちが攻撃されたとしか受け取りようがない。
シャルリー・エブドで12人がテロの犠牲になってから1ヶ月もたたない2015年1月末、日本人のジャーナリスト、後藤健二氏がシリアでテロリストに殺害されました。彼は常に社会的弱者に寄り添った報道を続けてきた人です。その弱者とはアフガニスタン、イラク、シリア、ルアンダ、シエラレオネなどでの戦争・内戦の難民や子供たちであり、その多くがイスラム教徒です。同じジャーナリズムでも(結果として)社会的弱者を攻撃するのとは全く対極的な後藤氏の姿勢です。「予言者の風刺画は絶対的権利」とするベルナール = アンリ・レビ氏の意見は、後藤氏とは全く正反対の「上から目線」を感じます。
「表現の自由」に戻りますと、社会におけるあらゆる制度や権利は、それが確立した背景と理由があります。それを無視して制度や権利の一人歩きを許すと、結果として制度や権利を形骸化させることになります。
「フランス的表現の自由」は、それがフランスの「国のかたち」であることは認めつつ、現実の社会環境を鑑みて、ある局面では「自制」が必要なのです。法律で規制できない(規制すべきでない)以上、自制しかない。当然ですが・・・・・・。メディアの世論調査にあったように、フランスにおいても少なからぬ人が「預言者の風刺画を掲載すべきではない」と思っています。2015年1月11日の「パリ大行進」に参加したフランス人の中にも「風刺画には反対だが、テロに屈しないという意志を表明するために参加した人」があったはずです。
フランスを代表する知識人の一人で、歴史学者・人類学者のエマニュエル・トッド氏は、読売新聞の電話インタビューに答えて次のように語っています。
同じ知識人でもレビ氏とは違い、このトッド氏の意見には大いに共感できます。彼は日本の新聞社の電話インタビューだから応じたわけですが、確信できることは、彼はフランスにおいても決して「独りぼっち」ではないということです。
「国のかたち」とグローバル化
グローバル化が進む現代において、異文化との共存は避けて通れない問題です。異なる文化と価値観を持った2つの集団が一つの国において共存する必要がでできたとき、互いの理解から始めるしかないと思います。そして共存の道を探り、模索する。伝統的なフランスの(ないしは民主主義国家の)価値観をもつ人はイスラム文化を理解する必要があるし、またイスラム教徒のフランス人もフランスの「国のかたち」や「伝統的な価値観」を理解する必要があります。それに同意したり従ったりする必要はないが、その理由を知る必要はある。その意味で、国家レベルの「異文化理解の教育」が非常に大切だと思います。
それはフランスだけの課題ではもちろんなく、日本の課題でもあり、今後ますます重要になる課題だと強く思いました。
シャルリー・エブド
2015年1月7日午前11時半ごろ(日本時間、同日19時半頃)フランスの週刊新聞「シャルリー・エブド」のパリの本社に2人のテロリストが乱入して銃を乱射し、編集長、編集関係者、風刺画家、警官の12人が射殺されました。テロリストは「シャルリー・エブド」がイスラム教の預言者・ムハンマドの風刺画を掲載していることに反発したようです。
1月11日、フランス全土で「シャルリー・エブド」への連帯を示すデモ行進が行われ、350万人以上が参加しました。パリでは100万人以上とも言われる規模の行進が行われました。このときの「私はシャルリー」というスローガンは、
| ・ | 反テロの決意 | ||
| ・ | 表現の自由を守る決意 |
の表明です。この「パリ大行進」では、フランス、イギリス、ドイツの大統領・首相と並んでイスラエルのネタニヤフ首相、パレスチナ自治政府のアッバス議長が先頭に立ったのが印象的でした。
1月14日に発行された「シャルリー・エブド」は再びムハンマドの風刺画を掲載しましたが、今度はこれに抗議するデモが世界各国のイスラム教国で発生しました。
今回のテロに関しては「アラビア半島のアルカイダ」が犯行声明を出しているので、いわゆるイスラム過激派、ないしはそれに感化された犯人によるテロであることは間違いないでしょう。しかし、テロリストはイスラム教徒を標榜してはいるが、イスラム教とは無縁の存在であることは確実です。自分たちはイスラム教徒の「つもり」かもしれないが、テロリストのやった行動は「イスラム教を貶めるもの」に他なりません。また、社会(フランス、ヨーロッパ)の混乱と不安定化を招こうとする意図があったのかもしれない。とにかく大多数のイスラム教徒にとってテロリストの行為は許しがたいものであり、また今後予想されるイスラム教徒への差別や迫害を予想して「迷惑千万」とも映ったでしょう。
ちなみに犯人は、フランスで生まれ、フランスで育ったフランス人でした。このことも今回の事件の大きなポイントです。
ところで私がこの事件で考えさせられたことは、表現の自由とは何かということです。テロを断固排斥することを大前提として、以下、この事件の背後にある「表現の自由」について考えてみたいと思います。
表現の自由

| |||
|
フランシスコ教皇
(Wikipedia) | |||
| 「 | 他人の信仰を侮辱してはならない。表現の自由には限界がある」 |
と発言しました。もちろん宗教家のサイドから発言ですが、極めて妥当で、まっとうな見解だと思いました。
またイスラムの側からの発言として、朝日新聞がパレスチナ自治政府のアッバス議長に行った単独インタビューがあります。アッバス議長はイスラエルのネタニヤフ首相らとともに「パリ大行進」に参加した理由について「テロに反対することを世界に示すため」と述べ、さらに次のように語っています。
|

| |||
|
アッバス議長
(Wikipedia) | |||
さらにフランスのあるメディアが行ったフランス人の世論調査でも「預言者の風刺画を掲載してもよい」という意見とともに「預言者の風刺画を掲載すべきでない」という意見もありました。テレビで見ただけでウロ覚えなのですが、両者は6対4ぐらいの比率だったと思います。世論調査はやり方によって結果が左右されるので確定的なことは言えませんが、フランスにおいても少なからぬ人々が預言者の風刺画に批判的なのです。
しかし(少なくともフランスにおいては)「預言者の風刺画を掲載してもよい」という意見が多数あるのも確かです。それも、どこかの新興宗教の預言者ではなく、キリスト、ムハンマド、モーゼといった、1000年、2000年という長期に渡って「数億人レベルの多数の人々の信仰の核となっている預言者」ないしは「民族のアイデンティティーとなっている預言者」なのです。この「掲載してもよい」とする代表的な意見が、朝日新聞(2015.1.20)のオピニオン・ページに載っていたので、それを紹介・考察してみたいと思います。
宗教への批判は絶対の権利
2015年1月20日付の朝日新聞のオピニオン・ページに、フランスの作家で哲学者のベルナール = アンリ・レビ氏にインタビューした記事が載っていました。レビ氏の経歴は以下のように紹介されています。
ベルナール = アンリ・レビ |
この記事の見出しは「宗教への批判は絶対の権利」です。この「絶対の権利」という言い方は過激ですが、実はレビ氏自身が語っていることなのです。以下、レビ氏の発言内容の紹介ですが(下線は原文にはありません)、まず記事の冒頭からです。
|
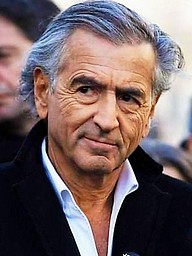
| |||
|
ベルナール=アンリ・レビ
(1948~) (site : www.asahi.com) | |||
もちろん「表現の自由の例外」が法律で規定されていなくても、表現の自由・言論の自由がある国では新聞やメディアが発達しているので、たとえば日本でも政治家が「人種差別発言」をするとメディアに批判され、陳謝に追い込まれたりして、そのことによって実質的に表現の自由が制限されるという仕掛けになっています(同時に、個人攻撃による表現の自由の圧迫や自粛の強要といった危険性もある)。
表現の自由だけではないですが、「自由がある」ということは「自由の例外がルール・法律によって規定されている、ないしは例外についての暗黙の合意が形成されている」ということです。自由を保障することイコール、その自由の例外を決めることです。ここまでは誰もが納得するでしょう。
問題はこのあとです。レビ氏は上の引用にすぐに続けてこう言っています。
|
「宗教を批判することは絶対の権利」という言い方には非常に違和感を感じますが、ここまで明白にレビ氏が言うのは、これが個人の考えではないからです。「1905年の法律」とありますが、それ以前のフランスの歴史も関係しているようです。
|
|
ベルナール = アンリ・レビ氏は、ラブレー(16世紀)やボルテール(18世紀)といったフランス史を持ち出して「宗教とて他のイデオロギーと同じで、法の前では横並び」と発言しているのですが、ここで私が連想したのが No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で書いたフランス革命の話でした。つまり、現在のフランスの「国のかたち」を作った発端が(少なくとも建前上は)フランス革命(18世紀末)だとすると、フランスは宗教を打倒してできた国だということです。
フランスは宗教を打倒してできた国
No.42「ふしぎなキリスト教(2)」で、王政とともにフランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)であり、その象徴的な出来事として「カルメル会修道女の処刑」と「監獄になったモン・サン・ミシェル」の2点をあげました。
| カルメル会修道女の処刑 |
フランス革命(1979 - )では、カトリックの聖職者が迫害され、投獄、処刑されました。革命政府の「理性神」や共和国憲法・法律に忠誠を誓う宣誓が聖職者に強要され、拒否するものは「反革命」とみなされたのです。1792年9月2日からの数日間、パリの監獄や(監獄として使われていた)修道院を民衆が襲い、収監されていた「反革命派」を殺害した事件(いわゆる"9月虐殺")では、多数の聖職者が犠牲になりました。これは、パリにおいては "サン・バルテルミの虐殺"(1572年8月24日。No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」参照)以来の事件だと言われています。
このカトリックの犠牲の象徴的な事件が、カルメル会修道女16人の処刑です。パリの北東のコンピエーニュにあったカルメル会修道院(カトリックの修道会の一つ)の修道女16人全員が、1794年7月17日、反革命の罪で処刑されました。これはフランシス・プーランクのオペラ「カルメル会修道女の対話」(1957)の題材になっています。このオペラは、16人の修道女たちが一人一人ギロチンにかけられるシーンで終わります。

| ||
|
フランシス・プーランク
「カルメル会修道女の対話」
フランス、サン=テティエンヌのオペラ場での公演より(2005年2月6日)。写真はオペラの最終場面。
(site : www.forumopera.com)
| ||
もちろんフランス革命においては聖職者だけが「選択的に」迫害されたわけではありません。革命政府の方針に反旗を掲げた民衆、穏健共和派、王党派も「反革命」として徹底的に弾圧されました(ヴェンデ戦争やリヨン大虐殺)。
| モン・サン・ミシェル監獄 |
フランス革命では、教会・修道院が略奪、破壊され、政府による建物・資産の接収と転用が行われました。この象徴がモン・サン・ミシェルです。
モン・サン・ミシェル修道院は革命後に監獄に転用され、聖職者や王党派といった「反革命派」が収監されました。この監獄が閉鎖され、再び修道院としての修復が始まったのが1863年と言いますから、約70年のあいだ監獄だったわけです。その間、投獄されたのは14,000人にのぼると言います。「海のバスティーユ(監獄)」と呼ばれて恐れられたようです。
現在、モン・サン・ミシェル修道院は世界遺産の有名な観光地ですが、現地に行ってみると修道院の歴史が説明されていて、その中には監獄だった過去の説明もあります。囚人が物資を運んだ車輪の設備など、監獄の「名残り」も見学できます。

先ほど「王政とともにフランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)」と書きましたが、これはちょっと不正確です。「フランス革命で打倒されたのは宗教(カトリック)であり、それとともに王政も打倒された」というのがより正確です。このフランス革命の経緯が「シャルリー・エブド」の風刺画の源流にあるようです。明治大学の鹿島茂教授は、2015年1月12日の読売新聞で次のように述べています。
|
鹿島教授は「1789年の仏革命の最大の敵はカトリック教会」と正確に指摘しています。確かに1792年に王政は廃止されたけれど、それまでは立憲君主的です。1790年当時の革命議会は、法と国王への忠誠を市民に要請しているぐらいです。また、王政廃止後のフランスには王政まがいの「皇帝」が現れました。フランス革命が一貫して「敵」としたのはカトリック教会であり、端的に言うと「宗教」そのものなのです。
1000年というレベルの長期にわたって根づいてきた宗教を打倒して国の基礎ができる・・・・・・。これは世界の歴史でもかなり特別なことではないでしょうか。王政を打倒してできた国はいっぱいあります。イギリスでは国王が処刑され(清教徒革命)、その後の紆余曲折の結果「君臨するも統治せず」の立憲君主制になった。しかし英国国教会はそのまま残っています。カトリックを「打倒」してプロテスタントになった国はヨーロッパにたくさんありますが(ドイツ、英国、オランダなど)、それはキリスト教の中の宗派の争いです。日本の明治維新期の「廃仏毀釈」も仏教の破壊活動であって、その一方で明治政府は神道を擁護・推進しました。
王政が打倒されるとともに宗教そのものが攻撃されたということで唯一思いつくのは、ロシア革命とその後の経緯です。ロマノフ朝が倒れ、国王が処刑されたあとのロシアでは、ロシア正教の教会が破壊され、僧侶が処刑されました。しかしこれは「コミュニズム理論」の実践によるものであって、その実践はわずか70年という短い期間で終わってしまった。世界史の流れからすると「一過性の」出来事に過ぎません。それに対してフランスは、フランス革命という「国のかたち」を作った出来事の継続として200年以上、現在も国が続いているわけです。
フランス革命で、宗教や信仰の特別扱いはなくなりました。信仰上の理由であっても反革命は反革命です。その「革命」の理念として掲げられたのは「自由・平等・友愛」であり、ここから「表現の自由・言論の自由」の考え方が定着するわけですね。それはフランスだけでなく、その後の世界の自由主義国家・民主主義国家に多大な影響を与えた。その「フランス的自由」は、国民同士の悲惨な殺し合いの経験を通してフランス人が勝ち取ったものなのです。そしてその自由の一部として宗教批判がある。
シャルリー・エブドのテロ事件に関するベルナール = アンリ・レビ氏の見解に戻りますと、彼は、
| ・ | 宗教を批判することは絶対の権利です。 | ||
| ・ | 宗教とて他のイデオロギーと変わりません。法の前では横並びです。 |
と言っています。この見解は、実はフランス革命を原点とする「フランスという国のかたち」そのものではないか、と思うわけです。国の出発点に宗教批判があるから、現在もそれがないと国の存在基盤が危うくなる(と感じられる)。ましてや「宗教批判はすべきでない」となると、それじゃカトリックの司祭や修道女を処刑したあのフランス革命は何だったのかということになってしまう。国のスタートが間違っていたということになりかねない。
ベルナール = アンリ・レビ氏は「フランスの根元的な価値観を体現する筋金入りの知識人」という印象を受けます。「絶対の権利」という言い方にそれを感じます。再度確認すると「宗教を批判する」とは「堕落した教会や聖職者を批判する」というようなこと(だけ)ではありません。キリスト教会を批判したいのなら、たとえばバチカンの法王や枢機卿の風刺画を載せればよいわけで、それならプロテスタントが500年前に起こした宗教改革と同じです。そうではなくキリストの風刺画を載せるということは、宗教そのものを(宗教の否定も含めて)批判するということです。
今回の「シャルリー・エブド」の襲撃で「表現の自由」が危機に瀕したような報道や論調がありました。しかし、それは違うのではないでしょうか。正しくは「フランス的表現の自由」が危機に陥ったのだと思います。そして日本を含めてフランス以外の国は「フランス的表現の自由」に同意する必要はないのです。
それにもかかわらず、日本を含む世界の一部のメディアは「シャルリー・エブド」の風刺画を(あるものはモザイク付きで)転載しました。その理由として「表現の自由についての議論の素材を提供する」とした日本のメディアがありましたが、違うと思いますね。預言者の風刺画は一般的な表現の自由の議論の素材にはなりません。「シャルリー・エブド」は(いいか悪いかは別にして)フランス固有の伝統にのっとり、フランス的表現の自由を守るという意識のもと、身の危険を承知で掲載したわけです。しかしそれを転載する(たとえば日本の)メディアには、そういった意識も覚悟もないでしょう。それでいて「表現の自由」を建前に、まともなジャーナリズムを装っているから悪質です。もっとも、このような「話題性を狙った扇情的報道」で発行部数を伸ばそうとするメディアが出ることは、言論や表現の自由のある国では避けられないことです。それは民主主義の根幹である「表現の自由」があるという証拠でもある。
社会的弱者を攻撃する「自由」
「表現の自由」は現代の民主主義社会の根幹ですが、そもそも何のためだったのかを考えてみる必要もあるでしょう。歴史を振り返ると明らかなのですが「表現の自由」は民衆の権力への反撃手段として発達し、定着してきたものです。まさにベルナール = アンリ・レビ氏がボルテールやラブレーの例をあげているように、教会、権力、権威、政治などを批判する権利として「表現の自由」があった。あったというよりフランス国民が血みどろの殺し合いの中から獲得したものです。その自由の一部としてフランスでは「宗教を批判する自由」があった。宗教とはもちろんカトリックです。つまり、1000年以上の長い期間にわたってフランスに根付いてきた「自らの宗教」をも批判する自由だった。
しかし、現代はフランス革命の時代や「1905年に法律で国と教会の分離を定めた時代」とは社会環境が全く違っています。今回問題になった「ムハンマドの風刺画」に関して言うと、フランスにおけるイスラム教徒は 7% だと報道されています。その多くは移民、ないしは移民の子であり、フランス社会でも比較的貧しく、若者が職を得るにも苦労すると言います。その移民の多くは、かつてフランスが植民地として支配・搾取した北アフリカのイスラム教国からきた人たちなのですね。移民社会のイスラム教徒にとっては「神とともに生きる」ことが彼らなりの「自由」です。預言者は神の言葉を伝える存在であり、預言者を風刺することは耐えがたいことになります。
ムハンマドの風刺画をメディアに掲載する「表現の自由」は、フランス社会では結果として「社会的弱者を攻撃する自由」になっています。風刺画を掲載する方は、攻撃ではない、それはフランス伝統のエスプリだと言うでしょうが、イスラム教徒からすると自分たちが攻撃されたとしか受け取りようがない。
シャルリー・エブドで12人がテロの犠牲になってから1ヶ月もたたない2015年1月末、日本人のジャーナリスト、後藤健二氏がシリアでテロリストに殺害されました。彼は常に社会的弱者に寄り添った報道を続けてきた人です。その弱者とはアフガニスタン、イラク、シリア、ルアンダ、シエラレオネなどでの戦争・内戦の難民や子供たちであり、その多くがイスラム教徒です。同じジャーナリズムでも(結果として)社会的弱者を攻撃するのとは全く対極的な後藤氏の姿勢です。「予言者の風刺画は絶対的権利」とするベルナール = アンリ・レビ氏の意見は、後藤氏とは全く正反対の「上から目線」を感じます。
「表現の自由」に戻りますと、社会におけるあらゆる制度や権利は、それが確立した背景と理由があります。それを無視して制度や権利の一人歩きを許すと、結果として制度や権利を形骸化させることになります。
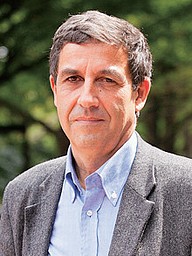
| |||
|
エマニュエル・トッド
(1951~) (site : president.jp) | |||
フランスを代表する知識人の一人で、歴史学者・人類学者のエマニュエル・トッド氏は、読売新聞の電話インタビューに答えて次のように語っています。
|
同じ知識人でもレビ氏とは違い、このトッド氏の意見には大いに共感できます。彼は日本の新聞社の電話インタビューだから応じたわけですが、確信できることは、彼はフランスにおいても決して「独りぼっち」ではないということです。
「国のかたち」とグローバル化
グローバル化が進む現代において、異文化との共存は避けて通れない問題です。異なる文化と価値観を持った2つの集団が一つの国において共存する必要がでできたとき、互いの理解から始めるしかないと思います。そして共存の道を探り、模索する。伝統的なフランスの(ないしは民主主義国家の)価値観をもつ人はイスラム文化を理解する必要があるし、またイスラム教徒のフランス人もフランスの「国のかたち」や「伝統的な価値観」を理解する必要があります。それに同意したり従ったりする必要はないが、その理由を知る必要はある。その意味で、国家レベルの「異文化理解の教育」が非常に大切だと思います。
それはフランスだけの課題ではもちろんなく、日本の課題でもあり、今後ますます重要になる課題だと強く思いました。
No.107 - 天然・鮮魚・国産への信仰 [社会]
前回の、No.106「食品偽装と格付けチェック」の続きです。No.106 で朝日新聞の読者アンケート「許せない誤表示・偽装食品ランキング」(2013.12.14)を紹介しまたが、再掲すると以下の通りです。
この中の9位である「養殖魚を天然ものと偽装するのは許せない」とするアンケート結果について考えてみたいと思います。この回答の裏には日本人の「天然もの信仰」があると思われるからです。
「天然もの」は自然の収奪
人間の歴史を振り返ってみると、遙か昔は「狩猟採集」で食料を得ていたわけです。No.105「鳥と人間の共生」に書いたように、アフリカ(そして南米など)には、今でも狩猟採集の生活を送っている人々がいます。
約1万年から始まった「農耕」によって、人類はいわゆる文明を発達させ、その後「牧畜や酪農」も進んできました。現代の日本においては、食料にする植物や鳥獣のほとんどが「栽培・飼育」されたものです。野生の植物を食用にするのはあまり思いつきません。山菜類やキノコ類(松茸、マイタケなど)ぐらいでしょうか。野生の鳥獣もイノシシ・シカ・鴨などだと思いますが、一般の食料品店では流通していません。もっともヨーロッパでは事情が違い、パリのマルシェでは野生のウサギやキジ、ヤマバトなど(いわゆる、ジビエ)をそのままの姿で売っています。しかしこれは「ご馳走」の部類であって、一般的なのは飼育された鳥獣肉です。
ところが、魚介類だけは「狩猟採集」が今もメジャーで、農耕(栽培)や牧畜(飼育)に相当する「養殖」は一部なのです。
養殖が難しいのは、魚介類は水の中に棲んでいるので、自然の生態をつぶさに観察・調査するのが困難だからです。ウナギ(ニホンウナギ)は最近まで産卵場所すら分からなかった。最低限、生態が分からないと養殖技術は確立できません。
養殖にかかる設備投資や餌代などのコストも問題です。そのコストに見合うだけの高価な魚介類でないと、事業としては成立しない。従って「需要はあるが天然ものの漁獲量が少なく、高価な魚介類」が養殖される(それしかできない)。
そういう障壁を乗り越えて、現代では数々の魚介類が養殖されています。ブリ類(ハマチなど)、鯛、鱒、ふぐ、牡蠣、ホタテ、クルマエビなどがすぐに思いつきます。クロマグロ(ホンマグロ)も養殖されるようになりました。2002年、近畿大学がクロマグロの養殖に初めて成功したのですが、ここに至るまでには30年間のノウハウ蓄積があったと言います。養殖は人知の結晶だという典型例だと思います。
農畜産業における「栽培・飼育」の大きなメリットは「品種改良」が可能だということです。現代の食生活は先人たちが苦労してやってきた品種改良の恩恵で成り立っています。野生種の米だと北海道での米作はありえないし、イノシシに近い豚でも(味は別にして)同一重量の肉の生産コストは数倍にハネあがるでしょう。
魚介類の養殖も、今後「品種改良」が進むと思われます。そしてそれが今後の食料確保の鍵になる可能性が高いと予想します。
いろいろと理由はつけられるでしょうが「狩猟採集は自然の収奪」であることに変わりはありません。天然資源の枯渇を招かないように、持続可能な形で「狩猟採集」するのは簡単ではない。まず、魚介類が海や河川でどういう生態なのかが理解できていません。ある年に急にイワシの漁獲量が減った(ないしは増えた)といっても、その理由が(明確には)分からない。東京湾で有名な鮨ネタに、漁獲量が激減している「小柴のシャコ」(神奈川県の柴漁港で揚がるシャコ)があります。東京湾を横断するアクアラインができた時期とシャコの激減時期が同じようですが、その因果関係もわからない。
たとえ生態が解明できたとしても、狩猟採集には「自然への敬意」が必要で、人間サイドの自制心が必要です。これが現代の自由主義社会ではなかなか難しい。たとえ日本が自制したとしても、他国が自制しないと海産物では意味がなくなるわけです。
こういった「天然の魚介類の減少」を危惧する記事が最近の雑誌に掲載されたので、それを紹介したいと思います。
鮨ネタがどんどん消えていく
文藝春秋の2013年8月号に「鮨ネタがどんどん消えていく」という興味深い記事が掲載されました。この記事は、銀座「すきやばし次郎」の初代である小野二郎氏をはじめ、漁業関係者にも取材してまとめたものです。この記事で、最近特に天然の鮨ネタが減少していることが報告されています。その要因として、
などがあげられていますが、大きな要因が
なのです。たとえば千葉県の鴨川漁港の漁労長の意見です。以下、下線は原文にはありません。
定置網は編み目を大きくして小さな魚を逃がせるけれど、巻き網は「根こそぎ穫る」ので資源に対する負荷が大きい、と解説されています。
魚のように自由に泳ぎ回ることができない貝類は、資源の枯渇が起こると魚以上に深刻な問題になります。「すきやばし次郎」の小野二郎氏は、次のように言っています。
小野二郎氏は、天然ものが極めて入手困難になってしまった例として、シマアジをあげています。
養殖ものは味が悪いのか
上の引用の最後のところに天然シマアジと養殖シマアジの味の比較が書いてあります。小野二郎氏は他の食材についても天然と養殖の比較を語っています。
銀座「すきやばし次郎」は、6年連続でミシュランの3つ星を獲得した店です。その初代である小野二郎氏は、政府が認定する「現代の名工」(2005年度)にも選ばれた方です。その見識はさすがだと思いますね。特に天然と養殖に関する率直な意見が印象的です。小野氏の考えを(少々の推測を加えて)まとめると、以下のようになると思います。
「すきやばし次郎」のような店こそ徹底的に天然ものにこだわり、ユネスコの無形文化遺産にも登録された「和食」の伝統と文化を守ってもらうべきです。そして「そういう鮨屋があるから日本に旅行する」という外国人の方を増やしたい(ミシュランの3つ星とはそういう意味です)。
そのための必須条件は、天然の上質な鮨ネタが入手できることなのですが、それを危うくしているのが天然資源の枯渇であり、その大きな理由が乱獲なのです。
天然もの信仰のあやうさ
乱獲による資源の枯渇を招いている一翼を担っているのが消費者に蔓延する「天然もの信仰」であり、それを増大させているマス・メディアではないでしょうか。
「天然と養殖では味に差がありすぎる」という小野二郎氏の見解は「すきやばし次郎」という「ミシュラン3つ星店の基準」であり、それは非常に大切です。その一方で小野氏も「シマアジ、貝類、クルマエビ」に関しては、養殖ものが天然ものと遜色ないことを認めています。「一般基準」では、差がない食材がもっと多いはずです。
かつて、養殖ものの安全性が懸念されたことがありました。魚介類が病気にならないために抗生物質を大量に投与するといった例です。しかし(少なくとも日本では)そういう安全性に問題はない。輸入食材が不安だと言うなら国産の養殖ものを選択すればよい。
ちょっと疑っているのですが、一般人が「天然ものが旨い」と感じるのは、一つには「それが高価だから」ではないでしょうか。漁獲量が少ないから高価になる、高価だから美味しいと感じる・・・・・・という原理です。というのも、天然の安価な魚(いわゆる大衆魚)が旨いと評価されない傾向があると思うからです。近所にイワシ料理を売り物にしている店があります。漁港から直接買い付けた新鮮なイワシをタタキ・刺身から揚げ物まで多様な料理にするのですが、大変に美味しいと感じます。食材には食材ごとに旨さがあり、それを最大限に引き出す(ないしは食材のマイナス面を消す)ことこそ、料理人の腕と言うべきでしょう。
よく西洋料理・日本料理をを問わず「天然 -食材名- の -料理名-」というメニューがありますよね。生で食べる刺身ならともかく、加熱調理し味付けする料理にこういったメニューを出す店は信用できません。消費者の「天然もの信仰」におもねり、原価を上げ、料理の値段も上げ、そのことで客単価を上げようとしているように見えるからです。
我々は価値観を変更する必要があります。従来は、養殖は天然の代替品でした。そうではなく
ということだと思います。
鮮魚信仰もあやうい
「許せない偽装食品ランキング」の6位は「解凍魚を鮮魚と偽った例」です。
この背景にも消費者の「鮮魚信仰」があると考えられます。この場合の「鮮魚信仰」というのは
です。スーパーマーケットの魚介類売場でも鮮魚は区別されています。かならず(生)か(解凍)かがラベルに明示されている。果たしてこの「信仰」は正しいのでしょうか。
我々の現代の食生活は冷凍・解凍魚に支えられています。たとえば、我々が普通食べるホンマグロ(クロマグロ)は冷凍ものがメインです。日本近海で穫れた「鮮魚としてのクロマグロ」は、それなりの鮨店やレストランが扱う食材であって、我々がスーパーマーケットで買ったり、一般の寿司店、回転寿司、レストランで出されるマグロは冷凍ものです。
冷凍と言っても、家庭用冷蔵庫での冷凍とは違います。太平洋で漁獲するクロマグロなどは、マイナス60℃ぐらいの極低温で急速冷凍しています。冷凍技術は非常に進歩しているので、食材本来の味を損なうことが少ないようになっています。また、冷凍技術が「魚介類の安定供給」を実現していることは言うまでもありません。冷凍魚は「在庫」できるので、供給量と需用量の変動をマッチングできる。冷凍技術がないと不漁の時には価格が急騰し、大漁が続くと穫った魚を(価格維持のために)破棄するようなことになりかねないでしょう。
もちろん、普通、冷凍では流通しない(鮮魚で流通している)魚もあります。アジ、イワシ、サンマなどです。これらは日本近海で大量に穫れ、そのため価格が安く、従って冷凍する意味が(今のところ)無いし、コスト的にも折り合わない魚種です。仮に資源が枯渇して、価格が高騰してくると冷凍されるでしょう。もちろん、そうなる以前に漁獲量をコントロールすべきです。
「鮮魚信仰」は根強いものがあるようです。その典型が、生け簀の魚をその場で調理する「活魚」でしょう。活魚は独特のおいしさがある(ものが多い)のも確かですが、それが魚の食べ方の最高だと考えるのは変です。肉もそうですが、魚もある程度の「熟成」が進むと別のおいしさが出てくる。
魚は冷凍・解凍で流通するのが基本であり、鮮魚は、日本近海で大量に穫れる魚は別にして、「すきやばし次郎」を代表格とする「鮮魚を取り扱う専門店」にまかせるべきでしょう。
だと思います。
国産食材が何故好まれるか
「許せない偽装食品ランキング」には「外国産を国産と偽った例」が2つ入っています。3位の牛肉と7位の豚肉です。
これを「許せない」とする背景には、
が(精肉に限らず一般的に)あるのだと思います。この信頼感は、農畜産業に携わる方々の長年の努力の結果であり、貴重なものだと思います。しかし国産食材を選ぶというのは、それだけの理由で良いのでしょうか。この「国産を選ぶ理由もあやうい」と思います。
というのも、もしそれだけの理由で国産食材を選ぶとしたら、外国産食材が国産と同等の品質(味と安全性)だということに確証が持てて、しかも外国産の方が値段が安いとなれば「外国産を選ぶ」といことになってしまうからです。もちろん消費行動としてはそれもアリですが、「国産」にはそれ以上の意味があります。
キーワードは「地産地消」です。それは地域レベルでも国レベルでも言える。
というのが正しい態度でしょう。食材を工業製品と同列に考えるのは間違っています。
無農薬の価値とは
「許せない偽装食品ランキング」には入っていませんが「無農薬栽培」も「鮮魚」や「国産」と似たところがあります。無農薬栽培された野菜などを購入する人の動機は、品質、特に安全性が理由だと思います。それは消費行動としては一応理解できます。
しかし現代では、農薬を使ったとしても残留農薬の安全性基準は明確だし、また厳しくチェックされています。農薬の安全性が実質的は問題になることは(少なくとも日本では)ないはずです。しかも、現代の農業全体を考えると農薬なしには成り立ちません。それは農業の効率化(労働コストの削減)大いに役立っている。またグローバルの視点で考えると、飢えている人々はいっぱいいるし、栄養不良が引き金となって病気になる子供も多数あるのだから、食料増産が非常に重要な課題であり、そのためにも農薬は欠かせません。
「無農薬栽培」に意義があるのは、人間に対するメリットではなく、人間以外の動植物に対するメリットです。農薬はその定義からして「農産物以外の植物と、害虫を含む昆虫や小動物を殺す薬剤」です。人間には好都合かもしれないが、自然環境に多大な影響を与える。もし農薬で死滅に追いやられる動植物だけを食料にしている鳥があったとしたら、その鳥も農薬で絶滅することになるでしょう(例えば、朱鷺の絶滅にはその側面がある)。
というのが「正しい」態度でしょう。
さらに言うと、有機肥料・有機栽培も似たところがあります。有機肥料の方が化学肥料よりも作物の栄養が豊富だとか、美味しいということは一般的には考えられません。作物が吸収する栄養分は同じだからです。もし、栽培した作物の栄養価に問題があるような化学肥料があったとしたら、製造した肥料会社は失格です。
有機栽培は農業におけるリユース・リサイクルを実現するものであり、それは循環型社会に向かう一翼をになうというところにこそ意義があるはずです。それに賛同するから価格が高くても有機栽培の農作物を購入するわけです。
「食」に関しては、
というキーワード、ないしは対立項があるわけですが、我々としては無自覚な「信仰」を排除し、マス・メディアに惑わされず、その意味(意義)を正しく理解した消費行動をとるべきだと思います。
外国産は別にして、養殖・解凍魚・農薬・化学肥料にネガティブなイメージがあるとしたら、そこに共通するのは「人工・人為」に対するマイナスのイメージでしょう。しかし畜産物で言うと、例えば、No.98「大統領の料理人」で「神戸ビーフ」の美味しさが世界的にも有名なことを書きました。それは、長年にわたる和牛の品種改良と、飼育方法のノウハウを蓄積してきた畜産家の努力の結果です。いわば「人工の極致」と言える。それを我々は、高いお金を出して、ありがたく食べています。「人工・人為」を排斥する必然性は何もないはずです。
本文の中で、主に魚介類についてですが、
という意味のことを書きました。東京湾で漁獲量が激減している「小柴のシャコ」(神奈川の柴漁港で揚がるシャコ)のことも書きました。
その東京湾での漁業を "持続可能" にしようと頑張っている船橋市の漁師さんのことが先日の新聞に出ていたので、是非それを紹介したいと思います。実は、この記事は2020年の東京オリンピック・パラリンピックとからんでいます。つまり、
ということが記事のポイントだからです。これが、東京湾における漁業(=江戸前の魚介類の漁)とからんでいる。以下にその記事を紹介します。下線は原文にはありません。
引用中に出てくるMSCとは Marine Stewardship Counsil というNPO団体で、もちろん日本にも支部があります。MSCでは「持続可能な漁業のための原則や規準」を定めていて、それにのっとって行われる漁業に対して「MSC漁業認証」(=海のエコラベル)を与えます。また「MSC漁業認証」で漁獲された水産物が消費者に渡るまでの流通経路に関わる企業に対して「CoC認証」を与えています。CoCとは「管理の連鎖(Chain of Custody)」で、認証水産物と非認証水産物を区別し、認証水産物のトレーサビリティを担保します。EUでは既に「MSC認証マーク」付きの魚が販売されています。
以上のこの記事に書かれている内容を要約すると、以下のようになるでしょう。
東京2020が決定したのは2013年9月7日です。開催の7年前であり、その7年間で組織委員会は環境省と連携して「持続可能な漁業」を推進し、それを "東京2020のレガシー" にする時間は十分にあったはずです。いわゆる "ハコモノ" よりこの方がよほどオリンピックのレガシーにふさわしい。
おそらく2024年のパリ・オリンピックでは、EUの "盟主" であるフランス(=近代オリンピックの提唱国)は必ずMSC認証を前提とするでしょう。その次の2028年のロサンジェルスもそうなる可能性が高いのではないでしょうか。カリフォルニアは民主党の牙城であり、"エコ" の意識の高い州です。このままでは「東京2020だけが世界のトレンドに逆らった異質な大会」になりかねません。そこがいかにも残念だと思いました。
我々はつい見過ごしがちなのですが、生食用のサケは養殖であることが必須です。その事情を書いた新聞記事を紹介します。
代表的な寄生虫のアニサキスはオキアミなどに寄生していて、サケはそれを餌として食べることで感染します。従って天然のサケを生で食べるのは危ない。まれに「生食用の天然サケ」を売っていますが、それは "ルイベ処理" といって、マイナス20度程度で24時間以上凍らせて殺菌処理をしたものです。天然のサケは加熱して食べるのが原則です。
一方、記事にあるように、養殖のサケは寄生虫の心配がないので生食が可能で、寿司や刺身やカルパッチョで食べられます。というわけで、現代の日本では、
天然サケ → 鮭
養殖サケ → サーモン(多くは輸入)
という言い方が定着しています。まさに、寿司ネタのサーモンは養殖のおかげなのです。
|
この中の9位である「養殖魚を天然ものと偽装するのは許せない」とするアンケート結果について考えてみたいと思います。この回答の裏には日本人の「天然もの信仰」があると思われるからです。
|
なお、以下の文章は「食品偽装という詐欺によって儲けを増やした業者」を擁護するつもりは全くありません。 |
「天然もの」は自然の収奪
人間の歴史を振り返ってみると、遙か昔は「狩猟採集」で食料を得ていたわけです。No.105「鳥と人間の共生」に書いたように、アフリカ(そして南米など)には、今でも狩猟採集の生活を送っている人々がいます。
約1万年から始まった「農耕」によって、人類はいわゆる文明を発達させ、その後「牧畜や酪農」も進んできました。現代の日本においては、食料にする植物や鳥獣のほとんどが「栽培・飼育」されたものです。野生の植物を食用にするのはあまり思いつきません。山菜類やキノコ類(松茸、マイタケなど)ぐらいでしょうか。野生の鳥獣もイノシシ・シカ・鴨などだと思いますが、一般の食料品店では流通していません。もっともヨーロッパでは事情が違い、パリのマルシェでは野生のウサギやキジ、ヤマバトなど(いわゆる、ジビエ)をそのままの姿で売っています。しかしこれは「ご馳走」の部類であって、一般的なのは飼育された鳥獣肉です。
ところが、魚介類だけは「狩猟採集」が今もメジャーで、農耕(栽培)や牧畜(飼育)に相当する「養殖」は一部なのです。
養殖が難しいのは、魚介類は水の中に棲んでいるので、自然の生態をつぶさに観察・調査するのが困難だからです。ウナギ(ニホンウナギ)は最近まで産卵場所すら分からなかった。最低限、生態が分からないと養殖技術は確立できません。
養殖にかかる設備投資や餌代などのコストも問題です。そのコストに見合うだけの高価な魚介類でないと、事業としては成立しない。従って「需要はあるが天然ものの漁獲量が少なく、高価な魚介類」が養殖される(それしかできない)。
そういう障壁を乗り越えて、現代では数々の魚介類が養殖されています。ブリ類(ハマチなど)、鯛、鱒、ふぐ、牡蠣、ホタテ、クルマエビなどがすぐに思いつきます。クロマグロ(ホンマグロ)も養殖されるようになりました。2002年、近畿大学がクロマグロの養殖に初めて成功したのですが、ここに至るまでには30年間のノウハウ蓄積があったと言います。養殖は人知の結晶だという典型例だと思います。
|
なお、ここで言う「養殖」とは、いわゆる「完全養殖」のことです。ウナギのように天然の稚魚(シラスウナギ)を捕らえて育てる方法(=蓄養)は「狩猟採集」であることに変わりがありません。最近ある雑誌を読んでいたら、シラスウナギの漁獲量はピーク時の40分の1に激減し、養殖業者の仕入れ価格は1キロあたり26万円(2006年)から250万円(2013年)にハネ上がったとありました。乱獲が招いた結果でしょう。既に環境省は2013年にニホンウナギを絶滅危惧種に指定しています。 そのウナギの完全養殖に(実験的に)成功したというニュースが近年流れました。これが資源の回復に貢献できるのか、注目したいと思います。 |
農畜産業における「栽培・飼育」の大きなメリットは「品種改良」が可能だということです。現代の食生活は先人たちが苦労してやってきた品種改良の恩恵で成り立っています。野生種の米だと北海道での米作はありえないし、イノシシに近い豚でも(味は別にして)同一重量の肉の生産コストは数倍にハネあがるでしょう。
魚介類の養殖も、今後「品種改良」が進むと思われます。そしてそれが今後の食料確保の鍵になる可能性が高いと予想します。
いろいろと理由はつけられるでしょうが「狩猟採集は自然の収奪」であることに変わりはありません。天然資源の枯渇を招かないように、持続可能な形で「狩猟採集」するのは簡単ではない。まず、魚介類が海や河川でどういう生態なのかが理解できていません。ある年に急にイワシの漁獲量が減った(ないしは増えた)といっても、その理由が(明確には)分からない。東京湾で有名な鮨ネタに、漁獲量が激減している「小柴のシャコ」(神奈川県の柴漁港で揚がるシャコ)があります。東京湾を横断するアクアラインができた時期とシャコの激減時期が同じようですが、その因果関係もわからない。
たとえ生態が解明できたとしても、狩猟採集には「自然への敬意」が必要で、人間サイドの自制心が必要です。これが現代の自由主義社会ではなかなか難しい。たとえ日本が自制したとしても、他国が自制しないと海産物では意味がなくなるわけです。
こういった「天然の魚介類の減少」を危惧する記事が最近の雑誌に掲載されたので、それを紹介したいと思います。
鮨ネタがどんどん消えていく
文藝春秋の2013年8月号に「鮨ネタがどんどん消えていく」という興味深い記事が掲載されました。この記事は、銀座「すきやばし次郎」の初代である小野二郎氏をはじめ、漁業関係者にも取材してまとめたものです。この記事で、最近特に天然の鮨ネタが減少していることが報告されています。その要因として、
| ・ |
黒潮の流れの変化(潮流が沖の方に離れた) | ||
| ・ |
海水温の上昇。特に秋になっても温度が下がらないという環境変化 | ||
| ・ |
世界的なSUSHIブームや、中国での需要増大 |
などがあげられていますが、大きな要因が
| ・ |
魚介類の穫りすぎ |
なのです。たとえば千葉県の鴨川漁港の漁労長の意見です。以下、下線は原文にはありません。
|
定置網は編み目を大きくして小さな魚を逃がせるけれど、巻き網は「根こそぎ穫る」ので資源に対する負荷が大きい、と解説されています。
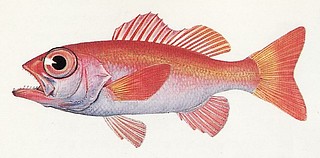
| ||
|
アカムツ(スズキ科)
(原色日本海水魚類図鑑。保育社 1985 より)
| ||
魚のように自由に泳ぎ回ることができない貝類は、資源の枯渇が起こると魚以上に深刻な問題になります。「すきやばし次郎」の小野二郎氏は、次のように言っています。
|
|
小野二郎氏は、天然ものが極めて入手困難になってしまった例として、シマアジをあげています。
|
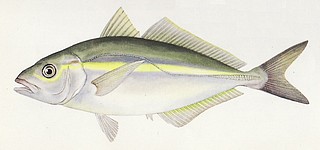
| ||
|
シマアジ(アジ科)
(原色日本海水魚類図鑑。保育社 1985 より)
| ||
養殖ものは味が悪いのか
上の引用の最後のところに天然シマアジと養殖シマアジの味の比較が書いてあります。小野二郎氏は他の食材についても天然と養殖の比較を語っています。
|
銀座「すきやばし次郎」は、6年連続でミシュランの3つ星を獲得した店です。その初代である小野二郎氏は、政府が認定する「現代の名工」(2005年度)にも選ばれた方です。その見識はさすがだと思いますね。特に天然と養殖に関する率直な意見が印象的です。小野氏の考えを(少々の推測を加えて)まとめると、以下のようになると思います。
|
「すきやばし次郎」のような店こそ徹底的に天然ものにこだわり、ユネスコの無形文化遺産にも登録された「和食」の伝統と文化を守ってもらうべきです。そして「そういう鮨屋があるから日本に旅行する」という外国人の方を増やしたい(ミシュランの3つ星とはそういう意味です)。
そのための必須条件は、天然の上質な鮨ネタが入手できることなのですが、それを危うくしているのが天然資源の枯渇であり、その大きな理由が乱獲なのです。
天然もの信仰のあやうさ
乱獲による資源の枯渇を招いている一翼を担っているのが消費者に蔓延する「天然もの信仰」であり、それを増大させているマス・メディアではないでしょうか。
「天然と養殖では味に差がありすぎる」という小野二郎氏の見解は「すきやばし次郎」という「ミシュラン3つ星店の基準」であり、それは非常に大切です。その一方で小野氏も「シマアジ、貝類、クルマエビ」に関しては、養殖ものが天然ものと遜色ないことを認めています。「一般基準」では、差がない食材がもっと多いはずです。
かつて、養殖ものの安全性が懸念されたことがありました。魚介類が病気にならないために抗生物質を大量に投与するといった例です。しかし(少なくとも日本では)そういう安全性に問題はない。輸入食材が不安だと言うなら国産の養殖ものを選択すればよい。
ちょっと疑っているのですが、一般人が「天然ものが旨い」と感じるのは、一つには「それが高価だから」ではないでしょうか。漁獲量が少ないから高価になる、高価だから美味しいと感じる・・・・・・という原理です。というのも、天然の安価な魚(いわゆる大衆魚)が旨いと評価されない傾向があると思うからです。近所にイワシ料理を売り物にしている店があります。漁港から直接買い付けた新鮮なイワシをタタキ・刺身から揚げ物まで多様な料理にするのですが、大変に美味しいと感じます。食材には食材ごとに旨さがあり、それを最大限に引き出す(ないしは食材のマイナス面を消す)ことこそ、料理人の腕と言うべきでしょう。
よく西洋料理・日本料理をを問わず「天然 -食材名- の -料理名-」というメニューがありますよね。生で食べる刺身ならともかく、加熱調理し味付けする料理にこういったメニューを出す店は信用できません。消費者の「天然もの信仰」におもねり、原価を上げ、料理の値段も上げ、そのことで客単価を上げようとしているように見えるからです。
我々は価値観を変更する必要があります。従来は、養殖は天然の代替品でした。そうではなく
| ・ |
「食」は栽培・飼育・養殖されたものが基本であり、農畜産物だけでなく魚介類もそうである。養殖できない(養殖されていない)ものはやむをえないが。 | ||
| ・ |
天然の魚介類は「味」の観点だけでなく「和食文化を守る」観点からも貴重である。しかしそれは料理の専門家の生食用に任せるべきである。 |
ということだと思います。
鮮魚信仰もあやうい
「許せない偽装食品ランキング」の6位は「解凍魚を鮮魚と偽った例」です。
| 順位 | 票数 | 表示食品 | 代用食品 | |||||
| 6位 | 532票 | 鮮魚 | 解凍魚 |
この背景にも消費者の「鮮魚信仰」があると考えられます。この場合の「鮮魚信仰」というのは
|
穫った魚介類を冷凍・解凍ぜず、冷蔵(ないしは常温)のまま調理するのが本来の姿だし、その方が美味しい、という信仰 |
です。スーパーマーケットの魚介類売場でも鮮魚は区別されています。かならず(生)か(解凍)かがラベルに明示されている。果たしてこの「信仰」は正しいのでしょうか。
我々の現代の食生活は冷凍・解凍魚に支えられています。たとえば、我々が普通食べるホンマグロ(クロマグロ)は冷凍ものがメインです。日本近海で穫れた「鮮魚としてのクロマグロ」は、それなりの鮨店やレストランが扱う食材であって、我々がスーパーマーケットで買ったり、一般の寿司店、回転寿司、レストランで出されるマグロは冷凍ものです。
冷凍と言っても、家庭用冷蔵庫での冷凍とは違います。太平洋で漁獲するクロマグロなどは、マイナス60℃ぐらいの極低温で急速冷凍しています。冷凍技術は非常に進歩しているので、食材本来の味を損なうことが少ないようになっています。また、冷凍技術が「魚介類の安定供給」を実現していることは言うまでもありません。冷凍魚は「在庫」できるので、供給量と需用量の変動をマッチングできる。冷凍技術がないと不漁の時には価格が急騰し、大漁が続くと穫った魚を(価格維持のために)破棄するようなことになりかねないでしょう。
もちろん、普通、冷凍では流通しない(鮮魚で流通している)魚もあります。アジ、イワシ、サンマなどです。これらは日本近海で大量に穫れ、そのため価格が安く、従って冷凍する意味が(今のところ)無いし、コスト的にも折り合わない魚種です。仮に資源が枯渇して、価格が高騰してくると冷凍されるでしょう。もちろん、そうなる以前に漁獲量をコントロールすべきです。
「鮮魚信仰」は根強いものがあるようです。その典型が、生け簀の魚をその場で調理する「活魚」でしょう。活魚は独特のおいしさがある(ものが多い)のも確かですが、それが魚の食べ方の最高だと考えるのは変です。肉もそうですが、魚もある程度の「熟成」が進むと別のおいしさが出てくる。
魚は冷凍・解凍で流通するのが基本であり、鮮魚は、日本近海で大量に穫れる魚は別にして、「すきやばし次郎」を代表格とする「鮮魚を取り扱う専門店」にまかせるべきでしょう。
むやみな「鮮魚信仰」は日本近海での魚介類の乱獲につながり、資源枯渇を招くだけ
だと思います。
国産食材が何故好まれるか
「許せない偽装食品ランキング」には「外国産を国産と偽った例」が2つ入っています。3位の牛肉と7位の豚肉です。
| 順位 | 票数 | 表示食品 | 代用食品 | |||||
| 3位 | 791票 | 和牛 | 外国産牛 | |||||
| 7位 | 499票 | 国産豚 | 外国産豚 |
これを「許せない」とする背景には、
|
同一の食材において「国産」と「外国産」があった場合、国産の方が品質(安全性、味)が良い。従って少々高くても国産を買うという、消費者の国産食材に対する信頼感 |
が(精肉に限らず一般的に)あるのだと思います。この信頼感は、農畜産業に携わる方々の長年の努力の結果であり、貴重なものだと思います。しかし国産食材を選ぶというのは、それだけの理由で良いのでしょうか。この「国産を選ぶ理由もあやうい」と思います。
というのも、もしそれだけの理由で国産食材を選ぶとしたら、外国産食材が国産と同等の品質(味と安全性)だということに確証が持てて、しかも外国産の方が値段が安いとなれば「外国産を選ぶ」といことになってしまうからです。もちろん消費行動としてはそれもアリですが、「国産」にはそれ以上の意味があります。
キーワードは「地産地消」です。それは地域レベルでも国レベルでも言える。
|
農畜産物は、国や地域の伝統文化、土地利用形態、人々の就業形態、自然環境との調和、さらには風景・景観にまで密接に結びついているから、それらを守り保全していくために地産地消が重要である。だから値段が高くても国産品(ないしは地域生産品)を選ぶ |
というのが正しい態度でしょう。食材を工業製品と同列に考えるのは間違っています。
無農薬の価値とは
「許せない偽装食品ランキング」には入っていませんが「無農薬栽培」も「鮮魚」や「国産」と似たところがあります。無農薬栽培された野菜などを購入する人の動機は、品質、特に安全性が理由だと思います。それは消費行動としては一応理解できます。
しかし現代では、農薬を使ったとしても残留農薬の安全性基準は明確だし、また厳しくチェックされています。農薬の安全性が実質的は問題になることは(少なくとも日本では)ないはずです。しかも、現代の農業全体を考えると農薬なしには成り立ちません。それは農業の効率化(労働コストの削減)大いに役立っている。またグローバルの視点で考えると、飢えている人々はいっぱいいるし、栄養不良が引き金となって病気になる子供も多数あるのだから、食料増産が非常に重要な課題であり、そのためにも農薬は欠かせません。
「無農薬栽培」に意義があるのは、人間に対するメリットではなく、人間以外の動植物に対するメリットです。農薬はその定義からして「農産物以外の植物と、害虫を含む昆虫や小動物を殺す薬剤」です。人間には好都合かもしれないが、自然環境に多大な影響を与える。もし農薬で死滅に追いやられる動植物だけを食料にしている鳥があったとしたら、その鳥も農薬で絶滅することになるでしょう(例えば、朱鷺の絶滅にはその側面がある)。
|
無農薬栽培は人間が利用する植物以外の動植物に対する影響がない(少ない)から、自然保護に役立つ。だから、高くても無農薬作物を選ぶ |
というのが「正しい」態度でしょう。
さらに言うと、有機肥料・有機栽培も似たところがあります。有機肥料の方が化学肥料よりも作物の栄養が豊富だとか、美味しいということは一般的には考えられません。作物が吸収する栄養分は同じだからです。もし、栽培した作物の栄養価に問題があるような化学肥料があったとしたら、製造した肥料会社は失格です。
有機栽培は農業におけるリユース・リサイクルを実現するものであり、それは循環型社会に向かう一翼をになうというところにこそ意義があるはずです。それに賛同するから価格が高くても有機栽培の農作物を購入するわけです。
「食」に関しては、
| 天然 | ←→ | 養殖 | ||||
| 鮮魚 | ←→ | 解凍魚 | ||||
| 国産 | ←→ | 外国産 | ||||
| 無農薬 | ←→ | 農薬 | ||||
| 有機肥料 | ←→ | 化学肥料 |
というキーワード、ないしは対立項があるわけですが、我々としては無自覚な「信仰」を排除し、マス・メディアに惑わされず、その意味(意義)を正しく理解した消費行動をとるべきだと思います。
外国産は別にして、養殖・解凍魚・農薬・化学肥料にネガティブなイメージがあるとしたら、そこに共通するのは「人工・人為」に対するマイナスのイメージでしょう。しかし畜産物で言うと、例えば、No.98「大統領の料理人」で「神戸ビーフ」の美味しさが世界的にも有名なことを書きました。それは、長年にわたる和牛の品種改良と、飼育方法のノウハウを蓄積してきた畜産家の努力の結果です。いわば「人工の極致」と言える。それを我々は、高いお金を出して、ありがたく食べています。「人工・人為」を排斥する必然性は何もないはずです。
(続く)
| 補記1:"江戸前" は持続可能か |
本文の中で、主に魚介類についてですが、
天然ものは "自然の収奪" であり、天然資源の枯渇を招かないように持続可能な形で漁業を続けるのは簡単ではない
という意味のことを書きました。東京湾で漁獲量が激減している「小柴のシャコ」(神奈川の柴漁港で揚がるシャコ)のことも書きました。
その東京湾での漁業を "持続可能" にしようと頑張っている船橋市の漁師さんのことが先日の新聞に出ていたので、是非それを紹介したいと思います。実は、この記事は2020年の東京オリンピック・パラリンピックとからんでいます。つまり、
オリンピックの選手村で使う魚介類は、持続可能な形で漁獲されたという「国際的な証明」を得たものに限るというトレンドになってきた。それは2012年のロンドン大会で始まり、2016年のリオデジャネイロ大会に引き継がれた。しかし東京2020は、そうはならなった。
ということが記事のポイントだからです。これが、東京湾における漁業(=江戸前の魚介類の漁)とからんでいる。以下にその記事を紹介します。下線は原文にはありません。
|
|
|
以上のこの記事に書かれている内容を要約すると、以下のようになるでしょう。
| 全国の漁業者の多くは「資源管理計画」を作り、行政当局に提出している。この計画にもとづく漁業は漁獲量べースで9割を占める。 | |
| しかしこの「資源管理計画」に第3者の審査はなく、計画通りに行うことも義務づけられていない。 | |
| 船橋市の漁協は、持続可能な漁業であるという日本の民間団体の認証を得た。国内の大多数の漁業者よりは一歩進んでいる。しかしこれは国際的な認証(その代表はMSC)ではない。現在、MSCの認証を得るための活動を続けている。 | |
| 2012年のオリンピック・ロンドン大会で、食材はMSC認証を受けたものを使うのが原則になった。これは2016年のリオデジャネイロ大会に引き継がれた。 | |
| しかし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックで使う食材は「資源管理計画」があればよいと、組織委員会が決めた。つまり「オリンピックで使う食材は持続可能性の認証を受けたもの」というトレンドが後退した。 |
東京2020が決定したのは2013年9月7日です。開催の7年前であり、その7年間で組織委員会は環境省と連携して「持続可能な漁業」を推進し、それを "東京2020のレガシー" にする時間は十分にあったはずです。いわゆる "ハコモノ" よりこの方がよほどオリンピックのレガシーにふさわしい。
おそらく2024年のパリ・オリンピックでは、EUの "盟主" であるフランス(=近代オリンピックの提唱国)は必ずMSC認証を前提とするでしょう。その次の2028年のロサンジェルスもそうなる可能性が高いのではないでしょうか。カリフォルニアは民主党の牙城であり、"エコ" の意識の高い州です。このままでは「東京2020だけが世界のトレンドに逆らった異質な大会」になりかねません。そこがいかにも残念だと思いました。
(2019.11.26)
| 補記2:生食用のサケは養殖が必須 |
我々はつい見過ごしがちなのですが、生食用のサケは養殖であることが必須です。その事情を書いた新聞記事を紹介します。
|
代表的な寄生虫のアニサキスはオキアミなどに寄生していて、サケはそれを餌として食べることで感染します。従って天然のサケを生で食べるのは危ない。まれに「生食用の天然サケ」を売っていますが、それは "ルイベ処理" といって、マイナス20度程度で24時間以上凍らせて殺菌処理をしたものです。天然のサケは加熱して食べるのが原則です。
一方、記事にあるように、養殖のサケは寄生虫の心配がないので生食が可能で、寿司や刺身やカルパッチョで食べられます。というわけで、現代の日本では、
天然サケ → 鮭
養殖サケ → サーモン(多くは輸入)
という言い方が定着しています。まさに、寿司ネタのサーモンは養殖のおかげなのです。
(2020.11.14)
No.106 - 食品偽装と格付けチェック [社会]
テレビ朝日系の正月番組である「芸能人 格付けチェック」について、以前に2つの記事で取り上げました。
の2つです。
2013年(の後半)で日本で大きな話題になった事件に、一流ホテルや一流レストラン・料亭での食品偽装がありましたが、この一連の報道で私は「格付けチェック」を思い出してしまいました。「食品偽装」と「格付けチェック」がどう関連しているのか、それを順に説明したいと思います。
食品偽装事件
食品の偽装は、単に謝って済むような話ではありません。特に「一流」と言われるホテル・レストラン・料亭は、商売で一番大事な信用が大きく傷ついた事件です。振り返ってみると、過去には食品偽装で廃業した料亭があったし(2008年。船場吉兆)、雪印食品は2001年の牛肉偽装事件(外国産牛肉を国産と偽って国に買い取らせた事件)で会社の清算に追い込まれました。
今回の2013年の一連の食品偽装では、痛ましい自殺者まで出たと報道されています。
食品加工業の方が亡くなられた日付が不明ですが、記事が配信された時点より一定程度前だと考えられます。また「京都吉兆」と「食品加工業者」の関係にも不明点があります。記事をストレートに読むと、
と理解できますが、そうなると「京都吉兆の仕入れ責任者、ないしは料理長は、そんな区別もつかないほどの味覚障害だった」ということになります。ないしは「京都吉兆は問題のローストビーフの試食などを一切せず、完全に業者まかせで客に販売・提供した」ということになる。料理や食品の味と品質に徹底的にこだわるはずの「高級料亭」において、果たしてそんなことがありえるのでしょうか。もしそうだとしたら、京都吉兆は食品偽装以上に信用を落とすことになります。
これ以上の詮索はできないので想像で書くのはやめますが、とにかく食品偽装は、料亭・レストラン・食品製造業・流通業などの存続や人の生死にも関わるものであることは確かです。
また食品偽装は立派な犯罪です。2013年10月に北海道警は、中国産ウナギを国内産と偽って販売したとして、札幌のウナギ加工販売業者と東京の食品輸入会社を家宅捜索しました。不正競争防止法違反(原産地を誤認させる行為)の容疑です。これは責任者の逮捕もしくは書類送検につながるはずです。食品偽装は、その内容と程度、悪質度合いによると思うのですが、刑事事件になりうるということです。
今回の一連の「事件」は、偽装が広い範囲に渡っていたことも特徴です。「日本ホテル協会加盟のホテル247カ所のうち、34%にあたる84カ所で虚偽表示があった」(日経産業新聞 2013.12.26)ということなので、(ホテルに限って言うと)ごく一部とは言い難いわけです。
しかし、まじめに「妥当な価格で美味しい」食品を作ろうと努力している食品製造業の方は多いはずだし、一般の料理人・シェフの方々は食材にこだわっていて、中には自ら産地と交渉したりする人もいるわけです。偽装業者によって外食産業の信用が低下したとしたら、大変に残念なことです。
この一連の食品偽装事件に関する「市民の声」が新聞に出ていました。
「許せない偽装」ランキング
2013年12月14日(土)朝日新聞の土曜版に「許せない誤表示・偽装食品 - 日本人の劣化を象徴する事件」と題する記事で、読者アンケートの結果が掲載されました。
このアンケートは、朝日新聞デジタルの会員に登録した人を対象にウェブサイトで行ったもので、2827人から回答を得たとあります。質問は、「誤表示・偽装」と各新聞で報道された食品をリストアップし、それぞれについて「許せない」「許せる範囲」「問題ない」という回答を求めたものです。
No.83, 84「社会調査のウソ」で書いたように、この手の調査は「市民の平均的な意見」ではなく、かなりのバイアスがかかっていると考えられます。この場合のバイアスは、
が回答している(と予想される)ことです。また、記事には書いていませんが、朝日新聞はかなりの数の偽装食品をリストアップしてアンケートをしたようなので、回答者がすべての食品に答えたとは思えません。「自分にとって関心がある食品・食材」が中心のはずであり(それは許せない!となる)、それもバイアスとして考えられます。
とは言え、このアンケートは正確な市民意識調査を行うことが目的ではないので、許される範囲の調査方法だと思います。結果を分かりやすくまとめると以下のようになります。
「代用食品」という表現は新聞記事にはありません。「表示されている食品の代わりに使われた」という意味で、劣っているという価値判断を示すものでは全くありません。
読者の声
記事にはアンケートで寄せられた読者の声も掲載されていました。まず重要な指摘は「誤表示ではなく、作意的な偽装だ」というものです。
「誤表示というのは嘘であり、作意的な偽装だ」というのは全くその通りです。ある学者の方が別の新聞で、明快に次の主旨の解説をしていました(誰だったか忘れてしまいました。すみません)。
今回の一連の事件の場合、AだけがあってBがない(安い食品を高い食品と表示した例しか出てこない)のだから「偽装」です。偽装ではない、誤表示だと主張したいのなら、レストランの全メニューを調べて、Aの数 = Bの数(ほぼ同じ)を証明すればよいわけです。「誤表示」を発表したレストランやホテルは、恥の上塗りをしないように全てのメニューをモレなく調べたはずだから、AとBの数の把握は簡単にできるでしょう。それが出来ない以上(それをしない以上)、偽装・詐欺です。
「誤表示」が嘘であることを象徴するような記事がありました。許せない食品偽装ランキングで1位になった伊勢エビの偽装ですが、あるホテルは「伊勢エビとロブスターは同じ種類だと思っていた」と弁解したそうです。こんな嘘が通用すると思っていること自体「哀れみ」さえ感じます。「伊勢エビとロブスターは同じ種類のエビ」と思っている料理人・仕入れ担当者は皆無のはずだからです。
読者の声で多かったのは、こうまでして儲けに走る人たちの卑しさです。
「日本には一流がない」「商人道徳は死語」などの意見は、偽装したホテル・レストランが少数派だったことを考えると、そこまで言うのは明らかに間違いです。記事の見出しである「日本人の劣化」も同様です。しかし読者の「憤り」は分かります。要するに「客に対する裏切り行為」「詐欺行為」であるわけです。読者の意見に
というのがありましたが、的を射ています。表示が違うのはよくないが、「安いものを安く売る」ということで最低限の商道徳は守られているからです。
ここまでの新聞記事は納得だし、異論は全くありません。しかし、この記事を含む一連の食品偽装の報道や記事を見て感じるのは、大切な視点が欠けているということです。それを以下に書きます。
代用食品の視点が必要
一連の偽装事件で一番迷惑を被ったのは、代用にされた食品でしょう。たとえば「許せない偽装食品ランキング」の
です。いわゆる「加工肉」ですが、これらは本来「安い肉を美味しく食べる工夫」のはずです。ハンバーグステーキもそうです。くず肉やスジ肉を挽き肉にし「つなぎ」を入れて成形してステーキ状にするのは、安い肉を美味しく食べる、ないしは貴重な牛肉を余すことなく使う工夫です。現在のハンバーグステーキは一種の調理方法になっていて、あえて高級肉を挽き肉にすることもありますが、原点は肉をおいしく食べる工夫でしょう。
3位の「外国産牛」も、その品質が和牛より劣っているとは必ずしも言えない。No.98「大統領の料理人」で「神戸ビーフ」がおいしい肉の代名詞と使われていることに象徴されるように、和牛の品質の高さには世界でも定評があるのは確かです。しかし、たとえばオーストラリアには日本の消費者の好みに合わせた牛肉生産をやっている畜産家がいます。放牧での肥育をやめて穀物肥育に変えたりしている。「外国産牛」を否定することはありません。「農畜産物は地産地消であるべきで、だから和牛を選ぶ」という意見は正しいと思いますが、それは別の問題です。
代用にされた食品は、安価で品質のよい(美味しい)ものを消費者に提供しようと生産者や流通業者が努力をした結果の食品が多いはずで、報道もこのあたりを強調すべきでした。
ほとんどの人は食品偽装が分からない
2013年の一連の食品偽装で分かった大きな点は
ということです。お店にクレームを言う人、ネットでクレームのコメントをつける人がほとんどなかったからこそ、店側も安心して「偽装」を続けられたのでしょう。
「食べても食品偽装が分からない」のは何故かを考えてみると、もちろん料理を出す「店」を信用していたということでしょう。「偽装」など思ってもみなかったと・・・・・・。しかし、信用以外の理由が幾つか考えられます。
第1に「表示食品」と「代用食品」の味にほとんど差がないケースがあるはずです。たとえば、「許せない偽装ランキング」のベストテンには登場していませんが、高価なエビであるクルマエビです。
一連の食品偽装報道の中で、「クルマエビ」と表示された料理・食品に使われていたのが、実際は、
などだったという報道が随分ありました。しかし、これらはすべてクルマエビ科に属する大型エビです。姿・形は別にして、本当に味に有意な差があるのでしょうか。「味」というのは、調理され、料理として出されたものの味という意味です。
2013年12月のNHKの朝の情報番組(2013.12.22)で「クマエビ」を取材していました。クマエビは鹿児島では比較的ポピュラーな食材のようで、値段はクルマエビの6割程度です。取材の中で「クマエビはクルマエビよりおいしい」と断言している人の声を紹介していました。味覚には個人差があるので一般化はできませんが、そういう意見もあるということです。
第2に、料理は「食材+調理技術」を味わうものであって「食材」だけを味わうものではない、ということです。料理人やシェフは安価だが少々味に難がある食材でも、レシピの工夫で美味しくしてしまう。それこそがプロです。誰が食べても美味しい食材を美味しく調理するのなら、料理人の腕の見せどころがない(少ない)というものです。
第3に、Aという食材を認識できるのは、Aでないものを認識できるから、という原則です。大げさに言うと人の認知能力の問題です。
「許せない偽装ランキング」で1位の伊勢エビですが、伊勢エビの「味」を認識できるのは、「伊勢エビでない海老の味を認識できていて、伊勢エビと区別できる」のが条件です。仮に「伊勢エビの刺身」と称して実は「ロブスターの刺身」が出てきたとき、ロブスターの刺身(ないしは伊勢エビ以外の刺身)を食べたことがない人には判別が困難だと思います。そういう私自身、「ロブスターの刺身」を食べた記憶がありません。ロブスターは、蒸して(あるいは茹でて)、身をほぐして、しかるべきソースで食べた記憶しかない。伊勢エビの偽装としてロブスターの刺身が出てきても分からないのではないか。それとも、伊勢エビとロブスターは、生で食べると明らかに違うものなのか・・・・・・。こういう疑問が出てくること自体、違いが分からない証拠だと思います。
調理されたときは、生の味とはまた違います。食品偽装事件でロブスターを伊勢エビと偽装したのは名鉄グランドホテルで、その料理はテルミドール(エビを半身にして“グラタン風に”仕上げた料理)でした。テルミドールのようにオーブンで加熱調理したとき、伊勢エビとロブスターはどう違うのか、はたして区別できるのでしょうか。
ほとんどの人は食品偽装が分からない理由として、「(ほとんど)味に差がない」「調理技術」「認知能力」の3つをあげましたが、しかしもっと本質的な理由があると考えられます。それは、ほとんどの人は、食品を舌ではなく「情報で」判断しているということです。
ほとんどの人は食品を「情報で」判断する
2013年の一連の食品偽装で分かったもう一つの大きな点は、多くの人は自分の舌でおいしさの判断をしないということだと思います。つまり、
ということなのですね。
例をあげますと、シャンパンと偽ってスパークリング・ワイン出したというホテルがありましたが、シャンパンを飲んで「さすがシャンパン、おいしい」と言うのは「シャンパンという情報」によるのだと思います。フランスのシャンパーニュ地方で醸造されるスパークリング・ワイン(発泡性ワイン)だけがシャンパンを名乗れるわけですが、(今となっては)特殊な作り方をしているわけではなく、スパークリング・ワインの一種であることは間違いない。シャンパンはブランドを守るための品質管理が徹底しているからハズレがないということは確かに言えると思います。それは明らかなメリットです。しかし一般論としてシャンパンだけの特別な品質があるとは思えません。
私が一番美味しいと思うスパークリング・ワインは、シャンパンのあるブランドですが、このブランド以外のシャンパンは、フランスの他の地域やスペイン、イタリア、カリフォルニアなどの発泡性ワインと比べても一般的な差があるとは思えないのです。あくまで「差は、銘柄による差」であって、シャンパンかそうでないかの違いではない。
シャンパンは一つの例ですが、ここまで書いてくると、No.32「芸能人 格付けチェック」に似てきたことに気づきます。No.32 の最後に書いたのは以下の2点でした。
これを仮に「格付けチェックの原理」と呼ぶことにします。
「芸能人 格付けチェック」に出題される高級品は、それが食材だとすると、普通の人はめったに味わったことがないような「超高級食材」でした。たとえば 100g で1万円する隠岐牛(No.31 の最後の方)などです。それに対して今回の「事件」で偽装された食品は、一般の人が食べる食品です。そこが明らかに違うのですが、「格付けチェックの原理」は同じように働いていると思えます。
No.32「芸能人 格付けチェック」では
という主旨を書きましたが、それは伝統が生み出した「超高級品」だからこそ言えることです。食品偽装事件は一般の人も口にする食品の偽装であって、そんなことは言ってられない。
結局、食品偽装事件の教訓をまとめると、
ということだと思います。食品偽装事件は、消費者自身が、自ら騙される下地を作った(という面が多々ある)のではないでしょうか。さらにマスメディアがそれを煽った・・・・・・。我々は「情報」を味わうのではなく「食材と料理」を味わうべきであり、この「事件」を契機にそのことを心に留めておきたいものです。
|
No.31 - ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ No.32 - 芸能人 格付けチェック |
の2つです。
2013年(の後半)で日本で大きな話題になった事件に、一流ホテルや一流レストラン・料亭での食品偽装がありましたが、この一連の報道で私は「格付けチェック」を思い出してしまいました。「食品偽装」と「格付けチェック」がどう関連しているのか、それを順に説明したいと思います。
食品偽装事件
食品の偽装は、単に謝って済むような話ではありません。特に「一流」と言われるホテル・レストラン・料亭は、商売で一番大事な信用が大きく傷ついた事件です。振り返ってみると、過去には食品偽装で廃業した料亭があったし(2008年。船場吉兆)、雪印食品は2001年の牛肉偽装事件(外国産牛肉を国産と偽って国に買い取らせた事件)で会社の清算に追い込まれました。
今回の2013年の一連の食品偽装では、痛ましい自殺者まで出たと報道されています。
|
食品加工業の方が亡くなられた日付が不明ですが、記事が配信された時点より一定程度前だと考えられます。また「京都吉兆」と「食品加工業者」の関係にも不明点があります。記事をストレートに読むと、
|
食品加工業者は。複数のブロック肉を結着剤で固めた「ローストビーフ」を、単一肉を使った(正しい)ローストビーフと偽って京都吉兆に納入していた。この偽装は京都吉兆の指示によるものではない |
と理解できますが、そうなると「京都吉兆の仕入れ責任者、ないしは料理長は、そんな区別もつかないほどの味覚障害だった」ということになります。ないしは「京都吉兆は問題のローストビーフの試食などを一切せず、完全に業者まかせで客に販売・提供した」ということになる。料理や食品の味と品質に徹底的にこだわるはずの「高級料亭」において、果たしてそんなことがありえるのでしょうか。もしそうだとしたら、京都吉兆は食品偽装以上に信用を落とすことになります。
これ以上の詮索はできないので想像で書くのはやめますが、とにかく食品偽装は、料亭・レストラン・食品製造業・流通業などの存続や人の生死にも関わるものであることは確かです。
また食品偽装は立派な犯罪です。2013年10月に北海道警は、中国産ウナギを国内産と偽って販売したとして、札幌のウナギ加工販売業者と東京の食品輸入会社を家宅捜索しました。不正競争防止法違反(原産地を誤認させる行為)の容疑です。これは責任者の逮捕もしくは書類送検につながるはずです。食品偽装は、その内容と程度、悪質度合いによると思うのですが、刑事事件になりうるということです。
今回の一連の「事件」は、偽装が広い範囲に渡っていたことも特徴です。「日本ホテル協会加盟のホテル247カ所のうち、34%にあたる84カ所で虚偽表示があった」(日経産業新聞 2013.12.26)ということなので、(ホテルに限って言うと)ごく一部とは言い難いわけです。
しかし、まじめに「妥当な価格で美味しい」食品を作ろうと努力している食品製造業の方は多いはずだし、一般の料理人・シェフの方々は食材にこだわっていて、中には自ら産地と交渉したりする人もいるわけです。偽装業者によって外食産業の信用が低下したとしたら、大変に残念なことです。
この一連の食品偽装事件に関する「市民の声」が新聞に出ていました。
「許せない偽装」ランキング
2013年12月14日(土)朝日新聞の土曜版に「許せない誤表示・偽装食品 - 日本人の劣化を象徴する事件」と題する記事で、読者アンケートの結果が掲載されました。
このアンケートは、朝日新聞デジタルの会員に登録した人を対象にウェブサイトで行ったもので、2827人から回答を得たとあります。質問は、「誤表示・偽装」と各新聞で報道された食品をリストアップし、それぞれについて「許せない」「許せる範囲」「問題ない」という回答を求めたものです。
No.83, 84「社会調査のウソ」で書いたように、この手の調査は「市民の平均的な意見」ではなく、かなりのバイアスがかかっていると考えられます。この場合のバイアスは、
| ・ |
朝日新聞デジタルの会員(新聞読者の一部)であり、かつ、 | ||
| ・ |
社会問題に積極的に発言しようとする人で、 | ||
| ・ |
正義感の強い人 |
が回答している(と予想される)ことです。また、記事には書いていませんが、朝日新聞はかなりの数の偽装食品をリストアップしてアンケートをしたようなので、回答者がすべての食品に答えたとは思えません。「自分にとって関心がある食品・食材」が中心のはずであり(それは許せない!となる)、それもバイアスとして考えられます。
とは言え、このアンケートは正確な市民意識調査を行うことが目的ではないので、許される範囲の調査方法だと思います。結果を分かりやすくまとめると以下のようになります。
|
「代用食品」という表現は新聞記事にはありません。「表示されている食品の代わりに使われた」という意味で、劣っているという価値判断を示すものでは全くありません。
読者の声
記事にはアンケートで寄せられた読者の声も掲載されていました。まず重要な指摘は「誤表示ではなく、作意的な偽装だ」というものです。
|
「誤表示というのは嘘であり、作意的な偽装だ」というのは全くその通りです。ある学者の方が別の新聞で、明快に次の主旨の解説をしていました(誰だったか忘れてしまいました。すみません)。
|
今回の一連の事件の場合、AだけがあってBがない(安い食品を高い食品と表示した例しか出てこない)のだから「偽装」です。偽装ではない、誤表示だと主張したいのなら、レストランの全メニューを調べて、Aの数 = Bの数(ほぼ同じ)を証明すればよいわけです。「誤表示」を発表したレストランやホテルは、恥の上塗りをしないように全てのメニューをモレなく調べたはずだから、AとBの数の把握は簡単にできるでしょう。それが出来ない以上(それをしない以上)、偽装・詐欺です。
「誤表示」が嘘であることを象徴するような記事がありました。許せない食品偽装ランキングで1位になった伊勢エビの偽装ですが、あるホテルは「伊勢エビとロブスターは同じ種類だと思っていた」と弁解したそうです。こんな嘘が通用すると思っていること自体「哀れみ」さえ感じます。「伊勢エビとロブスターは同じ種類のエビ」と思っている料理人・仕入れ担当者は皆無のはずだからです。
読者の声で多かったのは、こうまでして儲けに走る人たちの卑しさです。
|
「日本には一流がない」「商人道徳は死語」などの意見は、偽装したホテル・レストランが少数派だったことを考えると、そこまで言うのは明らかに間違いです。記事の見出しである「日本人の劣化」も同様です。しかし読者の「憤り」は分かります。要するに「客に対する裏切り行為」「詐欺行為」であるわけです。読者の意見に
| 「 |
誤表記や偽装があっても、安いものを安く売れば問題は生じない」 |
というのがありましたが、的を射ています。表示が違うのはよくないが、「安いものを安く売る」ということで最低限の商道徳は守られているからです。
ここまでの新聞記事は納得だし、異論は全くありません。しかし、この記事を含む一連の食品偽装の報道や記事を見て感じるのは、大切な視点が欠けているということです。それを以下に書きます。
代用食品の視点が必要
一連の偽装事件で一番迷惑を被ったのは、代用にされた食品でしょう。たとえば「許せない偽装食品ランキング」の
|
牛脂注入肉のステーキ | |||
|
牛肉の成型肉 |
です。いわゆる「加工肉」ですが、これらは本来「安い肉を美味しく食べる工夫」のはずです。ハンバーグステーキもそうです。くず肉やスジ肉を挽き肉にし「つなぎ」を入れて成形してステーキ状にするのは、安い肉を美味しく食べる、ないしは貴重な牛肉を余すことなく使う工夫です。現在のハンバーグステーキは一種の調理方法になっていて、あえて高級肉を挽き肉にすることもありますが、原点は肉をおいしく食べる工夫でしょう。
3位の「外国産牛」も、その品質が和牛より劣っているとは必ずしも言えない。No.98「大統領の料理人」で「神戸ビーフ」がおいしい肉の代名詞と使われていることに象徴されるように、和牛の品質の高さには世界でも定評があるのは確かです。しかし、たとえばオーストラリアには日本の消費者の好みに合わせた牛肉生産をやっている畜産家がいます。放牧での肥育をやめて穀物肥育に変えたりしている。「外国産牛」を否定することはありません。「農畜産物は地産地消であるべきで、だから和牛を選ぶ」という意見は正しいと思いますが、それは別の問題です。
代用にされた食品は、安価で品質のよい(美味しい)ものを消費者に提供しようと生産者や流通業者が努力をした結果の食品が多いはずで、報道もこのあたりを強調すべきでした。
ほとんどの人は食品偽装が分からない
2013年の一連の食品偽装で分かった大きな点は
|
ほとんどの人は、食べても食品偽装が分からない |
ということです。お店にクレームを言う人、ネットでクレームのコメントをつける人がほとんどなかったからこそ、店側も安心して「偽装」を続けられたのでしょう。
「食べても食品偽装が分からない」のは何故かを考えてみると、もちろん料理を出す「店」を信用していたということでしょう。「偽装」など思ってもみなかったと・・・・・・。しかし、信用以外の理由が幾つか考えられます。
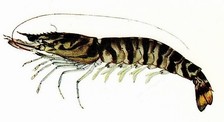
クルマエビ 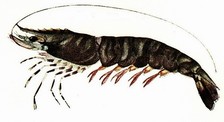
クマエビ 
ウシエビ(ブラックタイガー) | |||
|
日本近海に生息するクルマエビ科の大型エビ。ちなみに、最近養殖が盛んなバナメイエビは東太平洋(メキシコ付近)が原産である。原色甲殻類検索図鑑(北隆館 1982)より。
| |||
一連の食品偽装報道の中で、「クルマエビ」と表示された料理・食品に使われていたのが、実際は、
| ・ |
| ||
| ・ |
| ||
| ・ |
|
などだったという報道が随分ありました。しかし、これらはすべてクルマエビ科に属する大型エビです。姿・形は別にして、本当に味に有意な差があるのでしょうか。「味」というのは、調理され、料理として出されたものの味という意味です。
2013年12月のNHKの朝の情報番組(2013.12.22)で「クマエビ」を取材していました。クマエビは鹿児島では比較的ポピュラーな食材のようで、値段はクルマエビの6割程度です。取材の中で「クマエビはクルマエビよりおいしい」と断言している人の声を紹介していました。味覚には個人差があるので一般化はできませんが、そういう意見もあるということです。
第2に、料理は「食材+調理技術」を味わうものであって「食材」だけを味わうものではない、ということです。料理人やシェフは安価だが少々味に難がある食材でも、レシピの工夫で美味しくしてしまう。それこそがプロです。誰が食べても美味しい食材を美味しく調理するのなら、料理人の腕の見せどころがない(少ない)というものです。
第3に、Aという食材を認識できるのは、Aでないものを認識できるから、という原則です。大げさに言うと人の認知能力の問題です。
「許せない偽装ランキング」で1位の伊勢エビですが、伊勢エビの「味」を認識できるのは、「伊勢エビでない海老の味を認識できていて、伊勢エビと区別できる」のが条件です。仮に「伊勢エビの刺身」と称して実は「ロブスターの刺身」が出てきたとき、ロブスターの刺身(ないしは伊勢エビ以外の刺身)を食べたことがない人には判別が困難だと思います。そういう私自身、「ロブスターの刺身」を食べた記憶がありません。ロブスターは、蒸して(あるいは茹でて)、身をほぐして、しかるべきソースで食べた記憶しかない。伊勢エビの偽装としてロブスターの刺身が出てきても分からないのではないか。それとも、伊勢エビとロブスターは、生で食べると明らかに違うものなのか・・・・・・。こういう疑問が出てくること自体、違いが分からない証拠だと思います。
調理されたときは、生の味とはまた違います。食品偽装事件でロブスターを伊勢エビと偽装したのは名鉄グランドホテルで、その料理はテルミドール(エビを半身にして“グラタン風に”仕上げた料理)でした。テルミドールのようにオーブンで加熱調理したとき、伊勢エビとロブスターはどう違うのか、はたして区別できるのでしょうか。

| ||
|
伊勢エビとロブスター。「ホット・ロブスター」のホームページより引用( site : www.hotlobster.jp )
| ||
ここで一般化して考えてみると、世の中には食品偽装にかかわらず、本物の代わりにその代用物(偽物)を使った詐欺がいろいろあるわけです。こういった詐欺が成立するための条件は、
ということです(あたりまえだけれど)。偽造紙幣、偽ブランド品など、違いを教えられてよく見ないと分からない。偽ブランド品を満足して使っている人も多い。絵画などは専門家でも判断に迷う偽作(多くはプロの偽作者による)があります。テレビ東京系の「なんでも鑑定団」がバラエティー番組として成立する一つの理由は、まさに「素人では、本物と偽物の区別がつきにくい」という事実です。 もちろん「冷静に判断すれば、素人でも本物と偽物の区別がつくケースもあります。しかしそのような場合には、
わけです。振り込め詐欺が成立するゆえんです。不当に高額な商品の訪問販売とか、結婚詐欺とか、世の中にはいっぱいあります。もちろん偽物を販売する店の「ブランド」も「人間の認知能力を低下させる仕掛け」として働く。 結局のところ、食品偽造事件も、こういった一般的な「詐欺の原理」にのっとっているということでしょう。 |
ほとんどの人は食品偽装が分からない理由として、「(ほとんど)味に差がない」「調理技術」「認知能力」の3つをあげましたが、しかしもっと本質的な理由があると考えられます。それは、ほとんどの人は、食品を舌ではなく「情報で」判断しているということです。
ほとんどの人は食品を「情報で」判断する
2013年の一連の食品偽装で分かったもう一つの大きな点は、多くの人は自分の舌でおいしさの判断をしないということだと思います。つまり、
| ◆ |
食品を出す店のブランド(店の名前、その店が入っているホテルの名前など)で、食品のおいしさを判断する。 | ||
| ◆ |
食材・食品の名前を見て、それが高級という情報が(暗に)ついているから、おいしいと感じる |
ということなのですね。
例をあげますと、シャンパンと偽ってスパークリング・ワイン出したというホテルがありましたが、シャンパンを飲んで「さすがシャンパン、おいしい」と言うのは「シャンパンという情報」によるのだと思います。フランスのシャンパーニュ地方で醸造されるスパークリング・ワイン(発泡性ワイン)だけがシャンパンを名乗れるわけですが、(今となっては)特殊な作り方をしているわけではなく、スパークリング・ワインの一種であることは間違いない。シャンパンはブランドを守るための品質管理が徹底しているからハズレがないということは確かに言えると思います。それは明らかなメリットです。しかし一般論としてシャンパンだけの特別な品質があるとは思えません。
私が一番美味しいと思うスパークリング・ワインは、シャンパンのあるブランドですが、このブランド以外のシャンパンは、フランスの他の地域やスペイン、イタリア、カリフォルニアなどの発泡性ワインと比べても一般的な差があるとは思えないのです。あくまで「差は、銘柄による差」であって、シャンパンかそうでないかの違いではない。
シャンパンは一つの例ですが、ここまで書いてくると、No.32「芸能人 格付けチェック」に似てきたことに気づきます。No.32 の最後に書いたのは以下の2点でした。
| ◆ |
高級品と普及品(の上位クラス)の差は、意外にも少ない(ことがある)。特に、値段の差ほどの差はない。 | ||
| ◆ |
高級品を味わってみて(鑑賞してみて)素晴らしいと思うのは、それが高級品ということになっているから、つまり高級品だという情報がくっついているからである。 |
これを仮に「格付けチェックの原理」と呼ぶことにします。
「芸能人 格付けチェック」に出題される高級品は、それが食材だとすると、普通の人はめったに味わったことがないような「超高級食材」でした。たとえば 100g で1万円する隠岐牛(No.31 の最後の方)などです。それに対して今回の「事件」で偽装された食品は、一般の人が食べる食品です。そこが明らかに違うのですが、「格付けチェックの原理」は同じように働いていると思えます。
No.32「芸能人 格付けチェック」では
|
わずかな差を拡大して感じさせるのは蓄積された文化の力であり、それは大切である |
という主旨を書きましたが、それは伝統が生み出した「超高級品」だからこそ言えることです。食品偽装事件は一般の人も口にする食品の偽装であって、そんなことは言ってられない。
結局、食品偽装事件の教訓をまとめると、
| ◆ |
表示食品と代用食品の差は僅かである(ことが多い)。 | ||
| ◆ |
我々は安易なブランド(食品、食材、店)信仰をやめ、自分の舌で味や品質を判断すべきである。 | ||
| ◆ |
安易なブランド信仰は、食品・食材の価格高騰を招き、偽装(詐欺)の温床にもなりかねない。 |
ということだと思います。食品偽装事件は、消費者自身が、自ら騙される下地を作った(という面が多々ある)のではないでしょうか。さらにマスメディアがそれを煽った・・・・・・。我々は「情報」を味わうのではなく「食材と料理」を味わうべきであり、この「事件」を契機にそのことを心に留めておきたいものです。
(続く)
No.103 - 遺伝子組み換え作物のインパクト(2) [社会]
前回(No.102)に続いて遺伝子組み換え作物(GM作物)の話ですが、今回は「GM作物の問題点」ないしは「懸念」です。
GM作物による農業構造の変化
GM作物(特に農薬耐性作物)は、農業の構造を大きく変化させると考えられます。このことが、世界的にみると数々の社会問題を引き起こしかねない。
まず、GM作物の種子を研究・開発する会社(モンサント社など)は、
特定の作物にターゲットを絞るはずです。それは企業の売り上げを増やすためには当然の行為であって、この結果が「GM大豆」であり「GMトウモロコシ」です。「GM蕎麦」というのは永遠に出てこないでしょう。そんなものに研究投資をしても損をするだけです。
しかもGM作物は、非GM作物に比べて
という特徴を持っています。
これらのことが「特定作物の大規模栽培に農業を誘導する」ことは、容易に予測できます。その方向に進めば進むほど、農業としての「利益」を出しやすくなるからです。もちろん、国によって土地の広さや土質、気象条件、土地利用規制が違うので、進行の程度は違うでしょうが、一般論としてはそうなるはずです。この結果、
などが起こる。毎日新聞はアルゼンチンにおけるGM作物の現状を取材し、2013年10月に紙面で報告しました。以下、この記事を「アルゼンチン報告」と呼ぶことにします。「アルゼンチン報告」には以下のように書かれています。
GM大豆は栽培コストが安くて収穫量も多い。このことが、大豆の大規模農業へと誘導します。収穫期以外に1人か2人を雇用するのなら、その人数で維持できる最大面積まで農地を拡大した方が得です。3人か4人を雇用すると倍の面積の耕作が可能になる(資金と土地さえあれば)。いわゆる「規模のメリット」です。
9000ヘクタール(ほぼ、10キロメートル四方に相当)とは大変な広さですが、南米やオーストラリアで「大規模農家」というと、この程度の耕作面積のようです。GM作物以前の問題として、とても日本の農家がコスト的に競争できるものではありません。
しかし、このような大規模農業の裏では、土質の劣化や農薬使用量の増加といった「負の側面」が進行していきます。
「耐性雑草の増加」は、前回(No.102)でアメリカの事例を紹介しました(いわゆるスーパー雑草)。さらに、大豆農業の大規模化は、零細農家や牧畜業にも多大な影響を与えています。
引用の最後にある「農薬と雌牛の死産」の因果関係は、この記事だけでは明らかではありません。とりあえずは「そう農民が発言した」と受けとった方がよいと思います。
それはさておき、モノカルチャーという言葉は、普通「単一文化」という意味で使いますが、カルチャーの元々の意味は「耕作」です。その「耕作の単一化 = モノカルチャー化」が進んでいるわけです。
「生産コストが低い」「収穫量が多い」というようなキーワードは、それだけを聞くと全ての農家に恩恵があるように錯覚してしまいますが、自由経済・資本主義の原則を貫くと、決してそうはならないのです。
もちろん、いわゆる先進国では農業に対して各種の政府規制や補助金があり、アルゼンチンのようにはならないでしょう。しかし毎日新聞の「アルゼンチン報告」は、GM作物(特に、農薬耐性GM作物)がもたらすインパクトの本質を突いていると思います。
GM作物の懸念(1)安全性
GM作物については、長期に渡って人間が摂取したときの安全性が懸念されてきました。しかし現在においては、世界の多くの科学者は「安全」と考えています。日本でも大豆、トウモロコシなどの8品目が政府の審査を経て認可されています。「安全」という結論なのだと思います。
確かにグリホサート耐性大豆の「耐性のメカニズム」(前回 No.102)を見ると、そのGM大豆はEPSPS遺伝子とEPSPS酵素だけが変異形であり、アミノ酸もタンパク質も通常の大豆と全く変わらないようです。大豆の遺伝子や酵素は人間の体内に吸収されないので、安全という結論も一応は理解できます。
しかしGM作物は「農薬耐性」だけではありません。認可されているかどうかは別にして、主なGM作物には以下のようなものがあります。
などです。これらがおおむね人間にメリットをもたらすことは明らかです。「病害虫耐性」の作物は農薬使用量を減らし、また収穫量の増加につながります。「乾燥耐性」も干魃時における不作の緩和に役立つし、水資源の乏しい土地での食料生産に役立ちます。アフリカなどでは特に重要でしょう。現在、GM作物の商品化の最先端はこの「乾燥耐性」のようです。
以上のようなメリットはあるものの、GM作物の安全性の審査は厳格にするべきでしょう。遺伝子の人工的な改造の内容もいろいろです。
たとえばモンサント社は「害虫耐性」をもった新GM大豆をアルゼンチンとブラジルに投入しました(毎日新聞の「アルゼンチン報告」2013.10.23)。害虫がこの大豆を食べると死ぬそうです。本当に人間に影響はないのでしょうか。
作付けはされていませんが、自然界にはない「ビタミンAを含む米」が既に開発されています。世界的にみるとビタミンA欠乏症の人(ひどい場合は失明)が多いからです。それなら「食物アレルギーを起こさない大豆や小麦」も開発できるはずです。そのためには、大豆や小麦の本来のタンパク質を「改造」する必要があると思いますが、そういう風にどんどん突き進んでいいのかどうか(これらは一例です)。
GM作物について一番気になるのは、GM小麦が認可・栽培されていないことです。既に除草剤耐性をもつGM小麦は開発されているにもかかわらず、です。
GM小麦が安全なら、なぜモンサント社とアメリカ政府は自国の消費者や輸出業者や世界に向かって、堂々とその安全性を主張しないのかという疑問が当然出るわけです。
人類にとって小麦(そして米)こそ基幹食料であり、アフリカや新興国で飢えに苦しむ人は「小麦が入手できないから苦しんでいる」ケースが多いわけです。国連がUNマークを付けたトラックで小麦の袋を配っている様子がテレビで放映されたりします。GM小麦が小麦の増産につながるなら、それは人類にとって大きなプラスのはずです。
なぜGM小麦は栽培されないのか。それは人間が食べるものだから、ということのようです。
こういう話を聞くと、あくまで連想ですが、東京電力が「原子力発電は絶対安全」と言いつつ、原子力発電所を最大電力消費地域に近接した東京湾沿岸に作らずに、東北電力の管内(福島、新潟)に建設したことを思い出します。
まさか、GM作物を推進する人たちは
というようなイメージで考えているのではないでしょうね。そうでないとは思いますが・・・・・・。
GM作物の懸念(2)バイオメジャーによる食料支配
農業構造の変化や安全性やより(現時点で)もっと大きなGM作物の問題点だと思うのは、世界の食料、特に穀物のような基幹食料が、GM品種を作り出す「バイオメジャー」と呼ばれる、バイオ・テクノロジーで武装した特定の企業の支配下に置かれることです。支配下に置かれるというのが大袈裟なら、そういった企業が極めて強い影響力を持つということです。
まず農家に対する支配力ですが、GM作物は特許です。農家はモンサント社のGM作物の種子を購入するときに「自家採種をしない」という契約を結びます。つまり「収穫した種子をもとに再度栽培しない」という契約です。これに違反すると農家はモンサント社から特許侵害で訴訟を起こされることになります。アメリカ、カナダでは実際に訴訟になった例があるようです。モンサント社は農家の「契約違反」を監視するための組織を作り(俗称:モンサント・ポリス)畑の作物のDNA分析までやって「摘発」に努めています(以上、鈴木教授の本による)。
要するに農家はGM作物の種子をモンサント社だけから買い続けなければならないのです。
また、GM作物によりバイオメジャーの穀物市場支配力が強まります。GM種子が寡占市場になると(事実、現在のGM種子市場の 90% はモンサント社)、GM種子の値段を決める決定権は企業が握ることになる。綿の種子市場を席捲したあとに値上げという事例がインドであったようです。もちろん企業としては、研究開発費を捻出するためなどの理由があるのでしょう。
バイオテクノロジーを研究する大学の研究者・学者と企業の関係も気になります。GM作物の発展は、遺伝子組み換えを研究する研究者に企業から研究資金が流れる構造を生みます。こういった研究費の援助は一般的に行われています。ということは、「GM作物の安全性に疑問を投げかける」少数の学者の研究は、誹謗やバッシングを受けるでしょうね。日本の原子力発電の研究においても、安全性に疑問を投げかける少数の学者に対する誹謗が多々あったのを思い出します。学者の意見は政府の意志決定にも影響します。
さらにバイオメジャーの市場支配は、国に対する企業の強い影響力につながります。毎日新聞の「アルゼンチン報告」では、次のように書かれています。
アルゼンチンは、2001年にデフォルト(債務不履行)に陥りました。今も国家財政の建て直しが最重要課題のはずです。二度とデフォルトにはなりたくないと指導者は強く思っているでしょう。その財政建て直しの一端を担うのが「GM作物と35%の輸出税」というわけす。こうなるとモンサント社はアルゼンチンに対して強い影響力を行使できる条件が揃うことになります。
記事に「GM種子の特許保護を強化」とあります。内容は分からないのですが、たとえば特許侵害(GM作物の自家採種)をした農家への罰則強化などを想像します。GM種子の特許保護強化はモンサント社にとって有利です。この法改正はモンサント社の強い要求によるものではないでしょうか。それが当たっているかどうかはともかく、企業と国家の「密接関係」があり、それが企業収益と国家財政を潤すという構造が成立しうる状況だということは確かでしょう。
「アルゼンチン報告」には次のようなことも書かれています。
「害虫が食べると死ぬ新GM大豆」というのは、害虫耐性大豆というより「殺虫性大豆」です。詳細は分からないのですが、本当にこの大豆は人間に影響がないのでしょうか。ブラジルとアルゼンチンの政府は、安全性を厳格に審査したのでしょうか。企業と国家の「密接関係」によってこの作付けが可能になったのではないか。両国はモンサント社に「実験場」を提供したかっこうになっているのでは・・・・・・。いろいろと気になる報道です。
本家本元のアメリカに関して言うと、オバマ大統領は、俗称「モンサント保護法」と呼ばれる法律に署名し、議会に提出しました。「GM作物で健康被害が出ても、因果関係が証明できない限りGM種子の販売や植栽を差し止められない」という条項を含んだ法律です。これは世論の反発を招き、さすがに議会(上院)はこの条項を最終的に削除しました(2013年9月)。オバマ政権はモンサント社と密着していたが、議会が良識を示したということでしょうか。
しかし「モンサント保護法」が提出された背景には、GM大豆やGMトウモロコシが米国にとっての戦略輸出物資であり、それが他国を(間接的に)支配する道具であり、そのことに特定の企業が深く関わっているという事実があるのだと思います。GM作物に関するアメリカ政府の行動をみると、モンサントを筆頭とするバイオメジャーはアメリカの国策会社の面があるかのようです。
EU諸国はGM作物について厳しい態度をとっている国が多いわけです。栽培・輸入を一切認めていない国があるし、認可されている作物は少数です。食品への表示義務も厳格です。それはEU諸国が、食料が一握りの企業に支配されるのは国家の安全保障の観点からまずいと考えているのではないでしょうか。
そもそもアメリカやヨーロッパの先進国は、基幹食料(小麦、乳製品、肉など)を自前で確保することは国家安全保障の問題だと考えて行動していると感じます。特にヨーロッパはアメリカや南米やオーストラリアのような広大な土地があるわけではないので、自由競争をすれば不利です。従って農畜産物に関税をかけ、また多大な補助金を農業・畜産業に出して、70%以上の食料自給率を維持しています(フランスは100%超)。食料自給率が40%程度しかない日本とは、国家の運営方針がだいぶ違うのです。
このようなEUにしてみると、穀物生産の根幹のところが一握りのバイオメジャーに「支配」されることは何としても避けたいのだと思います。
GM作物の問題は、安全性よりも、企業の食料に対する影響力の問題の方がよほど大きいと感じます。
企業活動と基本食料
モンサント社は企業としての当然の行動をしていると考えられます。GM作物に対する懸念やマイナス面はあるが、GM作物が世界の食料増産に役立つこともまた事実です。それは農薬がない農業が(一般的には)考えられないのと似ています。特許で農民を縛るのも、そうしないと膨大な研究費を捻出(回収)できないからでしょう。CDやDVD、各種メディアの違法コピー・販売を野放しにしておくと、音楽産業や映画産業は成り立ちません。政府に対する影響力の行使やロビー活動もバイオメジャーだけの話ではありません。
要するにGM作物の種子は最先端技術で作り出された商品なのです。それは「商品」という観点だけからするとスマートフォンと変わらない。アップルが(今の形の)スマートフォンという概念を作り出し、サムスン電子が最速でそれに追従した。アップルとサムスンは、スマートフォン市場を独占したい、ないしは2社の寡占状態を維持したいと思っていることでしょう。それは、GM作物を研究・開発するバイオメジャーの独占状態と同じです。
しかし、そもそもスマートフォンと大豆を同列に考えてよいのかという問題があるわけです。
企業は3ヶ月から1年の「短期の業績」を最大重要指標として行動します(行動せざるを得ない)。それが株価・時価総額をあげることにつながる。増収・増益が数年間続くと、今年も減益には絶対したくないと経営者は考えるでしょう。
そう行動せざるを得ない企業に、穀物という人間の生存にとって必須で、健康に直結するものを任せていいとは思えません。企業の利益と社会の利益の乖離が激しくなるのは必定です。GM作物については、政府の強力な規制と認可のガイドラインの厳格化、国民への情報開示がなによりも重要だと思います。
米国における初めての「遺伝子組み換え表示法」が成立したようです。
これが米国における今後の流れを作るのか、それともバーモント州という小さな州(人口は米国の州で49位)だから可能になったことなのかは分かりません。しかしナショナル・ブランドの食品は、2016年7月以降は表示をしないとバーモント州では売れなくなることは確かだと思います。今後、注視したいと思います。
GM作物による農業構造の変化
GM作物(特に農薬耐性作物)は、農業の構造を大きく変化させると考えられます。このことが、世界的にみると数々の社会問題を引き起こしかねない。
まず、GM作物の種子を研究・開発する会社(モンサント社など)は、
| ・ |
商品価値が高く | ||
| ・ |
生産規模が大きく | ||
| ・ |
流通量が多く | ||
| ・ |
国際貿易量も多い |
特定の作物にターゲットを絞るはずです。それは企業の売り上げを増やすためには当然の行為であって、この結果が「GM大豆」であり「GMトウモロコシ」です。「GM蕎麦」というのは永遠に出てこないでしょう。そんなものに研究投資をしても損をするだけです。
しかもGM作物は、非GM作物に比べて
| ・ |
栽培が容易 | ||
| ・ |
生産コストが安い | ||
| ・ |
収穫量が多い |
という特徴を持っています。
これらのことが「特定作物の大規模栽培に農業を誘導する」ことは、容易に予測できます。その方向に進めば進むほど、農業としての「利益」を出しやすくなるからです。もちろん、国によって土地の広さや土質、気象条件、土地利用規制が違うので、進行の程度は違うでしょうが、一般論としてはそうなるはずです。この結果、
| ・ |
特定作物への集中 | ||
| ・ |
連作による土壌の劣化 | ||
| ・ |
中小農家の経営的破綻 | ||
| ・ |
土地利用形態の根本的な変化 |
などが起こる。毎日新聞はアルゼンチンにおけるGM作物の現状を取材し、2013年10月に紙面で報告しました。以下、この記事を「アルゼンチン報告」と呼ぶことにします。「アルゼンチン報告」には以下のように書かれています。
|
GM大豆は栽培コストが安くて収穫量も多い。このことが、大豆の大規模農業へと誘導します。収穫期以外に1人か2人を雇用するのなら、その人数で維持できる最大面積まで農地を拡大した方が得です。3人か4人を雇用すると倍の面積の耕作が可能になる(資金と土地さえあれば)。いわゆる「規模のメリット」です。
|
9000ヘクタール(ほぼ、10キロメートル四方に相当)とは大変な広さですが、南米やオーストラリアで「大規模農家」というと、この程度の耕作面積のようです。GM作物以前の問題として、とても日本の農家がコスト的に競争できるものではありません。
しかし、このような大規模農業の裏では、土質の劣化や農薬使用量の増加といった「負の側面」が進行していきます。
|
「耐性雑草の増加」は、前回(No.102)でアメリカの事例を紹介しました(いわゆるスーパー雑草)。さらに、大豆農業の大規模化は、零細農家や牧畜業にも多大な影響を与えています。
|
引用の最後にある「農薬と雌牛の死産」の因果関係は、この記事だけでは明らかではありません。とりあえずは「そう農民が発言した」と受けとった方がよいと思います。
それはさておき、モノカルチャーという言葉は、普通「単一文化」という意味で使いますが、カルチャーの元々の意味は「耕作」です。その「耕作の単一化 = モノカルチャー化」が進んでいるわけです。
「生産コストが低い」「収穫量が多い」というようなキーワードは、それだけを聞くと全ての農家に恩恵があるように錯覚してしまいますが、自由経済・資本主義の原則を貫くと、決してそうはならないのです。
もちろん、いわゆる先進国では農業に対して各種の政府規制や補助金があり、アルゼンチンのようにはならないでしょう。しかし毎日新聞の「アルゼンチン報告」は、GM作物(特に、農薬耐性GM作物)がもたらすインパクトの本質を突いていると思います。
GM作物の懸念(1)安全性
GM作物については、長期に渡って人間が摂取したときの安全性が懸念されてきました。しかし現在においては、世界の多くの科学者は「安全」と考えています。日本でも大豆、トウモロコシなどの8品目が政府の審査を経て認可されています。「安全」という結論なのだと思います。
確かにグリホサート耐性大豆の「耐性のメカニズム」(前回 No.102)を見ると、そのGM大豆はEPSPS遺伝子とEPSPS酵素だけが変異形であり、アミノ酸もタンパク質も通常の大豆と全く変わらないようです。大豆の遺伝子や酵素は人間の体内に吸収されないので、安全という結論も一応は理解できます。
しかしGM作物は「農薬耐性」だけではありません。認可されているかどうかは別にして、主なGM作物には以下のようなものがあります。
| ◆ |
農薬耐性 | ||
| ◆ |
病害虫耐性 | ||
| ◆ |
乾燥耐性 | ||
| ◆ |
人間にとって有用な物質を含む作物 |
などです。これらがおおむね人間にメリットをもたらすことは明らかです。「病害虫耐性」の作物は農薬使用量を減らし、また収穫量の増加につながります。「乾燥耐性」も干魃時における不作の緩和に役立つし、水資源の乏しい土地での食料生産に役立ちます。アフリカなどでは特に重要でしょう。現在、GM作物の商品化の最先端はこの「乾燥耐性」のようです。
なお、乾燥耐性については、日経産業新聞の2013年10月3日付の記事に、米国大手企業の競争が載っていました。その記事によると、
とのことです。 デュポン社の技術者は「乾燥が植物に与える影響は非常に複雑であり、耐性を実現するには、1つの遺伝子を入れるより、いくつもの要素を組み入れる交配が向く」と言っています。グリホサート耐性はEPSPS遺伝子だけを「狙いうち」すればよいが(前回 No.102)、乾燥耐性ではそうはいかない、ということでしょう。あくまでデュポン側の見解ですが、その一方でデュポン社は、乾燥耐性GM種の研究を大々的に行っていると想像します。 乾燥耐性は従来手法(交配による品種改良)をも巻き込んで「熱い競争」になっているようです。 |
以上のようなメリットはあるものの、GM作物の安全性の審査は厳格にするべきでしょう。遺伝子の人工的な改造の内容もいろいろです。
たとえばモンサント社は「害虫耐性」をもった新GM大豆をアルゼンチンとブラジルに投入しました(毎日新聞の「アルゼンチン報告」2013.10.23)。害虫がこの大豆を食べると死ぬそうです。本当に人間に影響はないのでしょうか。
作付けはされていませんが、自然界にはない「ビタミンAを含む米」が既に開発されています。世界的にみるとビタミンA欠乏症の人(ひどい場合は失明)が多いからです。それなら「食物アレルギーを起こさない大豆や小麦」も開発できるはずです。そのためには、大豆や小麦の本来のタンパク質を「改造」する必要があると思いますが、そういう風にどんどん突き進んでいいのかどうか(これらは一例です)。
GM作物について一番気になるのは、GM小麦が認可・栽培されていないことです。既に除草剤耐性をもつGM小麦は開発されているにもかかわらず、です。
|

| |||
人類にとって小麦(そして米)こそ基幹食料であり、アフリカや新興国で飢えに苦しむ人は「小麦が入手できないから苦しんでいる」ケースが多いわけです。国連がUNマークを付けたトラックで小麦の袋を配っている様子がテレビで放映されたりします。GM小麦が小麦の増産につながるなら、それは人類にとって大きなプラスのはずです。
なぜGM小麦は栽培されないのか。それは人間が食べるものだから、ということのようです。
|
こういう話を聞くと、あくまで連想ですが、東京電力が「原子力発電は絶対安全」と言いつつ、原子力発電所を最大電力消費地域に近接した東京湾沿岸に作らずに、東北電力の管内(福島、新潟)に建設したことを思い出します。
まさか、GM作物を推進する人たちは
| 小麦 | ─── | 東京湾沿岸 | |
| 大豆 | ─── | 福島 | |
| トウモロコシ | ─── | 新潟 |
というようなイメージで考えているのではないでしょうね。そうでないとは思いますが・・・・・・。
GM作物の懸念(2)バイオメジャーによる食料支配
農業構造の変化や安全性やより(現時点で)もっと大きなGM作物の問題点だと思うのは、世界の食料、特に穀物のような基幹食料が、GM品種を作り出す「バイオメジャー」と呼ばれる、バイオ・テクノロジーで武装した特定の企業の支配下に置かれることです。支配下に置かれるというのが大袈裟なら、そういった企業が極めて強い影響力を持つということです。
まず農家に対する支配力ですが、GM作物は特許です。農家はモンサント社のGM作物の種子を購入するときに「自家採種をしない」という契約を結びます。つまり「収穫した種子をもとに再度栽培しない」という契約です。これに違反すると農家はモンサント社から特許侵害で訴訟を起こされることになります。アメリカ、カナダでは実際に訴訟になった例があるようです。モンサント社は農家の「契約違反」を監視するための組織を作り(俗称:モンサント・ポリス)畑の作物のDNA分析までやって「摘発」に努めています(以上、鈴木教授の本による)。
要するに農家はGM作物の種子をモンサント社だけから買い続けなければならないのです。
また、GM作物によりバイオメジャーの穀物市場支配力が強まります。GM種子が寡占市場になると(事実、現在のGM種子市場の 90% はモンサント社)、GM種子の値段を決める決定権は企業が握ることになる。綿の種子市場を席捲したあとに値上げという事例がインドであったようです。もちろん企業としては、研究開発費を捻出するためなどの理由があるのでしょう。
バイオテクノロジーを研究する大学の研究者・学者と企業の関係も気になります。GM作物の発展は、遺伝子組み換えを研究する研究者に企業から研究資金が流れる構造を生みます。こういった研究費の援助は一般的に行われています。ということは、「GM作物の安全性に疑問を投げかける」少数の学者の研究は、誹謗やバッシングを受けるでしょうね。日本の原子力発電の研究においても、安全性に疑問を投げかける少数の学者に対する誹謗が多々あったのを思い出します。学者の意見は政府の意志決定にも影響します。
さらにバイオメジャーの市場支配は、国に対する企業の強い影響力につながります。毎日新聞の「アルゼンチン報告」では、次のように書かれています。
|
アルゼンチンは、2001年にデフォルト(債務不履行)に陥りました。今も国家財政の建て直しが最重要課題のはずです。二度とデフォルトにはなりたくないと指導者は強く思っているでしょう。その財政建て直しの一端を担うのが「GM作物と35%の輸出税」というわけす。こうなるとモンサント社はアルゼンチンに対して強い影響力を行使できる条件が揃うことになります。
記事に「GM種子の特許保護を強化」とあります。内容は分からないのですが、たとえば特許侵害(GM作物の自家採種)をした農家への罰則強化などを想像します。GM種子の特許保護強化はモンサント社にとって有利です。この法改正はモンサント社の強い要求によるものではないでしょうか。それが当たっているかどうかはともかく、企業と国家の「密接関係」があり、それが企業収益と国家財政を潤すという構造が成立しうる状況だということは確かでしょう。
「アルゼンチン報告」には次のようなことも書かれています。
|
「害虫が食べると死ぬ新GM大豆」というのは、害虫耐性大豆というより「殺虫性大豆」です。詳細は分からないのですが、本当にこの大豆は人間に影響がないのでしょうか。ブラジルとアルゼンチンの政府は、安全性を厳格に審査したのでしょうか。企業と国家の「密接関係」によってこの作付けが可能になったのではないか。両国はモンサント社に「実験場」を提供したかっこうになっているのでは・・・・・・。いろいろと気になる報道です。
本家本元のアメリカに関して言うと、オバマ大統領は、俗称「モンサント保護法」と呼ばれる法律に署名し、議会に提出しました。「GM作物で健康被害が出ても、因果関係が証明できない限りGM種子の販売や植栽を差し止められない」という条項を含んだ法律です。これは世論の反発を招き、さすがに議会(上院)はこの条項を最終的に削除しました(2013年9月)。オバマ政権はモンサント社と密着していたが、議会が良識を示したということでしょうか。
しかし「モンサント保護法」が提出された背景には、GM大豆やGMトウモロコシが米国にとっての戦略輸出物資であり、それが他国を(間接的に)支配する道具であり、そのことに特定の企業が深く関わっているという事実があるのだと思います。GM作物に関するアメリカ政府の行動をみると、モンサントを筆頭とするバイオメジャーはアメリカの国策会社の面があるかのようです。
EU諸国はGM作物について厳しい態度をとっている国が多いわけです。栽培・輸入を一切認めていない国があるし、認可されている作物は少数です。食品への表示義務も厳格です。それはEU諸国が、食料が一握りの企業に支配されるのは国家の安全保障の観点からまずいと考えているのではないでしょうか。
そもそもアメリカやヨーロッパの先進国は、基幹食料(小麦、乳製品、肉など)を自前で確保することは国家安全保障の問題だと考えて行動していると感じます。特にヨーロッパはアメリカや南米やオーストラリアのような広大な土地があるわけではないので、自由競争をすれば不利です。従って農畜産物に関税をかけ、また多大な補助金を農業・畜産業に出して、70%以上の食料自給率を維持しています(フランスは100%超)。食料自給率が40%程度しかない日本とは、国家の運営方針がだいぶ違うのです。
このようなEUにしてみると、穀物生産の根幹のところが一握りのバイオメジャーに「支配」されることは何としても避けたいのだと思います。
GM作物の問題は、安全性よりも、企業の食料に対する影響力の問題の方がよほど大きいと感じます。
企業活動と基本食料
モンサント社は企業としての当然の行動をしていると考えられます。GM作物に対する懸念やマイナス面はあるが、GM作物が世界の食料増産に役立つこともまた事実です。それは農薬がない農業が(一般的には)考えられないのと似ています。特許で農民を縛るのも、そうしないと膨大な研究費を捻出(回収)できないからでしょう。CDやDVD、各種メディアの違法コピー・販売を野放しにしておくと、音楽産業や映画産業は成り立ちません。政府に対する影響力の行使やロビー活動もバイオメジャーだけの話ではありません。
要するにGM作物の種子は最先端技術で作り出された商品なのです。それは「商品」という観点だけからするとスマートフォンと変わらない。アップルが(今の形の)スマートフォンという概念を作り出し、サムスン電子が最速でそれに追従した。アップルとサムスンは、スマートフォン市場を独占したい、ないしは2社の寡占状態を維持したいと思っていることでしょう。それは、GM作物を研究・開発するバイオメジャーの独占状態と同じです。
しかし、そもそもスマートフォンと大豆を同列に考えてよいのかという問題があるわけです。
企業は3ヶ月から1年の「短期の業績」を最大重要指標として行動します(行動せざるを得ない)。それが株価・時価総額をあげることにつながる。増収・増益が数年間続くと、今年も減益には絶対したくないと経営者は考えるでしょう。
そう行動せざるを得ない企業に、穀物という人間の生存にとって必須で、健康に直結するものを任せていいとは思えません。企業の利益と社会の利益の乖離が激しくなるのは必定です。GM作物については、政府の強力な規制と認可のガイドラインの厳格化、国民への情報開示がなによりも重要だと思います。
| 補記 |
米国における初めての「遺伝子組み換え表示法」が成立したようです。
|
これが米国における今後の流れを作るのか、それともバーモント州という小さな州(人口は米国の州で49位)だから可能になったことなのかは分かりません。しかしナショナル・ブランドの食品は、2016年7月以降は表示をしないとバーモント州では売れなくなることは確かだと思います。今後、注視したいと思います。
No.102 - 遺伝子組み換え作物のインパクト(1) [社会]
No.100「ローマのコカ・コーラ」の最後の方に、
との主旨を書きました。今回はその遺伝子組み換え作物について、それがどういうインパクトを社会に与えている(今後与える)のかを書いてみたいと思います。以下、「遺伝子組み換え」という意味で、GM作物、GM大豆、GM食品(=GM作物を原料とする食品)などと記述します。GMは、genetically modificated(遺伝的に改変された)の略です。
GM作物の現状
GM作物は「アメリカ発」の農産物なのですが、我々日本人にとって無関心ではいられません。というのも、一人当たりのGM食品摂取量が一番多いのは日本人だと考えられているからです。東京大学大学院の鈴木宣弘教授が書いた『食の戦争』(文春新書。2013)から引用します(下線は原文にはありません)。
GM作物は「アメリカ発」であるにもかかわらず、なぜアメリカでなく日本がGM食品摂取量が一番多い(と推定される)のか。その間接的な理由は、
では、日本人が直接摂取するGM大豆はどうなるのかという問題が出てくるわけです。納豆、味噌、大豆加工品である豆腐、醤油などです。GM作物は日本人にとって無関心ではいられないと書いたのは、こういう事情があります。
現代日本でGM作物の「流通状況」と「GM表示義務」について、鈴木教授の本から引用します。
最後の方に下線をつけた部分などは、とくに注視すべきでしょう。
この問題を考えるためには、そもそもGM作物とはどういうものか、それがどういう問題をはらんでいるのかを理解しておく必要があります。それを、世界最大のGM種子メーカーである米国・モンサント社の「除草剤・ラウンドアップと、それに耐性をもつGM作物(特に大豆)」について見ていきたいと思います。除草剤の「ラウンドアップ」は製造・販売元であるモンサント社の商品名であり、その主成分は「グリホサート」という化学物質です。
除草剤・グリホサート
農薬として使用される除草剤にはさまざまな種類がありますが、1970年に米国のモンサント社が開発した「グリホサート」という化学物質があります。これは除草剤(草を枯らす)というより「除植物剤」とでも言うべきで、全ての植物を枯らす薬品です。
植物には、植物だけにあるEPSPS(5 - エノールピルビルシキミ酸 - 3 - リン酸合成酵素。5-Enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase)という酵素があり、これは植物の生育に必須の3つのアミノ酸(トリプトファン、フェニルアラニン、チロシン)を作るのに不可欠な酵素(の一つ)です。グリホサートはEPSPSの酵素としての働きを阻害します。グリホサートを葉にかけると植物はその日のうちに成長が止まり、1~2週間で枯れてしまいます。
グリホサートの除草剤としての特徴は以下の3点です。
毒性と残留性が少ないのは明らかなメリットです。しかし全ての植物を枯らすということは、グリホサートの使用に制限がつくことになります。
グリホサートが使えるのは、基本的に作物の芽が出る前です。春に土地を耕し、作物の種を蒔く。そして作物の芽が出る前に生えてきた雑草に対し、グリホサートをあたり一面に散布する。すると雑草が枯れ、そのあとに作物の芽が出ることになります。
しかし作物が成長した後に生えてくる雑草にこの手は使えません。使うとしたら、畑に「分け入って」雑草だけに散布する必要があります。全ての植物を枯らすので「あたり一面に散布する」ことは出来ないのです。従って農家としては、他の除草剤も併用したり、人手で雑草を取ったりして「雑草管理」をすることになります。そもそも春に土地を耕すのも、雑草の種子を地中深く追いやり、発芽させないようにするため(が一つの目的)です。
ところが、モンサント社(本社:米国・ミズーリ州)は「GM作物」作り出すことによって、この状況を一変させました。
モンサント社の「グリホサート耐性作物」
もともとモンサント社は農薬会社です。グリホサートを主成分とする除草剤も「ラウンドアップ」という商品名で売り出していました。
このモンサント社がグリホサート耐性(グリホサートを散布しても枯れない)大豆を作り出したのです。モンサント社は1996年に、その大豆の種子を「ラウンドアップ・レディー」という商品名で発売開始しました。その後、綿、ナタネ、トウモロコシも発売しました。
グリホサート耐性をもつ大豆の開発には、モンサント社の長期に渡る研究があったようです。その様子を「日経サイエンス」から引用します。
「日経サイエンス」によると、モンサント社がこの開発にかけた費用は70万人・時とあります(モンサント社の発表)。どのくらいの金額かは書いてありませんが、個人的に推定してみると、1人・時を日本円で1万円と置くと、70億円という金額になります。これ以外に研究設備の費用がかかっているはずです。
「日経サイエンス」の記事にあるように、グリホサート耐性をもつ大豆を作り出すためには、
の、2つのステップが必要です。しかし、この2つともアテがあってできるものではないでしょう。(当時としては)ギャンブルとも思える研究・開発に(人件費だけで)70億円というオーダーの投資したわけです。ということは、モンサント社はグリホサート以外の除草剤に対する耐性遺伝子も探索・研究したと考えるのが自然です。「グリホサート決め打ち」で研究して失敗すると大きな損失が出るからです。たまたまヒットしたのがグリホサートだったのではないでしょうか。そして、後でも書きますが、他の除草剤に対する耐性遺伝子の探索は、現在も続いています。
グリホサート耐性大豆と除草剤・グリホサートの組み合わせは、農業の「雑草管理」の方法を一変させました。農家としては、除草するためにはとにかくグリホサートを散布すればよい。作物の芽が出る前でも、作物の生育中でも、です。しかも雑草と作物の両方に散布すると雑草だけが枯れる。これは、あたり一面に、たとえば飛行機からグリホサートを散布するというような手法が大々的に使えることを意味します。
農家の「雑草管理」の手間は圧倒的に少なくなり、農業のコストが削減されます。春先に畑を掘り返して雑草の発芽を防ぐ手間もいらなくなる。人が畑に分け入って雑草をとるような作業も皆無になる。しかも大規模農業ほどコスト削減効果が顕著になるはずです。また、明らかに大豆の増産効果があります。
しかし問題点もあります。グリホサート耐性大豆(商品名:ラウンドアップ・レディー)と、除草剤・グリホサート(商品名:ラウンドアップ)の組み合わせは「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導し、それが弊害を引き起こすことがあるのです。
スーパー雑草の拡大
単一農薬の広範囲使用で引き起こされる問題は「ラウンドアップに耐性をもつ雑草」つまりラウンドアップを散布しても枯れない雑草の出現です。
「日経サイエンス」2011年8月号に「はびこる農薬耐性雑草」という記事が掲載されまた。アメリカのサイエンス・ライターで元News Week編集長の J.アドラー氏が書いた記事です。この記事では、ラウンドアップ(有効成分:グリホサート)に耐性を持つ雑草を「スーパー雑草」と呼んでいて、アメリカでの状況が報告されています。
米国で作られているGM作物は、トウモロコシ、大豆、綿が主なものですが、これらの畑すべてにスーパー雑草は進出しているようです。
農業を効率化しコストを削減するはずの「除草剤・ラウンドアップと、ラウンドアップに耐性をもつGM作物」という組み合わせが、スーパー雑草の出現によって、本来の目的とは逆に農家の利益を圧迫する結果を招いているわけです。
雑草はどうやってラウンドアップ(グリホサート)から逃れるように進化したのでしょうか。そのメカニズムの一つが「日経サイエンス」に次のように解説されています(説明図参照)。
前の方で説明したように、グリホサートは全ての植物がもつEPSPS酵素の働きを阻害します。EPSPS酵素は植物の成長には欠かせないものなので、グリホサートを散布された植物は枯れてしまいます。
ところがスーパー雑草のDNAを調べると、EPSPS酵素を作り出す指令となっている「EPSPS遺伝子」の数が、普通の雑草の5~160倍もあります。つまり、グリホサートの阻害効果を打ち消してしまうほどの大量のEPSPS酵素を植物内に作り出して生き残るのです。
「日経サイエンス」の解説を読んで思うのですが、この雑草の生き残りメカニズムだと、グリホサートを通常使用量以上に大量に何回も散布すれば、スーパー雑草も枯れる(ものが出てくる)のではないでしょうか。ますます農薬使用量が増えるのではと想像します。いくらグリホサートの毒性が少ないと言っても、使用量が増加して「不適切使用」になるとメリットは無意味になってしまうのではと思います。
抗生物質を投与されても生き残る耐性菌と同じように、除草剤に耐性を持つ雑草の出現(進化)は以前から知られていました。スーパー雑草は別にラウンドアップに限ったことではありません。
しかし「ラウンドアップという単一の除草剤を、広範囲に使う農業」が、スーパー雑草の出現を助長(加速)していることは容易に想像できます。つまり、GM作物が植えられた広大な畑は、雑草の進化にとっての格好の実験場になっているということだと思います。
抗生物質にも耐性菌が出現しますが、抗生物質は人間の病気を治癒したり、人間の命を救う目的で開発されたものです。一方、GM作物は農業の効率化を狙っています。ふたつの目的はかなり違います。同じレベルで考えたり議論したりはできないでしょう。
モンサント社は、当然のことながらスーパー雑草(グリホサート耐性雑草)の出現(拡大)を予測していたはずです。農薬耐性雑草の出現は業界では常識だからです。何らかの対応策が必要ですが、除草剤はグリホサートはだけではありません。「日経サイエンス」にも、モンサント社が他の除草剤に対する耐性を持ったGM作物を売り出す計画だと書かれていました。GM作物の研究・開発には多大な資金が必要ですが、そのリターンも大きい。モンサント社にとって「折り込み済み」のスーパー雑草の出現・拡大は、また新たなビジネスチャンスをもたらすというわけです。
|
食料が企業に独占されると問題になる。その例が遺伝子組み換え作物(GM作物。大豆、とうもろこし、など) |
との主旨を書きました。今回はその遺伝子組み換え作物について、それがどういうインパクトを社会に与えている(今後与える)のかを書いてみたいと思います。以下、「遺伝子組み換え」という意味で、GM作物、GM大豆、GM食品(=GM作物を原料とする食品)などと記述します。GMは、genetically modificated(遺伝的に改変された)の略です。
GM作物の現状
GM作物は「アメリカ発」の農産物なのですが、我々日本人にとって無関心ではいられません。というのも、一人当たりのGM食品摂取量が一番多いのは日本人だと考えられているからです。東京大学大学院の鈴木宣弘教授が書いた『食の戦争』(文春新書。2013)から引用します(下線は原文にはありません)。
| ||||||||
GM作物は「アメリカ発」であるにもかかわらず、なぜアメリカでなく日本がGM食品摂取量が一番多い(と推定される)のか。その間接的な理由は、
|
アメリカで(および世界中で)「GM小麦」の栽培がされていない(認可されていない)からです。アメリカは、主食の(=人間が直接摂取する)小麦についてはGM小麦を作らないという方針を貫いているのです。反対論が強いからです。 |
では、日本人が直接摂取するGM大豆はどうなるのかという問題が出てくるわけです。納豆、味噌、大豆加工品である豆腐、醤油などです。GM作物は日本人にとって無関心ではいられないと書いたのは、こういう事情があります。
現代日本でGM作物の「流通状況」と「GM表示義務」について、鈴木教授の本から引用します。
|
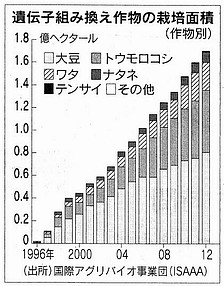
| |||
|
遺伝子組み換え作物の
2012年で栽培面積は1億7000万ヘクタールに急増し、栽培国は28カ国になった。作物は、大豆、トウモロコシ、ワタ、ナタネでほとんどを占める。米国では大豆、トウモロコシの9割がGM種である。日経産業新聞(2013.10.03)より。
| |||
この問題を考えるためには、そもそもGM作物とはどういうものか、それがどういう問題をはらんでいるのかを理解しておく必要があります。それを、世界最大のGM種子メーカーである米国・モンサント社の「除草剤・ラウンドアップと、それに耐性をもつGM作物(特に大豆)」について見ていきたいと思います。除草剤の「ラウンドアップ」は製造・販売元であるモンサント社の商品名であり、その主成分は「グリホサート」という化学物質です。
|
なお、以下のグリホサートについての説明は『日経サイエンス 2011年8月号』の記事「はびこる農薬耐性雑草」を参考にしました。 |
除草剤・グリホサート
農薬として使用される除草剤にはさまざまな種類がありますが、1970年に米国のモンサント社が開発した「グリホサート」という化学物質があります。これは除草剤(草を枯らす)というより「除植物剤」とでも言うべきで、全ての植物を枯らす薬品です。
植物には、植物だけにあるEPSPS(5 - エノールピルビルシキミ酸 - 3 - リン酸合成酵素。5-Enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase)という酵素があり、これは植物の生育に必須の3つのアミノ酸(トリプトファン、フェニルアラニン、チロシン)を作るのに不可欠な酵素(の一つ)です。グリホサートはEPSPSの酵素としての働きを阻害します。グリホサートを葉にかけると植物はその日のうちに成長が止まり、1~2週間で枯れてしまいます。
グリホサートの除草剤としての特徴は以下の3点です。
| ◆ |
グリホサートは全ての植物を枯らす。除草剤の中には単子葉植物(イネ科植物など)だけを枯らす(またはその逆)といったものがあるが、グリホサートにそういった性質はない。 | ||
| ◆ |
葉に直接散布する必要がある。土壌に散布すると除草効果が出るとか、そういったことはない。 | ||
| ◆ |
人間に対する毒性、植物への残留性が、他の除草剤と比較して少ない。 |
毒性と残留性が少ないのは明らかなメリットです。しかし全ての植物を枯らすということは、グリホサートの使用に制限がつくことになります。
グリホサートが使えるのは、基本的に作物の芽が出る前です。春に土地を耕し、作物の種を蒔く。そして作物の芽が出る前に生えてきた雑草に対し、グリホサートをあたり一面に散布する。すると雑草が枯れ、そのあとに作物の芽が出ることになります。
しかし作物が成長した後に生えてくる雑草にこの手は使えません。使うとしたら、畑に「分け入って」雑草だけに散布する必要があります。全ての植物を枯らすので「あたり一面に散布する」ことは出来ないのです。従って農家としては、他の除草剤も併用したり、人手で雑草を取ったりして「雑草管理」をすることになります。そもそも春に土地を耕すのも、雑草の種子を地中深く追いやり、発芽させないようにするため(が一つの目的)です。
ところが、モンサント社(本社:米国・ミズーリ州)は「GM作物」作り出すことによって、この状況を一変させました。
モンサント社の「グリホサート耐性作物」
もともとモンサント社は農薬会社です。グリホサートを主成分とする除草剤も「ラウンドアップ」という商品名で売り出していました。
このモンサント社がグリホサート耐性(グリホサートを散布しても枯れない)大豆を作り出したのです。モンサント社は1996年に、その大豆の種子を「ラウンドアップ・レディー」という商品名で発売開始しました。その後、綿、ナタネ、トウモロコシも発売しました。
グリホサート耐性をもつ大豆の開発には、モンサント社の長期に渡る研究があったようです。その様子を「日経サイエンス」から引用します。
|
「日経サイエンス」によると、モンサント社がこの開発にかけた費用は70万人・時とあります(モンサント社の発表)。どのくらいの金額かは書いてありませんが、個人的に推定してみると、1人・時を日本円で1万円と置くと、70億円という金額になります。これ以外に研究設備の費用がかかっているはずです。
「日経サイエンス」の記事にあるように、グリホサート耐性をもつ大豆を作り出すためには、
| ① |
グリホサート耐性をもつ「突然変異体の生物」を自然界の中から探し出す。 | ||
| ② |
その遺伝子を大豆に組み込んで、大豆として正常に生育し、グリホサート耐性をもち、かつその耐性が子孫に遺伝する「GM大豆」を作り出す。 |
の、2つのステップが必要です。しかし、この2つともアテがあってできるものではないでしょう。(当時としては)ギャンブルとも思える研究・開発に(人件費だけで)70億円というオーダーの投資したわけです。ということは、モンサント社はグリホサート以外の除草剤に対する耐性遺伝子も探索・研究したと考えるのが自然です。「グリホサート決め打ち」で研究して失敗すると大きな損失が出るからです。たまたまヒットしたのがグリホサートだったのではないでしょうか。そして、後でも書きますが、他の除草剤に対する耐性遺伝子の探索は、現在も続いています。
グリホサート耐性大豆と除草剤・グリホサートの組み合わせは、農業の「雑草管理」の方法を一変させました。農家としては、除草するためにはとにかくグリホサートを散布すればよい。作物の芽が出る前でも、作物の生育中でも、です。しかも雑草と作物の両方に散布すると雑草だけが枯れる。これは、あたり一面に、たとえば飛行機からグリホサートを散布するというような手法が大々的に使えることを意味します。
農家の「雑草管理」の手間は圧倒的に少なくなり、農業のコストが削減されます。春先に畑を掘り返して雑草の発芽を防ぐ手間もいらなくなる。人が畑に分け入って雑草をとるような作業も皆無になる。しかも大規模農業ほどコスト削減効果が顕著になるはずです。また、明らかに大豆の増産効果があります。
しかし問題点もあります。グリホサート耐性大豆(商品名:ラウンドアップ・レディー)と、除草剤・グリホサート(商品名:ラウンドアップ)の組み合わせは「単一農薬の広範囲使用」に農業を誘導し、それが弊害を引き起こすことがあるのです。
スーパー雑草の拡大
単一農薬の広範囲使用で引き起こされる問題は「ラウンドアップに耐性をもつ雑草」つまりラウンドアップを散布しても枯れない雑草の出現です。
「日経サイエンス」2011年8月号に「はびこる農薬耐性雑草」という記事が掲載されまた。アメリカのサイエンス・ライターで元News Week編集長の J.アドラー氏が書いた記事です。この記事では、ラウンドアップ(有効成分:グリホサート)に耐性を持つ雑草を「スーパー雑草」と呼んでいて、アメリカでの状況が報告されています。
|
米国で作られているGM作物は、トウモロコシ、大豆、綿が主なものですが、これらの畑すべてにスーパー雑草は進出しているようです。
|
農業を効率化しコストを削減するはずの「除草剤・ラウンドアップと、ラウンドアップに耐性をもつGM作物」という組み合わせが、スーパー雑草の出現によって、本来の目的とは逆に農家の利益を圧迫する結果を招いているわけです。
雑草はどうやってラウンドアップ(グリホサート)から逃れるように進化したのでしょうか。そのメカニズムの一つが「日経サイエンス」に次のように解説されています(説明図参照)。
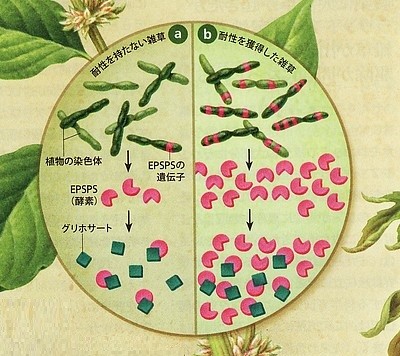
| ||
|
雑草がグリホサートから逃れる戦略
通常の雑草(a)は、グリホサートによってEPSPS酵素を阻害され、枯れる。しかしスーパー雑草(b)は、EPSPS遺伝子が大量に複製されている。この結果、グリホサートが阻害し切れないほどたくさんのEPSPS酵素が作り出される。
(日経サイエンス 2011.08 より)
| ||
前の方で説明したように、グリホサートは全ての植物がもつEPSPS酵素の働きを阻害します。EPSPS酵素は植物の成長には欠かせないものなので、グリホサートを散布された植物は枯れてしまいます。
ところがスーパー雑草のDNAを調べると、EPSPS酵素を作り出す指令となっている「EPSPS遺伝子」の数が、普通の雑草の5~160倍もあります。つまり、グリホサートの阻害効果を打ち消してしまうほどの大量のEPSPS酵素を植物内に作り出して生き残るのです。
「日経サイエンス」の解説を読んで思うのですが、この雑草の生き残りメカニズムだと、グリホサートを通常使用量以上に大量に何回も散布すれば、スーパー雑草も枯れる(ものが出てくる)のではないでしょうか。ますます農薬使用量が増えるのではと想像します。いくらグリホサートの毒性が少ないと言っても、使用量が増加して「不適切使用」になるとメリットは無意味になってしまうのではと思います。
抗生物質を投与されても生き残る耐性菌と同じように、除草剤に耐性を持つ雑草の出現(進化)は以前から知られていました。スーパー雑草は別にラウンドアップに限ったことではありません。
しかし「ラウンドアップという単一の除草剤を、広範囲に使う農業」が、スーパー雑草の出現を助長(加速)していることは容易に想像できます。つまり、GM作物が植えられた広大な畑は、雑草の進化にとっての格好の実験場になっているということだと思います。
抗生物質にも耐性菌が出現しますが、抗生物質は人間の病気を治癒したり、人間の命を救う目的で開発されたものです。一方、GM作物は農業の効率化を狙っています。ふたつの目的はかなり違います。同じレベルで考えたり議論したりはできないでしょう。
モンサント社は、当然のことながらスーパー雑草(グリホサート耐性雑草)の出現(拡大)を予測していたはずです。農薬耐性雑草の出現は業界では常識だからです。何らかの対応策が必要ですが、除草剤はグリホサートはだけではありません。「日経サイエンス」にも、モンサント社が他の除草剤に対する耐性を持ったGM作物を売り出す計画だと書かれていました。GM作物の研究・開発には多大な資金が必要ですが、そのリターンも大きい。モンサント社にとって「折り込み済み」のスーパー雑草の出現・拡大は、また新たなビジネスチャンスをもたらすというわけです。
(続く)
No.101 - インドのボトル・ウォーター [社会]
前回の No.100「ローマのコカ・コーラ」の続きです。コカ・コーラ社については強く覚えているテレビ番組があります。それは、2001年10月7日の「NHKスペシャル」で放映された「ウォーター・ビジネス」です。この中でNHKは、コカ・コーラ社がボトル・ウォーターのビジネスでインドに進出する過程を取材し、放映しました。以下その内容を紹介しますが、あくまで2001年時点でのインドの状況です。
インドの水道事情
このドキュメンタリー番組では、まずインドの水道事情が紹介されます。そもそもインドの水道普及率は少なく、正確には覚えていませんが、確か30%とかそういう数字だったと思います。
水道が施設されている大都市でも、朝夕の30分しか水が出ないことがあったり、また1週間全く水が出ないこともある。水質も劣っていて、水道水から大腸菌が検出されたりする。特に統一的な水質基準はないようです。
水道がない地域では、週1回来るか来ないかの水道局の給水車に頼るしかない。それもなければ、井戸の水か、川の水を飲むしかない。大変に不衛生なわけです。
インドのボトル・ウォーター事情
このような水道事情により、インドでは必然的にボトル・ウォーターのビジネスが盛んです。インドのボトル・ウォーター業者は数千社あります。値段は決して安くないのですが、ボトル・ウォーターは衛生的に見えるので、どんどん売れます。
しかし、ボトルの洗浄が不十分だったり、蜘蛛の巣が張っているような不衛生な工場もある。中には「悪徳業者」がいて、水道の水を堂々とボトルに詰めて売っている。「堂々と」というのは、水道の水を詰めるところを番組で取材していたからです。別に隠している感じではありませんでした。
このボトル・ウォーターにも、国としての水質基準はありません。
グローバル・スタンダードの水質基準
コカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーターのビジネスに進出する戦略は、「グローバル・スタンダード」の水質基準を制定することでした。コンサルタントを雇い、政府や業者にその必要性を説得します。ボトル・ウォーターも品質が重要であり、品質こそが消費者の信頼を勝ち取るものだと言うわけです。これは、全くもって「正しい」主張です。
そのかいもあって、2001年にボトル・ウォーターの水質基準が制定されました。それを守らなければ行政処分があるという、先進国ではあたりまえの話です。インド政府の関係者は、これで欧米並みの基準ができたと鼻高々です。
しかし地元の大半の業者にとっては、水の浄化装置、検査装置を導入する設備投資ができません。業者の倒産が相次ぎます。コカ・コーラは、急速にインドでのボトルウォーターのシェアを伸ばしたのです。
地元業者の3つの選択肢
この番組の白眉は、コカ・コーラ社が雇ったコンサルタントがインドの地元のボトル・ウォーター業者と会談する場面です。コンサルタントは地元業者に「あなた方には3つの選択肢がある」と言います。
の3つです。自前でビジネスを続けるためには①が必須です。なぜなら、水質基準を守っていることを常時証明する必要があるからです。その①が出来ない以上、選択肢は②か③ですが、どちらかを選ばざるを得ないのなら③でしょう。大手資本とは、もちろんコカ・コーラ社のことです。
この番組が取材した以降、インドでコカ・コーラ社のボトル・ウォーターのビジネスが成功したのかどうかは知りません。日本でボトル・ウォーター、ミネラル・ウォーターというと「南アルプスの天然水」(サントリー)や「森の水だより」(日本コカ・コーラ)などのブランドに象徴されるように、清流がこんこんと湧き出す所に工場を作り、自然の恵みの一部を人間がいただくというイメージですが、インド亜大陸ではそうはいかないでしょう。地下水を汲み上げる方式が主流になるはずです。地下水を汲み上げてフィルターを装着した浄水器に高圧で注入しボトル・ウォーターを作る手法です。番組では、アメリカの工場と周辺住民のトラブルを取材していました。地下水を汲み上げると地下の水位が低下し、沼や池が枯れたり、井戸が枯れて農園の運営に支障が出たり、地盤が沈下したりという問題が発生する(ことが往々にしてある)のです。
それはさておき、このコカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーター市場に参入する経緯を見ていると、次の2つのことを考えさせられます。
の二つです。番組は2001年時点の話ですが、一般的に言える教訓があると思うのです。ここからはその一般的に言える話です。
グローバル・スタンダード
「グローバル・スタンダード」と言われるものをよく考えてみると、
であることが多いわけです。「先進国標準」は「トップランナー標準」と言い換えてもよい。つまり「その分野で最も進んでいる(と自負している)国の標準」であるわけです。2001年時点でのインドのボトル・ウォーターの水質基準・検査基準は、水道水の基準がないのにボトル・ウォーターの基準ができるという大変に奇妙な話なのですが、それはさておき「方向として極めては正しい」のでしょう。
しかし、近代化の浸透には早い国・遅い国があります。そもそも近代文明のスタート時期が違っています。遅くスタートした国にとってみると「トップランナー標準」の採用によって地元業者が倒産し、外国資本の支配が拡大するわけです。自由競争の社会においては、新たな競争ルールは特定の企業に有利に働くようになる。
近代化の進展状況以外に、地理的な条件もありそうです。インドのように雨期と乾期が交代する気候では、水道施設のための水源の確保が日本のようにはいかないでしょう。ダムを作るのも、場所がなかったり、莫大な投資が必要ではないでしょうか。地下水を汲み上げると、さっき書いたように環境問題を引き起こしかねない。
NHKスペシャルは、使い回したボトルに水道水を詰めて売る「悪徳業者」を取材していましたが、そもそも水道普及率が悪く、川の水を飲まざるを得ないような地域がたくさんある限り、悪徳業者には社会的意味があるわけですね。その業者からボトルを買うと少なくとも水道品質の水を飲めるのだから。
以上のような歴史的条件、地理的条件とは全く無関係に「トップランナー標準」が制定されると、「悪徳業者」は根絶やしになるか、闇業者とならざるを得ない。その「社会的意味」など消し飛んでしまうわけです。また、まともな業者も大資本配下になってしまう。「グローバル・スタンダード」は、こういう風に作用することを承知しておかないといけないと思います。
企業行動のグローバル・スタンダード
さらに、この場合の「グローバル・スタンダード」とは、単に「水質基準のグローバル・スタンダード」というだけにとどまらず、「企業の行動パターン・行動原理のグローバル・スタンダード」と考えることが重要だと思います。
コカ・コーラ社から見ると(そして、先進国のボトル・ウォーター企業から見ると)、
なのですね。「グローバル」の視点からすると、明らかにそう見えると思います。「企業」と「企業でないもの」が同じ土俵とルールで経済的に戦うと、「企業でないもの」はひとたまりもありません。この企業行動の差の認識が重要でしょう。
この点をよく見ておかないと、問題の本質を見失しなうと思います。
企業の政治に対する影響力
コカ・コーラ社がボトル・ウォーターのビジネスでインドに進出した経緯をみると、企業活動の行き着くところが暗示されているように思います。
コカ・コーラ社が不当な行為をしているとか、そういうことではありません。TV番組で見る限り、コカ・コーラ社はまっとうなビジネスをしています。ボトル・ウォーターの水質基準を制定するように働きかけ、それをテコにインドのシェアを拡大するというのも、企業としては当然の行為でしょう。利潤を追求する企業なら、あたりまえと言ってもいい。しかもその水質基準は「正しい」のです。
しかし番組から予見されるのは、企業が政治に強い影響力をもち、さらにが政治(のある部分を)をコントロールするという姿です。それには大きな社会的リスクがあります。企業の行動原理は、極めて短期の利益を価値判断の基準として行われるため、それが特に
などの人間の生存に欠かせないものに関係すると、社会としての利益と反することが出てくる(こともある)と思うのです。
企業(=株式会社)の存在目的をたった1つだけ挙げよ、と言われたらなら、それは「利益」です。企業は利益をあげることで、従業員の雇用を維持し、給料を支払い、国家や地方公共団体に税金を払い(=国や地域に貢献し)、社会的貢献の原資としています。その「利益」は3ヶ月から1年の範囲で測定され、公表され、企業の評価がなされる。もちろん数年先を見越して投資をしないと長期的に存続できません。赤字を覚悟で投資することもある。しかしの数年先というのはせいぜい3年とか5年です。研究活動はもっと長くて10年ぐらいのスコープでなされるでしょうから、企業の行動原理は数ヶ月から10年程度の視野だと考えられます。
一方、民主主義の社会において、選挙における人々の投票行動や世論形成は、この1~2年(例:暮らしを良くする)から数10年(例:老後の福祉を充実する)の視野です。逆に、それ以上のことを考えにくいのが民主主義の弱点でしょう。「自分に関係ない」と思えることを基準にしにくいわけで、たとえば、次の世代の負担を残さないために国の借金は増やさないとか、100年後のために原子力発電は縮小しよう、とかは考えにくい。国民にとっては現在の快適さの方が重要なわけです。必然的に「今だけ、自分だけ」となり、それは政府の意志決定にも影響を与える。
こういった民主主義の「弱点」を補うのが、学者や研究者(および国の将来を考えるべき官僚)でしょう。地球温暖化は50年とか100年レンジの現象ですが、それを予測して、今から手を打つという提言をしたのは学者です(各国の利害不一致により、なかなか進まないですが)。
以上のことを考えると、企業の行動原理は最も短期視野であるといえます。もちろん資本主義経済においては企業の行動が富を生みだし、それが(たとえば)福祉の充実につながっていることは言うまでもないのですが、短期視野の行動が市民の利益と相反するリスクもある。特に、穀物などの代替し難い基幹食料では問題です。2011年、エジプトでの「アラブの春」はムバラク政権を崩壊させました。この引き金を引いたのは世界的な小麦価格の高騰です。メキシコでトウモロコシ価格の高騰に抗議するデモが全国に広がったこともありました(2007年)。基幹食料価格の短期の変動のもたらす影響は大きいのです。
日本の問題として考える
コカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーターに進出した過程を追ったNHKスペシャルは、日本から遠い、経済的新興国の話だと思ってしまいますが、そうではないと思います。一般化すると、現代の日本の問題としても十分考えられるはずです。例えば次のようなことが日本でも課題になっています。
という状況です。たとえばてTPP(環太平洋経済協力協定)の一環で、日本と米国が交渉する場合です。
自動車分野において、直接に交渉するのは政府ですが、その背後にいるのは米国と日本の自動車産業です。そしてこの「戦い」は「対等」だと考えられます。米国と日本の自動車産業は双方とも、技術、市場規模、競争力をもっているからです。日本政府が一方的に弱腰にならない限り、損だけをすることは無いはずだからです。
一方、農産物ではどうでしょうか。たとえば国際貿易が盛んな穀物です。交渉する政府のバックにいるのは、農家はもちろんですが、米国では「穀物メジャー」と呼ばれる企業群です。一方、それに「対抗する」日本の組織体は農協(JA)です。JAは共同組合であって利潤を追求する企業(株式会社)ではありません。企業と非企業が自由競争で経済的に戦うと(一般的に言って)非企業に勝ち目はないと思います。
企業は利益の確保(最大化)が生存原理であって、そのための行動が研ぎ澄まされています。効率化、コスト削減、品質の維持、市場の拡大、そのための宣伝活動などが徹底的に追求されています。穀物メジャーの支配する米国の農業生産では、その企業の論理が穀物生産農家や農機具メーカーや流通業者を巻き込んで、産業としての競争力が徹底的に高められているはずです。アメリカ政府の農業に対する補助金を差っ引いたとしても、それは言えると思います。
もちろん、自然環境や歴史的経緯が全く違う米国と日本の穀物生産を同等に比較するわけにはいきません。そもそも耕地面積(耕作可能面積)当たりの人口密度も農業人口も全く違うので、米国の方が穀物生産のコストは圧倒的に少ないはずです。日本もその点は十分に主張する必要がある。「自由貿易」というのは「世界最適生産」ということであり、それはテレビや衣料品や自動車ではアリかもしれないが、農業ではありえない。「世界最適生産」は「地産地消」の否定です。
しかしもうひとつ、米国と日本の穀物生産で大きいのは市場を支配・指導しているのが、一方では企業であり、一方では非企業だということだと思います。交渉して本当に大丈夫なのか、農業とは全く別の業種にしわ寄せがくることはないのか・・・・・・。
NHKスペシャルが2001年に放映したインドのボトル・ウォーターのストーリーは、決して人ごとではなく、現代の日本の問題でもあると思います。
インドの水道事情
このドキュメンタリー番組では、まずインドの水道事情が紹介されます。そもそもインドの水道普及率は少なく、正確には覚えていませんが、確か30%とかそういう数字だったと思います。
水道が施設されている大都市でも、朝夕の30分しか水が出ないことがあったり、また1週間全く水が出ないこともある。水質も劣っていて、水道水から大腸菌が検出されたりする。特に統一的な水質基準はないようです。
水道がない地域では、週1回来るか来ないかの水道局の給水車に頼るしかない。それもなければ、井戸の水か、川の水を飲むしかない。大変に不衛生なわけです。
インドのボトル・ウォーター事情
このような水道事情により、インドでは必然的にボトル・ウォーターのビジネスが盛んです。インドのボトル・ウォーター業者は数千社あります。値段は決して安くないのですが、ボトル・ウォーターは衛生的に見えるので、どんどん売れます。
しかし、ボトルの洗浄が不十分だったり、蜘蛛の巣が張っているような不衛生な工場もある。中には「悪徳業者」がいて、水道の水を堂々とボトルに詰めて売っている。「堂々と」というのは、水道の水を詰めるところを番組で取材していたからです。別に隠している感じではありませんでした。
このボトル・ウォーターにも、国としての水質基準はありません。
|
私も仕事で初めてインドに出張して帰国したあとは、1週間ほど下痢が続きました。飲み物や朝の手洗いなど、かなり注意していたつもりだったのですが・・・・・・。日本のように水道水が飲め、生魚や生野菜のサラダが食べられる環境のありがたさが分かりました(日本だけというわけではないですが)。 |
グローバル・スタンダードの水質基準
コカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーターのビジネスに進出する戦略は、「グローバル・スタンダード」の水質基準を制定することでした。コンサルタントを雇い、政府や業者にその必要性を説得します。ボトル・ウォーターも品質が重要であり、品質こそが消費者の信頼を勝ち取るものだと言うわけです。これは、全くもって「正しい」主張です。
そのかいもあって、2001年にボトル・ウォーターの水質基準が制定されました。それを守らなければ行政処分があるという、先進国ではあたりまえの話です。インド政府の関係者は、これで欧米並みの基準ができたと鼻高々です。
しかし地元の大半の業者にとっては、水の浄化装置、検査装置を導入する設備投資ができません。業者の倒産が相次ぎます。コカ・コーラは、急速にインドでのボトルウォーターのシェアを伸ばしたのです。
地元業者の3つの選択肢
この番組の白眉は、コカ・コーラ社が雇ったコンサルタントがインドの地元のボトル・ウォーター業者と会談する場面です。コンサルタントは地元業者に「あなた方には3つの選択肢がある」と言います。
| ① |
資金を投入して、水質検査装置を導入する。 | ||
| ② |
ボトル・ウォーターのビジネスから手を引く。 | ||
| ③ |
大手資本に買収される。 |

| |||
|
コカ・コーラ社のボトル・ウォーターのブランド、KINLEY。インドでもこのブランドで販売されている。Coca Cola Indiaのホームページより引用。本文とは関係ありません。
| |||
この番組が取材した以降、インドでコカ・コーラ社のボトル・ウォーターのビジネスが成功したのかどうかは知りません。日本でボトル・ウォーター、ミネラル・ウォーターというと「南アルプスの天然水」(サントリー)や「森の水だより」(日本コカ・コーラ)などのブランドに象徴されるように、清流がこんこんと湧き出す所に工場を作り、自然の恵みの一部を人間がいただくというイメージですが、インド亜大陸ではそうはいかないでしょう。地下水を汲み上げる方式が主流になるはずです。地下水を汲み上げてフィルターを装着した浄水器に高圧で注入しボトル・ウォーターを作る手法です。番組では、アメリカの工場と周辺住民のトラブルを取材していました。地下水を汲み上げると地下の水位が低下し、沼や池が枯れたり、井戸が枯れて農園の運営に支障が出たり、地盤が沈下したりという問題が発生する(ことが往々にしてある)のです。
それはさておき、このコカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーター市場に参入する経緯を見ていると、次の2つのことを考えさせられます。
| ◆ |
グローバル・スタンダードとは何か | ||
| ◆ |
企業の政治に対する影響力 |
の二つです。番組は2001年時点の話ですが、一般的に言える教訓があると思うのです。ここからはその一般的に言える話です。
グローバル・スタンダード
「グローバル・スタンダード」と言われるものをよく考えてみると、
| ◆ |
アメリカ標準(最強国標準) | ||
| ◆ |
アングロサクソン(米英)標準 | ||
| ◆ |
欧米標準 | ||
| ◆ |
先進国標準 |
であることが多いわけです。「先進国標準」は「トップランナー標準」と言い換えてもよい。つまり「その分野で最も進んでいる(と自負している)国の標準」であるわけです。2001年時点でのインドのボトル・ウォーターの水質基準・検査基準は、水道水の基準がないのにボトル・ウォーターの基準ができるという大変に奇妙な話なのですが、それはさておき「方向として極めては正しい」のでしょう。
しかし、近代化の浸透には早い国・遅い国があります。そもそも近代文明のスタート時期が違っています。遅くスタートした国にとってみると「トップランナー標準」の採用によって地元業者が倒産し、外国資本の支配が拡大するわけです。自由競争の社会においては、新たな競争ルールは特定の企業に有利に働くようになる。
近代化の進展状況以外に、地理的な条件もありそうです。インドのように雨期と乾期が交代する気候では、水道施設のための水源の確保が日本のようにはいかないでしょう。ダムを作るのも、場所がなかったり、莫大な投資が必要ではないでしょうか。地下水を汲み上げると、さっき書いたように環境問題を引き起こしかねない。
NHKスペシャルは、使い回したボトルに水道水を詰めて売る「悪徳業者」を取材していましたが、そもそも水道普及率が悪く、川の水を飲まざるを得ないような地域がたくさんある限り、悪徳業者には社会的意味があるわけですね。その業者からボトルを買うと少なくとも水道品質の水を飲めるのだから。
以上のような歴史的条件、地理的条件とは全く無関係に「トップランナー標準」が制定されると、「悪徳業者」は根絶やしになるか、闇業者とならざるを得ない。その「社会的意味」など消し飛んでしまうわけです。また、まともな業者も大資本配下になってしまう。「グローバル・スタンダード」は、こういう風に作用することを承知しておかないといけないと思います。
企業行動のグローバル・スタンダード
さらに、この場合の「グローバル・スタンダード」とは、単に「水質基準のグローバル・スタンダード」というだけにとどまらず、「企業の行動パターン・行動原理のグローバル・スタンダード」と考えることが重要だと思います。
コカ・コーラ社から見ると(そして、先進国のボトル・ウォーター企業から見ると)、
| インドのボトル・ウォーター業者は、インド固有の水事情(=低い水道普及率、水道水の品質の悪さ、水質の規制がない状況)に完全に依存しきって生き延びている、企業とは言えないような業態 |
なのですね。「グローバル」の視点からすると、明らかにそう見えると思います。「企業」と「企業でないもの」が同じ土俵とルールで経済的に戦うと、「企業でないもの」はひとたまりもありません。この企業行動の差の認識が重要でしょう。
この点をよく見ておかないと、問題の本質を見失しなうと思います。
企業の政治に対する影響力
コカ・コーラ社がボトル・ウォーターのビジネスでインドに進出した経緯をみると、企業活動の行き着くところが暗示されているように思います。
コカ・コーラ社が不当な行為をしているとか、そういうことではありません。TV番組で見る限り、コカ・コーラ社はまっとうなビジネスをしています。ボトル・ウォーターの水質基準を制定するように働きかけ、それをテコにインドのシェアを拡大するというのも、企業としては当然の行為でしょう。利潤を追求する企業なら、あたりまえと言ってもいい。しかもその水質基準は「正しい」のです。
しかし番組から予見されるのは、企業が政治に強い影響力をもち、さらにが政治(のある部分を)をコントロールするという姿です。それには大きな社会的リスクがあります。企業の行動原理は、極めて短期の利益を価値判断の基準として行われるため、それが特に
| ・ |
水 | ||
| ・ |
食料(穀物なのどの基幹食料) | ||
| ・ |
エネルギー |
などの人間の生存に欠かせないものに関係すると、社会としての利益と反することが出てくる(こともある)と思うのです。
企業(=株式会社)の存在目的をたった1つだけ挙げよ、と言われたらなら、それは「利益」です。企業は利益をあげることで、従業員の雇用を維持し、給料を支払い、国家や地方公共団体に税金を払い(=国や地域に貢献し)、社会的貢献の原資としています。その「利益」は3ヶ月から1年の範囲で測定され、公表され、企業の評価がなされる。もちろん数年先を見越して投資をしないと長期的に存続できません。赤字を覚悟で投資することもある。しかしの数年先というのはせいぜい3年とか5年です。研究活動はもっと長くて10年ぐらいのスコープでなされるでしょうから、企業の行動原理は数ヶ月から10年程度の視野だと考えられます。
一方、民主主義の社会において、選挙における人々の投票行動や世論形成は、この1~2年(例:暮らしを良くする)から数10年(例:老後の福祉を充実する)の視野です。逆に、それ以上のことを考えにくいのが民主主義の弱点でしょう。「自分に関係ない」と思えることを基準にしにくいわけで、たとえば、次の世代の負担を残さないために国の借金は増やさないとか、100年後のために原子力発電は縮小しよう、とかは考えにくい。国民にとっては現在の快適さの方が重要なわけです。必然的に「今だけ、自分だけ」となり、それは政府の意志決定にも影響を与える。
こういった民主主義の「弱点」を補うのが、学者や研究者(および国の将来を考えるべき官僚)でしょう。地球温暖化は50年とか100年レンジの現象ですが、それを予測して、今から手を打つという提言をしたのは学者です(各国の利害不一致により、なかなか進まないですが)。
以上のことを考えると、企業の行動原理は最も短期視野であるといえます。もちろん資本主義経済においては企業の行動が富を生みだし、それが(たとえば)福祉の充実につながっていることは言うまでもないのですが、短期視野の行動が市民の利益と相反するリスクもある。特に、穀物などの代替し難い基幹食料では問題です。2011年、エジプトでの「アラブの春」はムバラク政権を崩壊させました。この引き金を引いたのは世界的な小麦価格の高騰です。メキシコでトウモロコシ価格の高騰に抗議するデモが全国に広がったこともありました(2007年)。基幹食料価格の短期の変動のもたらす影響は大きいのです。
日本の問題として考える
コカ・コーラ社がインドのボトル・ウォーターに進出した過程を追ったNHKスペシャルは、日本から遠い、経済的新興国の話だと思ってしまいますが、そうではないと思います。一般化すると、現代の日本の問題としても十分考えられるはずです。例えば次のようなことが日本でも課題になっています。
| ◆ |
グローバルでの(あるいは、国をまたいだ広域経済圏での)経済活動に関する共通のルールを、政府間で決めようとしている。そのための交渉している。 | ||
| ◆ |
そのルールづくりには、企業が間接的に、ないしは直接的に強い影響力を発揮している。 |
という状況です。たとえばてTPP(環太平洋経済協力協定)の一環で、日本と米国が交渉する場合です。
自動車分野において、直接に交渉するのは政府ですが、その背後にいるのは米国と日本の自動車産業です。そしてこの「戦い」は「対等」だと考えられます。米国と日本の自動車産業は双方とも、技術、市場規模、競争力をもっているからです。日本政府が一方的に弱腰にならない限り、損だけをすることは無いはずだからです。
一方、農産物ではどうでしょうか。たとえば国際貿易が盛んな穀物です。交渉する政府のバックにいるのは、農家はもちろんですが、米国では「穀物メジャー」と呼ばれる企業群です。一方、それに「対抗する」日本の組織体は農協(JA)です。JAは共同組合であって利潤を追求する企業(株式会社)ではありません。企業と非企業が自由競争で経済的に戦うと(一般的に言って)非企業に勝ち目はないと思います。
企業は利益の確保(最大化)が生存原理であって、そのための行動が研ぎ澄まされています。効率化、コスト削減、品質の維持、市場の拡大、そのための宣伝活動などが徹底的に追求されています。穀物メジャーの支配する米国の農業生産では、その企業の論理が穀物生産農家や農機具メーカーや流通業者を巻き込んで、産業としての競争力が徹底的に高められているはずです。アメリカ政府の農業に対する補助金を差っ引いたとしても、それは言えると思います。
もちろん、自然環境や歴史的経緯が全く違う米国と日本の穀物生産を同等に比較するわけにはいきません。そもそも耕地面積(耕作可能面積)当たりの人口密度も農業人口も全く違うので、米国の方が穀物生産のコストは圧倒的に少ないはずです。日本もその点は十分に主張する必要がある。「自由貿易」というのは「世界最適生産」ということであり、それはテレビや衣料品や自動車ではアリかもしれないが、農業ではありえない。「世界最適生産」は「地産地消」の否定です。
しかしもうひとつ、米国と日本の穀物生産で大きいのは市場を支配・指導しているのが、一方では企業であり、一方では非企業だということだと思います。交渉して本当に大丈夫なのか、農業とは全く別の業種にしわ寄せがくることはないのか・・・・・・。
NHKスペシャルが2001年に放映したインドのボトル・ウォーターのストーリーは、決して人ごとではなく、現代の日本の問題でもあると思います。
No.100 - ローマのコカ・コーラ [社会]
No.7「ローマのレストランでの驚き」で、ローマのテルミニ駅の近くのレストランで見たテレビ番組の話を書きました。素人隠し芸勝ち抜き戦(敗者が水槽に落ちる!)に、オペラ『ノルマ』のソプラノのアリアを歌う男性が出てきて驚いたという話でした。
この時のローマ滞在で、もう一つ驚いたというか「印象に残った」ことがあったのでそれを書きます。
テルミニ駅の近くのホテル
ローマに着いた当日のことです。テルミニ駅の近くのホテル(日本人もよく泊まる、わりと有名なホテル)に到着したのは夜の9時ごろだったので、食事はそのホテルのレストランでとることにしました。そのホテルのレストランで目にした光景です。
私たち夫婦のテーブルの近くに、明らかにアメリカ人だと分かる夫婦がいました。その夫婦がコカ・コーラを飲みながら食事をしてたのです。誰でも知っている例の「コカ・コーラの瓶」がテーブルに置いてあったのですぐに分かりました。
この光景に少々「違和感」を抱きました。それはまず「観光でイタリアのホテルに来てまでコカ・コーラを注文しなくてもよいのに」という率直な感じです。
違和感の原因
しかしこれは、違和感を持つ方がおかしいわけです。イタリアのホテルでのコカ・コーラが「イタリアに抱く暗黙のイメージ」に反したのは確かですが、グローバル化の現代、コーラはあたりまえでしょう。ローマの街角にマクドナルドがあるのと同じです。レストランでコーラを要望するアメリカ人旅行客がいるという事実がある限り、ホテルがそれに応えるのは当然だと言える。
さらに、食事の際に何を飲もうと自由です。お酒はもちろんのこと、牛乳であってもよいし、トマトジュースであってもかまわない。もちろんコーラでもよい。コーラの甘みが食事の味を減じるとは思うのですが、本人がそれで満足であればよいわけです。
とは言うものの、今から自己分析してみると、もっと根本的な違和感の理由があるように思えます。それは単なる「コーラ」ではなく「コカ・コーラ」であったことが大きいと思うのです。つまり、
ということが、グローバル企業の戦略と密接に結びついていると考えられ、そこに「引っかかるもの」を感じたのだと思います。
コーラは、ハンバーガーやディズニーランド、ハリウッド映画と同じく「アメリカ文化」の典型、ないしは象徴です。そのアメリカ文化・コーラの主役は、アメリカに本社を置く2社のグローバル企業です。そしてコカ・コーラがイタリアのホテルのレストランで飲まれるまでになったのは、2社のビジネス戦略における
の結果だと考えられるのです。
コカ・コーラ社の戦略 = 独占
現代の自由主義経済では、規制業種を除いて本当の独占はないので、独占的状態、ないしは寡占状態を含めて「独占」と言うことにします。要するに、少数の企業の寡占状態があり、その少数企業が市場をコントロールをしている状況です。
一般の工業商品の寡占は色々あります。それはまず「特許」があるからです。以前の記事では、No.88「IGZOのブレークスルー」で書いたシャープのIGZO液晶ディスプレイがそうです。医薬品のビジネスも特許が重要です。特許切れの薬と同じ成分で製造するのがジェネリック薬です。
マイクロソフトのWindowsやOffice、IEなどの製品は、特許で固められているわけではありませんが、「利用者が多いほど便利になり、多数派に従わないと不利になる」という理由で寡占状態になったものです(いわゆる、ネットワーク外部性)。さらに、他社の追従を許さない飛び抜けた技術を持っていて独占的地位にある企業もあります。どちらかというと中規模以下の企業に多い。
しかし、食品(飲料を含む)は独占しにくいはずだと、我々は暗黙に考えています。特に広く行き渡っている食品はそうです。飲料で言うと、ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワイン、ボトル・ウォーター、ジュース、牛乳、コーヒー、紅茶、などは、それぞれの品目で多数の企業が競っています。基本的食料である米、小麦、野菜、牛肉、鶏肉、卵、大豆などもそうです。どこかの企業体が独占しているとか、寡占状態にあるということはない。
しかし「コーラ」は、世界的にみてもかなり広まっている飲料であるにもかかわらず、寡占状態(コカ・コーラ社とペプシコ社)が続いています。
実は「コーラ」に明確な定義はありません。120年ほど前にコーラがアメリカで発売された当時はコーラの実(コーラナッツ)のエキスが使われていましたが、現在は使われていないと見られています。コーラは「甘みと酸味があって、独特の香料の味がする炭酸飲料」であり、要するに「コカ・コーラとペプシコーラのような味の炭酸飲料がコーラである」と定義するしかないのです。
「現在はコーラナッツのエキスが使われていないと見られている」と説明したのは、レシピが不明だからです。コーラのレシピは極秘にされています。
他の飲料メーカでも、コカ・コーラ(ないしはペプシコーラ)相当の飲料は作れると思います。現代は化学分析の技術が極めて発達しているので、コカ・コーラの成分は詳細に分かるでしょう。似た炭酸飲料を作り出すことはできると思います。
しかしたとえ技術的に作れたとしても、どういう原料からどいういうプロセスで原液を作るか(=レシピ)が問題です。コスト面でコカ・コーラに対抗できないとビジネスとしては成り立ちません。さらに「味」が問題です。コカ・コーラ(ないしはペプシコーラ)の味に慣れてしまった消費者にどう売り込むのか。それは大きな壁になると思います。
その意味で、キリンのメッツ・コーラ(2012年発売)の(日本での)ヒットは画期的でした。食物繊維を配合し、食事の際に脂肪の吸収を押さえる効果があるということで、特定保険用食品(トクホ)に認定されました。初めての「トクホのコーラ」です。なるほど、こういうアプローチがあったのかと感心します。
こういったキリンの「挑戦」はあるものの、コカ・コーラ社、ペプシコ社の寡占状態は(今のところ)変わらないようです。その独占・寡占の源泉に、製品のレシピ(原料と製法)が秘匿されていることがあるわけです。
コカ・コーラの戦略 = 教育
コーラはグローバル企業・2社の寡占状態です。しかし清涼飲料全体を見ると「競争相手」は多いわけです。統計によると、日本では清涼飲料の生産量の18%が「炭酸飲料」であり、炭酸飲料の40%がコーラです。清涼飲料に占めるコーラのシェアは約7%ということになります。コーラ発祥の国、アメリカではもっと多いでしょう。
この状況の中でコーラの市場を拡大するには「炭酸+独特の味」というコーラに、子供の時から慣れてもらうことが必要です。「やみつき」とは言わないまでも、ある種の習慣性になるのがベストです。いわば「教育」が大切なわけです。
このためにコカ・コーラ社がとっている戦略が、ファスト・フードのチェーンに対する徹底的な売り込み(提携)だと思います。アメリカ発のファストフード店ではコーラがメジャーな清涼飲料として売られています。マクドナルド、ケンタッキー・フライドチキン、ミスター・ドーナッツ、サブウェイなどです。もちろんファストフードは子供だけのものではありませんが、特にアメリカ発のファストフード店は若年層が多い。日本発祥の牛丼とかの和食系ファストフードとはだいぶ違います。
さらに、これはアメリカでの話ですが「学校への売り込み」がされています。アメリカのジャーナリスト、エリック・シュローサーが書いた「ファストフードが世界を食いつくす」という本があります(楡井浩一訳。2001年。草思社。原題は、Fast Food Nation = ファストフードの国)。この本に、要約すると次のような記述があります。
学区とは、英語でスクール・ディストリクト(School District)です。アメリカでは「州」(State)の下に「郡」(County)があり、その下に「学区」があって教育行政を司っています。学区の運営費用(教育に関わる費用)はその地域からの固定資産税でまかなわれ、しかも独立採算です。教育設備や資材、教員の報酬などを充実させようとすると、収入をどう増やすか(=独自財源の確保)が問題になる。
アメリカの都市を歩いても自動販売機は見かけたことがありません。ところが学校には各種の自動販売機が置かれています(学校では盗まれる心配がないからだと思います)。この自動販売機からの収益の一部は学区の収入になります。また、スクールバスに広告を表示するといった例もあるようです。
上に引用したコロラドスプリングス第11学区の事例は、こういった「アメリカ事情」の文脈で理解する必要があります。コカ・コーラ社が製造・販売しているのはコカ・コーラだけではないので、他の飲料も含めた「コカ・コーラ社製品」の学区へのマーケティングと解釈できますが、その中でもコカ・コーラが重要な位置を占めているのは確かでしょう。
「学校への売り込み」は日本では考えられないことですが、この事例で言えるのは「コカ・コーラ社は若年層へのマーケティングに熱心だ」ということでしょう。コカ・コーラ社はグローバル企業です。世界中の国でコカ・コーラが販売されています。国によって販売促進の方法が違ってくるのは当然ですが「マーケティングの基本的考え方」は変わらないと思います。コカ・コーラ社はファストフード店との提携を含め、若い人たちや子供たちへの「教育」に熱心だと感じます。要するに「国民飲料」になってしまえば、企業としては安泰なわけです。かつ、寡占状態が維持できれば。
食料・食品と企業活動
ローマのホテルのコカ・コーラを思い出して考えたのは、消費者の「選択の自由」です。消費者サイドの自由意志による選択が、実は供給サイドによって作り出されている、ということは当然あるわけです。その「供給サイド」が、一握り企業で占められているケースがある。
それはファッションとかデジタル機器なら良いが、食品ではどうなのでしょうか。食品は人間が直接摂取するもので、健康に直結します。医薬品はそれ以上に健康に直結しますが(副作用など)、政府の厳しい認可管理がされています。それでも問題が起こる。
現代のコーラが健康問題を引き起こすというわけでは全くありません。昔と違って、カロリーもゼロになっています。しかし一般的に言って、食品という人間の健康に直結するものが、利益の最大化が目的である企業、それも一握りの企業のコントロール配下におかれると、問題を起こすことがあるのでは、という点を十分考えておくべきでしょう。
コーラは、たとえなくなったとしても(少なくとも日本では)大きな問題にはならないと思います。前のグラフでも明らかなように、清涼飲料の選択肢はほかにいっぱいあるからです。また、企業による独占といっても、コーラだけの問題であればどうということはないと思います。しかし一般に食料・食品が独占されると問題が起きる可能性がある。特に、代替がしにくい基幹食料である米、小麦、大豆などです。この点に関して非常に気になるのは、近年世界で問題になっている遺伝子組換え作物(GM作物。大豆、とうもろこしなど)です。このあたりは、我々消費者としても意識を高めていかないといけないと思います。
この時のローマ滞在で、もう一つ驚いたというか「印象に残った」ことがあったのでそれを書きます。
|
No.7 は3年前に書いた記事ですが、なぜそれを思い出したかと言うと、最近、ウッディ・アレン監督の『ローマでアモーレ』を見たからです。この映画では、葬儀屋の男が実は美声の持ち主という設定があり、家でシャワーを浴びながらオペラのアリアを歌うシーンが出てきます。ただし、以下の話はオペラとは全く無関係です。 |
テルミニ駅の近くのホテル
ローマに着いた当日のことです。テルミニ駅の近くのホテル(日本人もよく泊まる、わりと有名なホテル)に到着したのは夜の9時ごろだったので、食事はそのホテルのレストランでとることにしました。そのホテルのレストランで目にした光景です。
私たち夫婦のテーブルの近くに、明らかにアメリカ人だと分かる夫婦がいました。その夫婦がコカ・コーラを飲みながら食事をしてたのです。誰でも知っている例の「コカ・コーラの瓶」がテーブルに置いてあったのですぐに分かりました。
この光景に少々「違和感」を抱きました。それはまず「観光でイタリアのホテルに来てまでコカ・コーラを注文しなくてもよいのに」という率直な感じです。
違和感の原因

| |||
|
1915年にデザインされたコカ・コーラの歴史的な瓶、コンツアー・ボトル(contour bottle)。日本で初めての「立体商標=形そのものが商標」となった。日本コカ・コーラ社のホームページより引用。
| |||
さらに、食事の際に何を飲もうと自由です。お酒はもちろんのこと、牛乳であってもよいし、トマトジュースであってもかまわない。もちろんコーラでもよい。コーラの甘みが食事の味を減じるとは思うのですが、本人がそれで満足であればよいわけです。
とは言うものの、今から自己分析してみると、もっと根本的な違和感の理由があるように思えます。それは単なる「コーラ」ではなく「コカ・コーラ」であったことが大きいと思うのです。つまり、
|
アメリカの企業・2社(コカ・コーラ社とペプシコ社)がほぼ独占的に供給するアメリカ発の食品(飲料)を、イタリアのホテルのレストランで、アメリカ人旅行客が、食事の時に飲む |
ということが、グローバル企業の戦略と密接に結びついていると考えられ、そこに「引っかかるもの」を感じたのだと思います。
コーラは、ハンバーガーやディズニーランド、ハリウッド映画と同じく「アメリカ文化」の典型、ないしは象徴です。そのアメリカ文化・コーラの主役は、アメリカに本社を置く2社のグローバル企業です。そしてコカ・コーラがイタリアのホテルのレストランで飲まれるまでになったのは、2社のビジネス戦略における
| ・ |
独占(寡占) | ||
| ・ |
人々の嗜好に対する教育 |
の結果だと考えられるのです。
以降、
|
コカ・コーラ社の戦略 = 独占
現代の自由主義経済では、規制業種を除いて本当の独占はないので、独占的状態、ないしは寡占状態を含めて「独占」と言うことにします。要するに、少数の企業の寡占状態があり、その少数企業が市場をコントロールをしている状況です。
一般の工業商品の寡占は色々あります。それはまず「特許」があるからです。以前の記事では、No.88「IGZOのブレークスルー」で書いたシャープのIGZO液晶ディスプレイがそうです。医薬品のビジネスも特許が重要です。特許切れの薬と同じ成分で製造するのがジェネリック薬です。
マイクロソフトのWindowsやOffice、IEなどの製品は、特許で固められているわけではありませんが、「利用者が多いほど便利になり、多数派に従わないと不利になる」という理由で寡占状態になったものです(いわゆる、ネットワーク外部性)。さらに、他社の追従を許さない飛び抜けた技術を持っていて独占的地位にある企業もあります。どちらかというと中規模以下の企業に多い。
しかし、食品(飲料を含む)は独占しにくいはずだと、我々は暗黙に考えています。特に広く行き渡っている食品はそうです。飲料で言うと、ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワイン、ボトル・ウォーター、ジュース、牛乳、コーヒー、紅茶、などは、それぞれの品目で多数の企業が競っています。基本的食料である米、小麦、野菜、牛肉、鶏肉、卵、大豆などもそうです。どこかの企業体が独占しているとか、寡占状態にあるということはない。
しかし「コーラ」は、世界的にみてもかなり広まっている飲料であるにもかかわらず、寡占状態(コカ・コーラ社とペプシコ社)が続いています。
実は「コーラ」に明確な定義はありません。120年ほど前にコーラがアメリカで発売された当時はコーラの実(コーラナッツ)のエキスが使われていましたが、現在は使われていないと見られています。コーラは「甘みと酸味があって、独特の香料の味がする炭酸飲料」であり、要するに「コカ・コーラとペプシコーラのような味の炭酸飲料がコーラである」と定義するしかないのです。
「現在はコーラナッツのエキスが使われていないと見られている」と説明したのは、レシピが不明だからです。コーラのレシピは極秘にされています。
|
他の飲料メーカでも、コカ・コーラ(ないしはペプシコーラ)相当の飲料は作れると思います。現代は化学分析の技術が極めて発達しているので、コカ・コーラの成分は詳細に分かるでしょう。似た炭酸飲料を作り出すことはできると思います。
しかしたとえ技術的に作れたとしても、どういう原料からどいういうプロセスで原液を作るか(=レシピ)が問題です。コスト面でコカ・コーラに対抗できないとビジネスとしては成り立ちません。さらに「味」が問題です。コカ・コーラ(ないしはペプシコーラ)の味に慣れてしまった消費者にどう売り込むのか。それは大きな壁になると思います。
その意味で、キリンのメッツ・コーラ(2012年発売)の(日本での)ヒットは画期的でした。食物繊維を配合し、食事の際に脂肪の吸収を押さえる効果があるということで、特定保険用食品(トクホ)に認定されました。初めての「トクホのコーラ」です。なるほど、こういうアプローチがあったのかと感心します。
こういったキリンの「挑戦」はあるものの、コカ・コーラ社、ペプシコ社の寡占状態は(今のところ)変わらないようです。その独占・寡占の源泉に、製品のレシピ(原料と製法)が秘匿されていることがあるわけです。
コカ・コーラの戦略 = 教育
コーラはグローバル企業・2社の寡占状態です。しかし清涼飲料全体を見ると「競争相手」は多いわけです。統計によると、日本では清涼飲料の生産量の18%が「炭酸飲料」であり、炭酸飲料の40%がコーラです。清涼飲料に占めるコーラのシェアは約7%ということになります。コーラ発祥の国、アメリカではもっと多いでしょう。
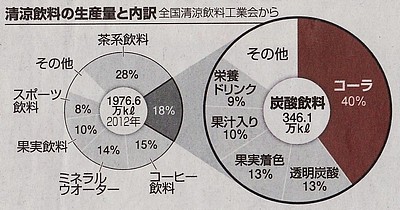
| ||
|
日本における清涼飲料の生産量
(朝日新聞 2013.9.21) | ||
この状況の中でコーラの市場を拡大するには「炭酸+独特の味」というコーラに、子供の時から慣れてもらうことが必要です。「やみつき」とは言わないまでも、ある種の習慣性になるのがベストです。いわば「教育」が大切なわけです。
このためにコカ・コーラ社がとっている戦略が、ファスト・フードのチェーンに対する徹底的な売り込み(提携)だと思います。アメリカ発のファストフード店ではコーラがメジャーな清涼飲料として売られています。マクドナルド、ケンタッキー・フライドチキン、ミスター・ドーナッツ、サブウェイなどです。もちろんファストフードは子供だけのものではありませんが、特にアメリカ発のファストフード店は若年層が多い。日本発祥の牛丼とかの和食系ファストフードとはだいぶ違います。
さらに、これはアメリカでの話ですが「学校への売り込み」がされています。アメリカのジャーナリスト、エリック・シュローサーが書いた「ファストフードが世界を食いつくす」という本があります(楡井浩一訳。2001年。草思社。原題は、Fast Food Nation = ファストフードの国)。この本に、要約すると次のような記述があります。
| ◆ |
1997年8月、コロラドスプリングス第11学区は、コカ・コーラ社を学区の独占的飲料供給者とする10年契約を結び、これが全米で最初の例となった。 | ||
| ◆ |
この契約により学区は、契約期間中に、最高1100万ドルの収入を得る。 | ||
| ◆ |
この契約では、年間の売り上げノルマが決められている。第11学区は少なくとも年7万箱のコカ・コーラ社製品を売る義務があり、それが達成できないと、コカ・コーラ社からの支払いが減額される。 | ||
| ◆ |
学区は、初年度にはノルマが達成できず、21,000箱しか売れなかった。 |
学区とは、英語でスクール・ディストリクト(School District)です。アメリカでは「州」(State)の下に「郡」(County)があり、その下に「学区」があって教育行政を司っています。学区の運営費用(教育に関わる費用)はその地域からの固定資産税でまかなわれ、しかも独立採算です。教育設備や資材、教員の報酬などを充実させようとすると、収入をどう増やすか(=独自財源の確保)が問題になる。
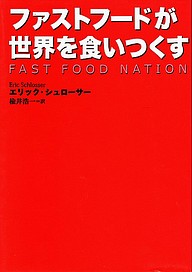
| |||
|
(草思社 2001年) | |||
上に引用したコロラドスプリングス第11学区の事例は、こういった「アメリカ事情」の文脈で理解する必要があります。コカ・コーラ社が製造・販売しているのはコカ・コーラだけではないので、他の飲料も含めた「コカ・コーラ社製品」の学区へのマーケティングと解釈できますが、その中でもコカ・コーラが重要な位置を占めているのは確かでしょう。
「学校への売り込み」は日本では考えられないことですが、この事例で言えるのは「コカ・コーラ社は若年層へのマーケティングに熱心だ」ということでしょう。コカ・コーラ社はグローバル企業です。世界中の国でコカ・コーラが販売されています。国によって販売促進の方法が違ってくるのは当然ですが「マーケティングの基本的考え方」は変わらないと思います。コカ・コーラ社はファストフード店との提携を含め、若い人たちや子供たちへの「教育」に熱心だと感じます。要するに「国民飲料」になってしまえば、企業としては安泰なわけです。かつ、寡占状態が維持できれば。
食料・食品と企業活動
ローマのホテルのコカ・コーラを思い出して考えたのは、消費者の「選択の自由」です。消費者サイドの自由意志による選択が、実は供給サイドによって作り出されている、ということは当然あるわけです。その「供給サイド」が、一握り企業で占められているケースがある。
それはファッションとかデジタル機器なら良いが、食品ではどうなのでしょうか。食品は人間が直接摂取するもので、健康に直結します。医薬品はそれ以上に健康に直結しますが(副作用など)、政府の厳しい認可管理がされています。それでも問題が起こる。
現代のコーラが健康問題を引き起こすというわけでは全くありません。昔と違って、カロリーもゼロになっています。しかし一般的に言って、食品という人間の健康に直結するものが、利益の最大化が目的である企業、それも一握りの企業のコントロール配下におかれると、問題を起こすことがあるのでは、という点を十分考えておくべきでしょう。
コーラは、たとえなくなったとしても(少なくとも日本では)大きな問題にはならないと思います。前のグラフでも明らかなように、清涼飲料の選択肢はほかにいっぱいあるからです。また、企業による独占といっても、コーラだけの問題であればどうということはないと思います。しかし一般に食料・食品が独占されると問題が起きる可能性がある。特に、代替がしにくい基幹食料である米、小麦、大豆などです。この点に関して非常に気になるのは、近年世界で問題になっている遺伝子組換え作物(GM作物。大豆、とうもろこしなど)です。このあたりは、我々消費者としても意識を高めていかないといけないと思います。
No.92 - コーヒーは健康に悪い? [社会]
No.83-84「社会調査のウソ」で、主に谷岡一郎著『「社会調査」のウソ』に従って、社会調査が陥りやすい誤りのパターンを紹介しました。今回はその補足です。
新聞報道
先日、コーヒーと死亡リスクについての記事が朝日新聞に掲載されていました。
この記事をうけて、翌8月27日の朝日新聞「天声人語」は、
という主旨の文章を書いていました。しかし、こういうコーヒーと健康(ないしは病気リスク)の議論って、はたしてまともな議論になっているのでしょうか。
「コーヒー調査」への疑問
No.83-84「社会調査のウソ」で引用した『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000)で、著者の谷岡一郎氏(大阪商業大学・学長)はこう書いています。
このニュースの内容について「数値があやふやで申し訳ないが、主旨は間違っていない」と谷岡氏は書いています。そして谷岡氏はこのニュースを聞いてすぐに疑問を持ったのです。
『「社会調査」のウソ』は2000年に出版された本です。ということは、谷岡氏が疑問を抱いた調査(=2000年の数年前)は1990年代です。朝日新聞の記事が指摘しているコーヒーと膀胱がんとの関係調査(WHO)は1991年です。天声人語が言及している厚生労働省の調査(2007年頃。コーヒーと肝臓がん)も合わせて考えると、少なくともこの20年以上に渡って、コーヒーは健康にいいとか悪いとかの各種「調査」が発表されてきたのですね。
砂糖入りの飲料を飲む人とは
ここで谷岡氏の指摘に従って、飲料と甘味料(砂糖、人工甘味料)の関係を考えてみます。人が飲料を飲むパターンは、
の3つです。このうち、Aの「もともと飲料に入っている甘味料」とは、現在では砂糖ということはなく、カロリーがない人工甘味料です。成分表に「砂糖」と書いてある飲料は見たことがありません。なぜそうなったかと言うと、それこそ砂糖の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼすからです。世界では何十種類という人工甘味料が開発されてきて、中には健康に悪いとの大論争になった(なっている)ものもありますが、なぜそこまでなるのかというと、砂糖の摂取量を減らしたいからです。
Cのケースは砂糖とは関係ないので、飲料経由で砂糖を摂取するとしたらBのケースです。Bのケースの甘味料は砂糖か人工甘味料の2つが考えられますが、圧倒的に砂糖(グラニュー糖)が多いのではと思います。
つまり、世の中に「砂糖が入っている飲料を飲む人」がいるとしたら、それは「コーヒー・紅茶に砂糖を入れて飲む人」ということになります(他にココアなどもあるでしょう)。
さらに私の観察によると(日本では)コーヒー・紅茶をブラックで飲むのは少数派です。ということは「コーヒーを(よく)飲む人」というのは「砂糖入りの飲料を(よく)飲む人」と統計的に重なる部分が多いことになる。そう推論できます。
その結果として、「コーヒーを飲む人」と「コーヒーを飲まない人」を対比させて何かを議論することは、「砂糖入りの飲料を飲む人」と「砂糖入りの飲料を飲まない人」を対比させることになりかねない。
朝日新聞が報道した調査はアメリカでの調査です。「アメリカではコーヒーを飲むほとんどの人がブラックで飲む」のなら、また「アメリカではコーヒーに入れられる甘味料のほとんどが人工甘味料」なら、砂糖の影響はないことになりますが、そうなのでしょうか。
ここでの議論の本質は、砂糖が問題だということではありません。コーヒーに入れる砂糖は健康に影響するかもしれないし、しないかもしれない。谷岡氏の言いたいことは、そういうことも考慮した(=コントロールした)調査をすべきだということです。朝日新聞が報道した調査は、どういうコントロールがされたのでしょうか。知りたいところです。
コーヒーの愛飲と喫煙率
さらに、重要と思える話があります。谷岡氏は『「社会調査」のウソ』とは別のある講演で、
と述べています。もちろん喫煙率は国によって違うので一概には言えないと思いますが、重要な指摘だと思います。もし仮に、コーヒーを飲まない人の喫煙率が20%で、コーヒーを4杯以上飲む人の喫煙率が50%だとしたら、それが死亡率に影響しないはずがないと思います。あくまで仮定の話ですが・・・・・・。コーヒー調査においてはそういう「コントロール」も必要でしょう。
コーヒーは日本でも世界でも極めて一般的な飲み物なので、学者も役人も調査しようという気になるし、またコーヒーと病気リスク・死亡リスクの関係は新聞社としても記事にしやすいのでしょう。読者の関心を引く記事、というわけです。しかしもっと踏み込んで調査しないと(ないしは調査方法のキモのところを報道しないと)「結局のところ何も分からない」記事になりかねないと思います。
新聞報道
先日、コーヒーと死亡リスクについての記事が朝日新聞に掲載されていました。
|
この記事をうけて、翌8月27日の朝日新聞「天声人語」は、
| 6年前には厚生労働省が「コーヒーが肝臓がんのリスクを下げる」と発表した。いったいコーヒーは健康にいいのか、よくないのか |
という主旨の文章を書いていました。しかし、こういうコーヒーと健康(ないしは病気リスク)の議論って、はたしてまともな議論になっているのでしょうか。
「コーヒー調査」への疑問
No.83-84「社会調査のウソ」で引用した『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000)で、著者の谷岡一郎氏(大阪商業大学・学長)はこう書いています。
|
このニュースの内容について「数値があやふやで申し訳ないが、主旨は間違っていない」と谷岡氏は書いています。そして谷岡氏はこのニュースを聞いてすぐに疑問を持ったのです。
|
『「社会調査」のウソ』は2000年に出版された本です。ということは、谷岡氏が疑問を抱いた調査(=2000年の数年前)は1990年代です。朝日新聞の記事が指摘しているコーヒーと膀胱がんとの関係調査(WHO)は1991年です。天声人語が言及している厚生労働省の調査(2007年頃。コーヒーと肝臓がん)も合わせて考えると、少なくともこの20年以上に渡って、コーヒーは健康にいいとか悪いとかの各種「調査」が発表されてきたのですね。
砂糖入りの飲料を飲む人とは
ここで谷岡氏の指摘に従って、飲料と甘味料(砂糖、人工甘味料)の関係を考えてみます。人が飲料を飲むパターンは、
| A: | もともと甘味料が入っている飲料を飲む | |
| B: |
甘味料なしの飲料に甘味料を入れて飲む (コーヒー・紅茶など) | |
| C: |
甘味料なしの飲料をそのまま飲む (ミネラル・ウォーター、日本茶など。およびコーヒー・紅茶をブラックで飲む場合) |
の3つです。このうち、Aの「もともと飲料に入っている甘味料」とは、現在では砂糖ということはなく、カロリーがない人工甘味料です。成分表に「砂糖」と書いてある飲料は見たことがありません。なぜそうなったかと言うと、それこそ砂糖の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼすからです。世界では何十種類という人工甘味料が開発されてきて、中には健康に悪いとの大論争になった(なっている)ものもありますが、なぜそこまでなるのかというと、砂糖の摂取量を減らしたいからです。
Cのケースは砂糖とは関係ないので、飲料経由で砂糖を摂取するとしたらBのケースです。Bのケースの甘味料は砂糖か人工甘味料の2つが考えられますが、圧倒的に砂糖(グラニュー糖)が多いのではと思います。
つまり、世の中に「砂糖が入っている飲料を飲む人」がいるとしたら、それは「コーヒー・紅茶に砂糖を入れて飲む人」ということになります(他にココアなどもあるでしょう)。
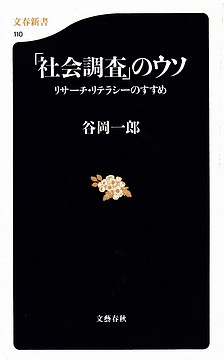
| |||
その結果として、「コーヒーを飲む人」と「コーヒーを飲まない人」を対比させて何かを議論することは、「砂糖入りの飲料を飲む人」と「砂糖入りの飲料を飲まない人」を対比させることになりかねない。
朝日新聞が報道した調査はアメリカでの調査です。「アメリカではコーヒーを飲むほとんどの人がブラックで飲む」のなら、また「アメリカではコーヒーに入れられる甘味料のほとんどが人工甘味料」なら、砂糖の影響はないことになりますが、そうなのでしょうか。
ここでの議論の本質は、砂糖が問題だということではありません。コーヒーに入れる砂糖は健康に影響するかもしれないし、しないかもしれない。谷岡氏の言いたいことは、そういうことも考慮した(=コントロールした)調査をすべきだということです。朝日新聞が報道した調査は、どういうコントロールがされたのでしょうか。知りたいところです。
コーヒーの愛飲と喫煙率
さらに、重要と思える話があります。谷岡氏は『「社会調査」のウソ』とは別のある講演で、
|
と述べています。もちろん喫煙率は国によって違うので一概には言えないと思いますが、重要な指摘だと思います。もし仮に、コーヒーを飲まない人の喫煙率が20%で、コーヒーを4杯以上飲む人の喫煙率が50%だとしたら、それが死亡率に影響しないはずがないと思います。あくまで仮定の話ですが・・・・・・。コーヒー調査においてはそういう「コントロール」も必要でしょう。
コーヒーは日本でも世界でも極めて一般的な飲み物なので、学者も役人も調査しようという気になるし、またコーヒーと病気リスク・死亡リスクの関係は新聞社としても記事にしやすいのでしょう。読者の関心を引く記事、というわけです。しかしもっと踏み込んで調査しないと(ないしは調査方法のキモのところを報道しないと)「結局のところ何も分からない」記事になりかねないと思います。
No.84 - 社会調査のウソ(2) [社会]
前回の No.83「社会調査のウソ(1)」からの続きで、『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000。以下「本書」) の事例に従って、社会調査の要注意点をとりあげます。ここからは社会調査の回答そのものにバイアス(偏向)がかかっていて、実態を表していない例です。
の事例に従って、社会調査の要注意点をとりあげます。ここからは社会調査の回答そのものにバイアス(偏向)がかかっていて、実態を表していない例です。
人は忘れるし、ウソをつく
社会調査の要注意点のひとつは、回答そのものの信頼性です。「本書」に次のような例が載っています。
1995年4月9日の大阪府知事選挙の得票は、
横山ノック 1,625,256 票
(山田勇 無新)
平野拓也 1,147,416 票
(無新。自新社さ公・推薦)
でした。ところが府知事選の1年後の1996年4月に読売新聞が行った横山知事の評価アンケートにおいて「昨年4月の知事選挙では誰に投票しましたか」という質問の答えは、
横山ノック 43.1%
平野拓也 9.5%
なのです(読売新聞 1996.4.20)。あきらかに多くの人が嘘をついていることになります。
但しこれは知事選挙の1年後の調査なので、記憶の問題かもしれません。忘れてしまったということもありうる。しかし、明らかに嘘をついていると分かる調査もあります。
谷岡氏は「読売新聞のこの調査はきちっとしたサンプリングを行っていて、回答者の偏りはそれほどないと考えられる。」と書いています。大人であれば当然のことながら「投票には行くべきだ」と思っているわけで、無記名回答と言えども嘘をつく人が多いのでしょう。
調査する側が質問票を操作することで、回答を誘導することがある
新聞社はフェアな社会調査をしていると思われていて、それは多くの場合正しいのですが、新聞社も「主張」を持っています。その主張に関わるような調査では、回答をその主張に沿った形に誘導することがあるわけです。たとえば次の誘導的質問です。
典型的な誘導質問であるにもかかわらず、42.6%もの人が「納得できない」と答えたことこそ重視すべきでしょう。はからずもこの調査は、当時、消費税値上げに納得できない人が多い(その前に税金の無駄使いをやめろ、といような)ことを明らかにしました。
質問票全体の構成テクニックで答えを誘導する調査もあります。つまり、最後の(後半の)質問に向け、前段部でわざといくつかの質問を設けておく。前段部である主の「先入観」を与えることによって最後の質問をある方向に誘導しようとするものです。この種の誘導を専門用語で「キャリーオーバー効果」と言うようです。
「本書」の例では、1994年6月9日の読売新聞に載った、
自衛隊「必要」84%
という調査結果がその典型です。自衛隊は必要という回答をできるだけ多くしたい、という特定の目的で「調査」が行われているわけです。
そもそも、なぜ「必要か、必要でないか」という調査を行うのかというと、それが国民的議論になっているからであり、国政の争点になっているからです。アメリカで「アメリカ軍は必要ですか」という調査をする新聞社はありえないでしょう。時間とお金の無駄だし、調査しようという発想がありえない。しかし日本では自衛隊の歴史的経緯と憲法との関係で(すくなくとも当時は)議論になっていたからこそ調査が行われる。従って「必要」「必要でない」が拮抗しているとは言わないまでも、2:1とか、せいぜい3:1という比率で論議がされていることが調査の前提です。もし84%の人が「必要」だと思っているのなら、国民的議論にも国政の争点にもなっていないはずであり、お金をかけて調査するだけ無駄というものです。つまり「調査をする主旨」と「84%が必要だという結果」は完全に矛盾しているのです。
もしこの調査が民主主義の原則にのっとって「16%の」少数意見を拾い上げるための調査だったのなら意味がありますね。しかしどうもそうではないようです。国民的議論を一定の方向に誘導しようとして実施された調査でしょう。
相関関係があったとしても、因果関係があるとは限らない。「隠れた変数」が相関関係を作り出すことがある
ここからは「相関関係」に関する要注意点です。
二つの量、AとBの間に相関関係が見いだせたとします。つまりAが大きいとBも大きいというような関係です。しかしそうであっても、AとBに因果関係がある(Aが原因でBになる。またはその逆)とは限らないわけです。AとBの共通の原因になっている「隠れた変数」があり、それがAとBの相関関係を作り出しているのかもしれない。
1994年4月に発表された、平成五年版「厚生白書」に関する次の記事は、その「隠れた変数」の例でしょう。
畳の数を増やすと子だくさんになる、と言わんばかりの厚生白書ですが、これは谷岡氏が指摘するように「隠れた変数」の効果であって、
◆地方の文化的伝統
├─⇒ 子だくさんの家庭
└─⇒ 家のスペースが広い
という図式でしょう。「文化的伝統」の補足として「土地の価格」なども入れていいと思います。
隠れた変数が相関関係を作り出すことを専門用語で「スプリアス効果」と呼ぶそうです。新聞を読む読者としてはスプリアス効果に気をつけるべきです。子どもの食事と非行の関係についての次の調査はその典型です。
この調査をした人たちの「ジャンクフードを食べ過ぎて栄養のバランスが崩れることを憂う気持ち」は分かるのですが、だからと言って「ジャンクフードをよく食べるから非行に走る」などとはとても結論できないわけです。ここは谷岡氏にならって、
◆親の子育ての手抜き
├─⇒ ジャンクフード
└─⇒ 非行
という図式が妥当でしょう。
子どもの非行については、次のような調査もあります。
総務庁(当時)は「だからテレビの暴力シーンは規制すべきだ」と言いたいのでしょうが、これも、
◆子供の暴力的な性格
├─⇒ 暴力的なTVをよく見る
└─⇒ 暴力・万引きなどの非行
という図式が、より納得性の高い説明です。それにしても、官庁がある意図を持って行ったと考えられる調査の「結果発表」を無批判に報道する新聞社は、新聞の存在意義をどう考えているのでしょうか。
以上をまとめると、相関関係は必ずしも因果関係を意味しないわけです。谷岡氏は「スプリアス効果」を「灰皿」と「肺ガン」を例にとって説明しています。
「家庭にある灰皿の数」と「家族の誰かが肺ガンにかかる率」の2つに相関関係が見い出せたとしましょう。しかし灰皿と肺ガンに因果関係がないことは明白です。灰皿が肺ガンを引き起こすわけではないし、肺ガンにかかったら、むやみやたらと灰皿を集めたくなるわけでもない。
◆喫煙
├─⇒ 灰皿の数
└─⇒ 肺ガン
という関係なのですね。あたりまえだけど・・・・・・。
この例は一目瞭然なのですが、これが「ジャンクフードと非行」とか「テレビの暴力的シーンと非行」となると、なんとなく「もっともらしく」なってしまう。よくよく注意すべきだと思います。
因果関係を逆にとらえてしまうことがある
いわゆる「逆の因果関係」であり、谷岡氏は次のような例を紹介しています。
この例の「応用問題」は、「大都市でガンによる死亡率が高くなったとしたら、それはよい治療施設が存在するから(という可能性を検討すべき)」でしょう。
他の例として「40代出産女性は長寿」というハーバード大学の研究グループの発表(1997年)も紹介されています。100歳以上の長寿者のうち40歳代で出産した女性は20%もあり、これは70歳台で死んだ女性の40歳代出産率より圧倒的に多い、というわけですが、これも「100歳まで生きるような元気な人だったからこそ、高齢出産ができた」と考えれば、どうということもない。
さきの「畳の数と子どもの数の関係」も「子どもが増えたので、畳の数の多い家に引っ越した」という要因があるはず、と谷岡氏は指摘しています。確かにその「逆の因果関係」ならありうるわけです。
カロリーオフ炭酸飲料と糖尿病
これは『「社会調査」のウソ』からの引用ではありませんが、因果関係のとらえかたに関して最近も新聞に奇妙な記事が掲載されました。
なんだか変な記事です。ごくごくシンプルに考えて、
だと思うのです。なぜかと言うと、
だからです。「糖尿病リスクが高いと自覚している人」というのは、例えば毎年の健康診断で血糖値が標準の範囲に収まらず、そのことでC判定になるような人です。あるいは自分は体質的に太りやすいと自覚している人です。さらには両親や親族に糖尿病患者がいるような人です。そして、
です。あたりまえだけど・・・・・・。
「ダイエット用炭酸飲料が糖尿病の発症に関係しているかはわからないが」などと、思わせぶりなことが書いてありますが、
というのが、原因(の一つ)と結果の常識的な解釈でしょう。
このことは「ダイエット食品」と「BMI(肥満度)」の関係を考えてみればすぐに分かります。仮に調査の結果、
という相関関係が判明したとしましょう。しかし、だからと言って
とは誰も考えないはずです。二つの事象の因果関係は全く逆であって、
のです。あたりまえです。この例は一目瞭然ですが、「カロリーオフ炭酸飲料と糖尿病リスク」というような、ちょっと「ひねった設定」にすると、人は騙されやすくなるのだと思います。だからそこにつけ込んで記事のネタを提供する人と、それを記事にする能天気な新聞記者が出てきて、その結果として「奇妙な新聞記事」が出現することになるのです。
こういう記事に引きずられて「ダイエット用炭酸飲料が糖尿病を引き起こす?」というような週刊誌記事が現れないことを願いますね。現れないと思いますが・・・・・・。
「後追い効果」で得られた情報には役立つものは少ない
谷岡氏は「そういえばこういう前兆があった、というような情報のなかに役立つものは少ない。それを承知の上での研究なら問題ない。」と言っています。ただし「問題は、こうした情報の山から一定の法則性を見つけ出して仮説を作ることをせず、地震の興奮さめやらぬうちに、すべてそのまま感嘆符(!)入りで出版を強行したことである。」と指摘しています。
地震の予兆といわれるもののほとんどは「後追い効果」で得られた情報でしょう。たとえば阪神・淡路大震災が起こった日の未明に「猫が異常な鳴き声を発した」という情報が何十件か寄せられたとしても、阪神・淡路地方の何百万匹という猫が「夜に異常な鳴き声をする」ことは、少ないながらも一定の確率であるわけです。毎夜どこかで猫が「異常な鳴き声」をしているのに、後追い効果で「地震の予兆」だと思ってしまう人が(少ないながらも)出てくる。大地震が極めて強烈な記憶となって残るからです。そういえば夜中に猫が・・・・・・というわけです。
相関関係の中には「単なる偶然」もある(疑似相関)
最後に、相関関係の中には単なる偶然もあることに注意すべきです。以下は谷岡氏の述懐です。
リサーチ・リテラシー
『「社会調査」のウソ』(文春新書)の副題は「リサーチ・リテラシーのすすめ」です。リテラシーとは「読み書き能力」のことなので、リサーチ・リテラシーとは「調査結果を読み解く能力」と解釈してよいでしょう。
本書を読んでまず感じるのは、まず新聞やテレビなどの報道メディアの「リサーチ・リテラシー」が必要だというこことです。社会調査を行う官公庁、NGO、政党、各種の任意団体などは、それぞれの「考え」や「主張」を持っています。その主張に添うような「社会調査の結果」が発表されることが多い。それを正しく判断し、デタラメを排除し、見出しの付け方を正しく伝える責任が、まず報道メディアにあると思うのです。そもそも報道メディアは世論調査専門の部門をもっているリサーチのプロフェッショナルなのです。「リサーチ・リテラシー」を発揮して当然です。
しかし報道メディア自身も「考え」や「主張」を持っています。それに合うような調査結果が発表され(作り出され)、合わないものは排除されることが往々にしてある。また No.82「新聞という商品」で書いたように、新聞記事やTV番組という商品は、その商品の魅力を高めるような内容になってしまいがちです。どうしても読者の目を引き付け、顧客満足度を高めるような社会調査の取り上げ方になる。
結局のところ社会調査と接する時には、最終的な「情報の消費者」である市民一人一人の「リサーチ・リテラシー」が必要です。それは、インターネットに溢れる玉石混交の情報を受け取る時の「リテラシー」と全く同じだと感じました。
社会調査は「公正な調査の結果という装い」で、しかも「デジタルな数値情報」で公表されます。だから逆に要注意なのです。
人は忘れるし、ウソをつく
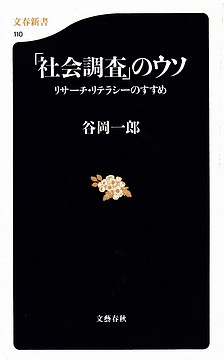
| |||
1995年4月9日の大阪府知事選挙の得票は、
(山田勇 無新)
平野拓也 1,147,416 票
(無新。自新社さ公・推薦)
でした。ところが府知事選の1年後の1996年4月に読売新聞が行った横山知事の評価アンケートにおいて「昨年4月の知事選挙では誰に投票しましたか」という質問の答えは、
横山ノック 43.1%
平野拓也 9.5%
なのです(読売新聞 1996.4.20)。あきらかに多くの人が嘘をついていることになります。
但しこれは知事選挙の1年後の調査なので、記憶の問題かもしれません。忘れてしまったということもありうる。しかし、明らかに嘘をついていると分かる調査もあります。
|
谷岡氏は「読売新聞のこの調査はきちっとしたサンプリングを行っていて、回答者の偏りはそれほどないと考えられる。」と書いています。大人であれば当然のことながら「投票には行くべきだ」と思っているわけで、無記名回答と言えども嘘をつく人が多いのでしょう。
調査する側が質問票を操作することで、回答を誘導することがある
新聞社はフェアな社会調査をしていると思われていて、それは多くの場合正しいのですが、新聞社も「主張」を持っています。その主張に関わるような調査では、回答をその主張に沿った形に誘導することがあるわけです。たとえば次の誘導的質問です。
|
典型的な誘導質問であるにもかかわらず、42.6%もの人が「納得できない」と答えたことこそ重視すべきでしょう。はからずもこの調査は、当時、消費税値上げに納得できない人が多い(その前に税金の無駄使いをやめろ、といような)ことを明らかにしました。
質問票全体の構成テクニックで答えを誘導する調査もあります。つまり、最後の(後半の)質問に向け、前段部でわざといくつかの質問を設けておく。前段部である主の「先入観」を与えることによって最後の質問をある方向に誘導しようとするものです。この種の誘導を専門用語で「キャリーオーバー効果」と言うようです。
「本書」の例では、1994年6月9日の読売新聞に載った、
自衛隊「必要」84%
という調査結果がその典型です。自衛隊は必要という回答をできるだけ多くしたい、という特定の目的で「調査」が行われているわけです。
|
そもそも、なぜ「必要か、必要でないか」という調査を行うのかというと、それが国民的議論になっているからであり、国政の争点になっているからです。アメリカで「アメリカ軍は必要ですか」という調査をする新聞社はありえないでしょう。時間とお金の無駄だし、調査しようという発想がありえない。しかし日本では自衛隊の歴史的経緯と憲法との関係で(すくなくとも当時は)議論になっていたからこそ調査が行われる。従って「必要」「必要でない」が拮抗しているとは言わないまでも、2:1とか、せいぜい3:1という比率で論議がされていることが調査の前提です。もし84%の人が「必要」だと思っているのなら、国民的議論にも国政の争点にもなっていないはずであり、お金をかけて調査するだけ無駄というものです。つまり「調査をする主旨」と「84%が必要だという結果」は完全に矛盾しているのです。
もしこの調査が民主主義の原則にのっとって「16%の」少数意見を拾い上げるための調査だったのなら意味がありますね。しかしどうもそうではないようです。国民的議論を一定の方向に誘導しようとして実施された調査でしょう。
相関関係があったとしても、因果関係があるとは限らない。「隠れた変数」が相関関係を作り出すことがある
ここからは「相関関係」に関する要注意点です。
二つの量、AとBの間に相関関係が見いだせたとします。つまりAが大きいとBも大きいというような関係です。しかしそうであっても、AとBに因果関係がある(Aが原因でBになる。またはその逆)とは限らないわけです。AとBの共通の原因になっている「隠れた変数」があり、それがAとBの相関関係を作り出しているのかもしれない。
1994年4月に発表された、平成五年版「厚生白書」に関する次の記事は、その「隠れた変数」の例でしょう。
|
畳の数を増やすと子だくさんになる、と言わんばかりの厚生白書ですが、これは谷岡氏が指摘するように「隠れた変数」の効果であって、
◆地方の文化的伝統
├─⇒ 子だくさんの家庭
└─⇒ 家のスペースが広い
という図式でしょう。「文化的伝統」の補足として「土地の価格」なども入れていいと思います。
隠れた変数が相関関係を作り出すことを専門用語で「スプリアス効果」と呼ぶそうです。新聞を読む読者としてはスプリアス効果に気をつけるべきです。子どもの食事と非行の関係についての次の調査はその典型です。
|
この調査をした人たちの「ジャンクフードを食べ過ぎて栄養のバランスが崩れることを憂う気持ち」は分かるのですが、だからと言って「ジャンクフードをよく食べるから非行に走る」などとはとても結論できないわけです。ここは谷岡氏にならって、
◆親の子育ての手抜き
├─⇒ ジャンクフード
└─⇒ 非行
という図式が妥当でしょう。
子どもの非行については、次のような調査もあります。
|
総務庁(当時)は「だからテレビの暴力シーンは規制すべきだ」と言いたいのでしょうが、これも、
◆子供の暴力的な性格
├─⇒ 暴力的なTVをよく見る
└─⇒ 暴力・万引きなどの非行
という図式が、より納得性の高い説明です。それにしても、官庁がある意図を持って行ったと考えられる調査の「結果発表」を無批判に報道する新聞社は、新聞の存在意義をどう考えているのでしょうか。
以上をまとめると、相関関係は必ずしも因果関係を意味しないわけです。谷岡氏は「スプリアス効果」を「灰皿」と「肺ガン」を例にとって説明しています。
「家庭にある灰皿の数」と「家族の誰かが肺ガンにかかる率」の2つに相関関係が見い出せたとしましょう。しかし灰皿と肺ガンに因果関係がないことは明白です。灰皿が肺ガンを引き起こすわけではないし、肺ガンにかかったら、むやみやたらと灰皿を集めたくなるわけでもない。
◆喫煙
├─⇒ 灰皿の数
└─⇒ 肺ガン
という関係なのですね。あたりまえだけど・・・・・・。
この例は一目瞭然なのですが、これが「ジャンクフードと非行」とか「テレビの暴力的シーンと非行」となると、なんとなく「もっともらしく」なってしまう。よくよく注意すべきだと思います。
因果関係を逆にとらえてしまうことがある
いわゆる「逆の因果関係」であり、谷岡氏は次のような例を紹介しています。
|
この例の「応用問題」は、「大都市でガンによる死亡率が高くなったとしたら、それはよい治療施設が存在するから(という可能性を検討すべき)」でしょう。
他の例として「40代出産女性は長寿」というハーバード大学の研究グループの発表(1997年)も紹介されています。100歳以上の長寿者のうち40歳代で出産した女性は20%もあり、これは70歳台で死んだ女性の40歳代出産率より圧倒的に多い、というわけですが、これも「100歳まで生きるような元気な人だったからこそ、高齢出産ができた」と考えれば、どうということもない。
さきの「畳の数と子どもの数の関係」も「子どもが増えたので、畳の数の多い家に引っ越した」という要因があるはず、と谷岡氏は指摘しています。確かにその「逆の因果関係」ならありうるわけです。
カロリーオフ炭酸飲料と糖尿病
これは『「社会調査」のウソ』からの引用ではありませんが、因果関係のとらえかたに関して最近も新聞に奇妙な記事が掲載されました。
|
なんだか変な記事です。ごくごくシンプルに考えて、
| カロリーオフ炭酸飲料を飲む人の糖尿病リスクが統計的に高いのはあたりまえ |
だと思うのです。なぜかと言うと、
| 糖尿病リスクが高いと自覚している人は、そうでない人よりもより高い確率でカロリーオフ炭酸飲料を飲むはず |
だからです。「糖尿病リスクが高いと自覚している人」というのは、例えば毎年の健康診断で血糖値が標準の範囲に収まらず、そのことでC判定になるような人です。あるいは自分は体質的に太りやすいと自覚している人です。さらには両親や親族に糖尿病患者がいるような人です。そして、
| 糖尿病リスクが高いと自覚している人は、そうでない人よりもより高い確率で糖尿病を発症するはず |
です。あたりまえだけど・・・・・・。
「ダイエット用炭酸飲料が糖尿病の発症に関係しているかはわからないが」などと、思わせぶりなことが書いてありますが、
|
糖尿病リスクの自覚 | |||
|
ダイエット用炭酸飲料をよく飲む |
というのが、原因(の一つ)と結果の常識的な解釈でしょう。
このことは「ダイエット食品」と「BMI(肥満度)」の関係を考えてみればすぐに分かります。仮に調査の結果、
| ダイエット食品をよく食べる人ほど、BMIの数値が高い(=太っている) |
という相関関係が判明したとしましょう。しかし、だからと言って
| ダイエット食品を食べると、そのことが原因でBMIの数値が高くなる(太る) |
とは誰も考えないはずです。二つの事象の因果関係は全く逆であって、
| BMIの数値が高いから、ダイエット食品をよく食べる |
のです。あたりまえです。この例は一目瞭然ですが、「カロリーオフ炭酸飲料と糖尿病リスク」というような、ちょっと「ひねった設定」にすると、人は騙されやすくなるのだと思います。だからそこにつけ込んで記事のネタを提供する人と、それを記事にする能天気な新聞記者が出てきて、その結果として「奇妙な新聞記事」が出現することになるのです。
こういう記事に引きずられて「ダイエット用炭酸飲料が糖尿病を引き起こす?」というような週刊誌記事が現れないことを願いますね。現れないと思いますが・・・・・・。
「後追い効果」で得られた情報には役立つものは少ない
|
谷岡氏は「そういえばこういう前兆があった、というような情報のなかに役立つものは少ない。それを承知の上での研究なら問題ない。」と言っています。ただし「問題は、こうした情報の山から一定の法則性を見つけ出して仮説を作ることをせず、地震の興奮さめやらぬうちに、すべてそのまま感嘆符(!)入りで出版を強行したことである。」と指摘しています。
地震の予兆といわれるもののほとんどは「後追い効果」で得られた情報でしょう。たとえば阪神・淡路大震災が起こった日の未明に「猫が異常な鳴き声を発した」という情報が何十件か寄せられたとしても、阪神・淡路地方の何百万匹という猫が「夜に異常な鳴き声をする」ことは、少ないながらも一定の確率であるわけです。毎夜どこかで猫が「異常な鳴き声」をしているのに、後追い効果で「地震の予兆」だと思ってしまう人が(少ないながらも)出てくる。大地震が極めて強烈な記憶となって残るからです。そういえば夜中に猫が・・・・・・というわけです。
相関関係の中には「単なる偶然」もある(疑似相関)
最後に、相関関係の中には単なる偶然もあることに注意すべきです。以下は谷岡氏の述懐です。
|
リサーチ・リテラシー
『「社会調査」のウソ』(文春新書)の副題は「リサーチ・リテラシーのすすめ」です。リテラシーとは「読み書き能力」のことなので、リサーチ・リテラシーとは「調査結果を読み解く能力」と解釈してよいでしょう。
本書を読んでまず感じるのは、まず新聞やテレビなどの報道メディアの「リサーチ・リテラシー」が必要だというこことです。社会調査を行う官公庁、NGO、政党、各種の任意団体などは、それぞれの「考え」や「主張」を持っています。その主張に添うような「社会調査の結果」が発表されることが多い。それを正しく判断し、デタラメを排除し、見出しの付け方を正しく伝える責任が、まず報道メディアにあると思うのです。そもそも報道メディアは世論調査専門の部門をもっているリサーチのプロフェッショナルなのです。「リサーチ・リテラシー」を発揮して当然です。
しかし報道メディア自身も「考え」や「主張」を持っています。それに合うような調査結果が発表され(作り出され)、合わないものは排除されることが往々にしてある。また No.82「新聞という商品」で書いたように、新聞記事やTV番組という商品は、その商品の魅力を高めるような内容になってしまいがちです。どうしても読者の目を引き付け、顧客満足度を高めるような社会調査の取り上げ方になる。
結局のところ社会調査と接する時には、最終的な「情報の消費者」である市民一人一人の「リサーチ・リテラシー」が必要です。それは、インターネットに溢れる玉石混交の情報を受け取る時の「リテラシー」と全く同じだと感じました。
社会調査は「公正な調査の結果という装い」で、しかも「デジタルな数値情報」で公表されます。だから逆に要注意なのです。
No.83 - 社会調査のウソ(1) [社会]
No.81「2人に1人が買春」で新聞報道の問題点(要注意点)を書いたのですが、これはまた「社会調査」の問題点(要注意点)でもあると言えます。「2人に1人が買春」の例では、12.5% という低い回答率で全体を推し測ることは全く出来ないのです。今回は「社会調査は要注意である」という視点で書いてみたいと思います。
まず一つの記事を取り上げます。今回もNo.81に引き続いて少々昔の読売新聞の記事ですが、たまたまそうなっただけであって、読売新聞に問題記事が多いとか、そういうことを言うつもりは全くありません。No.81と違って今回は、れっきとした政党組織による「社会調査」です。
愛知では半数が痴漢の被害
2001年3月22日の読売新聞に「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」という見出しの記事が掲載されました。その記事の全文を引用します。
公明党がこのような調査をすることや、また記事の最後に示唆してあるように痴漢被害の防止のため女性専用車両を導入する運動をしたり、ないしは街灯を増設する働きかけをしたりというのは、全く問題がありません。それは政党組織として正しい行動だし、評価すべき活動です。
ここで問題にしたいのはこの調査で「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」と言えるのかどうかで、それは違うと思うのです。公明党愛知県青年局がそう発表したのか、新聞社が勝手に見出しをつけたのかは定かではありませんが、前者だとして話を進めます。
公明党愛知県青年局の女性党員がどういう形で街頭調査をしたのかを想像してみると、おそらく「痴漢に関するアンケート実施中 公明党」というような看板か「のぼり」を掲げ、駅の入り口などの街頭に立って通行する人にアンケートへの協力を呼び掛けたのだと思います。
その場を通行する人はどう思うでしょうか。これは「痴漢を無くす(少なくする)ために公明党が何らかの動きをしようとしている、そのためのアンケートだ」と、誰もがパッと思うでしょう。れっきとした日本の政党がアンケートをとるからには、そうとしか考えられない。
とすると、このアンケートに立ち止まる可能性が高い人は次のような人たちです。
そして総じて言えることは「被害を受けたことがない人より、痴漢の被害者の方がこのアンケートに立ち止まる確率がよほど高いだろう」ということです。被害者は「もう二度とあんな目にあいたくない」という思いが強いでしょうから・・・・・・。
従って「アンケートに立ち止まった人の46%が痴漢被害を受けた」からといって「アンケートに立ち止まらなかった人の46%が痴漢被害を受けた」とは全く言えないわけです。「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」という新聞の見出しを見ると、愛知県の男性に痴漢常習者が多いのかと一瞬思ってしまいますが、記事の内容を読むとそんなことは全くないのです。
もし公明党が「痴漢被害者の割合」を調べたいのなら、簡便な方法があります。公明党愛知県青年局の党員とその家族で10-30代の女性全員に聞き取り調査をし、回収率90%以上を目標とする痴漢被害調査を実施すればよいのです。公明党の組織力であればそれは容易だと思います。こうすると11,000人というような回答数にはとてもならないでしょうが「痴漢被害者の割合」という観点からすると、よほど信頼性の高い調査になると思います。かつ労力は少ない。
公明党青年局のアンケート調査が無駄だと言っているわけではありません。11,000人から回答得て46%が痴漢被害者だということは、約5,000人の「証言」が得られたわけです。どの地下鉄路線が被害にあいやすいとか、公園ならどの場所に被害が集中しているのか(ないしは集中していないのか)を明らかにし、女性専用車両を導入する路線の優先度を提言したり、どこに街灯を設置すべきかを提言したりするための有益な情報が得られたと考えられます。ただ言いたいことは、この調査で「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」などとはとても言えない、ということなのです。
以上の例からも分かるように「社会調査」は調査のやり方とデータの解釈の仕方によっては信用できないものになってしまいます。そのことを各種の実例をあげて解説した本があります。次に、その本の内容から「社会調査」が陥りやすい誤りを書いてみたいと思います。
「社会調査」のウソ
『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000) という興味深い本(以下「本書」と記述)があります。谷岡一郎氏(大阪商業大学教授、学長)が書いた本で、世の中にはいかにずさんな「社会調査」が多いかを、数々の例をあげて解説しています。それと同時に、我々が「社会調査」にどう接し、どう解釈すべきかが説明されています。
という興味深い本(以下「本書」と記述)があります。谷岡一郎氏(大阪商業大学教授、学長)が書いた本で、世の中にはいかにずさんな「社会調査」が多いかを、数々の例をあげて解説しています。それと同時に、我々が「社会調査」にどう接し、どう解釈すべきかが説明されています。
ずさんな「社会調査」や価値のないアンケートを谷岡氏は「ゴミ」と呼んでいて、それはかなり過激な表現ですが、解説していることは極めて真っ当で、非常にためになる本だと思います。この本にあげられている数々の事例から一部をピックアップし、「社会調査」の報道を読むときの注意点をまとめてみます。なお引用した部分以外は谷岡氏の意見そのままではなく、谷岡氏の見解も参考にしながら私が考えたことです。
低い回答率の調査は信用できない
まず谷岡氏が何回か強調していることですが、低い回答率の調査は信用できないのです。なぜなら、その調査に「わざわざ回答をした人」は、回答するという特別な行動をとった理由があるはずだからです。
前々回のNo.81「2人に1人が買春」で書いた「買春調査」と「ハイト・レポート」(回答率はそれぞれ12.5%と6%)がまさにそうでした。前者は「買春の経験がある人、または売買春問題に関心のある人」の回答率が高いはずであり、また後者は「性的不満をもっている人」の回答率が高いはずなのです。従って、そのような回答からの分析でもって「一般論」を語ることは全く出来ないのでした。
経験調査は、経験した人が回答しやすい
あることを「経験したかどうかという調査」では、経験した人は経験しなかった人より調査に積極的に回答する傾向があります。No.81「2人に1人が買春」の「買春調査」と今回書いた公明党愛知県青年局の「痴漢被害調査」は、その経験調査です。
経験調査では、経験した人はいろいろと回答する項目があるのですが、経験していない人は基本的には「経験ありません」で終わりなのですね。回答率に差が出てきて当然です。
特定の考えの調査元が行う調査では、その考えに親和的な人が、より多く回答をしようとする
社会調査をやる団体や組織はさまざまですが、そういった組織は組織なりの「考え」や「方針」を持っていることが多いわけです。とすると、回答する人はその「考え」に添った人が多くなって当然です。以下に「本書」から何点かの例をあげます。
1993年、急速な円高が進む中で、当時の経済企画庁と通産省は、ほぼ同時期に実施した小売業の調査結果を発表しました。その経済企画庁の方の発表が「本書」に事例としてあげられています。以下、引用します。
(当時の)経済企画庁は、円高差益を還元する指導を行う立場の省庁であり、全国の小売業の人たちはそれを知っているわけです。従って「円高差益を還元している小売店、還元を計画している小売店」が、より積極的にこの調査に回答したはずです。64%というのは、200社を調査し、回答した小売業・45%のうちの64%です( = 58社)。「円高差益還元、200社中、少なくとも58社」というのがより正しい解釈です。
1990年代末の神戸空港の建設問題について、空港を作るという市の方針に対し「神戸空港・住民投票の会」という団体が「模擬投票」を実施しました。模擬投票というのは駅などに投票箱を置いて市民の意見を求めるものです。
そもそもこの団体の主張は神戸空港建設反対です。従って建設反対の人が、より「模擬投票」に参加するわけです。「神戸空港建設に反対を表明したものは94.7パーセント」だったとしても、それはあたりまえでしょう。
空港建設というような公共事業については、メリット・デメリットがあるわけで、どちらを重視するかで意見が分かれるはずです。賛成・反対が拮抗するとまではいかないまでも、2:1とか、ぜいぜい3:1とか(あるいはその逆)という範囲に納まるはずです。もし本当に「神戸市民全体の94.7パーセントが建設に反対」だったとしたら、神戸市は民主主義とは対極の、全体主義的な思想統制が行き渡った都市ということになります。戦前の日本とか、ナチス政権下のドイツとかでありました。今でもそういう国がありますが・・・・・・。
まさか元神戸大学長が「神戸市は思想統制が徹底した都市」だと思っているわけではないでしょうから、この団体は「模擬投票」の単純なカラクリを利用して、自分たちの意見を通そうとしたのだと考えられます。カラクリが分かっていながらあえて強弁するという確信犯的行動です。そんなことにいちいち付き合っていられないので、市長が直接面会しなかったのは正しいですね。市役所でもみ合いになったようですが・・・・・・。
この調査の回答率は59%と、比較的高い率です。しかしアムネスティは死刑制度に反対している団体としてよく知られています。従って「死刑制度に反対」という意見の人や「アムネスティ、もっと頑張れ」と思っている人が、より多く回答するはずです。また谷岡氏も指摘しているように、アムネスティはしばしば「反人権」の行為や言動を厳しく糾弾します。それは悪いことではないと思うのですが、「死刑制度に賛成」と回答したらアムネスティに糾弾されるのではないかと選挙の立候補者が思ったとしても理解できます。「自分の信念を、どういう場でも堂々と述べよ。政治家なんだから」という意見は全く正しいのですが、往々にして人間はその通りには行動できないのです。
死刑制度に反対と回答したのは、調査対象者からすると38%です( = 59% × 65%)。この数値に注目しておくべきだと思います。
比較の対象を欠く調査に早急な判断は禁物
「本書」に載っている例です。1994年12月、人事院は関東の女性国家公務員の中から300人を抽出したアンケートを行い、その結果が、翌1995年5月8日付の新聞紙上に発表されました。
調査の方法が妥当だったという前提で「関東の女性国家公務員の49%は能力評価に不満」ということは事実なのでしょう。問題は「だったとしたら、何が言えるのか」ということです。もし仮に「関東の男性国家公務員の55%は能力評価に不満」だとしたら、女性国家公務員の能力評価の満足度は男性国家公務員より高いということになってしまうのです。
比較の対象を欠く調査では、絶対値の高い低いをうんぬんできないのはあたりまえです。
まず一つの記事を取り上げます。今回もNo.81に引き続いて少々昔の読売新聞の記事ですが、たまたまそうなっただけであって、読売新聞に問題記事が多いとか、そういうことを言うつもりは全くありません。No.81と違って今回は、れっきとした政党組織による「社会調査」です。
愛知では半数が痴漢の被害
2001年3月22日の読売新聞に「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」という見出しの記事が掲載されました。その記事の全文を引用します。
|
公明党がこのような調査をすることや、また記事の最後に示唆してあるように痴漢被害の防止のため女性専用車両を導入する運動をしたり、ないしは街灯を増設する働きかけをしたりというのは、全く問題がありません。それは政党組織として正しい行動だし、評価すべき活動です。
ここで問題にしたいのはこの調査で「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」と言えるのかどうかで、それは違うと思うのです。公明党愛知県青年局がそう発表したのか、新聞社が勝手に見出しをつけたのかは定かではありませんが、前者だとして話を進めます。
公明党愛知県青年局の女性党員がどういう形で街頭調査をしたのかを想像してみると、おそらく「痴漢に関するアンケート実施中
その場を通行する人はどう思うでしょうか。これは「痴漢を無くす(少なくする)ために公明党が何らかの動きをしようとしている、そのためのアンケートだ」と、誰もがパッと思うでしょう。れっきとした日本の政党がアンケートをとるからには、そうとしか考えられない。
とすると、このアンケートに立ち止まる可能性が高い人は次のような人たちです。
| ◆ | 痴漢の被害者、被害を受けそうなった人 | |
| ◆ | 家族、知人、知り合いなどが痴漢被害にあった人 | |
| ◆ | 痴漢問題に関心がある人。 | |
| ◆ | 公明党の支持者 |
そして総じて言えることは「被害を受けたことがない人より、痴漢の被害者の方がこのアンケートに立ち止まる確率がよほど高いだろう」ということです。被害者は「もう二度とあんな目にあいたくない」という思いが強いでしょうから・・・・・・。
従って「アンケートに立ち止まった人の46%が痴漢被害を受けた」からといって「アンケートに立ち止まらなかった人の46%が痴漢被害を受けた」とは全く言えないわけです。「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」という新聞の見出しを見ると、愛知県の男性に痴漢常習者が多いのかと一瞬思ってしまいますが、記事の内容を読むとそんなことは全くないのです。
もし公明党が「痴漢被害者の割合」を調べたいのなら、簡便な方法があります。公明党愛知県青年局の党員とその家族で10-30代の女性全員に聞き取り調査をし、回収率90%以上を目標とする痴漢被害調査を実施すればよいのです。公明党の組織力であればそれは容易だと思います。こうすると11,000人というような回答数にはとてもならないでしょうが「痴漢被害者の割合」という観点からすると、よほど信頼性の高い調査になると思います。かつ労力は少ない。
公明党青年局のアンケート調査が無駄だと言っているわけではありません。11,000人から回答得て46%が痴漢被害者だということは、約5,000人の「証言」が得られたわけです。どの地下鉄路線が被害にあいやすいとか、公園ならどの場所に被害が集中しているのか(ないしは集中していないのか)を明らかにし、女性専用車両を導入する路線の優先度を提言したり、どこに街灯を設置すべきかを提言したりするための有益な情報が得られたと考えられます。ただ言いたいことは、この調査で「愛知の10-30代、半数が痴漢被害」などとはとても言えない、ということなのです。
以上の例からも分かるように「社会調査」は調査のやり方とデータの解釈の仕方によっては信用できないものになってしまいます。そのことを各種の実例をあげて解説した本があります。次に、その本の内容から「社会調査」が陥りやすい誤りを書いてみたいと思います。
「社会調査」のウソ
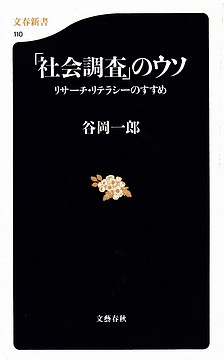
| |||
ずさんな「社会調査」や価値のないアンケートを谷岡氏は「ゴミ」と呼んでいて、それはかなり過激な表現ですが、解説していることは極めて真っ当で、非常にためになる本だと思います。この本にあげられている数々の事例から一部をピックアップし、「社会調査」の報道を読むときの注意点をまとめてみます。なお引用した部分以外は谷岡氏の意見そのままではなく、谷岡氏の見解も参考にしながら私が考えたことです。
低い回答率の調査は信用できない
まず谷岡氏が何回か強調していることですが、低い回答率の調査は信用できないのです。なぜなら、その調査に「わざわざ回答をした人」は、回答するという特別な行動をとった理由があるはずだからです。
前々回のNo.81「2人に1人が買春」で書いた「買春調査」と「ハイト・レポート」(回答率はそれぞれ12.5%と6%)がまさにそうでした。前者は「買春の経験がある人、または売買春問題に関心のある人」の回答率が高いはずであり、また後者は「性的不満をもっている人」の回答率が高いはずなのです。従って、そのような回答からの分析でもって「一般論」を語ることは全く出来ないのでした。
経験調査は、経験した人が回答しやすい
あることを「経験したかどうかという調査」では、経験した人は経験しなかった人より調査に積極的に回答する傾向があります。No.81「2人に1人が買春」の「買春調査」と今回書いた公明党愛知県青年局の「痴漢被害調査」は、その経験調査です。
経験調査では、経験した人はいろいろと回答する項目があるのですが、経験していない人は基本的には「経験ありません」で終わりなのですね。回答率に差が出てきて当然です。
特定の考えの調査元が行う調査では、その考えに親和的な人が、より多く回答をしようとする
社会調査をやる団体や組織はさまざまですが、そういった組織は組織なりの「考え」や「方針」を持っていることが多いわけです。とすると、回答する人はその「考え」に添った人が多くなって当然です。以下に「本書」から何点かの例をあげます。
| 経済企画庁(当時)の円高差益還元調査 |
1993年、急速な円高が進む中で、当時の経済企画庁と通産省は、ほぼ同時期に実施した小売業の調査結果を発表しました。その経済企画庁の方の発表が「本書」に事例としてあげられています。以下、引用します。
|
(当時の)経済企画庁は、円高差益を還元する指導を行う立場の省庁であり、全国の小売業の人たちはそれを知っているわけです。従って「円高差益を還元している小売店、還元を計画している小売店」が、より積極的にこの調査に回答したはずです。64%というのは、200社を調査し、回答した小売業・45%のうちの64%です( = 58社)。「円高差益還元、200社中、少なくとも58社」というのがより正しい解釈です。
| 神戸空港建設の是非を問う模擬投票 |
1990年代末の神戸空港の建設問題について、空港を作るという市の方針に対し「神戸空港・住民投票の会」という団体が「模擬投票」を実施しました。模擬投票というのは駅などに投票箱を置いて市民の意見を求めるものです。
|
そもそもこの団体の主張は神戸空港建設反対です。従って建設反対の人が、より「模擬投票」に参加するわけです。「神戸空港建設に反対を表明したものは94.7パーセント」だったとしても、それはあたりまえでしょう。
空港建設というような公共事業については、メリット・デメリットがあるわけで、どちらを重視するかで意見が分かれるはずです。賛成・反対が拮抗するとまではいかないまでも、2:1とか、ぜいぜい3:1とか(あるいはその逆)という範囲に納まるはずです。もし本当に「神戸市民全体の94.7パーセントが建設に反対」だったとしたら、神戸市は民主主義とは対極の、全体主義的な思想統制が行き渡った都市ということになります。戦前の日本とか、ナチス政権下のドイツとかでありました。今でもそういう国がありますが・・・・・・。
まさか元神戸大学長が「神戸市は思想統制が徹底した都市」だと思っているわけではないでしょうから、この団体は「模擬投票」の単純なカラクリを利用して、自分たちの意見を通そうとしたのだと考えられます。カラクリが分かっていながらあえて強弁するという確信犯的行動です。そんなことにいちいち付き合っていられないので、市長が直接面会しなかったのは正しいですね。市役所でもみ合いになったようですが・・・・・・。
| アムネスティの死刑制度についてのアンケート |
|
この調査の回答率は59%と、比較的高い率です。しかしアムネスティは死刑制度に反対している団体としてよく知られています。従って「死刑制度に反対」という意見の人や「アムネスティ、もっと頑張れ」と思っている人が、より多く回答するはずです。また谷岡氏も指摘しているように、アムネスティはしばしば「反人権」の行為や言動を厳しく糾弾します。それは悪いことではないと思うのですが、「死刑制度に賛成」と回答したらアムネスティに糾弾されるのではないかと選挙の立候補者が思ったとしても理解できます。「自分の信念を、どういう場でも堂々と述べよ。政治家なんだから」という意見は全く正しいのですが、往々にして人間はその通りには行動できないのです。
死刑制度に反対と回答したのは、調査対象者からすると38%です( = 59% × 65%)。この数値に注目しておくべきだと思います。
比較の対象を欠く調査に早急な判断は禁物
「本書」に載っている例です。1994年12月、人事院は関東の女性国家公務員の中から300人を抽出したアンケートを行い、その結果が、翌1995年5月8日付の新聞紙上に発表されました。
|
調査の方法が妥当だったという前提で「関東の女性国家公務員の49%は能力評価に不満」ということは事実なのでしょう。問題は「だったとしたら、何が言えるのか」ということです。もし仮に「関東の男性国家公務員の55%は能力評価に不満」だとしたら、女性国家公務員の能力評価の満足度は男性国家公務員より高いということになってしまうのです。
比較の対象を欠く調査では、絶対値の高い低いをうんぬんできないのはあたりまえです。
(次回に続く)
No.82 - 新聞という商品 [社会]
(前回から続く)
No.81「2人に1人が買春」からの続きです。前回に書いた「新聞は商品である」という視点から、もうすこし続けてみたいと思います。
警鐘に商品価値
No.81「2人に1人が買春」で、新聞記事では「警告・警鐘に商品価値がある」という主旨のことを書きました。その警告・警鐘が的を射たものかどうかにかかわらず、とにかく警告・警鐘であることに価値があるという主旨です。その例を何点かあげます。
| 児童の体力が低下したという記事 |
文部科学省は小学生・中学生(計 40万人)の運動能力測定を毎年行って公表しているのですが、これをもとに「児童の体力が低下したという記事」が掲載されることがしばしばあります。本当にそうでしょうか。
文部科学省のホームページに公開されている運動能力測定の結果(全国体力、運動能力、運動習慣等調査)を表にしてみたのが次です。比較可能な最も古いデータがある1985年度と、2010年度、2012年度の結果です。2011年度は東日本大震災で中止されました。表で赤く色をつけたのは「1985年度平均を上回った生徒の割合が40%未満だった種目」です。また青色をつけたのは「1985年度平均を上回った生徒の割合が50%以上だった種目」です。
| 学年 | 種目 | 1985年 | 2010年 | 2012年 | |||
| 平均 | 平均 | 85年平均以上の 生徒の割合 |
平均 | 85年平均以上の 生徒の割合 |
|||
| 小学5年生 | 握力 | 男 | 18.35kg | 16.91kg | 37.4% | 16.71kg | 35.2% |
| 女 | 16.93kg | 16.37kg | 46.2% | 16.23kg | 44.3% | ||
| 反復横飛び | 男 | 39.46点 | 41.47点 | 66.1% | 41.59点 | 66.5% | |
| 女 | 37.94点 | 39.18点 | 62.8% | 39.24点 | 63.5% | ||
| 50m走 | 男 | 9.05秒 | 9.38秒 | 42.0% | 9.36秒 | 42.8% | |
| 女 | 9.34秒 | 9.65秒 | 40.3% | 9.63秒 | 41.3% | ||
| ソフトボール 投げ |
男 | 29.94m | 25.23m | 30.6% | 23.77m | 24.3% | |
| 女 | 17.60m | 14.55m | 25.9% | 14.21m | 23.5% | ||
| 中学2年生 | 握力 | 男 | 31.61kg | 29.70kg | 40.0% | 29.57kg | 39.5% |
| 女 | 25.56kg | 23.86kg | 38.0% | 23.95kg | 38.8% | ||
| 持久走 男子:1500m 女子:1000m |
男 | 366.40秒 | 397.36秒 | 35.2% | 392.58秒 | 39.1% | |
| 女 | 267.11秒 | 295.67秒 | 27.8% | 292.88秒 | 30.4% | ||
| 50m走 | 男 | 7.90秒 | 8.05秒 | 51.1% | 8.02秒 | 52.5% | |
| 女 | 8.57秒 | 8.90秒 | 38.9% | 8.87秒 | 40.9% | ||
| ハンドボール 投げ |
男 | 22.10m | 21.18m | 46.9% | 21.15m | 46.7% | |
| 女 | 15.36m | 13.20m | 31.8% | 13.04m | 30.5% | ||
(文部科学省のホームページのデータより作成)
| 1985年度平均を超えた生徒が40%未満 | |
| 1985年度平均を超えた生徒が50%以上 |
この表を要約すると次にようになるでしょう。
| ◆ | 児童の運動能力は、1985年と比較して全般的に低い。 | |
| ◆ |
特に小学5年生の ・握力(男) ・ソフトボール投げ(男女) 中学2年生の ・握力(男女) ・持久走(男女) ・ハンドボール投げ(女) の低下幅が大きい(10~15%程度の低下) | |
| ◆ | 逆に、小学5年生の「反復幅跳び」は平均記録が向上している。また中学2年生男子の50m走は1985年とほぼ同じである。 |
これは新聞ではなくテレビなのですが、2013年3月のNHKの報道番組で「昭和60年(1985)のピークの年に比べて、50メートル走の記録が低下」とういう「ニュース」を言っていました(2012年度調査にもとづくニュース)。こういう報道姿勢は非常に疑問です。ピークの年と比較するなら、児童の体力は毎年低下していることになるからです。
この手のニュース報道におけるお決まりの解説は「子どもが外で遊ばなくなった」「遊び場が少なくなった」というものです。果たしてそうなのでしょうか。
運動能力テストの種目を見て思うのは、子どもが公園などで遊ぶこととは直接的関係が薄い種目がほとんどだということです。例外はソフトボール投げでしょうか。野球をやる子なら公園でキャッチボールをすることがあると思います(それでもソフトボールを投げている姿は見た記憶がありません)。ほとんどの種目は、それをやるとしたら学校です。50m走も単なる公園での駆けっこではありません。50m全力ダッシュです。持久走も、ジョギングやランニングが趣味の子もいるとは思いますが、やるとしたらまず学校のグランドでの周回走でしょう。「握力」という体育の授業はありませんが、握力に最も関係していそうなのは鉄棒だと思います。
そして「体力の低下」ということを「握力」を例にとると、はたして1985年当時の児童と2010/2012年の児童の鉄棒の練習量は同じなのでしょうか。先生が学校で鉄棒の技(逆上がりとか、蹴上がりとか)を指導し「テストをします」などと言うと、子どもは放課後でも公園でも練習するものです。学校の影響は大きいと思います。
あくまで直感ですが、児童の「運動能力」は、学校での指導内容、学校教育に起因する該当種目の練習量が左右するのではないでしょうか。
大人でジムに通っている人は、トレーニングを始める前と比較して始めた後では「握力」や「反復横飛び」の記録が向上することが理解できると思います。似たような「種目」をジムでやっている人は多いでしょう。また趣味でランニングを始めた人は、始める前と比較して持久走の記録が格段に向上したと実感できるはずです。
「体力が低下」という報道の言い方は、児童・生徒が「虚弱になった」というニュアンスです。そいういう警鐘のつもりでしょうが、もっと冷静に調べてみるべきだと思います。そもそも「運動能力」を「体力」と表現していいのかという問題がある。さらに児童の体力が低下したという報道は、小学5年生の反復横飛びの記録が向上していることについて全く触れません。それは「体力が低下」という報道にとっては都合が悪いからでしょう。不都合な真実、とうわけです。都合が悪いことはないことにするという姿勢でしょう。しかし「全般的には記録が低下しているのに、反復横飛びだけは向上している。なぜだろう」と考えることから、正しい報道は始まると思うのです。
「運動能力の変化は該当種目の練習量の多少に起因する」というのはあくまで仮説です。しかしそういう要因も十分考えられる。報道としては「警鐘を鳴らした」つもりかもしれませんが、もうすこし冷静にものごとを見た方がよいと思います。
| 若者が本を読まなくなったという記事 |
若者が本を読まなくなったという記事もよく掲載されます。若者の活字離れ、という言い方になることもある。こういう時になぜ決まって若者が主題になるのか、高齢者の活字離れはないのかが疑問ですが、それはさておいても若者の活字離れは本当かということがあります。
全国学校図書館協議会は毎日新聞と共同で、全国の小・中・高校の児童生徒、1万人を対象に読書調査を毎年行っています。学校に調査を依頼し、教師が生徒にヒアリングして「5月の1ヶ月に読んだ本の冊数」を調査するものです。また「5月に1冊も本を読まなかった人」を「不読者」と定義し、不読者の割合も公開されています。その年次変化(最新データは2012年)をホームページから引用します。
| 5月1か月間の平均読書冊数の推移 |
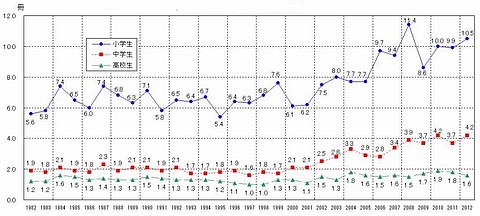
|
不読者(0冊回答者)の推移 |
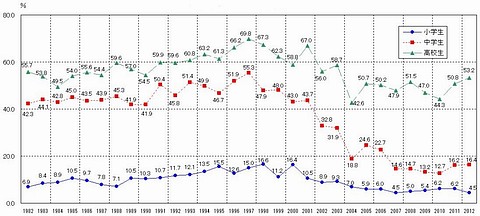
|
| (全国図書館協議会のホームページより引用) |
この調査結果をまとめると以下のようになるでしょう。
| ◆ | 平均読書冊数は、小学生、中学生では増加傾向にある。高校生では横ばいである。 | |
| ◆ | 不読者の割合は1990年代後半に向かって増加したが、それ以降は現在まで減少傾向にある。 | |
| ◆ | 小学生は本を読む児童と読まない児童の差が激しい。2012年度で不読者が53.2%あるにもかかわらず、平均読書数は10.5冊である。中学生・高校生の平均読書数は少ないが、不読者の割合も少なく、まんべんなく本を読んでいることがうかがえる。 |
もちろん、この調査だけで若者の読書傾向をうんぬんできません。しかしこの調査は「継続的に」「調査対象を広くとって」行われています。若者の読書傾向を議論するなら、こういったまじめな調査から分かる事実にもとづくべきでしょう。
付け加えると「若者の活字離れ」という言い方の大きな問題点は「比較の対象を欠いている」ことです(「児童の体力低下」も同じですが)。仮に10代 - 20代を「若者」とすると、たとえば30代 - 50代の「働き盛りの層」が活字離れしていないのかどうか、高齢者はどうなのかという視点がありません。もし働き盛りも高齢者も活字離れしているとしたら「日本人の活字離れ」ということになり、若者だけを取り上げてうんぬん、という話にはならないのです。
さらに「活字離れ」というときの「活字」は暗黙に本・雑誌・新聞を言っているようですが、現代では活字メディアが多様化しています。そのことも考慮すべきだと思います。
以上、警鐘・警告の報道として、
・児童の体力が低下した
・若者が本を読まなくなった
の二つを取り上げたのですが、この他にも新聞紙面ではいろいろの警鐘・警告があります。
経済面では、日本が世界市場で負けているという記事がその典型です。液晶テレビの世界市場で韓国のサムスン電子とLG電子に負けている、スマートフォンでアップルとサムスンに負けているというような記事です。
もちろん弱みを分析したり、負けている要因を明らかにするのは非常に重要なことであり、その記事自体が問題ではありません。しかしちょっと疑問に思うのは「日本が世界市場で勝っている」という記事があまり掲載されないことです。「勝っている」例をコンシューマー・エレクトロニクスで言うと、世界のデジタル1眼カメラのほぼ100%は日本製です。No.38「ガラパゴスの価値」に他の例を何点か書きましたが、なぜ強いのかを(浮かれずに、冷静に)分析することもまた重要なはずです。
気象現象、特に「異常気象」と思える現象を何でもかんでも地球温暖化に結びつける記事も要注意だと思います。台風の勢力が異常に強くても集中豪雨がきても地球温暖化の影響のように言われる。
有名な諏訪湖の「御神渡り」という自然現象があります。2009年はこの現象が見られませんでした(2010年、2011年もなかった)。それは地球温暖化の影響だと書いた報道があったと記憶しています。ところが、2012年に御神渡りが復活したときには「地球温暖化も一服」という記事にはならないのです(2013年にも御神渡りがあった)。御神渡りは毎年できるというわけではありません。せめて、記録が残っている期間で何%の年に御神渡りができたのか、それを調べてから報道すべきでしょう。
以上にとりあげた「警告・警鐘」には共通する事項があります。大多数の新聞購読者にとっては、直接かつ近々の被害が及ばないたぐいの警告・警鐘だという共通項です。「児童の体力が低下した」り「若者が本を読まなくなった」のは、それが本当だとすると確かに国の将来にとってまずい事態だと思えますが、それが新聞購読者の生活に直接影響するわけではありません。液晶テレビやスマホで日本製品が負けているとしても、生活に支障はない。地球温暖化で海面が上昇して日本の海岸地域がしばしば浸水に見舞われるようになったとすると、確かにそれは非常にまずいが、早くても数十年後の話だと「タカをくくって」いられる。
逆に大多数の新聞購読者に直接の被害が近々に及ぶたぐいの警告・警鐘は記事になりません。たとえば「このまま国債を発行し続けたら、国債金利が急上昇し、それがハイパーインフレへの引き金となって国家財政が破綻する」といった警告・警鐘は新聞では取り上げられないのです(これは例えば、という例です)。
新聞という商品
新聞は商品である、という観点からものを見るとさらにいろいろと見えてくることがあります。読者に「ウケがいい」「顧客満足度の高い」記事を書く傾向にあることを書きましたが、それはとりもなおさず「顧客満足度の低い記事は紙面には載りにくい」ということです。
東日本大震災のあとの「脱原発」の主張がそうです。「脱原発」は正しい主張だと思うのですが、そのデメリットはあまり新聞記事にならない。たとえば(一時的にせよ)電気料金の値上げは容認すべき、とは書かない。時と場合によっては計画停電も甘受しよう、とは書かないわけです。これらのことは読者にとって「イヤなこと」だからでしょう。しかし、世の中は(今、ない)何かを得れば(今、ある)何かが失われます。トータルとしてどちらが良いかという議論のはずです。
商品である以上、その商品を販売している企業のグループ企業の商品は批判できません。これはどの業種でもそうです。全国紙の新聞社はテレビ会社に出資しています。従ってテレビ番組を批判したりはしません。
一例をあげると、小泉首相の時の「郵政解散・郵政選挙」(2008)というのがありました。自民党執行部は郵政民営化に反対する議員の選挙区に「刺客候補」をたてたのですが、その選挙を(NHK以外の)民放テレビ局は情報番組でおもしろおかしく報道し、郵政選挙をあおりにあおりました。当時の民主党の岡田代表がいくら口を酸っぱくして「選挙の争点は郵政民営化だけではない」と言っても、その声はかき消されてしまった。テレビ局主導で日本中が小泉首相の術中にはまった格好になったわけです。
こういう状況は新聞が標榜する民主主義とは相入れない状況です。新聞は、自分では民放テレビ局のような「あおり報道」をしていないのだから、逆にテレビの報道を批判すべきです。新聞社が別の新聞社の記事や報道姿勢を批判することがありますね。それができるくらいなのだから、民放テレビ局の「あおり報道」を批判することなど、論理的にはいくらでもできるはずです。だけどそうはしない。それどころか某全国紙の論説委員がテレビ番組のコメンテーターとして登場し「刺客という言葉は私が作りました」と嬉しそうに発言する。
新聞社は民放テレビ局に出資しています。つまり「同一企業グループの商品は批判しないというあたりまえのことが実践されている」のだと思います。
新聞は「利潤を追求する株式会社が提供している商品」です。従って今まで書いたことの他に、自社のビジネス、ないしは新聞というビジネスにとって都合の悪い記事は掲載されません。
| ◆ | 新聞の広告主にとって都合の悪い記事 | |
| ◆ | 新聞を再販制度の対象からはずすべきだということを、ある団体が主張したというような記事 | |
| ◆ | 異種メディア(新聞・テレビ・ラジオ)間での資本関係を禁止すべきという政府や政治家の発言記事 |
などです。最後の件は民主党政権時時代に原口総務大臣が検討を明言しました(2010年)。先進国で常識化している、いわゆる「クロスオーナーシップの禁止」です。しかし新聞はいっさい報道しませんでした。この種の話題は大臣の発言といえども黙殺するわけです。
それは決して良い悪いの問題ではなく、現代社会で新聞社が新聞を発行するということはそういうことだと思います。自社のビジネスの足元を切り崩すような商品(記事)の提供はできないし、ビジネスの根幹を揺るがしかねない議論のトリガーになるような商品(記事)も提供できないのです。我々読者としては新聞のもつ「商品」の面を理解して接するべきだと思います。
No.81 - 2人に1人が買春 [社会]
No.48「日の丸起立問題について」で、満州事変以降の新聞による戦争への誘導報道について書きました。
歴史を調べてみると、満州事変以前は新聞もすいぶん軍部を批判する記事を掲載していました。この「軍部批判」とその後の「戦争誘導報道」には共通点があるというのが、No.48 に書いたことです。整理すると、
ということでした。
現代の新聞はもちろん戦争誘導をしているわけではありません。新聞は(ほとんどの場合)事実を正確に報道しているし、社会の不正や歪みを明らかにしている。オピニオン・ページにも、よりよい社会や市民生活のための(各新聞社なりの考えに沿った)主張が書かれていると思います。
しかしそいういう基本姿勢とは別に「読者にアピールすることを書く」「読者の目を引くことを書く」という傾向がいろいろとある。それは何も「戦争」というような国家的有事の状況ではなくても、ごく日常的に起こるさまざまな出来事の報道にもあって、そのことは我々読者が十分注意しないといけないと思うのです。今回はそのことを書いてみたいと思います。
2人に1人が買春経験
一つの新聞記事の例をあげます。少々昔の記事ですが、印象に残る記事だったので今でも切り抜きを持っています。1998年の読売新聞です。
記事の見出しである「男性の2人に1人が買春経験アリ」を見ると、えっ!と思いますね。そんなに多いはずないだろうと・・・・・・。
記事の内容を読むと、そのカラクリがすぐに分かります。アンケートに回答した人は約2500人と書いてありますが、きっかり2,500人だったとして、調査用紙を20,000枚配布したのだから回答率は12.5%です。12.5%のうちの46.2%が「買春経験あり」と答えたのだから、それは20000枚を母数とすると5.8%です。従って正確に言うと、
というのが正しい。あるいはもっと踏み込んで、
と言えるかもしれない。回答した人が正直に答えている前提ですが。
僅かな部分を全体に当てはめる愚かさ
12.5%というような低い回答率の調査で、全体がどうかという推定は全く出来ません。このような低い回答率の場合、買春アンケートに回答した人は「回答するという特別な行為をした理由」があると考えられます。それはおそらく買春したことがあるとか、知り合いが買春したとか、海外旅行で買春のオファーがあったとか、経験はないが売買春問題に関心があるとか、とにかく「買春問題の近辺にいる人」です。ということは、回答しなかった87.5%の「普通の」人は、買春という行為の経験も興味も意識もないのがほとんどだと推定されます。そういう人は「わざわざ」買春アンケートに回答したりは普通しないでしょう。「買春したことは? → ない」「売買春のない社会が望ましいと思いますか → はい」とだけしか記入しようのないアンケートに回答する人は少数のはずです。
余談になりますが「僅かな部分を全体に当てはめる」という「手法」は、有名な米国「ハイト・レポート」(シェア・ハイト著。1976/1982)と同じですね。アメリカ人の性的経験を調査したこのレポート(1回目:女性、2回目:男性)は、その数字の扱い方がデタラメです。数学者のA.K.デュードニーは、数々の「数学の罠」を解説した本の中で次のように書いています。( )内は引用注です。
「買春アンケート」は「ハイト・レポート」にならったのかもしれません。テーマに類似性があるし、調査用紙の配布方法も似ている。「男性の2人に1人が買春」と「70%が配偶者以外と性的交渉」という数字も似ている。もし仮に「買春アンケート」の回収率がハイトレポート(2回目)のように6%だったら「70%が買春」となったかもしれません。
「買春アンケート」に戻って、このアンケートには他の問題点もあります。正直に回答しているかどうか分からないという問題点です。さらに無作為抽出でないことも問題です。「買売春問題に取り組む団体や個人的つながりなどを通じて協力を求めた」とありますが、調査対象そのものにかなりのバイアスがかかっていることがうかがえます。
とにかくこのアンケートは、買春経験者の意識調査としては(正直に答えるているという前提で)意味があるでしょうが、男性の何割が買春経験者かという推定には全く役に立たないのです。それは記事の内容を読むと一目瞭然です。
それにもかかわらず、記事の見出しは
です。おそらく新聞社側に用意されている言い訳は「男性の2人に1人が買春経験アリ」と言ったのは「男性と買春を考える会」というグループであり、新聞社としてはそれを報道しただけだ、というものでしょう。しかし世の中にたくさんある「グループ」の言うことをそのまま見出しにするのでは、新聞の役割は無いに等しい。
新聞を読む多くの人は見出しだけを見て内容を判断します。それこそが見出しの目的です。その意味からすると、この記事は捏造記事と言っていいと思います。そして記事を書いた記者もデスクも確信犯的に見出しをつけている。なぜなら、記事内容を見ると事実はこの見出しから受ける印象とは全く違うということが分かるように書いてあるからです。回答率が分かるように書いてあるし、無作為抽出ではないことがちゃんと断ってある。それは記者やデスクの「良心」かもしれません。新聞社は「科学的な世論調査」のプロフェッショナルだという「プライド」からくる良心です。だからこそ、この記事は捏造見出しだと言えるのです。
そして案の定、この見出しに騙された人が出てきました。記事の1週間後の読者投書欄に、以下の文で始まる投書が掲載されたのです。
読売新聞もずいぶん丁寧なものです。捏造見出しをつけた記事を掲載し、それに騙された人の投書まで掲載するのだから・・・・・・。この記事を掲載した目的はこれで十分に達成されたということでしょう。
この記事は極端な例だとは思います。しかしこれほど極端ではなくても、これに類する記事は読売新聞だけでなく現在の新聞にしばしばあり、我々読者は注意して記事を読むべきだと思うのです。
2人に1人が買春という記事から、新聞記事が一般的に持っている性格が透けて見えます。
ニュースは news(ニューズ)であり「新しいもの」という意味です。新聞記事としては、新規性のある情報、人々に知られていない情報、人々を驚かせる情報に「価値」があるわけです。それが社会や人間生活にとって重要か重要でないかは問いません。とにかく新規性です。「2人に1人が買春」というのは、あまり聞いたことがない「新規性の高い」情報です。当然ですが・・・・・・。だから見出しが捏造される。
一般に、売買春を無秩序に放置しておくと社会にとってのマイナスをもたらします。女性の人権問題とか、児童虐待の問題とか、性感染症の蔓延とか、いろいろある。従って売買春を合法化している国(ヨーロッパの多くの国やタイなど)では、売買春を国の認可施設に限ってマイナス面を最小限にしようとしています。
一方、日本では売買春は非合法です。従って「売買春が広まっている」と思える情報は「日本社会に対する警告・警鐘」になります。新聞はこの「警告・警鐘」に価値がある(と考えられている)のです。だから見出しが捏造される。
新聞記事は「新情報に価値がある」「警告・警鐘に価値がある」という一般的な性格があり、それが「2人に1人が買春」という見出し捏造につながるのだと思います。これは極端な例だとは思います。しかし捏造までいかなくても「誇張」や「大袈裟」や「一方的すぎる」という記事は多々ある。そして、このような記事が書かれる根本のところには、
という「あたりまえのこと」があると思うのです。以降、「新聞は商品である」ということから派生する各種の側面についてです。
新聞の顧客満足度
我々は市場経済にもとづく資本主義の社会に生きています。この資本主義社会を支えているのが会社(特に株式会社)であり、商品やサービスを創り出して消費者に購入してもらい、そのことで経済が発展し、それが国の税収を支え、福祉の増進や安全な社会の実現につながっています。
新聞社も株式会社であり、その最大の商品は新聞です。この商品は競争にさらされていて、その競争を勝ち抜いてより多くの読者を獲得することにより、購読料収入が増え、広告収入も安定する。それによってデジタル新聞などに必要な投資の余力が生まれるわけです。
商品の販売数を伸ばすための最大のポイントは「顧客満足度の向上」です。顧客満足度の高い商品を消費者に届けるのが企業というものです。そして新聞という商品の顧客満足度を決める最大のものが、新聞の記事内容そのものです。
No.48「日の丸起立問題について」と今回の冒頭において、新聞の
・満州事変以前の軍部批判報道
・満州事変以降の戦争誘導報道
について、この二つは全く正反対に見えるけれども明確な共通点があり、それは両方とも「読者にウケる」ことだと書きました。言い換えると、前者は軍部の「横暴」を苦々しく思う読者の満足度が高く、後者は中国にどんどん進出しろ、もっとやれと思う読者の満足度が高いわけです。もちろんこの場合の「読者」は同じ人です。
満州事変は80年以上の前の出来事であり、もちろん現在の政治・社会の状況は当時とは全く違うのですが、この「顧客満足度の高い記事を読者に届ける」という姿勢は現代も続いていると思うのです。「顧客満足度の高い記事」の例を2点だけあげます。
「学歴社会批判」という記事や社説のスタンスが根強くあります。いわゆる有名大学(従って、入学するのが難しい難関大学)の出身者が社会における上位のポジションを得て、従って収入も多いという社会構造を批判的に報道・解説するものです。
しかしこれはちょっと考えてみると奇妙な議論です。たとえば企業が大学生を面接で採用するときに「有名大学だから」ということで有利になるような判断をしたとします。ないしは、特定の有名大学と連携して推薦で採用したとします。これは企業の行動としては理にかなっています。学歴という「ある程度、客観性のある基準」を考慮しているからです。有名大学・難関大学に入学したということは、本人がそれなりの努力をしてきており、かつ知的水準も標準以上だと推定できます。学歴を全く無視するとしたら、その方が企業の行動としては異常でしょう。
学歴でなく実力で、という議論は当たりません。実力は数10分の面接では分かりません。コミュニケーション能力や自己表現力は分かるかもしれませんが、それとて演技可能です。会社でどういう「実力」を発揮するかは本人の能力と入社後の努力いかんです。もし仮に、入社後に本人の昇進が能力や仕事上の成果でなく学歴や出身大学で決まるのなら、それこそ「いびつな」学歴社会(=学閥)と言えるでしょう。しかし、そんなことを続けていたら会社はおかしくなります。
「学歴社会」の反対語は「階級社会」でしょう。入社試験でいうと、親の経済力や親の職業、どういう家系の出身かで入社の成否が決まる社会です。階級社会はやめようということが学歴社会の意味です。つまり家が貧しくても、どういう家系であっても、学歴さえ獲得すれば社会の上位のポジションに行く道が開けるということです。もちろん道が開けたあとに本当に上位に行けるかは本人の努力次第ですが・・・・・・。そういう社会の方が健全です。家系や一族の財産といった固定性の強いものではなく、学歴という流動性の高いものを尺度にすることにより、社会が活性化する。
従って目指すべきは、たとえ親の経済力がなくても本人が努力すれば「学歴」を取得できる社会、有名大学にだっていけるという社会です。つまり、各種の公的な学習のしくみや奨学金制度の充実です。親が高収入でないと有名大学(の特定学部)へは行けないという社会を排除していく方向が望ましい。「学歴社会」が崩壊しないような国のシステムが必要なのです。
ではなぜ「学歴社会批判」なのか。それは新聞にとってみると「顧客満足度」の高い記事だからと考えられます。「学歴社会批判」は暗に「有名大学出身者批判」になっている。有名大学出身者は、新聞の購読者全体からすると一握りです。大多数の購読者はそうではない。従って批判は顧客満足度を向上させる。
消費者向けに大量販売される商品にはさまざまな購入者がいます。「特定の性格をもった顧客層」(=セグメント)に対してだけの「魅力づけ」はできません。全国紙でいうと、購読者の性別とか年齢や職業や居住地域でターゲットを絞ったりはできない。しかし「非・有名大学出身者」は新聞購読者なかでの大セグメントを構成しているはずです。95%以上とか・・・・・・。その大セグメントの満足度を向上させるのは、商品としての意味が大いにあるのです。
大きな事故の責任者が刑事訴訟で訴追されるという裁判があります。例をあげると、
などですが、こういった事故に起因する訴訟はいっぱいあります。上の例はすぐ思いついたものをあげただけで、特にこの二つを取り上げた意図はありません。医療事故や製品欠陥に起因する事故、薬害訴訟や公害訴訟もあります。
こういう訴訟における被害者の遺族の心境は大変よく分かります。何の落ち度もない人が突然亡くなる。遺族としてはどうしても納得できません。責任者が裁判で有罪になり処罰されることで、事故が少しでも起きにくいような制度や仕組みやルールにできたとしたら、亡くなった人の無念も少しは晴らせる。被害者の命と引き替えに社会が少しでも良くなるのだから・・・・・・。おそらくこういう心境だと思います。遺族が民事賠償訴訟を起こす場合も、賠償金を獲得することが目的ではないでしょう。社会が少しでも良くしたいという心境だと思います。
従って、被告が無罪になったり、有罪になっても微罪だったりすると、遺族としては「不当判決」「不当裁判」だということになります。「裁判官は遺族の心境を全く理解していない」「これでは不正を見過ごすことになる」「故人が浮かばれない」というようなコメントが出ることもある。これらのことは大変よく理解できて、遺族の心情としては当然だと思います。
問題はそれを報道する側の姿勢です。そこに強い違和感を覚えることが多い。つまり新聞としては、
の両方が必要だと思うのですが、前者の「被害者親族・遺族の視点」が強調された報道になる傾向が強い。これではまずいと思うのです。
裁判官は法律に照らして被告が有罪か無罪を判断し、量刑を言い渡します。もちろん過去の判例も参照されます。日本は法治国家であり、裁判官は「法の番人」です。
裁判官に「世の中の不正を正す役割」や「世の中から悪をなくす役割」を求めてはなりません。裁判官は大岡越前守ではない。法律に照らして(刑事訴訟なら)検察官と弁護人のどちらの言い分がより正当か、それを判断するのが役割です。裁判官に「世の中を正す役割」を求めるという、その態度自体が大変まずいと思います。世の中を正すというような重要な役割を法律の専門家に求めてはいけないのです。
もし裁判官が市民感情を考慮して法律を過大に拡大解釈し、被告に不利(ないしは有利)な判決を言い渡したとしたら、それこそ世の中を正すこととは逆行します。なぜなら、市民感情とは相入れない判決を出さざるを得ないという法律の不備を覆い隠すことになるからです。法律にもとづいて「市民感情とは相入れない判決」が出ることこそ、法律を改正したり、新たな法律を制定する原動力になるはずです。法律の改正・制定はもちろん国民の代表である議会の役割であって、裁判所ではありません。それが学校で習った三権分立の基本です。不当な判決ではなく、法律が不備なのだし、法律が時代の変化に追従できていないのです。
我々は(そして大多数の新聞購読者は)どうしても被害者の感情に自己を同一化します。いつ自分が被害者になるかもしれないと思うからです。反対に事故の責任を問われた被告にはシンパシーを感じにくい。自分が列車運行の責任者になる姿は想像しにくいし、警察の警備責任者である姿も考えにくい。
結局のところ「被害者親族・遺族の視点」だけが強調された報道というのは、大多数の購読者の心情にマッチしていて、従って「顧客満足度」が高いのだと思います。しかしそれでだけの報道は、社会をより良い方向に向かわせることにはならない。このことはよくよく注意すべきだと思います。
|
歴史を調べてみると、満州事変以前は新聞もすいぶん軍部を批判する記事を掲載していました。この「軍部批判」とその後の「戦争誘導報道」には共通点があるというのが、No.48 に書いたことです。整理すると、
| ◆ | 満州事変の以前は、新聞もすいぶん日本の軍部を批判する記事を掲載していた。 | |
| ◆ | しかし満州事変が起きると軍部を擁護し、共同宣言まで出して、むしろ軍部の先をゆく報道をした。 | |
| ◆ | 軍部批判と軍部擁護には明らかな共通点がある。それは「国民にウケる記事」という共通点である。軍部は横暴だ、軍人はえらそうにしていると苦々しく思っている人が多い時には軍部批判がウケる。日本はもっと中国大陸に進出しようと思っている人が多いときには軍部擁護がウケる。 |
ということでした。
現代の新聞はもちろん戦争誘導をしているわけではありません。新聞は(ほとんどの場合)事実を正確に報道しているし、社会の不正や歪みを明らかにしている。オピニオン・ページにも、よりよい社会や市民生活のための(各新聞社なりの考えに沿った)主張が書かれていると思います。
しかしそいういう基本姿勢とは別に「読者にアピールすることを書く」「読者の目を引くことを書く」という傾向がいろいろとある。それは何も「戦争」というような国家的有事の状況ではなくても、ごく日常的に起こるさまざまな出来事の報道にもあって、そのことは我々読者が十分注意しないといけないと思うのです。今回はそのことを書いてみたいと思います。
2人に1人が買春経験
一つの新聞記事の例をあげます。少々昔の記事ですが、印象に残る記事だったので今でも切り抜きを持っています。1998年の読売新聞です。
|
記事の見出しである「男性の2人に1人が買春経験アリ」を見ると、えっ!と思いますね。そんなに多いはずないだろうと・・・・・・。
記事の内容を読むと、そのカラクリがすぐに分かります。アンケートに回答した人は約2500人と書いてありますが、きっかり2,500人だったとして、調査用紙を20,000枚配布したのだから回答率は12.5%です。12.5%のうちの46.2%が「買春経験あり」と答えたのだから、それは20000枚を母数とすると5.8%です。従って正確に言うと、
| 調査対象とした人の5.8%が「買春経験あり」と答えた |
というのが正しい。あるいはもっと踏み込んで、
| 調査対象とした人の少なくとも5.8%は買春経験がある |
と言えるかもしれない。回答した人が正直に答えている前提ですが。
僅かな部分を全体に当てはめる愚かさ
12.5%というような低い回答率の調査で、全体がどうかという推定は全く出来ません。このような低い回答率の場合、買春アンケートに回答した人は「回答するという特別な行為をした理由」があると考えられます。それはおそらく買春したことがあるとか、知り合いが買春したとか、海外旅行で買春のオファーがあったとか、経験はないが売買春問題に関心があるとか、とにかく「買春問題の近辺にいる人」です。ということは、回答しなかった87.5%の「普通の」人は、買春という行為の経験も興味も意識もないのがほとんどだと推定されます。そういう人は「わざわざ」買春アンケートに回答したりは普通しないでしょう。「買春したことは? → ない」「売買春のない社会が望ましいと思いますか → はい」とだけしか記入しようのないアンケートに回答する人は少数のはずです。
余談になりますが「僅かな部分を全体に当てはめる」という「手法」は、有名な米国「ハイト・レポート」(シェア・ハイト著。1976/1982)と同じですね。アメリカ人の性的経験を調査したこのレポート(1回目:女性、2回目:男性)は、その数字の扱い方がデタラメです。数学者のA.K.デュードニーは、数々の「数学の罠」を解説した本の中で次のように書いています。( )内は引用注です。
|
「買春アンケート」は「ハイト・レポート」にならったのかもしれません。テーマに類似性があるし、調査用紙の配布方法も似ている。「男性の2人に1人が買春」と「70%が配偶者以外と性的交渉」という数字も似ている。もし仮に「買春アンケート」の回収率がハイトレポート(2回目)のように6%だったら「70%が買春」となったかもしれません。
「買春アンケート」に戻って、このアンケートには他の問題点もあります。正直に回答しているかどうか分からないという問題点です。さらに無作為抽出でないことも問題です。「買売春問題に取り組む団体や個人的つながりなどを通じて協力を求めた」とありますが、調査対象そのものにかなりのバイアスがかかっていることがうかがえます。
とにかくこのアンケートは、買春経験者の意識調査としては(正直に答えるているという前提で)意味があるでしょうが、男性の何割が買春経験者かという推定には全く役に立たないのです。それは記事の内容を読むと一目瞭然です。
それにもかかわらず、記事の見出しは
| 男性の2人に1人が「買春経験アリ」 |
です。おそらく新聞社側に用意されている言い訳は「男性の2人に1人が買春経験アリ」と言ったのは「男性と買春を考える会」というグループであり、新聞社としてはそれを報道しただけだ、というものでしょう。しかし世の中にたくさんある「グループ」の言うことをそのまま見出しにするのでは、新聞の役割は無いに等しい。
新聞を読む多くの人は見出しだけを見て内容を判断します。それこそが見出しの目的です。その意味からすると、この記事は捏造記事と言っていいと思います。そして記事を書いた記者もデスクも確信犯的に見出しをつけている。なぜなら、記事内容を見ると事実はこの見出しから受ける印象とは全く違うということが分かるように書いてあるからです。回答率が分かるように書いてあるし、無作為抽出ではないことがちゃんと断ってある。それは記者やデスクの「良心」かもしれません。新聞社は「科学的な世論調査」のプロフェッショナルだという「プライド」からくる良心です。だからこそ、この記事は捏造見出しだと言えるのです。
そして案の定、この見出しに騙された人が出てきました。記事の1週間後の読者投書欄に、以下の文で始まる投書が掲載されたのです。
|
読売新聞もずいぶん丁寧なものです。捏造見出しをつけた記事を掲載し、それに騙された人の投書まで掲載するのだから・・・・・・。この記事を掲載した目的はこれで十分に達成されたということでしょう。
この記事は極端な例だとは思います。しかしこれほど極端ではなくても、これに類する記事は読売新聞だけでなく現在の新聞にしばしばあり、我々読者は注意して記事を読むべきだと思うのです。
2人に1人が買春という記事から、新聞記事が一般的に持っている性格が透けて見えます。
| 新情報に価値がある |
ニュースは news(ニューズ)であり「新しいもの」という意味です。新聞記事としては、新規性のある情報、人々に知られていない情報、人々を驚かせる情報に「価値」があるわけです。それが社会や人間生活にとって重要か重要でないかは問いません。とにかく新規性です。「2人に1人が買春」というのは、あまり聞いたことがない「新規性の高い」情報です。当然ですが・・・・・・。だから見出しが捏造される。
| 警告・警鐘に価値がある |
一般に、売買春を無秩序に放置しておくと社会にとってのマイナスをもたらします。女性の人権問題とか、児童虐待の問題とか、性感染症の蔓延とか、いろいろある。従って売買春を合法化している国(ヨーロッパの多くの国やタイなど)では、売買春を国の認可施設に限ってマイナス面を最小限にしようとしています。
一方、日本では売買春は非合法です。従って「売買春が広まっている」と思える情報は「日本社会に対する警告・警鐘」になります。新聞はこの「警告・警鐘」に価値がある(と考えられている)のです。だから見出しが捏造される。
新聞記事は「新情報に価値がある」「警告・警鐘に価値がある」という一般的な性格があり、それが「2人に1人が買春」という見出し捏造につながるのだと思います。これは極端な例だとは思います。しかし捏造までいかなくても「誇張」や「大袈裟」や「一方的すぎる」という記事は多々ある。そして、このような記事が書かれる根本のところには、
| 新聞は商品である |
という「あたりまえのこと」があると思うのです。以降、「新聞は商品である」ということから派生する各種の側面についてです。
新聞の顧客満足度
我々は市場経済にもとづく資本主義の社会に生きています。この資本主義社会を支えているのが会社(特に株式会社)であり、商品やサービスを創り出して消費者に購入してもらい、そのことで経済が発展し、それが国の税収を支え、福祉の増進や安全な社会の実現につながっています。
新聞社も株式会社であり、その最大の商品は新聞です。この商品は競争にさらされていて、その競争を勝ち抜いてより多くの読者を獲得することにより、購読料収入が増え、広告収入も安定する。それによってデジタル新聞などに必要な投資の余力が生まれるわけです。
商品の販売数を伸ばすための最大のポイントは「顧客満足度の向上」です。顧客満足度の高い商品を消費者に届けるのが企業というものです。そして新聞という商品の顧客満足度を決める最大のものが、新聞の記事内容そのものです。
No.48「日の丸起立問題について」と今回の冒頭において、新聞の
・満州事変以前の軍部批判報道
・満州事変以降の戦争誘導報道
について、この二つは全く正反対に見えるけれども明確な共通点があり、それは両方とも「読者にウケる」ことだと書きました。言い換えると、前者は軍部の「横暴」を苦々しく思う読者の満足度が高く、後者は中国にどんどん進出しろ、もっとやれと思う読者の満足度が高いわけです。もちろんこの場合の「読者」は同じ人です。
満州事変は80年以上の前の出来事であり、もちろん現在の政治・社会の状況は当時とは全く違うのですが、この「顧客満足度の高い記事を読者に届ける」という姿勢は現代も続いていると思うのです。「顧客満足度の高い記事」の例を2点だけあげます。
| 学歴社会批判 |
「学歴社会批判」という記事や社説のスタンスが根強くあります。いわゆる有名大学(従って、入学するのが難しい難関大学)の出身者が社会における上位のポジションを得て、従って収入も多いという社会構造を批判的に報道・解説するものです。
しかしこれはちょっと考えてみると奇妙な議論です。たとえば企業が大学生を面接で採用するときに「有名大学だから」ということで有利になるような判断をしたとします。ないしは、特定の有名大学と連携して推薦で採用したとします。これは企業の行動としては理にかなっています。学歴という「ある程度、客観性のある基準」を考慮しているからです。有名大学・難関大学に入学したということは、本人がそれなりの努力をしてきており、かつ知的水準も標準以上だと推定できます。学歴を全く無視するとしたら、その方が企業の行動としては異常でしょう。
学歴でなく実力で、という議論は当たりません。実力は数10分の面接では分かりません。コミュニケーション能力や自己表現力は分かるかもしれませんが、それとて演技可能です。会社でどういう「実力」を発揮するかは本人の能力と入社後の努力いかんです。もし仮に、入社後に本人の昇進が能力や仕事上の成果でなく学歴や出身大学で決まるのなら、それこそ「いびつな」学歴社会(=学閥)と言えるでしょう。しかし、そんなことを続けていたら会社はおかしくなります。
「学歴社会」の反対語は「階級社会」でしょう。入社試験でいうと、親の経済力や親の職業、どういう家系の出身かで入社の成否が決まる社会です。階級社会はやめようということが学歴社会の意味です。つまり家が貧しくても、どういう家系であっても、学歴さえ獲得すれば社会の上位のポジションに行く道が開けるということです。もちろん道が開けたあとに本当に上位に行けるかは本人の努力次第ですが・・・・・・。そういう社会の方が健全です。家系や一族の財産といった固定性の強いものではなく、学歴という流動性の高いものを尺度にすることにより、社会が活性化する。
従って目指すべきは、たとえ親の経済力がなくても本人が努力すれば「学歴」を取得できる社会、有名大学にだっていけるという社会です。つまり、各種の公的な学習のしくみや奨学金制度の充実です。親が高収入でないと有名大学(の特定学部)へは行けないという社会を排除していく方向が望ましい。「学歴社会」が崩壊しないような国のシステムが必要なのです。
ではなぜ「学歴社会批判」なのか。それは新聞にとってみると「顧客満足度」の高い記事だからと考えられます。「学歴社会批判」は暗に「有名大学出身者批判」になっている。有名大学出身者は、新聞の購読者全体からすると一握りです。大多数の購読者はそうではない。従って批判は顧客満足度を向上させる。
消費者向けに大量販売される商品にはさまざまな購入者がいます。「特定の性格をもった顧客層」(=セグメント)に対してだけの「魅力づけ」はできません。全国紙でいうと、購読者の性別とか年齢や職業や居住地域でターゲットを絞ったりはできない。しかし「非・有名大学出身者」は新聞購読者なかでの大セグメントを構成しているはずです。95%以上とか・・・・・・。その大セグメントの満足度を向上させるのは、商品としての意味が大いにあるのです。
| 被害者視点だけの裁判報道 |
大きな事故の責任者が刑事訴訟で訴追されるという裁判があります。例をあげると、
| ◆ | 大列車事故に関して鉄道会社の運行責任者や会社幹部が訴追される。 | |
| ◆ | イベントで狭いスペースに人が集中して圧死者が出た事件において、警察の警備責任者が訴追される |
などですが、こういった事故に起因する訴訟はいっぱいあります。上の例はすぐ思いついたものをあげただけで、特にこの二つを取り上げた意図はありません。医療事故や製品欠陥に起因する事故、薬害訴訟や公害訴訟もあります。
こういう訴訟における被害者の遺族の心境は大変よく分かります。何の落ち度もない人が突然亡くなる。遺族としてはどうしても納得できません。責任者が裁判で有罪になり処罰されることで、事故が少しでも起きにくいような制度や仕組みやルールにできたとしたら、亡くなった人の無念も少しは晴らせる。被害者の命と引き替えに社会が少しでも良くなるのだから・・・・・・。おそらくこういう心境だと思います。遺族が民事賠償訴訟を起こす場合も、賠償金を獲得することが目的ではないでしょう。社会が少しでも良くしたいという心境だと思います。
従って、被告が無罪になったり、有罪になっても微罪だったりすると、遺族としては「不当判決」「不当裁判」だということになります。「裁判官は遺族の心境を全く理解していない」「これでは不正を見過ごすことになる」「故人が浮かばれない」というようなコメントが出ることもある。これらのことは大変よく理解できて、遺族の心情としては当然だと思います。
問題はそれを報道する側の姿勢です。そこに強い違和感を覚えることが多い。つまり新聞としては、
| ◆ | 被害者の親族・遺族の視点 | |
| ◆ | 裁判や法律のあり方の視点 |
の両方が必要だと思うのですが、前者の「被害者親族・遺族の視点」が強調された報道になる傾向が強い。これではまずいと思うのです。
裁判官は法律に照らして被告が有罪か無罪を判断し、量刑を言い渡します。もちろん過去の判例も参照されます。日本は法治国家であり、裁判官は「法の番人」です。
裁判官に「世の中の不正を正す役割」や「世の中から悪をなくす役割」を求めてはなりません。裁判官は大岡越前守ではない。法律に照らして(刑事訴訟なら)検察官と弁護人のどちらの言い分がより正当か、それを判断するのが役割です。裁判官に「世の中を正す役割」を求めるという、その態度自体が大変まずいと思います。世の中を正すというような重要な役割を法律の専門家に求めてはいけないのです。
もし裁判官が市民感情を考慮して法律を過大に拡大解釈し、被告に不利(ないしは有利)な判決を言い渡したとしたら、それこそ世の中を正すこととは逆行します。なぜなら、市民感情とは相入れない判決を出さざるを得ないという法律の不備を覆い隠すことになるからです。法律にもとづいて「市民感情とは相入れない判決」が出ることこそ、法律を改正したり、新たな法律を制定する原動力になるはずです。法律の改正・制定はもちろん国民の代表である議会の役割であって、裁判所ではありません。それが学校で習った三権分立の基本です。不当な判決ではなく、法律が不備なのだし、法律が時代の変化に追従できていないのです。
我々は(そして大多数の新聞購読者は)どうしても被害者の感情に自己を同一化します。いつ自分が被害者になるかもしれないと思うからです。反対に事故の責任を問われた被告にはシンパシーを感じにくい。自分が列車運行の責任者になる姿は想像しにくいし、警察の警備責任者である姿も考えにくい。
結局のところ「被害者親族・遺族の視点」だけが強調された報道というのは、大多数の購読者の心情にマッチしていて、従って「顧客満足度」が高いのだと思います。しかしそれでだけの報道は、社会をより良い方向に向かわせることにはならない。このことはよくよく注意すべきだと思います。
(次回に続く)
No.48 - 日の丸起立問題について [社会]
前回の、No.47「最後の授業・最初の授業」で、アメリカの公立学校で毎日、国旗に向かって唱えられている「忠誠の誓い」(The Pledge of Allegiance)について書きました。国によっていろいろと事情が違うのはあたりまえですが、感じるのはアメリカと日本の差異です。そこで日本の国旗に関する話を書いてみようと思います。No.37「富士山型の愛国心」で、以下のように日章旗(日の丸)に触れました。
今回はその補足です。国旗掲揚に対して起立しなかったため組織から処分を受け、それが裁判になっている件を取り上げます。
日の丸訴訟
2012年1月16日に最高裁判所で「日の丸訴訟」の一つに対する判決がありました。この訴訟は、東京都内の公立学校の教員など171人が、校長の業務命令に反して「日の丸に起立せず君が代を斉唱しなかった」として受けた処分の取り消しを求めた3件の訴訟です。最高裁の判決は、戒告(168人)は取り消さず、減給(1人)は処分取り消し、停職(2人)のうち一人は処分を取り消すが、一人は取り消さず、というものでした。停職を取り消さなかった一人は、過去に国旗掲揚を妨害し校長を批判する文書を生徒にくばったとあります。
最高裁の判断を要約すると、日の丸に対する不起立(=単なる不起立)で許される処分は戒告までであり、これは校長の裁量権の範囲内である。しかし減給や停職などの重い処分は慎重を期する必要がある、というものでしょう。2011年の5月に校長の職務命令は合憲、との最高裁判決があるので、これで一通りの最高裁判断がそろったことになります。「日の丸訴訟」には他にいろいろあって、特に「日の丸掲揚と君が代斉唱を義務化した東京都教育委員会の通達」が合憲かどうかが今でも争われていますが、校長の職務命令の合憲性と妥当な処分範囲を示した今回の判決が踏襲されるものと考えられます。
2011年1月29日付の朝日新聞によると、不起立などを理由に処分をうけた教員は、2000年度から2009年度の10年間で、全国で延べ1143人であり、このうち東京都が443人(39%)を占めるそうです。ある50代の都立高校教諭の話が載っていました。それによると、その教員は2005年以降、卒業式や入学式には出席していないと言います。2004年に不起立で戒告処分を受けてからは、毎回、来場者の受付や警備などの式場外の役割を担当している。「戒告処分を重ねないよう、校長が配慮しているのだろう」。だが校長からは「起立・斉唱ができないなら、式に出席する学級担任は任せられない」と言われたそうです。「思想信条にかかわることを強制するやり方はおかしい。教え子が卒業証書を受け取る姿が見られず、つらい」との教諭の弁です。
今回の最高裁判決の是非についての議論はここではしません。また都教育委員会の通達が妥当か、通達違反による処分が妥当かの議論もしません。ここで問題にしたいのは、学校におけるセレモニーにおいて、日章旗に対して起立しないという、教員としての行動の妥当性です。
以下「日の丸問題」とは、ある組織に所属していて、その組織の公式行事において国旗に対して起立し国歌を斉唱することを拒否したため(起立しない、斉唱しない)その組織から処分を受け、その結果として裁判ないしは係争になっていること、を言います。
また「不起立行動」とは、国旗に対して起立せず、国歌を斉唱しないという行動そのものを言います。「不起立行動」をとったため、組織から処分を受けて係争になっているのが「日の丸問題」というわけです。
なお、不起立行動をする教員の中には「日の丸=国旗」ということに異論を言う人もいると思いますが、実質的に日本の国旗として扱われてきたし、また1999年に法律でも定義されたので、国旗とも書きます。
以下は、この問題に関する何点かの感想です。
不起立行動は本当に思想・信条の問題なのか
まず考えないといけないのは、不起立行動は本当に思想・信条の問題なのかということです。たとえばスポーツの国際大会で国旗の掲揚と国歌の演奏があり、主催者から起立を求められることはよくあります。そいういう状況において、不起立行動をとる先生はどうするのでしょうか。対戦相手の外国の国旗に不起立というのは非常にまずいわけです。良識のある教師なら、そんな外国に失礼な行動はできないはずです。外国の国旗の時には起立して日の丸の時には着席するか、そうするのが嫌でスポーツの国際大会には行かないか、そのどちらかでしょう。
仮に、スポーツの国際大会では日章旗に起立するようであれば(起立してもよいと考えるようであれば)、その教員は「学校という場において、思想・信条以外の理由で不起立行動をとっている」ことになります。
報道を読んで何となく感じるのは、日の丸問題がもっと大きなコトの一部、ないしは別のコトの象徴として争われているのでは、という疑いです。たとえば教育委員会の(不起立行動をする教師からすると)「押しつけ」がいろいろあり「それに対する反発」というような、もっと一般的で大きな問題です。
私は教師ではないので教育現場の実態は分かりません。大きな問題の一部(ないしは別の問題の象徴)かもしれないし、そうでないかも知れない。ここでは「日の丸問題」を純粋に思想・信条の問題として考えることにします。従って、不起立行動をする教員は首尾一貫している、つまりスポーツの国際大会でも不起立だとして話を進めます。また国旗に起立する必要のある学校外のセレモニー、たとえば全国戦没者追悼式には、たとえ戦没者の遺族として招待されても出席しないとして話を進めます。
不起立行動の理由の例としては、
という、個人の「思想・信条」だと考えたいと思います。あるいは戦時だけでなく、もっと長期の視点で
という思想・信条の問題として考えます。もっと別の理由もあるかもしれませんが、以下はこの「思想・信条」および「不起立行動」が妥当か、が論点です。
「少数・教師・公務員」の問題
まず認識しておきたいことは、不起立行動をする教員はごく少数ということです。2011年1月29日の朝日新聞記事のグラフによると「日の丸・君が代」関係で処分をうけた教員の数は、多い年で年間260人程度です。小・中・高校の教員の数は約85万人ぐらいなので、全体の数からみるとごく僅かです。仮に「不起立行動をとったが処分をうけなかった人」「処分をうけるのを避けるために式の当日休んだ人」「休みはしなかったが、会場の受付などをして式場には入らなかった人」が100倍いるとしても全体の 3% 程度(1年あたり)であり、非常に少ないわけです。ごく一部の教員の話だということに注意する必要があると思います。
さらにもう1点、考えるべきは、不起立行動はほとんど公立学校の教員で起こっていることです。国旗を掲揚し起立するセレモニーは全国の数々の組織体で行われているはずです。しかし、企業や官庁や私立の学校で日の丸問題が起こったという話はあまり聞きません。公務員、しかも教員の間で「思想・信条の問題だから、組織の長の指示には従わない」ということが(一部で)起こっている。この背景には「公務員の教師は特別の存在である」という教師側の意識があるように感じます。しかしこのような意識があったとしても、それはごく一部であり、大部分の公立学校の先生たちが不起立行動をしていないことは確かなのです。
しかし少数とは言うものの、以前に不起立行動をとる教員と教育委員会の間で板挟みとなった校長先生が自殺するという痛ましい事件が起きました(1999年2月、広島)。不起立行動の教員がごく一部だとしても、人を死に追いやったケースもあるので看過できない問題です。
日の丸のもとに死んでいった人、という論理の妥当性
まず「日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、心情的に起立できない」という理由(の一つ)の妥当性です。
No.37「富士山型の愛国心」でも書いたように、過去に日の丸が「国民を戦争に駆り立てる道具」となった時代があったことは確かです。日章旗が「国のために立派に死ぬ」ことの象徴のような時期があった。
国家の責務は国民の生命と安全を守ることです。戦時にはもちろん戦争に勝つことが第1の優先事項になりますが、その次に重要な事項の一つは戦場における自国の兵隊の死者を減らすことです。それは戦力を維持する上で必須です。しかし日本ではそうでない時代があった。自国の兵士の生命はほとんど省みずに、国のためということが喧伝された。捕虜になったら死ねというような教育とか、自爆攻撃作戦があった。戦いの結果の戦死ならまだしも、太平洋戦争での戦死者の6割は餓死だといいますね(補給がなかったわけです)。戦闘員のみならず、米兵につかまることを恐れて非戦闘員が自決するということもサイパンや沖縄(の一部)であった。それらの「国のため」の象徴(の一つ)として日の丸があった。これは全くの事実だと思います。
しかし、このような「超国家主義」の時期は、満州事変(1931年)から太平洋戦争の敗戦(1945)の14年間とみなしてよいと思います。「日の丸」が制定されたのは1870年で、現在まで約140年たっています。この間の約1/10という比較的短い期間のことなのです。この比較敵短い期間のことにこだわって、それから65年以上も経過している現在も行動するのは建設的な態度ではありません。
そして「国民を戦争に駆り立てる道具」は国旗だけではなかった。その強力な道具となったのは新聞です。
80年ほど時代をさかのぼりますが、関東軍が満州事変を引き起こすと(1931)、大新聞は関東軍擁護・支那批判の論陣を張りました。満州での日本の行動を非難した国際連盟の調査団の結果が出ると、大新聞だけでなく全国の新聞社132社が共同宣言を出し、満州国設立の妥当性と国際連盟批判のアピールをします(1932)。日本が国際連盟を脱退して世界の「孤児」になったのは、その翌年(1933)です。
戦時中に「鬼畜米英」「米鬼」などとあおって、アメリカ兵に対する恐怖心を国民に植え付けたのも新聞です。No.47「最後の授業・最初の授業」で書いたように、故・青島幸夫氏は『23分間の奇跡』の訳者あとがきで、
と書いていますが、新聞はそういうスローガンを大量に書いていた。また、いかにアメリカ兵が残虐かを書き立てた。そういたった「誘導」が、非戦闘員の自決という悲劇の誘因になっことは容易に想像がつきます。
現在の新聞は「総括」を行って、軍部や政府に強要されてそのような報道を行ったと主張しています。強要はあったとしても、それだけではありません。むしろ「軍部の先を行っていた」のが新聞であり「軍部を積極的に後押しした」のが新聞です。このあたりの事情については数々の本が出版されています(たとえば、石田収『新聞が日本をダメにした - 太平洋戦争煽動の構図 - 』現代書林 1995)。
かつて「国民を戦争に駆り立てる道具」だったものを今でも拒否するのなら、不起立行動をとる教師は、現代も続いている大新聞の購読を拒否しなければなりません。はたして、そうなのでしょうか。
大新聞は一応の「反省」の弁を言っています。反省しているから現代の新聞は読むのだ、という論理もあるでしょう。しかしあたりまえだけど「日の丸」は反省を言えない。国旗をどう使うかは国民の問題であって国旗の責任ではないのです。責任を問うのなら、国旗をそういう風にした人の責任を問題にすべきです。
明治から満州事変までの日章旗
さらに不起立行動の理由として、満州事変から第2次世界大戦という戦争期間だけでなく、もっと大きく明治・大正時代を含む「軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴としての日の丸」という見方もあると思います。確かにその通りですが、同時に明治以降の時代は、近代化を推進し、国民皆教育が徹底し、産業が振興し、現代日本語を含む数々の新しい文化が作り出された時期でもあった。日の丸はそれらの象徴でもあるはずです。ものごとの一面だけを見た思考は意味がないと思います。
そもそも、太平洋戦争の敗戦の時点(1945年8月)において、明治の最終年(明治45年。1912年)に生まれた人は33歳です。大正の最終年(大正15年。1926年)に生まれた人は19歳です。戦後の日本の(奇跡の)復興、民主主義国家としての発展、高度経済成長、教育システムが確立していった時期、つまり「日の丸不起立行動をとる教師の人たちが育ってきた時期」は、
ことは誰の目にも明らかです。戦後の焼け野原から復興したのは昭和20年代以降なので誤解しそうですが、そこで「新しい日本」を作ったのは明治・大正生まれの人なのですね。あたりまえだけど・・・・・・。ちなみに、戦後の日本を代表する企業・ソニー(昭和21年・1946設立)の創業者である井深大氏は明治41年(1908)生まれであり、井深氏を支えた共同創業者の盛田昭夫氏は大正10年(1921)生まれです。明治・大正時代を一面だけからとらえることは、現代の日本社会の基盤を作った先人たちをないがしろにすることにつながるでしょう。
現代においても「軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴としての日の丸」を掲げる人たちがいることも確かですが、それは一部の人です。全体を見ない議論も意味がありません。
心情的にできないという理由は妥当か
「日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、心情的に起立できない」という理由の「心情」はどうでしょうか。
少なくとも2000年代において不起立行動をとっている人は、戦争の実体験者ではありません。太平洋戦争の終了時には生まれていないか、ないしは幼少です。「戦争」「戦死」「国家主義の象徴としての日章旗」を実体験したのは、不起立行動をとっている教員の親、ないしはそれ以上の世代です。
タクシーとの交通事故で親や兄弟を亡くした人がいたとします。その人がタクシーを嫌って今でもタクシーに乗らないとしたら、その行動はよく理解できます。タクシー全般が悪いのではなく事故を起こした運転手が悪いのですが、強い悲しみを受けた人の「心情」としては理解できるわけです。しかし、その人の子供までもがタクシーに乗らないとしたら、それは変です。親の行動をみてそうしているとしたら、親離れしていないということになります。
日の丸問題で「心情」を理由に不起立行動をする人は、親の世代以上の人から聞いて、ないしは歴史書を読んで、そこから生まれた「心情」を言っています。それは本人の実経験から生まれた心情ではないのです。
人間の心情は尊重すべきですが、心情はそのうち世代交代ともに薄れて風化します。大切なのは、事実を次世代に伝え、悲惨な結果をもたらした原因と反省を記録として残すことでしょう。心情を問題にしている限りそれはいずれ消え去り、次の世代には何も残らなくなると思います。
「思想の自由」は「行動の自由」ではない
不起立行動は思想・信条の問題であって、それに介入するのはおかしい、思想・信条の自由の侵害だという論理があります。「信条」と「心情」がややこしいので「思想の問題」「思想の自由」とします。
確かに「思想の自由」は極めて大切な基本的人権の一つであり、「言論の自由」とともに現代の民主主義社会を成立させている根幹です。
歴史を振り返ってみると、ある一定の考えをいだくこと、ある主義を信じることが処罰の対象になった時代がありました。権力者に批判的な考えだというだけで逮捕される時代があったし、キリスト教を信奉することだけで投獄されることもあった。コミュニストというだけで警察につかまることもあった。日本でも、また世界でもです。
しかし世界の歴史をみると、近代国家の形成とともに「思想の自由」が確立していく。もちろん、揺り戻しや紆余曲折があり、今でもあるわけですが、とにかく「思うこと、考えを抱くこと、主義、は自由」という原則が次第に確立していく。これは人類の歴史において、この200年程度の間におこった画期的なことだと思います。これに「言論の自由」が加わって近代の民主主義社会が成立するわけですね。
生活に困窮しコンビニに強盗に入ってお金を強奪したいと思っても、思っただけでは逮捕されたり処罰されたりはしません。大量殺人を指示した宗教の教祖を今でも崇拝しています、と言ったとしても、その「崇拝している」ことだけで逮捕されたり処罰されたりはしない。
しかし、思想の自由は「内心の自由」であって、外部に現れる「行動の自由」を意味するものではないのですね。外部に現れる行動がルール・法律に反すると処罰されることがある。どの程度の行動が罪になるかは、ルール違反の重さや罪の重さによって決まります。コンビニに強盗に入るつもりでおもちゃの鉄砲を買っただけでは罪には問われないが、クーデターなどの国家転覆では謀議だけで罪になる。
日の丸起立問題に即して言うと、
の二つは違います。前者は「思想」「考え」であり、後者は「行動」です。不起立行動をとる教員は、この「思想」と「行動」が直結しています。これが非常に問題だと思うのです。
もちろん起立行動を組織の長が指示することは「思想に対する制限」ともとれないことはない。しかしたとえそうだとしても、それは「間接的な制限」です。前述の新聞記事で不起立行動をとる教師も「思想信条にかかわることを強制」と言っていますね。「思想信条を強制」とは言っていない。そして「思想の自由」を「思想にかかわることの自由」と拡大し、しかも「かかわることとは何かの解釈を本人にゆだねる」ということでは、この現代社会は成り立ちません。「本人が決める、思想にかかわることの自由」が無制限に保証される、というのはありえないのです。
思想と行動は一致させるべきか
一般の社会においては「思想・考え・思い」と「行動」は必ずしも一致しないし、残念だけど一致させられないというのが、普通の社会人の考え、ないしは行動様式です。つまり、
などが一般的でしょう。普通の社会人はそう考えて行動しています。
さらに、思想の自由を守るためには、思想と行動の一致を「あえて」やめないといけない(やめた方がよい)場合があります。特定の思想を攻撃したい人がいたとします。近代国家では、思想を理由に人を攻撃できません。そこで攻撃者は必ず「外形として現れる行動のルール違反」を突いてきます。そのルール違反を罰することが目的ではなく、思想を攻撃したいために・・・・・・。これはいわゆる「別件逮捕」と似ています。有印私文書不実記載と聞くとどんな大変な罪かと思いますが、単に偽名で口座を作っただけだったりする。本当のヤマ(巨額脱税など)は別にあるのですね。
「日の丸は、軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴である」と考えて(こう考えることは本人の自由です)公的セレモニーにおける不起立行動をとる人は、いかにも行動が稚拙だと感じられます。
「国旗への起立を特定の思想と結びつける」行動
「戦前に日本を戦争に誘導した人たち」と「不起立行動をする人たち」の間には、明確な共通点があります。
という共通点です。
もちろん、特定の行動が特定の思想・信条・信教を受けいれる(受け入れている)ことの表明になることが、社会ではいっぱいあります。しかし近代国家において、1つの国が1つの国旗という状況下で、さらに多様な意見の表明をベースとする民主主義社会において、国旗に起立することを特定の思想と結びつけることはやってはならないし、それは排除すべき考えのはずです。
日の丸問題に即して言うと、日本人には少数派と多数派があって、次のような構図になっているのでしょう。
少数派は「国旗掲揚=国家主義想の表明」だと考える。これにはさらに2派あって
の2つです。広めたい人は、日の丸への起立は国家への忠誠を誓うことだと考え、起立するかをどうかを忠誠の「踏絵」としたい。一方、不起立行動をとる人は、そのことで国家主義に反対を表明したいわけです。今、国家主義と書きましたが、これは軍国主義でも(極端には)皇国思想でもよいわけです。
一方、多数派は「国旗掲揚=特定思想とは無縁」と考えています。多数派の意見は以下のようなものでしょう。
などです。
外国国籍の人を含め、日本在住の人は国家を構成してその恩恵(安全、教育、人権、福祉など)を受けています。学校には外国国籍の生徒や在日の生徒もいるし、最近では外国人の(臨時)教員もいる。日の丸への起立が特定の思想(例:日本への忠誠)の表明だとすると、外国国籍の人たちは起立できなくなります。それでは現代国家は成り立ちません。多数派の考えが妥当です。
しかしこのような多数派に抵抗して、不起立行動をとる教員は「国旗に対して起立することを、特定の政治思想と結びつけよう」と躍起になっています。これは、現代国家における国旗のあるべき姿を逸脱させようとするものです。と同時に「国旗への起立=国家主義の表明」としたい人にとっては歓迎でしょう。「国旗に起立することは、特定の思想の表明である」というムードが生まれるし、不起立行動を糾弾することは、憲法論まで持ち出すことを含めて、いくらでもできるからです。
要するに「不起立行動をする人たち」は、「戦前に日本を戦争に誘導した人たち」が作り上げたパラダイムのもとに行動しています。主義・主張は全く正反対ですが、おなじレールの上での主義・主張であることは間違いないのです。
不起立行動は「やってはいけない教育」
教師が学校という場で不起立行動をとるということは、生徒に対して、暗黙に「思想・信条を、組織の指示系統やルールを度外視して、外部に行動として表してよい」という教育をしていることになります。これは生徒にとっては大きなマイナスでしょう。学校生活において生徒が「思想・信条をたてに組織のルールや指示系統を無視した行動をとる」としたら、学級や学校は崩壊します。
内心はどういう考えをもっていようとも、外部に現れる行動を社会が要請する一定のパターンに当てはめるのが、教育の中心課題のはずです。いやなこと、やりたくないこと、自分の考えと違うことでも、行動としてはやらないといけない。これは生徒たちが大人になって社会に出ていくまでに学ばないといけない重要なことです。
もちろん、社会が要請する一定のパターン通りに行動するだけで、そこに留まっていたのでは発展はありません。人それぞれがパターンにない独自性(個性)を発揮し、それが自分自身の利益になり、かつ社会にも貢献をするのが望ましいわけです。しかしそのベースとして必須なのは、社会が要請する一定の行動パターンを身につけていることなのですね。
社会が要請する一定のパターン通りに行動することがほとんど出来ないけれど、個人の才能や独自性が際だっていて、そのことで社会から評価される人がいます。芸術家や作家にそういう人がいますね。企業人にも、中にはいる。2011年に亡くなったスティーブ・ジョブズはそれに近いかもしれません。しかし、そのような人はごくごく稀なのです。こういう稀なケースは学校教育でどうするという範疇ではありません。
大多数の市民にとって、まず最低限「社会が要請する一定のパターン通りに行動できる」ことが、社会を構成していく上での必須事項です。その上に立って社会を変えていく(結果として、社会が個人に要請する事項を変える)ことが重要です。
教師としての責任
「かつて日の丸が象徴していた軍国主義、皇国思想、国家主義に反対したい。その復活を阻止したい」という考えをもった教師がいたとしましょう。思想・信条は個人の自由なので、そういう考えを持つことは別にかまわないわけです。
そうであれば、教師としては次のようなことを生徒に教えるべきで、それが教師という職業についた人の責任でしょう。
などです。どうしても起立に抵抗がある人は、教師としての務めとして、教育の場である学校行事では起立し、私的に参加する場でのセレモニー(スポーツの国際大会など)では不起立行動をすべきです。教師という職業を選んだ以上、そのぐらいの覚悟で職(=生徒に教えること)をまっとうしてほしいものです。
「日の丸」が制定されたのは1870年で、現在まで約140年がたっています。この間、不幸なことに日章旗が国民を戦争に動員する道具のように使われたことがあったわけですね。それはざっと言うと、昭和に入ってからの約20年間です。この期間のことを指摘して、現在も「日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、国旗に起立はできない、それは思想と信条の問題」と言う人がいます。 |
今回はその補足です。国旗掲揚に対して起立しなかったため組織から処分を受け、それが裁判になっている件を取り上げます。
日の丸訴訟
2012年1月16日に最高裁判所で「日の丸訴訟」の一つに対する判決がありました。この訴訟は、東京都内の公立学校の教員など171人が、校長の業務命令に反して「日の丸に起立せず君が代を斉唱しなかった」として受けた処分の取り消しを求めた3件の訴訟です。最高裁の判決は、戒告(168人)は取り消さず、減給(1人)は処分取り消し、停職(2人)のうち一人は処分を取り消すが、一人は取り消さず、というものでした。停職を取り消さなかった一人は、過去に国旗掲揚を妨害し校長を批判する文書を生徒にくばったとあります。
最高裁の判断を要約すると、日の丸に対する不起立(=単なる不起立)で許される処分は戒告までであり、これは校長の裁量権の範囲内である。しかし減給や停職などの重い処分は慎重を期する必要がある、というものでしょう。2011年の5月に校長の職務命令は合憲、との最高裁判決があるので、これで一通りの最高裁判断がそろったことになります。「日の丸訴訟」には他にいろいろあって、特に「日の丸掲揚と君が代斉唱を義務化した東京都教育委員会の通達」が合憲かどうかが今でも争われていますが、校長の職務命令の合憲性と妥当な処分範囲を示した今回の判決が踏襲されるものと考えられます。
2011年1月29日付の朝日新聞によると、不起立などを理由に処分をうけた教員は、2000年度から2009年度の10年間で、全国で延べ1143人であり、このうち東京都が443人(39%)を占めるそうです。ある50代の都立高校教諭の話が載っていました。それによると、その教員は2005年以降、卒業式や入学式には出席していないと言います。2004年に不起立で戒告処分を受けてからは、毎回、来場者の受付や警備などの式場外の役割を担当している。「戒告処分を重ねないよう、校長が配慮しているのだろう」。だが校長からは「起立・斉唱ができないなら、式に出席する学級担任は任せられない」と言われたそうです。「思想信条にかかわることを強制するやり方はおかしい。教え子が卒業証書を受け取る姿が見られず、つらい」との教諭の弁です。
今回の最高裁判決の是非についての議論はここではしません。また都教育委員会の通達が妥当か、通達違反による処分が妥当かの議論もしません。ここで問題にしたいのは、学校におけるセレモニーにおいて、日章旗に対して起立しないという、教員としての行動の妥当性です。
| とは言うものの、教育委員会通達(ないしは大阪市のように条例)による強制と処分は、合憲だとしてもやはりまずいと思います。「強制に屈するのは教師としてのありかたに反する、だから起立しない」という、日の丸問題とは全く別の論理を生んで問題を複雑にします。組織での職務命令違反を繰り返したということで、(今回のように)組織内での処分や罰則にとどめるべき案件だと思いますが、それが出来ない理由もあるのでしょう。 |
以下「日の丸問題」とは、ある組織に所属していて、その組織の公式行事において国旗に対して起立し国歌を斉唱することを拒否したため(起立しない、斉唱しない)その組織から処分を受け、その結果として裁判ないしは係争になっていること、を言います。
また「不起立行動」とは、国旗に対して起立せず、国歌を斉唱しないという行動そのものを言います。「不起立行動」をとったため、組織から処分を受けて係争になっているのが「日の丸問題」というわけです。
なお、不起立行動をする教員の中には「日の丸=国旗」ということに異論を言う人もいると思いますが、実質的に日本の国旗として扱われてきたし、また1999年に法律でも定義されたので、国旗とも書きます。
以下は、この問題に関する何点かの感想です。
不起立行動は本当に思想・信条の問題なのか
まず考えないといけないのは、不起立行動は本当に思想・信条の問題なのかということです。たとえばスポーツの国際大会で国旗の掲揚と国歌の演奏があり、主催者から起立を求められることはよくあります。そいういう状況において、不起立行動をとる先生はどうするのでしょうか。対戦相手の外国の国旗に不起立というのは非常にまずいわけです。良識のある教師なら、そんな外国に失礼な行動はできないはずです。外国の国旗の時には起立して日の丸の時には着席するか、そうするのが嫌でスポーツの国際大会には行かないか、そのどちらかでしょう。
仮に、スポーツの国際大会では日章旗に起立するようであれば(起立してもよいと考えるようであれば)、その教員は「学校という場において、思想・信条以外の理由で不起立行動をとっている」ことになります。
報道を読んで何となく感じるのは、日の丸問題がもっと大きなコトの一部、ないしは別のコトの象徴として争われているのでは、という疑いです。たとえば教育委員会の(不起立行動をする教師からすると)「押しつけ」がいろいろあり「それに対する反発」というような、もっと一般的で大きな問題です。
私は教師ではないので教育現場の実態は分かりません。大きな問題の一部(ないしは別の問題の象徴)かもしれないし、そうでないかも知れない。ここでは「日の丸問題」を純粋に思想・信条の問題として考えることにします。従って、不起立行動をする教員は首尾一貫している、つまりスポーツの国際大会でも不起立だとして話を進めます。また国旗に起立する必要のある学校外のセレモニー、たとえば全国戦没者追悼式には、たとえ戦没者の遺族として招待されても出席しないとして話を進めます。
不起立行動の理由の例としては、
| 太平洋戦争(および、その以前からの日中戦争)で、日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、軍国主義の象徴であった日の丸に心情として起立できない |
という、個人の「思想・信条」だと考えたいと思います。あるいは戦時だけでなく、もっと長期の視点で
| 日の丸は、明治から昭和初期の時代までの、軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴として使われた。現代もそういう動きがある。そういった主義・思想に反対する立場からすると、起立することはできない |
という思想・信条の問題として考えます。もっと別の理由もあるかもしれませんが、以下はこの「思想・信条」および「不起立行動」が妥当か、が論点です。
「少数・教師・公務員」の問題
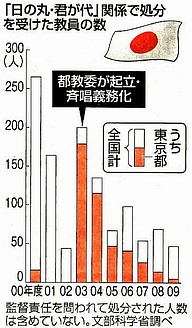
| |||
| 2011年1月29日 朝日新聞 | |||
さらにもう1点、考えるべきは、不起立行動はほとんど公立学校の教員で起こっていることです。国旗を掲揚し起立するセレモニーは全国の数々の組織体で行われているはずです。しかし、企業や官庁や私立の学校で日の丸問題が起こったという話はあまり聞きません。公務員、しかも教員の間で「思想・信条の問題だから、組織の長の指示には従わない」ということが(一部で)起こっている。この背景には「公務員の教師は特別の存在である」という教師側の意識があるように感じます。しかしこのような意識があったとしても、それはごく一部であり、大部分の公立学校の先生たちが不起立行動をしていないことは確かなのです。
しかし少数とは言うものの、以前に不起立行動をとる教員と教育委員会の間で板挟みとなった校長先生が自殺するという痛ましい事件が起きました(1999年2月、広島)。不起立行動の教員がごく一部だとしても、人を死に追いやったケースもあるので看過できない問題です。
日の丸のもとに死んでいった人、という論理の妥当性
まず「日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、心情的に起立できない」という理由(の一つ)の妥当性です。
No.37「富士山型の愛国心」でも書いたように、過去に日の丸が「国民を戦争に駆り立てる道具」となった時代があったことは確かです。日章旗が「国のために立派に死ぬ」ことの象徴のような時期があった。
国家の責務は国民の生命と安全を守ることです。戦時にはもちろん戦争に勝つことが第1の優先事項になりますが、その次に重要な事項の一つは戦場における自国の兵隊の死者を減らすことです。それは戦力を維持する上で必須です。しかし日本ではそうでない時代があった。自国の兵士の生命はほとんど省みずに、国のためということが喧伝された。捕虜になったら死ねというような教育とか、自爆攻撃作戦があった。戦いの結果の戦死ならまだしも、太平洋戦争での戦死者の6割は餓死だといいますね(補給がなかったわけです)。戦闘員のみならず、米兵につかまることを恐れて非戦闘員が自決するということもサイパンや沖縄(の一部)であった。それらの「国のため」の象徴(の一つ)として日の丸があった。これは全くの事実だと思います。
しかし、このような「超国家主義」の時期は、満州事変(1931年)から太平洋戦争の敗戦(1945)の14年間とみなしてよいと思います。「日の丸」が制定されたのは1870年で、現在まで約140年たっています。この間の約1/10という比較的短い期間のことなのです。この比較敵短い期間のことにこだわって、それから65年以上も経過している現在も行動するのは建設的な態度ではありません。
そして「国民を戦争に駆り立てる道具」は国旗だけではなかった。その強力な道具となったのは新聞です。
80年ほど時代をさかのぼりますが、関東軍が満州事変を引き起こすと(1931)、大新聞は関東軍擁護・支那批判の論陣を張りました。満州での日本の行動を非難した国際連盟の調査団の結果が出ると、大新聞だけでなく全国の新聞社132社が共同宣言を出し、満州国設立の妥当性と国際連盟批判のアピールをします(1932)。日本が国際連盟を脱退して世界の「孤児」になったのは、その翌年(1933)です。
| 補足しますと、満州事変以前の新聞は、ずいぶん軍部批判をしていたようです。ところが満州事変以降は軍部の行動支持に回った。一見、180度違うと思えますが、この「批判」と「支持」には明確な共通点があるように見えます。それは「国民にウケがいいことを書く」という共通点です。軍部が横暴だと密かに感じている国民に対しては批判がウケる。一方、中国にどんどん進出せよというのもウケがいい。「真実を書く」のが新聞だと思いますが、それと同時に「国民にウケがいいことを書く」というのも新聞であり、それは今も続いていると思います。「消費者に望まれる商品を届ける、というのがビジネスの鉄則」だからでしょう。 |
戦時中に「鬼畜米英」「米鬼」などとあおって、アメリカ兵に対する恐怖心を国民に植え付けたのも新聞です。No.47「最後の授業・最初の授業」で書いたように、故・青島幸夫氏は『23分間の奇跡』の訳者あとがきで、
「鬼畜米英われらの敵だ」、「撃ちてしやまん」、「一億玉砕」のスローガンのもとに育てられた "少国民" たち |
と書いていますが、新聞はそういうスローガンを大量に書いていた。また、いかにアメリカ兵が残虐かを書き立てた。そういたった「誘導」が、非戦闘員の自決という悲劇の誘因になっことは容易に想像がつきます。
現在の新聞は「総括」を行って、軍部や政府に強要されてそのような報道を行ったと主張しています。強要はあったとしても、それだけではありません。むしろ「軍部の先を行っていた」のが新聞であり「軍部を積極的に後押しした」のが新聞です。このあたりの事情については数々の本が出版されています(たとえば、石田収『新聞が日本をダメにした - 太平洋戦争煽動の構図 - 』現代書林 1995)。
かつて「国民を戦争に駆り立てる道具」だったものを今でも拒否するのなら、不起立行動をとる教師は、現代も続いている大新聞の購読を拒否しなければなりません。はたして、そうなのでしょうか。
大新聞は一応の「反省」の弁を言っています。反省しているから現代の新聞は読むのだ、という論理もあるでしょう。しかしあたりまえだけど「日の丸」は反省を言えない。国旗をどう使うかは国民の問題であって国旗の責任ではないのです。責任を問うのなら、国旗をそういう風にした人の責任を問題にすべきです。
明治から満州事変までの日章旗
さらに不起立行動の理由として、満州事変から第2次世界大戦という戦争期間だけでなく、もっと大きく明治・大正時代を含む「軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴としての日の丸」という見方もあると思います。確かにその通りですが、同時に明治以降の時代は、近代化を推進し、国民皆教育が徹底し、産業が振興し、現代日本語を含む数々の新しい文化が作り出された時期でもあった。日の丸はそれらの象徴でもあるはずです。ものごとの一面だけを見た思考は意味がないと思います。
そもそも、太平洋戦争の敗戦の時点(1945年8月)において、明治の最終年(明治45年。1912年)に生まれた人は33歳です。大正の最終年(大正15年。1926年)に生まれた人は19歳です。戦後の日本の(奇跡の)復興、民主主義国家としての発展、高度経済成長、教育システムが確立していった時期、つまり「日の丸不起立行動をとる教師の人たちが育ってきた時期」は、
| ・ |
明治生まれの人が社会の中核となって指導し | |
| ・ |
大正生まれの人が若手としてささえた |
ことは誰の目にも明らかです。戦後の焼け野原から復興したのは昭和20年代以降なので誤解しそうですが、そこで「新しい日本」を作ったのは明治・大正生まれの人なのですね。あたりまえだけど・・・・・・。ちなみに、戦後の日本を代表する企業・ソニー(昭和21年・1946設立)の創業者である井深大氏は明治41年(1908)生まれであり、井深氏を支えた共同創業者の盛田昭夫氏は大正10年(1921)生まれです。明治・大正時代を一面だけからとらえることは、現代の日本社会の基盤を作った先人たちをないがしろにすることにつながるでしょう。
現代においても「軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴としての日の丸」を掲げる人たちがいることも確かですが、それは一部の人です。全体を見ない議論も意味がありません。
心情的にできないという理由は妥当か
「日の丸のもとに死んでいった人のことを思うと、心情的に起立できない」という理由の「心情」はどうでしょうか。
少なくとも2000年代において不起立行動をとっている人は、戦争の実体験者ではありません。太平洋戦争の終了時には生まれていないか、ないしは幼少です。「戦争」「戦死」「国家主義の象徴としての日章旗」を実体験したのは、不起立行動をとっている教員の親、ないしはそれ以上の世代です。
タクシーとの交通事故で親や兄弟を亡くした人がいたとします。その人がタクシーを嫌って今でもタクシーに乗らないとしたら、その行動はよく理解できます。タクシー全般が悪いのではなく事故を起こした運転手が悪いのですが、強い悲しみを受けた人の「心情」としては理解できるわけです。しかし、その人の子供までもがタクシーに乗らないとしたら、それは変です。親の行動をみてそうしているとしたら、親離れしていないということになります。
日の丸問題で「心情」を理由に不起立行動をする人は、親の世代以上の人から聞いて、ないしは歴史書を読んで、そこから生まれた「心情」を言っています。それは本人の実経験から生まれた心情ではないのです。
人間の心情は尊重すべきですが、心情はそのうち世代交代ともに薄れて風化します。大切なのは、事実を次世代に伝え、悲惨な結果をもたらした原因と反省を記録として残すことでしょう。心情を問題にしている限りそれはいずれ消え去り、次の世代には何も残らなくなると思います。
「思想の自由」は「行動の自由」ではない
不起立行動は思想・信条の問題であって、それに介入するのはおかしい、思想・信条の自由の侵害だという論理があります。「信条」と「心情」がややこしいので「思想の問題」「思想の自由」とします。
確かに「思想の自由」は極めて大切な基本的人権の一つであり、「言論の自由」とともに現代の民主主義社会を成立させている根幹です。
歴史を振り返ってみると、ある一定の考えをいだくこと、ある主義を信じることが処罰の対象になった時代がありました。権力者に批判的な考えだというだけで逮捕される時代があったし、キリスト教を信奉することだけで投獄されることもあった。コミュニストというだけで警察につかまることもあった。日本でも、また世界でもです。
しかし世界の歴史をみると、近代国家の形成とともに「思想の自由」が確立していく。もちろん、揺り戻しや紆余曲折があり、今でもあるわけですが、とにかく「思うこと、考えを抱くこと、主義、は自由」という原則が次第に確立していく。これは人類の歴史において、この200年程度の間におこった画期的なことだと思います。これに「言論の自由」が加わって近代の民主主義社会が成立するわけですね。
生活に困窮しコンビニに強盗に入ってお金を強奪したいと思っても、思っただけでは逮捕されたり処罰されたりはしません。大量殺人を指示した宗教の教祖を今でも崇拝しています、と言ったとしても、その「崇拝している」ことだけで逮捕されたり処罰されたりはしない。
しかし、思想の自由は「内心の自由」であって、外部に現れる「行動の自由」を意味するものではないのですね。外部に現れる行動がルール・法律に反すると処罰されることがある。どの程度の行動が罪になるかは、ルール違反の重さや罪の重さによって決まります。コンビニに強盗に入るつもりでおもちゃの鉄砲を買っただけでは罪には問われないが、クーデターなどの国家転覆では謀議だけで罪になる。
日の丸起立問題に即して言うと、
| ◆ | 日の丸は、軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴であると考える | |
| ◆ | 卒業式・入学式において、組織の長の職務命令に反して不起立行動をとる |
の二つは違います。前者は「思想」「考え」であり、後者は「行動」です。不起立行動をとる教員は、この「思想」と「行動」が直結しています。これが非常に問題だと思うのです。
もちろん起立行動を組織の長が指示することは「思想に対する制限」ともとれないことはない。しかしたとえそうだとしても、それは「間接的な制限」です。前述の新聞記事で不起立行動をとる教師も「思想信条にかかわることを強制」と言っていますね。「思想信条を強制」とは言っていない。そして「思想の自由」を「思想にかかわることの自由」と拡大し、しかも「かかわることとは何かの解釈を本人にゆだねる」ということでは、この現代社会は成り立ちません。「本人が決める、思想にかかわることの自由」が無制限に保証される、というのはありえないのです。
思想と行動は一致させるべきか
一般の社会においては「思想・考え・思い」と「行動」は必ずしも一致しないし、残念だけど一致させられないというのが、普通の社会人の考え、ないしは行動様式です。つまり、
| ◆ | 思想と行動は一致させたい。ただし社会で生きている以上、それが難しいことが多い。 | |
| ◆ | 思想を広めるために、ルールに抵触しない範囲でどういうアクションをとるべきか、考えて行動する。 | |
| ◆ | 思想をダイレクトに行動で表現できるよう、ルールをどう変えていくか、その方法と作戦をよく考える。 | |
| ◆ | 自分の考えとは違う行動を(やむをえず)しながら、もともとの考え・志・思想をどうやって失わずに保つか、その強い意志を持ち続ける。 |
などが一般的でしょう。普通の社会人はそう考えて行動しています。
さらに、思想の自由を守るためには、思想と行動の一致を「あえて」やめないといけない(やめた方がよい)場合があります。特定の思想を攻撃したい人がいたとします。近代国家では、思想を理由に人を攻撃できません。そこで攻撃者は必ず「外形として現れる行動のルール違反」を突いてきます。そのルール違反を罰することが目的ではなく、思想を攻撃したいために・・・・・・。これはいわゆる「別件逮捕」と似ています。有印私文書不実記載と聞くとどんな大変な罪かと思いますが、単に偽名で口座を作っただけだったりする。本当のヤマ(巨額脱税など)は別にあるのですね。
「日の丸は、軍国主義、皇国思想、国家主義の象徴である」と考えて(こう考えることは本人の自由です)公的セレモニーにおける不起立行動をとる人は、いかにも行動が稚拙だと感じられます。
「国旗への起立を特定の思想と結びつける」行動
「戦前に日本を戦争に誘導した人たち」と「不起立行動をする人たち」の間には、明確な共通点があります。
| 国旗に起立することが、特定の思想を受け入れることだと考えている |
という共通点です。
もちろん、特定の行動が特定の思想・信条・信教を受けいれる(受け入れている)ことの表明になることが、社会ではいっぱいあります。しかし近代国家において、1つの国が1つの国旗という状況下で、さらに多様な意見の表明をベースとする民主主義社会において、国旗に起立することを特定の思想と結びつけることはやってはならないし、それは排除すべき考えのはずです。
日の丸問題に即して言うと、日本人には少数派と多数派があって、次のような構図になっているのでしょう。
少数派は「国旗掲揚=国家主義想の表明」だと考える。これにはさらに2派あって
| ・ |
国家主義を広めたい人 | |
| ・ |
国家主義に反対したい人 |
の2つです。広めたい人は、日の丸への起立は国家への忠誠を誓うことだと考え、起立するかをどうかを忠誠の「踏絵」としたい。一方、不起立行動をとる人は、そのことで国家主義に反対を表明したいわけです。今、国家主義と書きましたが、これは軍国主義でも(極端には)皇国思想でもよいわけです。
一方、多数派は「国旗掲揚=特定思想とは無縁」と考えています。多数派の意見は以下のようなものでしょう。
| ◆ | 国旗への起立は式典、セレモニーの一部であって、形式的なものである。 | |
| ◆ | 国旗は日本という国の象徴である。それ以上のものではない。 | |
| ◆ | 日本人というアイデンティティで生きていく以上、国旗に起立するのは自然である |
などです。
外国国籍の人を含め、日本在住の人は国家を構成してその恩恵(安全、教育、人権、福祉など)を受けています。学校には外国国籍の生徒や在日の生徒もいるし、最近では外国人の(臨時)教員もいる。日の丸への起立が特定の思想(例:日本への忠誠)の表明だとすると、外国国籍の人たちは起立できなくなります。それでは現代国家は成り立ちません。多数派の考えが妥当です。
しかしこのような多数派に抵抗して、不起立行動をとる教員は「国旗に対して起立することを、特定の政治思想と結びつけよう」と躍起になっています。これは、現代国家における国旗のあるべき姿を逸脱させようとするものです。と同時に「国旗への起立=国家主義の表明」としたい人にとっては歓迎でしょう。「国旗に起立することは、特定の思想の表明である」というムードが生まれるし、不起立行動を糾弾することは、憲法論まで持ち出すことを含めて、いくらでもできるからです。
要するに「不起立行動をする人たち」は、「戦前に日本を戦争に誘導した人たち」が作り上げたパラダイムのもとに行動しています。主義・主張は全く正反対ですが、おなじレールの上での主義・主張であることは間違いないのです。
不起立行動は「やってはいけない教育」
教師が学校という場で不起立行動をとるということは、生徒に対して、暗黙に「思想・信条を、組織の指示系統やルールを度外視して、外部に行動として表してよい」という教育をしていることになります。これは生徒にとっては大きなマイナスでしょう。学校生活において生徒が「思想・信条をたてに組織のルールや指示系統を無視した行動をとる」としたら、学級や学校は崩壊します。
内心はどういう考えをもっていようとも、外部に現れる行動を社会が要請する一定のパターンに当てはめるのが、教育の中心課題のはずです。いやなこと、やりたくないこと、自分の考えと違うことでも、行動としてはやらないといけない。これは生徒たちが大人になって社会に出ていくまでに学ばないといけない重要なことです。
もちろん、社会が要請する一定のパターン通りに行動するだけで、そこに留まっていたのでは発展はありません。人それぞれがパターンにない独自性(個性)を発揮し、それが自分自身の利益になり、かつ社会にも貢献をするのが望ましいわけです。しかしそのベースとして必須なのは、社会が要請する一定の行動パターンを身につけていることなのですね。
社会が要請する一定のパターン通りに行動することがほとんど出来ないけれど、個人の才能や独自性が際だっていて、そのことで社会から評価される人がいます。芸術家や作家にそういう人がいますね。企業人にも、中にはいる。2011年に亡くなったスティーブ・ジョブズはそれに近いかもしれません。しかし、そのような人はごくごく稀なのです。こういう稀なケースは学校教育でどうするという範疇ではありません。
大多数の市民にとって、まず最低限「社会が要請する一定のパターン通りに行動できる」ことが、社会を構成していく上での必須事項です。その上に立って社会を変えていく(結果として、社会が個人に要請する事項を変える)ことが重要です。
教師としての責任
「かつて日の丸が象徴していた軍国主義、皇国思想、国家主義に反対したい。その復活を阻止したい」という考えをもった教師がいたとしましょう。思想・信条は個人の自由なので、そういう考えを持つことは別にかまわないわけです。
そうであれば、教師としては次のようなことを生徒に教えるべきで、それが教師という職業についた人の責任でしょう。
| ◆ | 日の丸は、江戸時代から使われはじめ、明治の初期に国旗相当として制定されたこと。実質的に国旗として使われてきたこと。 | |
| ◆ | 日の丸が、国民を戦争に駆り立てる道具のように扱われたことがあったこと。日の丸のもとに、多くの人々が命を落とした一時期があったこと。 | |
| ◆ | 日本人が再び「日の丸を汚す」ようなことがあってはならないこと。日の丸を「不戦の誓い」の旗とすべきであること。日の丸に対して起立するときには、そのことを考えて起立すべきであること。自分(教師)もそうすること。 | |
| ◆ | 国旗は国の象徴であり、それを特定の政治思想を喧伝する道具としてはならないこと。 |
などです。どうしても起立に抵抗がある人は、教師としての務めとして、教育の場である学校行事では起立し、私的に参加する場でのセレモニー(スポーツの国際大会など)では不起立行動をすべきです。教師という職業を選んだ以上、そのぐらいの覚悟で職(=生徒に教えること)をまっとうしてほしいものです。
No.32 - 芸能人格付けチェック [社会]
(前回から続く)
前回の No.31「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」では、赤ワイン → 特徴が際立った味 → 高級食材 → 芸能人格付けチェック
という連想で書いたのですが、今回はその「芸能人格付けチェック」というTV番組(テレビ朝日。現在は正月番組)そのものを考えてみたいと思います。
「芸能人格付けチェック」はどういう番組か
前回に書いた「隠岐牛とスーパーの牛肉」もそうなのですが、この番組を何回か見て思うのは、番組が表向きの装い(表層)と、隠された裏の意味(深層)を持っていることです。もちろん「芸能人の高級品判別能力をテストする番組」というのは全くのタテマエであって、出演者も司会者も視聴者も、そんな単純なことだとは思っていない。
出演者・司会者・視聴者の全員が思っている、この番組の「表層」は次のようなものです。
セレブな芸能人、つまり数々の高級品を知っているはずの芸能人が、当然分かってしかるべき高級品と普通品の区別がつかないことを暴露してしまい、それを見た視聴者が「なんだ、大したことがないね、あの芸能人は」と感じて、爽快感を得るバラエティ番組。 |
このような番組であるかのように装っている。その「装い」を確かなものにするための仕掛けが、番組ではいっぱい用意されています。もちろん中には、ことごとく正解を出すような「真の」セレブもいます。そういう人は惜しみなく賞賛される。しかしことごとく正解を出す芸能人が多数だと番組が成り立たなくなります。あくまで多数の人は数問のうちの2、3問はハズし、あるいは全部をハズし、そのハズレ具合を見て視聴者は楽しむ、という構造にこの番組はなっているのです。回答者の芸能人も、そういう番組であることを承知の上で、ある人は挑戦意欲に燃え、ある人はリベンジを誓って出演する。
しかしここまでは「表層」に過ぎないのです。この番組の「深層」は次のようなものだと思います。
番組の問題出題者は、人が高級品に対して暗黙に抱いている「思いこみ」「固定概念」「先入観」を最大限に利用して回答者を「引っかけ」、不正解へと誘導しようとする。少なくとも、AとBのどっちが正解か分からないように回答者を混乱させようとする。 |
このような「出題者」と「回答者」の攻めぎ合いがこの番組の深層だと思います。すべての問題がそうだとは言いませんが、私の見た限りではこの深層構造をもつ問題がいろいろありました。
多くの芸能人回答者は、この深層に気づいていないようです。表層だけに捕らわれ、自分なら高級品をすぐ判別できるはずだと思い込む。番組司会者も「こんな問題はすぐに分かって当然ですよね」「これが分からないようじゃ一流ではありませんよ」という態度で囃し立てる。そして回答者は深くは考えずに問題に臨み、直感だけで高級品を判別しようとする。回答者のこういう態度は、実は出題者の思うツボなのです。そして回答者は「意外にも」どちらが高級品か、すぐには分からないことに気づいて、内心愕然とする。
前回の No.31「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」 で書いた「100g 15,000円の隠岐牛」と「100g 1,000円のスーパーの牛肉」問題は、まさにこのような「深層構造」を持っています。そこにどういう「落とし穴」が仕組まれていたのかは、前回に書いた通りです。そして、この深層構造をもつ問題がいろいろありました。代表的な2つをあげてみたいと思います。
ヴァイオリンの名器
楽器の問題はいろいろあったと思いますが、次のような問題が典型的です。ほぼこの通りの問題があったと記憶していますが、ビデオ録画を持っているわけではないので詳細部分は違うかもしれません。しかし本質は変わらないと思うので書いてみます。
2つのヴァイオリンが演奏されます。つまり、
| ◆ |
ストラディヴァリウスと同時代にクレモナで作られたヴァイオリン名器、時価数億円
|
| ◆ | 現代の日本製の練習用ヴァイオリン、20万円 |
の2つです。どちらが名器でしょうか、というのが問題です。
これはかなり難しい問題だと思います。そんなの簡単だ、と思ったら、落とし穴にはまる。
この問題の「引っかけ」は、まず高級でないヴァイオリンを「日本製」「練習用」と紹介していることです。これと「クレモナの名器」が対比されて、なんとなく「一方のヴァイオリンの音が悪い」といった印象を与える。しかし事実は全く違います。
たとえば日本で最大のヴァイオリン製造会社は「鈴木バイオリン製造」で、数万円から150万円程度の楽器を製造しています。鈴木のバイオリンは100年以上の歴史をもち、中国でヴァイオリン製造が盛んになる前は世界市場でもトップのシェアでした。職人が個人技で作る「個人工房」のバイオリンはイタリアをはじめとするヨーロッパで盛んですが、大量生産するヴァイオリン(といっても熟練した職人さん達の、手仕事の分業ですが)では、日本の実力が相当のものなのです。「日本製」を否定的にとらえてはいけません。
さらに、わざわざ「練習用の」という言葉が付け加えられているのがあやしい。ヴァイオリンに「練習用」と「演奏会用」の区別があるわけではないのです。ヴァイオリンはヴァイオリンです。確かに、日本製の20万円のヴァイオリンをプロのヴァイオリニストやプロのオーケストラの団員は使わないし、音大の学生も使いません。一般の大学のオーケストラや市民オーケストラだって、コンサートマスターともなれば数百万円の楽器を持っている人はよくあるし、その団員だって日本製・20万円のヴァイオリンはあまりないでしょう。日本製の20万円のヴァイオリンは、実質的に「演奏会では使われない」というのは全くの事実です。
しかしその「演奏会には使わない」のがあたりまえの楽器を、わざわざ「練習用」と言って問題に出す。この意図は明白で「練習用」と断ることで「音がよくない」というイメージを回答者に与えることです。しかし実態は違うはずです。日本製の20万円のヴァイオリンは、上級のアマチュア・ヴァイオリニスト以上の人が弾けば、そんなに苦労なく、そこそこ美しく、そこそこ豊かで音量もある音が、いつでも出せると思います。それこそが「練習用」ヴァイオリンが果たすべき使命だからです。第1弦の高音が鳴らないとか、ハーモニクスが出ないとか、そんなことはないはずです。それでは練習にならない。
20万円という値段も微妙です。これが150万円となると「日本製でも良い音がするはず」という印象を回答者に持たれかねない。日本製の方の音が悪いという印象に誘導するためには、値段は安ければ安いほどよい。しかしさすがに5万円のヴァイオリンでは良い音はしないかもしれず、問題として元も子もなくなる(可能性がある)。20万円という値段のヴァイオリンは、そのぎりぎりの所を狙って出題されたのだと思います。テレビ朝日はかなり綿密に検討しているはずです。
一方、時価数億円の、300年前に作られたヴァイオリンの名器はどうでしょうか。こういった名器は「誰がどんな場所で弾いても」本来の音が出るのでしょうか。ヴァイオリニストの千住真理子さんは、ストラディヴァリウスについて次のように書いています。太字(下線)は原文にはありません。
|
TVスタジオでストラディヴァリウスを聞くとどういう音がするのか、大変に興味があります。さらにその次に続く文章です。
もう一つ特徴的なこととして、ストラディヴァリほどの名器は、ある程度長い年月をかけて弾き込まななければ音が出ない、という点がある。本当に、実際に「音が出ない」。 |
恐ろしいことが書いてありますね。ストラディヴァリウスを購入した人は、ニセモノをつかまされた、いまさら人には言えない、と「あきらめて」弾き続けることが肝要らしいのです。練習に練習を重ねないと、ストラディヴァリウス本来の素晴らしい音は出ないと千住さんは言っているのです。
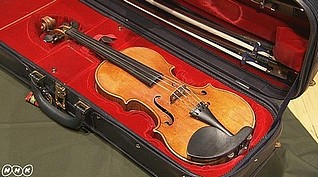
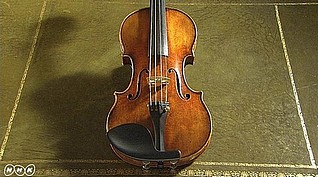
千住真理子さん所有のストラディヴァリウス「デュランティ」
NHK「美の壺」File 131 より [ site : NHK ]
NHK「美の壺」File 131 より [ site : NHK ]
ストラディヴァリウスほどではないにしろ、名器といわれるヴァイオリンはこういった傾向を持つようなのです。「芸能人格付けチェック」の問題のように、いくらプロといえども(たぶん)練習もあまりなしに300年前のイタリアの名器を弾いて、果たして本来の音が出せるのでしょうか。しかも、それ聞くのは演奏会場ではなくてTVスタジオなのです。そこをまず疑ってかからないといけない。パッと聴いたときに豊かで美しい音色と思えるのは「そば鳴り」がする「日本製・練習用・20万円」の方である可能性は十分にあると思うのです。
この問題を「フェアな問題」にするためには、たとえば千住真理子さんに依頼し、彼女の愛用のストラディヴァリウス「デュランティ」と日本製・20万円のヴァイオリンを、演奏会場で弾き比べてもらわないといけないわけです。しかしそんなことは番組ではしない。そんなことをすると、バラエティ番組ではなくなってしまうからです。
現代アートの大家の作品
絵画の鑑賞も「芸能人格付けチェック」の定番問題の一つです。典型的な問題は次のようなものです。2つの絵が出題されます。
| ◆ |
現代美術の巨匠が描いた抽象画。市場取引価格、数百万円。
|
| ◆ | 巨匠の作品に似せてテレビ朝日の大道具担当が描いた「作品」。市場価値ゼロ。 |
の2つです。さてどちらが巨匠の作品でしょう、というのが問題です。細部までこの通りの問題だったかどうかは記憶が鮮明ではありませんが、こういったタイプの問題が番組の一つの定番であることは確かでしょう。
これは非常に難しい問題だと思います。最低限、問題作成者がどういう罠を仕掛けているのか、想像を巡らしておく必要があります。でないと、落とし穴にはまる。
そもそも「テレビ朝日の大道具担当」とは、どういう経歴の人でしょうか。その人はひょっとしたら「美大のデザイン科を出て、高い競争率を勝ち抜いて、テレビ朝日ないしは関連の専門会社に就職した」ような人ではないでしょうか。だとするとその人は、小学校から高校まで「絵が好き、美術好き」で通っていたはずです。当然、美大の入試には絵を描いただろうし、デッサンもしたはずです。入試に備えて美大入試専門の学校にも通ったでしょう。入学してからも、デザイン科だとはいえ油絵も描いただろうし、何よりも数々の美術制作の現場を見てきたはずです。そうだとすると、その人は「美術の素養が完全にあるプロ」ということになるのです。ある絵に似せて絵を描くなんて「軽い」ことかもしれない。問題作成者は「大道具担当」という言葉を持ち出すことによって「美術に疎い」という印象を作り出そうとしています。だけど、事実は全くの逆かもしれないのです。「武蔵野美大を出たテレビ朝日のアートディレクター」とでも紹介すれば回答者が受ける印象は全く違うはずですが、そんな紹介は絶対にされない。
さらにもう一つの落とし穴は、巨匠が描いた「現代アートの抽象画」を、あまり見慣れない人がすんなりと受け入れられるかどうか、ということです。絵画に限りませんが「現代アート」の作品の中には「現代以前のアートの約束ごとや、決まり、方法論を否定したところに妙味がある」ものがあります。そして、そういう作品を鑑賞するには「現代以前のアートの歴史を知っていないと、おもしろさが全く分からない」ことがある。色の組み合わせが変だなと思っても、それはトラディショナルな配色の決まり事の逆をやっているわけであって、そこにこそ絵の妙味があったりする。良いか悪いかは別にして、鑑賞のための予備知識がいるアートや、素人が素直には楽しめないアートが存在するのです。
比喩的にいうと、漢字には楷書・行書・草書がありますが、草書体で書かれた書の美しさを味わいたいとき、楷書体・行書体を全く知らないで味わうことはできません。楷書の書き順や筆の運びを熟知した上で、それをどう行書で「崩すか」も知っていて、さらにそれ以上の「崩れ具合」を味わうのが草書の妙味です。あたりまえですが、元のものを知らないで、元のものを崩した妙味は分からないのです。このことは何も芸術としての書道に限りません。年配の、字が大変上手な方から手紙や葉書を受け取ったとき、よく「達筆すぎて読めない」なんて言いますよね。字がへただから読めないのではないのです。字がうますぎて読めないのです。
「芸能人格付けチェック」の現代アートの問題に戻ると、我々の思いこみを排除して冷静に考えると、テレビ局の大道具担当の人が現代アート風に描いた「作品」の方が、普通の人にはすんなりと受け入れられる可能性が強いわけです。出来るだけ多くの人に、直感的に受け入れられる・・・・・・。それこそが、テレビ局の人たちが日夜、必死に追及していることなのです。
すんなりと受け入れやすい方はあやしい・・・・・・。回答者はまずそう思って「身構えて」問題に臨まないと、全く逆の答えを出す可能性が強いと思います。
高い正解率を得るには
「芸能人格付けチェック」において、大変に正解率の高い人がいます。たとえばGACKTさんで、確か No.31 で書いた2010年の隠岐牛の問題も、彼は正解したと思います。2011年のこの番組は見なかったので最新状況は分かりませんが、確か彼は連続正解の記録を作ったことがあると記憶しています。
しかしちょっと考えてみると、いくらGACKTさんが「ホンモノが分かる、真のセレブ芸能人」であったとしても「この番組で出されるような高級品の全てを味わったり鑑賞した経験があって、かつその記憶が残っている」わけではないと思うのです。いくつかは初めての経験のはずです。たとえば高級牛肉はいろいろ食べたが、隠岐牛は初めて、というような・・・・・・。
おそらく彼はこの番組の「深層」を理解しているのだと思います。つまり番組の本質が「だまそうと思う出題者と、だまされまいとする回答者のバトル」だと分かっている。だから正解にたどり着きやすくなる。そういうことではないでしょうか。
その意味では、2010年の隠岐牛の問題(No.31参照)で、断定的に隠岐牛を否定して不正解になった回答者の方(仮にAさんとしておきます)は、味覚の鋭い人だと思います。だから2つの肉の違いが明確に分かった。一般の回答者は「どちらかと言えばB」とか「Bの方が・・・・・・の気がする」というように「迷いつつ回答する」のが普通です。はっきりと「Bです」という回答者も「心の中では迷ってるのが、ありありと分かる」ことが多い。しかしAさんは即座に断定しました。味が分かるのですね。しかし、残念ながらAさんはGACKTさんと違って、この番組の「深層」を理解していなかった。だから、味覚が鋭いにもかかわらず正反対の答えを出した。
GACKTさんのような人は少数です。普通の回答者は、Aさんも含めて表層だけでこの番組をとらえ、まんまとだまされて番組の「バラエティ化」に貢献しています。そして「だまされた」ことにさえ気づかず、自分の「高級品鑑賞力」が低いのだと思い込む。もちろんこの番組はバラエティ番組なので、そういう芸能人がいないと困るわけです。番組を成立させるためには、あなたは三流だと司会者が宣告できる芸能人が絶対に必要なのです。
ブルネッロと芸能人格付けチェック
前回の「ブルネッロ・ディ・モンタルチーノ」から「極端な味」へ、そして「高級品」から「芸能人格付けチェック」へと話が飛びましたが、これを「高級品」を中心にまとめると、以下のようになると思います。
| ◆ |
高級品の中には、特質を凝縮し、突出させ、際立たせたものがある。そういった高級品をストレートに味わうと(鑑賞すると)、それに慣れている人は別にして、一般には違和感を覚えることが多い。
|
| ◆ |
そのような高級品は、プロフェッショナルが行う「アレンジメント」のうまさによって違和感が解消され、本来の特質が誰にとっても心地よいものになる。それを行うのが一流の料理人であり、シェフであり、ソムリエであり、ブレンダーであり、一流のアーティストである。
|
| ◆ | 高級品を味わう(鑑賞する)には、味わう側にもバックグラウンドの知識や経験がそれなりに必要なケースがある。 |
さらに「芸能人格付けチェック」が示唆しているもう一つのことは、高級品と普及品(の上位クラス)の差は、それほど大きくはないということです。
前回書いたブルネッロ・ディ・モンタルチーノと赤ワインの話に戻ると、800円の赤ワインと5,000円の赤ワインを目隠しでテイスティングしてみて、どちらがどっちかを判別することは容易です。しかし5,000円と3万円の赤ワインでは普通の人には判別が難しいのではないか。少なくとも私には、全く自信がありません。5種類のブルネッロ・ディ・モンタルチーノのグラスがあり、その中の1つだけは3万円、あとは5,000円、テイスティングで分かりますか、と言われても、多分、分からない(ことが多い)と思います。訓練をうけた人やソムリエなら容易だろうけど・・・・・・。
| ◆ | 高級品と普及品(の上位クラス)の差は、意外にも少ない(ことがある)。特に値段の差ほどの差はない。 |
「芸能人格付けチェック」の最大の教訓はここです。高級品と普及品の判別を装っているこの番組は、実は高級品と普及品最上位クラス、ないしは超高級品と高級品の判別問題なのですね。その差はごく僅かです。だがら難しい。
| ◆ | 高級品を味わってみて(鑑賞してみて)素晴らしいと思うのは、それが高級品ということになっているから、つまり高級品だという情報がくっついているからである。 |
ということだと思うのです。高級品と普及品の上位クラスとの僅かな差を大きな差だと感じさせるのは、人間社会に蓄積されてきた文化なのですね。「僅かの差しかない」高級品の価値を否定しているのではありません。僅かの差を拡大させて感じさせる「文化」は大切なものだと思うのです。世の中にはピンからキリまで、いろんなバリエーションがある(と感じられる)からおもしろいのです。
No.30 - 富士山と世界遺産 [社会]
 No.18「ブルーの世界」で、プルシアン・ブルーを使った葛飾北斎の「富嶽三十六景」の中の「凱風快晴」をとりあげました。そこからの連想なのですが、画題としての富士山、富士山を愛する日本人の心、および富士山を世界遺産へ登録する運動について書いてみたいと思います。
No.18「ブルーの世界」で、プルシアン・ブルーを使った葛飾北斎の「富嶽三十六景」の中の「凱風快晴」をとりあげました。そこからの連想なのですが、画題としての富士山、富士山を愛する日本人の心、および富士山を世界遺産へ登録する運動について書いてみたいと思います。富士山と日本文化
富士山ほど絵画にしばしば取り上げられてきたテーマはないと思います。江戸時代における富士山の版画の連作は北斎だけではありません。安藤(歌川)広重も「富士三十六景」「不二三十六景」「富士見百図」などの連作を書いています。また明治以降も数々の日本画家、洋画家が富士山を描いてきました。
これらの中から一つだけ印象的な絵を日本画の中から取り上げると、2008年に東京国立博物館で「対決 - 巨匠たちの美術」という展覧会がありました。ここで並べて展示してあったのが富岡鉄斎と横山大観の作品です。富士山が芸術家に呼び起こすイメージの多様さに驚きます。
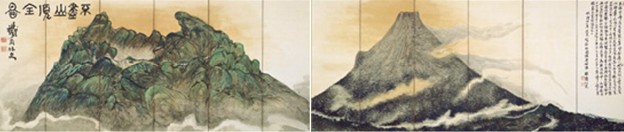
|
|
富岡鉄斎:富士山図屏風 [site : asahi.com] |

|
|
横山大観:雲中富士山図屏風 [site : asahi.com] |
代表作(の一つ)が富士山の絵である画家は多いし(大観、梅原龍三郎など)、ほとんど富士だけを一生描き続けた画家もいます。富士の絵だけの展覧会も開催されています。
絵画だけでなく、写真撮影のモチーフとして最も取り上げられるのも富士山ではないでしょうか。絵画と同じように、富士山だけを撮っている写真家もいます。また言うまでもなく、和歌・短歌・文学にも平安時代から数多く登場しています。
さらに大切なことですが、富士山は霊峰であり信仰の山です。山が信仰の対象になるのは日本ではあたりまえなのですが富士山もそうです。関東を中心にある1000社以上ある浅間神社は富士山を神格化した神をまつっています。その総本山は富士宮市の浅間神社で、ここの御神体は富士山そのものです。神社の奥宮は富士の頂上にあり、また8合目以上は今でもこの神社の境内のはずです。富士山に参拝する人も昔から多く、関東一円では江戸時代から「富士講」が盛んでした。現代でも白衣・金剛杖・鈴という姿の登拝者があとを絶ちません。
富士山はまた、切手や紙幣、硬貨にも使われています。つまり日本最高峰として国の象徴であり、日本を代表させる「アイコン」として使われているわけです。日の丸に代わる国旗のデザインをもし考えるとしたら、赤い丸の代わりに富士山をかたどったデザインを配置するのが適当と思えるほどです。
まとめると富士山は「信仰の対象」であり「芸術・文化との結びつき」が強く、さらに「国の象徴」にもなっているわけです。
信仰と文化:海外では・・・
海外で似たような存在はあるでしょうか。アジアに目を向けると、信仰の山・霊峰はたくさんあります。特に中国の道教の聖地である泰山や、チベット仏教とヒンズー教の聖地であるカイラス山(チベット高原)が有名です。

| |||
|
東山魁夷『黄山雨過』(1978) [site : 長野県信濃美術館] | |||
ヨーロッパの山岳地帯をもつ国、フランス、スイス、イタリア、オーストリア、ドイツ、スペインなどではどうでしょうか。これらの国では山を信仰するという文化的伝統はないようです。昔にあったとしてもキリスト教の影響ですたれてしまったはずです。山は登山やスキーの対象のようですが、その登山・スキーは近代以降に発達したものです
芸術、特に絵画ではどうか。ヨーロッパに有名な山はたくさんありますが、我々が知っているような著名画家の作品で特定の山を主題にした絵はあまり見た記憶がありません。マッターホルンやモンブランやモンテローザやヴェスビオ山の絵は、誰かが描いていたでしょうか。
さすがに山の「本場」のスイスでは、スイス人画家・ホドラーがユングフラウやアイガー、メンヒなどの山を主題とする絵を描いています。しかしスイスで活躍し「アルプスの画家」と言われたセガンティーニは、アルプス風景をいっぱい描いているわりには、山は背景として描かれるだけで、山を主題として描いたわけではない。山を主題にしたセガンティーニの絵はないはずです。ドイツのフリードリッヒも山岳風景をたくさん描いていますが、特定の山が主題の絵はごく少ないわけです。
フランスやイタリア、スペインは、歴史的にみてスイスやドイツ以上の絵画大国です。しかし山の景色を描いた絵はあるものの、特定の「山を主題にした絵」は少ないと思います。日本では富士山だけではなく、桜島、大山、浅間山、筑波山、磐梯山、八甲田山、出羽三山、羊蹄山などの特定の山が単独でよく画題になりますが、それと対照的な感じです。

|
| セザンヌ:大きな松の木がある サント・ヴィクトワール山 (ロンドン:コートールド美術館) |
ヨーロッパでは山に対する信仰がなく、かつ「山を愛でる」という行為も文化としてなかった感じです。セザンヌのように「故郷や郷土の風景や風土を愛する」というのは当然あるでしょうが・・・・・・。このことを端的に語っている記述があります。
山の名前は?
No.29「レッチェンタールの謝肉祭」でとりあげた、スイス政府外務省がスイスを対外的に紹介しているホームページがあります(http://www.swissworld.org/jp/)。ここに「ハイジ」の一節が紹介してありました。
「ねえ、見て!見て!」ハイジは興奮して叫んだ。「真っ赤に染まったわ!あの雪を見て!すごく高くて、とんがった岩!ペーター、あれは何て言う名前?」「山に名前なんてないよ」とペーターは答えた。 |
「ハイジ」は19世紀後半、1880年頃の小説です。その時点でさえ「山に名前なんてない」のです。人間社会において、モノは名前を付けられることによって初めて認識されます。名前がないということは、物理的に存在するものの、人間文化の観点からは存在しないわけです。「山の本場」のスイスでさえそうだったようです。
日本人の深層心理
以上をまとめると「信仰の対象」「芸術・文化との結びつき」「国の象徴」の3点が成立していることにおいて、富士山は世界でも特徴的だと言えると思います。似た存在としては、山水画のルーツとも言える中国の黄山ぐらいでしょうか。
そこまで日本人は富士山を「愛でる」のか。その背後にある日本人の富士山に対する心理を推測してみたいと思います。日本最高峰という以上に、普通の日本人が暗黙に抱いている「思い」は、
| 富士山は非常に美しく、それは日本の誇りである。さらにその美しさは世界でみても飛び抜けた美しさである。 |
というものではないでしょうか。そういう深層心理があるように思います。「自然の山」として、遠方からの「眺望」「景観」の美しさに対する「誇り」が無意識下にある。
しかしある外国人の弁なのですが「確かに富士山は美しいが、大騒ぎすることのほどでもない」という意見を読んだことがあります。新幹線に日本人と一緒に乗ったとき、車窓から見える富士山の美しさを日本人から長々と説明されて閉口したという話でした。果たして富士山は、世界の観点からみてどの程度「美しい」のでしょうか。
成層火山
富士山は成層火山(海抜3776メートル)です。つまり火口から火山灰が長年に渡って噴出され、次第に火口の周りに積もって高くなって出来た山です。従って火山地帯であれば成層火山はそんなに珍しいものではない。世界における標高6000メートル級の代表的な成層火山を3つあげます。
◆コトパクシ(エクアドル。5897m)
◆キリマンジャロ(タンザニア。5895m)
◆ミスティ(ペルー。5822m)
コトパクシはエクアドルの中央部にあり、今でも噴煙をあげている活火山です。キリマンジャロは、この3つの山では一番知られているアフリカの山ですね。タンザニアの北部、ケニアとの国境付近にあります。ミスティはペルー南部にあるペルー第2の都市、アレキパの郊外にある山です。以下に掲げる写真のように、コトパクシとミスティは富士山と同じ「独立峰」で、かつ「円錐形」をしています。キリマンジャロが円錐形でないのは火口が3つあるからです。いずれも海抜6000メートルに近い高山ですが、こういった山の「威容」は海抜よりも麓から頂上までの「比高」で決まります。たとえばミスティ山のあるアレキパの街は海抜2300メートルを越えています。ミスティ山の比高は3500メートル程度でしょう。その意味では富士山と「いい勝負」です。

|
| コトパクシ山(5897m) [site : エクアドル観光省] |
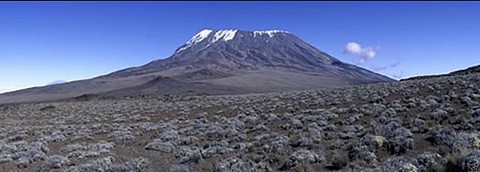
|
| キリマンジャロ山(5895m) [site : 駐日タンザニア大使館] |

|
| ミスティ山(5822m) [site : ペルー政府観光局] |
このほかの海抜5000メートル級の山、4000, 3000メートル級の山を含めると、成層火山は世界の火山地帯にいっぱいあります。そのすべてを知っているわけはもちろんないのですが、形の美しさを問題にするなら、コトパクシやミスティーがそうであるように「富士山なみ」の山、つまり「成層火山」で「独立峰」で「円錐形・円錐台形」の山は他にもあるはずです。たとえば南アメリカのパタゴニア地方、アルゼンチンとチリの国境にあるラニン山は「成層火山」「独立峰」「円錐形」で、しかも全くの偶然ですが、標高が富士山と同じ(3776m)です。

|
| ラニン山(3776m) [site : パタゴニア情報サイト www.patagonia.com.ar] |
そもそも世界の成層火山をうんぬんする前に、日本においても成層火山は数々あり、羊蹄山(蝦夷富士)、岩木山(津軽富士)をはじめ「何々富士」が日本中にあるくらいだから、富士山のような山が世界中にあっても何らおかしくありません。標高が同じ山があってもおかしくない。それは確率の問題です。

羊蹄山(1898m)
富士山を愛する心
以上からうかがえるのは、富士山が美しい山だというのは全くその通りですが、その美しさが世界的にみて「飛び抜けていて」「ダントツ」であり「他の山を圧倒的に凌駕する美しさ」とは言えないようです。「世界に冠たる山」だという無意識下の思いには根拠がないのです。
しかし多くの日本人はコトパクシやミスティを知らないし、知らないで富士山が「世界に冠たる山だ」と深層心理で思っている。それは主観的にそうだということです。それはそれでよいと思います。富士山を「美しい」と思い「誇り」に思い「愛する」。日本の象徴であり、大切に守るべき自然である・・・・・・。新幹線で外国人に富士山の美しさを長々と説明した人の行為は、自国の誇りを対外的に説明しようとする「シンプルな愛国心」の発露だと思います。
「愛国心」というとちょっと大げさなようですが、国を構成する重要な側面は「自然」です。そして日本の場合、富士山を含む「山」は自然の極めて重要なファクターです。従って「日本を愛する」ことの一部として「富士山を愛する」ことがあって当然だと思います。
富士山と世界自然遺産
以上の考察をもとに、富士山と世界遺産の関係を考えてみたいと思います。以前に「富士山を世界自然遺産に」という動きがありましたが、最終的に日本政府はユネスコへの登録申請はを見送りました。
もちろん「形の美しい成層火山」というだけでは世界自然遺産になりません。「形の美しい成層火山」ということだけで登録ができるなら、ほかにも登録すべき山がたくさん出てくる。富士山が世界自然遺産なのに、6000メートル級のコトパクシやミスティが世界自然遺産でないのは説明がつかないわけです。
ではなぜ富士山は世界自然遺産に申請されなかったのでしょうか。その理由を探るために、登録済の日本の世界自然遺産をみてみたいと思います。日本の世界自然遺産は、
◆屋久島
◆知床
◆白神山地
◆小笠原諸島(2011年6月24日 登録)
の4つです。これらがなぜ世界自然遺産なのか。

|
|
|

|
|
|

|
|
|
知床は、知床半島とその沿岸海域が世界遺産です。この海域は世界的にみても流氷が到達する南限です。流氷のもたらすプランクトンと魚類、知床半島を遡上する鮭、半島の豊富な植物と熊や鷲などの動物や鳥類、半島から海に注ぐ川がもたらす栄養分。これらが有機的に結びつけられた循環生態系を構成しています。
白神山地(秋田・青森)の世界遺産の理由は、言わずと知れたブナの原生林です。面積は世界でも最大級といわれています。
この3つの自然遺産に共通するのは、日本人として客観的に見ても世界遺産として保護する価値がある自然が残っていることです。もうひとつの共通点は、自然を保護するための厳しい規制があることです。屋久島、知床半島(遠音別岳)、白神山地は自然環境保全地域であり、法律によって開発の規制がされています。知床半島北部の観光は、船から眺めることしかできません。貴重な自然遺産として後世に残すのならこの程度の規制は当然です。
なお、4番目の自然遺産に登録された小笠原諸島ですが、ここは「東洋のガラパゴス」と言われる、生物の固有種の宝庫です。一つの例ですが、何とカタツムリの9割は固有種だと言いますね。小笠原では外来生物から固有種を守るための島民の方々の努力が続けられています。それは無人島に入るときには靴の裏の泥・土を水で洗う(外来種の種子などを持ち込まないため。観光客も)といった地道な努力の積み重ねです。また、飼い猫の飼育に数々の規制を設ける「飼いネコ適正飼養条例」もありますね。猫が希少動物を襲うことを避けるためです。
富士山とその周辺地域には、以上の4つに比べて自然遺産としての価値が弱く、かつ強力な自然保護活動もなかった、ということではないかと思います。樹海や各種の洞穴などの自然が残っていますが、5合目まで自動車道が通り、排気ガスがタレ流されています。また5合目以下はリゾート開発が進んでいます。登山道周辺や樹海がゴミだらけであり、これでは自然遺産にはならないと問題になりました。しかしゴミ問題以前に、富士山とその周辺地域の自然を保護するという強い流れになっていない。国の自然環境保全地域にも指定されていないのです。
そもそも富士山を「自然遺産」に登録しようとした意図は何でしょうか。富士山周辺の自然環境が破壊されていく現状を憂い、自然遺産に登録することによって、それを契機に屋久島・知床・白神山地なみの保護や規制を行うのが目的だとすると、それはそれで理解できます。たとえば世界遺産を契機に、
| ◆ |
5合目より下に厳しい開発規制を敷く |
| ◆ |
5合目まで通じているスバルライン、スカイラインの一般のクルマの通行は禁止する。公共交通(たとえば電気バス)のみ通行可にする。 |
| ◆ | ガイドなしでは入山できないようにする(登山道のゴミは皆無になるはず) |
などです。「遺産」は「次世代に引き継ぐ」ものです。引き継ぐために保護するのは当然です。しかし、どうもそういう目的でもなかったようです。
2009年6月、ユネスコは「ドレスデン・エルベ渓谷」の世界文化遺産登録を抹消しました。周辺の渋滞解消のため4車線の橋の建設が始まり、景観を損なうと判断されたためです。小笠原諸島の人たちは、自然保護のために数々の努力をしていますが、その中には住民生活に不便を強いるものもあるわけですね。世界遺産を守るということは、それによって「利便性」や、一般の国民が享受している「豊かさ」が一定程度失われることを意味します。その覚悟をするかどうかが、登録への出発点だと思います。
富士山と世界文化遺産
現在は富士山を「文化遺産」ないしは、文化と自然の融合体である「複合遺産」に登録しようとする運動がされています。そのポイントは、登録を推進する団体のアナウンスによると「芸術と文化の山」だとのことです。つまり初めに書いたように、日本でにおいて富士山は、絵画、短歌、文学、工芸などの主題として深く関わってきていて、かつ信仰の山だという点です。これは確かにその通りです。
その動きに反対するわけではありませんが、ちょっと危惧するのは「富士山が世界文化遺産として適当だ」という客観的判断から運動がされているのだろうか、という点です。
「富士山を世界文化遺産に」という今の運動の多くの部分は、実は「シンプルな愛国心」から来ているのではないのでしょうか。まず「富士山を世界遺産にするのだ」という「愛国心」ないしは山梨・静岡を中心とする「愛郷心」に裏打ちされた「目標」が先にあって、「世界遺産として適切な理由」が後から付け加えられているような気がする。その証拠に「自然遺産」への登録を見送ったら、手の掌を返すように「文化遺産」が持ち出されている。
「国の誇り」や「愛国心」から世界各国の人が世界遺産登録を言い出したらきりがないし、遺産としての「質」が保てません。富士山が「世界遺産」として適切と考えられるのはなぜなのか、何がユネスコに(世界に)対する訴求点なのか、遺産として何をどのような手段で次世代に伝えるべきなのか、登録を実現するためにもよく考えてみるべきだと思います。
日本の世界文化遺産
ここで自然遺産と同じように、日本の代表的な世界文化遺産をみてみたいと思います。日本の世界文化遺産は11あります。その中の代表的な以下の遺産を考えてみます。
◆京都の文化財
◆奈良の文化財
◆法隆寺地域の仏教建築
◆姫路城
◆紀伊山地の霊場と参詣道
◆原爆ドーム
◆石見銀山
これらの文化遺産を眺めてみると、自然遺産と同じように「世界というレベルで考えて、次世代に引き継ぐべき客観的な価値」が十分あると思えます。それはユネスコの世界遺産登録基準を知らなくても分かる。
京都や奈良の文化財は言うまでもないでしょう。世界的にみて京都・奈良ほど、宗教建築物、歴史的芸術(絵画・彫刻)、庭園、伝統文化の集積地域はあまりないと思います。これほどの密集地域はローマぐらいでしょうか。そのローマは、もちろん世界遺産です。
法隆寺は誰もが知っている「世界最古の木造建築」で、世界的にも有名です。法隆寺にいっぱいある国宝の仏像群を持ち出すまでもなく、この事実だけで世界文化遺産の資格はあると言えるでしょう。
姫路城は400年前に建てられてそのまま残っている木造の城郭です。これは世界的にみてもめずらしい。また白鷺城といわれる白漆喰の美しい姿は、美術品と考えても一級です。
紀伊山地の霊場と参詣道ですが、20近くのの寺院・神社と、熊野・大峰・高野山の参詣道のネットワークと、山と原生林と滝(那智)が一体となった「地域信仰複合体」です。これは千年を超える人間の活動によってできあがってきたものです。
広島の原爆ドームが世界文化遺産として適切なことは論をまたないでしょう。アメリカは反対したようですが、日本は何もアメリカへの非難や「あてつけ」のために世界遺産に登録申請したのではありません。核兵器がない世界を願ってのことです。これはプラハ演説に触発されて「オバマ大統領を広島に招こう」という運動をするのと同じ動機です。
石見銀山は、16世紀から17世紀にかけて、西のポトシ(ペルー)、東のイワミと言われたほど、銀鉱山として世界的に有名でした。No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で書いたように、銀は通貨や決済手段としては大変重要なもので、銀本位制をとっていた国も歴史上多々あります。ヨーロッパ製の地図で日本を単体で描いた最初の地図(ティセラの日本図)には、すでに石見の地名と銀鉱山の記述があります。当時のヨーロッパの「関心」が何にあったのかがうかがえます。また石見銀山では、まわりの自然環境を破壊することなく銀の採掘・精錬が行われたことも、次世代に残す遺産として重要です。歴上有名なスペインのビルバオ銀山やペルーのポトシ銀山の周辺が荒野になってしまったのとは大きな違いでしょう。
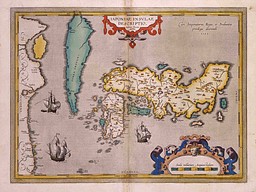
|

|
ティセラ「日本図」
ポルトガルの宣教師、ルイス・ティセラ作成の日本図(1595年頃)。ヨーロッパ製の地図で、日本を単体で描いた最初の地図。[site : 九州国立博物館] |
山陰部分の拡大図
ティセラ「日本図」の山陰地方を拡大したもの。石見の位置に「Hivami」(石見)と、ラテン語で「Argenti fodinae」(銀鉱山)と書かれている。[site : 山陰中央新報] |
文化遺産の「客観性」
以上を考えると、日本の世界文化遺産は、世界に残すべき遺産としての客観的な価値が、日本人から見てもあるようです。決して日本の「ひとりよがり」ではない。また日本人として「誇りに思う」とか「日本人の愛国心」から出たものでもない。確かに、京都、奈良、法隆寺などは「日本の誇り」であり、かつ「世界文化遺産」でしょうが、それは「たまたま」と考えた方がよく、そうでないものもある。
たとえば石見銀山を「日本の誇り」だと思っていた日本人は、歴史学者や地元の人を除いて、どれだけいたのでしょうか。むしろ世界文化遺産に登録されるまで石見銀山の存在さえ知らなかった日本人が多いはずです。さらに原爆ドームのような「誇り」とは無関係な「負の遺産」として残すべきものもある。あくまで次世代に残すべき遺産としての価値の問題なのです。
そこで富士山です。富士山は「世界文化遺産」として価値がどの程度なのか、世界にどう説明できるかです。ユネスコにどのようにロジカルに説明するかです。富士山は信仰の山であり、それが文化遺産に推薦する1つのポイントになっています。確かにそうなのですが、ひとつ気になるのは「紀伊山地の霊場と参詣道」が「信仰のジャンル」で既に世界遺産になっていることです。これに比べて富士山はやや「小ぶり」な感じがする。
やはり富士山の特徴は日本人の芸術・文化活動との結びつきの強さでしょう。しかしこの点をどう対外的に説明するのか。歌舞伎や能などの伝統芸能なら無形文化財として残すことができるし、演じることができるし、見学もできます。しかし富士山に関係した歴史的文化活動の「成果」は日本中に散らばっています。どこか一カ所で「見学」することはできない。どうやって、遺産として可視化して次世代に残すのか。その工夫は我々日本人自身にとっても重要な課題だと思います。
そして思うのですが、富士山を「芸術と文化の山」として世界文化遺産に登録する際の一番の障害となるものは、皮肉なことに「世界文化遺産に登録するという活動の動機」そのものではないでしょうか。「富士山を世界遺産にする国民会議」という組織があります。そのホームページには次のように書いてありました(2011.6.24 現在)。
日本一。とえいば、富士山。 |
| 補記1「世界に54の〇〇富士」 |
2012年6月30日の朝日新聞(夕刊)に「世界に54の〇〇富士」という記事が掲載されました。移民や旧日本兵が命名し、今でも現地の日系人の間で山の呼称として使われている「〇〇富士」が54あるとのことです。これは筑波大付属高校の田代教諭が調査し「世界の『富士山』」(新日本出版社)という本にまとめました。記事に名前が掲載されていた世界の「富士」と、その一つ「ニュージーランド富士」の写真をここに掲げておきます。
| ニュージーランド富士 | ナウルホエ山 | 2291m | ニュージーランド・北島・トンガリロ国立公園 |
| タコマ富士 | レーニア山 | 4392m | アメリカ・ワシントン州 |
| リベイラ富士 | ボツポカ山 | 416m | ブラジル・サンパウロ州 |
| ルソン富士 | マヨン山 | 2463m | フィリピン・ルソン島 |
| マナド富士 | クラバット山 | 2022m | インドネシア・スラウェシ島 |
| ラバウル富士 | コンビウ山 | 688m | パプアニューギニア・ニューブリテン島 |
| エルサルバドル富士 | イサルコ山 | 1910m | エルサルバドル |
| ジャワ富士 | メラピ山 | 2923m | インドネシア・ジャワ島 |

|
| ナウルホエ山(ニュージーランド富士) [site : ニュージーランド観光局] |
(2012.7.7)
| 補記2 - 標高6000m級の成層火山 |
南米にはエクアドルのコトパクシ山よりも標高の高い、6000mを越える成層火山があるようです。コトパクシのあるエクアドルの最高峰のチンボラソ山(6310m)も成層火山です(噴煙は出していない)。またチリとボリビアの国境にはパリナコータ山(6348m)やリカンカブール山(5916m)があります。さらにボリビアの最高峰であるサマハ山(6542m)も、活動した記録はないのですが、火山のようです。
下の写真はチリ・ボリビア国境のアタカマ高地にあるリカンカブール山で、標高は 5916m です。麓の標高は 4300m ぐらいなので、比高は1600m 程度でしょう。アタカマ富士と呼ばれているようです。

|
| リカンカブール山(アタカマ富士) [site : Smithsonian Institution, Global Volcano Program] |
(2012.7.8 / 2013.1.8)
| 補記3 - ALMA |
補記2の余談です。写真を掲載したリカンカブール山があるチリのアタカマ高地には、日米欧の共同プロジェクトである電波望遠鏡施設が建設されています。ALMA(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計 - Atacama Large Millimeter / submillimeter Array)と呼ばれるこの施設は、アタカマ高地の直径約18.5キロのスペース(山手線の内側と同程度の規模!)に電波望遠鏡・66基を設置し、それらを一体運用することで直径18.5キロメートルの巨大な電波望遠鏡として機能させ、宇宙観測を行うものです。ALMAの公式サイトからその写真を転載しておきます。

| ||
| 標高5000メートルの高地にある電波望遠鏡施設(AOS - Array Operation Site)。 | ||
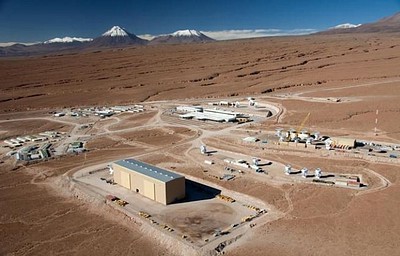
| ||
| 標高2900メートルの地点には、望遠鏡の遠隔制御やメンテナンスのためのサポート施設・OSF(Operations Support Facility)が設けられている。遠くに見える円錐状の山がリカンカブール。 | ||
(2013.3.16)
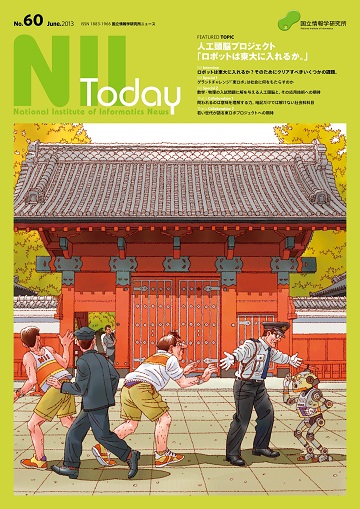
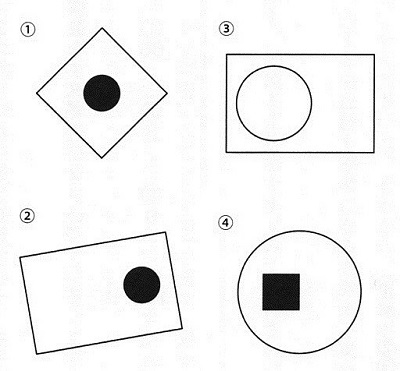
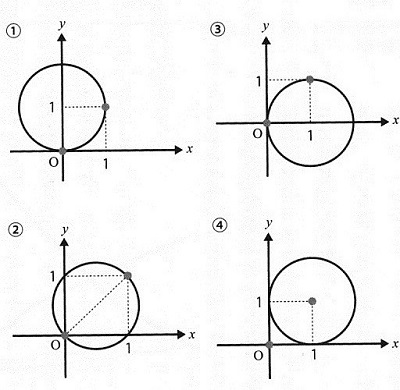

 もちろん見た目も美しいが、なんといっても魅惑的なのは音色だ。300年前には考えられなかったはずの現代の2000人の大コンサートホールに持って出て、きわめて小さな音を出しても客席の一番後ろまでピーンと美しく聞こえる、という現象には驚かされる。ほかの楽器は「そば鳴り」といって、近くでは大きくきれいな音が聞こえるが、大ホールに持って出るととたんに音が貧弱に鳴り、後ろの席まで音が通らない。ストラディヴァリは大ホールに持って出て、初めてその実力が確かめられると言える。両者の違いに大いに気づくことになるのだ。
もちろん見た目も美しいが、なんといっても魅惑的なのは音色だ。300年前には考えられなかったはずの現代の2000人の大コンサートホールに持って出て、きわめて小さな音を出しても客席の一番後ろまでピーンと美しく聞こえる、という現象には驚かされる。ほかの楽器は「そば鳴り」といって、近くでは大きくきれいな音が聞こえるが、大ホールに持って出るととたんに音が貧弱に鳴り、後ろの席まで音が通らない。ストラディヴァリは大ホールに持って出て、初めてその実力が確かめられると言える。両者の違いに大いに気づくことになるのだ。


