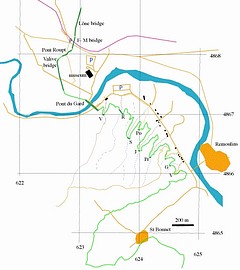No.368 - 命のビザが欲しかった理由 [歴史]
No.201「ヴァイオリン弾きとポグロム」に関連する話です。No.201 の記事は、シャガール(1887-1985)の絵画『ヴァイオリン弾き』(1912)を、中野京子さんの解説で紹介したものでした。有名なミュージカルの発想のもとになったこの絵画には、ユダヤ人迫害の記憶が刻み込まれています。シャガールは帝政ロシアのユダヤ人強制居住地区(現、ベラルーシ)に生まれた人です。
絵のキーワードは "ポグロム" でした。ポグロムとは何か。No.201 で書いたことを要約すると次のようになるでしょう。
その、ナチスによるホロコーストに関係した有名な話があります。当時のリトアニアの日本領事代理だった杉原千畝が、ユダヤ人に日本通過ビザ(いわゆる "命のビザ")を発行し、ドイツによるホロコーストから救ったという件です。
この "命のビザ" について、先日の朝日新聞に大変興味深い記事が掲載されました。「ユダヤ難民は誰から逃れたかったのか」を追求した、東京理科大学の菅野教授の研究です。それを以下に紹介します。記事の見出しは、
杉原千畝「命のビザ」で異説
ユダヤ人が逃れたかったのはソ連?
(朝日新聞 2023年11月20日 夕刊)
です。朝日新聞編集委員・永井靖二氏の署名入り記事です。
難民は何から逃れたかったのか
まず記事の出だしでは、当時の状況と命のビザの経緯が簡潔に書かれています。
東京理科大学の菅野教授は、当時の1次資料のみを読み解き、ユダヤ難民が何から逃れたかったのかを突き止めました。
あらためて歴史的経緯を時系列にまとめると、次のようになります。
この経緯のポイントは次の3つでしょう。
ユダヤ難民がなぜ命のビザを欲しがったのか。それは記事にあるように「ソ連から逃れるため」というのが正解でしょう。もちろん、ドイツの "ユダヤ人狩り" は難民も知っていたはずです。しかし、当時は独ソ不可侵条約が結ばれていて、その一方の当事者であるソ連にリトアニアは占領されていました。当時、ドイツの脅威が直接的にリトアニアに及んだわけではありません。シンプルに考えても、リトアニアのユダヤ難民が恐れたのはドイツではなくソ連だった。
加えてロシア・ソ連では、シャガールの絵に象徴されるように、19世紀以来、ポグロムの嵐が吹き荒れていました。ユダヤ人がリトアニアを占領したソ連から逃れたかったのは当然でしょう。
通説の経緯
しかし日本では「ナチスの迫害から逃れるため」というのが通説になっています。この通説ができた経緯が記事に紹介されています。
記事にある杉原氏の覚え書きによると、ビザを発給したのはポーランド難民で、その一部がユダヤ人ということになります。では「ユダヤ人でないポーランド難民」は何から逃れたかったのかというと、それはソ連からということになります。
しかし日本では当初から、ユダヤ難民は「ナチス・ドイツに追われ」たことになっていました。記事にも、
とあります。杉原氏自身でさえ、ユダヤ人難民は「ナチスに捕まってガスの部屋へ放り込まれる」からビザを欲したのだと、1988年に語っているわけです。「ナチスの迫害から逃れるため」という通説ができるのは当然です。もちろん、時間がたつと記憶が曖昧になるのは誰しもあるわけです。
これは、1960年の新聞報道を含め、ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストが、如何に世界の人々にショックと強烈な印象を与えたかという証だと思います。そして重要な点は、ユダヤ人難民がソ連から逃れたかったにしろ、杉原氏の行為に対する評価は変わらないということです。
複合的な視点で見る必要性
ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストという惨劇を知ってしまうと、それに強く影響された視点でものごとを考えがちです。しかし、複合的な視点はどのようなことでも重要です。記事の中で内田樹氏が発言していました。
この内田氏の指摘は鋭いと思います。
杉原氏は外交官であり、日本の国益のために働くのが使命です。明治以降の日本政府がユダヤ人に融和的だっというのは、数々の証拠があります。外交官である杉原氏はそれを知っていたのでしょう。その "融和的" な姿勢の発端は、日露戦争におけるユダヤ人資本家からの戦費調達であり、その背景にはロシアにおけるポグロムがある。ユダヤ人資本家は、ロシアと戦おうとする日本を応援したわけです。
という「複合的な視点」が重要でしょう。一面的に歴史をみることはまずいし、「歴史から学ぶ」ことにもならないのです。
絵のキーワードは "ポグロム" でした。ポグロムとは何か。No.201 で書いたことを要約すると次のようになるでしょう。
| ポグロムはロシア語で、もともと「破壊」の意味だが、歴史用語としてはユダヤ人に対する集団的略奪・虐殺を指す。単なるユダヤ人差別ではない。 | |
| ポグロムに加わったのは都市下層民や貧農などの経済的弱者で、シナゴーグ(ユダヤ教の礼拝・集会堂)への放火や、店を襲っての金品強奪、暴行、レイプ、果ては惨殺に及んだ。 | |
| ポグロムはロシアだけの現象ではない。現代の国名で言うと、ドイツ、ポーランド、バルト3国、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなどで、12世紀ごろから始まった。特に19世紀末からは各地でポグロムの嵐が吹き荒れた。 | |
| 嵐が吹き荒れるにつれ、ポグロムに警官や軍人も加わるようになり、政治性を帯びて組織化した。この頂点が、第2次世界大戦中のナチス・ドイツによるユダヤ人のホロコーストである。 |
|
この "命のビザ" について、先日の朝日新聞に大変興味深い記事が掲載されました。「ユダヤ難民は誰から逃れたかったのか」を追求した、東京理科大学の菅野教授の研究です。それを以下に紹介します。記事の見出しは、
杉原千畝「命のビザ」で異説
ユダヤ人が逃れたかったのはソ連?
(朝日新聞 2023年11月20日 夕刊)
です。朝日新聞編集委員・永井靖二氏の署名入り記事です。
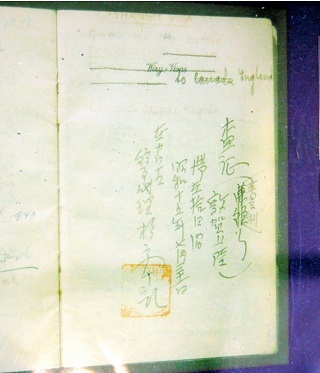
|
杉原氏が発給した手書きのビザ。"敦賀上陸" とある。 |
(朝日新聞より) |
難民は何から逃れたかったのか
まず記事の出だしでは、当時の状況と命のビザの経緯が簡潔に書かれています。
|
東京理科大学の菅野教授は、当時の1次資料のみを読み解き、ユダヤ難民が何から逃れたかったのかを突き止めました。
|
あらためて歴史的経緯を時系列にまとめると、次のようになります。
| 独ソ不可侵条約が締結 | |
| ドイツがポーランドに侵攻(=第2次世界大戦が勃発)。ソ連も侵攻し、10月、ポーランドは独ソ両国によって分割された。 | |
| ソ連がリトアニアに進駐 | |
| 杉原がリトアニアでユダヤ人に計2140件のビザを発給 | |
| ソ連がリトアニアを併合 | |
| 独ソ戦開戦 | |
| アウシュビッツ収容所で毒ガスが初めて使われた |
この経緯のポイントは次の3つでしょう。
| 杉原氏が命のビザを発給したのは、ソ連がリトアニアに進駐して併合する、まさにその時期にあたる。 | |
| 独ソ戦が始まったのは、命のビザより10ヶ月あとである(もちろん独ソ戦が始まった以上、リトアニアにドイツ軍が押し寄せてくることは想定できる)。 | |
| アウシュビッツ(ポーランド)で毒ガスによるホロコーストが始まったのは、命のビザより1年後である。 |
ユダヤ難民がなぜ命のビザを欲しがったのか。それは記事にあるように「ソ連から逃れるため」というのが正解でしょう。もちろん、ドイツの "ユダヤ人狩り" は難民も知っていたはずです。しかし、当時は独ソ不可侵条約が結ばれていて、その一方の当事者であるソ連にリトアニアは占領されていました。当時、ドイツの脅威が直接的にリトアニアに及んだわけではありません。シンプルに考えても、リトアニアのユダヤ難民が恐れたのはドイツではなくソ連だった。
加えてロシア・ソ連では、シャガールの絵に象徴されるように、19世紀以来、ポグロムの嵐が吹き荒れていました。ユダヤ人がリトアニアを占領したソ連から逃れたかったのは当然でしょう。
通説の経緯
しかし日本では「ナチスの迫害から逃れるため」というのが通説になっています。この通説ができた経緯が記事に紹介されています。
|
記事にある杉原氏の覚え書きによると、ビザを発給したのはポーランド難民で、その一部がユダヤ人ということになります。では「ユダヤ人でないポーランド難民」は何から逃れたかったのかというと、それはソ連からということになります。
しかし日本では当初から、ユダヤ難民は「ナチス・ドイツに追われ」たことになっていました。記事にも、
| 日本を通過したユダヤ人難民について、1960年7月1日付の朝日新聞朝刊は「ドイツを追われ日本に来た」としていた。8月7日発行の週刊読売も「ナチスに追われ」たと書いていた。 | |
| 1988年9月、杉原氏はフジテレビのドキュメンタリーで、難民にビザを発給したのは「ナチスにひっ捕まって」「ガスの部屋へ放り込まれる」からだったと語った。 |
とあります。杉原氏自身でさえ、ユダヤ人難民は「ナチスに捕まってガスの部屋へ放り込まれる」からビザを欲したのだと、1988年に語っているわけです。「ナチスの迫害から逃れるため」という通説ができるのは当然です。もちろん、時間がたつと記憶が曖昧になるのは誰しもあるわけです。
これは、1960年の新聞報道を含め、ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストが、如何に世界の人々にショックと強烈な印象を与えたかという証だと思います。そして重要な点は、ユダヤ人難民がソ連から逃れたかったにしろ、杉原氏の行為に対する評価は変わらないということです。
複合的な視点で見る必要性
ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストという惨劇を知ってしまうと、それに強く影響された視点でものごとを考えがちです。しかし、複合的な視点はどのようなことでも重要です。記事の中で内田樹氏が発言していました。
|
この内田氏の指摘は鋭いと思います。
| 日本政府はユダヤ人に融和的な姿勢を保っていたから、杉原氏には道義心に加えて、国益への配慮もあったはずだ。 | |
| リトアニアではソ連への恐怖の方がナチスよりも強かったし、難民らには局面ごとに多様な外力が働いていた。 |
杉原氏は外交官であり、日本の国益のために働くのが使命です。明治以降の日本政府がユダヤ人に融和的だっというのは、数々の証拠があります。外交官である杉原氏はそれを知っていたのでしょう。その "融和的" な姿勢の発端は、日露戦争におけるユダヤ人資本家からの戦費調達であり、その背景にはロシアにおけるポグロムがある。ユダヤ人資本家は、ロシアと戦おうとする日本を応援したわけです。
杉原氏の「命のビザ」は、ソ連から逃れようとする「ユダヤ人を含む難民」に発給されたものであり、それは人道的配慮と日本の国益への配慮に合致するものであった
という「複合的な視点」が重要でしょう。一面的に歴史をみることはまずいし、「歴史から学ぶ」ことにもならないのです。
2023-12-09 07:59
nice!(0)
No.333 - コンクリートが巨大帝国を生んだ [歴史]
今まで古代ローマについて何回かの記事を書いたなかで、ローマの重要インフラとなった各種の建造物(公衆浴場、水道、闘技場、神殿 ・・・・・・)を造ったコンクリート技術について書いたことがありました。
の2回です。実は、NHKの番組「世界遺産 時を刻む」で、古代ローマのコンクリート技術が特集されたことがありました(2012年)。この再放送が最近あり、録画することができました。番組タイトルは、
です。番組では現代に残る古代ローマの遺跡をとりあげ、そこでのコンクリートの使い方を詳細に解説していました。やはり画像を見ると良く理解できます。
そこで番組を録画したのを機に、その主要画像とナレーションをここに掲載したいと思います。番組の全部ではありませんが、ローマン・コンクリートに関する部分が全部採録してあります。
古代ローマのコンクリート
【ナレーション】
(NHKアナウンサー:武内陶子)
永遠の都、ローマ。立ち並ぶ巨大な建築は、ローマ帝国の栄光と力を今に示しています。その街並みを作ったのが、高度な土木技術です。
古代の最も優れた土木技術と言われるローマの水道。地下水道をささえているのはコンクリートです。円形闘技場、コロッセオ。5万人の観客が入る巨大娯楽施設でした。コロッセオもまた、そのほとんどがコンクリートで造られています。実は、古代ローマの街を形成する建造物のほとんどがコンクリートで出来ているのです。
円形闘技場:コロッセオ
【ナレーション】
考古学者のジュリアーナ・ガッリさん。25年間、古代ローマ建築を研究するうちに、ローマ独特のコンクリートの重要性を知りました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
(コロッセオを指して)この建物は、石積みの柱以外はコンクリートです。表面は大理石が覆っていました。(柱の部分を指して)この部分が石積みの柱です。あの穴には大理石の板を固定する金具が刺してありました。柱と柱の間に灰色の部分が見えます。アーチは全部コンクリート製なんです。あそこは壁の煉瓦が剥がれてコンクリートがむき出しになっていますね。柱以外はコンクリートで出来ていることがよく分かります。コンクリートは観客席まで続いています。
【ナレーション】
ローマ帝国の栄華を支えたと言われるコンクリート。この万能の建材は古代ローマコンクリートと呼ばれ、身近な産物から生まれました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
あるものが発見されたことで、古代ローマ人はコンクリートを使いこなせたのです。コンクリートを作り出したのはこの「魔法の砂」でした。
【ナレーション】
ここはローマ近郊の採掘所。ジュリアーナさんが持っていた魔法の砂が掘り出されています。ポッツォラーナと呼ばれます。
【ジュリアーナ・ガッリ】
ポッツォラーナは、もともとナポリの近くにあるポッツォーリ地方の火山灰のことでした。ヴェスビオ火山の灰です。その後、イタリアの火山灰全体を指すようになりました。堆積して固まった火山灰を細かく砕いたのがこのポッツォラーナです。
【ナレーション】
魔法の砂、ポッツォラーナとは、火山の噴火で生まれる火山灰です。火山国のイタリア、特に中南部には、数多くの火山が連なっています。
火山灰を建造物に最初に利用したのはエトルリア人でした。紀元前9世紀頃からイタリア半島に住んでいたエトルリア人。彼らは火山灰に水や石灰を混ぜてコンクリートのもとになるセメントを作り出しました。紀元前4世紀頃から、古代ローマはエトルリア人を制圧。その技術を自分たちのものにします。
では、火山灰をどのように古代コンクリートに生まれ変わるのでしょうか。2つの容器に石灰が入れてあります。そこに水を加えるとゆっくりと固まっていきます。右の容器に火山灰、ポッツォラーナを加えてみましょう。
【ジュリアーナ・ガッリ】
5時間後、石灰と水を混ぜた方はまだどろどろです。しかしそこにポッツォラーナを加えた方は固まってきました。これがセメントです。セメントにいろいろな石材と混ぜるとコンクリートが出来ます。こうして古代ローマ人は万能の建材、コンクリートを手に入れたのです。
【ナレーション】
火山灰の中では噴火で熱せられた酸化ケイ素が急速に冷やされガラス化し、化学反応しやすくなっています。石灰と水にこの酸化ケイ素を加えると、強い結合力を持つセメントになります。このセメントに砂や石を混ぜて強度を高めたのがコンクリートでした。火山の力が酸化ケイ素を化学反応しやすい形に変え、コンクリートの原料を大量にもたらしたのです。
紀元前3世紀頃、古代ローマ人はコンクリートを城壁の建設に使い始めました。セメントに砂や石を混ぜる割合などを工夫して強固なコンクリートを作り出し、エトルリア人から受け継いだ技術を発展させます。
その技術を生かしたのが歴代の皇帝でした。皇帝にとって、国民の支持を得て政権の安定を図ることが何より必要でした。そのために人口が集中するローマに市民のための公共施設をコンクリートで次々に造ったのです。
ヴィルゴ水道
【ナレーション】
観光客で賑わうトレビの泉。後ろ向きにコインを投げ入れると再びローマを訪れることができるという人気スポットです。
泉に水を運んでくるのは、古代ローマの地下水道です。建設したのは初代皇帝、アウグストゥスでした。紀元前27年に即位したアウグストゥスは、公共施設の整備に力を入れます。その一つが水道でした。
地下遺跡をめぐる同好会のメンバー、ダビデ(・コムネール)さんです。古代ローマの技術を調べてきたダビデさんに、地下水道を案内してもらいます。
水道を管理する建物から地下に入ります。水面が見えてきました。地下20メートルです。全長20キロ。地下部分が2キロあるこのヴィルゴ水道。今もきれいな水が流れています。
【ダビデ・コムネール】
これは現役で使われている唯一の古代ローマの水道です。皇帝、アウウグストゥスが共同浴場のために作りました。水道の終点は泉にして市民の目を楽しませたのです。
天井も壁も床もすべてコンクリート製です。すでにローマ人が自在にコンクリートを使いこなしていたことが分かりますね。
【ナレーション】
厚さ30センチのコンクリートにしっかりを支えられた地下空間です。コンクリートは作業がしにくいこうした現場に適していました。石材ほど運搬に人手がかからず、短時間で固まるからです。コンクリートは防水性にも優れています。床面に使うことで水漏れを防ぐことができました。
【ダビデ・コムネール】
ほとんで分かりませんが、ヴィルゴ水道は1キロに対し34センチほどの傾斜がつけてあります。これによって水は20キロ離れた水源からローマ市内まで流れてくることが出来るのです。微妙な傾斜をつけるのにコンクリートはうってつけでした。ローマ皇帝は戦争に勝つだけでは権威を保てません。人心を掌握するために市民生活を豊かにするこうした施設を次々に作る必要があったのです
【ナレーション】
2世紀までにローマに11本の水道が作られ、150万人の生活をまかなっていたと言います。コンクリート技術が大都市に豊かな水の安定供給を実現しました。
再びコロッセオ
【ナレーション】
第9代皇帝、ウェスパシアヌスです。彼が紀元79年に建設を始めたのが円形闘技場、コロッセオでした。皇帝ネロが暗殺されたあとの内乱を制したウェスパシアヌス。暴君と言われたネロが作った人工池を埋め立て、巨大な娯楽施設を建設することで支持を得ようとします。ここで行われた剣闘士の戦いは市民を興奮させました。
およそ8割がコンクリートというコロッセオ。舞台を支える地下構造はすべてコンクリートです。観客席もコンクリートを流し込んで作られています。
【ジュリアーナ・ガッリ】
こんな巨大な建物が8年で完成しました。コンクリートは形が自由に作れて材料の運搬が簡単でした。また値段の安さが威力を発揮したのです。
【ナレーション】
コロッセオの建設を担ったのは、戦争の捕虜や奴隷でした。訓練されていない労働者でもコンクリートは扱えました。石造りに求められるような熟練技術者の数はごく少数で済みました。これもコンクリートの大きなメリットです。
トラヤヌスの記念柱
【ナレーション】
第13代皇帝、トラヤヌスは、コンクリートを存分に活用して領土を拡大します。
ローマ市内に立つ石柱。トラヤヌスが、今のルーマニアに位置するダキアとの戦いに勝利した記念碑です。戦闘風景が描かれた柱には大土木工事の様子も見られます。兵士たちが運ぶ大量の煉瓦。コンクリートを流し込む枠に使われたと言われます。
建設されたのはドナウ河にかかる巨大な橋でした。ルーマニアを望むドナウ河の岸辺に橋脚が残っています。コンクリート製です。材料の火山灰はイタリアから運んだと言います。橋は2年で完成。早く固まり、短時間で建造物を作り出すコンクリートは軍事目的に適していました。橋を渡ったローマ軍は一気にダキアを攻略します。
トラヤヌスは領土を拡大する戦争を推進。彼が皇帝の座にあったときに、ローマ帝国の領土は最大となります。東西 5000キロ、南北 3500キロという広大な地域を支配することになったのです。
【ナレーション】(俳優:向井理)
ふたたびローマです。コンクリート技術によって築かれた永遠の都。その象徴といえるのがパンテオン神殿です。ローマの神々を祭る巨大な空間。円形ドームは当時のコンクリート技術の極みと言われます。自ら設計に携わったといわれるのが、第14代皇帝、ハドリアヌスです。五賢帝の一人、ローマ帝国に最大の国土と安定をもたらした皇帝です。
ティボリのハドリアヌス帝別荘
【ナレーション】(武内)
技術者としての才能にも長けていた皇帝、ハドリアヌス。その手腕を十分に発揮した建造物がローマ近郊にあります。世界遺産、ティボリのハドリアヌス帝別荘です。皇帝自ら設計した別荘は15年かけて造られ、紀元133年に完成しました。東京ドーム26個分という広大さ。3000人近くが住み、一つの町と呼べるほどの規模でした。30あまりの建物から主なものを見てみると、皇帝の宴会場、池を巡る遊歩道、皇帝の執務室、皇帝の住まい、そして住民のための大浴場。
大浴場はすべてコンクリートで出来ていました。ここは風呂あがりにマッサージを受け、談笑を交わす大広間です。日の出とともに働き、午後からは公共浴場でゆったりと過ごす。それが古代ローマ人の生活習慣でした。
こちらは使用人のための集合住宅。煉瓦の内側はコンクリートです。大きな建物を速く簡単に造れるコンクリートは、集合住宅にうってつけでした。
考古学者・ジュリアーナさんに皇帝が住んでいた区画を案内してもらいます。ハドリアヌスが最も気に入っていたという建物です。
皇帝の住まいです。水に囲まれた舞台のような形から「海の劇場」と名付けられています。ここもハドリアヌス自身が設計したといわれます。プライベートな空間を囲む水路。設計には水も巧みに取り入れられています
【ジュリアーナ・ガッリ】
すばらしいですね。ここが皇帝が生活していた場所です。中庭もありました。その横は最もプライベートな場所、寝室です。ベッドが置かれていました。皇帝のベッドです。ほら、煉瓦が崩れてコンクリートが見えてます。灰色の部分がセメント。その中に大ぶりの石が混ぜてありますね。
ハドリアヌスは孤独を愛したので、広い別荘で人と交わらずに過ごそうとしました。特に自分を外界から隔てるために水路は重要でした。
【ナレーション】
この建物、最大の特徴は完全な円形をしていることです。木枠にコンクリートを流し込んで基礎を造りました。外壁、水路、住まいの敷地は、3つの同心円でデザインされています。規模の大きさや豪華さを競い合った当時のローマ帝国の建物と違って、円形のデザインからは独創的で洒落たセンスが伝わってきます。
コンクリートを使えば、思い通りの造形が簡単にできます。皇帝がイメージした完全な円形の住居を石で造り出すのは大仕事ですね。でもコンクリートなら、設計者の発想を自由に表現することができるのです。
コンクリートだから可能になったさまざまな造りが、建物のここかしこに見られます。
【ジュリアーナ・ガッリ】
こちらは小さなスペースを利用したトイレ。煉瓦の壁の中はコンクリートです。ここには大理石の便座が渡されていて、水を流す管を置いたコンクリートの凹みが残っています。
【ナレーション】
住まいにふんだんに用いたコンクリート。ローマ帝国を支える土木技術への、皇帝の愛着が伝わってきます。
視察で知った帝国の現状を統治にどう生かしていくのか。ハドリアヌスは別荘で考え抜きました。政策決定で重要な意味を持ったのがこの場所です。それは皇帝の執務室。
【ジュリアーナ・ガッリ】
壁に7人の哲学者の像があったので「哲学者の間」と呼ばれています。像の前の玉座に座り、皇帝は仕事をしました。彼はローマよりこの別荘に居ることを好んだので、ここは政治にも大きな役割を果たした場所でした。
【ナレーション】
執務室で国政に集中するハドリアヌス。疲れを癒したのがこのドームと言われます。ドームには華麗なフレスコ画が描かれていました。壁の窪みには神々の彫像が並んでいました。装飾の素晴らしさだけでなく、このドームにはローマ帝国の土木技術の粋が詰まっています。コンクリートならではの特徴を生かした建築方法です。
【ジュリアーナ・ガッリ】
これはさまざまな分野で働く人々の技術の結晶です。木材を組み合わせて木枠を造る人、コンクリートを混ぜて木枠に流し込む人、コンクリートの原料を輸送する人、そうした専門家の能力と組織力が十分に発揮されたと言えます。
【ナレーション】
どんな技術が用いられているのか、見ていきましょう。まず、基礎の部分に煉瓦を積み上げ枠を作ります。そこに石を混ぜたセメントを流し込みます。これで全体の重みを支えるコンクリート基盤ができます。次は木で足場を作り、ドーム形の精密な木枠を組んでいきます。外側にも木枠を組み、内と外の間にコンクリートを入れます。上に行くに従って、混ぜる石の重さを軽くしていきます。頂上部分に混ぜるのは軽石です。コンクリートの厚さも上の方ほど薄くして、極力、重量を減らします。こうして、正確な曲線と一定の強度のあるドームを造ることができたのです。
パンテオン神殿
【ナレーション】
別荘で使われた技術を、ハドリアヌスがさらに極めた建造物があります。パンテオン神殿です。
世界の建築史上、傑作の一つとされるパンテオン。直径43メートルのドームは完成から1000年以上、世界最大の規模を誇っていました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
このコンクリートドームは、古代ローマの土木技術の頂点と言えます。斬新な設計を追求した皇帝の強い意志と、それを実現した人々の高い技術力が感じられます。
【ナレーション】
ここには鉄筋は使われていません。鉄筋なしでこの大きさのドームと造ることは、現代の技術をもってしても至難の技です。
ドームの厚さは最大で6メートル。上にいくにつれて薄くなり、頂上では 1.5メートルになります。厚さを調整することで全体を軽くしているのです。4角に窪んだ装飾は建物を軽くするとともに、段をつけることで壁を補強したと言われます。コンクリートで正確な円が造り出されたドーム。そこには、広大な帝国を治めるハドリアムスの決意がこめられていました。
天井から床までの高さは、横幅と同じ43メートルです。そのため、ドームの丸みに合わせた球体がすっぽりと入ります。歴代ローマ皇帝は、地中海を中心とした帝国の領土を球体と考えていました。これは、初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っています。ハドリアヌスは、パンテオンの中に世界全体を包み入れることでその権威を示したのだと言われます。
再びティボリのハドリアヌス帝別荘
【ナレーション】
ハドリアヌスがエジプトの旅の思い出を別荘に再現した水路です。ナイル河の支流、カノープスを模していると言われます。水路の端にあるコンクリートドームからこの情景を楽しみました。岸辺にはナイルで目撃したワニの彫刻も置かれています。ここで皇帝はしばしば大宴会を主催しました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
ここにはコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をしていました。宴会のとき、彼らはこのように横になり、ふんだんに提供される貴重な肉や果物を楽しみました。皇帝は安全の為に、あの上に居たんです。
【ナレーション】
皇帝の玉座から見たカノープスです。宴会では楽士が音楽を奏で、曲芸師が芸を披露しました。皇帝はどんな料理で人々をもてなしたのか。古代ローマ料理の研究家、ジュリア(・パッサレリ)さんにメニューを再現してもらいました。
【ナレーション】
60歳に近づいたハドリアヌスは健康を害し、ほとんどの時間を別荘で過ごしたといわれます。41歳で皇帝の位について以来、広大な帝国を廻り続けた日々。別荘にいればその思い出が目の前によみがえります。
紀元138年、ハドリアヌスは生涯を閉じます。62歳でした。ローマ帝国に安定した反映をもたらした皇帝。彼の死とともに、帝国も次第に黄昏を迎えていきます。
帝政末期、財政難と社会の混乱が続き、土木技術も衰えていきました。そして帝国の滅亡とともに、ヨーロッパではコンクリート技術が姿を消します。
【ジュリアーナ・ガッリ】
コンクリートはローマ帝国の象徴でした。国の技術力、組織力、管理力が総合された土木技術だったのです。だから、火山灰がたくさんあっても、帝国が滅亡するとコンクリートも滅亡してしまったんです。
【ナレーション】
ローマだからこそ生まれ、ローマの滅亡とともに消えていった土木技術。しかし古代のコンクリートは、その成果である建造物に生き続け、ローマの栄光を今に伝えています。
【ナレーション】(向井)
コンクリート無くしてローマは無く、ローマ無くしてコンクリートは無かった。その事実を今に語り続けるのが、ハドリアヌスが最も愛した海の劇場です。晩年、皇帝は、一日の多くをここで一人で過ごしたといいます。彼がコンクリート技術の粋を集めた完全な円形。直径は43メートルあります。この数字、ハドリアヌスのもう一つの傑作と一致しています。パンテオン神殿の円形ドームの直径です。広大な領土がすっぽり入るような形に仕上げられたドーム。ハドリアヌスはローマの栄光が永遠に続くと思っていたのでしょうか。
そしてもし、ハドリアヌスが現代のメガロポリスの数々を目にしたら、こう言うのではないでしょうか。「ここにもローマがある」と。
の2回です。実は、NHKの番組「世界遺産 時を刻む」で、古代ローマのコンクリート技術が特集されたことがありました(2012年)。この再放送が最近あり、録画することができました。番組タイトルは、
|
です。番組では現代に残る古代ローマの遺跡をとりあげ、そこでのコンクリートの使い方を詳細に解説していました。やはり画像を見ると良く理解できます。
そこで番組を録画したのを機に、その主要画像とナレーションをここに掲載したいと思います。番組の全部ではありませんが、ローマン・コンクリートに関する部分が全部採録してあります。
古代ローマのコンクリート
【ナレーション】
(NHKアナウンサー:武内陶子)
永遠の都、ローマ。立ち並ぶ巨大な建築は、ローマ帝国の栄光と力を今に示しています。その街並みを作ったのが、高度な土木技術です。
古代の最も優れた土木技術と言われるローマの水道。地下水道をささえているのはコンクリートです。円形闘技場、コロッセオ。5万人の観客が入る巨大娯楽施設でした。コロッセオもまた、そのほとんどがコンクリートで造られています。実は、古代ローマの街を形成する建造物のほとんどがコンクリートで出来ているのです。
円形闘技場:コロッセオ

|
円形闘技場:コロッセオ |
【ナレーション】
考古学者のジュリアーナ・ガッリさん。25年間、古代ローマ建築を研究するうちに、ローマ独特のコンクリートの重要性を知りました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
(コロッセオを指して)この建物は、石積みの柱以外はコンクリートです。表面は大理石が覆っていました。(柱の部分を指して)この部分が石積みの柱です。あの穴には大理石の板を固定する金具が刺してありました。柱と柱の間に灰色の部分が見えます。アーチは全部コンクリート製なんです。あそこは壁の煉瓦が剥がれてコンクリートがむき出しになっていますね。柱以外はコンクリートで出来ていることがよく分かります。コンクリートは観客席まで続いています。

|
コロッセオの説明をする考古学者のジュリアーナ・ガッリさん |

|
コロッセオの柱は石で出来ている。表面を覆っていた大理石の板を固定するための穴が見える。 |

|
柱と柱の間にあるアーチはコンクリート製である。 |

|
壁の煉瓦が剥がれて、柱の間のコンクリートがむき出しになっている。このコンクリートは観客席まで続いている。 |
【ナレーション】
ローマ帝国の栄華を支えたと言われるコンクリート。この万能の建材は古代ローマコンクリートと呼ばれ、身近な産物から生まれました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
あるものが発見されたことで、古代ローマ人はコンクリートを使いこなせたのです。コンクリートを作り出したのはこの「魔法の砂」でした。

|
ジュリアーナ・ガッリさんが手に、持った「魔法の砂」を見せている。 |
【ナレーション】
ここはローマ近郊の採掘所。ジュリアーナさんが持っていた魔法の砂が掘り出されています。ポッツォラーナと呼ばれます。
【ジュリアーナ・ガッリ】
ポッツォラーナは、もともとナポリの近くにあるポッツォーリ地方の火山灰のことでした。ヴェスビオ火山の灰です。その後、イタリアの火山灰全体を指すようになりました。堆積して固まった火山灰を細かく砕いたのがこのポッツォラーナです。
【ナレーション】
魔法の砂、ポッツォラーナとは、火山の噴火で生まれる火山灰です。火山国のイタリア、特に中南部には、数多くの火山が連なっています。
火山灰を建造物に最初に利用したのはエトルリア人でした。紀元前9世紀頃からイタリア半島に住んでいたエトルリア人。彼らは火山灰に水や石灰を混ぜてコンクリートのもとになるセメントを作り出しました。紀元前4世紀頃から、古代ローマはエトルリア人を制圧。その技術を自分たちのものにします。
では、火山灰をどのように古代コンクリートに生まれ変わるのでしょうか。2つの容器に石灰が入れてあります。そこに水を加えるとゆっくりと固まっていきます。右の容器に火山灰、ポッツォラーナを加えてみましょう。
【ジュリアーナ・ガッリ】
5時間後、石灰と水を混ぜた方はまだどろどろです。しかしそこにポッツォラーナを加えた方は固まってきました。これがセメントです。セメントにいろいろな石材と混ぜるとコンクリートが出来ます。こうして古代ローマ人は万能の建材、コンクリートを手に入れたのです。

|
石灰 + 水 + ポッツォラーナを混ぜた右の容器は、5時間後に固まってきている。左の石灰 + 水の容器は、まだドロドロの状態である。 |
【ナレーション】
火山灰の中では噴火で熱せられた酸化ケイ素が急速に冷やされガラス化し、化学反応しやすくなっています。石灰と水にこの酸化ケイ素を加えると、強い結合力を持つセメントになります。このセメントに砂や石を混ぜて強度を高めたのがコンクリートでした。火山の力が酸化ケイ素を化学反応しやすい形に変え、コンクリートの原料を大量にもたらしたのです。
紀元前3世紀頃、古代ローマ人はコンクリートを城壁の建設に使い始めました。セメントに砂や石を混ぜる割合などを工夫して強固なコンクリートを作り出し、エトルリア人から受け継いだ技術を発展させます。
その技術を生かしたのが歴代の皇帝でした。皇帝にとって、国民の支持を得て政権の安定を図ることが何より必要でした。そのために人口が集中するローマに市民のための公共施設をコンクリートで次々に造ったのです。
ヴィルゴ水道
【ナレーション】
観光客で賑わうトレビの泉。後ろ向きにコインを投げ入れると再びローマを訪れることができるという人気スポットです。
泉に水を運んでくるのは、古代ローマの地下水道です。建設したのは初代皇帝、アウグストゥスでした。紀元前27年に即位したアウグストゥスは、公共施設の整備に力を入れます。その一つが水道でした。
地下遺跡をめぐる同好会のメンバー、ダビデ(・コムネール)さんです。古代ローマの技術を調べてきたダビデさんに、地下水道を案内してもらいます。
水道を管理する建物から地下に入ります。水面が見えてきました。地下20メートルです。全長20キロ。地下部分が2キロあるこのヴィルゴ水道。今もきれいな水が流れています。


|
ヴィルゴ水道の内部。現在もきれいな水が流れている。 |
【ダビデ・コムネール】
これは現役で使われている唯一の古代ローマの水道です。皇帝、アウウグストゥスが共同浴場のために作りました。水道の終点は泉にして市民の目を楽しませたのです。
天井も壁も床もすべてコンクリート製です。すでにローマ人が自在にコンクリートを使いこなしていたことが分かりますね。



|
ダビデ・コムネールさんがヴィルゴ水道の説明をしている。水道の天井、壁、床面はすべてコンクリート製である。 |
【ナレーション】
厚さ30センチのコンクリートにしっかりを支えられた地下空間です。コンクリートは作業がしにくいこうした現場に適していました。石材ほど運搬に人手がかからず、短時間で固まるからです。コンクリートは防水性にも優れています。床面に使うことで水漏れを防ぐことができました。
【ダビデ・コムネール】
ほとんで分かりませんが、ヴィルゴ水道は1キロに対し34センチほどの傾斜がつけてあります。これによって水は20キロ離れた水源からローマ市内まで流れてくることが出来るのです。微妙な傾斜をつけるのにコンクリートはうってつけでした。ローマ皇帝は戦争に勝つだけでは権威を保てません。人心を掌握するために市民生活を豊かにするこうした施設を次々に作る必要があったのです
【ナレーション】
2世紀までにローマに11本の水道が作られ、150万人の生活をまかなっていたと言います。コンクリート技術が大都市に豊かな水の安定供給を実現しました。
再びコロッセオ
【ナレーション】
第9代皇帝、ウェスパシアヌスです。彼が紀元79年に建設を始めたのが円形闘技場、コロッセオでした。皇帝ネロが暗殺されたあとの内乱を制したウェスパシアヌス。暴君と言われたネロが作った人工池を埋め立て、巨大な娯楽施設を建設することで支持を得ようとします。ここで行われた剣闘士の戦いは市民を興奮させました。

|
コロッセオ |


|
(上)剣闘士の闘技会のモザイク画。倒れている剣闘士の名前のそばに φ の文字があるが、これは死を意味する。(下)闘獣士の野獣狩りのショーの様子で、動物はヒョウである。闘技会の前座として行われた。No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」参照。 |
およそ8割がコンクリートというコロッセオ。舞台を支える地下構造はすべてコンクリートです。観客席もコンクリートを流し込んで作られています。

|
コロッセオの地下構造。舞台を支える地下構造はすべてコンクリート製である。 |
【ジュリアーナ・ガッリ】
こんな巨大な建物が8年で完成しました。コンクリートは形が自由に作れて材料の運搬が簡単でした。また値段の安さが威力を発揮したのです。
【ナレーション】
コロッセオの建設を担ったのは、戦争の捕虜や奴隷でした。訓練されていない労働者でもコンクリートは扱えました。石造りに求められるような熟練技術者の数はごく少数で済みました。これもコンクリートの大きなメリットです。
トラヤヌスの記念柱
【ナレーション】
第13代皇帝、トラヤヌスは、コンクリートを存分に活用して領土を拡大します。
ローマ市内に立つ石柱。トラヤヌスが、今のルーマニアに位置するダキアとの戦いに勝利した記念碑です。戦闘風景が描かれた柱には大土木工事の様子も見られます。兵士たちが運ぶ大量の煉瓦。コンクリートを流し込む枠に使われたと言われます。


|
トラヤヌスの記念柱と、煉瓦を運ぶ兵士のフリーズ。 |
建設されたのはドナウ河にかかる巨大な橋でした。ルーマニアを望むドナウ河の岸辺に橋脚が残っています。コンクリート製です。材料の火山灰はイタリアから運んだと言います。橋は2年で完成。早く固まり、短時間で建造物を作り出すコンクリートは軍事目的に適していました。橋を渡ったローマ軍は一気にダキアを攻略します。


|
ドナウ河畔に残る橋脚と、完成した橋の想像図。 |
トラヤヌスは領土を拡大する戦争を推進。彼が皇帝の座にあったときに、ローマ帝国の領土は最大となります。東西 5000キロ、南北 3500キロという広大な地域を支配することになったのです。
石で造られた、エジプトのピラミッド、ギリシャのパルテノン神殿の紹介。それぞれ高度な土木・建設技術であるが、コンクリートのような素材は使われていない。
【ナレーション】(俳優:向井理)
ふたたびローマです。コンクリート技術によって築かれた永遠の都。その象徴といえるのがパンテオン神殿です。ローマの神々を祭る巨大な空間。円形ドームは当時のコンクリート技術の極みと言われます。自ら設計に携わったといわれるのが、第14代皇帝、ハドリアヌスです。五賢帝の一人、ローマ帝国に最大の国土と安定をもたらした皇帝です。
ティボリのハドリアヌス帝別荘
【ナレーション】(武内)
技術者としての才能にも長けていた皇帝、ハドリアヌス。その手腕を十分に発揮した建造物がローマ近郊にあります。世界遺産、ティボリのハドリアヌス帝別荘です。皇帝自ら設計した別荘は15年かけて造られ、紀元133年に完成しました。東京ドーム26個分という広大さ。3000人近くが住み、一つの町と呼べるほどの規模でした。30あまりの建物から主なものを見てみると、皇帝の宴会場、池を巡る遊歩道、皇帝の執務室、皇帝の住まい、そして住民のための大浴場。

|
ローマ近郊のティボリのハドリアヌス帝別荘 |
大浴場はすべてコンクリートで出来ていました。ここは風呂あがりにマッサージを受け、談笑を交わす大広間です。日の出とともに働き、午後からは公共浴場でゆったりと過ごす。それが古代ローマ人の生活習慣でした。


|
ハドリアヌス帝別荘の大浴場と大広間 |
こちらは使用人のための集合住宅。煉瓦の内側はコンクリートです。大きな建物を速く簡単に造れるコンクリートは、集合住宅にうってつけでした。

|
使用人のための集合住宅。外壁の煉瓦の内側はコンクリートである。 |
考古学者・ジュリアーナさんに皇帝が住んでいた区画を案内してもらいます。ハドリアヌスが最も気に入っていたという建物です。

|
「海の劇場」と呼ばれるハドリアヌス帝の住居跡 |
皇帝の住まいです。水に囲まれた舞台のような形から「海の劇場」と名付けられています。ここもハドリアヌス自身が設計したといわれます。プライベートな空間を囲む水路。設計には水も巧みに取り入れられています
【ジュリアーナ・ガッリ】
すばらしいですね。ここが皇帝が生活していた場所です。中庭もありました。その横は最もプライベートな場所、寝室です。ベッドが置かれていました。皇帝のベッドです。ほら、煉瓦が崩れてコンクリートが見えてます。灰色の部分がセメント。その中に大ぶりの石が混ぜてありますね。

|
皇帝の寝室の壁。煉瓦が崩れてコンクリートが見えている。 |
ハドリアヌスは孤独を愛したので、広い別荘で人と交わらずに過ごそうとしました。特に自分を外界から隔てるために水路は重要でした。
【ナレーション】
この建物、最大の特徴は完全な円形をしていることです。木枠にコンクリートを流し込んで基礎を造りました。外壁、水路、住まいの敷地は、3つの同心円でデザインされています。規模の大きさや豪華さを競い合った当時のローマ帝国の建物と違って、円形のデザインからは独創的で洒落たセンスが伝わってきます。


|
「海の劇場」の上空からの画像と、復元想像図。 |
コンクリートを使えば、思い通りの造形が簡単にできます。皇帝がイメージした完全な円形の住居を石で造り出すのは大仕事ですね。でもコンクリートなら、設計者の発想を自由に表現することができるのです。
コンクリートだから可能になったさまざまな造りが、建物のここかしこに見られます。
【ジュリアーナ・ガッリ】
こちらは小さなスペースを利用したトイレ。煉瓦の壁の中はコンクリートです。ここには大理石の便座が渡されていて、水を流す管を置いたコンクリートの凹みが残っています。
【ナレーション】
住まいにふんだんに用いたコンクリート。ローマ帝国を支える土木技術への、皇帝の愛着が伝わってきます。
ハドリアヌスが広大はローマ帝国の各地を視察したことの解説。ローマ帝国は領土にした各地に土木技術を使った建造物を造った。
視察で知った帝国の現状を統治にどう生かしていくのか。ハドリアヌスは別荘で考え抜きました。政策決定で重要な意味を持ったのがこの場所です。それは皇帝の執務室。
【ジュリアーナ・ガッリ】
壁に7人の哲学者の像があったので「哲学者の間」と呼ばれています。像の前の玉座に座り、皇帝は仕事をしました。彼はローマよりこの別荘に居ることを好んだので、ここは政治にも大きな役割を果たした場所でした。
【ナレーション】
執務室で国政に集中するハドリアヌス。疲れを癒したのがこのドームと言われます。ドームには華麗なフレスコ画が描かれていました。壁の窪みには神々の彫像が並んでいました。装飾の素晴らしさだけでなく、このドームにはローマ帝国の土木技術の粋が詰まっています。コンクリートならではの特徴を生かした建築方法です。


|
ドームとその復元想像図 |
【ジュリアーナ・ガッリ】
これはさまざまな分野で働く人々の技術の結晶です。木材を組み合わせて木枠を造る人、コンクリートを混ぜて木枠に流し込む人、コンクリートの原料を輸送する人、そうした専門家の能力と組織力が十分に発揮されたと言えます。
【ナレーション】
どんな技術が用いられているのか、見ていきましょう。まず、基礎の部分に煉瓦を積み上げ枠を作ります。そこに石を混ぜたセメントを流し込みます。これで全体の重みを支えるコンクリート基盤ができます。次は木で足場を作り、ドーム形の精密な木枠を組んでいきます。外側にも木枠を組み、内と外の間にコンクリートを入れます。上に行くに従って、混ぜる石の重さを軽くしていきます。頂上部分に混ぜるのは軽石です。コンクリートの厚さも上の方ほど薄くして、極力、重量を減らします。こうして、正確な曲線と一定の強度のあるドームを造ることができたのです。






|
ドームの建築方法と、現代のドームの正面画像 |
パンテオン神殿
【ナレーション】
別荘で使われた技術を、ハドリアヌスがさらに極めた建造物があります。パンテオン神殿です。

|
パンテオン神殿 |
世界の建築史上、傑作の一つとされるパンテオン。直径43メートルのドームは完成から1000年以上、世界最大の規模を誇っていました。
【ジュリアーナ・ガッリ】
このコンクリートドームは、古代ローマの土木技術の頂点と言えます。斬新な設計を追求した皇帝の強い意志と、それを実現した人々の高い技術力が感じられます。
【ナレーション】
ここには鉄筋は使われていません。鉄筋なしでこの大きさのドームと造ることは、現代の技術をもってしても至難の技です。

|
パンテオン神殿のドーム。コンクリートだけでこの構造が造られている。 |
ドームの厚さは最大で6メートル。上にいくにつれて薄くなり、頂上では 1.5メートルになります。厚さを調整することで全体を軽くしているのです。4角に窪んだ装飾は建物を軽くするとともに、段をつけることで壁を補強したと言われます。コンクリートで正確な円が造り出されたドーム。そこには、広大な帝国を治めるハドリアムスの決意がこめられていました。

|
ドームの4角に窪んだ装飾 |
天井から床までの高さは、横幅と同じ43メートルです。そのため、ドームの丸みに合わせた球体がすっぽりと入ります。歴代ローマ皇帝は、地中海を中心とした帝国の領土を球体と考えていました。これは、初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っています。ハドリアヌスは、パンテオンの中に世界全体を包み入れることでその権威を示したのだと言われます。

|
初代皇帝アウグストゥスがエジプトのクレオパトラを打ち破った時の記念銀貨。。勝利の女神が世界を表す球体の上に立っている。 |
万里の長城、マチュピチュの紹介。また、ハドリアヌスが紀元130年にエジプトのテーベや王家の谷の近くにあるメムノンの巨像を訪れたことの説明。
再びティボリのハドリアヌス帝別荘
【ナレーション】
ハドリアヌスがエジプトの旅の思い出を別荘に再現した水路です。ナイル河の支流、カノープスを模していると言われます。水路の端にあるコンクリートドームからこの情景を楽しみました。岸辺にはナイルで目撃したワニの彫刻も置かれています。ここで皇帝はしばしば大宴会を主催しました。

|
ティボリのハドリアヌス帝別荘の水路 |
【ジュリアーナ・ガッリ】
ここにはコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をしていました。宴会のとき、彼らはこのように横になり、ふんだんに提供される貴重な肉や果物を楽しみました。皇帝は安全の為に、あの上に居たんです。

|
皇帝の玉座から見た水路(カノープス)。手前にコンクリートで造られた寝台のようなものがあり、貴族たちは奴隷の給仕で宴会をした。 |
【ナレーション】
皇帝の玉座から見たカノープスです。宴会では楽士が音楽を奏で、曲芸師が芸を披露しました。皇帝はどんな料理で人々をもてなしたのか。古代ローマ料理の研究家、ジュリア(・パッサレリ)さんにメニューを再現してもらいました。
古代ローマ料理の再現映像。食材は、東南アジアの胡椒、スペインのオリーブオイル、イスラエルのナツメヤシ、ウツボ、川エビ、クジャク(インド原産・ローマで養殖)、ウニとバジル(ソース用)など。
【ナレーション】
60歳に近づいたハドリアヌスは健康を害し、ほとんどの時間を別荘で過ごしたといわれます。41歳で皇帝の位について以来、広大な帝国を廻り続けた日々。別荘にいればその思い出が目の前によみがえります。
紀元138年、ハドリアヌスは生涯を閉じます。62歳でした。ローマ帝国に安定した反映をもたらした皇帝。彼の死とともに、帝国も次第に黄昏を迎えていきます。
帝政末期、財政難と社会の混乱が続き、土木技術も衰えていきました。そして帝国の滅亡とともに、ヨーロッパではコンクリート技術が姿を消します。
【ジュリアーナ・ガッリ】
コンクリートはローマ帝国の象徴でした。国の技術力、組織力、管理力が総合された土木技術だったのです。だから、火山灰がたくさんあっても、帝国が滅亡するとコンクリートも滅亡してしまったんです。
【ナレーション】
ローマだからこそ生まれ、ローマの滅亡とともに消えていった土木技術。しかし古代のコンクリートは、その成果である建造物に生き続け、ローマの栄光を今に伝えています。
【ナレーション】(向井)
コンクリート無くしてローマは無く、ローマ無くしてコンクリートは無かった。その事実を今に語り続けるのが、ハドリアヌスが最も愛した海の劇場です。晩年、皇帝は、一日の多くをここで一人で過ごしたといいます。彼がコンクリート技術の粋を集めた完全な円形。直径は43メートルあります。この数字、ハドリアヌスのもう一つの傑作と一致しています。パンテオン神殿の円形ドームの直径です。広大な領土がすっぽり入るような形に仕上げられたドーム。ハドリアヌスはローマの栄光が永遠に続くと思っていたのでしょうか。
そしてもし、ハドリアヌスが現代のメガロポリスの数々を目にしたら、こう言うのではないでしょうか。「ここにもローマがある」と。
2022-03-19 08:27
nice!(0)
No.327 - 略奪された文化財 [歴史]
No.319「アルマ=タデマが描いた古代世界」で、英国がギリシャから略奪したパルテノン神殿のフリーズの話を書きました。今回はそれに関連した話題です。
エルギン・マーブル
まず始めに No.319 のパルテノン神殿のフリーズの話を復習すると次の通りです。
大英博物館が所蔵する略奪美術品・略奪文化財はエルギン・マーブルだけではありません。エジプト、メソポタミアの文化財の多くがそうです。このエジプト・メソポタミアのコレクションを築いた人物の話が、NHKのドキュメンタリー番組でありました。それを紹介します。
大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション
NHK BSプレミアムで「フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿」と題するドキュメンタリーのシリーズが放映されています。その2021年11月25日の放送は、
と題するものでした(2021年11月25日 21:00~21:45)。内容は、大英博物館(British Museum)のエジプト・コレクションに焦点を当て、その収集(略奪)の経緯を追ったものした。以降、番組の概要を紹介します。
大英博物館のエジプト・コレクションは総数が10万点以上で、世界最大級です。ミイラだけでも150点以上あります。このコレクションのうちの4万点を集めたのが、大英博物館の考古学者、ウォーリス・バッジ(Wallis Budge。1857-1934)でした。バッジは大英博物館の歴史上、最も多くの文化遺産を収集した人物と言われています。
彼の収集方法はもちろん違法で、嘘、賄賂、脅しなどで盗掘品を買い漁ったものでした。収集品の中で最も貴重なのが "死者の書" の最高傑作といわれる「アニのパピルス」ですが、これもエジプト当局を出し抜き、無許可で英国に持ち出したものです。
1882年、英国はエジプトを占領し、保護国にします。1886年、バッジは29歳でエジプト乗り込みました。彼は 150ポンド(現在の日本円で約300万円の価値)の資金を大英博物館から託されていました。
当時のエジプトでは、1880年5月19日に公布された遺跡や遺物に関する法令で、「エジプト考古学に関わるすべての文化遺産の持ち出しを絶対に禁止する」と決められていました。文化遺産を持ち帰るヨーロッパ人が後を絶たなかったためです。バッジに面会した英国総領事のイブリン・ベアリング(Evelyn Baring)も、エジプトの文化遺産を英国に持って帰らないようバッジにクギをさし、「エジプトの占領が歴史的な遺産を盗む口実になってははらない」と告げました。
しかし、バッジは文化遺産の買い付けに走ります。持ち前の語学力を武器に情報収集を行い、また、古代エジプト文字も読めたバッジは審美眼にもたけていました。そして現地のエジプト人が盗掘した文化遺産を次々と買い漁っていきました。盗掘品と知りながら購入する行為はもちろん違法ですが、盗掘人にもメリットがありました。盗掘品をエジプト当局に見つかると、没収されるか二束三文で買い上げられます。バッジに売る方が儲かります。
バッジはエジプト当局の監視をかいくぐり、イギリス軍と交渉して文化遺産を軍用貨物として英国に送りました。軍用貨物となると誰も検査できません。バッジは英国総領事・ベアリングの指示を全く無視したわけです。この初めてのエジプト行きでバッジは1500点もの文化遺産を持ち帰りました。
1887年、バッジは再びエジプトに向かいます。後に「アニのパピルス」と呼ばれる "死者の書" を手に入れるためです。番組のナレーションを紹介します。
しかしバッジは警告を無視します。バッジは到着の数日後、盗掘集団の案内でパピルスの巻物が発見された墓を訪れました。そこにあったのが「アニのパピルス」です。アニという人物に捧げられた死者の書で、完全な状態で残っていました。バッジはそれを墓から持ち出しました。つまり、これまでは盗掘品を買い取っていただけでしたが、ついに盗掘に手を染めたのです。
バッジはまたしてもイギリス軍に託しで持ち出すことに成功しました。
たった2度のエジプト行きで盗掘集団とのネットワークを築いたバッッジは、メソポタミアでも同様の手口で文化遺産を収集していきました。
バッジの行為は英国国内でも批判が噴出しました。「大英博物館のために働く無節操なコレクター」と新聞は書きました。バッジ批判の急先鋒はエジプト考古学の父といわれるフリンダーズ・ピートリーでした。彼はバッジを告発する手紙を考古学会に送ります。しかし、大英博物館の理事会メンバーの多くが政府の高官でした。政府はバッジの行為を把握し、承認していたのです。告発はスルーされました。
1894年、バッジは37歳で大英博物館のエジプト・アッシリア部長に昇進し、その後もコレクションを充実させます。そして67歳で退官するまでに、エジプト関連の文化遺産を4万点、メソポタミア関連を5万点収集しました。古代エジプトのミイラも、バッジが在職中に 63点が収集されています。
略奪された文化財、美術品を元の国に返還するよう、機運が高まっています。2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表しました。アメリカの聖書博物館も2021年、エジプトに5000点の文化遺産を返還しました。しかしこのような返還はまだ一握り、ごく一部に過ぎません。たとえば大英国博物館は1753年の創設以来、一切の返還要求に応じていません。
以上が「大英博物館 ─ 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム 2021年11月25日)の概要です。大英博物館を訪れると、有名なロゼッタ・ストーンに目を引かれ、巨大なアッシリアの彫像、大量のエジプトのミイラに驚きます。そういった古代文明を知ることは大切な経験ですが、それと同時に英国の略奪の歴史も知っておくべきでしょう。歴史の勉強としては、それもまた重要です。
ルーブル美術館
イギリスだけでなく、フランスのルーブル美術館も略奪美術品で有名です。ここの特色は、19世紀初頭のナポレオン戦争でナポレオンが持ち帰った文化財・美術品があることです。つまり、エジプトのみならずヨーロッパ各国から略奪した美術品がある。特にイタリアです。2021年6月9日の New York Times に、
と題するコラム記事が掲載されました。この記事の一部を試訳とともに掲げます。
ヴェロネーゼの『カナの婚礼』は、677cm × 994cm という巨大さで、ルーブル美術館の最大の絵画と言われています。この絵はもともとヴェネチアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の食堂に飾られていましたが、ナポレオン軍が剥奪しました。あまりに巨大なので、カンヴァスを水平にいくつかに切断し、それぞれをカーペットを丸めるようにしてフランスに持ち帰り、再び縫合しました。これだけでもカンヴァスの損傷があったと思われます。
しかしナポレオンは結局のところ "敗北" し、戦後処理の中で略奪美術品も返却されます。「ラオコーン」もその一つです。しかし返却されたのは全部ではありませんでした。
ナポレオンの強奪美術品がルーブル美術館でだけでなくフランス各地に分散されたのは、返還交渉を難しくするためと言われています。
話は変わりますが、以前、イタリア対フランスのサッカーのナショナルチームの試合があり、イタリアが勝った時の様子を特派員がレポートしたテレビ番組を見たことがあります。何の試合かは忘れました。ワールドカップのヨーロッパ予選だったか、ヨーロッパ国別選手権だったか、とにかく重要な試合です。これにイタリアが勝ったときの北イタリアの都市(ミラノだったと思います)の街の様子が放映されました。街頭に繰り出した人々が口々に叫んでいたのは、
というものです。良く知られているように、ダ・ヴィンチは最後の庇護者であるフランスのフランソワ1世のもとで亡くなったので、手元にあったモナ・リザがフランスに残されました。ダ・ヴィンチの遺品の "正式の" 相続権者が誰かという問題はあると思いますが、少なくともモナ・リザはフランスが強奪したものではありません。
しかし、フランスに勝ったことで熱狂し街頭に繰り出したイタリアの人々は「次はモナ・リザを取り戻すぞ!」なのですね。テレビを見たときにはその理由がわかりませんでした。しかしイタリアの美術品がフランスに強奪された歴史を知ると、あのような人々の叫びもわかるのです。
イタリアだけではありません。スペインやポルトガルに団体で旅行に行くと、現地のガイドさんが各種の文化遺産(教会、修道院、宮殿など)を案内してくれます。そこでは「ナポレオンにはひどい目にあった」という意味の解説がよくあります。
ポルトガルの世界遺産になっているある修道院に行ったとき、教会に安置されたポルトガル王族の棺があって、その大理石のレリーフがごっそりとはぎ取られているのを見たことがあります。ガイドさんによるとナポレオン軍が持っていったとのことでした。もちろん現在は行方不明です。ルーブル美術館の『カナの婚礼』とは違って、全く無名の職人の無名の作品です。こういった例がたくさんあるのだと想像できます。
略奪文化財・美術品ということで、イギリスとフランスの例を取り上げましたが、19世紀から20世紀にかけて植民地や保護領をもった国や、外国に出て行って戦争をして勝った国には、美術品強奪の歴史があります。ドイツもそうですが、日本も朝鮮半島を併合した歴史があります(1910-1945)。1965年の日韓基本条約には、韓国から日本に持ち込まれた美術品の返却が盛り込まれました。このあたりは、Wikipediaの「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」に詳しい解説があります。
仏の略奪美術品、ベナンに返却へ
はじめの方に紹介した「大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム。2021年11月25日 21:00~21:45)で、
とありました。この話が具体的に進み出しました。パリのケ・ブランリ美術館が所蔵するアフリカ美術・26点の返還です。2021年10月末の新聞報道を引用します。
こういった文化財は "民族の誇り" であり、民族の歴史を知り、民族のアイデンティティーの確立に重要でしょう。それは国家としての一体感を醸成するのに役立ちます。しかし記事にあるように現・ベナンの若者は、こういった文化遺産を全く知らずに育ってしまったわけです。文化財の略奪は単にモノの所在が移動しただけではありません。民族を破壊する行為である。そう感じます。さらに記事では、略奪美術品の一般状況についての解説がありました。
最後の一文が痛烈ですね(ちなみにサボワ教授はフランス人です)。我々は "本当のことを知らされていない被害者" にならないようにしたいものです。
ピカソ
ところで記事にあったように、マクロン大統領はパリのケ・ブランリ美術館に所蔵されている美術品、26点をベナン(旧・ダホメ王国)に返却することを表明しました。このケ・ブランリ美術館とは、セーヌ河のほとりにある美術館で(2006年開館)、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有文化の文化遺産、美術品が展示されています。
ここの収蔵品の多くは1937年設立の人類博物館の所蔵品であり、その人類博物館の前身は1882年に設立されたトロカデロ民族誌博物館です。そして1907年頃、そのトロカデロ民族誌博物館を訪れたアーティストがいます。ピカソです。
ピカソの作品を年代順に分類すると、1907年~1909年は「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれていて、アフリカ固有文化の彫刻の影響が顕著です。有名な例で『アヴィニョンの女たち』の右2人の女性の表現です。
ピカソだけでなく、マティスやモディリアーニにもアフリカ彫刻の影響が見られます。次の画像はバーンズ・コレクション(No.95 参照)の "Room 22 South Wall" ですが、ピカソとモディリアーニとアフリカ彫刻が展示されています。アルバート・バーンズ博士(1872-1951)はピカソやモディリアーニと同時代人です。20世紀初頭のパリのアーティストたちがアフリカ彫刻からインスピレーションを得たことを実感していたのでしょう。
ピカソ作品と旧・ダホメ王国の文化財が直接の関係を持っているというわけではありません。ただ当時は、アフリカの文化財が "略奪" や "正規の購入" も含めて大量にパリに運ばれ、美術館に展示されていた。この環境がピカソの一連の作品(を始めとする芸術作品)を生み出したわけです。我々はピカソの「アフリカ彫刻の時代」の作品を鑑賞するとき、なぜこのような作品が生まれたのかの歴史を思い出すべきなのだと思います。
エルギン・マーブル
まず始めに No.319 のパルテノン神殿のフリーズの話を復習すると次の通りです。
| 1800年、イギリスの外交官、エルギン伯爵がイスタンブールに赴任した。彼はギリシャのパルテノン神殿に魅了された。当時ギリシャはオスマン・トルコ帝国領だったので、エルギン伯はスルタンに譲渡許可を得てフリーズを神殿から削り取り、フリーズ以外の諸彫刻もいっしょに英国へ送った。 | |
| 数年後、帰国したエルギン伯はそれらをお披露目する。芸術品は大評判となるが、エルギン伯の評判はさんざんだった。「略奪」と非難されたのだ。非難の急先鋒は "ギリシャ愛" に燃える詩人バイロンで、伯の行為を激しく糾弾した。 | |
| 非難の嵐に嫌気のさしたエルギン伯は、1816年、フリーズを含む所蔵品をイギリス政府に売却した。展示場所となった大英博物館はそれらを「エルギン・マーブル(Elgin Marble)」、即ち「エルギン伯の大理石」という名称で公開し、博物館の目玉作品として今に至る。 |
-79758.jpg)
|
パルテノン神殿のフリーズ - 大英博物館 - |
(Wikimedia Commons) |
| 実は、古代ギリシャ・ローマの彫像や浮彫りは驚くほど極彩色で色づけされていたことが以前から知られていた。わずかながら色が残存していたからだ。大英博物館のフリーズにも彩色の痕跡が残っていた。 | |
| オランダ出身でイギリスに帰化した画家・アルマ=タデマは、大英博物館に通い詰め、フリーズの彩色の痕跡を調査し、それをもとに一つの作品を仕上げた。それが「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」(1868)である。 |

|
ローレンス・アルマ=タデマ 「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」(1868) |
(Pheidias and the Frieze of the Parthenon, Athens) 72.0.cm×110.5cm (バーミンガム市立美術館) |
| ところが1930年代、大英博物館の関係者が大理石の表面を洗浄し、彩色を落とし、白くしてしまった。彫刻は白くあるべきという、誤った美意識による。このため大理石の本来の着色は二度と再現できなくなった。「エルギン・マーブル事件」と呼ばれる大スキャンダルである。 | |
| ギリシャはパルテノン神殿のフリーズを返還するようにイギリスに要求し続けているが、イギリスは拒否したままである。しかたなくギリシャはアテネのアクロポリス博物館にレプリカを展示している。 | |
| アルマ=タデマの「フェイディアスとパルテノン神殿のフリーズ」は、今となってはパルテノン神殿の建設当時の姿を伝える貴重な作品になってしまった。 |
大英博物館が所蔵する略奪美術品・略奪文化財はエルギン・マーブルだけではありません。エジプト、メソポタミアの文化財の多くがそうです。このエジプト・メソポタミアのコレクションを築いた人物の話が、NHKのドキュメンタリー番組でありました。それを紹介します。
大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション
NHK BSプレミアムで「フランケンシュタインの誘惑 科学史 闇の事件簿」と題するドキュメンタリーのシリーズが放映されています。その2021年11月25日の放送は、
大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション
と題するものでした(2021年11月25日 21:00~21:45)。内容は、大英博物館(British Museum)のエジプト・コレクションに焦点を当て、その収集(略奪)の経緯を追ったものした。以降、番組の概要を紹介します。
大英博物館のエジプト・コレクションは総数が10万点以上で、世界最大級です。ミイラだけでも150点以上あります。このコレクションのうちの4万点を集めたのが、大英博物館の考古学者、ウォーリス・バッジ(Wallis Budge。1857-1934)でした。バッジは大英博物館の歴史上、最も多くの文化遺産を収集した人物と言われています。
彼の収集方法はもちろん違法で、嘘、賄賂、脅しなどで盗掘品を買い漁ったものでした。収集品の中で最も貴重なのが "死者の書" の最高傑作といわれる「アニのパピルス」ですが、これもエジプト当局を出し抜き、無許可で英国に持ち出したものです。
1882年、英国はエジプトを占領し、保護国にします。1886年、バッジは29歳でエジプト乗り込みました。彼は 150ポンド(現在の日本円で約300万円の価値)の資金を大英博物館から託されていました。
当時のエジプトでは、1880年5月19日に公布された遺跡や遺物に関する法令で、「エジプト考古学に関わるすべての文化遺産の持ち出しを絶対に禁止する」と決められていました。文化遺産を持ち帰るヨーロッパ人が後を絶たなかったためです。バッジに面会した英国総領事のイブリン・ベアリング(Evelyn Baring)も、エジプトの文化遺産を英国に持って帰らないようバッジにクギをさし、「エジプトの占領が歴史的な遺産を盗む口実になってははらない」と告げました。
しかし、バッジは文化遺産の買い付けに走ります。持ち前の語学力を武器に情報収集を行い、また、古代エジプト文字も読めたバッジは審美眼にもたけていました。そして現地のエジプト人が盗掘した文化遺産を次々と買い漁っていきました。盗掘品と知りながら購入する行為はもちろん違法ですが、盗掘人にもメリットがありました。盗掘品をエジプト当局に見つかると、没収されるか二束三文で買い上げられます。バッジに売る方が儲かります。
バッジはエジプト当局の監視をかいくぐり、イギリス軍と交渉して文化遺産を軍用貨物として英国に送りました。軍用貨物となると誰も検査できません。バッジは英国総領事・ベアリングの指示を全く無視したわけです。この初めてのエジプト行きでバッジは1500点もの文化遺産を持ち帰りました。
1887年、バッジは再びエジプトに向かいます。後に「アニのパピルス」と呼ばれる "死者の書" を手に入れるためです。番組のナレーションを紹介します。
|
しかしバッジは警告を無視します。バッジは到着の数日後、盗掘集団の案内でパピルスの巻物が発見された墓を訪れました。そこにあったのが「アニのパピルス」です。アニという人物に捧げられた死者の書で、完全な状態で残っていました。バッジはそれを墓から持ち出しました。つまり、これまでは盗掘品を買い取っていただけでしたが、ついに盗掘に手を染めたのです。
|
バッジはまたしてもイギリス軍に託しで持ち出すことに成功しました。
たった2度のエジプト行きで盗掘集団とのネットワークを築いたバッッジは、メソポタミアでも同様の手口で文化遺産を収集していきました。
バッジの行為は英国国内でも批判が噴出しました。「大英博物館のために働く無節操なコレクター」と新聞は書きました。バッジ批判の急先鋒はエジプト考古学の父といわれるフリンダーズ・ピートリーでした。彼はバッジを告発する手紙を考古学会に送ります。しかし、大英博物館の理事会メンバーの多くが政府の高官でした。政府はバッジの行為を把握し、承認していたのです。告発はスルーされました。
1894年、バッジは37歳で大英博物館のエジプト・アッシリア部長に昇進し、その後もコレクションを充実させます。そして67歳で退官するまでに、エジプト関連の文化遺産を4万点、メソポタミア関連を5万点収集しました。古代エジプトのミイラも、バッジが在職中に 63点が収集されています。

|
アニのパピルス |
(Wikipedia) |
略奪された文化財、美術品を元の国に返還するよう、機運が高まっています。2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表しました。アメリカの聖書博物館も2021年、エジプトに5000点の文化遺産を返還しました。しかしこのような返還はまだ一握り、ごく一部に過ぎません。たとえば大英国博物館は1753年の創設以来、一切の返還要求に応じていません。
以上が「大英博物館 ─ 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム 2021年11月25日)の概要です。大英博物館を訪れると、有名なロゼッタ・ストーンに目を引かれ、巨大なアッシリアの彫像、大量のエジプトのミイラに驚きます。そういった古代文明を知ることは大切な経験ですが、それと同時に英国の略奪の歴史も知っておくべきでしょう。歴史の勉強としては、それもまた重要です。
ルーブル美術館
イギリスだけでなく、フランスのルーブル美術館も略奪美術品で有名です。ここの特色は、19世紀初頭のナポレオン戦争でナポレオンが持ち帰った文化財・美術品があることです。つまり、エジプトのみならずヨーロッパ各国から略奪した美術品がある。特にイタリアです。2021年6月9日の New York Times に、
The masterpieces that Napoleon stole, and how some went back(ナポレオンが略奪した芸術作品と、その一部の返却経緯)
と題するコラム記事が掲載されました。この記事の一部を試訳とともに掲げます。
|
ヴェロネーゼの『カナの婚礼』は、677cm × 994cm という巨大さで、ルーブル美術館の最大の絵画と言われています。この絵はもともとヴェネチアのサン・ジョルジョ・マッジョーレ教会の食堂に飾られていましたが、ナポレオン軍が剥奪しました。あまりに巨大なので、カンヴァスを水平にいくつかに切断し、それぞれをカーペットを丸めるようにしてフランスに持ち帰り、再び縫合しました。これだけでもカンヴァスの損傷があったと思われます。

|
ヴェロネーゼ(1528-1588) 「カナの婚礼」(1563) |
ルーブル美術館 |
|
しかしナポレオンは結局のところ "敗北" し、戦後処理の中で略奪美術品も返却されます。「ラオコーン」もその一つです。しかし返却されたのは全部ではありませんでした。
|
|
ナポレオンの強奪美術品がルーブル美術館でだけでなくフランス各地に分散されたのは、返還交渉を難しくするためと言われています。
|
話は変わりますが、以前、イタリア対フランスのサッカーのナショナルチームの試合があり、イタリアが勝った時の様子を特派員がレポートしたテレビ番組を見たことがあります。何の試合かは忘れました。ワールドカップのヨーロッパ予選だったか、ヨーロッパ国別選手権だったか、とにかく重要な試合です。これにイタリアが勝ったときの北イタリアの都市(ミラノだったと思います)の街の様子が放映されました。街頭に繰り出した人々が口々に叫んでいたのは、
| フランスには勝った。次はモナ・リザを取り戻すぞ!」 |
というものです。良く知られているように、ダ・ヴィンチは最後の庇護者であるフランスのフランソワ1世のもとで亡くなったので、手元にあったモナ・リザがフランスに残されました。ダ・ヴィンチの遺品の "正式の" 相続権者が誰かという問題はあると思いますが、少なくともモナ・リザはフランスが強奪したものではありません。
しかし、フランスに勝ったことで熱狂し街頭に繰り出したイタリアの人々は「次はモナ・リザを取り戻すぞ!」なのですね。テレビを見たときにはその理由がわかりませんでした。しかしイタリアの美術品がフランスに強奪された歴史を知ると、あのような人々の叫びもわかるのです。
イタリアだけではありません。スペインやポルトガルに団体で旅行に行くと、現地のガイドさんが各種の文化遺産(教会、修道院、宮殿など)を案内してくれます。そこでは「ナポレオンにはひどい目にあった」という意味の解説がよくあります。
ポルトガルの世界遺産になっているある修道院に行ったとき、教会に安置されたポルトガル王族の棺があって、その大理石のレリーフがごっそりとはぎ取られているのを見たことがあります。ガイドさんによるとナポレオン軍が持っていったとのことでした。もちろん現在は行方不明です。ルーブル美術館の『カナの婚礼』とは違って、全く無名の職人の無名の作品です。こういった例がたくさんあるのだと想像できます。
略奪文化財・美術品ということで、イギリスとフランスの例を取り上げましたが、19世紀から20世紀にかけて植民地や保護領をもった国や、外国に出て行って戦争をして勝った国には、美術品強奪の歴史があります。ドイツもそうですが、日本も朝鮮半島を併合した歴史があります(1910-1945)。1965年の日韓基本条約には、韓国から日本に持ち込まれた美術品の返却が盛り込まれました。このあたりは、Wikipediaの「朝鮮半島から流出した文化財の返還問題」に詳しい解説があります。
仏の略奪美術品、ベナンに返却へ
はじめの方に紹介した「大英博物館 ── 世界最大の泥棒コレクション」(NHK BSプレミアム。2021年11月25日 21:00~21:45)で、
2017年、フランスのマクロン大統領がアフリカのベナン共和国に文化財を返還する方針を発表
とありました。この話が具体的に進み出しました。パリのケ・ブランリ美術館が所蔵するアフリカ美術・26点の返還です。2021年10月末の新聞報道を引用します。
|

|
ベナン |

|
ダホメ王国(現・ベナン)の王様などをかたどった木像 |

|
玉座 |

|
王宮からフランスに持ち帰られ、展示されている扉 |
いずれも2021年10月27日、パリのケ・ブランリ美術館、疋田多揚 撮影 |
こういった文化財は "民族の誇り" であり、民族の歴史を知り、民族のアイデンティティーの確立に重要でしょう。それは国家としての一体感を醸成するのに役立ちます。しかし記事にあるように現・ベナンの若者は、こういった文化遺産を全く知らずに育ってしまったわけです。文化財の略奪は単にモノの所在が移動しただけではありません。民族を破壊する行為である。そう感じます。さらに記事では、略奪美術品の一般状況についての解説がありました。
|
最後の一文が痛烈ですね(ちなみにサボワ教授はフランス人です)。我々は "本当のことを知らされていない被害者" にならないようにしたいものです。
ピカソ
ところで記事にあったように、マクロン大統領はパリのケ・ブランリ美術館に所蔵されている美術品、26点をベナン(旧・ダホメ王国)に返却することを表明しました。このケ・ブランリ美術館とは、セーヌ河のほとりにある美術館で(2006年開館)、アフリカ、アジア、オセアニア、南北アメリカの固有文化の文化遺産、美術品が展示されています。
ここの収蔵品の多くは1937年設立の人類博物館の所蔵品であり、その人類博物館の前身は1882年に設立されたトロカデロ民族誌博物館です。そして1907年頃、そのトロカデロ民族誌博物館を訪れたアーティストがいます。ピカソです。
ピカソの作品を年代順に分類すると、1907年~1909年は「アフリカ彫刻の時代」と呼ばれていて、アフリカ固有文化の彫刻の影響が顕著です。有名な例で『アヴィニョンの女たち』の右2人の女性の表現です。

|
パブロ・ピカソ(1881-1973) 「アヴィニョンの女たち」(1907) |
ニューヨーク近代美術館 |
ピカソだけでなく、マティスやモディリアーニにもアフリカ彫刻の影響が見られます。次の画像はバーンズ・コレクション(No.95 参照)の "Room 22 South Wall" ですが、ピカソとモディリアーニとアフリカ彫刻が展示されています。アルバート・バーンズ博士(1872-1951)はピカソやモディリアーニと同時代人です。20世紀初頭のパリのアーティストたちがアフリカ彫刻からインスピレーションを得たことを実感していたのでしょう。

|
バーンズ・コレクション Room 22 South Wall |
アフリカの彫刻とモディリアーニとピカソが展示されている。モディリアーニは「白い服の婦人」と「横向きに座るジャンヌ・エビュテルヌ」、その内側にピカソがあって「女の頭部」と「男の頭部」である(下図)。アフリカの彫刻(仮面、立像)とこれらの類似性を示している。 |

|
ピカソの「女の頭部」(左)と「男の頭部」(右) |
(バーンズ・コレクション) |
-a72b3.jpg) 
|
展示されている彫刻のうちの2つの仮面と、2つの立像。 |
(バーンズ・コレクション) |
ピカソ作品と旧・ダホメ王国の文化財が直接の関係を持っているというわけではありません。ただ当時は、アフリカの文化財が "略奪" や "正規の購入" も含めて大量にパリに運ばれ、美術館に展示されていた。この環境がピカソの一連の作品(を始めとする芸術作品)を生み出したわけです。我々はピカソの「アフリカ彫刻の時代」の作品を鑑賞するとき、なぜこのような作品が生まれたのかの歴史を思い出すべきなのだと思います。
2021-12-25 08:28
nice!(0)
No.269 - アンドロクレスとライオン [歴史]
No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で古代ローマの円形闘技場で行われた剣闘士の闘技会のことを書いたのですが、その時に思い出した話がありました。今回は No.203 の補足としてその話を書きます。
まず No.203 の復習ですが、紀元2世紀ごろのローマ帝国の闘技会はふつう午後に行われ、午前中にはその "前座" が開催されました。1日のスケジュールは次のようです。
No.203 では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(河出書房新社 2010)を引用してそれぞれの様子を紹介しました。この本は最新のローマ研究にもとづき、紀元115年のトラヤヌス帝の時代の首都ローマの1日を実況中継風に描いたものです。その中の野獣狩り・公開処刑のところで思い出した話がありました。「アンドロクレスとライオン」という話です。それを以下に書きます。
アンドロクレスとライオンの話
「アンドロクレスとライオン」は、手短かに要約すると次のような話です。
これは、いわゆる「動物の恩返し」ですね。この手の話は日本の民話や昔話にもいろいろあります。「鶴の恩返し」が有名ですが「キツネの恩返し」という話もありました。おそらく世界中にこのタイプの説話があるのでしょう。
「動物の恩返し寓話」として「アンドロクレスとライオン」を考えると、その教訓は「ライオンでさえ人から親切にしてもらったことを忘れないのだから、人は他人から受けた恩を忘れてはいけない」ということでしょう。ないしは「どんな相手に対しても良いことをすれば、それは何らかの利得となって返ってくる」でしょう。
この話の原典は、紀元2世紀の古代ローマの文法学者で著述家、アウルス・ゲッリウスが著した『アッティカの夜』(アッティカ夜話)の一節です。そして原典では寓話やフィクションではなく、実話として書かれているのです。そこで、以下にその原典を引用してみます。
アンドロクレスとライオン(『アッティカの夜』より)
『アッティカの夜』はゲッリウスがギリシャ滞在中に執筆を始めた書物で、彼が読んだり聞いたりした数々の事項が列記されています。内容も文法、哲学、歴史、逸話とさまざまです。ちなみに "アッティカ" とはギリシャのアテネ周辺を指す地名です。この本の第5巻 14節が「アンドロクレスとライオン」の話です。話は次のように始まります。
ここまでが "前置き" です。ここに出てくるアピオンという人物は、紀元1世紀のアレクサンドリア(エジプト)に在住のギリシャ人で、文法学者・ホメロス研究家でした。そのアピオンの著書『エジプト誌』は散逸して現存しません。しかし、ゲッリウスがそこから引用した文が現存している。『アッティカの夜』にはこういった例が多々あり、そういう意味で貴重な本なのです。
ゲッリウスが伝える「アンドロクレスとライオン」の話は、闘技場でアンドロクレスとライオンが再会する前半と、過去にアンドロクレスがライオンを助けた話の後半に分かれています。その前半が以下です。
アンドロクレスとライオン(前半)
アンドロクレスとライオン(後半)
ライオンがアンドロクレスを認識し、近づいて身をすり寄せたのは、過去にアンドロクレスがそのライオンを助けたからでした。後半はその話です。冒頭に「ガイウス・カエサル」という名が出てきますが、Wikipedia によると、これはおそらく第3代ローマ帝国皇帝・カリグラ(在位37年~41年)だろう、とのことです。
アンドロクレスが語るライオンを助けた話は以上ですが、その後アンドクレスとライオンがどうなったかで、全体の話が終わります。
イソップ/バーナード・ショー/ハリウッド映画
この「アンドロクレスとライオン」の話は、後世にイソップ寓話集に取り入れられました。イソップ寓話集を編纂したペリーによる、ペリー・インデックス:563の「羊飼いとライオン」です。
さらに現代になると、イギリスの作家、ジョージ・バーナード・ショーが『アンドロクレスとライオン』という戯曲を創作しました。ここではアンドロクレスはギリシャ人の仕立屋で、キリスト教徒であったため宗教迫害でライオンの餌食になりかけた、というストーリーになっています。もちろん、オリジナルの話は紀元1世紀であり、キリスト教が広まる以前です。
そしてこのショーの戯曲を原作として『アンドロクレスと獅子』というハリウッド映画が1952年に制作されました。
以上のように「アンドロクレスとライオン」は延々と語りつがれてきたということになります。よくある「動物の恩返し寓話」に思えるのに、この話には文豪やハリウッドの映画人までを引き付ける魅力があるのでしょう。
実話か
「アンドクレスとライオン」に戻ります。この話は、アレクサンドリア在住のホメロス学者、アピオンがローマで実際に体験した話を『エジプト誌』に書き、それをゲッリウスが『アッティカの夜』に転載したという形になっています。あくまで実話という立場で書かれています。
しかし本当に実話なのか、疑問が多々あります。話を良く読むと、次のような "不審点" が自然と浮かびます。
というような不審点です。直感的にはこの話はフィクションと思えます。百歩譲ったとしても、闘技場で丸腰の人間を襲わなかったライオンがいて、それが話の発端になった創作ではと思います。
ライオン、"クリスティアン" の物語
とは言うものの、実話だという可能性もあるわけです。アンドロクレスはエジプトでライオンと "何らかの交流" があり、ローマの闘技場でそのライオンと再会し、ライオンはアンドロクレスを認識したという可能性です。
そして "不審点" としてあげた最後の点、つまり「かつての恩人をライオンが認識した」ということに関して、実際に現代にそのようなことがあったことを知りました。
ゲッリウス著・大西英文訳『アッティカの夜』は京都大学学術出版会の西洋古典叢書の中の1冊ですが、この西洋古典叢書の「月報 119」に和歌山県立医科大学教授の西村賀子氏が次の文章を書いています。
補足しますと「ケニアの野生保護活動家の援助を受けながら自然の中に放した」と書いてある "野生保護活動家" とは、『野生のエルザ』(ノンフィクション作品。後に映画。原題 "Born Free")を書いたジョイ・アダムゾンの夫であるジョージ・アダムソンです。彼はケニアで自然保護区の管理をしており、そこに野生復帰のリハビリをしたクリスティアンを放したわけです。アダムソン夫妻はライオンのエルザを野生に戻したことがあり、その経験も生きたのでしょう。
実際に YouTube の動画を見ると、2人の青年がクリスティアンと再会する場面は確かに感動的です。そこでのクリスティアンの振る舞いは、まるで人にじゃれつく猫のようで、こういう姿を見るとライオンも "猫科" の動物だと感じてしまいます。この「実話・クリスティアン」で分かることは
ということです。これはアンドロクレスのライオンとはシチュエーションが少々違います。しかしライオンの認識能力を示す話であり、「アンドロクロスとライオン」の話の不審点の一つが少し緩和された気がします。一つだけですが。
野獣狩りと猛獣刑
「アンドロクロスとライオン」の話が実話かどうかという議論はひとまず置いて、この話から判明することを考えてみたいと思います。この物語の根幹は、
というところにあり、これが実話かどうかが疑わしいわけです。もちろんその他、ライオンの洞穴で刺を抜いてやったというのも怪しいし、3年間の共同生活も疑わしい。しかし根幹のところはさておき、この物語の背景・バックグラウンドになっているのは次のような事項です。
仮に「アンドロクレスとライオン」の根幹部分が創作物語だとしても、創作者はその背景となっている ① ~ ④ のような事項を出来るだけリアルに書いたはずです。常識的に考えて根幹部分は「驚くべき話、一見、眉唾ものの話」なのだから、少なくとも話の背景は紀元1世紀の誰もにとって自然なはずであり、そうでないと全体が完全に嘘っぽくなってしまいます。「真実は細部に宿る」というわけです。
最初に書いたように、No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』によって、古代ローマの円形闘技場で行われた「野獣狩り」や「公開処刑」の様子を紹介しました。それらは最新の "ローマ研究" にもとづく著者の想像だったのですが、紀元1世紀の人物が書いた「アンドロクレスとライオン」の話と併せて考えると、闘技場の様子が極めてリアルに感じられたのでした。
まず No.203 の復習ですが、紀元2世紀ごろのローマ帝国の闘技会はふつう午後に行われ、午前中にはその "前座" が開催されました。1日のスケジュールは次のようです。
| 野獣狩り(午前) ライオン、ヒョウ、クマ、鹿、ガゼル、ダチョウなどを闘獣士が狩る(殺す)ショー。猛獣の中には小さいときから人間を襲うように訓練されたものあり、そういう猛獣と闘獣士は互角に戦った。 | |
| 公開処刑(午前) 死刑判決を受けた罪人の公開処刑。処刑の方法はショーとしての演出があった。罪人が猛獣に喰い殺される "猛獣刑" もあった。 | |
| 闘技会(午後) 剣闘士同士の試合(殺し合い)。剣闘士には、武器と防具、戦い方によって、魚剣闘士、投網剣闘士、追撃剣闘士などの様々な種類があった。 |
No.203 では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(河出書房新社 2010)を引用してそれぞれの様子を紹介しました。この本は最新のローマ研究にもとづき、紀元115年のトラヤヌス帝の時代の首都ローマの1日を実況中継風に描いたものです。その中の野獣狩り・公開処刑のところで思い出した話がありました。「アンドロクレスとライオン」という話です。それを以下に書きます。
アンドロクレスとライオンの話
「アンドロクレスとライオン」は、手短かに要約すると次のような話です。
|
|
「動物の恩返し寓話」として「アンドロクレスとライオン」を考えると、その教訓は「ライオンでさえ人から親切にしてもらったことを忘れないのだから、人は他人から受けた恩を忘れてはいけない」ということでしょう。ないしは「どんな相手に対しても良いことをすれば、それは何らかの利得となって返ってくる」でしょう。
この話の原典は、紀元2世紀の古代ローマの文法学者で著述家、アウルス・ゲッリウスが著した『アッティカの夜』(アッティカ夜話)の一節です。そして原典では寓話やフィクションではなく、実話として書かれているのです。そこで、以下にその原典を引用してみます。
アンドロクレスとライオン(『アッティカの夜』より)
『アッティカの夜』はゲッリウスがギリシャ滞在中に執筆を始めた書物で、彼が読んだり聞いたりした数々の事項が列記されています。内容も文法、哲学、歴史、逸話とさまざまです。ちなみに "アッティカ" とはギリシャのアテネ周辺を指す地名です。この本の第5巻 14節が「アンドロクレスとライオン」の話です。話は次のように始まります。
なお、以下に引用する日本語訳の人名はラテン語読みで "アンドロクルス" となっています。また、段落を増やしたところや漢数字を算用数字にしたところ、ルビを追加したところがあります。
|
ここまでが "前置き" です。ここに出てくるアピオンという人物は、紀元1世紀のアレクサンドリア(エジプト)に在住のギリシャ人で、文法学者・ホメロス研究家でした。そのアピオンの著書『エジプト誌』は散逸して現存しません。しかし、ゲッリウスがそこから引用した文が現存している。『アッティカの夜』にはこういった例が多々あり、そういう意味で貴重な本なのです。
余談ですが、"アレクサンドリア"、"書物の散逸" と聞いて連想する話があります。No.27「ローマ人の物語(4)帝国の末路」で塩野七生さんの本から引用したように、ローマ帝国では4世紀のキリスト教の国教化にともなって図書館が閉鎖され、書物が散逸しました。図書館の蔵書が "異教の本" だったからです。この図書館の一つが有名なアレクサンドリアの図書館でした。アピオンの著書『エジプト誌』の散逸が図書館の閉鎖と関係あるかは知りませんが、とにかくローマ帝国の末期には文化の破壊と断絶が起こり、残った書物もあるが、失われたものも多い。そういうことかと理解しました。
ゲッリウスが伝える「アンドロクレスとライオン」の話は、闘技場でアンドロクレスとライオンが再会する前半と、過去にアンドロクレスがライオンを助けた話の後半に分かれています。その前半が以下です。
アンドロクレスとライオン(前半)
|
アンドロクレスとライオン(後半)
ライオンがアンドロクレスを認識し、近づいて身をすり寄せたのは、過去にアンドロクレスがそのライオンを助けたからでした。後半はその話です。冒頭に「ガイウス・カエサル」という名が出てきますが、Wikipedia によると、これはおそらく第3代ローマ帝国皇帝・カリグラ(在位37年~41年)だろう、とのことです。
|
アンドロクレスが語るライオンを助けた話は以上ですが、その後アンドクレスとライオンがどうなったかで、全体の話が終わります。
|
.jpg)
|
ジャン = レオン・ジェローム(1824-1904) 「アンドロクレス」(1902頃) |
No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で、ローマの闘技会を描いたジェロームの絵を引用したが(「差し下ろされた親指」と「皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち」)、そのジェロームはアンドロクレスの絵も描いている。晩年の78歳頃の作品で、No.203 の2作(30~40歳台)と比べると筆致の衰えを感じるが、ゲッリウスの「アッティカの夜」の場面を忠実に表現している。画像は Wikimedia Commons より引用した。 |
(アルゼンチン国立美術館) |
イソップ/バーナード・ショー/ハリウッド映画
この「アンドロクレスとライオン」の話は、後世にイソップ寓話集に取り入れられました。イソップ寓話集を編纂したペリーによる、ペリー・インデックス:563の「羊飼いとライオン」です。
ちなみにイソップ(アイソーポス)は紀元前6世紀ごろのギリシャ人ですが、イソップ寓話というのは、イソップ自身が作った(とされる)寓話や、ギリシャの民話、後世に作られた寓話などの集大成です。イソップ寓話集は「イソップ風の寓話を集めたもの」です。
さらに現代になると、イギリスの作家、ジョージ・バーナード・ショーが『アンドロクレスとライオン』という戯曲を創作しました。ここではアンドロクレスはギリシャ人の仕立屋で、キリスト教徒であったため宗教迫害でライオンの餌食になりかけた、というストーリーになっています。もちろん、オリジナルの話は紀元1世紀であり、キリスト教が広まる以前です。
そしてこのショーの戯曲を原作として『アンドロクレスと獅子』というハリウッド映画が1952年に制作されました。
以上のように「アンドロクレスとライオン」は延々と語りつがれてきたということになります。よくある「動物の恩返し寓話」に思えるのに、この話には文豪やハリウッドの映画人までを引き付ける魅力があるのでしょう。
実話か
「アンドクレスとライオン」に戻ります。この話は、アレクサンドリア在住のホメロス学者、アピオンがローマで実際に体験した話を『エジプト誌』に書き、それをゲッリウスが『アッティカの夜』に転載したという形になっています。あくまで実話という立場で書かれています。
しかし本当に実話なのか、疑問が多々あります。話を良く読むと、次のような "不審点" が自然と浮かびます。
| ゲッリウスが引用しているアピオンは著書で「この話は聞いたり読んだりしたものではなく、ローマで自分の目で見た」と書いている。伝聞ではなく、自ら体験した実話だと強調しているところが、かえって怪しい。 | |
| ゲッリウスはアピオンを評して「話が饒舌にすぎ、極端な自己宣伝家」と言っている。「アンドクレスとライオン」の話も "誇大に歪められている" のではないか。 | |
| アンドロクレスが語る「ライオンを助けた経緯」が詳細すぎる。その話を書板(木、または石)に記述してローマ市民に公開したとなっているが、そんなことが本当にあるのだろうか。アピオンは少なくとも尾鰭をつけて大げさに書いたのではないか。 | |
| 傷ついて住処の洞穴に戻ってきたライオンは、初めから人間(アンドロクレス)に馴れ馴れしくしている。野生動物の行動とも思えない。アンドロクレスがライオンから肉をもらいつつ、3年も洞穴で生活したというのも信じがたい。 | |
| アンドロクレスがライオンと別れてから闘技場で再会するまでの経過時間が書いていないが、たとえば1年だとすると、1年間離れたあとでライオンが人間の顔を覚えているのだろうか。 |
というような不審点です。直感的にはこの話はフィクションと思えます。百歩譲ったとしても、闘技場で丸腰の人間を襲わなかったライオンがいて、それが話の発端になった創作ではと思います。
ライオン、"クリスティアン" の物語
とは言うものの、実話だという可能性もあるわけです。アンドロクレスはエジプトでライオンと "何らかの交流" があり、ローマの闘技場でそのライオンと再会し、ライオンはアンドロクレスを認識したという可能性です。
そして "不審点" としてあげた最後の点、つまり「かつての恩人をライオンが認識した」ということに関して、実際に現代にそのようなことがあったことを知りました。
ゲッリウス著・大西英文訳『アッティカの夜』は京都大学学術出版会の西洋古典叢書の中の1冊ですが、この西洋古典叢書の「月報 119」に和歌山県立医科大学教授の西村賀子氏が次の文章を書いています。
|
補足しますと「ケニアの野生保護活動家の援助を受けながら自然の中に放した」と書いてある "野生保護活動家" とは、『野生のエルザ』(ノンフィクション作品。後に映画。原題 "Born Free")を書いたジョイ・アダムゾンの夫であるジョージ・アダムソンです。彼はケニアで自然保護区の管理をしており、そこに野生復帰のリハビリをしたクリスティアンを放したわけです。アダムソン夫妻はライオンのエルザを野生に戻したことがあり、その経験も生きたのでしょう。
実際に YouTube の動画を見ると、2人の青年がクリスティアンと再会する場面は確かに感動的です。そこでのクリスティアンの振る舞いは、まるで人にじゃれつく猫のようで、こういう姿を見るとライオンも "猫科" の動物だと感じてしまいます。この「実話・クリスティアン」で分かることは
少なくとも幼少期の1年を人間に育てられたライオンは、1年間離れていても育ての親を認識できて、愛情を示す
ということです。これはアンドロクレスのライオンとはシチュエーションが少々違います。しかしライオンの認識能力を示す話であり、「アンドロクロスとライオン」の話の不審点の一つが少し緩和された気がします。一つだけですが。

|
2人の青年、アンソニー・バーク(Anthony Bourke)、ジョン・レンダル(John Rendall)と再開して飛びつくクリスティアン。左はジョージ・アダムソン(George Adamson)。まだタテガミがないクリスティアンは幼獣であり、このような無邪気な行動はその特徴だという。 |
野獣狩りと猛獣刑
「アンドロクロスとライオン」の話が実話かどうかという議論はひとまず置いて、この話から判明することを考えてみたいと思います。この物語の根幹は、
ローマの闘技場でかつての恩人と再会したライオンが、その恩人を認識し、愛情を示した
というところにあり、これが実話かどうかが疑わしいわけです。もちろんその他、ライオンの洞穴で刺を抜いてやったというのも怪しいし、3年間の共同生活も疑わしい。しかし根幹のところはさておき、この物語の背景・バックグラウンドになっているのは次のような事項です。
| 紀元1世紀ごろにはエジプトにライオンが生息していた(現在はいない)。そのライオンを捕獲してローマに運び、猛獣狩りのショーが行われた。 | |
| ローマの大円形競技場(フォロ・ロマーノの近く)では、ライオンを筆頭とする多数の狂暴そうな猛獣が集められ、剣闘士(闘獣士)がそれと戦う「猛獣狩り」のショーが開催された。 | |
| そのショーと併せて、罪人を猛獣の餌食にする「猛獣刑」も行われた。 | |
| 執政官の経験があり、エジプト総督を勤めた元老院議員(=ローマ帝国では高位の貴族)は、所有していた奴隷が逃亡して捕まると、その逃亡奴隷をショーの余興として猛獣刑にしようとした。 |
仮に「アンドロクレスとライオン」の根幹部分が創作物語だとしても、創作者はその背景となっている ① ~ ④ のような事項を出来るだけリアルに書いたはずです。常識的に考えて根幹部分は「驚くべき話、一見、眉唾ものの話」なのだから、少なくとも話の背景は紀元1世紀の誰もにとって自然なはずであり、そうでないと全体が完全に嘘っぽくなってしまいます。「真実は細部に宿る」というわけです。
最初に書いたように、No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」では、アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』によって、古代ローマの円形闘技場で行われた「野獣狩り」や「公開処刑」の様子を紹介しました。それらは最新の "ローマ研究" にもとづく著者の想像だったのですが、紀元1世紀の人物が書いた「アンドロクレスとライオン」の話と併せて考えると、闘技場の様子が極めてリアルに感じられたのでした。
2019-10-04 17:23
nice!(0)
No.246 - 中世ヨーロッパの奴隷貿易 [歴史]
今回は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。そもそも "奴隷" というテーマは、No.18「ブルーの世界」で青色染料である "藍(インディゴ)" が、18世紀のアメリカ東海岸の奴隷制プランテーションで生産されたことを書いたのが最初でした。
このブログは初回の No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」以来、樹木の枝が伸びるように、連想・関連・追加・補足で次々と話を繋げているので、"奴隷" をテーマにした記事もかなりの数になりました。世界史の年代順に並べると以下の通りです。
◆紀元1~4世紀:ローマ帝国
No.162 - 奴隷のしつけ方
No.203 - ローマ人の "究極の娯楽"
No.239 - ヨークの首なしグラディエーター
◆8世紀~14世紀:ヨーロッパ
No.22 - クラバートと奴隷(1)スラヴ民族
No.23 - クラバートと奴隷(2)ヴェネチア
◆16世紀~17世紀:日本
No.33 - 日本史と奴隷狩り
No.34 - 大坂夏の陣図屏風
◆17世紀:スペイン
No.19 - ベラスケスの「怖い絵」
◆18世紀~19世紀:アメリカ
No.18 - ブルーの世界
No.104 - リンカーンと奴隷解放宣言
No.109 - アンダーソンヴィル捕虜収容所
以降は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた、中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。No.23の「補記2」でイタリア人商人による奴隷貿易の実態を、Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" という項目から訳出しました(日本語版はありせん)。この項目は中世ヨーロッパの奴隷や奴隷制度全般の記述ですが、その第2章が「2.奴隷貿易」で、次のような節の構成になっています。
2. 奴隷貿易
2.1 イタリア商人
2.2 ユダヤ商人
2.3 イベリア半島
2.4 ヴァイキング
2.5 モンゴル人
2.6 イギリス諸島
2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷
2.8 中世終焉期の奴隷貿易
No.23の「補記2」は「2.1 イタリア商人」だけの訳でしたが、今回は2章全体を訳出してみることにします。「2.1 イタリア商人」も再掲します。なお、Wikipedia にある出典への参照や参考文献は省略しました。以下の Wikipedia の引用や参照はすべて2018年11月2日現在のものです。
「中世ヨーロッパの奴隷 : 第2章 奴隷貿易」(Wikipedia) 試訳
2. 奴隷貿易
中世ヨーロッパの奴隷貿易を支配したのはイスラム世界からの要求であった。しかし多くの時期、キリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒に売るのは禁止されていた。840年にヴェネチアとカロリング朝フランク帝国で結ばれたロタール協定で、ヴェネチアは帝国内でキリスト教徒の奴隷を買わないこと、キリスト教徒の奴隷をイスラムに売らないこと約束した。教会もまたキリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒の国へ売ることを禁止した。たとえば、922年のコブレンツ(注)教会会議(the Council)、1102年のロンドン教会会議、1171年のアーマー(注)教会会議などである。
この結果、多くのキリスト教徒の奴隷商人は、非キリスト教地域の奴隷をイスラム圏のスペイン・北アフリカ・中東へと売ることに注力した。そして、教会の規則に縛られていなかった非キリスト教徒の奴隷商人もイスラムの奴隷マーケットに注力した。東ヨーロッパや南部スウェーデンで大量に見つかるアラブのディルハム銀貨は奴隷貿易に使われたものと推測できる。つまり、スラヴ圏からイスラム圏への交易があったことを示している。
2.1 イタリア商人
ローマ教皇・ザカリアス(在位:741-752)の治世の頃までに、ヴェネチア(地図)は奴隷交易での繁栄を確立した。彼らはイタリアやその他の地域から奴隷を買い、アフリカのムーア人に売った。もっともザカリアス自身はローマ外での奴隷交易を禁止したと伝えられている。
ロタール協定によってキリスト教徒の奴隷をイスラムに売ることが禁止されると、ヴェネチア商人はスラブ人やその他、東ヨーロッパの非キリスト教徒の奴隷の大々的な交易に乗り出した。東ヨーロッパから奴隷のキャラバンが、オーストリア・アルプスの山道を超えてヴェネチアに到着した。
ドナウ河畔のザンクト・フローリアンの近くのラッフェルステッテン(注)の通行税の記録(903-906)には、そんな商人たちの記述がある。商人の中にはボヘミアやキエフ公国のスラヴ人自身もいた。彼らはキエフ公国からプシェムシルやクラコフ(注)、プラハ、ボヘミアを経由して来ていた。
記録によると、女の奴隷は1トレミシス金貨(約1.5グラムの金。ディナール金貨の1/3)であり、女よりも圧倒的に数が多い男の奴隷は1サイガ銀貨(トレミシスより価値がかなり落ちる)であった。
宦官(eunch)(注)は非常に貴重であり、この需要に対応するため、他の奴隷市場と同じように "去勢所"(castration house)がヴェネチアに作られた。
ヴェネチアだけが奴隷貿易の拠点だったのではない。南部イタリアの都市も遠隔地からの奴隷獲得を競っていた。ギリシャやブルガリア、アルメニア、そしてスラヴ圏である。9~10世紀にはアマルフィ(地図)が北アフリカへの奴隷輸出の多くを担った。
ジェノヴァ(地図)は12世紀ごろからヴェネチアとともに東地中海での交易を押さえ、また13世紀からは黒海での交易を支配した。彼らはバルト海沿岸の民族やスラヴ人、アルメニア人、チェルケス人、ジョージア(グルジア)人、トルコ人、その他、黒海沿岸やコーカサス地方の民族を中東のイスラム国に売った。ジェノヴァはクリミアからマムルーク朝エジプトへの奴隷貿易を13世紀まで支配したが、東地中海でのヴェネチアの勢力が強大になると、ヴェネチアがとって代わった。
1414年から1423年の間だけで、少なくとも10,000人の奴隷がヴェネチアで取引された。
2.2 ユダヤ商人
長距離を交易するユダヤ人の奴隷商人の記録は、少なくとも西暦492年の昔に遡ることができる。この年、ローマ教皇・ゲラシウス(注)は、テレシナ(注)のユダヤ人の友人の求めに応じて、非キリスト教徒の奴隷をイタリアへ輸入する許可を与えた。ユダヤ人は、6世紀の終わりから7世紀になるとイタリアにおける主要な奴隷商人となり、また、ガリア地方でも活躍した。ローマ教皇・大グレゴリウス(注)はユダヤ人がキリスト教徒の奴隷を保有するのを禁じたが、それはユダヤ教に改宗するのを避けるためであった。ユダヤ商人は9世紀から10世紀までにヨーロッパ大陸全体の奴隷貿易の主要な勢力となった。彼らは "ラダニテ"(注)と呼ばれることがあった。
ユダヤ人はキリスト教国とイスラム世界を行き来して交易できる数少ない集団の一つだった。イブン・フルダーズベ(注)は『諸道と諸国の書』において、南フランスからスペインに至るユダヤ人の交易ルートを記録している。このルートでは、女奴隷、宦官、少年奴隷が、他の商品とともに運ばれた。彼はまた、ユダヤ商人がプラハでスラヴ人奴隷を買ったことも書いている。
リヨン大司教・アゴバール(在位 816-840)の手紙、ルイ敬虔王(注)の布告、845年のモー教会会議(注)での教会法第75番によって、ユダヤ商人のスラヴ人奴隷交易ルートの存在が確認できる。それはアルプスを越えてリヨン(地図)、南フランス、スペインへと至るルートであった。
ヴァレンシュタット(注)の税関の記録(842-843)から、スイスを通る別の交易ルートの存在がわかる。それはセッティモ峠(セプティマー峠)とスプルガ峠(スプリューゲン峠)(地図)を越えてヴェネチアに至り、そこから北アフリカにへと続くルートであった。
10世紀になってドイツのサクソン族の王国の支配者がスラヴ族の奴隷化と奴隷交易に乗り出すようになると、ユダヤ人商人はエルベ河(地図)付近で奴隷を購入し、キャラバンを組んでライン河渓谷に送った。多くの奴隷は、スペインと密接な関係があったヴェルダン(地図)に連れていかれ、去勢され、宦官として売られた。
クリミア(地図)在住のユダヤ人商人は、16世紀から18世紀にかけてのクリミア・ハン国(タタール人国家)の奴隷や捕虜の貿易にとって大変に重要であった。
ユダヤ人はヨーロッパの奴隷貿易において、16世紀から19世紀を頂点として大きな影響力があった。
2.3 イベリア半島
ウマイア朝スペインでは、マムルーク(奴隷の兵士)の供給源として兵役年齢の男の需要が常にあった。
(ロジャー・コリンズ著「中世初期のスペイン」からの引用)
ロジャー・コリンズによると、イベリア半島の奴隷交易におけるヴァイキングの役割は仮説の域を出ない。しかし彼らの略奪行為は明確に記録されている。ヴァイキングによるアンダルシア地方への襲撃は、844年、859年、966年、971年に報告されていて、これらは8世紀半ばから10世紀末に集中したヨーロッパ各地での襲撃の時期と一致する。
イスラム圏スペインは膨大な数の奴隷を輸入し、またイスラム商人やユダヤ商人が他のイスラム世界へ奴隷を輸出する中継地の役割を担った。
アブド・アッラフマーン3世(在位 912-961)の治世下のコルドバ(地図)(ウマイヤ朝イスラム帝国の首都)では、その初期に3,750人の "サカーリバ"、つまりスラヴ人奴隷がいたが、この数は6,087人に増え、最終的には13,750人になった。イブン・ハウカル(注)、イブラヒム・アル = カラウィー、クレモナのリウトプランド司教(注)の記述によると、ヴェルダンのユダヤ商人は去勢の専門技術があり、イスラム圏スペインで大変人気のあった "去勢サカーリバ" として奴隷を売った。
2.4 ヴァイキング
ヴァイキングの時代(793年~約1100年)に北欧からの襲撃者は、遭遇した武力の劣る人々を捕らえて、しばしば奴隷化した。北欧諸国では彼らを "スレール"(古北欧語ではトレール)と呼んだ。スレールはほとんどが西ヨーロッパ人で、フランク人、アングロサクソン人、ケルト人などであった。多くのアイルランドの奴隷は、アイスランドを(ヴァイキングの)植民地にするための探検にかり出された。ヴァイキングは修道院を襲撃し、若くて教育を受けた奴隷を手に入れたが、それはヴェネチアやビザンチン帝国で高値で売れた。8世紀末までにスカンジナビア商人の奴隷取引地は、デンマークのへーゼビュー(地図)やスウェーデンのビルカ(地図)から、東は北方ロシアのスタラヤ・ラドガ(地図)まで広がっていた。
このような交易は9世紀にも続き、スカンジナビア人はさらに奴隷取引地を増やしていった。南西ノルウェーのカウパング(地図)や、スタラヤ・ラドガより南にあるノヴゴロド(地図)、ビザンチン帝国にさらに近いキエフ(地図)である。ダブリンやその他の北西ヨーロッパのヴァイキングの居住地は、捕虜を北へと送る基地として作られた。たとえば、"ラックス谷の人々のサガ" には、スウェーデンのブレン島(地図)の市場で西ヨーロッパからの女奴隷が売られていて、そこにロシア商人が来る様子が描かれている。
ヴァイキングたちはドイツ人、バルチック人、スラヴ人、ラテン人も捕虜にした。10世紀のペルシャの旅行家、イブン・ルスタは、スウェーデンのヴァイキング(ロシアでは "ヴァリャーグ" と呼んだ)がヴォルガ河(地図)流域のスラヴ人を襲撃し、威嚇して奴隷にしたことを記述している。奴隷はしばしばヴォルガ河の交易路を経由して、南方のビザンチンやイスラム商人に売られた。バグダッドのアフマド・イブン・ファドラーン(注)は、この交易路の出発地でヴォルガのヴァイキングがスラヴ人奴隷を中東の商人に売る様子を記述をしている。
フィンランドもヴァイキングの奴隷狩りの標的になった。フィンランドやバルト海沿岸地域の奴隷は中央アジアまで売られていった。
2.5 モンゴル
13世紀におけるモンゴルの進入と征服は、奴隷交易の新たな隆盛をもたらした。モンゴル人は職人や女、子供を奴隷にしてカラコルムやサライ(地図)に連れていき、そこでユーラシア大陸全体へと売った。多くの奴隷がロシアのノヴゴロドの奴隷市場に送られた。
クリミアにいたジェノヴァとベネチアの商人は、キプチャク・ハン国(注)との奴隷取引に携わった。ハージー1世ギレイはキプチャク・ハン国から独立してクリミア・ハン国を建国したが、そのクリミア・ハン国は18世紀に至るまでの長い間、オスマン帝国や中東との大々的な奴隷貿易を続けた。「ステップ草原の刈り取り」と呼ばれた "行事" で、彼らは多数のスラヴ人の農民を奴隷にした。
2.6 イギリス諸島
イギリス諸島(注)では、奴隷は家畜と同じように、国内・国外を問わずに取り引きされる日用品であり、通貨のようなものであった。ウィリアム征服王はイギリスからの奴隷の輸出を禁止し、奴隷交易への国の関与を制限した。
2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷
奴隷取引の主要な流れはイスラム諸国へと向かうものだったが、キリスト教徒もムスリムの奴隷を保有していた。13世紀の南フランスでは、ムスリムの捕虜を奴隷にするのはきわめて一般的だった。
たとえば1248年にムスリムの少女の奴隷がマルセイユ(地図)で売られた記録があるが、これはキリスト教徒の十字軍がセビリア(地図)とその周辺地域を攻略した時期と一致する(注)。この戦勝で地域の多数のムスリムの女性が戦利品として奴隷になり、それはアラブ側の叙事詩、たとえばセビリア攻略の同時代人であった詩人、アル・ルンディの詩に詠われている。。
またキリスト教徒は戦争で捕虜にしたムスリム奴隷を売った。マルタ騎士団は海賊やムスリムの商船を襲撃し、騎士団の拠点は捕らえた北アフリカ人やトルコ人を売る交易の中心になった。マルタ(地図)は18世紀末までも奴隷市場として残った。騎士団が所有するガレー船団のためには1000人の奴隷の乗組員が必要だった。
2.8 中世終焉期の奴隷貿易
ヨーロッパのキリスト教化が進むと、大がかりな奴隷貿易はさらに遠隔地からのものになった。またそれにはキリスト教徒とイスラム教徒の敵対関係が強まったこともあった。たとえばエジプトに奴隷を送るのはローマ教皇によって禁止され、この命令は1317年、1327年、1329年、1338年、最終的には1425年に出されている。というのも、エジプトに送られた奴隷は往々にして兵士となり、元のキリスト教徒の主人と戦う結果になったからである。禁止令が繰り返されたことは、そのような交易が続いていたことと、交易がより好ましくないものになったことを示している。16世紀になるとアフリカ人の奴隷が、ヨーロッパの各民族・各宗派の奴隷にとって代わった。
「文明の中心」と「グローバル経済」
「中世ヨーロッパの奴隷貿易」という Wikipedia の記事を読んで改めて思うのは、中世の文明の中心はイスラム国家だということと、西ユーラシア大陸の全域をカバーするグローバルな交易、の2点です。
この地図には、奴隷という高額商品の買い手がほとんど描かれていませんが、イベリア半島南部の後ウマイヤ朝は買い手でした。首都のコルドバの人口は100万人を越え、当時のヨーロッパ最大の都市です。それよりも大きな奴隷の需要地は、現在のイランから北アフリカを版図とするアッバース朝です。中世ではこの2つのイスラム帝国が文明の中心であり、強大な経済力と軍事力を誇った。Wikipediaの記述でよく分かるのは、その結果として中世ヨーロッパの奴隷貿易があったということです。
文明の中心に関して言うと、訳文に出てくるアブド・アッラフマーン3世の息子のアル・ハカム2世(在位 961-976)は文化人で、コルドバに巨大図書館を建て、東方から50万冊に及ぶ書物を収集しました。文化の中心もまたイスラム帝国の巨大都市(コルドバ、バグダッドなど)にあったわけです。それが後のヨーロッパに引き継がれた。
このようなイスラム帝国へと続く奴隷交易ルートは、それに携わった商人が属する地域の経済発展に大きく寄与したと考えられます。ヴェネチアをはじめとするイタリア半島の海洋都市国家の繁栄や、北欧諸国の勃興は、こういった交易抜きには考えられないでしょう。ヴェネチアの勃興から衰退までの期間は、ちょうどイスラム帝国の勃興から衰退までの期間と重なっているのですが、偶然とは思えません。
ユーラシア大陸の西部で繰り広げられたグローバルな交易も印象的です。高額商品の需要がある限り、商人はその仕入れに "地の果てまで" 行く。ロシア・東欧を出発し、アルプスの標高2000メートル級の山道(セッティモ峠、スプルガ峠)を越え、ヴェネチアに至る交易路(その後、北アフリカや中東へ)があったのです。
もちろん中世ヨーロッパだけではなく、中国の絹がローマ帝国に運ばれたように、利潤があげられる貴重な商材の交易は昔から驚くほどの遠距離を越えました。そして中世ヨーロッパの奴隷貿易の場合は、商材の供給地と需要地の間に圧倒的な経済格差があり、それが交易をドライブしていた。経済のグローバル化は、程度問題こそあれ昔からそうだったことが改めて理解できました。
念のために、上の試訳のもとになった Wikipedia の原文(2018年11月2日現在)を掲げておきます。[数字] は出典・参考文献への参照ですが、文献名は省略しました。
Slavery in medieval Europe
2. Slave trade
2.1 Italian merchants
2.2 Jewish merchants
2.3 Iberia
2.4 Vikings
2.5 Mongols
2.6 British Isles
2.7 Christians holding Muslim slaves
2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages
2. Slave trade
Demand from the Islamic world dominated the slave trade in medieval Europe.[13][14][15][16] For most of that time, however, sale of Christian slaves to non-Christians was banned.[citation needed] In the pactum Lotharii of 840 between Venice and the Carolingian Empire, Venice promised not to buy Christian slaves in the Empire, and not to sell Christian slaves to Muslims.[13][17][18] The Church prohibited the export of Christian slaves to non-Christian lands, for example in the Council of Koblenz in 922, the Council of London in 1102, and the Council of Armagh in 1171.[19]
As a result, most Christian slave merchants focused on moving slaves from non-Christian areas to Muslim Spain, North Africa, and the Middle East, and most non-Christian merchants, although not bound by the Church's rules, focused on Muslim markets as well.[13][14][15][16] Arabic silver dirhams, presumably exchanged for slaves, are plentiful in eastern Europe and Southern Sweden, indicating trade routes from Slavic to Muslim territory.[20]
2.1 Italian merchants
By the reign of Pope Zachary (741-752), Venice had established a thriving slave trade, buying in Italy, amongst other places, and selling to the Moors in Northern Africa (Zacharias himself reportedly forbade such traffic out of Rome).[21][22][23] When the sale of Christians to Muslims was banned (pactum Lotharii[17]), the Venetians began to sell Slavs and other Eastern European non-Christian slaves in greater numbers. Caravans of slaves traveled from Eastern Europe, through Alpine passes in Austria, to reach Venice. A record of tolls paid in Raffelstetten (903-906), near St. Florian on the Danube, describes such merchants. Some are Slavic themselves, from Bohemia and the Kievan Rus'. They had come from Kiev through Przemysl, Krakow, Prague, and Bohemia. The same record values female slaves at a tremissa (about 1.5 grams of gold or roughly 1/3 of a dinar) and male slaves, who were more numerous, at a saiga (which is much less).[13][24] Eunuchs were especially valuable, and "castration houses" arose in Venice, as well as other prominent slave markets, to meet this demand.[20][25]
Venice was far from the only slave trading hub in Italy. Southern Italy boasted slaves from distant regions, including Greece, Bulgaria, Armenia, and Slavic regions. During the 9th and 10th centuries, Amalfi was a major exporter of slaves to North Africa.[13] Genoa, along with Venice, dominated the trade in the Eastern Mediterranean beginning in the 12th century, and in the Black Sea beginning in the 13th century. They sold both Baltic and Slavic slaves, as well as Armenians, Circassians, Georgians, Turks and other ethnic groups of the Black Sea and Caucasus, to the Muslim nations of the Middle East.[26] Genoa primarily managed the slave trade from Crimea to Mamluk Egypt, until the 13th century, when increasing Venetian control over the Eastern Mediterranean allowed Venice to dominate that market.[27] Between 1414 and 1423 alone, at least 10,000 slaves were sold in Venice.[28]
2.2 Jewish merchants
Records of long-distance Jewish slave merchants date at least as far back as 492, when Pope Gelasius permitted Jews to import non-Christian slaves into Italy, at the request of a Jewish friend from Telesina.[29][30][31] By the turn of the 6th to the 7th century, Jews had become the chief slave traders in Italy, and were active in Gaelic territories. Pope Gregory the Great issued a ban on Jews possessing Christian slaves, lest the slaves convert to Judaism.[31][32] By the 9th and 10th centuries, Jewish merchants, sometimes called Radhanites, were a major force in the slave trade continent-wide.[13][33][34]
Jews were one of the few groups who could move and trade between the Christian and Islamic worlds.[34] Ibn Khordadbeh observed and recorded routes of Jewish merchants in his Book of Roads and Kingdoms from the South of France to Spain, carrying (amongst other things) female slaves, eunuch slaves, and young slave boys. He also notes Jews purchasing Slavic slaves in Prague.[13][31][35] Letters of Agobard, archbishop of Lyons (816-840),[36][37][38][39] acts of the emperor Louis the Pious,[40][41] and the seventy-fifth canon of the Council of Meaux of 845 confirms the existence of a route used by Jewish traders with Slavic slaves through the Alps to Lyon, to Southern France, to Spain.[13] Toll records from Walenstadt in 842-843 indicate another trade route, through Switzerland, the Septimer and Splugen passes, to Venice, and from there to North Africa.[13]
As German rulers of Saxon dynasties took over the enslavement (and slave trade) of Slavs in the 10th century, Jewish merchants bought slaves at the Elbe, sending caravans into the valley of the Rhine. Many of these slaves were taken to Verdun, which had close trade relations with Spain. Many would be castrated and sold as eunuchs as well.[13][25]
The Jewish population of Crimea was a very important factor in the trade in slaves and captives of the Crimean Khanate (Tatars) in the sixteenth to eighteenth centuries.[42]
Jews would later become highly influential in the European slave trade, reaching their apex from the 16th to 19th centuries.[13]
2.3 Iberia
A ready market, especially for men of fighting age, could be found in Umayyad Spain, with its need for supplies of new mamelukes.
'Al-Hakam was the first monarch of this family who surrounded his throne with a certain splendour and magnificence. He increased the number of mamelukes (slave soldiers) until they amounted to 5,000 horse and 1,000 foot. ... he increased the number of his slaves, eunuchs and servants; had a bodyguard of cavalry always stationed at the gate of his palace and surrounded his person with a guard of mamelukes .... these mamelukes were called Al-l;Iaras (the Guard) owing to their all being Christians or foreigners. They occupied two large barracks, with stables for their horses.'[43]
According to Roger Collins although the role of the Vikings in the slave trade in Iberia remains largely hypothetical, their depredations are clearly recorded. Raids on AlAndalus by Vikings are reported in the years 844, 859, 966 and 971, conforming to the general pattern of such activity concentrating in the mid ninth and late tenth centuries.[44] Muslim Spain imported an enormous number[clarification needed] of slaves, as well as serving as a staging point for Muslim and Jewish merchants to market slaves to the rest of the Islamic world.[34]
During the reign of Abd-ar-Rahman III (912-961), there were at first 3,750, then 6,087, and finally 13,750 Saqaliba, or Slavic slaves, at Cordoba, capital of the Umayyad Caliphate. Ibn Hawqal, Ibrahim al-Qarawi, and Bishop Liutprand of Cremona note that the Jewish merchants of Verdun specialized in castrating slaves, to be sold as eunuch saqaliba, which were enormously popular[clarification needed] in Muslim Spain.[13] [25] [45]
2.4 Vikings
During the Viking age (793 - approximately 1100), the Norse raiders often captured and enslaved militarily weaker peoples they encountered. The Nordic countries called their slaves thralls (Old Norse: Trall).[46] The thralls were mostly from Western Europe, among them many Franks, Anglo-Saxons, and Celts. Many Irish slaves travelled in expeditions for the colonization of Iceland.[47] Raids on monasteries provided a source of young, educated slaves who could be sold in Venice or Byzantium for high prices. Scandinavian trade centers stretched eastwards from Hedeby in Denmark and Birka in Sweden to Staraya Ladoga in northern Russia before the end of the 8th century.[25]
This traffic continued into the 9th century as Scandinavians founded more trade centers at Kaupang in southwestern Norway and Novgorod, farther south than Staraya Ladoga, and Kiev, farther south still and closer to Byzantium. Dublin and other northwestern European Viking settlements were established as gateways through which captives were traded northwards. In the Laxdala saga, for example, a Rus merchant attends a fair in the Brenn Isles in Sweden selling female slaves from northwestern Europe.[25]
The Norse also took German, Baltic, Slavic and Latin slaves. The 10th-century Persian traveller Ibn Rustah described how Swedish Vikings, the Varangians or Rus, terrorized and enslaved the Slavs taken in their raids along the Volga River.[48] Slaves were often sold south, to Byzantine or Muslim buyers, via paths such as the Volga trade route. Ahmad ibn Fadlan of Baghdad provides an account of the other end of this trade route, namely of Volga Vikings selling Slavic Slaves to middle-eastern merchants.[49] Finland proved another source for Viking slave raids.[50] Slaves from Finland or Baltic states were traded as far as central Asia.[51][52]
2.5 Mongols
The Mongol invasions and conquests in the 13th century added a new force in the slave trade. The Mongols enslaved skilled individuals, women and children and marched them to Karakorum or Sarai, whence they were sold throughout Eurasia. Many of these slaves were shipped to the slave market in Novgorod.[53][54][55]
Genoese and Venetians merchants in Crimea were involved in the slave trade with the Golden Horde.[13][27] In 1441, Haci I Giray declared independence from the Golden Horde and established the Crimean Khanate. For a long time, until the early 18th century, the khanate maintained a massive[clarification needed] slave trade with the Ottoman Empire and the Middle East. In a process called the "harvesting of the steppe", they enslaved many Slavic peasants.[56]
2.6 British Isles
As a commonly traded commodity in the British Isles, like cattle, slaves could become a form of internal or trans-border currency.[57][58] William the Conqueror banned the exporting of slaves from England, limiting the nation's participation in the slave trade.[59]
2.7 Christians holding Muslim slaves
Although the primary flow of slaves was toward Muslim countries,[further explanation needed] Christians did acquire Muslim slaves; in Southern France, in the 13th century, "the enslavement of Muslim captives was still fairly common".[60] There are records, for example, of Saracen slave girls sold in Marseilles in 1248,[61] a date which coincided with the fall of Seville and its surrounding area, to raiding Christian crusaders, an event during which a large number of Muslim women from this area, were enslaved as war booty, as it has been recorded in some Arabic poetry, notably by the poet al-Rundi, who was contemporary to the events.
Christians also sold Muslim slaves captured in war. The Order of the Knights of Malta attacked pirates and Muslim shipping, and their base became a center for slave trading, selling captured North Africans and Turks. Malta remained a slave market until well into the late 18th century. One thousand slaves were required to man the galleys (ships) of the Order.[62][63]
2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages
As more and more of Europe Christianized, and open hostilities between Christian and Muslim nations intensified, large-scale slave trade moved to more distant sources. Sending slaves to Egypt, for example, was forbidden by the papacy in 1317, 1323, 1329, 1338, and, finally, 1425, as slaves sent to Egypt would often become soldiers, and end up fighting their former Christian owners. Although the repeated bans indicate that such trade still occurred, they also indicate that it became less desirable.[13] In the 16th century, African slaves replaced almost all other ethnicities and religious enslaved groups in Europe.[64]
このブログは初回の No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」以来、樹木の枝が伸びるように、連想・関連・追加・補足で次々と話を繋げているので、"奴隷" をテーマにした記事もかなりの数になりました。世界史の年代順に並べると以下の通りです。
◆紀元1~4世紀:ローマ帝国
No.162 - 奴隷のしつけ方
No.203 - ローマ人の "究極の娯楽"
No.239 - ヨークの首なしグラディエーター
| No.162はローマ帝国の奴隷の実態を記述した本の紹介。No.203,239 はローマ帝国における剣闘士の話。 |
◆8世紀~14世紀:ヨーロッパ
No.22 - クラバートと奴隷(1)スラヴ民族
No.23 - クラバートと奴隷(2)ヴェネチア
| 英語で奴隷を意味する "slave" が、民族名のスラヴと同じ語源であることと、その背景となった中世ヨーロッパの奴隷貿易。 |
◆16世紀~17世紀:日本
No.33 - 日本史と奴隷狩り
No.34 - 大坂夏の陣図屏風
| 戦国期~安土桃山~江戸初期における戦場での奴隷狩り。 |
◆17世紀:スペイン
No.19 - ベラスケスの「怖い絵」
| 17世紀のスペイン宮廷における奴隷の存在と、宮廷にいた小人症の人たち(慰み者)。 |
◆18世紀~19世紀:アメリカ
No.18 - ブルーの世界
No.104 - リンカーンと奴隷解放宣言
No.109 - アンダーソンヴィル捕虜収容所
| アメリカの独立前、18世紀のサウス・カロライナ州の奴隷制プランテーションで、青色染料の藍(インディゴ)が生産されたこと。及び、南北戦争の途中で出されたリンカーン大統領の「奴隷解放宣言」の背景と歴史的意義。 |
以降は、No.22-23「クラバートと奴隷」でとりあげた、中世ヨーロッパの奴隷貿易の補足です。No.23の「補記2」でイタリア人商人による奴隷貿易の実態を、Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" という項目から訳出しました(日本語版はありせん)。この項目は中世ヨーロッパの奴隷や奴隷制度全般の記述ですが、その第2章が「2.奴隷貿易」で、次のような節の構成になっています。
2. 奴隷貿易
2.1 イタリア商人
2.2 ユダヤ商人
2.3 イベリア半島
2.4 ヴァイキング
2.5 モンゴル人
2.6 イギリス諸島
2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷
2.8 中世終焉期の奴隷貿易
No.23の「補記2」は「2.1 イタリア商人」だけの訳でしたが、今回は2章全体を訳出してみることにします。「2.1 イタリア商人」も再掲します。なお、Wikipedia にある出典への参照や参考文献は省略しました。以下の Wikipedia の引用や参照はすべて2018年11月2日現在のものです。
「中世ヨーロッパの奴隷 : 第2章 奴隷貿易」(Wikipedia) 試訳

| ||
|
「中世ヨーロッパの奴隷貿易」関連地図
Wikipediaから訳出した部分に出てくる地名(その他、川、峠、島の名など)の位置を示した。訳文には出てこないが、ターナとコンスタンチノープルはヴェネチアの交易の拠点となった都市である(No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」参照)
| ||
2. 奴隷貿易
中世ヨーロッパの奴隷貿易を支配したのはイスラム世界からの要求であった。しかし多くの時期、キリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒に売るのは禁止されていた。840年にヴェネチアとカロリング朝フランク帝国で結ばれたロタール協定で、ヴェネチアは帝国内でキリスト教徒の奴隷を買わないこと、キリスト教徒の奴隷をイスラムに売らないこと約束した。教会もまたキリスト教徒の奴隷を非キリスト教徒の国へ売ることを禁止した。たとえば、922年のコブレンツ(注)教会会議(the Council)、1102年のロンドン教会会議、1171年のアーマー(注)教会会議などである。
この結果、多くのキリスト教徒の奴隷商人は、非キリスト教地域の奴隷をイスラム圏のスペイン・北アフリカ・中東へと売ることに注力した。そして、教会の規則に縛られていなかった非キリスト教徒の奴隷商人もイスラムの奴隷マーケットに注力した。東ヨーロッパや南部スウェーデンで大量に見つかるアラブのディルハム銀貨は奴隷貿易に使われたものと推測できる。つまり、スラヴ圏からイスラム圏への交易があったことを示している。
【訳注】
コブレンツ(Koblenz)(地図)アーマー(Armagh)
ドイツ西部、ライン河とモーゼル河の合流地点にある町。No.22「クラバートと奴隷(1)スラヴ民族」の「補記2」参照。
北アイルランドの町。アイルランドにキリスト教徒を布教した聖パトリックが布教拠点の教会を設立した。
2.1 イタリア商人
ローマ教皇・ザカリアス(在位:741-752)の治世の頃までに、ヴェネチア(地図)は奴隷交易での繁栄を確立した。彼らはイタリアやその他の地域から奴隷を買い、アフリカのムーア人に売った。もっともザカリアス自身はローマ外での奴隷交易を禁止したと伝えられている。
ロタール協定によってキリスト教徒の奴隷をイスラムに売ることが禁止されると、ヴェネチア商人はスラブ人やその他、東ヨーロッパの非キリスト教徒の奴隷の大々的な交易に乗り出した。東ヨーロッパから奴隷のキャラバンが、オーストリア・アルプスの山道を超えてヴェネチアに到着した。
ドナウ河畔のザンクト・フローリアンの近くのラッフェルステッテン(注)の通行税の記録(903-906)には、そんな商人たちの記述がある。商人の中にはボヘミアやキエフ公国のスラヴ人自身もいた。彼らはキエフ公国からプシェムシルやクラコフ(注)、プラハ、ボヘミアを経由して来ていた。
記録によると、女の奴隷は1トレミシス金貨(約1.5グラムの金。ディナール金貨の1/3)であり、女よりも圧倒的に数が多い男の奴隷は1サイガ銀貨(トレミシスより価値がかなり落ちる)であった。
宦官(eunch)(注)は非常に貴重であり、この需要に対応するため、他の奴隷市場と同じように "去勢所"(castration house)がヴェネチアに作られた。
ヴェネチアだけが奴隷貿易の拠点だったのではない。南部イタリアの都市も遠隔地からの奴隷獲得を競っていた。ギリシャやブルガリア、アルメニア、そしてスラヴ圏である。9~10世紀にはアマルフィ(地図)が北アフリカへの奴隷輸出の多くを担った。
ジェノヴァ(地図)は12世紀ごろからヴェネチアとともに東地中海での交易を押さえ、また13世紀からは黒海での交易を支配した。彼らはバルト海沿岸の民族やスラヴ人、アルメニア人、チェルケス人、ジョージア(グルジア)人、トルコ人、その他、黒海沿岸やコーカサス地方の民族を中東のイスラム国に売った。ジェノヴァはクリミアからマムルーク朝エジプトへの奴隷貿易を13世紀まで支配したが、東地中海でのヴェネチアの勢力が強大になると、ヴェネチアがとって代わった。
1414年から1423年の間だけで、少なくとも10,000人の奴隷がヴェネチアで取引された。
【訳注】
ラッフェルステッテン(地図)プシェムシル、クラコフ(地図)
現オーストリアのアステン。リンツより少しドナウ下流の位置にある。中世には税関があった。
eunach("ユーナック")
いずれも、現ポーランドの都市。
去勢された男性のこと。宦官は東アジア(日本以外)、中東諸国、東ローマ帝国、オスマントルコ帝国などの官吏である。去勢された奴隷=官吏というわけではないが、以下 eunach を "宦官" とした。なお castration は去勢という意味で、イタリアで発達した去勢男性歌手、カストラート(イタリア語: castrato)と同源の言葉である。

| ||
|
ジェノヴァの要塞
黒海に突き出たクリミア半島の都市・スダク(ウクライナ)には、ジェノヴァが14世紀~15世紀にかけて建設した要塞が残っている。当時のイタリアの都市国家が海洋貿易で繁栄したことがうかがわれる。
(site : ukrainetrek.com)
| ||
2.2 ユダヤ商人
長距離を交易するユダヤ人の奴隷商人の記録は、少なくとも西暦492年の昔に遡ることができる。この年、ローマ教皇・ゲラシウス(注)は、テレシナ(注)のユダヤ人の友人の求めに応じて、非キリスト教徒の奴隷をイタリアへ輸入する許可を与えた。ユダヤ人は、6世紀の終わりから7世紀になるとイタリアにおける主要な奴隷商人となり、また、ガリア地方でも活躍した。ローマ教皇・大グレゴリウス(注)はユダヤ人がキリスト教徒の奴隷を保有するのを禁じたが、それはユダヤ教に改宗するのを避けるためであった。ユダヤ商人は9世紀から10世紀までにヨーロッパ大陸全体の奴隷貿易の主要な勢力となった。彼らは "ラダニテ"(注)と呼ばれることがあった。
【訳注】
ゲラシウステレシナ(Telesina)
ローマ教皇、ゲラシウス1世。在位 492-496。
大グレゴリウス
イタリア南部、ベネヴェント(カンパニア州)の近郊の古代都市。
ラダニテ
ローマ教皇、グレゴリウス1世。在位 590-604。このブログでは、マグダラのマリアの解釈(=悔い改めた罪のある女)を確立させた教皇として書いたことがあります(No.118「マグダラのマリア」参照)。
英語で "Radhanites"。ユダヤ人の巡回商人を指す。
ユダヤ人はキリスト教国とイスラム世界を行き来して交易できる数少ない集団の一つだった。イブン・フルダーズベ(注)は『諸道と諸国の書』において、南フランスからスペインに至るユダヤ人の交易ルートを記録している。このルートでは、女奴隷、宦官、少年奴隷が、他の商品とともに運ばれた。彼はまた、ユダヤ商人がプラハでスラヴ人奴隷を買ったことも書いている。
リヨン大司教・アゴバール(在位 816-840)の手紙、ルイ敬虔王(注)の布告、845年のモー教会会議(注)での教会法第75番によって、ユダヤ商人のスラヴ人奴隷交易ルートの存在が確認できる。それはアルプスを越えてリヨン(地図)、南フランス、スペインへと至るルートであった。
ヴァレンシュタット(注)の税関の記録(842-843)から、スイスを通る別の交易ルートの存在がわかる。それはセッティモ峠(セプティマー峠)とスプルガ峠(スプリューゲン峠)(地図)を越えてヴェネチアに至り、そこから北アフリカにへと続くルートであった。
【訳注】
イブン・フルダーズベルイ敬虔王
820頃 - 912。アッバース朝イスラム帝国の官僚で地理学者。アラビア語で書かれた最古の地誌と言われる『諸道と諸国の書』を著した。
モー(Meaux)
カール大帝の息子で、フランク国王・ルイ1世のこと。ドイツ語ではルードヴィッヒ1世。在位 814-840。
ヴァレンシュタット(地図)
パリの東北東 45kmにある町。
現在のスイス東部、ヴァレン湖の湖畔の町。ちなみに、リストのピアノ曲集「巡礼の年 第1年 スイス」の第2曲は「ヴァレンシュタットの湖で」である。
10世紀になってドイツのサクソン族の王国の支配者がスラヴ族の奴隷化と奴隷交易に乗り出すようになると、ユダヤ人商人はエルベ河(地図)付近で奴隷を購入し、キャラバンを組んでライン河渓谷に送った。多くの奴隷は、スペインと密接な関係があったヴェルダン(地図)に連れていかれ、去勢され、宦官として売られた。
クリミア(地図)在住のユダヤ人商人は、16世紀から18世紀にかけてのクリミア・ハン国(タタール人国家)の奴隷や捕虜の貿易にとって大変に重要であった。
ユダヤ人はヨーロッパの奴隷貿易において、16世紀から19世紀を頂点として大きな影響力があった。
2.3 イベリア半島
ウマイア朝スペインでは、マムルーク(奴隷の兵士)の供給源として兵役年齢の男の需要が常にあった。
(ロジャー・コリンズ著「中世初期のスペイン」からの引用)
| アル・ハカム(注)は、彼の一族の中でも、華麗で豪華な王位を極めた君主であった。彼はマムルーク(奴隷の兵士)の数を増やし、それは1000人と兵馬5000頭の規模になった。また、奴隷、宦官、召使いを増やした。騎兵の親衛隊をもち、宮殿の門を守らせ、さらにマムルークの警備兵を周りに配置した。彼らマムルークはアル(Al-l)と呼ばれた。これら警備兵は、キリスト教徒か外国人であるがゆえの存在だった。彼らは2つの大きな兵舎を占め、また兵馬のための厩舎が併設されていた。 |
ロジャー・コリンズによると、イベリア半島の奴隷交易におけるヴァイキングの役割は仮説の域を出ない。しかし彼らの略奪行為は明確に記録されている。ヴァイキングによるアンダルシア地方への襲撃は、844年、859年、966年、971年に報告されていて、これらは8世紀半ばから10世紀末に集中したヨーロッパ各地での襲撃の時期と一致する。
イスラム圏スペインは膨大な数の奴隷を輸入し、またイスラム商人やユダヤ商人が他のイスラム世界へ奴隷を輸出する中継地の役割を担った。
アブド・アッラフマーン3世(在位 912-961)の治世下のコルドバ(地図)(ウマイヤ朝イスラム帝国の首都)では、その初期に3,750人の "サカーリバ"、つまりスラヴ人奴隷がいたが、この数は6,087人に増え、最終的には13,750人になった。イブン・ハウカル(注)、イブラヒム・アル = カラウィー、クレモナのリウトプランド司教(注)の記述によると、ヴェルダンのユダヤ商人は去勢の専門技術があり、イスラム圏スペインで大変人気のあった "去勢サカーリバ" として奴隷を売った。
【訳注】
アル・ハカムイブン・ハウカル
ウマイヤ朝のカリフ、アル・ハカム1世。在位 796-822。
クレモナのリウトプランド司教
10世紀のイスラムの地理学者、歴史学者。
神聖ローマ帝国の外交官・政治家・歴史家・宗教家。920- 972。
2.4 ヴァイキング
ヴァイキングの時代(793年~約1100年)に北欧からの襲撃者は、遭遇した武力の劣る人々を捕らえて、しばしば奴隷化した。北欧諸国では彼らを "スレール"(古北欧語ではトレール)と呼んだ。スレールはほとんどが西ヨーロッパ人で、フランク人、アングロサクソン人、ケルト人などであった。多くのアイルランドの奴隷は、アイスランドを(ヴァイキングの)植民地にするための探検にかり出された。ヴァイキングは修道院を襲撃し、若くて教育を受けた奴隷を手に入れたが、それはヴェネチアやビザンチン帝国で高値で売れた。8世紀末までにスカンジナビア商人の奴隷取引地は、デンマークのへーゼビュー(地図)やスウェーデンのビルカ(地図)から、東は北方ロシアのスタラヤ・ラドガ(地図)まで広がっていた。
このような交易は9世紀にも続き、スカンジナビア人はさらに奴隷取引地を増やしていった。南西ノルウェーのカウパング(地図)や、スタラヤ・ラドガより南にあるノヴゴロド(地図)、ビザンチン帝国にさらに近いキエフ(地図)である。ダブリンやその他の北西ヨーロッパのヴァイキングの居住地は、捕虜を北へと送る基地として作られた。たとえば、"ラックス谷の人々のサガ" には、スウェーデンのブレン島(地図)の市場で西ヨーロッパからの女奴隷が売られていて、そこにロシア商人が来る様子が描かれている。
ヴァイキングたちはドイツ人、バルチック人、スラヴ人、ラテン人も捕虜にした。10世紀のペルシャの旅行家、イブン・ルスタは、スウェーデンのヴァイキング(ロシアでは "ヴァリャーグ" と呼んだ)がヴォルガ河(地図)流域のスラヴ人を襲撃し、威嚇して奴隷にしたことを記述している。奴隷はしばしばヴォルガ河の交易路を経由して、南方のビザンチンやイスラム商人に売られた。バグダッドのアフマド・イブン・ファドラーン(注)は、この交易路の出発地でヴォルガのヴァイキングがスラヴ人奴隷を中東の商人に売る様子を記述をしている。
フィンランドもヴァイキングの奴隷狩りの標的になった。フィンランドやバルト海沿岸地域の奴隷は中央アジアまで売られていった。
【訳注】
アフマド・イブン・ファドラーン
10世紀アラブの旅行家。アッバース朝のカリフの使節団として、ヴォルガ河中流の国、ヴォルガ・ブルガール(地図)を訪問した。彼が書いた見聞録はヴァリャーグの貴重な資料となっている。

| ||
|
セルゲイ・イヴァノフ(1864-1910)
「東スラヴでの奴隷取引」(1909)
(M. Kroshitsky Art Museum, Sevastopol)
左側に奴隷を買い付けるイスラム商人がいるが、奴隷を売る右側の一団は服装からしてスラヴ民族のようである。もちろん想像で描かれたものだが、ファドラーンの見聞記はこのような取引がスラヴ地方やヴォルガ河沿岸で行われたことを示している。この絵は Wikipedia の "Slavery in medieval Europe" の項に掲載されている(フランス語、スペイン語などのページ)。 | ||
2.5 モンゴル
13世紀におけるモンゴルの進入と征服は、奴隷交易の新たな隆盛をもたらした。モンゴル人は職人や女、子供を奴隷にしてカラコルムやサライ(地図)に連れていき、そこでユーラシア大陸全体へと売った。多くの奴隷がロシアのノヴゴロドの奴隷市場に送られた。
クリミアにいたジェノヴァとベネチアの商人は、キプチャク・ハン国(注)との奴隷取引に携わった。ハージー1世ギレイはキプチャク・ハン国から独立してクリミア・ハン国を建国したが、そのクリミア・ハン国は18世紀に至るまでの長い間、オスマン帝国や中東との大々的な奴隷貿易を続けた。「ステップ草原の刈り取り」と呼ばれた "行事" で、彼らは多数のスラヴ人の農民を奴隷にした。
【訳注】
キプチャク・ハン国
ジンギス・カンの息子のジョチとその後裔の遊牧政権(=ウルス)。ジョチ・ウルスとも言う。首都はサライ。金で装飾された張幕を宮殿としたため、英語で Golden Horde(金の遊牧民)と呼ばれる。
2.6 イギリス諸島
イギリス諸島(注)では、奴隷は家畜と同じように、国内・国外を問わずに取り引きされる日用品であり、通貨のようなものであった。ウィリアム征服王はイギリスからの奴隷の輸出を禁止し、奴隷交易への国の関与を制限した。
【訳注】
イギリス諸島(British Isles)
ブリテン諸島とも言う。大ブリテン島、アイルランド島、およびその周辺の島を指す。
2.7 キリスト教徒が保有したイスラム奴隷
奴隷取引の主要な流れはイスラム諸国へと向かうものだったが、キリスト教徒もムスリムの奴隷を保有していた。13世紀の南フランスでは、ムスリムの捕虜を奴隷にするのはきわめて一般的だった。
たとえば1248年にムスリムの少女の奴隷がマルセイユ(地図)で売られた記録があるが、これはキリスト教徒の十字軍がセビリア(地図)とその周辺地域を攻略した時期と一致する(注)。この戦勝で地域の多数のムスリムの女性が戦利品として奴隷になり、それはアラブ側の叙事詩、たとえばセビリア攻略の同時代人であった詩人、アル・ルンディの詩に詠われている。。
【訳注】
セビリア攻防戦
カスティーリャ王国(キリスト教国)のセビリア攻略は1246年にはじまり、2年間の攻防戦の末、1248年11月にカスティーリャが制圧した。いわゆる "レコンキスタ"(=キリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動)の重要ポイントである。この結果、イベリア半島に残ったイスラム勢力はグラダナのナスル朝のみとなったが、ナスル朝はキリスト教国と融和的であり、カスティーリャ王国の指揮下でセビリア攻撃に加わっている。レコンキスタの完成は1492年のグラダナ陥落であるが、実質的にはセビリアが制圧された時点でレコンキスタはほぼ終わったと言える。
またキリスト教徒は戦争で捕虜にしたムスリム奴隷を売った。マルタ騎士団は海賊やムスリムの商船を襲撃し、騎士団の拠点は捕らえた北アフリカ人やトルコ人を売る交易の中心になった。マルタ(地図)は18世紀末までも奴隷市場として残った。騎士団が所有するガレー船団のためには1000人の奴隷の乗組員が必要だった。
2.8 中世終焉期の奴隷貿易
ヨーロッパのキリスト教化が進むと、大がかりな奴隷貿易はさらに遠隔地からのものになった。またそれにはキリスト教徒とイスラム教徒の敵対関係が強まったこともあった。たとえばエジプトに奴隷を送るのはローマ教皇によって禁止され、この命令は1317年、1327年、1329年、1338年、最終的には1425年に出されている。というのも、エジプトに送られた奴隷は往々にして兵士となり、元のキリスト教徒の主人と戦う結果になったからである。禁止令が繰り返されたことは、そのような交易が続いていたことと、交易がより好ましくないものになったことを示している。16世紀になるとアフリカ人の奴隷が、ヨーロッパの各民族・各宗派の奴隷にとって代わった。
(Wikipediaの訳・終)
「文明の中心」と「グローバル経済」
「中世ヨーロッパの奴隷貿易」という Wikipedia の記事を読んで改めて思うのは、中世の文明の中心はイスラム国家だということと、西ユーラシア大陸の全域をカバーするグローバルな交易、の2点です。

| ||
|
「中世ヨーロッパの奴隷貿易」関連地図
| ||
この地図には、奴隷という高額商品の買い手がほとんど描かれていませんが、イベリア半島南部の後ウマイヤ朝は買い手でした。首都のコルドバの人口は100万人を越え、当時のヨーロッパ最大の都市です。それよりも大きな奴隷の需要地は、現在のイランから北アフリカを版図とするアッバース朝です。中世ではこの2つのイスラム帝国が文明の中心であり、強大な経済力と軍事力を誇った。Wikipediaの記述でよく分かるのは、その結果として中世ヨーロッパの奴隷貿易があったということです。
文明の中心に関して言うと、訳文に出てくるアブド・アッラフマーン3世の息子のアル・ハカム2世(在位 961-976)は文化人で、コルドバに巨大図書館を建て、東方から50万冊に及ぶ書物を収集しました。文化の中心もまたイスラム帝国の巨大都市(コルドバ、バグダッドなど)にあったわけです。それが後のヨーロッパに引き継がれた。
このようなイスラム帝国へと続く奴隷交易ルートは、それに携わった商人が属する地域の経済発展に大きく寄与したと考えられます。ヴェネチアをはじめとするイタリア半島の海洋都市国家の繁栄や、北欧諸国の勃興は、こういった交易抜きには考えられないでしょう。ヴェネチアの勃興から衰退までの期間は、ちょうどイスラム帝国の勃興から衰退までの期間と重なっているのですが、偶然とは思えません。
ユーラシア大陸の西部で繰り広げられたグローバルな交易も印象的です。高額商品の需要がある限り、商人はその仕入れに "地の果てまで" 行く。ロシア・東欧を出発し、アルプスの標高2000メートル級の山道(セッティモ峠、スプルガ峠)を越え、ヴェネチアに至る交易路(その後、北アフリカや中東へ)があったのです。
もちろん中世ヨーロッパだけではなく、中国の絹がローマ帝国に運ばれたように、利潤があげられる貴重な商材の交易は昔から驚くほどの遠距離を越えました。そして中世ヨーロッパの奴隷貿易の場合は、商材の供給地と需要地の間に圧倒的な経済格差があり、それが交易をドライブしていた。経済のグローバル化は、程度問題こそあれ昔からそうだったことが改めて理解できました。
| Wikipediaの原文 |
念のために、上の試訳のもとになった Wikipedia の原文(2018年11月2日現在)を掲げておきます。[数字] は出典・参考文献への参照ですが、文献名は省略しました。
Slavery in medieval Europe
2. Slave trade
2.1 Italian merchants
2.2 Jewish merchants
2.3 Iberia
2.4 Vikings
2.5 Mongols
2.6 British Isles
2.7 Christians holding Muslim slaves
2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages
2. Slave trade
Demand from the Islamic world dominated the slave trade in medieval Europe.[13][14][15][16] For most of that time, however, sale of Christian slaves to non-Christians was banned.[citation needed] In the pactum Lotharii of 840 between Venice and the Carolingian Empire, Venice promised not to buy Christian slaves in the Empire, and not to sell Christian slaves to Muslims.[13][17][18] The Church prohibited the export of Christian slaves to non-Christian lands, for example in the Council of Koblenz in 922, the Council of London in 1102, and the Council of Armagh in 1171.[19]
As a result, most Christian slave merchants focused on moving slaves from non-Christian areas to Muslim Spain, North Africa, and the Middle East, and most non-Christian merchants, although not bound by the Church's rules, focused on Muslim markets as well.[13][14][15][16] Arabic silver dirhams, presumably exchanged for slaves, are plentiful in eastern Europe and Southern Sweden, indicating trade routes from Slavic to Muslim territory.[20]
2.1 Italian merchants
By the reign of Pope Zachary (741-752), Venice had established a thriving slave trade, buying in Italy, amongst other places, and selling to the Moors in Northern Africa (Zacharias himself reportedly forbade such traffic out of Rome).[21][22][23] When the sale of Christians to Muslims was banned (pactum Lotharii[17]), the Venetians began to sell Slavs and other Eastern European non-Christian slaves in greater numbers. Caravans of slaves traveled from Eastern Europe, through Alpine passes in Austria, to reach Venice. A record of tolls paid in Raffelstetten (903-906), near St. Florian on the Danube, describes such merchants. Some are Slavic themselves, from Bohemia and the Kievan Rus'. They had come from Kiev through Przemysl, Krakow, Prague, and Bohemia. The same record values female slaves at a tremissa (about 1.5 grams of gold or roughly 1/3 of a dinar) and male slaves, who were more numerous, at a saiga (which is much less).[13][24] Eunuchs were especially valuable, and "castration houses" arose in Venice, as well as other prominent slave markets, to meet this demand.[20][25]
Venice was far from the only slave trading hub in Italy. Southern Italy boasted slaves from distant regions, including Greece, Bulgaria, Armenia, and Slavic regions. During the 9th and 10th centuries, Amalfi was a major exporter of slaves to North Africa.[13] Genoa, along with Venice, dominated the trade in the Eastern Mediterranean beginning in the 12th century, and in the Black Sea beginning in the 13th century. They sold both Baltic and Slavic slaves, as well as Armenians, Circassians, Georgians, Turks and other ethnic groups of the Black Sea and Caucasus, to the Muslim nations of the Middle East.[26] Genoa primarily managed the slave trade from Crimea to Mamluk Egypt, until the 13th century, when increasing Venetian control over the Eastern Mediterranean allowed Venice to dominate that market.[27] Between 1414 and 1423 alone, at least 10,000 slaves were sold in Venice.[28]
2.2 Jewish merchants
Records of long-distance Jewish slave merchants date at least as far back as 492, when Pope Gelasius permitted Jews to import non-Christian slaves into Italy, at the request of a Jewish friend from Telesina.[29][30][31] By the turn of the 6th to the 7th century, Jews had become the chief slave traders in Italy, and were active in Gaelic territories. Pope Gregory the Great issued a ban on Jews possessing Christian slaves, lest the slaves convert to Judaism.[31][32] By the 9th and 10th centuries, Jewish merchants, sometimes called Radhanites, were a major force in the slave trade continent-wide.[13][33][34]
Jews were one of the few groups who could move and trade between the Christian and Islamic worlds.[34] Ibn Khordadbeh observed and recorded routes of Jewish merchants in his Book of Roads and Kingdoms from the South of France to Spain, carrying (amongst other things) female slaves, eunuch slaves, and young slave boys. He also notes Jews purchasing Slavic slaves in Prague.[13][31][35] Letters of Agobard, archbishop of Lyons (816-840),[36][37][38][39] acts of the emperor Louis the Pious,[40][41] and the seventy-fifth canon of the Council of Meaux of 845 confirms the existence of a route used by Jewish traders with Slavic slaves through the Alps to Lyon, to Southern France, to Spain.[13] Toll records from Walenstadt in 842-843 indicate another trade route, through Switzerland, the Septimer and Splugen passes, to Venice, and from there to North Africa.[13]
As German rulers of Saxon dynasties took over the enslavement (and slave trade) of Slavs in the 10th century, Jewish merchants bought slaves at the Elbe, sending caravans into the valley of the Rhine. Many of these slaves were taken to Verdun, which had close trade relations with Spain. Many would be castrated and sold as eunuchs as well.[13][25]
The Jewish population of Crimea was a very important factor in the trade in slaves and captives of the Crimean Khanate (Tatars) in the sixteenth to eighteenth centuries.[42]
Jews would later become highly influential in the European slave trade, reaching their apex from the 16th to 19th centuries.[13]
2.3 Iberia
A ready market, especially for men of fighting age, could be found in Umayyad Spain, with its need for supplies of new mamelukes.
'Al-Hakam was the first monarch of this family who surrounded his throne with a certain splendour and magnificence. He increased the number of mamelukes (slave soldiers) until they amounted to 5,000 horse and 1,000 foot. ... he increased the number of his slaves, eunuchs and servants; had a bodyguard of cavalry always stationed at the gate of his palace and surrounded his person with a guard of mamelukes .... these mamelukes were called Al-l;Iaras (the Guard) owing to their all being Christians or foreigners. They occupied two large barracks, with stables for their horses.'[43]
According to Roger Collins although the role of the Vikings in the slave trade in Iberia remains largely hypothetical, their depredations are clearly recorded. Raids on AlAndalus by Vikings are reported in the years 844, 859, 966 and 971, conforming to the general pattern of such activity concentrating in the mid ninth and late tenth centuries.[44] Muslim Spain imported an enormous number[clarification needed] of slaves, as well as serving as a staging point for Muslim and Jewish merchants to market slaves to the rest of the Islamic world.[34]
During the reign of Abd-ar-Rahman III (912-961), there were at first 3,750, then 6,087, and finally 13,750 Saqaliba, or Slavic slaves, at Cordoba, capital of the Umayyad Caliphate. Ibn Hawqal, Ibrahim al-Qarawi, and Bishop Liutprand of Cremona note that the Jewish merchants of Verdun specialized in castrating slaves, to be sold as eunuch saqaliba, which were enormously popular[clarification needed] in Muslim Spain.[13] [25] [45]
2.4 Vikings
During the Viking age (793 - approximately 1100), the Norse raiders often captured and enslaved militarily weaker peoples they encountered. The Nordic countries called their slaves thralls (Old Norse: Trall).[46] The thralls were mostly from Western Europe, among them many Franks, Anglo-Saxons, and Celts. Many Irish slaves travelled in expeditions for the colonization of Iceland.[47] Raids on monasteries provided a source of young, educated slaves who could be sold in Venice or Byzantium for high prices. Scandinavian trade centers stretched eastwards from Hedeby in Denmark and Birka in Sweden to Staraya Ladoga in northern Russia before the end of the 8th century.[25]
This traffic continued into the 9th century as Scandinavians founded more trade centers at Kaupang in southwestern Norway and Novgorod, farther south than Staraya Ladoga, and Kiev, farther south still and closer to Byzantium. Dublin and other northwestern European Viking settlements were established as gateways through which captives were traded northwards. In the Laxdala saga, for example, a Rus merchant attends a fair in the Brenn Isles in Sweden selling female slaves from northwestern Europe.[25]
The Norse also took German, Baltic, Slavic and Latin slaves. The 10th-century Persian traveller Ibn Rustah described how Swedish Vikings, the Varangians or Rus, terrorized and enslaved the Slavs taken in their raids along the Volga River.[48] Slaves were often sold south, to Byzantine or Muslim buyers, via paths such as the Volga trade route. Ahmad ibn Fadlan of Baghdad provides an account of the other end of this trade route, namely of Volga Vikings selling Slavic Slaves to middle-eastern merchants.[49] Finland proved another source for Viking slave raids.[50] Slaves from Finland or Baltic states were traded as far as central Asia.[51][52]
2.5 Mongols
The Mongol invasions and conquests in the 13th century added a new force in the slave trade. The Mongols enslaved skilled individuals, women and children and marched them to Karakorum or Sarai, whence they were sold throughout Eurasia. Many of these slaves were shipped to the slave market in Novgorod.[53][54][55]
Genoese and Venetians merchants in Crimea were involved in the slave trade with the Golden Horde.[13][27] In 1441, Haci I Giray declared independence from the Golden Horde and established the Crimean Khanate. For a long time, until the early 18th century, the khanate maintained a massive[clarification needed] slave trade with the Ottoman Empire and the Middle East. In a process called the "harvesting of the steppe", they enslaved many Slavic peasants.[56]
2.6 British Isles
As a commonly traded commodity in the British Isles, like cattle, slaves could become a form of internal or trans-border currency.[57][58] William the Conqueror banned the exporting of slaves from England, limiting the nation's participation in the slave trade.[59]
2.7 Christians holding Muslim slaves
Although the primary flow of slaves was toward Muslim countries,[further explanation needed] Christians did acquire Muslim slaves; in Southern France, in the 13th century, "the enslavement of Muslim captives was still fairly common".[60] There are records, for example, of Saracen slave girls sold in Marseilles in 1248,[61] a date which coincided with the fall of Seville and its surrounding area, to raiding Christian crusaders, an event during which a large number of Muslim women from this area, were enslaved as war booty, as it has been recorded in some Arabic poetry, notably by the poet al-Rundi, who was contemporary to the events.
Christians also sold Muslim slaves captured in war. The Order of the Knights of Malta attacked pirates and Muslim shipping, and their base became a center for slave trading, selling captured North Africans and Turks. Malta remained a slave market until well into the late 18th century. One thousand slaves were required to man the galleys (ships) of the Order.[62][63]
2.8 Slave trade at the close of the Middle Ages
As more and more of Europe Christianized, and open hostilities between Christian and Muslim nations intensified, large-scale slave trade moved to more distant sources. Sending slaves to Egypt, for example, was forbidden by the papacy in 1317, 1323, 1329, 1338, and, finally, 1425, as slaves sent to Egypt would often become soldiers, and end up fighting their former Christian owners. Although the repeated bans indicate that such trade still occurred, they also indicate that it became less desirable.[13] In the 16th century, African slaves replaced almost all other ethnicities and religious enslaved groups in Europe.[64]
タグ:アーマー カロリング朝 コブレンツ ヴェネチア ロタール協定 ザカリアス ディルハム銀貨 ヴァイキング クリミア・ハン国 サライ キプチャク・ハン国 ザンクト・フローリアン 宦官 ジェノヴァ アマルフィ ラッフェルステッテン マムルーク ウマイヤ朝 ヴェルダン ラダニテ ユダヤ人 ゲラシウス 大グレゴリウス イブン・フルダーズベ ヴァレンシュタット ルイ敬虔王 アゴバール ヴァリャーグ セビリア コルドバ レコンキスタ イブン・ハウカル アブド・アッラフマーン3世 イブン・ルスタ カラコルム ノヴゴロド ビルカ キエフ へーゼビュー スタラヤ・ラドガ ヴォルガ河 モンゴル ブレン島 ラックス谷の人々のサガ ダブリン アフマド・イブン・ファドラーン スレール アル・ハカム1世 セルゲイ・イヴァノフ マルタ騎士団 アル・ルンディ ウィリアム征服王 スダク ジェノヴァの要塞
2018-11-23 17:04
nice!(0)
No.239 - ヨークの首なしグラディエーター [歴史]
No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で、古代ローマの剣闘士の話を書きました。ジャン = レオン・ジェローム(1824-1904)が剣闘士の闘技会の様子を描いた有名な絵画「差し下ろされた親指」も紹介しましたが、今回はその剣闘士の話の続きです。
2004年8月、英国のイングランドの北部の町、ヨーク(York)で古代ローマ時代の墓地が発掘されました。この発掘の様子と、埋葬されていた遺体の分析が最近のテレビ番組で放映されました。
です。これは英国の Blink Films プロダクションが制作したドキュメンタリー、"The Headless Gladiators in York(2017)" を日本語訳で放送したものですが、古代ローマの剣闘士に関する大変に興味深い内容だったので、その放送内容をここに掲載しておきたいと思います。なお、グラディエーター(=剣闘士)は英語であり、ラテン語ではグラディアトルです。

(site : annamap.com)
出演者
このドキュメンタリー番組は、ナレーションとともに8人の考古学者・人類学者が解説をする形をとっています。出演したのは次の人たちです。
◆カート・ハンターマン(Kurt Hunter-Mann)
考古学者で「ヨーク考古学トラスト(York Archaelogy Trust)」の遺跡発掘の専門家。今回の古代ローマ墓地の発掘チームでリーダーを勤めた。
◆マーリン・ホルスト(Malin Holst)
英国の骨考古学(Oestearchaelogy。人の骨の分析による考古学)の専門家。ヨーク大学講師。
◆シャーロット・ロバーツ博士(Charlotte Roberts)
英国・ダラム(Durham)大学の考古学者。生物考古学(Bioearchaelogy。人・動物・植物など生物の分析による考古学)が専門。なお番組ではダーハム大学とありましたが、Durhamの h は発音しないので、ダラム(ないしはダーラム)が正解。ダラムはヨークの北、イングランド北部の大学町。
◆ジャネット・モンゴメリー博士(Janet Montgomery)
ダラム大学の考古学者(生物考古学)。骨の同位体分析を担当。
◆ティム・トムソン教授(Tim Thompson)
英国・ティーズサイド大学の人類学者。ティーズサイド大学はイングランド北部の町、ミドルズブラ(Middlesbrough)にある。
◆ダリウス・アーヤ博士(Darius Arya)
米・ローマ文化協会のディレクター。
◆ケビン・ディカス博士(Kevin Dicus)
米・オレゴン大学の考古学者。
◆リチャード・ジョーンズ
歴史学者。
以下に、番組の全スクリプトを掲載します。注 : ・・・・・・ と書いたのは番組にはないコメントです。「プロローグ」などのタイトルも付け加えたものです。番組の中で日本語訳がおかしい(ないしは曖昧な)部分がありましたが、それもコメントしました。【ナレーション】の部分は日本語訳のナレーションで、学者の解説の部分は日本語字幕付きの英語で放送されました。
プロローグ
【ナレーション】
古代考古学史上、最も凄惨な出土品がイギリスの都市・ヨークで発見されました。それは80体以上の男性の首を切られた白骨死体。
【カート・ハンターマン】
発掘を始めると何か奇妙だと感じたんです。
【マーリン・ホルスト】
遺体の6割以上が一撃で首を切り落とされていました。
【ナレーション】
彼らは残酷な死に方をしましたが、そこは常識を覆す墓だったのです。凶暴で生涯を鎖で拘束されていましたが、何と、宝物と一緒に埋められていたのです。男たちに刻まれた残虐な傷跡。
【シャーロット・ロバーツ博士】
(注:骨を見ながら)この人物は度重なる攻撃を受けています。
【ナレーション】
この傷だらけの男たちはいったい何者なのでしょう。10年の調査を経て、専門家チームはその謎をついに解き明かしたのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
彼らは生きる伝説でした。
【ナレーション】
遺跡に秘められた過去。金で、石で、そして血で記された歴史。古代の謎を解き明かし、歴史の偉大なる秘宝の数々をお見せしましょう。
イギリス、ヨークでの大発見
【ナレーション】
歴史ある町、ヨーク。西暦1000年までの過去を知ることは考古学者の夢。この町はイギリス2000年の歴史を今に伝えています。2004年8月、旧市街からほど近くにある小さな区画(注:ドリフフィールド・テラス。Driffield Terras)で発掘調査が行われました。単なる発掘調査のはずでしたが、とんでもない発見があったのです。
【発掘調査員の声】
ここに骨、そして頭蓋骨、まるい形状をしているだろう。この角にも骨があるぞ。
【ナレーション】
さらに深く掘ると、たくさんの白骨死体が完全な姿で出てきたのです。衝撃の事実とともに ・・・・・・。何と、遺体の多くは意図的に首を切り落とされていたのです。これが調査団長のカート・ハンターマンと大きな謎の出会いでした。
【カート・ハンターマン】
発掘を始めてすぐに奇妙だと思いました。首を切り落とされた白骨の遺体があまりにもたくさんあったからです。
【ナレーション】
発掘調査が始まって数日後には、発見された遺体の数は2桁にのぼり、どんどん増え続けました。
【カート・ハンターマン】
発掘作業終了時には 80体以上もの遺体を堀り出しました。そのうち4分の1が首を切り落とされていたのです。
【ナレーション】
考古学者40年のカートのキャリアの中でも、類のない発見だったのです。
【カート・ハンターマン】
ローマ時代の首なし遺体の墓を初めて見ました。しかも狭い面積にたくさんの遺体が埋まっていたなんて。
【ナレーション】
首なしの遺体はいったい何者なのか。謎を解明する第1のヒントは遺跡に隠されていました。過去の発掘調査で、この周辺は昔、大きな墓地だったことがわかっていました。出土品から、ここがヨークに存在する最大規模の墓地で、都市が建設された2世紀終盤ごろにさかのぼることもわかりました。ローマ時代のことです。
【カート・ハンターマン】
周辺にも古代ローマ時代の墓があるので、我々も同様の墓を発見するかもと思っていました。
【ナレーション】
首なし遺体と一緒に発見された陶器により、古代ローマ人の墓地だと裏付けられました。しかし、他のローマ時代の墓とは様相が異なっていたのです。
【カート・ハンターマン】
とても奇妙でした。
【ナレーション】
遺体の多くは首を切り落とされていただけでなく、その頭は両足の間に丁寧に置かれていたのです。
【カート・ハンターマン】
首を切り落とされていた事だけでも奇妙なのに、この変わった遺体の安置方法を見て、古代ローマ人は一体何を考えていたのかと首を傾げました。
【ナレーション】
考古学者たちを困惑させたのは、ひとつの墓地に埋葬されていた首なし遺体の数です。処刑された犯罪者だという見方もできますが、通常、ローマ時代の犯罪者はうつ伏せで埋葬されます。しかしこの墓では仰向けで埋められていました。この奇妙な墓には、いったいどのような意味があるのでしょうか。
謎解きの次のヒントはローマ帝国時代のヨークの役割を知ることでした。かつてエボラクムと呼ばれたこの都市には、2人のローマ皇帝が滞在していたことがわかりました。皇帝が宮廷を構え、軍事的にも重要な拠点だったのです。
【ケビン・ディカス博士】
皇帝の行く先には帝国の行政機関も全て移動します。そしてヨークはローマ帝国 属州の中心地になりました。
【ナレーション】
ローマ帝国のイギリス侵略は紀元43年に始まり、その後30年間にわたり侵攻を続けたのです。しかし北方の部族の抵抗はすさまじいものでした。
【ケビン・ディカス博士】
部族の抵抗にローマ軍は驚愕しました。森や沼地の中にひそみ、奇襲をかけ、攻撃を終えると姿をくらますというゲリラ戦法が彼らの得意技だったのです。鍛え抜かれ統率された軍隊が未開地の部族に完敗してしまうこともあったのです。
【ナレーション】
当初、墓地がローマ軍の侵攻と同時代のものであったことから、首なしの死体はローマ軍と部族の戦死者だと考えられていました。なぜなら、ほぼすべての白骨死体は男性で、戦闘に適した年齢にあったからです。
【マーリン・ホルスト】
ローマ時代の墓では男性の遺体の数が女性よりやや多い程度ですが、ドリフフィールド・テラスに埋められていたのは全員が成人男性だったのです。しかも45歳以上はいないという特異な例でした。つまりこれらは比較的若く、健康で、特別な存在だったのかもしれません。
【ナレーション】
彼らは健康な若い男たちで、人生の盛りに亡くなったようです。しかし無視できない疑問が一つありました。彼らがもし殺された兵士だとしたら、遺体は都市ではなく戦場に埋葬されるはずです。その一方で遺体には、まるで殺戮された兵士のように、すざましい戦闘を経験した痕跡がありました。首を切り落とされただけではなく、骨の多くに骨折が治った痕があったのです。そこで興味深い新説が浮上しました。戦いの中で鍛え抜かれ虐殺された男たちは古代ローマを象徴するだった。それはグラディエーターです。
剣闘士(グラディエーター)
【ナレーション】
ヨークに眠っていたおぞましい遺物。何10体もの男性の白骨。考古学者のカート・ハンターマンと調査団は、古代ローマの墓地で難解な謎に直面していました。男たちは戦闘経験者でしたが、兵士ではなかったのです。首を切り落とされた彼らは何者だったのでしょう。考古学者たちは驚くべき新説をたてました。それはこの墓がグラディエーター、つまり剣闘士のものではないかという説です。もしそれが本当なら、イギリスにおける古代ローマ人の歴史を塗り替えることになります。
【ケビン・ディカス博士】
イタリアのローマですら、グラディエーターの墓の発見はすごいことなんです。イギリスでグラディエーターの大規模な墓が発見されたら、とても驚くでしょう。
【ナレーション】
墓から遺体を掘り出した調査団は、グラディエター説を裏付ける証拠を探し始めました。すると彼らは、まぎれもなく壮絶な戦闘を経験した者たちであることが明らかになったのです。
【マーリン・ホルスト】
この人物は生存中にかなりの外傷を負ったことが骨折痕からわかります。肋骨にも外傷によると思われる骨折痕があり、そして右膝の裏には刀傷、脛には炎症性の損傷があって、ここも一撃されたようです。
【ナレーション】
この男は墓地で発見された中でもひどい傷跡がある一人です。骨折の多くは直っており、彼らが数年にわたって危険な戦闘に耐えてきたことがうかがわれます。そして白骨死体の多くに共通する致命傷があります。それは斬首です。
【マーリン・ホルスト】
6割以上が一撃で首を切り落とされていました。(注:骨を見せながら)これは首の脊椎と頸椎と呼ばれる部分です。この骨に頭が載っていて、その一つ下にあるのが頭を左右に動かす部分です。これを見ると頸椎のこの部分が完全に削ぎ落とされています。そしてこれが脊椎の部分全体を切断した痕です。
【ナレーション】
まっすぐに切断された骨を見ると、男たちが刀剣や斧などの鋭利な武器によって斬首されたことがわかります。
【マーリン・ホルスト】
首を切り落とした最後の一撃は、かなり強烈だったと思います。切り口がここから(注:マーリン・ホルストが手で自分の首の後ろを示す)あごの横まで到達しているのです。衝撃によりあごは粉々になり、たくさんの破片となって飛び散っています。
【ナレーション】
中には、頭を切り落とされるまでに何度も切りつけられた者もいます。
【シャーロット・ロバーツ博士】
この人は、数回首を切りつけられたと思われます。一撃でスパッと頭が切り落とされずに何回も刀を振るわれたのでしょう。一度目がうまくいかなかったか、あるいは確実に首を切り落とすために念を入れたのかもしれません。
【ナレーション】
遺体は斬首されるまで、壮絶な戦闘を強いられていたことを物語っています。さらに遺体にはグラディエーターだったことを裏付ける、ある手がかりが隠されていたのです。それは骨ではなく、歯に残されていました。
歯の分析から判明した出身地
【ナレーション】
ジャネット・モンゴメリー博士は生物考古学者で、専門は遺体の分析です。この2000年前の歯を調べた結果、男たちの出身地を突き止めたのです。彼らの素性を解明するためには貴重な情報で、それは同位体分析という技術(注:最後の「補記1」参照)が鍵となりました。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
同位体分析とは古代人の歯に残されている生存時の情報を引き出す技術です。彼らがどんなものを食べていたのか、住んでいた場所、環境、気候なども判別できます。さらに地元出身者であったか、それとも他所からやってきたのかを立証することもできるのです。
【ナレーション】
歯のエナメル質を同位体分析した結果、ここは国際的な墓地だったことがわかりました。発見された遺体の中でヨーク出身のものは少数で、多くはイギリス出身ですらなかったのです。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
寒い地域から温暖な地域まで様々な土地の出身者がいました。当時のイギリスの食習慣にはない植物を食べていたことも分かっています。彼らは他の土地から来た集団だったのです。
【ナレーション】
分析によると男たちはヨークで死亡しましたが、もともとはローマ帝国の各地からやってきたことがわかりました。そしてある男は驚くほど遠方の出身者でした。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
同位体のデータによると、この男は南方の温暖で乾燥した地域の出身であることがわかりました。その遺伝的祖先は中近東です。
【ナレーション】
何とこの男は母国のある中近東から4800キロも離れたヨークで死亡したのです。
多くの証拠が集まりました。この墓は帝国中から寄せ集められた、鍛え抜かれし戦闘経験者のものだったのです。彼らはまさにグラディエーターそのものでした。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターとは何者だったのでしょう ? その多くは犯罪者や戦争捕虜でした。軍隊経験があり、健康状態が良好で訓練を重ねれば立派なグラディエーターになれる者たちです。
【ナレーション】
ハンターマンにはもう一つ、極め付きの証拠がありました。彼らの墓地はイギリスにある他のローマ時代のものとは様相が異なっていたかもしれません。しかし、3200キロ離れたトルコにある墓地にそっくりだったのです。
エフェソス
【ナレーション】
ここはエフェソス。古代ローマ帝国に属する州の中心地で、25,000人を収容する円形闘技場がありました。1993年、ここからわずか数メートルのところで墓地が発見されました。ヨーク同様、ここで発見された遺体は戦闘経験のある男たちで、残酷な方法で処刑されていました。しかしエフェソスの男たちが何者であるかはすぐに判明しました。墓石に彼らが剣闘士、グラディエーターであったことが記されていたのです。そしてハンターマンはこの2つの墓地の類似点に驚愕しました。
【カート・ハンターマン】
ヨークの白骨遺体はエフェソスのものと良く似ています。私はグラディエーター説を支持しますが、それは生活様式や埋葬場所に説得力があるからです。私からみると全てが闘技場で闘っていたある特定の男達だけに当てはまるのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
ヨークでの発見は、剣闘士にまつわる環境がもう1つ存在していた可能性を開いたのです。
【ナレーション】
ヨークでのグラディエーターの墓と思われる遺跡の大発見は、考古学者たちに一世一代のチャンスをもたらしました。それは古代ローマ文明の闇を解き明かすこと。グラディエーターの試合、闘技会。娯楽のために人が殺される、残虐非道な競技です。
闘技会の多くは古代ローマを象徴する建物、コロセウムで開催されました。西暦80年に落成し5万人を収容するこの円形闘技場は、歴史上最も残酷な競技を興業するためのものだったのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターは強靱な人間たちでした。闘技場で死と直面しつつ、一般の観衆のために闘ったのです。彼らは生きる伝説でした。
【ナレーション】
コロセウムでは70万人以上のグラディエーターが闘い、死んだと推定されています。
【ダリウス・アーヤ博士】
現代ではグラディエーターのような見世物はありません。少なくとも合法的には。観客は流血沙汰を期待して行くわけですからね。誰かが腹を切られ、腕を切り落とされ、もしくは頭を切り落とされる。信じられないほどおぞましいものだったのです。
【ナレーション】
2000年もの時を経て、考古学者たちは過去最大規模のグラディエーターの墓を発掘したのかもしれません。しかもローマではなく、1,600キロも離れたイギリス、歴史ある町、ヨークで ・・・・・・。発掘された80体以上の白骨遺体は、古代ローマ帝国の様々な地域からやってきた男たちでした。彼らは壮絶な人生を送り、最終的には首を落とされましたが、埋葬される際には敬意が払われていたようです。これらの証拠は、彼らが古代ローマのグラディエーターだったことを物語っています。
【ダリウス・アーヤ博士】
ヨークで発見した証拠を調べ、科学分析を進めるにつれて、パズルのピースがはまっていきます。男たちががっしりした体格だったこと、年齢、その他どんどん説得力が増していきます。
食生活
【ナレーション】
現代ではグラディエーターは古代ローマのスーパースター、エリートだと見なされているかもしれません。しかし遺体の歯を分析するにつれて、彼らの過酷な生活を明らかにする驚きの新事実が判明したのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
エナメル質に異常が見られる歯がたくさんありました。この犬歯がよい例です。歯に横線が入っています。横線は歯の成長期にこの人物がストレスを受けていたことを示しています。この人は幸せな幼少期を過ごせず、こうした異常なことが人生で起こっていたのでしょう。
【ナレーション】
墓で発見された多くの男たちの歯にはこうした線が見受けられましたが、それは乳児栄養失調の証です。しかし彼らは成人してから高タンパクの食事をとっていたことが歯に現れています。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
彼らは野菜と肉の両方を食べていただけでなく、少量ですが魚も口にしていた可能性があります。
【ナレーション】
古代ローマ時代のヨークで肉と魚を食べていたということは、恵まれた食生活だったのでしょう。
【ダリウス・アーヤ博士】
彼らは食事を与えられ、良い栄養状態でした。そして強く、丈夫な体になっていきました。一体何があったのでしょう ?
【ナレーション】
歯の証拠から推測すると、ローマ帝国中から貧しい男たちが集められ、闘うための肉体づくりをさせられていたと考えられます。
【ケビン・ディカス博士】
彼らは最下層の身分でしたが、剣闘士の興行師 "ラニスタ" に素質を認められ、身請けされました。そして資金を回収するため訓練を施し、食事と住む場所を与えたのです。
【ナレーション】
男たちはグラディエーターの養成所で高タンパクの食事を与えられました。デビューまでに筋肉をつけて体を大きくするためです。
【ケビン・ディカス博士】
彼らの体格はかなり良かったはすです。帝国一、筋肉隆々で運動能力が高く、その肉体は世間から注目を浴びていたはずです。
副葬品と埋葬場所
【ナレーション】
彼らの墓の副葬品から、貧困層の身分であったグラディエーターたちが一目置かれていたことがわかります。
【カート・ハンターマン】
古代ローマ時代では、墓に副葬品を入れるのが一般的でした。故人が死後の世界で幸せになるための品物が入れられます。
【ナレーション】
ヨークの白骨遺体とともに発見したのは、数々の酒の器や大量に供えられた食べ物でした。さらに彼らの地位の高さを示す副葬品は、多くの銀貨でした。銀貨には様々なローマ皇帝の肖像が描かれていて、この埋葬方法はローマ帝国がイギリスを支配しているあいだ、ずっと行われていたことが明らかになったのです。つまり、グラディエーターたちは4世紀にわたりヨークで活躍していたことになります。
【カート・ハンターマン】
墓からは1世紀から4世紀までの銀貨数種類が出土しています。こちらはコンスタンティヌス2世のもので、紀元330年ごろになります。つまり古代ローマの終わりまで続いていたということです。
【ナレーション】
しかし、男たちが尊敬されていたことを示す一番の証拠は、墓の位置でした。帝国全体の習慣で墓の場所は社会的地位を表していたのです。墓地の発掘にあたっていた考古学者たちは、グラディエーターたち全ての墓が最も名誉ある場所にあったと確証を得たのです。
【カート・ハンターマン】
この墓地(注:Driffield Terras)は古代ローマ時代の大きな街道沿いにあります。当時、通行人に死者を思い出させるこの場所に埋葬されることは大変意味のあることでした。さらに小高い丘になっていることも、この場所の重要性を高めています。この場所は帝国有数の埋葬場所だったのです。
【ナレーション】
特別に鍛え抜かれた若い男たちの集団。死に際しては一般大衆からもその勇姿が称えられました。しかしその一方で、白骨からはある衝撃的な事実が判明しました。この優秀な戦士たちは、生前に奴隷よりは少しはましな扱いを受けていましたが、時には闘技場での生死を左右する恐ろしいハンデを背負わされていたのです。
足かせ
【ナレーション】
ローマ時代、グラディエーターは大きなビジネスでした。毎試合ごとの勝負で、巨額の金が動いていました。有望な新人を確保するために、奴隷売買が横行していたのです。闘技場デビューをさせるため、グラディエーターの育成にはたくさんの金がつぎ込まれました。男たちはただの奴隷よりりは少しはましな扱いを受けていたのです。
【ケビン・ディカス博士】
グラディエーターたちは訓練を受けながら、充実した食事や医療を施されていました。しかしその一方で彼らに自由はなく小部屋に閉じこめられていました。決められたスケジュール通りに過ごすことが強制され、まるで刑務所のようでした。
【リチャード・ジョーンズ】
奇妙な生活ですが、強い肉体をつくる上での待遇には恵まれていました。しかし、その待遇は一時的なものです。
【ナレーション】
(注:白骨遺体の画像が写し出される。次図)彼らが自分の運命ですら選択できなかったことを示す証拠があります。専門家は当初、足かせをはめられた状態で埋葬されていたと考えていました。
【カート・ハンターマン】
これが遺体の足にはまった状態で発見された足かせです。こんなものは初めて目にしました。まさに強運な考古学者が一生に一度だけ出会えるかもしれない稀有な物です。
【ナレーション】
これはただの足かせではありません。現代の足かせのように取り外しができるものではなかったのです。X線分析の結果、足かせはこのグラディエーターに死ぬまで装着されていたのです。
【カート・ハンターマン】
普通の足かせなら両足を鎖でつなぐための留め具があるはずですが、そのようなものは見当たりませんでした。
【ナレーション】
これらは特注の足の重りだったのです。この男に体の不自由と苦痛を与えるために作られました。分析の結果、この足かせは高温に熱した二つの鉄を足首に巻き付け、一つの輪に成形していたことがわかりました。
【カート・ハンターマン】
真っ赤に熱した鉄を人の足に巻きつけるなんて、野蛮としか言えません。
【ナレーション】
白骨の分析では、死ぬまではずせない足かせの残酷な実態が明らかになったのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
彼の足の骨には新しい骨形成の痕跡があり、これは炎症が起こった証です。つまり足首の部分に何らかの外傷が何度も加えられたということです。また当時はこのような炎症を治療できなかったので、彼らは赤く腫れ上がった炎症の痛みに死ぬまで耐えるしかなかったのです。
【ナレーション】
いったいなぜこの男は、これほど恐ろしい罰を受けていたのでしょう。彼は白骨遺体の中で最も大きな体格でした。重い足かせは、この巨体のグラディエーターの動きを鈍らせるものだったのでしょう。血を見て喜ぶローマの大衆に、より刺激的な試合を見せるために。
【ケビン・ディカス博士】
剣闘士に足かせなどを装着しハンデを負わせるということはたまにあったようです。例えば体の大きさが違いすぎて公平な試合にならない場合です。さらにそれがグラディエーターの個性となり、試合をより盛り上げるのです。
治療
【ナレーション】
この足かせの例は極めて珍しいですが、発見されたほとんどの遺体に、傷の治ったあとがありました。当時では贅沢なことですが、彼らには治療が施されていたようです(注:最後の「補記2」参照)。大金をかけて育てたグラディエーターを簡単には死なせないために。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターの訓練も大変危険で、彼らは治療や傷の縫合を受けていました。白骨にその痕跡があるということは、彼らがグラディエーターであったと言えるでしょう。
【ナレーション】
骨は、彼らが重傷を負っても、また闘いに戻っていったことを証明しています。
【マーリン・ホルスト】
この頭蓋骨には鈍器による傷が16箇所あります。何らかの武器で殴られたようですが傷は深くなく致命傷ではありませんでした。しかし彼らには同様の傷が異常に多いのです。
【ナレーション】
この男は大けがを負ったうちの一人です。頭蓋骨が損傷していましたが、驚くべき事に彼は生き延びたのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
これほどの傷がつくということは、相当な力で殴られたはずです。この傷を受け、内出血したかもしれませんが、頭蓋骨の状態を調べるとかなり治癒しています。ということはこの人物は死んだわけはなく、その後、一定期間生存していたということになります。
【ナレーション】
治癒した傷跡は、グラディエーターが医者の治療を受けていたという見方と辻褄が合います。しかしある男はひどい致命傷を負っていました。彼はグラディエーターよりもはるかに恐ろしい相手と対戦したのです。それは野生の猛獣です。
闘獣士
【ナレーション】
古代ローマ時代のヨークで、最も名誉ある墓に埋葬された80体の白骨死体。骨には恐ろしい傷跡が残されていました。彼らは古代ローマの属州であったイギリスのグラディエーターで、流血を楽しむ大衆のために闘い、残酷な試合の中で惨殺されました。記録によると30以上の異なるタイプのグラディエーターがいて、それぞれ武器や戦法に特徴があったようです。
【リチャード・ジョーンズ】
グラディエーターにはそれぞれ得意技があり、皆それに見合った武器や道具を使っていました。試合は同じ武器を持つ者同士や、違う武器を持つ相手などを組み合わせて闘わせていました。
【ナレーション】
そしてある白骨遺体には、残虐な試合を物語る恐ろしい傷痕が残っていました。この男は発見された遺体の中でも最も小柄でした。調査の結果、その骨から驚くことが判明したのです。何と彼の骨盤には猛獣によってあけられたような穴があいていたのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
この白骨遺体は非常に珍しいものです。私は初めて見ましたが、正直気分のいいものではありません。この右側の骨盤を見てください。2カ所の損傷、2つの穴がはっきりと確認できます。さらに左側にも穴や損傷が見受けられます。この咬み痕をつけたのはどんな動物でしょう ?
【ナレーション】
この男にはグラディエーターのなかでも特に残虐な試合をさせられた証拠があります。それは猛獣を相手に死ぬまで闘うことです。
【ケビン・ディカス博士】
ライオンや虎との闘いは極めて危険で、多くの者が命を落としました。
【ナレーション】
対戦相手はライオンや虎だけではありませんでした。野生の犬や雄牛、時には熊がグラディエーターと闘いました。
ティム・トムソンは人類学の教授です。彼はこの体に致命傷を与えた動物を特定しようとしています。
【ティム・トムソン教授】
これは成人の人体骨格です。猛獣と闘った人物の傷は骨盤部分の左右両側にあります。具体的にはこの腸骨稜と呼ばれる部分です。咬まれたあとがこことここ、そして こことここにもあります。この傷は間違いなく動物に咬まれた痕です。この人物には複数の傷痕があります。
【ナレーション】
トムソン教授は最新技術を用いて、この男を襲撃した動物を判別しようとしています。3Dスキャナーを使って骨盤の破片をつなぎ合わせ、バーチャルで骨盤を再現しました。
【ティム・トムソン教授】
スキャンを行い、粉々になっていた骨盤をデータ化します。粉々になった骨盤の破片をバーチャル空間で再構築できます。最終的には骨盤の咬まれた痕を様々な動物の歯形と照合します。実物の骨を使ってできることではありません。
【ナレーション】
復元されたバーチャルの骨盤から、この男を攻撃した猛獣を割り出すことができます。
【ティム・トムソン教授】
猫や犬のような小さな動物ではありません。かなり大型のネコ科動物のような大きさだと思います。
【ナレーション】
骨盤の歯形をヤマネコと比較するため、大人のライオンの頭蓋骨をスキャンしました。
【ティム・トムソン教授】
これは骨盤の一部で、骨には動物が咬んだ痕と穴があります。今からここにライオンの頭蓋骨のスキャン画像を取り込みます。ライオンの歯形と骨盤の咬まれた痕がぴったりはまりました。
【ナレーション】
獰猛なライオンに攻撃されたこの男の末路は一つしか考えられません。さらに骨を詳しく調べたところ、傷は治らなかったことが確認されました。彼はライオンとの闘いで命を落としたのです。
【ティム・トムソン教授】
この咬み傷が致命傷になりました。そして大型肉食動物のものと一致します。
【ナレーション】
この男は闘獣士という、人ではなく野生動物を相手に闘うことを運命づけられたグラディエーターです。
【ダリウス・アーヤ博士】
闘獣士は野生の猛獣と闘うために特殊な訓練を受けたグラディエーターです。観客への娯楽として猛獣と殺し合うのです。それはとてつもなく危険な行為でした。相手は猛獣です。勝てる見込みはどれほどあったのでしょう ?
エピローグ
【ナレーション】
80体の古代ローマ人の死体が見つかった謎の墓地がグラディエーターのものであるという仮説は、多くの証拠によって裏付けられました。しかしこの白骨死体は全てグラディエーターであるならば、なぜ最後に斬首されたのでしょうか。斬首はグラディエーターの試合を締めくくる、とどめの一撃だったと考えられています。
【カート・ハンターマン】
闘技場で首を切り落とされた人々は、闘いの最後に情けをかけられたのだと思います。敗北して瀕死になった者は首を斬られたのです。
【ナレーション】
闘技場では敗者の運命は皇帝や観衆にゆだねられました。
【リチャード・ジョーンズ】
もし皇帝が闘技場で観戦していれば、彼が敗北したグラディエーターの生死を決めました。よく知られる合図はこうです。親指を立てれば助けられ、親指を下に向ければ死を意味しました。
【ナレーション】
すべてのグラディエーターが対戦相手に殺されたわけではありません。敗北し、死を宣告されたグラディエーターは、闘技場の死刑執行人の手によって殺されました。
【ダリウス・アーヤ博士】
時には、死への一撃を与える人間が闘技場に登場することもありました。劇的なラストです。
【ナレーション】
これらの白骨死体は、ヨークのグラディエーターを今に伝える興味深い証拠です。帝国じゅうから選び抜かれた男たちの骨には、危険な訓練を受けていた証があり、傷痕は歴史上最も残虐な試合をさせられていた事実を伝えています。
【カート・ハンターマン】
骨に残された人間による攻撃の痕や猛獣による咬み痕と他の証拠から判断して、白骨遺体は闘技場で闘い、この名誉な場所に葬られたグラディエーターたちであると考えます。そういった意味で古代ローマ帝国のヨークは特別な場所でした。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターの興業は、ローマから帝国中に広がりました。そしてヨークでもグラディエーターたちが闘ったことを裏付ける証拠が見つかったわけです。
【ナレーション】
死に際し、この男たちは英雄の扱いをうけましたが、その人生は生き延びるための闘いでした。惨殺された白骨死体はローマ帝国の真の残虐性を露わにしたものであり、ローマ文明の心の闇の証だったのです。
剣闘士の墓とする根拠
以降はこの番組のまとめです。首を切断された遺体は戦死者や犯罪人という事も考えられましたが、調査チームが出した結論は剣闘士(グラディエーター)です。その根拠は以下ようになるでしょう。
ジグソーパズルのピースがはまるように、多くの証拠が剣闘士の墓であることを示唆しています。決定的とも言えるのは最後の「猛獣の牙によって骨盤に穴があくほどの致命傷を負った遺体」でしょう。
調査団長のカート・ハンターマンがネットに公表しているリポートを読むと、発見された白骨遺体は82体ですが、そのうちの1体は女性でした。そしてハンターマンは、この女性がグラディアトリクス(gladiatrix。女性剣闘士)ではないかと推測しています。
No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で紹介したように、ローマの剣闘士については数々の本が書かれ、映画が作られ、絵画も制作されてきました。しかしこの番組が示した「白骨遺体の分析レポート」は、本・映画・絵とは違った意味で、2000年前の状況を非常に生々しく感じることができ、大変に印象的でした。
ここからは補足です。No.221「なぜ痩せられないのか」で、同位体分析の手法を使ってヒトの消費エネルギーを精密測定する話を書きましたが、本番組にも同位体分析が出てきました。歯のエナメル質の同位体分析で、出身地や食性がわかるというのです。なぜ可能なのか、調べてみると次のようです。いずれも安定同位体(No.221参照)を利用するようです。
そして、このような同位体分析は今や世界の常識であり、考古学だけでなく、たとえば食物の原産地証明や生物の食性分析などにも利用されているようです。
以上は一般論であって番組中のモンゴメリー博士の手法の詳細はわかりませんが、類似の方法だったと推察されます。博士は遺体の歯から出身地を推定し、さらに「彼らは野菜と肉の両方を食べていただけでなく、少量ですが魚も口にしていた可能性があります」と語っていました。そこまで分析できる測定技術の進歩に感心しました。
本文中のナレーションに、
とありました。ここで思い出すのが古代ローマの医師、ガレノスです。このブログで何回か引用した東京大学名誉教授の本村凌二氏がガノレスに関するエッセイを書かれていました。それを紹介しますと、まずガレノスの簡単なプロフィールが次です。
題名に "国手" という言葉が使ってありますが、中国の故事の「国を治すほどの名手」という意味から転じて、名医の意味や、医者に対する敬称として使われます。
プロフィールの中に「ルネサンス期まで西洋医学に絶大な影響を及ぼした」とありますが、確か、レオナルド・ダ・ヴィンチは人体の研究のために解剖も行うかたわら、ガレノスの書物で勉強をしたはずです。
そのガレノスは、実は、剣闘士の医者だったことがあります。本村先生の文章はガレノスの生涯を詳しく記述していますが、剣闘士に関係するところの前後を引用します。
「ヨーク首なしグラディエーター」では、大金をかけて育てたグラディエーターを簡単には死なせないために治療を施したとの説明がありました。ヨークで発見された遺体が剣闘士であることの根拠の一つは、傷の治療が施されていることです。まさに、剣闘士養成所の医師は重要な役割を持っていた、それが本村先生が書いているように、医師からすると外科医としての貴重な経験になったわけです。
ちなみにガレノスの故郷であり、剣闘士の医師として働いたペルガモンは、本文で出てきたエフェソスと同じ小アジア(現在のトルコ)にあります。エフェソスと違ってペルガモンには現在、円形闘技場や剣闘士の墓の跡は残っていませんが、2000年前は都市の発展とともに剣闘士の試合が盛んに行われたのでしょう。
余談ですが、連想したので書きます。本文中でティム・トムソン教授は発掘された穴のあいた骨盤を分析し、ライオンがグラディエーター(具体的には闘獣士)に噛みついた痕跡と結論付けていました。
これで思い出すのが「ライオンは獲物を攻撃する時にお尻に噛みつく」との説です。必ずそうなのか、信憑性のほどは知りません。ただ、ライオンが人のお尻に噛みついている瞬間を描いた有名な彫刻があります。フランスのピエール・ピュジェ(1620-1694)作の「クロトンのミロン」(1671-1682頃)です。
クロトン(南イタリア、現在のクロトーネ)出身のミロンは、ギリシャでレスリング選手として活躍しました。伝説では、ミロンは腕力で木を倒そうとし平手で木を引き裂いた、木は引き裂けたものの手が木の裂け目に挟まって取れなくなってしまった、そのとき獣がミロンに襲いかかり、片腕しか使えなかったミロンは食い殺されてしまった、とされています。要するに「過信は禁物」という教訓話です。
ピュジェの彫刻は、獣をライオンとしています。ルーブル美術館のピュジェの広場(リシュリュー翼)にあります。

2004年8月、英国のイングランドの北部の町、ヨーク(York)で古代ローマ時代の墓地が発掘されました。この発掘の様子と、埋葬されていた遺体の分析が最近のテレビ番組で放映されました。
|
です。これは英国の Blink Films プロダクションが制作したドキュメンタリー、"The Headless Gladiators in York(2017)" を日本語訳で放送したものですが、古代ローマの剣闘士に関する大変に興味深い内容だったので、その放送内容をここに掲載しておきたいと思います。なお、グラディエーター(=剣闘士)は英語であり、ラテン語ではグラディアトルです。

| ||
|
ヨークの首なしグラディエーター
2000年前に死んだ80人の謎を解く
(BS朝日「地球大紀行」より。画像はヨーク市街)
| ||

(site : annamap.com)
出演者
このドキュメンタリー番組は、ナレーションとともに8人の考古学者・人類学者が解説をする形をとっています。出演したのは次の人たちです。
◆カート・ハンターマン(Kurt Hunter-Mann)
考古学者で「ヨーク考古学トラスト(York Archaelogy Trust)」の遺跡発掘の専門家。今回の古代ローマ墓地の発掘チームでリーダーを勤めた。
◆マーリン・ホルスト(Malin Holst)
英国の骨考古学(Oestearchaelogy。人の骨の分析による考古学)の専門家。ヨーク大学講師。
◆シャーロット・ロバーツ博士(Charlotte Roberts)
英国・ダラム(Durham)大学の考古学者。生物考古学(Bioearchaelogy。人・動物・植物など生物の分析による考古学)が専門。なお番組ではダーハム大学とありましたが、Durhamの h は発音しないので、ダラム(ないしはダーラム)が正解。ダラムはヨークの北、イングランド北部の大学町。
◆ジャネット・モンゴメリー博士(Janet Montgomery)
ダラム大学の考古学者(生物考古学)。骨の同位体分析を担当。
◆ティム・トムソン教授(Tim Thompson)
英国・ティーズサイド大学の人類学者。ティーズサイド大学はイングランド北部の町、ミドルズブラ(Middlesbrough)にある。
◆ダリウス・アーヤ博士(Darius Arya)
米・ローマ文化協会のディレクター。
◆ケビン・ディカス博士(Kevin Dicus)
米・オレゴン大学の考古学者。
◆リチャード・ジョーンズ
歴史学者。
以下に、番組の全スクリプトを掲載します。注 : ・・・・・・ と書いたのは番組にはないコメントです。「プロローグ」などのタイトルも付け加えたものです。番組の中で日本語訳がおかしい(ないしは曖昧な)部分がありましたが、それもコメントしました。【ナレーション】の部分は日本語訳のナレーションで、学者の解説の部分は日本語字幕付きの英語で放送されました。
プロローグ
【ナレーション】
古代考古学史上、最も凄惨な出土品がイギリスの都市・ヨークで発見されました。それは80体以上の男性の首を切られた白骨死体。
【カート・ハンターマン】
発掘を始めると何か奇妙だと感じたんです。
【マーリン・ホルスト】
遺体の6割以上が一撃で首を切り落とされていました。
【ナレーション】
彼らは残酷な死に方をしましたが、そこは常識を覆す墓だったのです。凶暴で生涯を鎖で拘束されていましたが、何と、宝物と一緒に埋められていたのです。男たちに刻まれた残虐な傷跡。
【シャーロット・ロバーツ博士】
(注:骨を見ながら)この人物は度重なる攻撃を受けています。
【ナレーション】
この傷だらけの男たちはいったい何者なのでしょう。10年の調査を経て、専門家チームはその謎をついに解き明かしたのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
彼らは生きる伝説でした。
【ナレーション】
遺跡に秘められた過去。金で、石で、そして血で記された歴史。古代の謎を解き明かし、歴史の偉大なる秘宝の数々をお見せしましょう。

| ||
|
ヨークのギルドホールに安置された白骨遺体。合計80体以上の古代ローマ時代の遺体が発掘された。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
イギリス、ヨークでの大発見
【ナレーション】
歴史ある町、ヨーク。西暦1000年までの過去を知ることは考古学者の夢。この町はイギリス2000年の歴史を今に伝えています。2004年8月、旧市街からほど近くにある小さな区画(注:ドリフフィールド・テラス。Driffield Terras)で発掘調査が行われました。単なる発掘調査のはずでしたが、とんでもない発見があったのです。
【発掘調査員の声】
ここに骨、そして頭蓋骨、まるい形状をしているだろう。この角にも骨があるぞ。
【ナレーション】
さらに深く掘ると、たくさんの白骨死体が完全な姿で出てきたのです。衝撃の事実とともに ・・・・・・。何と、遺体の多くは意図的に首を切り落とされていたのです。これが調査団長のカート・ハンターマンと大きな謎の出会いでした。
【カート・ハンターマン】
発掘を始めてすぐに奇妙だと思いました。首を切り落とされた白骨の遺体があまりにもたくさんあったからです。

| ||
|
発掘現場で作業を行う調査団のリーダー、カート・ハンターマン(右側)
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【ナレーション】
発掘調査が始まって数日後には、発見された遺体の数は2桁にのぼり、どんどん増え続けました。
【カート・ハンターマン】
発掘作業終了時には 80体以上もの遺体を堀り出しました。そのうち4分の1が首を切り落とされていたのです。
| 注:プロローグのところで骨考古学者のマーリン・ホルストは、6割以上が首を切り落とされていたと発言しています。上記のハンターマンの "4分の1" と不一致ですが、これはおそらく、発掘現場では4分の1が首なし遺体だったが(頭蓋骨が首とは別のところにあったなど)、骨を詳しく分析すると6割が首を切り落とされてた、ということだと思います。ハンターマンがネットに公開している論文をみても「6割が斬首されていた」が正しいようです。 |
【ナレーション】
考古学者40年のカートのキャリアの中でも、類のない発見だったのです。
【カート・ハンターマン】
ローマ時代の首なし遺体の墓を初めて見ました。しかも狭い面積にたくさんの遺体が埋まっていたなんて。
【ナレーション】
首なしの遺体はいったい何者なのか。謎を解明する第1のヒントは遺跡に隠されていました。過去の発掘調査で、この周辺は昔、大きな墓地だったことがわかっていました。出土品から、ここがヨークに存在する最大規模の墓地で、都市が建設された2世紀終盤ごろにさかのぼることもわかりました。ローマ時代のことです。
【カート・ハンターマン】
周辺にも古代ローマ時代の墓があるので、我々も同様の墓を発見するかもと思っていました。
【ナレーション】
首なし遺体と一緒に発見された陶器により、古代ローマ人の墓地だと裏付けられました。しかし、他のローマ時代の墓とは様相が異なっていたのです。
【カート・ハンターマン】
とても奇妙でした。
【ナレーション】
遺体の多くは首を切り落とされていただけでなく、その頭は両足の間に丁寧に置かれていたのです。

| ||
|
発掘遺体の1例。頭蓋骨が首から切断され、両足の間に置かれている。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【カート・ハンターマン】
首を切り落とされていた事だけでも奇妙なのに、この変わった遺体の安置方法を見て、古代ローマ人は一体何を考えていたのかと首を傾げました。
【ナレーション】
考古学者たちを困惑させたのは、ひとつの墓地に埋葬されていた首なし遺体の数です。処刑された犯罪者だという見方もできますが、通常、ローマ時代の犯罪者はうつ伏せで埋葬されます。しかしこの墓では仰向けで埋められていました。この奇妙な墓には、いったいどのような意味があるのでしょうか。
謎解きの次のヒントはローマ帝国時代のヨークの役割を知ることでした。かつてエボラクムと呼ばれたこの都市には、2人のローマ皇帝が滞在していたことがわかりました。皇帝が宮廷を構え、軍事的にも重要な拠点だったのです。
【ケビン・ディカス博士】
皇帝の行く先には帝国の行政機関も全て移動します。そしてヨークはローマ帝国 属州の中心地になりました。
【ナレーション】
ローマ帝国のイギリス侵略は紀元43年に始まり、その後30年間にわたり侵攻を続けたのです。しかし北方の部族の抵抗はすさまじいものでした。
【ケビン・ディカス博士】
部族の抵抗にローマ軍は驚愕しました。森や沼地の中にひそみ、奇襲をかけ、攻撃を終えると姿をくらますというゲリラ戦法が彼らの得意技だったのです。鍛え抜かれ統率された軍隊が未開地の部族に完敗してしまうこともあったのです。
【ナレーション】
当初、墓地がローマ軍の侵攻と同時代のものであったことから、首なしの死体はローマ軍と部族の戦死者だと考えられていました。なぜなら、ほぼすべての白骨死体は男性で、戦闘に適した年齢にあったからです。
【マーリン・ホルスト】
ローマ時代の墓では男性の遺体の数が女性よりやや多い程度ですが、ドリフフィールド・テラスに埋められていたのは全員が成人男性だったのです。しかも45歳以上はいないという特異な例でした。つまりこれらは比較的若く、健康で、特別な存在だったのかもしれません。
| 注:マーリン・ホルストは "almost soley man adults" と発言しているので「ほぼ全てが成人男性」が正しい理解です。カート・ハンターマンがネットに公開している論文をみると、発掘された白骨遺体は 82体 で、そのうちの1体は女性だったようです。 |
【ナレーション】
彼らは健康な若い男たちで、人生の盛りに亡くなったようです。しかし無視できない疑問が一つありました。彼らがもし殺された兵士だとしたら、遺体は都市ではなく戦場に埋葬されるはずです。その一方で遺体には、まるで殺戮された兵士のように、すざましい戦闘を経験した痕跡がありました。首を切り落とされただけではなく、骨の多くに骨折が治った痕があったのです。そこで興味深い新説が浮上しました。戦いの中で鍛え抜かれ虐殺された男たちは古代ローマを象徴するだった。それはグラディエーターです。

| ||
|
白骨遺体を調査するヨーク大学のマーリン・ホルスト(骨考古学)。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
剣闘士(グラディエーター)
【ナレーション】
ヨークに眠っていたおぞましい遺物。何10体もの男性の白骨。考古学者のカート・ハンターマンと調査団は、古代ローマの墓地で難解な謎に直面していました。男たちは戦闘経験者でしたが、兵士ではなかったのです。首を切り落とされた彼らは何者だったのでしょう。考古学者たちは驚くべき新説をたてました。それはこの墓がグラディエーター、つまり剣闘士のものではないかという説です。もしそれが本当なら、イギリスにおける古代ローマ人の歴史を塗り替えることになります。
【ケビン・ディカス博士】
イタリアのローマですら、グラディエーターの墓の発見はすごいことなんです。イギリスでグラディエーターの大規模な墓が発見されたら、とても驚くでしょう。
| 注:番組の字幕は「とても驚くでしょう」となっていましたが、ディカス博士は "would be truely remarkable" と言っているので「(剣闘士の墓だとしたら)本当に驚くべきことです」ぐらいが妥当。 |
【ナレーション】
墓から遺体を掘り出した調査団は、グラディエター説を裏付ける証拠を探し始めました。すると彼らは、まぎれもなく壮絶な戦闘を経験した者たちであることが明らかになったのです。
【マーリン・ホルスト】
この人物は生存中にかなりの外傷を負ったことが骨折痕からわかります。肋骨にも外傷によると思われる骨折痕があり、そして右膝の裏には刀傷、脛には炎症性の損傷があって、ここも一撃されたようです。
【ナレーション】
この男は墓地で発見された中でもひどい傷跡がある一人です。骨折の多くは直っており、彼らが数年にわたって危険な戦闘に耐えてきたことがうかがわれます。そして白骨死体の多くに共通する致命傷があります。それは斬首です。
【マーリン・ホルスト】
6割以上が一撃で首を切り落とされていました。(注:骨を見せながら)これは首の脊椎と頸椎と呼ばれる部分です。この骨に頭が載っていて、その一つ下にあるのが頭を左右に動かす部分です。これを見ると頸椎のこの部分が完全に削ぎ落とされています。そしてこれが脊椎の部分全体を切断した痕です。
【ナレーション】
まっすぐに切断された骨を見ると、男たちが刀剣や斧などの鋭利な武器によって斬首されたことがわかります。

| ||
|
鋭利な刃物の一撃でスパッと切断された頸椎をマーリン・ホルストが示している。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【マーリン・ホルスト】
首を切り落とした最後の一撃は、かなり強烈だったと思います。切り口がここから(注:マーリン・ホルストが手で自分の首の後ろを示す)あごの横まで到達しているのです。衝撃によりあごは粉々になり、たくさんの破片となって飛び散っています。
【ナレーション】
中には、頭を切り落とされるまでに何度も切りつけられた者もいます。
【シャーロット・ロバーツ博士】
この人は、数回首を切りつけられたと思われます。一撃でスパッと頭が切り落とされずに何回も刀を振るわれたのでしょう。一度目がうまくいかなかったか、あるいは確実に首を切り落とすために念を入れたのかもしれません。

| ||
|
白骨遺体を調査するダラム大学のシャーロット・ロバーツ博士(生体考古学)。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【ナレーション】
遺体は斬首されるまで、壮絶な戦闘を強いられていたことを物語っています。さらに遺体にはグラディエーターだったことを裏付ける、ある手がかりが隠されていたのです。それは骨ではなく、歯に残されていました。
歯の分析から判明した出身地
【ナレーション】
ジャネット・モンゴメリー博士は生物考古学者で、専門は遺体の分析です。この2000年前の歯を調べた結果、男たちの出身地を突き止めたのです。彼らの素性を解明するためには貴重な情報で、それは同位体分析という技術(注:最後の「補記1」参照)が鍵となりました。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
同位体分析とは古代人の歯に残されている生存時の情報を引き出す技術です。彼らがどんなものを食べていたのか、住んでいた場所、環境、気候なども判別できます。さらに地元出身者であったか、それとも他所からやってきたのかを立証することもできるのです。

| ||
|
同位体分析を行うダラム大学のジャネット・モンゴメリー博士(生体考古学)。遺体の歯から出身地を推定した。同位体分析の手法については最後の「補記1」を参照。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【ナレーション】
歯のエナメル質を同位体分析した結果、ここは国際的な墓地だったことがわかりました。発見された遺体の中でヨーク出身のものは少数で、多くはイギリス出身ですらなかったのです。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
寒い地域から温暖な地域まで様々な土地の出身者がいました。当時のイギリスの食習慣にはない植物を食べていたことも分かっています。彼らは他の土地から来た集団だったのです。
【ナレーション】
分析によると男たちはヨークで死亡しましたが、もともとはローマ帝国の各地からやってきたことがわかりました。そしてある男は驚くほど遠方の出身者でした。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
同位体のデータによると、この男は南方の温暖で乾燥した地域の出身であることがわかりました。その遺伝的祖先は中近東です。
【ナレーション】
何とこの男は母国のある中近東から4800キロも離れたヨークで死亡したのです。
多くの証拠が集まりました。この墓は帝国中から寄せ集められた、鍛え抜かれし戦闘経験者のものだったのです。彼らはまさにグラディエーターそのものでした。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターとは何者だったのでしょう ? その多くは犯罪者や戦争捕虜でした。軍隊経験があり、健康状態が良好で訓練を重ねれば立派なグラディエーターになれる者たちです。
【ナレーション】
ハンターマンにはもう一つ、極め付きの証拠がありました。彼らの墓地はイギリスにある他のローマ時代のものとは様相が異なっていたかもしれません。しかし、3200キロ離れたトルコにある墓地にそっくりだったのです。
エフェソス

| ||
|
エフェソスの円形闘技場。トルコ西部のエフェソスは、古代ギリシャ時代から古代ローマにかけて繁栄した都市。数々の遺跡が残っており、世界遺産に登録されている。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【ナレーション】
ここはエフェソス。古代ローマ帝国に属する州の中心地で、25,000人を収容する円形闘技場がありました。1993年、ここからわずか数メートルのところで墓地が発見されました。ヨーク同様、ここで発見された遺体は戦闘経験のある男たちで、残酷な方法で処刑されていました。しかしエフェソスの男たちが何者であるかはすぐに判明しました。墓石に彼らが剣闘士、グラディエーターであったことが記されていたのです。そしてハンターマンはこの2つの墓地の類似点に驚愕しました。
【カート・ハンターマン】
ヨークの白骨遺体はエフェソスのものと良く似ています。私はグラディエーター説を支持しますが、それは生活様式や埋葬場所に説得力があるからです。私からみると全てが闘技場で闘っていたある特定の男達だけに当てはまるのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
ヨークでの発見は、剣闘士にまつわる環境がもう1つ存在していた可能性を開いたのです。
| 注:「剣闘士にまつわる環境がもう1つ存在していた可能性」とは、意味のとりにくい字幕です。アーヤ博士の発言は "open up the possibility we found an another similiar situation of gladiators" で、明らかにエフェソスの剣闘士の墓をふまえています。「剣闘士について(エフェソスとは)別の、類似の場所を発見した可能性」が正確な意味でしょう。 |
【ナレーション】
ヨークでのグラディエーターの墓と思われる遺跡の大発見は、考古学者たちに一世一代のチャンスをもたらしました。それは古代ローマ文明の闇を解き明かすこと。グラディエーターの試合、闘技会。娯楽のために人が殺される、残虐非道な競技です。
闘技会の多くは古代ローマを象徴する建物、コロセウムで開催されました。西暦80年に落成し5万人を収容するこの円形闘技場は、歴史上最も残酷な競技を興業するためのものだったのです。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターは強靱な人間たちでした。闘技場で死と直面しつつ、一般の観衆のために闘ったのです。彼らは生きる伝説でした。
【ナレーション】
コロセウムでは70万人以上のグラディエーターが闘い、死んだと推定されています。
【ダリウス・アーヤ博士】
現代ではグラディエーターのような見世物はありません。少なくとも合法的には。観客は流血沙汰を期待して行くわけですからね。誰かが腹を切られ、腕を切り落とされ、もしくは頭を切り落とされる。信じられないほどおぞましいものだったのです。
【ナレーション】
2000年もの時を経て、考古学者たちは過去最大規模のグラディエーターの墓を発掘したのかもしれません。しかもローマではなく、1,600キロも離れたイギリス、歴史ある町、ヨークで ・・・・・・。発掘された80体以上の白骨遺体は、古代ローマ帝国の様々な地域からやってきた男たちでした。彼らは壮絶な人生を送り、最終的には首を落とされましたが、埋葬される際には敬意が払われていたようです。これらの証拠は、彼らが古代ローマのグラディエーターだったことを物語っています。
【ダリウス・アーヤ博士】
ヨークで発見した証拠を調べ、科学分析を進めるにつれて、パズルのピースがはまっていきます。男たちががっしりした体格だったこと、年齢、その他どんどん説得力が増していきます。
食生活
【ナレーション】
現代ではグラディエーターは古代ローマのスーパースター、エリートだと見なされているかもしれません。しかし遺体の歯を分析するにつれて、彼らの過酷な生活を明らかにする驚きの新事実が判明したのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
エナメル質に異常が見られる歯がたくさんありました。この犬歯がよい例です。歯に横線が入っています。横線は歯の成長期にこの人物がストレスを受けていたことを示しています。この人は幸せな幼少期を過ごせず、こうした異常なことが人生で起こっていたのでしょう。
【ナレーション】
墓で発見された多くの男たちの歯にはこうした線が見受けられましたが、それは乳児栄養失調の証です。しかし彼らは成人してから高タンパクの食事をとっていたことが歯に現れています。
【ジャネット・モンゴメリー博士】
彼らは野菜と肉の両方を食べていただけでなく、少量ですが魚も口にしていた可能性があります。
【ナレーション】
古代ローマ時代のヨークで肉と魚を食べていたということは、恵まれた食生活だったのでしょう。
【ダリウス・アーヤ博士】
彼らは食事を与えられ、良い栄養状態でした。そして強く、丈夫な体になっていきました。一体何があったのでしょう ?
【ナレーション】
歯の証拠から推測すると、ローマ帝国中から貧しい男たちが集められ、闘うための肉体づくりをさせられていたと考えられます。
【ケビン・ディカス博士】
彼らは最下層の身分でしたが、剣闘士の興行師 "ラニスタ" に素質を認められ、身請けされました。そして資金を回収するため訓練を施し、食事と住む場所を与えたのです。
【ナレーション】
男たちはグラディエーターの養成所で高タンパクの食事を与えられました。デビューまでに筋肉をつけて体を大きくするためです。
【ケビン・ディカス博士】
彼らの体格はかなり良かったはすです。帝国一、筋肉隆々で運動能力が高く、その肉体は世間から注目を浴びていたはずです。
副葬品と埋葬場所
【ナレーション】
彼らの墓の副葬品から、貧困層の身分であったグラディエーターたちが一目置かれていたことがわかります。
【カート・ハンターマン】
古代ローマ時代では、墓に副葬品を入れるのが一般的でした。故人が死後の世界で幸せになるための品物が入れられます。
【ナレーション】
ヨークの白骨遺体とともに発見したのは、数々の酒の器や大量に供えられた食べ物でした。さらに彼らの地位の高さを示す副葬品は、多くの銀貨でした。銀貨には様々なローマ皇帝の肖像が描かれていて、この埋葬方法はローマ帝国がイギリスを支配しているあいだ、ずっと行われていたことが明らかになったのです。つまり、グラディエーターたちは4世紀にわたりヨークで活躍していたことになります。
【カート・ハンターマン】
墓からは1世紀から4世紀までの銀貨数種類が出土しています。こちらはコンスタンティヌス2世のもので、紀元330年ごろになります。つまり古代ローマの終わりまで続いていたということです。
【ナレーション】
しかし、男たちが尊敬されていたことを示す一番の証拠は、墓の位置でした。帝国全体の習慣で墓の場所は社会的地位を表していたのです。墓地の発掘にあたっていた考古学者たちは、グラディエーターたち全ての墓が最も名誉ある場所にあったと確証を得たのです。
【カート・ハンターマン】
この墓地(注:Driffield Terras)は古代ローマ時代の大きな街道沿いにあります。当時、通行人に死者を思い出させるこの場所に埋葬されることは大変意味のあることでした。さらに小高い丘になっていることも、この場所の重要性を高めています。この場所は帝国有数の埋葬場所だったのです。
【ナレーション】
特別に鍛え抜かれた若い男たちの集団。死に際しては一般大衆からもその勇姿が称えられました。しかしその一方で、白骨からはある衝撃的な事実が判明しました。この優秀な戦士たちは、生前に奴隷よりは少しはましな扱いを受けていましたが、時には闘技場での生死を左右する恐ろしいハンデを背負わされていたのです。
足かせ
【ナレーション】
ローマ時代、グラディエーターは大きなビジネスでした。毎試合ごとの勝負で、巨額の金が動いていました。有望な新人を確保するために、奴隷売買が横行していたのです。闘技場デビューをさせるため、グラディエーターの育成にはたくさんの金がつぎ込まれました。男たちはただの奴隷よりりは少しはましな扱いを受けていたのです。
【ケビン・ディカス博士】
グラディエーターたちは訓練を受けながら、充実した食事や医療を施されていました。しかしその一方で彼らに自由はなく小部屋に閉じこめられていました。決められたスケジュール通りに過ごすことが強制され、まるで刑務所のようでした。
【リチャード・ジョーンズ】
奇妙な生活ですが、強い肉体をつくる上での待遇には恵まれていました。しかし、その待遇は一時的なものです。
【ナレーション】
(注:白骨遺体の画像が写し出される。次図)彼らが自分の運命ですら選択できなかったことを示す証拠があります。専門家は当初、足かせをはめられた状態で埋葬されていたと考えていました。

| ||
|
足かせをはめられて発見された遺体。白骨遺体の中では最も大きな体格だった。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【カート・ハンターマン】
これが遺体の足にはまった状態で発見された足かせです。こんなものは初めて目にしました。まさに強運な考古学者が一生に一度だけ出会えるかもしれない稀有な物です。
【ナレーション】
これはただの足かせではありません。現代の足かせのように取り外しができるものではなかったのです。X線分析の結果、足かせはこのグラディエーターに死ぬまで装着されていたのです。
【カート・ハンターマン】
普通の足かせなら両足を鎖でつなぐための留め具があるはずですが、そのようなものは見当たりませんでした。
【ナレーション】
これらは特注の足の重りだったのです。この男に体の不自由と苦痛を与えるために作られました。分析の結果、この足かせは高温に熱した二つの鉄を足首に巻き付け、一つの輪に成形していたことがわかりました。
【カート・ハンターマン】
真っ赤に熱した鉄を人の足に巻きつけるなんて、野蛮としか言えません。
【ナレーション】
白骨の分析では、死ぬまではずせない足かせの残酷な実態が明らかになったのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
彼の足の骨には新しい骨形成の痕跡があり、これは炎症が起こった証です。つまり足首の部分に何らかの外傷が何度も加えられたということです。また当時はこのような炎症を治療できなかったので、彼らは赤く腫れ上がった炎症の痛みに死ぬまで耐えるしかなかったのです。
【ナレーション】
いったいなぜこの男は、これほど恐ろしい罰を受けていたのでしょう。彼は白骨遺体の中で最も大きな体格でした。重い足かせは、この巨体のグラディエーターの動きを鈍らせるものだったのでしょう。血を見て喜ぶローマの大衆に、より刺激的な試合を見せるために。
【ケビン・ディカス博士】
剣闘士に足かせなどを装着しハンデを負わせるということはたまにあったようです。例えば体の大きさが違いすぎて公平な試合にならない場合です。さらにそれがグラディエーターの個性となり、試合をより盛り上げるのです。
治療
【ナレーション】
この足かせの例は極めて珍しいですが、発見されたほとんどの遺体に、傷の治ったあとがありました。当時では贅沢なことですが、彼らには治療が施されていたようです(注:最後の「補記2」参照)。大金をかけて育てたグラディエーターを簡単には死なせないために。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターの訓練も大変危険で、彼らは治療や傷の縫合を受けていました。白骨にその痕跡があるということは、彼らがグラディエーターであったと言えるでしょう。
【ナレーション】
骨は、彼らが重傷を負っても、また闘いに戻っていったことを証明しています。
【マーリン・ホルスト】
この頭蓋骨には鈍器による傷が16箇所あります。何らかの武器で殴られたようですが傷は深くなく致命傷ではありませんでした。しかし彼らには同様の傷が異常に多いのです。
【ナレーション】
この男は大けがを負ったうちの一人です。頭蓋骨が損傷していましたが、驚くべき事に彼は生き延びたのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
これほどの傷がつくということは、相当な力で殴られたはずです。この傷を受け、内出血したかもしれませんが、頭蓋骨の状態を調べるとかなり治癒しています。ということはこの人物は死んだわけはなく、その後、一定期間生存していたということになります。
【ナレーション】
治癒した傷跡は、グラディエーターが医者の治療を受けていたという見方と辻褄が合います。しかしある男はひどい致命傷を負っていました。彼はグラディエーターよりもはるかに恐ろしい相手と対戦したのです。それは野生の猛獣です。
闘獣士
【ナレーション】
古代ローマ時代のヨークで、最も名誉ある墓に埋葬された80体の白骨死体。骨には恐ろしい傷跡が残されていました。彼らは古代ローマの属州であったイギリスのグラディエーターで、流血を楽しむ大衆のために闘い、残酷な試合の中で惨殺されました。記録によると30以上の異なるタイプのグラディエーターがいて、それぞれ武器や戦法に特徴があったようです。
【リチャード・ジョーンズ】
グラディエーターにはそれぞれ得意技があり、皆それに見合った武器や道具を使っていました。試合は同じ武器を持つ者同士や、違う武器を持つ相手などを組み合わせて闘わせていました。
| 注:No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で、魚剣闘士(ムルミッロ)と投網剣闘士(レティアリウス)の話を書きましたが、剣闘士にはその他、いろいろの種類がありました。日本語版 Wikipedia にその解説があります。 |
【ナレーション】
そしてある白骨遺体には、残虐な試合を物語る恐ろしい傷痕が残っていました。この男は発見された遺体の中でも最も小柄でした。調査の結果、その骨から驚くことが判明したのです。何と彼の骨盤には猛獣によってあけられたような穴があいていたのです。
【シャーロット・ロバーツ博士】
この白骨遺体は非常に珍しいものです。私は初めて見ましたが、正直気分のいいものではありません。この右側の骨盤を見てください。2カ所の損傷、2つの穴がはっきりと確認できます。さらに左側にも穴や損傷が見受けられます。この咬み痕をつけたのはどんな動物でしょう ?

| ||
|
動物に咬まれた痕が残る骨盤の一部
(site : www.yorkarchaeology.co.uk) | ||
【ナレーション】
この男にはグラディエーターのなかでも特に残虐な試合をさせられた証拠があります。それは猛獣を相手に死ぬまで闘うことです。
【ケビン・ディカス博士】
ライオンや虎との闘いは極めて危険で、多くの者が命を落としました。

| ||
|
闘獣士のモザイク画
(ローマ:ボルゲーゼ美術館) | ||
【ナレーション】
対戦相手はライオンや虎だけではありませんでした。野生の犬や雄牛、時には熊がグラディエーターと闘いました。
ティム・トムソンは人類学の教授です。彼はこの体に致命傷を与えた動物を特定しようとしています。
【ティム・トムソン教授】
これは成人の人体骨格です。猛獣と闘った人物の傷は骨盤部分の左右両側にあります。具体的にはこの腸骨稜と呼ばれる部分です。咬まれたあとがこことここ、そして こことここにもあります。この傷は間違いなく動物に咬まれた痕です。この人物には複数の傷痕があります。
【ナレーション】
トムソン教授は最新技術を用いて、この男を襲撃した動物を判別しようとしています。3Dスキャナーを使って骨盤の破片をつなぎ合わせ、バーチャルで骨盤を再現しました。
【ティム・トムソン教授】
スキャンを行い、粉々になっていた骨盤をデータ化します。粉々になった骨盤の破片をバーチャル空間で再構築できます。最終的には骨盤の咬まれた痕を様々な動物の歯形と照合します。実物の骨を使ってできることではありません。
【ナレーション】
復元されたバーチャルの骨盤から、この男を攻撃した猛獣を割り出すことができます。
【ティム・トムソン教授】
猫や犬のような小さな動物ではありません。かなり大型のネコ科動物のような大きさだと思います。
【ナレーション】
骨盤の歯形をヤマネコと比較するため、大人のライオンの頭蓋骨をスキャンしました。
| 注:ここは日本語として変な訳になっています。"ヤマネコ" は英語で wild cat だと推定されますが、ここではヤマネコではなく「野生のネコ科動物」の意味でしょう。 |
【ティム・トムソン教授】
これは骨盤の一部で、骨には動物が咬んだ痕と穴があります。今からここにライオンの頭蓋骨のスキャン画像を取り込みます。ライオンの歯形と骨盤の咬まれた痕がぴったりはまりました。

| ||
|
発見された破片をコンピュータ上で骨盤に復元した画像を説明する、ティーズサイド大学のティム・トムソン教授(人類学)。
| ||

| ||
|
骨盤に大人のライオンの頭蓋骨を重ねた画像。ライオンの歯形と骨盤の咬まれた痕がぴったりとはまった。
(BS朝日「地球大紀行」より)
| ||
【ナレーション】
獰猛なライオンに攻撃されたこの男の末路は一つしか考えられません。さらに骨を詳しく調べたところ、傷は治らなかったことが確認されました。彼はライオンとの闘いで命を落としたのです。
【ティム・トムソン教授】
この咬み傷が致命傷になりました。そして大型肉食動物のものと一致します。
【ナレーション】
この男は闘獣士という、人ではなく野生動物を相手に闘うことを運命づけられたグラディエーターです。
【ダリウス・アーヤ博士】
闘獣士は野生の猛獣と闘うために特殊な訓練を受けたグラディエーターです。観客への娯楽として猛獣と殺し合うのです。それはとてつもなく危険な行為でした。相手は猛獣です。勝てる見込みはどれほどあったのでしょう ?
| 注:「特殊な訓練を受けたグラディエーター」とアーヤ博士は言っていますが、No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で書いたように、猛獣の方も幼いころに捕らえられ、闘獣士と闘うために特別の訓練を受けました。これはローマでの話ですが、ヨークでもそうだったのではと思います。要するに「観客を熱狂させて興業的価値をあげる」わけです。 |
エピローグ
【ナレーション】
80体の古代ローマ人の死体が見つかった謎の墓地がグラディエーターのものであるという仮説は、多くの証拠によって裏付けられました。しかしこの白骨死体は全てグラディエーターであるならば、なぜ最後に斬首されたのでしょうか。斬首はグラディエーターの試合を締めくくる、とどめの一撃だったと考えられています。
【カート・ハンターマン】
闘技場で首を切り落とされた人々は、闘いの最後に情けをかけられたのだと思います。敗北して瀕死になった者は首を斬られたのです。
【ナレーション】
闘技場では敗者の運命は皇帝や観衆にゆだねられました。
【リチャード・ジョーンズ】
もし皇帝が闘技場で観戦していれば、彼が敗北したグラディエーターの生死を決めました。よく知られる合図はこうです。親指を立てれば助けられ、親指を下に向ければ死を意味しました。
【ナレーション】
すべてのグラディエーターが対戦相手に殺されたわけではありません。敗北し、死を宣告されたグラディエーターは、闘技場の死刑執行人の手によって殺されました。
【ダリウス・アーヤ博士】
時には、死への一撃を与える人間が闘技場に登場することもありました。劇的なラストです。
【ナレーション】
これらの白骨死体は、ヨークのグラディエーターを今に伝える興味深い証拠です。帝国じゅうから選び抜かれた男たちの骨には、危険な訓練を受けていた証があり、傷痕は歴史上最も残虐な試合をさせられていた事実を伝えています。
【カート・ハンターマン】
骨に残された人間による攻撃の痕や猛獣による咬み痕と他の証拠から判断して、白骨遺体は闘技場で闘い、この名誉な場所に葬られたグラディエーターたちであると考えます。そういった意味で古代ローマ帝国のヨークは特別な場所でした。
【ダリウス・アーヤ博士】
グラディエーターの興業は、ローマから帝国中に広がりました。そしてヨークでもグラディエーターたちが闘ったことを裏付ける証拠が見つかったわけです。
【ナレーション】
死に際し、この男たちは英雄の扱いをうけましたが、その人生は生き延びるための闘いでした。惨殺された白骨死体はローマ帝国の真の残虐性を露わにしたものであり、ローマ文明の心の闇の証だったのです。
■■■■■■ 番組終了 ■■■■■■
剣闘士の墓とする根拠
以降はこの番組のまとめです。首を切断された遺体は戦死者や犯罪人という事も考えられましたが、調査チームが出した結論は剣闘士(グラディエーター)です。その根拠は以下ようになるでしょう。
| ◆ | 通常、ローマ時代の犯罪人はうつ伏せで埋葬された。しかしこの墓では仰向けで埋められていた。犯罪人とは考えにくい。 | ||
| ◆ | 戦闘で死んだ兵士だとしたら、遺体は都市ではなく、戦場ないしは前線基地に埋葬されたはずである。 | ||
| ◆ | 骨には数多くの骨折痕とそれが治癒したあとがあり、彼らが数年にわたって危険な戦闘に耐えてきたことがうかがわれる。 | ||
| ◆ | 男たちの出身地はローマ帝国の全域(最も遠くは中東)に散らばっている。イギリス出身者は少数である。 | ||
| ◆ | まっすぐに切断された骨を見ると、男たちが刀剣や斧などの鋭利な武器によって斬首されたことがわかる。これは敗北した剣闘士が対戦相手によって、ないしは闘技場の死刑執行人によって斬首されたという歴史事実と合致する。 | ||
| ◆ | 男たちの副葬品から、彼らが尊敬されていたことがわかる。特に銀貨の副葬品はそれを示している。 | ||
| ◆ | 墓地は、古代ローマ時代のヨークの大きな街道沿いにあった。これは墓地としては最もステータスの高い場所である。剣闘士が敬意をもって埋葬されたという歴史と合致する。 | ||
| ◆ | トルコのエフェソスで発見された剣闘士の墓とヨークの墓が酷似している。遺体は首を斬られており、遺体には戦闘経験があり、かつ敬意をもって埋葬された。 | ||
| ◆ | 分析によると、男たちの歯には乳児栄養失調の兆候が見られたが、成人してからは高タンパクの食事をとっていた。これは剣闘士が養成所で高タンパクの食事を与えられたという歴史的事実と合致する。 | ||
| ◆ | 最も大きな体格の男は "足かせ" をはめられていた。これは取り外し不可能で、鎖をつなぐ穴もなく、単なる奴隷の足かせではない。巨体の剣闘士の動きを鈍らせる "重り" だったと推定できる。 | ||
| ◆ | 発見されたほとんどの遺体の骨には傷が治ったあとがあり、治療が施されていた。治療は古代ローマにおいては贅沢なことである。剣闘士だとすると辻褄が合う。 | ||
| ◆ | 一人の白骨遺体の骨盤には猛獣によってあけられた穴があり、これが致命傷となった。この骨盤の穴は大型肉食獣の牙と一致する。この状況が考えられるのは剣闘士(闘獣士)である。 |
ジグソーパズルのピースがはまるように、多くの証拠が剣闘士の墓であることを示唆しています。決定的とも言えるのは最後の「猛獣の牙によって骨盤に穴があくほどの致命傷を負った遺体」でしょう。
調査団長のカート・ハンターマンがネットに公表しているリポートを読むと、発見された白骨遺体は82体ですが、そのうちの1体は女性でした。そしてハンターマンは、この女性がグラディアトリクス(gladiatrix。女性剣闘士)ではないかと推測しています。
No.203「ローマ人の "究極の娯楽"」で紹介したように、ローマの剣闘士については数々の本が書かれ、映画が作られ、絵画も制作されてきました。しかしこの番組が示した「白骨遺体の分析レポート」は、本・映画・絵とは違った意味で、2000年前の状況を非常に生々しく感じることができ、大変に印象的でした。
| 補記1:同位体分析 |
ここからは補足です。No.221「なぜ痩せられないのか」で、同位体分析の手法を使ってヒトの消費エネルギーを精密測定する話を書きましたが、本番組にも同位体分析が出てきました。歯のエナメル質の同位体分析で、出身地や食性がわかるというのです。なぜ可能なのか、調べてみると次のようです。いずれも安定同位体(No.221参照)を利用するようです。
| ◆ | ストロンチウム(Sr)は土壌中に含まれるが、安定同位体として 84Sr 86Sr 87Sr 88Sr の4種がある(88Sr が最も多い)。この安定同位体の存在比が地質によって微妙に違い、これがその土地の生物のストロンチウム量に影響する。このことから、生物がどの地域で育ったかを推定できる。 | ||
| ◆ | 生物においては、窒素(普通は 14N)の安定同位体である 15N の存在比が、食物連鎖によって少しずつ高まっていくことがわかっている。これを利用して人や動物の食物(肉、魚、植物)が判別できる。 | ||
| ◆ | 植物の光合成回路には3種の違ったタイプがあり、それぞれ炭素(普通は 12C)の安定同位体である 13C を取り込む率が違う。これを使って人や動物が食べていた植物が大まかに判別できる。これと 15N の分析を合わせて食性が推定できる。 |
そして、このような同位体分析は今や世界の常識であり、考古学だけでなく、たとえば食物の原産地証明や生物の食性分析などにも利用されているようです。
以上は一般論であって番組中のモンゴメリー博士の手法の詳細はわかりませんが、類似の方法だったと推察されます。博士は遺体の歯から出身地を推定し、さらに「彼らは野菜と肉の両方を食べていただけでなく、少量ですが魚も口にしていた可能性があります」と語っていました。そこまで分析できる測定技術の進歩に感心しました。
| 補記2:ガレノス |
本文中のナレーションに、
発見されたほとんどの遺体には、傷の治ったあとがありました。当時では贅沢なことですが、彼らには治療が施されていたようです。
とありました。ここで思い出すのが古代ローマの医師、ガレノスです。このブログで何回か引用した東京大学名誉教授の本村凌二氏がガノレスに関するエッセイを書かれていました。それを紹介しますと、まずガレノスの簡単なプロフィールが次です。
|
題名に "国手" という言葉が使ってありますが、中国の故事の「国を治すほどの名手」という意味から転じて、名医の意味や、医者に対する敬称として使われます。
プロフィールの中に「ルネサンス期まで西洋医学に絶大な影響を及ぼした」とありますが、確か、レオナルド・ダ・ヴィンチは人体の研究のために解剖も行うかたわら、ガレノスの書物で勉強をしたはずです。
そのガレノスは、実は、剣闘士の医者だったことがあります。本村先生の文章はガレノスの生涯を詳しく記述していますが、剣闘士に関係するところの前後を引用します。
|
|
ちなみにガレノスの故郷であり、剣闘士の医師として働いたペルガモンは、本文で出てきたエフェソスと同じ小アジア(現在のトルコ)にあります。エフェソスと違ってペルガモンには現在、円形闘技場や剣闘士の墓の跡は残っていませんが、2000年前は都市の発展とともに剣闘士の試合が盛んに行われたのでしょう。
| 補記3:ライオンが人を襲う |
余談ですが、連想したので書きます。本文中でティム・トムソン教授は発掘された穴のあいた骨盤を分析し、ライオンがグラディエーター(具体的には闘獣士)に噛みついた痕跡と結論付けていました。
これで思い出すのが「ライオンは獲物を攻撃する時にお尻に噛みつく」との説です。必ずそうなのか、信憑性のほどは知りません。ただ、ライオンが人のお尻に噛みついている瞬間を描いた有名な彫刻があります。フランスのピエール・ピュジェ(1620-1694)作の「クロトンのミロン」(1671-1682頃)です。
クロトン(南イタリア、現在のクロトーネ)出身のミロンは、ギリシャでレスリング選手として活躍しました。伝説では、ミロンは腕力で木を倒そうとし平手で木を引き裂いた、木は引き裂けたものの手が木の裂け目に挟まって取れなくなってしまった、そのとき獣がミロンに襲いかかり、片腕しか使えなかったミロンは食い殺されてしまった、とされています。要するに「過信は禁物」という教訓話です。
ピュジェの彫刻は、獣をライオンとしています。ルーブル美術館のピュジェの広場(リシュリュー翼)にあります。

タグ:グラディエーター Janet Montgomery 剣闘士 リチャード・ジョーンズ Kevin Dicus ケビン・ディカス Darius Arya 骨考古学 同位体分析 ダリウス・アーヤ Tim Thompson ティム・トムソン ジャネット・モンゴメリー Charlotte Roberts シャーロット・ロバーツ マーリン・ホルスト Malin Holst Kurt Hunter-Mann カート・ハンターマン Blink Films ヨークの首なしグラディエーター 地球大紀行 BS朝日 闘獣士 考古学 人類学 コロセウム 生物考古学 エフェソス ローマ帝国 york ヨーク グラディアトリクス ガレノス クロトンのミロン ピュジェ ルーブル美術館
2018-08-17 16:19
nice!(0)
No.203 - ローマ人の "究極の娯楽" [歴史]
今まで古代ローマに関する記事をいくつか書きました。リストすると次の通りです。
発端は、No.24-No.27 で塩野七生氏の大作『ローマ人の物語』の感想を書いたことでした。ローマ人の宗教だけに絞った感想です。また、No.112、113、123 はインフラストラクチャ(のうちの建造物)の話で、その建設に活躍した古代ローマのコンクリートの技術のことも書きました。No.162 は奴隷制度の実態です。
今回はこの継続で、古代ローマの円形闘技場で繰り広げられた闘技会のことを書きたいと思います。「宗教 = ローマ固有の多神教・キリスト教」や「巨大建造物・コンクリート技術」は、古代ローマそのままではないにしろ現代にも相当物があり、私たちが想像しやすいものです。奴隷制度は現代では(原則的に)ありませんが、奴隷的労働はあるので、それも想像しやすい。
しかし大観衆が見守る円形闘技場での "剣闘士の殺し合い" は現代人の想像を越えていて、そこが非常に興味を引くところです。ボクシングの試合で相手を倒すのとは訳が違う。その想像を越えたところに古代ローマの(一つの)特徴があると思うし、歴史から学ぶポイントもあるかもしれないと思うのです。
今までのブログで円形闘技場での闘技会について触れたことがありました。No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたユリウス・カエサルの話です。カエサルは財務官に当選したとき(BC.65 カエサル35歳)、ローマで一番の資産家であったクラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに320組の剣闘士を借り切った闘技会を開催しました。のべ25万人のローマ市民を集めたこの闘技会で、カエサルは借金を全部使い切りました。2500万セステルティウスという金額は、現在の貨幣価値にして約30億円程度です。この記述は、本村凌二『はじめて読む人のローマ史 1200年』祥伝社(2014)によったのですが、塩野七生氏も『ローマ人の物語』でこの闘技会のことを書いていました。
これは、当時のローマの貴族階級の財力がものすごかったという例として引用したのですが、では、その剣闘士の闘技会とはどいうものだったか、それが以降です。
差し下ろされた親指
古代ローマの剣闘士(=グラディエーター)を描いた絵画として、ジャン = レオン・ジェロームの傑作『差し下ろされた親指』(1872)があります。まず例によって中野京子さんの解説で、この絵を見ていきたいと思います。引用にあたっては漢数字を算用数字に置き換えました。一部段落を増やしたところがあります。
画家は歴史考証を踏まえて描いています。画面に描かれた数本の白っぽい筋は何かと思ってしまいますが、これはコロセウムの上を覆う天幕の間から漏れてくる光線なのですね。実際にこのように見えるかどうかはともかく、歴史を踏まえて描いていることを示していて、画家の芸の細かいところです。

中野さんが指摘しているのですが、画家はサムズダウンをしている右手の観客たちの表情を意図的に醜く描いています。そして上段の男性観客ですが、中には沈痛な表情の老人も混じっている(上の部分図の左上の男など)。敗者を応援していたのでしょうか。それに呼応するかように左手のアリーナ観客は、ヒートアップしている右手の観客とは様子が違うのです。
まさに劇的瞬間というのでしょうか。「殺せ、殺せ」と叫ぶ右側のアリーナの観客、それには同調していない左のアリーナの観客、そして描かれていない皇帝の親指・・・・・・。補足しますと、中野さんが「決定は皇帝が下す」と書いているのは、詳しく言うと、
ということであり、それが正しい理解の仕方です。カエサルが主催者の闘技会だと、敗者の生死を決めるのは費用を負担したカエサルです。
中野さんによると、画家・ジェロームはこの絵で敗者を美形に描いているといいます。思想家・セネカの「もっとも価値のある剣闘士は美形の者だ」という言葉が思い出されると・・・・・・。しかし画家が敗者を美形に描いたのには、さらに理由があります。それはこの敗者が「投網闘士」だからです。


魚兜闘士の肘防具にも注目したいと思います。カエサルは財務官就任記念に開催した「大闘技会」で、640人の剣闘士全員に銀製の腕鎧(肘防具)を新調して着用させたと『ローマ人の物語』で塩野七生氏が書いていました(最初の引用)。この絵を見るとその意味がよく分かります。陽光に煌めく銀の効果です。
もう一つこの絵で気づかされるのは、魚兜闘士と投網闘士が戦っていることです。つまり魚と漁師が戦っている。これは興業的なおもしろさを狙ったと考えられますが、単に「魚と漁師」のおもしろさだけではないでしょう。武器が違います。武器にはそれぞれ長所・短所があります。つまりこの絵の試合は、現代でいうと異種格闘技の試合のようなものだと思います。空手とプロレスのどっちが強いか、みたいな・・・・・・。あるいは時代劇に出てくる日本刀(ヒーロー)と鎖鎌(悪役)の戦いです。異種の武器での戦いは観衆の興味を大いに引いたと考えられます。
我々は剣闘士の試合というと、奴隷同士が戦ったというイメージが強いのですが(スタンリー・キューブリック監督の「スパルタカス」という映画がありました)、ローマも帝政の時代になると変質していったようです。
このジェロームの絵は、映画『グラディエーター』の制作に一役買ったようです。20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は・・・・・・。
2000年前に5万人を収容できるアリーナを建設できる圧倒的な技術力と高度な文明、そのアリーナで繰り広げられる "人間同士の殺し合いショー" と、瀕死の敗者を殺せと連呼する観衆・・・・・・。リドリー・スコット監督は「栄光と邪悪」と言っていますが、この絵が表しているものはまさにそうだし、現代人が古代ローマの歴史に惹かれる理由もそこなのでしょう。
ちなみに cinemareview.com の記事によると『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサは、スコット監督に脚本を見せる以前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそもプロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だと言います。この絵にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるのでしょう。
皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち
画家のジェロームは『差し下ろされた親指』(1872)より以前にも剣闘士をテーマとした作品を描いています。『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』という作品です。
この絵を所有しているイェール大学アート・ギャラリーの公式サイトにもあるのですが、ジェロームは歴史考証を踏まえてこの絵を描いています。その考証の一つですが、この絵にはコロセウムを覆う天幕が描かれていて、その構造がよくわかります。中心部を円形にあけ、その周りにアリーナの最高部まで部分的に布が張られる。布の下の観客席は日陰になり、闘技舞台には日光が差し込むというわけです。『差し下ろされた親指』もそういう絵になっていました。ユリウス・カエサルの闘技会のように剣闘士が銀製の腕鎧をつけたとしたら、陽光が銀に反射して日陰の観客席に煌めき、その効果は抜群だったと想像できます。
この絵の原題は「Ave Caesar, Morituri te Slutant」というラテン語で、「皇帝万歳! 我ら死にゆく者が敬意を捧げます」というような意味です。スエトニウスの「ローマ皇帝伝」にある語句です(第5巻 クラウディウス帝)。その「皇帝万歳」と叫ぶ剣闘士たちは、描かれた盾と三叉鉾の数から4人の魚兜闘士と4人の投網闘士でしょう。皇帝に敬意を表してから試合に臨むようです。

画面の左手前には、試合が終わった投網闘士と網をかぶせられた魚兜闘士の2人が倒れています。相討ちになったのでしょうか。そのうしろ方のハイライトの部分では、奴隷が剣闘士の死体を引きずってアリーナから出そうとしています。

『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』は、13年後に描かれた『差し下ろされた親指』と似ています。ともに剣闘士と皇帝を低い位置からとらえた構図であり、あえて試合中の剣闘士を描かず、魚兜闘士と投網闘士の武器や防具、そしてアリーナの構造が歴史考証をもとに描かれています。しかし明らかに試合の決着がついた直後、生か死かという瞬間を描いた『差し下ろされた親指』の方が劇的です。殺せと叫ぶ観衆を間近に描いたのもインパクトがある。アリーナの巨大さを実感できる空や天幕を描くのをあきらめざるを得なかったが、その代わりに天幕から漏れてくる光の筋を描き込んだ。2つの絵を比べると『差し下ろされた親指』を制作した画家の意欲が分かるのでした。
補足ですが、古代ローマの剣闘士については Wikipedia日本版に詳しい情報があります。また画家のジェロームについては、以前の記事で次の3つの作品をとりあげました。
野獣狩り
最初に引用した塩野七生氏の「ローマ人の物語」の他に、このブログで古代ローマの闘技会について引用したことがあります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの「捕食者なき世界」にあった、"人間が大型捕食動物を根絶してきた歴史" です(No.127「捕食者なき世界 2」)。人間が大型動物を狩る第一の理由は食料を確保するためでしたが、歴史を振り返ると理由はそれだけではありません。
ソウルゼンバーグが書いているのは、円形闘技場で行われた「野獣狩り」のことです。それは「最高に楽しい娯楽」でした。このあたりの歴史を別の本から引用してみたいと思います。
アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(関口英子訳。河出書房新社 2010)は最新の歴史研究を踏まえて、紀元115年のトラヤヌス帝の時代のローマの一日を民衆の視点からの「実況中継風の記述」とその「解説」で綴った本です。以前の No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」では "ウェスタの巫女" に出会う部分を引用したのですが、この本には円形闘技場の描写も出てきます。以下にその記述を引用します。
円形闘技場での剣闘士の闘技会の前には、実は "前座" があったわけです。前座の最初は「野獣狩り」です。
野獣狩りは闘獣士が野獣を "狩る" というショーですが、中には闘獣士と野獣の "互角の闘い" もあった。その互角の闘いをする猛獣の例として、当時有名だったウィクトルという名前のヒョウの話が出てきます。
単に闘獣士が動物を殺すだけの "野獣狩り" よりも、闘獣士と猛獣のどちらが勝つかわからない「互角」の闘いの方がショーとしての価値があるわけです。「古代ローマ人の24時間」にはスピッタラという名前の闘獣士とヒョウのウィクトルが闘う場面がでてくるのですが、闘獣士は鎧も兜も剣も無しに脛当てだけをつけ、1本の槍でヒョウと闘います。これもショーをおもしろくする工夫でしょう。完全武装ではつまらない。
ローマ帝国の特別のイベントでは、多数の剣闘士が殺されると同時に、夥しい数の野獣も殺されたようです。
ソウルゼンバーグは「1日にクマ100頭、ヒョウ400頭、ライオン500頭が虐殺されることもあった」と書いていましたが(=1日に1000頭を殺害)、いかにありそうです。
公開処刑
前座の第2弾は犯罪人の公開処刑です。『古代ローマ人の24時間』には、後ろ手に縛られた罪人を2人の死刑執行人がコロッセウムの闘技場に連れ出す場面が描写されています。コロッセウムでは数万人の観衆がざわめいています。罪人が受けた判決は「猛獣による食い殺しの刑」です。
コロッセウムにおける公開処刑は、上に引用したような "単純な" もの以外に、見せ物・ショーとしての "演出" がされることもありました。
こういう記述を読むと、古代ローマの文明のレベルの高さが直感できます。まず観衆はギリシャ神話を知っているわけです。知っているからこそ演出としての価値が出てくる。さらに引用にあるコロッセウムの有名な「せり上がり舞台」の仕組みも、それが2000年前だと考えるとすごいものだと思います。
この記述から、よく言われるローマ帝国における「キリスト教徒迫害」を思い出しました。キリスト教徒は捕らえられ、闘技場に引き出され、猛獣の餌食になったと・・・・・・。決まって引き合いに出される悪役は皇帝ネロです。しかし注意すべきは、古代ローマにおける猛獣刑は "死刑と決まった罪人" を処刑する方法の一つだったことです。キリスト教徒だけが猛獣刑にあったわけではありません。ちなみに弾圧された宗教もキリスト教だけでもありません。紀元前186年のディオニュソス教徒の弾圧では7000人が処刑されたと、古代ローマの歴史家が書いています(No.24「ローマ人の物語(1)寛容と非寛容」)。
歴史をひもとくと、公開処刑は古代ローマだけでなく日本を含む世界各国で行われてきました。現代でも東アジアの某国や中東のある種の国では行われています。むしろ「見せしめ」や「戒め」のために、罪人の処刑は公開が原則だったと言えるでしょう。
しかし古代ローマの公開処刑の特徴は、それが見せ物、ショー、エンターテインメントとして実施されたことです。しかも最大数万人の観衆の注視の中でのショーであり、演出上の工夫があり、猛獣刑の場合は食いちぎられた人体のパーツがアレーナに散乱する陰惨な光景で終わる見せ物です。こういった例は世界史でも希有でしょう。
剣闘士の戦い
「野獣狩り」と「公開処刑」という前座が終わると、いよいよ待ちに待った剣闘士の闘いが始まります。
ジェロームが『差し下ろされた親指』で描いたのは、魚兜闘士と投網闘士の戦いでした。『古代ローマ人の24時間』では「魚剣闘士」(=ムルミッロ)と「投網剣闘士」(=レティアリウス)と訳されています。そして魚剣闘士と投網剣闘士の戦いの様子が、剣闘士の視点で描写されています。魚剣闘士の名前はアステュアナクス、投網剣闘士の名前はカレンディオです。魚剣闘士の装備は兜、盾、腕当て、両刃の短剣(グラディウス)であり、投網剣闘士は投網と三叉鉾、肩防具、短剣(とどめを刺すために使用)で、兜は無しです。
戦いが始まるとすぐ、投網剣闘士は魚剣闘士の周りをぐるぐる走り回ります。
投網剣闘士のカレンディオは、すぐには攻撃しません。相手が網から逃れようともがくうちに、ますます網に絡まるか、あるいはつまづく。それを待っているのです。
「教官」と出てきますが、これは剣闘士養成所の教官という意味です。剣闘士は養成所での厳しい訓練を経てきているのです。二人は投網剣闘士が有利のうちに一進一退を繰り返すのですが、途中で状況が変わります。
もちろん以上の記述は著者の想像です。ただし最後に書いてあるように、著者はこの戦いの経過を描いた当時のモザイク画をもとに文章を書いています。細部の描写はともかく、古代ローマの剣闘士の試合がどんなものだったかが理解できます。最後の方の「そよ風が彼(=投網剣闘士)の髪を撫でる」というところは、投網剣闘士だけは兜を被らなかったという歴史的事実を反映しています。
最初のジェロームの絵『差し下ろされた親指』に戻ります。ここにはまさに魚剣闘士と投網剣闘士との戦いが終わったばかりの場面が描かれています。そして右の観客席の観衆は「殺せ」とコールしている。
ここで想像すると、全員とまでは言わないまでも「殺せ」と叫んでいる観衆は、午前中の「猛獣狩り」で動物が死ぬ場面を見物し、その次には公開処刑を見学し、そして剣闘士の試合と流れる血に興奮して「殺せ」と叫んでいるわけです。「死」と「血」が充満した円形闘技場に長時間いた人間が「殺せ、殺せ」と連呼するのは、当然そうなるだろうという気がします。
究極の娯楽
今まで書いた「死を見せ物にする」古代ローマの歴史を、我々はどう受けとめればいいのでしょうか。"歴史から学ぶ" とすると、何か学ぶものはあるのでしょうか。このことについて2つのことを考えました。
確実に言えるのは、この見せ物=娯楽は「これほど刺激の強いものはない、究極の娯楽」だということです。長いローマの歴史の中でより強い刺激を求めてエスカレートした結果なのでしょうが、もうこれ以上エスカレートのしようがないわけです。ものごとは究極に達すると後は下降しかありません。「パンとサーカス」と言われるように、闘技会(=サーカス)は、民衆が皇帝に要求する権利だったわけですが、そのローマ市民が要求するものを皇帝がいずれ与えられなくなることは目に見えています。人間は誰しも死にたくはないので、死を前提にした見せ物はエスカレートすればするほど、どこかで無理がきます。
ローマの高度なインフラを思い出します。No.112-3「ローマ人のコンクリート」、No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたように、2000年前の高度文明で作られた水道網、道路、橋、テルマエ(公衆浴場)などは、メインテナンス・コストとエネルギー資源の問題で "持続可能" ではなくなり、次第に劣化・縮小していったわけですね。究極に達すると下降しかない。これが第一に思ったことです。
2つ目に思ったのは「人や動物が殺される様子を娯楽として楽しむ」のは "人間性" とどういう関係があるかです。それは古代ローマ人だけの特殊なものだとも考えられます。しかし動物を殺して楽しむというのは、現代のスペインやポルトガル(および文化を受け継いだ中南米の国)の闘牛がそうだし、大型動物を狩るレジャー・ハンティングがそうです。現代のテロリストの中には殺人を楽しんでいるとしか思えないものもいる。人間にはそういった性向がないとは言えないでしょう。では「ローマ人の究極の娯楽」はどう考えればよいのか。
最も妥当な解釈は「人間は本能が崩れた動物だ」ということだと思いました。これは岸田秀氏(和光大学名誉教授)の言い方ですが、人間の行動は本能によるのではないということです。つまり、生存のために必須の行動を除き、人間の行動は生得のものではない。人間の行動は "文化"(広い意味での文化)によって決まります。文化が人間の行動規範になり、文化が人間を行動に駆り立てる。岸田流に言うと「文化は本能の代替物」ということになります。
その "文化" は人間が作りあげてきたものなので、生物学的条件からくる根拠がありません。従って極めて多様であり、社会によって千変万化します。二人が戦う格闘技を観客が見て楽しむという競技は世界中にありますが、「剣闘士=殺し合い」から「相撲=倒れたら負け」までのバリエーションがある。
全くの想像ですがローマの闘技会も、もとはと言えば戦争捕虜同士を戦わせて楽しむ程度のものではなかったのでしょうか。それが剣を使うようになり、次には殺してもよいことになり、さらには敗者が殺されるようになり、猛獣とも戦うようになりと、そういう風に文化が "発展" してきた。生物学的な歯止めがない人間はどこまでもエスカレートしていく(ことがある)。その文化の中で生まれてからずっと生活していると、別に何とも思わない。世界中のほとんとの地域はそういう "発展" はしなかったが、古代ローマは(たまたま)そういう経緯をたどったのではないでしょうか。
古代ローマ史の闘技会で思うのは、人間社会は「何でもアリ」だということです。だからこそ「何でもアリではない社会」を構成するための "文化的装置" を作る努力が必要なのでしょう。「人間は生まれながらにして基本的人権をもつ」という近代国家ではあたりまえのコンセプトも、実は、生まれながらに持っているものや行動規範が無いからこそ「人権」というものを仮想し、それをベースに社会の体系を作ろうとする(作ってきた)人間社会の努力だと考えられます。そして、その努力は大切なものだということを思いました。
| No. 24 | ローマ人の物語(1)寛容と非寛容 | |||
| No. 25 | ローマ人の物語(2)宗教の破壊 | |||
| No. 26 | ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ | |||
| No. 27 | ローマ人の物語(4)帝国の末路 | |||
| No.112 | ローマ人のコンクリート(1)技術 | |||
| No.113 | ローマ人のコンクリート(2)光と影 | |||
| No.123 | ローマ帝国の盛衰とインフラ | |||
| No.162 | 奴隷のしつけ方 |
発端は、No.24-No.27 で塩野七生氏の大作『ローマ人の物語』の感想を書いたことでした。ローマ人の宗教だけに絞った感想です。また、No.112、113、123 はインフラストラクチャ(のうちの建造物)の話で、その建設に活躍した古代ローマのコンクリートの技術のことも書きました。No.162 は奴隷制度の実態です。
今回はこの継続で、古代ローマの円形闘技場で繰り広げられた闘技会のことを書きたいと思います。「宗教 = ローマ固有の多神教・キリスト教」や「巨大建造物・コンクリート技術」は、古代ローマそのままではないにしろ現代にも相当物があり、私たちが想像しやすいものです。奴隷制度は現代では(原則的に)ありませんが、奴隷的労働はあるので、それも想像しやすい。
しかし大観衆が見守る円形闘技場での "剣闘士の殺し合い" は現代人の想像を越えていて、そこが非常に興味を引くところです。ボクシングの試合で相手を倒すのとは訳が違う。その想像を越えたところに古代ローマの(一つの)特徴があると思うし、歴史から学ぶポイントもあるかもしれないと思うのです。
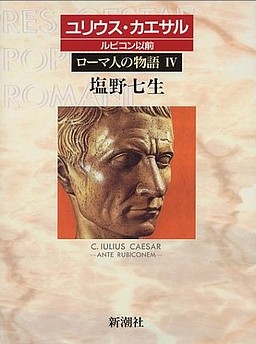
| |||
|
| |||
|
これは、当時のローマの貴族階級の財力がものすごかったという例として引用したのですが、では、その剣闘士の闘技会とはどいうものだったか、それが以降です。
差し下ろされた親指
古代ローマの剣闘士(=グラディエーター)を描いた絵画として、ジャン = レオン・ジェロームの傑作『差し下ろされた親指』(1872)があります。まず例によって中野京子さんの解説で、この絵を見ていきたいと思います。引用にあたっては漢数字を算用数字に置き換えました。一部段落を増やしたところがあります。
.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム(1824-1904)
「差し下ろされた親指」(1872)
(フェニックス美術館。米:アリゾナ州)
| ||
|
画家は歴史考証を踏まえて描いています。画面に描かれた数本の白っぽい筋は何かと思ってしまいますが、これはコロセウムの上を覆う天幕の間から漏れてくる光線なのですね。実際にこのように見えるかどうかはともかく、歴史を踏まえて描いていることを示していて、画家の芸の細かいところです。
|

中野さんが指摘しているのですが、画家はサムズダウンをしている右手の観客たちの表情を意図的に醜く描いています。そして上段の男性観客ですが、中には沈痛な表情の老人も混じっている(上の部分図の左上の男など)。敗者を応援していたのでしょうか。それに呼応するかように左手のアリーナ観客は、ヒートアップしている右手の観客とは様子が違うのです。
|
 | |||
|
| |||
| 決定は闘技会の "主催者"(=エーディトル)が下す。この絵の場合、主催者は皇帝 |
ということであり、それが正しい理解の仕方です。カエサルが主催者の闘技会だと、敗者の生死を決めるのは費用を負担したカエサルです。
|
中野さんによると、画家・ジェロームはこの絵で敗者を美形に描いているといいます。思想家・セネカの「もっとも価値のある剣闘士は美形の者だ」という言葉が思い出されると・・・・・・。しかし画家が敗者を美形に描いたのには、さらに理由があります。それはこの敗者が「投網闘士」だからです。
|


魚兜闘士の肘防具にも注目したいと思います。カエサルは財務官就任記念に開催した「大闘技会」で、640人の剣闘士全員に銀製の腕鎧(肘防具)を新調して着用させたと『ローマ人の物語』で塩野七生氏が書いていました(最初の引用)。この絵を見るとその意味がよく分かります。陽光に煌めく銀の効果です。
もう一つこの絵で気づかされるのは、魚兜闘士と投網闘士が戦っていることです。つまり魚と漁師が戦っている。これは興業的なおもしろさを狙ったと考えられますが、単に「魚と漁師」のおもしろさだけではないでしょう。武器が違います。武器にはそれぞれ長所・短所があります。つまりこの絵の試合は、現代でいうと異種格闘技の試合のようなものだと思います。空手とプロレスのどっちが強いか、みたいな・・・・・・。あるいは時代劇に出てくる日本刀(ヒーロー)と鎖鎌(悪役)の戦いです。異種の武器での戦いは観衆の興味を大いに引いたと考えられます。
我々は剣闘士の試合というと、奴隷同士が戦ったというイメージが強いのですが(スタンリー・キューブリック監督の「スパルタカス」という映画がありました)、ローマも帝政の時代になると変質していったようです。
|
このジェロームの絵は、映画『グラディエーター』の制作に一役買ったようです。20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は・・・・・・。
|

| |||
|
| |||
ちなみに cinemareview.com の記事によると『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサは、スコット監督に脚本を見せる以前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそもプロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だと言います。この絵にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるのでしょう。
皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち
画家のジェロームは『差し下ろされた親指』(1872)より以前にも剣闘士をテーマとした作品を描いています。『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』という作品です。
-d078c.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム(1824-1904)
「皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち」(1859)
(イェール大学アート・ギャラリー。米:コネチカット州)
| ||
この絵を所有しているイェール大学アート・ギャラリーの公式サイトにもあるのですが、ジェロームは歴史考証を踏まえてこの絵を描いています。その考証の一つですが、この絵にはコロセウムを覆う天幕が描かれていて、その構造がよくわかります。中心部を円形にあけ、その周りにアリーナの最高部まで部分的に布が張られる。布の下の観客席は日陰になり、闘技舞台には日光が差し込むというわけです。『差し下ろされた親指』もそういう絵になっていました。ユリウス・カエサルの闘技会のように剣闘士が銀製の腕鎧をつけたとしたら、陽光が銀に反射して日陰の観客席に煌めき、その効果は抜群だったと想像できます。
この絵の原題は「Ave Caesar, Morituri te Slutant」というラテン語で、「皇帝万歳! 我ら死にゆく者が敬意を捧げます」というような意味です。スエトニウスの「ローマ皇帝伝」にある語句です(第5巻 クラウディウス帝)。その「皇帝万歳」と叫ぶ剣闘士たちは、描かれた盾と三叉鉾の数から4人の魚兜闘士と4人の投網闘士でしょう。皇帝に敬意を表してから試合に臨むようです。

画面の左手前には、試合が終わった投網闘士と網をかぶせられた魚兜闘士の2人が倒れています。相討ちになったのでしょうか。そのうしろ方のハイライトの部分では、奴隷が剣闘士の死体を引きずってアリーナから出そうとしています。

『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』は、13年後に描かれた『差し下ろされた親指』と似ています。ともに剣闘士と皇帝を低い位置からとらえた構図であり、あえて試合中の剣闘士を描かず、魚兜闘士と投網闘士の武器や防具、そしてアリーナの構造が歴史考証をもとに描かれています。しかし明らかに試合の決着がついた直後、生か死かという瞬間を描いた『差し下ろされた親指』の方が劇的です。殺せと叫ぶ観衆を間近に描いたのもインパクトがある。アリーナの巨大さを実感できる空や天幕を描くのをあきらめざるを得なかったが、その代わりに天幕から漏れてくる光の筋を描き込んだ。2つの絵を比べると『差し下ろされた親指』を制作した画家の意欲が分かるのでした。
補足ですが、古代ローマの剣闘士については Wikipedia日本版に詳しい情報があります。また画家のジェロームについては、以前の記事で次の3つの作品をとりあげました。
| 『奴隷市場』 | No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」 | |||
| 『虎と子虎』 | No.94「貴婦人・虎・うさぎ」 | |||
| 『仮面舞踏会後の決闘』 | No.114「道化とピエロ」 |
野獣狩り
最初に引用した塩野七生氏の「ローマ人の物語」の他に、このブログで古代ローマの闘技会について引用したことがあります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの「捕食者なき世界」にあった、"人間が大型捕食動物を根絶してきた歴史" です(No.127「捕食者なき世界 2」)。人間が大型動物を狩る第一の理由は食料を確保するためでしたが、歴史を振り返ると理由はそれだけではありません。
|
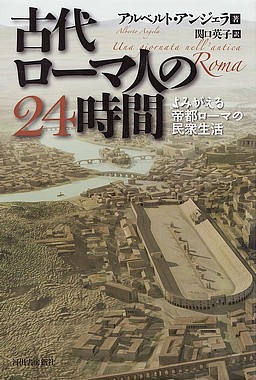
| |||
|
| |||
アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(関口英子訳。河出書房新社 2010)は最新の歴史研究を踏まえて、紀元115年のトラヤヌス帝の時代のローマの一日を民衆の視点からの「実況中継風の記述」とその「解説」で綴った本です。以前の No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」では "ウェスタの巫女" に出会う部分を引用したのですが、この本には円形闘技場の描写も出てきます。以下にその記述を引用します。
|
円形闘技場での剣闘士の闘技会の前には、実は "前座" があったわけです。前座の最初は「野獣狩り」です。
|
野獣狩りは闘獣士が野獣を "狩る" というショーですが、中には闘獣士と野獣の "互角の闘い" もあった。その互角の闘いをする猛獣の例として、当時有名だったウィクトルという名前のヒョウの話が出てきます。
|
単に闘獣士が動物を殺すだけの "野獣狩り" よりも、闘獣士と猛獣のどちらが勝つかわからない「互角」の闘いの方がショーとしての価値があるわけです。「古代ローマ人の24時間」にはスピッタラという名前の闘獣士とヒョウのウィクトルが闘う場面がでてくるのですが、闘獣士は鎧も兜も剣も無しに脛当てだけをつけ、1本の槍でヒョウと闘います。これもショーをおもしろくする工夫でしょう。完全武装ではつまらない。
|
ローマ帝国の特別のイベントでは、多数の剣闘士が殺されると同時に、夥しい数の野獣も殺されたようです。
|
ソウルゼンバーグは「1日にクマ100頭、ヒョウ400頭、ライオン500頭が虐殺されることもあった」と書いていましたが(=1日に1000頭を殺害)、いかにありそうです。

| ||
|
闘獣士のモザイク画
(ローマ:ボルゲーゼ美術館) | ||
 
|
イタリアのシチリア島の都市、ピアッツァ・アルメリーナの郊外に、4世紀初頭のローマ帝国時代に作られた大規模な別荘の跡が残っている(カサーレの別荘)。その規模の大きさから、建てたのはローマ皇帝(マクシミアヌス帝)との説がある。 このカサーレの別荘は、建物や庭の床のほとんどにモザイク画が施されていることで有名である。そのモザイク画を見ると当時のローマ人の様子が分かるが、その中に海外から野獣を船で運ぶ様子を描いたものがある。 上図は象を船に乗せているところで、その上方にはラクダとおぼしき動物が見える。下図はだいぶ欠けているが、虎を船から降ろしているところで、この虎はインドのベンガル地方のものだと言う。野獣を「輸入」して「野獣狩り」を行ったというローマの歴史がリアルに分かる。 |
公開処刑
前座の第2弾は犯罪人の公開処刑です。『古代ローマ人の24時間』には、後ろ手に縛られた罪人を2人の死刑執行人がコロッセウムの闘技場に連れ出す場面が描写されています。コロッセウムでは数万人の観衆がざわめいています。罪人が受けた判決は「猛獣による食い殺しの刑」です。
|
コロッセウムにおける公開処刑は、上に引用したような "単純な" もの以外に、見せ物・ショーとしての "演出" がされることもありました。
|
こういう記述を読むと、古代ローマの文明のレベルの高さが直感できます。まず観衆はギリシャ神話を知っているわけです。知っているからこそ演出としての価値が出てくる。さらに引用にあるコロッセウムの有名な「せり上がり舞台」の仕組みも、それが2000年前だと考えるとすごいものだと思います。
| 蛇足ですが、現代の "アリーナ" は「舞台」の部分とそのまわりを取り囲む観客席の部分の両方を言いますが、語源となった "アレーナ" は「舞台」だけを指すようです。 |
この記述から、よく言われるローマ帝国における「キリスト教徒迫害」を思い出しました。キリスト教徒は捕らえられ、闘技場に引き出され、猛獣の餌食になったと・・・・・・。決まって引き合いに出される悪役は皇帝ネロです。しかし注意すべきは、古代ローマにおける猛獣刑は "死刑と決まった罪人" を処刑する方法の一つだったことです。キリスト教徒だけが猛獣刑にあったわけではありません。ちなみに弾圧された宗教もキリスト教だけでもありません。紀元前186年のディオニュソス教徒の弾圧では7000人が処刑されたと、古代ローマの歴史家が書いています(No.24「ローマ人の物語(1)寛容と非寛容」)。
歴史をひもとくと、公開処刑は古代ローマだけでなく日本を含む世界各国で行われてきました。現代でも東アジアの某国や中東のある種の国では行われています。むしろ「見せしめ」や「戒め」のために、罪人の処刑は公開が原則だったと言えるでしょう。
しかし古代ローマの公開処刑の特徴は、それが見せ物、ショー、エンターテインメントとして実施されたことです。しかも最大数万人の観衆の注視の中でのショーであり、演出上の工夫があり、猛獣刑の場合は食いちぎられた人体のパーツがアレーナに散乱する陰惨な光景で終わる見せ物です。こういった例は世界史でも希有でしょう。
剣闘士の戦い
「野獣狩り」と「公開処刑」という前座が終わると、いよいよ待ちに待った剣闘士の闘いが始まります。
ジェロームが『差し下ろされた親指』で描いたのは、魚兜闘士と投網闘士の戦いでした。『古代ローマ人の24時間』では「魚剣闘士」(=ムルミッロ)と「投網剣闘士」(=レティアリウス)と訳されています。そして魚剣闘士と投網剣闘士の戦いの様子が、剣闘士の視点で描写されています。魚剣闘士の名前はアステュアナクス、投網剣闘士の名前はカレンディオです。魚剣闘士の装備は兜、盾、腕当て、両刃の短剣(グラディウス)であり、投網剣闘士は投網と三叉鉾、肩防具、短剣(とどめを刺すために使用)で、兜は無しです。
戦いが始まるとすぐ、投網剣闘士は魚剣闘士の周りをぐるぐる走り回ります。
|
投網剣闘士のカレンディオは、すぐには攻撃しません。相手が網から逃れようともがくうちに、ますます網に絡まるか、あるいはつまづく。それを待っているのです。
|
「教官」と出てきますが、これは剣闘士養成所の教官という意味です。剣闘士は養成所での厳しい訓練を経てきているのです。二人は投網剣闘士が有利のうちに一進一退を繰り返すのですが、途中で状況が変わります。
|
|
もちろん以上の記述は著者の想像です。ただし最後に書いてあるように、著者はこの戦いの経過を描いた当時のモザイク画をもとに文章を書いています。細部の描写はともかく、古代ローマの剣闘士の試合がどんなものだったかが理解できます。最後の方の「そよ風が彼(=投網剣闘士)の髪を撫でる」というところは、投網剣闘士だけは兜を被らなかったという歴史的事実を反映しています。

| ||
|
追撃剣闘士(セクトル)のアステュアナクスと投網剣闘士(レティアリイ)のカレンディオの戦いを描いたローマ時代のモザイク画。時間の経過は下から上である。上の絵でカレンディオは傷つき、短剣を差し出している。カレンディオの名前の後にある丸と棒の記号は "NULL" を示していて、主催者(エーディトル)の決定は「死」であったことを示す。投網剣闘士は追撃剣闘士と組まされることが多かった。追撃剣闘士の装備は魚剣闘士と似ているが、兜に突起物はなく、投網剣闘士の網から逃れやすかったという。「古代ローマ人の24時間」の記述はこのモザイク画をもとにしているはずである。
(スペイン国立考古学博物館:マドリード)
| ||
最初のジェロームの絵『差し下ろされた親指』に戻ります。ここにはまさに魚剣闘士と投網剣闘士との戦いが終わったばかりの場面が描かれています。そして右の観客席の観衆は「殺せ」とコールしている。
ここで想像すると、全員とまでは言わないまでも「殺せ」と叫んでいる観衆は、午前中の「猛獣狩り」で動物が死ぬ場面を見物し、その次には公開処刑を見学し、そして剣闘士の試合と流れる血に興奮して「殺せ」と叫んでいるわけです。「死」と「血」が充満した円形闘技場に長時間いた人間が「殺せ、殺せ」と連呼するのは、当然そうなるだろうという気がします。
.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム「差し下ろされた親指」
| ||
究極の娯楽
今まで書いた「死を見せ物にする」古代ローマの歴史を、我々はどう受けとめればいいのでしょうか。"歴史から学ぶ" とすると、何か学ぶものはあるのでしょうか。このことについて2つのことを考えました。
確実に言えるのは、この見せ物=娯楽は「これほど刺激の強いものはない、究極の娯楽」だということです。長いローマの歴史の中でより強い刺激を求めてエスカレートした結果なのでしょうが、もうこれ以上エスカレートのしようがないわけです。ものごとは究極に達すると後は下降しかありません。「パンとサーカス」と言われるように、闘技会(=サーカス)は、民衆が皇帝に要求する権利だったわけですが、そのローマ市民が要求するものを皇帝がいずれ与えられなくなることは目に見えています。人間は誰しも死にたくはないので、死を前提にした見せ物はエスカレートすればするほど、どこかで無理がきます。
ローマの高度なインフラを思い出します。No.112-3「ローマ人のコンクリート」、No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたように、2000年前の高度文明で作られた水道網、道路、橋、テルマエ(公衆浴場)などは、メインテナンス・コストとエネルギー資源の問題で "持続可能" ではなくなり、次第に劣化・縮小していったわけですね。究極に達すると下降しかない。これが第一に思ったことです。
2つ目に思ったのは「人や動物が殺される様子を娯楽として楽しむ」のは "人間性" とどういう関係があるかです。それは古代ローマ人だけの特殊なものだとも考えられます。しかし動物を殺して楽しむというのは、現代のスペインやポルトガル(および文化を受け継いだ中南米の国)の闘牛がそうだし、大型動物を狩るレジャー・ハンティングがそうです。現代のテロリストの中には殺人を楽しんでいるとしか思えないものもいる。人間にはそういった性向がないとは言えないでしょう。では「ローマ人の究極の娯楽」はどう考えればよいのか。
最も妥当な解釈は「人間は本能が崩れた動物だ」ということだと思いました。これは岸田秀氏(和光大学名誉教授)の言い方ですが、人間の行動は本能によるのではないということです。つまり、生存のために必須の行動を除き、人間の行動は生得のものではない。人間の行動は "文化"(広い意味での文化)によって決まります。文化が人間の行動規範になり、文化が人間を行動に駆り立てる。岸田流に言うと「文化は本能の代替物」ということになります。
その "文化" は人間が作りあげてきたものなので、生物学的条件からくる根拠がありません。従って極めて多様であり、社会によって千変万化します。二人が戦う格闘技を観客が見て楽しむという競技は世界中にありますが、「剣闘士=殺し合い」から「相撲=倒れたら負け」までのバリエーションがある。
全くの想像ですがローマの闘技会も、もとはと言えば戦争捕虜同士を戦わせて楽しむ程度のものではなかったのでしょうか。それが剣を使うようになり、次には殺してもよいことになり、さらには敗者が殺されるようになり、猛獣とも戦うようになりと、そういう風に文化が "発展" してきた。生物学的な歯止めがない人間はどこまでもエスカレートしていく(ことがある)。その文化の中で生まれてからずっと生活していると、別に何とも思わない。世界中のほとんとの地域はそういう "発展" はしなかったが、古代ローマは(たまたま)そういう経緯をたどったのではないでしょうか。
古代ローマ史の闘技会で思うのは、人間社会は「何でもアリ」だということです。だからこそ「何でもアリではない社会」を構成するための "文化的装置" を作る努力が必要なのでしょう。「人間は生まれながらにして基本的人権をもつ」という近代国家ではあたりまえのコンセプトも、実は、生まれながらに持っているものや行動規範が無いからこそ「人権」というものを仮想し、それをベースに社会の体系を作ろうとする(作ってきた)人間社会の努力だと考えられます。そして、その努力は大切なものだということを思いました。
No.198 - 侵略軍を撃退した日本史 [歴史]
No.37「富士山型の愛国心」の中で元寇(文永の役:1274年、弘安の役:1281年)についてふれたのですが、今回はその継続というか、補足です。
最近の新聞に、元寇について近年唱えられた説の紹介がありました。日本の勝因は「神風」ではなかったという説です。それを紹介したいと思います。
日本の勝因は「神風」ではなかった
くまもと文学・歴史館の館長・服部英雄氏(日本中世史)は著書の『蒙古襲来』(2014年、山川出版社)で「神風=暴風雨」説を否定し、学界の内外にセンセーションを巻き起こしました。

朝日新聞(2017年1月8日)
(www.asahi.com より)
ちなみに「モンゴル軍」と書いてあるところは「モンゴル・高麗連合軍」の方がより正確でしょう。記事の内容をまとめると次の通りになります。
① ② は歴史資料から見えてきた事実であり、③ の「鎌倉武士は戦果を誇った」というのは当然です。また ④ の「敵国調伏の祈祷の成果だと誇った」のも、神社・仏閣の立場としては当然でしょう。
しかし異常なのは明治から昭和にかけての「神風勝因説」( ⑤ )です。これは国家とマスコミが宣伝したわけですが、侵略軍を撃退した自国の歴史を否定し、暴風雨によって敵が去ったと主張することは、長い歴史を有し独立性を維持してきた国家としては異常だと思います。
無敵艦隊を撃退したアルマダの海戦
視野を広げて考えてみるために、外国の例をあげてみたいと思います。「侵略軍の撃退と暴風雨」というテーマでひとつ思いつくのは、16世紀に英国とスペインが戦った「アルマダの海戦(アルマダ戦争)」です。
1588年、スペインのフェリペ2世は無敵艦隊(アルマダ)をイギリスに向かわせました。時の英国国王はエリザベス1世です。フェリペ2世が無敵艦隊を出撃させた経緯は少々複雑なので省略します。とにかく、フェリペ2世はイギリスを "やっつける" ために無敵艦隊(約130隻)を差し向け、イギリス上陸をめざした(艦隊に軍馬を積んでいます)。対するエリザベス1世も海上で迎え撃つために艦隊を繰り出します。イギリス艦隊の副指令官は、元海賊だったフランシス・ドレークで、これは有名な話です。
決戦は英仏海峡付近の数回の海戦(=アルマダの海戦)でした。近年の歴史家の研究では、戦いはほぼ互角です。もちろんスペインは苦戦したし、イギリス側が有利に終わったとする見解もあります。しかし決定的な差がついたわけではない。スペインの誤算は、短期決戦で決定的に勝利できなかったことです。スペインにとっては完全に "アウェイ" の戦いなので、戦争が長引けば補給などの関係で不利になります。スペインはいったん自国に引き上げることにしました。
無敵艦隊は、英仏海峡からスコットランドの北をグルッと迂回して北海から大西洋に出るルートでスペインに帰ろうとしました。ところがアイルランド沖で暴風雨に遭遇し、多くの船を失ってしまいます。スペインに帰港できたのは約半数と言います。
この戦争を、その後のイギリスではどのように自国民に宣伝したのでしょうか。当然、
です。神の加護を言うにしても、まず最初に自国を侵略から守ったイギリス国民の勇気と働きを称え、その次に(補足として)神の加護です。神の加護に全くふれない(無視する)のもいいでしょう。それが普通の、正常な国家のあり方です。事実、エリザベス1世はイギリスの勝利を大々的に宣伝したし、その後のイギリスの歴史でも「無敵艦隊の撃破」が語り継がれました。
侵略軍を撃退した事実を否定する史観
日本史に話を戻します。文永・弘安の役ですが、史料によると「暴風雨はなかったか、あったとしてもモンゴル軍の被害は軽微」だったようです。もちろん、史料に残っていない(ないしはまだ確認されていない史料に記載されている)暴風雨があったのかも知れません。モンゴル軍の被害も、史料にないだけで大きかったのかも知れない。しかし百歩譲って、たとえ暴風雨が主たる勝因だったとしても、
と説明するのが正常な国家というものでしょう。もちろん暴風雨には一切ふれずに、
とするのもいいと思います。
侵略軍を迎え撃つ防衛戦を戦うためには、綿密な準備と作戦が必要です。海岸線の防衛設備、武器、機材、戦闘員の手配とその配置など、リアルな計画がいる。朝鮮半島に軍を出兵するのとはわけが違って、負けたら国が終わりです。一方、「神風」は空想の世界です。「勝因は神風」と喧伝するということは、「戦争をリアルには戦うな、空想の世界で戦争をやれ」と言っているに等しい。これでは絶対に戦争に勝てません。
また、文永・弘安の役は日本史において一方的に迫ってきた外国侵略軍を撃退した貴重な歴史です。勝因を「神風」だと言うことは、勇敢に戦った武士たちを愚弄するものだし、死んでいった武士たちや虐殺された対馬の住民の魂に唾をかけるようなものです。武士だけでなく、日本人そのものを貶めています。さらに、勝因は神風などと言っている限り、"自らの手で国を守る気概" など生まれようがないと思います。
自虐史観というのはイヤな言葉で、あまり使いたくはないのですが、自虐史観と呼ぶに値する唯一のものは「文永・弘安の役の勝因は暴風雨」説だと思います。
最近の新聞に、元寇について近年唱えられた説の紹介がありました。日本の勝因は「神風」ではなかったという説です。それを紹介したいと思います。
日本の勝因は「神風」ではなかった
くまもと文学・歴史館の館長・服部英雄氏(日本中世史)は著書の『蒙古襲来』(2014年、山川出版社)で「神風=暴風雨」説を否定し、学界の内外にセンセーションを巻き起こしました。
|
|

朝日新聞(2017年1月8日)
(www.asahi.com より)
ちなみに「モンゴル軍」と書いてあるところは「モンゴル・高麗連合軍」の方がより正確でしょう。記事の内容をまとめると次の通りになります。
| ① | 文永の役で嵐があったという史料はない。嵐があったとしてもモンゴルの軍船に被害が出たという史料はない。 | ||
| ② | 弘安の役では嵐があったが、嵐によるモンゴルの被害は一部にとどまる。 | ||
| ③ | 鎌倉武士は勝因を神風とは考えていなかった。武士は自らの戦績を誇った。 | ||
| ④ | 「神風」の主張したのは敵国調伏の祈祷をした神社・仏閣である。 | ||
| ⑤ | 明治期と第2次世界大戦中の2度にわたり「神風」が勝因だと叫ばれた。 |
① ② は歴史資料から見えてきた事実であり、③ の「鎌倉武士は戦果を誇った」というのは当然です。また ④ の「敵国調伏の祈祷の成果だと誇った」のも、神社・仏閣の立場としては当然でしょう。
しかし異常なのは明治から昭和にかけての「神風勝因説」( ⑤ )です。これは国家とマスコミが宣伝したわけですが、侵略軍を撃退した自国の歴史を否定し、暴風雨によって敵が去ったと主張することは、長い歴史を有し独立性を維持してきた国家としては異常だと思います。
無敵艦隊を撃退したアルマダの海戦
視野を広げて考えてみるために、外国の例をあげてみたいと思います。「侵略軍の撃退と暴風雨」というテーマでひとつ思いつくのは、16世紀に英国とスペインが戦った「アルマダの海戦(アルマダ戦争)」です。
1588年、スペインのフェリペ2世は無敵艦隊(アルマダ)をイギリスに向かわせました。時の英国国王はエリザベス1世です。フェリペ2世が無敵艦隊を出撃させた経緯は少々複雑なので省略します。とにかく、フェリペ2世はイギリスを "やっつける" ために無敵艦隊(約130隻)を差し向け、イギリス上陸をめざした(艦隊に軍馬を積んでいます)。対するエリザベス1世も海上で迎え撃つために艦隊を繰り出します。イギリス艦隊の副指令官は、元海賊だったフランシス・ドレークで、これは有名な話です。
決戦は英仏海峡付近の数回の海戦(=アルマダの海戦)でした。近年の歴史家の研究では、戦いはほぼ互角です。もちろんスペインは苦戦したし、イギリス側が有利に終わったとする見解もあります。しかし決定的な差がついたわけではない。スペインの誤算は、短期決戦で決定的に勝利できなかったことです。スペインにとっては完全に "アウェイ" の戦いなので、戦争が長引けば補給などの関係で不利になります。スペインはいったん自国に引き上げることにしました。

| ||
|
無敵艦隊とイギリス艦隊
16世紀の作者不詳の絵(Wikipediaより) | ||
無敵艦隊は、英仏海峡からスコットランドの北をグルッと迂回して北海から大西洋に出るルートでスペインに帰ろうとしました。ところがアイルランド沖で暴風雨に遭遇し、多くの船を失ってしまいます。スペインに帰港できたのは約半数と言います。
この戦争を、その後のイギリスではどのように自国民に宣伝したのでしょうか。当然、
| イギリスの軍人と兵士は勇敢に戦い、世界最強と言われたスペインの無敵艦隊を撃破した。その上、神の加護(嵐)もイギリス側にあった。 |
です。神の加護を言うにしても、まず最初に自国を侵略から守ったイギリス国民の勇気と働きを称え、その次に(補足として)神の加護です。神の加護に全くふれない(無視する)のもいいでしょう。それが普通の、正常な国家のあり方です。事実、エリザベス1世はイギリスの勝利を大々的に宣伝したし、その後のイギリスの歴史でも「無敵艦隊の撃破」が語り継がれました。
.jpg)
| ||
|
エリザベス1世の肖像画。いわゆる「アルマダの肖像」で、背後にわざわざ無敵艦隊が描かれている。無敵艦隊を破ったあとの1588年の絵で、右手を地球儀の上に置いているという念の入れようである。Wikipediaより。
| ||
侵略軍を撃退した事実を否定する史観

| ||
| 蒙古襲来絵詞 [部分](宮内庁・三の丸尚蔵館)。肥後の御家人・竹崎季長(すえなが)が、自分の戦いぶりを描かせたものと言われる。図は、モンゴル・高麗連合軍の船に乗り込む季長たち(至文堂 日本の美術 第414号 2000 より引用) | ||
日本史に話を戻します。文永・弘安の役ですが、史料によると「暴風雨はなかったか、あったとしてもモンゴル軍の被害は軽微」だったようです。もちろん、史料に残っていない(ないしはまだ確認されていない史料に記載されている)暴風雨があったのかも知れません。モンゴル軍の被害も、史料にないだけで大きかったのかも知れない。しかし百歩譲って、たとえ暴風雨が主たる勝因だったとしても、
| 日本全国から集まった武士は勇敢に戦い、侵略してくるモンゴル軍を撃退した。さらに神風の追い打ちもあって、モンゴル軍は退散した |
と説明するのが正常な国家というものでしょう。もちろん暴風雨には一切ふれずに、
| 日本全国から集まった武士は勇敢に戦い、侵略してくるモンゴル軍を撃退した |
とするのもいいと思います。
侵略軍を迎え撃つ防衛戦を戦うためには、綿密な準備と作戦が必要です。海岸線の防衛設備、武器、機材、戦闘員の手配とその配置など、リアルな計画がいる。朝鮮半島に軍を出兵するのとはわけが違って、負けたら国が終わりです。一方、「神風」は空想の世界です。「勝因は神風」と喧伝するということは、「戦争をリアルには戦うな、空想の世界で戦争をやれ」と言っているに等しい。これでは絶対に戦争に勝てません。
また、文永・弘安の役は日本史において一方的に迫ってきた外国侵略軍を撃退した貴重な歴史です。勝因を「神風」だと言うことは、勇敢に戦った武士たちを愚弄するものだし、死んでいった武士たちや虐殺された対馬の住民の魂に唾をかけるようなものです。武士だけでなく、日本人そのものを貶めています。さらに、勝因は神風などと言っている限り、"自らの手で国を守る気概" など生まれようがないと思います。
自虐史観というのはイヤな言葉で、あまり使いたくはないのですが、自虐史観と呼ぶに値する唯一のものは「文永・弘安の役の勝因は暴風雨」説だと思います。
No.195 - げんきな日本論(2)武士と開国 [歴史]
(前回から続く)
江戸時代の武士という特異な存在

| |||
| 幕藩体制 |
徳川家康が作った「幕藩体制」において、日本は300程度の独立国ないしは自治州(藩)に別れ、各藩は徴税権、裁判権、戦闘力を持っていました。圧倒的な軍事力は幕府にはありません。直接国税もない。それでいて250年ものあいだ平和が続いたのは驚異的です。なぜ平和が維持できたのか。
|
もちろん幕府は "空気" を維持するために、さまざまな手を打ちました。大名がしくじると改易したり領地をとりあげたりします。参勤交代をやらせたり、大名の妻子を江戸に住まわせて人質にしました。空気を維持する上で、かなり成功したわけです。
しかし空気は "水を差す" とすぐにしぼみます。誰かが公然と空気に反して行動すると、皆が空気通りに行動するだろうという予期が壊れるので、しぼんでしまうのです。幕藩体制の場合、水を差したのは幕末にアメリカからやってきたぺリーでした。幕府はペリーに対して「圧倒的に強いもの」として振る舞えなかったので、空気が消えてしまった。その後「いくつかの藩を束ねて勝負すれば勝てる」ことが実証されました。
| イエ制度 |
幕藩体制を下部構造としてささえたのが「イエ制度」です。イエは、次男・三男には行き場所がない「単独相続」です。また血統とは無関係に養子をとってもよい。女の子がいれば男の養子をとって跡を継がせる。誰もいなければ男と女を養子にとって結婚させ、跡を継がせる(=両養子)。両養子の制度は世界中で日本だけです。
イエ制度は最小の経済単位であるだけでなく、世間のすべての業務を分担するシステムとして機能しました。
|
その一方で、イエ制度は日本の近代を準備するものともなりました。イエが割り当てる職務を果たしさえすれば、あとは自由です。そうすると、イエ制度の力学から相対的に自由な人びとが精神的自由の担い手になります。次男・三男坊、上層の農民、上層の町人などです。その人たちが、文化や学問(儒学、国学、蘭学)の担い手となりました。
この単独相続(=長子相続)のイエ制度と、その上部構造の幕藩体制は、世界史にも例がない空前絶後のシステムです。
| 武士の矛盾 |
イエ制度に支えられた幕藩体制を支配していたのは武士階級ですが、この体制の中で大きな矛盾を抱えていました。
武士は生まれながらの戦闘者であり、小さいころから武芸の鍛錬をします。しかしそれを戦闘には使わないし、平和が続いているので使いようがありません。もし仮に戦争が起こったとしても、刀と槍では敵に勝てません。すでに鉄砲の時代であり、鉄砲を持つものが圧倒的な戦闘能力を持つことは、信長をはじめとする戦国大名が証明済みです。鉄砲どころか、世界史的には大砲の時代に入っていて、そのことは幕末に、70門以上もの大砲を搭載した4隻のペリー艦隊で実証されました。
武士が実際にやっていることはデスクワークです。番方(軍事系)と役方(行政官僚系)があって、番方が上ということになっているのですが、実際に藩で重要であり、藩を動かしていたのは役方です。つまり武士は「戦闘なき戦闘者集団」という矛盾を抱えていた。これを象徴するのが『葉隠』という書物です。
|
江戸時代の武士がかかえる「矛盾」を最も端的に、かつ時代錯誤的に体現したのが幕末の新撰組です。すでに鉄砲はライフル銃の時代です。アメリカから最新鋭のライフル銃が輸入されていた。そういう時代に、幕府方は剣術の使い手を取り立てて京都で人殺しをさせた。
|
江戸時代の武士は「戦闘なき戦闘者」であり「戦闘者でありながら現実にやっていることはデスクワーク」という矛盾をかかえていました。これでは武士は "アイデンティティ・クライシス" に陥ります。
幕府はこの矛盾を緩和するため、儒学、特に朱子学を奨励しました。儒学によって武士の倫理を保とうとしたのです。日本に儒学が入ってきたのは6世紀ですが、それ以降、儒学者はほとんどいません。江戸時代になって急に儒学者がいっぱい出てきたのはこういう事情によります。
しかしこの朱子学が尊皇思想の土壌になりました。それは朱子学が中国の天子の正統性を説明する学問でもあったからです。さらに、古事記が成立した時代を研究した国学は、武士が天下を支配する以前の日本を明らかにしました。朱子学と国学が尊皇思想を生み、それがと倒幕へとつながっていきました。
第16章には儒学、国学の社会的意味が詳しく語られているのですが、それは省略しました。この第16章(と18章)の感想ですが、江戸時代の武士は非常に特異な存在だという認識を新たにしました。18章では新撰組のことが論じられていて「新撰組は時代錯誤的に武士の原理に執着した人たち」だと大澤氏は述べていますが、ここで連想したのが「赤穂事件」です。忠臣蔵のもとになった、江戸城松の廊下の刀傷から四十七士の切腹までを「赤穂事件」と呼ぶとすると、この事件は非常に不可解なものです。
まず発端が不可解です。江戸城で刃傷に及ぶなど絶対のご法度であって、そんなことをすれば本人は死罪、お家断絶になることは誰もが知っていたわけです。幕藩体制は "戦争禁止" であり、江戸城に昇殿する武士が帯刀を許されなかったことがその象徴でした。浅野長矩(内匠頭)は錯乱したか、コトの意味を全く理解できない精神状態に陥ったとしか考えられないわけです。しかし、そもそも一国の主がそのようになるのだろうかと思います。もしそうだとしたら完全に藩主失格です。
四十七士の討ち入りという "復讐" も不可解感が否めません。浅野内匠頭と吉良上野介が殿中で取っ組み合いの喧嘩でもしたのなら、喧嘩両成敗で、たとえば「両名、数ヶ月の蟄居」のような処罰を受けたのでしょうが、問題は内匠頭が江戸城で小刀を抜いたことなのです。幕府(将軍)はそれに怒って即日切腹を申し付けた。吉良上野介に何の咎めもなかったのは幕府の手落ちでしょうが、だからといって浅野内匠頭の切腹が無くなるわけではない。仮に吉良上野介に「数ヶ月の蟄居」のような処分があったとしても、四十七士は吉良邸に討ち入ったのではないでしょうか。何となく割り切れない感じがします。
しかし「武士という矛盾した存在」という視点でみると、少しは理解できるかもしれないと思いました。つまり、
| ◆ | 浅野内匠頭は「侮辱されたのなら刀を抜くのが本来の武士」だということを、身をもって示した。 | ||
| ◆ | 四十七士は、たとえ主君が藩主としてふさわしくなくとも、主君のために命を捨てるのが武士だということを示した。また、自らの命をかけて敵を殺すのが「本来の武士」だと、行動で示した。 |
というような理解です(考えにくい面もありますが)。とにかく新撰組も赤穂事件も、江戸時代の "武士の矛盾" が露呈したものという感じがしました。こういった矛盾が頂点にまで達し、爆発して一挙に解消に向かったのが明治維新なのでしょう。
・・・・・・・・・・・・
大澤氏は上に引用した文章の中で、『葉隠』は、武士道なんていうものは、ほとんどもうないからこそ語られていることだ、と言っています。これはちょっと違うと思いました。
| 武士道は、平和だからこそ語られ、戦闘をする必要がないからこそ完成された概念 |
だと思います。「死ぬことと見つけたり」とは平和だからこそ言えることであって、隣国との戦争が続いている時にこんな悠長なことは言ってられません。戦争に勝つためには「生き延びて機会をうかがい、反撃に出て国を守る」ことが必須です。
主君のために命をかけるものよいが、愚鈍な主君だと国が滅びます。謀反を起こさないまでも、さっさと主君を取り替えるべきであり、そういう例が戦国時代にはありました。そもそも、自分が仕える主君を替える武将が数々いたわけです(典型は藤堂高虎)。戦国時代の合戦は、寝返りで勝敗が決まったものが多々あります。国や領地を守るためには当然でしょう。
鉄砲があれだけ急速に広まり、フランスの10倍の数を保有するに至ったのも(No.194「げんきな日本論(1)定住と鉄砲」参照)、戦国武将たちが、戦いに勝つためには何をすべきかを理解した "リアリスト" だったからでしょう。鉄砲は卑怯だと言っているのでは戦争に勝てません。
江戸時代の武士は、刀の鍔や武具のモチーフによくトンボを使いました。トンボは前に進むだけで後退しない(後退できない)からです。恐れずに前に進むことは重要ですが、後退を一切しないのでは、これも戦争に勝てません。全国の統一寸前までいった織田信長は、まずいと判断すれば兵を引き、じっと戦力を蓄えて機が熟するのを待つタイプでした。もちろん家康もそうです。
越前・朝倉家の家臣であった朝倉宗滴の『朝倉宗滴話記』の有名な一節に「武者は犬ともいへ、畜生ともいえ、勝つことが本にて候」というのがあります。全くその通りです。要するに、一般に理解されている「武士道」で戦争はできない。「武士道」は平和な時代の産物です。
従って、幕末のリアリストたち、たとえば高杉晋作は鉄砲が政権を生むと確信していて、町民と農民を組織し、鉄砲を持たせて戦ったわけです。官軍の方にリアリストがより多かったのが、倒幕が成功した要因でしょう。幕末の会津戦争において、官軍の板垣隊は会津若松への急襲を成功させますが、山道を道案内したのは会津藩の農民だったという話を読んだことがあります。会津藩では武士が戦って農民は見物していたのですね。幕府方が敗北した理由につながる象徴的なエピソードだと思います。
・・・・・・・・・・・・
明治維新で武士はなくなりましたが、その後も「武士道」は生き残り、その概念が "一人歩き" するようになったと考えられます。そもそも武士道という言葉が広く認知されるようになったのは、新渡戸稲造の『武士道』(明治33年。1900年)からといいます。そして「一人歩きした武士道」は桜の花と結びつけられるまでになった。パッと咲いてパッと散るというわけです。
小川和佑著『日本の桜、歴史の桜』(NHKライブラリー 2000)によると、桜が武士と結びついたのは江戸時代中期以降とあります。まさに武士道は平和な時代の産物なのです。その桜が明治になって「軍国の花」となり、国民思潮に強烈な影響を及ぼしました。パッと散るというのは、戦争をするには最も不適切な価値観です。パッと散ったとすると、敵方は大歓迎でしょう。さらに、捕虜になるぐらいなら死ねと言わんばかりの教えがありましたが、このような考えで戦争はできません。旧日本軍の将校は日本刀を持っていたという話も暗示的です。「一人歩きした武士道」は極めて歪んだものになり、国民に多大な惨禍をもたらした。
江戸時代の武士の矛盾は、あとあとまで尾を引いた・・・・・・。そう感じました。まだ尾を引いているのかもしれません。今も、日本人は忠臣蔵と新撰組が好きです。
日米和親条約:攘夷から開国への転換
第18章「なぜ攘夷のはずが開国になるのか」では、日本の開国、特に日米和親条約が論じられています。以下の引用は長くなりますが、重要な指摘がしてあると思いました。
日本が尊皇思想でまとまったのは、外国と戦争することを想定したからです。そして勤王派も幕府も、戦争をするためには何をすべきかが分かっていた。
アメリカの南北戦争が終結すると、余った中古のライフル銃を商人が売り込みに来ました。これを買ったのが中国と日本です。長州も薩摩も、そして幕府も買った。こんな最新式の銃の前では、武士の伝統的な戦闘能力は役にたたないことがますます明らかになりました。
攘夷とは戦争をすることであり、つまり日本の独立を保つということです。明治維新前後の歴史をみると「攘夷」のはずが「開国」へと180度変化したように見えますが、攘夷と開国は2つの対立するオプションではありません。独立を保つこと=主権を維持することが最重要事項です。その主権を保つことになったのが「日米和親条約」でした。
|
条約を結ぶことによって、国際社会に独立国として認められるという意味では、第二次世界大戦後のサンフランシスコ講話条約と似ています。
|
この章の感想ですが、引用した日米和親条約についての指摘は重要だと思いました。日米和親条約(を始めとする欧米との条約)は、その不平等面が強調され、明治政府はその解消のために多大な努力をしたと、学校の日本史で習いました。現代の視点からすると確かに不平等条約です。しかしその視点だけで過去を見てはいけないのですね。幕末に視点を移すと、交渉当事者の思いがどうであれ、たとえ不平等であっても主権国家としてアメリカと条約を結べたのが大きいわけです。欧米諸国に侵略されて領土をもぎ取られ、ボロボロになっていた東アジアの状況を考えれば・・・・・・。
橋爪さんは「世界的に見て、超例外」と言っています。確かにその通りなのでしょう。ラッキーだったという言い方があたるかもしれません。しかし幕府の方としても蘭学者からの情報でアメリカがどういう国かを知っていたはず、というのが橋爪さんの指摘です。アメリカは海外に植民地を持たない国(当時)だと・・・・・・。
ちょっと思い出したことがあります。ペリーが日本に開国を迫った大きな理由は、アメリカの捕鯨船の補給だったことはよく指摘されます。No.20「鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」で書いたように、当時の日本近海にはアメリカの捕鯨船がウヨウヨいたわけです。日本沿岸まできて薪と水を要求したり、沿岸住民とトラブルになったこともあった。捕鯨船に物資を密輸する日本人さえいたようです。捕鯨船の補給はアメリカにとって重要な問題でした。「日本を開国させることができたら、それはアメリカの捕鯨産業の功績だ」という意味のことを『白鯨』の著者であるハーマン・メルヴィルは書いています(ペリー来航以前にそう書いている。No.20参照)。
地球儀を念頭に当時の日本を想像してみると、たとえば鹿島灘にはボストン近郊の捕鯨基地からやってきた捕鯨船がいた。航行ルートは南アメリカ大陸南端(ホーン岬)まわりか、アフリカ大陸南端(喜望峰)まわりです。なぜわざわざ地球を半周以上も航海してきたかというと、大西洋で鯨がとれなくなったからです。そして、アメリカ東海岸のヴァージニアを出航したペリーは、喜望峰をまわって浦賀にやってきた。
なぜ捕鯨船とペリーが日本に来たかというと、日本近海が鯨の格好の漁場であることに加え、日本がアメリカからみて一番近いアジアの国だからです。距離は数千キロ離れているが「一番近い」。そして、その地政学的ポジションは今も変わらないのです。鎖国をしていた日本が開国の条約を最初に結んだのがアメリカだったのは確かにラッキーでしたが、それは必然だったのかもしれないと思いました。
社会学という武器
『げんきな日本論』を通読しての印象ですが、この本は2人の社会学者の対論です。そこに感じるのは、社会の成り立ちや "ありよう" をミクロからマクロまで研究する「社会学という方法」の意義です。
社会学者は、社会の成り立ちという観点から日本史を論じてもいいし、前著の『ふしぎなキリスト教』のように "西欧社会を作ったキリスト教" を論じてもいい。さらに、戦争史、マスメディア、資本主義、日本語、文学、芸術などを議論してもいいわけです。社会の成り立ちという観点から考察することで、それぞれのジャンルを深堀りする専門家とはまた違った切り口が見いだせそうです。橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の次作に期待したいと思います。
No.194 - げんきな日本論(1)定住と鉄砲 [歴史]
No.41、No.42で2人の社会学者、橋爪大三郎氏と大澤真幸氏の対論を本にした『ふしぎなキリスト教』(講談社現代新書 2012)を紹介しました。この本はキリスト教の解説書ではなく、"西欧社会を作った" という観点からキリスト教を述べたものです。社会学の視点から宗教を語ったという点で、大変興味深いものでした(2012年の新書大賞受賞)。
その橋爪氏と大澤氏が日本史を論じた本を最近出版されたので紹介したいと思います。『げんきな日本論』(講談社現代新書 2016) です。「二匹目のドジョウ」を狙ったのだと思いますが、社会学者が語る日本史という面で数々の指摘があって、大変におもしろい本でした。多数の話題が語られているので全体の要約はとてもできないのですが、何点かをピックアップして紹介したいと思います。
です。「二匹目のドジョウ」を狙ったのだと思いますが、社会学者が語る日本史という面で数々の指摘があって、大変におもしろい本でした。多数の話題が語られているので全体の要約はとてもできないのですが、何点かをピックアップして紹介したいと思います。
そもそも我々は「日本論 = 日本とは何か」に興味があるのですが、それは本質的には「自分とは何か」を知りたいのだと思います。日本語を使い、日本文化(外国文化の受容も含めて)の中で生活している以上、"自分" の多くの部分が "日本" によって規定されていると推測できるからです。
「日本とは何か」を知るためには「日本でないもの」や「諸外国のこと」、歴史であれば「世界史」を知らなければなりません。社会学とは簡単に言うと、社会はどうやって成り立っているか(成り立ってきたか)を研究する学問であり、それは日本を含む世界の社会について、歴史的な発展経緯を含めて研究対象としています。その意味で、歴史学者ではない「社会学者が語る日本とは何か」に期待が持てるのです。この本を読んでみて、その期待は裏切られませんでした。
げんきな日本論
『げんきな日本論』は3部、18章から成っていて、その内容は以下の通りです。
第1部 はじまりの日本
第2部 なかほどの日本
第3部 たけなわの日本
章のタイトルからも明らかなように、縄文時代から幕末までの日本史が取り上げられています。この中から最初と最後、つまり第1章の縄文時代と、第15章以降の江戸時代の中か何点かのポイントを以下に紹介します。
森と定住と土器
第1章は「なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか」と題されています。日本の土器の起源は世界史的にみて極めて古いことはよく指摘されますが、これについての論考であり、以下のようです。
まず日本の自然環境条件ですが、現在、国土の森林被服率は60%を越えています。これは先進国ではめずらしい状況です。一つの理由は山地が多く、可住面積が国土の25%程度と少ないことです。フランスやイギリスの可住面積は70%~80%程度もあります。このあたりが日本を考える上での初期条件として重要です。
日本には照葉樹林があり、ドングリやクルミなどがとれます。根菜類ではヤマイモなどがある。青森県の三内丸山遺跡の周辺には栗林があって食用にしていたことが分かっています。
また日本の水系は細かく分かれていて、飲める水にこと欠きません。このような場所が数百、数千とあります。海岸線は長く、貝や魚がとれて、それはタンパク源になります。
このような自然環境条件を前提に、農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特徴です。定住しても狩猟採集でやっていける環境にあったわけです。世界史的には、農業が始まってから定住するのが普通です。
もちろん農業は狩猟採集より効率的であり、同一面積で養える人口は狩猟採集の10倍から100倍だとい言います。従って、いったん農業で人口が増えると農業が大前提となります。しかし日本ではそうなる以前から定住が始まった。そして、定住の結果として生まれたのが土器です。
なぜ定住したのか、一言でいうと、気候も含めて自然環境が「住みやすい」からなのです。
第1章の感想ですが、日本の歴史を語る上でまず自然環境から入るのは大正解だと思います。キーワードは森林ですね。森林を起点として、森林 → 水・食料 → 定住 → 土器と連鎖しています。
No.37「富士山型の愛国心」にも書きましたが、森林被服率が60%を越えて70%近い国は、先進国(たとえばG20)ではまずないわけです(最も多い高知県は84%もある)。この数字はスウェーデン、フィンランドなみです。しかしスウェーデン、フィンランドの人口密度は日本の1/20とか、そういう値であって、人口も全く違います。No.37では森林の多さと人口の多さに関する象徴的な例として「熊と人間が近接して生活している」をあげました。小学生が熊よけの鈴をつけて登校する例が全国のあちこちにある国は、まず他にないと思います。
森林の保水力が河川の源泉になっています。さらに森林から流れ出した栄養分は海にそそぎ、沿岸の漁業資源を増やします。森林が水や食料をもたらす元になっています。
山地が多くても、森林を伐採してしまったのではダメなのですね。文明が古くから発達したギリシャやトルコの海岸をエーゲ海から撮った観光写真を見ると、海岸の山地が写っていても木がありません。ギリシャ神話を読むと、鬱蒼とした森がないと成り立たない話がいろいろとあるのですが、現在は禿山だらけです。「人が住むと1000年ぐらいの間に森がなくなってしまう」と大澤氏が言うのは、まさにその通りだと思います。そうなると土地の保水力がなくなり、表土は流出して岩だらけになり、河川は埋まり、海に栄養分が届かなくなる。森林からの水分の蒸発がなくなって、気候も変わってしまいます。降水量が減って悪循環に陥る。
日本は海岸の景観を見ても違います。そこが山地だと木が密集しているのが普通であり、それが内陸までつながっています。日本はこのような環境条件にあり、それは縄文時代から続いているということに、まず着目すべきでしょう。まとめると、
ということになります。日本史を考える上での出発点です。
以下、『げんきな日本論』の第2章以降は、
などのキーワードをもとに日本史が俯瞰されています。特に、漢字と仮名の問題をとりあげた章(第5章:なぜ日本人は仏教を受け入れたのか、第8章:なぜ日本には源氏物語が存在するのか)は、日本史を語る上で欠かせないものだと思いました。
以降は、江戸時代を中心にその前後を含めて何点か紹介します。
武家政権という希有な歴史
江戸時代とその前後を語るためには、武士について触れないわけにはいかないのですが、第11章「なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか」の冒頭に次のような指摘があります。
我々日本人は、小学校以来の教育、時代劇、大河ドラマなどから、日本にはかつて武士がいて、武士が政権を担当していたということに何の疑問も抱きません。鎌倉幕府の成立から大政奉還まで武家政権だった。そして我々は暗黙に、鎌倉幕府以降が今の日本に直結していると感じています。特に戦国時代以降、もっと絞ると安土桃山時代以降です。平安時代、ないしは奈良時代やそれ以前となると、あまりに今とは違いすぎて遠い昔に感じます。今の日本の礎になり、また日本独自の文化や精神面でのカルチャーは安土桃山時代以降に確立したと、我々は暗黙に感じていると思います。その時代はというと "武家政権の時代" なのです。
その武家政権は、世界史の視野でみると極めて特異なものというのが橋爪・大澤両氏の指摘です。これは我々が気づきにくい点です。
武家政権を担った武士は、生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や弓や乗馬の練習をしてきたプロフェショナルであり、代々受け継がれた階級です。そういった武士の政権が世の中を支配するのが世界史的に特異だということは、そこに日本史や日本の独自性につながるさまざまな事柄が派生すると想像できます。この視点に関係したことを以下に何点か書きます。まず鉄砲の話です。
鉄砲が歴史を動かす
世界史をひもとくと武器の革新が歴史を動かし、社会を変革してきた例が数々あります。騎兵(乗馬)がそうだし、馬を使った戦車がそうです。もっと古くは鉄製の武器(剣、槍、矢尻、など)もそうだった。鉄砲(銃)も、そういった歴史を動かした武器です。
第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」では「鉄砲史観」とでも言うべき "鉄砲と歴史の関係" が、ヨーロッパと日本を対比させて語られています。その概要は以下のようです。
火薬は中国で発明されましたが、火薬を応用した鉄砲はヨーロッパで実用化されました。鉄砲の製造は難しいのですが、いったん製造できたとなると誰でも引き金を引けば人を殺せる武器になります。甲冑を射抜いて敵を倒せるわけであり、重装備の歩兵も騎兵も無力になります。
さらに大型の「大砲」となると要塞を破壊できます。戦史の本では、ナポリにあった難攻不落の要塞は7年持ちこたえたが、大砲で攻撃したら7時間で打ち壊されたとあります。結果として、封建領主の騎兵と要塞は無意味になりました。
鉄砲は強い軍事力をもたらすともに、個人戦から集団戦へと戦い方を変えました。また、鉄砲をコントロールしていたのが都市の住民だったので、軍事力の中心は市民階級や傭兵になりました。これに目をつけたのが絶対君主です。傭兵を使って鉄砲を装備した常備軍を組織し、貴族をやっつけて強力な政府を作りあげました。傭兵はスイス人が多かったのですが、その理由はスイスが中立だからで、つまり戦いの相手に寝返ることがないからです。
鉄砲を撃つ兵士を「銃士」と言います。デュマの小説「三銃士」(時代設定は17世紀)の "銃士" がそうです。この小説でもわかるように、ヨーロッパでは銃が得意だということが威信の根拠になりました。
絶対君主の次の時代に起こったのが、鉄砲で武装した市民による革命です。以上のようにヨーロッパでは「鉄砲のない封建制」→「鉄砲のある傭兵制(絶対君主)」→「鉄砲のある市民革命」というように社会が変化した歴史があります。鉄砲によって社会変動が生じたわけであり、社会の変化と武器の変化は連動していました。
一方の日本はというと、鉄砲がヨーロッパからもたらされたことは衆知の事実です(1543年)。そしてすぐさま日本で製造されるようになり、鉄砲は急速に普及しました。それだけの製鉄や鍛冶、冶金の技術が日本にあったわけです。しかし鉄砲の社会的意味はヨーロッパとはかなり違った。
戦国時代、鉄砲の使い方がうまかったのが織田信長です。刀と槍で相手に襲いかかる戦法をとり(桶狭間など)、鉄砲では襲ってくる敵を向かえ打つというように(長篠など)、両方の特性をうまく使い分けた。そして何よりも、戦争は個人戦ではなく集団戦であることを徹底させました。
しかし信長は同時に、今まで武器を持っていなかったものが鉄砲を持つことによって政治的な力にならないよう、注意を払いました。いわゆる「兵農分離」もそれが念頭におかれています。信長だけでなく、鉄砲伝来から関ヶ原の戦いに至るまで、戦国武将は鉄砲を使いました。鉄砲隊を組織し、鉄砲の数もジャレット・ダイアモンドが言うように世界史的にみても非常に多かった。しかし鉄砲は、戦術として補助的に使われました。関ヶ原の戦いでも中心は騎兵や歩兵です。
そして日本の特徴は、武士が常に鉄砲をコントロールしたことです。ヨーロッパでは都市が発達し、都市に富が集中して、そこに鉄砲が蓄えられました。日本ではそういう都市の発達がなかったことが一つの原因だと考えられます。また、日本では伝統的に武士だけが戦闘員資格をもち、農民や商人は戦闘員にはなれませんでした。必然、武士が鉄砲を独占することになった。例外は紀州の雑賀衆ぐらいです。
武士は生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や乗馬の練習をしてきたプロフェッショナルです。刀や槍で戦う限り、付け焼き刃では武士に太刀打ちできません。従って武士と農民が戦えば必ず武士が勝ちました。例外は島原の乱ですが、天草四郎の軍には武士も加わっていました。
しかし、急速に普及した鉄砲は誰でも使える武器です。しかも刀や槍より圧倒的に強い。これは武士の地位を危うくします。従って武士は刀狩りをやって兵(武士)と農(農民)を分離し、身分を固定化する方向にいった。もともと鉄砲は平民性(=誰でも使える)と反武士性(=武士の地位を危うくする)がありますが、それが抑止されたわけです。
その抑止が完成された江戸時代においては、銃が得意だということが戦闘者としての威信の根拠にはなりません。あくまで刀が武士の威信の最大の根拠です。刀は一騎討ち向きであり、個人の英雄性に結びつく武器です。武士は刀に異様にこだわることになりました。
鉄砲は威信の根拠にならないだけでなく、軽蔑されました。武士は子供の頃から10年、20年と鍛錬を重ねて刀が槍を使いこなせるようになったのに、鉄砲はすぐに使えます。しかも刀や槍より強い。鉄砲に対する軽蔑は武士の屈折した心理と言えるでしょう。
従って、鉄砲を持っているからといって政治的主体にはならなかった。鉄砲は威力があるが、鉄砲を持っている人間は威力がないということにしたわけです。日本では鉄砲の戦術的効果と社会的無効性の対比が際だっています。
江戸時代を特徴づけるのは「戦争の禁止」と「幕藩制による現状凍結」ですが、以上の考察からすると、幕藩制は鉄砲が入ってきたことによる武士の防衛反応だと考えられます。鉄砲によってヨーロッパは身分の平等化が促進されましたが、日本では逆に武士が上位となる身分化が固定されたのです。
これ以降は、第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」の感想というか、補足です。大澤氏はジャレット・ダイアモンドが『銃・病原菌・鉄』で「1600年の段階でみたとき、日本は世界でもっとも高性能な銃を世界のどの国より多く持っていた」と書いていることに言及しています。このブログでも、No.33「日本史と奴隷狩り」で堺屋太一氏の文章を引用しました。再掲すると次の通りです。
しかしその鉄砲を、武士は(武士であるがゆえに)放棄してしまった。鉄砲を作る技術は急速に衰えていきました。そのあたりの経緯を『銃・病原菌・鉄』から引用すると次の通りです。
ジャレット・ダイアモンドがここでなぜ江戸時代の銃の放棄を説明しているのかというと、世界史では一度獲得した重要技術が放棄されることがあり、その典型例としてあげているのです。ダイアモンドによると、ヨーロッパでも銃を嫌い、銃の使用を制限した人がいた。しかしヨーロッパでは国と国が始終戦争をしていたので、銃の制限や放棄は長くは続かなかった。一方、日本は孤立した島国だったので銃の放棄が現実化した。しかしそれは大砲を備えたペリー艦隊で終わりを告げた・・・・・・。そういう文脈です。
武士が政権を担当し社会の支配層である状況(=世界史てみると特異な状況)の中に鉄砲が突如入ってきて、全国統一の決め手になった。決め手なったからこそ鉄砲は捨てられ非武装社会(=江戸時代)が出来上がった・・・・・・。こういう風に理解できます。

| |||
・・・・・・・・・・
そもそも我々は「日本論 = 日本とは何か」に興味があるのですが、それは本質的には「自分とは何か」を知りたいのだと思います。日本語を使い、日本文化(外国文化の受容も含めて)の中で生活している以上、"自分" の多くの部分が "日本" によって規定されていると推測できるからです。
「日本とは何か」を知るためには「日本でないもの」や「諸外国のこと」、歴史であれば「世界史」を知らなければなりません。社会学とは簡単に言うと、社会はどうやって成り立っているか(成り立ってきたか)を研究する学問であり、それは日本を含む世界の社会について、歴史的な発展経緯を含めて研究対象としています。その意味で、歴史学者ではない「社会学者が語る日本とは何か」に期待が持てるのです。この本を読んでみて、その期待は裏切られませんでした。
げんきな日本論
『げんきな日本論』は3部、18章から成っていて、その内容は以下の通りです。
第1部 はじまりの日本
| なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか | |||
| なぜ日本には、青銅器時代がないのか | |||
| なぜ日本では、大きな古墳が造られたのか | |||
| なぜ日本には、天皇がいるのか | |||
| なぜ日本人は、仏教を受け入れたのか | |||
| なぜ日本は、律令制を受け入れたのか |
第2部 なかほどの日本
| なぜ日本には、貴族なるものが存在するのか | |||
| なぜ日本には、源氏物語が存在するのか | |||
| なぜ日本では、院政なるものが生まれるのか | |||
| なぜ日本には、武士なるものが存在するのか | |||
| なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか | |||
| なぜ日本人は、一揆なるものを結ぶのか |
第3部 たけなわの日本
| なぜ信長は、安土城を造ったのか | |||
| なぜ秀吉は、朝鮮に攻め込んだのか | |||
| なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか | |||
| なぜ江戸時代の人びとは、儒学と国学と蘭学を学んだのか | |||
| なぜ武士たちは、尊皇思想にとりこまれていくのか | |||
| なぜ攘夷のはずが、開国になるのか |
章のタイトルからも明らかなように、縄文時代から幕末までの日本史が取り上げられています。この中から最初と最後、つまり第1章の縄文時代と、第15章以降の江戸時代の中か何点かのポイントを以下に紹介します。
森と定住と土器
第1章は「なぜ日本の土器は、世界で一番古いのか」と題されています。日本の土器の起源は世界史的にみて極めて古いことはよく指摘されますが、これについての論考であり、以下のようです。
まず日本の自然環境条件ですが、現在、国土の森林被服率は60%を越えています。これは先進国ではめずらしい状況です。一つの理由は山地が多く、可住面積が国土の25%程度と少ないことです。フランスやイギリスの可住面積は70%~80%程度もあります。このあたりが日本を考える上での初期条件として重要です。
|
日本には照葉樹林があり、ドングリやクルミなどがとれます。根菜類ではヤマイモなどがある。青森県の三内丸山遺跡の周辺には栗林があって食用にしていたことが分かっています。
また日本の水系は細かく分かれていて、飲める水にこと欠きません。このような場所が数百、数千とあります。海岸線は長く、貝や魚がとれて、それはタンパク源になります。
このような自然環境条件を前提に、農業が始まる前から定住が始まったことが日本の大きな特徴です。定住しても狩猟採集でやっていける環境にあったわけです。世界史的には、農業が始まってから定住するのが普通です。
もちろん農業は狩猟採集より効率的であり、同一面積で養える人口は狩猟採集の10倍から100倍だとい言います。従って、いったん農業で人口が増えると農業が大前提となります。しかし日本ではそうなる以前から定住が始まった。そして、定住の結果として生まれたのが土器です。
|
なぜ定住したのか、一言でいうと、気候も含めて自然環境が「住みやすい」からなのです。
第1章の感想ですが、日本の歴史を語る上でまず自然環境から入るのは大正解だと思います。キーワードは森林ですね。森林を起点として、森林 → 水・食料 → 定住 → 土器と連鎖しています。
No.37「富士山型の愛国心」にも書きましたが、森林被服率が60%を越えて70%近い国は、先進国(たとえばG20)ではまずないわけです(最も多い高知県は84%もある)。この数字はスウェーデン、フィンランドなみです。しかしスウェーデン、フィンランドの人口密度は日本の1/20とか、そういう値であって、人口も全く違います。No.37では森林の多さと人口の多さに関する象徴的な例として「熊と人間が近接して生活している」をあげました。小学生が熊よけの鈴をつけて登校する例が全国のあちこちにある国は、まず他にないと思います。
森林の保水力が河川の源泉になっています。さらに森林から流れ出した栄養分は海にそそぎ、沿岸の漁業資源を増やします。森林が水や食料をもたらす元になっています。
山地が多くても、森林を伐採してしまったのではダメなのですね。文明が古くから発達したギリシャやトルコの海岸をエーゲ海から撮った観光写真を見ると、海岸の山地が写っていても木がありません。ギリシャ神話を読むと、鬱蒼とした森がないと成り立たない話がいろいろとあるのですが、現在は禿山だらけです。「人が住むと1000年ぐらいの間に森がなくなってしまう」と大澤氏が言うのは、まさにその通りだと思います。そうなると土地の保水力がなくなり、表土は流出して岩だらけになり、河川は埋まり、海に栄養分が届かなくなる。森林からの水分の蒸発がなくなって、気候も変わってしまいます。降水量が減って悪循環に陥る。
日本は海岸の景観を見ても違います。そこが山地だと木が密集しているのが普通であり、それが内陸までつながっています。日本はこのような環境条件にあり、それは縄文時代から続いているということに、まず着目すべきでしょう。まとめると、
| ◆ | 日本の土器は、世界史で考えても最も古いもののひとつである。 | ||
| ◆ | それは定住の結果である。 | ||
| ◆ | 農業なしに、狩猟採集だけでも定住できる自然環境条件が日本にあった。 | ||
| ◆ | その環境の源泉は森林である。 |
ということになります。日本史を考える上での出発点です。
以下、『げんきな日本論』の第2章以降は、
| 鉄器と青銅器、古墳、天皇、仏教、律令制、貴族、漢字と仮名、院政、武士、幕府、一揆、信長と安土城、秀吉と朝鮮出兵 |
などのキーワードをもとに日本史が俯瞰されています。特に、漢字と仮名の問題をとりあげた章(第5章:なぜ日本人は仏教を受け入れたのか、第8章:なぜ日本には源氏物語が存在するのか)は、日本史を語る上で欠かせないものだと思いました。
以降は、江戸時代を中心にその前後を含めて何点か紹介します。
武家政権という希有な歴史
江戸時代とその前後を語るためには、武士について触れないわけにはいかないのですが、第11章「なぜ日本には、幕府なるものが存在するのか」の冒頭に次のような指摘があります。
|
我々日本人は、小学校以来の教育、時代劇、大河ドラマなどから、日本にはかつて武士がいて、武士が政権を担当していたということに何の疑問も抱きません。鎌倉幕府の成立から大政奉還まで武家政権だった。そして我々は暗黙に、鎌倉幕府以降が今の日本に直結していると感じています。特に戦国時代以降、もっと絞ると安土桃山時代以降です。平安時代、ないしは奈良時代やそれ以前となると、あまりに今とは違いすぎて遠い昔に感じます。今の日本の礎になり、また日本独自の文化や精神面でのカルチャーは安土桃山時代以降に確立したと、我々は暗黙に感じていると思います。その時代はというと "武家政権の時代" なのです。
その武家政権は、世界史の視野でみると極めて特異なものというのが橋爪・大澤両氏の指摘です。これは我々が気づきにくい点です。
武家政権を担った武士は、生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や弓や乗馬の練習をしてきたプロフェショナルであり、代々受け継がれた階級です。そういった武士の政権が世の中を支配するのが世界史的に特異だということは、そこに日本史や日本の独自性につながるさまざまな事柄が派生すると想像できます。この視点に関係したことを以下に何点か書きます。まず鉄砲の話です。
鉄砲が歴史を動かす
世界史をひもとくと武器の革新が歴史を動かし、社会を変革してきた例が数々あります。騎兵(乗馬)がそうだし、馬を使った戦車がそうです。もっと古くは鉄製の武器(剣、槍、矢尻、など)もそうだった。鉄砲(銃)も、そういった歴史を動かした武器です。
第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」では「鉄砲史観」とでも言うべき "鉄砲と歴史の関係" が、ヨーロッパと日本を対比させて語られています。その概要は以下のようです。
| ヨーロッパでは |
火薬は中国で発明されましたが、火薬を応用した鉄砲はヨーロッパで実用化されました。鉄砲の製造は難しいのですが、いったん製造できたとなると誰でも引き金を引けば人を殺せる武器になります。甲冑を射抜いて敵を倒せるわけであり、重装備の歩兵も騎兵も無力になります。
さらに大型の「大砲」となると要塞を破壊できます。戦史の本では、ナポリにあった難攻不落の要塞は7年持ちこたえたが、大砲で攻撃したら7時間で打ち壊されたとあります。結果として、封建領主の騎兵と要塞は無意味になりました。
鉄砲は強い軍事力をもたらすともに、個人戦から集団戦へと戦い方を変えました。また、鉄砲をコントロールしていたのが都市の住民だったので、軍事力の中心は市民階級や傭兵になりました。これに目をつけたのが絶対君主です。傭兵を使って鉄砲を装備した常備軍を組織し、貴族をやっつけて強力な政府を作りあげました。傭兵はスイス人が多かったのですが、その理由はスイスが中立だからで、つまり戦いの相手に寝返ることがないからです。
鉄砲を撃つ兵士を「銃士」と言います。デュマの小説「三銃士」(時代設定は17世紀)の "銃士" がそうです。この小説でもわかるように、ヨーロッパでは銃が得意だということが威信の根拠になりました。
絶対君主の次の時代に起こったのが、鉄砲で武装した市民による革命です。以上のようにヨーロッパでは「鉄砲のない封建制」→「鉄砲のある傭兵制(絶対君主)」→「鉄砲のある市民革命」というように社会が変化した歴史があります。鉄砲によって社会変動が生じたわけであり、社会の変化と武器の変化は連動していました。
| ちなみに中国は先進文明でありながら、鉄砲をあまり使わなかった文明です。この結果、軍事技術にヨーロッパと差がついただけでなく、社会のタイプがヨーロッパとは異なるものになりました。 |
| 日本では |
一方の日本はというと、鉄砲がヨーロッパからもたらされたことは衆知の事実です(1543年)。そしてすぐさま日本で製造されるようになり、鉄砲は急速に普及しました。それだけの製鉄や鍛冶、冶金の技術が日本にあったわけです。しかし鉄砲の社会的意味はヨーロッパとはかなり違った。
|
戦国時代、鉄砲の使い方がうまかったのが織田信長です。刀と槍で相手に襲いかかる戦法をとり(桶狭間など)、鉄砲では襲ってくる敵を向かえ打つというように(長篠など)、両方の特性をうまく使い分けた。そして何よりも、戦争は個人戦ではなく集団戦であることを徹底させました。
しかし信長は同時に、今まで武器を持っていなかったものが鉄砲を持つことによって政治的な力にならないよう、注意を払いました。いわゆる「兵農分離」もそれが念頭におかれています。信長だけでなく、鉄砲伝来から関ヶ原の戦いに至るまで、戦国武将は鉄砲を使いました。鉄砲隊を組織し、鉄砲の数もジャレット・ダイアモンドが言うように世界史的にみても非常に多かった。しかし鉄砲は、戦術として補助的に使われました。関ヶ原の戦いでも中心は騎兵や歩兵です。
そして日本の特徴は、武士が常に鉄砲をコントロールしたことです。ヨーロッパでは都市が発達し、都市に富が集中して、そこに鉄砲が蓄えられました。日本ではそういう都市の発達がなかったことが一つの原因だと考えられます。また、日本では伝統的に武士だけが戦闘員資格をもち、農民や商人は戦闘員にはなれませんでした。必然、武士が鉄砲を独占することになった。例外は紀州の雑賀衆ぐらいです。
武士は生まれながらの戦闘員です。小さいときから刀や槍や乗馬の練習をしてきたプロフェッショナルです。刀や槍で戦う限り、付け焼き刃では武士に太刀打ちできません。従って武士と農民が戦えば必ず武士が勝ちました。例外は島原の乱ですが、天草四郎の軍には武士も加わっていました。
| ちなみに中国史では、しばしば皇帝の軍が農民軍に負けました。農民を雇って武器の訓練をさせたものが皇帝軍だからです。 |
しかし、急速に普及した鉄砲は誰でも使える武器です。しかも刀や槍より圧倒的に強い。これは武士の地位を危うくします。従って武士は刀狩りをやって兵(武士)と農(農民)を分離し、身分を固定化する方向にいった。もともと鉄砲は平民性(=誰でも使える)と反武士性(=武士の地位を危うくする)がありますが、それが抑止されたわけです。
その抑止が完成された江戸時代においては、銃が得意だということが戦闘者としての威信の根拠にはなりません。あくまで刀が武士の威信の最大の根拠です。刀は一騎討ち向きであり、個人の英雄性に結びつく武器です。武士は刀に異様にこだわることになりました。
鉄砲は威信の根拠にならないだけでなく、軽蔑されました。武士は子供の頃から10年、20年と鍛錬を重ねて刀が槍を使いこなせるようになったのに、鉄砲はすぐに使えます。しかも刀や槍より強い。鉄砲に対する軽蔑は武士の屈折した心理と言えるでしょう。
従って、鉄砲を持っているからといって政治的主体にはならなかった。鉄砲は威力があるが、鉄砲を持っている人間は威力がないということにしたわけです。日本では鉄砲の戦術的効果と社会的無効性の対比が際だっています。
江戸時代を特徴づけるのは「戦争の禁止」と「幕藩制による現状凍結」ですが、以上の考察からすると、幕藩制は鉄砲が入ってきたことによる武士の防衛反応だと考えられます。鉄砲によってヨーロッパは身分の平等化が促進されましたが、日本では逆に武士が上位となる身分化が固定されたのです。
これ以降は、第15章「なぜ鉄砲は、市民社会をうみ出さなかったか」の感想というか、補足です。大澤氏はジャレット・ダイアモンドが『銃・病原菌・鉄』で「1600年の段階でみたとき、日本は世界でもっとも高性能な銃を世界のどの国より多く持っていた」と書いていることに言及しています。このブログでも、No.33「日本史と奴隷狩り」で堺屋太一氏の文章を引用しました。再掲すると次の通りです。
|
しかしその鉄砲を、武士は(武士であるがゆえに)放棄してしまった。鉄砲を作る技術は急速に衰えていきました。そのあたりの経緯を『銃・病原菌・鉄』から引用すると次の通りです。
|
ジャレット・ダイアモンドがここでなぜ江戸時代の銃の放棄を説明しているのかというと、世界史では一度獲得した重要技術が放棄されることがあり、その典型例としてあげているのです。ダイアモンドによると、ヨーロッパでも銃を嫌い、銃の使用を制限した人がいた。しかしヨーロッパでは国と国が始終戦争をしていたので、銃の制限や放棄は長くは続かなかった。一方、日本は孤立した島国だったので銃の放棄が現実化した。しかしそれは大砲を備えたペリー艦隊で終わりを告げた・・・・・・。そういう文脈です。
| ちなみに「一度獲得した重要技術の放棄」は中国でも起こりました。外洋船・外洋航海(鄭和はアラビア半島やアフリカまで航海した!)、水力紡績機、機械式時計がそうだと、ジャレット・ダイアモンドは書いています。 |
武士が政権を担当し社会の支配層である状況(=世界史てみると特異な状況)の中に鉄砲が突如入ってきて、全国統一の決め手になった。決め手なったからこそ鉄砲は捨てられ非武装社会(=江戸時代)が出来上がった・・・・・・。こういう風に理解できます。
(次回に続く)
No.162 - 奴隷のしつけ方 [歴史]
今まで「古代ローマ」と「奴隷」について、いくつかの記事を書きました。「古代ローマ」については塩野七生氏の大著『ローマ人の物語』の感想を書いたのが始まりで(No.24-27)、以下の記事です。
また「奴隷」については No.18「ブルーの世界」で、青色染料の "藍" が、18世紀にアメリカのサウス・カロライナ州の奴隷制プランテーションで生産されたという歴史を書いたのが発端でした。
この「古代ローマ」と「奴隷」というテーマの接点である「ローマ帝国の奴隷」について解説した本が2015年に出版されました。『奴隷のしつけ方』(ジェリー・トナー著。橘明美訳。太田出版。2015)という本です。その内容の一部を紹介し、読後感を書きたいと思います。
『奴隷のしつけ方』
『奴隷のしつけ方』の著者は、英国・ケンブリッジ大学のジェリー・トナー教授で、教授は古代ローマの社会文化史の専門家です。この本の特徴は、紀元1~2世紀のローマ帝国の架空の人物、"マルクス・シドニウス・ファルクス" が「奴隷の管理方法」を語り、それをトナー教授が解説するという形をとっていることです。"マルクス・シドニウス・ファルクス" は先祖代々、大勢の奴隷を使ってきた貴族の家系という想定であり、奴隷の扱い方に大変詳しい。そのノウハウを生々しく語るという体裁をとることによって、古代ローマの奴隷制度、ないしはローマ社会の一面がクリアに分かるようになっています。
このような本の作り方は、紀元2世紀の首都・ローマの1日を当時のローマ人の目線で実況中継風に描いた『古代ローマ人の24時間』(アルベルト・アンジェラ。河出書房新社。2010)を思い出させます。この本は、No.22「クラバートと奴隷(1)スラブ民族」、No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」で引用しました。影響されたのかもしれません。
『奴隷のしつけ方』という日本語訳の題名になっていますが、原題は、
です。その内容も「しつけ」だけでなく、以下のように多岐に渡っている「ハウ・ツー本」です。
以下、この本の内容の一部を紹介しますが、本からの引用で(本文)としたものは "マルクス・シドニウス・ファルクス" が奴隷管理法を語っている部分、(解説)としたのは、トナー教授が "マルクスの話の解説" や "その根拠とした文献" を書いている部分です。いずれも下線は原文にはありません。
奴隷の種類
まず奴隷の種類ですが、私的奴隷(家内奴隷・農場奴隷)と公的奴隷がありました。
家長の支配下にある家族、自由人の使用人、奴隷をファミリアと言いますが、家内奴隷はそのファミリアの奴隷です。要するに「主人とその家族がやりたくないこと全般をやる」のが家内奴隷です。食事の用意とか炊事、洗濯、掃除から始まり、子供の世話、物の運搬、家屋の修理などなどです。さらに都市の貴族の間では「自己顕示欲を満たすために、不必要な数の奴隷を所有する」こともあったと言います。現代的に言うと「贅沢品」としての奴隷です。
農場奴隷は、大規模農場で農作業をする奴隷、および農場の管理人として働く奴隷です。農場の中には小規模農民が自ら耕作するものもあったし、また自由人が小作人となって農業を行う場合もありました。しかし "マルクス・シドニウス・ファルクス"のような貴族が所有する農場では奴隷を使うことが多かったし、また奴隷がどんどん増えていき、自由民の農民が減っていったことが本書に書かれています。
公的奴隷は、国家や属州に所属する奴隷であり、各種雑務を行うのはもちろんですが、会計事務などをする奴隷もいました。
奴隷は肉体労働や単純労働だけではありません。家庭教師、学者、会計事務など、専門性の高い「ホワイト・カラーの奴隷」もいました。
しかしその一方で過酷な労働を強いられる奴隷もあり、たとえば鉱山労働やガレー船の漕ぎ手など、命を削るような労働もありました。奴隷同士の殺し合い(ないしは猛獣との殺し合い)のショーをする「剣闘士」も奴隷です。さらに女奴隷であれば「売春婦」という仕事もありました。
奴隷は「主人の所有物」であり、それは現在の家電製品やクルマと同じです。主人がお金を出して購入するものであり、売り飛ばすのも自由です。従って奴隷には一切の「権利」がありません。ただし、主人の承認のもとに「私有財産」は認められていたようです(法的には主人の財産)。奴隷同士の結婚も法的には認められていませんでしたが、これも主人の承認のもとの「事実婚」がありました。
奴隷の数
その奴隷はどれほどの数だったのでしょうか。現存する資料は少なく、あくまで推測だとトナー教授は断っていますが、次のような記述があります。
以前の記事で、塩野七生氏の本に書かれている奴隷の数を書きました。
塩野氏も文献を詳しく調査して書いているはずです。トナー教授も言っているように "あくまで推測" なのですが、イタリア半島において(ないしは首都・ローマにおいて)人口の30%程度(ないしは1/3程度)が奴隷だったと考えていいと思います。なお塩野氏が書いているのは紀元前1世紀、トナー教授の本は紀元1~2世紀ですが、この間、イタリア半島に限っていうとローマ帝国の領土はほぼ同じです。
人口の30%が奴隷ということからすると、当たり前かもしれませんが、全ての自由人が奴隷をもっていたわけではないことに注意すべきでしょう。
奴隷の発生源
奴隷はどのようにして発生するのか。それはまず戦争の捕虜です。
2番目は、女奴隷から生まれた子供(=家内出生奴隷)です。戦争捕虜か奴隷の子供、この二つが奴隷の発生源でした。しかし、それ以外の奴隷もあった。つまり、
などです。
奴隷の購入
奴隷はどこで購入するかというと、奴隷商人が経営する「奴隷販売店」です。いつの世にもあることですが、奴隷商人は奴隷の欠陥を隠して高く売りつけようとします。そのため「奴隷売買の規則」がありました。
「身の回りの世話をさせる奴隷に、若いブリトン人はやめた方がいい、荒っぽくて行儀が悪い」というくだりは、イギリス人であるトナー教授の "ジョーク" かと一瞬思えますが、何らかの文献によっているのでしょう。
その他の購入のノウハウとして、ローマ市民だった者を奴隷として買うな(使う方も居心地が悪い)とか、同じ出身地・部族の奴隷を集めるな(仲間同士で "つるむ" から)とか、家内出生奴隷は従順でいいが、それなりに育成のコストがかかることを覚悟せよとか、さなざまなことが書かれています。
奴隷の値段については、だいたい1000セステルティウスという推測です。一家四人が1年間、食べていける食費が500セステルティウスとのことなので、奴隷はそれなりの値段だったわけです。
これらは普通の奴隷であって、値段の上はキリがありません。本書には、文法学者、俳優、会計管理人、美少年などが高価で取引された例が出てきます。
奴隷の管理
"マルクス・シドニウス・ファルクス" は奴隷の管理のノウハウをこと細かに書いています。よい行為をしたときには誉めたり、ちょっとした小物を与えたりという「モチベーション・アップ」が重要だとしています。また奴隷の間での役割分担の明確化が重要で、これがないと責任が曖昧になり、奴隷は怠けるとしてあります。このあたりはいつの時代も同じと言えるでしょう。
特に力が入っているのが「農場管理人」の人選です。これは「奴隷を管理する奴隷」なので重要です。「管理人の心得」が30箇条も列記してあり、主人たるもの常に管理人に言い聞かせ、目を光らせておくことが大切です。
奴隷と性
さきほどあげたように、奴隷同士の結婚は法的には認められていません。しかし主人の承認のもとに奴隷同士が「事実婚」の関係になることはありました。こうしてできた子供が「家内出生奴隷」です。
さらに、主人が女奴隷と性交渉をもつことも多々あったようです。こうして生まれた子供も奴隷になります。一般に主人の正式の子供は、幼児の時には乳母となる女奴隷が世話をしますが、それ以降は奴隷の世話係がつきます。
哲人皇帝、マルクス・アウレリウスは、美しい二人の奴隷を所有していたが、それを寝室に侍らせないことを自慢していたそうです。それが自慢になるほど、奴隷に性的なサービスをさせることが一般的だったということになります。トナー教授は次のように書いています。
奴隷に対する懲罰と拷問
奴隷が犯罪を犯した場合は、もちろん公の裁きを受けます。重罪の場合は猛獣刑(闘技場で猛獣の餌食にされる)もありました。
しかし家内奴隷が主人の意に反したことをやったり、不始末をしでかしたり、罪を犯したりしたときには、主人が懲罰を与えるのが普通でした。このとき、カッとなって奴隷の脚を折ったり、二階から付き落としたりするのは厳に慎むべきだと、"マルクス・シドニウス・ファルクス" は力説しています。奴隷も貴重な財産なのです。
一般的な懲罰は「鞭打ち」です。"マルクス・シドニウス・ファルクス" は、その場合、請負人に依頼すると言っています。
奴隷の逃亡にはもっと厳しい罰が待っています。逃亡奴隷を捕まえるプロがいました。ただし料金が高い。"マルクス・シドニウス・ファルクス" が勧めるのは、懸賞金をかけ、奴隷の特徴を書いた張り紙をローマ市内に出すことです。
捕えられた逃亡奴隷は、額に烙印を押されたり、首輪をつけられたりしました。そのような奴隷は、後に解放されて自由人になったとしても("解放" は後述)ローマ市民権は得られないという決まりがありました。
奴隷としての重罪は主人が殺された場合です。主人が何らかの犯罪者に殺害された場合、その主人を助けようとしなかった「同じ屋根の下の奴隷」は全員死刑になるのが普通でした。奴隷の最大の責務は主人を守ることであり、かつ連帯責任というわけです。
さら古代ローマでは法的手続きの一環として、奴隷に対する拷問が行われていました。それは奴隷が裁判の証人になった場合です。というのも、奴隷は道徳的に劣った存在であり、拷問しないと真実を言わない、と見なされていたからです。
奴隷の解放
古代ローマには「奴隷の解放」という公式の制度があり、これが古代ギリシャの奴隷制度と大きく違うところでした。
奴隷の解放は、主人の遺言によるものと、主人が生前に解放する場合があります。そのとき "解放税(奴隷の価値の5%)" を納める必要がありました。また無制限に解放はできず、所有する奴隷の数で解放できる割合(たとえば、大半の奴隷所有者が該当する10人以下の奴隷所有の場合は半数まで)が決まっていました。もちろん主人としては自分に忠節であった奴隷を解放するわけです。主人が愛情を持った女奴隷の場合、正式の妻として迎えるために解放することもあったようです。
奴隷の解放は主として都市部の現象だったと、トナー教授は書いています。農場の管理人が解放された例はあるが、その下の農夫として働く奴隷が解放されることはほとんどなかったと推定されるそうです。主人と顔を合わせるわけでもなく、解放するメリットもなかったからです。
解放され自由人になったとしても、数年は元主人のもとで働くのが普通でした。しかし多くの奴隷は解放を切望していました。「自由人になった解放奴隷の多くは、それまでできなかったことを成し遂げようと必死に働きました」と、トナー教授は書いています。
以上は本書に書かれている内容の一部ですが、通読するとローマ帝国時代の奴隷制度がどういうものであったか、よく理解できました。以下は、本書を読んだ感想です。
感想 : ローマの発展と奴隷
この本はローマの政治史や軍事史はまったく扱っていません。あくまで「奴隷」という社会の最下層の人たちを貴族がどう見ていて、どう扱ったか(扱うべきか)という視点の本です。しかしそれでいて(それだからこそ)ローマの発展と凋落の理由がうっすらと見えてくるような気がしました。
ローマの発展の理由の一つに「ローマ的奴隷制度」があったこと間違いないと思います。周りの国と戦争をし、領土を拡大していくと、同時に奴隷も供給されます。現代に置き換えると、家電製品やクルマや農業機械を手に入るようなものです。貴族や富裕層はその奴隷(=最低限の衣食住を与えられて無給で労働する人)を買い、農場を運営する。一切の家事・労働から解放された裕福なローマ市民は、政治や戦争に専念できます。これが富の集中をもたらし、富裕層はますます富裕になる。こういった富の蓄積が文化や芸術を生み、また各種のインフラストラクチャが整備されました(No.112, No.113, No.123)。
戦争捕虜の奴隷はもともと自由民だったわけで、誇りも自負もあるはずです。それが奴隷の身分になっている。しかしローマには「解放」という公式の制度があり、主人に一所懸命仕えれば、自由民になることが期待できる。解放されたとしたら、奴隷生活を取り戻すべく自由民として必死に働く。このローマの柔軟さが社会の活力を生むことになったでしょう。人間は「希望」がある限り、非常につらいことにも耐えられるものです。
しかし、領土の拡大がなくなり、戦争捕虜=奴隷の供給が止まったら、この社会は変質していくと考えられます。農業生産を増やすにしても、領土拡大ではなく生産性を上げるしかないわけですが、本書にも書いてあるように、奴隷には生産性をあげるモチベーションがありません。「最近の農業はほとんと奴隷になった。嘆かわしい」との主旨の記述がありました。かといって、農業経験がない自由民に農業をやれといっても出来ない(やりたくない)でしょう。
奴隷の発生源も、家内出生奴隷や捨て子がメジャーになります。つまり「生まれた時からの奴隷」であり、解放へのモチベーションが戦争捕虜とはだいぶ違うのでなないでしょうか。
「身の回りをさせる奴隷なら、ブリトン人よりもエジプト人」と本書にあります。まえに引用した『古代ローマ人の24時間』(アルベルト・アンジェラ)では、首都・ローマには帝国の各地から連れてこられた奴隷であふれている様子が活写されていました。この状況はある種の軋轢を生むでしょうが(極端には奴隷の反乱)、社会の活力になったことは間違いないと思います。しかし、帝国が最大版図で固定化すると、この状況が大きく変質していくでしょう。
発展の要因が、あるターニング・ポイントを越えると発展の阻害要因になる。そういう風に思いました。
感想 : 歴史に学ぶ意義
本書を読んで感じることの2番目は「人間のやることは昔も今も変わらない」ということです。それはまず第一に、世界というレベルでみると、現代でも奴隷状態に置かれている人が多くいることです。トナー教授は次のように書いています。
これが世界の実態でしょう。奴隷は決して過去の話ではありません。前に引用したトナー教授の推定に従ってローマ帝国全体の奴隷の数を仮に800~900万人とすると、現代社会にはローマ帝国の3倍の奴隷がいることになります(推定)。
さらに、奴隷ではないが身近な問題として、極めて低い賃金で働き続けなければならない「貧困層」の存在があります。そして、現代の社会は「貧困層」の存在を必要としていて、それを作り出すメカニズムが働いていると思います。
分かりやすいのは移民です。アメリカ西海岸のホテルに泊まったりすると、そこでベッド・メイキングしている人たちは、ヒスパニック系の人が非常に多い。英語が話せなかったりします。"生粋の"アメリカ人は、そういう仕事につかないわけです。ドイツでも、たとえばゴミ収集などはドイツ人はしないと言います。
日本では移民を厳しく制限していることもあって、アメリカやドイツの状況とは違います。しかし貧困に苦しむ人は多い。この前もテレビで、あるシングル・マザーの人を取材していました。高校生の娘が一人いますが、パートで晩まで働きづめで、月収はよくて20万円だそうです。大都会の生活ではギリギリです。それに解雇されるリスクがある。この方の母親もシングルマザーで、本人は経済的理由から大学進学は断念したとのことでした。娘が心配と語っていましたが、それはそうでしょう。親子3代にわたって貧困が連鎖する可能性があるのだから。
これはあくまで一つの例ですが、冷静になって考えてみると、今の社会は「大都会で、年収200万円程度の(あるいはそれ以下の)、働き盛りの年代の人」を必要としているということでしょう。そして、そういう層を作り出すメカニズムがある。その最たるものは「やりたいようにやろう。好きなことを自由にして生きよう。他人に命令されずに生きよう」という、マスコミのキャンペーンです。ここに大きな落とし穴が仕掛けられている。そして、貧困層の人たちにもモチベーチョンをもって働いてもらう「管理方法」があります。さらに、貧困から抜け出す道も(必ずそうなるというわけではないが)ちゃんと開けている。
もちろん奴隷ではありません。人権があり、職業選択の自由があり、健康な生活を送る権利も有している。しかしこの資本主義社会の中では、古代ローマの奴隷と似たような役割を果たしていると感じます。
『奴隷のしつけ方』という本は、社会における貧困層の人たちを、どうやって動機付け、どうやって働かせるか、という "指南書" として読むと、現代もほとんど変わらない、歴史に学ぶ意義はこの例だけからしてもある、そう感じました。「愚者は経験に学ぶ、賢者は歴史に学ぶ」という金言がありますが、その通りです。愚者は「自分」の経験に学んでしまうのですが(そして、成功体験に学んでしまって失敗したりするのですが)、賢者は「人間」の歴史に学ぶのです。
| No.24-27 | 「ローマ人の物語」 |
| No.112-3 | 「ローマ人のコンクリート」 |
| No.123 | 「ローマ帝国の盛衰とインフラ」 |
また「奴隷」については No.18「ブルーの世界」で、青色染料の "藍" が、18世紀にアメリカのサウス・カロライナ州の奴隷制プランテーションで生産されたという歴史を書いたのが発端でした。
| No.18 | 「ブルーの世界」 |
| No.22-23 | 「クラバートと奴隷」 |
| No.33 | 「日本史と奴隷狩り」 |
| No.34 | 「大坂夏の陣図屏風」 |
| No.104 | 「リンカーンと奴隷解放宣言」 |
| No.109 | 「アンダーソンヴィル捕虜収容所」 |
この「古代ローマ」と「奴隷」というテーマの接点である「ローマ帝国の奴隷」について解説した本が2015年に出版されました。『奴隷のしつけ方』(ジェリー・トナー著。橘明美訳。太田出版。2015)という本です。その内容の一部を紹介し、読後感を書きたいと思います。
『奴隷のしつけ方』

| |||
このような本の作り方は、紀元2世紀の首都・ローマの1日を当時のローマ人の目線で実況中継風に描いた『古代ローマ人の24時間』(アルベルト・アンジェラ。河出書房新社。2010)を思い出させます。この本は、No.22「クラバートと奴隷(1)スラブ民族」、No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」で引用しました。影響されたのかもしれません。
『奴隷のしつけ方』という日本語訳の題名になっていますが、原題は、
| How to Manage Your Slaves (奴隷管理法) |
です。その内容も「しつけ」だけでなく、以下のように多岐に渡っている「ハウ・ツー本」です。
| 奴隷の買い方 | |||
| 奴隷の活用法 | |||
| 奴隷と性 | |||
| 奴隷は劣った存在か | |||
| 奴隷の罰し方 | |||
| なぜ拷問が必要か | |||
| 奴隷の楽しみ | |||
| スパルタクスを忘れるな! | |||
| 奴隷の解放 | |||
| 解放奴隷の問題 | |||
| キリスト教徒と奴隷 |
以下、この本の内容の一部を紹介しますが、本からの引用で(本文)としたものは "マルクス・シドニウス・ファルクス" が奴隷管理法を語っている部分、(解説)としたのは、トナー教授が "マルクスの話の解説" や "その根拠とした文献" を書いている部分です。いずれも下線は原文にはありません。
奴隷の種類
まず奴隷の種類ですが、私的奴隷(家内奴隷・農場奴隷)と公的奴隷がありました。
| ◆ | 私的奴隷
| ||||||||||
| ◆ | 公的奴隷 |
家長の支配下にある家族、自由人の使用人、奴隷をファミリアと言いますが、家内奴隷はそのファミリアの奴隷です。要するに「主人とその家族がやりたくないこと全般をやる」のが家内奴隷です。食事の用意とか炊事、洗濯、掃除から始まり、子供の世話、物の運搬、家屋の修理などなどです。さらに都市の貴族の間では「自己顕示欲を満たすために、不必要な数の奴隷を所有する」こともあったと言います。現代的に言うと「贅沢品」としての奴隷です。
農場奴隷は、大規模農場で農作業をする奴隷、および農場の管理人として働く奴隷です。農場の中には小規模農民が自ら耕作するものもあったし、また自由人が小作人となって農業を行う場合もありました。しかし "マルクス・シドニウス・ファルクス"のような貴族が所有する農場では奴隷を使うことが多かったし、また奴隷がどんどん増えていき、自由民の農民が減っていったことが本書に書かれています。
公的奴隷は、国家や属州に所属する奴隷であり、各種雑務を行うのはもちろんですが、会計事務などをする奴隷もいました。
奴隷は肉体労働や単純労働だけではありません。家庭教師、学者、会計事務など、専門性の高い「ホワイト・カラーの奴隷」もいました。
しかしその一方で過酷な労働を強いられる奴隷もあり、たとえば鉱山労働やガレー船の漕ぎ手など、命を削るような労働もありました。奴隷同士の殺し合い(ないしは猛獣との殺し合い)のショーをする「剣闘士」も奴隷です。さらに女奴隷であれば「売春婦」という仕事もありました。
奴隷は「主人の所有物」であり、それは現在の家電製品やクルマと同じです。主人がお金を出して購入するものであり、売り飛ばすのも自由です。従って奴隷には一切の「権利」がありません。ただし、主人の承認のもとに「私有財産」は認められていたようです(法的には主人の財産)。奴隷同士の結婚も法的には認められていませんでしたが、これも主人の承認のもとの「事実婚」がありました。
奴隷の数
その奴隷はどれほどの数だったのでしょうか。現存する資料は少なく、あくまで推測だとトナー教授は断っていますが、次のような記述があります。
|
以前の記事で、塩野七生氏の本に書かれている奴隷の数を書きました。
|
塩野氏も文献を詳しく調査して書いているはずです。トナー教授も言っているように "あくまで推測" なのですが、イタリア半島において(ないしは首都・ローマにおいて)人口の30%程度(ないしは1/3程度)が奴隷だったと考えていいと思います。なお塩野氏が書いているのは紀元前1世紀、トナー教授の本は紀元1~2世紀ですが、この間、イタリア半島に限っていうとローマ帝国の領土はほぼ同じです。
人口の30%が奴隷ということからすると、当たり前かもしれませんが、全ての自由人が奴隷をもっていたわけではないことに注意すべきでしょう。
奴隷の発生源
奴隷はどのようにして発生するのか。それはまず戦争の捕虜です。
|
2番目は、女奴隷から生まれた子供(=家内出生奴隷)です。戦争捕虜か奴隷の子供、この二つが奴隷の発生源でした。しかし、それ以外の奴隷もあった。つまり、
| ・ | 貧しい者が借金の返済に困って自らを売る | ||
| ・ | 親が子供たちを食べさせていくために、子供の一人を売る | ||
| ・ | 捨て子 | ||
| ・ | 人買いにさらわれたり、海賊に襲われて奴隷になる |
などです。
奴隷の購入
奴隷はどこで購入するかというと、奴隷商人が経営する「奴隷販売店」です。いつの世にもあることですが、奴隷商人は奴隷の欠陥を隠して高く売りつけようとします。そのため「奴隷売買の規則」がありました。
|
「身の回りの世話をさせる奴隷に、若いブリトン人はやめた方がいい、荒っぽくて行儀が悪い」というくだりは、イギリス人であるトナー教授の "ジョーク" かと一瞬思えますが、何らかの文献によっているのでしょう。
その他の購入のノウハウとして、ローマ市民だった者を奴隷として買うな(使う方も居心地が悪い)とか、同じ出身地・部族の奴隷を集めるな(仲間同士で "つるむ" から)とか、家内出生奴隷は従順でいいが、それなりに育成のコストがかかることを覚悟せよとか、さなざまなことが書かれています。
奴隷の値段については、だいたい1000セステルティウスという推測です。一家四人が1年間、食べていける食費が500セステルティウスとのことなので、奴隷はそれなりの値段だったわけです。
| 『古代ローマ人の24時間』(アルベルト・アンジェラ)では、紀元2世紀の1セステルティウスが現代の約2ユーロの価値と推定してありました。とすると、1000セステルティウスは今のレートで約25万円ですが、貨幣価値は現代も古代ローマも変動します。ローマ帝国の初期で「数十万円」というぐらいの理解でいいでしょう。 |
これらは普通の奴隷であって、値段の上はキリがありません。本書には、文法学者、俳優、会計管理人、美少年などが高価で取引された例が出てきます。
奴隷の管理
"マルクス・シドニウス・ファルクス" は奴隷の管理のノウハウをこと細かに書いています。よい行為をしたときには誉めたり、ちょっとした小物を与えたりという「モチベーション・アップ」が重要だとしています。また奴隷の間での役割分担の明確化が重要で、これがないと責任が曖昧になり、奴隷は怠けるとしてあります。このあたりはいつの時代も同じと言えるでしょう。
特に力が入っているのが「農場管理人」の人選です。これは「奴隷を管理する奴隷」なので重要です。「管理人の心得」が30箇条も列記してあり、主人たるもの常に管理人に言い聞かせ、目を光らせておくことが大切です。
奴隷と性
さきほどあげたように、奴隷同士の結婚は法的には認められていません。しかし主人の承認のもとに奴隷同士が「事実婚」の関係になることはありました。こうしてできた子供が「家内出生奴隷」です。
さらに、主人が女奴隷と性交渉をもつことも多々あったようです。こうして生まれた子供も奴隷になります。一般に主人の正式の子供は、幼児の時には乳母となる女奴隷が世話をしますが、それ以降は奴隷の世話係がつきます。
|
哲人皇帝、マルクス・アウレリウスは、美しい二人の奴隷を所有していたが、それを寝室に侍らせないことを自慢していたそうです。それが自慢になるほど、奴隷に性的なサービスをさせることが一般的だったということになります。トナー教授は次のように書いています。
|
奴隷に対する懲罰と拷問
奴隷が犯罪を犯した場合は、もちろん公の裁きを受けます。重罪の場合は猛獣刑(闘技場で猛獣の餌食にされる)もありました。
しかし家内奴隷が主人の意に反したことをやったり、不始末をしでかしたり、罪を犯したりしたときには、主人が懲罰を与えるのが普通でした。このとき、カッとなって奴隷の脚を折ったり、二階から付き落としたりするのは厳に慎むべきだと、"マルクス・シドニウス・ファルクス" は力説しています。奴隷も貴重な財産なのです。
一般的な懲罰は「鞭打ち」です。"マルクス・シドニウス・ファルクス" は、その場合、請負人に依頼すると言っています。
|
奴隷の逃亡にはもっと厳しい罰が待っています。逃亡奴隷を捕まえるプロがいました。ただし料金が高い。"マルクス・シドニウス・ファルクス" が勧めるのは、懸賞金をかけ、奴隷の特徴を書いた張り紙をローマ市内に出すことです。
捕えられた逃亡奴隷は、額に烙印を押されたり、首輪をつけられたりしました。そのような奴隷は、後に解放されて自由人になったとしても("解放" は後述)ローマ市民権は得られないという決まりがありました。
奴隷としての重罪は主人が殺された場合です。主人が何らかの犯罪者に殺害された場合、その主人を助けようとしなかった「同じ屋根の下の奴隷」は全員死刑になるのが普通でした。奴隷の最大の責務は主人を守ることであり、かつ連帯責任というわけです。
さら古代ローマでは法的手続きの一環として、奴隷に対する拷問が行われていました。それは奴隷が裁判の証人になった場合です。というのも、奴隷は道徳的に劣った存在であり、拷問しないと真実を言わない、と見なされていたからです。
奴隷の解放
古代ローマには「奴隷の解放」という公式の制度があり、これが古代ギリシャの奴隷制度と大きく違うところでした。
奴隷の解放は、主人の遺言によるものと、主人が生前に解放する場合があります。そのとき "解放税(奴隷の価値の5%)" を納める必要がありました。また無制限に解放はできず、所有する奴隷の数で解放できる割合(たとえば、大半の奴隷所有者が該当する10人以下の奴隷所有の場合は半数まで)が決まっていました。もちろん主人としては自分に忠節であった奴隷を解放するわけです。主人が愛情を持った女奴隷の場合、正式の妻として迎えるために解放することもあったようです。
奴隷の解放は主として都市部の現象だったと、トナー教授は書いています。農場の管理人が解放された例はあるが、その下の農夫として働く奴隷が解放されることはほとんどなかったと推定されるそうです。主人と顔を合わせるわけでもなく、解放するメリットもなかったからです。
解放され自由人になったとしても、数年は元主人のもとで働くのが普通でした。しかし多くの奴隷は解放を切望していました。「自由人になった解放奴隷の多くは、それまでできなかったことを成し遂げようと必死に働きました」と、トナー教授は書いています。
以上は本書に書かれている内容の一部ですが、通読するとローマ帝国時代の奴隷制度がどういうものであったか、よく理解できました。以下は、本書を読んだ感想です。
感想 : ローマの発展と奴隷
この本はローマの政治史や軍事史はまったく扱っていません。あくまで「奴隷」という社会の最下層の人たちを貴族がどう見ていて、どう扱ったか(扱うべきか)という視点の本です。しかしそれでいて(それだからこそ)ローマの発展と凋落の理由がうっすらと見えてくるような気がしました。
ローマの発展の理由の一つに「ローマ的奴隷制度」があったこと間違いないと思います。周りの国と戦争をし、領土を拡大していくと、同時に奴隷も供給されます。現代に置き換えると、家電製品やクルマや農業機械を手に入るようなものです。貴族や富裕層はその奴隷(=最低限の衣食住を与えられて無給で労働する人)を買い、農場を運営する。一切の家事・労働から解放された裕福なローマ市民は、政治や戦争に専念できます。これが富の集中をもたらし、富裕層はますます富裕になる。こういった富の蓄積が文化や芸術を生み、また各種のインフラストラクチャが整備されました(No.112, No.113, No.123)。
戦争捕虜の奴隷はもともと自由民だったわけで、誇りも自負もあるはずです。それが奴隷の身分になっている。しかしローマには「解放」という公式の制度があり、主人に一所懸命仕えれば、自由民になることが期待できる。解放されたとしたら、奴隷生活を取り戻すべく自由民として必死に働く。このローマの柔軟さが社会の活力を生むことになったでしょう。人間は「希望」がある限り、非常につらいことにも耐えられるものです。
しかし、領土の拡大がなくなり、戦争捕虜=奴隷の供給が止まったら、この社会は変質していくと考えられます。農業生産を増やすにしても、領土拡大ではなく生産性を上げるしかないわけですが、本書にも書いてあるように、奴隷には生産性をあげるモチベーションがありません。「最近の農業はほとんと奴隷になった。嘆かわしい」との主旨の記述がありました。かといって、農業経験がない自由民に農業をやれといっても出来ない(やりたくない)でしょう。
奴隷の発生源も、家内出生奴隷や捨て子がメジャーになります。つまり「生まれた時からの奴隷」であり、解放へのモチベーションが戦争捕虜とはだいぶ違うのでなないでしょうか。
「身の回りをさせる奴隷なら、ブリトン人よりもエジプト人」と本書にあります。まえに引用した『古代ローマ人の24時間』(アルベルト・アンジェラ)では、首都・ローマには帝国の各地から連れてこられた奴隷であふれている様子が活写されていました。この状況はある種の軋轢を生むでしょうが(極端には奴隷の反乱)、社会の活力になったことは間違いないと思います。しかし、帝国が最大版図で固定化すると、この状況が大きく変質していくでしょう。
発展の要因が、あるターニング・ポイントを越えると発展の阻害要因になる。そういう風に思いました。
感想 : 歴史に学ぶ意義
本書を読んで感じることの2番目は「人間のやることは昔も今も変わらない」ということです。それはまず第一に、世界というレベルでみると、現代でも奴隷状態に置かれている人が多くいることです。トナー教授は次のように書いています。
|
これが世界の実態でしょう。奴隷は決して過去の話ではありません。前に引用したトナー教授の推定に従ってローマ帝国全体の奴隷の数を仮に800~900万人とすると、現代社会にはローマ帝国の3倍の奴隷がいることになります(推定)。
さらに、奴隷ではないが身近な問題として、極めて低い賃金で働き続けなければならない「貧困層」の存在があります。そして、現代の社会は「貧困層」の存在を必要としていて、それを作り出すメカニズムが働いていると思います。
分かりやすいのは移民です。アメリカ西海岸のホテルに泊まったりすると、そこでベッド・メイキングしている人たちは、ヒスパニック系の人が非常に多い。英語が話せなかったりします。"生粋の"アメリカ人は、そういう仕事につかないわけです。ドイツでも、たとえばゴミ収集などはドイツ人はしないと言います。
日本では移民を厳しく制限していることもあって、アメリカやドイツの状況とは違います。しかし貧困に苦しむ人は多い。この前もテレビで、あるシングル・マザーの人を取材していました。高校生の娘が一人いますが、パートで晩まで働きづめで、月収はよくて20万円だそうです。大都会の生活ではギリギリです。それに解雇されるリスクがある。この方の母親もシングルマザーで、本人は経済的理由から大学進学は断念したとのことでした。娘が心配と語っていましたが、それはそうでしょう。親子3代にわたって貧困が連鎖する可能性があるのだから。
これはあくまで一つの例ですが、冷静になって考えてみると、今の社会は「大都会で、年収200万円程度の(あるいはそれ以下の)、働き盛りの年代の人」を必要としているということでしょう。そして、そういう層を作り出すメカニズムがある。その最たるものは「やりたいようにやろう。好きなことを自由にして生きよう。他人に命令されずに生きよう」という、マスコミのキャンペーンです。ここに大きな落とし穴が仕掛けられている。そして、貧困層の人たちにもモチベーチョンをもって働いてもらう「管理方法」があります。さらに、貧困から抜け出す道も(必ずそうなるというわけではないが)ちゃんと開けている。
もちろん奴隷ではありません。人権があり、職業選択の自由があり、健康な生活を送る権利も有している。しかしこの資本主義社会の中では、古代ローマの奴隷と似たような役割を果たしていると感じます。
『奴隷のしつけ方』という本は、社会における貧困層の人たちを、どうやって動機付け、どうやって働かせるか、という "指南書" として読むと、現代もほとんど変わらない、歴史に学ぶ意義はこの例だけからしてもある、そう感じました。「愚者は経験に学ぶ、賢者は歴史に学ぶ」という金言がありますが、その通りです。愚者は「自分」の経験に学んでしまうのですが(そして、成功体験に学んでしまって失敗したりするのですが)、賢者は「人間」の歴史に学ぶのです。
(続く)
No.123 - ローマ帝国の盛衰とインフラ [歴史]
No.112-113「ローマ人のコンクリート」の続きです。
古代ローマ人は社会のインフラストラクチャー(道路・街道、上水道・下水道、城壁、各種の公共建築物、など。以下、インフラ)を次々と建設したのですが、その建設にはコンクリート技術が重要な位置を占めていました。またその建設資金は、元老院階級(貴族)の富裕層の寄付が多々あったことも書きました。
No.112 に写真を掲げたインフラの中に、「ポン・デュ・ガール」(世界遺産)がありました。これは南フランスの都市、ニームに水を供給するために敷設された「ニーム水道」の一部です。古代ローマ人の驚異的なインフラ建設技術を物語るものなので、写真と図を掲載しておきます。
そういったインフラと古代ローマの盛衰の関係を、本村凌二氏が書いていたので紹介したいと思います。本村氏は元東京大学教授(現・早稲田大学教授)で、古代ローマ史の専門家です。以前、No.24「ローマ人の物語(1)」と、No.26「ローマ人の物語(3)」で、本村氏の『多神教と一神教』(岩波新書)を引用したことがあります。
以下、少々長くなりますが、ローマの盛衰とインフラの関係についての記述を引用します。下線は原文にはありません。
ローマ帝国の滅亡
インフラはメンテナンスが何よりも重要(むしろ建設するよりも重要)であり、ローマ帝国もインフラの補修をこまめに続けた。しかし帝国後期になるとそれも滞り、帝国の凋落の一因になったというのが、引用部分のおおまかな主旨です。
引用の最後の下線の部分に、インフラと富裕層の関係が書かれています。富裕層は私財でインフラを建設するが、メンテナンスはしないし、ましてや老朽化したインフラを作り替えたりはしない。それらは国家の責任になる・・・・・・。そこにはある種の社会的な不整合があるわけです。「富裕層の私財で造られた」ローマ帝国のインフラが抱える本質的な問題点が指摘されています。
普通、歴史上のインフラの建設資金は、国家が出すか、あるいは人民の労役の提供という形の「税金」でまかなわれたものだと、我々は考えます。現代においてもインフラの建設は税金か、ないしは受益者負担が原則でしょう。
現代でも「メセナ」という言葉があるように、企業やオーナー企業のトップが文化活動に寄付をすることは、欧米各国を先頭に一般化しています。しかし寄付で社会インフラを造る、というのはあまり聞きません。メセナという言葉は、古代ローマの初代皇帝、アウグストゥスの腹心だったガイウス・マエケナスの名前からきています。彼は文化人の支援に非常に熱心だった。しかし古代ローマでは、文化の育成のみならずインフラ建設も私財だったわけです。
小さな政府と富裕層
なぜローマ帝国では富裕層が私財を出してインフラを造ったのか。それには、ローマ帝国が「小さな政府」だったことが背景にあります。
貴族は中央にいたときからの子分(=平民)を連れて属州に行くこともあれば、属州のエリートたちを子分として雇い入れることもあったようです。いずれにせよ国家が負担するのは派遣した貴族(役人)の分だけです。
古代ローマの軍事費が国家財政の7割というのは、現代国家と違って、医療や福祉などの社会保障費がなかったこともあるのでしょうが、ベースには「小さな政府」があるわけです。
国家による「差額を自分のものにすることの黙認」は当然でしょうね。10億セステルティウスを徴税し、10億セステルティウスを中央に納めたとしたら、貴族(役人)の財産は目減りする一方です。なぜなら、徴税請負人をはじめとする子分たち(属州統治の実務担当者)は、貴族が私的なお金で雇ったものだからです。
しかし貴族が「子分を雇う費用相当分の差額を自分のものにした」ということはありえないでしょう。人間というものはそのようには行動はしません。必ず、出費を差し引いた「余得」や「役得」が貴族の収入になる。属州といっても、現代の地中海沿岸諸国の一つの「国」の広さがあります。そういう「国」から得られる「余得や役得」は巨大なものだったと思います。
もちろん中には「度を過ぎた税金の取り立て」もあり、属州民が中央政府に訴えて裁判になったケースがあったと、本村教授の本にありました。
本村教授が(例として)あげている「差額の2億セステルティウス」というのは、現代の貨幣価値にすると200億円とか300億円とか、そういうオーダーの金額です。属州という「国」レベルの税金なので、そういう金額になります。2億セステルティウスが事実かどうかはともかく、そいういう規模の話だということに注意すべきしょう。
思い起こすのはカエサルです。有名な話ですが、カエサルは借金王でした。彼はローマで一番の資産家であったマルクス・リキニウス・クラッススから借金を続けます。本村教授によると、財務官に当選したときには(BC.65 カエサル35歳)、クラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに25万人を集めた競技会(!)を開催し、借りたお金を全部使い切りました。2500万セステルティウスは、現在の貨幣価値にして30億円(!)です。
本村教授は「競技会」とマイルドに書いていますが、要するに剣闘士の試合(殺し合い)で、このとき集められた剣闘士は320組と言います。「ローマ人の物語」で塩野七生さんは次のように書いていました。()は引用注です。
カエサルの「太っ腹」には驚きますが、この件だけではなく、カエサルにお金を貸し続けたクラッススも相当な人です。クラッススの資産は国家予算の半分もあった(No.112「ローマ人のコンクリート(1)」参照)からこそでしょうが、それだけではなく、カエサルが地位を上り詰めることを見込んだことと、地位を上り詰めれば借金は返せることが分かっていたらからだと想像します。
事実、カエサルは亡くなったときには財産を残しています。それまでにカエサルは、属州(ヒスパニア)の総督を経験し、有名なガリア遠征の総指揮官を努めています。属州総督の余得は先述した通りだし、戦役では(勝てば)戦利品が得られる。クラッススの「見立て」は正しかったと言えるでしょう。
話がそれてしまいましたが、古代ローマの富裕層の話でした。カエサルは「財務官当選記念競技会」に数10億円(しかも借金)を使ったという認識を持つことで、当時のローマの富裕層の「富裕の規模」がイメージできると思います。「富裕層とインフラ建設」に話を戻すと、要するに古代ローマでは、
ということだと思います。小さな政府を背景とした、私財による公共投資。これは経済の成長期・繁栄期において、考えようによっては「最適な」システムです。
しかし経済成長が止まり、ないしはマイナス成長になると、このやり方は裏目に出てしまう。しかも、建て直す必要があるインフラがどんどん出てくると、非常に困ったことになる。インフラの老朽化が経済の停滞を招き、それが負のスパイラルとなって一挙に国家の凋落を招く可能性があるわけです。
本村教授は、ローマ帝国の後期になるとこの「負のスパイラル」がボディー・ブローのようにして利いてきて、国の体力を奪っていったことを指摘しているのだと考えます。
ローマの水使用量
インフラの例ですが、本村教授が「道路は、まだ地表を走っているのでいいのですが、上下水道、特に上水道の修理は大変です。」と指摘している「上水道」です。この上水道とテルマエ(公衆浴場)の関係を紹介しておきたいと思います。
計算すると、ローマ市民一人当たりの水使用量は、現代の横浜市民の3倍ということになります。これだけの大量の水を使った理由の一つがテルマエ(公衆浴場)でした。
日本人は温泉が大好きですが、温泉は地下から湧いてくるもので、いわば「自然の恵み」にあずかっているわけです。しかし、テルマエは温泉ではありません。超巨大銭湯であり、「都市型健康ランド」です。それを成り立たせるのに必須なのは、
であり、これらを負担する国家財政です。
テルマエの使用料はクァドランス銅貨1枚とありますが、ローマ帝政期における「クァドランス」は「セステルティウス」の16分の1です。トラヤヌス帝の時代のセステルティウスを現在の価値で2ユーロだとすると(前述のアルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」による)、テルマエの使用料は8分の1ユーロで、15円程度になります。まさに「タダ同然」です。
これら①~④の条件が、ローマ帝国の末期になるとなくなってきます。
さらにテルマエの衰退のもう一つの要因は、水の確保が難しくなったことだと、本村教授は言います。
No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」で、テルマエの維持のために、ローマ周辺の木材資源が枯渇してしまったという話を紹介しましたが、燃料となる木材の供給だけでなく水の供給も困難になってしまったというが、本村教授の指摘です。さらに、高度な建設技術で作られた水道は高度なメンテナンス技術が必要であり、その技術を維持し続けるためには、それなりの継続的な資金投入が必要だということも言えるでしょう。
インフラの重要性
インフラ(インフラストラクチャ)は、日本語で言うと「下部構造」です。言葉の定義からしても、インフラの上部構造として国が造られます。そういう発想のもとに世界史上で最初の国を作ったのがローマ人だった。ローマ人が「インフラの父」と言われるゆえんです。国力は経済力が第一ですが、インフラ国家における経済力は「インフラが維持され、正常に機能している前提」で発展するということになります。従って、その前提が無くなったとしたら、経済力は弱体化し、国力の凋落を招く。
ローマ市は(最盛期11本の)水道がある前提で、100万都市だった。その水道が機能不全に陥ると、ローマ市は凋落の道をたどる。もちろん水道がなくても人は生活していけるが、そのため疫病が蔓延したり、人口が数分の1に減少したとしたら、ローマ市の繁栄は消し飛んでしまう。これはあくまで想定ですが・・・・・・。
古代ローマ史のおもしろさは、一つの国の誕生から成長、繁栄、凋落、終焉までがワンセットとしてあり、文献資料もそれなりにあって研究されていることです。その歴史は、人間の生き方や人間集団の運営に関する示唆や教訓に満ちています。そこには現代にも通用しそうなものが一杯ある。
インフラに関していうと、No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」に書いたのは、「交通・輸送網」「上下水道」「エネルギー供給網」ですが、現代はそれに加えて「情報通信網」なども重要であり、さらに「社会福祉システム」などのソフト面のインフラも大変に重要です。はたしてそれらが「持続可能」なのかどうか。我々は考えてみるべきでしょう。
古代ローマ人は社会のインフラストラクチャー(道路・街道、上水道・下水道、城壁、各種の公共建築物、など。以下、インフラ)を次々と建設したのですが、その建設にはコンクリート技術が重要な位置を占めていました。またその建設資金は、元老院階級(貴族)の富裕層の寄付が多々あったことも書きました。
No.112 に写真を掲げたインフラの中に、「ポン・デュ・ガール」(世界遺産)がありました。これは南フランスの都市、ニームに水を供給するために敷設された「ニーム水道」の一部です。古代ローマ人の驚異的なインフラ建設技術を物語るものなので、写真と図を掲載しておきます。

| ||
|
ポン・デュ・ガール
(Wikipedia)
| ||

|


|
|
|
ポン・デュ・ガール付近に残る、ニーム水道の遺跡。
(http://www.avignon-et-provence.com/) |
||
|
|
|||||
|
左図は(A)、右図は(B)より引用。説明は(B)を参考にした。 (A) http://www.avignon-et-provence.com/ (B) http://www.romanaqueducts.info/ |
||||||
そういったインフラと古代ローマの盛衰の関係を、本村凌二氏が書いていたので紹介したいと思います。本村氏は元東京大学教授(現・早稲田大学教授)で、古代ローマ史の専門家です。以前、No.24「ローマ人の物語(1)」と、No.26「ローマ人の物語(3)」で、本村氏の『多神教と一神教』(岩波新書)を引用したことがあります。
以下、少々長くなりますが、ローマの盛衰とインフラの関係についての記述を引用します。下線は原文にはありません。
ローマ帝国の滅亡
|
インフラはメンテナンスが何よりも重要(むしろ建設するよりも重要)であり、ローマ帝国もインフラの補修をこまめに続けた。しかし帝国後期になるとそれも滞り、帝国の凋落の一因になったというのが、引用部分のおおまかな主旨です。
引用の最後の下線の部分に、インフラと富裕層の関係が書かれています。富裕層は私財でインフラを建設するが、メンテナンスはしないし、ましてや老朽化したインフラを作り替えたりはしない。それらは国家の責任になる・・・・・・。そこにはある種の社会的な不整合があるわけです。「富裕層の私財で造られた」ローマ帝国のインフラが抱える本質的な問題点が指摘されています。
普通、歴史上のインフラの建設資金は、国家が出すか、あるいは人民の労役の提供という形の「税金」でまかなわれたものだと、我々は考えます。現代においてもインフラの建設は税金か、ないしは受益者負担が原則でしょう。
現代でも「メセナ」という言葉があるように、企業やオーナー企業のトップが文化活動に寄付をすることは、欧米各国を先頭に一般化しています。しかし寄付で社会インフラを造る、というのはあまり聞きません。メセナという言葉は、古代ローマの初代皇帝、アウグストゥスの腹心だったガイウス・マエケナスの名前からきています。彼は文化人の支援に非常に熱心だった。しかし古代ローマでは、文化の育成のみならずインフラ建設も私財だったわけです。
小さな政府と富裕層
なぜローマ帝国では富裕層が私財を出してインフラを造ったのか。それには、ローマ帝国が「小さな政府」だったことが背景にあります。
|
貴族は中央にいたときからの子分(=平民)を連れて属州に行くこともあれば、属州のエリートたちを子分として雇い入れることもあったようです。いずれにせよ国家が負担するのは派遣した貴族(役人)の分だけです。
古代ローマの軍事費が国家財政の7割というのは、現代国家と違って、医療や福祉などの社会保障費がなかったこともあるのでしょうが、ベースには「小さな政府」があるわけです。
|
国家による「差額を自分のものにすることの黙認」は当然でしょうね。10億セステルティウスを徴税し、10億セステルティウスを中央に納めたとしたら、貴族(役人)の財産は目減りする一方です。なぜなら、徴税請負人をはじめとする子分たち(属州統治の実務担当者)は、貴族が私的なお金で雇ったものだからです。
しかし貴族が「子分を雇う費用相当分の差額を自分のものにした」ということはありえないでしょう。人間というものはそのようには行動はしません。必ず、出費を差し引いた「余得」や「役得」が貴族の収入になる。属州といっても、現代の地中海沿岸諸国の一つの「国」の広さがあります。そういう「国」から得られる「余得や役得」は巨大なものだったと思います。
もちろん中には「度を過ぎた税金の取り立て」もあり、属州民が中央政府に訴えて裁判になったケースがあったと、本村教授の本にありました。
本村教授が(例として)あげている「差額の2億セステルティウス」というのは、現代の貨幣価値にすると200億円とか300億円とか、そういうオーダーの金額です。属州という「国」レベルの税金なので、そういう金額になります。2億セステルティウスが事実かどうかはともかく、そいういう規模の話だということに注意すべきしょう。
思い起こすのはカエサルです。有名な話ですが、カエサルは借金王でした。彼はローマで一番の資産家であったマルクス・リキニウス・クラッススから借金を続けます。本村教授によると、財務官に当選したときには(BC.65 カエサル35歳)、クラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに25万人を集めた競技会(!)を開催し、借りたお金を全部使い切りました。2500万セステルティウスは、現在の貨幣価値にして30億円(!)です。
本村教授は「競技会」とマイルドに書いていますが、要するに剣闘士の試合(殺し合い)で、このとき集められた剣闘士は320組と言います。「ローマ人の物語」で塩野七生さんは次のように書いていました。()は引用注です。
|
カエサルの「太っ腹」には驚きますが、この件だけではなく、カエサルにお金を貸し続けたクラッススも相当な人です。クラッススの資産は国家予算の半分もあった(No.112「ローマ人のコンクリート(1)」参照)からこそでしょうが、それだけではなく、カエサルが地位を上り詰めることを見込んだことと、地位を上り詰めれば借金は返せることが分かっていたらからだと想像します。
事実、カエサルは亡くなったときには財産を残しています。それまでにカエサルは、属州(ヒスパニア)の総督を経験し、有名なガリア遠征の総指揮官を努めています。属州総督の余得は先述した通りだし、戦役では(勝てば)戦利品が得られる。クラッススの「見立て」は正しかったと言えるでしょう。
| 古代ローマの貨幣価値についての余談です。カエサルの時代(前1世紀)、本村教授によると2500万セステルティウスが30億円なので、1セステルティウス青銅貨は、現代日本の120円という換算になります。一方、No.22「クラバートと奴隷(1)」で書いたのですが、アルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」(2010出版)では、トラヤヌス帝の時代(紀元2世紀初頭)の1セステルティウス青銅貨は、現在の貨幣価値で2ユーロと結論づけていました。 貨幣価値は時代で変わるし(カエサルとトラヤヌス帝では200年近い差がある)、現代の貨幣価値も数年でかなり変動します。また2000年前の貨幣価値を何を基準にして計測するかは、難しい問題があると思います。「現代の貨幣価値で」というのは、あくまで概算と考えた方が良いと思われます。 |
話がそれてしまいましたが、古代ローマの富裕層の話でした。カエサルは「財務官当選記念競技会」に数10億円(しかも借金)を使ったという認識を持つことで、当時のローマの富裕層の「富裕の規模」がイメージできると思います。「富裕層とインフラ建設」に話を戻すと、要するに古代ローマでは、
| ・ | 富裕層に富が集中していて(そういう社会の仕組みであり)、 | ||
| ・ | 富裕層による「富の再分配」があり、 | ||
| ・ | 再分配として、私財によるインフラ建設があり、 | ||
| ・ | それが国家レベルで大々的に行われていた |
ということだと思います。小さな政府を背景とした、私財による公共投資。これは経済の成長期・繁栄期において、考えようによっては「最適な」システムです。
しかし経済成長が止まり、ないしはマイナス成長になると、このやり方は裏目に出てしまう。しかも、建て直す必要があるインフラがどんどん出てくると、非常に困ったことになる。インフラの老朽化が経済の停滞を招き、それが負のスパイラルとなって一挙に国家の凋落を招く可能性があるわけです。
本村教授は、ローマ帝国の後期になるとこの「負のスパイラル」がボディー・ブローのようにして利いてきて、国の体力を奪っていったことを指摘しているのだと考えます。
ローマの水使用量
インフラの例ですが、本村教授が「道路は、まだ地表を走っているのでいいのですが、上下水道、特に上水道の修理は大変です。」と指摘している「上水道」です。この上水道とテルマエ(公衆浴場)の関係を紹介しておきたいと思います。
|
計算すると、ローマ市民一人当たりの水使用量は、現代の横浜市民の3倍ということになります。これだけの大量の水を使った理由の一つがテルマエ(公衆浴場)でした。
|
日本人は温泉が大好きですが、温泉は地下から湧いてくるもので、いわば「自然の恵み」にあずかっているわけです。しかし、テルマエは温泉ではありません。超巨大銭湯であり、「都市型健康ランド」です。それを成り立たせるのに必須なのは、
| ① | 浴場の建設とメンテナンス | ||
| ② | 水道 | ||
| ③ | 燃料(=木) | ||
| ④ | 浴場運営を行う労働者(古代ローマでは奴隷) |
であり、これらを負担する国家財政です。
テルマエの使用料はクァドランス銅貨1枚とありますが、ローマ帝政期における「クァドランス」は「セステルティウス」の16分の1です。トラヤヌス帝の時代のセステルティウスを現在の価値で2ユーロだとすると(前述のアルベルト・アンジェラ著「古代ローマ人の24時間」による)、テルマエの使用料は8分の1ユーロで、15円程度になります。まさに「タダ同然」です。
これら①~④の条件が、ローマ帝国の末期になるとなくなってきます。
|
さらにテルマエの衰退のもう一つの要因は、水の確保が難しくなったことだと、本村教授は言います。
|
No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」で、テルマエの維持のために、ローマ周辺の木材資源が枯渇してしまったという話を紹介しましたが、燃料となる木材の供給だけでなく水の供給も困難になってしまったというが、本村教授の指摘です。さらに、高度な建設技術で作られた水道は高度なメンテナンス技術が必要であり、その技術を維持し続けるためには、それなりの継続的な資金投入が必要だということも言えるでしょう。
インフラの重要性
インフラ(インフラストラクチャ)は、日本語で言うと「下部構造」です。言葉の定義からしても、インフラの上部構造として国が造られます。そういう発想のもとに世界史上で最初の国を作ったのがローマ人だった。ローマ人が「インフラの父」と言われるゆえんです。国力は経済力が第一ですが、インフラ国家における経済力は「インフラが維持され、正常に機能している前提」で発展するということになります。従って、その前提が無くなったとしたら、経済力は弱体化し、国力の凋落を招く。
ローマ市は(最盛期11本の)水道がある前提で、100万都市だった。その水道が機能不全に陥ると、ローマ市は凋落の道をたどる。もちろん水道がなくても人は生活していけるが、そのため疫病が蔓延したり、人口が数分の1に減少したとしたら、ローマ市の繁栄は消し飛んでしまう。これはあくまで想定ですが・・・・・・。
古代ローマ史のおもしろさは、一つの国の誕生から成長、繁栄、凋落、終焉までがワンセットとしてあり、文献資料もそれなりにあって研究されていることです。その歴史は、人間の生き方や人間集団の運営に関する示唆や教訓に満ちています。そこには現代にも通用しそうなものが一杯ある。
インフラに関していうと、No.113「ローマ人のコンクリート(2)光と影」に書いたのは、「交通・輸送網」「上下水道」「エネルギー供給網」ですが、現代はそれに加えて「情報通信網」なども重要であり、さらに「社会福祉システム」などのソフト面のインフラも大変に重要です。はたしてそれらが「持続可能」なのかどうか。我々は考えてみるべきでしょう。
(続く)
No.113 - ローマ人のコンクリート(2)光と影 [歴史]
(前回から続く)
建造物の例
前回に書いたローマン・コンクリートを活用した建造物の例を2点だけあげます。
| パンテオン |
前回に何回か言及したローマのパンテオンはコンクリートによる建築技術の結晶です。この建築は「柱廊玄関」と「円堂」からなり、円堂の高さと直径は44mです。円堂は以下のような構造をしています。
| 直径44mの半球形。上に行くほど壁厚を薄くして重量を軽減している。 | |||
| 高さ30m、厚さ6.2m の円筒型。窓や開口部を設けて重量を軽減している。 | |||
| 幅.7.3m 深さ4.5mの地下構造物。 |
円堂は基礎を含めて全体がローマン・コンクリートの塊であり、このような複雑な構造物はコンクリートの使用ではじめて可能になったものです。パンテオンは古代ローマ時代のものが完全な形で残っている希な建造物です。
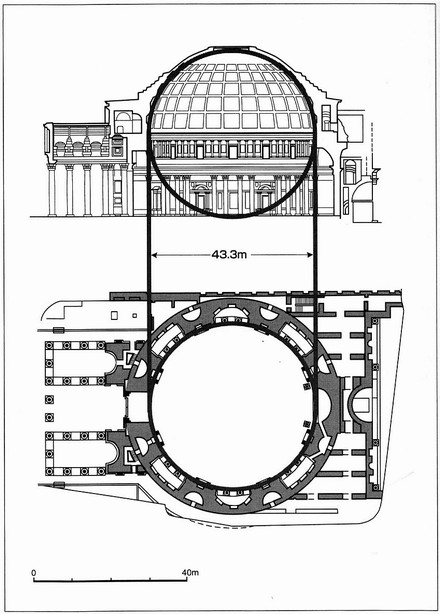
| ||
|
パンテオン断面図と立面図
塩野七生「ローマ人の物語 第9巻 賢帝の世紀」より。直径43.3メートルの球が描きこんである。
| ||

| ||
|
パンテオンの内部
ドームを見上げた写真。右下の明るいところは天井の穴から差し込んだ光である。
| ||
| 公衆浴場 |
建築物の他の例として公衆浴場(テルマエ)をあげておきます。写真と平面図はカラカラ浴場です。現在、遺跡として残っているのは一部ですが、平面図からは当時の威容が想像できます。浴場部分だけで200m×100mもあります。

| ||
|
カラカラ浴場遺跡
(site : www.archeorm.arti.beniculturali.it)
| ||
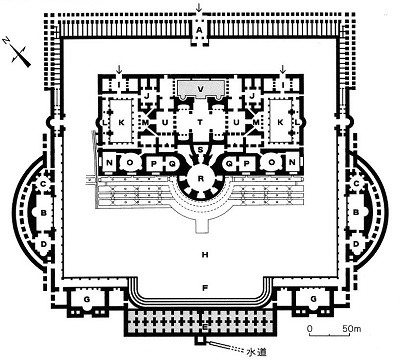
| ||
|
カラカラ浴場平面図
大浴場全体 : 337m×328m、浴場部分 : 220m×114m の規模がある。「ローマ人の物語 第10巻 すべての道はローマに通ず」より
| ||
このような公衆浴場はローマ市内に多数ありました。公衆浴場と水道の配置を、塩野七生「ローマ人の物語 第10巻 すべての道はローマに通ず」から引用しておきます。
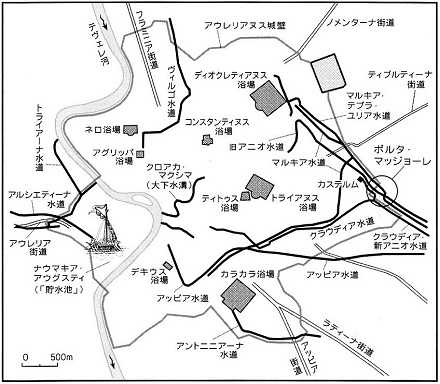
| ||
|
ローマ市内の水道と公衆浴場の配置
「ローマ人の物語 第10巻 すべての道はローマに通ず」より。ローマの水道で最後に建設されたアントニニアーナ水道は、カラカラ浴場に水を引き込むために作られた。
| ||
エネルギー消費型の文明
以上のように、ローマ人が高度なコンクリート技術を駆使し(それ以外の建築技術も使って)社会のインフラを次々と建設していったのは、ローマ文明の「光」の部分です。しかし当然ですが、それに伴って「影」の部分が出てきます。その「影」の部分は、志村史夫著『古代世界の超技術』には指摘されていないし、また塩野さんの本にも書いてありません。
それはまず、セメントを作るのには多量のエネルギー(燃料)が必要ということです。セメントの作り方を振り返ってみると、石灰岩を900℃程度の高温の窯に投入して生石灰を作り(焼成し)、これがセメントの原料になります。この火力を作り出すものは、古代では薪です。つまり、セメントを作るには木が必要ということになります。ちなみに、現代のセメントを焼成する温度は1400℃を超えています。つまり900℃は最低温度であって、高温になればなるほどセメントの質が良くなる。ローマ人のことだから、おそらく900℃を超える高温の炉を使ったのではないでしょうか。それにはますます木が必要ということになる。
大型建造物を何で作ったかで、文明を分類することができると思います。セメントや鉄は、原料(石灰岩や鉄鉱石)から作り出すのにエネルギー(燃料・火力)が必要です。現代ではそのエネルギーを化石燃料(石油、石炭、天然ガス)から得ています。
一方、古代から世界で使われてきた建築材料は石や木です。木や石を切り出し、建築資材として使えるまでに加工し現場で組み上げるのには、技術と労力が必要です。しかしこの過程でエネルギー(燃料)を投入する必要はありません。
建築材料を「省エネルギー型」と「エネルギー消費型」に分類すると、次の表になるでしょう。
| 省エネル ギー型 |
木 | ● | ||
| 石 | ● | ● | ||
| エネルギー 消費型 |
コンクリート | ● | ● | |
| 鉄 | ● | |||
ちなみに、建築材料としての煉瓦は、
| 省エネルギー型 | |||
| エネルギー消費型 |
と言えるでしょう。もちろん、ローマ人が使ったのは焼き煉瓦です。
エネルギー源としての化石燃料を使えない古代において、エネルギー消費型の建築材料(=セメント)を作るには、木を切って薪を作る(ないしは、それから木炭を作る)しかありません。ここで問題になってくるのは「自然破壊」の懸念です。もちろん、樹木は再生可能であり、薪は再生可能エネルギーだといえます。しかし樹木が再生可能なのは、その土地の気候風土(特に降水量)に応じた適切な量を伐採し、植林・施肥などで再生を促進する場合に限られます。果たしてローマ人は「適切な対応」ができたのでしょうか。
エネルギー(燃料)が必要なのは、焼き物(素焼き、陶器、磁器、瓦、タイルなど)を作る窯も同じです。しかしそれらは日用品や、建物の一部に使うものです。ローマのインフラとしての建造物(水道、橋、城壁、大型建築物・・・・・・ )に必要なセメントの量は、その規模が全く違うだろうし、必要な燃料も膨大だと想像します。エネルギー消費型文明の、一つの象徴がコンクリートだと思うのです。
古代ローマにおけるコンクリートと燃料の相互関係について書かれた本を読んだことはないのですが。煉瓦建築のことならあります。エコロジスト、ジョージ・マーシュは19世紀の人ですが、ローマの煉瓦建築の数世紀にわたる変遷を研究しました。ジョン・バーリン著『森と文明』(晶文社 1994)に、そのことが載っています。
| ちなみにジョージ・マーシュ(1801-1882)は米国の外交官でエコロジストです。1861年、リンカーン大統領は彼を初代イタリア大使に任命し、以降、亡くなるまでの21年間をイタリアで過ごしました。 |
|
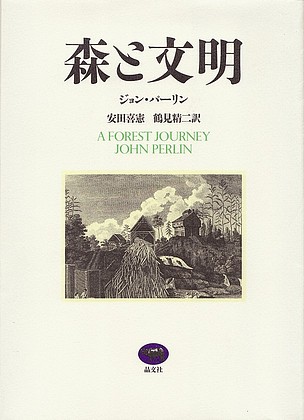
| |||
|
| |||
・・・・・・・・・・・
煉瓦やコンクリートによるインフラの建設と補修には、建築材料を作るために燃料が必要ですが、ローマには「日常の運用のために多量の燃料が必要なインフラ」もありました。それは公衆浴場(テルマエ)です。湯が湧き出す温泉地に行って入浴するのとは違い、都市の中での浴場の維持には水道と燃料が必要です。上に掲げた『ローマ人の物語』から引用した図でも、ローマ市内には公衆浴場が配置され、そこに水道が引かれています。さきほど引用した『森と文明』には、帝政後期の様子が書かれています。
|
これらの森がその百年後に底をついてしまうと、権力者はギルドを創設し、そのギルドに60隻の船を貸与して、浴場の用の燃料の供給をいっさいまかせることにした。まえにカンパニア地方のようなローマの近隣でも木は入手できたが、通常は、主に北アフリカの森にまで手を伸ばさざるをえなくなっていたのである。テヴェレ川やエトルリア地方の海岸からローマに木を運んでいた時代とはまさに隔世の感がある。ローマ人がこれほど遠くまで燃料を求めて旅していたことからもわかるように、ローマの近辺では木が皆無に近くなり、木の供給は全面的に外国にあおがなければならなくなっていた。 |
エネルギー源(木)を外国に頼るのは別に悪いことではありませんが(外国といっても、ローマ帝国の属州です)、普通に考えると輸送コストの増大を招き、薪の価格に跳ね返るでしょう。それは経済の低迷を招きかねません。
「コンクリートによる建設」や「公衆浴場の運営」以外にも「エネルギー消費型」の国家事業はあります。それは金属の精錬です。以前、No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で、ローマ帝国の銀の生産地であったスペインで、で薪の枯渇のために公衆浴場の運営を制限したという話を書きました。それを再度書くと以下の通りです。
まずローマの通貨制度ですが、ローマは銀本位制であり、基軸通貨は「デナリウス銀貨」でした。
|
この銀の採掘、精錬、銀貨の鋳造の一大中心地だったのがイベリア半島(現在のスペイン)でした。それは、16-17世紀のスペイン帝国を、南米ボリビアのポトシ銀山が支えていたのと相似形です。
|
以降、『森と文明』の記述を要約しますと、スペインの銀鉱山の周辺では森林資源が枯渇してきます。そこでローマ帝国は燃料供給のコントロールに乗り出します。浴場経営者などの非採掘業に対し、経営上必要とする量のみの森の木を取得するように命令を出し、木材価格の高騰を防ぐため木の転売を禁止します。
しかし2世紀末に、ついに銀の生産量が減少し始めます。銀鉱石はまだ豊富にあったにもかかわらずです。そしてコンモドゥス帝(180-192)はついに銀貨における銀の含有量を30%も下げてしまったのです。すぐあとのセプティミウス・セウェルス帝(193-211)はさらに20%下げ、銀の含有量は50%を切りました。こうなると事態は急速に進展し、3世紀末には銀の含有量が2%にまで減り、貨幣価値が激減しました。4世紀初頭にはすでに、物々交換や物による支払いが制度化されたと言います。
塩野さんの『ローマ人の物語 第13巻 最後の努力』には、銀貨の銀含有量の変遷が表にしてあります(下表の「銅」と書いてあるところは「銅やその他の金属」の意味のはずです)。
| 銀の含有量 | |||||
| 純銀 | |||||
| 銀 93% 銅 7% | |||||
| 銀 50% 銅 50% | |||||
| 銀 5% 銅 95% |
これでは通貨の信用が激減し、それはとりもなおさず国家の崩壊にもつながりかねない事態です。通貨制度は「ソフトなインフラ」の代表格です。それが金属精錬という「エネルギー消費型」の技術に頼ることによって、危機に瀕したわけです。
最重要インフラとしての「ライフライン」
ここで再度、国の「インフラストラクチャ」を考えてみたいと思います。
「インフラストラクチャ」にもさまざまなものがありますが、「自給自足を脱した文明生活」をするための最重要のインフラは、現代ではライフラインと呼ばれる「人間の生存・生活に必須のインフラ」でしょう。災害時などに言われるライフラインは「電気・ガス・水道」などですが、もうすこし広く一般化すると「交通・輸送網」「水道」「エネルギー供給網」になると考えられます。これらを現代と古代ローマで対比して考えるみると、次の表のようになるでしょう。
| 現代人 | ローマ人 | |
| 道路(橋を含む) 公共交通機関 港湾設備 |
道路(橋を含む) 港湾設備 |
|
| 上水道 下水道 |
上水道 下水道 |
|
| 電気 ガス 石油製品供給網 |
燃料(薪)を製造・供給するしくみ |
|
上の表の「エネルギー供給網」のところ、つまり、ローマ人にとっての「燃料(薪)を製造・供給するしくみ」については、それについて書かれた書物を読んだことがないので、どういうものだったのかは知りません。しかし都市・ローマだけで最盛期には100万人が居住していたと言います。それにはエネルギー(薪、ないしは木炭)の供給システムが必須です。『森と文明』が指摘しているように、ローマ近郊に木が無くなったのなら、イタリア半島の各地、さらには属州から薪を運ぶ必要があります。それが再生可能・持続可能な形だったのか、知りたいところです。
塩野七生『ローマ人の物語 第10巻:すべての道はローマに通ず』には、「交通・輸送網」(道路・街道)と「水道網」の記述があります。まさにこの点において、ローマ人は現代人と「肩を並べている」のですね。しかしもう一つのライフラインである「エネルギー供給網」の記述はありません。このあたりを含めると「インフラストラクチャという視点からローマ文明を考察することの現代的意義」が鮮明になったと思います。
その現代に視点を移して考えてみると、現代文明は化石燃料(石油・石炭・天然ガス)に大きく依存していて、それが文明の基礎となっています。しかし「たまたま」地球に存在した化石燃料は、再生不可能な有限の資源です。あと50年とか100年とか、さまざまな説がありますが、将来、枯渇するのは必定です。しかも地球温暖化という深刻な「影」を引きずっていて、資源の枯渇以前に繁栄の限界に突き当たることも確実です。化石燃料への依存度を下げるということで原子力発電を推進したが、とんでもないリスクを内包してることが日本でも証明されてしまった。原子力発電に利用可能なウランも、再生不可能な有限の資源です。再生不可能などころか、何万年にも渡って危険物質であり続ける「核のゴミ」が出るという、極めてやっかいなしろものです。
人類史を長期の視野で眺めてみると、産業革命以降、現代までの200数十年は「たまたま地球にあった化石燃料を利用できた」ことで成立した「文明の宴」でしょう。その「宴」はいずれ終わります。これにどう対処し、文明を継続させるか。「宴の影の部分」にどう対処するかを含めて、現代の世界で取り組むべき最重要の課題だと思います。
失われたコンクリート技術
話を最初のコンクリートに戻します。コンクリート技術が不思議なのは、古代ローマでは高度に発達したが、その後(19世紀までは)全く失われてしまったことです。ローマ帝国の版図だった地域、およびその周辺で大規模なコンクリート建築が作られた形跡はありません(志村史夫『古代世界の超技術』による)。それは何故なのでしょうか。
シンプルに考えると、国(ローマ帝国)の滅亡で技術が失われたということでしょう。国家がなくなり、富の集中がなくなり、公共工事がなくなれば、技術者も霧散してしまって、技術の継承はできなくなる。
しかし直感的に思うのですが、コンクリート技術は、継承したくても出来なかったという側面があるのではないでしょうか。「エネルギー消費型の建築技術」は続けられなかった。だから、石を切り出し、研磨し、一つずつ積み上げるという「省エネルギー型建築」に戻った。労力はかかるし時間もかかるが、職人の技術と人力さえあれば強固な建築物が作れる。燃料がなくても・・・・・・。
古代ローマのコンクリート技術が消え去ったことは、再生不可能エネルギーにたよる限り、エネルギー消費型文明は長続きしないことの暗示だと思えました。
(続く)
No.112 - ローマ人のコンクリート(1)技術 [歴史]
ローマ人の物語
No.24 - 27 の4回に渡って、塩野七生・著「ローマ人の物語」をとりあげました。
| ローマ人の物語(1)寛容と非寛容 | |||
| ローマ人の物語(2)宗教の破壊 | |||
| ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ | |||
| ローマ人の物語(4)帝政の末路 |
の4つです。
「ローマ人の物語」は全15巻に及ぶ大著であり、1000年以上のローマ史がカバーされています。そこで語られている多方面の事項についての感想を書くことはとてもできません。そこで No.24 - 27 では「宗教」の観点だけの感想を書きました。
今回はその継続で「インフラストラクチャー」をとりあげます。
インフラストラクチャー
『ローマ人の物語』の大きな特長は
| すべての道はローマに通ず |
という巻でしょう。一冊の内容全部が、ローマ人が作り出した「社会インフラ」の記述に当てられています。ちなみに目次は、
第1部 ハードなインフラ
第2部 ソフトなインフラ
|
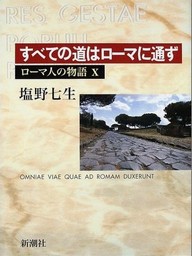
| |||
|
| |||
以降は、この第10巻の感想というより、インフラに関係して特にローマ人が優れていた点と、現代文明との対比について書きます。
ローマ文明に接する驚き
現代人である我々が古代ローマ文明の一端に接して驚くのは、やはり「ハードなインフラ」の部分で、特に各種の大規模建造物です。
ローマ市内に行くと、パンテオンが2000年前のままに建っているし、コロッセオ(円形闘技場)も、崩れているところはあるが、建設当時の威容が十分に想像できます。カラカラ浴場は「遺跡」ですが、浴場部分の建物だけで200m×100mの大きさだったという話を聞くと、率直にすごいと思える。ローマを囲む分厚い城塞も所々に残っています。
ローマ市内を離れると、たとえば水道橋です。これはローマ帝国の版図であった地中海沿岸の各所に遺跡が残っています。クラウディア水道(ローマ郊外)や、南フランスのニームの水道橋(ポン・デュ・ガール:世界遺産)は大変に有名です。『ローマ人の物語』によると、ヨーロッパの中世の人々はポン・デュ・ガールを「悪魔橋」と呼んだそうです。とても人間が作ったものとは思えない、という理由からです。

|
パンテオン
|
(site : www.abcroma.com) |

|

|
コロッセオ
(site : www.abcroma.com, Wikipedia)
(site : www.abcroma.com, Wikipedia)

| ||
|
クラウディア水道
(Wikipedia)
| ||

| ||
|
ポン・デュ・ガール
(Wikipedia)
| ||
これらのインフラをなぜローマ人は建設したのか、ないしは建設できたのか。それは塩野さんが書いているように、
| 社会の公的なインフラを重視するという、ローマ人の世界史上初の考え方や思想 |
でしょう。それに加えて、
| ものすごい「富の集中」 |
が前提にあるはずと思います。国家とローマの元老院階級に富が集中し、富が局在化する仕組みがあった。『ローマ人の物語』の中にありましたが(第9巻 賢帝の世紀)、建造物の中には「有力者の寄付」が多々あったわけです。上に掲げたパンテオンも正面に「マルクス・アグリッパが3度目の執政官の時に建てた」という意味の文字が刻まれています(建て直す前の初代パンテオンのことを言っている。マルクス・アグリッパはアウグストゥスの腹心)。また紀元前の共和政の時代では、「アッピウスがアッピア街道やアッピア水道を建設した」と歴史書にあります。アッピウスも、またアグリッパも執政官にまでなった人です。だから「執政官が発案し、国費で建設した」と思ってしまうのは現代人の感覚なのですね。「アッピウスやアグリッパが発案し、建設費用として私財を出した」というのが正しい。それが「建てた」の意味です。
その「富裕層」の財力の例ですが、ユリウス・カエサルは多額の借金をしていて、その最大の債権者は、マルクス・リキニウス・クラッススでした。『ローマ人の物語』には以下のようにあります。
|
そして、富が集中に加えて忘れてはならないのは、
| インフラ建設を可能にする「高度技術」 |
です。塩野さんの本にも、街道や橋、水道を建設する技術がいろいろと書かれています。そして思うのですが、
| 高度技術の最たるもの、特に大型建造物を作るのに必須だったのがコンクリート |
なのですね。現在のローマ市内に行って最も驚くのはパンテオンです。2000年前によく作れたものだと・・・・・・(正確に言うと、今のパンテオンは1880年ほど前に建て直されたのもの)。これを可能にした秘密が「コンクリート技術」なのです。それはパンテオンだけでなく大型建造物の構築に活用されました。
石で作った大規模建造物は古代エジプトにもあったし、古代ギリシャにもあった。またインカ文明にもあった。煉瓦造りの建築も世界の各地にあった。しかしコンクリートを多用した文明は、現代文明を除いてはローマしかないのです。それはローマ文明の大きな特徴だと言えます。
このコンクリート技術の話は塩野さんの本にあまりないので、志村史夫著『古代世界の超技術』(講談社 ブルーバックス 2013)、および土木学会関西支部編集『コンクリートなんでも小事典』(講談社 ブルーバックス 2008)を参考にしながら、ローマ人の技術を振り返ってみたいと思います。
コンクリートとは
古代ローマで使われたコンクリートを理解するためには、そもそも「コンクリート」とは何かを知る必要があります。現代のコンクリートは、主として次の4成分(および水)の混合物です。
セメント
| 水で練って放置すると固まる性質をもった物質です。現代のセメントは石灰岩と粘土を細かく粉砕し、それを約1450℃の高温の窯で焼いて作ります。その主成分は生石灰(酸化カルシウム)であり、シリカ(二酸化珪素)やアルミナ(酸化アルミニウム)が含まれます。 |
細骨材
| セメントに混ぜて強度を出す物質を「骨材」といいます。人間の骨に相当するという意味でしょう。骨材の中で、おおむね5mm以下ものが「細骨材」で、普通、各種の「砂」や、石を細かく砕いた「砕石」が使われます。 セメントに砂を混ぜたものが「モルタル」で、壁を塗ったり、煉瓦やブロックを積む目的などで使われます。 |
粗骨材
| 大きさがおおむね5mm以上の骨材を「粗骨材」と呼びます。30mm程度より小さい「砂利」や「割石」が使われます。重量比でコンクリートの約半分は粗骨材です。 |
混和材
| コンクリートの強度や耐久性の向上、ないしは硬化速度の向上などために混ぜられる材料全般を「混和材」と呼びます。これには高炉スラグ(鉱滓。ガラス状の粉末)、フライアッシュなどが使われます。フライアッシュは石炭を燃やしたあとの灰で、コンクリートにできる微細なヒビ割れを化学反応で埋める作用があります。コンクリートの強度が大幅に高まります。 |
以上の4種の物質に水を加えてを混ぜてたのがコンクリートです。コンクリートが固まる原理は複雑なようですが、基本的にはセメントが水と反応し(水和反応)、水和物を生成します。そのとき砂や砂利などの骨材を結びつけて固まります。コンクリートは水を吸収して固まるので、基本的に水中でも固まります。
強いコンクリートを作るには「養生期間」が必要です。この期間、コンクリートの表面が乾かないように湿潤状態を保つ必要があります。養生期間は気温が高いほど短い傾向にあり、
| 15℃ 以上 | 3日 | |||
| 5℃~15℃ | 5日 | |||
| 5℃以下 | 8日 |
が目安です。
コンクリートは圧縮力には強いのですが、引っ張り力に弱いのが弱点です。ビルで言うと、自重を支えるにはいいが、地震など横揺れには弱いということでしょう。そこで現代では、コンクリートの中に鉄筋を入れて構造物を作るのが一般的です(=鉄筋コンクリート)。ないしは鉄骨と鉄筋を埋め込む工法(鉄骨・鉄筋コンクリート)を行います。
しかし、鉄は腐食するという大きな弱点があります。高速道路の橋脚が劣化しているというニュースで報道されたりします。それは鉄筋が腐食して周囲のコンクリートが剥がれるという劣化が多いわけです。鉄筋コンクートの耐用年数は各種の条件がからんでくるようですが、おおむね50-60年程度とされています。もちろん耐用年数を伸ばす研究もいろいろあります。
ローマン・コンクリート
ここからは古代ローマのコンクリートです。現代のコンクリートと区別するために「ローマン・コンクリート」と呼びます。ローマン・コンクリートは、現代のコンクリートと比較すると、その成分や固まる原理、速度に違いがあります。
セメント
| まずセメントが現代とは違います。ローマン・コンクリートに使われたセメントは、石灰岩を砕いて900℃程度の窯で焼成して生石灰を作り、それを水と反応させてできた「消石灰」(水酸化カルシウム)が主成分です。消石灰も「水硬性」(=水によって硬化する性質)を持っていて、これは堤防、橋脚、港湾施設の工事などには重要な性質です。 |
細骨材
| 細骨材としては砂(川砂、海砂)も使われましたが、ローマン・コンクリートの特長は凝灰岩を砕いた砂が使われたことです。これはコンクリートの強度と耐久性を増し、固まる速度を早めるという効果があります。 |
粗骨材
| 使われたのは石を割った割石や煉瓦片ですが、現代のコンクリートとは大きさに違いがあります。ローマン・コンクリートでは「手で握ることができる大きさ以上」と定められていて、直径10cmを越えるような大きな石も使われました。 |
混和材
| 混和材として使われたのが「ポッツォラーナ」です。これは、ヴェスビオ火山周辺、およナポリ近郊でとれる火山灰で、大量のシリカ(二酸化珪素)が含まれています。この混和材は消石灰と反応して(=ポゾラン反応)強度が高いコンクリートを作り出します。また水硬性も高めます。「コンクリートなんでも小事典」によると「ローマ人は、水1、石灰2、ポッツォラーナ4の割合で混ぜ合わせ」とあるので、ポッツォラーナは混和材というより、ローマン・コンクリートのセメントは石灰とポッツォラーナの混合物と言った方が良いのかもしれません。 |
ローマン・コンクリートは、現代のものと違って、固まるのに時間が必要です。消石灰とポッツォラーナのポゾラン反応、また消石灰そのものが硬化して炭酸カルシウムになっていく過程は、長い時間をかけて徐々に進みます。現代コンクリートのように水和反応で短期間に強度を出すわけではないのです。その養生期間は、古代ローマの建築書に「きわめて長い年月」とあるようで、相当の時間がかかったようです。少なくとも現代コンクリートの「3日から8日」とは全く違う、年というオーダーの期間でしょう。その意味では、現代社会には向かないコンクリートだと言えます。
以上のローマン・コンクリートの特質を、現代のコンクリートとの比較でまとめておきます。
| ローマン・コンクリート | 現代コンクリート | |
| 石灰岩を焼成し、水と反応させてできる消石灰(水酸化カルシウム)が主成分 | 石灰岩や粘土を焼成してできる生石灰(酸化カルシウム)、シリカ(二酸化珪素)などが主成分 | |
| 凝灰岩の砕砂、海砂、川砂 | 砂、砂利、砕石、人工骨材などで、おおむね5mm以下のもの。 | |
| 割石、石材、煉瓦くずなど。手で握れる大きさ以上。10cmを越える大型骨材も用いられた。 | 直径5mm程度以上の砂利など。30mm程度まで。 | |
| ポッツォラーナ | 高炉スラグ(鉱滓)、フライアッシュなど | |
| 長い期間 | 気温に応じて、3日から8日 |
志村史夫著『古代世界の超技術』
の表を簡略化して作成
の表を簡略化して作成
ローマン・コンクリートとは何か、それをマクロ的に見ると、石灰岩を火山灰(ポッツォラーナ)の力を借りて、思い通りの形に造形する技術だと言えるでしょう。
コンクリートの文明
「コンクリートから人へ」という政治スローガンがあったように、コンクリートは現代文明の象徴(の一つ)になっています。その歴史は比較的新しく、実用的なコンクリートは19世紀以降のものであり、コンクリート建築が多量に作られるのは20世紀になってからです。それ以前は世界中において、建造物を「石、煉瓦、木」で作っていました。ところが古代ローマにだけは(ないしはその先生であった古代ギリシャには)コンクリートの技術があった。ローマ人はその技術を大々的に使って、各種のインフラストラクチャーを次々と作ったわけです。
ローマン・コンクリートに、現代のような鉄筋は埋め込まれていません。それだけ引張り強度が劣るともいえる。しかしローマン・コンクリートは、養生に長い時間がかかるのと引き替えに、徐々に硬化(ポゾラン反応や炭酸カルシウム化)が進むという性質をもっています。年とともに強固になるわけです。このことにより、鉄筋がなくても現代コンクリートと遜色がない強度を実現できたようです。またローマ人は、アーチやドームといった建築構造で部材にかかる力を分散し、強固な建造物を作る技術を持っていました。
さらに鉄筋が入っていない「無筋コンクリート」には大きなメリットがあります。それは耐用年数が長いことで、その証明がパンテオンです。現代の鉄筋コンクリートが2000年もつということはありえません。100年はもたないと言われています。そこが大きな違いです。
「コンクリート文明 = コンクリートによる建造物の構築」は、石で作るのとに比較して極めて大きな利点があります。それはまず「成型が非常に容易」だということです。パンテオンは円筒の外壁の上に半球形のドームが乗っていて、ドームの各部材は曲面の大きさが少しずつ違う複雑な形をしています。こういった建築は石では難しい。コンクリートならではです。
「工事に熟練が不要」というのもインフラ建設にとっては大きなメリットです。技術を持った石工(ないしは煉瓦職人)の数が少なくて済むわけです。石を切り出し、研磨・加工し、精密に積み上げるのは、かなりの技術が必要です。そのため、西洋でも日本でも専門の石工職人集団がいました。西洋のフリーメーソンや、日本では滋賀の穴太衆が有名です。しかしコンクリート工法に高度な技術は不要です。
志村史夫著『古代世界の超技術』には、城壁の作り方として次の図が載っています。
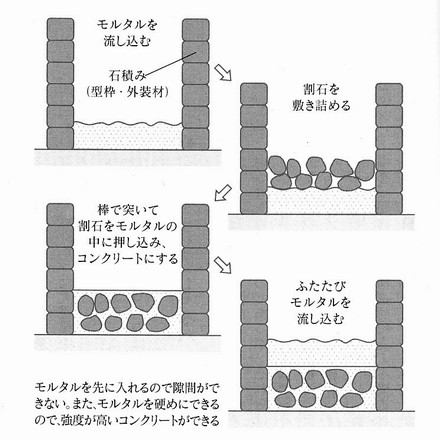
| ||
|
古代ローマ人のコンクリート工法
この工法(ブラケット工法)では、粗骨材(割石)とモルタルを「現場で混合」している。モルタルを先に入れるので、モルタルと外枠の間に隙間はできない。ローマン・コンクリートは現代のコンクリートに比較して粘度が高い(流動性が少ない)ので、このように「順番に敷き詰めていく」工法が可能になる。
志村史夫著『古代世界の超技術』より
| ||
この工法をとると、外枠の石積み(ないしは煉瓦積み)のためにはそれなりの技術者が必要ですが、コンクリート工事そのものは非熟練者でも可能です。ローマン・コンクリートの正しい調合を指示する技術者、そのノウハウを持った技術者さえいれば、あとは非熟練者を動員して工事ができる。と同時に、外枠の石組みさえ精密に作れば、あとはコンクリートの「成形が容易」という性質をフルに活用できる。ローマ人が大規模インフラ(の建造物)を次々に建設できたのも、コンクリート技術があればこそなのです。現在のローマ市内にある遺跡、コロッセオ、フォロ・ロマーノ、カラカラ浴場などは全部、この工法のコンクリートが使われています。
(次回に続く)
| 補記1:ポッツォラーナ |
2016年7月24日(日)の18:00から放映されたTBSの『世界遺産』で、ローマン・コンクリートがテーマの一つになっていました。ローマン・コンクリートがテレビで取り上げられるとはめずらしいと思います。以下のような内容でした。
| ◆ | ローマのコロッセオの 80% はローマン・コンクリートでできている。 | ||
| ◆ | ローマン・コンクリートの強度の秘密はポッツォラーナ(ナポリ近郊でとれる火山灰)にある。 | ||
| ◆ | ナポリ近郊のバイアの温泉保養地跡には、ローマン・コンクリートで作られた温泉のドームが2000年以上を経て残っている。温泉は硫黄分を含んでいるが、ローマン・コンクリートは硫黄分にも強い。 |
番組では、ローマの遺跡修復士の方が出演して、
| ・ | 消石灰と砂と水 | ||
| ・ | 消石灰と砂と水とポッツォラーナ |
という2つのサンプルを用意し、それらを混合して5時間経過した後を比較していました。明らかにポッツォラーナを入れた方が "堅い" わけです。砂(=細骨材)として凝灰岩を砕いたものが使われたことには触れていませんでしたが、そこまで言うと専門的になりすぎるのでしょう。
とにかく、ローマ人の建築技術の秘密(の一つ)はコンクリート製造においてポッツォラーナという混和材を発見したことである・・・・・・。このことがよく理解できました。
| 補記2:コンクリートが巨大帝国を生んだ |
NHK BS プレミアムで、古代ローマ帝国のコンクリート技術を解説した番組、
世界遺産 時を刻む
土木 ~ コンクリートが巨大帝国を生んだ ~
NHK BSP 2022年3月2日 18:00~19:00
土木 ~ コンクリートが巨大帝国を生んだ ~
NHK BSP 2022年3月2日 18:00~19:00
が放映されました。この内容を No.333「コンクリートが巨大帝国を生んだ」に紹介しました。
(2022.3.19)
No.109 - アンダーソンヴィル捕虜収容所 [歴史]
No.104「リンカーンと奴隷解放宣言」の続きです。No.104では、朝日新聞の奴隷解放宣言についての解説記事(2013.5.13)の見出しである、
という表現について、
という主旨のことを書きました。
政治家はリーダーシップで国を導いていくものですが、同時にその国・その時代の大衆の意識や意見に影響されます。世論と極端に違う意見を、政治家は(特に国政の中枢に行こうとする政治家は)とれない。アメリカは民主主義国家なのです。
しかし見出しはともかく、朝日新聞の解説記事では奴隷解放とその背景となった南北戦争について、3つの重要な指摘をしていました。
の3点です。今回はこの3つの指摘について考えてみたいを思います。3つのうち、「①リンカーンが人種差別の考え方をもっていた」ことは、No.104「リンカーンと奴隷解放宣言」の「補記」で引用したイリノイ州上院議員選挙でのディベートの記録で明らかです。リンカーンはそこで、
という主旨の演説をしています。もっとも、こういった選挙演説は「当選すること」が目的なので、その場の聴衆の大多数の考えに沿った(従って聴衆の支持を得やすい)内容になりがちなことが想像できます。リンカーンの人種差別の「程度」をこの演説内容だけから判断するのは危険だと思いますが、程度はさておき「リンカーンが人種差別の考え方をもっていた」のは事実で、それは当時としては「自然な」考え方です。
以降は、朝日新聞が指摘していた②と③について、ちょっと掘り下げてみたいと思います。
奴隷解放の結果、人種差別が始まった
「②奴隷解放で形の上では平等になっため、逆に黒人に対する圧迫が強くなった」という解説は、全くその通りです。圧迫が強くなったというより、奴隷解放の結果として人種差別が始まったというのが正確でしょう。今までは「人間と奴隷」だったのに「全部が人間」になってしまった。そうなると「以前は奴隷だった人間=黒人を差別・圧迫しないと社会が成り立たない」と、「以前からの人間=白人」が考えるのは極めて自然です。
南北戦争時の南部の人口は900万人、そのうち400万人が奴隷だと言います。人口の45%が奴隷というのは異様な多さです。ちょっと比較してみますと、900万人という南部の人口は、紀元前1世紀頃の古代ローマの人口(イタリア半島の人口)とほぼ同じです。この時点の奴隷の比率は30%程度です。古代ローマは「労働は奴隷が行う」という奴隷制社会で、農場における労働だけでなく社会の隅々にまで奴隷がいた。それでもこの程度なのです。
奴隷制廃止の結果、このままでは州議会議員の過半数が黒人になる時が来るかもしれない、という危機感を白人が抱くのは当然でしょう。それは阻止しなれけばならない。その具体策として歴史の本にあるのは、たとえば「投票権の前提となる税(人頭税)」を作ることです。つまり投票権を税の支払い能力で制限するわけです。また「識字能力がないと投票できない」という法律を作った州もありました。かつて奴隷だった当時の黒人に字が読めない人が多いことに「つけ込む」わけです。
学校、公共施設、公共交通機関を「白人用」と「黒人用」に分離するのもよくある手でした。たとえ同じ学校に入学を認めたとしても、同じ教室で授業を受けてはいけないという法律を作った州もあった。そうしておいて黒人用の学校、教室、公共施設、公共交通機関の「供給量」を少なくする。実質的には黒人差別ということになります。重要なのは学校の差別ですね。教育の機会均等を奪うことで、社会の中心的な位置に黒人が進出するのを阻止できます。
公的な差別制度ではない「差別意識」も生まれたでしょう。たとえば、白人の貧困層の人たちにとってみると、今までは自分たちが社会の最下層だったのが、新たに自分たちより下の層が出現したわけです。これは差別意識の源泉になると思います。「自分が他人にやられた嫌なことを、ほかの他人にはしない」という人と、「自分がやられた嫌なことを、他人にやり返す」という人と、どちらが多いかというと、人間社会では一般には後者でしょう。また白人貧困層の人たちからすると「差別しなければ職を奪われかねない」とも見えてしまう。
暴力事件も起こるでしょうね。奴隷制度の時代、もし白人が自分とは無関係の黒人奴隷を殴ったとすると、それは奴隷の所有者(たとえばプランテーションのオーナー)の「私有財産を毀損する」ことになります。そんなことは、おいそれとはできません。
しかし奴隷解放のあとに白人が「以前は奴隷だった黒人=今は人間」を殴ったとすると、それは人間同士の暴力事件であり、法治国家では刑法の範疇になります。刑法の範疇になると、白人警官は(殴った)白人と(殴られた)黒人を公平には扱わないでしょう。白人は黒人を「安心して」殴れるわけです。これは単なるたとえ話ではありません。黒人をリンチにかけて、場合によっては殺害までするような白人至上主義団体ができたのは、奴隷解放の以降です。
奴隷解放から1世紀を経た1964年に公民権法が成立し、差別制度は撤廃されました。そしてその45年後にオバマ大統領が登場しました。かつての奴隷の子孫たち=アフリカ系アメリカ人を法的・制度的に差別することは、今はありません。しかし実態としての黒人=アフリカ系アメリカ人差別は厳然としてあり、今でも「奴隷制度の残滓」を引きずっているのではと思えることがあります。
あくまで歴史的な経緯によってですが、貧困、犯罪歴、低学歴、無職といった人たちは、黒人=アフリカ系アメリカ人にその比率が高い傾向にあります。そういった人たちを救おうとする政府の政策は、白人のある層からみると「黒人を救う政策」のように無意識に見えてしまうのではないでしょうか。
オバマ大統領は「オバマ・ケア」という政策で、アメリカの医療保険制度を改革しようとしています。無保険者を無くすというのが重要な柱です。しかしこれには反対も強い。2013年には予算の不成立と2週間の政府閉鎖まで引き起こしました。反対の理由は「自助努力を尊ぶ」「公的援助を嫌う」「自分は自分で守る」「小さな政府を志向する」といった、建国以来のアメリカ人の気風、精神だと説明されます。「オバマ・ケアは社会主義だ」という反発です。確かにその通りなのでしょうが、隠れた反対理由は「オバマ・ケア」が「黒人救済策」に見えてしまうことではないのでしょうか。
別の視点ですが、アメリカは日本などからみると異様にも見える銃社会です。銃の乱射事件も「定期的に」あるし、家族が同居の家族を銃で(誤って)死なせる悲劇がたびたび起こっています。かつて、ロサンジェルスのアメリカ人の自宅に招かれたことがあります。奥さんはオランダ人ですが、彼女は「結婚してロスに住んでから、すでにロスの学校内で数人が銃で死んだ。信じられない」と言っていました。アメリカの銃社会を異様と思うのは日本人だけではないのです。
何度となく提出された銃規制法案はその都度頓挫しています。銃を持つ権利、武器をもつ権利は憲法で保証されているという理由です。そして「自分の身は自分で守るのがアメリカの建国以来の伝統だ」という風に説明されるわけです。では、なぜそういう伝統ができたのでしょうか。自分の身を何から守るのでしょうか。家に押し入る強盗か、街にたむろする「ならず者」か、それともネイティヴ・アメリカンの襲撃から自分の身を守るのか。
もちろんそれもあるでしょうが、かつて「一番切実だったのは黒人奴隷の反乱から身を守ること」ではと想像します。南部の人口の45%が奴隷だったと書きましたが、歴史上まれにみる異様な数の多さです。こうなると、奴隷の反乱は白人にとっての最大の恐怖のはずです。各人が武装しないとやっていけません。実際に反乱が起きるかどうかより、個人レベルでの非武装状態は心理的にもたないでしょう。
制度は撤廃されても、意識とか考え方は「伝統」になって残ってしまい、後世に影響を与える・・・・・・。そういう風にみえます。
近代戦の幕開けとしての「アメリカ内戦」
南北戦争の米国での言い方は「The Civil War」で、直訳すると「内戦」です。また世界的に標準の呼び方は「American Civil War」で、「アメリカ内戦」です。以降、南北戦争を「アメリカ内戦(南北戦争)」ないしは「アメリカ内戦」と表記します。
朝日新聞が③で指摘するように、アメリカ内戦は20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった戦争です。この「事象」のなかから、
の3つについて以下に書きます。
戦略攻撃:海への進軍
1864年5月から9月にかけての「アトランタ作戦」で、連邦軍(北軍)は、南部連合軍(南軍)が守るジョージア州・アトランタを陥落させ、市のほぼ全域を炎上させます(映画「風と共に去りぬ」のシーン)。そして北軍は11月からジョージア州の大西洋岸の町・サバンナまでの約400キロを進軍し、殲滅戦を展開しました。進軍は幅約50-100キロに渡り、途中の家屋、農家、農園、工場、市街地などに火を放ち、また鉄道や橋が徹底的に破壊されました。そしてその年の12月末までに大西洋岸に到達したのです。これがいわゆる「海への進軍 - The March to the Sea」です。南軍の抵抗はほとんど無かったと言います。
地図をみるとアトランタはジョージア州の北西部にあり、サバンナは南東方向の海岸の町です。まさに、ジョージア州の中央部が焦土と化したわけです。当時の様子を描いた絵をみると、北軍の兵士はツルハシで一所懸命、鉄道のレールを剥がしています。破壊された鉄道の写真も残っています。
この「海への進軍」は、軍隊と軍隊が戦って死傷者が多い方が負け、というような戦争形態では全くないのですね。攻撃の相手は軍隊ではありません。敵の都市機能を破壊し、農場を壊滅させ、社会インフラ(鉄道・道路)を破壊・寸断するという作戦です。作戦の目的は、
の2点です。これは20世紀の戦争で言う「戦略攻撃」です。要するに「敵の後背地に対する破壊作戦」や「兵站線の寸断」です。
20世紀の戦争、特に飛行機が発達した第2次世界大戦では戦略攻撃が頻繁に行われました。もちろんそれは「戦略爆撃機」で敵の領土の上から爆弾を落とし、工場や市街地を壊滅させる作戦です。もしくは全く無差別に大量の爆弾を落とす作戦です(いわゆる絨毯爆撃)。No.34「大坂夏の陣図屏風」で書いた「有名な」作戦では、
がありました。
一方、戦略爆撃機がないアメリカ内戦(南北戦争)の時代では、軍隊が地上を進軍してあたり一面に火を放ち、鉄道のレールを兵士がツルハシで引き剥がすわけです。しかし戦略の考え方は同じと言えます。北軍はこいういった「戦略攻撃」を、ジョージア州での「海への進軍」だけでなくサウス・カロライナ州などでも行いました。
第2次世界大戦を振り返ると、敵側の兵站線(補給路)を寸断することは戦略の核心でした。ドイツ軍は北大西洋で英国の輸送船を潜水艦で次々と沈めたし(第1次世界大戦でも同様)、太平洋戦争でアメリカ軍は日本軍の輸送船を徹底的に狙ったわけです(日本軍の暗号を全部解読していたので、輸送船の発見は容易だったようです)。補給を断たれて南の島に残された日本の兵隊は悲惨です。太平洋戦争における日本兵の死者の半数以上は餓死だと言います。
アメリカ内戦は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」と言えるでしょう。アメリカにとっての最初の「近代戦」は、日本の明治維新以前に起こった、自国での内戦だったわけです。その学習効果(成功も失敗も含めて)は大きかったと思います。
大量の戦死者
アメリカ内戦(南北戦争)の死者は62万人で、これはアメリカの戦死者の最高記録です。第2次世界大戦でのアメリカ軍の死者はヨーロッパ戦線と太平洋戦線を合わせて40万人程度ですが、その1.5倍も多い。
しかし「第2次世界大戦の1.5倍の死者が、アメリカ内戦(南北戦争)で出た」とするのは誤った見方です。そもそも国の総人口が違うからです。アメリカ内戦(南北戦争)が起こった1860年代のアメリカの人口は3000万程度です。一方、第2次世界大戦の1940年代は1億4000万人程度です。人口は5倍近く違います。つまり、
というのが、正しいモノの見方でしょう。アメリカ内戦で国民の2%が戦争で死んだということは、男性人口だけからすると4%が死んだわけです。兵役適齢人口を仮に男性の半分とすると、その8%が死んだという計算になります。当時としては非常に多い数です。
その後の歴史をみると、20世紀の戦争ではアメリカ内戦(南北戦争)を上回る死者が出たケースが多数あります。第2次世界大戦の日本の死者は、非戦闘員を含んで300万人と言われています。当時の日本の人口は8000万人程度なので「死亡率」はアメリカ内戦(南北戦争)の倍です。第2次世界大戦では、ソ連はもっと多くの死者を出しているし、その前の第1次世界大戦でもヨーロッパ各国は多数の死者を出している。第1次世界大戦のフランスの死者は約170万人で、この数は第2次世界大戦の3倍です。要するに20世紀の戦争は「総力戦」なのですね。この点でもまさにアメリカ内戦(南北戦争)は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」と言えるでしょう。
アンダーソンヴィル捕虜収容所
その死者という点ですが、アメリカ内戦(南北戦争)は、
という、これもまた20世紀の戦争を予告するような事態が起きました。
「海への進軍」の舞台となったジョージア州に、南軍の最大の捕虜収容所、アンダーソンヴィル捕虜収容所(Andersonville Prison)がありました(「海への進軍」の地図参照)。この収容所に延べ45,000人の北軍兵士が収容され、そのうち13,000人が死亡しました。死亡の原因は栄養失調(餓死)や病気です。
残された写真を見ると、捕虜は敷地の中の粗末なテントに「野宿」の形で収容されていたことがわかります。10,000人を収容する「施設」のはずが、最大で33,000人の捕虜を詰め込んだようです。それでなくても南軍は敗勢であり、食料や医薬品の補給は困難なはずだから、収容人数の3倍もの捕虜を詰め込んで野宿させると何が起こるかは明白でしょう。1864年8月(真夏)には、1ヶ月で3,000人が亡くなったと言います(アメリカ政府内務省・国立公園局のサイトの解説による)。毎日100人を埋葬する日が続くという悲惨さです。
アメリカ内戦(南北戦争)の終結後、収容所の所長は捕虜虐待で逮捕され、裁判にかけられて死刑判決をうけ、執行されました。アメリカ内戦後の死刑判決はこの所長だけです。
補足しますと、南軍に捕虜虐待の意図があったかどうかは別として、これだけの捕虜の大量死が起こったのだから「外形的には捕虜虐待」でしょう。さらに、このような事件は戦勝側が敗戦側の捕虜虐待を大いに宣伝し、それが歴史として残ってしまうのが常なので、北軍側の捕虜虐待が無かったとは言えないと思います
この「アンダーソンヴィル事件」も、20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こったと言えます。つまり、
の2点です。
ちなみに、戦勝国が敗戦国の責任者を裁判にかけるというのは20世紀の戦争の特徴というより、アメリカの戦争の特徴ですね。ヨーロッパ諸国間の戦争で、そんなことはなかったはずです。アメリカ内戦(南北戦争)が終結(1865)した5年後にヨーロッパで普仏戦争(プロイセン・フランスの戦争。1870-71)が勃発しますが、勝ったプロイセン(ドイツ)はフランスから賠償金と領土(アルザス・ロレーヌ地方)を巻き上げただけでした。もっとも北軍にしてみれば、アメリカ内戦(南北戦争)はあくまで「アメリカ国内における反乱勢力との戦い」なので、人間を虐待するのは刑法犯罪であり、従って裁判にかけるという論理でしょう。アメリカはこの論理を外国との戦争に拡大したと考えられます。
アメリカ内戦と太平洋戦争
アメリカ内戦(南北戦争)は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」としましたが、その「20世紀の戦争」は日米間の太平洋戦争についても言えます。それどころか、アメリカの視点で見ると、太平洋戦争の経緯はアメリカ内戦(南北戦争)と非常によく似ているのです。対比してみると以下のようです。
まさに、太平洋戦争で典型的にみられた事象がアメリカ内戦(南北戦争)で予告的に起こっていたと見えます。また一歩進んで、アメリカ内戦(南北戦争)における北軍=連邦政府の行動パターンを、80年後の太平洋戦争とその戦後処理でアメリカ軍=アメリカ政府が繰り返したとも感じます。
アメリカ内戦(南北戦争)は、国家分裂という建国以来の最大の危機にアメリカが陥った時期です。この危機をリンカーン大統領の連邦(Union)政府と連邦軍(北軍)は乗り切ったわけです。この「国家最大の危機が到来したが、それを克服した」という成功物語が、アメリカの歴史意識の根幹にあるのでしょう。
アメリカ内戦での連邦政府(北軍)の個々の成功体験は、20世紀になってアメリカ政府(アメリカ軍)がより精緻な形で反復し、また、アメリカ内戦で連邦政府(北軍)が正当化した軍事行動や政策は、それが正当だということを証明するために、20世紀になっても繰り返されたのではないでしょうか。
国家の行動は歴史に影響されるということだと思います。国家のアイデンティティとなっている「近代史上の成功物語」は、現在の国家の正当性を暗黙に保証するものである以上、繰り返さざるを得ないのでしょう。それは現代における組織や会社の成功体験とも似ていると感じます。
しかし、過去の成功物語を繰り返すことは、環境の変化のために失敗につながることもあるし、むしろその方が多い・・・・・・。このあたりが重要だとも思います。
| 人種差別主義者だった? リンカーン |
という表現について、
| ◆ | 「人種差別主義者」というような言葉を新聞記事の見出しにするのは良くない。誤解を招く。 | ||
| ◆ | リンカーンが生きた時代のアメリカでは「人種差別」が普通のことであり、現代の価値観で過去を判断してはいけない。 |
という主旨のことを書きました。
政治家はリーダーシップで国を導いていくものですが、同時にその国・その時代の大衆の意識や意見に影響されます。世論と極端に違う意見を、政治家は(特に国政の中枢に行こうとする政治家は)とれない。アメリカは民主主義国家なのです。
しかし見出しはともかく、朝日新聞の解説記事では奴隷解放とその背景となった南北戦争について、3つの重要な指摘をしていました。
| ① | リンカーンは人種差別の考え方をもっていた。 | ||
| ② | 奴隷解放で形の上では平等になっため、逆に黒人に対する圧迫が強くなった。 | ||
| ③ | 南北戦争の死者は、第2次世界大戦での米軍の死者を上回る62万人であり、都市の徹底破壊や殲滅戦が行われるなど近代戦の幕開けとなった。 |
の3点です。今回はこの3つの指摘について考えてみたいを思います。3つのうち、「①リンカーンが人種差別の考え方をもっていた」ことは、No.104「リンカーンと奴隷解放宣言」の「補記」で引用したイリノイ州上院議員選挙でのディベートの記録で明らかです。リンカーンはそこで、
| 「 | 国民の権利は白人と黒人で違って当然であり、白人を優位に位置づけるべき」 |
という主旨の演説をしています。もっとも、こういった選挙演説は「当選すること」が目的なので、その場の聴衆の大多数の考えに沿った(従って聴衆の支持を得やすい)内容になりがちなことが想像できます。リンカーンの人種差別の「程度」をこの演説内容だけから判断するのは危険だと思いますが、程度はさておき「リンカーンが人種差別の考え方をもっていた」のは事実で、それは当時としては「自然な」考え方です。
以降は、朝日新聞が指摘していた②と③について、ちょっと掘り下げてみたいと思います。
奴隷解放の結果、人種差別が始まった
「②奴隷解放で形の上では平等になっため、逆に黒人に対する圧迫が強くなった」という解説は、全くその通りです。圧迫が強くなったというより、奴隷解放の結果として人種差別が始まったというのが正確でしょう。今までは「人間と奴隷」だったのに「全部が人間」になってしまった。そうなると「以前は奴隷だった人間=黒人を差別・圧迫しないと社会が成り立たない」と、「以前からの人間=白人」が考えるのは極めて自然です。
南北戦争時の南部の人口は900万人、そのうち400万人が奴隷だと言います。人口の45%が奴隷というのは異様な多さです。ちょっと比較してみますと、900万人という南部の人口は、紀元前1世紀頃の古代ローマの人口(イタリア半島の人口)とほぼ同じです。この時点の奴隷の比率は30%程度です。古代ローマは「労働は奴隷が行う」という奴隷制社会で、農場における労働だけでなく社会の隅々にまで奴隷がいた。それでもこの程度なのです。
| 古代ローマの奴隷の数ですが、塩野七生著「ローマ人の物語 3 勝者の混迷」には、紀元前1世紀のローマ国家において、イタリア半島に住む、60歳以上の老人に女子供もふくんだ自由民の総数は600万人~700万人、それに対し奴隷は200万人から300万人、とあります。自由民を650万人、奴隷を250万人とすると、人口は900万人であり、奴隷の全人口に対する比率は30%程度ということになります。 |
奴隷制廃止の結果、このままでは州議会議員の過半数が黒人になる時が来るかもしれない、という危機感を白人が抱くのは当然でしょう。それは阻止しなれけばならない。その具体策として歴史の本にあるのは、たとえば「投票権の前提となる税(人頭税)」を作ることです。つまり投票権を税の支払い能力で制限するわけです。また「識字能力がないと投票できない」という法律を作った州もありました。かつて奴隷だった当時の黒人に字が読めない人が多いことに「つけ込む」わけです。
学校、公共施設、公共交通機関を「白人用」と「黒人用」に分離するのもよくある手でした。たとえ同じ学校に入学を認めたとしても、同じ教室で授業を受けてはいけないという法律を作った州もあった。そうしておいて黒人用の学校、教室、公共施設、公共交通機関の「供給量」を少なくする。実質的には黒人差別ということになります。重要なのは学校の差別ですね。教育の機会均等を奪うことで、社会の中心的な位置に黒人が進出するのを阻止できます。
| 余談ですが「教育の機会均等を奪うことで、奪われた人たちの社会進出を阻止する」というのは、現在でも特定の国の特定の団体が声高に主張しています。つまり「女子教育の廃止」です。 |
公的な差別制度ではない「差別意識」も生まれたでしょう。たとえば、白人の貧困層の人たちにとってみると、今までは自分たちが社会の最下層だったのが、新たに自分たちより下の層が出現したわけです。これは差別意識の源泉になると思います。「自分が他人にやられた嫌なことを、ほかの他人にはしない」という人と、「自分がやられた嫌なことを、他人にやり返す」という人と、どちらが多いかというと、人間社会では一般には後者でしょう。また白人貧困層の人たちからすると「差別しなければ職を奪われかねない」とも見えてしまう。
暴力事件も起こるでしょうね。奴隷制度の時代、もし白人が自分とは無関係の黒人奴隷を殴ったとすると、それは奴隷の所有者(たとえばプランテーションのオーナー)の「私有財産を毀損する」ことになります。そんなことは、おいそれとはできません。
しかし奴隷解放のあとに白人が「以前は奴隷だった黒人=今は人間」を殴ったとすると、それは人間同士の暴力事件であり、法治国家では刑法の範疇になります。刑法の範疇になると、白人警官は(殴った)白人と(殴られた)黒人を公平には扱わないでしょう。白人は黒人を「安心して」殴れるわけです。これは単なるたとえ話ではありません。黒人をリンチにかけて、場合によっては殺害までするような白人至上主義団体ができたのは、奴隷解放の以降です。
奴隷解放から1世紀を経た1964年に公民権法が成立し、差別制度は撤廃されました。そしてその45年後にオバマ大統領が登場しました。かつての奴隷の子孫たち=アフリカ系アメリカ人を法的・制度的に差別することは、今はありません。しかし実態としての黒人=アフリカ系アメリカ人差別は厳然としてあり、今でも「奴隷制度の残滓」を引きずっているのではと思えることがあります。
あくまで歴史的な経緯によってですが、貧困、犯罪歴、低学歴、無職といった人たちは、黒人=アフリカ系アメリカ人にその比率が高い傾向にあります。そういった人たちを救おうとする政府の政策は、白人のある層からみると「黒人を救う政策」のように無意識に見えてしまうのではないでしょうか。
オバマ大統領は「オバマ・ケア」という政策で、アメリカの医療保険制度を改革しようとしています。無保険者を無くすというのが重要な柱です。しかしこれには反対も強い。2013年には予算の不成立と2週間の政府閉鎖まで引き起こしました。反対の理由は「自助努力を尊ぶ」「公的援助を嫌う」「自分は自分で守る」「小さな政府を志向する」といった、建国以来のアメリカ人の気風、精神だと説明されます。「オバマ・ケアは社会主義だ」という反発です。確かにその通りなのでしょうが、隠れた反対理由は「オバマ・ケア」が「黒人救済策」に見えてしまうことではないのでしょうか。
別の視点ですが、アメリカは日本などからみると異様にも見える銃社会です。銃の乱射事件も「定期的に」あるし、家族が同居の家族を銃で(誤って)死なせる悲劇がたびたび起こっています。かつて、ロサンジェルスのアメリカ人の自宅に招かれたことがあります。奥さんはオランダ人ですが、彼女は「結婚してロスに住んでから、すでにロスの学校内で数人が銃で死んだ。信じられない」と言っていました。アメリカの銃社会を異様と思うのは日本人だけではないのです。
何度となく提出された銃規制法案はその都度頓挫しています。銃を持つ権利、武器をもつ権利は憲法で保証されているという理由です。そして「自分の身は自分で守るのがアメリカの建国以来の伝統だ」という風に説明されるわけです。では、なぜそういう伝統ができたのでしょうか。自分の身を何から守るのでしょうか。家に押し入る強盗か、街にたむろする「ならず者」か、それともネイティヴ・アメリカンの襲撃から自分の身を守るのか。
もちろんそれもあるでしょうが、かつて「一番切実だったのは黒人奴隷の反乱から身を守ること」ではと想像します。南部の人口の45%が奴隷だったと書きましたが、歴史上まれにみる異様な数の多さです。こうなると、奴隷の反乱は白人にとっての最大の恐怖のはずです。各人が武装しないとやっていけません。実際に反乱が起きるかどうかより、個人レベルでの非武装状態は心理的にもたないでしょう。
制度は撤廃されても、意識とか考え方は「伝統」になって残ってしまい、後世に影響を与える・・・・・・。そういう風にみえます。
近代戦の幕開けとしての「アメリカ内戦」
南北戦争の米国での言い方は「The Civil War」で、直訳すると「内戦」です。また世界的に標準の呼び方は「American Civil War」で、「アメリカ内戦」です。以降、南北戦争を「アメリカ内戦(南北戦争)」ないしは「アメリカ内戦」と表記します。
朝日新聞が③で指摘するように、アメリカ内戦は20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった戦争です。この「事象」のなかから、
| ◆ | 戦略攻撃 | ||
| ◆ | 大量の戦死者 | ||
| ◆ | 捕虜の大量死 |
の3つについて以下に書きます。
戦略攻撃:海への進軍
1864年5月から9月にかけての「アトランタ作戦」で、連邦軍(北軍)は、南部連合軍(南軍)が守るジョージア州・アトランタを陥落させ、市のほぼ全域を炎上させます(映画「風と共に去りぬ」のシーン)。そして北軍は11月からジョージア州の大西洋岸の町・サバンナまでの約400キロを進軍し、殲滅戦を展開しました。進軍は幅約50-100キロに渡り、途中の家屋、農家、農園、工場、市街地などに火を放ち、また鉄道や橋が徹底的に破壊されました。そしてその年の12月末までに大西洋岸に到達したのです。これがいわゆる「海への進軍 - The March to the Sea」です。南軍の抵抗はほとんど無かったと言います。
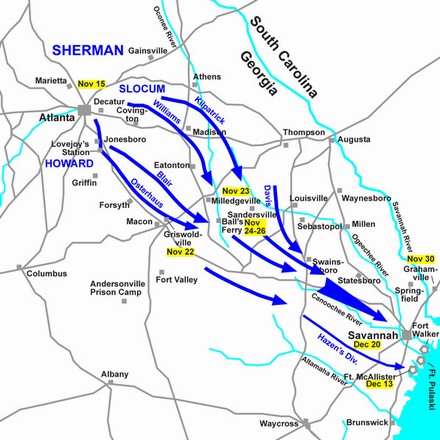
| ||
|
「海への進軍」のルートを示した地図。左上のアトランタから右下のサバンナに至る。このルートの南西方向に Andersonville Prison の位置が示されている。
( site : georgiainfo.galileo.usg.edu )
| ||

| ||
|
「海への進軍」で、建物に火を放ち、鉄道を破壊しながら進軍する様子を描いた絵。
( site : georgiainfo.galileo.usg.edu )
| ||
地図をみるとアトランタはジョージア州の北西部にあり、サバンナは南東方向の海岸の町です。まさに、ジョージア州の中央部が焦土と化したわけです。当時の様子を描いた絵をみると、北軍の兵士はツルハシで一所懸命、鉄道のレールを剥がしています。破壊された鉄道の写真も残っています。

|

|
北軍の兵士が「金テコ」と「ツルハシ」で鉄道を壊している様子が描かれている。右は破壊された鉄道の写真。
( site : georgiainfo.galileo.usg.edu )
この「海への進軍」は、軍隊と軍隊が戦って死傷者が多い方が負け、というような戦争形態では全くないのですね。攻撃の相手は軍隊ではありません。敵の都市機能を破壊し、農場を壊滅させ、社会インフラ(鉄道・道路)を破壊・寸断するという作戦です。作戦の目的は、
| ◆ | 南軍の補給路(兵站線)を断ち、後背地を焦土と化すことによって補給物資をなくし、そのことによって戦争を有利に進める。 | ||
| ◆ | 南軍の兵士と南部の一般市民にショックと恐怖と諦めを与え、心理的に追い詰めることによって戦争を有利に進める。 |
の2点です。これは20世紀の戦争で言う「戦略攻撃」です。要するに「敵の後背地に対する破壊作戦」や「兵站線の寸断」です。
20世紀の戦争、特に飛行機が発達した第2次世界大戦では戦略攻撃が頻繁に行われました。もちろんそれは「戦略爆撃機」で敵の領土の上から爆弾を落とし、工場や市街地を壊滅させる作戦です。もしくは全く無差別に大量の爆弾を落とす作戦です(いわゆる絨毯爆撃)。No.34「大坂夏の陣図屏風」で書いた「有名な」作戦では、
| ドイツ軍 | |||||
| 日本軍 | |||||
| 英米連合軍 | |||||
| アメリカ軍(=東京大空襲) |
がありました。
一方、戦略爆撃機がないアメリカ内戦(南北戦争)の時代では、軍隊が地上を進軍してあたり一面に火を放ち、鉄道のレールを兵士がツルハシで引き剥がすわけです。しかし戦略の考え方は同じと言えます。北軍はこいういった「戦略攻撃」を、ジョージア州での「海への進軍」だけでなくサウス・カロライナ州などでも行いました。
第2次世界大戦を振り返ると、敵側の兵站線(補給路)を寸断することは戦略の核心でした。ドイツ軍は北大西洋で英国の輸送船を潜水艦で次々と沈めたし(第1次世界大戦でも同様)、太平洋戦争でアメリカ軍は日本軍の輸送船を徹底的に狙ったわけです(日本軍の暗号を全部解読していたので、輸送船の発見は容易だったようです)。補給を断たれて南の島に残された日本の兵隊は悲惨です。太平洋戦争における日本兵の死者の半数以上は餓死だと言います。
| 一方の日本軍は、潜水艦でアメリカの輸送船を狙うことをしませんね。また、潜水艦だけではありません。ガダルカナル戦の初期の「第1次ソロモン海戦」で日本軍は、連合軍(アメリカ・イギリス・オーストラリア)の駆逐艦や巡洋艦のほとんどを撃沈するか大破するという勝利をあげたにもかかわらず、それらに護衛されていた肝心の輸送船団を攻撃しませんでした。日米の開戦となった真珠湾攻撃も、ハワイのアメリカ軍の石油備蓄基地を使用不能にするという目的はなかったようです。何が戦略的に重要かの判断がアメリカ軍とはだいぶ違う感じです。このあたりは「近代戦慣れ」していない日本軍としてはやむをえなかったのかもしれません。 |
アメリカ内戦は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」と言えるでしょう。アメリカにとっての最初の「近代戦」は、日本の明治維新以前に起こった、自国での内戦だったわけです。その学習効果(成功も失敗も含めて)は大きかったと思います。
大量の戦死者
アメリカ内戦(南北戦争)の死者は62万人で、これはアメリカの戦死者の最高記録です。第2次世界大戦でのアメリカ軍の死者はヨーロッパ戦線と太平洋戦線を合わせて40万人程度ですが、その1.5倍も多い。
しかし「第2次世界大戦の1.5倍の死者が、アメリカ内戦(南北戦争)で出た」とするのは誤った見方です。そもそも国の総人口が違うからです。アメリカ内戦(南北戦争)が起こった1860年代のアメリカの人口は3000万程度です。一方、第2次世界大戦の1940年代は1億4000万人程度です。人口は5倍近く違います。つまり、
| 人口比で考えると、アメリカ内戦(南北戦争)の死者は、第2次世界大戦の約7倍 |
というのが、正しいモノの見方でしょう。アメリカ内戦で国民の2%が戦争で死んだということは、男性人口だけからすると4%が死んだわけです。兵役適齢人口を仮に男性の半分とすると、その8%が死んだという計算になります。当時としては非常に多い数です。
その後の歴史をみると、20世紀の戦争ではアメリカ内戦(南北戦争)を上回る死者が出たケースが多数あります。第2次世界大戦の日本の死者は、非戦闘員を含んで300万人と言われています。当時の日本の人口は8000万人程度なので「死亡率」はアメリカ内戦(南北戦争)の倍です。第2次世界大戦では、ソ連はもっと多くの死者を出しているし、その前の第1次世界大戦でもヨーロッパ各国は多数の死者を出している。第1次世界大戦のフランスの死者は約170万人で、この数は第2次世界大戦の3倍です。要するに20世紀の戦争は「総力戦」なのですね。この点でもまさにアメリカ内戦(南北戦争)は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」と言えるでしょう。
アンダーソンヴィル捕虜収容所
その死者という点ですが、アメリカ内戦(南北戦争)は、
| 捕虜収容所での、捕虜の大量死 |
という、これもまた20世紀の戦争を予告するような事態が起きました。
「海への進軍」の舞台となったジョージア州に、南軍の最大の捕虜収容所、アンダーソンヴィル捕虜収容所(Andersonville Prison)がありました(「海への進軍」の地図参照)。この収容所に延べ45,000人の北軍兵士が収容され、そのうち13,000人が死亡しました。死亡の原因は栄養失調(餓死)や病気です。

| ||
|
Andersonville Prison
( site : www.nps.gov )
| ||

|

|
北軍捕虜を撮影した写真と、現在の「アンダーソンヴィル歴史地区」に復元されている当時の「テント」。
( site : georgiainfo.galileo.usg.edu )
残された写真を見ると、捕虜は敷地の中の粗末なテントに「野宿」の形で収容されていたことがわかります。10,000人を収容する「施設」のはずが、最大で33,000人の捕虜を詰め込んだようです。それでなくても南軍は敗勢であり、食料や医薬品の補給は困難なはずだから、収容人数の3倍もの捕虜を詰め込んで野宿させると何が起こるかは明白でしょう。1864年8月(真夏)には、1ヶ月で3,000人が亡くなったと言います(アメリカ政府内務省・国立公園局のサイトの解説による)。毎日100人を埋葬する日が続くという悲惨さです。
| なお、アンダーソンヴィル捕虜収容所の跡地とその周辺の墓地は「アンダーソンヴィル歴史地区」(Andersonville National Historic Site)として、アメリカ政府内務省・国立公園局(National Park Service)が管理しています。国立公園局のウェブサイトは、http://www.nps.gov/。このサイトで捕虜収容所の歴史も解説されています。 |
アメリカ内戦(南北戦争)の終結後、収容所の所長は捕虜虐待で逮捕され、裁判にかけられて死刑判決をうけ、執行されました。アメリカ内戦後の死刑判決はこの所長だけです。
補足しますと、南軍に捕虜虐待の意図があったかどうかは別として、これだけの捕虜の大量死が起こったのだから「外形的には捕虜虐待」でしょう。さらに、このような事件は戦勝側が敗戦側の捕虜虐待を大いに宣伝し、それが歴史として残ってしまうのが常なので、北軍側の捕虜虐待が無かったとは言えないと思います
この「アンダーソンヴィル事件」も、20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こったと言えます。つまり、
| ◆ | 戦争の捕虜収容所における「虐待」の結果、多数の捕虜が死亡するに至る。 | ||
| ◆ | 戦争後、勝った側が、負けた側の責任者を「捕虜虐待の罪」や「人道に対する罪」で、「戦争犯罪人」として裁判にかける。 |
の2点です。
ちなみに、戦勝国が敗戦国の責任者を裁判にかけるというのは20世紀の戦争の特徴というより、アメリカの戦争の特徴ですね。ヨーロッパ諸国間の戦争で、そんなことはなかったはずです。アメリカ内戦(南北戦争)が終結(1865)した5年後にヨーロッパで普仏戦争(プロイセン・フランスの戦争。1870-71)が勃発しますが、勝ったプロイセン(ドイツ)はフランスから賠償金と領土(アルザス・ロレーヌ地方)を巻き上げただけでした。もっとも北軍にしてみれば、アメリカ内戦(南北戦争)はあくまで「アメリカ国内における反乱勢力との戦い」なので、人間を虐待するのは刑法犯罪であり、従って裁判にかけるという論理でしょう。アメリカはこの論理を外国との戦争に拡大したと考えられます。
アメリカ内戦と太平洋戦争
アメリカ内戦(南北戦争)は「20世紀の戦争で典型的にみられる事象が予告的に起こった」としましたが、その「20世紀の戦争」は日米間の太平洋戦争についても言えます。それどころか、アメリカの視点で見ると、太平洋戦争の経緯はアメリカ内戦(南北戦争)と非常によく似ているのです。対比してみると以下のようです。
| 北軍は海軍力で南部の大西洋沿岸を海上封鎖した。これが南部連合の体力を徐々に消耗させた(No.104「リンカーンと奴隷解放宣言」参照)。北軍はアメリカ北部の工業力・経済力をバックに優位に戦争を進めた。 | アメリカを中心とする連合国は、日本の海外資産を凍結し、石油の禁輸などの経済封鎖を行った。アメリカは、日本とは比較にならない工業力・経済力をバックに(戦争初期はともかく)圧倒的優位に戦争を進めた。 | |
| 後背地の 戦略攻撃 |
北軍は「敵国」であるジョージア州やサウス・カロライナ州で、無差別の破壊作戦を展開した。「海への進軍」はその典型である。 | アメリカ軍は戦略爆撃機による日本本土の絨毯爆撃を行い、主な大都市は焼け野原となった。また広島と長崎に原爆を投下した。 |
| 兵站線の 寸断 |
北軍はジョージア州やサウス・カロライナ州で鉄道網や橋を破壊し、鉄道・道路を使用不能にした。 | アメリカ軍は日本軍の輸送船を徹底的に攻撃した。広大な太平洋での輸送船の発見は困難なはずだが、暗号解読でそれを可能にした。 |
| 南軍のアンダーソンヴィル捕虜収容所で、北軍の捕虜13,000人が餓死または病死した(アンダーソンヴィルだけが有名なのは、北軍=アメリカ連邦政府の宣伝だと考えられる)。 | インドシナ半島やフィリピンで日本軍の「捕虜虐待事件」があった(日本軍だけに虐待があったというのは戦勝国の言い分である。また、シベリア抑留では日本兵が虐待された)。 | |
| 戦争犯罪 裁判 |
北軍は「捕虜虐待」の罪で、南軍のアンダーソンヴィル捕虜収容所の責任者を裁判にかけた。 | アメリカは「捕虜虐待」の罪で、日本軍の責任者(いわゆるB・C級戦犯)を裁判にかけた。 |
| 敗戦国の 改革 |
勝った北軍=連邦政府は、憲法を改正して奴隷制度を廃止した。これによって、南部の社会・経済構造は抜本的な変革を迫られた。 | 日本を占領したアメリカ軍は、農地解放、財閥解体、教育制度改革など、社会の仕組みを根本から変える変革を実施した。 |
まさに、太平洋戦争で典型的にみられた事象がアメリカ内戦(南北戦争)で予告的に起こっていたと見えます。また一歩進んで、アメリカ内戦(南北戦争)における北軍=連邦政府の行動パターンを、80年後の太平洋戦争とその戦後処理でアメリカ軍=アメリカ政府が繰り返したとも感じます。
アメリカ内戦(南北戦争)は、国家分裂という建国以来の最大の危機にアメリカが陥った時期です。この危機をリンカーン大統領の連邦(Union)政府と連邦軍(北軍)は乗り切ったわけです。この「国家最大の危機が到来したが、それを克服した」という成功物語が、アメリカの歴史意識の根幹にあるのでしょう。
アメリカ内戦での連邦政府(北軍)の個々の成功体験は、20世紀になってアメリカ政府(アメリカ軍)がより精緻な形で反復し、また、アメリカ内戦で連邦政府(北軍)が正当化した軍事行動や政策は、それが正当だということを証明するために、20世紀になっても繰り返されたのではないでしょうか。
国家の行動は歴史に影響されるということだと思います。国家のアイデンティティとなっている「近代史上の成功物語」は、現在の国家の正当性を暗黙に保証するものである以上、繰り返さざるを得ないのでしょう。それは現代における組織や会社の成功体験とも似ていると感じます。
しかし、過去の成功物語を繰り返すことは、環境の変化のために失敗につながることもあるし、むしろその方が多い・・・・・・。このあたりが重要だとも思います。
No.104 - リンカーンと奴隷解放宣言 [歴史]
このブログの記事で、今まで何回か歴史上の「奴隷」についての記述をしました。
の5つです。その継続で、今回は「リンカーンの奴隷解放宣言」についてです。なぜこのテーマかと言うと、最近の(と言っても半年以上前ですが)朝日新聞に奴隷解放宣言についての解説記事(2013.5.13)が掲載されたことを思い出したからです。その記事の要点も、あとで紹介します。
奴隷解放宣言
そもそも「奴隷解放宣言」は、南北戦争の途中で出されたものであり、それはリンカーン大統領率いる合衆国(=北軍)が、南部連合(=南軍)との南北戦争を戦うための「大義」を「後づけで」示したものというように理解していました。
改めて、事実関係を調べて整理すると以下のようになります。
1861年1月
1861年2月
1861年4月
1863年1月
1863年11月
1864年9月
1865年4月
1865年12月
リンカーン大統領の奴隷解放宣言(1863年1月1日の大統領布告)の核心部分は以下です。
下線の部分にあるように、奴隷解放の対象となる地域は合衆国に対して反逆している地域です。宣言の中には、その地域が明記されています(表記を分かりやすくしました)。
この宣言に記載されていない地域、つまり「奴隷解放の対象とはならない地域」を考えてみると、宣言の意味が一層明確になります。
まず、州の名前を数えてみると10しかありません。あれっ、南北戦争における「南部」は11州のはずなのに、と思ってしまいますが、ないのはテネシーです。テネシー州は1863年1月の時点で、すでに合衆国主導の政府と軍隊ができており、反乱地域ではないので奴隷解放の対象とはならないのです。
またルイジアナ州のニューオリンズ、その他や、ヴァージニア州のウェスト・ヴァージニア地方などは、奴隷解放の例外地区です。このうちウェスト・ヴァージニアはヴァージニア州から分離し、独立州として合衆国に加盟するプロセスが進んでいました。そもそもウェスト・ヴァージニアは南部連合には入らなかったのです。現在のウェスト・ヴァージニア州です。
さらに、当然と言えば当然ですが、南部連合に加盟せずに合衆国に留まった「奴隷州」(奴隷制を認めている州)も奴隷解放の対象ではありません。ミズーリ、ケンタッキー、メリーランド、デラウェアの4州です。
考えてみると「奴隷解放宣言」という大統領布告は奇妙です。奴隷は所有者がお金を払って手に入れた財産なので、それを大統領が「解放する」というのは、明らかに個人の財産権の侵害です。
もちろん「財産権より人権が優先する」という決定はあるわけですが、こういう基本的な市民の権利を定めるのは憲法です。アメリカは三権分立の法治国家なので、憲法を改正できるのは議会(連邦議会)であり、大統領ではありません。事実、南北戦争が終わったあとの連邦議会で合衆国憲法修正13条が可決され、合衆国全地域で奴隷制度が廃止されたわけです。
では、なぜリンカーン大統領は「奴隷解放宣言」を出せたのか。その理由は「奴隷解放宣言」そのものに書いてあります。
奴隷解放宣言の根拠になっているのは
であり、言わば「戦争時における大統領の非常大権」です。従って、合衆国政府に反逆していない地域の奴隷解放はできません。リンカーンは法治国家としてのアメリカを尊重しているのです。
南部を制圧するための「奴隷解放宣言」
ではなぜリンカーン大統領は「合衆国に対する反乱地域における奴隷を解放する布告」を出したのでしょうか。朝日新聞の解説記事(2013.5.13)にもあるのですが、最近の研究では、奴隷解放宣言の目的は
です。
「奴隷解放」は南部連合が「絶対にのめない」条件です。講和のテーブルにはつけなくなる。「もう最後の最後まで戦うしかない」と、南部連合は思ったでしょう。また合衆国内部に芽生えてきた「講和をすべき」という意見を断ち切ることができます。「南北戦争の目的は奴隷解放です。それに反対してあなたは講和を主張するのですか」と言われたとしたら、「自由州」(奴隷制度がない州)が多い合衆国の議員は反論出来ないでしょう。
さらに奴隷解放宣言の副次効果で、ヨーロッパの「人権国家」は南部連合を支持しにくくなります。この時点でヨーロッパに奴隷制度はありません。たとえば、かつての「植民地・アメリカ」の宗主国であるイギリスは、とっくの昔の1772年に奴隷を禁止しています。南部連合を「国」として承認するなどできないでしょう。
そのかつての宗主国・イギリスは、歴史的経緯によりアメリカ南部地域と非常に深い関係を持っていました。その一例ですが、No.40「小公女」で、この小説の作者の生い立ちを書きました。
というのが、バーネットの生い立ちです。
イギリスの綿織物産業にとって、アメリカ南部の大規模プランテーションの奴隷労働で栽培される綿花が「生命線」だったことをうかがわせます。議会制民主主義国家である英国の政府は、当然、アメリカ南部連合を「応援」したくなると思います。しかし「奴隷解放宣言」が出た以上、それは「人権国家」としてできない相談になる。
さらに副次効果として、南部連合の奴隷たちが戦線を離脱したり、合衆国側に投降したりということも期待できます。奴隷解放宣言には次のような「あからさまな」文言があります。括弧内は引用注です。
なるほど。「適切な健康状態にある者は」というところがミソですね。要するに、北軍との戦闘で負傷したような南軍の奴隷は受け入れないということでしょう。
まさに「奴隷解放宣言」は一石二鳥というか、三鳥も、四鳥もの効果がある(効果を狙った)宣言だったわけです。この宣言はリンカーン大統領の「南部を完全に制圧するまで戦争を戦い、そのことによって合衆国を再統一する」という強い意志に基づいています。北部にとっても、また南部にとっても「退路を断ち切った」宣言になっている。「賭け」かもしれないが、合衆国の再統一のためにはこれが最適である。そしてリンカーンはそれをやり抜いた。リンカーンがアメリカ史上、最も偉大な大統領と言われることも納得できます。
リンカーンの真意
「奴隷解放宣言の目的はアメリカの再統合だった。そもそも南北戦争の目的が再統合」というわけですが、そのことはリンカーン自身が語っています。朝日新聞 2013.5.13 号に「人種差別主義者だった? リンカーン」という見出しの解説記事(編集委員が執筆)が掲載されました。そこから引用します(記事に下線はありません)。
1862年は南北戦争まっただ中で、奴隷解放宣言を出す前です。そこに注目すべきだと思います(補記参照)。
「もし奴隷は一人も自由にせずに連邦を救うことができるのなら、そうするでしょう」というリンカーンの言葉の解釈ですが、「奴隷解放宣言」という「戦争時における大統領の非常大権を使った布告」は自分の本意ではないという意味だと私は解釈しています。
リンカーンが奴隷制廃止論者であったことは間違いありません。奴隷制廃止を掲げて大統領に当選したのだし、それに反発する南部11州が合衆国から離脱して南部連合を作ったわけです。
しかし、奴隷制廃止論者も多様なはずです。「最もラディカルな奴隷制廃止論者」は
と主張するでしょう。しかし「最も穏健な奴隷制廃止論者」は、
という風に考えるでしょう。
リンカーンは「穏健な奴隷制廃止論者」に近い考え方なのではと想像します。このあたりはもう少しアメリカ史を調べてみたいところです。
「人種差別主義者」リンカーン
朝日新聞の解説記事が指摘しているもう一つのポイントはリンカーンの「人種差別」です。
要するに、リンカーンの考えでは、
ということです(補記参照)。朝日新聞も指摘しているのですが、これは当時としては極めて一般的な考えでした。そして奴隷制度が廃止された以降のアメリカは、このリンカーンの言葉通りに進んでいったのです。この流れを大きく変えたターニング・ポイントが、1964年の「公民権法」の成立というわけです。
朝日新聞の解説記事は、
をあわせ、「リンカーンこそ、現代に至る、アメリカの光と影を培った大統領と言えるのではないか」とまとめられています。
現代の感覚で過去を見てはならない
朝日新聞 2013.5.13付けの解説記事の見出しは
ですが、これは「いただけない」見出しです。クエスチョンマーク(?)が付いてはいますが、ここで「人種差別主義者」という言葉を(特に、見出しに)使うのは不適切だと思います。
現代人がリンカーンのような発言をしたとしたら、明らかにその人は「人種差別主義者」ですが、150年前のリンカーンの時代は、それがごく普通の考え方だったわけです。現代人の視点と用語で過去を語るのはよくない。
No.73「ニュートンと錬金術」で、アイザック・ニュートンの「業績」を、
の3つだと書きましたが、②と③があるからといって①の分野での業績、つまり近代科学を作り上げたニュートンの偉大さが減るわけではありません。ニュートンを「最後の魔術師」などと言うのは適当でないのです。②③は当時としてはまじめな「科学的研究」だった。
リンカーンの「現代人が言ったとしたら人種差別になる発言」もそれと同じです。それは、朝日新聞の言うようなリンカーンの「影」ではありえない。現代感覚で過去の人物を「評価」したり「断罪」してはならないと思います。
朝日新聞が引用している「知人にあてた手紙(1862年)」というのは、当時の、ニューヨーク・トリビューン紙の創立者で編集長のホーレス・グリーリに宛てた書簡です。これは紙面で公表されました。書簡の日付は1862年8月22日で、南北戦争の真っ最中です。この時すでに「奴隷解放宣言」の草稿がリンカーンの机の中に入っていました。リンカーンはこの草稿をもとに1862年9月22日に「奴隷解放予備宣言」(100日後にこういう布告を出すよ、という宣言)を出したのです。
この書簡はリンカーンの書簡の中でも最も有名なものの一つのようです。その全文と、核心部分の日本語訳を掲げておきます。
意味深長なところがある文章です。「連邦を救うのが至高の目的」であることを、奴隷を解放する・しないという例示をしつこいぐらいにして説明しています。そしてこの書簡の後に出された「奴隷解放宣言」は、例示の最後にある「ある奴隷を解放し他の奴隷を放置しておくことによって連邦を救う」という通りになったわけです。
さらに、朝日新聞が引用している「民主党候補との論争の演説(1858年)」とは、イリノイ州の上院議員選挙を民主党のスティーヴン・ダグラス候補と争った時の討論会(ディベート)です。このディベートもアメリカ史上、有名なようです。該当する部分の原文と訳を掲げておきます。
No.18「ブルーの世界」
|
の5つです。その継続で、今回は「リンカーンの奴隷解放宣言」についてです。なぜこのテーマかと言うと、最近の(と言っても半年以上前ですが)朝日新聞に奴隷解放宣言についての解説記事(2013.5.13)が掲載されたことを思い出したからです。その記事の要点も、あとで紹介します。
奴隷解放宣言
そもそも「奴隷解放宣言」は、南北戦争の途中で出されたものであり、それはリンカーン大統領率いる合衆国(=北軍)が、南部連合(=南軍)との南北戦争を戦うための「大義」を「後づけで」示したものというように理解していました。
改めて、事実関係を調べて整理すると以下のようになります。
1861年1月
|
リンカーンが第16代のアメリカ合衆国大統領に就任 |
1861年2月
|
南部11州がアメリカ合衆国から脱退し、南部連合を結成 |
1861年4月
|
合衆国と南部連合の戦争(いわゆる南北戦争)が勃発 |
1863年1月
|
奴隷解放宣言 |
1863年11月
|
ゲティスバーグ演説 |
1864年9月
|
アトランタ陥落(「風と共に去りぬ」のシーン) |
1865年4月
|
南北戦争終結(9日)。リンカーン、暗殺される(14日) |
1865年12月
|
連邦議会で合衆国憲法修正13条が可決され、合衆国全地域で奴隷制度は廃止された。 |
リンカーン大統領の奴隷解放宣言(1863年1月1日の大統領布告)の核心部分は以下です。
|
| 奴隷解放の対象地域 |
下線の部分にあるように、奴隷解放の対象となる地域は合衆国に対して反逆している地域です。宣言の中には、その地域が明記されています(表記を分かりやすくしました)。
|
この宣言に記載されていない地域、つまり「奴隷解放の対象とはならない地域」を考えてみると、宣言の意味が一層明確になります。
まず、州の名前を数えてみると10しかありません。あれっ、南北戦争における「南部」は11州のはずなのに、と思ってしまいますが、ないのはテネシーです。テネシー州は1863年1月の時点で、すでに合衆国主導の政府と軍隊ができており、反乱地域ではないので奴隷解放の対象とはならないのです。
またルイジアナ州のニューオリンズ、その他や、ヴァージニア州のウェスト・ヴァージニア地方などは、奴隷解放の例外地区です。このうちウェスト・ヴァージニアはヴァージニア州から分離し、独立州として合衆国に加盟するプロセスが進んでいました。そもそもウェスト・ヴァージニアは南部連合には入らなかったのです。現在のウェスト・ヴァージニア州です。
さらに、当然と言えば当然ですが、南部連合に加盟せずに合衆国に留まった「奴隷州」(奴隷制を認めている州)も奴隷解放の対象ではありません。ミズーリ、ケンタッキー、メリーランド、デラウェアの4州です。
| 大統領の権限? |
考えてみると「奴隷解放宣言」という大統領布告は奇妙です。奴隷は所有者がお金を払って手に入れた財産なので、それを大統領が「解放する」というのは、明らかに個人の財産権の侵害です。
もちろん「財産権より人権が優先する」という決定はあるわけですが、こういう基本的な市民の権利を定めるのは憲法です。アメリカは三権分立の法治国家なので、憲法を改正できるのは議会(連邦議会)であり、大統領ではありません。事実、南北戦争が終わったあとの連邦議会で合衆国憲法修正13条が可決され、合衆国全地域で奴隷制度が廃止されたわけです。
では、なぜリンカーン大統領は「奴隷解放宣言」を出せたのか。その理由は「奴隷解放宣言」そのものに書いてあります。
|
奴隷解放宣言の根拠になっているのは
|
政府に対する武力による反逆が実際に起きたときの、合衆国陸海軍の最高司令官としての大統領に与えられた権限 |
であり、言わば「戦争時における大統領の非常大権」です。従って、合衆国政府に反逆していない地域の奴隷解放はできません。リンカーンは法治国家としてのアメリカを尊重しているのです。
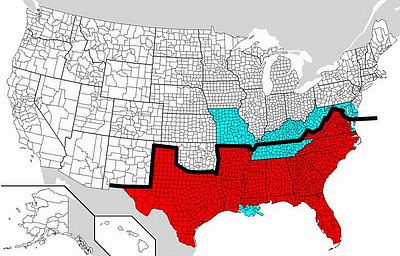
| ||
|
奴隷解放の対象となった州・地域(赤色)と、奴隷解放の対象とはならなかった州・地域(青色)。黒線より南が南部連合である。黒線に接して南の青色の州がテネシー州。黒線より北の青色の州(奴隷州)は、西からミズーリ、ケンタッキー、ウェスト・ヴァージニア、メリーランド、デラウェアである。地図はWikipediaより引用した。
| ||
南部を制圧するための「奴隷解放宣言」
ではなぜリンカーン大統領は「合衆国に対する反乱地域における奴隷を解放する布告」を出したのでしょうか。朝日新聞の解説記事(2013.5.13)にもあるのですが、最近の研究では、奴隷解放宣言の目的は
|
南北戦争における講和の芽を排除し、南部を完全に制圧するまで戦争を戦い抜き、そのことによって合衆国を再統一するため |
です。
「奴隷解放」は南部連合が「絶対にのめない」条件です。講和のテーブルにはつけなくなる。「もう最後の最後まで戦うしかない」と、南部連合は思ったでしょう。また合衆国内部に芽生えてきた「講和をすべき」という意見を断ち切ることができます。「南北戦争の目的は奴隷解放です。それに反対してあなたは講和を主張するのですか」と言われたとしたら、「自由州」(奴隷制度がない州)が多い合衆国の議員は反論出来ないでしょう。
さらに奴隷解放宣言の副次効果で、ヨーロッパの「人権国家」は南部連合を支持しにくくなります。この時点でヨーロッパに奴隷制度はありません。たとえば、かつての「植民地・アメリカ」の宗主国であるイギリスは、とっくの昔の1772年に奴隷を禁止しています。南部連合を「国」として承認するなどできないでしょう。
そのかつての宗主国・イギリスは、歴史的経緯によりアメリカ南部地域と非常に深い関係を持っていました。その一例ですが、No.40「小公女」で、この小説の作者の生い立ちを書きました。
| ◆ |
「小公女」の作者のフランシス・バーネットは英国・マンチェスターの家具の卸問屋に生まれた(1849)。 | |||||
| ◆ |
当時のマンチェスターは英国の綿織物産業の中心地だった。 | |||||
| ◆ |
ところが南北戦争が始まると(1861)アメリカ南部からの綿花の輸入がストップしてしまい、マンチェスターの町は大不況に陥った。
| |||||
| ◆ |
この結果、フランシス一家の生活も苦しくなり、家族は親族をたよってアメリカのテネシー州に移住した(1865)。 |
というのが、バーネットの生い立ちです。
イギリスの綿織物産業にとって、アメリカ南部の大規模プランテーションの奴隷労働で栽培される綿花が「生命線」だったことをうかがわせます。議会制民主主義国家である英国の政府は、当然、アメリカ南部連合を「応援」したくなると思います。しかし「奴隷解放宣言」が出た以上、それは「人権国家」としてできない相談になる。
さらに副次効果として、南部連合の奴隷たちが戦線を離脱したり、合衆国側に投降したりということも期待できます。奴隷解放宣言には次のような「あからさまな」文言があります。括弧内は引用注です。
|
なるほど。「適切な健康状態にある者は」というところがミソですね。要するに、北軍との戦闘で負傷したような南軍の奴隷は受け入れないということでしょう。
まさに「奴隷解放宣言」は一石二鳥というか、三鳥も、四鳥もの効果がある(効果を狙った)宣言だったわけです。この宣言はリンカーン大統領の「南部を完全に制圧するまで戦争を戦い、そのことによって合衆国を再統一する」という強い意志に基づいています。北部にとっても、また南部にとっても「退路を断ち切った」宣言になっている。「賭け」かもしれないが、合衆国の再統一のためにはこれが最適である。そしてリンカーンはそれをやり抜いた。リンカーンがアメリカ史上、最も偉大な大統領と言われることも納得できます。

リンカーン記念館の外観 |

内部のリンカーン像 | |
リンカーン記念館(Lincoln Memorial)はワシントン D.C.にあり、リンカーン像の高さは約6メートルある。ここを訪れると、リンカーンが「アメリカで最も偉大な大統領」とみなされていることがよく分かる。 | ||
リンカーンの真意
「奴隷解放宣言の目的はアメリカの再統合だった。そもそも南北戦争の目的が再統合」というわけですが、そのことはリンカーン自身が語っています。朝日新聞 2013.5.13 号に「人種差別主義者だった? リンカーン」という見出しの解説記事(編集委員が執筆)が掲載されました。そこから引用します(記事に下線はありません)。
|
1862年は南北戦争まっただ中で、奴隷解放宣言を出す前です。そこに注目すべきだと思います(補記参照)。
「もし奴隷は一人も自由にせずに連邦を救うことができるのなら、そうするでしょう」というリンカーンの言葉の解釈ですが、「奴隷解放宣言」という「戦争時における大統領の非常大権を使った布告」は自分の本意ではないという意味だと私は解釈しています。
リンカーンが奴隷制廃止論者であったことは間違いありません。奴隷制廃止を掲げて大統領に当選したのだし、それに反発する南部11州が合衆国から離脱して南部連合を作ったわけです。
しかし、奴隷制廃止論者も多様なはずです。「最もラディカルな奴隷制廃止論者」は
| ◆ |
人間は皆平等だ | ||
| ◆ |
今すぐ奴隷制を廃止せよ | ||
| ◆ |
奴隷は即時解放せよ |
と主張するでしょう。しかし「最も穏健な奴隷制廃止論者」は、
| ◆ |
まず、これ以上奴隷制が広がるのを阻止し(たとえば、アメリカ西部の正式の州ではない準州) | ||
| ◆ |
次に、奴隷制廃止を議会で検討可能な州の州法を変え(たとえば南部連合に参加しなかった奴隷州、ミズーリ、ケンタッキー、メリーランド、デラウェアなど) | ||
| ◆ |
奴隷制廃止に強硬に反対する州に対しては、時間をかけて粘り強く説得していく。 |
という風に考えるでしょう。
リンカーンは「穏健な奴隷制廃止論者」に近い考え方なのではと想像します。このあたりはもう少しアメリカ史を調べてみたいところです。
「人種差別主義者」リンカーン
朝日新聞の解説記事が指摘しているもう一つのポイントはリンカーンの「人種差別」です。
|
要するに、リンカーンの考えでは、
|
「奴隷解放 = 人種の平等」ではない |
ということです(補記参照)。朝日新聞も指摘しているのですが、これは当時としては極めて一般的な考えでした。そして奴隷制度が廃止された以降のアメリカは、このリンカーンの言葉通りに進んでいったのです。この流れを大きく変えたターニング・ポイントが、1964年の「公民権法」の成立というわけです。
朝日新聞の解説記事は、
| ① |
リンカーンが人種差別の考え方をもっていたこと(上記)。 | ||
| ② |
奴隷解放で形の上では平等になっため、逆に黒人に対する圧迫が強くなったこと。 | ||
| ③ |
南北戦争の死者は、第2次世界対戦での米軍の死者を上回る62万人であり、都市の徹底破壊や殲滅戦が行われるなど近代戦の幕開けとなったこと。 |
をあわせ、「リンカーンこそ、現代に至る、アメリカの光と影を培った大統領と言えるのではないか」とまとめられています。
現代の感覚で過去を見てはならない
朝日新聞 2013.5.13付けの解説記事の見出しは
|
人種差別主義者だった? リンカーン |
ですが、これは「いただけない」見出しです。クエスチョンマーク(?)が付いてはいますが、ここで「人種差別主義者」という言葉を(特に、見出しに)使うのは不適切だと思います。
現代人がリンカーンのような発言をしたとしたら、明らかにその人は「人種差別主義者」ですが、150年前のリンカーンの時代は、それがごく普通の考え方だったわけです。現代人の視点と用語で過去を語るのはよくない。
No.73「ニュートンと錬金術」で、アイザック・ニュートンの「業績」を、
| ① |
物理学・数学 | ||
| ② |
錬金術 | ||
| ③ |
聖書研究(聖書の「科学的」解読) |
の3つだと書きましたが、②と③があるからといって①の分野での業績、つまり近代科学を作り上げたニュートンの偉大さが減るわけではありません。ニュートンを「最後の魔術師」などと言うのは適当でないのです。②③は当時としてはまじめな「科学的研究」だった。
リンカーンの「現代人が言ったとしたら人種差別になる発言」もそれと同じです。それは、朝日新聞の言うようなリンカーンの「影」ではありえない。現代感覚で過去の人物を「評価」したり「断罪」してはならないと思います。
(続く)
| 補記 |
朝日新聞が引用している「知人にあてた手紙(1862年)」というのは、当時の、ニューヨーク・トリビューン紙の創立者で編集長のホーレス・グリーリに宛てた書簡です。これは紙面で公表されました。書簡の日付は1862年8月22日で、南北戦争の真っ最中です。この時すでに「奴隷解放宣言」の草稿がリンカーンの机の中に入っていました。リンカーンはこの草稿をもとに1862年9月22日に「奴隷解放予備宣言」(100日後にこういう布告を出すよ、という宣言)を出したのです。
この書簡はリンカーンの書簡の中でも最も有名なものの一つのようです。その全文と、核心部分の日本語訳を掲げておきます。
|
意味深長なところがある文章です。「連邦を救うのが至高の目的」であることを、奴隷を解放する・しないという例示をしつこいぐらいにして説明しています。そしてこの書簡の後に出された「奴隷解放宣言」は、例示の最後にある「ある奴隷を解放し他の奴隷を放置しておくことによって連邦を救う」という通りになったわけです。
さらに、朝日新聞が引用している「民主党候補との論争の演説(1858年)」とは、イリノイ州の上院議員選挙を民主党のスティーヴン・ダグラス候補と争った時の討論会(ディベート)です。このディベートもアメリカ史上、有名なようです。該当する部分の原文と訳を掲げておきます。
|
(続く)
No.75 - 結核と初キス [歴史]
前回の No.74「現代感覚で過去を見る落とし穴」を連想させる日本経済新聞の記事が最近あったので、その記事を紹介したいと思います。作家の渡辺 淳一氏が連載している『私の履歴書』です。
渡辺淳一「私の履歴書」
2013年1月12日付の日本経済新聞の『私の履歴書』で、渡辺 淳一氏は以下のような文章を書いていました。札幌南高等学校のときに同級生の加清純子という女性と恋をした話です。その女性は絵が大変に上手で、中学生の頃から「天才少女画家」と言われていたようです。渡辺少年は純子と知り合って逢瀬を重ねます。そして高校3年生になりました。
さすがですね。これは渡辺先生でないと書けない文章だと思います。結核に怯えながら初めての接吻をするというところがきまっています。
この純子という女性は相当な人です。「うぶな」渡辺少年に「できないの?」迫ってキスをさせる。こう言われると男は、後がどうなろうとキスするしかありません。他の選択肢は絶対にない。彼女は芸術家肌で「悪魔に引きずられていくような魅力」がある。渡辺さんが『私の履歴書』に書くだけの強烈な印象を残した女性だったようです。
そして推測できるのは、彼女が結核であり、結核にかかるのではと怯えながらの初めてのキスだったからこそ強烈な印象となったことです。この文章を読んで、同じ日本経済新聞に連載された『失楽園』(1995 - 6)を思い出してしまいました。『失楽園』の最後は心中で終わるのですが、ひょっとしたらこういった「愛 = 死」というイメージは、高校3年生の時の作家の原体験からきているのではないでしょうか。
それはともかく「結核に怯えながらのキス」が渡辺氏に強烈な思い出を残したことは確信しました。そして思ったのですが、渡辺氏にその強烈な思い出を残した「功績者」は(かつ、ひょっとしたら後の小説作品に影響を与えたかもしれない功績者は)、もとをたどると19世紀のドイツの医学者、ロベルト・コッホだということです。
ロベルト・コッホ
ロベルト・コッホ(1843-1910)は、1882年に結核菌を発見しました。そしてその病原性を証明し、結核の原因は細菌であることを明らかにしました。ヒトにおいて細菌が病原体であることが証明されたのはこれが最初です。これ以降、様々な細菌が発見され、やがてウイルスの発見へとつながり、それが感染症の予防や治療薬の開発につながりました。
我々は病気の多くのものが感染症であり、細菌やウイルスが原因で起こることを知っています。もちろん感染症でない病気もある。生活習慣病と言われる病気やリウマチなどの(遺伝的要素の強い)自己免疫疾患、脚気などのビタミン欠乏症があり、それらは感染することはない。しかし細菌やウイルスによる病気は感染する。現代では小学生でも知っている知識です。
しかし昔はそうではありません。特に結核(肺結核)のように感染から発病までの時間が長い病気は「うつる」とは認識されなかったわけです。渡辺少年は純子に「キスをして」と言われて怯えたわけですが、渡辺少年を怯えさせたのはコッホ以降の医学知識の蓄積です。それ以前は結核が「うつる」とは認識されていなかった。それを証明する話があります。渡辺少年が高校3年の時(1950年頃)から100年ほど前の話です。
椿姫
ヴェルディの『椿姫』というオペラがあります(1853年初演)。アレクサンドル・デュマ・フィス(小デュマ)の小説『椿姫』(1848)を原作とするオペラですが、主人公のヴィオレッタ(小説ではマルグリット)は娼婦です。そもそも「椿姫」という題名の由来は、彼女が生理期間中は赤い椿を身につけ、それ以外は白い椿をつけたからです。白い椿は「営業中」のサインというわけです。
この主人公のヴィオレッタ(マルグリット)は結核にかかっているのですね。コホン、コホンとやっている。そして男たちは彼女が結核であることを百も承知なのです。承知していながら彼女と寝ている(オペラではそういう「仕事」の場面はありませんが)。同棲までする男もいる。そして最後に彼女は結核で死んでしまいます。
自分も死ぬかもしれないという恐怖が、美しい彼女と寝ることの魅力をいっそう増進させる・・・・・・というのではありません。渡辺少年とは違います。ヴィオレッタ(マルグリット)に群がった男たちは(そして当時の人たちは)単に知らなかったのです。結核は発病者の咳に含まれる細菌で空気感染する、ということを知っていたとしたら、男たちの行動は違ったでしょう。
椿姫以前
「病原菌が病気を引き起こす」というのは19世紀後半以降の知識です。それ以前はそうとは分かわからない。もちろん、感染から発病までの期間が短い病気は「うつる」という認識はあったでしょうが「病原菌という微生物が原因」だとは知り得ないわけです。
近代以前の世界を想像してみたいと思います。ある地域、地方、国で人々が病気にかかり、バタバタと倒れ、多数の死者が出たとします。「病原菌という微生物が原因だとは全く分からない」という前提で、人間はどう考えるでしょうか。
などと考えるのではないでしょうか。病原菌の存在を知らないという前提では、こういった考えがロジカルに思えます。神・悪魔・悪霊を「ロジカル」というのも変な話ですが、まっとうな人間の思考として、それなりに筋道がたっているという意味です。
神・悪魔・悪霊と書きましたが、とすると、疫病の蔓延、その原因究明、さらに疫病から逃れる方法については「宗教の領域」に属することになります。また政治と宗教が表裏一体のケースでは「祭り(まつり)ごとを行う」という意味での「政治の領域」になります。従って疫病の蔓延と多数の死者の発生は、人々の間に宗教(ないしは宗教政治)に対する「動き」を引き起こすと考えられます。これには大きく二つあり、一つは宗教に加護を求めるもので、もう一つは自分たちを守ってくれない宗教に対する反発だと思うのです。
致死性の疫病の蔓延は近代以前では世界中であり、日本でも奈良・平安時代には天然痘の大流行がありました。奈良時代ですが、藤原不比等の息子で当時の政権の中枢にあった「藤原四兄弟」が、あいついで天然痘で死亡したのは有名な話です。天然痘と言えば、No.24「ローマ人の物語(1)」に古代ローマ帝国における天然痘の流行のことを書きました。それは2世紀後半のアントニウスの疫病(165-180)で、帝国の人口の3分の1が死んだと言われています(青柳正規「ローマ帝国」岩波書店 2004 による)。No.24を引用すると次の通りです。
致死性の疫病の蔓延が宗教不信や政治不信を招き、それが社会体制の崩壊につながったという事例も(ローマ帝国がそうだとは言いませんが)いろいろあったのではないでしょうか。
全く不明の原因で人がバタバタと倒れていく。それは神に対立する悪魔のしわざとしか思えない(例えば)。そういった感覚で過去の歴史の動きをみる必要があると思います。我々にとってあたりまえの「病気に対する知識」は近代医学がもたらしたものがほとんどで、それは高々100年程度の歴史しかないのです。
前回、およびその前の No.73「ニュートンと錬金術」で何回か強調したように、我々は無意識に現代人の感覚で過去の歴史を見てしまいがちです。そのことには十分注意すべきだと思います。
渡辺淳一「私の履歴書」
2013年1月12日付の日本経済新聞の『私の履歴書』で、渡辺 淳一氏は以下のような文章を書いていました。札幌南高等学校のときに同級生の加清純子という女性と恋をした話です。その女性は絵が大変に上手で、中学生の頃から「天才少女画家」と言われていたようです。渡辺少年は純子と知り合って逢瀬を重ねます。そして高校3年生になりました。
|
さすがですね。これは渡辺先生でないと書けない文章だと思います。結核に怯えながら初めての接吻をするというところがきまっています。
この純子という女性は相当な人です。「うぶな」渡辺少年に「できないの?」迫ってキスをさせる。こう言われると男は、後がどうなろうとキスするしかありません。他の選択肢は絶対にない。彼女は芸術家肌で「悪魔に引きずられていくような魅力」がある。渡辺さんが『私の履歴書』に書くだけの強烈な印象を残した女性だったようです。
そして推測できるのは、彼女が結核であり、結核にかかるのではと怯えながらの初めてのキスだったからこそ強烈な印象となったことです。この文章を読んで、同じ日本経済新聞に連載された『失楽園』(1995 - 6)を思い出してしまいました。『失楽園』の最後は心中で終わるのですが、ひょっとしたらこういった「愛 = 死」というイメージは、高校3年生の時の作家の原体験からきているのではないでしょうか。
それはともかく「結核に怯えながらのキス」が渡辺氏に強烈な思い出を残したことは確信しました。そして思ったのですが、渡辺氏にその強烈な思い出を残した「功績者」は(かつ、ひょっとしたら後の小説作品に影響を与えたかもしれない功績者は)、もとをたどると19世紀のドイツの医学者、ロベルト・コッホだということです。
ロベルト・コッホ
ロベルト・コッホ(1843-1910)は、1882年に結核菌を発見しました。そしてその病原性を証明し、結核の原因は細菌であることを明らかにしました。ヒトにおいて細菌が病原体であることが証明されたのはこれが最初です。これ以降、様々な細菌が発見され、やがてウイルスの発見へとつながり、それが感染症の予防や治療薬の開発につながりました。
我々は病気の多くのものが感染症であり、細菌やウイルスが原因で起こることを知っています。もちろん感染症でない病気もある。生活習慣病と言われる病気やリウマチなどの(遺伝的要素の強い)自己免疫疾患、脚気などのビタミン欠乏症があり、それらは感染することはない。しかし細菌やウイルスによる病気は感染する。現代では小学生でも知っている知識です。
しかし昔はそうではありません。特に結核(肺結核)のように感染から発病までの時間が長い病気は「うつる」とは認識されなかったわけです。渡辺少年は純子に「キスをして」と言われて怯えたわけですが、渡辺少年を怯えさせたのはコッホ以降の医学知識の蓄積です。それ以前は結核が「うつる」とは認識されていなかった。それを証明する話があります。渡辺少年が高校3年の時(1950年頃)から100年ほど前の話です。
椿姫
ヴェルディの『椿姫』というオペラがあります(1853年初演)。アレクサンドル・デュマ・フィス(小デュマ)の小説『椿姫』(1848)を原作とするオペラですが、主人公のヴィオレッタ(小説ではマルグリット)は娼婦です。そもそも「椿姫」という題名の由来は、彼女が生理期間中は赤い椿を身につけ、それ以外は白い椿をつけたからです。白い椿は「営業中」のサインというわけです。
この主人公のヴィオレッタ(マルグリット)は結核にかかっているのですね。コホン、コホンとやっている。そして男たちは彼女が結核であることを百も承知なのです。承知していながら彼女と寝ている(オペラではそういう「仕事」の場面はありませんが)。同棲までする男もいる。そして最後に彼女は結核で死んでしまいます。
自分も死ぬかもしれないという恐怖が、美しい彼女と寝ることの魅力をいっそう増進させる・・・・・・というのではありません。渡辺少年とは違います。ヴィオレッタ(マルグリット)に群がった男たちは(そして当時の人たちは)単に知らなかったのです。結核は発病者の咳に含まれる細菌で空気感染する、ということを知っていたとしたら、男たちの行動は違ったでしょう。

| |||
|
ヴェルディ「椿姫」第1幕の「乾杯の歌」のシーン ヴィオレッタはアンジェラ・ゲオルギュー | |||
椿姫以前
「病原菌が病気を引き起こす」というのは19世紀後半以降の知識です。それ以前はそうとは分かわからない。もちろん、感染から発病までの期間が短い病気は「うつる」という認識はあったでしょうが「病原菌という微生物が原因」だとは知り得ないわけです。
近代以前の世界を想像してみたいと思います。ある地域、地方、国で人々が病気にかかり、バタバタと倒れ、多数の死者が出たとします。「病原菌という微生物が原因だとは全く分からない」という前提で、人間はどう考えるでしょうか。
| ◆ | これは神の罰である。人間が不遜な行いをしたために、神がその地域の人々を処罰したのである。 | |
| ◆ | これは悪魔が人間を攻撃しているのだ。 | |
| ◆ | 悪霊が人間にとりつき、それがうつることによって人が死んでいくのだ。 |
などと考えるのではないでしょうか。病原菌の存在を知らないという前提では、こういった考えがロジカルに思えます。神・悪魔・悪霊を「ロジカル」というのも変な話ですが、まっとうな人間の思考として、それなりに筋道がたっているという意味です。
神・悪魔・悪霊と書きましたが、とすると、疫病の蔓延、その原因究明、さらに疫病から逃れる方法については「宗教の領域」に属することになります。また政治と宗教が表裏一体のケースでは「祭り(まつり)ごとを行う」という意味での「政治の領域」になります。従って疫病の蔓延と多数の死者の発生は、人々の間に宗教(ないしは宗教政治)に対する「動き」を引き起こすと考えられます。これには大きく二つあり、一つは宗教に加護を求めるもので、もう一つは自分たちを守ってくれない宗教に対する反発だと思うのです。
致死性の疫病の蔓延は近代以前では世界中であり、日本でも奈良・平安時代には天然痘の大流行がありました。奈良時代ですが、藤原不比等の息子で当時の政権の中枢にあった「藤原四兄弟」が、あいついで天然痘で死亡したのは有名な話です。天然痘と言えば、No.24「ローマ人の物語(1)」に古代ローマ帝国における天然痘の流行のことを書きました。それは2世紀後半のアントニウスの疫病(165-180)で、帝国の人口の3分の1が死んだと言われています(青柳正規「ローマ帝国」岩波書店 2004 による)。No.24を引用すると次の通りです。
「パックス・ロマーナ」においてローマ帝国が防衛・保障してくれるのは外敵の進入や内乱からの安全であって、病原菌からの安全ではないのです。あたりまえですが・・・・・・。こういった数百万人規模が死亡したとされる疫病の蔓延は、当然社会不安を引き起こします。病気の原因が神の怒りだとする人々からすると、神の怒りをなだめられない皇帝は皇帝の資格がないわけで、皇帝に対する不信感にもつながるでしょう。皇帝が神格化されていればなおさらです。 |
致死性の疫病の蔓延が宗教不信や政治不信を招き、それが社会体制の崩壊につながったという事例も(ローマ帝国がそうだとは言いませんが)いろいろあったのではないでしょうか。
全く不明の原因で人がバタバタと倒れていく。それは神に対立する悪魔のしわざとしか思えない(例えば)。そういった感覚で過去の歴史の動きをみる必要があると思います。我々にとってあたりまえの「病気に対する知識」は近代医学がもたらしたものがほとんどで、それは高々100年程度の歴史しかないのです。
前回、およびその前の No.73「ニュートンと錬金術」で何回か強調したように、我々は無意識に現代人の感覚で過去の歴史を見てしまいがちです。そのことには十分注意すべきだと思います。
No.74 - 現代感覚で過去を見る落とし穴 [歴史]
前回のNo.73「ニュートンと錬金術」で書いたように「大坂夏の陣図屏風・左隻」と「ニュートンの錬金術研究」の教訓は、
という至極当然のことであり、往々にして我々はそのことを忘れがちだということです。
という視点で考えると、いろいろのことが思い浮かびます。それを2点だけ書いてみたいと思います。一つは古代文明の巨大遺跡に関するものです。
古代文明の巨大遺跡
ペルーに「ナスカの地上絵」と呼ばれる有名な世界遺産があります。そもそも、地上からは全体像が分からない「絵」を、いったい何のために作ったのか。
「絵」が作られた当時に空を飛ぶ何らかの装置があったとか、宇宙人へのメッセージだとかの説がありました。ほとんどオカルトに近いような空想ですが、このような説が出てくる背景を推測してみると、次のようだと思います。
というわけです。
間違ってるのは②ですね。正しくは「昔の人は、自分たちでは全体像を把握できない絵を、多大な労力をかけて、喜んで作ることもありうる」でしょう。それは神に対する感謝のためでもいいし、太陽神への恭順のしるしであってもよい(これらはあくまで例です)。べつに不思議はないと思います。人間の思考様式を現代を基準に考えてはいけないのです。
「ピラミッドの謎」というのも、何だか怪しい議論だと思います。つまり、エジプトの巨大ピラミッドは何のために建造されたのかという「謎」です。たとえばギザの大ピラミッド(クフ王のピラミッド。B.C.2500頃)は「クフ王の墓」と言われていますが、いやそうではないという説がある。天体の観測装置からはじまって、幾多の説があります。
しかし単純に「王の墳墓」では、なぜまずいのでしょうか。天体の観測装置というような説を唱える人は、おそらく「たった一人の王のために、何十年もかけて(一説には何百年もかけて)、何十万人もを動員して、巨大な墓を作る」という行為が納得できないのでしょう。それは「現代人なら、絶対にそんなことはしない」からです。
しかし4500年前の古代エジプトの人々の考えは現代人とは全く異なるはずです。人々は喜んで王のための墓作りに邁進したかもしれない。奴隷が強制されて作ったわけではなく、庶民がつらい労働に耐え、意欲的に取り組んだかも知れない。もちろん建設の背景には、ナイル河沿岸の農業を中心とする古代エジプトの巨大な経済力があることは容易に推測できます。それが、建設を可能にした一番の理由です。しかし建設の目的が「一人の王の墓のため」であっても何ら不思議はないと思うのです。
海上交通が人々を結び、交易を促す
「現代人の感覚で過去を眺めてはいけない」の2つ目は、交通の発達に関することです。現代人が暗黙に考えるイメージは
海は人の交流を困難にし、陸は容易にする
という感じではないでしょうか。陸・海・空の交通手段を考えると、容易さの面では
空 > 陸 > 海
の順だと暗黙に考えている。このうち、空路は20世紀になってからのものであることは誰もが知っています。従って昔からある交通手段だけをとると
陸 > 海
だと(暗黙に)考えています。
しかし、鉄道もクルマもなく道路も整備されていない時代には、海上交通の方がコスト、移動・運送の労力、所用時間の面で圧倒的に有利だったはずです。特に長距離の移動はそうです。その例を2つあげます。
司馬遼太郎の『坂の上の雲』において、主人公(の一人)の秋山真之は明治16年に松山の中学を中退して上京します。その上京の交通手段は船であり、彼は松山の三津浜港から出航します。
あたりまえですが「鉄道馬車」がない時代は、少なくとも一般庶民は「船」が長距離移動の唯一の選択肢であるわけです。それがたとえ豚小屋であったとしても、です。秋山真之も、松山→神戸→横浜と船で上京しました。そして馬車とは全く違って陸上を「かるがると走ってゆく」鉄道を見て驚愕したわけです。
江戸時代に参勤交代で街道を行くのは大名の話です。多大な出費が必要であり、それが幕府の狙いでもあった。近畿以西の大名は、船をチャーターして、家来と使用人とともに江戸に直行すれば随分と経費削減になったはずだと思いますが、それは許されないのです。
秋山真之が上京する約35年前の1850年頃、アメリカではゴールドラッシュが起きました。アメリカの東部からもカリフォルニアへと人が移動したのです。
ある大学教授の講演を聞いたことがあります。講演のテーマと内容は忘れてしまいました。しかしその講演の中で一つだけ覚えているのは、ゴールドラッシュの時代に東海岸のボストンで作られたポスターです。それは今で言う「旅行代理店」がカリフォルニアへのツアー(ないしは移住)を勧誘するもので、その移動手段はクリッパーと呼ばれるスピード重視の帆船なのです。そのポスターには帆船の絵が描いてありました。
ボストンからアメリカ西海岸まで、帆船でどうやって行くのか。ゴールドラッシュの時代にパナマ運河はありません(パナマ運河の開通は1914年)。金の採掘で大金持ちになる夢をみる人々を乗せたクリッパーは、アメリカ東海岸を南下し、カリブ海を渡り、南アメリカ東海岸を南下します。そして大陸最南端のホーン岬を回って太平洋へ出て、再び南アメリカ西岸を北上し、メキシコ沿岸へ、そしてカリフォルニアへと向かうのです。
アメリカ大陸横断鉄道が開通したのは1869年であり、ゴールドラッシュ当時に鉄道はつながっていません。もちろん馬車でアメリカ大陸を横断することは可能ですが、何ヶ月もかかります。陸路で大陸を横断するよりも、ホーン岬経由の海路の方がコスト(期間・労力・運賃)が安いのです。
No.20「鯨と人間(1)」で書いたように、ボストンを出航してホーン岬経由で太平洋に出るルートは、まさに19世紀前半にボストン地方(ナンタケット島)で盛んになった太平洋捕鯨のルートでした。そうして太平洋に出た捕鯨船が日本近海にウジャウジャいたのだから、金鉱発見の夢を抱く人々をクリッパーでアメリカ西海岸に運ぶのは、たやすいことだったのでしょう。
造船技術と操船技術があれば(そして、近代までは木があれば)、海は人々をつなげるものである・・・・・・。海上交通が重要な傾向は、時代を遡るほど強いはずです。
明治時代以前の都であった京都は、海路(+ 淀川水系)で北海道とつながっていました。湯豆腐も千枚漬けも北海道から運ばれた昆布がないとあり得ない料理・食材です。この北海道とつながる海路とは言うまでもなく北前船のルートであり、大坂から瀬戸内海を西進し、関門海峡を経由して日本海を東進・北上し、蝦夷に至るルート(とその逆)です。もちろん京都だけでなく日本全国に(沖縄まで)昆布文化が広まったのは海上交通のおかげですね。江戸時代は街道(東海道五十三次など)ばかりが有名ですが、水上交通も非常に重要だったはずです。街道ばかりが有名なのは、浮世絵や旅行記や名所案内が街道に沿って作られたからだと推測されます。それはそうですね。船から見た様子を浮世絵にしても売れないだろうし、「豚小屋」に入れられて船酔いでうなっていたというような旅行記も読む気がしません。海の上には絵にすべきものもないし、書くべきこともないのです。
飛鳥時代の北九州に視点を置くと、北九州から朝鮮半島南岸に行くのと、大和朝廷があった河内・飛鳥地方に行くのと、どちらが容易だったかと言うと、似たようなものでしょう。瀬戸内海の方が航海は容易でしょうが、距離としては対馬海峡を渡った朝鮮の方が断然近いわけです。仮に「近畿以西の本州、九州北部、朝鮮半島南部が一つの国だった」としたとしても、人・物資・情報・文化の交流面だけから言うと、おかしくはないわけです。
南太平洋に点在する島には「ポリネシア人」と総称される人たちが居住しています。人類史ではこれらの人々は、今のインドシナ半島やジャワ島のあたりから、徐々に太平洋の島々への拡散していったようです。島から島へと船で渡っていくのはそんなに難しいことではない。島が見えていれば目的地は分かるし、見えていなくても雲の様子を観察するとどこに島があるかが判別できる。昔、南太平洋には大きな大陸があった(それが沈んで島が残った)というような説があり(ほとんど空想ですが)、その証拠として広範囲に点在する島々に類似の文化があることが理由とされました。しかし海路を行けば文化は容易に島々へと伝達するのですね。海こそが人々を結ぶのです。
No.24 - No.27で塩野七生さんの『ローマ人の物語』の感想を書きましたが、ローマ帝国がなぜ繁栄したかというと、地中海のまわりをぐるりと一つの帝国にし、地中海の制海権を完全に掌握したからだと考えられます。ローマ帝国の交通路というと「ローマ街道」だけが脚光をあびて、そのインフラ整備がいかに進んでいたかばかり強調されますが、ローマ街道以上に重要だったのは海上交通(+ 河川の交通)のはずで、港湾の整備や造船技術の育成にローマ帝国は注力したはずです。
海(ないしは大きな河川)は人々をつなぐが、陸は人々を分断しかねない、という視点で昔をながめると、見えてくることが多いと思います。日本は周囲が全部海で、海岸線は非常に長いわけです。しかしすべての海岸が良港になるわけではありません。船が接岸しやすく港を作りやすいポイントがある。そのような地点に港が作られると、日本列島から朝鮮半島、サハリン、沖縄から台湾へと海路のネットワークができあがる。日本史はこの視点で見ることが大切だと思います。
暗黙に現代の感覚で過去を見てはならないのです。
| 現代人が「あたりまえ」か「常識」と思うことが、過去ではそうではない |
という至極当然のことであり、往々にして我々はそのことを忘れがちだということです。
| ◆ | 過去の人間の意識や文化、技術は現代とは相違する(ことが多い)。 | |
| ◆ | (暗黙に)現代人の感覚で過去を眺めて判断してはいけない |
という視点で考えると、いろいろのことが思い浮かびます。それを2点だけ書いてみたいと思います。一つは古代文明の巨大遺跡に関するものです。
古代文明の巨大遺跡

| |||
| (site : ペルー政府観光局) | |||
「絵」が作られた当時に空を飛ぶ何らかの装置があったとか、宇宙人へのメッセージだとかの説がありました。ほとんどオカルトに近いような空想ですが、このような説が出てくる背景を推測してみると、次のようだと思います。
| ① | 現代人なら、自分たちでは全体像を把握できない絵を、多大な労力をかけて作ったりはしない(これは正しい)。 | |
| ② | ペルーの「ナスカの地上絵」の時代(B.C.2世紀~A.D.6世紀)の人も、現代人と同じ考えだろうと(無意識の内に)思ってしまう。 | |
| ③ | 従って、何らかの手段で地上絵の全体像を見る手段が当時にあったのだろう、と推測する。 |
というわけです。
間違ってるのは②ですね。正しくは「昔の人は、自分たちでは全体像を把握できない絵を、多大な労力をかけて、喜んで作ることもありうる」でしょう。それは神に対する感謝のためでもいいし、太陽神への恭順のしるしであってもよい(これらはあくまで例です)。べつに不思議はないと思います。人間の思考様式を現代を基準に考えてはいけないのです。
「ピラミッドの謎」というのも、何だか怪しい議論だと思います。つまり、エジプトの巨大ピラミッドは何のために建造されたのかという「謎」です。たとえばギザの大ピラミッド(クフ王のピラミッド。B.C.2500頃)は「クフ王の墓」と言われていますが、いやそうではないという説がある。天体の観測装置からはじまって、幾多の説があります。
しかし単純に「王の墳墓」では、なぜまずいのでしょうか。天体の観測装置というような説を唱える人は、おそらく「たった一人の王のために、何十年もかけて(一説には何百年もかけて)、何十万人もを動員して、巨大な墓を作る」という行為が納得できないのでしょう。それは「現代人なら、絶対にそんなことはしない」からです。
しかし4500年前の古代エジプトの人々の考えは現代人とは全く異なるはずです。人々は喜んで王のための墓作りに邁進したかもしれない。奴隷が強制されて作ったわけではなく、庶民がつらい労働に耐え、意欲的に取り組んだかも知れない。もちろん建設の背景には、ナイル河沿岸の農業を中心とする古代エジプトの巨大な経済力があることは容易に推測できます。それが、建設を可能にした一番の理由です。しかし建設の目的が「一人の王の墓のため」であっても何ら不思議はないと思うのです。

| |||
| (site : エジプト大使館・観光局) | |||
海上交通が人々を結び、交易を促す
「現代人の感覚で過去を眺めてはいけない」の2つ目は、交通の発達に関することです。現代人が暗黙に考えるイメージは
海は人の交流を困難にし、陸は容易にする
という感じではないでしょうか。陸・海・空の交通手段を考えると、容易さの面では
空 > 陸 > 海
の順だと暗黙に考えている。このうち、空路は20世紀になってからのものであることは誰もが知っています。従って昔からある交通手段だけをとると
陸 > 海
だと(暗黙に)考えています。
しかし、鉄道もクルマもなく道路も整備されていない時代には、海上交通の方がコスト、移動・運送の労力、所用時間の面で圧倒的に有利だったはずです。特に長距離の移動はそうです。その例を2つあげます。
| 松山から横浜へ |
司馬遼太郎の『坂の上の雲』において、主人公(の一人)の秋山真之は明治16年に松山の中学を中退して上京します。その上京の交通手段は船であり、彼は松山の三津浜港から出航します。
|
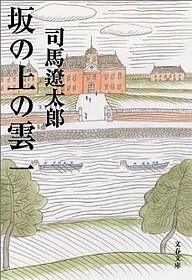
| |||
江戸時代に参勤交代で街道を行くのは大名の話です。多大な出費が必要であり、それが幕府の狙いでもあった。近畿以西の大名は、船をチャーターして、家来と使用人とともに江戸に直行すれば随分と経費削減になったはずだと思いますが、それは許されないのです。
| ボストンからカリフォルニアへ |
秋山真之が上京する約35年前の1850年頃、アメリカではゴールドラッシュが起きました。アメリカの東部からもカリフォルニアへと人が移動したのです。

| |||
|
代表的なクリッパー船、
カティー・サーク(英国)
(1880年代の写真)
(site:www.rmg.co.uk/cuttysark/)
| |||
ボストンからアメリカ西海岸まで、帆船でどうやって行くのか。ゴールドラッシュの時代にパナマ運河はありません(パナマ運河の開通は1914年)。金の採掘で大金持ちになる夢をみる人々を乗せたクリッパーは、アメリカ東海岸を南下し、カリブ海を渡り、南アメリカ東海岸を南下します。そして大陸最南端のホーン岬を回って太平洋へ出て、再び南アメリカ西岸を北上し、メキシコ沿岸へ、そしてカリフォルニアへと向かうのです。
アメリカ大陸横断鉄道が開通したのは1869年であり、ゴールドラッシュ当時に鉄道はつながっていません。もちろん馬車でアメリカ大陸を横断することは可能ですが、何ヶ月もかかります。陸路で大陸を横断するよりも、ホーン岬経由の海路の方がコスト(期間・労力・運賃)が安いのです。
No.20「鯨と人間(1)」で書いたように、ボストンを出航してホーン岬経由で太平洋に出るルートは、まさに19世紀前半にボストン地方(ナンタケット島)で盛んになった太平洋捕鯨のルートでした。そうして太平洋に出た捕鯨船が日本近海にウジャウジャいたのだから、金鉱発見の夢を抱く人々をクリッパーでアメリカ西海岸に運ぶのは、たやすいことだったのでしょう。
造船技術と操船技術があれば(そして、近代までは木があれば)、海は人々をつなげるものである・・・・・・。海上交通が重要な傾向は、時代を遡るほど強いはずです。
明治時代以前の都であった京都は、海路(+ 淀川水系)で北海道とつながっていました。湯豆腐も千枚漬けも北海道から運ばれた昆布がないとあり得ない料理・食材です。この北海道とつながる海路とは言うまでもなく北前船のルートであり、大坂から瀬戸内海を西進し、関門海峡を経由して日本海を東進・北上し、蝦夷に至るルート(とその逆)です。もちろん京都だけでなく日本全国に(沖縄まで)昆布文化が広まったのは海上交通のおかげですね。江戸時代は街道(東海道五十三次など)ばかりが有名ですが、水上交通も非常に重要だったはずです。街道ばかりが有名なのは、浮世絵や旅行記や名所案内が街道に沿って作られたからだと推測されます。それはそうですね。船から見た様子を浮世絵にしても売れないだろうし、「豚小屋」に入れられて船酔いでうなっていたというような旅行記も読む気がしません。海の上には絵にすべきものもないし、書くべきこともないのです。
飛鳥時代の北九州に視点を置くと、北九州から朝鮮半島南岸に行くのと、大和朝廷があった河内・飛鳥地方に行くのと、どちらが容易だったかと言うと、似たようなものでしょう。瀬戸内海の方が航海は容易でしょうが、距離としては対馬海峡を渡った朝鮮の方が断然近いわけです。仮に「近畿以西の本州、九州北部、朝鮮半島南部が一つの国だった」としたとしても、人・物資・情報・文化の交流面だけから言うと、おかしくはないわけです。
南太平洋に点在する島には「ポリネシア人」と総称される人たちが居住しています。人類史ではこれらの人々は、今のインドシナ半島やジャワ島のあたりから、徐々に太平洋の島々への拡散していったようです。島から島へと船で渡っていくのはそんなに難しいことではない。島が見えていれば目的地は分かるし、見えていなくても雲の様子を観察するとどこに島があるかが判別できる。昔、南太平洋には大きな大陸があった(それが沈んで島が残った)というような説があり(ほとんど空想ですが)、その証拠として広範囲に点在する島々に類似の文化があることが理由とされました。しかし海路を行けば文化は容易に島々へと伝達するのですね。海こそが人々を結ぶのです。
No.24 - No.27で塩野七生さんの『ローマ人の物語』の感想を書きましたが、ローマ帝国がなぜ繁栄したかというと、地中海のまわりをぐるりと一つの帝国にし、地中海の制海権を完全に掌握したからだと考えられます。ローマ帝国の交通路というと「ローマ街道」だけが脚光をあびて、そのインフラ整備がいかに進んでいたかばかり強調されますが、ローマ街道以上に重要だったのは海上交通(+ 河川の交通)のはずで、港湾の整備や造船技術の育成にローマ帝国は注力したはずです。
海(ないしは大きな河川)は人々をつなぐが、陸は人々を分断しかねない、という視点で昔をながめると、見えてくることが多いと思います。日本は周囲が全部海で、海岸線は非常に長いわけです。しかしすべての海岸が良港になるわけではありません。船が接岸しやすく港を作りやすいポイントがある。そのような地点に港が作られると、日本列島から朝鮮半島、サハリン、沖縄から台湾へと海路のネットワークができあがる。日本史はこの視点で見ることが大切だと思います。
暗黙に現代の感覚で過去を見てはならないのです。
No.73 - ニュートンと錬金術 [歴史]
「大坂夏の陣図屏風」についての誤解
No.34「大坂夏の陣図屏風」で、この屏風の左隻に描かれているシーンについて以下の主旨のことを書きました。
| ◆ |
大坂夏の陣図屏風・左隻には徳川方の武士・雑兵が、逃げまどう非戦闘員に対し暴力行為・略奪・誘拐(これらを「濫妨狼藉」という)をする姿が描かれている。 | |
| ◆ |
しかしこの屏風について「市民が戦争に巻き込まれた悲惨な姿を描き戦争を告発した、ないしは徳川方の悪行を告発した」というような見方は当たらない。 | |
| ◆ |
戦国時代の戦場において濫妨狼藉は日常的に行われていた(藤本久志『雑兵たちの戦場』。No.33「日本史と奴隷狩り」参照)。それはむしろ戦勝側の権利でさえあった。大坂夏の陣図屏風は徳川方の戦勝記念画であり、その左隻は「戦果」を描いたものと考えるのが自然である。 | |
| ◆ |
大坂夏の陣図屏風・左隻を「戦国のゲル二カ」と称したNHKの番組があったが、ピカソの「ゲル二カ」とは意味が全く違う。「ゲルニカ」は無差別爆撃を行った当時のファシスト軍を告発したものだが、大坂夏の陣図屏風・左隻は徳川方を告発したものではないし、豊臣家への挽歌でもない。 | |
| ◆ | もし現代人が「一般市民が戦争に巻き込まれた悲惨な姿」を描いたのなら、それは「戦争を告発」したものであることは確実である。しかしそういう現代の視点で過去を見ると落とし穴にはまり、誤解してしまう。 |

|

|
| 大坂夏の陣図屏風・左隻。第3扇(部分。左)と第5扇(部分。右) | |
過去の文化・技術・人々の意識は、現代のそれとは違います。それは十分に分かっているはずだけれど、ついつい我々は暗黙に現代と同じような仮定を置いて過去の歴史を観察してしまい、誤解してしまうのです。
この「現代感覚で過去を見る落とし穴」について、一つの素材があります。No.41「ふしぎなキリスト教(1)」で書いた、アイザック・ニュートン(1642-1724)の業績です。ニュートンの「業績」は
| ① | 物理学・数学 | |
| ② | 錬金術 | |
| ③ | 聖書研究(聖書の「科学的」解読) |
の3つだと書きました。その「錬金術」について詳しくみたいと思います。
ニュートンの錬金術研究
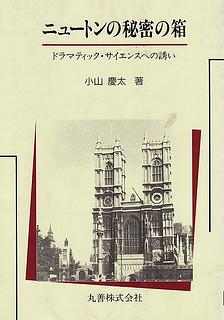
| |||
| 小山慶太「ニュートンの秘密の箱」 | |||
この本の内容をもとに、ニュートンの生涯と、彼の錬金術研究が世に出るまでのいきさつを要約すると以下の通りです。
| ◆ |
アイザック・ニュートンは、1642年、イングランド北東部のウールスソープ村で生まれた。 | |
| ◆ |
1661年、ケンブリッジ大学のトリニティ・カレッジに入学。ケプラー、ガリレオ、デカルトなどの著作に親しむ。 但し入学当時は神学、古典学、哲学などが主流であり、自然科学系の講座はなかった。最初の自然科学系講座(=ルーカス講座)が設けられたのは1663年である。従ってニュートンの自然科学系の学問の修得は独学であった。 | |
| ◆ |
1665年、ペストの流行のため大学は一時閉鎖され、ニュートンは郷里のウールスソープ村に1年半帰省する。この間に、万有引力の法則、運動の法則、光学、微積分、二項定理などの研究を行う。 | |
| ◆ |
1669年、弱冠26歳でルーカス講座の二代目の教授に就任。教授になって最初に選んだ講義のテーマは「光学」であった。このときの講義録は後に『光学』(1704)としてまとめられた。 | |
| ◆ |
1687年に『自然哲学の数学的原理(プリンキピア)』を刊行し、古典力学の基礎を築く。 | |
| ◆ |
ルーカス講座教授に就任した直後から錬金術への関心を高める。錬金術の書物を買い集め、自ら実験も行う。トリニティ・カレッジの礼拝堂の庭にあった小屋を実験室にし、そこにこもる時間が多くなっていく。錬金術の研究に注力していた時期と『プリンキピア』を執筆していた時期は重なる。錬金術の研究の結果は夥しい量の手稿となって残された。 | |
| ◆ |
1696年、ニュートンは造幣局監事となり、ロンドンに転出した。そして赴任するときに錬金術の手稿を「箱」にしまい込んで持参した。その後ニュートンは、1702年に造幣局長官になる。また1703年からは王立協会(Royal Society。1660年設立)の会長にも就任して英国の科学者を統括する立場になり、1727年に84歳で亡くなるまでその地位にあった。 | |
| ◆ |
生涯独身であったニュートンは、身の回りの世話のため姪のキャサリン・バートンをロンドンに呼び寄せた。キャサリンは1717年にジョン・コンデュイットと結婚し、夫婦でニュートンと10年間同居して、ニュートンの最後を看取った。 | |
| ◆ |
ニュートンの「箱」は遺産としてコンデュイット家に渡った。コンデュイット家には一人娘があり、その娘がポーツマス伯爵と結婚したため「箱」はポーツマス伯爵家の所有となった。 | |
| ◆ | ポーツマス伯爵家に代々伝えられたきたニュートンの「箱」は、1936年にロンドンのサザビーズで競売にかけられた。このとき、ケンブリッジ大学が生んだ著名な経済学者・ケインズは、ニュートンの手稿が散逸してしまうことを危惧し、約半分を競り落とした。ケインズは後にそれをケンブリッジ大学・キングスカレッジに遺贈した。 |
経済学者・ケインズの一文
以上がアイザック・ニュートンの生涯と、その錬金術研究の手稿が経済学者・ケインズの手に渡るまでの概略です。「箱」の中身を検討したケインズは、以下のような一文をしるしました。それは1946年にケンブリッジ大学・トリニティ・カレッジで行われた「ニュートン生誕300年祭」(1942年が生誕300年だが、戦争で延期)で披露されました。
|
我々がニュートンを見るとき、どうしても「近代科学の父」の側面だけを見ようとします。現代の視点で300年前を振り返って見ると、ニュートンの物理学や数学の業績ばかりに光が当たって見える。もちろん科学の分野での偉大さは言を待たないのですが、もう一方で錬金術研究も事実なのです。その面も見ないとニュートンの本当の偉大さはわからない。ケインズの言いたかったことはそういうことでしょう。
現代感覚で過去を見る落とし穴
しかし上の文章で感じるのは、ケインズもまた現代人の感覚で過去を見ているということです。それはニュートンを「理性の時代」と対比する言い方で「最後の魔術師」と表現している点です。
魔術師とは「超常現象を起こす人」「超自然現象が起こったというイルージョンを与える人」を指して言う表現です。確かに現代人の科学知識からすると、錬金術の成功(純金を作るという意味での錬金術の成功)はありえません。それは「超自然現象」であり、成功した話があるとしたらファンタジー小説の中だけです。
しかしニュートンの当時は、錬金術は「まじめな」研究の一つでした。それどころか錬金術は(密かに)成功していると考えられていたようです。ニュートンがケンブリッジ大学のルーカス講座の教授だった1688年のことですが、イギリスのウィリアム3世は「錬金術で得られた金銀はロンドン塔にある造幣局に持ってくれば、いっさいの詰問はせずに市価で買い上げる」と宣言したといいます(山本茂・九州女子大学教授『つい他人に話したくなる歴史のホント 250』光文社 2002 による)。
もちろん、錬金術に成功したからといって造幣局に持って行くようなバカな錬金術師はいません。拘束されて厳しく「詰問」されることが火を見るより明らかだからです。錬金術に成功した人やそのスポンサーになった貴族などは、そんなバカなことはしない。あくまで錬金術の成功を極秘にし、作った純金を小出しに売りさばきつつ、大金持ちになるストーリーを描く・・・・・・と、誰しもこう想像するのですね。「錬金術は密かに成功している」と当時の人々が考えたとしても、それには理由があるのです。
あくまで空想ですが、ひょっとしたらニュートンが造幣局監事として赴任したのは、錬金術研究を見込まれたからかもしれません。古代から中世まで「錬金術禁止令」を出した国は多くあり、英国もその一つです。「錬金術に対抗して通貨の安定を保つためには、錬金術に長けた人材が造幣局に必要」と英国政府が考えたとしてもおかしくはありません。毒をもって毒を制する、というわけです。あるいは、そもそもニュートンが錬金術の研究を始めたのは、気鋭の学者を見込んだ英国造幣局からの極秘の依頼だった・・・・・・。空想するだけなら、いろいろ可能です。
脱線しましたが、ともかく錬金術は古代エジプトの時代から綿々とあり、化学や技術の発達を促したことは数々の歴史的事実があります。錬金術を広くとらえて
| ① | 卑金属から純金を作り出す(狭義の錬金術) | |
| ② | 金を増量する(合金など) | |
| ③ | 金メッキをする |
の3つと考えると、②③は可能であり(純金だと騙せるかどうかはともかく)、それが技術の発達を促したのは理解できます。確か英語の「化学・chemistry」の語源はアラビア語の「錬金術」だったはずです。
No.18「ブルーの世界」で書いたように、ニュートンが生きた同時代のヨーロッパで、プルシアン・ブルー(顔料)を作り出したり(ベルリン。1704)、マイセンでヨーロッパ産の磁器を作り出した(1709)のは錬金術師と呼ばれた人たちでした。中国や日本からヨーロッパに輸入された白磁は、同じ重さの金より高価だったと言います。まさに形をかえた「錬金術」です。
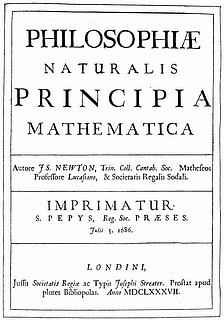
| |||
|
アイザック・ニュートン 『自然哲学の数学的諸原理』 (プリンキピア。1687) 「ニュートンの秘密の箱」より | |||
そしてニュートンの偉大さは、一方で錬金術のように古代から続く伝統的な研究をやる一方で、ほとんど独学により古典力学や、そのベースとなる微積分学などの理論を打ち立て、近代科学を切り開いたことです。No.41「ふしぎなキリスト教(1)」で書いたように、ニュートンは聖書研究もやっています。伝統にどっぷりと片足をつっこみながら、もう一方の足で前人未踏の新しい領域に踏み出し革新を遂げる。ここが並の学者と全く違うことろです。
現代感覚で過去を見てニュートンの錬金術研究を無視したり、逆にニュートンを「最後の魔術師」と見ることは、ニュートンの真の偉大さを理解しそこねると思います。
No.34 - 大坂夏の陣図屏風 [歴史]
前回の、No.33「日本史と奴隷狩り」で、藤本久志 著『新版 雑兵たちの戦場』に添って戦国時代の「濫妨狼藉(らんぼうろうぜき)」の実態を紹介したのですが、この本の表紙は「大坂夏の陣図屏風」の左隻(させき)の一部でした。今回はこの屏風についてです。
大坂夏の陣図屏風・左隻
「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵)は六曲一双の屏風です。これは黒田長政が徳川方の武将として大坂夏の陣(1615)に参戦したあと、その戦勝を記念して作らせたものです。現存する黒田家文書によると、長政自身が存命中に自ら作成を指示したとされています。
黒田長政は黒田官兵衛の長男として播磨・姫路城で生まれ、秀吉に仕えた戦国武将でした。秀吉の死後、関ヶ原の合戦(1600)では東軍として戦い、東軍勝利の立役者の一人となります。その功績で筑前・福岡藩50万石の藩主になりました。
「大坂夏の陣図屏風」の右隻の六曲には、徳川軍と豊臣軍の戦闘場面が描かれています。そして左隻には大坂城から淀川方面へ逃げる敗残兵や民衆、それを追いかけたり待ち受けたりする徳川方の武士・雑兵が描かれています。この左隻の中に『雑兵たちの戦場』の表紙になった「濫妨狼藉の現場」が描かれているのです。その左隻の第1扇から第6扇までを以下に掲げます。
一見してわかるようにものすごい人の数です。六曲一双で5071人と言いますから、左隻は2千人程度でしょうか。数えたわけではないのですが、とにかくおびただしい人の数であることは間違いありません。以下は、その左隻の人物群の中から「濫妨狼藉の現場」を中心に、ごく一部を紹介します。
戦国のゲルニカ ?
以前、NHK総合で「その時、歴史は動いた」という番組がありました。そこで「大坂夏の陣図屏風・左隻」が「戦国のゲルニカ」という番組タイトルのもとに紹介されたことがあります(2008年6月25日)。
NHKといえども、番組視聴率をあげるためには視聴者の「気を引く」タイトルを付けたいわけです。日本の「戦国」と「ゲルニカ」という異色の組み合わせは、確かに「気を引く」タイトルであることは確かです。もちろん「ゲルニカ」とはピカソの有名な絵を指しています。しかしこういったタイトルは、視聴者を誤ったものの見方に導くものでもあると思うのです。
確かに「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風・左隻」には共通点があります。それは「戦争に一般市民が巻き込まれ、多数の死傷者が出た状況を念頭に描かれた絵」という共通点です。しかし、共通点はこの1点でしかありません。あとの点は全然違っている。

「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」の相違点(1)
まず相違点の第1点は「ゲルニカ」は、当時としては「あまりなかった状況」を描いた絵だということです。1936年からのスペイン内戦(スペイン市民戦争)は、スペイン共和国軍と、共和国を転覆させようとするフランコ反乱軍の戦いです。そのフランコ軍を支援していたのがドイツでした。1937年4月26日、ドイツ空軍は共和国軍の支配地域であるスペイン北部・バスク地方の小都市、ゲルニカ(人口、7000人程度)を無差別爆撃します。無差別爆撃とは、軍事目標であろうとなかろうと、とにかくその地域全体の壊滅をねらった爆撃です。従って、多数の一般市民に死傷者が出ますが、それは「折り込み済み」の作戦なのです。ゲルニカでは事前のドイツ軍の警告もなかったとこともあり、数百人の死者がでました。
ゲルニカという小さな都市にどれほどの軍事的意味があったのか、意見は分かれるところだと思います。こういった「市民戦争」では補給基地も全国的に散らばるので、軍事的意味がない都市はないと思います。ゲルニカも共和国軍の拠点の一つではあったようです。しかしゲルニカの近くには、スペイン北部の工業都市であるビルバオ(当時、共和国側)があります。軍事目標を攻撃するならこちらの方がよほど「価値」が高いものがある。ゲルニカを狙ったのは多数の死者を出し、共和国軍にドイツに支援されたフランコ軍の「脅威」を示すものだったと考えられます。
もちろん軍事目標を狙った爆撃で一般人が「巻き添え」になることは、それ以前にもありました。しかし一般人の殺傷が「折り込み済み」である都市の無差別爆撃という手法は、当時の世界の戦争行為としては決して一般的なものではありませんでした。だからこそ、フランコ軍・ドイツ軍は世界中から非難を受けたわけです。
この「ゲルニカ無差別爆撃」に怒りを感じてピカソが描いたのがゲルニカ(1937)です。この絵は今、マドリードのソフィア王妃芸術センターにあり、スペインの宝となっています。
一方、「大坂夏の陣図屏風・左隻」はどうでしょうか。そこには逃げまどう避難民とともに、雑兵たちの「濫妨狼藉」が描かれています。そして戦争時における農民や町民に対する濫妨狼藉(人と物の略奪、暴力行為)は、前回の No.33「日本史と奴隷狩り」で紹介したように、日本の戦国時代において「しばしば」行われていました。大坂夏の陣の終了後、蜂須賀軍は「奴隷狩り」の戦果を177人と徳川幕府に報告しています(No.33 参照)。この報告の目的は「蜂須賀軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張するものでした。屏風の注文主である黒田長政も秀吉に仕え、朝鮮出兵にも参加して朝鮮半島各地を転戦しています。No.33 で紹介したように、そこでも数々の濫妨狼藉があったわけです。
もちろん、大坂夏の陣が一般の戦国時代の戦争と違った面もあります。それは大坂城およびその周辺という「市街地 = 人口密集地域」で戦争が行われたということです。従って濫妨狼藉の被害も通常の戦国時代の戦闘よりは大きかった。これは確かだと思います。しかし濫妨狼藉そのものは日本全国で、また朝鮮半島で、戦争時には当然のように行われていたことも事実なのです。それは『雑兵たちの戦場』で詳述されている通りです。
ゲルニカの無差別爆撃は、当時としては「それまでになかった状況」、大坂夏の陣における濫妨狼藉は、当時として「それまでにもよくあった状況」です。ここがまず違います。ゲルニカは最初の無差別爆撃、大坂夏の陣は最後の濫妨狼藉なのです。
「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」の相違点(2)
「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」のもう一つの相違点は、絵の描き手(注文主)です。いうまでもなく「ゲルニカ」を描いたのはピカソという画家であり、一市民です。ゲルニカ市民およびスペイン共和国軍という、ゲルニカで被害をうけた側の立場に立った画家です。
それに比較して「大坂夏の陣図屏風」を画家に描かせたのは、黒田長政という大坂夏の陣で勝利した側の大名です。勝利者が自分の功績、ないしは徳川方の戦績を記録するために描かせたものが「大坂夏の陣図屏風」なのです。そこが決定的に違います。
現代人の感覚で歴史を見る落とし穴
「大坂夏の陣図屏風」を評して
というような意見があります。この屏風を「戦国のゲルニカ」だとする表現は、このような見方からきています。しかし、はたしてそうなのでしょうか。また、絵を引用した『戦国合戦絵屏風集成 第4巻』の解説には、
と書かれています。こんなことを言ってしまってよいのでしょうか。
最低限、推定できるのは、
ということです。なぜそう言えるのかと言うと、
だからです。そして
のです。もし仮にそんなものを注文して作らせ、それが噂になって、その噂が徳川幕府の耳に入ればどうなるか。理由は何とでもつけられます。謹慎ぐらいならまだましで、悪くすると長政は切腹、黒田家は取り潰しではないでしょうか。そんなリスクを福岡藩のトップがおかすはずはない。長政のように紆余曲折を経ながら戦国の世を生き抜き、徳川体制の藩主にまで上り詰めた人間というのは、余計なリスクを負わない「したたかさ」があって当然なのです。
父親の黒田官兵衛もそうですが、長政はキリシタン大名ですね。しかし長政は、秀吉が「バテレン追放令」(No.33「日本史と奴隷狩り」 参照)を出すとキリスト教を棄教し、徳川時代にはキリスト教徒を厳しく弾圧します。この程度は、当時を生き抜くための「したたかさ」以前の「分別」のたぐいでしょう。当時のカトリックの教えに従ってせっせと領内の寺院・神社を破壊した高山右近や大村純忠(No.28「マヤ文明の抹殺」)とはわけが違うのです。
黒田長政は豊臣家に恩義がある・・・・・・。これは全くの事実です。そのため家康は、大坂冬の陣では長政の徳川方での参戦を許さなかった。関が原の合戦の東軍勝利の立役者であるにもかかわらず、です。長政は夏の陣でやっと参戦を許され、そして徳川方は勝利し、徳川の世は確固としたものになった。
黒田長政のような立場の人間は、もとから徳川方だった大名以上に、徳川家に対する恭順の「しるし」を表そうとするはずです。大坂夏の陣の時のように・・・・・・。たとえ内心では豊臣家に恩義を感じていたとしても(それはありうる)、ゆめゆめそうは見られないように細心の注意を払って行動したでしょう。
日光東照宮の重要文化財・石鳥居は、石材だけで作られた鳥居では日本最大と言われていますが、この鳥居を寄進したのは黒田長政です。もちろん福岡藩主にまでとりたててもらった家康への恩義からだろうし、徳川幕府への忠誠の証としての石鳥居です。長政が「豊臣家への挽歌を描いた絵」を注文するはずがないと思うのです。
「大坂夏の陣図屏風」の右隻は戦闘場面であり、当然黒田長政が描かれているし、家康も秀忠もいます。右隻は戦勝記念画なのです。そして左隻は、戦勝の結果としての「戦果」を描いています。ここには、大坂城から淀川にいたる戦場が実況中継のように描かれています。この左隻は徳川方にとってポジティブな情景(戦果としての濫妨)か、ないしはニュートラルなものだと思います。少なくとも徳川方にとってネガティブなものではない。
大坂夏の陣図屏風の中心テーマは、
右隻が「武士たちの戦場」
左隻が「雑兵たちの戦場」
だと思います。藤本久志さんの著書『雑兵たちの戦場』の表紙には、本の題名そのものズバリの絵、つまり「大坂夏の陣図屏風・左隻=雑兵たちの戦場」が用いられているのです。
「大坂夏の陣図屏風・左隻」を見て「ゲルニカ」のように考えてしまうのは(ないしは反戦画のように考えてしまうのは)、現代人の感覚で歴史を見る落とし穴にはまっているのだと思います。
怖い絵
要するに「大坂夏の陣図屏風・左隻」は、中野京子さん流に言うと「怖い絵」なのです。No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、中野さんは「ラス・メニーナス」に描かれている小人症の「慰み者」に着目し、
と書いています。この表現をそのまま借用すると、
と言えるでしょう。絵は「見方」によってその意味がガラッと変わることがあります。『大坂夏の陣図屏風・左隻』は、「ゲルニカ」ではなくて「怖い絵」だと思います。
なお、以下の図は『戦国合戦絵屏風集成 第4巻』(中央公論社 1988)から引用しました。また絵の解説も、この本を参考にしています。
大坂夏の陣図屏風・左隻
「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵)は六曲一双の屏風です。これは黒田長政が徳川方の武将として大坂夏の陣(1615)に参戦したあと、その戦勝を記念して作らせたものです。現存する黒田家文書によると、長政自身が存命中に自ら作成を指示したとされています。
黒田長政は黒田官兵衛の長男として播磨・姫路城で生まれ、秀吉に仕えた戦国武将でした。秀吉の死後、関ヶ原の合戦(1600)では東軍として戦い、東軍勝利の立役者の一人となります。その功績で筑前・福岡藩50万石の藩主になりました。
「大坂夏の陣図屏風」の右隻の六曲には、徳川軍と豊臣軍の戦闘場面が描かれています。そして左隻には大坂城から淀川方面へ逃げる敗残兵や民衆、それを追いかけたり待ち受けたりする徳川方の武士・雑兵が描かれています。この左隻の中に『雑兵たちの戦場』の表紙になった「濫妨狼藉の現場」が描かれているのです。その左隻の第1扇から第6扇までを以下に掲げます。

|
大坂夏の陣図屏風・左隻 : 第1扇(右)から第3扇 |

|
大坂夏の陣図屏風・左隻 : 第4扇(右)から第6扇 |
一見してわかるようにものすごい人の数です。六曲一双で5071人と言いますから、左隻は2千人程度でしょうか。数えたわけではないのですが、とにかくおびただしい人の数であることは間違いありません。以下は、その左隻の人物群の中から「濫妨狼藉の現場」を中心に、ごく一部を紹介します。

|
部分図1 : 第1扇の中央より少し上 |
画面の中央、金雲の間の黒っぽい部分は大坂城周辺の川です。避難民は川を渡って逃げますが、画面中央では兵士が避難民の男から荷物を奪おうとしています。男は奪われまいと、男の妻(でしょうか)に荷物を渡そうとしています。 |

|
部分図2 : 部分図1の下方を拡大 |
部分図1の下部の中央を拡大したものです。裸足で逃げる婦女から、兵士が赤い包みを奪おうとしています。 |

|
部分図3 : 第3扇の中央の左方 |
「雑兵たちの戦場」の表紙になった部分です。画面の右上では東軍の兵士が、左手を切り落とされた落武者の首を打とうとしています。落武者の首は「追い首」といってあまり功名にはなりませんが、東軍の功名の中には「追い首」が多く、それどころか町人・農民などの首(にせ首)も少なくなかったと言います。 画面左下では、泣きじゃくる若い娘を東軍の兵士が連れていこうとしています。その右は母親でしょうか、観念した様子で、娘を慰めています。 |

|
部分図4 : 第3扇、部分図3の少し下 |
画面左下方では、荷物を持ち、乳飲み子を抱え、子供を背負った避難民が左方向へ逃げ、そこに兵士が追いすがります。右上では兵士が男を捕まえています。荷物を奪おうとしてるのか、あるいは「にせ首」を狙ったのか。画面右下の鳥居は天満天神を表しています。 |

|
部分図5 : 第5扇の中央より少し下の右方 |
兵士たちが若い娘を取り囲んでいます。乱暴しようとしているのか、あるいは「人取り」か。その両方かもしれません。 |

|
部分図6 : 第6扇の中央より少し上 |
神崎川を渡って北に逃げた避難民を待ち受けるのは、野盗の一団です。太刀や長刀を振りかざして、身ぐるみを剥がし(画面右端)、あるいは荷物を奪い、人を捕らえています。画面中央の上にふんぞり返っている男が、野盗のリーダでしょうか。その前には「戦利品」が積まれています。 「江戸初期の村人にとっても、戦争は魅力ある稼ぎ場であった。慶長十九年(1614)冬、大坂で戦争が始まる、という噂が広まると、都近くの国々から百姓たちがとめどなく戦場の出稼ぎに殺到しはじめていた。」(「新版 雑兵たちの戦場」。No.33「日本史と奴隷狩り」参照)。大坂の陣は野盗・盗賊の「出稼ぎ」の場でもあったようです。 |
戦国のゲルニカ ?
以前、NHK総合で「その時、歴史は動いた」という番組がありました。そこで「大坂夏の陣図屏風・左隻」が「戦国のゲルニカ」という番組タイトルのもとに紹介されたことがあります(2008年6月25日)。
NHKといえども、番組視聴率をあげるためには視聴者の「気を引く」タイトルを付けたいわけです。日本の「戦国」と「ゲルニカ」という異色の組み合わせは、確かに「気を引く」タイトルであることは確かです。もちろん「ゲルニカ」とはピカソの有名な絵を指しています。しかしこういったタイトルは、視聴者を誤ったものの見方に導くものでもあると思うのです。
確かに「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風・左隻」には共通点があります。それは「戦争に一般市民が巻き込まれ、多数の死傷者が出た状況を念頭に描かれた絵」という共通点です。しかし、共通点はこの1点でしかありません。あとの点は全然違っている。

ピカソ「ゲルニカ」(1937)
(site : ソフィア王妃芸術センター)
(site : ソフィア王妃芸術センター)
「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」の相違点(1)
まず相違点の第1点は「ゲルニカ」は、当時としては「あまりなかった状況」を描いた絵だということです。1936年からのスペイン内戦(スペイン市民戦争)は、スペイン共和国軍と、共和国を転覆させようとするフランコ反乱軍の戦いです。そのフランコ軍を支援していたのがドイツでした。1937年4月26日、ドイツ空軍は共和国軍の支配地域であるスペイン北部・バスク地方の小都市、ゲルニカ(人口、7000人程度)を無差別爆撃します。無差別爆撃とは、軍事目標であろうとなかろうと、とにかくその地域全体の壊滅をねらった爆撃です。従って、多数の一般市民に死傷者が出ますが、それは「折り込み済み」の作戦なのです。ゲルニカでは事前のドイツ軍の警告もなかったとこともあり、数百人の死者がでました。
ゲルニカという小さな都市にどれほどの軍事的意味があったのか、意見は分かれるところだと思います。こういった「市民戦争」では補給基地も全国的に散らばるので、軍事的意味がない都市はないと思います。ゲルニカも共和国軍の拠点の一つではあったようです。しかしゲルニカの近くには、スペイン北部の工業都市であるビルバオ(当時、共和国側)があります。軍事目標を攻撃するならこちらの方がよほど「価値」が高いものがある。ゲルニカを狙ったのは多数の死者を出し、共和国軍にドイツに支援されたフランコ軍の「脅威」を示すものだったと考えられます。
もちろん軍事目標を狙った爆撃で一般人が「巻き添え」になることは、それ以前にもありました。しかし一般人の殺傷が「折り込み済み」である都市の無差別爆撃という手法は、当時の世界の戦争行為としては決して一般的なものではありませんでした。だからこそ、フランコ軍・ドイツ軍は世界中から非難を受けたわけです。
この「ゲルニカ無差別爆撃」に怒りを感じてピカソが描いたのがゲルニカ(1937)です。この絵は今、マドリードのソフィア王妃芸術センターにあり、スペインの宝となっています。
一方、「大坂夏の陣図屏風・左隻」はどうでしょうか。そこには逃げまどう避難民とともに、雑兵たちの「濫妨狼藉」が描かれています。そして戦争時における農民や町民に対する濫妨狼藉(人と物の略奪、暴力行為)は、前回の No.33「日本史と奴隷狩り」で紹介したように、日本の戦国時代において「しばしば」行われていました。大坂夏の陣の終了後、蜂須賀軍は「奴隷狩り」の戦果を177人と徳川幕府に報告しています(No.33 参照)。この報告の目的は「蜂須賀軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張するものでした。屏風の注文主である黒田長政も秀吉に仕え、朝鮮出兵にも参加して朝鮮半島各地を転戦しています。No.33 で紹介したように、そこでも数々の濫妨狼藉があったわけです。
もちろん、大坂夏の陣が一般の戦国時代の戦争と違った面もあります。それは大坂城およびその周辺という「市街地 = 人口密集地域」で戦争が行われたということです。従って濫妨狼藉の被害も通常の戦国時代の戦闘よりは大きかった。これは確かだと思います。しかし濫妨狼藉そのものは日本全国で、また朝鮮半島で、戦争時には当然のように行われていたことも事実なのです。それは『雑兵たちの戦場』で詳述されている通りです。
ゲルニカの無差別爆撃は、当時としては「それまでになかった状況」、大坂夏の陣における濫妨狼藉は、当時として「それまでにもよくあった状況」です。ここがまず違います。ゲルニカは最初の無差別爆撃、大坂夏の陣は最後の濫妨狼藉なのです。
しかし残念なことにゲルニカが先例となった「都市の無差別爆撃(絨毯爆撃)」はその後何回か繰り返され、まれな状況ではなくなってしまいました。
などです。また広島・長崎も「都市の無差別爆撃」だと言えるでしょう。たった一つの爆弾による無差別爆撃です。
重慶は当時の中国国民党政府が移転してきた都市であり、もちろん軍事的意味はあります。しかし重慶爆撃は第二次大戦の戦勝国からは強く非難され、また重慶市民には今でも反日感情が根強いようです。ドレスデンには「軍事基地や軍需工場、関連施設」があったわけではありません。ドレスデンは芸術と文化と歴史の町です。この無差別爆撃は、ドイツ文化を破壊しドイツ国内の厭戦気分を盛り上げようとするかのようです。1945.3.10 の東京大空襲も、日本の軍需産業を支える東京下町の町工場群を破壊した、という言い訳はできるでしょうが、苦しい説明です。10万人が死んだと言われる大空襲の目的は「10万人が死ぬこと」だった(日本の降伏を早めるため)と考えられます。
| 重慶(1938-43。日本軍) | |
| ドレスデン(1945.2.13。英米連合軍) | |
| 東京(1945.3.10。アメリカ軍。東京大空襲) |
重慶は当時の中国国民党政府が移転してきた都市であり、もちろん軍事的意味はあります。しかし重慶爆撃は第二次大戦の戦勝国からは強く非難され、また重慶市民には今でも反日感情が根強いようです。ドレスデンには「軍事基地や軍需工場、関連施設」があったわけではありません。ドレスデンは芸術と文化と歴史の町です。この無差別爆撃は、ドイツ文化を破壊しドイツ国内の厭戦気分を盛り上げようとするかのようです。1945.3.10 の東京大空襲も、日本の軍需産業を支える東京下町の町工場群を破壊した、という言い訳はできるでしょうが、苦しい説明です。10万人が死んだと言われる大空襲の目的は「10万人が死ぬこと」だった(日本の降伏を早めるため)と考えられます。
「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」の相違点(2)
「ゲルニカ」と「大坂夏の陣図屏風」のもう一つの相違点は、絵の描き手(注文主)です。いうまでもなく「ゲルニカ」を描いたのはピカソという画家であり、一市民です。ゲルニカ市民およびスペイン共和国軍という、ゲルニカで被害をうけた側の立場に立った画家です。
それに比較して「大坂夏の陣図屏風」を画家に描かせたのは、黒田長政という大坂夏の陣で勝利した側の大名です。勝利者が自分の功績、ないしは徳川方の戦績を記録するために描かせたものが「大坂夏の陣図屏風」なのです。そこが決定的に違います。
現代人の感覚で歴史を見る落とし穴
「大坂夏の陣図屏風」を評して
戦争に巻き込まれた非戦闘員の悲惨な姿を描き、戦争を告発した
というような意見があります。この屏風を「戦国のゲルニカ」だとする表現は、このような見方からきています。しかし、はたしてそうなのでしょうか。また、絵を引用した『戦国合戦絵屏風集成 第4巻』の解説には、
豊臣恩顧の大名でありながら、心ならずも徳川氏に従って、豊臣氏の滅亡に力をかさなければならなかった黒田長政が、滅びゆく旧主のために捧げた挽歌ともいうべきものではなかっただろうか
と書かれています。こんなことを言ってしまってよいのでしょうか。
最低限、推定できるのは、
この屏風を見たはずの黒田長政の家臣をはじめとする周囲の人たちは、戦争の悲惨さを描いた(ないしは告発した)ものだとか、豊臣家への挽歌だとは思わなかった
ということです。なぜそう言えるのかと言うと、
もし、この屏風を見た黒田長政の家臣をはじめとする周囲の人たちが、戦争の悲惨さを描いたものだとか豊臣家への挽歌だと思ったのであれば、黒田長政は事前にそれが予測できたはず
だからです。そして
戦争の悲惨さや豊臣家への挽歌を描いた絵だと周囲が受け取るような絵を、黒田長政が注文するはずがない
のです。もし仮にそんなものを注文して作らせ、それが噂になって、その噂が徳川幕府の耳に入ればどうなるか。理由は何とでもつけられます。謹慎ぐらいならまだましで、悪くすると長政は切腹、黒田家は取り潰しではないでしょうか。そんなリスクを福岡藩のトップがおかすはずはない。長政のように紆余曲折を経ながら戦国の世を生き抜き、徳川体制の藩主にまで上り詰めた人間というのは、余計なリスクを負わない「したたかさ」があって当然なのです。
父親の黒田官兵衛もそうですが、長政はキリシタン大名ですね。しかし長政は、秀吉が「バテレン追放令」(No.33「日本史と奴隷狩り」 参照)を出すとキリスト教を棄教し、徳川時代にはキリスト教徒を厳しく弾圧します。この程度は、当時を生き抜くための「したたかさ」以前の「分別」のたぐいでしょう。当時のカトリックの教えに従ってせっせと領内の寺院・神社を破壊した高山右近や大村純忠(No.28「マヤ文明の抹殺」)とはわけが違うのです。
黒田長政は豊臣家に恩義がある・・・・・・。これは全くの事実です。そのため家康は、大坂冬の陣では長政の徳川方での参戦を許さなかった。関が原の合戦の東軍勝利の立役者であるにもかかわらず、です。長政は夏の陣でやっと参戦を許され、そして徳川方は勝利し、徳川の世は確固としたものになった。
黒田長政のような立場の人間は、もとから徳川方だった大名以上に、徳川家に対する恭順の「しるし」を表そうとするはずです。大坂夏の陣の時のように・・・・・・。たとえ内心では豊臣家に恩義を感じていたとしても(それはありうる)、ゆめゆめそうは見られないように細心の注意を払って行動したでしょう。
|
「大坂夏の陣図屏風」の右隻は戦闘場面であり、当然黒田長政が描かれているし、家康も秀忠もいます。右隻は戦勝記念画なのです。そして左隻は、戦勝の結果としての「戦果」を描いています。ここには、大坂城から淀川にいたる戦場が実況中継のように描かれています。この左隻は徳川方にとってポジティブな情景(戦果としての濫妨)か、ないしはニュートラルなものだと思います。少なくとも徳川方にとってネガティブなものではない。
大坂夏の陣図屏風の中心テーマは、
右隻が「武士たちの戦場」
左隻が「雑兵たちの戦場」
だと思います。藤本久志さんの著書『雑兵たちの戦場』の表紙には、本の題名そのものズバリの絵、つまり「大坂夏の陣図屏風・左隻=雑兵たちの戦場」が用いられているのです。
「大坂夏の陣図屏風・左隻」を見て「ゲルニカ」のように考えてしまうのは(ないしは反戦画のように考えてしまうのは)、現代人の感覚で歴史を見る落とし穴にはまっているのだと思います。
怖い絵
要するに「大坂夏の陣図屏風・左隻」は、中野京子さん流に言うと「怖い絵」なのです。No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、中野さんは「ラス・メニーナス」に描かれている小人症の「慰み者」に着目し、
|
と書いています。この表現をそのまま借用すると、
|
と言えるでしょう。絵は「見方」によってその意味がガラッと変わることがあります。『大坂夏の陣図屏風・左隻』は、「ゲルニカ」ではなくて「怖い絵」だと思います。
No.33 - 日本史と奴隷狩り [歴史]
No.22, No.23 の「クラバートと奴隷」では、スレイヴ(奴隷)の語源がスラヴ(=民族名)である理由からはじまって、中世ヨーロッパにおける奴隷貿易の話を書きました。そこで、中世の日本における奴隷狩りや奴隷交易のこともまとめておきたいと思います。
山椒大夫
日本における「奴隷」と聞いてまず思い出すのは、森鷗外の小説『山椒大夫』です。この小説は「人買い」や「奴婢(奴隷)」が背景となっています。以下のような話です。
物語のはじめの部分において、二人の人買いは親子三人を拉致したあと「佐渡の二郎」は母親を佐渡へ売りにいき「宮崎の三郎」は安寿と厨子王を、佐渡とは反対の方向へ海づたいに買い手を探して南下します(宮崎は今の富山県の地名)。その南下の様子を「山椒大夫」から引用すると、次のとおりです。
この小説の主題は、物語の山場での「安寿の自己犠牲」だと思いますが、背景となっているのは「人商人」「人身売買」「奴隷(奴婢)」の存在です。上の引用でも明らかなように、宮崎の三郎のような「人商人(=人身売買を行う商人)」が存在し、それが定常化していて、奴隷を買う者も定常的に存在したというのが、この小説が成り立つための重要な背景となっているのです。
もちろん小説はフィクションなので、この通りのことがあったわけではありません。しかし鷗外は日本における「山椒大夫伝説」をもとに、歴史小説としてこの物語を書きました。特に、仏教の教化と普及のために説教僧が町々・村々を廻って語り伝えた「説教節」の定番である「さんせう大夫」がもとになっています。「さんせう大夫」の結末は小説と違って、山椒大夫が厨子王の報復によって実の息子にのこぎりで首を切られて死に、その息子も民衆に処刑されるという「勧善懲悪」のストーリーのようです。つまり、勧善懲悪のための説教節ということは、物語の成立の背景である中世の日本において「人商人」や「人身売買」「奴隷(奴婢)」が、説教節を聞く村人や町人にとって、少なくとも不自然でない程度に事実としてあったと推測できます。
人商人
説教節だけでなく、平安時代から室町時代にかけての謡曲・お伽草紙・古浄瑠璃には「人商人」による拉致・誘拐や人身売買をテーマにしたものが多数あります。この時代、実態として「人商人」や人の売買が存在したようです。
日本の歴史を振り返ってみると、大化の改新以降の律令制においては「奴婢」と呼ばれた奴隷が存在し、その売買も認められていました。また明治・大正時代まで続いた遊女や娼婦の場合のように「人身売買スレスレの雇用契約」もあったわけです。
しかし一般的に人身売買は国禁であり、平安から鎌倉時代にはそれを禁じる法令が何度も出されました。もちろん飢饉のときに親が子供を売るようなことはあったわけで、黙認されたケースもあったようです。しかし原則的には人身売買は違法です。ましてや人を拉致・誘拐して売るのは犯罪です。このような誘拐のことを「かどわかす(拐かす)」と言いました。古くは「かどわかす」に「略」の字をあて、人を誘拐して売ることを「略売」などとも言いました。「山椒大夫」に描かれているのは、まさにそういった状況です。しかし実態としてあったにしろ、それはれっきとした犯罪なので「人商人」の活動は記録には残りにくいわけです。
一方「有事」の時、つまり戦争の時には、人を奴隷として略奪・拉致し売買することは容認されていたし、戦争の手段として行われていました。それを記録した公的文書、武士の日記、私的な記録文書もたくさん残されています。世界の歴史だけでなく日本の歴史においても「戦争は奴隷の最大の発生源」だったのです。以降は、日本の戦国時代における「奴隷狩り」「奴隷売買」の話です。
雑兵たちの戦場
戦国時代における「奴隷狩り」や「奴隷売買」を詳述した本として、藤本久志・立教大学名誉教授の『新版 雑兵たちの戦場 ─ 中世の傭兵と奴隷狩り ─』(朝日選書。2005)があります。以降は、この本の内容から奴隷狩り・奴隷売買の部分を紹介します。
まず本のタイトルになっている「雑兵」ですが、雑兵とは「身分の低い兵卒」を言います。一般に戦国大名の軍は次の4つの階層から成っていました。
①武士
②侍
③下人
④百姓
雑兵とは ② ③ ④ を言っています。この雑兵の視点からみた戦場を記述したのが『新版 雑兵たちの戦場』です。
戦場における「濫妨狼藉」と「苅田」
我々が暗黙に思い浮かべる戦国時代の「戦場」というと、NHKの大河ドラマに出てくるものが代表的です。そこでは大名を総大将とし、家臣団が戦争を指揮し、武士が戦うという姿です。もちろん雑兵は武士の手足となって矢を放ったり、鉄砲を撃ったり、突撃したり、物資の輸送にあたります。このような戦場のイメージは、①武士の視点からみた戦場、ないしは、NHK大河ドラマ視点の戦場です。
しかし② ③ ④ の雑兵の視点からみた戦場は違った様相になります。その代表が、戦争の一部として行われた「濫妨狼藉(らんぼうろうぜき)」と「苅田(かりた)」です。
戦国時代の戦争では、城を攻める時にはまず雑兵が敵国の村に押し入り、放火、略奪、田畑の破壊をするのが常道でした。濫妨とは略奪を意味します。何を略奪するかというと、人と物です。物は農民の家財、貯蔵してある穀物、牛馬などです。濫妨はまた「乱取り」とか「乱妨取り」、「乱妨」とも呼ばれていました。狼藉とは暴力行為です。従って「濫妨狼藉」は現代用語の「乱暴狼藉」とは少し意味が違うので注意が必要です。
田畑の破壊・作物の略奪を苅田と言いました。小早川隆景の戦術書『永禄伝記』は、大名・毛利元就の戦法を伝えたものと言われています。その「攻城」の項に「苅田戦法」が記述されています。苅田戦法の結果はどうなるのか。『新版 雑兵たちの戦場』で藤本さんは次のように記述しています。
苅田の目的は「麦や稲を奪い取る」「敵国を兵糧攻めにする」「敵国の村々を脅かして味方につける」などでした。被害にあう農民は悲惨な状況になるわけですが、これが戦争の実態だったようです。
奴隷狩り
日本史と奴隷狩りというテーマなので、以降は濫妨(=略奪)の中の「人の略奪・奴隷狩り」に焦点を絞りたいと思います。
「人の略奪」は、戦国時代の各種記録で「人を捕る」「生捕る」「人取り」などと記述されています。生け捕られた人は、もちろん成人男子もいますが、女や子供がかなりの割合を占めていました。
略奪した人をどうするのか。一つは、町人や富農の下人として強制労働に従事させます。それはもちろん略奪した雑兵の下人という場合もあったでしょうが、「山椒大夫」のようにニーズのあるところに売るわけです。売買には商人(人商人)も介在しました。また後で紹介しますが、外国へも転売されたのです。
一部の生け捕られた人は、親族などが身代金を支払って身柄が返却されました。これはもちろん身代金を支払えるほど裕福な階層ということが前提です。身代金の授受にも「人商人」や海賊が介在して手数料を稼いだようです。
戦国の奴隷狩り・九州
戦国の各地の奴隷狩りの実態です。まず九州の島津藩ですが、著者の藤本さんは島津藩の家臣が書いた『北郷忠相日記』『蒲生山本氏日記』『北郷時久日記』などにみられる戦闘の記録を分析して、次のように書いています。
同じ九州ですが、肥後の小大名であった相良氏の年代記『八代日記』に記録された戦争の様子も分析されています。
戦場における人取りが日常的に行われていたことがうかがえます。
戦国の奴隷狩り・武田藩
甲斐・武田藩の軍書である『甲陽軍鑑』にも、雑兵たちの乱取りの記述が数々出てきます。『甲陽軍鑑』には武田信玄が上杉謙信と戦った北信濃の戦場が記述されていますが、その内容の解説です。
『甲陽軍鑑』には雑兵たちの乱取りを非難する記述があります。しかし乱取りそのものを否定しているわけではありません。戦いの勝ち負けそっちのけで乱取りに熱中するのは困る、と言っているのです。戦闘を妨げない限り乱取りは勝手、というのが当時の通念だったようです。雑兵たちに恩賞があるわけではありません。彼らを軍隊で活用するには、戦いの無い日には「乱取り休暇」を設け、敵城が落城したあとは褒美の略奪を解禁した ・・・・・・ 藤本さんはそう解説しています。
戦国の奴隷狩り・上杉藩
では、一方の上杉謙信はどうだったのか。謙信は武田信玄との戦いだけでなく、関東から北陸一円を戦場としました。永禄9年(1566)2月、上杉軍が関東に遠征し、常陸の国の小田城を攻め落としたときの様子が文書に記録されています。
上杉軍の人取りは小田城だけでなく、常陸の筑波の城や上野の藤岡城でもあったとの記録があります。小田城の例のような「城下での人の売買」は「人商人」の介在を強く示唆しています。
以上、島津、肥後、武田、上杉の事例をあげましたが、このほか『新版 雑兵たちの戦場』には、紀伊や奥羽の事例が掲げられています。戦争における奴隷狩りは全国的な現象だったようです。
食うための戦争
戦国時代の戦争における濫妨(略奪)の大きな要因は、戦争が「食うため」「略奪が目当て」という側面を強く持っていたからです。上杉謙信の出兵の記録が分析されています。謙信は関東、北信濃、北陸へ20回以上にわたって出兵していますが、その出兵時期を調査すると2つのパターンが浮かび上がります。晩秋に出兵して年内に帰る「短期年内型」と、晩秋に出かけて戦場で年を越し春に帰る「長期越冬型」です。
上杉謙信の出兵には明らかな「季節性」があるのです。北陸はともかく、北信濃や関東への出兵は武田氏や北条氏といった強豪が相手です。いくら謙信と言えども「自分の都合のよい時だけに出兵する」ことなど、本来は無理なはずです。にもかかわらず上杉軍に見られる「戦争の季節性」は端境期(はざかいき)の「飢え」と深い関係がある、と(新潟出身の)藤木さんは分析しています。
二毛作のできない越後では、春から畠の作物がとれる夏までが食料の端境期であり、深刻な食料不足に直面しました。これを乗り切るための「冬場の口減らし」は切実な問題であり、そのための出稼ぎが関東への出兵だった ・・・・・・、というわけです。雪のない関東に出兵すれば、補給がなくても濫妨で食いつなげる。出兵した軍隊の分の食料は「助かる」わけで、出兵は一種の「公共事業」です。もっとも軍が敗北して壊滅状態になったのでは元も子もありません。しかし謙信は強かった。謙信が越後の人々から英雄視されたのは当然だと考えられます。
冬場に雪に閉じこめられる越後だけでなく、作物の凶作による飢饉や、戦争の苅田による農地の荒廃により「食うこと」は戦国時代には極めて切実な問題でした。戦争には「食うための戦争」という側面が強くあるのです。
秀吉の天下統一と人身売買の禁止(天正18年 1590)
秀吉の天下統一は、今まで述べた濫妨狼藉と人の売買に終止符を打ち、戦争の惨禍を絶つという大きな意味がありました。秀吉は平定した土地に「人身売買の禁止令」を次々と出していきます。天正18年(1590)に奥羽に出された秀吉令は、
という内容です。戦場と人の売買は同時に封じ込めないと平和にはならなかったのです。
天正18年(1590)の北条氏滅亡と奥羽地方平定を最後に、日本から戦場はなくなりました。しかし「秀吉の平和」が日本全国を覆ったまさにその瞬間、朝鮮出兵の大号令が出されたのです。
朝鮮での奴隷狩り(文禄元年-慶長3年 1592-1598)
朝鮮出兵(文禄・慶長の役。1592-1598)の大本営は、肥前・名護屋城(佐賀県唐津市)にありました。常陸・佐竹軍に従軍した武士が、名護屋城に到着して見たものを国元に書き送った書簡が残されています。それによると
とのことなのです。藤木さんは
と解説しています。朝鮮の戦場における濫妨狼藉は相当なもので、たとえば島津軍の兵は船を使って川伝いに奥地まで入り込み、苅田や乱妨を働いていた、と本にあります。石田三成は島津義弘に島津軍の逸脱ぶりを警告したほどです。しかし、ほかならぬ秀吉自身が「捕まえた朝鮮人の中から腕利きの技術者や女性たちを選び出して献上せよ」という命令を出していました。秀吉も日本軍の大がかりな奴隷狩りを見越して、その一部の召し上げようとしていたわけです。
朝鮮の戦場における奴隷狩りをまとめて、藤木さんは以下のように説明しています。
徳川幕府の重要な外交課題は朝鮮との復交であり、数万にのぼった被虜人の返還問題でした。しかし正規の外交ルートで故郷に返されたのは、朝鮮側の正史(李朝実録)や各種記録を合わせても7500人程度だったようです。
朝鮮出兵をもう一度振り返ると、秀吉は日本から戦場を駆逐したとたんに、朝鮮侵略をはじめているわけです。このことの重要な意味について藤木さんは次のように書いています。
大坂の陣(慶長19年-20年 1614-1615)
秀吉が死に、関ヶ原の合戦があり、時代は江戸時代になりました。しかし徳川幕府が天下を支配するようになって以降も戦争がありました。もちろんそれは、大坂冬の陣と夏の陣です。
『新版 雑兵たちの戦場』のカバー絵になっている「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵。重要文化財)には、町なかで兵士が人や物の略奪を働く場面が克明に描かれています。兵士たちの具足には「葵の紋」もあります。徳川軍そのものが奴隷狩りをしていたわけです。
興味深い文書があります。幕府は戦争が終わった後の「落人改令」の中で、大坂より外で略奪した人を解放し返せ、との命令を出します。この幕令をうけた蜂須賀軍は、ただちに自軍の奴隷狩りの実状を調査し、その結果を「大坂濫妨人ならびに落人改之帳」という文書にして幕府に提出しました。この文書によると、略奪された人の数は、
です(奉公人は「武家の奉公人」の意味)。これを見ると、成年男子は全体の4分の1に過ぎず、明らかに女と子供が多数を占めています。
蜂須賀軍は「自軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張していて、それを証明するのが「濫妨人改之帳」を提出した狙いでした。蜂須賀軍の戦場での人取りだけでこの数字です。全幕府軍の戦場・戦場外での人取りの総計は、相当の数にのぼったと推定されます。
大坂の陣が終わった直後にも、徳川幕府は「人身売買の停止令」を出しました。人の略奪や人の売買が日常の街角に持ち込まれていたからです。それを抑え込んでこそ平和が実現できたのです。
秀吉の奴隷問答(天正15年 1587)と奴隷貿易
時代を少しさかのぼります。戦国時代の日本国内と朝鮮における奴隷狩り・奴隷売買は、その帰結として「奴隷貿易=海外への奴隷の輸出」を引き起こしました。16世紀の日本には、いわゆる南蛮人が多数来日し、船舶の往来も激しかったからです。
秀吉は天正15年(1587)年の4月に南九州の島津氏を降し、全九州を平定します。そして6月に博多に軍を返すと、日本イエズス会・準管区長、ガスパール・コエリョに対し「ポルトガル人が多数の日本人を買い、奴隷としてつれていくのは何故であるか」と詰問します。コエリョはその事実を認めつつも「ポルトガル人が日本人を買うのは、日本人がこれを売るからだ」とつっぱねました(1587年のイエズス会・日本年報による)。
ポルトガルの日本貿易において、奴隷は東南アジア向けの重要商品だったのです。
ポルトガル国王は「日本人奴隷の輸出が布教の妨げになる」というイエズス会からの訴えに基づいて、1570年3月12日(元亀元年)に日本人奴隷取引の禁止令を出します。また、それ以降もたびたび禁止令が出されます。イエズス会も1596年に、日本人奴隷を輸出したものは破門にすると議決しました。
これらのことは裏を返すと、各種の禁令にもかかわらず奴隷貿易が続いていたことを示しています。そもそもイエズス会自身が、もともと日本から少年少女の奴隷を連れ出すポルトガル商人に公然と輸出許可の署名を与えていたのでした。
秀吉はコエリョと激論した直後の天正15年(1587)6月18日、有名な「バテレン追放令」を出します。この内容は、
が骨子ですが、その第10条は
です。「バテレン追放」の理由は「キリスト教への強制改宗」「神社仏閣の打ち壊し」とともに「日本人奴隷の海外輸出」というわけです。
東南アジアの日本人奴隷と傭兵
奴隷だけでなく、16世紀から17世紀初頭にかけて大量の日本人が東南アジアに渡りました。この時期、東南アジアではスペイン・ポルトガルと、オランダ・イギリスが激突していたわけで、日本は傭兵や武器の供給基地となっていたのです。
東南アジアに渡った日本人は「おそらく10万人以上にのぼり、住み着いた人々もその1割ほどはいた」と推定されています。その日本人を「分類」すると、一つは自ら海を渡った人たちで、海賊、船乗り、商人、失業者、追放キリシタンなどです。二つめは西欧人に雇われて渡海した人で、伝道者、官史、商館員、船員、傭兵、労働者です。三つめが奴隷や捕虜です。
日本人傭兵は東南アジアでの戦争や抗争に大きな影響をもちました。有名なのは山田長政ですが、彼は日本では徳川方の小大名・大久保氏に仕えた駕籠をかつぐ下僕だったようです。それがシャムの内乱に雇われ、日本人傭兵隊をひきいて活躍し、最後は毒殺されました。本書の中では、スペイン領だったフィリピンの様子が紹介されています。
スペイン・ポルトガルが日本人傭兵を駆使していたことは、
との記述でも分かります。
スペイン側だけでなく、オランダ側も大量の日本人傭兵を使っていました。日本の平戸商館はオランダ(東インド会社)の軍事行動をささえる東南アジア随一の兵站基地であり、さまざまな軍事物資が平戸から積み出されていたのです。最大の主力商品は銀です(世界遺産・石見銀山を思い出します。No.30参照)。それ以外に、武器・弾薬、銅・鉄・木材・食料・薬品などです。
元和6年(1620)の末、オランダとイギリスは連合して新たに「蘭英防禦艦隊」を結成し、平戸を母港とします。翌年(1621)の7月、両国の軍隊は、台湾の近海で捕らえた日本行きのポルトガル船とスペイン人宣教師を幕府に突き出します。そして幕府に「マニラ(スペインの拠点)・マカオ(ポルドガルの拠点)を滅ぼすために、二千~三千人の日本兵を派遣してほしい」との要請を出すのです。
秀忠令(元和7年 1621)
幕府は英蘭の日本兵派遣要請を拒否します。そして拒否しただけでなく、幕令(秀忠令)を出します。その骨子は、
です。①は、傭兵に陽には触れていません。しかしオランダ側が作った秀忠令のオランダ語訳には「雇用であれ人身売買であれ」と詳しく記載されています。幕府の意図は人身売買と傭兵による日本人の海外流出の阻止であり、オランダ側もそう受け取ったわけです。
当時の東南アジア情勢を考えると、日本は極めて危険な状況にありました。日本は戦争物資と傭兵の補給基地になっていたからです。特定の外国の依頼で「公式に」出兵したりするものなら、その敵対国からの日本侵略の口実を作ることにもなります。幕府の出兵拒否と秀忠令は、日本が新たな戦乱に巻き込まれるリスクを無くすための当然の処置でしょう。
オランダはこの秀忠令に困惑し、回避しようと努力したようです。しかし、平戸がある松浦藩は外国船の臨検をはじめ、武器を押収しました。秀忠令は実行され、日本人奴隷の海外流出はようやく止まりました。戦国期から続いた「公然の」人身売買も最終的に終りを迎えたのです。
幕府が鎖国に踏み切り、それを完成させるのは、秀忠令から18年後(寛永16年 1639)です。
「奴隷狩り」から見る日本史
これ以降は『新版 雑兵たちの戦場』を読んだ感想です。戦国時代の「奴隷狩り」の実態をみると、その後の、
という歴史経緯の重要性が理解できたような気がしました。大名同士が戦争で争い「濫妨狼藉」や「苅田」を繰り返していたのでは、農地は荒廃し、農村からは人が奴隷となって流出します。その流出は、奴隷船によって海外にまで及びます。奴隷にならないまでも農地が荒れると食べていけなくなり、農民は浮浪民化し、都市に流入して社会不安を引き起こすでしょう。「人商人」が暗躍し、犯罪が多発し、それがまた社会不安を助長する。
この状況は悪循環となり、各藩の経済力にダメージを与えるでしょう。そうなれば藩の財政も苦しくなるし、日本全体の国力も低下します。天下統一の大きな意味は「戦場を日本から無くし、濫妨狼藉の負のスパイラルを断ち切り、人民の生活を安定させ、国力を回復する」ということではないでしょうか。おりしも東南アジアでは欧米の列強が争っていて、その火の粉は日本にも降りかかりつつあります。統一と安定は必須の事項でした。
その後の徳川幕府は、藩の集合体という「日本のかたち」を前提として、戦国状態に再び戻るのを避けるための徹底的な施策をとったのだと思います。その例ですが、秀吉の刀狩り・鉄砲狩りからはじまり、江戸時代は「武装解除社会」ないしは「軽武装社会」になります。
武士の命は刀と言いますが、刀は戦争の雌雄を決するものではありません。刀は戦闘の最後の接近戦や白兵戦のためのものです。戦争で重要な武器は長槍であり、弓矢などの「飛び道具」であり、戦国時代以降はもちろん鉄砲です(その後、大砲になる)。優秀な戦国武将は鉄砲を徹底的に利用しました。
江戸時代直前の日本は世界有数の武装社会だったわけです。それが江戸時代になると一転して鉄砲を捨てて「武装解除社会」「軽武装社会」になる。あれだけ短期間で高度に発達した鉄砲鍛冶の技術も、急激に失われていきました。武士の刀は自衛のための武器と考えるべきでしょう。江戸期における「武士」とは、武器を自衛のための最低限のものにとどめ、「士 = 教養や徳のある立派な人間」として生きる、ということだと思います。
この状況は、戦場の再来をなくしたいという、戦国期の反動ではないでしょうか。江戸時代の意味は、戦国期の「雑兵の視点からみた戦場」の実態を知ることによって理解が進むと、この本を読んで思いました。
山椒大夫
日本における「奴隷」と聞いてまず思い出すのは、森鷗外の小説『山椒大夫』です。この小説は「人買い」や「奴婢(奴隷)」が背景となっています。以下のような話です。
陸奥の国に住んでいた母と2人の子(姉が安寿、弟が厨子王)が、筑紫の国に左遷された父を訪ねていきます。途中の越後・直江の浦(現在の直江津)で人買いにつかまり、母は佐渡の農家に売られ、2人の子は丹後・由良の山椒大夫に売られます。
2人の子は奴婢として使役されますが、姉は意を決して弟を脱出させ、自らは入水自殺します。弟は国分寺の住職に救われ、都に上って関白師実の子となります。そして丹後の国守に任ぜられたのを機に、人の売買を禁止します。そして最後の場面で佐渡に旅し、鳥追いになっていた盲目の母と再会します。
2人の子は奴婢として使役されますが、姉は意を決して弟を脱出させ、自らは入水自殺します。弟は国分寺の住職に救われ、都に上って関白師実の子となります。そして丹後の国守に任ぜられたのを機に、人の売買を禁止します。そして最後の場面で佐渡に旅し、鳥追いになっていた盲目の母と再会します。
物語のはじめの部分において、二人の人買いは親子三人を拉致したあと「佐渡の二郎」は母親を佐渡へ売りにいき「宮崎の三郎」は安寿と厨子王を、佐渡とは反対の方向へ海づたいに買い手を探して南下します(宮崎は今の富山県の地名)。その南下の様子を「山椒大夫」から引用すると、次のとおりです。
|
この小説の主題は、物語の山場での「安寿の自己犠牲」だと思いますが、背景となっているのは「人商人」「人身売買」「奴隷(奴婢)」の存在です。上の引用でも明らかなように、宮崎の三郎のような「人商人(=人身売買を行う商人)」が存在し、それが定常化していて、奴隷を買う者も定常的に存在したというのが、この小説が成り立つための重要な背景となっているのです。
もちろん小説はフィクションなので、この通りのことがあったわけではありません。しかし鷗外は日本における「山椒大夫伝説」をもとに、歴史小説としてこの物語を書きました。特に、仏教の教化と普及のために説教僧が町々・村々を廻って語り伝えた「説教節」の定番である「さんせう大夫」がもとになっています。「さんせう大夫」の結末は小説と違って、山椒大夫が厨子王の報復によって実の息子にのこぎりで首を切られて死に、その息子も民衆に処刑されるという「勧善懲悪」のストーリーのようです。つまり、勧善懲悪のための説教節ということは、物語の成立の背景である中世の日本において「人商人」や「人身売買」「奴隷(奴婢)」が、説教節を聞く村人や町人にとって、少なくとも不自然でない程度に事実としてあったと推測できます。
人商人
説教節だけでなく、平安時代から室町時代にかけての謡曲・お伽草紙・古浄瑠璃には「人商人」による拉致・誘拐や人身売買をテーマにしたものが多数あります。この時代、実態として「人商人」や人の売買が存在したようです。
日本の歴史を振り返ってみると、大化の改新以降の律令制においては「奴婢」と呼ばれた奴隷が存在し、その売買も認められていました。また明治・大正時代まで続いた遊女や娼婦の場合のように「人身売買スレスレの雇用契約」もあったわけです。
しかし一般的に人身売買は国禁であり、平安から鎌倉時代にはそれを禁じる法令が何度も出されました。もちろん飢饉のときに親が子供を売るようなことはあったわけで、黙認されたケースもあったようです。しかし原則的には人身売買は違法です。ましてや人を拉致・誘拐して売るのは犯罪です。このような誘拐のことを「かどわかす(拐かす)」と言いました。古くは「かどわかす」に「略」の字をあて、人を誘拐して売ることを「略売」などとも言いました。「山椒大夫」に描かれているのは、まさにそういった状況です。しかし実態としてあったにしろ、それはれっきとした犯罪なので「人商人」の活動は記録には残りにくいわけです。
一方「有事」の時、つまり戦争の時には、人を奴隷として略奪・拉致し売買することは容認されていたし、戦争の手段として行われていました。それを記録した公的文書、武士の日記、私的な記録文書もたくさん残されています。世界の歴史だけでなく日本の歴史においても「戦争は奴隷の最大の発生源」だったのです。以降は、日本の戦国時代における「奴隷狩り」「奴隷売買」の話です。
雑兵たちの戦場
戦国時代における「奴隷狩り」や「奴隷売買」を詳述した本として、藤本久志・立教大学名誉教授の『新版 雑兵たちの戦場 ─ 中世の傭兵と奴隷狩り ─』(朝日選書。2005)があります。以降は、この本の内容から奴隷狩り・奴隷売買の部分を紹介します。
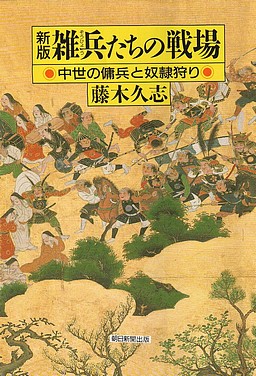
|
まず本のタイトルになっている「雑兵」ですが、雑兵とは「身分の低い兵卒」を言います。一般に戦国大名の軍は次の4つの階層から成っていました。
①武士
100人の軍があったとしたとき、その中の武士は10人たらずが普通でした。
②侍
悴者、若党、足軽などと呼ばれました。武士に奉公し、主人とともに戦います。侍は武士のことではありません。
③下人
侍の下です。中間、小者、あらしこ、などと呼ばれました。戦場では主人を助けて馬を引き、槍を持ちます。
④百姓
夫、夫丸などと呼ばれ、村から駆り出されて物を運ぶ人夫です。
雑兵とは ② ③ ④ を言っています。この雑兵の視点からみた戦場を記述したのが『新版 雑兵たちの戦場』です。
戦場における「濫妨狼藉」と「苅田」
我々が暗黙に思い浮かべる戦国時代の「戦場」というと、NHKの大河ドラマに出てくるものが代表的です。そこでは大名を総大将とし、家臣団が戦争を指揮し、武士が戦うという姿です。もちろん雑兵は武士の手足となって矢を放ったり、鉄砲を撃ったり、突撃したり、物資の輸送にあたります。このような戦場のイメージは、①武士の視点からみた戦場、ないしは、NHK大河ドラマ視点の戦場です。
しかし② ③ ④ の雑兵の視点からみた戦場は違った様相になります。その代表が、戦争の一部として行われた「濫妨狼藉(らんぼうろうぜき)」と「苅田(かりた)」です。
戦国時代の戦争では、城を攻める時にはまず雑兵が敵国の村に押し入り、放火、略奪、田畑の破壊をするのが常道でした。濫妨とは略奪を意味します。何を略奪するかというと、人と物です。物は農民の家財、貯蔵してある穀物、牛馬などです。濫妨はまた「乱取り」とか「乱妨取り」、「乱妨」とも呼ばれていました。狼藉とは暴力行為です。従って「濫妨狼藉」は現代用語の「乱暴狼藉」とは少し意味が違うので注意が必要です。
田畑の破壊・作物の略奪を苅田と言いました。小早川隆景の戦術書『永禄伝記』は、大名・毛利元就の戦法を伝えたものと言われています。その「攻城」の項に「苅田戦法」が記述されています。苅田戦法の結果はどうなるのか。『新版 雑兵たちの戦場』で藤本さんは次のように記述しています。
|
苅田の目的は「麦や稲を奪い取る」「敵国を兵糧攻めにする」「敵国の村々を脅かして味方につける」などでした。被害にあう農民は悲惨な状況になるわけですが、これが戦争の実態だったようです。
奴隷狩り
日本史と奴隷狩りというテーマなので、以降は濫妨(=略奪)の中の「人の略奪・奴隷狩り」に焦点を絞りたいと思います。
「人の略奪」は、戦国時代の各種記録で「人を捕る」「生捕る」「人取り」などと記述されています。生け捕られた人は、もちろん成人男子もいますが、女や子供がかなりの割合を占めていました。
略奪した人をどうするのか。一つは、町人や富農の下人として強制労働に従事させます。それはもちろん略奪した雑兵の下人という場合もあったでしょうが、「山椒大夫」のようにニーズのあるところに売るわけです。売買には商人(人商人)も介在しました。また後で紹介しますが、外国へも転売されたのです。
一部の生け捕られた人は、親族などが身代金を支払って身柄が返却されました。これはもちろん身代金を支払えるほど裕福な階層ということが前提です。身代金の授受にも「人商人」や海賊が介在して手数料を稼いだようです。
戦国の奴隷狩り・九州
戦国の各地の奴隷狩りの実態です。まず九州の島津藩ですが、著者の藤本さんは島津藩の家臣が書いた『北郷忠相日記』『蒲生山本氏日記』『北郷時久日記』などにみられる戦闘の記録を分析して、次のように書いています。
|
同じ九州ですが、肥後の小大名であった相良氏の年代記『八代日記』に記録された戦争の様子も分析されています。
|
戦場における人取りが日常的に行われていたことがうかがえます。
戦国の奴隷狩り・武田藩
甲斐・武田藩の軍書である『甲陽軍鑑』にも、雑兵たちの乱取りの記述が数々出てきます。『甲陽軍鑑』には武田信玄が上杉謙信と戦った北信濃の戦場が記述されていますが、その内容の解説です。
|
『甲陽軍鑑』には雑兵たちの乱取りを非難する記述があります。しかし乱取りそのものを否定しているわけではありません。戦いの勝ち負けそっちのけで乱取りに熱中するのは困る、と言っているのです。戦闘を妨げない限り乱取りは勝手、というのが当時の通念だったようです。雑兵たちに恩賞があるわけではありません。彼らを軍隊で活用するには、戦いの無い日には「乱取り休暇」を設け、敵城が落城したあとは褒美の略奪を解禁した ・・・・・・ 藤本さんはそう解説しています。
戦国の奴隷狩り・上杉藩
では、一方の上杉謙信はどうだったのか。謙信は武田信玄との戦いだけでなく、関東から北陸一円を戦場としました。永禄9年(1566)2月、上杉軍が関東に遠征し、常陸の国の小田城を攻め落としたときの様子が文書に記録されています。
|
上杉軍の人取りは小田城だけでなく、常陸の筑波の城や上野の藤岡城でもあったとの記録があります。小田城の例のような「城下での人の売買」は「人商人」の介在を強く示唆しています。
以上、島津、肥後、武田、上杉の事例をあげましたが、このほか『新版 雑兵たちの戦場』には、紀伊や奥羽の事例が掲げられています。戦争における奴隷狩りは全国的な現象だったようです。
食うための戦争
戦国時代の戦争における濫妨(略奪)の大きな要因は、戦争が「食うため」「略奪が目当て」という側面を強く持っていたからです。上杉謙信の出兵の記録が分析されています。謙信は関東、北信濃、北陸へ20回以上にわたって出兵していますが、その出兵時期を調査すると2つのパターンが浮かび上がります。晩秋に出兵して年内に帰る「短期年内型」と、晩秋に出かけて戦場で年を越し春に帰る「長期越冬型」です。
|
上杉謙信の出兵には明らかな「季節性」があるのです。北陸はともかく、北信濃や関東への出兵は武田氏や北条氏といった強豪が相手です。いくら謙信と言えども「自分の都合のよい時だけに出兵する」ことなど、本来は無理なはずです。にもかかわらず上杉軍に見られる「戦争の季節性」は端境期(はざかいき)の「飢え」と深い関係がある、と(新潟出身の)藤木さんは分析しています。
二毛作のできない越後では、春から畠の作物がとれる夏までが食料の端境期であり、深刻な食料不足に直面しました。これを乗り切るための「冬場の口減らし」は切実な問題であり、そのための出稼ぎが関東への出兵だった ・・・・・・、というわけです。雪のない関東に出兵すれば、補給がなくても濫妨で食いつなげる。出兵した軍隊の分の食料は「助かる」わけで、出兵は一種の「公共事業」です。もっとも軍が敗北して壊滅状態になったのでは元も子もありません。しかし謙信は強かった。謙信が越後の人々から英雄視されたのは当然だと考えられます。
冬場に雪に閉じこめられる越後だけでなく、作物の凶作による飢饉や、戦争の苅田による農地の荒廃により「食うこと」は戦国時代には極めて切実な問題でした。戦争には「食うための戦争」という側面が強くあるのです。
秀吉の天下統一と人身売買の禁止(天正18年 1590)
秀吉の天下統一は、今まで述べた濫妨狼藉と人の売買に終止符を打ち、戦争の惨禍を絶つという大きな意味がありました。秀吉は平定した土地に「人身売買の禁止令」を次々と出していきます。天正18年(1590)に奥羽に出された秀吉令は、
| 人の売り買いはすべて停止せよ。 | |
| 天正16年以後の人の売買は無効。したがって、買い取った人は元に戻せ。 | |
| 以後、人の「売り」「買い」はともに違法。 |
という内容です。戦場と人の売買は同時に封じ込めないと平和にはならなかったのです。
天正18年(1590)の北条氏滅亡と奥羽地方平定を最後に、日本から戦場はなくなりました。しかし「秀吉の平和」が日本全国を覆ったまさにその瞬間、朝鮮出兵の大号令が出されたのです。
朝鮮での奴隷狩り(文禄元年-慶長3年 1592-1598)
朝鮮出兵(文禄・慶長の役。1592-1598)の大本営は、肥前・名護屋城(佐賀県唐津市)にありました。常陸・佐竹軍に従軍した武士が、名護屋城に到着して見たものを国元に書き送った書簡が残されています。それによると
|
とのことなのです。藤木さんは
|
と解説しています。朝鮮の戦場における濫妨狼藉は相当なもので、たとえば島津軍の兵は船を使って川伝いに奥地まで入り込み、苅田や乱妨を働いていた、と本にあります。石田三成は島津義弘に島津軍の逸脱ぶりを警告したほどです。しかし、ほかならぬ秀吉自身が「捕まえた朝鮮人の中から腕利きの技術者や女性たちを選び出して献上せよ」という命令を出していました。秀吉も日本軍の大がかりな奴隷狩りを見越して、その一部の召し上げようとしていたわけです。
秀吉の命令の「腕利きの技術者」ということで思い出されるのが、島津軍に捕えられて薩摩に連行された朝鮮の陶芸職人たちです。彼らが薩摩焼のルーツで、薩摩焼の窯元の一つである沈壽官家は現代まで15代続いています。
朝鮮の戦場における奴隷狩りをまとめて、藤木さんは以下のように説明しています。
|
|
徳川幕府の重要な外交課題は朝鮮との復交であり、数万にのぼった被虜人の返還問題でした。しかし正規の外交ルートで故郷に返されたのは、朝鮮側の正史(李朝実録)や各種記録を合わせても7500人程度だったようです。
朝鮮出兵をもう一度振り返ると、秀吉は日本から戦場を駆逐したとたんに、朝鮮侵略をはじめているわけです。このことの重要な意味について藤木さんは次のように書いています。
|
大坂の陣(慶長19年-20年 1614-1615)
秀吉が死に、関ヶ原の合戦があり、時代は江戸時代になりました。しかし徳川幕府が天下を支配するようになって以降も戦争がありました。もちろんそれは、大坂冬の陣と夏の陣です。
|
『新版 雑兵たちの戦場』のカバー絵になっている「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵。重要文化財)には、町なかで兵士が人や物の略奪を働く場面が克明に描かれています。兵士たちの具足には「葵の紋」もあります。徳川軍そのものが奴隷狩りをしていたわけです。

|
「新版 雑兵たちの戦場」の表紙をさらに拡大した図(表紙の左の中ほど)。武士の具足に葵の紋が見える。 |
興味深い文書があります。幕府は戦争が終わった後の「落人改令」の中で、大坂より外で略奪した人を解放し返せ、との命令を出します。この幕令をうけた蜂須賀軍は、ただちに自軍の奴隷狩りの実状を調査し、その結果を「大坂濫妨人ならびに落人改之帳」という文書にして幕府に提出しました。この文書によると、略奪された人の数は、
| 男 | 女 | 計 | |
| 奉公人 | 17 | 33 | 50 |
| 町人 | 29 | 47 | 76 |
| 子ども | 35 | 16 | 51 |
| 合計 | 81 | 96 | 177 |
です(奉公人は「武家の奉公人」の意味)。これを見ると、成年男子は全体の4分の1に過ぎず、明らかに女と子供が多数を占めています。
蜂須賀軍は「自軍の人取りはすべて戦場の行為であり、合法だ」と主張していて、それを証明するのが「濫妨人改之帳」を提出した狙いでした。蜂須賀軍の戦場での人取りだけでこの数字です。全幕府軍の戦場・戦場外での人取りの総計は、相当の数にのぼったと推定されます。
大坂の陣が終わった直後にも、徳川幕府は「人身売買の停止令」を出しました。人の略奪や人の売買が日常の街角に持ち込まれていたからです。それを抑え込んでこそ平和が実現できたのです。
秀吉の奴隷問答(天正15年 1587)と奴隷貿易
時代を少しさかのぼります。戦国時代の日本国内と朝鮮における奴隷狩り・奴隷売買は、その帰結として「奴隷貿易=海外への奴隷の輸出」を引き起こしました。16世紀の日本には、いわゆる南蛮人が多数来日し、船舶の往来も激しかったからです。
秀吉は天正15年(1587)年の4月に南九州の島津氏を降し、全九州を平定します。そして6月に博多に軍を返すと、日本イエズス会・準管区長、ガスパール・コエリョに対し「ポルトガル人が多数の日本人を買い、奴隷としてつれていくのは何故であるか」と詰問します。コエリョはその事実を認めつつも「ポルトガル人が日本人を買うのは、日本人がこれを売るからだ」とつっぱねました(1587年のイエズス会・日本年報による)。
|
ポルトガルの日本貿易において、奴隷は東南アジア向けの重要商品だったのです。
No.22「クラバートと奴隷(1)スラヴ民族」と、No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」で、ヨーロッパにおいて非キリスト教徒のスラヴ民族が奴隷の供給源になった歴史を書きました。最初は中央ヨーロッパ、その次は黒海沿岸のスラヴ民族です。
しかし大航海時代を経てヨーロッパ人が世界に拡散すると、奴隷の供給源も世界に拡散していった。非キリスト教徒に満ち溢れていた世界は、キリスト教布教の対象であると同時に奴隷の供給源となった。その一つが、ヨーロッパからみた東の果て(極東、Far East)の日本だった、というわけです。
しかし大航海時代を経てヨーロッパ人が世界に拡散すると、奴隷の供給源も世界に拡散していった。非キリスト教徒に満ち溢れていた世界は、キリスト教布教の対象であると同時に奴隷の供給源となった。その一つが、ヨーロッパからみた東の果て(極東、Far East)の日本だった、というわけです。
ポルトガル国王は「日本人奴隷の輸出が布教の妨げになる」というイエズス会からの訴えに基づいて、1570年3月12日(元亀元年)に日本人奴隷取引の禁止令を出します。また、それ以降もたびたび禁止令が出されます。イエズス会も1596年に、日本人奴隷を輸出したものは破門にすると議決しました。
これらのことは裏を返すと、各種の禁令にもかかわらず奴隷貿易が続いていたことを示しています。そもそもイエズス会自身が、もともと日本から少年少女の奴隷を連れ出すポルトガル商人に公然と輸出許可の署名を与えていたのでした。
秀吉はコエリョと激論した直後の天正15年(1587)6月18日、有名な「バテレン追放令」を出します。この内容は、
| バテレンの追放 | |
| キリスト教への強制改宗の禁止 | |
| 神社仏閣の打ち壊しの禁止 |
が骨子ですが、その第10条は
| 日本人奴隷の海外禁輸、および国内での人身売買の禁止 |
です。「バテレン追放」の理由は「キリスト教への強制改宗」「神社仏閣の打ち壊し」とともに「日本人奴隷の海外輸出」というわけです。
東南アジアの日本人奴隷と傭兵
奴隷だけでなく、16世紀から17世紀初頭にかけて大量の日本人が東南アジアに渡りました。この時期、東南アジアではスペイン・ポルトガルと、オランダ・イギリスが激突していたわけで、日本は傭兵や武器の供給基地となっていたのです。
東南アジアに渡った日本人は「おそらく10万人以上にのぼり、住み着いた人々もその1割ほどはいた」と推定されています。その日本人を「分類」すると、一つは自ら海を渡った人たちで、海賊、船乗り、商人、失業者、追放キリシタンなどです。二つめは西欧人に雇われて渡海した人で、伝道者、官史、商館員、船員、傭兵、労働者です。三つめが奴隷や捕虜です。
日本人傭兵は東南アジアでの戦争や抗争に大きな影響をもちました。有名なのは山田長政ですが、彼は日本では徳川方の小大名・大久保氏に仕えた駕籠をかつぐ下僕だったようです。それがシャムの内乱に雇われ、日本人傭兵隊をひきいて活躍し、最後は毒殺されました。本書の中では、スペイン領だったフィリピンの様子が紹介されています。
|
スペイン・ポルトガルが日本人傭兵を駆使していたことは、
|
との記述でも分かります。
キリスト教を布教するはずの神父が中国征服とその方法論を国王に提案するのも、ずいぶん変な話なのですが、当時の宣教師の一面が如実に現れています。中国は「征服しないとキリスト教が広まらない国」と判断したのでしょうか。神の恩寵を中国人に与えるために征服しよう、という論理でしょう。
スペイン側だけでなく、オランダ側も大量の日本人傭兵を使っていました。日本の平戸商館はオランダ(東インド会社)の軍事行動をささえる東南アジア随一の兵站基地であり、さまざまな軍事物資が平戸から積み出されていたのです。最大の主力商品は銀です(世界遺産・石見銀山を思い出します。No.30参照)。それ以外に、武器・弾薬、銅・鉄・木材・食料・薬品などです。
元和6年(1620)の末、オランダとイギリスは連合して新たに「蘭英防禦艦隊」を結成し、平戸を母港とします。翌年(1621)の7月、両国の軍隊は、台湾の近海で捕らえた日本行きのポルトガル船とスペイン人宣教師を幕府に突き出します。そして幕府に「マニラ(スペインの拠点)・マカオ(ポルドガルの拠点)を滅ぼすために、二千~三千人の日本兵を派遣してほしい」との要請を出すのです。
秀忠令(元和7年 1621)
幕府は英蘭の日本兵派遣要請を拒否します。そして拒否しただけでなく、幕令(秀忠令)を出します。その骨子は、
| 人身売買の停止 男女を買い取って異国へ渡海することを停止せよ。 | |
| 武器輸出の停止 武具の類を異国へ渡してはならぬ。 | |
| 海賊の停止 海上における海賊行為をやめよ。 |
です。①は、傭兵に陽には触れていません。しかしオランダ側が作った秀忠令のオランダ語訳には「雇用であれ人身売買であれ」と詳しく記載されています。幕府の意図は人身売買と傭兵による日本人の海外流出の阻止であり、オランダ側もそう受け取ったわけです。
当時の東南アジア情勢を考えると、日本は極めて危険な状況にありました。日本は戦争物資と傭兵の補給基地になっていたからです。特定の外国の依頼で「公式に」出兵したりするものなら、その敵対国からの日本侵略の口実を作ることにもなります。幕府の出兵拒否と秀忠令は、日本が新たな戦乱に巻き込まれるリスクを無くすための当然の処置でしょう。
オランダはこの秀忠令に困惑し、回避しようと努力したようです。しかし、平戸がある松浦藩は外国船の臨検をはじめ、武器を押収しました。秀忠令は実行され、日本人奴隷の海外流出はようやく止まりました。戦国期から続いた「公然の」人身売買も最終的に終りを迎えたのです。
幕府が鎖国に踏み切り、それを完成させるのは、秀忠令から18年後(寛永16年 1639)です。
「奴隷狩り」から見る日本史
これ以降は『新版 雑兵たちの戦場』を読んだ感想です。戦国時代の「奴隷狩り」の実態をみると、その後の、
| 秀吉による天下統一 | |
| 人身売買の禁止 | |
| 鎖国(=人の往来を禁止し、交易を中国・朝鮮・オランダに限定する) | |
| 徳川幕府による社会の安定と国内平和の維持 |
という歴史経緯の重要性が理解できたような気がしました。大名同士が戦争で争い「濫妨狼藉」や「苅田」を繰り返していたのでは、農地は荒廃し、農村からは人が奴隷となって流出します。その流出は、奴隷船によって海外にまで及びます。奴隷にならないまでも農地が荒れると食べていけなくなり、農民は浮浪民化し、都市に流入して社会不安を引き起こすでしょう。「人商人」が暗躍し、犯罪が多発し、それがまた社会不安を助長する。
この状況は悪循環となり、各藩の経済力にダメージを与えるでしょう。そうなれば藩の財政も苦しくなるし、日本全体の国力も低下します。天下統一の大きな意味は「戦場を日本から無くし、濫妨狼藉の負のスパイラルを断ち切り、人民の生活を安定させ、国力を回復する」ということではないでしょうか。おりしも東南アジアでは欧米の列強が争っていて、その火の粉は日本にも降りかかりつつあります。統一と安定は必須の事項でした。
その後の徳川幕府は、藩の集合体という「日本のかたち」を前提として、戦国状態に再び戻るのを避けるための徹底的な施策をとったのだと思います。その例ですが、秀吉の刀狩り・鉄砲狩りからはじまり、江戸時代は「武装解除社会」ないしは「軽武装社会」になります。
武士の命は刀と言いますが、刀は戦争の雌雄を決するものではありません。刀は戦闘の最後の接近戦や白兵戦のためのものです。戦争で重要な武器は長槍であり、弓矢などの「飛び道具」であり、戦国時代以降はもちろん鉄砲です(その後、大砲になる)。優秀な戦国武将は鉄砲を徹底的に利用しました。
|
江戸時代直前の日本は世界有数の武装社会だったわけです。それが江戸時代になると一転して鉄砲を捨てて「武装解除社会」「軽武装社会」になる。あれだけ短期間で高度に発達した鉄砲鍛冶の技術も、急激に失われていきました。武士の刀は自衛のための武器と考えるべきでしょう。江戸期における「武士」とは、武器を自衛のための最低限のものにとどめ、「士 = 教養や徳のある立派な人間」として生きる、ということだと思います。
この状況は、戦場の再来をなくしたいという、戦国期の反動ではないでしょうか。江戸時代の意味は、戦国期の「雑兵の視点からみた戦場」の実態を知ることによって理解が進むと、この本を読んで思いました。
No.28 - マヤ文明の抹殺 [歴史]
前回の No.27「ローマ人の物語 (4) 」の最後のところで、
と書きました。今回はその補足です。「民族伝統の神々の破壊活動」はその後も延々と続けられ、ヨーロッパの外へと波及していきました。そして16世紀にその波は日本にまでやってきます。つまりキリシタン大名といわれる人たちの一部は、領内の寺院・神社を破壊しました。高山 右近(高槻、明石)がそうですし、大村 純忠(肥前)は寺院や神社の破壊だけでなく領内の墓所まで壊したはずです。しかし日本におけるこのような動きはごく一部であり、その後の幕府の強力なキリシタン禁制でなくなりました。逆に教会が破壊され、多数の殉教者を出すことになったわけです。
しかしアメリカ大陸へと波及した「民族伝統の神々の破壊活動」は、日本とは様相が違ったのです。
マヤ文明
マヤ文明は中米に興った文明です。現在の国名ではメキシコの南東部、グアテマラ、ベリーズ、ホンジュラスなどに相当します。この地の文明は紀元前から始まり、紀元200年ごろから大きな都市が建設されはじめました。3世紀から9世紀がマヤの繁栄期です。ユカタン半島の有名なチチェン・イッツァ遺跡(世界遺産)はこの時期の後期に建設されものです。マヤは統一国家を形成することはなく、都市国家が散在して合従連衝、興亡を繰り返しました。
そして16世紀になって、この地にスペイン人がやってきたのです。
抹殺されたマヤ文明
2010年11月9日の、NHK BS hi-vison「プレミアム8 世界史発掘 時空タイムズ 古代マヤ文明」で、マヤ文字の解読の歴史と最新の研究成果が紹介されました。マヤ文明は南北アメリカ大陸で発達した文明の中では唯一、文字を持つ文明です。同じ中米のアステカ文明や南米のインカ文明には文字がありません。その意味でマヤ文字の解読は、欧米人が到達する以前の新大陸の様子を知る意味で極めて重要です。
この番組の中で、2008年にアメリカのNOVAプロダクションが制作したドキュメンターが放映されました。このドキュメンタリーはマヤ文字の解読の歴史を詳細にたどり、解読の成果として分かってきたマヤの文化を解説したものです。その前半でマヤ文字の解読が困難な理由、つまりマヤ文字が抹殺された経緯が語られています。実はマヤ文字だけでなく、マヤの伝統や宗教を含む文明そのものが地上から抹殺されたのです。2人の学者がその経緯を語っています。NPO法人「マヤ研究所」の所長、ジョージ・スチュアートと、著名なマヤ学者であるイェール大学のマイケル・コウ教授です。その部分を番組から再録します。
マヤ文字の解読
マヤ文字を書くこと読むことは禁止され、文書は町の広場で焼却処分。文字を書くと処刑される。言葉は話言葉だけが頼りで、物語は口伝で伝えるしかない・・・・・・。レイ・ブラッドベリの名作「華氏451度」(1953) を連想させる話ですが、これは小説ではなく歴史上の実話なのです。これは全くの想像ですが、おそらく「華氏451度」のように、密かに隠されたマヤ文字文書をもとに文字を伝承する秘密裏の行動が行われたのではないでしょうか。見つかると処刑されるので「命懸け」ですが、民族の誇りを伝えるという目的なら人間はその程度のことはやるものです。しかし仮にそうだとしても、マヤ文字は途絶えてしまったのです。
「かろうじて焼け残った書物、ないしは書物の一部は4点だけでした」とあります。番組ではこのうちのドレスデン絵文書(ドレスデン国立博物館)を紹介していました。この絵文書を含め文書はわずかに4点しか残らなかったのです(ドレスデンの他に、パリ、マドリード、グロリアの各絵文書が残っている)。
マヤ文字は石碑や建造物の壁にも刻まれていました。これらの残された少ない文字を頼りに、マヤ文字を解読するという学者たちの苦闘が19世紀から始まります。マヤ文字のサンプルを入手するのは大変です。密林に分け入ってマヤの遺跡を探し、石碑などの文字を書き写すという作業から始めなければなりません。写真が発達していない時代には、絵文字の書き写しの曖昧さからくる混乱もあったようです。
学者たちの努力の結果、マヤ文字の解読は20世紀になってから急速に進展し、マヤの1500年の歴史が次第に明らかになってきました。神話、天体観測と暦(極めて精密なことで有名)、数の概念、宇宙観などです。また農業や当時の暮らしなど、大航海時代以前のアメリカの様子も解明が進んできました。現代では約4万種と言われるマヤ文字の8割が「読める」ようになったようです。しかし文書が焼却され、そこに書かれていたことが消滅してしまったことには変わりがありません。マヤ文字が読めるようになっても、読む対象が限られているのです。
文明の存在証明
一般に現代人が「古代文明」の存在を認識するのは何をもとにしているのでしょうか。一つは「石で作られた建造物の遺跡」です。ストーンヘンジ、エジプトのピラミッド、ローマのコロッセオやパンテオン、地中海世界一帯に残る水道橋、万里の長城、マチュピチュの「空中都市」などを見ると、その時代に文明が存在したことが誰の目にも明らかです。石で作られた建造物は後世に残りやすいので「文明の存在証明」には非常に有利です。
しかし「石で作られた建造物の遺跡」以上に文明の証明となるのは「文書」です。紀元前後の古代ローマや古代中国は文書が大量に残りそれが継承されているので、文明の様子が手に取るように分かるのです。遺跡がほとんどなくても「文書」が残っていてそれが解読できれば文明の様子は明らかになります。古代メソポタミア文明の遺跡はほとんど現存しませんが、大量に発掘された粘土板に書かれた楔形文字の解読が進んで、文明の様子がはっきりしてきました。
ある日本の歴史学者の発言を読んだことがあるのですが「鎌倉幕府の存在を考古学的発掘から証明することはできない、鎌倉に幕府があったことを証明できるのは文書記録」だそうです。なるほど。日本では「石で作られた建造物の遺跡」はほとんどないし、発掘物だけから鎌倉幕府の存在を証明するのは困難でしょう。
そしてアメリカ大陸に目を向けると、南米のインカの数々の遺跡やマチュピチュの「空中都市」の存在は、そこに高度な文明が存在したことの明かしです。しかしインカは文字を持っていません。その文明の内容は非常に解明しにくいのです。
では中米のマヤはどうでしょうか。現在残っているチチェン・イッツァ遺跡だけを見ても高度な文明の発達を推測できます。そしてマヤ文明は文字を持つ文明でした。もしマヤの文書が全て残っていたのなら、文字は比較的短期間に解読され、この文明の全貌が容易に明らかになったはずです。暗号解読と同じで、文字サンプルは多ければ多いほどよい。しかしそのマヤ文字の文書がたった4点を残して地上から姿を消してしまった。
マヤ文明は、16世紀に文明そのものが地上から消滅したのですが、それだけでなく文字記録が抹殺されることで歴史からも消滅してしまったのです。
文明の消滅
文化は文字がなくても発展できるし、継承できます。このような社会では口伝で継承する技術が発達するはずだし、特定分野の口伝専門家が育成されたり、さらにそれが代々引き継がれたりするはずです。南米のインカは文字なしで文明を築きました。しかし文字を前提とする文化が文字を禁止されると文化の継承は不可能でしょうね。「文字なし文化」や「別の文字文化」に移行するのが一朝一夕に行くとは思えない。それまで継承してきたものはほとんど全て失われていくでしょう。
文字を抹殺するということは、それまであった文化を全て抹殺し、しかも歴史上からも抹殺するということなのです。今からすると信じられないような「残虐行為」なのですが、400年前には実はこういうことが平気で行われていたのです。これはどう考えるべきなのでしょうか。
というのは誰しも思うことだと思います。
というのも妥当でしょう。マヤ文明を抹殺したのはそこにやってきたスペイン人、中でも強い宗教的使命感を持った修道士のディエゴ・デ・ランダです。しかしメキシコ高原部のアステカ王国や南米のインカ帝国で別のスペイン人の一団が何をしたかを思い出せば、異種文明をせっせと抹殺して金銀財宝を略奪していたのが当時16世紀のスペインの「行動パターン」でした。
しかしここで思うのですが、16世紀のスペイン人だけを「悪者」にするのは当たらないのではないか。程度と内容の差はありますが、マヤで起こったことと本質的に同じことが、ヨーロッパにおいて、ヨーロッパ人の手によってなされたのではないかと思うのです。
ヨーロッパの神々
No.27「ローマ人の物語 (4) 」の最後でふれたように、12世紀から13世紀にかけてヴェンド十字軍などの十字軍が組織され、北方ヨーロッパ「異教徒征伐」が繰り返えされました。この結果ゲルマン族やスラヴ族が持っていたその土地固有の宗教とそれに関連していた文化は衰退していきます。
そして十字軍を問題にする以前に4世紀末のローマ帝国の首都で、16世紀のマヤで起こったことと本質的に同じことが起こったのではないでしょうか。No.25で「ローマ人の物語」から引用した「神殿、神の像、皇帝の像、家庭の神棚などの破壊と宗教行事の廃止と禁止」そして No.27 で引用した「図書館の閉鎖」がまさにそうだと思うのです。スペイン人がマヤ文化を破壊した時には文書までもが焼却されました。しかしローマではマヤとは違ってラテン語の文書や文字は残りました。「幸いなことに」破壊したのがローマ人だったので、自分たちの言葉(文字)までは抹殺しようがなかった。
「マヤ人は悲惨な目にあった」わけですが、同じ理屈で「ローマ人も悲惨な目にあった」し、その後に「ヨーロッパ人も悲惨な目にあった」のだと思います。悲惨の程度は違いますが・・・・・・。
しかしヨーロッパにおいてはマヤとは違って、固有文化が全く消滅したわけではありません。ギリシャ・ローマ・ゲルマン・スラヴの神話は伝承され続けています。No.14 - No.17 の「ニーベルングの指環」はそういった神話を「ネタ」にしているのでした。また紀元前からヨーロッパにあったケルト文化は、近代以降それを発掘・保存し、また伝承しようという動きが広まります。No.8「リスト:ノルマの回想」でふれたベッリーニのオペラ「ノルマ」の主人公はケルトの巫女であり、オペラのストーリーはケルト人社会とローマ軍の葛藤を描いているわけですが、これもケルトに光をあてようという大きな動きの中で出てきた一つの芸術作品だと思います。
そしてヨーロッパの固有文化を強く感じさせる典型的な例が、No.27「ローマ人の物語 (4) 」の最後のところにも書いた「レッチェンタールの謝肉祭」です。
| 「民族伝統の神々の破壊」はローマやコンスタンチノープルという首都だけでなく、ローマ帝国全域で行われました。さらにその後のヨーロッパの歴史をみると、ローマ帝国の領域の周辺へと「民族伝統の神々の破壊活動」が拡大していきます。 |
と書きました。今回はその補足です。「民族伝統の神々の破壊活動」はその後も延々と続けられ、ヨーロッパの外へと波及していきました。そして16世紀にその波は日本にまでやってきます。つまりキリシタン大名といわれる人たちの一部は、領内の寺院・神社を破壊しました。高山 右近(高槻、明石)がそうですし、大村 純忠(肥前)は寺院や神社の破壊だけでなく領内の墓所まで壊したはずです。しかし日本におけるこのような動きはごく一部であり、その後の幕府の強力なキリシタン禁制でなくなりました。逆に教会が破壊され、多数の殉教者を出すことになったわけです。
しかしアメリカ大陸へと波及した「民族伝統の神々の破壊活動」は、日本とは様相が違ったのです。
マヤ文明
 | |||
チチェン・イッツァ遺跡
マヤの最高神ククルカン(羽毛のあるヘビの姿の神)を祀る。春分と秋分の日に太陽が沈む時、遺跡は真西から照らされ、階段の西側に蛇が身をくねらせた姿が現れる。
| |||
そして16世紀になって、この地にスペイン人がやってきたのです。
抹殺されたマヤ文明
2010年11月9日の、NHK BS hi-vison「プレミアム8 世界史発掘 時空タイムズ 古代マヤ文明」で、マヤ文字の解読の歴史と最新の研究成果が紹介されました。マヤ文明は南北アメリカ大陸で発達した文明の中では唯一、文字を持つ文明です。同じ中米のアステカ文明や南米のインカ文明には文字がありません。その意味でマヤ文字の解読は、欧米人が到達する以前の新大陸の様子を知る意味で極めて重要です。
この番組の中で、2008年にアメリカのNOVAプロダクションが制作したドキュメンターが放映されました。このドキュメンタリーはマヤ文字の解読の歴史を詳細にたどり、解読の成果として分かってきたマヤの文化を解説したものです。その前半でマヤ文字の解読が困難な理由、つまりマヤ文字が抹殺された経緯が語られています。実はマヤ文字だけでなく、マヤの伝統や宗教を含む文明そのものが地上から抹殺されたのです。2人の学者がその経緯を語っています。NPO法人「マヤ研究所」の所長、ジョージ・スチュアートと、著名なマヤ学者であるイェール大学のマイケル・コウ教授です。その部分を番組から再録します。
|
マヤ文字の解読
マヤ文字を書くこと読むことは禁止され、文書は町の広場で焼却処分。文字を書くと処刑される。言葉は話言葉だけが頼りで、物語は口伝で伝えるしかない・・・・・・。レイ・ブラッドベリの名作「華氏451度」(1953) を連想させる話ですが、これは小説ではなく歴史上の実話なのです。これは全くの想像ですが、おそらく「華氏451度」のように、密かに隠されたマヤ文字文書をもとに文字を伝承する秘密裏の行動が行われたのではないでしょうか。見つかると処刑されるので「命懸け」ですが、民族の誇りを伝えるという目的なら人間はその程度のことはやるものです。しかし仮にそうだとしても、マヤ文字は途絶えてしまったのです。
「かろうじて焼け残った書物、ないしは書物の一部は4点だけでした」とあります。番組ではこのうちのドレスデン絵文書(ドレスデン国立博物館)を紹介していました。この絵文書を含め文書はわずかに4点しか残らなかったのです(ドレスデンの他に、パリ、マドリード、グロリアの各絵文書が残っている)。

|
|
|
学者たちの努力の結果、マヤ文字の解読は20世紀になってから急速に進展し、マヤの1500年の歴史が次第に明らかになってきました。神話、天体観測と暦(極めて精密なことで有名)、数の概念、宇宙観などです。また農業や当時の暮らしなど、大航海時代以前のアメリカの様子も解明が進んできました。現代では約4万種と言われるマヤ文字の8割が「読める」ようになったようです。しかし文書が焼却され、そこに書かれていたことが消滅してしまったことには変わりがありません。マヤ文字が読めるようになっても、読む対象が限られているのです。
文明の存在証明
一般に現代人が「古代文明」の存在を認識するのは何をもとにしているのでしょうか。一つは「石で作られた建造物の遺跡」です。ストーンヘンジ、エジプトのピラミッド、ローマのコロッセオやパンテオン、地中海世界一帯に残る水道橋、万里の長城、マチュピチュの「空中都市」などを見ると、その時代に文明が存在したことが誰の目にも明らかです。石で作られた建造物は後世に残りやすいので「文明の存在証明」には非常に有利です。
しかし「石で作られた建造物の遺跡」以上に文明の証明となるのは「文書」です。紀元前後の古代ローマや古代中国は文書が大量に残りそれが継承されているので、文明の様子が手に取るように分かるのです。遺跡がほとんどなくても「文書」が残っていてそれが解読できれば文明の様子は明らかになります。古代メソポタミア文明の遺跡はほとんど現存しませんが、大量に発掘された粘土板に書かれた楔形文字の解読が進んで、文明の様子がはっきりしてきました。
ある日本の歴史学者の発言を読んだことがあるのですが「鎌倉幕府の存在を考古学的発掘から証明することはできない、鎌倉に幕府があったことを証明できるのは文書記録」だそうです。なるほど。日本では「石で作られた建造物の遺跡」はほとんどないし、発掘物だけから鎌倉幕府の存在を証明するのは困難でしょう。
そしてアメリカ大陸に目を向けると、南米のインカの数々の遺跡やマチュピチュの「空中都市」の存在は、そこに高度な文明が存在したことの明かしです。しかしインカは文字を持っていません。その文明の内容は非常に解明しにくいのです。
では中米のマヤはどうでしょうか。現在残っているチチェン・イッツァ遺跡だけを見ても高度な文明の発達を推測できます。そしてマヤ文明は文字を持つ文明でした。もしマヤの文書が全て残っていたのなら、文字は比較的短期間に解読され、この文明の全貌が容易に明らかになったはずです。暗号解読と同じで、文字サンプルは多ければ多いほどよい。しかしそのマヤ文字の文書がたった4点を残して地上から姿を消してしまった。
マヤ文明は、16世紀に文明そのものが地上から消滅したのですが、それだけでなく文字記録が抹殺されることで歴史からも消滅してしまったのです。
文明の消滅
文化は文字がなくても発展できるし、継承できます。このような社会では口伝で継承する技術が発達するはずだし、特定分野の口伝専門家が育成されたり、さらにそれが代々引き継がれたりするはずです。南米のインカは文字なしで文明を築きました。しかし文字を前提とする文化が文字を禁止されると文化の継承は不可能でしょうね。「文字なし文化」や「別の文字文化」に移行するのが一朝一夕に行くとは思えない。それまで継承してきたものはほとんど全て失われていくでしょう。
文字を抹殺するということは、それまであった文化を全て抹殺し、しかも歴史上からも抹殺するということなのです。今からすると信じられないような「残虐行為」なのですが、400年前には実はこういうことが平気で行われていたのです。これはどう考えるべきなのでしょうか。
| マヤ人は悲惨な目にあった |
というのは誰しも思うことだと思います。
| 当時の、アメリカに渡ったスペイン人はひどいことをした |
というのも妥当でしょう。マヤ文明を抹殺したのはそこにやってきたスペイン人、中でも強い宗教的使命感を持った修道士のディエゴ・デ・ランダです。しかしメキシコ高原部のアステカ王国や南米のインカ帝国で別のスペイン人の一団が何をしたかを思い出せば、異種文明をせっせと抹殺して金銀財宝を略奪していたのが当時16世紀のスペインの「行動パターン」でした。
ディエゴ・デ・ランダについて私はよく知らないのですが、どういう人物だったのでしょうか。
のどちらに近いのでしょうか。マヤ文明の抹殺の顛末からすると①だと思ってしまいますが、②かもしれません。日本で寺院・神社を打ち壊し僧侶・神官を迫害した高山右近は明らかに②です。彼を慕ってキリスト教に入信した人も多かったようです。 |
しかしここで思うのですが、16世紀のスペイン人だけを「悪者」にするのは当たらないのではないか。程度と内容の差はありますが、マヤで起こったことと本質的に同じことが、ヨーロッパにおいて、ヨーロッパ人の手によってなされたのではないかと思うのです。
ヨーロッパの神々
No.27「ローマ人の物語 (4) 」の最後でふれたように、12世紀から13世紀にかけてヴェンド十字軍などの十字軍が組織され、北方ヨーロッパ「異教徒征伐」が繰り返えされました。この結果ゲルマン族やスラヴ族が持っていたその土地固有の宗教とそれに関連していた文化は衰退していきます。
そして十字軍を問題にする以前に4世紀末のローマ帝国の首都で、16世紀のマヤで起こったことと本質的に同じことが起こったのではないでしょうか。No.25で「ローマ人の物語」から引用した「神殿、神の像、皇帝の像、家庭の神棚などの破壊と宗教行事の廃止と禁止」そして No.27 で引用した「図書館の閉鎖」がまさにそうだと思うのです。スペイン人がマヤ文化を破壊した時には文書までもが焼却されました。しかしローマではマヤとは違ってラテン語の文書や文字は残りました。「幸いなことに」破壊したのがローマ人だったので、自分たちの言葉(文字)までは抹殺しようがなかった。
「マヤ人は悲惨な目にあった」わけですが、同じ理屈で「ローマ人も悲惨な目にあった」し、その後に「ヨーロッパ人も悲惨な目にあった」のだと思います。悲惨の程度は違いますが・・・・・・。
しかしヨーロッパにおいてはマヤとは違って、固有文化が全く消滅したわけではありません。ギリシャ・ローマ・ゲルマン・スラヴの神話は伝承され続けています。No.14 - No.17 の「ニーベルングの指環」はそういった神話を「ネタ」にしているのでした。また紀元前からヨーロッパにあったケルト文化は、近代以降それを発掘・保存し、また伝承しようという動きが広まります。No.8「リスト:ノルマの回想」でふれたベッリーニのオペラ「ノルマ」の主人公はケルトの巫女であり、オペラのストーリーはケルト人社会とローマ軍の葛藤を描いているわけですが、これもケルトに光をあてようという大きな動きの中で出てきた一つの芸術作品だと思います。
そしてヨーロッパの固有文化を強く感じさせる典型的な例が、No.27「ローマ人の物語 (4) 」の最後のところにも書いた「レッチェンタールの謝肉祭」です。
(次回に続く)
No.23 - クラバートと奴隷(2)ヴェネチア [歴史]
(前回より続く)
前回の No.22「クラバートと奴隷(1) 」の最後に、ヨーロッパの商人は、中央ヨーロッパとは別の奴隷の仕入れ先を開拓、と書きました。ヴェネチアの興亡を描いた、塩野七生著「海の都の物語」には、前回の中世ヨーロッパとは別のタイプの奴隷貿易が書かれています。
第4回十字軍と黒海貿易
| ||||||||
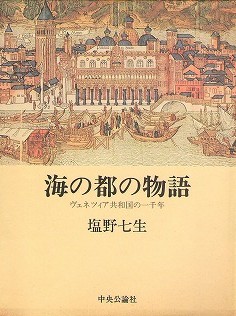
| ||||||||
一方、地中海地方では何と、キリスト教国である東ローマ帝国を攻める「第4次十字軍」が組織され、首都・コンスタンティノープルを征服しました(13世紀初頭。1202-03)。十字架を掲げる国を「十字軍」が攻撃するのだから何とも奇妙な話なのですが、要するに「宗教戦争」とは無縁の、東ローマ帝国の国力の衰えにつけこんだ領土拡張・戦利品略奪戦争だったわけです。この結果、ヴェネチアはコンスタンティノープルに居留地を確保し、地中海と黒海をつなぐボスフォロス海峡を自由に通行できるようになりました。それまでヴェネチアはコンスタンティノープルでギリシャ商人が黒海沿岸から運んでくる交易品を買い、それを西欧やエジプトに運んで売っていたのですが、黒海沿岸と直接に交易できるようになったのです。おそらくそれこそが、東ローマ帝国に戦争をしかけた最大の理由だったのでしょう。
この黒海沿岸からの輸入品とは何だったのでしょうか。
塩野七生さんの「海の都の物語 ヴェネツィア共和国の一千年」(中央公論社 1980)は、ヴェネツィアの勃興から終焉までの1000年を描いた興味深い本です。以下、この本から引用します。
|
「ヨーロッパ地方に(奴隷の)供給源がなくなってしまった」と塩野さんが書いているのは、前回 No.22「クラバートと奴隷 (1) 」 の「ヴェンド十字軍」の説明のところで書いたように、ヨーロッパがキリスト教国化された、ということです。「黒海を新たに市場に加えられることになったのは、この面でも、西欧の商人にとっては大きな収穫であった」とありますね。ということは「西欧に奴隷の供給源がある時期には、ヴェネチア商人(西欧の商人)にとっての奴隷の供給源は西欧であった」ということです。これは前回 (No.22) の中世の奴隷貿易の話と整合的です。
 上記の引用に出てくる「ターナ」とは、黒海沿岸の最北部の町で、現在のアゾフ(ロシア連邦共和国)です。ターナにはヴェネチア人が都市を築いて居住し、貿易の拠点としていました。
上記の引用に出てくる「ターナ」とは、黒海沿岸の最北部の町で、現在のアゾフ(ロシア連邦共和国)です。ターナにはヴェネチア人が都市を築いて居住し、貿易の拠点としていました。また文中に出てくるカフカス(コーカサス)の奴隷(女性)で有名なのが「チェルケスの美女」ですね。チェルケスはカフカス地方北部の小さな地域なのですが、ここは金髪・碧眼のアングロ・サクソンにも似た風貌の人たちが多い。山内昌之・東京大学教授の「帝国のシルクロード」(朝日新書。2008)には、少し時代は下りますが、オスマン帝国の奴隷の様子が次のように書いてあります。
|
奴隷として売られていく女性の立場から言うと、幸運な者だけがハーレムに入り、その中の一部が皇帝の寵愛をうけ、そのまた幸運な者が皇帝の子(王子)を生み、その中の一人が次期皇帝の母となったわけですね。限りなくゼロに近い確率だろうけど・・・・・・。ハーレムにさえ入れなかった奴隷は悲惨な運命をたどったでしょう。
塩野さんの本にはヴェネチアの黒海貿易を支えた貿易航路(ムーダ)の話も出てきます。当時のヴェネチアの隆盛が垣間見える記述なので、紹介します。
ムーダ
「ムーダ」とはヴェネチア政府が運営する定期貿易船の制度で、1255年に創設されました。数隻の船団を組み、春にヴェネチアを出港して秋に帰国する、または秋に出港し、翌春に帰国するというパターンでした。
「ムーダ」は基本的にガレー船(漕ぎ手がオールで漕ぐ船)でしたが、帆船も併用されていました。船と積み荷の関係を理解するため、ガレー船と帆船がどのように使い分けられていたのか、まずそれについての塩野さんの解説を引用します。太字は原文にはありません。
|
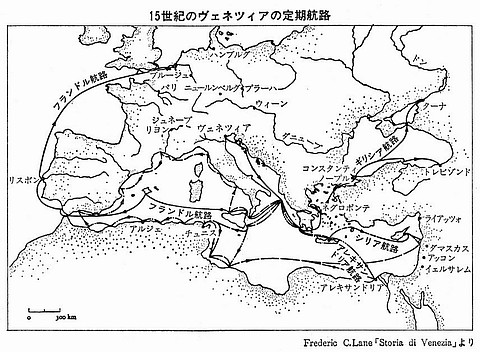
「ムーダ」のメイン航路は4つありました。
| 1. | ギリシア航路(コンスタンティノープル経由で黒海) |
| 2. | キプロス、シリア、パレスティーナ航路 |
| 3. | アレキサンドリア航路 |
| 4. | フランドル航路(ジブラルタル海峡を経由してイギリス、フランドル) |
の4つです。1~3の航路は、ヴェネツィアからギリシャ(ペロポネソス半島)までは同じです。そこから、黒海方面、中東方面、エジプト方面と分かれたわけです。では、これらそれぞれの航路の、ヴェネツィアにとっての輸入品と輸出品は何だったのでしょうか。再び塩野さんの解説です。
|
|
「奴隷はガレー船に積むのを禁止する」という政府の規制は、要するに「単位体積あたり」ないしは「単位重量あたり」の商品価値の問題ですね。ガレー船は輸送コストが高い、従って単位体積(重量)当たりの利幅が大きい商品しか積載してはダメである、奴隷は高額商品だが、輸送のコスト・パフォーマンスの観点からは木材の部類である・・・・・・。きわめてまっとうなビジネス判断です。
このムーダはメイン航路であり、そこにつながる種々の「サブ航路」があったようです。
|
アンドレア・バルバリーゴという、1400年頃に生まれたヴェネチア商人が紹介されています。この商人の簿記はすべて残されているのです。その簿記から彼が「ムーダ」を活用してどんなビジネスをしていたかが分かります。
|
シャイロックの反論
少々余談になります。塩野さんも書いているように、ヴェネチア人は奴隷貿易をするだけでなく、自らも奴隷を使っていました。これに関して思いだすのが、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』です。
『ヴェニスの商人』の中の、例の「人肉裁判」のシーンで、シャイロックはアントニオの借金の担保として契約書に明記した人肉1ポンドを差し出すよう、強硬に主張します。それに対し「人でなし!」などの非難ごうごうになるのですが、シャイロックは「奴隷」を持ち出して次のように反論します。
シャイロック |
要するに、金で買った奴隷は自分のもの、それと同じで、人肉1ポンドは大金で買ったも同然で自分のもの、早く頂戴したい、という論理です。
黒海・地中海奴隷貿易
本題に戻ります。塩野さんの解説を奴隷との関係で要約しますと、以下のようになるでしょう。
| 1. | ヴェネチアは、黒海から地中海をむすぶ海上交易船路を運営していて、奴隷も交易品の一つだった。この交易船路において奴隷はガレー船ではなく、帆船で輸送された。 |
| 2. | 奴隷の「仕入れ」は黒海沿岸(ターナなど)であり、主な販売先はキプロス、クレタ、シリア、エジプトなどの東地中海であった。また西欧に販売することもあった。 |
| 3. | 黒海沿岸で奴隷になったのは、タタール人、スラヴ人、カフカス人などであった。 |
ヴェネチアが興隆した中世から近代の時期において、イタリアには海洋貿易で繁栄した都市国家が他にもあります。ジェノヴァ、アマルフィ、ピサなどです。中でもジェノヴァの勢力は強大で、ヴェネチアとの覇権争いが何度も起きました。そしてこの時代の黒海沿岸地方の有力な輸出品が「奴隷」であり、その奴隷にスラヴ民族も含まれていた。「スラヴ=スレイヴ」の状況は、まだ続いていたのです。
クラバートと奴隷
題名とした「クラバートと奴隷」の関連を、前回 (No.22) の内容とあわせてまとめると次のようになります。
クラバートの舞台であるドイツのラウジッツ地方(およびそれより東方)のスラヴ人たちが奴隷貿易の対象になったと推定できるのは8世紀から11世紀の頃でした。クラバートは18世紀初頭の話です。クラバートの先祖は700年以上前に「スラヴ人=奴隷」の時代を経験したのだと想像します。クラバートの物語にキリスト教の行事がたびたび出てくるように、キリスト教に改宗してからすでに長い時間が経っています。この時代に奴隷はありません。
しかしクラバートの時代、オスマン・トルコ帝国がまだ強大な勢力を誇っていました。少し前の17世紀後半には、オスマン帝国によるウィーン包囲戦(第2次ウィーン包囲。1683)という大戦闘が起きました。この戦いはヨーロッパ軍の勝利に終わり、これ以降、ヨーロッパのオスマン帝国に対する軍事的優位が確立していきます。ということは、17世紀後半にオスマン・トルコが最も強大だったということです。クラバートの物語の中には、水車場の親方が魔法使いとして神聖ローマ帝国軍に従軍し、オスマン帝国軍と戦うエピソードが出てきます(No.1「千と千尋の神隠し」と「クラバート」(1) )。親方はこの戦いでオスマン帝国軍にやとわれていた友人の魔法使いのイルコーを殺したのでした。当時の神聖ローマ帝国もオスマン帝国も、ともにスラヴ民族を含む多民族国家です。スラヴ民族同士が戦ったことも十分考えられるでしょう。オスマン帝国は奴隷を兵士にもしました。クラバートの親方が戦ったトルコ軍の中にはスラヴ人の奴隷もいたかもしれません。そしてもちろん、オスマン帝国の首都(のハーレム)には、スラヴ人の女性奴隷がいたのです。
優秀な奴隷商人
奴隷貿易の成立の条件を考えてみたいと思います。奴隷の供給源は、一つは戦争の捕虜や強制拉致です。古代ローマが周辺国と戦争をする時には、確か軍隊とともに奴隷商人が一緒についていったはずです。奴隷商人にとって戦争は大きなビジネスチャンスです。こういった「戦争捕虜」「強制拉致」「奴隷狩り」などによる奴隷は、いわば「強制奴隷」です。直感的には奴隷のほとんどが「強制奴隷」でしょう。
しかし、もう一つの非常に気になる奴隷の供給源があります。それは、前述の「帝国のシルクロード」で山内教授が指摘しているように、奴隷商人が「正当な対価」を払って奴隷を「仕入れる」ケースです。これを「半強制奴隷」と呼ぶことにします。いくらお金を積まれても、奴隷になる本人の自由意志で進んで奴隷になりたい、というケースはまれでしょうから「半強制」とします。
この「半強制奴隷」の貿易が「継続的かつ長期に」成立するとき、それがなぜ成立するのか。これが以下の考察のテーマです。これは次の3つの条件が成立するからだと思います。
| 条件1(需要): | 奴隷を使う生活スタイルや、奴隷を使った農業・鉱業生産の地域や国が存在する。つまり「需要」がある。かつ、その需要者が奴隷という「高額商品」を購入できるほど経済的に豊かである。 |
| 条件2(商人): | 交易で利益をあげようとする商人が存在し、交易のインフラストラクチャ(輸送手段など)を持っている。ないしは活用できる。ムーダのように。 |
| 条件3(供給): | 貧しい者、ないしは自分は貧しいと認識している者が交易(取引)をしたいと考え、差し出すものに窮したときに、最後に出してくるのが「人」である。このシチュエーションが成立する。 |
まず条件1(需要)が前提です。これがないと奴隷貿易はありません。その次に重要なのは条件2(商人)つまり「奴隷商人」の存在でしょう。ちょっと「優秀な奴隷商人」はどういうものか、考えてみたいと思います。奴隷の需要があることを認識した「優秀な奴隷商人」が、武力を一切使わずに、自ら半強制奴隷の供給地を開拓し、継続的に奴隷の貿易をやって多大な利益をあげようと思ったら、おそらく次のようにすると思いますね。
まず、奴隷の供給地を探しに出かけます。香料、織物、宝飾品などの高額商品の産地には行きません。そういう地域は奴隷の供給源にならない。そこからは高額商品を輸入すればよいわけです。飢饉などで生活が困窮している地域、戦争で荒廃した地域は奴隷の有力な供給地です。しかし「継続的かつ長期の供給地」にはならないでしょう。飢饉はいずれ終わります。
優秀な奴隷商人は、めぼしい産物のない、自給自足的な生活を昔から送っている「貧しい」地域に行き、そこに拠点を築きます。そしてその地域を「商品経済」に巻き込もうとします。精製塩、食料、宝飾品、衣類など、その地域では簡単には入手できないような素晴らしい品を持っていって、そこで売るのです。めぼしい産物がない「貧しい」地域なので住民にお金は大してなく、商品はあまり売れません。しかし優秀な奴隷商人の真の狙いは商品を売ることではありません。「あなたがたは貧しいのですよ」というメッセージを住民に送り続け「自分たちは貧しいのだ」と思いこませ「お金さえあればもっと楽な生活ができる」と感化することが真の狙いです。
この「感化」が成功すると、あとは比較的簡単です。「あなたの息子(娘)を XXX のお金でどうです」と持ちかければよい。住民としては価値の高い有力な産物を作り出せればよいが(そして、それがまっとうなやり方だが)、差し出すものがなければ「人」を交易品とするしかない。
いったんこの取引が成立すると、その地域で継続的になる可能性が強いと思います。苦労して遠くの山に岩塩を取りにいくという生活ではなく、商人から精製塩をお金で買うという生活がいったん出来あがると、元には戻れない。人間の欲望を増進させる手段は限りなくあるのです。ひとたび誰かが奴隷を差し出すと、他の家族も心理的障壁がなくなります。家族を奴隷商人に売るにしても「一家のため」「地域のため」という理由づけができる。売られていく少年(少女)にしても「一家や地域のための自己犠牲」という物語が作れる。
つまり「半強制奴隷」の交易を継続的に続けようと思ったら、条件3(供給)の「自分は貧しいと認識した者が交易をしたいと考え、差し出すものに窮したときに最後に出してくるのが "人" である。このシチュエーションを成立させる」わけです。優秀な奴隷商人としては。
奴隷は過去のものか
以上の考察はあくまで想像上のものです。しかし、意味としてはこれとそっくりな状況が現代社会においても起こっているのではないでしょうか。
現代でも「人身売買」はあるようです。新聞紙にときどき発展途上国での人身売買の記事がのります。人身売買スレスレの、金銭で拘束した強制労働もあるようです。しかしこういった「人身売買」はあくまで非合法なものです。少なくとも、基本的人権を確立している現代国家において「奴隷」は、ない。
しかし現代ではそういった「非合法人身売買」ではなく、自由意志で自ら進んで奴隷的状態に身を置く人が増えているのではないでしょうか。つまり「貧しい者が交易をしたいと考え、差し出すものに窮したときに最後に出してくるのが "人" である。このシチュエーションが現代日本のある部分においても成立している」のではと思うのです。特に、決まった職業を持たず、アルバイトで食いつないで最低限の生活をしている、いわゆる「若年貧困層」と言われる人たちです。
ある人が標準的、ないしは標準以上の収入を得ようとすると、その人が「技術」「経験」「知識」「ノウハウ」「人間力」(リーダーシップ、コミュニケーション能力、等)などの「稼ぎの源泉」となる能力を持っていることが必要です。その稼ぎの源泉に対して「お金」が支払われる。企業がそういう能力をあまり持たない新入社員に給料を払うのは、何年か後に「稼ぎの源泉」を持つだろう(そして企業に貢献するだろう)という強い想定があるからです。
従って、金銭面で標準的な生活をするためには、次のA~Dのような行動に出ることが是非とも必要になります。
| A. | 長期の学習を行って、知識ないしは技術を身につける。この最たるものが医者や弁護士ですが、それ以外にもいっぱいあります。 |
| B. | 組織に入り、上司の叱責にも耐えながら、仕事を覚え、その分野や業界のプロをめざす。 |
| C. | 技術の伝承を目的に「弟子入り」をして、下積み生活をしながら、その道の腕を磨く。 |
| D. | 勉強ないしは実務経験によって公的資格をとり、その資格で職に就く。 |
これらはあくまで例なので、A~D以外にもいろいろとあります。しかしどのような方法であれ、自己の欲求を制限して努力をすることが前提になります。人間社会で生きていくためには、自らの欲望を制限し、自由行動を抑制しながら、外的環境に自己を合わせ、努力を重ねて、応分の対価が得られる労働ができるまでに自己を成長させることが必要なわけです。あたりまえだけど。
しかし現代日本の一部のメディアは、それとは別の事を言っている。つまり「A~Dのような行為に必要な自己の抑制や欲望の制限は人間的な生活に反するものだから、もっと自由に生きよう」とか「外的条件に自分をあわせるのではなく、自分のやりたいことをやろう。そのための自分探しをしよう」というようなメッセージを陰に陽にタレ流しているメディアがある。もちろん多くの人はそういったメッセージの誘惑には引っかからないのですが、小さいときから「自分の欲望を制限すること」や「自由行動を抑制すること」をしていない人間、「がまんすることの価値」や「努力することの価値」を教えられないで育った人間の中には、そういうメッセージを鵜呑みにする者も出てくる。さすがに初めから「鵜呑み」にする人は少ないのかもしれない。つまり「応分の対価が得られる労働ができるまでに自己を成長させる」努力を少しはやる。しかしすぐにそれを放棄してしまう。努力したのだけどできなかった、という自分に対する言い訳のもとに・・・・・・。
少数の潜在能力に長けた人間は、自己の抑制や規制をしなくてもうまくいくかもしれません。しかし多くの人はそうではない。「技術」「経験」「知識」「ノウハウ」「人間力」のどれもなく、短期雇用を繰り返して「差し出すものが生身の"人"しかない」状態になり、悪循環で貧困層に陥るというパターンをたどる。
もちろん、若年貧困層と言われる人たちの中には「就職した会社が倒産した」とか「会社の業績不振で解雇された」とか「体を壊して正規雇用で働けなくなった」といった、本人の責任とは言えない「かわいそうなケース」もあるのは確かです。しかしそうではなく「自由意志で」若年貧困層になる人も多いのではないか。親に「寄生」している人は外面的には貧しいと見えないはずです。だけど実態は「貧しい」。こういうケースも多いのではないか。
あえて現実と小説を比較しますと、対照的なのがクラバート (No.1, No.2) です。水車場での3年間は、絶対権力者の親方のもとでの厳しい労働の連続でした。外面的にはいかにも奴隷のように見えます。しかしクラバートは奴隷ではない。3年の間に彼は、粉ひき職人として親方にもなれるだけの技量や指導力を身につけ、水車場から脱出することによって自立します。「人間社会で生きていく」とはどういうことかが典型として描かれています。
現代社会において「差し出すものが生身の "人" しかない」貧困層に対する需要は膨大にあります。そして一部のメディアは人間の欲望を肥大化させ、それと同時に自己抑制を悪であると暗に宣伝することによって貧困層の生産に役立っています。「貧しい者が交易をしたいと考え、差し出すものに窮したときに最後に出してくるのが "人" である。このシチュエーションが成立している」のは、奴隷貿易が行われていた時代だけでなく、現代日本においてもではないでしょうか。「優秀な奴隷商人」は現代にもいるのだと思います。
No.19「ベラスケスの怖い絵」で、
| 世界の歴史をマクロ的に見ると「生きた人間を何の疑問も持たず、牛馬と同等の労働力や愛玩物とし、売買の対象やそれと同等の扱いとした時代」がほとんどだったわけです。そのことを忘れてはならないと思います。 |
と書きましたが、人間社会で起こることは突き詰めて本質を考えると、時代が1000年・2000年と違っても、そうは変わらないと思うのです。歴史を振り返る現代的な意義はそこにあると思います。
| 補記1:ジェローム『奴隷市場』 |
アメリカのマサチューセッツ州の西端に「クラーク美術館」があります。この美術館は建築家・安藤忠雄氏の設計による増築・改築進んでおり、そのため2011年から主要美術品を集めた巡回展が世界各国で開催されています。日本での展覧会が2013年2月9日から東京丸の内の三菱一号館美術館で開催されたので行ってきました。
何しろ出展された73作品のうち59作品が日本初公開だとあります。またクラーク美術館は日本からは非常に行きにくいところにあります(ボストンからクルマで3時間)。今回展示された絵画の「実物」を見た日本人は僅かだと思います。もちろん私も初めてでした。
展示作品は印象派の絵(特に、ルノワール)が圧巻だったのですが、中には印象派の「仇敵」だったアカデミズムの大家、ジャン=レオン・ジェローム(1824-1904)の作品が3点ありました。その中の1枚は有名な『奴隷市場』(1868)です。

| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム
分かりにくいが、よく見ると画面の右端に黒人男性の奴隷が取引されている様子が描かれている。
| ||
この作品は「現実」を描いたものでしょうか。ジェロームは数々の取材旅行を行い、特にエジプトとトルコには7回も行ったとあります。しかし展覧会の「図録」には、19世紀においてこの絵で描かれたような戸外での奴隷取引があったという証拠はないと解説してあります。画家は時代・場所を特定せずに「想像で」この絵を描いたものと考えられます。
しかし、No.22-23「クラバートと奴隷」で書いたように、この絵と類似した情景が8世紀から18世紀のヨーロッパと地中海沿岸地域であったことは事実でしょう。そしてその場所も、ジェロームの絵が示しているような北アフリカや中東(現在のイスラム文化圏)だけでなく、イタリア、スペイン、フランス、ドイツなど(現在のキリスト教文化圏)も含まれ、また奴隷も奴隷商人も買い手も、白人からアラブ人、黒人まで多様だったのが歴史的事実なのです。
展覧会の図録でクラーク美術館の学芸員はこの絵を次のように解説していましたが、非常に正確だと思いました。
|
(2013.3.17)
| 補記2:イタリア商人による奴隷貿易 |
記事の本文で13世紀の第4回十字軍の結果、ヴェネチアが黒海沿岸を新たな奴隷の供給地として開拓したことを書きました。これはもちろん「新たな奴隷の供給地」であって、それ以前からヴェネチアを含むイタリアの商人たちは奴隷貿易に従事していたわけです。このあたりの歴史を Wikipedia の記述で紹介します。
前回の No.22「クラバートと奴隷(1)スラヴ民族」の「補記1」で、Wikipedia の「Slavery in medieval Europe(中世ヨーロッパの奴隷)」という記事からユダヤ商人の奴隷貿易を引用しましたが、この記事にはイタリア商人による奴隷貿易も書かれています。その試訳を掲載します。念のために原文も引用しておきます(参考文献の注釈は省略しました)。
Wikipedia(2018.10.11 現在) 【試訳】
中世ヨーロッパの奴隷
2. 奴隷貿易
2.1 イタリア商人
ローマ法王・ザカリアス(在位:741-752)の治世の頃までに、ヴェネチアは奴隷交易での繁栄を確立した。彼らはイタリアやその他の地域から奴隷を買い、アフリカのムーア人に売った。もっともザカリアス自身はローマ外での奴隷交易を禁止したと伝えられている。
ロタール協定(訳注:ベネチアとカロリング朝フランク王国の協定。840年)によってキリスト教徒の奴隷をイスラムに売ることが禁止されると、ヴェネチア商人はスラヴ人やその他、東ヨーロッパの非キリスト教徒の奴隷の大々的な交易に乗り出した。東ヨーロッパから奴隷のキャラバンが、オーストリア・アルプスの山道を超えてヴェネチアに到着した。
ドナウ河畔のザンクト・フローリアンの近くのラッフェルステッテン(訳注:現オーストリアのアステン。リンツより少しドナウ下流)の通行税の記録(903-906)には、そんな商人たちの記述がある。商人の中にはボヘミアやキエフ公国のスラヴ人自身もいた。彼らはキエフ公国からプシェムシルやクラコフ(訳注:いずれもポーランドの都市)、プラハ、ボヘミアを経由して来ていた。
記録によると、女の奴隷は1トレミシス金貨(約1.5グラムの金。ディナール金貨の1/3)であり、女よりも圧倒的に数が多い男の奴隷は1サイガ銀貨(トレミシスより価値がかなり落ちる)であった。
宦官は非常に貴重であり、この需要に対応するため、他の奴隷市場と同じように "去勢所"(castration house)がヴェネチアに作られた。
ヴェネチアだけが奴隷貿易の拠点だったのではない。南部イタリアの都市も遠隔地からの奴隷獲得を競っていた。ギリシャやブルガリア、アルメニア、そしてスラヴ圏である。9~10世紀にはアマルフィが北アフリカへの奴隷輸出の多くを担った。
ジェノヴァは12世紀ごろからヴェネチアとともに東地中海での交易を押さえ、また13世紀からは黒海での交易を支配した。彼らはバルト海沿岸の民族やスラヴ人、アルメニア人、チェルケス人、ジョージア(グルジア)人、トルコ人、その他、黒海沿岸やコーカサス地方の民族を中東のイスラム国に売った。ジェノヴァはクリミアからマムルーク朝エジプトへの奴隷貿易を13世紀まで支配したが、東地中海でのヴェネチアの勢力が強大になると、ヴェネチアがとって代わった。
1414年から1423年の間だけで、少なくとも10,000人の奴隷がヴェネチアで取引された。
Wikipedia(as of 2018.10.11)
Slavery in medieval Europe
2. Slave trade
2.1 Italian merchants
By the reign of Pope Zachary (741-752), Venice had established a thriving slave trade, buying in Italy, amongst other places, and selling to the Moors in Northern Africa (Zacharias himself reportedly forbade such traffic out of Rome). When the sale of Christians to Muslims was banned (pactum Lotharii), the Venetians began to sell Slavs and other Eastern European non-Christian slaves in greater numbers. Caravans of slaves traveled from Eastern Europe, through Alpine passes in Austria, to reach Venice. A record of tolls paid in Raffelstetten (903-906), near St. Florian on the Danube, describes such merchants. Some are Slavic themselves, from Bohemia and the Kievan Rus'. They had come from Kiev through Przemysl, Krakow, Prague, and Bohemia. The same record values female slaves at a tremissa (about 1.5 grams of gold or roughly 1/3 of a dinar) and male slaves, who were more numerous, at a saiga (which is much less). Eunuchs were especially valuable, and "castration houses" arose in Venice, as well as other prominent slave markets, to meet this demand.
Venice was far from the only slave trading hub in Italy. Southern Italy boasted slaves from distant regions, including Greece, Bulgaria, Armenia, and Slavic regions. During the 9th and 10th centuries, Amalfi was a major exporter of slaves to North Africa. Genoa, along with Venice, dominated the trade in the Eastern Mediterranean beginning in the 12th century, and in the Black Sea beginning in the 13th century. They sold both Baltic and Slavic slaves, as well as Armenians, Circassians, Georgians, Turks and other ethnic groups of the Black Sea and Caucasus, to the Muslim nations of the Middle East. Genoa primarily managed the slave trade from Crimea to Mamluk Egypt, until the 13th century, when increasing Venetian control over the Eastern Mediterranean allowed Venice to dominate that market. Between 1414 and 1423 alone, at least 10,000 slaves were sold in Venice.
(2018.10.11)
No.22 - クラバートと奴隷(1)スラヴ民族 [歴史]
No.18「ブルーの世界」とNo.19「ベラスケスの怖い絵」で奴隷に触れましたが、奴隷について思い出した話があるのでそれを書きます。No.1, No.2 『「千と千尋の神隠し」と「クラバート」』で書いたクラバートと、奴隷の関係です。
クラバート少年は水車場において、絶対的権力者である親方のもと、粉挽き職人としての労働にあけくれます。親方は職人たちの "生殺与奪権" をもっており、クラバートは外面的には "奴隷" の状態です。しかしクラバートは職人としての技術を磨き、町の少女と心を通わせ、ついには親方と対決して水車場からの脱出を果たします。クラバート少年は決して奴隷ではありません。もちろん、小説の舞台となった18世紀初頭のドイツのラウジッツ地方に奴隷制度があったというわけでもありません。
しかし、クラバート少年が属する民族に着目すると、奴隷制度とある種の関係があるのです。クラバートはソルブ語を話すソルブ人です。小説『クラバート』の作者・プロイスラーは、ヴェンド語を話すヴェンド人と書いていますが、No.5「交響詩・モルダウ」で書いたようにヴェンドはドイツ語であって、自民族の言葉ではソルブです。そしてソルブは「スラヴ民族」の中の一民族です。そのスラヴは、今の国名で言うと、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ブルガリア、セルビア、クロアチア、モラヴィア、モンテネグロなどを中心に居住する大民族集団であり、各民族が話すそれぞれの言葉はスラヴ語と呼ばれる「大言語族」に属しています。
この「スラヴ」と、英語における奴隷を意味する言葉「スレイヴ(slave)」は同一語源の言葉なのです。なぜそうなっているのか、がテーマです。
スラヴとスレイヴ(奴隷)は同一語源
英語の辞書でもっとも権威があるとされる The Oxford English Dictionary (1933。以下、OEDと略)をみると、Slave の語源の説明に、
と書いてあります。「語源は民族名である Sclavus と同じであり、Slav の項を見よ」というわけです。民族の名前である現代英語 Slav の項をみると、語源は Sclavus という言葉で、それはスラヴ族を意味する中世ラテン語だとあります。
ではなぜ民族の名前が「奴隷」の語源になったのでしょうか。OEDの Slave の項に、その理由の説明があります。原文とともに掲げます。
実は民族の名前である「スラヴ」を「奴隷」の意味に転用したのは英語だけではないのです。
などの、現代の西ヨーロッパ言語で奴隷を意味する言葉は、みな中世ラテン語の Sclavus(スラヴ)が語源であり、それが奴隷の意味に転用された、とOEDには説明してあるのです。このことは、西ヨーロッパにおいて「スラヴ人と言えば奴隷、奴隷といえばスラヴ人」という時期があったことを強く示唆しています。
中世ヨーロッパの奴隷貿易
「中央ヨーロッパ地域のスラヴ人たちが、征服によって奴隷状態になった、それがスラヴ=奴隷の理由である」というのがOEDの説明なのですが、その背景となったのが中世ヨーロッパの奴隷貿易です。スラヴ人を奴隷にしなければならない理由があったのです。No.20「鯨と人間 (1) 」でも紹介した「環境と文明の世界史」(石弘之、安田喜憲、湯浅赳男。洋泉社新書 2001) という本があります。この本の中で、湯浅・新潟大学名誉教授が、中世においてスラヴ族が奴隷になった事情に触れています。
という本があります。この本の中で、湯浅・新潟大学名誉教授が、中世においてスラヴ族が奴隷になった事情に触れています。
それによると、ローマ帝国には奴隷制度があったわけですが、西ローマ帝国が5世紀末に滅びても、ヨーロッパにおいては近代まで奴隷の獲得と貿易が続きました。このときの奴隷獲得のターゲットは、主にキリスト教徒でないスラヴ族やスカンジナビアのゲルマン族でした。
9世紀、10世紀になるとヨーロッパ中世の政治体制も整い、王宮もできます。そうすると贅沢品が欲しくなる。絹、宝石、香料、陶磁器などです。これらはほとんどはオリエントからの輸入品です。これを何で支払うのか。支払うものがないときの、最後の支払い手段が奴隷だったというわけです。以下、本からそのまま引用します。
「白人奴隷は、だいたい8世紀から11世紀の十字軍時代までは東ヨーロッパやスカンジナビアで供給」と、湯浅さんは述べています。OEDによると、スラヴという民族名が奴隷の意味に転用されるのは(文献でたどれるのは)9世紀からとのことでした。奴隷貿易の時期と一致していることになります。
「ユダヤ民族経済史」(湯浅赳男 著。洋泉社。2008)という本には、この当時の西ヨーロッパとイスラム圏の奴隷貿易のルートが図示されています。
湯浅さんはこの本で次のように書いています。
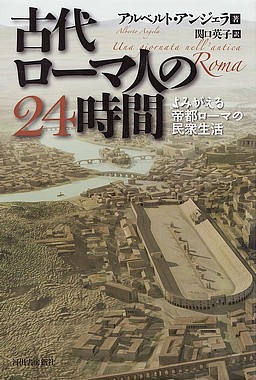 奴隷は、人間という「ありふれた」商品であり、かつ「高値で売れる」「奥の手」商品だったわけです。では、奴隷の値段はどれくらいだったのでしょうか。残念ながら、この時期の奴隷の値段について書いてある書物を読んだ記憶はありません。そこで値段の感覚をつかむために、ローマ帝国時代の奴隷の売買価格をあげておきます。「古代ローマ人の24時間」(アルベルト・アンジェラ著。関口英子訳。河出書房新社。2010)
奴隷は、人間という「ありふれた」商品であり、かつ「高値で売れる」「奥の手」商品だったわけです。では、奴隷の値段はどれくらいだったのでしょうか。残念ながら、この時期の奴隷の値段について書いてある書物を読んだ記憶はありません。そこで値段の感覚をつかむために、ローマ帝国時代の奴隷の売買価格をあげておきます。「古代ローマ人の24時間」(アルベルト・アンジェラ著。関口英子訳。河出書房新社。2010) は、紀元2世紀の初頭(西暦115年)のローマを描いたものですが、この中に当時の「物価表」がでてきます。もちろん物価は時代によって変動するし、No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で紹介したように、ローマ帝国は3世紀にインフレに見舞われます。しかし2世紀初頭は政治・経済の安定期です。アルベルト・アンジェラは研究の結果、紀元2世紀初頭の1セステルティウス青銅貨が、現在の貨幣価値で約2ユーロだと結論づけています。本の訳者の関口さんはこの貨幣価値をもとに、1ユーロ=120円の換算で価格表を作っています。いくつか選択したのが次の表です。
は、紀元2世紀の初頭(西暦115年)のローマを描いたものですが、この中に当時の「物価表」がでてきます。もちろん物価は時代によって変動するし、No.16「ニーベルングの指環(指環とは何か)」で紹介したように、ローマ帝国は3世紀にインフレに見舞われます。しかし2世紀初頭は政治・経済の安定期です。アルベルト・アンジェラは研究の結果、紀元2世紀初頭の1セステルティウス青銅貨が、現在の貨幣価値で約2ユーロだと結論づけています。本の訳者の関口さんはこの貨幣価値をもとに、1ユーロ=120円の換算で価格表を作っています。いくつか選択したのが次の表です。
紀元2世紀のローマ帝国と8世紀~11世紀の西ヨーロッパの物価事情が似たようなものだとは限りません。しかしこの表で生活必需物資の価格と奴隷の価格を比較した感じはつかめそうです。当然と言えば当然ですが、奴隷はかなりの高額商品です。「めぼしい商品を持たない国が最後の奥の手として持ち出してくるのが奴隷である」と湯浅さんが書いているのは、ズバリだと思います。
スラヴ民族と奴隷の関係についてOEDの説明だけを読むと「(政治的ないしは軍事的理由で)征服されたスラヴ民族が、その結果として奴隷になった」と暗黙に考えてしまいます。征服が先で、奴隷はその結果だと・・・・・・。はたして、そうなのでしょうか。奴隷貿易の歴史からすると、むしろ「奴隷にするために征服された」のではないでしょうか。奴隷の需要があり、商人がいて、交易手段があり、取引で多大な利益が出る。そうすると、暴力的手段を用いてでも奴隷の供給源を開拓しにいく。これが人間社会としては自然な形だと思います。このあたりは、専門家に聞いてみたいものです。
少々わき道にそれますが「めぼしい商品を持たない国が最後の奥の手として持ち出してくるのが奴隷である。このことは交易する二つの国の経済落差があまりに大きいことを示している」という湯浅名誉教授の文章から、いやがおうでも思い浮かべるのは古代における中国大陸と日本列島の関係です。
20世紀の東洋史学の第一人者、宮崎市定(1901-1995。京都大学教授)は、「東洋史の上の日本」で次のように書いています(引用中の「幌馬車」と「トラック」は、前後の文脈上の比喩です。下線は原文にはありません)。
中世ヨーロッパ奴隷貿易の終焉
スラヴ民族と奴隷の話に戻ります。湯浅さんは「白人奴隷は、だいたい8世紀から11世紀の十字軍時代までは東ヨーロッパやスカンジナビアで供給」と言っています。つまりこの間が奴隷貿易の最盛期で、その後は衰退に向かうのです。この間の事情はどうなのでしょうか。
10世紀の西ヨーロッパに「神聖ローマ帝国」が出現すると、帝国の東方に住んでいたスラブ人に対する征服と、逆に征服されたスラブ人の蜂起が繰り返されるようになります。そして12世紀に中頃(1147)にはローマ教皇の「教勅」のもとに「ヴェンド十字軍」が組織されます。十字軍というのは、当初は聖地エルサレムのイスラム教徒からの回復を目的としたものでしたが(第1回十字軍は11世紀末。1096年)、それは拡大解釈され「異教徒征伐」ための軍が東・北部ヨーロッパにも向けられたのです。このあたりの経緯は『北の十字軍』(山内進 著。講談社選書メチエ。1997) に詳しく書かれています。なお「ヴェンド」という言葉は、当時のドイツからみた周辺の異民族、特にスラヴ民族を指す言葉ですね。クラバートの民族をドイツ語で「ヴェンド人」と呼ぶのもこの名残りです。
に詳しく書かれています。なお「ヴェンド」という言葉は、当時のドイツからみた周辺の異民族、特にスラヴ民族を指す言葉ですね。クラバートの民族をドイツ語で「ヴェンド人」と呼ぶのもこの名残りです。
この結果、今のポーランド、バルト3国、そしてさらにはスカンジナビア地方にまでキリスト教が広まっていきました。キリスト教徒がキリスト教徒を奴隷とすることは原則として禁止です。この結果、上の図に示された奴隷貿易は次第になくなっていきました。つまり「ヨーロッパ全域がキリスト教化されたため、次第に奴隷貿易がなくなっていった」、これが普通の説明だと思います。しかし、それだけなのでしょうか。
ここで世界史の復習をしてみたいと思います。北アフリカを支配したイスラム勢力(ウマイヤ朝)は、8世紀にジブラルタル海峡を渡り、現在のスペインにあった西ゴート帝国を滅ぼし(711)イベリア半島の多くを支配下におさめます。732年には、現在のフランスのトゥール・ポワティエでフランク王国軍と戦うという、世界史上有名な戦闘までありました(フランク王国の勝利)。フランスへの進出はなりませんでしたが、コルドバを首都としたウマイヤ朝は発展を続け、10世紀に最盛期を迎えます。しかし11世紀(1031)に複数の小国に分裂してしまいます。それらの小国は次第にキリスト教国に滅ぼされていき(=キリスト教国からみたレコンキスタ)、最後に残ったイスラム国家であるグラナダ王国が陥落したのが1492年(コロンブスのアメリカ発見の年)です。
ちなみに、10世紀のコルドバは人口が100万人を超えていて、間違いなくヨーロッパ最大の都市でした。我々が習ったヨーロッパの歴史からはイスラム世界であった頃のスペインが意図的に除外されているようなのですが、当時のコルドバは経済面でも文化面でもヨーロッパの中心です。上に掲げた「中世ヨーロッパの奴隷貿易」という図も、コルドバがヨーロッパの中心だったと考えるとよく理解できます。現在のコルドバは市内の「コルドバ歴史地区」が世界遺産に指定されています。この世界遺産の「目玉」は、スペイン政府観光局のホームページにもあるようにメスキータとユダヤ人街です。メスキータ(モスクの意)はもともとイスラム教のモスクとして建設され、レコンキスタ後にキリスト教の教会に改装されたものです。コルドバがイスラム教、ユダヤ教、キリスト教という3つの宗教が交錯する接点でだったことがよくわかります。
本題に戻ります。8世紀から11世紀という中世ヨーロッパの奴隷貿易の時期は「イベリア半島におけるウマイヤ王朝の成立から、その最盛期、国の分裂までの時期」にあたっていることになります。奴隷貿易がなくなっていったのは、奴隷を大量購入する裕福な国家がイベリア半島からなくなっていき(=需要が減少し)、かつ、最大の需要先であったオリエントまでの奴隷交易ルートが絶たれたのが原因ではないかと思うのです。奴隷の需要があり、商人がいて、交易手段があるのなら、たとえ遠隔地であってもキリスト教圏の外へ外へと奴隷の供給地を開拓しにいくはずですね。私は西洋史の専門家ではないのでこのあたりの事情はよく知らないのですが、一度、有識者に聞いてみたいと思います。
西ヨーロッパ各国の言語において「スラヴ」と「奴隷」が同一語源である理由は、今まで書いたような歴史的経緯によります。しかし初めに書いたように「スラヴ」は大民族集団で、その "本拠地" とも言えるのはロシア平原です。そしてロシア平原のスラヴ民族は中世において、西ヨーロッパ経由とは別ルートで奴隷貿易の対象になりました。松原久子氏の著作にその記述があります。
西ヨーロッパ経由の奴隷貿易は、上に書いたように11世紀頃から衰退に向かいました。しかしヨーロッパの商人は、中央ヨーロッパとは別の奴隷の仕入れ先を13世紀に開拓しました。それを次回書きます。
Wikipedia に「Slavery in medieval Europe(中世ヨーロッパの奴隷)」という項目があります。残念ながら日本語はないのですが、この中に奴隷貿易の詳しい説明があります。その説明に「ユダヤ人商人」の項があって、5世紀末以降、ユダヤ人商人が奴隷貿易の中心的役割を担ったことが解説されています。その最後の方の文章を試訳とともにに引用します(参考文献の表示は省略)。
引用に出てくるエルベ河はドレスデン市内を流れている河で、北海に注ぎます。そして、No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」で紹介した小説「クラバート」の舞台となったソルブ人(スラヴ族)の住むラウジッツ地方は、ドレスデンの北東、エルベ河の東に位置しています。「クラバート」は18世紀初頭の物語ですが、クラバートの先祖の中には奴隷となってスペインにまで売られていったものがいたことでしょう。
ドイツの西部、ケルンの南にコブレンツという都市があります。ここはライン河とモーゼル河(源流はフランス)が合流するという交通の要衝であり、古代ローマ人が建設した都市が発祥です(ケルンもそうです)。
このコブレンツの旧市街のヨーゼフ・ゲレス広場に「歴史の柱」というモニュメントが建っています。これは1992年の「コブレンツ発祥2000年記念」を契機に建設されたもので、コブレンツの2000年の歴史を10の年代にわけ、それぞれの年代を象徴するテーマが彫刻で表現されています。その年代の4番目は「12-13世紀」ですが、彫像のテーマは、
です。なるほどと思います。東ヨーロッパの「異教徒」征伐に向かった十字軍と、東ヨーロッパからの奴隷の交易でにぎわった12-13世紀のコブレンツ、というわけです。
コブレンツはライン河クルーズの下船場所(の一つ)であり、ヨーロッパ観光で訪れる人も多いと思いますが、2000年の歴史のある町です。ぜひ地元の歴史に詳しいガイドの方と訪問してみたい町です。
補記1に書いたように、Wikipediaに "Slavery in medieval Europe"(中世ヨーロッパの奴隷) という項目がありますが、その第2章が "Slave Trade"(奴隷貿易)です(英語版のみ。2018.11.23 現在)。これを見るとユダヤ人奴隷商人による中央ヨーロッパからの奴隷交易は、本文に書いたフランスのヴェルダンを経由するルートだけでなく、アルプスを越えてヴェネチアに至るルートがあったようです。第2章の全文を、
No.246 - 中世ヨーロッパの奴隷貿易
に訳出しました。
クラバート少年は水車場において、絶対的権力者である親方のもと、粉挽き職人としての労働にあけくれます。親方は職人たちの "生殺与奪権" をもっており、クラバートは外面的には "奴隷" の状態です。しかしクラバートは職人としての技術を磨き、町の少女と心を通わせ、ついには親方と対決して水車場からの脱出を果たします。クラバート少年は決して奴隷ではありません。もちろん、小説の舞台となった18世紀初頭のドイツのラウジッツ地方に奴隷制度があったというわけでもありません。
しかし、クラバート少年が属する民族に着目すると、奴隷制度とある種の関係があるのです。クラバートはソルブ語を話すソルブ人です。小説『クラバート』の作者・プロイスラーは、ヴェンド語を話すヴェンド人と書いていますが、No.5「交響詩・モルダウ」で書いたようにヴェンドはドイツ語であって、自民族の言葉ではソルブです。そしてソルブは「スラヴ民族」の中の一民族です。そのスラヴは、今の国名で言うと、ポーランド、チェコ、スロヴァキア、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、ブルガリア、セルビア、クロアチア、モラヴィア、モンテネグロなどを中心に居住する大民族集団であり、各民族が話すそれぞれの言葉はスラヴ語と呼ばれる「大言語族」に属しています。
この「スラヴ」と、英語における奴隷を意味する言葉「スレイヴ(slave)」は同一語源の言葉なのです。なぜそうなっているのか、がテーマです。
スラヴとスレイヴ(奴隷)は同一語源
英語の辞書でもっとも権威があるとされる The Oxford English Dictionary (1933。以下、OEDと略)をみると、Slave の語源の説明に、
| identical with the racial name Sclavus (see Slav) |
と書いてあります。「語源は民族名である Sclavus と同じであり、Slav の項を見よ」というわけです。民族の名前である現代英語 Slav の項をみると、語源は Sclavus という言葉で、それはスラヴ族を意味する中世ラテン語だとあります。
ではなぜ民族の名前が「奴隷」の語源になったのでしょうか。OEDの Slave の項に、その理由の説明があります。原文とともに掲げます。
|
| have been reduced という完了形がうまく日本語に置き換えられないのですが、意味としては「(奴隷の状態に)落とされて、それが継続した」ということですね。 |
実は民族の名前である「スラヴ」を「奴隷」の意味に転用したのは英語だけではないのです。
| sklave | ドイツ語 |
| esclave | フランス語 |
| schiavo,-va | イタリア語 |
| esclavo,-va | スペイン語 |
| escravo,-va | ポルトガル語 |
などの、現代の西ヨーロッパ言語で奴隷を意味する言葉は、みな中世ラテン語の Sclavus(スラヴ)が語源であり、それが奴隷の意味に転用された、とOEDには説明してあるのです。このことは、西ヨーロッパにおいて「スラヴ人と言えば奴隷、奴隷といえばスラヴ人」という時期があったことを強く示唆しています。
中世ヨーロッパの奴隷貿易

|
それによると、ローマ帝国には奴隷制度があったわけですが、西ローマ帝国が5世紀末に滅びても、ヨーロッパにおいては近代まで奴隷の獲得と貿易が続きました。このときの奴隷獲得のターゲットは、主にキリスト教徒でないスラヴ族やスカンジナビアのゲルマン族でした。
9世紀、10世紀になるとヨーロッパ中世の政治体制も整い、王宮もできます。そうすると贅沢品が欲しくなる。絹、宝石、香料、陶磁器などです。これらはほとんどはオリエントからの輸入品です。これを何で支払うのか。支払うものがないときの、最後の支払い手段が奴隷だったというわけです。以下、本からそのまま引用します。
|
「白人奴隷は、だいたい8世紀から11世紀の十字軍時代までは東ヨーロッパやスカンジナビアで供給」と、湯浅さんは述べています。OEDによると、スラヴという民族名が奴隷の意味に転用されるのは(文献でたどれるのは)9世紀からとのことでした。奴隷貿易の時期と一致していることになります。
「ユダヤ民族経済史」(湯浅赳男 著。洋泉社。2008)という本には、この当時の西ヨーロッパとイスラム圏の奴隷貿易のルートが図示されています。
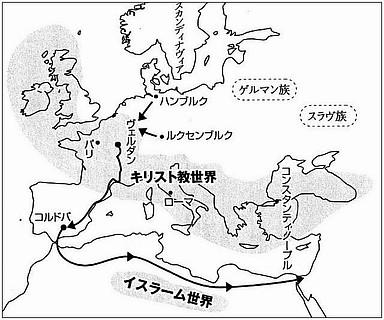 |
| 中世ヨーロッパの奴隷貿易(「ユダヤ民族経済史」より) |
湯浅さんはこの本で次のように書いています。
|
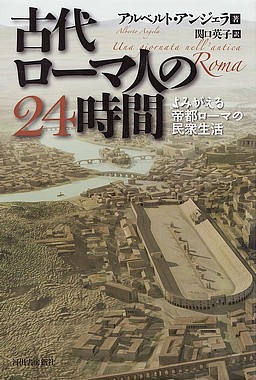 奴隷は、人間という「ありふれた」商品であり、かつ「高値で売れる」「奥の手」商品だったわけです。では、奴隷の値段はどれくらいだったのでしょうか。残念ながら、この時期の奴隷の値段について書いてある書物を読んだ記憶はありません。そこで値段の感覚をつかむために、ローマ帝国時代の奴隷の売買価格をあげておきます。「古代ローマ人の24時間」(アルベルト・アンジェラ著。関口英子訳。河出書房新社。2010)
奴隷は、人間という「ありふれた」商品であり、かつ「高値で売れる」「奥の手」商品だったわけです。では、奴隷の値段はどれくらいだったのでしょうか。残念ながら、この時期の奴隷の値段について書いてある書物を読んだ記憶はありません。そこで値段の感覚をつかむために、ローマ帝国時代の奴隷の売買価格をあげておきます。「古代ローマ人の24時間」(アルベルト・アンジェラ著。関口英子訳。河出書房新社。2010)| オリーブオイル 1リットル | 約720円 |
| 並のワイン 1リットル | 約240円 |
| 小麦 1キログラム | 約120円 |
| トゥニカ(服) 1着 | 約3600円 |
| ラバ 1頭 | 約12万5000円 |
| 奴隷 1人 | 約29万円~60万円 |
紀元2世紀のローマ帝国と8世紀~11世紀の西ヨーロッパの物価事情が似たようなものだとは限りません。しかしこの表で生活必需物資の価格と奴隷の価格を比較した感じはつかめそうです。当然と言えば当然ですが、奴隷はかなりの高額商品です。「めぼしい商品を持たない国が最後の奥の手として持ち出してくるのが奴隷である」と湯浅さんが書いているのは、ズバリだと思います。
スラヴ民族と奴隷の関係についてOEDの説明だけを読むと「(政治的ないしは軍事的理由で)征服されたスラヴ民族が、その結果として奴隷になった」と暗黙に考えてしまいます。征服が先で、奴隷はその結果だと・・・・・・。はたして、そうなのでしょうか。奴隷貿易の歴史からすると、むしろ「奴隷にするために征服された」のではないでしょうか。奴隷の需要があり、商人がいて、交易手段があり、取引で多大な利益が出る。そうすると、暴力的手段を用いてでも奴隷の供給源を開拓しにいく。これが人間社会としては自然な形だと思います。このあたりは、専門家に聞いてみたいものです。
少々わき道にそれますが「めぼしい商品を持たない国が最後の奥の手として持ち出してくるのが奴隷である。このことは交易する二つの国の経済落差があまりに大きいことを示している」という湯浅名誉教授の文章から、いやがおうでも思い浮かべるのは古代における中国大陸と日本列島の関係です。
20世紀の東洋史学の第一人者、宮崎市定(1901-1995。京都大学教授)は、「東洋史の上の日本」で次のように書いています(引用中の「幌馬車」と「トラック」は、前後の文脈上の比喩です。下線は原文にはありません)。
|
中世ヨーロッパ奴隷貿易の終焉
スラヴ民族と奴隷の話に戻ります。湯浅さんは「白人奴隷は、だいたい8世紀から11世紀の十字軍時代までは東ヨーロッパやスカンジナビアで供給」と言っています。つまりこの間が奴隷貿易の最盛期で、その後は衰退に向かうのです。この間の事情はどうなのでしょうか。
10世紀の西ヨーロッパに「神聖ローマ帝国」が出現すると、帝国の東方に住んでいたスラブ人に対する征服と、逆に征服されたスラブ人の蜂起が繰り返されるようになります。そして12世紀に中頃(1147)にはローマ教皇の「教勅」のもとに「ヴェンド十字軍」が組織されます。十字軍というのは、当初は聖地エルサレムのイスラム教徒からの回復を目的としたものでしたが(第1回十字軍は11世紀末。1096年)、それは拡大解釈され「異教徒征伐」ための軍が東・北部ヨーロッパにも向けられたのです。このあたりの経緯は『北の十字軍』(山内進 著。講談社選書メチエ。1997)
この結果、今のポーランド、バルト3国、そしてさらにはスカンジナビア地方にまでキリスト教が広まっていきました。キリスト教徒がキリスト教徒を奴隷とすることは原則として禁止です。この結果、上の図に示された奴隷貿易は次第になくなっていきました。つまり「ヨーロッパ全域がキリスト教化されたため、次第に奴隷貿易がなくなっていった」、これが普通の説明だと思います。しかし、それだけなのでしょうか。
ここで世界史の復習をしてみたいと思います。北アフリカを支配したイスラム勢力(ウマイヤ朝)は、8世紀にジブラルタル海峡を渡り、現在のスペインにあった西ゴート帝国を滅ぼし(711)イベリア半島の多くを支配下におさめます。732年には、現在のフランスのトゥール・ポワティエでフランク王国軍と戦うという、世界史上有名な戦闘までありました(フランク王国の勝利)。フランスへの進出はなりませんでしたが、コルドバを首都としたウマイヤ朝は発展を続け、10世紀に最盛期を迎えます。しかし11世紀(1031)に複数の小国に分裂してしまいます。それらの小国は次第にキリスト教国に滅ぼされていき(=キリスト教国からみたレコンキスタ)、最後に残ったイスラム国家であるグラナダ王国が陥落したのが1492年(コロンブスのアメリカ発見の年)です。

|

|
|
「メスキータ」と その内部の「円柱の森」 (スペイン政府観光局のホームページより) |
本題に戻ります。8世紀から11世紀という中世ヨーロッパの奴隷貿易の時期は「イベリア半島におけるウマイヤ王朝の成立から、その最盛期、国の分裂までの時期」にあたっていることになります。奴隷貿易がなくなっていったのは、奴隷を大量購入する裕福な国家がイベリア半島からなくなっていき(=需要が減少し)、かつ、最大の需要先であったオリエントまでの奴隷交易ルートが絶たれたのが原因ではないかと思うのです。奴隷の需要があり、商人がいて、交易手段があるのなら、たとえ遠隔地であってもキリスト教圏の外へ外へと奴隷の供給地を開拓しにいくはずですね。私は西洋史の専門家ではないのでこのあたりの事情はよく知らないのですが、一度、有識者に聞いてみたいと思います。
西ヨーロッパ各国の言語において「スラヴ」と「奴隷」が同一語源である理由は、今まで書いたような歴史的経緯によります。しかし初めに書いたように「スラヴ」は大民族集団で、その "本拠地" とも言えるのはロシア平原です。そしてロシア平原のスラヴ民族は中世において、西ヨーロッパ経由とは別ルートで奴隷貿易の対象になりました。松原久子氏の著作にその記述があります。
|
西ヨーロッパ経由の奴隷貿易は、上に書いたように11世紀頃から衰退に向かいました。しかしヨーロッパの商人は、中央ヨーロッパとは別の奴隷の仕入れ先を13世紀に開拓しました。それを次回書きます。
(以降、続く)
| 補記1:中世ヨーロッパの奴隷貿易 |
Wikipedia に「Slavery in medieval Europe(中世ヨーロッパの奴隷)」という項目があります。残念ながら日本語はないのですが、この中に奴隷貿易の詳しい説明があります。その説明に「ユダヤ人商人」の項があって、5世紀末以降、ユダヤ人商人が奴隷貿易の中心的役割を担ったことが解説されています。その最後の方の文章を試訳とともにに引用します(参考文献の表示は省略)。
| (Wikipedia : Slavery in medieval Europeより。2018.10.6 現在) As German rulers of Saxon dynasties took over the enslavement (and slave trade) of Slavs in the 10th century, Jewish merchants bought slaves at the Elbe, sending caravans into the valley of the Rhine. Many of these slaves were taken to Verdun, which had close trade relations with Spain. Many would be castrated and sold as eunuchs as well. 【試訳】 10世紀になってドイツのサクソン族の王国の支配者がスラヴ族の奴隷化と奴隷交易に乗り出すようになると、ユダヤ人商人はエルベ河付近で奴隷を購入し、キャラバンを組んでライン河渓谷に送った。多くの奴隷は、スペインと密接な関係があったヴェルダンに連れていかれ、去勢され、宦官として売られた。 |
引用に出てくるエルベ河はドレスデン市内を流れている河で、北海に注ぎます。そして、No.1-2「千と千尋の神隠しとクラバート」で紹介した小説「クラバート」の舞台となったソルブ人(スラヴ族)の住むラウジッツ地方は、ドレスデンの北東、エルベ河の東に位置しています。「クラバート」は18世紀初頭の物語ですが、クラバートの先祖の中には奴隷となってスペインにまで売られていったものがいたことでしょう。
(2018.10.6)
| 補記2:コブレンツ |
ドイツの西部、ケルンの南にコブレンツという都市があります。ここはライン河とモーゼル河(源流はフランス)が合流するという交通の要衝であり、古代ローマ人が建設した都市が発祥です(ケルンもそうです)。
このコブレンツの旧市街のヨーゼフ・ゲレス広場に「歴史の柱」というモニュメントが建っています。これは1992年の「コブレンツ発祥2000年記念」を契機に建設されたもので、コブレンツの2000年の歴史を10の年代にわけ、それぞれの年代を象徴するテーマが彫刻で表現されています。その年代の4番目は「12-13世紀」ですが、彫像のテーマは、
| Crusades and slave trade (十字軍と奴隷貿易) |
です。なるほどと思います。東ヨーロッパの「異教徒」征伐に向かった十字軍と、東ヨーロッパからの奴隷の交易でにぎわった12-13世紀のコブレンツ、というわけです。
コブレンツはライン河クルーズの下船場所(の一つ)であり、ヨーロッパ観光で訪れる人も多いと思いますが、2000年の歴史のある町です。ぜひ地元の歴史に詳しいガイドの方と訪問してみたい町です。

| ||
|
コブレンツの旧市街、ヨーゼフ・ゲレス広場に立つ「歴史の柱 - History Column」。都市の2000年の歴史を、年代ごとに彫刻で表している。
(site : vanderkrogt.net)
| ||

| ||
|
柱の前にあるドイツ語と英語を併記した説明パネル。一番下にコブレンツを象徴する「ワイン船」があり、その上に①~⑩までの年代ごとに、その年代を表すテーマが彫刻されている。①は1世紀~5世紀で、ローマ人による都市建設を表す。⑩が現代である。
| ||

| ||
|
④が12~13世紀で、この年代のテーマは「Crusades, slave trade」、つまり「十字軍と奴隷貿易」である。
| ||

| ||
|
12~13世紀のテーマである「Crusades, slave trade」の彫刻。この画像では中央から左に十字軍、右に奴隷の一団が彫刻されている。
(site : vanderkrogt.net)
| ||
(2018.10.6)
| 補記3:中世ヨーロッパの奴隷貿易(再) |
補記1に書いたように、Wikipediaに "Slavery in medieval Europe"(中世ヨーロッパの奴隷) という項目がありますが、その第2章が "Slave Trade"(奴隷貿易)です(英語版のみ。2018.11.23 現在)。これを見るとユダヤ人奴隷商人による中央ヨーロッパからの奴隷交易は、本文に書いたフランスのヴェルダンを経由するルートだけでなく、アルプスを越えてヴェネチアに至るルートがあったようです。第2章の全文を、
No.246 - 中世ヨーロッパの奴隷貿易
に訳出しました。
(2018.11.23)
No.6 - メアリー・ダイアー [歴史]
No.3「ドイツ料理万歳」 で書いた「ウィーンの白アスパラ」のように、海外旅行の大きな楽しみは「日本ではできなかった経験や発見」をすることでしょう。それは No.3 のように食事であったり、また、遺跡などの観光、美術館・博物館、自然の景観などの体験です。しかし現代では日本に居ながらにして入手できる「海外情報」が大量にあるので「日本ではできない経験」も予想の範囲内や想定内であることが多いわけです。「思ってもみない経験をして、強く印象に残った、感動した」ということは少なくなったのではないでしょうか。
もちろん「想像以上だった」というのはあると思います。「ローマのコロッセオは想像以上に巨大な建造物だった」とか「カナディアンロッキーの雄大な眺めは想像以上にすばらしかった」とかのたぐいです。しかしこれは、ガイドブックやテレビ番組を見て想像していたのよりはレベルが上だったとか、予想以上の規模であったということであって、「全く想像だにしなかった発見、経験だった」というものではありません。スリにあったというようなネガティブな突発事態でさえ、現代では「想定範囲内のこと」となってしまった感があります。
その、比較的まれになった「想定範囲外の、意外な発見」を米国のボストンでしたことがあります。
ボストンとフリーダムトレイル
 ボストンはアメリカの「建国の地」であり、国内からの観光客はもとより世界各国からの観光客も多い街です。日本で言うと京都・奈良でしょうか。かつての米国大統領、ジョン・F・ケネディの生誕の地でもあり、北に近接しているケンブリッジにはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学があります。ボストンで活躍した日本人も多く、たとえばボストン交響楽団の音楽監督だった小澤征爾さんです。最近では、松坂大輔投手が属するボストン・レッドソックスの本拠地としても日本のスポーツ番組にたびたび登場しています。
ボストンはアメリカの「建国の地」であり、国内からの観光客はもとより世界各国からの観光客も多い街です。日本で言うと京都・奈良でしょうか。かつての米国大統領、ジョン・F・ケネディの生誕の地でもあり、北に近接しているケンブリッジにはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学があります。ボストンで活躍した日本人も多く、たとえばボストン交響楽団の音楽監督だった小澤征爾さんです。最近では、松坂大輔投手が属するボストン・レッドソックスの本拠地としても日本のスポーツ番組にたびたび登場しています。
ボストン観光の基本は「フリーダム・トレイル」と呼ばれている「観光経路」をたどる「名所・史跡めぐり」です。フリーダム・トレイル(右図)は、街の中心部の公園である「ボストン・コモン」を出発点とし、歩道に赤い線がつけてあります。この赤い線をたどっていくと、独立宣言が読み上げられた旧州議事堂、ファニュエル・ホール(サミュエル・アダムスの像が建っている)、独立の英雄であるポール・リビアの家、などの「名所・史跡」を一通りたどることができるというしかけです。
 フリーダム・トレイルを出発して最初に遭遇する建物は、ボストン・コモンの北東部にあるマサチューセッツ州議事堂(Massachusetts State House。右写真)です。門を入るとすぐにジョン・F・ケネディの像が目につき、記念写真をとっている観光客も多い。そこを離れて、建物に向かって右手の方へずっと進んでいくと、観光客も少なくなります。その右手の端の方に、一人の女性のブロンズの座像があります。メアリー・ダイアー(Mary Dyer)の像です。
フリーダム・トレイルを出発して最初に遭遇する建物は、ボストン・コモンの北東部にあるマサチューセッツ州議事堂(Massachusetts State House。右写真)です。門を入るとすぐにジョン・F・ケネディの像が目につき、記念写真をとっている観光客も多い。そこを離れて、建物に向かって右手の方へずっと進んでいくと、観光客も少なくなります。その右手の端の方に、一人の女性のブロンズの座像があります。メアリー・ダイアー(Mary Dyer)の像です。
メアリー・ダイアー
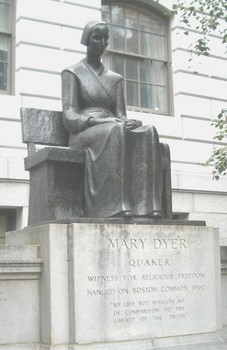 メアリー・ダイアーは「クエーカー教徒」でした。1660年、彼女はクエーカー教徒であることをやめなかった罪で、ボストン・コモンで絞首刑になりました。40歳代後半でした。
メアリー・ダイアーは「クエーカー教徒」でした。1660年、彼女はクエーカー教徒であることをやめなかった罪で、ボストン・コモンで絞首刑になりました。40歳代後半でした。
ボストン市民の名誉のために付け加えると、彼女はいわゆる「リンチ」で絞首刑になったのではありません。当時のマサチューセッツでは「クエーカー教禁止例」という法律が制定され(1658)、クエーカー教徒であることやその布教には厳罰が課せられていました。メアリー・ダイアーはクエーカー教を布教した罪で3度逮捕され、はじめの2度はマサチューセッツからの追放処分になり、3度目は死刑判決を受けたものの恩赦を受け、3たび追放されました。しかし彼女は再びマサチューセッツに戻って布教をしたため、今度こそ、死刑宣告をうけて絞首刑になったのです。完全な「確信犯」でした。
メアリー・ダイアーの「殉教」はさまざまな思いを想起させます。独立以前のアメリカへの移民の歴史で大きく強調されるのが「清教徒」(ピルグリム・ファーザーズ)がイングランドでの迫害から逃れメイフラワー号で「ニューイングランド」に渡ったという一件です。清教徒は英国国教会における改革派ないしは分離派であり、正統に対する異端と言えるでしょう。その英国国教会を含むプロテスタントも、カトリックに対する「異端」として始まりました。そして清教徒たちが到着したニューイングランドでは、今度はクエーカー教徒が「異端」であり、メアリー・ダイアーは絞首刑になったわけです。
アメリカ合衆国憲法では「信教の自由」が高らかにうたわれています。しかし憲法制定(1787年)の120年ほど前には「異端」の罪で人が処刑されていたのです。「信教の自由」はメアリー・ダイアーを始めとして流された多くの血によって獲得されたと考えられます。クエーカー教徒の処刑は彼女だけではないのですが、「いくらなんでも、まずい」という思いが植民地の人々に徐々に広まったのではないでしょうか。もちろん憲法の制定で問題が解決したわけではなく、現代までも続いていることは知られているとおりです。
歴史に目を向けると、キリスト教徒をはじめとする「殉教」は枚挙にいとまがありません。ヨーロッパの著名な教会にいくと殉教者の像や絵画は山ほどあります。日本でも殉教はありました。長崎に行くと殉教者の像もあります(日本二十六聖人記念碑)。メアリー・ダイアーの処刑も、そういった歴史の中のごく小さなひとコマに過ぎません。
しかし私にとって「全く意外」だったのは、民主主義の殿堂である「州議会の議事堂」というまさにその場所に、そこに集まる議員たちの先祖が目と鼻の先の公園で処刑した「殉教者」のブロンズ像が建っている、というその事実でした。
ボストン・ダック・ツアー
 メアリー・ダイアーの像の存在を私に教えてくれたのは、ボストン・ダック・ツアーの運転手兼ガイドのお兄さんです。ボストン・ダック・ツアーというのは、もともと軍事用だった水陸両用車を改造した小型の観光バス(観光トラックと言うべきか)でボストンの主要観光スポットをめぐり、チャールズ川のクルーズをするというツアーです。ダック(あひる)というのはこの水陸両用車の愛称です。いかにも「典型的アメリカ人」という感じの陽気なお兄さんは、途切れることなく観光名所の解説を英語でまくしたてていましたが、州議事堂の前を通った時、女性の像をさして「彼女は Boston Common で was hanged.」と言ったのです。一瞬、聞き間違いかと思いました。しかし彼は確かに hanged と言ったのです。
メアリー・ダイアーの像の存在を私に教えてくれたのは、ボストン・ダック・ツアーの運転手兼ガイドのお兄さんです。ボストン・ダック・ツアーというのは、もともと軍事用だった水陸両用車を改造した小型の観光バス(観光トラックと言うべきか)でボストンの主要観光スポットをめぐり、チャールズ川のクルーズをするというツアーです。ダック(あひる)というのはこの水陸両用車の愛称です。いかにも「典型的アメリカ人」という感じの陽気なお兄さんは、途切れることなく観光名所の解説を英語でまくしたてていましたが、州議事堂の前を通った時、女性の像をさして「彼女は Boston Common で was hanged.」と言ったのです。一瞬、聞き間違いかと思いました。しかし彼は確かに hanged と言ったのです。
「なぜ?」と思って、ダック・ツアーが終わってから州議事堂にいって確認したのが、メアリー・ダイアーの像です。像の台座には次の文字が刻んであります。
この碑文にあるavailethは古語で、avail の三人称単数現在形です。現代英語では avails で、従って not availeth は does not avail です。not avail me という言い方がいかにも英語っぽくて、日本語に直訳するのは難しいのですが、意訳すると次のようになるでしょう。
The Liberty of The Truth を「真実の自由」とすると日本語としては意味が変わってしまうので「信教の自由」と意訳しました。The Truth というのはつまり「神の言葉」の意味ですね。The Liberty of The Truth は「神の言葉を自由に語ること」と解釈して「信教の自由」としました。
フリーダム・トレイルの意味
フリーダム・トレイルは以前に歩いたことがあります。その時の印象は「アメリカ史の勉強になった」というものでした。なぜフリーダム・トレイル、つまり「自由の道」なのか、それは明白で「自由のために独立戦争を戦った古き良き時代のアメリカを、建国の地ボストンでたどる道」であり、アメリカ万歳、というような暗黙の意味があると思っていました。
しかしメアリー・ダイアーの像を知って「フリーダム・トレイル」の意味は一変しました。それは「アメリカ万歳」ではなく、その名前が直接的に表現しているように、人間の歴史が獲得してきた自由の大切さ、強制の排除と寛容の精神で社会を構成することの大切さを認識するための道だと思えたのです。だって、そうですよね。信教の自由(Religious Freedom)の証人(Witness)の像が、トレイルの出発点(ボストン・コモン)を見おろす位置にあるのですから。フリーダム・トレイルの「最重要スポット」は、その言葉の意味からして明らかにメアリー・ダイアーの像です。ガイドブックには全く書いてないけれど・・・・・・。
メアリー・ダイアーの像は、ダック・ツアーのガイドさんが紹介するぐらいなのだから、ボストン市民にとってはよく知られているのでしょう。ガイドのお兄さんに感謝したいと思います。
メアリー・ダイアーはクエーカー教の初期の伝道者であり、17世紀後半のアメリカではクエーカー教徒は弾圧されました。その後、宗教の自由が認められるようになり、クエーカー教徒の数も増えていきます。そしてボストン近郊におけるクエーカー教徒のコミュニティが、アメリカの捕鯨産業の中心となります。この経緯を「No.20 - 鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」に書きました。
歴史上、最も有名な日本人のクエーカー教徒は新渡戸稲造(1862-1933)です。彼の妻(メアリー・エルキントン)はフィラデルフィア出身のクエーカー教徒であり、新渡戸稲造がアメリカのボルチモアに留学(1884-87)していたときにクエーカーの集会に出席して知り合ったのが縁で、結婚に至ったのでした。
言うまでもなく、新渡戸稲造の功績は「武士道」(1899)という本を英語で書いて出版し、日本の精神文化を世界に紹介したことです。山本博文・訳「武士道」(ちくま新書)の訳者序文によると「新渡戸にとってクエーカー主義の影響は大きく、この思想に出会ったことで、キリスト教と東洋思想を調和させることができたと語っている。」そうです。
メアリー・ダイアーのボストンにおける殉教は、アメリカ東海岸のクエーカー教徒を通じて「武士道」まで、細い糸で繋がっているようです。
もちろん「想像以上だった」というのはあると思います。「ローマのコロッセオは想像以上に巨大な建造物だった」とか「カナディアンロッキーの雄大な眺めは想像以上にすばらしかった」とかのたぐいです。しかしこれは、ガイドブックやテレビ番組を見て想像していたのよりはレベルが上だったとか、予想以上の規模であったということであって、「全く想像だにしなかった発見、経験だった」というものではありません。スリにあったというようなネガティブな突発事態でさえ、現代では「想定範囲内のこと」となってしまった感があります。
その、比較的まれになった「想定範囲外の、意外な発見」を米国のボストンでしたことがあります。
ボストンとフリーダムトレイル
 ボストンはアメリカの「建国の地」であり、国内からの観光客はもとより世界各国からの観光客も多い街です。日本で言うと京都・奈良でしょうか。かつての米国大統領、ジョン・F・ケネディの生誕の地でもあり、北に近接しているケンブリッジにはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学があります。ボストンで活躍した日本人も多く、たとえばボストン交響楽団の音楽監督だった小澤征爾さんです。最近では、松坂大輔投手が属するボストン・レッドソックスの本拠地としても日本のスポーツ番組にたびたび登場しています。
ボストンはアメリカの「建国の地」であり、国内からの観光客はもとより世界各国からの観光客も多い街です。日本で言うと京都・奈良でしょうか。かつての米国大統領、ジョン・F・ケネディの生誕の地でもあり、北に近接しているケンブリッジにはハーバード大学やマサチューセッツ工科大学があります。ボストンで活躍した日本人も多く、たとえばボストン交響楽団の音楽監督だった小澤征爾さんです。最近では、松坂大輔投手が属するボストン・レッドソックスの本拠地としても日本のスポーツ番組にたびたび登場しています。ボストン観光の基本は「フリーダム・トレイル」と呼ばれている「観光経路」をたどる「名所・史跡めぐり」です。フリーダム・トレイル(右図)は、街の中心部の公園である「ボストン・コモン」を出発点とし、歩道に赤い線がつけてあります。この赤い線をたどっていくと、独立宣言が読み上げられた旧州議事堂、ファニュエル・ホール(サミュエル・アダムスの像が建っている)、独立の英雄であるポール・リビアの家、などの「名所・史跡」を一通りたどることができるというしかけです。
 フリーダム・トレイルを出発して最初に遭遇する建物は、ボストン・コモンの北東部にあるマサチューセッツ州議事堂(Massachusetts State House。右写真)です。門を入るとすぐにジョン・F・ケネディの像が目につき、記念写真をとっている観光客も多い。そこを離れて、建物に向かって右手の方へずっと進んでいくと、観光客も少なくなります。その右手の端の方に、一人の女性のブロンズの座像があります。メアリー・ダイアー(Mary Dyer)の像です。
フリーダム・トレイルを出発して最初に遭遇する建物は、ボストン・コモンの北東部にあるマサチューセッツ州議事堂(Massachusetts State House。右写真)です。門を入るとすぐにジョン・F・ケネディの像が目につき、記念写真をとっている観光客も多い。そこを離れて、建物に向かって右手の方へずっと進んでいくと、観光客も少なくなります。その右手の端の方に、一人の女性のブロンズの座像があります。メアリー・ダイアー(Mary Dyer)の像です。メアリー・ダイアー
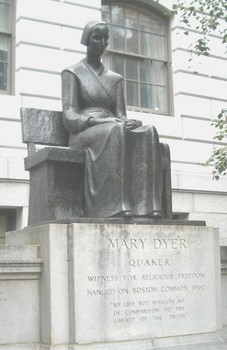 メアリー・ダイアーは「クエーカー教徒」でした。1660年、彼女はクエーカー教徒であることをやめなかった罪で、ボストン・コモンで絞首刑になりました。40歳代後半でした。
メアリー・ダイアーは「クエーカー教徒」でした。1660年、彼女はクエーカー教徒であることをやめなかった罪で、ボストン・コモンで絞首刑になりました。40歳代後半でした。ボストン市民の名誉のために付け加えると、彼女はいわゆる「リンチ」で絞首刑になったのではありません。当時のマサチューセッツでは「クエーカー教禁止例」という法律が制定され(1658)、クエーカー教徒であることやその布教には厳罰が課せられていました。メアリー・ダイアーはクエーカー教を布教した罪で3度逮捕され、はじめの2度はマサチューセッツからの追放処分になり、3度目は死刑判決を受けたものの恩赦を受け、3たび追放されました。しかし彼女は再びマサチューセッツに戻って布教をしたため、今度こそ、死刑宣告をうけて絞首刑になったのです。完全な「確信犯」でした。
メアリー・ダイアーの「殉教」はさまざまな思いを想起させます。独立以前のアメリカへの移民の歴史で大きく強調されるのが「清教徒」(ピルグリム・ファーザーズ)がイングランドでの迫害から逃れメイフラワー号で「ニューイングランド」に渡ったという一件です。清教徒は英国国教会における改革派ないしは分離派であり、正統に対する異端と言えるでしょう。その英国国教会を含むプロテスタントも、カトリックに対する「異端」として始まりました。そして清教徒たちが到着したニューイングランドでは、今度はクエーカー教徒が「異端」であり、メアリー・ダイアーは絞首刑になったわけです。
アメリカ合衆国憲法では「信教の自由」が高らかにうたわれています。しかし憲法制定(1787年)の120年ほど前には「異端」の罪で人が処刑されていたのです。「信教の自由」はメアリー・ダイアーを始めとして流された多くの血によって獲得されたと考えられます。クエーカー教徒の処刑は彼女だけではないのですが、「いくらなんでも、まずい」という思いが植民地の人々に徐々に広まったのではないでしょうか。もちろん憲法の制定で問題が解決したわけではなく、現代までも続いていることは知られているとおりです。
歴史に目を向けると、キリスト教徒をはじめとする「殉教」は枚挙にいとまがありません。ヨーロッパの著名な教会にいくと殉教者の像や絵画は山ほどあります。日本でも殉教はありました。長崎に行くと殉教者の像もあります(日本二十六聖人記念碑)。メアリー・ダイアーの処刑も、そういった歴史の中のごく小さなひとコマに過ぎません。
しかし私にとって「全く意外」だったのは、民主主義の殿堂である「州議会の議事堂」というまさにその場所に、そこに集まる議員たちの先祖が目と鼻の先の公園で処刑した「殉教者」のブロンズ像が建っている、というその事実でした。
ボストン・ダック・ツアー
 メアリー・ダイアーの像の存在を私に教えてくれたのは、ボストン・ダック・ツアーの運転手兼ガイドのお兄さんです。ボストン・ダック・ツアーというのは、もともと軍事用だった水陸両用車を改造した小型の観光バス(観光トラックと言うべきか)でボストンの主要観光スポットをめぐり、チャールズ川のクルーズをするというツアーです。ダック(あひる)というのはこの水陸両用車の愛称です。いかにも「典型的アメリカ人」という感じの陽気なお兄さんは、途切れることなく観光名所の解説を英語でまくしたてていましたが、州議事堂の前を通った時、女性の像をさして「彼女は Boston Common で was hanged.」と言ったのです。一瞬、聞き間違いかと思いました。しかし彼は確かに hanged と言ったのです。
メアリー・ダイアーの像の存在を私に教えてくれたのは、ボストン・ダック・ツアーの運転手兼ガイドのお兄さんです。ボストン・ダック・ツアーというのは、もともと軍事用だった水陸両用車を改造した小型の観光バス(観光トラックと言うべきか)でボストンの主要観光スポットをめぐり、チャールズ川のクルーズをするというツアーです。ダック(あひる)というのはこの水陸両用車の愛称です。いかにも「典型的アメリカ人」という感じの陽気なお兄さんは、途切れることなく観光名所の解説を英語でまくしたてていましたが、州議事堂の前を通った時、女性の像をさして「彼女は Boston Common で was hanged.」と言ったのです。一瞬、聞き間違いかと思いました。しかし彼は確かに hanged と言ったのです。「なぜ?」と思って、ダック・ツアーが終わってから州議事堂にいって確認したのが、メアリー・ダイアーの像です。像の台座には次の文字が刻んであります。
|
この碑文にあるavailethは古語で、avail の三人称単数現在形です。現代英語では avails で、従って not availeth は does not avail です。not avail me という言い方がいかにも英語っぽくて、日本語に直訳するのは難しいのですが、意訳すると次のようになるでしょう。
(試訳) |
The Liberty of The Truth を「真実の自由」とすると日本語としては意味が変わってしまうので「信教の自由」と意訳しました。The Truth というのはつまり「神の言葉」の意味ですね。The Liberty of The Truth は「神の言葉を自由に語ること」と解釈して「信教の自由」としました。
フリーダム・トレイルの意味
フリーダム・トレイルは以前に歩いたことがあります。その時の印象は「アメリカ史の勉強になった」というものでした。なぜフリーダム・トレイル、つまり「自由の道」なのか、それは明白で「自由のために独立戦争を戦った古き良き時代のアメリカを、建国の地ボストンでたどる道」であり、アメリカ万歳、というような暗黙の意味があると思っていました。
しかしメアリー・ダイアーの像を知って「フリーダム・トレイル」の意味は一変しました。それは「アメリカ万歳」ではなく、その名前が直接的に表現しているように、人間の歴史が獲得してきた自由の大切さ、強制の排除と寛容の精神で社会を構成することの大切さを認識するための道だと思えたのです。だって、そうですよね。信教の自由(Religious Freedom)の証人(Witness)の像が、トレイルの出発点(ボストン・コモン)を見おろす位置にあるのですから。フリーダム・トレイルの「最重要スポット」は、その言葉の意味からして明らかにメアリー・ダイアーの像です。ガイドブックには全く書いてないけれど・・・・・・。
メアリー・ダイアーの像は、ダック・ツアーのガイドさんが紹介するぐらいなのだから、ボストン市民にとってはよく知られているのでしょう。ガイドのお兄さんに感謝したいと思います。
| 補記1 |
メアリー・ダイアーはクエーカー教の初期の伝道者であり、17世紀後半のアメリカではクエーカー教徒は弾圧されました。その後、宗教の自由が認められるようになり、クエーカー教徒の数も増えていきます。そしてボストン近郊におけるクエーカー教徒のコミュニティが、アメリカの捕鯨産業の中心となります。この経緯を「No.20 - 鯨と人間(1)欧州・アメリカ・白鯨」に書きました。
| 補記2 |

| |||
|
新渡戸稲造夫妻 [site : 十和田市立 新渡戸記念館] | |||
言うまでもなく、新渡戸稲造の功績は「武士道」(1899)という本を英語で書いて出版し、日本の精神文化を世界に紹介したことです。山本博文・訳「武士道」(ちくま新書)の訳者序文によると「新渡戸にとってクエーカー主義の影響は大きく、この思想に出会ったことで、キリスト教と東洋思想を調和させることができたと語っている。」そうです。
メアリー・ダイアーのボストンにおける殉教は、アメリカ東海岸のクエーカー教徒を通じて「武士道」まで、細い糸で繋がっているようです。