No.27 - ローマ人の物語(4)帝政の末路 [本]
(前回より続く)
帝政による「ローマ文化」の破壊
キリスト教の国教化に至る道筋を読んで強く印象に残るのは、キリスト教徒を組織的に迫害したすぐ後の皇帝がキリスト教を公認しているということです。
ディオクレティアヌス帝(285-305)は「ローマ史上初めての本格的かつ組織的なキリスト教弾圧(第13巻:最後の努力)」に乗り出します。303年の「キリスト教弾圧勅令」は、
| ◆ | キリスト教教会の破壊 | |
| ◆ | 信徒の集まり、ミサ、洗礼式などの行事の厳禁 | |
| ◆ | 聖書、十字架などを没収し焼却 | |
| ◆ | 教会財産の没収 | |
| ◆ | キリスト教徒の公職追放 |
という徹底ぶりです。キリスト教を根絶しようという非常に強い意図が感じられます。
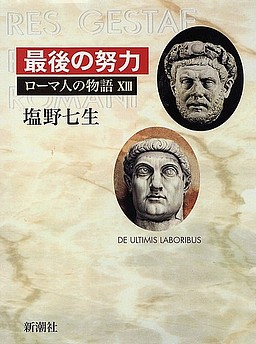 ところがその直後の皇帝・コンスタンティヌス(306-337)は、312年に有名なミラノ勅令を出してキリスト教を公認します。勅令は公認しただけであって国教としたわけではありませんが、その後のコンスタンティヌス帝は国教化に向けた動きとしか思えない行動に出るのです。この時点からテオドシウスス帝(379-395)による392年のキリスト教の国教化は一直線です。
ところがその直後の皇帝・コンスタンティヌス(306-337)は、312年に有名なミラノ勅令を出してキリスト教を公認します。勅令は公認しただけであって国教としたわけではありませんが、その後のコンスタンティヌス帝は国教化に向けた動きとしか思えない行動に出るのです。この時点からテオドシウスス帝(379-395)による392年のキリスト教の国教化は一直線です。ディオクレティアヌス帝によるキリスト教の根絶を目指した大弾圧と、コンスタンティヌス帝によるキリスト教の公認。このわずか8年の間に行われた、大弾圧から公認という政策の大転換に、帝国としての統一的な考えがあったとはとても思えません。
では、コンスタンティヌス帝によるキリスト教公認の理由は何でしょうか。それは塩野さんによると「支配の道具としてキリスト教を使うため」です。皇帝が帝国を支配する根拠を「神」に求めたい。この「神」の位置になりうるのは一神教の神しかない。ユダヤ教はユダヤ民族の宗教にとどまっている。消去法で残された選択肢はキリスト教しかない、というわけです。
現実世界における、つまり俗界における、統治ないしは支配の権利を君主に与えるのが、「人間」ではなく「神」である、とする考え方の有効性に気づいたとは、驚嘆すべきコンスタンティヌスの政治センスの冴えであった |
「支配の道具」としてキリスト教を位置づけた以上、一神教からみた「異教」は排除しなければなりません。ローマ皇帝自身、ローマの政治システム自身がローマ固有宗教の破壊に邁進し出します。それは、帝国自身による組織的かつ強権的なローマ文化の破壊だったわけです。
文明の破壊
キリスト教の国教化による影響はローマ固有の宗教の破壊だけに止まりませんでした。塩野さんは次のように書いています。
首都ローマだけでも28も存在した公共図書館をふくめ、ローマ帝国の中にあった膨大な数の図書館の閉鎖も始まったのだ。ローマ時代の公共図書館の蔵書は、バイリンガル帝国を反映してギリシャ語とラテン語の書物に2分されて公開されていたのだが、これらの書物の内容はほとんどすべて、異教の世界を叙述したものだからであった。図書館の閉鎖につづくのは、蔵書の散逸である。 |
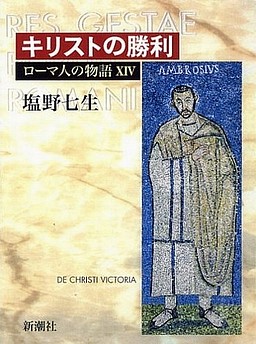 こういう記述を読んで直感的に思うのですが、公共図書館の書物や、それから派生した各種の知的マテリアルに依存して生活していた人たちがいたはずです。哲学、語学、雄弁術、歴史、天文学、幾何学などの学者や教師、文筆で生計をたてている人などです。こういった知識人はこの時期、社会の隅に追いやられたり、攻撃されたり、おおっぴらに活動できなくなったのではないでしょうか。最低限、彼らは図書館が閉鎖され書物が散逸して意気消沈したはずです。「書物の散逸や破棄、知識の軽視」は、国の存続を危うくする行為の代表的なものだと思います。
こういう記述を読んで直感的に思うのですが、公共図書館の書物や、それから派生した各種の知的マテリアルに依存して生活していた人たちがいたはずです。哲学、語学、雄弁術、歴史、天文学、幾何学などの学者や教師、文筆で生計をたてている人などです。こういった知識人はこの時期、社会の隅に追いやられたり、攻撃されたり、おおっぴらに活動できなくなったのではないでしょうか。最低限、彼らは図書館が閉鎖され書物が散逸して意気消沈したはずです。「書物の散逸や破棄、知識の軽視」は、国の存続を危うくする行為の代表的なものだと思います。いや、国の存続を危うくするというより「文明を滅ぼす行為」です。事実、文明の中心地はその後に興ったイスラム世界になっていきます。ギリシャ・ローマの「知」を受け継いだのもイスラム世界です。アラビア語に翻訳され、バグダッドやカイロやイベリア半島のコルドバやトレドに蓄積され研究されたギリシャ・ローマの「知」は、それを西ヨーロッパが発見することでルネサンスへと繋がるわけですね。
塩野さんが書いている「図書館の閉鎖」ですが、この影響を受けて破壊され、蔵書が散逸した世界史上で非常に有名な図書館があります。アレキサンドリアの図書館です。それはプトレマイオス朝のエジプトの時代に作られ、戦乱による建物の破壊と修復を繰り返しつつ維持されてきました。それは数百年かけて蓄積されてきた、ローマ帝国の、というより地中海世界の「知」の結晶であり、文明の粋であったわけです。これを破壊してしまった。
「ローマ人の物語」の最後の数巻を読んで感じるのは、帝政が自らの保身のために、ローマの文化と文明、ローマの強み、ローマがローマたるゆえんを自らの手で破壊していくという、悲惨としか言いようのない姿です。
帝政の末路
帝政が自らの保身のために、ローマを破壊していくという結末を見るにつけ、ローマ的帝政という専制統治システムの機能不全を感じます。
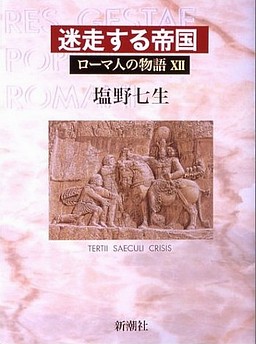 皇帝が国を統治するという「帝政」の機能不全とそれがローマ帝国に与えた悪影響はいろいろあると思いますが、典型的なのは軍人皇帝の乱立です。211年から73年間に、22人の皇帝が登場しては消え、そのうち14人は謀殺だったとあります(第12巻:迷走する帝国)。238年には1年間に5人もの皇帝が(死亡で)退位し、その5人の死亡原因は3人が謀殺、1人が自殺、1人が戦死でした。
皇帝が国を統治するという「帝政」の機能不全とそれがローマ帝国に与えた悪影響はいろいろあると思いますが、典型的なのは軍人皇帝の乱立です。211年から73年間に、22人の皇帝が登場しては消え、そのうち14人は謀殺だったとあります(第12巻:迷走する帝国)。238年には1年間に5人もの皇帝が(死亡で)退位し、その5人の死亡原因は3人が謀殺、1人が自殺、1人が戦死でした。ローマ皇帝は「終身」です。従って皇帝にふさわしくない人物を「意図的に」退位させるには「謀殺」しかないのでしょう。問題はなぜそのような状況に陥るのか、なぜその程度の人物が皇帝の地位につけるのかです。結局のところローマの帝政は一面からみると実質的な軍事独裁制であり、これが人の心をむしばむという「世界史における共通原理」が働いているのだと思います。第7巻「悪名高き皇帝たち」で描かれている「悪名皇帝たち」もそうです。
そのような帝政であっても優れたリーダが出てくることは当然ある。五賢帝の時代、つまりネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、アントニヌス・ピウス、マルクス・アウレリウスの5人の皇帝の治世時代 (96-180) は優れたリーダが輩出した時代と言えるでしょう(第9巻:賢帝の世紀)。しかし「五賢帝」という言い方が広まったということは、裏を返すと「愚帝が輩出してローマが傾いた」こと人々が感じ取ったからだと思います。73年間に22人の皇帝が乱立したのは、五賢帝のすぐ後の時代(211-283)です。
そしてローマ帝国の最終段階で起こったことは、帝政が自らの保身のために、また皇帝が自らの権力を正当化するために新たな「支配の道具」を持ち込み、ローマの文化やローマがローマたるゆえんを破壊していくという結末でした。もともとアウグストゥスが完成させたとされる帝政の目的は、簡潔に言うと「広大になった帝国の現状を見据え、意志決定を迅速にして効率的に統治するため」だったはずです。
しかし統治システムを含むあらゆる制度は遅かれ早かれ自己目的化します。自己目的化とは、その制度を作った本来の目的や狙いの実現が二の次、三の次になり、外部環境が変化しているにもかかわらず「制度を守る」ことが第一の目標になることです。なぜ自己目的化するかというと、時間がたつと本来の目的が忘れられるからだし、その制度に依存した既得権益者を生むからです。国のリーダ自身が既得権益者になるという、恐ろしい事態も起こりうる。それ以前に、リーダの周りには既得権益者が群がってくる。
優秀な統治システムとは、その統治システムが自己目的化したときに最も国としての被害が少なく、国家が生き残りやすいシステム、ないしは生き残りやすい方向に自らを修正できるシステムだと思います。そして、自己目的化したときに最悪の制度がローマ的帝政だったというのが率直な感想です。
現代国家における民主制(民主主義)は「あやうい」制度です。民主的に選ばれたリーダが市民を扇動した結果、市民の財産や生命をあやうくするような選択を市民自身が「自由意志で」する、というような事が起こる。現代日本もそれと無縁ではありません。また「民主制の中から独裁制を生む」ようなリスクもあります。完璧と思える民主制の中から、その政体を自ら否定してしまうような国を生んだ20世紀のドイツの例があります。にもかかわらず現代の先進国家の多くが民主制を選んでいる理由は究極的には一つしかないと思います。それは民主制が、制度を守ることが自己目的化したときに最も国民の被害が少なく、衰退の度合いが少なく、国が生き残る可能性が高い統治システムだからです。
混乱の時代
経済が安定的に成長し、外敵の進入少なく、国が安定している時期は、どんな統治システムでも良いのだと思います。安定期のことだけを考えて統治システムの優劣は計れない。統治システムの優劣は、経済の停滞期や下降期、ないしは危機や混迷の時代をどう乗り切れるかにかかっているはずです。「ローマ人の物語」の率直な読後感から言うと危機や混迷を「制度の力」や「システムの力」で乗り切ったのは共和制の時代です。明らかにそう見える。「第2巻:ハンニバル戦記」と「第3巻:勝者の混迷」、および「第4・5巻 ユリウス・カエサル」にはそれが鮮やかに描かれています。
第1巻から5巻までの共和制の時代のローマの政治を形容す言葉を選ぶとすると、一つは「混乱」だと思います。貴族と平民は対立し、その後融和し、再び激しく抗争する。改革を断行するリーダが出現したと思えば、その次のリーダはまったく逆行する政策をとる。そもそも国の指導者層である元老員議員同士が抗争し、内戦状態にもなり、殺し合いにさえなる。独裁的指導者と大衆的指導者がめまぐるしく交代する・・・・・・。仮にオリエントの専制国家の国王から派遣された「大使」がローマに駐在していたとすると「ローマは混乱している。この国の先は長くない」と何度も本国に報告したと思います。常にではないにせよ、そうとしか見えない状況が何度もあったはずです。しかしローマは「長くない」どころか全く逆だった。その「全く逆」を実現したのは、一見「混乱」に見えるもののベースにある「統治システム=ローマ的共和制」であり、宗教を含む広い意味での「文化」なのだと思います。
帝政前期は「パックス・ロマーナ」の時代と言われています。この「パックス・ロマーナ」は共和制の時代に作られた「財産」や「資産」を維持できた時代だと見えます。この財産を、帝政後期に完全に食いつぶしてしまった。
3月15日
「ローマ人の物語」でたびたび引用されているカエサルの言葉があります。
|
この言葉の意味は「意図は正しくても、結果や事実として起きていることが、それに反することが多い。人間は意図を大切にし過ぎるから間違う。」ということでしょう。塩野さんもそう解釈しています。
これは一つの「事例」について言っていますが、これを拡大解釈して、カエサルが構想しオクタヴィアヌスが完成させたとされる「ローマの帝政」について当てはめてみるとどうなるでしょうか。広大なローマ支配地域を統治するためには、共和制ではなく一人の皇帝が効率的に統治するローマ的帝政、という「意図」は正しいと思います。しかしその帝国の400年の結果として起こったことは、自らの基盤を破壊するという自殺行為に等しいものでした。「意図は正しくても、結果や事実として起きていることが、それに反する」わけです。カエサルが構想しオクタヴィアヌスが完成させた帝政は、少なくとも失敗の端緒か遠因を作ってしまった。
優秀な人間は「自分のような人間が将来もリーダになる」ということを(そんなことはあり得ないと分かりながら)暗黙に考えてしまいます。「リーダは、目的と手段をとりちがえるような本末転倒のことはしない」と暗黙に考えてしまいます。自分がそうではないからです。しかし優秀でないリーダは必ず出ます。血筋による継承では「玉石混合」になるのはあたりまえだし、リーダが選ばれるタイプの統治システムにおいても、優秀でないからこそリーダに選ばれる(指名される)という例が多々あります。人間社会とはそういうものです。またある制度が定着すると、その制度に依存した既得権者が必ず出現し、制度本来の目的の遂行を妨害します。必然的にそういう動きになります。
紀元前44年3月15日、カエサルは「共和制維持派」の人たちに暗殺されました。「3月15日は西欧人なら誰でも知っているカエサル暗殺の日」(第4巻:ユリウス・カエサル ルビコン以後)です。この日、カエサルを暗殺した人たちは、伝統的なローマの統治体制の維持しか頭にない、保守的で、蒙昧で、先が読めず、既得権益の維持しか頭にない人たちだったのでしょうか。
むしろ、カエサルを暗殺した人たちの方が直感的にものごとの本質を理解していたのかもしれません。なぜなら最も本質をよく理解できるのは、リーダとしての素質・洞察力・実行力が十分にありながら、自分が「本当はリーダとしては愚鈍な人物かもしれないという恐れ」や「既得権にしがみつくような、リーダとしてはふさわしくない人物かもしれないという恐れ」を無自覚に抱いている人間だからです。
内部環境、外部環境の変化にマッチさせて国を運営していくためには、その阻害要因を取り除く「改革」や「変革」や「修正」が不断に必要になります。これが可能なシステムとその実行能力が国家の、そしてもっと一般化すると組織の必須要件でしょう。これが「ローマ人の物語」の、ローマの興亡に関する部分の読後感です。
神々のその後
「民族伝統の神々の破壊」はローマやコンスタンチノープルという首都だけでなく、ローマ帝国全域で行われました。さらにその後のヨーロッパの歴史をみると、ローマ帝国の領域の周辺へと「民族伝統の神々の破壊活動」が拡大していきます。たとえば12世紀から13世紀にかけては「ヴェンド十字軍」という名目のもとに「異教徒征伐」の戦争が行われ、現在のバルト3国やポーランド付近にもキリスト教が普及していきます。これにともなってその土地の固有宗教は絶滅するか、陰に追いやられて行きました。では固有宗教が全く死に絶えたのかと言うと、そうでもありません。それらは神話、伝承、民話、魔女・魔法使い・妖精の伝説や、各地の伝統行事として残ることとなります。
No.22「クラバートと奴隷 (1) 」に書いたように、ヴェンド十字軍の「ヴェンド」とは、もともとゲルマン民族からみた周辺民族、特にスラヴ人をさす言葉です。No.1, No.2 の「クラバート」において、クラバートは「ヴェンド人」と紹介されていました。このヴェンド人という言い方はドイツ語であって、自民族の言葉ではソルブ人です(No.5「交響詩・モルダウ」)。シュヴァルツコルムのクラバートは、その昔「周辺の非キリスト教民族」として征服され、キリスト教に改宗した(させられた)スラヴ系民族の末裔だという気がします。小説「クラバート」はソルブ人に伝わる「クラバート伝説」がもとになっています。水車場の親方、および彼が駆使する「魔法」や「魔法典」は、ソルブ人が本来持っていた神々や宗教の記憶ではないでしょうか。
現代においても、神々の記憶がキリスト教と共存している例もあります。以前、NHKのTV番組「地球に乾杯」で、スイスのレッチェンタールという村の謝肉祭の様子が放映されました。鬼のような異形の面をかぶった人たちが村中をまわるのですが、日本の秋田県の「なまはげ」とどこが違うのかとさえ思いました。謝肉祭ではあるものの、民族の固有宗教・文化の記憶を強く感じさせるものです。
では「ローマの神々」はどうなったのでしょうか。キリスト教(特にカトリック)には、本来の一神教ではありえない「多神教的性格」があります。
| ◆ | 聖母マリアの崇拝 | |
| ◆ | 数々の聖者や聖人、町の守護聖人の存在 | |
| ◆ | 聖者や聖人に関する「聖遺物」への崇拝 | |
| ◆ | 奇蹟の伝承とその崇拝 | |
| ◆ | ヨーロッパ各地にある聖地への巡礼 |
などです。ローマの神々はキリスト教の枠内で、数百年の時間を経る中で、形を変えて生き残ったとも言えるでしょう。
人間集団のアイデンティティの再構築には時間がかります。と同時に、消し去ろうと思っても容易にはできないコアな部分があって、それが人間社会の持続性と、それに密接に関係している文化の発達をさえているのだと思います。
2011-05-20 20:20
nice!(0)
トラックバック(0)



