No.12 - バベットの晩餐会(1) [映画]
No.3 「ドイツ料理万歳!」で紹介しましたが、この本の著者の川口さんはドイツ料理が発達しなかった理由について、
などをあげ、最後に
に言及しています。私は④が一番の理由じゃないかと No.3 で書いたのですが、それは映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからだ、とも書きました。その「バベットの晩餐会」(1987年、デンマーク映画)についてです。
映画「バベットの晩餐会」のあらすじ
舞台は19世紀のデンマーク、北海に突き出たユトランド半島の海辺の寒村です。この地に住みついた一人の牧師がルター派の小さな教会をはじめ、村人たちに神の教えを説きます。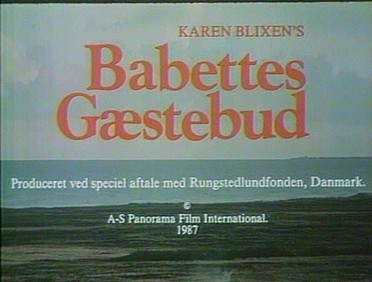 牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。
牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。
この村に外から偶然やって来て、姉妹に心を引かれた男が二人いました。一人は騎兵隊のローレンス・レーヴェンイェルム士官です。彼は賭事による借金を親に叱責され、ユトランド半島の叔母の家に3ヶ月間滞在して心を入れ替えろと命令されてやってきました。そして村を通りかかった時に、上の娘のマルチーネと出会います。士官は彼女に強く引かれ教会に足繁く通いますが、滞在期間が過ぎ、忘れがたい思いを残しつつ村を去ります。士官は王妃の侍女と結婚しました。
もう一人はパリで活躍しているフランス人のオペラ歌手、アシール・パパンです。彼はストックホルムに公演にきたとき、ユトランド半島の自然を見て帰りたいということで、村にやって来て食料品店に宿をとりました。そして教会に行ったとき、牧師の下の娘・フィリパの美しい声に惚れ込んでしまいます。パリで歌手としてもやっていける才能があると感じたパパンは、父親の牧師の了解をとって村でフィリパに歌のレッスンを始めます(ちなみにこの場面では、モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンニの中の2重唱が大変効果的に使われています)。しかしフィリパは神に仕える意志が強く、父親にレッスンの中止を申し出ます。パパンは失意のうちにパリへと去ります。
その後、牧師も亡くなり、牧師の弟子の村人は残された2人の娘に託されました。そして月日がたちました。
1971年の9月の、嵐雨の夜のことです。疲れきった表情の見知らぬ女性が姉妹を訪ねてきます。そして、一通の手紙を姉妹に差し出します。 それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」
それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」

姉妹は「家政婦を雇う余裕はないのです」と言いますが、バベットは「お金はいりません。置いてもらうだけでよいのです」と懇願します。姉妹も納得し、バベットは姉妹の召使いとして働き始めます。姉妹は土地の言葉や、村での生活のすべをバベットに教えます。例えば水につけてもどした干し魚を切り身にし、パンをいれ、ビールを加えて煮込む料理の方法などです。
そうやって14年が経過しました。牧師の弟子だった村の人たちも年をとり、怒りっぽくなり、教会においても些細なことでいさかいが絶えなくなります。姉妹は心配します。そこで亡くなった牧師の生誕100周年の日に、牧師を知る村人を招いて晩餐会をやろうと企画します。姉妹の狙いは牧師の教えを再び思い返し、村人たちの神に仕える気持ちを高め、融和をはかることでした。
一方バベットには唯一パリとのつながりがありました。それはパリにいる親友が、預けたお金で毎年買って送ってくれる宝くじです。晩餐会も近づいた頃、バベットはその親友から手紙を受け取ります。驚いたことに「1万フランの宝くじがあたった」という内容です。これを知った姉妹は、とうとうバベットと別れる時が来た、バベットはパリに帰るものとあきらめます。
その夜、姉妹はバベットからある申し出を受けます。それは「牧師の誕生日の晩餐会に料理を作らせてほしい。フランス料理を作りたい。費用は私が出す。いままで頼みごとをしたことはない。たった一度のお願いを聞いてほしい。その準備のために数日間の休みを欲しい」との申し出です。姉妹は「バベットが費用を出す」ということを固辞しますが、バベットの「たった一度のお願いですから」という言葉に説得され、了承します。
バベットは休暇をとり、船乗りの甥に頼んでフランスから食材を取り寄せます。村に戻ってきたバベットは、晩餐会に使う食材を船から次々と運び込みました。海亀、ウズラ、クロ・ヴージョ(ワイン)・・・・・・。姉妹や村人にとっては見たこともないような食材です。姉妹は心配になってきました。バベットが「魔女の饗宴」をやるように見えてきたからです。姉妹は村人を集めて謝ります。「牧師の誕生日の晩餐会で魂を危険にさらすことになった。何を食べさせられるかもわからない。災いを招くかもしれない。こんなことになるとは思わなかった。私たちはただ、バベットの望みをかなえてあげたかっただけです。」
これに対して村人たちは答えます。「大丈夫です。晩餐会では何があっても食べ物や飲み物の話はしません。どんな言葉も出さないようにします」「舌は、神をたたえるが、一方では手に負えない毒の塊です。晩餐会の日には皆、味がないように振る舞いましょう。舌はお祈りのために使います」
晩餐会も迫ってきたころ、レーベンイェルム夫人から手紙がきます。「甥のレーベンイェルム将軍も、牧師の生誕100年の晩餐会に是非出たいといっている。将軍を一緒につれていきたい」との内容です。将軍とは、かつて士官の時代に村を訪れた、その人です。こうして晩餐会には姉妹を含めて12人が出席することにになりました。
晩餐会の当日です。村人たちは「味わってはなならぬ、料理の話はするな、何も考えないように」と言い合いながら席につきます。レーベンイェルム将軍も叔母といっしょに到着しました。そして晩餐会が始まります。
晩餐会の場面を文章で表現するのは難しいのですが、要するに、言葉にするかしないかは別にして、あまりのおいしさに出席者全員が圧倒されていくのです。出席者のうち唯一の「食通」は将軍ですが、 最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。
最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。
メインディッシュの「ウズラのパイケース入り」が出たとき、将軍はフランスに駐在していた頃にフランス騎兵隊の軍人とパリのレストランに行った思い出を語ります。「パリの最高級レストラン、カフェ・アングレに行ったことがある。驚いたことにそこの料理長は女性だった。そして彼女の創作料理がウズラのパイだった。その夜のホストだったフランスの将軍はこう言っていた。ここの料理長は食事を恋愛に変えることのできる女性だ。近頃のパリには決闘してでも欲しい思える女性はいなくなった。唯一、決闘に値する女性はこの店の料理長だと・・・。彼女は厨房の天才として有名だった」
村人たちの会話も弾んでいきます。牧師の生前の思い出に話がはずみ、いさかいをしていた村人同士が互いに詫びたり、いたわりの言葉をかけたりと、次第に和やかな雰囲気に包まれていきます。村人たちの表情もやさしくおだやかになっていき、人と人の信頼関係がふただび取り戻せたように見えます。
晩餐会がすべて終わり、満ち足りた表情を浮かべて客たちが帰ったあと、姉妹とバベットは会話を交わします。この最終場面の会話はすべて掲げましょう。



料理とは何か
「寓話」と言うならその通りです。しかし強い印象を残す「寓話」です。この映画の、晩餐会にまつわる基本的なメッセージは、
ということでしょう。映画では「魂を危険にさらす」覚悟で晩餐会に臨んだ村人たちの、最初はこわばった表情が次第に和んでいく様子が精緻なカメラワークでとらえられています。この映画を見た人が誰しも強烈な印象を覚えるのは、この晩餐会の場面における人々の表情と、その背後にあるメッセージだと思います。
宗教と料理
しかしそれ以外に私が強く印象に残ったことがあります。それは村人が晩餐会に臨むときの彼らの考えなのです。村人からすると「おいしい料理を味わうことは、魂を危険にさらす」ことであり「料理をおいしいと思うこと自体が神への裏切り」になり「舌は、言葉によってお祈りをするものであって、料理を味わうものではない」のです。
最初に書いたように、No.3「ドイツ料理万歳!」でドイツ料理が発達しなかった理由について「プロテスタントに影響されたドイツ人の気質」が一番じゃないかとしたのですが、それはこの「バベットの晩餐会」の印象が強かったからです。バベットの晩餐会に出てくる村人のような考えでいる限り、料理は発達のしようがないのです。もちろん現在では村人のように考える人はいないと思います。しかしプロテスタントの教えが原型としてあって、それが国民の気質にまで影響を与えるとき、その気質は長期間残るのではと思うのです。
この映画の舞台はデンマークの寒村です。ドイツではありません。しかし歴史的にプロテスタントがメジャーだった地域には、料理についての共通性があるのではないでしょうか。私の経験でも「ドイツ、オランダ、ベルギー北部、イギリス」と「イタリア、フランス、ベルギー南部、スペイン」の間には、どうも明確な境界線があるように思えてならないのです。
ちょっと脇道にそれますが、この「境界線」を皮肉ったジョークがいろいろと思い出されますね。たとえばフランスには次のようなジョークがあるようです。
 イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。
イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。
これをフランス人が書くと「傲慢」に聞こえると思いますが、イギリス人の(かつプロヴァンスに惚れ込んでいる人の)著書だからこういう記述もアリなのでしょう。
こういう文章を読むと「食」に関心が高い人は「ラムを一度しか殺さない」プロヴァンスに是非行ってみたい、と思うのではないでしょうか。この本が出版されたあと、ヨーロッパ中からこの本を手にした観光客がプロヴァンスに押し寄せたようですね。分かります。

| ① | 食材の不足 |
| ② | 狩猟文化 |
| ③ | イタリア・フランスとの格差 |
などをあげ、最後に
| ④ | プロテスタントに影響されたドイツ人の気質 |
に言及しています。私は④が一番の理由じゃないかと No.3 で書いたのですが、それは映画「バベットの晩餐会」の強烈な印象があるからだ、とも書きました。その「バベットの晩餐会」(1987年、デンマーク映画)についてです。
映画「バベットの晩餐会」のあらすじ
(以下には物語のストーリーが明かされています)
舞台は19世紀のデンマーク、北海に突き出たユトランド半島の海辺の寒村です。この地に住みついた一人の牧師がルター派の小さな教会をはじめ、村人たちに神の教えを説きます。
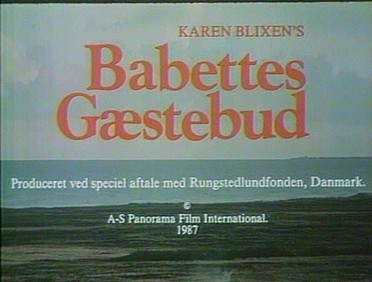 牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。
牧師にはマルチーネとフィリパという2人の美しい娘がいました。姉妹は父親ともに神に仕える道を選び、町の社交界などには顔を出しません。村の男たちは姉妹に会うために教会へ足を運んだほどでした。この村に外から偶然やって来て、姉妹に心を引かれた男が二人いました。一人は騎兵隊のローレンス・レーヴェンイェルム士官です。彼は賭事による借金を親に叱責され、ユトランド半島の叔母の家に3ヶ月間滞在して心を入れ替えろと命令されてやってきました。そして村を通りかかった時に、上の娘のマルチーネと出会います。士官は彼女に強く引かれ教会に足繁く通いますが、滞在期間が過ぎ、忘れがたい思いを残しつつ村を去ります。士官は王妃の侍女と結婚しました。
もう一人はパリで活躍しているフランス人のオペラ歌手、アシール・パパンです。彼はストックホルムに公演にきたとき、ユトランド半島の自然を見て帰りたいということで、村にやって来て食料品店に宿をとりました。そして教会に行ったとき、牧師の下の娘・フィリパの美しい声に惚れ込んでしまいます。パリで歌手としてもやっていける才能があると感じたパパンは、父親の牧師の了解をとって村でフィリパに歌のレッスンを始めます(ちなみにこの場面では、モーツァルトのオペラ、ドン・ジョバンニの中の2重唱が大変効果的に使われています)。しかしフィリパは神に仕える意志が強く、父親にレッスンの中止を申し出ます。パパンは失意のうちにパリへと去ります。
その後、牧師も亡くなり、牧師の弟子の村人は残された2人の娘に託されました。そして月日がたちました。
1971年の9月の、嵐雨の夜のことです。疲れきった表情の見知らぬ女性が姉妹を訪ねてきます。そして、一通の手紙を姉妹に差し出します。
 それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」
それはパリにいるパパンからの手紙で、次のようなことが書かれていました。「手紙を持参したのはバベット・エルサン夫人といいます。パリで革命が起こり、バベットの夫と子供は殺され、彼女もあやうく処刑されるところでした。船でコックをしているバベットの甥が逃亡を助けました。その甥からデンマークに知人はいないかと聞かれ、お二人のことを思い出しました。夫人は料理の名手です。私も今は不遇の身ですが、昔の友の心からの敬意をお受け取りください。」
姉妹は「家政婦を雇う余裕はないのです」と言いますが、バベットは「お金はいりません。置いてもらうだけでよいのです」と懇願します。姉妹も納得し、バベットは姉妹の召使いとして働き始めます。姉妹は土地の言葉や、村での生活のすべをバベットに教えます。例えば水につけてもどした干し魚を切り身にし、パンをいれ、ビールを加えて煮込む料理の方法などです。
そうやって14年が経過しました。牧師の弟子だった村の人たちも年をとり、怒りっぽくなり、教会においても些細なことでいさかいが絶えなくなります。姉妹は心配します。そこで亡くなった牧師の生誕100周年の日に、牧師を知る村人を招いて晩餐会をやろうと企画します。姉妹の狙いは牧師の教えを再び思い返し、村人たちの神に仕える気持ちを高め、融和をはかることでした。
一方バベットには唯一パリとのつながりがありました。それはパリにいる親友が、預けたお金で毎年買って送ってくれる宝くじです。晩餐会も近づいた頃、バベットはその親友から手紙を受け取ります。驚いたことに「1万フランの宝くじがあたった」という内容です。これを知った姉妹は、とうとうバベットと別れる時が来た、バベットはパリに帰るものとあきらめます。
その夜、姉妹はバベットからある申し出を受けます。それは「牧師の誕生日の晩餐会に料理を作らせてほしい。フランス料理を作りたい。費用は私が出す。いままで頼みごとをしたことはない。たった一度のお願いを聞いてほしい。その準備のために数日間の休みを欲しい」との申し出です。姉妹は「バベットが費用を出す」ということを固辞しますが、バベットの「たった一度のお願いですから」という言葉に説得され、了承します。
バベットは休暇をとり、船乗りの甥に頼んでフランスから食材を取り寄せます。村に戻ってきたバベットは、晩餐会に使う食材を船から次々と運び込みました。海亀、ウズラ、クロ・ヴージョ(ワイン)・・・・・・。姉妹や村人にとっては見たこともないような食材です。姉妹は心配になってきました。バベットが「魔女の饗宴」をやるように見えてきたからです。姉妹は村人を集めて謝ります。「牧師の誕生日の晩餐会で魂を危険にさらすことになった。何を食べさせられるかもわからない。災いを招くかもしれない。こんなことになるとは思わなかった。私たちはただ、バベットの望みをかなえてあげたかっただけです。」
これに対して村人たちは答えます。「大丈夫です。晩餐会では何があっても食べ物や飲み物の話はしません。どんな言葉も出さないようにします」「舌は、神をたたえるが、一方では手に負えない毒の塊です。晩餐会の日には皆、味がないように振る舞いましょう。舌はお祈りのために使います」
晩餐会も迫ってきたころ、レーベンイェルム夫人から手紙がきます。「甥のレーベンイェルム将軍も、牧師の生誕100年の晩餐会に是非出たいといっている。将軍を一緒につれていきたい」との内容です。将軍とは、かつて士官の時代に村を訪れた、その人です。こうして晩餐会には姉妹を含めて12人が出席することにになりました。
晩餐会の当日です。村人たちは「味わってはなならぬ、料理の話はするな、何も考えないように」と言い合いながら席につきます。レーベンイェルム将軍も叔母といっしょに到着しました。そして晩餐会が始まります。
晩餐会の場面を文章で表現するのは難しいのですが、要するに、言葉にするかしないかは別にして、あまりのおいしさに出席者全員が圧倒されていくのです。出席者のうち唯一の「食通」は将軍ですが、
 最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。
最初の「海亀のスープ」のおいしさに、スープ皿を手にもって残ったスープを直接口に注いだりします。村人もそれを見てまねをします。メインディッシュの「ウズラのパイケース入り」が出たとき、将軍はフランスに駐在していた頃にフランス騎兵隊の軍人とパリのレストランに行った思い出を語ります。「パリの最高級レストラン、カフェ・アングレに行ったことがある。驚いたことにそこの料理長は女性だった。そして彼女の創作料理がウズラのパイだった。その夜のホストだったフランスの将軍はこう言っていた。ここの料理長は食事を恋愛に変えることのできる女性だ。近頃のパリには決闘してでも欲しい思える女性はいなくなった。唯一、決闘に値する女性はこの店の料理長だと・・・。彼女は厨房の天才として有名だった」

村人たちの会話も弾んでいきます。牧師の生前の思い出に話がはずみ、いさかいをしていた村人同士が互いに詫びたり、いたわりの言葉をかけたりと、次第に和やかな雰囲気に包まれていきます。村人たちの表情もやさしくおだやかになっていき、人と人の信頼関係がふただび取り戻せたように見えます。
晩餐会がすべて終わり、満ち足りた表情を浮かべて客たちが帰ったあと、姉妹とバベットは会話を交わします。この最終場面の会話はすべて掲げましょう。

- マルチーヌ:
- バベット、すばらしい食事だったわ。みんなも同じ気持ちよ。
- バベット:
- 私はカフェ・アングレの料理長でした。
- マルチーヌ:
- あなたがパリに戻っても、このことは忘れないわ。
- バベット:
- パリには戻りません。
- マルチーヌ:
- パリに戻らないの?
- バベット:
- 私は戻れないのです。すべて失いました。お金もありません。

- マルチーヌ:
- お金がない? でもあの1万フランは?
- バベット:
- 使いました。
- マルチーヌ:
- 1万フランも?
- バベット:
- カフェ・アングレの12人分は1万フランです。
- フィリパ:
- でもバベット。私たちのために全部使ってしまうなんて。
- バベット:
- 理由はほかにもあります。

- マルチーヌ:
- 一生、貧しいままになるわ。
- バベット:
- 貧しい芸術家はいません。
- フィリパ:
- あれがカフェ・アングレで出した料理なの?
- バベット:
- お客さまを幸せにしました。力の限りを尽くして。パパン氏がご存知です。
- フィリパ:
- アシール・パパン!
- バベット:
- ええ、彼が言いました。世界中で芸術家の心の叫びが聞こえる。私に最高の仕事をさせてくれ。
- フィリパ:
- でも、これが最後ではないわ。絶対に最後ではないわ。天国であなたは至高の芸術家になる。それが神の定め。天使もうっとりするわ。(日本語訳:関 美冬)
料理とは何か
「寓話」と言うならその通りです。しかし強い印象を残す「寓話」です。この映画の、晩餐会にまつわる基本的なメッセージは、
|
料理は食べる人の心に直接的に働きかけ、心を豊かにし、なごませ、幸せな気分にし、人と人とのつながりを強める演出ができる。それは食べる人の宗教や国籍、階級、財力、地位、年齢には無関係で、ちょうど音楽や絵画がそうであるように、料理は芸術。 |
ということでしょう。映画では「魂を危険にさらす」覚悟で晩餐会に臨んだ村人たちの、最初はこわばった表情が次第に和んでいく様子が精緻なカメラワークでとらえられています。この映画を見た人が誰しも強烈な印象を覚えるのは、この晩餐会の場面における人々の表情と、その背後にあるメッセージだと思います。
宗教と料理
しかしそれ以外に私が強く印象に残ったことがあります。それは村人が晩餐会に臨むときの彼らの考えなのです。村人からすると「おいしい料理を味わうことは、魂を危険にさらす」ことであり「料理をおいしいと思うこと自体が神への裏切り」になり「舌は、言葉によってお祈りをするものであって、料理を味わうものではない」のです。
最初に書いたように、No.3「ドイツ料理万歳!」でドイツ料理が発達しなかった理由について「プロテスタントに影響されたドイツ人の気質」が一番じゃないかとしたのですが、それはこの「バベットの晩餐会」の印象が強かったからです。バベットの晩餐会に出てくる村人のような考えでいる限り、料理は発達のしようがないのです。もちろん現在では村人のように考える人はいないと思います。しかしプロテスタントの教えが原型としてあって、それが国民の気質にまで影響を与えるとき、その気質は長期間残るのではと思うのです。
この映画の舞台はデンマークの寒村です。ドイツではありません。しかし歴史的にプロテスタントがメジャーだった地域には、料理についての共通性があるのではないでしょうか。私の経験でも「ドイツ、オランダ、ベルギー北部、イギリス」と「イタリア、フランス、ベルギー南部、スペイン」の間には、どうも明確な境界線があるように思えてならないのです。
ちょっと脇道にそれますが、この「境界線」を皮肉ったジョークがいろいろと思い出されますね。たとえばフランスには次のようなジョークがあるようです。
|
 イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。
イギリス人であるピーター・メイルは、その著書「南仏プロヴァンスの12ヶ月」(河出書房新社 1993。池央耿 訳)でこのジョークについて書いています。まずメイルは「プロヴァンスでは石を投げればグルメにあたる」としたうえで、知り合った床磨き職人のムッシュー・バニョーの話を書きます。ムッシュー・バニョーは正午きっかりに仕事を中断して、地元のレストランへ出かけていき、たっぷり2時間はかけて昼食をとる。彼は料理についてうるさ型のようだ・・・・・・などとした上で、次のように書いています。
|
これをフランス人が書くと「傲慢」に聞こえると思いますが、イギリス人の(かつプロヴァンスに惚れ込んでいる人の)著書だからこういう記述もアリなのでしょう。
こういう文章を読むと「食」に関心が高い人は「ラムを一度しか殺さない」プロヴァンスに是非行ってみたい、と思うのではないでしょうか。この本が出版されたあと、ヨーロッパ中からこの本を手にした観光客がプロヴァンスに押し寄せたようですね。分かります。
(以降、続く)
2010-11-06 16:58
nice!(1)
トラックバック(2)



