No.203 - ローマ人の "究極の娯楽" [歴史]
今まで古代ローマに関する記事をいくつか書きました。リストすると次の通りです。
発端は、No.24-No.27 で塩野七生氏の大作『ローマ人の物語』の感想を書いたことでした。ローマ人の宗教だけに絞った感想です。また、No.112、113、123 はインフラストラクチャ(のうちの建造物)の話で、その建設に活躍した古代ローマのコンクリートの技術のことも書きました。No.162 は奴隷制度の実態です。
今回はこの継続で、古代ローマの円形闘技場で繰り広げられた闘技会のことを書きたいと思います。「宗教 = ローマ固有の多神教・キリスト教」や「巨大建造物・コンクリート技術」は、古代ローマそのままではないにしろ現代にも相当物があり、私たちが想像しやすいものです。奴隷制度は現代では(原則的に)ありませんが、奴隷的労働はあるので、それも想像しやすい。
しかし大観衆が見守る円形闘技場での "剣闘士の殺し合い" は現代人の想像を越えていて、そこが非常に興味を引くところです。ボクシングの試合で相手を倒すのとは訳が違う。その想像を越えたところに古代ローマの(一つの)特徴があると思うし、歴史から学ぶポイントもあるかもしれないと思うのです。
今までのブログで円形闘技場での闘技会について触れたことがありました。No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたユリウス・カエサルの話です。カエサルは財務官に当選したとき(BC.65 カエサル35歳)、ローマで一番の資産家であったクラッススから2500万セステルティウスを借金し、当選祝いに320組の剣闘士を借り切った闘技会を開催しました。のべ25万人のローマ市民を集めたこの闘技会で、カエサルは借金を全部使い切りました。2500万セステルティウスという金額は、現在の貨幣価値にして約30億円程度です。この記述は、本村凌二『はじめて読む人のローマ史 1200年』祥伝社(2014)によったのですが、塩野七生氏も『ローマ人の物語』でこの闘技会のことを書いていました。
これは、当時のローマの貴族階級の財力がものすごかったという例として引用したのですが、では、その剣闘士の闘技会とはどいうものだったか、それが以降です。
差し下ろされた親指
古代ローマの剣闘士(=グラディエーター)を描いた絵画として、ジャン = レオン・ジェロームの傑作『差し下ろされた親指』(1872)があります。まず例によって中野京子さんの解説で、この絵を見ていきたいと思います。引用にあたっては漢数字を算用数字に置き換えました。一部段落を増やしたところがあります。
画家は歴史考証を踏まえて描いています。画面に描かれた数本の白っぽい筋は何かと思ってしまいますが、これはコロセウムの上を覆う天幕の間から漏れてくる光線なのですね。実際にこのように見えるかどうかはともかく、歴史を踏まえて描いていることを示していて、画家の芸の細かいところです。

中野さんが指摘しているのですが、画家はサムズダウンをしている右手の観客たちの表情を意図的に醜く描いています。そして上段の男性観客ですが、中には沈痛な表情の老人も混じっている(上の部分図の左上の男など)。敗者を応援していたのでしょうか。それに呼応するかように左手のアリーナ観客は、ヒートアップしている右手の観客とは様子が違うのです。
まさに劇的瞬間というのでしょうか。「殺せ、殺せ」と叫ぶ右側のアリーナの観客、それには同調していない左のアリーナの観客、そして描かれていない皇帝の親指・・・・・・。補足しますと、中野さんが「決定は皇帝が下す」と書いているのは、詳しく言うと、
ということであり、それが正しい理解の仕方です。カエサルが主催者の闘技会だと、敗者の生死を決めるのは費用を負担したカエサルです。
中野さんによると、画家・ジェロームはこの絵で敗者を美形に描いているといいます。思想家・セネカの「もっとも価値のある剣闘士は美形の者だ」という言葉が思い出されると・・・・・・。しかし画家が敗者を美形に描いたのには、さらに理由があります。それはこの敗者が「投網闘士」だからです。


魚兜闘士の肘防具にも注目したいと思います。カエサルは財務官就任記念に開催した「大闘技会」で、640人の剣闘士全員に銀製の腕鎧(肘防具)を新調して着用させたと『ローマ人の物語』で塩野七生氏が書いていました(最初の引用)。この絵を見るとその意味がよく分かります。陽光に煌めく銀の効果です。
もう一つこの絵で気づかされるのは、魚兜闘士と投網闘士が戦っていることです。つまり魚と漁師が戦っている。これは興業的なおもしろさを狙ったと考えられますが、単に「魚と漁師」のおもしろさだけではないでしょう。武器が違います。武器にはそれぞれ長所・短所があります。つまりこの絵の試合は、現代でいうと異種格闘技の試合のようなものだと思います。空手とプロレスのどっちが強いか、みたいな・・・・・・。あるいは時代劇に出てくる日本刀(ヒーロー)と鎖鎌(悪役)の戦いです。異種の武器での戦いは観衆の興味を大いに引いたと考えられます。
我々は剣闘士の試合というと、奴隷同士が戦ったというイメージが強いのですが(スタンリー・キューブリック監督の「スパルタカス」という映画がありました)、ローマも帝政の時代になると変質していったようです。
このジェロームの絵は、映画『グラディエーター』の制作に一役買ったようです。20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は・・・・・・。
2000年前に5万人を収容できるアリーナを建設できる圧倒的な技術力と高度な文明、そのアリーナで繰り広げられる "人間同士の殺し合いショー" と、瀕死の敗者を殺せと連呼する観衆・・・・・・。リドリー・スコット監督は「栄光と邪悪」と言っていますが、この絵が表しているものはまさにそうだし、現代人が古代ローマの歴史に惹かれる理由もそこなのでしょう。
ちなみに cinemareview.com の記事によると『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサは、スコット監督に脚本を見せる以前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそもプロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だと言います。この絵にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるのでしょう。
皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち
画家のジェロームは『差し下ろされた親指』(1872)より以前にも剣闘士をテーマとした作品を描いています。『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』という作品です。
この絵を所有しているイェール大学アート・ギャラリーの公式サイトにもあるのですが、ジェロームは歴史考証を踏まえてこの絵を描いています。その考証の一つですが、この絵にはコロセウムを覆う天幕が描かれていて、その構造がよくわかります。中心部を円形にあけ、その周りにアリーナの最高部まで部分的に布が張られる。布の下の観客席は日陰になり、闘技舞台には日光が差し込むというわけです。『差し下ろされた親指』もそういう絵になっていました。ユリウス・カエサルの闘技会のように剣闘士が銀製の腕鎧をつけたとしたら、陽光が銀に反射して日陰の観客席に煌めき、その効果は抜群だったと想像できます。
この絵の原題は「Ave Caesar, Morituri te Slutant」というラテン語で、「皇帝万歳! 我ら死にゆく者が敬意を捧げます」というような意味です。スエトニウスの「ローマ皇帝伝」にある語句です(第5巻 クラウディウス帝)。その「皇帝万歳」と叫ぶ剣闘士たちは、描かれた盾と三叉鉾の数から4人の魚兜闘士と4人の投網闘士でしょう。皇帝に敬意を表してから試合に臨むようです。

画面の左手前には、試合が終わった投網闘士と網をかぶせられた魚兜闘士の2人が倒れています。相討ちになったのでしょうか。そのうしろ方のハイライトの部分では、奴隷が剣闘士の死体を引きずってアリーナから出そうとしています。

『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』は、13年後に描かれた『差し下ろされた親指』と似ています。ともに剣闘士と皇帝を低い位置からとらえた構図であり、あえて試合中の剣闘士を描かず、魚兜闘士と投網闘士の武器や防具、そしてアリーナの構造が歴史考証をもとに描かれています。しかし明らかに試合の決着がついた直後、生か死かという瞬間を描いた『差し下ろされた親指』の方が劇的です。殺せと叫ぶ観衆を間近に描いたのもインパクトがある。アリーナの巨大さを実感できる空や天幕を描くのをあきらめざるを得なかったが、その代わりに天幕から漏れてくる光の筋を描き込んだ。2つの絵を比べると『差し下ろされた親指』を制作した画家の意欲が分かるのでした。
補足ですが、古代ローマの剣闘士については Wikipedia日本版に詳しい情報があります。また画家のジェロームについては、以前の記事で次の3つの作品をとりあげました。
野獣狩り
最初に引用した塩野七生氏の「ローマ人の物語」の他に、このブログで古代ローマの闘技会について引用したことがあります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの「捕食者なき世界」にあった、"人間が大型捕食動物を根絶してきた歴史" です(No.127「捕食者なき世界 2」)。人間が大型動物を狩る第一の理由は食料を確保するためでしたが、歴史を振り返ると理由はそれだけではありません。
ソウルゼンバーグが書いているのは、円形闘技場で行われた「野獣狩り」のことです。それは「最高に楽しい娯楽」でした。このあたりの歴史を別の本から引用してみたいと思います。
アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(関口英子訳。河出書房新社 2010)は最新の歴史研究を踏まえて、紀元115年のトラヤヌス帝の時代のローマの一日を民衆の視点からの「実況中継風の記述」とその「解説」で綴った本です。以前の No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」では "ウェスタの巫女" に出会う部分を引用したのですが、この本には円形闘技場の描写も出てきます。以下にその記述を引用します。
円形闘技場での剣闘士の闘技会の前には、実は "前座" があったわけです。前座の最初は「野獣狩り」です。
野獣狩りは闘獣士が野獣を "狩る" というショーですが、中には闘獣士と野獣の "互角の闘い" もあった。その互角の闘いをする猛獣の例として、当時有名だったウィクトルという名前のヒョウの話が出てきます。
単に闘獣士が動物を殺すだけの "野獣狩り" よりも、闘獣士と猛獣のどちらが勝つかわからない「互角」の闘いの方がショーとしての価値があるわけです。「古代ローマ人の24時間」にはスピッタラという名前の闘獣士とヒョウのウィクトルが闘う場面がでてくるのですが、闘獣士は鎧も兜も剣も無しに脛当てだけをつけ、1本の槍でヒョウと闘います。これもショーをおもしろくする工夫でしょう。完全武装ではつまらない。
ローマ帝国の特別のイベントでは、多数の剣闘士が殺されると同時に、夥しい数の野獣も殺されたようです。
ソウルゼンバーグは「1日にクマ100頭、ヒョウ400頭、ライオン500頭が虐殺されることもあった」と書いていましたが(=1日に1000頭を殺害)、いかにありそうです。
公開処刑
前座の第2弾は犯罪人の公開処刑です。『古代ローマ人の24時間』には、後ろ手に縛られた罪人を2人の死刑執行人がコロッセウムの闘技場に連れ出す場面が描写されています。コロッセウムでは数万人の観衆がざわめいています。罪人が受けた判決は「猛獣による食い殺しの刑」です。
コロッセウムにおける公開処刑は、上に引用したような "単純な" もの以外に、見せ物・ショーとしての "演出" がされることもありました。
こういう記述を読むと、古代ローマの文明のレベルの高さが直感できます。まず観衆はギリシャ神話を知っているわけです。知っているからこそ演出としての価値が出てくる。さらに引用にあるコロッセウムの有名な「せり上がり舞台」の仕組みも、それが2000年前だと考えるとすごいものだと思います。
この記述から、よく言われるローマ帝国における「キリスト教徒迫害」を思い出しました。キリスト教徒は捕らえられ、闘技場に引き出され、猛獣の餌食になったと・・・・・・。決まって引き合いに出される悪役は皇帝ネロです。しかし注意すべきは、古代ローマにおける猛獣刑は "死刑と決まった罪人" を処刑する方法の一つだったことです。キリスト教徒だけが猛獣刑にあったわけではありません。ちなみに弾圧された宗教もキリスト教だけでもありません。紀元前186年のディオニュソス教徒の弾圧では7000人が処刑されたと、古代ローマの歴史家が書いています(No.24「ローマ人の物語(1)寛容と非寛容」)。
歴史をひもとくと、公開処刑は古代ローマだけでなく日本を含む世界各国で行われてきました。現代でも東アジアの某国や中東のある種の国では行われています。むしろ「見せしめ」や「戒め」のために、罪人の処刑は公開が原則だったと言えるでしょう。
しかし古代ローマの公開処刑の特徴は、それが見せ物、ショー、エンターテインメントとして実施されたことです。しかも最大数万人の観衆の注視の中でのショーであり、演出上の工夫があり、猛獣刑の場合は食いちぎられた人体のパーツがアレーナに散乱する陰惨な光景で終わる見せ物です。こういった例は世界史でも希有でしょう。
剣闘士の戦い
「野獣狩り」と「公開処刑」という前座が終わると、いよいよ待ちに待った剣闘士の闘いが始まります。
ジェロームが『差し下ろされた親指』で描いたのは、魚兜闘士と投網闘士の戦いでした。『古代ローマ人の24時間』では「魚剣闘士」(=ムルミッロ)と「投網剣闘士」(=レティアリウス)と訳されています。そして魚剣闘士と投網剣闘士の戦いの様子が、剣闘士の視点で描写されています。魚剣闘士の名前はアステュアナクス、投網剣闘士の名前はカレンディオです。魚剣闘士の装備は兜、盾、腕当て、両刃の短剣(グラディウス)であり、投網剣闘士は投網と三叉鉾、肩防具、短剣(とどめを刺すために使用)で、兜は無しです。
戦いが始まるとすぐ、投網剣闘士は魚剣闘士の周りをぐるぐる走り回ります。
投網剣闘士のカレンディオは、すぐには攻撃しません。相手が網から逃れようともがくうちに、ますます網に絡まるか、あるいはつまづく。それを待っているのです。
「教官」と出てきますが、これは剣闘士養成所の教官という意味です。剣闘士は養成所での厳しい訓練を経てきているのです。二人は投網剣闘士が有利のうちに一進一退を繰り返すのですが、途中で状況が変わります。
もちろん以上の記述は著者の想像です。ただし最後に書いてあるように、著者はこの戦いの経過を描いた当時のモザイク画をもとに文章を書いています。細部の描写はともかく、古代ローマの剣闘士の試合がどんなものだったかが理解できます。最後の方の「そよ風が彼(=投網剣闘士)の髪を撫でる」というところは、投網剣闘士だけは兜を被らなかったという歴史的事実を反映しています。
最初のジェロームの絵『差し下ろされた親指』に戻ります。ここにはまさに魚剣闘士と投網剣闘士との戦いが終わったばかりの場面が描かれています。そして右の観客席の観衆は「殺せ」とコールしている。
ここで想像すると、全員とまでは言わないまでも「殺せ」と叫んでいる観衆は、午前中の「猛獣狩り」で動物が死ぬ場面を見物し、その次には公開処刑を見学し、そして剣闘士の試合と流れる血に興奮して「殺せ」と叫んでいるわけです。「死」と「血」が充満した円形闘技場に長時間いた人間が「殺せ、殺せ」と連呼するのは、当然そうなるだろうという気がします。
究極の娯楽
今まで書いた「死を見せ物にする」古代ローマの歴史を、我々はどう受けとめればいいのでしょうか。"歴史から学ぶ" とすると、何か学ぶものはあるのでしょうか。このことについて2つのことを考えました。
確実に言えるのは、この見せ物=娯楽は「これほど刺激の強いものはない、究極の娯楽」だということです。長いローマの歴史の中でより強い刺激を求めてエスカレートした結果なのでしょうが、もうこれ以上エスカレートのしようがないわけです。ものごとは究極に達すると後は下降しかありません。「パンとサーカス」と言われるように、闘技会(=サーカス)は、民衆が皇帝に要求する権利だったわけですが、そのローマ市民が要求するものを皇帝がいずれ与えられなくなることは目に見えています。人間は誰しも死にたくはないので、死を前提にした見せ物はエスカレートすればするほど、どこかで無理がきます。
ローマの高度なインフラを思い出します。No.112-3「ローマ人のコンクリート」、No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたように、2000年前の高度文明で作られた水道網、道路、橋、テルマエ(公衆浴場)などは、メインテナンス・コストとエネルギー資源の問題で "持続可能" ではなくなり、次第に劣化・縮小していったわけですね。究極に達すると下降しかない。これが第一に思ったことです。
2つ目に思ったのは「人や動物が殺される様子を娯楽として楽しむ」のは "人間性" とどういう関係があるかです。それは古代ローマ人だけの特殊なものだとも考えられます。しかし動物を殺して楽しむというのは、現代のスペインやポルトガル(および文化を受け継いだ中南米の国)の闘牛がそうだし、大型動物を狩るレジャー・ハンティングがそうです。現代のテロリストの中には殺人を楽しんでいるとしか思えないものもいる。人間にはそういった性向がないとは言えないでしょう。では「ローマ人の究極の娯楽」はどう考えればよいのか。
最も妥当な解釈は「人間は本能が崩れた動物だ」ということだと思いました。これは岸田秀氏(和光大学名誉教授)の言い方ですが、人間の行動は本能によるのではないということです。つまり、生存のために必須の行動を除き、人間の行動は生得のものではない。人間の行動は "文化"(広い意味での文化)によって決まります。文化が人間の行動規範になり、文化が人間を行動に駆り立てる。岸田流に言うと「文化は本能の代替物」ということになります。
その "文化" は人間が作りあげてきたものなので、生物学的条件からくる根拠がありません。従って極めて多様であり、社会によって千変万化します。二人が戦う格闘技を観客が見て楽しむという競技は世界中にありますが、「剣闘士=殺し合い」から「相撲=倒れたら負け」までのバリエーションがある。
全くの想像ですがローマの闘技会も、もとはと言えば戦争捕虜同士を戦わせて楽しむ程度のものではなかったのでしょうか。それが剣を使うようになり、次には殺してもよいことになり、さらには敗者が殺されるようになり、猛獣とも戦うようになりと、そういう風に文化が "発展" してきた。生物学的な歯止めがない人間はどこまでもエスカレートしていく(ことがある)。その文化の中で生まれてからずっと生活していると、別に何とも思わない。世界中のほとんとの地域はそういう "発展" はしなかったが、古代ローマは(たまたま)そういう経緯をたどったのではないでしょうか。
古代ローマ史の闘技会で思うのは、人間社会は「何でもアリ」だということです。だからこそ「何でもアリではない社会」を構成するための "文化的装置" を作る努力が必要なのでしょう。「人間は生まれながらにして基本的人権をもつ」という近代国家ではあたりまえのコンセプトも、実は、生まれながらに持っているものや行動規範が無いからこそ「人権」というものを仮想し、それをベースに社会の体系を作ろうとする(作ってきた)人間社会の努力だと考えられます。そして、その努力は大切なものだということを思いました。
| No. 24 | ローマ人の物語(1)寛容と非寛容 | |||
| No. 25 | ローマ人の物語(2)宗教の破壊 | |||
| No. 26 | ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ | |||
| No. 27 | ローマ人の物語(4)帝国の末路 | |||
| No.112 | ローマ人のコンクリート(1)技術 | |||
| No.113 | ローマ人のコンクリート(2)光と影 | |||
| No.123 | ローマ帝国の盛衰とインフラ | |||
| No.162 | 奴隷のしつけ方 |
発端は、No.24-No.27 で塩野七生氏の大作『ローマ人の物語』の感想を書いたことでした。ローマ人の宗教だけに絞った感想です。また、No.112、113、123 はインフラストラクチャ(のうちの建造物)の話で、その建設に活躍した古代ローマのコンクリートの技術のことも書きました。No.162 は奴隷制度の実態です。
今回はこの継続で、古代ローマの円形闘技場で繰り広げられた闘技会のことを書きたいと思います。「宗教 = ローマ固有の多神教・キリスト教」や「巨大建造物・コンクリート技術」は、古代ローマそのままではないにしろ現代にも相当物があり、私たちが想像しやすいものです。奴隷制度は現代では(原則的に)ありませんが、奴隷的労働はあるので、それも想像しやすい。
しかし大観衆が見守る円形闘技場での "剣闘士の殺し合い" は現代人の想像を越えていて、そこが非常に興味を引くところです。ボクシングの試合で相手を倒すのとは訳が違う。その想像を越えたところに古代ローマの(一つの)特徴があると思うし、歴史から学ぶポイントもあるかもしれないと思うのです。
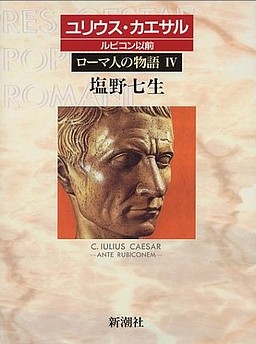
| |||
|
| |||
|
これは、当時のローマの貴族階級の財力がものすごかったという例として引用したのですが、では、その剣闘士の闘技会とはどいうものだったか、それが以降です。
差し下ろされた親指
古代ローマの剣闘士(=グラディエーター)を描いた絵画として、ジャン = レオン・ジェロームの傑作『差し下ろされた親指』(1872)があります。まず例によって中野京子さんの解説で、この絵を見ていきたいと思います。引用にあたっては漢数字を算用数字に置き換えました。一部段落を増やしたところがあります。
.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム(1824-1904)
「差し下ろされた親指」(1872)
(フェニックス美術館。米:アリゾナ州)
| ||
|
画家は歴史考証を踏まえて描いています。画面に描かれた数本の白っぽい筋は何かと思ってしまいますが、これはコロセウムの上を覆う天幕の間から漏れてくる光線なのですね。実際にこのように見えるかどうかはともかく、歴史を踏まえて描いていることを示していて、画家の芸の細かいところです。
|

中野さんが指摘しているのですが、画家はサムズダウンをしている右手の観客たちの表情を意図的に醜く描いています。そして上段の男性観客ですが、中には沈痛な表情の老人も混じっている(上の部分図の左上の男など)。敗者を応援していたのでしょうか。それに呼応するかように左手のアリーナ観客は、ヒートアップしている右手の観客とは様子が違うのです。
|
 | |||
|
| |||
| 決定は闘技会の "主催者"(=エーディトル)が下す。この絵の場合、主催者は皇帝 |
ということであり、それが正しい理解の仕方です。カエサルが主催者の闘技会だと、敗者の生死を決めるのは費用を負担したカエサルです。
|
中野さんによると、画家・ジェロームはこの絵で敗者を美形に描いているといいます。思想家・セネカの「もっとも価値のある剣闘士は美形の者だ」という言葉が思い出されると・・・・・・。しかし画家が敗者を美形に描いたのには、さらに理由があります。それはこの敗者が「投網闘士」だからです。
|


魚兜闘士の肘防具にも注目したいと思います。カエサルは財務官就任記念に開催した「大闘技会」で、640人の剣闘士全員に銀製の腕鎧(肘防具)を新調して着用させたと『ローマ人の物語』で塩野七生氏が書いていました(最初の引用)。この絵を見るとその意味がよく分かります。陽光に煌めく銀の効果です。
もう一つこの絵で気づかされるのは、魚兜闘士と投網闘士が戦っていることです。つまり魚と漁師が戦っている。これは興業的なおもしろさを狙ったと考えられますが、単に「魚と漁師」のおもしろさだけではないでしょう。武器が違います。武器にはそれぞれ長所・短所があります。つまりこの絵の試合は、現代でいうと異種格闘技の試合のようなものだと思います。空手とプロレスのどっちが強いか、みたいな・・・・・・。あるいは時代劇に出てくる日本刀(ヒーロー)と鎖鎌(悪役)の戦いです。異種の武器での戦いは観衆の興味を大いに引いたと考えられます。
我々は剣闘士の試合というと、奴隷同士が戦ったというイメージが強いのですが(スタンリー・キューブリック監督の「スパルタカス」という映画がありました)、ローマも帝政の時代になると変質していったようです。
|
このジェロームの絵は、映画『グラディエーター』の制作に一役買ったようです。20世紀末、ハリウッド映画で "古代ローマもの" を復活させようと熱意をもった映画人が集まり、おおまかな脚本を書き上げました。紀元180年代末の皇帝コンモドスを悪役に、架空の将軍をヒーローにした物語です。将軍は嫉妬深いコンモドス帝の罠にはまり、奴隷の身分に落とされ、剣闘士(グラディエーター)にされてしまう。そして彼は剣闘士として人気を博し、ついにはローマのコロセウムで、しかもコンモドス帝の面前で命を賭けた戦いをすることになる。果たして結末は・・・・・・。
|

| |||
|
| |||
ちなみに cinemareview.com の記事によると『グラディエーター』の制作会社であるドリームワークスのプロデューサは、スコット監督に脚本を見せる以前に監督のオフィスを訪問して『差し下された親指』の複製を見せたそうです。そもそもプロデューサが『グラディエーター』の着想を得たのもこの絵がきっかけ(の一つ)だと言います。この絵にはハリウッドの映画人をホットにさせる魔力があるのでしょう。
皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち
画家のジェロームは『差し下ろされた親指』(1872)より以前にも剣闘士をテーマとした作品を描いています。『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』という作品です。
-d078c.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム(1824-1904)
「皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち」(1859)
(イェール大学アート・ギャラリー。米:コネチカット州)
| ||
この絵を所有しているイェール大学アート・ギャラリーの公式サイトにもあるのですが、ジェロームは歴史考証を踏まえてこの絵を描いています。その考証の一つですが、この絵にはコロセウムを覆う天幕が描かれていて、その構造がよくわかります。中心部を円形にあけ、その周りにアリーナの最高部まで部分的に布が張られる。布の下の観客席は日陰になり、闘技舞台には日光が差し込むというわけです。『差し下ろされた親指』もそういう絵になっていました。ユリウス・カエサルの闘技会のように剣闘士が銀製の腕鎧をつけたとしたら、陽光が銀に反射して日陰の観客席に煌めき、その効果は抜群だったと想像できます。
この絵の原題は「Ave Caesar, Morituri te Slutant」というラテン語で、「皇帝万歳! 我ら死にゆく者が敬意を捧げます」というような意味です。スエトニウスの「ローマ皇帝伝」にある語句です(第5巻 クラウディウス帝)。その「皇帝万歳」と叫ぶ剣闘士たちは、描かれた盾と三叉鉾の数から4人の魚兜闘士と4人の投網闘士でしょう。皇帝に敬意を表してから試合に臨むようです。

画面の左手前には、試合が終わった投網闘士と網をかぶせられた魚兜闘士の2人が倒れています。相討ちになったのでしょうか。そのうしろ方のハイライトの部分では、奴隷が剣闘士の死体を引きずってアリーナから出そうとしています。

『皇帝に敬意を捧げる剣闘士たち』は、13年後に描かれた『差し下ろされた親指』と似ています。ともに剣闘士と皇帝を低い位置からとらえた構図であり、あえて試合中の剣闘士を描かず、魚兜闘士と投網闘士の武器や防具、そしてアリーナの構造が歴史考証をもとに描かれています。しかし明らかに試合の決着がついた直後、生か死かという瞬間を描いた『差し下ろされた親指』の方が劇的です。殺せと叫ぶ観衆を間近に描いたのもインパクトがある。アリーナの巨大さを実感できる空や天幕を描くのをあきらめざるを得なかったが、その代わりに天幕から漏れてくる光の筋を描き込んだ。2つの絵を比べると『差し下ろされた親指』を制作した画家の意欲が分かるのでした。
補足ですが、古代ローマの剣闘士については Wikipedia日本版に詳しい情報があります。また画家のジェロームについては、以前の記事で次の3つの作品をとりあげました。
| 『奴隷市場』 | No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」 | |||
| 『虎と子虎』 | No.94「貴婦人・虎・うさぎ」 | |||
| 『仮面舞踏会後の決闘』 | No.114「道化とピエロ」 |
野獣狩り
最初に引用した塩野七生氏の「ローマ人の物語」の他に、このブログで古代ローマの闘技会について引用したことがあります。ウィリアム・ソウルゼンバーグの「捕食者なき世界」にあった、"人間が大型捕食動物を根絶してきた歴史" です(No.127「捕食者なき世界 2」)。人間が大型動物を狩る第一の理由は食料を確保するためでしたが、歴史を振り返ると理由はそれだけではありません。
|
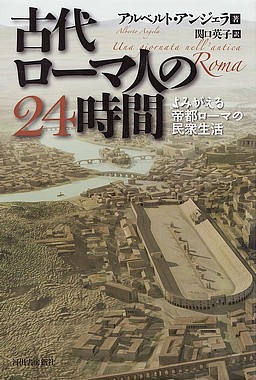
| |||
|
| |||
アルベルト・アンジェラ著『古代ローマ人の24時間』(関口英子訳。河出書房新社 2010)は最新の歴史研究を踏まえて、紀元115年のトラヤヌス帝の時代のローマの一日を民衆の視点からの「実況中継風の記述」とその「解説」で綴った本です。以前の No.26「ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ」では "ウェスタの巫女" に出会う部分を引用したのですが、この本には円形闘技場の描写も出てきます。以下にその記述を引用します。
|
円形闘技場での剣闘士の闘技会の前には、実は "前座" があったわけです。前座の最初は「野獣狩り」です。
|
野獣狩りは闘獣士が野獣を "狩る" というショーですが、中には闘獣士と野獣の "互角の闘い" もあった。その互角の闘いをする猛獣の例として、当時有名だったウィクトルという名前のヒョウの話が出てきます。
|
単に闘獣士が動物を殺すだけの "野獣狩り" よりも、闘獣士と猛獣のどちらが勝つかわからない「互角」の闘いの方がショーとしての価値があるわけです。「古代ローマ人の24時間」にはスピッタラという名前の闘獣士とヒョウのウィクトルが闘う場面がでてくるのですが、闘獣士は鎧も兜も剣も無しに脛当てだけをつけ、1本の槍でヒョウと闘います。これもショーをおもしろくする工夫でしょう。完全武装ではつまらない。
|
ローマ帝国の特別のイベントでは、多数の剣闘士が殺されると同時に、夥しい数の野獣も殺されたようです。
|
ソウルゼンバーグは「1日にクマ100頭、ヒョウ400頭、ライオン500頭が虐殺されることもあった」と書いていましたが(=1日に1000頭を殺害)、いかにありそうです。

| ||
|
闘獣士のモザイク画
(ローマ:ボルゲーゼ美術館) | ||
 
|
イタリアのシチリア島の都市、ピアッツァ・アルメリーナの郊外に、4世紀初頭のローマ帝国時代に作られた大規模な別荘の跡が残っている(カサーレの別荘)。その規模の大きさから、建てたのはローマ皇帝(マクシミアヌス帝)との説がある。 このカサーレの別荘は、建物や庭の床のほとんどにモザイク画が施されていることで有名である。そのモザイク画を見ると当時のローマ人の様子が分かるが、その中に海外から野獣を船で運ぶ様子を描いたものがある。 上図は象を船に乗せているところで、その上方にはラクダとおぼしき動物が見える。下図はだいぶ欠けているが、虎を船から降ろしているところで、この虎はインドのベンガル地方のものだと言う。野獣を「輸入」して「野獣狩り」を行ったというローマの歴史がリアルに分かる。 |
公開処刑
前座の第2弾は犯罪人の公開処刑です。『古代ローマ人の24時間』には、後ろ手に縛られた罪人を2人の死刑執行人がコロッセウムの闘技場に連れ出す場面が描写されています。コロッセウムでは数万人の観衆がざわめいています。罪人が受けた判決は「猛獣による食い殺しの刑」です。
|
コロッセウムにおける公開処刑は、上に引用したような "単純な" もの以外に、見せ物・ショーとしての "演出" がされることもありました。
|
こういう記述を読むと、古代ローマの文明のレベルの高さが直感できます。まず観衆はギリシャ神話を知っているわけです。知っているからこそ演出としての価値が出てくる。さらに引用にあるコロッセウムの有名な「せり上がり舞台」の仕組みも、それが2000年前だと考えるとすごいものだと思います。
| 蛇足ですが、現代の "アリーナ" は「舞台」の部分とそのまわりを取り囲む観客席の部分の両方を言いますが、語源となった "アレーナ" は「舞台」だけを指すようです。 |
この記述から、よく言われるローマ帝国における「キリスト教徒迫害」を思い出しました。キリスト教徒は捕らえられ、闘技場に引き出され、猛獣の餌食になったと・・・・・・。決まって引き合いに出される悪役は皇帝ネロです。しかし注意すべきは、古代ローマにおける猛獣刑は "死刑と決まった罪人" を処刑する方法の一つだったことです。キリスト教徒だけが猛獣刑にあったわけではありません。ちなみに弾圧された宗教もキリスト教だけでもありません。紀元前186年のディオニュソス教徒の弾圧では7000人が処刑されたと、古代ローマの歴史家が書いています(No.24「ローマ人の物語(1)寛容と非寛容」)。
歴史をひもとくと、公開処刑は古代ローマだけでなく日本を含む世界各国で行われてきました。現代でも東アジアの某国や中東のある種の国では行われています。むしろ「見せしめ」や「戒め」のために、罪人の処刑は公開が原則だったと言えるでしょう。
しかし古代ローマの公開処刑の特徴は、それが見せ物、ショー、エンターテインメントとして実施されたことです。しかも最大数万人の観衆の注視の中でのショーであり、演出上の工夫があり、猛獣刑の場合は食いちぎられた人体のパーツがアレーナに散乱する陰惨な光景で終わる見せ物です。こういった例は世界史でも希有でしょう。
剣闘士の戦い
「野獣狩り」と「公開処刑」という前座が終わると、いよいよ待ちに待った剣闘士の闘いが始まります。
ジェロームが『差し下ろされた親指』で描いたのは、魚兜闘士と投網闘士の戦いでした。『古代ローマ人の24時間』では「魚剣闘士」(=ムルミッロ)と「投網剣闘士」(=レティアリウス)と訳されています。そして魚剣闘士と投網剣闘士の戦いの様子が、剣闘士の視点で描写されています。魚剣闘士の名前はアステュアナクス、投網剣闘士の名前はカレンディオです。魚剣闘士の装備は兜、盾、腕当て、両刃の短剣(グラディウス)であり、投網剣闘士は投網と三叉鉾、肩防具、短剣(とどめを刺すために使用)で、兜は無しです。
戦いが始まるとすぐ、投網剣闘士は魚剣闘士の周りをぐるぐる走り回ります。
|
投網剣闘士のカレンディオは、すぐには攻撃しません。相手が網から逃れようともがくうちに、ますます網に絡まるか、あるいはつまづく。それを待っているのです。
|
「教官」と出てきますが、これは剣闘士養成所の教官という意味です。剣闘士は養成所での厳しい訓練を経てきているのです。二人は投網剣闘士が有利のうちに一進一退を繰り返すのですが、途中で状況が変わります。
|
|
もちろん以上の記述は著者の想像です。ただし最後に書いてあるように、著者はこの戦いの経過を描いた当時のモザイク画をもとに文章を書いています。細部の描写はともかく、古代ローマの剣闘士の試合がどんなものだったかが理解できます。最後の方の「そよ風が彼(=投網剣闘士)の髪を撫でる」というところは、投網剣闘士だけは兜を被らなかったという歴史的事実を反映しています。

| ||
|
追撃剣闘士(セクトル)のアステュアナクスと投網剣闘士(レティアリイ)のカレンディオの戦いを描いたローマ時代のモザイク画。時間の経過は下から上である。上の絵でカレンディオは傷つき、短剣を差し出している。カレンディオの名前の後にある丸と棒の記号は "NULL" を示していて、主催者(エーディトル)の決定は「死」であったことを示す。投網剣闘士は追撃剣闘士と組まされることが多かった。追撃剣闘士の装備は魚剣闘士と似ているが、兜に突起物はなく、投網剣闘士の網から逃れやすかったという。「古代ローマ人の24時間」の記述はこのモザイク画をもとにしているはずである。
(スペイン国立考古学博物館:マドリード)
| ||
最初のジェロームの絵『差し下ろされた親指』に戻ります。ここにはまさに魚剣闘士と投網剣闘士との戦いが終わったばかりの場面が描かれています。そして右の観客席の観衆は「殺せ」とコールしている。
ここで想像すると、全員とまでは言わないまでも「殺せ」と叫んでいる観衆は、午前中の「猛獣狩り」で動物が死ぬ場面を見物し、その次には公開処刑を見学し、そして剣闘士の試合と流れる血に興奮して「殺せ」と叫んでいるわけです。「死」と「血」が充満した円形闘技場に長時間いた人間が「殺せ、殺せ」と連呼するのは、当然そうなるだろうという気がします。
.jpg)
| ||
|
ジャン=レオン・ジェローム「差し下ろされた親指」
| ||
究極の娯楽
今まで書いた「死を見せ物にする」古代ローマの歴史を、我々はどう受けとめればいいのでしょうか。"歴史から学ぶ" とすると、何か学ぶものはあるのでしょうか。このことについて2つのことを考えました。
確実に言えるのは、この見せ物=娯楽は「これほど刺激の強いものはない、究極の娯楽」だということです。長いローマの歴史の中でより強い刺激を求めてエスカレートした結果なのでしょうが、もうこれ以上エスカレートのしようがないわけです。ものごとは究極に達すると後は下降しかありません。「パンとサーカス」と言われるように、闘技会(=サーカス)は、民衆が皇帝に要求する権利だったわけですが、そのローマ市民が要求するものを皇帝がいずれ与えられなくなることは目に見えています。人間は誰しも死にたくはないので、死を前提にした見せ物はエスカレートすればするほど、どこかで無理がきます。
ローマの高度なインフラを思い出します。No.112-3「ローマ人のコンクリート」、No.123「ローマ帝国の盛衰とインフラ」で書いたように、2000年前の高度文明で作られた水道網、道路、橋、テルマエ(公衆浴場)などは、メインテナンス・コストとエネルギー資源の問題で "持続可能" ではなくなり、次第に劣化・縮小していったわけですね。究極に達すると下降しかない。これが第一に思ったことです。
2つ目に思ったのは「人や動物が殺される様子を娯楽として楽しむ」のは "人間性" とどういう関係があるかです。それは古代ローマ人だけの特殊なものだとも考えられます。しかし動物を殺して楽しむというのは、現代のスペインやポルトガル(および文化を受け継いだ中南米の国)の闘牛がそうだし、大型動物を狩るレジャー・ハンティングがそうです。現代のテロリストの中には殺人を楽しんでいるとしか思えないものもいる。人間にはそういった性向がないとは言えないでしょう。では「ローマ人の究極の娯楽」はどう考えればよいのか。
最も妥当な解釈は「人間は本能が崩れた動物だ」ということだと思いました。これは岸田秀氏(和光大学名誉教授)の言い方ですが、人間の行動は本能によるのではないということです。つまり、生存のために必須の行動を除き、人間の行動は生得のものではない。人間の行動は "文化"(広い意味での文化)によって決まります。文化が人間の行動規範になり、文化が人間を行動に駆り立てる。岸田流に言うと「文化は本能の代替物」ということになります。
その "文化" は人間が作りあげてきたものなので、生物学的条件からくる根拠がありません。従って極めて多様であり、社会によって千変万化します。二人が戦う格闘技を観客が見て楽しむという競技は世界中にありますが、「剣闘士=殺し合い」から「相撲=倒れたら負け」までのバリエーションがある。
全くの想像ですがローマの闘技会も、もとはと言えば戦争捕虜同士を戦わせて楽しむ程度のものではなかったのでしょうか。それが剣を使うようになり、次には殺してもよいことになり、さらには敗者が殺されるようになり、猛獣とも戦うようになりと、そういう風に文化が "発展" してきた。生物学的な歯止めがない人間はどこまでもエスカレートしていく(ことがある)。その文化の中で生まれてからずっと生活していると、別に何とも思わない。世界中のほとんとの地域はそういう "発展" はしなかったが、古代ローマは(たまたま)そういう経緯をたどったのではないでしょうか。
古代ローマ史の闘技会で思うのは、人間社会は「何でもアリ」だということです。だからこそ「何でもアリではない社会」を構成するための "文化的装置" を作る努力が必要なのでしょう。「人間は生まれながらにして基本的人権をもつ」という近代国家ではあたりまえのコンセプトも、実は、生まれながらに持っているものや行動規範が無いからこそ「人権」というものを仮想し、それをベースに社会の体系を作ろうとする(作ってきた)人間社会の努力だと考えられます。そして、その努力は大切なものだということを思いました。
2017-04-14 18:51
nice!(0)
トラックバック(0)



