No.92 - コーヒーは健康に悪い? [社会]
No.83-84「社会調査のウソ」で、主に谷岡一郎著『「社会調査」のウソ』に従って、社会調査が陥りやすい誤りのパターンを紹介しました。今回はその補足です。
新聞報道
先日、コーヒーと死亡リスクについての記事が朝日新聞に掲載されていました。
この記事をうけて、翌8月27日の朝日新聞「天声人語」は、
という主旨の文章を書いていました。しかし、こういうコーヒーと健康(ないしは病気リスク)の議論って、はたしてまともな議論になっているのでしょうか。
「コーヒー調査」への疑問
No.83-84「社会調査のウソ」で引用した『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000)で、著者の谷岡一郎氏(大阪商業大学・学長)はこう書いています。
このニュースの内容について「数値があやふやで申し訳ないが、主旨は間違っていない」と谷岡氏は書いています。そして谷岡氏はこのニュースを聞いてすぐに疑問を持ったのです。
『「社会調査」のウソ』は2000年に出版された本です。ということは、谷岡氏が疑問を抱いた調査(=2000年の数年前)は1990年代です。朝日新聞の記事が指摘しているコーヒーと膀胱がんとの関係調査(WHO)は1991年です。天声人語が言及している厚生労働省の調査(2007年頃。コーヒーと肝臓がん)も合わせて考えると、少なくともこの20年以上に渡って、コーヒーは健康にいいとか悪いとかの各種「調査」が発表されてきたのですね。
砂糖入りの飲料を飲む人とは
ここで谷岡氏の指摘に従って、飲料と甘味料(砂糖、人工甘味料)の関係を考えてみます。人が飲料を飲むパターンは、
の3つです。このうち、Aの「もともと飲料に入っている甘味料」とは、現在では砂糖ということはなく、カロリーがない人工甘味料です。成分表に「砂糖」と書いてある飲料は見たことがありません。なぜそうなったかと言うと、それこそ砂糖の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼすからです。世界では何十種類という人工甘味料が開発されてきて、中には健康に悪いとの大論争になった(なっている)ものもありますが、なぜそこまでなるのかというと、砂糖の摂取量を減らしたいからです。
Cのケースは砂糖とは関係ないので、飲料経由で砂糖を摂取するとしたらBのケースです。Bのケースの甘味料は砂糖か人工甘味料の2つが考えられますが、圧倒的に砂糖(グラニュー糖)が多いのではと思います。
つまり、世の中に「砂糖が入っている飲料を飲む人」がいるとしたら、それは「コーヒー・紅茶に砂糖を入れて飲む人」ということになります(他にココアなどもあるでしょう)。
さらに私の観察によると(日本では)コーヒー・紅茶をブラックで飲むのは少数派です。ということは「コーヒーを(よく)飲む人」というのは「砂糖入りの飲料を(よく)飲む人」と統計的に重なる部分が多いことになる。そう推論できます。
その結果として、「コーヒーを飲む人」と「コーヒーを飲まない人」を対比させて何かを議論することは、「砂糖入りの飲料を飲む人」と「砂糖入りの飲料を飲まない人」を対比させることになりかねない。
朝日新聞が報道した調査はアメリカでの調査です。「アメリカではコーヒーを飲むほとんどの人がブラックで飲む」のなら、また「アメリカではコーヒーに入れられる甘味料のほとんどが人工甘味料」なら、砂糖の影響はないことになりますが、そうなのでしょうか。
ここでの議論の本質は、砂糖が問題だということではありません。コーヒーに入れる砂糖は健康に影響するかもしれないし、しないかもしれない。谷岡氏の言いたいことは、そういうことも考慮した(=コントロールした)調査をすべきだということです。朝日新聞が報道した調査は、どういうコントロールがされたのでしょうか。知りたいところです。
コーヒーの愛飲と喫煙率
さらに、重要と思える話があります。谷岡氏は『「社会調査」のウソ』とは別のある講演で、
と述べています。もちろん喫煙率は国によって違うので一概には言えないと思いますが、重要な指摘だと思います。もし仮に、コーヒーを飲まない人の喫煙率が20%で、コーヒーを4杯以上飲む人の喫煙率が50%だとしたら、それが死亡率に影響しないはずがないと思います。あくまで仮定の話ですが・・・・・・。コーヒー調査においてはそういう「コントロール」も必要でしょう。
コーヒーは日本でも世界でも極めて一般的な飲み物なので、学者も役人も調査しようという気になるし、またコーヒーと病気リスク・死亡リスクの関係は新聞社としても記事にしやすいのでしょう。読者の関心を引く記事、というわけです。しかしもっと踏み込んで調査しないと(ないしは調査方法のキモのところを報道しないと)「結局のところ何も分からない」記事になりかねないと思います。
新聞報道
先日、コーヒーと死亡リスクについての記事が朝日新聞に掲載されていました。
|
この記事をうけて、翌8月27日の朝日新聞「天声人語」は、
| 6年前には厚生労働省が「コーヒーが肝臓がんのリスクを下げる」と発表した。いったいコーヒーは健康にいいのか、よくないのか |
という主旨の文章を書いていました。しかし、こういうコーヒーと健康(ないしは病気リスク)の議論って、はたしてまともな議論になっているのでしょうか。
「コーヒー調査」への疑問
No.83-84「社会調査のウソ」で引用した『「社会調査」のウソ』(文春新書。2000)で、著者の谷岡一郎氏(大阪商業大学・学長)はこう書いています。
|
このニュースの内容について「数値があやふやで申し訳ないが、主旨は間違っていない」と谷岡氏は書いています。そして谷岡氏はこのニュースを聞いてすぐに疑問を持ったのです。
|
『「社会調査」のウソ』は2000年に出版された本です。ということは、谷岡氏が疑問を抱いた調査(=2000年の数年前)は1990年代です。朝日新聞の記事が指摘しているコーヒーと膀胱がんとの関係調査(WHO)は1991年です。天声人語が言及している厚生労働省の調査(2007年頃。コーヒーと肝臓がん)も合わせて考えると、少なくともこの20年以上に渡って、コーヒーは健康にいいとか悪いとかの各種「調査」が発表されてきたのですね。
砂糖入りの飲料を飲む人とは
ここで谷岡氏の指摘に従って、飲料と甘味料(砂糖、人工甘味料)の関係を考えてみます。人が飲料を飲むパターンは、
| A: | もともと甘味料が入っている飲料を飲む | |
| B: |
甘味料なしの飲料に甘味料を入れて飲む (コーヒー・紅茶など) | |
| C: |
甘味料なしの飲料をそのまま飲む (ミネラル・ウォーター、日本茶など。およびコーヒー・紅茶をブラックで飲む場合) |
の3つです。このうち、Aの「もともと飲料に入っている甘味料」とは、現在では砂糖ということはなく、カロリーがない人工甘味料です。成分表に「砂糖」と書いてある飲料は見たことがありません。なぜそうなったかと言うと、それこそ砂糖の過剰摂取が健康に悪影響を及ぼすからです。世界では何十種類という人工甘味料が開発されてきて、中には健康に悪いとの大論争になった(なっている)ものもありますが、なぜそこまでなるのかというと、砂糖の摂取量を減らしたいからです。
Cのケースは砂糖とは関係ないので、飲料経由で砂糖を摂取するとしたらBのケースです。Bのケースの甘味料は砂糖か人工甘味料の2つが考えられますが、圧倒的に砂糖(グラニュー糖)が多いのではと思います。
つまり、世の中に「砂糖が入っている飲料を飲む人」がいるとしたら、それは「コーヒー・紅茶に砂糖を入れて飲む人」ということになります(他にココアなどもあるでしょう)。
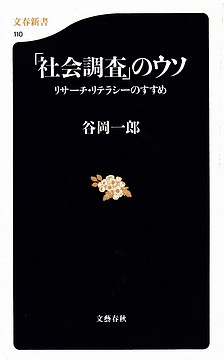
| |||
その結果として、「コーヒーを飲む人」と「コーヒーを飲まない人」を対比させて何かを議論することは、「砂糖入りの飲料を飲む人」と「砂糖入りの飲料を飲まない人」を対比させることになりかねない。
朝日新聞が報道した調査はアメリカでの調査です。「アメリカではコーヒーを飲むほとんどの人がブラックで飲む」のなら、また「アメリカではコーヒーに入れられる甘味料のほとんどが人工甘味料」なら、砂糖の影響はないことになりますが、そうなのでしょうか。
ここでの議論の本質は、砂糖が問題だということではありません。コーヒーに入れる砂糖は健康に影響するかもしれないし、しないかもしれない。谷岡氏の言いたいことは、そういうことも考慮した(=コントロールした)調査をすべきだということです。朝日新聞が報道した調査は、どういうコントロールがされたのでしょうか。知りたいところです。
コーヒーの愛飲と喫煙率
さらに、重要と思える話があります。谷岡氏は『「社会調査」のウソ』とは別のある講演で、
|
と述べています。もちろん喫煙率は国によって違うので一概には言えないと思いますが、重要な指摘だと思います。もし仮に、コーヒーを飲まない人の喫煙率が20%で、コーヒーを4杯以上飲む人の喫煙率が50%だとしたら、それが死亡率に影響しないはずがないと思います。あくまで仮定の話ですが・・・・・・。コーヒー調査においてはそういう「コントロール」も必要でしょう。
コーヒーは日本でも世界でも極めて一般的な飲み物なので、学者も役人も調査しようという気になるし、またコーヒーと病気リスク・死亡リスクの関係は新聞社としても記事にしやすいのでしょう。読者の関心を引く記事、というわけです。しかしもっと踏み込んで調査しないと(ないしは調査方法のキモのところを報道しないと)「結局のところ何も分からない」記事になりかねないと思います。
2013-08-30 19:41
nice!(0)
トラックバック(0)



