No.26 - ローマ人の物語(3)宗教と古代ローマ [本]
(前回より続く)
古代地中海世界における宗教
前回、宗教上の像や施設の破壊の経緯を「ローマ人の物語」から引用しました。以降では、古代地中海世界における宗教がどういうものだったかを振り返り、宗教の破壊がどういう意味をもつのかについての想像を巡らせてみたいと思います。
現代の我々日本人は、多くの人が冠婚葬祭やお正月は別として日常は宗教と疎遠な生活をしています。また政治に特定の宗教が影響するということは、政教分離が原則の国家では考えられません。しかし古代では邪馬台国の卑弥呼がそうであったように宗教は日常生活を支配していたし、政治や軍事とまでも結びついていました。No.8「リスト:ノルマの回想」で書いたベッリーニのオペラ「ノルマ」では、ドルイド教の巫女の神託でローマ軍との不戦(ないしは開戦)が決まるわけです。オペラはあくまでフィクションですが、このように神託で政治や軍事が動く例は、古代中国でも邪馬台国でもエジプトでもガリアでもマヤでも、世界各国にいっぱいあったわけです。
では古代地中海世界のギリシャ・ローマではどうだったのかというと、やはり神託で政治が動く例は多々ありました。まず思い出すのはギリシャにおけるデルフォイ(デルポイ)の神託です。デルフォイはパルナッソス山(アテネの西方)の麓にあった都市国家で、アポロン神殿がありました。ここでデルフォイの巫女(ピュティア)が神託を告げます。この神託はギリシャの人々に珍重され、ポリスの政策決定にも影響を与えました。ギリシャの各都市はここに財産庫を構えて神殿に献納しています。
| ちなみにミケランジェロは、カトリックの総本山であるバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井画に古代地中海世界の5人の代表的な巫女を描いていますが、その一人がデルフォイの巫女です。 |
デルフォイの神託の有名な例が、ヘロドトスの「歴史」に書かれている、神託とサラミスの海戦の顛末です。ことの発端はギリシャが大危機に陥ったペルシャ戦争の時、アテナイの滅亡を暗示する神託があったことです。そこでアテナイの使者は出直して再度巫女に乞い、新たな神託を得ます。重要部分だけを抜き書きすると次のようです。
・・・・・・ゼウスはアテナがために木の砦をば、唯一不落の塁となり、汝と汝の子らを救うべく賜るであろうぞ。・・・・・・ |
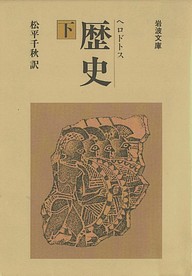 この「木の砦」とは以前は茨の垣根に囲まれていたアクロポリスのことであり、従ってアクロポリスに籠城して戦うべきだと解釈する者もいました。しかしテミストクレスは「木の壁」を船と解釈してアテナイ市民に訴え、三段櫂船を主力としてサラミスの海戦に臨み、ペルシャ軍を破りました。もちろん指導者・テミストクレスにしてみると、神託をうまく利用して自分が正しいと考える戦術を実現しただけかもしれません。しかし印象的なのは、ペルシャ戦争においてギリシャ連合軍が最終勝利を得る転機となった「サラミスの海戦」に至る過程において神託が重要な位置を占めていることです。兵士たちが一致団結する原動力にも神託が役立ったことは想像に難くありません。歴史書に書かれていることがすべて事実とは限りませんが、歴史書に「堂々と」書かれるほど神託は身近なものであり、戦争にも影響を与えたということは、最低限認めざるを得ないと思います。
この「木の砦」とは以前は茨の垣根に囲まれていたアクロポリスのことであり、従ってアクロポリスに籠城して戦うべきだと解釈する者もいました。しかしテミストクレスは「木の壁」を船と解釈してアテナイ市民に訴え、三段櫂船を主力としてサラミスの海戦に臨み、ペルシャ軍を破りました。もちろん指導者・テミストクレスにしてみると、神託をうまく利用して自分が正しいと考える戦術を実現しただけかもしれません。しかし印象的なのは、ペルシャ戦争においてギリシャ連合軍が最終勝利を得る転機となった「サラミスの海戦」に至る過程において神託が重要な位置を占めていることです。兵士たちが一致団結する原動力にも神託が役立ったことは想像に難くありません。歴史書に書かれていることがすべて事実とは限りませんが、歴史書に「堂々と」書かれるほど神託は身近なものであり、戦争にも影響を与えたということは、最低限認めざるを得ないと思います。|
余談ですが、巫女がトランス状態となって予言の神であるアポロンの神託を告げるのは、活断層から出てくる火山性ガスの効果だと言われています。この説は活断層が見つからないため一時否定されましたが、最近の精密な地質調査によって活断層の存在が立証されました。これについては、日経サイエンス 2004年 1月号 に詳しい論文が載っています。 「火山性ガス」と「巫女」と聞いて直感的に思い出すのは下北半島の恐山ですね。恐山は日本のパルナッソス山というところでしょうか。 |
ポエニ戦争と女神
この「デルフォイの神託とサラミスの海戦の顛末」と似たエピソードが共和制時代のローマにあります。ペルシャ戦争の時のギリシャのように、ローマが一大危機に陥った時の話です。これはローマと宗教の関係がどういうものかをうかがわせるものです。No.24「ローマ人の物語(1)」でも引用した、本村凌二・東大教授の「多神教と一神教」から引用します。
前216年、ローマ軍はハンニバル率いるカルダゴ軍に大敗北を喫した。いわゆるカンナエの戦いであるが、その戦死者を上回る戦闘は第一次世界大戦までなかったといわれるほどである。このときローマ人はかかる大敗北の原因として自分たちがあがめるべき神への崇拝を怠ったからではないかと自問する。地中海世界で広く霊験あらたかと信じられていた巫女シビュラの予言にうかがいを立てると、それは小アジアのキュベレ女神であるという。このようにしてキュベレ女神の聖石は大母神としてローマの都に迎えられ、その祭礼の跡は今日でもパラティヌス丘に残されている。この女神の到着後、ローマ軍は反撃し、やがて大勝するのだから、キュベレ女神の加護たるやはかりしれないと喧伝されたにちがいない。 |
このようにして「キュベレ女神」は紀元前3世紀にオリエントからローマに初めて導入されたのですが、同じ本に次のような記述もあります。
キュベレ女神は帝政期の貨幣にも刻印され、公認の祭儀が捧げられている。牡牛と牡羊を殺害する儀礼があり、その血を全身に浴びた者は20年間神聖な人生をおくることができるという。背教者の哲人皇帝ユリアヌス(在位 361-363)にとって、キュベレは「全生命の女主人であり、あらゆる生成の原因者」であった。 |
 オリエントからの外来の神であるキュベレ女神は、少なくとも600年近く、ローマで信仰されたことになります。
オリエントからの外来の神であるキュベレ女神は、少なくとも600年近く、ローマで信仰されたことになります。「ローマ帝国の神々」(小川 英雄 著。中公新書。2003)という本には、ローマおよびローマ帝国内に広まったオリエント由来の神々や宗教が詳しく書かれています。それによると、主だった神だけでもキュベレ神(小アジア)、イシス神(エジプト)、ミトラス(ミトラ)教(ペルシャ由来)、ユダヤ教、キリスト教など、多彩です。キュベレ神をローマに迎えた経緯の詳細も書かれているのですが、ローマはこの神の招請のためにプブリウス・スキピオ・ナシカという名門貴族を団長とする公式使節団を小アジアのペルガモン王国に派遣しているのですね。キュベレ女神の聖石とは隕石だったようです。この聖石は紀元前204年4月4日にローマ到着し、パラティヌス丘に安置されました。
このキュベレ崇拝の輸入の効果はすぐに現れた。翌年のうちにハンニバルはアフリカに押し戻され、紀元前202年のザマの戦いでのローマの勝利によって、第二次ポエニ戦争は終わった。 |
キュベレ女神が第二次ポエニ戦争の勝利をもたらしたという「直接の因果関係」を信じるローマの指導者は、さすがに当時でもいなかったのではと想像します。ローマの指導者たちはローマ市民の気を奮い立たせ、団結を再度強固にし、カルタゴとの戦争の局面を打開するために小アジアの神を利用したのでしょう。しかしこれは非常に重要なことだと思うのです。
キュベレ女神だけではありません。オリエント由来の数々の信仰がローマに広まり、それはローマの指導者層にも及んだようです。ポエニ戦争に勝利したあとの内乱状態において、スッラとマリウスの対決があるのですが、「ローマ帝国の神々」には次のように書かれています。
第三次ポエニ戦役(前149-前146)以後の社会変動と内乱はオリエント系の宗教にとって有利に働いた。まず、シリアの地母神アタルガティス信者エウヌスの下で、シチリアのシリア人奴隷が叛乱を起こした。将軍マリウス(前157-前86)にはシリア人の女予言者マルタがいつも離れることなく従っていた。これに対して、マリウスの敵スラ(前138-前78)はカッパドキアの地母神マー・ベローナを信じていた。スラはまた、イシス女神の祭司たちを連れてきた。 |
ローマの活力
このようなエピソードを読むと、ローマ人の「多神教」、つまり「宗教的寛容」を基礎として外来の神をも受け入れ、それを活力の源泉としていくローマ人の伝統的なメンタリティがローマの発展の根幹にあるのではないかと感じます。そして前回の No.25「ローマ人の物語(2)」で書いたように、4世紀末の時点でこれらのすべての「宗教」は抹殺されてしまいます。これはローマ人のエネルギー源を奪うことになったのではと思うのです。
キュベレ像でも聖石でも、また前回書いたニケ像でもよいのですが、ある神のモニュメント回りに集結したローマの兵士が戦勝を誓ったとします。そしてその行為が最近始まったものではなく百年というレベルの伝統だったとします。そのニケ像なりキュベレ像、聖石が倒されて破棄されたとしたらどうでしょうか。兵士たちに戦意は生まれるのでしょうか。像などは些細なことだと考えるのは、現代人の考え方だと思います。
現代においても「組織がある目標に向かって一致団結し、モチベートされることの強さ」は相当なものです。組織のリーダたるのもは、このモチベートをどうやって実現するのか、それこそが仕事だと言ってもよいでしょう。企業活動を例にとると、もちろんビジネスモデルの優劣や事業戦略の良し悪し、思い切った投資の決断や新事業への進出の判断は重要です。しかし現実はモチベートされ団結した組織さえあれば、戦略や決断はあとからついてくるということがよくある。
現代では「宗教」や「神の像」でモチベートされるわけではなく、企業なら世界最高の製品やサービスを提供するとか、誰もやったことのないことにチャレンジするとか、そういうことです。現代の国家も「戦争の惨禍からの復興」とか「先進国なみの豊かな生活」とかの目標のもとに国民が団結したときは強いし、そういう明白なものを失った時に混迷に至るのは、理解できるはずです。
宗教のありかたが国家の骨格を決めるというのは、近代以前ではあたりまえです。宗教や神のもとに結束して大きな力を発揮することは、有事である戦争に限らずよくあったはずです。ローマは、キリスト教以前の多神教の時代もキリスト教以降も、宗教と国家運営が表裏一体だったことでは一貫していたのではないでしょうか。
ローマの固有信仰
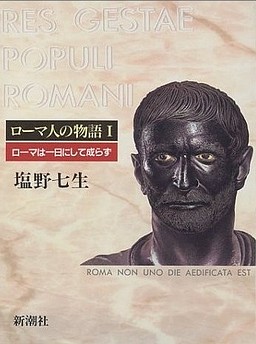 キュベレ女神はオリエントからきた「外来の」神の一つです。しかしもちろん、ローマにはそれ以前から信仰されてた神々がありました。ローマは多神教なので神は数え切れなくあるのですが、まずラテン民族の古来の神であるヤヌス、ラル、ウェスタなどがあります。ローマ建国以来の由緒ある神々は、最高神であるユピテル、ユノ、ミネルヴァの国家の主要三神、マルス、ウェヌス、ディアナなどです。またローマの版図の拡大とともにギリシャの神であるポセイドン、デュオニソス、ヘルメスなども輸入され、信仰されました。ユピテル=ゼウスなど、ローマの神とギリシャの神の同一視(習合)も起こりました。
キュベレ女神はオリエントからきた「外来の」神の一つです。しかしもちろん、ローマにはそれ以前から信仰されてた神々がありました。ローマは多神教なので神は数え切れなくあるのですが、まずラテン民族の古来の神であるヤヌス、ラル、ウェスタなどがあります。ローマ建国以来の由緒ある神々は、最高神であるユピテル、ユノ、ミネルヴァの国家の主要三神、マルス、ウェヌス、ディアナなどです。またローマの版図の拡大とともにギリシャの神であるポセイドン、デュオニソス、ヘルメスなども輸入され、信仰されました。ユピテル=ゼウスなど、ローマの神とギリシャの神の同一視(習合)も起こりました。これれらの神は、国家から家庭まで、戦争から日常生活までの守り神です。もちろん国家レベルの祭祀は、国家公務員である最高神祀官・神祀官・祭司という祭司たちがとりしきります。鳥の飛び方をみて未来を占う鳥占官(アウグル)という公務員もいました。日常生活に関係した神の例として「ローマ人の物語」では、夫婦喧嘩の守護神とされた「ヴィリプラカ女神」が紹介されています。
夫と妻の間に、どこかの国では犬も食わないといわれる口論がはじまる。双方とも理は自分にあると思っているので、それを主張するのに声量もついついエスカレートする。黙ったら負けると思うから、相手に口を開かせないためにもしゃべりつづけることになる。こうなると相手も怒り心頭に発して、つい手がでる、となりそうなところをそうしないで、二人して女神ヴィリプラカを祭る祠に出向くのである。 |
相手の言い分を聞かざるを得ない状況になって、興奮が収まっていき、仲直りにつながるというわけです。
ウェスタの巫女
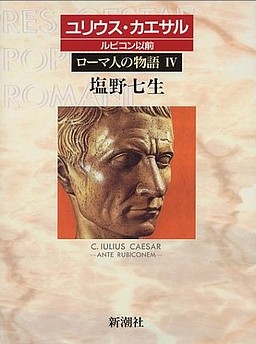 ローマに古くからある固有信仰からの印象的なエピソードを「ローマ人の物語」の中から取りあげます。「ウェスタの巫女」が関係したある「事件」で、これは若きユリウス・カエサルの生涯の分岐点となったものです。
ローマに古くからある固有信仰からの印象的なエピソードを「ローマ人の物語」の中から取りあげます。「ウェスタの巫女」が関係したある「事件」で、これは若きユリウス・カエサルの生涯の分岐点となったものです。話の発端は「独裁者スッラ」の登場です。紀元前1世紀における「民衆派」マリウスと「元老院派」スッラの、血で血を争う内戦の詳細については「ローマ人の物語 第3巻 勝者の混迷」を読むしかないのですが、とにかく紀元前82年にスッラはこの戦いに勝利します。そして「民衆派」の一掃を目指して元老院議員80人を含む4700人の「処罰者名簿」を作成し、処刑と財産没収を始めます。この名簿に18歳の若者の名前があったのです。以下「ローマ人の物語」からの引用です。下線は原文にはありません。
スッラの作成した「処罰者名簿」には、一人の若者の名もあった。マリウスの甥でありキンナの婿であるところから、スッラにすれば若きカエサルも、一掃さるべき「民衆派」の立派な一員だった。 |
塩野さんのこの文章の意図は、引用の最後のところ、スッラが若きユリウス・カエサルを「百人のマリウス」と評したことを書くことですね。つまり「才能は、才能によってのみ認知される」ということだと思います。
しかしそれとは別に、下線の部分に注目すべきことが書かれています。下線の部分の「女祭司(ヴェスターリ)」は、普通ラテン名で「ウェスタの巫女 Vestalis」と呼ばれています(ウェスタの処女、ウェスタの聖女とも言う)。ウェスタの巫女は、かまどの火を司り、家政と結婚の神でもある「ウェスタ神 Vesta」に仕える巫女の一団(6人)です。ウェスタ神はローマの建国以前からラテン民族に伝えられてきた古い神です。巫女となる女性は6~10歳のローマ市民の子女の中から選ばれ、30年の間、実家からは離れて専用の家に住み、勤めを果たします。巫女の最大の責務はパラティヌスのウェスタ神殿の「聖なる火」を絶やさないことです。また各種の聖具を管理し、典礼に参加します。
アルベルト・アンジェラの「古代ローマ人の24時間」(関口英子訳。河出書房新社。2010)は、最新の古代ローマ研究の成果をもとに、紀元115年(皇帝トラヤヌスの時代)のある1日のローマを実況中継風に描いた本です。この中に、パラティヌスの近くで警備隊や従者に囲まれた豪華な飾りの馬車に出会う場面があります。馬車は円形の神殿の前で止まります。
最初に、ベールをかぶった高齢の女性があらわれる。続いて、華奢な女の子が手を借りながら降りてくる。おそらくまだ10歳にもなっていないだろう。ゆったりとした衣服のせいか、動きが少しぎこちない。 |
ウェスタの巫女の最大のポイントは「処女であること」です。従って巫女である間は、彼女たちは純潔を守り通さなければなりません。もしこれに反すると死刑です。この刑の執行方法は独特です。
聖なる火が消えてしまった場合や、巫女が処女を失った場合には、見せしめとしての罰が与えられる。巫女の愛人はフォルムで死ぬまで鞭打たれ、巫女も死刑にされる。ただし、巫女を殺す際には血を一滴も流してはいけないと法律で定められていたため、一塊のパンとランプとともに地下の独房に入れられ、生き埋めにされるのだ。地下の独房はカンプス・スケレラートゥス(呪われた野、の意)というあらかじめ準備された場所にあり、そのまま紛れもない墓となる。 |
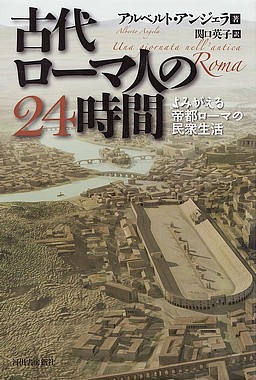 実際にこの刑が行われた例が、西暦1世紀から2世紀にかけてのローマ人であるスエトニウスが書いた「ローマ皇帝伝」(国原吉之助訳。岩波文庫。1986)に出てきます(第8巻 ドミティアヌス帝)。
実際にこの刑が行われた例が、西暦1世紀から2世紀にかけてのローマ人であるスエトニウスが書いた「ローマ皇帝伝」(国原吉之助訳。岩波文庫。1986)に出てきます(第8巻 ドミティアヌス帝)。ウェスタの巫女は祭礼を司るだけではありません。塩野さんやアルベルト・アンジェラが書いてるように、ローマ市民の大変な敬意を払われていたと同時に極めて強い「権威」があったようです。この権威について Wikipedia の「ウェスタの処女(Vestal Virgin)」の項から一部を引用すると、
| ◆ | 競技会や公演会があるときには来賓席が用意された。 |
| ◆ | ローマの女性たちとは異なり、家父長制のもとになく、財産権をもち、意志の表明や投票ができた。 |
| ◆ | 清廉潔白な人間であるとされ、条例のような公文書や重要な決定などでその意見が求められていた。 |
| ◆ | その人格は不可侵なものであった。その身体を傷つけることは死罪を意味し、つねに護衛する人間がついた。 |
| ◆ | 彼女たちは有罪となった囚人や奴隷に面会することで解放してやることができた。 |
| ◆ | 5月15日にはテヴェレ川へアルジェイと呼ばれた宗教的な藁人形を投げ込む役がまかされていた。 |
などです。我々が普通「巫女、女祭司」という言葉から受けるイメージとはかけ離れた「権威」を持っていたわけです。通常の生活から離れてローマのために身を捧げ、処女を貫き通し(=神と結婚し)、厳しい掟を守り、重大な責任を負い、(身代わりの藁人形が) 毎年犠牲になる極めて特別な女性たちの集団。この「特別さ」が権威の源泉ですね。考えてみると、これに類似した話は世界中にありそうです。
|
ここまで書いて直感的に思い出すのは、平安時代から鎌倉時代にあった、賀茂神社と伊勢神宮の「斎王」です。上賀茂神社・下賀茂神社では斎院、伊勢神宮では斎宮とも呼ばれていました。いずれも皇室の未婚女性から選ばれ、1~2年の準備期間の後、特別の場所に住みます。賀茂神社では京都・紫野にあった「斎院御所」、伊勢神宮の場合は「斎宮寮」です。そして巫女としての神事を行うわけです。現代の葵祭(賀茂神社の祭)で一般女性から「斎王代」が選ばれるのは古いしきたりを模しています。 斎王は天皇が皇室から神に差し出す未婚女性ですが、ウェスタの巫女の場合、差し出すのも差し出されるのもローマ市民です。このあたりは国のありようの違いが現れていて興味深いところです。 |

| |||
|
ルーベンス 「マルスとレア・シルウィア」 (リヒテンシュタイン侯爵家蔵) | |||
伝承では、オオカミに育てられた双子のロムルスとレムスがローマを建国しました。このローマ建国神話におけるロムルスとレムスは、軍神・マルスと、ウェスタの巫女であったレア・シルウィアの子です。ウェスタの巫女は「ローマの母」とでも言うべき存在なのです。
話を「ローマ人の物語」に戻します。絶対権力者のスッラは、周囲の助言ぐらいではカエサルを「処罰者名簿」からはずことはなかったが、ウェスタの巫女の要請によってはじめて名簿からはずしたわけです。これはウェスタの巫女がもつ「権威」の大きさを考えると、むしろ当然だったと考えられます。
スッラは温情で処罰者名簿からはずすような「甘さ」がある人間では全くありません。冷徹で鋭利な執政官であり、独裁者だった。しかしスッラは非情な独裁者である以前に「ローマ市民」だった。だから処罰者名簿からカエサルをはずした。
塩野さんがスッラとマリウスの戦いを記述した巻を「勝者の混迷」と名付けているように、当時のローマはまさに内戦状態です。民衆派と元老院派が激しく論争し、互いに殺し合っている。しかしスッラとウェスタの巫女のエピソードからうかがえるのは、処刑する者と処刑される者があったとしても、その根底のところではローマ市民としての強固な「ある種の価値観」を共有していることです。スッラの一見「甘い」と見える行動に、ローマの真の「強さ」を感じます。
ウェスタ神殿に永遠に燃えていた「ローマの運命を左右する象徴的な意味合いをもつ聖なる火」は、スッラがカエサルを処罰者名簿からはずしてから475年後に消されました。古代オリンピックの廃止と同時期です。それは、ほかでもないローマ皇帝の命令によってです。この聖なる火が消えた時点で実質的にローマは滅んだのではないでしょうか。
聖なる火はローマの信仰の極く一部です。そのほかに固有の神々があり、加えてオリエントからの外来の神々があり、数々の神殿があって各種祭祀が執り行われ、日常生活のあらゆるところに(塩野さんが書いているように、夫婦喧嘩の守護神までの)神がいた。前回の No.25「ローマ人の物語(2)」で「ローマ人物語」からいろいろと引用したように、それらはオリエント由来のたった一つの宗教を除いて破壊されたわけです。
ポンペイ展
2010年の3月から6月まで横浜美術館で「ポンペイ展」が開催されたので行ってきました(展示会は日本各地を巡回)。改めて思ったのはポンペイには「神殿、神の像、神を描いたフレスコ画がずいぶんある」ということです。
ポンペイは南北650メートル、東西1200メートル程度の町で、正確な人口は不明ですが、ヴェスビオ山の大噴火の当時は約8000人程度が住んでいたとされます。遺跡の地図をみると西南に公共広場(フォルム)があって、その周りに神殿がかなりあります。ちょっと数えてみただけでも、
| ◆ | アポロ神殿 |
| ◆ | カピトリウム神殿(ローマの3主神であった、ユピテル、ユノ、ミネルヴァを祭る) |
| ◆ | ラル神殿(ラルは家庭の守護神) |
| ◆ | ウェスパシアヌス帝神殿(69-79在位の皇帝) |
| ◆ | ドリス式神殿 |
| ◆ | イシス神殿(イシスはエジプト由来の神) |
という具合です。
 ポンペイ遺跡からは、神殿を飾っていた数々の神の像が出土しています。神殿の名称になっている神以外にも、ウェヌス、ヘルクレス、メルクリウス、ポセイドンなど多様です。右の図はポンペイ展に展示されていたウェヌス(ヴィーナス)像(高さ90センチ)ですが、大変に優美で見事な造形です。前に古代の地中海世界にはルーブルの「ミロのヴィーナス」に匹敵する像がいろいろあったはず、という推測を書きましたが、このウェヌス像を見るとそれはほとんど確信となります。
ポンペイ遺跡からは、神殿を飾っていた数々の神の像が出土しています。神殿の名称になっている神以外にも、ウェヌス、ヘルクレス、メルクリウス、ポセイドンなど多様です。右の図はポンペイ展に展示されていたウェヌス(ヴィーナス)像(高さ90センチ)ですが、大変に優美で見事な造形です。前に古代の地中海世界にはルーブルの「ミロのヴィーナス」に匹敵する像がいろいろあったはず、という推測を書きましたが、このウェヌス像を見るとそれはほとんど確信となります。No.25「ローマ人の物語(2)」に引用しましたが、塩野さんはローマにある「カピトリーノのヴィーナス」について「あまりに美しいために破壊するにしのびず、誰かが意図的に隠しておいたものではないか」という推測をしています。しかしこのポンペイのウェヌス像についてはこういった推測は成り立ち得ない。それは「あたりまえのように」ポンペイの町に飾られていて「たまたま」火山噴火で埋まり「運良く」土の中から掘り出されたものに過ぎないことが明白です。それでいてこのレベルの高さなのです。
 一方、家庭内をみると、展示品には家の中に祭った「小ぶり」の神々の像がありました。右の図は家の守り神であるラル神の小像(高さ19センチ)です。ポンペイの家庭にはララリウムと呼ばれる小さな祠、あるいは祭壇がありました。塩野さんが「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていた」と書いている、その「神棚」です(No.25「ローマ人の物語(2)」の引用を参照)。ラル神はそこに安置されていました。
一方、家庭内をみると、展示品には家の中に祭った「小ぶり」の神々の像がありました。右の図は家の守り神であるラル神の小像(高さ19センチ)です。ポンペイの家庭にはララリウムと呼ばれる小さな祠、あるいは祭壇がありました。塩野さんが「ローマ人の家にはどこでも、神棚と考えてよい、中庭に面した一角に家の守護神や先祖を祭る場所がもうけられていた」と書いている、その「神棚」です(No.25「ローマ人の物語(2)」の引用を参照)。ラル神はそこに安置されていました。像だけでなくフレスコ画の壁画もあり、神の姿を描いたものも多数あります。展示ではディオニュソスの絵がありました。ディオニュソス信仰はローマでは禁止されていたはずなのですが「地方都市」ポンペイにまでは及んでいなかったようです。
これらを見るにつけポンペイの人たちは私的場所や公的空間にかかわらず、神々の像や絵に囲まれて生活していたことが分かります。それはローマの他の都市でも同じだったはずです。もし仮にポンペイの町が噴火で埋没せずに4世紀まで残り、キリスト教の国教化に遭遇したらどうでしょうか。これらの神殿、像、壁画、家庭内の祭壇は全部破壊され、かつ宗教行事が全部禁止されたことになります。違反すると死刑です。これはいったいどのような影響を人々に与えたのでしょうか。
あなたが京都人なら
私たちはちょっと想像力を働かせる必要があります。1600年前のローマを想像することは困難なので、現代の日本に置き換えて考えてみます。
いまあなたが仮に京都市内に生まれ育ち、京都で働いているとします。町内会の活動にも熱心で、かつ「京都人」であることに誇りを持っているとします。その誇りを支えている極めて重要なファクターは何かというと、それは京都に現存する神社・仏閣であり、1000年レベルの伝統がある京都の各種行事ではないでしょうか。
もし現在、政府によって仏教・神道が「邪教」とされ、京都においてローマ帝国と同じことが、以下のように政府の強権で実施されたと想像してみます。
主要な神社・寺院・仏閣は破壊し、その他は調度品を破棄して建物を別目的に転用する。従って祇園神社、北野天満宮、貴船神社、上賀茂神社、下鴨神社、平安神宮などの主要神社は破壊。清水寺、知恩寺、南禅寺、東本願寺、東寺、銀閣寺、金閣寺、大徳寺、大覚寺、妙心寺、龍安寺、広隆寺、高台寺、東福寺も破壊。五重の塔も破壊。仏像も破棄。広隆寺の弥勒菩薩半跏思惟像も三十三間堂の千手観音像も焼却処分。
仏教に関係する行事はすべて禁止。檀家組織は解体。大文字山などの五山の送り火や、お盆の種々の行事はすべて禁止。神社にまつわる行事も禁止。従って祇園祭りは廃止。祇園祭りに使用する山鉾もすべて焼却処分。葵祭も時代祭も廃止。各町内の秋祭りも禁止。新年の初詣も禁止。
個人の家にある神棚、仏壇、仏像は撤去。各家庭の台所にある「阿多古祀符 火迺要慎」と書かれた火除けの祀符も、これは愛宕神社の祀符だから破棄。
こういいう事態になっても、あなたはなおかつ「京都人」だと言い続けるでしょうか。もちろん企業に勤めているので生活には困らないでしょう。しかし政府主導の「新しい京都をつくる会」に参加したいとは全く思わないでしょう。
全く同様のことが奈良でも起こったとします。そうするとすべての神社や寺院・仏像の破壊、宗教関連行事の禁止に加えて、例えば正倉院の宝物は全て焼却処分でしょう。正倉院はもともと東大寺の一部だったのですから・・・・・・。もちろん東大寺の大仏は消失します。こうなると京都・奈良以外の人たちにとっても「日本人としての誇り」の一つが完全に失われたことに気づくと思います。そして京都・奈良の人は思うでしょうね。果たしてこれは日本なのか、と。
重要なのは現代の多くの日本人はそんなに宗教に熱心ではないということです。神社は秋祭りや初詣に参加したり、七五三とか厄除け、合格祈願に訪れる程度が一般だと思います。仏教に熱心な人はもちろん多くいますが、仮に統計をとったとすると、日本人が寺院を訪れる理由は仏像鑑賞を含めた広い意味での「観光」が数で圧倒するのではないでしょうか。
にもかかわらず、神社・仏閣とそれに関連した行事・文物がすべてなくなったとすると「日本でなくなる」。宗教を甘くみてはいけないのです。1000年というレベルで長く国民に浸透した宗教は、国民のアイデンティティーの重要部分を占めています。現代日本で言うとそれは「日常生活」「年中行事」「仕事」「観光」「人生の節目」「美術・芸術」「文学」などと、さまざまな関連性をもった「巨大な体系」を作っているのです。
No.21「鯨と人間(2)」に、日本に数え切れないぐらいある「動物供養」の話を書きました。しかし「動物供養」どころか、日本では「モノの供養」も数多くあります。人形供養、針供養を筆頭に、印章、筆、入れ歯、下駄、包丁などの「供養」が限りなくあります。そしてこれらの動物供養やモノ供養の背景には、仏教の殺生を否定する教義や、神社のアニミズム的信仰をルーツとする日本人の「宗教感情」があるわけですね。ほとんど意識はされないと思うけれど・・・・・・。動物供養やモノ供養も広い意味での「宗教体系」の一部です。
この「体系」は、一握りの誰かが決めたものではありません。長い年月をかけ、自然発生的に増殖を繰り返してできあがったネットワークです。
「宗教体系」の破壊
現代の京都・奈良と違って、古代ローマの話です。宗教と人間の日常生活や国家運営との結びつきが現代よりもよほど強いわけです。この世のあらゆる出来事は神々の意思によるものと考えられていた時代であり、占いが神々の意思を知るための大切な行為と考えられていた時代です。その「宗教体系」の破壊は国家が滅びかねないほどの影響を持つのではないでしょうか。
それだけではありません。「新たな宗教体系」として採用された当時のキリスト教は一神教です。一神教の特徴は、もちろん他の宗教との共存を拒否し非寛容であることです。しかしもう一つの特徴、むしろ一神教の最大の特徴は、塩野さんが明確に書いていますが「人間の倫理・道徳や生活スタイルに介入する」ということなのです。
ギリシャ・ローマに代表される多神教と、ユダヤ・キリスト教を典型とする一神教のちがいは、次の一事につきると思う。多神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割を神に求めない。一方、一神教では、それこそが神の専売特許なのである。 |
当時のキリスト教を現代のキリスト教と思ってはいけません。当時のキリスト教はピュアな一神教であり、塩野さんが正確に言い当てているように「人間の行いや倫理道徳を正す役割が神の専売特許」である宗教なのです。「行いや倫理道徳を正す」というのも現代のイメージで考えると大きな間違いです。甘く見てはいけません。非常に強く人間の生き方と社会活動を拘束するものです。
たとえば、もし仮に一神教の聖職者が神の教えとして「自分が食べるものだけを生産しましょう、あとは神に祈りましょう」と説教し、農業に従事する奴隷がその通りにしたら、生産性は低下します。それが社会全体に広まったら、奴隷制度を根幹とする国は衰退するはずです。
「利子をとって金を貸すのは悪いことです。やめましょう」と聖職者が教え、国家がそれを後押し、それが国全体に広まったとしら、国の経済力は確実に衰退します。
「戦うことは悪です」と聖職者が説教し、その教えを実践する「兵役拒否者」が続出したとしたら、軍事力は間違いなく低下します。
以上はあくまで想像ですが、ありうることだと思います。実際のところ、最後の「兵役拒否者」の例は塩野さんの本に出てきます(第14巻:キリストの勝利)。「人間の行いや倫理道徳を正す」ことは国のレベルの経済や軍事にまで影響するはずです。これはちょうど現代のイスラム原理主義をかかげる人たちの行動パターンを考えてみると分かりやすいのではないでしょうか。
新渡戸稲造と「武士道」
少し脇道にそれますが「一神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割こそが神の専売特許」という塩野さんの文章に関して思い出す話があります。新渡戸稲造(1862-1933)の「武士道」(1899。明治39年。初版)です。新渡戸稲造は、その序文で次のように書いています。
約10年前、著名なベルギーの法学者、故ラヴレー氏の家で歓待を受けて数日を過ごしたことがある。ある日の散策中、私たちの会話が宗教の話題に及んだ。 |
新渡戸稲造が尊敬するこのベルギーの法学者にとって、倫理道徳の教育が宗教のテリトリだということは、何の疑いもなく自明のことなのですね。新渡戸稲造はこの言葉にショックを受けて『武士道』を書くことになるのです。普通の日本人の感覚では、倫理や道徳は「社会に共有され、受け継がれているもの」であって、特定の宗教とは関係ありません。しかしキリスト教では「人間の行いや倫理道徳を正すのが神の役割」であり、つまり、宗教なしに倫理や道徳(教育)はありえないのです。
新渡戸稲造はキリスト教徒です。尊敬する老教授の言葉にショックを受け「キリスト教を広めて日本に道徳教育を根付かせよう」と考えてもよいはずです。そう考えてキリスト教系学校を設立した人もいたわけだから・・・・・・。しかし彼はそうではなかった。新渡戸稲造の偉いところは、特定の宗教とは無関係に日本にも倫理・道徳の体系はあると考え、それを諸外国に説明するために、英文で『武士道』という本にまとめたことです。『武士道』は世界的なベストセラーになり、現代まで読み継がれています。
『武士道』の序文を踏まえて話を古代ローマに戻します。キリスト教の国教化前後のローマ帝国では、倫理・道徳についての二つの異なる考えがあったと推定できます。
| ◆A |
古代ローマ(や日本)の伝統的考え方 倫理・道徳は、長年に渡って社会に蓄積され共有された、人間がとるべき行動や態度の規範である。特定の宗教に依存するものではない。 | |
| ◆B |
一神教(キリスト教)の考え方 倫理・道徳を人々に教えるのは宗教の役割である。それこそが宗教の存在理由である。 |
AとBはかなり違います。AをBに完全に転換するということは、並大抵ではないと思います。それは社会を作り直すことに等しく、簡単にはいかないはずです。そのAからBへの「作り直し」をローマ帝国はキリスト教の国教化でやろうとした。社会に共有された共通の価値観(A)は「国のかたち」を決める最も重要なことのはずですが、それが別のもの=キリスト教の倫理・道徳(B)になる。ローマ市民としてのアイデンティティは極めて不安定になり、国のかたちは崩れ、社会が混乱するでしょう。そういう時に強い外圧があれば、国が滅びかねない。ローマ帝国の末期で起こったことは、どうもそういうことだと感じます。
ローマ帝国と宗教の関係を考えるとき
多神教では、人間の行いや倫理道徳を正す役割を神に求めない。一方、一神教では、それこそが神の専売特許なのである。 |
インフラストラクチャの破壊
もちろん一神教であるキリスト教という新たな宗教のもと、新たな倫理道徳や生活スタイルの体系化を前提とした国を作り、その国を発展させることは可能です。事実、西ヨーロッパは数百年かけてそうなっていきます。しかし、国家のシステム全体を再建するのは、一朝一夕にいくはずはないのです。
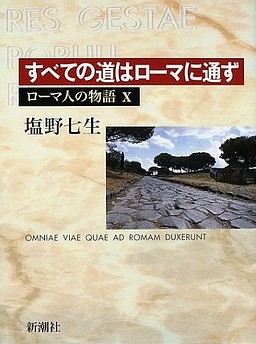 塩野さんの「ローマ人の物語」の大きな特徴は、インフラストラクチャの構築にいかにローマ人が先進的であったかということが詳細に記述されていることです。道路、橋、上下水道、浴場などのハード面はもちろん、法律、教育制度などのソフト・制度面もです。「第10巻:すべての道はローマに通ず」は、1巻がまるまるこのインフラストラクチャの記述に当てられています。
塩野さんの「ローマ人の物語」の大きな特徴は、インフラストラクチャの構築にいかにローマ人が先進的であったかということが詳細に記述されていることです。道路、橋、上下水道、浴場などのハード面はもちろん、法律、教育制度などのソフト・制度面もです。「第10巻:すべての道はローマに通ず」は、1巻がまるまるこのインフラストラクチャの記述に当てられています。こうしたインフラストラクチャのほどんどは「継承」できるわけです。メインテナンスさえすれば継承できます。キリスト教の国教化以降もローマ街道は使われたし、有名な「ローマ法大全」が編纂されたのは、西ローマ帝国が滅亡した後の東ローマ帝国においてでした。しかし、こういったローマ街道に代表されるインフラストラクチャを継承したつもりでも、もっとも本質的なところ、文明を成立させていた最重要のインフラストラクチャ=「人間の心、マインド、アイデンティティ」を、宗教を破壊することによってなくしてしまったのだと思います。その「アイデンティティ」という最重要インフラストラクチャを具体的な目に見える形に可視化し、象徴していたのが、神殿、神々の像、祭壇、聖石、そして言うまでもなくウェスタ神殿に燃え続ける「聖なる火」だった。
No.25「ローマ人の物語(2)」で書いたように、ローマの宗教は「ローマがローマたるゆえん」であり「ローマの最大の強み」だったのではないでしょうか。その1000年間続いた宗教体系をローマは破壊してしまいました。神の像も、宗教行事も、それと密接な関係があったはずの「人の心」もです。新たな宗教体系のもとに国を再建・再構築するのは、一朝一夕にはできないと思うのです。
(以降、続く)
2011-05-07 17:26
nice!(0)
トラックバック(0)



