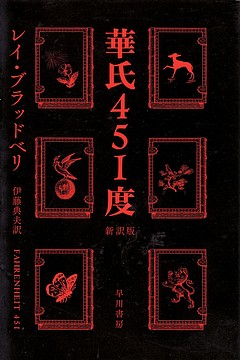No.132 - 華氏451度(3)新訳版 [本]
レイ・ブラッドベリ(1920-2012。米国)の小説『華氏451度』(Fahrenheit 451。1953)について、以前に2回にわたって感想を書きました。
の二つです。
日付から推測できるかもしれませんが、作者のレイ・ブラッドベリは、記事を書いた直後(2012.6.5)に92歳で亡くなられました。その時も何か書こうと思ったのですが、適当なテーマが見つけられませんでした。
そうこうするうち、2014年に小説の新訳が出版されました。『華氏451度〔新訳版〕』(伊藤典夫・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房。2014.6.25)です。今回はこの新訳の感想を、ブラッドベリの追悼の意味も込めて書きたいと思います。『華氏451度』のあらすじや、そこで語られていることについては、No.51、No.52 を参照ください。
マルクス・アウレリウス
No.51「華氏451度(1)焚書」に書いたのですが、旧訳の違和感は、Marcus Aurelius という人名を、英語読みそのままに「マーカス・オーレリアス」としてあることです。ここは日本人になじみのあるラテン語読みで「マルクス・アウレリウス」(第16代ローマ皇帝。121-180)とすべきです。マルクス・アウレリウスは世界文学史上に残る『自省録』を書いた人物です。こだわるようですが、「本」をテーマにした小説『華氏451度』で、こういうところをおろそかにする態度はよくない。
新訳ではちゃんとマルクス・アウレリウスとなっていて安心しました。訳者の伊藤氏は当たり前だと言うでしょうが・・・・・・。
人名が出たついでの余談ですが、新訳では主人公・モンターグの上司(隊長)の Beatty を、英語の発音に近い「ベイティー」と表記しています(旧訳ではビーティ)。
ハリウッド俳優に、ウォーレン・ベイティ(Warren Beatty)がいます。彼と、姉のシャーリー・マクレーンの本名は、
Henry Warren Beaty
Shirley MacLean Beaty
です。日本でも昔はウォーレン・ビューティと表記されていましたが、本人の要望で発音に近いベイティとなったようです。本名から t を一つ増やして芸名にしているのは、できるだけ「ビーティ」などと呼ばれることを避けるためだそうです(これはWikipediaの情報)。日本語もそうですが、英語の固有名詞の発音はスペルからは判読しにくいものがあります。しかし固有名詞の翻訳は原則として「原音主義」をとるべきであり、これも伊藤氏の(ささやかな)修正です。
ファイアーマン
主人公のモンターグの職業はファイアーマン(fireman)ですが、言うまでもなく英語で消防士のことです(最近は女性消防士も含めて firefighter と呼ぶのが米国のトレンドのようです)。旧訳では「焚書官」となっていましたが、新訳では「消火」にひっかけた「昇火士」という造語をあてています。これを含めて「火」に関する一連の訳語は、
としてあります。fireは名詞の「火」であり、動詞としては「火をつける」意味です。そのことからすると、現代英語の fireman は「火を消す人」という通常の意味の下に「火をつける人」の意味を内在していると考えられます。事実、蒸気ボイラーなどの火を焚く「缶焚き」の意味でも使われる。新訳は漢字を活用して日本語訳としてのダブル・ミーニングを狙った工夫でしょう。
文芸作品からの引用
ここからが、いわば本題です。新訳の大きな特徴は『華氏451度』に含まれる文芸作品からの引用を、引用だと分かるように翻訳し、かつ巻末に注釈をつけたことです。
英米の小説で、文章の中に文芸作品からの語句を引用することはよくあるわけです。特に、聖書とシェイクスピアを知らないと翻訳はできない、とさえ言われるぐらいです。引用はとりたてて珍しくはありません。
しかし『華氏451度』は、ほかでもない「本」をテーマにした小説です。「本」をテーマにした小説で「本」からの引用がどういう風に使われているのか、それは作者が小説に込めた思いやテーマに直結する可能性があります。「引用を引用と分かるように翻訳する」ことは、とりわけ『華氏451度』では重要だと考えられる。その意味で、伊藤氏の新訳は意義が深いと思いました。
引用で思い出すのが『赤毛のアン』です。No.77「赤毛のアン(1)文学」、No.78「赤毛のアン(2)魅力」で書いたように、あの本には英米文学と聖書からの引用が溢れています。そして実は『赤毛のアン』と『華氏451度』に共通の引用があるのです。まずそのことから始めます。
『赤毛のアン』を振り返る
『赤毛のアン』(1908)には英米の文学作品と聖書からの引用が多数あるのですが、中でも最も有名なのは物語の一番最後のものでしょう。『赤毛のアン』の最終章である第38章「道の曲がり角」の最後の場面は、グリーン・ゲイブルズの窓辺にたたずむアンの記述です。
物語の最後の最後でアンがつぶやく言葉が、文芸作品からの引用です。翻訳者の松本さんの解説を引用します。
ブラウニング(1812-1889)はイギリスのヴィクトリア朝(1837-1901)の詩人です。その詩の一節をつぶやいて物語が終わるところなど、いかにも詩の朗読が得意なアンらしいと言えるでしょう。ちなみに『赤毛のアン』の本の扉に書かれた題辞(モットー)もブラウニングの詩の引用です。作者のモンゴメリ(1874-1942)は明らかにそう計画して書いているわけで、ブラウニングが好きだったようです。参考までに、上田敏の『海潮音』の訳詩と原文は以下です。
実は、この詩の最後の1行が『華氏451度』にも出てきます。本に目覚めた主人公のモンターグは、隠れた本の愛好家であるフェーバー教授と知り合いになり、これから進むべき道についてのアドバイスを受けます。そのあたりの教授の発言の一節ですが、伊藤氏の訳文とブラッドベリの原文は以下です。アンダーラインは原文にはありません。
この最後の一文は、ブラウニングの「All's right with the world !」を踏まえ、それを否定形にしたものですね。『華氏451度』は、ブラウニングの詩や『赤毛のアン』の世界とは全くの対極にある "ディストピア"(アンチ・ユートピア)を描いた小説です。だからこの引用が意味を持つ。新訳ではそれが明瞭になる形で翻訳されています。しかも、松本さんのような原文のストレートな訳( "この世はすべてよし" )ではなく、上田敏の訳( "すべて世は事も無し" )をそのまま持ってきている。この方がよく知られているということだと思います。
聖書
英米文学の「伝統」に従って、聖書からの引用もいろいろ出てくるですが、その例として『華氏451度』のエンディングの部分の新訳を掲げます。
最初の3つの引用は、旧約聖書の「伝道の書」(コヘレトの言葉)の第3章 第1節、第3節、第7節からです。また最後の長めの引用は、新約聖書の「ヨハネの黙示録」の第22章 第2節からです。第22章は、最後の審判のあとの「新しい天と新しい地(=新天新地)」を描く部分であり、黙示録の最終章にあたります。訳者の伊藤氏はここで、文語訳("大正訳")の日本語聖書の文章をもってきています。引用であることを明確にするためでしょう。
『華氏451度』の原書(Del Ray Book版)をみると、旧約聖書・伝道の書の部分には「引用のしるし」はついていません。従って、聖書を知らない人にとって引用だとは分からない。一方、新約聖書・黙示録の部分はイタリック体になっていて、引用だということが明確にされています。『華氏451度』の旧訳では、この黙示録の部分も平文と同じようなスタイルで訳されていたので、我々日本の読者には聖書の引用だとは分かりづらいものでした。
しかし「引用のしるし」があるかないかにかかわらず、クリスチャンで聖書に親しんだ人なら、ないしは英米人なら常識として聖書からの引用だとパッと分かるのでしょう。さらに、最後の最後の引用が新約聖書・黙示録の「新天新地」ということで、作者が『華氏451度』のエンディングに込めた意味が一目瞭然なのだと思います。
そもそも作家が書物からの引用で小説を終えるのは、熟考した結果のはずです。それは小説のテーマや作家の思想にとって重要であり、「重い」ものであることが容易に想像できます。さきほど例示した『赤毛のアン』の最後の引用である、
について訳者の松本さんは「神への信頼と未来への希望に満ちて『赤毛のアン』は幕を閉じる」と書いていました。それに習うとすると『華氏451度』の最後の引用である、
については、「神への信頼と、本が禁止された "ディストピア" が崩壊して新しい世界がくることの希望とともに『華氏451度』は幕を閉じる」と言えるでしょう。新訳ではそれがクリアに分かるのでした。
さらに想像を広げると、ここで「ヨハネの黙示録」を持ち出すのには意図があるのかもしれません。黙示録は紀元1世紀末のローマ帝国によるユダヤ人に対する圧制とキリスト教徒弾圧の時代に書かれた文書と言われています。そこでは「弾圧者への憎悪」と「キリスト教徒への励まし」がないまぜになっているように見える。それはとりもなおさず『華氏451度』の世界における「本を愛読・伝承する人たち」と、その人たちを「弾圧する体制」との関係に思えます。ブラッドベリがそういう構図を意識して最後に黙示録の文章を持ってきたのはありうることだと思いました。
ガリバー旅行記
英国文学からの引用の一つの例として、スウィフトの『ガリバー旅行記』をあげてみます。主人公のモンターグは、密かに本を所持していることを妻のミルドレッドに告白し、いっしょに読もうと誘います。
モンターグがとりあげた本は、スウィフトの『ガリバー旅行記』です。『ガリバー旅行記』の第1篇「リリパット国渡航記」は、リリパットの海岸に打ち上げられて気絶したガリヴァーが、小人の軍隊によって縛られるという出だしです。インド洋の島国・リリパットは、海峡を挟んだ隣の島国のブレフスキュと長年に渡って交戦状態にあります。その戦争の原因は「ゆで卵の殻の正しい剥き方は、大きな端から剥くか、小さな端(尖った方)から剥くかについての意見の違い」に由来します。
風刺文学である『ガリバー旅行記』がここで何を風刺しているのかというと、リリパット国 = 英国、ブレフスキュ国 = フランス、卵 = キリスト教、卵の大きな端 = カトリック、卵の小さな端 = 英国国教会・プロテスタント、というのが一般的な解釈です。作者のジョナサン・スウィフト自身が聖職者だったというのが、この風刺の重要なポイントです。
ブラッドベリは『華氏451度』で、なぜここを引用したのでしょうか。モンターグがまず読む本として、世界文学史上の最も有名な作品の一つから、その比較的よく知られた部分を引用したということでしょうか。
そうかもしれませんが、さらに理由があるように思えます。それは『ガリバー旅行記』の「卵」のくだりを読むと分かります。以下は岩波文庫からの引用です。原文に段落はありません。
2つ目のアンダーラインのところ、つまり「本の禁止」がポイントですね。だからブラッドベリはこの部分を引用した。『ガリバー旅行記』に親しんだ人なら「本の禁止」を思い出すかも知れません。また作者は読者に「わかりますか」という、ささやかな挑戦をしたのかも知れません。
さらに連想することがあります。『ガリバー旅行記』における「卵の割り方に起因する対立」とは「新教と旧教の対立」を揶揄したものと解釈されています。「卵を割るときには小さな端から割るべし。大きな端から割る者は厳罰」という勅令を出した「皇帝」とは、カトリックに対抗して英国国教会を設立したヘンリー8世のことだと考えられているのです。
そこで思い出すのは、英国史における「新教と旧教の対立」を背景にした別の引用が『華氏451度』にあることです。No.51「華氏451度(1)焚書」でも紹介したくだりですが、新訳によってもう一度引用します。「隣人が本を所持している」という密告をうけて「昇火士」たちが老女の家を急襲する場面です。
16世紀の英国において、メアリー1世(ヘンリー8世の娘で、カトリック教徒)はプロテスタントを弾圧し、延べ300人以上を処刑しました。このプロテスタントの中に、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimar)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という、オックスフォードで同時に処刑された2人の主教がいました。老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉です。『華氏451度』の中では、隊長のベイティーもそう解説しています(No.51「華氏451度(1)焚書」参照)。
『ガリバー旅行記』を含めたこのあたりの引用は、英国史、ないしは英文学に関するブラッドベリの強いこだわりが感じられるところです。
ベイティーの挑発
『華氏451度』のストーリーにおいて「昇火士」の隊長のベイティーは、部下のモンターグが密かに本を隠し持ち、読んでいることに気づいています。任務から帰還し、署の隊員仲間でカードゲームをする場面がありますが、そこでベイティーは、本からの引用を「満載」した言葉をモンターグに投げつけ、モンターグを挑発します。『華氏451度』において文芸作品からの引用が最も多く出てくるのはこの場面なのですが、その一部を掲げてみます。①~⑤の数字は原文にはありません。
伊藤氏の注釈によると①~⑤の出典は以下のとおりです。
多数の文芸作品を引用したベイティーの「挑発」は、文庫本で3ページ以上に渡って長々と続きます。
新訳は、引用が引用だとわかるように《》つきで翻訳されています。ブラッドベリの原文でも引用符(')がつけられている。ここで非常に明瞭になることは、本を焼き払う責任者であるベイティーが、実は本の世界に精通していることです。これはどういうことかというと、No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、
のどちらかだと思います。常識的には後者でしょうが、前者のような解釈も捨てがたいと思います。とにかく、次々と出てくる英国文学からの引用を引用だと明確にわかるようにした新訳は、作家の意図をより明確にしているようです。
イギリス文学
「英国文学」と書きましたが、ブラッドベリの引用は聖書を除いてはほとんどがイギリスの文芸作品であり(自国の)アメリカ文学は(少なくとも新訳で伊藤氏が指摘している限りでは)ありません。引用を一覧すると以下の通りです。()内の数字は作家の生年です。
(英国)
(フランス)
(スペイン)
No.51「華氏451度(1)焚書」にも書いたように『華氏451度』には禁止されている本の作者名として、ホイットマン、ソロー、フォークナーなどのアメリカ人作家の名前も出てくるのですが、作品の一部を引用している作家は、そのほとんどが英国人です。
『赤毛のアン』がそうであったように、聖書とシェイクスピアからの引用は一般的ですが、それ以外の引用は作家の個性によります。『赤毛のアン』にはイギリス文学からの引用が多いのですが、アメリカ人作家からのも多々ある(作者のモンゴメリはカナダ人)。そういった意味で『華氏451度』引用はブラッドベリの嗜好を表していると考えられます。また、特に16世紀から19世紀の作品が取り上げられていることからすると、書物の世界における「古典」の重要性、ないしは人類の「知的財産」としの本の重要性を言いたかったのかもしれません。
『華氏451度』の意味 : 反知性主義の世界
翻訳に関する話題はこれぐらいにして、以下は『華氏451度』の感想です。新訳が出たのを機会に改めて『華氏451度』を読み直したのですが、この本の現代的な意義を強く感じました。
No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、『華氏451度』を「本が禁止された世界」だと考えるのは表面的です。『華氏451度』は「本を読むような人が迫害される世界」を描いたものです。もちろん、ここで言う「本」とは知的財産としての本であって、(ブラッドベリの考える)消費財としての本(たとえばダイジェスト本とか漫画)ではありません。
では「本を読むような人」とはどういう人かと言うと、本によって「知識の獲得」や「教養の深化」を目指す人でしょう。また自分のできない体験を疑似的に経験したり、さまざまな人に「会える」のも読書の大きな効用です。しかし「困ったことに」、本の中の言説には応々にして相反することが書いてあります。それは小説の中で、隊長のベイティーが何度か強調していることで、「ベイティーの挑発」として上に引用した箇所にもありました。引用はしませんでしたが、彼は「知識人」を「相反する思想や理論で人を不幸にしたがる連中」と呼んでいます。
しかし考えてみると「相反する」のは当然なのです。一般的に言って、社会における重要な問題、人生の重要な問題には複数の回答案があり、しかもそれらが相反していることが多いわけです。答えは一つではありません。重要になればなるほどそうです。それはビジネスにおける重要課題でも同様です。我々は自ら考え、その中から最良と思うものを選んで決断し、行動に移す。これはある意味では悩ましく、苦しいことです。
そのため、多様なモノの見方や異質な考え方触れることを放棄したり、多様な考えを勘案しつつ「考える」ことをやめてしまって「指導者」の言うがままに行動するとか、同質のグループで凝り固まって「社会的孤立」に向かう人たちが出てくる。
しかしそれでは社会状況や自身をとりまく環境の変化についていけないし、結局のところ人間社会に不幸をもたらす要因になるのだと思います。変化についていくためには、自らが変わらないといけないし、変わるきっかけは「知ること」しかありません。
『華氏451度』が描くのは「考えない」人たちが大量に生み出された世界です。ここで重要なのは、それが上からの押しつけではなく、大衆自らがそういう世界を選びとったということでしょう。小説ではそう説明してあります(No.52「華氏451度(2)核心」参照)。『華氏451度』は究極の「反知性主義の世界」を、その「作られ方」を含めて描いたと言えるでしょう。ここに『華氏451度』の今日的な意味があると思います。
ちょっと思い出すのが、前々回の No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介した、内田樹氏の文章です。内田さんは『街場の共同体論』で次のように警告しているのでした。
内田さんの論は、引用の最後にあるように、反知性主義が階層下位を生みだし、階層下位を固定するように働いているということであり、階層二極化との関連性を述べています。『華氏451度』はそれが究極まで行った "ディストピア" を描いたとも言えるでしょう。
小説の中における隊長のベイティーは本の焼却の責任者である一方で(善か悪かは別にして)極めて知的な人間であり、本の世界に精通しています。モンターグの妻のミルドレッドは「壁テレビ」に浸りきり、上からの指示どおりに動く人間として描かれています。『華氏451度』の世界においては彼女のような人がほとんどです。その間に立ったモンターグは「知の世界に目覚めた普通の人」です。こういう人物配置によって、戯画のような「究極の世界」が描き出されています。
ブラッドベリが1950年代の初頭に行った「問題提起」は、明らかにテレビに代表されるメディアの発達に対する危機感からきています。まるで21世紀の現代を予見したかのような「壁テレビ」がその象徴です。しかしそういう「メディアの問題」にとどまらず、『華氏451度』は人間の本質、ないしは「弱さ」の深いところを突いています。その問題提起は、60年以上たった現代でも全く色褪せていないと感じました。
| ・ | No.51 - 華氏451度(1)焚書〔2012.3.24〕 | ||
| ・ | No.52 - 華氏451度(2)核心〔2012.4.06〕 |
の二つです。
日付から推測できるかもしれませんが、作者のレイ・ブラッドベリは、記事を書いた直後(2012.6.5)に92歳で亡くなられました。その時も何か書こうと思ったのですが、適当なテーマが見つけられませんでした。
そうこうするうち、2014年に小説の新訳が出版されました。『華氏451度〔新訳版〕』(伊藤典夫・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房。2014.6.25)です。今回はこの新訳の感想を、ブラッドベリの追悼の意味も込めて書きたいと思います。『華氏451度』のあらすじや、そこで語られていることについては、No.51、No.52 を参照ください。
| 以下、従来の『華氏451度』(宇野利泰・訳。ハヤカワ文庫SF。早川書房)を「旧訳」と呼ぶことにします。 |
マルクス・アウレリウス
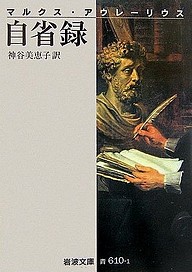
| |||
|
マルクス・アウレーリウス 「自省録」(岩波文庫) | |||
新訳ではちゃんとマルクス・アウレリウスとなっていて安心しました。訳者の伊藤氏は当たり前だと言うでしょうが・・・・・・。
人名が出たついでの余談ですが、新訳では主人公・モンターグの上司(隊長)の Beatty を、英語の発音に近い「ベイティー」と表記しています(旧訳ではビーティ)。
ハリウッド俳優に、ウォーレン・ベイティ(Warren Beatty)がいます。彼と、姉のシャーリー・マクレーンの本名は、
Henry Warren Beaty
Shirley MacLean Beaty
です。日本でも昔はウォーレン・ビューティと表記されていましたが、本人の要望で発音に近いベイティとなったようです。本名から t を一つ増やして芸名にしているのは、できるだけ「ビーティ」などと呼ばれることを避けるためだそうです(これはWikipediaの情報)。日本語もそうですが、英語の固有名詞の発音はスペルからは判読しにくいものがあります。しかし固有名詞の翻訳は原則として「原音主義」をとるべきであり、これも伊藤氏の(ささやかな)修正です。
ファイアーマン
主人公のモンターグの職業はファイアーマン(fireman)ですが、言うまでもなく英語で消防士のことです(最近は女性消防士も含めて firefighter と呼ぶのが米国のトレンドのようです)。旧訳では「焚書官」となっていましたが、新訳では「消火」にひっかけた「昇火士」という造語をあてています。これを含めて「火」に関する一連の訳語は、
| 原書 | 訳語 | 意味 | ||||
| fireman | 昇火士 | 消防士 | ||||
| firehouse | 昇火署 | 消防署 | ||||
| (fire) engine | 昇火車 | 消防車 |
としてあります。fireは名詞の「火」であり、動詞としては「火をつける」意味です。そのことからすると、現代英語の fireman は「火を消す人」という通常の意味の下に「火をつける人」の意味を内在していると考えられます。事実、蒸気ボイラーなどの火を焚く「缶焚き」の意味でも使われる。新訳は漢字を活用して日本語訳としてのダブル・ミーニングを狙った工夫でしょう。
文芸作品からの引用
ここからが、いわば本題です。新訳の大きな特徴は『華氏451度』に含まれる文芸作品からの引用を、引用だと分かるように翻訳し、かつ巻末に注釈をつけたことです。
英米の小説で、文章の中に文芸作品からの語句を引用することはよくあるわけです。特に、聖書とシェイクスピアを知らないと翻訳はできない、とさえ言われるぐらいです。引用はとりたてて珍しくはありません。
しかし『華氏451度』は、ほかでもない「本」をテーマにした小説です。「本」をテーマにした小説で「本」からの引用がどういう風に使われているのか、それは作者が小説に込めた思いやテーマに直結する可能性があります。「引用を引用と分かるように翻訳する」ことは、とりわけ『華氏451度』では重要だと考えられる。その意味で、伊藤氏の新訳は意義が深いと思いました。
引用で思い出すのが『赤毛のアン』です。No.77「赤毛のアン(1)文学」、No.78「赤毛のアン(2)魅力」で書いたように、あの本には英米文学と聖書からの引用が溢れています。そして実は『赤毛のアン』と『華氏451度』に共通の引用があるのです。まずそのことから始めます。
『赤毛のアン』を振り返る
『赤毛のアン』(1908)には英米の文学作品と聖書からの引用が多数あるのですが、中でも最も有名なのは物語の一番最後のものでしょう。『赤毛のアン』の最終章である第38章「道の曲がり角」の最後の場面は、グリーン・ゲイブルズの窓辺にたたずむアンの記述です。
|
物語の最後の最後でアンがつぶやく言葉が、文芸作品からの引用です。翻訳者の松本さんの解説を引用します。
|
ブラウニング(1812-1889)はイギリスのヴィクトリア朝(1837-1901)の詩人です。その詩の一節をつぶやいて物語が終わるところなど、いかにも詩の朗読が得意なアンらしいと言えるでしょう。ちなみに『赤毛のアン』の本の扉に書かれた題辞(モットー)もブラウニングの詩の引用です。作者のモンゴメリ(1874-1942)は明らかにそう計画して書いているわけで、ブラウニングが好きだったようです。参考までに、上田敏の『海潮音』の訳詩と原文は以下です。
|
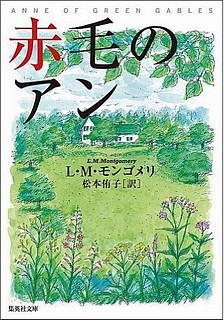
| |||
実は、この詩の最後の1行が『華氏451度』にも出てきます。本に目覚めた主人公のモンターグは、隠れた本の愛好家であるフェーバー教授と知り合いになり、これから進むべき道についてのアドバイスを受けます。そのあたりの教授の発言の一節ですが、伊藤氏の訳文とブラッドベリの原文は以下です。アンダーラインは原文にはありません。
|
この最後の一文は、ブラウニングの「All's right with the world !」を踏まえ、それを否定形にしたものですね。『華氏451度』は、ブラウニングの詩や『赤毛のアン』の世界とは全くの対極にある "ディストピア"(アンチ・ユートピア)を描いた小説です。だからこの引用が意味を持つ。新訳ではそれが明瞭になる形で翻訳されています。しかも、松本さんのような原文のストレートな訳( "この世はすべてよし" )ではなく、上田敏の訳( "すべて世は事も無し" )をそのまま持ってきている。この方がよく知られているということだと思います。
聖書
英米文学の「伝統」に従って、聖書からの引用もいろいろ出てくるですが、その例として『華氏451度』のエンディングの部分の新訳を掲げます。
|
最初の3つの引用は、旧約聖書の「伝道の書」(コヘレトの言葉)の第3章 第1節、第3節、第7節からです。また最後の長めの引用は、新約聖書の「ヨハネの黙示録」の第22章 第2節からです。第22章は、最後の審判のあとの「新しい天と新しい地(=新天新地)」を描く部分であり、黙示録の最終章にあたります。訳者の伊藤氏はここで、文語訳("大正訳")の日本語聖書の文章をもってきています。引用であることを明確にするためでしょう。
『華氏451度』の原書(Del Ray Book版)をみると、旧約聖書・伝道の書の部分には「引用のしるし」はついていません。従って、聖書を知らない人にとって引用だとは分からない。一方、新約聖書・黙示録の部分はイタリック体になっていて、引用だということが明確にされています。『華氏451度』の旧訳では、この黙示録の部分も平文と同じようなスタイルで訳されていたので、我々日本の読者には聖書の引用だとは分かりづらいものでした。
しかし「引用のしるし」があるかないかにかかわらず、クリスチャンで聖書に親しんだ人なら、ないしは英米人なら常識として聖書からの引用だとパッと分かるのでしょう。さらに、最後の最後の引用が新約聖書・黙示録の「新天新地」ということで、作者が『華氏451度』のエンディングに込めた意味が一目瞭然なのだと思います。
そもそも作家が書物からの引用で小説を終えるのは、熟考した結果のはずです。それは小説のテーマや作家の思想にとって重要であり、「重い」ものであることが容易に想像できます。さきほど例示した『赤毛のアン』の最後の引用である、
|
について訳者の松本さんは「神への信頼と未来への希望に満ちて『赤毛のアン』は幕を閉じる」と書いていました。それに習うとすると『華氏451度』の最後の引用である、
|
については、「神への信頼と、本が禁止された "ディストピア" が崩壊して新しい世界がくることの希望とともに『華氏451度』は幕を閉じる」と言えるでしょう。新訳ではそれがクリアに分かるのでした。
さらに想像を広げると、ここで「ヨハネの黙示録」を持ち出すのには意図があるのかもしれません。黙示録は紀元1世紀末のローマ帝国によるユダヤ人に対する圧制とキリスト教徒弾圧の時代に書かれた文書と言われています。そこでは「弾圧者への憎悪」と「キリスト教徒への励まし」がないまぜになっているように見える。それはとりもなおさず『華氏451度』の世界における「本を愛読・伝承する人たち」と、その人たちを「弾圧する体制」との関係に思えます。ブラッドベリがそういう構図を意識して最後に黙示録の文章を持ってきたのはありうることだと思いました。
ガリバー旅行記
英国文学からの引用の一つの例として、スウィフトの『ガリバー旅行記』をあげてみます。主人公のモンターグは、密かに本を所持していることを妻のミルドレッドに告白し、いっしょに読もうと誘います。
|
モンターグがとりあげた本は、スウィフトの『ガリバー旅行記』です。『ガリバー旅行記』の第1篇「リリパット国渡航記」は、リリパットの海岸に打ち上げられて気絶したガリヴァーが、小人の軍隊によって縛られるという出だしです。インド洋の島国・リリパットは、海峡を挟んだ隣の島国のブレフスキュと長年に渡って交戦状態にあります。その戦争の原因は「ゆで卵の殻の正しい剥き方は、大きな端から剥くか、小さな端(尖った方)から剥くかについての意見の違い」に由来します。
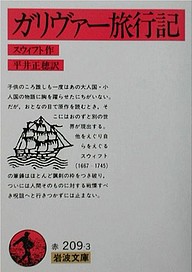
| |||
ブラッドベリは『華氏451度』で、なぜここを引用したのでしょうか。モンターグがまず読む本として、世界文学史上の最も有名な作品の一つから、その比較的よく知られた部分を引用したということでしょうか。
そうかもしれませんが、さらに理由があるように思えます。それは『ガリバー旅行記』の「卵」のくだりを読むと分かります。以下は岩波文庫からの引用です。原文に段落はありません。
|
2つ目のアンダーラインのところ、つまり「本の禁止」がポイントですね。だからブラッドベリはこの部分を引用した。『ガリバー旅行記』に親しんだ人なら「本の禁止」を思い出すかも知れません。また作者は読者に「わかりますか」という、ささやかな挑戦をしたのかも知れません。
さらに連想することがあります。『ガリバー旅行記』における「卵の割り方に起因する対立」とは「新教と旧教の対立」を揶揄したものと解釈されています。「卵を割るときには小さな端から割るべし。大きな端から割る者は厳罰」という勅令を出した「皇帝」とは、カトリックに対抗して英国国教会を設立したヘンリー8世のことだと考えられているのです。
そこで思い出すのは、英国史における「新教と旧教の対立」を背景にした別の引用が『華氏451度』にあることです。No.51「華氏451度(1)焚書」でも紹介したくだりですが、新訳によってもう一度引用します。「隣人が本を所持している」という密告をうけて「昇火士」たちが老女の家を急襲する場面です。
|
16世紀の英国において、メアリー1世(ヘンリー8世の娘で、カトリック教徒)はプロテスタントを弾圧し、延べ300人以上を処刑しました。このプロテスタントの中に、ヒュー・ラティマー(Hugh Latimar)とニコラス・リドリー(Nicholas Ridley)という、オックスフォードで同時に処刑された2人の主教がいました。老女が発した言葉は、ヒュー・ラティマーの最期の言葉です。『華氏451度』の中では、隊長のベイティーもそう解説しています(No.51「華氏451度(1)焚書」参照)。
『ガリバー旅行記』を含めたこのあたりの引用は、英国史、ないしは英文学に関するブラッドベリの強いこだわりが感じられるところです。
ベイティーの挑発
『華氏451度』のストーリーにおいて「昇火士」の隊長のベイティーは、部下のモンターグが密かに本を隠し持ち、読んでいることに気づいています。任務から帰還し、署の隊員仲間でカードゲームをする場面がありますが、そこでベイティーは、本からの引用を「満載」した言葉をモンターグに投げつけ、モンターグを挑発します。『華氏451度』において文芸作品からの引用が最も多く出てくるのはこの場面なのですが、その一部を掲げてみます。①~⑤の数字は原文にはありません。
|
伊藤氏の注釈によると①~⑤の出典は以下のとおりです。
| ① | 旧約聖書『イザヤ書』53章 6節 の「われわれはみな羊のように迷って、おのおの自分の道に向かって行った。」を踏まえたもの。 | ||
| ② | シェイクスピア『尺には尺を』第5幕 第1場。修道女見習いのイザベラのせりふ。 | ||
| ③ | サー・フィリップ・シドニー(1558-86)の『アーケイディア』(1593)より。シドニーは詩人で廷臣、軍人。エリザベス朝の英国において最も傑出した人物のひとりといわれる。 | ||
| ④ | サー・フィリップ・シドニー『詩の弁護』(1583頃)より。 | ||
| ⑤ | 英国の詩人、アレクサンダー・ポープ(1688-1744)の『批評論』(1711)より |
多数の文芸作品を引用したベイティーの「挑発」は、文庫本で3ページ以上に渡って長々と続きます。
新訳は、引用が引用だとわかるように《》つきで翻訳されています。ブラッドベリの原文でも引用符(')がつけられている。ここで非常に明瞭になることは、本を焼き払う責任者であるベイティーが、実は本の世界に精通していることです。これはどういうことかというと、No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、
| ・ | 『華氏451度』の世界においては、大衆は本から遮断されているが、指導者層は実は本の世界に精通している(それが許されている)。 | ||
| ・ | ベイティーは若いころは(隠れた)読書家であったが、「転向」して本を焼き払う側に回った。 |
のどちらかだと思います。常識的には後者でしょうが、前者のような解釈も捨てがたいと思います。とにかく、次々と出てくる英国文学からの引用を引用だと明確にわかるようにした新訳は、作家の意図をより明確にしているようです。
イギリス文学
「英国文学」と書きましたが、ブラッドベリの引用は聖書を除いてはほとんどがイギリスの文芸作品であり(自国の)アメリカ文学は(少なくとも新訳で伊藤氏が指摘している限りでは)ありません。引用を一覧すると以下の通りです。()内の数字は作家の生年です。
(英国)
| ◆ | ジョン・フォックス(1516) 作品中での老女の言葉「男らしく・・・・・・」の出典となった本を書いた人物。No.51「華氏451度(1)焚書」参照。 | ||
| ◆ | フィリップ・シドニー(1558) | ||
| ◆ | フランシス・ベーコン(1561) | ||
| ◆ | ウィリアム・シェイクスピア(1564) 引用作品は『尺には尺を』『ヴェニスの商人』『テンペスト』『ジュリアス・シーザー』 | ||
| ◆ | ジョン・ダン(1572) 詩人、作家。形而上詩の先駆者。 | ||
| ◆ | ベン・ジョンソン(1572) 劇作家、詩人。シェイクスピアの追悼詩が有名。 | ||
| ◆ | トマス・デッカー(1572頃) 劇作家。 | ||
| ◆ | ロバート・バートン(1577) 神学者、作家。 | ||
| ◆ | ジョナサン・スウィフト(1667) | ||
| ◆ | アレクサンダー・ポープ(1688) 詩人 | ||
| ◆ | サミュエル・ジョンソン(1709) 英語辞典の編纂で著名な文学者。 | ||
| ◆ | ジェイムズ・ボズウェル(1740) 法律家、作家。師匠のサミュエル・ジョンソンの伝記を書いた。 | ||
| ◆ | ロバート・ブラウニング(1812) 詩人 | ||
| ◆ | マシュー・アーノルド(1822) 詩人、文芸評論家。『ドーバー海岸』という詩の一節をモンターグが朗読する場面がある。No.51「華氏451度(1)焚書」参照。 | ||
| ◆ | アレクサンダー・スミス(1829) スコットランドのレース製造業者、詩人、エッセイスト |
(フランス)
| ◆ | ポール・ヴァレリー(1871) |
(スペイン)
| ◆ | ファン・ラモン・ヒメネス(1881) 詩人。ノーベル文学賞受賞。『華氏451度』の題辞はヒメネスから採られている。 |
No.51「華氏451度(1)焚書」にも書いたように『華氏451度』には禁止されている本の作者名として、ホイットマン、ソロー、フォークナーなどのアメリカ人作家の名前も出てくるのですが、作品の一部を引用している作家は、そのほとんどが英国人です。
『赤毛のアン』がそうであったように、聖書とシェイクスピアからの引用は一般的ですが、それ以外の引用は作家の個性によります。『赤毛のアン』にはイギリス文学からの引用が多いのですが、アメリカ人作家からのも多々ある(作者のモンゴメリはカナダ人)。そういった意味で『華氏451度』引用はブラッドベリの嗜好を表していると考えられます。また、特に16世紀から19世紀の作品が取り上げられていることからすると、書物の世界における「古典」の重要性、ないしは人類の「知的財産」としの本の重要性を言いたかったのかもしれません。
『華氏451度』の意味 : 反知性主義の世界
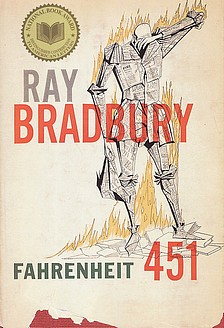
| |||
|
Ray Bradbury Fahrenheit 451 (Del Ray Book, 1996) 1953年に最初に出版されたハードカヴァーの表紙を採用している
| |||
No.52「華氏451度(2)核心」にも書いたのですが、『華氏451度』を「本が禁止された世界」だと考えるのは表面的です。『華氏451度』は「本を読むような人が迫害される世界」を描いたものです。もちろん、ここで言う「本」とは知的財産としての本であって、(ブラッドベリの考える)消費財としての本(たとえばダイジェスト本とか漫画)ではありません。
では「本を読むような人」とはどういう人かと言うと、本によって「知識の獲得」や「教養の深化」を目指す人でしょう。また自分のできない体験を疑似的に経験したり、さまざまな人に「会える」のも読書の大きな効用です。しかし「困ったことに」、本の中の言説には応々にして相反することが書いてあります。それは小説の中で、隊長のベイティーが何度か強調していることで、「ベイティーの挑発」として上に引用した箇所にもありました。引用はしませんでしたが、彼は「知識人」を「相反する思想や理論で人を不幸にしたがる連中」と呼んでいます。
しかし考えてみると「相反する」のは当然なのです。一般的に言って、社会における重要な問題、人生の重要な問題には複数の回答案があり、しかもそれらが相反していることが多いわけです。答えは一つではありません。重要になればなるほどそうです。それはビジネスにおける重要課題でも同様です。我々は自ら考え、その中から最良と思うものを選んで決断し、行動に移す。これはある意味では悩ましく、苦しいことです。
そのため、多様なモノの見方や異質な考え方触れることを放棄したり、多様な考えを勘案しつつ「考える」ことをやめてしまって「指導者」の言うがままに行動するとか、同質のグループで凝り固まって「社会的孤立」に向かう人たちが出てくる。
しかしそれでは社会状況や自身をとりまく環境の変化についていけないし、結局のところ人間社会に不幸をもたらす要因になるのだと思います。変化についていくためには、自らが変わらないといけないし、変わるきっかけは「知ること」しかありません。
『華氏451度』が描くのは「考えない」人たちが大量に生み出された世界です。ここで重要なのは、それが上からの押しつけではなく、大衆自らがそういう世界を選びとったということでしょう。小説ではそう説明してあります(No.52「華氏451度(2)核心」参照)。『華氏451度』は究極の「反知性主義の世界」を、その「作られ方」を含めて描いたと言えるでしょう。ここに『華氏451度』の今日的な意味があると思います。
ちょっと思い出すのが、前々回の No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」で紹介した、内田樹氏の文章です。内田さんは『街場の共同体論』で次のように警告しているのでした。
|
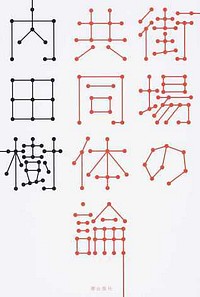 |
小説の中における隊長のベイティーは本の焼却の責任者である一方で(善か悪かは別にして)極めて知的な人間であり、本の世界に精通しています。モンターグの妻のミルドレッドは「壁テレビ」に浸りきり、上からの指示どおりに動く人間として描かれています。『華氏451度』の世界においては彼女のような人がほとんどです。その間に立ったモンターグは「知の世界に目覚めた普通の人」です。こういう人物配置によって、戯画のような「究極の世界」が描き出されています。
ブラッドベリが1950年代の初頭に行った「問題提起」は、明らかにテレビに代表されるメディアの発達に対する危機感からきています。まるで21世紀の現代を予見したかのような「壁テレビ」がその象徴です。しかしそういう「メディアの問題」にとどまらず、『華氏451度』は人間の本質、ないしは「弱さ」の深いところを突いています。その問題提起は、60年以上たった現代でも全く色褪せていないと感じました。
2014-11-29 11:41
nice!(0)
トラックバック(0)