No.130 - 中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録 [音楽]
No.64~68 は「中島みゆきの詩」と題して、中島みゆきさんが35年に渡って書いた詩(の一部。約70編)を振り返りました。その中の No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」では、現代社会に対するメッセージと考えられる詩や、社会と個人の関わりについての詩を取り上げました。今回はその続きです。
最近、内田樹氏の「街場の共同体論」(潮出版社 2014) を読んでいたときに、中島さんの「社会に関わった詩」を強く思い出す文章があったので、そのことを書きます。
を読んでいたときに、中島さんの「社会に関わった詩」を強く思い出す文章があったので、そのことを書きます。
内田 樹・著「街場の共同体論」は、家族論、地域共同体論、教育論、コミュミケーション論、師弟論などの「人と人との結びつき」のありかたについて、あれこれと論じたものです。主張の多くは内田さんの今までのブログや著作で述べられていることなのですが、「共同体 = 人と人との結びつき」に絞って概観されていて、その意味ではよくまとまった本だと思いました。この中に「階層社会」について論じた部分があります。
階層社会の本質
「階層社会」という言葉をどうとらえるかは難しいのですが、ここではごくアバウトに、
という風に考えておきます。人の格差を測定する"ものさし"とは、その人の「年収」や、もっと曖昧には「社会的地位」であり、固定的とは、階層上位のものは(あるいは集団は)ずっと上位にとどまり、それは世代を越えて続く傾向にあることを言います。この階層社会の特徴、ないしは本質を、内田さんは
と、とらえています。でないと階層社会はできあがらないと・・・・・・。格差の"ものさし"である年収で言うと、誰だって年収は多い方がいいわけです。なぜ「自らの意志で階層下位にとどまろうとする」のか。その重要な要因は、
というのが、内田さんの見立てです。そのメッセージは時とともに変わる。それは、あまり長く続けているとメッセージの欺瞞性がバレてしまうからです。一時「自分探し」とか「自分らしさの探求」とか「自己実現」が大々的に宣伝されたことがありました。しかし、さすがにそれではまずいと多くの人が気づいた。趣味の世界の話ならまだしも、「自分探し」などという理由で転職をすると、ごく一部の人はそれで成功するかもしれないが、多くの人はそうではなく、結局「転職産業」と「人材派遣会社」と「低賃金かつ解雇しやすい労働者を確保したい企業」の利益になるだけなのですね。「自分探し」は、大多数の人にとっては「自滅的イデオロギー」です。
しかし「階層下位のものが階層下位にとどまるように仕向けるメッセージ」は、手を変え品を変えて継続的に続いています。その例として内田さんがあげている代表格が、
です。反知性主義について、内田さんは次のように書いています。
確かに、自分の興味の範囲だけで生きていては上位には行けません。「自分はものごとを知らない、だから知りたい」という態度で人に教えを請い、また勉強もする。そして人的ネットワークを広げ、自分の興味の幅も広げて、自身の能力を磨く・・・・・・。会社を考えてみても、新入社員の時からその後のキャリア・アップまで、そういうタイプの人間の査定が高くなり上位ポジションへと引き上げられる(=年収が多くなる)のは当然です。
なかなか中島みゆきさんの詩との関係にまで行かないのですが、次の「クレーマー」ついての内田さんの文章が、それと関係しています。
クレーマー的人間
「階層社会では、階層下位のものが、自らの意志で階層下位にとどまろうとする」例の一つとして内田さんが指摘しているのが、クレーマー的人間です。そして、クレーマーの増加を助長したのはメディアの責任だと、内田さんは言っています。
内田さんが指摘するメディアの責任とは、
ということです。確かに、大きな事件や事故が起きたときにテレビの情報番組を見ていると「レポーター」や「コメンテーター」と称する人たちが出てきて、その事件・事故の「責任者」を「一方的」に宣告し、いかにも「被害者に成り代わってという態度で」責任を追求する(強く言えば、糾弾する)ことがよくあります。宣告された「責任者」とは、公的な職についている人だったり(警察、自治体の担当官、学校の先生、・・・・・・)、企業の経営層だったりです。こういう報道姿勢がクレーマー的人間の増長させている一つの要因でしょう。内田さんは一つの報道をあげています。
内田さんが言う「暴漢が小学校に進入して、小学生を襲った事件(その結果、二人の先生が死傷)」とは何でしょうか。まず思い出すのは、2001年、大阪教育大学附属池田小学校にテロリストが進入し、小学生を無差別に刃物で殺傷した前代未聞の事件です(=附属池田小事件)。この事件では児童8名が殺され、児童13名と教員2名が重軽傷を負いました。わずか5~10分間の犯行だったと言います。
また2005年には、大阪の寝屋川市立中央小学校に暴漢(卒業生の少年)が侵入し、一人の教師の方を殺害し、教師と栄養士2人に重傷を負わせる事件が発生しました(=寝屋川中央小事件)。この時には授業中の小学生は襲われませんでした。犯人の在校当時の教師に対する恨み(死傷した教師は無関係)が「動機」だったようです。
どちらかの事件だと思いますが、附属池田小事件だとすると「教師が死亡」というのは違っているし、寝屋川中央小事件だとすると「小学生を襲う」というところが違っています。内田さんも混同したのかもしれません(ただし、私の記憶にない別の事件の可能性もある)。
しかしそれは些細なことであって、論旨には影響しません。内田さんの言いたいことは、こういう事件でメディアは何を報道すべきかということです。仮に附属池田小事件の例だとしても、重傷を負った教師は死ぬかもしれなかったわけだし、凶器を振り回すテロリストを素手で取り押さえた教師たちも一歩間違えば死んでもおかしくはなかった。前代未聞の、しかもわずか10分以内の無差別テロに対して、附属池田小の教師の方々は混乱状況の中で精一杯のことをしたのではないでしょうか。また、寝屋川中央小事件だとすると、実際に教師の方が包丁で刺されて亡くなっているのです。
「学校は何をしていたんだと怒鳴りつける発言を、まず報道するのはおかしい」という内田さんの指摘は、全くその通りだと思います。
実は『街場の共同体論』のこの部分で、中島みゆきさんのある歌を連想してしまいました。No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でもとりあげた《4.2.3.》です。
メディアの報道に対する異議申し立て
No.67で書いたことを簡単に振り返りますと、1996年12月17日、ペルーの首都・リマにある在ペルー日本大使公邸に反政府組織(トパク・アマル革命運動。MRTA)のメンバーが乱入し、日本人・日系ペルー人を中心に約600人を人質にとって立てこもるという事件が勃発しました。「ペルー日本大使公邸占拠事件」です。事件は4ヶ月後の1997年4月22日(日本時間、4月23日)、ペルー軍の特殊部隊が大使公邸に突入し、最後まで残った人質72人のうち71人を救出することで幕を閉じました。しかし人質一人(ペルー最高裁判事)と突入したペルー軍特殊部隊の兵士二人が犠牲になったのです。特殊部隊の突入と人質救出の模様は全世界にテレビ中継され、その映像はニュースで何回となく放映されました。負傷した特殊部隊の兵士が担架で運び出される生々しい様子などです。
そして中島さんは「日本人人質の安否や、日本人は無事ということだけを放送し、人質を救うため命をかけて突入して重傷を負った(実際は死んだ)兵士の安否については、全く一言も触れなかった日本のテレビの実況中継」に対して、非常に強い違和感をいだいたのです。
『街場の共同体論』における内田さんの論と、中島さんの《4.2.3.》はテーマは全く違いますが、以下の点で大変よく似ています。
の2点です。「テロリストを許すな」とか「テロに屈服するな」と論陣を張るメディアなら、現場の最前線でテロと対峙した人たち、しかもそれによって死傷した人たちのことを大きく(賞賛も込めて)報道するのが当然でしょう。『街場の共同体論』を読んでいて中島みゆきさんの歌を連想したという一つはこの点でした。
しかし、ここまでに書いたことは、実は「前振り」と言うか、連想したことの一部です。『街場の共同体論』を読んでいて最も強く中島さんの歌を連想したのは別の部分なのです。
黙示録
内田さんは『街場の共同体論』で、少年犯罪件数の戦後のピークが1958年だったことを述べています。自殺率のピークも1958年だそうです。これは「少年犯罪が最近増えている、という全く根拠のない論調」に対する反論なのですが、その議論はここではさておきます。その1960年前後がどういう時代だったのか、内田さんは次のように書いています。
「黙示録」というのは言うまでもなく、新約聖書の最終文書である「ヨハネの黙示録」のことです。そこでは世界の終末、キリストの降臨、最後の審判などが語られています。
現代史を振り返ってみると、第2次世界大戦が終了してから旧ソ連の崩壊(1989年)までの45年の期間は、いわゆる「冷戦 = Cold War」の期間でした。アメリカとソ連という、大量の核兵器を保有する2つの超大国の「冷たい」戦争が続きました。最も核戦争の危機に近づいたのは1962年のキューバ危機だと思いますが、両大国の直接戦争にならないまでも、冷戦を背景とする「代理戦争」がいろいろあった。アメリカ軍がベトナムに介入したベトナム戦争(1960-1975)や、ソ連軍のアフガニスタン侵攻(1979-1989)などです。ソ連のアフガニスタン侵攻は、1980年のモスクワオリンピックを西側諸国がボイコットするという事態に発展しました。
1983年には、ソ連の領空に進入した大韓航空の旅客機が撃墜されるという事件が起こりました。真相は不明の部分が多いのですが、大韓航空機は「誤って」ソ連領空を侵犯し、ソ連空軍は民間航空機を「誤って敵の軍用機とみなして」撃墜したとされています。ということは、偶発的事件が米ソの直接対決を招きかねないということです。その最悪の事態は核戦争です。
冷戦は文学作品や映画にも影響を与えています。有名なところで言うと、ネヴィル・シュートの小説『渚にて』(1957。映画:1959)は「核戦争で人類が終末を迎える、その終末の迎えかた」の物語です。スタンリー・キューブリック監督の映画『博士の異常な愛情』(1964)は、核戦争というテーマをブラック・コメディに仕立てたものでした。1980年代に至っても影響は続きます。アーノルド・シュワルツネッガーを一躍スターにした映画『ターミネーター』(ジェームズ・キャメロン監督。1984)においては、未来の地球がロボットと人類の戦争状態になっています。その戦争は、意志を持ってしまったコンピュータが人類を抹殺するために核戦争のボタンを起動したのが発端、という設定です。ここにあげた作品はいずれもSF(Science Fiction)ですが、そもそもSFは冷戦を背景として興隆したジャンルなのですね(内田さんの指摘)。
冷戦の約45年間の期間は、緊張が極度に高まった時から、緩んだ時期までいろいろあり、それが繰り返されたのですが、とにかくこの期間は日本のみならず世界の人たちが「黙示録的な恐怖」を潜在的に感じていたのだと思います。少なくとも内田さんは、同時代を生きた経験からそう振り返っている。人々が日常会話で口に出すことは決してなかったけれど・・・・・・。
内田さんが「黙示録的な恐怖」を持ち出したのは、高い自殺率と少年犯罪件数の背景にそれがあるという仮説につなげるためなのですが、その論の妥当性はここではさておきます。
実はこの「黙示録的な恐怖」という文章で強く連想した中島みゆきさんの楽曲があります。映画『ターミネーター』と同じ1984年(32歳)に発表されたアルバム『はじめまして』に収録されている《僕たちの将来》です。
僕たちの将来
何となく「危うい感じ」がする若い男女の物語です。アルバムが発表された1984年というと、高度成長期の真っただ中ですね。そこで描かれるのは、宿で寝た恋人たちが(いわゆるラブホテルでしょう)、深夜に抜け出して24時間営業のファミレス(おそらく)に行き、ビールを飲みながらスパゲティとステーキを食べるという情景です。2人の若者が生まれた頃(たとえば1960年前後)には考えられもしなかった「ライフスタイル」が、ここでは現実になっている。いかにもありそうな光景ですが、当時としては、ある意味では「時代の最先端の」風俗だったのでしょう。
しかしこの曲は単に風俗を描いただけではありません。4つの点で「えっ」と思わせるものがある。一つ目は「閃光」という言葉です。実は、
というところを、中島さんは、
と歌っています。歌としては、つまり聴いているだけでは「光」です。しかし文字で書かれた「詩」としては「閃光」なのです。
閃光とは瞬間的に輝く強い光のことです。日常生活で経験するのは、稲妻、打ち上げ花火、カメラのフラッシュなどでしょう。しかし「非日常の」閃光もある。それは、爆弾の爆発や大砲の発射時に出る閃光です。そして人類が作り出した最も強い閃光を放つものが何かは書くまでもないでしょう。「将来は光の中」だと「未来は明るい」というようなイメージをまず持ちますが、「将来は閃光の中」だと、全く反対の意味にとる方が自然です。
2つ目は、詩の終わりの方で唐突とも思える感じで出てくる「戦争」という言葉です。ファミレスでの男女のたわいのない会話を並べただけの詩だと思って聴いていると、それは完全に裏切られてしまう。「暑い国の戦争」とありますが、アルバムが発売された1984年当時は、たとえばアフガン戦争のまっただ中でした。
3つ目は、最後にある、
という一言です。「将来は良くなってゆく筈だね」と2回繰り返したあとに出てくるのは、「良くなってゆくだろうか」という疑問形なのです。中島さんは、この部分だけは「強く、厳しく、問い詰めるような口調」で歌っています。
4つ目は、歌が終わったあとに挿入された「カウントダウン」のエフェクトです。ゆっくりとした、低い、押し殺したような男の声で、Six から始まって Three まで続き、Two の途中で途切れます(アルバムでは途切れてすぐに最後の曲である『はじめまして』が始まる)。
「閃光」「戦争」「カウントダウン」という"仕掛け"が配置されたうえに、最後は「将来は良くなってゆくだろうか」という疑問形で終わるこの曲は、「黙示録的な不安感」をバックにしたものだと思います。それが核戦争のことかどうかは分かりません。しかし、もっと一般化して、
と考えるなら、そういう感情を背景にしているのだと思います。深夜の24H営業のファミレスでの、男女のたわいのない会話から透けて見える人間関係の「危うさ」と、それに対比された「閃光・戦争・カウントダウン」で、この曲は1984年当時の「時代の気分」の一端を、潜在意識まで含めて見事に切り取ってみせた。
中島みゆきというシンガー・ソングライターのある面での真骨頂というか、凄さを感じる楽曲です。
現代の「黙示録」
アルバム『はじめまして』が発表されたのは、まだ冷戦が続いている1984年で、今から30年前です。かなり昔のことで、それから世界は大きく変わりました。冷戦が終結し、経済はグローバル化し、戦争の原因も東西対立ではなく、民族対立や宗教要因になった。では、この現代において「黙示録的な恐怖」はないのでしょうか。
そんなことはないと思います。「自分たちの運命が、世界のどこかで決められる」という状況は、強弱は別にして起こっている(起こる)のではないでしょうか。もちろん、核戦争の危険性も依然として続いているのですが(いがみ合っている隣国同士が核兵器を保有しているケースがある)、それはさておいても近年で思い起こすのは2008年のリーマン・ショックです。
アメリカの「金融貴族」たちが、サブプライム・ローンという信用度の低い債権をもとにした金融商品のバブルを作り出したあげく、手仕舞いに遅れた(ババが残ってしまった)リーマン・ブラザースが破綻する。それが金融・保険業界の連鎖的な信用不安を招き、金融危機がグローバルに波及して、日本の景気後退と、産業界やサービス業界の売上げダウンにまでつながる。当時、派遣労働者の契約打ち切り(いわゆる派遣切り)や、一部は正規労働者の解雇までありました。アメリカの金融貴族のマネーゲームが原因で、日本の(一部の)若者が職を失う・・・・・・。これは現実に起こったことなのですね。
そういう意味も含めれば《僕たちの将来》で語られた「時代の気分」は形を変えながら続いていると思うし、我々はそれを感じるべきなのだろうと思います。
《僕たちの将来》という曲を改めて聴いてみて思ったのは、この曲が30年前の社会情勢のもとで書かれたはずなのに、全く色褪せていないということでした。
同世代からの発言
ここからは補足です。「黙示録」というキーワードで、内田樹氏の「街場の共同体論」の中の文章から、中島みゆきさんの《僕たちの将来》という楽曲を連想したのですが、この連想には、もう少し意味があるように思います。それは内田さんと中島さんが「同世代」だということです。2人の誕生日を比較すると、
です。ということは、小・中・高校は1学年違いということになります。また、大学入学の年は2人とも1970年春です。出身地は違うものの(内田さん:東京、中島さん:札幌)、明らかに同世代です。全く面識はないだろうけれど。
人の考え方や価値観は、同世代で共有する部分があるのではないでしょうか。1950年前後に生まれた人で言うと、ものごごろついた10歳の頃が1960年であり、30歳台の終わりまでが日本では高度成長期です。その間、世界情勢としてはずっと東西対立を軸とする冷戦が続いていた。この間に日本で起こった数々の政治情勢や社会的事件、新しい風俗や、メディアの発達や変化を、同世代ならリアルタイムで共有してきたわけです。
一例をあげると、内田さんと中島さんが大学に入った1970年は、大学紛争がピークを迎え、東京大学の入試が中止になるという前代未聞の事態になった1969年の翌年です。それが何らかの影響を与えなかったはずがない。中島さんの『世情』(1978。アルバム「元気ですか」)という名曲を思いだします(No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」参照)。
同世代が共有している何かがあるのでは、といったことをふと思いました。
作曲家:中島みゆき
もう一つ補足したいのは、《僕たちの将来》という曲を改めて聴いて思ったことです。中島さんは、今でこそ演劇活動などにもアーティストとしての活動の幅を広げていますが、《僕たちの将来》が発表された1984年当時は「ピュアな」シンガー・ソングライターでした(プラス、他の歌手に楽曲を提供するソングライターだった)。
言うまでもなく、シンガー・ソングライターとは「歌手」「作曲家」「作詞家」の3つを兼ねた存在なのですが、この3つの力量が極めて高いレベルで統合されているということで、中島さんはアーティストとして突出していると思います。特に、作曲については語られることが少ないと思うのですが(歌唱力や、詩人としての才能を絶賛する人は多い)、《僕たちの将来》を聴いても、作曲の部分が(作曲の部分も)非常に優れています。3拍子の曲なのですが、たわいのない軽い気分のノリで、なんとなく「けだるい」感じも漂わせ、会話調の言葉の繋がりをサラッと歌にしてしまうメロディー・ラインがとても印象的です。
歌手・作詞家・作曲家、中島みゆきの、もっと優れた部分がストレートに現れた曲だと感じました。
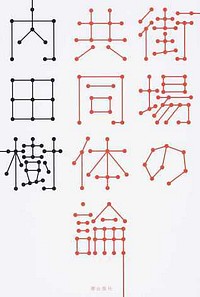
| |||
|
| |||
内田 樹・著「街場の共同体論」は、家族論、地域共同体論、教育論、コミュミケーション論、師弟論などの「人と人との結びつき」のありかたについて、あれこれと論じたものです。主張の多くは内田さんの今までのブログや著作で述べられていることなのですが、「共同体 = 人と人との結びつき」に絞って概観されていて、その意味ではよくまとまった本だと思いました。この中に「階層社会」について論じた部分があります。
階層社会の本質
「階層社会」という言葉をどうとらえるかは難しいのですが、ここではごくアバウトに、
| 単一の、あるいは数少ない "ものさし"で測定される「格差」があり、その格差が「固定的」である社会 |
という風に考えておきます。人の格差を測定する"ものさし"とは、その人の「年収」や、もっと曖昧には「社会的地位」であり、固定的とは、階層上位のものは(あるいは集団は)ずっと上位にとどまり、それは世代を越えて続く傾向にあることを言います。この階層社会の特徴、ないしは本質を、内田さんは
| 階層社会では、階層下位のものが、自らの意志で(進んで)階層下位にとどまろうとする |
と、とらえています。でないと階層社会はできあがらないと・・・・・・。格差の"ものさし"である年収で言うと、誰だって年収は多い方がいいわけです。なぜ「自らの意志で階層下位にとどまろうとする」のか。その重要な要因は、
| 階層下位のものが階層下位にとどまるように仕向ける「メッセージ」が、マスメディアを通して大々的に流されているから |
というのが、内田さんの見立てです。そのメッセージは時とともに変わる。それは、あまり長く続けているとメッセージの欺瞞性がバレてしまうからです。一時「自分探し」とか「自分らしさの探求」とか「自己実現」が大々的に宣伝されたことがありました。しかし、さすがにそれではまずいと多くの人が気づいた。趣味の世界の話ならまだしも、「自分探し」などという理由で転職をすると、ごく一部の人はそれで成功するかもしれないが、多くの人はそうではなく、結局「転職産業」と「人材派遣会社」と「低賃金かつ解雇しやすい労働者を確保したい企業」の利益になるだけなのですね。「自分探し」は、大多数の人にとっては「自滅的イデオロギー」です。
しかし「階層下位のものが階層下位にとどまるように仕向けるメッセージ」は、手を変え品を変えて継続的に続いています。その例として内田さんがあげている代表格が、
| ・ | 反知性主義 | ||
| ・ | クレーマー |
です。反知性主義について、内田さんは次のように書いています。
|
確かに、自分の興味の範囲だけで生きていては上位には行けません。「自分はものごとを知らない、だから知りたい」という態度で人に教えを請い、また勉強もする。そして人的ネットワークを広げ、自分の興味の幅も広げて、自身の能力を磨く・・・・・・。会社を考えてみても、新入社員の時からその後のキャリア・アップまで、そういうタイプの人間の査定が高くなり上位ポジションへと引き上げられる(=年収が多くなる)のは当然です。
なかなか中島みゆきさんの詩との関係にまで行かないのですが、次の「クレーマー」ついての内田さんの文章が、それと関係しています。
クレーマー的人間
「階層社会では、階層下位のものが、自らの意志で階層下位にとどまろうとする」例の一つとして内田さんが指摘しているのが、クレーマー的人間です。そして、クレーマーの増加を助長したのはメディアの責任だと、内田さんは言っています。
|
内田さんが指摘するメディアの責任とは、
| 一番うるさく文句を言う人の言い分を最優先に聞くべきだということを、その報道姿勢によって暗黙のルールにしてしまった |
ということです。確かに、大きな事件や事故が起きたときにテレビの情報番組を見ていると「レポーター」や「コメンテーター」と称する人たちが出てきて、その事件・事故の「責任者」を「一方的」に宣告し、いかにも「被害者に成り代わってという態度で」責任を追求する(強く言えば、糾弾する)ことがよくあります。宣告された「責任者」とは、公的な職についている人だったり(警察、自治体の担当官、学校の先生、・・・・・・)、企業の経営層だったりです。こういう報道姿勢がクレーマー的人間の増長させている一つの要因でしょう。内田さんは一つの報道をあげています。
|
内田さんが言う「暴漢が小学校に進入して、小学生を襲った事件(その結果、二人の先生が死傷)」とは何でしょうか。まず思い出すのは、2001年、大阪教育大学附属池田小学校にテロリストが進入し、小学生を無差別に刃物で殺傷した前代未聞の事件です(=附属池田小事件)。この事件では児童8名が殺され、児童13名と教員2名が重軽傷を負いました。わずか5~10分間の犯行だったと言います。
また2005年には、大阪の寝屋川市立中央小学校に暴漢(卒業生の少年)が侵入し、一人の教師の方を殺害し、教師と栄養士2人に重傷を負わせる事件が発生しました(=寝屋川中央小事件)。この時には授業中の小学生は襲われませんでした。犯人の在校当時の教師に対する恨み(死傷した教師は無関係)が「動機」だったようです。
どちらかの事件だと思いますが、附属池田小事件だとすると「教師が死亡」というのは違っているし、寝屋川中央小事件だとすると「小学生を襲う」というところが違っています。内田さんも混同したのかもしれません(ただし、私の記憶にない別の事件の可能性もある)。
しかしそれは些細なことであって、論旨には影響しません。内田さんの言いたいことは、こういう事件でメディアは何を報道すべきかということです。仮に附属池田小事件の例だとしても、重傷を負った教師は死ぬかもしれなかったわけだし、凶器を振り回すテロリストを素手で取り押さえた教師たちも一歩間違えば死んでもおかしくはなかった。前代未聞の、しかもわずか10分以内の無差別テロに対して、附属池田小の教師の方々は混乱状況の中で精一杯のことをしたのではないでしょうか。また、寝屋川中央小事件だとすると、実際に教師の方が包丁で刺されて亡くなっているのです。
「学校は何をしていたんだと怒鳴りつける発言を、まず報道するのはおかしい」という内田さんの指摘は、全くその通りだと思います。
実は『街場の共同体論』のこの部分で、中島みゆきさんのある歌を連想してしまいました。No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でもとりあげた《4.2.3.》です。
メディアの報道に対する異議申し立て

| |||
|
中島みゆき 「わたしの子供になりなさい」 (1998) | |||
そして中島さんは「日本人人質の安否や、日本人は無事ということだけを放送し、人質を救うため命をかけて突入して重傷を負った(実際は死んだ)兵士の安否については、全く一言も触れなかった日本のテレビの実況中継」に対して、非常に強い違和感をいだいたのです。
|
『街場の共同体論』における内田さんの論と、中島さんの《4.2.3.》はテーマは全く違いますが、以下の点で大変よく似ています。
| ◆ | マスメディアの報道姿勢に対する異議申し立てである。 | ||
| ◆ | 自らの職務を全うするためにテロリストに立ち向かい、その結果負傷した人たちのことを全く報道しないメディアに対する抗議である。 |
の2点です。「テロリストを許すな」とか「テロに屈服するな」と論陣を張るメディアなら、現場の最前線でテロと対峙した人たち、しかもそれによって死傷した人たちのことを大きく(賞賛も込めて)報道するのが当然でしょう。『街場の共同体論』を読んでいて中島みゆきさんの歌を連想したという一つはこの点でした。
しかし、ここまでに書いたことは、実は「前振り」と言うか、連想したことの一部です。『街場の共同体論』を読んでいて最も強く中島さんの歌を連想したのは別の部分なのです。
黙示録
内田さんは『街場の共同体論』で、少年犯罪件数の戦後のピークが1958年だったことを述べています。自殺率のピークも1958年だそうです。これは「少年犯罪が最近増えている、という全く根拠のない論調」に対する反論なのですが、その議論はここではさておきます。その1960年前後がどういう時代だったのか、内田さんは次のように書いています。
|
「黙示録」というのは言うまでもなく、新約聖書の最終文書である「ヨハネの黙示録」のことです。そこでは世界の終末、キリストの降臨、最後の審判などが語られています。
現代史を振り返ってみると、第2次世界大戦が終了してから旧ソ連の崩壊(1989年)までの45年の期間は、いわゆる「冷戦 = Cold War」の期間でした。アメリカとソ連という、大量の核兵器を保有する2つの超大国の「冷たい」戦争が続きました。最も核戦争の危機に近づいたのは1962年のキューバ危機だと思いますが、両大国の直接戦争にならないまでも、冷戦を背景とする「代理戦争」がいろいろあった。アメリカ軍がベトナムに介入したベトナム戦争(1960-1975)や、ソ連軍のアフガニスタン侵攻(1979-1989)などです。ソ連のアフガニスタン侵攻は、1980年のモスクワオリンピックを西側諸国がボイコットするという事態に発展しました。
1983年には、ソ連の領空に進入した大韓航空の旅客機が撃墜されるという事件が起こりました。真相は不明の部分が多いのですが、大韓航空機は「誤って」ソ連領空を侵犯し、ソ連空軍は民間航空機を「誤って敵の軍用機とみなして」撃墜したとされています。ということは、偶発的事件が米ソの直接対決を招きかねないということです。その最悪の事態は核戦争です。
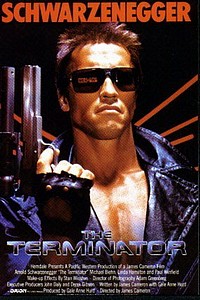
| |||
|
The Terminator(1984)
| |||
冷戦の約45年間の期間は、緊張が極度に高まった時から、緩んだ時期までいろいろあり、それが繰り返されたのですが、とにかくこの期間は日本のみならず世界の人たちが「黙示録的な恐怖」を潜在的に感じていたのだと思います。少なくとも内田さんは、同時代を生きた経験からそう振り返っている。人々が日常会話で口に出すことは決してなかったけれど・・・・・・。
内田さんが「黙示録的な恐怖」を持ち出したのは、高い自殺率と少年犯罪件数の背景にそれがあるという仮説につなげるためなのですが、その論の妥当性はここではさておきます。
実はこの「黙示録的な恐怖」という文章で強く連想した中島みゆきさんの楽曲があります。映画『ターミネーター』と同じ1984年(32歳)に発表されたアルバム『はじめまして』に収録されている《僕たちの将来》です。
僕たちの将来
|
何となく「危うい感じ」がする若い男女の物語です。アルバムが発表された1984年というと、高度成長期の真っただ中ですね。そこで描かれるのは、宿で寝た恋人たちが(いわゆるラブホテルでしょう)、深夜に抜け出して24時間営業のファミレス(おそらく)に行き、ビールを飲みながらスパゲティとステーキを食べるという情景です。2人の若者が生まれた頃(たとえば1960年前後)には考えられもしなかった「ライフスタイル」が、ここでは現実になっている。いかにもありそうな光景ですが、当時としては、ある意味では「時代の最先端の」風俗だったのでしょう。

| ||
|
中島みゆき「はじめまして」(1984)
収録曲:①僕は青い鳥 ②幸福論 ③ひとり ④生まれた時から ⑤彼女によろしく ⑥不良 ⑦シニカル・ムーン ⑧春までなんぼ ⑨僕たちの将来 ⑩はじめまして
| ||
しかしこの曲は単に風俗を描いただけではありません。4つの点で「えっ」と思わせるものがある。一つ目は「閃光」という言葉です。実は、
| 僕たちの将来はめくるめく閃光の中 |
というところを、中島さんは、
| ぼくたちのしょうらいは めくるめくひかりのなか |
と歌っています。歌としては、つまり聴いているだけでは「光」です。しかし文字で書かれた「詩」としては「閃光」なのです。
閃光とは瞬間的に輝く強い光のことです。日常生活で経験するのは、稲妻、打ち上げ花火、カメラのフラッシュなどでしょう。しかし「非日常の」閃光もある。それは、爆弾の爆発や大砲の発射時に出る閃光です。そして人類が作り出した最も強い閃光を放つものが何かは書くまでもないでしょう。「将来は光の中」だと「未来は明るい」というようなイメージをまず持ちますが、「将来は閃光の中」だと、全く反対の意味にとる方が自然です。
2つ目は、詩の終わりの方で唐突とも思える感じで出てくる「戦争」という言葉です。ファミレスでの男女のたわいのない会話を並べただけの詩だと思って聴いていると、それは完全に裏切られてしまう。「暑い国の戦争」とありますが、アルバムが発売された1984年当時は、たとえばアフガン戦争のまっただ中でした。
3つ目は、最後にある、
| 僕たちの将来は良くなってゆくだろうか |
という一言です。「将来は良くなってゆく筈だね」と2回繰り返したあとに出てくるのは、「良くなってゆくだろうか」という疑問形なのです。中島さんは、この部分だけは「強く、厳しく、問い詰めるような口調」で歌っています。
4つ目は、歌が終わったあとに挿入された「カウントダウン」のエフェクトです。ゆっくりとした、低い、押し殺したような男の声で、Six から始まって Three まで続き、Two の途中で途切れます(アルバムでは途切れてすぐに最後の曲である『はじめまして』が始まる)。
「閃光」「戦争」「カウントダウン」という"仕掛け"が配置されたうえに、最後は「将来は良くなってゆくだろうか」という疑問形で終わるこの曲は、「黙示録的な不安感」をバックにしたものだと思います。それが核戦争のことかどうかは分かりません。しかし、もっと一般化して、
| 自分たちの運命が、自分たちの全くあずかり知らない、世界レベルの巨大な力によって決められるのではないか、ないしは決まっているのではないかという、潜在意識としての不安感 |
と考えるなら、そういう感情を背景にしているのだと思います。深夜の24H営業のファミレスでの、男女のたわいのない会話から透けて見える人間関係の「危うさ」と、それに対比された「閃光・戦争・カウントダウン」で、この曲は1984年当時の「時代の気分」の一端を、潜在意識まで含めて見事に切り取ってみせた。
中島みゆきというシンガー・ソングライターのある面での真骨頂というか、凄さを感じる楽曲です。
現代の「黙示録」
アルバム『はじめまして』が発表されたのは、まだ冷戦が続いている1984年で、今から30年前です。かなり昔のことで、それから世界は大きく変わりました。冷戦が終結し、経済はグローバル化し、戦争の原因も東西対立ではなく、民族対立や宗教要因になった。では、この現代において「黙示録的な恐怖」はないのでしょうか。
そんなことはないと思います。「自分たちの運命が、世界のどこかで決められる」という状況は、強弱は別にして起こっている(起こる)のではないでしょうか。もちろん、核戦争の危険性も依然として続いているのですが(いがみ合っている隣国同士が核兵器を保有しているケースがある)、それはさておいても近年で思い起こすのは2008年のリーマン・ショックです。
アメリカの「金融貴族」たちが、サブプライム・ローンという信用度の低い債権をもとにした金融商品のバブルを作り出したあげく、手仕舞いに遅れた(ババが残ってしまった)リーマン・ブラザースが破綻する。それが金融・保険業界の連鎖的な信用不安を招き、金融危機がグローバルに波及して、日本の景気後退と、産業界やサービス業界の売上げダウンにまでつながる。当時、派遣労働者の契約打ち切り(いわゆる派遣切り)や、一部は正規労働者の解雇までありました。アメリカの金融貴族のマネーゲームが原因で、日本の(一部の)若者が職を失う・・・・・・。これは現実に起こったことなのですね。
そういう意味も含めれば《僕たちの将来》で語られた「時代の気分」は形を変えながら続いていると思うし、我々はそれを感じるべきなのだろうと思います。
《僕たちの将来》という曲を改めて聴いてみて思ったのは、この曲が30年前の社会情勢のもとで書かれたはずなのに、全く色褪せていないということでした。
同世代からの発言
ここからは補足です。「黙示録」というキーワードで、内田樹氏の「街場の共同体論」の中の文章から、中島みゆきさんの《僕たちの将来》という楽曲を連想したのですが、この連想には、もう少し意味があるように思います。それは内田さんと中島さんが「同世代」だということです。2人の誕生日を比較すると、
| 1950年9月30日 | |||
| 1952年2月23日 |
です。ということは、小・中・高校は1学年違いということになります。また、大学入学の年は2人とも1970年春です。出身地は違うものの(内田さん:東京、中島さん:札幌)、明らかに同世代です。全く面識はないだろうけれど。
人の考え方や価値観は、同世代で共有する部分があるのではないでしょうか。1950年前後に生まれた人で言うと、ものごごろついた10歳の頃が1960年であり、30歳台の終わりまでが日本では高度成長期です。その間、世界情勢としてはずっと東西対立を軸とする冷戦が続いていた。この間に日本で起こった数々の政治情勢や社会的事件、新しい風俗や、メディアの発達や変化を、同世代ならリアルタイムで共有してきたわけです。
一例をあげると、内田さんと中島さんが大学に入った1970年は、大学紛争がピークを迎え、東京大学の入試が中止になるという前代未聞の事態になった1969年の翌年です。それが何らかの影響を与えなかったはずがない。中島さんの『世情』(1978。アルバム「元気ですか」)という名曲を思いだします(No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」参照)。
| 内田さんと中島さんが大学に入ったのが1970年春ということで思い出したのですが、その年の秋に公開された、学生運動をテーマにしたアメリカ映画があります。「いちご白書」です。No.35「中島みゆき:時代」に、中島さんは大学1年生のときに(札幌で)この映画を見たのではないかという憶測を書きました。一方、内田さんは大学時代に学生運動にずいぶん関わったようです。ひょっとしたら内田さんも(東京で)「いちご白書」を見たのではないでしょうか。「いちご白書」のような同じ世代を描いた映画を同じ時期にみるというのは、同一世代であることの典型例です。 |
同世代が共有している何かがあるのでは、といったことをふと思いました。
作曲家:中島みゆき
もう一つ補足したいのは、《僕たちの将来》という曲を改めて聴いて思ったことです。中島さんは、今でこそ演劇活動などにもアーティストとしての活動の幅を広げていますが、《僕たちの将来》が発表された1984年当時は「ピュアな」シンガー・ソングライターでした(プラス、他の歌手に楽曲を提供するソングライターだった)。
言うまでもなく、シンガー・ソングライターとは「歌手」「作曲家」「作詞家」の3つを兼ねた存在なのですが、この3つの力量が極めて高いレベルで統合されているということで、中島さんはアーティストとして突出していると思います。特に、作曲については語られることが少ないと思うのですが(歌唱力や、詩人としての才能を絶賛する人は多い)、《僕たちの将来》を聴いても、作曲の部分が(作曲の部分も)非常に優れています。3拍子の曲なのですが、たわいのない軽い気分のノリで、なんとなく「けだるい」感じも漂わせ、会話調の言葉の繋がりをサラッと歌にしてしまうメロディー・ラインがとても印象的です。
歌手・作詞家・作曲家、中島みゆきの、もっと優れた部分がストレートに現れた曲だと感じました。
(続く)
2014-10-30 08:26
nice!(1)
トラックバック(0)



