No.157 - ノートン・サイモン美術館 [アート]
今までの記事で、個人コレクションをもとにした美術館について書きました。
の2つです。今回はその "シリーズ" の続きとして、アメリカのカリフォルニアにあるノートン・サイモン美術館のことを書きたいと思います。
電車で行ける
ノートン・サイモン美術館はロサンゼルス近郊のパサデナにありますが、ポイントの一つはロサンゼルスのダウンタウンから電車で行けることです。
ロサンゼルスの観光スポットと言うと、クルマがないと行けないところ、ないしは大層不便なところ(バスの乗り継ぎなど)もあるのですが(ディズニーランド、ナッツベリーファームなど)、ノートン・サイモン美術館に関しては2003年にメトロの「ゴールドライン」が開通し、電車で行けるようになりました。ダウンタウンのユニオン駅から乗って「メモリアル・パーク」という駅で下車します。
パサデナ・オールドタウン
メモリアル・パーク駅からノートン・サイモン美術館までは約1.2~3kmの距離ですが、是非、歩いていきましょう。というのも途中に "パサデナ・オールドタウン地区" があるからです。
パサデナは高級住宅街ですが、その中のオールドタウン地区は、昔からのレンガ造りの建物を生かした街づくりがされています。ここには各種のショップやアート・スポット、レストラン、カフェが立ち並び、大変おしゃれな感じのエリアです。そもそもパサデナ・オールドタウンがロサンゼルスの観光・ショッピングスポットの一つになっていて、美術に興味のない人でも楽しめます。
私は過去3回、ノートン・サイモン美術館に行ったことがありますが、はじめの2回はクルマで、3回目は当時開通していたメトロで行きました。パサデナ・オールドタウンを散策し、ランチを食べ(KABUKI という寿司・和食レストラン)、それから美術館に行ったことを覚えています。
ノートン・サイモン美術館は、実業家であったノートン・サイモン(1907-1993)のコレクションを元に開設されたものです。その意味ではバーンズ・コレクションやコートールド・コレクションと似ています。その多くの所蔵作品のごく一部を以下に紹介します。
スルバラン
実は次のスルバランの静物画が、個人的にはノートン・サイモン美術館の "一押し" の作品です。
スルバランは17世紀のスペインの画家で、ベラスケスとほぼ同時代人です。ほとんどの作品は宗教画ですが、この絵は静物画です。ちなみにこの絵は『レモン、籠のオレンジ、茶碗』と呼ばれるのが普通です。プラド美術館に同じスルバランの『茶碗、アンフォラ、壷』という作品があります。
このプラド美術館の絵がスペイン静物画(ボデゴン。厨房画)の最高傑作という評価らしいのですが、個人的にはノートン・サイモン美術館の絵のほうが上だと感じます。アメリカの美術館にあるのが "不利" に働いているのではないでしょうか。
ノートン・サイモン美術館の『レモンとオレンジとバラの静物』は、ひょとしたら何らかの祭壇の静物を描いたものかもしれません。また、描かれているレモン、オレンジ、バラ、カップのそれぞれは、宗教的な何かの象徴かもしれない。ほとんど宗教画しか描かなかった作者を考えると、その可能性はあると思います。しかし我々としては、これを "純粋な静物画" として見たいわけです。
静物画として考えると、果物と食器を中心にした絵は他にもいっぱいあります。果物では柑橘類や葡萄、苺などが多く、食器では素焼、陶器、金属、ガラスなどが描かれます。画家が目指すのはまず、光で照らされた静物の「質感」の表現で、その描写技術を追求するわけです。このような静物画は、17世紀~18世紀のオランダ絵画にヤマのようにあるし、現代でもいろいろと描かれています。
しかし問題は「リアルな質感表現」以上のものを絵から感じられるかどうかです。この手の静物画は実際に現物を見て、その場で何かビビッと感じるものが「あるか・ないか」、それで評価をするしかない。それは極めて個人的なものだし、画像ではわからないところが多々あります。この絵を実際に見たときの「感じ」を言葉で表現するのは難しいのですが、何とか箇条書きにすると、
となるでしょうか。レモンと籠のオレンジとバラとカップがシンプルに横一列に並んでいるだけで、構図に作為が全くない(ように見えてしまう)のも影響しているのだと思います。本当は計算し尽くされた構図なのだろうけれど・・・・・・。描かれたレモンとオレンジのサイズが重要なのかも知れません。とにかくこの絵を見たときは率直に素晴らしいと感じました。
静物画を見て「あっ、いいな」を思ったのは、このスルバランの絵が初めてではありません。ミラノのドゥオーモの近くに「アンブロジアーナ絵画館」がありますが、そこにカラヴァッジョの「果物籠」という傑作があります。この絵も初めて見たときには感動しましたが、真横から果物籠を描くという構図のシンプルさは、スルバランに通じるものがあるような気がします。
カニャッチ
今までの記事で宗教画をとりあげたことはほとんどなかったのですが、以前に唯一書いたマグダラのマリア( No.118「マグダラのマリア」)にちなんで、ノートン・サイモン美術館にある宗教画を取り上げます。
何だか "騒々しい" 画面構成ですが、描かれている光景からしてキリスト教の題材と推測できます。画面の中央の床の女性はマグダラのマリアです。彼女のアトリビュート(持物)である香油の瓶が描かれています。マリアは肌を露出したり、また半裸の姿で描かれることも多い。
No.118「マグダラのマリア」に書いたように、一般に言われている「マグダラのマリア」のイメージは、聖書にある数カ所の女性の記述をパッチワークのように合体し、またその後の伝説も加味して作り上げられたものです。その中に、マグダラのマリアには姉のマルタがいて、マルタはキリストの昇天後に財産を使徒たちに寄付したが、マリアは自分の財産と美貌をもとに享楽的な生活にふけっていた、しかしその後マリアは改悛して神に帰依した、という聖書解釈(というより創作物語)があります。
そのマリアを、右側の姉のマルタが諫めている場面です。マリアはそれに従って豪華な衣装を脱ぎ捨て、宝石を床に投げやった。左の上には悪魔が描かれていて、おそらくマリアを誘惑しようとしているのでしょう。中央の天使は、そうはさせまいと必死に悪魔を追い払っています。右の上には、この家の侍女と思える女性二人が描かれている、そういう構図です。
ただしマリアの手をよく見ると、まだ宝石をつかんでいます。"回心しきれていない" マリアを描いているようであり、つまり心の葛藤を描いたのでしょう。ちなみにこの絵は普通「マグダラのマリアの回心」と呼ばれています。
西洋の古典絵画は、聖書(とギリシャ・ローマ神話)を知らないと意味がわからない、とよく言われます。確かにそうですが、聖書を熟知しているとしても意味が分からない絵がたくさんあるのですね。特に、キリストの使徒や弟子にまつわる絵画がそうで、この絵はその典型と言えそうです。聖書においてマグダラのマリアは、キリストの磔刑・埋葬・復活というキリスト教の根幹にかかわる重要場面のすべてに登場する女性です。この絵に描かれたような "マグダラのマリア" は、聖書とは無縁です。聖書の隅々まで知っていたとしてもこの絵の意味は分からない。このあたりが、キリスト教徒ではない日本人からすると "敷居が高い" ところでしょう。カトリック教国の人たちからすると常識かも知れないけれど。
しかしこの絵は、そういう宗教画としての解釈を離れたとしても、絵としての完成度が高い。強い光が劇的場面を演出しているのですが、明暗のコントラストだけでなく、外からの穏やかな光を感じます。
その中の「青」の色使いが美しい。右上の空の青、左上のガラスを通した空の微かな青、中央の天使の布と、左下のマリアが着ていたはずの衣装の高貴な(豪華な)青、そして右下のマルタの質素で "くすんだ" 青。この五箇所の青の配置が光っています。空の青はマリアが "完全に" 改悛することを示しているのでしょう。画家の技量の冴えを感じる一枚です。
クールベ
ノルマンディー地方の海を描いた作品です。スイス国境に近い山間部、オルナン出身のクールベは、大人になってから初めて海を見て感激したそうです。そして海の光景を多く描きました。全部で170点ほどあるとされます。我々が良く知っているのは、上野の国立西洋美術館やオルセー美術館にあるような「波が海岸に激しく打ち寄せる光景」の絵ですが、この絵は違います。「海」とはいいながら、海らしきものはあまり見あたりません。
遠浅の海で、潮の干満差が大きく、引き潮の時には広い干潟が出現する、その干潟を描いたと思われます。画面の3分の2以上は空で、湾の向こうにあると思える低い山が遠くに見えます。写実絵画なのだろうけれど、後の印象派の絵のようにも見えるし、それを通り越して抽象画のような感じもある。青と白とバラ色の色使いが美しい、よい作品だと思います。
マネ
No.36「ベラスケスへのオマージュ」で次のようなことを書きました。
ノートン・サイモン美術館の『くず拾い』も、まさにベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(No.36参照)の影響を感じる作品です。
ベラスケスの絵とマネのこの作品に共通するのは「背景をほとんど描かずに人物の全身像を描く」という手法です。かつ、職業に携わる人物の存在感を活写している。この絵もまた、マネが "ベラスケスの弟子" であることを表しているのでした。
ちなみに「くず拾い」というテーマでは、ボナールも描いていますね。No.95で書いた「バーンズ・コレクション」にボナールの「The Ragpickers」という作品があります(コレクションの Room 3 West Wall)。マネよりは40年ほど後の作品ですが、都市化が進んだパリの実状を描いたと言えるでしょう。社会における最下層の人であり、今で言うならホームレスでしょうが、そういうテーマにも斬新さを感じます。
もう一枚のマネ作品、『魚とエビのある静物』です。
No.155「コートールド・コレクション」で、マネの静物画が素晴らしいことを書きました。これはコートールド・コレクションを代表する作品と言える『フォーリーベルジェールのバー』に描かれた「カウンターの上の薔薇とミカン」のことでした。この絵以外に、マネの静物画を今まで2点とりあげています。
ノートン・サイモン美術館の『魚とエビのある静物』も優れた作品です。"テーブルの海産物" というテーマはフランドル絵画によくありますが、このように画面の中心に "ゴロッと魚が一匹横たわっている図" はめすらしいのではと思います。『アスパラガス』も『スモモ』もそうですが、画家は明らかに魚にしかない固有の質感や雰囲気の表現だけに興味を持っています。印象派の先駆者らしい筆さばきで "鮮魚" の感じをうまくとらえていると思います。
ドガ
ノートン・サイモン美術館はドガの作品が非常に充実しています。それも油絵やパステル画だけでなく、彫刻がそろっている。彫刻といっても、ほとんどは No.86「ドガとメアリー・カサット」に出てきた "マケット" というやつです。ポーズの研究のために画家が制作した小さな彫刻です。この美術館には「踊り子」や「馬」のマケットがたくさんあって、それとともに「踊り子」や「馬」を画題とする絵が展示されています。ドガの制作態度がよく分かります。
なお、No.86で紹介した原田マハ氏の『エトワール』という短編小説は『14歳の小さな踊り子』という(マケットではない)ドガの彫刻がテーマになっていましたが、その像もあります(上の画像)。
ノートン・サイモン美術館が所蔵するドガの絵画作品を一つだけあげると、次の「Waiting」というパステル画です。母親と娘の踊り子でしょうか、何かを待っています。おそらくオーディションとか、何らかの試験、ないしは単に出番を待っているのかもしれない。踊り子は、待ち時間のあいだに手で足の踝をさすっているようです。一方の母親は緊張してじっと顔を前に向けている。視線には何も入っていないはずです。
ある一瞬を切り取る、というドガの画風が現れた一枚です。俯瞰する構図をとり、女性の表情を全く描かない、という描きかたも印象的です。
ゴッホ
Mulberry とは「桑の実」のことですね。ということはこの絵は「桑の木 = 日本で言うヤマグワ」を描いたものです。
しかしこの絵から受ける印象として、黄葉になったヤマグワを描くことが目的という感じはしません。すべての形がうねっていて、現実とは遊離しています。そのように見えたというより、現実の形そのものには画家の関心がないようです。
画家が描こうとしたのは「色」そのものでしょう。ヤマグワの黄葉の美しい黄色と、土地の白っぽい黄色、空の青と、木の緑と、それから "何かの赤" です。画家はまず黄色に感動し、その周りに青・緑・赤を配して絵にした。使われている黄色も「カラスが群れ飛ぶ麦畑」のような不吉な黄色ではなく、明るく、晴れやかで、鮮やかな黄色です。
画面に描かれている橙色のものは何でしょうか。必ずしも明確ではないのですが、個人的には「ヤマグワの実 = Mulberry」と解釈することにしています。もっとも、桑の実にしては大きすぎるし、それに色が変です。桑の葉が黄色に染まるとき、まだ残っている完熟した桑の実は橙色ではなく、赤黒いというか、人の目には黒く見えるものです。しかし画家にとってそれはどうでもよい。この位置に橙色を "分かるように" 配することが重要だったのでしょう。
黄・青をメインに緑・橙を配して絵を描く・・・・・・。まるで美術の演習のようですが、ゴッホの手にかかるとこういう絵になってしまうわけです。画家のずば抜けた色彩感覚を感じる一枚です。
余談ですが、前に掲げたカラヴァッジョの『果物籠』という絵にも、一見して桑(ヤマグワ)と分かる植物が描かれています。桑の若い木は葉に不規則な亀裂が入ることが特徴で、こういう形の葉は、人になじみのある木ではまず桑です。『果物籠』というタイトルの絵に桑を描き込むのは日本人からすると違和感があるのですが、これは当然、西欧文化においては「桑 = 実(Mulberry)= 果物」ということでしょう。もちろん東アジア文化では「桑 = 葉 = 養蚕」です。
なお、ノートン・サイモン美術館にはゴッホが母親を描いた肖像画があります。妹から送られてきた写真をもとに描いたものです。
アンリ・ルソー
"空想の中の熱帯のジャングル" といった風情の作品です。こういったタイプの絵はルソー作品によくあります。以前の記事でとりあげた例では、No.72「楽園のカンヴァス」で引用した『夢』『蛇使いの女』、No.95「バーンズ・コレクション」の『虎に襲われる斥候』(Room 14 North Wall)『熱帯の森を散歩する女』『原始林の猿とオウム』(Room 11 North Wall)などです。
一連の絵で感じるのは「植物」や「緑」に対する画家の強いこだわりです。「植物でカンヴァスを埋め尽くすために、わざわざ見たこともない熱帯のジャングルを描いている」という感じがします。No.155「コートールド・コレクション」で引用した『税関』という絵を思い出します。パリの南門の税関を描いているはずなのに「ありえないほどの緑」が溢れている。つまり、パリの税関なら違和感が出くる、しかし異国の熱帯ならいいだろう、みたいな・・・・・・。
パリでの生活が長い画家にとって、都市化が進む大都会からどんどん失われていく「緑」に対する郷愁を絵にした、それが "ジャングル・シリーズ" であり、画家にとっての楽園だった・・・・・・。そんなことを想像したりします。
モディリアーニ
妻のジャンヌを描いた絵ですが、その形といい、目の描き方といい、モディリアーニの絵の一つの典型です。ジャンヌも非常に落ち着いていて、穏やかという感じを受けます。
ジャンヌを描いた絵は多くありますが、この絵はモディリアーニが妻のジャンヌを最もヴィーナスに引き寄せて描いた絵だと思います。ヴィーナスとは、もちろんボッティチェリが「ヴィーナスの誕生」で描いた女性像です。
ピカソ
ノートン・サイモン美術館のホームページに次のような意味のことが書いてあります。
実際に美術館に行くと、このピカソの絵の解説の横にアングルの絵の写真が掲示されていました。
なるほど、と思います。ピカソの絵の後ろの方に "黄色い額縁の絵のようなもの" がかかっているのですが、実はこれは『モワテシエ夫人の肖像』における "鏡に映った横顔" なのですね。またピカソの絵では女性が本を妙な形に開いていますが、これはアングルの絵の「扇」に似せたということでしょう。ピカソは "アングルを踏まえて描いた" という証拠を絵の中に残したわけです。
ピカソの「アングルを踏まえた絵」は、この絵だけでなくいろいろあると言います。No.72で引用した原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』に、
という意味のことが書かれていました。小説の中の人物の発言ですが、作者の(ないしは美術界の)意見が入っていると見ていいと思います。確かにアングルが人物を描いた絵には、一見リアリズムのように見えながら、よく見ると「異様に引き延ばされた人体 = 現実にはありえないデフォルメ」がよくあります。そういえば『モワテシエ夫人の肖像』も、鏡に映った夫人の顔は、光学的にはありえない配置・構図です。
その『モワテシエ夫人の肖像』ですが、アングルはこの絵の5年前にも肖像画を描いています。それは夫人の立像で、アメリカのワシントン D.C.のナショナル・ギャラリーにあります。
2つの絵から伝わってくるのは、夫人の "豊満でふくよかな感じ" であり、"ギリシャ・ローマ彫刻によくあるような彫りの深い古典的な顔立ち" です。これはピカソのいわゆる「新古典主義の時代」の絵に描かれた人物像を連想させます。特に額と鼻筋がつながっている顔立ちはピカソの人物像とそっくりだと思うのです。ピカソの「新古典主義の時代」の絵は『モワテシエ夫人の肖像』を始めとするアングル作品、特に古典的風貌の人物像に触発されたのではないでしょうか。
アングルとの関係はさておき、「本を持つ女」を見て直感的に連想する、別のピカソの絵があります。ニューヨーク近代美術館(MoMA)にある『鏡の前の少女』という作品です。非常によく似ています。それもそのはずで『鏡の前の少女』もまたマリー=テレーズを描いた絵なのです。MoMA のサイトにそう書いてあります。
この MoMA の絵は、No.150「クリスティーナの世界」で引用した原田氏の短編小説集『モダン』の表紙になりました。モダン・アートの殿堂である MoMA を舞台とし、モダン・アートをテーマにした短編集だから『モダン』という本の題名になっているわけです。その表紙にピカソの『鏡の前の少女』を採用するということは、この絵は MoMA が所有するモダン・アートの代表格ということでしょう(少なくとも原田氏の考えでは)。
だとすると、ノートン・サイモン美術館の『本をもつ女』もモダン・アートの代 表格と言っていいのではないか。そして、描かれているテーマの影響だと思うのですが、ノートン・サイモンの絵の方が MoMA の絵より "品がある" 感じがします。
黒くて太い線で画面を区切り、強い色彩を乱舞させるという "どぎつい" 絵画手法だけれど、絵の全体から受ける印象は不思議と落ち着いていて、すっきりとしています。女性の可愛らしさや色香もしっかりと出ている。それでいて、ピカソの絵に時として見かける "下品な感じ" がありません。
ノートン・サイモン美術館のホームページの解説にもあるのですが、20世紀の画家の大きな仕事は「抽象と具象のバランスをどうとるか」だったわけです。『本をもつ女』は『鏡の前の少女』と似ていると書きましたが、"抽象化の度合い" は明らかに違います。ピカソも、同じモデルを描きつつ、いろいろと試行しているのです。一歩間違えば駄作になりかねないような微妙な均衡の上にこの絵は成り立っているようで、大変にいい絵だと思います。この作品は、スルバランに次いでノートン・サイモン美術館の「二押し」の作品です。
個人的には、ノートン・サイモン美術館の「一押し」がスルバラン、「二押し」がこのピカソなのですが、二つとも(たまたま)スペイン人の作品です。そして、スルバランはプラド美術館の静物よりも訴えてくるものがあり、ピカソは MoMA のマリー=テレーズよりも素晴らしい・・・・・・。というのが言い過ぎなら、プラド美術館とMoMAと同等の作品がノートン・サイモン美術館にある・・・・・・。この美術館のレベルの高さを象徴しています。
ノートン・サイモン美術館
ノートン・サイモン美術館が所蔵している欧米の絵画は、上にあげた以外にも、ルネサンス以前の宗教画の数々から始まり、有名な画家では、
などの作品があります(絵を紹介した画家を除く)。またこの美術館は広重の浮世絵を大量に所蔵していて、さらに北斎もあります。私が3回目に行ったときには、広重の『富士三十六景』や『名所江戸百景』からの数枚が展示してありました。
この美術館は、全体的に質が高く「中庸でノーマルなコレクション」という感じです。No.95 で紹介した「バーンズ・コレクション」と比較すると、それが鮮明です。バーンズ・コレクションは、ルノワールが 181点あるとか、セザンヌやマティスも大量にあるとか、23ある展示室にはアメリカ絵画が少なくとも2点あるとか、コレクターの「強いこだわり」が随所にあるのですが、ノートン・サイモン美術館にはそれはありません。美術好きの実業家が大金持ちになり、有名画家の良い絵を素直に集めたという感じがします。西洋の絵画の歴史もよく分かる、そういった美術館です。
ノートン・サイモン美術館は、中庭と敷地内の庭が広くて美しいことも特徴です。しゃれたティー・ハウスもあります。また始めに述べたように、近くにはパサデナ・オールドタウンがあります。そういった周辺まで含めて、ロサンゼルスで1日を過ごすにはよい場所だと思います。
本文中でノートン・サイモン美術館の "二押し" の作品が、ピカソの『本を持つ女』だとしましたが、この絵は「アングルを踏まえたマリー・テレーズの肖像」です。ノートン・サイモン美術館では絵の解説の横にアングル作品の写真が掲示されていました(2012年時点)。その写真と説明(英文と試訳)を以下に掲載しておきます。
この解説の最後の方でピカソとアングルの類似性があげられていますが、その中で「優美で感覚的な線(graceful, sensuous lines)」と書かれているのが印象的です。
そして、このことは "本をもつ女" に関してだけではないのかも知れません。つまり「ピカソはアングルから学んだ」とはよく言われることですが、それはアングルの絵によくある「様式化」だけでなく、「優美で感覚的な線」も学んだのかと思います。
| バーンズ・コレクション | |||
| コートールド・コレクション |
の2つです。今回はその "シリーズ" の続きとして、アメリカのカリフォルニアにあるノートン・サイモン美術館のことを書きたいと思います。
電車で行ける
ノートン・サイモン美術館はロサンゼルス近郊のパサデナにありますが、ポイントの一つはロサンゼルスのダウンタウンから電車で行けることです。
ロサンゼルスの観光スポットと言うと、クルマがないと行けないところ、ないしは大層不便なところ(バスの乗り継ぎなど)もあるのですが(ディズニーランド、ナッツベリーファームなど)、ノートン・サイモン美術館に関しては2003年にメトロの「ゴールドライン」が開通し、電車で行けるようになりました。ダウンタウンのユニオン駅から乗って「メモリアル・パーク」という駅で下車します。
パサデナ・オールドタウン
メモリアル・パーク駅からノートン・サイモン美術館までは約1.2~3kmの距離ですが、是非、歩いていきましょう。というのも途中に "パサデナ・オールドタウン地区" があるからです。
パサデナは高級住宅街ですが、その中のオールドタウン地区は、昔からのレンガ造りの建物を生かした街づくりがされています。ここには各種のショップやアート・スポット、レストラン、カフェが立ち並び、大変おしゃれな感じのエリアです。そもそもパサデナ・オールドタウンがロサンゼルスの観光・ショッピングスポットの一つになっていて、美術に興味のない人でも楽しめます。

| ||
|
パサデナ・オールドタウンの界隈
| ||
私は過去3回、ノートン・サイモン美術館に行ったことがありますが、はじめの2回はクルマで、3回目は当時開通していたメトロで行きました。パサデナ・オールドタウンを散策し、ランチを食べ(KABUKI という寿司・和食レストラン)、それから美術館に行ったことを覚えています。
ノートン・サイモン美術館は、実業家であったノートン・サイモン(1907-1993)のコレクションを元に開設されたものです。その意味ではバーンズ・コレクションやコートールド・コレクションと似ています。その多くの所蔵作品のごく一部を以下に紹介します。

| ||
|
ノートン・サイモン美術館
| ||
スルバラン
実は次のスルバランの静物画が、個人的にはノートン・サイモン美術館の "一押し" の作品です。
| 以下に掲げる画像と英語の題名は、美術館のホームページに掲載されているものです。題名の直訳をつけました。 |

| ||
|
フランシスコ・デ・スルバラン
Francisco de Zurbaran(1598-1664) Still Life with Lemons, Oranges and a Rose(1633)
「レモンとオレンジとバラの静物」
( 62cm×110cm ) | ||
スルバランは17世紀のスペインの画家で、ベラスケスとほぼ同時代人です。ほとんどの作品は宗教画ですが、この絵は静物画です。ちなみにこの絵は『レモン、籠のオレンジ、茶碗』と呼ばれるのが普通です。プラド美術館に同じスルバランの『茶碗、アンフォラ、壷』という作品があります。

| ||
|
スルバラン
「茶碗、アンフォラ、壷」
プラド美術館
( site:www.museodelprado.es ) | ||
このプラド美術館の絵がスペイン静物画(ボデゴン。厨房画)の最高傑作という評価らしいのですが、個人的にはノートン・サイモン美術館の絵のほうが上だと感じます。アメリカの美術館にあるのが "不利" に働いているのではないでしょうか。
ノートン・サイモン美術館の『レモンとオレンジとバラの静物』は、ひょとしたら何らかの祭壇の静物を描いたものかもしれません。また、描かれているレモン、オレンジ、バラ、カップのそれぞれは、宗教的な何かの象徴かもしれない。ほとんど宗教画しか描かなかった作者を考えると、その可能性はあると思います。しかし我々としては、これを "純粋な静物画" として見たいわけです。
静物画として考えると、果物と食器を中心にした絵は他にもいっぱいあります。果物では柑橘類や葡萄、苺などが多く、食器では素焼、陶器、金属、ガラスなどが描かれます。画家が目指すのはまず、光で照らされた静物の「質感」の表現で、その描写技術を追求するわけです。このような静物画は、17世紀~18世紀のオランダ絵画にヤマのようにあるし、現代でもいろいろと描かれています。
しかし問題は「リアルな質感表現」以上のものを絵から感じられるかどうかです。この手の静物画は実際に現物を見て、その場で何かビビッと感じるものが「あるか・ないか」、それで評価をするしかない。それは極めて個人的なものだし、画像ではわからないところが多々あります。この絵を実際に見たときの「感じ」を言葉で表現するのは難しいのですが、何とか箇条書きにすると、
| ・ | 静粛 | ||
| ・ | 質素 | ||
| ・ | 澄んだ空気感 | ||
| ・ | モノが存在をしっかりと主張している | ||
| ・ | すがすがしい |
となるでしょうか。レモンと籠のオレンジとバラとカップがシンプルに横一列に並んでいるだけで、構図に作為が全くない(ように見えてしまう)のも影響しているのだと思います。本当は計算し尽くされた構図なのだろうけれど・・・・・・。描かれたレモンとオレンジのサイズが重要なのかも知れません。とにかくこの絵を見たときは率直に素晴らしいと感じました。
静物画を見て「あっ、いいな」を思ったのは、このスルバランの絵が初めてではありません。ミラノのドゥオーモの近くに「アンブロジアーナ絵画館」がありますが、そこにカラヴァッジョの「果物籠」という傑作があります。この絵も初めて見たときには感動しましたが、真横から果物籠を描くという構図のシンプルさは、スルバランに通じるものがあるような気がします。

| ||
|
カラヴァッジョ
「果物籠」(1599)
アンブロジアーナ絵画館(ミラノ)
( Wikimedia ) | ||
カニャッチ
今までの記事で宗教画をとりあげたことはほとんどなかったのですが、以前に唯一書いたマグダラのマリア( No.118「マグダラのマリア」)にちなんで、ノートン・サイモン美術館にある宗教画を取り上げます。

| ||
|
グイド・カニャッチ
Guido Cagnacci(1601-1663) Martha Rebuking Mary for her Vanity(1660)
「マリアの虚栄を責めるマルタ」
( 229cm×266cm ) | ||
何だか "騒々しい" 画面構成ですが、描かれている光景からしてキリスト教の題材と推測できます。画面の中央の床の女性はマグダラのマリアです。彼女のアトリビュート(持物)である香油の瓶が描かれています。マリアは肌を露出したり、また半裸の姿で描かれることも多い。
No.118「マグダラのマリア」に書いたように、一般に言われている「マグダラのマリア」のイメージは、聖書にある数カ所の女性の記述をパッチワークのように合体し、またその後の伝説も加味して作り上げられたものです。その中に、マグダラのマリアには姉のマルタがいて、マルタはキリストの昇天後に財産を使徒たちに寄付したが、マリアは自分の財産と美貌をもとに享楽的な生活にふけっていた、しかしその後マリアは改悛して神に帰依した、という聖書解釈(というより創作物語)があります。
そのマリアを、右側の姉のマルタが諫めている場面です。マリアはそれに従って豪華な衣装を脱ぎ捨て、宝石を床に投げやった。左の上には悪魔が描かれていて、おそらくマリアを誘惑しようとしているのでしょう。中央の天使は、そうはさせまいと必死に悪魔を追い払っています。右の上には、この家の侍女と思える女性二人が描かれている、そういう構図です。
ただしマリアの手をよく見ると、まだ宝石をつかんでいます。"回心しきれていない" マリアを描いているようであり、つまり心の葛藤を描いたのでしょう。ちなみにこの絵は普通「マグダラのマリアの回心」と呼ばれています。
西洋の古典絵画は、聖書(とギリシャ・ローマ神話)を知らないと意味がわからない、とよく言われます。確かにそうですが、聖書を熟知しているとしても意味が分からない絵がたくさんあるのですね。特に、キリストの使徒や弟子にまつわる絵画がそうで、この絵はその典型と言えそうです。聖書においてマグダラのマリアは、キリストの磔刑・埋葬・復活というキリスト教の根幹にかかわる重要場面のすべてに登場する女性です。この絵に描かれたような "マグダラのマリア" は、聖書とは無縁です。聖書の隅々まで知っていたとしてもこの絵の意味は分からない。このあたりが、キリスト教徒ではない日本人からすると "敷居が高い" ところでしょう。カトリック教国の人たちからすると常識かも知れないけれど。
しかしこの絵は、そういう宗教画としての解釈を離れたとしても、絵としての完成度が高い。強い光が劇的場面を演出しているのですが、明暗のコントラストだけでなく、外からの穏やかな光を感じます。
その中の「青」の色使いが美しい。右上の空の青、左上のガラスを通した空の微かな青、中央の天使の布と、左下のマリアが着ていたはずの衣装の高貴な(豪華な)青、そして右下のマルタの質素で "くすんだ" 青。この五箇所の青の配置が光っています。空の青はマリアが "完全に" 改悛することを示しているのでしょう。画家の技量の冴えを感じる一枚です。
クールベ

| ||
|
ギュスターヴ・クールベ
Gustave Courbet(1819-1877) Marine(1865/66)
「海」
( 50cm×61cm ) | ||
ノルマンディー地方の海を描いた作品です。スイス国境に近い山間部、オルナン出身のクールベは、大人になってから初めて海を見て感激したそうです。そして海の光景を多く描きました。全部で170点ほどあるとされます。我々が良く知っているのは、上野の国立西洋美術館やオルセー美術館にあるような「波が海岸に激しく打ち寄せる光景」の絵ですが、この絵は違います。「海」とはいいながら、海らしきものはあまり見あたりません。
遠浅の海で、潮の干満差が大きく、引き潮の時には広い干潟が出現する、その干潟を描いたと思われます。画面の3分の2以上は空で、湾の向こうにあると思える低い山が遠くに見えます。写実絵画なのだろうけれど、後の印象派の絵のようにも見えるし、それを通り越して抽象画のような感じもある。青と白とバラ色の色使いが美しい、よい作品だと思います。
マネ

| ||
|
エドゥアール・マネ
Edouard Manet(1832-1883) The Ragpicker(1865/70)
「くず拾い」
( 195cm×131cm ) | ||
No.36「ベラスケスへのオマージュ」で次のようなことを書きました。
| ◆ | マネはプラド美術館を訪れ、ベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けた。 | ||
| ◆ | 帰国後、ベラスケスへのオマージュとして『悲劇役者』(1866。ワシントン・ナショナル・ギャラリー)を描いた。 | ||
| ◆ | さらに、その一環として有名な『笛を吹く少年』(1866。オルセー美術館)を描いた。 |
ノートン・サイモン美術館の『くず拾い』も、まさにベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(No.36参照)の影響を感じる作品です。
ベラスケスの絵とマネのこの作品に共通するのは「背景をほとんど描かずに人物の全身像を描く」という手法です。かつ、職業に携わる人物の存在感を活写している。この絵もまた、マネが "ベラスケスの弟子" であることを表しているのでした。
ちなみに「くず拾い」というテーマでは、ボナールも描いていますね。No.95で書いた「バーンズ・コレクション」にボナールの「The Ragpickers」という作品があります(コレクションの Room 3 West Wall)。マネよりは40年ほど後の作品ですが、都市化が進んだパリの実状を描いたと言えるでしょう。社会における最下層の人であり、今で言うならホームレスでしょうが、そういうテーマにも斬新さを感じます。
もう一枚のマネ作品、『魚とエビのある静物』です。
|
| ||
|
エドゥアール・マネ
Edouard Manet Still Life with Fish and Shrimp(1864)
「魚とエビのある静物」
(45cm×73cm) | ||
No.155「コートールド・コレクション」で、マネの静物画が素晴らしいことを書きました。これはコートールド・コレクションを代表する作品と言える『フォーリーベルジェールのバー』に描かれた「カウンターの上の薔薇とミカン」のことでした。この絵以外に、マネの静物画を今まで2点とりあげています。
| 「アスパラガス」(1880) No.3「ドイツ料理万歳」 | |||
| 「スモモ」(1880) No.111「肖像画切り裂き事件」 |
ノートン・サイモン美術館の『魚とエビのある静物』も優れた作品です。"テーブルの海産物" というテーマはフランドル絵画によくありますが、このように画面の中心に "ゴロッと魚が一匹横たわっている図" はめすらしいのではと思います。『アスパラガス』も『スモモ』もそうですが、画家は明らかに魚にしかない固有の質感や雰囲気の表現だけに興味を持っています。印象派の先駆者らしい筆さばきで "鮮魚" の感じをうまくとらえていると思います。
ドガ
ノートン・サイモン美術館はドガの作品が非常に充実しています。それも油絵やパステル画だけでなく、彫刻がそろっている。彫刻といっても、ほとんどは No.86「ドガとメアリー・カサット」に出てきた "マケット" というやつです。ポーズの研究のために画家が制作した小さな彫刻です。この美術館には「踊り子」や「馬」のマケットがたくさんあって、それとともに「踊り子」や「馬」を画題とする絵が展示されています。ドガの制作態度がよく分かります。

| ||
|
| ||
なお、No.86で紹介した原田マハ氏の『エトワール』という短編小説は『14歳の小さな踊り子』という(マケットではない)ドガの彫刻がテーマになっていましたが、その像もあります(上の画像)。
ノートン・サイモン美術館が所蔵するドガの絵画作品を一つだけあげると、次の「Waiting」というパステル画です。母親と娘の踊り子でしょうか、何かを待っています。おそらくオーディションとか、何らかの試験、ないしは単に出番を待っているのかもしれない。踊り子は、待ち時間のあいだに手で足の踝をさすっているようです。一方の母親は緊張してじっと顔を前に向けている。視線には何も入っていないはずです。
ある一瞬を切り取る、というドガの画風が現れた一枚です。俯瞰する構図をとり、女性の表情を全く描かない、という描きかたも印象的です。

| ||
|
エドガー・ドガ
Edgar Degas(1834-1917) Waiting(1879/82)
「待つ」
( 48cm×61cm ) | ||
ゴッホ

| ||
|
フィンセント・ファン・ゴッホ
Vincent van Gogh(1853-1890) The Mulberry Tree(1889)
「桑の木」
( 54cm×65cm ) | ||
Mulberry とは「桑の実」のことですね。ということはこの絵は「桑の木 = 日本で言うヤマグワ」を描いたものです。
しかしこの絵から受ける印象として、黄葉になったヤマグワを描くことが目的という感じはしません。すべての形がうねっていて、現実とは遊離しています。そのように見えたというより、現実の形そのものには画家の関心がないようです。


| |||
|
ヤマグワの実のと黄葉
(site:www.tokyo-park.or.jp) | |||
画面に描かれている橙色のものは何でしょうか。必ずしも明確ではないのですが、個人的には「ヤマグワの実 = Mulberry」と解釈することにしています。もっとも、桑の実にしては大きすぎるし、それに色が変です。桑の葉が黄色に染まるとき、まだ残っている完熟した桑の実は橙色ではなく、赤黒いというか、人の目には黒く見えるものです。しかし画家にとってそれはどうでもよい。この位置に橙色を "分かるように" 配することが重要だったのでしょう。
黄・青をメインに緑・橙を配して絵を描く・・・・・・。まるで美術の演習のようですが、ゴッホの手にかかるとこういう絵になってしまうわけです。画家のずば抜けた色彩感覚を感じる一枚です。
余談ですが、前に掲げたカラヴァッジョの『果物籠』という絵にも、一見して桑(ヤマグワ)と分かる植物が描かれています。桑の若い木は葉に不規則な亀裂が入ることが特徴で、こういう形の葉は、人になじみのある木ではまず桑です。『果物籠』というタイトルの絵に桑を描き込むのは日本人からすると違和感があるのですが、これは当然、西欧文化においては「桑 = 実(Mulberry)= 果物」ということでしょう。もちろん東アジア文化では「桑 = 葉 = 養蚕」です。
なお、ノートン・サイモン美術館にはゴッホが母親を描いた肖像画があります。妹から送られてきた写真をもとに描いたものです。

|
フィンセント・ファン・ゴッホ Portrait of the Artist's Mother(1888) |
「画家の母の肖像」 ( 41cm×32cm ) |
アンリ・ルソー

| ||
|
アンリ・ルソー
Henri Rousseau(1844-1910) Exotic Landscape(1910)
「異国の風景」
( 130cm×163cm ) | ||
"空想の中の熱帯のジャングル" といった風情の作品です。こういったタイプの絵はルソー作品によくあります。以前の記事でとりあげた例では、No.72「楽園のカンヴァス」で引用した『夢』『蛇使いの女』、No.95「バーンズ・コレクション」の『虎に襲われる斥候』(Room 14 North Wall)『熱帯の森を散歩する女』『原始林の猿とオウム』(Room 11 North Wall)などです。
一連の絵で感じるのは「植物」や「緑」に対する画家の強いこだわりです。「植物でカンヴァスを埋め尽くすために、わざわざ見たこともない熱帯のジャングルを描いている」という感じがします。No.155「コートールド・コレクション」で引用した『税関』という絵を思い出します。パリの南門の税関を描いているはずなのに「ありえないほどの緑」が溢れている。つまり、パリの税関なら違和感が出くる、しかし異国の熱帯ならいいだろう、みたいな・・・・・・。
パリでの生活が長い画家にとって、都市化が進む大都会からどんどん失われていく「緑」に対する郷愁を絵にした、それが "ジャングル・シリーズ" であり、画家にとっての楽園だった・・・・・・。そんなことを想像したりします。
モディリアーニ

| ||
|
アメディオ・モディリアーニ
Amedeo Modigliani(1884-1920) Portrait of the Artist's Wife,Jeanne Hebuterne(1918)
「画家の妻、ジャンヌ・エビュテルヌの肖像」
( 101cm×66cm ) | ||
妻のジャンヌを描いた絵ですが、その形といい、目の描き方といい、モディリアーニの絵の一つの典型です。ジャンヌも非常に落ち着いていて、穏やかという感じを受けます。
ジャンヌを描いた絵は多くありますが、この絵はモディリアーニが妻のジャンヌを最もヴィーナスに引き寄せて描いた絵だと思います。ヴィーナスとは、もちろんボッティチェリが「ヴィーナスの誕生」で描いた女性像です。
ピカソ

| ||
|
パブロ・ピカソ
Pablo Picasso(1881-1973) Woman with a Book(1932)
「本を持つ女」
( 131cm×98cm ) | ||
ノートン・サイモン美術館のホームページに次のような意味のことが書いてあります。
| この絵は、ピカソがアングルの『モワテシエ夫人の肖像』を踏まえ、マリー=テレーズを描いたものである。 |
実際に美術館に行くと、このピカソの絵の解説の横にアングルの絵の写真が掲示されていました。

| ||
|
ドミニク・アングル
「モワテシエ夫人の肖像」(1856) ロンドン・ナショナル・ギャラリー ( site:www.nationalgallery.org.uk ) | ||
なるほど、と思います。ピカソの絵の後ろの方に "黄色い額縁の絵のようなもの" がかかっているのですが、実はこれは『モワテシエ夫人の肖像』における "鏡に映った横顔" なのですね。またピカソの絵では女性が本を妙な形に開いていますが、これはアングルの絵の「扇」に似せたということでしょう。ピカソは "アングルを踏まえて描いた" という証拠を絵の中に残したわけです。
ピカソの「アングルを踏まえた絵」は、この絵だけでなくいろいろあると言います。No.72で引用した原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』に、
| ・ | ピカソはアングルから様式化を学んだ。 | ||
| ・ | 様式化があって、その究極に抽象化がある。 |
という意味のことが書かれていました。小説の中の人物の発言ですが、作者の(ないしは美術界の)意見が入っていると見ていいと思います。確かにアングルが人物を描いた絵には、一見リアリズムのように見えながら、よく見ると「異様に引き延ばされた人体 = 現実にはありえないデフォルメ」がよくあります。そういえば『モワテシエ夫人の肖像』も、鏡に映った夫人の顔は、光学的にはありえない配置・構図です。
その『モワテシエ夫人の肖像』ですが、アングルはこの絵の5年前にも肖像画を描いています。それは夫人の立像で、アメリカのワシントン D.C.のナショナル・ギャラリーにあります。

| ||
|
ドミニク・アングル
「モワテシエ夫人の肖像」(1851)
ワシントン・ナショナル・ギャラリー
( site : www.nga.gov ) | ||
2つの絵から伝わってくるのは、夫人の "豊満でふくよかな感じ" であり、"ギリシャ・ローマ彫刻によくあるような彫りの深い古典的な顔立ち" です。これはピカソのいわゆる「新古典主義の時代」の絵に描かれた人物像を連想させます。特に額と鼻筋がつながっている顔立ちはピカソの人物像とそっくりだと思うのです。ピカソの「新古典主義の時代」の絵は『モワテシエ夫人の肖像』を始めとするアングル作品、特に古典的風貌の人物像に触発されたのではないでしょうか。
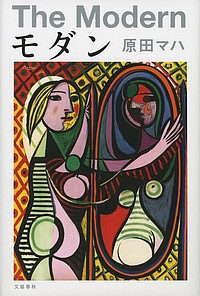
| |||
|
原田マハ「モダン」
表紙の絵は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵するピカソの「鏡の前の少女」
| |||
この MoMA の絵は、No.150「クリスティーナの世界」で引用した原田氏の短編小説集『モダン』の表紙になりました。モダン・アートの殿堂である MoMA を舞台とし、モダン・アートをテーマにした短編集だから『モダン』という本の題名になっているわけです。その表紙にピカソの『鏡の前の少女』を採用するということは、この絵は MoMA が所有するモダン・アートの代表格ということでしょう(少なくとも原田氏の考えでは)。
だとすると、ノートン・サイモン美術館の『本をもつ女』もモダン・アートの代 表格と言っていいのではないか。そして、描かれているテーマの影響だと思うのですが、ノートン・サイモンの絵の方が MoMA の絵より "品がある" 感じがします。
黒くて太い線で画面を区切り、強い色彩を乱舞させるという "どぎつい" 絵画手法だけれど、絵の全体から受ける印象は不思議と落ち着いていて、すっきりとしています。女性の可愛らしさや色香もしっかりと出ている。それでいて、ピカソの絵に時として見かける "下品な感じ" がありません。
ノートン・サイモン美術館のホームページの解説にもあるのですが、20世紀の画家の大きな仕事は「抽象と具象のバランスをどうとるか」だったわけです。『本をもつ女』は『鏡の前の少女』と似ていると書きましたが、"抽象化の度合い" は明らかに違います。ピカソも、同じモデルを描きつつ、いろいろと試行しているのです。一歩間違えば駄作になりかねないような微妙な均衡の上にこの絵は成り立っているようで、大変にいい絵だと思います。この作品は、スルバランに次いでノートン・サイモン美術館の「二押し」の作品です。
個人的には、ノートン・サイモン美術館の「一押し」がスルバラン、「二押し」がこのピカソなのですが、二つとも(たまたま)スペイン人の作品です。そして、スルバランはプラド美術館の静物よりも訴えてくるものがあり、ピカソは MoMA のマリー=テレーズよりも素晴らしい・・・・・・。というのが言い過ぎなら、プラド美術館とMoMAと同等の作品がノートン・サイモン美術館にある・・・・・・。この美術館のレベルの高さを象徴しています。
ノートン・サイモン美術館
ノートン・サイモン美術館が所蔵している欧米の絵画は、上にあげた以外にも、ルネサンス以前の宗教画の数々から始まり、有名な画家では、
| リッピ、ボッティチェリ、ラファエロ、エル・グレコ、ルーベンス、レーニ、ロラン、ルイスダール、レンブラント、ハルス、シャルダン、ゴヤ、ヴジェ=ルブラン、アングル、コロー、ドービニー、ドーミエ、ファンタン=ラトゥール、セザンヌ、モネ、ルノワール、ピサロ、ロートレック、ゴーギャン、ボナール、シャヴァンヌ、マティス、ルオー、ブラック、カンディンスキー、クレー、サム・フランシス、ウォーホール |
などの作品があります(絵を紹介した画家を除く)。またこの美術館は広重の浮世絵を大量に所蔵していて、さらに北斎もあります。私が3回目に行ったときには、広重の『富士三十六景』や『名所江戸百景』からの数枚が展示してありました。
この美術館は、全体的に質が高く「中庸でノーマルなコレクション」という感じです。No.95 で紹介した「バーンズ・コレクション」と比較すると、それが鮮明です。バーンズ・コレクションは、ルノワールが 181点あるとか、セザンヌやマティスも大量にあるとか、23ある展示室にはアメリカ絵画が少なくとも2点あるとか、コレクターの「強いこだわり」が随所にあるのですが、ノートン・サイモン美術館にはそれはありません。美術好きの実業家が大金持ちになり、有名画家の良い絵を素直に集めたという感じがします。西洋の絵画の歴史もよく分かる、そういった美術館です。
| 蛇足ですが、バーンズ・コレクションと違って、ここは "普通の美術館" です。展示替えや貸し出しで、上にかかげた作品も常に展示してあるとは限りません。ホームページを見ると、ドガの『Waiting』は今は展示していないようです(2015年10月17日現在)。パステル画を常時展示するのは難しいのかもしれません。 |
ノートン・サイモン美術館は、中庭と敷地内の庭が広くて美しいことも特徴です。しゃれたティー・ハウスもあります。また始めに述べたように、近くにはパサデナ・オールドタウンがあります。そういった周辺まで含めて、ロサンゼルスで1日を過ごすにはよい場所だと思います。

| ||
|
ノートン・サイモン美術館の庭
| ||
| 補記:本を持つ女 |
本文中でノートン・サイモン美術館の "二押し" の作品が、ピカソの『本を持つ女』だとしましたが、この絵は「アングルを踏まえたマリー・テレーズの肖像」です。ノートン・サイモン美術館では絵の解説の横にアングル作品の写真が掲示されていました(2012年時点)。その写真と説明(英文と試訳)を以下に掲載しておきます。

| ||
|
ノートン・サイモン美術館の「本を持つ女」の説明パネルとアングル作品の写真(2012年)。
| ||
|
この解説の最後の方でピカソとアングルの類似性があげられていますが、その中で「優美で感覚的な線(graceful, sensuous lines)」と書かれているのが印象的です。
そして、このことは "本をもつ女" に関してだけではないのかも知れません。つまり「ピカソはアングルから学んだ」とはよく言われることですが、それはアングルの絵によくある「様式化」だけでなく、「優美で感覚的な線」も学んだのかと思います。
No.156 - 世界で2番目に有名な絵 [アート]
前回の No.155「コートールド・コレクション」で、日本女子大学の及川教授の、
という主旨の発言を紹介しました。これはあるIT企業(JBCC)の情報誌に掲載された対談の一部です。その対談で及川教授は別の発言をしていました。大変興味をそそられたので、その部分を紹介したいと思います(下線は原文にありません)。
このくだりを読んで、なるほどと思いました。及川教授の、
という主旨の発言に共感するものがあったからです。この絵の世界における通称は「The Great Wave」もしくは「The Big Wave」です。なお日本語題名の「浪裏」は「波裏」と表記されることもあります。
海外旅行に行くと、絵のポスターや絵はがきを売っている店があります。もちろんその「ご当地(画家や題材)に関する絵」が多いわけですが、世界の有名な絵のポスターや絵はがきも売っていたりする。美術館のミュージアム・ショップにも、その美術館の絵だけでなく、一般に有名な絵のカードや複製があったりします。そういうところで「The Great Wave」は何回か見かけた記憶があるのです。
私の配偶者は、この絵の "波頭" の部分だけを取り出して巨大なオブジェにしたものにヨーロッパの街中で遭遇しました(ドレスデン。次の画像)。また私もプラド美術館のミュージアムショップで、「神奈川沖浪裏」をもとに自由に発想を膨らませて作られた子供向け絵本を見かけたことがあります。

(ドレスデン。後ろに見えるのはエルベ河)
街のオブジェになったり絵本になったりと、単に絵が紹介されたり複製画が売られるだけなく、絵のもつイメージが増殖しているわけで、この絵の認知度は相当高いと推測できます。
北斎のこの版画は、19世紀後半からヨーロッパで知られていました。有名なのはドビュッシーの交響詩「海」(1905)です。その楽譜が出版されたとき、表紙に使われたのが北斎の「The Great Wave」でした。そもそもドビュッシーの作曲の契機になったのが、この絵を見たことだと言われています。また、ラヴェルが作曲したピアノ組曲「鏡」(1905)の第3曲「海原の小舟」も「The Great Wave」からインスピレーションを得て作曲されたものと言われています。
ドビュッシーに戻りますと、作曲家にとって書き上げた楽譜は、いわば「命」のはずです。アーティストが自分の命とも言うべき出版物の表紙に別のアーティストの作品(絵)をもってくるということは、その絵、ないしは絵の作者に対する "オマージュ" だと考えられます。ドビュッシーは北斎を見て、どこにでもある波をアートに仕立てたことに感じ入り「自分は音楽で」と考えたとしても、それはありうることだし、楽譜の表紙からすると "ごく自然な推測" だと思います。
次の写真はドビュッシーがストラヴィンスキーと写っている写真です。音楽に変革をもたらした両巨人のツーショットですが、後ろの壁に2枚の浮世絵が飾られていて、そのうちの上の方は『神奈川沖浪裏』です。ちなみに写真を撮影したのは、これも著名作曲家のサティです。
そのドビュッシーと一時 "親しい仲" だったのが、2歳年下の彫刻家、カミーユ・クローデルです。彼女はロダンの弟子ですが、その彼女も北斎に影響を受けた彫刻を作っているのです。そのあたりの事情を、木々康子氏の本から引用します。
二人の中は4年ほどで終わるのですが、ドビュッシーは別れた後もカミーユを想っていたそうです。またカミーユも、有名な「ワルツ」という彫刻をドビュッシーに贈ると約束した、とあります。カミーユ・クローデルが北斎に影響を受けたとされる彫刻は、パリのロダン美術館にある『波』という作品です。
以上は北斎の影響を受けた絵・彫刻・音楽などのアート作品ですが、『神奈川沖浪裏』はさらに現代のデザインの分野にも影響しています。その一つの例ですが、ボードショーツ(サーフィン用のショートパンツ)で有名なアパレル・ブランドに Quiksilver(クイックシルバー。スペルに c はない)があります。もともとオーストラリア発のブランドですが、現在はアメリカ・カリフォルニア州のハンチントンビーチに本社があります。この Quiksilver のロゴは、北斎の『神奈川沖浪裏』を図案化したものです。ということは、このロゴには富士山がデザインされていることにもなります。
Quiksilver の創始者が『神奈川沖浪裏』に感動してロゴにしたそうですが、絵に描かれた舟をサーフボードに見立てると、いかにもサーフィンに似つかわしい。"The Great(Big)Wave" というタイトルの絵をボードショーツのブランド・ロゴにするのはまさにピッタリだと思います。
神奈川沖とは江戸時代の神奈川宿の沖で、つまり東京湾のどこかでしょうが、現代人としては湘南の海と考えてもよいわけです。鎌倉・藤沢・茅ヶ崎の湘南海岸でサーフィンを楽しむ日本人サーファーは、是非とも Quiksilver のボードショーツを着用して欲しい気がします。
本題の「世界で2番目に有名な絵」に戻ります。冒頭に引用した及川教授の発言を読んだときに思ったのですが、「The Great Wave(神奈川沖浪裏)が世界で2番目に有名な絵」というのは、そこまでは断言出来ないのではないでしょうか。つまり「モナ・リザが世界で1番有名な絵」とは誰もが認めるでしょうが、2番目というのは果たしてどうなのか。
が実状に近いのではと思ったのです。ということで、以下に「世界で2番目に有名な絵の候補」をいろいろと推測してみたいと思います。
「世界で2番目に有名」とは?
推測の前提として「世界で2番目に有名」という言葉の定義をする必要があります。まず「世界で」のところですが、対象は世界中の国々であり、特定の地域・文化圏ではないこととします。かつ、美術の愛好家というのではなく、普通の人、美術に関心がない人までも含みます。また子供は別にして、老若男女すべてということにします。
次に「有名な」の定義ですが、
という3つの条件が満たされることとします。① の「知っている」だけでは「有名」というには弱い。① に加えて、② か ③ のどちらかという条件にすると候補は断然増えるでしょうが(それでもいいとは思いますが)ここでは「厳格に」① ② ③ のアンド条件だと考えます。
もちろんアンケート調査ができるわけではありません。そんな調査をするメディアもないと思います。そこで ① ② ③ を満たしやすい「付加条件」を想定して推定の助けにしたいと思います。
まず、多くの人が「① 絵を知っている」ためには、
ことが重要でしょう。そういう絵は「世界で有名」の定義からして有利になります。もちろんこういった条件がなくても多くの人に認知されていればよいわけですが、一般論としての "有利な条件" ということです。また「② 画家の名前が言える」ためには、
と断然有利です。さらに「③題名を言える」ためには、
と有利になります。こうなると、各国の義務教育の教科書に出てくるような絵や画家が候補になる気もしますが、現在はメディアが発達しているので、それだけでは決まらないでしょう。
2番目に有名な絵の候補
以上の「条件」を前提に「世界で2番目に有名な絵の候補」をあげてみたいと思います。
まず対談に出てきた『ゴッホのひまわり』です。これは鋭い指摘で「世界で2番目に有名な絵の候補」に十分なると思います。花瓶の向日葵の束をカンヴァスに "ドン" と描いた画家はあまりいないし、モチーフがシンプルで、絵としてのインパクトも強い。そもそも向日葵という花が、突出して "インパクトの強い花" です。これが「アイリス」や「白いバラ」だと、ここまで有名にはならないのですね(メトロポリタンにゴッホの傑作があるけれど)。花そのものに "威力" があり、また世界の多くの地域で栽培されてもいる。題名の「ひまわり(Sunflowers)」も簡潔で覚えやすい。さらにゴッホは超有名な画家です。
しかし「世界で有名な絵のランキング」にとって非常に残念なのは『ゴッホのひまわり』は複数あることですね。「花瓶の向日葵の束」という構図に限定しても、消失したものを除いて現存する作品が6点あり、そのうち美術館で見られる絵は5点あります。描かれている向日葵の本数とともにリストすると、
となります(そのほかに3本のひまわりの絵がある)。つまり『ゴッホのひまわり』は "作品群" なのです。どれかがダントツに有名というわけではありません。普通、写真などでよく見かけるのは15本の3作品で、日本ではもちろん東京の作品ですが、ミュンヘンとフィラデルフィアの12本も捨てがたい。つまり『ゴッホのひまわり』が「世界で2番目に有名な絵』だとすると、2番目が5つあることになります。これはちょっと "マイナス・ポイント" になるでしょう。
19世紀の近代絵画つながりで他の2番目候補をあげると、『ドガの踊り子』も『ゴッホのひまわり』と似たような事情にあります。写真を見せられて「知っています。ドガの踊り子です」と答えられる人は世界にものすごくいる気がします。
しかしドガが描いた踊り子の絵は、有名なものだけで複数あります。最も有名なのはオルセー美術館の絵でしょうが、前回紹介したコートールド・コレクションの絵もよく見る絵です。むしろこちらの方が踊り子らしい感じもする。オルセーの絵がよく知られているのは、コートールド・ギャラリーよりは桁違いに有名な "オルセー美術館にあるから" という気がします。『ドガの踊り子』が世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては確定しない。
しかも『ゴッホのひまわり』とは違って『ドガの踊り子』は構図が多様です。それこそが芸術家としての創造性の発揮であり、デッサンや習作は別にして、ドガは全く同じ構図の完成作を6枚も7枚も描くというような "アマチュアっぽい" ことはしないわけです。しかしこのことが「有名な絵ランキング」にとっては "減点" の対象になるでしょう。
19世紀の著名画家をもっと考えてみると、印象派の巨匠、クロード・モネはどうでしょうか。『モネの睡蓮』は著名ですが、睡蓮の絵は『ゴッホのひまわり』や『ドガの踊り子』以上にたくさんあります。写真を見せられて「知っています。モネの睡蓮です」と答えられる人は多数いるでしょうが、世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては全く確定しないことになります。
では『睡蓮』がだめなら、パリのマルモッタン美術館に1枚しかない『印象・日の出』はどうか。この絵の "難点" は、朝靄のたちこめる港にボーッと昇った太陽というモチーフが、絵全体のインパクトとしては弱いことです。そういう、少々霞んだ朝の空気感から受ける人間心理をダイレクトにカンヴァスに定着したのが「印象派」の印象派たるゆえんであり、絵画史を塗り変えた作品なのだけれど・・・・・・。
ルノワールはどうでしょうか。ルノワールの「かわいらしい少女の絵」や「家庭的な雰囲気の中にいる複数の女性の絵」(たとえばピアノを弾く光景)には、大変に有名な絵があります。しかしそういうジャンルのルノワールの絵は複数あって、どれかがダントツに有名というわけではないと思います。パリの風俗を活写した絵としては『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』が非常に有名ですが、この絵の "難点" は、題名が(フランス人以外には)難しいことです。
その他、マネ、セザンヌ、マティスなどを考えてみても、傑作はたくさんあるけれどダントツに有名な "この1枚" が思い当たりません。「ミレーの落穂拾い」は有力な感じがしますが、淡々とした農家の日常を描いたという画題のインパクトが弱いような気がします。そういう画題を芸術にしたのが価値なのだけれど。
少しだけ時代を遡ってドラクロワはどうでしょうか。ルーブルに『民衆を導く自由の女神』という有名な絵があります。絵の題名として「自由の女神」ないしは「自由」でもよいとするなら、この絵は「世界で2番目に有名」の候補になる感じもします。
しかし問題は絵のモチーフです。描かれた文化的背景を全く知らない人にとってみると、この絵は「死屍累々の男の中を、裸のお姉さんが進んでいる不思議な絵」としか見えないでしょう。この絵はフランス革命の理念(実際には1830年の7月革命)を表していて、「裸のお姉さん」は「自由」の擬人化であり、フランス語の題名を直訳すると「民衆を率いる自由」となるわけです。
しかし世界にはいろんな文化があり、こういうフランス史や西欧文化(抽象概念の擬人化)ベッタリの絵は「世界で2番目に有名」と言えるほどには広まりにくいのではないかと思います。自由の女神がフランス国旗を持っていたりするのも、グローバル視点ではマイナス・ポイントになるでしょう。
18 - 19世紀の絵画
ルーブルつながりでは「ナポレオンの戴冠式」も有名ですが、この絵も「フランスの歴史ベッタリの(当時における)プロパガンダ絵画」というのがマイナス・ポイントになるし、それに、この絵の作者名を即答できる人は多くはないのではと思います(= ダヴィッド)。
ダヴィッドの同時代人に、スペインのゴヤがいます。『ゴヤの裸のマハ、着衣のマハ』の2部作はどうでしょうか。この作品の "難点" は2枚でペアということと、それをさしおいたとしても、女性の裸体を描いていることです。「世界」というレベルで考えると女性の裸体がオープンになることを嫌う、ないしはタブーになっている文化圏があります。「世界で2番目」とするには問題があるような気がします。それはドラクロワの『民衆を導く自由の女神』も同じでした。
17世紀の絵画
時代を遡って、17世紀の絵画で「世界で2番目に有名な絵」の候補を探すと、やはりフェルメールの『真珠の耳飾りの少女』でしょう。女性の肖像画はいっぱいありますが、「女性の振り向きざまを視線を合わせる構図で描いた "西洋版・見返り美人" の絵」というのは極めて少ない。名のある絵ではグイド・レーニの『ベアトリーチェ・チェンチの肖像』、ヴィンターハルターの『オーストリア皇后エリザベートの肖像』ぐらいでしょう。この絵の独自性と、少女の表情から受けるインパクトの強さは、有名になる素質十分といったところです。
しかし、フェルメールの人気は最近の数十年のことだと言いますね。「世界」というレベルで考えたとき、この絵の浸透度合いはどうか、少々疑問になるところです。日本でも「フェルメール、フェルメール」と大騒ぎするようになったのは、せいぜいこの20年程度でしょう。それと、題名が少々長いのが気にかかる。ただし、題名は画家がつけたわけではないので『真珠の耳飾り』でもよいし、別名である『青いターバンの少女』でもいいわけです。
17世紀の絵画ということで考えると、ベラスケス、ルーベンス、レンブラントといったビッグ・ネームがあるわけですが、作品の芸術的価値は別にしてダントツに「世界で」有名な1枚という視点だけで考えると、いずれも弱いと考えます。
ルネサンス絵画
では時代をさらに遡って、イタリア・ルネサンス期の絵画はどうか。まず思いつくのは『ダ・ヴィンチの最後の晩餐』でしょう。
しかし「最後の晩餐」の難点は、1番目も2番目もダ・ヴィンチではおもしろくない(?)ということです。さらにもっと本質的には、この絵のテーマがキリスト教そのものだということです。「世界」という範囲で考えるとキリスト教と無関係な人たちも多いし、それどころかキリスト教と対立している人たちがいる。たとえばイスラム教の世界人口は15億人と言いますね。イスラム教の人たちにとってダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はよく知られた絵なのかどうか。どうも違うような気がします。もちろん大多数のイスラム教徒の人たちはキリスト教徒と仲良くしようと考えていると思いますが・・・・・・。
宗教画であることがマイナス点になるという事情は「ラファエロの聖母」や「ミケランジェロの最後の審判」も同じです。ラファエロの聖母は "似たような絵" が何枚かあり(『聖母子とヨハネ』『牧場の聖母』『大公の聖母』など)、ピンポイントで特定するのが難しいという問題点もあります。"似たような絵" をたくさん描いたからこそ「聖母の画家」なのです。
では、ルネサンス期の「キリスト教とは無関係な絵画」はどうでしょうか。その筆頭は『ボッティチェリのヴィーナスの誕生』でしょう。これは有名な絵ですが、いくつか問題点があって、まずキリスト教とは無縁だけれどもギリシャ神話という、これまた特定文化圏のモチーフであることです。さらに "女性の裸" を描いたことがこの絵の西洋絵画史上における革命なのだけれど、それを嫌う人たちが世界にはいるに違いない。ボッティチェリという画家の名前も言いにくいし、覚えにくい。ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロよりは、画家の有名度においてワン・ランク下がるような気がします。
20世紀 - ピカソ
時代を逆に20世紀に向けると、超有名画家であるピカソが思い浮かびます。『ピカソのゲルニカ』はどうでしょうか。確かにこれは有名という感じがします。
しかし難点は、ゲルニカがスペインの小さな都市の名前であり、かつ絵のモチーフがスペイン内戦という20世紀の歴史に根ざしていることです。それだからこそ、この絵の意義があるのだけど・・・・・・。モチーフとしても、何が描かれているのかが一見しただけでは分かりにくい。歴史的背景を知ってよく見ると圧倒される、という絵なのです。
「アヴィニョンの娘たち」という、これまたピカソの有名な絵もありますが、これは「絵画の革命」だから有名なのであって、果たして美術に関心がない人からみてどうなのか、大いに疑問が残るところです。
「ゲルニカ」や「アヴィニョンの娘たち」よりも、ひょとしたら世界で2番目に有名の候補になりやすいのは『ピカソの泣く女』でしょう。モチーフはシンプルだし、絵のインパクトも強い。題名も簡潔です。この絵に問題があるとしたら、絵としてのインパクトが強い分、キュビズムという絵画手法に違和感を覚える人が多いのではと想像されることです。それが絵の浸透にネックになるのではないか。
北斎の強力なライバル
以上のように順に考えてみると『葛飾北斎の神奈川沖浪裏』=『Hokusai の The Great Wave (The Big Wave)』は、世界で2番目に有名な絵の候補であるだけでなく、極めて有力な候補だと言えそうです。最初に引用した及川教授の「(世界で2番目に有名な絵は)葛飾北斎の大波の絵と言われています」という発言も、一部の美術関係者の憶測ではなく、それなりの根拠がある信憑性が高い話だと考えられるのです。
・・・・・・ と、安心するのはまだ早いことに気づきました。北斎の「強力なライバル」があることに思い立ったのです。それは『ムンクの叫び』です。
この絵はまず、何が描かれているかが一目瞭然であり、題名も絵をストレートに表していて、単純で覚えやすい。ムンク独特の表現手法が強烈で、他にはあまりなく、印象に残りやすい。画家の名前はピカソやダ・ヴィンチほどには有名でないが、それを言い出すと Hokusai も同じです。『叫び』を知って "ムンク" の名を覚えた人も多いはずだし、逆にムンクの作品はこれしか知らない人も多いと思える。このあたりは Hokusai と似ているでしょう。この絵は2番目に有名の候補になりうるし、しかもかなりの有力候補ではないでしょうか。
『ムンクの叫び』について思い当ることがあります。![[げっそり]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/252.gif) は docomo/au 共通絵文字で「げっそり」という名前がついていますが、実はこれは『ムンクの叫び』にヒントを得てデザインされたものではないでしょうか。叫んでいるのは「げっそり」と痩せた人です。だとしたら、その影響力や恐るべしということになります。北斎もうかうかしていられない。
は docomo/au 共通絵文字で「げっそり」という名前がついていますが、実はこれは『ムンクの叫び』にヒントを得てデザインされたものではないでしょうか。叫んでいるのは「げっそり」と痩せた人です。だとしたら、その影響力や恐るべしということになります。北斎もうかうかしていられない。
考えてみると『The Great Wave』と『叫び』には次のような共通点があります。
などです。ちなみに北斎の波の装飾的表現は、別に北斎独自のものではありませんが、それはあくまで「日本人だからそう考える」わけです。日本美術史を知らない世界の多く人にとって、あの波の表現方法は「Hokusai の Wave」であり、また「Hokusai」の名はこの絵で知った、ないしは「Hokusai」の作品はこれしか知らない、という人は多いと思います。
北斎の "ライバル" ということでは『ゴッホのひまわり』『ピカソの泣く女』『フェルメールの真珠の耳飾りの少女』なども有力なことには違いありません。今まで書いたように、それぞれ難点があるけれど・・・・・・。
「世界で2番目に有名な絵」は何か、「葛飾北斎の神奈川沖浪裏」はその最有力候補ではないかという考察(?)を通して感じたことが2つあります。それを以下に書きます。これは "まじめな" 考察です。
『モナ・リザ』という特別な存在
「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して分かるのは、『モナ・リザ』(国によっては『マダム・ジョコンダ』)という絵が特別であることです。確かにこの絵は画家がメジャー、モチーフがシンプル、題名もシンプル(固有名詞だけど)、特定文化に依存しないなど、有名になるベーシックな条件が備わっています。
しかし『モナ・リザ』は、どこにでもありそうな女性の肖像画なのですね。そこに北斎やムンクのような特有のデフォルメや印象に残る強烈さがあるわけではない。我々は小さい頃から『モナ・リザ』と知っているから、一見して他の絵と区別できます。しかしそういう知識が全くないという前提で考えてみると、これが一見して他と区別できる絵だとはとても思えない。
しかし人々の印象に残り、語り伝えられ、メディアでも紹介され、小説のテーマにもなり、大傑作だという評価をうけ、ルーブルのこの絵の周りは長蛇の列になる。その理由はというと、多くは「モナ・リザの表情」に起因しているのですね。これについては No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で、次のように書きました。
「どこにでもありそうな女性の肖像画が世界で1番有名な絵である」という、この事実にこそ『モナ・リザ』の驚異があるのだと思います。結局のところ、人間は人間に一番関心があるのでしょう。それを暗示しているようです。『ムンクの叫び』が北斎の強力なライバルと書いたのも、実は「人間を描いているから」でした。
我々は「神奈川沖浪裏」を知っているか
「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して感じたことの2番目は、我々日本人は、たとえば外国の人に『神奈川沖浪裏』を説明できるか、ということです。まず日本人として、この絵を "本当に" 知っているかどうかが問題です。はじめの方に「有名」の定義として、
の3条件をあげました。おそらく多くの日本人は ① ② は大丈夫だと思います。しかし ③ はどうでしょうか。及川教授の対談にあったように、題名は? と聞かれて、
のどちらかを答えることができる人がどれほどいるかが問題です。「大きな波」では、絵の説明にはなっているけれど「題名」ではない。『大波』という略称が日本で一般的になっているわけでもないでしょう。波間に見える富士山、と答えたとしたら、ますます題名ではない。
世界で2番目に有名な絵(の有力候補)だから、この絵を知っている人は世界中に大変たくさんいます。絵の作者名(Hokusai)を言える人も多いはずです。そして「題名は ?」と聞かれたとき、たとえば英語圏や英語を話せる人で Hokusai を知っている人なら「The Great/Big Wave」と答えるのではないでしょうか。だとしたら、
という公算が大だと思うのです。日本文化を象徴する絵なのだから、せめて日本人としては題名だけでも知っておきたいものです。
この絵を外国の方に説明するときには「富士山を描いた絵」ということは言った方がよいと思います。そうとは気づかない人もいるはずです。また三隻の舟には人が乗っていて、18世紀の日本では実際にこのような舟で沿岸輸送をしていたことも知っておいた方がよいと思います(こんな大波の中で輸送するかどうかは別にして)。
この絵を一言で言うと「ローカルだけどグローバル」ということかと思います。完全な日本文化の中から一人の「天才」によって生み出されてものだけど、グローバルに認知され「世界で2番目に有名な絵」になった。
しかしこの絵は完全にローカルなわけではありません。西欧から2つの点で影響を受けています。まず北斎の当時から、使われた青色が輸入合成顔料であるプルシアン・ブルーです(No.18「ブルーの世界」参照)。江戸時代の言い方では「ベロ藍」ですが、この "ベロ" とはベルリンのことなのですね。発明されたのが当時のプロイセンの首都、ベルリンです。
さらにこの絵は西洋画法(特に遠近法)の影響を受けているのでしょう。厳密な遠近法ではないかもしれません。しかし構図は、明らかに円と螺旋と直線で構成されていると感じます。「幾何学的な描線で骨格の構図を決める」というところに遠近法との非常な類似性を感じます。
ローカルだけれどグローバル。それは「グローバルな絵画技術を取り入れつつ、あくまでローカルに描き、結果としてグローバルに有名になった」という意味です。そして、それを生み出した北斎という画家のすごさに改めて感嘆するのです。
| サント・ヴィクトワール山は、セザンヌにとっての富士山 |
という主旨の発言を紹介しました。これはあるIT企業(JBCC)の情報誌に掲載された対談の一部です。その対談で及川教授は別の発言をしていました。大変興味をそそられたので、その部分を紹介したいと思います(下線は原文にありません)。
|
このくだりを読んで、なるほどと思いました。及川教授の、
| 葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」は世界で2番目に有名な絵 |
という主旨の発言に共感するものがあったからです。この絵の世界における通称は「The Great Wave」もしくは「The Big Wave」です。なお日本語題名の「浪裏」は「波裏」と表記されることもあります。

| ||
|
葛飾北斎
「神奈川沖浪裏」 | ||
海外旅行に行くと、絵のポスターや絵はがきを売っている店があります。もちろんその「ご当地(画家や題材)に関する絵」が多いわけですが、世界の有名な絵のポスターや絵はがきも売っていたりする。美術館のミュージアム・ショップにも、その美術館の絵だけでなく、一般に有名な絵のカードや複製があったりします。そういうところで「The Great Wave」は何回か見かけた記憶があるのです。
私の配偶者は、この絵の "波頭" の部分だけを取り出して巨大なオブジェにしたものにヨーロッパの街中で遭遇しました(ドレスデン。次の画像)。また私もプラド美術館のミュージアムショップで、「神奈川沖浪裏」をもとに自由に発想を膨らませて作られた子供向け絵本を見かけたことがあります。

(ドレスデン。後ろに見えるのはエルベ河)
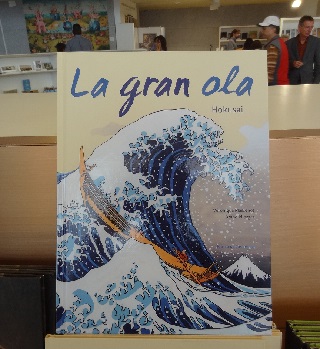
| ||
|
プラド美術館の北斎
プラド美術館のミュージアム・ショップで見かけたスペイン語の絵本、「La gran ola Hokusai」。「神奈川沖浪裏」をもとに、ストーリーを膨らませて絵本に仕立てたものである。「La gran ola」はスペイン語で「大きな波」という意味で、英語の「The great wave」に相当。
| ||
街のオブジェになったり絵本になったりと、単に絵が紹介されたり複製画が売られるだけなく、絵のもつイメージが増殖しているわけで、この絵の認知度は相当高いと推測できます。

| |||
|
クロード・ドビュッシー
(1862-1918) - Wikipedia - | |||
ドビュッシーに戻りますと、作曲家にとって書き上げた楽譜は、いわば「命」のはずです。アーティストが自分の命とも言うべき出版物の表紙に別のアーティストの作品(絵)をもってくるということは、その絵、ないしは絵の作者に対する "オマージュ" だと考えられます。ドビュッシーは北斎を見て、どこにでもある波をアートに仕立てたことに感じ入り「自分は音楽で」と考えたとしても、それはありうることだし、楽譜の表紙からすると "ごく自然な推測" だと思います。
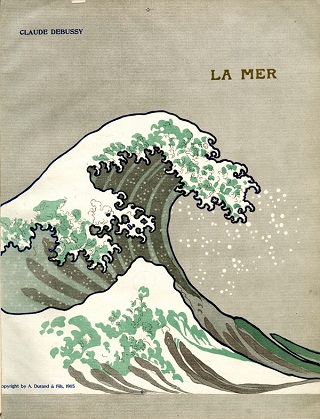
| ||
|
ドビュッシー「海」のスコア(1905)
- Wikipedia -
| ||
次の写真はドビュッシーがストラヴィンスキーと写っている写真です。音楽に変革をもたらした両巨人のツーショットですが、後ろの壁に2枚の浮世絵が飾られていて、そのうちの上の方は『神奈川沖浪裏』です。ちなみに写真を撮影したのは、これも著名作曲家のサティです。

| ||
|
ドビュッシー(左)とストラヴィンスキー
パリのドビュッシー宅にて(1910) (大浮世絵展・図録より。2014.1.2~ 江戸東京博物館) | ||
そのドビュッシーと一時 "親しい仲" だったのが、2歳年下の彫刻家、カミーユ・クローデルです。彼女はロダンの弟子ですが、その彼女も北斎に影響を受けた彫刻を作っているのです。そのあたりの事情を、木々康子氏の本から引用します。
|
二人の中は4年ほどで終わるのですが、ドビュッシーは別れた後もカミーユを想っていたそうです。またカミーユも、有名な「ワルツ」という彫刻をドビュッシーに贈ると約束した、とあります。カミーユ・クローデルが北斎に影響を受けたとされる彫刻は、パリのロダン美術館にある『波』という作品です。

| ||
|
カミーユ・クローデル(20歳)
(1864-1943) - Wikipedia - | ||

| ||
|
カミーユ・クローデル
「波」(1897-1903)
(ロダン美術館)
| ||
|
以上は北斎の影響を受けた絵・彫刻・音楽などのアート作品ですが、『神奈川沖浪裏』はさらに現代のデザインの分野にも影響しています。その一つの例ですが、ボードショーツ(サーフィン用のショートパンツ)で有名なアパレル・ブランドに Quiksilver(クイックシルバー。スペルに c はない)があります。もともとオーストラリア発のブランドですが、現在はアメリカ・カリフォルニア州のハンチントンビーチに本社があります。この Quiksilver のロゴは、北斎の『神奈川沖浪裏』を図案化したものです。ということは、このロゴには富士山がデザインされていることにもなります。
Quiksilver の創始者が『神奈川沖浪裏』に感動してロゴにしたそうですが、絵に描かれた舟をサーフボードに見立てると、いかにもサーフィンに似つかわしい。"The Great(Big)Wave" というタイトルの絵をボードショーツのブランド・ロゴにするのはまさにピッタリだと思います。
神奈川沖とは江戸時代の神奈川宿の沖で、つまり東京湾のどこかでしょうが、現代人としては湘南の海と考えてもよいわけです。鎌倉・藤沢・茅ヶ崎の湘南海岸でサーフィンを楽しむ日本人サーファーは、是非とも Quiksilver のボードショーツを着用して欲しい気がします。


| ||
|
Quiksilver のロゴ(上・左)と、カリフォルニア州・ハンチントンビーチにある本社(上・右)。下は Quiksilver のロゴが入ったボードとシャツでサーフィンをするサーファー
(www.surfertoday.com)。
| ||

| ||
|
湘南海岸の近くにある伝説のサーフショップ、Mabo Royal(藤沢市)の北側の壁には、Quiksilverの巨大なロゴが飾り付けてある。海岸に出ると富士山が望め、あたりにはサーファーが絶えることがない。このロゴを見ると北斎が "里帰り" したような印象を受ける。
(Google Street View)
| ||
本題の「世界で2番目に有名な絵」に戻ります。冒頭に引用した及川教授の発言を読んだときに思ったのですが、「The Great Wave(神奈川沖浪裏)が世界で2番目に有名な絵」というのは、そこまでは断言出来ないのではないでしょうか。つまり「モナ・リザが世界で1番有名な絵」とは誰もが認めるでしょうが、2番目というのは果たしてどうなのか。
| 世界で2番目に有名な絵の候補はいくつかあり、その中でも「The Great Wave(神奈川沖浪裏)」は有力候補 |
が実状に近いのではと思ったのです。ということで、以下に「世界で2番目に有名な絵の候補」をいろいろと推測してみたいと思います。
「世界で2番目に有名」とは?
推測の前提として「世界で2番目に有名」という言葉の定義をする必要があります。まず「世界で」のところですが、対象は世界中の国々であり、特定の地域・文化圏ではないこととします。かつ、美術の愛好家というのではなく、普通の人、美術に関心がない人までも含みます。また子供は別にして、老若男女すべてということにします。
次に「有名な」の定義ですが、
| ① | その絵を知っている。 たとえば、写真を見せられて "知っています" と言える。 | ||
| ② | 画家の名前が言える。 | ||
| ③ | 絵の題名が言える(俗称・通称・略称でも可)。 |
という3つの条件が満たされることとします。① の「知っている」だけでは「有名」というには弱い。① に加えて、② か ③ のどちらかという条件にすると候補は断然増えるでしょうが(それでもいいとは思いますが)ここでは「厳格に」① ② ③ のアンド条件だと考えます。
もちろんアンケート調査ができるわけではありません。そんな調査をするメディアもないと思います。そこで ① ② ③ を満たしやすい「付加条件」を想定して推定の助けにしたいと思います。
まず、多くの人が「① 絵を知っている」ためには、
| ◆ | 絵のモチーフがシンプルで明確である | ||
| ◆ | 世界中の誰もが理解できるモチーフである | ||
| ◆ | 絵としては、他にない独自性があるモチーフである |
ことが重要でしょう。そういう絵は「世界で有名」の定義からして有利になります。もちろんこういった条件がなくても多くの人に認知されていればよいわけですが、一般論としての "有利な条件" ということです。また「② 画家の名前が言える」ためには、
| ◆ | その絵に限らず、画家の名前そのものが有名であり、世界中に知られている |
と断然有利です。さらに「③題名を言える」ためには、
| ◆ | 題名(俗称)がシンプルで、モチーフと直結している |
と有利になります。こうなると、各国の義務教育の教科書に出てくるような絵や画家が候補になる気もしますが、現在はメディアが発達しているので、それだけでは決まらないでしょう。
2番目に有名な絵の候補
以上の「条件」を前提に「世界で2番目に有名な絵の候補」をあげてみたいと思います。
まず対談に出てきた『ゴッホのひまわり』です。これは鋭い指摘で「世界で2番目に有名な絵の候補」に十分なると思います。花瓶の向日葵の束をカンヴァスに "ドン" と描いた画家はあまりいないし、モチーフがシンプルで、絵としてのインパクトも強い。そもそも向日葵という花が、突出して "インパクトの強い花" です。これが「アイリス」や「白いバラ」だと、ここまで有名にはならないのですね(メトロポリタンにゴッホの傑作があるけれど)。花そのものに "威力" があり、また世界の多くの地域で栽培されてもいる。題名の「ひまわり(Sunflowers)」も簡潔で覚えやすい。さらにゴッホは超有名な画家です。
しかし「世界で有名な絵のランキング」にとって非常に残念なのは『ゴッホのひまわり』は複数あることですね。「花瓶の向日葵の束」という構図に限定しても、消失したものを除いて現存する作品が6点あり、そのうち美術館で見られる絵は5点あります。描かれている向日葵の本数とともにリストすると、
| 東京 | 損保ジャパン日本興亜美術館 | |||||
| ロンドン | ナショナル・ギャラリー | |||||
| アムステルダム | ゴッホ美術館 | |||||
| ミュンヘン | ノイエ・ピナコテーク | |||||
| フィラデルフィア | フィラデルフィア美術館 |
となります(そのほかに3本のひまわりの絵がある)。つまり『ゴッホのひまわり』は "作品群" なのです。どれかがダントツに有名というわけではありません。普通、写真などでよく見かけるのは15本の3作品で、日本ではもちろん東京の作品ですが、ミュンヘンとフィラデルフィアの12本も捨てがたい。つまり『ゴッホのひまわり』が「世界で2番目に有名な絵』だとすると、2番目が5つあることになります。これはちょっと "マイナス・ポイント" になるでしょう。

|

|
|
|
ロンドン |
アムステルダム |
|

|

|
|
|
ミュンヘン |
フィラデルフィア |
|

|
||
| 東京 | ||
19世紀の近代絵画つながりで他の2番目候補をあげると、『ドガの踊り子』も『ゴッホのひまわり』と似たような事情にあります。写真を見せられて「知っています。ドガの踊り子です」と答えられる人は世界にものすごくいる気がします。
しかしドガが描いた踊り子の絵は、有名なものだけで複数あります。最も有名なのはオルセー美術館の絵でしょうが、前回紹介したコートールド・コレクションの絵もよく見る絵です。むしろこちらの方が踊り子らしい感じもする。オルセーの絵がよく知られているのは、コートールド・ギャラリーよりは桁違いに有名な "オルセー美術館にあるから" という気がします。『ドガの踊り子』が世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては確定しない。
しかも『ゴッホのひまわり』とは違って『ドガの踊り子』は構図が多様です。それこそが芸術家としての創造性の発揮であり、デッサンや習作は別にして、ドガは全く同じ構図の完成作を6枚も7枚も描くというような "アマチュアっぽい" ことはしないわけです。しかしこのことが「有名な絵ランキング」にとっては "減点" の対象になるでしょう。

|

|
| パリ | ロンドン |
19世紀の著名画家をもっと考えてみると、印象派の巨匠、クロード・モネはどうでしょうか。『モネの睡蓮』は著名ですが、睡蓮の絵は『ゴッホのひまわり』や『ドガの踊り子』以上にたくさんあります。写真を見せられて「知っています。モネの睡蓮です」と答えられる人は多数いるでしょうが、世界で2番目に有名だとすると、2番目が絵としては全く確定しないことになります。

| |||
|
| |||
ルノワールはどうでしょうか。ルノワールの「かわいらしい少女の絵」や「家庭的な雰囲気の中にいる複数の女性の絵」(たとえばピアノを弾く光景)には、大変に有名な絵があります。しかしそういうジャンルのルノワールの絵は複数あって、どれかがダントツに有名というわけではないと思います。パリの風俗を活写した絵としては『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』が非常に有名ですが、この絵の "難点" は、題名が(フランス人以外には)難しいことです。
その他、マネ、セザンヌ、マティスなどを考えてみても、傑作はたくさんあるけれどダントツに有名な "この1枚" が思い当たりません。「ミレーの落穂拾い」は有力な感じがしますが、淡々とした農家の日常を描いたという画題のインパクトが弱いような気がします。そういう画題を芸術にしたのが価値なのだけれど。
少しだけ時代を遡ってドラクロワはどうでしょうか。ルーブルに『民衆を導く自由の女神』という有名な絵があります。絵の題名として「自由の女神」ないしは「自由」でもよいとするなら、この絵は「世界で2番目に有名」の候補になる感じもします。

| |||
|
| |||
しかし世界にはいろんな文化があり、こういうフランス史や西欧文化(抽象概念の擬人化)ベッタリの絵は「世界で2番目に有名」と言えるほどには広まりにくいのではないかと思います。自由の女神がフランス国旗を持っていたりするのも、グローバル視点ではマイナス・ポイントになるでしょう。
| 蛇足ですが、ニューヨークの港の入口に立っている像は、Statue of Liberty = 自由の像、です。あれは女神が立っているのではなく、自由が立っているのです。 |
18 - 19世紀の絵画


| |||
|
| |||
ダヴィッドの同時代人に、スペインのゴヤがいます。『ゴヤの裸のマハ、着衣のマハ』の2部作はどうでしょうか。この作品の "難点" は2枚でペアということと、それをさしおいたとしても、女性の裸体を描いていることです。「世界」というレベルで考えると女性の裸体がオープンになることを嫌う、ないしはタブーになっている文化圏があります。「世界で2番目」とするには問題があるような気がします。それはドラクロワの『民衆を導く自由の女神』も同じでした。
17世紀の絵画

| |||
|
| |||
しかし、フェルメールの人気は最近の数十年のことだと言いますね。「世界」というレベルで考えたとき、この絵の浸透度合いはどうか、少々疑問になるところです。日本でも「フェルメール、フェルメール」と大騒ぎするようになったのは、せいぜいこの20年程度でしょう。それと、題名が少々長いのが気にかかる。ただし、題名は画家がつけたわけではないので『真珠の耳飾り』でもよいし、別名である『青いターバンの少女』でもいいわけです。
17世紀の絵画ということで考えると、ベラスケス、ルーベンス、レンブラントといったビッグ・ネームがあるわけですが、作品の芸術的価値は別にしてダントツに「世界で」有名な1枚という視点だけで考えると、いずれも弱いと考えます。
ルネサンス絵画
では時代をさらに遡って、イタリア・ルネサンス期の絵画はどうか。まず思いつくのは『ダ・ヴィンチの最後の晩餐』でしょう。
しかし「最後の晩餐」の難点は、1番目も2番目もダ・ヴィンチではおもしろくない(?)ということです。さらにもっと本質的には、この絵のテーマがキリスト教そのものだということです。「世界」という範囲で考えるとキリスト教と無関係な人たちも多いし、それどころかキリスト教と対立している人たちがいる。たとえばイスラム教の世界人口は15億人と言いますね。イスラム教の人たちにとってダ・ヴィンチの「最後の晩餐」はよく知られた絵なのかどうか。どうも違うような気がします。もちろん大多数のイスラム教徒の人たちはキリスト教徒と仲良くしようと考えていると思いますが・・・・・・。
宗教画であることがマイナス点になるという事情は「ラファエロの聖母」や「ミケランジェロの最後の審判」も同じです。ラファエロの聖母は "似たような絵" が何枚かあり(『聖母子とヨハネ』『牧場の聖母』『大公の聖母』など)、ピンポイントで特定するのが難しいという問題点もあります。"似たような絵" をたくさん描いたからこそ「聖母の画家」なのです。

| |||
|
| |||
20世紀 - ピカソ
時代を逆に20世紀に向けると、超有名画家であるピカソが思い浮かびます。『ピカソのゲルニカ』はどうでしょうか。確かにこれは有名という感じがします。

| |||
|
| |||

| |||
|
| |||
「ゲルニカ」や「アヴィニョンの娘たち」よりも、ひょとしたら世界で2番目に有名の候補になりやすいのは『ピカソの泣く女』でしょう。モチーフはシンプルだし、絵のインパクトも強い。題名も簡潔です。この絵に問題があるとしたら、絵としてのインパクトが強い分、キュビズムという絵画手法に違和感を覚える人が多いのではと想像されることです。それが絵の浸透にネックになるのではないか。
北斎の強力なライバル
以上のように順に考えてみると『葛飾北斎の神奈川沖浪裏』=『Hokusai の The Great Wave (The Big Wave)』は、世界で2番目に有名な絵の候補であるだけでなく、極めて有力な候補だと言えそうです。最初に引用した及川教授の「(世界で2番目に有名な絵は)葛飾北斎の大波の絵と言われています」という発言も、一部の美術関係者の憶測ではなく、それなりの根拠がある信憑性が高い話だと考えられるのです。
・・・・・・ と、安心するのはまだ早いことに気づきました。北斎の「強力なライバル」があることに思い立ったのです。それは『ムンクの叫び』です。

| |||
|
| |||
『ムンクの叫び』について思い当ることがあります。
考えてみると『The Great Wave』と『叫び』には次のような共通点があります。
| ◆ | モチーフと題名の分かりやすさ 何が描かれているか、一目瞭然です。題名(俗称)もシンプルで、描かれているものと直結している。 | ||
| ◆ | 独特のデフォルメが強烈な印象を残す あらゆる絵の中でその絵しかない、と言ってもいいほど個性的です。それはデフォルメがもたらしたものですが、その絵画手法はキュビズムとは違って現実の自然な延長線上にあります。美術に関心が無い人でも違和感がない。 | ||
| ◆ | 特定の文化に依存しない | ||
| 「波」も「叫び」も特定文化に根ざす題材ではないし、特定地域の歴史が背景にあるわけではない。 |
などです。ちなみに北斎の波の装飾的表現は、別に北斎独自のものではありませんが、それはあくまで「日本人だからそう考える」わけです。日本美術史を知らない世界の多く人にとって、あの波の表現方法は「Hokusai の Wave」であり、また「Hokusai」の名はこの絵で知った、ないしは「Hokusai」の作品はこれしか知らない、という人は多いと思います。
北斎の "ライバル" ということでは『ゴッホのひまわり』『ピカソの泣く女』『フェルメールの真珠の耳飾りの少女』なども有力なことには違いありません。今まで書いたように、それぞれ難点があるけれど・・・・・・。
「世界で2番目に有名な絵」は何か、「葛飾北斎の神奈川沖浪裏」はその最有力候補ではないかという考察(?)を通して感じたことが2つあります。それを以下に書きます。これは "まじめな" 考察です。
『モナ・リザ』という特別な存在
「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して分かるのは、『モナ・リザ』(国によっては『マダム・ジョコンダ』)という絵が特別であることです。確かにこの絵は画家がメジャー、モチーフがシンプル、題名もシンプル(固有名詞だけど)、特定文化に依存しないなど、有名になるベーシックな条件が備わっています。
しかし『モナ・リザ』は、どこにでもありそうな女性の肖像画なのですね。そこに北斎やムンクのような特有のデフォルメや印象に残る強烈さがあるわけではない。我々は小さい頃から『モナ・リザ』と知っているから、一見して他の絵と区別できます。しかしそういう知識が全くないという前提で考えてみると、これが一見して他と区別できる絵だとはとても思えない。
しかし人々の印象に残り、語り伝えられ、メディアでも紹介され、小説のテーマにもなり、大傑作だという評価をうけ、ルーブルのこの絵の周りは長蛇の列になる。その理由はというと、多くは「モナ・リザの表情」に起因しているのですね。これについては No.90「ゴヤの肖像画:サバサ・ガルシア」で、次のように書きました。
|
「どこにでもありそうな女性の肖像画が世界で1番有名な絵である」という、この事実にこそ『モナ・リザ』の驚異があるのだと思います。結局のところ、人間は人間に一番関心があるのでしょう。それを暗示しているようです。『ムンクの叫び』が北斎の強力なライバルと書いたのも、実は「人間を描いているから」でした。
我々は「神奈川沖浪裏」を知っているか

| ||
|
葛飾北斎
「神奈川沖浪裏」 | ||
「世界で2番目に有名な絵」をあれこれと推測して感じたことの2番目は、我々日本人は、たとえば外国の人に『神奈川沖浪裏』を説明できるか、ということです。まず日本人として、この絵を "本当に" 知っているかどうかが問題です。はじめの方に「有名」の定義として、
| ① | その絵を知っている。 たとえば写真を見せられて "あっ、知ってる" と言える | ||
| ② | 画家の名前が言える。 | ||
| ③ | 絵の題名が言える(俗称・通称でも可)。 |
の3条件をあげました。おそらく多くの日本人は ① ② は大丈夫だと思います。しかし ③ はどうでしょうか。及川教授の対談にあったように、題名は? と聞かれて、
| ・ | 神奈川沖浪裏 | ||
| ・ | The Great Wave(The Big Wave) |
のどちらかを答えることができる人がどれほどいるかが問題です。「大きな波」では、絵の説明にはなっているけれど「題名」ではない。『大波』という略称が日本で一般的になっているわけでもないでしょう。波間に見える富士山、と答えたとしたら、ますます題名ではない。
世界で2番目に有名な絵(の有力候補)だから、この絵を知っている人は世界中に大変たくさんいます。絵の作者名(Hokusai)を言える人も多いはずです。そして「題名は ?」と聞かれたとき、たとえば英語圏や英語を話せる人で Hokusai を知っている人なら「The Great/Big Wave」と答えるのではないでしょうか。だとしたら、
| 世界中で、日本人だけがこの絵の題名(ないしは俗称)を答えられない |
という公算が大だと思うのです。日本文化を象徴する絵なのだから、せめて日本人としては題名だけでも知っておきたいものです。
この絵を外国の方に説明するときには「富士山を描いた絵」ということは言った方がよいと思います。そうとは気づかない人もいるはずです。また三隻の舟には人が乗っていて、18世紀の日本では実際にこのような舟で沿岸輸送をしていたことも知っておいた方がよいと思います(こんな大波の中で輸送するかどうかは別にして)。
この絵を一言で言うと「ローカルだけどグローバル」ということかと思います。完全な日本文化の中から一人の「天才」によって生み出されてものだけど、グローバルに認知され「世界で2番目に有名な絵」になった。
しかしこの絵は完全にローカルなわけではありません。西欧から2つの点で影響を受けています。まず北斎の当時から、使われた青色が輸入合成顔料であるプルシアン・ブルーです(No.18「ブルーの世界」参照)。江戸時代の言い方では「ベロ藍」ですが、この "ベロ" とはベルリンのことなのですね。発明されたのが当時のプロイセンの首都、ベルリンです。
さらにこの絵は西洋画法(特に遠近法)の影響を受けているのでしょう。厳密な遠近法ではないかもしれません。しかし構図は、明らかに円と螺旋と直線で構成されていると感じます。「幾何学的な描線で骨格の構図を決める」というところに遠近法との非常な類似性を感じます。
ローカルだけれどグローバル。それは「グローバルな絵画技術を取り入れつつ、あくまでローカルに描き、結果としてグローバルに有名になった」という意味です。そして、それを生み出した北斎という画家のすごさに改めて感嘆するのです。
No.155 - コートールド・コレクション [アート]
前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介した絵画『ヴァイオリンを奏でるパガニーニ』があるのは、アメリカのワシントン D.C.にあるフィリップス・コレクションでした。また以前に、No.95 でバーンズ・コレクション(米・フィラデルフィア)のことを書きましたが、これらはいずれも個人のコレクションを美術館として公開したものです。
個人コレクションとしては、日本でも大原美術館(大原孫三郎。倉敷市。1930 ~ )、ブリヂストン美術館(石橋正二郎。東京。1952 ~ )、足立美術館(足立全康。島根県安来市。1970 ~ )などが有名だし、海外でもノートン・サイモン(米・カリフォルニア)、クラーク(米・マサチューセッツ)、フリック(米・ニューヨーク)、クレラー・ミュラー(オランダ)、オスカー・ラインハルト(スイス)など、コレクターの名前を冠した美術館が有名です。
こういった個人コレクションで最も感銘を受けたのが、ロンドンにある「コートールド・コレクション」でした。今回はこのコレクションのことを書きたいと思います。実は以前、知人に新婚旅行でイギリスに行くという人がいて、ロンドンの「おすすめスポット」を尋ねられたことがありましたが、私は「コートールド・コレクション」と答えました。新婚旅行から帰ってから、その方に「よかった」と、たいそう感謝された記憶があります。
サミュエル・コートールド
サミュエル・コートールド(1876-1947)は、イギリスで繊維業を営んだ実業家で、フランスの印象派・後期印象派の絵画を収集しました。彼はロンドン大学付属の「コートールド美術研究所 The Courtauld Institute of Art」を設立し(資金を提供)、その研究所のギャラリー(コートールド・ギャラリー)に自らのコレクションを寄贈しました。これがコートールド・コレクションです。
コートールド・ギャラリーは、ロンドンのコヴェントガーデンに近い「サマセット・ハウス」という公共建築物の中にあります。広い中庭がある大きな建物ですが、その北側の一角の1階から3階までがギャラリーになっています。ナショナル・ギャラリーやテート・ギャラリーと違って独立した建物があるわけではなく、旅行ガイドを頼りに場所を探しても、少々わかりにくい。内部の展示スペースもこじんまりしています。展示室は基本的に2階と3階で、それぞれ数室しかありません。印象派・後期印象派の絵画は、わずか2室程度にあるだけです。しかし収集された絵画の質は素晴らしく、傑作が目白押しに並んでいる部屋の光景は壮観です。
その絵画の何点かを以下に紹介します。コートールド・ギャラリーにはコートールドが寄贈した絵画以外にも、ルネサンス、バロック、ロココなどの絵画が収集されているのですが、以下の話はコートールドの寄贈作品に絞ります。といっても、すべての絵の紹介はできないので、画家の特質をよく表している傑作(と個人的に思うもの)の一部に絞ります。
セザンヌのサント=ヴィクトワール山
まず、セザンヌ(1839-1906)の『大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山(Montagne Sainte-Victoire with Large Pine)』(1887)です。
セザンヌは、故郷のエクス=アン=プロヴァンスにあるサント=ヴィクトワール山を描き続けたことで有名です。油絵だけでも40点以上あるといいます。従って「セザンヌのサント=ヴィクトワール山」は各国の美術館が所蔵していて、日本にもあります。たとえばブリヂストン美術館の『サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール』は中景に赤い建物が配置されている作品です。横浜美術館にも『ガルダンヌからみたサント=ヴィクトワール山』という作品があります。
コートールドのこの絵も40数点の中の1枚であり、特に「めずらしい」ものではありません。しかし特にこの絵が印象深いのは、この絵を初めて見たとき、直感的に日本画(浮世絵)を感じたからです。近景に木をクローズアップで(全容を描かずに)描き、中景に田園風景、遠景に山、というこの構図が浮世絵を連想させます。
サント=ヴィクトワール山ではないですが、ゴッホが描いた風景画を以前に紹介したことがありました。No.10「バーバー:ヴァイオリン協奏曲」で引用した『アルルの風景』(ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク所蔵)という作品です。この絵も、近景の3本のポプラの木はその全容が描かれていません。構図の視点から、ゼザンヌのコートールドの絵との親和性を感じます。
ゴッホを持ち出さなくても、そもそもコートールドには、似た構図のセザンヌの別の絵があります。フランス・アルプスの山麓の湖を描いた『アヌシー湖 - Le Lac d'Annecy』(1896)という作品です。
サント=ヴィクトワール山の絵に戻りますと、こういった近景に木を配した山の絵はコートールドだけではありません。実は、前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介したフィリップス・コレクションにも、コートールドの絵とそっくりの作品があります。ただし松の木は2本になっています。セザンヌはいろいろと構図の研究したようです。
浮世絵を連想させる、ということで次に思い浮かべるのは葛飾北斎(1760-1849)の『富嶽三十六景』(ないしは歌川広重の『富士三十六景』)です。セザンヌのサント=ヴィクトワール山の連作は『富嶽三十六景』に影響されたのではと感じます。
No.30「富士山と世界遺産」にも書いたのですが、そもそも特定の山を主題に絵を描くというのは、ヨーロッパの絵画ではあまり思い当たりません。山岳地帯をもつ国はイタリア、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンなどがありますが、有名画家の "山の絵" はあまり思い当たらない。唯一思い当たるのは、スイスの "国民的画家" のホドラー(1853-1918)で、ユングフラウ、アイガー、メンヒなどのアルプスの山を主題に描いています。セガンティーニ(イタリア人)やフリードリッヒ(ドイツ人)は山岳風景をたくさん描いていますが、特定の山を描いた作品は見たことがありません。
従ってセザンヌは「特定の山を主題に、しかも連作で描いた希な画家」ということになります。もちろんそれは彼の郷土愛であり、幼少期から親しんだ風景への愛着なのだろうけれど、その「山の連作」のヒントになったのは北斎というのは十分考えられると思うのです。
考えてみると『富嶽三十六景』には「現実に画家が見たのではない構図」がいろいろとあります。有名な『神奈川沖浪裏』は、波の装飾的表現は別にして、富士山をバックにした大波の光景は、溺れるのを覚悟で沖に漕ぎ出さない限り見ることはできません。もっと日常的な光景では、たとえば『尾州不二見原』というこれも有名な作品です。桶職人の所作や道具はリアルで、画家は職人が大きな桶を作る姿を観察したに違いありません。しかしこの構図は実際の光景ではなく「創作」ではないでしょうか。もちろん実際に画家が見た光景だとも考えられますが、しかし富士山の "三角"と桶の "円" をピッタリと "幾何学的に配置" したのは北斎の創作だと強く感じます。
二つの作品で言えることは、個々のモチーフである「富士山」「大波」「人の乗った舟」「大樽」「樽職人」はあくまで現実のものだし、デフォルメは別にして、現実をトレースしようとしています。しかしその「組み合わせ方」に画家の創作行為が入っていて、それこそが芸術だということなのです。
そこでコートールドの『サント=ヴィクトワール山』です。ここに描かれた松の木の "枝ぶり" は、ちょうどサント=ヴィクトワールの稜線に沿うように描かれています。これは実際の光景なのでしょうか。そうとも考えられるが、より強い可能性は画家の創作だと思うのですね。まるで松の木を「自然の額縁」かのようにしてサント=ヴィクトワール山を描いたこの絵は、画家が「そうしたい」と思ったからではないかと想像します。これは、前に引用したフィリップス・コレクションの絵でも同じです。松の枝は山の稜線にしっかり沿っているし、松の木を二本配置することで「自然の額縁」の感じがよりはっきりしています。松の木はリアルだし、サント=ヴィクトワール山もリアル、しかしその配置と組み合わせ方が画家の創作行為である ・・・・・・ そいうことではないでしょうか。セザンヌにはそのような絵がいろいろあります。静物画でも、個々の事物はリアルだが、全体としては "絶対に現実にはないような(= 現実には絶対にそうは見えないような)組み合わせである" というような絵です。
葛飾北斎の『富嶽三十六景』は、手を変え品を変えた構図とモチーフの配置で富士山を描いています。セザンヌも同様に手を変え品を変えてサント=ヴィクトワール山を描いた。ブリヂストン美術館の絵は赤い建物が非常に印象的だし、横浜美術館の絵は、サント=ヴィクトワール山を "大きな丘" という感じに見えるアングルから描いています。40枚以上描くのだから、絵描きとしてはヴァリエーションを追求するわけです。その中には創作もある。構図の探求をするなら当然でしょう。このあたりも『富嶽三十六景』との親和性を感じます。別に北斎から学んだわけではないでしょうが・・・・・・。
最近知ったのですが、セザンヌは北斎から影響を受けたと発言している専門家の方がいます。比較文化学が専門の及川茂・日本女子大学教授です。2009年に発行されたあるIT企業(JBCCホールディングス)の社長との対談ですが、その発言を引用しておきます。
モネ / スーラ / ゴッホ
セザンヌの風景画をとりあげたので、3人の画家の風景画を紹介します。まずクロード・モネの『アンティーブ(Antibes)』(1888)という作品です。アンティーブはコートダジュールに面する町ですが、この絵は「木と風景」という点でセザンヌとの類似性があるので掲げました。セザンヌよりももっと強く浮世絵の影響をうかがわせる構図です。なお全く同じ構図で時刻を変えて描いた絵が愛媛県美術館にあります。
コートールド・ギャラリーはスーラの絵も何点か所蔵していますが、上に掲げたのは『クールブヴォアの橋(The bridge at Courbevoie)』(1886/7)で、スーラが絵の全体に点描を使った初めての作品です。パリ近郊のセーヌ河の中州であるグランド・ジャット島の水辺の静謐な風景で、点描の特質を大変よく生かした優れた絵だと思います。実はこの絵もまた近景の木が構図上のポイントになっています。
コートールド・コレクションのゴッホの絵で有名なのは『耳に包帯をした自画像』でしょう。ここでは、風景画つながりで『桃の花盛り(Peach Trees in Blossom)』(1889)を掲げます。アルル近郊のラ・クロー平野の絵です。前景の柵と桃の木、中景の畑と家、遠景の山並みがパノラマ的にとらえられています。春先を感じさせるおだやかな色使いが大変美しい絵です。ちなみにアムステルダムのゴッホ美術館には、よく似た構図で描かれた『ラ・クローの収穫』があります。
コートールドの3つの "富士山"
ゴッホの「桃の花盛り」をよく見ると、右の方の遠景に「冠雪している三角の山」が小さく描かれています。これについて、
とした評論を読んだことがあります。なるほど、と思いました。アルルは南フランスの地中海沿岸です。普通、真冬でも気温は零下にはならないはずです。平地に雪が降ることもあるようですが、滅多にないといいます。近郊の山といっても、アルプスやピレネーではないので、せいぜい標高1000メートル台でしょう(サント・ヴィクトワール山は1011メートル)。桃の花が満開ということは、描かれた時期は4月上旬あたりです。もしこれが画家が実際に見た光景だとしたら、南仏の真冬に低い山に雪が積もり、それが4月まで残っていることになる。アルルに居住したことがある人ならすぐに分かるはずですが、推測をすると「この冠雪した山は現実の光景ではない」可能性が大いにあるのではないでしょうか。
だとすると、浮世絵を何点も所有し、その模写までもやったゴッホが「富士山のつもりで描き込んだ」というのはありうると思います。実際に冠雪した山があったとしても、それを富士山に "見立てて" 配置したということもありうるでしょう。
その富士山つながりなのですが、コートールドにあるゴッホ作品としては "桃の花" よりも、同じ年に描かれた『耳に包帯をした自画像』の方が断然有名です。この自画像の背後には画中画としてゴッホが所有していた浮世絵が描かれているのですが、その画題はというと「芸者」と「鶴」と「富士山」です。桃の花の絵に富士山を描き込んだのでは、というのはあくまで憶測ですが、ゴッホは『耳に包帯をした自画像』にはまさしく富士山を描き込んだのです。
ちなみに、ゴッホが画中画として浮世絵を描くということは、そのこと自体に特別な意味があると考えなければなりません。有名な『タンギー爺さん』には6枚もの浮世絵が描き込まれていますが、これはとりも直さず "感謝" の意味でしょう。貧しくて売れない画家である自分を支援してくれた画材店の店主に対する感謝と、画家として多大な啓示を受けた日本の浮世絵に対する感謝です。そして、このコートールドの絵の場合は、耳切り事件を起こしたあとの再出発の決意でしょう。浮世絵を描き込むことでその"決意" を鮮明にしたのだと考えられます。
以上のゴッホの2枚の絵と、セザンヌのところで引用した及川教授の「サント・ヴィクトワール山はセザンヌにとっての富士山」という指摘を合わせると、
ことになります。コートールド・ギャラリーを訪れたならそう思って絵を鑑賞するのも(我々日本人にとっては)楽しいでしょう。私がコートールドを紹介した知人も、夫婦でコートールドを再訪する機会があったら、是非「3つの富士山」の話をパートナーにして "知ったかぶり" をしてほしいと思います。
余談になりますが、ゴッホがパリをたってアルルに到着したのは1888年の2月です。その、1888年の1月、2月のヨーロッパは例年になく雪が多く、南フランスのアルルにも "めったに降らない" 雪が降ったようです。南フランスの明るい太陽にあこがれてやって来たゴッホも、さぞかしびっくりしたのではないでしょうか。そのゴッホも『雪のある風景』(1888.2)という、雪景色のアルルを描いています。コートールド・コレクションの「桃の花盛り」の絵は、その1年後の4月の絵ということになります。
モディリアーニの裸婦
モディリアーニは多数の裸婦像を描いていますが、コートールドにあるこの『裸婦 - Female Nude』(1916)は特別です。普通、モディリアーニの裸婦というと、明らかにプロのモデルを使った絵が多いわけです。というより、モディリアーニに限らず普通の画家はそうです。
ところがこの絵のモデルは「素人のモデル」だと強く感じさせます。全体から受ける印象がそうです。このモデルは、モディリアーニの恋人だったベアトリス・ヘイスティングスだという説があります。彼女はイギリス人の詩人で、モディリアーニと2年間の同棲生活をおくりました。この説が正しいとすると、まさに素人ということになります。
ベアトリスだという確実な証拠はないようです。しかしモデルが誰かをさし置いたとしても、この絵の女性は「モディリアーニに強く頼まれてモデルを引き受けてしまった」という感じがします。実際にギャラリーで実物をみると、恐ろしく速く描いた、という印象が強い。タッチは素早く大胆だし、絵の下の方などは、まともには絵の具が塗られていません。30分ぐらいで描いたのではないかとさえ思えます(大袈裟ですが)。とにかく「モデルとじっくり向き合い、デッサンを重ねて、時間をかけて描いた絵」では全くないという印象が強いのです。そういうところも、プロのモデルではないという感じを強めます。
ヌード(nude)という美術用語があります。これは単なる「裸」でありません。アートの対象としての「裸体像」であり、ある種の美化や理想化(その一つとしてのデフォルメ)が行われることがよくある。しかしこの絵はちょっと違います。nude ではなく naked(裸)と強く感じさせる絵です。「見てはいけないものを見てしまったような感じ」もする。
線は確かに単純化されてはいますが、モディリアーニの絵によくある "様式化" はそれほどでもありません。線描によるデッサンの天才であったモディリアーニらしく、的確に描かれた線の美しさは格別です。肌色と緑がかった絵の具を波状に、こすり付けるようにして体を描いていて、それが生々しい感じをよく出している。全体として、女性のヴィヴィッドな美しさがよく出た傑作だと思います。
マネが描いた「鏡」
次は「コートールドといえばこの作品」「この作品と言えばコートールド」という感じの絵で、マネの『フォリー・ベルジェールのバー(A bar at the Folies-bergere)』(1881/2)です。
フォリー・ベルジェールは19世紀後半のパリにおいて、時代の先端をいく「カフェ・コンセール」(音楽カフェ)でした(今でもある)。そこでは音楽の演奏や演劇も行われ、ホールがあり、カフェがあり、バー・カウンターがあった。その都会の最先端スポットを描いた風俗画がこの作品です。
ポイントは二つあると思います。一つは「労働者としての女性」を中心に当時の風俗を描いたことです。それも、家政婦、洗濯女、娼婦などの、昔からあった "働く女性" ではなく、産業革命を経て近代的な都市が出現し、多くの人が集まり、富が蓄積し、人々に余裕ができる ・・・・・・ その結果として出現した女性バーテンダーを描いたという点です。当然のことながら、彼女の社会的地位は低いはずですが(豪華に見える服は制服)、そういった新しい女性を描いたのがこの絵の第一のポイントだと思います。
二つ目は「鏡」です。この女性の背後には大きな鏡があって、女性の後ろ姿と、女性と話している(であろう)男性客が描かれています。女性の後ろ姿と男性客の位置関係は変で、実際にこの通りの光景はありえません。しかし鏡を使った絵画において「実際にはありえない光景」というのはよくあります。この絵も画家の創作であって、芸術作品としては十分許されることでしょう。ちなみに男性客と女性バーテンダーの組み合わせは、ドガの絵に出てくる「踊り子とシルクハットの男性」を連想させます。
鏡を使った絵画としては、以前の記事でも何点か紹介しました。まずファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(No.93「生物が主題の絵」)であり、ファン・エイクに影響されたと言われるベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)です。ベラスケスは、有名な『鏡のヴィーナス』という絵を残しています。
これらの絵の鏡は、せいぜい手鏡の程度大きさのものです。大きな鏡を作るには大きな平面の板ガラスを作る必要があるのですが、これが昔は困難だった。溶けたガラスをローラーで延ばし、平面に研磨するという方法だったからです。そこに錫箔を貼って鏡にした。完全な平面でないと鏡にはなりませんが、大きな平面ガラスを作るのが難しいわけです。ベルサイユ宮殿の有名な「鏡の間」も、複数の鏡を連結して作ってあります。
しかし、19世紀も後半になると産業革命とともに平面ガラスを作る技術が発達し、大きな鏡も安価に入手できるようになった。その例が、No.87「メアリー・カサットの少女」で紹介した、メアリー・カサットの版画作品『着付け - The Fitting』です。ここでは大きな「姿見」が登場しています。画家が狙ったのは、鏡を使って「二つの世界を画面に同居させる」ことでしょう。
マネの『フォリー・ベルジェールのバー』も同じです。シルクハットの男性と多数の客を、バーテンダーの女性の背後に配置することによって、不思議な空間を作り出しています。
シャンデリアの向こうのバルコニー席に座っている客は何をしているのでしょうか。うっかりすると見逃してしまうのですが、この絵の左上には小さく「上からぶら下がった二本の足」が描かれています。そのサイズから、男性客と観客の間にある足だと分かる。これは空中ブランコの演技を客が見ている、それが鏡に写っている、そういう絵なのですね。つまり鏡の向こうは、ホールと高い天井、舞台、曲芸師、バルコニー席、大勢の客のおしゃべり、賑やかな音楽、どよめきと歓声と拍手・・・・・・という世界です。バーのカウンターの中の狭いスペースとは違う世界が広がっているのです。
話は飛ぶのですが、イギリスのルイス・キャロルは『不思議の国のアリス』を出版したあと、好評に応えて続編の『鏡の国のアリス』(1871)を書きました。マネの絵が描かれる10年前のことです。この本の原題は「Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて」です。アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まる冒険譚です。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける瞬間の挿し絵があります。
鏡は大昔からありました。しかし人の全身より大きいような鏡が出現し、鏡の向こうにも世界があるようにリアルに感じられるようになったからこそ、ルイス・キャロルはインスピレーションを得て『鏡の国のアリス』を書いたのだと思います。そう言えば、ベラスケスに触発されて書かれたオスカー・ワイルドの童話「王女の誕生日」(1891)もまた、全身が映るような鏡がストーリーのキー・アイテムとなっているのでした(No.63 「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」参照)。
現代人である我々は、全面が鏡になっている壁を見ても何とも思いません。そういう鏡はよくあるからです。しかし19世紀後半の人々にとって、大きな「鏡」や「姿見」によって、こちら側の世界とあちら側の世界が同居する、という光景は極めて斬新だったのではないでしょうか。昔ならヴェルサイユ宮殿に招かれないと体感できないような光景が、パリのカフェで一般人が味わえる・・・・・・。それは文明がもたらした新たな光景だったのでしょう。
19世紀後半の絵画をみると、産業革命以降の文明によって庶民に身近になった事物がいろいろと描かれています。汽車やその関連設備(駅、鉄道、鉄橋)、汽船、工場、などです。No.115「日曜日の午後に無いもの」で触れた日用品としてのパラソルもその一つでしょう。そういう文明の利器の一つとして、フォリー・ベルジェールのバーに設置された大きな鏡があった。
『フォリー・ベルジェールのバー』という作品は、画家の総決算ともいえる晩年の作であり、まさに「その時代」を描いた作品です。そして制作の発端になったのは、鏡が作り出す世界が画家に与えたある種の "感動" だと感じます。
この絵について付け加えたいのは、マネの静物の描き方ですね。以前の記事で、
というマネの静物画を引用しましたが、『フォリー・ベルジェールのバー』のカウンターに置かれた薔薇とみかんの描写も秀逸です。マネの静物は天下一品だと思います。

コートールド・コレクションの「顔」
コートールド・コレクションにはこの他にも印象派・後期印象派の画家の代表作があります。"代表作" が言い過ぎなら「画家の最良の特質をストレートに表した絵」です。そんな絵を5点あげておきます。
個人コレクションとしては、日本でも大原美術館(大原孫三郎。倉敷市。1930 ~ )、ブリヂストン美術館(石橋正二郎。東京。1952 ~ )、足立美術館(足立全康。島根県安来市。1970 ~ )などが有名だし、海外でもノートン・サイモン(米・カリフォルニア)、クラーク(米・マサチューセッツ)、フリック(米・ニューヨーク)、クレラー・ミュラー(オランダ)、オスカー・ラインハルト(スイス)など、コレクターの名前を冠した美術館が有名です。
こういった個人コレクションで最も感銘を受けたのが、ロンドンにある「コートールド・コレクション」でした。今回はこのコレクションのことを書きたいと思います。実は以前、知人に新婚旅行でイギリスに行くという人がいて、ロンドンの「おすすめスポット」を尋ねられたことがありましたが、私は「コートールド・コレクション」と答えました。新婚旅行から帰ってから、その方に「よかった」と、たいそう感謝された記憶があります。
サミュエル・コートールド
サミュエル・コートールド(1876-1947)は、イギリスで繊維業を営んだ実業家で、フランスの印象派・後期印象派の絵画を収集しました。彼はロンドン大学付属の「コートールド美術研究所 The Courtauld Institute of Art」を設立し(資金を提供)、その研究所のギャラリー(コートールド・ギャラリー)に自らのコレクションを寄贈しました。これがコートールド・コレクションです。
コートールド・ギャラリーは、ロンドンのコヴェントガーデンに近い「サマセット・ハウス」という公共建築物の中にあります。広い中庭がある大きな建物ですが、その北側の一角の1階から3階までがギャラリーになっています。ナショナル・ギャラリーやテート・ギャラリーと違って独立した建物があるわけではなく、旅行ガイドを頼りに場所を探しても、少々わかりにくい。内部の展示スペースもこじんまりしています。展示室は基本的に2階と3階で、それぞれ数室しかありません。印象派・後期印象派の絵画は、わずか2室程度にあるだけです。しかし収集された絵画の質は素晴らしく、傑作が目白押しに並んでいる部屋の光景は壮観です。

| ||
|
サマセット・ハウス(北ウィング)
コートールド・ギャラリーへのエントランスは写真の入り口の右手にある。
| ||
その絵画の何点かを以下に紹介します。コートールド・ギャラリーにはコートールドが寄贈した絵画以外にも、ルネサンス、バロック、ロココなどの絵画が収集されているのですが、以下の話はコートールドの寄贈作品に絞ります。といっても、すべての絵の紹介はできないので、画家の特質をよく表している傑作(と個人的に思うもの)の一部に絞ります。
セザンヌのサント=ヴィクトワール山
まず、セザンヌ(1839-1906)の『大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山(Montagne Sainte-Victoire with Large Pine)』(1887)です。

| ||
|
ポール・セザンヌ(1839-1906)
「大きな松の木のあるサント=ヴィクトワール山」
Montagne Sainte-Victoire with Large Pine(1887)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

| |||
|
セザンヌ
「サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール」 (ブリヂストン美術館) | |||

| |||
|
セザンヌ
「ガルダンヌからみたサント=ヴィクトワール山」 (横浜美術館) | |||
コートールドのこの絵も40数点の中の1枚であり、特に「めずらしい」ものではありません。しかし特にこの絵が印象深いのは、この絵を初めて見たとき、直感的に日本画(浮世絵)を感じたからです。近景に木をクローズアップで(全容を描かずに)描き、中景に田園風景、遠景に山、というこの構図が浮世絵を連想させます。
サント=ヴィクトワール山ではないですが、ゴッホが描いた風景画を以前に紹介したことがありました。No.10「バーバー:ヴァイオリン協奏曲」で引用した『アルルの風景』(ミュンヘンのノイエ・ピナコテーク所蔵)という作品です。この絵も、近景の3本のポプラの木はその全容が描かれていません。構図の視点から、ゼザンヌのコートールドの絵との親和性を感じます。
ゴッホを持ち出さなくても、そもそもコートールドには、似た構図のセザンヌの別の絵があります。フランス・アルプスの山麓の湖を描いた『アヌシー湖 - Le Lac d'Annecy』(1896)という作品です。

| ||
|
ポール・セザンヌ
「アヌシー湖」
Lac d'Annecy(1896)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
サント=ヴィクトワール山の絵に戻りますと、こういった近景に木を配した山の絵はコートールドだけではありません。実は、前回の No.154「ドラクロワが描いたパガニーニ」で紹介したフィリップス・コレクションにも、コートールドの絵とそっくりの作品があります。ただし松の木は2本になっています。セザンヌはいろいろと構図の研究したようです。
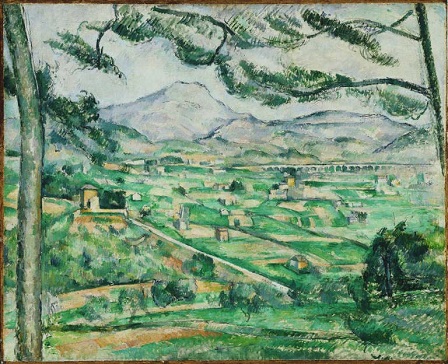
| ||
|
ポール・セザンヌ
「サント=ヴィクトワール山」
La Montagne Sainte-Victoire(1886/7)
フィリップス・コレクション ( site : www.phillipscollection.org ) | ||
浮世絵を連想させる、ということで次に思い浮かべるのは葛飾北斎(1760-1849)の『富嶽三十六景』(ないしは歌川広重の『富士三十六景』)です。セザンヌのサント=ヴィクトワール山の連作は『富嶽三十六景』に影響されたのではと感じます。
No.30「富士山と世界遺産」にも書いたのですが、そもそも特定の山を主題に絵を描くというのは、ヨーロッパの絵画ではあまり思い当たりません。山岳地帯をもつ国はイタリア、フランス、スイス、オーストリア、スペイン、ドイツ、ノルウェー、スウェーデンなどがありますが、有名画家の "山の絵" はあまり思い当たらない。唯一思い当たるのは、スイスの "国民的画家" のホドラー(1853-1918)で、ユングフラウ、アイガー、メンヒなどのアルプスの山を主題に描いています。セガンティーニ(イタリア人)やフリードリッヒ(ドイツ人)は山岳風景をたくさん描いていますが、特定の山を描いた作品は見たことがありません。
従ってセザンヌは「特定の山を主題に、しかも連作で描いた希な画家」ということになります。もちろんそれは彼の郷土愛であり、幼少期から親しんだ風景への愛着なのだろうけれど、その「山の連作」のヒントになったのは北斎というのは十分考えられると思うのです。

| |||
|
葛飾北斎
「神奈川沖浪裏」 | |||

| |||
|
葛飾北斎
「尾州不二見原」 | |||
二つの作品で言えることは、個々のモチーフである「富士山」「大波」「人の乗った舟」「大樽」「樽職人」はあくまで現実のものだし、デフォルメは別にして、現実をトレースしようとしています。しかしその「組み合わせ方」に画家の創作行為が入っていて、それこそが芸術だということなのです。
そこでコートールドの『サント=ヴィクトワール山』です。ここに描かれた松の木の "枝ぶり" は、ちょうどサント=ヴィクトワールの稜線に沿うように描かれています。これは実際の光景なのでしょうか。そうとも考えられるが、より強い可能性は画家の創作だと思うのですね。まるで松の木を「自然の額縁」かのようにしてサント=ヴィクトワール山を描いたこの絵は、画家が「そうしたい」と思ったからではないかと想像します。これは、前に引用したフィリップス・コレクションの絵でも同じです。松の枝は山の稜線にしっかり沿っているし、松の木を二本配置することで「自然の額縁」の感じがよりはっきりしています。松の木はリアルだし、サント=ヴィクトワール山もリアル、しかしその配置と組み合わせ方が画家の創作行為である ・・・・・・ そいうことではないでしょうか。セザンヌにはそのような絵がいろいろあります。静物画でも、個々の事物はリアルだが、全体としては "絶対に現実にはないような(= 現実には絶対にそうは見えないような)組み合わせである" というような絵です。
葛飾北斎の『富嶽三十六景』は、手を変え品を変えた構図とモチーフの配置で富士山を描いています。セザンヌも同様に手を変え品を変えてサント=ヴィクトワール山を描いた。ブリヂストン美術館の絵は赤い建物が非常に印象的だし、横浜美術館の絵は、サント=ヴィクトワール山を "大きな丘" という感じに見えるアングルから描いています。40枚以上描くのだから、絵描きとしてはヴァリエーションを追求するわけです。その中には創作もある。構図の探求をするなら当然でしょう。このあたりも『富嶽三十六景』との親和性を感じます。別に北斎から学んだわけではないでしょうが・・・・・・。
最近知ったのですが、セザンヌは北斎から影響を受けたと発言している専門家の方がいます。比較文化学が専門の及川茂・日本女子大学教授です。2009年に発行されたあるIT企業(JBCCホールディングス)の社長との対談ですが、その発言を引用しておきます。
|
モネ / スーラ / ゴッホ

| ||
|
クロード・モネ(1840-1926)
「アンティーブ」
Antibes(1888)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||

| |||
|
モネ「アンティーブ岬」
(愛媛県美術館) | |||

| ||
|
ジョルジュ・スーラ(1859-1891)
「クールブヴォアの橋」
Bridge at Courbevoie(1886/7)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
コートールド・ギャラリーはスーラの絵も何点か所蔵していますが、上に掲げたのは『クールブヴォアの橋(The bridge at Courbevoie)』(1886/7)で、スーラが絵の全体に点描を使った初めての作品です。パリ近郊のセーヌ河の中州であるグランド・ジャット島の水辺の静謐な風景で、点描の特質を大変よく生かした優れた絵だと思います。実はこの絵もまた近景の木が構図上のポイントになっています。

| ||
|
フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)
「桃の花盛り」
Peach Trees in Blossom(1889)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
コートールド・コレクションのゴッホの絵で有名なのは『耳に包帯をした自画像』でしょう。ここでは、風景画つながりで『桃の花盛り(Peach Trees in Blossom)』(1889)を掲げます。アルル近郊のラ・クロー平野の絵です。前景の柵と桃の木、中景の畑と家、遠景の山並みがパノラマ的にとらえられています。春先を感じさせるおだやかな色使いが大変美しい絵です。ちなみにアムステルダムのゴッホ美術館には、よく似た構図で描かれた『ラ・クローの収穫』があります。
コートールドの3つの "富士山"
ゴッホの「桃の花盛り」をよく見ると、右の方の遠景に「冠雪している三角の山」が小さく描かれています。これについて、
| 「 | 日本に憧れたゴッホが富士山のつもりで描き込んだのかもしれない」 |

| |||
|
| |||
だとすると、浮世絵を何点も所有し、その模写までもやったゴッホが「富士山のつもりで描き込んだ」というのはありうると思います。実際に冠雪した山があったとしても、それを富士山に "見立てて" 配置したということもありうるでしょう。
その富士山つながりなのですが、コートールドにあるゴッホ作品としては "桃の花" よりも、同じ年に描かれた『耳に包帯をした自画像』の方が断然有名です。この自画像の背後には画中画としてゴッホが所有していた浮世絵が描かれているのですが、その画題はというと「芸者」と「鶴」と「富士山」です。桃の花の絵に富士山を描き込んだのでは、というのはあくまで憶測ですが、ゴッホは『耳に包帯をした自画像』にはまさしく富士山を描き込んだのです。
ちなみに、ゴッホが画中画として浮世絵を描くということは、そのこと自体に特別な意味があると考えなければなりません。有名な『タンギー爺さん』には6枚もの浮世絵が描き込まれていますが、これはとりも直さず "感謝" の意味でしょう。貧しくて売れない画家である自分を支援してくれた画材店の店主に対する感謝と、画家として多大な啓示を受けた日本の浮世絵に対する感謝です。そして、このコートールドの絵の場合は、耳切り事件を起こしたあとの再出発の決意でしょう。浮世絵を描き込むことでその"決意" を鮮明にしたのだと考えられます。

| ||
|
フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)
「耳に包帯をした自画像」
Self-Portrait with Bandaged Ear(1889)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
以上のゴッホの2枚の絵と、セザンヌのところで引用した及川教授の「サント・ヴィクトワール山はセザンヌにとっての富士山」という指摘を合わせると、
| コートールド・コレクションには、3つの "富士山" がある |
ことになります。コートールド・ギャラリーを訪れたならそう思って絵を鑑賞するのも(我々日本人にとっては)楽しいでしょう。私がコートールドを紹介した知人も、夫婦でコートールドを再訪する機会があったら、是非「3つの富士山」の話をパートナーにして "知ったかぶり" をしてほしいと思います。

| |||
|
フィンセント・ファン・ゴッホ
「雪のある風景」(1888.2) グッゲンハイム美術館(NY) (site:www.guggenheim.org) | |||
モディリアーニの裸婦

| ||
|
アメディオ・モディリアーニ(1884-1920)
「裸婦」
Female Nude(1916)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
モディリアーニは多数の裸婦像を描いていますが、コートールドにあるこの『裸婦 - Female Nude』(1916)は特別です。普通、モディリアーニの裸婦というと、明らかにプロのモデルを使った絵が多いわけです。というより、モディリアーニに限らず普通の画家はそうです。

| |||
|
モディリアーニ
「ベアトリス・ヘイスティングス」
バーンズ財団(フィラデルフィア)の Room 19 South Wall にある。No.95「バーンズ・コレクション」参照。
| |||
ベアトリスだという確実な証拠はないようです。しかしモデルが誰かをさし置いたとしても、この絵の女性は「モディリアーニに強く頼まれてモデルを引き受けてしまった」という感じがします。実際にギャラリーで実物をみると、恐ろしく速く描いた、という印象が強い。タッチは素早く大胆だし、絵の下の方などは、まともには絵の具が塗られていません。30分ぐらいで描いたのではないかとさえ思えます(大袈裟ですが)。とにかく「モデルとじっくり向き合い、デッサンを重ねて、時間をかけて描いた絵」では全くないという印象が強いのです。そういうところも、プロのモデルではないという感じを強めます。
ヌード(nude)という美術用語があります。これは単なる「裸」でありません。アートの対象としての「裸体像」であり、ある種の美化や理想化(その一つとしてのデフォルメ)が行われることがよくある。しかしこの絵はちょっと違います。nude ではなく naked(裸)と強く感じさせる絵です。「見てはいけないものを見てしまったような感じ」もする。
線は確かに単純化されてはいますが、モディリアーニの絵によくある "様式化" はそれほどでもありません。線描によるデッサンの天才であったモディリアーニらしく、的確に描かれた線の美しさは格別です。肌色と緑がかった絵の具を波状に、こすり付けるようにして体を描いていて、それが生々しい感じをよく出している。全体として、女性のヴィヴィッドな美しさがよく出た傑作だと思います。
マネが描いた「鏡」
次は「コートールドといえばこの作品」「この作品と言えばコートールド」という感じの絵で、マネの『フォリー・ベルジェールのバー(A bar at the Folies-bergere)』(1881/2)です。

| ||
|
エドゥアール・マネ(1832-1883)
「フォリー・ベルジェールのバー」
A Bar at the Folies-Bergere(1881/2)
( site : www.artandarchitecture.org.uk ) | ||
フォリー・ベルジェールは19世紀後半のパリにおいて、時代の先端をいく「カフェ・コンセール」(音楽カフェ)でした(今でもある)。そこでは音楽の演奏や演劇も行われ、ホールがあり、カフェがあり、バー・カウンターがあった。その都会の最先端スポットを描いた風俗画がこの作品です。
ポイントは二つあると思います。一つは「労働者としての女性」を中心に当時の風俗を描いたことです。それも、家政婦、洗濯女、娼婦などの、昔からあった "働く女性" ではなく、産業革命を経て近代的な都市が出現し、多くの人が集まり、富が蓄積し、人々に余裕ができる ・・・・・・ その結果として出現した女性バーテンダーを描いたという点です。当然のことながら、彼女の社会的地位は低いはずですが(豪華に見える服は制服)、そういった新しい女性を描いたのがこの絵の第一のポイントだと思います。
二つ目は「鏡」です。この女性の背後には大きな鏡があって、女性の後ろ姿と、女性と話している(であろう)男性客が描かれています。女性の後ろ姿と男性客の位置関係は変で、実際にこの通りの光景はありえません。しかし鏡を使った絵画において「実際にはありえない光景」というのはよくあります。この絵も画家の創作であって、芸術作品としては十分許されることでしょう。ちなみに男性客と女性バーテンダーの組み合わせは、ドガの絵に出てくる「踊り子とシルクハットの男性」を連想させます。
鏡を使った絵画としては、以前の記事でも何点か紹介しました。まずファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(No.93「生物が主題の絵」)であり、ファン・エイクに影響されたと言われるベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)です。ベラスケスは、有名な『鏡のヴィーナス』という絵を残しています。
これらの絵の鏡は、せいぜい手鏡の程度大きさのものです。大きな鏡を作るには大きな平面の板ガラスを作る必要があるのですが、これが昔は困難だった。溶けたガラスをローラーで延ばし、平面に研磨するという方法だったからです。そこに錫箔を貼って鏡にした。完全な平面でないと鏡にはなりませんが、大きな平面ガラスを作るのが難しいわけです。ベルサイユ宮殿の有名な「鏡の間」も、複数の鏡を連結して作ってあります。

| |||
|
Mary Cassatt
「The Fitting」 | |||
マネの『フォリー・ベルジェールのバー』も同じです。シルクハットの男性と多数の客を、バーテンダーの女性の背後に配置することによって、不思議な空間を作り出しています。
シャンデリアの向こうのバルコニー席に座っている客は何をしているのでしょうか。うっかりすると見逃してしまうのですが、この絵の左上には小さく「上からぶら下がった二本の足」が描かれています。そのサイズから、男性客と観客の間にある足だと分かる。これは空中ブランコの演技を客が見ている、それが鏡に写っている、そういう絵なのですね。つまり鏡の向こうは、ホールと高い天井、舞台、曲芸師、バルコニー席、大勢の客のおしゃべり、賑やかな音楽、どよめきと歓声と拍手・・・・・・という世界です。バーのカウンターの中の狭いスペースとは違う世界が広がっているのです。
話は飛ぶのですが、イギリスのルイス・キャロルは『不思議の国のアリス』を出版したあと、好評に応えて続編の『鏡の国のアリス』(1871)を書きました。マネの絵が描かれる10年前のことです。この本の原題は「Through the Looking Glass - 鏡を通り抜けて」です。アリスが「鏡の向こうはどんな世界だろう」と空想するところから始まる冒険譚です。原書には、まさにアリスが鏡をすり抜ける瞬間の挿し絵があります。
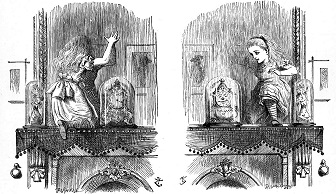
| ||
|
「鏡の国のアリス」より
(Through the Looking Glass)
初版本にジョン・テニエルが描いた挿し絵
| ||
鏡は大昔からありました。しかし人の全身より大きいような鏡が出現し、鏡の向こうにも世界があるようにリアルに感じられるようになったからこそ、ルイス・キャロルはインスピレーションを得て『鏡の国のアリス』を書いたのだと思います。そう言えば、ベラスケスに触発されて書かれたオスカー・ワイルドの童話「王女の誕生日」(1891)もまた、全身が映るような鏡がストーリーのキー・アイテムとなっているのでした(No.63 「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」参照)。
現代人である我々は、全面が鏡になっている壁を見ても何とも思いません。そういう鏡はよくあるからです。しかし19世紀後半の人々にとって、大きな「鏡」や「姿見」によって、こちら側の世界とあちら側の世界が同居する、という光景は極めて斬新だったのではないでしょうか。昔ならヴェルサイユ宮殿に招かれないと体感できないような光景が、パリのカフェで一般人が味わえる・・・・・・。それは文明がもたらした新たな光景だったのでしょう。
19世紀後半の絵画をみると、産業革命以降の文明によって庶民に身近になった事物がいろいろと描かれています。汽車やその関連設備(駅、鉄道、鉄橋)、汽船、工場、などです。No.115「日曜日の午後に無いもの」で触れた日用品としてのパラソルもその一つでしょう。そういう文明の利器の一つとして、フォリー・ベルジェールのバーに設置された大きな鏡があった。
『フォリー・ベルジェールのバー』という作品は、画家の総決算ともいえる晩年の作であり、まさに「その時代」を描いた作品です。そして制作の発端になったのは、鏡が作り出す世界が画家に与えたある種の "感動" だと感じます。
この絵について付け加えたいのは、マネの静物の描き方ですね。以前の記事で、
| 「アスパラガス」(1880) No.3「ドイツ料理万歳」 | |||
| 「スモモ」(1880) No.111「肖像画切り裂き事件」 |
というマネの静物画を引用しましたが、『フォリー・ベルジェールのバー』のカウンターに置かれた薔薇とみかんの描写も秀逸です。マネの静物は天下一品だと思います。

コートールド・コレクションの「顔」
コートールド・コレクションにはこの他にも印象派・後期印象派の画家の代表作があります。"代表作" が言い過ぎなら「画家の最良の特質をストレートに表した絵」です。そんな絵を5点あげておきます。

| ||
|
エドガー・ドガ(1834-1917)
「舞台の二人の踊り子」
Two Dancers on a Stage(1874)
( site : www.artandarchitecture.org.uk )
多数あるドガの踊り子の絵では、オルセー美術館の絵が最も有名だが、このコートールドの絵も代表作。オルセーの絵と同じく俯瞰する位置から見た絵で、二人の踊り子を極端に右上の方に配置し、しかも一人の左手を全部は描かないという構図が印象的である。カメラにたとえると、二人の踊り子を追ったが、動きが素早いのでシャッターを切り損ねて手がはみ出したかのようである。左端にも三人目の踊り子の一部が見える。そういう意図的な構図が作り出す躍動感がある。
| ||

| ||
|
オーギュスト・ルノワール(1841-1919)
「桟敷席」
La Loge(1874)
( site : www.artandarchitecture.org.uk )
ルノワールが33歳の時の作品で、第1回印象派展に出品された。ルノワールの若い頃の画風を代表する絵である。女性はじっと観劇しているが、同伴の男性は観劇には興味がなく、おそらくオペラグラスで別の桟敷席の女性客を観察しているのだろう。「別の女性客を観察」というのは、メアリー・カサットがまさにそういう絵を描いていて(ボストン美術館)、それからの連想。もっとも、舞台以外で、オペラグラスで観察する価値があるのは女性しかないとも言える。
| ||

| ||
|
ジョルジュ・スーラ(1859-1891)
「化粧する若い女」
Young woman powdering herself(1888/90)
( site : www.artandarchitecture.org.uk )
スーラが同棲していた女性を描いた作品。この女性の圧倒的に "ふくよかな" 感じが点描で表されている。
| ||

| ||
|
ポール・ゴーギャン(1848-1903)
「ネバーモア」
Nevermore(1897)
( site : www.artandarchitecture.org.uk )
先にモディリアーニの裸婦をあげたが、こちらの方は正真正銘の素人モデルである。モディリアーニと対比すると、描かれた場所、モデルの人種・民族、文化的背景は全く違うが、まわりの色使いや装飾模様とタヒチアンの女性のヌードがマッチした美しい作品。Nevermore(2度とない)というタイトルと、いわくありげな鳥と2人の人物がさまざまな解釈を呼んでいる。
| ||

| ||
|
アンリ・ルソー(1844-1910)
「税関」
Toll Gate(1890)
( site : www.artandarchitecture.org.uk )
パリの税関史だったアンリ・ルソーが自分の「職場」を描いた唯一の作品。パリ市の南門の税関を描いたという。しかし、19世紀後半とはいえ、こんな田園風景がパリに広がっていたとは思えない。プッチーニのオペラ「ラ・ボエーム」にも入市税を徴収する税関が出てくるが、そこは当然のことながら交通の要衝であり、人々が行き交い、近くに居酒屋・旅籠があるというシチュエーションである。
この絵には空想の風景が多分にミックスされていると考えられ、「木」や「植物」に対する画家の愛着が感じられる。アンリ・ルソーの絵は空想も含めて「緑」が多く、それはバーンズ・コレクションに多数あるルソー作品をみても一目瞭然である。 | ||
No.152 - ワイエス・ブルー [アート]
No.150「クリスティーナの世界」と No.151「松ぼっくり男爵」でアンドリュー・ワイエス(1917-2009)の絵画をとりあげましたが、その継続です。今回はアンドリュー・ワイエスの "色づかい" についてです。No.18「ブルーの世界」の続きという意味もあります。
まず「クリスティーナの世界」の画題となったオルソン家の話からはじめます。
オルソン家
No.150「クリスティーナの世界」で描かれたクリスティーナ・オルソンは、1歳年下の弟・アルヴァロとともにオルソン・ハウスと呼ばれた家に住んでいました。その家はアメリカ東海岸の最北部、メイン州のクッシングにあるワイエス家の別荘の近くです。オルソン家とアンドリュー・ワイエスの出会いを、福島県立美術館・学芸員の荒木康子氏が書いています。
アンドリュー・ワイエスにとって、妻・ベッツィとの出会いが、すなわちオルソン家との出会いだったわけです。ワイエスの "オルソン・シリーズ" の中の、オルソン・ハウスを描いたテンペラ画と水彩画をあげてみます。
ちなみに上の絵の「Weatherside」とは「風上側」という意味ですね。建物などの "風が吹き付ける側" を言います。長い年月のあいだ風雨にさらされ、切妻の板が古びて変色した感じがリアルに表現されています。
この2枚の絵の「色づかい」に着目すると、目立つのは明度・彩度の異なるさまざまな黄色・茶色・褐色系統の色、白と灰色から黒の無彩色です。このような色づかいは上の2枚だけでなく、ワイエスの絵に夥しく現れます。これらの色に No.151 の「松ぼっくり男爵」でも使われた緑(特に、濃い緑)を加えたのが、ワイエスの典型的な色づかいだと言えるでしょう。これを「ワイエス・カラー」と呼ぶことにします。つまり、
です。もちろんプロの画家としては、これ以外の色を混ぜたり、重ねたり、下地に塗ったりするわけです。No.151「松ぼっくり男爵」で引用したワイエスの "自作解説" では「松の木の赤錆たような感じを出すために下地に赤を塗り、その上に緑を塗った」とありました。
そしてワイエスの絵には「ワイエス・カラー」に、それとは異質な色を組み合わせたものがいろいろあります。たとえば No.150の「クリスティーナの世界」では、クリスティーナのドレスの淡いピンク色が実に効果的に使われていました。この絵の大きな魅力はドレスのピンク色だといってもいいでしょう。
その「異質な色との組み合わせ」の一つとして、ワイエス・カラーの中に一部分だけ「青」を特徴的に使った絵があります。それは、数は多くはないけれど「ワイエス・ブルー」と呼んでいいほど強い印象を受ける「青」です。以下、そのワイエス・ブルーの絵画を何点か取り上げてみます。
ワイエスの "オルソン・シリーズ" の絵に『アルヴァロとクリスティーナ』という、ズバリの題が付けられた絵があります。
『アルヴァロとクリスティーナ』という題ですが、この絵にはアルヴァロもクリスティーナも描かれていません。この絵についてワイエスは、メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングのインタビューに答えて、次のように語っています。
つまり『アルヴァロとクリスティーナ』と題するこの絵は、アルヴァロとクリスティーナが亡くなってから描かれたわけです。この絵でひときわ目立つのが青いドアです。このドアが青く塗られている理由について、美術史家の岡部幹彦氏(元・福島県立美術館学芸員、元・文化庁文化財部)が「ワイエス水彩素描展」の図録に次の主旨の解説を書いていました。
描かれているのは青いドアと、もう一つの左側のドアです。左のドアの前には籠(ワイエスの自作解説では "バスケット")があります。これはアルヴァロがブルーベリーを収穫するときに使っていた籠で、ワイエスはこの籠を何枚も描いています。真ん中にはバケツがあり、その上にはエプロンらしきものが掛かっています。フライパンもある。おそらく、クリスティーナが使っていたものでしょう。
この絵はワイエス自身が語っているように、2枚のドアと籠やバケツでアルヴァロとクリスティーナを代弁させた絵です。かつ、姉弟の父親が塗った青いペンキは、船乗りの家系であるオルソン家の象徴だと考えられる。アンドリュー・ワイエスはオルソン姉弟に聞いたに違いないのですね。なぜこのドアは青く塗られているのかと・・・・・・。それに対してオルソン姉弟は父親から聞いた話を答える・・・・・・。これはごく自然な想像だと思います。
この状況は No.151で書いた『松ぼっくり男爵』とそっくりです。『松ぼっくり男爵』では、鉄兜がカール・カーナー、松ぼっくりがアンナ・カーナー、松並木は夫妻の歴史の象徴だという感想を書いたのですが、それと全くパラレルなことが『アルヴァロとクリスティーナ』にも言えるわけです。
この絵は "モノに執着するワイエス" を如実に示しています。しかも、人が使い込んだものはその人の魂を宿すという発想を感じます。これは我々日本の文化風土からすると非常に分かりやすい。逆にいうと「モノに心を感じる」ような精神はアメリカ人にも(少なくともワイエスには)あることが分かります。
しかし何よりもこの絵で印象深いのは、鮮烈な青色です。決して強い青色ではなく、どちらかというと淡い青だけれど、絵の中に置かれると非常に鮮やかで、そこだけが強く輝いて見える。このたぐいの青を「ワイエス・ブルー」と名付けたい理由です。
ブルーベリーの栽培はオルソン家の重要な収入源であり、アルヴァロは籠(バスケット)を使って収穫をしていました。この水彩画に描かれた籠は少し破損していて、ブルーベリーがのぞいている様子も描かれています。
「オルソン・ハウスの物置のドアや計量器、箱などの多くのものが青いペイントで塗られていた」との解説を引用しましたが、その計量器と箱をワイエスは描いています。

チャッズ・フォード
ここからはワイエスの生家があるベンシルヴァニア州のチャッズ・フォードで描かれたものです。
ワイエスの妻、ベッツィの友人を描いた肖像画です。白髪まじりの髪を後ろに束ね、着古した感じの青いジャケットを着ています。そこには茶色のシミやこすれのような表現がいろいろとあります。全く飾らない質素ないでたちですが、顔の表情を見ると目は輝き、鼻筋がとおり、口は上品に結ばれていて、気品を感じる姿です。この絵は "鮮やかな青" が人物の性格を引き立ているようです。
下の絵はワイエス家の水車小屋(粉ひき小屋)の内部から外を見た光景です。青いペンキで塗られた窓枠は、暗い青色で、古びたような色ですが、それと戸外の明るくて黄色っぽい風景の対比がきいています。
『大水のあと - Flood Plain』と題された絵です。あたり一面が水浸しになり、水が引いたあとの光景です。ワイエスの「自作解説」によると、この絵に描かれた青いモノは、幌馬車の残骸です。ワイエスはこれを発見したときに、洪水の後の風景が "絵になる" と思ったのでしょう。
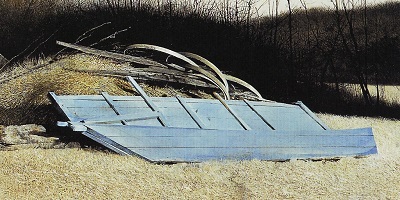
No.151「松ぼっくり男爵」で書いたように、ワイエスは自宅近くのカーナー農場とカーナー夫妻を描き続けたのですが、この絵もその1枚です。アンナ・カーナー(当時87歳。夫のカールとは既に死別)が農作業をしていますが、そこに青い矢車草が咲いています。縮小画像にすると矢車草はほとんど分からないのですが、実際に展覧会でこの絵を見ると、青い点々が下のほうに散らばっているのに気づきます。
ワイエスはこの絵の題を「矢車草」としています。小さな花の青色が絵の主題になっているわけです。

ワイエスの作品を貫くテーマの一つは「多民族国家としてのアメリカ」です。アルヴァロとクリスティーナのオルソン兄弟はスウェーデン移民の2世だし、カールとアンナのカーナー夫妻はドイツからの移民です(No.151「松ぼっくり男爵」)。No.151で引用したワイエス展のポスターの「Gunning Rocks」という絵は、フィンランド人とネイティブ・アメリカンの血をひく男性の横顔でした。他にもフィンランド移民の男性の肖像を描いているし、その娘(シリという名)の美しいヌードもあります。ネイティブ・アメリカンの男性の肖像もありました。
その多民族国家・アメリカの象徴ですが、ワイエスは子どものころからカーナー農場の向こうにあった「リトル・アフリカ」というアフリカ系アメリカ人の集落に出入りしていました。そこの子どもと友人になり、人々の絵を描きました。そのなかから "ワイエス・ブルー" を使った2作品を引用します。この作品もそうですが、一見してアフリカ系アメリカ人が辿った苦難の歴史を想像させるような絵がいろいろとあります。
ワイエスが火の描写に挑戦した1枚です。チャッズ・フォードのある情景ですが、その色づかいに着目したいと思います。写真を縮小した画像では分かりにくいのですが、実際にこの絵を見ると、炎の中にわずかに青みがかった灰色が描かれています。火の中に青みがかった色が見えるのはありえることですが、普通のたき火ではあまりないでしょう。これはワイエスの画家としての感性にもとづく絵画だと考えられます。
メイン州
ふたたびメイン州の光景に戻ります。青は空の色であり、また海や湖、川なども青く見えることがよくあります。こういった「空や水の青」もワイエスの絵にはいろいろありますが、1枚だけあげるとすると「The Carry」という晩年の絵です。"carry" とは、川の水深が浅くなっている場所で、ボートが航行できないため岸にあげて運ぶ、そういう場所のことです。訳すと「陸上運搬」でしょうか。
この絵は、川や湖水の水の青が大変に美しい絵です。空はほとんど描かれていないのですが、上空にも青空が広がっていることが、ありありと想像できる。この絵は実物を見たことがないのですが、ぜひ一度、鑑賞してみたいものです。
これもメイン州・クッシングの光景です。草原の木陰で昼寝をしている人がいます。犬がそばにいて、双眼鏡とカップと、ブルーベリーの入った小さな籠がそばにある。
青いシャツの胸の膨らみから、この人が女性だと分かります。とすると、女性が無防備な姿で寝ていることになる。実際に散歩をしていてこういう場面に出会ったら少々ドキッとするはずですが、ここはメイン州・クッシングの "田舎" です。もちろん安全なのでしょう。犬もいます。
アンドリュー・ワイエスの "自作解説" によると女性は妻のベッツィです。そしてこのとき「ウォルドボロの方角から雷鳴が聞こえてきた」とあります。ウォルドボロはクッシングの北西、数10kmの町です。ということは、犬はかすかな雷鳴に気づいて頭をもたげたということでしょう。「遠雷」という題のゆえんです。
この絵の魅力となっているのが「ワイエス・ブルー」だと思います。女性のシャツの淡い青と、小さく描かれたブルーベリーの濃いめの青、その対比が印象的です。このブルーが、茶と緑の入り交じった「ワイエス・カラー」の草原風景によく映えています。

ブルーの魅力
No.18「ブルーの世界」で、青色染料・顔料の歴史とともに、青を使った絵画を取り上げました。ラピスラズリを使ったフェルメールの絵画は有名で「フェルメール・ブルー」と呼ばれたりします。ピカソの「青の時代」の絵は、プルシアン・ブルーを使った青の濃淡だけで絵が構成されています。
日本では植物顔料である藍が浮世絵に多用されました。この藍色を西欧では「ヒロシゲ・ブルー」と言ったりします。またプルシアン・ブルー(江戸時代の言い方ではベロ藍)を効果的に使った葛飾北斎の浮世絵もありました。現代日本画では東山魁夷画伯の「ヒガシヤマ・ブルー」が有名です。
アンドリュー・ワイエスという画家の "青" は、上にあげた画家とは違って、白が混じったような "淡くて薄い青"、ないしは "くすんだ青" です。それを画面の一部だけに使う(ことが多い)。しかし絵の中ではその青が強い輝きを放っています。
これはいわゆる「補色効果」というやつですね。つまりワイエス・カラーで多用される黄・茶色系統の色、これと青が補色関係にあるわけです。この効果で「淡い、薄い青」でも引き立つ。そういうことだと思います。
もちろん「青」と「黄・茶」の補色関係を利用した絵は昔からあります。No.18「ブルーの世界」であげたフェルメールはラピスラズリの青のそばに黄色系を配置したものがあるし(No.18 の「牛乳を注ぐ女」など)、ゴッホもそういう名手です。まっ黄色の麦畑の上にプルシアン・ブルーの紺碧の空が広がっている(そこにカラスが飛んでいる)ゴッホの絵は何枚かあるし、有名な『夜のカフェテラス』も、カフェから漏れる強烈な光の黄色と夕闇が迫る空の深い青の対比が素晴らしい。このようなラピスラズリやプルシアン・ブルーの青は、色そのものに個性がある青、いわば「主張する青」です。
それに対してワイエスは、絵の中に配置されることによって初めて引き立つ "控えめな青" を極めて巧みに使っています。それと対比される補色も、彩度の低い、おだやかな黄・茶系統の色です。しかし絵として美しく、印象的なことには変わりがない。アンドリュー・ワイエスもまた「青を使う名手」だと思います。
まず「クリスティーナの世界」の画題となったオルソン家の話からはじめます。
オルソン家
No.150「クリスティーナの世界」で描かれたクリスティーナ・オルソンは、1歳年下の弟・アルヴァロとともにオルソン・ハウスと呼ばれた家に住んでいました。その家はアメリカ東海岸の最北部、メイン州のクッシングにあるワイエス家の別荘の近くです。オルソン家とアンドリュー・ワイエスの出会いを、福島県立美術館・学芸員の荒木康子氏が書いています。
|
アンドリュー・ワイエスにとって、妻・ベッツィとの出会いが、すなわちオルソン家との出会いだったわけです。ワイエスの "オルソン・シリーズ" の中の、オルソン・ハウスを描いたテンペラ画と水彩画をあげてみます。
なお、以下に掲げる絵で、引用元を明示しなかったものは日本で開催された以下の3つの展覧会、
|

| ||
|
「さらされた場所」
- Weatherside - 1965(48歳)。テンペラ | ||

| ||
|
「オルソンの家」
- Olson House - 1966(49歳)。水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||
ちなみに上の絵の「Weatherside」とは「風上側」という意味ですね。建物などの "風が吹き付ける側" を言います。長い年月のあいだ風雨にさらされ、切妻の板が古びて変色した感じがリアルに表現されています。
この2枚の絵の「色づかい」に着目すると、目立つのは明度・彩度の異なるさまざまな黄色・茶色・褐色系統の色、白と灰色から黒の無彩色です。このような色づかいは上の2枚だけでなく、ワイエスの絵に夥しく現れます。これらの色に No.151 の「松ぼっくり男爵」でも使われた緑(特に、濃い緑)を加えたのが、ワイエスの典型的な色づかいだと言えるでしょう。これを「ワイエス・カラー」と呼ぶことにします。つまり、
ワイエス・カラー:
|
です。もちろんプロの画家としては、これ以外の色を混ぜたり、重ねたり、下地に塗ったりするわけです。No.151「松ぼっくり男爵」で引用したワイエスの "自作解説" では「松の木の赤錆たような感じを出すために下地に赤を塗り、その上に緑を塗った」とありました。
そしてワイエスの絵には「ワイエス・カラー」に、それとは異質な色を組み合わせたものがいろいろあります。たとえば No.150の「クリスティーナの世界」では、クリスティーナのドレスの淡いピンク色が実に効果的に使われていました。この絵の大きな魅力はドレスのピンク色だといってもいいでしょう。
その「異質な色との組み合わせ」の一つとして、ワイエス・カラーの中に一部分だけ「青」を特徴的に使った絵があります。それは、数は多くはないけれど「ワイエス・ブルー」と呼んでいいほど強い印象を受ける「青」です。以下、そのワイエス・ブルーの絵画を何点か取り上げてみます。
| アルヴァロとクリスティーナ |
ワイエスの "オルソン・シリーズ" の絵に『アルヴァロとクリスティーナ』という、ズバリの題が付けられた絵があります。

| ||
|
「アルヴァロとクリスティーナ」
- Alvaro and Christina - 1968(51歳)。水彩 (ファーンズワース美術館・所蔵) | ||
『アルヴァロとクリスティーナ』という題ですが、この絵にはアルヴァロもクリスティーナも描かれていません。この絵についてワイエスは、メトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングのインタビューに答えて、次のように語っています。
|
つまり『アルヴァロとクリスティーナ』と題するこの絵は、アルヴァロとクリスティーナが亡くなってから描かれたわけです。この絵でひときわ目立つのが青いドアです。このドアが青く塗られている理由について、美術史家の岡部幹彦氏(元・福島県立美術館学芸員、元・文化庁文化財部)が「ワイエス水彩素描展」の図録に次の主旨の解説を書いていました。
|
描かれているのは青いドアと、もう一つの左側のドアです。左のドアの前には籠(ワイエスの自作解説では "バスケット")があります。これはアルヴァロがブルーベリーを収穫するときに使っていた籠で、ワイエスはこの籠を何枚も描いています。真ん中にはバケツがあり、その上にはエプロンらしきものが掛かっています。フライパンもある。おそらく、クリスティーナが使っていたものでしょう。
この絵はワイエス自身が語っているように、2枚のドアと籠やバケツでアルヴァロとクリスティーナを代弁させた絵です。かつ、姉弟の父親が塗った青いペンキは、船乗りの家系であるオルソン家の象徴だと考えられる。アンドリュー・ワイエスはオルソン姉弟に聞いたに違いないのですね。なぜこのドアは青く塗られているのかと・・・・・・。それに対してオルソン姉弟は父親から聞いた話を答える・・・・・・。これはごく自然な想像だと思います。
この状況は No.151で書いた『松ぼっくり男爵』とそっくりです。『松ぼっくり男爵』では、鉄兜がカール・カーナー、松ぼっくりがアンナ・カーナー、松並木は夫妻の歴史の象徴だという感想を書いたのですが、それと全くパラレルなことが『アルヴァロとクリスティーナ』にも言えるわけです。
この絵は "モノに執着するワイエス" を如実に示しています。しかも、人が使い込んだものはその人の魂を宿すという発想を感じます。これは我々日本の文化風土からすると非常に分かりやすい。逆にいうと「モノに心を感じる」ような精神はアメリカ人にも(少なくともワイエスには)あることが分かります。
しかし何よりもこの絵で印象深いのは、鮮烈な青色です。決して強い青色ではなく、どちらかというと淡い青だけれど、絵の中に置かれると非常に鮮やかで、そこだけが強く輝いて見える。このたぐいの青を「ワイエス・ブルー」と名付けたい理由です。
| ブルーベリー |
ブルーベリーの栽培はオルソン家の重要な収入源であり、アルヴァロは籠(バスケット)を使って収穫をしていました。この水彩画に描かれた籠は少し破損していて、ブルーベリーがのぞいている様子も描かれています。

| ||
|
「パイ用のブルーベリー・習作」
- Study for Pie Berries - 1967(50歳)。水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||
| 計量器と箱 |
「オルソン・ハウスの物置のドアや計量器、箱などの多くのものが青いペイントで塗られていた」との解説を引用しましたが、その計量器と箱をワイエスは描いています。

| ||
|
「青い計量器」 - Blue Measure -
1959(42歳)。ドライブラッシュ・水彩 (丸沼芸術の森・所蔵) | ||

(部分)
 | ||
|
「青い箱」 - Blue Box -
1956(39歳)。水彩 | ||
チャッズ・フォード
ここからはワイエスの生家があるベンシルヴァニア州のチャッズ・フォードで描かれたものです。
| 肖像 |
ワイエスの妻、ベッツィの友人を描いた肖像画です。白髪まじりの髪を後ろに束ね、着古した感じの青いジャケットを着ています。そこには茶色のシミやこすれのような表現がいろいろとあります。全く飾らない質素ないでたちですが、顔の表情を見ると目は輝き、鼻筋がとおり、口は上品に結ばれていて、気品を感じる姿です。この絵は "鮮やかな青" が人物の性格を引き立ているようです。

| ||
|
「アラベラ」 - Arabella -
1969(52歳)。ドライブラッシュ・水彩(紙)
The Metropolitan Museum of Art
| ||
| 窓 |
下の絵はワイエス家の水車小屋(粉ひき小屋)の内部から外を見た光景です。青いペンキで塗られた窓枠は、暗い青色で、古びたような色ですが、それと戸外の明るくて黄色っぽい風景の対比がきいています。
 | ||
|
「昼下がりの想い」
- Love in the Afternoon - 1992(75歳)。テンペラ | ||
| 幌馬車 |
『大水のあと - Flood Plain』と題された絵です。あたり一面が水浸しになり、水が引いたあとの光景です。ワイエスの「自作解説」によると、この絵に描かれた青いモノは、幌馬車の残骸です。ワイエスはこれを発見したときに、洪水の後の風景が "絵になる" と思ったのでしょう。
 | ||
|
「大水のあと」 - Flood Plain -
1986(69歳)。テンペラ | ||
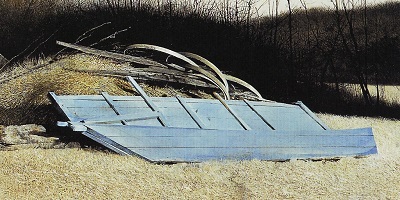
(部分)
| 矢車草 |
No.151「松ぼっくり男爵」で書いたように、ワイエスは自宅近くのカーナー農場とカーナー夫妻を描き続けたのですが、この絵もその1枚です。アンナ・カーナー(当時87歳。夫のカールとは既に死別)が農作業をしていますが、そこに青い矢車草が咲いています。縮小画像にすると矢車草はほとんど分からないのですが、実際に展覧会でこの絵を見ると、青い点々が下のほうに散らばっているのに気づきます。
ワイエスはこの絵の題を「矢車草」としています。小さな花の青色が絵の主題になっているわけです。
 | ||
|
「矢車草」 - Cornflowers -
1986(69歳)。水彩 | ||

(部分)
| リトル・アフリカ |
ワイエスの作品を貫くテーマの一つは「多民族国家としてのアメリカ」です。アルヴァロとクリスティーナのオルソン兄弟はスウェーデン移民の2世だし、カールとアンナのカーナー夫妻はドイツからの移民です(No.151「松ぼっくり男爵」)。No.151で引用したワイエス展のポスターの「Gunning Rocks」という絵は、フィンランド人とネイティブ・アメリカンの血をひく男性の横顔でした。他にもフィンランド移民の男性の肖像を描いているし、その娘(シリという名)の美しいヌードもあります。ネイティブ・アメリカンの男性の肖像もありました。
その多民族国家・アメリカの象徴ですが、ワイエスは子どものころからカーナー農場の向こうにあった「リトル・アフリカ」というアフリカ系アメリカ人の集落に出入りしていました。そこの子どもと友人になり、人々の絵を描きました。そのなかから "ワイエス・ブルー" を使った2作品を引用します。この作品もそうですが、一見してアフリカ系アメリカ人が辿った苦難の歴史を想像させるような絵がいろいろとあります。

| ||
|
「アダム」- Adam -
1963(46歳)。テンペラ
Brandywine River Museum of Art
| ||

| ||
|
「孫娘」- Granddaughter -
1956(39歳)。水彩
Wadsworth Atheneum Museum
| ||
| たき火 |
ワイエスが火の描写に挑戦した1枚です。チャッズ・フォードのある情景ですが、その色づかいに着目したいと思います。写真を縮小した画像では分かりにくいのですが、実際にこの絵を見ると、炎の中にわずかに青みがかった灰色が描かれています。火の中に青みがかった色が見えるのはありえることですが、普通のたき火ではあまりないでしょう。これはワイエスの画家としての感性にもとづく絵画だと考えられます。
 | ||
|
「たき火」 - Bonfire -
1993(76歳)。水彩 | ||
メイン州
| 空と水 |
ふたたびメイン州の光景に戻ります。青は空の色であり、また海や湖、川なども青く見えることがよくあります。こういった「空や水の青」もワイエスの絵にはいろいろありますが、1枚だけあげるとすると「The Carry」という晩年の絵です。"carry" とは、川の水深が浅くなっている場所で、ボートが航行できないため岸にあげて運ぶ、そういう場所のことです。訳すと「陸上運搬」でしょうか。
 | ||
|
「The Carry」
2003(86歳)。テンペラ (andrewwyeth.com より引用) | ||
この絵は、川や湖水の水の青が大変に美しい絵です。空はほとんど描かれていないのですが、上空にも青空が広がっていることが、ありありと想像できる。この絵は実物を見たことがないのですが、ぜひ一度、鑑賞してみたいものです。
| 遠雷 |
これもメイン州・クッシングの光景です。草原の木陰で昼寝をしている人がいます。犬がそばにいて、双眼鏡とカップと、ブルーベリーの入った小さな籠がそばにある。
青いシャツの胸の膨らみから、この人が女性だと分かります。とすると、女性が無防備な姿で寝ていることになる。実際に散歩をしていてこういう場面に出会ったら少々ドキッとするはずですが、ここはメイン州・クッシングの "田舎" です。もちろん安全なのでしょう。犬もいます。
 | ||
|
「遠雷」 - Distant Thunder -
1961(44歳)。テンペラ | ||
アンドリュー・ワイエスの "自作解説" によると女性は妻のベッツィです。そしてこのとき「ウォルドボロの方角から雷鳴が聞こえてきた」とあります。ウォルドボロはクッシングの北西、数10kmの町です。ということは、犬はかすかな雷鳴に気づいて頭をもたげたということでしょう。「遠雷」という題のゆえんです。
この絵の魅力となっているのが「ワイエス・ブルー」だと思います。女性のシャツの淡い青と、小さく描かれたブルーベリーの濃いめの青、その対比が印象的です。このブルーが、茶と緑の入り交じった「ワイエス・カラー」の草原風景によく映えています。

(部分)
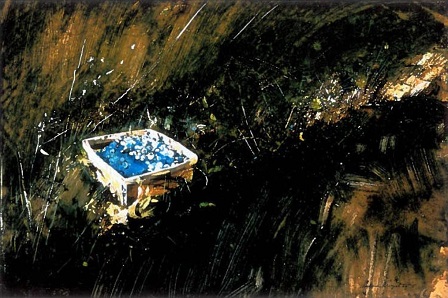 | ||
|
「ブルーベリー、遠雷のための習作」
- Blueberries, Study for Distant Thunder - 1961(44歳)。水彩 (ファーンズワース美術館・所蔵) (www.farnsworthmuseum.org より引用) | ||
ブルーの魅力
No.18「ブルーの世界」で、青色染料・顔料の歴史とともに、青を使った絵画を取り上げました。ラピスラズリを使ったフェルメールの絵画は有名で「フェルメール・ブルー」と呼ばれたりします。ピカソの「青の時代」の絵は、プルシアン・ブルーを使った青の濃淡だけで絵が構成されています。
日本では植物顔料である藍が浮世絵に多用されました。この藍色を西欧では「ヒロシゲ・ブルー」と言ったりします。またプルシアン・ブルー(江戸時代の言い方ではベロ藍)を効果的に使った葛飾北斎の浮世絵もありました。現代日本画では東山魁夷画伯の「ヒガシヤマ・ブルー」が有名です。
アンドリュー・ワイエスという画家の "青" は、上にあげた画家とは違って、白が混じったような "淡くて薄い青"、ないしは "くすんだ青" です。それを画面の一部だけに使う(ことが多い)。しかし絵の中ではその青が強い輝きを放っています。
これはいわゆる「補色効果」というやつですね。つまりワイエス・カラーで多用される黄・茶色系統の色、これと青が補色関係にあるわけです。この効果で「淡い、薄い青」でも引き立つ。そういうことだと思います。
もちろん「青」と「黄・茶」の補色関係を利用した絵は昔からあります。No.18「ブルーの世界」であげたフェルメールはラピスラズリの青のそばに黄色系を配置したものがあるし(No.18 の「牛乳を注ぐ女」など)、ゴッホもそういう名手です。まっ黄色の麦畑の上にプルシアン・ブルーの紺碧の空が広がっている(そこにカラスが飛んでいる)ゴッホの絵は何枚かあるし、有名な『夜のカフェテラス』も、カフェから漏れる強烈な光の黄色と夕闇が迫る空の深い青の対比が素晴らしい。このようなラピスラズリやプルシアン・ブルーの青は、色そのものに個性がある青、いわば「主張する青」です。
それに対してワイエスは、絵の中に配置されることによって初めて引き立つ "控えめな青" を極めて巧みに使っています。それと対比される補色も、彩度の低い、おだやかな黄・茶系統の色です。しかし絵として美しく、印象的なことには変わりがない。アンドリュー・ワイエスもまた「青を使う名手」だと思います。
No.151 - 松ぼっくり男爵 [アート]
福島県立美術館
前回の No.150「クリスティーナの世界」で、福島県立美術館が所蔵するアンドリュー・ワイエスの「松ぼっくり男爵」にふれました。今回はこの絵についてです。

| |||
|
ポスターの絵は「Faraway」(遥か彼方に。1952)。モデルは息子のジェイムズ。
| |||
しかし福島県立美術館で出会ったワイエス、特に「松ぼっくり男爵」は心に残るものでした。それは「思いがけず」ということに加えて「不思議な絵だな」という感触を持ったからだと思います。もちろん、福島で見たときには、この絵が描かれた経緯を知りませんでした。以下の「描かれた経緯」は全てあとで知ったものです。
なお以下の説明は、
| ◆ | テレビ東京「美の巨人たち」で放映された「松ぼっくり男爵」(2013.6.22) | ||
| ◆ | 福島県立美術館の学芸員・荒木康子氏の解説 = 「アンドリュー・ワイエス 創造への道程展 2008」の図録所載 |
を参考にしました。荒木康子氏は「美の巨人たち」のインタビューにも答えていました。

| ||
|
福島県立美術館
| ||
松ぼっくり男爵
アンドリュー・ワイエス(1917-2009)の「松ぼっくり男爵 Pine Baron」は、1976年に描かれた作品です。ワイエス59歳のときの作品ということになります。正方形の板の上にテンペラの手法で描かれています。

| ||
|
アンドリュー・ワイエス
(1917-2009) 「松ぼっくり男爵 - Pine Baron - 」(1976) (福島県立美術館) | ||
これは一見して「不思議な絵」です。「松並木」と「松ぼっくり」と、道に落ちている「松葉」はいたって普通ですが、そこに「鉄兜」が登場するのが不思議です。もし鉄兜ではなく何らかのカゴかバケツに松ぼっくりが入っていたとしたら、誰かが松ぼっくりを集め、あとで取りにくるまでの光景だと思うでしょう。それなら普通の光景です。しかしここに鉄兜がある。これはどういう意味なのか。
題名も不思議です。「男爵」とは何か。「松ぼっくり」と「男爵」を続けて言うのは(英語題名はPine Baron)どういう意味があるのか、謎です。心に引っかかる。
「描かれた経緯を知らないと真の意味が理解しがたい絵」があります。前回の No.150 「クリスティーナの世界」がそうでした。クリスティーナが小児麻痺であり、這いつくばるようにして我が家へ向かっている、ということを知らなければ、この絵の真の意味が理解できません。こういったたぐいの絵はワイエスには少ないと思うのですが「松ぼっくり男爵」はそういったタイプの絵です。
そして「クリスティーナの世界」と「松ぼっくり男爵」は他にも共通点があります。人の人生を絵の中に凝縮させたという共通点です。「松ぼっくり男爵」がなぜ「人生」なのか、それが以下です。
ワイエスはペンシルベニア州フィラデルフィア郊外のチャッズ・フォードに生まれ、生涯、生まれ故郷と別荘のあるメーン州クッシング以外には移動を好まず、ひたすらその周辺の風景や人物を描き続けたのは、前回書いた通りです。
そのワイエスの生家の裏手の丘の向こうに「カーナー農場」があり、カールとアンナのカーナー夫妻が経営していました。カーナー夫妻はドイツからの移民です。カールは1898年生まれで、シュヴァルツヴァルトの村の羊飼いでしたが、第1次世界大戦にドイツ陸軍に従軍し、鉄十字勲章を受けました。故郷に戻ってから一歳年下のアンナと結婚したのですが、おりからのインフレで生活が苦しく、1926年にアメリカに渡って開いたのがカーナー農場でした。「松ぼっくり男爵」に描かれている鉄兜は、カールが第1次世界大戦で使ったドイツ軍のヘルメットです。戦場でカールの命を守ったヘルメットでした。
| そういえばこのヘルメットの形は少し変わっています。ヘルメットの周囲の一部が突き出た形をしている。この形をどこかで見たことがあるなと思い出すと、それは第二次世界大戦のヨーロッパ戦線を描いた映画でした。そこでのドイツ軍のヘルメットがこういう形をしていた。ドイツ軍は第一時世界大戦当時から似た形のヘルメットを使っていたことになります。 |
カールは無骨で粗野な男です。アンナは英語がしゃべれず、話相手もいませんでした。内気で、気むずかしい女性です。二人は日の出から日没まで、農場で働き詰めでした。
ワイエスがカーナー農場を初めて訪れたのは13歳の時だといいます。16歳のときには「カーナー農場の春景色」(1933)という油絵を描いてカーナー夫妻にプレゼントしました。カール・カーナーはワイエスより19歳年上です。16歳の少年が35歳の男に絵をプレゼントする・・・・・・。ワイエスとカーナーの関係を物語っています。ワイエスは、この10代の時から約60年間もこの農場に通い続け、カーナー夫妻や農場をモチーフに絵を描き続けたのでした。カールが亡くなったのは1979年・81歳、アンナは長生きをし、1997年・98歳で亡くなりました。
このカーナー農場の入り口には松並木がありました。これは、カールが故郷のドイツから持ってきた松の苗木を植えたものです。ホームシックになったアンナをなぐさめる意味もあったと言います。
ワイエスが59歳、カールは78歳の時です。火を起こすための松ぼっくりを集めるのはアンナの仕事でした。ワイエスはたまたま、農場の松並木で鉄兜に入ったままの松ぼっくりを目撃するのです。その時の様子は、ワイエス自身がメトロポリタン美術館・館長のトーマス・ホーヴィングのインタビューに答えて語っています。以下にそれを引用します。
|
| ちなみに上の引用に出てくる "ニーダム" とは、ボストン近郊の町で、父親のニューウェル・C・ワイエスが生まれ、育った町です。アンドリューも子供の頃、夏に何回か訪れています。 |
ワイエスは以前にも、アンナがカールの鉄兜をバケツがわりにして松ぼっくりを集めているのを目撃したことがあります。そのアンナの姿のスケッチが何枚か残っています。しかしこの時、目撃した光景にアンナの姿はなかった。それが画家に不思議な感覚を与え、絵画へのインスピレーションとなった。そこにアンナの労働がなかったからこそ、逆にカールとアンナを象徴するように見えたのだと思います。
題名についてですが、チャッツ・フォードの人たちは、頑固者のカールをバロンと呼んだようです。福島県立美術館の学芸員の荒木康子氏は「美の巨人たち」のなかで、次のように語っていました。
|

| ||
|
アンドリュー・ワイエス
「カーナー夫妻」(1971)
「アンドリュー・ワイエス展」(1995)の図録より引用
| ||
絵に込められたもの
「松ぼっくり男爵」は福島県立美術館で見た以降、2回の「ワイエス展」で見たことがあります。愛知県立美術館(1995)と、Bunkamura ミュージアム(2008)です。

| ||
|
愛知県美術館(1995.2.3 - 4.2)
Bunkamura ザ・ミュージアム(1995.4.15 - 6.4) 兵庫県立近代美術館(1995.6.10 - 7.3) ポスターの絵は「遠雷 - Distant Thunder」(1961) | ||
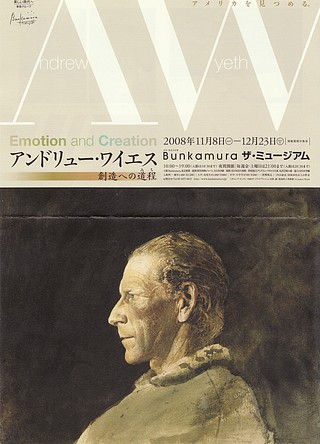
| ||
|
Bunkamura ザ・ミュージアム(2008.11.8 - 12.23)
愛知県美術館(2009.1.4 - 3.8) 福島県立美術館(2009.3.17 - 5.10) ポスターの絵は「Gunning Rocks」(1966)。福島県立美術館蔵。Gunning Rocks とは、ワイエス家の別荘があったメイン州クッシングに近い、沿岸の小島。描かれているのはネイティブ・アメリカンとフィンランド人の血をひくウォルター・アンダーソンという人物で、ワイエスとはよく小舟で一緒に海にでかけた。 | ||

| ||
|
アンドリュー・ワイエス
(1917-2009) 「松ぼっくり男爵 - Pine Baron - 」(1976) (福島県立美術館) | ||
「松ぼっくり男爵」だけではないのですが、ワイエスの鋭い観察力と迫真の描写には驚きます。松の幹はきわめてリアルに、細密に描き込まれています。"松やに" が浮いているところなどは、従来の絵にはあまりないのではと思います。松の葉は1本1本描かれ、しかも色を変えながら描かれています。松ぼっくりからは、カサカサ音がするような乾いた感触まで伝わってきます。ワイエスのインタビューにあるように、松ぼっくりにも "松やに" が描かれている。
細部の描写は真に迫っているのですが、しかし、福島県立美術館の荒木康子氏は「実際の光景とは違う」と指摘しています。
|
実際の松はもっと細く、松並木も短い。この絵は実際のカーナー農場より誇張されている、という指摘です。確かにこれによって、見る者の視線は奥に吸い込まれ、松並木はずっと奥まで続いているように見えます。

| ||
|
アンドリュー・ワイエス
「ドイツ人の住むところ」(1973) (福島県立美術館)
カーナー農場の入口を描いた水彩画で、「松ぼっくり男爵」と同じ場所である。実際の松並木はこの絵に近かったと想定できる。「アンドリュー・ワイエス展」(2008)の図録より引用
| ||
しかしワイエスが実際とは違う「太い幹の、長い松並木」にした理由は他にもあると思います。つまり、それによってカーナー夫妻がたどってきた長い年月を表現しようとしたのでしょう。インタビューにあるように、ワイエスの松に対する見方は「筋張った枝は全くタフで、弾力があり、たわみ、そして鉄よりも強靱だ」というものです。これはそっくりそのままカーナー夫妻のことではないか。
シンプルに解釈すると、画家は「松並木、松葉に覆われた道」にカーナー夫妻の人生そのものを象徴させ、鉄兜でカールを、松ぼっくりでアンナを表したのだと思います。同時に、農場の豊かな自然と、そこでの営みの一端を描き込んだ。
この絵は、人生の歳月と人の精神を絵画に結晶させたものだと思います。それは前回の「クリスティーナの世界」と大変よく似ています。クリスティーナ・オルソンは、ワイエス家の別荘があったメイン州クッシングの女性です。一方のカールとアンナのカーナー夫妻はペンシルベニア州のワイエスの生家の隣人です。描かれている場所、テーマ、画題は全く違うが、人生をギュッと一枚に凝縮させたという点では同じでしょう。描かれているのは、あくまで現実にワイエスが目撃した、ある一瞬です。その一瞬の光景に、画家は人の精神と人生を結晶させた。
そして前回にも書いたのですが、ワイエスの、緻密な作業を膨大に積み重ねるテンペラ画法が、二つの絵が表現しようとしたものにピタッとはまっていると、改めて思わずにはいられません。
さらに付け加えると「松ぼっくり男爵」は、ワイエスの自然やモノへの愛着・こだわりを如実に示した作品だとも言えます。インタビューにもあるようにワイエスは「松葉」「松ぼっくり」「鉄兜」「風の音」などに並々ならぬ関心や愛情を注いでいます。このあたりはワイエスの色使いとあいまって、日本人の琴線に触れるところでしょう。そのあたりも「松ぼっくり男爵」の見どころだと思います。
(次回に続く)
No.150 - クリスティーナの世界 [アート]
今までに原田マハさんの "美術小説" に関して二回書きました。
の二つの記事です。この続きなのですが、最近、原田さんは新しい短編小説集『モダン』(文藝春秋。2015) を出版しました。収められたのはいずれも美術をテーマとする小説ですが、すべてがニューヨーク近代美術館(MoMA - Museum of Modern Art)を舞台にしているので、"美術小説" というよりは "美術館小説" です。むしろ "MoMA小説" と言うべきかもしれません。
を出版しました。収められたのはいずれも美術をテーマとする小説ですが、すべてがニューヨーク近代美術館(MoMA - Museum of Modern Art)を舞台にしているので、"美術小説" というよりは "美術館小説" です。むしろ "MoMA小説" と言うべきかもしれません。
以下でとりあげるのは『モダン』の冒頭の『中断された展覧会の記憶』です。この小説は私にとっては過去の記憶を呼び醒まされた一編でした。そのストーリーは次のようです。
『中断された展覧会の記憶』
ニューヨーク近代美術館(MoMA)の「展示会ディレクター」である杏子・ハワードは、夫のディルとともにマンハッタンのアパートに暮らしています。杏子の両親は若いときにボストンに移住した日本人で、彼女はアメリカ国籍ですが、英語と日本語のバイリンガルです。
杏子はMoMAでの仕事を続けつつ、博士論文を執筆中でした。というのも、彼女は「キュレーター(学芸員)」になるという "野望" を持っていたからです。MoMAのキュレーターは全員が博士号をもっています。彼女も30歳台のうちに博士号をとり、それをキュレーターへの第1歩としたいのでした。
論文の提出期限まで2ヶ月となった2011年のある金曜日の朝のことです。前夜も遅くまで論文に添付する資料を印刷していたのですが、途中で寝てしまい、朝、夫に声をかけられて初めて目が覚めました。その夫が「ちょっと来てくれ。すごいことになっている。トウホクってどこ ?」と言ったのです。すぐに起きあがった杏子は、テレビの画面を見て自分の目を疑いました。夫が「インディペンデンス・デイの最終場面かと思った」と表現した光景が映し出されていたからです。
杏子はすぐに "ふくしま近代美術館" の学芸員、長谷部伸子と連絡をとりはじめます。というのも、ふくしま近代美術館では現在『アンドリュー・ワイエスの世界』展が開催されていて、MoMAはそこにワイエスの「クリスティーナの世界」を貸し出していたからです。この貸し出し交渉にあたったのが杏子であり、日本への輸送・搬入時にはMoMAのコンサバター(修復家)とともに杏子も立ち会ったのでした。
長谷部伸子からのメールには、美術館では一時断水があったものの被害はないこと、ワイエスの作品はまったく問題がないこと、『アンドリュー・ワイエスの世界』展は一時中断せざるを得ないが、引き続き作品の貸し出しをお願いしたいこと、などが書かれていました。
杏子はほっとするのですが、翌週の月曜に出勤しようとした杏子のスマートフォンに、MoMAの館長の秘書から【至急】と題されたメールが入ります。MoMAに着いたら席にすわらずに館長室にくるようにという内容です。
館長が杏子に告げたのは「クリスティーナの世界をフクシマから "救出する"」という、月曜早朝のMoMA緊急理事会の決定でした。杏子は、それでは契約違反になる、展覧会はまだ2ヶ月残っている、と抗議します。しかし館長は、これは契約にある "天変地異" によるものであり、放射能のリスクなど、今後何がおこるか分からないと説明します。理事会の決定は絶対だと分かっている杏子は、従うほかありませんでした。
さらに館長は杏子にクーリエを依頼します。一般に美術館は作品を他の美術館に貸し出すとき、搬入・搬出時に貸し出し側の専門家を責任者として同行させます。これがクーリエですが、クーリエはキュレーターかコンサバターが勤めるものです。杏子のような、そのどちらでもない人間がアサインされるのは異例中の異例です。その理由の推測がついた杏子はクーリエを引き受けました。そして、作品の輸送の手はずが両美術館の間で整った後、杏子は日本へ向ったのでした。
その後の経緯は割愛したいと思います。ただ、何らかの "波乱" が起きるとか、そういうことはありません。これは基本的に「日米の美術館の、作品の貸し借りに関するストーリー」です。波乱が起きる余地はありません。物語はどちらかというと淡々と、ないしは粛々と進みます。その中で杏子と日本の学芸員の伸子との交流が語られ、この作品のテーマが浮かび上がってきます。
4つのポイント
この短編小説には4つのポイントがあります。まず第1は、これが『オール讀物』(文藝春秋)2011年12月号に掲載されたということです。ということは、遅くとも9-10月頃には書きあがっていた、そういう時間経緯だということを押さえておく必要があります。
2つ目は、この小説が東日本大震災からの復興、特に傷つき、打ちひしがれた人たちへの作者なりの "エール" として書かれたということです。この小説の最後の部分は、そのことが明確になるように書かれています。
3つ目は、ここが大切なことですが、この小説はフィクションだということです。2011年3月11日の時点で「クリスティーナの世界」が日本に貸し出されていたという事実はありません。そもそも "ふくしま近代美術館" という美術館は日本にはないのです。ただし、福島県立美術館ならあります。そして福島県立美術館は、日本の公的な美術館ではめずらしくアンドリュー・ワイエスの絵を数点(6点だったと思います)所蔵していることで有名です。おそらく作者の原田さんは、
東日本大震災
↓
福島
↓
福島県立美術館
↓
ワイエス
↓
クリスティーナの世界
↓
MoMA
という連想が、ほとんと直感的に働いたのでしょう。そして是非とも「クリスティーナの世界」を素材にした小説を書こうと思った。
第4のポイントは、そのワイエスの絵です。実はこの小説のテーマは「クリスティーナの世界」という絵そのものなのです。
クリスティーナの世界
「クリスティーナの世界」(1948)は、アンドリュー・ワイエスが31歳のときに制作したテンペラ画で、彼の代表作の一つです。この絵については『中断された展覧会の記憶』に原田マハさん自身が書いている "解説" を引用するのが適切でしょう。
小説の中で主人公の杏子が二ヶ月ぶりに福島を訪れ、美術館の収蔵庫で「クリスティーナの世界」と再会する場面があります。
「クリスティーナの世界」の英語題名は "Christina's World" です。そして『中断された展覧会の記憶』には、この英語題名を踏まえた副題がついています。
というものです。小説家が伝えたかったメッセージはこの副題が表しています。そしてこの絵はクリスティーナという一人の女性の生き方をギュッと凝縮したような絵だと行って良いでしょう。
想像するに原田マハさんは、過去に何度となく見たはずの「クリスティーナの世界」という絵を "再発見" したのだと思います。この絵がもつ深い意味と普遍性のあるメッセージが "真に" 理解できた。そのきっかけとなったのが、2011年3月11日に東日本で起こった出来事だった。だから小説を書こうと思った。いや、書くことが、MoMAに勤務したことがあり、かつ物書きである自分の使命だと思った・・・・・・。そういうことだと想像します。
「時代」と「クリスティーナ」
話は飛ぶのですが、この短編小説を読んで中島みゆきさんの「時代」を思い出してしまいました。No.35「中島みゆき:時代」に書いたように、この曲は一青窈さんや八神純子さんが被災地で歌っています。また、歌うのはこの二人だけではないし、何よりも数々のアマチュアの合唱団や学校の合唱サークルが被災地で歌っています。歌い手は、被災された方への希望のメッセージを「時代」という歌に託しているわけです。
「時代」は40年前に作られた曲であり、震災や災害とは何の関係もありません。しかし「時代」の詩がもつ普遍性が歌い手をして、この曲に "自分の思いを託したい" という気にさせるのだと思います。
そこで「クリスティーナの世界」です。これは絵なので、何らかの言葉が付随しているわけではありません。絵についての画家の言葉があるだけです。そこからクリスティーナがどういう女性だったかは理解できます。しかし絵を見ると、空の下の"荒涼とした" 草原に家が2軒、女性がひとり、たったそれだけです。たったそれだけの中に、人は深い意味を見つけ、そして原田マハさんのように被災された方々へのメッセージを託することまでできる。1枚の絵画がもつ "ちから" を感じます。
その "ちから" を絵にもたらしたのは、言うまでもなくクリスティーナという女性そのものです。常に前を向き、自分に与えられた環境の中で、真摯に、やるべきことを全うする。そのクリスティーナの "ちから" を倍増させているのが、実はアンドリュー・ワイエスの絵の描き方だと思います。テンペラの手法を用い、細かい作業を、一つ一つ、膨大に積み重ねていって、空と草原と家と女性という、たったそれだけの世界を真摯に描くというその制作態度・・・・・・。これがあるからこそ、表情の分からないクリスティーナは永遠の生命を持ったし、見る人に強いインパクトを与えることになった。
この絵は、描かれたモチーフと絵画手法が最上の形でマッチした傑作でしょう。だからこそ、この絵が強烈なメッセージ性を宿すことになったのだと思います。『中断された展覧会の記憶』という "フィクション" が書かれるほどに・・・・・・。
『モダン』
原田マハさんの『モダン』には、
の5つの短編小説が収められています。『ロックフェラー・ギャラリーの幽霊』と『私の好きなマシン』は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の初代館長、アルフレッド・バー・ジュニアに関係した物語、『新しい出口』は「マティス ピカソ展」に関した話です。また最後の『あえてよかった』は「ニューヨークに居住したことのある日本人」でないとまず思いつかないような "小洒落た" ストーリーになっています。
最初に書いたように、いずれの短編もMoMAが舞台であり、主人公は "MoMA関係者" です。ただし5編の主人公はぜんぶ違ったタイプの "MoMA関係者" です。そして全体に感じたのは、原田マハさんのストーリー・メイキングのうまさです。その腕が冴えた小説集だと思いました。
ポーラ美術館のセザンヌ展
ここからは原田マハさんの『中断された展覧会の記憶』とは直接の関係がない余談です。
箱根のポーラ美術館でゼザンヌ展が開催されています。会期は2015年4月4日(土)~ 9月27日(日)で、会期中は無休です。この展覧会の最大のポイントは、日本全国の美術館のセザンヌの作品、21点が一堂に会することです。分類すると、
◆ポーラ美術館所蔵: 9点
◆他美術館所蔵:12点
です。ただし他美術館所蔵のうち、東京国立近代美術館(皇居・北の丸公園)が2014年に20億円で購入したばかりの「大きな花束」は、6月7日までの展示です。従って6月8日以降は20点のセザンヌ作品ということになります。
さらにこの展覧会では、セザンヌの前の時代クールベ、マネ、セザンヌの師のピサロ、友人のモネとルノアール、セザンヌから出発して絵画に革命を起こしたピカソとマティスなどを合わせて53作品が展示され、近代絵画におけるセザンヌのポジションが一望できるようになっています。
ところが、2015年7月3日にポーラ美術館はホームページで「展示作品の一部変更について」というアナウンスを行いました。そのアナウンスは現在(2015.7.18)次のようになっています。
この結果、展示されているセザンヌ作品は、
◆ポーラ美術館所蔵:9点
◆他美術館所蔵:4点
ということになります。こうなると、残念ながら「国内のセザンヌが一同に会した展覧会」ではなくなってしまいました。なお展覧会は今も(2015.7.18 現在)続いています。
おそらくポーラ美術館は、セザンヌを貸し出してくれた美術館に対して、箱根山の火山活動への対応を丁寧に説明したと思います。管理に万全を期すとか、万一の場合の対応など、こと細かに説明したと想像します。しかし上記の7作品を所蔵する美術館の判断は「レベル3で展示中止」だった。作品をどうしたかは、ホームページに書いていないので分かりません。箱根から離れた場所に避難させたのか、あるいは所蔵美術館に返されたのか、それは不明です。
他館からの4作品は現在も展示中のようです。つまり貸し出した側の対応も分かれたわけですが、それはやむをえないと思います。噴火のリスクがある以上、展示は中止する。それも分かるし、ポーラ美術館側の対応を信頼して展示を続けるのも分かる。こういった自然災害のリスクをどう考えるかは難しいものです。
この展覧会を企画・実現したポーラ美術館の学芸員はさぞかし無念だと思いますね。(おそらく)2年も3年もかけて企画した展覧会のはずです。国内最多のセザンヌ所蔵数を誇る美術館だからこその企画だという自負もあっただろうし、ある種の "使命感" があったかもしれない。しかも「大きな花束」という、所蔵する東京国立近代美術館にとっての「超目玉」作品まで(はじめの2ヶ月とはいえ)借り受けた。交渉には紆余曲折があったと想像します。他の美術館も、セザンヌを9点も所蔵しているポーラ美術館だからこそ協力したのでしょう。
しかし、セザンヌ展が華々しくオープンした2015年4月4日の "矢先" と言ってもいい4月の下旬、箱根山で不吉な火山性微動が観測され始めた。その後の経緯はマスメディアで報道されている通りです。そして今回の7作品の展示中止です。
ポーラ美術館のセザンヌ展の経緯をみていると『中断された展覧会の記憶』のストーリーが、極めてリアルなものに思えてきました。もちろん小説はフィクションなので、日米にまたがる「話の組み立て」は大きいし、背景となっている災害の規模も桁違いだけれど・・・・・・。
あえて "余談" を書いた理由です。
本文の最後に、作品の一部の展示が中断されたポーラ美術館のセザンヌ展(セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで)のことを書きましたが、原田マハさんはこの展覧会とそこに展示されたセザンヌのある作品をエンディングにもってきた短篇小説を書きました。短篇集『<あの絵>のまえで』(幻冬舎 2020)に収められた『檸檬』です。この短篇小説の内容を、
No.291 - ポーラ美術館のセザンヌ
で紹介しました。
| ◆ | 『楽園のカンヴァス』(2012) No.72「楽園のカンヴァス」 | ||
| ◆ | 『エトワール』 - 短編集『ジヴェルニーの食卓』(2013)より No.86「ドガとメアリー・カサット」 |
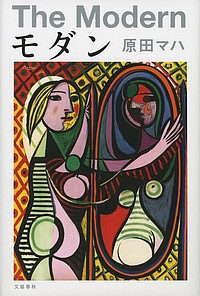
| |||
|
| |||
以下でとりあげるのは『モダン』の冒頭の『中断された展覧会の記憶』です。この小説は私にとっては過去の記憶を呼び醒まされた一編でした。そのストーリーは次のようです。
『中断された展覧会の記憶』
| ( | 以下では『中断された展覧会の記憶』のストーリーの前半が明らかにされています) |
ニューヨーク近代美術館(MoMA)の「展示会ディレクター」である杏子・ハワードは、夫のディルとともにマンハッタンのアパートに暮らしています。杏子の両親は若いときにボストンに移住した日本人で、彼女はアメリカ国籍ですが、英語と日本語のバイリンガルです。
杏子はMoMAでの仕事を続けつつ、博士論文を執筆中でした。というのも、彼女は「キュレーター(学芸員)」になるという "野望" を持っていたからです。MoMAのキュレーターは全員が博士号をもっています。彼女も30歳台のうちに博士号をとり、それをキュレーターへの第1歩としたいのでした。
論文の提出期限まで2ヶ月となった2011年のある金曜日の朝のことです。前夜も遅くまで論文に添付する資料を印刷していたのですが、途中で寝てしまい、朝、夫に声をかけられて初めて目が覚めました。その夫が「ちょっと来てくれ。すごいことになっている。トウホクってどこ ?」と言ったのです。すぐに起きあがった杏子は、テレビの画面を見て自分の目を疑いました。夫が「インディペンデンス・デイの最終場面かと思った」と表現した光景が映し出されていたからです。
杏子はすぐに "ふくしま近代美術館" の学芸員、長谷部伸子と連絡をとりはじめます。というのも、ふくしま近代美術館では現在『アンドリュー・ワイエスの世界』展が開催されていて、MoMAはそこにワイエスの「クリスティーナの世界」を貸し出していたからです。この貸し出し交渉にあたったのが杏子であり、日本への輸送・搬入時にはMoMAのコンサバター(修復家)とともに杏子も立ち会ったのでした。
長谷部伸子からのメールには、美術館では一時断水があったものの被害はないこと、ワイエスの作品はまったく問題がないこと、『アンドリュー・ワイエスの世界』展は一時中断せざるを得ないが、引き続き作品の貸し出しをお願いしたいこと、などが書かれていました。
杏子はほっとするのですが、翌週の月曜に出勤しようとした杏子のスマートフォンに、MoMAの館長の秘書から【至急】と題されたメールが入ります。MoMAに着いたら席にすわらずに館長室にくるようにという内容です。
館長が杏子に告げたのは「クリスティーナの世界をフクシマから "救出する"」という、月曜早朝のMoMA緊急理事会の決定でした。杏子は、それでは契約違反になる、展覧会はまだ2ヶ月残っている、と抗議します。しかし館長は、これは契約にある "天変地異" によるものであり、放射能のリスクなど、今後何がおこるか分からないと説明します。理事会の決定は絶対だと分かっている杏子は、従うほかありませんでした。
さらに館長は杏子にクーリエを依頼します。一般に美術館は作品を他の美術館に貸し出すとき、搬入・搬出時に貸し出し側の専門家を責任者として同行させます。これがクーリエですが、クーリエはキュレーターかコンサバターが勤めるものです。杏子のような、そのどちらでもない人間がアサインされるのは異例中の異例です。その理由の推測がついた杏子はクーリエを引き受けました。そして、作品の輸送の手はずが両美術館の間で整った後、杏子は日本へ向ったのでした。
・・・・・・・・・・・・・・・・
その後の経緯は割愛したいと思います。ただ、何らかの "波乱" が起きるとか、そういうことはありません。これは基本的に「日米の美術館の、作品の貸し借りに関するストーリー」です。波乱が起きる余地はありません。物語はどちらかというと淡々と、ないしは粛々と進みます。その中で杏子と日本の学芸員の伸子との交流が語られ、この作品のテーマが浮かび上がってきます。
4つのポイント
この短編小説には4つのポイントがあります。まず第1は、これが『オール讀物』(文藝春秋)2011年12月号に掲載されたということです。ということは、遅くとも9-10月頃には書きあがっていた、そういう時間経緯だということを押さえておく必要があります。
2つ目は、この小説が東日本大震災からの復興、特に傷つき、打ちひしがれた人たちへの作者なりの "エール" として書かれたということです。この小説の最後の部分は、そのことが明確になるように書かれています。
3つ目は、ここが大切なことですが、この小説はフィクションだということです。2011年3月11日の時点で「クリスティーナの世界」が日本に貸し出されていたという事実はありません。そもそも "ふくしま近代美術館" という美術館は日本にはないのです。ただし、福島県立美術館ならあります。そして福島県立美術館は、日本の公的な美術館ではめずらしくアンドリュー・ワイエスの絵を数点(6点だったと思います)所蔵していることで有名です。おそらく作者の原田さんは、
東日本大震災
↓
福島
↓
福島県立美術館
↓
ワイエス
↓
クリスティーナの世界
↓
MoMA
という連想が、ほとんと直感的に働いたのでしょう。そして是非とも「クリスティーナの世界」を素材にした小説を書こうと思った。
第4のポイントは、そのワイエスの絵です。実はこの小説のテーマは「クリスティーナの世界」という絵そのものなのです。
| 余談になりますが、私がこの小説に惹かれたのは福島県立美術館に行ったときを思い出したからでした。だいぶ前になりますが、東北地方の南部をクルマで家族旅行したとき、帰路の途中にたまたま立ち寄ったのが福島県立美術館でした。計画して行ったわけでなく、ガイドブックを見るとクルマですぐだから立ち寄ってみようかと・・・・・・。そこで強い印象を受けたのが "予想外だった" アンドリュー・ワイエスの作品であり、特に『松ぼっくり男爵』だったのです。 |
クリスティーナの世界
「クリスティーナの世界」(1948)は、アンドリュー・ワイエスが31歳のときに制作したテンペラ画で、彼の代表作の一つです。この絵については『中断された展覧会の記憶』に原田マハさん自身が書いている "解説" を引用するのが適切でしょう。

| ||
|
アンドリュー・ワイエス
(1917-2009) 「クリスティーナの世界」(1948)
(ニューヨーク近代美術館)
| ||
|
|
|
小説の中で主人公の杏子が二ヶ月ぶりに福島を訪れ、美術館の収蔵庫で「クリスティーナの世界」と再会する場面があります。
|
「クリスティーナの世界」の英語題名は "Christina's World" です。そして『中断された展覧会の記憶』には、この英語題名を踏まえた副題がついています。
| Christina's Will |
というものです。小説家が伝えたかったメッセージはこの副題が表しています。そしてこの絵はクリスティーナという一人の女性の生き方をギュッと凝縮したような絵だと行って良いでしょう。
想像するに原田マハさんは、過去に何度となく見たはずの「クリスティーナの世界」という絵を "再発見" したのだと思います。この絵がもつ深い意味と普遍性のあるメッセージが "真に" 理解できた。そのきっかけとなったのが、2011年3月11日に東日本で起こった出来事だった。だから小説を書こうと思った。いや、書くことが、MoMAに勤務したことがあり、かつ物書きである自分の使命だと思った・・・・・・。そういうことだと想像します。
「時代」と「クリスティーナ」
話は飛ぶのですが、この短編小説を読んで中島みゆきさんの「時代」を思い出してしまいました。No.35「中島みゆき:時代」に書いたように、この曲は一青窈さんや八神純子さんが被災地で歌っています。また、歌うのはこの二人だけではないし、何よりも数々のアマチュアの合唱団や学校の合唱サークルが被災地で歌っています。歌い手は、被災された方への希望のメッセージを「時代」という歌に託しているわけです。
「時代」は40年前に作られた曲であり、震災や災害とは何の関係もありません。しかし「時代」の詩がもつ普遍性が歌い手をして、この曲に "自分の思いを託したい" という気にさせるのだと思います。
そこで「クリスティーナの世界」です。これは絵なので、何らかの言葉が付随しているわけではありません。絵についての画家の言葉があるだけです。そこからクリスティーナがどういう女性だったかは理解できます。しかし絵を見ると、空の下の"荒涼とした" 草原に家が2軒、女性がひとり、たったそれだけです。たったそれだけの中に、人は深い意味を見つけ、そして原田マハさんのように被災された方々へのメッセージを託することまでできる。1枚の絵画がもつ "ちから" を感じます。
その "ちから" を絵にもたらしたのは、言うまでもなくクリスティーナという女性そのものです。常に前を向き、自分に与えられた環境の中で、真摯に、やるべきことを全うする。そのクリスティーナの "ちから" を倍増させているのが、実はアンドリュー・ワイエスの絵の描き方だと思います。テンペラの手法を用い、細かい作業を、一つ一つ、膨大に積み重ねていって、空と草原と家と女性という、たったそれだけの世界を真摯に描くというその制作態度・・・・・・。これがあるからこそ、表情の分からないクリスティーナは永遠の生命を持ったし、見る人に強いインパクトを与えることになった。
この絵は、描かれたモチーフと絵画手法が最上の形でマッチした傑作でしょう。だからこそ、この絵が強烈なメッセージ性を宿すことになったのだと思います。『中断された展覧会の記憶』という "フィクション" が書かれるほどに・・・・・・。
『モダン』
原田マハさんの『モダン』には、
| 『中断された展覧会の記憶』 『ロックフェラー・ギャラリーの幽霊』 『私の好きなマシン』 『新しい出口』 『あえてよかった』 |
の5つの短編小説が収められています。『ロックフェラー・ギャラリーの幽霊』と『私の好きなマシン』は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の初代館長、アルフレッド・バー・ジュニアに関係した物語、『新しい出口』は「マティス ピカソ展」に関した話です。また最後の『あえてよかった』は「ニューヨークに居住したことのある日本人」でないとまず思いつかないような "小洒落た" ストーリーになっています。
最初に書いたように、いずれの短編もMoMAが舞台であり、主人公は "MoMA関係者" です。ただし5編の主人公はぜんぶ違ったタイプの "MoMA関係者" です。そして全体に感じたのは、原田マハさんのストーリー・メイキングのうまさです。その腕が冴えた小説集だと思いました。
ポーラ美術館のセザンヌ展
ここからは原田マハさんの『中断された展覧会の記憶』とは直接の関係がない余談です。
箱根のポーラ美術館でゼザンヌ展が開催されています。会期は2015年4月4日(土)~ 9月27日(日)で、会期中は無休です。この展覧会の最大のポイントは、日本全国の美術館のセザンヌの作品、21点が一堂に会することです。分類すると、
◆ポーラ美術館所蔵: 9点
◆他美術館所蔵:12点

| |||
|
| |||
さらにこの展覧会では、セザンヌの前の時代クールベ、マネ、セザンヌの師のピサロ、友人のモネとルノアール、セザンヌから出発して絵画に革命を起こしたピカソとマティスなどを合わせて53作品が展示され、近代絵画におけるセザンヌのポジションが一望できるようになっています。
ところが、2015年7月3日にポーラ美術館はホームページで「展示作品の一部変更について」というアナウンスを行いました。そのアナウンスは現在(2015.7.18)次のようになっています。
|
この結果、展示されているセザンヌ作品は、
◆ポーラ美術館所蔵:9点
◆他美術館所蔵:4点
ということになります。こうなると、残念ながら「国内のセザンヌが一同に会した展覧会」ではなくなってしまいました。なお展覧会は今も(2015.7.18 現在)続いています。
おそらくポーラ美術館は、セザンヌを貸し出してくれた美術館に対して、箱根山の火山活動への対応を丁寧に説明したと思います。管理に万全を期すとか、万一の場合の対応など、こと細かに説明したと想像します。しかし上記の7作品を所蔵する美術館の判断は「レベル3で展示中止」だった。作品をどうしたかは、ホームページに書いていないので分かりません。箱根から離れた場所に避難させたのか、あるいは所蔵美術館に返されたのか、それは不明です。
他館からの4作品は現在も展示中のようです。つまり貸し出した側の対応も分かれたわけですが、それはやむをえないと思います。噴火のリスクがある以上、展示は中止する。それも分かるし、ポーラ美術館側の対応を信頼して展示を続けるのも分かる。こういった自然災害のリスクをどう考えるかは難しいものです。
この展覧会を企画・実現したポーラ美術館の学芸員はさぞかし無念だと思いますね。(おそらく)2年も3年もかけて企画した展覧会のはずです。国内最多のセザンヌ所蔵数を誇る美術館だからこその企画だという自負もあっただろうし、ある種の "使命感" があったかもしれない。しかも「大きな花束」という、所蔵する東京国立近代美術館にとっての「超目玉」作品まで(はじめの2ヶ月とはいえ)借り受けた。交渉には紆余曲折があったと想像します。他の美術館も、セザンヌを9点も所蔵しているポーラ美術館だからこそ協力したのでしょう。
しかし、セザンヌ展が華々しくオープンした2015年4月4日の "矢先" と言ってもいい4月の下旬、箱根山で不吉な火山性微動が観測され始めた。その後の経緯はマスメディアで報道されている通りです。そして今回の7作品の展示中止です。
ポーラ美術館のセザンヌ展の経緯をみていると『中断された展覧会の記憶』のストーリーが、極めてリアルなものに思えてきました。もちろん小説はフィクションなので、日米にまたがる「話の組み立て」は大きいし、背景となっている災害の規模も桁違いだけれど・・・・・・。
あえて "余談" を書いた理由です。
(次回に続く)
| 補記 |
本文の最後に、作品の一部の展示が中断されたポーラ美術館のセザンヌ展(セザンヌ ── 近代絵画の父になるまで)のことを書きましたが、原田マハさんはこの展覧会とそこに展示されたセザンヌのある作品をエンディングにもってきた短篇小説を書きました。短篇集『<あの絵>のまえで』(幻冬舎 2020)に収められた『檸檬』です。この短篇小説の内容を、
No.291 - ポーラ美術館のセザンヌ
で紹介しました。
(2020.8.8)
No.133 - ベラスケスの鹿と庭園 [アート]
以前に何回かベラスケスの作品と、それに関連した話を書きました。
No.19 - ベラスケスの「怖い絵」
No.36 - ベラスケスへのオマージュ
No.45 - ベラスケスの十字の謎
No.63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」
の4つの記事ですが、今回はその続きです。
スペインの宮廷画家としてのベラスケス(1599-1660)は、もちろん王侯貴族の肖像画や宗教画、歴史画を多数描いているのですが、それ以外に17世紀当時の画家としては他の画家にないような特徴的な作品がいろいろとあり、それが後世に影響を与えています。
ます「絵画の神学」と言われる『ラス・メニーナス』は後世の画家にインスピレーションを与え、ベラスケスに対するオマージュとも言うべき作品群を生み出しました。以前の記事であげた画家では、サージェント(No.36)、ピカソ(No.45)などです。オスカー・ワイルドは『ラス・メニーナス』にインスパイアされて童話『王女の誕生日』を書き(No.63)、ツェムリンスキーはそれを下敷きにオペラ『こびと』を作曲しました。近年ではスペインの作家、カンシーノが小説『ベラスケスの十字の謎』を書いています(No.45)。
圧倒的な描写力という点でベラスケスは突出しています。それは、若い時の作品、たとえば『セビーリャの水売り』(1619頃。20歳)の質感表現を見るだけで十分に分かるのですが、極めつけは『インノケンティウス10世の肖像』(1650)でしょう。この絵については No.19 で詳しく紹介しました。この絵に触発されて描かれた作品もあります。
絵画技法でも「革新的な」絵がいろいろあります。背景をほとんど描かない道化の像(No.36)はマネに影響を与え、その結果『笛を吹く少年』が描かれました。『ラス・メニーナス』の王女の服は、遠くから見ると精緻なリアリズムで描かれているように見えますが、近寄って見ると「太い筆」で「荒くて速いタッチ」で「書きなぐって」あります。印象派が得意とする技法です。
画題に注目すると、何よりも印象的なのはスペイン王室に集められた「道化」「小人」「異形の者たち」の絵です。No.19、No.36、No.45、No.63 のすべての記事がそれに関係しています。No.114「道化とピエロ」でも道化の絵に触れました。
今回は、その「画題」と「絵画手法」に関係した話を書きます。ベラスケスの「動物画」と「風景画」です。
鹿の頭部
No.93「生物が主題の絵」で西洋絵画を中心に動物と植物の絵をとりあげたのですが、その中に鹿の絵がありました。クールべと川合玉堂の作品です。両方とも雪の中の鹿を描いていて、クールべは「狩猟の対象としての鹿」を感じさせ、川合玉堂のの作品は「山に生息する自然の一部としての鹿」といった風情です。
実はベラスケスも鹿の絵を描いています。『鹿の頭部』(1634)という作品です。
プラド美術館のWebサイトの説明では、この絵はマドリードの北方にあるトーレ・デ・ラ・パラーダ(Torre de la Parada = 狩猟休憩塔)の内部に飾られていたのではないか、とあります。トーレ・デ・ラ・パラーダは狩猟のための休憩所というか、「狩猟基地」のための建物です。この館の壁には、ベラスケスをはじめとして「狩猟」をテーマにした数々の絵が飾られていたようです。
しかしこの絵は単に「王侯貴族の休憩所を飾る、狩猟がテーマの作品」ではありません。普通、我々が目にする鹿の絵はクールべや川合玉堂(No.93)のように鹿の全身を描いたものです。しかしこのベラスケスの絵は頭部だけが描かれていて、その鹿の左目はじっとこちらを見つめている。これは「鹿の肖像画」とでも言うべき作品です。
「肖像画」なので普通の鹿の絵とは違った印象を受けます。鹿の「美しさ」や「かわいらしさ」ではなく、動物の「生々しさ」や「野獣の感じ」を受ける。動物は特有の匂いを持つことが多いのですが、その匂いが迫ってきそうな気がします。あたりまえですが、日本画の鹿の絵(川合玉堂 -No.93- や竹内栖鳳など)とは、絵画技法の違いを越えた方向性の違いを感じます。
ベラスケスの肖像画は、美化して描いた(描かざるを得なかった)国王の絵などは別にして、「リアリズムで対象とする人物の本質に迫っていく力」を感じることが多いわけです。『インノケンティウス10世の肖像』(No.19)や『セバスティアン・デ・モーラ』(No.19、No.45、No.114)がその典型です。「動物の肖像画」であるこの『鹿の頭部』もまたしかり、ということでしょう。「動物画」としてはめずらしく、また他のメジャーな画家の動物画の作例があまりないということで印象に残る作品です。
ヴィラ・メディチの庭園
ベラスケスは風景画も描いています。『ヴィラ・メディチの庭園』(1630頃)ですが、2014年7月26日のTV東京の「美の巨人たち」でこの絵が解説されていました。以下、番組の内容に沿った紹介です。
ローマのボルゲーゼ公園の中に「ヴィラ・メディチ」があります。ここはかつてメディチ家の別荘でした。レスピーギの交響詩『ローマの噴水』はこの庭園の噴水を題材にしています。またフランスの画家、バルテュス(1908-2001)が館長をしていたことがあります。なぜかというと「ヴィラ・メディチ」は1803年以降「在ローマ・フランス・アカデミー」が使用しているからです。
ベラスケスは絵の勉強や絵の買い付けのために、生涯に2度のイタリア旅行をしました。1回目は30歳の頃(1629-1631)、2回目は50歳の頃です(1648-1651)。その1回目の旅行ではヴィラ・メディチに2ヶ月間滞在し、その時に描いたのが『ヴィラ・メディチの庭園』です。ちなみに2回目のイタリア旅行では
という重要作品が生まれています。『ヴィラ・メディチの庭園』はこの2作品ほどには有名ではありませんが、重要度では勝るとも劣らない。44cm × 38cm の大きさの油絵作品で、「名画の大作」オンパレードのプラド美術館の中にあっては見逃してしまいそうな小さな絵です。
風景画
夏の昼下がりの庭園風景です。近景の上部には木立の緑が描かれ、その下に2人の人物が配置されています。庭師(左)と主人(右)でしょうか。
中景のアーチの建造物は、この庭園の回廊です。そこにマント姿の男と、彫刻らしきものが描かれています。彫刻は古代ローマ時代の「眠れるアリアドネ」の彫刻で、現在はフィレンツェに返され、ウフィツィ美術館が所有しています。そして遠景には、明るい背景に映えるように糸杉が描かれています。奥行きを感じさせる構図です。
この絵の第1の特徴は、これが「風景画」だということです。ベラスケスの時代、風景画はきわめて希れでした。番組に登場したマドリッド自治大学のマリアス教授は、
だと発言していました。
驚きの技法
なぜ、ベラスケスはこの庭園の風景を描いたのか。それを探るヒントは、この作品に使われた革新的な技法にあります。
絵の具をたっぷり含んだ筆で、短いタッチで、素早く、軽快に走らせるように描いてあります。特に木の描き方がそうです。そして、濃い色と薄い色を使い分け、そのことで「明暗」や「空気の動き感」や「質感」を表現している。陰影をつけて彫刻的な立体表現する伝統手法は捨てられています。輪郭線もほとんどありません。
これは印象派と同じ技法なのです。つまり、当時としては革新的な技法を使った実験的な作品です。それを印象派の200年以上前にやった。
2枚目の『ヴィラ・メディチの庭園』
実は『ヴィラ・メディチの庭園』を描いた作品はもう1枚あります。「ヴィラ・メディチの庭園(夕暮れ)」(1630頃)という絵です。この絵は、明らかに最初の絵と「対」になっています。近景の2人の人物。建物の彫刻ともう1人の人物(2枚目では洗濯物を取り込む人)。遠景の糸杉・・・・・・。二枚は連作と言ってよいでしょう。
しかし、描かれた時間が違います。2枚目の絵は1日の終わりの穏やかな風景です。光の感じも、しっとりと、穏やかで、落ち着いた弱い光です。それに見合うように1枚目の絵とは描き方が違います。筆のスピードは明らかに遅く、トラディショナルな絵画手法に近い。印象派っぽくありません。
ベラスケスはこの「連作」で、光を描き分け、また空気感を描き分けたのでしょう。まるでモネが時間帯をわけて同じモチーフを何枚も描いたように(積み藁、ルーアン大聖堂、ジヴェルニーの池・・・・・・)。
ラス・メニーナスとの意外な関係
1枚目の『ヴィラ・メディチの庭園』に戻ると、この絵は『ラス・メニーナス』(1656)と構図が似ています。
とう構図であり、この①②③で「視線を奥へといざなう」効果を出しています。この①②③が『ラス・メニーナス』とそっくりなのです。
ということは、『ヴィラ・メディチの庭園』に描かれた黒いマントの男はベラスケス本人とも考えられます。「ラス・メニーナス」の中景には、まさに絵画を制作しているベラスケス自身が描かれているのだから・・・・・・。中景に画家自身を描く。これが『ヴィラ・メディチの庭園』と『ラス・メニーナス』のもう一つの共通点なのかもしれません。
この絵はベラスケスが自由に羽を延ばせるイタリアで描いた「実験」と「発見」の絵だと言えるでしょう。それが、のちの傑作につながった。番組の終わりにマネの言葉が紹介されていました。
番組を見た感想です。ベラスケス → マネ → 印象派 という絵画史の流れを感じさせる話なのですが、この例に限らずアートの世界においては、どんなに革命的で斬新で、それまでのアートを一変させるような芸術家が出たとしても、必ずその先駆者がいたり、前の時代に「革新の萌芽」が見られたり、ということがあるわけです。アートや文化は前時代からの継承で作られる、革新も継承の一種ということを思いました。
さらに番組を見て改めて思ったのですが、こういう絵の「筆のタッチ」は、現物を美術館で見るよりもテレビカメラで接写して大画面で見た方がクリアに分かるのですね。有名美術館では「近接さえできない」ことが多々あります。テレビで絵画を見るメリットと美術番組の意義を強く感じました。
No.19 - ベラスケスの「怖い絵」
No.36 - ベラスケスへのオマージュ
No.45 - ベラスケスの十字の謎
No.63 - ベラスケスの衝撃:王女と「こびと」
の4つの記事ですが、今回はその続きです。
スペインの宮廷画家としてのベラスケス(1599-1660)は、もちろん王侯貴族の肖像画や宗教画、歴史画を多数描いているのですが、それ以外に17世紀当時の画家としては他の画家にないような特徴的な作品がいろいろとあり、それが後世に影響を与えています。
ます「絵画の神学」と言われる『ラス・メニーナス』は後世の画家にインスピレーションを与え、ベラスケスに対するオマージュとも言うべき作品群を生み出しました。以前の記事であげた画家では、サージェント(No.36)、ピカソ(No.45)などです。オスカー・ワイルドは『ラス・メニーナス』にインスパイアされて童話『王女の誕生日』を書き(No.63)、ツェムリンスキーはそれを下敷きにオペラ『こびと』を作曲しました。近年ではスペインの作家、カンシーノが小説『ベラスケスの十字の謎』を書いています(No.45)。
圧倒的な描写力という点でベラスケスは突出しています。それは、若い時の作品、たとえば『セビーリャの水売り』(1619頃。20歳)の質感表現を見るだけで十分に分かるのですが、極めつけは『インノケンティウス10世の肖像』(1650)でしょう。この絵については No.19 で詳しく紹介しました。この絵に触発されて描かれた作品もあります。
絵画技法でも「革新的な」絵がいろいろあります。背景をほとんど描かない道化の像(No.36)はマネに影響を与え、その結果『笛を吹く少年』が描かれました。『ラス・メニーナス』の王女の服は、遠くから見ると精緻なリアリズムで描かれているように見えますが、近寄って見ると「太い筆」で「荒くて速いタッチ」で「書きなぐって」あります。印象派が得意とする技法です。
画題に注目すると、何よりも印象的なのはスペイン王室に集められた「道化」「小人」「異形の者たち」の絵です。No.19、No.36、No.45、No.63 のすべての記事がそれに関係しています。No.114「道化とピエロ」でも道化の絵に触れました。
今回は、その「画題」と「絵画手法」に関係した話を書きます。ベラスケスの「動物画」と「風景画」です。
鹿の頭部
No.93「生物が主題の絵」で西洋絵画を中心に動物と植物の絵をとりあげたのですが、その中に鹿の絵がありました。クールべと川合玉堂の作品です。両方とも雪の中の鹿を描いていて、クールべは「狩猟の対象としての鹿」を感じさせ、川合玉堂のの作品は「山に生息する自然の一部としての鹿」といった風情です。
実はベラスケスも鹿の絵を描いています。『鹿の頭部』(1634)という作品です。

| ||
|
ディエゴ・ベラスケス
『鹿の頭部』 1634。66cm × 52cm (プラド美術館) | ||
プラド美術館のWebサイトの説明では、この絵はマドリードの北方にあるトーレ・デ・ラ・パラーダ(Torre de la Parada = 狩猟休憩塔)の内部に飾られていたのではないか、とあります。トーレ・デ・ラ・パラーダは狩猟のための休憩所というか、「狩猟基地」のための建物です。この館の壁には、ベラスケスをはじめとして「狩猟」をテーマにした数々の絵が飾られていたようです。
しかしこの絵は単に「王侯貴族の休憩所を飾る、狩猟がテーマの作品」ではありません。普通、我々が目にする鹿の絵はクールべや川合玉堂(No.93)のように鹿の全身を描いたものです。しかしこのベラスケスの絵は頭部だけが描かれていて、その鹿の左目はじっとこちらを見つめている。これは「鹿の肖像画」とでも言うべき作品です。
「肖像画」なので普通の鹿の絵とは違った印象を受けます。鹿の「美しさ」や「かわいらしさ」ではなく、動物の「生々しさ」や「野獣の感じ」を受ける。動物は特有の匂いを持つことが多いのですが、その匂いが迫ってきそうな気がします。あたりまえですが、日本画の鹿の絵(川合玉堂 -No.93- や竹内栖鳳など)とは、絵画技法の違いを越えた方向性の違いを感じます。
ベラスケスの肖像画は、美化して描いた(描かざるを得なかった)国王の絵などは別にして、「リアリズムで対象とする人物の本質に迫っていく力」を感じることが多いわけです。『インノケンティウス10世の肖像』(No.19)や『セバスティアン・デ・モーラ』(No.19、No.45、No.114)がその典型です。「動物の肖像画」であるこの『鹿の頭部』もまたしかり、ということでしょう。「動物画」としてはめずらしく、また他のメジャーな画家の動物画の作例があまりないということで印象に残る作品です。
ヴィラ・メディチの庭園
ベラスケスは風景画も描いています。『ヴィラ・メディチの庭園』(1630頃)ですが、2014年7月26日のTV東京の「美の巨人たち」でこの絵が解説されていました。以下、番組の内容に沿った紹介です。
ローマのボルゲーゼ公園の中に「ヴィラ・メディチ」があります。ここはかつてメディチ家の別荘でした。レスピーギの交響詩『ローマの噴水』はこの庭園の噴水を題材にしています。またフランスの画家、バルテュス(1908-2001)が館長をしていたことがあります。なぜかというと「ヴィラ・メディチ」は1803年以降「在ローマ・フランス・アカデミー」が使用しているからです。
ベラスケスは絵の勉強や絵の買い付けのために、生涯に2度のイタリア旅行をしました。1回目は30歳の頃(1629-1631)、2回目は50歳の頃です(1648-1651)。その1回目の旅行ではヴィラ・メディチに2ヶ月間滞在し、その時に描いたのが『ヴィラ・メディチの庭園』です。ちなみに2回目のイタリア旅行では
| 『インノケンティウス10世の肖像』 『鏡をみるヴィーナス』 |
という重要作品が生まれています。『ヴィラ・メディチの庭園』はこの2作品ほどには有名ではありませんが、重要度では勝るとも劣らない。44cm × 38cm の大きさの油絵作品で、「名画の大作」オンパレードのプラド美術館の中にあっては見逃してしまいそうな小さな絵です。

| ||
|
ディエゴ・ベラスケス
『ヴィラ・メディチの庭園』 1630頃。44cm × 38cm (プラド美術館)
プラド美術館のWebサイト(英語版)では「of the Gardens of the Villa Medici in Rome, with the statue of Ariadne」というタイトルになっている。
| ||
風景画
夏の昼下がりの庭園風景です。近景の上部には木立の緑が描かれ、その下に2人の人物が配置されています。庭師(左)と主人(右)でしょうか。
中景のアーチの建造物は、この庭園の回廊です。そこにマント姿の男と、彫刻らしきものが描かれています。彫刻は古代ローマ時代の「眠れるアリアドネ」の彫刻で、現在はフィレンツェに返され、ウフィツィ美術館が所有しています。そして遠景には、明るい背景に映えるように糸杉が描かれています。奥行きを感じさせる構図です。
この絵の第1の特徴は、これが「風景画」だということです。ベラスケスの時代、風景画はきわめて希れでした。番組に登場したマドリッド自治大学のマリアス教授は、
| 世界で初めて屋外の光の元で描かれた、油絵の風景画 |
だと発言していました。
驚きの技法
なぜ、ベラスケスはこの庭園の風景を描いたのか。それを探るヒントは、この作品に使われた革新的な技法にあります。
絵の具をたっぷり含んだ筆で、短いタッチで、素早く、軽快に走らせるように描いてあります。特に木の描き方がそうです。そして、濃い色と薄い色を使い分け、そのことで「明暗」や「空気の動き感」や「質感」を表現している。陰影をつけて彫刻的な立体表現する伝統手法は捨てられています。輪郭線もほとんどありません。
これは印象派と同じ技法なのです。つまり、当時としては革新的な技法を使った実験的な作品です。それを印象派の200年以上前にやった。
2枚目の『ヴィラ・メディチの庭園』
実は『ヴィラ・メディチの庭園』を描いた作品はもう1枚あります。「ヴィラ・メディチの庭園(夕暮れ)」(1630頃)という絵です。この絵は、明らかに最初の絵と「対」になっています。近景の2人の人物。建物の彫刻ともう1人の人物(2枚目では洗濯物を取り込む人)。遠景の糸杉・・・・・・。二枚は連作と言ってよいでしょう。
しかし、描かれた時間が違います。2枚目の絵は1日の終わりの穏やかな風景です。光の感じも、しっとりと、穏やかで、落ち着いた弱い光です。それに見合うように1枚目の絵とは描き方が違います。筆のスピードは明らかに遅く、トラディショナルな絵画手法に近い。印象派っぽくありません。
ベラスケスはこの「連作」で、光を描き分け、また空気感を描き分けたのでしょう。まるでモネが時間帯をわけて同じモチーフを何枚も描いたように(積み藁、ルーアン大聖堂、ジヴェルニーの池・・・・・・)。

| ||
|
ディエゴ・ベラスケス
『ヴィラ・メディチの庭園(夕暮れ)』 1630頃。48.5cm × 43cm (プラド美術館)
プラド美術館のWebサイト(英語版)では「View of the Gardens of the Villa Medici in Rome」というタイトルになっている。
| ||
ラス・メニーナスとの意外な関係
1枚目の『ヴィラ・メディチの庭園』に戻ると、この絵は『ラス・メニーナス』(1656)と構図が似ています。
| ① | 近景に光のあたる人物を置く
| |||||
| ② | 中景を暗く描く
| |||||
| ③ | 遠景にハイライトの光を当てる
|
とう構図であり、この①②③で「視線を奥へといざなう」効果を出しています。この①②③が『ラス・メニーナス』とそっくりなのです。

|
|
ベラスケス:ラス・メニーナス
(プラド美術館) |
ということは、『ヴィラ・メディチの庭園』に描かれた黒いマントの男はベラスケス本人とも考えられます。「ラス・メニーナス」の中景には、まさに絵画を制作しているベラスケス自身が描かれているのだから・・・・・・。中景に画家自身を描く。これが『ヴィラ・メディチの庭園』と『ラス・メニーナス』のもう一つの共通点なのかもしれません。
この絵はベラスケスが自由に羽を延ばせるイタリアで描いた「実験」と「発見」の絵だと言えるでしょう。それが、のちの傑作につながった。番組の終わりにマネの言葉が紹介されていました。
|
番組を見た感想です。ベラスケス → マネ → 印象派 という絵画史の流れを感じさせる話なのですが、この例に限らずアートの世界においては、どんなに革命的で斬新で、それまでのアートを一変させるような芸術家が出たとしても、必ずその先駆者がいたり、前の時代に「革新の萌芽」が見られたり、ということがあるわけです。アートや文化は前時代からの継承で作られる、革新も継承の一種ということを思いました。
さらに番組を見て改めて思ったのですが、こういう絵の「筆のタッチ」は、現物を美術館で見るよりもテレビカメラで接写して大画面で見た方がクリアに分かるのですね。有名美術館では「近接さえできない」ことが多々あります。テレビで絵画を見るメリットと美術番組の意義を強く感じました。
No.125 - カサットの「少女」再び [アート]
青い肘掛け椅子の少女
No.86「ドガとメアリー・カサット」では、エドガー・ドガ(1834-1917)とメアリー・カサット(1844-1926)の交友関係を紹介しました。また No.87「メアリー・カサットの少女」では、カサットの絵画・版画作品、特に『青い肘掛け椅子の少女』の感想を書きました。その続きというか、補足です。
2014年5月11日から10月5日まで、ワシントン・ナショナル・ギャラリーで「ドガ カサット」という特別展が開催されています。2人の画家の芸術上の相互の影響と、ドガをアメリカに紹介するにあたってのカサットの役割を回顧する特別展です。私はもちろん行かなかった(行けなかった)のですが、展示会の内容を記した小冊子のデジタル・データがナショナル・ギャラリーのホームページに公開されたので、さっそく読んでみました。ナショナル・ギャラリーのフランス絵画部門のキュレーター、Kimberly Jones氏が執筆したものです。
その小冊子の中に、ワシントン・ナショナル・ギャラリーが所蔵する『青い肘掛け椅子の少女』(1878)の制作過程に関する最近の発見が書いてあったので、それを紹介します。
-9d191.jpg)
| ||
|
メアリー・カサット(1844-1926)
『青い肘掛け椅子の少女』(1878) (ワシントン・ナショナル・ギャラリー)
(site:www.nga.gov)
| ||
ドガの関与
No.87「メアリー・カサットの少女」にも書いたように、この作品には「ドガの手が入っている」とされています。他ならぬカサット自身が、画商に宛てた手紙にそう書いているのです。では、どこにどういう風にドガの手が入っているのか。ナショナル・ギャラリーの特別展小冊子では、次のように解説していました。この絵の修復と赤外線調査の結果、明らかになったものです。
| ◆ | もともとカサットは、後ろの壁を一つに描き、床と壁の間は水平線だった。 | ||
| ◆ | ドガは壁に「隅」を描くことを提案した。つまり2つの壁が隅で交わる構図である。そして自ら筆をとって「隅」を描き込んだ。 | ||
| ◆ | カサットはこの変更に従って、中央の椅子(肘掛けのない、英語で言うコーチ)の配置を変更し、斜めになった壁の線に添うようにした。 | ||
| ◆ | さらにカサットは、犬をコーチの前に配置しようと描き直してみたが、それは取りやめて、元の位置、つまり手前左の肘掛け椅子に戻した。 |
.jpg)
| ||
|
「青い肘掛け椅子の少女」の赤外線写真。床と壁の境界が線で示してある。実線がカサットの元々の境界で、破線がドガによる変更を示す。
(site:www.nga.gov)
| ||
No.87「メアリー・カサットの少女」で書いたように、この絵の特徴は、
| ◆ | 少女のポーズ | ||
| ◆ | 独特の室内空間表現 |
の2つです。そして「独特の室内空間表現」を詳しく言うと、
| ① | すこし上から見下ろすような視点 | ||
| ② | 4つの椅子を不均等に配置した構図 | ||
| ③ | すべての椅子をカンヴァスからはみ出して描く「クローズアップ」表現 |
の3点です。上から見下ろすような視点なので、床の縁は画面の上部にあります。風景画であれば地平線が画面の上の方にある感じです。そういう風景画は(西洋では)あまりないし、室内画も少ないと思います。そしてこの絵を見る我々は全く気づかないのですが、この絵の空間表現は、ドガの「隅を描き込む」「水平線ではなく、広角の斜線の構図にする」という提案によって完成された、というわけです。
アーティストのコラボレーション
ということは、この絵は部分的とは言え、2人のアーティストのコラボレーションで成り立ったということになります。これは近代以降の画家の作品としてはかなり珍しいのではないでしょうか。
15世紀とか17世紀ごろまでの作品にならしばしばあります。フィレンツェで工房を構えていたヴェロッキオは、作品の一部を弟子のレオナルド・ダ・ヴィンチに描かせた、みたいな・・・・・・(ウフィツィ美術館にある「キリストの洗礼」という絵)。
しかしこれは画家が「職人」であった時代の話です。近代以降の画家は「芸術家」であって、何よりも独自性を大切にし、自分の絵だと誰しも認識してくれるようなテーマや描画方法を創造するこそ「画家の命」だったはずです。それが芸術家の絶対に譲れないプライドです。
ドガはカサットの10歳年上で、画家としては先輩です。カサットはドガを「先生」のように見ていたのかも知れませんが、この絵を描いた時点(1878。34歳)ではサロン(パリの官展)に何回か入選の経験もある、れっきとした画家です。その観点からすると、この絵の成り立ちは、かなりめずらしいと言えるでしょう。
また、No.87「メアリー・カサットの少女」でも紹介したように、ドガやカサットと同時代の画商であるヴォラールの回想録(『親友ドガ』)には、
| ・ | ドガはこの絵に特別な愛情を持っていた | ||
| ・ | ドガは自分の絵との交換を申し入れた |
ということが書かれています。そういうエピソードも含めて、通常の「親しい2人の画家」という以上の関係があったようです。
似たもの同士
その理由を推測すると、要するにドガとカサットは「似たもの同士」ということではないでしょうか。
| ◆ | 生い立ち
| |||||
| ◆ | 画風
| |||||
| ◆ | 古典
|
『青い肘掛け椅子の少女』の独創性
『青い肘掛け椅子の少女』は、2人の画家の特別なコラボレーションで生まれた絵のようです。しかし、改めて絵を見て思うのですが、ドガのアドバイスによる「構図の修正」を抜きにしたとしても、カサットがこの絵で作り上げたオリジナリティというか、独創性は際だっていると思います。世界の絵画史上「これしかない」と思わせるものがある。確かに「印象派っぽい」筆使いだけれど、「室内の」「人物を」「リアリズムの原則で」描くという西洋絵画の本流に忠実に沿っています。それでいて「何か」を完全にブチ壊してしまっている。マネの絵のように・・・・・・。画家の意図がどうであれ、そう感じます。

| |||
|
バルテュス
「夢見るテレーズ」(1938) (メトロポリタン美術館)
この絵は2014年に日本で開催されたバルテュス展で展示された。
| |||
メアリー・カサットという人は絵画の伝統をよく知っているし、勉強もしています。その点はドガや、マネとも似ている。伝統を革新する者の必要条件の一つは、伝統を熟知していることである・・・・・・。そういうことかと思います。
ワシントン・ナショナル・ギャラリーの分析
ワシントン・ナショナル・ギャラリーがウェブサイトに公開しているこの絵の分析(日本語試訳)を以下に掲げます。念のために原文も載せておきます。
(試訳) |
| 補記1 |
本文で『青い肘掛け椅子の少女』という絵には革新性を感じる、としたのですが、それから連想して思い出したことがあるので書きます。箱根のポーラ美術館はセザンヌの作品を数点所蔵していますが、その中の1枚に『ラム酒の瓶がある静物』という絵があります。

| ||
|
ポール・セザンヌ(1839-1906)
「ラム酒の瓶がある静物」(1890頃) (ポーラ美術館) | ||
ポーラ美術館に行くと、この絵は「かつて、メアリー・カサットが所有していた」との説明が書いてありました。彼女の自宅はパリ北方のル・メニル・テリビュにあったのですが(シャトー・ド・ボーフレーヌという館)、その自宅にモネ、ピサロ、クールベ、ドガ、セザンヌの絵や浮世絵・約100点を飾っていたと伝記に書かれていました(No.86で引用した伝記)。その中の1枚が、このセザンヌの『ラム酒の瓶がある静物』というわけでしょう。
一見して分かるように、絵には複数の視点(多視点)が混在しています。その意味で、セザンヌの静物画の一つの典型です。かつ、描かれている静物が比較的少ないため、その"多視点ぶり" がよく分かる。明らかにテーブルは上からの視点で描かれていますが、ラム酒の瓶は真横から見た姿です。テーブルの右端はテーブルの右からの視点ですが、左端はテーブルの真ん中あたりからの見た感じで、そのためテーブルが奥に広がっているように感じる。
現代の我々は、こういうセザンヌの描き方がその後のキュビズムや20世紀のモダンアートの先駆けとなったことを知っています。まさに近代絵画史における革新だったわけです。
一方、この絵を所有していたメアリー・カサットはどうかというと、No.87「メアリー・カサットの少女」に数点引用した絵のように、描くテーマはほとんどが人物です。それも、女性、家庭の人々(家族、家政婦)、母と子、少女が多い。それは当時の「女性画家」に暗黙に許されたテーマだったのでしょう(ベルト・モリゾもそうです)。描き方は "印象派" という当時の「前衛」に従っていて、筆触分割も使い、明るい色彩を多用し、構図も大胆です。しかし彼女の画家としての基本的なスタンスは、しっかりとしたデッサンに裏付けられたリアリズムの絵画です。
しかし「前衛」は「新たな前衛」によってとって代わられる。特に、20世紀になってからはマティスやピカソのような描き方が出てくるわです。メアリー・カサットはマティスには随分批判的だったようです。彼女の画風からするとそれも当然でしょう。
しかし気になるのは『ラム酒の瓶がある静物』です。メアリー・カサットはなぜこの絵を購入したのでしょうか。絵画の革新と言える絵であり、自分の画風からすると「異質」なことが一目瞭然です。彼女はサロンに何回も入選し、その後は印象派展に出品し、さらに個展を何回も開いたプロの画家です。『ラム酒の瓶がある静物』が "絵画の秩序の破壊" であることは一目で理解できたはずです。
彼女が『ラム酒の瓶がある静物』を所有していた理由は分かりません。たまたま人に頼まれて購入したのかも知れない。しかし思うのですが、彼女はこの絵が好きだったのではないかと・・・・・・。その理由は、この記事のテーマである『青い肘掛け椅子の少女』という絵です。『青い肘掛け椅子の少女』は『ラム酒の瓶がある静物』と似たところがあると思うのですね。もちろん多視点描画というわけではありません。しかし、一人の少女と4つの青い肘掛け椅子をじっくりと観察し、それをカンヴァスの最適な位置に、一番印象が強くなるように、あまり他にない感じで配置するという画面構成は、『ラム酒の瓶がある静物』に一脈通じるものを感じます。多視点かどうか以前に、絵を描く基本的なところで共通するコンセプトがあるのではないか。
『青い肘掛け椅子の少女』に革新性を感じるのは理由があると思います。
| 補記2 |
補記1に、かつてメアリー・カサットが所有していたセザンヌの『ラム酒の瓶のある静物』(1890頃。ポーラ美術館蔵)のことを書きましたが、それに関連する話です。No.187「メアリー・カサット展」に、2016年に開催された展覧会を書きましたが、この出展作品のひとつに『家族』(1893。クライスラー美術館蔵)という作品がありました。

| ||
|
メアリー・カサット
「家族」(1893。49歳)
クライスラー美術館
(米:ヴァージニア州) | ||
この絵を見て直感するのは、西洋絵画の伝統的な宗教画の画題である「聖母子と聖ヨハネ」を踏まえていることです。No.187 にはラファエロの作品を引用しましたが、ダ・ヴィンチの作品なども有名です。『家族』では女の子が "聖ヨハネ" に見立てられています。もちろん全体の描き方は印象派的です。つまり伝統(古典絵画)を踏まえつつ、前衛(印象派)の技法を用い、カサットの得意とする「母と子」のテーマを描いたと言えるでしょう。
しかし気になる点があります。この絵には2つの視点が混在していることです。母と男の子と背景の庭は少し上から見下ろした角度で描かれています。一方、女の子は真横から見た姿です。母、男の子、女の子の頭の位置関係はこの順に低くなっているはずで、もし視点が一つだとすると、男の子の頭の上の方が見えるのだから、女の子も同じようでないといけない。しかしそうはなっていません。
ここで『ラム酒瓶のある静物』の多視点描法を連想してしまいました。カサットがセザンヌに影響されたとか、そういうことではありません。そもそもカサットが傾倒した日本美術には、複数の視点から描いた絵はいくらでもあるわけです。セザンヌが革新的だと言われるのはあくまで "西洋絵画基準" です。この絵でカサットは横顔の女の子と少々斜め上からの母子を混在させたのですが、それは画家にとっては自然なことだったのでしょう。
カサットが『ラム酒の瓶のある静物』を所有していたこと、およびこの『家族』という「聖母子と聖ヨハネ・印象派・多視点」的な作品を考えると、カサットという画家の柔軟で自由な感性を感じました。伝統(古典絵画)を踏まえつつ、当時の "前衛"(印象派や平面的な描き方)にコミットし、かつ独自のテーマを追求する(母と子)という画家の姿勢がよいと思います。
(2016.10)
No.118 - マグダラのマリア [アート]
最近の記事、No.114とNo.115で、中野京子さんによる絵の評論を紹介し、その感想を書きました。
の2作品です。また以前には、No.19「ベラスケスの怖い絵」で、中野さんによる
の評論を紹介しました。今回もその継続で、別の絵を紹介します。ティツィアーノ『悔悛するマグダラのマリア』(1533。フィレンツェ・ピッティ宮)です。この絵は「マグダラのマリア」を描いた数ある絵の中で、最も有名なもの(の一つ)だと思いますが、中野さんはこの絵の解説でサマセット・モームの小説を持ち出していました。それが印象に残っているので取り上げます。
まず「マグダラのマリア」がどういう女性(聖女)か、その歴史的背景を踏まえておく必要があります。中野さんも解説(「名画の謎 ── 旧約・新約聖書篇」文藝春秋。2012)の中で書いているのですが、紙数の制約もあり短いものです。ここでは、京都大学・岡田温司教授の著書である『マグダラのマリア ─ エロスとアガペーの聖女』(中公新書。2005)によって振り返ってみたいと思います。以下の「歴史的背景」はすべて岡田教授の本によります。
聖書における「マグダラのマリア」
新約聖書における「マグダラのマリア」に関する記述は、次の4つです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの各福音書の記述を総合すると以下のようになります。
「悪霊を追い出して(イエスに)病気を治していただいた女たち」の一人で、「七つの悪霊を追い出したいただいたマグダラと呼ばれるマリア」が、使徒たちとともにイエスに従って福音の旅をする。
マタイ、マルコにはキリストの磔刑を「遠くから眺めている女たち」の一人として「マグダラのマリア」が明記されている。ルカには「ガラリアからイエスについてきた女たち」とだけ書かれているが、「福音の旅」の記述からしてこの中に「マグダラのマリア」がいたと推測できる。
ヨハネだけは違っていて「遠くから眺めている」のではなく、「イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた」と記述されている。
マタイとマルコには「マグダラのマリア」(を含む女たち)が埋葬に立ち会ったと書かれている。ルカによると、立ち会ったのは「イエスといっしょにガラリアから出てきた女たち」である。
4つの福音書とも、マグダラのマリア(を含む女たち)が復活したイエスに出会い、そのことを使徒たちに告げるということでは一致している。特にヨハネの記述では、復活したイエスに会うのはマグダラのマリアだけである。
またマルコとルカによると、マグダラのマリアら3人の女性はイエスに香油を塗ろうと思って墓を訪れたことになっている。このことから後の絵画において、香油壷がマグダラのマリアを象徴する持物(アトリビュート)となる。
以上の新約聖書の記述から、3つのことが言えます。まず第1ですが、意外なことに「悔い改めた罪ある女(娼婦)」というマグダラのマリアの一般的な概念やイメージは、聖書のどこにもないことです。そのイメージは後世の創作、ないしは聖書解釈で付け加えられたものなのです。
第2に、キリストの磔刑・埋葬・復活という聖書の重要シーンのすべてにマグダラのマリアが登場することです。特に「キリストの復活」は、キリスト教の教義の根本に係わる超重要シーンですが、その復活の証人になり、かつ復活を使徒に伝えるのはマグダラのマリアです。
第3に、これは岡田教授が指摘していることですが、4つの福音書で「マグダラのマリア」に対する「微妙な温度差」があることです。岡田教授によると、ヨハネがマグダラのマリアに対して最も親和的で、かつ重要な役割を与えているのに対し、ルカはマグダラのマリアの役割をできるだけ引き下げようとしているようです。
マグダラのマリアの変貌
マグダラのマリアを新約聖書の記述から変身させたのは、教皇・大グレゴリウス(590-604)の「貢献」が大きいと岡田教授は言っています。大グレゴリウスは、聖書に登場する2人の女性を取り上げます。
の2人です。そして大グレゴリウスは、マグダラのマリア、①罪深い女、②ベタニアのマリア、の3人は同じ女性という説を唱えるのです。なぜそのような「聖書解釈」が可能なのでしょうか。
まず、「七つの悪霊」(ルカ)を「罪」と読み代えることにより、マグダラのマリア = ①罪深い女、と解釈します。そして「イエスにひざまづき、髪の毛でイエスの足をぬぐう」という「行為の同等性」により、①罪深い女 = ②ベタニアのマリアとなる。三段論法で3人は同一人物となるわけです。ベタニアのマリアは、聖書(ルカ)の記述から「瞑想的生活」を好む女性です。ここに、
というイメージの基本線が成立します。さらに新約聖書にある、
も「堕落や性的な罪にもかかわらずイエスに許された」という類似性で ① との連想を生み、「悔い改めた罪ある女」というマグダラのマリアのイメージを強化することになります。さらには娼婦ということから「金髪の美貌の女性」というイメージが加わります。
さらにマグダラのマリアには「苦行者」というイメージが加わってきます。それは次の2つの伝承が重ね合わされたものです。
以上のような結果、マグダラのマリアは
というような複数のイメージが重ね合わされた「ハイブリッドな聖女」へと変貌してしまったのです。
そもそも教皇・大グレゴリウスの説は、強引な聖書解釈というより「創作」ですね。なぜなら、福音書はキリストの弟子たちが書いた文書であり、その弟子たちはマグダラのマリアと顔見知りだからです。もし仮に「罪深き女」や「ベタニアのマリア」がマグダラのマリアなら、弟子たちは福音書にそう書いたはずです。「この女は後にマグダラのマリアと呼ばれるようになった」というように・・・・・・。つまり、教皇によってマグダラのマリアは「娼婦という濡れ衣を着せられた」(岡田教授)ことになります。ではなぜ教皇はこのようなイメージを作りあげたのでしょうか。
と岡田教授は書いています。つまり、マグダラのマリアは、
だと言えます。この最後の「官能と聖性の両義性」というイメージを的確に表した絵画の代表格が、冒頭に掲げたティツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』なのです。岡田教授の本にも、口絵の先頭にこの絵が掲げられています。マグダラのマリアの絵画の代表的存在ということだと思います。
ティッツィアーノの「マグダラのマリア」
ここからが本題で、ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての中野京子さんの解説です。中野さんは「官能と聖性の両義性」、特に、聖母マリアとの対比において「官能・エロスが強調されるマグダラのマリア」のポジションから論を起こしています。
マグダラのマリアの絵画表現の典型的なパターンは、美貌のマリア(半裸や全裸で描かれることがある)が改心し、神への愛に目覚める(ないしは祈る)というものであり、数々の名画が作られました。そしてこのテーマに人々が(ないしは画家が)惹かれ、何世紀にも渡って図像化されてきた要因を、中野さんはサマセット・モームの短編小説『雨』を引き合いに出して説明しています。
サマセット・モームの『雨』
その『雨』を引き合いに出しての解説を、少々長くなりますが引用してみましょう。以下の引用は『雨』の要約が過半数なのですが、全体としてゾクッとするような研ぎ澄まされた文章です。
『雨』は、サマセット・モームの最も有名な短編小説であり、「世界短編小説上にも永久に残る傑作」という評価もあるぐらいで、読んだ人も多いと思います。この小説は、中野さんも書いているように「善と悪の、理性と本能の闘い」というように見るか、ないしは「執拗に降り続く雨が人間の心理に影響し、理性を狂わす」といった風に捉えられることが多いと思います。しかし中野さんによると、これは「マグダラのマリアの物語」なのですね。『雨』には、牧師夫妻と医師夫妻が聖書の「姦淫の場で捕らえられた女」(ヨハネ。4:6-27)の節を朗読し、4人で祈る場面が出てきます。
マグダラのマリアはティッツィアーノのような絵画だけでなく、文学や映画にも多大な影響を与えてきました。岡田教授の本には数々の例が紹介されています。比較的最近の映画を例にとると、たとえばジュゼッペ・トルトナーレ監督の『マレーナ』です。モニカ・ベルッチが主演したこの映画は、第2次世界大戦で夫を戦地に送ったシチリアの美しい女性・マレーナが「娼婦」呼ばわりされる顛末を描いたものですが、マレーナ = マグダラのマリアです。マグダラのマリアはイタリア語で「マリア マッダレーナ」であり、マッダレーナの愛称がマレーナなのです。
文学(小説)の例では、
などにおけるヒロインの造型は、マグダラのマリアの影響なしには考えられない、と岡田教授は言っています。なるほどそうかもしれません。しかし、中野さんの解説で気づかされるのは、
なのですね。なぜなら、彼女は「明確に娼婦」であり、しかも「牧師によって(一旦は)改悛する」のだから・・・・・。その舞台はサント・ボームの洞窟ならぬ、降りしきる雨に閉じこめられた熱帯の島です。しかし、その改悛は最後の最後でゼロ・クリアされてしまう、ほかならぬ牧師の「裏切り」によって、というところがモームの皮肉です。モームは『雨』において「悔い改めた娼婦」というイメージに強い性的魅力を感じてしまう男性心理の歪つさを揶揄しているというのが、中野さんの見立てです。
しかしモームの短編は「揶揄」や「皮肉」というレベルにはとどまらない感じですね。それは『雨』の最後の2つのセンテンスを読めば一目瞭然です。小説の最後を原文から引用すると以下です。「マクフェイル博士」とは、中野さんが「医師」と書いている人物です。
そもそも娼婦は、必要とする男たちがいるから成立するわけです。ミス・トムソンが吐き捨てた「同じ穴の狢」という言葉の意味は、
が全部同類だということでしょう。モームの『雨』においては、牧師よりも、医師よりも、ミス・トムソンの方がよほど人間的に描かれています。
マグダラのマリアという「文化装置」
ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての解説のはずが、意外な方向に広がってきました。改めて中野さんの論を要約すると、次の2点になると思います。
という2点です。「二重の官能性」については、確かにそのような気がします。男が女性に惹かれる度合いを「式」で表すと、
聖女 < 娼婦 < 娼婦だった聖女
ということでしょうか(単純ですが)。「聖女」とか「娼婦」というのは極端であり、そういう人と付き合ったことがないので確信は持てないのですが、現実のもっと軽い例で置き換えてみると、お化粧をバッチリと決め、服装はトレンドをちゃんと押さえ、じゃべり方もハキハキしていて、快活で、話していても飽きない美しい女性、しかしどこか微かに「崩れているところ」を感じてしまう女性、その「崩れ感」に魅力を感じてしまうということがありますね(現代の女優でいうと米倉涼子さんのイメージか)。それに近い感情かと思います。
「男社会の歪つな眼差し」というのはどうでしょうか。確かに、女性にそう言われてもしかたがないかと思います。
というのも、ティツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』は裸体だからです。この絵だけでなく、半裸ないしは全裸の姿でマリアを描いた絵が沢山あります。ギリシャ・ローマ神話の「異教の女神」ならともかく、マグダラのマリアはれっきとしたキリスト教の聖女であり、使徒であり、イエスの復活の証人となった超重要人物です。その女性を裸体で描くというのは、そもそも女性の裸体を描きたいという画家(男性)の興味と欲求が先に立っているのだろうと思います。そこに「元娼婦」という格好のモチーフがあった。その欲求が「歪つな眼差し」の根底にあると思います。
しかし男の立場から少々言い訳をすると、「元娼婦である聖女」に対する男性の眼差しが歪つなのは、そうなるべき理由があると思うのです。それは、
からです。「マグダラのマリア」という女性像がいったん出来上がると、それは文化として広まり、逆に「マグダラのマリア的女性」に魅力を感じるようになってしまう、そのように暗黙に刷り込まれてしまうという面が強いと思うのです。映画や小説の例のように、マグダラとは言ってなくても「マグダラのマリア的女性に男性が強く惹かれるという物語」は蔓延しています。
No.115「日曜日の午後に無いもの」で紹介したように、中野さんは、19世紀のフランス女性が外出時にハンドバックを持たなかったことについて(= 持つのを拒否したことについて)、「それが時代の雰囲気であり、文化装置だ」と言っていました。「マグダラのマリア」も一つの文化装置であり、その文化装置が男性の女性への情熱(の一つのパターン)を作り出しているのだと思います。
「文化装置」にはいろいろの種類があり、文化圏によって、また時代によって多様です。同じ時代でもさまざまな「文化装置」があり、個人個人をみると「女性への情熱の持ち方」はいろいろある。「感情の起伏が激しく、言動も変化し、男を翻弄する女性」に魅力を感じる人もいるだろうし、「金髪の美女」ではなく「抜けるように白い肌の女性」(もしくはその逆)に強く惹かれる人もいる。「女としては未熟な10代の少女」に情熱を傾ける男もいる。
そしてマグダラのマリアとミス・トムソンの「職業」に関して言うと、「お金を払って女性と寝る」ことに執着する男がいるわけです。お金を払うことで満足感を得る。これが「娼婦」という職業が成立する一番根本的な理由でしょう。
「文化装置」は「作りもの」であり、フィクションです。それは「悔悛した娼婦」という「聖書に根拠がない創作物語」に象徴的に現れています。「作りもの」だから、基本的には「何でもあり」です。その「作りもの感」や「何でもあり感」が、「歪つだ」「不自然だ」と女性が感じる要因になっているのだと推測します。
中野さんが書いた、ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての文章は、単なる絵の評論でなく、人間心理に言及しているところが印象的でした。と同時に、これは、
になっている。そう言えば中野京子さんの本職は美術評論家ではなく、文学研究者(ドイツ文学)なのでした。
最後に、マグダラのマリアを図像化した2つの作品を掲げておきます。16-17世紀のイタリアの親子の画家(父と娘)、オラツィオ・ジェンティレスキ(1563-1639)とアルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1652)の作品です。西洋のアートの歴史から言うと、いわゆる「バロック」の画家で、カラヴァッジョの影響が強く現れています。この2作品は岡田教授の本の口絵にも挙げられていました。
父・オラツィオの作品は、サント・ボームの洞窟で瞑想と祈りに捧げるマリアを描いた作品で、骸骨、聖書といった定番アイテムが描かれています。中野さんは、前に引用した中で、
と書いていましたが、まさにそういう感じがします。カラヴァッジョ流の強い陰影の表現が印象的です。
一方の、娘・アルテミジアの作品は、マリアの肩をはだけた姿と、豪華そうな衣装(や椅子)が特徴で、おそらく見る人に当時のイタリアの娼婦を連想させたのだと思います。かつ、よく見ると右下にわずかに香油壷が描かれている。つまりマリアの伝統的解釈に忠実です。
この絵は明らかにティッアーノの絵を踏まえています。しかし娼婦としての官能表現は最低限に押さえられている。むしろこの絵は、マリアの「悔いる思い」や「改心の意志を訴える気持ち」、「神に帰依する決意」などが前面に押し出されています。マリアに当たっている強い光(神の光でしょう)も効果的です。その神の光が最も強く当たっているのは胸であり、この直後に顔に当たって悔悛が成就する ・・・・・・。この構図が素晴らしいし、また女性目線で描いたマリアという意味で印象に残る作品です。
| 『仮面舞踏会後の決闘』(No.114) | ||||
| 『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(No.115) |
の2作品です。また以前には、No.19「ベラスケスの怖い絵」で、中野さんによる
| 『インノケンティウス十世の肖像』 | ||||
| 『ラス・メニーナス』 |
の評論を紹介しました。今回もその継続で、別の絵を紹介します。ティツィアーノ『悔悛するマグダラのマリア』(1533。フィレンツェ・ピッティ宮)です。この絵は「マグダラのマリア」を描いた数ある絵の中で、最も有名なもの(の一つ)だと思いますが、中野さんはこの絵の解説でサマセット・モームの小説を持ち出していました。それが印象に残っているので取り上げます。

| ||
|
ティツィアーノ
『悔悛するマグダラのマリア』(1533)
(フィレンツェ・ピッティ宮)
- Wikipedia - | ||
まず「マグダラのマリア」がどういう女性(聖女)か、その歴史的背景を踏まえておく必要があります。中野さんも解説(「名画の謎 ── 旧約・新約聖書篇」文藝春秋。2012)の中で書いているのですが、紙数の制約もあり短いものです。ここでは、京都大学・岡田温司教授の著書である『マグダラのマリア ─ エロスとアガペーの聖女』(中公新書。2005)によって振り返ってみたいと思います。以下の「歴史的背景」はすべて岡田教授の本によります。
聖書における「マグダラのマリア」
新約聖書における「マグダラのマリア」に関する記述は、次の4つです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの各福音書の記述を総合すると以下のようになります。
| 福音の旅 (ルカ) |
「悪霊を追い出して(イエスに)病気を治していただいた女たち」の一人で、「七つの悪霊を追い出したいただいたマグダラと呼ばれるマリア」が、使徒たちとともにイエスに従って福音の旅をする。
| キリスト磔刑の立会人 (マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ) |
マタイ、マルコにはキリストの磔刑を「遠くから眺めている女たち」の一人として「マグダラのマリア」が明記されている。ルカには「ガラリアからイエスについてきた女たち」とだけ書かれているが、「福音の旅」の記述からしてこの中に「マグダラのマリア」がいたと推測できる。
ヨハネだけは違っていて「遠くから眺めている」のではなく、「イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた」と記述されている。
| キリスト埋葬の立会人 (マタイ、マルコ、ルカ) |
マタイとマルコには「マグダラのマリア」(を含む女たち)が埋葬に立ち会ったと書かれている。ルカによると、立ち会ったのは「イエスといっしょにガラリアから出てきた女たち」である。
| キリスト復活の証人 (マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ) |
4つの福音書とも、マグダラのマリア(を含む女たち)が復活したイエスに出会い、そのことを使徒たちに告げるということでは一致している。特にヨハネの記述では、復活したイエスに会うのはマグダラのマリアだけである。
またマルコとルカによると、マグダラのマリアら3人の女性はイエスに香油を塗ろうと思って墓を訪れたことになっている。このことから後の絵画において、香油壷がマグダラのマリアを象徴する持物(アトリビュート)となる。

| |||
第2に、キリストの磔刑・埋葬・復活という聖書の重要シーンのすべてにマグダラのマリアが登場することです。特に「キリストの復活」は、キリスト教の教義の根本に係わる超重要シーンですが、その復活の証人になり、かつ復活を使徒に伝えるのはマグダラのマリアです。
第3に、これは岡田教授が指摘していることですが、4つの福音書で「マグダラのマリア」に対する「微妙な温度差」があることです。岡田教授によると、ヨハネがマグダラのマリアに対して最も親和的で、かつ重要な役割を与えているのに対し、ルカはマグダラのマリアの役割をできるだけ引き下げようとしているようです。
マグダラのマリアの変貌
マグダラのマリアを新約聖書の記述から変身させたのは、教皇・大グレゴリウス(590-604)の「貢献」が大きいと岡田教授は言っています。大グレゴリウスは、聖書に登場する2人の女性を取り上げます。
| ① | 罪深い女(ルカ。7:37-50) パリサイ人・シモンの家でイエスが食卓についているとき、イエスの足下に駆け寄り、その足を自分の涙でぬらし、髪の毛でぬぐい、さらにその足に口づけをして、みずからの罪を悔い改めようとした女性。 | |||||
| ② | ベタニアのマリア(ヨハネ。11:1-44。12:1-8) ラザロとマルタの姉妹のマリア。イエスは奇跡でラザロを生き返らせたが、そのラザロの姉妹のマリアは、イエスの足に香油を塗り、髪の毛でイエスの足をぬぐった。 別のシーンで、マリアとマルタが自分の家にイエスを迎えたとき、マリアはじっとイエスの言葉に聞き入っていたが、姉妹のマルタは忙しく働いていた。イエスは「マリアが良い方を選んだ」と語った(ルカ。11:38-42)。
|
の2人です。そして大グレゴリウスは、マグダラのマリア、①罪深い女、②ベタニアのマリア、の3人は同じ女性という説を唱えるのです。なぜそのような「聖書解釈」が可能なのでしょうか。
まず、「七つの悪霊」(ルカ)を「罪」と読み代えることにより、マグダラのマリア = ①罪深い女、と解釈します。そして「イエスにひざまづき、髪の毛でイエスの足をぬぐう」という「行為の同等性」により、①罪深い女 = ②ベタニアのマリアとなる。三段論法で3人は同一人物となるわけです。ベタニアのマリアは、聖書(ルカ)の記述から「瞑想的生活」を好む女性です。ここに、
| 悔い改めた罪ある女(=娼婦)で、瞑想的生活を好むマグダラのマリア |
というイメージの基本線が成立します。さらに新約聖書にある、
| ③ | サマリアの女(ヨハネ。4:6-27) 5人の夫をもった上に、不法な夫と暮らしている女。 | ||
| ④ | 姦淫の場で捕らえられた女(ヨハネ。4:6-27) | ||
| 「あなたたちのなかで罪のないものが石を投げなさい」とイエスが言う、有名な場面の女。 |
も「堕落や性的な罪にもかかわらずイエスに許された」という類似性で ① との連想を生み、「悔い改めた罪ある女」というマグダラのマリアのイメージを強化することになります。さらには娼婦ということから「金髪の美貌の女性」というイメージが加わります。
さらにマグダラのマリアには「苦行者」というイメージが加わってきます。それは次の2つの伝承が重ね合わされたものです。
| ⑤ | エジプトのマリア 12歳のときに娼婦になり、17年間その生活を続けていたが、エルサレムの巡礼をきっかけに自分の罪の深さに打ちのめされ、発心して世を捨て、苦行のなか、47年の長きにわたって、ひとり砂漠で純潔を守って生きた(5世紀)。 | ||
| ⑥ | プロバンス地方に伝わる伝承 この伝承によると、ローマ帝国の迫害を逃れたマグダラのマリアと弟子たちの一行は、地中海を渡ってマルセイユの港に辿りつき、そこでゴール人に布教した。そしてマリアは、郊外のサント・ボームの洞窟に引き籠もり、禁欲的な瞑想と苦行に余生を捧げた。 |
以上のような結果、マグダラのマリアは
| ◆ | キリストの使徒(新訳聖書) | ||
| ◆ | 悔い改めた娼婦 | ||
| ◆ | 金髪で美貌 | ||
| ◆ | 瞑想的生活 | ||
| ◆ | 洞窟での苦行(サント・ボーム) |
というような複数のイメージが重ね合わされた「ハイブリッドな聖女」へと変貌してしまったのです。
そもそも教皇・大グレゴリウスの説は、強引な聖書解釈というより「創作」ですね。なぜなら、福音書はキリストの弟子たちが書いた文書であり、その弟子たちはマグダラのマリアと顔見知りだからです。もし仮に「罪深き女」や「ベタニアのマリア」がマグダラのマリアなら、弟子たちは福音書にそう書いたはずです。「この女は後にマグダラのマリアと呼ばれるようになった」というように・・・・・・。つまり、教皇によってマグダラのマリアは「娼婦という濡れ衣を着せられた」(岡田教授)ことになります。ではなぜ教皇はこのようなイメージを作りあげたのでしょうか。
|
と岡田教授は書いています。つまり、マグダラのマリアは、
| ◆ | 罪を悔い改める、というカトリックの教義に沿った存在。 | ||
| ◆ | 聖母・マリアとイヴの間を埋める存在。人々が幅広いイメージを投影できる存在。 | ||
| ◆ | 特に、官能と聖性の両義性をもつ存在。 |
だと言えます。この最後の「官能と聖性の両義性」というイメージを的確に表した絵画の代表格が、冒頭に掲げたティツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』なのです。岡田教授の本にも、口絵の先頭にこの絵が掲げられています。マグダラのマリアの絵画の代表的存在ということだと思います。
ティッツィアーノの「マグダラのマリア」
ここからが本題で、ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての中野京子さんの解説です。中野さんは「官能と聖性の両義性」、特に、聖母マリアとの対比において「官能・エロスが強調されるマグダラのマリア」のポジションから論を起こしています。
|

| ||
|
| ||
|
マグダラのマリアの絵画表現の典型的なパターンは、美貌のマリア(半裸や全裸で描かれることがある)が改心し、神への愛に目覚める(ないしは祈る)というものであり、数々の名画が作られました。そしてこのテーマに人々が(ないしは画家が)惹かれ、何世紀にも渡って図像化されてきた要因を、中野さんはサマセット・モームの短編小説『雨』を引き合いに出して説明しています。
サマセット・モームの『雨』
その『雨』を引き合いに出しての解説を、少々長くなりますが引用してみましょう。以下の引用は『雨』の要約が過半数なのですが、全体としてゾクッとするような研ぎ澄まされた文章です。
|
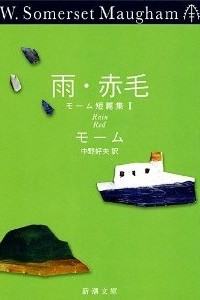
| |||
マグダラのマリアはティッツィアーノのような絵画だけでなく、文学や映画にも多大な影響を与えてきました。岡田教授の本には数々の例が紹介されています。比較的最近の映画を例にとると、たとえばジュゼッペ・トルトナーレ監督の『マレーナ』です。モニカ・ベルッチが主演したこの映画は、第2次世界大戦で夫を戦地に送ったシチリアの美しい女性・マレーナが「娼婦」呼ばわりされる顛末を描いたものですが、マレーナ = マグダラのマリアです。マグダラのマリアはイタリア語で「マリア マッダレーナ」であり、マッダレーナの愛称がマレーナなのです。
文学(小説)の例では、
| ・ | アンナ・カレーニナ(トルストイ) | ||
| ・ | 復活(トルストイ) | ||
| ・ | ボヴァリー夫人(フロベール) | ||
| ・ | マノン・レスコー(アヴェ・プレヴォ。プッチーニのオペラ化作品も有名) |
などにおけるヒロインの造型は、マグダラのマリアの影響なしには考えられない、と岡田教授は言っています。なるほどそうかもしれません。しかし、中野さんの解説で気づかされるのは、
| 小説に関しては、サマセット・モームの『雨』のミス・トムソンこそ、マグダラのマリアのもっともストレートな後継者 |
なのですね。なぜなら、彼女は「明確に娼婦」であり、しかも「牧師によって(一旦は)改悛する」のだから・・・・・。その舞台はサント・ボームの洞窟ならぬ、降りしきる雨に閉じこめられた熱帯の島です。しかし、その改悛は最後の最後でゼロ・クリアされてしまう、ほかならぬ牧師の「裏切り」によって、というところがモームの皮肉です。モームは『雨』において「悔い改めた娼婦」というイメージに強い性的魅力を感じてしまう男性心理の歪つさを揶揄しているというのが、中野さんの見立てです。
しかしモームの短編は「揶揄」や「皮肉」というレベルにはとどまらない感じですね。それは『雨』の最後の2つのセンテンスを読めば一目瞭然です。小説の最後を原文から引用すると以下です。「マクフェイル博士」とは、中野さんが「医師」と書いている人物です。
|
そもそも娼婦は、必要とする男たちがいるから成立するわけです。ミス・トムソンが吐き捨てた「同じ穴の狢」という言葉の意味は、
| ・ | 娼婦を買う男 | ||
| ・ | 娼婦=罪、として改悛させる男 | ||
| ・ | 改悛した娼婦に理性を失う男 |
が全部同類だということでしょう。モームの『雨』においては、牧師よりも、医師よりも、ミス・トムソンの方がよほど人間的に描かれています。
マグダラのマリアという「文化装置」
ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての解説のはずが、意外な方向に広がってきました。改めて中野さんの論を要約すると、次の2点になると思います。
| ◆ | 敬虔さの背後に娼婦の名残りが透けて見える「二重の官能性」。これがマグダラのマリアに人が(男が)惹かれる理由だろう。 | ||
| ◆ | それは「男の(男社会の)歪つな眼差し」だと思える。女性からみると(少なくとも中野さんからすると)そう見える。サマセット・モームもそう見ている。 |
という2点です。「二重の官能性」については、確かにそのような気がします。男が女性に惹かれる度合いを「式」で表すと、
聖女 < 娼婦 < 娼婦だった聖女
ということでしょうか(単純ですが)。「聖女」とか「娼婦」というのは極端であり、そういう人と付き合ったことがないので確信は持てないのですが、現実のもっと軽い例で置き換えてみると、お化粧をバッチリと決め、服装はトレンドをちゃんと押さえ、じゃべり方もハキハキしていて、快活で、話していても飽きない美しい女性、しかしどこか微かに「崩れているところ」を感じてしまう女性、その「崩れ感」に魅力を感じてしまうということがありますね(現代の女優でいうと米倉涼子さんのイメージか)。それに近い感情かと思います。
「男社会の歪つな眼差し」というのはどうでしょうか。確かに、女性にそう言われてもしかたがないかと思います。
というのも、ティツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』は裸体だからです。この絵だけでなく、半裸ないしは全裸の姿でマリアを描いた絵が沢山あります。ギリシャ・ローマ神話の「異教の女神」ならともかく、マグダラのマリアはれっきとしたキリスト教の聖女であり、使徒であり、イエスの復活の証人となった超重要人物です。その女性を裸体で描くというのは、そもそも女性の裸体を描きたいという画家(男性)の興味と欲求が先に立っているのだろうと思います。そこに「元娼婦」という格好のモチーフがあった。その欲求が「歪つな眼差し」の根底にあると思います。
しかし男の立場から少々言い訳をすると、「元娼婦である聖女」に対する男性の眼差しが歪つなのは、そうなるべき理由があると思うのです。それは、
| 男性の女性に対する(性的な)情熱は、本能とか生理学的な条件よりも、文化による影響が大きい |
からです。「マグダラのマリア」という女性像がいったん出来上がると、それは文化として広まり、逆に「マグダラのマリア的女性」に魅力を感じるようになってしまう、そのように暗黙に刷り込まれてしまうという面が強いと思うのです。映画や小説の例のように、マグダラとは言ってなくても「マグダラのマリア的女性に男性が強く惹かれるという物語」は蔓延しています。
No.115「日曜日の午後に無いもの」で紹介したように、中野さんは、19世紀のフランス女性が外出時にハンドバックを持たなかったことについて(= 持つのを拒否したことについて)、「それが時代の雰囲気であり、文化装置だ」と言っていました。「マグダラのマリア」も一つの文化装置であり、その文化装置が男性の女性への情熱(の一つのパターン)を作り出しているのだと思います。
「文化装置」にはいろいろの種類があり、文化圏によって、また時代によって多様です。同じ時代でもさまざまな「文化装置」があり、個人個人をみると「女性への情熱の持ち方」はいろいろある。「感情の起伏が激しく、言動も変化し、男を翻弄する女性」に魅力を感じる人もいるだろうし、「金髪の美女」ではなく「抜けるように白い肌の女性」(もしくはその逆)に強く惹かれる人もいる。「女としては未熟な10代の少女」に情熱を傾ける男もいる。
そしてマグダラのマリアとミス・トムソンの「職業」に関して言うと、「お金を払って女性と寝る」ことに執着する男がいるわけです。お金を払うことで満足感を得る。これが「娼婦」という職業が成立する一番根本的な理由でしょう。
「文化装置」は「作りもの」であり、フィクションです。それは「悔悛した娼婦」という「聖書に根拠がない創作物語」に象徴的に現れています。「作りもの」だから、基本的には「何でもあり」です。その「作りもの感」や「何でもあり感」が、「歪つだ」「不自然だ」と女性が感じる要因になっているのだと推測します。
中野さんが書いた、ティッツィアーノの『悔悛するマグダラのマリア』についての文章は、単なる絵の評論でなく、人間心理に言及しているところが印象的でした。と同時に、これは、
| 絵画評論であり、文学評論 |
になっている。そう言えば中野京子さんの本職は美術評論家ではなく、文学研究者(ドイツ文学)なのでした。
最後に、マグダラのマリアを図像化した2つの作品を掲げておきます。16-17世紀のイタリアの親子の画家(父と娘)、オラツィオ・ジェンティレスキ(1563-1639)とアルテミジア・ジェンティレスキ(1593-1652)の作品です。西洋のアートの歴史から言うと、いわゆる「バロック」の画家で、カラヴァッジョの影響が強く現れています。この2作品は岡田教授の本の口絵にも挙げられていました。

| ||
|
オラツィオ・ジェンティレスキ
『悔悛のマグダラ』(1625頃)
(ウィーン美術史美術館)
- Wikigallery - | ||

| ||
|
アルテミジア・ジェンティレスキ
『悔悛のマグダラ』(1620頃)
(フィレンツェ・ピッティ宮)
- Wikimedia Commons - | ||
父・オラツィオの作品は、サント・ボームの洞窟で瞑想と祈りに捧げるマリアを描いた作品で、骸骨、聖書といった定番アイテムが描かれています。中野さんは、前に引用した中で、
|
と書いていましたが、まさにそういう感じがします。カラヴァッジョ流の強い陰影の表現が印象的です。
一方の、娘・アルテミジアの作品は、マリアの肩をはだけた姿と、豪華そうな衣装(や椅子)が特徴で、おそらく見る人に当時のイタリアの娼婦を連想させたのだと思います。かつ、よく見ると右下にわずかに香油壷が描かれている。つまりマリアの伝統的解釈に忠実です。
この絵は明らかにティッアーノの絵を踏まえています。しかし娼婦としての官能表現は最低限に押さえられている。むしろこの絵は、マリアの「悔いる思い」や「改心の意志を訴える気持ち」、「神に帰依する決意」などが前面に押し出されています。マリアに当たっている強い光(神の光でしょう)も効果的です。その神の光が最も強く当たっているのは胸であり、この直後に顔に当たって悔悛が成就する ・・・・・・。この構図が素晴らしいし、また女性目線で描いたマリアという意味で印象に残る作品です。
No.115 - 日曜日の午後に無いもの [アート]
No.114「道化とピエロ」で、中野京子さんが解説するジャン = レオン・ジェロームの『仮面舞踏会後の決闘』を紹介しました。中野さんの解説のおもしろいところは、一般的な絵の見方に留まらず、今まで気づかなかった点、漫然と見過ごしていた点、あまり意識しなかった点に焦点を当てている(ものが多い)ことです。『仮面舞踏会後の決闘』では、それは「ピエロ」という存在の社会的・歴史的な背景や意味でした。
No.19「ベラスケスの怖い絵」で取り上げた絵に関して言うと、ベラスケスの『ラス・メニーナス』では「道化」が焦点であり、ドガの『踊り子』の絵では「黒服の男」でした。そういった「気づき」を与えてくれることが多いという意味で、中野さんの解説は大変におもしろいのです。
今回もその継続で、別の絵を取り上げたいと思います。ジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』です。言わずと知れた点描の傑作です。
グランド・ジャット島の日曜日の午後
まずこの絵の社会的背景ですが、舞台となっている19世紀後半のパリは「高度成長期」でした。1850-60年代のパリ大改造で街並みが一新し、産業革命が浸透し、貧富の差はあるものの人々は余暇を楽しむ余裕ができた。川辺でピクニックをし、清潔になった橋や大通りを散策し、鉄道に乗って郊外に出かけ、ダンスホールで夜を楽しんだ。そういった時代の絵です。まず中野さんが描写する絵の中の情景を見てみましょう。
大体において、絵を見る人はこの解説通りの印象を受けるでしょう。看護婦、軍人、娼婦(推測)を識別するには歴史知識が必要だと思いますが、それを抜きにしても解説どおりの情景であることは納得できると思います。しかし中野さんはこの絵の解説で、さらに2つの点を指摘しています。
です。
「あるもの」と「ないもの」
まず、「この絵に描かれているもの」とはパラソルです。中野さんは次のように書いています。
この絵を見る人は、誰しもパラソル(日傘)を目にすると思います。しかし我々は暗黙に、「日光が降り注ぐ日曜の午後に戸外を散策するのだから女性が日傘を持つのはあたりまえだろう。何も特別なことではない」と思ってしまい、日傘に特に気を留めることはないと思います。
しかし、ここに描かれた日傘には意味があるのです。それは技術革新で軽量化がなされ、大量生産で価格が低下したという産業革命の浸透ぶりの象徴なのですね。もちろんその裏には傘工場で働く(貧しい)労働者と、傘工場を経営する資本家がいたわけです。
中野さんは同時に「この絵に描かれていないもの」を指摘しています。もし仮に、現代の画家が「日曜日の午後の、都市近郊でのピクニック風景」を写実の手法で描いたとしたら、そこに絶対に描かれるはずのものが、この絵にはないのです。
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』に女性の持ち物としてのバッグが描かれていないという指摘は、これが初めてではないでしょうか。
要するに「女性が働くこと自体が蔑視されていた」時代なのですね。そう言えば、当時を舞台にした小説、オペラ、絵画などに現れる「働く女性」は「下層階級」の扱いを受けているのを思い出します。ユーゴーの『レ・ミゼラブル』に出てくる工場で働くファンティーヌがそうだし、プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』のミミはパリのお針子です。ドガが描いた踊り子たちも、まさにそうなのですね(No.86「ドガとメアリー・カサット」参照)。中野さんの本には、デュマ・フィスの『椿姫』のモデルとなったマリー・デュプレシは、パリに出てきてお針子になったが、一時、傘工場で働いていたとあります。なるほど・・・・・・。
これを逆に言うと「女性の持ち物としてのバッグは、女性の自立の象徴」ということになります。この典型が、No.4「プラダを着た悪魔」のファッション誌編集長・ミランダです。あの映画に出てくるたくさんのプラダのバッグは、まさに女性の自立を象徴しています。
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』に「あるもの=日傘」と「ないもの=ハンドバッグ」という中野さんの解説は、絵を見るときの「気づき」を与えてくれるものでした。
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の価値
もちろん『グランド・ジャット島の日曜日の午後』という絵の価値は、当時の(現代人には気づきにくい)風俗を表していることではありません。以降は「気づき」を離れて、なぜこの絵が名画なのかについてです。
この絵を見て感じるのは、絵全体に「強い静けさ」が漂っていて、それが明るい戸外の光やピクニックを楽しむ人々と解け合って独特の美しさを作っていることでしょう。中野さんは次のように書いています。
中野さんは文章が非常にうまい人です。この引用のところも、スーラのこの絵になぜ人が惹かれるのか、なぜ名作なのかが、ピタリと適切な言葉に置き換えられています。
しかし、現代では名作とされているこの絵も、同時代の人々には理解されませんでした。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』には「無いもの」があります。それは「バッグ」だけではありません。「動き」や「現実感」も無いのです。
同時代には評価されなかった絵
スーラの、いわゆる点描法は、同時代の画家や批評家からは批判されました。その批判と絵が辿った運命を、中野さんは次のように書いています。
「あとの祭り」とはこのことでしょう。「シカゴ美術館の至宝」というより「アメリカの至宝」である芸術作品なので、売買というような「一般社会の概念」は超越しているのだと思います。
しかし、同時代から評価されなかったというは分からないでもないのです。点描法は「動き」を消し去るので、「人気の無い、静かな港の風景」的な作品にはフィットしていると思います。たとえばオルセー美術館の『ポール・タン・ベッサンの外港』(1888)です。これと類似の風景画の小品(港、海辺、川辺・・・・)は各地の美術館で見た記憶があります。
しかし、人物画であれ風景画であれ、また風俗画であれ、多くの場合に鑑賞者は暗黙に何らかの「動き」を想像します。従って点描法には違和感を感じる。スーラが描いた大作のうち、明らかな「動きの場面」を描いたものがあります。『シャユ踊り』(1890)と『サーカス』(1890/1)の2作品です。点描でも動きを表現できることを実証したかったのだと思いますが、成功しているとは言えない。
動きだけでなく、人の肌のような微妙な質感の表現も難しいと思います。No.95「バーンズ・コレクション」で引用した『ポーズする女たち』に描かれたモデルたちも「生々しさ」が消えています。魅力的な絵であり、引き込まれるのは確かなのですが、女性の肌の表現に限っていうと(それがこの絵の大きなポイントのはずですが)疑問が残ります。
そもそも画家が油絵で肌の質感を出そうとするときには、さまざまな工夫をしますね。たとえば、白っぽい肌色で下地をつくり、その上にグリーン系の色を重ね、さらにその上に赤みのある暖色系を塗るというような・・・・・・。あくまで例ですが。
目に見える色は反射光ですが、それは物体の表面だけからの反射ではありません。表面の少し下で反射してくる透過光もあります。油絵の具の重ね塗りはそういったものも追求できるわけです。点描は、カンヴァスに置かれた無数の点が人間の目で色に見える(=だから明るい)のですが、原理上、どうしても「平面的」にならざるを得ないわけです。
スーラは『ポーズする女たち』の中に『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を画中画として描き込んでいます。「戸外の風景だけでなく、ヌードも点描で描ける」ことを実証したかったのだろうと思いますが「ヌードで点描」が成功しているとは言えない。
しかしです。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』だけは違うのですね。中野さんの表現を借りると「他のスーラ作品に比べ、これだけは別格」なのです。点描という手法による「奇跡のような絵」と言える。絵の中には散歩している人もいれば、飛び跳ねているペットの猿もいるというように、本来「動き」のあるモチーフも含まれるわけです。なぜこの絵だけが「奇跡」になり得たのでしょうか。
現代人の感性を刺激する
前に引用したように中野さんは、この絵を「別格」とする理由を書いています。それをもう一度箇条書きにすると、以下のようです。
全くその通りだと思います。

しかし付け加えると、我々現代人がこの絵に強く惹かれるのは、さらに理由があると思うのです。それは絵の題名の一部である「日曜日の午後」というキーワードに我々が反応するからです。スーラの意図とは別に(= スーラの意図がどうであれ)、現代人が日曜日の午後の公園(ないしは公園と同等の場所)に暗黙に抱いているイメージがあり、そのイメージとこの絵が見事にシンクロしていると思うのです。
もしあなたが都会の会社に勤めていて、郊外に自宅があるとしましょう。土曜日・日曜日は休みとします。1週間のうち、最も高揚感があるのは金曜の夜でしょうね。さあ、明日から休みだ、という感じで・・・・・・。そして土曜日は、たとえば家族サービスで「活動的な」一日を送る。そして日曜日は家でゆっくり過ごすことになったとします。
その日曜日の午後、あなたは近くの広い公園に出かけ、散歩をしたあと、目の前に広がる芝生を眺めながら、ベンチで佇んでいるとします。
気分は少しブルーです。休日がもう終わってしまうという寂しさと、明日からまた"戦争"だ、ということを感じてのブルーです。
公園を散策する人があちこちにいて、母親は子供を芝生で遊ばせている。日光が降り注ぎ、鳥の鳴き声、噴水の音、子供のはしゃぎ声、公園の外の車のかすかな音などが聞こえてくる。あなたはベンチに座って、どこを見るともなく辺りを眺め、「無為」の時間を過ごす・・・・・・。穏やかで、静かな時間です。目に入る風景に大きな変化はなく、時の流れが極めてゆっくりに感じられる。このままずっとこうしていたいと、ふと思うが、もちろんそうはいかない。
おそらく誰しも、そういった「日曜日の午後」の経験があるのでは思います。スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』から受ける印象は、現代人も経験する「日曜日の午後の公園の気分」と非常にマッチしていると思うのです。この絵の「奇跡的なまでに美しく」「全てがフリーズし」「現実感をなくし」「幻想的で」「静謐で」「一場の夢のよう」な雰囲気が、ピタリとその気分にはまっている。特に「時間がフリーズした感じ」に、私たちは非常な共感を覚えるのです。我々は意識することなく「既視感」を覚え、そして絵に引き込まれる・・・・・・。
この雰囲気を作り出している大きな要因が、スーラが用いた絵画手法だということは明らかでしょう。この作品は、点描法に内在している数々の困難さやマイナス面、それらの全てを一気にプラスに変えてしまった、奇跡のような作品だと思います。この絵には、
があります。描かれた人々は、その中で「無為の時間」を過ごしています。寝そべり、無意識に川面を眺め、そぞろ歩きをし、じっと釣り糸を垂れている。当然ですが、目的がある行動をしている人は誰一人いません。休日における、つかの間の「空っぽの(Vacant)」時間であり、それが本来の意味での「休暇(Vacation)」なのです。
この絵には点描法に最適なモチーフが描かれています。それこそ、奇跡を生み出した大きな要因でしょう。
「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884/6)に「パラソル」が描かれていると、中野京子さんはあたりまえのことを改めて指摘したのですが、パラソルと聞いてすぐに思い出す絵があります。クロード・モネが妻のカミーユを描いた3枚の絵、「パラソルの女」です。
ワシントン・ナショナルギャラリーの絵(1875)には、息子のジャンも描かれいて、またカミーユの表情もあります。この絵の4年後の1879年にカミーユは亡くなりました。オルセー美術館の2枚の絵(1886)は亡くなったカミーユを回想して描いたもので、表情は描かれていません。
この3枚の絵の評論はたくさんありますが、「パラソル」に注目したものは少ないのではないでしょうか。ワシントン・ナショナルギャラリーの絵が描かれたのは、スーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」の10年前です。ということは、パラソルをもって郊外に遊ぶこと自体が当時のパリないしはその近郊における最先端のファッションであり、またトレンドであったと考えられます。クロード・モネは妻・カミーユのそういう姿を描き、それを「幾分、誇らしげに」カンヴァスに定着させたと思える。それはもちろん、カミーユを愛する思いからでしょう。
我々は、女性が日傘をさすのは当たり前だと(暗黙に)思ってしまって気づかないのですが、当時の状況を考えてみると、画家の思いの一端がうかがえると思います。
パラソルを持った1人の女性がモデルの絵は他にもあります。モネの「パラソルの女」(1875)の6年前に、ベルト・モリゾがパラソルを持ったた女性の絵を描いています。「ロリアンの小さな港」という作品で、1875年版のモネの絵と同じくワシントンのナショナルギャラリーが所蔵しています。ロリアンはブルターニュ地方の港町で、この絵のモデルの女性はベルトの姉のエドマです。
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の右端手前の女性の足元には猿が描かれています。この猿について、中野京子さんが本文に引用したのとは別の本で解説されていました。次にその「怖いへんないきものの絵」(幻冬舎 2018)から引用しますが、この本は著作家の早川いくを氏と中野さんの対話形式になっています。その中野さんの部分だけを引用します。
No.19「ベラスケスの怖い絵」で取り上げた絵に関して言うと、ベラスケスの『ラス・メニーナス』では「道化」が焦点であり、ドガの『踊り子』の絵では「黒服の男」でした。そういった「気づき」を与えてくれることが多いという意味で、中野さんの解説は大変におもしろいのです。
今回もその継続で、別の絵を取り上げたいと思います。ジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』です。言わずと知れた点描の傑作です。
グランド・ジャット島の日曜日の午後

| ||
|
ジョルジュ・スーラ(1859-1891)
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(1884/6)
(シカゴ美術館蔵)
| ||
まずこの絵の社会的背景ですが、舞台となっている19世紀後半のパリは「高度成長期」でした。1850-60年代のパリ大改造で街並みが一新し、産業革命が浸透し、貧富の差はあるものの人々は余暇を楽しむ余裕ができた。川辺でピクニックをし、清潔になった橋や大通りを散策し、鉄道に乗って郊外に出かけ、ダンスホールで夜を楽しんだ。そういった時代の絵です。まず中野さんが描写する絵の中の情景を見てみましょう。
|
大体において、絵を見る人はこの解説通りの印象を受けるでしょう。看護婦、軍人、娼婦(推測)を識別するには歴史知識が必要だと思いますが、それを抜きにしても解説どおりの情景であることは納得できると思います。しかし中野さんはこの絵の解説で、さらに2つの点を指摘しています。
| ◆ | この絵に描かれているもの | ||
| ◆ | この絵に描かれていないもの |
です。
「あるもの」と「ないもの」
まず、「この絵に描かれているもの」とはパラソルです。中野さんは次のように書いています。
|
この絵を見る人は、誰しもパラソル(日傘)を目にすると思います。しかし我々は暗黙に、「日光が降り注ぐ日曜の午後に戸外を散策するのだから女性が日傘を持つのはあたりまえだろう。何も特別なことではない」と思ってしまい、日傘に特に気を留めることはないと思います。
しかし、ここに描かれた日傘には意味があるのです。それは技術革新で軽量化がなされ、大量生産で価格が低下したという産業革命の浸透ぶりの象徴なのですね。もちろんその裏には傘工場で働く(貧しい)労働者と、傘工場を経営する資本家がいたわけです。
|
|
||||||||||||||||
中野さんは同時に「この絵に描かれていないもの」を指摘しています。もし仮に、現代の画家が「日曜日の午後の、都市近郊でのピクニック風景」を写実の手法で描いたとしたら、そこに絶対に描かれるはずのものが、この絵にはないのです。
|
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』に女性の持ち物としてのバッグが描かれていないという指摘は、これが初めてではないでしょうか。
要するに「女性が働くこと自体が蔑視されていた」時代なのですね。そう言えば、当時を舞台にした小説、オペラ、絵画などに現れる「働く女性」は「下層階級」の扱いを受けているのを思い出します。ユーゴーの『レ・ミゼラブル』に出てくる工場で働くファンティーヌがそうだし、プッチーニのオペラ『ラ・ボエーム』のミミはパリのお針子です。ドガが描いた踊り子たちも、まさにそうなのですね(No.86「ドガとメアリー・カサット」参照)。中野さんの本には、デュマ・フィスの『椿姫』のモデルとなったマリー・デュプレシは、パリに出てきてお針子になったが、一時、傘工場で働いていたとあります。なるほど・・・・・・。
これを逆に言うと「女性の持ち物としてのバッグは、女性の自立の象徴」ということになります。この典型が、No.4「プラダを着た悪魔」のファッション誌編集長・ミランダです。あの映画に出てくるたくさんのプラダのバッグは、まさに女性の自立を象徴しています。
| 中野さんの言う「文化装置」でちょっと思い出しました。さきほどの日傘ですが、現代の夏のパリに行っても、日傘をしている現地の女性はほとんどいませんね。見た記憶がありません。逆に、日本人観光客の女性などは日傘をしている人がいる。おそらくフランス女性にしてみると、たとえ日焼けをしたとしてもその方が健康的であり、ナチュラルであり、それが自立した女性だ、ということではと想像します。それを「文化装置」というのは大袈裟だけれど。 |
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』に「あるもの=日傘」と「ないもの=ハンドバッグ」という中野さんの解説は、絵を見るときの「気づき」を与えてくれるものでした。
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の価値
もちろん『グランド・ジャット島の日曜日の午後』という絵の価値は、当時の(現代人には気づきにくい)風俗を表していることではありません。以降は「気づき」を離れて、なぜこの絵が名画なのかについてです。
この絵を見て感じるのは、絵全体に「強い静けさ」が漂っていて、それが明るい戸外の光やピクニックを楽しむ人々と解け合って独特の美しさを作っていることでしょう。中野さんは次のように書いています。
|
中野さんは文章が非常にうまい人です。この引用のところも、スーラのこの絵になぜ人が惹かれるのか、なぜ名作なのかが、ピタリと適切な言葉に置き換えられています。
しかし、現代では名作とされているこの絵も、同時代の人々には理解されませんでした。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』には「無いもの」があります。それは「バッグ」だけではありません。「動き」や「現実感」も無いのです。
同時代には評価されなかった絵
スーラの、いわゆる点描法は、同時代の画家や批評家からは批判されました。その批判と絵が辿った運命を、中野さんは次のように書いています。
|
|
「あとの祭り」とはこのことでしょう。「シカゴ美術館の至宝」というより「アメリカの至宝」である芸術作品なので、売買というような「一般社会の概念」は超越しているのだと思います。

| |||
|
スーラ 『ポール・アン・ベッサンの外港』(1888)
(オルセー美術館) | |||
しかし、人物画であれ風景画であれ、また風俗画であれ、多くの場合に鑑賞者は暗黙に何らかの「動き」を想像します。従って点描法には違和感を感じる。スーラが描いた大作のうち、明らかな「動きの場面」を描いたものがあります。『シャユ踊り』(1890)と『サーカス』(1890/1)の2作品です。点描でも動きを表現できることを実証したかったのだと思いますが、成功しているとは言えない。
|
|
||||||||||||||||
動きだけでなく、人の肌のような微妙な質感の表現も難しいと思います。No.95「バーンズ・コレクション」で引用した『ポーズする女たち』に描かれたモデルたちも「生々しさ」が消えています。魅力的な絵であり、引き込まれるのは確かなのですが、女性の肌の表現に限っていうと(それがこの絵の大きなポイントのはずですが)疑問が残ります。

| |||
|
スーラ 『ポーズする女たち』(1886/8)
(バーンズ・コレクション) | |||
目に見える色は反射光ですが、それは物体の表面だけからの反射ではありません。表面の少し下で反射してくる透過光もあります。油絵の具の重ね塗りはそういったものも追求できるわけです。点描は、カンヴァスに置かれた無数の点が人間の目で色に見える(=だから明るい)のですが、原理上、どうしても「平面的」にならざるを得ないわけです。
スーラは『ポーズする女たち』の中に『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を画中画として描き込んでいます。「戸外の風景だけでなく、ヌードも点描で描ける」ことを実証したかったのだろうと思いますが「ヌードで点描」が成功しているとは言えない。
しかしです。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』だけは違うのですね。中野さんの表現を借りると「他のスーラ作品に比べ、これだけは別格」なのです。点描という手法による「奇跡のような絵」と言える。絵の中には散歩している人もいれば、飛び跳ねているペットの猿もいるというように、本来「動き」のあるモチーフも含まれるわけです。なぜこの絵だけが「奇跡」になり得たのでしょうか。
現代人の感性を刺激する
前に引用したように中野さんは、この絵を「別格」とする理由を書いています。それをもう一度箇条書きにすると、以下のようです。
| ◆ | 奇跡的なまでに美しい。 | ||
| ◆ | 斬新で、個性的。 | ||
| ◆ | 全てがこの世ならぬ静止状態にある。人も動物も風さえも光の粒の中にフリーズし、音も声もかき消える。 | ||
| ◆ | 現実の風景のはずなのに、現実感をなくしている。 | ||
| ◆ | 失われた過去そのもののように懐しい。 | ||
| ◆ | 幻想的で、静謐で、一場の夢のよう。 |
全くその通りだと思います。

しかし付け加えると、我々現代人がこの絵に強く惹かれるのは、さらに理由があると思うのです。それは絵の題名の一部である「日曜日の午後」というキーワードに我々が反応するからです。スーラの意図とは別に(= スーラの意図がどうであれ)、現代人が日曜日の午後の公園(ないしは公園と同等の場所)に暗黙に抱いているイメージがあり、そのイメージとこの絵が見事にシンクロしていると思うのです。
もしあなたが都会の会社に勤めていて、郊外に自宅があるとしましょう。土曜日・日曜日は休みとします。1週間のうち、最も高揚感があるのは金曜の夜でしょうね。さあ、明日から休みだ、という感じで・・・・・・。そして土曜日は、たとえば家族サービスで「活動的な」一日を送る。そして日曜日は家でゆっくり過ごすことになったとします。
その日曜日の午後、あなたは近くの広い公園に出かけ、散歩をしたあと、目の前に広がる芝生を眺めながら、ベンチで佇んでいるとします。
気分は少しブルーです。休日がもう終わってしまうという寂しさと、明日からまた"戦争"だ、ということを感じてのブルーです。
公園を散策する人があちこちにいて、母親は子供を芝生で遊ばせている。日光が降り注ぎ、鳥の鳴き声、噴水の音、子供のはしゃぎ声、公園の外の車のかすかな音などが聞こえてくる。あなたはベンチに座って、どこを見るともなく辺りを眺め、「無為」の時間を過ごす・・・・・・。穏やかで、静かな時間です。目に入る風景に大きな変化はなく、時の流れが極めてゆっくりに感じられる。このままずっとこうしていたいと、ふと思うが、もちろんそうはいかない。
おそらく誰しも、そういった「日曜日の午後」の経験があるのでは思います。スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』から受ける印象は、現代人も経験する「日曜日の午後の公園の気分」と非常にマッチしていると思うのです。この絵の「奇跡的なまでに美しく」「全てがフリーズし」「現実感をなくし」「幻想的で」「静謐で」「一場の夢のよう」な雰囲気が、ピタリとその気分にはまっている。特に「時間がフリーズした感じ」に、私たちは非常な共感を覚えるのです。我々は意識することなく「既視感」を覚え、そして絵に引き込まれる・・・・・・。
この雰囲気を作り出している大きな要因が、スーラが用いた絵画手法だということは明らかでしょう。この作品は、点描法に内在している数々の困難さやマイナス面、それらの全てを一気にプラスに変えてしまった、奇跡のような作品だと思います。この絵には、
| ・ | 明るい光と、美しい色 | ||
| ・ | フリーズした時間 |
があります。描かれた人々は、その中で「無為の時間」を過ごしています。寝そべり、無意識に川面を眺め、そぞろ歩きをし、じっと釣り糸を垂れている。当然ですが、目的がある行動をしている人は誰一人いません。休日における、つかの間の「空っぽの(Vacant)」時間であり、それが本来の意味での「休暇(Vacation)」なのです。
この絵には点描法に最適なモチーフが描かれています。それこそ、奇跡を生み出した大きな要因でしょう。
| 補記1:パラソル |
「グランド・ジャット島の日曜日の午後」(1884/6)に「パラソル」が描かれていると、中野京子さんはあたりまえのことを改めて指摘したのですが、パラソルと聞いてすぐに思い出す絵があります。クロード・モネが妻のカミーユを描いた3枚の絵、「パラソルの女」です。
ワシントン・ナショナルギャラリーの絵(1875)には、息子のジャンも描かれいて、またカミーユの表情もあります。この絵の4年後の1879年にカミーユは亡くなりました。オルセー美術館の2枚の絵(1886)は亡くなったカミーユを回想して描いたもので、表情は描かれていません。
この3枚の絵の評論はたくさんありますが、「パラソル」に注目したものは少ないのではないでしょうか。ワシントン・ナショナルギャラリーの絵が描かれたのは、スーラの「グランド・ジャット島の日曜日の午後」の10年前です。ということは、パラソルをもって郊外に遊ぶこと自体が当時のパリないしはその近郊における最先端のファッションであり、またトレンドであったと考えられます。クロード・モネは妻・カミーユのそういう姿を描き、それを「幾分、誇らしげに」カンヴァスに定着させたと思える。それはもちろん、カミーユを愛する思いからでしょう。
我々は、女性が日傘をさすのは当たり前だと(暗黙に)思ってしまって気づかないのですが、当時の状況を考えてみると、画家の思いの一端がうかがえると思います。

|
1875年作。100cm × 81cm (ワシントン・ナショナルギャラリー) |
|
|
|||||
(オルセー美術館) | ||||||
| 補記2:パラソル2 |
パラソルを持った1人の女性がモデルの絵は他にもあります。モネの「パラソルの女」(1875)の6年前に、ベルト・モリゾがパラソルを持ったた女性の絵を描いています。「ロリアンの小さな港」という作品で、1875年版のモネの絵と同じくワシントンのナショナルギャラリーが所蔵しています。ロリアンはブルターニュ地方の港町で、この絵のモデルの女性はベルトの姉のエドマです。

|
ベルト・モリゾ(1841-1895) 「ロリアンの小さな港」(1869) (ワシントン・ナショナルギャラリー) |
| 補記3:猿 |
『グランド・ジャット島の日曜日の午後』の右端手前の女性の足元には猿が描かれています。この猿について、中野京子さんが本文に引用したのとは別の本で解説されていました。次にその「怖いへんないきものの絵」(幻冬舎 2018)から引用しますが、この本は著作家の早川いくを氏と中野さんの対話形式になっています。その中野さんの部分だけを引用します。
|
No.114 - 道化とピエロ [アート]
No.19「ベラスケスの怖い絵」で、中野京子さんの解説によるベラスケスの『ラス・メニーナス』を紹介しましたが、話をそこに戻したいと思います。中野さんは、王女の向かって右に描かれた小人症の女性、マリア・バルボラに着目し、当時のスペイン宮廷に集められた道化の話を展開していました。
No.19 以降、「ベラスケスと道化」に関係した話題を何回か取り上げています。まず、No.45「ベラスケスの十字の謎」では、マリア・バルボラの横に描かれている小人症の少年、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にした小説「ベラスケスの十字の謎」を紹介しました。
さらに、No.63「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」では、英国の詩人・文学者、オスカー・ワイルドが「ラス・メニーナス」からインスピレーションを得て書いた童話『王女の誕生日』と、その童話を原案として作られたツェムリンスキーのオペラ『こびと』に関して書きました。
また、No.36「ベラスケスへのオマージュ」では、エドゥアール・マネがベラスケスの『道化師 パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けて『笛を吹く少年』を描いたことに触れました。
No.19, No.36 に引用したように、ベラスケスはスペイン宮廷の道化を多数描いています。しかし宮廷道化師はスペインだけではなくヨーロッパの各国にあり、それは中世からの歴史的経緯があります。
こういった道化の流れをくむ一つの存在が、近代から現代のピエロです。今回は、そのピエロを描いた19世紀フランス絵画の傑作を、中野さんの解説に従って紹介します。ジャン = レオン・ジェロームの『仮面舞踏会後の決闘』(1857。エルミタージュ美術館蔵)です。
仮面舞踏会後の決闘
登場する6人の男は全員が仮装をしていて、皆が仮面舞踏会の客だったことが分かります。一番左に描かれた男がこの決闘の「証人」で、第三者の立場でこの決闘を仕切る役割です。彼は16世紀の貴族の装束をしています。首に巻いたラフ(蛇腹状のレース襟)でそれが分かります。
ピエロのすぐ右の2人の男は、死にゆく敗者の「立会人」です。頭を抱えている男は僧服を着ていて、おそらく司祭の仮装であり、傷を確かめている男は赤い中国服を着ています。
右の方、右から2番目の男は道化の仮装をしていて、彼が勝者側の立会人です。一番右側、この決闘に勝った男は、アメリカ・インディアンの衣装です。よく見ると画面の右下、白い雪の上にインディアンの仮装から落ちた羽根が描かれています。
中野京子という人も困ったものです。絵が傑作だからこういう文章が書けるのか、文章が素晴らしいから絵も傑作に見えてくるのか、その狭間の混乱に読者を落とし入れるのだから・・・・・・。
それはともかく、この絵で分かることは、19世紀においても決闘が行われていたことです(20世紀初頭まであったようです)。武器は剣か拳銃で、双子の拳銃を用意してあるホテルもあったと本にあります。拳銃はあらかじめ撃つ弾の数を決めておくため、双方が無傷で終わることもあった。しかし命を賭けた戦いであることには間違いありません。まさに、剣で闘ったこの絵のように・・・・・・。中野さんの本には、著名人の決闘経験者がでてきます。
有名な話ですが、現代数学の開始者の一人である天才数学者・ガロアは、わずか20歳で決闘で死にました。決闘の前日までガロアは代数方程式に関する研究ノートを書いていた。その余白に彼は書き込んだ。「僕には時間がない」・・・・・・。
この絵は「決闘」という、当時のフランスの「風俗」が描かれているところに特徴があります。一般的にジェロームの絵で良く知られているのは「歴史画」か「異国趣味の絵」です。前に、2つの作品を引用しました。
の2つですが、いずれも異国の風物(動物)です。ところが『仮面舞踏会後の決闘』はパリでも起こりうる(現実に起こっていた)事件を描いた。それもあってか、世間には好評のうちに受け入れられたようです。しかし中野さんは、死を迎えようとしている男がピエロの仮装をしていることこそ、この絵の価値だと言います。
この絵に仮装として出てくるピエロとアルレッキーノは、「コメディア・デラルテ」の舞台道化師がルーツです。コメディア・デラルテは、北部イタリアを発祥としてヨーロッパに広まった、即興性の強い仮面笑劇です。俳優たちが類型的なキャラクターをユーモラスに演じるのが特徴です。その類型キャラクターにはいろいろありますが、『仮面舞踏会後の決闘』に関係するのは次の3つです。
アルレッキーノ
プルチネッラ
ペドロリーノ
中野さんによると、プルチネッラの白塗りと白い衣装がペドロリーノに応用されたのが、フランスにおけるピエロの起源だと言います。しかし18世紀にもなると、コメディア・デラルテは下品で粗野なもの、下層民の娯楽と見なされるようになっていきました。それが19世紀に一変します。
レオンカヴァッロのオペラ『道化師』(1892)は、旅回りのコメディア・デラルテ一座の話です。主人公は妻の浮気を知りながら、舞台では観客を笑わせなければならない。その「秘した感情表現」がオペラの見どころ、聞きどころになっています。
中野さんの解釈による『仮面舞踏会後の決闘』の結論は次です。
中野さんは数々の絵画の評論を書いてますが、この『仮面舞踏会後の決闘』についての文章は特に冴えています。この絵に対する「思い入れ」の強さが感じられるし、ほとんど絶賛と言っていい文章になっています。
この絵はいわゆる「物語絵」です。物語絵は西洋でも日本でも数々描かれていますが、多くは宗教、神話、故事であり、近代以降は世相風刺・社会風刺が多い。この絵も「世相風刺の物語絵」なのでしょう。しかし、そこに
という構図をピタリと重ね合わせている。傑作と言っていい絵でしょう。
深い感情を秘した存在としての道化
ここからはジェロームの絵からの連想です。「道化の悲しみ」を描いた絵には先駆者がいると思うのですね。それは道化を描いた先駆者・ベラスケスの作品で、No.19「ベラスケスの怖い絵」で引用した『セバスティアン・デ・モーラの肖像』です。この絵は2002年に日本で開催された「プラド美術館展」で展示されたので(マドリードに行ったことがなくても)実際に見た人は多いと思います。
この絵はまさに「内面に深い感情を秘した存在としての道化」を描いた絵と言うしかないでしょう。その「深い感情」についての中野さんの解説を No.19 に引用しました。国王の「お抱え絵師」だった人がこういう絵を描くのは奇跡的だと思うし、ベラスケスという画家の凄さというか、先進性を表していると思います。
先駆者がいれば、後継者もいます。19世紀以降に道化を描いた絵はいろいろあって、たとえばセザンヌも何点か描いていますが、1枚あげるとするとオランジュリー美術館にあるアンドレ・ドラン(1880-1954)の「アルルカンとピエロ」(1924)です。アルルカンは『仮面舞踏会後の決闘』の説明にあったアルレッキーノ(絵では勝者側の立会人)に相当するフランス語で、パッチワークのような、菱形模様が特徴的な衣装を着ています。
この絵は一見して非常に不思議な感じがします。背景は何故か荒涼とした丘のような土地で、空の下半分が雲に覆われているのは普通ではありません。二人の道化は虚ろな表情で、その「踊り」はとってつけたような「稚拙な」感じです。ギターとマンドリンを持ってはいるが、ギターには弦さえ描かれていません。楽器を奏でているのではないということでしょうが、そもそも楽器をもって何をしているのか ? 背景からしても、彼らが何らかの意味のある行動をしているとは思えません。絵全体に「ミスマッチ感」や「ちぐはぐ感」が漂っています。
この絵のピエロの顔は、アンドレ・ドランの専属画商だったポール・ギヨームの似顔絵だと言われています(オランジュリー美術館の公式カタログによる。オランジュリーにはギヨームの所有絵画が多数展示されている)。だとするとアルルカンは画家自身であり、画家と画商という立場をアルルカンとピエロで表したと考えられます。意図的に「ちぐはぐ感」を出すことで、シニカルに自画像を描いたのでしょう。道化を描くことは何か特別のことがある、と感じさせる絵です。
道化の絵では「真打ち」とでも言うべき画家がいます。ドランと同世代であるパブロ・ピカソ(1881-1973)です。ピカソはアルルカンを多数描いているし、サルタンバンクと呼ばれた、特定の一座に属さない放浪の旅芸人や曲芸師を描いた絵もあります。
これらの絵はピカソの「バラ色の時代」(24~26歳ごろ)に多いわけですが、後のキュビズムの絵にも道化のテーマが出てくるし、ブリジストン美術館の「腕を組んで座るサルタンバンク」は40歳台前半の作品です。また晩年の作品にも道化が登場します。さらに、自らアルルカンの格好で絵の中に登場したり、息子(ポール)にアルルカンやピエロの格好をさせて描いた絵もある。これだけ執拗に道化の絵を描くというのは、特別な思い入れがあったのでしょう。
しかし画家の思いはどうであれ、絵を見る我々の受けとめ方としては、道化(ないしは旅芸人)の「哀愁」を感じさせるものが多いわけです。ピカソもまた、道化を「内面に深い感情を秘した存在」と見ているのだと思います。No.95「バーンズ・コレクション」で紹介した作品と、プーシキン美術館の傑作を最後に引用しておきます。
背景は街並みのようですが、おぼろげに描かれています。その"街頭" に描かれた二人の旅芸人は、兄と弟でしょう。剣を持っている兄はアクロバット(曲芸師)の装束であり、弟はアルルカンの衣装を着ている。二人は顔をそむけたような構図で等身大に描かれ、無表情な顔からは孤独の雰囲気が漂っています。あいまいに描かれた街は、彼らと街との距離感を暗示しているようです。ただ兄が弟の肩に伸ばした手から、弟への気遣いが伝わってきます。「街角」「旅芸人」「孤独」「家族愛」といった、若い二人のその時点での人生を凝縮したような美しい作品。この絵を見るためだけにフィラデルフィアまで足を伸ばす価値は十分にあると思います。
全くの余談ですが、この絵は1994年に国立西洋美術館で開催された「バーンズ・コレクション展」で展示されました。この展覧会にはコレクションから80点が出品され、100万人という驚異的な入場者を集めました。この展覧会の入場券に印刷されたのがピカソのこの絵でした。ところが、これがピカソの相続人の許諾なしに行われたために提訴され、展覧会の主催者(読売新聞社)は敗訴しました。もちろん、著作権の保護期間中の絵画(ピカソが亡くなったのは1973年)を許諾なしに入場券に印刷するのはルール違反です。しかし、幾多のバーンズ・コレクションの名品からこの絵を選んで入場券にした主催者側の気持ちは、わかるような気がします。
赤・青・白のトリコロールと黒、というシンプルな色調の中に、絶妙に配置された男と女とグラスが重厚な迫力で迫ってきます。全く平面的に描かれた顔や背景と、立体的な腕やグラスの対比が効いています。現実とファンタジーの間をさまよっているような人物像ですが、ポイントとなっているアルルカンの装束が哀愁を感じさせます。絵画史上この一枚しかないとも思える、天才の名に恥じない傑作です。
No.19 以降、「ベラスケスと道化」に関係した話題を何回か取り上げています。まず、No.45「ベラスケスの十字の謎」では、マリア・バルボラの横に描かれている小人症の少年、ニコラス・ペルトゥサトを主人公にした小説「ベラスケスの十字の謎」を紹介しました。
さらに、No.63「ベラスケスの衝撃:王女とこびと」では、英国の詩人・文学者、オスカー・ワイルドが「ラス・メニーナス」からインスピレーションを得て書いた童話『王女の誕生日』と、その童話を原案として作られたツェムリンスキーのオペラ『こびと』に関して書きました。
また、No.36「ベラスケスへのオマージュ」では、エドゥアール・マネがベラスケスの『道化師 パブロ・デ・バリャドリード』に感銘を受けて『笛を吹く少年』を描いたことに触れました。
No.19, No.36 に引用したように、ベラスケスはスペイン宮廷の道化を多数描いています。しかし宮廷道化師はスペインだけではなくヨーロッパの各国にあり、それは中世からの歴史的経緯があります。
|
こういった道化の流れをくむ一つの存在が、近代から現代のピエロです。今回は、そのピエロを描いた19世紀フランス絵画の傑作を、中野さんの解説に従って紹介します。ジャン = レオン・ジェロームの『仮面舞踏会後の決闘』(1857。エルミタージュ美術館蔵)です。
仮面舞踏会後の決闘
|

| ||
|
ジャン = レオン・ジェローム(1824-1904)
『仮面舞踏会後の決闘』(1857)
(エルミタージュ美術館蔵)
| ||
登場する6人の男は全員が仮装をしていて、皆が仮面舞踏会の客だったことが分かります。一番左に描かれた男がこの決闘の「証人」で、第三者の立場でこの決闘を仕切る役割です。彼は16世紀の貴族の装束をしています。首に巻いたラフ(蛇腹状のレース襟)でそれが分かります。
ピエロのすぐ右の2人の男は、死にゆく敗者の「立会人」です。頭を抱えている男は僧服を着ていて、おそらく司祭の仮装であり、傷を確かめている男は赤い中国服を着ています。
右の方、右から2番目の男は道化の仮装をしていて、彼が勝者側の立会人です。一番右側、この決闘に勝った男は、アメリカ・インディアンの衣装です。よく見ると画面の右下、白い雪の上にインディアンの仮装から落ちた羽根が描かれています。
|
中野京子という人も困ったものです。絵が傑作だからこういう文章が書けるのか、文章が素晴らしいから絵も傑作に見えてくるのか、その狭間の混乱に読者を落とし入れるのだから・・・・・・。
それはともかく、この絵で分かることは、19世紀においても決闘が行われていたことです(20世紀初頭まであったようです)。武器は剣か拳銃で、双子の拳銃を用意してあるホテルもあったと本にあります。拳銃はあらかじめ撃つ弾の数を決めておくため、双方が無傷で終わることもあった。しかし命を賭けた戦いであることには間違いありません。まさに、剣で闘ったこの絵のように・・・・・・。中野さんの本には、著名人の決闘経験者がでてきます。
| 決闘経験者 | ビスマルク(宰相。決闘25回) デュマ(作家。大デュマ) バイロン(詩人) マネ(画家) | |||
| 決闘で死亡 | プーシキン(1799-1837。37歳) ガロア(1811-1832。20歳。数学者) |
有名な話ですが、現代数学の開始者の一人である天才数学者・ガロアは、わずか20歳で決闘で死にました。決闘の前日までガロアは代数方程式に関する研究ノートを書いていた。その余白に彼は書き込んだ。「僕には時間がない」・・・・・・。
この絵は「決闘」という、当時のフランスの「風俗」が描かれているところに特徴があります。一般的にジェロームの絵で良く知られているのは「歴史画」か「異国趣味の絵」です。前に、2つの作品を引用しました。
| No.23「クラバートと奴隷(2)ヴェネチア」 | ||||
| No.94「貴婦人・虎・うさぎ」 |
の2つですが、いずれも異国の風物(動物)です。ところが『仮面舞踏会後の決闘』はパリでも起こりうる(現実に起こっていた)事件を描いた。それもあってか、世間には好評のうちに受け入れられたようです。しかし中野さんは、死を迎えようとしている男がピエロの仮装をしていることこそ、この絵の価値だと言います。
|
この絵に仮装として出てくるピエロとアルレッキーノは、「コメディア・デラルテ」の舞台道化師がルーツです。コメディア・デラルテは、北部イタリアを発祥としてヨーロッパに広まった、即興性の強い仮面笑劇です。俳優たちが類型的なキャラクターをユーモラスに演じるのが特徴です。その類型キャラクターにはいろいろありますが、『仮面舞踏会後の決闘』に関係するのは次の3つです。
アルレッキーノ
| 軽業師。明るい性格で、活動的。場をかき回す。赤・緑・青のまだら模様の衣装をきている。フランス語ではアルルカン、英語ではハーレクイン。 |
プルチネッラ
| 繊細な夢想家。白いだぶだぶの服を着ている。 |
ペドロリーノ
| お人好しで純粋だが無知。ピエロの起源とされる。 |
中野さんによると、プルチネッラの白塗りと白い衣装がペドロリーノに応用されたのが、フランスにおけるピエロの起源だと言います。しかし18世紀にもなると、コメディア・デラルテは下品で粗野なもの、下層民の娯楽と見なされるようになっていきました。それが19世紀に一変します。
|
レオンカヴァッロのオペラ『道化師』(1892)は、旅回りのコメディア・デラルテ一座の話です。主人公は妻の浮気を知りながら、舞台では観客を笑わせなければならない。その「秘した感情表現」がオペラの見どころ、聞きどころになっています。
中野さんの解釈による『仮面舞踏会後の決闘』の結論は次です。
|
中野さんは数々の絵画の評論を書いてますが、この『仮面舞踏会後の決闘』についての文章は特に冴えています。この絵に対する「思い入れ」の強さが感じられるし、ほとんど絶賛と言っていい文章になっています。
この絵はいわゆる「物語絵」です。物語絵は西洋でも日本でも数々描かれていますが、多くは宗教、神話、故事であり、近代以降は世相風刺・社会風刺が多い。この絵も「世相風刺の物語絵」なのでしょう。しかし、そこに
| 若者の愚行 = ピエロ = 悲しみ |
という構図をピタリと重ね合わせている。傑作と言っていい絵でしょう。
深い感情を秘した存在としての道化
ここからはジェロームの絵からの連想です。「道化の悲しみ」を描いた絵には先駆者がいると思うのですね。それは道化を描いた先駆者・ベラスケスの作品で、No.19「ベラスケスの怖い絵」で引用した『セバスティアン・デ・モーラの肖像』です。この絵は2002年に日本で開催された「プラド美術館展」で展示されたので(マドリードに行ったことがなくても)実際に見た人は多いと思います。

| ||
|
ベラスケス(1599-1660)
『セバスティアン・デ・モーラの肖像』(1646)
(プラド美術館)
| ||
この絵はまさに「内面に深い感情を秘した存在としての道化」を描いた絵と言うしかないでしょう。その「深い感情」についての中野さんの解説を No.19 に引用しました。国王の「お抱え絵師」だった人がこういう絵を描くのは奇跡的だと思うし、ベラスケスという画家の凄さというか、先進性を表していると思います。
先駆者がいれば、後継者もいます。19世紀以降に道化を描いた絵はいろいろあって、たとえばセザンヌも何点か描いていますが、1枚あげるとするとオランジュリー美術館にあるアンドレ・ドラン(1880-1954)の「アルルカンとピエロ」(1924)です。アルルカンは『仮面舞踏会後の決闘』の説明にあったアルレッキーノ(絵では勝者側の立会人)に相当するフランス語で、パッチワークのような、菱形模様が特徴的な衣装を着ています。

| ||
|
アンドレ・ドラン(1880-1954)
「アルルカンとピエロ」(1924)
(パリ:オランジュリー美術館)
| ||
この絵は一見して非常に不思議な感じがします。背景は何故か荒涼とした丘のような土地で、空の下半分が雲に覆われているのは普通ではありません。二人の道化は虚ろな表情で、その「踊り」はとってつけたような「稚拙な」感じです。ギターとマンドリンを持ってはいるが、ギターには弦さえ描かれていません。楽器を奏でているのではないということでしょうが、そもそも楽器をもって何をしているのか ? 背景からしても、彼らが何らかの意味のある行動をしているとは思えません。絵全体に「ミスマッチ感」や「ちぐはぐ感」が漂っています。
この絵のピエロの顔は、アンドレ・ドランの専属画商だったポール・ギヨームの似顔絵だと言われています(オランジュリー美術館の公式カタログによる。オランジュリーにはギヨームの所有絵画が多数展示されている)。だとするとアルルカンは画家自身であり、画家と画商という立場をアルルカンとピエロで表したと考えられます。意図的に「ちぐはぐ感」を出すことで、シニカルに自画像を描いたのでしょう。道化を描くことは何か特別のことがある、と感じさせる絵です。
道化の絵では「真打ち」とでも言うべき画家がいます。ドランと同世代であるパブロ・ピカソ(1881-1973)です。ピカソはアルルカンを多数描いているし、サルタンバンクと呼ばれた、特定の一座に属さない放浪の旅芸人や曲芸師を描いた絵もあります。
これらの絵はピカソの「バラ色の時代」(24~26歳ごろ)に多いわけですが、後のキュビズムの絵にも道化のテーマが出てくるし、ブリジストン美術館の「腕を組んで座るサルタンバンク」は40歳台前半の作品です。また晩年の作品にも道化が登場します。さらに、自らアルルカンの格好で絵の中に登場したり、息子(ポール)にアルルカンやピエロの格好をさせて描いた絵もある。これだけ執拗に道化の絵を描くというのは、特別な思い入れがあったのでしょう。
しかし画家の思いはどうであれ、絵を見る我々の受けとめ方としては、道化(ないしは旅芸人)の「哀愁」を感じさせるものが多いわけです。ピカソもまた、道化を「内面に深い感情を秘した存在」と見ているのだと思います。No.95「バーンズ・コレクション」で紹介した作品と、プーシキン美術館の傑作を最後に引用しておきます。

| ||
|
パブロ・ピカソ(1881-1973)
『曲芸師と若いアルルカン』(1905) | ||
全くの余談ですが、この絵は1994年に国立西洋美術館で開催された「バーンズ・コレクション展」で展示されました。この展覧会にはコレクションから80点が出品され、100万人という驚異的な入場者を集めました。この展覧会の入場券に印刷されたのがピカソのこの絵でした。ところが、これがピカソの相続人の許諾なしに行われたために提訴され、展覧会の主催者(読売新聞社)は敗訴しました。もちろん、著作権の保護期間中の絵画(ピカソが亡くなったのは1973年)を許諾なしに入場券に印刷するのはルール違反です。しかし、幾多のバーンズ・コレクションの名品からこの絵を選んで入場券にした主催者側の気持ちは、わかるような気がします。

| ||
|
パブロ・ピカソ
『アルルカンと女友達』(1901)
(プーシキン美術館)
| ||
No.111 - 肖像画切り裂き事件 [アート]
No.86「ドガとメアリー・カサット」で、原田マハさんの短編小説「エトワール」の素材となった、エドガー・ドガ(1834-1917)とメアリー・カサット(1844-1926)の画家同士の交友を紹介しました。今回はドガとエドゥアール・マネ(1832-1883)の交友の話です。二人は2歳違いの「ほぼ同い年」です。
エドガー・ドガ 『マネとマネ夫人像』
2014年1月18日の『美の巨人たち』(TV東京)は、ドガの『マネとマネ夫人像』(1868/69)をテーマにしていました。ドガが35歳頃の作品です。この絵は北九州市立美術館が所蔵していますが、絵の右端が縦に切り裂かれていて、無くなった部分にカンヴァスが継ぎ足されていることで有名です。ピアノを弾いているはずのマネ夫人(シュザンヌ)のところがバッサリと切り取られています。
番組で紹介されたこの絵の由来は、以下のような主旨でした。
新事実は④ですね。普通、この絵にカンヴァスを継ぎ足したのはドガ自身だと言われています。絵を所蔵している北九州市立美術館のホームページにも、
と書かれています。しかし「新事実 ④」からすると、この説明はおかしいわけです。ドガとマネが絵を交換したのはドガが35歳の頃です。ドガが切り裂かれた絵を発見したのは絵の交換のすぐあとと考えられます。ドガはマネの家をたびたび訪問したはずだから、たとえば10年もあとになってマネの家で切り裂かれた絵を発見するというのは考えにくい。そしてドガが49歳のときにマネは亡くなってしまいます。「美の巨人たち」で紹介された証拠写真は、晩年のドガの家の写真です。ドガは60歳台か、それ以降でしょう。少なくともその時点までは絵を「切り裂かれたままで」持っていた。ドガが継ぎ足したのではないと強く推定できます。
とすると、カンヴァスを継ぎ足したのは誰かということになる。その誰かとは次のような人物だと考えるのが妥当です。3つぐらいのポイントがあると思います。
の3つです。こういう人物はドガと親しかった画商でしょう。番組でもそう解説していました。画商だとすると、絵の価値を上げる意図が当然あると思いますが、印象派という「絵画の革命」に立ち会った画商としての使命感のようなものも動機かと思いました。
なぜマネは切り裂いたか:女の視点
しかしなぜマネは絵を切り取ったのでしょうか。北九州市立美術館の「公式の」解説は次です。
これは何となく納得性に乏しい解説です。「顔の歪みが気に入らない」と言うけれど、そんなに怒るほど、夫人を(この時点で)愛していたのだろうか。
番組では「ドガがこの絵を描いた当時、マネはベルト・モリゾと不倫関係にあった」ことを解説していました。これは有名な話ですね。不倫の程度は窺い知れませんが、単なる師弟関係以上のものがあったことは確かなようです。絵においてマネは「だらしなく」「横柄な」態度でソファに寝そべっていて「心ここにあらず」というように見える。夫人のピアノの演奏に退屈しているようでもある。これは当時の夫婦関係が冷えていたことを表していて、ドガはその夫婦の内面までを描いた・・・・・・ そういう主旨の番組の解説でした。
夫婦の隠された現実を描いてしまった、そこにマネは激怒して絵を切り取った・・・・・・という解説はありませんでしたが、そう暗示したかったのかもしれません。番組スタッフも「マネはドガの描いた夫人の顔の歪みが気に入らず、顔のあたりから切り取ってしまった。」という公式の解説に納得がいかないのでしょう。しかし、たとえ冷えた夫婦の内面を描いたからといって、夫人の顔の部分だけを切り取るという行為の説明はできないと思いました。
ところがです。番組が終わった直後、いっしょに見ていた私の妻が「絵を切り取った理由は簡単」と言ったのですね。彼女は、
と言ったのです。あなたはそんなことも分からないの、という感じで・・・・・・・。
うーん、ありうるかもと、その場では思ったのですが、あとから考えてみると、これはなかなか説得力のある説だと思えてきました。それには4つの理由があります。まず第1の理由ですが、それは
ということです。それは現代において「スナップ写真を人にあげる」ことを考えてみると分かります。たとえば、既婚のA子さんがいたとして、姉の一家(夫婦と1歳の娘)が自分の家に来たとします。記念にと、A子さんが1歳の姪を抱いている写真を何枚か撮った。それを後で姉にあげるとき、A子さんは「姪が最も可愛く写っている写真を選択しない」と思います。「自分が最もきれいに撮れている写真」を選択するはずです。「子供の写真をとるのは難しくって」とか言いながら・・・・・・・。姉としてもそれが真っ赤な嘘だとは感じながら「そうよね」と答えたりする。
それは何も姪だからというわけではありません。A子さん夫婦にも1歳の娘が一人いたとします。一家のスリー・ショットを写真年賀状にする場合、A子さんは「娘が一番可愛く写っている写真」という基準では選ばないと思います。あくまで「自分がきれいに写っているかどうか」で、まず写真を「ふるい」にかけるのではないでしょうか。その中から娘ができるだけ「まし」なのを選ぶ。
一般化するまでは出来ないでしょうが、少なくとも私が知っている女性はそうです。現代の写真を19世紀フランスの肖像画と考えると、マネ夫人も「自分がきれいに描かれているかどうか、ものすごく気にした」のではないか。そう推測します。それが第1の理由です。
第2の理由ですが、夫人に「切り取って」と迫られると、マネはしぶしぶ(ドガとの友情のことを考えながらも)そうしただろうと考えられます。なぜならマネは夫人に大きな負い目があるからです。それはまさに当時のベルト・モリゾとの「不倫関係」です。逆に夫人はマネに強気に出られる理由あるわけです。また、マネが切り取ったのではなく、怒った夫人が自ら切り取ったとも考えられる。だとしても、マネが阻止できなかったのは夫人に対する負い目だと想像できます。
第3の理由は、「切り裂き事件」があったにもかかわらずドガとマネはその後も良好な関係を続けたという歴史的事実です。絵は画家の分身のはずです。自分の作品を切り裂かれた画家は、切り裂いた画家と絶交してもおかしくはない。切り裂いた方は、絶交される覚悟でそうするはずです。画家なら、作品が芸術家にとっての分身だと分かっているからです。ところが意外にも、二人は良好な関係が続く。これはマネがドガに切り裂いた本当の理由を言ったからではないでしょうか。「ドガよ、許してくれ。本当のことは黙っておいてくれ。全部俺のせいにしておいてくれ」みたいな・・・・・・。
第4の理由ですが、「夫人がドガの描いた自分の姿に怒った」のがいかにもありうると考えられるのは、一般的に「ドガは女性を美しく描かない」からです。
女性を美しく描かない
誰だったか忘れたのですが、女性作家だったと思います。「ドガは嫌い、女性を美しく描かないから」という意味の文章を読んだことがあります。
確かにドガは女性を美しくは描きませんね。依頼されて描いたような一部の肖像画は別にして、女性の生活を描いた絵はきれいに描こうなどとは全く思っていないようです。絵の構図や人体のフォルム、瞬間を定着させることなど、そういったところにしか関心がない。踊り子の絵とか、歌手とか、働く女性とか、知り合いの家族とか、そういった作品を見れば強く感じます。
それでは、ドガは友人・マネの夫人であるシュザンヌをどう描いたのか。
それに関連して思い出す話があります。No.86「ドガとメアリー・カサット」で、ドガの友人の一人であるメアリー・カサットのことを書いたのですが、ドガがそのメアリーを描いた肖像画があります。
この絵を所蔵しているアメリカの国立肖像画美術館(The National Portrait Gallery, Washington D.C.)のウェブサイトの解説によると、メアリー・カサットは、この絵について次のように語ったそうです。
でしょうね。カードを持ったメアリーが前のめりになって、含み笑いというか「にやけた」ような表情をしています。カードの「手」がいいのでしょうか。フィラデルフィアの良家出身の女性がするポーズだとも思えない。絵が描かれた当時、彼女は30歳台の半ばです。ドガからするとメアリーは、フランスにあこがれてパリに定住した10歳下のアメリカ人女性画家であり、絵の才能を高く評価していて、アドバイスをしたりもした。自分を尊敬してくれている画家であり、友人でもあり、(芸術上の)喧嘩もするが、毎日のように会っていた時期もある(No.86「ドガとメアリー・カサット」参照)。そういう二人の関係と、この絵の表現は「落差」を感じます。メアリーは決して美人というわけではありませんが(No.86に写真を掲載)「こういう風に描くことはないでしょ!」と言いたくなる気持ちは分かります。
メアリー・カサットはこの絵をドガから贈られて持っていたが、ドガの死後すぐに売り払ったそうです(スーザン・マイヤー著「メアリー・カサット」による)。ドガが亡くなるまで(いやいやながらも)持っていたというのが、メアリー・カサットの律義なところですね。ドガは友人であり、ある意味では師匠でもあったからでしょう。また破棄せずに売ったのは、画家としての良心からだと想像します。メアリーはドガの死後にドガからもらった手紙をすべて焼き払ったのですが(No.86 参照)、さすがに絵を焼くことはできなかった。画家としては。
この絵は、ドガとメアリーの交流の中のどこかであった真実の瞬間なのだろうと思います。良家のお嬢さんがカード・ゲームをしてはいけないことはないし、ゲームでは当然、絵のような表情をすることもある。それをどう切り取って、どう絵にするかです。ドガはメアリーがみせた意外な表情としぐさをカンヴァスに定着させた。美化しようとか、女性をきれいに描こうとか、そんなことは一切思わない。それがメアリー・カサットにショックを与え、傷つけることになった。ドガにそんな意図は全くなかったはずだけれど・・・・・・。
マネ夫人もドガの絵を見てショックを受け、傷ついたのではないでしょうか。この絵が世に残るのは絶対に嫌だ。ドガに返すわけにはいかない。だからといって、夫の友人が描いた絵を破棄するのはどうか。幸いなことに、(メアリー・カサットの肖像とは違って)夫人の肖像は画面の右端にある。切り取ったとしても、絵として全く成り立たないというわけではない。じゃ、そうするしかない・・・・・・。画家であるメアリー・カサットは、ショックを受けた自分の肖像画にも「芸術的価値」を認めて、その絵を持っていたのですが、マネ夫人は画家ではありません(ピアニストです)。絵の芸術的価値よりもっと大事なことがあってもおかしくはない・・・・・・。
以上の「肖像画が切り裂かれた理由」は、全くの想像というか、推量です。本当のことは分かりません。しかし、以前にも何度か書いたように、絵を鑑賞する楽しみの一つは、そこからいろいろな想像を膨らませることです。こういう推量が許されてもいいと思います。
しかし想像とは別に、ドガの『マネとマネ夫人像』および『メアリー・カサットの肖像』を見て強く感じることがあります。それは「現実を美化・誇張しないで」「今、その時、その瞬間を描いた」と思わせる絵だということです。この2作品にかかわらず、ドガの絵にはそういう絵が多い。特に画家としての後半生の「有名な」絵はそうだと思います。
「女性を美しく描かない」のもそれと関係があるはずです。現代ではよく女性が「写真うつりが悪い」ことを気にしますね。写真が被写体をデフォルメすることはないので、要するにその女性が見せる表情の多くは(本人にとっては)写真うつりが悪い表情であり、ある時だけは写真うつりが良く見える。アマチュア写真ではその「ある時」をとらえるのが難しいということでしょう。プロの写真家はその瞬間をとらえるのにものすごく長けています。
ということは、プロの写真家と同じく、画家にとっては「どういう瞬間を描くか」が重要になってきます。たとえば『マネとマネ夫人像』のマネの姿です。ピアノに退屈し、心ここにあらず、という表情と態度に見える。ドガは「その時」を描いた。もしこれが冷えた夫婦関係を暗示したのなら(マネ夫人の表情が分からないのは残念ですが)、ドガはある瞬間を切り取ることで「現実には見えないものまで描いてしまった」ことになります。
リアリズムを突き詰めると、現実の切り取り方によって、目には見えないが画家が感じ取ったものを描いてしまう。そして結果的にリアリズムを越えてしまう。そういう感じがします。
マネがドガに贈った絵は?
ドガの『マネとマネ夫人像』は、互いの友情のしるしとしてマネとドガが絵を交換したときの、一方の絵でした。ではマネはドガにどんな絵を贈ったのか。
マネがドガに贈ったのは、スモモ(プラム)を描いた静物画でした。その絵は「切り裂き事件」のときに、ドガがマネに送り返しました。そしてマネはその絵を売ってしまった。ドガと親しかった画商、ヴォラールの回想録に次のようにあります。「この絵」とはもちろん『マネとマネ夫人像』です。
マネがドガに贈り、ドガが送り返した『スモモ』は、今は所在不明です。しかし「切り裂き事件」の10年後、マネは新たなスモモの静物画を描きました。その絵は今、アメリカのテキサス州にあります。マネがもともとドガに贈った絵、ドガが「送り返さなければよかった」と悔やんだ絵もこんな感じだったと想像できます。マネは「肖像画切り裂き事件」のことを思い出しながら、この絵を描いたに違いありません。
マネがドガの絵を切り裂き、ドガはそれを取り戻し、ドガはマネの絵を送り返し、マネはそれを売り払う・・・・・・。この二人は絶交に違いない思ってしまいますが、そうではないのですね。ヴォラールの回想録にあるように、マネとドガは「より」を戻し、ふたたび交流は続きます。
前に「カンヴァスを継ぎ足した人物像」について、3つのポイントをあげましたが、4つ目を付け加えてもよいと思います。つまり、
というポイントです。
よりを戻したのは、互いに芸術家としての敬意があって、それが崩れなかったからでしょう。回想録に言葉を補うと、ドガは「ああ、(私以外に)マネと長続きできる者は、誰もいないよ。」と言っていますね。マネの芸術家としての偉大さを真に理解できるのは自分しかいないという自負に聞こえます。
マネが亡くなる3年前(1880)に再び『スモモ』描いたのも、そういった敬意の象徴のような気がします。ドガが切り取られたままの『マネとマネ夫人像』を自分の部屋に晩年まで飾っていたことも・・・・・・。
エドガー・ドガ 『マネとマネ夫人像』
2014年1月18日の『美の巨人たち』(TV東京)は、ドガの『マネとマネ夫人像』(1868/69)をテーマにしていました。ドガが35歳頃の作品です。この絵は北九州市立美術館が所蔵していますが、絵の右端が縦に切り裂かれていて、無くなった部分にカンヴァスが継ぎ足されていることで有名です。ピアノを弾いているはずのマネ夫人(シュザンヌ)のところがバッサリと切り取られています。
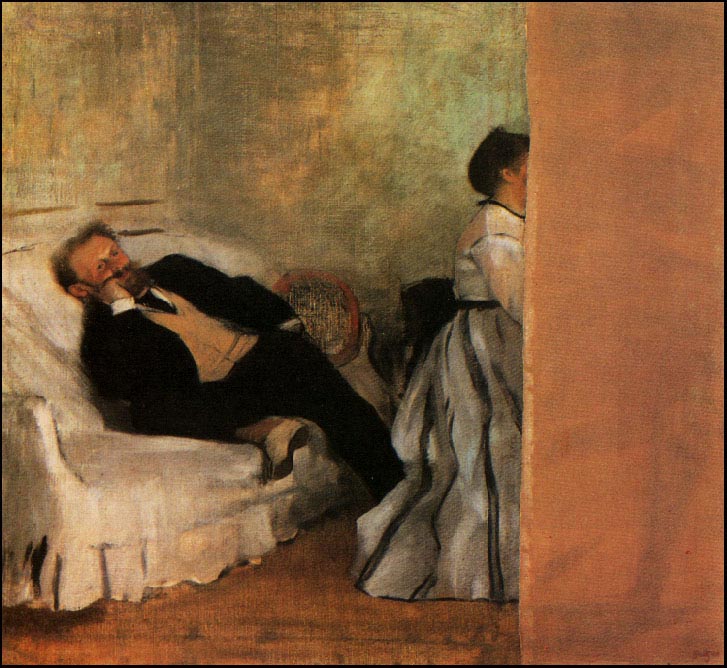
| ||
|
エドガー・ドガ
『マネとマネ夫人像』(1868/69)
(北九州市立美術館蔵)
| ||
番組で紹介されたこの絵の由来は、以下のような主旨でした。
| ① | ドガとマネは友情のあかしとして、互いに絵を描いて交換することにした。ドガがマネに贈った絵が『マネとマネ夫人像』である。 | ||
| ② | ドガがこの絵を描いた当時、マネは女性画家のベルト・モリゾと「不倫関係」にあった。 | ||
| ③ | 後日、マネの家を訪問したドガは、絵の右端が切り裂かれていることを発見し、怒ってその絵を自分の家に持ち帰った。 | ||
| ④ | 晩年のドガの家の室内写真がある。そこにはドガとともに『マネとマネ夫人像』が、切り取られたままで(カンヴァスが継ぎ足されないで)壁に飾ってあるのが写っている。つまり、この写真が撮られて以降に誰かがカンヴァスを継ぎ足した。 |
新事実は④ですね。普通、この絵にカンヴァスを継ぎ足したのはドガ自身だと言われています。絵を所蔵している北九州市立美術館のホームページにも、
| 変わり果てた自分の絵に怒ったドガはそれを取り返した。後に、夫人を復元するつもりで下塗りしたカンヴァスを継ぎ足したが、一日延ばしにしているうちに、そのままの状態になってしまった。 |
と書かれています。しかし「新事実 ④」からすると、この説明はおかしいわけです。ドガとマネが絵を交換したのはドガが35歳の頃です。ドガが切り裂かれた絵を発見したのは絵の交換のすぐあとと考えられます。ドガはマネの家をたびたび訪問したはずだから、たとえば10年もあとになってマネの家で切り裂かれた絵を発見するというのは考えにくい。そしてドガが49歳のときにマネは亡くなってしまいます。「美の巨人たち」で紹介された証拠写真は、晩年のドガの家の写真です。ドガは60歳台か、それ以降でしょう。少なくともその時点までは絵を「切り裂かれたままで」持っていた。ドガが継ぎ足したのではないと強く推定できます。
とすると、カンヴァスを継ぎ足したのは誰かということになる。その誰かとは次のような人物だと考えるのが妥当です。3つぐらいのポイントがあると思います。
| ◆ | ドガとマネが絵を交換したこと、かつ、ドガが切り裂かれた絵を持ち帰ったことを知る人物。 | ||
| ◆ | 何も描かれていないカンヴァスを継ぎ足すことによって「肖像画切り裂き事件」という、印象派を先導した2人の巨匠の芸術上のエピソードを後世に残そう考えた人物。 | ||
| ◆ | 切り裂かれたままより、あえて損傷した絵だということが一目で分かるようにした方が、絵の価値が上がることを理解できた人物。 |
の3つです。こういう人物はドガと親しかった画商でしょう。番組でもそう解説していました。画商だとすると、絵の価値を上げる意図が当然あると思いますが、印象派という「絵画の革命」に立ち会った画商としての使命感のようなものも動機かと思いました。
なぜマネは切り裂いたか:女の視点
しかしなぜマネは絵を切り取ったのでしょうか。北九州市立美術館の「公式の」解説は次です。
| マネはドガの描いた夫人の顔の歪みが気に入らず、顔のあたりから切り取ってしまった。 |
これは何となく納得性に乏しい解説です。「顔の歪みが気に入らない」と言うけれど、そんなに怒るほど、夫人を(この時点で)愛していたのだろうか。
番組では「ドガがこの絵を描いた当時、マネはベルト・モリゾと不倫関係にあった」ことを解説していました。これは有名な話ですね。不倫の程度は窺い知れませんが、単なる師弟関係以上のものがあったことは確かなようです。絵においてマネは「だらしなく」「横柄な」態度でソファに寝そべっていて「心ここにあらず」というように見える。夫人のピアノの演奏に退屈しているようでもある。これは当時の夫婦関係が冷えていたことを表していて、ドガはその夫婦の内面までを描いた・・・・・・ そういう主旨の番組の解説でした。
夫婦の隠された現実を描いてしまった、そこにマネは激怒して絵を切り取った・・・・・・という解説はありませんでしたが、そう暗示したかったのかもしれません。番組スタッフも「マネはドガの描いた夫人の顔の歪みが気に入らず、顔のあたりから切り取ってしまった。」という公式の解説に納得がいかないのでしょう。しかし、たとえ冷えた夫婦の内面を描いたからといって、夫人の顔の部分だけを切り取るという行為の説明はできないと思いました。
ところがです。番組が終わった直後、いっしょに見ていた私の妻が「絵を切り取った理由は簡単」と言ったのですね。彼女は、
| 絵を切り取った理由は簡単。マネ夫人は、自分の顔がきれいに描けていないことに怒ったのよ。そして夫に「こんな絵は絶対イヤ。切り取って」とマネに迫った。そうに決まっている。 |
と言ったのです。あなたはそんなことも分からないの、という感じで・・・・・・・。
うーん、ありうるかもと、その場では思ったのですが、あとから考えてみると、これはなかなか説得力のある説だと思えてきました。それには4つの理由があります。まず第1の理由ですが、それは
| 女性は、自分が美しく描かれているかどうかを、ものすごく気にする |
ということです。それは現代において「スナップ写真を人にあげる」ことを考えてみると分かります。たとえば、既婚のA子さんがいたとして、姉の一家(夫婦と1歳の娘)が自分の家に来たとします。記念にと、A子さんが1歳の姪を抱いている写真を何枚か撮った。それを後で姉にあげるとき、A子さんは「姪が最も可愛く写っている写真を選択しない」と思います。「自分が最もきれいに撮れている写真」を選択するはずです。「子供の写真をとるのは難しくって」とか言いながら・・・・・・・。姉としてもそれが真っ赤な嘘だとは感じながら「そうよね」と答えたりする。
それは何も姪だからというわけではありません。A子さん夫婦にも1歳の娘が一人いたとします。一家のスリー・ショットを写真年賀状にする場合、A子さんは「娘が一番可愛く写っている写真」という基準では選ばないと思います。あくまで「自分がきれいに写っているかどうか」で、まず写真を「ふるい」にかけるのではないでしょうか。その中から娘ができるだけ「まし」なのを選ぶ。
一般化するまでは出来ないでしょうが、少なくとも私が知っている女性はそうです。現代の写真を19世紀フランスの肖像画と考えると、マネ夫人も「自分がきれいに描かれているかどうか、ものすごく気にした」のではないか。そう推測します。それが第1の理由です。
第2の理由ですが、夫人に「切り取って」と迫られると、マネはしぶしぶ(ドガとの友情のことを考えながらも)そうしただろうと考えられます。なぜならマネは夫人に大きな負い目があるからです。それはまさに当時のベルト・モリゾとの「不倫関係」です。逆に夫人はマネに強気に出られる理由あるわけです。また、マネが切り取ったのではなく、怒った夫人が自ら切り取ったとも考えられる。だとしても、マネが阻止できなかったのは夫人に対する負い目だと想像できます。
第3の理由は、「切り裂き事件」があったにもかかわらずドガとマネはその後も良好な関係を続けたという歴史的事実です。絵は画家の分身のはずです。自分の作品を切り裂かれた画家は、切り裂いた画家と絶交してもおかしくはない。切り裂いた方は、絶交される覚悟でそうするはずです。画家なら、作品が芸術家にとっての分身だと分かっているからです。ところが意外にも、二人は良好な関係が続く。これはマネがドガに切り裂いた本当の理由を言ったからではないでしょうか。「ドガよ、許してくれ。本当のことは黙っておいてくれ。全部俺のせいにしておいてくれ」みたいな・・・・・・。
第4の理由ですが、「夫人がドガの描いた自分の姿に怒った」のがいかにもありうると考えられるのは、一般的に「ドガは女性を美しく描かない」からです。
女性を美しく描かない
誰だったか忘れたのですが、女性作家だったと思います。「ドガは嫌い、女性を美しく描かないから」という意味の文章を読んだことがあります。
確かにドガは女性を美しくは描きませんね。依頼されて描いたような一部の肖像画は別にして、女性の生活を描いた絵はきれいに描こうなどとは全く思っていないようです。絵の構図や人体のフォルム、瞬間を定着させることなど、そういったところにしか関心がない。踊り子の絵とか、歌手とか、働く女性とか、知り合いの家族とか、そういった作品を見れば強く感じます。
それでは、ドガは友人・マネの夫人であるシュザンヌをどう描いたのか。
それに関連して思い出す話があります。No.86「ドガとメアリー・カサット」で、ドガの友人の一人であるメアリー・カサットのことを書いたのですが、ドガがそのメアリーを描いた肖像画があります。

| ||
|
エドガー・ドガ
『メアリー・カサットの肖像』(1880/84)
(アメリカ国立肖像画美術館)
| ||
この絵を所蔵しているアメリカの国立肖像画美術館(The National Portrait Gallery, Washington D.C.)のウェブサイトの解説によると、メアリー・カサットは、この絵について次のように語ったそうです。
|
でしょうね。カードを持ったメアリーが前のめりになって、含み笑いというか「にやけた」ような表情をしています。カードの「手」がいいのでしょうか。フィラデルフィアの良家出身の女性がするポーズだとも思えない。絵が描かれた当時、彼女は30歳台の半ばです。ドガからするとメアリーは、フランスにあこがれてパリに定住した10歳下のアメリカ人女性画家であり、絵の才能を高く評価していて、アドバイスをしたりもした。自分を尊敬してくれている画家であり、友人でもあり、(芸術上の)喧嘩もするが、毎日のように会っていた時期もある(No.86「ドガとメアリー・カサット」参照)。そういう二人の関係と、この絵の表現は「落差」を感じます。メアリーは決して美人というわけではありませんが(No.86に写真を掲載)「こういう風に描くことはないでしょ!」と言いたくなる気持ちは分かります。
メアリー・カサットはこの絵をドガから贈られて持っていたが、ドガの死後すぐに売り払ったそうです(スーザン・マイヤー著「メアリー・カサット」による)。ドガが亡くなるまで(いやいやながらも)持っていたというのが、メアリー・カサットの律義なところですね。ドガは友人であり、ある意味では師匠でもあったからでしょう。また破棄せずに売ったのは、画家としての良心からだと想像します。メアリーはドガの死後にドガからもらった手紙をすべて焼き払ったのですが(No.86 参照)、さすがに絵を焼くことはできなかった。画家としては。
| しかしメアリーの「私がモデルだということを知られたくありません」という思いとは裏腹に、この絵は結局、アメリカの首都のスミソニアン博物館地区にある「国立肖像画美術館」に「ドガ作:メアリー・カサット」として収められてしまったわけです。二人とも有名アーティストだからやむをえないでしょう。 |
この絵は、ドガとメアリーの交流の中のどこかであった真実の瞬間なのだろうと思います。良家のお嬢さんがカード・ゲームをしてはいけないことはないし、ゲームでは当然、絵のような表情をすることもある。それをどう切り取って、どう絵にするかです。ドガはメアリーがみせた意外な表情としぐさをカンヴァスに定着させた。美化しようとか、女性をきれいに描こうとか、そんなことは一切思わない。それがメアリー・カサットにショックを与え、傷つけることになった。ドガにそんな意図は全くなかったはずだけれど・・・・・・。
マネ夫人もドガの絵を見てショックを受け、傷ついたのではないでしょうか。この絵が世に残るのは絶対に嫌だ。ドガに返すわけにはいかない。だからといって、夫の友人が描いた絵を破棄するのはどうか。幸いなことに、(メアリー・カサットの肖像とは違って)夫人の肖像は画面の右端にある。切り取ったとしても、絵として全く成り立たないというわけではない。じゃ、そうするしかない・・・・・・。画家であるメアリー・カサットは、ショックを受けた自分の肖像画にも「芸術的価値」を認めて、その絵を持っていたのですが、マネ夫人は画家ではありません(ピアニストです)。絵の芸術的価値よりもっと大事なことがあってもおかしくはない・・・・・・。
以上の「肖像画が切り裂かれた理由」は、全くの想像というか、推量です。本当のことは分かりません。しかし、以前にも何度か書いたように、絵を鑑賞する楽しみの一つは、そこからいろいろな想像を膨らませることです。こういう推量が許されてもいいと思います。
しかし想像とは別に、ドガの『マネとマネ夫人像』および『メアリー・カサットの肖像』を見て強く感じることがあります。それは「現実を美化・誇張しないで」「今、その時、その瞬間を描いた」と思わせる絵だということです。この2作品にかかわらず、ドガの絵にはそういう絵が多い。特に画家としての後半生の「有名な」絵はそうだと思います。
「女性を美しく描かない」のもそれと関係があるはずです。現代ではよく女性が「写真うつりが悪い」ことを気にしますね。写真が被写体をデフォルメすることはないので、要するにその女性が見せる表情の多くは(本人にとっては)写真うつりが悪い表情であり、ある時だけは写真うつりが良く見える。アマチュア写真ではその「ある時」をとらえるのが難しいということでしょう。プロの写真家はその瞬間をとらえるのにものすごく長けています。
ということは、プロの写真家と同じく、画家にとっては「どういう瞬間を描くか」が重要になってきます。たとえば『マネとマネ夫人像』のマネの姿です。ピアノに退屈し、心ここにあらず、という表情と態度に見える。ドガは「その時」を描いた。もしこれが冷えた夫婦関係を暗示したのなら(マネ夫人の表情が分からないのは残念ですが)、ドガはある瞬間を切り取ることで「現実には見えないものまで描いてしまった」ことになります。
リアリズムを突き詰めると、現実の切り取り方によって、目には見えないが画家が感じ取ったものを描いてしまう。そして結果的にリアリズムを越えてしまう。そういう感じがします。
マネがドガに贈った絵は?
ドガの『マネとマネ夫人像』は、互いの友情のしるしとしてマネとドガが絵を交換したときの、一方の絵でした。ではマネはドガにどんな絵を贈ったのか。
マネがドガに贈ったのは、スモモ(プラム)を描いた静物画でした。その絵は「切り裂き事件」のときに、ドガがマネに送り返しました。そしてマネはその絵を売ってしまった。ドガと親しかった画商、ヴォラールの回想録に次のようにあります。「この絵」とはもちろん『マネとマネ夫人像』です。
|
マネがドガに贈り、ドガが送り返した『スモモ』は、今は所在不明です。しかし「切り裂き事件」の10年後、マネは新たなスモモの静物画を描きました。その絵は今、アメリカのテキサス州にあります。マネがもともとドガに贈った絵、ドガが「送り返さなければよかった」と悔やんだ絵もこんな感じだったと想像できます。マネは「肖像画切り裂き事件」のことを思い出しながら、この絵を描いたに違いありません。

| ||
|
エドゥアール・マネ
『スモモ(The Plums)』(1880)
ヒューストン美術館(Museum of Fine Arts, Houston. Texas)所蔵。スピード感あふれる筆使いだが、新鮮なフルーツのみずみずしさが伝わってくる美しい小品。背景がほとんど塗りつぶされているのも効果的で、画題は全く違うが「笛を吹く少年」を思い起こさせる。WikiPaintings より引用。
| ||
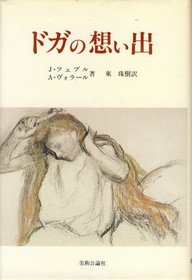
| |||
|
| |||
前に「カンヴァスを継ぎ足した人物像」について、3つのポイントをあげましたが、4つ目を付け加えてもよいと思います。つまり、
| ◆ | ドガとマネの交友関係は「肖像画切り裂き事件」では崩れなかったことを知っている人物。事件があからさまに分かるようにしても、一方的にマネがひどい人間だという世の中の評価にはならない、と確信できた人物。 |
というポイントです。
よりを戻したのは、互いに芸術家としての敬意があって、それが崩れなかったからでしょう。回想録に言葉を補うと、ドガは「ああ、(私以外に)マネと長続きできる者は、誰もいないよ。」と言っていますね。マネの芸術家としての偉大さを真に理解できるのは自分しかいないという自負に聞こえます。
マネが亡くなる3年前(1880)に再び『スモモ』描いたのも、そういった敬意の象徴のような気がします。ドガが切り取られたままの『マネとマネ夫人像』を自分の部屋に晩年まで飾っていたことも・・・・・・。
No.97 - ミレー最後の絵(続・フィラデルフィア美術館) [アート]
前回の No.96「フィラデルフィア美術館」の続きです。この美術館について、もう一回書くことにします。
フィラデルフィア美術館のような「巨大美術館」を紹介するのは難しいものです。有名アーティストの作品がたくさんあるので、いちいちあげていったらキリがありません。そこで前回はあえて「あまり有名ではない画家の作品」を取りあげ、最後に1枚だけ(超有名画家である)アンリ・ルソーの作品を紹介しました。
しかし、ちょっと考え直しました。有名アーティストの作品をあげていったらキリがないけれど、
なら何点かあげられると思ったのです。今回はその「印象に残る絵」という視点での紹介です。もちろん個人の印象です。
カサット(1844-1926)
まずフィラデルフィア出身のメアリー・カサットが「馬車で行く婦人と少女」を描いた作品です。
この絵の特徴は構図です。カメラに望遠レンズを付け、クローズアップで寄っていって撮ったような感じです。馬、馬車の下部、後部、後方の木々など、四方のすべてが「切り取られて」いる。全体の広がり感を見る人に想像させるという手法です。これは、No.87「メアリー・カサットの少女」で感想を書いた『舟遊び』に大変よく似ています。馬車に乗った人物をこういう風に描いた絵は珍しいという意味で印象に残る作品です。
この絵が印象的なのは、もう一つ理由があります。一見するとメアリー・カサットの得意な「母と子」のモチーフに見えますが、そうではありません。見ると、女性2人の表情は「こわばった」感じで、母と子の絵に一般的な「穏やかな」表情ではない。フィラデルフィア美術館の解説にもあるのですが、描かれている2人の女性は、メアリー・カサットの姉のリディアとエドガー・ドガの姪(オディル・フェーヴル)です。メアリーとドガが家族ぐるみの交際をしていたことの証拠となる絵です。
ドガの名前が出たところで、完全な余談ですが、この絵から連想するドガの絵があります。ボストン美術館にある「郊外での競馬」という絵です。肝心の競馬は遠くに小さく描かれているだけで、近景の「切り取られた」馬車が広々とした草原を的確に表現している。「馬車を使った構図の妙」という連想です。
マネ(1832-1883)
題名を意訳すると「ビールがうまい!」というのがピッタリの絵だと思います。Bockはビールの一種です。モデルはマネの友人の版画家です。
このマネの絵を見て思うのは、フランス・ハルス(1580頃-1666)の絵に似ているということです。描き方に加えて「酒を飲む、赤ら顔の男」というモチーフそのものがハルスを連想させます。フィラデルフィア美術館の解説によると、マネは1872年にオランダを訪問し、オランダの画家の絵を研究しました。その成果がこの絵というわけです。マネは、いろいろと「物議をかもす」絵も描きましたが、この絵はそういうところはありません。極めてオーソドックスな絵であり、細部の描き方や筆遣いに画家の個性が出る絵です。
No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがマドリードを訪問してベラスケスに学んだことを書きましたが、彼はハルスの弟子でもあったことが分かります。
コロー(1796-1875)
このコローの絵(アンリ氏の家と工場)は、奥の方に見える一軒の家と、その家主が所有している織物工場を描いたものです。コローというと、人物画や独特の色合いの風景画が有名ですが、工場という「近代の産物」も描いているわけです。こういったモチーフはコローの絵としては珍しいと思います。
この絵は「建物」を主題にして描かれています。建物が描かれた絵はたくさんありますが、普通、街の風景としての建物とか、田園風景の中に農家があったり教会があったり古城があったり、といった絵が多いわけです。しかしこの絵は違います。基本的に「建物だけ」を描いていて、しかも描写の中心は工場です。また、小さく描かれた人物や遠景の邸宅とあわせて、まるで「遠近法の練習」のような感じもする絵です(そんなはずはないですが)。
パリの街並みとは違って、昼下がりの工場の、無機質で冷たい感じがよく出ていると思います。「遠近法の練習」的な構図もそれにマッチしている。街でもなく田園でもない、新しい風景。画家は、こういう題材を描こうとチャレンジした、そいういう感じを受ける作品です。
ゴッホ(1853-1890)
ゴッホの『The Rain - 雨』と題された絵です。ゴッホの生涯はよく知られています。彼は南フランスのアルルにいったあと、結局、サン・レミの病院に入院することになるのですが、その時に描いた絵です。小麦畑に雨が降っています。
この絵を見て、日本人なら誰しも雨の情景を描いた歌川広重(1797-1858)の版画を思い出すに違いありません。名所江戸百景の「大はしあたけの夕立」、東海道五十三次の「庄野」「土山」などです。「大はしあたけの夕立」は、ゴッホが模写した絵が残されていることで有名です。
雨を描いた絵はターナー、クールベ、カイユボットなどの絵が思い浮かびますが、雨足を線で表現した絵は少ないはずです。この絵以外にはドガの絵(下図)があるぐらいではないでしょうか。土砂降りでもない限り、普通の雨では、雨の日の屋外を眺めても「線」は見えません。広重のような感じで雨足を線で表現するのはリアリズムではないのです。このゴッホの絵は明らかに広重の影響下にある作品と言えるでしょう。
しかしこの絵の雨の表現は、広重そのものではありません。広重の線の描き方には独特の様式性がありますが、ゴッホの線はそれとは違って、かなり「乱れて」います。たとえ強風の中の雨だったとしても、雨足がこのようにはならないはずです。これは画家のその時点における「心」の表現なのでしょう。広重流表現を取り込んで独自表現にした。そう言っていいと思います。
この作品は傑作とは言えないでしょう。しかし印象に残る作品です。特に日本人にとっては。
ミレー(1814-1875)
この記事のタイトルにもあげたように、実は次のミレーの絵が「フィラデルフィア美術館で一番印象に残る絵」です。そしてこの絵は、初めてパッと見ると何が描かれているのか分からない絵です。いったい画家は何を描いたのか。
これは「野鳩狩り」の様子です。農民たちが、夜、野鳩の群れが休んでいるところに近づき、松明を照らします。光に目が眩んだ野鳩は逃げまどい、それを二人の農民が棍棒で叩き落とす。羽を折られて地上に落ちた鳥を別の二人の農民(妻でしょう)が捕まえる。ほとんど即死の鳥もあるでしょう。それを拾う。そういった光景です。
絵の中で行われている行為は、現代の基準からすれば残酷なものです。しかし18-19世紀のフランスの農民にとって、野鳩は貴重なタンパク源だったのでしょう。想像をたくましくすると、農作物の不作で農民は飢えていて、食料を手に入れようと必死に野鳩に棍棒を振るっている・・・・・・そういう感じも受けます。農民は、ご馳走を目の前にして狂喜しているようにも見える(現代でも鳩料理は高級料理です)。
何が描かれているかが理解できたとして、この絵から受ける強い印象は、画面を覆い尽くす鳥の大群です。まるで人間が鳥の大群に襲われて、必死に逃れようと棍棒で鳥を振り払っているようにも錯覚してしまう。半世紀前の映画ですが、アルフレッド・ヒッチコック監督の『鳥』という作品(1963。鳥が人間を襲うというストーリー)がありました。
この絵は見る人にある種の「怖さ」を感じさせる絵です。また、こういった光景を体験したこともないし映像で見たこともない現代人にとっては、これは現実の光景なのかどうかという不可思議な感じも受けます。そもそも絵のタイトルが不思議です。
Bird's-Nesters
とはいったい何でしょうか。nesterとはあまり使わない単語です。これは nest(巣)に er がついていると解釈すべきでしょう。では、なぜハイフンが付いているのか・・・・・・。これは bird's nest(鳥の巣)が原型だと思います。つまり、
ということでしょう。この「採る」のところは「狩る」でもよいと思います。描かれているのがいかにも「狩り」なので、日本語に訳すとしたら「鳥の巣狩り」が適当でしょう。
鳥の巣採り・鳥の巣狩りという行為をするとしたら、その目的は巣ではなく、巣の中の卵や雛・若鳥を採ることです。しかしこの絵は飛び交う鳥(野バト)そのものを狩っている絵であり、Bird Hunters(鳥狩り人)の絵、「深夜の野鳩狩り」の絵です。推測すると、Bird's-Nesters に相当するフランス語が原題だったのではないでしょうか。フィラデルフィア美術館が「Bird Hunters」とか「Hunting Birds at Night」とかの分かりやすい題にしなかったのは、美術館としての見識だと想像します。フィラデルフィア美術館のウェブサイトには、この絵が次のように解説されています。
解説にあるように、この絵はミレー最後の作品(絶筆)です。ミレーは労働にいそしむ農民の姿を共感をもって描いた「農民画家」と見なされています。農民の絵だけを描いたわけではないが、それがミレーの代表的イメージです。それはそれで間違ってはいない。
しかしミレーは人生最後の作品で「深夜の野鳩狩り」を描いたわけです。農民の労働を描いていることには変わりないが、何となく、画家自身の心の奥底に潜む「闇」のようなものを感じます。ある種の「怖さ」と言ったらいいのでしょうか。子どもの頃の話が強烈な印象として残り、その暗いイメージがずっと潜在していて、時折りそれが脳裏をよぎる、または夢に出てくる。死期を悟った画家は、どうしてもそのイメージをカンヴァスに表現したかった・・・・・・というような。
と同時にこの絵は、動物を殺さずには生きていけない人間の悲しみを描いているようにも見えます(日本的な考えでしょうが)。また、農民に対して、その「生」の最も深いところに万感の共感を抱いて描いた絵とも考えられます。
ちょっと脇道にそれますが、この絵の「怖さ」からの連想で、中野京子さんが著書の『怖い絵』に書いていたミレーの絵の解説を思い出しました。これは、かなり手が込んだ解説です。
まず中野さんは、誰もが知っているミレーの『晩鐘』(オルセー美術館。1857-9)持ち出します。そして『晩鐘』についてのサルバトーレ・ダリの評論を紹介します。ダリいわく、
えっ、まさか、と思ってしまいますが、20世紀アートの巨匠であるダリの発言です。棺を描いた形跡があるかどうか、X線調査まで行われたようです。しかし棺は見つからなかった。それでもダリの「妄想」は変わらなかった・・・・・・という話です。
中野さんも、ダリの言うことを信じているのではありません。『晩鐘』は、ダリが怖いと言っているだけで、怖い絵ではない。しかし最低限言えることは『晩鐘』にはダリの「妄想」をかき立てる何かがあったということです。
ここまでは解説の「前振り」に過ぎません。このあと中野さんはミレーが描いた「本当に怖い絵」を持ち出します。『死と樵』という絵です。
確かにこれは怖い絵です。「行きがけの駄賃の怖さ」です。しかもこの絵が描かれた時期(1859年のサロンに出品・落選)は、『晩鐘』が描かれた時期(オルセー美術館のサイトによると1857年から59年の間)とほぼ同じなのです。ということは、ダリの「妄想」も、ひょっとしたら、と思ったりもします。
それはともかく、この絵は農民の視点からすると、単なる「怖い絵」ではなく、別の見方ができると思うのです。
「人が死ぬということは、死神が鎌を振るうことだ」と固く信じている人々がいたとします。たとえば19世紀のフランスの農民です。「人が何の前触れもなく、突然、極めて短時間のうちに死ぬ」ということがありますよね。心筋梗塞とか、くも膜下出血とか、これだけ医療が発達した現代でもあります。農作業から帰る農夫が、突然の心臓発作で倒れ、そのまま帰らぬ人となる・・・・・・。「死神信仰」を持つ人々がそういう現実に遭遇したとき、まさにこのミレーの絵と同じイメージを想像してしまうのではないでしょうか。「死神の、行きがけの駄賃で死んだ」と・・・・・・。
この絵は、勤勉に働き、しかし報われることは何もなく、あっけなく突然死をしてしまった農民(ないしは樵)を、農民のイマジネーションの視点から描いたと考えられます。
フィラデルフィア美術館のミレーの絵の話に戻ります。「死神の絵」はファンタジーですが、「深夜の野鳩狩り」はミレーの子どものころの体験であり、ファンタジーではありません。しかし両方とも、農民に対する極めて深い思い入れと共感で描かれた絵だという感じがします。
「深夜の野鳩狩り」の絵はミレーの代表作ではないし、傑作とは言えないでしょう。しかし、ミレーを語る上で欠かせない絵だと思います。古今東西、ミレーの作品に惹かれた人は多いわけです。アルルの病院で『雨』を描いたゴッホはミレーを師と仰ぎ、『種蒔く人』を模写し『種蒔く人』をモチーフに絵を数点描いたのは有名です。ダリもまさにその一人です(その「惹かれかた」が独特だけれど)。明治以降の日本の文化人もミレーが好きな人は多い。日本を代表する出版社のロゴマークにもなっています。山梨の県立美術館が多額の予算(税金)をつぎこんで『種蒔く人』を購入する ミレーだから納得されるのだと思います。
しかし「農民が労働にいそしんでます」みたいな感じだけでミレーの絵をとらえるのは違うのではないか・・・・・。「深夜の野鳩狩り」はそういう思いを抱かせる絵です。ミレーのコレクションを誇り「ミレー美術館」との別名がある山梨県立美術館も、そのあたりを是非掘り下げ、情報発信してほしいと思います。
ここからは『Bird's-Nesters』の題名についての補足です。インターネットで "Bird's-Nesters" を検索すると、ヴィクトル・ユーゴーの小説(の英訳)がヒットします。そこで、ちょっと調べてみました。
ヴィクトル・ユーゴー(1802-1885)の小説『海に働く人びと』(=『海の労働者』。原題:Les Travailleurs de la Mer。1866)の「第1部・第5編・第5章」の題名は「鳥の巣をあさる者たち」です(潮文庫。1978。山口三夫・篠原義近 訳)。この章題の英訳が「Bird's-Nesters」なのですね。原文のフランス語では「Les deniquoiseaux」(デニクワゾー)です。
ヴィクトル・ユーゴーは文学者ですが、政治家でもあり、ナポレオン3世が政権をとると、弾圧から逃れるためベルギーに渡り、イギリス海峡のジャージー島、ガーンジー島へと亡命しました。これらの島はフランスのノルマンディーの沖合いにありますが、イギリス領です。ユーゴーはガーンジー島で15年間を過ごし(1855-1870)、『レ・ミゼラブル』はそこで完成させています。このガーンジー島で書いた小説の一つが『海に働く人びと』です。
「鳥の巣をあさる者たち」という章は、ガーンジー島の3人の子供の冒険譚ですが、その子供たちが次のように説明されています。
英語訳の bird's-nesters は deniche-oiseaux の直訳ですね。もちろん海岸の断崖などで採る鳥の巣はカモメ(などの海鳥)です。これは島の子供たちの「仕事」だったと考えられます。「あさる」という訳は、子供たちの行動をよく表現していると思います。鳥の巣から卵や鳥(雛)を採るのに特別な用具はいらず、子供でもできます。断崖や岩場の危険はあるけれども。
ところで、ジャン・フランソワ・ミレーは、ヴィクトル・ユーゴーの同時代人です。そしてミレーが生まれたのは、フランス・ノルマンディー地方のイギリス海峡に面した海岸の村・グリュシー(シェルブールの西方)であり、19歳までそこで過ごしています。グリュシー村とヴィクトル・ユーゴーが亡命生活を送ったガーンジー島は、近い距離にあるのです。
ミレーが画家として名をなしたのは、もちろんバルビゾン村であり、海とは無縁の農村地帯です。しかしミレーは何度も故郷を訪問し、晩年の1871年にも訪れて海岸の絵を描いています。『グレヴィルの断崖』(大原美術館)というパステル画です。『Bird's-Nesters』を描く3年前のことです。グレヴィルはミレーの故郷・グリュシー村がある地域名です。
まとめると、Bird's-Nestersという語は「鳥の巣をあさる者」という意味(元々の意味)のようです。しかし、ミレーの絵に描かれている情景は「鳥狩り」だということに注意すべきでしょう。描かれている鳥も、フィラデルフィア美術館の解説によると鳩であり、カモメや海鳥ではありません。海岸の情景ではないのです。海岸地方であったとしても、海辺ではなく(海辺に鳩はいない)、内陸部の情景です。
ここからは全くの想像です。題名を調べて、ひょっとしたらと思ったことが2点あります。
の2点です。ガーンジー島でやることは近くのノルマンディーの海岸の村でもやるだろう、ということと、ミレーが晩年に故郷を訪問して絵を描いていることの2つからの推測です。『グレヴィルの断崖』の絵を見ていると、いかにも岩場にカモメの巣がありそうな気がします。もしこの推測が正しければ、『Bird's-Nesters』という絵は、子供時代と、この絵を描いた晩年、故郷の村とバルビゾン、生(農民)と死(鳥)を重ね合わせた、人生の総括のようなものかも知れません。
2つの推測は実証などできないでしょうが、否定もできないはずです。絵は多様な解釈が可能であり、絵を見るそれぞれの人にとって一番納得がいく解釈というのも大切だと思います。
フィラデルフィア美術館の「印象に残る絵」
以上、カサット、マネ、コロー、ゴッホ、ミレーと、5つの作品を取り上げましたが、フィラデルフィア美術館には他にも、ピカソの花瓶の花束の絵とか、クールべの美しい海岸風景とか、ロートレックのムーラン・ルージュの絵とか、印象に残る作品がいろいろあります。これらの画像はウェブサイトに公開されています。
このブログ記事をアップしてから2年後、中野京子さんは『絶筆で人間を読む』(NHK出版新書 2015)を出版し、その中でミレーの『鳥の巣狩り』を解説しました。その文章を、絵とともに引用したいと思います。
ここで、ミレー(1814-1875)の生涯を復習しておきますと、ミレーはノルマンディー地方の生まれで、生地の近くのシェルブールで絵を学びました。そしてパリに出てサロンに挑戦しますが落選を重ね、赤貧の中、生活のためにポルノまがいのヌード画を描いたこともありました。
転機となったのはバルビゾン派の画家、テオドール・ルソーと親友になったことです。そして農民画への傾倒をはじめ、バルビゾンに移住します。当初、ミレーの農民画は社会への抗議と受け取られ、保守層からの激しい反発を受けます。しかし次第に上流階級の支持も集め、絵は売れるようになり、『羊飼いの少女』はサロンで1等にもなりました。ミレーの名声は高まり、ついにはレジオン・ドヌール勲章まで授与されます。そして生涯の最後に描いたのが『鳥の巣狩り』だったのです。
そして中野さんは、本に掲載した『鳥の巣狩り』の画像に次のような注釈をつけていました。
私はこの絵をフィラデルフィア美術館で初めて知ったのですが、予備知識なしに見ても衝撃を受ける絵です。それを実際に見ることができて、本当によかったと思います。そしてこの中野さんの文章を読んで是非もう一度見たいと思いました。山梨県立美術館は、この絵をフィラデルフィアから借り受けて「大ミレー展」を開催してくれないでしょうか。一番最後にこの絵が展示してあるという展覧会を・・・・・・。

| ||
|
Philadelphia Museum of Art
East Entrance 側より
( site : press.visitphilly.com ) | ||
フィラデルフィア美術館のような「巨大美術館」を紹介するのは難しいものです。有名アーティストの作品がたくさんあるので、いちいちあげていったらキリがありません。そこで前回はあえて「あまり有名ではない画家の作品」を取りあげ、最後に1枚だけ(超有名画家である)アンリ・ルソーの作品を紹介しました。
しかし、ちょっと考え直しました。有名アーティストの作品をあげていったらキリがないけれど、
| 有名画家の、代表作とは言えないし傑作でもないけれど、印象に残る絵 |
なら何点かあげられると思ったのです。今回はその「印象に残る絵」という視点での紹介です。もちろん個人の印象です。
| なお以下に取り上げる絵画は、フィラデルフィア美術館が所蔵している作品であって、常に展示されているとは限りません。美術館は展示状況をウェブサイトで公開しています。 |
カサット(1844-1926)
まずフィラデルフィア出身のメアリー・カサットが「馬車で行く婦人と少女」を描いた作品です。

| ||
|
Mary Stevenson Cassatt 『A Woman and a Girl Driving』(1881) (89.7 x 130.5 cm) | ||
この絵の特徴は構図です。カメラに望遠レンズを付け、クローズアップで寄っていって撮ったような感じです。馬、馬車の下部、後部、後方の木々など、四方のすべてが「切り取られて」いる。全体の広がり感を見る人に想像させるという手法です。これは、No.87「メアリー・カサットの少女」で感想を書いた『舟遊び』に大変よく似ています。馬車に乗った人物をこういう風に描いた絵は珍しいという意味で印象に残る作品です。
この絵が印象的なのは、もう一つ理由があります。一見するとメアリー・カサットの得意な「母と子」のモチーフに見えますが、そうではありません。見ると、女性2人の表情は「こわばった」感じで、母と子の絵に一般的な「穏やかな」表情ではない。フィラデルフィア美術館の解説にもあるのですが、描かれている2人の女性は、メアリー・カサットの姉のリディアとエドガー・ドガの姪(オディル・フェーヴル)です。メアリーとドガが家族ぐるみの交際をしていたことの証拠となる絵です。
ドガの名前が出たところで、完全な余談ですが、この絵から連想するドガの絵があります。ボストン美術館にある「郊外での競馬」という絵です。肝心の競馬は遠くに小さく描かれているだけで、近景の「切り取られた」馬車が広々とした草原を的確に表現している。「馬車を使った構図の妙」という連想です。

| ||
|
Edgar Degas 『At the Races in the Countryside』(1869) (Museum of Fine Arts Boston) (36.5 x 55.9 cm) | ||
マネ(1832-1883)

| ||
|
Edouard Manet 『Le Bon Bock』(1873) (94.6 x 83.3 cm) | ||
題名を意訳すると「ビールがうまい!」というのがピッタリの絵だと思います。Bockはビールの一種です。モデルはマネの友人の版画家です。
このマネの絵を見て思うのは、フランス・ハルス(1580頃-1666)の絵に似ているということです。描き方に加えて「酒を飲む、赤ら顔の男」というモチーフそのものがハルスを連想させます。フィラデルフィア美術館の解説によると、マネは1872年にオランダを訪問し、オランダの画家の絵を研究しました。その成果がこの絵というわけです。マネは、いろいろと「物議をかもす」絵も描きましたが、この絵はそういうところはありません。極めてオーソドックスな絵であり、細部の描き方や筆遣いに画家の個性が出る絵です。
No.36「ベラスケスへのオマージュ」で、マネがマドリードを訪問してベラスケスに学んだことを書きましたが、彼はハルスの弟子でもあったことが分かります。
コロー(1796-1875)

| ||
|
Jean-Baptiste-Camille Corot 『House and Factory of Monsieur Henry』(1833) (81.4 x 100.3 cm) | ||
このコローの絵(アンリ氏の家と工場)は、奥の方に見える一軒の家と、その家主が所有している織物工場を描いたものです。コローというと、人物画や独特の色合いの風景画が有名ですが、工場という「近代の産物」も描いているわけです。こういったモチーフはコローの絵としては珍しいと思います。
この絵は「建物」を主題にして描かれています。建物が描かれた絵はたくさんありますが、普通、街の風景としての建物とか、田園風景の中に農家があったり教会があったり古城があったり、といった絵が多いわけです。しかしこの絵は違います。基本的に「建物だけ」を描いていて、しかも描写の中心は工場です。また、小さく描かれた人物や遠景の邸宅とあわせて、まるで「遠近法の練習」のような感じもする絵です(そんなはずはないですが)。
パリの街並みとは違って、昼下がりの工場の、無機質で冷たい感じがよく出ていると思います。「遠近法の練習」的な構図もそれにマッチしている。街でもなく田園でもない、新しい風景。画家は、こういう題材を描こうとチャレンジした、そいういう感じを受ける作品です。
ゴッホ
ゴッホの『The Rain - 雨』と題された絵です。ゴッホの生涯はよく知られています。彼は南フランスのアルルにいったあと、結局、サン・レミの病院に入院することになるのですが、その時に描いた絵です。小麦畑に雨が降っています。

| ||
|
Vincent van Gogh(1853-1890) 『Rain』(1889) (73.3 x 92.4 cm) | ||
この絵を見て、日本人なら誰しも雨の情景を描いた歌川広重(1797-1858)の版画を思い出すに違いありません。名所江戸百景の「大はしあたけの夕立」、東海道五十三次の「庄野」「土山」などです。「大はしあたけの夕立」は、ゴッホが模写した絵が残されていることで有名です。

『大はしあたけの (名所江戸百景) |

『庄野宿』 (東海道五十三次) | |

『土山宿』 (東海道五十三次) |
雨を描いた絵はターナー、クールベ、カイユボットなどの絵が思い浮かびますが、雨足を線で表現した絵は少ないはずです。この絵以外にはドガの絵(下図)があるぐらいではないでしょうか。土砂降りでもない限り、普通の雨では、雨の日の屋外を眺めても「線」は見えません。広重のような感じで雨足を線で表現するのはリアリズムではないのです。このゴッホの絵は明らかに広重の影響下にある作品と言えるでしょう。
しかしこの絵の雨の表現は、広重そのものではありません。広重の線の描き方には独特の様式性がありますが、ゴッホの線はそれとは違って、かなり「乱れて」います。たとえ強風の中の雨だったとしても、雨足がこのようにはならないはずです。これは画家のその時点における「心」の表現なのでしょう。広重流表現を取り込んで独自表現にした。そう言っていいと思います。
この作品は傑作とは言えないでしょう。しかし印象に残る作品です。特に日本人にとっては。

| ||
|
エドガー・ドガ 「雨の中の騎手」(1880/81)
「Jockeys in the Rain」
Kelvingrove Art Gallery and Museum(Glasgow) ( site : www.wga.hu )
このドガのパステル画も雨を線で表現している。そういえば、ドガもまたゴッホと同様に浮世絵のファンであった。No.86「ドガとメアリー・カサット」参照。
| ||
ミレー(1814-1875)
この記事のタイトルにもあげたように、実は次のミレーの絵が「フィラデルフィア美術館で一番印象に残る絵」です。そしてこの絵は、初めてパッと見ると何が描かれているのか分からない絵です。いったい画家は何を描いたのか。

| ||
|
Jean-Francois Millet 『Bird's-Nesters』(1874) (73.7 x 92.7 cm) | ||
これは「野鳩狩り」の様子です。農民たちが、夜、野鳩の群れが休んでいるところに近づき、松明を照らします。光に目が眩んだ野鳩は逃げまどい、それを二人の農民が棍棒で叩き落とす。羽を折られて地上に落ちた鳥を別の二人の農民(妻でしょう)が捕まえる。ほとんど即死の鳥もあるでしょう。それを拾う。そういった光景です。
絵の中で行われている行為は、現代の基準からすれば残酷なものです。しかし18-19世紀のフランスの農民にとって、野鳩は貴重なタンパク源だったのでしょう。想像をたくましくすると、農作物の不作で農民は飢えていて、食料を手に入れようと必死に野鳩に棍棒を振るっている・・・・・・そういう感じも受けます。農民は、ご馳走を目の前にして狂喜しているようにも見える(現代でも鳩料理は高級料理です)。
何が描かれているかが理解できたとして、この絵から受ける強い印象は、画面を覆い尽くす鳥の大群です。まるで人間が鳥の大群に襲われて、必死に逃れようと棍棒で鳥を振り払っているようにも錯覚してしまう。半世紀前の映画ですが、アルフレッド・ヒッチコック監督の『鳥』という作品(1963。鳥が人間を襲うというストーリー)がありました。
この絵は見る人にある種の「怖さ」を感じさせる絵です。また、こういった光景を体験したこともないし映像で見たこともない現代人にとっては、これは現実の光景なのかどうかという不可思議な感じも受けます。そもそも絵のタイトルが不思議です。
Bird's-Nesters
とはいったい何でしょうか。nesterとはあまり使わない単語です。これは nest(巣)に er がついていると解釈すべきでしょう。では、なぜハイフンが付いているのか・・・・・・。これは bird's nest(鳥の巣)が原型だと思います。つまり、
| bird's nest | 鳥の巣 | |
| bird's-nest | 鳥の巣(一語) | |
| bird's-nest | 鳥の巣を採る(動詞) | |
| bird's-nester | 鳥の巣を採る人 | |
| bird's-nesters | 鳥の巣を採る人(複数形) |
ということでしょう。この「採る」のところは「狩る」でもよいと思います。描かれているのがいかにも「狩り」なので、日本語に訳すとしたら「鳥の巣狩り」が適当でしょう。
鳥の巣採り・鳥の巣狩りという行為をするとしたら、その目的は巣ではなく、巣の中の卵や雛・若鳥を採ることです。しかしこの絵は飛び交う鳥(野バト)そのものを狩っている絵であり、Bird Hunters(鳥狩り人)の絵、「深夜の野鳩狩り」の絵です。推測すると、Bird's-Nesters に相当するフランス語が原題だったのではないでしょうか。フィラデルフィア美術館が「Bird Hunters」とか「Hunting Birds at Night」とかの分かりやすい題にしなかったのは、美術館としての見識だと想像します。フィラデルフィア美術館のウェブサイトには、この絵が次のように解説されています。
|
解説にあるように、この絵はミレー最後の作品(絶筆)です。ミレーは労働にいそしむ農民の姿を共感をもって描いた「農民画家」と見なされています。農民の絵だけを描いたわけではないが、それがミレーの代表的イメージです。それはそれで間違ってはいない。
しかしミレーは人生最後の作品で「深夜の野鳩狩り」を描いたわけです。農民の労働を描いていることには変わりないが、何となく、画家自身の心の奥底に潜む「闇」のようなものを感じます。ある種の「怖さ」と言ったらいいのでしょうか。子どもの頃の話が強烈な印象として残り、その暗いイメージがずっと潜在していて、時折りそれが脳裏をよぎる、または夢に出てくる。死期を悟った画家は、どうしてもそのイメージをカンヴァスに表現したかった・・・・・・というような。
と同時にこの絵は、動物を殺さずには生きていけない人間の悲しみを描いているようにも見えます(日本的な考えでしょうが)。また、農民に対して、その「生」の最も深いところに万感の共感を抱いて描いた絵とも考えられます。

| |||
|
ミレー『晩鐘』(1857/9) (オルセー美術館) | |||
まず中野さんは、誰もが知っているミレーの『晩鐘』(オルセー美術館。1857-9)持ち出します。そして『晩鐘』についてのサルバトーレ・ダリの評論を紹介します。ダリいわく、
| 「 | 女の足元におかれた手籠は不自然である。最初は彼らの子どもを入れた小さな棺を描いたのではないか。つまりこれは一日の終わりの感謝の祈りではなく、亡き子を土に埋めた後、母は祈り、父は泣いている情景だった。ところがミレーは気が変わったか、誰かに忠告されたかで、最終的にこういう絵になった・・・・・・。」 |
えっ、まさか、と思ってしまいますが、20世紀アートの巨匠であるダリの発言です。棺を描いた形跡があるかどうか、X線調査まで行われたようです。しかし棺は見つからなかった。それでもダリの「妄想」は変わらなかった・・・・・・という話です。
中野さんも、ダリの言うことを信じているのではありません。『晩鐘』は、ダリが怖いと言っているだけで、怖い絵ではない。しかし最低限言えることは『晩鐘』にはダリの「妄想」をかき立てる何かがあったということです。
ここまでは解説の「前振り」に過ぎません。このあと中野さんはミレーが描いた「本当に怖い絵」を持ち出します。『死と樵』という絵です。

| ||
|
ミレー『死と樵』(1859) ニイ・カールスベルグ・グリプトテク美術館 (コペンハーゲン:Ny Carlsberg Glyptotek) (77 x 100 cm) | ||
|
確かにこれは怖い絵です。「行きがけの駄賃の怖さ」です。しかもこの絵が描かれた時期(1859年のサロンに出品・落選)は、『晩鐘』が描かれた時期(オルセー美術館のサイトによると1857年から59年の間)とほぼ同じなのです。ということは、ダリの「妄想」も、ひょっとしたら、と思ったりもします。
それはともかく、この絵は農民の視点からすると、単なる「怖い絵」ではなく、別の見方ができると思うのです。
「人が死ぬということは、死神が鎌を振るうことだ」と固く信じている人々がいたとします。たとえば19世紀のフランスの農民です。「人が何の前触れもなく、突然、極めて短時間のうちに死ぬ」ということがありますよね。心筋梗塞とか、くも膜下出血とか、これだけ医療が発達した現代でもあります。農作業から帰る農夫が、突然の心臓発作で倒れ、そのまま帰らぬ人となる・・・・・・。「死神信仰」を持つ人々がそういう現実に遭遇したとき、まさにこのミレーの絵と同じイメージを想像してしまうのではないでしょうか。「死神の、行きがけの駄賃で死んだ」と・・・・・・。
この絵は、勤勉に働き、しかし報われることは何もなく、あっけなく突然死をしてしまった農民(ないしは樵)を、農民のイマジネーションの視点から描いたと考えられます。
フィラデルフィア美術館のミレーの絵の話に戻ります。「死神の絵」はファンタジーですが、「深夜の野鳩狩り」はミレーの子どものころの体験であり、ファンタジーではありません。しかし両方とも、農民に対する極めて深い思い入れと共感で描かれた絵だという感じがします。
「深夜の野鳩狩り」の絵はミレーの代表作ではないし、傑作とは言えないでしょう。しかし、ミレーを語る上で欠かせない絵だと思います。古今東西、ミレーの作品に惹かれた人は多いわけです。アルルの病院で『雨』を描いたゴッホはミレーを師と仰ぎ、『種蒔く人』を模写し『種蒔く人』をモチーフに絵を数点描いたのは有名です。ダリもまさにその一人です(その「惹かれかた」が独特だけれど)。明治以降の日本の文化人もミレーが好きな人は多い。日本を代表する出版社のロゴマークにもなっています。山梨の県立美術館が多額の予算(税金)をつぎこんで『種蒔く人』を購入する
しかし「農民が労働にいそしんでます」みたいな感じだけでミレーの絵をとらえるのは違うのではないか・・・・・。「深夜の野鳩狩り」はそういう思いを抱かせる絵です。ミレーのコレクションを誇り「ミレー美術館」との別名がある山梨県立美術館も、そのあたりを是非掘り下げ、情報発信してほしいと思います。
| Bird's-Nesters とは |
ここからは『Bird's-Nesters』の題名についての補足です。インターネットで "Bird's-Nesters" を検索すると、ヴィクトル・ユーゴーの小説(の英訳)がヒットします。そこで、ちょっと調べてみました。

| |||
|
ヴィクトル・ユーゴー 『海に働く人びと』 (潮出版社) | |||
ヴィクトル・ユーゴーは文学者ですが、政治家でもあり、ナポレオン3世が政権をとると、弾圧から逃れるためベルギーに渡り、イギリス海峡のジャージー島、ガーンジー島へと亡命しました。これらの島はフランスのノルマンディーの沖合いにありますが、イギリス領です。ユーゴーはガーンジー島で15年間を過ごし(1855-1870)、『レ・ミゼラブル』はそこで完成させています。このガーンジー島で書いた小説の一つが『海に働く人びと』です。
「鳥の巣をあさる者たち」という章は、ガーンジー島の3人の子供の冒険譚ですが、その子供たちが次のように説明されています。
|
英語訳の bird's-nesters は deniche-oiseaux の直訳ですね。もちろん海岸の断崖などで採る鳥の巣はカモメ(などの海鳥)です。これは島の子供たちの「仕事」だったと考えられます。「あさる」という訳は、子供たちの行動をよく表現していると思います。鳥の巣から卵や鳥(雛)を採るのに特別な用具はいらず、子供でもできます。断崖や岩場の危険はあるけれども。
ところで、ジャン・フランソワ・ミレーは、ヴィクトル・ユーゴーの同時代人です。そしてミレーが生まれたのは、フランス・ノルマンディー地方のイギリス海峡に面した海岸の村・グリュシー(シェルブールの西方)であり、19歳までそこで過ごしています。グリュシー村とヴィクトル・ユーゴーが亡命生活を送ったガーンジー島は、近い距離にあるのです。
ミレーが画家として名をなしたのは、もちろんバルビゾン村であり、海とは無縁の農村地帯です。しかしミレーは何度も故郷を訪問し、晩年の1871年にも訪れて海岸の絵を描いています。『グレヴィルの断崖』(大原美術館)というパステル画です。『Bird's-Nesters』を描く3年前のことです。グレヴィルはミレーの故郷・グリュシー村がある地域名です。

| ||
|
ミレー『グレヴィルの断崖』 (1871。大原美術館) | ||
まとめると、Bird's-Nestersという語は「鳥の巣をあさる者」という意味(元々の意味)のようです。しかし、ミレーの絵に描かれている情景は「鳥狩り」だということに注意すべきでしょう。描かれている鳥も、フィラデルフィア美術館の解説によると鳩であり、カモメや海鳥ではありません。海岸の情景ではないのです。海岸地方であったとしても、海辺ではなく(海辺に鳩はいない)、内陸部の情景です。
ここからは全くの想像です。題名を調べて、ひょっとしたらと思ったことが2点あります。
| ◆ | ミレーは子供ころ、故郷のノルマンディーの海岸で「鳥の巣あさり」をしたことがある。つまり、彼自身がデニクワゾーだった。 | |
| ◆ | 『Bird's-Nesters』の絵の中の bird's-nesters(=農民の姿) は、自分自身の投影である。 |
の2点です。ガーンジー島でやることは近くのノルマンディーの海岸の村でもやるだろう、ということと、ミレーが晩年に故郷を訪問して絵を描いていることの2つからの推測です。『グレヴィルの断崖』の絵を見ていると、いかにも岩場にカモメの巣がありそうな気がします。もしこの推測が正しければ、『Bird's-Nesters』という絵は、子供時代と、この絵を描いた晩年、故郷の村とバルビゾン、生(農民)と死(鳥)を重ね合わせた、人生の総括のようなものかも知れません。
2つの推測は実証などできないでしょうが、否定もできないはずです。絵は多様な解釈が可能であり、絵を見るそれぞれの人にとって一番納得がいく解釈というのも大切だと思います。
フィラデルフィア美術館の「印象に残る絵」
以上、カサット、マネ、コロー、ゴッホ、ミレーと、5つの作品を取り上げましたが、フィラデルフィア美術館には他にも、ピカソの花瓶の花束の絵とか、クールべの美しい海岸風景とか、ロートレックのムーラン・ルージュの絵とか、印象に残る作品がいろいろあります。これらの画像はウェブサイトに公開されています。

| ||
|
Philadelphia Museum of Art
West Entrance 側より
( site : press.visitphilly.com ) | ||
| 補記 |
このブログ記事をアップしてから2年後、中野京子さんは『絶筆で人間を読む』(NHK出版新書 2015)を出版し、その中でミレーの『鳥の巣狩り』を解説しました。その文章を、絵とともに引用したいと思います。
ここで、ミレー(1814-1875)の生涯を復習しておきますと、ミレーはノルマンディー地方の生まれで、生地の近くのシェルブールで絵を学びました。そしてパリに出てサロンに挑戦しますが落選を重ね、赤貧の中、生活のためにポルノまがいのヌード画を描いたこともありました。
転機となったのはバルビゾン派の画家、テオドール・ルソーと親友になったことです。そして農民画への傾倒をはじめ、バルビゾンに移住します。当初、ミレーの農民画は社会への抗議と受け取られ、保守層からの激しい反発を受けます。しかし次第に上流階級の支持も集め、絵は売れるようになり、『羊飼いの少女』はサロンで1等にもなりました。ミレーの名声は高まり、ついにはレジオン・ドヌール勲章まで授与されます。そして生涯の最後に描いたのが『鳥の巣狩り』だったのです。

| ||
|
ジャン=フランソワ・ミレー 『鳥の巣狩り』(1874) (73.7 x 92.7 cm) | ||
|
そして中野さんは、本に掲載した『鳥の巣狩り』の画像に次のような注釈をつけていました。
| ◆ | 松明がぎらつく。鳩の動きにつれて、明かりまでが乱舞するようだ。 | ||
| ◆ | 棍棒を振り回す男たちは、ちょうど正面と背面、合わせ鏡になっている。 | ||
| ◆ | 鳩を集める男女の、地べたを這うごとき動きも、棍棒の男たちと同じ興奮が感じられる。 | ||
| ◆ | 凄まじい羽ばたきの音、啼き声、血しぶき、死の臭いが伝わってくる異様な作品。これまでのミレーをくつがえす驚きに満ちる。 |
私はこの絵をフィラデルフィア美術館で初めて知ったのですが、予備知識なしに見ても衝撃を受ける絵です。それを実際に見ることができて、本当によかったと思います。そしてこの中野さんの文章を読んで是非もう一度見たいと思いました。山梨県立美術館は、この絵をフィラデルフィアから借り受けて「大ミレー展」を開催してくれないでしょうか。一番最後にこの絵が展示してあるという展覧会を・・・・・・。
No.96 - フィラデルフィア美術館 [アート]
フィラデルフィア美術館
前回の No.95「バーンズ・コレクション」の続きです。バーンズ・コレクションから歩いて行ける「フィラデルフィア美術館(Philadelphia Museum of Art)」について書きます。

| ||
|
Philadelphia Museum of Art ( site : www.visitphilly.com ) | ||
フィラデルフィア美術館は、所蔵点数も多い全米屈指の「大美術館」です。3階建ての2階と3階が展示スペースになっていて、それぞれ約100の展示室があります。西洋美術では中世から現代アートまでがあり、また東洋・アジアの美術もある。江戸期の日本画も所蔵されているし、館内には日本の茶室まで造営されています。ちゃんと見るには1日がかり(でも時間がないほど)です。
しかも近くには別館があり、さらにバーンズ・コレクションとの間にはロダン美術館があって、この3つのミュージアムが共同運営されています。つまりフィラデルフィア美術館のチケットで3館に入場でき、チケットは2日間有効です。2日がかりで見学しなさいということでしょう。良心的なやり方だと思います。
しかし我々は前回に書いたように「ニューヨークからの日帰り」を前提にしているので「フィラデルフィア美術館の見どころ」だけに話を絞ります。バーンズ・コレクションと同じジャンルである「19世紀のヨーロッパ美術」と「アメリカ美術」です。
| ちなみに、フィラデルフィアはアメリカ独立宣言が起草され採択された都市ですが、シルヴェスター・スタローンの出世作となった映画『ロッキー』(1976)の舞台ともなった町です。フィラデルフィア美術館の正面の大階段で映画のロケが行われました。この階段(ロッキー・ステップと言うそうです)を駆けあがって両手を上にあげたポーズをする地元住民や観光客を見かけます。大階段の下には「ロッキーの像」もあります。 |
| もう一つ、補足です。バーンズ・コレクションとフィラデルフィア美術館の間に位置するロダン美術館は、フランス国外では最大のロダン作品の所蔵を誇るところです。 |

| ||
|
2階の展示エリアに続く大階段の上に、ローマ神話の狩りの女神・ディアナ(ダイアナ)の像がある。
( site : press.visitphilly.com )
| ||
19世紀のヨーロッパ美術
この美術館のみどころは、やはり2階(1st Floor)の「Europian Art 1850-1900」と題されたウィングに展示されているヨーロッパの近代アートです。よく知られている画家だけをあげても、
(英)ターナー、コンスタブル、ゲインズバラ、(仏)アングル、ドラクロア、マネ、コロー、セザンヌ(「大水浴図」がある!)、ルノアール、ミレー、クールベ、ドガ、スーラ、アンリ・ルソー、モネ、ロートレック、ピサロ、シスレー、(他)ピカソ、ダリ、ゴッホ(「向日葵」がある!)、モディリアーニ、クレー、カサット(ヨーロッパに分類)
など、メジャーな画家の作品がそろっています(上記の一部はモダンアートのウイングにある)。

| |||
|
ゴッホ「ひまわり」
「花瓶のひまわりの束」という構図の絵は6枚が現存している。美術館が所蔵しているのは5作品で、その所在は、東京、ロンドン、アムステルダム、ミュンヘン、そしてフィラデルフィア美術館。
(site : withart.visitphilly.com)
| |||
あまり見かけない良い絵があるということでは、バーンズ・コレクションと似ています。フィラデルフィア美術館がコレクションを形成してきた態度というか、見る目の確かさを感じます。フィラデルフィアへの日帰りの旅は、そいういう意味でも「発見の旅」になること請け合いです。
作品の画像は公式のウェブサイトに公開されているので、代表的な作品の紹介は割愛したいと思います。そのかわりではないですが、ここでは「日本ではあまり知られていないと思われる画家、なしは作品」を3つ書きます。
3人の画家の3つの作品
以降は、フィラデルフィア美術館が所蔵する19世紀ヨーロッパの3人の画家の作品です。この3人は1840年代に生まれ、ほぼ同時代に画家として活躍した人です。しかも出身国は、オーストリア、イタリア、ノルウェーと、ちょっと異色です。
| Edward Charlemont |
エドアルト・シャールモントの『The Moorish Chief』(1878)と題された作品です。「ムーア人のチーフ」ですね。フィラデルフィア美術館の解説によると、この絵は最初「ハーレムのガード」と呼ばれ、次に「アルハンブラのガード」になり、そして「ムーア人のチーフ」となったようです。また、描かれている建物はアルハンブラ宮殿のある部分に似ているそうです。
とにかく、画家がイスラム文化圏のどこか(北アフリカ、オスマン・トルコ帝国、など)かで目にした光景にもとづくものだと想像されます。複数のスケッチを合体させているとも考えられる。「イスラム系王国の宮廷の後宮の警備隊長」という、ヨーロッパ人からすると「異国趣味」の絵です。
しかしこの絵の、剣を抜き、自信たっぷりで、屈強そのものの雰囲気で立ちはだかっている「警備隊長」の迫真性は相当なものです。白い衣装と、アフリカ系の褐色の肌の対比が強烈です。

| ||
|
Eduard Charlemont 『The Moorish Chief』(1878) (150.2 x 97.8 cm) | ||
実はこの絵は、美術館の「マップ」に出ています。「マップ」とは、建物の平面図と展示室を図示し、トイレや階段やカフェがどこにあるかを示した小冊子です(よくあるやつです)。このマップの2階(1st Floor)「Europian Art 1850-1900」のウイングのところに写真が紹介されている作品が、セザンヌの「大水浴図」とともに、この作品なのです。アフリカ系アメリカ人への配慮という要素があるのかもしれまんせんが、「フィラデルフィア美術館の顔」の一つとなっている絵であることがうかがえます。
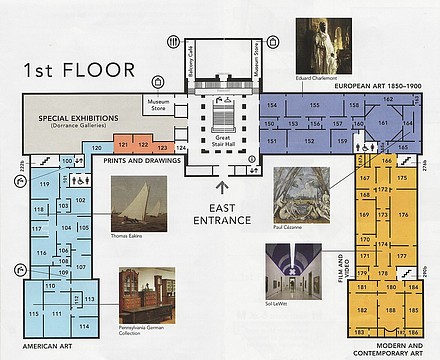
| ||
|
フィラデルフィア美術館 1st Floor
このMAPの右上のウイングに、セザンヌの『大水浴図』とともに『The Moorish Chief』の展示位置が示されている。
| ||
| Giovanni Boldini(1842-1931):イタリア |

| |||
| ヴェルディの肖像(ローマ国立近代美術館) | |||
ボルディーニはイタリアで生まれ、パリで活躍した画家で、まず肖像画家として有名です。19世紀における肖像画ではサージェントが有名ですが、ボルディーニの画風はサージェントと大変よく似ています。いや、ボルディーニの方が14歳年上なので、サージェントがボルディーニに似ていると言うべきでしょう。クラシック音楽が好きな人なら、オペラ作曲家・ヴェルディの肖像画を何度も見たことがあると思いますが、この絵がボルディーニの作です。またボルディーニはパリの市民生活を描いた風俗画も描いています。2013年に日本で開催されたクラーク・コレクション展では、『道を渡る』『かぎ針編みをする若い女』という2作品が展示されました。
ちなみにボルディーニはドガの親友ですね(ドガが8歳年上)。1889年、ドガが55歳の時、ボルディーニといっしょにスペインとモロッコに旅行しています。

| ||
|
Giovanni Boldini 『Highway of Combes-la-Ville』(1873) (69.2 x 101.4 cm) | ||
フィラデルフィア美術館のこの作品は、肖像画や風俗画とはうってかわった「風景画」です。Combes-la-ville(コン・ラ・ヴィル)はパリ郊外の村です。『コン・ラ・ヴィルの大通り』という感じでしょうか。Highwayなので、公道とか幹線道路とか大通りというニュアンスですね。
この作品の特徴を一言で言うと「あたりに充満する光」を描いたことです。屋外の光を描くのは印象派画家の十八番です。筆触分割の描き方で、物体に当たって跳ね返る光の煌めきや移ろいを描写しました。しかしこの作品は、特別な絵画手法によるのではなく、伝統的なリアリズムの手法で「充満する光」が描かれています。決して逆光とか目映いという表現ではないのですが、かなり強い光を感じる。もちろん光は見えないので物体からの反射光で表すのですが、構図、コントラスト、色使いのすべてに渡る微妙な絵画技術の結果だと思います。
また同時に「空気感」を感じる絵です。それは日本とはだいぶ違って「湿度20%の真夏の日」というか、「女性の肌には悪いような空気感」が表現されていると感じます。いい絵だと思います。
| Frits Thaulow(1847-1906):ノルウェー |
フリッツ・タウロヴの『Water Mill』(1892)という作品で、水車小屋を描いています。画家の名前ですが、ノルウェー語の W はドイツ語と同じく V の発音なので、原音重視の原則に従って、読み方は TAULOV(タウロヴ)です。本国のノルウェーとパリで活躍した画家です(フランス風にトーロウと言われることもある)。ちなみに、タウロヴの母親はムンク一族の出身で、画家のエドヴァルド・ムンクとは親戚筋です。タウロヴはムンクの才能を早くから認め、フランスなどへの美術研修旅行の資金を提供したそうです。

| ||
|
Frits Thaulow 『Water Mill』(1892) (81.3 x 121 cm) | ||
この作品のポイントは「水そのものを描いた」と感じさせる点です。一般に戸外で描かれた川、池、湖の絵は、水の表面しか描きませんね。地上のモノが反射しているとか、太陽で水面がきらめいているとか、冬に氷が浮かんでいるとか、睡蓮が咲いているとか、さざ波がたっているとか、そういった「水の表面現象を描く」わけです。
しかし水(川、池、湖)には水底があり、底には藻と水草があり、深さがあります。また水も一般には半透明であり(程度の差はあるが)、さらに水中と水面を含めた水流がある。もちろん底まで全部が見通せるわけではないが、それらのモノの総体としての水があるわけです。
この絵は「水の表面現象」だけなく「深さ感と流れを含めた、水の総体を描いた」と強く感じさせる絵です。水車の作用で水は不規則に動き、流れています。緑で描かれたのは藻か水草の反映か、それとも深さゆえの緑なのか・・・・・・。これもいい絵だと思います。
ちなみに、オルセー美術館にはタウロヴが同時期に描いた別の作品があります。ノルウェーの冬の工場を描いたパステル画ですが、ほとんど単色のような色使いで、雪と水(と氷)を描写した美しい作品です。

| ||
|
Frits Thaulow 『Une fabrique sous la neige en Norvège』(1892) (ノルウェーの雪の中の工場) (63 x 95 cm) | ||
美術館の「レベル」を評価するとしたら、一つは「有名ではない画家の絵で、どれだけいい絵がそろっているか」でしょう。セザンヌを購入するのはタイミングとお金の問題で、両方が満たされば誰も反対はしません。寄付したいという人が現れたら、美術館は大喜びで受け付けるでしょう。所蔵するセザンヌをあえて展示しないという美術館も考えられない。
しかし「マイナーな画家」については、何を購入し、何を展示するかは美術館の見識の問題です。画家の認知度は関係なく「その絵だけ」が勝負なのだから・・・・・・。紹介した3つの作品は、この美術館のレベルの高さを物語っていると感じます。
アメリカの近代絵画
「Europian Art 1850-1900」の次は、同じ2階の「American Art」ウイング(マップ参照)です。ここはアメリカの美術館なので、このウイングは是非とも訪れたいところです。バーンズ・コレクションのグラッケンズ、プレンダーガストもそうですが、我々日本人があまり知らないような作品に出会える可能性も大です。
No.86「ドガとメアリー・カサット」および No.87「メアリー・カサットの少女」で書いたメアリー・カサットは、フィラデルフィア出身の画家でした(生まれはピッツバーグ)。彼女はフィラデルフィアのペンシルヴァニア美術アカデミーに学んだ人です。彼女の作品もフィラデルフィア美術館に所蔵されています。
しかし彼女はパリに定住し、パリで活躍した画家です。その彼女と全く同じ年にフィラデルフィアで生まれ、フィラデルフィアで活躍した画家がいます。トーマス・エイキンズです。
| Thomas Eakins |
トーマス・エイキンズは1844年に生まれ、ペンシルヴァニア美術アカデミーに学び、パリに渡ってジェロームのレッスンをうけました。ここまではメアリー・カサットと全く同じです。しかし彼はパリで絵の修行をしたあとフィラデルフィアに戻り、美術アカデミーの教師にもなり、また画家・彫刻家として活躍した人です。アメリカ近代絵画の父と言われることがあるのは、そういった彼の経歴からくるのでしょう。
フィラデルフィア美術館は、相当数のエイキンズ作品を所蔵しているようです。また展示数も多い。地元の画家ということもあるのでしょう。その中から「マップ」にものっている絵を掲げておきます。「セイリング」という、いかにもアメリカ文化らしい光景です。

| ||
|
Thomas Eakins 『Sailboats Racing on the Delaware』(1874) (61 x 91.4 cm) | ||
| John Singer Sargent(1856-1925) |
もう一作品だけ「American Art」からです。No.36「ベラスケスへのオマージュ」で書いたサージェントはアメリカ人ですが、フィレンツェで生まれ、ロンドンやパリで活躍した人です。フィラデルフィア美術館はサージェントの絵も何点か所蔵していますが、ここではちょっとめずらしい絵を引用します。

| ||
|
John Singer Sargent(1856-1925) 『A Waterfall』(1910) (113 x 72.4 cm) | ||
滝は、日本画では頻繁に現れるモチーフです。これは、急峻な山と人間の居住地域が近接しているという環境条件がまずあって、さらに滝が信仰の対象にもなってきたからでしょう。
これと比較して、欧米の絵画で滝をモチーフとしたものはあまりないと思います。著名な画家では、ターナー、クールベぐらいでしょうか(他にもあるかもれません)。これはやはり自然環境の違いがあると思います。
サージェントは、ターナーやクールベと違って肖像画家として出発しました。風景画も描いていますが、この絵のような「自然そのものの絵」はめずらしいと思います。フィラデルフィア美術館の解説によると、サージェントがイタリア・スイスに旅行した時に見たアルプスの氷河から流れ出る滝を描いたようです。水けむりと濡れた岩の描写が美しい作品です。
アンリ・ルソー
もう一度「Europian Art 1850-1900」のウイングに戻ります。メジャーな画家の作品をいちいち紹介することはしない、と前に書きましたが、一点だけ掲げておきます。No.72「楽園のカンヴァス」、No.94「貴婦人・虎・うさぎ」でアンリ・ルソーの絵を引用しましたが、そのルソーが描いた『Carnival Evening』(カーニバルの夜、ないしは夕べ)です。

| ||
|
Henri Rousseau 『Carnival Evening』(1886) (117.3 x 89.5 cm) | ||
この絵は、カーニバルが終わったあと、夕べを家へと帰る男女を描いた絵と解釈するのが最もふさわしいでしょう。ルソー作品の多くがそうであるように、これは現実の光景ではありません。幻想の光景というか、ちょっと不思議な、夢の中に出てくるような光景です。画家の意図はどうであれ、受け取る方としてはそう感じます。
この絵を見る人が感じるのは、一見して分かる「静けさ」と、「祭りのあとの、冬の夕暮れの情景」が醸し出す微かな「寂寥感」です。その心情を背景に、月・空・雲・林の木々・小屋の影・2人の人物が織りなす、うっとりとするような光景が描かれています。対角線と水平線の作る構図の安定感が心地よく、色づかいはおだやかで美しい。この「構図と色づかいの調和感」から受ける印象は「安らぎ」ですね。「寂しさを秘めた静けさの中の安らぎ」という心象風景でしょうか。
調和を少し攪乱するように、空に浮かんでいる変わった形の一つの雲が(なぜ一つだけ形と色が異質なのでしょうか?)、逆に全体を引き締めています。
幻想の光景と言っていいと思いますが、ルソー作品によくあるジャングルとか、熱帯を思わす風景とか、そういうものとは違います。見る人に、これと類似の風景、ないしは「類似の感情を引き起こす現実の光景」を見たことがあると強く感じさせる絵です。
ニューヨークに行き、フィラデルフィアに日帰りすると、アンリ・ルソーの作品をかなり鑑賞できることになります。ニューヨーク近代美術館(MoMA)の『夢』(No.72「楽園のカンヴァス」)と『眠れるジプシー女』は、教科書にも載っている有名な絵です。また、バーンズ・コレクションには21点あり、フィラデルフィア美術館は7点を所蔵しています。
その中でも『Carnival Evening』は、「ニューヨーク・フィラデルフィア地域」にあるルソー作品の中でもピカ一の絵だと思います。この作品もまた、バーンズ・コレクションを2~3時間で切り上げてフィラデルフィア美術館に行くべき理由の一つなのでした。
以上に掲げた絵は、バーンズ・コレクションと違って常に展示してあるとは限りません。公的な美術館は皆そうです。しかしフィラデルフィア美術館には同等以上の作品が他に多数あります。
また2階には「モダン・アート」のウイングがあります。特にこの美術館はマルセル・デュシャンのコレクションでは世界一と言われています。3階は「東洋・アジア美術」と「18世紀以前のヨーロッパ美術」(ルーベンス、ファン・エイク・・・・・・)の展示室です。さらに、初めに書いたように共同運営されているロダン美術館があります。何を重点にするかは各人の好みによるでしょう。
とにかくフィラデルフィア美術館は「ニューヨークからの日帰り」で訪れる価値のあるミュージアム(群)です。
(続く)
| 補記 |
フィラデルフィア美術館が所蔵するセザンヌの『大水浴図』の画像と、美術史家・秋田麻早子氏のコメントを、No.284「絵を見る技術」に掲載しました。
(2020.5.2)
No.95 - バーンズ・コレクション [アート]
前回の No.94「貴婦人・虎・うさぎ」の最後の方で、アンリ・ルソーのウサギの絵を紹介しましたが、この絵を所蔵しているのは、アメリカのフィラデルフィアにある「バーンズ財団 The Barnes Foundation」でした。今回はこの財団が管理するバーンズ・コレクションのことを書きます。
バーンズ・コレクションは、現在はフィラデルフィアの中心部に近い財団の「施設」に展示され、公開されています。施設の正式名は「The Barnes Foundation Philadelphia Campus」のようですが、以降、この「施設」も、その中の「展示作品」も区別せずに「バーンズ・コレクション」と表記します。
アメリカの美術館を訪れる
もしあなたが美術好きで、美術館を訪れるのが趣味で、海外旅行の際にも美術館によく行き、かつ、パリやローマには行ったので、今度はアメリカに行くとします。
アメリカの有名美術館は、ヨーロッパ絵画、特に19世紀以降の近代絵画の宝庫です。ヨーロッパ絵画に興味があるなら、パリ、ロンドン、アムステルダム、ローマ、フィレンツェ、マドリードに旅行するだけでは不十分であり、特に近代絵画をおさえておくためにはアメリカに行く必要があります。2011年に日本で開催された「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」の宣伝文句に「これを見ずに、印象派は語れない」とありましたが、これは大袈裟でもなんでもなく、事実をストレートに言っているに過ぎないのです。
そのアメリカの有名美術館を訪れる目的で一つだけ都市を選ぶとすると、やはりニューヨークです。ここには
という、全く性格の違う3つの美術館が(近接して)あるからです。もちろん、メトロポリタンはヨーロッパ美術だけではありません。またニューヨークには他にも、グッゲンハイム美術館やホイットニー美術館をはじめ、数々の美術館・ギャラリーがあります。
そしてニューヨークに旅行するのなら、是非ともお勧めしたいのがフィラデルフィアに行くことです。フィラデルフィアはニューヨークから列車で1.5時間の距離で、日帰りが十分に可能です。もちろん、フィラデルフィアに行く理由はバーンズ・コレクションがあるからです。
以降、バーンズ・コレクションに関する何点かのポイントや見どころを書きます。
予約が必要
バーンズ・コレクションは基本的に予約が必要です。入場者数を制限しているのです。なぜそうなのかはあとで説明します。人数に余裕がある時は予約なしでも入場できるようなのですが、日本から行って入場できない(ないしは数時間後に来てくれと言われる)のはまずいので、必ず予約してから行きましょう。
予約は日本からもウェブサイトで可能です。何月何日の何時ということを指定して予約します。
完全な日本語音声ガイド
バーンズ・コレクションのポイントの一つは「完全な日本語音声ガイド」があるということです。「完全な」という意味は
という意味です。そんなのあたりまえだろう、と思うのは甘い。某美術館などは、日本語ガイドと言いながら、音声ガイドが設定されている作品の一部だけにしか日本語音声がなく、残りは英語で聴く必要があります。騙されたという気分にもなるのですが、意外にこういう著名美術館がある。もっとも、日本語ガイドがあるだけ有り難いとも言えますが・・・・・・。英語で聴くのもアリですが、内容を把握するためにはリスニングに集中する必要があり(普通の日本人はそうだと思います)絵画の鑑賞という本来の目的を殺ぐことになります。やはり音声ガイドはある程度は「聞き流し」て、ハッとする解説があったときに集中するという風にしたい。絵の鑑賞が第一なのだから・・・・・・。
バーンズ・コレクションの音声ガイドは、財団のキュレーターや大学教授が解説をしていて、非常にしっかりしたものです。まず日本語音声ガイドがある。そしてそれが完全な日本語音声ガイドである。このことは重要ポイントとしてあげていいと思います。
バーンズ邸の展示室と展示方法を再現
バーンズ・コレクションは、フィラデルフィア出身の実業家で美術研究家のアルバート・バーンズ博士(1872-1951)が収集した美術品を展示してあるのですが、もともとこのコレクションはフィラデルフィアの郊外、北西10kmぐらいにあるメリオンのバーンズ邸に飾られていたものです。メリオンの建物は美術品を展示するために造ったようですが、個人の私有物なので「バーンズ邸」と言うことにします。バーンズ邸は今でもありますが、2012年にバーンズ財団はフィラデルフィアの中心部に近い場所に新たに「施設」を建設し、そこにコレクションを移設しました。我々海外からの旅行者にも随分とアクセスしやすくなったわけです。
フィラデルフィアのバーンズ・コレクションの最大の特徴は次の2点です。
の2点です。つまり鑑賞者は、かつてのバーンズ邸を訪問した時と同じ雰囲気で絵画コレクションを味わえるのです。しかもここの絵は基本的に「門外不出」です。
予約が必要という理由は、まさにこの点にあります。「施設」の内部の展示室は、大きい部屋もあるが、小さい部屋が多い(バーンズ邸を模しているのだから)。もし入場者数をコントロールしなければ、部屋によっては人が溢れ返ることになります。
アルバート・バーンズの絵画の展示方法は独特です。画家ごとに飾るとか、年代順に飾るとか、絵画の流派で分けるとか、そういった「美術館っぽい」ことはいっさいしない。壁の中心にメインの絵を飾り、その絵と(バーンズなりの考えによる)関連性のある絵を、左右対称に、左右の大きさを揃えて、壁一面に、画家はごちゃまぜにして飾る・・・・・・。簡単に言うとそんな飾り方です。いいとか悪いとか、そういう次元の話ではありません。基本的に「私邸」なのだから、鑑賞者はそれを受け入れるべきなのです。
ちなみに、左右対称(シンメトリー)という絵の飾り方は、いかにも欧米文化という感じがします。私などは、シンメトリーを基調にしつつも、それをあえて「崩す」ところや「はずした」ところをあちこちに作った方が「動き」や「味」が出ていいと思うのですが、それはあくまで日本的な考え方なのでしょう。もう一度確認すると、ここは私邸であって、オーナーの感性を味わうべき場所なのです。
付け加えると、バーンズ・コレクションにおいては、24ある展示室の配置も完全なシンメトリーをなしています。
以降にバーンズ・コレクションの公開画像を掲載しますが、原則として、
Room 1-23 East/West/South/North Wall
というようにで、展示室の壁ごとに紹介します。普通の美術館なら絵の展示場所は変わるので、こういった紹介には意味がないのですが、バーンズ・コレクションでは「どの絵を、どの部屋の、どの壁の、どの位置に展示するか」ということが厳密に決まっているので、最適な方法だと思います。もしあなたが今後バーンズ・コレクションを訪れたとしても、全く同じ光景に出合うはずです。なお、ここに掲載した画像はバーンズ・コレクションがメリオンのバーンズ邸にあった頃の写真が一部含まれていますが、本質的には全く同じです。
補足しますと、
ということは、
ということです。普通の美術館なら「貸出し」や「展示替え」で、こうはいきません。このことはバーンズ・コレクションの大きな特徴と言っていいと思います。ひょっとしたら「一生に一度だけの日本からの旅行者」にとってはこれが最大のメリットかもしれません。
ルノワールが大量にある
ここに収集されたルノワールは181点と言います。バーンズ・コレクションを鑑賞してまず感じるのは、「ルノワールだらけだ」という驚きです。よくもこれだけ集めたものだと・・・・・・。あのオルセー美術館でさえ、所蔵するルノワールは125点といいます。個人コレクションであるにもかかわらずオルセー美術館の1.5倍のルノワールがあるというのは、かなり衝撃的な事実ではないでしょうか。これに驚かないようでは "絵画ファン" だとは言えないでしょう。
美術が好きな人には「ルノワールが好き」な人も多いでしょうが、中には「ルノワールは嫌い」という人もいると思います。絵の好みは "人それぞれ" なので当然です。では「ルノワール嫌い」にとっては、バーンズ・コレクションを訪れる価値が薄くなるかと言うと、そんなことは全くありません。
のです。これだけの作品を集めたというコレクターの「愛着、こだわりと執念、尋常ではない想い、常軌を逸した執着心とその徹底ぶり」に直に触れる感じがして、それはそれで「感動さえ覚える」のです。そして、たとえ「ルノワール嫌い」の人であっても、これだけの数の絵があると、
と思うのです(たぶん)。とにかく圧巻のルノワール・コレクションは一見の価値があります。しかもバーンズ流の飾り方では、ルノワールだけが連続して現れることはあまりないので「食傷する」ことはなく、鑑賞しやすくなっています。
セザンヌとマティス、その他の画家
ルノワールの次の多いのが、セザンヌ(69点)とマティス(59点)です。アルバート・バーンズはアンリ・マティスと交流があり、マティスはバーンズ邸の壁画を制作しています。その壁画(『ダンス』)も移設されています。
その次は、ブルガリア出身のエコール・ド・パリの画家、パスキン(57点*)です。また、ピカソも46点あります。10~20作品程度の有名画家は、
などです。
これらの画家は、バーンズの同時代の画家が多いことに注目すべきでしょう。画家の生年を古い順にあげてバーンズの生年との差をリストすると以下のようです。
これを見るとはっきりするのですが、バーンズ本人より一世代前と言えるのは、セザンヌ、ルノワール、アンリ・ルソーだけであり、あとは同世代の画家です。スーティンなどは次の世代と言ってもいい。ということは、バーンズの時代には評価が(全く)定まっていない画家も多かったはずです(そもそもスーティンはバーンズに見出された画家です)。コレクターとしての目の確かさがうかがえます。
バーンズの「一世代前」と「同世代」の対比を良く表しているのがメインルーム(Room 1)です。引用画像にもあるように、メインルームの North Wall に飾られているのは33枚のルノワールとセザンヌです。一方、その反対側の South Wall にあるのは、
で、この二つの作品は North Wall の絵とは明らかに違います。色が現実とは遊離しているし、形も画家が自由に造形しています。我々はマティスやピカソをよく知っているので、この二つを見ても絵としての違和感を感じることはありません。もちろん「好き・嫌い」はあるだろうけれど「絵として変だ」とか「絵になっていない」と思う人はいないはずです。
しかしバーンズと同世代の「一般の美術愛好家」はどうだったのでしょうか。メリオンのバーンズ邸で『座るリフ族の男』と『農夫たち』を見せられた "普通の" フィラデルフィア市民は、「これでは絵になっていない」と思った(人が多かった)のではないでしょうか。現代人の感覚を単純にバーンズの時代に当てはめることはできないと思うのです。
バーンズ・コレクションのメインルームでは「ルノワール・セザンヌ - North Wall」と「マティス・ピカソ - South Wall」が同居しています。我々はそれを「あたりまえ」だと思うのですが、バーンズの時代の "個人コレクター" としては必ずしもあたりまえではないはずです。バーンズの「絵を見る目の確かさ」は、このメインルームに現れていると感じます。
画家の名前をあげていくときりがないので、以降は簡略化しますが、10点以下の主な画家は、ゴッホ(7点)、スーラ(6点)、マネ(4点)、モネ(4点)、クールベ(3点*)、ゴーギャン(2点*)、ロートレック(2点)などです。
ルノワール、セザンヌ、マティスが大量にあるので我々は感覚が麻痺してしまって、ゴッホもあるな、ぐらいの感じなのですが、ゴッホ作品が7点あるだけでも本当は大変なことです。しかも、あまり写真や画集などで紹介されない作品です。
ここまで作品数の紹介ばかりで、作品の話が全く出てこないのですが、それだけ「圧倒的な数」に驚くということです。しかし作品数だけをうんぬんするのはまずいので、1点だけあげると、メインルームの West Wall にあるスーラの『ポーズする女たち』(1886/8)です。これはバーンズ・コレクションの「顔」の一つともなっている点描の大作で、モデルの「オーディションの光景」( = バーンズ・コレクションの音声ガイドでの解説)を描いています。
この絵のポイントは次の3点だと思います。
の3点です。思うのですが、この絵が強い印象を残すのは③が大きいのではないでしょうか。「通常は知り得ない光景をかいま見る」といった・・・・・・。「舞台裏」を描いた先人はドガですね(スーラ以後の画家ではロートレック)。影響されたのかもしれません。とにかく、「本来描くべき光景の一段階前のシーンを描写し、しかも画中画を描き込む」という、ちょっと複雑なコンセプトがこの絵の魅力でしょう。また、同一のモデルを3つの時間差で描いた(3つの時間を共存させた)ように見えてしまうのも、さらにこの絵を謎めいたものにし、魅力を増しているのでしょう。
ちなみに、スーラが短い生涯(31歳で死去)に描いた大作は、この作品を含めて6点しかありません。残りのうちの2つはアメリカにあります。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(シカゴ美術館)と『サーカスの客寄せ』(メトロポリタン美術館)です。つまりアメリカの美術館に「スーラの大作」の半分、3作品があるわけです。しかも、誰の目にも明らかだと思うのですが、アメリカにある3作品がスーラのベスト・スリーです。これをもってしても「近代フランス絵画におけるアメリカの美術館の重要性」が直感できます。
以上はフランス、ないしはフランスで活躍した画家の近代の作品ですが、バーンズ・コレクションにはそれ以前の時代・国の画家の作品も、数は少ないですが、ちゃんとあります。ティントレット、ティツィアーノ、ヴェロネーゼ、ボス、ルーベンス、ハルス、エル・グレコ、ゴヤ、・・・・・・などです。ルネサンス以前の宗教画もあります。ヨーロッパ絵画史の全域に渡るというわけではないですが、「バーンズの時代に購入できる絵」という観点から見ると極めてカバー率が高いコレクションです。
アメリカの画家
バーンズ・コレクションの特色の一つは、アメリカ人画家の作品もちゃんと収集されていることです。その代表が
です。この2人の画家は、日本では一般的にはあまり知られていないと思います。私もバーンズ・コレクションで初めて見ました。
ウィリアム・グラッケンズ(1870-1938)は、バーンズより2歳年上のアメリカの画家で、「アメリカのルノワール」と呼ばれたこともあったようです。彼はバーンズ・コレクションの成立に大きな役割を果たした画家で、バーンズの意向を受け、ヨーロッパで絵を買い付けたり、アドバイスをしたりしました。No.86「ドガとメアリー・カサット」で紹介した、ハブマイヤー夫妻(コレクター)とメアリー・カサット(画家)の関係を思いだします。というより、倉敷の大原美術館を作った大原孫三郎(コレクター)と児島虎次郎(画家)の関係、と言った方がより適切でしょう。
モーリス・プレンダーガスト(1858-1924)は後期印象派の代表的なアメリカの画家で、独特の個性的なタッチと色使いが印象的な画家です。彼もバーンズと同時代の画家です。
グラッケンズとプレンダーガストの作品をそれぞれ1つ、掲げておきます。いずれもメインルームにある絵で、グラッケンズは北東の出入り口の上、プレンダーガストはスーラの左側に展示されている作品です。
グラッケンズとプレンダーガスト以外にも、次のようなアメリカ人画家の作品が収集されています。
などです。なお、多数収集されているパスキン(ブルガリア生まれ、パリで活躍)はアメリカ国籍を取得しているのでアメリカ人ということになります。Barnes Foundation のホームページには次のような記述があります。
これはちょっと意外な感じですが、そう言われてみるとメインルームにもアメリカ人画家の3作品(グラッケンズ×2、プレンダーガスト)があるのですね。
我々は欧米の近代絵画というと、ほぼヨーロッパ出身画家の作品を思い浮かべます。バーンズ・コレクションを訪れても、どうしてもそういう目線で鑑賞してしまいます。ルノワール、セザンヌ、マティスだらけの展示室を見せつけられるとそれもやむを得ないのですが、「アメリカの画家」という視点でバーンズ・コレクションを見るのも一つの見方でしょう。
アンサンブル
仮に、ルノワールを4~5枚持っている個人コレクターがいたとします(それもだけでも凄い)。たぶん彼は自宅の一室にルノワールだけを集め、「ルノワール・ルーム」とか称し、客を招いて絵の解説をして(自慢して)悦に入るでしょう。しかしアルバート・バーンズにしてみれば、そんなことは「駆け出しコレクター」か「マイナー・コレクター」のやることなのですね。彼はルノワールを181枚集めて、20以上の部屋にばらまき、他の画家の絵とごちゃまぜに展示するわけです。ルノワール以外の画家も同様です。
前にアルバート・バーンズ独特の絵の飾り方を書きましたが、もう一度整理すると次のようです。
この美術品の飾り方をバーンズ・コレクションではアンサンブルと呼んでいます。一つの壁の美術品・工芸品が「総体としてアルバート・バーンズの作品」だと言いたいのでしょう。では、なぜこういう展示方法なのか。
それは、アルバート・バーンズの独創性であり、彼の感性であり、こだわりだと言われます。それは全くその通りだと思うのですが、バーンズ・コレクションを見て強く感じるのは、
ということなのです。
その理由ですが、まず、バーンズ邸は「私邸」です。私邸としては広いといっても、20数室の小さめの部屋しかない。国立の美術館のような建物の大きさと展示室の作りでは全くないのです。ここに大量の絵を展示するとなると、壁一面に絵を飾るしかないわけです。
さらに、同一画家の絵が多数あることを考える必要があります。ルノワールは181作品もあります。もし「ルノワール・ルーム」を作ったとしたら、3つか4つの部屋がルノワール作品で埋め尽くされることになります。それは何とも「味気ない」展示方法です。いくら「ルノワール好き」でも飽きる。「ルノワール・ルーム」を作ったとしたならコレクターの感性を疑われることになるでしょう。セザンヌしかり、マティスしかりです。
バーンズ・コレクションの特長の一つは、パリのオランジュリー美術館と双璧を成すスーティンのコレクションです。これはバーンズと懇意だったパリの画商、ポール・ギヨームが無名のスーティンを買い、その絵を見たバーンズが感銘を受けたことによります(ちなみにオランジュリー美術館はギヨーム・コレクションがベースになっている)。上にも書いたようにスーティンはバーンズに見い出された画家といってよい。
そういう経緯もあって、バーンズ・コレクションのスーティンは21点も(!)あります。もしこれらをまとめて展示するとなると、壁の2面は必要でしょう。壁の2面がスーティンの絵で埋まっている部屋を想像してみると、それはちょっと問題ありではないでしょうか。私ならそういう部屋にすすんで行こうという気にはならない。やはりマティスがあり、スーティンがあり、その次にモディリアーニがあってこそ、あの独特の画風というか、厳しい色彩と、いささかショッキングなフォルムが生きるのだと思います。「スーティン・ルーム」を作るとなると、今度はコレクターの品格(?)に疑問符がつくことになる。
それでは、画家たちの絵をシャッフルし、一つの壁に10作品とか15作品を飾るにはどうしたらよいのか。まさか、くじ引きで決めるわけにはいかにないから、どうしても「絵と絵の間の何らかの関連性」に注目するしかありません。サイズとか、色合いとか、描かれているもののフォルムとか、絵の主題とかです。そして「その壁のテーマ」みたいなものを作る・・・・・・。A画家の比較的大きめの作品を真ん中に置き、その左右にB画家の小ぶりの似たサイズの2つの作品、しかもA画家作品と何らかの関連性のあるものを飾る・・・・・・これなどはとても自然な発想に思えます。
「アンサンブル」はバーンズの独創性・感性・こだわりのたまものなのだろうけど、何となく「所蔵数」という量の問題も大きいのではと感じます。
我々としてはまず作品群を「アンサンブル」として鑑賞し、その中で「これは」と思った作品(気に入ったもの、目に付いた絵画)をじっくり見る・・・・・・、これがバーンズ・コレクションの「正しい鑑賞の方法」でしょう。鑑賞者にとっても量の問題があるわけです。とてもすべての絵をじっくりみる時間はありません。フィラデルフィアに住んでいるのならともかく、ニューヨークからの日帰り旅行者にとっては・・・・・・。
コレクターの嗜好を越えて
バーンズ・コレクションは、個人コレクターが収集して私邸に飾った絵を鑑賞するものです。その意味では、フリック・コレクション(ニューヨーク)やフィリップス・コレクション(ワシントン DC)、クラーク・コレクション(マサチューセッツ州、ウィリアムズタウン)と同様ですが、特にバーンズ・コレクションはアルバート・バーンズの好み、嗜好、趣味、こだわりが濃厚に現れています。単刀直入に言うと、ギャラリーとしてはかなり歪んでいる。
たとえば、クロード・モネの作品はあまりありません(4点)。別にモネの絵を集めないとコレクターとして一流じゃない、というわけでは全くないのですが、あれだけのコレクションにモネが4点というのも「少なすぎる」感じがします。バーンズ・コレクションにおいては、モネの作品は非常に影が薄いのです。
アメリカの画家もそうです。たとえば、アメリカ近代絵画の父とも言われるエイキンズ(フィラデルフィア出身)の作品はありません。ホーマーの作品もない。バーンズと盟友だったグラッケンズ、およびプレンダーガストの絵を見たとしても、それは決して「アメリカ美術史」を概観したことにはならない。ここは美術館ではないのです。あくまで「アルバート・バーンズというフィルターで濾過された絵画群に触れる場所」です。
しかし、あくまで個人のフィルターを通してという限定つきだけれど、ここに集められた絵、特に「多くの作品がある画家の絵」「収集に邁進したに違いない画家の絵」(スーラが6点!)には、共通するものがあるような気がします。それは、
という共通点です。全部が全部そうではないが、何となくそういう感じがする。コレクターの「絵画のあるべき姿はこうだ」という主張も感じ取れます。モネ、シスレー、ピサロなどの「いかにも印象派っぽい絵 = 筆触分割を使い、明るい色調で戸外の風景を描いた絵」が少ないのも分かるような気がする。
我々はバーンズ・コレクションを鑑賞する中で、たとえばピカソのある時期の作品とモディリアーニの共通項を見い出すのですね。コレクションに大量にあるセザンヌは現代美術を切り開いた画家であり、ピカソやブラックに直結していると言われます。それは全くその通りだと思いますが、では、セザンヌとルノワールは関係ないのか。実は、深いところで共通するものがあるという疑いが・・・・・・みたいなことを考えてもいいと思います(次の図)。
結局のところ、画家の個性・技法・画題がどんなに違っても、人間の感性に訴える絵であるかぎり、極めてベーシックなところで何らかの共通点があるものだと、アルバート・バーンズは言いたかったのかもしれません。人によって感じ方は違うと思いますが・・・・・・。
そういう意味で、絵画の鑑賞が好きな人にとっては、フィラデルフィアへの日帰りが、その人その人にとっての「発見の旅」になると思います。
ニューヨークから日帰りをするなら
初めに書いたように、ニューヨークからフィラデルフィアには十分に日帰りができます。そこで日帰りという前提で、バーンズ・コレクションに滞在する時間はせいぜい2~3時間にとどめましょう。そうすると、頑張って朝早めにニューヨークを出発したとして、美術館の閉館時刻までにはまだ時間があります。その時間を利用して、絵の鑑賞が大好きなあなたとしては絶対に行くべき場所があります。バーンズ・コレクションから歩いて行けるフィラデルフィア美術館です。
バーンズ・コレクションは、現在はフィラデルフィアの中心部に近い財団の「施設」に展示され、公開されています。施設の正式名は「The Barnes Foundation Philadelphia Campus」のようですが、以降、この「施設」も、その中の「展示作品」も区別せずに「バーンズ・コレクション」と表記します。
アメリカの美術館を訪れる
もしあなたが美術好きで、美術館を訪れるのが趣味で、海外旅行の際にも美術館によく行き、かつ、パリやローマには行ったので、今度はアメリカに行くとします。
アメリカの有名美術館は、ヨーロッパ絵画、特に19世紀以降の近代絵画の宝庫です。ヨーロッパ絵画に興味があるなら、パリ、ロンドン、アムステルダム、ローマ、フィレンツェ、マドリードに旅行するだけでは不十分であり、特に近代絵画をおさえておくためにはアメリカに行く必要があります。2011年に日本で開催された「ワシントン・ナショナル・ギャラリー展」の宣伝文句に「これを見ずに、印象派は語れない」とありましたが、これは大袈裟でもなんでもなく、事実をストレートに言っているに過ぎないのです。
そのアメリカの有名美術館を訪れる目的で一つだけ都市を選ぶとすると、やはりニューヨークです。ここには
| ◆ | メトロポリタン美術館 | |
| ◆ | ニューヨーク近代美術館(MoMA) | |
| ◆ | フリック・コレクション |
という、全く性格の違う3つの美術館が(近接して)あるからです。もちろん、メトロポリタンはヨーロッパ美術だけではありません。またニューヨークには他にも、グッゲンハイム美術館やホイットニー美術館をはじめ、数々の美術館・ギャラリーがあります。
そしてニューヨークに旅行するのなら、是非ともお勧めしたいのがフィラデルフィアに行くことです。フィラデルフィアはニューヨークから列車で1.5時間の距離で、日帰りが十分に可能です。もちろん、フィラデルフィアに行く理由はバーンズ・コレクションがあるからです。
以降、バーンズ・コレクションに関する何点かのポイントや見どころを書きます。

| ||
|
The Barnes Foundation Philadelphia Campus
地上2階、地下1階建の施設である。上には採光のための構造物がある。手前の道路(Benjamin Franklin Parkway)を左手に行くと、ロダン美術館とフィラデルフィア美術館がある。ロダン美術館は、写真左上方の小さめの建物。 ( site : www.parkwaymuseumsdistrictphiladelphia.org )
| ||
予約が必要
バーンズ・コレクションは基本的に予約が必要です。入場者数を制限しているのです。なぜそうなのかはあとで説明します。人数に余裕がある時は予約なしでも入場できるようなのですが、日本から行って入場できない(ないしは数時間後に来てくれと言われる)のはまずいので、必ず予約してから行きましょう。
予約は日本からもウェブサイトで可能です。何月何日の何時ということを指定して予約します。

| ||
|
The Barnes Foundation Philadelphia Campus
反対側(北側、エントランス側)からみた写真。左奥の方に高層ビルが見えるが、このあたりがフィラデルフィアの中心部である。 ( site : withart.visitphilly.com )
| ||
完全な日本語音声ガイド
バーンズ・コレクションのポイントの一つは「完全な日本語音声ガイド」があるということです。「完全な」という意味は
| 音声ガイドが設定されている作品すべてに日本語のガイドがある |

| |||
|
エントランス
( archrecord.construction.com )
| |||
バーンズ・コレクションの音声ガイドは、財団のキュレーターや大学教授が解説をしていて、非常にしっかりしたものです。まず日本語音声ガイドがある。そしてそれが完全な日本語音声ガイドである。このことは重要ポイントとしてあげていいと思います。
バーンズ邸の展示室と展示方法を再現
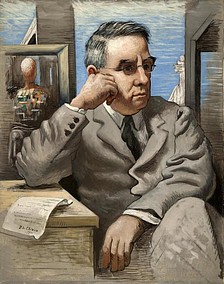
| |||
|
アルバート・バーンズの肖像
ジョルジョ・デ・キリコ(1926) ( www.barnesfoundation.org ) | |||
フィラデルフィアのバーンズ・コレクションの最大の特徴は次の2点です。
| ◆ | メリオンのバーンズ邸の24の部屋を、できるだけそのままの形で内部に再現してある。 | |
| ◆ | バーンズ邸の部屋の壁に飾られていた絵画は、全く同じ飾り方で移された。 |
の2点です。つまり鑑賞者は、かつてのバーンズ邸を訪問した時と同じ雰囲気で絵画コレクションを味わえるのです。しかもここの絵は基本的に「門外不出」です。
予約が必要という理由は、まさにこの点にあります。「施設」の内部の展示室は、大きい部屋もあるが、小さい部屋が多い(バーンズ邸を模しているのだから)。もし入場者数をコントロールしなければ、部屋によっては人が溢れ返ることになります。
アルバート・バーンズの絵画の展示方法は独特です。画家ごとに飾るとか、年代順に飾るとか、絵画の流派で分けるとか、そういった「美術館っぽい」ことはいっさいしない。壁の中心にメインの絵を飾り、その絵と(バーンズなりの考えによる)関連性のある絵を、左右対称に、左右の大きさを揃えて、壁一面に、画家はごちゃまぜにして飾る・・・・・・。簡単に言うとそんな飾り方です。いいとか悪いとか、そういう次元の話ではありません。基本的に「私邸」なのだから、鑑賞者はそれを受け入れるべきなのです。
ちなみに、左右対称(シンメトリー)という絵の飾り方は、いかにも欧米文化という感じがします。私などは、シンメトリーを基調にしつつも、それをあえて「崩す」ところや「はずした」ところをあちこちに作った方が「動き」や「味」が出ていいと思うのですが、それはあくまで日本的な考え方なのでしょう。もう一度確認すると、ここは私邸であって、オーナーの感性を味わうべき場所なのです。
付け加えると、バーンズ・コレクションにおいては、24ある展示室の配置も完全なシンメトリーをなしています。
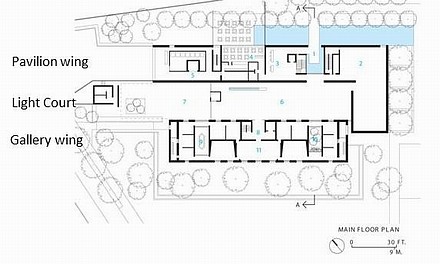
| ||
|
Philadelphia Campusの1階平面図
建物は、エントランスがあるL字型の Pavilion wing と展示室のある Gallery wing に分かれ、その間に外光が差し込む Light Court がある。絵が展示されているのは1階と2階のGallery wingである。Pavilion wing および地階は、講堂、研究室、図書室、財団オフィス、カフェ、ショップなどに利用されている。
( site : archrecord.construction.com )
| ||

| ||
|
Light Court
右手前がエントランス。左奥にGallery wingの入口がある。
( site : archrecord.construction.com ) | ||
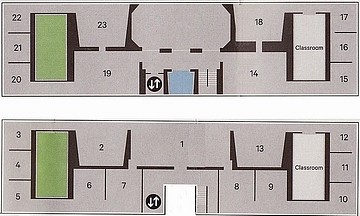
| ||
|
Gallery Wing - 1階(下)と2階
キャンパス全体の平面図とは上下が逆で、上方向が南側(South)である。1階は、中央の入口を入ったところがメイン・ルーム(Room 1)で、Room 13 までの展示室がある。2階は Room 14 から Room 23 までの10の展示室がある。24番目の展示室は2階の中央部(図の青い所)にあり、ここにはマティスの「The Joy of Life(=生きる歓び)」が展示してある。図で明らかなように、展示室群は完全なシンメトリーの構造になっている。 | ||

| ||
|
Gallery への入り口
奥が Room 1(メイン・ルーム)。途中にアルバート・バーンズの肖像画(キリコ作)がある。( google street view )
| ||

| ||
|
メイン・ルーム(Room 1) South Wall
ギャラリーに入ると目に飛び込んでくるのがメイン・ルーム(Room 1)の南側の壁である。上方にマティスの壁画があり、壁には極めて雰囲気の似た2枚の絵だけが飾られている。左がマティスの「座るリフ族の男」(1912)、右がピカソの「農夫たち」(1906)。
( site : www.moma.org )
| ||
以降にバーンズ・コレクションの公開画像を掲載しますが、原則として、
Room 1-23 East/West/South/North Wall
というようにで、展示室の壁ごとに紹介します。普通の美術館なら絵の展示場所は変わるので、こういった紹介には意味がないのですが、バーンズ・コレクションでは「どの絵を、どの部屋の、どの壁の、どの位置に展示するか」ということが厳密に決まっているので、最適な方法だと思います。もしあなたが今後バーンズ・コレクションを訪れたとしても、全く同じ光景に出合うはずです。なお、ここに掲載した画像はバーンズ・コレクションがメリオンのバーンズ邸にあった頃の写真が一部含まれていますが、本質的には全く同じです。
補足しますと、
| どの絵を、どの部屋の、どの壁の、どの位置に展示するかということが厳密に決まっている |
ということは、
| お目当ての「絵」なり「画家」なりを鑑賞する目的でバーンズ・コレクションを訪れたとしても裏切られない |
ということです。普通の美術館なら「貸出し」や「展示替え」で、こうはいきません。このことはバーンズ・コレクションの大きな特徴と言っていいと思います。ひょっとしたら「一生に一度だけの日本からの旅行者」にとってはこれが最大のメリットかもしれません。
ルノワールが大量にある
ここに収集されたルノワールは181点と言います。バーンズ・コレクションを鑑賞してまず感じるのは、「ルノワールだらけだ」という驚きです。よくもこれだけ集めたものだと・・・・・・。あのオルセー美術館でさえ、所蔵するルノワールは125点といいます。個人コレクションであるにもかかわらずオルセー美術館の1.5倍のルノワールがあるというのは、かなり衝撃的な事実ではないでしょうか。これに驚かないようでは "絵画ファン" だとは言えないでしょう。
美術が好きな人には「ルノワールが好き」な人も多いでしょうが、中には「ルノワールは嫌い」という人もいると思います。絵の好みは "人それぞれ" なので当然です。では「ルノワール嫌い」にとっては、バーンズ・コレクションを訪れる価値が薄くなるかと言うと、そんなことは全くありません。
| バーンズ・コレクションに行くと、ルノワールが好きとか嫌いとかは枝葉末節であり、そんなことはどうでもよいという気分になる |
のです。これだけの作品を集めたというコレクターの「愛着、こだわりと執念、尋常ではない想い、常軌を逸した執着心とその徹底ぶり」に直に触れる感じがして、それはそれで「感動さえ覚える」のです。そして、たとえ「ルノワール嫌い」の人であっても、これだけの数の絵があると、
| ルノワールにも、中にはいい絵があるんだな、という感想を持つ |
と思うのです(たぶん)。とにかく圧巻のルノワール・コレクションは一見の価値があります。しかもバーンズ流の飾り方では、ルノワールだけが連続して現れることはあまりないので「食傷する」ことはなく、鑑賞しやすくなっています。

| ||
|
メイン・ルーム(Room 1) West View
1階の Gallery wing の中央ある「メイン・ルーム」。左の壁(South Wall)の上の方にマティスの壁画がある。下の絵はマティスとピカソ。正面(West Wall)にスーラとセザンヌの作品が見える。右の壁(North Wall)は、ルノワールとセザンヌだけの作品が33点展示されている。その上は Balcony と呼ばれる「中2階」になっていて、マティスの壁画が正面から鑑賞できる。 ( site : archrecord.construction.com )
| ||

| ||
|
Room 1 - West Wall に展示されているセザンヌの「カード遊びをする人たち」(1890/2)。セザンヌは「カード遊びをする人たち」を5作品描いており、それぞれバーンズ・コレクション(人物は5人)、メトロポリタン美術館(4人)、オルセー美術館(2人)、コートールド・ギャラリー(2人)、カタール王室(2人)が所蔵している。後に描かれたほど人物の数が減って簡素になる。人物2人の3作品は構図が極めて似通っている。バーンズ・コレクションの本作はセザンヌの制作過程を知る上で貴重である。
( site:donate.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
メイン・ルーム(Room 1)North Wall
この壁に展示されている33枚の絵は、すべてルノワールかセザンヌである。中央に Gallery への入り口があり、壁の上部は中2階の「バルコニー」になっている。 ( site : www.nytimes.com )
| ||

| ||
|
バルコニーからメイン・ルームの南西方向を見る
( site : press.visitphilly.com ) | ||

| ||
|
Henri Matisse
The Dance(1932/33)
( site : articles.philly.com )
| ||

| ||
|
メイン・ルーム(Room 1)East Wall
画像が切れてしまっているが、左右の出入口の上にあるのはバーンズの盟友だったグラッケンズの作品。
( site : press.visitphilly.com )
| ||

| ||
|
メイン・ルーム(Room 1)North East View
( site : www.washingtonpost.com )
| ||
セザンヌとマティス、その他の画家
ルノワールの次の多いのが、セザンヌ(69点)とマティス(59点)です。アルバート・バーンズはアンリ・マティスと交流があり、マティスはバーンズ邸の壁画を制作しています。その壁画(『ダンス』)も移設されています。
| 所蔵作品点数はWikipediaの情報をもとにしています。ただし(*)はバーンズ・コレクションのホームページに画像が掲載されている作品数で、それ以上の所蔵作品があることになります。 |
その次は、ブルガリア出身のエコール・ド・パリの画家、パスキン(57点*)です。また、ピカソも46点あります。10~20作品程度の有名画家は、
| ◆ | スーティン | 21点 | ||
| ◆ | アンリ・ルソー | 18点 | ||
| (その中の1枚が No.94 のウサギの絵) | ||||
| ◆ | モディリアーニ | 16点 | ||
| ◆ | ドガ | 11点 | ||
| ◆ | クレー | 10点* | ||
| ◆ | キリコ | 10点* | ||
などです。
これらの画家は、バーンズの同時代の画家が多いことに注目すべきでしょう。画家の生年を古い順にあげてバーンズの生年との差をリストすると以下のようです。
| セザンヌ | 1839(-33) | |
| ルノワール | 1841(-31) | |
| アンリ・ルソー | 1844(-28) | |
| マティス | 1869(- 3) | |
| バーンズ | 1872 | |
| クレー | 1879(+ 7) | |
| ピカソ | 1881(+ 9) | |
| モディリアーニ | 1884(+12) | |
| パスキン | 1885(+13) | |
| キリコ | 1888(+16) | |
| スーティン | 1893(+21) |
これを見るとはっきりするのですが、バーンズ本人より一世代前と言えるのは、セザンヌ、ルノワール、アンリ・ルソーだけであり、あとは同世代の画家です。スーティンなどは次の世代と言ってもいい。ということは、バーンズの時代には評価が(全く)定まっていない画家も多かったはずです(そもそもスーティンはバーンズに見出された画家です)。コレクターとしての目の確かさがうかがえます。
バーンズの「一世代前」と「同世代」の対比を良く表しているのがメインルーム(Room 1)です。引用画像にもあるように、メインルームの North Wall に飾られているのは33枚のルノワールとセザンヌです。一方、その反対側の South Wall にあるのは、
| 『座るリフ族の男』 | |||
| 『農夫たち』 |
で、この二つの作品は North Wall の絵とは明らかに違います。色が現実とは遊離しているし、形も画家が自由に造形しています。我々はマティスやピカソをよく知っているので、この二つを見ても絵としての違和感を感じることはありません。もちろん「好き・嫌い」はあるだろうけれど「絵として変だ」とか「絵になっていない」と思う人はいないはずです。
しかしバーンズと同世代の「一般の美術愛好家」はどうだったのでしょうか。メリオンのバーンズ邸で『座るリフ族の男』と『農夫たち』を見せられた "普通の" フィラデルフィア市民は、「これでは絵になっていない」と思った(人が多かった)のではないでしょうか。現代人の感覚を単純にバーンズの時代に当てはめることはできないと思うのです。
バーンズ・コレクションのメインルームでは「ルノワール・セザンヌ - North Wall」と「マティス・ピカソ - South Wall」が同居しています。我々はそれを「あたりまえ」だと思うのですが、バーンズの時代の "個人コレクター" としては必ずしもあたりまえではないはずです。バーンズの「絵を見る目の確かさ」は、このメインルームに現れていると感じます。
Gallery 1階 東側
(south)
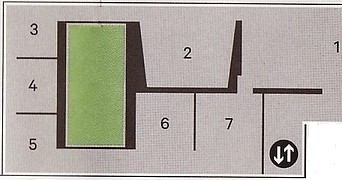
(north)
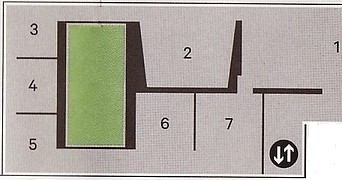
(north)

| ||
|
Room 2 North West View
West Wallの右から2番目の風景画は、セザンヌの「Gardanne(ガルダンヌ)」。その左には、画像が途切れてしまっているが、マネの「洗濯」が飾られている。さらにその左にセザンヌの「サント・ヴィクトワール山」がある。
( site : www.parkwaymuseumsdistrictphiladelphia.org )
| ||

| ||
|
Room 2 North Wall
左端と右端にゴッホが配置されている。左端の「郵便配達夫ルーランの肖像」は、同じ構図の絵がMoMAとオランダのクレラー・ミュラーにある。ルーランの右はセザンヌの「鉢植えの花」。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 2 East Wall
中央の絵は、エル・グレコの「聖ヒヤシンスの前に出現した聖母子」。この画像の右の方に Room 3 との出入り口があるが、そこに少し見える Room 3 South Wall の絵は、20世紀のアメリカの画家、ミルトン・エイブリーの「The Nursemaid」。なお、Room 2 の South Wall には「聖ローレンスの殉教」という15世紀の宗教画が飾られている。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 3 North West View
左の奥がメイン・ルームの方向。出入り口の上にあるのはボナールの「The Ragpickers(くず拾い)」。West Wall(左側)に、やけに横に長い絵があるが、これは伝・ティッツィアーノの「眠る羊飼い」。North Wall(右側)にある大きな絵はルノワールの「Embroiderers(刺繍をする女たち)」。右の奥に Room 5 North Wall のスーティンの絵が見える(次の画像参照)。一つ前の画像のエイブリーの作品は、この画像の背後の South Wall にある。South Wall にはシャヴァンヌもある。また East Wall にはエル・グレコの「聖衣剥奪」がある。
( site : www.themagazineantiques.com )
| ||

| ||
|
Room 5 - East Wall
真ん中の絵は、フランス・ハルスの「時計を持つ男の肖像」。右端の絵はルノワールの「扇を持つ女」。East Wall の左端の絵はルノワールの「りんご売り」。画像の一番左は North Wall に展示されているスーティンの「Woman with Round Eyes」。
(site : www.philly.com)
| ||

| ||
|
Room 5 - South Wall
下段の中央の絵はルーベンスの「ハープを弾くダヴィデ王」。その左はヒエロニムス・ボスの「聖アントニウスの誘惑」。
(site : www.philly.com)
| ||

| ||
|
Room 5 West Wall
この壁の正面の上の方にある絵は、スーラの「オンフルール港の入口」である。スーラの絵には港や川辺を描いた傑作が多い。メインルームの大作ばかりに目が行くが、この絵も見逃せない作品。スーラの下は、都市風景画で知られる17世紀オランダの画家、ベルクヘイデの作品。その左右はルノワールの作品で「ポンタヴァンの栗の木」と「風景」。出入口の上に掲げられた絵は、ペンシルヴァニア出身のアメリカの画家、ホーラス・ピピンがリンカーンとその父を描いた作品。右の方の壁(North Wall)に、スーティンの「皮を剥がれた兎」が見える。
(site : www.barnesfoundation.org)
| ||

| ||
|
Room 6 East Wall
左の出入り口の奥に、Room 5 East Wall の「りんご売り」が見える。出入り口の上に飾られているのはボナールの作品。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 6 - East Wall
(site : www.philly.com)
| ||

| ||
|
Room 6 South Wall
中央の絵はゴーギャンがタヒチで描いた「ハエレ・パぺ」。その両側はアメリカの画家、モーリス・プレンダーガストの作品(左の絵と右の絵)。ルノワールの2枚の裸婦像の上にあるのは、両方ともスーラがノルマンディーのグランカン村の海岸を描いた小品である(左の絵と右の絵)。ちなみに「グランカンの干潮」というスーラの作品が箱根のポーラ美術館にある。
( site : www.philly.com )
| ||

| ||
|
Room 6 Souh West View
West Wall の大き目の絵はセザンヌの「赤い縞のドレスを着た婦人」だが、その右はゴッホの「アニエールの工場」。その上はセザンヌが20歳台半ばで描いた初期の作品。「赤い縞のドレスを着た婦人」の左はマネの「タールを塗られるボート」で、ボートの黒が印象的な作品である。なお、Room 6 の North Wall にはキリコの「ソフォクレスとエウリピデス」がある。
( site : www.myhabitfix.com )
| ||

| ||
|
Room 7 South View
奥に見える部屋はメイン・ルーム(Room1)。South Wall の中心にあるのはルノワールの「洗濯女と子ども」。画像の左端の East Wall の絵はクールベの「白いストッキングの女」。この画像の背後の North Wall にはドガのパステル画がある。
( site : www.architectural-review.com )
| ||

| ||
|
Room 7 West Wall
( site : hiddencityphila.org )
| ||

| ||
|
Room 7 West Wall(部分)
手前はゴーギャンがブルターニュの少年を描いた「ルールーの肖像」。バーンズ・コレクションの「顔」の一つとなっている作品である。その向こうはモネの「刺繍するモネ夫人」。
(site : www.philly.com)
| ||
画家の名前をあげていくときりがないので、以降は簡略化しますが、10点以下の主な画家は、ゴッホ(7点)、スーラ(6点)、マネ(4点)、モネ(4点)、クールベ(3点*)、ゴーギャン(2点*)、ロートレック(2点)などです。
ルノワール、セザンヌ、マティスが大量にあるので我々は感覚が麻痺してしまって、ゴッホもあるな、ぐらいの感じなのですが、ゴッホ作品が7点あるだけでも本当は大変なことです。しかも、あまり写真や画集などで紹介されない作品です。
ここまで作品数の紹介ばかりで、作品の話が全く出てこないのですが、それだけ「圧倒的な数」に驚くということです。しかし作品数だけをうんぬんするのはまずいので、1点だけあげると、メインルームの West Wall にあるスーラの『ポーズする女たち』(1886/8)です。これはバーンズ・コレクションの「顔」の一つともなっている点描の大作で、モデルの「オーディションの光景」( = バーンズ・コレクションの音声ガイドでの解説)を描いています。

| ||
|
Georges Seurat(1859-1891)
『ポーズする女たち』(Models) (200 x 249.9 cm) ( site : www.barnesfoundation.org ) | ||
この絵のポイントは次の3点だと思います。
| ① | わざわざ、自作(グランド・ジャット島の日曜日の午後)を絵の中描き込んだ。 | |
| ② | 点描の手法でヌードを描いた(ヌードに挑戦した)。点描は「日曜の昼下がりの戸外の情景」を描くだけのものでないことを証明(しようと)した。 | |
| ③ | オーディションという、いわば「舞台裏」を描いた。 |
の3点です。思うのですが、この絵が強い印象を残すのは③が大きいのではないでしょうか。「通常は知り得ない光景をかいま見る」といった・・・・・・。「舞台裏」を描いた先人はドガですね(スーラ以後の画家ではロートレック)。影響されたのかもしれません。とにかく、「本来描くべき光景の一段階前のシーンを描写し、しかも画中画を描き込む」という、ちょっと複雑なコンセプトがこの絵の魅力でしょう。また、同一のモデルを3つの時間差で描いた(3つの時間を共存させた)ように見えてしまうのも、さらにこの絵を謎めいたものにし、魅力を増しているのでしょう。
ちなみに、スーラが短い生涯(31歳で死去)に描いた大作は、この作品を含めて6点しかありません。残りのうちの2つはアメリカにあります。『グランド・ジャット島の日曜日の午後』(シカゴ美術館)と『サーカスの客寄せ』(メトロポリタン美術館)です。つまりアメリカの美術館に「スーラの大作」の半分、3作品があるわけです。しかも、誰の目にも明らかだと思うのですが、アメリカにある3作品がスーラのベスト・スリーです。これをもってしても「近代フランス絵画におけるアメリカの美術館の重要性」が直感できます。
以上はフランス、ないしはフランスで活躍した画家の近代の作品ですが、バーンズ・コレクションにはそれ以前の時代・国の画家の作品も、数は少ないですが、ちゃんとあります。ティントレット、ティツィアーノ、ヴェロネーゼ、ボス、ルーベンス、ハルス、エル・グレコ、ゴヤ、・・・・・・などです。ルネサンス以前の宗教画もあります。ヨーロッパ絵画史の全域に渡るというわけではないですが、「バーンズの時代に購入できる絵」という観点から見ると極めてカバー率が高いコレクションです。
Gallery 1階 西側
(south)
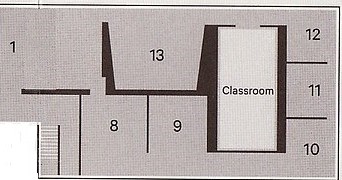
(north)
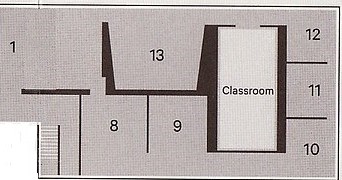
(north)

| ||
|
Room 8 East Wall
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 8 South Wall
奥に見える部屋はメイン・ルーム(Room1)。その出入口の上にあるのはフランスの画家、ヴュイヤールの作品。壁の右の方にはセザンヌの3点とルノワールの3点の絵が交差するように配置されている(後の解説参照)。( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 8 West Wall
中央の作品はセザンヌの「静物」(果物皿、水差し、果実)。その左にゴッホの作品、右にモネの作品がある。「静物」の上は、セザンヌが水辺の村を描いた風景画。右の方に Room 9 との出入り口があるが、その上に掲げられているのはアメリカの画家、チャールズ・プレンダーガストの「天使」。チャールズはモーリス・プレンダーガストの弟である。その出入り口の向こうに Room 9 North Wall の絵が見えるが、その大きい方はドガが踊り子を描いたパステル画。なお、Room 8 のNorth Wallにはモネが描いた肖像画がある。
( site : google scrapbook photo )
| ||

| ||
|
Room 9 East Wall
中央の絵はルノワールの「セーラー・ボーイ」(イポールの浜辺の少年)。この画像の一番左の上の絵は、アンリ・ルソーの「卵の籠をもった女」。
(site : www.tumblr.com)
| ||

| ||
|
Room 9 South Wall
ルノワール:6点、モネ:1点(左下のアトリエ・ボートの絵)、シスレー:1点(中央上)、マティス:2点(シスレーの斜め左下と斜め右下の海岸風景)が展示されている。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 9 West Wall(部分)
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 10 South East View
バーンズ・コレクションがメリオンにあった頃の画像。左の一番奥には Room 8、その手前には Room 9 の East Wall が見える。出入り口の上はマティスの「青い目の横たわる裸婦」。バーンズ・コレクションの公式カタログの表紙にはこの絵が採用されている。East Wall の大きめの絵は、スーティンの「青の女」。右の一番奥には Room 12、その手前には Room 11 の South Wall が見える。Room 11 South Wall の横長の絵はデュフィの作品。この作品から見て正面にあたる位置にもデュフィの絵がある(Room 11 North Wall の画像参照)。この右の出入り口の上はボナールの作品。
( site : www.new-york-art.com)
| ||

| ||
|
Room 10 South Wall(部分)
中央の絵はピカソの「煙草をもつ女」。その左右と上にマティスの絵が配置されている。「横たわる女」(左)「中国の小箱」(右)「横たわるオダリスク」(上)。
(site : www.whyy.org)
| ||

| ||
|
Room 10 West Wall
中央のモディリアーニの絵(赤毛の女)が目立つように配置されている。コレクションで感じるのは、ルノワール、セザンヌ、マティス、ルソー、ピカソなどとともに、モディリアーニの作品に対するバーンズの執着である。モディリアーニの周りの小品はマティスが多いが、ピカソ(若いアクロバット)、スーティン、アフロ・バサルデラなどもある。左の出入り口(South Wall)の上にボナールの作品が見える(2つ前の画像参照)。この画像の右端、North Wall の一番下の絵はピカソの「縞の床に座る女」という作品。( site : amberzuber.com )
| ||

| ||
|
Room 11 North Wall
ここには4枚のアンリ・ルソーの絵が飾られている。中央にあるのは「熱帯の森を散歩する女」、その上は「原始林の猿とオウム」、左が「パリ郊外」、右が「風景と4人の少女」である。左の方に Room 10 との出入り口があるが、その上にあるのはデュフィの作品。その向こうに Room 10 West Wall のモディリアーニの絵が見える。なお、Room 11 West Wall にはキリコの「海賊」がある。
(www.barnesfoundation.org)
| ||

| ||
|
Room 11 East Wall
中央はマティスの「青い静物」。その上は作者不詳の女の子の絵である。あえて作者不詳を飾るのは、女の子がブドウとリンゴを持っており、「あたかもマティスの絵から取り出したかのよう」という、一種のユーモアである。マティスの左右には、North Wall と同じくアンリ・ルソーの作品が4つ配置されている。マティスのすぐ左右の2枚は「花束」、一番左は「シャラントン橋の洗濯船」、右端は「家族」。バーンズの "ルソー好き" がうかがえる。ルソーの左の花束の上の絵と、右の花束の上の絵は、フランスの画家、ジャン・ユゴー(Jean Hugo)の作品である。左端のルソーの上と、右端のルソーの上の絵はホアン・ミロの作品。なお、Room 11 South Wall には4つ前の画像にあるデュフィ以外に、モディリアーニ、スーティン、マティス、ピカソなどがある。
( site : donate.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 12 North Wall
Room 12 は「アメリカの画家」の作品だけを展示している。この North Wall にはバーンズの盟友だったフィラデルフィア出身の画家・グラッケンズの作品が3点ある。真ん中は「競馬場」、左は「緑のターバンの少女」、右が「自画像」。「競馬場」の上はパスキンの作品。パスキンの左と右にある小さめの絵は、アメリカの画家、モーラーの作品。ちなみに、パスキンはブルガリア生まれでパリで活躍した画家だが、アメリカ国籍を取得している。
(site : www.whyy.org)
| ||

| ||
|
Room 12 East Wall
この East Wall もパスキンを含む「アメリカの画家」の作品が展示されている。下段の中央がパスキンで、その左はプレンダーガストの作品。上段の左の絵、中央、右の絵は、いずれもピピンの作品である。ピピンの絵は Room 5 West Wall にもあった。なお、Room 12 West Wall にはグラッケンズの作品があり、また South Wall にもグラッケンズ、パスキン、モーラーなどがある。
(site : philly360.visitphilly.com)
| ||

| ||
|
Room 13 West Wall
この壁の大き目の絵、5枚はすべてルノワールである。中央の絵は、印象派を世に出すことに尽力した画商、ポール・デュラン=リュエルの娘、ジャンヌの肖像。画像の左端に South Wall のパスキンの絵が見える。
( site : www.americanstyle.com )
| ||

| ||
|
Room 13 North Wall
7枚の絵を左から1-7の番号を振ったとすると、中央(4)はルノワールの「若い母親」、左右にあるのは、ルノワールの風景画3点(1,5,7)、ゴッホ(2)、セザンヌ(3)、マネ(6)である。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 13 North East View
East Wall の大きな絵はセザンヌの「頭蓋骨を前にした青年」。同じく、East Wallの北東寄りに楕円形の絵がかかっているが、これはドラクロワの「悪魔を打ち負かす聖ミカエル」。パリのサン・シュルピス教会に同じテーマでドラクロワが描いた天井画がある。ドラクロワの上にシスレーの作品がある。
( site : www.antiquesandauctionnews.net)
| ||
アメリカの画家
バーンズ・コレクションの特色の一つは、アメリカ人画家の作品もちゃんと収集されていることです。その代表が
| ◆ | グラッケンズ | 71点* | ||
| ◆ | プレンダーガスト | 21点* (=兄のモーリス。弟のチャールズも画家) |
です。この2人の画家は、日本では一般的にはあまり知られていないと思います。私もバーンズ・コレクションで初めて見ました。
ウィリアム・グラッケンズ(1870-1938)は、バーンズより2歳年上のアメリカの画家で、「アメリカのルノワール」と呼ばれたこともあったようです。彼はバーンズ・コレクションの成立に大きな役割を果たした画家で、バーンズの意向を受け、ヨーロッパで絵を買い付けたり、アドバイスをしたりしました。No.86「ドガとメアリー・カサット」で紹介した、ハブマイヤー夫妻(コレクター)とメアリー・カサット(画家)の関係を思いだします。というより、倉敷の大原美術館を作った大原孫三郎(コレクター)と児島虎次郎(画家)の関係、と言った方がより適切でしょう。
モーリス・プレンダーガスト(1858-1924)は後期印象派の代表的なアメリカの画家で、独特の個性的なタッチと色使いが印象的な画家です。彼もバーンズと同時代の画家です。
グラッケンズとプレンダーガストの作品をそれぞれ1つ、掲げておきます。いずれもメインルームにある絵で、グラッケンズは北東の出入り口の上、プレンダーガストはスーラの左側に展示されている作品です。

| ||
|
William James Glackens(1870-1938)
『The Bathing Hour, Chester, Nova Scotia』 (66 x 81.3 cm) ( site : www.barnesfoundation.org ) | ||

| ||
|
Maurice Brazil Prendergast(1858-1924)
『The Beach "No. 3"』 (61 x 124.8 cm) ( site : www.barnesfoundation.org ) | ||
グラッケンズとプレンダーガスト以外にも、次のようなアメリカ人画家の作品が収集されています。
| ジョン・ケイン | John Kane | 1860-1934 | ||||
| アルフレッド・モーラー | Alfred Maurer | 1868-1932 | ||||
| チャールス・デムス | Charles Demuth | 1883-1935 | ||||
| ホーラス・ピピン | Horace Pippin | 1888-1946 |
などです。なお、多数収集されているパスキン(ブルガリア生まれ、パリで活躍)はアメリカ国籍を取得しているのでアメリカ人ということになります。Barnes Foundation のホームページには次のような記述があります。
| ◆ | 展示作品の約 1/4 はアメリカ人の作である。 | ||
| ◆ | アメリカ人画家だけを展示した部屋もある( = Room 12 )。 | ||
| ◆ | すべての展示室には、少なくとも2つのアメリカ人画家の絵がある。 |
これはちょっと意外な感じですが、そう言われてみるとメインルームにもアメリカ人画家の3作品(グラッケンズ×2、プレンダーガスト)があるのですね。
我々は欧米の近代絵画というと、ほぼヨーロッパ出身画家の作品を思い浮かべます。バーンズ・コレクションを訪れても、どうしてもそういう目線で鑑賞してしまいます。ルノワール、セザンヌ、マティスだらけの展示室を見せつけられるとそれもやむを得ないのですが、「アメリカの画家」という視点でバーンズ・コレクションを見るのも一つの見方でしょう。
アンサンブル
仮に、ルノワールを4~5枚持っている個人コレクターがいたとします(それもだけでも凄い)。たぶん彼は自宅の一室にルノワールだけを集め、「ルノワール・ルーム」とか称し、客を招いて絵の解説をして(自慢して)悦に入るでしょう。しかしアルバート・バーンズにしてみれば、そんなことは「駆け出しコレクター」か「マイナー・コレクター」のやることなのですね。彼はルノワールを181枚集めて、20以上の部屋にばらまき、他の画家の絵とごちゃまぜに展示するわけです。ルノワール以外の画家も同様です。
前にアルバート・バーンズ独特の絵の飾り方を書きましたが、もう一度整理すると次のようです。
| ◆ | 部屋の壁一面に絵を飾る | |
| ◆ | 一つの壁に飾られた絵は、画家とか年代とか流派によって分けられているのではない。いろいろの画家の作品を「ごちゃまぜにして」飾る。中には、ルノワールとセザンヌだけという壁があるが、それは特別。 | |
| ◆ | 作品は、絵の大きさ、構図、モチーフ、描かれたものの形、色使いなどの関連性から左右対称に配置され、その配置方法はアルバート・バーンズの感性によって決められている。 | |
| ◆ | 絵以外に工芸品(壁に飾ることから、主として平面的なもの)を飾り、また収集した調度品を床に置くことが多い。その工芸品や調度品は、絵と何らかの関連性(形など)を持っている。 |

| ||
|
メイン・ルーム West Wall の絵の配置
(メイン・ルームの写真参照)
スーラの絵とセザンヌのカードをする人は、ともに三角形の構図である。セザンヌの絵にはV字の構図もあるから、スーラの構図と対称形をなしている。プレンダーガストとアンリ・ルソーの絵は、横長のカンヴァスに描かれた海岸と河岸の風景画であり、水平線の中に人物ないしは樹木が「林立する」構図である。セザンヌの絵とコローの絵が対になっているが、セザンヌは酒を飲む男、コローは妻の肖像であって、題材としては何の関係もない。しかし人物のフォルムが似ており(左右対称)、色使いも似ている。セザンヌの静物画とヌードの絵(ギリシャ神話の女神・レダと白鳥(=ゼウス)の絵)は、テーマとしては全く関係がないが、描かれた題材の配置と構図が似ている(これも左右対称)。 以上のように、スーラとセザンヌの大作を除く残りの絵は「左右対称になるようなペア」という基準で選択されている。メインルームは入口正面の最も目立つ部屋であり、普通の考えでは各画家の「よりすぐり」の作品を飾ってよい場所であるが、そうはなっていない。例えば、メインルームではこの壁にしかないプレンダーガストとルソーの絵は、もちろん悪い絵ではないが、コレクションに多数ある作品からの「よりすぐり」だとは言えない。あくまでカンヴァスの形と「水平線と多数の垂直線」という構図の類似性で選ばれている。 まとめるとこの壁は、構図とフォルムの類似性で絵の選択と配置が決められていて、全体を貫く考え方を一言でいうと「シンメトリー」である。「シンメトリー過ぎて面白くない」と思うよりも、「これが欧米的美意識の王道」だと考えて鑑賞すべきなのである。 ただ、このような展示ができるということは、たとえ画題が全く違ったとしても構図には一定のパターンがある(ことが多い)ということにほかならない。その視点で見ると、美術の教科書で習うよりも「絵画の構図」が実感できる。アルバート・バーンズの大量のコレクションは、こういうところで生きる。この壁は実は、言葉を一切使わずに、絵の配置だけで「構図の基礎」を説明しようとしたと考えられる。 というわけで、絵の見方についてのバーンズ先生の講義を聴く感じもするが、ここは私邸だと割り切ればよい。 | ||
この美術品の飾り方をバーンズ・コレクションではアンサンブルと呼んでいます。一つの壁の美術品・工芸品が「総体としてアルバート・バーンズの作品」だと言いたいのでしょう。では、なぜこういう展示方法なのか。
それは、アルバート・バーンズの独創性であり、彼の感性であり、こだわりだと言われます。それは全くその通りだと思うのですが、バーンズ・コレクションを見て強く感じるのは、
| 「アンサンブル」がバーンズ・コレクションにとって最適の展示方法である。もっと言うと、「アンサンブル」になるのは必然的 |
ということなのです。
その理由ですが、まず、バーンズ邸は「私邸」です。私邸としては広いといっても、20数室の小さめの部屋しかない。国立の美術館のような建物の大きさと展示室の作りでは全くないのです。ここに大量の絵を展示するとなると、壁一面に絵を飾るしかないわけです。
さらに、同一画家の絵が多数あることを考える必要があります。ルノワールは181作品もあります。もし「ルノワール・ルーム」を作ったとしたら、3つか4つの部屋がルノワール作品で埋め尽くされることになります。それは何とも「味気ない」展示方法です。いくら「ルノワール好き」でも飽きる。「ルノワール・ルーム」を作ったとしたならコレクターの感性を疑われることになるでしょう。セザンヌしかり、マティスしかりです。
バーンズ・コレクションの特長の一つは、パリのオランジュリー美術館と双璧を成すスーティンのコレクションです。これはバーンズと懇意だったパリの画商、ポール・ギヨームが無名のスーティンを買い、その絵を見たバーンズが感銘を受けたことによります(ちなみにオランジュリー美術館はギヨーム・コレクションがベースになっている)。上にも書いたようにスーティンはバーンズに見い出された画家といってよい。
そういう経緯もあって、バーンズ・コレクションのスーティンは21点も(!)あります。もしこれらをまとめて展示するとなると、壁の2面は必要でしょう。壁の2面がスーティンの絵で埋まっている部屋を想像してみると、それはちょっと問題ありではないでしょうか。私ならそういう部屋にすすんで行こうという気にはならない。やはりマティスがあり、スーティンがあり、その次にモディリアーニがあってこそ、あの独特の画風というか、厳しい色彩と、いささかショッキングなフォルムが生きるのだと思います。「スーティン・ルーム」を作るとなると、今度はコレクターの品格(?)に疑問符がつくことになる。
それでは、画家たちの絵をシャッフルし、一つの壁に10作品とか15作品を飾るにはどうしたらよいのか。まさか、くじ引きで決めるわけにはいかにないから、どうしても「絵と絵の間の何らかの関連性」に注目するしかありません。サイズとか、色合いとか、描かれているもののフォルムとか、絵の主題とかです。そして「その壁のテーマ」みたいなものを作る・・・・・・。A画家の比較的大きめの作品を真ん中に置き、その左右にB画家の小ぶりの似たサイズの2つの作品、しかもA画家作品と何らかの関連性のあるものを飾る・・・・・・これなどはとても自然な発想に思えます。
「アンサンブル」はバーンズの独創性・感性・こだわりのたまものなのだろうけど、何となく「所蔵数」という量の問題も大きいのではと感じます。
我々としてはまず作品群を「アンサンブル」として鑑賞し、その中で「これは」と思った作品(気に入ったもの、目に付いた絵画)をじっくり見る・・・・・・、これがバーンズ・コレクションの「正しい鑑賞の方法」でしょう。鑑賞者にとっても量の問題があるわけです。とてもすべての絵をじっくりみる時間はありません。フィラデルフィアに住んでいるのならともかく、ニューヨークからの日帰り旅行者にとっては・・・・・・。
| なお、バーンズ・コレクションの日本語音声ガイドは、要所要所の作品の解説と同時に、その作品が含まれる「アンサンブル」の解説になっています。他の美術館ではまずない展示方法なので、美術に詳しいと自信がある方でも、音声ガイドを借りることをお勧めします。最初の方で書いた、バーンズ・コレクションの「完全な日本語音声ガイド」のもう一つの価値はここです。 |
Gallery 2階 西側
(south)
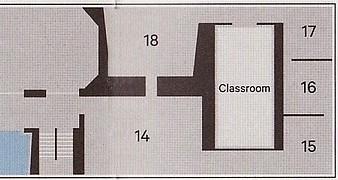
(north)
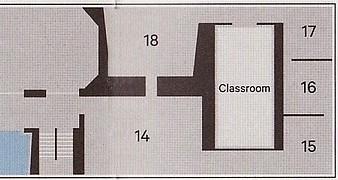
(north)

| ||
|
Room 14 East Wall
正面にあるのは、ルノワールの「ベルヌヴァルのムール貝採り」。箱根のポーラ美術館が同じ題材の絵を所蔵している。ルノワールの左右の下段の絵はセザンヌの風景画だが、上段の左の絵と右の絵はともにジョルジュ・デ・キリコの作品。
( site : www.latimes.com )
| ||

| ||
|
Room 14 North Wall
中央にあるのはアンリ・ルソーの「虎に襲われる斥候」。この壁は16世紀から19世紀までの画家が混在している。横一線に並んでいる大きめの絵・9枚に左から1~9の番号を付けたとすると、1:ルドン、2:ヴェロネーゼ、3:ヤン・ファン・ホーエン(17世紀オランダ)、4と7:ティントレット、5:ルソー、6:クールベ、8:スーティン、9:ルノワールである。Room 14 と19 の North Wall は2階の最も広い壁。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 14 West Wall
中央にあるのはドーミエの作品。スコットランドのグラスゴーにある「粉屋と息子とロバ」という、イソップ物語に取材した絵の習作である。ドーミエの左はアンリ・ルソーの「4人の釣り人のいる光景」。ドーミエの右側もルソーの作品と思ってしまうが、実は違って、アメリカの画家、ジョン・ケインの「サスケハナ河畔」という作品。ジョン・ケインは「日曜画家」であり、素朴派と言われるところなどはルソーとそっくりである。この飾り方にはバーンズの「たくらみ」を感じる。ルソーとケインを対比させた展示は Room 23 にもある。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 14 South Wall(西側)
中央にある絵は伝・ティツィアーノの「父と子」。なお画像にはないが、South Wall(東側)にはエル・グレコの(可能性がある)「Saint Francis and Brother Leo Meditating on Death」、セザンヌの「Toward Mont Sainte-Victoire」、ゴッホの「売春宿」がある。
( site : www.whyy.org )
| ||

| ||
|
Room 15 South Wall(部分)
中央にあるのはマティスの「赤いマドラス頭巾(マティス夫人)」。この絵はバーンズ・コレクションの「顔」となっている作品のひとつである。両側にロラン(左)とルイスダール(右)の風景画がある。マティスの両サイドに17世紀のフランスとオランダの風景画を配置するのは少々違和感があるが、この二つの風景画には船が描かれている。おそらく、マドラス → インドの港町 → 船、という連想による配置だと考えられる。マティスの上は、20世紀フランスの画家、ジャン・ユゴーの作品。なお、Room 15 の West Wall にはカサットの水彩画があり、North Wall にはルノワールが5点ある。また East Wall にはセザンヌの静物画やアーネスト・ローソンの風景画がある。
( site : www.flickr.com )
| ||

| ||
|
Room 17 South Wall
中央にあるのはマティスの「黄色と赤の室内にいる二人の娘」。その左斜め上と右の斜め上にパウル・クレーの絵がある。左斜め上は「Place-Signs」、右斜め上は「Sicilian Landscape」。その他、6枚程度のクレー作品がある。この South Wall と同じようにマティス作品を中心にしつらえてあるのが East Wall と North Wall である。West Wall にはパスキンの作品がある。
( site : withart.visitphilly.com )
| ||

| ||
|
Room 18 South View
( site : lightingcontrolsassociation.org )
| ||

| ||
|
Room 18 East Wall
この壁にはアメリカ人画家の作品が4つ展示されている。マティスの「横たわる裸婦」の左の絵と右の絵はチャールズ・デムス(Charles Demuth)の作品。さらにその左の絵と右の絵はランドール・モーガン(Randall Morgan)がフィレンツェとアマルフィを描いた作品である。なお、モディリアーニの内側にある2つの絵は、19世紀フランスの全く無名の画家、ジャン・ジロー(Jean Baptiste Guiraud )の作品(左側と右側)。バーンズの「素朴な絵」に対する好みがよく分かる。
( site : withart.visitphilly.com )
| ||

| ||
|
Room 18 North East View
North Wall の大きな絵は、ピカソの「苦行者」。画面の左の方に Room 14 との出入り口があるが、その上に飾られているのは、キリコ作「アレクサンドロス」。
( site : www.nytimes.com )
| ||

| ||
|
Room 18 North West View
Room 18 West Wall にある大きな絵は、ルノワールの「散歩」という作品。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||
コレクターの嗜好を越えて
バーンズ・コレクションは、個人コレクターが収集して私邸に飾った絵を鑑賞するものです。その意味では、フリック・コレクション(ニューヨーク)やフィリップス・コレクション(ワシントン DC)、クラーク・コレクション(マサチューセッツ州、ウィリアムズタウン)と同様ですが、特にバーンズ・コレクションはアルバート・バーンズの好み、嗜好、趣味、こだわりが濃厚に現れています。単刀直入に言うと、ギャラリーとしてはかなり歪んでいる。
たとえば、クロード・モネの作品はあまりありません(4点)。別にモネの絵を集めないとコレクターとして一流じゃない、というわけでは全くないのですが、あれだけのコレクションにモネが4点というのも「少なすぎる」感じがします。バーンズ・コレクションにおいては、モネの作品は非常に影が薄いのです。
アメリカの画家もそうです。たとえば、アメリカ近代絵画の父とも言われるエイキンズ(フィラデルフィア出身)の作品はありません。ホーマーの作品もない。バーンズと盟友だったグラッケンズ、およびプレンダーガストの絵を見たとしても、それは決して「アメリカ美術史」を概観したことにはならない。ここは美術館ではないのです。あくまで「アルバート・バーンズというフィルターで濾過された絵画群に触れる場所」です。
しかし、あくまで個人のフィルターを通してという限定つきだけれど、ここに集められた絵、特に「多くの作品がある画家の絵」「収集に邁進したに違いない画家の絵」(スーラが6点!)には、共通するものがあるような気がします。それは、
| 形と色使いに関する「個性的な様式美」をもった画家の絵。特に、形・フォルムの様式性が目立つ絵 |
という共通点です。全部が全部そうではないが、何となくそういう感じがする。コレクターの「絵画のあるべき姿はこうだ」という主張も感じ取れます。モネ、シスレー、ピサロなどの「いかにも印象派っぽい絵 = 筆触分割を使い、明るい色調で戸外の風景を描いた絵」が少ないのも分かるような気がする。
我々はバーンズ・コレクションを鑑賞する中で、たとえばピカソのある時期の作品とモディリアーニの共通項を見い出すのですね。コレクションに大量にあるセザンヌは現代美術を切り開いた画家であり、ピカソやブラックに直結していると言われます。それは全くその通りだと思いますが、では、セザンヌとルノワールは関係ないのか。実は、深いところで共通するものがあるという疑いが・・・・・・みたいなことを考えてもいいと思います(次の図)。
結局のところ、画家の個性・技法・画題がどんなに違っても、人間の感性に訴える絵であるかぎり、極めてベーシックなところで何らかの共通点があるものだと、アルバート・バーンズは言いたかったのかもしれません。人によって感じ方は違うと思いますが・・・・・・。
そういう意味で、絵画の鑑賞が好きな人にとっては、フィラデルフィアへの日帰りが、その人その人にとっての「発見の旅」になると思います。

| ||
|
Room 8 South Wall の絵の配置
この壁にはルノワールとセザンヌがV字と逆V字に交差して展示してあり、友人でもあった2人の画家の「類似」ないしは「影響」を示そうとしている。まず、中央のセザンヌ ② とルノワール ② は、ともに水浴する5人の女性を描いている。女性の描き方は全く違うが画題が同じである。そう言われると、19世紀の画家で「集団水浴図」を多数描いたのはセザンヌとルノワールであることに気づく。
下段のルノワール ② とセザンヌ ①、セザンヌ ③ は、画題は全く違うが、色づかいが非常によく似ている。ルノワール ② は裸婦を5人描いているため肌色が勝っているが、使っている色の種類がそっくりである。これも、このような展示をされてみて初めて気づく。 さらに上段のルノワール ① と ルノワール ③ については、「バーンズ・コレクション」(講談社 1993)によると制作年がポイントである。ルノワール ③(1875)は、互いに知り合う前に描かれた絵で、青とアイボリーで薄塗りされている。一方、ルノワール ①(1885)はセザンヌと知り合い、その量感表現を学ぼうとした時期の作品だという。確かに両方とも青い服の若い女性だが、その表現スタイルはかなり違っている。 美術史的な論議はさておいても、このような展示はルノワールを181点、セザンヌを69点も購入したアルバート・バーンズだからこそできる展示であることは確かだろう。またこれを見ると、彼が単なる美術コレクターではなく美術研究家であったことがよくわかる。 | ||
Gallery 2階 東側
(south)
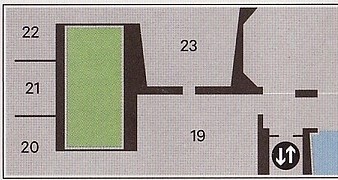
(north)
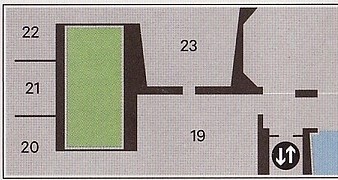
(north)

| ||
|
Room 19 West Wall
マティスの「三姉妹」の3連画(1917)が壁一面に飾られている。「家庭的な雰囲気の中の3人の女性を描いた3連画」は喜多川歌麿の浮世絵に先例があり、マティスはそこからヒントを得たという(「バーンズ・コレクション」講談社 1993 による)。「3人女性・3連画」は(西洋絵画では)この絵しか思い当たらないが、歌麿の影響だとすると納得がいく。なおマティスの「3人女性の1枚の絵」ならパリのオランジェリー美術館にある。
( site : www.forbes.com )
| ||

| ||
|
Room 19 North West View
(site : www.whyy.org)
| ||

| ||
|
Room 19 North Wall
中央はマティスの「音楽のレッスン」(1917)。両サイドにスーティンの絵があり、その間にユトリロ、モディリアーニ、アンリ・ルソー、キリコが配置されている。バーンズ・コレクションは、特にマティスとモディリアーニについては傑作が集結している。2人の画家の「ベスト20」を選んだとすると、その過半数はここにあるという感じがする。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 19 North Wall(部分)
一番左の絵はモディリアーニの「セイラー服の少年(Boy in Sailor Suit)」。
二つあるルソーの作品は、一番右が「過去と現在、あるいは哲学思想」、モディリアーニの右が「モンスリー公園(あずまや)」。後者は、その習作が箱根のポーラ美術館にある。
(site : www.whyy.org)
| ||

| ||
|
Room 19 South West View
左の奥の部屋は Room 23。その出入口の上にあるのは、マティスの「ドミノ・プレーヤー」。
West Wall にある出入口の上の絵は、スーティンの「赤い教会」。
(site : www.aegispg.com)
| ||

| ||
|
Room 19 South Wall(部分・西側)
中央はマティスの「金魚のいる室内」。マティスの金魚の絵は何点かあって、プーシキン美術館の絵は有名。その左はモディリアーニの「カーニュの糸杉と家」。モディリアーニの風景画は珍しく、生涯に数点しか描いていないはずである。モディリアーニの左2つ目はジョン・ケインの「庭の階段を下る少女」。
(site : www.barnesfoundation.org)
| ||

| ||
|
Room 19 South Wall(部分・東側)
真ん中の絵はアンリ・ルソーの「Portrait of a Woman in a Landscape」。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 19 East Wall
中央の絵はピカソの「曲芸師と幼いアルルカン」。その2つ左は、同じく「肘掛け椅子に座る子供」。バーンズ・コレクションのピカソ作品はピカソ20歳台の作品に偏っているが、展示されている作品はどれも文句なしの傑作である。左端のピカソの上にあるのは、マティスがマドラス頭巾の夫人を描いた作品。Room 15 South Wall に同じ画題の作品があった。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 20 South Wall
Room 20, 21, 22 にはアフリカの彫刻が置かれている。この South Wall の真ん中の絵は、18世紀のヴェネチアの風俗画家、ピエトロ・ロンギの「仮面パーティの室内」(Interior Scene - Masked Party)。その左側の絵と右側の絵は、セザンヌが水彩で描いたサント・ヴィクトワール山。その他、Room 20 にはグラッケンズ(East Wall と North Wall)やルオー(West Wall)がある。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 21 South West View
South Wall(左) のモディリアーニの「背中を見せて横たわる裸婦」の下は、ルノワールの「サンジャン半島」。West Wall(右)には、マネの「庭の若い女」があり、その右のアフリカの彫刻に隠れているのは、ユトリロがシャルトルのサンテニャン教会(Saint-Aignan)を描いた絵。なお、Room 21 の North Wall にはスーティンの作品、East Wall にはトルコ出身のアーティスト、カルディスの作品がある。
( site : www.artnet.com )
| ||

| ||
|
Room 22 North Wall
ギャラリーの「順路」も終わりに近くなって出会うロートレックの絵には強い印象を受ける。「モンルージュにて ~ 赤毛のローザ」という作品で、強い印象の理由は、このような19世紀のリアリズムの絵がこのコレクションには少ないからだと思われる。ロートレックの左上にある大きめの作品は、フランスのキュビズムの画家・フレネーの「結婚生活」。その左下はマティスの「ニースの室内(鏡台で読書する女)」。この画像の右に Room 21 との出入り口があるが、その上に飾られているのはジョン・ケインの「農場」。なお、Room 22 East Wall には20世紀アメリカのアーティスト、メシボブの作品がある。
( site : brunoclaessens.com )
| ||

| ||
|
Room 22 - South West View
この画像の右端(West Wall)に見える大きめの絵は、イタリアの画家、アフロ・バサルデラ(Afro Basaldella)の「St. Martin(Saint Martino)」。その上に、パウル・クレーの「岩の間の村」(Village Among Rocks - Ort in Felsen)がある。その左は、フランスの画家・ロティロンの「バックギャモンをする二人の男」(上)と、パスキンの「Southern Scene」(下)。出入り口の上はグラッケンズの「工場のある風景」。
(site : www.whyy.org)
| ||

| ||
|
Room 22 South Wall
2枚のモディリアーニ(「白い服の婦人」「横向きに座るジャンヌ・エビュテルヌ」)の内側には、2枚のピカソの人物画(「女の頭部」「男の頭部」)が配置されていて、真ん中のケースの中にアフリカの民族彫刻がある。この3者の類似点を言いたいのだろうし、「絵はこういう風に鑑賞するものだ」という、ある種の「押しつけがましさ」も感じるが、ここは「私邸」だということを思い起こすべきである。ただ少々驚くのは、ピカソもモディリアーニもバーンズよりは年下(約10歳)の画家だということである。モディリアーニの上にあるのは、左の絵も右の絵もアメリカの画家、チャールズ・デムスの水彩画。モディリアーニとのフォルムの類似性からここに飾られている。さらに、中央上方はマティスの「座像のある室内」で、これはアフリカ彫刻・ピカソ・モディリアーニ・デムスのどれともフォルムの類似性は全くないが、「椅子に腰掛ける女性」という画題がモディリアーニと共通していて、この壁の展示の "落ち" になっている。全体として、連想ゲームの連続という感じである。
( site : www.barnesfoundation.org )
| ||

| ||
|
Room 23 East Wall
中央の絵はルノワールの「コンセルバトワールの出口」。この画像の左端の下の絵は、North Wall のキリコ作「赤い塔」。さらにその左(North Wall 東側)に、画像には映っていないがピカソの「羊と少女」がある。
( site : www.nytimes.com )
| ||

| ||
|
Room 23 North Wall(部分・西側)
大きな絵はマティスの「ヴェネシャン・ブラインド - The Venetian Blinds (ニースのフランス窓)」。その両側の絵(下段)はユトリロの作品(画像非公開)。No.94で紹介したアンリ・ルソーのウサギの絵が Room 19 との出入り口の上lに飾られている。
(site : www.flickr.com)
| ||

| ||
|
Room 23 West Wall
真ん中の大きな絵は、アンリ・ルソーの「不愉快な出会い」(Unpleasant Suprise)。その両サイドの上側の絵は2つともユトリロである(Street:Wineshops、Street:Red Tower)。ルソーの2つ右にある大きめの絵はマティスの静物画「皿とメロン」。画面の一番右の下の絵は、アンリ・ルソーの「セーブル橋の眺め(習作)」。絵には気球が描かれているが、完成作であるプーシキン美術館にある絵は、気球と飛行船と飛行機が描かれている。そのルソーの上にある絵は、ジョン・ケインの「ひな菊を摘む子供」。ルソーとケインを対比させた展示は Room 14 West Wall にもあった。中央のルソーの2つ左の大きめの絵は、ジャン・ユゴーの作品。画面の一番左の上にピカソの作品が見える。なお、Room 23 South Wall にはマティスの「ひょうたんのある静物」がある。
( site : withart.visitphilly.com )
| ||
The Joy of Life Room

| ||
|
Le Bonheur de Vivre Room
バーンズ・コレクションには、マティスの「生きる喜び」が飾られた部屋がある(最初に掲げた見取り図の青い所)。ルオーとピカソのタピストリーが一緒に展示されている。
(The Joy of Life Room) ( site : www.vogue.com )
| ||

| ||
|
アンリ・マティス
生きる喜び(1905/6) ( site : www.barnesfoundation.org ) 遠景に海があり、海から手前までには木々の生い茂る田園風景が広がっていて、そこに16人の男女が憩っている。古典絵画のコンセプトそのものであるが、マティスの表現手法は斬新である。 木々や田園風景に塗られた色は現実とは全くかけ離れていて、多様な色彩が攻めぎあっている。それに合わせるかのように人物の色も各種に塗り分けられている。その人物を描く線も一定していない。正面手前の2本の笛を吹く女性とその後の中景の2人の女性を比較すると、手前の女性がより小さく描かれていて、遠近法を守ろうとする考えはない。 以上のように、この絵は約束事を確信犯的に破るべく描かれているが、それでいてタイトルの「生きる喜び」を直接的に表現しているように感じるから不思議である。この絵が「生きる喜び」と言えるのなら、生きる喜びを表すもっと多彩な表現形式があるはずだと誰しも思ってしまう。 ニューヨークからフィラデルフィアに旅行すると、ピカソの「アビニョンの娘たち」(MoMA)とこの絵を観ることができる。このほぼ同時期に描かれた2作品は、好きだとか嫌いだという次元を超えて、モダン・アートを理解するための必見の作。 | ||
ニューヨークから日帰りをするなら
初めに書いたように、ニューヨークからフィラデルフィアには十分に日帰りができます。そこで日帰りという前提で、バーンズ・コレクションに滞在する時間はせいぜい2~3時間にとどめましょう。そうすると、頑張って朝早めにニューヨークを出発したとして、美術館の閉館時刻までにはまだ時間があります。その時間を利用して、絵の鑑賞が大好きなあなたとしては絶対に行くべき場所があります。バーンズ・コレクションから歩いて行けるフィラデルフィア美術館です。

| ||
|
( site : press.visitphilly.com )
| ||
(次回に続く)
No.94 - 貴婦人・虎・うさぎ [アート]
前回の No.93「生物が主題の絵」で西欧絵画に描かれた動物のことを書きましたが、今回はその補足です。
忠節のシンボルとしての犬
No.93 で引用したヤン・ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(1434)には、夫妻の足もとに一匹の犬(グリフォン犬)が描かれていました。神戸大学准教授で美術史家の宮下規久朗氏によると、この犬は「忠節」のシンボルとして描かれたものです。犬は主人を裏切らないから忠節を表すのです。
この「足もとに一匹の犬が描かれている」ということで気になる作品があります。パリのクリュニー中世美術館にある『貴婦人と一角獣』(1500年頃)という有名なタペストリーです。このタペストリーは2013年に日本に貸し出され、東京では国立新美術館で4月27日~7月15日に展示されました(大阪展は国立国際美術館で、7/27-10/20)。
『貴婦人と一角獣』は6枚のタペストリーから構成され、そのうち5枚の意味(表現しているもの)は明確になっています。つまり「味覚」「聴覚」「視覚」「嗅覚」「触覚」という人間の五感です。しかし最後の一枚、「我が唯一の望みへ」との文字が書かれたタペストリーの意味は謎であり、これまでさまざまな説が提出されてきました。
この「我が唯一の望みへ」をよく見ると、貴婦人の足もとに一匹の犬が描かれている(というより、タペストリーだから織られている)のですね。
この犬は、ひょっとしたらファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』に描かれた犬(ベルギー原産のグリフォン犬)の近縁種ではないでしょうか。格好が似ているし、タペストリーが織られたのはフランドル地方(=ベルギー)です。
しかし犬の種類はともかく、この位置に犬が描かれていることが重要だと思うのです。No.93「生物が主題の絵」での引用を再掲します。
そうだとすると「我が唯一の望みへ」というタペストリーの意味は、次のような解釈が可能になります。
もちろん男性は一角獣によって象徴されているのでしょう。私は美術史家ではないので確定的なことは言えないのですが、いちど専門家に聞いてみたいものです。
虎
虎の生息地はインドから中国大陸・朝鮮半島までの東アジアです。中国文化においては「龍虎」という言い方もあって、強いものの代表であり、画題にされてきました。その中国文化の影響を受けた日本においても虎の絵は多数描かれました。しかし日本に生息していないために、伝聞だけで描いたような絵、大きな猫のような感じの絵もあります。
ヨーロッパも虎の生息地域ではありません。しかしヨーロッパ人のインドからアジアへの進出に従って虎はよく知られるようになり、また19世紀以降のヨーロッパには動物園も作られたので、虎は画題として描かれるようになりました。このうち、19世紀フランスの著名な画家であるドラクロアとジェロームの作品を掲げておきます。いずれも、リアリズムの伝統に従った見事な絵だと思います。
ドラクロアもジェロームも虎の親子を描いていますね。特にジェロームの作品は生まれて間もないような子どもの虎です。
日本で「虎の子」というように、中国を中心とする東アジア文化圏において虎は「子を大切にする動物の典型」と考えられています。「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という諺も、大きな危険(=虎穴に入る)を何故おかすかというと、想定する成果(虎子を得る)が巨大だからです。それは、長年の人々の観察が積み重なっているのだと思います。だから「虎は子を大切にする動物」となった。
ドラクロアもジェロームも、おそらく動物園などにおいて虎を観察し、その習性までを見て描いたのだと考えています。
ウサギ
前回の No.93「生物が主題の絵」で、アルブレヒト・デューラーの野ウサギの絵を引用しましたが、ウサギの絵で見逃せないのがアンリ・ルソーの「The Rabbit's Meal」(1908。フィラデルフィアのバーンズ財団所蔵。題名はバーンズ財団による英語名)という作品です。
No.72「楽園のカンヴァス」で紹介したアンリ・ルソーの絵には動物がしばしば登場しますが、その多くは、どことも知れない熱帯地方の森(や砂漠)の中の光景の中に、人がいて、そこにヒョウやライオンや猿が現れるというものです。No.72で引用した『蛇使いの女』の場合は蛇ですね。
動物だけを「主人公」にして描いたアンリ・ルソーの絵は、このウサギの絵を含め数少ないと思います(あとは、飢えたライオンがカモシカを襲うとか、牧場風景としての牛の絵がある)。絵の題名は The Rabbit's Meal = ウサギの食事(餌)となっていて、どこかの家の庭らしき場所を背景として、丸々と太ったウサギと人参とキャベツの葉が、ポンと投げ出されたように描かれています。ウサギの描写はリアルです。しかし全体としてはちょっと不思議な感じがする絵です。画家は何を描きたかったのでしょうか。
アンリ・ルソーは単にウサギが好きで、その好物とともに描いたのか。それともウサギが人参とキャベツのどちらを食べようかと迷っている姿なのか・・・・・・。あるいは、これ以上食べると太り過ぎになるかと思案しているのか・・・・・・。じっと見ていると、シュルレアリズムの絵のようにも見えてきます。
No.72「楽園のカンヴァス」の補記で紹介したフランスのある画家の言葉をもう一度引用しておきます。この絵を評するにもピッタリだと思うのです。
このコメントのキーワードは「コラージュ」と「前衛的」ですね。ウサギの絵はまさにコラージュという感じがします。
「前衛的」について言うと、原田マハ氏の小説『楽園のカンヴァス』のストーリーでは、当時のパリの批評家や大衆はアンリ・ルソーの絵を嘲笑したけれど、パブロ・ピカソはいち早く評価したという歴史的事実が重要な役割を担っていました。ピカソはルソーの絵のどこに惹かれたのでしょうか。おそらく「シュルレアリズムにつながる前衛性」なのでしょう。
この絵には「ウサギの食事」という題名がついていますが、もし仮に「哲学者」という題名なら、ないしは「これはウサギではない」という題名なら、ルネ・マグリットの絵だと言っても通用するのでは・・・・・・と思ったりします。それは半ば冗談ですが、しかしマグリットはアンリ・ルソーから決定的な影響を受けているはずです。
・・・というような、いろいろな思いを起こさせる「ウサギの絵」です。
忠節のシンボルとしての犬
No.93 で引用したヤン・ファン・エイクの『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(1434)には、夫妻の足もとに一匹の犬(グリフォン犬)が描かれていました。神戸大学准教授で美術史家の宮下規久朗氏によると、この犬は「忠節」のシンボルとして描かれたものです。犬は主人を裏切らないから忠節を表すのです。
この「足もとに一匹の犬が描かれている」ということで気になる作品があります。パリのクリュニー中世美術館にある『貴婦人と一角獣』(1500年頃)という有名なタペストリーです。このタペストリーは2013年に日本に貸し出され、東京では国立新美術館で4月27日~7月15日に展示されました(大阪展は国立国際美術館で、7/27-10/20)。
『貴婦人と一角獣』は6枚のタペストリーから構成され、そのうち5枚の意味(表現しているもの)は明確になっています。つまり「味覚」「聴覚」「視覚」「嗅覚」「触覚」という人間の五感です。しかし最後の一枚、「我が唯一の望みへ」との文字が書かれたタペストリーの意味は謎であり、これまでさまざまな説が提出されてきました。
この「我が唯一の望みへ」をよく見ると、貴婦人の足もとに一匹の犬が描かれている(というより、タペストリーだから織られている)のですね。

| ||
|
「貴婦人と一角獣 - 我が唯一の望みへ」 (パリ。クリュニー中世美術館) | ||

| |||
しかし犬の種類はともかく、この位置に犬が描かれていることが重要だと思うのです。No.93「生物が主題の絵」での引用を再掲します。
|
そうだとすると「我が唯一の望みへ」というタペストリーの意味は、次のような解釈が可能になります。
| 味覚・聴覚・視覚・嗅覚・触覚という五感を超越し、人にとって最も尊い感覚は愛。私は愛に生き、あなたへの忠節を誓います。 |
もちろん男性は一角獣によって象徴されているのでしょう。私は美術史家ではないので確定的なことは言えないのですが、いちど専門家に聞いてみたいものです。
虎
虎の生息地はインドから中国大陸・朝鮮半島までの東アジアです。中国文化においては「龍虎」という言い方もあって、強いものの代表であり、画題にされてきました。その中国文化の影響を受けた日本においても虎の絵は多数描かれました。しかし日本に生息していないために、伝聞だけで描いたような絵、大きな猫のような感じの絵もあります。
ヨーロッパも虎の生息地域ではありません。しかしヨーロッパ人のインドからアジアへの進出に従って虎はよく知られるようになり、また19世紀以降のヨーロッパには動物園も作られたので、虎は画題として描かれるようになりました。このうち、19世紀フランスの著名な画家であるドラクロアとジェロームの作品を掲げておきます。いずれも、リアリズムの伝統に従った見事な絵だと思います。

| ||
|
ドラクロア「母虎と戯れる子虎」(1831) (ルーブル美術館) | ||

| ||
|
ジェローム「虎と子虎」(1884) (メトロポリタン美術館) | ||
ドラクロアもジェロームも虎の親子を描いていますね。特にジェロームの作品は生まれて間もないような子どもの虎です。
日本で「虎の子」というように、中国を中心とする東アジア文化圏において虎は「子を大切にする動物の典型」と考えられています。「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という諺も、大きな危険(=虎穴に入る)を何故おかすかというと、想定する成果(虎子を得る)が巨大だからです。それは、長年の人々の観察が積み重なっているのだと思います。だから「虎は子を大切にする動物」となった。
ドラクロアもジェロームも、おそらく動物園などにおいて虎を観察し、その習性までを見て描いたのだと考えています。
ウサギ
前回の No.93「生物が主題の絵」で、アルブレヒト・デューラーの野ウサギの絵を引用しましたが、ウサギの絵で見逃せないのがアンリ・ルソーの「The Rabbit's Meal」(1908。フィラデルフィアのバーンズ財団所蔵。題名はバーンズ財団による英語名)という作品です。

| ||
|
アンリ・ルソー「The Rabbit's Meal」 (Le Repas du lapin. 1908) (バーンズ財団) | ||
No.72「楽園のカンヴァス」で紹介したアンリ・ルソーの絵には動物がしばしば登場しますが、その多くは、どことも知れない熱帯地方の森(や砂漠)の中の光景の中に、人がいて、そこにヒョウやライオンや猿が現れるというものです。No.72で引用した『蛇使いの女』の場合は蛇ですね。
動物だけを「主人公」にして描いたアンリ・ルソーの絵は、このウサギの絵を含め数少ないと思います(あとは、飢えたライオンがカモシカを襲うとか、牧場風景としての牛の絵がある)。絵の題名は The Rabbit's Meal = ウサギの食事(餌)となっていて、どこかの家の庭らしき場所を背景として、丸々と太ったウサギと人参とキャベツの葉が、ポンと投げ出されたように描かれています。ウサギの描写はリアルです。しかし全体としてはちょっと不思議な感じがする絵です。画家は何を描きたかったのでしょうか。
アンリ・ルソーは単にウサギが好きで、その好物とともに描いたのか。それともウサギが人参とキャベツのどちらを食べようかと迷っている姿なのか・・・・・・。あるいは、これ以上食べると太り過ぎになるかと思案しているのか・・・・・・。じっと見ていると、シュルレアリズムの絵のようにも見えてきます。
No.72「楽園のカンヴァス」の補記で紹介したフランスのある画家の言葉をもう一度引用しておきます。この絵を評するにもピッタリだと思うのです。
|
このコメントのキーワードは「コラージュ」と「前衛的」ですね。ウサギの絵はまさにコラージュという感じがします。
「前衛的」について言うと、原田マハ氏の小説『楽園のカンヴァス』のストーリーでは、当時のパリの批評家や大衆はアンリ・ルソーの絵を嘲笑したけれど、パブロ・ピカソはいち早く評価したという歴史的事実が重要な役割を担っていました。ピカソはルソーの絵のどこに惹かれたのでしょうか。おそらく「シュルレアリズムにつながる前衛性」なのでしょう。
この絵には「ウサギの食事」という題名がついていますが、もし仮に「哲学者」という題名なら、ないしは「これはウサギではない」という題名なら、ルネ・マグリットの絵だと言っても通用するのでは・・・・・・と思ったりします。それは半ば冗談ですが、しかしマグリットはアンリ・ルソーから決定的な影響を受けているはずです。
・・・というような、いろいろな思いを起こさせる「ウサギの絵」です。
No.93 - 生物が主題の絵 [アート]
No.85「洛中洛外図と群鶴図」で、尾形光琳(1658-1716)の「群鶴図屏風」(米国・フリーア美術館蔵)のことを書きました。この六曲一双の屏風には19羽の鶴が描かれているのですが、西洋の絵画と対比したところで、
と書きました。
確かに近代までの西洋の絵画は圧倒的に人物が中心で、宗教画・神話画・歴史画・肖像画・自画像など、人物(ないしは神や聖人)が画題になっています。中には「希望」「哲学」「妬み」といった抽象概念を擬人化して人物の格好で表した絵まである。「そこまでやるか」という感じもするのですが、とにかく人物が溢れています。人物画の次は静物画や風俗画、近代以降の風景画でしょうか。光琳の群鶴図のような野生動物はもとより、動物・植物・昆虫などの生物を描いた有名な絵はあまり思い当たらなかったのです。今回はそのことについての随想を書いてみたいと思います。
もちろん動物が登場する絵はいっぱいあります。たとえばNo.87「メアリー・カサットの少女」で感想を書いた、メアリー・カサットの『青い肘掛け椅子の少女』(1878)です。
グリフォン犬
『青い肘掛け椅子の少女』では、少女の向かって左の椅子に寝そべっている犬がいます。この犬については、No.86「ドガとメアリー・カサット」でメアリーの伝記から引用しました。
メアリー・カサットはグリフォン犬をたいそうかわいがったようです。他の絵にもこの愛犬が登場します。下の絵は『Young Girl at a Window』(1883/4。コーコラン美術館 - Corcoran Gallery of Art。ワシントン DC)という作品です。スーザン・マイヤーの伝記では『犬を抱いてバルコニーに座るスーザン』というタイトルで紹介されている絵です。
グリフォン犬(現代で言うブリュッセル・グリフォン)はベルギー原産の犬です。ドガがグリフォン犬の子犬をメアリー・カサットのために骨を折って見つけ出したと伝記にありますが、19世後半のパリでは貴重な犬だったことをうかがわせます。
そしてこのグリフォン犬に関してなのですが、メアリー・カサットの時代の450年以上前のベルギーで、この犬を描いた絵が制作されているのです。それは、西洋美術史では「超」がつくほど有名な絵画です。
ファン・エイク:アルノルフィーニ夫妻の肖像
ロンドン・ナショナル・ギャラリーにある『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(1434)は、ヤン・ファン・エイク(1390頃 - 1441)の作品です。ファン・エイクはブルッヘ(仏語・英語名はブルージュ。現在のベルギー、当時はフランドルの都市)を中心に活躍した画家です。ファン・エイクは西洋における油絵を完成させた人と言われていますね。精緻に描くその技法は、のちの西洋絵画に多大な影響を与えました。
この絵の夫妻の足もとにいる犬がグリフォン犬です。犬の「容貌」は、現代のブリュッセル・グリフォンやメアリー・カサットが描く犬とも少々違いますが、それは数百年の年月の経過を考える必要があります。犬や猫といった家畜は品種改良が行われるからです。
メアリー・カサットのグリフォン犬は彼女のペットでした。では『アルノルフィーニ夫妻の肖像』のグリフォン犬もペットなのでしょうか。どうもそれは違うようなのです。
神戸大学准教授で美術史家の宮下規久朗氏の著書『モチーフで読む美術史』(ちくま文庫。2013)には『アルノルフィーニ夫妻の肖像』を解説して次のように書かれています。
宮下先生の解説にあるように、この絵において「犬」は特定の意味をもつシンボルとして描かれています。そして西洋の絵画における動物や生物は、主題(この絵の場合夫妻、ないしは夫妻の結婚)を補足するサブの存在として描かれ、かつ「シンボル」として使われることが大変に多いのです。
西洋画における生物
『アルノルフィーニ夫妻の肖像』に典型的にみられるように、西洋画における「生物」は、まず「シンボル」として描かれるケースが思い浮かびます。宗教画(キリスト教絵画)では数々の「象徴」があります。鳩は聖霊の象徴で、平和の象徴でもあるというたぐいです。聖人の持物(じもつ = アトリビュート)としての生物もあります。つまり人物が誰かを見分けるための伝統的な道具や動物で、鶏が描かれていれば、そばの人物はペテロという感じです。
シンボルやアトリビュートとしての生物はいろいろあり、羊、驢馬、鴉、蛇、魚、百合、葡萄、石榴、棕櫚、などが思いつきます。こういったシンボルは宗教画以外にも進出しています。No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」で、英国の画家・ミレイが「サン・バルテルミの虐殺」の当日を描いた作品を紹介しましたが、その絵のトケイソウ(Passion Flower)は受難の象徴でした。
ギリシャ・ローマ神話を描いた絵にも、神話に登場する動物や植物、果実がいろいろあります。鷲や雄牛がゼウスの化身だとか、林檎がヴィーナスの持ち物だとかです。
宗教・歴史・神話を離れて、一般的な寓意を表す生物もあります。『アルノルフィーニ夫妻の肖像』の犬は「忠節」の象徴でした。No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したブリューゲルの「絞首台の上のかささぎ」では、かささぎが「偽善」や「告げ口」といった意味を持っていました。豚が「貪欲」の象徴のこともあります。
もちろん絵の主題の一部として描かれた生物もあります。乗馬や競馬や狩猟の情景の馬とか、風俗画における家畜や、家庭内のペット(犬や猫、小鳥)、牧場風景の牛や羊などです。
また、静物画の動植物もあります。獲物としての動物(兎、鳥、など)、肉、魚介類、野菜、果物(石榴、葡萄、林檎、梨)などです。花瓶の花や花束も静物画の一大ジャンルになっています。しかしフランス語で静物画のことを "nature morte"(=死んだ自然)と言うように、これらは生きているわけではありません。
西欧の絵画で生物が描かれるのは、上記のような「シンボル」「象徴」「主題の一部」「静物」というのがよくあるケースであり、生物そのものが主題という絵はそう多くはないようです。少なくとも、欧米の第1級の美術館ではあまり見かけないわけです。
日本の「生物画」
一方、日本の伝統的では生物を主役とする絵画が大きなポジションを占めています。ここで、静物画ならぬ「生物画」を次のように定義するとします。
この意味での「生物画」が日本画には非常に多いわけです。
樹木は日本画の一大ジャンルになっています。「松」「梅」「桜」「竹」「柳」「楓」「桐」「椿」「槙」「柿」などは、繰り返し画題になってきました。
草花では、「朝顔」「杜若」「菖蒲」「花菖蒲」「牡丹」「紫陽花」「罌粟」「菊」「葵」「芙蓉」「百合」「藤」「つつじ」「桔梗」「芭蕉」などが思い浮かびます。「春・秋の七草」も画題の中心です。各種の「野菜」も描かれました。
鳥では、「鶏」「雀」「鴉」「鶴(光琳の群鶴図など)」「白鷺」「百舌」「鴛鴦」「孔雀」「鷹」「雁」「鴨」などでしょう。伊藤若冲は、かなりの数の鶏の絵を描いていますね。自分で飼育して観察したようです。
動物では、「犬」「猫」「猿」「鹿」「牛」「栗鼠」などです。江戸後期の森狙仙を開祖とする「森派」は、猿の絵で有名です。なお、虎は日本に生息しないので伝聞で描かれた絵が多いのですが、「虎」も超有力な画題です。
魚では、静物ではない生きた魚(水の中で泳ぐ魚)を描くのが日本画の特徴です。「鯉」「鮎」「鯰」「亀」(爬虫類ですが)などです。昆虫を描いた絵もあります。「蝶」「蛍」「蜻蛉」などです。
伊藤若冲の「動植綵絵」(最初にプルシアン・ブルーを使った作品。No.18「ブルーの世界」参照)は、こういった生物たちを総体的に描いた絵です。また、さまざまなモチーフを組み合わせた「花鳥図」「草木図」も、歴史上、多数制作されました。
No.30「富士山と世界遺産」で「特定の山を主題に描いた絵は西洋に少ない」と書きました。例外的に思い浮かぶのは(有名な画家では)セザンヌとホドラーぐらいだと・・・・・・。一方、日本では(近代以降は)全く逆です。これは昔から「山」を信仰の対象にしていた日本と、19世紀までは「山に名前をつけることさえ一般的でなかった」西洋との文化的相違と考えるのが妥当でしょう。
日本では「生物画」がメジャーであり、西洋ではそうではないということについて、安易な解釈をするのは禁物ですが、やはり「永遠なるもの」「神聖なるもの」を何に感じるかという、人の心の相違だと考えられます。
西洋における「生物画」の傑作
しかし、よくよく考えてみると「野生動物を主題にした西洋絵画はあまり思い当たらない」というのは速断すぎました。西洋絵画にも「生物画」はあり、野生動物の絵もあります。絵というのは主題の自由さ(何でもよい)が特長なのです。
西洋絵画の「生物画」の何点かの絵、特に印象的な絵画を(個人的主観で)あげてみます。まず最初は、カサットやファン・エイクの作品に描かれていた犬で、犬だけを描いた作品です。
18世紀イギリスの画家、ゲインズバラがポメラニアンの親子を描いた作品です。テート・ギャラリーの公式サイトによると、ゲインズバラの友人にエイベルというヴィオラ・ダ・ガンバの名手がいて、二人で演奏することもあった。この絵は音楽のレッスンを受けた謝礼に、エイベルの飼い犬を描いたもの、とあります。
親犬は何かの物音に気づいたように、耳をたて、左の方向を凝視しています。一方の子犬は、親犬とは無関係に下の方の何かに気を取られています。その2匹を対比させた描き方がうまいと思います。立派な毛並みは、いかにも上流階級の飼い犬といった雰囲気です。
イタリア出身の政治家・銀行家で東洋美術コレクターだったアンリ・セルヌッシ(チェルヌスキ)の愛犬、タマを描いた作品です。日本犬というタイトルのとおり、この犬は日本原産の狆です。セルヌッシは日本に旅行し、この犬を持ち帰りました。タマの前に転がっているのは日本人形のようです。
1世紀前のゲインズバラの絵と比べると、マネのこの絵は19世紀後半の絵画らしくスピーディで荒い筆致で描かれています。それによって、小型犬のすばしっこい様子や、舌を出したり、きょろきょろと辺りを見たりといった愛らしさが表現されています。
日本人的感覚から言うと「タマ」は猫の名前ですが、この場合のタマは日本語の "玉" で、宝石の意味のようです。飼い主はこの犬をたいそう可愛がったようで、ルノワールにもマネと同時期にタマの絵の制作を依頼しています。分かりにくいですが、TAMAと絵の左上に書いてあるのもマネの絵と同じです。
なお、マネの描いた犬の絵では他に『キング・チャールズ・スパニエル犬』があります。この絵もまた、ワシントン・ナショナル・ギャラリーの所蔵です。イギリス原産の犬で、その名のとおりイギリス王室の愛玩犬でした。
フランスの画家、ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)は「生物画」を描いています。画題としては、鹿、狐、鱒、樫の木などがあり、野生生物を描いているのが特長です。その「鹿」と「樫」の例を下に掲げます。
鹿を画題とする絵は何点かあって、野生の鹿、追われる鹿、死んだ鹿と、狩猟という視点での一連の作品があります。下に掲げたブリジストン美術館の絵も狩猟で追われている鹿を描いたのでしょう。また、東京の国立西洋美術館には『罠にかかった狐』という絵がありますが、これらの絵をみても「狩猟画の延長、ないしは変型としての動物画」という感じです。
西欧にも木を描いた絵がありますが、多くは風景の一部としての木、ないしは森や林の情景の中の木であり、樹木だけを主体的に描いたものは少ないと思います。このクールベの樫の絵は、巨木の存在感を描くことに徹したものです。
余談ですが、上の絵の「樫」と訳されている絵は、原題では「Le Chêne de Flagey(The Oak of Flagey)」です。Chêne(Oak。オーク)はコナラ属の木の総称ですが、日本語でそれに相当する樹は、樫(常緑性)や楢(落葉性)です。ヨーロッパのオークは多くが落葉性で、クールベが描いた樹も絵からすると日本で言う「楢」ですね。オークは古代ヨーロッパから神聖な樹とされてきました。
クールベは絵画史で「写実派」とされています。要するに「想像では描かない」わけです。その画題は、人物、自画像、風俗(葬儀の場面、画家のアトリエ、など)自然の風景、海岸に打ち寄せる波、石割り人夫、ヌード、女性の下半身(オルセー美術館の有名な絵)と多岐に渡っていて、そういった「写実の目」は野生生物にも向けられたわけです。
クールベの樫の絵を引用したので、別の樫の絵を掲げます。ロシアの風景画家、シーシキンの作品です。
シーシキンは、特に樫の木立や森をテーマにすることを好んだようです。その中でもこの絵は "樫の大木そのもの" を描こうとしています。一般に森や林を描いた風景画には樹木が描かれますが、それはあくまで「風景の一部としての樹木」です。そうではなく「樹木そのものに焦点を当てて描く」ということには意味があると考えられます。
つまり我々は大木や巨木に出会うと、人間の寿命よりはるかに長い時間(数百年、時には1000年以上)をかけて成長し、風雪に耐えて生きながらえ、現在も成長を続けているという実感を持つことができます。木に触れたり叩いたりしてもビクともせず、そこに屹立している。その重量感と実在感に圧倒されるわけです。さらに、最初はごく些細な芽生えであったはずのものが長い年月の間に数10トンもの巨大な存在になるという "生命の不思議さ" を感じ、そこまでになる植物の生命力に打たれることにもなります。
それが高じると「人智を遙かに超えたもの」を感じてしまい、神聖なものとしてとらえることになります。日本の古来の伝統では、大木や巨木に神が宿る(ないしは降臨する)という概念があり、注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にあります。こういった感性は程度の差はあれ、森林が多い地域に発生した文化に共通です。
クールベとシーシキンの絵を見て思うのは、画家が樹木そのものを描こうと思った動機が、上に述べたような感性(のどれか)にもとづくのではないかということです。さらに思うのは、大木や巨木に向き合ったときに人が覚える感動とか感慨をカンヴァスに表現するためには、リアリズム絵画の手法こそ有効だということです。印象派以降の絵画手法ではそうはいかないでしょう。シーシキンのこの絵は、パリで印象派が全盛の頃に描かれたものですが、改めてリアリズム絵画の意味を考えされられます。
馬は西洋では非常になじみのある家畜です。現在でもヨーロッパの都市の大きな公園に行くと、乗馬している人とすれ違ったりします。公園に乗馬道があるのです。
そういった文化的伝統からか、馬を描いた絵もいっぱいあります。多くは人が騎乗した姿ですが、狩りの情景や競馬のシーンなどの「風俗画」もあります。下の絵はフランスの女性画家、ローザ・ボヌール(1822-1899)の『馬市』(1853)という作品。メトロポリタン美術館の「人気コーナー」であるヨーロッパ近代絵画の展示室にあり、幅5メートルという巨大な絵なので、いやがおうでも目につきます。メトロポリタン美術館を訪れた日本人は多いと思いますが、(この絵は展示替えがないだろうという前提で)ほぼ全員が目にしているはずの絵です。
この絵はパリ郊外の「馬市」を描いた一種の「風俗画」ですが、馬を描くこと自体が目的という感じがします。
馬だけを描いた絵もあります。フランスの画家、テオドール・ジェリコーやエドガー・ドガは馬そのものを主題とした作品を制作しています。またボヌールも馬だけの絵を多数描いています。
馬だけの絵で最も印象深いのは、英国の画家、ジョージ・スタッブス(1724-1806)が描いた『Whistlejacket』(1762頃)で、『アルノルフィーニ夫妻の肖像』と同じく、ロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵しているものです。Whistlejacket という名前の競争馬を描いたものですが、3m × 2.5m という大きなカンヴァスに、背景なしで馬だけが描かれています。スタッブスの絵はこれしか見たことがないのですが「馬の画家」と呼ばれていて、馬をかなり描いているようです。
ロンドンのナショナル・ギャラリーを訪れると、この絵がやけに印象的です。私の経験からですが「ロンドン・ナショナル・ギャラリーにおいて、予備知識が全く無いという前提で鑑賞して、最も印象的な作品」ではないでしょうか。要するに、こういうタイプの絵が珍しいからインパクトが強いのだと思います。
なお、ジョージ・スタッブスは馬だけでなく、動物園で観察したライオンやカンガルーをはじめ、各種の動物を描いたようです。また『馬市』のローザ・ボヌールも、牛・羊・山羊・狐・鹿・犬といった動物の絵を多数描いています。
動物画を描くということにおいてスタッブスはボヌールの「先輩」にあたるわけですが、さらにその先輩がいます。オランダの画家、パウルス・ポッテル(1625-1654)です。ポッテルは牛や馬といった家畜を多数描いています。
この絵はルーブル美術館のフランドル絵画のエリアにある、Le Cheval Pie(英語題名は The Spotted Horse。まだら馬)と題する絵です。ボヌールやスタッブスの絵とは違って、この絵は 40cm×30cm という小品です。しかし斑の馬の確かな造形が光っています。ボヌール、スタッブス、ポッテルのように動物画を主体に描いた画家は、私が知らないだけで、もっとあると想像されます。
牛については「馬市」と同じく、ローザ・ボヌールが印象的な絵を描いています。オルセー美術館の「ニヴェルネー地方の耕作」という絵です。
これは「農村風景」を描いた絵ですが、オルセー美術館で実際に見ると、明らかに牛を描くことが目的の絵だということがよくわかります。幅2.6メートルの大きな絵で、牛の力強さが迫ってきます。パリを訪れる日本人の大多数はオルセー美術館に行くと思うので、この絵も「馬市」と同じく(展示替えがないだろうという前提で)多くの人が目にしているはずの絵です。
牛を描いた絵では、オランダの首都、デン・ハーグに傑作があります。
デン・ハーグ : マウリッツハイス美術館
オランダの首都、デン・ハーグに「マウリッツハイス美術館」があります。貴族の館を改装した非常に小さな美術館(正式名称:王立絵画陳列室)ですが、ここにはフェルメール(1632-1675)が3点あります。中でも、
は超有名作品です。フェルメール作品は「傑作」と「普通の絵」の2つに分かれると思うのですが(どんな画家でもそうですが)、この2つは傑作中の傑作でしょう。
その他の作品ですが、レンブラント(1606-1669)の
も有名な絵画です。
しかしこの美術館の「みどころ」は他にもあります。それは、同じ年に30歳前後で夭折した二人のオランダ人画家が描いた「生物画」です。
一つは、ルーブルの馬の絵を描いた、パウルス・ポッテルの『雄牛』(1647)です。この『雄牛』は2.5m×3.5m程度の非常に大きな絵で、中心に描かれた雄牛は実寸大です。雄牛の生命力が大変な迫力で迫ってくる絵です。
もう一つの作品は、カレル・ファブリティウス(1622-1654)の『ごしきひわ』(1654)です。ポッテルとはうってかわった 33.5cm×22.8cm という小さな作品で、ペットとして飼われていた小鳥(足に鎖がついている)をシンプルに描いています。壁が背景なので、この絵を家の壁に飾っておくとあたかも小鳥がそこにいるような感覚になるでしょう。一種のだまし絵的な要素のある絵ですが、造形の確かさと美しい色使い、小鳥の部分の軽やかな筆運びが印象に残る作品です。
動物画の画家
今まで引用したなかに、主に動物画を描いた画家がいます。年代順にあげると、
の3人です。活躍した世紀も国も違いますが、こうしてみるとヨーロッパには動物画の歴史や流れがあることが推測できます。そうした画家の一人が、スウェーデンのリリエフォッシュです。スウェーデンの画家というと、我々はカール・ラーション(1853-1919)ぐらいしか知らないのですが、リリエフォッシュも本国では有名な画家のようです。
ブルーノ・リリエフォッシュ(Bruno Liljefors、1860-1939)は19世紀末から20世紀初期にかけて活動した画家で、動物画を得意としていました。彼の動物画の多くの特徴は、
というものです。もちろん動物を描くためには観察が必要です。画家は自然の中に家とアトリエを建て、野生動物を捕獲してケージで飼育し、その観察をもとに描きました。あるいは、狩猟の獲物を観察して描くこともしたようです。私は実物の絵を見たことがないのですが、リリエフォッシュの2作品を引用します。
一見するとキツネは1匹のようですが、右端に寝そべっているもう1匹がいます。おそらく画家はキツネの習性を観察し、2匹のこの瞬間を絵にしたのだと思います。
季節は秋で、背景は色づき始めた木の葉で埋め尽くされています。その中に小鳥が3羽、配置されている(コガラだと思います)。自然の中のキツネという雰囲気を盛り上げています。
イェーテボリ美術館の解説によると、このキツネは同じ年の春に生まれた若いキツネとのことです。いかにも柔らかそうな、ふさふさした毛並みがそれを表しています。
オオタカの幼鳥が雷鳥(クロライチョウ)を襲った瞬間を描いています。真冬の、あたり一面に雪が舞う中で、オオタカが雷鳥の群を狙い、その中の一羽を襲う。オオタカの右下に描かれているのはクロライチョウの雌でしょう。雌は黒ではなく茶色をしています。オオタカが "つがい" のクロライチョウを襲ったという想定です。
スウェーデン国立美術館の解説によると、リリエフォッシュは狩猟でしとめたオオタカの幼鳥とクロライチョウを林の中に持って行き、この絵をすべて戸外で描いたそうです。もちろんそれだけでは、この絵の迫真の感じは出せないでしょう。画家はオオタカが獲物を襲う瞬間をよく観察したのだと思います。その観察の成果が現れているようです。
雪が舞い、クロライチョウの群が逃げ出す背景は、淡い色使いの幻想的な描き方です。その中で、狩りの瞬間が極めてリアルに描写されている。その対比も光っていると思います。
ウィーン : アルベルティーナ美術館
ウィーン市内の中心部にアルベルティーナ美術館がありますが、ここにアルブレヒト・デューラー(1471-1528)の「生物画」の傑作があります。
まず、有名な『野兎』(1502)です。水彩・グアッシュで紙に描かれた25cm程度の小さな絵ですが、ウサギの毛の細密描写が見事です。
さらにこの美術館では、同じデューラーの『芝草』(1503)が非常に印象的な作品です。『野兎』と同じく水彩・グアッシュの絵で、40cm ×31.5cm の大きさです。描かれているのは芝草、イネ科の植物らしい草、タンポポ、アザミなど、日常生活の周辺のどこにでもありそうなものです。日本でも十分にありうる光景と言っていいでしょう。
西欧では「ボタニカル・アート」という絵のジャンルがありますね。花や草などの「植物だけを背景なしに描いた絵」ですが、ボタニカル(=植物学)というだけあって記録ないしは学術的意味に重点が置かれている絵です。
しかしデューラーの『芝草』はボタニカル・アートではありません。描かれているのは、どこにでもある「雑草」です。その雑草に目を向け、一つの作品(素描)に仕上げた画家の「目」に注目したいと思います。
ひるがえって考えてみると、実は「雑草」は日本画の伝統的なモチーフです。一つだけ例をあげると、たとえば酒井抱一(1761-1829)の『夏秋草図屏風』(1821。東京国立博物館所蔵)です。
日本では春の七草、秋の七草などと言われます。これらの草の中で、桔梗や撫子などの可憐な花をつける草はともかく、春のセリ、ナズナ、ハコベ、秋のフジバカマ、クズ、オミナエシなどは、その草の名前を知らない人にとっては「雑草」としか見えないでしょう。しかしそういった草に名前をつけ、年中行事に使い(七草粥など)、画題にもしてきたのが日本の文化的伝統です。
デューラーの『芝草』、そして『野兎』を見て感じるのは、日本画にも通じる画家の目です。文化はいったん確立すると拡大・再生産されます。一方では生物を画題とする絵が綿々と作られ、他方では宗教画や人物画が自律運動的に広がっていく。しかしそういった文化的伝統の相違を除いてみると、「画家の目」は日本でも西欧でも似ているのではないか・・・・・・。デューラーの絵をみたとき、そういった思いに駆られました。と同時に、絵画は「何を描くか」もあるが「どう描くか」が重要である・・・・・・。デューラーと抱一の絵で感じるのはそのことです。
ゴッホ
近代以降の画家で "生物画" を多数描いたのは、ゴッホが一番でしょう。その画題は、
などです。果樹や樹木の絵では、花が咲く頃を描いたものが多くあります。またこれ以外に、数は少ないですが、鳥(カワセミ)や昆虫(蛾、蝶)を描いた作品もあります。
花に関して言うと、もちろんゴッホは静物画としての花の絵(=花瓶に飾られた切り花の絵)を多数描いていますが、それとあわせて大地に生えている草や木に花が咲いている姿を画題として描いている。生命の息づかいを描いたということで、画家として特徴的だと思います。その例を引用したいのですが、ゴッホの "生物画" は多数あります。何をあげるか迷うのですが、アイリスの絵にします。
アイリスは日本で言うアヤメです。ないしはアヤメ属の花を指すものとすると、「アヤメ」「ハナショウブ」「カキツバタ」「イチハツ」などです(そもそもこれらの種は見分けにくい)。
アヤメ類は日本画では定番の画題の一つで、誰しも思い出すのは尾形光琳の「燕子花図屏風」(根津美術館)でしょう。日本画と比較してみるのもおもしろいと思います。
このゴッホの作品はサン・レミの療養院の時代の絵です。群生するアヤメが、ゴッホらしい鮮やかな色彩で生き生きととらえられています。この絵から受ける印象は、あでやかで大ぶりの花をつけるアヤメの生命力です。それを描きたかったのだと思います。
モネ
ゴッホと同時代の画家では、モネが花や樹木の "生物画" を描いています。もちろん有名なのは『睡蓮』を描いた一連の(数百の)作品です。ただこの連作のほとんどの作品は "睡蓮の池" に焦点があり、特に時間や天候によって千変万化する様子を描いています。睡蓮の花だけを描いた作品もありますが一部です。というわけで「睡蓮シリーズ」はここでは割愛します。
睡蓮以外に目を向けると、モネは、アイリス、バラ、リンゴの花、クレマティスなどを描いています。その中からゴッホつながりで、国立西洋美術館が所蔵するアイリスの絵を次に引用します
この絵について、国立西洋美術館のサイトには次のような説明がしてありました。
確かにこの絵は装飾性が強く、縦長の大画面は日本趣味を感じさせます。一方、同じ黄色いアイリスの絵で全くイメージの違った絵がパリのマルモッタン・モネ美術館にあります。
マルモッタン美術館というと『印象・日の出』で有名な美術館ですが、この絵も記憶に残る絵です。その理由は "アイリスと空" という取り合わせでしょう。樹木の花と空という組み合わせならともかく、草花と空を描くのは日本画にはあまりありません。そもそも日本画には空を描いた絵が少ない。一部の浮世絵だけでしょう。
というわけで、この絵は国立西洋美術館の絵の "日本趣味" とは全く違っています。アングルも地表からアイリスを見上げたような構図になっていて、モネならではの作品だと思います。
モネは若い時に、鳥を主題にした作品を描いています。それが次の『七面鳥』です。
画題もめずらしいが、正方形のカンヴァスも一般的ではありません。これは、当時モネのパトロンだった美術愛好家、エルネスト・オシュデの注文で、パリ郊外のモンジュロンにあったオシュデの別荘を飾るために描かれた作品です。別荘に放し飼いにされていた七面鳥を描いています。
木陰に10数羽の鳥がいますが、描き方は木々や草むらと似ていて、庭の風景の一部になっているような感じを受けます。正方形のカンヴァスも含めて、別荘の壁にかける装飾画ということが関係しているのでしょう。
生物を描く
以上、20世紀初頭までの作品をあげましたが、もちろん現代作家も "生物画" を描きます。実際に見たことのある現代作家の絵で印象的だったのは、スペインの具象画家、アントニオ・ロペス(1936 -)の『マルメロの木』(1990)です。この絵は日本での「アントニオ・ロペス展」に出品されました(Bunkamura ザ・ミュージアム。2013.4.27 - 6.16)。アントニオ・ロペスは制作時間が長いことで有名で、この絵も「晴れた日の午前中の決まった時間」に少しずつ描くわけです。マルメロの実や葉の白い線は、実際に画家がマルメロにつけた線です。なぜ線をつけるのかと言うと、描いている期間で実が熟して枝が垂れ下がり、全体のバランスが変化してくる。その初期配置を記憶するための線ということらしい。結局、この絵は未完だそうですが、たわわに実ったマルメロと長時間向き合おうとする画家の執念が現れているようです。
以上のように、いろいろ思い出して(かつ確認して)みると、西洋絵画にも動植物を主題にした「生物画」はいろいろあることが認識できます。著名な画家も描いているし、実際に実物を見た絵もいろいろある。なぜ「生物画」はあまりないと(No.85「洛中洛外図と群鶴図」で)思ってしまったのか。
日本画の伝統では「生物画」が主流(の一つ)です。一方、西洋の伝統的な具象画では、宗教・歴史・神話・人物・風景・静物といった画題が主流です。当然、その主流に沿って絵が注文され、画家は画題を選び、絵が取り引きされ、美術館のコレクションがなされ、展示する作品がセレクションされ、美術教育があり、アートに関するジャーナリズムも作られる。われわれ一般人のモノの見方も、その「主流」に添って形成されるわけです。
我々は「見たいと思うものを見る」のであり「見たいと思わないものは見えない、ないしは意識に残らない・残りにくい」のでしょう。どうも、そういうことだと思われました。
日本画
デューラーの『芝草』のところで酒井抱一の絵を引用したので、最後に日本画をもうひとつ引用します。クールべが雪景色の中の鹿を描いた絵を前に掲げましたが、同じ雪景色の中の鹿を描いた日本画です。
川合玉堂という人は、古今東西の著名画家の中でも最もデッサンが上手な画家の一人だと思います。この絵を見るとそれがよく分かる。玉堂が20歳台の作品で、上京した直後あたりのものです。我々がよく目にする玉堂作品というと「日本の自然や風景の中に溶け込んだ人の営み」的なテーマが多いのですが、この絵はそのテーマに至る前の作品であり、1頭の鹿を描くという日本画ではよくあるものです。しかしそれだけに純粋に画力が現れていると思います。
本文中にローザ・ボヌールの『馬市』と『ニヴェルネー地方の耕作』を引用しましたが、この2つの作品の詳しい解説を、
No.266 - ローザ・ボヌール
に掲載しました。
本文中にゴッホの『アイリス』の画像を引用しましたが、そこでも書いたようにゴッホは多数の "生物画" を描いています。その主なものを、
No.292 - ゴッホの生物の絵
に掲載しました。
国立西洋美術館は2019年にドイツの印象派を代表する画家、ロヴィス・コリント(1858-1925)の『樫の木』(1907)を購入しました。その絵は常設展示室に展示してあります。この作品は、本文に引用したクールベの作品と比較してみるのがよさそうです。
2つの作品とも1本の樫の木だけを描いています。そして画家の目的は「樹木のもつ生命力」をカンヴァスに描き出すことだと感じます。しかし、その生命力の表現方法は2つの絵で違います。
クールベの作品は巨大な幹を丹念に描いているように、数百年の時を経てなお屹立し、生き続ける巨樹の生命力を描いているようです。
一方のコリントの作品は木全体に葉をまとった姿であり、無数の葉をつける木の生命力を表現しています。クールベもコリントも「樫」というタイトルがついていますが、英語で oak、フランス語で chêne、ドイツ語で eiche と呼ばれる木の和名は "ヨーロッパナラ" であり、落葉性の木です(日本語では常緑性の樫と落葉性の楢を使い分ける)。
冬に葉を落として幹と枝だけになっていた木(= 楢)が、新緑の季節に芽吹き、やがて大木が一面の葉に覆われて、真冬には想像できないような姿になる。その生命の息吹きを描いたものでしょう。そのイメージでこの絵を鑑賞すべきだと思います。
本文のクールベの『フラジェの樫の木』のところと「補記3」で、ヨーロッパでオーク(英語で oak、フランス語で chêne、ドイツ語で eiche)と呼ばれる木は、和学名はヨーロッパナラであり、日本語に訳す場合は楢とすべきだと書きました。オークも楢もコナラ属の落葉性の樹木です。コナラ属の常緑性の木を日本では樫と言いますが、たとえばイタリアなどには常緑性のオークがあり、英語では live oak、ないしは evergreen oak と言うそうです(Wikipedia による)。
オークが楢であることの説明を、鳥飼玖美子氏の「歴史をかえた誤訳」から引用します。
「樫」という木は固すぎて家具に加工するのはむずかしい、とありますが、確かにその通りです。樫がよく使われるのは、たとえば道具類の柄で、金槌やスコップの柄を木で作る場合は、その堅さを生かして樫が使われます。木偏に堅いという漢字の通りです。
鳥飼氏の文章に「オーク・ヴィレッジ」主宰者、稲本正氏のことが出てきます。稲本氏がなぜ岐阜の工芸村にオークという名前をつけたかと言うと、楢が家具の素材の本命だからです。稲本氏の本から引用します。
国立西洋美術館がロヴィス・コリントの『Der Eichbaum』を『樫の木』としたのは、辞書にそうあるからでしょうが、芸術作品を所蔵している美術館の責任として「楢の木」ないしは「オークの木」とすべきでしょう。
| 野生動物を主題にした西洋絵画はあまり思い当たらない |
と書きました。

|
| 尾形光琳「群鶴図屏風」(米・ワシントンDC。フリーア美術館) |
確かに近代までの西洋の絵画は圧倒的に人物が中心で、宗教画・神話画・歴史画・肖像画・自画像など、人物(ないしは神や聖人)が画題になっています。中には「希望」「哲学」「妬み」といった抽象概念を擬人化して人物の格好で表した絵まである。「そこまでやるか」という感じもするのですが、とにかく人物が溢れています。人物画の次は静物画や風俗画、近代以降の風景画でしょうか。光琳の群鶴図のような野生動物はもとより、動物・植物・昆虫などの生物を描いた有名な絵はあまり思い当たらなかったのです。今回はそのことについての随想を書いてみたいと思います。
なお以下の話は、主として記録を目的とした「植物画」や「博物画」を除いて考えます。
もちろん動物が登場する絵はいっぱいあります。たとえばNo.87「メアリー・カサットの少女」で感想を書いた、メアリー・カサットの『青い肘掛け椅子の少女』(1878)です。
グリフォン犬
『青い肘掛け椅子の少女』では、少女の向かって左の椅子に寝そべっている犬がいます。この犬については、No.86「ドガとメアリー・カサット」でメアリーの伝記から引用しました。
|
メアリー・カサットはグリフォン犬をたいそうかわいがったようです。他の絵にもこの愛犬が登場します。下の絵は『Young Girl at a Window』(1883/4。コーコラン美術館 - Corcoran Gallery of Art。ワシントン DC)という作品です。スーザン・マイヤーの伝記では『犬を抱いてバルコニーに座るスーザン』というタイトルで紹介されている絵です。

| ||
|
メアリー・カサット
「犬を抱いてバルコニーに座る (Corcoran Gallery of Art。Washington DC) 「多くの印象派画家がそうであったように、メアリーも戸外で描くのを好んだ。自宅のバルコニーからモンマルトルを望むこの絵は、パリの風景を描いた数少ない作品のうちの一つである。メアリーはこの絵の中に、ドガからもらったベルギー産のグリフォン犬バティーも描いている。」 モデルのスーザンは、メアリーの家政婦・マチルドの従妹と推定されている。 | ||

| |||
| ブリュッセル・グリフォン | |||
そしてこのグリフォン犬に関してなのですが、メアリー・カサットの時代の450年以上前のベルギーで、この犬を描いた絵が制作されているのです。それは、西洋美術史では「超」がつくほど有名な絵画です。
ファン・エイク:アルノルフィーニ夫妻の肖像

| ||
|
ヤン・ファン・エイク
「アルノルフィーニ夫妻の肖像」(1434) (National Gallery。London) | ||
ロンドン・ナショナル・ギャラリーにある『アルノルフィーニ夫妻の肖像』(1434)は、ヤン・ファン・エイク(1390頃 - 1441)の作品です。ファン・エイクはブルッヘ(仏語・英語名はブルージュ。現在のベルギー、当時はフランドルの都市)を中心に活躍した画家です。ファン・エイクは西洋における油絵を完成させた人と言われていますね。精緻に描くその技法は、のちの西洋絵画に多大な影響を与えました。

| |||
メアリー・カサットのグリフォン犬は彼女のペットでした。では『アルノルフィーニ夫妻の肖像』のグリフォン犬もペットなのでしょうか。どうもそれは違うようなのです。
神戸大学准教授で美術史家の宮下規久朗氏の著書『モチーフで読む美術史』(ちくま文庫。2013)には『アルノルフィーニ夫妻の肖像』を解説して次のように書かれています。
|
宮下先生の解説にあるように、この絵において「犬」は特定の意味をもつシンボルとして描かれています。そして西洋の絵画における動物や生物は、主題(この絵の場合夫妻、ないしは夫妻の結婚)を補足するサブの存在として描かれ、かつ「シンボル」として使われることが大変に多いのです。
西洋画における生物
『アルノルフィーニ夫妻の肖像』に典型的にみられるように、西洋画における「生物」は、まず「シンボル」として描かれるケースが思い浮かびます。宗教画(キリスト教絵画)では数々の「象徴」があります。鳩は聖霊の象徴で、平和の象徴でもあるというたぐいです。聖人の持物(じもつ = アトリビュート)としての生物もあります。つまり人物が誰かを見分けるための伝統的な道具や動物で、鶏が描かれていれば、そばの人物はペテロという感じです。
シンボルやアトリビュートとしての生物はいろいろあり、羊、驢馬、鴉、蛇、魚、百合、葡萄、石榴、棕櫚、などが思いつきます。こういったシンボルは宗教画以外にも進出しています。No.44「リスト:ユグノー教徒の回想」で、英国の画家・ミレイが「サン・バルテルミの虐殺」の当日を描いた作品を紹介しましたが、その絵のトケイソウ(Passion Flower)は受難の象徴でした。
ギリシャ・ローマ神話を描いた絵にも、神話に登場する動物や植物、果実がいろいろあります。鷲や雄牛がゼウスの化身だとか、林檎がヴィーナスの持ち物だとかです。
宗教・歴史・神話を離れて、一般的な寓意を表す生物もあります。『アルノルフィーニ夫妻の肖像』の犬は「忠節」の象徴でした。No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したブリューゲルの「絞首台の上のかささぎ」では、かささぎが「偽善」や「告げ口」といった意味を持っていました。豚が「貪欲」の象徴のこともあります。
もちろん絵の主題の一部として描かれた生物もあります。乗馬や競馬や狩猟の情景の馬とか、風俗画における家畜や、家庭内のペット(犬や猫、小鳥)、牧場風景の牛や羊などです。
また、静物画の動植物もあります。獲物としての動物(兎、鳥、など)、肉、魚介類、野菜、果物(石榴、葡萄、林檎、梨)などです。花瓶の花や花束も静物画の一大ジャンルになっています。しかしフランス語で静物画のことを "nature morte"(=死んだ自然)と言うように、これらは生きているわけではありません。
西欧の絵画で生物が描かれるのは、上記のような「シンボル」「象徴」「主題の一部」「静物」というのがよくあるケースであり、生物そのものが主題という絵はそう多くはないようです。少なくとも、欧米の第1級の美術館ではあまり見かけないわけです。
日本の「生物画」
一方、日本の伝統的では生物を主役とする絵画が大きなポジションを占めています。ここで、静物画ならぬ「生物画」を次のように定義するとします。
|
生物画: 人間社会やその周辺に日常的に存在する動物・植物・生物の「生きている姿」を主題に描く絵。空想(龍、鳳凰)や伝聞(江戸時代以前の日本画の象・ライオン・獅子など)で描くのではない絵。生物だけ、ないしは生物を主役に描き、風俗や風景が描かれていたとしても、それは脇役である絵。 |
この意味での「生物画」が日本画には非常に多いわけです。
樹木は日本画の一大ジャンルになっています。「松」「梅」「桜」「竹」「柳」「楓」「桐」「椿」「槙」「柿」などは、繰り返し画題になってきました。
草花では、「朝顔」「杜若」「菖蒲」「花菖蒲」「牡丹」「紫陽花」「罌粟」「菊」「葵」「芙蓉」「百合」「藤」「つつじ」「桔梗」「芭蕉」などが思い浮かびます。「春・秋の七草」も画題の中心です。各種の「野菜」も描かれました。
鳥では、「鶏」「雀」「鴉」「鶴(光琳の群鶴図など)」「白鷺」「百舌」「鴛鴦」「孔雀」「鷹」「雁」「鴨」などでしょう。伊藤若冲は、かなりの数の鶏の絵を描いていますね。自分で飼育して観察したようです。
動物では、「犬」「猫」「猿」「鹿」「牛」「栗鼠」などです。江戸後期の森狙仙を開祖とする「森派」は、猿の絵で有名です。なお、虎は日本に生息しないので伝聞で描かれた絵が多いのですが、「虎」も超有力な画題です。
魚では、静物ではない生きた魚(水の中で泳ぐ魚)を描くのが日本画の特徴です。「鯉」「鮎」「鯰」「亀」(爬虫類ですが)などです。昆虫を描いた絵もあります。「蝶」「蛍」「蜻蛉」などです。
伊藤若冲の「動植綵絵」(最初にプルシアン・ブルーを使った作品。No.18「ブルーの世界」参照)は、こういった生物たちを総体的に描いた絵です。また、さまざまなモチーフを組み合わせた「花鳥図」「草木図」も、歴史上、多数制作されました。
No.30「富士山と世界遺産」で「特定の山を主題に描いた絵は西洋に少ない」と書きました。例外的に思い浮かぶのは(有名な画家では)セザンヌとホドラーぐらいだと・・・・・・。一方、日本では(近代以降は)全く逆です。これは昔から「山」を信仰の対象にしていた日本と、19世紀までは「山に名前をつけることさえ一般的でなかった」西洋との文化的相違と考えるのが妥当でしょう。
日本では「生物画」がメジャーであり、西洋ではそうではないということについて、安易な解釈をするのは禁物ですが、やはり「永遠なるもの」「神聖なるもの」を何に感じるかという、人の心の相違だと考えられます。
西洋における「生物画」の傑作
しかし、よくよく考えてみると「野生動物を主題にした西洋絵画はあまり思い当たらない」というのは速断すぎました。西洋絵画にも「生物画」はあり、野生動物の絵もあります。絵というのは主題の自由さ(何でもよい)が特長なのです。
西洋絵画の「生物画」の何点かの絵、特に印象的な絵画を(個人的主観で)あげてみます。まず最初は、カサットやファン・エイクの作品に描かれていた犬で、犬だけを描いた作品です。
| 犬 |

| ||
|
トマス・ゲインズバラ(1727-1788)
「ポメラニアンの親子」(1777頃) (テート・ギャラリー) | ||
18世紀イギリスの画家、ゲインズバラがポメラニアンの親子を描いた作品です。テート・ギャラリーの公式サイトによると、ゲインズバラの友人にエイベルというヴィオラ・ダ・ガンバの名手がいて、二人で演奏することもあった。この絵は音楽のレッスンを受けた謝礼に、エイベルの飼い犬を描いたもの、とあります。
親犬は何かの物音に気づいたように、耳をたて、左の方向を凝視しています。一方の子犬は、親犬とは無関係に下の方の何かに気を取られています。その2匹を対比させた描き方がうまいと思います。立派な毛並みは、いかにも上流階級の飼い犬といった雰囲気です。

|
エドゥアール・マネ(1832-1883) 「タマ、日本犬」(1875頃) |
(ワシントン・ナショナル・ギャラリー) |
イタリア出身の政治家・銀行家で東洋美術コレクターだったアンリ・セルヌッシ(チェルヌスキ)の愛犬、タマを描いた作品です。日本犬というタイトルのとおり、この犬は日本原産の狆です。セルヌッシは日本に旅行し、この犬を持ち帰りました。タマの前に転がっているのは日本人形のようです。
1世紀前のゲインズバラの絵と比べると、マネのこの絵は19世紀後半の絵画らしくスピーディで荒い筆致で描かれています。それによって、小型犬のすばしっこい様子や、舌を出したり、きょろきょろと辺りを見たりといった愛らしさが表現されています。
日本人的感覚から言うと「タマ」は猫の名前ですが、この場合のタマは日本語の "玉" で、宝石の意味のようです。飼い主はこの犬をたいそう可愛がったようで、ルノワールにもマネと同時期にタマの絵の制作を依頼しています。分かりにくいですが、TAMAと絵の左上に書いてあるのもマネの絵と同じです。

|
ピエール・オーギュスト・ルノワール(1841-1919) 「タマ、日本犬」(1876頃) |
(クラーク美術館:米・マサチューセッツ州) |
なお、マネの描いた犬の絵では他に『キング・チャールズ・スパニエル犬』があります。この絵もまた、ワシントン・ナショナル・ギャラリーの所蔵です。イギリス原産の犬で、その名のとおりイギリス王室の愛玩犬でした。

|
エドゥアール・マネ 「キング・チャールズ・スパニエル犬」(1866頃) |
(ワシントン・ナショナル・ギャラリー) |
| クールベの野生生物 |
フランスの画家、ギュスターヴ・クールベ(1819-1877)は「生物画」を描いています。画題としては、鹿、狐、鱒、樫の木などがあり、野生生物を描いているのが特長です。その「鹿」と「樫」の例を下に掲げます。
鹿を画題とする絵は何点かあって、野生の鹿、追われる鹿、死んだ鹿と、狩猟という視点での一連の作品があります。下に掲げたブリジストン美術館の絵も狩猟で追われている鹿を描いたのでしょう。また、東京の国立西洋美術館には『罠にかかった狐』という絵がありますが、これらの絵をみても「狩猟画の延長、ないしは変型としての動物画」という感じです。

| ||
|
ギュスターヴ・クールベ(1819-1877) 「雪の中を駆ける鹿」(1856-57) (ブリジストン美術館) | ||

| ||
|
ギュスターヴ・クールベ 「フラジェの樫の木」(1864) (クールベ美術館) | ||
西欧にも木を描いた絵がありますが、多くは風景の一部としての木、ないしは森や林の情景の中の木であり、樹木だけを主体的に描いたものは少ないと思います。このクールベの樫の絵は、巨木の存在感を描くことに徹したものです。
余談ですが、上の絵の「樫」と訳されている絵は、原題では「Le Chêne de Flagey(The Oak of Flagey)」です。Chêne(Oak。オーク)はコナラ属の木の総称ですが、日本語でそれに相当する樹は、樫(常緑性)や楢(落葉性)です。ヨーロッパのオークは多くが落葉性で、クールベが描いた樹も絵からすると日本で言う「楢」ですね。オークは古代ヨーロッパから神聖な樹とされてきました。
| 余談の余談になりますが、No.72「楽園のカンヴァス」の「補記」で紹介したアンリ・ルソーの「樫の枝」というデッサンも、そこに描かれている枝と葉とドングリは明らかに日本で言う楢の木です。 |
クールベは絵画史で「写実派」とされています。要するに「想像では描かない」わけです。その画題は、人物、自画像、風俗(葬儀の場面、画家のアトリエ、など)自然の風景、海岸に打ち寄せる波、石割り人夫、ヌード、女性の下半身(オルセー美術館の有名な絵)と多岐に渡っていて、そういった「写実の目」は野生生物にも向けられたわけです。
| 樫 |
クールベの樫の絵を引用したので、別の樫の絵を掲げます。ロシアの風景画家、シーシキンの作品です。

| ||
|
イワン・シーシキン(1832-1898)
「樫の木立、夕刻」(1887) (トレチャコフ美術館) | ||
シーシキンは、特に樫の木立や森をテーマにすることを好んだようです。その中でもこの絵は "樫の大木そのもの" を描こうとしています。一般に森や林を描いた風景画には樹木が描かれますが、それはあくまで「風景の一部としての樹木」です。そうではなく「樹木そのものに焦点を当てて描く」ということには意味があると考えられます。
つまり我々は大木や巨木に出会うと、人間の寿命よりはるかに長い時間(数百年、時には1000年以上)をかけて成長し、風雪に耐えて生きながらえ、現在も成長を続けているという実感を持つことができます。木に触れたり叩いたりしてもビクともせず、そこに屹立している。その重量感と実在感に圧倒されるわけです。さらに、最初はごく些細な芽生えであったはずのものが長い年月の間に数10トンもの巨大な存在になるという "生命の不思議さ" を感じ、そこまでになる植物の生命力に打たれることにもなります。
それが高じると「人智を遙かに超えたもの」を感じてしまい、神聖なものとしてとらえることになります。日本の古来の伝統では、大木や巨木に神が宿る(ないしは降臨する)という概念があり、注連縄と紙垂をつけた大木・巨木が至る所にあります。こういった感性は程度の差はあれ、森林が多い地域に発生した文化に共通です。
クールベとシーシキンの絵を見て思うのは、画家が樹木そのものを描こうと思った動機が、上に述べたような感性(のどれか)にもとづくのではないかということです。さらに思うのは、大木や巨木に向き合ったときに人が覚える感動とか感慨をカンヴァスに表現するためには、リアリズム絵画の手法こそ有効だということです。印象派以降の絵画手法ではそうはいかないでしょう。シーシキンのこの絵は、パリで印象派が全盛の頃に描かれたものですが、改めてリアリズム絵画の意味を考えされられます。
| 馬 |
馬は西洋では非常になじみのある家畜です。現在でもヨーロッパの都市の大きな公園に行くと、乗馬している人とすれ違ったりします。公園に乗馬道があるのです。
そういった文化的伝統からか、馬を描いた絵もいっぱいあります。多くは人が騎乗した姿ですが、狩りの情景や競馬のシーンなどの「風俗画」もあります。下の絵はフランスの女性画家、ローザ・ボヌール(1822-1899)の『馬市』(1853)という作品。メトロポリタン美術館の「人気コーナー」であるヨーロッパ近代絵画の展示室にあり、幅5メートルという巨大な絵なので、いやがおうでも目につきます。メトロポリタン美術館を訪れた日本人は多いと思いますが、(この絵は展示替えがないだろうという前提で)ほぼ全員が目にしているはずの絵です。
この絵はパリ郊外の「馬市」を描いた一種の「風俗画」ですが、馬を描くこと自体が目的という感じがします。

|
|
ローザ・ボヌール(1822-1899) 「馬市」(1853) (メトロポリタン美術館) |
馬だけを描いた絵もあります。フランスの画家、テオドール・ジェリコーやエドガー・ドガは馬そのものを主題とした作品を制作しています。またボヌールも馬だけの絵を多数描いています。
馬だけの絵で最も印象深いのは、英国の画家、ジョージ・スタッブス(1724-1806)が描いた『Whistlejacket』(1762頃)で、『アルノルフィーニ夫妻の肖像』と同じく、ロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵しているものです。Whistlejacket という名前の競争馬を描いたものですが、3m × 2.5m という大きなカンヴァスに、背景なしで馬だけが描かれています。スタッブスの絵はこれしか見たことがないのですが「馬の画家」と呼ばれていて、馬をかなり描いているようです。

|
|
ジョージ・スタッブス(1724-1806) 「Whistlejacket」(1762) (ロンドン・ナショナル・ギャラリー) |
ロンドンのナショナル・ギャラリーを訪れると、この絵がやけに印象的です。私の経験からですが「ロンドン・ナショナル・ギャラリーにおいて、予備知識が全く無いという前提で鑑賞して、最も印象的な作品」ではないでしょうか。要するに、こういうタイプの絵が珍しいからインパクトが強いのだと思います。
なお、ジョージ・スタッブスは馬だけでなく、動物園で観察したライオンやカンガルーをはじめ、各種の動物を描いたようです。また『馬市』のローザ・ボヌールも、牛・羊・山羊・狐・鹿・犬といった動物の絵を多数描いています。
動物画を描くということにおいてスタッブスはボヌールの「先輩」にあたるわけですが、さらにその先輩がいます。オランダの画家、パウルス・ポッテル(1625-1654)です。ポッテルは牛や馬といった家畜を多数描いています。

| ||
|
パウルス・ポッテル(1625-1654)
Le Cheval Pie(まだら馬)
(ルーブル美術館)
| ||
この絵はルーブル美術館のフランドル絵画のエリアにある、Le Cheval Pie(英語題名は The Spotted Horse。まだら馬)と題する絵です。ボヌールやスタッブスの絵とは違って、この絵は 40cm×30cm という小品です。しかし斑の馬の確かな造形が光っています。ボヌール、スタッブス、ポッテルのように動物画を主体に描いた画家は、私が知らないだけで、もっとあると想像されます。
| 牛 |
牛については「馬市」と同じく、ローザ・ボヌールが印象的な絵を描いています。オルセー美術館の「ニヴェルネー地方の耕作」という絵です。

|
|
ローザ・ボヌール(1822-1899) 「ニヴェルネー地方の耕作」(1849) (オルセー美術館) |
これは「農村風景」を描いた絵ですが、オルセー美術館で実際に見ると、明らかに牛を描くことが目的の絵だということがよくわかります。幅2.6メートルの大きな絵で、牛の力強さが迫ってきます。パリを訪れる日本人の大多数はオルセー美術館に行くと思うので、この絵も「馬市」と同じく(展示替えがないだろうという前提で)多くの人が目にしているはずの絵です。
牛を描いた絵では、オランダの首都、デン・ハーグに傑作があります。
デン・ハーグ : マウリッツハイス美術館

| |||
| ◆ | デルフトの眺望(1660頃) | |
| ◆ | 真珠の耳飾りの少女(1665頃) |
は超有名作品です。フェルメール作品は「傑作」と「普通の絵」の2つに分かれると思うのですが(どんな画家でもそうですが)、この2つは傑作中の傑作でしょう。
その他の作品ですが、レンブラント(1606-1669)の
| ◆ | テュルプ博士の解剖学講義(1632) |
も有名な絵画です。
しかしこの美術館の「みどころ」は他にもあります。それは、同じ年に30歳前後で夭折した二人のオランダ人画家が描いた「生物画」です。
一つは、ルーブルの馬の絵を描いた、パウルス・ポッテルの『雄牛』(1647)です。この『雄牛』は2.5m×3.5m程度の非常に大きな絵で、中心に描かれた雄牛は実寸大です。雄牛の生命力が大変な迫力で迫ってくる絵です。

| ||
|
パウルス・ポッテル 「雄牛」(1647) (マウリッツハイス美術館) | ||
もう一つの作品は、カレル・ファブリティウス(1622-1654)の『ごしきひわ』(1654)です。ポッテルとはうってかわった 33.5cm×22.8cm という小さな作品で、ペットとして飼われていた小鳥(足に鎖がついている)をシンプルに描いています。壁が背景なので、この絵を家の壁に飾っておくとあたかも小鳥がそこにいるような感覚になるでしょう。一種のだまし絵的な要素のある絵ですが、造形の確かさと美しい色使い、小鳥の部分の軽やかな筆運びが印象に残る作品です。

| ||
|
カレル・ファブリティウス 「ごしきひわ」(1654) (マウリッツハイス美術館) | ||
動物画の画家
今まで引用したなかに、主に動物画を描いた画家がいます。年代順にあげると、
| 1625-1654 | ||
| イギリス | 1724-1806 | |
| フランス | 1822-1899 |
の3人です。活躍した世紀も国も違いますが、こうしてみるとヨーロッパには動物画の歴史や流れがあることが推測できます。そうした画家の一人が、スウェーデンのリリエフォッシュです。スウェーデンの画家というと、我々はカール・ラーション(1853-1919)ぐらいしか知らないのですが、リリエフォッシュも本国では有名な画家のようです。
ブルーノ・リリエフォッシュ(Bruno Liljefors、1860-1939)は19世紀末から20世紀初期にかけて活動した画家で、動物画を得意としていました。彼の動物画の多くの特徴は、
| 野生動物の | |
| 野生の環境における | |
| 野生の生態を描く |
というものです。もちろん動物を描くためには観察が必要です。画家は自然の中に家とアトリエを建て、野生動物を捕獲してケージで飼育し、その観察をもとに描きました。あるいは、狩猟の獲物を観察して描くこともしたようです。私は実物の絵を見たことがないのですが、リリエフォッシュの2作品を引用します。

|
ブルーノ・リリエフォッシュ (1860-1939) 「キツネたち」(1885) |
(イェーテボリ美術館) |
一見するとキツネは1匹のようですが、右端に寝そべっているもう1匹がいます。おそらく画家はキツネの習性を観察し、2匹のこの瞬間を絵にしたのだと思います。
季節は秋で、背景は色づき始めた木の葉で埋め尽くされています。その中に小鳥が3羽、配置されている(コガラだと思います)。自然の中のキツネという雰囲気を盛り上げています。
イェーテボリ美術館の解説によると、このキツネは同じ年の春に生まれた若いキツネとのことです。いかにも柔らかそうな、ふさふさした毛並みがそれを表しています。

|
ブルーノ・リリエフォッシュ 「鷹と黒い獲物」(1884) |
- Hawk and Black-Game - (スウェーデン国立美術館) |
オオタカの幼鳥が雷鳥(クロライチョウ)を襲った瞬間を描いています。真冬の、あたり一面に雪が舞う中で、オオタカが雷鳥の群を狙い、その中の一羽を襲う。オオタカの右下に描かれているのはクロライチョウの雌でしょう。雌は黒ではなく茶色をしています。オオタカが "つがい" のクロライチョウを襲ったという想定です。
スウェーデン国立美術館の解説によると、リリエフォッシュは狩猟でしとめたオオタカの幼鳥とクロライチョウを林の中に持って行き、この絵をすべて戸外で描いたそうです。もちろんそれだけでは、この絵の迫真の感じは出せないでしょう。画家はオオタカが獲物を襲う瞬間をよく観察したのだと思います。その観察の成果が現れているようです。
雪が舞い、クロライチョウの群が逃げ出す背景は、淡い色使いの幻想的な描き方です。その中で、狩りの瞬間が極めてリアルに描写されている。その対比も光っていると思います。
ウィーン : アルベルティーナ美術館

| |||
まず、有名な『野兎』(1502)です。水彩・グアッシュで紙に描かれた25cm程度の小さな絵ですが、ウサギの毛の細密描写が見事です。

| ||
|
アルブレヒト・デューラー 「野兎」(1502) (アルベルティーナ美術館) | ||
さらにこの美術館では、同じデューラーの『芝草』(1503)が非常に印象的な作品です。『野兎』と同じく水彩・グアッシュの絵で、40cm ×31.5cm の大きさです。描かれているのは芝草、イネ科の植物らしい草、タンポポ、アザミなど、日常生活の周辺のどこにでもありそうなものです。日本でも十分にありうる光景と言っていいでしょう。

| ||
|
アルブレヒト・デューラー 「芝草」(1503) (アルベルティーナ美術館) | ||
西欧では「ボタニカル・アート」という絵のジャンルがありますね。花や草などの「植物だけを背景なしに描いた絵」ですが、ボタニカル(=植物学)というだけあって記録ないしは学術的意味に重点が置かれている絵です。
しかしデューラーの『芝草』はボタニカル・アートではありません。描かれているのは、どこにでもある「雑草」です。その雑草に目を向け、一つの作品(素描)に仕上げた画家の「目」に注目したいと思います。
ひるがえって考えてみると、実は「雑草」は日本画の伝統的なモチーフです。一つだけ例をあげると、たとえば酒井抱一(1761-1829)の『夏秋草図屏風』(1821。東京国立博物館所蔵)です。

| ||
|
酒井抱一 「夏秋草図屏風」(二曲一双。1821) (東京国立博物館。重要文化財) | ||
日本では春の七草、秋の七草などと言われます。これらの草の中で、桔梗や撫子などの可憐な花をつける草はともかく、春のセリ、ナズナ、ハコベ、秋のフジバカマ、クズ、オミナエシなどは、その草の名前を知らない人にとっては「雑草」としか見えないでしょう。しかしそういった草に名前をつけ、年中行事に使い(七草粥など)、画題にもしてきたのが日本の文化的伝統です。
デューラーの『芝草』、そして『野兎』を見て感じるのは、日本画にも通じる画家の目です。文化はいったん確立すると拡大・再生産されます。一方では生物を画題とする絵が綿々と作られ、他方では宗教画や人物画が自律運動的に広がっていく。しかしそういった文化的伝統の相違を除いてみると、「画家の目」は日本でも西欧でも似ているのではないか・・・・・・。デューラーの絵をみたとき、そういった思いに駆られました。と同時に、絵画は「何を描くか」もあるが「どう描くか」が重要である・・・・・・。デューラーと抱一の絵で感じるのはそのことです。
ゴッホ
近代以降の画家で "生物画" を多数描いたのは、ゴッホが一番でしょう。その画題は、
| 果樹(モモ、スモモ、梨、アーモンド、など) | |
| 樹木(マロニエ、ライラック、糸杉、オリーヴ、など) | |
| 花(アイリス、薔薇、ポピー、など) | |
| 草、麦の穂 |
などです。果樹や樹木の絵では、花が咲く頃を描いたものが多くあります。またこれ以外に、数は少ないですが、鳥(カワセミ)や昆虫(蛾、蝶)を描いた作品もあります。
花に関して言うと、もちろんゴッホは静物画としての花の絵(=花瓶に飾られた切り花の絵)を多数描いていますが、それとあわせて大地に生えている草や木に花が咲いている姿を画題として描いている。生命の息づかいを描いたということで、画家として特徴的だと思います。その例を引用したいのですが、ゴッホの "生物画" は多数あります。何をあげるか迷うのですが、アイリスの絵にします。

|
フィンセント・ファン・ゴッホ (1853 - 1890) 「アイリス」(1889) |
(米:ゲティ・センター) |
アイリスは日本で言うアヤメです。ないしはアヤメ属の花を指すものとすると、「アヤメ」「ハナショウブ」「カキツバタ」「イチハツ」などです(そもそもこれらの種は見分けにくい)。
アヤメ類は日本画では定番の画題の一つで、誰しも思い出すのは尾形光琳の「燕子花図屏風」(根津美術館)でしょう。日本画と比較してみるのもおもしろいと思います。
このゴッホの作品はサン・レミの療養院の時代の絵です。群生するアヤメが、ゴッホらしい鮮やかな色彩で生き生きととらえられています。この絵から受ける印象は、あでやかで大ぶりの花をつけるアヤメの生命力です。それを描きたかったのだと思います。
モネ
ゴッホと同時代の画家では、モネが花や樹木の "生物画" を描いています。もちろん有名なのは『睡蓮』を描いた一連の(数百の)作品です。ただこの連作のほとんどの作品は "睡蓮の池" に焦点があり、特に時間や天候によって千変万化する様子を描いています。睡蓮の花だけを描いた作品もありますが一部です。というわけで「睡蓮シリーズ」はここでは割愛します。
睡蓮以外に目を向けると、モネは、アイリス、バラ、リンゴの花、クレマティスなどを描いています。その中からゴッホつながりで、国立西洋美術館が所蔵するアイリスの絵を次に引用します

|
クロード・モネ(1840-1926) 「黄色いアイリス」(1914/7) |
(国立西洋美術館) |
この絵について、国立西洋美術館のサイトには次のような説明がしてありました。
|
確かにこの絵は装飾性が強く、縦長の大画面は日本趣味を感じさせます。一方、同じ黄色いアイリスの絵で全くイメージの違った絵がパリのマルモッタン・モネ美術館にあります。

|
クロード・モネ 「黄色いアイリス」(1917/9) |
(マルモッタン・モネ美術館) |
マルモッタン美術館というと『印象・日の出』で有名な美術館ですが、この絵も記憶に残る絵です。その理由は "アイリスと空" という取り合わせでしょう。樹木の花と空という組み合わせならともかく、草花と空を描くのは日本画にはあまりありません。そもそも日本画には空を描いた絵が少ない。一部の浮世絵だけでしょう。
というわけで、この絵は国立西洋美術館の絵の "日本趣味" とは全く違っています。アングルも地表からアイリスを見上げたような構図になっていて、モネならではの作品だと思います。
モネは若い時に、鳥を主題にした作品を描いています。それが次の『七面鳥』です。

|
クロード・モネ 「七面鳥」(1876) |
(オルセー美術館) |
画題もめずらしいが、正方形のカンヴァスも一般的ではありません。これは、当時モネのパトロンだった美術愛好家、エルネスト・オシュデの注文で、パリ郊外のモンジュロンにあったオシュデの別荘を飾るために描かれた作品です。別荘に放し飼いにされていた七面鳥を描いています。
木陰に10数羽の鳥がいますが、描き方は木々や草むらと似ていて、庭の風景の一部になっているような感じを受けます。正方形のカンヴァスも含めて、別荘の壁にかける装飾画ということが関係しているのでしょう。
生物を描く
以上、20世紀初頭までの作品をあげましたが、もちろん現代作家も "生物画" を描きます。実際に見たことのある現代作家の絵で印象的だったのは、スペインの具象画家、アントニオ・ロペス(1936 -)の『マルメロの木』(1990)です。この絵は日本での「アントニオ・ロペス展」に出品されました(Bunkamura ザ・ミュージアム。2013.4.27 - 6.16)。アントニオ・ロペスは制作時間が長いことで有名で、この絵も「晴れた日の午前中の決まった時間」に少しずつ描くわけです。マルメロの実や葉の白い線は、実際に画家がマルメロにつけた線です。なぜ線をつけるのかと言うと、描いている期間で実が熟して枝が垂れ下がり、全体のバランスが変化してくる。その初期配置を記憶するための線ということらしい。結局、この絵は未完だそうですが、たわわに実ったマルメロと長時間向き合おうとする画家の執念が現れているようです。

|
アントニオ・ロペス(1936-) 「マルメロの木」(1990) |
(フォクス・アベンゴア財団) - Wikimedia Commonsより画像を引用 - |
以上のように、いろいろ思い出して(かつ確認して)みると、西洋絵画にも動植物を主題にした「生物画」はいろいろあることが認識できます。著名な画家も描いているし、実際に実物を見た絵もいろいろある。なぜ「生物画」はあまりないと(No.85「洛中洛外図と群鶴図」で)思ってしまったのか。
日本画の伝統では「生物画」が主流(の一つ)です。一方、西洋の伝統的な具象画では、宗教・歴史・神話・人物・風景・静物といった画題が主流です。当然、その主流に沿って絵が注文され、画家は画題を選び、絵が取り引きされ、美術館のコレクションがなされ、展示する作品がセレクションされ、美術教育があり、アートに関するジャーナリズムも作られる。われわれ一般人のモノの見方も、その「主流」に添って形成されるわけです。
我々は「見たいと思うものを見る」のであり「見たいと思わないものは見えない、ないしは意識に残らない・残りにくい」のでしょう。どうも、そういうことだと思われました。
日本画
デューラーの『芝草』のところで酒井抱一の絵を引用したので、最後に日本画をもうひとつ引用します。クールべが雪景色の中の鹿を描いた絵を前に掲げましたが、同じ雪景色の中の鹿を描いた日本画です。

|
川合玉堂(1873-1957) 「冬嶺孤鹿」(1898) (山中湖高村美術館) |
美術年鑑社「川合玉堂の世界」(1998)より画像を引用 |
川合玉堂という人は、古今東西の著名画家の中でも最もデッサンが上手な画家の一人だと思います。この絵を見るとそれがよく分かる。玉堂が20歳台の作品で、上京した直後あたりのものです。我々がよく目にする玉堂作品というと「日本の自然や風景の中に溶け込んだ人の営み」的なテーマが多いのですが、この絵はそのテーマに至る前の作品であり、1頭の鹿を描くという日本画ではよくあるものです。しかしそれだけに純粋に画力が現れていると思います。
| 補記1:ローザ・ボヌール |
本文中にローザ・ボヌールの『馬市』と『ニヴェルネー地方の耕作』を引用しましたが、この2つの作品の詳しい解説を、
No.266 - ローザ・ボヌール
に掲載しました。
(2019.8.23)
| 補記2:ゴッホの生物画 |
本文中にゴッホの『アイリス』の画像を引用しましたが、そこでも書いたようにゴッホは多数の "生物画" を描いています。その主なものを、
No.292 - ゴッホの生物の絵
に掲載しました。
(2020.8.22)
| 補記3:ロヴィス・コリント |
国立西洋美術館は2019年にドイツの印象派を代表する画家、ロヴィス・コリント(1858-1925)の『樫の木』(1907)を購入しました。その絵は常設展示室に展示してあります。この作品は、本文に引用したクールベの作品と比較してみるのがよさそうです。

|
ロヴィス・コリント(1858-1925) 「樫の木」(1907) |
- Der Eichbaum - |
(国立西洋美術館) |

| ||
|
ギュスターヴ・クールベ 「フラジェの樫の木」(1864) (クールベ美術館) | ||
2つの作品とも1本の樫の木だけを描いています。そして画家の目的は「樹木のもつ生命力」をカンヴァスに描き出すことだと感じます。しかし、その生命力の表現方法は2つの絵で違います。
クールベの作品は巨大な幹を丹念に描いているように、数百年の時を経てなお屹立し、生き続ける巨樹の生命力を描いているようです。
一方のコリントの作品は木全体に葉をまとった姿であり、無数の葉をつける木の生命力を表現しています。クールベもコリントも「樫」というタイトルがついていますが、英語で oak、フランス語で chêne、ドイツ語で eiche と呼ばれる木の和名は "ヨーロッパナラ" であり、落葉性の木です(日本語では常緑性の樫と落葉性の楢を使い分ける)。
冬に葉を落として幹と枝だけになっていた木(= 楢)が、新緑の季節に芽吹き、やがて大木が一面の葉に覆われて、真冬には想像できないような姿になる。その生命の息吹きを描いたものでしょう。そのイメージでこの絵を鑑賞すべきだと思います。
(2020.10.07)
| 補記4:オーク |
本文のクールベの『フラジェの樫の木』のところと「補記3」で、ヨーロッパでオーク(英語で oak、フランス語で chêne、ドイツ語で eiche)と呼ばれる木は、和学名はヨーロッパナラであり、日本語に訳す場合は楢とすべきだと書きました。オークも楢もコナラ属の落葉性の樹木です。コナラ属の常緑性の木を日本では樫と言いますが、たとえばイタリアなどには常緑性のオークがあり、英語では live oak、ないしは evergreen oak と言うそうです(Wikipedia による)。
オークが楢であることの説明を、鳥飼玖美子氏の「歴史をかえた誤訳」から引用します。
|
「樫」という木は固すぎて家具に加工するのはむずかしい、とありますが、確かにその通りです。樫がよく使われるのは、たとえば道具類の柄で、金槌やスコップの柄を木で作る場合は、その堅さを生かして樫が使われます。木偏に堅いという漢字の通りです。
鳥飼氏の文章に「オーク・ヴィレッジ」主宰者、稲本正氏のことが出てきます。稲本氏がなぜ岐阜の工芸村にオークという名前をつけたかと言うと、楢が家具の素材の本命だからです。稲本氏の本から引用します。
|
国立西洋美術館がロヴィス・コリントの『Der Eichbaum』を『樫の木』としたのは、辞書にそうあるからでしょうが、芸術作品を所蔵している美術館の責任として「楢の木」ないしは「オークの木」とすべきでしょう。
(2020.10.07)
タグ:稲本正 鳥飼玖美子 宮下規久朗 アルノルフィーニ夫妻の肖像 ファン・エイク グリフォン犬 青い肘掛け椅子の少女 メアリー・カサット 伊藤若冲 夏秋草図屏風 酒井抱一 群鶴図屏風 尾形光琳 デューラー ファブリティウス ポッテル ボヌール スタッブス クールベ ロンドン・ナショナル・ギャラリー コーコラン美術館 メトロポリタン美術館 アルベルティーナ美術館 マウリッツハイス美術館 動植綵絵 山中湖高村美術館 川合玉堂 冬嶺孤鹿 マネ ロヴィス・コリント オルセー美術館 ゲティ・センター アントニオ・ロペス ゴッホ テート・ギャラリー ゲインズバラ スウェーデン国立美術館 イェーテボリ美術館 リリエフォッシュ モネ マルモッタン・モネ美術館 国立西洋美術館 トレチャコフ美術館 シーシキン ルノワール
No.90 - ゴヤの肖像画「サバサ・ガルシア」 [アート]
No.86-87 の
◆ ドガとメアリー・カサット
◆ メアリー・カサットの「少女」
でメアリー・カサット(1844-1926)が描いた絵を何点か取り上げました。そのときに書いたのですが、彼女は30歳になる前にスペインに滞在し、スペインの巨匠の絵を研究し、模写をし、また自らも絵の制作に励みました。その彼女に影響を与えた画家の一人がフランシスコ・デ・ゴヤ(1746-1828)です。今回はそのスペイン絵画の巨匠・ゴヤが描いた一枚の絵について書いてみたいと思います。
No.87「メアリー・カサットの少女」で『青い肘掛け椅子の少女』(1878)の感想を書きましたが、この作品を所蔵しているのはアメリカの首都・ワシントン DC にあるナショナル・ギャラリー(National Gallery of Art)でした。その同じ美術館に、ゴヤが描いた一人の女性の肖像画があります。『セニョーラ・サバサ・ガルシア』という作品です。私はワシントン・ナショナル・ギャラリーに一度だけ行ったことがあるのですが、そのときにこの絵は展示してあり、実物を鑑賞することができました。
『セニョーラ・サバサ・ガルシア』
西欧絵画史の巨匠・ゴヤはいろいろなジャンルの絵を書いています。スペインの宮廷画家だったので、もちろん王侯貴族の肖像画を描いているし、誰もが知っている「裸のマハ/着衣のマハ」もある。「戦争の惨禍」のような作品もあるし、最晩年には「黒い絵」シリーズを描いています。しかし、肖像画に限って言うと『セニョーラ・サバサ・ガルシア』が最高傑作だと思うのです。なぜそう思うのかが今回のテーマです。
すぐに分かることですが、この絵は徹底的にモデルだけを引き立たせるように描かれています。背景は暗い色で塗り潰されているし、頭から上半身と手にかけてヴェールやショールや衣装で覆われている。宝飾品のたぐいはいっさいありません。つけていたとしても隠されている。手のポーズはレオナルド・ダ・ヴィンチを意識して画家が指示したのでしょう。ひと言で言うと「スペイン美女の肖像」です。
しかしこの絵は「単に美女を描いただけの絵ではない」と感じられるのです。ここから以降の文章は絵から受ける印象であって、それは個人によって違うことを断っておきます。あくまで個人的印象です。
ポイントは描かれた彼女の表情です。この表情には、かすかな「陰」のようなものを感じるのですね。それはまず口もとの雰囲気です。また、じっと見つめる右目(向かって左)が見せる表情であり、左とは感じが違います。そもそも顔の左と右で微妙に表情が違うように見える。そのあたりに何となく「陰」を感じるのです。
No.87「メアリー・カサットの少女」において『青い肘掛け椅子の少女』に描かれた少女が
に見えることに関連して、以下のように書きました。
ゴヤが描くサバサ・ガルシアは、青い肘掛け椅子に座っている少女とは違って、別に「ふてくされている」わけではありません。真剣そうな、普通の表情です。しかしその中に何となく、僅かにあるネガティブな感情を感じてしまうのです。そうだとしたら、そのネガティブな感情とは何かを以下に推測してみたいと思います。
伝説
この絵には、描かれた経緯に関する「伝説」があります。それをワシントン・ナショナル・ギャラリーのホームぺージを日本語訳して引用すると次の通りです。
"according to an perhaps legendary anecdote"とあるように、この話がどこまで本当なのかは分からないようです。しかしこの「言い伝え」の通りだとすると、どのような想像ができるでしょうか。たとえば次のような状況です。
大臣にしてみれば、途中で描くのをやめてしまったゴヤを失敬だと思ったかもしれません。いやそうではなく、大臣にとってもサバサは「自慢の姪」だったので「ゴヤよ、やっぱりそうか」と思ったかもしれない。それは分かりません。しかし彼女のほうは間違いなく「とまどった」でしょうね。初対面の画家に肖像画を書きたいと、突如として言い出されるのだから・・・・・・。
かすかな「陰」
ここまでの想像をもとに、彼女の表情がみせるポジティブではない要素、かすかな「陰り」といったものの原因が何か、それを3つ推測してみたいと思います。
まず肖像画のモデルになることの「恥ずかしさ」や「恥じらい」が考えられます。ゴヤは宮廷画家です。その「スペイン最高の画家」に自分の姿をカンヴァスに描かれてしまう。現在なら、写真を撮られるのを恥ずかしがる若い女性はいないでしょう。しかし19世紀初頭のスペインでは違います。肖像画を描いてもらうというのは基本的に王侯貴族や裕福な一部の人たちであり、一般の人(しかも若い女性)はそういうことがないわけです。お金がかかるし、印象派の画家のようにスピーディに一気に描くというわけではないので、時間もかかる。サバサにとって絵のモデルになるのは生まれて初めての経験のはずです。恥ずかしいと思うのは当然だと考えられます。
2つ目は、肖像画のモデルを続けることが嫌だという感情です。「恥じらい」に加えてそういう感情があることが考えられる。「もういいでしょう、帰してください」と、微かに哀願しているのかもしれません。16歳の彼女には夫がいます。気にならないはずがない。伯父の大臣に「モデルになってやりなさい」と言われて嫌々ながら承諾したのかもしれません。
3つ目に、ひょっとしたらありうると思うのは、画家に対する微かな軽蔑です。彼女は自分の美しさを完全に自覚しているはずです。そして今まで、美人だというだけで言い寄ってくる男が数々いたのではないでしょうか。女性の外見だけからチヤホヤする男たち・・・・・・。彼女はそういった男たちを内心では軽蔑していたのかもしれない。そして、伯父の肖像を描いていた画家も、彼女の姿を見たとたんに絵筆を置いて「肖像を描きたい」と申し出たのです。ゴヤの場合はアーティストとしてのインスピレーションが働いたのだろうけれど・・・・・・。
もっといろいろ考えられると思いますが、とにかくそういったネガティブな感情を彼女は内心抱いていて、それが微かな表情となって現れ、見る人に単純ではない印象を与え、それが絵に引き込まれる要因になっているのだと感じます。
肖像画の傑作
肖像画の名作と言われる絵は、まずモデルの特徴(ないしは部分的な特徴)を的確にとらえていて、平たく言うと「似ている」「そっくり」と感じられる絵です。しかし昔の絵だと、どれだけ似ているかは現代の我々には分かりません。「似ている」「そっくり」は、基本的には同時代作家の作品でしか評価できない。
絵が描かれた時期にかかわらず、肖像画の傑作と言われる絵に共通しているのは、鑑賞する人に「描かれた人物の性格や内面を感じさせる」ということです。その典型が、No.19「ベラスケスの怖い絵」の冒頭に掲げた『インノケンティウス十世の肖像』(1650)です。中野京子さんは著書の「怖い絵」の中でこの絵を評して、
と断言しています。そこまで書いてしまっていいのかと思うぐらいですが、それだけ人物の内面や性格をあらわにした(と、見る人に感じられる)絵だということです。
時代が下っても「人物の内面や性格を感じさせる絵」はいろいろあります。ほとんど肖像画しか描かなかった画家にモディリアーニがいますが、線と色が非常にシンプルにもかかわらず人の内面を感じさせる絵が多い。農夫を描いた絵を見ると「この人は勤勉で、実直で、穏やかな性格だ」と思ってしまう・・・・・・、そういった具合です。
東洲斎写楽が役者を描いた浮世絵もそうです。人物の性格(ないしは、歌舞伎の役の上での人物の性格)を的確に表現したと感じられるものが多々ある。
ベラスケスとモディリアーニと東洲斎写楽では、文化背景が違い、時代も違い、描き方も、写実の度合いも、線の使い方も全く違うのですが、肖像画の傑作が人物の内面を感じさせる、という点についてはかなり共通していると思います。
しかし肖像画の傑作と言われる絵には、人物の内面を感じさせるという以上に、別の観点で素晴らしい絵があります。それは、モデルとなった人が見せる「微妙な表情」が描かれていて、その描写力で傑作と言われる作品です。単にポジティフな表情でもないし、ネガティブというわけでもない。複雑で奥深い表情の絵です。その典型がレオナルド・ダヴィンチの『モナ・リザ』ですね。微笑んではいるが、単なる微笑ではない(と思える)。見る人は何か奥深いものを感じてしまい、それが何かは謎でもある。謎を通り越して「崇高」とか「神秘」というようなイメージを人に与える絵です。
人は人の表情に極めて敏感に反応します。笑いの中に僅かに異質なものがあっても、それを感じてしまう。笑顔にもかかわらず「眼は笑っていない」などと言いますよね。人は笑顔だと眼が細くなる。その細くなり具合が少しだけ足りない。だから眼は笑っていない・・・・・・。たとえばそういうたぐいの微妙な「感じ」です。人は人とコミュニケーションをしないと生きていけないのですが、その手段は「言葉」に加えて「表情」です。
人が見せる表情の奥深さや微妙さ、複雑さ。それを描きえたという意味で『セニョーラ・サバサ・ガルシア』は肖像画の傑作だし、ゴヤの肖像画では最も優れた作品だと思います。『インノケンティウス十世の肖像』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)を描いたベラスケスの天才ぶりは言をまたないのですが、ゴヤの画力もずば抜けている。
さきほども書いたように、この作品は明らかにダ・ヴィンチのモナ・リザを意識して描かれています。女性の年齢は違いますが、二人とも既婚者です。人が見せる表情の複雑さを描いたということも考慮して、この絵を「ワシントンのモナ・リザ」と呼んでもいいでしょう。
そして思うのですが、人が見せる表情の複雑さを描くことによって傑作といえる肖像画は、19世紀以前に確立した西欧絵画技法で可能な表現なのですね。印象派以降の絵になるとそういう絵はあまり思い当たらないし、日本画にもない。性格描写で傑出した絵はいろいろあるけれども・・・・・・。その理由は、絵画における「リアリズム」や「細密な描写」がないと(=絵を見る人がリアルだと思える描写がないと)人が見せる微妙な表情は描きにくいからです。その意味では、現代日本の「超リアリズム」の画家にそういった作品があるのは注目すべきだと思います。
リアリズムから離れることで得られるものも大きいが、そのことによって失われるものもあり、リアリズムでしか出来ないこともある。ゴヤの『セニョーラ・サバサ・ガルシア』を見て、改めてそう思います。
◆ ドガとメアリー・カサット
◆ メアリー・カサットの「少女」
でメアリー・カサット(1844-1926)が描いた絵を何点か取り上げました。そのときに書いたのですが、彼女は30歳になる前にスペインに滞在し、スペインの巨匠の絵を研究し、模写をし、また自らも絵の制作に励みました。その彼女に影響を与えた画家の一人がフランシスコ・デ・ゴヤ(1746-1828)です。今回はそのスペイン絵画の巨匠・ゴヤが描いた一枚の絵について書いてみたいと思います。

| |||
|
National Gallery of Art ( Washington DC ) | |||
『セニョーラ・サバサ・ガルシア』

| ||
|
フランシスコ・デ・ゴヤ
「セニョーラ・サバサ・ガルシア」 (c. 1806/1811 71×58cm) (ワシントン・ナショナル・ギャラリー) | ||
西欧絵画史の巨匠・ゴヤはいろいろなジャンルの絵を書いています。スペインの宮廷画家だったので、もちろん王侯貴族の肖像画を描いているし、誰もが知っている「裸のマハ/着衣のマハ」もある。「戦争の惨禍」のような作品もあるし、最晩年には「黒い絵」シリーズを描いています。しかし、肖像画に限って言うと『セニョーラ・サバサ・ガルシア』が最高傑作だと思うのです。なぜそう思うのかが今回のテーマです。
|
ちなみに「セニョーラ」は既婚女性ですね。日本語で言うと「サバサ・ガルシア夫人」でしょうか。しかしそういう日本語は全くそぐわない絵の雰囲気です。16歳の時の肖像だと言います。結婚したてのようです。 |
すぐに分かることですが、この絵は徹底的にモデルだけを引き立たせるように描かれています。背景は暗い色で塗り潰されているし、頭から上半身と手にかけてヴェールやショールや衣装で覆われている。宝飾品のたぐいはいっさいありません。つけていたとしても隠されている。手のポーズはレオナルド・ダ・ヴィンチを意識して画家が指示したのでしょう。ひと言で言うと「スペイン美女の肖像」です。
しかしこの絵は「単に美女を描いただけの絵ではない」と感じられるのです。ここから以降の文章は絵から受ける印象であって、それは個人によって違うことを断っておきます。あくまで個人的印象です。
ポイントは描かれた彼女の表情です。この表情には、かすかな「陰」のようなものを感じるのですね。それはまず口もとの雰囲気です。また、じっと見つめる右目(向かって左)が見せる表情であり、左とは感じが違います。そもそも顔の左と右で微妙に表情が違うように見える。そのあたりに何となく「陰」を感じるのです。
No.87「メアリー・カサットの少女」において『青い肘掛け椅子の少女』に描かれた少女が
|
退屈で 何となく不機嫌で もっと言うと、ふてくされている感じ |
に見えることに関連して、以下のように書きました。
|
若い女性や少女をモデルした絵は、モデルの「ポジティブな感情や表情」を表したものが多いわけです。笑顔、微笑、真剣、清楚、可憐、おだやか、安心、幸福、信頼、大人の成熟や自信、母の愛情といったものです。それらとは反対の「ネガティブな感情や表情」、つまり、退屈、不機嫌、無気力、怒り、冷笑、悲哀、軽蔑、嫌悪、不安などを表した女性像は少ない。 |
ゴヤが描くサバサ・ガルシアは、青い肘掛け椅子に座っている少女とは違って、別に「ふてくされている」わけではありません。真剣そうな、普通の表情です。しかしその中に何となく、僅かにあるネガティブな感情を感じてしまうのです。そうだとしたら、そのネガティブな感情とは何かを以下に推測してみたいと思います。
伝説
この絵には、描かれた経緯に関する「伝説」があります。それをワシントン・ナショナル・ギャラリーのホームぺージを日本語訳して引用すると次の通りです。
|
"according to an perhaps legendary anecdote"とあるように、この話がどこまで本当なのかは分からないようです。しかしこの「言い伝え」の通りだとすると、どのような想像ができるでしょうか。たとえば次のような状況です。
|
外務大臣が自宅にゴヤを招き、書斎で肖像画を描いてもらっている。姪のサバサは、たまたま何かの用事で伯父の家に来ていた。 外務大臣の夫人は、サバサに書斎に飲み物を運ぶように頼み、そこで彼女が前触れなく画家の前に現れることになった。その姿を見て画家は大臣を描くことを中断した・・・・・・。 |
大臣にしてみれば、途中で描くのをやめてしまったゴヤを失敬だと思ったかもしれません。いやそうではなく、大臣にとってもサバサは「自慢の姪」だったので「ゴヤよ、やっぱりそうか」と思ったかもしれない。それは分かりません。しかし彼女のほうは間違いなく「とまどった」でしょうね。初対面の画家に肖像画を書きたいと、突如として言い出されるのだから・・・・・・。
かすかな「陰」
ここまでの想像をもとに、彼女の表情がみせるポジティブではない要素、かすかな「陰り」といったものの原因が何か、それを3つ推測してみたいと思います。
まず肖像画のモデルになることの「恥ずかしさ」や「恥じらい」が考えられます。ゴヤは宮廷画家です。その「スペイン最高の画家」に自分の姿をカンヴァスに描かれてしまう。現在なら、写真を撮られるのを恥ずかしがる若い女性はいないでしょう。しかし19世紀初頭のスペインでは違います。肖像画を描いてもらうというのは基本的に王侯貴族や裕福な一部の人たちであり、一般の人(しかも若い女性)はそういうことがないわけです。お金がかかるし、印象派の画家のようにスピーディに一気に描くというわけではないので、時間もかかる。サバサにとって絵のモデルになるのは生まれて初めての経験のはずです。恥ずかしいと思うのは当然だと考えられます。
2つ目は、肖像画のモデルを続けることが嫌だという感情です。「恥じらい」に加えてそういう感情があることが考えられる。「もういいでしょう、帰してください」と、微かに哀願しているのかもしれません。16歳の彼女には夫がいます。気にならないはずがない。伯父の大臣に「モデルになってやりなさい」と言われて嫌々ながら承諾したのかもしれません。
3つ目に、ひょっとしたらありうると思うのは、画家に対する微かな軽蔑です。彼女は自分の美しさを完全に自覚しているはずです。そして今まで、美人だというだけで言い寄ってくる男が数々いたのではないでしょうか。女性の外見だけからチヤホヤする男たち・・・・・・。彼女はそういった男たちを内心では軽蔑していたのかもしれない。そして、伯父の肖像を描いていた画家も、彼女の姿を見たとたんに絵筆を置いて「肖像を描きたい」と申し出たのです。ゴヤの場合はアーティストとしてのインスピレーションが働いたのだろうけれど・・・・・・。
もっといろいろ考えられると思いますが、とにかくそういったネガティブな感情を彼女は内心抱いていて、それが微かな表情となって現れ、見る人に単純ではない印象を与え、それが絵に引き込まれる要因になっているのだと感じます。
肖像画の傑作
肖像画の名作と言われる絵は、まずモデルの特徴(ないしは部分的な特徴)を的確にとらえていて、平たく言うと「似ている」「そっくり」と感じられる絵です。しかし昔の絵だと、どれだけ似ているかは現代の我々には分かりません。「似ている」「そっくり」は、基本的には同時代作家の作品でしか評価できない。
絵が描かれた時期にかかわらず、肖像画の傑作と言われる絵に共通しているのは、鑑賞する人に「描かれた人物の性格や内面を感じさせる」ということです。その典型が、No.19「ベラスケスの怖い絵」の冒頭に掲げた『インノケンティウス十世の肖像』(1650)です。中野京子さんは著書の「怖い絵」の中でこの絵を評して、
| どの時代のどの国にも必ず存在する、ひとつの典型としての人物が、ベラスケスの天才によって、くっきりと輪郭づけられた。すなわち、ふさわしくない高位へ政治力でのし上がった人間、いっさいの温かみの欠如した人間。 |
と断言しています。そこまで書いてしまっていいのかと思うぐらいですが、それだけ人物の内面や性格をあらわにした(と、見る人に感じられる)絵だということです。
時代が下っても「人物の内面や性格を感じさせる絵」はいろいろあります。ほとんど肖像画しか描かなかった画家にモディリアーニがいますが、線と色が非常にシンプルにもかかわらず人の内面を感じさせる絵が多い。農夫を描いた絵を見ると「この人は勤勉で、実直で、穏やかな性格だ」と思ってしまう・・・・・・、そういった具合です。
東洲斎写楽が役者を描いた浮世絵もそうです。人物の性格(ないしは、歌舞伎の役の上での人物の性格)を的確に表現したと感じられるものが多々ある。
ベラスケスとモディリアーニと東洲斎写楽では、文化背景が違い、時代も違い、描き方も、写実の度合いも、線の使い方も全く違うのですが、肖像画の傑作が人物の内面を感じさせる、という点についてはかなり共通していると思います。
しかし肖像画の傑作と言われる絵には、人物の内面を感じさせるという以上に、別の観点で素晴らしい絵があります。それは、モデルとなった人が見せる「微妙な表情」が描かれていて、その描写力で傑作と言われる作品です。単にポジティフな表情でもないし、ネガティブというわけでもない。複雑で奥深い表情の絵です。その典型がレオナルド・ダヴィンチの『モナ・リザ』ですね。微笑んではいるが、単なる微笑ではない(と思える)。見る人は何か奥深いものを感じてしまい、それが何かは謎でもある。謎を通り越して「崇高」とか「神秘」というようなイメージを人に与える絵です。
人は人の表情に極めて敏感に反応します。笑いの中に僅かに異質なものがあっても、それを感じてしまう。笑顔にもかかわらず「眼は笑っていない」などと言いますよね。人は笑顔だと眼が細くなる。その細くなり具合が少しだけ足りない。だから眼は笑っていない・・・・・・。たとえばそういうたぐいの微妙な「感じ」です。人は人とコミュニケーションをしないと生きていけないのですが、その手段は「言葉」に加えて「表情」です。
人が見せる表情の奥深さや微妙さ、複雑さ。それを描きえたという意味で『セニョーラ・サバサ・ガルシア』は肖像画の傑作だし、ゴヤの肖像画では最も優れた作品だと思います。『インノケンティウス十世の肖像』(No.19「ベラスケスの怖い絵」)を描いたベラスケスの天才ぶりは言をまたないのですが、ゴヤの画力もずば抜けている。
さきほども書いたように、この作品は明らかにダ・ヴィンチのモナ・リザを意識して描かれています。女性の年齢は違いますが、二人とも既婚者です。人が見せる表情の複雑さを描いたということも考慮して、この絵を「ワシントンのモナ・リザ」と呼んでもいいでしょう。
そして思うのですが、人が見せる表情の複雑さを描くことによって傑作といえる肖像画は、19世紀以前に確立した西欧絵画技法で可能な表現なのですね。印象派以降の絵になるとそういう絵はあまり思い当たらないし、日本画にもない。性格描写で傑出した絵はいろいろあるけれども・・・・・・。その理由は、絵画における「リアリズム」や「細密な描写」がないと(=絵を見る人がリアルだと思える描写がないと)人が見せる微妙な表情は描きにくいからです。その意味では、現代日本の「超リアリズム」の画家にそういった作品があるのは注目すべきだと思います。
リアリズムから離れることで得られるものも大きいが、そのことによって失われるものもあり、リアリズムでしか出来ないこともある。ゴヤの『セニョーラ・サバサ・ガルシア』を見て、改めてそう思います。
No.87 - メアリー・カサットの「少女」 [アート]
前回の No.86「ドガとメアリー・カサット」で、メアリー・カサット(Mary Stevenson Cassatt, 1844-1926)の絵を何点か引用しました。今回はそれらの絵の感想を書きます。
スペイン絵画
No.86 の最初の方に掲げたのは、パリの官展(サロン)の入選作で、
の2作品です。『コルティエ婦人の肖像』をサロンで見たドガが「私と同じ感性の画家」と評したことも書きました。
メアリー・カサットは1872-3年にスペインのマドリードとセヴィリアに8ヶ月間滞在し、スペイン絵画に触れ、模写をし、自らも制作に励みました。上の2作品はスペインの巨匠の影響を感じますね。『闘牛士』はベラスケスのようだし『コルティエ婦人』の方はゴヤの影響を感じる。ゴヤと言えば、メアリーの『バルコニーにて』(1873-4)は明らかにゴヤの『バルコニーのマハたち』(1810頃)を踏まえて制作されています。
彼女はスペインに行く前にイタリアのパルマに滞在し、コレッジョの『聖母子と聖ヒエロニムスとマグダラのマリア』(1523年頃。パルマ国立美術館)を模写しています。メアリーはもちろん、マネやドガをはじめとするフランス印象派の画家に学んだのですが、それと同時に、西洋絵画の源流であるイタリアやスペインの巨匠たちから多くを吸収したことも忘れてはならないと思います。
浮世絵
No.86「ドガとメアリー・カサット」に書いたように、メアリー・カサットもまた日本の浮世絵に強く影響を受けた画家でした。No.86 の最後に掲載した『舟遊び』(1893。49歳)という作品もそうです。この絵のユニークな構図と平面的に分割された画面、細部を塗り潰したような表現は浮世絵の影響でしょう。まるで湖岸からカメラを向け、望遠レンズでボートにグッと寄っていって撮った写真のような感じもします。スナップ写真に触発されたのかもしれません。
この絵に描かれているのはメアリーの弟の家族で、絵の中心は一家の子供です。「帆」「オール」「ボートの縁」「夫婦の体の輪郭、特に夫の左腕と妻の右腕」の線(=リーディング・ライン)の配置によって、見る人の視線を子供に誘導する構図はメアリーの画家としてのなみなみならぬ力量を示していると思います。構図の大胆さと斬新さという点でも北斎・広重なみの作品でしょう
No.86 で引用したスーザン・マイヤー著「メアリー・カサット」によると、『舟遊び』は母と子の情景に男性が加わっている唯一の絵だそうです。そう言えば、「母と子の情景」はメアリーがたくさん描いているテーマだし(下に「縫い物をする若い母親」を引用)、「母と子の情景にもう一人が加わった絵」もあります。しかしその場合の "もう一人" は子供の兄弟姉妹のことが多いわけです(たとえば姉)。この絵のように、もう一人が大人の男性の絵というのは、確かにほかに見たことがありません。
そのことを踏まえてこの絵のテーマを推測してみると、子供に周りから放射状にリーディング・ラインが集まっていることから、明らかに絵の "主役" は子供です。顔には光も当たっている。また抱いている母親は、顔が陰になってはいるが "準主役" でしょう。一方、後ろ向きに描かれている父親は "副次的存在" です。この画面構成は "聖家族" を意識しているのではないでしょうか。
上に書いたように、メアリーは20代の時にスペイン、イタリアに滞在して古典絵画の模写までしています。この絵は浮世絵の影響も含んで、描き方はいかにも19世紀後半の絵画なのですが、西洋絵画の伝統もしっかりと踏まえていると思います。
浮世絵に非常な興味を抱いたメアリー・カサットは、自ら版画の制作に乗り出します。彼女は「画家・版画家」と紹介されることもあるぐらいです。もちろん木彫ではなく、ドライポイントやアクアチントといった「西洋版画技法」で作るわけです。多数ある版画作品から一つあげるとすると、たとえば『着付け(The Fitting)』(1891。47歳)という作品です。
これを見るとまず、メアリーが浮世絵の作風を完全に自分のものとしたことが分かります。線は美しいし、構図は見事です。壁と床の文様の装飾性も、人物との対比で際だっています。この壁と床の文様は現実の光景ではないような感じもします。そして何が浮世絵っぽいかというと、最大のポイントは着付けをしてもらっている女性の姿態・ポーズですね。こういう格好は鈴木春信や鳥居清長の作品にいっぱいあったような気がします。
それとは全く逆ですが、画面に大型の鏡を登場させ、2つの空間を一枚の絵の中に共存させるという挑戦もしている。こんなことは浮世絵にはありえません。彼女がいかに好奇心が旺盛で、貪欲に学ぼうとする姿勢があり、アートに対する探求心に富んでいたかを物語る作品だと思います。
母と子/子ども
メアリー・カサットの作品というとすぐに思い浮かぶのは「母と子」や「子ども」を明るい色調で描いた一連の絵です。No.86「ドガとメアリー・カサット」に掲げたのはメトロポリタン美術館が所蔵する『縫い物をする若い母親』(1900。56歳)でした。
メアリー・カサットの多くの絵に共通するのはモチーフを「自然体で」描いていることで、この絵もそうです。母親はレースの縫い物に集中しています。初めは興味深げに見ていた少女も、次第に退屈してきて、母親に甘えつつ、気を引こうとする。「ねえ外に行こうよ」なんて言っているのかもしれません。子どもが見せる「一瞬の自然な表情としぐさ」を的確に写し取っていると思います。
彼女はドガの影響でパステル画も多く描いています。「闘牛士にパナルを差し出す女」のクラーク美術館が所蔵している、パステルで描かれた子どもの肖像画を掲げておきます。
「母と子」や「子ども」をモチーフにした絵は、若いころに学んだイタリア、スペイン絵画の影響があるのかもしれません。たとえば、彼女がパルマで模写したコレッジョの『聖母子と聖ヒエロニムスとマグダラのマリア』の聖母子です。また彼女が感銘をうけたスペインの画家の一人、ムリーリョは、子どもの絵が有名です。
青い肘掛け椅子の少女(1878。34歳)
この絵はメアリー・カサットの最高傑作だと思います。「最高傑作」というのは「ある程度の客観性が必要な言い方」だと思うので、それがそぐわないのなら「メアリー・カサットの作品で個人的に一番好きな絵」です。メアリーは 50-60 歳代に子どもをモチーフに数々の傑作を描いているのですが、この作品は30歳台前半の若い時の作品です。
この絵はメアリー・カサットの友人だったエドガー・ドガと関係があります。ドガとも、またメアリーとも懇意だった画商・ヴォラールの回想録に「ドガは、この絵と自分の裸婦像を交換しよう、とメアリーに申し出たことがある」と書かれているのです。その理由として、次のようにあります。
メアリー・カサットの手紙にも、ヴォラールの回想録の記述を裏付けることが書かれています。
2人は互いにアトリエを訪問し合う仲だったので、ドガの「指導」や「示唆」(その程度は不明ですが)、また「背景に手を入れる」こともあったでしょう。この絵はメアリー・カサットとドガの交友関係の中から生み出され、かつ、ドガが大変に好んだ絵( = 手もとに置きたいと思うほど好んだ絵)であることは間違いないようです。
この絵は部屋の中で少女をモデルにして描いたものだと考えられますが、直ぐに気づくのは普通の絵にはあまりない少女の「表情としぐさ」です。
まず少女の表情ですが、受ける印象としては
がします(人によって感じ方は違うと思いますが)。
若い女性や少女をモデルした絵は、モデルの「ポジティブな感情や表情」を表したものが多いわけです。笑顔、微笑、真剣、清楚、可憐、おだやか、安心、幸福、信頼、大人の成熟や自信、母の愛情といったものです。それらとは反対の「ネガティブな感情や表情」、つまり、退屈、不機嫌、無気力、怒り、冷笑、悲哀、軽蔑、嫌悪、不安などを表した女性像は少ない。
もちろん、風俗画や歴史画、神話による作品、事件や出来事を扱った絵には「ネガティブな表情」の絵がいろいろあります。「戦争で家族を失って悲嘆にくれる女性」というのもあるし、ドガも『アブサンを飲む女』のように「沈み込んで虚ろな表情の女性」を描いている。しかしモデルを部屋やアトリエに座らせて描いた絵で「ネガティブな感情や表情」のものは少ないはずです。その意味で『青い肘掛け椅子の少女』は珍しいと思うのです。
次に少女の格好としぐさです。彼女は左手を頭の後ろに回し、両足をだらっと広げる「奔放な姿勢」をとっています。こういう姿勢の絵はあまり見たことがありません。これは大人の女性はしないポーズですね(するとしたら男を挑発する場合です)。また良家の子女なら、こういう恰好をすると母親から「だらしない恰好はやめなさい」と厳しく注意され、叱責されそうです。しかし、少女としては(また、本来人間としては)自然な姿だとも言える。
以上のように、モデルの表情としぐさは、少女としては自然なのかもしれないけれど「絵画の主題としてはかなり独特」だと思うのですね。それはルノアールがたくさん描いた少女の絵と比べてみれば明らかです。全然違います。
メアリー・カサットは意図的にそういうポーズを少女にとらせたのでしょうか。そうかもしれません。しかし、絵から受ける第一印象は「自然とそういうポーズになった」というものです。この絵を見て直感的に思うのは
です。この少女はドガの友人の娘です。ということは、メアリー・カサットと顔見知りでしょう。画家はその少女をモデルに絵を描こうとし、おめかしをした少女を青い肘掛け椅子に座らせ「じっとしてるのよ」とか言いながらデッサンを始める。絵のモデルになることで、初めは緊張しておとなしく肘掛け椅子に座っていた少女も、次第に退屈になり、不機嫌になり、「まだ終わらないの」とか言いだし、画家も「じゃ、もっと楽にして」とか言って、少女の姿勢は次第に崩れていく。その姿がおもしろいと思った画家は、素早くデッサンを繰り返す・・・・・・。そんな情景を想像してしまいます。あくまで想像ですが。
この絵の少女から受ける印象は、少女が見せるはずのいろいろの「表情」や「しぐさ」のうち、ある瞬間をリアルに捕らえている感じ、ないしは、つくりものではない自然体を描いている感じです。「今この瞬間」を描く達人はメアリーの友人のドガですね。その影響を受けているのかもしれません。こうした「感じ」は、上に引用した『縫い物をする若い母親』に描かれた少女に通じるものがあります。
ちなみに、この絵の左の椅子で寝ているのは、メアリーの愛犬(グリフォン犬)でしょう(No.86 参照)。少女の「退屈」とは無関係に、超然と寝込んでいる姿の対比が利いています。
この絵でまず目に飛び込んでくるのは白い服と明るい肌色の少女ですが、第2の印象は4つの青い肘掛け椅子です。後方の一つはソファのようですが、便宜上「4つの青い肘掛け椅子」と呼ぶことにします。
絵をじっと眺めていると、4つの青い肘掛け椅子が圧倒的な存在感で迫ってきます。どっしりとした重量感があると同時に、その青色でもって(少女以外の)カンヴァスを支配している。青と言っても緑を感じさせる明るい青色です。No.18「ブルーの世界」で書いた青の分類からいうと、ターコイズ・ブルーとセルリアン・ブルーの中間のような色でしょうか。
少女は退屈して不機嫌で、ちょっと「だらしなく」座っています。しかし椅子はどっしりとその位置を占めている。そして眺めていると、この絵は肘掛け椅子を描くことが目的のようにも思えてきます。少女はそれを強調する手段のような・・・・・・。画家はこの4つの椅子で「何か」を象徴したかったのかもしれません。
椅子の配置は独特です。手前から奥へと、非対称に、不揃いに、ずらして配置されています。その青い椅子が配置された室内を、少し上からの視線のクローズアップで、すべての椅子をカンヴァスからはみ出して描く・・・・・・。西欧絵画で室内を描いた絵として、これはかなり特異で大胆な構図ではないでしょうか。この構図の斬新さがこの絵の大きな特徴だと思います。
構図の大胆さといえば、すぐに思い出すのがドガです。ドガは浮世絵や北斎漫画を彷彿とさせる構図の絵をたくさん描いています。その構図の斬新さという意味でもまた、この絵はメアリー・カサットの友人・ドガの影響を感じます。
画家はこの構図により、西洋的遠近法を使わないで部屋の広々とした奥行き感を出すことに成功しました。この空間表現は『青い肘掛け椅子の少女』に独特のものだと思います。絵に使われている色は、白っぽい色(少女の服と肌)と、肘掛け椅子の青と、その他の黒っぽい色(濃い青や茶色)という単純なものです。この単純さも空間の表現にマッチしています。
まとめるとこの絵は「少女のしぐさ」と「青い肘掛け椅子を配した空間表現」で、唯一無二とも言える絵であり、そこが何とも言えず魅力的で、絵の中に引き込まれる感じがします。
連想と想像
『青い肘掛け椅子の少女』(1878)をみて、どうしても連想してしまう絵画があります。メアリー・カサットと同じアメリカ人であるジョン・シンガー・サージェントが、メアリーの絵の4年後にパリで描いた『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館所蔵)です。この絵は No.36「ベラスケスへのオマージュ」で紹介しました。以下『ボイト家の娘たち』と略します。
なぜ『ボイトの娘たち』を連想するかと言うと、
部屋の中に不均等に配置し、そのことによって独特の空間表現や奥行き感を作り出したという類似性があるからです。
『ボイトの娘たち』はベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」参照)からインスピレーションを得て描かれた絵です。サージェントは1879年にプラド美術館を訪れ、『ラス・メニーナス』を模写しました。そして3年後に描いたのが『ボイト家の娘たち』です。No.36「ベラスケスへのオマージュ」で書いたように、この絵は2010年にプラド美術館へ貸し出され、プラド美術館は「招待作品」として『ラス・メニーナス』と並べて展示しました。
そこで思い当たることがあります。サージェントよりメアリー・カサットの方がよほど「スペイン通」だということです。何しろ彼女は20歳台後半にスペインのマドリードとセヴィリアに8ヶ月も滞在しているのです。そこで描いた絵はパリのサロンに入選しています。もちろん彼女はプラド美術館を訪れていて、伝記(No.86 参照)によると「ベラスケスやムリーリョやゴヤの絵に感銘を受けた」とあります。
そしてこれはサージェントの絵からの全くの想像なのですが
ではないのでしょうか。なぜそう感じるかという理由はありません。何となくそう思うのであり、しいていうと、サージェントの『ボイト家の娘たち』がそうなら『青い肘掛け椅子の少女』もそうであっておかしくない、ぐらいでしょうか。もっと言うなら「少女」が主人公であり、そばに「寝そべった犬」がいることでしょうか。理由にはなりませんが・・・・・・。
画家が絵からインスピレーションを受けて絵を描くといった場合、そのインスピレーションの「ありよう」は千差万別です。ほんの些細な点にピカッと光るものを感じ、そこから自分のイメージを膨らませる。それは基本的に「制作の秘密」であり、公表されることはあまりない。だからこそ、このような「想像」もべつにかまわないと思っています。
メアリー・カサットの絵のごく一部を見てきたわけですが、これだけでも彼女の「画家像」が分かります。メアリー・カサットは、
画家です。前回の No.86「ドガとメアリー・カサット」で書いた、
という彼女の経歴とも合わせ、アートに対する飽くなき探求心とともに生きた画家だったと思います。
『青い肘掛け椅子の少女』に関する別の記事を、No.125「カサットの"少女"再び」に掲載しました。
スペイン絵画
No.86 の最初の方に掲げたのは、パリの官展(サロン)の入選作で、
| 『闘牛士にパナルを差し出す女』(1873。29歳) 『コルティエ婦人の肖像』(1874。30歳) |
の2作品です。『コルティエ婦人の肖像』をサロンで見たドガが「私と同じ感性の画家」と評したことも書きました。
| ちなみに、パナルとはスペイン語で蜂の巣(蜜蜂の巣)の意味です。女は闘牛士に水の入ったコップとパナルを差しだし、闘牛士はパナルを水に浸して飲み物を作ろうとしています。 |

|

|
||||
|
メアリー・カサット
「闘牛士にパナルを差し出す女」(1873) (クラーク美術館) |
メアリー・カサット 「コルティエ婦人の肖像」(1874) (個人蔵。WikiPaintingsより) | ||||
メアリー・カサットは1872-3年にスペインのマドリードとセヴィリアに8ヶ月間滞在し、スペイン絵画に触れ、模写をし、自らも制作に励みました。上の2作品はスペインの巨匠の影響を感じますね。『闘牛士』はベラスケスのようだし『コルティエ婦人』の方はゴヤの影響を感じる。ゴヤと言えば、メアリーの『バルコニーにて』(1873-4)は明らかにゴヤの『バルコニーのマハたち』(1810頃)を踏まえて制作されています。
彼女はスペインに行く前にイタリアのパルマに滞在し、コレッジョの『聖母子と聖ヒエロニムスとマグダラのマリア』(1523年頃。パルマ国立美術館)を模写しています。メアリーはもちろん、マネやドガをはじめとするフランス印象派の画家に学んだのですが、それと同時に、西洋絵画の源流であるイタリアやスペインの巨匠たちから多くを吸収したことも忘れてはならないと思います。
| コレッジョの絵の模写の件は、No.86「ドガとメアリー・カサット」で紹介したスーザン・E・マイヤー著『メアリー・カサット』によります。 |
浮世絵
No.86「ドガとメアリー・カサット」に書いたように、メアリー・カサットもまた日本の浮世絵に強く影響を受けた画家でした。No.86 の最後に掲載した『舟遊び』(1893。49歳)という作品もそうです。この絵のユニークな構図と平面的に分割された画面、細部を塗り潰したような表現は浮世絵の影響でしょう。まるで湖岸からカメラを向け、望遠レンズでボートにグッと寄っていって撮った写真のような感じもします。スナップ写真に触発されたのかもしれません。

| ||
|
メアリー・カサット
「舟遊び」(1893/94) (ワシントン・ナショナル・ギャラリー) | ||
この絵に描かれているのはメアリーの弟の家族で、絵の中心は一家の子供です。「帆」「オール」「ボートの縁」「夫婦の体の輪郭、特に夫の左腕と妻の右腕」の線(=リーディング・ライン)の配置によって、見る人の視線を子供に誘導する構図はメアリーの画家としてのなみなみならぬ力量を示していると思います。構図の大胆さと斬新さという点でも北斎・広重なみの作品でしょう
No.86 で引用したスーザン・マイヤー著「メアリー・カサット」によると、『舟遊び』は母と子の情景に男性が加わっている唯一の絵だそうです。そう言えば、「母と子の情景」はメアリーがたくさん描いているテーマだし(下に「縫い物をする若い母親」を引用)、「母と子の情景にもう一人が加わった絵」もあります。しかしその場合の "もう一人" は子供の兄弟姉妹のことが多いわけです(たとえば姉)。この絵のように、もう一人が大人の男性の絵というのは、確かにほかに見たことがありません。
そのことを踏まえてこの絵のテーマを推測してみると、子供に周りから放射状にリーディング・ラインが集まっていることから、明らかに絵の "主役" は子供です。顔には光も当たっている。また抱いている母親は、顔が陰になってはいるが "準主役" でしょう。一方、後ろ向きに描かれている父親は "副次的存在" です。この画面構成は "聖家族" を意識しているのではないでしょうか。
上に書いたように、メアリーは20代の時にスペイン、イタリアに滞在して古典絵画の模写までしています。この絵は浮世絵の影響も含んで、描き方はいかにも19世紀後半の絵画なのですが、西洋絵画の伝統もしっかりと踏まえていると思います。
浮世絵に非常な興味を抱いたメアリー・カサットは、自ら版画の制作に乗り出します。彼女は「画家・版画家」と紹介されることもあるぐらいです。もちろん木彫ではなく、ドライポイントやアクアチントといった「西洋版画技法」で作るわけです。多数ある版画作品から一つあげるとすると、たとえば『着付け(The Fitting)』(1891。47歳)という作品です。

| ||
|
メアリー・カサット
「着付け」(1891) - ドライポイント・アクアチント - (ワシントン・ナショナル・ギャラリー) | ||
これを見るとまず、メアリーが浮世絵の作風を完全に自分のものとしたことが分かります。線は美しいし、構図は見事です。壁と床の文様の装飾性も、人物との対比で際だっています。この壁と床の文様は現実の光景ではないような感じもします。そして何が浮世絵っぽいかというと、最大のポイントは着付けをしてもらっている女性の姿態・ポーズですね。こういう格好は鈴木春信や鳥居清長の作品にいっぱいあったような気がします。
それとは全く逆ですが、画面に大型の鏡を登場させ、2つの空間を一枚の絵の中に共存させるという挑戦もしている。こんなことは浮世絵にはありえません。彼女がいかに好奇心が旺盛で、貪欲に学ぼうとする姿勢があり、アートに対する探求心に富んでいたかを物語る作品だと思います。
母と子/子ども
メアリー・カサットの作品というとすぐに思い浮かぶのは「母と子」や「子ども」を明るい色調で描いた一連の絵です。No.86「ドガとメアリー・カサット」に掲げたのはメトロポリタン美術館が所蔵する『縫い物をする若い母親』(1900。56歳)でした。

| ||
|
メアリー・カサット
「縫い物をする若い母親」(1900) (メトロポリタン美術館) | ||
メアリー・カサットの多くの絵に共通するのはモチーフを「自然体で」描いていることで、この絵もそうです。母親はレースの縫い物に集中しています。初めは興味深げに見ていた少女も、次第に退屈してきて、母親に甘えつつ、気を引こうとする。「ねえ外に行こうよ」なんて言っているのかもしれません。子どもが見せる「一瞬の自然な表情としぐさ」を的確に写し取っていると思います。
彼女はドガの影響でパステル画も多く描いています。「闘牛士にパナルを差し出す女」のクラーク美術館が所蔵している、パステルで描かれた子どもの肖像画を掲げておきます。

| ||
|
メアリー・カサット
「赤い帽子の子供」(1908) (クラーク美術館。WikiPaintingsより) | ||
「母と子」や「子ども」をモチーフにした絵は、若いころに学んだイタリア、スペイン絵画の影響があるのかもしれません。たとえば、彼女がパルマで模写したコレッジョの『聖母子と聖ヒエロニムスとマグダラのマリア』の聖母子です。また彼女が感銘をうけたスペインの画家の一人、ムリーリョは、子どもの絵が有名です。
青い肘掛け椅子の少女(1878。34歳)
この絵はメアリー・カサットの最高傑作だと思います。「最高傑作」というのは「ある程度の客観性が必要な言い方」だと思うので、それがそぐわないのなら「メアリー・カサットの作品で個人的に一番好きな絵」です。メアリーは 50-60 歳代に子どもをモチーフに数々の傑作を描いているのですが、この作品は30歳台前半の若い時の作品です。

| ||
|
メアリー・カサット
「青い肘掛け椅子の少女」(1878) (ワシントン・ナショナル・ギャラリー) | ||
この絵はメアリー・カサットの友人だったエドガー・ドガと関係があります。ドガとも、またメアリーとも懇意だった画商・ヴォラールの回想録に「ドガは、この絵と自分の裸婦像を交換しよう、とメアリーに申し出たことがある」と書かれているのです。その理由として、次のようにあります。
|
メアリー・カサットの手紙にも、ヴォラールの回想録の記述を裏付けることが書かれています。
|
2人は互いにアトリエを訪問し合う仲だったので、ドガの「指導」や「示唆」(その程度は不明ですが)、また「背景に手を入れる」こともあったでしょう。この絵はメアリー・カサットとドガの交友関係の中から生み出され、かつ、ドガが大変に好んだ絵( = 手もとに置きたいと思うほど好んだ絵)であることは間違いないようです。
| 少女 |
この絵は部屋の中で少女をモデルにして描いたものだと考えられますが、直ぐに気づくのは普通の絵にはあまりない少女の「表情としぐさ」です。
まず少女の表情ですが、受ける印象としては
|
退屈で 何となく不機嫌で もっと言うと、ふてくされている感じ |
がします(人によって感じ方は違うと思いますが)。
若い女性や少女をモデルした絵は、モデルの「ポジティブな感情や表情」を表したものが多いわけです。笑顔、微笑、真剣、清楚、可憐、おだやか、安心、幸福、信頼、大人の成熟や自信、母の愛情といったものです。それらとは反対の「ネガティブな感情や表情」、つまり、退屈、不機嫌、無気力、怒り、冷笑、悲哀、軽蔑、嫌悪、不安などを表した女性像は少ない。
もちろん、風俗画や歴史画、神話による作品、事件や出来事を扱った絵には「ネガティブな表情」の絵がいろいろあります。「戦争で家族を失って悲嘆にくれる女性」というのもあるし、ドガも『アブサンを飲む女』のように「沈み込んで虚ろな表情の女性」を描いている。しかしモデルを部屋やアトリエに座らせて描いた絵で「ネガティブな感情や表情」のものは少ないはずです。その意味で『青い肘掛け椅子の少女』は珍しいと思うのです。
次に少女の格好としぐさです。彼女は左手を頭の後ろに回し、両足をだらっと広げる「奔放な姿勢」をとっています。こういう姿勢の絵はあまり見たことがありません。これは大人の女性はしないポーズですね(するとしたら男を挑発する場合です)。また良家の子女なら、こういう恰好をすると母親から「だらしない恰好はやめなさい」と厳しく注意され、叱責されそうです。しかし、少女としては(また、本来人間としては)自然な姿だとも言える。
以上のように、モデルの表情としぐさは、少女としては自然なのかもしれないけれど「絵画の主題としてはかなり独特」だと思うのですね。それはルノアールがたくさん描いた少女の絵と比べてみれば明らかです。全然違います。
メアリー・カサットは意図的にそういうポーズを少女にとらせたのでしょうか。そうかもしれません。しかし、絵から受ける第一印象は「自然とそういうポーズになった」というものです。この絵を見て直感的に思うのは
| モデルを続けるのが厭になった少女 |
です。この少女はドガの友人の娘です。ということは、メアリー・カサットと顔見知りでしょう。画家はその少女をモデルに絵を描こうとし、おめかしをした少女を青い肘掛け椅子に座らせ「じっとしてるのよ」とか言いながらデッサンを始める。絵のモデルになることで、初めは緊張しておとなしく肘掛け椅子に座っていた少女も、次第に退屈になり、不機嫌になり、「まだ終わらないの」とか言いだし、画家も「じゃ、もっと楽にして」とか言って、少女の姿勢は次第に崩れていく。その姿がおもしろいと思った画家は、素早くデッサンを繰り返す・・・・・・。そんな情景を想像してしまいます。あくまで想像ですが。
この絵の少女から受ける印象は、少女が見せるはずのいろいろの「表情」や「しぐさ」のうち、ある瞬間をリアルに捕らえている感じ、ないしは、つくりものではない自然体を描いている感じです。「今この瞬間」を描く達人はメアリーの友人のドガですね。その影響を受けているのかもしれません。こうした「感じ」は、上に引用した『縫い物をする若い母親』に描かれた少女に通じるものがあります。
ちなみに、この絵の左の椅子で寝ているのは、メアリーの愛犬(グリフォン犬)でしょう(No.86 参照)。少女の「退屈」とは無関係に、超然と寝込んでいる姿の対比が利いています。
| 青い肘掛け椅子 |
この絵でまず目に飛び込んでくるのは白い服と明るい肌色の少女ですが、第2の印象は4つの青い肘掛け椅子です。後方の一つはソファのようですが、便宜上「4つの青い肘掛け椅子」と呼ぶことにします。
絵をじっと眺めていると、4つの青い肘掛け椅子が圧倒的な存在感で迫ってきます。どっしりとした重量感があると同時に、その青色でもって(少女以外の)カンヴァスを支配している。青と言っても緑を感じさせる明るい青色です。No.18「ブルーの世界」で書いた青の分類からいうと、ターコイズ・ブルーとセルリアン・ブルーの中間のような色でしょうか。
少女は退屈して不機嫌で、ちょっと「だらしなく」座っています。しかし椅子はどっしりとその位置を占めている。そして眺めていると、この絵は肘掛け椅子を描くことが目的のようにも思えてきます。少女はそれを強調する手段のような・・・・・・。画家はこの4つの椅子で「何か」を象徴したかったのかもしれません。

|
椅子の配置は独特です。手前から奥へと、非対称に、不揃いに、ずらして配置されています。その青い椅子が配置された室内を、少し上からの視線のクローズアップで、すべての椅子をカンヴァスからはみ出して描く・・・・・・。西欧絵画で室内を描いた絵として、これはかなり特異で大胆な構図ではないでしょうか。この構図の斬新さがこの絵の大きな特徴だと思います。
構図の大胆さといえば、すぐに思い出すのがドガです。ドガは浮世絵や北斎漫画を彷彿とさせる構図の絵をたくさん描いています。その構図の斬新さという意味でもまた、この絵はメアリー・カサットの友人・ドガの影響を感じます。
画家はこの構図により、西洋的遠近法を使わないで部屋の広々とした奥行き感を出すことに成功しました。この空間表現は『青い肘掛け椅子の少女』に独特のものだと思います。絵に使われている色は、白っぽい色(少女の服と肌)と、肘掛け椅子の青と、その他の黒っぽい色(濃い青や茶色)という単純なものです。この単純さも空間の表現にマッチしています。
まとめるとこの絵は「少女のしぐさ」と「青い肘掛け椅子を配した空間表現」で、唯一無二とも言える絵であり、そこが何とも言えず魅力的で、絵の中に引き込まれる感じがします。
連想と想像
『青い肘掛け椅子の少女』(1878)をみて、どうしても連想してしまう絵画があります。メアリー・カサットと同じアメリカ人であるジョン・シンガー・サージェントが、メアリーの絵の4年後にパリで描いた『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館所蔵)です。この絵は No.36「ベラスケスへのオマージュ」で紹介しました。以下『ボイト家の娘たち』と略します。
なぜ『ボイトの娘たち』を連想するかと言うと、
|
『青い肘掛け椅子の少女』は4つの肘掛け椅子を | |||
|
『ボイトの娘たち』は4人の姉妹を |
部屋の中に不均等に配置し、そのことによって独特の空間表現や奥行き感を作り出したという類似性があるからです。
『ボイトの娘たち』はベラスケスの『ラス・メニーナス』(No.19「ベラスケスの怖い絵」参照)からインスピレーションを得て描かれた絵です。サージェントは1879年にプラド美術館を訪れ、『ラス・メニーナス』を模写しました。そして3年後に描いたのが『ボイト家の娘たち』です。No.36「ベラスケスへのオマージュ」で書いたように、この絵は2010年にプラド美術館へ貸し出され、プラド美術館は「招待作品」として『ラス・メニーナス』と並べて展示しました。
そこで思い当たることがあります。サージェントよりメアリー・カサットの方がよほど「スペイン通」だということです。何しろ彼女は20歳台後半にスペインのマドリードとセヴィリアに8ヶ月も滞在しているのです。そこで描いた絵はパリのサロンに入選しています。もちろん彼女はプラド美術館を訪れていて、伝記(No.86 参照)によると「ベラスケスやムリーリョやゴヤの絵に感銘を受けた」とあります。
そしてこれはサージェントの絵からの全くの想像なのですが
| 『青い肘掛け椅子の少女』もまた『ラス・メニーナス』からインスピレーションを得て描かれた絵 |
ではないのでしょうか。なぜそう感じるかという理由はありません。何となくそう思うのであり、しいていうと、サージェントの『ボイト家の娘たち』がそうなら『青い肘掛け椅子の少女』もそうであっておかしくない、ぐらいでしょうか。もっと言うなら「少女」が主人公であり、そばに「寝そべった犬」がいることでしょうか。理由にはなりませんが・・・・・・。
画家が絵からインスピレーションを受けて絵を描くといった場合、そのインスピレーションの「ありよう」は千差万別です。ほんの些細な点にピカッと光るものを感じ、そこから自分のイメージを膨らませる。それは基本的に「制作の秘密」であり、公表されることはあまりない。だからこそ、このような「想像」もべつにかまわないと思っています。
メアリー・カサットの絵のごく一部を見てきたわけですが、これだけでも彼女の「画家像」が分かります。メアリー・カサットは、
| ◆ | イタリア、スペインなどの西欧絵画の源流に学び | |
| ◆ | マネをはじめとする印象派に学び | |
| ◆ | 友人のドガからの影響を強くうけ | |
| ◆ | 日本の浮世絵に斬新さに感動し | |
| ◆ | 自ら版画の制作にまで乗りだし | |
| ◆ | 母子像や子どもを描いた絵で独自世界を作った |
画家です。前回の No.86「ドガとメアリー・カサット」で書いた、
| ◆ | パリのアメリカ人の女性の画家 | |
| ◆ | アメリカの絵画コレクターたちに対する強力なアドバイザーとして、印象派絵画を世界に広めた功績者 |
という彼女の経歴とも合わせ、アートに対する飽くなき探求心とともに生きた画家だったと思います。
| 補記 |
『青い肘掛け椅子の少女』に関する別の記事を、No.125「カサットの"少女"再び」に掲載しました。
No.86 - ドガとメアリー・カサット [アート]
No.19「ベラスケスの怖い絵」で中野京子さんの『怖い絵』に従って、ドガの傑作『エトワール、または舞台の踊り子』を紹介しました。
この「踊り子が当時置かれていた立場」を鮮やかに描き出した小説が最近出版されたので、その内容を紹介したいと思います。No.72で紹介した小説『楽園のカンヴァス』を書いた原田マハさんの『ジヴェルニーの食卓』です。
『ジヴェルニーの食卓』は次の4編からなる短編小説集です。
◆ うつくしい墓
◆ エトワール
◆ タンギー爺さん
◆ ジヴェルニーの食卓
いずれも19世紀から20世紀前半にかけてのフランスの画家とその周辺を主題にした短編小説で、歴史的事実を織り交ぜて作られたフィクションです。今回紹介するのは、その中の『エトワール』です。
『エトワール』は、エドガー・ドガ(1834-1917)と、10歳年下の画家メアリー・カサット(1844-1926)との友情を背景とし、ドガの画家像をメアリー・カサットの視点で書くという構成になっています。そこでまず最初に、メアリー・カサットの生涯とドガとの関係をまとめておきます。メアリー・カサットがどういう画家かを踏まえておかないと、小説の意味が理解しにくいと思うからです。以下はスーザン・E・マイヤー著『メアリー・カサット』(渡辺眞 監訳。山口知子 訳。同朋社。1992)からの要約です。この本の著者は絵画雑誌の編集者を長年勤めた人で、アメリカ人画家に関する著書が多数あります。
メアリー・カサットの生涯
◆1844(0歳)
ペンシルヴァニア州ピッツバーグで生まれる。男3人・女2人の5人兄弟の次女であり、父親は銀行業や不動産業で財をなしていた。
◆1849(5歳)
カサット一家は同じペンシルヴァニア州のフィラデルフィアに移る。
◆1851(7歳)
一家は子供たちの教育のためにパリに移住。そこで2年間を過ごす。
◆1853(9歳)
さらに一家はドイツに移住(ハイデルベルク、ダルムシュタット)。長男をエンジニアの学校に入れるのが大きな目的であった。
◆1855(11歳)
一家はパリに数ヶ月滞在したあと、フィラデルフィアに戻る。
◆1860(16歳)
メアリーはペンシルヴァニア美術アカデミーに入学。
◆1865(21歳)
メアリーはパリに行って画家になる決心を固め、両親にそう宣言する。初め猛反対していた父親も、メアリーの説得を受け入れ、娘のパリ行きを支援した。
◆1866(22歳)
メアリーはパリに到着。ルーブル美術館での模写に励む。国立美術学校で教えていた画家・ジェロームのレッスンも受けた。
この年、メアリーは官展(サロン)に行き、初めてドガの作品を目にします。『メアリー・カサット』では以下のように記述されています。
原田さんの『エトワール』では、この年のサロンでメアリーは、唯一ドガの「障害競馬 - 落馬した騎手」(ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵)に心を惹かれたと書かれています。ちなみに上の引用にあるモネの作品は、妻・カミーユを等身大に描いた「緑衣の女」(独:ブレーメン美術館)という作品です。
◆1868(24歳)
メアリーの作品『マンドリンを弾く女』が官展(サロン)に初入選。
◆1870(26歳)
この年、普仏戦争が勃発。メアリーはアメリカに戻る。
◆1871(27歳)
ピッツバーグの司教から、イタリアのパルマにあるコレッジョの2枚の宗教画を模写するよう依頼をうけ、イタリアに旅立つ。
◆1872(28歳)
スペインのマドリードとセヴィリアに8か月滞在。プラド美術館ではベラスケスやムリーリョ、ゴヤの絵に感銘をうける。この間、多数の絵を制作する。
なお、世界美術全集「印象派の画家たち 9 カサット」(八重樫春樹・柏 健 解説。千趣会 1978)には、「首都マドリードのプラド美術館ではベラスケス、リューベンス、ゴヤなどの作品を熱心に模写した」とあります。
◆1873(29歳)
スペインで描いた『闘牛士にパナルを差し出す女(トレーロと少女)』がサロンに入選。これを機会に、オランダ、ベルギーへの旅行を経てパリに移る。
◆1874(30歳)
『コルティエ婦人の肖像』がサロンに入選。この年、有名な第1回印象派展が開催された。
1874年のサロンをドガが訪れた時のことが『メアリー・カサット』に記述されています。下の引用の「ナダールの展覧会」とはもちろん、第1回印象派展のことです。
◆1875(31歳)
メアリーはパリに永住する意向を固める。彼女は以前に画廊で見たドガの作品に強く惹かれていく。
この頃、メアリーはパリで友人になったアメリカ人のルイジーン・エルダーにドガのパステル画『バレエのリハーサル』を買うように強く勧めます。ルイジーンは100ドルで購入し、これがアメリカ人が購入した最初の印象派作品になりました。ルイジーンはのちに精糖会社を経営していたヘンリー・ハブマイヤーと結婚し、ハブマイヤー夫妻はメアリーをアドバイザーとして印象派の大コレクションを築きます。これらはのちにメトロポリタン美術館に寄贈されました。
メアリーはハブマイヤー夫妻以外にも美術品を収集しているアメリカ人コレクターに印象派の絵を買うように勧めます。アメリカ東部のエスタブリッシュメントの間では「カサット家のお嬢さん推薦」というのが一種の「ブランド」になったようです。現代のアメリカに印象派の重要な作品が数多く存在するのはメアリー・カサットの功績であり、そもそも印象派の絵画が世界的に成功した、その立役者の一人が彼女なのです。
◆1877(33歳)
ドガが、友人のジョセフ・ツアニーの紹介でメアリーのアトリエを訪問。印象派展に出品するよう、メアリーを勧誘する。
◆1879(35歳)
第4回印象派展にメアリー・カサット初出展。出展作は『青い肘掛け椅子の少女』など11点。
これ以降、1880年代・90年代と、メアリーの画家としての才能が大きく開花します。当初酷評された印象派の絵画を擁護し世に広めた画商、ポール・デュラン=リュエルの画廊で個展も開催しました。彼女はフランスでも高名な画家になります。特に「母と子」や「子ども」のモチーフを独特の暖かいタッチで描いた一連の作品は有名です。
◆1904(60歳)
メアリーはフランス政府からレジオン・ド・ヌール勲章(シュヴァリエ)を受ける。1910年代以降は白内障で視力が衰え、ほどんど描かなくなります。
◆1917(73歳)
アトリエで倒れたドガが急逝。ドガ83歳。
◆1926(82歳)
メアリー・カサット逝去
ドガとメアリーは互いのアトリエを訪問し、画家同士の友情で結ばれていました。と同時に、メアリーは画家としてドガの影響を受けています。彼女がパステル画を多く描くようになったのはドガの影響です。二人の関係を『メアリー・カサット』は次のように記述しています。
「死の数年前にドガからの手紙をすべて焼き払った」とありますね。その時点でドガは既に亡くなっています。絶対に他人に読まれたくない手紙ということでしょう。メアリー・カサットからみてドガはどういう人だったのでしょうか。
ちなみにドガがメアリーに贈ったグリフォン犬は『青い肘掛け椅子の少女』(前掲)に描き込まれています。メアリーの他の絵にもこの愛犬が登場します。なお、上の引用には小型テリアとありますが、グリフォン犬とテリア犬は違うので著者の勘違いかと思います。
原田マハ『エトワール』 (短編集『ジヴェルニーの食卓』より)
本題の原田さんの小説『エトワール』です。舞台はパリのポール・デュラン=リュエルの画廊で、ドガの死の翌年、1918年に設定されています。ポール・デュラン=リュエルは一貫して印象派を擁護した画商で、幾多の困難を乗り越えて印象派を世に認知させた立役者です。ドガをはじめとする印象派の画家たちとの付き合い広く、もちろんメアリー・カサットとも旧知の間柄です。
おりしもポール・デュラン=リュエルの画廊では「ドガ回顧展」が開催されていました。メアリー・カサットは招待をうけ、ポールが差し向けたクルマで画廊に到着します。このときポールは87歳、メアリーは74歳です。二人は久しぶりの再会を喜びます。
ドガが亡くなった後のアトリエからは、大量の油彩画、パステル画、デッサンが発見され、画廊はその目録を作ったのでした。その目録の完成記念に開催したのが「ドガ回顧展」です。メアリーとポールはドガの作品を見ながら思い出を語ります。
しかしポールがわざわざ車を差し向けて隠居中のメアリーを画廊に招いたのは、ある目的がありました。ポールはメアリーを車に乗せ、デュラン=リュエル画廊の美術倉庫へと連れていきます。
何重にも鍵がかかった倉庫の中でポールがメアリーに見せたのは、ドガのアトリエで発見された多数の小さな立体作品です。それは蝋で作られたバレエの踊り子で、踊り子がいろいろなポーズをとっているものでした。メアリーはドガがこのような作品を作っていたことを知り、驚きます。ポールは、これは彫刻作品以前の「試作(マケット)」と呼ぶべきで、おそらくドガは絵画を描く際にこれらのマケットを使って踊り子のポーズを研究していたのだという推測を述べます。確かに生身の人間につま先で長時間立つポーズをさせるなど無理です。
しかしポールがメアリーに一番見せたかったのは別のものでした。美術倉庫の一番奥にあったのは、メアリーがよく知っている、彼女にとっても忘れられない作品でした。それはドガの生前に発表された唯一の彫刻作品『14歳の小さな踊り子』です。メアリーは40年近く前にドガのアトリエを訪れた時のことを思い出します。
メアリーはアトリエの前室にコートをかけると、隣室のドガに話かけながらアトリエに入ろうとします。そしてハッと立ち止まってしまいます。黒い布を垂らした壁の前に少女が立っています。少女は全裸です。
ドガはにこやかにメアリーに話かけますが、気が動転したメアリーは前室に戻り、長椅子に腰掛けます。ドガがモデルを前に制作をするのはいつものことでしたが、全裸の女性に行き合ったのは初めてした。しかも年端もいかない少女です。
少女が帰ったあと、メアリーはドガに話かけます。
以前からドガは、アトリエに連れてきた踊り子をモデルに熱心にポーズの研究をしていました。メアリーはその光景を何度も目にしていたのです。
「あの少女もそういう境遇であるに違いない」とメアリーは思いますが、全裸の少女の姿を目撃して以来、メアリーはドガのアトリエから足が遠のきます。
しかし次の印象派展のための作品の制作開始が迫ってきた時期、メアリーは出展作品の意見を交わすためにドガのアトリエを訪問します。その時ドガは蝋で作った少女の小さな像(マケット)を数点見せます。
そしてこのマケットをもとにドガは1メートルほどの大きさの少女の像を作ったのでした。メアリーが再び尋ねてきた時、印象派展まで絶対に秘密にするという条件でドガはその像をメアリーに見せます。
メアリーはモデルになった少女に会おうと決心します。ドガが少女の像を制作した真の理由をどうしても知りたくなったのです。教えられた少女の名前はマリー・ヴァン・ゴーテム。メアリーは冬の夕方、オペラ座の裏口に面した路地で、踊り子たちのレッスンが終わるのを待ちます。
そうして待っている間にも、何台もの馬車が止まり、シルクハットを被った紳士が裏口から劇場に消えていきました。メアリーにはかつてドガが語った言葉が忘れられません。
メアリーはマリーとオペラ座の裏口で出会い、自分も画家であることを言い、自分のアトリエにつれていきます。アトリエに入るなり「全部脱げばいいですか」と吐き捨てるように言うマリーに対し、メアリーはそうじゃない、話を聞きたいだけだと言います。そしてドガのモデルになった経緯や、ドガがマリーにした約束を聞き出します。
ドガがマリーにした約束、およびポール・デュラン=リュエルが『14歳の小さな踊り子』をメアリー・カサットに見せた目的は割愛したいと思います。このあたりが小説のストーリーのキモになっています。
付け加えますと『14歳の小さな踊り子』は第6回印象派展(1881)に出品され、批評家たちから酷評を浴びます。そして売れることもなく、ドガのアトリエにしまい込まれたのでした。
アートにかける情熱
紹介したのはストーリの骨子だけです。この骨子の部分はほとんどフィクション(ないしは作者の推測)でしょう。しかしその骨子の中にドガやメアリーカサットの生涯、二人に出会いと交流などの歴史的事実が多数織り込まれています。また19世紀後半のフランスの美術界の状況やアメリカとの関係が概観できるようになっています。作者は「史実にもとづいたフィクション」と書いています。
『エトワール』の一番のポイントは、アーティストが作品の創造にかける桁外れの情熱を描き出したことでしょう。No.72で紹介した『楽園のカンヴァス』で作者の原田さんは画家(アンリ・ルソー)、コレクター、研究者、キュレーターがそれぞれの立場でアートに賭ける情熱を描いたのですが、この『エトワール』の場合はエドガー・ドガの情熱です。それを友人の画家であるメアリー・カサットの目を通して描くことによってより鮮明にし、その構図の中で当時のパリ・オペラ座の踊り子が置かれていた状況を描き出す・・・・・・。小説の構成テクニックがピタリと決まった作品です。
そしてこの小説のもう一つのポイントはメアリー・カサットですね。小説では彼女はドガという画家を見る「視点」としての役割ですが、よくよく考えれば彼女も相当な人です。
ペンシルヴァニアの良家のお嬢さんが、当時ほとんどいなかった女性の画家を目指し、退路を絶ってパリに移住し、しかも批評家・大衆から酷評されていた前衛アート(=印象派)の運動に参加して「いばらの道」を歩む。ドガに多大な影響を受けつつも、それを乗り越えて「母と子」や「子ども」のモチーフに見られる独自の作品世界を作る。その上、印象派の絵画をアメリカに広めることに注力し、印象派の世界的成功の立役者になる。ただし、そのことを人にひけらかすことはない・・・・・・・・。
メアリー・カサットという画家もまた、そのアートに対する飽くことのない探求心においてはドガに引けをとらないのです。そしてメアリーの伝記、スーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』で何回か強調されていることは、メアリーはアートに対する強い情熱とは別に、人間としては実に控えめで謙虚だったということです。原田マハさんの『エトワール』は、実はそういったメアリー・カサットの人間像もうまく掬い取っていると思いました。
ここからは余談です。モネやゴッホがそうであったように、19世紀後半のパリにいた画家の多くは、日本美術、特に浮世絵の影響を受けています。『エトワール』の二人の画家もそうです。
メアリー・カサットが印象派を世界に広める貢献をしたこと、また、彼女の謙虚な人柄についての証言があります。画商のヴォラールが書いた「画商の想い出」という回想録の中の記述です。英訳版からの引用と、日本語試訳が以下です。
補足しますと、ハブマイヤー夫妻の夫人、ルイジーン・ハブマイヤーはメアリー・カサットの親友であり、本文中に書いたように、カサットの勧めによって購入したドガのパステル画はアメリカ人が初めて買った印象派絵画なのでした。
展示会での会話の部分は必ずしも分かりやすくはないのですが、ヴォラールが展覧会で二人の女性の会話を聞いていたと想像できます。一人はメアリー・カサットであり、会話している二人は互いに誰かは知らない。メアリー・カサットの名前をあげた「もう一人」は、"Oh, nonsense!" と答えた相手が「画家で、メアリー・カサットに嫉妬している」と思ったのでしょう。そういう情景だと解釈するのが最も妥当だと思います。
このエピソードは、スーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』の最後の締めくくりとして出てきます。伝記作者にとっても印象的だったのでしょう。
さらにヴォラールの回想録には重要な点があります。メアリー・カサットがアメリカの実業家に印象派の絵を売ることに非常に熱心だったという事実です。カサットの写真を引用したフィリップ・フック著「印象派はこうして世界を征服した」には、
とありました。今では想像することさえ難しいけれども、印象派とそれに続くポスト印象派は当時の "前衛アート" です。それらの絵を購入してアートとしての成立を支えたのは、フランスのみならずアメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、ロシアなどのコレクターです。そのなかでも最大の顧客であるアメリカへの橋渡しを最初にしたのがカサットだった。絵が売れるということは画家の生活が安定し、アートが発展するということに他なりません。ヴォラールが言うようにカサットは "前衛アート" を扱う画商にとって有り難い存在だったわけですが、一番助かったのは画家のはずです。
我々は、現代において高名な画家は当時も有名だったと錯覚しそうでが、決してそんなことはない。たとえばシスレーは困窮の中で死んだし、ゴッホは絵がほとんど売れずにピストル自殺をしました。ゴーギャンもタヒチで亡くなっています。なぜわざわざタヒチにまで行くのか ─── 。シスレー、ゴッホ、ゴーギャンは、画家としての絶望の中で死んでいったのだと思います。
そしてもちろん、生前から高い評価を受け、絵が売れ、安定した生活を送った "前衛アート" の画家がいたわけです。その背景(の一つ)に当時の新興国家であるアメリカがあり、そこへのブリッジとなった一人がメアリー・カサットだった。まさに印象派が世界に広まる手助けをしたわけで、このことを過小評価してはならないと思います。
なお『画商の想い出』は日本語訳が出版されています(美術公論社 1980)。
現代では全く想像しがたいのですが、本文中に書いたように印象派は当時の批評家から酷評されていました。そのあたりをフィリップ・フック著『印象派はこうして世界を征服した』から引用します(メアリー・カサットの写真を引用した本です)。著者はサザビーズの印象派&近代絵画部門のシニア・ディレクターを勤めた人です。引用に出てくるヴォルフは当時の有名な批評家です。
ちなみに、決闘を申し込もうとしたベルト・モリゾ(1841-1895)の夫とは、マネの弟のウージェーヌ・マネですね(1874年結婚)。この文章で気づくのは、当時のパリには決闘の習慣があったということです。
それはともかく、我々が目にするベルト・モリゾの作品というと、いかにも "おだやか" で "ノーマル" で "家庭的" ですが、それでも批評家からすると「精神異常者」なのです。本文で引用した原田マハさんの短篇小説『エトワール』には、画家(ドガ)のアートにかける情熱と戦いが描かれていたわけですが、そのバックにあるのは印象派に対する酷評や揶揄だった。そこを考えないと小説の真の意味は理解しにくいと思います。
メアリー・カサットとエドガー・ドガの関係についてのエピソードの一つです。『髪を整える少女』(1886。ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵)という作品に関するものです。
本文で引用したスーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』には、二人の関係がいろいろと記述されています。「二人の長い友情の間には、ぶつかり合いも頻繁に起こり、メアリーがドガの振る舞いに怒って会うのを拒むこともあった」ということも書かれていました。この『髪を整える少女』の件も、そういった一つなのだろうと思います。「女に様式などわからない」などと、ひどいことを言われたメアリーが、見返してやろうと発奮して絵を描き、ドガはそれに感嘆した・・・・・・。二人の関係を物語っていると思います。
この絵の「片方の肘をあげ、片方の手は髪をつかむ」というポーズで直観的に思い出すのは、アングルの『ヴィーナスの誕生』と、それとほぼ同じポーズの『泉』ですね。明らかにそれを踏まえていると思います。また、ひょっとしたらこの絵は、ドガの代表作の一つである『アイロンをかける女たち』(1884/6 オルセー美術館)を意識しているのではないでしょうか。メアリーはかなり意図的にモチーフを選んだのかもしれません。
ドガがメアリー・カサットの作品を評した、別のエピソードを紹介します。「化粧」(Woman Bathing)という版画です。一見して日本の浮世絵の影響が見てとれる作品です。
補記3もそうですが、どうも伝えられるドガの発言には「現代人が言ったとしたらセクシャル・ハラスメントになりそうなもの」がいろいろありますね。もちろん当時のヨーロッパは完全な「男社会」であり、そこに出現したアメリカの上流階級出身の女性画家など、ドガがらすると本来「ありえない」存在だったからでしょう。
「女性は素描が下手だ。ただしメアリーだけは別格だ」という意味にとれます。この版画を絶賛した発言だと思います。
2016年6月25日~9月11日の予定で、横浜美術館で「メアリー・カサット展」が開かれています(その後、京都国立近代美術館に巡回)。その音声ガイドで、カサットとドガの関係を暗示するような解説があったので、掲げておきます。
またこの展示会では、メアリー・カサットの年譜の中に次のような記述がありました。
この記事の本文に引用したスーザン・マイヤーの伝記には、「メアリーは、死の数年前にドガからの手紙をすべて焼き払っている」と書かれていました。メアリー・カサットは自分とドガの間で交わした書簡が後世に残ることのないよう、念入りに行動したようです。
この記事の本文でメアリー・カサットの23歳の写真を掲載しましたが、それはフィリップ・クック著『印象派はこうして世界を征服した』からの引用でした。また「補記2」も同じ本からの引用です。
そのフィリップ・クックはオークション会社・サザビーズのシニア・ディレクターですが、彼の別の著書にドガの『14歳の小さな踊り子』を評した箇所があります。この彫刻は本文でとりあげた短編小説『エトワール』(原田マハ)の主題になっているので、是非その箇所を引用したいと思います。
「ホッケー場の香り」とは意外性があるたとえですが、要するに "スポーツをやっている少女から受けるような、健康的ではつらつとしが雰囲気" ということでしょう。
上の文章でフィリップ・クックは、ドガの技量や芸術性に疑問を呈しているのではありません。全く逆で、ドガを非常に高く評価しているのです。同じ本には次のように書いています。
フィリップ・クックが『14歳の小さな踊り子』を評した「男たらしの娘のコケティッシュな気配」とか、「高慢で、金銭ずくで、だらしなく、抜け目ない、そのすべてが入り混じったような表情」というのは偏見でしょうか。彼は美術のプロなので、1880年当時のパリの踊り子の状況を熟知しているはずです(=パトロンを求める下層階級の少女)。「金銭ずくで」などという表現は、その知識なしには書けないでしょう。つまりこの彫刻を見るときの "バイアスがかかった見方" と言えそうです。
しかしそれよりも大きいのは、ドガが真実の姿、リアルな表情を切り取る技量のすごさでしょう。"ドガに魅了されている" 美術のプロフェッショナルが『14歳の小さな踊り子』を評した率直な(率直過ぎる)発言は、一切の美化を排して現実を映し出すアーティスト = ドガ の姿勢を浮き彫りにしています。
1880年のパリのオペラ座の14歳のダンサーと、2009年のロンドンのロイヤル・バレエ学校の14歳のダンサーは全く違う境遇にある。そのことを改めて思い起こす必要があると思いました。
|

| |||
| (パリ・オルセー美術館) | |||
『ジヴェルニーの食卓』は次の4編からなる短編小説集です。
◆ うつくしい墓
◆ エトワール
◆ タンギー爺さん
◆ ジヴェルニーの食卓
いずれも19世紀から20世紀前半にかけてのフランスの画家とその周辺を主題にした短編小説で、歴史的事実を織り交ぜて作られたフィクションです。今回紹介するのは、その中の『エトワール』です。

| |||
|
原田マハ 「ジヴェルニーの食卓」 (集英社。2013) | |||
| 以降、本からの引用にあるアンダーラインは、いずれも原文にはありません。 |
メアリー・カサットの生涯

| ||
|
メアリー・カサット (メトロポリタン美術館) | ||
◆1844(0歳)
ペンシルヴァニア州ピッツバーグで生まれる。男3人・女2人の5人兄弟の次女であり、父親は銀行業や不動産業で財をなしていた。
◆1849(5歳)
カサット一家は同じペンシルヴァニア州のフィラデルフィアに移る。
◆1851(7歳)
一家は子供たちの教育のためにパリに移住。そこで2年間を過ごす。
◆1853(9歳)
さらに一家はドイツに移住(ハイデルベルク、ダルムシュタット)。長男をエンジニアの学校に入れるのが大きな目的であった。
◆1855(11歳)
一家はパリに数ヶ月滞在したあと、フィラデルフィアに戻る。
◆1860(16歳)
メアリーはペンシルヴァニア美術アカデミーに入学。
◆1865(21歳)
メアリーはパリに行って画家になる決心を固め、両親にそう宣言する。初め猛反対していた父親も、メアリーの説得を受け入れ、娘のパリ行きを支援した。
◆1866(22歳)
メアリーはパリに到着。ルーブル美術館での模写に励む。国立美術学校で教えていた画家・ジェロームのレッスンも受けた。
この年、メアリーは官展(サロン)に行き、初めてドガの作品を目にします。『メアリー・カサット』では以下のように記述されています。
|
原田さんの『エトワール』では、この年のサロンでメアリーは、唯一ドガの「障害競馬 - 落馬した騎手」(ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵)に心を惹かれたと書かれています。ちなみに上の引用にあるモネの作品は、妻・カミーユを等身大に描いた「緑衣の女」(独:ブレーメン美術館)という作品です。
◆1868(24歳)
メアリーの作品『マンドリンを弾く女』が官展(サロン)に初入選。
◆1870(26歳)
この年、普仏戦争が勃発。メアリーはアメリカに戻る。
◆1871(27歳)
ピッツバーグの司教から、イタリアのパルマにあるコレッジョの2枚の宗教画を模写するよう依頼をうけ、イタリアに旅立つ。
◆1872(28歳)
スペインのマドリードとセヴィリアに8か月滞在。プラド美術館ではベラスケスやムリーリョ、ゴヤの絵に感銘をうける。この間、多数の絵を制作する。
なお、世界美術全集「印象派の画家たち 9 カサット」(八重樫春樹・柏 健 解説。千趣会 1978)には、「首都マドリードのプラド美術館ではベラスケス、リューベンス、ゴヤなどの作品を熱心に模写した」とあります。
◆1873(29歳)
スペインで描いた『闘牛士にパナルを差し出す女(トレーロと少女)』がサロンに入選。これを機会に、オランダ、ベルギーへの旅行を経てパリに移る。
◆1874(30歳)
『コルティエ婦人の肖像』がサロンに入選。この年、有名な第1回印象派展が開催された。
|
|
1874年のサロンをドガが訪れた時のことが『メアリー・カサット』に記述されています。下の引用の「ナダールの展覧会」とはもちろん、第1回印象派展のことです。
|
◆1875(31歳)
メアリーはパリに永住する意向を固める。彼女は以前に画廊で見たドガの作品に強く惹かれていく。
この頃、メアリーはパリで友人になったアメリカ人のルイジーン・エルダーにドガのパステル画『バレエのリハーサル』を買うように強く勧めます。ルイジーンは100ドルで購入し、これがアメリカ人が購入した最初の印象派作品になりました。ルイジーンはのちに精糖会社を経営していたヘンリー・ハブマイヤーと結婚し、ハブマイヤー夫妻はメアリーをアドバイザーとして印象派の大コレクションを築きます。これらはのちにメトロポリタン美術館に寄贈されました。

| ||
|
エドガー・ドガ
「バレエのリハーサル」(c.1876) ネルソン・アトキンス美術館(The Nelson-Atkins Museum of Art。Kansas City, Missouri, USA)所蔵。パステルとグアッシュ。 ルイジーン・エルダーはメアリー・カサットの強い勧めにより1877年にこの絵を購入し、これがアメリカ人が購入した最初の印象派の絵となった。MoMAのサイトにあるドガの経歴によると、ルイジーンは1878年にこの絵をニューヨークの展覧会に貸し出し、ドガが(従って印象派が)アメリカに紹介された最初の機会となった。つまり、2つの意味で「歴史的」な作品である。リハーサルをしている踊り子を2人の男が見守っているが、右端に描いてあるのは「エトワール、または舞台の踊り子」と同じような「黒服の男」である。この絵もまた、「踊り子が当時置かれていた立場」を表している。画像は Wikimedia Commons より引用。ちなみに、ネルソン・アトキンス美術館は、海北友松の「月下渓流図屏風」を所蔵している美術館である。 | ||
メアリーはハブマイヤー夫妻以外にも美術品を収集しているアメリカ人コレクターに印象派の絵を買うように勧めます。アメリカ東部のエスタブリッシュメントの間では「カサット家のお嬢さん推薦」というのが一種の「ブランド」になったようです。現代のアメリカに印象派の重要な作品が数多く存在するのはメアリー・カサットの功績であり、そもそも印象派の絵画が世界的に成功した、その立役者の一人が彼女なのです。
◆1877(33歳)
ドガが、友人のジョセフ・ツアニーの紹介でメアリーのアトリエを訪問。印象派展に出品するよう、メアリーを勧誘する。
◆1879(35歳)
第4回印象派展にメアリー・カサット初出展。出展作は『青い肘掛け椅子の少女』など11点。

| ||
|
メアリー・カサット
この絵はワシントン・ナショナル・ギャラリー展(国立新美術館。2011.6)で展示された。
「青い肘掛け椅子の少女」(1878) (ワシントン・ナショナル・ | ||
これ以降、1880年代・90年代と、メアリーの画家としての才能が大きく開花します。当初酷評された印象派の絵画を擁護し世に広めた画商、ポール・デュラン=リュエルの画廊で個展も開催しました。彼女はフランスでも高名な画家になります。特に「母と子」や「子ども」のモチーフを独特の暖かいタッチで描いた一連の作品は有名です。

| ||
|
メアリー・カサット
「縫い物をする若い母親」(1900) (メトロポリタン美術館) | ||
◆1904(60歳)
メアリーはフランス政府からレジオン・ド・ヌール勲章(シュヴァリエ)を受ける。1910年代以降は白内障で視力が衰え、ほどんど描かなくなります。
◆1917(73歳)
アトリエで倒れたドガが急逝。ドガ83歳。
◆1926(82歳)
メアリー・カサット逝去
ドガとメアリーは互いのアトリエを訪問し、画家同士の友情で結ばれていました。と同時に、メアリーは画家としてドガの影響を受けています。彼女がパステル画を多く描くようになったのはドガの影響です。二人の関係を『メアリー・カサット』は次のように記述しています。
|
「死の数年前にドガからの手紙をすべて焼き払った」とありますね。その時点でドガは既に亡くなっています。絶対に他人に読まれたくない手紙ということでしょう。メアリー・カサットからみてドガはどういう人だったのでしょうか。
ちなみにドガがメアリーに贈ったグリフォン犬は『青い肘掛け椅子の少女』(前掲)に描き込まれています。メアリーの他の絵にもこの愛犬が登場します。なお、上の引用には小型テリアとありますが、グリフォン犬とテリア犬は違うので著者の勘違いかと思います。

| ||
|
エドガー・ドガ (オルセー美術館) | ||
本題の原田さんの小説『エトワール』です。舞台はパリのポール・デュラン=リュエルの画廊で、ドガの死の翌年、1918年に設定されています。ポール・デュラン=リュエルは一貫して印象派を擁護した画商で、幾多の困難を乗り越えて印象派を世に認知させた立役者です。ドガをはじめとする印象派の画家たちとの付き合い広く、もちろんメアリー・カサットとも旧知の間柄です。
おりしもポール・デュラン=リュエルの画廊では「ドガ回顧展」が開催されていました。メアリー・カサットは招待をうけ、ポールが差し向けたクルマで画廊に到着します。このときポールは87歳、メアリーは74歳です。二人は久しぶりの再会を喜びます。
ドガが亡くなった後のアトリエからは、大量の油彩画、パステル画、デッサンが発見され、画廊はその目録を作ったのでした。その目録の完成記念に開催したのが「ドガ回顧展」です。メアリーとポールはドガの作品を見ながら思い出を語ります。
しかしポールがわざわざ車を差し向けて隠居中のメアリーを画廊に招いたのは、ある目的がありました。ポールはメアリーを車に乗せ、デュラン=リュエル画廊の美術倉庫へと連れていきます。
何重にも鍵がかかった倉庫の中でポールがメアリーに見せたのは、ドガのアトリエで発見された多数の小さな立体作品です。それは蝋で作られたバレエの踊り子で、踊り子がいろいろなポーズをとっているものでした。メアリーはドガがこのような作品を作っていたことを知り、驚きます。ポールは、これは彫刻作品以前の「試作(マケット)」と呼ぶべきで、おそらくドガは絵画を描く際にこれらのマケットを使って踊り子のポーズを研究していたのだという推測を述べます。確かに生身の人間につま先で長時間立つポーズをさせるなど無理です。

| ||
|
ドガが制作した踊り子のマケット (メトロポリタン美術館) | ||
しかしポールがメアリーに一番見せたかったのは別のものでした。美術倉庫の一番奥にあったのは、メアリーがよく知っている、彼女にとっても忘れられない作品でした。それはドガの生前に発表された唯一の彫刻作品『14歳の小さな踊り子』です。メアリーは40年近く前にドガのアトリエを訪れた時のことを思い出します。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
|
メアリーはアトリエの前室にコートをかけると、隣室のドガに話かけながらアトリエに入ろうとします。そしてハッと立ち止まってしまいます。黒い布を垂らした壁の前に少女が立っています。少女は全裸です。
ドガはにこやかにメアリーに話かけますが、気が動転したメアリーは前室に戻り、長椅子に腰掛けます。ドガがモデルを前に制作をするのはいつものことでしたが、全裸の女性に行き合ったのは初めてした。しかも年端もいかない少女です。
少女が帰ったあと、メアリーはドガに話かけます。
|
以前からドガは、アトリエに連れてきた踊り子をモデルに熱心にポーズの研究をしていました。メアリーはその光景を何度も目にしていたのです。
|
「あの少女もそういう境遇であるに違いない」とメアリーは思いますが、全裸の少女の姿を目撃して以来、メアリーはドガのアトリエから足が遠のきます。
しかし次の印象派展のための作品の制作開始が迫ってきた時期、メアリーは出展作品の意見を交わすためにドガのアトリエを訪問します。その時ドガは蝋で作った少女の小さな像(マケット)を数点見せます。
そしてこのマケットをもとにドガは1メートルほどの大きさの少女の像を作ったのでした。メアリーが再び尋ねてきた時、印象派展まで絶対に秘密にするという条件でドガはその像をメアリーに見せます。

| |||
|
エドガー・ドガ
「14歳の小さな踊り子」(1881) (ワシントン・ナショナル・ この作品はドガの死後にブロンズに鋳造され、約30の像が欧米の美術館に所蔵されている。写真はドガが作ったオリジナルの塑像である。高さは約1mで、モデルとなった少女の2/3のサイズである。 ワシントン・ナショナル・ギャラリーの公式カタログは次のように書いている。 ・・・・ そのレアリスムに加えて、ドガは彫像に本物のチュチュとリボンを付けために、ぎょっとさせるものがあった。アカデミー派の、多くは古典に主題を得た裸婦像のなめらかな仕上げに慣れた批評家たちは、「小さいバレリーナ」のレアリスムをグロテスクと評した。作家で美術評論家のJ・K・ユイスマンスは違う感想を持った。「実際のところ、ムッシュー・ドガは一撃にして、彫像の伝統を覆した」。 | |||
|
メアリーはモデルになった少女に会おうと決心します。ドガが少女の像を制作した真の理由をどうしても知りたくなったのです。教えられた少女の名前はマリー・ヴァン・ゴーテム。メアリーは冬の夕方、オペラ座の裏口に面した路地で、踊り子たちのレッスンが終わるのを待ちます。
そうして待っている間にも、何台もの馬車が止まり、シルクハットを被った紳士が裏口から劇場に消えていきました。メアリーにはかつてドガが語った言葉が忘れられません。
|
メアリーはマリーとオペラ座の裏口で出会い、自分も画家であることを言い、自分のアトリエにつれていきます。アトリエに入るなり「全部脱げばいいですか」と吐き捨てるように言うマリーに対し、メアリーはそうじゃない、話を聞きたいだけだと言います。そしてドガのモデルになった経緯や、ドガがマリーにした約束を聞き出します。
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・
ドガがマリーにした約束、およびポール・デュラン=リュエルが『14歳の小さな踊り子』をメアリー・カサットに見せた目的は割愛したいと思います。このあたりが小説のストーリーのキモになっています。
付け加えますと『14歳の小さな踊り子』は第6回印象派展(1881)に出品され、批評家たちから酷評を浴びます。そして売れることもなく、ドガのアトリエにしまい込まれたのでした。
アートにかける情熱
紹介したのはストーリの骨子だけです。この骨子の部分はほとんどフィクション(ないしは作者の推測)でしょう。しかしその骨子の中にドガやメアリーカサットの生涯、二人に出会いと交流などの歴史的事実が多数織り込まれています。また19世紀後半のフランスの美術界の状況やアメリカとの関係が概観できるようになっています。作者は「史実にもとづいたフィクション」と書いています。
『エトワール』の一番のポイントは、アーティストが作品の創造にかける桁外れの情熱を描き出したことでしょう。No.72で紹介した『楽園のカンヴァス』で作者の原田さんは画家(アンリ・ルソー)、コレクター、研究者、キュレーターがそれぞれの立場でアートに賭ける情熱を描いたのですが、この『エトワール』の場合はエドガー・ドガの情熱です。それを友人の画家であるメアリー・カサットの目を通して描くことによってより鮮明にし、その構図の中で当時のパリ・オペラ座の踊り子が置かれていた状況を描き出す・・・・・・。小説の構成テクニックがピタリと決まった作品です。

| |||
|
「パリのアメリカ人」、娘時代のメアリー・カサット。印象派の画家としても活躍したが、印象派絵画を収集する多くのアメリカ人コレクターの強力なアドヴァイザーでもあった。 | |||
ペンシルヴァニアの良家のお嬢さんが、当時ほとんどいなかった女性の画家を目指し、退路を絶ってパリに移住し、しかも批評家・大衆から酷評されていた前衛アート(=印象派)の運動に参加して「いばらの道」を歩む。ドガに多大な影響を受けつつも、それを乗り越えて「母と子」や「子ども」のモチーフに見られる独自の作品世界を作る。その上、印象派の絵画をアメリカに広めることに注力し、印象派の世界的成功の立役者になる。ただし、そのことを人にひけらかすことはない・・・・・・・・。
メアリー・カサットという画家もまた、そのアートに対する飽くことのない探求心においてはドガに引けをとらないのです。そしてメアリーの伝記、スーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』で何回か強調されていることは、メアリーはアートに対する強い情熱とは別に、人間としては実に控えめで謙虚だったということです。原田マハさんの『エトワール』は、実はそういったメアリー・カサットの人間像もうまく掬い取っていると思いました。
ここからは余談です。モネやゴッホがそうであったように、19世紀後半のパリにいた画家の多くは、日本美術、特に浮世絵の影響を受けています。『エトワール』の二人の画家もそうです。
|

| ||
|
メアリー・カサット
「舟遊び」(1893/94) (ワシントン・ナショナル・ギャラリー)
| ||
次回に続く
| 補記1 |
メアリー・カサットが印象派を世界に広める貢献をしたこと、また、彼女の謙虚な人柄についての証言があります。画商のヴォラールが書いた「画商の想い出」という回想録の中の記述です。英訳版からの引用と、日本語試訳が以下です。
|
補足しますと、ハブマイヤー夫妻の夫人、ルイジーン・ハブマイヤーはメアリー・カサットの親友であり、本文中に書いたように、カサットの勧めによって購入したドガのパステル画はアメリカ人が初めて買った印象派絵画なのでした。
展示会での会話の部分は必ずしも分かりやすくはないのですが、ヴォラールが展覧会で二人の女性の会話を聞いていたと想像できます。一人はメアリー・カサットであり、会話している二人は互いに誰かは知らない。メアリー・カサットの名前をあげた「もう一人」は、"Oh, nonsense!" と答えた相手が「画家で、メアリー・カサットに嫉妬している」と思ったのでしょう。そういう情景だと解釈するのが最も妥当だと思います。
このエピソードは、スーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』の最後の締めくくりとして出てきます。伝記作者にとっても印象的だったのでしょう。
さらにヴォラールの回想録には重要な点があります。メアリー・カサットがアメリカの実業家に印象派の絵を売ることに非常に熱心だったという事実です。カサットの写真を引用したフィリップ・フック著「印象派はこうして世界を征服した」には、
| ( | メアリー・カサットは)印象派の画家としても活躍したが、印象派絵画を収集する多くのアメリカ人コレクターの強力なアドバイザーでもあった。 |
とありました。今では想像することさえ難しいけれども、印象派とそれに続くポスト印象派は当時の "前衛アート" です。それらの絵を購入してアートとしての成立を支えたのは、フランスのみならずアメリカ、イギリス、オランダ、ドイツ、ロシアなどのコレクターです。そのなかでも最大の顧客であるアメリカへの橋渡しを最初にしたのがカサットだった。絵が売れるということは画家の生活が安定し、アートが発展するということに他なりません。ヴォラールが言うようにカサットは "前衛アート" を扱う画商にとって有り難い存在だったわけですが、一番助かったのは画家のはずです。
我々は、現代において高名な画家は当時も有名だったと錯覚しそうでが、決してそんなことはない。たとえばシスレーは困窮の中で死んだし、ゴッホは絵がほとんど売れずにピストル自殺をしました。ゴーギャンもタヒチで亡くなっています。なぜわざわざタヒチにまで行くのか ─── 。シスレー、ゴッホ、ゴーギャンは、画家としての絶望の中で死んでいったのだと思います。
そしてもちろん、生前から高い評価を受け、絵が売れ、安定した生活を送った "前衛アート" の画家がいたわけです。その背景(の一つ)に当時の新興国家であるアメリカがあり、そこへのブリッジとなった一人がメアリー・カサットだった。まさに印象派が世界に広まる手助けをしたわけで、このことを過小評価してはならないと思います。
なお『画商の想い出』は日本語訳が出版されています(美術公論社 1980)。
| 補記2 |
現代では全く想像しがたいのですが、本文中に書いたように印象派は当時の批評家から酷評されていました。そのあたりをフィリップ・フック著『印象派はこうして世界を征服した』から引用します(メアリー・カサットの写真を引用した本です)。著者はサザビーズの印象派&近代絵画部門のシニア・ディレクターを勤めた人です。引用に出てくるヴォルフは当時の有名な批評家です。
|
ちなみに、決闘を申し込もうとしたベルト・モリゾ(1841-1895)の夫とは、マネの弟のウージェーヌ・マネですね(1874年結婚)。この文章で気づくのは、当時のパリには決闘の習慣があったということです。
それはともかく、我々が目にするベルト・モリゾの作品というと、いかにも "おだやか" で "ノーマル" で "家庭的" ですが、それでも批評家からすると「精神異常者」なのです。本文で引用した原田マハさんの短篇小説『エトワール』には、画家(ドガ)のアートにかける情熱と戦いが描かれていたわけですが、そのバックにあるのは印象派に対する酷評や揶揄だった。そこを考えないと小説の真の意味は理解しにくいと思います。
| 補記3 |
メアリー・カサットとエドガー・ドガの関係についてのエピソードの一つです。『髪を整える少女』(1886。ワシントン・ナショナル・ギャラリー所蔵)という作品に関するものです。

| ||
|
メアリー・カサット
『髪を整える少女』(1886)
(ワシントン・ナショナル・ギャラリー)
| ||
|
本文で引用したスーザン・マイヤー著『メアリー・カサット』には、二人の関係がいろいろと記述されています。「二人の長い友情の間には、ぶつかり合いも頻繁に起こり、メアリーがドガの振る舞いに怒って会うのを拒むこともあった」ということも書かれていました。この『髪を整える少女』の件も、そういった一つなのだろうと思います。「女に様式などわからない」などと、ひどいことを言われたメアリーが、見返してやろうと発奮して絵を描き、ドガはそれに感嘆した・・・・・・。二人の関係を物語っていると思います。
この絵の「片方の肘をあげ、片方の手は髪をつかむ」というポーズで直観的に思い出すのは、アングルの『ヴィーナスの誕生』と、それとほぼ同じポーズの『泉』ですね。明らかにそれを踏まえていると思います。また、ひょっとしたらこの絵は、ドガの代表作の一つである『アイロンをかける女たち』(1884/6 オルセー美術館)を意識しているのではないでしょうか。メアリーはかなり意図的にモチーフを選んだのかもしれません。
|
|

| ||
|
エドガー・ドガ
『アイロンをかける女たち』(1884/6)
(オルセー美術館)
| ||
| 補記4 |
ドガがメアリー・カサットの作品を評した、別のエピソードを紹介します。「化粧」(Woman Bathing)という版画です。一見して日本の浮世絵の影響が見てとれる作品です。

| ||
|
メアリー・カサット
『化粧』(1990/1991)
(アクアチント + ドライポイント + エッチング)
(メトロポリタン美術館蔵) | ||
|
補記3もそうですが、どうも伝えられるドガの発言には「現代人が言ったとしたらセクシャル・ハラスメントになりそうなもの」がいろいろありますね。もちろん当時のヨーロッパは完全な「男社会」であり、そこに出現したアメリカの上流階級出身の女性画家など、ドガがらすると本来「ありえない」存在だったからでしょう。
「女性は素描が下手だ。ただしメアリーだけは別格だ」という意味にとれます。この版画を絶賛した発言だと思います。
| 補記5 |
2016年6月25日~9月11日の予定で、横浜美術館で「メアリー・カサット展」が開かれています(その後、京都国立近代美術館に巡回)。その音声ガイドで、カサットとドガの関係を暗示するような解説があったので、掲げておきます。
|
またこの展示会では、メアリー・カサットの年譜の中に次のような記述がありました。
|
この記事の本文に引用したスーザン・マイヤーの伝記には、「メアリーは、死の数年前にドガからの手紙をすべて焼き払っている」と書かれていました。メアリー・カサットは自分とドガの間で交わした書簡が後世に残ることのないよう、念入りに行動したようです。
(2016.7.31)
| 補記6 |
この記事の本文でメアリー・カサットの23歳の写真を掲載しましたが、それはフィリップ・クック著『印象派はこうして世界を征服した』からの引用でした。また「補記2」も同じ本からの引用です。
そのフィリップ・クックはオークション会社・サザビーズのシニア・ディレクターですが、彼の別の著書にドガの『14歳の小さな踊り子』を評した箇所があります。この彫刻は本文でとりあげた短編小説『エトワール』(原田マハ)の主題になっているので、是非その箇所を引用したいと思います。
|
「ホッケー場の香り」とは意外性があるたとえですが、要するに "スポーツをやっている少女から受けるような、健康的ではつらつとしが雰囲気" ということでしょう。
上の文章でフィリップ・クックは、ドガの技量や芸術性に疑問を呈しているのではありません。全く逆で、ドガを非常に高く評価しているのです。同じ本には次のように書いています。
| 私はドガに魅了されている。私にとって、ドガは芸術におけるフランスの真髄を体現している。彼はおそらく19世紀の最も偉大なデッサン家であり、また構図に対する卓越した眼をもった、技巧的にも最高の革新者だった。 |

| |||
|
2009年のサザビーズのオークションのプロモーションの写真。フィリップ・クック「サザビーズで朝食を」より
| |||
しかしそれよりも大きいのは、ドガが真実の姿、リアルな表情を切り取る技量のすごさでしょう。"ドガに魅了されている" 美術のプロフェッショナルが『14歳の小さな踊り子』を評した率直な(率直過ぎる)発言は、一切の美化を排して現実を映し出すアーティスト = ドガ の姿勢を浮き彫りにしています。
1880年のパリのオペラ座の14歳のダンサーと、2009年のロンドンのロイヤル・バレエ学校の14歳のダンサーは全く違う境遇にある。そのことを改めて思い起こす必要があると思いました。
(2018.11.12)
No.85 - 洛中洛外図と群鶴図 [アート]
No.34 の主題の「大坂夏の陣図屏風」(大阪城天守閣蔵)は六曲一双の屏風で、右隻には戦闘場面が、左隻は敗残兵や戦火を逃れる市民が描かれていました。No.34 に掲げた左隻を見ても分かるのですが、ここにはものすごい数の人が描かれています。六曲一双で5000人程度と言います。大坂城という「市街地」での大戦闘なので、必然的にそうなるのでしょう。
それに関係してですが、ものすごい数の人が描かれた屏風は他にもあります。有名なのが「洛中洛外図屏風」で、これは「大坂夏の陣図屏風」以上に良く知られています。歴史の教科書でも見た記憶があります。
実は先日「洛中洛外図屏風(上杉本)」の実物大の複製を見る機会がありました。京都市の北西隣の亀岡市で「複製画の日本美術展」が開催されていたので、3月末に京都へ行ったついで見てきたのです。今回はその「複製画の日本美術展」と、そこに出品されていた「洛中洛外図屏風」をはじめとする日本画の感想を書きたいと思います。
文化財デジタル複製品展覧会
亀岡市で開かれていた複製画の日本美術展は「文化財デジタル複製品展覧会 - 日本の美」という名称で、2013年3月12日から24日までの期間でした。ここに出品された複製画は以下の通りです。
複製画美術展の驚き
まず、この美術展全体の感想です。
ここで展示されていたのは、江戸期とそれ以前の日本美術の「至宝」ともいうべき作品ばかりです。展示された作品は、アメリカにある5点を除くと13作品ですが、そのうち国宝は6点、重要文化財が5点あります。「国宝・重文率」が85%(11/13)という、超豪華な美術展なのです。合計18作品のうち何点かは実物を見たことがあるのですが、多くは初めてでした。それもそのはずで、これだけの作品が一堂に会することは実物展示では考えられないでしょう。また、狩野派の作品が、
狩野元信(1476-1559)
狩野永徳(1543-1590)
狩野山楽(1559-1635)
狩野内膳(1570-1616)
狩野山雪(1589-1651)
狩野探幽(1602-1674)
と、狩野派の基礎を築いた元信(室町時代)から江戸時代まで、ズラッと揃っていることも特筆すべきです。
滅多に見られない作品もありました。特にアメリカの首都・ワシントンのフリーア美術館の3点、俵屋宗達「雲龍図屏風」「松島図屏風」と、尾形光琳「群鶴図屏風」は、本物を見た日本人は極くわずかなのではないでしょうか。この3点は、日本にあれば国宝になるべき絵だと思います。
展示されている複製画は、実物大で極めて精巧に作られていて、それを見たときの印象、ないしは感動は本物と変わりません。どうやって複製したのか。
上の表で★印をつけたのは、キヤノン株式会社が社会貢献活動として京都文化協会と共同で行っている「綴プロジェクト」(正式名称:文化財未来継承プロジェクト)で作られた作品です。「綴プロジェクト」の制作過程を次に掲げておきます。
複製の制作は、最新の光学(カメラ)技術・デジタル技術・インクジェット印刷技術が駆使されていて、それに現代に受け継がれている伝統工芸がミックスされているわけです。近づいてみても「本物と変わらない」という印象を受けるはずです。
この複製画美術展の大きな特色は「極めて接近して鑑賞できる」という点です。出品された18点のうち16点は屏風絵か襖絵です。制作された当時は、当然、屋敷や寺院の屏風や襖として設置されたわけです。人がそれを「鑑賞」するときには、数メートル離れて全体を見ることも、数10センチの距離に近づいて細部を見ることも、また斜めに俯瞰して見ることも自由に出来たのです。この複製画の美術展ではそれが自由にできます。
本物だと一般にそうはいきません。長谷川等伯「松林図屏風」を東京の美術館で見た時には(確か、丸の内にある出光美術館)、この屏風はガラスケースの中に鎮座していました。今回のテーマの「洛中洛外図屏風」もそうで、上杉博物館のテレビ映像を見るとガラスの展示ケースの中にあります。両方とも国宝なのでそれはやむをえないと思います。それが「松林図や洛中洛外図の現代における鑑賞スタイルだ」と言ってしまえば、確かにそうです。
しかし屏風絵や襖絵は、やはり近寄っても見てみたい。端に立って斜めにも見たい。もともと人間との距離感がそう作られているからです。そして「最接近して鑑賞できる」という「複製画美術展」のメリットを最も感じたのが、この文章の最初に書いた「洛中洛外図屏風」だったのです。
狩野永徳「洛中洛外図屏風」(国宝)
京都の市街と郊外を俯瞰的に描いた「洛中洛外図」は、日本の歴史上、数多く作られたのですが、この狩野永徳の六曲一双の屏風(上杉本)は、その中でも随一の傑作です。織田信長が上杉謙信に贈ったと言われています。
金雲の隙間をよく見ると、祇園祭の山鉾があるし、御所をはじめ、神社・仏閣、公家や武家の屋敷、庶民の家が描かれています。田畑があり、川が流れ、周辺には山(比叡山、愛宕山)がある。しかし全体的に最も目を引くのは「人の多さ」です。六曲一双に登場する「人」は約2500人と言います(2013.6.1のTV東京「美の巨人たち」によると2485人)。とにかくかなりの数の「人」が描かれている。
その「人」も、公家から武家、僧侶、庶民までさまざまです。しかも、当時の都の生活や風俗が克明に描かれています。屏風に2-30センチメートル程度に近づいて、目をこらして順番に見ていくと、それがよく分かる。この屏風が第一級の歴史研究資料でもある理由が納得できました。これは近接して見ないと本当の価値が分からない絵なのです。上に掲げた図もそうなのですが、全体を俯瞰する位置だけで見ても、この屏風の意義とおもしろさは分からない。その意味で「2-30センチメートル程度に目を近づけて順番に見る」という「複製画美術展でしか出来ない鑑賞スタイル」が出来たのが良かったと思います。
国宝である本物だとこうはいかないでしょう。その意味では、この「複製画美術展」は貴重な経験だったと思います。
さらにこの展覧会は「滅多に見れない絵」を見れたということでも印象深いものでした。その一つがフリーア美術館所蔵の「群鶴図屏風」です。
フリーア美術館
アメリカのワシントン D.C.にスミソニアン博物館があります。スミソニアンは「博物館群」であり、あたりには航空宇宙博物館、自然史博物館などの巨大建造物が立ち並んでいて、またナショナル・ギャラリーも同じ一帯にあります。この博物館群の一角に東洋美術の宝庫であるフリーア美術館があります。
今回の「複製画美術展」ではフリーア美術館の3点が展示されていました。俵屋宗達の「雲龍図屏風」「松島図屏風」、尾形光琳の「群鶴図屏風」です。いずれも、もし日本にあれば(たぶん)国宝になるはずの傑作です。
私はフリーア美術館に行ったことがありますが、この美術館は比較的“こぶり”です。六曲一双の屏風のように展示スペースを多くとる作品の常設展示は無理なのでしょう。作品の保護の問題もある。私が行った時には、宗達と光琳の3点はいずれも展示されていませんでした。
フリーア美術館は鉄道王、チャールズ・フリーア(1854-1919)のコレクションを展示する美術館ですが、遺言によって美術品は門外不出です。宗達と光琳だけみてもフリーアの審美眼は大したものだと思いますが、門外不出で展示もなしということは実質的に死蔵ということになります。亡くなってから1世紀近くたつので、そろそろ方針を変えた方がいいのではと思うのですが・・・・・・。とにかく宗達と光琳に関して言うと、本物を見るのはまず難しいということになります。その意味では今回の「複製画美術展」は大変に貴重な機会でした。
尾形光琳「群鶴図屏風」
本題の尾形光琳(1658-1716)の「群鶴図屏風」です。左隻に9羽、右隻に10羽、合計19羽の鶴が向かい合ってる姿が描かれています。鶴は(ほとんど)白黒モノトーンの二色、背景は金地と黒の二色です。黒は水のようですが、池か川か、はっきりはしません。水辺を抽象的に表現しています。全体に最小限の色使いであり、鶴以外は具象的に描かれたものがない。
近接して見ると、屏風の天地いっぱいに描かれた巨大な鶴たちが異様な迫力で迫ってきます。実物大の複製だからこそです。一方、全体を俯瞰して見ると、大胆な構図が印象的で、左隻と右隻の鶴たちが向かい合った対比、集団として対峙している姿が鮮烈です。
この絵をじっと見ていると「これは何を描こうとしたのか」という思いが湧いてくるのですね。江戸期の京都生まれの絵師である光琳が、シンプルに鶴を描こうとして鶴を描いた(ないしは鶴の絵の注文を受けて描いた)のは間違いないでしょう。しかし現代人である我々は、光琳以降の現代までの絵画やヨーロッパの近代絵画を知っています。光琳の意図と別に、現代人として絵を見て感じるものがあってもよい。
ヨーロッパの近代絵画に「象徴主義」といわれる絵画があります。「そこに表現されている具象物は、単なる具象ではなく、別のなにかの象徴としてある」というような作品です。絵画は多かれ少なかれ象徴性があると言えますが、その「象徴性を最大限に押し出した絵」ということかと思います。
群鶴図は、何か非常に存在感のあるモノの一群が対峙しているという、そのシチュエーションそのものを描いた絵ではないでしょうか。「鶴」は、鶴であって単なる鶴ではなく、何かの象徴のように思えてくるのです。
19世紀末から20世紀初頭のオーストリアの画家にグスタフ・クリムト(1862-1918)がいます。クリムトの絵は象徴主義の気配が非常に強く、かつ、明らかに日本画の影響を受けています。金地・金箔を多用し、装飾的で平面的な画面構成が多い。もし仮に群鶴図に「出会い」とか「遭遇」とか、そういった題を付け、クリムトに強く影響されたヨーロッパの画家の作品だといったら通用してしまうのではと、ふと考えてしまうのです。もちろんそれは言い過ぎなのですが(野生動物が画題のヨーロッパ絵画はあまり思い浮かばない)、そう思ってしまうほどこの絵から受けるただものではない感じは強いわけです。また、ある種の普遍性を感じる。
よく考えると、光琳の絵におけるこの種の「象徴性のようなもの」は群鶴図だけではありません。私見で尾形光琳の傑作をあげると、
の4点です。「八橋図」は複製画美術展にも出品されていました。これらの絵に描かれる梅・カキツバタ・鶴・橋ななどは、いずれも象徴性が感じられます。なぜそう感じるかというと、おそらくそれは、これらの絵が「構図で勝負している」からでしょう。
4つの絵に共通する、シンプルなモチーフと斬新で大胆な構図。それが際だっているのが群鶴図だと思いました。
綴プロジェクト
それにしても「綴プロジェクト」というキヤノンの社会貢献活動の価値は大きいと思います。企業が自社の技術を駆使して文化財の価値を世の中に広めているわけで、それは文化財の保護と継承にも役立っている。最新テクノロジーが金箔や表装の伝統技術と一体化しているところも素晴らしいと思いました。また私にとっては、尾形光琳の「4大傑作」のうち、唯一実物を見たことがなかった「群鶴図」を鑑賞する機会を与えてくれたのでした。キヤノンさんに感謝したいと思います。
そして思ったのですが、是非とも「綴プロジェクト」で「大坂夏の陣図屏風」の複製を作ってほしい。No.34 の紹介でも明らかなように、この屏風は「洛中洛外図屏風」と同じで、近接して舐めるように見ないと価値がわからない絵です。作者不詳作品であっても、複製を作る意義は非常に大きいと思います。
スミソニアン博物館は所蔵する美術品のデジタル画像を公開するプロジェクトを推進してきましたが、その第1弾としてフリーア美術館の美術品が公開されました(2015.1)。尾形光琳の「群鶴図屏風」もフリーア美術館の公式サイトの Collections から検索できます("Korin Cranes")。
それに関係してですが、ものすごい数の人が描かれた屏風は他にもあります。有名なのが「洛中洛外図屏風」で、これは「大坂夏の陣図屏風」以上に良く知られています。歴史の教科書でも見た記憶があります。
実は先日「洛中洛外図屏風(上杉本)」の実物大の複製を見る機会がありました。京都市の北西隣の亀岡市で「複製画の日本美術展」が開催されていたので、3月末に京都へ行ったついで見てきたのです。今回はその「複製画の日本美術展」と、そこに出品されていた「洛中洛外図屏風」をはじめとする日本画の感想を書きたいと思います。
文化財デジタル複製品展覧会
亀岡市で開かれていた複製画の日本美術展は「文化財デジタル複製品展覧会 - 日本の美」という名称で、2013年3月12日から24日までの期間でした。ここに出品された複製画は以下の通りです。
| 作者 | 作品 | 国宝 重文 |
原本所蔵 | 綴 | |
| 複製所蔵 | |||||
| ① | 伝・ 藤原隆信 |
神護寺三像 | 国宝 | 神護寺(京都市) | ★ |
| 神護寺(京都市) | |||||
| ② | 狩野元信 | 四季花鳥図屏風 | 重文 | 白鶴美術館(神戸市) | ★ |
| 白鶴美術館(神戸市) | |||||
| ③ | 狩野永徳 | 花鳥図襖 | 国宝 | 大徳寺(京都市) | |
| 大徳寺(京都市) | |||||
| ④ | 狩野内膳 | 南蛮屏風 | 重文 | 神戸市立博物館 | ★ |
| 神戸市立博物館 | |||||
| ⑤ | 狩野山楽 | 龍虎図屏風 | 重文 | 妙心寺(京都市) | |
| 妙心寺(京都市) | |||||
| ⑥ | 狩野山雪 | 老梅図襖 | - | メトロポリタン美術館(米国) | ★ |
| 妙心寺(京都市) | |||||
| ⑦ | 狩野探幽 | 群虎図襖 | 重文 | 南禅寺(京都市) | |
| 南禅寺(京都市) | |||||
| ⑧ | 狩野永徳 | 洛中洛外図屏風 (上杉本) |
国宝 | 上杉博物館(米沢市) | ★ |
| 米沢市 | |||||
| ⑨ | 長谷川等伯 | 松林図屏風 | 国宝 | 東京国立博物館 | ★ |
| 東京国立博物館 | |||||
| ⑩ | 俵屋宗達 | 雲龍図屏風 | - | フリーア美術館(米国) | ★ |
| 東京藝術大学大学美術館 | |||||
| ⑪ | 俵屋宗達 | 風神雷神図屏風 | 国宝 | 建仁寺(京都市) | ★ |
| 建仁寺(京都市) | |||||
| ⑫ | 俵屋宗達 | 松島図屏風 | - | フリーア美術館(米国) | ★ |
| 祥雲寺(大阪府堺市) | |||||
| ⑬ | 尾形光琳 | 群鶴図屏風 | - | フリーア美術館(米国) | ★ |
| 東京都美術館 | |||||
| ⑭ | 尾形光琳 | 八橋図屏風 | - | メトロポリタン美術館(米国) | ★ |
| 京都市 | |||||
| ⑮ | 円山応挙 | 龍門鯉魚図 | 大乗寺(兵庫県美方郡) | ||
| 大乗寺(兵庫県美方郡) | |||||
| ⑯ | 円山応挙 | 雪松図屏風 | 国宝 | 三井記念美術館(東京) | ★ |
| 三井記念美術館(東京) | |||||
| ⑰ | 曾我簫白 | 楼閣山水図屏風 | 重文 | 近江神宮(滋賀県大津市) | ★ |
| 近江神宮(滋賀県大津市) | |||||
| ⑱ | 伊藤若沖 | 樹花鳥獣図屏風 | 静岡県立美術館 | ★ | |
| 静岡県立美術館 |
複製画美術展の驚き
まず、この美術展全体の感想です。
| 日本美術の至宝 |
ここで展示されていたのは、江戸期とそれ以前の日本美術の「至宝」ともいうべき作品ばかりです。展示された作品は、アメリカにある5点を除くと13作品ですが、そのうち国宝は6点、重要文化財が5点あります。「国宝・重文率」が85%(11/13)という、超豪華な美術展なのです。合計18作品のうち何点かは実物を見たことがあるのですが、多くは初めてでした。それもそのはずで、これだけの作品が一堂に会することは実物展示では考えられないでしょう。また、狩野派の作品が、
狩野元信(1476-1559)
狩野永徳(1543-1590)
狩野山楽(1559-1635)
狩野内膳(1570-1616)
狩野山雪(1589-1651)
狩野探幽(1602-1674)
と、狩野派の基礎を築いた元信(室町時代)から江戸時代まで、ズラッと揃っていることも特筆すべきです。
滅多に見られない作品もありました。特にアメリカの首都・ワシントンのフリーア美術館の3点、俵屋宗達「雲龍図屏風」「松島図屏風」と、尾形光琳「群鶴図屏風」は、本物を見た日本人は極くわずかなのではないでしょうか。この3点は、日本にあれば国宝になるべき絵だと思います。
| 非常に精巧な複製 |
展示されている複製画は、実物大で極めて精巧に作られていて、それを見たときの印象、ないしは感動は本物と変わりません。どうやって複製したのか。
上の表で★印をつけたのは、キヤノン株式会社が社会貢献活動として京都文化協会と共同で行っている「綴プロジェクト」(正式名称:文化財未来継承プロジェクト)で作られた作品です。「綴プロジェクト」の制作過程を次に掲げておきます。
|

|

|
|||
|
①撮影 綴プロジェクトのために開発された回転台の上にデジタル1眼カメラ・EOS-1Ds MarkIIIを設置し、文化財を多分割撮影する。 |
②色合わせ 照明の違いによる色の見え方を補正し、本物の色と合わせる。 |
||||
| | |||||

|

|

|
|||
|
③印刷 12色の顔料インクシステムを採用した大型プリンタを使い、綴プロジェクトのために開発された和紙や絹本に印刷する。 |
④金箔 金箔・金泥や雲母(きら)を伝統工芸技術で再現する。経年変化を表す「古色」と呼ばれる風合いを重視。 |
⑤表装 表具師により、日本独自の表装材料を用いて襖や屏風が完成する。 |
|||
複製の制作は、最新の光学(カメラ)技術・デジタル技術・インクジェット印刷技術が駆使されていて、それに現代に受け継がれている伝統工芸がミックスされているわけです。近づいてみても「本物と変わらない」という印象を受けるはずです。
| なお、綴プロジェクトの作品は、キヤノンのホームページで公開されています。 |
| 最接近して鑑賞できる |
この複製画美術展の大きな特色は「極めて接近して鑑賞できる」という点です。出品された18点のうち16点は屏風絵か襖絵です。制作された当時は、当然、屋敷や寺院の屏風や襖として設置されたわけです。人がそれを「鑑賞」するときには、数メートル離れて全体を見ることも、数10センチの距離に近づいて細部を見ることも、また斜めに俯瞰して見ることも自由に出来たのです。この複製画の美術展ではそれが自由にできます。
本物だと一般にそうはいきません。長谷川等伯「松林図屏風」を東京の美術館で見た時には(確か、丸の内にある出光美術館)、この屏風はガラスケースの中に鎮座していました。今回のテーマの「洛中洛外図屏風」もそうで、上杉博物館のテレビ映像を見るとガラスの展示ケースの中にあります。両方とも国宝なのでそれはやむをえないと思います。それが「松林図や洛中洛外図の現代における鑑賞スタイルだ」と言ってしまえば、確かにそうです。
しかし屏風絵や襖絵は、やはり近寄っても見てみたい。端に立って斜めにも見たい。もともと人間との距離感がそう作られているからです。そして「最接近して鑑賞できる」という「複製画美術展」のメリットを最も感じたのが、この文章の最初に書いた「洛中洛外図屏風」だったのです。
狩野永徳「洛中洛外図屏風」(国宝)

|

|
| 洛中洛外図屏風(上杉本)の左隻(上)と右隻(下)- Wikipediaより |
京都の市街と郊外を俯瞰的に描いた「洛中洛外図」は、日本の歴史上、数多く作られたのですが、この狩野永徳の六曲一双の屏風(上杉本)は、その中でも随一の傑作です。織田信長が上杉謙信に贈ったと言われています。
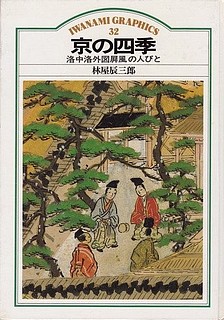
| |||
|
林屋辰三郎「京の四季」
この本は「洛中洛外図屏風(上杉本)」に登場する公家から庶民に至る人々の各種の風俗シーンを、季節ごと12か月に分類し解説したものである。1冊がまるごと「洛中洛外図屏風」の解説になっている。表紙は公家の館の蹴鞠の風景。
(岩波書店。1985) | |||
その「人」も、公家から武家、僧侶、庶民までさまざまです。しかも、当時の都の生活や風俗が克明に描かれています。屏風に2-30センチメートル程度に近づいて、目をこらして順番に見ていくと、それがよく分かる。この屏風が第一級の歴史研究資料でもある理由が納得できました。これは近接して見ないと本当の価値が分からない絵なのです。上に掲げた図もそうなのですが、全体を俯瞰する位置だけで見ても、この屏風の意義とおもしろさは分からない。その意味で「2-30センチメートル程度に目を近づけて順番に見る」という「複製画美術展でしか出来ない鑑賞スタイル」が出来たのが良かったと思います。
国宝である本物だとこうはいかないでしょう。その意味では、この「複製画美術展」は貴重な経験だったと思います。
さらにこの展覧会は「滅多に見れない絵」を見れたということでも印象深いものでした。その一つがフリーア美術館所蔵の「群鶴図屏風」です。
フリーア美術館

| |||
| Freer Gallery of Art | |||
今回の「複製画美術展」ではフリーア美術館の3点が展示されていました。俵屋宗達の「雲龍図屏風」「松島図屏風」、尾形光琳の「群鶴図屏風」です。いずれも、もし日本にあれば(たぶん)国宝になるはずの傑作です。
私はフリーア美術館に行ったことがありますが、この美術館は比較的“こぶり”です。六曲一双の屏風のように展示スペースを多くとる作品の常設展示は無理なのでしょう。作品の保護の問題もある。私が行った時には、宗達と光琳の3点はいずれも展示されていませんでした。
フリーア美術館は鉄道王、チャールズ・フリーア(1854-1919)のコレクションを展示する美術館ですが、遺言によって美術品は門外不出です。宗達と光琳だけみてもフリーアの審美眼は大したものだと思いますが、門外不出で展示もなしということは実質的に死蔵ということになります。亡くなってから1世紀近くたつので、そろそろ方針を変えた方がいいのではと思うのですが・・・・・・。とにかく宗達と光琳に関して言うと、本物を見るのはまず難しいということになります。その意味では今回の「複製画美術展」は大変に貴重な機会でした。
尾形光琳「群鶴図屏風」

|
| 群鶴図(各166.0×371.0cm) |
本題の尾形光琳(1658-1716)の「群鶴図屏風」です。左隻に9羽、右隻に10羽、合計19羽の鶴が向かい合ってる姿が描かれています。鶴は(ほとんど)白黒モノトーンの二色、背景は金地と黒の二色です。黒は水のようですが、池か川か、はっきりはしません。水辺を抽象的に表現しています。全体に最小限の色使いであり、鶴以外は具象的に描かれたものがない。
近接して見ると、屏風の天地いっぱいに描かれた巨大な鶴たちが異様な迫力で迫ってきます。実物大の複製だからこそです。一方、全体を俯瞰して見ると、大胆な構図が印象的で、左隻と右隻の鶴たちが向かい合った対比、集団として対峙している姿が鮮烈です。
この絵をじっと見ていると「これは何を描こうとしたのか」という思いが湧いてくるのですね。江戸期の京都生まれの絵師である光琳が、シンプルに鶴を描こうとして鶴を描いた(ないしは鶴の絵の注文を受けて描いた)のは間違いないでしょう。しかし現代人である我々は、光琳以降の現代までの絵画やヨーロッパの近代絵画を知っています。光琳の意図と別に、現代人として絵を見て感じるものがあってもよい。
ヨーロッパの近代絵画に「象徴主義」といわれる絵画があります。「そこに表現されている具象物は、単なる具象ではなく、別のなにかの象徴としてある」というような作品です。絵画は多かれ少なかれ象徴性があると言えますが、その「象徴性を最大限に押し出した絵」ということかと思います。
群鶴図は、何か非常に存在感のあるモノの一群が対峙しているという、そのシチュエーションそのものを描いた絵ではないでしょうか。「鶴」は、鶴であって単なる鶴ではなく、何かの象徴のように思えてくるのです。
19世紀末から20世紀初頭のオーストリアの画家にグスタフ・クリムト(1862-1918)がいます。クリムトの絵は象徴主義の気配が非常に強く、かつ、明らかに日本画の影響を受けています。金地・金箔を多用し、装飾的で平面的な画面構成が多い。もし仮に群鶴図に「出会い」とか「遭遇」とか、そういった題を付け、クリムトに強く影響されたヨーロッパの画家の作品だといったら通用してしまうのではと、ふと考えてしまうのです。もちろんそれは言い過ぎなのですが(野生動物が画題のヨーロッパ絵画はあまり思い浮かばない)、そう思ってしまうほどこの絵から受けるただものではない感じは強いわけです。また、ある種の普遍性を感じる。

|

|
よく考えると、光琳の絵におけるこの種の「象徴性のようなもの」は群鶴図だけではありません。私見で尾形光琳の傑作をあげると、
| ◆ | 紅梅白梅図(国宝) | 熱海・MOA美術館 | |
| ◆ | 燕子花図(国宝) | 東京・根津美術館 | |
| ◆ | 八橋図 | 米国・メトロポリタン美術館 | |
| ◆ | 群鶴図 | 米国・フリーア美術館 |
の4点です。「八橋図」は複製画美術展にも出品されていました。これらの絵に描かれる梅・カキツバタ・鶴・橋ななどは、いずれも象徴性が感じられます。なぜそう感じるかというと、おそらくそれは、これらの絵が「構図で勝負している」からでしょう。
4つの絵に共通する、シンプルなモチーフと斬新で大胆な構図。それが際だっているのが群鶴図だと思いました。

|
|
紅梅白梅図(各156.0×172.2cm) |

|
|
燕子花図(各150.9×338.8cm) |

|
|
八橋図(各179.1×371.5cm) |
綴プロジェクト
それにしても「綴プロジェクト」というキヤノンの社会貢献活動の価値は大きいと思います。企業が自社の技術を駆使して文化財の価値を世の中に広めているわけで、それは文化財の保護と継承にも役立っている。最新テクノロジーが金箔や表装の伝統技術と一体化しているところも素晴らしいと思いました。また私にとっては、尾形光琳の「4大傑作」のうち、唯一実物を見たことがなかった「群鶴図」を鑑賞する機会を与えてくれたのでした。キヤノンさんに感謝したいと思います。
そして思ったのですが、是非とも「綴プロジェクト」で「大坂夏の陣図屏風」の複製を作ってほしい。No.34 の紹介でも明らかなように、この屏風は「洛中洛外図屏風」と同じで、近接して舐めるように見ないと価値がわからない絵です。作者不詳作品であっても、複製を作る意義は非常に大きいと思います。
| 補記 |
スミソニアン博物館は所蔵する美術品のデジタル画像を公開するプロジェクトを推進してきましたが、その第1弾としてフリーア美術館の美術品が公開されました(2015.1)。尾形光琳の「群鶴図屏風」もフリーア美術館の公式サイトの Collections から検索できます("Korin Cranes")。
(2015.3.7)
No.72 - 楽園のカンヴァス [アート]
アビニョンの娘たち

| |||
|
パブロ・ピカソ 「アビニョンの娘たち」(1907) (ニューヨーク近代美術館) | |||
最近、原田マハ・著『楽園のカンヴァス』(新潮社。2012)
小説ではまず、ピカソのアトリエを訪れて『アビニョンの娘たち』を見た友人・知人の芸術家たち、つまり、アポリネール(詩人)、ガートルード・スタイン(米国の作家)、画家のブラック、ドラン、マティスなどが一様に衝撃を受け、絵を批判したことが述べられます。その後に続く文章です。
|
『楽園のカンヴァス』はあくまで小説であり、フィクションです。また引用部分は小説の中で、ある人の「書き物」として提示されている部分です。これが著者の原田氏の意見かどうかは分かりません。しかし原田氏は MoMA に勤務経験がある美術のプロフェッショナルです。『アビニョンの娘たち』という「MoMA の至宝」についての著者の考えが文章に現れたとみるのが妥当でしょう。
そして著者の考えはどうであれ、上記の文章は『アビニョンの娘たち』という絵に対するで典型的な評価の一つであることは確かだと思います。
ちょっと唐突かも知れませんが、上に引用した部分を読んで1年半ほど前にクラシックのコンサートで聴いた曲を思い出しました。絵画と音楽でジャンルは違うけれど非常に似ていると思ったのです。
シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』
私と妻はオーケストラの定期演奏会に毎回出かけています(東京交響楽団)。定期演奏会というのは「おまかせ」のコンサートであり、自分で曲を選べないので聴きたい曲だけを聴くという訳にはいきません。しかしそれだけに全く知らなかった曲に感銘を受けたり、素晴らしいソリストに出会えたりする楽しみがあります。No.11「ヒラリー・ハーンのシベリウス」で書いたように、ヴァイオリニストの庄司紗矢香さんを初めて知った(彼女はその時15歳ぐらいだった)のも定期演奏会でした。
1年半ほど前の定期演奏会です。取り上げられた曲の中にシェーンベルクの『室内交響曲 第1番(オーケストラ版)』がありました。『室内交響曲 第1番 作品9』は1906年に作曲された作品で、15人のソリストの「管弦楽」で演奏されます。この曲は作曲家自身が1914年にフル・オーケストラ用に編曲し、さらに1935年にそれを改訂しました。定期演奏会ではその1935年・オーケストラ版が演奏されたというわけです。
演奏会が終わり、席を立って出口に向かいながら、その『室内交響曲 第1番』について妻が感想を言ったのですね。
| 「 | 音楽学って感じ。音楽を聴きに来たのに、音楽学を聴かされた」 |
なるほど・・・・・・。私は思わず納得してしまいました。この曲に対して抱いていたある種の「違和感」を言い当てていると思ったからです。

| |||
| 「室内交響曲 第1番」が収録されているオルフェウス管弦楽団のCD。15人で演奏するオリジナル版である。ジャケットはムンクの木版画「宇宙での出会い - Encounter in Space」 | |||
しかし『室内交響曲 第1番』はマーラーやツェムリンスキーやコルンゴルトの曲とはだいぶ違うのです。『室内交響曲 第1番』を特徴づけるのは、曲想のめまぐるしい変化です。オーケストラの各楽器の特性を生かし切ることを狙ったような音型・リズム・テンポのバリエーションが、次々と出てきます。音の響きは「斬新」というか、従来にないような「独特の」響きが随所にある。
旋律性のある「主題」「テーマ」「動機」は、あるにはあるが、あまり明確には感じられません。全体は5つほどの「部分」に分かれますが、連続して演奏されます。従来の交響曲にみられるような楽章とか、主題とその展開といった「構成」も、あるにはあるが、あまり感じられない。しかしその中でも細部を注意して聴くと、力強さ、美しさ、繊細さ、諧謔性といった特徴の部分、音楽でしか表現し得ない要素を持った部分が、いろいろと発見できるのです。
全体としてこの曲から受ける印象は
| ◆ | 音楽の数々のエッセンスを抽出し、それを抽象化して、ギュッと凝縮した感じ | |
| ◆ | 音楽の旋律・和音・リズムなどを、個別の要素に一旦分解し、それを再構成している感じ | |
| ◆ | 調性音楽の枠組みの中で、音楽の流れや構成方法に対する既成概念を壊し、どこまで進んで行けるかを徹底的に追求している感じ |
などです。
『室内交響曲 第1番』を「好き」か「嫌い」か、二者択一で答えよと強制されたら「好き」の方でしょうね。しかし「大好き」かと問われたらそうではない。この音楽に「のめり込む」には違和感がある。演奏家の人は間違いなくのめり込んで、楽しくてしかたがないだろうけれど・・・・・・。
その違和感の原因を一言で表現すると、いみじくも妻が言ったように『室内交響曲 第1番』は「音楽」というよりも「音楽学」なのですね。新しい音楽を作り出そうという意欲は分かる。既存の暗黙の約束ごとや概念を越えたいという意図も理解できる。よく分かるのだけれど「学」が先に立ってしまって「楽」が聞こえてこない。そういう感じなのです。
もちろん作曲をするには「学」が必要です。西洋音楽で言うとバッハ、モーツァルト、ベートーベンの時代からそうだし、ジャズやロック、現代日本のポップスに至るまで、その基礎には「音楽学」があります。「学」を身につけるには専門教育を受けたり、師匠や先生、音楽家の親に教えてもらったりというのが一般的でしょう。もちろん「独学」というのも大いにありうる。また、ピアノ演奏の訓練を小さいときから受けてきた人は、自然と「音楽学」が体に染み付いているということもあるでしょう。そういう「音楽学」という基礎の上に立って、いかに「音楽」を作るか。そこが作曲家やアーティストの腕の見せ所だと思います。
シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』に戻ると、その「音楽学」は過去の蓄積から学んだものだけではないわけです。既存の音楽の構成方法には頼らない、新しい「音楽学」を作りだそうとしています。ある意味では既成概念の「破壊」ですね。もちろん、シェーンベルクのように過去からの音楽文化の蓄積を知り尽くした人だから「破壊」ができるのです。対象の性質を熟知していないと破壊はできません。
『室内交響曲 第1番』を聴くと、そのシェーンベルクなりの「音楽学」は分かるが、しかしそれ以上の「音楽」が非常に希薄な感じがする。つまり、人間の感性に直接訴えて人を虜にする「楽」の部分が聞こえてこないのです。
絵画学
シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』(1906)は、既成の音楽の構成概念から逸脱した作品です。この作品と、ちょうど翌年に発表された『アビニョンの娘たち』(1907)はよく似ているのですね。
『アビニョンの娘たち』もまた「絵画学」なのだと思います。それはまさに『楽園のカンヴァス』で記述されているように、絵画に革命を起こし新しい絵画の概念を打ち立てようと意図されたものでしょう。もちろん、既成の絵画を知り尽くし、デッサンで線を引く達人だったパブロ・ピカソだからこそできたのです。『アビニョンの娘たち』はピカソが若干26歳で描いた作品ですが、歳が若いとかそんなことは関係ない。No.46「ピカソは天才か」で紹介した数枚の絵だけみても、ピカソが絵画を知り尽くしていることが分かります。さっきも書いたように、対象を熟知していないと破壊さえ出来ないのです。
しかし「美術の革命であること」や「パブロ・ピカソしか成し得なかった偉業である」ことと、その絵が「絵画学」に留まらず「絵画」として人の心を打つものであることとは違います。『アビニョンの娘たち』を見ていると、あまりに既存の「絵画学」を壊すことに集中し過ぎたために「(新しい)絵画学」に留まらざるを得なかった、そういう感じがします。
そして「音楽学」「絵画学」と言う以上に、『アビニョンの娘たち』と『室内交響曲 第1番』は芸術のジャンルを越えて似ています。発表された年は1907年と1906年で同時期です。両方ともアートにおける革新ないしは革命を狙っている。アーティストであるピカソとシェーンベルクは従来手法で傑作を作り出した人、つまりその力量が十二分にあった人です。ピカソの「青の時代」の一連の作品(1901-1904)は素晴らしいし、シェーンベルクの『浄夜』(1899)の美しさは比類がない。それでも彼らは従来手法を超えた革新・革命を目指した・・・・・・。これは当時の「時代の雰囲気」の影響もあると考えられます。
科学の分野に目を向けると、アインシュタインの「特殊相対性理論」が発表されたのが1905年であり、これは物理学に革命を起こしました。同じ年にアインシュタインが発表した「光量子仮説」は、やがて量子力学へとつながります。絵画や音楽だけでなくサイエンスの分野でも1905-1907年というのは革命の時期だったのです。
『アビニョンの娘たち』と『室内交響曲 第1番』の共通点を端的に言うと
|
ものごとは要素に分解してみると本質がわかる |
という概念が底流にあることです。この考えは19世紀から20世紀に至るサイエンスの根底にある要素還元主義と同じです。この考えは正しくもあり、正しくないこともある。「ものごとを要素に分解してみても本質は分からない」ことも多いわけです。しかし要素に分解してみると本質が見通せることもまた多い。マクロ的に言うと、科学・絵画・音楽を越えた「知的創造に関する時代の雰囲気」が相互に影響しているのではないでしょうか。
『アビニョンの娘たち』は「絵画学」だと書きましたが、それはピカソの独創性が作り出したとともに「時代の雰囲気にも影響された」絵画学ではないかと思います。
そして思うのですが、一方で「絵画学」とは全く対極の作品も同時代にあるのです。その典型が、まさに『楽園のカンヴァス』のテーマとなっているアンリ・ルソーの作品群です。
アンリ・ルソーの作品
アンリ・ルソー(1844-1910)は、27歳でパリの税関史になり、絵を描き始め、49歳で役人をやめて「画家」になった人です。その絵は「素朴派」と言われるように、まさに素朴な感じで、「日曜画家」とも揶揄されたこともありました。「素朴派」という現代の通称も、何となく揶揄している雰囲気がある(ルソーが本当に素朴なのかは大いに疑問です)。ルソーが美術の教育を受けた形跡はありません。
もちろん音楽と同じように、絵画を独学で学ぶことは可能です。特にパリに住んでいれば、おびだたしい名画が容易に見られるわけだから、例えばそれを(許可を得て)模写して勉強することも可能です。「遠近法」とか「陰影法」とか、そういう技術を知らなくても「見よう見まね」から入っていける。
しかし、たとえ独学で絵を学んだとしても、同時代の有名な印象派の画家たちとの比較で言うと、アンリ・ルソーは「絵画学」とは最も縁の薄い画家であることは確かだと思います。そして「絵画学」は無くても人の心を打つ「絵画」は制作できる。『楽園のカンヴァス』にはルソー作品に魅せられた人たちの言葉が書き綴られています。
| 夢 |
『アビニョンの娘たち』を所蔵する MoMA(ニューヨーク近代美術館)の至宝の一つにアンリ・ルソーの最晩年の傑作、死を前にして描いた『夢』(1910)があります。以下の文章は MoMA のアシスタント・キュレーターの視点で書かれています。
|

| ||
|
アンリ・ルソー「夢」(1910) (ニューヨーク近代美術館) | ||
MoMA のキュレーターであるティムは『夢』を目の前にして思いを巡らせているところです。そして初めてこの絵に出会った時を回想します。
|
| 私自身、肖像=風景 |
アンリ・ルソーの別の作品を小説から取り上げてみましょう。プラハ国立美術館所蔵の『私自身、肖像=風景』(1890)です。
小説の主人公の(一人の)織絵が、母親と、一人娘の真絵と3人で夕食のテーブルを囲んでいます。小説のストーリーは割愛しますが、ある経緯があって織絵は娘に MoMA の説明をします。その場面です。
|

| ||
|
アンリ・ルソー 「私自身、肖像=風景」(1890) (プラハ国立美術館) | ||
「生きてる」という言葉は『私自身、肖像=風景』に関しての言葉ですが、アンリ・ルソーの作品全体に対する著者の賛辞でもあると思います。そして最初に書いたピカソについて強く推測するのですが、『アビニョンの娘たち』についても「生きてる」と感じる人は多いのではないか。単なる「近代絵画史上の価値」だけでこの絵があれほどまでに有名だとは思えません。絵の見方はあくまで個人の領域に属するものであり、「生きてる」感覚も人によって違うはずなのです。
楽園のカンヴァス
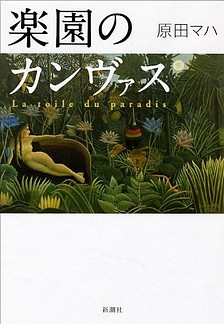
|
しかしそういった「ストーリー」や「謎」や「ミステリー」は、この作品の言わば「よそおい」であって、本質ではありません。
この小説の主要登場人物は、
| ① | アンリ・ルソー | |
| ② | パブロ・ピカソ | |
| ③ | ルソーの絵のモデルになる女性 | |
| ④ | モデルになる女性の夫 | |
| ⑤ | 大資産家の絵画コレクター | |
| ⑥ | MoMA のキュレーター | |
| ⑦ | ソルボンヌ大学・美術史科の研究者 | |
| ⑧ | 国際刑事警察機構の芸術品コーディネーター |
の8人です。この8人の絵画に対する並はずれた強い思い、8人それぞれの立場からの「アートに賭ける激しい情熱」を描いたところに、この小説の価値があります。それは絵画論を越えた「芸術賛歌」になっている。そこに惹かれました。
そしてピカソとルソーの絵に戻ると、MoMA にある2つの作品、『アビニョンの娘たち』と『夢』は、それが「絵画学」か「絵画」かは別として、芸術に対する激しい情熱が生み出した作品であることは確かでしょう。描いた一人は天才少年の時代を過ごし、まだ26歳だが描くことにかけてはプロ中のプロとも言える画家です。もう一人は正反対で、アマチュアの日曜画家からスタートして49歳で画家になり、66歳になって死期を悟っている画家です。その両方の作品が MoMA の至宝となっている。この驚くような「幅の広さ」が絵画の魅力なのだと思います。
| 補記 |

| |||
|
アンリ・ルソー 「蛇使いの女」(1907) [site : オルセー美術館] | |||
それはともかく、番組の中でルプロー氏が『蛇使いの女』について語った次の言葉が大変に印象的でした。
|

| |||
|
アンリ・ルソー「樫の枝」(1885) テレビ東京「美の巨人たち」2012.11.17 より | |||
そう言えば『楽園のカンヴァス』の、あるシーンが思い出されます。ソルボンヌ大学のルソー研究者・早川織絵とニューヨーク近代美術館のキュレーター、ティム・ブラウンが、スイスのバーゼルのある邸宅で初めて対面する場面です。
|
はたして織絵とティムのどちらが正しいのでしょうか。よく読むと、織絵は二つのことを主張しています。
|
ルソーは卓越した技術を身につけられなかったわけではない。つまり、技術はあった。 | |||
|
ルソーは確信犯的に「稚拙な技術」と言われ続ける技法で勝負した。 |
ティムが反論しようとしているのはBの部分です。Aに反対ではないようです(そういう風に読める)。ということは程度の差はあれ「楽園のカンヴァス」の織絵とティム、「美の巨人たち」のルプロー氏の3人の意見はAについては一致していることになります。そのことはテレビで「樫の枝」と題するデッサンをみて感じ取れました。
(2013.2.16)
No.46 - ピカソは天才か [アート]
前回の No.45「ベラスケスの十字の謎」の最後で「ラス・メニーナス」に登場するニコラス・ペルトゥサト少年を下敷きにしてピカソが描いた『ピアノ』という作品を紹介しました。ピカソの作品は以前にも No.34「大坂夏の陣図屏風」で『ゲルニカ』に触れています。今回はピカソをとりあげ、『ピアノ』と『ゲルニカ』の感想までを書いてみたいと思います。
開高健のエッセイ
ピカソについて思い出す文章があります。作家・開高健が書いた「ピカソはほんまに天才か」というエッセイです。雑誌『藝術新潮』に掲載されたものですが、大事なところだけを抜き出してみます。この文章を「とっかかり」にしたいというのが主旨です(原文に段落はありません)。
文中の「モダ ン・アート・ミュージアム」というのは、ニューヨーク近代美術館(MoMA - The Museum of Modern Art, New York)のことです。要約すると開高健の言いたいことは次のようになるでしょう。
絵の鑑賞は個人的なものです。開高健も同じエッセイの中で「絵は究極的には、好きか嫌いかである」と言っています。上に引用したのは、あくまで開高健という人の個人的な好みの表明です。しかし「全ては個人の好き嫌い」と言ってしまうと、絵を評する文章は成り立たなくなります。そこで「天才」というキーワードを足がかりに話を進めたいと思います。「ピカソはほんまに天才か」という文章のタイトルからして「ピカソは天才とは思えない」というのが開高健の言いたいこと(の一つ)であるようです。これは正しいのかというのがテーマです。
以降に取り上げるのは、ピカソの3つ時代の作品です。つまり、
の3つです。ピカソは膨大な数の作品をさまざまな画風で描いたので、もちろん3種に分類できるということではありません。キュビズムを開始した以降も「具象的な作品」を多く描いていて、たとえばブリジストン美術館の『腕を組んで座るサルタンバンク』(1923)のような作品もあるし、新古典主義と呼ばれる作品群、また版画や彫刻まで、多様な傾向とジャンルの作品があるのはよく知られている通りです。
少年時代:バルセロナのピカソ美術館
「ピカソは天才とは思えない」との意見なのですが、この開高健の見方に反して、ピカソはやはり天才だと思います。それは少年時代のピカソの絵を見れば(おそらく誰しも)納得できます。
そもそも「天才」とは「天性の才能。生れつき備わったすぐれた才能。また、そういう才能をもっている人。」(広辞苑)です。芸術の世界で言うと、技術の習得や鍛錬、努力と経験の積み重ねだけではとうてい到達できないと感じる作品に出会ったとき、そしてそれを作った作家の天賦の才能を強く感じるときに、そのアーティストを「天才」と呼ぶわけです。
端的な例は、少年や少女がすばらしい作品を創造する場合です。努力して「高み」に到達する時間も経験も蓄積もないはずなのに、大人のプロフェッショナルを凌駕する作品を作る子供がいる。
音楽の世界での典型がモーツァルトです。モーツァルトの最初の交響曲は8歳で作曲されています。映画「アマデウス」の冒頭に使われた交響曲 第25番 ト短調 は、モーツァルトの管弦楽曲の中でも屈指の名曲ですが、17歳の作品です。ディヴェルティメント ニ長調 K136 は良く知られた曲ですが、これはもう「完璧な音楽」としか言いようがない。この曲はモーツァルトが16歳の時のなのですね。
画家における「モーツァルト的な」ポジションが、少年ピカソと言えるでしょう。少年時代にピカソはスペインの3つの都市に住んでいます。
ラ・コルーニア時代とバルセロナ時代のピカソのデッサンや絵画は、バルセロナのピカソ美術館にあります。作家の堀田善衛はスペインに長く住んだ人ですが、彼がピカソ美術館を訪問して書いた文章があります。ラ・コルーニア時代のピカソの作品を評したものです。
ゴヤには気の毒ですが、堀田善衛は大作「ゴヤ」を書くほどゴヤに精通しているので、引き合いに出されるのはやむをえないでしょう。ゴヤが下手というわけではありません。以下にラ・コルーニア時代、バルセロナ時代の作品を3つ掲げておきます。『子供たちの巣』と『ベレー帽の男』はラ・コルーニア時代、『画家の母の肖像』はバルセロナ時代の作品です。
日本の画家、外国の画家を含めて子供時代に上手な絵を描く人は多々あるのですが、ピカソはずば抜けていると思います。絵として完成しているのです。
それは描くという技術面だけではありません。バルセロナのピカソ美術館で最も有名で良く知られている絵は「科学と慈愛」(1897年。15-6歳)です。死にゆく女性を医者(科学)と子供を抱いた修道女(慈愛)が見守っている姿を描いているのですが、「死」というテーマに真正面から取り組んだ作品も少年の絵としては異例でしょう。このテーマは父親に与えられたものと言われていますが、一枚の絵として描き切る画力はずば抜けていると思います。
青の時代、およびその前後(1900-1905)
1900年、ピカソはパリに出ます。そして1901年頃から1904年頃まで「青の時代」と呼ばれる作品群を描きました。プルシアン・ブルー独特の深い青(No.18「ブルーの世界」参照)を多用したこれらの作品を好きな人は多いはずです。「ピカソは天才か?」と言っている開高健も「青の時代」の絵を讃美する文章を書いています。以前、NHKの日曜美術館で作家の五木寛之さんが「青の時代」の絵に対する「思い入れ」を熱く語っていたのを思い出します。
青の時代の絵を絶賛する人は多いので、その前後の時期のピカソの絵を2つ掲げておきます。一つはピカソがパリにやってきたころに描いた『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』(1900)という作品です。
中野京子さんは、ルノアールの有名な絵『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』と対比しつつ、同じ場所を描いたピカソの絵を次のように評しています。「本作」とはルノアールの絵のことです。
もう一枚は、青の時代のあとの「バラ色の時代」と呼ばれる時期の作品、『カナルス夫人の肖像』です。
この絵に描かれている女性は、当時パリに在住してたカタルーニャ出身の版画家、リカルド・カナルスと生活を共にしていたイタリア人のモデルで、名前はベルナディット・ビアンコといい、当時35歳です(バルセロナ・ピカソ美術館のカタログによる)。
イタリア的というか、ローマ的というか、ラテン系ヨーロッパ人の女性の典型的な美しさを凝縮したような感じの人です。古代ギリシャ・ローマ時代の女神の彫像のような雰囲気もある。青の時代とはうってかわった明るく落ち着いた色、薄いバラ色が、服、肌、髪飾りに使われています。それとは対照的に、真っ黒なショールが極めて粗いタッチで一気に描かれていて、女性を際だたせている。それ以前にまず、デッサンが完璧です。
モデルになったカナルス夫人の印象は、画像だけからすると理知的な女性で、なんとなくちょっと "冷たい" 感じもします。しかし実際にバルセロナのピカソ美術館でこの絵を見ると、印象はかなり違います。暖かみがあり、情熱的で、ふくよかな女性、という感じなのです。ピカソの肌の描き方、特に暖色系の微妙なグラディエーションがそういう印象を生むのだと思います。
この絵は、一人の女性の肖像を越えた「美の象徴」ないしは「ヴィーナス」を描いているようでもあり、傑作だと思います。
キュビズム以降
「ピカソはほんまに天才か」で開高健は、
と書いています。
ここでいう「ピカソ」とは、キュビズム以降のピカソ作品のことを言っているはずです。「ピカソ作品 = キュビズム以降の、具象とは大きく乖離した作品」という暗黙の前提がある。この、キュビズム以降の具象とは大きく乖離した作品群をどうとらえるか、ここが意見の分かれるところでしょう。
個人的な意見を言うと、キュビズム以降のピカソの絵の中には素晴らしいと思うものがあります。しかしそれは少数で、多くの絵は訴えてくるものがない。たとえば前回のNo.45「ベラスケスの十字の謎」の最後に掲げた『ピアノ』という作品です。
この作品をみると「人がピアノを弾いている姿」ということはわかるのですが、それ以上のことは不明でしょう。「ラス・メニーナス」を下敷きにしていると知って、右下で犬に足をかけている少年を描いたとわかります。また解説を読んで、少年の両手がピアノを弾いているように画家には感じられたのだとも分かる。しかし、だからといって何なのか、とも思います。ベラスケスへのオマージュとなりうる絵だとも思えない。オマージュというなら『カナルス夫人の肖像』の方がはるかに近い。ショールの描き方など、ベラスケスを彷彿とさせます。この『ピアノ』という絵から何かを「感じる」ことができる人はいるのでしょうか。
『ピアノ』はピカソの作品の中では「マイナーな」絵で、ピカソにとっては「余技」のようなものかもしれない。では有名な『アビニョンの女たち』はどうか。
アビニョンの女たち(1907)
ニューヨークのMoMAにあるこの作品は、世間ではキュビズムを切り開いたということで特に有名なのですが、だからといって良い作品とは思えません。たとえば、女性を描くのに意図的に稚拙な線を使う意味が分からないのです。はじめに引用した開高健のエッセイに、
とありますが、『アビニョンの女たち』を念頭に置いて書かれた文章ではないでしょうか。だとしたら同感です。
しかし、この絵はひょっとしたら傑作かもしれないとも思うこともあります。それは、この絵がフランスの都市・アビニョンの女ではなく、バルセロナの裏通りの女を描いたものだからです。堀田善衛の解説を引用します。
ダイレクトには書いていませんが、要するにこの絵はバルセロナの裏通りの売春婦たちを描いているのですね。ピカソはバルセロナに住んでいました。パリに出てからもバルセロナに何回も「帰郷」しています。この絵はピカソの経験がもとになっているのでしょう。そこで(一例として)つぎのような想像が可能になります。
『アビニョン の女たち』を特徴づけるのは(意図的に)稚拙に描かれた線と輪郭、未処理で未完成な感じ、立方体を直接画面に描き入れるような描法、そして形を分解し、省略して部分的に再構成する手法です。こういう手法を意図的に使って、人間の「悲惨」や「空虚さ」、「生身の人間ではあるが、人格とは乖離した感じ」、そして「形が分解していくように感じる画家の意識」を表そうとしたのなら、『アビニョンの女たち』は名作と言えるのかもしれないし、新しい絵画表現の創造かもしれない。
しかし通常の絵画評論としては、堀田善衛の解説の最後にあるように「人間讃歌」なのですね。それはないだろうと思います。キュビズムを切り開いたという絵画史的価値はあるのでしょうが、これが「人間讃歌」としたら駄作だと思います。画家は伝えたいことがあるのだとは思いますが、それが伝わってこない。絵と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しないのです。
『アビニョンの女たち』以降、絵の技法はきわめて多様化します。シュルレアリズムもあり、抽象絵画もある。しかし手法は何でも良いのですが、作者の一方的な思いを画面に出しただけの作品、おしつけがましい作品、絵と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しない作品を、少なくとも美術館に飾るのはやめてほしいと思います。
個人に絵を売ることを目的にして、画家が良いと思う方法で描き、良いと思った個人が購入して書斎を飾るのは何ら問題ありません。しかし美術館、とくに公的な美術館を飾る絵は、画家と鑑賞する多くの人の間で何らかのコミュニケーションが成立することが前提です。傑作かもしれないが、なぜ傑作か、その解説を聞かないとわからない作品は必要ありません。「傑作」を鑑賞するのではなく「傑作だという解説」を鑑賞する作品は不要です。美術大学の講義室ではないのだから・・・・・・。
ピカソの「キュビズム以降の絵」には、画家と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しない絵が多い。しかし中にはそうでない絵があります。その代表が『泣く女』です。
泣く女(1937)
キュビズム以降のピカソの作品で文句なしに傑作だと思うのは、これも『アビニョンの女たち』と並んで有名な『泣く女』です。キュビズムの代表的な作品と言えるでしょう。
「ピカソは天才か」というタイトルではじめたので、ピカソは天才だと主張している2人目の文章を紹介しておきましょう。『泣く女』を直接評した文章ではありませんが『泣く女』を含むピカソのキュビズム作品を評した養老孟司氏の文章です。
養老孟司氏も、引用文の中に出てくる岩田誠氏も医者です。つまり医学・生理学の立場からの発言です。人間の脳の働きを熟知している立場からすると、ピカソは特別の能力をもった人 = 天才だった。これはその通りなのでしょう。大脳の視覚野を意識的にコントロールすることは普通の人にはできない、ピカソは天性の能力がある、つまり天才だというわけですね。
もちろん、だからといってピカソのキュビズム作品が良いというわけではありません。養老さんも文中で「病気になると、ある能力が消えて、ひとりでにピカソの絵みたいなものを描くケースがある」と言っています。ごく普通の画力の人が病気になって「ピカソ的な絵」を描くこともあるわけです。特別の能力を持った天才が描いたから傑作だ、とは言えないのです。
それどころか、養老さんの分析から推定できることは、「ピカソのキュビズム作品は、普通の人には理解しがたいものだ」ということです。なぜなら、
だということは、そこからロジカルに推論すると
はずだからです。最初に引用したように、開高健は「ピカソに何も感染させてもらえなかった」と書いていますが、「ピカソは天才だからこそ、普通の人は感染しない」のであり、「ピカソに感染する人がいたとしたら、その人は普通の能力ではない人」と言える。岩田・養老理論が正しければ、論理的にそうなるのです。
しかし、それにもかかわらず『泣く女』は名作だと思います。それは「空間イメージ構成力」どうのこうのではなく、描かれているテーマに絵画手法がピッタリとハマっているからです。ストライク・ゾーンのど真ん中に絵がいっている感じがする。
『泣く女』はピカソの愛人で同棲していた、画家で写真家のドラ・マール(当時30歳。ピカソは56歳)を描いた絵と言われていますね。どういうシチュエーションで彼女が泣いているのかは分かりませんが、例えばピカソの別の愛人の女性と喧嘩をした彼女が、激しく慟哭している様子を想像します。泣き叫び、男をなじり、詰め寄り、また一人で泣く。男はその激しさにたじろぎ、どうすることもできず、茫然としている・・・・・・。単なる想像であって、その通りかは全く分かりませんが・・・・・・。
しかしどういうシチュエーションであれ、激しく泣く、慟哭するというのは非日常的な行為であり、普段は隠れている人間の別の面を露出させる行為です。近親者や親しい人が「泣く」のを見て、普段は分からないその人の全く別の一面を知った・・・・・・というような話はいっぱありますね。その泣くという行為の本質を、この絵は極めてうまくキャンバスに定着している。人間の非日常性を、絵画手法がピッタリと表現している作品だと思います。
ゲルニカ(1937)
『泣く女』と同じ年の『ゲルニカ』も、絵のテーマと絵画手法がよくマッチした傑作です。この絵のテーマになったスペイン市民戦争の時のゲルニカ無差別爆撃は、No.34「大坂夏の陣図屏風」のところで書いた通りです。人も動物も、爆弾の雨が降り注ぐ中で逃げまどい、死んでいく。爆風の直撃をうけた人の体はちぎれてあちこちに飛び散り、子どもを殺された母親は泣き叫び、地獄絵図のような光景があたり一面に展開される・・・・・・。ピカソは想像で描いているし、我々も想像するしかないのですが、この絵からうける「イメージ」どおりのことが実際に起こったことは確実でしょう。

パブロ・ピカソ「ゲルニカ」(1937) (マドリード・ソフィア王妃芸術センター)
『ゲルニカ』は絵そのものの価値以上に「反ファシズム」という政治的意味、思想的価値で解釈されてきた絵です。またこの絵が制作された経緯が流布することで、非常に有名になった。もしこの絵の制作経緯が一切明らかにされず、たとえば「戦争」というような題がついていたら、ここまで有名にはならなかったと思います。
しかし「反ファシズム」のという意図で絵を制作し、またその文脈で解釈するのは、別に悪いことではありません。要は、政治的意味や思想的価値を離れて、その絵が持っている表現力や強さ、伝達力がどうかです。丸木位里・俊 夫妻の「原爆の図」という絵がありますが、「原爆の図」のリアリズムとは全く対極の表現を使い、想像力だけで「爆撃の図」を描き切ったピカソの力量はやはり天才というべきでしょう。
『ゲルニカ』と『泣く女』に共通しているのは、人間社会における「悲惨」や「悲哀」を描いていることです。もちろん「悲惨」や「悲哀」だけが「キュビズム以降の、具象とは大きく乖離した手法」の存在意義ではありません。ピカソの静物画にも、中には素晴らしい作品がある。しかしハマった、と感じる絵が少ないのも事実です。キュビズムというボールを投げるとき、そのストライク・ゾーンは大変に狭いと思います。そのゾーンにコントロールよく投げられるかが、良し悪しの分かれ目です。
マヤに授乳するマリー・テレーズ(1936)
『ゲルニカ』と『泣く女』はともに1937年に描かれた絵ですが、これとほぼ同時期、1936年に描かれた絵を最後に取り上げたいと思います。『マヤに授乳するマリー・テレーズ』という、ペンとインク、水彩で描かれた作品です。
この絵はピカソの作品の中でもごく「ささいな」ものでしょう。何らかの絵画史的な意味があるわけではないし、有名でもない。画家は日常の中で、紙の上にさっとペンを走らせ、水彩を塗り、おそらく数十分で描いてしまったのではないでしょうか。
しかし、この絵のマリー・テレーズの姿には独特の存在感があります。足を組んで椅子に堂々と腰掛け、我が子に授乳し、画家をキリッと見つめています。口をハンカチのようなもので覆っていますが、なぜなのかは分かりません。風邪でもひいて赤ちゃんにうつるのを避けようとしたのでしょうか。そのため彼女の表情は分からないのですが、画家を見つめるまなざしが、心のうちを語っていると思います。淡い水彩で塗られた画面は「おだやか」「安心」「やすらぎ」といった雰囲気を作っています。その中で毅然としている母親の強い存在感。画家はこの母としてのマリー・テレーズの姿に感動してペンを走らせたのだと思います。
マリー・テレーズはこのとき26歳、ピカソより約30歳も若い女性です。ピカソの女性遍歴や女性関係の「問題点」はさておき、純粋に1枚の絵として見たとき、鑑賞者に「伝わってくる」絵だと思います。
『マヤに授乳するマリー・テレーズ』と『泣く女』は、ともに画家と同棲した20代後半の女性を描いた絵です。この2枚の絵が示しているのは、人間の多様さ表現する「絵画表現の幅広さ」です。この振幅の広さが、ピカソの天才たるゆえんなのだと思います。
ピカソが道化を描いた2枚の絵、
を、No.114「道化とピエロ」に掲げました。
『マヤに授乳するマリー・テレーズ』と同じマリー・テレーズを描いた作品、
の画像を、No.157「ノートン・サイモン美術館」に掲げました。
マリー・テレーズを描いた作品、
の画像を、No.251「マリー・テレーズ」に掲げました。
開高健のエッセイ
ピカソについて思い出す文章があります。作家・開高健が書いた「ピカソはほんまに天才か」というエッセイです。雑誌『藝術新潮』に掲載されたものですが、大事なところだけを抜き出してみます。この文章を「とっかかり」にしたいというのが主旨です(原文に段落はありません)。
|
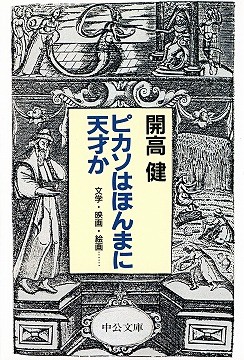
| |||
|
開高 健 「ピカソはほんまに天才か」 (中公文庫。1991) | |||
| ◆ | ピカソの「青の時代」の絵には秀作が多い。 | |
| ◆ | しかし後年の作品にはウンザリする。自分を「感染」させてはくれなかった。 | |
| ◆ | 青の時代の作品も「天才が描いた」という気はしない。 ピカソは天才だと皆が言うが、私にはそうは思えない。 |
絵の鑑賞は個人的なものです。開高健も同じエッセイの中で「絵は究極的には、好きか嫌いかである」と言っています。上に引用したのは、あくまで開高健という人の個人的な好みの表明です。しかし「全ては個人の好き嫌い」と言ってしまうと、絵を評する文章は成り立たなくなります。そこで「天才」というキーワードを足がかりに話を進めたいと思います。「ピカソはほんまに天才か」という文章のタイトルからして「ピカソは天才とは思えない」というのが開高健の言いたいこと(の一つ)であるようです。これは正しいのかというのがテーマです。
以降に取り上げるのは、ピカソの3つ時代の作品です。つまり、
| ① |
少年時代 スペインで過ごした19歳までに描いた作品 | |
| ② |
青の時代、およびその前後 パリに出てから「青の時代」を経て「バラ色の時代」までの期間の作品 | |
| ③ |
キュビズム以降 キュビズムを創造して以降の具象とは大きく乖離した作品。 |
の3つです。ピカソは膨大な数の作品をさまざまな画風で描いたので、もちろん3種に分類できるということではありません。キュビズムを開始した以降も「具象的な作品」を多く描いていて、たとえばブリジストン美術館の『腕を組んで座るサルタンバンク』(1923)のような作品もあるし、新古典主義と呼ばれる作品群、また版画や彫刻まで、多様な傾向とジャンルの作品があるのはよく知られている通りです。
少年時代:バルセロナのピカソ美術館
「ピカソは天才とは思えない」との意見なのですが、この開高健の見方に反して、ピカソはやはり天才だと思います。それは少年時代のピカソの絵を見れば(おそらく誰しも)納得できます。
そもそも「天才」とは「天性の才能。生れつき備わったすぐれた才能。また、そういう才能をもっている人。」(広辞苑)です。芸術の世界で言うと、技術の習得や鍛錬、努力と経験の積み重ねだけではとうてい到達できないと感じる作品に出会ったとき、そしてそれを作った作家の天賦の才能を強く感じるときに、そのアーティストを「天才」と呼ぶわけです。
端的な例は、少年や少女がすばらしい作品を創造する場合です。努力して「高み」に到達する時間も経験も蓄積もないはずなのに、大人のプロフェッショナルを凌駕する作品を作る子供がいる。
音楽の世界での典型がモーツァルトです。モーツァルトの最初の交響曲は8歳で作曲されています。映画「アマデウス」の冒頭に使われた交響曲 第25番 ト短調 は、モーツァルトの管弦楽曲の中でも屈指の名曲ですが、17歳の作品です。ディヴェルティメント ニ長調 K136 は良く知られた曲ですが、これはもう「完璧な音楽」としか言いようがない。この曲はモーツァルトが16歳の時のなのですね。
画家における「モーツァルト的な」ポジションが、少年ピカソと言えるでしょう。少年時代にピカソはスペインの3つの都市に住んでいます。
| ◆ | スペイン南部のマラガに生まれる(1981年10月25日) | |
| ◆ | スペインの北東、ラ・コルーニアに転居(1991年9月 : 9歳) | |
| ◆ | バルセロナに移る(1995年9月 : 13歳) |
ラ・コルーニア時代とバルセロナ時代のピカソのデッサンや絵画は、バルセロナのピカソ美術館にあります。作家の堀田善衛はスペインに長く住んだ人ですが、彼がピカソ美術館を訪問して書いた文章があります。ラ・コルーニア時代のピカソの作品を評したものです。
|
ゴヤには気の毒ですが、堀田善衛は大作「ゴヤ」を書くほどゴヤに精通しているので、引き合いに出されるのはやむをえないでしょう。ゴヤが下手というわけではありません。以下にラ・コルーニア時代、バルセロナ時代の作品を3つ掲げておきます。『子供たちの巣』と『ベレー帽の男』はラ・コルーニア時代、『画家の母の肖像』はバルセロナ時代の作品です。
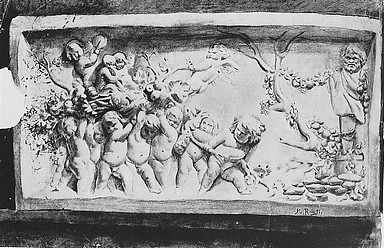
| ||
|
パブロ・ピカソ「子供たちの巣」 木炭・絵コンテ(13歳) (バルセロナ・ピカソ美術館) | ||
|
堀田善衛氏の評: またデッサンのうまさにかけては、これはもう言うがこともなく、「子供たちの巣」と題された彫刻のデッサンなどは、奇妙な老人の見守るなかでも十数人の天使を扱っており、十三か十四の子供にできることではない。(「若き日のピカソ」より) | ||

|

| ||||
|
パブロ・ピカソ「ベレー帽の男」 油絵(13歳) (バルセロナ・ピカソ美術館) |
パブロ・ピカソ「画家の母の肖像」 パステル(14-5歳) (バルセロナ・ピカソ美術館) | ||||
| ベレー帽はスペイン北東部のバスク地方の「民族衣装」である。そこからラ・コルーニアにやってきた男であろうか。絵による人間観察を試みたような作品である。 | 母親、マリア・ロペス・ピカソの肖像である。目を閉じて半分眠ったようにしている母の姿が的確に捉えられている。パステル画が、いっそう少年ピカソのデッサンの力量を際だたせている。 | ||||
日本の画家、外国の画家を含めて子供時代に上手な絵を描く人は多々あるのですが、ピカソはずば抜けていると思います。絵として完成しているのです。
それは描くという技術面だけではありません。バルセロナのピカソ美術館で最も有名で良く知られている絵は「科学と慈愛」(1897年。15-6歳)です。死にゆく女性を医者(科学)と子供を抱いた修道女(慈愛)が見守っている姿を描いているのですが、「死」というテーマに真正面から取り組んだ作品も少年の絵としては異例でしょう。このテーマは父親に与えられたものと言われていますが、一枚の絵として描き切る画力はずば抜けていると思います。
青の時代、およびその前後(1900-1905)
1900年、ピカソはパリに出ます。そして1901年頃から1904年頃まで「青の時代」と呼ばれる作品群を描きました。プルシアン・ブルー独特の深い青(No.18「ブルーの世界」参照)を多用したこれらの作品を好きな人は多いはずです。「ピカソは天才か?」と言っている開高健も「青の時代」の絵を讃美する文章を書いています。以前、NHKの日曜美術館で作家の五木寛之さんが「青の時代」の絵に対する「思い入れ」を熱く語っていたのを思い出します。
青の時代の絵を絶賛する人は多いので、その前後の時期のピカソの絵を2つ掲げておきます。一つはピカソがパリにやってきたころに描いた『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』(1900)という作品です。

|

| ||||
|
パブロ・ピカソ (グッゲンハイム美術館。ニューヨーク) |
オーギュスト・ルノアール (オルセー美術館) | ||||
中野京子さんは、ルノアールの有名な絵『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会』と対比しつつ、同じ場所を描いたピカソの絵を次のように評しています。「本作」とはルノアールの絵のことです。
|
もう一枚は、青の時代のあとの「バラ色の時代」と呼ばれる時期の作品、『カナルス夫人の肖像』です。

| ||
|
パブロ・ピカソ 「カナルス夫人の肖像」(1905) (バルセロナ・ピカソ美術館) | ||
この絵に描かれている女性は、当時パリに在住してたカタルーニャ出身の版画家、リカルド・カナルスと生活を共にしていたイタリア人のモデルで、名前はベルナディット・ビアンコといい、当時35歳です(バルセロナ・ピカソ美術館のカタログによる)。
イタリア的というか、ローマ的というか、ラテン系ヨーロッパ人の女性の典型的な美しさを凝縮したような感じの人です。古代ギリシャ・ローマ時代の女神の彫像のような雰囲気もある。青の時代とはうってかわった明るく落ち着いた色、薄いバラ色が、服、肌、髪飾りに使われています。それとは対照的に、真っ黒なショールが極めて粗いタッチで一気に描かれていて、女性を際だたせている。それ以前にまず、デッサンが完璧です。
| このショールの描き方などは、No.36「ベラスケスへのオマージュ」で紹介したサージェントの絵と一脈通じるものがありますね。二人ともベラスケスから学んだということでしょう。 |
モデルになったカナルス夫人の印象は、画像だけからすると理知的な女性で、なんとなくちょっと "冷たい" 感じもします。しかし実際にバルセロナのピカソ美術館でこの絵を見ると、印象はかなり違います。暖かみがあり、情熱的で、ふくよかな女性、という感じなのです。ピカソの肌の描き方、特に暖色系の微妙なグラディエーションがそういう印象を生むのだと思います。
この絵は、一人の女性の肖像を越えた「美の象徴」ないしは「ヴィーナス」を描いているようでもあり、傑作だと思います。
キュビズム以降
「ピカソはほんまに天才か」で開高健は、
| これまで何人かの日本人の画家や評論家に私的な会話の席で、「ほんとにピカソはいいと思うか、そう感じたことがあるか」とたずねたが、確信をこめた断言体で、イエスと答えかえした人は一人もいなかった。 |
と書いています。
ここでいう「ピカソ」とは、キュビズム以降のピカソ作品のことを言っているはずです。「ピカソ作品 = キュビズム以降の、具象とは大きく乖離した作品」という暗黙の前提がある。この、キュビズム以降の具象とは大きく乖離した作品群をどうとらえるか、ここが意見の分かれるところでしょう。
個人的な意見を言うと、キュビズム以降のピカソの絵の中には素晴らしいと思うものがあります。しかしそれは少数で、多くの絵は訴えてくるものがない。たとえば前回のNo.45「ベラスケスの十字の謎」の最後に掲げた『ピアノ』という作品です。

| |||
|
パブロ・ピカソ 『ピアノ』(1957) (バルセロナ・ピカソ美術館) | |||
『ピアノ』はピカソの作品の中では「マイナーな」絵で、ピカソにとっては「余技」のようなものかもしれない。では有名な『アビニョンの女たち』はどうか。
アビニョンの女たち(1907)

| |||
|
パブロ・ピカソ 「アビニョンの女たち」(1907) (ニューヨーク近代美術館) | |||
| 後年の作品を特徴づける、画面のあちらこちらに露出している仰々しさ、未処理、不消化といったもの、おそらくはそれらの化合物としてたちあらわれるおしつけがまさには、ときどきうんざりさせられる。 |
とありますが、『アビニョンの女たち』を念頭に置いて書かれた文章ではないでしょうか。だとしたら同感です。
しかし、この絵はひょっとしたら傑作かもしれないとも思うこともあります。それは、この絵がフランスの都市・アビニョンの女ではなく、バルセロナの裏通りの女を描いたものだからです。堀田善衛の解説を引用します。
|
ダイレクトには書いていませんが、要するにこの絵はバルセロナの裏通りの売春婦たちを描いているのですね。ピカソはバルセロナに住んでいました。パリに出てからもバルセロナに何回も「帰郷」しています。この絵はピカソの経験がもとになっているのでしょう。そこで(一例として)つぎのような想像が可能になります。
|
港町・バルセロナの「酒池肉林通り」を歩いている画家を、娼館の客引きの女性がドアの中に引き入れる。そしてカーテンをあけると、そこには娼婦たちがいる。 彼女たちは全裸に近い姿で、画家に向かって「自分を買ってくれ」と、満身の笑顔で媚びを売る。くる日もくる日も見知らぬ客や船員を客にとり、性を売り、それは女としての「商品価値」がなくなるまで続く。 このように生きていかねばならない、人間としての「悲哀」や「空虚さ」を思うと、画家は暗澹とした気持ちになり、目の前の女たちの形はくずれ、分解し、輪郭さえ定まらないように感じてくる・・・・・・。 |
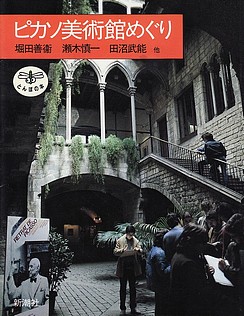
| |||
|
「ピカソ美術館めぐり」 (新潮社。1984) | |||
しかし通常の絵画評論としては、堀田善衛の解説の最後にあるように「人間讃歌」なのですね。それはないだろうと思います。キュビズムを切り開いたという絵画史的価値はあるのでしょうが、これが「人間讃歌」としたら駄作だと思います。画家は伝えたいことがあるのだとは思いますが、それが伝わってこない。絵と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しないのです。
『アビニョンの女たち』以降、絵の技法はきわめて多様化します。シュルレアリズムもあり、抽象絵画もある。しかし手法は何でも良いのですが、作者の一方的な思いを画面に出しただけの作品、おしつけがましい作品、絵と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しない作品を、少なくとも美術館に飾るのはやめてほしいと思います。
個人に絵を売ることを目的にして、画家が良いと思う方法で描き、良いと思った個人が購入して書斎を飾るのは何ら問題ありません。しかし美術館、とくに公的な美術館を飾る絵は、画家と鑑賞する多くの人の間で何らかのコミュニケーションが成立することが前提です。傑作かもしれないが、なぜ傑作か、その解説を聞かないとわからない作品は必要ありません。「傑作」を鑑賞するのではなく「傑作だという解説」を鑑賞する作品は不要です。美術大学の講義室ではないのだから・・・・・・。
ピカソの「キュビズム以降の絵」には、画家と鑑賞者の間でのコミュニケーションが成立しない絵が多い。しかし中にはそうでない絵があります。その代表が『泣く女』です。
泣く女(1937)
キュビズム以降のピカソの作品で文句なしに傑作だと思うのは、これも『アビニョンの女たち』と並んで有名な『泣く女』です。キュビズムの代表的な作品と言えるでしょう。
「ピカソは天才か」というタイトルではじめたので、ピカソは天才だと主張している2人目の文章を紹介しておきましょう。『泣く女』を直接評した文章ではありませんが『泣く女』を含むピカソのキュビズム作品を評した養老孟司氏の文章です。
|

| |||
|
養老孟司 「バカの壁」 (新潮新書。2003) | |||
もちろん、だからといってピカソのキュビズム作品が良いというわけではありません。養老さんも文中で「病気になると、ある能力が消えて、ひとりでにピカソの絵みたいなものを描くケースがある」と言っています。ごく普通の画力の人が病気になって「ピカソ的な絵」を描くこともあるわけです。特別の能力を持った天才が描いたから傑作だ、とは言えないのです。
それどころか、養老さんの分析から推定できることは、「ピカソのキュビズム作品は、普通の人には理解しがたいものだ」ということです。なぜなら、
| 脳の「空間イメージ構成力」を意識的にコントロールし、それを一時的に消して絵を描ける、特別な能力をもった人間の描いた作品 |
だということは、そこからロジカルに推論すると
| そういった特別な能力を持たない人間は、常に空間イメージ構成力が働いてしまうから、作品が不可解に思える |
はずだからです。最初に引用したように、開高健は「ピカソに何も感染させてもらえなかった」と書いていますが、「ピカソは天才だからこそ、普通の人は感染しない」のであり、「ピカソに感染する人がいたとしたら、その人は普通の能力ではない人」と言える。岩田・養老理論が正しければ、論理的にそうなるのです。
しかし、それにもかかわらず『泣く女』は名作だと思います。それは「空間イメージ構成力」どうのこうのではなく、描かれているテーマに絵画手法がピッタリとハマっているからです。ストライク・ゾーンのど真ん中に絵がいっている感じがする。

| |||
|
パブロ・ピカソ 「泣く女」(1937) (ロンドン・テートギャラリー) | |||
しかしどういうシチュエーションであれ、激しく泣く、慟哭するというのは非日常的な行為であり、普段は隠れている人間の別の面を露出させる行為です。近親者や親しい人が「泣く」のを見て、普段は分からないその人の全く別の一面を知った・・・・・・というような話はいっぱありますね。その泣くという行為の本質を、この絵は極めてうまくキャンバスに定着している。人間の非日常性を、絵画手法がピッタリと表現している作品だと思います。
ゲルニカ(1937)
『泣く女』と同じ年の『ゲルニカ』も、絵のテーマと絵画手法がよくマッチした傑作です。この絵のテーマになったスペイン市民戦争の時のゲルニカ無差別爆撃は、No.34「大坂夏の陣図屏風」のところで書いた通りです。人も動物も、爆弾の雨が降り注ぐ中で逃げまどい、死んでいく。爆風の直撃をうけた人の体はちぎれてあちこちに飛び散り、子どもを殺された母親は泣き叫び、地獄絵図のような光景があたり一面に展開される・・・・・・。ピカソは想像で描いているし、我々も想像するしかないのですが、この絵からうける「イメージ」どおりのことが実際に起こったことは確実でしょう。

『ゲルニカ』は絵そのものの価値以上に「反ファシズム」という政治的意味、思想的価値で解釈されてきた絵です。またこの絵が制作された経緯が流布することで、非常に有名になった。もしこの絵の制作経緯が一切明らかにされず、たとえば「戦争」というような題がついていたら、ここまで有名にはならなかったと思います。
しかし「反ファシズム」のという意図で絵を制作し、またその文脈で解釈するのは、別に悪いことではありません。要は、政治的意味や思想的価値を離れて、その絵が持っている表現力や強さ、伝達力がどうかです。丸木位里・俊 夫妻の「原爆の図」という絵がありますが、「原爆の図」のリアリズムとは全く対極の表現を使い、想像力だけで「爆撃の図」を描き切ったピカソの力量はやはり天才というべきでしょう。
『ゲルニカ』と『泣く女』に共通しているのは、人間社会における「悲惨」や「悲哀」を描いていることです。もちろん「悲惨」や「悲哀」だけが「キュビズム以降の、具象とは大きく乖離した手法」の存在意義ではありません。ピカソの静物画にも、中には素晴らしい作品がある。しかしハマった、と感じる絵が少ないのも事実です。キュビズムというボールを投げるとき、そのストライク・ゾーンは大変に狭いと思います。そのゾーンにコントロールよく投げられるかが、良し悪しの分かれ目です。
マヤに授乳するマリー・テレーズ(1936)
『ゲルニカ』と『泣く女』はともに1937年に描かれた絵ですが、これとほぼ同時期、1936年に描かれた絵を最後に取り上げたいと思います。『マヤに授乳するマリー・テレーズ』という、ペンとインク、水彩で描かれた作品です。

| ||
|
パブロ・ピカソ 「マヤに授乳するマリー・テレーズ」(1936) (個人蔵・ピカソ 子供の世界展(2000)より) | ||
この絵はピカソの作品の中でもごく「ささいな」ものでしょう。何らかの絵画史的な意味があるわけではないし、有名でもない。画家は日常の中で、紙の上にさっとペンを走らせ、水彩を塗り、おそらく数十分で描いてしまったのではないでしょうか。
しかし、この絵のマリー・テレーズの姿には独特の存在感があります。足を組んで椅子に堂々と腰掛け、我が子に授乳し、画家をキリッと見つめています。口をハンカチのようなもので覆っていますが、なぜなのかは分かりません。風邪でもひいて赤ちゃんにうつるのを避けようとしたのでしょうか。そのため彼女の表情は分からないのですが、画家を見つめるまなざしが、心のうちを語っていると思います。淡い水彩で塗られた画面は「おだやか」「安心」「やすらぎ」といった雰囲気を作っています。その中で毅然としている母親の強い存在感。画家はこの母としてのマリー・テレーズの姿に感動してペンを走らせたのだと思います。
マリー・テレーズはこのとき26歳、ピカソより約30歳も若い女性です。ピカソの女性遍歴や女性関係の「問題点」はさておき、純粋に1枚の絵として見たとき、鑑賞者に「伝わってくる」絵だと思います。
『マヤに授乳するマリー・テレーズ』と『泣く女』は、ともに画家と同棲した20代後半の女性を描いた絵です。この2枚の絵が示しているのは、人間の多様さ表現する「絵画表現の幅広さ」です。この振幅の広さが、ピカソの天才たるゆえんなのだと思います。
| 補記 |
ピカソが道化を描いた2枚の絵、
| ◆ | 曲芸師と若いアルルカン(バーンズ・コレクション) | ||
| ◆ | アルルカンと女友達(プーシキン美術館) |
(2014.05.09)
『マヤに授乳するマリー・テレーズ』と同じマリー・テレーズを描いた作品、
| ◆ | 本を持つ女(ノートン・サイモン美術館) |
(2015.10.17)
マリー・テレーズを描いた作品、
| ◆ | 夢 |
(2019.2.2)
No.36 - ベラスケスへのオマージュ [アート]
No.19「ベラスケスの怖い絵」で、中野京子さんの著書『怖い絵』の解説に従って『ラス・メニーナス』を取り上げました。今回はこの絵に関した話からです。
No.19 にも書いたように『ラス・メニーナス』については、ありとあらゆる評論が書かれてきました。また評論だけでなく、この絵を模写した画家も多くあり、有名なところでは、ピカソがキュビズムのタッチで模写した作品がバルセロナのピカソ美術館に所蔵されています。
しかし何といっても印象深いのは『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描かれた、サージェントの『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館蔵)です(以下「ボイト家の娘たち」と略します)。
ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)は、主にパリとロンドンで活躍したアメリカ人画家です。彼は1879年にプラド美術館を訪れ『ラス・メニーナス』を模写しました。そして『ラス・メニーナス』から得たインスピレーションをもとに後日描いたのが『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』で、彼が26歳の時の作品です。ボストン美術館に行くと、サージェントの絵だけが展示してある部屋があり、その部屋を圧するようにこの絵が飾ってあります。縦横 222.5 cm という、正方形の大きな絵です。
この絵は2010年にプラド美術館へ貸し出され、プラド美術館は「招待作品」として、この絵と『ラス・メニーナス』を並べて展示しました。天下の2大美術館が揃って、この絵を『ラス・メニーナス』へのオマージュであると認めたことになります。
エドワード・ダーレー・ボイトは、サージェントの友人のアメリカ人画家です。当時、ボイトの一家はパリに住んでいて、そのパリでのボイト家の4人娘を描いたのがこの作品です。一番手前、床に座っているのが最年少のジュリアで当時4歳、左の方に立っているのがメアリーで8歳、奥の方で正面を向いているのがジェーンで12歳、横を向いてしまっているのがフローレンスで14歳です(名前と年齢はボストン美術館の公式サイトによる)。
サージェント:エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち
ボストン美術館へは2回行ったことがありますが、初めて訪れて「ボイト家の娘たち」を見た時は、この絵が『ラス・メニーナス』へのオマージュとは知りませんでした。もちろん絵を見ただけでは、そうとは気付きません。知ったのはその後です。そう言われてみれば『ラス・メニーナス』との類似性に気付くのです。「類似性」をキーに「ボイト家の娘たち」を鑑賞すると、次のようになるでしょう。
一つは絵の「主人公」です。「ボイト家の娘たち」の主人公は、床に座っている4歳のジュリアでしょう。最も光が強く当たっている描写がされています。一方の『ラス・メニーナス』はもちろんマルガリータ王女です。王女は当時5歳。2つの絵とも、4~5歳の幼女を主役にしています。
2つ目は、部屋に入ってきた誰かに登場人物たちの視線が集まった、その一瞬を描いたと感じさせる点です。「ボイト家の娘たち」を見て感じるのは、次のような情景です。友人の家を訪問したサージェントが、カメラを持って4人の娘の居る部屋に入っていく。「写真を撮ろう。そのままの位置でいいよ。カメラに向いて・・・・・・」。幼いジュリアはそのままの姿勢でカメラに目をむける。メアリーとジェーンはシャンと立って、カメラを見据える。年長のフローレンスは、今は写真など撮られたくないわ、とばかりに、サージェントの言葉を無視して横を向く・・・・・・。そんな情景の一瞬です。
もちろんサージェントの時代に(一瞬で撮影できる)カメラがあったわけではありません。しかし想像させられるのはそれと類似の状況です。たとえば、ボイト氏が初めて友人を娘たちに紹介するつもりで部屋に入っていった、というような・・・・・・。
『ラス・メニーナス』は、国王夫妻がベラスケスのアトリエに様子を見に来て、視線が国王夫妻に集まった一瞬を描いたという説がありますね。だから後方の鏡に夫妻が映っているのだというわけです(別の説もある)。この、一瞬を切り取った、その一瞬のありようが「ボイト家の娘たち」は『ラス・メニーナス』と非常によく似ています。
3つ目は「ボイト家の娘たち」の構図と人物・事物の配置がかもし出す「ミステリアスな雰囲気」です。
4人の娘は、やけに左に偏って配置されていて、かつ手前から奥に向かって配置されています。二人は直立不動のような格好で正面を向いていますが、それとは全く対照的に一人は横を向いてしまっている。そして、ふっと自然な感じの視線を合わせた女の子が前の方に座っています。いったいこの4人の関係やいかに・・・・・・と詮索したくなる、思わせぶりな構図です。
そして印象的なのが、2つの染付けの大きな花瓶です。ボストン美術館の公式サイトによると、これは日本の有田焼です。右の方は半分しか描かれていません。しかしこの大きな花瓶の、静かに場を圧する存在感は相当なものです。
そして、右側の花瓶の横に描き込まれた赤いものは何でしょうか。何かのスクリーンのようなものだと思いますが、何のためのものなのか不明です。このスクリーン(のようなもの)は、『ラス・メニーナス』の絵の中に登場する大きなキャンバスに対応させたものでしょう。左右が反転していますが、構図がキャンバスに似ています。ひょっとしたらサージェントは、この絵を『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描いたことの証(あかし)として、意図的に描き加えたのかもしれません。
とにかく、こういった構図と人物・事物の配置がかもし出す「ミステリアスな雰囲気」が『ラス・メニーナス』に非常に似ています。
4つ目は、非常に広い「幅」や「奥行き」がある空間を感じさせる絵だということです。「ボイト家の娘たち」は、人物の配置と光の効果で「広大な空間」を作り出した絵だと思います。
まず、4人娘をことさら画面の左側に偏って配置しています。そうすることで4人のさらに左にも、この絵の右半分と同等の空間があると想像させます。右端の半分に切れた花瓶も、さらにその右へと部屋が広がっていることを明確にしている。これは日本画にもよくある手法です。
またサージェントの絵では、娘たちを前から奥に順に配置していて、奥に行くに従って娘の受ける光はだんだんと薄暗くなっていきます。そのさらに奥は暗闇に近くなり、窓の明かりがかすかに見える。光によって空間の奥行きが演出されています。
光による空間演出という意味では、フェルメールに何点かありますね。左の窓から差し込む淡い光が、個人が使用する、比較的狭い、こじんまりした、暖かみのある空間(部屋)を作り出す。
サージェントは光の演出だけでなく、人物の配置と構図で「空間を描いた」作品を作った。そう思います。その点ではまさにベラスケスの『ラス・メニーナス』と相似形です。また、この2つの作品は日本語で言う「奥」を描くことに成功した作品です。「奥」は日本語の独特表現なのかどうか確信はありませんが、少なくとも英語に「奥」を直訳できる単語はないはずです。西欧の絵画では、遠近法で「遠く」を描いた作品はいっぱいありますが、「奥」を描いた作品はあまりなく、その意味ではこの2作品は際だっていると思います。
さらにサージェントの作品について言うと、前から奥に行くに従って、姉妹の年齢は高くなっていきます。床に座っているのは幼児のジュリア。後ろで横を向いているのは10歳年上の姉のフローレンス。その間を真正面を向いたメアリーとジェーンがつないでいる。横を向いてしまったフローレンスは、あたかも子どもから脱して大人に向かっていくかのようです。じっと見ていると、手前から奥に向かって時間が流れていくように見える。サージェントはこの構図で、時の経過までもキャンバスに閉じ込めようしたと見えます。
5つ目は「広い空間の演出」と関係しますが、多様性がある光(と影)の表現です。特にサージェントの絵では、子供用エプロンの目に染み入るような「白」と、有田焼の磁器の釉薬を通した白色が印象的です。磁器の反射光の表現も鮮烈です。
この作品は「白による多様な光の表現が最も印象的な絵画作品」と言えるでしょう。白で光の効果を演出してみせよう、それに挑戦してみよう、白だけで十分なことを証明してみせよう・・・・・・。26歳の若いサージェントの、そういった意気込みというか、野心が伝わってくるような作品です。
最後に、この2つの絵だけの特徴ではないのですが、きわめて粗いタッチ、ラフな筆さばきが効果的に使われていることも共通しています。
「ボイト家の娘たち」の一番手前のジュリアは、よく見ると人形を持っています。この人形の服の表現は、まさに「書きなぐった」という言葉にふさわしい。実際、ほとんど一瞬で描かれたのでしょう。ベラスケスの絵もそうです。マルガリータ王女やその左の侍女の、袖のあたりは「書きなぐりによる迫真表現」です。よくよく見ると驚いてしまう。
こういった表現は『ラス・メニーナス』だけでなく、ベラスケスのほかの絵にも多々ありますが、サージェントもそうです。またサージェントだけでなく、印象派の時代の画家がベラスケスから学んだ重要な絵画技法だと思います。
サージェントの絵を見て思うのは、アーティストが先人の作品から受けるインスピレーションというのは、非常に微妙で個人的なものだということです。作品のどのポイントに霊感を感じるのか、それはアーティストの個人的な感覚に依存しています。「ボイト家の娘たち」は『ラス・メニーナス』へのオマージュである、と言われなければ分からない。しかし「言われなければ分からない」けど、先人の作品を踏まえていることは確かなのです。
そして、これは最近知ったのですが、ベラスケスのある作品からインスピレーションを得て描かれた絵で、誰もが知っている超有名絵画があるのです。エドゥアール・モネの『笛を吹く少年』です。
マネ:笛を吹く少年
2011年7月30日にテレビ東京で放映された「美の巨人たち」のテーマは、マネ(1832-1883)の『笛を吹く少年』(1866。オルセー美術館蔵)でした。マネは「印象派の父」と言われています。番組では「絵画の新時代はマネから始まった(セザンヌ)」とか、「絵画はマネをもって始まる(ゴーギャン)」といった、画家たちの敬愛の言葉が紹介されていました。
『笛を吹く少年』は、確か教科書に採用されていた(時期があった)はずです。広く日本人が最もよく知っているマネの作品はこれ、と言っていいと思います。実はこの作品は、ベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(1624-32頃。プラド美術館蔵)からインスピレーションを得て描かれた、というのが番組の主眼でした。美術界では常識かもしれませんが、私は初めて知りました。
No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、宮廷画家であるベラスケスは王侯貴族の絵だけでなく、慰み者や道化師、貧しい市民、芸人、乞食の絵を描いています。『道化師パブロ・デ・バリャドリード』はその中の1枚で、プラド美術館のホームページで確認すると、No.19 で紹介した『セバスティアン・デ・モーラ』『ディエゴ・ディ・アセド』『フランシスコ・レスカーノ』と同じ部屋に飾られています。『ラス・メニーナス』は(現在は)別の部屋のようです。
マネは33歳の時に『オランピア』(1865。オルセー美術館所蔵)を描き、サロンに入選します。現代ではマネの傑作としてよく知られているこの絵ですが、当時は、娼婦を描いた作品だということで評論家から非難轟々、罵声を浴びせられます。落ち込んだマネはマドリッドに旅行し、プラド美術館でベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』に出会うのです。
番組で紹介されていたマネ自身の言葉によると「僕はこの作品に、僕自身の理想とする絵画の実現をみた」そうです。絶賛の言葉ですね。帰国後、マネはさっそく『道化師パブロ・デ・バリャドリード』へのオマージュ作品を2つ描きました。第1作が『悲劇役者(ハムレットに扮するルビエール)』(1866。ワシントン・ナショナル・ギャラリー [NGA] 蔵)であり、そして決定版が第2作の『笛を吹く少年』です。こうしてみると『悲劇役者』の方がベラスケスに非常に近いことが分かります。
普通『笛を吹く少年』は日本の浮世絵に影響されたと言われていますね。はっきりした輪郭、平面的な色使い、最小限の色数、背景が無いことなど、これらは版画である浮世絵の特徴です。美術史の研究でも『笛を吹く少年』は浮世絵に影響をうけたことが定説となっているようです。しかしもう一つ強く影響をうけた画家がいた。それがベラスケスだった。
そういえば思いあたることがあります。マネがエミール・ゾラを自分のアトリエに招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868。オルセー美術館蔵)という作品があります。この絵の右上には、画中画として絵の複製が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』であり、もう一つは、歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右ヱ門』(1860)です。マネは浮世絵の影響を受けたという予備知識があるので、我々は(特に日本人である我々は)浮世絵に目が行きます。左の方に描かれている琳派を思わせる屏風ともあわせ、ジャポニズムの雰囲気をぷんぷんと感じる。
しかし『大鳴門灘右ヱ門』の後ろには、もう一枚の複製画があるのですね。分かりにくいのですが、これはベラスケスの『バッカスの勝利』(1628-29。プラド美術館蔵)なのです。『エミール・ゾラの肖像』は、マネが浮世絵の「賛美者」であると同時に、ベラスケスの「弟子」だということを雄弁に物語っています。
日本という共通項
サージェントの『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』と、マネの『笛を吹く少年』は、2つとも「ベラスケスへのオマージュ」でした。しかし、もう一つの共通項があります。それは、少々意外なことに「日本」です。『笛を吹く少年』が浮世絵の影響下に描かれたことはもちろんなのですが、『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』に描かれているのも有田焼の花瓶なのです。
この有田焼に関してなのですが、サージェントは「たまたま」ボイト家にあった花瓶を描いただけなのでしょうか。そうとも限らないと思います。ボイト家で巨大な有田焼に出会い、それに絵心をかき立てられた、ということも十分に考えられる。たとえ「たまたま」であったとしても、ボイト氏を含むパリ在住の画家たちに「日本趣味」が浸透していたことは、モネやゴッホを引き合いに出すまでもなく明らかです。サージェントも、画面に提灯と百合の花をちりばめた「ジャポニズム」の絵を描いているのです。『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』(1885-6。ロンドンのテート・ギャラリー蔵)という、薄暮時の一瞬を描いた傑作です。
江戸時代の末期から明治初期という日本の激動期において、日本から輸出された美術品、日本では美術品としては認められなかった「作品」が、実は欧米のアーティストに深く影響を与えていたことが、よく理解できる2作品です。

|
| ベラスケス『ラス・メニーナス』(プラド美術館) |
No.19 にも書いたように『ラス・メニーナス』については、ありとあらゆる評論が書かれてきました。また評論だけでなく、この絵を模写した画家も多くあり、有名なところでは、ピカソがキュビズムのタッチで模写した作品がバルセロナのピカソ美術館に所蔵されています。
しかし何といっても印象深いのは『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描かれた、サージェントの『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』(1882。ボストン美術館蔵)です(以下「ボイト家の娘たち」と略します)。
ジョン・シンガー・サージェント(1856-1925)は、主にパリとロンドンで活躍したアメリカ人画家です。彼は1879年にプラド美術館を訪れ『ラス・メニーナス』を模写しました。そして『ラス・メニーナス』から得たインスピレーションをもとに後日描いたのが『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』で、彼が26歳の時の作品です。ボストン美術館に行くと、サージェントの絵だけが展示してある部屋があり、その部屋を圧するようにこの絵が飾ってあります。縦横 222.5 cm という、正方形の大きな絵です。
この絵は2010年にプラド美術館へ貸し出され、プラド美術館は「招待作品」として、この絵と『ラス・メニーナス』を並べて展示しました。天下の2大美術館が揃って、この絵を『ラス・メニーナス』へのオマージュであると認めたことになります。

|
|
John Singer Sargent "The Daughters of Edward Darley Boit" (1882) Museum of Fine Arts, Boston |
エドワード・ダーレー・ボイトは、サージェントの友人のアメリカ人画家です。当時、ボイトの一家はパリに住んでいて、そのパリでのボイト家の4人娘を描いたのがこの作品です。一番手前、床に座っているのが最年少のジュリアで当時4歳、左の方に立っているのがメアリーで8歳、奥の方で正面を向いているのがジェーンで12歳、横を向いてしまっているのがフローレンスで14歳です(名前と年齢はボストン美術館の公式サイトによる)。

|

|

|

|
||
サージェント:エドワード・ダーレー・
Sargent : The Daughters of Edward Darley Boit
ボストン美術館へは2回行ったことがありますが、初めて訪れて「ボイト家の娘たち」を見た時は、この絵が『ラス・メニーナス』へのオマージュとは知りませんでした。もちろん絵を見ただけでは、そうとは気付きません。知ったのはその後です。そう言われてみれば『ラス・メニーナス』との類似性に気付くのです。「類似性」をキーに「ボイト家の娘たち」を鑑賞すると、次のようになるでしょう。
| 主人公 |
一つは絵の「主人公」です。「ボイト家の娘たち」の主人公は、床に座っている4歳のジュリアでしょう。最も光が強く当たっている描写がされています。一方の『ラス・メニーナス』はもちろんマルガリータ王女です。王女は当時5歳。2つの絵とも、4~5歳の幼女を主役にしています。
| 一瞬の定着 |
2つ目は、部屋に入ってきた誰かに登場人物たちの視線が集まった、その一瞬を描いたと感じさせる点です。「ボイト家の娘たち」を見て感じるのは、次のような情景です。友人の家を訪問したサージェントが、カメラを持って4人の娘の居る部屋に入っていく。「写真を撮ろう。そのままの位置でいいよ。カメラに向いて・・・・・・」。幼いジュリアはそのままの姿勢でカメラに目をむける。メアリーとジェーンはシャンと立って、カメラを見据える。年長のフローレンスは、今は写真など撮られたくないわ、とばかりに、サージェントの言葉を無視して横を向く・・・・・・。そんな情景の一瞬です。
もちろんサージェントの時代に(一瞬で撮影できる)カメラがあったわけではありません。しかし想像させられるのはそれと類似の状況です。たとえば、ボイト氏が初めて友人を娘たちに紹介するつもりで部屋に入っていった、というような・・・・・・。
『ラス・メニーナス』は、国王夫妻がベラスケスのアトリエに様子を見に来て、視線が国王夫妻に集まった一瞬を描いたという説がありますね。だから後方の鏡に夫妻が映っているのだというわけです(別の説もある)。この、一瞬を切り取った、その一瞬のありようが「ボイト家の娘たち」は『ラス・メニーナス』と非常によく似ています。
| ミステリアス |
3つ目は「ボイト家の娘たち」の構図と人物・事物の配置がかもし出す「ミステリアスな雰囲気」です。
4人の娘は、やけに左に偏って配置されていて、かつ手前から奥に向かって配置されています。二人は直立不動のような格好で正面を向いていますが、それとは全く対照的に一人は横を向いてしまっている。そして、ふっと自然な感じの視線を合わせた女の子が前の方に座っています。いったいこの4人の関係やいかに・・・・・・と詮索したくなる、思わせぶりな構図です。
そして印象的なのが、2つの染付けの大きな花瓶です。ボストン美術館の公式サイトによると、これは日本の有田焼です。右の方は半分しか描かれていません。しかしこの大きな花瓶の、静かに場を圧する存在感は相当なものです。
|
ボストン美術館の公式ホーム・ページによって補足しますと、この花鳥の染付けの花瓶は、実際にボイト家の所有物でした。ボイト家は、出身地のボストンとパリを往復して生活していたのですが、花瓶は一家の移動とともに大西洋を何回も往復したそうです。つまりボイト家のシンボルとして大切にされていたのですね。そしてボイト氏が亡くなったあと、娘たちは絵とともに花瓶をボストン美術館に寄贈しました。 ボストン美術館の「ボイト家の娘たち」の部屋に行くと、この花瓶も飾ってあります。公式サイトによると、この花瓶の高さは 188cm という大きなものです。ボイト家の娘たち4人は今はもう誰もいなし、絵を描いた画家もいないのですが、花瓶だけは百数十年の時を越えて生き抜いている。ますます、その圧倒的な存在感が伝わってくるような展示です。 |

|
|
『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』の展示 [site : ボストン美術館] |
そして、右側の花瓶の横に描き込まれた赤いものは何でしょうか。何かのスクリーンのようなものだと思いますが、何のためのものなのか不明です。このスクリーン(のようなもの)は、『ラス・メニーナス』の絵の中に登場する大きなキャンバスに対応させたものでしょう。左右が反転していますが、構図がキャンバスに似ています。ひょっとしたらサージェントは、この絵を『ラス・メニーナス』へのオマージュとして描いたことの証(あかし)として、意図的に描き加えたのかもしれません。
とにかく、こういった構図と人物・事物の配置がかもし出す「ミステリアスな雰囲気」が『ラス・メニーナス』に非常に似ています。
| 幅と奥行きのある空間 |
4つ目は、非常に広い「幅」や「奥行き」がある空間を感じさせる絵だということです。「ボイト家の娘たち」は、人物の配置と光の効果で「広大な空間」を作り出した絵だと思います。
まず、4人娘をことさら画面の左側に偏って配置しています。そうすることで4人のさらに左にも、この絵の右半分と同等の空間があると想像させます。右端の半分に切れた花瓶も、さらにその右へと部屋が広がっていることを明確にしている。これは日本画にもよくある手法です。
またサージェントの絵では、娘たちを前から奥に順に配置していて、奥に行くに従って娘の受ける光はだんだんと薄暗くなっていきます。そのさらに奥は暗闇に近くなり、窓の明かりがかすかに見える。光によって空間の奥行きが演出されています。
光による空間演出という意味では、フェルメールに何点かありますね。左の窓から差し込む淡い光が、個人が使用する、比較的狭い、こじんまりした、暖かみのある空間(部屋)を作り出す。
サージェントは光の演出だけでなく、人物の配置と構図で「空間を描いた」作品を作った。そう思います。その点ではまさにベラスケスの『ラス・メニーナス』と相似形です。また、この2つの作品は日本語で言う「奥」を描くことに成功した作品です。「奥」は日本語の独特表現なのかどうか確信はありませんが、少なくとも英語に「奥」を直訳できる単語はないはずです。西欧の絵画では、遠近法で「遠く」を描いた作品はいっぱいありますが、「奥」を描いた作品はあまりなく、その意味ではこの2作品は際だっていると思います。
さらにサージェントの作品について言うと、前から奥に行くに従って、姉妹の年齢は高くなっていきます。床に座っているのは幼児のジュリア。後ろで横を向いているのは10歳年上の姉のフローレンス。その間を真正面を向いたメアリーとジェーンがつないでいる。横を向いてしまったフローレンスは、あたかも子どもから脱して大人に向かっていくかのようです。じっと見ていると、手前から奥に向かって時間が流れていくように見える。サージェントはこの構図で、時の経過までもキャンバスに閉じ込めようしたと見えます。
| 多様な光 |
5つ目は「広い空間の演出」と関係しますが、多様性がある光(と影)の表現です。特にサージェントの絵では、子供用エプロンの目に染み入るような「白」と、有田焼の磁器の釉薬を通した白色が印象的です。磁器の反射光の表現も鮮烈です。
この作品は「白による多様な光の表現が最も印象的な絵画作品」と言えるでしょう。白で光の効果を演出してみせよう、それに挑戦してみよう、白だけで十分なことを証明してみせよう・・・・・・。26歳の若いサージェントの、そういった意気込みというか、野心が伝わってくるような作品です。
| 粗いタッチ |
最後に、この2つの絵だけの特徴ではないのですが、きわめて粗いタッチ、ラフな筆さばきが効果的に使われていることも共通しています。
「ボイト家の娘たち」の一番手前のジュリアは、よく見ると人形を持っています。この人形の服の表現は、まさに「書きなぐった」という言葉にふさわしい。実際、ほとんど一瞬で描かれたのでしょう。ベラスケスの絵もそうです。マルガリータ王女やその左の侍女の、袖のあたりは「書きなぐりによる迫真表現」です。よくよく見ると驚いてしまう。
| このあたりは日本画における「付立て(つけたて)」という手法を思い起こさせます。円山応挙やその一門の絵によくあります。たとえば草木を描くときに、花の部分は精緻にデッサンをし、輪郭を書き、リアルに、写実的に描く。しかし幹の部分は輪郭を描かず、筆の濃淡だけをたよりに、一気呵成に描く。この「一気呵成」の部分が付立てですね。写実的部分との対比の妙で、互いが互いを引き立てるというわけです。 |
こういった表現は『ラス・メニーナス』だけでなく、ベラスケスのほかの絵にも多々ありますが、サージェントもそうです。またサージェントだけでなく、印象派の時代の画家がベラスケスから学んだ重要な絵画技法だと思います。
サージェントの絵を見て思うのは、アーティストが先人の作品から受けるインスピレーションというのは、非常に微妙で個人的なものだということです。作品のどのポイントに霊感を感じるのか、それはアーティストの個人的な感覚に依存しています。「ボイト家の娘たち」は『ラス・メニーナス』へのオマージュである、と言われなければ分からない。しかし「言われなければ分からない」けど、先人の作品を踏まえていることは確かなのです。
そして、これは最近知ったのですが、ベラスケスのある作品からインスピレーションを得て描かれた絵で、誰もが知っている超有名絵画があるのです。エドゥアール・モネの『笛を吹く少年』です。
マネ:笛を吹く少年
2011年7月30日にテレビ東京で放映された「美の巨人たち」のテーマは、マネ(1832-1883)の『笛を吹く少年』(1866。オルセー美術館蔵)でした。マネは「印象派の父」と言われています。番組では「絵画の新時代はマネから始まった(セザンヌ)」とか、「絵画はマネをもって始まる(ゴーギャン)」といった、画家たちの敬愛の言葉が紹介されていました。

|
|
マネ『笛を吹く少年』 (1866。オルセー美術館) |
『笛を吹く少年』は、確か教科書に採用されていた(時期があった)はずです。広く日本人が最もよく知っているマネの作品はこれ、と言っていいと思います。実はこの作品は、ベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』(1624-32頃。プラド美術館蔵)からインスピレーションを得て描かれた、というのが番組の主眼でした。美術界では常識かもしれませんが、私は初めて知りました。
No.19「ベラスケスの怖い絵」で紹介したように、宮廷画家であるベラスケスは王侯貴族の絵だけでなく、慰み者や道化師、貧しい市民、芸人、乞食の絵を描いています。『道化師パブロ・デ・バリャドリード』はその中の1枚で、プラド美術館のホームページで確認すると、No.19 で紹介した『セバスティアン・デ・モーラ』『ディエゴ・ディ・アセド』『フランシスコ・レスカーノ』と同じ部屋に飾られています。『ラス・メニーナス』は(現在は)別の部屋のようです。

|
|
ベラスケス 『道化師パブロ・デ・バリャドリード』 (1624-32頃。プラド美術館) |
マネは33歳の時に『オランピア』(1865。オルセー美術館所蔵)を描き、サロンに入選します。現代ではマネの傑作としてよく知られているこの絵ですが、当時は、娼婦を描いた作品だということで評論家から非難轟々、罵声を浴びせられます。落ち込んだマネはマドリッドに旅行し、プラド美術館でベラスケスの『道化師パブロ・デ・バリャドリード』に出会うのです。

| |||
|
マネ (1866。 NGA) | |||
普通『笛を吹く少年』は日本の浮世絵に影響されたと言われていますね。はっきりした輪郭、平面的な色使い、最小限の色数、背景が無いことなど、これらは版画である浮世絵の特徴です。美術史の研究でも『笛を吹く少年』は浮世絵に影響をうけたことが定説となっているようです。しかしもう一つ強く影響をうけた画家がいた。それがベラスケスだった。
そういえば思いあたることがあります。マネがエミール・ゾラを自分のアトリエに招いて描いた『エミール・ゾラの肖像』(1868。オルセー美術館蔵)という作品があります。この絵の右上には、画中画として絵の複製が描き込まれています。一つはマネ自身の『オランピア』であり、もう一つは、歌川国明の相撲絵『大鳴門灘右ヱ門』(1860)です。マネは浮世絵の影響を受けたという予備知識があるので、我々は(特に日本人である我々は)浮世絵に目が行きます。左の方に描かれている琳派を思わせる屏風ともあわせ、ジャポニズムの雰囲気をぷんぷんと感じる。
しかし『大鳴門灘右ヱ門』の後ろには、もう一枚の複製画があるのですね。分かりにくいのですが、これはベラスケスの『バッカスの勝利』(1628-29。プラド美術館蔵)なのです。『エミール・ゾラの肖像』は、マネが浮世絵の「賛美者」であると同時に、ベラスケスの「弟子」だということを雄弁に物語っています。

|

|
|
マネ『エミール・ゾラの肖像』(1868。オルセー美術館) 右は相撲絵の部分を拡大したもの [site : NGA] | |

|
|
ベラスケス『バッカスの勝利』 (1628-29。プラド美術館) |
日本という共通項
サージェントの『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』と、マネの『笛を吹く少年』は、2つとも「ベラスケスへのオマージュ」でした。しかし、もう一つの共通項があります。それは、少々意外なことに「日本」です。『笛を吹く少年』が浮世絵の影響下に描かれたことはもちろんなのですが、『エドワード・ダーレー・ボイトの娘たち』に描かれているのも有田焼の花瓶なのです。
この有田焼に関してなのですが、サージェントは「たまたま」ボイト家にあった花瓶を描いただけなのでしょうか。そうとも限らないと思います。ボイト家で巨大な有田焼に出会い、それに絵心をかき立てられた、ということも十分に考えられる。たとえ「たまたま」であったとしても、ボイト氏を含むパリ在住の画家たちに「日本趣味」が浸透していたことは、モネやゴッホを引き合いに出すまでもなく明らかです。サージェントも、画面に提灯と百合の花をちりばめた「ジャポニズム」の絵を描いているのです。『カーネーション、リリー、リリー、ローズ』(1885-6。ロンドンのテート・ギャラリー蔵)という、薄暮時の一瞬を描いた傑作です。
江戸時代の末期から明治初期という日本の激動期において、日本から輸出された美術品、日本では美術品としては認められなかった「作品」が、実は欧米のアーティストに深く影響を与えていたことが、よく理解できる2作品です。

|
|
John Singer Sargent "Carnation, Lily, Lily, Rose" (1885-6) Tate Gallary, London |








 ところで本作から二十数年後、ピカソも同じダンス場を取り上げました。タイトルも『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』。しかし見てのとおり、とても同じ場所とは思えません。ルノワールの健全さを嘲笑うかのように、ピカソはこれでもかと隠微な雰囲気を盛り上げます。昼と夜との違いというより、このカフェ自体が次第に売春婦たちのたまり場へと変貌していったという事実があります。だとしても、この、ムンクのような妖しさ。これほどの退廃ムードをピカソは十九歳で、しかもスペインからパリに出てきてまだたった二ヶ月というのに、やすやすと描きあげた。真の天才というのは、実に何とも恐るべきものです。
ところで本作から二十数年後、ピカソも同じダンス場を取り上げました。タイトルも『ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏場』。しかし見てのとおり、とても同じ場所とは思えません。ルノワールの健全さを嘲笑うかのように、ピカソはこれでもかと隠微な雰囲気を盛り上げます。昼と夜との違いというより、このカフェ自体が次第に売春婦たちのたまり場へと変貌していったという事実があります。だとしても、この、ムンクのような妖しさ。これほどの退廃ムードをピカソは十九歳で、しかもスペインからパリに出てきてまだたった二ヶ月というのに、やすやすと描きあげた。真の天才というのは、実に何とも恐るべきものです。


