No.227 - 中島みゆきの詩(14)世情 [音楽]
今年の正月のテレビ番組を思い出したので書きます。No.32 でも書いたテレビ朝日系列の「芸能人格付けチェック」(2018年1月1日 放映)のことで、今年久しぶりに見ました。No.32 で書いたのは、この番組の本質です。それは、
としました。もちろんここで言う回答者とは「番組の本質が分かっている回答者」であり、そういう回答者ばかりでないのは見ていて良く分かります。そして、久しぶりに見て改めて感じたのは、番組の "フォーマット" の良さです。つまり、
のです。このフォーマットがなければ全くつまらない番組になるでしょう。これを発明した人はすごいと思います。日本のテレビ番組のフォーマットは海外に輸出した実績がありますが(料理の鉄人など)、この番組も売れるのではないでしょうか。
今年の「芸能人格付けチェック」はGACKTチームとしてYOSHIKIさんが出演していました。GACKTさんは例によって全問正解で連勝記録を伸ばしていましたが、YOSHIKIさんも全問正解でした。問題の一つのワインのテイスティングでは、YOSHIKIさんが自分の名前の入ったワインを作っていることを初めて知りました。相当なワイン通のようです。GACKTさんが5年越しで説得して番組に出演してもらったそうですが、かなりの "目利き" だと分かっていたからでしょう。単に親しいミュージシャンだからという理由でこの番組への出演を説得するはずがありません。
番組の最後には「ミニ格付けチェック」というコーナーがあって、司会の浜田雅功さんと伊東四朗さんと女性アシスタントが問題に挑戦します。ここで浜田さんが2年連続の「写す価値なし」となってしまいました。そしてこのとき流れた BGM が、中島みゆき《世情》でした。《世情》の "時の流れを止めて" というフレーズが聞こえてきたので、「これ以上 "写す価値なし" にならないで」という意味を重ねたのでしょう。
中島ファンとしては、こんなところで《世情》という名曲を使わないで欲しいと思うのですが(そして単に "言葉尻" をとらえた使い方をして欲しくないと思うのですが)、この曲はかつてTBSのドラマ「3年B組金八先生」で用いられたことがあるので(1981年)、テレビとは縁があるのでしょう。また「芸能人格付けチェック」の制作スタッフの中に中島みゆきの楽曲を熟知している人がいる感じもして、それはそれで良しとしましょう。
今回はその、中島みゆき《世情》についてです。この詩は No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でも取り上げたのですが、詩の一部だけだったので、改めてこの詩だけにフォーカスして書くことにします。
中島みゆき 《世情》
《世情》は1978年(中島みゆき 26歳)に発売されたアルバム『愛していると云ってくれ』の最後の収録された曲で、次のような詩です。
曲はギターだけで始まり、小さく合唱が出てきて、それがだんだん大きくなったところで中島さんが歌い出します。上の詩が終わったあとのエンディングでは再び合唱が出てきて、「シュプレヒコール ~ 戦うため」の部分がさらに4回繰り返されるうちにフェイドアウトして楽曲が(=アルバムが)終わります。
この詩のキーワードは、4回出てくる "シュプレヒコール" です。誰が聴いてもそう思うはずです。最初と最後に出てくる合唱は、シュプレヒコールをあげながら行進するデモ隊が近づいてきて、通り過ぎていく情景が浮かびます。そして、このキーワードが学生運動を連想させます。詩の中の "学者" という言葉が大学を暗示している。シュプレヒコールは一般にデモ隊が発するものなので限定して考える必要はないのですが、ここでは学生運動を想定することにします。
このアルバムが発売されたのは1978年です。今では「学生運動」は死語に近くなっていますが、1978年当時はその10年前ほどから全国に広がった学生運動のリアルな記憶ある頃でした。そこで、アルバム発売のちょうど10年まえ、1968年に戻ってみます。
1968年からの数年間
1968年の1月です。従来から医者のインターン制度(無給の研修医制度)の改革を要求していた東京大学医学部の学生は、新制度に反対してストライキに突入しました。この中で、医学部教授が長時間拘束されるという事態になりました。3月、医学部は学生17人を退学や停学の処分にします(この中には拘束の現場にいなかった学生もいた)。これが学生たちの怒りに火をつけ、闘争が始まりました。6月、学生たちは東大のシンボルである安田講堂を占拠し立てこもります。そして東大闘争全学共闘会議(全共闘)が組織され、医学部のみならず全学の自治会がストに突入しました。
その後の経緯は紆余曲折があるのですが、結局大学側は翌年の1969年1月に機動隊の出動を要請し、安田講堂の封鎖は解除され、多数の逮捕者を出しました。その安田講堂の "攻防戦" はテレビで全国に大々的に生中継されました。この一連の紛争の結果、東京大学の入学試験が中止されるという前代未聞の事態になりました。1969年4月に東大に入学した人はゼロです。そして1969年から1970年にかけて、大学の改革を要求する学生たちの運動は全国的に波及しました。また1970年は1960年に締結された日米安全保障条約の改定の年であり、いわゆる「70年安保闘争」にもつながっていきました。
1968年というと、日本大学の不正会計に端を発した日大闘争が起きた年です。また、この年には欧米でも学生運動が多発しました。フランスでベトナム戦争反対、大学運営の民主化を要求して大規模なデモとストライキが起こったのも1968年です(5月革命、ないしは5月危機)。またアメリカの学生運動で有名なコロンビア大学闘争も1968年です。ちなみに1968年にはチェコスロバキア(当時)で自由化・民主化を求める「プラハの春」が起きました(ソ連が武力介入して弾圧)。またアメリカの公民権運動の指導者だったキング牧師が暗殺されたのもこの年でした。
そもそも1960年代後半は、アメリカがベトナムに介入したベトナム戦争に反対する市民運動やデモが、アメリカのみならず日本やヨーロッパでも多発していました。もちろん学生たち(あるいは高校生たち)もそこに参加していました。
以上のような1960年代後半の学生運動を描いた映画も作られました。有名なのが、No.35「中島みゆき:時代」で書いた『いちご白書』です。この映画はまさに1968年のコロンビア大学闘争が題材となっていました。『いちご白書』の日本公開は1970年の秋です。
以上の経緯に中島みゆきさんの経歴を重ねるとどうなるでしょうか。中島さんは1952年2月23日生まれです。高校・大学の経歴を各年の4月の時点でみると、
ということになります。つまり高校1年の3学期に東大闘争がはじまり、高校2年のときに闘争がピークを迎えて安田講堂攻防戦のテレビ生中継があり、高校3年では学生運動が全国に波及し、東大入試がなかった1969年4月の1年後に大学に進学したことになります。『いちご白書』の日本公開は大学1年の秋です(中島さんの『時代』は『いちご白書』の主題歌に影響されたところがあるのでは、という推測を No.35「中島みゆき:時代」に書きました)。
高校生というと、社会への関心が芽生える頃です。中島さんの作品から判断すると、彼女は社会への関心が極めて強いと考えられます(No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」)。極端には "この国は危うい" という詩も書いている(「4.2.3.」という詩。1998年のアルバム「わたしの子供になりなさい」に収録)。そういう社会への関心、社会との関係性で人間を考えるというスタンスは、普通、高校生時代に芽生えるものです。彼女も帯広の高校で学生運動の報道を見聞きしながら、そういった思いを膨らませていったと推測します。
『世情』という詩は、歌手デビュー(1975年)してから3年後(1978年)に、1968年~1970年ごろを振り返って作った作品だと考えられます。
シュプレヒコールの波
しかし作品はあくまで独立したものなので、それを作者の個人史をもとに解釈するのは本来の姿ではありません。そういう解釈は中島さんが嫌う態度でしょう。学生運動のイメージに頼りすぎずに『世情』を詩として解釈するとどうなるかです。解釈のポイントは4回繰り返される、
という部分でしょう。これは詩であって、論理的な文章ではありません。省略されている言葉があるし、また中島さんの詩には二重の意味にとれる言葉が多々あります(言葉の多義性を利用した詩)。上の引用の「変わらない夢」も二重の意味にとれると思います。まず、
という理解があります。これが普通の受け止め方だと想います。ただ、この詩の場合は、
ともとれるでしょう。つまり夢の内容が「変わらないこと」であるという解釈です。こういうニュアンスもあって、シュプレヒコールからの4行をどのように解釈するかは人によって差異が生じて当然です。その差異があるという前提で解釈を書くとすると、
ということでしょう。政治的なニュアンスで表現したとしたら「改革派」と「現状維持派」ということになるのでしょうが、こういう対立は何も政治に限りません。人間社会におけるさまざまな組織やグループにみられるものです。一人の個人の中にもこの二つの思いがあったりする。これはどちらが良いとか悪いとかではなく、普遍的な二項対立です。
これと関連して「変わらない」ということばが出てくる次の部分も重要だと思います。
これをさきほどの「改革派」と「現状維持派」という言葉をあえて使って解釈すると、
という感じでしょうか。ただしこの様に "固定的に" 考えるのはあまりよくないのかも知れません。中島さんの作品には、聴く人のその時の心情によって違うイメージを重ねてもいいような言葉使いがいろいろとあるからです。
ただ、この詩は「シュプレヒコール」に加えて「変わらない」という言葉がキーワードになっていることは確かでしょう。冒頭の1行から「変わっている」という「変わらない」の反対語が出てきます。その直後の「頑固者」は「変わらないもの」と類似の意味の言葉です。さらに、変わることの象徴である「時の流れ」、あるいは省略して「流れ」もこの詩のキーワードになっています。
そして4回繰り返される「シュプレヒコール ~ 戦うため」は、やはり「時の流れを止めようとするもの」との "戦い" へのシンパシーを表現したものだと思います。アルバムを聴くと、中島さんは一番最後の「戦うため」という言葉だけを強く、長く伸ばして歌っているのですが、その歌い方に詩を書いた意図が表されていると思います。
"世情" というタイトル
さらにこの詩には、世の中に関する次のような認識が盛り込まれています。
「シュプレヒコール」「変わらない夢」「変わらないもの」「時の流れ」に加えて、これらすべてが "世情" という言葉でくくられています。この "世情" というタイトルに注目すべきだと思います。"世情" とは「世の中のありさま」とか「世の中の状況」とか「世間一般の人の考えや人情」といった意味です。"世情" は、何らかの価値判断をしている言葉ではなく、いわば無色透明な言葉です。26歳の新進気鋭のシンガー・ソングライターなら、ふつう曲の題名にはしないような、もっと言うとポップ・ミュージックの題名にはそぐわないような言葉です。ちょうど『時代』というタイトルの付け方に似ています。
このタイトルが示しているのは、世の中はこういうもの、という認識でしょう。これはいつの世にもありうる状況を切り取った詩だと思います。はじめに学生運動を想起させると書きましたが、そういう固定的な解釈はそぐわない。「時の流れの中に夢をみるもの」と「時の流れを止める夢を見るもの」の対立は普遍的にあるものだからです。学生運動の記憶がこの詩のきっかけだったかもしれないが(それとて本当かどうか不明です)、この詩が見据えている本質ではありません。
《世情》を他の歌手の方が歌っているのをテレビで視聴したことがあります。その方は強い感情を込め、思い入れたっぷりに、まるで「戦いに破れて挫折した人たちに対する哀悼やエール」のような歌い方をしていました。何だか違和感がありましたね。そういう歌い方をすべき詩なのだろうかと思ったわけです。もちろん "思い入れ" があってもいいのですが、全体としては "世情" についての詩、"世の中の状況" についての詩です。感情をあからさまにせず、どちらかいうと淡々と歌った方がいい。その中から "思い入れ" が滲み出てくるような歌い方 ・・・・・・。アルバムでの中島さんがまさにそうです。
『世情』のような内容の曲を他の歌手がカバーするのは危険だと思います。歌手としてのよほどの力量がないと、本来の姿からねじ曲がってしまう。
やはりポイントは、いつの時代にもいえる普遍性を表現した詩だということです。それが "世情" だと思います。
作曲家:中島みゆき
詩の内容ではないのですが、作曲の面から付け加えたいと思います。4回繰り返される(最後の合唱まで含めると8回繰り返される)、
の部分ですが、ここのメロディーが詩の内容に良くマッチしています。上昇し下降する旋律が、同じリズム(似たリズム)で8回繰り返されるのですが、これが「シュプレヒコールの波」という詩の「波」という言葉と良く合っている。波が幾度となく押し寄せるように、シュプレヒコールが何度も近づき、遠ざかっていく様子が、メロディー・ラインでうまく表現されています。また、モノローグのように始まる最初の部分との対比もよく利いています。
前にも書きましたが、中島作品の評価やコメントにおいて「作曲家・中島みゆき」が語られることは、「歌手」や「詩人」と比較すると少ないと思います。だけど彼女は、歌手、詩人と同程度に、作曲家として優れていると思います。その3つが非常に高いレベルにあり、かつ融合している。この文章を書くために久しぶりに《世情》を聴いてみて、改めてそう思いました。
| 問題出題者は、高級品・高級食材に人々が抱いている暗黙の思いこみを利用して回答者を "引っかけ" ようとする。回答者は思いこみを排し、問題にどんな "罠" が仕掛けられているのかを推測して正解にたどり着こうとする。 |
としました。もちろんここで言う回答者とは「番組の本質が分かっている回答者」であり、そういう回答者ばかりでないのは見ていて良く分かります。そして、久しぶりに見て改めて感じたのは、番組の "フォーマット" の良さです。つまり、
| 回答者を順に Aの部屋とBの部屋に入れ、互いをモニターできるようにし、かつ視聴者は2つの部屋をモニターでき、最後は司会者が正解の部屋の扉を開けることによって正解者が驚喜するという、このテレビ番組のフォーマットが素晴らしい |
のです。このフォーマットがなければ全くつまらない番組になるでしょう。これを発明した人はすごいと思います。日本のテレビ番組のフォーマットは海外に輸出した実績がありますが(料理の鉄人など)、この番組も売れるのではないでしょうか。
今年の「芸能人格付けチェック」はGACKTチームとしてYOSHIKIさんが出演していました。GACKTさんは例によって全問正解で連勝記録を伸ばしていましたが、YOSHIKIさんも全問正解でした。問題の一つのワインのテイスティングでは、YOSHIKIさんが自分の名前の入ったワインを作っていることを初めて知りました。相当なワイン通のようです。GACKTさんが5年越しで説得して番組に出演してもらったそうですが、かなりの "目利き" だと分かっていたからでしょう。単に親しいミュージシャンだからという理由でこの番組への出演を説得するはずがありません。
番組の最後には「ミニ格付けチェック」というコーナーがあって、司会の浜田雅功さんと伊東四朗さんと女性アシスタントが問題に挑戦します。ここで浜田さんが2年連続の「写す価値なし」となってしまいました。そしてこのとき流れた BGM が、中島みゆき《世情》でした。《世情》の "時の流れを止めて" というフレーズが聞こえてきたので、「これ以上 "写す価値なし" にならないで」という意味を重ねたのでしょう。
中島ファンとしては、こんなところで《世情》という名曲を使わないで欲しいと思うのですが(そして単に "言葉尻" をとらえた使い方をして欲しくないと思うのですが)、この曲はかつてTBSのドラマ「3年B組金八先生」で用いられたことがあるので(1981年)、テレビとは縁があるのでしょう。また「芸能人格付けチェック」の制作スタッフの中に中島みゆきの楽曲を熟知している人がいる感じもして、それはそれで良しとしましょう。
今回はその、中島みゆき《世情》についてです。この詩は No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」でも取り上げたのですが、詩の一部だけだったので、改めてこの詩だけにフォーカスして書くことにします。
| なお、中島みゆきさんの詩についての記事の一覧が、No.35「中島みゆき:時代」の「補記2」にあります。 |
中島みゆき 《世情》
《世情》は1978年(中島みゆき 26歳)に発売されたアルバム『愛していると云ってくれ』の最後の収録された曲で、次のような詩です。
|
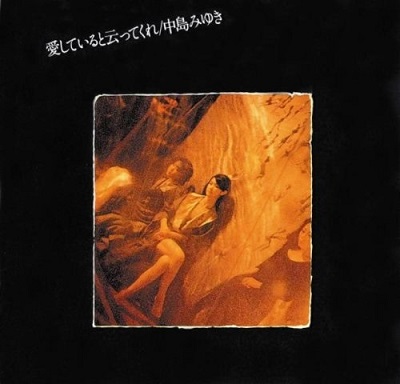
| ||
|
①「元気ですか」 ②怜子 ③わかれうた ④海鳴り ⑤化粧 ⑥ミルク32 ⑦あほう鳥 ⑧おまえの家 ⑨世情
| ||
曲はギターだけで始まり、小さく合唱が出てきて、それがだんだん大きくなったところで中島さんが歌い出します。上の詩が終わったあとのエンディングでは再び合唱が出てきて、「シュプレヒコール ~ 戦うため」の部分がさらに4回繰り返されるうちにフェイドアウトして楽曲が(=アルバムが)終わります。
この詩のキーワードは、4回出てくる "シュプレヒコール" です。誰が聴いてもそう思うはずです。最初と最後に出てくる合唱は、シュプレヒコールをあげながら行進するデモ隊が近づいてきて、通り過ぎていく情景が浮かびます。そして、このキーワードが学生運動を連想させます。詩の中の "学者" という言葉が大学を暗示している。シュプレヒコールは一般にデモ隊が発するものなので限定して考える必要はないのですが、ここでは学生運動を想定することにします。
このアルバムが発売されたのは1978年です。今では「学生運動」は死語に近くなっていますが、1978年当時はその10年前ほどから全国に広がった学生運動のリアルな記憶ある頃でした。そこで、アルバム発売のちょうど10年まえ、1968年に戻ってみます。
1968年からの数年間
1968年の1月です。従来から医者のインターン制度(無給の研修医制度)の改革を要求していた東京大学医学部の学生は、新制度に反対してストライキに突入しました。この中で、医学部教授が長時間拘束されるという事態になりました。3月、医学部は学生17人を退学や停学の処分にします(この中には拘束の現場にいなかった学生もいた)。これが学生たちの怒りに火をつけ、闘争が始まりました。6月、学生たちは東大のシンボルである安田講堂を占拠し立てこもります。そして東大闘争全学共闘会議(全共闘)が組織され、医学部のみならず全学の自治会がストに突入しました。
その後の経緯は紆余曲折があるのですが、結局大学側は翌年の1969年1月に機動隊の出動を要請し、安田講堂の封鎖は解除され、多数の逮捕者を出しました。その安田講堂の "攻防戦" はテレビで全国に大々的に生中継されました。この一連の紛争の結果、東京大学の入学試験が中止されるという前代未聞の事態になりました。1969年4月に東大に入学した人はゼロです。そして1969年から1970年にかけて、大学の改革を要求する学生たちの運動は全国的に波及しました。また1970年は1960年に締結された日米安全保障条約の改定の年であり、いわゆる「70年安保闘争」にもつながっていきました。
| 余談ですが、No.130「中島みゆきの詩(6)メディアと黙示録」に書いたように、評論家・思想家の内田 樹氏は1950年9月生まれなので、順当なら大学入学は1969年4月です。しかし内田さんは1970年4月に東大に入学しています。おそらく東大入試が中止されたので、あえて一浪したのでしょう。入試中止というのは現役で東大を目指していた人にはショックだったでしょうが、一浪して目指していた人にとってはもっとショックだったはずです。 |
1968年というと、日本大学の不正会計に端を発した日大闘争が起きた年です。また、この年には欧米でも学生運動が多発しました。フランスでベトナム戦争反対、大学運営の民主化を要求して大規模なデモとストライキが起こったのも1968年です(5月革命、ないしは5月危機)。またアメリカの学生運動で有名なコロンビア大学闘争も1968年です。ちなみに1968年にはチェコスロバキア(当時)で自由化・民主化を求める「プラハの春」が起きました(ソ連が武力介入して弾圧)。またアメリカの公民権運動の指導者だったキング牧師が暗殺されたのもこの年でした。
そもそも1960年代後半は、アメリカがベトナムに介入したベトナム戦争に反対する市民運動やデモが、アメリカのみならず日本やヨーロッパでも多発していました。もちろん学生たち(あるいは高校生たち)もそこに参加していました。
以上のような1960年代後半の学生運動を描いた映画も作られました。有名なのが、No.35「中島みゆき:時代」で書いた『いちご白書』です。この映画はまさに1968年のコロンビア大学闘争が題材となっていました。『いちご白書』の日本公開は1970年の秋です。
以上の経緯に中島みゆきさんの経歴を重ねるとどうなるでしょうか。中島さんは1952年2月23日生まれです。高校・大学の経歴を各年の4月の時点でみると、
| ◆ | 1968年4月・16歳 高校2年(帯広柏葉高校) | ||
| ◆ | 1969年4月・17歳 高校3年 | ||
| ◆ | 1970年4月・18歳 大学1年(藤女子大学・札幌) |
ということになります。つまり高校1年の3学期に東大闘争がはじまり、高校2年のときに闘争がピークを迎えて安田講堂攻防戦のテレビ生中継があり、高校3年では学生運動が全国に波及し、東大入試がなかった1969年4月の1年後に大学に進学したことになります。『いちご白書』の日本公開は大学1年の秋です(中島さんの『時代』は『いちご白書』の主題歌に影響されたところがあるのでは、という推測を No.35「中島みゆき:時代」に書きました)。
高校生というと、社会への関心が芽生える頃です。中島さんの作品から判断すると、彼女は社会への関心が極めて強いと考えられます(No.67「中島みゆきの詩(4)社会と人間」)。極端には "この国は危うい" という詩も書いている(「4.2.3.」という詩。1998年のアルバム「わたしの子供になりなさい」に収録)。そういう社会への関心、社会との関係性で人間を考えるというスタンスは、普通、高校生時代に芽生えるものです。彼女も帯広の高校で学生運動の報道を見聞きしながら、そういった思いを膨らませていったと推測します。
『世情』という詩は、歌手デビュー(1975年)してから3年後(1978年)に、1968年~1970年ごろを振り返って作った作品だと考えられます。
シュプレヒコールの波
しかし作品はあくまで独立したものなので、それを作者の個人史をもとに解釈するのは本来の姿ではありません。そういう解釈は中島さんが嫌う態度でしょう。学生運動のイメージに頼りすぎずに『世情』を詩として解釈するとどうなるかです。解釈のポイントは4回繰り返される、
|
という部分でしょう。これは詩であって、論理的な文章ではありません。省略されている言葉があるし、また中島さんの詩には二重の意味にとれる言葉が多々あります(言葉の多義性を利用した詩)。上の引用の「変わらない夢」も二重の意味にとれると思います。まず、
| ◆ | 以前からずっと抱いていて、今後も抱くであろう "夢"(=こういう風になりたい、ありたい、との願い) |
という理解があります。これが普通の受け止め方だと想います。ただ、この詩の場合は、
| ◆ | 今の状況のままでありたい、変わらないで欲しいという夢や願い |
ともとれるでしょう。つまり夢の内容が「変わらないこと」であるという解釈です。こういうニュアンスもあって、シュプレヒコールからの4行をどのように解釈するかは人によって差異が生じて当然です。その差異があるという前提で解釈を書くとすると、
| ◆ | 「シュプレヒコールをあげる人たち」が、「別の誰か」と戦っている。 | ||
| ◆ | その「別の誰か」とは、時の流れが止まってほしい、このままであって欲しいという「変わらぬ夢」を見ている人たちである。 | ||
| ◆ | その反対に、シュプレヒコールをあげる人たちの「変わらぬ夢」とは、時の流れを進め、流れに乗って、現状とは違う新しい世界を願う人たちである。 |
ということでしょう。政治的なニュアンスで表現したとしたら「改革派」と「現状維持派」ということになるのでしょうが、こういう対立は何も政治に限りません。人間社会におけるさまざまな組織やグループにみられるものです。一人の個人の中にもこの二つの思いがあったりする。これはどちらが良いとか悪いとかではなく、普遍的な二項対立です。
これと関連して「変わらない」ということばが出てくる次の部分も重要だと思います。
|
これをさきほどの「改革派」と「現状維持派」という言葉をあえて使って解釈すると、
| 改革派は現状維持派を何かにたとえて自らの主張の正当性を言い、その主張が崩れると現状維持派のせいにする |
という感じでしょうか。ただしこの様に "固定的に" 考えるのはあまりよくないのかも知れません。中島さんの作品には、聴く人のその時の心情によって違うイメージを重ねてもいいような言葉使いがいろいろとあるからです。
ただ、この詩は「シュプレヒコール」に加えて「変わらない」という言葉がキーワードになっていることは確かでしょう。冒頭の1行から「変わっている」という「変わらない」の反対語が出てきます。その直後の「頑固者」は「変わらないもの」と類似の意味の言葉です。さらに、変わることの象徴である「時の流れ」、あるいは省略して「流れ」もこの詩のキーワードになっています。
そして4回繰り返される「シュプレヒコール ~ 戦うため」は、やはり「時の流れを止めようとするもの」との "戦い" へのシンパシーを表現したものだと思います。アルバムを聴くと、中島さんは一番最後の「戦うため」という言葉だけを強く、長く伸ばして歌っているのですが、その歌い方に詩を書いた意図が表されていると思います。
"世情" というタイトル
さらにこの詩には、世の中に関する次のような認識が盛り込まれています。
| ・ | 世の中はいつも変化している | ||
| ・ | 頑固者が悲しい思いをする | ||
| ・ | 世の中はとても臆病 | ||
| ・ | 世の中には他愛のない嘘があふれている | ||
| ・ | 他愛のない嘘を指摘して思い上がる人たちがいる(= "学者" と表現されている) |
「シュプレヒコール」「変わらない夢」「変わらないもの」「時の流れ」に加えて、これらすべてが "世情" という言葉でくくられています。この "世情" というタイトルに注目すべきだと思います。"世情" とは「世の中のありさま」とか「世の中の状況」とか「世間一般の人の考えや人情」といった意味です。"世情" は、何らかの価値判断をしている言葉ではなく、いわば無色透明な言葉です。26歳の新進気鋭のシンガー・ソングライターなら、ふつう曲の題名にはしないような、もっと言うとポップ・ミュージックの題名にはそぐわないような言葉です。ちょうど『時代』というタイトルの付け方に似ています。
このタイトルが示しているのは、世の中はこういうもの、という認識でしょう。これはいつの世にもありうる状況を切り取った詩だと思います。はじめに学生運動を想起させると書きましたが、そういう固定的な解釈はそぐわない。「時の流れの中に夢をみるもの」と「時の流れを止める夢を見るもの」の対立は普遍的にあるものだからです。学生運動の記憶がこの詩のきっかけだったかもしれないが(それとて本当かどうか不明です)、この詩が見据えている本質ではありません。
《世情》を他の歌手の方が歌っているのをテレビで視聴したことがあります。その方は強い感情を込め、思い入れたっぷりに、まるで「戦いに破れて挫折した人たちに対する哀悼やエール」のような歌い方をしていました。何だか違和感がありましたね。そういう歌い方をすべき詩なのだろうかと思ったわけです。もちろん "思い入れ" があってもいいのですが、全体としては "世情" についての詩、"世の中の状況" についての詩です。感情をあからさまにせず、どちらかいうと淡々と歌った方がいい。その中から "思い入れ" が滲み出てくるような歌い方 ・・・・・・。アルバムでの中島さんがまさにそうです。
『世情』のような内容の曲を他の歌手がカバーするのは危険だと思います。歌手としてのよほどの力量がないと、本来の姿からねじ曲がってしまう。
やはりポイントは、いつの時代にもいえる普遍性を表現した詩だということです。それが "世情" だと思います。
作曲家:中島みゆき
詩の内容ではないのですが、作曲の面から付け加えたいと思います。4回繰り返される(最後の合唱まで含めると8回繰り返される)、
|
の部分ですが、ここのメロディーが詩の内容に良くマッチしています。上昇し下降する旋律が、同じリズム(似たリズム)で8回繰り返されるのですが、これが「シュプレヒコールの波」という詩の「波」という言葉と良く合っている。波が幾度となく押し寄せるように、シュプレヒコールが何度も近づき、遠ざかっていく様子が、メロディー・ラインでうまく表現されています。また、モノローグのように始まる最初の部分との対比もよく利いています。
前にも書きましたが、中島作品の評価やコメントにおいて「作曲家・中島みゆき」が語られることは、「歌手」や「詩人」と比較すると少ないと思います。だけど彼女は、歌手、詩人と同程度に、作曲家として優れていると思います。その3つが非常に高いレベルにあり、かつ融合している。この文章を書くために久しぶりに《世情》を聴いてみて、改めてそう思いました。
(続く)
2018-03-16 20:22
nice!(0)



