No.144 - 全然OK [文化]
No.139-143 の5回連続で「言葉(日本語)」をテーマに書いたのですが、今回もそれを続けます。今までに書いたのは「言葉が人間の思考と行動に影響を与える」という観点でしたが(No.49, 50, 139, 140, 141, 142, 143)、今回は視点を変えて「言葉の使い方が時とともに変化する」という視点です。その例として、最近の新聞の投書欄に載った「全然」という言葉の使い方を取り上げます。
「全然OK」の表現はOK?
約1ヶ月前の、2015年4月7日の朝日新聞の投書欄に、以下のような投書が掲載されました。
この投書で気になったのは「言葉遣いの乱れ」という一言です。確かに辞書には「全然 + 肯定」を "俗な言い方" と書いてあります(たとえば『広辞苑』第6版)。しかし辞書の "俗な言い方" を「言葉遣いの乱れ」だと言ってしまうと、現代の日本は「言葉が乱れきっている」ことになってしまいます。
「言葉の乱れ」を問題にするときに注意すべきは "文章語"(書き言葉)と "口頭語"(口語。話し言葉)の違いです。口頭語としてはよく使うが、文章語としては使わない言葉(またはその逆の言葉)はたくさんあります。文章語としては使わない口頭語を「言葉の乱れ」とは即断できません。
私は「肯定する使い方の "全然"」に(少なくとも口頭語としては)違和感はないのですが、新潟県・会社員氏は話し言葉としても「変だ」と感じるようです。そして思ったのは、新聞社に投書するほど「肯定する使い方の "全然"」に強い違和感を抱く人がいるという事実です。そして「なぜ朝日新聞がこの投書をわざわざ取り上げたのか」にも興味を抱きました。そのことはあとで分析するとして、まず投書の内容を吟味したいと思います。
新潟県・会社員氏の意見をもう一度まとめると、
ということでしょう。言葉を使う感覚は個人によって違うので、これは一人の意見としては "全くOK" だと思います(全然OKとは、あえて書かないようにします)。
しかし思うのですが、(A)と(B)だけでは "全然" の使い方のすべてを尽くしてはいません。たとえば、
はどうでしょう。話し言葉を想定して例文を作ってみると、
という感じです。こういう使い方について、新潟県・会社員氏は「条件反射のように、おやっ、変だな」と思うか、それとも思わないか、どちらでしょうか。さらに、
はどうでしょう。これも例文を作ってみると、
という感じです。実はこのブログでも過去にこのタイプの「全然」を何回か使っています。
というようにです。
もし新潟県・会社員氏が(B)だけに違和感を感じるなら「肯定的表現に使う "全然" はおかしい」と考えているのであり、そうではなくて(B)(C)(D)のすべてに違和感を感じるなら(A)の「全然・・・・・・ない」という使い方だけが正しい、と考えているわけです。投書からそのどちらかは分かりませんが、人の言葉の感覚は微妙なので、違和感の境目はもっと違うのかもしれません。
しかし歴史的にみると "全然" という言葉は「ない」が続く場合も続かない場合もあったし、また肯定的意味と否定的な意味の両方で使われてきました。つまり(A)(B)(C)(D)の "全てで" 使われてきたわけです。このことを、日本語史が専門の学者の方の本で紹介します。
"全然" の用法
宇都宮大学教授(当時)の小池清治氏の書いた『日本語はどんな言語か』(ちくま新書 1994)に、明治時代からの "全然"(副詞)の使い方が、文学作品からの例を引いて説明されています。ここであげられている例を紹介したいと思います。この中で「情態副詞」「程度副詞」「呼応副詞」という "難しい" 文法用語が出てきますが、言っていることは比較的単純なので、そのまま紹介します。
動作・行為を表す語を修飾し「完全に」「すっかり」「まったく」という意味を与える "全然" の使い方です。
小説の神様と言われた志賀直哉の代表作の一つに『暗夜行路』(1921-1937。大正10-昭和12年)があります。主人公の時任謙作は、幼なじみの愛子に結婚を申し込みますが、なかなか返事をもらえません。そこで謙作は、大阪に赴任している愛子の長兄の慶太郎が東京に帰省している時に電話をかけ、会う約束をとりつけます。愛子の父はすでに亡くなっているので、慶太郎に結婚の返事を聞こうとしたのです(今と違って家同士の結婚です)。ところが行ってみると2人の先客がいました。その時の慶太郎の発言です。
そして後日、慶太郎から断りの手紙がきます。愛子の結婚については先約があると言うのです。その手紙の要約に以下のくだりがあります。
森鷗外に『半日』(1909。明治42年)という短編小説があります。大学教授(文科の博士)とその妻、7才の娘(玉ちゃん)、教授の母親という一家の、ある日の午前中を描いた小説です。奥さんと母親(姑)の折り合いが悪いというのが話のポイントになっていて、食事は教授・娘・母親でとり、奥さんは後で食事をするという状況にまでなっています。要するに、森鷗外の実生活での愚痴を小説化したような作品です。その中の一節です(ルビを付け加えました)。
夏目漱石の『三四郎』(1908。明治41年)の例もあります。次の引用中の「二人」とは、主人公の小川三四郎、および佐々木与次郎のことです。
次の例は、夏目漱石の弟子である芥川龍之介の『羅生門』(1915。大正4年)からの引用で、この小説のいわばクライマックスのところです。
形容詞や形容動詞を修飾し、修飾される言葉が表している「程度がはなはだしい」ことを意味します。夏目漱石は『坊っちゃん』(1906。明治39年)で、以下の引用のように使っています。生徒が悪ふざけで坊っちゃんの宿直の寝床にバッタを入れるという「バッタ事件」を起こすのですが、その生徒の処分についての先生たちの会議の場面です。
ここでの「全然悪い」は、地の文ではなく会話の中に出てきます。つまり最低限言えることは、「全然悪い」を東京人(坊っちゃん)が口頭語(口語)として使うのは自然だと、漱石が思っていたということです。
「全然・・・・・・ない」というように、打消しを表す「ない」と "呼応" する("ない" という陳述部を予告する)使い方です。
芥川龍之介の『戯作三昧』(1917。大正6年)は、江戸時代の天保年間の滝沢馬琴を主人公としています。下の引用は銭湯での会話ですが、彼とは馬琴、近江屋平吉とは発句が趣味の小間物屋、「性に合はない」とは「発句が性に合はない」という意味です。
以上のような「全然」の使い方を、小池教授は次のように総括しています。
なぜ「誤用」という人がいるのか
そこで疑問が生じます。
というような「全然」の使い方の中で、
という疑問です。最初に紹介した投書を書いた人はもちろんですが、投書を採用した朝日新聞の編集部も「誤用」と考えているからこそ、日本語を正しく使おうという「問題提起」のために掲載したわけです(おそらく)。この疑問に答える記事を書いているのが(投書を掲載した朝日新聞ではなく)日本経済新聞です。その内容を次に紹介します。
「全然いい」は誤用、という迷信
日本経済新聞・電子版(PC版)に「ことばオンライン」とい連載記事があります(トップページ → ライフ → くらし → ことばオンライン)。この中の記事で「全然いい」は誤用、という説が広まった経緯が報告されています。
の二つの記事です。これを読むと、まず、2011年12月13日の記事の先頭に、
とあります。なるほど。上で紹介した小池清治教授(日本語史)の『日本語はどんな言語か』にも、あたりまえのように否定を伴う場合・伴わない場合の事例が書かれていたのですが、これは「国語研究者の常識」なのですね。朝日新聞編集部では "非・常識" のようですが。
記事によると、国立国語研究所の新野・准教授を中心とする研究班は、この「迷信」がいつ頃に広まったのかを研究し、2011年10月22日の日本語学会で発表しました。研究班は、昭和10年代(1935-1944)における日本の代表的な国語学・国語教育の研究誌、3誌に研究者が書いた論文・記事を網羅的に調べ、「全然」がどういう使い方をされているのかを調査しました。その結果が次の表です。
ちなみに「肯定を伴う」のところの、①~④の例文を作ってみると、
となるでしょう。この表で一目瞭然なのは、
ということです。この調査のポイントは「国語学者が、専門誌上で、本来の用法からはずれた言葉の使い方をするはずがない」ということですね。それはそうでしょう。「あいつは国語学者のくせに言葉の使い方を知らない」と "後ろ指" を指されたくないでしょうから・・・・・・。従ってこの表にみられる「全然」の使い方は、昭和10年代に「標準語として正しい」と考えられていたものと推測できます。
このうち、④の「肯定的な全然」については、高名な国語学者も使っているようです。記事(2011.12.13)には、
という「全然」の使用例があげられていました。ちなみに、このブログで「全然違っている」という使い方をしたと上の方に書きましたが、これは②に相当し、昭和10年代から続く伝統的な日本語の使い方であったわけです。
一方、昭和28年~昭和29年(1953-1954)に学術誌「言語生活」(筑摩書房)に「最近 "全然" が正しく使われていない、"全然"は本来否定を伴う」といった趣旨の記事が集中的にみられます。このことから研究班は、
と結論づけています。研究班は、規範意識が急速に広まった理由については「今後の研究」としたのですが、この理由を探るべく各年代の国語辞書の記述を調査した方がいます。日本経済新聞 電子版「ことばオンライン」(2012.6.26)から紹介します。
「全然」についての辞書の記述
日本近代語研究会・会長の飛田良文氏(元、国立国語研究所)は、明治から現代までの代表的な辞書における「全然」の使い方を調べました。それが次の表です。
「全然」と打消しとの呼応について、この調査の結果を要約すると次のようになります。
この調査は「昭和20年代の後半に "全然" は打消しを伴うとの規範意識が、世の中に急速に広まった」とする国立国語研究所の推定と一致してます。
ちなみに「全然いい」は新しい使い方、という「例解新国語辞典(1984)」の記述から強く推測できることは、「全然+肯定」という使い方が「最近」広まってきたが、これは本来の使い方ではないという意見が30年以上前から(1984年以前から)あっただろう、ということですね。
流行語や外来語は別にして、一般に "日本語の乱れ" を指摘する言説には、一定のパターンがあります。
というパターンです。「② 本来の使い方ではない」と言いたいがために「① 最近、目立つ」を持ち出すわけです。「昔から使われているが、正しい日本語ではない」では論理的に破綻します。「言葉の実態がずっとそうであったのなら、それは "正しい言葉" だろう」となるからです。ところが実は「・・・・・・」は昔から綿々とある言い方だったり、明治時代から使われていたりすることがある。「全然」ががまさにそのケースです。
ちなみに "①最近「・・・・・・」との言い方が目立つ" のところは "①若い人に「・・・・・・」との言い方が目立つ" になることが多々あり、これも典型的な「日本語の乱れ批判パターン」となっています。
この文章の冒頭から順に「文芸作品での使用例」「昭和10年代の国語雑誌の調査」「明治以来の国語辞書の調査」の3つを取り上げました。これらをまとめると、
ということだと思います。そして飛田良文氏は「全然+肯定」は誤用だという "規範意識" を広めたのは辞書だという「仮説」を述べています。
『ローマ字で引く国語新辞典』
さらに、日本経済新聞 電子版の記事では、ちょっと意外な事実が明らかにされています。最初に「必ず打消しを伴う」とした 1952年(昭和27年)の『辞海』の1ヶ月前に『ローマ字で引く国語新辞典』(研究社。1952)が刊行されたのですが、そこでは「全然」について、
と説明されているのです。「必ず打消しを伴う」とした『辞海』ほど強い規則ではないのですが、この辞書が、日本の辞書で初めて "打消しとの呼応" に触れ、かつ語義を2つに分類し、「全然+肯定」を "崩れた用法" としたのです。この辞書の編纂には英文学者の福原麟太郎が参加しており、日本語の語義に英語を対応させています。辞書を調査した飛田良文氏は次のように言っています。
飛田良文氏は、福原麟太郎が「全然」を英語「not at all」と「wholly」に対訳した、とだけ言っているのですが、これはどういう理由からでしょうか。なぜ、打消しを伴う場合とそうでない場合の2つに語義を分けたのでしょうか。
『ローマ字で引く国語新辞典』の編集方針はかなりユニークです。まず見出し語をヘボン式のローマ字表記にしたことです。これについては『ローマ字で引く国語新辞典』の初版のカバーに次のように解説されています。
今では想像しにくいのですが、当時は旧仮名遣いと新仮名遣いの問題がありました。つまり、現代の「言う」の発音は iu ですが、当時の文字表記は「言う」と「言ふ」(旧仮名遣い)の両方がありうるわけで、それを平仮名にすると「いう」と「いふ」になり、あいうえお順では離れた位置に配置されることになります。もし、新仮名遣いで配列された辞書で iu と発音する単語を旧仮名遣いの「いふ」で引こうとすると混乱します。ローマ字で見出しを配列するということは「発音で見出しを配列する」ということで、これはこれで意味があるわけです。ちなみに、ローマ字見出しの国語辞書はそれ以前にもありました。
この辞書が真にユニークなのは、国文学者(山岸徳平)だけでなく、英文学者の福原麟太郎が辞典の編纂に加わり、日本語の語義解説のあとに相当する英語を記述したことです。全然についていうと (not) at all と wholly です。この理由については、初版のカバーに、
とあります。これはかなりユニークな辞書の編纂方針ですが、この方針は果たして妥当なのでしょうか。簡単な和英辞典として使えるために、というのなら分からないでもないのですが、「日本語を正確に理解するために英語に訳す」というのは明らかに話が逆です。その「話が逆」が顕著になったのが「全然」の語義解説だと思うのです。
必ず英語を付加するという制約のもとに、日本語の副詞である「全然」の語義解説を書こうとしたらどうなるでしょうか。「まったく」「すっかり」「完全に」という意味の英語の副詞を考えてみると、
などが浮かびます。このうち at all は否定と相性のいい言葉です。
というようにです。at all を肯定に使う場合もあるようですが、それこそ崩れた用法です(辞書にはない)。辞書にある否定文以外の使い方は、疑問文や if 節ですが、たとえば疑問文では、
のように、日本語の「全然」とは違った意味になります。at all が日本語の「全然」に相当するのは否定文で使われるときだけなのです。
一方、wholly / completely は肯定文に使います。
というようにです。ところが at all と違って、wholly / completely を否定文に使うと、今度は日本語の「全然」と同じ意味にはならないのです。
を、学校の英語のテストで「彼女は全然満足しなかった」と訳したら、先生はここぞとばかりに × にするでしょう。これは英文法でいう「部分否定」であって「彼女は完全には満足しなかった」という意味です。満足した部分もあったが、完全に満足したわけではなかった。学校英文法では、この「部分否定」がかなり丁寧に説明してあったと記憶しています。
このような背景から「最近似の英語句」をつけるという前提で「全然」の語義を一つで説明しようとすると困ったことになります。つまり、
とすると「全然+肯定」のケースが at all には当てはまらなくなります。しかし、だからと言って、
とすると、今度は「打消しと呼応する全然」が wholly では表せなくなります。not wholly は部分否定であって「全然・・・・・・ない」(=完全否定)ではないからです。つまり「最近似の英語句を対応させた」とは言えなくなる。
従って英語と対応させるという前提である限り、全然の語義を「打消しが伴う場合」と「肯定が続く場合」の2つに分けざるを得なくなります。英語を熟知した人ほどそう思うでしょう。もちろん辞典の編纂者の一人である福原麟太郎は、日本の英文学学会の会長までつとめた、英語に精通した学者です。
英語には「否定文に使うと "全然" と同じ意味になる言葉」(at all)と、「肯定文に使うと "全然" と同じ意味になる言葉」(wholly / completely など)がある・・・・・・。『ローマ字で引く国語新辞典』は日本で初めて「全然」を2つの語義に分けた辞書ですが、その「分けた」理由は英語にあったのです。「全然」という言葉の語義のルーツ(の一つ)をたどっていくと、英語の「完全否定」と「部分否定」の違いが関係してくる・・・・・・。これはまったく意外な話なのですが、太平洋戦争の敗戦直後である昭和20年代という時代の気分が背景にあるのでしょう。
しかし『ローマ字で引く国語新辞典』は語義を2つに分けただけでなく「打消しを伴う全然」が「普通」としています。また、1ヶ月後に刊行された『辞海』は「必ず打消しを伴う」としています。この規範意識がなぜ生まれたのか、それはまだ解明されていません。
その研究手段として、飛田良文氏は前に引用したところで「英和辞典や和英辞典を調べたりするなどの研究を進めれば」と言っています。ここで暗に匂わされているのは、英和辞典ないしは和英辞典に影響された可能性です。そうなのかもしれません。英語に影響されて「全然」を「(not) at all」と同一視したということも考えられると思います。
言葉は進化する
「全然」という言葉が使われてきた歴史から言えることは、
ということだと思います。もちろん、はやり言葉、流行語、外来語などを除いた「基本語としての言葉」についてです。
「言葉」は「文化」を構成する最大の要素だと思いますが、新規性や革新を取り入れると同時に「積み重ねで進化する」のが文化であり、言葉だと思います。
この記事の本文で
との主旨を書きました。しかし30年以上前どころか少なくとも50年以上前からあったようです。そのことが分かる新聞記事を引用します。この記事は No.145「とても嬉しい」で引用したものですが「全然+肯定」に言及しているので、その部分を再掲します。朝日新聞社の記者(ないしは校閲関係の人)が書いたと推測されるコラム記事です。原文に下線はありません。
ちなみにこのコラム記事が掲載された日付は、東海道新幹線の開業(1964.10.1)と東京オリンピックの開幕(1964.10.10)の間にあたります。
ブログの記事本文に書いたように「全然+肯定は誤用という迷信」が広まったのは昭和20年代後半(1950年~1954年)と推定されるのでした。上記の朝日新聞の記事はそれから10年程度たっていて、そのときすでに「全然+肯定はとんでもない使い方だ」と非難する "年寄りたち" がいたことになります。しかしその "年寄りたち" が10代~50代の頃は「全然+肯定」が正しい言葉として使われていた(使っていた)わけです。
以上をまとめると、
わけです。朝日新聞に投書された方は49歳なので、その方が生まれる前から延々と続いているということになります。まさに世代を越えて迷信が受け継がれているわけです。今後もまだ続くのでしょう。
「全然OK」の表現はOK?
約1ヶ月前の、2015年4月7日の朝日新聞の投書欄に、以下のような投書が掲載されました。
|
この投書で気になったのは「言葉遣いの乱れ」という一言です。確かに辞書には「全然 + 肯定」を "俗な言い方" と書いてあります(たとえば『広辞苑』第6版)。しかし辞書の "俗な言い方" を「言葉遣いの乱れ」だと言ってしまうと、現代の日本は「言葉が乱れきっている」ことになってしまいます。
「言葉の乱れ」を問題にするときに注意すべきは "文章語"(書き言葉)と "口頭語"(口語。話し言葉)の違いです。口頭語としてはよく使うが、文章語としては使わない言葉(またはその逆の言葉)はたくさんあります。文章語としては使わない口頭語を「言葉の乱れ」とは即断できません。
私は「肯定する使い方の "全然"」に(少なくとも口頭語としては)違和感はないのですが、新潟県・会社員氏は話し言葉としても「変だ」と感じるようです。そして思ったのは、新聞社に投書するほど「肯定する使い方の "全然"」に強い違和感を抱く人がいるという事実です。そして「なぜ朝日新聞がこの投書をわざわざ取り上げたのか」にも興味を抱きました。そのことはあとで分析するとして、まず投書の内容を吟味したいと思います。
新潟県・会社員氏の意見をもう一度まとめると、
| "全然" の本来の使い方は「全然・・・・・・ない」という使い方である。 | |||
| 「全然・・・・・・ない」という形ではなく、かつ "全然" のあとに肯定的なニュアンスの言葉、たとえば大丈夫、平気、おもしろい、おいしい、OK、良い、などを続けるのは "全然" の本来の使い方ではなく、違和感を感じる。これは日本語の乱れの一つである。 |
ということでしょう。言葉を使う感覚は個人によって違うので、これは一人の意見としては "全くOK" だと思います(全然OKとは、あえて書かないようにします)。
しかし思うのですが、(A)と(B)だけでは "全然" の使い方のすべてを尽くしてはいません。たとえば、
| 「全然・・・・・・ない」という形ではなく、かつ "全然" のあとに否定的なニュアンスの言葉、たとえば「駄目(だめ)」とか「悪い」などを続ける使い方 |
はどうでしょう。話し言葉を想定して例文を作ってみると、
| ・ | そんなバットの構え方ではボールにかすりもしない。全然だめだ。 | ||
| ・ | そりゃあ、彼の方が全然悪いと思うよ。 |
という感じです。こういう使い方について、新潟県・会社員氏は「条件反射のように、おやっ、変だな」と思うか、それとも思わないか、どちらでしょうか。さらに、
| 「全然・・・・・・ない」という形ではなく、"全然" のあとに肯定的とも否定的とも言えない "相違" を表す言葉、たとえば「違う」や「別」を続ける使い方 |
はどうでしょう。これも例文を作ってみると、
| ・ | 彼が趣味の陶芸にうち込んでいる時の表情は真剣そのもので、目つきも普段とは全然違った。 | ||
| ・ | 彼はいわゆる「プロの経営者」であり、全然別の業種の社長を4回も経験している。 |
という感じです。実はこのブログでも過去にこのタイプの「全然」を何回か使っています。
|
というようにです。
もし新潟県・会社員氏が(B)だけに違和感を感じるなら「肯定的表現に使う "全然" はおかしい」と考えているのであり、そうではなくて(B)(C)(D)のすべてに違和感を感じるなら(A)の「全然・・・・・・ない」という使い方だけが正しい、と考えているわけです。投書からそのどちらかは分かりませんが、人の言葉の感覚は微妙なので、違和感の境目はもっと違うのかもしれません。
しかし歴史的にみると "全然" という言葉は「ない」が続く場合も続かない場合もあったし、また肯定的意味と否定的な意味の両方で使われてきました。つまり(A)(B)(C)(D)の "全てで" 使われてきたわけです。このことを、日本語史が専門の学者の方の本で紹介します。
"全然" の用法
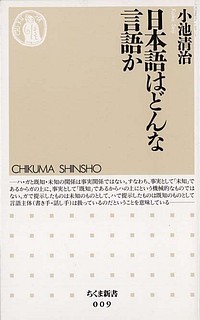
| |||
|
小池清治
「日本語はどんな言語か」 (ちくま新書 1994) | |||
| 以下の引用で下線は原文にはありません。また引用のうちの2点は「青空文庫」から引用しました。「青空文庫」に結集されている方々に感謝します。 |
| 情態副詞としての "全然" |
動作・行為を表す語を修飾し「完全に」「すっかり」「まったく」という意味を与える "全然" の使い方です。
小説の神様と言われた志賀直哉の代表作の一つに『暗夜行路』(1921-1937。大正10-昭和12年)があります。主人公の時任謙作は、幼なじみの愛子に結婚を申し込みますが、なかなか返事をもらえません。そこで謙作は、大阪に赴任している愛子の長兄の慶太郎が東京に帰省している時に電話をかけ、会う約束をとりつけます。愛子の父はすでに亡くなっているので、慶太郎に結婚の返事を聞こうとしたのです(今と違って家同士の結婚です)。ところが行ってみると2人の先客がいました。その時の慶太郎の発言です。
|
そして後日、慶太郎から断りの手紙がきます。愛子の結婚については先約があると言うのです。その手紙の要約に以下のくだりがあります。
|
森鷗外に『半日』(1909。明治42年)という短編小説があります。大学教授(文科の博士)とその妻、7才の娘(玉ちゃん)、教授の母親という一家の、ある日の午前中を描いた小説です。奥さんと母親(姑)の折り合いが悪いというのが話のポイントになっていて、食事は教授・娘・母親でとり、奥さんは後で食事をするという状況にまでなっています。要するに、森鷗外の実生活での愚痴を小説化したような作品です。その中の一節です(ルビを付け加えました)。
|
夏目漱石の『三四郎』(1908。明治41年)の例もあります。次の引用中の「二人」とは、主人公の小川三四郎、および佐々木与次郎のことです。
|
次の例は、夏目漱石の弟子である芥川龍之介の『羅生門』(1915。大正4年)からの引用で、この小説のいわばクライマックスのところです。
|
| 程度副詞としての "全然" |
形容詞や形容動詞を修飾し、修飾される言葉が表している「程度がはなはだしい」ことを意味します。夏目漱石は『坊っちゃん』(1906。明治39年)で、以下の引用のように使っています。生徒が悪ふざけで坊っちゃんの宿直の寝床にバッタを入れるという「バッタ事件」を起こすのですが、その生徒の処分についての先生たちの会議の場面です。
|
ここでの「全然悪い」は、地の文ではなく会話の中に出てきます。つまり最低限言えることは、「全然悪い」を東京人(坊っちゃん)が口頭語(口語)として使うのは自然だと、漱石が思っていたということです。
| 呼応副詞としての "全然" |
「全然・・・・・・ない」というように、打消しを表す「ない」と "呼応" する("ない" という陳述部を予告する)使い方です。
芥川龍之介の『戯作三昧』(1917。大正6年)は、江戸時代の天保年間の滝沢馬琴を主人公としています。下の引用は銭湯での会話ですが、彼とは馬琴、近江屋平吉とは発句が趣味の小間物屋、「性に合はない」とは「発句が性に合はない」という意味です。
|
以上のような「全然」の使い方を、小池教授は次のように総括しています。
|
なぜ「誤用」という人がいるのか
そこで疑問が生じます。
| ・ | 全然伝わらない(呼応副詞) | ||
| ・ | 全然悪い | ||
| ・ | 全然失敗した |
というような「全然」の使い方の中で、
| 「全然」は呼応副詞(例:全然伝わらない)というように使うのが一般的ではあるが、形容詞の程度を強めたり(全然悪い)、"完全に"という意味(例:全然失敗した)でも使われる とは考えずに、 | |||
| 「全然」は呼応副詞(例:全然伝わらない)として使うのが正しい日本語であり、その他の用法は誤用である と考える人がいるのはなぜか |
という疑問です。最初に紹介した投書を書いた人はもちろんですが、投書を採用した朝日新聞の編集部も「誤用」と考えているからこそ、日本語を正しく使おうという「問題提起」のために掲載したわけです(おそらく)。この疑問に答える記事を書いているのが(投書を掲載した朝日新聞ではなく)日本経済新聞です。その内容を次に紹介します。
「全然いい」は誤用、という迷信
日本経済新聞・電子版(PC版)に「ことばオンライン」とい連載記事があります(トップページ → ライフ → くらし → ことばオンライン)。この中の記事で「全然いい」は誤用、という説が広まった経緯が報告されています。
| ◆ | なぜ広まった?「『全然いい』は誤用」という迷信(2011.12.13) | ||
| ◆ | 「『全然いい』は誤用」という迷信 辞書が広めた?(2012.6.26) |
の二つの記事です。これを読むと、まず、2011年12月13日の記事の先頭に、
| 「全然は本来否定をともなうべき副詞である」というのは国語史上の迷信であることが、研究者の間では常識 |
とあります。なるほど。上で紹介した小池清治教授(日本語史)の『日本語はどんな言語か』にも、あたりまえのように否定を伴う場合・伴わない場合の事例が書かれていたのですが、これは「国語研究者の常識」なのですね。朝日新聞編集部では "非・常識" のようですが。
記事によると、国立国語研究所の新野・准教授を中心とする研究班は、この「迷信」がいつ頃に広まったのかを研究し、2011年10月22日の日本語学会で発表しました。研究班は、昭和10年代(1935-1944)における日本の代表的な国語学・国語教育の研究誌、3誌に研究者が書いた論文・記事を網羅的に調べ、「全然」がどういう使い方をされているのかを調査しました。その結果が次の表です。
|
昭和10年代の代表的な国語学誌・国語教育誌、 3誌における "全然" の使い方 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
日本経済新聞・電子版「ことばオンライン」(2011.12.13)より引用(一部簡略化)。 調査対象は「コトバ」「綴り方学校」「日本語」の3つの国語研究誌。 |
||||||||||||||||||||||||||||
ちなみに「肯定を伴う」のところの、①~④の例文を作ってみると、
| ① | 全然不愉快だ。 | ||
| ② | 全然違う。 | ||
| ③ | 全然駄目だ。 | ||
| ④ | 全然いい。 |
となるでしょう。この表で一目瞭然なのは、
| ◆ | 全体の6割(590例のうち354例)は否定語を伴わず、 | ||
| ◆ | そのうちの約4分の1(354例のうちの85例)は「否定的意味やマイナス評価でない語」を伴う |
ということです。この調査のポイントは「国語学者が、専門誌上で、本来の用法からはずれた言葉の使い方をするはずがない」ということですね。それはそうでしょう。「あいつは国語学者のくせに言葉の使い方を知らない」と "後ろ指" を指されたくないでしょうから・・・・・・。従ってこの表にみられる「全然」の使い方は、昭和10年代に「標準語として正しい」と考えられていたものと推測できます。
このうち、④の「肯定的な全然」については、高名な国語学者も使っているようです。記事(2011.12.13)には、
|
という「全然」の使用例があげられていました。ちなみに、このブログで「全然違っている」という使い方をしたと上の方に書きましたが、これは②に相当し、昭和10年代から続く伝統的な日本語の使い方であったわけです。
一方、昭和28年~昭和29年(1953-1954)に学術誌「言語生活」(筑摩書房)に「最近 "全然" が正しく使われていない、"全然"は本来否定を伴う」といった趣旨の記事が集中的にみられます。このことから研究班は、
| "全然"は本来否定を伴うべきだという、言葉の使用実態とはかけ離れた「規範意識」が、昭和20年代後半に急速に広まった |
と結論づけています。研究班は、規範意識が急速に広まった理由については「今後の研究」としたのですが、この理由を探るべく各年代の国語辞書の記述を調査した方がいます。日本経済新聞 電子版「ことばオンライン」(2012.6.26)から紹介します。
「全然」についての辞書の記述
日本近代語研究会・会長の飛田良文氏(元、国立国語研究所)は、明治から現代までの代表的な辞書における「全然」の使い方を調べました。それが次の表です。
「全然」に関する主な辞書(初版本)の語義記述
| 刊年 | 書名(発行元) | 打消との 呼応 | "全然いい" への判断 | ||
| 1907 | 明治40 | 辞林(三省堂書店) | 1 | 無 | |
| 1908 | 明治41 | ことばの泉補遺(大倉書店) | 1 | 無 | |
| 1911 | 明治44 | 辞林44年版(三省堂書店) | 1 | 無 | |
| 1912 | 明治45 | 大辞典(嵩山堂) | 1 | 無 | |
| 1912 | 大正1 | 新式辞典(大倉書店) | 1 | 無 | |
| 1915 | 大正4 | ローマ字で引く国語辞典(冨山房) | 1 | 無 | |
| 1916 | 大正5 | 発音横引国語辞典(京華堂) | 1 | 無 | |
| 1916 | 大正5 | 袖珍国語辞典(有朋堂) | 1 | 無 | |
| 1917 | 大正6 | ABCびき日本辞典(三省堂) | 1 | 無 | |
| 1917 | 大正6 | 大日本国語辞典(金港堂/冨山房) | 1 | 無 | |
| 1934 | 昭和9 | 大言海(冨山房) | 1 | 無 | |
| 1935 | 昭和10 | 大辞典(平凡社) | 1 | 無 | |
| 1935 | 昭和10 | 辞苑(博文館) | 1 | 無 | |
| 1938 | 昭和13 | 言苑(博文館) | 1 | 無 | |
| 1943 | 昭和18 | 明解国語辞典(三省堂) | 1 | 無 | |
| 1952 | 昭和27 | ローマ字で引く国語新辞典(研究社) | 2 | 有 | (注3) |
| 1952 | 昭和27 | 辞海(三省堂) | 1 | 有 | |
| 1955 | 昭和30 | 広辞苑(岩波書店) | 1 | 無 | (注4) |
| 1956 | 昭和31 | 例解国語辞典(中教出版) | 2 | 有 | 俗語 |
| 1956 | 昭和31 | 角川国語辞典(角川書店) | 1 | 有 | |
| 1958 | 昭和33 | 旺文社版学生国語辞典(旺文社) | 1 | 有 | |
| 1959 | 昭和34 | 新選国語辞典(小学館) | 1 | 有 | |
| 1960 | 昭和35 | 三省堂国語辞典(三省堂) | 2 | 無 | [俗] |
| 1963 | 昭和38 | 岩波国語辞典(岩波書店) | 1 | 有 | くずれた用法 |
| 1965 | 昭和40 | 新潮国語辞典(新潮社) | 1 | 有 | |
| 1966 | 昭和41 | 講談社国語辞典(講談社) | 1 | 有 | |
| 1972 | 昭和47 | 新明解国語辞典(三省堂) | 1 | 有 | 俗に |
| 1973 | 昭和48 | 角川国語中辞典(角川書店) | 2 | 有 | [俗に] |
| 日本国語大辞典12巻(小学館) | 3 | 有 | (口頭語で) | ||
| 1978 | 昭和53 | 学研国語大辞典(学習研究社) | 3 | 有 | [俗] |
| 1981 | 昭和56 | 角川新国語辞典(角川書店) | 2 | 有 | [俗] |
| 1984 | 昭和59 | 例解新国語辞典(三省堂) | 1 | 有 | 新しい使い方 |
| 1985 | 昭和60 | 新潮現代国語辞典(新潮社) | 2 | 有 | |
| 1985 | 昭和60 | 現代国語例解辞典(小学館) | 1 | 有 | 俗に |
| 1986 | 昭和61 | 言泉(小学館) | 1 | 有 | 俗語的 |
| 1988 | 昭和63 | 大辞林(三省堂) | 3 | 有 | 俗な言い方 |
| 1988 | 昭和63 | 三省堂現代国語辞典(三省堂) | 3 | 有 | [俗] |
| 1989 | 平成1 | 福武国語辞典(福武書店) | 2 | 有 | |
| 1993 | 平成5 | 集英社国語辞典(集英社) | 1 | 有 | 俗に |
| 1995 | 平成7 | 角川必携国語辞典(角川書店) | 1 | 有 | 俗な言い方 |
| 1995 | 平成7 | 大辞泉(小学館) | 3 | 有 | 俗な言い方 |
| 2002 | 平成14 | 明鏡国語辞典(大修館書店) | 3 | 有 | [俗] |
| 2005 | 平成17 | 小学館日本語新辞典(小学館) | 2 | 有 | 俗に |
| 飛田良文氏の調査を基に日経新聞電子版が作成した表(2012.6.26)を引用した。色付けや(注)は引用者。 | |||
| 濃い色は「必ず(正しくは)打消しと対応」か「全然いいは俗用」としている辞書。 | |||
| 語義で「下に打消しを伴わない」のを「くずれた用法」と記述している。 | |||
| 最新版の「広辞苑 第6版」では、肯定的に使う全然を「俗な用法」としている。 |
「全然」と打消しとの呼応について、この調査の結果を要約すると次のようになります。
| ◆ | 明治時代から昭和10年代までに発行された代表的な辞書においては、そもそも「全然・・・・・・ない」といった "打消しとの呼応" について触れているものが全くない。1907年(明治40年)から1943年(昭和18年)に発行された15種の辞書すべてがそうである。 | ||
| ◆ | 1952年(昭和27年)刊行の『辞海』(三省堂。金田一京助編)において初めて「下必ずに打消を伴う」と記述された。これ以降、「必ず打消しを伴う」とする辞書や、必ずとはしないまでも「全然+肯定」を「俗用」や「崩れた用法」とした辞書が増えていく。 | ||
| ◆ | 1952年(昭和27年)から2005年(平成17年)までに発行された28種の辞書では、26種が "打消しとの呼応" について触れており、このうち3種は "必ず(正しくは)打消しと呼応" とし、19種は「全然いい」を "俗な言い方"、"崩れた言い方"、"口頭語" などとしている。 | ||
| ◆ | 『例解新国語辞典』(三省堂 1984 昭和59)に至っては「全然いい」を「新しい使い方」としている。 |
この調査は「昭和20年代の後半に "全然" は打消しを伴うとの規範意識が、世の中に急速に広まった」とする国立国語研究所の推定と一致してます。
ちなみに「全然いい」は新しい使い方、という「例解新国語辞典(1984)」の記述から強く推測できることは、「全然+肯定」という使い方が「最近」広まってきたが、これは本来の使い方ではないという意見が30年以上前から(1984年以前から)あっただろう、ということですね。
流行語や外来語は別にして、一般に "日本語の乱れ" を指摘する言説には、一定のパターンがあります。
| ① | 最近(または、このごろ)「・・・・・・」との言い方が目立つ。 | ||
| ② | これは日本語本来の使い方ではない。 | ||
| ③ | 正しい日本語を使おう。 |
というパターンです。「② 本来の使い方ではない」と言いたいがために「① 最近、目立つ」を持ち出すわけです。「昔から使われているが、正しい日本語ではない」では論理的に破綻します。「言葉の実態がずっとそうであったのなら、それは "正しい言葉" だろう」となるからです。ところが実は「・・・・・・」は昔から綿々とある言い方だったり、明治時代から使われていたりすることがある。「全然」ががまさにそのケースです。
ちなみに "①最近「・・・・・・」との言い方が目立つ" のところは "①若い人に「・・・・・・」との言い方が目立つ" になることが多々あり、これも典型的な「日本語の乱れ批判パターン」となっています。
この文章の冒頭から順に「文芸作品での使用例」「昭和10年代の国語雑誌の調査」「明治以来の国語辞書の調査」の3つを取り上げました。これらをまとめると、
| ◆ | 「全然+肯定」は明治時代から綿々と、途切れることがなく使われてきた。もちろん、時代によってメジャーな使い方は変化した。 | ||
| ◆ | ところが(理由は明らかではないが)昭和20年代後半から「全然+肯定」は誤用だという規範意識が広まった。 | ||
| ◆ | しかしその規範意識は言語の実態を無視したものであった。従って「規範意識」が「言語の実態」を駆逐することはなかった。 | ||
| ◆ | その状況が長く続き「全然+肯定」は誤用という意見が折りに触れて言われるようになった。それが今でも(朝日新聞の投書欄のように)続いている。 |
ということだと思います。そして飛田良文氏は「全然+肯定」は誤用だという "規範意識" を広めたのは辞書だという「仮説」を述べています。
|
『ローマ字で引く国語新辞典』
さらに、日本経済新聞 電子版の記事では、ちょっと意外な事実が明らかにされています。最初に「必ず打消しを伴う」とした 1952年(昭和27年)の『辞海』の1ヶ月前に『ローマ字で引く国語新辞典』(研究社。1952)が刊行されたのですが、そこでは「全然」について、
| 全く、まるで(普通、下に打消を伴う) [(not) at all] (例)全然見当がつかない。 | |||
| すっかり、全く(前者のくずれた用法で、下に打消を伴わない) [wholly] (例)全然間違っている。 |
と説明されているのです。「必ず打消しを伴う」とした『辞海』ほど強い規則ではないのですが、この辞書が、日本の辞書で初めて "打消しとの呼応" に触れ、かつ語義を2つに分類し、「全然+肯定」を "崩れた用法" としたのです。この辞書の編纂には英文学者の福原麟太郎が参加しており、日本語の語義に英語を対応させています。辞書を調査した飛田良文氏は次のように言っています。
|
飛田良文氏は、福原麟太郎が「全然」を英語「not at all」と「wholly」に対訳した、とだけ言っているのですが、これはどういう理由からでしょうか。なぜ、打消しを伴う場合とそうでない場合の2つに語義を分けたのでしょうか。
『ローマ字で引く国語新辞典』の編集方針はかなりユニークです。まず見出し語をヘボン式のローマ字表記にしたことです。これについては『ローマ字で引く国語新辞典』の初版のカバーに次のように解説されています。
|

| |||
|
「ローマ字で引く国語新辞典」
(研究社 1952。復刻版) | |||
この辞書が真にユニークなのは、国文学者(山岸徳平)だけでなく、英文学者の福原麟太郎が辞典の編纂に加わり、日本語の語義解説のあとに相当する英語を記述したことです。全然についていうと (not) at all と wholly です。この理由については、初版のカバーに、
|
とあります。これはかなりユニークな辞書の編纂方針ですが、この方針は果たして妥当なのでしょうか。簡単な和英辞典として使えるために、というのなら分からないでもないのですが、「日本語を正確に理解するために英語に訳す」というのは明らかに話が逆です。その「話が逆」が顕著になったのが「全然」の語義解説だと思うのです。
必ず英語を付加するという制約のもとに、日本語の副詞である「全然」の語義解説を書こうとしたらどうなるでしょうか。「まったく」「すっかり」「完全に」という意味の英語の副詞を考えてみると、
| at all, wholly, completely |
などが浮かびます。このうち at all は否定と相性のいい言葉です。
| She was not satisfied at all. (彼女は全然満足しなかった) |
というようにです。at all を肯定に使う場合もあるようですが、それこそ崩れた用法です(辞書にはない)。辞書にある否定文以外の使い方は、疑問文や if 節ですが、たとえば疑問文では、
| Is there any truth at all ?
(そこに少しでも真実があるのか?) |
のように、日本語の「全然」とは違った意味になります。at all が日本語の「全然」に相当するのは否定文で使われるときだけなのです。
一方、wholly / completely は肯定文に使います。
| She was wholly satisfied. (彼女は完全に満足した) |
というようにです。ところが at all と違って、wholly / completely を否定文に使うと、今度は日本語の「全然」と同じ意味にはならないのです。
| She was not completely satisfied. |
を、学校の英語のテストで「彼女は全然満足しなかった」と訳したら、先生はここぞとばかりに × にするでしょう。これは英文法でいう「部分否定」であって「彼女は完全には満足しなかった」という意味です。満足した部分もあったが、完全に満足したわけではなかった。学校英文法では、この「部分否定」がかなり丁寧に説明してあったと記憶しています。
このような背景から「最近似の英語句」をつけるという前提で「全然」の語義を一つで説明しようとすると困ったことになります。つまり、
| zenzen(全然) まったく、すっかり、完全に、の意味 [at all] |
とすると「全然+肯定」のケースが at all には当てはまらなくなります。しかし、だからと言って、
| zenzen(全然) まったく、すっかり、完全に、の意味 [wholly] |
とすると、今度は「打消しと呼応する全然」が wholly では表せなくなります。not wholly は部分否定であって「全然・・・・・・ない」(=完全否定)ではないからです。つまり「最近似の英語句を対応させた」とは言えなくなる。
従って英語と対応させるという前提である限り、全然の語義を「打消しが伴う場合」と「肯定が続く場合」の2つに分けざるを得なくなります。英語を熟知した人ほどそう思うでしょう。もちろん辞典の編纂者の一人である福原麟太郎は、日本の英文学学会の会長までつとめた、英語に精通した学者です。
英語には「否定文に使うと "全然" と同じ意味になる言葉」(at all)と、「肯定文に使うと "全然" と同じ意味になる言葉」(wholly / completely など)がある・・・・・・。『ローマ字で引く国語新辞典』は日本で初めて「全然」を2つの語義に分けた辞書ですが、その「分けた」理由は英語にあったのです。「全然」という言葉の語義のルーツ(の一つ)をたどっていくと、英語の「完全否定」と「部分否定」の違いが関係してくる・・・・・・。これはまったく意外な話なのですが、太平洋戦争の敗戦直後である昭和20年代という時代の気分が背景にあるのでしょう。
しかし『ローマ字で引く国語新辞典』は語義を2つに分けただけでなく「打消しを伴う全然」が「普通」としています。また、1ヶ月後に刊行された『辞海』は「必ず打消しを伴う」としています。この規範意識がなぜ生まれたのか、それはまだ解明されていません。
その研究手段として、飛田良文氏は前に引用したところで「英和辞典や和英辞典を調べたりするなどの研究を進めれば」と言っています。ここで暗に匂わされているのは、英和辞典ないしは和英辞典に影響された可能性です。そうなのかもしれません。英語に影響されて「全然」を「(not) at all」と同一視したということも考えられると思います。
言葉は進化する
「全然」という言葉が使われてきた歴史から言えることは、
| ◆ | 言葉の使い方が「正しい」「正しくない」という「規範意識」は時代とともに変わる。しかも10-20年というレベルで、かなり急に変わることがある。 | ||
| ◆ | しかし言葉が使われている実態は、そう急には変化しない。言葉の使用実態は「積み重なって」進化する。 |
ということだと思います。もちろん、はやり言葉、流行語、外来語などを除いた「基本語としての言葉」についてです。
「言葉」は「文化」を構成する最大の要素だと思いますが、新規性や革新を取り入れると同時に「積み重ねで進化する」のが文化であり、言葉だと思います。
(次回に続く)
| 補記 |
この記事の本文で
| 「最近、全然+肯定という使い方が広まってきたが、これは本来の使い方ではない」という意見が30年以上前からあったと推定できる |
との主旨を書きました。しかし30年以上前どころか少なくとも50年以上前からあったようです。そのことが分かる新聞記事を引用します。この記事は No.145「とても嬉しい」で引用したものですが「全然+肯定」に言及しているので、その部分を再掲します。朝日新聞社の記者(ないしは校閲関係の人)が書いたと推測されるコラム記事です。原文に下線はありません。
|
ちなみにこのコラム記事が掲載された日付は、東海道新幹線の開業(1964.10.1)と東京オリンピックの開幕(1964.10.10)の間にあたります。
ブログの記事本文に書いたように「全然+肯定は誤用という迷信」が広まったのは昭和20年代後半(1950年~1954年)と推定されるのでした。上記の朝日新聞の記事はそれから10年程度たっていて、そのときすでに「全然+肯定はとんでもない使い方だ」と非難する "年寄りたち" がいたことになります。しかしその "年寄りたち" が10代~50代の頃は「全然+肯定」が正しい言葉として使われていた(使っていた)わけです。
以上をまとめると、
「全然+肯定」に関して
|
わけです。朝日新聞に投書された方は49歳なので、その方が生まれる前から延々と続いているということになります。まさに世代を越えて迷信が受け継がれているわけです。今後もまだ続くのでしょう。
2015-05-08 21:35
nice!(0)
トラックバック(0)



