No.143 - 日本語による科学(2) [文化]
(前回より続く)
分類学は分類の科学である(ドーキンス)
英語の "高級語彙" は普通の人には分かりにくい(前回参照)という事情から、英米の科学者が一般向けに書いた本の日本語訳を読んでいると、ときどき「あれっ」と思う表現に出会うことがあります。
リチャード・ドーキンス(1941 - )は英国の進化生物学者・動物行動学者で、世界的に大変著名な方です。特に、著書である『利己的な遺伝子』(1976)はベストセラーになりました。これは巧みな比喩を駆使して現代の進化学を概説した本です。その続編の一つが『ブラインド・ウォッチメーカー』(1986)ですが、この本の中に次のような一節が出てきます。
|
「分類学は分類の科学である」とは、分かりきったことを言う奇妙な文章です。しかし原文に当たってみるとその理由が分かります。
|

| |||
|
リチャード・ドーキンス
「ブラインド・ウォッチメーカー」 (早川書房 1993初版) | |||
この文章のあとの方に出てくる "タクシダーミー(taxidermy, 剥製術)" は、日本語の意味は明快ですが、英語としては taxonomy に輪をかけて難しい言葉です。この言葉を知っている普通の日本人はいないだろうし、英米人も非常に少ないはずです。普通、博物館にある「剥製」は stuffed animals とか stuffed birds と言うからです。そういう日常語と taxidermy は全く結びつかない。ではなぜドーキンスは「taxonomy が taxidermy と混同されている」と書いているのでしょうか。そんなことありえないはずなのに。
これはドーキンス流のウィットだと思われます。辞書を引くと taxonomy の taxo- も taxidermy の taxi- もギリシャ語の taxis に由来していて、「配列」「順序」「整理」という意味だとあります。まさに前回にもあった「ギリシャ語由来の造語要素」なのです。博覧強記のドーキンスはそれを理解していて「混同」という "ありえないこと" を書いたのでしょう(たぶん)。
余談になりますが、ドーキンスという人は科学(彼の場合は進化学)のキモのところを適切な自然言語(英語)に置き換えてイメージ膨らませる技に長けています。The Selfish Gene(利己的な遺伝子)という題も、遺伝子を擬人化した selfish(利己的)という言葉を使って、現代進化論の基礎をうまく言い表しています。
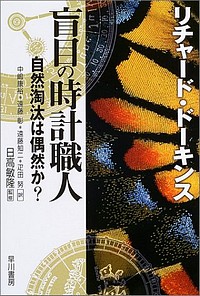
| |||
|
リチャード・ドーキンス
「盲目の時計職人」 (早川書房 2004新版) | |||
この本の日本語訳を「ブラインド・ウォッチメーカー」とするのは、全くいただけません。"ブラインド" も "ウォッチメーカー" も一般的なカタカナ英語ではないし、"ブラインド"は別の意味の言葉として一般的です。「盲目の時計職人」の方がよほといい。この本の訳者は、言葉(自然言語)が持つ「イメージの喚起力」が理解できていなかったようです。著者のドーキンスは科学における言葉の重要性を十分に理解して題をつけているというのに ・・・・・・。
なお、このことを反省したのか、2004年に「盲目の時計職人」と改題され、新装版で発売されました。本の表紙を見ただけで、なじみのある日本語(漢字)が持つイメージの喚起力が明白です。それは前回に紹介したように、鈴木・慶応大学名誉教授が強調していることでした。
漢字による造語のデメリット
今まで造語要素としての漢字の意義を書いてきたのですが、漢字による造語と引き替えに同音異義語が多数発生したことは確かです。特に「同じジャンルやカテゴリーの同音意義語」が混乱のもとになる。典型的なのは「しりつ(市立)」と「しりつ(私立)」ですね。学校の経営主体を表す用語が同音だと、言い分けをせざるを得なくなります。
何か売り買いするという「売」と「買」が同じ音であるのも、同じカテゴリーなので混乱のもとです。従って「ばいしゅん(売春)」と「ばいしゅん(買春)」というように区別せざえるを得なくなります。そもそも「日本語による科学」というテーマの、その「かがく(科学)」と「かがく(化学)」が同じカテゴリーの同音意義語なのです。
しかし考えてみると、日本語の音節の数は100程度であり、これは世界の言語の中でも極めて数が少ない方です。英語は数千から(数え方によっては)1万以上と言われています。日本語で同音意義語が発生するのはやむをえないとも言えるでしょう。さらに、同音意義語と言えども「同じジャンルでない同音意義語は意外と問題にならない」とも言えます。
また漢字の問題点として、アルファベットに比べると数が多いため(文科省の常用漢字だけで約2136字)、印刷物の作成が大変だ(素人にはむずかしい)ということがありました。しかしこれは、コンピュータ技術の発展で劇的に変わりました。いわゆる「日本語ワープロ」の発達と、その後のパソコンの「ワープロ・ソフト」の普及です。今やワープロという言葉は死語になっていて、パソコンやスマホを使う人は各種アプリの入力画面で、ごく自然に日本語入力をしています。
| ちなみに、松尾義之氏の『日本語の科学が世界を変える』(以下『前掲書』)に指摘してあるのですが、韓国はハングル優先で漢字を棄てました。これは韓国の将来にとって良いことなのか悪いことなのか。100年・200年というレンジで考えたときに禍根を残すことになるやしれません。漢字が広まった東アジア文化圏ではベトナムも漢字を捨てました。本家本元の中国(および台湾)と日本だけが漢字に固執している。 つまり日本は「中国語とは全く違う言語体系でありながら、なおかつ漢字=表意文字を使っている国」です。漢字はもともと中国からの輸入品ですが、完全に日本化しています。これこそが日本文化の独自性の最大のものの一つだと思います。これを生かさない手はないのです。 さらに補足すると、漢字は「偏」や「つくり」という「文字を構成する部品」が意味をもっていることが多いわけです。正確に言うと、漢字は「表意部品文字」です。 |
日本語で科学する
科学における日本語環境(もっと広くは、学問、政治、経済、社会全般の日本語)を作る上で漢字が果たした役割の話が長くなりました。それを含めて「日本語と科学」について、前回(No.142 - 日本語による科学(1))から今までの議論を振り返ってまとめると、以下のようになります。
| ◆ | 科学の領域では、日本語で思考することがマイナス要因にはならない
| |||||
| ◆ | 日本語で論理的思考が十分に可能である
| |||||
| ◆ | 日本語で最先端の研究ができるまでになれる「日本語環境」が揃っている
| |||||
| ◆ | 音読みと訓読みの二重構造をもつ日本の漢字が、科学における日本語環境(学術用語・科学用語)を作り上げる上で多大な貢献をした |
この最後の点に関して、前回(No.142 - 日本語による科学(1))で何度か引用した鈴木・慶應義塾大学名誉教授は、次のように言っています。
|
この鈴木教授( = 言語学者)のコメントと類似性を感じるのが、物理学者のハイゼンベルクの考えです。ハイゼンベルク(1901-1976)は、現代物理学の基礎となっている量子力学を作りあげた一人で、20世紀の理論物理学の巨人です。彼は『現代物理学の思想』で、言葉( = 自然言語)と物理学の探求の関係を次のように言っています。
|
関係代名詞をそのまま訳したような、分かりにくい日本語訳ですが、要約すると、
| 自然言語は知識を発展させる土台となる安定した言語である。それはリアリティと直結しているからこそ安定している。 |
ということです。自然言語に対比されるのが「科学言語」で、それは数式や化学式、論理式のたぐいです(特に物理学においては数式)。さらにハイゼンベルクは次のように述べています。
|

| |||
|
ハイゼンベルク
「現代物理学の思想」(新版) (みすず書房。1967初版) | |||
| 日常使う、リアルなイメージをもった言葉による「理解」の重要性 |
です。引用した二人の文章に共通しているのは「安定」というキーワードですね。安定した言葉による知的活動の重要性を、二人は言いたかったのだと思います。
ハイゼンベルクの言葉には、さらに二つのキーワードがあります。一つは「リアリティ」です。これは外界の事物、社会概念、身体感覚、感情などのすべて指していると思います。もう一つは、自然言語が「漠然と定義されている」ということです。かみ砕いて言うと、自然言語のもつ「曖昧性」と「多義性」だと思います。言葉の意味は境界線が厳密に引かれているわけではないし、一つの言葉は多様な意味に使われる。実は「リアリティ」にもとづくからこそ、自然言語には曖昧性・多義性があるのです。「リアリティ」は変化するし、人によってとらえ方が違う。「リアリティ」にもとづかない、たとえば数学用語などはいくらでも厳密に、一意に定義できます(そうでないとまずい)。さらに、曖昧性や多義性があるからこそ、自然言語は安定していると言えます。言葉のコアの意味を保持しつつ、「リアリティ」の変化や解釈の相違に柔軟に追従していける。最も安定した建造物とは、大地の揺れに最も "しなやかに" 追従できる建物(例:五重の塔)、という事実に似ています。
「リアリティ」に根拠をもち、曖昧性・多義性があり、かつ安定している自然言語を用いるからこそ、人間は深く考えられるし、新たな発想を生み出せる・・・・・・。ハイゼンベルクの言葉はそう解釈できると思います。そしてこのような性質を強くもった自然言語とは「母語」であることは言うまでもないでしょう。外国語として習得した言語では(外国で生活しているのでない限り)限界がある。それが「母語で考える」ことの意味だと思います。
ところで、ハイゼンベルクは言葉と科学の関係について、さらに次のように述べています。
|
「極東( = 日本)の文化的伝統があったからこそ、日本の学者は理論物理学に大きな貢献ができたのではないか」という主旨の推測(ないしは仮説、予想)ですが、次にこのことを考えてみたいと思います。
「日本語による科学」は有利か
「日本語による科学」が「マイナス要因にはならない」ということを通り越して「積極的に有利だ」ということがあるのでしょうか。
これは非常に難しい質問です。というのは、仮に日本語が有利だ(有利な面がある)としても、それを証拠とともに証明することは困難だと考えられるからです。益川博士がもしアメリカで生まれて英語環境で育っていたらノーベル賞をとれたか、というような質問には答えられません。
また仮に「日本語による科学」が他言語(たとえば英語)より有利な面があるとしたら、「英語による科学」も日本語より有利なことがあると想定できます。人間の思考の道具となっている言語の違いが発想の違いを生むはずだからです。
以上を踏まえつつ「日本語による科学は有利か」ということを考えてみると、一つは鈴木名誉教授が指摘する、漢字の造語要素としての優秀性でしょう。つまり「日常卑近な、生活のレベルに必要な安定したことばと、抽象度の高い高級な概念とを連結する、真に貴重な言語媒体としての漢字」(著書より再度引用)です。
これ以外に「有利」と想定できる要素が日本語にあるでしょうか。それを示唆する話が、松尾義之・著『日本語の科学が世界を変える』にあります。それは、「日本語には英語で表現しきれない科学の概念がある」という指摘で、その一つが「物性」という言葉です。
|
日本における物理学の領域を研究対象のスケールに応じて大まかに分けると「素粒子」「物性」「地球物理」「宇宙物理」というのが一般的でしょう。特に「物性」の研究者が多い。この「物性」が日本語独自の概念だというのは、ちょっと意外です。
さらに別の科学概念の話を、松尾氏は編集者としての経験から書いています。
|
「生き物らしさ」が英語では表現できない、とは重要な指摘だと思います。もし、ある日本の研究者がいて「私のライフワークは生き物らしさの追求だ、すべての研究はそこに繋がるようにしよう」と思ったとしたら、そういう研究者は日本以外にはいないことになるからです。その研究者を突き動かしているのは、実は「言葉」なのではないでしょうか。
| ちなみに「生物の必須条件でありながら、しなやかな漠然とした一面も含んだ特徴」という「生き物らしさ」の "定義" で直感的に連想するのが、No.69-70「自己と非自己の科学」で述べた人間の免疫(獲得免疫)のシステムですね。免疫は生物に必須の精緻なシステムですが、同時に柔軟で、冗長で、かつ曖昧なものでした。 |
さきほどの「物性」もそうです。私の専門は「物性」だと意識している研究者は、もちろん個々の研究は物性の中の極く一部なのだろうけれども、折に触れて「物性という間口の広い視野」で思索にふけるでしょう。東京大学の物性研究所に集結している科学者たちは、一人一人の研究分野は狭いはずですが、研究所仲間の内部情報に自然に接しているはずです。その内部情報は、物性という、英語化できない日本語によってひとくくりにされた情報なのです。
言葉は人間の思考と行動に影響を与えます。そのことを軽く考えてはならいと思います。
日本語こそ武器
以上のことから推測できることがあります。英語では表現し難い日本語の科学概念があるということは、英語にも日本語にしにくい科学概念があるだろう、ということです。そう考えるのが自然です。
そして、ここまでくると気づくのは、日本の科学者は日本語と英語の科学概念の両方に接している、という事実です。前回(No.142 - 日本語による科学(1))の冒頭の益川博士のインタビューにあったように、日本の科学者は英語論文を読まないと研究ができません。もちろん英語と日本語の科学概念は、同一意味内容のものが大多数でしょう。科学なのだから、そうでないとまずいわけです。しかし「生き物らしさ」にみられるように「日常語に近い概念や思考方法を表すことば」や「まだ世界的にも定まっていない新しい概念」は、言語による微妙な相違が多いのではないでしょうか。
日本の科学者は、科学の探求において日本語と英語の両方に接している・・・・・・。これとは全く対照的なのがアメリカ生まれのアメリカ人科学者です。アメリカの科学者は最も自国内に「引きこもる」率が高いと言われています。日本人科学者はよくアメリカに留学するが、アメリカ人科学者はあまり外国に留学したりしない。なぜなら、自国で世界最先端の研究に接することが十分にできるからです。しかも生まれてから研究生活までずっと英語です。すべてが英語でこと足りるのです。
以上のような考察からすると、日本人科学者にとって英語は必要条件だが十分条件ではないと言えるでしょう。英語をいくら頑張ってみても「よくできたとして英米人なみ」なのです。著書を引用した科学ジャーナリストの松尾義之氏は、次のように表現しています。
|
これは「そこにしかないもの、その人しかできないことがまずあり、それをいかに強みに転化できるかが勝負である」という、世の中の通例と同じだと思います。それは国の経済発展から地方再生まで、さらには個人の社会に対する貢献までを貫いている原理です。
日本語の将来:ハンディキャップの克服
前にワープロの発明が日本語のハンディキャップを劇的に解消した、その証拠にワープロという言葉自体が死語になってしまった、と言いました。このように、技術で日本語のハンディキャップを解消する努力は今後も続くはずです。この面で将来あたりまえになるだろうと確信できるのが「日本語・英語の自動同時通訳」です。自動同時通訳に必要な要素技術は、
| ① | 音声認識 | ||
| ② | 自然言語認識(文脈解析) | ||
| ③ | 自動翻訳 | ||
| ④ | 音声合成 | ||
| ⑤ | 以上を超高速に処理する技術 |
などですが、すでにGoogleなどでは無料の自動翻訳ができます。Googleの翻訳が使いものになるかどうかは議論があると思いますが、ビジネス・ユースの有料の翻訳ソフトはもっと精度が高い。専門用語の辞書も各種揃っています。また、スマホに向かってしゃべれば答えを返してくれるところまできている。
② ③は、いわゆる人工知能(AI)の研究の一分野ですが、人工知能研究は最近急激に進歩しています。IBMの「ワトソン」というコンピュータはクイズ番組で人間に勝ったことで有名ですが、日本の大手銀行ではコールセンターの質問回答業務に「ワトソン」の導入が始まりました。
日本でも国立情報学研究所の新井紀子教授が主導する「ロボットは東大に入れるか?」プロジェクト(略称:東ロボ)が有名です。ロボットに東大入試問題を解かせようとするプロジェクトですが、これが20年前なら新井教授は「正気ではない」と見なされたでしょう。ちなみに、東ロボ君が完成するということは「東大入試レベルの英文和訳と和文英訳が、合格点をとれる程度に、機械で可能になる」ということです。東ロボ君が英語を「捨てて」いるのなら別ですが。
最近の人工知能研究の発展は、大量のサンプル・データを集め、それを "機械学習" でコンピュータに学習させる手法の進歩に負うところが大きい。「日本語・英語の自動同時通訳」でも、今後「プロによる同時通訳のデータ蓄積」がものすごく貴重になると思います。日本の文部科学省も「科学技術立国・日本」を標榜するなら、小学校での英語教育だけでなく「日本語・英語 自動同時通訳」の研究開発を主導してもらいたいと思います。これは日本しかできない(日本しか絶対にやらない)研究です。
実用性の高い「日本語・英語の自動同時通訳」が将来できることは確実だと思います。そうなったとき、日本人は改めて "何が本当に貴重なのか" に気づくと思います。
日本語論の必要性
現在までに多くの「日本語論」が書かれてきましたが、そのほとんどは文科系の学者や評論家、作家などによるものであり、対象とする日本語は「普段使いの日本語」か、文芸作品(小説、評論、詩歌など)がほとんどでした。これはこれでよいのですが、問題は、学問を探求する言葉としての日本語、特に科学技術を探求する言葉としての日本語を論じた日本語論がほとんどないことです。この視点からの日本語論は「科学技術立国・日本」としては、十分、論ずるに値すると思います。
今の日本には「カタカナ英語」や「カタカナの英語もどき」が氾濫しています。ジャーナリズム、官庁の文書、スポーツ、ファッション、サービス業、ブランド名などに蔓延している。これらの中には十分日本語で表現可能なものが多々あります。
マスメディアは今だに「交ぜ書き」をしていますね。「腹腔鏡手術」を「腹くう鏡手術」( = NHK)とあえて書く意味は何かあるのでしょうか(2010-2014年に群馬大学病院で肝臓切除手術を受けた8人が死亡した事件などの報道)。漢字にルビを振ることなど、今の技術では簡単です。「ふくくうきょう」でカナ漢字変換すれば一発で「腹腔鏡」と出てくる時代です(たった今その操作をしました)。マスメディアが時代錯誤なことを続けていると「腔」という字がもつ「体に関係したことで何らかの空洞を示す」というイメージが失われていくでしょう。漢字は "偏" や "つくり" に意味があることが多く、つまり「表意部品文字」でもあるのです。「腔」を学校で教えなくても、また書けなくてもかまいません。見たときに音と意味が分かればいいのです。これは「腔」という字の問題でなく「一事が万事」ということです。
こういったジャーナリズムはさておき、せめて科学技術の世界だけは、英語を英語として尊重にすると同時に、日本の科学技術の武器としての日本語を大切にして欲しいと思います。新しい科学の概念が出てきたら、漢字の造語機能を生かして新しい語を創り出し、日本語で深く考える環境を維持して欲しいと思うわけです。
「科学する言葉としての日本語論」に、今後期待したいと思います。
2015-04-25 18:29
nice!(1)
トラックバック(0)



