No.120 -「不在」という伝染病(2) [科学]
(前回より続く)
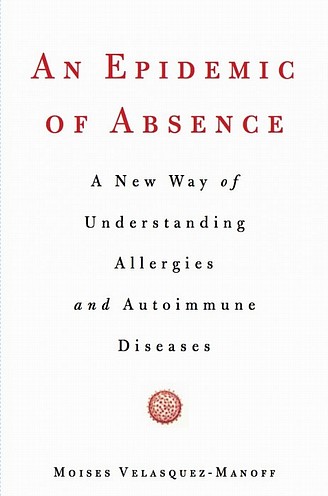
21世紀の免疫学の発見
21世紀の免疫学の発見は、免疫の発動を制御し抑制する細胞群が発見されたことです。この代表が、大阪大学の坂口教授が発見した制御性T細胞です。免疫を抑制する細胞群があることは20世紀の免疫学でも仮説としてはありました。しかし実験的に立証されたのは21世紀(1990年代後半以降)です。
制御性T細胞は、生後、外界からの微生物や寄生虫に接触することで発現します。かつ、腸内細菌が制御性T細胞の発現に関わっていることも分かってきました。この制御性T細胞がアレルギーの発症を抑制しているのです。
東京大学の新幸二博士、本田賢也博士の研究成果があります。両博士は、特定の腸内細菌をターゲットとする抗生物質を使って、特定種の腸内細菌を徐々に減らすという実験をマウスで行いました。この結果、
| ・ | 抗生物質のバンコマイシンで腸内細菌のクロストリジウム属を徐々に減らすと、 | ||
| ・ | ある時点で制御性T細胞が急減し、 | ||
| ・ | それがクローン病(炎症性腸疾患)の発症を招く |
ことを発見しました。クロストリジウム属を増やすと制御性T細胞は回復し、炎症も治まります。これは特定の腸内細菌が制御性T細胞の誘導(未分化のT細胞を制御性T細胞に変化させる)に重要な役割をもっていることを実証しています。なお、クロストリジウム属の話は、No.119「不在」という伝染病(1)の冒頭近くで引用した日経サイエンス 2012年10月号の記事に出てきました。
『寄生虫なき病』には載っていませんが、No.70「自己と非自己の科学(2)」で紹介した「日経サイエンス 2012年10月号」の記事には、別の研究が紹介されていました。そこには、
|
20世紀の免疫学(No.69-70 参照)では、免疫系が自己を攻撃しない理由として、
| ・ | 全ての細胞には自己を示す標識(= MHC)がついている。 | ||
| ・ | 自己に反応する免疫細胞は、胸線(Thymus)で死滅する。 |
と説明されていました。しかしそれだけではなく、制御性T細胞という重要なプレーヤーがいたのです。
ではなぜ、腸内細菌が制御性T細胞を発現させるのでしょうか。それを理解するキーワードは「共生」です。共生の基本ルールは
| 宿主から容認されている共生者は、宿主の免疫抑制機構を作動させる(= 免疫寛容を引き出す)ことによって排除を免れている |
というものです。この「ルール」が、人体の免疫機構と微生物を結びつけます。前に「アレルゲンとなるタンパク質は寄生虫のタンパク質と似ている」と書きましたが(No.119)、その理由は、
| 寄生虫は制御性T細胞を増やし、免疫寛容を引き出す。しかし花粉などのタンパク質にそのような機能はない。だから免疫の過剰反応が起きる。 |
と理解できます。
ヒトには免疫を抑制する機構があり、それはヒトが微生物と共生していることを前提に成り立っています。その免疫抑制機構の弱体化は免疫関連疾患を招きます。なぜ弱体化するかというと、本来の共生していた微生物が人体からいなくなってしまったため、ないしは微生物相が大きく変化してしまったためです。なぜ微生物が人体からいなくなった(変化した)のか。
それはもちろん生まれてから子供時代にかけて微生物が少ない環境で育つようになったからですが、別の理由もあります。
一つは抗生物質の多用です。さきほどあげた東京大学の新博士・本田博士の研究でも分かるように、抗生物質は腸内の細菌相を変化させます。抗生物質の多用は人間にとって良くない結果を招く(可能性がある)のです。
化学物質の問題もあります。抗菌剤やハンド・ローション、洗剤などは、人間と共生している(有益な)常在菌を消失・減少させます。これらの多用でアレルギーの発生リスクが増えるという研究が多数あります。
その化学物質のひとつは医薬品です。広く使用されている鎮痛剤・アセトアミノフェンは、アレルギー疾患との関係を繰り返し指摘されています。原因と結果が逆(喘息を発症する子供は、幼い頃から病弱でアセトアミノフェンの服用機会が多かった)の可能性がないわけではないので、今後の実証が待たれます。
食生活の変化もあります。工場で作られ、殺菌された出来合いの食品(=工業製品)ばかりを食べていると、微生物に接する機会が減少します。ないしは腸内微生物の様相が変化してしまう。新鮮な食材を包丁とまな板で調理して料理を作る(その間に微生物が入る)のとは大違いです。
21世紀の免疫学の知識からすると、20世紀後半からの先進国は、免疫関連疾患を増やすように動いてきたことがわかります。ということは、20世紀後半、特に1990年代に確立した免疫学は、
| 少なくともヒトの免疫に関しては、本来あるべき姿からかけ離れた姿を研究対象にしてきたのではないか |
という疑問にもつながるのです。
最初に説明したように、免疫関連疾患は「現代病」です。その「現代病」は、免疫関連疾患だけではありません。本書には、心臓疾患や自閉症、うつ病、(ある種の)ガン、肥満なども、免疫系の異常が関係しているのではという「疑い」が書かれています。もちろん実証されたわけではなく、今後の研究を待つ必要があります。ただ、こういった「現代病」ないしは「文明病」は、免疫との関係を疑ってかかるべきなのです。
ピロリ菌は悪玉菌か善玉菌か
本書に書かれているピロリ菌の話も、人間と微生物の共生という観点から大変興味深いものです。人間の消化器官で共生している常在菌の多くは小腸にいますが、ピロリ菌は胃に住みつきます。胃は強い酸性なので、微生物にとっては悪い生息環境と言えます。
ピロリ菌は胃潰瘍と胃ガンの原因になることが発見され、大変「有名」になりました。ピロリ菌が原因の胃潰瘍と診断されれば、ピロリ菌除去の治療をうけるのが普通です。
しかし胃潰瘍はともかく、胃ガンは60歳台以降の高齢者に多い病気です。人間が60歳台以降まで生きるのがあたりまえになったのは近代以降のことであり、それまではピロリ菌が人間に決定的なダメージを与えることは少なかったと推測できます。
事実、ピロリ菌とヒトとの関係は極めて古いことが分かってきました。世界各地のピロリ菌を遺伝子解析で比較した結果、ピロリ菌の主要7種の菌株は全てアフリカ起源であることが分かりました。また遺伝子解析によると、7種が最初に枝分かれしたのは5万8000年前です。ということは、ピロリ菌は現世人類の出現とともにあった、ということになります。このことは、ピロリ菌がヒトに何らかのメリット与えてきたことを示唆しています。
調べてみると、ピロリ菌の感染者は「胃食道逆流症」(その一つの病態が逆流性食道炎)の有病率が低く、また食道ガンも少ないことが分かってきました。なぜそうなるのかと言うと、胃の酸性度が強くなると、ピロリ菌は胃壁からの胃液の分泌を妨害するからです。だから胃液が逆流しても食道に炎症が起きにくい。ピロリ菌はヒトの胃の酸性度を調節していることになります。さらに、
| ・ | ピロリ菌に感染している人は、結核菌に感染しても発病しにくい。ピロリ菌は免疫系の抗細菌作用を増大させる。 なお、常在菌と結核の発病の関係については、No.121 「結核はなぜ大流行したのか」を参照。 | ||
| ・ | ピロリ菌感染者は制御性T細胞の数が多く、喘息のリスクも低下する |
という研究も出てきました。また、
| ・ | 乳幼児の段階でピロリ菌に感染すると、胃潰瘍や胃ガンのリスクが低い |
という観察結果もあります。「乳幼児の段階でピロリ菌に感染する」というのは、まさに現在の発展途上国の状況です。アフリカはピロリ菌に感染している人が多いところですが、アフリカで胃潰瘍や胃ガンが極度に少ない(いわゆる「アフリカの謎」)理由も納得できます。ピロリ菌は善玉菌か悪玉菌か・・・・・・。それは感染するタイミングにもよるということです。
人間という「超個体」
本書に次の言葉が引用されています。
|
「共生微生物群」という言葉が出てきます。この記事の最初に書いた「常在菌」とほぼ同じ意味ですが、寄生虫などの細菌以外のものも含む共生生物全体を示すものと考えてよいと思います。以下、病原菌に対応する言葉として常在菌(病原性を示さない共生細菌)ということにし、微生物全体は「共生微生物群」と言うことにします。
ヒトは、自然界の微生物の中から「選択して」共生微生物群を作りあげてきました。たとえば、細菌は分類学上、50以上の「門」に分かれますが、ヒトに住みついている常在菌はそのうちの4門だけです。
一方、「ヒトと関係のある細菌」という観点からすると、常在菌は約1000種もありますが、病原菌は50~100種しかありません。ヒトと「友好関係にある」細菌の方が圧倒的に多いのです。その常在菌の中には、明らかにヒトに役だっているものがあります。
| ◆ | 人体にとって重要な「葉酸」や「ビタミンK」を合成する。 | ||
| ◆ | オリゴ糖や多糖類を分解し、消化を助ける。 | ||
| ◆ | 免疫を制御する。 |
などです。なぜヒトは常在菌と共生し、しかも合成・消化・免疫といった重要な機能を常在菌に「分担させる」のでしょうか。
それは微生物と共生するのが有利だからです。
微生物は繁殖のペースがヒトより格段に速いので、進化のペースも速いわけです。従ってヒトが微生物を攻撃しても、微生物は遺伝子変異を繰り返して攻撃から逃れる可能性が高い。どうせ排除できないのなら共存したらどうか。もし共存できたとしたら、微生物の進化が速いことがヒトのメリットになりうる。つまり、ヒトは自分の遺伝子の変化だけに頼るよりも遙かに柔軟に「変化」できることになります。生物にとって最も重要なのは、環境(気候や、食物や、病原菌など)の変化に柔軟に対応できることです。
さらに常在菌は種類が多く、その総体としての遺伝子の数が多い。この記事の最初の方に「消化器官にいる微生物の遺伝子の総数は330万個で、ヒトゲノムの遺伝子2万~2万5000個の約150倍に相当する」と書きましたが(No.119 参照)、消化器官だけをとってみても、こういった「遺伝子の多さ」をヒトは利用できるわけです。
常在菌は進化のスピードが早く、また遺伝子の数がヒトに比べて桁違いに多いということは、一言でいうと多様性があるということです。ヒトは「ヒト + 共生微生物群」を「超個体」とすることで、個体だけに頼るより多様性を獲得できた。共生微生物群は人によって違います。たとえ一卵性双生児でも違います。この多様性こそ、ヒトが存続していくための重要事項なのです。多様性に関して言うと、そもそも生物の多くが有性生殖をするのも、遺伝子の多様性を確保する手段だというのが通説です。
そういった共生微生物群との相互作用で作られるのが人間の免疫機構です。免疫機構は極めて適応性に富んだシステムです。「非自己」を「自己」から区別するといっても、その「非自己」の種類は無限だし、また環境によって変わるからです。
人体はにいくつかの「原則」がありますが、その一つは
| 適応性に富んだシステムは、その発達段階でインプットを必要とする |
というものです。適応性に富んだシステムを設計図だけで決めることはできません。「設計図+インプット」で決まる。免疫に関して言うと、インプットが過小であったり偏っていると、それなりの免疫機構しかできないわけです。さらに、宇宙飛行士の筋力低下を引き合いに出すまでもなく、
| 人体の機能は、使わなければ衰える |
のが大原則です。免疫を制御し抑制する必要性が無い状態が続くと、その制御し抑制する能力が萎縮します。そして免疫制御能力が萎縮すると、アレルギーや自己免疫疾患が起きる。
現代の人間社会の重要課題は、崩れてしまった2つの生態系の回復です。2つとは、自然生態系と人体生態系です。人体生態系とは言うまでもなく、ヒトと共生微生物群の生態系(= 超個体)です。生態系の回復は容易ではありません。自然生態系の回復の原則は、
| トラを絶滅から守るためには、トラが暮らすジャングルとそこで生きているものすべて ── 土壌細菌からアリや木々に至るまで ── を保全しなければならない |
からです。人体生態系でも同じことが言えるはずです。
いまさら昔には戻れないことも多いでしょう。人体生態系の回復のために、寄生虫を意図的に体内に入れるわけにはいかない(免疫関連疾患の治療は別にして)。しかし「現代人の生活」と「人体生態系の回復」の妥協点は、何とかあるのではないか。それを模索していくことが、人類にとっての緊急の課題です。
以上が本書『寄生虫なき病』の(重要だと思える)ポイントの要約です。本書にはもっと多方面の話題があります。寄生虫治療の実態、マラリアと自己免疫疾患の関係、完全な無菌状態で飼育されたマウスがどうなるか、ヒトに無害なはずのヘルペス・ウイルスがなぜ疾患を引き起こすのかなど、興味深い話題は多々あるのですが、省略しました。また、旧友仮説(衛生仮説)の証拠となる研究も大変念入りに紹介されています。それらは本書を読んでもらうしかありません。
『寄生虫なき病』の感想
以降は本書『寄生虫なき病』の感想です。
本書の解説で生物学者の福岡伸一氏が書いていることなのですが、この本は医学・生理学における考え方の転換、パラダイムの転換を迫るものです。
つまり従来は、病原菌やウイルス、寄生虫といった「存在」が病を引き起こすことに注目が集まり、その「存在」をいかに排除するかが医学・生理学のテーマだった。ところが21世紀になって、共生微生物の「不在」が病を引き起こすという認識に至った。これはパラダイムの転換だというわけです。確かに「栄養不足による病」はあるが「細菌不足による病」というのはあまり聞いたことがない。
「不在」が病を引き起こすという意味で、福岡氏は解説のタイトルに「不在という病」というタイトルをつけています。しかし、これはちょっと不十分です。本書の原題は、この記事の冒頭にも掲げたように、
|
です。Epidemicとは単なる病気ではありません。「伝染病」のことです。「不在」が病を引き起こし、その病は伝染する・・・・・・。これが著者が言いたかったことでしょう。
なぜこの「不在」という病が伝染するのか。それは「不在」が文明によってもたらされたからです。文明は伝播します。「進んだ」文明は、より「遅れた」文明にとってかわる。そもそも文明は伝染病と非常に良く似ています。その感染力は非常に強い。この「文明の感染」を防ぐのは、鎖国でもしない限り(鎖国をしたとしても)非常に難しい。だから「不在」という病も伝染する。
微生物の「不在」は、文明によってもたらされた生活環境と広範囲に関係する可能性があります。それは「清潔指向」「消毒」「殺菌」「抗菌剤・抗菌加工」「抗生物質」「医薬品」「農薬」「殺虫剤」「除草剤」「食品保存剤」などからはじまって、「加工食品中心の食生活」「下水道の完備」「道路の舗装」「緑視率の減少」「小動物や昆虫の減少」などまでが関係する(可能性がある)わけです。人類はこの200年程度で自然生態系を大きく破壊してきたのですが、それと全く同じ行動様式・思考パターンで人体生態系を破壊してきたのではないか。自然生態系の破壊と同時期に、平行して・・・・・・。
「不在」によって引き起こされる病は、それが文明の進歩と表裏一体であるからこそ、非常に根が深いと思いました。
しかし、パラダイム転換と言うなら、もう一つ重要なパラダイム転換があると思います。それは免疫(獲得免疫)は何のために存在するのかということに関係したことです。20世紀の免疫学によると、
| 免疫は「自己」と「非自己」を区別し、「非自己」を排除することによって「自己」の統一性を保つためのもの |
です。免疫に対するこのような認識は、No.69-70「自己と非自己の科学」に詳しく書きました。しかし本書を読むと、
| 免疫は、「非自己」を「自己」に取り込み、自己の一部として共生して「超個体」を作り出すためのものでもある。もちろん、自己と共生できない「非自己」は排除する |
という考えになるのです。もしそうだとしたら、これこそが大きなパラダイム転換でしょう。
ヒトの免疫機構が微生物に対応するやりかたは、非寛容(攻撃)と寛容(攻撃の抑制)のセットです。自己を危うくするような微生物に対しては非寛容(免疫による攻撃)が続きます(攻撃の失敗もある)。しかし、共存できる微生物に対しては寛容(免疫の抑制)が優勢になる。微生物の方もヒトから寛容を引き出すように進化し(それがヒトの体内で生き残る道だから)、ヒトが受け入れてくれると、生息場所と栄養分をもらう代わりに、ヒトにメリットを与える(消化やビタミン合成など)。そして共生が成立する。
No.69-70「自己と非自己の科学」でも紹介したように、ヒトの免疫システムには、
・曖昧性
・偶然性
が含まれています(それでいてほとんどの場合、自己の統一性が保たれている)。生死にかかわるところに曖昧性があっていいのかと思ってしまいますが、実は曖昧なところがないとまずいのですね。自己と非自己の境目が設計図によって厳密に決まっているような生命体は、環境と外界の変化についていけません。もちろん、曖昧性が原因となって「個」の破綻を招くこともある。しかし、それを補って余りある「種」としてのメリットがあるということでしょう。
No.69-70「自己と非自己の科学」は、免疫学者の故・多田富雄が著した2冊の本によっているのですが、その多田氏は免疫系を「超システム」と呼び、
|
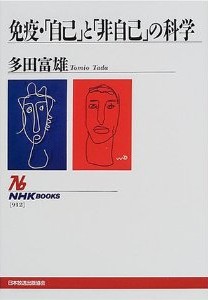
| |||
|
| |||
まさに「ヒトは免疫システムそのものを獲得していく = 自ら作り出してゆく」のですね。その「超システム」としての免疫システムが作り出すのが、「ヒト + 共生微生物群」という「超個体」なのでしょう。それが「獲得されるもの」です。ヒトの「獲得免疫」のありようは遺伝的に決まっているわけではありません。たとえ一卵性双生児であっても違います。そこに共生微生物群が加わると、一人一人でさらに違ってくる。自己とは何か、そのの根幹のところは極めて個性的であり、多様性に富むものなのです。
生命現象と社会現象を単純なアナロジーで考えるのはまずいとは思うのですが、本書を読んでいて、社会における「複雑な組織」と生命体の類似を考えずにはいられませんでした。
たとえば企業という組織ですが、純粋さ(コアとなる事業や技術、組織風土、企業理念など)を保ちつつ、異質さ(外国の人材、M&A、新分野、異業種連携、など)をいかに取り入れて共存していくかが重要です。これは生命体と非常に良く似ています。思い返すと、生物の進化をテーマにした No.56「強い者は生き残れない」の結論は「環境変化に柔軟に対応できるものが生き残る」でした。それは生命体も企業組織も全く同じだと思います。
サイエンス・ライターという職業
本書の著者であるモイゼス・ベラスケス = マノフは、コロンビア大学の大学院のジャーナリズム科でサイエンス・ライティングを専攻した科学ジャーナリストです。本書は8500本もの論文をあたって書いたと言います。本文には約700の注釈があって、引用した文献・論文が巻末に明記されています。
著者の姿勢もフェアで、個別の研究結果について反対意見があればそれも公平に書かれています。因果関係が実証されていないことは、実証されていないと書いてある。著者自身も自己免疫疾患を抱えていて、そのため寄生虫を体内に入れるという「治療」にチャレンジするのですが、その結果も(効果あり・効果なしの両方あった)、ありのままに書かれています。
本書で思ったのは「サイエンス・ライター」という職業の重要性です。現代は科学技術に関わる事項が社会の大問題になったり、人間社会の行く末に大きく関わったりするわけです。原子力発電がそうだし、地球温暖化もそうです。以前の記事で言うと、遺伝子組み換え作物(No.102-103「遺伝子組み換え作物のインパクト」)もそうでしょう。ガン研究もその一例です。しかしこういった重要事項は、それ自体が大変にこみ入っていて、複雑なわけです。一般人が理解するのは並大抵ではない。そのことから、人を惑わすいいかげんな説や、科学的根拠の全くない宣伝文句、誤った風説がまかり通ったりする。
このような科学技術に関わる複雑な事項を、科学者・技術者の研究成果や論文に基づきつつも、分かりやすく解説することは大変に重要だと思います。分かりやすく、というのは文章の分かりやすさも重要です。モイゼス・ベラスケス = マノフ氏の文章は非常に論理的で読みやすい。そのことも本書の優れた点だと思いました。
また同時に、この本は日本語訳が優れています。訳したのは赤根洋子さんという翻訳家です。もちろん原文の英語も良いのでしょうが、日本語文章が非常に明晰で感心しました。巻末の注釈(約700)を省略せずに記載したのも好感が持てます。
とにかく、アメリカでは全米屈指の名門大学でサイエンス・ライティングを専攻できるようなのです。日本ではどうなのでしょうか。
マイクロバイオームの再生医療
ここからは完全な補足です。
アメリカの雑誌「Scientific American」の2013年12月号に「World Changing Ideas」という記事が掲載されました。「世界を変えるアイデア」です(日経サイエンスの日本語訳では「常識を変える先端技術」)。この記事は、世界を変える(かもしれない)10の技術を紹介したものですが、その一つが「腸内細菌の再生」に関するものでした。『寄生虫なき病』と大いに関係する内容なので、日経サイエンスの日本語訳で一部を紹介します。
|
我々が発酵食品を食べたり乳酸菌やビフィズス菌入りの飲料を飲むのは、腸内細菌を「整えよう」とする努力です。この記事にある「メタゲノミクス」は、DNA解析技術を駆使して、大々的・組織的にマイクロバイオーム(細菌叢)を「整える」もののようです。
これはかなり難しい技術だというのが直感です。「普通の人に比べて、数種の腸内細菌が不足している」ことが分かったとしても、その数種を注入すればよいというわけではないはずです。ヒトは「数種の腸内細菌が不足している状態を前提に、それなりに最適化されている」はずです。人体生態系なのだから・・・・・・。
しかし「不在という伝染病」と戦うには、このような医療技術を突き詰めることしかないのだと感じました。
(続く)
| 補記 |
本文の中に本書を読んだ感想として、
|
つまり免疫システムのキーである「抗体」の一種、免疫グロブリンA(IgA)が、人体との共存を許す細菌だけに選択的に取り付き、腸の壁を覆っている粘液層に細菌が入りやすくしています。IgAが「取り付く」ことで粘液層に入るときの抵抗が少なくなるようです。これを研究している日本の理化学研究所のシドニア・ファガラサン氏がインタビューに答えていました。
|
人間の免疫システム(獲得免疫)が何をやっているかというと、それは、
| ① | 自己と非自己の認識 | ||
| ② | 特定の非自己の認識(特異性) |
の二つです。①はもちろん生命体としての自己同一性を保つためですが、②は何のためにあるのか。それは「特定の非自己」を攻撃するためと同時に、「特定の非自己」と共存し「自己」の一部とするためでもあるようです。
(2015.3.1)
2014-07-25 20:17
nice!(0)
トラックバック(0)



